タルコット・パーソンズ
Talcott
Parsons, 1902-1979

タルコット・パーソンズ
Talcott
Parsons, 1902-1979

★タルコット・パーソンズ(Talcott Parsons、1902年12月13日 - 1979年5月8日)は、古典派の伝統を持つアメリカの社会学者で、彼の社会行動論と構造的機能主義で最もよく知られている人物である。経済学で博士号を 取得後、1927年から1929年までハーバード大学の教員を務めた。1930年に彼はハーバード大学の新しい社会学部の最初の教授の一人とな り、その後、ハーバード大学の社会関係学部の設立に貢献している(→「タルコット・パーソンズの理論」)。
| Talcott Parsons
(December 13, 1902 – May 8, 1979) was an American sociologist of the
classical tradition, best known for his social action theory and
structural functionalism. Parsons is considered one of the most
influential figures in sociology in the 20th century.[17] After earning
a PhD in economics, he served on the faculty at Harvard University from
1927 to 1929. In 1930, he was among the first professors in its new
sociology department.[18] Later, he was instrumental in the
establishment of the Department of Social Relations at Harvard. Based on empirical data, Parsons' social action theory was the first broad, systematic, and generalizable theory of social systems developed in the United States and Europe.[19] Some of Parsons' largest contributions to sociology in the English-speaking world were his translations of Max Weber's work and his analyses of works by Max Weber, Émile Durkheim, and Vilfredo Pareto. Their work heavily influenced Parsons' view and was the foundation for his social action theory. Parsons viewed voluntaristic action through the lens of the cultural values and social structures that constrain choices and ultimately determine all social actions, as opposed to actions that are determined based on internal psychological processes.[19] Although Parsons is generally considered a structural functionalist, towards the end of his career, in 1975, he published an article that stated that "functional" and "structural functionalist" were inappropriate ways to describe the character of his theory.[20] From the 1970s, a new generation of sociologists criticized Parsons' theories as socially conservative and his writings as unnecessarily complex. Sociology courses have placed less emphasis on his theories than at the peak of his popularity (from the 1940s to the 1970s). However, there has been a recent resurgence of interest in his ideas.[18] Parsons was a strong advocate for the professionalization of sociology and its expansion in American academia. He was elected president of the American Sociological Association in 1949 and served as its secretary from 1960 to 1965. |
タルコット・パーソンズ
(Talcott
Parsons、1902年12月13日 -
1979年5月8日)は、古典派の伝統を持つアメリカの社会学者で、彼の社会行動論と構造的機能主義で最もよく知られている人物である。経済学で博士号を
取得後、1927年から1929年までハーバード大学の教員を務めた[17]。1930年に彼はハーバード大学の新しい社会学部の最初の教授の一人とな
り、その後、ハーバード大学の社会関係学部の設立に貢献した[18]。 経験的データに基づいたパーソンズの社会行動理論は、アメリカやヨーロッパで開発された社会システムの最初の幅広く体系的で一般化可能な理論であった [19]。英語圏の社会学に対するパーソンズの最大の貢献はマックス・ウェーバーの作品の翻訳とマックス・ウェーバー、エミール・デュルケーム、ヴィルフ レド・パレトの作品の分析であった。彼らの研究は、パーソンズの見解に大きな影響を与え、彼の社会的行為論の基礎となった。パーソンズは内的な心理的プロ セスに基づいて決定される行動とは対照的に、選択を制約し、最終的にすべての社会的行動を決定する文化的価値と社会構造のレンズを通して自発的な行動を捉 えていた[19]。 パーソンズは一般的に構造的機能主義者と考えられているが、彼のキャリアの終わり頃、1975年に彼は「機能的」や「構造的機能主義者」が彼の理論の特徴 を表すのに不適切な方法であると述べている論文を発表している[20]。 1970年代から、社会学者の新しい世代はパーソンズの理論を社会的に保守的であると批判し、彼の著作を不必要に複雑であると批判していた。社会学のコー スは、彼の人気のピーク時(1940年代から1970年代まで)よりも彼の理論に重点を置いていない。しかし、最近になって彼の思想に対する関心が復活し ている[18]。 パーソンズは社会学の専門化とアメリカのアカデミズムにおけるその拡大の強い擁護者であった。彼は1949年にアメリカ社会学会の会長に選出され、 1960年から1965年まで同学会の幹事を務めていた。 |
| Early life He was born on December 13, 1902, in Colorado Springs, Colorado. He was the son of Edward Smith Parsons (1863–1943) and Mary Augusta Ingersoll (1863–1949). His father had attended Yale Divinity School, was ordained as a Congregationalist minister, and served first as a minister for a pioneer community in Greeley, Colorado. At the time of Parsons' birth, his father was a professor in English and vice-president at Colorado College. During his Congregational ministry in Greeley, Edward had become sympathetic to the Social Gospel movement but tended to view it from a higher theological position and was hostile to the ideology of socialism.[21] Also, both he and Talcott would be familiar with the theology of Jonathan Edwards. The father would later become the president of Marietta College in Ohio. Parsons' family is one of the oldest families in American history. His ancestors were some of the first to arrive from England in the first half of the 17th century.[22] The family's heritage had two separate and independently developed Parsons lines, both to the early days of American history deeper into British history. On his father's side, the family could be traced back to the Parsons of York, Maine. On his mother's side, the Ingersoll line was connected with Edwards and from Edwards on would be a new, independent Parsons line because Edwards' eldest daughter, Sarah, married Elihu Parsons on June 11, 1750. |
幼少期 1902年12月13日、コロラド州コロラドスプリングスで生まれた。エドワード・スミス・パーソンズ(1863-1943)とメアリー・オーガスタ・イ ンガーソル(1863-1949)の息子である。父はエール大学神学部で学び、会衆派牧師に叙階され、コロラド州グリーリーの開拓者コミュニティの牧師と して活躍した。パーソンズが生まれた当時、父親はコロラド大学の英語教授と副学長を務めていた。グリーリーでの会衆派牧師時代、エドワードは社会福音運動 に共感していたが、より高い神学的立場から見る傾向があり、社会主義の思想に敵対していた[21]。 また、彼とタルコットは共にジョナサン・エドワーズの神学に親しむことになった。父親は後にオハイオ州のマリエッタ・カレッジの学長となる。 パーソンズの家系は、アメリカ史の中で最も古い家系の一つである。彼の祖先は、17世紀前半にイギリスから最初にやってきた人々である[22]。この一族 の遺産には、アメリカの歴史の初期にイギリスの歴史に深く入り込んだ、2つの別々の、独立して発展したパーソンズの家系があった。父方はメイン州ヨークの パーソンズ家に遡ることができる。母方のインガソルの系統はエドワーズにつながり、エドワーズから先は、1750年6月11日にエドワーズの長女サラがエ リフ・パーソンズと結婚したため、新たに独立したパーソンズの系統となる。 |
| Education Amherst College As an undergraduate, Parsons studied biology and philosophy at Amherst College and received his BA in 1924. Amherst College had become the Parsons' family college by tradition; his father and his uncle Frank had attended it, as had his elder brother, Charles Edward. Initially, Parsons was attracted to a career in medicine, as he was inspired by his elder brother[23]: 826 so he studied a great deal of biology and spent a summer working at the Oceanographic Institution at Woods Hole, Massachusetts. Parsons' biology professors at Amherst were Otto C. Glaser and Henry Plough. Gently mocked as "Little Talcott, the gilded cherub," Parsons became one of the student leaders at Amherst. Parsons also took courses with Walton Hale Hamilton and the philosopher Clarence Edwin Ayres, both known as "institutional economists". Hamilton, in particular, drew Parsons toward social science.[23]: 826 They exposed him to literature by authors such as Thorstein Veblen, John Dewey, and William Graham Sumner. Parsons also took a course with George Brown in the philosophy of Immanuel Kant and a course in modern German philosophy with Otto Manthey-Zorn, who was a great interpreter of Kant. Parsons showed from early on, a great interest in the topic of philosophy, which most likely was an echo of his father's great interest in theology in which tradition he had been profoundly socialized, a position unlike with his professors'. Two term papers that Parsons wrote as a student for Clarence E. Ayres's class in Philosophy III at Amherst have survived. They are referred to as the Amherst Papers and have been of strong interest to Parsons scholars. The first was written on December 19, 1922, "The Theory of Human Behavior in its Individual and Social Aspects."[24] The second was written on March 27, 1923, "A Behavioristic Conception of the Nature of Morals".[25] The papers reveal Parsons' early interest in social evolution.[26] The Amherst Papers also reveal that Parsons did not agree with his professors since he wrote in his Amherst papers that technological development and moral progress are two structurally-independent empirical processes. London School of Economics After Amherst, he studied at the London School of Economics for a year, where he was exposed to the work of Bronisław Malinowski, R. H. Tawney, L. T. Hobhouse, and Harold Laski.[23]: 826 During his days at LSE, he made friends with E. E. Evans-Pritchard, Meyer Fortes, and Raymond Firth, who all participated in the Malinowski seminar. Also, he made a close personal friendship with Arthur and Eveline M. Burns. At the LSE he met Helen Bancroft Walker, a young American, and they married on April 30, 1927. The couple had three children: Anne, Charles, and Susan and eventually four grandchildren. Walker's father was born in Canada but had moved to the Boston area and later become an American citizen. |
教育内容 アマースト大学 1924年、パーソンズはアマースト大学で生物学と哲学を学び、学士号を取得した。アマースト大学は、パーソンズ家の伝統的な大学であり、父と叔父のフラ ンク、兄のチャールズ・エドワードが在籍していた。パーソンズは当初、兄の影響で医学の道に惹かれていた[23]: 826 ので、生物学を大いに学び、夏にはマサチューセッツ州ウッズホールの海洋研究所で働いた。 アマースト大学でパーソンズの生物学の教授を務めたのは、オットー・C・グレーザーとヘンリー・プラウであった。パーソンズは、「金ぴかのケルビム、小さ なタルコット」と揶揄されながらも、アマースト大学の学生指導者の一人となった。また、パーソンズは、「制度経済学者」として知られるウォルトン・ヘイ ル・ハミルトンや哲学者のクラレンス・エドウィン・エアーズの講義も受けた。特にハミルトンはパーソンズを社会科学に向かわせた[23]: 826 彼らは、トースタイン・ヴェブレン、ジョン・デューイ、ウィリアム・グラハム・サムナーといった著者の文献に彼を触れさせた。また、パーソンズは、ジョー ジ・ブラウンからイマニュエル・カントの哲学の講義を受け、オットー・マンテイ=ゾーンから現代ドイツ哲学の講義を受けた。パーソンズは早くから哲学に強 い関心を抱いていたが、それは、神学に強い関心を抱いていた父親の影響であったようで、その伝統の中で、教授陣とは異なる立場で深く社会性を身につけた。 パーソンズが学生時代にアマースト大学のクラレンス・E・エアズの哲学IIIの授業で書いた2つの論文も残っている。これらはアマースト・ペーパーズと呼 ばれ、パーソンズ研究者の強い関心を集めている。また、アマースト論文では、技術的発展と道徳的進歩は構造的に独立した経験的過程であると書いており、 パーソンズが教授と意見が合わなかったことも明らかにされている[26]。 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス アマーストの後、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに1年間留学し、マリノフ スキー、R. H. トーニー、L. T. ホブハウス、ハロルド・ラスキらの研究に触れる[23]: 826 LSE時代には、マリノフスキーのセミナーに参加したE. E. エバンス=プリチャード、メイヤー・フォータス、レイモンド・フィースと友人になり、また、アーサー・バーンズ、エヴリン・M・バーンズとも親交を深め た。また、アーサー・バーンズやエヴリン・M・バーンズとも個人的に親交を深めた。 LSEでは、若いアメリカ人のヘレン・バンクロフト・ウォーカーと出会い、1927年4月30日に結婚した。1927年4月30日に結婚し、3人の子供を もうけた。アン、チャールズ、スーザンの3人の子供と、4人の孫が生まれた。ウォーカーの父親はカナダ出身だが、ボストン近郊に移り住み、後にアメリカ国 籍を取得した。 |
| University of Heidelberg In June, Parsons went on to the University of Heidelberg, where he received his PhD in sociology and economics in 1927. At Heidelberg, he worked with Alfred Weber, Max Weber's brother; Edgar Salin, his dissertation adviser; Emil Lederer; and Karl Mannheim. He was examined on Kant's Critique of Pure Reason by the philosopher Karl Jaspers.[27] At Heidelberg, Parsons was also examined by Willy Andreas on the French Revolution. Parsons wrote his Dr. Phil. thesis on The Concept of Capitalism in the Recent German Literature, with his main focus on the work of Werner Sombart and Weber. It was clear from his discussion that he rejected Sombart's quasi-idealistic views and supported Weber's attempt to strike a balance between historicism, idealism and neo-Kantianism. The most crucial encounter for Parsons at Heidelberg was with the work of Max Weber about whom he had never heard before. Weber became tremendously important for Parsons because his upbringing with a liberal but strongly-religious father had made the question of the role of culture and religion in the basic processes of world history a persistent puzzle in his mind. Weber was the first scholar who truly provided Parsons with a compelling theoretical "answer" to the question, so Parsons became totally absorbed in reading Weber. Parsons decided to translate Weber's work into English and approached Marianne Weber, Weber's widow. Parsons would eventually translate several of Weber's works into English.[28][29] His time in Heidelberg had him invited by Marianne Weber to "sociological teas", which were study group meetings that she held in the library room of her and Max's old apartment. One scholar that Parsons met at Heidelberg who shared his enthusiasm for Weber was Alexander von Schelting. Parsons later wrote a review article on von Schelting's book on Weber.[30] Generally, Parsons read extensively in religious literature, especially works focusing on the sociology of religion. One scholar who became especially important for Parsons was Ernst D. Troeltsch (1865–1923). Parsons also read widely on Calvinism. His reading included the work of Emile Doumerque,[31] Eugéne Choisy, and Henri Hauser. |
ハイデルベルク大学 6月、パーソンズはハイデルベルク大学に進学し、1927年に社会学と経済学の博士号を取得した。ハイデルベルクでは、マックス・ウェーバーの弟アルフレッド・ウェーバー、学位論文の指導者エ ドガー・サリン、エミール・レーデラー、カール・マンハイムらと研究した。ハイデルベルクでは、カントの『純粋理性批判』について哲学者のカール・ヤス パースの審査を受けた[27]。また、フランス革命についてウィリー・アンドレアスの審査を受けた。パーソンズは、博士論文を「最近のドイ ツ文学における資本主義の概念」について執筆し、主にヴェルナー・ゾンバートとヴェーバーの作品に焦点を当てた。ソンバートの準理想主義的な考え方を否定 し、歴史主義、観念論、新カント主義とのバランスをとろうとするウェーバーの考え方を支持したことは、彼の議論から明らかであった。 ハイデルベルクでのパーソンズにとって最も重要な出会いは、それまで聞 いたこともなかったマックス・ウェーバーの仕事との出会いであった。自由主義者でありながら宗教心の強い父親のもとで育ったパーソンズにとって、世界史の 基本的過程における文化や宗教の役割の問題は、彼の心の中にある持続的なパズルであったからである。ウェーバーは、その問いに真に説得力のある理論的な 「答え」を与えてくれた最初の学者であり、パーソンズはウェーバーを読むことに没頭するようになった。 パーソンズは、ウェーバーの著作を英語に翻訳することを決意し、ウェー バーの未亡人であるマリアンヌ・ウェーバーに声をかけた。パーソンズは最終的にウェーバーの著作のいくつかを英語に翻訳することになる[28][29]。 ハイデルベルクでの時間は、マリアンヌ・ウェーバーから「社会学茶会」に招待されることになった。これは、彼女とマックスの古いアパートの図書館室で彼女 が開いていた研究会の会合だった。ハイデルベルクで出会った学者のうち、ウェーバーへの熱意を共有したのがアレクサンダー・フォン・シェルティングであっ た。パーソンズは、後にフォン・シェルティングのヴェーバーに関する本のレビュー記事を書いている[30]。一般的にパーソンズは、宗教文献、特に宗教社 会学に焦点を当てた著作を広く読んでいた。パーソンズにとって特に重要となった学者の一人がエルンスト・D・トロエルシュ(1865-1923)であっ た。パーソンズはまた、カルヴァン主義についても広く読んでいる。エミール・ドゥメルク、ウジェーヌ・ショワジー、アンリ・ハウザーの著作を読んでいた[31]。 |
| Early academic career Harvard Economics Department In 1927, after a year of teaching at Amherst (1926–1927), Parsons entered Harvard, as an instructor in the Economics Department,[32] where he followed F. W. Taussig's lectures on economist Alfred Marshall and became friends with the economist historian Edwin Gay, the founder of Harvard Business School. Parsons also became a close associate of Joseph Schumpeter and followed his course General Economics. Parsons was at odds with some of the trends in Harvard's department which then went in a highly-technical and a mathematical direction. He looked for other options at Harvard and gave courses in "Social Ethics" and in the "Sociology of Religion". Although he entered Harvard through the Economics Department, his activities and his basic intellectual interest propelled him toward sociology. However, no Sociology Department existed during his first years at Harvard. Harvard Sociology Department The chance for a shift to sociology came in 1930, when Harvard's Sociology Department was created[33] under Russian scholar Pitirim Sorokin. Sorokin, who had fled the Russian Revolution from Russia in 1923, was given the opportunity to establish the department. Parsons became one of the new department's two instructors, along with Carl Joslyn. Parsons established close ties with biochemist and sociologist Lawrence Joseph Henderson, who took a personal interest in Parsons' career at Harvard. Parsons became part of L. J. Henderson's famous Pareto study group, in which some of the most important[citation needed] intellectuals at Harvard participated, including Crane Brinton, George C. Homans, and Charles P. Curtis. Parsons wrote an article on Pareto's theory[34] and later explained that he had adopted the concept of "social system" from reading Pareto. Parsons also made strong connections with two other influential intellectuals with whom he corresponded for years: economist Frank H. Knight and Chester Barnard, one of the most dynamic businessmen of the US. The relationship between Parsons and Sorokin quickly turned sour. A pattern of personal tensions was aggravated by Sorokin's deep dislike for American civilization, which he regarded as a sensate culture that was in decline. Sorokin's writings became increasingly anti-scientistic in his later years, widening the gulf between his work and Parsons' and turning the increasingly positivistic American sociology community against him. Sorokin also tended to belittle all sociology tendencies that differed from his own writings, and by 1934 was quite unpopular at Harvard. Some of Parsons' students in the department of sociology were people such as Robin Williams Jr., Robert K. Merton, Kingsley Davis, Wilbert Moore, Edward C. Devereux, Logan Wilson, Nicholas Demereth, John Riley Jr., and Mathilda White Riley. Later cohorts of students included Harry Johnson, Bernard Barber, Marion Levy and Jesse R. Pitts. Parsons established, at the students' request, a little, informal study group which met year after year in Adams' house. Toward the end of Parsons' career, German systems theorist Niklas Luhmann also attended his lectures. In 1932, Parsons bought a farmhouse near the small town of Acworth, but Parsons often, in his writing, referred to it as "the farmhouse in Alstead". The farmhouse was not big and impressive; indeed, it was a very humble structure with almost no modern utilities. Still, it became central to Parsons' life, and many of his most important works were written in its peace and quiet. In the spring of 1933, Susan Kingsbury, a pioneer of women's rights in America, offered Parsons a position at Bryn Mawr College; however, Parsons declined the offer because, as he wrote to Kingsbury, "neither salary nor rank is really definitely above what I enjoy here".[35] In the academic year of 1939–1940 Parsons and Schumpeter conducted an informal faculty seminar at Harvard, which discussed the concept of rationality. Among the participants were D. V. McGranahan, Abram Bergson, Wassily Leontief, Gottfried Haberler, and Paul Sweezy. Schumpeter contributed the essay "Rationality in Economics", and Parsons submitted the paper "The Role of Rationality in Social Action" for a general discussion.[36] Schumpeter suggested that he and Parsons should write or edit a book together on rationality, but the project never materialized. Neoclassical economics vs. institutionalists In the discussion between neoclassical economics and the institutionalists, which was one of the conflicts that prevailed within the field of economics in the 1920s and early 1930s, Parsons attempted to walk a very fine line. He was very critical about neoclassical theory, an attitude he maintained throughout his life and that is reflected in his critique of Milton Friedman and Gary Becker. He was opposed to the utilitarian bias within the neoclassical approach and could not embrace them fully. However, he agreed partly on their theoretical and methodological style of approach, which should be distinguished from its substance. He was thus unable to accept the institutionalist solution. In a 1975 interview, Parsons recalled a conversation with Schumpeter on the institutionalist methodological position: "An economist like Schumpeter, by contrast, would absolutely have none of that. I remember talking to him about the problem and .. I think Schumpeter was right. If economics had gone that way [like the institutionalists] it would have had to become a primarily empirical discipline, largely descriptive, and without theoretical focus. That's the way the 'institutionalists' went, and of course Mitchell was affiliated with that movement."[37] Anti-Nazism Parsons returned to Germany in the summer of 1930 and became an eyewitness to the feverish atmosphere in Weimar Germany during which the Nazi Party rose to power. Parsons received constant reports about the rise of Nazism through his friend, Edward Y. Hartshorne, who was traveling there. Parsons began, in the late 1930s, to warn the American public about the Nazi threat, but he had little success, as a poll showed that 91 percent of the country opposed the Second World War.[38] Most of the US thought also that the country should have stayed out of the First World War and that the Nazis were, regardless of what they did in Germany or even Europe, no threat to the US. Many Americans even sympathized with Germany, as many had ancestry from there, and the latter both was strongly anticommunist and had gotten itself out of the Great Depression while the US was still suffering from it. One of the first articles that Parsons wrote was "New Dark Age Seen If Nazis Should Win". He was one of the key initiators of the Harvard Defense Committee, aimed at rallying the American public against the Nazis. Parsons' voice sounded again and again over Boston's local radio stations, and he also spoke against Nazism during a dramatic meeting at Harvard, which was disturbed by antiwar activists. Together with graduate student Charles O. Porter, Parsons rallied graduate students at Harvard for the war effort. (Porter later became a Democratic US Representative for Oregon.) During the war, Parsons conducted a special study group at Harvard, which analyzed what its members considered the causes of Nazism, and leading experts on that topic participated. Second World War In the spring of 1941, a discussion group on Japan began to meet at Harvard. The group's five core members were Parsons, John K. Fairbank, Edwin O. Reischauer, William M. McGovern, and Marion Levy Jr. A few others occasionally joined the group, including Ai-Li Sung and Edward Y. Hartshorne. The group arose out of a strong desire to understand the country whose power in the East had grown tremendously and had allied itself with Germany, but, as Levy frankly admitted, "Reischauer was the only one who knew anything about Japan."[39] Parsons, however, was eager to learn more about it and was "concerned with general implications." Shortly after the Japanese attack on Pearl Harbor, Parsons wrote in a letter to Arthur Upham Pope (1881–1969) that the importance of studies of Japan certainly had intensified.[40] In 1942, Parsons worked on arranging a major study of occupied countries with Bartholomew Landheer of the Netherlands Information Office in New York.[41] Parsons had mobilized Georges Gurvitch, Conrad Arnsberg, Dr. Safranek and Theodore Abel to participate,[42] but it never materialized for lack of funding. In early 1942, Parsons unsuccessfully approached Hartshorne, who had joined the Psychology Division of the Office of the Coordinator of Information (COI) in Washington to interest his agency in the research project. In February 1943, Parsons became the deputy director of the Harvard School of Overseas Administration, which educated administrators to "run" the occupied territories in Germany and the Pacific Ocean. The task of finding relevant literature on both Europe and Asia was mindboggling and occupied a fair amount of Parsons' time. One scholar Parsons came to know was Karl August Wittfogel and they discussed Weber. On China, Parsons received fundamental information from Chinese scholar Ai-Li Sung Chin and her husband, Robert Chin. Another Chinese scholar Parsons worked closely with in this period was Hsiao-Tung Fei (or Fei Xiaotong) (1910–2005), who had studied at the London School of Economics and was an expert on the social structure of the Chinese village. Intellectual exchanges Parsons met Alfred Schütz during the rationality seminar, which he conducted together with Schumpeter, at Harvard in the spring of 1940. Schutz had been close to Edmund Husserl and was deeply embedded in the latter's phenomenological philosophy.[43] Schutz was born in Vienna but moved to the US in 1939, and for years, he worked on the project of developing a phenomenological sociology, primarily based on an attempt to find some point between Husserl's method and Weber's sociology.[44] Parsons had asked Schutz to give a presentation at the rationality seminar, which he did on April 13, 1940, and Parsons and Schutz had lunch together afterward. Schutz was fascinated with Parsons' theory, which he regarded as the state-of-the-art social theory, and wrote an evaluation of Parsons' theory that he kindly asked Parsons to comment. That led to a short but intensive correspondence, which generally revealed that the gap between Schutz's sociologized phenomenology and Parsons' concept of voluntaristic action was far too great.[45] From Parsons' point of view, Schutz's position was too speculative and subjectivist, and tended to reduce social processes to the articulation of a Lebenswelt consciousness. For Parsons, the defining edge of human life was action as a catalyst for historical change, and it was essential for sociology, as a science, to pay strong attention to the subjective element of action, but it should never become completely absorbed in it since the purpose of a science was to explain causal relationships, by covering laws or by other types of explanatory devices. Schutz's basic argument was that sociology cannot ground itself and that epistemology was not a luxury but a necessity for the social scientist. Parsons agreed but stressed the pragmatic need to demarcate science and philosophy and insisted moreover that the grounding of a conceptual scheme for empirical theory construction cannot aim at absolute solutions but needs to take a sensible stock-taking of the epistemological balance at each point in time. However, the two men shared many basic assumptions about the nature of social theory, which has kept the debate simmering ever since.[46][47] By request from Ilse Schutz, after her husband's death, Parsons gave, on July 23, 1971, permission to publish the correspondence between him and Schutz. Parsons also wrote "A 1974 Retrospective Perspective" to the correspondence, which characterized his position as a "Kantian point of view" and found that Schutz's strong dependence on Husserl's "phenomenological reduction" would make it very difficult to reach the kind of "conceptual scheme" that Parsons found essential for theory-building in social sciences.[48] Between 1940 and 1944, Parsons and Eric Voegelin (1901–1985) exchanged intellectual views through correspondence.[49][50][51] Parsons had probably met Voegelin in 1938 and 1939, when Voegelin held a temporary instructor appointment at Harvard. The bouncing point for their conversation was Parsons' manuscript on anti-Semitism and other materials that he had sent to Voegelin. Discussion touched on the nature of capitalism, the rise of the West, and the origin of Nazism. The key to the discussion was the implication of Weber's interpretation of Protestant ethics and the impact of Calvinism on modern history. Although the two scholars agreed on many fundamental characteristics about Calvinism, their understanding of its historical impact was quite different. Generally, Voegelin regarded Calvinism as essentially a dangerous totalitarian ideology; Parsons argued that its current features were temporary and that the functional implications of its long-term, emerging value-l system had revolutionary and not only "negative" impact on the general rise of the institutions of modernity. The two scholars also discussed Parsons' debate with Schütz and especially why Parsons had ended his encounter with Schutz. Parsons found that Schutz, rather than attempting to build social science theory, tended to get consumed in philosophical detours. Parsons wrote to Voegelin: "Possibly one of my troubles in my discussion with Schuetz lies in the fact that by cultural heritage I am a Calvinist. I do not want to be a philosopher – I shy away from the philosophical problems underlying my scientific work. By the same token I don't think he wants to be a scientist as I understand the term until he has settled all the underlying philosophical difficulties. If the physicists of the 17th century had been Schuetzes there might well have been no Newtonian system."[52] In 1942, Stuart C. Dodd published a major work, Dimensions of Society,[53] which attempted to build a general theory of society on the foundation of a mathematical and quantitative systematization of social sciences. Dodd advanced a particular approach, known as an "S-theory". Parsons discussed Dodd's theoretical outline in a review article the same year.[54] Parsons acknowledged Dodd's contribution to be an exceedingly formidable work but argued against its premises as a general paradigm for the social sciences. Parsons generally argued that Dodd's "S-theory", which included the so-called "social distance" scheme of Bogardus, was unable to construct a sufficiently sensitive and systematized theoretical matrix, compared with the "traditional" approach, which has developed around the lines of Weber, Pareto, Émile Durkheim, Sigmund Freud, William Isaac Thomas, and other important agents of an action-system approach with a clearer dialogue with the cultural and motivational dimensions of human interaction. In April 1944, Parsons participated in a conference, "On Germany after the War", of psychoanalytical oriented psychiatrists and a few social scientists to analyze the causes of Nazism and to discuss the principles for the coming occupation.[55] During the conference, Parsons opposed what he found to be Lawrence S. Kubie's reductionism. Kubie was a psychoanalyst, who strongly argued that the German national character was completely "destructive" and that it would be necessary for a special agency of the United Nations to control the German educational system directly. Parsons and many others at the conference were strongly opposed to Kubie's idea. Parsons argued that it would fail and suggested that Kubie was viewing the question of Germans' reorientation "too exclusively in psychiatric terms". Parsons was also against the extremely harsh Morgenthau Plan, published in September 1944. After the conference, Parsons wrote an article, "The Problem of Controlled Institutional Change", against the plan.[56] Parsons participated as a part-time adviser to the Foreign Economic Administration Agency between March and October 1945 to discuss postwar reparations and deindustrialization.[57][58] Parsons was elected a Fellow of the American Academy of Arts and Sciences in 1945.[59] Taking charge at Harvard Parsons' situation at Harvard University changed significantly in early 1944, when he received a good offer from Northwestern University. Harvard reacted to the offer by appointing Parsons as the chairman of the department, promoting him to the rank of full professor and accepting the process of reorganization, which led to the establishment of the new department of Social Relations. Parsons' letter to Dean Paul Buck, on April 3, 1944, reveals the high point of this moment.[60] Because of the new development at Harvard, Parsons chose to decline an offer from William Langer to join the Office of Strategic Services, the predecessor of the Central Intelligence Agency. Langer proposed for Parsons to follow the American army in its march into Germany and to function as a political adviser to the administration of the occupied territories. Late in 1944, under the auspices of the Cambridge Community Council, Parsons directed a project together with Elizabeth Schlesinger. They investigated ethnic and racial tensions in the Boston area between students from Radcliffe College and Wellesley College. This study was a reaction to an upsurge of anti-Semitism in the Boston area, which began in late 1943 and continued into 1944.[61] At the end of November 1946, the Social Research Council (SSRC) asked Parsons to write a comprehensive report of the topic of how the social sciences could contribute to the understanding of the modern world. The background was a controversy over whether the social sciences should be incorporated into the National Science Foundation. Parsons' report was in form of a large memorandum, "Social Science: A Basic National Resource", which became publicly available in July 1948 and remains a powerful historical statement about how he saw the role of modern social sciences.[62] |
初期の学問的キャリア ハーバード大学 経済学部 1927年、アマースト大学で1年間教えた後(1926-1927)、パーソンズはハーバード大学の経済学部の講師として入学し、F・W・タウシグの経済 学者アルフレッド・マーシャルに関する講義を受け、経済学者の歴史学者でハーバードビジネススクールの創設者のエドウィン・ゲイと友人になった[32]。 パーソンズはまた、ヨーゼフ・シュンペーターの側近となり、彼の講義「一般経済学」を受講した。パーソンズは、高度に技術的、数学的な方向に進んでいった ハーバード大学の学部の動向と対立していた。彼は、ハーバード大学に他の選択肢を求め、「社会倫理学」や「宗教社会学」の講義を行った。経済学部からハー バード大学に入ったものの、彼の活動や基本的な知的関心は、社会学へと駆り立てた。しかし、ハーバード大学での最初の数年間は、社会学部は存在しなかっ た。 ハーバード大学社会学部 社会学への転換のチャンスは、1930年にロシア人学者ピティリム・ソローキンの下でハーバード大学の社会学部が創設されたときに訪れた[33]。ソロー キンは1923年にロシアからロシア革命を逃れてきており、学科設立の機会を与えられていた。パーソンズは、カール・ジョスリンとともに新学科の2人の教 官のひとりとなった。パーソンズは、生化学者で社会学者のローレンス・ジョセフ・ヘ ンダーソンと親密な関係を築き、彼はパーソンズのハーバード大学でのキャリアに個人的に関心を寄せていた。このグループには、クレイン・ブリントン、 ジョージ・C・ホーマンス、チャールズ・P・カーティスなど、ハーバード大学で最も重要な知識人たちが参加していた[citation needed]。パーソンズはパレートの理論に関する論文を書き[34]、後にパレートを読んで「社会システム」の概念を取り入れたと説明している。また パーソンズは、経済学者のフランク・H・ナイトやアメリカで最もダイナミックな実業 家の一人であるチェスター・バーナードという、長年にわたって文通を続けた有力な知識人たちとも強い結びつきをもっていた。パーソンズとソ ローキンの関係は、すぐに険悪になった。パーソンズとソローキンの関係は急速に悪化し、ソローキンがアメリカ文明を深く嫌い、アメリカ文明は衰退しつつあ る感覚的な文化だと考えていたこともあり、個人的な緊張が高まり、パーソンズとソローキンの関係は悪化した。晩年、ソローキンの著作はますます反科学的な ものとなり、パーソンズとの溝を深め、実証主義的なアメリカ社会学界を敵に回すことになった。ソローキンはまた、彼自身の著作と異なるすべての社会学の傾 向を軽んじる傾向があり、1934年までにハーバード大学でかなり不人気となった。 パーソンズの社会学部の学生には、ロビン・ウィリアム・ジュニア、ロバート・K・マートン、キングスレー・デイヴィス、ウィルバート・ムーア、エドワー ド・C・デヴリュー、ローガン・ウィルソン、ニコラス・デミアス、ジョン・ライリー・ジュニア、マチルダ・ホワイト・ライリーといった人たちがいる。その 後、ハリー・ジョンソン、バーナード・バーバー、マリオン・レヴィ、ジェシー・R・ピッツらが入学している。パーソンズは、学生たちの要望で、毎年アダム ズの家で会合を持つ小さな非公式の研究会を設立した。パーソンズのキャリアの終わりには、ドイツのシステム理論家ニクラス・ルーマンも彼の講義を受講して いた。 1932年、パーソンズはアクワースという小さな町の近くに農家を購入したが、パーソンズは執筆の際、しばしばそれを「アルステッドの農家」と呼んでい る。その農家は、大きく印象的なものではなかった。実際、近代的な設備はほとんどなく、非常に質素な建物であった。それでも、この農家はパーソンズの生活 の中心となり、彼の最も重要な作品の多くは、この平穏で静かな場所で書かれた。 1933年の春、アメリカにおける女性の権利の先駆者であるスーザン・キングスベリーはパーソンズにブリンマー大学での地位を提供したが、パーソンズはキ ングスベリーに書いたように、「給与も地位も私がここで楽しむものよりも本当に間違いなく上」なのでその申し出を辞退している[35]。 1939年から1940年にかけて、パーソンズとシュンペーターはハーバード大学で非公式な教授セミナーを行い、合理性の概念について議論していた。参加 者にはD. V. McGranahan、Abram Bergson、Wassily Leontief、Gottfried Haberler、Paul Sweezyが含まれていた。シュンペーターは「経済学における合理性」を、パーソンズは「社会的行為における合理性の役割」という論文を提出し、総合討 論に参加した[36]。 新古典派経済学と制度学派の比較 1920年代から1930年代初頭にかけて経済学の分野で起こった対立の一つである新古典派経済学と制度派の議論において、パーソンズは非常に微妙なライ ンを歩もうとした。彼は新古典派理論に対して非常に批判的であり、その姿勢は生涯を通じて維持され、ミルトン・フリードマンやゲイリー・ベッカーに対する 批判にも反映されている。彼は、新古典派アプローチの中にある功利主義的なバイアスに反対しており、彼らを完全に受け入れることはできなかった。しかし、 その実質とは区別されるべき、彼らの理論的・方法論的なアプローチのスタイルについては、部分的に同意していた。そのため、彼は制度学派の解決策を受け入 れることができなかった。パーソンズは、1975年のインタビューのなかで、制度主義の方法論の立場について、シュンペーターとの会話を回想している。 「シュンペーターのような経済学者は、それとは対照的に、まったくそのようなことはしないでしょう。私は彼とこの問題について話したことを覚えています。 もし経済学が(制度学派のように)そのような方向に進んでいたら、主に経験的な学問にならざるを得ず、大部分は記述的で、理論的な焦点を持たないものに なったでしょう。それが「制度派」の行き方であり、もちろんミッチェルはその運動に加わっていた」[37]。 反ナチズム パーソンズは1930年の夏にドイツに戻り、ナチス党が権力を握ったワイマール・ドイツの熱狂的な雰囲気を目撃することになる。パーソンズは、現地に出張 していた友人のエドワード・Y・ハーツホーンを通じて、ナチズムの台頭について絶えず報告を受けていた。パーソンズは1930年代後半にナチスの脅威についてアメリカ国民に警告を与え始めたが、 91%の国民が第二次世界大戦に反対しているという世論調査があるように、ほとんど成功はしなかった[38]。 また、第一次世界大戦には参戦すべきではなかった、ナチスはドイツやヨーロッパで何をしようが、アメリカにとって何の脅威にもならない、とほとんどのアメ リカ人が思っていた。アメリカ人の多くはドイツに先祖を持ち、ドイツは反共産主義が 強く、アメリカがまだ大恐慌に苦しんでいる間に自国を立ち直らせたので、ドイツに同情的でさえあった。 パーソンズが最初に書いた論文の1つに「もしナチスが勝利したら、新しい暗黒時代がやってくる」というのがある。彼は、アメリカ国民をナチスに反対させる ための「ハーバード・ディフェンス委員会」の主要な発起人の一人であった。ハーバード大学では、反戦運動家たちの妨害にあいながらも、ナチズムに反対する 劇的な集会が開かれ、パーソンズの声はボストンの地元ラジオ局から幾度となく流れた。大学院生のチャールズ・O・ポーターとともに、ハーバード大学の大学 院生を戦争支援のために結集させた。(戦時中、ハーバード大学では、ナチズムの原因を分析する特別研究会が開かれ、第一線の専門家が参加した。 第二次世界大戦 1941年春、ハーバード大学で日本に関する討論会が始まった。パーソンズ、ジョン・K・フェアバンク、エドウィン・O・ライシャワー、ウィリアム・M・ マクガバン、マリオン・レヴィ・ジュニアの五人が中心メンバーで、他に宋愛麗、エドワード・Y・ハートソーンらが時折参加していた。東洋の国力が驚異的に 発展し、ドイツと同盟を結んだこの国を理解したいという強い願いから生まれたが、レヴィが率直に認めたように、「日本について知っているのはライシャワー だけだった」[39]。 しかしパーソンズはもっと知りたがり、「一般的意味合いに関心があった」という。 日本が真珠湾を攻撃した直後、パーソンズはアーサー・ウファム・ポープ(1881-1969)に宛てた手紙の中で、日本研究の重要性が確かに強まったと書 いている[40]。 1942年にパーソンズはニューヨークのオランダ情報局のバーソロミュー・ランドヒアと共に占領下の国々に関する大規模な研究の手配に取り組んでいた [41]。 パーソンズはジョルジュ・グルヴィッチ、コンラッド・アーンスバーグ、サフラネック博士、セオドア・アベルを参加に動員していたが、資金不足で実現するこ とはなかった[42]。1942年初頭、パーソンズはワシントンの情報調整官事務所(COI)の心理学部門に加わったハーツホーンに、彼の機関に研究プロ ジェクトに関心を持たせるようアプローチしたが、失敗に終わっている。1943年2月、パーソンズは、ドイツと太平洋の占領地を「運営」する管理者を教育 するハーバード大学海外管理学部の副部長に就任していた。ヨーロッパとアジアの両方について関連する文献を見つける作業は気の遠くなるようなもので、パー ソンズの時間のかなりの部分を占めた。パーソンズが知り合った学者にカール・アウグスト・ヴィットフォーゲルがおり、彼らはヴェーバーについて議論した。 中国については、中国の学者であるアイリ・ソン・チンとその夫ロバート・チンから基本的な情報を得た。また、この時期にパーソンズが親交を深めた中国人学 者として、ロンドン大学経済学校で学び、中国村落の社会構造の専門家であった飛暁東(または飛暁東)(1910-2005年)がいる。 知的交流 パーソンズは、1940年の春にハーバード大学でシュンペーターとともに行った合理性セミナーでアルフレッド・シュッツと出会った。シュッツはエドムン ド・フッサールと親交があり、後者の現象学的哲学に深く入り込んでいた[43] ウィーンで生まれたシュッツは1939年にアメリカに移住し、長年にわたって現象学的社会学の開発プロジェクトに取り組み、主にフッサールの方法とウェー バーの社会学の間のある点を見つける試みに基づいていた[44] パーソンズはシュッツに合理性セミナーで発表するよう依頼しており、彼は1940年4月13日にそれを行って、その後パーソンズとシュッツは一緒に昼食を 取ったという。シュッツは、社会理論の最先端とされるパーソンズの理論に魅了され、パーソンズの理論に対する評価を書き、パーソンズに親切にもコメントを 求めている。その結果、短いながらも集中的な書簡が交わされ、シュッツの社会学化された現象学とパーソンズの自発的行為という概念の間のギャップがあまり にも大きいことが概ね明らかになった[45]。 パーソンズの立場からは、シュッツの立場はあまりにも推測的かつ主観的で、社会過程をレーベンスヴェルト意識の調合に還元する傾向があったとされる。パー ソンズにとって、人間生活の決定的な端緒は歴史的変化の触媒としての行動であり、科学としての社会学は行動の主観的要素に強い関心を払うことが不可欠で あったが、科学の目的は因果関係を、法則を網羅したり他の種類の説明装置によって説明することにあるので、決してそれに完全に没頭してはならなかった。 シュッツの基本的な主張は、社会学は自らを根拠づけることができず、認識論は贅沢品ではなく、社会科学者にとって必要なものであるということであった。 パーソンズもこれに同意していたが、科学と哲学を区別する現実的な必要性を強調し、さらに、経験的理論構築のための概念的スキームの根拠は絶対的解を目指 すものではなく、各時点における認識論的バランスの賢明な棚卸しが必要であると主張していた。しかし、二人は社会理論の本質について多くの基本的な前提を 共有しており、そのことが以後も議論を沸騰させている[46][47] 夫の死後、イルゼ・シューズからの要請により、パーソンズは1971年7月23日にシュッツとの間の書簡を公開する許可を得ている。またパーソンズはこの 書簡に対して「1974年の回顧的視点」を書き、その中で自分の立場を「カント的視点」として特徴づけ、フッサールの「現象学的還元」に強く依存する シュッツの姿勢は、パーソンズが社会科学の理論構築に不可欠とする「概念図」に達することを非常に困難にしていることを見出していた[48]。 1940年から1944年にかけて、パーソンズとエリック・ヴェーゲリン(1901-1985)は、書簡を通じて知的見解を交換した[49][50] [51] パーソンズは、ヴェーゲリンがハーバード大学の臨時講師を務めていた1938年と1939年に、おそらくヴェーゲリンと会っていた。パーソンズが反ユダヤ 主義に関する原稿やその他の資料をヴォーゲリンに送ったことが、二人の会話のきっかけとなった。議論は、資本主義の本質、西洋の台頭、ナチズムの起源に及 んだ。特に重要だったのは、ヴェーバーのプロテスタント倫理観の解釈と、カルヴァン主義が近代史に与えた影響についてであった。二人の学者は、カルヴァン 主義に関する多くの基本的な特徴については同意していたが、その歴史的影響についての理解はかなり異なっていた。一般に、ヴェーゲリンはカルヴァン主義を 本質的に危険な全体主義思想とみなしていたが、パーソンズは、その現在の特徴は一時的なものであり、その長期的で新興の価値体系が持つ機能的意味は、近代 の制度全般の台頭に「負の」影響のみならず革命的な影響を与えたと主張している。 また二人の学者は、パーソンズとシュッツとの論争、特にパーソンズがシュッツとの出会いを終えた理由について議論した。パーソンズは、シュッツが社会科学 理論を構築しようとするよりも、むしろ哲学的な回り道をする傾向にあることを見つけたのである。パーソンズはヴェーゲリンに次のように書いている。「おそ らく、シュッツとの議論における私の悩みの一つは、文化的遺産として私がカルヴァン主義者であるという事実にあるのだろう。私は哲学者にはなりたくありま せん。自分の科学的研究の根底にある哲学的な問題から遠ざかるのです。同じことですが、彼は、哲学的な問題を解決しない限り、私の理解する科学者にはなり たがらないと思います。もし17世紀の物理学者がシュエッツであったなら、ニュートン・システムは存在しなかったかもしれない」[52]。 1942年、スチュアート・C・ドッドは主要な著作である『社会の次元』[53]を発表し、社会科学の数学的・数量的体系化を基礎として社会の一般理論を 構築しようと試みていた。ドッドは「S理論」として知られる特定のアプローチを進めていた。パーソンズは同年のレビュー論文でドッドの理論的アウトライン を論じており、ドッドの貢献が非常に手ごわい仕事であると認めているが、社会科学の一般的パラダイムとしてのその前提に対して異議を唱えている[54]。 パーソンズは一般的に、ボガードスのいわゆる「社会的距離」スキームを含むドッドの「S理論」は、ウェーバー、パレート、エミール・デュルケーム、ジーク ムント・フロイト、ウィリアム・アイザック・トーマス、そして人間の相互作用の文化と動機の次元との明確な対話と行動システムアプローチの他の重要なエー ジェントのラインの周りに発展した「従来の」アプローチと比較して、十分に敏感で系統だった理論マトリックスを構築できなかったと主張している。 1944年4月、パーソンズは精神分析を志向する精神科医と少数の社会科学者による「戦後のドイツについて」という会議に参加し、ナチズムの原因を分析 し、来るべき占領のための原則を議論していた[55]。 この会議でパーソンズは、ローレンス・S・キュービーの還元主義に見つけたものに反対した。キュービーは精神分析医で、ドイツの国民性は完全に「破壊的」 であり、国連の特別機関がドイツの教育制度を直接管理することが必要であると強く主張した。パーソンズをはじめ、この会議に出席していた多くの人々は、ク ビーの考えに強く反対していた。パーソンズは、この案は失敗すると主張し、クビーはドイツ人の方向転換の問題を「あまりにも精神医学的な観点からしか見て いない」と指摘した。パーソンズは、1944年9月に発表された極めて厳しいモーゲンソー計画にも反対していた。会議の後、パーソンズはこの計画に反対す る論文「制御された制度変更の問題」を書いている[56]。 パーソンズは1945年3月から10月にかけて対外経済行政庁の非常勤顧問として参加し、戦後賠償と脱工業化について議論している[57][58]。 パーソンズは1945年にアメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選出された[59]。 ハーバード大学で指揮をとる パーソンズのハーバード大学での状況は、1944年初めにノースウェスタン大学から良いオファーを受け、大きく変化した。ハーバード大学では、パーソンズ を学科長に任命し、正教授に昇進させ、社会関係学科の新設という組織改編のプロセスを受け入れることで、このオファーに対応した。1944年4月3日、 パーソンズが学長ポール・バックに宛てた手紙には、この時の高揚感が表れている[60] ハーバード大学での新しい展開のため、パーソンズは、ウィリアム・ランガーからの中央情報局の前身である戦略サービス局への誘いを断ることを選択する。ラ ンガーは、パーソンズにアメリカ軍のドイツ進軍に同行し、占領地行政の政治顧問として機能させることを提案した。1944年末、パーソンズはケンブリッジ 地域評議会の支援のもと、エリザベス・シュレジンジャーとともにあるプロジェクトを指揮した。1944年末、パーソンズは、エリザベス・シュレシンジャー (Elizabeth Schlesinger)と共に、ケンブリッジ地域評議会の支援のもと、ボストン周辺のラドクリフ大学、ウェルズリー大学の学生間の民族・人種間の緊張を 調査するプロジェクトを指揮した。1946年11月末、社会調査評議会(SSRC)はパーソンズに、社会科学が現代世界の理解にどのように貢献できるかと いうテーマについて包括的な報告書を書くよう要請する。背景には、社会科学を全米科学財団に編入すべきかどうかという論争があった。 パーソンズの報告は、「社会科学」という大きなメモの形をとっていた。これは1948年7月に公開され、彼が現代の社会科学の役割をどのように考えていた かを示す強力な歴史的発言として残っている[62]。 |
| Postwar Russian Research Center Parsons became a member of the Executive Committee of the new Russian Research Center at Harvard in 1948, which had Parsons' close friend and colleague, Clyde Kluckhohn, as its director. Parsons went to Allied-occupied Germany in the summer of 1948, was a contact person for the RRC, and was interested in the Russian refugees who were stranded in Germany. He happened to interview in Germany a few members of the Vlasov Army, a Russian Liberation Army that had collaborated with the Germans during the war.[63] The movement was named after Andrey Vlasov, a Soviet general captured by the Germans in June 1942. The Vlasov movement's ideology was a hybrid of elements and has been called "communism without Stalin", but in the Prague Manifesto (1944), it had moved toward the framework of a constitutional liberal state.[64] In Germany in the summer of 1948 Parsons wrote several letters to Kluckhohn to report on his investigations. Anticommunism Parsons' fight against communism was a natural extension of his fight against fascism in the 1930s and the 1940s. For Parsons, communism and fascism were two aspects of the same problem; his article "A Tentative Outline of American Values", published posthumously in 1989,[65] called both collectivistic types "empirical finalism", which he believed was a secular "mirror" of religious types of "salvationalism". In contrast, Parsons highlighted that American values generally were based on the principle of "instrumental activism", which he believed was the outcome of Puritanism as a historical process. It represented what Parsons called "worldly asceticism" and represented the absolute opposite of empirical finalism. One can thus understand Parsons' statement late in life that the greatest threat to humanity is every type of "fundamentalism".[66] By the term empirical finalism, he implied the type of claim assessed by cultural and ideological actors about the correct or "final" ends of particular patterns of value orientation in the actual historical world (such as the notion of "a truly just society"), which was absolutist and "indisputable" in its manner of declaration and in its function as a belief system. A typical example would be the Jacobins' behavior during the French Revolution. Parsons' rejection of communist and fascist totalitarianism was theoretically and intellectually an integral part of his theory of world history, and he tended to regard the European Reformation as the most crucial event in "modern" world history. Like Weber,[67] he tended to highlight the crucial impact of Calvinist religiosity in the socio-political and socio-economic processes that followed.[68] He maintained it reached its most radical form in England in the 17th century and in effect gave birth to the special cultural mode that has characterized the American value system and history ever since. The Calvinist faith system, authoritarian in the beginning, eventually released in its accidental long-term institutional effects a fundamental democratic revolution in the world.[69] Parsons maintained that the revolution was steadily unfolding, as part of an interpenetration of Puritan values in the world at large.[70] American exceptionalism Parsons defended American exceptionalism and argued that, because of a variety of historical circumstances, the impact of the Reformation had reached a certain intensity in British history. Puritan, essentially Calvinist, value patterns had become institutionalized in Britain's internal situation. The outcome was that Puritan radicalism was reflected in the religious radicalism of the Puritan sects, in the poetry of John Milton, in the English Civil War, and in the process leading to the Glorious Revolution of 1688. It was the radical fling of the Puritan Revolution that provided settlers in early 17th-century Colonial America, and the Puritans who settled in America represented radical views on individuality, egalitarianism, skepticism toward state power, and the zeal of the religious calling. The settlers established something unique in the world that was under the religious zeal of Calvinist values. Therefore, a new kind of nation was born, the character of which became clear by the time of the American Revolution and in the US constitution,[71] and its dynamics were later studied by Alexis de Tocqueville.[72] The French Revolution was a failed attempt to copy the American model. Although America has changed in its social composition since 1787, Parsons maintained that it preserves the basic revolutionary Calvinist value pattern. That has been further revealed in the pluralist and highly individualized America, with its thick, network-oriented civil society, which is of crucial importance to its success and these factors have provided it with its historical lead in the process of industrialization. Parsons maintained that this has continued to place it in the leading position in the world, but as a historical process and not in "the nature of things". Parsons viewed the "highly special feature of the modern Western social world" as "dependent on the peculiar circumstances of its history, and not the necessary universal result of social development as a whole".[73] Defender of modernity In contrast to some "radicals", Parsons was a defender of modernity.[74] He believed that modern civilization, with its technology and its constantly evolving institutions, was ultimately strong, vibrant, and essentially progressive. He acknowledged that the future had no inherent guarantees, but as sociologists Robert Holton and Bryan Turner said that Parsons was not nostalgic[75] and that he did not believe in the past as a lost "golden age" but that he maintained that modernity generally had improved conditions, admittedly often in troublesome and painful ways but usually positively. He had faith in humanity's potential but not naïvely. When asked at the Brown Seminary in 1973 if he was optimistic about the future, he answered, "Oh, I think I'm basically optimistic about the human prospects in the long run." Parsons pointed out that he had been a student at Heidelberg at the height of the vogue of Oswald Spengler, author of The Decline of the West, "and he didn't give the West more than 50 years of continuing vitality after the time he wrote.... Well, its more than 50 years later now, and I don't think the West has just simply declined. He was wrong in thinking it was the end."[76] Harvard Department of Social Relations At Harvard, Parsons was instrumental in forming the Department of Social Relations, an interdisciplinary venture among sociology, anthropology, and psychology. The new department was officially created in January 1946 with him as the chairman and with prominent figures at the faculty, such as Stouffer, Kluckhohn, Henry Murray and Gordon Allport. An appointment for Hartshorne was considered but he was killed in Germany by an unknown gunman as he was driving on the highway. His position went instead to George C. Homans. The new department was galvanized by Parsons' idea of creating a theoretical and institutional base for a unified social science. Parsons also became strongly interested in systems theory and cybernetics and began to adopt their basic ideas and concepts to the realm of social science, giving special attention to the work of Norbert Wiener (1894–1964). Some of the students who arrived at the Department of Social Relations in the years after the Second World War were David Aberle, Gardner Lindzey, Harold Garfinkel, David G. Hays, Benton Johnson, Marian Johnson, Kaspar Naegele, James Olds, Albert Cohen, Norman Birnbaum, Robin Murphy Williams, Jackson Toby, Robert N. Bellah, Joseph Kahl, Joseph Berger, Morris Zelditch, Renée Fox, Tom O'Dea, Ezra Vogel, Clifford Geertz, Joseph Elder, Theodore Mills, Mark Field, Edward Laumann, and Francis Sutton. Renée Fox, who arrived at Harvard in 1949, would become a very close friend of the Parsons family. Joseph Berger, who also arrived at Harvard in 1949 after finishing his BA from Brooklyn College, would become Parsons' research assistant from 1952 to 1953 and would get involved in his research projects with Robert F. Bales. According to Parsons' own account, it was during his conversations with Elton Mayo (1880–1949) that he realized it was necessary for him to take a serious look at the work of Freud. In the fall of 1938, Parsons began to offer a series of non-credit evening courses on Freud. As time passed, Parsons developed a strong interest in psychoanalysis. He volunteered to participate in nontherapeutic training at the Boston Psychoanalytic Institute, where he began a didactic analysis with Grete Bibring in September 1946. Insight into psychoanalysis is significantly reflected in his later work, especially reflected in The Social System and his general writing on psychological issues and on the theory of socialization. That influence was also to some extent apparent in his empirical analysis of fascism during the war. Wolfgang Köhler's study of the mentality of apes and Kurt Koffka's ideas of Gestalt psychology also received Parsons' attention. The Social System and Toward a General Theory of Action During the late 1940s and the early 1950s, he worked very hard on producing some major theoretical statements. In 1951, Parsons published two major theoretical works, The Social System[77] and Toward a General Theory of Action.[78] The latter work, which was coauthored with Edward Tolman, Edward Shils and several others, was the outcome of the so-called Carnegie Seminar at Harvard University, which had taken place in the period of September 1949 and January 1950.[79] The former work was Parsons' first major attempt to present his basic outline of a general theory of society since The Structure of Social Action (1937). He discusses the basic methodological and metatheoretical principles for such a theory. He attempts to present a general social system theory that is built systematically from most basic premises and so he featured the idea of an interaction situation based on need-dispositions and facilitated through the basic concepts of cognitive, cathectic, and evaluative orientation. The work also became known for introducing his famous pattern variables, which in reality represented choices distributed along a Gemeinschaft vs. Gesellschaft axis. The details of Parsons' thought about the outline of the social system went through a rapid series of changes in the following years, but the basics remained. During the early 1950s, the idea of the AGIL model took place in Parsons's mind gradually. According to Parsons, its key idea was sparked during his work with Bales on motivational processes in small groups.[80] Parsons carried the idea into the major work that he co-authored with a student, Neil Smelser, which was published in 1956 as Economy and Society.[81] Within this work, the first rudimentary model of the AGIL scheme was presented. It reorganized the basic concepts of the pattern variables in a new way and presented the solution within a system-theoretical approach by using the idea of a cybernetic hierarchy as an organizing principle. The real innovation in the model was the concept of the "latent function" or the pattern maintenance function, which became the crucial key to the whole cybernetic hierarchy. During its theoretical development, Parsons showed a persistent interest in symbolism. An important statement is Parsons' "The Theory of Symbolism in Relation to Action".[82] The article was stimulated by a series of informal discussion group meetings, which Parsons and several other colleagues in the spring of 1951 had conducted with philosopher and semiotician Charles W. Morris.[83] His interest in symbolism went hand in hand with his interest in Freud's theory and "The Superego and the Theory of Social Systems", written in May 1951 for a meeting of the American Psychiatric Association. The paper can be regarded as the main statement of his own interpretation of Freud,[84] but also as a statement of how Parsons tried to use Freud's pattern of symbolization to structure the theory of social system and eventually to codify the cybernetic hierarchy of the AGIL system within the parameter of a system of symbolic differentiation. His discussion of Freud also contains several layers of criticism that reveal that Parsons' use of Freud was selective rather than orthodox. In particular, he claimed that Freud had "introduced an unreal separation between the superego and the ego". Subscriber to systems theory Parsons was an early subscriber to systems theory. He had early been fascinated by the writings of Walter B. Cannon and his concept of homeostasis[85] as well as the writings of French physiologist Claude Bernard.[86] His interest in systems theory had been further stimulated by his contract with L.J. Henderson. Parsons called the concept of "system" for an indispensable master concept in the work of building theoretical paradigms for social sciences.[87] From 1952 to 1957, Parsons participated in an ongoing Conference on System Theory under the chairmanship of Roy R. Grinker, Sr., in Chicago. Parsons came into contact with several prominent intellectuals of the time and was particularly impressed by the ideas of social insect biologist Alfred Emerson. Parsons was especially compelled by Emerson's idea that, in the sociocultural world, the functional equivalent of the gene was that of the "symbol". Parsons also participated in two of the meetings of the famous Macy Conferences on systems theory and on issues that are now classified as cognitive science, which took place in New York from 1946 to 1953 and included scientists like John von Neumann. Parsons read widely on systems theory at the time, especially works of Norbert Wiener[88] and William Ross Ashby,[89] who were also among the core participants in the conferences. Around the same time, Parsons also benefited from conversations with political scientist Karl Deutsch on systems theory. In one conference, the Fourth Conference of the problems of consciousness in March 1953 at Princeton and sponsored by the Macy Foundation, Parsons would give a presentation on "Conscious and Symbolic Processes" and embark on an intensive group discussion which included exchange with child psychologist Jean Piaget.[90] Among the other participants were Mary A.B. Brazier, Frieda Fromm-Reichmann, Nathaniel Kleitman, Margaret Mead and Gregory Zilboorg. Parsons would defend the thesis that consciousness is essentially a social action phenomenon, not primarily a "biological" one. During the conference, Parsons criticized Piaget for not sufficiently separating cultural factors from a physiologistic concept of "energy". McCarthy era During the McCarthy era, on April 1, 1952, J. Edgar Hoover, the director of the Federal Bureau of Investigation, received a personal letter from an informant who reported on communist activities at Harvard. During a later interview, the informant claimed that "Parsons... was probably the leader of an inner group" of communist sympathizers at Harvard. The informant reported that the old department under Sorokin had been conservative and had "loyal Americans of good character" but that the new Department of Social Relations had turned into a decisive left-wing place as a result of "Parsons's manipulations and machinations". On October 27, 1952, Hoover authorized the Boston FBI to initiate a security-type investigation on Parsons. In February 1954, a colleague, Stouffer, wrote to Parsons in England to inform him that Stouffer had been denied access to classified documents and that part of the stated reason was that Stouffer knew communists, including Parsons, "who was a member of the Communist Party".[91] Parsons immediately wrote an affidavit in defense of Stouffer, and he also defended himself against the charges that were in the affidavit: "This allegation is so preposterous that I cannot understand how any reasonable person could come to the conclusion that I was a member of the Communist Party or ever had been."[92] In a personal letter to Stouffer, Parsons wrote, "I will fight for you against this evil with everything there is in me: I am in it with you to the death." The charges against Parsons resulted in Parsons being unable to participate in a UNESCO conference, and it was not until January 1955 that he was acquitted of the charges. Family, Socialization and Interaction Process Since the late 1930s, Parsons had continued to show great interest in psychology and in psychoanalysis. In the academic year of 1955–1956, he taught a seminar at Boston Psychoanalytic Society and Institute entitled "Sociology and Psychoanalysis". In 1956, he published a major work, Family, Socialization and Interaction Process,[93] which explored the way in which psychology and psychoanalysis bounce into the theories of motivation and socialization, as well into the question of kinship, which for Parsons established the fundamental axis for that subsystem he later would call "the social community". It contained articles written by Parsons and articles written in collaboration with Robert F. Bales, James Olds, Morris Zelditch Jr., and Philip E. Slater. The work included a theory of personality as well as studies of role differentiation. The strongest intellectual stimulus that Parsons most likely got then was from brain researcher James Olds, one of the founders of neuroscience and whose 1955 book on learning and motivation was strongly influenced from his conversations with Parsons.[94] Some of the ideas in the book had been submitted by Parsons in an intellectual brainstorm in an informal "work group" which he had organized with Joseph Berger, William Caudill, Frank E. Jones, Kaspar D. Naegele, Theodore M. Mills, Bengt G. Rundblad, and others. Albert J. Reiss from Vanderbilt University had submitted his critical commentary. In the mid-1950s, Parsons also had extensive discussions with Olds about the motivational structure of psychosomatic problems, and at this time Parsons' concept of psychosomatic problems was strongly influenced by readings and direct conversations with Franz Alexander (a psychoanalyst, originally associated with the Berlin Psychoanalytic Institute, who was a pioneer of psychosomatic medicine), Grinker and John Spiegel.[95] In 1955, François Bourricaud was preparing a reader of some of Parsons' work for a French audience, and Parsons wrote a preface for the book Au lecteur français (To the French Reader); it also went over Bourricaud's introduction very carefully. In his correspondence with Bourricaud, Parsons insisted that he did not necessarily treat values as the only, let alone "the primary empirical reference point" of the action system since so many other factors were also involved in the actual historical pattern of an action situation.[96] Center of Advanced Study in the Behavioral Sciences Parsons spent 1957 to 1958 at the Center of Advanced Study in the Behavioral Sciences in Palo Alto, California, where he met for the first time Kenneth Burke; Burke's flamboyant, explosive temperament made a great impression on Parsons, and the two men became close friends.[97] Parsons explained in a letter the impression Burke had left on him: "The big thing to me is that Burke more than anyone else has helped me to fill a major gap in my own theoretical interests, in the field of the analysis of expressive symbolism." Another scholar whom Parsons met at the Center of Advanced Studies in the Behavioral Sciences at Palo Alto was Alfred L. Kroeber, the "dean of American anthropologists". Kroeber, who had received his PhD at Columbia and who had worked with the Arapaho Indians, was about 81 when Parsons met him. Parsons had the greatest admiration for Kroeber and called him "my favorite elder statesman". In Palo Alto, Kroeber suggested to Parsons that they write a joint statement to clarify the distinction between cultural and social systems, then the subject of endless debates. In October 1958, Parsons and Kroeber published their joint statement in a short article, "The Concept of Culture and the Social System", which became highly influential.[98] Parsons and Kroeber declared that it is important both to keep a clear distinction between the two concepts and to avoid a methodology by which either would be reduced to the other. |
戦後 ロシア研究センター パーソンズは、1948年にハーバード大学に新設されたロシア研究センターの執行委員会のメンバーとなり、パーソンズの親友で同僚のクライド・クラック ホーンを所長とした。パーソンズは、1948年夏、連合国占領下のドイツに行き、RRCの窓口となり、ドイツに取り残されたロシア難民に関心を持った。彼 はドイツで、戦時中にドイツに協力したロシア解放軍であるヴラソフ軍のメンバー数人に偶然インタビューした[63]。この運動は、1942年6月にドイツ 軍に捕らえられたソ連の将軍アンドレイ・ヴラソフにちなんで名づけられた。ヴラソフ運動のイデオロギーは要素の混成であり、「スターリン抜きの共産主義」 と呼ばれていたが、プラハ宣言(1944年)において、立憲自由主義国家の枠組みに向かっていた[64]。 1948年の夏、ドイツでパーソンズは自分の調査について報告するためにクルックホーンに何通かの手紙を書いている。 反共産主義 パーソンズの共産主義に対する戦いは、1930年代から1940年代にかけてのファシズムに対する戦いの自然な延長線上にあるものであった。パーソンズに とって、共産主義とファシズムは同じ問題の二つの側面であった。1989年に死後に出版された彼の論文「A Tentative Outline of American Values」[65]は、両方の集団主義のタイプを「経験的最終主義」と呼び、それは「救済主義」の宗教的タイプの世俗的「ミラー」であると彼は信じて いた。これに対して、パーソンズはアメリカの価値観が一般的に「道具的活動主義」の原理に基づいていることを強調し、それは歴史的プロセスとしてのピュー リタニズムの結果であると信じていた。それは、パーソンズが「世俗的禁欲主義」と呼ぶものであり、経験的最終主義の絶対的な対極にあるものであった。した がって、晩年のパーソンズの人類に対する最大の脅威はあらゆるタイプの「原理主義」であるという発言を理解することができる[66] 経験的最終主義という用語によって、彼は実際の歴史的世界における特定の価値志向のパターンの正しいまたは「最終」な結末について文化的・思想的行為者に よって評価されるタイプの主張(例えば「真に公正な社会」の概念)を意味しており、その宣言方法と信念体系としての機能において絶対主義で「議論の余地も なかった」ものであった。その典型が、フランス革命時のジャコバン派の行動であろう。パーソンズの共産主義やファシストの全体主義に対する拒絶は理論的に も知性的にも彼の世界史の理論の不可欠な部分であり、ヨーロッパの宗教改革を「近代」世界史における最も決定的な出来事と見なす傾向があった。ウェーバー のように[67]、彼はその後の社会政治的・社会経済的プロセスにおけるカルヴァン派の宗教性の決定的な影響を強調する傾向があった。 68] 彼はそれが17世紀にイングランドで最もラディカルな形に達し、それ以来、アメリカの価値体系と歴史を特徴付ける特別な文化様式を事実上誕生させることに なったと主張していた。カルヴァン主義の信仰制度は当初は権威主義的であったが、最終的にはその偶然的な長期的制度的効果において世界における根本的な民 主主義革命を解放した[69]。 パーソンズはその革命が世界全体におけるピューリタンの価値の相互浸透の一部として着実に展開されていると主張していた[70]。 アメリカの例外主義 パーソンズは、アメリカの例外主義を擁護し、さまざまな歴史的経緯から、宗教改革の影響がイギリスの歴史において一定の強度を持つに至ったと主張した。 ピューリタン、つまり本質的にはカルヴァン派の価値観が、イギリスの内情に制度化されていたのである。その結果、ピューリタンの急進主義は、ピューリタン 諸派の宗教的急進主義、ジョン・ミルトンの詩、イギリス内戦、そして1688年の栄光革命に至る過程に反映されることになったのである。17世紀初頭の植 民地時代のアメリカに入植者をもたらしたのは、ピューリタン革命の過激なフライングであり、アメリカに入植したピューリタンは、個性、平等主義、国家権力 への懐疑、宗教的使命の熱意などに関する過激な意見を代表するものであった。入植者たちは、カルヴァン主義的価値観の宗教的熱意のもとに、世界で唯一無二 のものを築き上げた。 したがって、新しい種類の国家が誕生し、その性格はアメリカ革命の時代までに、そしてアメリカ憲法において明らかになり[71]、そのダイナミクスは後に アレクシス・ド・トクヴィルによって研究された[72]。 フランス革命はアメリカモデルをコピーする試みとしては失敗していた。アメリカは1787年以降その社会的構成が変化したが、パーソンズは基本的な革命的 カルヴァン主義者の価値観パターンを保持していると主張していた。それはさらに、多元的で高度に個人化されたアメリカ、その成功にとって極めて重要なネッ トワーク指向の厚い市民社会、そしてこれらの要因が産業化の過程において歴史的なリードをもたらしたということに現れている。 パーソンズは、これが世界の主導的地位を占め続けてきたが、それは歴史的なプロセスとしてであり、「物事の本質」ではないと主張している。パーソンズは 「近代西洋社会世界の極めて特殊な特徴」を「その歴史の特殊な状況に依存しており、全体として社会発展の必要な普遍的な結果ではない」と見なしていた [73]。 近代の擁護者 一部の「急進派」とは対照的に、パーソンズは近代の擁護者であった[74]。 彼はそのテクノロジーと絶えず進化する制度を持つ近代文明が究極的に強く、活気に満ちており、本質的に進歩的であると信じていた。彼は未来が固有の保証を 持たないことを認めていたが、社会学者のロバート・ホルトンとブライアン・ターナーが言っていたように、パーソンズはノスタルジックではなく[75]、失 われた「黄金時代」として過去を信じるのではなく、近代が一般的に状況を改善しており、確かにしばしば厄介で痛みを伴う方法ではあったが通常はポジティブ であったと主張していた。彼は、人類の可能性を信じていたが、決してナイーブではなかった。1973年にブラウン神学校で、将来について楽観的かどうか尋 ねられたとき、彼は「ああ、私は基本的に長い目で見れば、人間の見通しについて楽観的だと思う」と答えている。パーソンズは、『西洋の衰退』の著者である オズワルド・スペングラーの流行の絶頂期にハイデルベルクの学生だったことを指摘し、「彼は執筆後50年以上西洋の生命力が続くとは思っていなかっ た......」と述べている。その50年後の今、私は西洋が単に衰退したとは思わない。彼はそれが終わりであると考えたのは間違いであった」[76]。 ハーバード大学社会関係学部 ハーバード大学では、パーソンズは社会学、人類学、心理学の学際的なベンチャーである社会関係学部の形成に貢献した。この新しい学科は、彼を委員長とし、 ストゥファー、クラックホーン、ヘンリー・マーレイ、ゴードン・オールポートといった著名な教授陣とともに、1946年1月に正式に創設された。ハーツ ホーンの就任も検討されたが、彼はドイツで高速道路を運転中に何者かに殺害された。ハーツホーンの代わりに、ジョージ・C・ホーマンス(George C. Homans)が就任した。新しい学科は、統一された社会科学のための理論的、制度的基盤を作ろうというパーソンズの考えによって活気づいた。パーソンズ はまた、システム論やサイバネティックスに強い関心を持ち、それらの基本的な考え方や概念を社会科学の領域に取り入れるようになり、特にノーバート・ ウィーナー(1894-1964)の研究に注目した。 第二次世界大戦後の数年間に社会関係学科に着任した学生には、デビッド・アベール、ガードナー・リンゼイ、ハロルド・ガーフィンケル、デビッド・G・ヘイ ズ、ベントン ジョンソン、マリアン ジョンソン、カスパー ネゲール、ジェームズ オールズ、アルバート コーヘン、ノーマン バーンバウム、ロビン マーフィー ウィリアムズ、ジャクソン トビー、ロバート N. ベラ、ジョセフ・カール、ジョセフ・バーガー、モリス・ゼルディッチ、レネー・フォックス、トム・オディア、エズラ・ヴォーゲル、クリフォード・ギアツ、 ジョセフ・エルダー、セオドア・ミルズ、マーク・フィールド、エドワード・ラウマン、フランシス・サットンなど。 1949年にハーバード大学に着任したルネ・フォックスは、パーソンズ一家と非常に親しい友人となる。同じく1949年にブルックリン・カレッジを卒業し てハーバードに来たジョセフ・バーガーは、1952年から1953年にかけてパーソンズの研究助手となり、ロバート・F・ベールズとともに彼の研究プロ ジェクトに関わることになる。 パーソンズ自身の説明によれば、エルトン・メイヨー(1880-1949)との会話の中で、フロイトの仕事を本格的に見直す必要があることを悟ったとい う。1938年秋、パーソンズはフロイトに関する一連のノンクレジット夜間講座を開講しはじめた。時が経つにつれ、パーソンズは精神分析に強い関心を抱く ようになった。彼は、ボストン精神分析研究所での非治療的トレーニングに参加することを志願し、1946年9月からグレーテ・ビブリングのもとで教則的な 分析を始めた。精神分析への洞察は、その後の彼の作品に大きく反映されており、特に『社会システム』や心理学的問題や社会化の理論に関する一般的な著作に 反映されている。その影響は、戦時中のファシズムに関する彼の実証的な分析にもある程度現れている。また、ウォルフガング・ケーラーの類人猿のメンタリ ティに関する研究やクルト・コフカのゲシュタルト心理学の考え方もパーソンズの関心を集めた。 社会システムと行為の一般理論に向けて 1940年代後半から1950年代前半にかけて、彼はいくつかの主要な理論的記述を生み出すことに懸命に取り組んでいた。1951年にパーソンズは『社会 システム』[77]と『行為の一般理論』[78]という2つの主要な理論的著作を発表した。後者はエドワード・トルマンやエドワード・シルス、その他数人 と共著した作品で、ハーバード大学におけるいわゆるカーネギーセミナー(1949年9月から50年1月の期間に行われた)の結果だった[79] 前者はパーソンズの最初の大きな試みで、社会に関する一般理論の基本概要を『社会行為の構造』(1937)以来提示したものであった。彼はそのような理論 のための基本的な方法論的およびメタ理論的な原理を論じている。彼は、最も基本的な前提から体系的に構築された一般的な社会システム理論の提示を試みてお り、そのために、欲求-性向に基づき、認知的、緊張的、評価的志向性の基本概念によって促進される相互作用状況という考えを取り上げたのである。また、こ の作品は、現実にはゲマインシャフト対ゲゼルシャフトという軸で分布する選択肢を表す有名なパターン変数を導入したことでも知られている。 社会システムの輪郭に関するパーソンズの思想の細部は、その後、急速に変化していったが、基本的な部分は残っていた。1950年代前半には、AGILモデ ルの構想がパーソンズの頭の中で徐々に進行していった。パーソンズによれば、その重要なアイデアはベールズと一緒に小集団における動機づけのプロセスにつ いて研究していた時に閃いたものであった[80]。 パーソンズはこのアイデアを学生のニール・スメルサーと共著で1956年に『経済と社会』として出版された大著に持ち込んだ[81]。この著作の中で AGILスキームの最初の初歩的モデルが提示されている。それはパターン変数の基本的な概念を新しい方法で再編成し、組織化原理としてサイバネティックな 階層の考え方を使うことによってシステム理論的なアプローチで解決策を提示したものであった。このモデルにおける真の革新は、「潜在機能」またはパターン 維持機能の概念であり、これがサイバネティック階層全体の重要な鍵となった。 その理論的展開の中で、パーソンズは象徴主義に根強い関心を示していた。重要な記述はパーソンズの「行動と関連した象徴主義の理論」である[82]。この 論文は1951年の春にパーソンズと他の数人の同僚が哲学者であり記号学者であるチャールズ・W・モリスと行った一連の非公式なディスカッショングループ 会議によって刺激されていた[83]。象徴主義に対する彼の関心はフロイトの理論に対する関心と手を携えて、アメリカ精神医学会での会議のために1951 年5月に書かれた「スーパーエゴと社会システムの理論」にも及んでいる。この論文は彼自身のフロイトの解釈の主な記述とみなすことができるが[84]、同 時にパーソンズがフロイトの象徴化のパターンを使って社会システムの理論を構成し、最終的にAGILシステムのサイバネティックな階層を象徴分化のシステ ムのパラメータの中でコード化しようとしたことを述べているものでもある。また、彼のフロイトに関する議論には、パーソンズのフロイトの使い方が正統的と いうよりは選択的であったことを明らかにする批判が幾重にも含まれている。特に、彼はフロイトが「超自我と自我の間に非現実的な分離を導入した」と主張し ている。 システム論への加入者 パーソンズはシステム理論の初期の購読者であった。彼は早くからウォルター・B・キャノンの著作や彼のホメオスタシス[85]の概念、またフランスの生理 学者クロード・ベルナールの著作に魅了されていた[86] システム理論に対する彼の関心はL・J・ヘンダーソンとの契約によってさらに刺激されることとなった。パーソンズは社会科学の理論的パラダイムを構築する 作業において、「システム」の概念を不可欠なマスターコンセプトと呼んでいた[87]。1952年から1957年にかけて、パーソンズはシカゴでロイ・ R・グリンカー・シニアの議長の下で行われていたシステム理論に関するカンファレンスに参加している。 パーソンズは当時の著名な知識人たちと接触し、特に社会昆虫生物学者アルフレッド・エマーソンの思想に感銘を受けていた。特に、社会文化的な世界では、遺 伝子の機能的な等価物は「シンボル」であるというエマーソンの考え方に強い印象を受けた。またパーソンズは、1946年から1953年にかけてニューヨー クで開催された、システム理論や現在認知科学として分類されている問題についての有名なメイシー会議のうち2つの会議に参加し、ジョン・フォン・ノイマン のような科学者も参加している。パーソンズは当時システム理論について広く読んでおり、特に会議の中心的参加者でもあったノーバート・ウィーナー[88] やウィリアム・ロス・アシュビー[89]の著作を読んでいる。また同じ頃、パーソンズは政治学者のカール・ドイッチュとシステム理論について会話すること で利益を得ていた。1953年3月にプリンストンで開催されたメイシー財団が主催する第4回意識問題会議では、パーソンズは「意識と象徴のプロセス」につ いてプレゼンテーションを行い、児童心理学者のジャン・ピアジェとの交流を含む集中的なグループ討議に乗り出すことになる[90]。 他の参加者には、メアリー・A・B・ブラジール、フリーダ・フロム・ライヒマン、ナサニエル・クライトマン、マーガレット・ミード、グレゴリー・ジルボー グがいた。パーソンズは、意識は本質的に社会的行為現象であり、主として「生物学的」なものではないというテーゼを擁護することになる。この会議の中で パーソンズは、ピアジェが文化的要因を生理的な「エネルギー」の概念から十分に切り離していないと批判している。 マッカーシー時代 マッカーシー時代、1952年4月1日、連邦捜査局長官J・エドガー・フーバーは、ハーバード大学での共産主義者の活動について報告した情報提供者から私 信を受け取った。この情報提供者は、その後のインタビューで、「パーソンズは、おそらくハーバード大学の共産主義者の内部グループのリーダーであった」と 主張している。情報提供者は、ソローキン率いる旧学部は保守的で「性格の良い忠実なアメリカ人」がいたが、新しい社会関係学部は「パーソンズの操作と策 略」の結果、決定的な左翼の場所に変わってしまったと報告している。1952年10月27日、フーバーはボストンFBIにパーソンズに対する保安型調査を 開始することを許可した。1954年2月、同僚のストゥファーはイギリスのパーソンズに手紙を出し、ストゥファーが機密文書へのアクセスを拒否されたこ と、その理由の一部としてストゥファーはパーソンズを含む共産党員と知り合いであったことを伝えた[91]。 パーソンズは、すぐにストゥッファーを擁護する宣誓供述書を書き、宣誓供述書にあった容疑に対しても自己弁護をした。「この疑惑はあまりにもばかげたもの で、私が共産党員であった、あるいはかつてそうであったという結論に合理的な人が達することができるのか理解できない」[92] パーソンズはストウファーへの私信で、「私はこの悪に対してあなたのために私の中にあるすべてをかけて戦います。私は死ぬまであなたと共にあります "と書いている。パーソンズに対する告発によって、パーソンズはユネスコの会議に参加することができなくなり、無罪となったのは1955年1月になってか らであった。 家族、社会化、相互作用の過程 1930年代後半から、パーソンズは心理学と精神分析に大きな関心を示し続けていた。1955年から1956年にかけては、ボストン精神分析協会で「社会 学と精神分析」と題するセミナーを開催している。1956年に彼は主要な著作である『家族、社会化、相互作用過程』を出版し[93]、心理学と精神分析が 動機づけと社会化の理論に、そしてパーソンズにとって後に彼が「社会共同体」と呼ぶことになるサブシステムの基本軸を確立した親族の問題にどのように影響 を及ぼすかを探求していた。 パーソンズの論文と、ロバート・F・ベールズ、ジェームズ・オールズ、モリス・ゼルディッチ・ジュニア、フィリップ・E・スレーターとの共同執筆による論 文が収録されている。その中には、パーソナリティの理論や役割分化の研究などが含まれていた。パーソンズが当時受けた最も強い知的刺激は、神経科学の創始 者の一人である脳研究者のジェームズ・オールズからであり、彼の1955年の学習と動機づけに関する著書はパーソンズとの会話から強い影響を受けている [94]。この本のアイデアの一部は、パーソンズがジョセフ・バーガー、ウィリアム・コーディル、フランクEジョーンズ、カスパーDナゲレ、テオドアMミ ルズ、ベントGランドブラッドらと組織した非公式の「ワークグループ」で知的ブレインストームをしながら提出したものであった。ヴァンダービルト大学のア ルバート・J・ライス(Albert J. Reiss)は、批判的な解説を寄せていた。 1950年代半ばには、パーソンズもオールズと心身症の問題の動機構造について幅広く議論しており、この頃のパーソンズの心身症の概念は、フランツ・アレ クサンダー(元々はベルリン精神分析研究所に所属する精神分析医で、心身医学の先駆者)、グリンカー、ジョン・シュピーゲルを読んだり直接会話することに よって強く影響を受けていた[95]。 1955年、フランソワ・ブールリコーはフランスの読者向けにパーソンズの著作の一部の読本を準備しており、パーソンズは『Au lecteur français(フランスの読者へ)』の序文を書いており、ブールリコーの序文も非常に慎重に検討されている。パーソンズはブリコーとの書簡の中で、行 動状況の実際の歴史的パターンには他の多くの要素も関与しているため、必ずしも価値を行動システムの唯一、ましてや「主要な経験的基準点」として扱ってい るわけではないと主張している[96]。 行動科学高等研究センター パーソンズは1957年から1958年にかけてカリフォルニア州パロアルトにある行動科学高等研究センターで過ごし、そこで初めてケネス・バークと出会 う。バークの華やかで爆発的な気質はパーソンズに大きな印象を与え、二人は親しい友人となった[97]。パーソンズはバークが彼に残した印象を手紙で説明 している。「私にとって重要なことは、バークが他の誰よりも、私の理論的関心事である表現的象徴の分析という分野における大きなギャップを埋める手助けを してくれたということです」[97]。 パーソンズがパロアルトの行動科学高等研究センターで出会ったもう一人の学者は、「アメリカの人類学者の長」であるアルフレッド・L・クローバーであっ た。コロンビア大学で博士号を取得し、アラパホ・インディアンとともに研究していたクローバーは、パーソンズが会った時、81歳くらいだった。パーソンズ はクローバーに最大の敬意を払い、「私の好きな長老」と呼んでいた。 パロアルトで、クローバーはパーソンズに文化システムと社会システムの区別を明確にするための共同声明を書くことを提案したが、当時は果てしない議論の対 象になっていた。1958年10月、パーソンズとクルーバーは共同声明を「文化の概念と社会システム」という短い論文として発表し、大きな影響力を持つこ とになった[98]。パーソンズとクルーバーは、2つの概念を明確に区別しておくことと、どちらかをもう一方に還元してしまう方法論を避けることが重要で あるとしている。 |
| Later career Public conferences In 1955 to 1956, a group of faculty members at Cornell University met regularly and discussed Parsons' writings. The next academic year, a series of seven widely attended public seminars followed and culminated in a session at which he answered his critics. The discussions in the seminars were summed up in a book edited by Max Black, The Social Theories of Talcott Parsons: A Critical Examination. It included an essay by Parsons, "The Point of View of the Author".[99] The scholars included in the volume were Edward C. Devereux Jr., Robin M. Williams Jr., Chandler Morse, Alfred L. Baldwin, Urie Bronfenbrenner, Henry A. Landsberger, William Foote Whyte, Black, and Andrew Hacker. The contributions converted many angles including personality theory, organizational theory, and various methodological discussions. Parsons' essay is particularly notable because it and another essay, "Pattern Variables Revisited",[100] both represented the most full-scale accounts of the basic elements of his theoretical strategy and the general principles behind his approach to theory-building when they were published in 1960. One essay also included, in metatheoretical terms, a criticism of the theoretical foundations for so-called conflict theory. Criticism of theories From the late 1950s to the student rebellion in the 1960s and its aftermath, Parsons' theory was criticized by some scholars and intellectuals of the left, who claimed that Parsons's theory was inherently conservative, if not reactionary. Alvin Gouldner even claimed that Parsons had been an opponent of the New Deal. Parsons' theory was further regarded as unable to reflect social change, human suffering, poverty, deprivation, and conflict. Theda Skocpol thought that the apartheid system in South Africa was the ultimate proof that Parsons's theory was "wrong".[101] At the same time, Parsons' idea of the individual was seen as "oversocialized", "repressive", or subjugated in normative "conformity". In addition, Jürgen Habermas[102] and countless others were of the belief that Parsons' system theory and his action theory were inherently opposed and mutually hostile and that his system theory was especially "mechanical", "positivistic", "anti-individualistic", "anti-voluntaristic", and "de-humanizing" by the sheer nature of its intrinsic theoretical context. By the same token, his evolutionary theory was regarded as "uni-linear", "mechanical", "biologistic", an ode to world system status quo, or simply an ill-concealed instruction manual for "the capitalist nation-state". The first manifestations of that branch of criticism would be intellectuals like Lewis Coser,[103] Ralf Dahrendorf,[104] David Lockwood,[105] John Rex,[106] C. Wright Mills,[107] Tom Bottomore[108] and Gouldner.[109] Democratic Party supporter Parsons supported John F. Kennedy on November 8, 1960; from 1923, with one exception, Parsons voted for Democrats all his life.[110] He discussed the Kennedy election widely in his correspondence at the time. Parsons was especially interested in the symbolic implications involved in the fact of Kennedy's Catholic background for the implications for the United States as an integral community (it was the first time that a Catholic had become President of the United States). In a letter to Robert N. Bellah, he wrote, "I am sure you have been greatly intrigued by the involvement of the religious issue in our election."[111] Parsons, who described himself as a "Stevenson Democrat", was especially enthusiastic that his favored politician, Adlai Stevenson II, had been appointed United States Ambassador to the United Nations. Parsons had supported Stevenson in 1952 and 1956 and was greatly disappointed that Stevenson lost heavily both times. Modernization theory influence In the early 1960s, it became obvious that his ideas had a great impact on much of the theories of modernization at the time. His influence was very extensive but at the same time, the concrete adoption of his theory was often quite selective, half-hearted, superficial, and eventually confused. Many modernization theorists never used the full power of Parsons' theory but concentrated on some formalist formula, which often was taken out of the context that had the deeper meaning with which Parsons originally introduced them. In works by Gabriel A. Almond and James S. Coleman, Karl W. Deutsch, S. N. Eisenstadt, Seymour Martin Lipset, Samuel P. Huntington, David E. Apter, Lucian W. Pye, Sidney Verba, and Chalmers Johnson, and others, Parsons' influence is clear. Indeed, it was the intensive influence of Parsons' ideas in political sociology that originally got scholar William Buxton interested in his work.[112] In addition, David Easton would claim that in the history of political science, the two scholars who had made any serious attempt to construct a general theory for political science on the issue of political support were Easton and Parsons.[113] Interest in religion One of the scholars with whom he corresponded extensively with during his lifetime and whose opinion he highly valued was Robert N. Bellah. Parsons's discussion with Bellah would cover a wide range of topics, including the theology of Paul Tillich.[114] The correspondence would continue when Bellah, in the early fall of 1960, went to Japan to study Japanese religion and ideology. In August 1960, Parsons sent Bellah a draft of his paper on "The Religious Background of the American Value System" to ask for his commentary.[115] In a letter to Bellah of September 30, 1960, Parsons discussed his reading of Perry Miller's Errand into the Wilderness.[116] Parsons wrote that Miller's discussion of the role of Calvinism "in the early New England theology... is a first rate and fit beautifully with the broad position I have taken."[117] Miller was a literary Harvard historian whose books such as The New England Mind[118] established new standards for the writing of American cultural and religious history. Miller remained one of Parsons' most favoured historians throughout his life. Indeed, religion had always a special place in Parsons' heart, but his son, in an interview, maintained that he that his father was probably not really "religious." Throughout his life, Parsons interacted with a broad range of intellectuals and others who took a deep interest in religious belief systems, doctrines, and institutions. One notable person who interacted with Parsons was Marie Augusta Neal, a nun of the Sisters of Notre Dame de Namur who sent Parsons a huge number of her manuscripts and invited him to conferences and intellectual events in her Catholic Church. Neal received her PhD from Harvard under Parsons's supervision in 1963, and she would eventually become professor and then chair of sociology at Emmanuel College in Boston. She was very enthusiastic about the Second Vatican Council and became known for the National Sisters Survey, which aimed at improving women's position in the Catholic Church.[119] Criticism of Riesman Parsons and Winston White cowrote an article, "The Link Between Character and Society", which was published in 1961.[120] It was a critical discussion of David Riesman's The Lonely Crowd,[121] which had been published a decade earlier and had turned into an unexpected bestseller, reaching 1 million sold copies in 1977. Riesman was a prominent member of the American academic left, influenced by Erich Fromm and the Frankfurt School. In reality, Riesman's book was an academic attempt to give credit to the concept of "mass society" and especially to the idea of an America suffocated in social conformity. Riesman had essentially argued that at the emerging of highly advanced capitalism, the America basic value system and its socializing roles had change from an "inner-directed" toward an "other-directed" pattern of value-orientation. Parsons and White challenged Riesman's idea and argued that there had been no change away from an inner-directed personality structure. The said that Riesman's "other-directness" looked like a caricature of Charles Cooley's looking-glass self,[122] and they argued that the framework of "institutional individualism" as the basic code-structure of America's normative system had essentially not changed. What had happen, however, was that the industrialized process and its increased pattern of societal differentiation had changed the family's generalized symbolic function in society and had allowed for a greater permissiveness in the way the child related to its parents. Parsons and White argued that was not the prelude to greater "otherdirectness" but a more complicated way by which inner-directed pattern situated itself in the social environment. Political power and social influence 1963 was a notable year in Parsons's theoretical development because it was the year when he published two important articles: one on political power[123] and one on the concept of social influence.[124] The two articles represented Parsons's first published attempt to work out the idea of Generalized Symbolic Media as an integral part of the exchange processes within the AGIL system. It was a theoretical development, which Parsons had worked on ever since the publication of Economy and Society (1956). The prime model for the generalized symbolic media was money and Parsons was reflecting on the question whether the functional characteristics of money represented an exclusive uniqueness of the economic system or whether it was possible to identify other generalized symbolic media in other subsystems as well. Although each medium had unique characteristics, Parsons claimed that power (for the political system) and influence (for the societal community) had institutional functions, which essentially was structurally similar to the general systemic function of money. Using Roman Jakobson's idea of "code" and "message", Parsons divided the components of the media into a question of value-principle versus coordination standards for the "code-structure" and the question of factor versus product control within those social process which carried the "message" components. While "utility" could be regarded as the value-principle for the economy (medium: money), "effectiveness" was the value-principle for the political system (by political power) and social solidarity for the societal community (by social influence). Parsons would eventually choose the concept of value-commitment as the generalized symbolic medium for the fiduciary system with integrity as the value principle.[125] Contacts with other scholars In August 1963, Parsons got a new research assistant, Victor Lidz, who would become an important collaborator and colleague. In 1964, Parsons flew to Heidelberg to celebrate the 100th birthday of Weber and discuss Weber's work with Habermas, Herbert Marcuse, and others.[126] Parsons delivered his paper "Evaluation and Objectivity in Social Science: An Interpretation of Max Weber's Contribution".[127] The meeting became mostly a clash between pro-Weberian scholars and the Frankfurt School. Before leaving for Germany, Parsons discussed the upcoming meeting with Reinhard Bendix and commented, "I am afraid I will be something of a Daniel in the Lion's den."[128] Bendix wrote back and told Parsons that Marcuse sounded very much like Christoph Steding, a Nazi philosopher.[129] Parsons conducted a persistent correspondence with noted scholar Benjamin Nelson,[130] and they shared a common interest in the rise and the destiny of civilizations until Nelson's death in 1977. The two scholars also shared a common enthusiasm for the work of Weber and would generally agree on the main interpretative approach to the study of Weber. Nelson had participated in the Weber Centennial in Heidelberg. Parsons was opposed to the Vietnam War but was disturbed by what he considered the anti-intellectual tendency in the student rebellion: that serious debate was often substituted by handy slogans from communists Karl Marx, Mao Zedong and Fidel Castro.[citation needed] Opposition to the Frankfurt School Nelson got into a violent argument with Herbert Marcuse and accused him of tarnishing Weber.[131] In reading the written version of Nelson's contribution to the Weber Centennial, Parsons wrote, "I cannot let the occasion pass without a word of congratulations which is strong enough so that if it were concert I should shout bravo."[132] In several letters, Nelson would keep Parsons informed of the often-turbulent leftist environment of Marcuse.[133] In the letter of September 1967, Nelson would tell Parsons how much he enjoyed reading Parsons' essay on Kinship and The Associational Aspect of Social Structure.[134] Also, one of the scholars on whose work Parsons and Nelson would share internal commentaries was Habermas. Ethnicity, kinship, and diffuse solidarity Parsons had for years corresponded with his former graduate student David M. Schneider, who had taught at the University of California Berkeley until the latter, in 1960, accepted a position as professor in anthropology at the University of Chicago. Schneider had received his PhD at Harvard in social anthropology in 1949 and had become a leading expert on the American kinship system. Schneider, in 1968, published American Kinship: A Cultural Account[135] which became a classic in the field, and he had sent Parsons a copy of the copyedited manuscript before its publication. Parsons was highly appreciative of Schneider's work, which became in many ways a crucial turning point in his own attempt to understand the fundamental elements of the American kinship system, a key to understanding the factor of ethnicity and especially building the theoretical foundation of his concept of the societal community, which, by the beginning of the early 1970s, had become a strong priority in the number of theoretical projects of his own intellectual life. Parsons borrowed the term "diffuse enduring solidarity" from Schneider, as a major concept for his own considerations on the theoretical construction of the concept of the societal community. In the spring of 1968, Parsons and Schneider had discussed Clifford Geertz's article on religion as a cultural system[136] on which Parsons wrote a review.[137] Parsons, who was a close friend of Geertz, was puzzled over Geertz's article. In a letter to Schneider, Parsons spoke about "the rather sharp strictures on what he [Geertz] calls the extremely narrow intellectual tradition with special reference to Weber, but also to Durkheim. My basic point is in this respect, he greatly overstated his case seeming to argue that this intellectual tradition was by now irrelevant."[138] Schneider wrote back to Parsons, "So much, so often, as I read Cliff's stuff I cannot get a clear consistent picture of just what the religious system consist in instead only how it is said to work."[139] In a letter of July 1968 to Gene Tanke of the University of California Press, Parsons offered a critical note on the state of psychoanalytical theory and wrote: "The use of psychoanalytical theory in interpretation of social and historical subject matter is somewhat hazardous enterprise, and a good deal of nonsense has been written in the name of such attempts."[140] Around 1969, Parsons was approached by the prestigious Encyclopedia of the History of Idea about writing an entry in the encyclopedia on the topic of the "Sociology of Knowledge". Parsons accepted and wrote one of his most powerful essays, "The Sociology of Knowledge and the History of Ideas",[141] in 1969 or 1970. Parsons discussed how the sociology of knowledge, as a modern intellectual discipline, had emerged from the dynamics of European intellectual history and had reached a kind of cutting point in the philosophy of Kant and further explored by Hegel but reached its first "classical" formulation in the writing of Mannheim,[142] whose brilliance Parsons acknowledged but disagreed with his German historicism for its antipositivistic epistemology; that was largely rejected in the more positivistic world of American social science. For various reasons, the editors of the encyclopedia turned down Parsons' essay, which did not fit the general format of their volume. The essay was not published until 2006.[143] Parsons had several conversations with Daniel Bell on a "post-industrial society", some of which were conducted over lunch at William James Hall. After reading an early version of Bell's magnum opus, The Coming of the Post-Industrial Society, Parsons wrote a letter to Bell, dated November 30, 1971, to offer his criticism. Among his many critical points, Parsons stressed especially that Bell's discussion of technology tended to "separate off culture" and treat the two categories "as what I would call culture minus the cognitive component". Parsons' interest in the role of ethnicity and religion in the genesis of social solidarity within the local community heavily influenced another of his early 1960s graduate students, Edward Laumann. As a student, Laumann was interested in the role of social network structure in shaping community-level solidarity. Combining Parsons' interest in the role of ethnicity in shaping local community solidarity with W. Lloyd Warner's structural approach to social class, Laumann argued that ethnicity, religion, and perceived social class all play a large role in structuring community social networks.[144][145][146] Laumann's work found that community networks are highly partitioned along lines of ethnicity, religion, and occupational social status. It also highlighted the tension individuals experience between their preference to associate with people who are like them (homophily) and their simultaneous desire to affiliate with higher-status others. Later, at the beginning of his career at the University of Chicago, Laumann would argue that how the impulses are resolved by individuals forms the basis of corporate or competitive class consciousness within a given community.[147] In addition to demonstrating how community solidarity can be conceptualized as a social network and the role of ethnicity, religion, and class in shaping such networks, Laumann's dissertation became one of the first examples of the use of population-based surveys in the collection of social network data, and thus a precursor to decades of egocentric social network analysis.[148] Parsons thus played an important role in shaping the early interest of social network analysis in homophily and the use of egocentric network data to assess group- and community-level social network structures. Systems theory on biological and social systems In his later years, Parsons became increasingly interested in working out the higher conceptual parameters of the human condition, which was in part what led him toward rethinking questions of cultural and social evolution and the "nature" of telic systems, the latter which he especially discussed with Bellah, Lidz, Fox, Willy de Craemer, and others. Parsons became increasingly interested in clarifying the relationship between biological and social theory. Parsons was the initiator of the first Daedalus conference on "Some Relations between Biological and Social Theory", sponsored by the American Academy of Arts and Sciences. Parsons wrote a memorandum dated September 16, 1971, in which he spelled out the intellectual framework for the conference. As Parsons explained in the memo, the basic goal of the conference was to establish a conceptual fundament for a theory of living systems. The first conference was held on January 7, 1972. Among the participants beside Parsons and Lidz were Ernst Mayr, Seymour Kety, Gerald Holton, A. Hunter Dupree, and William K. Wimsatt. A second Daedalus Conference on Living Systems was held on March 1–2, 1974 and included Edward O. Wilson, who was about to publish his famous work on sociobiology. Other new participants were John T. Bonner, Karl H. Pribram, Eric Lennenberg, and Stephen J. Gould. Sociology of law Parsons began in the fall of 1972 to conduct a seminar on "Law and Sociology" with legal philosopher Lon L. Fuller, well known for his book The Morality of Law (1964). The seminar and conversations with Fuller stimulated Parsons to write one of his most influential articles, "Law as an Intellectual Stepchild".[149] Parsons discuses Roberto Mangabeira Unger's Law in Modern Society (1976). Another indication of Parsons' interest in law was reflected in his students, such as John Akula, who wrote his dissertation in sociology, Law and the Development of Citizenship (1973). In September 1972, Parsons participated in a conference in Salzburg on "The Social Consequences of Modernization in Socialist Countries". Among the other participants were Alex Inkeles, Ezra Vogel, and Ralf Dahrendorf. Criticism of Bendix In 1972, Parsons wrote two review articles to discuss the work of Bendix, which provide a clear statement on Parsons' approach to the study of Weber. Bendix had become well known for his interpretations of Weber. In the first review article, Parsons analyzed the immigrant Bendix's Embattled Reason,[150] and he praised its attempt to defend the basic values of cognitive rationality, which he unconditionally shared, and he agreed with Bendix that the question of cognitive rationality was primarily a cultural issue, not a category that could be reduced from biological, economic, and social factors. However, Parsons criticized how Bendix had proceeded, who he felt especially had misrepresented the work of Freud and Durkheim. Parsons found that the misrepresentation was how Bendix tended to conceive the question of systematic theorizing, under the concept of "reductionism".[151] Parsons further found that Bendix's approach suffered from a "conspicuous hostility" to the idea of evolution. Although Parsons assessed that Weber rejected the linear evolutionary approaches of Marx and Herbert Spencer, Weber might not have rejected the question of evolution as a generalized question. In a second article, a review of Bendix and Guenther Roth's Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber,[152] Parsons continued his line of criticism. Parsons was especially concerned with a statement by Bendix that claimed Weber believed Marx's notion that ideas were "the epiphenomena of the organization of production". Parsons strongly rejected that interpretation: "I should contend that certainly the intellectual 'mature' Weber never was an 'hypothetical' Marxist."[153] Somewhere behind the attitudes of Bendix, Parsons detected a discomfort for the former to move out of an "idiographic" mode of theorizing. Study of US university In 1973, Parsons published The American University, which he had authored with Gerald M. Platt.[154] The idea had originally emerged when Martin Meyerson and Stephen Graubard of the American Academy of the Art and Sciences, in 1969, asked Parsons to undertake a monographic study of the American university system. The work on the book went on for years until it was finished in June 1972. From a theoretical point of view, the book had several functions. It substantiated Parsons' concept of the educational revolution, a crucial component in his theory of the rise of the modern world. What was equally intellectually compelling, however, was Parsons' discussion of "the cognitive complex", aimed at explaining how cognitive rationality and learning operated as an interpenetrative zone on the level of the general action-system in society. In retrospect, the categories of the cognitive complex are a theoretical foundation to understand what has been called the modern knowledge-based society. |
その後のキャリア 公開会議 1955年から1956年にかけて、コーネル大学の教授陣のグループが定期的に会合を開き、パーソンズの著作について議論した。翌学年度には、広く一般に 公開された7回にわたるセミナーが開催され、多くの参加者を集めた。セミナーでの議論は、マックス・ブラックが編集した書籍『タルコット・パーソンズの社 会理論:批判的検証』にまとめられた。この本には、パーソンズの論文「著者の視点」も収録されている。[99] この本に寄稿した学者には、エドワード・C・デヴルー・ジュニア、ロビン・M・ウィリアムズ・ジュニア、チャンドラー・モース、アルフレッド・L・ボール ドウィン、ユリー・ブロンフェンブレンナー、ヘンリー・A・ランズバーガー、ウィリアム・フート・ホワイト、ブラック、アンドリュー・ハッカーなどがい る。寄稿論文は、性格理論、組織理論、さまざまな方法論的議論など、さまざまな角度から書かれている。パーソンズの論文は、特に注目に値する。なぜなら、 もう一つの論文「パターン・ヴァリアブル・リビジット」[100]とともに、1960年に発表された時点で、彼の理論構築へのアプローチにおける基本要素 と一般的な原則について、最も包括的な説明を提示していたからである。 また、もう一つの論文では、メタ理論的な観点から、いわゆる葛藤理論の理論的基礎に対する批判も含まれていた。 理論への批判 1950年代後半から1960年代の学生反乱とその余波まで、パーソンズの理論は一部の学者や左派の知識人から批判された。彼らは、パーソンズの理論は本 質的に保守的であり、反動的ではないとしても反動的であると主張した。アルヴィン・グールドナーは、パーソンズはニューディールの反対派であったと主張し た。パーソンズの理論は、社会の変化や人間の苦悩、貧困、剥奪、紛争などを反映できないものだとみなされた。テダ・スコットポールは、南アフリカのアパル トヘイト制度こそがパーソンズの理論が「誤り」であることの究極的な証拠であると考えた。[101] 同時に、パーソンズの個人の概念は「過剰社会化」されたもの、「抑圧的」なものであり、規範的な「順応」に服従するものだと見なされた。さらに、ユルゲ ン・ハーバーマス(Jürgen Habermas)[102]をはじめとする数多くの人々は、パーソンズのシステム理論と行動理論は本質的に相反し、相互に敵対するものであり、パーソン ズのシステム理論は特に、その本質的な理論的背景の性質によって「機械的」、「実証主義的」、「反個人主義的」、「反意志論的」、そして「人間性を奪う」 ものであると信じていた。 同様に、彼の進化論は「単線的」、「機械的」、「生物学的」、世界システムの現状維持を称賛するもの、あるいは単に「資本主義的国家」のための隠しきれな い指示書であるとみなされた。その批判の最初の兆候は、ルイス・コーザー(Lewis Coser)[103]、ラルフ・ダレニウス(Ralf Dahrendorf)[104]、デビッド・ロックウッド(David Lockwood)[105]、ジョン・レックス(John Rex)[106]、C・ライト・ミルズ(C. Wright Mills)[107]、トム・ボットモア(Tom Bottomore)[108]、そしてゴールドナー(Gouldner)[109]といった知識人たちに見られる。 民主党支持者 パーソンズは1960年11月8日、ジョン・F・ケネディを支持した。1923年から、1つの例外を除いて、パーソンズは生涯を通じて民主党員に投票し た。[110] 彼は当時の書簡の中で、ケネディの当選について広く論じている。パーソンズは、ケネディがカトリック信者であったという事実が、不可欠な共同体としてのア メリカ合衆国に与える象徴的な意味合いについて、特に興味を持っていた(カトリック信者がアメリカ合衆国大統領に選出されたのは初めてのことだった)。 ロバート・N・ベラー宛ての手紙で、パーソンズは「今回の選挙における宗教問題の関わりに、あなたは大いに興味をそそられたことでしょう」と書いている。 [111] パーソンズは自らを「スティーブンソン民主党員」と称していたが、特に、彼が支持する政治家、アドレー・スティーブンソン2世が国連大使に任命されたこと を喜んでいた。パーソンズは1952年と1956年にスティーブンソンを支援したが、両方ともスティーブンソンが大差で落選したことに大きな失望を覚え た。 近代化理論の影響 1960年代初頭、彼の考えが当時の近代化理論の多くに大きな影響を与えていたことは明らかであった。彼の影響力は非常に広範囲にわたっていたが、同時 に、彼の理論の具体的な採用は、しばしば非常に選択的で中途半端で表面的であり、最終的には混乱を招くものであった。多くの近代化理論家は、パーソンズの 理論の持つ力を十分に活用することなく、形式主義的な公式にのみ注目し、パーソンズが当初それらに付与した深い意味を持つ文脈からそれらを切り離してし まっていた。 ガブリエル・A・アルモンドとジェームズ・S・コールマン、カール・W・ドイッチュ、S・N・アイゼンスタット、シーモア・マーティン・リプセット、サ ミュエル・P・ハンティントン、デビッド・E・アプター、ルシアン・W・パイ、シドニー・バーバ、チャルマーズ・ジョンソンなどの著作には、パーソンズの 影響が明白である。実際、政治社会学におけるパーソンズの思想の影響が強かったことが、学者ウィリアム・バクストンが彼の研究に関心を持つきっかけとなっ た。[112] さらに、デビッド・イーストンは、政治学の歴史において、政治的支持の問題をめぐって政治学の一般理論の構築に真剣に取り組んだ学者は、イーストンとパー ソンズの2人だけだと主張している。[113] 宗教への関心 パーソンズが生前、頻繁に意見を交わし、その意見を非常に高く評価していた研究者の一人にロバート・N・ベラーがいた。パーソンズとベラーの議論は、パウ ル・ティリッヒの神学を含む幅広いトピックに及んだ。[114] 1960年初秋にベラーが日本の宗教とイデオロギーを研究するために日本を訪れた際にも、彼らの文通は続いた。1960年8月、パーソンズはベラに「アメ リカの価値体系の宗教的背景」に関する論文の草稿を送付し、コメントを求めた。[115] 1960年9月30日付のベラ宛ての手紙で、パーソンズはペリー・ミラー著『荒野への旅』の読後感を述べた。[116] パーソンズは、ミラーが「初期のニューイングランド神学における」カルヴァン主義の役割について論じている部分について、「 神学におけるカルヴァン主義の役割に関するミラーの議論は、一流であり、私がとってきた幅広い立場に完璧に一致する」と書いた。[117] ミラーは文学的なハーバード大学の歴史家であり、『ニューイングランドの精神』[118] などの著作は、アメリカ文化および宗教史の記述に新たな基準を打ち立てた。ミラーは生涯を通じて、パーソンズが最も好んだ歴史家の一人であった。実際、 パーソンズにとって宗教は常に特別な位置を占めていたが、彼の息子はインタビューで、父親は本当は「宗教的」ではなかっただろうと主張している。 生涯を通じて、パーソンズは宗教的信念体系、教義、制度に深い関心を持つ幅広い知識人やその他の人々と交流した。パーソンズと交流のあった著名な人物の一 人に、ノートルダム・ド・ナミュール修道会の修道女マリー・オーガスタ・ニールがいる。彼女はパーソンズに膨大な数の原稿を送付し、自身のカトリック教会 での会議や知的イベントに彼を招待した。ニールは1963年にパーソンズの指導の下でハーバード大学から博士号を取得し、後にボストンのエマニュエル・カ レッジの社会学教授および学科長となった。彼女は第2バチカン公会議に非常に熱心であり、カトリック教会における女性の地位向上を目的とした「ナショナ ル・シスターズ・サーベイ」で知られるようになった。 リースマン批判 パーソンズとウィンストン・ホワイトは「性格と社会のつながり」という論文を共同執筆し、1961年に発表した。[120] これは、10年前に発表され、予想外のベストセラーとなり、1977年には100万部が売れたデビッド・リースマンの『孤独な群衆』[121] に対する批判的な議論であった。ライズマンは、エーリッヒ・フロムやフランクフルト学派の影響を受けた、アメリカ学術左派の著名なメンバーであった。実際 には、リースマンの著書は「大衆社会」という概念、特に社会的な同調に息苦しさを感じているアメリカの考え方に正当性を与えようとする学術的な試みであっ た。 リースマンは、高度資本主義が台頭する中で、アメリカの基本的価値体系とその社会化の役割が「内面志向型」から「外面志向型」の価値志向パターンへと変化 したと本質的に論じていた。 パーソンズとホワイトはリースマンの考えに異議を唱え、内面志向的な性格構造からの変化はなかったと主張した。彼らは、リースマンの「他者志向」はチャー ルズ・コールの鏡像自己の風刺画のようだと述べ[122]、アメリカの規範システムの基本的コード構造としての「制度的個人主義」の枠組みは本質的には変 わっていないと主張した。しかし、実際には、産業化のプロセスと社会分化のパターンが増加したことにより、社会における家族の一般的な象徴的機能が変化 し、子どもが親と関わる方法に、より寛容な態度が許容されるようになった。パーソンズとホワイトは、それはより大きな「他者直接性」の前兆ではなく、内面 に向かうパターンが社会環境の中で位置づけられる、より複雑な方法であると主張した。 政治権力と社会的影響力 1963年は、パーソンズの理論的発展において特筆すべき年であった。なぜなら、この年に彼は2つの重要な論文を発表したからである。1つは政治権力に関 するもの[123]、もう1つは社会的影響力の概念に関するもの[124]である。この2つの論文は、パーソンズがAGILシステム内の交換プロセスの不 可欠な要素として一般化された象徴媒体の概念を解明しようとした最初の試みを発表したものである。これは、パーソンズが『経済と社会』(1956年)の出 版以来取り組んできた理論的発展であった。 一般化された象徴媒体の主なモデルは「貨幣」であり、パーソンズは貨幣の機能的特性が経済システムの排他的な独自性を表しているのか、あるいは他のサブシ ステムにも他の一般化された象徴媒体を特定できるのかという問題について考察していた。各メディアはそれぞれ独自の特性を持つが、パーソンズは、権力(政 治システム)と影響力(社会共同体)には制度的な機能があり、それは本質的には貨幣の一般的なシステム機能と構造的に類似していると主張した。パーソンズ は、ローマン・ヤコブソンの「コード」と「メッセージ」の考え方を用いて、メディアの構成要素を「コード構造」の価値原則対調整基準の問題と、「メッセー ジ」の構成要素を運ぶ社会過程内の要因対産物制御の問題に分けた。「効用」は経済(媒体:貨幣)の価値原則とみなすことができるが、「有効性」は政治シス テム(政治権力による)と社会共同体(社会的影響力による)の社会的連帯の価値原則であった。パーソンズは最終的に、価値原則としての誠実性を持つ受託者 システムのための一般化された象徴媒体として、価値コミットメントの概念を選択した。 他の学者との交流 1963年8月、パーソンズは新たな研究助手としてビクター・リッツを迎え入れた。リッツは後に重要な協力者となり、同僚となった。1964年、パーソン ズはハイデルベルクに飛び、ウェーバーの生誕100年を祝うとともに、ウェーバーの業績についてハーバーマス、ハーバート・マルクーゼらと議論した。 [126] パーソンズは「社会科学における評価と客観性: マックス・ウェーバーの貢献についての解釈」を発表した。[127] この会合は、ウェーバー主義の学者とフランクフルト学派の学者との間で主に衝突するものとなった。ドイツに向かう前に、パーソンズはラインハルト・ベン ディックスと会合について話し合い、「ライオンの巣窟に飛び込むダニエルのようなものになるのではないかと心配している」とコメントした。[128] ベンディックスはパーソンズに手紙を書き、マルクーゼはナチスの哲学者であるクリストフ・シュテディングに非常に似ていると伝えた。[129] パーソンズは著名な学者ベンジャミン・ネルソンと粘り強く文通を続け[130]、1977年にネルソンが亡くなるまで、文明の興亡について共通の関心を抱 いていた。2人の学者はヴェーバーの研究に対する熱意も共通しており、ヴェーバー研究の主な解釈アプローチについても概ね同意していた。ネルソンはハイデ ルベルクで開催されたヴェーバー生誕100周年記念行事に参加していた。 パーソンズはベトナム戦争に反対していたが、学生の反乱には反知性主義的な傾向があるとみていた。真剣な議論が、共産主義者のカール・マルクス、毛沢東、 フィデル・カストロの便利なスローガンに置き換えられていることが多かったからだ。 フランクフルト学派への反対 ネルソンはハーバート・マルクーゼと激しい口論となり、ウェーバーを汚したと非難した。[131] ウェーバー生誕100周年記念式典におけるネルソンの寄稿文を読んだパーソンズは、「もしコンサートであればブラボーと叫ぶほどに、お祝いの言葉を述べず にはいられない」と書いた。[132] ネルソンはいくつかの手紙で、 マルクーゼの左派の環境がしばしば混乱していることをパーソンズに知らせていた。[133] 1967年9月の手紙で、ネルソンはパーソンズの『親族』と『社会構造の連合的側面』に関するエッセイをどれほど楽しんで読んだかを伝えている。 [134] また、パーソンズとネルソンが研究上の論評を共有していた学者の一人にハーバーマスがいた。 エスニシティ、親族関係、拡散的連帯 パーソンズは、かつての大学院生であったデイヴィッド・M・シュナイ ダーと長年文通を続けていた。シュナイダーは1960年にシカゴ大学の文化人類学教授に就任するまで、カリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとってい た。シュナイダーは1949年にハーバード大学で社会人類学の博士号を取得し、アメリカの親族制度の第一人者となっていた。シュナイダーは1968年に 『アメリカ親族関係:文化論』[135]を出版し、この分野における古典となった。出版前に、シュナイダーは校正済みの原稿をパーソンズに送っていた。 パーソンズはシュナイダーの業績を高く評価していた。それは、アメリカ的な親族制度の基本要素を理解しようとするパーソンズ自身の試みにおいて、多くの点 で重要な転換点となった。それは、民族性の要因を理解し、特に社会共同体という概念の理論的基盤を構築するための鍵であり、1970年代初頭の初めには、 パーソンズ自身の知的活動における理論的プロジェクトの多くで優先事項となっていた。 パーソンズは、社会共同体という概念の理論的構築に関する自身の考察の 主要概念として、シュナイダーから「拡散持続連帯」という用語を借用した。1968年春、パーソンズとシュナイダーは、文化システムとしての宗教に関する クリフォード・ゲーツの論文について議論し[136]、パーソンズはそれについて書評を書いた[137]。ゲーツと親しい友人であったパーソンズは、ゲー ツの論文に困惑した。シュナイダー宛ての手紙の中で、パーソンズは「彼(ゲーツ)が、特にウェーバー、そしてデュルケムを引用しながら、極めて狭い知的伝 統と呼ぶものに対するかなり厳しい批判」について語っている。私の基本的な主張は、この点において、彼はこの知的伝統はもはや無関係であるかのように主張 しているように、自分の主張を大げさに言い過ぎているということだ」[138] シュナイダーはパーソンズにこう書き返した。「クリフの論文を読めば読 むほど、宗教システムがどのようなものなのか、その代わりにそれがどのように機能しているのかということだけが語られているという、明確で一貫したイメー ジが得られない」[139] 1968年7月、カリフォルニア大学出版局のジーン・タンケ宛てに、 パーソンズは精神分析理論の現状に関する批判的な意見を述べた手紙を送り、「社会や歴史を主題とする解釈に精神分析理論を用いることは、ある意味で危険な 試みであり、 そのような試みという名のもとに、多くのナンセンスが書かれてきた」と述べている。[140] 1969年頃、パーソンズは権威ある『思想の歴史百科事典』から、「知識社会学」というテーマで同百科事典に項目を執筆しないかという打診を受けた。パー ソンズはこれを受け入れ、最も力強い論文のひとつである「知識社会学と思想の歴史」を1969年か1970年に執筆した。パーソンズは、知識社会学が近代 的な知的学問分野として、ヨーロッパの知的歴史の力学からどのようにして生まれ、カントの哲学におけるある種の画期に達し、さらにヘーゲルによって掘り下 げられたが、マンハイムの著作において初めて「古典的」な定式化に達したかについて論じている。[142] パーソンズはその才気は認めるものの、反実証主義的な認識論を掲げる彼のドイツ歴史主義には反対であった。それは、より実証主義的なアメリカの社会科学の 世界では概ね否定された。さまざまな理由により、百科事典の編集者は、その論文が一般的な形式に合わないとしてパーソンの論文を却下した。その論文は 2006年まで出版されなかった。[143] パーソンズは「ポスト産業社会」についてダニエル・ベルと何度か会話を 交わし、そのうちのいくつかはウィリアム・ジェームズ・ホールでの昼食時に交わされた。ベルの代表作『脱工業化社会の到来』の初期の版を読んだ後、パーソ ンズは1971年11月30日付けでベルに手紙を書き、自身の批判を伝えた。数多くの批判的指摘の中で、パーソンズは特に、ベルのテクノロジーに関する議 論が「文化を切り離す」傾向があり、2つのカテゴリーを「私が文化から認知的要素を除いたものと呼ぶもの」として扱っていることを強調した。 パーソンズが地域社会における社会連帯の形成における民族性と宗教の役 割に関心を抱いていたことは、1960年代初頭の彼のもうひとりの大学院生、エドワード・ローマンに大きな影響を与えた。ローマンは学生時代、地域社会レ ベルの連帯を形成する上で社会ネットワーク構造が果たす役割に関心を抱いていた。パーソンズの地域社会の連帯形成における民族性の役割への関心と、W.ロ イド・ワーナーの社会階級に対する構造的アプローチとを組み合わせ、ラウマンは、民族性、宗教、そして認識される社会階級がすべて地域社会の社会的ネット ワークの形成に大きな役割を果たしていると主張した。[144][145][146] ラウマンの研究では、地域社会のネットワークは民族性、宗教、職業的地位の線に沿って高度に区分されていることが分かった。また、同様の傾向を持つ人々と 付き合いたいという希望(ホモフィリー)と、同時に、より地位の高い人々と付き合いたいという欲求との間で、個人が経験する緊張関係も浮き彫りにした。そ の後、シカゴ大学でのキャリアの初期に、ラウマンは、個人が衝動をどのように解決するかによって、特定のコミュニティにおける企業や競争的な階級意識の基 礎が形成されると主張した。[147] 地域社会の連帯が社会ネットワークとしてどのように概念化され、そのようなネットワークを形成する上で民族、宗教、階級がどのような役割を果たすかを示し たことに加え、ラウマンの博士論文は、 人口ベースの調査をソーシャルネットワークデータの収集に用いた最初の事例のひとつとなり、自己中心型ソーシャルネットワーク分析の先駆けとなった。 [148] パーソンズは、同質性(ホモフィリー)に対する初期のソーシャルネットワーク分析の関心や、自己中心型ネットワークデータの使用によるグループおよびコ ミュニティレベルのソーシャルネットワーク構造の評価を形作る上で重要な役割を果たした。 生物学的および社会的システムに関するシステム理論 晩年、パーソンズは人間の状態に関するより高度な概念的パラメータの解明にますます関心を寄せるようになった。これは、文化と社会の進化や目的論的システ ムの「本質」に関する問題を再考するきっかけとなった。パーソンズは、生物学的理論と社会的理論の関係を明確にすることにますます関心を寄せるようになっ た。パーソンズは、アメリカ芸術科学アカデミーの主催による「生物学的理論と社会的理論の関係」に関する最初のダイダロス会議の発起人となった。パーソン ズは1971年9月16日付の覚書に、会議の知的枠組みを詳細に記している。パーソンズが覚書で説明しているように、会議の基本的な目的は、生命システム の理論の概念的基礎を確立することだった。第1回目の会議は1972年1月7日に開催された。パーソンズとリッズのほか、エルンスト・マイヤー、シーモ ア・ケティ、ジェラルド・ホルトン、A.ハンター・デュプリー、ウィリアム・K・ウィムサットが参加した。第2回目の「ダイダロス会議:生命システム」は 1974年3月1日~2日に開催され、有名な社会生物学の著作を間もなく発表する予定であったエドワード・O・ウィルソンも参加した。その他の新たな参加 者には、ジョン・T・ボナー、カール・H・プリブラム、エリック・レネンバーグ、スティーブン・J・グールドなどがいた。 法社会学 パーソンズは1972年秋から、著書『法の道徳性』(1964年)で知られる法哲学者ロン・L・フラーとともに「法と社会学」に関するセミナーを開始し た。このセミナーとフラーとの会話は、パーソンズに最も影響力のある論文のひとつである「知的な私生児としての法」を執筆する刺激となった。[149] パーソンズはロベルト・マンガベイラ・ウンガーの『近代社会における法』(1976年)について論じている。パーソンズが法に関心を抱いていたことを示す もう一つの例として、彼の学生であるジョン・アクーラが社会学の論文『法と市民権の発展』(1973年)を書いたことが挙げられる。1972年9月、パー ソンズはザルツブルクで開催された「社会主義諸国における近代化の社会的帰結」に関する会議に参加した。他の参加者には、アレックス・インケレス、エズ ラ・ボーゲル、ラルフ・ダレングがいた。 ベンディックスへの批判 1972年、パーソンズはベンディックスの研究を論評する2つの論文を執筆した。この論文では、ウェーバー研究に対するパーソンズのアプローチについて明 確な見解が示されている。ベンディックスはウェーバーの解釈でよく知られていた。最初の書評論文において、パーソンズは移民ベンディックスの『苦境に立つ 理性』を分析し、[150] 彼は、認知合理性の基本的価値を守ろうとする試みを称賛し、それを無条件に共有していると述べた。また、認知合理性に関する問題は、生物学、経済、社会の 要因から還元できる範疇ではなく、主として文化的な問題であるというベンディックスの主張に同意した。しかし、パーソンズはベンディックスの研究手法を批 判し、特にフロイトとデュルケムの研究を誤って解釈していると指摘した。パーソンズは、ベンディックスが「還元主義」の概念のもとで体系的な理論化の問題 を捉えがちであることを誤解していると指摘した。[151] パーソンズはさらに、ベンディックスのアプローチは進化論に対する「顕著な敵意」に苦しんでいると指摘した。パーソンズはウェーバーがマルクスやハーバー ト・スペンサーの直線的な進化論的アプローチを否定したと評価したが、ウェーバーは進化論という問題を一般化された問題として否定したわけではないかもし れない。 2つ目の論文で、ベンディックスとギュンター・ロスの著書『学問と党派性:マックス・ウェーバーに関する論文集』[152]のレビューを掲載し、パーソン ズは批判の論調を続けた。パーソンズは特に、ベンディックスがウェーバーはマルクスの「生産の組織化の副現象」という考えを信じていたと主張したことに懸 念を抱いていた。パーソンズは、その解釈を強く否定した。「私は、確かに知的成熟を遂げたウェーバーは決して『仮説的』マルクス主義者ではなかったと主張 するべきである」[153] ベンディックスの態度の背後には、パーソンズは、前者が理論化の「個別的」な様式から抜け出せないことへの不快感があることを察知した。 米国の大学に関する研究 1973年、パーソンズはジェラルド・M・プラットとの共著『The American University』を出版した。[154] このアイデアは、1969年にマーティン・メイヤーソンとスティーブン・グラウバード(米国芸術科学アカデミー)がパーソンズに米国の大学制度に関する単 独研究を依頼したときに生まれた。この本の執筆作業は1972年6月に完成するまで何年も続いた。 理論的な観点から見ると、この本にはいくつかの機能がある。それは、近代世界の勃興に関する彼の理論の重要な要素である教育革命というパーソンズの概念を 裏付けるものであった。しかし、同様に知的にも説得力があったのは、パーソンズが「認知複合体」について論じた部分である。この部分では、認知的な合理性 と学習が、社会における一般的な行動システムのレベルで相互浸透する領域としてどのように機能するかを説明しようとしている。振り返ってみると、認知複合 体のカテゴリーは、いわゆる知識基盤社会を理解するための理論的基礎となっている。 |
| Retirement He officially retired from Harvard in 1973 but continued his writing, teaching, and other activities in the same rapid pace as before. Parsons also continued his extensive correspondence with a wide group of colleagues and intellectuals. He taught at the University of Pennsylvania, Brown University, Rutgers University, the University of Chicago, and the University of California at Berkeley. At Parsons' retirement banquet, on May 18, 1973, Robert K. Merton was asked to preside, while John Riley, Bernard Barber, Jesse Pitts, Neil J. Smelser, and John Akula were asked to share their experiences of the man with the audience. Brown seminars One scholar who became important in Parsons' later years was professor Martin U. Martel, of Brown University. They had made contact in the early 1970s at a discussion of an article that Martel had written about Parsons' work.[155] Martel arranged a series of seminars at Brown University in 1973 to 1974, and Parsons spoke about his life and work and answered questions from students and faculty.[156] Among the participants at the seminars were Martel, Robert M. Marsh, Dietrich Rueschemeyer, C. Parker Wolf, Albert F. Wessen, A. Hunter Dupree, Philip L. Quinn, Adrian Hayes and Mark A. Shields. In February to May 1974, Parsons also gave the Culver Lectures at Brown and spoke on "The Evolution of Society". The lectures and were videotaped. Refinement of AGIL model Late in life, Parsons began to work out a new level of the AGIL model, which he called "A Paradigm of the Human Condition".[157] The new level of the AGIL model crystallized in the summer of 1974. He worked out the ideas of the new paradigm with a variety of people but especially Lidz, Fox and Harold Bershady. The new metaparadigm featured the environment of the general action system, which included the physical system, the biological system, and what Parsons called the telic system. The telic system represents the sphere of ultimate values in a sheer metaphysical sense. Parsons also worked toward a more comprehensive understanding of the code-structure of social systems[158] and on the logic of the cybernetic pattern of control facilitating the AGIL model. He wrote a bulk of notes: two being "Thoughts on the Linking of Systems" and "Money and Time".[159] He had also extensive discussions with Larry Brownstein and Adrian Hayes on the possibility of a mathematical formalization of Parsons' theory.[160] Sick role theory Parsons had worked intensively with questions of medical sociology, the medical profession, psychiatry, psychosomatic problems, and the questions of health and illness. Most of all Parsons had become known for his concept of "the Sick role". The last field of social research was an issue that Parsons constantly developed through elaboration and self-criticism. Parsons participated at the World Congress of Sociology in Toronto in August 1974 at which he presented a paper, "The Sick Role Revisited: A Response to Critics and an Updating in Terms of the Theory of Action", which was published under a slightly different title, "The Sick Role and the Role of the Physician Reconsidered", in 1975.[161] In this essay, Parsons highlighted that his concept of "sick role" never was meant to be confined to "deviant behavior", but "its negative valuation should not be forgotten". It was also important to keep a certain focus on the "motivatedness" of illness, since there is always a factor of unconscious motivation in the therapeutic aspects of the sick role. Criticism of broken covenant theory In 1975, Bellah published The Broken Covenant.[162] Bellah referred to the sermon delivered by John Winthrop (1587–1649) to his flock on the ship Arbella on the evening of the landing in Massachusetts Bay in 1630. Winthrop declared that the Puritan colonists' emigration to the New World was part of a covenant, a special pact with God, to create a holy community and noted: "For we must consider that we shall be a city on the hill. The eyes of all people are upon us." Parsons disagreed strongly with Bellah's analysis and insisted that the covenant was not broken. Parsons later used much of his influential article, "Law as an Intellectual Stepchild",[163] to discuss Bellah's position. Parsons thought that Bellah trivialized the tensions of individual interests and society's interests by reducing them to "capitalism"; Bellah, in his characterization of the negative aspects of American society, was compelled by a charismatic-based optimalism moral absolutism. Symbolic interactionism In 1975, Parsons responded to an article by Jonathan H. Turner, "Parsons as a Symbolic Interactionist: A Comparison of Action and Interaction Theory".[164] Parsons acknowledged that action theory and symbolic interactionism should not be regarded as two separate, antagonistic positions but have overlapping structures of conceptualization.[165] Parsons regarded symbolic interactionism and the theory of George Herbert Mead as valuable contributions to action theory that specify certain aspects of the theory of the personality of the individual. Parsons, however, criticized the symbolic interactionism of Herbert Blumer since Blumer's theory had no end to the openness of action. Parsons regarded Blumer as the mirror image of Claude Lévi-Strauss,[166] who tended to stress the quasi-determined nature of macro-structural systems. Action theory, Parsons maintained, represented a middle ground between both extremes. Review of Piaget In 1976, Parsons was asked to contribute to a volume to celebrate the 80th birthday of Jean Piaget. Parsons contributed with an essay, "A Few Considerations on the Place of Rationality in Modern Culture and Society". Parsons characterized Piaget as the most eminent contributor to cognitive theory in the 20th century. However, he also argued that the future study of cognition had to go beyond its narrow encounter with psychology to aim at a higher understanding of how cognition as a human intellectual force was entangled in the processes of social and cultural institutionalization.[167] In 1978, when James Grier Miller published his famous work Living Systems,[168] Parsons was approached by Contemporary Sociology to write a review article on Miller's work. Parsons had already complained in a letter to A. Hunter Dupree[169] that American intellectual life suffered from a deep-seated tradition of empiricism and saw Miller's book the latest confirmation of that tradition. In his review, "Concrete Systems and "Abstracted Systems",[170] he generally praised the herculean task behind Miller's work but criticized Miller for getting caught in the effort of hierarchize concrete systems but underplay the importance of structural categories in theory building. Parsons also complained about Miller's lack of any clear distinction between cultural and non-cultural systems. Lectures in Japan Japan had long been a keen interest in Parsons' work. As early as 1958, a Japanese translation of Economy and Society appeared. Also, The Structure of Social Action was translated into Japanese.[171] The Social System was translated into Japanese by Tsutomu Sato in 1974. Indeed, Ryozo Takeda had, as early as 1952 in his Shakaigaku no Kozo ("The Framework of Sociology") introduced Japanese scholars to some of Parsons' ideas. Parsons had visited Japan for the first time in 1972 and he gave a lecture on November 25 to the Japanese Sociological Association, "Some Reflections on Post-Industrial Society" that was published in The Japanese Sociological Review.[172] At the same time, Parsons participated in an international symposium on "New Problems of Advanced Societies", held in Tokyo, and he wrote short articles written that appeared in the proceedings of the symposium.[173][174] Tominaga, born in 1931, a leading figure in Japanese sociology and a professor at the University of Tokyo, was asked by Lidz to contribute to a two-volume collection of essays to honor Parsons. Tominaga wrote an essay on the industrial growth model of Japan and used Parsons' AGIL model.[175] In 1977, Washio Kurata, the new dean of the Faculty of Sociology of Kwansei Gakuin University, wrote to Parsons and invited him to visit Japan during the 1978–1979 academic year. In early spring, Parsons accepted the invitation, and on October 20, 1978, Parsons arrived at the Osaka Airport, accompanied by his wife, and was greeted royally by a large entourage. Parsons began weekly lectures at Kwansei's sociology department from October 23 to December 15. Parsons gave his first public lecture to a huge mass of undergraduates, "The Development of Contemporary Sociology". Professor Hideichiro Nakano served as an interpreter. On November 17–18, when the Sengari Seminar House was opened, Parsons was invited as the key speaker at the event and gave two lectures, "On the Crisis of Modern Society"[176] and "Modern Society and Religion".[177] Present were Tominaga, Mutsundo Atarashi, Kazuo Muto, and Hideichiro Nakano. On November 25, lectures at Kobe University were organized by Hiroshi Mannari. Parsons lectured on organization theory to the faculty and the graduate students from the Departments of Economics, Management and Sociology. Also, faculty members from Kyoto and Osaka universities were present. A text was published the next year.[178] On November 30 to December 1, Parsons participated in a Tsukuba University Conference in Tokyo; Parsons spoke on "Enter the New Society: The Problem of the Relationship of Work and Leisure in Relation to Economic and Cultural Values".[179] On December 5, Parsons gave a lecture at Kyoto University on "A Sociologist Looks at Contemporary U.S. Society".[180] At a special lecture at Osaka on December 12, Parsons spoke, at the suggestion of Tominaga, on "Social System Theory and Organization Theory" to the Japanese Sociological Association. Earlier that day, Parsons had a discussion with Tominaga at Iwanami Shoten, which was published in a journal SHISO. On December 14, Kwansei Gakuin University granted Parsons an honorary doctor degree. Some of his lectures would be collected into a volume by Kurata and published in 1983. The Parsons flew back to the US in mid-December 1978. As a sign of friendship Hideichiro Nakano sent Parsons a Buddha mask. Parsons had especially been captivated by certain aspects of Zen Buddhism. He told his friends that after his experience in Japan, he was going to reconsider certain aspects of his interpretation of the origins of modern civilizations. Death Parsons died May 8, 1979, in Munich on a trip to Germany, where he was celebrating the 50th anniversary of his degree at Heidelberg. The day before, he had given a lecture on social class to an audience of German intellectuals, including Habermas, Niklas Luhmann and Wolfgang Schluchter. |
退職 1973年にハーバード大学を正式に退職したが、執筆や教育などの活動は以前と変わらぬペースで継続した。また、パーソンズは幅広い分野の同僚や知識人と の広範な文通も継続した。パーソンズはペンシルベニア大学、ブラウン大学、ラトガース大学、シカゴ大学、カリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとった。 1973年5月18日、パーソンズの退職祝賀会では、ロバート・K・マートンが司会を務め、ジョン・ライリー、バーナード・バーバー、ジェシー・ピッツ、 ニール・J・スメルサー、ジョン・アクーラがパーソンズとの思い出を披露した。 ブラウン大学のセミナー パーソンズの晩年において重要な存在となった学者の一人に、ブラウン大学のマーティン・U・マーテル教授がいる。 パーソンズの業績についてマーテルが執筆した論文の討論会で、1970年代初頭に二人は知り合った。[155] マーテルは1973年から1974年にかけてブラウン大学で一連のセミナーを企画し、パーソンズは自身の生涯と業績について語り 学生や教職員からの質問に答えた。[156] セミナーの参加者は、マーテル、ロバート・M・マーシュ、ディートリッヒ・ルーシェマイヤー、C・パーカー・ウルフ、アルバート・F・ウェッセン、A・ハ ンター・デュプリー、フィリップ・L・クイン、エイドリアン・ヘイズ、マーク・A・シールズなどであった。1974年2月から5月にかけて、パーソンズは ブラウン大学でカルバー・レクチャーを行い、「社会の進化」について講演した。この講演はビデオに録画された。 AGILモデルの洗練 晩年、パーソンズは「人間条件のパラダイム」と名付けたAGILモデルの新たなレベルの構築に取り組み始めた。[157] AGILモデルの新たなレベルは1974年の夏に結晶化した。彼はさまざまな人々と共に新たなパラダイムのアイデアを練り上げたが、特にリッズ、フォック ス、ハロルド・バーシャディと取り組んだ。この新しいメタパラダイムは、一般的な行動システムの環境を特徴とし、これには物理システム、生物システム、 パーソンズが目的システムと呼んだものが含まれていた。目的システムは、純粋に形而上学的意味における究極的価値の領域を表している。パーソンズはまた、 社会システムのコード構造のより包括的な理解[158]と、AGILモデルを促進するサイバネティック制御パターンの論理についても研究した。彼は膨大な 量のメモを書き残しており、そのうちの2つは「システムの結合に関する考察」と「貨幣と時間」である。[159] また、パーソンズの理論の数学的定式化の可能性について、ラリー・ブラウンスタインとエイドリアン・ヘイズと広範な議論を行っていた。[160] 病役割理論 パーソンズは医療社会学、医療専門職、精神医学、心身医学の問題、健康と病気の問題について集中的に研究していた。とりわけパーソンズは「病める役割」と いう概念で知られるようになった。社会研究の最後の分野は、パーソンズが絶えず精緻化と自己批判を通じて発展させてきた問題であった。パーソンズは 1974年8月にトロントで開催された世界社会学会議に参加し、そこで「病める役割の再考: 批判への回答と行為理論の観点からの更新」というタイトルで発表された。この論文でパーソンズは、自身の「病める役割」の概念が決して「逸脱行動」に限定 されるものではないことを強調し、「その否定的な評価は忘れてはならない」と述べた。また、病気の「動機づけ」に一定の焦点を当てることも重要であった。 なぜなら、病気の治療の側面には常に無意識の動機づけの要因が存在するからである。 契約破棄理論への批判 1975年、ベラーは『破られた聖約』を出版した。[162] ベラーは、1630年にマサチューセッツ湾に上陸した夜、ジョン・ウィンズロップ(1587年-1649年)がアルベルタ号の船上で信者たちに語った説教 について言及している。ウィンズロップは、清教徒入植者たちの新世界への移住は、神との特別な契約である聖約の一部であり、神聖な共同体を築くためのもの だと宣言し、次のように述べた。「我々は丘の上の町となることを考えなければならない。すべての人の目が我々を見つめている」と述べた。パーソンズはベ ラーの分析に強く反対し、契約は破られていないと主張した。パーソンズは後に、影響力のある論文「法という知的な連れ子」[163]の多くをベラーの立場 を論じるために用いた。 パーソンズは、ベラーが「資本主義」に還元することで、個人の利益と社会の利益の間の緊張関係を矮小化していると考えた。ベラーは、アメリカ社会の負の側 面を特徴づけるにあたり、カリスマに基づくオプティミズムの道徳的絶対主義に駆られていた。 象徴的相互作用主義 1975年、パーソンズはジョナサン・H・ターナーの論文「パーソンズを象徴的相互作用主義者として: 行動理論と象徴的相互作用論は、2つの別個の対立する立場ではなく、概念化の構造が重複しているとパーソンズは認めた。[165]パーソンズは、象徴的相 互作用論とジョージ・ハーバート・ミードの理論を、個人の人格理論の特定の側面を明確にする行動理論への貴重な貢献とみなした。しかし、パーソンズはブ ルーマーの理論には行動のオープンエンド性がないとして、ブルーマーの記号相互作用論を批判した。パーソンズはブルーマーを、マクロ構造システムの準決定 された性質を強調する傾向のあったクロード・レヴィ=ストロースの鏡像であるとみなした。パーソンズは、行動理論は両極端の中間を代表するものであると主 張した。 ピアジェのレビュー 1976年、パーソンズはジャン・ピアジェの80歳の誕生日を祝う本の執筆を依頼された。パーソンズは「現代文化と社会における合理性の位置に関するいく つかの考察」という論文を寄稿した。パーソンズはピアジェを20世紀における認知理論への最も著名な貢献者と評した。しかし、彼はまた、認知に関する今後 の研究は心理学との狭い関わりを越え、人間の知的力としての認知が社会や文化の制度化の過程にどのように絡み合っているかについて、より深い理解を目指さ なければならないと主張した。[167] 1978年、ジェームズ・グリア・ミラーが有名な著書『リビング・システムズ』を出版すると、パーソンズは『現代社会学』誌からミラーの著作についての書 評を依頼された。パーソンズはすでにA・ハンター・デュプリー宛ての手紙で、アメリカの知的活動は経験主義の根深い伝統に苦しめられていると訴えており、 ミラーの著作をその伝統の最新の裏付けと見ていた。「具体的なシステムと抽象化されたシステム」[170]という書評で、彼はミラーの仕事の背後にある困 難な作業を概ね称賛したが、ミラーが具体的なシステムを階層化する努力に捕らわれて、理論構築における構造的カテゴリーの重要性を軽視していると批判し た。また、ミラーが文化システムと非文化システムを明確に区別していない点についても、パーソンズは不満を述べている。 日本での講演 日本では、パーソンズの研究に以前から強い関心が寄せられていた。早くも1958年には『経済と社会』の日本語訳が出版されている。また、『社会行動の構 造』も日本語に翻訳された。[171] 『社会システム』は1974年に佐藤勉によって日本語に翻訳された。実際、武田良造は1952年の『社会学の構造』で、パーソンの考えの一部を日本の学者 たちに紹介していた。パーソンズは1972年に初めて来日し、11月25日には日本社会学会で「ポスト産業社会についての若干の考察」と題する講演を行 い、その講演は『日本社会学会誌』に掲載された。[172] 同時期にパーソンズは東京で開催された「先進社会の新しい問題」に関する国際シンポジウムに参加し、 東京で開催された「先進社会の新しい問題」に関する国際シンポジウムに参加し、シンポジウムの議事録に掲載された短い論文を執筆した。[173] [174] 1931年生まれの富永は、日本の社会学の第一人者であり、東京大学教授であった。リッズは、パーソンズを称える2巻構成の論文集への寄稿を富永に依頼し た。富永は、日本の産業成長モデルに関する論文を執筆し、パーソンズのAGILモデルを使用した。[175] 1977年、関西学院大学社会学部新学部長の倉田總一郎は、パーソンズに手紙を書き、1978年から1979年の学年度中に日本を訪問するよう招待した。 早春にパーソンズは招待を受け入れ、1978年10月20日、パーソンズは妻と共に大阪空港に到着し、大勢の随行員から盛大な歓迎を受けた。 パーソンズは10月23日から12月15日まで、関西学院大学社会学部で毎週講義を行った。パーソンズは、膨大な数の学部生を前にして、最初の公開講義 「現代社会学の発展」を行った。中野秀一郎教授が通訳を務めた。 11月17日~18日、仙刈セミナーハウス開館記念行事の基調講演者として招かれたパーソンズは、「現代社会の危機について」[176]、「現代社会と宗 教」[177]の2つの講演を行った。出席者は富永、新雅俊、武藤一雄、中野秀一郎であった。 11月25日、萬成博が神戸大学で講演会を主催した。パーソンズは、経済学部、経営学部、社会学部の教員と大学院生を対象に組織論について講義した。ま た、京都大学と大阪大学の教員も出席した。翌年にはテキストが出版された。[178] 11月30日から12月1日にかけて、パーソンズは東京で開催された筑波大学会議に参加し、「新しい社会への参入:経済的・文化的価値との関連における労 働と余暇の関係の問題」について講演した。[179] 12月5日には、パーソンズは京都大学で「現代米国社会を社会学的に見る」というテーマで講演を行った。[180] 12月12日、大阪での特別講演で、富永の提案により、パーソンズは「社会システム論と組織論」について日本社会学会で講演した。その日の朝、パーソンズ は岩波書店で富永と会談し、その内容は雑誌『思想』に掲載された。 12月14日、関西学院大学はパーソンズに名誉博士号を授与した。 パーソンズの講義の一部は、倉田によって1冊にまとめられ、1983年に出版された。 パーソンズ夫妻は1978年12月中旬にアメリカへ帰国した。 中野秀一郎は友情の印としてパーソンズに仏教の仮面を送った。パーソンズは特に禅仏教のいくつかの側面に魅了されていた。彼は友人たちに、日本での経験の 後、近代文明の起源に関する自身の解釈のいくつかの側面を再考するつもりだと語った。 死 パーソンズは1979年5月8日、ドイツ旅行中のミュンヘンで死去した。ハイデルベルク大学卒業50周年を祝うためであった。前日にパーソンズは、ハー バーマス、ニクラス・ルーマン、ヴォルフガング・シュルヒターを含むドイツの知識人たちを前に、社会階級に関する講演を行っていた。 |
| Work Parsons produced a general theoretical system for the analysis of society, which he called "theory of action", based on the methodological and epistemological principle of "analytical realism" and on the ontological assumption of "voluntaristic action".[181] Parsons' concept of analytical realism can be regarded as a kind of compromise between nominalist and realist views on the nature of reality and human knowledge.[182] Parsons believed that objective reality can be related to only by a particular encounter of such reality and that general intellectual understanding is feasible through conceptual schemes and theories. Interaction with objective reality on an intellectual level should always be understood as an approach. Parsons often explained the meaning of analytical realism by quoting a statement by Henderson: "A fact is a statement about experience in terms of a conceptual scheme."[183] Generally, Parsons maintained that his inspiration regarding analytical realism had been Lawrence Joseph Henderson and Alfred North Whitehead[184] although he might have gotten the idea much earlier. It is important for Parsons' "analytical realism" to insist on the reference to an objective reality since he repeatedly highlighted that his concept of "analytical realism" was very different from the "fictionalism" of Hans Vaihiger (Hans Vaihinger):[185] We must start with the assertion that all knowledge which purports to be valid in anything like the scientific sense presumes both the reality of object known and of a knower. I think we can go beyond that and say that there must be a community of knowers who are able to communicate with each other. Without such a presupposition it would seem difficult to avoid the pitfall of solipsism. The so-called natural sciences do not, however, impute the "status of knowing subjects" to the objects with which they deal.[186] The Structure of Social Action The Structure of Social Action (SSA), Parsons' most famous work, took form piece by piece. Its central figure was Weber, and the other key figures in the discussion were added, little by little, as the central idea took form. One important work that helped Parsons' central argument in was, in 1932, unexpectedly found: Élie Halévy's La formation du radicalisme philosophique (1901–1904); he read the three-volume work in French. Parsons explained, "Well, Halévy was just a different world ... and helped me to really get in to many clarifications of the assumptions distinctive to the main line of British utilitarian thought; assumptions about the 'natural identity of interest', and so on. I still think it is one of the true masterpieces in intellectual history."[37] Parsons first achieved significant recognition with the publication of The Structure of Social Action (1937), his first grand synthesis, combining the ideas of Durkheim, Weber, Pareto, and others. In 1998, the International Sociology Association listed it as the third most important sociological book of the 20th Century Action theory Parsons' action theory can be characterized as an attempt to maintain the scientific rigour of positivism while acknowledging the necessity of the "subjective dimension" of human action incorporated in hermeneutic types of sociological theories. It is cardinal in Parsons' general theoretical and methodological view that human action must be understood in conjunction with the motivational component of the human act. Social science must consider the question of ends, purpose, and ideals in its analysis of human action. Parsons' strong reaction to behavioristic theory as well as to sheer materialistic approaches derives from the attempt of the theoretical positions to eliminate ends, purpose, and ideals as factors of analysis. Parsons, in his term papers at Amherst, was already criticizing attempts to reduce human life to psychological, biological, or materialist forces. What was essential in human life, Parsons maintained, was how the factor of culture was codified. Culture, however, was to Parsons an independent variable in that it could not be "deducted" from any other factor of the social system. That methodological intention is given the most elaborate presentation in The Structure of Social Action, which was Parsons' first basic discussion of the methodological foundation of the social sciences. Some of the themes in The Structure of Social Action had been presented in a compelling essay two years earlier in "The Place of Ultimate Values in Sociological Theory".[187] An intense correspondence and dialogue between Talcott Parsons and Alfred Schutz serves to highlight the meaning of central concepts in The Structure of Social Action. Relations to cybernetics and system theory Parsons developed his ideas during a period when systems theory and cybernetics were very much on the front burner of social and behavioral science. In using systems thinking, he postulated that the relevant systems treated in social and behavioral science were "open:" they were embedded in an environment with other systems. For social and behavioral science, the largest system is "the action system," the interrelated behaviors of human beings, embedded in a physical-organic environment.[188] As Parsons developed his theory, it became increasingly bound to the fields of cybernetics and system theory but also to Emerson's concept of homeostasis[189] and Ernst Mayr's concept of "teleonomic processes".[190] On the metatheoretical level, Parson attempted to balance psychologist phenomenology and idealism on the one hand and pure types of what Parsons called the utilitarian-positivistic complex, on the other hand. The theory includes a general theory of social evolution and a concrete interpretation of the major drives of world history. In Parsons' theory of history and evolution, the constitutive-cognitive symbolization of the cybernetic hierarchy of action-systemic levels has, in principle, the same function as genetic information in DNA's control of biological evolution, but that factor of metasystemic control does not "determine" any outcome but defines the orientational boundaries of the real pathfinder, which is action itself. Parsons compares the constitutive level of society with Noam Chomsky's concept of "deep structure". As Parsons wrote, "The deep structures do not as such articulate any sentences which could convey coherent meaning. The surface structures constitute the level at which this occurs. The connecting link between them is a set of rules of transformation, to use Chomsky's own phrase."[191] The transformative processes and entities are generally, at least on one level of empirical analysis, performed or actualized by myths and religions,[192] but philosophies, art systems, or even semiotic consumer behavior can, in principle, perform that function.[193] Unified concept of social science Parsons' theory reflects a vision of a unified concept of social science and indeed of living systems[194] in general. His approach differs in essence from Niklas Luhmann's theory of social systems because Parsons rejects the idea that systems can be autopoietic, short of the actual action system of individual actors. Systems have immanent capacities but only as an outcome of the institutionalized processes of action-systems, which, in the final analysis, is the historical effort of individual actors. While Luhmann focused on the systemic immanence, Parsons insisted that the question of autocatalytic and homeostatic processes and the question about the actor as the ultimate "first mover" on the other hand was not mutually exclusive. Homeostatic processes might be necessary if and when they occur but action is necessitating. It is only that perspective of the ultimate reference in action that Parsons' dictum (that higher-order cybernetic systems in history will tend to control social forms that are organized on the lower levels of the cybernetic hierarchy) should be understood. For Parsons, the highest levels of the cybernetic hierarchy as far as the general action level is concerned is what Parsons calls the constitutive part of the cultural system (the L of the L). However, within the interactional processes of the system, attention should be paid especially to the cultural-expressivistic axis (the L-G line in the AGIL). By the term constitutive, Parsons generally referred to very highly codified cultural values especially religious elements (but other interpretation of the term "constitutive" is possible).[195] Cultural systems have an independent status from that of the normative and orientational pattern of the social system; neither system can be reduced to the other. For example, the question of the "cultural capital" of a social system as a sheer historical entity (in its function as a "fiduciary system"), is not identical to the higher cultural values of that system; that is, the cultural system is embodied with a metastructural logic that cannot be reduced to any given social system or cannot be viewed as a materialist (or behavioralist) deduction from the "necessities" of the social system (or from the "necessities" of its economy).[196] Within that context, culture would have an independent power of transition, not only as factors of actual sociocultural units (like Western civilization) but also how original cultural bases would tend to "universalize" through interpenetration and spread over large numbers of social systems as with Classical Greece and Ancient Israel, where the original social bases had died but the cultural system survived as an independently "working" cultural pattern, as in the case of Greek philosophy or in the case of Christianity, as a modified derivation from its origins in Israel.[197] Parsons and Habermas The difference between Parsons and Jürgen Habermas lies essentially in how Habermas uses Parsons' theory to establish the basic propositions of his own.[198] Habermas takes the division between Parsons' separation between the "outer" and the "inner" dimensions of the social system and labels them "system" (outer dimension (A-G)) and "lifeworld" (inner dimension (I-L)). The problem with this model from Parsons' point of view is a) that conflict within the social system can in reality emerge from any relational point and not simply from the system-lifeworld dichotomy, and b) by relating the system-lifeworld model to some kind of "liberation"-ethos, Habermas produces the Utopian notion that the potential for conflict within the social system has some kind of "final solution," which produces a misleading concept of the nature of systemic conflict. General theory It is important to highlight that Parsons distinguished two "meanings" or modes of the term general theory. He sometimes wrote about general theory as aspects of theoretical concerns of social sciences whose focus is on the most "constitutive" elements of cognitive concern for the basic theoretical systematization of a given field. Parsons would include the basic conceptual scheme for the given field, including its highest order of theoretical relations and naturally also the necessary specification of this system's axiomatic, epistemological, and methodological foundations from the point of view of logical implications.[199][200] All the elements would signify the quest for a general theory on the highest level of theoretical concern. However, general theory could also refer to a more fully/operational system whose implications of the conceptual scheme were "spelled out" on lower levels of cognitive structuralization, levels standing closer to a perceived "empirical object". In his speech to the American Sociological Society in 1947, he spoke of five levels:[201] The General Theory level, which took form primarily as a theory of social systems. The theory of motivation of social behavior, which especially addressed questions of the dynamics of the social system and naturally presupposed theories of motivation, personality and socialization. The theoretical bases of systematic comparative analysis of social structure, which would involve a study of concrete cultures in concrete systems on various levels of generalization. Special theories around particular empirical problem areas. The "fitting" of the theories to specific empirical research techniques, such as statistics, and survey techniques. During his life, he would work on developing all five fields of theoretical concerns but pay special attention to the development on the highest "constitutive" level, as the rest of the building would stand or fall on the solidity of the highest level.[202] Despite myths, Parsons never thought that modern societies exist in some kind of perfect harmony with their norms or that most modern societies were necessarily characterized by some high level of consensus or a "happy" institutional integration. Parsons highlighted that is almost logically impossible that there can be any "perfect fit" or perfect consensus in the basic normative structure of complex modern societies because the basic value pattern of modern societies is generally differentiated in such a way that some of the basic normative categories exist in inherent or at least potential conflict with each other. For example, freedom and equality are generally viewed as fundamental and non-negotiable values of modern societies. Each represents a kind of ultimate imperative about what the higher values of humanity. However, as Parsons emphasizes, no simple answer on the priority of freedom or equality or any simple solution on how they possibly can be mediated, if at all. Therefore, all modern societies are faced with the inherent conflict prevailing between the two values, and there is no "eternal solution" as such. There cannot be any perfect match between motivational pattern, normative solutions, and the prevailing value pattern in any modern society. Parsons also maintained that the "dispute" between "left" and "right" has something to do with the fact that they both defend ultimately "justified" human values (or ideals), which alone is indispensable as values but are always in an endless conflictual position to each other. Parsons always maintained that the integration of the normative pattern in society is generally problematic and that the level of integration that is reached in principle is always far from harmonious and perfect. If some "harmonious pattern" emerges, it is related to specific historical circumstances but is not a general law of the social systems. AGIL paradigm The heuristic scheme that Parsons used to analyze systems and subsystems is called the AGIL paradigm or the AGIL scheme.[203] To survive or maintain equilibrium with respect to its environment, any system must to some degree adapt to that environment (adaptation), attain its goals (goal attainment), integrate its components (integration), and maintain its latent pattern (latency pattern Maintenance), a sort of cultural template. The concepts can be abbreviated as AGIL and are called the system's functional imperatives. It is important to understand that Parsons AGIL model is an analytical scheme for the sake of theoretical "production", but it is not any simple "copy" or any direct historical "summary" of empirical reality. Also, the scheme itself does not explain "anything", just as the periodic table explains nothing by itself in the natural sciences. The AGIL scheme is a tool for explanations and is no better than the quality of the theories and explanation by which it is processed. In the case of the analysis of a social action system, the AGIL paradigm, according to Parsons, yields four interrelated and interpenetrating subsystems: the behavioral systems of its members (A), the personality systems of those members (G), the social system (as such) (I), and the cultural system of that society (L). To analyze a society as a social system (the I subsystem of action), people are posited to enact roles associated with positions. The positions and roles become differentiated to some extent and, in a modern society, are associated with things such as occupational, political, judicial, and educational roles. Considering the interrelation of these specialized roles as well as functionally differentiated collectivities (like firms and political parties), a society can be analyzed as a complex system of interrelated functional subsystems: The pure AGIL model for all living systems: (A) Adaptation. (G) Goal attainment. (I) Integration. (L) Latency (pattern maintenance). The Social System Level: The economy — social adaptation to its action and non-action environmental systems The polity — collective goal attainment The societal community — the integration of its diverse social components The fiduciary system — processes that function to reproduce historical culture in its "direct" social embeddedness. The General Action Level: The behavioral organism (or system), in later versions, the foci for generalized "intelligence". The personality system. The social system. The cultural system. (See cultural level.) The cultural level: Cognitive symbolization. Expressive symbolization. Evaluative symbolization. (Sometimes called: moral-evaluative symbolization.) Constitutive symbolization. The Generalized Symbolic media: Social System level: (A) Economic system: Money. (G) Political system: Political power. (I) The Societal Community: Influence. (L) The Fiduciary system (cultural tradition): Value-commitment. Parsons elaborated upon the idea that each of these systems also developed some specialized symbolic mechanisms of interaction analogous to money in the economy, like influence in the social community. Various processes of "interchange" among the subsystems of the social system were postulated. Parsons' use of social systems analysis based on the AGIL scheme was established in his work Economy and Society (with N. Smelser, 1956) and has prevailed in all his work ever since. However, the AGIL system existed only in a "rudimentary" form in the beginning and was gradually elaborated and expanded in the decades which followed. A brief introduction to Parsons' AGIL scheme can be found in Chapter 2 of The American University (with G. Platt, 1973). There is, however, no single place in his writing in which the total AGIL system is visually displayed or explained: the complete system have to be reconstructed from multiple places in his writing. The system displayed in "The American University" has only the most basic elements and should not be mistaken for the whole system. Social evolutionism Parsons contributed to social evolutionism and neoevolutionism. He divided evolution into four sub-processes: differentiation, which creates functional subsystems of the main system, as discussed above; adaptation, in which those systems evolve into more efficient versions; inclusion of elements previously excluded from the given systems; generalization of values, increasing the legitimization of the increasingly-complex system. Furthermore, Parsons explored the sub-processes within three stages of evolution: primitive archaic modern Parsons viewed Western civilization as the pinnacle of modern societies and the United States as the one that is most dynamically developed. Parsons' late work focused on a new theoretical synthesis around four functions that he claimed are common to all systems of action, from the behavioral to the cultural, and a set of symbolic media that enables communication across them. His attempt to structure the world of action according to a scheme that focused on order was unacceptable for American sociologists, who were retreating from the grand pretensions of the 1960s to a more empirical, grounded approach. Pattern variables Parsons asserted that there are not two dimensions to societies (instrumental and expressive) but that there are qualitative differences between kinds of social interaction. He observed that people can have personalized and formally detached relationships, based on the roles that they play. The pattern variables are what he called the characteristics that are associated with each kind of interaction. An interaction can be characterized by one of the identifiers of each contrastive pair: affectivity – affective neutrality self-orientation – collectivity-orientation universalism – particularism ascription – achievement specificity – diffusity Legacy From the 1940s to the 1970s, Parsons was one of the most famous and most influential but also most controversial sociologists in the world, particularly in the US.[18] His later works were met with criticism and were generally dismissed in the 1970s by the view that his theories were too abstract, inaccessible, and socially conservative.[18][204] Recently, interest has increased in Parsons' ideas and especially often-overlooked later works.[17] Attempts to revive his thinking have been made by Parsonsian sociologists and social scientists like Jeffrey Alexander, Bryan Turner, Richard Münch, and Roland Robertson, and Uta Gerhardt has written about Parsons from a biographical and historical perspective. In addition to the United States, the key centers of interest in Parsons today are Germany, Japan, Italy, and the United Kingdom.[citation needed] Parsons had a seminal influence and early mentorship of many American and international scholars, such as Ralf Dahrendorf, Alain Touraine, Niklas Luhmann, and Habermas.[citation needed] His best-known pupil was Merton.[18] Parsons was a member of the American Philosophical Society.[205] |
仕事 パーソンズは、方法論的・認識論的原則である「分析的実在論」と存在論的前提である「意志的行為」に基づき、社会分析のための一般的な理論体系を構築し、 それを「行為の理論」と呼んだ。[181] パーソンズの分析的実在論の概念は 現実の本質と人間の知識に関するノミナリストとリアリストの考え方の妥協案の一種とみなすことができる。[182] パーソンズは、客観的な現実とは、その現実が特定の状況と遭遇したときにのみ関連付けられるものであり、一般的な知的理解は概念スキームや理論を通じて可 能であると信じていた。知的レベルにおける客観的な現実との相互作用は、常にアプローチとして理解されるべきである。パーソンズは、ヘンダーソンの次の言 葉を引用して分析的実在論の意味を説明するのを常としていた。「事実とは、概念スキームの観点から見た経験についてのステートメントである」[183] 一般的に、パーソンズは分析的実在論に関する自身の着想はローレンス・ジョセフ・ヘンダーソンとアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドによるものだと主張 していたが[184]、実際にはもっと以前から着想を得ていた可能性もある。パーソンズの「分析的実在論」にとって、客観的な現実への言及を主張すること は重要である。なぜなら、パーソンズは自身の「分析的実在論」の概念がハンス・ヴァイヒンガー(Hans Vaihinger)の「虚構説」とは全く異なるものであることを繰り返し強調していたからである[185] 我々は、科学的な意味で妥当であると主張されるあらゆる知識は、知られている対象の現実性と、それを知る者の現実性の両方を前提としているという主張から 始めなければならない。私は、さらに一歩進んで、互いにコミュニケーションを取ることのできる知識者の共同体が存在しなければならないと言うことができる と思う。そうした前提なしには、自己同一論の落とし穴を避けるのは難しいと思われる。しかし、いわゆる自然科学は、扱う対象に「知る主体としての地位」を 帰属させてはいない。[186] 社会行動の構造 パーソンズの最も有名な著作『社会行動の構造(SSA)』は、少しずつ形作られていった。中心的な人物はウェーバーであり、中心的な考えが形作られるにつ れ、議論における他の主要人物が少しずつ加えられていった。パーソンズの中心的な議論を助けることになった重要な著作が、1932年に思いがけず発見され た。エリー・ハレヴィ著『哲学上のラジカリズムの形成』(1901年~1904年)であった。彼はフランス語で書かれた3巻からなるこの著作を読んだ。 パーソンズは次のように説明している。「ハレヴィはまったく異なる世界の人だったが... ...私を英国の功利主義思想の主流に特有な仮定の数々を明確に理解する手助けをしてくれた。『自然な利害の同一性』に関する仮定などだ。今でも、これは 知的歴史における真の傑作のひとつであると私は考えている」[37] パーソンズは、デュルケーム、ウェーバー、パレートなどの思想を統合した最初の壮大な総合である『社会行動の構造』(1937年)の出版により、初めて広 く知られるようになった。1998年には、国際社会学協会が20世紀の社会学の書籍のなかで3番目に重要な書籍としてこれを挙げている アクション理論 パーソンズのアクション理論は、解釈学的な社会学理論に組み込まれた人間の行動の「主観的側面」の必要性を認めながらも、実証主義の科学的厳密性を維持し ようとする試みとして特徴づけることができる。人間の行動は、その動機的要素と併せて理解されなければならないという考え方は、パーソンズの一般的な理論 的・方法論的見解の根幹をなすものである。社会科学は、人間の行動の分析において、目的、目的、理想の問題を考慮しなければならない。パーソンズが行動主 義理論や唯物論的アプローチに強く反発した理由は、分析の要素として目的、目的、理想を排除しようとする理論的立場に由来する。パーソンズは、アマースト 大学での論文で、すでに人間の生活を心理学的、生物学的、あるいは唯物論的な力に還元しようとする試みを批判していた。パーソンズは、人間の生活において 本質的なのは、文化という要素がどのように体系化されるかであると主張した。しかし、パーソンズにとって文化とは、社会システムの他の要素から「演繹」で きない独立変数であった。その方法論的意図は、パーソンズが社会科学の方法論的基礎について初めて基本的な議論を行った『社会行動の構造』の中で最も精巧 に示されている。 社会行動の構造』のテーマのいくつかは、2年前に発表された「社会学理論における究極的価値の位置」という説得力のある論文で提示されていた。[187] タルコット・パースンズとアルフレッド・シュッツの間の熱心な書簡のやりとりや対話は、『社会行動の構造』における中心概念の意味を浮き彫りにしている。 サイバネティクスとシステム理論との関係 パーソンズは、システム理論とサイバネティクスが社会・行動科学の分野で非常に注目されていた時期に、自身の理論を発展させた。システム思考を用いるにあ たり、パーソンズは、社会・行動科学で扱われる関連システムは「開放系」であると仮定した。すなわち、それらは他のシステムとともに環境に組み込まれてい るという考え方である。社会・行動科学にとって最大のシステムは「行動システム」であり、それは物理的・有機的な環境に組み込まれた、相互に関連する人間 の行動である。 パーソンズが自身の理論を発展させていくにつれ、それはサイバネティクスやシステム理論の分野と、エマーソンのホメオスタシスの概念[189]、エルンス ト・マイヤーの「テレオノミックプロセス」の概念[190]とますます結びつきを強めていった。メタ理論的なレベルでは、パーソンズは、心理学者の現象学 と観念論と、パーソンズが功利主義的実証主義複合体と呼んだ純粋型とのバランスを取ろうとした。 この理論には、社会進化の一般理論と世界史の主要な原動力の具体的な解釈が含まれている。パーソンズの歴史と進化の理論において、サイバネティックスの階 層的行動システムレベルの構成的認知記号化は、原理的には、生物進化を制御するDNAの遺伝情報と同じ機能を持つが、メタシステム制御の要因は、いかなる 結果も「決定」するのではなく、実際の開拓者である行動そのものの方向性の境界を定義する。パーソンズは、社会の構成レベルをノーム・チョムスキーの「深 層構造」の概念と比較している。 パーソンズは次のように書いている。「深層構造それ自体は、一貫した意味を伝えるような文章を明確に表現するものではない。表面構造が、これを実現するレ ベルを構成する。それらをつなぐリンクは、ノーム・チョムスキー自身の表現を借りれば、変換のルールセットである」[191] 変換プロセスとエンティティは、少なくとも経験的分析の1つのレベルでは、一般的に神話や宗教によって実行または実現されるが、[192] 哲学、芸術システム、あるいは記号論的な消費者行動でも、原理的にはその機能を果たすことができる。[193] 社会科学の統一概念 パーソンズの理論は、社会科学の統一概念、そして実際には生活システム[194]一般の統一概念のビジョンを反映している。パーソンズは、個々の行為者の 実際の行動システムを欠いたシステムがオートポイエーシス(自己生成)的になり得るという考えを否定しているため、彼の考え方は、ニクラス・ルーマンの社 会システム理論とは本質的に異なる。システムには内在的な能力があるが、それはあくまでも行動システムの制度化されたプロセスの結果であり、最終的には個 々の行為者の歴史的努力の結果である。ルーマンがシステム内在性に焦点を当てた一方で、パーソンズは、自己触媒的および恒常性維持プロセスに関する問題 と、究極の「ファーストムーバー」としての行為者に関する問題は、相互に排他的ではないと主張した。恒常性維持プロセスは、それが発生した場合に必要とな るかもしれないが、行動は必要不可欠である。 パーソンズの言葉(歴史上の高次サイバネティック・システムは、サイバネティック階層の低レベルで組織化された社会形態を制御する傾向にある)を理解する には、行動における究極の参照という観点が必要である。パーソンズにとって、一般的な行動レベルに関する限り、サイバネティック階層における最高レベルと は、パーソンズが文化システムの構成部分(LのL)と呼ぶものである。しかし、そのシステムの相互行為プロセスにおいては、特に文化的表現主義的軸 (AGILにおけるL-Gライン)に注目すべきである。パーソンズは「構成」という用語で、特に宗教的要素を含む高度に規範化された文化的価値を一般的に 指していた(ただし、「構成」という用語の他の解釈も可能である)[195]。 文化システムは、社会システムの規範的・方向付け的なパターンとは独立した地位を占めており、いずれのシステムも他方に還元されるものではない。例えば、 社会システムの「文化的資本」という純粋に歴史的な実体(「受託システム」としての機能)の問題は、そのシステムにおけるより高度な文化的価値とは同一で はない。つまり、文化システムは、いかなる社会システムにも還元できないメタ構造論理を体現しており、社会システムの「必要条件」から唯物論的 (または行動主義者)による社会システム(またはその経済の「必要条件」)からの演繹とは見なされないメタ構造論理によって体現されている。[196] その文脈において、文化は、実際の社会文化単位(西洋文明のような)の要因としてだけでなく、古典ギリシャや古代イスラエルのように、独自の文化的基盤が 浸透し、多数の社会システムに広がることで「普遍化」する傾向にある。古典ギリシャや古代イスラエルのように、元の社会基盤は消滅したが、文化的システム は独立して「機能する」文化的パターンとして生き残った場合、ギリシャ哲学やキリスト教のように、イスラエルに起源を持つ修正された派生形として生き残っ た場合などである。[197] パーソンズとハーバーマス パーソンズとユルゲン・ハーバーマスの違いは、ハーバーマスがパーソンズの理論をどのように用いて自身の基本命題を確立するかという点にある。[198] ハーバーマスは、パーソンズが社会システムの「外側」と「内側」の次元を区別したことを受け、それを「システム」(外側次元(A-G))と「生活世界」 (内側次元(I-L))と名付けた。パーソンズの視点から見た場合、このモデルの問題点は、a) 社会システム内の対立は、実際にはあらゆる関係点から生じる可能性があり、単純にシステムと生活世界の二分法から生じるわけではないこと、b) システムと生活世界モデルを 解放」の精神と結びつけることによって、ハーバーマスは、社会システム内の対立の可能性には「最終的解決」があるというユートピア的な概念を生み出し、そ れはシステム的対立の本質について誤解を招く概念を生み出す。 一般理論 パーソンズが「一般理論」という用語の2つの「意味」または様式を区別していたことを強調することは重要である。彼は、ある分野の基本的な理論的体系化に 対する認識上の関心の中で最も「構成的な」要素に焦点を当てた社会科学の理論的関心として、一般理論について論じることがあった。パーソンズは、その分野 における基本的な概念体系、すなわち、その分野における最高位の理論的関係、そして当然ながら、論理的帰結の観点から見たこの体系の公理、認識論、方法論 の基礎の必要な特定も含めていた。[199][200] すべての要素は、理論的関心における最高レベルでの一般理論の探究を意味する。 しかし、一般理論は、認知構造化のより低いレベル、すなわち知覚された「経験的対象」に近いレベルにおいて、概念的スキームの含意が「明確に」示された、 より完全な/運用可能なシステムを指す場合もある。1947年のアメリカ社会学会での講演で、彼は5つのレベルについて語っている。 一般理論レベルは、主に社会システムの理論として形作られた。 社会行動の動機付け理論は、特に社会システムの力学に関する問題を取り上げ、動機付け、性格、社会化の理論を当然の前提とした。 社会構造の体系的比較分析の理論的基礎は、さまざまな一般化レベルにおける具体的な文化の具体的なシステム研究を含む。 特定の実証的問題領域に関する特殊な理論。 統計や調査技術などの特定の実証的研究手法に理論を「適合」させること。 生涯を通じて、彼は理論的関心事の5つの分野すべてを発展させることに取り組んだが、とりわけ最高位の「構成」レベルの発展に特別な注意を払った。なぜな ら、他の部分は最高位の堅固さによって成り立つか、あるいは成り立たないかのどちらかだからである。 神話にもかかわらず、パーソンズは、現代社会がその規範とある種の完璧な調和を保っているとは考えず、また、ほとんどの現代社会が必ずしも高度な合意や 「幸福な」制度的統合によって特徴づけられているとも考えなかった。パーソンズは、複雑な現代社会の基本的な規範構造において、完全な一致や完璧な合意が 存在することはほぼ論理的に不可能であると強調した。なぜなら、現代社会の基本的な価値パターンは一般的に分化しており、基本的な規範カテゴリーの一部は 本質的または少なくとも潜在的に互いに相反するものとして存在しているからである。例えば、自由と平等は一般的に現代社会の基本的かつ譲歩不可能な価値観 と見なされている。それぞれが、人間性のより高い価値観についての一種の究極の命令を表している。しかし、パーソンズが強調しているように、自由や平等、 あるいはそれらが調停される可能性がある場合の単純な解決策について、優先順位に関する単純な答えはない。したがって、すべての現代社会は、この2つの価 値観の間に蔓延する本質的な対立に直面しており、そのような「永遠の解決策」は存在しない。いかなる近代社会においても、動機付けのパターン、規範的解決 策、そして支配的な価値観のパターンが完全に一致することはない。パーソンズはまた、「左派」と「右派」の「論争」は、両者が究極的には「正当化された」 人間的価値(あるいは理想)を擁護しているという事実と関係がある、と主張した。この価値は、それだけでは価値として不可欠であるが、常に互いに終わりな き対立的な立場にある。 パーソンズは常に、社会における規範的パターンの統合は一般的に問題があり、原則的に達成される統合のレベルは常に調和的で完璧なものとは程遠いと主張し ていた。もし「調和的パターン」が現れるとすれば、それは特定の歴史的状況に関連するものであり、社会システムの一般的な法則ではない。 AGILパラダイム パーソンズがシステムおよびサブシステムを分析するために用いた発見的枠組みは、AGILパラダイムまたはAGILスキームと呼ばれる。[203] 環境に対して生存または均衡を維持するためには、あらゆるシステムはある程度、その環境に適応(適応)し、目標を達成(目標達成)し、構成要素を統合(統 合)し、潜在的なパターン(潜伏パターンの維持)を維持しなければならない。これは一種の文化的テンプレートである。これらの概念はAGILと略記され、 システムの機能的要請と呼ばれている。パーソンズのAGILモデルは理論的な「生産」のための分析的枠組みであるが、経験的現実の単純な「模倣」や直接的 な歴史的「要約」ではないことを理解することが重要である。また、この枠組み自体は「何か」を説明しているわけではなく、自然科学における周期表がそれ自 体で何かを説明しているわけではないのと同様である。AGILの枠組みは説明のためのツールであり、それを加工する理論や説明の質以上のものはない。 社会行動システムの分析の場合、パーソンズによれば、AGILパラダイムは相互に関連し、浸透し合う4つのサブシステムを生み出す。すなわち、構成員の行 動システム(A)、それらの構成員のパーソナリティ・システム(G)、社会システム(それ自体)(I)、そしてその社会の文化システム(L)である。社会 を社会システム(行動のIサブシステム)として分析するため、人々はそれぞれの立場に関連する役割を演じると仮定される。立場と役割はある程度分化し、現 代社会では職業、政治、司法、教育などの役割と関連付けられる。 これらの専門化された役割の相互関係、および機能的に分化した集団(企業や政党など)を考慮すると、社会は相互に関連する機能的サブシステムからなる複雑 なシステムとして分析することができる。 すべての生命システムのための純粋なAGILモデル: (A) 適応。 (G) 目標達成。 (I) 統合。 (L) 潜伏(パターン維持)。 社会システムレベル: 経済 — その行動および非行動に対する社会的適応 政治体制 — 集団としての目標達成 社会共同体 — その多様な社会的構成要素の統合 受託者システム — その「直接的な」社会的埋め込みにおいて歴史的文化を再生する機能を持つプロセス 一般的な行動レベル: 行動有機体(またはシステム)、後のバージョンでは、一般化された「知性」の焦点。 人格システム。 社会システム。 文化システム。(文化レベルを参照) 文化レベル: 認識的象徴化。 表現的象徴化。 評価的象徴化。(時折、道徳的評価的象徴化と呼ばれる) 構成象徴化。 一般化された象徴媒体: 社会システムレベル: (A)経済システム:貨幣。 (G)政治システム:政治権力。 (I)社会共同体:影響力。 (L)受託システム(文化的伝統):価値観へのコミットメント。 パーソンズは、これらの各システムが、経済における貨幣のように、社会集団における影響力のような、相互作用の専門的な象徴的メカニズムを開発したという 考えを詳しく説明した。社会システムのサブシステム間の「交換」のさまざまなプロセスが仮定された。 パーソンズによるAGILスキームに基づく社会システム分析の使用は、著書『経済と社会』(N. Smelserとの共著、1956年)で確立され、それ以来、彼のすべての著作で用いられてきた。しかし、AGILシステムは当初は「初歩的」な形でのみ 存在し、その後数十年の間に徐々に洗練され、拡大されていった。パーソンズのAGILスキームの簡単な紹介は、『The American University』(G. Plattとの共著、1973年)の第2章に記載されている。しかし、彼の著作のどこか一箇所で、AGILシステム全体が視覚的に表示または説明されてい るわけではない。このシステム全体は、彼の著作の複数の箇所から再構成する必要がある。『The American University』に示されているシステムは、最も基本的な要素のみであり、システム全体と誤解すべきではない。 社会進化論 パーソンズは社会進化論と新進化論に貢献した。彼は進化を4つの副次的なプロセスに分けた。 上述の通り、主たるシステムの機能的サブシステムを創り出す「分化」、 適応(それらのシステムがより効率的なバージョンへと進化すること)、 特定のシステムから以前に排除された要素の包含、 価値の一般化(ますます複雑化するシステムの正当性を高めること)である。 さらに、パーソンズは進化の3つの段階におけるサブプロセスを探究した。 原始的 古風な 近代的 パーソンズは西洋文明を近代社会の頂点と捉え、米国を最もダイナミックに発展した国と見なした。 パーソンズの晩年の研究は、行動のあらゆるシステムに共通する4つの機能(行動から文化まで)と、それらをまたいだコミュニケーションを可能にする象徴メ ディアのセットに焦点を当てた新しい理論的統合に焦点を当てた。秩序に焦点を当てた枠組みに従って行動の世界を構造化しようとするパーソンズの試みは、 1960年代の壮大な主張からより実証的で根拠のあるアプローチへと後退していたアメリカの社会学者たちには受け入れられなかった。 パターン変数 パーソンズは、社会には2つの次元(道具的次元と表現的次元)があるのではなく、社会相互作用の種類によって質的な違いがあるのだと主張した。 彼は、人々はそれぞれの役割に基づいて、個人的な関係と形式的な関係を切り離して持つことができると観察した。パターン変数とは、パーソンズが各相互作用 の種類に関連する特性と呼んだものである。 相互作用は、各対照的なペアの識別子のいずれかによって特徴づけることができる。 情動性 - 情動的中立性 自己志向 - 集団志向 普遍主義 - 特殊主義 帰属 - 達成 特殊性 - 拡散性 レガシー 1940年代から1970年代にかけて、パーソンズは世界、特に米国において最も著名で影響力があり、かつ最も論争の的となった社会学者の一人であった。 [18] 彼の後期の作品は批判にさらされ、1970年代には、彼の理論は抽象的で理解しがたく、社会的に保守的すぎるとの見解によって概ね否定された。[18] [204] 近年、パーソンズの思想、特に見過ごされがちであった後期の作品への関心が高まっている。[17] パーソンズの思想を復活させようとする試みは、ジェフリー・アレクサンダー、ブライアン・ターナー、リチャード・ミュンヒ、ローランド・ロバートソンと いったパーソンズ派の社会学者や社会科学者によって行われており、ユタ・ゲルハルトは伝記的・歴史的な観点からパーソンズについて書いている。 現在、パーソンズへの関心の中心となっているのは、アメリカ合衆国に加えて、ドイツ、日本、イタリア、イギリスである。[要出典] パーソンズは、ラルフ・ダレニウス、アラン・トゥレーヌ、ニクラス・ルーマン、ハーバーマスなど、多くのアメリカ人および国際的な学者たちに多大な影響を 与え、初期の指導者でもあった。[要出典] 彼の最も有名な弟子はマートンであった。[18] パーソンズはアメリカ哲学協会の会員であった。[205] |
| Selected bibliography Author 1983. The Structure and Change of the Social System Edited by Washio Kurata (lectures from Parsons' second visit to Japan). 1986, Social Science: A Basic National Resource Edited by S.Z. Klausner & Victor Lidz. (Written around 1948). 1991, The Early Essays (Essays from the late 1920s and the 1930s). Edited by Charles Camic. 1993, On National Socialism (Essays from the late 1930s and the 1940s). Edited by Uta Gerhardt. 2007, American Society: Toward a Theory of Societal Community Edited by Giuseppe Sciortino. Paradigm ISBN 978-1-59451-227-8. Compilations Talcott Parsons and Kenneth B. Clark (eds.), The Negro American. Beacon Press, 1967. Talcott Parsons (ed.), Knowledge and Society: American Sociology. New York: Basic Books, 1968. (collection of essays with an introduction by Talcott Parsons) Talcott Parsons and Victor M. Lidz (eds.), Readings in Premodern Societies. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1972. Translations Main articles: Iron cage and The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism In 1930 Parson's published a translation of Weber's classic work The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. (1905) Translated by Parsons in 1930. (It was the book's first English translation.) Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization. (1921–22) Translated by Parsons with Alexander Morell Henderson in 1947. |
参考文献 著者 1983年 『社会システムの構造と変動』 倉田和枝編(パーソンズの二度目の来日時の講義)。 1986年 『社会科学:国民の基本資源』 S.Z.クラウスナー&ビクター・リッツ編(1948年頃執筆)。 1991年、『初期の論文集』(1920年代後半から1930年代の論文)。編集:チャールズ・カミック。 1993年、『国家社会主義について』(1930年代後半から1940年代の論文)。編集:ユタ・ゲルハルト。 2007年、アメリカ社会:社会共同体理論に向けて ジュゼッペ・シオルティーノ編著。パラダイム ISBN 978-1-59451-227-8。 編集 タルコット・パールソンズ、ケネス・B・クラーク(編)、『The Negro American』ビーコン・プレス、1967年。 タルコット・パールソンズ(編)、『知識と社会:アメリカ社会学』ニューヨーク:ベーシック・ブックス、1968年。(タルコット・パールソンによる序文 付きの論文集) タルコット・パールソン、ビクター・M・リッズ(編)、『前近代社会の研究』。 エンゲルウッド・クリフス、プレンティス・ホール、1972年。 翻訳 詳細は「鉄の檻」および『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を参照 1930年、パールソンはウェーバーの古典的名著『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の翻訳を出版した マックス・ヴェーバー著『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』。1905年)1930年にパーソンズが翻訳。(同書の最初の英語訳) マックス・ヴェーバー著『社会と経済の組織理論』。1921年~1922年)1947年にパーソンズとアレクサンダー・モーレル・ヘンダーソンが共同で翻 訳。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons |
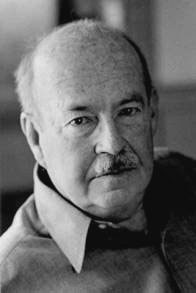
+++
Links
リンク
文献
その他の情報



Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099