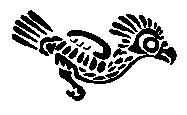
文化人類学を教えることの「効用」
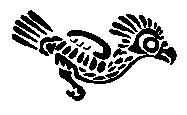
——「社会学者のメチエ(=専門技術)をもつというこ と、それはハビトゥス、場などの基本概念のなかに含まれていることをすべて、実践状態でマスターすることなのです」(ブルデュ 1994[1988]:474)。
|
目次 1.反語的意味 2.文化人類学者へのステレオタイプ—人類学者のマイナスイメージ 3.日本の文化人類学[教育]には一貫したディシプリンがあったか? 4.Doing Ethnography of Teaching Anthropology 5.提言 |
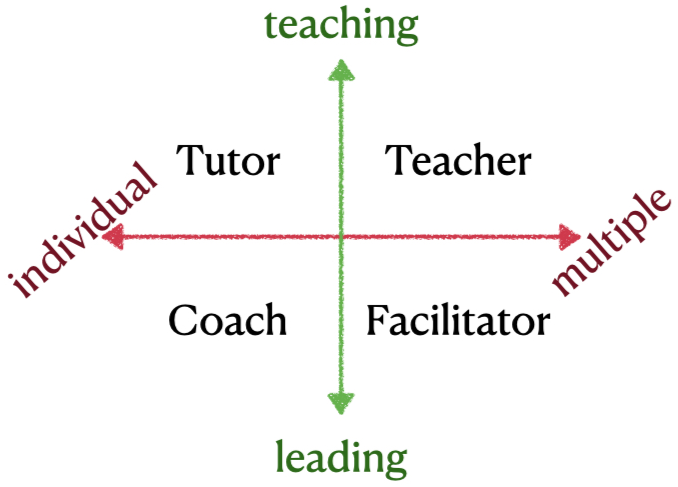
熊本大学文学部では、97年から始まると予想されて いる改組(ポストスクリプト2005:これは1997年度から実施され文化人類学教室は民俗学教室と合併し文化表象学教室となった。2005年度に地域科学科の改組にともない、同学科は人間科学科と合併 し、総合人間学科となった。総合人間学科において社会人間学コースが新設され、それにともない研究組織として文化人類学の名前は今一度復活している)にと もなって文化人類学の名前を冠した講座はなくなる運命にある。また、文学部や文化人類学をめぐる状況は、後に述べるように必ずしも楽観をゆるさない。した がって私自身には「21世紀をめざす文化人類学専門教育」という明るい将来を約束されたタイトルに手放しで喜べない事情がある。その意味では、私は場違い なところにいることになる。ここでは熊本大学の文化人類学講座の公式見解ではなく、そこに所属するひとりの専門教育者としての見解を申し述べることにしま す。
ところで、文化人類学が「外部世界」に向かって説かれる際には、その学問自体あるいはそれ を学ぶことの効用がまず主張されるのであって、「教えることの効用」という内向きの話題は表面には出てこない。しかしながら、その学問に惹かれ、その学問 を志し、その学問の有用性を説く主体としての文化人類学者/文化人類学徒の再生産にとって、文化人類学を教えることの意味を問うこともまた強調されるべき である。このことはまた、一部の新興あるいは後発の国立大学や私立大学で試みられるようになった比較的多数の人類学者が組織的かつ総合的に教育にとり組 み、有為な人材を育てていくという戦略が登場する一方で、清水昭俊さんが最新号の『フォーラム』で指摘するように、日本の多くの人類学者たちが「非公式的 な教育プログラム」という「大学・大学院の制度外の教員や学生の個人的努力に」よって育てられてきたし、また育てられているもうひとつの現状に鑑みると き、特に重要なポイントになる。
そして「教えられる内容」の正当性の議論だけでなく、「教えるという行為」の正当性をめぐ る議論も重要なのではないだろうか。というのは非公式的プログラムによって育てられてきた多くの人類学者たちが、今度は教師となったときにおこなう教育内 容は想像するにきわめて多様であるだろう。これは科学社会学的に言えば、文化人類学の教育内容は当事者による自主的な管理を除けば、ほとんどクオリ ティー・コントロールがなされたことがないということになる。仮に学会が過去にさまざまな調査をおこない、また教育のあり方に関する記事を掲載し集会をお こなったとしても、自主的な管理が中心であったことは拭いきれない。学会がこのようなことに直接介入することには是非はあるが、少なくとも今よりもより強 固に啓発活動をする必要はあると思われる。
以上のことを踏まえながら、私の結論を先に述べておきます。つまり、教えることの効用は無 益な徒労にも純粋な喜びにも還元されません。むしろ文化人類学という共通のディシプリンを確保することができてはじめて共通の議論が可能になること、その 学問でしか味わえない独自性を獲得することが「教えることの効用」につながると考えます。文化人類学において「教えることの効用」が保証されるためには、 ある程度のディシプリンの共有化がなされなければならないというのが私の立場です。もちろん、そのための代価として学問内部のリベラルな活動が抑圧される ことがあってはならない。ディシプリンが野放しになっている現状に異議申し立てをおこない、より明確な戦略とモラルをもって人類学者としてどのような生き 方=教育実践があるのか?、次の世代に何が提示できるか?が文化人類学専門教育に今問われていることだと思います。
Copyright Mitsuho Ikeda, 1996-2003
さて、私の前任地の医療系の私立大学では教養部に属していたために、外部世界から文化人類 学の教育者であることに特段の関心や教育上の役割をもたせられることはなかった。しかし、社会学、民俗学、地理学、考古学、言語学など隣接分野で研究教育 に従事する同僚がいる現在の職場では、学部内での文化人類学のアイデンティティについて考えさせられることが多い。あるいは考えさせらることを半ば強要さ せられているといっても過言ではない。とくに、学部改組など旧講座の利害に係わることがあればなおさらである。
ここで人類学者に押しつけられるステレオタイプについて考えてみます。
人類学者が自分たちのまわりの世界を「未開社会」としてカリカチャライズする手管は方法と しては手垢に汚れており時代遅れであるばかりか有害である。しかし、それでもなお使ってみたくなる衝動にかられる。ただし、ここでは人類学者が現地の人び ととして周囲からどのように表象されているかということを問題にしたい。したがって現地の人びとが外部から押しつけられた自分たちの表象を拒否する姿に、 人類学者像を重ねてみたい。異議申し立てをする側から言えば、それはカリカチャーではなくステレオタイプと言うほうが正確である。同年代の何人かの同僚に 聞いたこの種のステレオタイプは大きく2つに分けられる。つまり、(1)「未開社会」調査のエキスパートであり、(2)特殊技能者である。
まず(1)「 未開社会調査」のエキスパートとしての人類学者ですが、これは珍しい言語をあやつり、特別な社会に出入りすることのできるエキスパートとしてみなされてい ます。同僚にとって未開の経験を教えてくれる一種の語り部であり、同僚の非人類学者が学生に対して同僚の人類学者(=私)を紹介するときにもこのステレオ タイプが貼られる。<比較文化>という分野の登場で、現在では必ずしも必要な存在ではないが、居れば学部の特色をいろどる重要な要素になるとみなされてい る。
つぎに(2)特殊技能者として人類学者がみなされている。芸能とか民具など、文献ではフォ ローすることができない「アルカイック」なことについて該博なエキスパートである。これは文学部では民俗学者やフィールド言語学者と同じポジションにあ る。この特殊技能は知識の点でもステレオタイプ化される。例えばレヴィ=ストロースや山口昌男さんのようなスーパースターの仕事に代表される知識の体現者 としての人類学者像が先にあり、我々人類学者はそのミニチュアあるいはフォーク・バージョンとして期待されている。 以上を要約すれば、人類学者は同僚からある種のエキゾティシズムの対象としてみられている。これは多くの人類学者の営為とはほとんど無関係なカリカチャー であり、このようなイメージを払拭できないのは残念である。ただし、このようなカリカチャーを人類学者自身は積極的には否定せず、ある文脈においてはその 同僚に対して、状況を上手く定義するための表象として利用してきたところもあるのではないだろうか。したがって、この人類学者のカリカチャー構築に人類学 者がまったく無罪であったということはできない。
Copyright Mitsuho Ikeda, 1996-2003
文化人類学が体系化されたディシプリンがあるのかか否かについてはさまざまな論がある。ま た体系以前にその情報の多さがあげられる。文化人類学を学ぶことにおいて、そこでおこなわれている全ての現象をフォローするというのは至難の業であり、は たしてそのようなことが可能かどうかもわからない。ちょうど『フォーラム』に掲載された京都文教大学の充実したカリキュラムの中で開講されるすべての授業 を4年間では取得できないように、かりに体系があったとしてもそれを限られた時間で網羅することは不可能である。またコメンテーターの森山さんは、同じ フォーラムのなかで広島市立大学の国際学部における多角的な学習課程の問題を指摘する一方で、文化人類学が「基礎から始めて段階的に高度な内容に進むとい う教育上の体系的な方法が確立した学問分野であるか否かでについても大いに議論の余地」があると述べている。
もちろん、文化人類学が学内ポリティクスのなかで存在理由を主張するときには、その学問の 体系性や有用性を弁明のために動員することがありえるし、教育の現場でさえ「これくらいは知っていてほしい」というかたちで文化人類学の正統的知識の体系 を示唆することはある。しかし、日本の文化人類学の教科書ながめてみてもバランスとれたものは少なく、多くは、それが書かれた当時のアメリカの教科書の内 容構成をまねたものか、教科書を利用する共著者たちが調整した結果、それぞれの執筆者になる論文のアンソロジーでしかない。
明確なディシプリンがないことの最大の問題は、それがリベラルな総合という形にはまとまら ずに、文化人類学に対する無手勝流の教育手法を暗黙のうちに容認してしまうことにある。もちろん個々の人類学者はそのことを危惧しており、それぞれに「バ ランス」のとれた教育内容になるように配慮しているだろう。しかし、それは個人レベルの問題であり、学会や専門教育をおこなっている組織が一定のガイドラ インや、場合によっては教科書を編纂することがあっても決して悪くない。またそのようなものが編纂されることで、何を教えるべきかという問題点もより明確 化するだろう。文化人類学のリベラルな伝統は、むしろそのような論争のなかで活かされるべきである。
Copyright Mitsuho Ikeda, 1996-2003
文化人類学の知識の体系化について偉そうに私見を述べたが、実は私自身は学部で専門科目と して開講されている「文化人類学概論」を担当していない。文化人類学のみならず地域科学科で開講されている人文地理学、社会学、民俗学の概論は教授が担当 することになっているからである。だから、私は教養部で担当する文化人類学関連の授業をおこなう際に、この問題を考えるだけであり、専門教育のなかで文化 人類学の体系に基づく教育について思い悩んだことは少ない。教養教育において文化人類学を教えてきたキャリアーを私は6年近く持っているのだが、専門教育 は過去2年間の経験しかない。おまけに修了した大学院は医学研究科で、文化人類学の専門教育がどのようなものかという体験もない。
というわけで、この2年間は専門教育に携わっている諸先輩と電子メールと電話で、テキスト や論文の選択や授業の運営のノウハウなどをうかがいつつ、毎時間相応の予習と即興演奏まがいの綱渡りをおこなってきた(今でもその状況は変わらぬが)。余 裕をもって学生との議論を楽しめるようになったのは、じつに今春以降だと言ってよい。ただし、毎年同じことをやるほどの根気もないので、学生には前年度の シラバスを配って、文献リストを示しておき、どのようなことをやったのかの説明をしてから、新年度/新学期の方針を述べるようにしている(ただしそんなこ とを弁明したからといって、学生が旧年度でやった内容について勉強してくれる気配はないようだ)。
受講生はほとんど十数名前後なので授業は「特講」であっても、すべて演習形式でおこない、 発表と討論、とくに討論に力点をおいておこなっている。というのは、(これは文化人類学の知的伝統からいって正統なのか異端なのかわからないが)私が人類 学を勉強することに最大の魅力を感じているのが、人類学の批判的能力だからである。つまり、リアリズムに対する実証主義(あるいはその逆)、伝統的な解釈 に対する異端的読解、多数派の意見ではなく少数派の見解、について考える視座を提供すると信じているからである。だから、無難な解釈を期待するのではな く、異端的意見をのべ、その解釈がどこまで論理的に妥当なのか、あるいはどのような社会的文脈を想像すればそれが妥当になりえるのか、という思考実験をお こなうように心がけている。だから、そのように議論が展開しない場合は私は極めて機嫌が悪くなる。おまけに、自分が教育者として権威を振りかざしながら、 学生にそのような思考を押しつけているのではないかと反省するようなことでもあれば、ほどんど自己嫌悪に陥ってしまう。もっとも学生はそんなことがあって もケロっとしている、あるいはそのように見えるので、深刻には悩みませんけれども。
大学の授業よりも面白い(そして疲れる)のが実習である。コースの学生は2年と3年次にそ れぞれ3単位の実習が必修となっており、私は2年次のそれを担当している。実習は4人程度の3つの班を編成して、調査のテーマや内容をなるべく自主的に決 めてもらっている。定期的に事前調査の進捗状況や中間報告などを義務づけ、グループ間で競争させてよりよいものを出すようにと指導している。「よりよいも の」とは調査の内容のレベルというよりも、私が信じて止まない「文化人類学の批判能力」を実地調査で発揮できるようなものであり、何度もくりかえし指導す る。今年は天草の自然保護と町おこしをテーマにして、一回目の調査を一週間前に終えたところである。町おこしの調査は我々を受け入れてくれた地域が、現在 2つに分裂するほどの問題を抱えている。我々の調査のことを、マスメディアがとりあげたことから、学生たちにはどちらの側からもラブコールがかかることに なった。先日おこなわれた反省会では、学生たちは調査結果がある種の政治的効果をもたらすのではないかとか、両方に遠慮すると何も書けなくなるのではない かと危惧する意見も出たが、私は、むしろ、これぞ多くの人類学者が直面している調査の真実である。その中でよりよい視点をみつけだそう、などと宥めつつ激 励している。学生たちはそれ以降調査被害や調査者の社会的責任に関する勉強をはじめている。
Copyright Mitsuho Ikeda, 1996-2003
以上の私的な経験が中心になりましたが、それをまとめて最後に2つの提言をおこないたい。
ひとつは文化人類学のディシプリンの強化と共有化である。
文化人類学とは何かという議論は、学会内部で今後ますます必要になる。これは人類学者 に与えられてきたステレオタイプ=偏見と戦うための強化刺激となるだろう。人類学にはりつけられてきたステレオタイプの克服においては、まず人類学者が自 分たちの身の回りでどのように表象されているのかについての具体的な調査や検討が必要になるだろう。
文化人類学専門教育においては、大学間、教育者間の相互の恒常的な情報・意見交換は不 可欠となるだろう。カリキュラムの内容の相互の公開、合同授業や合同調査実習の開催を通して、情報交換をより促進させるべきである。将来的には文化人類学 関連単位の相互互換などをおこなうべきだと考えるが、制度上の煩瑣な手続きによって迅速な対応が阻まれるならば、インフォーマルな情報交換、ネットワーキ ング、あるいは実質的な合同授業の開催などを試みるべきだろう。
もうひとつは文化人類学という学問を、もっと多くの人びとに知ってもらうよう努力すること である。
同僚に対してはそのステレオタイプ=偏見を正し、人類学的な営為をより正確に理解して もらうよう啓発を強化する。また隣接科学に論戦をいどみ、自分たちの知り得る情報から最良の判断をくだすことは不可欠である。たとえば人類学的な視点から 中学高校の教科書に記載されている内容を検討した、青柳真智子編『中学・高校教育と文化人類学』大明堂、1996年などは、それ自体で学生にとっても文化 人類学演習や実習の基本文献になりえるものである。
文化人類学専門教育でおこなわれる調査実習においては、従来の報告書の贈呈以上に現地 に対するより積極的な還元や広報をおこなうべきである。たとえば、現地での報告会をもって地元の人から直接感想を聞いたり、シンポジウムなり話し合いをも つ。人びとにより親しみやすいマルチメディア機材で報告書(=メディア)を地元の教員や郷土史家の方たちと共同で制作する。もちろん、そのためにはカリ キュラムのなかにマルチメディアの編集や視聴覚教材の扱い方を習熟する科目を組み込む必要がある。
長期的にみればそのような活動じたいが文化人類学の専門教育者の生き方へもはねかえってく ることだろう。このような一連の活動から得られることがらもまた、文化人類学教えることの「効用」といっても差し支えないのではなかろうか。
分科会「21世紀をめざす文化人類学専門教育」第30回日本民族学会研究大会1996年5月 26日14:30-17:00(静岡大学)
※この発表は、池田光穂の下記の論文として結実しました。千葉大学(当時)の中村光男先生を はじめ熊本大学大学教育研究センターの関係者に感謝します。このウェブ・ページの論文と下記の論文には若干の異同があります。
池田光穂「大学における文化人類学教育をどう活性化するか—専門学徒への提言 —」,『大学教育』(熊本大学大学教育研究センター)第1号,pp.20-25,1998年3月
