gerontocide and negrect against
aged people
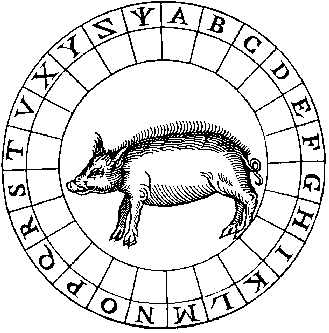
老人遺棄と殺害
gerontocide and negrect against
aged people
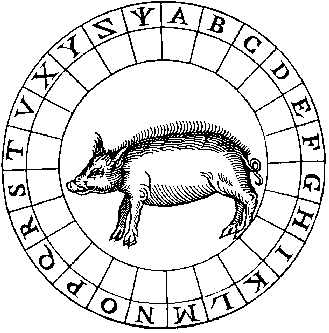
殺人とは、人間の同種内の殺傷行為 (killing)のことである。死に至らない場合は、殺人未遂(さつじん・みすい)という。
OEDの語源は、直接にはフランス古語、そして古く
はラテン語からきており、人間を殺すことである。[a. F. homicide (12th c.), ad. L. homicīda, f.
shortened stem of homo, homini-s man + cædĕre, -cīdĕre to kill: see
-cide 1.]
●老人遺棄と殺害(ある草稿から)
高齢者の遺棄と殺害の方法は、ジャレッド・ダイア
モンドの解説(二〇一三:三六六—三三九)(Diamond
2012:214-216)によると次の五つに大別できる。(一)高齢者をケアしない、ないしは虐待したり放置する方法、(二)狩猟採集民のように集団が
キャンプから別のキャンプに移動する際に、意図的に置き去りにする方法、(三)高齢者自身が自殺という手段を選んだり、また自殺することを示唆する方法、
(四)高齢者の自殺を助けたり、当人あるいは親族によって依頼されて殺害する方法、(五)高齢者を計画的に殺害する方法、である。 通文化研究の質的情報
データベースのフラーフ(Human Relations Area Files,
HRAF)の本部はエール大学にあるが、その先駆資料をつかってレオ・シモンズは一九四五年に『未開社会における高齢者の役割』(Simmons
1970)という著作をまとめた。それによると調査された三九の社会のうち一八の社会で老人の殺害が実施されている(Simmons
1945:225)。これらの社会では、頻繁におこなわれたのが一一社会、時におこなわれたのが一〇社会、存在しないのが二二社会であり、残りの二八社会
はそれに関する情報そのものがなかったという(Simmons
1945:239)。シモンズは、死に至るまでの間に社会が老人をどう扱うかは多様であることをいまいちど確認し、過度の一般化を戒めるために、そのまと
めの部分でロケット(一九三三)の報告を引用した。ワルピ(地名)で目撃された、一九二八年七月四日に亡くなったホピの太陽司祭とよばれたスペラ
(Supela)という長老の最期を思い出すように、彼は読者に喚起する。臨終のスペラは共同体に降雨をもたらすために自らの命を犠牲にすることを決意す
る。
「人びとは長引く干ばつに苦しんでいた、そして古老スペラは[一九二八年七月四日の死後]シパウと呼ばれる途を通り、雨と芽吹きを支配している諸霊が住む
地下世界に降りていったが、彼は躊躇することなく、神々の状況を説明し、また地上の人びとと仲裁し、スペラが地上に戻った後に、即座にその結果を期待する
だろうことを、神々と約束した。彼の人生は宗教的にまっとうであり、神々により受け入れられていたために、スペラがそのための旅の時間を記録し、その道中
でどんな贖いも処罰を課せられ邪魔されることなく、四日間旅をするだろうとする、彼とその友人[=神々]たちへの信仰があったのだ。スペラはこのことを約
束し、人びとは[雨がもたらされるだろうという]願望の成就が達成されることを期待した。スペラの死後四日を経て、ものすごい雷鳴をともなった恐ろしい嵐
雨により、その長い干ばつは終焉を迎えた。ホピの人びとは驚きを見せただろうか? いや、その反対に、満足げに顔を紅潮させ、スペラが四日かけてようやく
『切り抜けて』感動的な請け合いということをお互いに祝福しあった、最も素晴らしい賞賛がそこでなされたのだった」(Lockett
1933:41-42、ただし引用はSimons 1945:243)。
この引用をした後に、シモンズは「未開社会において、老人の死というものは、単一の問題でもなく統一した問題によって表されるようなものでもない。また高
齢者やその親族(が取るような)の役割も完全に受動的なものでもない。死の状況も、死への態度というものも、その両方ともに極度に多様なのである」と述べ
ている(Simmons 1970:243)。老人遺棄や高齢者の取り扱いにもまた社会的多様性がある。他方、遺棄はしばしば「死者の家」(house
of dead)という遺棄のための小屋(Simmons 1970:227-229)などの具体的存在に関連づけられる。
私たちが抱く疑問は、老人遺棄と老人への殺害行為は、人類に普遍的にみられるものなのか、あるいは伝統社会にのみ見られるものなのか、それとも近代社会
こそが老人遺棄と殺害を、まさに私たちが自覚することなしに自家薬籠中のものにしている残酷な社会なのかといことなのである。しかし、翻って考えてみる
と、もし残酷さ(=情動を伴う価値づけ)の基準も文化的多様性の中に位置づけられるとすると、ナーシングホームにおいて手厚くケアされる高齢者像を当然の
ごとく「よいケア」だと自明視する私たちの無反省な「自然的態度(natural
attitude)」を自覚することはとても困難を伴う(シュッツとルックマン
二〇一五:五一—六三)。しかし、文化を異にする他者からの指摘は、この私たちの自然的態度の前提を突き崩すきっかけをもたらしてくれることがある。生物
地理学者でありかつ人類進化について造詣の深いダイアモンドは、自分が経験したかつてのフィジー諸島の島民との会話を思い起こす。
「あるとき、私[ダイアモンド:引用者注]は、南太平洋のフィジー諸島にあるビティレブ島(Viti
Levu)にいった。そして、とある村の、地元の男とたまたま話し込んだことがある。男はアメリカにいったことがあった。そして、そのときの感想を、つぎ
のように語ってくれたのである。アメリカには、自分が感心する部分もあるし、うらやましく思うような部分もある。しかし、嫌だなと思う部分もある。一番嫌
だと思ったのは、高齢者に対する処遇だ。フィジーでは、お年寄りは自分が生涯を過ごした土地で暮らす。そこには家族もいる。昔からの友達だって住んでい
る。たいていの場合、子どもたちの家に同居するのがふつうだ。子どもも親の世話をよくやく。面倒もみる。歯がだめになって自分で物を噛めなくなってしまっ
た親に、食べ物を細かく噛み砕いて、食べさせてあげる。そんなことさえフィジーではするんだ。ところがアメリカではどうだっ? 年寄りはみんな施設送り
だ。そこに年寄りを預けっぱなしにして、子どもはたまに会いにいくだけだ。「アメリカって国は、年寄りを捨てたり、自分の両親の面倒をみない国なんです
か!(“You throw away your old people and your own
parents!”)」非難がましい口調で男が私にそういったのである」(ダイアモンド 二〇一三:三五八)(Diamond 2012:210)。
ビティレブ島民のこの男が主張する、高齢者とは末期にいたるまで親族と暮らすことが良いという「フィジー版の人道主義(Fujian
humanitarianism)」からみると、アメリカにおけるナーシングホームは、老人遺棄を報告した初期の西洋人類学者が未開社会のなかにみた「死
の家(house of
dead)」と呼んだ、おぞましい老人遺棄の場所にほかならない。つまり「未開社会」における老人遺棄を残酷なものと見なしている西洋人や私たち日本人
は、他方、自分たちが老人のために良かれと思って作り上げたものが、他者から非常に残酷なものとして映るということなのである。その意味で、ビティレブ島
民の指摘は、まことに西洋社会がもつ自民族中心主義への鋭い批判を見事に体現しているのである。
スチュアート(二〇〇四)は、ダイアモンドが描くビティレブ島民と同じ立場をとり、イヌイト社会には棄老の伝統などないと厳しく弾劾している。「欧米人
が残している手記には、イヌイト社会には何もしない厄介者の老人を置き去りにする、残酷な習俗があると書かれている。姥捨て伝説でも有名だが、棄老習俗と
いわれる老人を置き去りにして見殺しにするこの習俗は、実際には近代文明以外の社会ではほとんど確認されていないようである」(スチュアート
二〇〇四:一一九—一二〇、強調は引用者)。この立場は、かつてのカニバリズム(人食い)論争時において、カニバリズムを実際に見聞した民族誌家が皆無に
等しいということをもって、カニバリズムは西洋世界の「未開や野蛮」の表象にすぎず、想定されているよりも遥かに低い比率でしかおこっていないと主張した
ウィリアム・アレンズ(Arens
1979)の主張と軌を一にする。それにもかかわらず、イヌイト自身にも棄老伝説があるのは、それは棄老をおこなわないための教訓すなわち反面教師である
という。スチュアートは続ける。
「姥捨てなどの棄老伝説が説くのは、老人を大事にしないと禍のもとになるという教訓であることが多い。イヌイトの伝承には、老夫婦とその未婚の娘が置き去
りにされた話がある。食べものがなくなり、三人は飢えに苦しんでいたが、ある日、ホッキョクグマ(カリブーという説もある)がイグルーに押し入ろうとして
入り口にはまり身動きできなくなった。そのホッキョクグマを殺して肉で腹を満たすと、見知らぬ男性が目の前に現われた。その男性は娘を妻にして毎日のよう
に獲物を仕留めたので、皆で幸せに暮らした。反対に、年老いた両親を家の外に追い出して凍え死にさせた男性は、村八分にされ次々と起こる禍に苦しむという
言い伝えもある」(スチュアート 二〇〇四:一二〇、強調は引用者)。
そして、イヌイトが「棄老習俗」をもつと誤ったステレオタイプで、近代社会に誤解されるようになった歴史的メカニズムについて次のように説明する。
「棄老習俗という欧米人の記録は、実は食料不足のときに若い人たちが老人をひとまずキャンプに置いて行き、獲物を捕ってからすぐ引き帰してくる、一時的な
避難措置で、あったようである。ときには、一族が飢餓に苦しんでいるときに、老人が子どもたちに自分の食べものを与えて自ら餓死するのをいとわないという
伝承もある。また、体が不自由になり一族の足手まといとなる場合、自らの命を絶つことも知られているが、若い人が老人を死に追いやることは、反社会的な暴
挙として指弾されるのだった。棄老習俗をことのほかに書きたてる背景には、老人を邪険にする欧米の近代社会の風潮をイヌイト社会に投射して、イヌイトの
「野蛮性」を強調したことがあるようである」(スチュアート 二〇〇四:一二〇、強調は引用者)。
イヌイトに「棄老習俗」はないという主張は、シモンズ(Simmons
1945)が指摘したように、老人遺棄や殺害は、高緯度地方の狩猟採集民に多いという一般的説明からは外れるように思われる。しかしながら、シモンズが老
人の老人遺棄や殺害について議論した箇所に引用されているイヌイト(エスキモー)では、たしかに遺棄という事例はない。シモンズが紹介している民族誌デー
タは、高齢者の自殺にのみ言及されており、その目的は高齢者への尊敬に由来するものであると説明されている。そう考えると、スチュアートが「老人が子ども
たちに自分の食べものを与えて自ら餓死するのをいとわない」という高齢者の道徳原則とも齟齬をきたさない。老人遺棄の伝承は、老人自身の生き方に対する共
同体の尊厳を通して、老人への敬意にも結びつく可能性があるのだ。現代の人類学者の課題は、そのことを歴史人類学的に検証することである。
原ひろ子(一九八九)が報告するヘヤー・インディアン(アサバスカン系のディネ先住民)の五〇歳のチャーニーという老人の「死に方」にもそのような荘厳
さがある。チャーニーは一九六二年八月末のある日、数日風邪で寝込んだ。そして、投薬した地元の看護師はすぐに治ることを予告した。にもかかわらず、原は
五歳のマーサ(チャーニーの弟の娘)から「オジさんが死ぬことにしたから、すぐ行ってあげて。たくさん集まってるよ」と告げられてびっくりした。そして急
いで彼のテントを訪問する。
「チャーニーは一昨日から食物を少ししかとらなくなり、死ぬと言いだしてからは、紅茶を時折口に含むだけになったという。たたみ六畳くらいのテントには、
すでに一七〜八人集まっていた。たばこの煙の立ちこめるなか、全員チャーニーの話を聞いている。横臥してボソボソと思い出話をつづけるチャーニーに、みん
なはフム、フムと相槌を打っている。ふだんの冬の夜長の体験談を聞くときには、聞き手は「フム、フム、それから?」とつづきを催促したり、ときには冗談を
言って話をまぜ返すのだが、死にゆく人には、本人が言いたいことだけを話してもらうために、「それから」と聞いてはいけないことになっている。チャーニー
氏は時折、話を止めて、大きく息をし、紅茶を一口すすっては、目を閉じる。まわりの者は互いに身をすり寄せ合っては、チャーニーを見つめる」(原
一九八九:三六七、強調は引用者)。
チャーニーの末期を理解するためには、先住民ディネの伝統的な身体観や霊魂観を知ることが不可欠である。それによると、霊魂は肉体のあいだを自由に入った
り出たりすることができる。我々が忘我に浸るとき、魂は我々の身体から離脱している。夢見は霊魂が旅をしているのである。また人が眼を閉じ瞑想している時
には魂は守護霊と交流している。チャーニーが死を決意したのも夢見から醒めて守護霊のお告げを人びとに素直に伝えたからなのである(原
一九八九:三六八)。
「肉体が生きているとき、霊魂は再び肉体に戻ってくるが、死ぬと霊魂が出て行ったきり戻ってこなくなる。だから、チャーニーが話を休めると、まわりの者は
互いに身をすり寄せ合っては、チャーニーが良い死に顔で死ぬようにと祈るのである。人が死ぬと、その霊魂は、自分のミウチ[身内:引用者]や生前のキャン
プ仲間のもとや、自分が一生の間に旅をしキャンプをして泊ったところを巡り歩くという。遺体が埋葬されると、あの世への旅をはじめる。そして、良い死に顔
をして死んだ者の霊魂は、再びこの世に生まれるべく旅につく。そして埋葬前にも、悪い死に顔の人ほどには、この世の近しい人の霊を道連れにしようとつきま
とわない。だから、良い死に顔で死ぬことは、死にゆく本人の願いでもあり、見送る人々の願いでもある」(原 一九八九:三六八、強調は引用者)。
ここで注意しなければならないことは、ディネ先住民においては、霊魂の次元では、肉体の死とは無関係にこの世の人との連続性をもつことである。私たちが死
を忌むべきものとして嫌っており、なるべくそのことを考えたり、その話題に触れることを避けたりしようとするのに対して、先住民ディネの人たちは、むしろ
自分のみならず他人の死をも受容して、静かに「よい死」を迎えようとする。ディネにおいて死の受容が重要なことになるのは、死者の霊魂が「旅につく」前
に、私たちの周りに引き続き存在し、生者との存在論的な関係性を維持しようとするからである。個人の死が生者との存在論的連続性をもたない私たちの感覚で
は、チャーニーがどう考えても早い死を迎えることに強い反発を覚え、できれば現代医学の力で治せるものなら治ってほしいと祈るだろう。だが、ディネは、当
人が受け入れようとする死に方を全面的に受け入れ、それを共同体全体で支える。死後の霊魂がしばらく共同体の生者との関係をもち、その後の共同体の成員の
社会的関係をさまざまな形で影響を与えることは、別稿で述べるアチェ先住民の場合にも当てはまる。
リンク
文献(→「殺人に関する考察」の文献を参照)