Infanticide
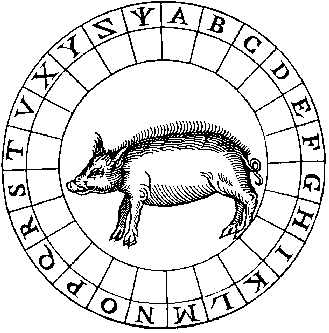
子殺し
Infanticide
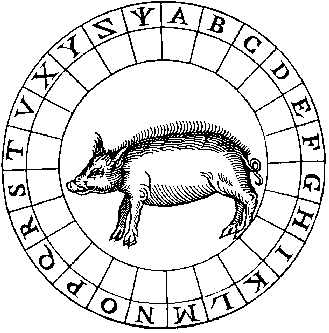
殺人とは、人間の同種内の殺傷行為 (killing)のことである。死に至らない場合は、殺人未遂(さつじん・みすい)という。
OEDの語源は、直接にはフランス古語、そして古く
はラテン語からきており、人間を殺すことである。[a. F. homicide (12th c.), ad. L. homicīda, f.
shortened stem of homo, homini-s man + cædĕre, -cīdĕre to kill: see
-cide 1.]
●子殺し(ある草稿から)
日本民俗学者は子殺しを、法的処罰の対象になる明治
以降の社会とそれ以前の——彼/彼女らが研究対象になるフィクショナルな時空間である——「民俗社会」とでは、全く異なった取り扱いをおこなっていたとい
う解説からはじめる。比較家族史学会編『事典 家族』(弘文堂)によると、民俗学者である岩本通弥は「嬰児殺し」——「子殺し」のことであり本章では引用
以外は後者を優先的に使う——において次のように書く。
「近代法治国家では嬰児殺しは、反道徳的で犯罪的な行為としてみなされるが、『新約聖書』マタイ伝のヘロデ王の幼児虐殺にもあるように、人類史的には普遍
的にみられる現象である。いわゆる未開社会などでは容認されている社会も多く、むしろ義務づけられている場合もあり、狩猟採集民社会では人口調整の一方法
として一般的であったとされ、また不具児をはじめ・逆子・歯の生えた子や私生児など、その社会が異常児とみなす特定要件を有する嬰児を殺害したり、産褥死
した母とともに生き埋めにする風習などがあった」(原文ママ、岩本 一九九六:七四)。
このように、子殺しが近代以前の社会では制度として根づいていたことが手際よくまとめられている。しかしながら、子殺しを実際におこなっている当事者たち
は、そのことを好き好んで調査者に語ってはこなかったようだ。これが当事者の「悲劇的な経験」(Daly and Wilson
1988:38)(ディリーとウィルソン
一九九九:七七)に根ざすものなのか、それともそれ以外の要因——たとえば、白人や植民地政府が禁止してきたので現地人の間にも「恥ずべき」慣習と見なさ
れるに至った——によるものなのかは、識者のあいだでも分かれているところである。長い間、英国の宣教師や行政官による人類学の調査マニュアルであった
『人類学における覚書と質問』(一九二九)には次のような記述があるが、これは後者(=恥ずべき慣習)の代表例である。
「子殺し——もし、社会の性別の割合[系譜法のページを示して参照指示している(引用者)]を調査しているのなら、男性あるいは女性の比率に有意な違いを
発見したら、子殺しの存在あるいはその試みがなされたかどうかという質問は必ずおこなわれるべきだろう。そして、それがどの程度おこなわれたのかについて
も[調べよ]。食人や子殺しのような、その種のケースは文明人(the
civilized)によって、非難されたりまたは処罰されたりしてきたことはよく知られるところである。それゆえ、とにかく[調査の]初期の段階でその
ような質問をすることは[結果的にデータが得られないという]失敗を招くであろう。しかしながら、ついうっかりと行われたのかもしれないそのような行為
[=子殺し]徴候が、すこしでも人々によって示唆されるかもしれないことに細心の注意を払うこと。そして[人々との]信頼関係がしっかりと築かれたなら
ば、完璧な真実(the full truth)について[人類学者は]学ぶことができるように試みなければならない」(Royal
Anthropological Institute 1929:85-86)[ ]内は引用者による補足。
岩本の説明では「普遍的」現象であったはずの子殺しが、この『覚書と質問』では、文明人により廃絶される方向に進んでいるが、彼らのあいだに、いまだ行
われている可能性があると示唆されている。そして『覚書と質問』は、現地社会における慣行を把握する人類学者は、そのようなデリケートな情報を確実に自分
の手にしなければならないと指摘する。他方「食人(cannibalism)」の調査項目に関する記述では、そのような慎重な姿勢なしに「食人——それは
頻繁か?例外的か?」という質問を皮切りに、次々とたずねるべき二一の質問項目が淡々と記載されている(Royal Anthropological
Institute
1929:215-216)。あたかも「未開人」は食人には躊躇することなく話すが、子殺しには言いよどむことがあるのだと言わんばかりである。つまり
『記録と質問』の認識では、子殺しは食人よりも調査しにくい社会的事実として認定されているわけである。
さて他方、このような努力の末に収集された可能性のある民族誌データの人口学的意義は、きわめて明確に解釈される(Scrimshaw
1984)。子殺しとは明確に「人口調節のための集団レベルでの適応とみなされることが多い」し(子殺しの性比の不均衡現象をも考慮した)「個人の包括適
応度を増大させるための手段として説明」されている(ハインド 一九八九:二二〇)。リチャード・アレグザンダー(原著
一九七九)の説明では、現生人類である私たちが子殺しをしているのは、(人間以外の)霊長類や初期の人類同様、オスの遺伝子を次世代に伝えるための基本的
な戦略のレパートリーのひとつにすぎない。
「初期の人類にあっては、[オスが]他オスの子どもを殺したり、メスにそれを捨てさせたりする傾向は、そうした行為がメスの排卵を促進し、そのオス自身の
子のためにメスの繁殖能力を温存させる場合には、つねにオスの利益になったはずである。ヒトの母親によってますます集中的となった子の保護、その期間の増
大、そして幼児期の集中的な保護や乳児の無力化と結びついて長期化した出産間隔、これらの結果として子殺しの利益は上昇し、他のオスからメスを獲得したオ
スは[前夫の]子どもを捨てることになっただろう」(アレグザンダー 一九八八:二八九)。
この論理に立てば、オスは(遺伝的な意味での)自分の子供とそれを養育するメスにはともにケアをし、自分の遺伝子をもたないメスの子供は殺すということが
遺伝的には理に適うことになる。チンパンジーのカニバリズムは日本の鈴木晃が一九七一年に報告したものを嚆矢とするが、チンパンジーはメスが群れ間を移動
し帰属した群れで発情、出産することで群れの遺伝子の多様性を確保すると言われる(Bygott 1972:410)(北村
一九八二:六二)。アレグザンダーは、バイゴットの野生チンパンジーの観察やイタリアの人類学者エトレ・ビオッカ(Ettore
Biocca)が聞き取りをしたヤノマミに幼女時代に誘拐され養育されたエレナ・ヴァレロの語りを根拠に、子殺しにおける動物と人間の進化行動学上におけ
る連続性を主張する(Bygott 1972; Biocca 1970)。
「バイゴットの観察(一九七二)からは、チンパンジーではよそもの[メス]の乳児(迎えいれたグループに父親がいない)はそのグループのオスによって殺さ
れやすいことが示唆される。たとえば南米のヤノマミ・インディアンに見られるような、共同体間の戦争や婦人の交換によって父なし子になった子どもを殺した
男(または女)の報告(ビオッカ
一九七〇)からは、このことが人類の歴史においても親による保護が[自然]選択された重要な要因であったかもしれないこと、また乳児の依存期間の延長がも
たらしたもう一つの間接的結末であったかもしれないことがうかがえる」(アレグザンダー 一九八八:二八九)[訳は一部変えた]。
人間集団において、中絶、子殺し、あるいは性交禁止は出生力を制御するという方法であることは、カール=サンダースがすでに『人口問題:人類進化の一研
究』(一九二二)という広闊な書物を著して以来よく知られている(Carr-Saunders
1922)。また現在では母親の頻繁な授乳は性交を禁止しなくても受胎機会を低下させることがわかっている。ウィン=エドワーズは一九六三年に、人類進化
におけるグループ(=群れ)内での淘汰(=進化的選択)という観点からカール=サンダースの議論をとらえなおした(Wynne-Edwards
1963)。それによると、子殺しによる出生力を制御する方法が必要とされる社会とは、利用できる資源が稀少な狩猟採集民の環境でありブッシュマンがそれ
に相当すると言っている。しかし、サン・ブッシュマンの専門家である田中二郎は、そしてクン・ブッシュマンの[未開]経済を報告したロルナ・マーシャルも
また、ブッシュマンの社会は私たちが想像する以上に資源が豊富であり、ブッシュマンの生息環境の「資源が稀少」というのは、その社会を知らない者の偏見に
すぎないと批判している(田中 一九七七、二〇〇八)(Marshall 1961)。
ところで子殺しをする動物でもっともよく研究されているのはサルである。単雄群のハーレムを形成するインドのハヌマンラングールにおいては他のオスによ
る乗っ取り時に子殺しがみられる。その際に乗っ取りオスにより、授乳期にある子供の子殺しがおこなわれ、それに引き続いてメスが発情するという。これらの
説明は、端的に言うと種は集団で進化的選択(=淘汰)するという論法では説明できず、当初は、個体数の増加による病理的な説明で片づけられていた。しか
し、その後、個体数の調整メカニズムという説明が登場し、これはその種が、個体数に見合った資源を管理しているのだという解釈に置き換わった。しかしなが
ら、もしそうだとすれば、個体群密度の高い群れにのみ子殺しが多いことになる。それに単純に個体数を調整するためであれば、メスの小さいサルや(その後す
ぐに個体群の再生産活動に加わる)若いサルを選択的に殺せばよいことになる。これらは、子殺しが、集団の利益に関わる選択(淘汰)でおこるという説明の枠
組みであった。
しかし、ロバート・トリヴァース(一九九一)は、それまで集団単位で働くと考えてられていた選択のメカニズムを、むしろ個体単位で解釈したほうがより理にかなうことを明らかにした。
「オスが殺す子の父親は自分ではない。そのオスが取ってかわったオスともおとなメスたちとも血縁が薄ければ(たいていはそういう状況にあると思われる)、
殺す子供とも血縁的なつながりは薄い。そうであれば、子殺しをはたらくオスにとってのコストは小さく、一方繁殖成功上の利益はほとんど即時に手に入る。子
に授乳中の母親は排卵せず、したがって次の子を殺すことで、自分と血縁のない子に費やすであろうメスの努力量を節約している」(トリヴァース 一九九一:
九一)(Trivers 1985:74-75)。
トリヴァースは、いくつかの生物、とりわけその中でも栄養条件がよかったり、生後に子供の世話をする傾向があったり、また個体間関係において順位制をとる
ことが見られる動物——人間もそれに含まれる——においては、生まれてくる子供の性比は1〈対〉1にならず、オスのほうが多くなるという事実を発見した。
そして、そのメカニズムを、ダン・ウィラードと協力して親の投資に見合った報酬の仮説で説明しようとした。この仮説では、一夫多妻の生物社会において子孫
の数をたくさん残すことを、生存競争に勝利したと考える。一夫多妻制の動物では、オスが社会的に優位の場合多くのメスを独占することができるために多くの
子孫をそのオスが持つことができる。だがうまくいかなかったオスの子供の将来は、うまくいかなかったメスの子供の将来よりも悲惨である。つまりオスの競争
はメスよりもハイリスクでハイリターンである。そこでその子供がどのような母親から産まれるかと考えてみると、よい条件に育った母親——社会的地位が高い
と採餌のための資源にも容易にアクセスできる——のオスの子供もまた条件のよいハーレムを形成する機会をもつ可能性をもつことがわかる。すなわち条件に恵
まれた両親からはオスが多くうまれるチャンスが増える。他方、条件の悪い母親が、条件の悪いオスの子供を産むと、そのような子供は運がわるければ一匹の子
孫も残すチャンスすらない。しかしメスの子供だと条件が悪くても——一夫多妻という条件を思い出してほしい——ハーレムに加わり子孫を残すことができる。
したがって、トリヴァース=ウィラードの仮説とは「一夫多妻の動物においては、条件に恵まれた親はオスを多く産むのに対して、恵まれない親はメスを多く産
む傾向がある」ということになる(Trivers and Willard 2002:115-122)(リドレー 二〇一四:一九三—一九五)。
さて、人間社会でも性比はオスに偏っているわけだが、動物とは異なり、それは意図的な性別をわけた子殺しによる結果であることがわかる(クラストル 二〇
〇七:二五〇)(Clastres
1972:197)。キム・ヒルとマグダレーナ・ウルタードが調べたパラグアイのアチェ(族)では、一〇歳までに殺される男児の数は一四パーセントである
が、女児は二三パーセントにおよぶという。また、両親がどちらか不在の子供が殺される確率は、両親がそろっている場合にくらべて四倍にも上るという
(Hill and Hurtado
1996:437)。これだけをみるとアチェは、意図的に男児よりも女児に偏向して殺害していると判断される。しかしながら、アチェの子殺しの第一の動機
は、死者が出た際の「殉死」なのである——この「殉死」の意味は私たちのそれとは根本的に異なることを本章第4節で示し詳しく検討する。つまり選択される
際に女児が優先されるのではなく、男児が将来の狩人になるために取っておかれる傾向があるが、それが必ずしも女児でなければならないという理由にはなって
いない(Hill and Hurtado 1996:435-436; Clastres
1972:201-202)(クラストル 二〇〇七:二五六—二五七)。
女児殺しは、出生力を制御する方法としては人類進化の研究の初期から指摘されてきたことである(Carr-Saunders
1922)。この分かりやすい人口学的説明と、人間における女児よりも男児が殺害されにくい狩猟採集民の説明——「男は狩人にならなければならない」——
は、子殺しの性別の偏りという結果において一致しているが、それを調停する人類学者も進化心理学者もトリヴァース=ウィラードの仮説をあれこれ事例に適合
させることに専念している状態で、必ずしも決定的な解決に至っていないのが現状である。
それよりも、実際に子殺しを目撃した報告者たちが直面するもっと深刻な課題は、進化モデルの思考実験とは異なり、どのようにして客観化されたデータを集
められるかということである。おまけに近年の採集狩猟民の国民国家への統合と彼らの「伝統文化」への権原の付与における様々な取捨選択——例えば首狩や戦
争や子殺しの慣行(Rosaldo 1980; Matthiessen 1969; Bugos and McCarthy
1984)は廃止され、言語や芸術や神話などの口頭伝承は文字化され継承が推奨される——のため、現在ではそれらは過去のデータの解釈、再解釈、再々解釈
しか手段というものがない。かつてそのような慣習がまだ実践されていた時代、つまりヒルとウルタード(Hill and Hurtado
1996)やピーエル・クラストル(Clastres
1972)が調査した時代には、まだ調観察が可能であった。彼らの民族誌に見られる子殺しの記述はとても婉曲的であり、あたかも読者に間接的にニュアンス
を伝えるかのような文章であることが多い。しかし、ボリビアとパラグアイ国境の近くにすむアヨレオの子殺しについて調査したポール・ブゴスとロレイン・
マッカーシー(一九八四)は、そのケースに出会った時の驚愕を隠さない。
「私たちは、女性にインタビューを始める前に、すでにアヨレオの人々と六か月いっしょに暮らしていた。私たちは、彼女らがバナナを満載した荷を頭にのせて
畑から帰ってきたり、泥壁の家の前にすわって、マットを編んだり、おしゃべりをしたりするのを見なれていた。どこの母親もそうであるように、彼女らも、赤
ん坊が病気になれば心配し、かわいい赤ん坊だと言われると喜びに顔をほころばせた。サンプルで示した女性のうちの何人かは、私たちのよい友だちになった。
私たちがエホの村に住み込んですぐ、エホは私たちに鶏をくれた。彼女は、しばしば私たちのところを訪れ、私たちに子どもがいないことを嘆いては、もし子ど
もが生まれたら絶対かわいい子に違いないと言っていた。エホが嬰児殺しをしているという話を、他の女性から聞いたとき、はじめは信じられなかった。人類学
者として訓練された者[女性のロレインのこと、引用者]にとってすら、チャーミングな友だちである人物、夫につくす妻、子どもをかわいがる母親である人物
が、自分自身の文化が忌むべきものとしている行為をするような人物だとは、なかなか信じられないものだ。それでも、アヨレオの中で過ごしたもっとも不寛容
な宣教師でさえ、赤ん坊を埋めることに慈悲を感じずにはいられないだろう」(Bugos and McCarthy 1984:512)[(Daly
and Wilson 1998:74-75)に引用された長谷川眞理子・寿一訳を参照にした]。
アヨレオにおける出生時の子殺しについてブゴスらの報告のなかにはアンビバレントな感情がみられる。ただし、子殺しが「彼らの社会」においておこる状況
は、十分に人類学者の間では把握されている。すなわち、生まれながらの奇形、先天性の虚弱状態(あるいは出産時における仮死状態)、逆子、出産間隔の短い
妊娠、双子、父親が不在や出生時死亡のシングルマザーの出産などでは、容易に子殺しがおこる。また、出生時に女児とわかった場合は男児よりも選択的に殺害
される。これは当該社会における男性への性比の偏りを生じさせる。これらの理由の多くは、調査される側の説明よりも、調査者や論文の著者による機能主義的
な説明によるものが多い。例えば、——母体ならびに社会が不用なコストを抱えないようにする社会的措置【という説明】——が行われると言われる。によるも
のが多い。言い方を変えると、ブゴスとマッカーシー(Bugos and MaCarthey
1984)が感じているような葛藤を、淡々とした科学的説明で納得する人類学者の心理的穴埋めのようにも思える。つまり、どんな悲惨な話でも、その背景に
ある社会制度による正当化が文化的慣行として埋め込まれていれば、何でも機能主義的に論じることができると言わんばかりである。ドゥーブ・クン・ブッシュ
マンの専門家であるナンシー・ハウエルの叙述は、そのことを物語る。
「女性の単独出産が慣習化している社会、もしくは単独出産が可能な社会では、母親に嬰児の生殺与奪権が与えられている。したがって、生まれた直後の子ども
の体を念入りに調べ、先天性異常の有無を見極めるのが母親としての責任なのである。……もし、赤ん坊に奇形がある場合には、その子を窒息させるのが母親の
義務なのである。私が話したクン族の人々の多くがこの赤ん坊の身体検査と、生殺与奪の判断は出産と切り離すことができないものである、と教えてくれた。ク
ン族の人々の考えかたでは、嬰児殺しは殺人に該当しない。彼らは人(zun/wa)[=クンすなわち人のこと]の人生は出生時にはじまるとは考えないから
である。クンの人としての人生がはじまるのは、出生し、名前を与えられ、村の一員として受け入れられたときなのである」(Howell
2010)——引用は(ダイアモンド 二〇一三:三〇七)(Diamond 2012:178-179) なお訳文は一部変えた。
言うまでもないことであるが、人間の集団で先天異常や異常出産はそれほど頻繁に起こることではない。にもかかわらず、伝統社会における子殺しについて人類
学者が記録し、かつ、またその正当化にさまざまな論述上の工夫を凝らしてきたということは、単純に考えると、人類学者の側に価値論的な文化的バイアスがあ
ることを示す。そのバイアスとは、子殺しは「野蛮人の風習」でありそれが文明化により禁止されて珍しいことになったが、本来、子殺しにはなんらかの意味が
あるという信念である。他方、子殺しは必要にかられた遺習であり、当事者たちも本当は放棄したがっているという主張も多くなされる。いくつかの伝統社会に
おける子殺しの記録において、当事者たちにとっても心痛む経験であり、またなるべく触れたくない経験でもあることは確かなようだ(Bugos and
MaCarthy 1984:511;ピンカー 二〇一五:七四)。
かつての幼児殺しが慣行化されていた社会の母親が、近代社会にみられる人工妊娠中絶(堕胎)の話を聞かされた時、これは(自分たちの社会とはまったく異
質の)「残酷な」子殺しであり、そのことを通して、未開社会の人たちが、近代社会の「蛮行」に怒り打ち震えることもある(次節のビティレブ島民の主張を参
照してほしい)。どのような思い込みが両者の間にあろうとも、その疑念や思い込みを解消すべく、私たちはさらなる異文化間「仮想」コミュニケーションを試
みることを忘れてはならない。
リンク
文献(→「殺人に関する考察」の文献を参照)