中央アメリカのメスティソ社会における苦悩の諸相
Body and soul among the
Central American Mestizo
中央アメリカのメスティソ社会における苦悩の諸相
Body and soul among the
Central American Mestizo
Descripción de la foto: Imagen de María
Mercedes Coroy quien usa un vestido blanco y lleva un velo
transparente blanco. (Crédito: Ámbito.com)
1. メスティソ社会における苦悩の表現 ホモ・パティエンス(受苦 的人間)
人は病いにおちいり病いを苦しむ。受苦的な存在と共に生きることは人間の宿命である。私たちは他者の「苦悩」(distress)を体験で きないが、それを感じることはできる。あるいは、そのように私たちは信じている。他者に対して苦悩を表現すること、そして他者の苦悩に居合わせること。こ のようなことは病気や災難との遭遇を通して日常の生活のなかで頻繁に経験する。どのような些細な苦悩を取り上げてみても、そこにはその個人、家族、社会に 関することがらが盛り込まれている。私たちは他者の苦悩を「拾い上げ」、その理解を他者に「投げ返す」ことによって、その苦悩に関わってゆく。
ここでは、中央アメリカのメスティソ社会に見られる人びとの苦悩あるいは病気の民衆的表現のひとつであるネルビオスを例にとって、この問題 をより具体化させようと思う。他者の苦悩とその表現に出会った際に生じるさまざまな解釈を通して、その意味の多様性について考える(1)。
1.1 苦悩の諸事例
ネルビオス(nervios)は、スペイン語で「神経」をさすネルビオ(nervio)――ポルトガル語ではネルボ(nervo)――に関 係することばであるが、ここで取り扱うものにはアタケス・デ・ネルビオス(ataques de nervios――神経の侵襲)あるいはたんにアタケスと呼ばれるものもふくまれる。メスティソ社会においてこれらの一連の用語は、ある種の身体の状態ひ いては一種の病気とみなせる。ネルビオスは、各個人においてその様態が多様でまた地域によっても差が認められるので、実際それを研究する者は多様に解釈し てきた[Davis and Guarnaccia eds.,1989]。
具体的にどのような体験をさして人はネルビオスというのだろうか。コスタリカの村落の調査事例[Barlett and Low,1980]と米国に住むエルサルバドル難民の女性事例[Guarnaccia and Farias,1988]から検討してみよう。
【事例1】 「医者は、わたしにネルビオスを伴った重い病気だと言いました。わたしは、自分が死にそうになっていたのに、たんに頭の中の病気だと言われたことに、と ても驚いてしまいました。サン・ホセのまちでは、卵やそのほかの食べ物を摂ることはできますが、それを食べると、わたしの胃袋がひっくり返ってしまうよう な気がします。頭や胸や両足が、恐ろしく痛くなり、とても恐ろしい気持ちになります。この病気が、いったい何であるのか、わたしには解りません。医者は、 療養のために転地する必要があり、できる範囲で良いから出かけるように、と言います。‥‥」(女性・五〇歳代)[Barlett and Low,1980:544]
このケースは、ネルビオスになった原因については語られていない。話者はネルビオスが「からだの病気」であると言う。ネルビオスになると 手足の感覚がなくなり恐ろしい感じになる。だから、医師に「頭の中の病気」と言われたとき、この女性は当惑する。医師は同時に転地(気分転換?)をすすめ ており、彼女の訴えを心身症状として理解していることが示唆される。
【事例2】 「わたしは、とてもひどいネルビオスに二度なったことがあります。それはわたしの子供たちが、死にそうになったときです。最初は息子が馬から落ちて、死 にそうだと言われたのです。わたしは倒れて、動けなくなりました。――手足の感覚がなくなったのです。感覚がなくなったまま手や足を動かしました。人びと は、わたしに民間薬をくれました。そして、わたしは町に行き医者は注射を打ち、薬を飲ましてくれました。わたしは治りました。 二度目は娘のアナが馬から落ちたときです。使い走りの子供がやってきて、アナが馬から落ちたと告げたとき、わたしの肌はこの恐ろしい感じに襲われたので す――それは膝から始まり、だんだん上に登ってきて、頭にまで達しました。病院で気がつくまで、わたしは何も覚えていません。娘は頭の三カ所が切れてお り、病院に四日いました。わたしは病院には一日だけ入院していました。」(女性)[Barlett and Low,1980:544]
ここで、ネルビオスになったことと自分の子供の事は関連づけて説明されている。だがこの文脈ではネルビオスは病気というよりも、それらの ショックに伴う心身の喪失を表現することばになっている。
先の事例に比べると「心身の喪失」と表現するにはあまりにもマイルドな「症状」である。たんなるふさぎ込んだ状態と解してもおかしくな い。我々には、先のものと同じネルビオスとみなされていることのほうが驚きである。
【事例4】 「タバコ(の作付)は私にいろいろなネルビオスを引き起こします。まず銀行に融資を申し出なければならないし、苗床を作らねばならない。(そのために)降 雨を期待することは難しいし、そしてけっこう危険な農薬を扱わねばならないのですから。」(男性――文中の丸括弧は池田)[Barlett and Low,1980:546]
バーレットらが紹介する諸事例はこのケースを除いてすべて女性のものである。この男性のネルビオスは、もはや身体症状としての「ふさぎ込 んだ状態」というよりも、仕事の辛さや生活における苦渋を表現することに主眼がおかれている。
【事例5】 「私は本当に分かりません。夫には問題がないのです。彼は酒も飲まないし煙草も吸いません。家では本当に静かなのです。わたしは、どうしてそう[ネルビ オス]なのか分からない。自分自身に聞きます、どうして? わたしがこの病気になることなんて、ありえません。なぜなら、わたしはひどい生活をしていない からです。夫が妻に対してひどい生活を強いるなら、そのとき問題は起きます。けれど、私の夫はそんなのじゃない。彼はいつもここにおり、私たちは決して言 い争いません。なのに私は、いつもネルビオスになるのです。」(女性、三十五歳)[Guarnaccia and Farias,1988:1227]
米国で働くこのエルサルバドル難民の女性は、どうしたらネルビオスになるかという、生成の問題を語っている。そのなかでも焦点が当てられ るのは女性の地位についてであり、「夫が問題」「夫が酒や煙草をのむ」「夫が妻に対してひどい生活を強いる」ことに現れている。ここにはメスティソ社会に ついてしばしば指摘されるマチスモ(machismo)と呼ばれる「男性優位イデオロギー」が、実生活のなかでどのように表出するのかということが示され ている。マチスモについては後ほど触れる。
2 研究対象としての苦悩
2.1 苦悩のイディオム
専門研究者たちは、ネルビオスを、ひろくラテンアメリカのメスティソ社会を中心に用いられる「民俗病」(folk disease)あるいは「民族医学的概念」(ethnomedical concept)というカテゴリーにおいて把握した。
ネルビオスを報告した近代医学者、心理学者、人類学者はそれを、「不定愁訴」「文化結合症候群」「精神病理的反応パターンおよびヒステリー 的人格」「急性分離反応」「急性分裂病的動揺」「詐病」「急性人格転換症状」「自殺発作」「多動症的なエピソードのある人格転換反応」「分裂病的障害」 「文化的に受け入れ可能な苦悩症状」などと解釈した。まさに病気の博物館である。 他方、人びとが心身の状態を表現することばは、ネルビオス以外にもたくさんある。コレラ(c<lera)、ビリス(bilis)、エンビディア (envidia)、ムイナ(muina)、ススト(susto)、エスパント(espanto)などがそれである。これらは、私たちの「感情表現」語 --例えば、怒り、悲しみ、憂鬱、など--と一対一の翻訳をすることはできない。むしろ、ミード[1976]が言うサモア人のムス(musu)、ギアーツ [1987]によって人類学者に膾炙したバリ人のレク(lek)のようにその地域(=文化?)に独特な表現であり、人びとによって共有されている心身の状 態・感情体験なのである。
我々の関心に引きつけるとこの種のことばは、人類学者ニッチャーにちなんで、人々に了解された苦しみを表現するという謂で「苦悩のイディオ ム」(idiom of distress)[Nicher,1981]と名づけてもよいかもしれない。このような概念でくくることの効用とは、これらのことばを身体に対して貼り 付ける病名のアナロジーで考えるよりも、身体の外部と密接に関わる人間の存在様式を社会的次元に拡張して考えることができる点にある。
このような考え方は唐突にでてきたのではない。米国への移民や難民の受け入れにおいて「あたらしい社会にたいして適応できない患者」のなか に「身体表現性障害」(somatoform disorder)を訴えるものが増えてきたという臨床的理由。それと独立ないしは呼応するかたちで一九八〇年代以降の米国人類学会などを中心にした「感 情の人類学」や医療人類学領域における「文化と抑欝」という研究テーマの隆盛という背景があったのだ。
人類学者にとって「苦悩のイディオム」研究は、きわめて挑戦的な分野である。それは、文化的環境と個人の関係が、すなわち広義の社会関係が 身体を媒介して表象されるからであり[ダグラス、一九八三]、医療における実践と文化人類学のあり方が試されるフィールドであるからだ。
2.2 「神経」の意味論
医療にたずさわる研究者がネルビオスを「民俗的な」病気のラベルとして貼り続けることには無理からぬところがある。それは、人びとが治療を 求めて医療機関を訪れるからである。人びとの治療要求とそれに対して病気を同定し治療的に関与してゆく運動のなかでネルビオスが「病気」として実体化して ゆくことは当然として予想される。だが、先の事例でみたようにネルビオスという身体の状態を表現することばは極めて多様であり、また多義的である。ホン ジュラスの山岳地方のメスティソ村落で調査していた私自身の視点からみてもそれを病態として理解するには抵抗がある。
ネルビオスは「精神の変調の状態をあらわすの人びとの用語」であり「ネルビオスの表出のパターンには、ネルビオスになった人の個人的・家族 的・社会的な経歴となんらかの関係がある」ということは経験的に言えそうである。だが、農村でのネルビオスのエピソードは、現代医療の対象圏外におかれ た、単なる人びとの「気分の変調」として取り扱われ、医療の対象として問題化することなくすごされている。フィールドでの経験を私は次のようにノートに記 したことがある。
イーラ(hirra)あるいはコレラ(c<lera)は、怒りや激怒を表わす状態ないし病気(enfermedad)と考えられ ている。イーラになると、人は忍耐が欠けてきて、時に人を殺(あや)めることもある。病名としてイーラを使うとき、それは「ネルビオスの病いのひとつであ る」([hirra] es una enfermedad de nervios)と表現される。「ネルビオス」は、我々のいうところの「神経質」あるいは「気がたっている」状態である。これは、ふつうの人びとが一過性 に経験する感情の状態あるいは病名である。「気むづかしい」人を表現するのに使われるネルビオーソまたはネルビオーサは彼らの常套句である。
ネルビオスは、何らかの心身(=身体)の変調であるにもかかわらず、人びとの言うところの「狂気」ではない。ネルビオスを狂気との対比のな かでみるとどうであろうか。 ネルビオスは、人びとにとって「狂気/狂人」(locura/lunatico)ではない。
「狂気」(lunatico)とは、「月 luna」が、その姿を変えるように、人の性格が周期的に変わっていく、そのような情動をいう。ネルビオスが一時的な状態であるのにたいして、狂気は固定 的である。だから「狂気は治らない」。ただし例外もある「呪術」(hechicer<a)による狂気だけは回復が可能である。
狂気もネルビオスも共に、時間を遡及してなんらかの道徳的原因について言及されることはない。狂人というラベルを貼られた人に対しては回り の人びとは「哀れみ」(lastima)の感情で接するべきだと人びとは言う――これは公的な意見としては誰もが同意するが、実際は忌避や嘲笑ときには恐 怖の対象になる。だがネルビオスになることに対して誰もそのような憐憫の情を持つべきだと主張する者はいなかったし、実際そのようなことも見られなかっ た。
ネルビオスは、一方では神経(ネルビオ)という身体の器官のひとつの病いをさしながら、他方では「神経質」という訳語で与えられる気質のよ うなものであった。この場合のネルビオ=神経とは生物医学的な意味における神経系のことではなく、そのような気質を形づくると人びとによって考えられてい る器官のことである。人びとはネルビオスが「気質のようなもの」と「神経という実体」が相互に関係するものと考えているのか、あるいは「気質のようなも の」と「神経」の統一体と考えていたのかは不明である。ただ後者のような言及はなく、前者の二つの意味を彼らは会話の中で使い分けていたというのが私の印 象である。
別の角度から考えてみよう。人びとによるとネルビオスは誰でも起こりうる。だが、それはネルビオスになり易い人間の傾向を否定するものでは ない。神経すなわちネルビオが「弱い」ことと「ネルビオス」という状態(あるいは病気)になることを関連づけて言及することも広くおこなわれていた。
では、人びとにとって「弱い」とは、どのようなことだろうか。人びとにとって「弱い」(debil)ということばは反対語としての「強い」 (fuerte)との対比の中で考える。また、この一組みのセットは身体の壮健さに関する「わるい」(malo/-la)/「よい」(bueno/- na)という別のセットと意味論的にはオーバーラップする。例えば、血液の属性が「よい」(=病気になりにくい)あるいは「わるい」(=病気になりやす い、あるいは病気そのもの)と言われるときには、それは同時にそれぞれ「強い血液」(sangre fuerte)と「弱い血液」(sangre debil)が含意されている。血液がこのような属性で分けられることは、男女という性差や人びとが考える「遺伝」(herencia)という面からも説 明される。身体的な壮健さにおいて、男は女より「弱い」ものであり、生まれながらに「弱い血」をもつ。
以上は「強い/弱い」ということを先天的にあるいは固定的にみる見方であったが、それが同じ個人において盛衰するという見方も他方にある。 例えば「弱さ」(debilidad)という用語が、身体が一時的にだるく疲れた状態や病気を意味する。この原因となるのは、大人では「働きすぎ」や「考 えすぎ」であり、また子供では、栄養(nutrici<n)の不足によっておこる。子供は、ある種の病気、例えば、ススト(susto)によって身 体がだるくなる、虚弱状態になることはしばしば見うけられる。スストとは、びっくりした拍子に魂が抜け落ちて、元気がなくなり、病気になりやすくなること である。逆に、日頃の「養生」(cuidado)によって血液を「強く」することも可能である。工業医薬品の「滋養の飲み薬」の類を飲む、野菜を多く摂る ことがそれにあたる。
このように「弱さ」の概念は、まず先天的な決定論――例えば大人に対する子供、男に対する女、「遺伝」――の大枠の上に、後天的な操作に よって「強く」したり、病気によって「弱く」なったりすると説明されるのである。
3. ネルビオスの生成
3.1 欲望と苦悩
メスティソ社会における諸地域の報告をひもとくと、ネルビオスになる多くは女性である。このことは先に述べたように、男性が「強く」、女性 が「弱い」という、人びとが規定する身体のあり方と無関係ではない。ネルビオス生成の因果関係を説明したいという欲望に駆られて近代医療の言説を援用し、 ネルビオスのしめす身体症状がいわゆる「身体化」――「精神的ストレスや葛藤を身体症状へと変換する防衛機制」(2)――であると解釈し、女性のネルビオ スを生成させた「精神的ストレスや葛藤」がジェンダーの非対象性によるものであるという説明について考えたい。
すでに事例5で指摘したように、男性が女性を暴力性をもって支配するマチスモの論理の中にネルビオスが生成するということを、エルサルバド ル難民の女性は経験的に知っていた。メキシコのナワ系インディヘナ社会では、内に向かう怒りがムイナという病的な状態を生じさせると人びとは考えている。 そこでムイナは男性よりも女性のほうがなりやすいという。なぜなら「男は欲求不満を友人や女[つまり妻]を殴ることによって解消できるが、女はそれができ ない」からだと説明される[Madsen,1960]。
むろん男性の暴力行使と虐待がマチスモの本質であるという表現は同語反復の域をこえない。むしろその維持がなにゆえに可能なのか、あるいは どのようにして再生産されているのか、に興味を持たざるをえない。事実、男性の支配はより象徴的な次元にまで拡張されており、その欲望を貫徹するために具 体的な手管すら用意されている。例えば求愛中の男の女に対する甘い誘惑や誉めそやしがそれである。マチスモという欲望系における男性の権力の再生産のため には、セックスを通しての支配を貫徹し、その結果女を「孕ませる」ことがなされねばならない。実際、男性同士の会話の中で男性が女性を支配した戦果の報告 として孕ませた女性と子どもの数を誇らしげに語る場面に遭遇することは別に珍しいことではない。他方、男性がいかに「家畜」のように欲望を発散させ、女性 がいかなる迷惑を被るのかという主張もしばしば耳にする。
このような社会的状況に想いを馳せるとき、民話あるいは伝説(時には実話)として語られるジョロナの話は非常に示唆的である(3)。ジョロ ナ(la llorona)についての語りはいくつもの変種があるが、基本的なあらすじは次のようなものである。
ジョロナ(泣き女)は、もとは貧しい[インディオや農家とも]女であり、愛人とのあいだに何人かの子供(庶子)をもうけていた。愛人が彼女 を顧みなくなったとき[あるいは結婚への希望が打ち砕かれたとき]、彼女は自失のうちに自分の子どもたちを川で溺れさせ殺してしまい、自分も死ぬ。彼女の 死後、亡霊となった彼女は毎夜子どもたちを探しまわり泣き叫ぶという。彼女は長い髪と白い装束をまとった美しいいでたちであらわれる。男たちは彼女に魅惑 され、彼女の後をついてゆき、彼らを危険な場所[例えば川の深みあるいは崖]に連れてゆく。翌朝、男たちは死体となって発見されるのである [Horcasitas and Butterworth,1963]。
ジョロナはメスティソ社会における女のあり方の極北に位置する。ジョロナの物語は現実の社会の誇張された反映である。むろん日常生活では子 どもは殺されず虐待もされない。また女性本人が自殺することもない(4)。そのようなことが成就されているのは抑圧という反世界においてである。だから ジョロナはすべての人びとに不気味に映る。くり返すが亡霊としてのジョロナは、男の欲望の対象としての究極の女であるといえる。長い髪と白い服は純潔とし ての処女を暗示する。処女の征服は、女の身体に拭いきれない刻印をしるすことによって男性の名誉となる。彼は「女の最初の主」(primer duen~o de la mujer)になるのだ。しかし、彼は女に忘我するほど夢中になってはならない。でないと、欲望の深みにはまり自らを屍として曝すことになるのだ。現実の 世界で女を搾取しコントロールすることに成功した男が、抑圧の反世界ではジョロナという超女性の罠にかかり確立した支配を失墜させるばかりでなく命すら 失ってしまう。ジョロナはその点で男性にとっての究極のアブジェクト(嫌悪すべきもの)となる(5)。
¿Quién es la Chingada? Ante todo, es la Madre. No una Madre de
carne y hueso, sino una figura mítica. La Chingada es una de las
representaciones mexicanas de la Maternidad, como la Llorona o la
"sufrida madre mexicana" que festejamos el diez de mayo. La Chingada es
la madre que ha sufrido, metafórica o realmente, la acción corrosiva e
infamante implícita en el verbo que le da nombre. Vale la pena
detenerse en el significado de esta voz. = Paz, Octavio, EL LABERINTO
DE LA SOLEDAD, 1950.
民話では、まずマチスモの餌食になった女性が死後亡霊となって男性そのものを抹殺するという一種の復讐を敢行する。しかし、現実の世界で は、女性は生き続けねばならず男性支配から抜けでることができずに身体化という病気の中に「逃げ込む」。あるいは身体化をもって「抵抗する」[ロック、一 九八三]。ネルビオスやムイナは、ラテンアメリカにおける男女の権力関係に基づく性役割の差異のもとでの女性の「苦悩」を表出していることになる。
このような解釈は他の事例をも眺めるかぎりにおいては唐突で牽強附会な見解に映るかもしれない(6)。しかし、身体化の原因がその患者を取 りまく外部環境によるものであるとするならば、メスティソ社会における患者=女性のおかれた位置に対する配慮は不可欠である。問題はその原因の範囲をどこ まで拡張するか、である。
3.2 変貌する苦悩
メスティソ社会において、ネルビオスは、その人がおかれている状況から発せられる「苦悩のイディオム」であることは別の観点からも指摘でき る。わずかな事例からも分かるように、人びとはネルビオスを通して別の「何か」を語っている。したがってネルビオスの諸事例を山のように集積し、そこに一 貫した「民俗的病いの論理」を見いだそうとしても徒労に終わるだろう。ネルビオスは、人びとがそれを通して苦悩ひいては生活そのものを語るある種の容器= 媒体みたいなものだからだ。
苦悩のイディオムとは、ある苦悩の状態を言語化し意識化する作用をもつ。その意味では、特定の文化や社会が「苦悩する人」にたいして、社会 に容認されたかたちでその表現形式――ここではネルビオス――を提供する。自分たちが構築しているネルビオスという表現の網のなかに、人びとは入って行き ネルビオスになる。
だがネルビオスの意味は常に同じところにとどまっているわけではない。例えば、ネルビオスが治療の対象となり社会が医療に対してその治療を 期待し、またネルビオスになった「患者」が医療機関に吸収されてゆくという医療化(medicalization)を通してそれは変貌してゆく。近代医療 の普及は、ネルビオスを精神的な疾患として位置づけており、コスタリカでは、それがネルビオスの社会的意味を徐々にではあるが変容させている[Low, 1988]。
ただし、この過程は、ネルビオス=文化的伝統、精神疾患=制度的近代化という二つの体系の単純な競合の結果ではない。なぜなら、事例1でみ たように現地の医師もネルビオスの患者との相互了解に立ち、そのことばで説明している。さらにネルビオスに効果のある工業医薬品――神経を強力にする! ――すら用意されている。ネルビオスとは、文化という実体が人びとの思念と感情を拘束する静態的な「文化結合症候群」(7)のひとつなのではなく、医療の 対象になりネルビオスに効く商業医薬品を利用しながら生活している人びとの動態的な現実なのである。
3.3 苦悩とわれわれ
今まで述べてきた議論ははたして中央アメリカのメスティソ社会を研究する者それも「文化における心身症状」という問題領域に関心のある人間 だけに向けられているだろうか。答は否である。比較というレンズは、それ通して我々の生活の常態を特殊な像として結ばなければ意味がない[太田、一九九 三](8)。 我々の社会にはネルビオス「のようなもの」があるだろうか。一見そのようなものは見あたらないようだ。しかし日常生活の中で人びとの会話にしばしば登場 する「自律神経失調症」(autonomic dysregulation)はどうだろう。神経症の多様な身体的表現である不定愁訴に付されるこの生物医学的「病名」は、わが国の医療者が好んで利用す る身体化のラベルとして機能しているのが現状だ。専門医が強調するように、この診断の際には「器質的」疾患を極力除外することに神経が注がれる。ところ が、それが患者として人びとが理解する「病気」においては、「自律神経」(=器質)という実体が「病んでいる」と了解されていることがほとんどなのであ る。
まさに現代日本の治療者は「身体化」というラベルを患者に意識させ、「身体」を癒すことを通して「こころ」を癒そうとしているのである。あ るいは我々にとって両者を区分することなど、たんなる空虚な遊戯にすぎないのかも知れない。そして、この奇妙なすれ違いにもかかわらず何の問題もなく、こ の病名が日々再生産され続けているのである。これは人類学者にとって驚き以外のなにものでもない。
確かに「自律神経失調症の患者」は生物医学によって管理されている。にもかかわらず、その意味了解について言えばそれは別の世界に住んでい るようなものである。医療を提供する側の概念である自律神経失調症は、人びとによって換骨奪胎され現代日本における苦悩のイディオム=意味の容器としての 地位を確立したのである。だからこそ、自分の「自律神経失調症」を語る人びとの話のなかには、人びとのさまざま生活の諸相が垣間見える。
同様なことは中国においても言える。米国精神医学会の診断規準DSM-Ⅲに対して、中国の精神科医たちが「神経衰弱」 (nerasthenia)という診断記述への配慮がないと批判した[Kleinman,1982]。これは中国文化における「神経」がわが国における 「自律神経」と同じような取り扱いを受けていること、すなわち病気全体を器質疾患に収斂させる文化的な性向を如実に物語る(9)。そして、中国における実 生活においても「神経」という概念は病気以上の意味をもつイディオムであることをクラインマン[一九九二]は豊富な事例に基づいて描写している。 比較という方法は両者の差異を通して、個々の内部における力の不均衡の様態を認識論的に暴露する。そして、比較は新たな均衡点を模索することを我々に要 求するのだ。苦悩のイディオムは世界に遍在している。あとは我々がそれをどのように問題化し、他者のイディオムが我々とどのような関係にあり、どう関与す るかということにかかっている。
【初
出:クレジット】池田光穂、「苦悩を表現すること」の意味−ネルビオスとラテンアメリカ社会,からだの科学,151 号,pp.18-23 ,1990
年3 月。後に、『現代人類学を学ぶ人のために』[共著]米山俊直編,世界思想社,(担当箇所:10. 苦悩と神経の医療人類学,pp.205-221
),1995 年3 月に収載。
【注】
(1)本章は、池田光穂「『苦悩を表現 すること』の意味」『からだの科学』一五一号、一八-二三頁、一九九〇を下敷きにしている。だが解釈や 主張は旧稿とはほとんど異なったものになった。理由は筆者の見解と立場の変化の一言につきる。興味のある方は、旧稿をU・エーコ(谷口勇訳)「原稿の作 成」[『論文作法』而立書房、一九九一、所収]を参照しながら、その変化について検討していただきたい。
(2)柏瀬宏隆「身体化」『増補精神医 学事典』弘文堂、一九八五による。
(3)ジョロナについては旧稿[↓注 (1)]を読みコメントしていただいた黒田悦子先生からうかがった。しかしジョロナのテクスト読んで当初 これがどのように関連するのか理解できなかった。その三年後にフィールドを再訪したときに、かつてのインフォーマントである友人が、当時ジョロナと遭遇し 死にそうになったプロテスタント(!)の牧師の「実話」をその現場で臨場感溢れんばかりに話してくれた。だが又しても私はそのことをあまり気にせず再び うっちゃっておいた。今般ジョロナと欲望について考えてみた際に先のコメントの示唆することがやっと自覚できるようになった。職業として文化人類学を教え る人間にとっては情けない話ではあるが、これを読んだ学生には他山の石として、あらゆる資料や体験を関連づけて常に考えることの重要性を改めて確認してい ただきたい。
(4)ここで現実のメスティソ社会にお ける自殺率のデータを提示しても論証にはほど遠い。だが参考までに、コスタリカ(一九八三)の人口十万 人に対する自殺による死亡率(実数換算)は五・四、殺人は三・九である。ちなみに日本(一九八九)では自殺一七・三、殺人を含むその他の外因は二・八、米 国(一九八八)ではそれぞれ一二・四と一〇・二である。(Pan American Health Organization(PAHO),1986,"Health Conditions in the Americas,1981-1984(I)",PAHO,p.211.厚生統計協会『国民衛生の動向』一九九一、四二二頁)。
(5)フィールドで私が聞いた、女性へ の性的魅力と恐怖のもうひとつの物語としては女性の妖怪ドウェンダ(duenda)の話がある(池田光 穂「いのちの民族学(10)もっと恐い話を‥‥」『看護実践の科学』一九九二年十月号、五二-三頁)。いたずら者として男の妖怪ドウェンデは女性に横恋慕 し、彼女に近づく男性を邪魔をする存在として語られるが、ドウェンダは美しくエロティック――セックスをせずに男を快楽に溺れさせる――で、正体を明かす と今度は男性を恐怖のどん底に落とす存在である。この話は私にクラパンザーノの著作(↓参考文献)に出てくる女の精霊アイシャ・カンディーシャを思い起こ させる。
(6)ラテンアメリカにおける女性解放 の思想は、男性中心的なそれまでの歴史的ビジョンを完全に転倒させる。歴史は「白人男性によるインディ オ女性の征服」にはじまり「両性関係に暴力的要素をもち込んだマチスモの伝統は‥‥男性優位のみならず、独裁性、大土地所有制、外国の支配と干渉、軍事政 権など権威主義的現象と結びつい」ているのだ。国際婦人年メキシコ会議(七五年)は「ラテン・アメリカの多くの女性が貧困と不正義からの解放と、これを再 生産するマチスモ的な国際・国内秩序の変革を求め」るという行動指針を提起した。それは、世界認識が変わることが世界に対する関わりをどのように変える か、それがどのようなところに結びついてゆくのかについて我々に教える。(乗浩子「女性解放」『ラテンアメリカを知る事典』平凡社、一九八七、二〇九-一 〇頁)
(7)この用語と概念を育んできた比較 精神医学領域からも良質で総合的な研究[J・レフ『地球をめぐる精神医学』星和書店、一九九一]が公刊 されているいるが、その著作でさえ「文化」に対するイメージ[同書、四八-九頁]は極めて静態的である。
(8)R・ベネディクト(米山俊直訳) 『文化の型』社会思想社、一九七三(原著は一九三四)は、例のプエブロ=アポロ型、クワキウトル=ディ オニソス型を「論じた」ことで有名な古典であるが、私は偏見(こんなもの古くさい!)に捕らわれていてよく親しむことはなかった。だがM・カフリー『さま よえる人ルース・ベネディクト』(福井七子他訳)関西大学出版部、一九九三を読み、作品としてのこの著作が彼女の文化人類学者としての文化概念への挑戦、 そして女性としての生き方と価値の創出に深く根ざしたものであることを知るにつけ認識を新たにし、このテクスト読解が以前よりも面白くなった。同様の示唆 は太田好信さんご本人および彼のいくつかの論文より学んだ。読者の中で、先生に「いい本だから読みなさい」とすすめられて手にとってみても「分からず」途 方に暮れている学生がいたら、ひとまずその著者の経歴や評伝を読んで、独断でもいいから著者の生きてきた生活とその作品を結びつけるように読むと意外に局 面が打開できるかもしれません。
(9)大貫恵美子『日本人の病気観』岩 波書店、一九八五、一一八-一三七頁は、この傾向をレヴィ=ストロースから構想を得て物態化 (physiomorphism)の用語をもって身体化概念を批判しつつかつそれをも包摂する概念の確立に向けた議論をしている。この可能性と限界を考え ることも我々にとっての課題である。
【参考文献】

| La Llorona es una
canción zapoteca escrita y nacida en la comunidad zapoteca del istmo de
Tehuantepec, Oaxaca. Cuenta la historia que un joven de Tehuantepec fue a una fiesta en la comunidad vecina llamada Juchitán y ahí conoció a una chica tan hermosa que salía de la iglesia vistiendo el famoso traje regional istmeño llamado huipil. Por un tiempo se esforzó para conquistar a la joven. Después consiguió la aprobación de los padres para casarse con ella. Pero los vientos de la revolución soplaron en Oaxaca (1911/1912) y antes de irse a la guerra, le dijo algo como esto: “ʀᴇᴄᴜᴇʀᴅᴏ ᴇʟ ᴅɪ́ᴀ ϙᴜᴇ ғᴜɪᴍᴏs ᴀʟ ʀɪ́ᴏ ʏ ʟᴀs ғʟᴏʀᴇs ᴅᴇʟ ᴄᴀᴍᴘᴏ ᴘᴀʀᴇᴄɪ́ᴀɴ ʟʟᴏʀᴀʀ, ᴄᴏɴᴛɪɢᴏ ʟᴀs ɴᴜʙᴇs ᴅᴇ ᴍɪ ᴄɪᴇʟᴏ ɴᴏ sᴏɴ ɴᴀᴅᴀ, ɪɴᴄʟᴜsᴏ ᴇʟ sᴏʟ ᴄᴏᴍᴘɪᴛᴇ ᴄᴏɴ ᴛᴜ sᴏɴʀɪsᴀ. ʟᴀ ɢᴜᴇʀʀᴀ ᴍᴇ ᴇsᴛᴀ́ ʟʟᴀᴍᴀɴᴅᴏ ᴘᴏʀϙᴜᴇ ʟᴀ ᴘᴀᴢ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ ᴘᴀɪ́s ʜᴀ sɪᴅᴏ ʀᴏʙᴀᴅᴀ. ᴠᴏʟᴠᴇʀᴇ́ ᴀ ᴛɪ́ ʏ ᴘᴏʀ ɴᴜᴇsᴛʀᴀ ғᴜᴛᴜʀᴀ ғᴀᴍɪʟɪᴀ. ɴᴜɴᴄᴀ ᴅᴇᴊᴀʀᴇ́ ᴅᴇ ᴀᴍᴀʀᴛᴇ, ᴇɴ ᴇsᴛᴀ ᴠɪᴅᴀ ʏ ᴇɴ ʟᴀ ᴍᴜᴇʀᴛᴇ”. Finalmente el día de partir llegó y cuando él se despedía de ella, el llanto corrió por sus ojos y los suspiros de dolor invadían el rostro de su amada. Mientras hablaba con ella le tomaba ambas manos, al mismo tiempo que la limpiaba con las suyas las lágrimas que caían por las mejillas de su esposa y entonces la llamó “llorona” porque ella no paraba de llorar, sabiendo que quizás no volvería a ver a su esposo. Besos y promesas volaron por el aire y él juró que volvería por ella de la vida y la muerte con impunidad total. Ella también prometió esperarlo sin importar lo que sucediera. Muchas personas de la época conocían a la pareja y se consternaron por ellos. El joven se fue a la guerra pero nunca regresó. Tiempo después un amigo mutuo de ellos regresó al pueblo y le dijo: tu esposo fue alcanzado por las balas y las heridas eran tan terribles que fue imposible salvarlo. Pero mientras agonizaba me pidió que te dijera que siempre te amará y que por favor lo perdones. Te entrego la carta que me dio para tí. Extractos de esa carta decían: "sᴀʟɪ́ᴀs ᴅᴇʟ ᴛᴇᴍᴘʟᴏ ᴜɴ ᴅɪ́ᴀ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴄᴜᴀɴᴅᴏ ᴀʟ ᴘᴀsᴀʀ ʏᴏ ᴛᴇ ᴠɪ́ ʜᴇʀᴍᴏsᴏ ʜᴜɪᴘɪʟ ʟʟᴇᴠᴀʙᴀs ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ϙᴜᴇ ʟᴀ ᴠɪʀɢᴇɴ ᴛᴇ ᴄʀᴇɪ́ ᴇɴ ᴇʟ ᴄɪᴇʟᴏ ɴᴀᴄᴇ ᴇʟ sᴏʟ ᴍɪ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ʏ ᴇɴ ᴇʟ ᴍᴀʀ ɴᴀᴄᴇ ʟᴀ ʟᴜɴᴀ ʏ ᴇɴ ᴍɪ ᴄᴏʀᴀᴢᴏ́ɴ ɴᴀᴄᴇ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ϙᴜᴇʀᴇʀᴛᴇ ᴄᴏᴍᴏ ɴɪɴɢᴜɴᴀ. ᴀᴜɴϙᴜᴇ ᴍᴇ ᴄᴜᴇsᴛᴇ ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ɴᴏ ᴅᴇᴊᴀʀᴇ́ ᴅᴇ ϙᴜᴇʀᴇʀᴛᴇ. ¡ᴀʏ, ᴅᴇ ᴍɪ́ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ! ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴛᴜ́ ᴇʀᴇs ᴍɪ xʜᴜɴᴄᴀ ᴍᴇ ᴘᴇᴅɪʀᴀ́ɴ ᴅᴇᴊᴀʀ ᴅᴇ ϙᴜᴇʀᴇʀᴛᴇ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴘᴇʀᴏ ᴅᴇ ϙᴜᴇʀᴇʀᴛᴇ ɴᴜɴᴄᴀ, ɴᴏ ᴄʀᴇᴀs ϙᴜᴇ ᴛᴇ ᴄᴀɴᴛᴏ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴛᴇɴɢᴏ ᴇʟ ᴄᴏʀᴀᴢᴏ́ɴ ᴀʟᴇɢʀᴇ, ᴛᴀᴍʙɪᴇ́ɴ ᴅᴇ ᴅᴏʟᴏʀ sᴇ ᴄᴀɴᴛᴀ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴄᴜᴀɴᴅᴏ ʟʟᴏʀᴀʀ ɴᴏ sᴇ ᴘᴜᴇᴅᴇ, ɴᴏ ʟʟᴏʀᴇs ᴘʀᴇɴᴅᴀ ϙᴜᴇʀɪᴅᴀ ᴛᴇ ᴇsᴘᴇʀᴀʀᴇ́ ᴇɴ ᴇʟ ʜᴏʀɪᴢᴏɴᴛᴇ ᴄᴀᴅᴀ ᴍᴀᴅʀᴜɢᴀᴅᴀ." Está de más decir que ella lloraba todo el tiempo por esa carta y nunca volvió a casarse porque esperaba reunirse con su amado en el paraíso y cumplir con su promesa. El bebé de ellos nació una semana después de la noticia. Cada 30 de octubre cenaban juntos. Una esposa y un hijo en la tierra de los vivos y un esposo del reino de los muertos... hasta que la gran águila los juntó nuevamente. El tiempo pasó y la historia fue escrita como una canción folclórica local y ha sobrevivido todo este tiempo. Entonces, esta hermosa canción no trata acerca de la leyenda de la llorona azteca engañada que ahogó a sus hijos en el río. La Llorona zapoteca es una historia de amor, una historia triste, pero una bella historia de amor. https://www.facebook.com/leerescrecerok |
ラ・ジョロナは、オアハカ州テワンテペック地峡のサポテカ・コミュニ
ティで作られ、生まれたサポテカの歌である。 物語は、テワンテペック出身のある青年が隣のフチタン集落で開かれたパーティに出かけ、そこで教会から出てきたフイピルと呼ばれる有名な民族衣装を着た美 しい少女に出会った。 しばらくの間、彼は懸命に彼女を口説こうとした。そして、彼女の両親の承諾を得て結婚した。しかし、オアハカに革命の風が吹き荒れ(1911/1912 年)、出征する前、彼は彼女にこんなことを言った: 「ʀᴇᴄᴜᴇʀᴅᴏ ᴇʟ ᴅɪ́ᴀ ϙᴜᴇ ғᴜɪᴍᴏs ᴀʟ ʀɪ́ᴏ ʏ ʟᴀs ғʟᴏʀᴇs ᴅᴇʟ ᴅᴇʟ ᴄᴀᴍᴘᴏ ᴘᴀʀᴇᴄɪ́ᴀɴ ᴀɴ ʟʟᴏʀᴀʀ, ᴄᴏɴᴛɪɢᴏ ʟᴀs ɴᴜʙᴇs ᴅᴇ ᴍɪ ᴄɪᴇʟᴏ ɴᴏ sᴏɴ ɴᴀᴅᴀ, ɪɴᴄʟᴜsᴏ ᴇʟ sᴏʟ ᴄᴏᴍᴘɪᴛᴇ ᴄᴏɴ ᴛᴜ sᴏɴʀɪsᴀ. ʟᴀ ɢᴜᴇʀʀᴀ ᴍᴇ ᴇsᴛᴀ́ ʟʟᴀᴍᴀɴᴅᴏ ᴘᴏʀϙᴜᴇ ʟᴀ ᴘᴀᴢ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ ᴘᴀɪ́s ʜᴀ sɪᴅᴏ ʀᴏʙᴀᴅᴀ. ᴠᴏʟᴠᴇʀᴇ́ ᴀ ᴛɪ́ ʏ ᴘᴏʀ ɴᴜᴇsᴛʀᴀ ғᴜᴛᴜʀᴀ ғᴀᴍɪʟɪᴀ. ɴᴜɴᴄᴀ ᴅᴇᴊᴀʀᴇ́ ᴅᴇ ᴀᴍᴀʀᴛᴇ, ᴇɴ ᴇsᴛᴀ ᴠɪᴅᴀ ᴇsᴛᴀ ᴠɪᴅᴀ ʏ ᴇɴ ʟᴀ ᴍᴜᴇʀᴛᴇ」. ついに旅立ちの日が来た。彼女に別れを告げるとき、彼の目には涙が流れ、最愛の人の顔には痛みのため息が浮かんでいた。話しかけながら、彼は妻の両手を握 り、妻の頬を伝う涙を自分の手でぬぐった。もう夫に会えないかもしれないと思いながら泣き続ける妻を、彼は「ジョロナ」と呼んだ。キスと約束が宙を飛び交 い、彼は生死を問わず彼女のために平然と戻ってくると誓った。彼女もまた、何があっても彼を待つと約束した。 当時の多くの人々がこの夫婦を知り、彼らのために狼狽した。青年は戦争に出かけたが、戻ってくることはなかった。しばらくして、二人の共通の友人が村に戻 り、彼女に言った:あなたの夫は銃弾に倒れ、その傷はとてもひどく、彼を救うことは不可能だった。でも、死ぬ間際に、あなたをずっと愛しているから、どう か許してやってくれと頼まれた。あなたのために、彼からもらった手紙を渡すわ」。 その手紙の一部を抜粋する: 「sᴀʟɪ́ᴀs ᴅᴇʟ ᴛᴇᴍᴘʟᴏ ᴜɴ ᴅɪ́ᴀ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴄᴜᴀɴᴅᴏ ᴀʟ ᴘᴀsᴀʀ ʏᴏ ᴛᴇ ᴠɪ́ ᴅɪ́ᴀᴀ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴄᴜᴀɴᴅᴏ ᴀʟ ᴘᴀsᴀʀ ʏᴏ ᴛᴇ ᴠɪ́. ʜᴇʀᴍᴏsᴏ ʜᴜɪᴘɪʟ ʟʟᴇᴠᴀʙᴀs ʟʟᴇᴠᴀʙᴀs ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ϙᴜᴇ ʟᴀ ᴠɪʀɢᴇɴ ᴛᴇ ᴄʀᴇɪ́ ᴇɴ ᴇʟ ᴄɪᴇʟᴏ ɴᴀᴄᴇ ᴇʟ sᴏʟ ᴍɪ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ʏ ᴇɴ ᴇʟ ᴍᴀʀ ɴᴀᴄᴇ ʟᴀ ʟᴜɴᴀ ʏ ᴇɴ ᴍɪ ᴄᴏʀᴀᴢᴏ́ɴ ɴᴀᴄᴇ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ϙᴜᴇʀᴇᴏᴍᴦɴɢᴜɴᴀ. ᴀᴜɴϙᴜᴇ ᴀᴜɴϙᴜᴇ ᴍᴇ ᴄᴜᴇsᴛᴇ ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ɴᴏ ᴅᴇᴇ́ ᴅᴇ Ǚᴇᴜᴇʀᴇᴛᴇ. ᴀʏ ᴅᴇ ɪ́ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ! ʟʟᴏʀᴜ́ ᴇʀᴇs ǐɪ xʜᴜɴᴄᴀ ᴍᴇ ᴘᴇᴅɪʀᴀ́ɴ ᴅᴇᴊᴀʀ ᴅᴇ ϙᴜᴇʀᴇʀᴛᴇ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴘᴇʀᴇ ϙᴜᴇʀᴇ ɴᴄᴀ、 ɴᴏ ᴄʀᴇ ᴛᴇ ᴄᴀ𝁴ᴛ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴛᴇɴɢᴏʀᴀᴢᴏ́ɴ、 ᴛᴀᴍʙɪᴇ́ɴ ᴅᴇᴇ ᴅᴏʟᴏᴏʀ sᴇ ᴄᴀɴᴛᴀ ᴄᴀɴᴛᴀ ʟʟᴏʀᴏɴᴀ ᴄᴜ ᴀ ᴅ ᴏ ᴀ ʀ ɴ ᴏ ʀ ᴀ ʀ ɴ ᴇ ᴇ ᴅ ᴇ ᴈ ᴜᴇ ɴᴏ ʟᴇ ʀᴇ ᴘʀᴇɴᴅ ᴀ ϙᴜᴇʀɪᴅᴀ ᴛᴇ ᴇsᴘᴇʀᴀʀᴇ́ ᴇɴ ᴇʟ ʜᴏʀɪᴢᴏɴᴛᴇ ᴄᴀᴅᴀ ᴍᴀᴅʀᴜɢᴀᴅᴀ.」 言うまでもなく、彼女はその手紙のことでずっと泣いていたし、楽園で最愛の人に会って約束を果たすことを望んでいたので、再婚することはなかった。その知 らせから1週間後、ふたりの間に赤ちゃんが生まれた。毎年10月30日には、ふたりは夕食を共にした。生者の国の妻子と死者の国の夫......大鷲が二 人を再び引き合わせるまで。時は流れ、この物語は地元の民謡として作られ、今に至っている。 つまり、この美しい歌は、子供たちを川に沈めたアステカの欺かれたジョロナ伝説を歌っているのではない。サポテカ・ロロナは愛の物語であり、悲しい物語だ が、美しい愛の物語なのだ。 |
リンク
文献
その他の情報
【参照画像】
【翻訳】マッサージします。アジア[医学]的ネルビオ(神経)の不調等――撮影地:不詳
【解説】中南米ではマッサージは筋肉や疲れのほかに、内臓疾患(例:エンパチョ)や心理的不調(例:ここでのネルビオ:ただし綴りはnervioが正し
い)などにも施術されます。西洋医学的なエビデンス?それはほとんどありませんが、CAMとしては、比較的広く民間療法として普及していますし、また利用
者の評判もそこそこです~♪ 興味ある方はこちらへ~♪ →「民間療法事典」
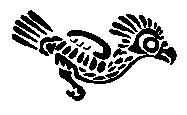
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
++
☆
 ☆
☆