
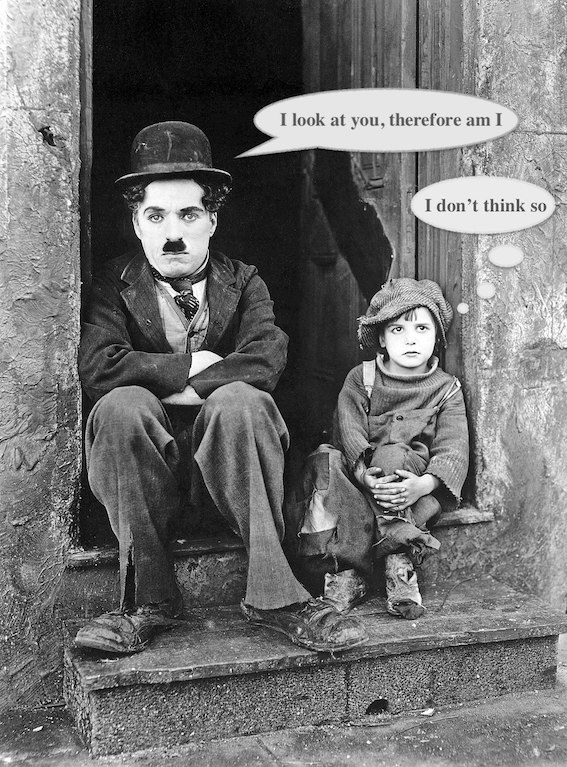
存在論的ナイーブさ
Ontological nativety
このページは、ハイデガー『存在と時間』高田珠樹訳 における、《 ハイデガー自身の未開観》を明らかにして、彼の推論や解釈学的存在論的の境界を描きだす。
| ■第11節 実存論的な分析作業と未開の現存
在
の解釈、「自然な世界概念」を獲得するのに伴うさまざまな困難 ※(n)は節内のパラグラフの順。[n]は原著のページ |
|
| (1)
もっとも、現存在をそれが日常的にあるがままの姿で解釈するというのは、人類学が知
識を経験的に伝えたり
する現存在の未開段階を記述するのと同じではない。日常的というのは、未開であるというのと重なりあわない。
むしろ、現存在が高度に発達し細分化した文化の中にあっても、あるいはそのような場合にこそ、日常的という
のは、現存在のひとつの存在様態なのである。他方では、未開の現存在もそれなりにさまざまの非日常的な在り[051]
方をしているし、それに特有の日常性を備えてもいる。「未開の民族の生活」を拠りどころとするのには、方法と
して積極的な意義がないわけではない。当の現存在による自己解釈がすでにかなり進んでいて「未開の現象」が覆
われたり複雑になったりしている、ということが概してあまりないからである。未開の現存在は何か言うにも、
往々にして(前現象学的な意味での)「現象」の内に埋没した、それらとの根源的な一体感の中から、より直
接に語っていることが多い。用いられる概念構制は、私たちから見るとぎごちなく大雑把であるかもしれないが、
さまざまな現象の存在論的構造を的確に浮かび上がらせる上では積極的に働いて有益なこともある。 |
・「未開の現存在は何か言うにも、
往々にして(前現象学的な意味での)「現象」の内に埋没した、それらとの根源的な一体感の中から、より直
接に語っていることが多い」。 ・このあたりの論理は、レヴィ=ブリュルの融即の論理に近い |
| (2)
ところが、従来、未開人に関する知識を私たちに提供してくれているのは民族学である。
この民族学は、最初
に資料を「採集」し、それを選別し整理する際にすでに、人間の現存在全般についての特定の予備概念の解釈に身
を置き、あくまでその中を動いている。民族学者が携える常識的な心理学はもとより、
学問的な心理学や社会学
にしても、調査しようとする諸現象に迫っていってそれらを解釈し世に紹介する適切な手立てを学問的に保証し
てくれるとは限らない。ここでもやはり、先に挙げた学問分野と同じ事態が頭をもたげてくる。民族学そのもの
がすでに、手掛かりとなる現存在の分析作業が十分に行なわれていることを前提としているのである。しかし、
実証的な学問は哲学の存在論的な作業を待っていることは「でき」ないし、また待っているべきでもないから、研
究の前進は、存在相上での発見の「進捗」として生じるのではなく、この発見されているものの反復に加え、存在
論的に見通しがもっと利くようになる純化として行なわれることになるだろう。(脚注※1) (脚注※1) 最近、エルンスト・カッシーラーは、神話的現存在を哲学的な解釈の主題として取り上げた。これについては 『象徴形式の哲学』第二部「神話的思考」(1925年)を参照されたい。民族学の研究は、この考察によって、こ れまでにない包括的な指針を手にしたことになる。もっとも、哲学的な問題構制から見 るとき、はたしてその 解釈の基礎が十分に見通しの利くものとなっているのか、とりわけカントの『純粋理性批判』の構図やその体系 的内実が、そもそもこのような課題のための青写真となりうるのか、ここではむしろもっと根源的な視座を新 たに設定することが必要ではないか、という疑問が残る。カッシーラー本人がこのような課題の可能性を見て とっていることは、彼が16-17ページの注で、フッサールの切り拓いた現象学的な地平に言及していること から窺える。著者は1932年12月にカント学会のハンブルク支部で「現象学的研究の課題と道筋」と題する 講演を行なった。その際、カッシーラーと討論する機会を得たが、著者が右に挙げた講演で素描した実存論的 な分析作業というものが必要であるという点で、すでにふたりの見解に一致が見られた。 |
・「
実証的な学問は哲学の存在論的な作業を待っていることは「でき」ないし、また待って
いるべきでもないから、研
究の前進は、存在相上での発見の「進捗」として生じるのではなく、この発見されているものの反復に加え、存在
論的に見通しがもっと利くようになる純化として行なわれることになるだろう」 |
| (3)
形式的な線引きによって存在論的な問題構制を存在相上の研究から切り離すのは容易であるにしても、現存在[052]
の実存論的な分析作業を実行する上で、とりわけまずその視座を設定する上でいろいろ困難がないわけではない。
この作業が取り組む課題の中には、以前から哲学がぜがひでも解決しようとして頭を悩ませながら、何度やって
もうまく行かないひとつの宿題も含まれる。「自然な世界概念」という理念を練り上げることである。今日では実
に多様ではなはだ遠隔の地の文化や現存在の形式について豊富な知識が手に入り、この課題に着手するにはいか
にも好都合であるかに見える。しかし、これは単にそう見えるにすぎない。実際のところは、これだけ知識が過
剰になると、それに乗せられ、つい本来の問題を見誤りがちになる。何もかもを一律に比較し類型ごとに分類し……(高田訳 Pp.72-73) |
|
| ■第49節 死の実存的分析を、死の現象について考えられる別の解釈か
ら
峻別する(p.367) |
|
| (2)
こういった生物学の立場から行なわれる死についての存在相上の探求の根底には、ひとつの存在論的な問題構
制が潜んでいる。生命の存在論的な本質からは死の本質がどのように規定されることになるのか、これがやはり
なお問われなくてはならないのである。ある意味では、死の存在相上の研究はこの点について常にすでに一定の[247]
判断を下している。どこまで明確に整理されたものであるかは別にして、そういった研究の中では生と死に関す
るさまざまの予備概念が働いている。これらの予備概念は、現存在の存在論によって大雑把ながらその輪郭が描
かれる必要がある。順序からすれば現存在の存在論は生命の存在論の前に位置し、またこの現存在の存在論の内
部でもさらに死の実存論的分析は現存在の根本体制の性格規定の後ろに位置する。生きているものが終わるのを
私たちは「息絶える」と呼んだ。現存在にもやはり生命体としての生理学的な死があり、しかもこの死は存在相上、
孤立しているのではなく、現存在の根源的な在りようからも規定されている。しかも、現存在は本来的に死ぬこ
となく終わりもするが、他方でまた現存在である以上、ただ単に息絶えるわけではない。そのかぎりでは、この
中間的な現象を私たちは「絶命」と呼ぶことにしよう。一方、「死ぬ」という言葉は、現存在が自分の死に臨んで
在る在りようを指すものとしよう。これに従うなら、現存在はけっして息絶えることがないと言わねばならない。
基本的な方向が死の実存論的な解釈にあることが揺るがないかぎり、医学と生物学の立場から進められる研究も
存在論的に重要な意義を持つことがある。あるいは、そもそも病気や死でさえ、医学的にも、まずは実存論的な
現象として把握されねばならないのだろうか。 |
|
| (3)
死の実存論的な解釈は、あらゆる生物学や生命の存在論に対してその前に位置している。しかしまた、この実
存論的な解釈があって初めて、伝記や歴史学、あるいは民族学や心理学
の立場から行なわれる死の研究のいずれ
にもその基盤が与えられることになる。絶命がどのように「体験される」のか、その状
態や次第の特徴を分類する
「死に方」の「類型学」は、すでに死の概念を前提としている。加えて「死ぬこと」の心理学といったものからは、
死ぬことそれ自体よりも、むしろ「死んでゆく人」の「生」について教えられるものである。これは、現存在が事
実的な絶命を体験する中で初めて死んだり、ましてや本来的に死んだりするのではないことを反映するものにほ
かならない。同様にまた未開人における死の捉え方や、呪術なり祭礼なりにおいて彼らが死に対して取る態度も、
まずは、そこに作用する現存在了解を照らし出すものであり、これを解釈するには、すでにひとつの実存論的な
分析作業とそれに対応した死の概念とが必要となる。 |
|
| (4)
他方で、終わりに臨んで在ることの存在論的な分析は、死とどう向かいあうかに関するひとつの実存的な態度決
定を先取りするわけではない。死を現存在の「終わり」として、すなわち世界=内=存在の終わりとして規定する
といっても、それでもって「死後に」もうひとつ別の、もっと高い、あるいは低い存在が可能であるのか、現存在
は「生き続ける」のか、それとも自分の人生を越えて「永らえる」のか、「不死」であるのか、といったことについ
て存在相上の決定が下されるわけではない。また、死に臨む態度の規範や規則を提示して「教化」しようというの[248]
でもないから、「彼岸」やその可能性について、存在相上、なんらかの決定を下すわけではない。「此岸」について
もこれは同じである。ただし、ここで試みる死の分析は、死という現象がそのつどの現存在のひとつの存在の可能
性としてこの現存在の内にどのように入り込んでいるのかに注目しながら死を解釈するのだから、そのかぎりにお
いては、あくまで純粋に「此岸的」である。まずは死がその存在論的な本質総体において把握されていないかぎり、
死後に何が在るのかといったことはそもそもまともな問いとして方法的に確実なかたちで問うことすらできない。
はたしてこのような問いがそもそも理論的な問いとして可能であるのかについては、ここでの決定は控えよう。此
岸的かつ存在論的な死の解釈は、存在相的かつ彼岸的な思弁のいかなるものよりもその前に位置するのである。(Pp.368-369) |
|
| ■第74節 歴史性の根本体制(p.568) |
|
| (4)
現存在が自分自身に果断に立ち返って来るとき、この果断さは、それが被投的な果断さである以上、自分が引
き受けることになる遺産から、本来的に実存するそのつどの事実的なさまざまの可能性を開示することになる。
被投性へ果断に立ち返ることは、伝来の可能性を自らに引き渡すとともに、その可能性が自らを引き渡すという
働きを内に秘めている。ただし、そこでこの可能性がことさらに伝来のものとして納得されているとは限らない。
「善きもの」がすべて遺産であり、この「善さ」という性格が本来的な実存を可能とすることにあるのなら、果断
さの中ではそのつどひとつの遺産の受け渡しが構成されることになる。現存在ができるだけ本来的に決断するな
ら[384]、つまり死の内へ先駆ける中で紛れもなく自分に最も固有な格別の可能性から可能なかぎり自分を本来的に理
解するなら、自分の実存の可能性を見つけて選ぶのも、その分いよいよ鮮明にして偶然を脱したものとなる。死
の内へ先駆けることによってしか、偶然の行きずりにすぎない、自分に「先走る」可能性をすべて追いはらうこと
はできない。死を受け入れこれに向かって自由に開かれて在ることだけが、現存在に端的な目標を与え、実存を
その有限性の中へ突きいれるのである。現存在の身辺には、安逸、安直に走り惰弱に流れるための可能性がそれ
こそ我勝ちに押し寄せ、あの手この手で現存在を誘惑しているが、実存の有限性が掴み取られることによって、
現存在は、そういった可能性の果てしない氾濫からもぎ離され、唯一単純な自身の運命に引き人れられることに
なる。私たちが運命と呼ぶのは、本来的な果断さの中に含まれる現存在の根源的な生起のことであり、この中で
現存在は死に向かって自由に開かれ、遺産として得たとはいえ、やはり自ら選び取った可能性において自ら自身
を自分自身に伝え渡すのである。 |
|
| (5)
現存在が運命のさまざまな痛撃をこうむったりするのは、ひとえに現存在がその存在の根底において、右に述
べた意味で運命であるからである。自らを伝え渡す果断さにおいて運命的に実存しつつ、現存在は、世界=内=
存在として、「幸運」な事情や偶然による酷い仕打ちを受け容れるべくそれに向かって打ち開かれている。さまざ
まな事情や事件のめぐり合わせによって初めて運命が成立するのではない。優柔不断な者であっても、そういっ
た事情や事件に翻弄される。自ら選び取った者以上にそれらに振り回される。それでいながら、一個の運命を
「持つ」ということはついぞない。 |
|
| (6)
先駆けることで、自分の中に死が力強く涼ってくる。死をそのように涜らせるとき、現存在は、死に向かって
自由に開かれ、自分の有限的な自由に宿る自ら自身の圧倒的な威力において自分を理解する。そうすることで、
それぞれ選択を選び取ったことの中にのみ「在る」この自由において、現存在は、自ら自身に委ねられていること
の無力を引き受け、また開示される状況のさまざまな偶然を鮮明に見きわめることになる。しかし、運命を蔵す
る現存在が、世界=内=存在として本質的に他者たちとの共同存在において実存している以上、現存在の歴史生
起とはまたともに歴史生起することであり、命運である定めにある。この命運ということで、私たちは共同体、
民族の歴史生起を指している。個々の運命がいくつか合わさればそれが命運となるのではない。相互共同存在を
主観がいくつか集まつている状態として捉えるわけにはいかないのと同じである。同じ世界の内で相互共同存在
し、また一定の可能性に向けて果断に在る中で、それらの運命には初めからすでにともに歩む道連れがいる。
ともに分かちあう闘う中で初めて、命運が秘める威力は自由に解き放たれる。自分の「世代」の中でこの「世代」とともにする
現存在の運命的な命運をもって、現存在の本来的な歴史生起が余すところなく成立する(高田訳, Pp.570-572) |
|
+++
Links
リンク
文献
その他の情報


++
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆