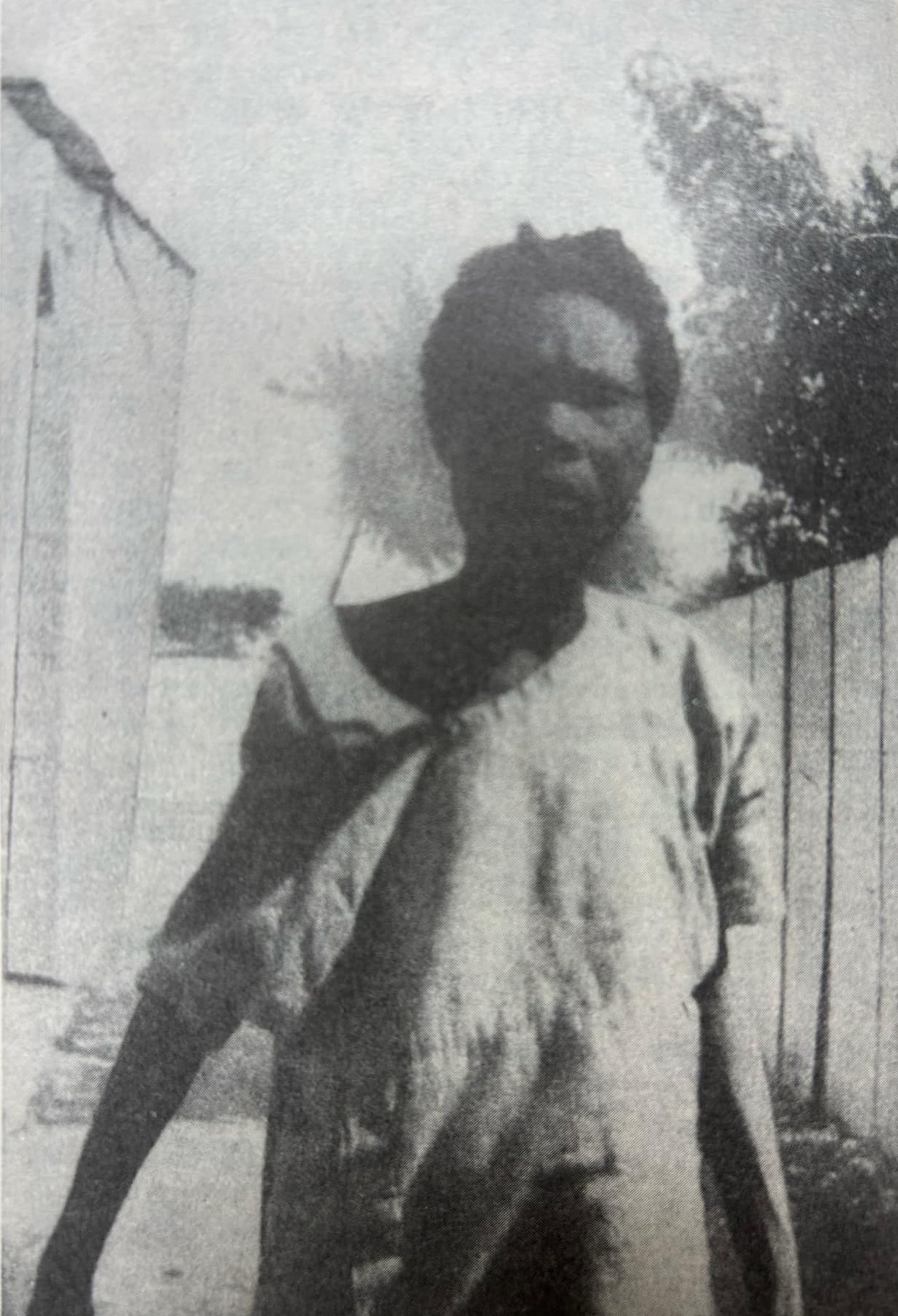
ゾンビとわれわれ人類学者は zombies_and_we_anthros.html に移転しています!!!
My web-page on we, Anthropological
Zombies is now moved to zombies_and_we_anthros.html
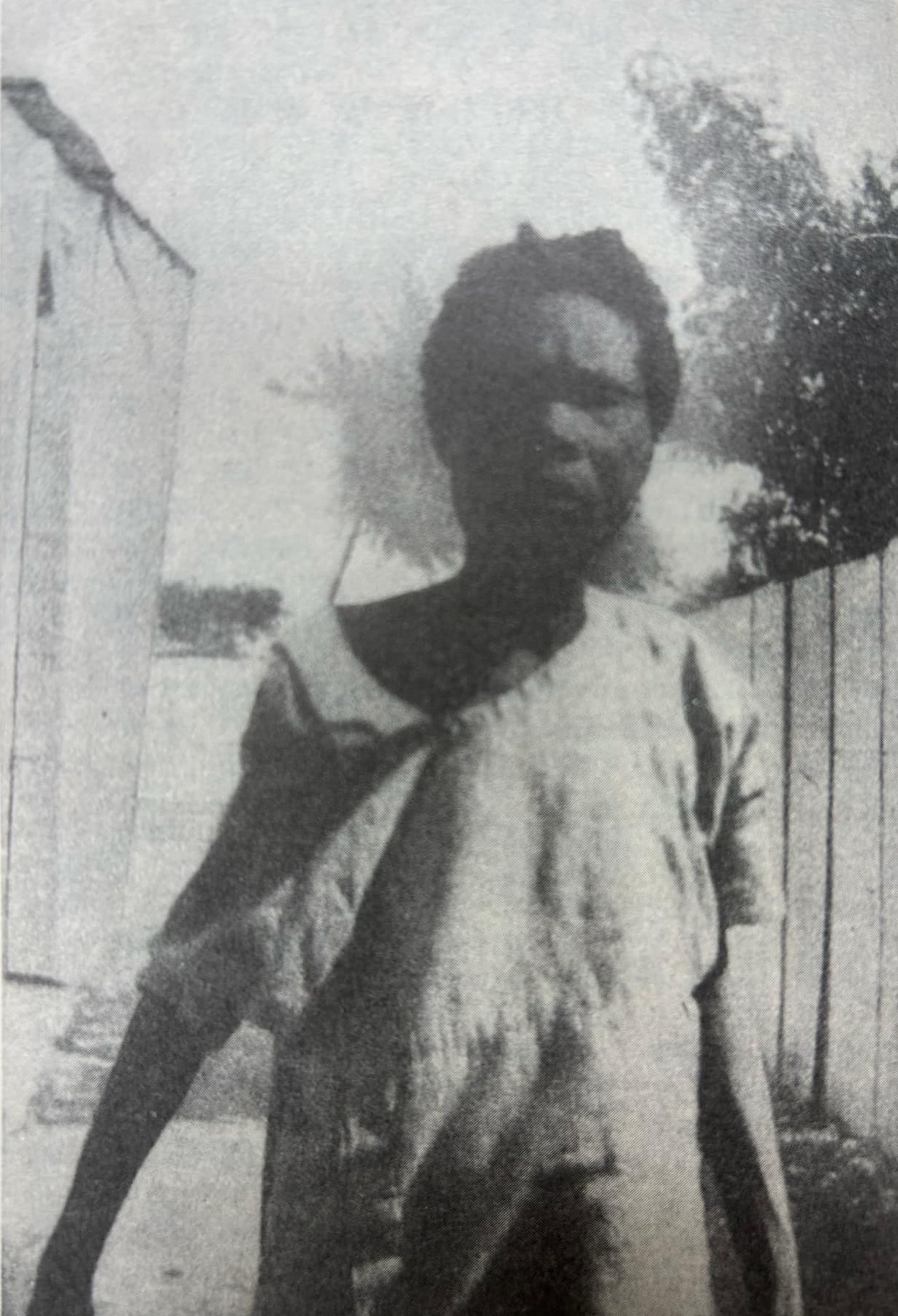
Felicia
Felix-Mentor as a Haitian Zombie from Zora Neale Hurston's "Tell My
Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica," 1938