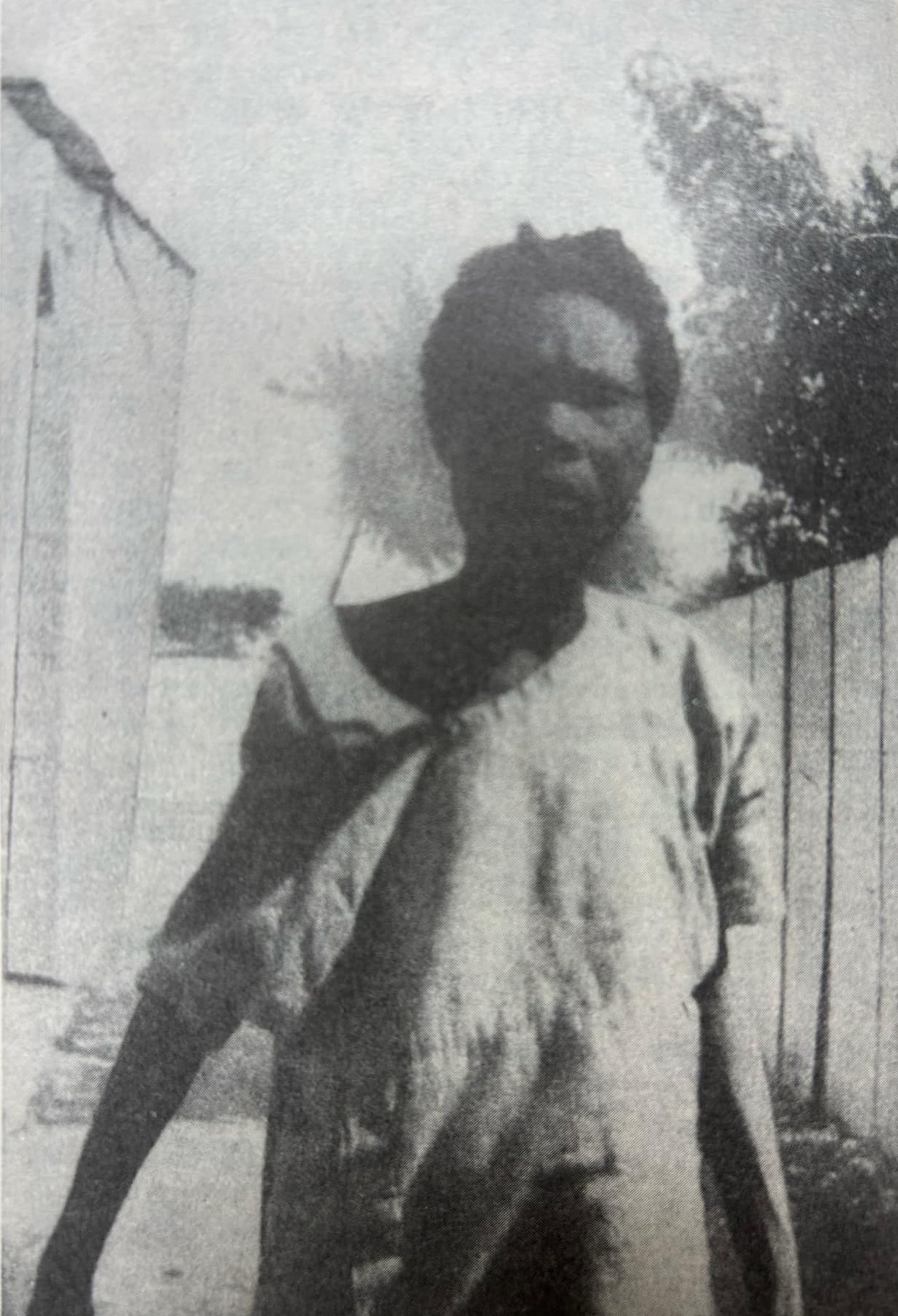
ゾンビとわれわれ人類学者
——
感染のメタファーとその現実 ——
Anthropological Zombie or Anthropology as Zombie existence
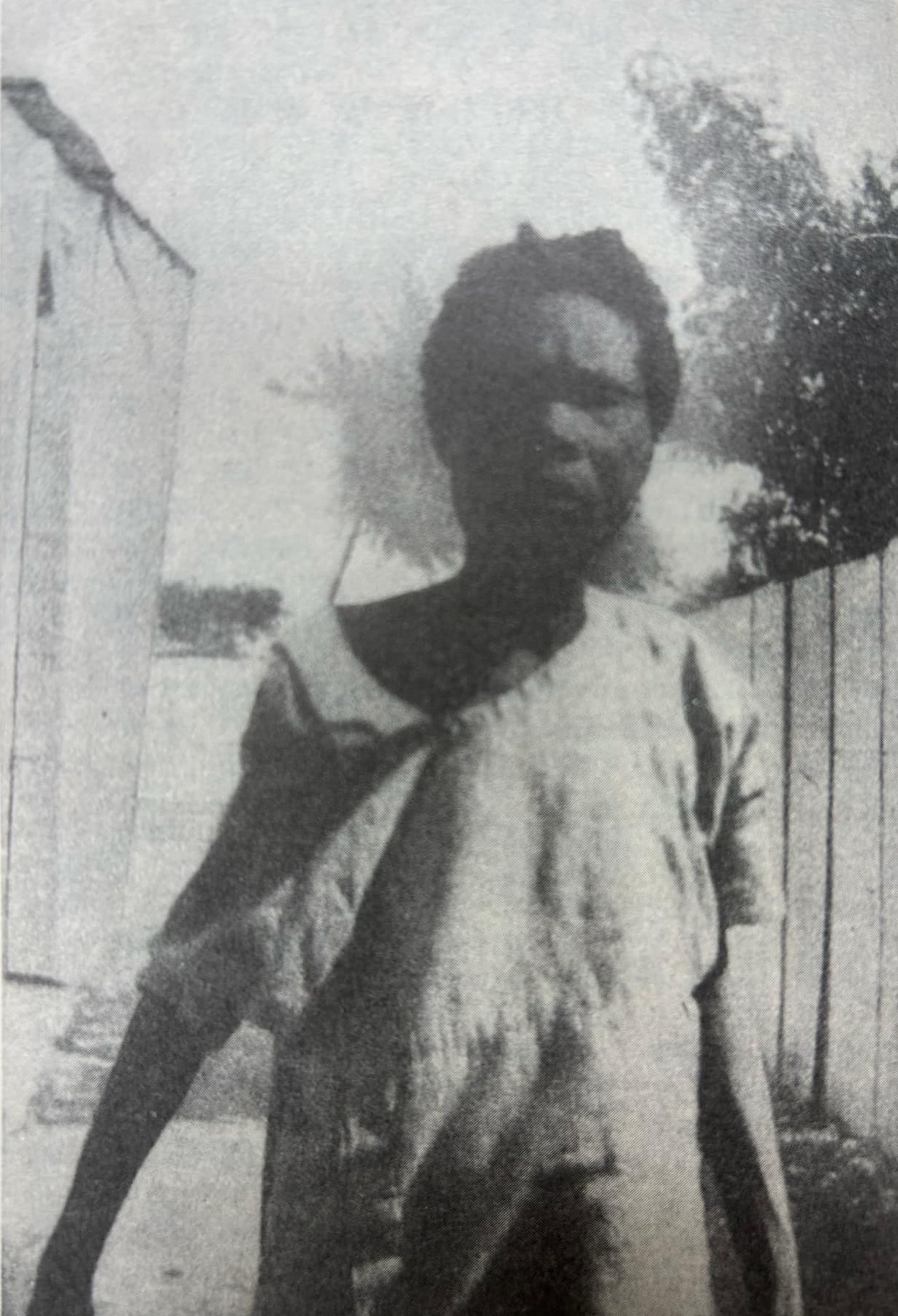
Felicia
Felix-Mentor as a Haitian Zombie from Zora Neale Hurston's "Tell My
Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica," 1938
☆「生 なるものは、それ以外の形で生きることをしらない」(デリダ 2007:11)。
★
ゾンビとわれわれ人類学者—— 感染のメタファーとその現実 —— スライドのpdf [Zombie_and_we_anthros4.pdf]
1. リアルゾンビ写真との出会い
2. 複数性の人類学のなかにおけるゾンビ
3. エージェントモデルとしてのゾンビ(→ゾンビ宣言とポストヒューマニズム)
4. 感染の恐怖/感染の快楽またはアイデンティティの問題
5. ゾンビの身体論を共有する現代人
6. メディアゾンビ、あるいは増殖[複数化]するゾンビ
7. ポストコロニアルな否定の表象としてのゾンビ
8. 要約と結論
+++
| 1. リアルゾンビ写真との出会い ゾ ラ・ニール・ハーストン(1891-1960)は、グッゲンハイム財団の支援をうけて1936年から1937年にかけてジャマイカとハイチでフィールド ワークをした。その結果が翌年に出版される"Tell My Horse: Voodoo and Life in Hati and Jamaica"(邦題:『ヴードゥーの神々』)である。その中で「かつてフェリシア・フェリックス=メントールだった人の残骸(ないしはぬけ殻)」の姿 を撮った写真がある。ゴナイブの病院の中庭で著者によって撮られたゾンビの写真は、病院の患者用のガウンをつけて、こちらを見据えて仁王立ちしている。 ハーストンは、ゾンビを前にして、彼女[それ]にかける言葉もなく、見る以外に得られるものはなく、そしてその「生きる屍」の姿を長く見続けることはでき ないと落胆しながら記述している。 |
1. Encounter with Real Zombie Photos Zora Neale Hurston (1891–1960) conducted fieldwork in Jamaica and Haiti from 1936 to 1937 with the support of the Guggenheim Foundation. The results were published the following year as “Tell My Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica” (Japanese title: “The Gods of Voodoo”). Among the photographs in the book is one of what was once Felicia Felix-Mentor, now reduced to a lifeless shell. Taken by the author in the courtyard of a hospital in Gonaive, the zombie is dressed in a hospital gown, standing tall and staring straight ahead.Harston describes standing before the zombie, unable to find words to speak to it, with nothing to gain from looking, and eventually growing disheartened as he realizes he cannot continue to gaze upon that “living corpse” for much longer. |
| 2. 複数性の人類学のなかにおけるゾンビ この発表は、その写真の姿に取り憑かれた私が「複数性・複数化の文化人 類学」で考えられる、さまざまな問題提起に対してゾンビ的存在論 (Zombic ontology)から考察するものである。 |
2. Zombies in the Anthropology of Multiplicity This presentation is an examination of various issues raised by the “cultural anthropology of multiplicity and pluralization” from the perspective of zombic ontology, inspired by the image captured in the photograph. |
| 3. エージェントモデルとしてのゾンビ(→ゾンビ宣言とポストヒューマニズム) 「ゾ ンビ」つまりノーマルな生者を襲ったり危害を加えたりすることを通して感染、増殖する想像上あるいは民族誌に登場するエージェント[モデル]という存在に 焦点をあて、複数性と非同一性のテーマが伏在することを指摘する。Lauro and Embry(2008)による"A Zombie Manifesto"を含めてさまざまな言説の議論を踏まえて、ハーストンが描写した1930年代中頃のヴードゥー信仰を中心としたゾンビを標準的なもの として、フーンガン(ヴードゥー司祭)により死体から蘇らせられ、様々なことに使役される非主体的存在(non-subjective agent)として考えてみる。 |
3. Zombies as Agent Models (→ Zombie Manifesto and Post-Humanism) Focusing on the existence of agents [models] that appear in imagination or ethnography and spread and multiply by attacking or harming normal living beings, this section points out the underlying themes of multiplicity and non-identity. Drawing on various discourses, including Lauro and Embry (2008)'s “A Zombie Manifesto,” we consider the zombies described by Harston in the mid-1930s, centered on Voodoo beliefs, as the standard model: non-subjective agents resurrected from corpses by a Houngan (Voodoo priest) and used for various purposes. |
| 4. 感染の恐怖/感染の快楽またはアイデンティティの問題 (1) ゾンビ存在論の第一の特徴。ゾンビとして蘇らせる犠牲者は、年をとっていなければ誰でもいいという。生前のジェンダーや社会的属性は関係ない。その意味で はCOVID-19の感染のように、感染のチャンスは貴賤により差別されるのではなく誰にでも起こりうる。蘇らせる呪薬と墓場の土には強い結びつきがある ので、そのような汚染土に対して人は忌避心を抱く。しかし感染現象は防いでも防ぎきれない無力感がある。他者との普遍的同一性——個体的個性を単一の犠牲 者(患者)へと変えてしまうこと——への恐怖とその運命論に引きずり込むのだ。そこで人々は個別の歴史をもったアイデンティティ(内的首尾一貫性)を失 い、ゾンビ(患者)としての同一性(ゾンビアイデンティティ)のもとに普遍的に統一される。 |
4. The fear of infection / the pleasure of infection or issues of identity (1) The first characteristic of zombie ontology. The victims resurrected as zombies can be anyone, as long as they are not elderly. Their gender or social attributes prior to death are irrelevant. In this sense, like COVID-19 infection, the opportunity to be infected is not discriminated against based on social status but can occur to anyone. There is a strong connection between the resurrection potion and the soil of the graveyard, so people feel aversion toward such contaminated soil.However, there is a sense of helplessness in the fact that the infection phenomenon cannot be completely prevented. The fear of universal sameness with others—the transformation of individual uniqueness into a single victim (patient)—and the fatalism that pulls one into it. As a result, people lose their individual histories and identities (internal consistency) and are universally unified under the sameness of zombies (patients) (zombie identity). |
| 5. ゾンビの身体論を共有する現代人 (2) ゾンビ化への恐怖は、ハーストンが元フェリシアという女性[それ]と邂逅したときに覚えたように、両者の間のコミュニケーション不能性のなかに現れる。ゾ ンビの存在論の二番目の特徴は、[それは]生者か死者がわからない宙吊りの身体である。そのプラトンの「牢獄としての身体」の中には心というものがなく、 ただ主人の言うことを聞く機械のような無機質なものにすぎない。そこには生者がもつ生々しい命の輝きがない。生と死のあいだの煉獄的状況におかれている。 |
5. Modern people who share a zombie body theory (2) The fear of becoming a zombie appears in the inability to communicate between the two, as Harston felt when he encountered a woman named Felicia.The second characteristic of zombie ontology is that [it] is a suspended body whose status as living or dead is unclear. Within Plato's “body as a prison,” there is no mind, and it is nothing more than an inorganic machine that merely obeys its master's commands. There is no vibrant glow of life that living beings possess. It is trapped in a purgatorial state between life and death. |
| 6. メディアゾンビ、あるいは増殖[複数化]するゾンビ (3) ゾンビの存在論の第三番目の特異性は、ハイチのオリジナルの「伝統的」ゾンビと、1968年以降のジョージ・ロメロ監督の"Night of the Living Dead"の世界的流行以降に全世界あるいは全思潮世界に膾炙した「隠喩」としてのゾンビあるいは思考実験としての「ゾンビ状態」のあいだの想像もできな いほどの乖離である。それを「ゾンビ・マニュフェスト(ゾンビ宣言)」の著者たちLauro and Embry(2008)は、グローバル資本主義[の犠牲者たち]とポスト・ヒューマニズムの理論学派のあいだの両立しがたい緊張関係にあると巧みに表現し ている。すなわち、リアルである/であったゾンビのほうは、生きている間による経済的人的搾取にあったプレモダン時代のプレカリアート——植民地主義や人 種主義という構造的暴力の必然的帰結としてのルンペンプロレタリアート——であり、生きているあいだにおいてでも、劣った主体としての生きるに値しない生 命体が、死んでもなお呪術により蘇らせられて搾取可能の限界を超えて使役されるという植民地状況の過酷な現実を体現する。他方、隠喩としてのゾンビは、映 像やドラマさらにはゲームソフトのなかで自己増殖を遂げる(福田 2024)だけでなく、時には哲学上の思考実験(Chalmers 1996)の対象になったり、挙句にはゾンビ・マニュフェストの著者たちのように、ポストヒューマン時代の変革の主体になったりして資本主義体制の終焉を 予見してくれる存在なのである(妄想のフラクタルな増殖)。 |
6. Media Zombies, or Proliferating [Multiplicating] Zombies (3) The third distinctive feature of the ontology of zombies lies in the unimaginable divergence between the original “traditional” zombies of Haiti and the zombies that emerged as metaphors or thought experiments following the global popularity of George A. Romero's “Night of the Living Dead” in 1968, spreading across the entire world or the entire ideological landscape.The authors of the “Zombie Manifesto,” Lauro and Embry (2008), skillfully express this as an irreconcilable tension between the victims of global capitalism and the theoretical school of post-humanism. That is, the real/realized zombies are the premodern precariat who were subjected to economic exploitation during their lives——the lumpen proletariat, an inevitable outcome of structural violence such as colonialism and racism—who were subjected to economic exploitation during their lives as inferior beings unworthy of life, and who, even after death, are resurrected through sorcery and exploited beyond their limits in a brutal colonial reality.On the other hand, zombies as metaphors not only proliferate in films, dramas, and video games (Fukuda 2024), but also become subjects of philosophical thought experiments (Chalmers 1996) and, in the end, like the authors of the Zombie Manifesto, become agents of change in the post-human era, foreshadowing the end of the capitalist system (the fractal proliferation of delusions). |
| 7. ポストコロニアルな否定の表象としてのゾンビ 最後に存在論分析に手を休めて歴史的文脈にハイチの文化表象としてのゾ ンビを押し返してみよう。1915-1934年までの米国海兵隊の占領以降、独裁と貧困と暴力の跋扈、1980年代のエイズ流行の際のホモフォビアパニッ ク、先の米国大統領選挙における移民への中傷など、ハイチはポストコロニアルな否定の表象の収蔵庫でありつづけてきた。ハイチの外でのゾンビは平和な社会 の[仮想的]想像力として豊かとも言えるゾンビ研究の活況を呈している。〈発祥の地の不幸〉と〈移植先の奇妙な多幸感〉という著しい対比とその解決への模 索を我々は決して忘れるわけにはいかないのだ。 |
7. Zombies as a representation of postcolonial negation Finally, let us take a break from ontological analysis and return to the historical context of zombies as a cultural representation of Haiti.Since the U.S. Marine Corps occupation from 1915 to 1934, Haiti has been a repository of postcolonial negation, marked by dictatorship, poverty, violence, the homophobia panic during the AIDS epidemic of the 1980s, and recent attacks on immigrants during the U.S. presidential election.Outside of Haiti, zombies have sparked a vibrant field of zombie studies, often seen as a rich source of [virtual] imagination for a peaceful society. We must never forget the striking contrast between the “misfortune of the birthplace” and the “strange sense of euphoria in the transplanted land,” nor the ongoing search for resolution. |
| 8. 要約と結論 ゾラ・ニール・ハーストン(1891-1960)が1936年ごろ写したと思われる「かつてフェリシア・フェリックス=メントールだった人」つまり現存し た唯一のゾンビの写真との出会いを出発点にして、現代社会におけるゾンビ表象とゾンビ増殖についての感染のメタファーについて考察した。本分科会のテーマ である「複数性・複数化の文化人類学」のレパートリーを紹介し、1)エージェントモデルとしてのゾンビ、2)感染の恐怖あるいは快楽のアイデンティティ、 3)ゾンビ身体論の特徴、4)増殖するメディアゾンビとリアルゾンビの比較、を紹介した。本発表の表題「ゾンビとわれわれ人類学者」は、そのようなゾンビ を文化研究の対象にするだけでなく、ゾンビが含意するグローバル資本主義におけるプレカリアートやマルチチュードの表象としてのゾンビすなわちハイチ人の 否定的な表象とわたしたちが出会う政治権力空間への反省的考察に誘うのである。 |
8. Summary and Conclusion Starting from my encounter with what is believed to be a photograph taken by Zora Neale Hurston (1891-1960) around 1936 of “the person who was once Felicia Felix-Menthol,” the only existing photograph of a zombie, I examined the metaphor of infection in relation to zombie representations and proliferation in contemporary society.This paper introduces the repertoire of the subcommittee's theme, “Cultural Anthropology of Multiplicity and Pluralization,” focusing on four key points: 1) zombies as agents, 2) the fear or pleasure of infection as identity, 3) characteristics of zombie body theory, and 4) comparisons between proliferating media zombies and real zombies.The title of this presentation, “Zombies and We Anthropologists,” not only positions zombies as objects of cultural study but also invites a reflective examination of the political power spaces where we encounter zombies as representations of the precariat and multitude in global capitalism—specifically, the negative representations of Haitians—that zombies imply. |
★
キーワード:ゾンビ、ゾラ・ニール・ハーストン、ハイチ、感染と告発、脱
植民地主義.
☆ ゾンビ研究テーゼ集(→元クレジット「人類学的ゾンビあるいはゾンビ存在としての人類学:Anthropological Zombie or Anthropology as Zombie existence」)
「生
なるものは、それ以外の形で生きることをしらない」(デリダ 2007:11)。
|
★ゾン ビと憑在学(hauntology)との深い関係(→ハウントロジー=憑在 論 - 過去の観念の回帰または持続) ★リアル「感染」に関する情報 ★ゾン ビは、生者と死者のオントロジー的区分に疑問符をなげかける(→「存在論=オントロジー」) ★ゾン ビは、自己と他者のオントロジー的区分に疑問符をなげかける(→「アイデンティティ」「同定」「人類学における自己と他者」) ★ゾラ・ニール・ハーストンの「ゾンビ」であったフェリシア・フェリックス=メントールは、1907年 に死亡し、埋葬されたのに、1936年10月に「ここは父の農場だ。ここで暮らしていた」と呟き、裸で徘徊することになるのは、亡くなった当時のフェリシ アと、29年後に蘇ったゾンビのあいだの「人格の同一性」はたもたれてい る。 ★ラングトン・ヒューズやリチャード・ライトと比較され、黒人文学表現の伝統の中から一度消滅して、再度アリス・ウォーカーらに再発見された、ゾラ・ニール・ハーストンそのものが、口頭伝承やフォークロアを基調とする黒人文学作家として、再発見されるのは、ゾンビのような復活だとも言うことができる。 ★別に ゾンビがアイデンティティが単数であっても問題ではない。ゾンビとノーマルが競争的に存在する社会のダイナミズムが「ゾンビ問題」にとって重要だからだ (→「人類学における自己と他者」)。 ・「ベタニアのラザロ[a]は、新約聖書に登場する人物で、ヨハネによる福音書に
よると、死後4日目にイエスによって蘇生したとされる。この復活は、イエスの
奇跡のひとつと考えられている。東方正教会では、ラザロは「義人のラザロ」、「4日間死んでいた者」として崇敬されている[4]。東方正教会とカトリック
教会では、彼のその後の生涯について、さまざまな説明がなされている。
ヨハネによる福音書における7つの奇跡の文脈において、ベタニア(現在のヨルダン川西岸地区にあるアル・エザリヤという町で、「ラザロの地」を意味する)
でのラザロの復活は、クライマックスとなる物語である。すなわち、イエスの「人類にとって最後の、そして最も抵抗しがたい敵である死に対する」力を示すも
のである。このため、福音書の中でも重要な位置を占めている。
ラザロという名前は、科学や大衆文化において、一見したところ生命が回復したことを指して頻繁に使用されている。例えば、科学用語のラザロ分類群は、一見
絶滅したように見えた後に化石記録に再び現れた生物を指し、また、ラザロ徴候やラザロ症候群もある。この用語は文学においても数多く使用されている。
同じ名前の個性的な人物は、ルカによる福音書にあるイエスのたとえ話「金持ちとラザロ」にも登場する。このたとえ話では、同名の登場人物2人ともが死に、
前者は地獄での苦しみから救ってくれるよう後者に懇願する」(→ベタニアのラザロ) ★他者(ゾンビに恐れるハイチ人)を単純化すること自体が疑わしい(→他者を単 純なものに還元することに人類学は抵抗しなければならない)。 「タウシグが
指摘するクナ族文化のもう一つの特異性として、クナ族が伝統的なモラ (mola)に、ジャックダニエル(Jack
Daniel's)のボトルの歪んだ反射像や、蓄音機の広告に用いられた20世紀初頭の人気アイコンである「おしゃべり犬」など、西洋のポップカルチャー
のイメージを取り入れていることが挙げられる。タウシグは、クナ族文化を、クナ族が過去に白人の入植者と遭遇し、彼らの大きな船や異国の技術に感銘を受
け、彼らを神と誤解しただけのものに還元する人類学を批判している。タウシグにとって、他者をこのように単純化すること自体が疑わしい。『模倣』と『他者
性』を通して、彼は両方の側面から論じ、人類学者がなぜクナ文化をこのように単純化するようになったのか、また、この視点の価値を明らかにすると同時に、
人類学的還元主義から生活文化の独自性を擁護している」(→「マイケル・タウシグ」) ★私た ちのゲームのルールを他者のゲームに押し付けないこと。物語ゲームの複数性を維持すること。
★ゾン ビに食われる(=感染する)という、トラウマ的現実は、現実の本質に 亀裂をもたらす。それは不在で支配的な終末として現実の観念をに迫るものではなく、存在そのものの空白を表現するものだ。
・「消滅したものも生成すべきものもいま現存していない点では隠された状態にあると言ってよい。ところがあるものの存在とは、いまだ現存していない状態か ら既に現存していない状態への移り行きのなかで、たまたまいまの時点で現存している状態のことをあらわす。あらゆる存在者はこのように、未だ存在しない状態から、存在するものへと生成し、すでに存在し ない状態へと消滅してゆく、そのような移行のなかの結節点のようなものとして生じてくるのである」——知の快楽「ア ナクシマンドロスの言葉:ハイデガーの存在論」 ☆名前を失った存在としてのゾンビ ・人々が恐れれるゾンビは、各人が個性を失い、ゾンビ一般として呼び習わせることである。そこでは、一人の個人が複数の名前で呼ばれたり、各クランにより 共通の個人名がみられるような伝統社会のような呼称の複数性の概念がない(モース 1995: 21) ★ポストヒューマンすなわちヒーローとしてのゾンビ ・→「ゾンビ・マニュフェスト(ゾンビ宣言)」 ★感覚をもたないゾンビの「思考」の状態とはどのようなものか? ・メルロ=ポンティ『知覚の現象学』から、感覚をもった我々が、どのように世界を受肉するのか考えてみよう?: ・「感覚するとは 実は性質にひとつの生命的な価値を授与することであり、性質をまず何よ りもわれわれにとってのその意味、われわれの身体というこのどっしりした塊にとってのその意味のなかで捉えることであって、そこから感覚することがいつも 身体への照合を伴うということもできるわけである。……感覚するとは、世界とのこうした生活的な交流のことであって、この交流によって世界がわれわれに とって、われわれの生活のなじみ深い場としてあらわれくるわけである。知覚対象と知覚主体とがその厚みもち得るのは、感覚のおかげである。感覚は指向的な 織物であって、認識の努力がこれをかえって解体させてしまうのである」(『知覚の現象 学(1)』竹内芳郎ほか訳、104ページ)。 |
★→文化表象としてのゾンビ.
★ ゾンビリンク集
☆ 人類学の対象としてハイチのゾンビについて考える。その題材は、ゾラ・ニール・ハーストンの "Tell My Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica," 1938(邦訳『ヴードゥーの神々』常田景子、筑摩書房、2021年)である。
リ ンク(ゾラ・ニール・ハーストン)
リンク(文化人類学と複数性の概念)
リンク(歴史)
リンク(存在論と憑在論)
ゾ ンビリンク
文 献(pdf)
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆