James Clifford's critical commentary on Said's Orientalism.
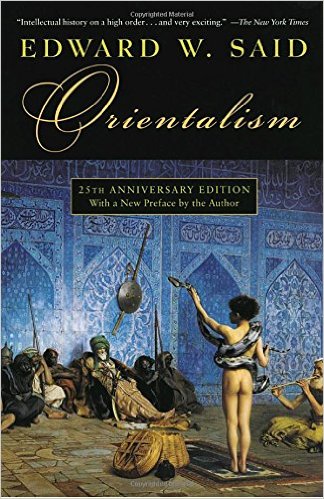
ジェイムズ・クリフォードによる『オリエンタリズム』の書評について
James Clifford's critical commentary on Said's Orientalism.
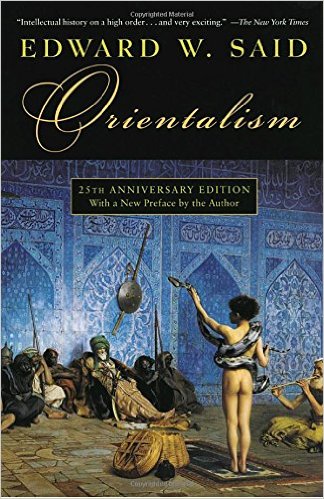
ジェイムズ・クリフォードによる『オリエンタリズ
ム』(エドワード・サイード著)の書評について(「『オリエンタリズム』について」『文化の窮状』所収)
James Clifford's critical commentary on Said's Orientalism.
|
|
|
|
+++++++++++++
■ネグリチュードの言語混淆性
「それはまた新造語を散りばめ、新しいリズムの数々
で区切られたフランス語、だった。セゼールにとっては「故郷」とは複雑で異種混靖的な何ものかだったの
であり、それは失われた起源から救出され、汚辱に満ちた現在から構築され、ひとつの植民地的言語の内部で、しかもその言語に抗ってはっきりと表現されたの
である」(クリフォード 2003:321)。
■文化言説に関する認識論的省察の書
「また、「純粋な」学問などは存在しないという信念から書いてもいる。彼の考えでは、知識は権力と解きがたく結び合わされている。知識が制度化され、文化
的に蓄積され、その定義が過度に限定的になったとき、対抗的知識による積極的な抵抗がなされねばならないのである。『オリエンタリズム」は論争の書であ
り、その分析は辛錬をきわめる。しかしながら、サイードの本はいくつものレヴェルで論を展開しているのだから、その意味を必要以上に限定することは誤りだ
ろう。『ォリエンタリズム』はテクスト批評の真撃な試みであると同時に、いちばん根本的なところでは、文化的言説の一般的なスタイルや手続についての、実
験的ではあるが重要な一連の認識論的省察の書なのである」(クリフォード 2003:323)。
■オリエンタリズムの特徴
1)演繹的、構築的
2)言説
3)「完全に編み上げられた力」(原著 p.6)
4)系譜的なもの(考古学的ではなく)
5)「過度に広汎かつ抽象的に問題を扱いすぎる」(クリフォード 2003:324)。
6)常に体系化されすぎる
■要約を許さない修辞だが、対象の信用を失墜させるのには成功
「サイードの批評方法のもつ複雑な編込みの数々は、
要約というものを許さないーーあるときは才気きらめく、またあるときは強引な連想的方法であり、また最
終的には感覚が麻痺するほど反復的である。しかし少なくとも、一連の「東洋的」ステレオタイプーー永遠不変の東洋、性欲のおさまることのないアラブ人、
「女性としての」異国情緒、ごったがえす市場、腐敗した専制君主制、神秘的宗教性などーーを分離抽出し、それらの信用を失墜させることには成功している」
(クリフォード 2003:325)。
■真理の再構成と知の権威化と他者の本質化を拒む文化の叙述法
「サイードはとりわけ、オリエンタリストたちの「権
威」の批判的分析において手腕の冴えを見せている。問題の権威とは、西洋の書き手たちが薦踏なく我がも
のとしている、父性的温情主義を帯びた諸々の特権のことであり、これらの書き手は、語ることのないひとつの東洋(オリエント)「のために語る」かと思う
と、衰退したり解体してしまった「真理」を再構成し、また、東洋の真正さが消失してゆくことを嘆くかと思うと、たんなるネイティヴの知りうる以上のことを
知っている、というわけなのだ。他者について書くことが苧む再構成的手法への、このような方法的懐疑は、オリエンタリズムにとどまらず、人類学的実践一般
についても有効であるにちがいない」(クリフォード 2003:325)。
■真理への意思を疑うニーチェ的センス
「フーコーの直接的影響の背後に、ニーチェへのアン
ピヴァレントな尊敬の念が存在している。サイードは彼の本の色々な場面で、あらゆる文化的定義は限定的
でなければならず、いかなる知識も権力的であると同時に虚構性を帯びており、いかなる言語も歪曲を孕んでいるという議論に導かれている。そして、「真正
さ」、「経験」、「現実」、「現前」といったものが、修辞的な約束事にすぎないことを示唆している」(クリフォード 2003:326)。
■オリエンタリズムの3つの「意味」=歴史的一般化
「第一に、オリエンタリズムとは、オリエンタリスト
(東洋学者)たちがいまやっていること、そしてこれまでやってきたことを意味する。オリエンタリストと
は、「東洋(オリエント)について……その特定の、あるいは一般的な諸相において……教え、書き、あるいは研究する人のことである」。このグループに含ま
れるのは、文献学者、社会学者、歴史家、人類学者といった、アカデミックな研究者や政府の専門家である。第二に、オリエンタリズムとは、「『東洋』と(た
いていの場合)『西洋』とのあいだに作り出された存在論的・認識論的区分にもとづいた思考のスタイルである」(原著 p.2)
。これに続いてサイードが示唆するところによれば、いかなる著作であれ、またそれが西洋史のいかなる時期のものであれ、その出発点として東洋と西洋との根
本的な二分法を受け入れ、「東洋、東洋の民、風習、『精神』、宿命、等々」について本質主義的な叙述をおこなうものは、オリエンタリズムに属する。最後
に、オリエンタリズムとは「東洋を扱うためのひとつの集合的な制度」であり、これがおおむね十人世紀後半以降の植民地時代を通じて、「東洋を支配し、再構
造化し、権威を振りかざす」権力を行使するのである(原著
p.3)。この三番目の指示は他の二つとは違い、明確に個人を超えた文化的なレヴェルに位置づけられているとともに、オリエントについておよそ語られ、書
かれることすべてを組織し、そのかなりの部分を規定する力をもっ「おそろしく体系的な」メカニズムを示唆している」(クリフォード 2003:327)。
■オリエンタリズムがもたらす知的課題
「「実際上、人間的現実ははっきりと異なった文化、
歴史、伝統べ社会、あるいは人種にさえも見事に分割されているように見えるが、そうやって人間的現実を
分割しながら、そのことがもたらすさまざまな帰結にもかかわらず人間的に生きつづけるということが、いったい可能なのだろうか」(原著
p.45)という問いである。彼の論じるところでは、このような区別の結果として、差別的な、そして帝国主義にとって有用な対立が生み出され、それが「異
なった文化、伝統、社会のあいだの人間的出会いを制限する」(原著
p.46)ことに貢献してしまうという。(付言しておくと、サイードが断罪しているようなわれわれ=彼らの区別は反=帝国主義や民族解放の運動にとっても
有用である)」(クリフォード 2003:329)。
■オリエンタリズムの理論的課題
「オリエンタリズム』が提起しているもっとも重要な
理論的問題は、他なる存在を扱うための思考と表象のあらゆる形態の現状にかかわるものである。異文化や
異なった伝統についての解釈を述べる場合に、二分法を作り出し、再構造化し、テクスト化するような手続から、最終的には逃れることができるのだろうか。も
しそうであるならば、それはどのように可能なのか」(クリフォード 2003:329)。
■言説の一貫性=真実・批判(ルイ・マシニョンの言説批判)
「サイードはマシニョンのイスラーム神秘主義への深
い共感、繊細かつ豊かな表現、さらには搾取されている東洋人たちのための政治的なコミットメントなどを
全面的に認め、惜しげもなく評価している。しかし彼は、この偉大な学者の仕事にしても、結局は制限的な「言説的一貫性」のなかにあいかわらず囚われている
と言う。サイード/はここで彼のもっともニーチェ的な議論を展開する。つまり、いかなる表象も「『真実』というもの以外の幾多の事柄に巻き込まれ、織り合
わされ、埋め込まれ、編み込まれており、その『真実」からしてひとつの表象なのである」(原著 p.272)」(クリフォード
2003:330-331)。
「私たちはすでに、言説という中心的概念に出会っている。サイードにとって言説とは、「テクスト的態度」(原著
pp.92-94)の文化的=政治的布置のことを指す」(クリフォード 2003:333)。
■グローバルな真理
「すなわち、あらゆる人間的表現は最終的には文化の
「古文書館」によって規定されている、そして、グローバルな真理は、「言説的編成」の闘いの結果でなけ
ればならず、その闘いのなかではもっとも強いものが勝利する、という結論である。サイードはこのあまりにフーコー的な結論に不安を覚える。そこで彼は、ふ
たたび超越的なヒューマニズム的基準を持ち出し、結局は「どでも人間味のある存在」であるマシニョンを、いまや彼の「生産的能力」のひとつの「次元」に
す、ぎないらしい制度的規定から救い出す。マシニョンは最後には彼自身の文化を克服し、「より広汎な歴史と人類学」へと向かう。マシニョンの「われわれは
みなセム族である」という言明は、サイードによれば「彼の東洋についての思想が、フランス人とフランス社会というローカルで偶発的な状況をどれだけ超越で
きたか」(原著 p.274)を示すものなのだ。とても人間味のある存在、というのがヒューマニストになる」(クリフォード 2003:331)。
■静的なイメージの構築
「サイードはオリエンタリズムが、歴史的ないしは個
人的な「物語群」よりも、静的なイメージ群を構築してしまうことを厳しく非難している。「人間的な経
験」が、オリエンタリスト個人のそれであれ、オリエンタリストの研究対象のそれであれ、一方ではあらかじめ肯定されている権威の名のもとに、また一方では
一般化の名のもとに、平板化されてしまうというのだ。サイードはこのようにして省略されてしまった人間的現実を、イエイツを引きながらこう特徴づけてい
るーー「そこにすべての人間が生きている『野獣の床の上の御し難き神秘』」、そして「心をあきなう汚れ果てた屑屋の店先」(原著 pp.230, 110)」
■フーコーとサイードの相違点
「サイードのヒューマニスト的な視点は、フーコーか
ら借用した方法と調和しない。フーコーはいうまでもなく、ヒューマニズムのラディカルな批判者だからで
ある。しかし、そうした援用がいかに慎重かつ矛盾に満ちたもので
あっても、『オリエンタリズム』が広汎な文化分析にフーコーを体系的に使った先駆的な試みであることに変わりはない。この仕事が苧むさまざまな困難や成功
はしたがって、歴史家、批評家、そして人類学者たちにとっても、関心の対象であるにちがいない」(クリフォード 2003:333)。
■テクスト的態度は人間的欠点
「このテクスト的態度は、個人がある実際の事柄につ
いて表現できることを決定してしまうような、堅牢な文化的諸定義の集合体となって硬化する。この「現
実」は、言説によって生産された表象群のフィールドとして凝固するのである。サイi
ドは言説的硬化の諸条件については明確には定義していないが、しかしそれらは、技術的に強い文化や集団が弱い集団を定義することを許すーーあるいはそうす
ることを強制するーーような、現在も続く不均衡な力関係にかかわっているように見える。こうして、サイードの分析においては、西洋の文化、がオリエンタリ
ズムの言説を通じて、東洋人たちの活動を「意味、解読可能性、そして現実性」で「満たした」ということになる。オリエンタリズムの言説は、サイl
ドによれば十八世紀後半以降も大きな変化をこうむることなく、オリエントの数々のイメージが織り成す無言劇を生み出したのである。「東洋人と西洋とのあいだの本物の交流」(原著
p.95)は体系的に抑圧された。東洋人は「オリエンタリズムの舞台」では声をもたなかったのだ」(クリフォード 2003:334)。
■フーコーの分析のもつ自民族中心主義
「サイードによる、フーコーの言説概念をエキゾ
ティックな存在の文化的構築の分野に敷衍する一般的な試みには、将来性がある。もちろん、フーコーの企図の
全体は、徹底的なまでに自民族中心主義的である。ヨーロッパの思想の認識論的地層を特定する試みにおいて、フーコーはその他の意味世界へのあらゆる比較言
及を回避している。野生の思考にも、ホピの言語カテゴリーにも、それに類した他の事柄にも、いっさい触れられることはない。フーコーはおそらく、そういっ
たものの助けを借りることは方法論的に疑わしいと考えているのであり、『言葉と物』の冒頭で西洋文明をボルヘスの「中国の百科事典」と対比しているのも、
たんなる気まぐれからのことにすぎない。フーコーが興味をもっているのは、ある文化的秩序が、正気=狂気、健康=病気、合法=犯罪、正常=倒錯といった
言説的定義を使っていかに自己を構成するか、ということである。非正当性の側にある諸カテゴリーは、法の及ばない自由の領域としてではなく、文化的に生産
され、配置された諸経験として存在しているのである」(クリフォード 2003:334)。
■オリエンタリズムの目論見=文書館からの一掃
「サイードはフーコーの分析を敷街し、ある文化秩序
がエキゾティックな「他者」との関係によって外部からどのように定義されるのかという問題も視野に入れ
ている。帝国主義の文脈では、従属的な諸民族や場所の定義、表象、テクスト化は、「内部の」表象(たとえば十九世紀ヨーロッパにおける犯罪者階級の表象)
と同じ構成的役割を演じ、また、同じ帰結を導くーーすなわち、物理的かつイデオロギー的な規律と監禁という帰結である。それゆえ、サイードの分析において
は、「東洋(オリエント)」はひとえに西洋のために存在する。『オリエンタリズム』での彼の務めは、言説を解体し、その抑圧的な体系を白日のもとにさら
し、一般に受け入れられてきた観念や静的なイメージの数々を「古文書館から一掃する」ことである」(クリフォード 2003:335)。
■フーコーとデリダのやり方の違い(クリフォード 2003:335)
■フーコーは状況に根ざした責任ある立場をとっているとはいえない
「全体化し、定義し、本質化しようとする知識と権力
のすべての連携に抗して、排除されたものに代わって遂行されてきたフーコーの疲れを知らないゲリラ活動
を、「状況に根ざした責任ある」と形容することにはやや無理がある」(クリフォード 2003:336)。
■対抗理論における折衷主義
「サイード自身は、フーコー
、グラムシ、ルカーチ、ファノン、またはその他の論者から引き出した複数の「対抗的理論モデル」の、どちらかというと緩やかな寄せ集めを使って議論を展開
している(Said
1979:16)。サイードにとって鍵となる政治的な用語は対抗的という言葉であり、『オリエンタリズム』のような書物の限定的な文脈においては、この言
葉の意味するところははっきりしている。この書物は、おのれの現実を歪曲され否定された東洋人(オリエンタル)の立場から、帝国の言説に対して「書くこと
で応答する」ものなのである。しかしより一般的に見た場合、サイードの対抗的分析からは、西洋ヒューマニズムの諸前提が形作る広汎な領域が抜け落ちてお
り、また、反植民地的な運動、なかでも民族主義的な運動によって生み出される知識と権力の言説的連携も、彼の分析を逃れている」(クリフォード
2003:336)。
■系譜学的アプローチ
「もっとも重要なのは彼が、ニーチェ、かかって系譜
学と呼んだ批判的回顧の構えを採用していることである。これに関しては、サイl ドはフl コl
の後期の展開に忠実に従っている。つまり、『言葉と物』、『知の考古学』に典型的に見られる、地層状の「考古学的」非連続性の方法論から『監獄の誕生』
や、とりわけ『性の歴史』第一巻に典型的な、現在につながっている系譜の提示へと向かう展開である」(クリフォード 2003:336)。
■系譜学の2つの方法
「オリエンタリズムというフィールドは、系譜学的に
二つの方法で分配されている。ひとつは共時的な(ある統一的体系のもとに、西洋のテクストに見られる東
洋のあらゆるヴァージョンを構成する)方法、もうひとつは通時的な(アイスキュロスからルナン、さらには近代的政治社会学や「地域研究」に至る東洋につい
ての一言及を、ひとつの系譜にまとめあげる)方法である」(クリフォード 2003:336)。
■系譜学の限界
「系譜学は、あらゆる歴史的措写や分析と同様、構築
的である。それは、過去から(out
of)選択的に意味を取り出すことにより、現在において意味をなす。系譜学による包括と排除、その物語的連続性、中心か周縁かの判断などは、最終的には伝
統的な慣習によって、あるいは、系譜作成者に授けられていたり、彼が僭称していたりする権威によって、正当化されるのである。系譜学は歴史研究の種々の様
態のなかでも、おそらくもっとも政治的なものである。しかし、それが効果的であるためには、あまりはっきりと特定の立場性を見せるわけにはゆかない。サ
イードの系譜学の弱点はそこにある。さすがサイードというべきか、彼は制限的選択をおこなったことを包み隠さず明らかにしている」(クリフォード
2003:337)。
■オリエンタリズムがもつ現実の問題系の議論との齟齬
「フランスの文脈では、サイードが投げかけている批
判的な問いの数々は、アルジェリア戦争以来いくどとなく問われてきた種類のものであり、一九五〇年以前
にも強く表明されていたとさえ言えるかもしれない。だから、現代アメリカの中東「専門家」たちの言説、すなわち、いまだに冷戦パターンとアラブ、イスラエ
ル両極間の抗争によって輪郭づけられているような言説を批判するようなやり方で、近年のフランスの「オリエンタリズム」を批判しようとしても、それはどだ
い無理な話なのだ」(クリフォード 2003:337)。
■さまざまな「除外」とその帰結
「サイードの第二の系譜学的限定は、検討すべきナ
ショナルな伝統を、イギリスとフランスの流れに制限し、それに/わずかに最近のアメリカでの所産を付け加
える、という形で現れている。彼はイタリア、スペイン、なかでもドイツのオリエンタリズムを除外することを余儀なくされている。高度な発展をとげた十九世
紀ドイツの伝統は、フランスやイギリスのパイオニアたちと比べて周縁的な位置にあるものとして除外されている。だがさらに重要なのは、ドイツの伝統が、フ
ランスやイギリスのように、植民地としての東洋(オリエント)の占有・支配と密接に結びついて構成されたものではない、という理由で除外されていることだ
(原著, pp.16-19)」(クリフォード 2003:337-338)。
■連続性が提示できない弱点
「彼の試みはそれ[=立場性を明示してフィールドを
形成すること]とは違ったものとして構想されたのであり、はっきりと対抗的系譜学を標携している。サ
イードの系譜学が時折その場しのぎの、ぎごちない立論と感じられるにしても(たとえば、あまりにも見え透いたかたちで中東に照準を定め、ヨーロッパ大陸か
らいきなりアメリカの「オリエンタリズム」にジャンプする最終章のくだりなどは、その「連続性」のなかでももっとも説得力に欠ける部分である)、彼の批評
的パラダイム全体をまるごと退ける必要はない」(クリフォード 2003:338)。
■オリエンタリズムと「言説」の混同は避けるべき
「ひとつの「言説」というのが、他者を描出しながら
二分化と本質化をおこなう、そして、植民地支配の一要素として複雑ではあるが体系的に機能するものであ
るとすれば、サイードがそれを遡及的に同定してゆくことはまったく正しい。どこであれ、そのような言説が存在するのであれば、それを識別することは重要で
ある。しかし、言説をオリエンタリズムという特定の伝統とそのまま同一視するべきではない。言説の適用領域はそれよりもはるかに一般的である。この本の問
題点は、少なくとも理論的な観点からすると、本のタイトルにある。サイードは「言説」をひとつの「伝統」から直接引き出そうと試みることで、フーコーの提
案する文化批評のレヴェルを放棄し、伝統的な思想史に逆戻りしてしまうのである。さらにはその言説を、基本的に十九世紀の思考様態を土台にしたものとして
描き出すことで、サイードはあまりに容易な標的を設定している」(クリフォード 2003:338)。
■人類学批判の観点の消失
「彼はフィールドワークにおける出会いの神話、そし
て解釈/学的傾向の文化理論にもとづいた、人類学の正統的潮流を疑問視することがない。それどころか、
そうした正統をサイードはたびたび共有しているように見える」(クリフォード 2003:338-339)。
■テキストがもつ自律性への抵抗?
「「言説」分析を、再定義された「伝統」の上に無理
なく基礎づけることができないのは明らかである。かといって、それを「作者」の研究から引き出すことも
できない。現代のテクスト研究の一般的傾向はこれまで、ある個人主体によるテクスト創造の根拠を、それを生成した、あるいは潜在的に有意味な複数の文脈
(コンテクスト)のうちの、ただひとつのものに還元する、というものだった。作品からのテクストのこうした分離(バルトによれば、「作品とは手のなかにも
つもの、テクストとは言語のなかにあるものである」)の重要性を認めながらも、サイードは現象学に対する、また、作者の意図(志向性)のもつ(書き始め、
書きつづけるという)本質的な機能に対する構造主義からのラディカルな攻撃には抵抗する」(クリフォード 2003:339)。
■作者とはなにか?——『始まりの現象』
「『オリエンタリズム』の前に書かれた『始まりの現
象』(Said
1975)は、こうした一連の問題についての詳細で明快な考察を提供している。多くのモダニズム作家たちが経験した、「作者」であるとはどういうことか、
という問題が、まさにそこでは扱われている。一方に個人主義的な創造性の観念、他方には、「生命と行動の動きゆく力、成形する形、志向性」(p.319)
を、文化的にせよ批評的にせよ、とにかくひとつの外部の体系に還元するというやり方、というこつの選択肢のあいだを複雑な航跡を描いて舵取りしながら、サ
イl
ドはその中間に位置するひとつの分析的トポスを提案し、それを「経歴(キャリア)」と名づける。近代の作者たちの意図とは、作品を生産することよりも、書
き始める(そして書き始めつづける)ことなのだ。経歴とはそういった、歴史的・文化的に位置づけられた幾多の複雑な意図(志向性)の集合体である。それは
つねに形成過程にあり、つねに特定の状況下で始められ、安定した本質も具体的な形をした伝記的な最終地点もけっしてもつこどがない。作者という存在は再度
構想し直され、構造主義による解体から救い出されるのである」(クリフォード 2003:339)。
「『オリエンタリズム』で論じられている作者の誰一人として、『始まりの現象』で提起された複合的意味における「経歴」を与えられてはいない。そうではな
く、全員がオリエンタリズムの言説の例として描き出されている。しかしながら、作者の名前が言説的陳述のさまざまなレッテルとしてのみ機能すると考える
フーコーとは違って、サイードの取り上げている作者たちは、心理的歴史的典型を与えられているといえそうで、しばしば彼らのテクストを通じて代表的なオリ
エンタリズム的経験をもっているように造形されている」(クリフォード 2003:340)。
■マルクス「イギリスのインド支配」のサイードの論評について
「マルクスは「人間の感情」に対する侮辱を告発して
いるーーすなわち、インドの社会生活が帝国主義によって容赦なく中断されて、「災いの海のなかに投げ込
まれて」しまった光景のことだ。しかしマルクスはただちに、「これらの牧歌的村落共同体」が、つねに「東洋的専制」の温床であったことを、読者に喚起す
る。これらの共同体は、「人間の精神をおよそ可能な限り小さな範囲に限定し、それを抵抗を知らぬ道具と化し、伝統的統治に隷属させ、そのあらゆる偉大さや
歴史的エネルギーを奪い取ってしまった」のである。さらにマルクスは、ある、と続ける。イギリスの務めは「西洋社会の物質的基盤をアジアに築くこと」なの
だ。サイードはマルクスによ/る専制への言及と、後のほうに出てくるゲーテの『西東詩集』への言及に、オリエンタリズムの匂いを喚、ぎつけている。彼はそ
こに、東洋を——停滞し、解体され、腐敗した東洋を——元に戻すという西洋全般の特権を前提とした、「ロマン主義的な贖罪のプロジェクト」を同定してい
る。マルクスもまた、「個人」や「実存的な人間のアイデンティティ」を「東洋人(オリエンタル)」、「アジア人」、「セム人」といった「人工的な実体概
念」のもとに、あるいは「人種」、「心性」、「民族」といった集合体のなかに包括したかどで、断罪されるのである」(クリフォード
2003:340-341)。
■マルクスに対して不平等な取り扱いをするサイード——「誤読」の一例(→「カール・マルクス・プラザ」)
(オリエンタリズム批判をマルクスの「イギリスのイ
ンド支配」を題材にあげて紹介した後に)「ここに至って、それまで有効だった解読がコントロールを失い
はじめる。サイードがなぜマルクスを、個人を「階級」や「歴史」という「人工的な実体概念」に包括したかどでも断罪しないのかは不明確である。さらにいえ
ば、もしマルクスのオリエンタリズムへの関与が、実存的、個人的なケースヘ注意を振り向けないことに起因するのであれば、どんなものであれ社会理論や文化
理論がいかにして「人間的に」打ち立てられるべきなのか、という疑問が
浮かんでくる。付け加えれば、よく知られているように、マルクスは「田園生活の愚かさ加減」を見出すたびに、「オリエンタリズム的な」侮蔑や見下したよう
な態度を繰り返した。しかしそれは、そのような停滞した抑圧的状況が、それが改善される前に暴力的に変革されるべきだと信じていたからである。ここではサ
イードはマルクスに対してほとんど「不公平」であるに等しい」(クリフォード 2003:341)。
■マルクスの心情に直接介入するサイード
「彼が私たちに言うのはこうだ。マルクスは最初は東
洋人たちの苦しみに対する「当然の人間的嫌悪」を表現した。そして彼は「人間的共感」、「同じ人間とし
ての感情」を抱いた。ところがごの「個人的で人間的な経験」が、こんどはオリエンタリズム的なレッテル貼りと抽象によって「検閲され」、「感情の波」は
「揺らぐことのない定義の数々」によって抑圧されてしまった、というのである。(サイードは、いかにもこれが実際にマルクスの心に起こった事柄であるかの
ように、過去形で書いている。)「感情の語棄は、オリエンタリズム的学問やさらにはオリエンタリズム的芸術の語彙論的警察行動に屈服することによって消滅
してしまった。ひとつの経験が辞書的定義によって放逐されてしまったの/である。ここまでくると、サイードはフーコーの厳格なページからは、およそかけ離
れたところにいる。フーコーの議論ではいかなる心理化も禁じられているし、作者たちは少なくとも、このような教訓的な「経験」を通過しなければならない義
務を免れている。サイードのオリエンタリズム的言説の描写は、しばしば抑圧された真正さについてのヒューマニズム的寓話によって脱線させられている」(ク
リフォード 2003:341-342)。
■サイードによる人類学的カテゴリーとしての「文化という概念」批判
「サイードは、オリエンタリズムに典型的に見られる
ような西洋文化を、地球上の西洋以外の場所に及ぼされる知識と制度的権力を生み出すことのできる、ひと
つの独立した単位と描き出しているが、その限りにおいてはフーコーやデリダと同じ前提に立っている。このように見た場合、西洋的秩序は帝国的、非相互的、
攻撃的で、潜在的にヘゲモニー的なものである。しかしサイードは折に触れて、近代文化、がエキゾティックなものをイデオロギー的に構築することを通じてた
えず自らを構成してゆくという、より複雑な弁証法の働きを見ることを可能にしてくれる。このような見方からすれば、「西洋」それ自体、が、複雑で移ろいや
すい他者性の、投影、二重化、理想化、そして拒絶の戯れになる。「東洋(オリエント)」はつねに起源あるいは他我の役割を演じる。たとえばルナンは、彼の
「文献学的実験室」で作業をしながら、セム族的東洋という学問的トポスをひねり出すだけでなく、同じプロセスのなかで、ヨーロッパ人であり近代人であるこ
とが何を意味するかについて、ひとつの概念を生産するのだ(pp.132,146)」(クリフォード 2003:343)。
「ここにおいてサイードは……西洋文化は、未開人というフィクションとの関係においてはじめて、自らを批判的に概念化できる、という主張を補強している」
(クリフォード 2003:343)。
■「文化という概念」批判(つづき)
「人類学者たちが用いている文化概念は、いうまでも
なくヨーロッパの理論家たちが、人間の多様性が諸集団へと分節される事実を説明するために発明したもの
である。……)。このあと多くの再定義が試みられたが、文化概念の孕む有機体主義的前提は生き残ってきた。文化システムはそれぞれのまとまりを保つ。そし
てそれらは、なによりも言語と場所につなぎとめられたまま、多かれ少なかれ連続性をもって変化してゆく。文化をコミュニケーションとみなす最近の記号論的
あるいは象徴的モデルにしても、この意味では機能主義的である(Learch 1976:1; Geertz 1973; Schneider
1968 参照)」(クリフォード 2003:345)。
■個人と文化の権威は、他者との関係により構築されるもの
「東洋の「沈黙」が破られたいま、また、[ミッシェ
ル・]レリスが示唆しているように、民族誌が多方向的なものでありうるようになったいま、そして、個人
と文化との両方のレヴェルにおける権威が、他者との関係において構築されるものとして理解されるようになったいま、これらの新たな状況をどのように考える
べきなのだろうか」(クリフォード 2003:346)。
■個人と文化のアイデンティティは決して所与ではなく交渉されなければならない
「これらの処方築が、コンラッドが『閣の奥』のなか
で主張したもの——「故意に信じること」——と同じ性質をもっていることも指摘しておくべきだろう。地
球の文化的未来は実際、レヴィ=ストロースが『悲しき熱帯』で嘆いている均質化(エントロピー)か、でなければ、サイードがもっと悲観的な筆で描き出して
いるイデオロギー的ヘゲモニーのうちにあるのかもしれない(Said
1978a:323-325)。サイードの人間的なるものへのコミットメントもそうだが、文化へのーーすなわち、集団が実際に差異を作り出す継続的能力へ
の——残された信頼は、本質的にはひとつの観念的な選択であり、私たちの時代への——コンラッドの言葉を借りれば、「私たちが、けばけばしくて気の休まら
ないホテルで途方に暮れる旅行者さながらに、仮住まいさせられている」(Conrad
1911:1)この時代への——ひとつの政治的反応なのである。『オリエンタリズム』の長所は、読者をそのような問題群に、同時に個人的、理論的、政治的
に直面させるところにある。著者のサイードにとっては、コンラッドにとってそうであったように、自然な解決法などはありえない。おそらくパレスチナとは、
分断された、そして再創造されるべき国家という意味では、二十世紀のポーランドである。そしてサイードは、彼が尊敬し、頻繁に引用しているこのポーランド
系英語作家と同じように、個人と文化のアイデンティティはけっして所与ではなく、交渉されなければがらないことを認めている。このことは、サイードの最初
の本である透徹したコンラッド研究(Said
1966)のなかでも力説されている重要な点である。このような状況を、亡命者の抱える異常な状況として片づけてしまうのは誤りだろう。『オリエンタリズ
ム』の示している不安定な窮状やその方法論的アンビヴァレンスは、ますます一般化しつつある地球規模の経験の特徴なのだ」(クリフォード
2003:347)。
■21世紀の知識人の課題とは?
「二十世紀が終わりを迎えようとするとき、エメ・セ
ゼールのように「故郷」について語ることにはどのような意味があるのだろうか。文化的アイデンティティ
にかかわる現在のさまざまな経験には、どのような本質、ではなくプロセスが関与しているのか。パレスチナ人として書くということは、何を意味しているのだ
ろうか。あるいは、アメリカ人として、パプア・ニューギニア人として、ヨーロッパ人として書くということは。……少なくとも知識人は、文学的グローバル状
況のなかで、セゼールのように帰還のノートを書くことによって、故郷というものを構築しなければならないのだろか」(クリフォード 2003:347)。
出典:
クリフォード、ジェイムズ「『オリエンタリズム』について」(第11章)『文化の窮状』太田好信ほか訳、Pp.321-348、京都:人文書院 (Clifford, James. 1988. The predicament of culture: twentieth-century ethnography, literature, and art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.)。
リンク
文献
その他の情報
***
☆
 ☆
☆