池田光穂
アレクサンドリアのフィロンによる徳の概念は、古代 ギリシャのそれとは異なっている。
「フィロンは、ストア派とプラトン派の伝統の継承者 であり、その思想のなかでアレテーの概念と名称に重要な位置をあたえた。しかし彼においてこの徳はどのように提示されているのだろうか。ま ずフィロンは、 魂のなかに生まれる徳が神からのものであって、われわれ自身からのものではないことを、飽くことなく強調した。彼によれば、徳は神の恩寵により「外部か ら」または「上から」到来して魂のなかに入る。そこに自己は何ら寄与していない。神のみがその作者である。魂そのものはいかなる卓越性ももたず、ただそれ を憧憬することができるだけである。しかも魂はこの憧憬、および徳に到達しようとする努力さえも自分のものと言うことはできない。それらもまた神に帰すべ きものなのである。神こそがエロースを、すなわち徳への傾向を「あたえる」。フィロンは、神の活動性と人間の受容性との関係を描写するため に種々のイメー ジを用いている、が、特に顕著なのは種蒔きおよび受胎のイメージで ある。それは、当時のグノーシスの世界でも広く見られた準—性的な観念を示唆している。 つまり、魂は女性であり、妊娠する側であって、これが神によって受胎するというのである。「神のみが魂たちの子宮を開き、そのなかに徳を蒔いて魂を孕ませ ることにより、善きことどもを産み出させること、ができる」。この観念がきわめて非ギリシア的であることは、アレテーの原義が本来、自己の活動性として考 えられていたことを想起すれば一目瞭然だ。しかもこのイメージは魂における徳の発生だけでなく、その所有の様態にまで関わっている。というのもフィロンに よれば、徳の起源がこのように否定的意味をもつこと、すなわちそれを自己に帰することができないというまさにその事実のゆえに、その起源の意識が徳そのも のの一つの本質要素とならねばならない(この「ねばならない」は新たな倫理的命令である)からである——この点はきわめて重要で、徳が徳であるための要件 の一つでさえあり、この意識なしに所有される徳はもはや徳でなくなってしまう」。
「ここで問題となっているのは、人間の無性( nothingness)〔人間が無に等しい存在であること〕についての考察である。これは、徳の意味そのものをひどく逆説的な状況のなか におくことにな る。伝統的倫理におけるいくつかの基本的な徳目は、フィロンのス トア派風の称讃にもかかわらず、もはやみずからの内在的な内容に立脚していない。その内容 自体がすでに両義的になっているからだ。新しい意味での徳と悪徳を決定する真の次元はむしろ、それらの徳目の現前にたいして自己がみずからを関係づける仕 方なのである。人間主体は徳をみずからが達成したものと考え、それを自分に帰するかもしれない(そしてこれが卓越としてのアレテーの原義で ある)。ところ がフィロンにとっては、徳をこのように自己に帰属させることは、 それらの「徳」の道徳的価値をいわば消尽させ、むしろ悪徳へと歪めてしまう。それは自己完 成の様態ではなく、誘惑であり、まさに自己完成であるかのように見えるという事実によって、人をまどわすものなのである。「みずからを神に等しいと思いこ み、本当は動かされているのにみずから行動していると信じ込むヌースは、利己的にして不敬虔である。善行の種を蒔き、植えるのは神であるから、私が植える と言うのはヌースの不遜である」(Leg. all. I. 49f; cf. III. 32 f.)。あるいはまた、自己は「私が徳を作ったのではない」と言い、自分が根本において無力であることを認めるかもしれない——そしてこの二次的な反省、 あるいはむしろそれが表現している一般的な態度こそが、道徳的命令の真の目的であり、それ自体が「徳」と見なされる。実際のところこれは自己に徳がありう ることをすべて否定するに等しいのだが——。こうして、アレテーの意味そのものが人格の積極的諸能力から転じて、その無性の知識〔人間の人格が無に等しい という自覚〕に変容される。自分自身の道徳的な力への信頼、それにもとづく自己完成のための一切の企て、そして達成されたものの自己帰属——これらはギリ シア的な徳性概念に不可欠な要素だった——、こういった態度全体がここでは自己愛と思い上がりの悪徳として断罪される。自分自身の無能力の認識とその告 白、魂が自力では到達しえぬものを神が許し与えるだろうということのみへの信頼が神に由来することの承認——これこそが本来の「徳」に属する態度であ る」。
「このように定義された「徳」をフィロンは伝統的な 徳のリストに加える。彼は伝統的な徳も、少なくとも名目上は、保持している。これは、ギリシア的観点と「新しい」観点の折衷という立場にたつフィロンらし いやり方である。新しい徳はリストの冒頭に置かれており、あたかも他の徳目と同じ序列にあるように見える。しかし実はそれらは、他のすべての徳目の独立的 地位を無効とし、それらの価値の唯一の条件となるのだ。これに対応する悪徳についても同じことが言える。こうして、「徳の女王」、「諸々の徳のうちもっと も完全なもの」は信仰でありそれが、神の方を向くことと人間がみずからの無性を認識してそれを軽蔑することを結びつけるこの徳を得るならば、人はその果実 として他のすべての徳も得ることになる。他方、「神がもっとも忌み嫌う悪徳」は、虚栄、自己愛、倣慢、思い上り——要するに、自分自身をみずからの主およ び支配者とみなし、自力に頼ろうとする高慢な態度である」。
「ギリシア的な徳の理念の全面的な解体は、その人間 学的基盤の解体をも含む。「われわれのうちには悪の富があるが、神とともにあるのは善の富だけである」(Fug. et . inv. 79)。プラトンからプロティノスにいたるギリシア人にとって人 間は道徳的な自己完成を通じて神に到達するとされていたのにたいし、フィロンにとってそれ はみずからが無であることの認識による絶望を通じてなされる。「汝自身を知れ」はどちらにとっても本質的要素である。だがフィロンの場合、自己認識とは 「死すべき種族の無性を知ること」(Mut. nom. 54)を意味しており、人はこの知識を通じて神の知識に到達する。「なぜなら被造物、が己れの無性を認識したとをこそ、創造主に出会うときだからである」 (Rer. div. her. 30)。神を知ることと自己を放棄することはフィロンにおいて常に相関している。この連闘で彼が鋳造した印象的なイメージ(聖書のアレゴ リーを用いたイ メージ)には、たとえば「自己からの脱走」というものがあり、また彼が好んで用いるのは「自分自身を飛び立って神のもとへ逃げこむ」というものである。 「自分自身のヌースから飛び立つ者は〈万有〉のヌースのもとに逃げこむ」(Leg. all, III. 29.; cf. ibid. 48)。
「自分自身からのこの逃走は、われわれがこれまで考
察してきた倫理的意味とともに、神秘的な意味も持ちうる。たとえば次の箇所がその一例である、「出でよ、汝の身体〔「国」〕から、感覚〔「親族」〕から理
性〔「父の家」〕からーーさらには、汝自身からも逃れよ、汝自身の外に出て、ディオニュソス的コリュバンテスのごとく神に憑かかれて狂乱せよ」(Rer.
div. her. 69; cf. ibid
85)。自己放棄のこの神秘的ヴィジョンについては、われわれはこれをグノーシス的心理学の文脈において扱わねばならない」。
リンク集
文献
- 出典;ハンス・ヨナス『グノーシスの宗教』秋山さと子・入江良平訳、Pp.370-373 、人文書院。
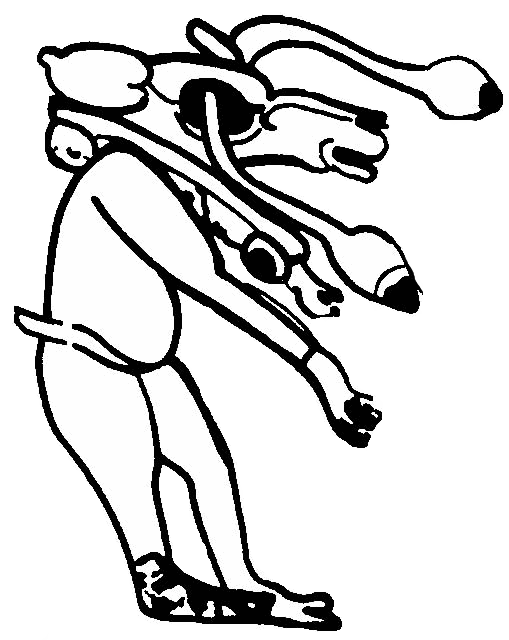
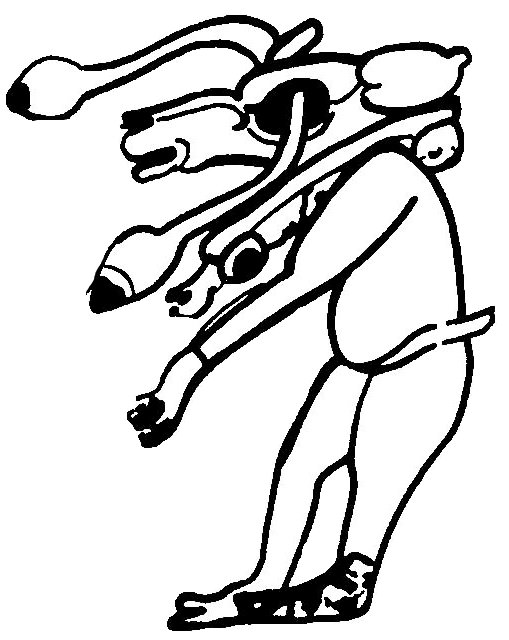
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!