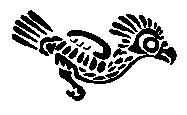
ムブティの狩猟民における「動物残虐趣味」について
On sadism toward animals among the Mbuti people
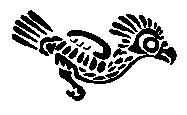
私の関心は、人間と犬の関係の多様な態度の分析にある(→「狗類学[こうるいがく]」)。
さて、ムブティの人びと(Mbuti, Bambuti
かつて「イトゥーリのピグミー(Pygmies
of the Ituri Forest)」と呼ばれた)のコリン・
タンブールの民族誌『森の民』を読んでいるときに、猟犬の態度についても気になる態度をあったために、それを引用してみよう。
■「皆 の注意がそちらに向けられているあいだに一匹のミズネズミジ力、 シンドゥラ(sindula)がモケの網にかかって踠(もが)いていた。/ シンドゥラは最も珍重視されている動物の一つで、小犬 ほどの大きさしかないが、狂暴で危険である。他の者たち が皆エキアンガがソンドゥをしとめるのを助けに離れてし まったため、モケの甥は一人でこの獣のかたをつけねばな らなかった。彼はたぶんまだ13歳そこそこの少年にすぎ なかったが、それに彼の最初の一撃を加えた。彼は獲物の 国目のあたりの肉の厚いところにヤりを突き刺して、地所に 押さえつけた。が、獣はこの一撃にへこたれず、逃げよう と腕いた。網をすでに時み切り、苦痛のあまり、身を二つ に折ってその鋭い歯でヤリの柄に噛みついた。マイペがそ の首もとに別のヤリを突き刺したが、それでも相手はひる まず、逃れようと腕いた。3本目のヤリが心臓を貫くまで、 獣は抵抗をあきらめなかった。/ 私がピグミーたちから心の隔たりを最も強く覚えたのは このようなときである。彼らは瀕死の状態にある獣のまわ りに集まって、指差したり笑ったりした。一人の九歳ぐら いの男の子などは地面に寝転ろび、グロテスクな身振りで// シンドゥラの最後の腕きをまねて見せた。男たちは、それ ぞれヤリを引き抜き、こんなちっぽけな奴を恐がるとは奇 妙なことだ、とへらず口を叩きながら、引き裂かれ血にま みれた死体を蹴った。そのうちマイペの母親、がやってきて、 血まみれの後足をつかみ、肩越しに背中の緯の中に放りこ んだ」(タンブール 1976:85-86)。
■
「また、これは別の機会に目撃したことだ、か、彼らはまだ
生きている烏の羽根をむしり取り、時間をかけて殺したほ
うが肉が柔らかい、と説明した。猟犬にしたところが、貴重なものであるはずなのに、
生まれた日から死ぬ間際まで、
こき使う。また、獣にしろ鳥にしろ、猟犬を除けば、家で
これを飼うなどという例には一度も出あったことがない。
ピグミーたちにこの点を私、が指摘すると、彼らは私を馬鹿
にしたように笑ってき口った。「わしらは動物を食糧として
森からもらうんだ。この結構な贈り物を断わって飢え死ん
だほうがよいとでも言うのかね?」こんなふうに言われる
と、七面鳥飼養場や感謝祭のことを、それに、われわれ自
身の社会が何百万という動物を殺して食用にする目的だけ
で飼っているのを思い出さないわけにはいかなかった」(タンブール 1976:86)。
さて、狩猟民が猟犬に対してこのように残酷かというとそうでない事例もある。
イトゥーリの森から2,000キロも西の熱帯雨林に住む狩猟採集民バカ・ピグミー(Baka) を調べ てい る大石高典さんによると、一緒に猟をするには、観察にもとづく、一定の評価と犬の固有性についての解釈をおこなう。
■「カ
メルーンの熱帯雨林にくらす狩猟採
集民バカ・ピグミーのキャンプには決まっ
て犬がいた。どこかに行くときには、かな
らず犬を連れてゆく。犬は森の中で動物の
気配を感じると、いち早く人に知らせる。
人と野生動物のあいだに犬が入る。犬は狩
猟に欠かせないだけではなく、人と犬の距
離が近くて、まさに人と生活を
ともにしている感じがしたも
のだ。/
狩人は猟のパートナーである犬に特別
の思い入れをもつ。経験豊富な狩人にたず
ねると、「最近の犬は飼い主への態度が悪く
なった」といって、目の前の生きている犬
よりも死んだ犬について多くを語ってく
れた。/
アンデマニヨ(バカ語で、「もし、知って
いたのなら」の意味)は、飼い主マイケルの
義理の兄コリンの犬だったが、コリンの妻
だったリンダになついた。コリンとリンダ
が別れたとき、アンデマニヨはリンダにつ
いてきたのだが、リンダはその犬をマイケ
ルに贈った。アンデマニヨは勇敢な犬で、
最後は狩猟中にアカカワイノシシに殺され
た。マイケルは、5年間飼って死んだアンデ
マニヨを思い出しながら、「最近の犬はどこ
でもうろつくが、この犬はずっと飼い主の
周りにいつもいてくれた」と語ってくれた。
病気で死んだ犬、モクンゲンジャ(バカ語
で「ヘルニア持ち」の意味)は、1匹でゴリラ
を噛み殺した猛者だったが女癖が悪かっ
た。飼い主といっしょに訪れたほかのキャ
ンプに気に入ったメスがいると、どんなに
遠くても夜になるとそのキャンプに舞い
戻ってきた。そういったエピソードがたく
さん出てくる。/
カメルーンの森の犬の生きざまや死に
ざまは、英雄談ばかりではなく苛烈なもの
もある。犬たちは、飼い主の罠にかかった
り、川を泳いでワニに喰いつかれたり、毒ヘ
ビに噛まれたり、といった運命をたどる。
しかし、死してなお深い共感をもって語ら
れる犬は、ただ狩猟のための道具と片づけ
られる存在ではけっしてない」(大石 2016:12)。
もちろん、大石さんの調査は2002年から現在(〜2017)まで続いているものに基づ くものであり、今から40年以上前に出版されたムブティの人たちの情報を単純に比較することはできない。
さて、犬に対するこれほど対比的な扱いがあるという事実は、同じ熱帯雨林の狩猟をめぐる サバイバルのための環境要因——タンブールの記述を読むと他ならぬムブティ自身が「彼らの流の環境要因」で説明[folk theory]している——では説明することができないだろう。
動物に対する態度は、社会階層の間で多様であり、また長い時間のスパンの間でも、変化す る。動物愛護の先進国のEUヨーロッパのフランスでも、18世紀(1730年代)にパリのサンセベリン通りの印刷工たちの間で(残酷な雇用者に対する[プ ロレタリアートの反逆にはるか先行する形の]「抵抗」表現として)猫への虐待のみならず、大虐殺がおこなわれのだと、歴史家のロバート・ダーントンは記し ている(Darntom 1984)。その猫たちは、雇用主の印刷業者の夫人たちの愛玩動物であったのだ。印刷工たちは、猫を捕獲し、虐待するのみならず[魔女裁判のように]「裁 判」にかけ、吊るして「処刑」までおこなったという。すなわち「動物に対する態度は、社会階層の間で多様であり、また長い時間のスパンの間でも、変化す る」—— これをロバート・ダーントンのテーゼ(命題)と言ってもいいだろう。
ヨーロッパにおいて18世紀になると、動物虐待への関心がうまれるが、それはジョー ジ・ボアズによると下記のごとくである。
「18世紀はあらゆる点で反デカルト的であった.へスター・へイステイングズ
(1936)は,動物生活へのいかなる科学的接近方法が哲学的なものに先行し
たかを明らかにしている.人間が先人たちの教義にあるセリオフイカルな洗練に退屈しなかった間に,セリオフィリーは人間生活の評価というよりも動物受難に
対する感情となった.このような感情は熱烈さを増し,動物愛護協会というものを発足させた1824年にはアイルランドの下院議員リチヤード・マーティンの
尽力によって,動物虐待保護王立協会(Royal Society for the Prevention of Cruety to
Animals) が設立された.アメリカ合衆国では, 1866 年にへンリー・パーグによって動物虐待保護アメリカ協会(American
Society for the Preventionof Cruelty to Animals. A.S.P.
C.A.)が設立された.獣たちは物質的な魂を持っているのかそれとも非物質的な魂を持っている、のか,彼らは論理的に考えることができるのか否か,彼ら
は苦しみを感じるのかどうか.こうしたことは結局のところ,獣と人間とのあいだの緊密な関係を作り出すのに十分であるのかどうか,と考えられるようになっ
たのである.獣たちの理性的性質という問題については,本能とその想定される驚異的な力がそれに取って代わった.つまり科学的な動物学が博物学のなかに場
を得,セリオフィリストたちを強く動かしていた諸問題が,書斎でなしに,実験室や現場の中に移されていったのである」(ボアズ 1990:
143-144).(→出典等は「動物優越論」を参照)
動物に対する、この虐待趣味とは正反対の人間による趣味を「動物優越論(セリオフィリー:Theriophily)」という。これは、動物は人間
の同等ないしはそれ以上に理性的で、道徳的で、そして人間よりも幸せであるという、歴史上の過去から現在までにみられる思考あるいは趣味をそのように表現
する。
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
For all undergraduate students!!!, you do not paste but [re]think my
message.
Remind Wittgenstein's phrase, "I should not like my writing to spare
other people the trouble of thinking. But, if possible, to stimulate
someone to thoughts of his own," - Ludwig Wittgenstein