「生駒の行者像」試論
「生駒の行者像」試論
Esoteric Shamanism in the Ikoma mountains,
Osaka-Nara, Japan

1. はじめに
本稿は、生駒の修験系寺院における“行者”に対しておこなった聞き取り調査——特にインタ ビューと参与観察——によって採取した“資料”の再構成とその解釈である。
【ここで生駒山系について不案内な方に説明します】
標高六四二メートルの生駒山を中心として南北に連なる生 駒山系は万葉集にも数多く詠まれ、また奈良と大阪を結ぶ交通の要所として栄えてきた。生駒山そのものを神山とみたてて往馬坐伊古麻津彦、伊古麻津姫を祀る 生駒神社や、生駒山口に対する生駒水分の神が祀られていた生駒山口神社の存在は、元々が山全体を信仰対象とした「神奈備信仰」の一形態であると考えられて いる。このような神道的な対象としての神体山や磐座が後に仏教信仰の場に取って代わる例は、吉野の金峰山、東北の羽黒三山などの修験道場にも数多くみら れ、神仏習合の形態を色濃く残していることがわかる。
生駒山中の街道の要所には数多くの石仏、仏塔の類が残っており、それにまつわる伝承や奇蹟の一端は今昔物語などの中世の説話からうかがい知ることができ る。それは、また組織的な修験道の信仰体系に組み込まれる以前には*(5)、農産物の収穫や雨乞いを祈願する民俗的な山岳信仰(ダケノボリ)として近隣の 村落共同体の人びとの崇敬を集めていたと考えられている*(6)。
生駒の修験道に関する寺社の伝承には、役行者や弘法大師が行を積んで行場を開いたり遺物を残したと言う歴史説話的な形式が多く見られる*(7)。しかし このような伝承は単に逸話だけに留まらず、現在でも行者のイニシエーション(=行者になる契機、加入儀礼)や修行にまつわる経験のなかにしばしば登場し て、そこで活躍する彼らの呪術力の源泉に歴史的な根拠を与えている。
生駒山系はこのように古い時代から聖性を持っていた。しかしながら、修験道最大の行場のひとつである大峯山系のような組織・系統だった行場としては展開 しなかった。その理由は明確ではない。中世以降、そこに国家あるいは貴族の庇護による宗教的センターが作られなかったこと、比較的低い山系であること、交 通の要所としてあり<神秘性>に欠けることなどが大規模な宗教センターとして発達しなかったことが、その理由として挙げられよう。しかし、このことが逆に 現在に至るまで、人々に手軽な「聖域」を提供することに成功したのである。聖と俗が交錯する位置に生駒はある。
出典はこちら:池田光穂「治療の文化的構成」
行者とは「広義には仏道に入って修行する者‥‥。狭義には山岳において峰入りなどの修験の行を 修する者」(1)を言う。しかしながら、生駒山系に定着あるいは出入りしている宗教的職能者と信者の間では、個々の規定やイメージには差はあるものの、漠 然と“呪術力を駆使して、透視、予言、徐災、病気治療などをおこなう能力のある者”と見なされている、と言ってもよいだろう。本稿の事例において検討する 多くの“行者”は修験系の教団に属するものであるが、先にあげた修験道独自の「峰入り」という様式化を踏まないことも多く、“生駒において使われている慣 用法”に従ってそれを理解する。
本稿の目的は、当事者ならびに周囲の人々の語りによって描出される生駒の“行者像”を構築し、 それを整理することにある。調査を通してしばしば聞かれることは、行者についてのパーソナリティに関する言及である。そこには、“行者とは 〜 のような ものだ”といういくつかの“言説”=説明原理がみられる。この言説は、その語りを理解する研究者の側においても共有されることもあり、行者についての大き な言説(の体系)の一部を構成しているとみなすことができる。また人々によって共有されているこのような説明原理が、行者そのもののアイデンティティに フィードバックしている可能性も否定できない。なぜならば、社会的相互作用が生起するミクロな場においては、行者−信者関係というものがあり、役割行動と 役割期待の交流といったものが存在するからである。
そして、このような語りについての再構成を試みながら、行者の“資質”に関する宗教社会学的な 説明——例えばカリスマ性、あるいは宗教的入信や行者の“生成”に関する宗教心理的な説明——例えば剥奪仮説、などについても再考することを筆者は同時に 狙っている。なぜ、このようなことを検討しなければならないのか。それは、例えば、我々宗教を研究する者の多くが、行者や信者たちから「霊能力のもったも のが集団の中で“生き残る”(=淘汰される)」あるいは「寺の隆盛は創始者の行者の霊能力のおかげ」という言説を調査の過程で聞かされ、その現象を解釈す る際にこのようないくつかの既存のパラダイムにあてはめてしまい、その細部について検討する判断力を失ってしまう危険性があるからである。あるいは、“生 駒行者のカリスマ性の分類”云々といった作業に専心してしまうという陥穽があるからである。問題は、カリスマ性の妥当如何ではなくて、細部を検討すること なく類型化に向う研究者の“批判的な精神の欠如”なのである。
そこで、1982年から83年にかけて採集された二つの寺院(A寺院・B寺院)における“行者 たちのライフ・ヒストリー”(2)を中心に、聞き取りによって得られた資料が、どの様に、解釈者である筆者の側に引きつけられ編集されていったかを、個別 の事例報告を通して提示する。
2. 事例 I .A寺院
2.1 一般的素描
A寺院は、昭和10(1935)年に現在の住職(“総主”)のDさんの先代で、Dさんの父親に あたるCさん(故人)が寺院を建立したことに始まる。この寺院は最初はきわめて小規模なものであったが、予言や透視などのCさんのたぐい稀なる霊能力に よって信者が集まり、その人たちの長年の帰依と喜捨によって、大寺院になったと言われている。
Cさんは、一代で築いた寺院を長男に継がせようとしたが、本人の拒否にあい、これを果たせない でいた。しかし晩年は、寺で長年修行を積んでいた三男であるDさんに信頼を寄せ、彼のほうに継がせる決意をしていたと言う。
A寺院のケースにおいて、焦点が当てられるのは、「カリスマ性豊か」あるいは「単なる呪的カリ スマを乗り越えた存在」と表現された寺院の創設者であるCさんと、当時寺院の継承者と目されたCさんの息子であるDさんの、それぞれの発言の内容である。
Cさんは、調査当時高齢で、また筆者には体系的にライフ・ヒストリーを語らなかった。Cさん は、生前に信徒会報に自伝めいた話を、第三者のライターの手を通して語っており、没後はDさんの編集によってまとめられている。筆者との間で交わされたC さんの発言を理解する上でも、(第三者の語り口を通した)彼のライフ・ヒストリーを整理しておくことは不可欠であるので、最初に掲げる。これは1982年 当時、寺院提供の資料をもとにCさんのライフ・ヒストリーを筆者が要約し、それに注釈をほどこしたノートをそのまま再掲したものである。なお、固有名詞な ど具体的な情報は改変してある

初代Cさんが、昭和 初年に八代龍王大神の神示にて昭和 10(1935)年に遷宮、以来 伽藍建立に一意専念精進し、現在 敷地 3万坪、建坪1千余坪の境内を有す(寺院HPより、写真は1930年)。
2.2 筆者によって整理されたCさんのライフ・ヒストリー覚書と注釈
Cさんのライフ・ヒストリー。 明治34(1901)年大阪に生まれる。小学校中退後、芝居小屋雑役を経て、11歳で大阪陸軍幼年学校給仕となる。小学校夜間部入学。そこでA氏と知り 合う。小学校卒業後、幼年学校の理科の助手となる【理科助手の経験】。21歳のとき学校の廃校により失業。東京でメッキ会社に就職。3カ月で離職。玉造の マッチ工場を皮切りに工場を転々とす。
○○鉄工所に就職(23歳)。酒と女の日々を過ごす。組合の委員長的存在となる。大阪同盟 ○○支部の専従となり、組合運動に熱中。24歳、最初の女性と離婚(結婚3カ月で?)。特高に組合からの離脱をすすめられる。(結核による)喀血による病 床生活。【←Crisis】回復途中で養鶏所に手伝いに出る。すぐに離職。
A氏との再会。大正14年9月生駒の八代さんへA氏とお参りにいく(24歳)。B師ならび に○○師との出会い。参篭の翌朝「八代さんのおかげをいただく」はじめての水行をおこなう。【←宗教との出会い】。一週間の参篭。4日目に信仰の生活に入 ることを決意、B師のすすめ。(1年後の)昭和元年9月入信し千日の行をはじめる。当日の夜「八代大神のお告げ」千日満願(3年後?)【→これより神示は 頻繁にもらうことになる】★昭和4年現在の場所で開山することを決意(それまで○○に通う生活)。昭和9年9月B師死亡。同年再婚。昭和10年10月○○ に移転。昭和10年の信徒数245名。昭和15年最終的な遷座。
★★昭和25年5月重大な神示を受ける。「水は流れて清浄となる/気は動いて清浄となり/ 雨降りて大地清浄となり/人働いて清浄となる/身体、万物みな無常となる/これ清浄なり」以後、「働きこそ人に与えられた使命」。毎日欠かしたことのない 水行をやめる。苦行をすてて悩む人に接していくことが大切になる。【←行に対する考え方が根本的に変わっている】 昭和26年5月本殿落慶。昭和31年妻死亡。昭和32年再婚
このことから、筆者はCさんのライフ・ヒストリーの中のなんらかの契機=結節点を見つけ出そうと していることが分かる。すなわち、1.入信前の社会経験、2.人生における危機、3.宗教との出会い、彼の宗教体験における、4.“道徳的秩序”の形成あ るいは変 化、5,常態的な“超自然的体験”(=神示)などを鍵にして、調査者が“彼の人生”を因果的に理解していこうとする姿勢が容易に読み取れる。
もっとも、これそのものが調査者自身の認識論的な枠組みによる被調査者であるCさんのリアリ ティを“暴力的に切り刻んで勝手に再構成したもの”とは一概に言えない。このノートのもとになった資料は彼の監督のもとに第三者によつて編まれたものであ り、信徒会報に掲載された、言わば“正史としての”性格を有するものだからである。(3)
オーソライズされたCさんの“宗教者としての人生”とは別に、調査を通してCさん自身が語った ことのなかにも、彼自身の姿をみることができる。そこで、生前のCさんが語ってくれたことを中心に、別のかたちの再構成を次に提示する。
2.3 行者Cさん——インタビューを通して
彼のライフ・ヒストリーにおいて、理科助手時代について筆者が注記した(㈰)のは、そのことが 彼の生命観を形成するよすがとなっていたのでないかと理解していたためである。彼は、「なんでも、見聞することはええことや。昔(代用教員をやっていた 頃)、動植物や物理の知識はいろいろ役に立った。(顕微鏡を使って)一滴の水のなかにも、あれだけの生き物がいることがわかった」と述べている。
調査当時、彼は人生における自己の危機体験(㈪)を述懐することは少なかった。それは、信者に 対する法話や相談においても、きわめて抽象的な——“血を吐いて死ぬことを覚悟した”程度の——かたちで言及するに留まっていた。A氏の導きによってCさ んは生駒にお参りに登るが、彼の心のなかで、どのようなことがあったのだろうか。
宗教への入信の要因として、専門の研究者はおろかごく普通の生活者においても言及されるものの うち、“剥奪”は最もポピュラーなものである。事例において、それはこの時期に起こったと解釈されている。そして、それを裏付けるような出来事(最初の女 性との離婚、特高による組合離脱の勧告、結核による喀血など)が列挙されている。もっとも、彼のライフ・ヒストリーを構成する際に“剥奪体験”として事後 的に思い起こされたものなのか、生駒のことを紹介した友人A氏との邂逅とそれらの諸体験が“決定的要因”であったのかは定かではない。
Cさんの宗教との出会い(㈫)は、生駒山上で出会った「静かな先生だった」宗教的職能者のもと で祈祷を受けたことに始まる。しかし、「先代の先生」から伝わった種々の行の作法の他には、その影響についてCさんは多くを語らなかった。むしろ、その作 法を通して実践した修行時代のことをよく語った。
「昭和4年ごろ、千日の行を行なっていたときは、山頂から5丁ほど下の“薬師の滝”に行に出てい た。滝場の前に小屋を建てて、1日2合のおかいさん(粥)だけでやっていた。毎朝4時頃起きて、滝行を一時間ほどやり、お勤め(読経)をして、その後、朝 食の粥を取った。7時ごろ生駒山上にいって、昼には小屋に戻ってきて座禅をする。そのような行をおこなって15日ほどを過ぎると、歩いてゆく道が3本に見 えてくる。1本のろうそくも3本に見えてきて、ほっぺたを叩いたもんや。21日(満行)を終わって、“終わりました”と言って空を見ると、星がさーっと降 りてきて、体のなかを通り抜けた」。
Cさんが行なった修行の厳しさについては、古くからの彼を知っている信者などによっても、彼自 身の“意思の強靭さ”や人柄の厳しさ・険しさ(=“こわさ”)と相まって、よく知られている。例えば「山に上がってくる前は、睡眠を克服すること第一の目 標としたから、片目づつ瞑って睡眠時間を短縮した」という。Cさんは、修行をおこなうことを通して“神示”を受けるまでに至った、つまり“獲得された”こ とであると主張した。しかし、それは“厳しい行”を通してのみ可能となることではなく、「すべては八代[龍王]さんのおかげ」なのである。
また、修行というものはCさんにとって——そして多くの行者と呼ばれる人たちにとっても—— 「無我でなにも考えない」ものだという。これは後述するように、Cさんが修行を、滝行、座禅、読経といった宗教儀礼的な様相をもったものから“日々の働 き”そのものであると劇的に規定しなおした後になっても、“考えずに実践する”という理念は常に引き継がれた。加えて、Cさんにとって修行がもつ独自性 は、宗派や行者の集団といった組織そのものをも二義的なものにしてしまう。「修験の行者は外側だけで、十分な修行をしてない。自分は○○(宗派名)に属し ているが、それは形だけで、自分が信仰するのは“八代[龍王]さん”だけや」。
このような理念は、ノートを取りながら聞き取りをしていた筆者に向かっても「言葉や文字で表わ すことはできん。まず、(信仰は)自分で体験せなあかん」と語り、寺院に居住していた弟子たちに対しても「人間辛抱せんとあかん。文句ばっかり言うて、体 を動かさんやつは、やっぱりあかん。辛抱の“棒”を持たんとあかん」と叱咤した彼の言葉に表われている。また、寺院正面の掲示板にあった「行フ、ネテモ、 サメテモ、まじめに」というスローガンにも垣間みることができる。彼は“日常的行”というイデオロギーの戦士だったのである。
ところで、Cさんが当初行なっていた滝行には行の理念の達成の他に“穢れを落とす”ということ もあった。それが、先に触れた昭和24年の重要な神示によって変わることになるのである。
「なぜ滝行をしたのか。それは、ひとつには自分の行のために入ったのであり、他のひとつは、夫婦 生活をしていたので(自分自身が)穢れており、その穢れを落とすためにやっていた。しかし、ある日、神さんのお告げがあった。それは夫婦が円満に生活する ための夫婦生活は穢れや不浄やない、ちゅうことやった。それから、滝行はやらんようになった」。
「人働いて清浄となる」という神示——あるいは“行”の規定の変更——は、行動面においては滝行 の停止とそれに代わる「働き」という行の開始というかたちで現われた。彼の宗教的体験における“道徳的秩序”(㈬)が転回したのである。それはまた、早朝 における“お勤め”に採用されている『理趣経』読経にも反映されている。「朝に理趣経を唱えるのは、理趣経の教えが世の中を清浄にする」ということだから である。
A寺院における修行の内容が、密教ないしは修験道系における苦行から、日常生活における「働 き」に変わったことは、寺院経営とその後の寺院の発展にとって、非常に示唆的である。働きとは、息子のDさんや弟子たちに言わせれば日々の「土方仕事」で あり、信者に対しては「真面目に生業を全うする」ことに他ならない。すなわち、宗教的職能者に要求されていた“宗教的苦行”を寺院整備のための労働力に転 化させ、信者の霊能力への期待の中にある現世利益信仰を、“働き”というマイルドな世俗内禁欲へと向かわせた。それはさらに、掃き清められた境内、磨かれ た床、簡素な拝殿の装飾など、初めて訪れた人が感じる、およそ“呪術の園”からは縁遠いこの寺院の情景にまで反映されている。
大正末期から昭和初期に生駒山系を中心に活躍した行者たちにとって、“霊能力”つまり、常態的 な超自然的体験や感覚(㈭)の意義は大きい。例えば、Cさんにとって「八代八重姫龍神の感得」は次のように語られた。「八重姫は生駒山上におった。金色の 亀が赤い蛙になって現われた。自分が捕まえると眼が見えなくなったが、周りから神さんが出てくるのが見えた」。また、インタビューとも雑談ともつかない話 をしている時に、「いま、(筆者と)話していても、朝鮮海峡が見える。朝鮮海峡に橋がかかっていて、それが揺れている。密輸に注意せよ」とCさんが語る状 況があった。最後の“密輸”の意味について、Cさんはそれを詳しく語ってはくれなかったが、シャーマニズムに広くみられる変性意識状態といったものがここ でも展開する。この感覚は常態的であり「朝夕の回向で般若心経を唱えるとき、 それぞれの巻が終わったら、神さんの“よし”という声が聞こえる」という。
霊能力については、Cさんが81歳当時このような状況にあった。しかしながら、筆者自身の関心 ——それはまた宗教現象に興味のある人にとっての関心でもあろう——から問いかけてみた“憑きもの”や“水子”には、Cさんは否定的であった。
「キツネやタヌキが憑くことは実際にあるが、こういうことはあまり言わんほうがええ。もっともキ ツネやタヌキの住んでいるところが少のうなっているのに、(それらの憑きものが)減るのは当り前や」。 「水子の霊が無いとは言えんが、そんなものはほとんどあらへん。この寺の信者に(対して)は、墓場に地蔵があるので、そこへ参れと言っている。水子で金儲 けするちゅうのはけしからん」。 総じて、調査者が“霊能力”云々について特異な関心を持つことに関して、それは“本義ではない”ことを彼はくり返し語っていた。「霊能力みたいなものは、 あんまり濫用せんほうがええ。それはお金のようなもので、場合に応じて使い分けたらええんや」。
霊能力体験を常態的にもち、それを信者との関係においても十分に発揮していたCさんに対して、 筆者が呪術的雰囲気をつよく感じなかったのは、先に述べたような宗教的苦行から日常的“働き”への“道徳的秩序”における転回の結果であり、またこのよう な霊能力に傾斜しすぎないCさん自身のバランス感覚によるものであろう。そして、このようなスタンスは、生涯において出会ってきた呪術的“行者”に対する 批判からもうかがえる。
「○○○(寺院名:生駒では比較的有名だった同時代の行者のことを指している)は、昔の行者や。 いつも“大きいことを言うてた”。生きているうちに“開山堂(4)”を作りよった。儂は好かん」。
「昭和8年頃、(兄弟?)弟子は10人ほどいた。そのなかで素質をもった者が、2、3人いたが、 山を降りて“先生”になるとだめになった。みんな自惚れたからや」。
Cさんが亡くなる3年前にインタビューが取られたが、そのとき寺院では“後継者”について、あ らゆる人々——本人、子息、弟子、信者、そして調査研究者たち——のあいだで公にあるいは密かに話されていた。ほとんどの人たちは、「それはやっぱり、親 子関係や」という弟子の一人が語るように、三男のDさんが次の代を継承することを当然視していた。Cさんは筆者に対して、寺院組織の成長について「寺の外 観はもう終わった、次は中味や」と話す一方で、「自分の遺言は決めてある。『神様にお仕えして働く、24時間働く』や」と、自分の時期が終わることを示唆 する発言をおこなっていた。そして、自分の子供たちが寺を継承することに対して、「○○(長男の名前)は、この寺に生まれてきたことを“あたりまえ”やと 思うとる。自分は、今まで(八代龍王の)“お告げ”のままにやってきた、あとは、(三男の)Dでも○○がやろうと、どうでもええ」と言い、またDさんのこ とを「現代的や」と評していたのである。
2.4 Dさん——創始者を継ぐもの
DさんはCさんの三男で、1992年現在寺院の二代目“総主”である。しかし、調査当時は、C さんの長男が寺院を継がない——彼は会社員としての仕事をもっていた——かも知れないという“雰囲気”のなかで、Dさんは積極的に寺院の職務を遂行してい た。Dさんは信者、弟子たちの間でも好感のもてる気さくな人だと見なされていた。実際、筆者が寺院に寝泊まりして“調査”した——寺院には“お勤めへの参 加”ということで許可された——が、信者たちに筆者=“その場には不適切な調査者という存在”を紹介する時もDさんは冗談を放って座を和らげたりしてい た。
彼は筆者の質問に対しても積極的に応えた。以下は、Dさんが述べたライフ・ヒストリーを筆者が 書き留めたものである。話題の展開もほぼ時間的な経過に沿って出てきた。
「子供の頃は病気がちで赤痢や結核で苦労した。自分は学校にもあまり通っていない。19歳の時ぐ らいからダンスホールに出かけたりしとった。25、6歳になるまでは、いろいろなところで遊んだり、喧嘩をしたり、また刀を持った男に追いかけられたりも した。このままでは、自分はヤクザになると思ったし、また家のものも見放していた。
自分はこのままではあかんと思い、○○(宗派)の[養成所である]○○学院に入った。○○学院 では(修験や密教の)作法ばかり教えてもらったが、肝心のその作法の意味や理由を教えてはくれなかった——しかし、これはどこの宗教団体(の養成機関)で も同じような事情ちゃいますか?。とにかく、そこで免状をもらって家(=寺院)に帰ってきた。
それからは、四国や秩父などのいろいろな霊場を寝袋などをもって回った。高野山にもいった。高 野山には“行”を教えてくれる養成所がありますけど、もう免状をもらっても仕方がないので、(養成所には入らず)高野山の寺で“行”(=密教の儀礼の作法 など)を中心に教えてもらいました。しかし、そこでも儀礼の作法を教えてはくれるけど、その意味や理由については教えてくれない。
いろいろなところを回って家に帰りましたが、やはり何も分からなかった。それから、何をやって も実感がわかない。お経を念じても別のことを考える。滝に入っても“こんなもん水泳みたいなもんや”と思ったりした。先生(父親であるCさん)に言わせる と『神さんの手がすーっと体の中を通る感じがする』というが、自分にはない。それが、原因で一種のノイローゼのようになり、このままでは“気が狂う”と感 じた。
自分の悩みを先生に打ち明けると、先生には“一心にそのことしか考えたらあかん”と言われた。 そのようにして行を積んでいくと、自分なりに分からんかったものが、次々に分かるようになってきた。ちょうど、ぼけっとしている時に、ビンタを喰らわされ ると“痛い”と感じるように。これは、言葉では説明しにくいけど。好きな女で、惚れて惚れて惚れぬいて、やっとできるようになったキスは、成行きまかせの キスとは全然違うやろ——それでいて、やっている行為そのものは同じやろ。しかし全然、真実味が異なる。
それから後は、すっきりと苦痛なくお経が読めるようになり、前のような“変なこだわり”はなく なった。(宗教者としての自覚ですか?——と筆者が相槌をうつと)そんな、ええもんやない」。
「修行とも言えないが、寝袋をもって四国霊場、小豆島、秩父などにいった。どこへ行っても、(修 行というものは)自分の問題なのやから、“こんなことをして何になるんや?”“お経を読んでも何にも分からへん”という気持ちで、気ばかりあせった。毎日 いらいらしたり、人にあたったりしていた。頬っぺたでも、叩けば“痛い”と思ってはっとするが、そんな感じが全くなかった。嫁さんもらって精神状態が安定 してきた。(余裕がでると)お経を読んでも、ときどき自分の声が外から聞こえてくるようになる。そういう様になって、人に対する気持ちが素直になってきた り、人にあたらなくなり、(行に対しても)あせらず、落ちつくようになった」。
Dさんの宗教者としてのライフ・ヒストリーの中には、父親であるCさんと同じような“剥奪”が 宗教との最初の出会いとして語られている。すなわち、人間として安寧でいることからの剥奪=「自分はこのままではあかん」である。これは、彼自身が一般論 として語っている宗教の入信についての因果的説明にも見られる。すなわち「宗教をはじめるきっかけは異常なことからはじまる。病気、会社の倒産など、およ そまともなことから宗教ははじまらない」と彼は言う。もっとも、それは事後的に語られた調査者への因果的な“説明”かも知れないし、なぜ、そのことが○○ 学院への入学に繋がるのかは分からない。ただ重要なことは、学院への入門が彼にとっての“行”——我々にとっての“宗教的行為”——の意味を解くことには 結びつかなかったことである。
ここで注目したいのは、Dさんにとって父親であり先生であるCさんが占める位置である。Cさん が存命中、寺院の信者たちは、彼の霊能力の卓抜さや修行の厳しさについてしばしば言及した。寺院が大きくなったのは、創始者Cさんに言わせると「八代さん のおかげ」なのであるが、信者たちはこぞってCさんの能力に帰するのである。また、折につけ信者たちは、二代目を目されているDさんとその霊能力の違いに ついて、陰に陽に筆者に対比して話すことがあった。このような状況のもとで、Dさんがその“行者”としてのアイデンティティの確立に悩んできたことは想像 に難くない。Dさんの一種の“行ノイローゼ”はそのことを指しているのだろう。では、Dさんにとって“先生”——筆者の前では“オヤジ”と呼ぶことがあっ たが、信者たちの前ではこのように呼ぶ——はどのような人なのであろうか。
「生母は、(Dさんが)7、8歳の時に死別した。母に対する特別な思いはない。父親にも一度も抱 かれた記憶はない。一緒に寝たという記憶もない。覚えているのは、高野山にお参りにいったときに一緒に寝たことと、吉野にいったときに手を引いたくらい や。
「まだ、15、6年前(1970年代の中頃)までは(Cさんは)厳しかった。すぐに作業着に着替 えなかったら、すぐ“飯抜き”と言われた」。
「自分にとって先生は、いつも土方仕事ばかりやらされて嫌なこともあった。しかし、先生はいつも 『働きをもって信仰の第一とせよ』と言っている。『神さんは飯を食わしてくれない。人間の生活が第一や』と言うが、自分もそのとうりやと思う。人間の生活 が第一であり、神や仏は側面から補うものだと思う」。
ここには、DさんにとってCさんは、父親よりも宗教の“教え親”といった感がする。もっとも、こ のことはDさんが育った環境において、象徴的に両親が“完全に不在”であったとは言えない。なぜならば、この寺院はCさんの弟子や信者など様々な人たちが 衣食を共にする大家族的な集団であり、82年の調査当時にもそのような形態は続いていたからである。そして、Dさんが結婚して家族をもったことは、もうひ とつの側面からの安定の一因であり、先の発言のなかの「嫁さんもらって精神状態が安定してきた」という発言にそれを見ることができる。
さて、Cさんへの重要な神示である“苦行”から“働き”への転回というものがあっても、この寺 院で行をおこなう宗教者には、“働き”と同様に宗教的な“行”を行なうことが期待されていた。この寺院の“新しい神学”を継承したDさんにとって、行はど のようにとらえられていたのだろうか。月の例祭には、信者を前に護摩が焚かれるが「護摩をおこなうことは、行を積むことになる」し、またDさん自身も “行”——例えば滝行をおこなう。「滝行なんかは、鯉の滝のぼりみたいな(滑稽な)ものや。しかし、滝に入るときは何もかも忘れて、精神が集中できるの で、滝行には確かに良い面がある」と肯定的にとらえらている。また、「行と言うものは、人が寝ている間にしないといけない。人と同じようにしていては、行 にはならないやろ」と積極的に行をおこなう必要性についても述べている。もっとも、それらは彼自身の行についての自己規定であり、信者やCさんの弟子にそ れを強要するといったことは見られなかった。
Dさんは、信仰的実践である行をおこなうことの効用は説くが、それが霊能力の獲得のためにあ る、という指摘は筆者には一切なかった。Dさんが信仰について語るとき、それは“信仰において個人がどのように神仏に対峙するか”が強調された。「信じる も信じないも自分次第です。信じるものに神さんはある」。「自分の最初の息子は生後1ヶ月で死んだ。しかし、それによって宗教心を捨てるつもりにはならな かった。また宗教に対する不信もない」という発言には、何か実存的な決意すらうかがわれる。また、他者との関係については、「人は1人では生きて行けんの や、誰からも他人から“おかげ”をもらっているのや」。あるいは「赤ん坊の熱を親が感じるように、我々も人の熱を感じることができる。他人の熱とは霊的な ものである」と述べている。そのような感覚のうえに神仏への一途な信仰を説いて、「修験や真言宗では、いろいろな神仏に対する祈りがあるが、自分で助けて いただこうとするなら、結局わき目もふらず、一心にひとつの神さんや仏さんを念ずるのが、集中できてええみたいや」と言う。
後に寺院を継承することになるDさんは、調査当時その“継承問題”についていくつか語ってい る。そこには、不世出と言われたCさんを“験力”で乗りこえるというスタンスではなく、Cさんの功績を顕彰し、かつ彼が感得した宗教的シンボル=八代龍王 に帰依する内容の発言が——特に信者などを前にした対他的なプレゼンテーションの際には——多い。例えば、例祭の護摩を終えた後、多数の信者を前に、Dさ んは「今日は私が護摩を勤めさせてもらいました。私はこのようにええかげんな者ですが、中心(祭壇中央の神さん)は立派なもの確かなものです。中心のほう にしっかりとお願いしてください。どうかよろしくお願いいたします」と述べている。また、筆者がDさんと出会って初期のころのインタビューで「この寺は先 生の信者の寺である。(寺の隆盛は)先生の才覚、行徳によるものだ。そして信者さんのお参りによって支えられている」と説明している。
もっとも、それは対他的パフォーマンスの一種であり、インタビューを重ねていった後にDさんか ら伺った現状分析はより冷静である。「(寺が)これだけ成功した陰には、泣いた人もいてる。(先生は)昔はずいぶん験力を競ったそうやから」と、寺院が発 展してきた背景に弱肉強食の論理があったことを示唆し、「父の代で50年。山は維持されてきたが、今後この繁栄が続くかは分からない」と心情を吐露するこ ともあった。また、“最近は墓場も立派になって檀家的寺院になりましたね”という筆者の発話に対して——「あの墓も無縁仏が多いで、いっこもお参りにけえ へん人もいる。ほんまに(寺の将来は)どないなるか、分からへん」とも言っている。
しかし、このような認識こそが“継承者”としての自覚を形成しているのではないかと思われる。 無我夢中でやってきたCさんに比べて、Dさんには行をめぐる宗教者としてのアイデンティティの葛藤があったり、信仰の様式においてよりシンプルな“神仏へ の一心の祈り”という神学めいたものが見られたりするが、それらについて語るDさんはある意味で自己を見つめる“行者の新しいタイプ”であるように思われ る。「この寺がこないな風(に立派)になって、人は“新興宗教”と言うけれども、別に気にならへん」というDさんは、当時早朝マラソンをおこなっていた。
「早朝マラソンをした。コースは滝場を回って「府民の森」に出て、そこで日の出を拝んで、本堂ま で戻り、お祈りする。日の出を拝むのはとても気持ちがいい。毎日が、すがすがしくなる。朝の光が大阪府から神戸の方に向かって照らすとき、この寺で育って きてええなと思う」。
3. 事例 II .B寺院
3.1 一般的素描
この寺院は、生駒の山中にある名刹に付随した滝行場が“行者”と呼ばれる人たちの定着化—— “滝守”になること——によって発展してきた。
生駒において著名ないくつか滝行場は、大阪を中心とした都市定住の“行者”に対して、電車で通 える霊場としての機能を現在まで提供してきた。ふつう滝守は、滝行場を霊場として管理し、外来の行者の滝場の利用に対して経済的な報酬を受ける、と[行者 たちの間では]考えられている。そして行者は、滝行場の霊場としての“名声”に引かれ、それを自己の修行の場にしたり、弟子たちをそこで修行させる。著名 な行者の活躍は、滝行場そのものの名声を高める。行者と滝行場はこのようにして相互依存的な関係にある。それゆえ、行者が特定の滝行場を独占した結果とし て、機能分化している“行場(=環境)”と“行者(=職能者)”を統合した“寺院”の形成がみられることがある。あるいは、“寺院形成”を目的とした“行 場”と“行者”それらの統合ということが積極的に試みられることがある。B寺院はまさにこのようにして大正末期に出来上がった。
この寺院の住職のFさんは、先代のEさん(故人)の婿養子である。事例㈵.のA寺院において先 代のCさんの伝記という“正史”が早い時期から編纂されていたのとは対照的に、「つよい霊能者」であったEさんについては、そのようなものが残っていな い。また、生前のEさんならびにその同時代を生きた行者のB寺院の沿革をめぐる“証言”には、相互に矛盾する言及が多く、“秩序だった沿革”という観点か らは十分には把握できなかった。また、滝行場から寺院を興した世代——Eさんの一世代上にあたる——の行者の行状については、事実関係の整合性よりも、霊 能力の起源やその正統性について力点が置かれているために“歴史”というよりも“説話”や“神話”といった様式・コード(記号体系)で語られることが多 かった。以上のことを前提にして、B寺院の“形成の起源”について要約する。
それは天王寺の行者だった“藤本先生”(仮名・故人)が大正末期に生駒の著名な滝行場に修行を するために登ってきたことに始まる。この滝行場はもともとは、現在B寺院の上にある名刹C寺院の境内にある行場であった。役行者あるいは弘法大師の修行場 だったという“名声”のもとに、藤本先生のほかに“柏木先生”(仮名・故人)などが、大阪から通いの修行場として利用に来ていた。藤本先生の弟子になった のがEさんの父親である。藤本先生は滝の所有者であるC寺院の当時の住職と意気投合することとなり、最終的に“滝守”としてその行場に定住することになっ た。Eさんも最初、藤本先生のもとで滝行をしていたが、やがて各地の霊場を回る修行に出た。戦後Eさんは“行の生活”から遠ざかっていたが、昭和24 (1949)年、滝を守っていた藤本先生の息子夫婦のところに戻ってきて、滝守を継承することになった。所属宗派によって寺院の院号を付与されたのは 1970年代になってからである。
いろいろな行者たちが「B寺院=名刹に付随した滝行場」を舞台にしてどのような活動をおこなっ たか、ということは“生駒の行者”像を考える上で重要である。つぎに、Eさんの発言を中心に藤本先生、柏木先生、Eさんの父親、という三者の行者像を構成 してみたい。
3.2 藤本先生——神話的な創始者
「藤本先生はそのころ(大正時代の後半期)、四天王寺の南門あたりの○○2丁目(地名)に「藤本 道場」あるいは「○○道場」という宗教道場を開いていた。しかし、その道場とは、別に看板を掲げるではなく、外から見るとふつうの民家やった。当時は、 (公安)警察がうるさかったからや。藤本先生はおもに北浜の相場師を相手に(相場の売り買いの予想を)していた。ある日、その相場に関係している人に告げ た予想がはずれ、それ以来、勝負事の相談は受け付けなくなった」。
「藤本先生は“字も知らん人”やったから、行者の行の作法も自己流でやっていた。例えば、護摩の 時は、木を燃やしてただ一心に祈るだけの護摩やった。また、人に祈祷を頼まれても、一心に“お不動さん”に祈るだけやった。滝行場に石造りのお不動さんが あるが、これは藤本先生が建てたもので、“不思議不動”という」。
「藤本先生は、6年間この滝行場に天王寺から日参した。この滝はもともとC寺院の境内の行場やか ら(滝行には)その住職の先代の許可をもらってはった。先代と藤本先生は意気投合したので、最終的に藤本先生はここの滝守になった。藤本先生と(Eさん の)父親の法名は、先代の法名から一字づつもらってつけた」。
「藤本先生は、昭和4年に52歳で亡くなった。先生は次第に衰弱してきたが、死ぬ前の日に『自分 は明日の午前11時23分に死ぬ』といった。滝行場の弟子たちは、藤本先生を戸板に乗せて下まで降りて、近鉄で○○病院まで運んだ。そして、予言通り、翌 朝の同じ時間に弟子に看取られて死んだ。藤本先生の死後、(Eさんの)父が、おなじ“滝守”としてその後を継いだ」。
3.3 柏木先生——寺院を持たなかった行者
「藤本先生の同じ時代に柏木先生という先生がいた。柏木先生の名は通称で、本名は○○○○と言 い、京大を卒業した。なんで柏木と言うたかというと、大阪の証券会社の屋号である「柏木屋証券」(仮名)をとってそう呼ばれた。いつも着物と下駄の姿で あった先生は“信者で食べていく行者”ではなかった。つまり、別に個人的動機で行者になったのではなく、勤め先の柏木屋から毎日五十銭の手当をもらい、柏 木屋の商売繁盛を祈願しにこの滝に日参していた。柏木先生には道場もなにも無かったが、やがて信者がつき、山の麓からこの滝までの間のどこかに信者が待っ ていて、山に登る柏木先生と一緒について登ってきて、この滝で一緒にお滝を受けたり信者に加持をしたりした」。
「柏木先生は予言者的な人で、ラジオが発明され普及される三年前に、“将来、宇宙から電波が来 る”といってその登場を言い当てたという。柏木先生は、藤本先生が死んでから後三年に、石切で倒れて死んだ」(柏木先生の信者たちは、死後の昭和8年に、 彼を顕彰する碑をこの滝場に建立している)。
3.4 藤本先生と柏木先生——その異説
Eさんの叙述によると、藤本先生と柏木先生がどのような関係にあったのかは定かではない。少な くとも両者の間には対抗的な関係があったとは示唆されていない。藤本先生が、先代のC寺院の住職と懇意になり、その滝守となる一方で、柏木先生は滝行場に は定着せず“インテリ”で経済的に余裕があり「信者で食べてゆく行者」ではなかった、と指摘されているにすぎない。
ここで、Eさんの6歳ほど年上で、同じ時期に行をおこなった別の行者Gさんが藤本先生について 語ったこと(要約)を、別の資料から提示してみよう(5)。その中では、藤本先生と柏木先生、さらにはEさんの父親も交えた別の側面の人間関係の像が提示 されている。
「藤本先生は、自分(Gさん)が修行中の17歳の時に出会った行者で、“神仏と話がつき弁も立 つ”人だった。“入墨もち”であったが、先輩格にあたる柏木(注:Gさんは呼び捨てでこう呼んだ)に病気を治してもらってから、行を始めて自分でも治せる ようになった。藤本先生は信者から金を取らないことから(信者たちには)尊敬されていた。生駒だけでなく、周辺の行場でも行を重ねていた」。
「昭和4年ころ藤本先生と柏木がいた行場を(Gさん自身が)去った。兵役をすませて戻ると、すで に藤本先生は他界していた。生前は、藤本先生よりも自分(Gさん)が上座におり、お滝にも自分が(藤本先生よりも)先にあたらしてくれた。しかし、兵役を 終えて滝行場に戻ると、行の同僚の○○(Eさんの父親のことと思われる)が私を嘲笑した。『お前はアホや。今は柏木さんの世や、何やってんや』と。そこ で、私は『8月16日で柏木の寿命はしまいだ』と予言して、『このお滝は絶対に来んさかいに』と言って出て行った」。
Gさんの発言によると、(Eさん自身が語るように)Eさんの父親が藤本先生の“衣鉢をついだ”の ではないことになる。また、生前の藤本先生と柏木先生の間にはなんらかの拮抗的な関係があったことが示唆されている。柏木先生がその間の3年間どのような 位置にあったかは不明だが、最終的には滝守の地位は、藤本先生からEさんの父親へと受け継がれてゆくのである。次にEさんの父親像についてEさんの発言か ら構成してみよう。
3.5 Eさんの父親——藤本先生の“腰巾着”
「○○(父親の法名)は自分の父親であり、かつまた自分の“先生”でもあった。父は“極道者”で あり、大阪市の日本橋に住んでいた。(注:Eさんが10歳のとき足をくじいた。その際Eさんは藤本先生に気合いを入れてもらい治してくれた思い出があり、 当時すでにEさんの父親と藤本先生の間の交流はあったと思われる)。自分が11歳のとき、父は私と私の6歳下の弟を連れて、親子心中するつもりでこの滝場 にやってきた。夜半、そこで父は滝にあたりながも、その心の中は死ぬつもりでいた。
この時、藤本先生は天王寺の道場で弟子たちに囲まれていた。父が自殺するつもりである、という ことを予言した藤本先生は、彼の弟子たちに、父と自分たちを心中から救うために、弟子たちを天王寺から生駒の滝まで派遣した。
そのとき、私と弟は、滝の上にある○○(C寺院)の不動堂の薄暗いなかで父親を待っていた。弟 は、何も知らずお堂の中で寝入っていたが、私は恐ろしい形相の“烏枢沙摩明王”の像を見ながら父を待っていた。
やがて、藤本先生の派遣した弟子たちが、私たちを迎えに滝場にやってきた。そして、私たちは天 王寺の藤本先生の道場に迎えられた。父は藤本先生に得々と説教され、やがて改心したという。その後、父は藤本先生の指導の下にこの滝に8年間通った。ま た、藤本先生が山に上がって来るときには、父はいつもついてくるようになった。自分自身で“藤本先生の腰巾着”と称していた」。
3.6 Eさん——霊能力のある行者
Eさん自身は、自分の父親を“先生”と位置づけている。実際、Eさんが16歳の時に父親は彼に 対して滝に当たらせ、初めての“行”を授けている。しかしながら、彼との会話を通して、少なくとも信仰や修行に関する面においては、父親から大きな影響を 受けたことはないようだ。Eさんにとっては、父親の師匠であり、また10歳のとき足の捻挫を治してくれた藤本先生の影響力のほうが大きかったように思われ る。またその偉大な“霊能力”の継承者として自己を位置づけていたようである。Eさんは、筆者との対話でしばしば、時に好んで藤本先生にまつわるエピソー ドを話した。それは、まるで(そのファンタジーという点では劣るものの)“役行者”にまつわる説話のようであった。そして、藤本先生が「字も読めん」人な がら、一心に祈りに専心したことをいつも評価していた。Eさんが藤本先生に“生駒の行者の原像”を見たこと——それは筆者自身においても同様である——は 想像に難くない。
Eさんにとって、行者への入門には“剥奪体験”は必要なかった。幼年時代に経験したの親子心中 の失敗も父親にとっての剥奪経験でこそあれ、彼自身のものではない。初めての滝行においても、それはイニシエーション以外のなにものでもなく、特に強烈な 体験をもってはいない。彼が四国、引き続いて木曽御岳の霊場をまわったのは26歳頃である。“行者”として生きるという意識もないまま、行脚が始まった。 「当時は、滝を守ろうという気はなかった。自分は好んで全国のいろいろなところに行に行ったが。一人前の行者になるという意識はなかった」という。
それは、彼が感じた霊的体験を通しても“行者”としてアイデンティティを形成するには至らな かったようだ。「最初に霊感を感じたのは、四国八十八箇所巡礼をしていた26歳のとき。『ごらいこうの滝』で未明に滝行をした。滝を眺めて合掌していたと きに、日の出になった。陽の光とともにその日光に照らされた滝の上に、不動明王、阿弥陀仏、弁天さんなどが次々と映っているのが見えた。その時は、ただ有 難いという気持ちで一杯だった」。彼が自分の修行時代を語るときも比較的淡々としている。
不動明王(棟方志功)
「自分は26歳のとき(四国巡礼を終えて次に)木曽御岳で修行した。○○村の○○旅館に住み込ん で、百草——ダラニスケのことという——を作るアルバイト仕事をしていた。そのころの日課は、夜中の零時ごろまで仕事をして、床につく。午前3時頃になる と“神さんの声”がして起き出し、4時頃に近くの滝行場にゆく。お滝を受け、勤行をし、5時頃には旅館に戻っていた。朝食をとり、旅館で作ってもらった “おにぎり”をもって、6キロほど上の清滝にいって滝行した。その滝は大きく、ゆうに50人は滝をうけられるほどの大きさであった。日暮れには修行を終え て、旅館にもどり夕食をとり、夜半まで百草のアルバイト仕事をおこなった」。
このような“冷静さ”は、彼の生来の性格によるものか、彼が修行によって獲得したものかは検証す るすべもないが、Eさん自身は“修行によって得た”というふうに筆者に説明した。
「自分は全国の行場を回っているうちに、多くの行者の話を聞く機会を得た。私の方法は、“相手の 話をじっと聞く”ことだった。多くの人たちが“天狗”になっているのを見て、“自分はああなってはだめだ”と感じた。逆に言えば、多くの行者が自分に対し て“行者とはどうあるべきか?”を、知らず知らずのうちに教えてくれたことになる。言うことは誰にもできるので、“聞き上手”になることが肝心だと思っ た」。
「だいたい“行者”と言われるような人たちは、“一匹狼”と言われるような“我の強い人”が多 い。そして、その多くは自分のことを自慢する“天狗”になっている」
彼が、最初に行者として生きる決心がついたのは、日本が敗戦してからである。「兵隊から帰って からは本格的に滝を守ろうと決心した。なぜなら、いままで多くの人に“救い”をもらってきたので、今度は“人を助けよう”と思ったからや」。しかし、結 局、生駒の滝行場に戻って定着を再開したのは昭和24(1949)年になってからである。「戦後のドサクサのなかで、いろいろな体験をした。“人に騙され るような生活”が嫌になり、これは自分に向いていないと自覚して、滝に帰ってきた」。
我々の研究者の間では——あるいは自称・他称の“行者”たちによっても、霊能力をもつ人たちは 個性的で“我の強い”人が多い、というコンセンサスがある。しかしながら、行者として大成するためには、そのような性格は(ある局面において)マイナスと なる。A寺院のCさんも周囲の人たちによって、たいへん“自我の強い人”とラベルされていたにもかかわらず、Cさん本人は、他の行者たちが大成しなかった 理由を自己の能力への“自惚れ”に帰していた。Eさんの場合、先に指摘したように、そのような陥穽は“人の話を聞くこと”によって乗りこえられたと説明さ れていた。しかし、後述するように“霊能力ゆたかな”Eさんにとって、それはたんに人の話を聞ける能力のことだけを指しているのではない。人の話を聞きな がら“その人を見抜く能力”のことを言っているのである。それゆえに、“人の言うことを聞く”ことは、Eさんにとって能力の源泉であり、彼がその能力を筆 者に対して(間接的に)“誇示”するという逆説的な状況をも生じさせた。「(この滝行場に定着するようになって以降)“道場破り”(6)もたくさん山に 登ってきたが、私と話しているうちに“これはかなわん”と道場破りが思ったのか、下山していった。もちろん今(82年当時)は、そんなことをする奴などい ない」。
彼はA寺院のCさんのように霊能力があると——調査に参加した研究者の間では——見なされてき たが、Cさんのような“神示”を受けるタイプではない。言語的な神示ではなく、どちらかと言うと“幻視したメタファーを解釈する”タイプである。また、霊 的なビジョンもCさんのような“透視”的なものは少なく、本人の言を使えば“霊感”という感覚が生じるという。
「夜は精神統一がよくできるので、いろいろな霊と出会いやすい。私が見た龍神さんは、太さが人間 のひと抱えほどあり、目玉はこれぐらい(両手の親指と人差指で輪をつくる)。鱗もそれぐらいかな。髭もピンと立っていた。」
「霊感とは、“ひらめき”のような体験や。しかし、それがじわじわと出てくることもある。また、 時にはそれが眼に見えることもあるし、電話を聞くように“神さんの声”を聞くこともある」。 Eさんの奥さんも“霊感”があり、筆者とEさんの三人で話している最中に(私には見えない)“お不動さん”の眼の前での現出について、二人が語り始めると いうことにも遭遇した。このような感覚は、最初に“ごらいこうの滝”で彼が体験して以来、彼にそなわった独特で共通した感覚のパターンとして見なすことが できる。そして「(最初に霊感体験をして以来)やがて、こころを次第に落ちつけていると、すぐに感じられるようになった。この滝に戻ってくるようになって 以来、人と話しているときにも自然と感じられるようになった」という。
B寺院は沿革のように「(滝)行場をもった道場である」。そして、滝行と言うものを、一部の行 者だけに限られたものとしていない。“家族的な雰囲気であたれる滝”ということを標榜している。「修行者が生活を投げて苦行するという時代は終わった。ま た、信者に対して厳しく接する必要もない。今の人は言えば分かる世代や、頭ごなしに言いつける必要はない」という発言はこれに合致する。
Eさんが、時には[論理整合という観点からみれば]“矛盾”しながらも“行”および“滝行”に ついて語ることは、伝統的な“ケガレ”の概念と“修行”を中心的なモデルとする身体論におおむね合致する。
「行には滝行と心行(しんぎょう)がある。ふつう『一に心行、二に荒行』と言われる。修験はさき に荒行から入っていくが、心行もそれ以上に大切や。心行を簡単に言うと“怒らんことや”。怒るのは犬や猫でもできる。心行をおこなうには、笑顔を絶やさな いことが肝心や。しかし、単に怒らないことではだめで、それを乗り越えないとあかん。知らず知らずのうちに乗り越えていることが心行や」。
「信者が滝行によって行力をつけるのは、行者と同じである。しかし、行者は長生きできない。身体 を無理して信者のために使うからである。もっとも、行の道にすすむということは、それは何かの因縁があるからや」。
“滝は長く受けるほうが良いのですか?”という筆者の質問に対して——「そのようなことはない。 長く滝を受けるということは、それだけ“我が入る”ということだ。すなわち、長く入る人ほど因縁や罪障を、他の人より多く持っている。ちょうど、身体に汚 れがある人は、汚れていない人よりも、より多く洗い流す必要があるからや。罪の“垢”を持っている人ほど、回数が多くないと落とすことができない。(しか しながら、また別の場面では)行力は滝に当たれば当たるほどつく。若いときにつけた行は減っていくものではないが、その行力を保っていく必要がある。(だ から)行は充電みたいなものや、しかし年がとると、バッテリーが古くなるようによく充電できなくなる」。
Eさんは、1985年に亡くなった。インタビューが行なわれたのは、その3年前であったが、彼 は自己を“滝守”であると規定し、(実際にはその霊能力で信者を魅了しながらも)“神の救い”を説いていた。
「この滝は、諸々の因縁のゴミ捨て場だ。儂はゴミ捨て場の掃除人なのや」。
「信仰で金儲けする人は、(こんな生駒の山中ではなくて)交通の便利なところに住んでいる。生駒 に登ってくる人にあまり裕福な人はいない。医者に見放された人や、高度な医療を受けようとしても、お金の払えない人が登ってくるのだ」。
「儂はよう助けん、自分は神との中継ぎであり、神さんに助けてくださいとお願いするのだ‥‥信仰 の態度として大切なのは、自分のことを我先に言わないことである。“人の願いを聞いてくれる”のが神さんやからや」。
3.7 Fさん——霊能力の“非相続者”
Fさんは、85年よりB寺院の住職となった。彼には“もともと”霊能力はなかった。関西圏外の 出身で、宗教とは比較的無縁の世界で育った。母に連れられてやってきたこの寺院で、Eさんの娘と知り合うことになり、結果的に“行者”の仲間入りをするこ とになったからである。筆者のB寺院への度重なる訪問に際して、Eさんとその奥さんという、時には私自身が理解不能に陥る“霊感”のプレッシャーに挟まれ ている際に、彼の気さくな人柄が、その霊的な世界との緩衝帯として機能したことも確かである。従って、彼の義父であるEさんが亡くなる以前には、彼は寺に おいて諸般にわたる事務的な業務を一手に引き受けていた。
Eさんやその奥さんの霊能力に比べて、Fさんには遜色があることを本人も自覚しており、「自分 のようなペイペイでは信者さんが納得できないようなところでは、Eさんが中心になって信者参りをする」と述べていた。そして彼は、滝行という修行によって 霊能力を獲得しなければならなかった。
「滝行をはじめたのはこの滝に来て住むようになってから。行をはじめて2、3年目ぐらいから、霊 感が出てきたり、神さんがつくようになった。しかし、それをすぎるとまたおとなしくなった」。
「滝行や霊能力は体得するものなので、他人にはうまく説明できないだろう。身体で感じるものだか ら言葉では説明できない」。
「滝行をしていると感覚が鋭くなる。滝場の蛇口から水の出るときの音、落ちて来る途中の水の音、 肩に当たる音が聞き分けるようになる。自分が滝行をしていても、滝場の足場が板ごと宙に浮かんだような経験をしたことがある。また、合掌している手がもの すごく大きくなる。しかしそこで、自分が眼を開けてみると別になにもない。そのような体験は何度もある」。 Fさんには、A寺院の2代目のDさんを一時的に襲った、激しい苛立ちというものが見受けられなかった。滝行も職務上必要な“霊能力”をつけるためのルー ティンとして、彼自身“行”を楽しんでいるように受けとめられた。Eさんが生前言っていた「修行者が生活を投げて苦行するという時代は終わった。‥‥今の 人は言えば分かる世代や、頭ごなしに言いつける必要はない」という言葉を、“霊能力の非相続者”であるFさんはそのまま実践し続けているのである。
4. おわりに
生駒の行者は、滝行が急速に普及した大正末期から昭和初期に活躍した“第一世代”、その次の子 息の世代である“第二世代”という類型が、明言されることはないが漠然として理解されている。有り体に言えば——そして既存のパラダイムの用語を用いれば ——、第一世代は、宗教の入信の直前に「強烈な剥奪体験」を持ち、「厳しい修行を積んだ」「カリスマ性豊かな」「行者らしい行者」であり、第二世代は、第 一世代が興した「拡大した寺院や信者を管理する」必要に迫られ、「宗教者としてのアイデンティティを模索することに」に苦慮している人たちである。
しかしながら、個々の事例に立ち戻れば、その類型から逸脱するものが多く存在することは明らか である。ただ「 〜 らしい」という属性をもとに一定のカテゴリーに分類するという性向においては、調査される側も調査する側も同様の地平に立っている。 両者における差異とは、後者がそれをいかに上手に専門用語に当てはめ、その生成や実態を因果的ないし論理整合的にまとめるかの違いだけなのである。
類型化をおこなう人間の営為があるかぎり、生駒では様々な行者のタイプについていつまでも語り 継がれてゆくことであろう。ただ、調査する側の行者の類型論に関して指摘しておきたいことは、第一世代の行者たちが、始祖として「行者らしい行者」という レッテルを貼られ、その行状については神話的・説話的コード(記号体系)で語られることが多いと言うことである。そして、それ以降の世代は周囲で観察する 人にとっても、また本人自身によっても、そこからの「世俗的後退」として認識され、その行状は現実的コードで語られることが多い。しかしながら、生駒とい う文脈においては、それらが常に神話的・説話的コードに回帰する一定の経路が存在する。なぜならば、行者にとって常に関心の的になる“霊能力”にまつわる 言説はこのコードに属する事柄だからである(7)。
冒頭に提起した問題を、ここに掲げた事例報告のなかで有効に叙述したかということについて、筆 者の心境はいささか心許ない。また、“客観的叙述”に徹するべきだという(研究者の)道徳的秩序が(未だに)要求される状況のもとで、事例の中に込められ た筆者による“行者の理解”の編集の過程や“手練”を暴露すること——これすらもフィールドワークの認識論における政治的な手法(8)なのである——が、 ともすればナイーブであると判断されるかもしれない。報告者としては、事例を報告した過程についてさらに内省的な分析を加えるための前段階としての資料の 提出の意味を込めて、表題に“試論”を冠した。残念ながら、使われた資料は10年近く前に採集されたものである。またA寺院のCさんも、B寺院のEさんも 既に故人になられて、再調査することが不能である。しかし、生駒において「行者らしい行者」というステレオタイプが人びとによって貼られる限り、この種の 問題関心とそれに基づく研究の可能性があることを筆者は信じたい。
【図像解説】

歓喜聖天像(Nandikeśvara):歓喜天(かんぎてん、梵:Nandikeśvara、ナンディケーシュヴァラ、歓喜自在天とも)は、仏教の守護神である天部の一つ。ヒンドゥー教のガネーシャに相当する尊格で、ガネーシャと同様に象の頭を持つ。
註
(1)宮家準編『修験道辞典』東京堂、1986年、p.80。
(2)生駒における行者のライフ・ヒストリーに関連する研究——本稿もそこから大いなる示唆を 受けた——として次の2報告がある。沼田健哉、生駒における龍神信仰と修験道——八代龍王神感寺を中心として、昭和60・61年度科学研究費補助金研究成 果報告書『日本宗教の複合的構造と都市住民の宗教行動に関する実証的研究』1987年、pp.106-114。村田充八、生駒の中小寺院:南陽院——住職 主導型寺院の発展と展望、同書、pp.115-125。また、行者と信者が共有するコスモロジーについては、池田光穂、「治療」の文化的構成——生駒にお ける信者と行者、『宗教学と医療』(黒岩卓夫編)所収、弘文堂、1991年、pp.8-36、がある。
(3)信徒会報に掲載され、Cさんの死後Dさんによってまとめられたこの伝記について、生前の Cさん自身が興味深い言及をしている。伝記はある地方新聞の記者に依頼して書かれたものである。Cさんの“神示”は彼が起きている間にあったのだが、この 記者は“自分が体験したことのないことは書けない”とのことで、Cさんの神示が夢の中で行なわれたと記述した。Cさんは取材されたときに語った内容を“書 き換えられた”と筆者に半ば抗議まじりに語った。このようなことは“事件報道”や“文化の翻訳”をめぐるプロセスの中でも“常に問題となる論点”である。 これは、Sperber, Dan., 1982, Le savoir de anthropologues, Paris: Hermann. の第㈼章「一見して非合理な信念」で展開された状況が“異文化”でなくても、“身の周り”で生起していることを示している。ダン・スペルベル(菅野盾樹 訳)『人類学とはなにか』紀伊國屋書店、1984年。
(4)その開山堂では、開基者(故人)すらも祀られており、そのことを指しているように思われ る。かつてA寺院にこの開基者は弟子を派遣して“道場破り”に来たという。霊能者であった彼の妻は筆者のインタビューに応じてくれた。その当時の“道場破 り”——彼女の言によると“道場あらし”——とは次のようなものであったという。「修行は滝行のほかに、他の行者と弁論による論争を行なったり、道場あら しということも行なった。道場あらしとは、別の行者と気合いによって勝負することを目的として、他の道場に勝負を申し込むことである。勝者(の行者)は敗 者の道場の看板を奪うことができた。また、敗者にはその見返りとして“あがり賃”——どのようなものかは不明——が支払われた」。
(5)筆者と菅康弘氏、谷富夫氏が、1982年2月22日に共同にとったインタビューで、谷氏 が整理した取材ノートに全面的に依拠した。
(6)注(4)を参照。
(7)宮本袈裟雄は、修験道研究において「今日活躍しているところの山岳修行者」をターゲット にすることの重要性を強調する論文の中で、「‥‥修行内容・霊験・奇蹟など役行者伝承において可変部分であるところは、修験者のより理想と考える事柄が次 々と追加されてきたものと思われるが、それが単なる空想ではなく、修験道の世界の中で、始祖伝承の形成←→始祖の行状の追体験という循環の繰り返しによっ て、形成されてきたものと思われる」(p.365)と述べている。これは、行者のアイデンティティが神話コードと現実コードの弁証法的なプロセスのなかで 生成することを示唆しているのである。宮本袈裟雄『里修験の研究』吉川弘文館、1984年。
(8)例えば Vincent Crapanzano の "Tuhami: Portrait of a Moroccan"(1980) などは、この政治的なスタンスを明確に意識して書かれている。クラパンザーノ(大塚和夫・渡部重行訳)『精霊と結婚した男』紀伊國屋書店、1991年。
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
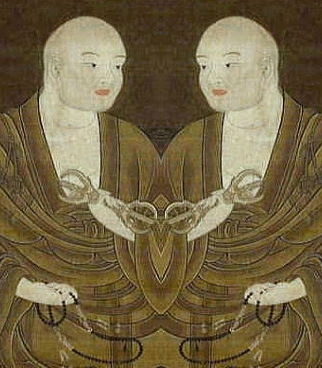


【クレジット・出典】→業績一覧
池田光穂「生駒の行者像」試論,平成2・ 3年度文部省科学研究費・総合A「現代日本における ネットワークの研究」(代表者:塩原勉)補助金研究成果報告書『宗教行動と社会的ネットワーク』所収 [共著],pp.249-267,1992年3月※毎日新聞大阪本社記者の某氏からのアクセスを記念してリニューアル しました!(2000.08.17)
旧クレジット:「「生駒の行者像」試論 :
研究者による霊能力者のライフヒストリーの構成に関する考察」
リンク
文献

科学研究費補助金・総合研究(A)「現代日本における
ネットワークの研究」 02301023の補助を受けて調査研究しています