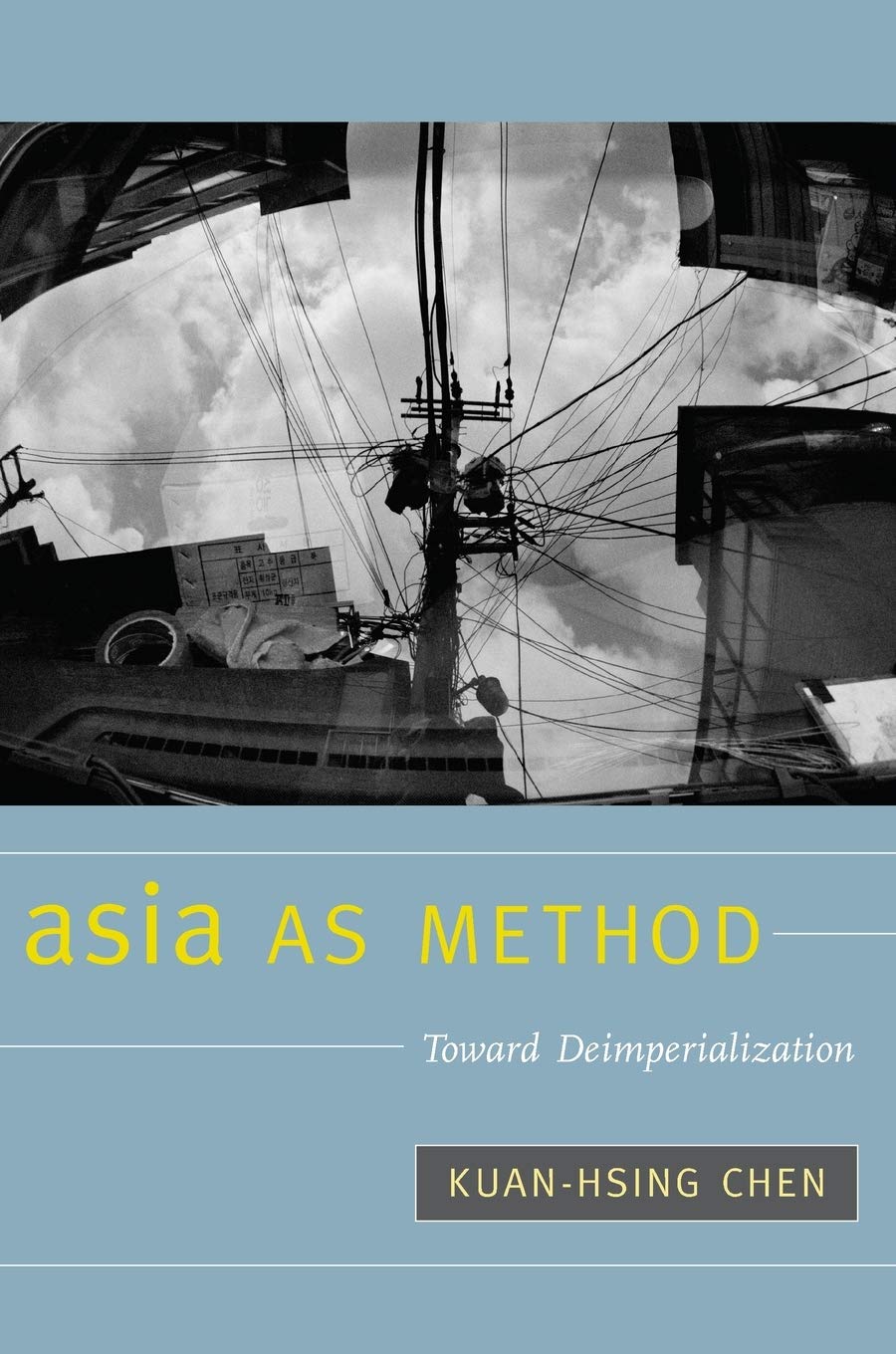
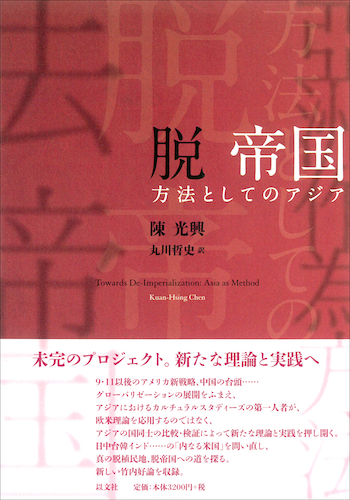
陳光興『方法としてのアジア』
Asia as Method
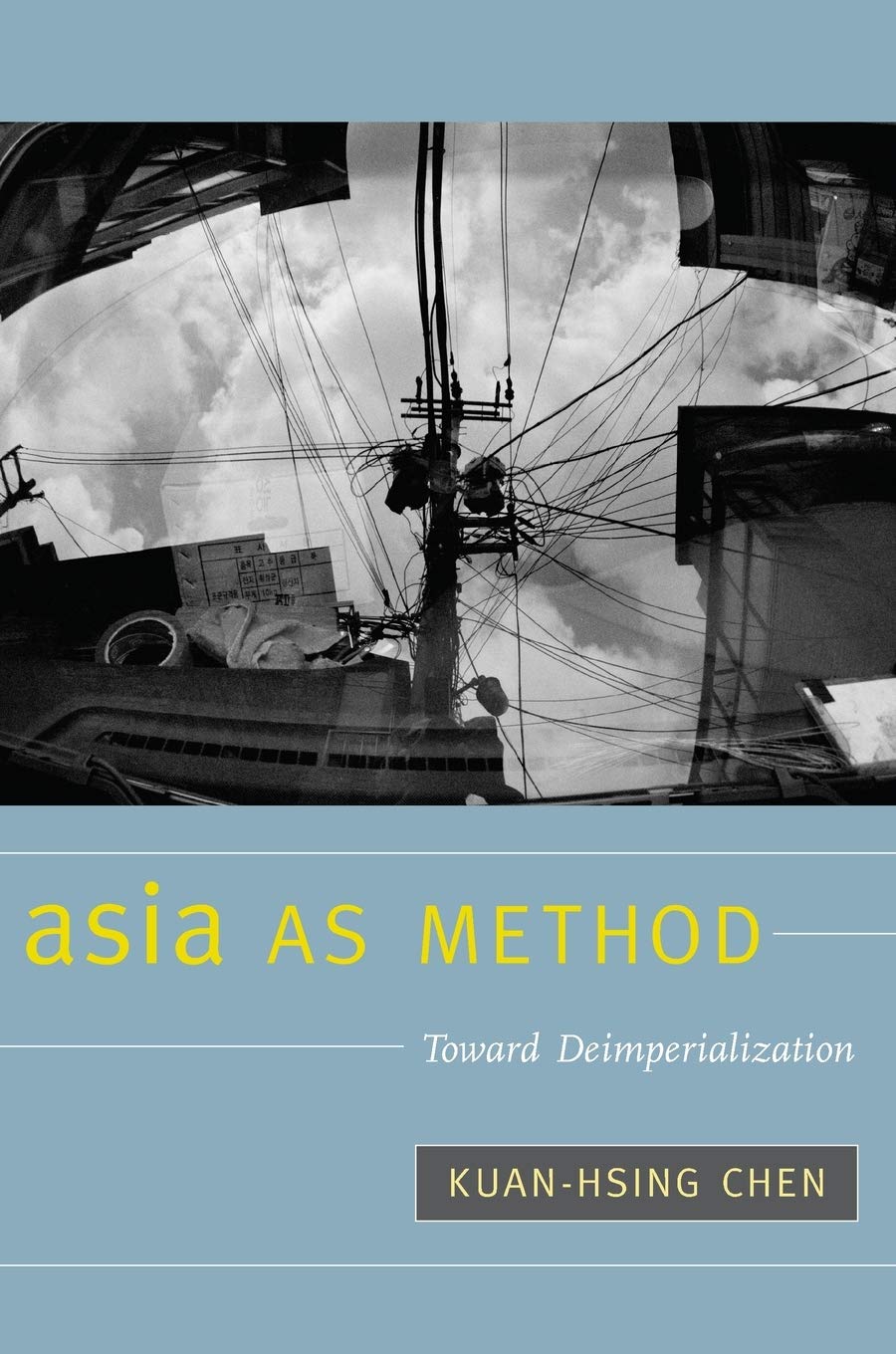
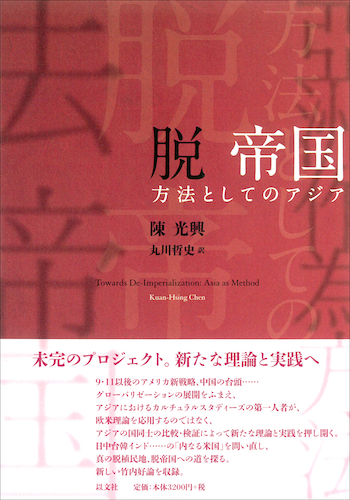
☆ このページは、陳光興『方法としてのアジア』ノート(Note on "Asia as Method: Toward deimperialization," 2010.)のスピン・オフ・プロジェクトの一環です。
| Chen
Kuan-Hsing is a Taiwanese intellectual who works in the field of
inter-Asian cultural studies.[1] He is one of the editors-in-chief of
the journal Inter-Asia Cultural Studies. He is the author of Asia as
Method: Toward Deimperialization (Duke University Press, 2010) and
numerous other publications. His approach to cultural studies has been described as one of calling 'for using 'Asia as method' ... the basic idea being to multiply points of reference within Asia so as to de-emphasize, if not necessarily abandon, the orthodox preoccupations of the west'.[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Kuan-hsing |
陳光興は、
アジア文化研究の分野で活躍する台湾の知識人である。[1] 彼は学術誌『Inter-Asia Cultural
Studies』の編集者の一人である。著書に『Asia as Method: Toward
Deimperialization』(デューク大学出版、2010年)など多数。 彼の文化研究へのアプローチは、「アジアを方法として用いる」ことを呼びかけているものとして説明されている。その基本的な考え方は、西洋の正統的な関心を必ずしも放棄しないまでも、その比重を減らすために、アジアにおける参照点を増やすことである。[2] |
| In
confronting the long lasting impacts of “leaving Asia for America”
(tuo-yaru-mei) in the Post World War II Taiwan, this essay puts forward
“Asia as method” as a critical proposition to transform the existing
knowledge structure and to transform ourselves. Its bottom line
implication is that, mediating through the horizon of “Asia” as an
imaginary anchoring point, societies in Asia could begin to mutually
see the existence of one another and become one another’s reference
points, so that the understanding of the self can be transformed, and
subjectivity rebuilt. On this basis, to push one step further, historical experiences and practices in Asia can be developed as an alternative horizon or perspective, and seen as method to advance a different understanding of world history. The argument must be placed in the context of a new global order after the 911 Incident. Various regional mechanisms have gradually emerged to counter US imperialism and global hegemony. In this process, the integration of Asia remains slow and informal. “Asia as method” is then a call for regional integration in Asia as a necessary mechanism to maintain global peace. The paper is organized in the form of a series of dialogues. (I) The first part deals with the question of the ‘West’, as it is rehearsed again in the postcolonial discursive strategies. Here, the essay confronts the historical question of the West and to pinpoint understandable but unnecessary obsession with the question of the west, and then point towards the imaginary Asia as a possibility to shift its referent point. (II) In the second part, the essay tries to demonstrate what can be gained from this shift by engaging dialogue with Partha Chatterjee’s recent proposed theory of ‘political society’, with reference to practices emerging in India, in that the analytical notion of ‘min-jian’, which was a “pre-modern” term and is still operating in the mandarin Chinese speaking places, was rediscovered as a contemporary living space, intersecting but somehow excluded by the imposed concept of ‘civil society’. By analyzing how civil society has been “translated” as min-jian society, it argues that “translation” provides a means to conduct the re-investigation so that the organic shape and characteristics of local society and modernity can begin to emerge. (III) The third part comes to the theoretical formulation of ‘Asia as method’, through dialogue with Misogugi Yozo’s “China as method”, by focusing on his historical-ontological claim of a theory of ‘base-entity’ (ji-ti), which is closer to my own earlier attempt to work and rework a ‘geo-colonial historical materialism’, in that we argue the necessity to capture the constantly changing base entity, through which different base entity in different locales in Asia could become the referent point of each other and become part of each other’s subjectivity, so that the ‘self’ can be transformed. Therefore, ‘Asia as method’ ceases to look at Asia as object of analysis, but actually means medium to transform knowledge production, and the driving force of the rediscover and transforming of the self. The conclusion section comes back to the “leaving Asia for America” problematic and teases out the implication of Asia as method for “Taiwan” to reposition itself so as to reconstitute a critical subjectivity. It argues that Cross-Strait relation, Chinese International and Asia Regional are in fact the trajectories and routes of globalization, and Taiwan has to self-consciously place itself within these network of relations as its own self-positioning. |
本
稿では、第二次世界大戦後の台湾における「アジアからアメリカへ去る(tuo-yaru-mei)」という長期的な影響に立ち向かうため、「アジアを方法
として」という命題を提示し、既存の知識体系を変革し、自らを変革するための重要な命題として打ち出している。その根本的な含意は、「アジア」という想像
上の基点としての地平を媒介とすることで、アジアの社会がお互いの存在を認識し始め、互いに参照し合う存在となる可能性があるということである。そうする
ことで、自己の理解が変化し、主体性が再構築される。 このことを踏まえてさらに一歩進めば、アジアにおける歴史的経験や実践は、オルタナティブな地平や視点として発展させることができ、世界史に対する異なる 理解を深めるための方法として捉えることができる。この議論は、911事件後の新たな世界秩序の文脈に位置づけられなければならない。米国の帝国主義と世 界覇権に対抗するさまざまな地域メカニズムが徐々に登場している。このプロセスにおいて、アジアの統合は依然として緩やかで非公式なままである。「方法と してのアジア」は、世界平和を維持するための必要なメカニズムとして、アジアにおける地域統合を呼びかけるものである。 本稿は一連の対話形式で構成されている。(I)最初の部分では、ポストコロニアルの言説戦略において再び繰り返されている「西洋」の問題を取り扱う。ここ では、西洋の歴史的問題を直視し、西洋の問題に対する理解はできるが不要なこだわりを指摘し、その参照点をシフトさせる可能性としての想像上のアジアを提 示する。(II) 第二部では、インドで台頭しつつある実践を参照しながら、パルタ・チャタジーが最近提唱した「政治社会」理論との対話を試み、このシフトから何が得られる かを明らかにしようとする。「民間」という分析概念は「前近代」の用語であり、今でも中国語話者の間で使用されているが、それは「市民社会」という押し付 けられた概念と交差しながらも、何らかの形で排除された現代的な生活空間として再発見された。 。市民社会がどのように「民間社会」として「翻訳」されてきたかを分析することで、この論文は、「翻訳」が再調査を行う手段を提供し、それによって地域社 会と近代の有機的な形と特徴が浮かび上がってくるようになる、と論じている。(III)第3部では、三島由紀夫の「方法としての中国」との対話を通じて、 「方法としてのアジア」の理論的定式化に至る。三島が「基体(ji-ti)」という歴史的存在論的主張に焦点を当てている点に注目し、それは、私が以前に 「地政学植民地主義的唯物史観」を再構築しようとした試みにより近い。アジアの異なる地域における異なる基盤的存在が互いの参照点となり、互いの主観の一 部となることで、「自己」が変容しうる。したがって、「方法としてのアジア」は、アジアを分析の対象として見ることをやめ、実際には知識生産を変容させる 媒体となり、自己の再発見と変容の原動力となる。 結論部分では、「アメリカのためにアジアを去る」という問題に戻り、「台湾」が批判的な主体性を再構成するために自らを再配置するための方法としてのアジ アの含意を明らかにする。海峡両岸関係、中国国際、アジア地域は、実際にはグローバル化の軌跡であり経路であると論じ、台湾は自覚的にこれらの関係のネッ トワーク内に自らを位置づけ、自己を位置づける必要があると主張する。 |
| 03◎呼びかけの書 |
|
| "this
book calls for critical intellectuals in the former and current
colonies of the third world to once again deepen and widen
decolonization movements""(Chen Kuan-Hsing 2010: vii) "It further calls for critical intellectuals in countries that were or are imperialist to undertake a deimperialization movement by re examining their own imperialist histories and the harmful impacts those histories have had on the world. Dialectical interaction between these two processes is a precondition for reconciliation between the colonizer and the colonized, and only after such a reconciliation has been accomplished will it be possible for both groups to move together toward global democracy."(Chen Kuan-Hsing 2010: vii) |
「この本は、第三世界の旧植民地および現植民地において、脱植民地化運動を再び深化させ、拡大させるために、批判的な知識人たちに呼びかけている」(チェン・クァンシン、2010年:vii) 「さらに、帝国主義であった国々、または現在も帝国主義である国々において、自国の帝国主義の歴史を再検証し、その歴史が世界に与えた有害な影響を明らか にすることで、脱帝国主義化運動を行うよう、批判的な知識人たちに呼びかけている。この2つのプロセス間の弁証法的な相互作用は、植民地支配者と被植民地 支配者の和解の前提条件であり、そのような和解が達成された後で初めて、両グループが共にグローバルな民主主義に向かって進むことが可能になる。」(陳光 興 2010: vii) |
| 04◎ On Pin Pin’s film, Singapore Ga Ga |
|
| "The
director [Tan Pin Pin] uses sounds familiar to Singaporeans as a means
of articulation. Interviews with several "average" Singaporeans
document the details of their daily lives, including their fantasies,
such as the old man who plays the harmonica and dances to his own
rhythms in the subway, and who claims to be a Singapore national
treasure recognized by the National Arts Council"(Chen Kuan-Hsing 2010:
vii-viii) |
「監督(タン・
ピンピン)は、シンガポール人に馴染みのある音を表現手段として用いている。
複数の「平均的な」シンガポール人へのインタビューでは、彼らの日常生活の詳細が記録されている。その中には、地下鉄でハーモニカを演奏し、自分のリズム
に合わせて踊る老人など、彼らの空想も含まれている。この老人は、シンガポール国民の宝であり、ナショナル・アーツ・カウンシルに認められていると主張し
ている」(チェン・クアンシン 2010: vii-viii) |
| 05◎ナショナリズムに対する態度は「純粋な否定」から「条件付き受容」へ |
|
| "My
own attitude toward nationalism has thus changed over the years from
pure negation to a conditional acceptance."(Chen Kuan-Hsing 2010: x) |
「ナショナリズムに対する私の態度は、純粋な否定から条件付きの容認へと、長年にわたって変化してきた。」(陳光興 2010: x) |
| 06◎脱=冷戦の定義、しかし、これでは擬人化した社会の冷戦の「トラウマ」状況? |
|
| "what I call "de-cold war," confronting the legacies and continuing tensions of the cold war"(Chen Kuan-Hsing 2010: x) |
「私が「脱冷戦」と呼ぶものは、冷戦の遺産と継続する緊張に立ち向かうことである」(陳光興 2010: x) |
| 07◎「方法としての〜」標題と、分析/理論手法を示さないこと |
|
| "He [Lu Xun] puts himself inside
the event itself and, with no trace of self-indulgence, attempts to
intervene. Lu Xun seldom begins or ends a discussion with theoretical
abstractions, though the political and intellectual implications of his
writing often go far beyond the event to which he responds. To reclaim
this mode of intellectual practice through the space opened up by
cultural studies is to ground ourselves in the cultures of our own -
that is, to address the issues arising out of our own puzzling
environments. As readers will notice, most of the chapters of this book
do not begin with an analytical concept or a set of theoretical
propositions."(Chen Kuan-Hsing 2010: xi) |
「彼は(魯迅は)その出来事そのものの中に身を置き、自己中心的な態度
を一切見せずに介入しようとする。魯迅は、議論を理論的な抽象概念から始めることも、また、それによって終わらせることも滅多にないが、彼の著作の政治
的・知的含意は、彼が反応する出来事をはるかに超えることが多い。文化研究によって開かれた空間を通じて、この知的な実践の方法を再発見することは、自分
自身の文化に根ざすこと、つまり、自分自身の困惑する環境から生じる問題に取り組むことを意味する。読者はお気づきだろうが、本書のほとんどの章は、分析
的概念や理論的命題から始まっていない。」(陳光興 2010: xi) |
| 08◎[具体的]社会世界に[効果的に]関わることと、学問的言説 |
|
| "My primary concern is with the
social world, and I engage with academic discourse only when this kind
of explanatory machinery (=academic discourse?) is necessary to
understand real conditions"(Chen Kuan-Hsing 2010: xi) "There is no desire to formulate theoretical concepts which are applicable to all events and in all contexts. The point is to generate historically grounded explanations so that specific interventions can be waged more effectively."(Chen Kuan-Hsing 2010: xi) |
「私の主な関心は社会的な世界に向けられており、現実の状況を理解するためにこうした説明装置(=学術的言説?)が必要な場合にのみ、学術的言説に関与する」(陳光興 2010: xi) 「あらゆる出来事やあらゆる文脈に適用できる理論的概念を構築したいとは思わない。重要なのは、特定の介入をより効果的に行うために、歴史的に根拠のある説明を生み出すことだ。」(陳光興 2010: xi) |
| 09◎未完の脱植民地化/台湾はまだ帝国の陰のもとに |
|
| "What we discover is that
decolonization in Taiwan has not yet really taken place. This
conclusion is the point of departure for the central argument of the
book, which emerges step by step in the following chapters."(Chen
Kuan-Hsing 2010: xiii) "After tracing the changing images of the United States in global politics before and after September 11, 2001, the chapter argues that in the instance of Club 51, we find a continuing commitment to identify with the empire, a clear result of three earlier moments of imperialization: those of the Chinese empire, the Japanese military occupation, and U.S. imperialism in the period after the Second World War."(Chen Kuan-Hsing 2010: xiv-xv) |
「我々が発見したのは、台湾における脱植民地化はまだ本当には起こっていないということだ。この結論は、この本の中心的な議論の出発点であり、次の章で段階的に明らかにされる。」(陳光興 2010: xiii) 「2001年9月11日以前と以後の世界政治における米国のイメージの変化をたどった後、本章では、クラブ51の例では、帝国との同一化への継続的な傾倒 が見られると論じている。これは、中国帝国、日本軍の占領、第二次世界大戦後の米国の帝国主義という3つの帝国化の時期の明確な結果である。」(Chen Kuan-Hsing 2010: xiv-xv) 2010: xiv-xv) |
| 10a◎方法としてアジアの可能性 |
|
| "Asia as method creates new
possibilities for intellectual work. The implication of Asia as method
is that using Asia as an imaginary anchoring points can allow societies
in Asia to become one another's reference points, so that the
understanding of the self can be transformed, and subjectivity
rebuilt"(Chen Kuan-Hsing 2010: xv) |
「アジアを方法として捉えることは、知的作業に新たな可能性を生み出
す。アジアを方法として捉えることの含意は、アジアを想像上の拠り所として使用することで、アジアの社会がお互いの参照点となり、自己の理解が変化し、主
観性が再構築される可能性があるということだ」(陳光興 2010: xv) |
| 12◎ポスト植民地主義の「動機」:グローバリゼーション理解の位相 |
|
| "If postcolonial studies is
obsessed with the critique of the West and its transgressions, the
discourses surrounding globalization tend to have shorter memories,
thereby obscuring the relationships between globalization and the
imperial and colonial past from which it emerged. This book puts the
history of colonialism and imperialism back into globalization studies.
In my view, without the trajectories of imperialism and colonialism,
one cannot properly map the formation and conditions of globalization.
Most importantly, the critical desire for a progressive form of
globalization can be endorsed only if it puts the intent to
deimperialize before all else. Globalization without deimperialization
is simply a disguised reproduction of imperialist conquest."(Chen
Kuan-Hsing 2010: 2) |
「ポストコロニアル研究が西洋とその罪に対する批判に執着する一方で、
グローバリゼーションをめぐる言説は記憶が浅く、それゆえ、グローバリゼーションが生まれた帝国主義的・植民地的過去との関係を曖昧にしてしまいがちであ
る。本書は、植民地主義と帝国主義の歴史をグローバリゼーション研究に再び位置づける。私の考えでは、帝国主義と植民地主義の軌跡を抜きにしては、グロー
バリゼーションの形成と条件を正しく把握することはできない。何よりも重要なのは、進歩的なグローバル化の形を求める批判的な願望は、脱帝国化の意図を何
よりも優先させる場合にのみ支持されるということだ。脱帝国化のないグローバル化は、単に帝国主義的征服の偽装された再生産にすぎない。」(陳光興
2010: 2) |
| 14◎脱植民地化されていない「普遍主義者」のヴィジョン |
|
| "The epistemological implication
of Asian studies in Asia is clear. If "we" have been doing Asian
studies, Europeans, North Americans, Latin Americans, and Africans have
also been doing studies in relation to their own living spaces. That
is, Martin Heidegger was actually doing European studies, as were
Michel Foucault, Pierre Bourdieu, and Jiirgen Habermas. European
experiences were their system of reference. Once we recognize how
extremely limited the current conditions of knowledge are, we learn to
be humlble about our knowledge claims. The universalist assertions of
theory are premature, for theory too must be deimperialized."(Chen
Kuan-Hsing 2010: 3) |
「アジアにおけるアジア研究の認識論的含意は明らかである。もし「我
々」がアジア研究を行っているのであれば、ヨーロッパ人、北米人、中南米人、そしてアフリカ人もまた、自分たちの生活空間に関連した研究を行っている。つ
まり、マルティン・ハイデガーは実際にはヨーロッパ研究を行っていたし、ミシェル・フーコー、ピエール・ブルデュー、ユルゲン・ハーバーマスも同様であっ
た。彼らにとってヨーロッパの経験は参照体系であった。現在の知識の状況が極めて限定的であることを認識すれば、私たちは自らの知識主張に対して謙虚にな
る。理論の普遍主義的主張は時期尚早であり、理論もまた脱帝国化されなければならない。(陳光興 2010: 3) |
| 15◎グローバリゼーション |
|
| "My use of the word
"globalization" does not imply the neoliberal assertion that
imperialism is a historical ruin, or that now different parts of the
world have become interdependent, interlinked, and mutually
beneficiary. Instead, by globalization I refer to capital-driven forces
which seek to penetrate and colonize all spaces on the earth with
unchecked freedom, and that in so doing have eroded national frontiers
and integrated previously unconnected zones. In this ongoing process of
globalization, unequal power relations become intensified, and
imperialism expresses itself jn a new form."(Chen Kuan-Hsing 2010: 4) |
私が「グローバリゼーション」という言葉を使う場合、帝国主義は歴史的
な遺物であるという新自由主義の主張や、現在では世界の異なる地域が相互依存、相互連結し、相互に利益を得ているという主張を意味するものではない。むし
ろ、私がグローバル化と呼ぶのは、資本主導の力が地球上のあらゆる空間を抑制されない自由で浸透し、植民地化しようとすることを指し、そうすることで、国
民の境界を浸食し、それまでつながりのなかった地域を統合してきた。この進行中のグローバル化のプロセスにおいて、不平等な力関係が強まり、帝国主義は新
たな形態で現れる。」(チェン・クァンシン 2010: 4) |
| 16◎脱植民地化の時間的位相が脱・冷戦を招来する |
|
| "Only after the cold war eased,
creating the condition of possibility for globalization, did
decolonization return with the full force of something long repressed.
But unlike the immediate postwar period, this moment of decolonization
requires us to confront and explore the legacies and ongoing tensions
of the cold war-an imperative I designate as "de-cold war.""(Chen
Kuan-Hsing 2010: 4) |
「冷戦が緩和され、グローバル化の可能性が生まれた後、長い間抑圧され
ていたものが勢いを取り戻し、脱植民地化が再び始まった。しかし、戦後間もない時期とは異なり、この脱植民地化の瞬間においては、冷戦の遺産や現在も続く
緊張に立ち向かい、探求することが求められる。私はこれを「脱冷戦」と呼ぶ。」(陳光興 2010: 4) |
| 17◎国民国家形成以前の歴史的痕跡やアレンジメント |
|
| "Although the political
structure of East Asia has been reshaped along the lines of the modern
nation-state, the dense history of the region has prevented it from
complete or rapid disintegration. The current configuration of big and
small nation-states in the region, for example, closely mirrors the
historical arrangement of suzerain and vassal states that existed
before the Second World War. Simply put, the current international
order in East Asia is a reconfiguration of the old Sinocentric
structure combined with the so-called "moden" system of the
nation-state."(Chen Kuan-Hsing 2010: 5) |
「東アジアの政治体制は近代国民国家の路線に沿って再編されてきたが、
この地域には濃密な歴史があるため、完全な、あるいは急速な解体は起こらなかった。例えば、この地域における大小さまざまな国民国家の現在の構成は、第二
次世界大戦前に存在した宗主国と属国の歴史的な配置を反映している。簡単に言えば、現在の東アジアの国際秩序は、いわゆる「近代」の国民国家システムと組
み合わさった、古い中華中心主義の構造の再編成である。(陳光興 2010: 5) |
| 18◎皇民化(imperialization of the subject) |
|
| "the Japanese colonial state
launched an "imperialization of the subject" (kominka) movement in 1937
to transform the colonized people in Taiwan and Korea into its imperial
subjects (Chou 1996).... [double process: (1) Assimilation, (2)
Empire’s Identity formation by “colonized” system - M. Ikeda] ... the
Japanese kominka movement can now be read as one instance of a
historical practice, one that allows us to foreground the problematic
of this double process. If this theoretical move stands, it raises a.
more burning question: what would be the consequences if
deimperialization did not happen? When the empire is eroded and the de
colonization process gathers momentum, we expect deimperialization to
occur in both the imperial country and the colony, but the experience
in East Asia after the Second World War has shown us that this process
can be interrupted."(Chen Kuan-Hsing 2010: 6-7) |
「日本植民地国家は、1937年に「皇民化」運動を開始し、台湾と朝鮮
の被植民民を帝国臣民へと変えようとした(周1996年)... 二重過程:(1)同化、(2)「植民地化」システムによる帝国のアイデンティティ形成
- M. Ikeda] ...
日本の皇民化運動は、この二重過程の問題を浮き彫りにする歴史的実践の一例として解釈することができる。この理論的立場が正しいとすれば、より切迫した問
題が提起される。脱帝国化が起こらなかった場合、どのような結果がもたらされるだろうか?帝国が衰退し脱植民地化のプロセスが勢いを増すとき、帝国国と植
民地の両方で脱帝国化が起こると予想されるが、第二次世界大戦後の東アジアでの経験は、このプロセスが中断される可能性があることを示している。」(陳光
興 2010: 6-7) |
| 19◎連合軍による「日本占領」 |
|
| "In 1945, when Japan was finally
defeated, the deimperialization process had just begun, but Japan was
then occupied for seven years by the Allies, who put General Douglas
MacArthur in charge of the country, and its status shifted quickly from
that of colonizer to colonized."(Chen Kuan-Hsing 2010: 7) |
「1945年、日本がようやく敗北したとき、脱帝国化プロセスは始まっ
たばかりだったが、日本はその後7年間連合国に占領され、連合国はダグラス・マッカーサー元帥を日本の統治責任者に任命し、その地位は植民地支配者から植
民地被支配者に急速に変化した。」(陳光興 2010: 7) |
| 20■ Caherine Hall(2002)の仕事 |
|
| - (1) Assimilation: Colonizer attempts to transform the colonized.. - "Much recent historical research, in particular the work of Catherine Hall (2002), has forcefully demonstrated that (2) the identity of the empire is directly shaped by its relation with the colony. In light of this discussion, the Japanese kominka movement can now be read as one instance of a historical practice, one that allows us to foreground the problematic of this double process."(Chen Kuan-Hsing 2010: 7) |
- (1) 同化:植民地支配者は被植民地化を試みる。 「多くの最近の歴史研究、特にキャサリン・ホール(2002年)の研究は、帝国のアイデンティティは植民地との関係によって直接的に形作られることを力強 く示している。この議論を踏まえると、日本の古民家ムーブメントは、この二重のプロセスの問題を浮き彫りにする歴史的実践の一例として読むことができ る。」(陳光興 2010: 7) |
| 21◎帝国の中枢/周辺システムの再編成(近代化?) | |
| "The improvement of the Chinese
economy has not only put China back in the center of global power, it
has facilitated imaginings - both positive and negative - of regional
reintegration in Northeast Asia. Although it is true that a new
regional structure is forming as the center of gravity in Asia shifts,
it would be ridiculous and unacceptable to understand the situation as
simply the return of the old Chinese empire in the form of an updated
tributary system. Nevertheless, the view of China as a the rhetoric of
globalization began to take off, and by the early 1990s,
"globalization" had become a buzzword in the academy."(Chen Kuan-Hsing
2010: 7-8) |
「中国経済の改善は、中国を世界の中心に再び位置づけただけでなく、北
東アジアにおける地域再統合について、肯定的なものから否定的なものまで、さまざまな想像を促した。アジアの重心が移動する中で、新たな地域構造が形成さ
れつつあるのは事実であるが、その状況を単に、更新された朝貢体制という形で昔の中国帝国が復活したと理解するのは、馬鹿げており、受け入れがたい。しか
し、中国をグローバル化のレトリックとして捉える見方が広まり始め、1990年代初頭には「グローバル化」が学問の世界で流行語となっていた。(陳光興 2010: 7-8) |
| 22■何をもって「中国」と表象するのか?——現今の多様な中国はグローバリゼーションの産物? |
|
| "China's reopening to the world
in the late 1970s was an important condition for the formation of
neoliberal globalization, especially in East Asia. Inside China, Deng
Xiaoping's southern tour (nanxun) in 1992 officially marked the
country's market turn, and the changes brought about by this shift have
only escalated since then."(Chen Kuan-Hsing 2010: 12) "on the one hand, there is the real sentiment of suffering that is the legacy of Western and Japanese imperialist invasions, and the corresponding reactive dangers inherent in the presently emerging Chinese triumphalism; on the other hand, there is the deeper necessity to reflexively take up China's empire (if not imperialist) status in relation to the rest of Asia, which - though from an earlier historical moment - has generated lasting hegemonic, pressure on the whole of East Asia."(Chen Kuan-Hsing 2010: 13) |
「1970年代後半における中国の対外開放は、新自由主義的グローバリ
ゼーションの形成にとって重要な条件であり、特に東アジアにおいてそうであった。中国国内では、1992年の鄧小平による南巡(nanxun)が公式に市
場化への転換を意味し、それ以来、この転換によってもたらされた変化はエスカレートする一方である。」(陳光興 2010: 12) 「一方には、西洋と日本の帝国主義的侵略の遺産である苦悩の真の感情があり、現在台頭しつつある中国の勝利主義に内在するそれに対応する危険性がある。他 方には、より深い必要性として、アジアの他の地域との関係において、反射的に中国の帝国(帝国主義的ではないとしても)の地位を捉える必要がある。これ は、より早い歴史的瞬間からではあるが、東アジア全体に持続的な覇権的圧力を生み出してきた。」(陳 2010: 13) |
| "In 1957 Albert Memmi made a
clear demand: "'The disclosures having been made, the cruelty of the
truth having been admitted., the relationship of Europe with her former
colonies must be reconsidered. Having abandoned the colonial framework,
it is important for all of us to discover a new way of living with that
relationship" (Memmi 1991 [1957], 146)"(Chen Kuan-Hsing 2010: 14) "[C]ounter neoliberal globalization,...." p.16 "But to counter neoliberal globalization, a global decolonization and deimperialization movement must first be carried out. If the colonized and colonizer do not address the history of imperialism and colonialism together, it is impossible to build solidarity among the so called global multitudes. If the world is not to go on as a theater of imperial conquests and rivalries, then deimperialization is a necessary intellectual and political commitment."(Chen Kuan-Hsing 2010: 16) |
「1957年、アルベルト・メンミは明確な要求を提示した。「『暴露』
がなされ、『真実』の残酷さが認められた今、ヨーロッパと旧植民地との関係は再考されなければならない。植民地体制を放棄した今、その関係性とともに生き
る新しい道を、私たち全員が発見することが重要である」(Memmi 1991 [1957], 146)」(陳光興 2010: 14) 「新自由主義グローバリゼーションに対抗して」p.16 「しかし、新自由主義グローバリゼーションに対抗するには、まず世界的な脱植民地化と脱帝国化の運動が実施されなければならない。被植民地化された者と植民地主義者が帝国主義と植民地主義の歴史を共に直視しなければ、いわゆるグローバル・マルチチュードの連帯を築くことは不可能である。世界が帝国主義の征服と対立の舞台として存続しないのであれば、脱帝国主義化は知的にも政治的にも必要な取り組みである。」(陳光興 2010: 16) |
| 24◎準帝国[主義者]subempire, subimperialist |
|
| "[D]id Taiwan finally express its true subimperialist nature," p.18, p.20(third paragraph) "I use the word "subempire" to refer to a lower-level empire that is dependent on an empire at a higher level in the imperialist hierarchy. Neocolonial imperialism here refers to a form of structural domination in which a country with more global power uses political and economic interventions in other countries to influence, policy and exercise control over markets. Unlike the earlier colonial imperialism, which depended on, invasion, occupation, and usurpation of sovereignty to further economic interests, neocolonial imperialism uses military force as a support mechanism and employs it only as a last resort. '"(Chen Kuan-Hsing 2010: 18) |
「台湾はついにその真の亜帝国主義的本性を露わにした」p.18、p.20(3段落目) 「私は、帝国主義のヒエラルキーにおいて上位の帝国に依存する下位の帝国を指す言葉として、「サブエンパイア」という言葉を使用している。 ここでいう新植民地主義とは、より大きな世界的影響力を持つ国が、他国に対して政治的・経済的介入を行い、政策に影響を与え、市場を支配する構造的支配の 形態を指す。経済的利益を追求するために侵略、占領、主権の簒奪に依存していた初期の植民地帝国主義とは異なり、新植民地主義は軍事力を支援メカニズムと して使用し、あくまでも最後の手段としてのみ用いる。「(チェン・クアンシン 2010: 18)」 |
| 25◎台湾=準帝国の諸相 |
|
| "The state-capital alliance is
the engine for the formation of Taiwanese subimperialism. The emergence
of the southward-advance discourse in the 1990s demonstrated that
capital accumulation in Taiwan had accelerated to the extent that
within fifty years, the island had metamorphosed from a colony into a
quasi-empire, no longer occupying a marginal position on the map of
global capitalism. Constricted economically by a mega-empire, it joined
the game of imperialist competition by investing downward in order to
seize markets, resources, and labor in less developed countries. Taking
into consideration the three-worlds theory put forward at the 1955
Bandung Conference, we may ask if this means that some third-world
areas-such as the so-called Four Little Tigers (Hong Kong, Singapore,
South Korea, and Taiwan) or other newly industrialized countries - have
acquired the strength to expand abroad and have thereby redrawn the
world map. Or do we need to produce a layered analysis to chart the
political meanings of the emerging internal differences within the
third world?"(Chen Kuan-Hsing 2010: 20) |
「国家資本同盟は台湾の半帝国主義形成の原動力である。1990年代に
南進論が浮上したことは、台湾における資本蓄積が加速し、50年という短期間で植民地から準帝国へと変貌を遂げ、もはやグローバル資本主義の地図上で周辺
的な位置を占めることはなくなったことを示している。超大国に経済的に締め付けられた台湾は、後進国における市場、資源、労働力を獲得するために投資を行
い、帝国主義的競争に参入した。1955年のバンドン会議で提唱された「3つの世界」理論を考慮すると、いわゆる「4小虎」(香港、シンガポール、韓国、
台湾)やその他の新興工業国といった一部の第三世界の地域が海外進出する力を獲得し、それによって世界地図が塗り替えられたということなのだろうか。ある
いは、第三世界内部に生じている新たな相違の政治的意味を明らかにするために、重層的な分析を行う必要があるのだろうか?」(陳光興 2010: 20) |
| 26◎第三世界カルスタの問題系:文化の歴史的空間的文脈性? |
|
| - The Problematic of Third-World Cultural Studies, pp.20- "In the field of cultural studies, the third world as an analytical category has also been ignored.... (1) First, if historical materialism is the assumed methodology of cultural studies, and industrial capitalism its assumed reference system of practices, then what sort of analytical machinery can be developed to engage with agricultural societies in third-world spaces, where peasants are still the dominant group in the population? (2) Second, without a category such as the third world, local analysis is shaped by concept of the nation-state, which explains the emergence of British, American, Canadian, Australian, and other "national" cultural studies. (3) Third, questions of colonialism and imperialism have been pushed to the side in former imperial centers."(Chen Kuan-Hsing 2010: 21) |
- 『第三世界の文化研究の問題点』、20ページ 「文化研究の分野では、分析カテゴリーとしての第三世界も無視されてきた。(1)まず、歴史的唯物論が文化研究の想定される方法論であり、産業資本主義が 想定される実践の参照体系であるとすると、農民が人口の主要な集団である第三世界の空間における農業社会を扱うために、どのような分析的機械装置を開発で きるだろうか?(2) 第二に、第三世界のようなカテゴリーがなければ、ローカルな分析は国民国家の概念によって形作られる。これが、英国、米国、カナダ、オーストラリア、その 他の「国民的」文化研究の出現を説明するものである。 (3) 第三に、植民地主義と帝国主義の問題は、かつての帝国の中心地では脇に追いやられてきた。(Chen Kuan-Hsing 2010: 21) |
| 27◎第三世界/グローバリゼーション/帝国主義の問題点 |
|
| "Finally, with the rejection of
the third world as an outdated category, globalization has become an
alibi that is used to erase history and politics. One overt example of
this is John Tomlinson's Cultural Imperialism (1991). The concluding
chapter, "From Imperialism to Globalization," exemplifies the strategy
of replacing the pejorative "imperialism" with the neutral
"globalization.""(Chen Kuan-Hsing 2010: 21) |
「最後に、第三世界という時代遅れのカテゴリーが否定されたことで、グ
ローバリゼーションは歴史と政治を消し去るためのアリバイとして使われるようになった。その顕著な例として、ジョン・トムリンソンの著書『文化帝国主義』
(1991年)がある。この本の結論となる章「帝国主義からグローバリゼーションへ」は、否定的な意味を持つ「帝国主義」を中立的な「グローバリゼーショ
ン」に置き換える戦略の典型例である。(陳光興 2010: 21) |
| 28◎帝国主義の現状(ネオ〜?) |
|
| "the critical conditions and
constitutive effects of imperialism have not changed and may have
intensified: (1) the corporate monopoly system persists in core
metropolitan centers; (2) the continuous expansion of economic power in
the center intensifies its ambition to control resources and markets
elsewhere; (3) the international division of labor continues to enrich
the advanced capitalist zones; (4) powerful industrialized countries
continue to increase their exports and investments abroad; (5) the
exploitation of labor deepens; (6) the gap between the rich and the
poor grows around the world; and (7) the environment in colonized areas
continues to deteriorate."(Chen Kuan-Hsing 2010: 22) |
「帝国主義の重大な状況と構成上の影響は変わっておらず、むしろ強まっ
ている可能性がある。(1) 企業独占体制が主要都市中心部で継続している。 (2)
中心部における経済力の継続的な拡大が、他の地域の資源や市場を支配したいという野望を強めている。 (3)
国際分業が先進資本主義地域をさらに豊かにし続けている。 (4) 強力な工業国が海外への輸出と投資を増加させ続けている。 (5)
労働搾取が深まっている。 (6) 世界中で富裕層と貧困層の格差が拡大している。 (7)
植民地化された地域の環境は悪化の一途をたどっている」(陳光興 2010: 22) |
| 29◎「文化と帝国主義」(Summary points of Said's Culture and Imperialism(1993), p.25) |
|
| "For Said, imperialism and
colonialism are not simply matters of capital accumulation and the
seizure of territory and resources. Only with the backing of a powerful
ideological formation can a state overcome internal differences while
at the same time amassing enough energy and resources to conquer
external territories (ibid., 9). During the process of imperial
expansion, the imperial power projects its own understanding onto the
colony in its attempt to define the colonized culture. Through its
continuously changing relations with the colony, the imperialist
country reaches self-definition and self-affirmation. Its imperialist
subjectivity is constituted by its power relations with the
colony"(Chen Kuan-Hsing 2010: 24-25) "three interpretive directions emerge from reading Said: (1) the formation of imperialism is inevitably supported by cultural discourse and ideology; (2) the imperialist subject's identity can only be affirmed in relation to the colonized; and (3) the imperialist cultural imaginary conditions the vision and horizon of the colonized."(Chen Kuan-Hsing 2010: 25) on Renato Constantino (Filipino historian, 1919-1999), pp.31- Japanese scientists visions on the nature of Taiwan, pp.32-35 (relation from Wallace to Gramusci) |
「サイードにとって、帝国主義と植民地主義は、単に資本蓄積や領土・資
源の獲得の問題ではない。強力なイデオロギー的枠組みの支援があってこそ、国家は内部の異なる意見を克服し、同時に外部の領土を征服するのに十分なエネル
ギーと資源を蓄積することができる(同書、9ページ)。帝国主義の拡大の過程において、帝国主義国家は植民地に自らの理解を押し付け、植民地化された文化
を定義しようとする。植民地との絶え間なく変化する関係を通じて、帝国主義国は自己定義と自己主張に達する。帝国主義国の主観性は、植民地との力関係に
よって構成される」(Chen Kuan-Hsing 2010: 24-25) 「サイードの研究から、次の3つの解釈の方向性が浮かび上がる。(1)帝国主義の形成は、必然的に文化的言説とイデオロギーによって支えられている。 (2)帝国主義的主体のアイデンティティは、植民地化された人々との関係においてのみ肯定される。(3)帝国主義的文化の想像力は、植民地化された人々の 視野と地平を規定する。」(陳光興 2010: 25) レナート・コンスタンティーノ(フィリピン人歴史家、1919-1999)について、31ページ 日本の科学者の台湾観、32-35ページ (ウォーレスからグラムシまで) |
| 30◎ファノンへの言及 |
|
| "Fanon's self-psychoanalytic
account suggests that the writing subject's strong desire is to replace
the white colonizer and become him, rather than to recognize his own
existence as a black man."(Chen Kuan-Hsing 2010: 40) |
「ファノンの自己精神分析的な説明によると、文章の主題の強い願望は、黒人としての自身の存在を認識することではなく、白人の植民者と入れ替わり、彼になることである」(陳冠興 2010: 40) |
| 31◎中国文化イデオロギー(?) |
|
| "The identification with
cultural China can be very oppressive to ethnic Chinese who do not live
in mainland China. They are marginalized in their local environment,
but at the same time they are often asked to be Chinese. A strong
ethnocentric tendency often operates in the concept of cultural
China."(Chen Kuan-Hsing 2010: 40) on "Aboriginal, " p.53 aboriginal rebellion against the Dutch invaders, 1635, p.55 Taiwanese Nationalism Co-opted, pp.52-59 "The Taiwanese subimperialist eye, a role performed by the cultural discourse in question, was constructed to see the world according to a new southward-advance worldview, but its role was, mediated through the eye of the old Japanese empire."(Chen Kuan-Hsing 2010: 59) "The old empire's I refers to 1930s Tokyo, headquarters of the first southward advance, and its subject positions were located within the Japanese military state. The subempire's I, however, was located in 1990s Taipei -- the headquarters of its southward advance was the office of the president of Taiwan, in a building that had housed the office of the Japanese colonial governor -- and the subject positions of President Lee as the articulating agent were ruler, Han Chinese, Taiwanese, heterosexual, and male. The differences that emerged during the transition between the two were geopolitical location and ethnic identity: Taipei replaced Tokyo, and Han Chinese and Taiwanese replaced Japanese."(Chen Kuan-Hsing 2010: 60) |
「中国本土に住んでいない華人にとって、中国文化との同一視は非常に圧
迫的なものとなりうる。彼らは地元の環境で疎外されているが、同時にしばしば中国人であることを求められる。中国文化という概念には、強い民族中心主義的
な傾向がしばしば作用している。」(陳光興 2010: 40) 「原住民」p.53 「オランダ人侵略者に対する原住民の反乱、1635年」p.55 「台湾ナショナリズムの取り込み」pp.52-59 「台湾人の亜帝国主義的な眼差しは、問題となっている文化的な言説によって演じられる役割であり、新しい南進世界観に従って世界を見るように構築されたが、その役割は、旧日本帝国の眼差しを通して媒介されたものだった。」(陳光興 2010: 59) 「旧帝国のI(私?)は、1930年代の東京、すなわち第一次南進の拠点であり、その主観的位置は日本軍国主義国家の中にあった。しかし、亜帝国のIは 1990年代の台北に位置していた。すなわち、その南進の本拠地は、日本植民地時代の総督府のあった建物に台湾総統府が置かれたことで、その南進の本拠地 は台湾総統府となり、その推進役である李登輝総統の主体的地位は、支配者、漢民族、台湾人、異性愛者、男性であった。この2つの間に生じた相違は、地政学 上の位置と民族的なアイデンティティであった。すなわち、台北が東京に取って代わり、漢民族と台湾人が日本人に取って代わったのだ。」(陳光興 2010: 60) |
| 32◎第三世界カルチュラルスタディーズ |
|
| On the third-world nationalist imagination (Anderson 1991:163-185), p.63 "The third-world cultural studies,....," p.64 "Third-world cultural studies, actively confronting the phenomena and problems of lived reality, can be more powerful and more liberating if, in our analysis, we can identify and act on points for intervention."(Chen Kuan-Hsing 2010: 64) |
第三世界のナショナリストの想像力について(アンダーソン 1991:163-185)、p.63 「第三世界の文化研究は、...」 p.64 「第三世界の文化研究は、生活現実の諸現象や諸問題に積極的に立ち向かうものであり、我々の分析において介入すべき点を特定し、行動を起こすことができれば、より強力でより解放的なものとなるだろう。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 64) |
| 33■2. Decolonization: A Geocolonial Historical Materialism 65 |
|
| "Through the international
system of nation-states, global capitalism unifies the plurality of
geographical spaces and histories into a single, measurable
structure."(Chen Kuan-Hsing 2010: 66) |
「グローバル資本主義は、国民国家の国際システムを通じて、地理的空間と歴史の多様性を、測定可能な単一の構造へと統合する。」(陳光興 2010: 66) |
| 34◎ポストコロニアル批判(Fanon, Memmi and Nandy) |
|
| "Fanon's critique of nationalism
at the peak of the third-world independence movement in the 1950s and
1960s, Memmi's questioning of nativism during the 1950s and 1960s, and
Nandy's revitalization of a critical traditionalism (what I shall later
describe as civilizationalism) in the early 1980s all emerged in
response to problems of de colonization."(Chen Kuan-Hsing 2010: 67) "my purpose is to analyze and disarticulate colonialist and imperialist cultural imaginaries that are still actively shaping our present. By questioning the objects of identification, theoretical discourse on colonial identifications offers a way to address pressing contemporary issues. But this reading is a critical exercise, not a blind appreciation. As we move along, the limits of these positions will also be identified."(Chen Kuan-Hsing 2010: 69) |
「1950年代と1960年代における第三世界の独立運動のピーク時に
ファノンがナショナリズムを批判し、1950年代と1960年代にメンミがネイティヴィズムを問い直し、1980年代初頭にナディが批判的伝統主義(後に
私が文明主義として説明するもの)を再活性化したことは、すべて脱植民地化の問題への対応として現れたものである 。」(チェン・クワンシン
2010: 67) 「私の目的は、現在もなお私たちの現在を形作っている植民地主義的・帝国主義的文化イマジネーションを分析し、解体することである。植民地的な同一化の対 象を問うことで、植民地的な同一化に関する理論的言説は、差し迫った現代的な問題に対処するための方法を提供する。しかし、この解釈は盲目的な評価ではな く、批判的な試みである。私たちが進むにつれ、これらの立場にも限界があることが明らかになるだろう。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 69) |
| 35◎マノーニの視点 |
|
| "Mannoni brings the colonizer into the picture of colonial relations
and starts to address the psychological condition of the previously
concealed master. Unlike the colonial psychologist, whose central
concern was the colony and whose enunciative position was left
unexamined, Mannoni had the colonizer as his target, and his analysis
presupposed a relationship of mutually constituted subjectivity."(Chen
Kuan-Hsing 2010: 74) "Even though Mannoni was obviously against colonial exploitation and racial discrimination, in his position as a colonial information officer - who attempted to account for the 1947 anticolonial revolt in which more than a hundred thousand Madagascans were killed - he could not escape the epistemic limits of Eurocentrism."(Chen Kuan-Hsing 2010: 75) "his analysis prepared the colonizer to face the anxiety of having to leave the colony. Mannoni's work can be located within the wave of writings and practices that constitute the postwar decolonization movement, but his particular contribution was to document the psychological struggles of that specific historical moment, which prepared the way for later psychoanalyses of the colonizer."(Chen Kuan-Hsing 2010: 75) |
「マノーニは、植民地関係の図式に植民地主義者を登場させ、それまで隠
されていた支配者の心理状態を明らかにし始めた。植民地心理学者は、植民地を主な関心事とし、その発話上の立場は検証されることなく放置されていたが、マ
ノーニは植民地主義者を対象とし、彼の分析は相互に構成された主観性の関係を前提としている。」(チェン・クワン・シン 2010: 74) 「マノーニは明らかに植民地搾取と人種差別に反対していたが、植民地情報将校として、1947年に10万人以上のマダガスカル人が死亡した反植民地蜂起を 説明しようとした立場では、彼はユーロセントリズムの認識論的限界から逃れることはできなかった。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 75) 「彼の分析は、植民地を去らなければならないという不安に植民地主義者が直面する準備を整えた。マノーニの研究は、戦後の脱植民地化運動を構成する一連の 著作や実践の中に位置づけることができるが、彼の特別な貢献は、その特定の歴史的瞬間の心理的葛藤を記録したことであり、それは後の植民地主義者の精神分 析への道筋を作った。」(チェン・クァンシン 2010: 75) |
| 36■精神分析的脱植民地化 The Psychoanalysis of Decolonization |
|
| "[Aime] Cesaire attacked
Mannoni's Eurocentric superiority in his Discourse on Colonialism (1972
[1953]) a text that served as an inspiration for Fanon's
intervention....[In Fannon's discussion] The alienation of the black
cannot be reduced to the question of individual psychology. It is the
social structure that conditions the collective psyche; hence, to use
his words, "the black man must wage his war on both levels" (ibid.).
Fanon's emphasis on the historical conditions of power relations is
what distinguishes his basic analytical stand from Mannoni's."(Chen
Kuan-Hsing 2010: 77) "Mannoni argues that "colonial exploitation is not the same as other forms of exploitation, and colonial racialism is different from other kinds of racialism" (quoted ibid., 88). Fanon counters that "colonial racism is no different from any other racism," and that "all forms of exploitation are identical because all of them are applied against the same 'object' man" (ibid.).... Many postcolonial theorists focus on a singular structure of domination-along the continuum of race, ethnicity, nation, and civilization - and are unwilling to bring other structures into the picture. But if structures of domination have historically always been interlinked and mutually referencing, then colonial structures are necessarily entangled with other structures of power."(Chen Kuan-Hsing 2010: 80) |
「[エメ・]セゼールは、マノーニの『植民地主義に関する言説』
(1972年[1953年])におけるヨーロッパ中心主義的な優越性を攻撃した。この文章は、ファノンの介入のインスピレーションとなったものである。
ファノンの議論では、黒人の疎外は個人の心理の問題に還元することはできない。集団心理を規定するのは社会構造であり、したがって、彼の言葉を借りれば、
「黒人は両方のレベルで戦わなければならない」(同書)のである。ファノンが力関係の歴史的条件を強調している点こそが、彼の基本的分析的立場をマノーニ
の立場と区別するものである。」(チェン・クワン・シン 2010: 77) 「マノーニは『植民地による搾取は他の搾取形態とは異なるものであり、植民地主義的な人種主義は他の人種主義とは異なる』と主張している(同書、88ペー ジ)。これに対し、ファノンは『植民地主義的な人種主義は他の人種主義と何ら変わらない』と反論し、『あらゆる搾取形態は同一のものであり、なぜなら、そ れらはすべて同じ「対象」である人間に対して適用されるからだ』と主張している(同書)」。多くのポストコロニアル理論家は、支配の単一構造に焦点を当て ている。すなわち、人種、民族、国民、文明の連続体である。そして、他の構造を視野に入れることを嫌う。しかし、支配の構造が歴史的に常に相互に結びつ き、相互に参照し合っているのであれば、コロニアルな構造は必然的に他の権力の構造と絡み合うことになる。(陳光興 2010: 80) |
| 37◎ホブソン:ナショナリズムと帝国主義の結びつき |
|
| "J.A. Hobson, as early as 1902,
had remarked on the dose ties between nationalism and imperialism: the
latter, he argued, cannot function without the former (Hobson 1965
[1902])."(Chen Kuan-Hsing 2010: 82) |
「J.A.ホブソンは早くも1902年に、ナショナリズムと帝国主義の密接な関係について言及していた。後者は前者なしには機能しないと彼は主張した(Hobson 1965 [1902])。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 82) |
| 38◎メンミの忘れられた意義 |
|
| "In the last two chapters of his
seminal work, The Colonizer and the Colonized, Albert Memmi documented
and analyzed this nativist "self rediscovery movement." Although Memmi
never used the word "nativism," the phenomenon he described is what I
understand today to be the nativist movement. The book was originally
published in 1957, five years after the first publication of Black
Skin, White Masks, and four years before that of The Wretched of the
Earth. But unlike Fanon's work, Memmi's important statement about
nativism was neglected by the third-world nativist movement, and it has
not received enough attention in contemporary postcolonial studies. If
Mannoni's text can be understood as a colonizer's, confession, and
Fanon's as a self-analysis of the colonized then Memmi's occupies a
position closer to that of the subject with a split identity."(Chen
Kuan-Hsing 2010: 85) |
「植民地主義者と被植民者」という彼の代表作の最後の2章で、アルベー
ル・メミは、このネイティビズムの「自己再発見運動」を記録し分析した。メミは「ネイティビズム」という言葉を使ったことはなかったが、彼が説明した現象
こそ、今日私がネイティビズムの運動と理解しているものである。この本は、1957年に出版された。『黒い肌と白い仮面』の初版から5年後、『被虐の大
地』の出版から4年前のことである。しかし、ファノンの著作とは異なり、メッミのネイティヴィズムに関する重要な主張は、第三世界のネイティヴィズム運動
からは無視され、現代のポストコロニアル研究においても十分な注目を集めてはいない。マノーニの文章が植民地主義者の告白であり、ファノンの文章が植民地
化された者の自己分析であると理解されるならば、メンミの文章はアイデンティティが分裂した主体に近い位置を占めることになる。」(チェン・クワン・シン
2010: 85) |
| 39◎ネイティヴィズム運動(否定から自己形成へ) |
|
| "For Memmi, the deep hurt of the
colonized cannot be completely cured: "we must await the complete
disappearance of the colonization - including the period of revolt"
(ibid., 141). Indeed, the period of revolt is a moment of pure
negation. Nativist movements will have to move beyond this negativity
to reconstitute the self. And it is in that moment of overcoming that
nativism can be transformed."(Chen Kuan-Hsing 2010: 88) the critical traditionalism of Gandhi, pp.90- (see, “Gandhi wanted to liberate India and at the same time liberate England,” p.200) "If nationalism is a general form of decolonization which targets the nation-state at the political level, then nativism is a downward cultural movement operating in everyday life, and civilizationalism is an upward version of nativism, often formed in physically larger geographical spaces with relatively long histories, and usually set against the imaginary West. These three forms cannot be reduced to a single plane of analysis."(Chen Kuan-Hsing 2010: 94) "As Memmi points out, the colonizer's racism is always offensive, but the racism of the colonized is reactive and defensive in nature. As he puts it, "though xenophobia and racism of the colonized undoubtedly contain enormous resentment and are negative forces, they could be the prelude to a positive movement, the regaining of self-control by the colonized"(ibid.)."(Chen Kuan-Hsing 2010: 95) |
「植民地化された人々の深い傷は、完全に癒えることはない。「私たち
は、植民地化の完全な消滅を待たなければならない。それは、抵抗の時期も含めてである」(同書、141ページ)。確かに、抵抗の時期は純粋な否定の瞬間で
ある。ネイティビズム運動は、自己を再構成するために、この否定性を乗り越えなければならない。そして、その克服の瞬間においてこそ、ネイティヴィズムは
変容しうるのである。」(陳光興 2010: 88) ガンディーの批判的伝統主義、pp.90-(「ガンディーはインドを解放すると同時にイギリスをも解放しようとした」p.200) 「ナショナリズムが政治レベルにおける国民国家を標的とする一般的な脱植民地化の形態であるとすれば、ネーティヴィズムは日常生活で作用する下向きの文化 的運動であり、文明主義はネーティヴィズムの上位版であり、通常は想像上の西洋と対立する形で、比較的長い歴史を持つ物理的に大きな地理的空間で形成され ることが多い。この3つの形態は、単一の分析平面に還元することはできない。」(チェン・クワン・シン 2010: 94) 「メンミが指摘しているように、植民地主義者の人種主義は常に攻撃的であるが、被植民者の人種主義は本質的に反応的で防御的なものである。彼が言うよう に、「被植民者の外国人嫌悪や人種主義は、間違いなく膨大な憤りを内包しており、否定的な力であるが、それは前向きな運動、すなわち被植民者が自己統制を 取り戻すための序曲となり得る」(同書)。」(陳光興 2010: 95) |
| 40◎ディアスポラ・アイデンティティは… |
|
| "the colonizer and the
colonized. Recent postcolonial studies have criticized the tendencies
of binarism and essentialism implicit in these two subject positions.
The notion of diaspora, popular in the 1990s, stressed the fluidity of
identity, but this and other similar theoretical moves run the risk of
denying the relevance of the colonial structure, or indeed of any form
of stable identity. Most of the important issues in colonial history
cannot be discussed without having the colonial structure in mind. At
the same time, we need to remember Fanon's point about other structures
coexisting in the same social formation. The colonial regime is a
"structure in dominance" (in the Althusserian sense) that intersects
with other structural forces."(Chen Kuan-Hsing 2010: 95) |
「植民地主義者と被植民者。最近のポストコロニアル研究では、この2つ
の主題の位置づけに内在する二元論と本質主義の傾向が批判されている。1990年代に流行したディアスポラの概念は、アイデンティティの流動性を強調した
が、これやその他の類似した理論的展開は、植民地構造の関連性、あるいは実際には安定したアイデンティティのいかなる形態をも否定する危険性がある。植民
地史における重要な問題のほとんどは、植民地構造を念頭に置かずに論じることはできない。同時に、同じ社会構造の中に共存する他の構造について、ファノン
が指摘した点を忘れてはならない。植民地体制は、他の構造的力と交差する「支配的構造」(アルチュセール流に言えば)である。(チェン・クワン・シン
2010: 95) |
| 41◎批判的ごちゃまぜ主義 A Critical Syncretism |
|
| "First, critical identity
politics needs to shift and to multiply its objects of identification
so that structural divisions can be breached, making it possible to
seek alliances outside one's own limited frame. Second, the
articulating agent, critical for building connections across
structures, needs to be especially conscious of cultivating and even
occupying identities defined by multiple structures."(Chen Kuan-Hsing
2010: 99) |
「まず、批判的なアイデンティティ・ポリティクスは、その同一化の対象
をシフトさせ、増殖させる必要がある。そうすることで、構造的な分裂を乗り越え、自らの限られた枠組みの外に同盟を求めることが可能になる。次に、構造を
越えたつながりを構築する上で重要な役割を果たす明確化の主体は、複数の構造によって定義されたアイデンティティを育成し、場合によっては占拠することに
特に意識を傾ける必要がある。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 99) |
| 42◎文化的アイデンティティ(S・ホール) |
|
| "In the essay "The Question of Cultural Identity" Stuart Hall proposes a list of the contradictory effects of globalization: 1. Cultural homogeneity and the global-postmodern breaks down national identity. 2. Resistance to globalization has deepened national and local identity. 3 National identity is in decline, but new forms of hybrid identity are gaining their positions. (Hall 1992a, 330 )"(Chen Kuan-Hsing 2010: 100) "cultural studies should be understood not simply as an academic discipline, but as a field of intellectual practices connecting with various other forms of struggle."(Chen Kuan-Hsing 2010: 102) |
「スチュアート・ホールはエッセイ『文化アイデンティティの問題』において、グローバル化の矛盾する効果のリストを提案している。 1. 文化の均質性とグローバル・ポストモダンのせいで、国民的アイデンティティは崩壊する。 2. グローバル化への抵抗は、国民的・地域的アイデンティティを深める。 3 国民的アイデンティティは衰退しつつあるが、ハイブリッドなアイデンティティの新たな形態が台頭しつつある。(Hall 1992a, 330)」(陳光興 2010: 100) 「カルチュラル・スタディーズは、単に学問分野としてではなく、さまざまな闘争形態と結びついた知的実践の分野として理解されるべきである。」(陳光興 2010: 102) |
| 43◎方法論としての歴史的唯物論の見直し |
|
| "If cultural studies can be
repositioned as an integral part of the global decolonization movement,
then its assumed methodology - historical materialism - must also be
renewed and reworked in the new context of globalization."(Chen
Kuan-Hsing 2010: 102) |
「文化研究がグローバルな脱植民地化運動の不可欠な一部として再定義されるのであれば、その前提となる方法論である唯物史観もまた、グローバル化という新たな文脈の中で刷新され、再構築されなければならない。」(陳光興 2010: 102) |
| 44◎ウィットフォーゲル |
|
| "In an important essay,
"Geopolitics, Geographical Materialism and Marxism" (1985 [1929]),
Wittfogel considers the central problematic for the early German
geographical materialist tradition to be the relation between nature
and human society. By nature, he means the environment, ecology,
weather, natural resources, and topography. Bringing the issue to the
framework of historical materialism, the question posed at the time
was: "which factor ultimately determines historical development, the
natural or the social?" (Wittfogel 1985 [1929],54).... Wittfogel
writes: "If the totality of the powers of production determine the
character of the mode of production -at any given historical moment, it
is the social aspects which (being the actively motivating agents)
determine change, whereas the naturally conditioned agents determine
whether and if change is possible and accordingly the direction of this
change. Even as man puts nature to his 'service/ he thereby submits
himself to nature (Plekhanov) and follows her" (ibid., 55j emphasis in
original)."(Chen Kuan-Hsing 2010: 103) "Having connected spatiality to the mode of production, Soja and Hadjimichalis immediately suggest that "it is primarily the reproduction process, however, which lies at the center of the spatial problematic" (ibid., 61). Here they turn to the three levels of the reproduction processes identified by Henri Lefebvre (biophysiological, labor power and means of production, and social relations of production) to locate the sites of the spatial problematic."(Chen Kuan-Hsing 2010: 105) "Lefebvre's groundbreaking books The Production of Space (1991 [1974]) and The Survival of Capitalism (1976 [1973]) were critical transitional works, linked to the earlier moment while opening the way for work such as that of Manuel Castells and David Harvey."(Chen Kuan-Hsing 2010: 105) |
「地政学、地理的唯物論、マルクス主義」(1985年[1929年])
という重要な論文において、ヴィットフォーゲルは初期のドイツ地理的唯物論の伝統における中心的な問題は、自然と人間社会の関係であるとみなしている。こ
こでいう「自然」とは、環境、生態系、気候、天然資源、地形などを指す。この問題を史的唯物論の枠組みに当てはめると、当時提起された疑問は、「歴史的発
展を最終的に決定するのは、自然要因か社会的要因か」というものであった(Wittfogel 1985
[1929],54)...。ヴィトフォゲルは次のように書いている。「生産力の総体が生産様式の性格を決定するのであれば、いかなる歴史的瞬間において
も、変化を決定するのは(能動的に動機づける要因である)社会的側面であり、自然条件に左右される要因は変化が可能かどうか、また可能であればその方向性
を決定する。人間が自然を「利用」するとしても、それによって人間は自然に従属し(プレハーノフ)、自然に従うことになる」(同書、55j、強調は原文の
まま)。(陳光興 2010: 103) 「空間性を生産様式と結びつけたソジャとハジミハリスは、すぐに「しかし、空間的な問題の中心にあるのは、主に再生産プロセスである」と示唆している(同 書、61ページ)。ここで彼らは、アンリ・ルフェーヴルが特定した再生産プロセスの3つのレベル(生物物理学的、労働力および生産手段、生産の社会的関 係)に目を向け、空間的な問題の所在を明らかにする。」(陳光興 2010: 105) 「ルフェーヴルの画期的な著作『空間の生産』(1991年[1974年])と『資本主義の生存』(1976年[1973年])は、マニュエル・カステルス やデイヴィッド・ハーヴェイの著作のような研究への道を開きつつ、それ以前の時代とつながった重要な過渡期の著作であった。」(陳光興 2010: 105) |
| 45◎ヨーロッパモデルは普遍ではなく… |
|
| "To spatialize historical
materialism is not only to remove Eurocentrism, but also to launch
another round of spatializing (after historicizing) epistemology. For
instance, the analysis of the Asiatic mode of production can no longer
take the European mode of production as the ideal model or point of
comparison. It is no longer a question of explaining why a Chinese mode
of production cannot develop into a real (European) capitalist mode of
production. Instead, the question becomes: within the imminent
historical-geographical formation, how does a geographical space
historically generate its own mode of production?"(Chen Kuan-Hsing
2010: 106) "Colonialism has transfigured the inner structure of the cultural imaginary in both the colony and the imperial center. To consider the colonial question on the same level as historical materialism and geographical historical materialism is (1) to politicize the epistemological grounding of historical materialism, so that colonization is necessarily placed at the center of analysis; (2) to remove the hidden Eurocentric elements, so that a more balanced account of the formation of different regional spaces of the world can surface; and (3) to emphasize the relative autonomy of local history and to insist on grasping analytically the specificities of the historical and the geographical."(Chen Kuan-Hsing 2010: 108) |
「歴史的唯物論を空間化することは、単にヨーロッパ中心主義を排除する
だけでなく、認識論を(歴史化の後に)空間化する新たな段階へと進めることでもある。例えば、アジアの生産様式の分析では、もはやヨーロッパの生産様式を
理想的なモデルや比較対象として捉えることはできない。中国における生産様式が、なぜ真の(ヨーロッパ的な)資本主義的生産様式へと発展できないのかを説
明することが問題なのではもはやない。むしろ、差し迫った歴史地理学的形成の中で、地理的空間が歴史的に独自の生産様式を生み出すのはどのような仕組みな
のか、という問いが重要になる」(陳光興 2010: 106) 「植民地主義は、植民地と帝国の中心の両方において、文化的想像力の内的構造を変容させた。植民地問題を唯物史観や地理的唯物史観と同じレベルで考えるこ とは、(1)唯物史観の認識論的根拠を政治化し、植民地化が必然的に分析の中心に置かれるようにすること、(2)隠れたヨーロッパ中心主義的要素を排除 し、世界の異なる地域空間の形成に関するよりバランスのとれた説明が浮上するようにすること、(3)ローカルな歴史の相対的な自律性を強調し、歴史的およ び地理的な特殊性を分析的に把握することに固執することである 歴史と地理の特殊性を分析的に把握することに重点を置く」(陳光興 2010: 108) |
| 46◎ 他者の想像的知覚 |
|
| "The difference is that the
Althusserian attempt is a general theory establishing the relation
between the subject and its living world, whereas the cultural
imaginary refers to an operating space within a social formation, in
which the imaginary perception of the Other and self-understanding are
articulated. In this domain, the structure of sentiment is the link and
mediator between the colonizer and the colonized."(Chen Kuan-Hsing
2010: 111) "colonialism is not yet a legacy but is still active in geocolonial sites on the levels of identification and cultural imaginary, and it continually reconfigures itself amid changing historical processes to reshape the colonial cultural imaginary."(Chen Kuan-Hsing 2010: 112) |
「アルチュセール的な試みは、主体と生活世界の関係を確立する一般的な
理論であるのに対し、文化的想像力は、他者についての想像上の知覚と自己理解が明確化される社会形成内の活動領域を指す。この領域において、感情の構造
は、植民地支配者と被植民地化された人々との間のつながりと仲介者である。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 111) 「植民地主義はまだ遺産ではないが、同一化と文化的想像のレベルにおけるジオコロニアルな場所では依然として活発であり、歴史的プロセスが変化する中で、植民地的文化的想像を再形成するために、絶えず自らを再構成している。」(陳光興 2010: 112) |
| 47■3. De-Cold War: The Im/possibility of "Great Reconciliation" 115 |
|
| (Citation)""For a long time, in
Taiwan, anyone who criticized the U.S. would be labeled a "communist
spy," which would destroy one's life and family. Unlike other
progressive Intellectuals in the Third World, those in Taiwan lost the
knowledge, ideas, and ability to criticize the hegemony of U.S.
neo-colonialism.... "the best will study in the U.S." has become the
highest value for young students in Taiwan." CHEN YING-ZHEN, "THE
MAKING OF TAIWAN'S AMERICANIZATION""(Chen Kuan-Hsing 2010: 115) "in Taiwan in the late 1980s and early 1990s, when one-way visits to mainland China were officially made possible. Loaded with gifts and longing for home, groups of travelers passed through the old Hong Kong airport, eager to reunite with their relatives. In the early 1990s, after my mother died, my father, escorted by my older brother, was one of these travelers. He came home to Taipei silent, not even mentioning the living conditions of his children there. He never went again, dying in 1995."(Chen Kuan-Hsing 2010: 117) "Chalmers Johnson argues in his well-documented book, Blowback: The Costs and Consequences of American Empire (2000), that even after the so-called end of the cold war, the United States has continued to rely on the same basic military strategy that it has deployed for the previous forty years. He warns that if the United States does not demobilize its empire, it will become an enemy to the rest of the world."(Chen Kuan-Hsing 2010: 119) Within the category of bensheng ren (本省人), Minnanese (who speak the language of southern Fujian province) are the largest population; Hakkanese and aboriginal people do not necessarily identity themselves as bensheng ren"(Chen Kuan-Hsing 2010: 124) bensheng ren (本省人) waisheng ren (外省人):"there is no common language or customs among the waisheng population,14 and the term "waisheng ren" is meaningful only in relation to the term "bensheng ren.""(Chen Kuan-Hsing 2010: 125) |
(引用)「長い間、台湾では米国を批判する者は誰でも「共産主義のスパ
イ」のレッテルを貼られ、人生と家族を台無しにされてきた。第三世界の他の進歩的な知識人と異なり、台湾の知識人は米国のネオ・コロニアリズムの覇権を批
判する知識、アイデア、能力を失ってしまった。台湾の若い学生にとって、「米国で学ぶのが最善」という考えが最高の価値観となっている。」
陳英倫著『台湾のアメリカ化の形成』、陳光興著『1980年代後半から1990年代前半の台湾では、 「1980年代後半から1990年代前半の台湾では、中国本土への一方的な訪問が公式に可能になった。故郷への思いを胸に、たくさんの贈り物を携えた旅行 者たちが、親戚との再会を心待ちにしながら、香港の古い空港を通過していった。1990年代初頭、私の母が亡くなった後、父は兄に付き添われて、そうした 旅行者の一人となった。台北に戻った父は、子供たちの生活状況について一言も口にせず、無口なままだった。 父は二度と台湾に戻ることなく、1995年に亡くなった。」(陳光興 2010: 117) 「チャールズ・ジョンソンは、詳細な調査に基づく著書『ブローバック: 『ブローバック:アメリカ帝国のコストと帰結』(2000年)という詳細な研究書の中で、チャルマーズ・ジョンソンは、いわゆる冷戦の終結後も、米国は過 去40年間展開してきたのと同じ基本的な軍事戦略に依拠し続けていると論じている。同氏は、米国がその帝国を非軍事化しなければ、世界にとっての敵となる だろうと警告している。」(陳光興 2010: 119) 本省人(bensheng ren)というカテゴリーでは、福建省南部の方言を話す閩南人が最も人口が多い。客家系住民や原住民は、必ずしも本省人であると自認しているわけではない」(陳光興 2010: 124) 本省人(bensheng ren) 外省人(waisheng ren):「外省人には共通の言語や習慣はなく、14 「外省人」という用語は「本省人」という用語との関連においてのみ意味がある。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 125) |
| 48■Dou-sang, or the Logic of Hierarchy: Japan> Taiwan> Mainland China (Chen Kuan-Hsing 2010: 125) |
|
| "Dou-sang is a Taiwanese term for father that comes from the Japanese otosan"(Chen Kuan-Hsing 2010: 125) "First, there is an intergenerational conflict between Dou-sang and his children: in contrast to Dou-sang's Japaneseness, the children's patriotism has been shaped by the KMT state's nationalist education policies. Second, Dou-sang struggles to defend his masculine dignity as the head of the family. As a man who married into his wife's family, normally something done only by men from very poor families, Dou-sang does not have enough social capital to perform the expected patriarchal role... "A man," he says, "has to stand up to pee."(Chen Kuan-Hsing 2010: 126) "Noticing that Dou-sang cannot understand her, the daughter speaks in Mandarin again, this time yelling in a high-pitched voice: "You are a Han traitor, a running dog. You are a Wang Jingwei!" Dou-sang turns to Wenjian for help and scolds the daughter in stronger terms: "What is she saying now? Bakayarou [a rude Japanese term for "idiot"]!""(Chen Kuan-Hsing 2010: 128) ""Evil wife, devil children is an expression not so much of Dou-sang's discontent with his family, but of an unspeakable sense of loneliness and powerlessness: "Pitiful, my youth. Sorrowful, Ply fate.""(Chen Kuan-Hsing 2010: 131-132) "The complex passion for Japan intensified when it was set in sharp contrast with the even harder life in the immediate postwar, Kuomintang era. Nostalgia for the good old days surfaced almost immediately. "We'd probably be better off if we were still living under Japanese rule" has been a general sentiment shared by the older generation of bensheng ren."(Chen Kuan-Hsing 2010: 133) "By the 1970s, Japan had also become globally recognized as an advanced country. Thus Japan's position as the archetype of the modem was further consolidated, and to Dou-sang's generation, the perception was simply not open to challenge."(Chen Kuan-Hsing 2010: 133) "The third-world nationalist desire for the model and the colonialist civilizing mission are complementary; together they form the horizon of the popular structure of sentiment."(Chen Kuan-Hsing 2010: 134) |
「『Dou-sang』は日本語の『お父さん』に由来する台湾語で、父親を指す」(陳光興 2010: 125) 「第一に、Dou-sangと彼の子供たちとの間に世代間の対立がある。Dou-sangの日本人としての側面とは対照的に、子供たちの愛国心は、国民党 政府による国家主義的教育政策によって形作られてきた。第二に、ドゥーサンは一家の主としての男らしさを守ろうともがいている。妻の家族と結婚した男とし て、通常は極貧家庭の男だけが行うことだが、ドゥーサンには期待される家父長的役割を果たすだけの社会的資本がない。「男は、立ちションをするために立ち 上がらなければならない」と彼は言う(Chen Kuan-Hsing 2010: 126)。 ドゥーサンが彼女の言葉を理解できないことに気づいた娘は、再び北京語で話し、今度は甲高い声で叫んだ。「あなたは漢人の裏切り者、走狗よ。あなたは汪兆 銘よ!」ドゥーサンはウェンジアンに助けを求め、娘を強い口調で叱った。「今度は何だって?バカヤロウ!」(Chen Kuan-Hsing 2010: 128) 「悪妻、悪子」という表現は、ドウサンの家族に対する不満というよりも、言いようのない孤独感と無力感の表れである。「哀れな我が青春。悲しい運命。」 (Chen Kuan-Hsing 2010: 131-132) 「日本への複雑な思いは、戦後の国民党時代におけるさらに厳しい生活との鮮明な対比によって、さらに強まった。古き良き時代への郷愁は、ほぼ直ちに表面化 した。「日本統治下に留まっていた方が、おそらくは良かっただろう」という考えは、一般的に、ベンシェンレン(本省人)の高齢世代によって共有されてい た。」(陳光興 2010: 133) 「1970年代までに、日本もまた世界的に先進国として認められるようになっていた。そのため、日本が近代の模範であるという立場はさらに強固なものとなり、同世代の台湾人にとっては、その認識に異議を唱える余地はなかった。」(陳光興 2010: 133) 「第三世界のナショナリストが抱くモデルへの欲望と、植民地主義者の文明化の使命は補完的なものであり、両者は共に大衆の感情構造の地平を形成している。」(陳光興 2010: 134) |
| 49■Banana Paradise: Trajectories: Anti-Japan -> Anticommunism -> Returning Home (Chen Kuan-Hsing 2010: 135) |
|
| "Unlike Dou-sangs unsentimental storytelling, Banana Paradise is full of black humor"(Chen Kuan-Hsing 2010: 137) "The film was released only two years after the 1987 lifting of martial law, when the political mood was still darkened by the shadow of the police state. Those decades of fear and violence inflicted by the state may account for the film's use of black humor, which was probably a textual strategy to soften the film's critical stance toward the state."(Chen Kuan-Hsing 2010: 137) |
「『ドウサンズ』の無感情な語り口とは異なり、『バナナパラダイス』はブラックユーモアに満ちている」(陳光興 2010: 137) 「この映画は、1987年の戒厳令解除からわずか2年後に公開された。その頃の政治情勢は、依然として警察国家の影に覆われ、暗い雰囲気に包まれていた。 国家による恐怖と暴力の数十年が、この映画のブラックユーモアの使用を説明しているのかもしれない。それは、おそらく、国家に対する映画の批判的な姿勢を 和らげるためのテキスト上の戦略であったのだろう。」(チェン・クァンシン 2010: 137) |
| 50■The Entanglements of Colonialism and the Cold War (pp.149-) | |
| "Dou-sang is about the effects
and "representations" of Japanese colonialism, and Banana Paradise
deals primarily with the effects of the cold war, but by juxtaposing
the two films one cannot help but identify "tears of suffering" as an
affective trope common to the historical experiences of both whlsheng
ren and bensheng ren."(Chen Kuan-Hsing 2010: 149) "In Banana Paradise, on the other hand, colonialism has been co:mpletely supplanted by the cold-war structure and is not touched on at all."(Chen Kuan-Hsing 2010: 149) "A double resentment is at work, as the Chinese think: Japan has learned from us for centuries, but they humiliated and attacked our nation when it was in crisis; we will never forget this. What is crucial to understand is that the anti-Japanese sentiment of wrusheng ren is not informed at all by the Japanese occupation of Taiwan because they did not experience it themselves. Colonialism and 1895 - the year the Japanese occupied Taiwan - two deeply meaningful signs for hensheng ren, never became part of the wrusheng ren's historical memory, probably in part because of the nationalist versions of history written in the postwar era."(Chen Kuan-Hsing 2010: 150) |
「『二重奏』は日本の植民地主義の影響と「表現」についてであり、『バ
ナナ・パラダイス』は主に冷戦の影響についてであるが、この2つの映画を並置することで、苦難の涙が、被害者と生存者の両方の歴史的経験に共通する感情的
な表現として認識されることは避けられない。」(陳光興 2010: 149) 「一方、『バナナ・パラダイス』では、植民地主義は完全に冷戦構造に取って代わられており、まったく触れられていない。」(陳光興 2010: 149) 「中国人は、二重の憤りを感じている。日本は何世紀にもわたって我々から学んできたのに、我々の国民が危機に瀕したときに屈辱を与え、攻撃した。我々は決 してこれを忘れない。重要なのは、本省人(wrusheng ren)の反日感情は、彼ら自身が経験していないため、日本による台湾占領からまったく影響を受けていないということだ。植民地主義と1895年、つまり 日本が台湾を占領した年は、台湾人にとって非常に意味深い出来事であるが、戦後に書かれた国粋主義的な歴史観の影響もあってか、おそらくは、台湾人にとっ て歴史の一部とはならなかった。」(陳光興 2010: 150) |
| 51◎小林よしのり漫画 |
|
| "The controversy over Kobayashi
Yoshinori's manga, Thesis on Taiwan, which triggered a clash of
opinions when a Taiwanese edition was published in 2001, clearly
expresses such structural differences."(Chen Kuan-Hsing 2010: 150) "the 1980s "Orphan of Asia" narrative expresses for the bensheng population an unforgettable historical wound: Taiwan was abandoned to Japan by China in 1895."(Chen Kuan-Hsing 2010: 152) |
「2001年に台湾版が出版された際に意見の衝突を引き起こした、小林よしのりの漫画『台湾論』をめぐる論争は、このような構造的な相違を明確に表現している。」(陳光興 2010: 150) 「1980年代の『アジアの孤児』という物語は、本省人にとって忘れがたい歴史的傷を表現している。1895年に中国から日本に捨てられた台湾。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 152) |
| 52◎日帝の影 |
|
| "They developed a hierarchical
worldview, with "modern" Japan on top, then "modernizing" Taiwan, and
finally "backward" China. For fifty years, there was no indication that
Taiwan would ever be liberated from Japanese colonialism; the colonized
population had no alternative but to struggle to survive under the
colonial regime."(Chen Kuan-Hsing 2010: 152) "Several important questions underlie the present discussion. First, how do we, in analytical terms, understand the 1949 forced immigration of the wrusheng population? How do we position the KMT regime?"(Chen Kuan-Hsing 2010: 153) "The 1947 partition of India and Pakistan split up huge numbers of families who were forced to choose between the two new countries, but that conflict centered on religious differences. After the Korean War, neither the North nor the South was forced to abandon the Korean Peninsula and move to another territory, such as Cheju Island."(Chen Kuan-Hsing 2010: 154) "Are they settlers, migrants, immigrants, refugees, or people m exile? Are they part of a diaspora, to use the fashionable academic term? Is the KMT regime a government in exile (which would mean that it resides abroad), a regime from another province, a defeated regime, or simply a cold-war regime?(Chen Kuan-Hsing 2010: 154) "A second concern that arises from the analyses of the films is the plight of the nobodies (xiao laobaixing), both bensheng and waisheng, who have been innocently caught up m larger political currents, and who have to endure much pain and suffering. Not being able to maintain their basic human dignity, some have gone mad (Desheng), some have committed suicide (Dou-sang), and still others have been stigmatized for either willingly making themselves slaves (nuxing) to the Japanese, or not fully identifying with Taiwan. In my view, the twin ideologies of statism and nationalism must shoulder much of the responsibility for this suffering" (Chen Kuan-Hsing 2010: 154). "experiencing the war against Japan on the mainland made it impossible for waisheng ren(外省人) to have a sympathetic understanding of the suffering of bensheng ren(本省人) under Japanese colonialism or of the mind-set engendered by that experience; at the same time, bensheng ren cannot empathize with the suffering that waisheng ren endured as a result of their forced migration with a defeated regime. Conditioned mainly by colonial structures, bensheng ren cannot really understand the waisheng structure of sentiment, which was shaped primarily by cold-war structures, just as wrusheng ren cannot truly understand on an emotional level the cultural effects of Japanese colonialism. What makes things worse is that each side uses its own suffering to ignore the possibility of acknowledging the other's grief."(Chen Kuan-Hsing 2010: 155-156). |
「彼らは階層的世界観を構築し、頂点に「近代」日本、その下に「近代
化」する台湾、そして最後に「後進的」中国を位置づけた。50年間、台湾が日本の植民地主義から解放される兆しはまったくなかった。植民地化された住民
は、植民地体制の下で生き残るために必死に闘う以外に選択肢はなかった。」(陳光興 2010: 152) 「現在の議論の根底には、いくつかの重要な問題がある。まず、1949 年の台湾住民の強制移住を分析的に理解するにはどうすればよいのか? また、国民党政府をどう位置づけるのか?」(陳光興 2010: 153) 「1947年のインドとパキスタンの分割は、膨大な数の家族を分断し、その家族たちは2つの新しい国家のどちらかを選択することを余儀なくされたが、その 対立は宗教の違いに起因するものであった。朝鮮戦争後、北も南も朝鮮半島を放棄して済州島などの別の領土に移住することを強制されたわけではなかった。」 (陳光興 2010: 154) 彼らは入植者なのか、移住者なのか、移民なのか、難民なのか、それとも亡命者なのか? 彼らは流行りの学術用語を使うならディアスポラの一部なのか? KMT政権は亡命政府(つまり国外に存在する政権)なのか、他省の政権なのか、敗北した政権なのか、それとも単に冷戦下の政権なのか?(Chen Kuan-Hsing 2010: 154) 「映画の分析から生じる第二の懸念は、ベンシェンとワイシェン双方のノバディーズ(小人物)の苦境である。彼らは、より大きな政治的潮流に無邪気に巻き込 まれ、多くの苦痛と苦悩を耐え忍ばなければならない。人間としての尊厳を保てず、狂気に走る者(Desheng)、自殺する者(Dou-sang)、ある いは自ら進んで日本人の奴隷となる(nuxing)か、台湾に完全には同化しないことで汚名を着せられる者もいた。 私の考えでは、国家主義とナショナリズムという二つのイデオロギーが、この苦しみの責任の多くを負わねばならない」(Chen Kuan-Hsing 2010: 154)。 「中国大陸で日本との戦争を経験した外省人は、日本による植民地支配下で苦しんだ本省人の苦しみや、その経験から生まれた考え方を理解することができな かった。同時に、敗戦政権とともに強制移住を余儀なくされた外省人の苦しみに対して、本省人は共感することができなかった。主に植民地構造によって形作ら れた「ベンシェン」は、主に冷戦構造によって形作られた「ワイシェン」の感情構造を本当に理解することはできない。同様に、「ルシェン」は、日本による植 民地支配の文化的影響を感情レベルで本当に理解することはできない。さらに悪いことに、双方とも自らの苦しみを利用して、他者の悲しみを認める可能性を無 視している。」(陳光興 2010: 155-156)。 |
| 53■Why Is a "Great Reconciliation" Im/possible? (pp.156-) 和解の問題 |
|
| "Reconciliation between these
two segments of the population will be made possible only by
establishing mutual recognition of each other's history of suffering.
This cannot be done in the very superficial way attempted by those
politicians who have called for a temporary suspension of the
controversy over unification versus independence. If reconciliation is
to be possible, repressed historical memories have to be reopened and
confronted. We have to be able to see the provincial register
contradiction as a historical-structural question, one that dwells
within everyone living in Taiwan. From here we must all recognize the
different histories suffered by both benshengren and wrusheng ren, to
bridge the gap of understanding and initiate a process of
reconciliation."(Chen Kuan-Hsing 2010:156) "if reconciliation between Taiwan and China is to be possible, it cannot be discussed simply in political or economic terms; nor will nationalist sentiments, which do nothing but cover up real differences, be of any use."(Chen Kuan-Hsing 2010:156-157) "In terms of international relations, engaging with the historical memories of Japanese colonialism is key to advancing reconciliation and peace in East Asia."(Chen Kuan-Hsing 2010:157) "Mizoguchi's urgent desire to seek reconciliation comes too early. In East Asia, as Sun Ge (2001a) suggests, intellectuals, governments, and the public in general have not yet openly discussed the issue of the region's historical memory in any meaningful way. So how do we respond to Mizoguchi's sincere invitation to collectively deal with the question of apology? The history suppressed by the cold war has not yet been opened up for critical reflection, so how can we talk about regional reconciliation?"(Chen Kuan-Hsing 2010:158) "The fact that no country in Asia has yet accepted an apology from the Japanese state reflects the general sentiment that much of this history has not been forgotten. The lack of forgiveness is partly due to the fact that these historical questions have not yet been adequately thought through within Japan."(Chen Kuan-Hsing 2010:159) "In the era of globalization that has emerged in the wake of the cold war, it is even clearer that these questions can no longer be addressed inside any national border. If attempts to engage these questions are locked within national boundaries, we will never break out of the imposed nation-state structure."(Chen Kuan-Hsing 2010:159) |
「この2つの集団間の和解は、お互いの苦難の歴史を相互に認識すること
によってのみ可能となる。統一か独立かという論争の一時停止を呼びかけた政治家たちが試みたような、ごく表面的なやり方では、これは達成できない。和解が
実現可能であるためには、抑圧された歴史的記憶を再び開示し、直視しなければならない。私たちは、省籍矛盾を歴史的構造的な問題として、台湾に住むすべて
の人々に内在する問題として捉える必要がある。そこから、私たちは、本省人と外省人がそれぞれに経験してきた異なる歴史を認識し、相互理解のギャップを埋
め、和解へのプロセスを開始しなければならない。」(陳光興 2010:156) 「台湾と中国との和解が実現可能であるならば、それは政治的あるいは経済的な観点のみで議論されるべきではない。また、現実の相違を覆い隠すだけのナショナリズム的感情も何の役にも立たないだろう。」(陳光興 2010:156-157) 「国際関係という観点では、日本の植民地主義の歴史的記憶と向き合うことが、東アジアにおける和解と平和を促進する鍵となる。」(Chen Kuan-Hsing 2010:157) 「溝口の和解を求める切なる願いは時期尚早である。東アジアでは、孫歌(2001a)が指摘するように、知識人、政府、そして一般市民が、この地域の歴史 的記憶の問題について、まだ有意義な形で公に議論したことはない。では、私たちは溝口の誠実な謝罪問題への呼びかけにどう応えるべきだろうか?冷戦によっ て抑圧された歴史は、まだ批判的な反省の対象として開かれていない。それでは、どうやって地域的な和解について語ることができるだろうか」(陳光興 2010:158) 「アジアのどの国も、日本国からの謝罪を受け入れていないという事実は、この歴史の多くが忘れ去られていないという一般的な感情を反映している。許しが得 られていないのは、こうした歴史問題が日本国内で十分に考え抜かれていないという事実にも起因している。」(陳光興 2010:159) 「冷戦後のグローバル化時代において、これらの問題はもはやいかなる国境の内側でも対処できないことはより明白である。もしこれらの問題への取り組みが国 境内に閉じ込められてしまうならば、私たちは押し付けられた国民国家の構造から抜け出すことは決してできないだろう。」(Chen Kuan-Hsing 2010:159) |
| 55■Club 51&AIT |
|
| "The letter was signed by Chou
Wei-ling on behalf of a group named Club 51. Next to the signature was
a circular drawing featuring a map of Taiwan in the center and a series
of slogans in English: "Statehood for Taiwan-Save Taiwan-Say Yes to
America....In early 1999, when Lee Teng-hui redefined relations between
Taiwan and mainland China as "a special relationship between two
countries," Club 51 took to the streets in front of the American
Institute in Taiwan (AIT), the de facto U.S. embassy on the island, to
protest Washington's ambiguous position on Taiwan's status"(Chen
Kuan-Hsing 2010:161) "Founded on the Fourth of July, 1994, by fifty-one intellectuals and businessmen with strong ties to the United States, Club 51 had grown to some five hundred members by 1996.... In March 2000, Club 51's sister organization, the Foundation for Establishing the 51st State, released ''A Report on the Public Opinion Survey of the Will to Build a Taiwan State," a thirty-page analysis of data gathered by a public opinion research firm."(Chen Kuan-Hsing 2010:162) "In 1998, encouraged by sympathetic as well as antagonistic reactions to Club 51's program, Chou published a highly imaginative work to substantiate his arguments and articulate his dream. A Date with the us. -The Ultimate Resolution of Taiwan's Future: Taiwan Becomes a State of the US. in 2013; Say Yes to America advocates a two-stage strategy. First, Taiwan becomes a U.S. territory, along the lines of Puerto Rico, then it seeks full statehood, as Hawaii did. Then, on 1 January 2013 - naturally, a splendid, sunny day-Taiwan officially becomes the fifty-first state of the United States of America. All Chinese surnames are changed forthwith: Yuan to Adams, Kung to Cohen, Chen to Dunn, Ding to Dean, and Chou to Jefferson. All Taiwanese cities and districts acquire new place names. Eight pages of the book are devoted to the renaming: Taipei is renamed as Cambridge, Taichung as Dalton, Kaohsiung as Farfax, Hsinchu as Talcom, and Makung as Malcolm."(Chen Kuan-Hsing 2010:163) "America is now an integral part of Asia, as a result of the culture of U.S. imperialism that emerged in the wake of the Second World War. But this crucial problematic also needs to be understood in the wider context of what can be described as an insecurity born of global uncertainty, a new structure of sentiment that is the direct product of neoliberal globalization. The emergence of this sentiment of insecurity cannot be explained except in the context of the currently emerging reconfiguration of imperialism and capitalism, of which globalization is a form of expression."(Chen Kuan-Hsing 2010:165) "In East Asia, the United States has always been regarded by critical intellectuals and others on the Left as an outsider-simultaneously outside the territory and the cultural psyche. But after a century of insinuating itself as the dominant point of reference in East Asia, it no longer seems analytically accurate to say that the United States is exterior to the histories of the region."(Chen Kuan-Hsing 2010:165) "The message is clear: Let us give up our own nation-state, with its hopelessly ambiguous status, and instead join another nation of our choice. State building would then no longer require endless unsuccessful efforts to join the United Nations. Our partial Americanization over the past fifty years can expand to fully embrace a new nationality - one allowing Taiwanese to say of their island "this is America.""(Chen Kuan-Hsing 2010:167) "Club 51's blunt use of the word "begging" reveals the hierarchical nature of the Taiwan-U.S. relationship and Taiwan's subcolonial status or, as Club 51 imagines it, Taiwan's quasi-state status, similar to the relationship between the suzerain and vassal states in the classic tributary system. Club 51's pragmatic realism cancels out all rhetorical pretensions of national dignity."(Chen Kuan-Hsing 2010:168) "If Taiwan were forced to become a part of China, then something like a refugee government would be set up in Los Angeles. By what chain of equivalents could the quasi-nation-state of Taiwan somehow effortlessly shift categories and borders to set up shop in the city of Los Angeles? But this idea is by no means ungrounded. From the 1960s to the 1990s, the United States, in particular Los Angeles, was the destination of choice for Taiwanese emigrants, and the city is now home to the largest concentration anywhere of middle-class immigrants from the island. In the Taiwanese imagination, Taiwan has long been inside Los Angeles and is an integral part of that city."(Chen Kuan-Hsing 2010:168) "It is slightly unclear why American and German are mentioned as identities of preference, and why Russian or Japanese are silently discarded. Indeed, German itself seems little more than a rhetorical flourish when the choice of cities is confined to the United States. Why this selectivity?/ The answer is offered a little later when the letter quotes Professor Lee Hsiao-fung, a professor of history at Shih Hsin University: "We would rather be stuffed to death by the hamburgers of American imperialism than shot to death by machine guns of Chinese Communist imperialism... Hamburger heaven is the outward expression of an implicit dream: America is the pinnacle of human civilization; a powerful, prosperous, democratic society; a land of certainty and security.""(Chen Kuan-Hsing 2010:170) "the great imperial dream of be coining American is never simply imposed from the outside. On the contrary, it is also cultivated within the local milieu -- and in our particular case, within the "new Taiwanese" middle class. The longing to become an American imperial subject occupies a prominent and intimate position in the Taiwanese psyche."(Chen Kuan-Hsing 2010:171) "To be effective, Club 51 must take account of nationalist sentiment, which is deeply rooted in historical experience. It wider stands that the intended readers of its letter are likely to feel uneasy "at an emotional level" about the idea of becoming American."(Chen Kuan-Hsing 2010:172) "The emergence of Club 51 in the 1990s was symptomatic not only of specific anxieties about Taiwan's status vis-a-vis mainland China and the United States, but also of a general uneasiness about the direction of the world as a whole."(Chen Kuan-Hsing 2010:173) "Club 51's nostalgic desire for empire, energized by the pressures of globalization, strongly marks the continuity of imperialism even after the Second World War."(Chen Kuan-Hsing 2010:173) "In East Asia, after all, there was a direct connection between the traditional form of colonialism and the cold-war structures that emerged after 1945. Ever since the bombing of Hiroshima and Nagasaki, the Japanese state has lived under the permanent shadow of American rule. In many parts of East Asia, Japanese imperial holdings were handed directly over to the United States. Meanwhile, authoritarian anticommunist regimes in South Korea, Taiwan, and South Vietnam were strongly supported by the United States as part of its effort to establish a vast arc of strategic protectorates to defend against the spread of communism. All of these imperialistic developments have ironically served to displace the question of U.S. imperialism."(Chen Kuan-Hsing 2010:175) ""As it is described as "a microscope on the politics of postwar Korea,” the 4.3 Event remains stigmatized as a primal scene in the acceleration of Korean modernity that is closely related to political violence of the state." (Kim 1996, 8)"(cited in Chen Kuan-Hsing 2010:176) "Cultural studies of U.S. imperialism in the region are only just starting to emerge, and it is important to caution against counter positioning one (subaltern) nationalism against another (paramount) nationalism."(Chen Kuan-Hsing 2010:176) "For some thirty years now, Hong Kong films have captured a significant share of the market in various East and Southeast Asian countries. By the 1990s, younger East Asians were no longer singing American pop songs in karaoke bars. The false consciousness thesis no longer has explanatory power. It cannot persuasively articulate these imported products to the internal logic of local cultural history. The theoretical turn from cultural imperialism to the culture of imperialism enables a more sophisticated understanding."(Chen Kuan-Hsing 2010:177) "In East Asia, colonial identifications and disidentifications since the Second World War have set the boundaries of the local cultural imagination, consciously and unconsciously articulated by and through various institutions of the nation state in alliance with capital and even sectors of the civil society. The power behind the culture of U.S. imperialism comes from its ability to insert itself into a geocolonial space as the imaginary figure of modernity, and as such, the natural object of identification from which the local people are to learn."(Chen Kuan-Hsing 2010:177) "and Japan is also undergoing a re-Asianization phase. These self-rediscovery movements are obviously connected to the regionalization of global capital, but the psychological drive at their core is once again grounded in colonial history"(Chen Kuan-Hsing 2010:178) "If we wish to honestly understand the subjectivity of the self in East Asia, we have to recognize that the United States has not merely defined our identities but has become deeply embedded within our subjectivity."(Chen Kuan-Hsing 2010:178) "Most responses to the attack from around the world could be divided into two types. The first strongly supported U.S. military action to combat terrorism, which was Club 51's position. The second' reflected the anti-American sentiment that rapidly surfaced throughout the world on an unprecedented scale."(Chen Kuan-Hsing 2010:179) "By the 1930s, some Japanese intellectuals felt that America had become a constitutive element of Japanese identity. A startling passage from Takanobu Murobuse's America, published in 1929, makes this quite clear: "Where could you find Japan not Americanized? How could Japan exist without America? And where could we escape from Americanization? I dare to even declare that America has become the world, Japan is nothing but America today" (quoted in Yoshimi 2000,202-3)."(Chen Kuan-Hsing 2010:180) "The United States was a relative newcomer to imperialist power politics, and led by President Woodrow Wilson, it proposed a strategy of self-determination for colonized spaces, which proved to be effective not only in U.S. competition with established imperial powers in already occupied territories, but also in leading colonized nationalist subjects to collaborate with the United States."(Chen Kuan-Hsing 2010:180) "The historian Bruce Cumings has traced a direct transition from Japanese to U.S. imperialism throughout East Asia in the years following the Second World War (Cumings 1984). In addition to occupying the Japanese mainland, the United States assumed control of Japan's colonial apparatus directly from the defeated Japanese empire."(Chen Kuan-Hsing 2010:180-181) "The shift from liberator to global enemy was what enabled the explosive critique of the United States that emerged in the run-up to the 2003 invasion of Iraq"(Chen Kuan-Hsing 2010:183) "Even if we accept the argument that anticommunism and pro-Americanism are major elements of Taiwanese subjectivity to explain Taiwan's relatively weak opposition to the U.S. invasion of Iraq, the depth of pro-Americanism in Taiwan is still difficult to acknowledge. Being anti-American is like opposing ourselves, and to love Taiwan is to love America. This is why we cannot oppose U.S. imperialist intervention. Taiwan's popular culture has a long tradition of Japano-philia; the Korean Wave (Korean popular culture circulated widely during the last decade) that swept through Asia has created its share of Taiwanese Korea-philes; and there are even groups of Taiwanese Shanghaiphiles. But no one speaks of Americaphilia. The desire for America is so deep that we have no easy way of addressing it."(Chen Kuan-Hsing 2010:186-187) "Club 51 is willing to honestly face the political realities of the present; its problem lies with its obviously fantastic vision of the future. What makes it think that American citizens will accept Taiwan as a state, or that mainland China will accept that arrangement? Nevertheless, Club 51 relentlessly pushes its views: Taiwanese must choose whether they want to be Chinese or American."(Chen Kuan-Hsing 2010:190) "On 22 April 2005, the fiftieth anniversary of the Bandung Conference, Prime Minister Koizumi once again apologized on behalf of his government for Japan's invasions of different parts of Asia during the Second World War."(Chen Kuan-Hsing 2010:192) "The implications are clear. First, the rapid recovery of the postwar Japanese economy was made possible in part by Japan's passing defense spending along to the United States. Japan now declares itself to be a world power, but at the same time, it is unwilling to relinquish its reliance on the US. military. The trade-off is immense: on the surface, Japan is an independent country, but in reality, it subordinates itself to US. military power. Culturally belonging to the third world, Japan refuses to position itself accordingly and stand with its Asian neighbors. Second, democracy in South Korea and Taiwan was achieved through difficult and persistent struggles against authoritarian regimes. Problematic as they are, the democracies in South Korea and Taiwan were not gifts from a U.S. military government, but achievements won in spite of American strategic interests."(Chen Kuan-Hsing 2010:193) |
「その手紙は、クラブ51というグループを代表して周偉嶺が署名した。
署名の隣には、台湾の地図を中央に配した円形の図があり、英語で次のようなスローガンが並んでいた。「台湾の国家承認を求める、台湾を守ろう、アメリカに
イエスと言おう...」1999年初頭、李登輝が台湾と中国本土の関係を「二つの国間の特別な関係」と再定義した際、クラブ51は台湾における事実上の米
国大使館であるアメリカン・インスティテュート・イン・タイワン(AIT)の前でデモを行い、台湾の地位に関するワシントンのあいまいな立場に抗議した
(陳光興 2010:161) :161) 「1994年7月4日、米国とのつながりが深い51人の知識人や実業家によって設立されたクラブ51は、1996年までに500人ほどの会員にまで成長し た。2000年3月、クラブ51の姉妹団体である「第51番目の州設立財団」は、世論調査会社が収集したデータを30ページにわたって分析した「台湾国家 樹立の意志に関する世論調査報告書」を発表した。」(陳光興 2010:162) 「1998年、クラブ51の番組に対する好意的な反応と敵対的な反応に後押しされた周は、自らの主張を裏付ける非常に想像力豊かな作品を発表し、夢を明確 に表現した。2013年、アメリカとのデート - 台湾の未来の究極の解決策:台湾はアメリカの州になる。『アメリカにイエスと言おう』は2段階の戦略を提唱している。まず、台湾はプエルトリコにならって 米国の領土となり、その後ハワイがそうしたように完全な州となることを目指す。そして2013年1月1日、当然ながら素晴らしい晴天の日に、台湾は正式に 米国の51番目の州となる。すべての中国姓は即座に変更される。Yuan(ユアン)はAdams(アダムス)、Kung(クン)はCohen(コーエ ン)、Chen(チェン)はDunn(ダン)、Ding(ディン)はDean(ディーン)、Chou(チョウ)はJefferson(ジェファーソン)に 変更される。台湾のすべての都市と地区には新しい地名が付けられる。この本の8ページが名称変更に割かれている。台北はケンブリッジ、台中はダルトン、高 雄はファラックス、新竹はタルコム、そしてマクンはマルコムに改名される。」(陳光興 2010:163) 「アメリカは今やアジアの不可欠な一部となっている。これは第二次世界大戦後に生まれた米国帝国主義の文化の結果である。しかし、この重要な問題は、グ ローバルな不確実性から生じる不安、新自由主義グローバリゼーションの直接的な産物である新しい情緒構造とでも呼べるもの、というより広い文脈で理解され る必要がある。この不安の情緒の出現は、現在生じつつある帝国主義と資本主義の再編という文脈でしか説明できない。グローバリゼーションはその表現形態の ひとつである。」(陳光興 2010:165) 「東アジアでは、米国は常に批判的な知識人や左派の人々から、領土と文化心理の両面で外部に位置する部外者とみなされてきた。しかし、1世紀にわたって東 アジアにおける支配的な参照点として存在を示唆してきた後では、もはや米国がこの地域の歴史の外にあると分析的に言うのは正確ではないように思われる。」 (Chen Kuan-Hsing 2010:165) 「メッセージは明確である。絶望的に曖昧な地位にある自国の国民国家を放棄し、代わりに我々が選択する別の国家に加わるべきである。そうすれば、国家建設 はもはや国連加盟に向けた無限の失敗を繰り返す必要はなくなる。過去50年間の部分的アメリカ化は、完全に新しい国籍を受け入れるまでに拡大し、台湾人が 自分たちの島を「ここはアメリカだ」と言えるようになるだろう。」(Chen Kuan-Hsing 2010:167) 「クラブ51が『物乞い』という言葉を露骨に使用したことは、台湾と米国の関係における階層的な本質と、台湾の半植民地的な地位、あるいはクラブ51が想 像するような、古典的な朝貢体制における宗主国と属国の関係に類似した台湾の準国家的な地位を明らかにしている。クラブ51の現実主義は、ナショナリズム の尊大さをすべて打ち消す。」(陳光興 2010:168) 「もし台湾が中国の一部になることを強いられた場合、ロサンゼルスに亡命政府のようなものが設立されるだろう。準国民国家である台湾が、どのような等価の 連鎖によって、なんなくカテゴリーや国境を移行し、ロサンゼルスに拠点を設立できるというのだろうか?しかし、この考えは決して根拠のないものではない。 1960年代から1990年代にかけて、米国、特にロサンゼルスは台湾からの移民の目的地として人気が高かった。現在、この都市には台湾からの移民の中流 階級が世界で最も多く集中している。台湾人の想像力の中では、台湾は長い間ロサンゼルスの中にあり、その都市の不可欠な一部となっている。」(陳光興 2010:168) 「アメリカやドイツが好みのアイデンティティとして挙げられ、ロシアや日本が黙殺されている理由は、少し不明瞭である。実際、都市の選択がアメリカに限定 されている場合、ドイツという言葉自体は、修辞的な飾り文句に過ぎないように思われる。なぜこのような選択がなされるのか?その答えは、手紙が師範大学歴 史学部の教授であるリー・シャオフォン教授の言葉を引用していることから、少し後に示されている。「私たちは、中国共産主義帝国主義の機関銃で撃たれて死 ぬくらいなら、アメリカ帝国主義のハンバーガーで腹を満たして死ぬことを選ぶだろう... ハンバーガー天国は、暗黙の夢の表出である。アメリカは人類文明の頂点であり、強力で繁栄した民主的社会であり、確実性と安全性の国である。」 (Chen Kuan-Hsing 2010:170) 「アメリカ人になるという偉大な帝国の夢は、決して外部から一方的に押し付けられたものではない。それどころか、それは地元の環境の中で育まれてきたもの でもある。そして、我々のような個別的なケースでは、「新しい台湾人」の中流階級の中で育まれてきたものである。アメリカ帝国の支配者になりたいという憧 れは、台湾人の精神において、際立った親密な位置を占めている。」 (Chen Kuan-Hsing 2010:171) 「効果を上げるためには、クラブ51は歴史的経験に深く根ざした民族主義的感情を考慮しなければならない。さらに言えば、その手紙の想定読者は、アメリカ 人になるという考えに「感情的なレベル」で不安を感じる可能性が高い。」(Chen Kuan-Hsing 2010:172) 「1990年代にクラブ51が現れたことは、台湾が中国本土や米国と比較してどのような地位にあるかという特定の不安の表れであるだけでなく、世界全体の方向性に対する一般的な不安の表れでもあった。」(陳光興 2010:173) 「グローバリゼーションの圧力によって活性化された、クラブ51の帝国へのノスタルジックな欲望は、第二次世界大戦後も帝国主義の継続性を強く印象づけている。」(陳光興 2010:173) 「結局のところ、東アジアでは、伝統的な植民地主義の形態と、1945年以降に登場した冷戦構造との間に直接的なつながりがあった。広島と長崎への原爆投 下以来、日本国家はアメリカの支配という永続的な影の下に置かれてきた。東アジアの多くの地域では、日本の帝国領は直接アメリカに引き継がれた。一方、韓 国、台湾、南ベトナムにおける権威主義的反共産主義政権は、共産主義の拡大を防ぐための広大な戦略的保護領を確立するという米国の取り組みの一環として、 米国から強力に支援されていた。こうした帝国主義的な展開はすべて皮肉にも、米国の帝国主義という問題を置き去りにする結果となった。」(陳光興 2010:175) 「「戦後韓国政治の顕微鏡」と表現されているように、4.3事件は、国家による政治的暴力と密接に関連する韓国近代化の加速における原初の場面として、今も汚名を着せられたままである。」(キム 1996, 8)」(陳光興 2010:176より引用) 「この地域における米国帝国主義の文化研究は、まだ始まったばかりであり、ある(サバルタン)ナショナリズムを別の(パラマウント)ナショナリズムに対抗するものとして位置づけることに対しては、警戒することが重要である。」(チェン・クワン・シン 2010:176) 「ここ30年ほど、香港映画は東アジアおよび東南アジア諸国の市場で大きなシェアを獲得してきた。1990年代までには、東アジアの若者たちはカラオケ バーでアメリカのポップソングを歌うことはなくなっていた。偽りの意識論はもはや説明力を失っている。これらの輸入された製品を、地域の文化史の内部論理 に説得力を持って明確化することはできない。文化帝国主義から帝国主義の文化への理論的転換は、より洗練された理解を可能にする。」(陳光興 2010:177) 「東アジアでは、第二次世界大戦以降の植民地化と脱植民地化が、資本と提携する国民国家のさまざまな制度によって、また時には市民社会のセクターによっ て、意識的にも無意識的にも、ローカルな文化の想像力の境界を形作ってきた。米国帝国主義の文化の背後にある力は、地政学的な植民地空間に近代性の想像上 の姿として入り込む能力に由来しており、それゆえ、現地の人々が学ぶべき自然な同一化の対象となっている。」(陳光興 2010:177) 「そして日本もまた再アジア化の段階にある。こうした自己再発見の動きは明らかにグローバル資本の地域化と関連しているが、その根底にある心理的な原動力は、再び植民地化の歴史に根ざしている」(Chen Kuan-Hsing 2010:178) 「東アジアにおける自己の主観性を正直に理解したいのであれば、米国が単に我々のアイデンティティを定義しただけではなく、我々の主観性に深く入り込んでいることを認識しなければならない。」(チェン・クァンシン 2010:178) 「世界中のテロ攻撃に対する反応のほとんどは、2つのタイプに分けることができる。1つ目は、テロと戦う米国の軍事行動を強く支持するもので、これはクラ ブ51の立場であった。2つ目は、世界中で急速に表面化した前例のない規模の反米感情を反映したものだった」(陳光興 2010:179) 「1930年代には、一部の日本の知識人は、アメリカが日本のアイデンティティの構成要素となっていると感じていた。1929年に出版された室伏高信著 『アメリカ』の驚くべき一節は、このことをはっきりと示している。「アメリカ化されていない日本がどこにあるだろうか?アメリカなしで日本が存在しうるだ ろうか?そして、アメリカ化から逃れることができる場所があるだろうか? 私はあえて宣言する。アメリカが世界となり、日本は今日、アメリカ以外の何者でもない」(吉見2000:202-3)と。(陳冠雄 2010:180) 「米国は帝国主義的な権力政治においては相対的に新参者であり、ウッドロー・ウィルソン大統領の主導により、植民地化された地域に対する自己決定戦略を提 案した。この戦略は、米国が既占領地域において既成帝国主義諸国と競合する際に有効であっただけでなく、植民地化された民族主義者たちを米国と協力させる ことにも有効であった。」(陳光興 2010:180) 「歴史学者ブルース・カミングズは、第二次世界大戦後の東アジアにおける日本から米国への帝国主義の直接的な移行を追跡している(カミングズ 1984)。米国は日本本土を占領しただけでなく、敗戦した日本帝国から日本の植民地機構を直接的に掌握したのである」(チェン・クァンシン 2010:180-181) 「解放者からグローバルな敵への転換こそが、2003年のイラク侵攻に先立って現れた米国に対する爆発的な批判を可能にしたのである」(陳光興 2010:183) 「反共主義と親米主義が、台湾のイラク侵攻に対する比較的弱い反対を説明する台湾の主観的な要素の主要なものであるという主張を受け入れたとしても、台湾 における親米主義の深さは依然として認めがたい。反米主義は自分自身に反対することであり、台湾を愛することはアメリカを愛することである。これが、我々 がアメリカの帝国主義的介入に反対できない理由である。台湾のポピュラー文化には親日的な伝統が長い歴史を持っている。また、アジアを席巻した韓流(ここ 10年で広く普及した韓国のポピュラー文化)は、台湾にも韓国好きを生み出した。さらに、台湾には上海好きのグループさえ存在する。しかし、アメリカ好き について語る人は誰もいない。アメリカに対する欲求はあまりにも根深いので、それに対処する簡単な方法はないのだ。」(陳光興 2010:186-187) 「クラブ51は、現在の政治的現実を正直に直視しようとしている。その問題は、明らかに空想的な未来ビジョンにある。アメリカ市民が台湾を国家として受け 入れると考えるのはなぜか、あるいは中国本土がそのような取り決めを受け入れると考えるのはなぜか? それにもかかわらず、クラブ51は自らの見解を執拗に押し付けている。台湾人は中国人になるかアメリカ人になるかを選択しなければならないのだ。」 (Chen Kuan-Hsing 2010:190) 「2005年4月22日、バンドン会議50周年のこの日、小泉首相は第二次世界大戦中に日本がアジアの異なる地域を侵略したことについて、再び政府を代表して謝罪した。」(チェン・クァンシン 2010:192) 「その含意は明らかである。第一に、戦後の日本経済の急速な復興は、防衛費を米国に肩代わりしてもらったことによってもたらされた部分がある。日本は今や 自らを世界の大国と宣言しているが、同時に米国の軍事力への依存を手放すつもりはない。そのトレードオフは甚大である。表面的には日本は独立国であるが、 実際には米国の軍事力に従属している。文化的に第三世界に属する日本は、それに見合った立場を拒み、アジアの近隣諸国と肩を並べることを拒んでいる。第二 に、韓国と台湾の民主主義は、権威主義体制との困難で根気強い闘争を経て達成された。問題を抱えているとはいえ、韓国と台湾の民主主義は、米国の軍事政権 からの贈り物ではなく、米国の戦略的利益に反して勝ち取られた成果である。(陳光興 2010:193) |
| 56◎竹内好 |
|
| "His [=Y. Takeuchi's] notion of
"cultural independence" can be understood as an attempt to build a more
penetrating critical subjectivity at the societal level."(Chen
Kuan-Hsing 2010:195) "Takeuchi was one of the few scholars who, despite overwhelming national shame, could self-reflexively address Japan's historical problems in the years immediately following the Second World War. He demanded that in the struggle for independence, Japan's citizens not fall once again into the trap of formalism, which would result in their once again becoming slaves of imperialism."(Chen Kuan-Hsing 2010:195) "Being a slave is not necessarily shameful. What is embarrassing is when a slave adopts the superior attitude of the master."(Chen Kuan-Hsing 2010:195) "When China becomes strong and prosperous, if it learns from the imperialism of world powers to destroy other countries, China would be repeating their mistakes. Therefore, we need to make a policy to support the weak and to help the ones in trouble [zhiruo foqing]. That is our nation's natural duty. We have to support weak nations and resist world powers."(Chen Kuan-Hsing 2010:196) "In Asia, the deimperialization question cannot be limited to a reexanunation of the impacts of Western imperialist invasion, Japanese colonial violence, and U.S. neoimperialist expansion, but must also include the oppressive practices of the Chinese empire. Since the status of China has shifted from an empire to a big country, how should China position itself now? In what new ways can it interact with neighboring countries?(Chen Kuan-Hsing 2010:197) |
「彼の(竹内氏の)「文化的独立」の概念は、社会レベルにおいてより鋭い批判的主体性を構築しようとする試みとして理解することができる。」(陳光興 2010:195) 「竹内氏は、圧倒的な国民的恥辱にもかかわらず、第二次世界大戦直後の時期に日本の歴史問題を自己反省的に取り上げた数少ない研究者の一人であった。彼 は、独立のための闘争において、日本の市民が形式主義の罠に再び陥り、再び帝国主義の奴隷となることを要求した。」(陳光興 2010:195) 「奴隷であることは必ずしも恥ずべきことではない。恥ずべきことは、奴隷が主人としての優越的な態度を取ることである。」(陳光興 2010:195) 「中国が強大で繁栄したとき、もし世界の列強の帝国主義から学び、他国を破壊するようなことをすれば、それは彼らの過ちを繰り返すことになる。 したがって、弱者を支援し、困っている人々を助ける政策を打ち立てる必要がある。 それが我々の国民の当然の義務である。 我々は弱小国を支援し、世界の列強に抵抗しなければならない。」(陳冠興 2010:196) 「アジアにおいて脱帝国化の問題は、西洋の帝国主義的侵略、日本の植民地支配の暴力、米国のネオ帝国主義的拡大の影響の再評価に限定されるものではなく、 中国帝国の抑圧的な慣行も含むものでなければならない。中国の地位が帝国から大国へと変化した今、中国はどのように自己を位置づけるべきか?近隣諸国とど のような新しい形で交流できるだろうか。(陳光興 2010:197) |
| 57■Deimperialization and the Global Democratic Movement (pp.198-) |
|
| "the senior journalist Fu
Jianchung, was published in Taiwan's China Times. Given the
extraordinary nature of the subject, the tone of the article is
matter-of-fact: "An organization called the "Taiwan Defense Alliance"
bought a full-page advertisement today in The Washington Post urging
the U.S. government and Congress to take over Taiwan, include Taiwan as
part of the U.S. defense system, dissolve the government of the
Republic of China, and terminate the operation of the Ministries of
National Defense and Foreign Affairs."(Chen Kuan-Hsing 2010:198) "policy statements posted on the website of the Taiwan Defense Alliance (TDA) indicate that its position is quite different from that of Club SIP Club 51's agenda is to completely give up on the idea of Taiwan independence and have the country join the United States, whereas the TDAs position is that Taiwan's being taken over by the United States is only a necessary first step toward eventually achieving independence."(Chen Kuan-Hsing 2010:199) "the process of imperialization is wider in scope than the process of colonization because imperialist expansion is always based on domestic mobilization, which is itself a process of imperialization.... Without a dialectical arrangement, de colonization will be unidirectional and incomplete. Gandhi wanted to liberate India and at the same time liberate England. Fanon thought likewise: he argued that there is a symbiotic and intimate relation between the colonizer and the colonized. The colony not only has to decolonize, but it must also pass through-a deimperializing process to undercut its loyalty to the empire and undo imperial desire."(Chen Kuan-Hsing 2010:200) "Consequently decolonization and deimperialization movements could not successfully advance in the third world, and they were unable to build enough momentum to drive the former imperial powers to take on the historical responsibility of self-reflection. This seems to be a hopeless, self-perpetuating loop, but we must recognize that, in contrast to the former empires, the third world has developed a tradition of large-scale decolonization movements, which can now be mobilized to drive the next round of deimperialization."(Chen Kuan-Hsing 2010:200) |
台湾の中国時報に、シニアジャーナリストの傅崑聰氏の記事が掲載され
た。この主題の異常性を考慮すると、記事のトーンは淡々としている。「台湾防衛同盟」と呼ばれる団体が、ワシントンポスト紙に全面広告を掲載し、米国政府
と議会に台湾の接収、台湾を米国の防衛システムの一部に組み込むこと、中華民国政府の解散、国防省と外務省の業務停止を要求した。」(陳光興
2010:198) 「台湾防衛同盟(TDA)のウェブサイトに掲載された政策声明は、その立場がクラブSIPクラブ51のそれとはかなり異なることを示している。クラブ SIPクラブ51の目的は、台湾独立の考えを完全に放棄し、台湾を米国に併合させることである。一方、TDAの立場は、台湾が米国に占領されることは、最 終的に独立を達成するための必要な第一段階に過ぎないというものである。」(陳光興 2010:199) 「帝国化のプロセスは、植民地化のプロセスよりも範囲が広い。なぜなら、帝国主義の拡大は常に国内動員を基盤としているが、それ自体が帝国化のプロセスだ からである。弁証法的配置がなければ、脱植民地化は一方向かつ不完全なものとなる。ガンジーはインドを解放すると同時にイギリスをも解放しようとした。 ファノンも同様に考えた。彼は、植民地支配者と被植民地支配者との間には共生かつ親密な関係がある、と主張した。植民地は単に脱植民地化するだけでなく、 帝国への忠誠心を弱め、帝国主義の欲望を覆す脱帝国化のプロセスを経なければならない。」(チェン・クワン・シン 2010:200) 「その結果、脱植民地化と脱帝国化の運動は第三世界で成功を収めることができず、旧帝国諸国に自省の歴史的責任を負わせるほどの勢いを生み出すこともでき なかった。これは絶望的な自己増殖ループのように思えるが、旧帝国とは対照的に、第三世界では大規模な脱植民地化運動の伝統が育まれており、それを動員し て次の脱帝国化の動きを起こすことができると認識しなければならない。」(陳光興 2010:200) |
| 58●On "Modern History of the Three Countries in East Asia, pp.202- |
|
| On "Modern History of the Three
Countries in East Asia: Learning from History, Facing the Future,
Building a New Peaceful and Friendly Framework Together" (2005) "The book is not without its problems. An emphasis on the Japanese colonization of Korea at the expense of investigating the situation in Taiwan and Manchuria, the absence of any detailed treatment of Okinawa, and the relative invisibility of locations at the peripheries of the region are among the short comings of the work.... From the analytical standpoint of deimperialization, the fact that authors from Japan are willing to use imperialism to frame Japan's expansionist invasions is commendable indeed."(Chen Kuan-Hsing 2010:203) "we can imagine the difficulty the Japanese authors may have faced in dialogues with their counterparts from Japan's formerly colonized regions. In my view, it is this human dimension that is one of the most challenging tasks of deimperialization. The writing of this book proves that collectively facing difficult historical issues is possible."(Chen Kuan-Hsing 2010:203) "Although Modern History of the Three Countries in East Asia cannot be considered a model for the work of deimperialization, its method should be appreciated."(Chen Kuan-Hsing 2010:204) "Simply because Japan is a defeated empire and is located in Asia does not mean that it has had to deal with its neighbors. The lack of substantive communication between former imperial powers and their former colonies is a general problem of imperialism, neither diminished nor increased by geographic proximity."(Chen Kuan-Hsing 2010:204) "Euro-American studies on decolonization in Southeast Asia, for example, are mostly conducted in a mode that neglects the political impacts of past imperialism on the present. Through the cultivation of individualism, relationships between the individual (scholar) and the state (nation) are always fragmented; therefore, there is no imperative for the individual to assume responsibility for the actions of the state."(Chen Kuan-Hsing 2010:204-205) |
「東アジア三国の近現代史―歴史に学び、未来に向き合い、共に新たな平和友好の枠組みを構築する」(2005年)について 「この本には問題がないわけではない。台湾や満州の状況を調査することなく、日本の韓国植民地化に重点を置いていること、沖縄に関する詳細な記述がないこ と、そしてこの地域の周辺地域の記述が比較的少ないことなどが、この本の欠点である。脱帝国化という分析の観点から見ると、日本の著者が日本の拡張主義的 な侵略を帝国主義の枠組みで論じようとしていることは、確かに称賛に値する。」(陳光興 2010:203) 「日本人の著者が、かつての植民地地域の同業者との対話において直面したであろう困難を想像することができる。私の考えでは、脱帝国化の最も困難な課題の ひとつは、この人間的な次元である。この本の執筆は、困難な歴史問題に共同で取り組むことが可能であることを証明している。」(Chen Kuan-Hsing 2010:203) 「東アジア三国の近現代史は脱帝国化の模範とはなりえないが、その手法は評価されるべきである。」(陳光興 2010:204) 「日本が敗戦国でありアジアに位置しているという理由だけで、近隣諸国と向き合わなければならないというわけではない。旧帝国と旧植民地間の実質的なコ ミュニケーションの欠如は、帝国主義の一般的な問題であり、地理的な近さによって減少することも増大することも無い。」(陳光興 2010:204) 「例えば、欧米諸国による東南アジアの脱植民地化に関する研究は、ほとんどが過去の帝国主義が現在に与える政治的影響を無視した方法で行われている。個人 主義の育成により、個人(学者)と国家(国民)の関係は常に断片化されているため、個人が国家の行動に責任を負う必要はない。」(陳光興 2010:204-205) |
| 59◎花崎皋平(HANAZAKI, Kohei, 1931-):未完の脱植民地主義 |
|
| "After Japan's defeat and the
collapse of the Japanese empire, decolonialization was commonly
understood as demilitarization and democratization. Hanasaki argues
that this interpretation is incorrect, and I agree. Such reductionism
is a legacy of the cold-war power structure, which has frozen the
resolution of historical relations between former colonies and former
imperial centers."(Chen Kuan-Hsing 2010:205) "Hanasaki asks, quite directly, who should be held responsible for undertaking the task of decolonialization. He considers Japan's general lack of national responsibility to be a result of the common postwar historical narrative of how the Japanese nation came to be: "Japan's modem past was never properly grasped as a history of empire building and the eventual failure of this project and, as Kang [Sanjung] points out, the exclusion of Koreans and other former subjects of the Japanese Empire has been obliterated*" (ibid., 74)."(Chen Kuan-Hsing 2010:206) *obliterated: erase, wipe out |
「日本の敗戦と大日本帝国の崩壊後、脱植民地化は一般的に非軍事化と民
主化として理解されていた。花崎は、この解釈は誤りであると主張しており、私も同意見である。このような還元主義は、旧植民地と旧帝国の中心地との間の歴
史的な関係の解決を凍結してきた、冷戦期の権力構造の遺産である。」(陳光興 2010:205) 「花崎は、脱植民地化という課題を誰が担うべきかについて、極めて直接的に問いかけている。彼は、日本国民が一般的に国家に対する責任を欠いているのは、 日本という国家がどのようにして誕生したかという戦後の一般的な歴史解釈の結果であると考えている。「日本の近代は、帝国建設の歴史であり、そのプロジェ クトが最終的に失敗したものとして、正しく理解されることは決してなかった。そして、カン(サンジュン)が指摘するように、韓国人やその他の旧日本帝国の 臣民の排除は、抹消されてきたのである*」(同書、74ページ)。(陳光興 2010:206) *抹消:消去、全滅 |
| 60■The Meaning of Deimperlalization pp.208- |
|
| "I believe that regionalization
may afford a means to move beyond earlier failed attempts to counter
real strength.... The question of what kind of democracy is needed to
allow this to happen is discussed in detail in the next chapter." (Chen
Kuan-Hsing 2010:209) |
「地域化は、実力に対抗する以前の失敗した試みを乗り越える手段となり得るだろう。... これを実現するためにどのような民主主義が必要かという問題は、次章で詳しく論じられている。」(陳光興 2010:209) |
| 61■5. Asia as Method: Overcoming the Present Conditions of Knowledge Production 211 |
|
| "Knowledge production is one of
the major sites in which imperialism operates and exercises its power.
The analyses in the preceding chapters suggest that the
underdevelopment of deimperialization movements is a Significant
contributing factor in local, regional, and global conflicts throughout
the contemporary world. This underdevelopment, I submit, has to do with
the current conditions of knowledge production, which have serious
structural limitations. To break through the impasse, critical
intellectual work on deimperialization first and foremost has to
transform these problematic conditions, transcend the structural
limitations, and uncover alternative possibilities."(Chen Kuan-Hsing
2010: 211) |
「知識生産は、帝国主義が活動し、その力を発揮する主要な場の一つであ
る。前章の分析は、脱帝国化運動の未発達が、現代世界における地域的、世界的紛争の重要な要因であることを示唆している。この未発達は、深刻な構造的限界
を持つ知識生産の現状と関係している。この袋小路を打開するには、脱帝国化に関する重要な知的作業が、何よりもまず、これらの問題のある状況を変革し、構
造的な限界を乗り越え、代替的な可能性を明らかにしなければならない。」(陳光興 2010: 211) |
| 62■アジアを離れてアメリカへ Leaving Asia for America, pp.212- |
|
| (1)"Asia as method" as a
critical proposition to transform the existing knowledge structure and
at the same time to transform ourselves. The potential of Asia as
method is this: using the idea of Asia as an imaginary anchoring point,
societies in Asia can become each other's points of reference, so that
the understanding of the self may be transformed, and subjectivity
rebuilt. On this basis, the diverse historical experiences and rich
social practices of Asia may be mobilized to provide alternative
horizons and perspectives. This method of engagement, I believe, has
the potential to advance a different understanding of world
history."(Chen Kuan-Hsing 2010: 212) (2)"the formulation of Asia as method is also an attempt to move forward on the tripartite problematic of decolonization, deimperialization, and de-cold war. To briefly recap the analysis developed over the previous four chapters: the historical processes of imperialization, tolonization, and the cold war have become mutually entangled structures, which have shaped and conditioned both intellectual and popular knowledge production"(Chen Kuan-Hsing 2010: 212) (3)"Asia as method is grounded in the critical discourses of an earlier generation of thinkers, with whom we now imagine new possibilities."(Chen Kuan-Hsing 2010: 212) "Choi Wan Ju, was based on the sentiment..." p.214- three dialogues 1) The question of the West, pp.216- 2) Political Society and Minjian: A Dialogue with Partha Chatterjee, pp.224- 3) Asia as Method: A Dialogue with Mizoguchi Yuzo, pp.245- |
(1)「方法としてのアジア」は、既存の知識体系を変革し、同時に私た
ち自身をも変革するという批判的命題である。方法としてのアジアの潜在的可能性とは、アジアという概念を架空の基点として使用し、アジアの社会がお互いの
参照点となり、自己理解が変革され、主観性が再構築されることである。この基盤の上に、アジアの多様な歴史的経験と豊かな社会的実践が動員され、代替的な
地平と視点が提供される可能性がある。この関与の方法は、世界史に対する異なる理解を促進する潜在的可能性を持っていると私は信じている。」(陳光興
2010: 212) (2)「アジアを方法として定式化することは、脱植民地化、脱帝国化、脱冷戦という3つの問題を前進させる試みでもある。これまでの4章で展開された分析 を簡単にまとめると、帝国化、トルニアリゼーション、冷戦の歴史的プロセスは相互に絡み合った構造となり、知的および大衆的な知識生産の両方を形成し、条 件づけてきた」(チェン・クワン・シン 2010: 212) (3)「方法としてのアジアは、批判的な言説を基盤とする、より以前の世代の思想家たちによるものであり、彼らとともに、我々は今、新たな可能性を想像している。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 212) 「Choi Wan Ju, was based on the sentiment...」p.214- 3つの対話 1) 西洋の問題、pp.216- 2)政治社会と民衆:パルタ・チャタジーとの対話、224ページ 3)方法としてのアジア:溝口雄三との対話、245ページ |
| 63■The Question of the West, pp.216- |
|
| "Chakrabarty explains this Eurocentric discursive...," p.219 "Chakrabarty's strategy is to wrest the ownership of modernity from..." On Neil Garcia's "Philippine Gay Culture," 1996, pp.221- "Garcia reminds us of the analytical value of concepts that....", p.222 "Internationalist localism acknowledge the existence of the nation-state as...," p.223 |
「チャクラバーティは、このヨーロッパ中心的な議論を説明している...」p.219 「チャクラバーティの戦略は、近代性の所有権を...から奪い取るというものである。」 ニール・ガルシア著『フィリピンのゲイ文化』1996年、221ページから 「ガルシアは、...という概念の分析的価値を私たちに思い出させる。」222ページ 「国際主義的ローカリズムは、国民国家の存在を...として認める。」223ページ |
| 64■国際主義的地方主義 | |
| "Internationalist localism
acknowledges the existence of the nation-state as a product of history
but analytically keeps a critical distance from it. The operating site
is local, but at the same time internationalist localism actively
transgresses nation-states' boundaries. It looks for new political
possibilities emerging out of the practices and experiences accumulated
during encounters between local history and colonial history -- that
is, the new forms and energies produced by the mixing brought about by
modernization. Internationalist localism respects tradition without
essentializing it, and will not mobilize the resources of tradition
simply for the sake of opposing the West."(Chen Kuan-Hsing 2010: 223) |
「インターナショナリスト・ローカリズムは、国民国家を歴史の産物とし
て認めながらも、分析的には批判的な距離を保つ。活動の場はローカルであるが、同時にインターナショナリスト・ローカリズムは、国民国家の境界を積極的に
越境する。それは、ローカルな歴史と植民地化の歴史の遭遇の過程で蓄積された実践や経験から生まれる新たな政治的可能性を模索する。つまり、近代化によっ
てもたらされたミヘン(混合)によって生み出された新たな形態やエネルギーである。国際主義的ローカリズムは、伝統を固定化することなく尊重し、西洋に反
対するということだけを理由に伝統の資源を動員することはない」(陳光興 2010: 223) |
| 65■Political Society and Mfnjlin: A Dialogue with Partha Chatterjee, pp.224- |
|
| "The implication of Chatterjee's is that the existing....," p.227 "Chatterjee puts forward three theoretical propositions arising...,1) 2) 3).." pp.229-230. Taiwan's example on "Civil society versus popular democracy," pp.230- "Our third challenge was to move beyond the reductionist state versus civil society model,..." p.232- "The articulation of a political society shares the spirit and concerns of the popular democratic position. Political society marks the operating site of popular democracy, giving a much more precise name to the latter space. The most valuable part of this encounter with Chatterjee's idea of political society is the reminder that we should not allow ourselves to be defined by our enemy. Civil society; alternatively understood, has real strategic value. Civil society can become part of the power bloc, and in certain circumstances, it can launch merciless attacks on subaltern subjects. Under other conditions, it can become a useful ally for subject groups in struggle. Turning civil society from a normative category into an analytical category enables us to better understand the locations and directions of the social forces at work."(Chen Kuan-Hsing 2010: 233) ""English rule without the Englishman". The real force dominating India is, according to Gandhi, not the Englishman but his civilization," p.234 "This is one reason why in contemporary Chinese societies, the protection of civil law is not a priority" p.238. "The annual festival for Mazu." pp.240- |
「チャタジーの主張は、既存の...」p.227 「チャタジーは、3つの理論的命題を提示している。1) 2) 3)」pp.229-230. 「市民社会対人民民主主義」に関する台湾の例、pp.230- 「私たちの3つ目の課題は、還元主義的な国家対市民社会モデルを乗り越えることだった。」p.232- 「政治社会の明確な定義は、大衆民主主義の立場と精神を共有するものである。政治社会は大衆民主主義の活動領域を明確にし、後者の空間により正確な名称を 与える。チャタジーの政治社会の概念とのこの出会いにおいて最も価値ある部分は、我々は敵によって定義されるべきではないという認識である。市民社会は、 別の見方をすれば、真の戦略的価値を持つ。市民社会は権力ブロックの一部となり、特定の状況下ではサバルタン(被支配民)に対して容赦ない攻撃を仕掛ける こともある。また、別の状況下では、闘争中の支配民グループにとって有益な同盟者となることもある。市民社会を規範的なカテゴリーから分析的なカテゴリー へと転換することで、私たちは社会の力の所在と方向性をよりよく理解できるようになる。」(チェン・クワン・シン 2010: 233) 「英国人なしの英国支配」。ガンディーによれば、インドを支配している真の力は英国人ではなく、英国の文明である。p.234 「これが、現代の中国社会において、民法の保護が優先事項ではない理由の一つである。」p.238 「媽祖の年次祭。」pp.240- |
| 67■翻訳の問題 |
|
| "Modernity is not a normative
drive to become modern, but an analytical concept that attempts to
capture the effectiveness of modernizing forces as they negotiate and
mix with local history and culture. In other words, modernity as an
analytical term refers to the overall effects of modernization.
Tradition is not opposed to modernity but is an integral and living
part of it. The diversity and density of local histories guarantee the
emergence of multiple modernities, a recently formulated concept that,
in my view, is redundant. Translation thus gives us a way to conduct
reinvestigations that allow the organic shape and characteristics of
local society and modernity to surface. In this sense, translation is
not simply a linguistic exercise but a social linguistics, or an
intersection of history, sociology, and politics. In the end,
translation allows us to more precisely identify what aspects of
modernity have been articulated to the existing social formation. Civil
society has indeed been able to translate and insert itself in Asian
contexts, but in a limited and profoundly different way than in the
West."(Chen Kuan-Hsing 2010: 244) "Asia as method is not a slogan but a practice. That practice begins with multiplying the sources of our readings to include those produced in other parts of Asia."(Chen Kuan-Hsing 2010: 255) |
「近代性とは、近代化を目指す規範的な推進力ではなく、近代化の推進力
が地域の歴史や文化と交渉し、混ざり合う中で、その有効性を捉えようとする分析的概念である。言い換えれば、分析用語としての近代性とは、近代化の全体的
な効果を指す。伝統は近代性と対立するものではなく、その不可欠な生きた一部である。地域の歴史の多様性と密度は、複数のモダニティの出現を保証する。こ
れは最近提唱された概念だが、私見では冗長である。翻訳は、地域社会とモダニティの有機的な形と特徴を浮き彫りにする再調査を行う方法を与えてくれる。こ
の意味で、翻訳は単なる言語的作業ではなく、社会言語学、あるいは歴史、社会学、政治学の交差点である。結局のところ、翻訳によって、近代のどの側面が既
存の社会構造に組み込まれたのかをより正確に特定することができる。市民社会は、アジアの文脈に翻訳され、組み込まれることは確かに可能であるが、西洋と
は限定的に、そして根本的に異なる方法でである。」(チェン・クァンシン 2010: 244) 「方法としてのアジアはスローガンではなく実践である。その実践は、アジアの他の地域で作成されたものも含むように、我々の読解のソースを多様化することから始まる。」(Chen Kuan-Hsing 2010: 255) |
| 68■Epilogue: The Imperial Order of Things, or Notes on Han Chinese |
|
| "Deimperialization is an ongoing
intellectual project, and therefore a conventional conclusion would be
inappropriate here"(Chen Kuan-Hsing 2010: 257). "In mainland China, the Han are by far the largest official ethnic group. The nation's official language is Hcmyu (Mandarin, also known simply as the national language, or guoyii), which uses Hcmzl (Chinese characters). In the global context, the word "Han" is increasingly being displaced by "Chinese" (for people, Huaren or Zhongguorin). My insistence on the use of Han (rather than simply Chinese) is to indicate analytically that even as the meanings of "Han" continue to evolve, the Han people's long history continues to condition our practices in the arenas of daily life, intellectual thought, and cultural production. Politically, the Han are one of the dominant populations in the world, and distinguishing the Han from the many minority groups subsumed under the category Chinese (Huaren)is a necessary step toward critically confronting the history and current expressions of Han racism. To problematize racism is to call attention to the fluidity of terms such as race (zhongzu), ethnicity (zuqun), and nationality (m{nzu), which now overlap in both Chinese and English.""(Chen Kuan-Hsing 2010: 259). "Two important feminist works on the Qing Dynasty inspire the following analysis. Maram Epstein's essay "Confucian Imperialism and Masculine Chinese Identity in the Novel Yesou Puyan" contrasts descriptions of the sexual encounters of the Han protagonist in the 1880s edition of the novel with those in the abridged version published in the 1930s."(Chen Kuan-Hsing 2010: 260). "Here I rely on Liu Jen-peng's work. In "The Disposition of Hierarchy and the Late Qing Discourse of Gender Equality," the first chapter of Feminist Discourse in Early Modern China: Natiqn, Translation and Gender Politics (2000), Liu borrows from Louis Dumont's analysis of the Indian caste system in his classic Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, published in 1980, to understand the Chinese construction of hierarchy. She sees Dumont's theory of hierarchy as an articulation of a relation between "the encompassing" and, “the encompassed": within the totality of a system of relations, the higher position is able to encompass the lower one, but not the reverse"(Chen Kuan-Hsing 2010: 262). "According to Liu, in the Chinese scholarly tradition, the relation between the subject and object is not conceptualized as a binary opposition. Rather, it is a relation of yin and yang, a relation of complementarity, negotiation, and division of lab or. But Liu points out that this tradition ignores a crucial structural relation. She argues that the Taoist concept of taiji, as a structural totality in place prior to the existence of yin and yang, has to be analyzed on two levels. On the higher level, the unity of yin and yang is complementary and indeed encompasses a totality. But on the lower level, yang is higher than yin, and the former governs and encompasses the latter."(Chen Kuan-Hsing 2010: 264). "In Taiwan, racism is expressed in the dominant population's treatment of aboriginal peoples, foreign laboreres, migrant domestic workers, foreign and mainland Chinese brides, and foreign English-language teachers. The so-called democratization of Taiwan has not yet resulted in more democratic ways of relating to others."(Chen Kuan-Hsing 2010: 266). "In February 2006, the London-based Guardian published an essay by Marlin Jacques (2006) titled “Europe's Contempt for Other Cultures Can't Be Sustained," a piece critically reflecting on the problem of racism across Europe. The deck copy clearly brings out his main argument: "A continent that inflicted colonial brutality all over the globe for 200 years has little claim to the superiority of its values." Martin sees the wide-ranging reactions to the Danish cartoons within Europe as a revealing combination of "defensiveness, fear, provincialism and arrogance." The controversy clearly demonstrated that Europe is ill prepared to cope with the changing world."(Chen Kuan-Hsing 2010: 266). "Even though Hari most likely lost her life to the racism of Hong Kong Chinese, Martin has never emotionally turned against the Chinese. On the contrary, he hopes that his beloved son, Ravi, will learn Mandarin, and in addition to having him study Indian music, Martin is also encouraging him to play the erhu, a two-stringed Chinese musical instrument. Instead of fostering resentment, Hari's tragic death has been the driving force behind Martin's persistent exploration of contemporary racism and its intimate connection with the history of European imperialism."(Chen Kuan-Hsing 2010: 267). "This book challenges those assumptions and the arrogant conditions of knowledge production that sustain them. These conditions attempt to regulate academic production into a singularity, coated with professionalism but stripped of critical concerns and political positions. 'The imperialist apparatus and the collaborationist desire of the colonized to catch up have ensured that the mechanisms which have evolved to shape intellectuals into professional academics are now firmly in place throughout the globe. But the rules of the game were set by the empire. Carrying with us the historical experiences of the colonized third world, we cannot allow ourselves to be swept up in the rush toward neoliberal globalization."(Chen Kuan-Hsing 2010: 268). |
「脱帝国化は進行中の知的プロジェクトであり、したがって、ここで従来の結論を出すことは不適切である」(陳光興 2010: 257)。 「中国大陸では、漢族が圧倒的に最大の公式民族である。この国の公用語は、漢語(マンダリン、単に国語、または国語として知られている)であり、漢字(中 国文字)を使用する。世界的な文脈では、「漢族」という言葉は「中国人」(華人または中国帰国者)という言葉に置き換えられつつある。私が「中国人」では なく「漢族」という言葉の使用にこだわるのは、「漢族」という言葉の意味が変化し続けているとしても、漢族の人々の長い歴史が、日常生活、知的思考、文化 生産の分野における私たちの実践を規定し続けていることを分析的に示すためである。政治的には、漢族は世界でも支配的な民族のひとつであり、中国人(華 人)というカテゴリーに含まれる多くの少数民族から漢族を区別することは、漢族の人種差別の歴史と現状を批判的に直視する上で必要なステップである。人種 主義を問題化することは、人種(zhongzu)、民族(zuqun)、国民(m{nzu)といった用語の流動性に注意を促すことでもある。これらの用語 は現在、中国語と英語の両方で重複している。」(陳光興 2010: 259) 「清王朝に関する2つの重要なフェミニストの研究が、以下の分析にインスピレーションを与えている。マラム・エプスタインの論文「小説『Yesou Puyan』における儒教帝国主義と男性的な中国人アイデンティティ」では、1880年代の小説の漢人主人公の性的遭遇の描写と、1930年代に出版され た短縮版での描写とを比較している。」(陳光興 2010: 260)。 「ここでは劉振邦の研究に依拠する。劉振邦は『階層の性向と清末の男女平等論』という論文で、著書『中国近現代におけるフェミニスト言説:ナティク、翻 訳、ジェンダー政治』(2000年)の第1章で、ルイ・デュモンによる古典的名著『ホモ・ヒエラルキクス:カースト制度とその意味合い』(1980年)の インディアン・カースト制度に関する分析を引用し、 1980年に出版された古典的名著『ホモ・ヒエラルキクス:カースト制度とその意味合い』におけるインドのカースト制度の分析を、中国におけるヒエラル キーの構築を理解するために借用している。彼女は、デュモンのヒエラルキー理論を「包括するもの」と「包括されるもの」の関係の明確な表現と捉えている。 関係の体系の全体性の中で、上位の立場は下位の立場を包括することができるが、その逆はありえないのである(Chen Kuan-Hsing 2010: 262)。 劉によれば、中国の学問の伝統では、主体と対象の関係は二項対立として概念化されていない。むしろ、それは陰と陽の関係であり、相補性、交渉、領域の分割 の関係である。しかし、劉は、この伝統が重要な構造的関係を無視していると指摘している。彼女は、陰と陽の存在以前に存在していた構造的な全体としての太 極の道教的概念は、2つのレベルで分析されなければならないと主張している。上位レベルでは、陰と陽の統一は補完的であり、全体性を包含している。しか し、下位レベルでは、陽は陰よりも上位にあり、前者が後者を統治し、包含している。」(陳光興 2010: 264) 「台湾では、人種主義は支配的な人口層による原住民、外国人労働者、移住家事労働者、外国人花嫁や中国本土の花嫁、外国人英語教師に対する扱いにおいて表 れている。 いわゆる台湾の民主化は、他者とのより民主的な関わり方を生み出すには至っていない。」(陳光興 2010: 266)。 「2006年2月、ロンドンを拠点とするガーディアン紙は、マーリン・ジャック(2006)による「ヨーロッパの他文化に対する軽蔑は持続できない」と題 されたエッセイを掲載した。このエッセイは、ヨーロッパ全体に広がる人種主義の問題を批判的に振り返ったものである。デッキコピーは、彼の主な主張を明確 に表している。「200年にわたって世界中で植民地支配の残虐行為を繰り返してきた大陸が、自らの価値観の優越性を主張する権利はほとんどない。マーティ ンは、欧州におけるデンマークの風刺漫画に対する幅広い反応を、「防衛的、恐怖、偏狭、傲慢」の組み合わせの表れと見ている。この論争は、欧州が変化する 世界に対応する準備ができていないことを明らかに示した。 「ハリは香港人の人種主義によって命を落とした可能性が高いが、マーティンは中国人に対して感情的になることは決してなかった。それどころか、彼は愛息子 のラヴィに北京語を学ばせ、インディアン音楽の勉強に加えて、2本の弦を持つ中国の楽器である二胡を弾くことを勧めている。ハリ氏の悲劇的な死は、憤りを 生むのではなく、マーティン氏が現代の人種主義とヨーロッパの帝国主義の歴史との密接な関係を粘り強く探究する原動力となった。」(陳光興 2010: 267) 「この本は、そうした思い込みやそれを支える傲慢な知識生産の条件に異議を唱える。こうした条件は、専門性を装いながら、批判的関心や政治的立場を排除 し、学術生産を単一性に統制しようとする。「帝国主義的装置と、植民地化された人々の追いつこうとする協力主義的な願望により、知識人を専門家の学者へと 形作るために発展したメカニズムが、今や世界中でしっかりと定着している。しかし、そのゲームのルールは帝国によって決められたものだ。植民地化された第 三世界の歴史的経験を私たちは抱えながら、新自由主義的なグローバル化への突進に自らを巻き込まれるわけにはいかないのだ。」 (Chen Kuan-Hsing 2010: 268) |
| 69日本語コメント(備忘) |
この書物の意義 1)東アジアの国民国家における何度目かの排外主義的ナショナリズムの台頭がもたらす諸国民・市民あいだの相互不理解やディスコミュニケーショ ンの現状とそれらの起源を焦点化したこと。 2)英国で生まれ、米国で英国とは異なった形で隆盛したカルチュラルスタディーズの「学問的パラダイム化」に抵抗し、脱中心化のプログラムのひ とつとして、東アジアにおけるカルチュラルスタディーズの可能性を切り開いたこと。 3)東アジアにおける、脱植民地化、脱帝国主義化、脱冷戦化という実践の可能性を、この地域の研究者たちに呼びかける、自らその実例(実践例) を試みようとしたこと。 ・脱植民地主義、脱帝国主義、脱=冷戦、の言葉の(多型配列的)定義の必要性 ・帝国・準帝国(subimperial)の区分、類型論の可能性 ・アジア的なるものの問題("a set of Asian questions"; Interview with S. Hall, 1996: 393) ・アジアは想像の共同体になってしまわないか? ・先住民と国民国家 ・ディアスポラ ・Academic activism inside/outside campus ・On identity politics ・Gramuscian Intellectual concepts: Organic/Traditional ・グローバル資本主義の位置づけと意味理解、飼いならしの方法 ・言語の多様性と、言語のヘゲモニー的配列 ・他者の言語 ・複数のアジア(Asians) ・脱・東アジア中心主義 ・自分の経験世界から出発すること:教育(ペダゴジック)的相対化 ・脱構築的方法論(?)の扱い方 ・西洋=近代=帝国(植民地の不可欠性)→代替としての東洋→アジア→複数のアジアという、一連の脱構築あるいは認識論的視座の移転のプロセ ス? ・先住民と国民国家 ・カルチュラルスタディーズの基盤としての歴史唯物論は、第三世界CSにも可能か? |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆