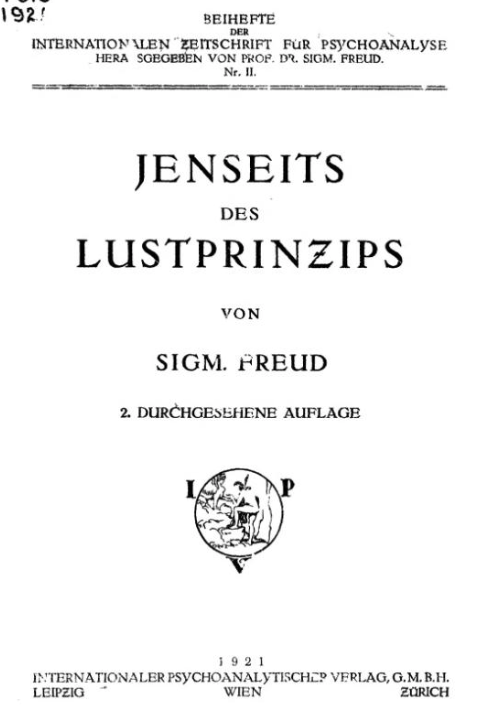
快楽原則の彼岸
Beyond the Pleasure Principle,
Jenseits des Lustprinzips, 1920
☆ 『快楽原則を超えて』(ドイツ語: Jenseits des Lustprinzips)は、ジークムント・フロイトが1920年に著した論文である。これは、フロイトがそれまで人間の行動における自己保存を快楽原 則によって支配されるエロスという本能とリビドーの調整に帰していた彼の欲動理論の定式化における大きな転換点となった。この考えを結論に至らないものと して修正し、フロイトは快楽原則を超えた死の欲動(またはタナトス、ギリシャ神話における死の擬人化)を新たに考察した。死の欲動とは、破壊や消滅に向か う傾向を指し、攻撃性、反復強迫、自滅的傾向などの行動によってしばしば表現される。
★飛翔によって成し遂げられないものは、跛行しながら成し遂げられなければならない、跛行はなんら罪ではないと、聖なる書もいう(フロイト 1920)
1)臨床的証拠(第I章~第III章
2)快楽原則の例外
3)反復強迫
4)快楽原則からの独立
5)推測(第IV章~第VII章)
6)反復強迫の生物学的な基礎
7)臨床的症状としてのマゾヒズム
8)結論
| Beyond
the Pleasure Principle (German: Jenseits des
Lustprinzips) is a 1920
essay by Sigmund Freud. It marks a major turning point in the
formulation of his drive theory, where Freud had previously attributed
self-preservation in human behavior to the drives of Eros and the
regulation of libido, governed by the pleasure principle. Revising this
as inconclusive, Freud theorized beyond the pleasure principle, newly
considering the death drives[1] (or Thanatos, the Greek personification
of death[2]) which refers to the tendency towards destruction and
annihilation, often expressed through behaviors such as aggression,
repetition compulsion, and self-destructiveness.[3] |
『快
楽原則を超えて』(ドイツ語: Jenseits des
Lustprinzips)は、ジークムント・フロイトが1920年に著した論文である。これは、フロイトがそれまで人間の行動における自己保存を快楽原
則によって支配されるエロスという本能とリビドーの調整に帰していた彼の欲動理論の定式化における大きな転換点となった。この考えを結論に至らないものと
して修正し、フロイトは快楽原則を超えた死の欲動(またはタナトス、ギリシャ神話における死の擬人化)を新たに考察した。死の欲動とは、破壊や消滅に向か
う傾向を指し、攻撃性、反復強迫、自滅的傾向などの行動によってしばしば表現される。 |
| Overview The essay, marking Freud's major revision of his drive theory, elaborates on the struggle between two opposing drives. In the first few sections, Freud describes these as Eros, which produces creativity, harmony, sexual connection, reproduction, and self-preservation; and the "death drives" (what some call "Thanatos"[4]), which brings destruction, repetition, aggression, compulsion, and self-destruction. In sections IV and V, Freud posits that the process of creating living cells binds energy and creates an imbalance. It is the pressure of matter to return to its original state which gives cells their quality of living. The process is analogous to the creation and exhaustion of a battery. This pressure for molecular diffusion is referred to as a "death-wish". The compulsion of the matter in cells to return to a diffuse, inanimate state extends to the whole living organism. Thus, the psychological death-wish is a manifestation of an underlying physical compulsion present in every cell, which Freud directly corresponds to the death drives. Freud also states the basic differences, as he saw them, between his approach and Carl Jung's and summarizes published research into basic drives in Section VI to establish his revisions. |
概要 フロイトの「力動説」の主要な修正を記したこの論文では、2つの相反する力動の間の闘争について詳しく述べている。最初の数節で、フロイトは創造性、調 和、性的結合、生殖、自己保存を生み出す「エロス」と、破壊、反復、攻撃、強迫、自己破壊をもたらす「死の力動」(「タナトス」と呼ばれることもある [4])について説明している。 第4節と第5節において、フロイトは、生命細胞の生成過程においてエネルギーが結合し、不均衡が生じると仮定している。物質が元の状態に戻ろうとする圧力 が、細胞に生命の質を与えるのである。この過程は、電池の生成と消耗に類似している。分子拡散に対するこの圧力は、「死の願望」と呼ばれる。細胞内の物質 が拡散し、生命のない状態に戻ろうとする強迫観念は、生物全体に広がる。したがって、心理的な死の願望は、すべての細胞に内在する物理的な強迫観念の表れ であり、フロイトはそれを死の衝動に直接対応させている。 フロイトはまた、彼の見解による彼のアプローチとカール・ユングのアプローチとの基本的な相違点を述べ、第6章で基本的な衝動に関する公表された研究を要約し、彼の修正を確立している。 |
| Analysis and synopsis What have been called the "two distinct frescoes or canti"[5] of Beyond the Pleasure Principle break between sections III and IV. If, as Otto Fenichel remarked, Freud's "new [instinctual] classification has two bases, one speculative, and one clinical",[6] thus far the clinical. In Freud's own words, the second section "is speculation, often far-fetched speculation, which the reader will consider or dismiss according to his individual predilection"[7]—it has been noted that "in Beyond the Pleasure Principle, Freud used that unpromising word "speculations" more than once".[8] Clinical evidence (sections I–III) Freud begins with "a commonplace then unchallenged in psychoanalytic theory: 'The course of mental events is automatically regulated by the pleasure principle ... a strong tendency toward the pleasure principle'".[9] After considering the inevitable presence of unpleasant experiences in the life of the mind, he concludes the book's first section to the effect that the presence of such unpleasant experiences "does not contradict the dominance of the pleasure principle ... does not seem to necessitate any far-reaching limitation of the pleasure principle."[10] Exceptions to the pleasure principle Freud proceeds to look for "evidence, for the existence of hitherto unsuspected forces 'beyond' the pleasure principle."[9] He found exceptions to the universal power of the pleasure principle—"situations ... with which the pleasure principle cannot cope adequately"[11]—in four main areas: children's games, as exemplified in his grandson's2) famous "fort-da" game;[12] "the recurrent dreams of war neurotics ...; the pattern of self-injuring behaviour that can be traced through the lives of certain people ["fate neurosis"]; the tendency of many patients in psycho-analysis to act out over and over again unpleasant experiences of their childhood."[13] Repetition compulsion From these cases, Freud inferred the existence of motivations beyond the pleasure principle.[13] Freud already felt in 1919 that he could safely postulate "the principle of a repetition compulsion in the unconscious mind, based upon instinctual activity and probably inherent in the very nature of the instincts—a principle powerful enough to overrule the pleasure-principle".[14] In the first half of Beyond the Pleasure Principle, "a first phase, the most varied manifestations of repetition, considered as their irreducible quality, are attributed to the essence of drives"[15] in precisely the same way. Building on his 1914 article "Recollecting, Repeating and Working Through", Freud highlights how the "patient cannot remember the whole of what is repressed in him, and ... is obliged to repeat the repressed material as a contemporary experience instead of ... remembering it as something belonging to the past:"[16] a "compulsion to repeat." Independence from the pleasure principle Freud still wanted to examine the relationship between repetition compulsion and the pleasure principle.[17] Although compulsive behaviors evidently satisfied some sort of drive, they were a source of direct unpleasure.[17] Somehow, "no lesson has been learnt from the old experience of these activities having led only to unpleasure. In spite of that, they are repeated, under pressure of a compulsion".[18] Also noting repetitions in the lives of normal people—who appeared to be "pursued by a malignant fate or possessed by some 'daemonic' power,"[18] likely alluding to the Latin motto errare humanum est, perseverare autem diabolicum ("to err is human, to persist [in committing errors] is of the devil")—Freud concludes that the human psyche includes a compulsion to repeat that is independent of the pleasure principle.[19][page needed] Speculation (sections IV–VII) Arguing that dreams in which one relives trauma serve a binding function in the mind, connected to repetition compulsion, Freud admits that such dreams are an exception to the rule that the dream is the fulfillment of a wish.[20] Asserting that the first task of the mind is to bind excitations to prevent trauma (so that the pleasure principle does not begin to dominate mental activities until the excitations are bound), he reiterates the clinical fact that for "a person in analysis ... the compulsion to repeat the events of his childhood in the transference evidently disregards the pleasure principle in every way".[21] Biological basis for repetition compulsion Freud begins to look for analogies of repetition compulsion in the "essentially conservative ... feature of instinctual life ... the lower we go in the animal scale the more stereotyped does instinctual behavior appear".[22] Thereafter "a leap in the text can be noticed when Freud places the compulsion to repeat on an equal footing with 'an urge ... to restore an earlier state of things'"[23]—ultimately that of the original inorganic condition. Declaring that "the aim of life is death" and "inanimate things existed before living ones",[24] Freud interprets an organism's drive to avoid danger only as a way of avoiding a short-circuit to death: the organisms seeks to die in its own way. He thus found his way to his celebrated concept of the death drive, an explanation that some scholars have labeled as "metaphysical biology".[25] Thereupon, "Freud plunged into the thickets of speculative modern biology, even into philosophy, in search of corroborative evidence"[26]—looking to "arguments of every kind, frequently borrowed from fields outside of psychoanalytic practice, calling to the rescue biology, philosophy, and mythology".[27] He turned to prewar experiments on protozoa—of perhaps questionable relevance, even if it is not the case that 'his interpretation of the experiments on the successive generations of protozoa contains a fatal flaw'.[28] The most that can perhaps be said is that Freud did not find "any biological argument which contradicts his dualistic conception of instinctual life",[29] but at the same time, "as Jones (1957) points out, 'no biological observation can be found to support the idea of a death instinct, one which contradicts all biological principles'"[30] either. Masochism as clinical manifestation Freud then continued with a reference to "the harbour of Schopenhauer's philosophy"; but in groping for a return to the clinical he admitted that "it looks suspiciously as though we were trying to find a way out of a highly embarrassing situation at any price".[31] Freud eventually decided that he could find a clinical manifestation of the death instinct in the phenomenon of masochism, "hitherto regarded as secondary to sadism ... and suggested that there could be a primary masochism, a self-injuring tendency which would be an indication of the death instinct".[32] In a footnote he cited Sabina Spielrein admitting that "A considerable part of this speculation has been anticipated in a work which is full of valuable matter and ideas but is unfortunately not entirely clear to me: (Sabina Spielrein: Die Destruktion als Ursache des Werdens, Jahrbuch für Psychoanalyse, IV, 1912). She designates the sadistic component as 'destructive'."[33] To then explain the sexual instinct as well in terms of a compulsion to repeat, Freud inserts a myth from Plato that humans are driven to reproduce in order to join together the sexes, which had once existed in single individuals who were both male and female—still "in utter disregard of disciplinary distinctions";[34] and admits again the speculative nature of his own ideas, "lacking a direct translation of observation into theory ... One may have made a lucky hit or one may have gone shamefully astray".[35] Conclusion Nevertheless, with the libido or Eros as the life force finally set out on the other side of the repetition compulsion equation, the way was clear for the book's closing "vision of two elemental pugnacious forces in the mind, Eros and Thanatos, locked in eternal battle".[26] |
分析と概要 『快楽原則』の「2つの明確なフレスコ画またはカンティ」[5]と呼ばれる第III部と第IV部の間には、区切りがある。オットー・フェニケルが述べたよ うに、フロイトの「新しい(本能的な)分類には2つの根拠があり、1つは思索的、もう1つは臨床的」[6]であるとすれば、ここまでは臨床的なものであ る。フロイト自身の言葉によると、第2章は「憶測であり、しばしば突飛な憶測である。読者は各自の好みに応じて考慮するか、あるいは却下するだろう」 [7]。「『快楽原則の彼方』において、フロイトは「憶測」という見込みのない言葉を一度以上使用している」と指摘されている。[8] 1)臨床的証拠(第I章~第III章 フロイトは「精神分析理論において、当時一般的であり、かつ異論のなかった考え方」から始めている。「精神の出来事は快楽原則によって自動的に制御されて いる...快楽原則への強い傾向」である。[9] 精神生活において不快な経験が避けられないものであることを考慮した上で、 彼は、不快な経験が心の生活に存在することは避けられないと結論づけ、その不快な経験の存在は「快楽原則の優位性に矛盾するものではない。快楽原則の広範 囲にわたる制限を必要とするものではない」と、この本の最初の章を締めくくっている。 2)快楽原則の例外 フロイトは「快楽原則の『向こう側』に存在する、これまで疑われることのなかった力の存在を示す証拠」を探し求めた。[9] 彼は快楽原則の普遍的な力に対する例外、すなわち「快楽原則が適切に対処できない状況」[11]を、主に4つの分野で見出した。それは、孫の有名な「いな いいないばあ」という遊びに代表されるような子供の遊び[12]、 孫の有名な「いないいないばあ」という遊びに代表される「子供の遊び」、[12] 「戦争神経症患者に繰り返し現れる戦争の夢」、「特定の人物の生涯をたどると見られる自己傷害行動のパターン(「宿命神経症」)、精神分析を受けている患 者の多くが、子供の頃の不快な経験を何度も何度も再現する傾向」[13] 3)反復強迫 これらの事例から、フロイトは快楽原則を超える動機の存在を推論した。[13] フロイトは1919年にはすでに、「本能的活動に基づく無意識の反復強迫の原則、おそらく本能の本質に内在する原則、 快楽原則を覆すほど強力な原則」であると仮定しても安全であると感じていた。[14] 『快楽原則を超えて』の前半では、「最初の段階として、還元不可能な性質として考えられる反復の最も多様な現象は、衝動の本質に起因する」[15]と、 まったく同じように述べられている。 1914年の論文「想起、反復、作業化」を基に、フロイトは「患者は自分の中に抑圧されていることのすべてを思い出すことはできず、... 抑圧された内容を過去の出来事として思い出す代わりに、現代の経験として反復せざるを得ない」[16]ことを強調している。「反復の強迫」である。 4)快楽原則からの独立 フロイトは、反復強迫と快楽原則の関係をさらに調査したいと考えていた。[17] 強迫行動は明らかに何らかの欲求を満たすものであるが、それは直接的な不快感の源でもあった。[17] しかし、なぜか「これらの行動が不快感をもたらすだけだという過去の経験から何も学んでいない。にもかかわらず、強迫観念に駆られて、それらは繰り返され る」[18] また、正常な人々の生活にも繰り返しが見られることに言及している。「悪意のある運命に追われたり、何らかの『悪魔的な』力に憑りつかれた」ように見える 人々について、おそらくは ラテン語のモットー「人間は過ちを犯すものだが、悪魔は過ちを犯し続けるものだ」を暗示している可能性が高い。フロイトは、人間の精神には快楽原則とは無 関係に繰り返すという強迫観念が含まれていると結論づけている。[19][要ページ番号] 5)推測(第IV章~第VII章) 心的外傷を追体験する夢は、反復強迫と関連して、精神に束縛の機能を果たすという主張を展開するフロイトは、そのような夢は「夢は願望の成就である」とい う原則の例外であることを認めている。[20] 精神の最初の課題は、興奮を束縛して (そうすることで、快楽原則が精神活動を支配し始めるのを防ぐことができる)」と主張し、彼は「分析中の人物の場合、転移において幼少期の出来事を繰り返 す強迫観念は、あらゆる面で快楽原則を無視している」という臨床的事実を繰り返し述べている。[21] 6)反復強迫の生物学的な基礎 フロイトは、反復強迫の類似性を「本質的に保守的な...本能的な生活の特徴...動物界の低級な生物になるほど、本能的な行動はより型にはまる」 [22]という点に見出そうとし始めた。その後、「フロイトが反復強迫を『以前の状態に戻そうとする衝動...』と同等に扱う際に、文章に飛躍が見られ る」[23]ことに気づく。つまり、最終的には、元の無機質な状態である。「生命の目的は死である」と「生命のないものが生命あるものより先に存在してい た」と宣言し[24]、フロイトは生物の危険を回避しようとする衝動を、死へのショートサーキットを回避する方法としてのみ解釈した。生物は独自の方法で 死を求めるのである。こうして彼は、著名な死の衝動という概念にたどり着いた。この説明は、一部の学者から「形而上生物学」と名付けられている[25]。 「フロイトは、確証となる証拠を求めて、思弁的な近代生物学の森羅万象、さらには哲学にまで分け入っていった」[26]。「あらゆる種類の議論、しばしば 精神分析の実践以外の分野から借用された議論を、生物学、哲学、神話の援用に役立てようとした」[27]。彼は、原生動物に関する戦前の実験に目を向け た。その関連性は疑わしいかもしれないが、 。おそらく言えるのは、フロイトは「彼の二元論的な本能の概念に反する生物学的論拠」を見つけられなかったということだけだろうが[29]、同時に、 「ジョーンズ(1957年)が指摘しているように、『死の本能という考えを裏付ける生物学的観察は見つかっていない。それは、生物学的原則すべてに反する ものだ』」[30]。 7)臨床的症状としてのマゾヒズム フロイトはその後、「ショーペンハウアー哲学の港」に言及しながら話を続けたが、臨床的なものへの回帰を模索する中で、「非常に厄介な状況から、どんな犠 牲を払ってでも抜け出す方法を見つけようとしているように見えるのは疑わしい」と認めた。[31] フロイトは最終的に、死の本能の臨床的症状はマゾヒズムの現象に見られると判断し、「 サディズムの二次的なものと見なされていた... そして、死の本能の兆候である自己傷害傾向の一次的なマゾヒズムが存在する可能性を示唆した」[32] 脚注で、彼はサビーナ・スピルレインの言葉を引用し、「この推測の相当な部分は、貴重な内容とアイデアに満ちたある著作で予想されていたが、残念ながら私 には完全に理解できない。(サビーナ・スピルレイン著『 破壊が成長の原因である』、精神分析年報、第4巻、1912年)。彼女はサディスト的要素を「破壊的」と表現している。」[33] その後、性的本能についても繰り返すという強迫観念の観点から説明するために、フロイトは、人間は かつて単一の個体に存在していた、男性と女性の両方の性質を併せ持つ存在に再びなるために、人間は生殖を迫られるのだ。そして、自身の考えが思弁的なもの であることを再び認める。「観察結果を理論に直接的に翻訳することができないため、... ある者は幸運にも正解を導き出すかもしれないし、ある者は恥ずべきほどに迷走してしまうかもしれない」[35]。 8)結論 しかし、リビドーまたはエロスを生命力として、ついに反復強迫の等式の反対側にたどり着いたことで、この本の締めくくりとして「心の中にある2つの根源的な闘争的な力、エロスとタナトスが永遠の戦いに身を置く」という「ビジョン」を提示する道が開けた。[26] |
| The essay's relation to Freud's grief Freud's daughter Sophie died at the start of 1920, partway between Freud's first (1919) version and the version of Beyond the Pleasure Principle reworked and published in 1920. Freud insisted that the death had no relation to the contents of the book. In a July 18, 1920, letter to Max Eitingon, Freud wrote, "The Beyond is now finally finished. You will be able to confirm that it was half ready when Sophie lived and flourished".[36] He had however already written (in June) to colleague and psychoanalyst Sándor Ferenczi "that 'curious continuations' had turned up in it, presumably the part about the potential immortality of protozoa". Ernest Jones considers Freud's claim on Eitingon "a rather curious request ... [perhaps] an inner denial of his novel thoughts about death having been influenced by his depression over losing his daughter".[37] Others have also wondered about "inventing a so-called death instinct—is this not one way of theorising, that is, disposing of—by means of a theory—a feeling of the "demoniac" in life itself ... exacerbated by the unexpected death of Freud's daughter"?[38]—and it is certainly striking that "the term 'death drive'—Todestrieb—entered his correspondence a week after Sophie Halberstadt's death"; so that we may well accept at the very least that the "loss can claim a subsidiary role ... [in]his analytic preoccupation with destructiveness".[39] |
フロイトの悲しみとこの論文の関係 フロイトの娘ソフィーは、1920年の初頭に亡くなった。この時期は、1919年に発表された最初の版と、1920年に改訂版『快楽原則を超えて』として 出版された版の中間であった。フロイトは、この死と本の内容とは何の関係もないと主張した。1920年7月18日、フロイトはマックス・エーティンゴン宛 ての手紙で、「『快楽原則を超えて』はようやく完成した。ソフィーが生きていた頃には、この本は半分しか完成していなかったが、今ようやく完成した。」と 書いている。[36] しかし、彼は同僚であり精神分析家のサンドール・フェレンツィに宛てた手紙(6月)で、「『奇妙な続き』が現れた。おそらく原生動物の潜在的な不死性に関 する部分だ」とすでに書いていた。アーネスト・ジョーンズは、フロイトがエーティンゴンに求めたことは「かなり奇妙な要求」であり、「おそらくは、娘を 失ったことによる彼のうつ状態が、死に関する彼の新しい考えを内面から否定した」ものだと考えている。[37] また、他の人々は「いわゆる死の衝動を発明すること、つまり、理論によって「悪魔のような」人生そのものに対する感情を理論化し、処理することではない か」と疑問を呈している。。「死の本能」という用語が、ソフィー・ハルバーシュタットの死から1週間後にフロイトの書簡に登場したことは確かに注目に値す る。少なくとも、「喪失は、彼の分析における破壊性への強い関心において、脇役としての役割を担うことができる」と受け止めることはできるだろう。 |
| Continuation of themes in the essay On his final page, Freud acknowledges that his theorising "in turn raises a host of other questions to which we can at present find no answer".[40] Whatever legitimate reservations there may be about "the improbability of our speculations. A queer instinct, indeed, directed to the destruction of its own organic home",[41] Freud's speculative essay has proven remarkably fruitful in stimulating further psychoanalytic research and theorising, both in himself and in his followers; and we may consider it as a prime example of Freud in his role "as a problem finder—one who raises new questions ... called attention to a whole range of human phenomena and processes".[42] Thus for example André Green has suggested that Freud "turned to the biology of micro-organisms ... because he was unable to find the answers to the questions raised by psychoanalytic practice": the fruitfulness of the questions—in the spirit of 'Maurice Blanchot's sentence, "La réponse est le malheur de la question" [The answer is the misfortune of the question]'[43]—remains nonetheless unimpaired. Freud's later writing and legacy The distinction between pleasure principle and death drive led Freud to restructure his model of the psyche.[44] With Beyond the Pleasure Principle, Freud also introduced the question of violence and destructiveness in humans.[44] These themes play an important role in Civilization and Its Discontents, in which Freud suggests that civilization has repeatedly tried and failed to repress the death drives. Freud's indication "that in cases of traumatism there is a 'lack of any preparedness for anxiety' ... is a forerunner of the distinction he would later make ... between 'automatic anxiety' and 'anxiety as a signal'".[45] For Jacques Lacan, repetition compulsion was one of the "four ... terms introduced by Freud as fundamental concepts, namely, the unconscious, repetition, the transference and the drive".[46] Eric Berne adapted the way "Freud speaks of the repetition compulsion and the destiny compulsion ... to apply them to the entire life courses"[47] of normals and neurotics alike. Gilles Deleuze observed that "in Beyond the Pleasure Principle, Freud is not really preoccupied with the exceptions to that principle", concluding that "there are no exceptions to the principle—though there would indeed seem to be some rather strange complications in the workings of pleasure."[48] Both Melanie Klein and Lacan were to adopt versions of the death drive in their own theoretical constructs. "Klein's concept of the death drive differs from Freud's ... but there is an ever-increasing reference to the death drive as a given cause of mental development"[49] in her works. Lacan for his part considered that "the death drive is only the mask of the symbolic order, in so ... far as it has not been realised", adding modestly of Beyond the Pleasure Principle "... either it makes not the least bit of sense or it has exactly the sense I say it has".[50] |
論文のテーマの続き 最後のページで、フロイトは、自身の理論化が「次々と、現時点では答えを見つけられないような、多くの新たな疑問を生み出す」ことを認めている。[40] 「我々の推測の不確実性」について正当な懸念があるとしても、 実に奇妙な本能が、自身の有機的な棲み家の破壊へと向かう」[41] フロイトの思索的な論文は、彼自身や彼の信奉者たちによるさらなる精神分析的研究や理論化を刺激する上で、非常に有益であることが証明されている。そし て、それは「問題発見者、すなわち新たな問題提起者」としてのフロイトの役割の典型的な例であると考えることができる。「... あらゆる人間現象や過程に注意を促した」[42] 例えば、アンドレ・グリーンは、フロイトが「微生物の生物学に目を向けたのは、精神分析の実践から生じた疑問に対する答えを見つけられなかったからだ」と 指摘している。モーリス・ブランショの「答えは質問の不幸である」という言葉の精神に則った疑問の豊かさは、しかし、依然として損なわれることはない。 フロイトの後の著作と遺産 快楽原則と死の欲動の区別により、フロイトは精神のモデルを再構築した。[44] 『快楽原則を超えて』で、フロイトは人間における暴力と破壊性という問題も提起した。[44] これらのテーマは『文明とその不満』でも重要な役割を果たしており、フロイトは文明が死の欲動を抑圧しようとして繰り返し失敗してきたと示唆している。フ ロイトの指摘した「外傷症の場合には『不安に対する備えが欠如している』という指摘は、後に彼が区別することになる『自動的な不安』と『シグナルとしての 不安』の区別の先駆けである」[45]。 ジャック・ラカンにとって、反復強迫は「フロイトが基本概念として導入した4つの用語、すなわち、無意識、反復、転移、そして駆動」のひとつであった。[46] エリック・バーンは、「フロイトが反復強迫と運命強迫について述べた方法を、... 正常者と神経症患者の生涯全体に適用する」ために応用した。[47] ジル・ドゥルーズは、「『快楽の原理』において、フロイトは、その原理に対する例外について、実際にはそれほど懸念していない」と指摘し、「快楽の作用には、確かにいくつかのかなり奇妙な複雑さがあるように見えるが、原理に対する例外は存在しない」と結論づけている。 メラニー・クラインとラカンは、それぞれ独自の理論構成において死の欲動のバージョンを採用した。「クラインの死の欲動の概念はフロイトのそれとは異なる が、彼女の作品では精神発達における死の欲動の役割について言及されることが増えている」[49]。ラカンは「死の欲動は、それが実現されていない限り、 象徴秩序の仮面でしかない」と考え、「快の原則を超えて」は「まったく意味をなさないか、あるいは私が言うようにまさに意味をなすかのどちらかだ」と控え めに付け加えた。[50] |
| Critical reception Beyond the Pleasure Principle may be Freud's most controversial text. Jacques Lacan described it as an "extraordinary text of Freud's, unbelievably ambiguous, almost confused".[51] Peter Gay remarked in Freud: A Life for Our Time that "Beyond the Pleasure Principle is a difficult text ... the reassuring intimacy with clinical experience that marks most of Freud's papers, even at their most theoretical, seems faint here, almost absent".[52] On the same terms, Gilles Deleuze wrote in his 1967 literary study Masochism: Coldness and Cruelty that "the masterpiece which we know as Beyond the Pleasure Principle is perhaps the one where he engaged most directly—and how penetratingly—in specifically philosophical reflection."[53] Ernest Jones, one of Freud's closest associates and a member of his Inner Ring, stated that "the train of thought [is] by no means easy to follow ... and Freud's views on the subject have often been considerably misinterpreted."[54] Jones concluded that "This book is further noteworthy in being the only one of Freud's which has received little acceptance on the part of his followers".[55] Many of Freud's colleagues and students initially rejected the theories proposed in Beyond the Pleasure Principle because the idea of a drive towards death seemed strange.[56][57] |
批評家の評価 『快楽原則を超えて』は、フロイトの著作の中で最も論争を呼んだものかもしれない。ジャック・ラカンは「信じられないほど曖昧で、ほとんど混乱している、 フロイトの驚くべきテキスト」と評した。[51] ピーター・ゲイは『フロイト: 『快楽原則を超えて』は難しい論文である。フロイトの論文のほとんどにみられる、臨床経験に基づく安心感のある親密さは、この論文ではほとんど感じられ ず、ほとんど存在していないように思われる」と述べている。[52] 同様に、ジル・ドゥルーズは1967年の文学研究『マゾヒズム: 「『快楽原則を超えて』として知られるこの傑作は、おそらく、彼が最も直接的に、そしていかに鋭く、特に哲学的な考察を行ったものだ」と述べている。 [53] フロイトの最も親しい協力者の一人であり、彼の「内輪の会合」のメンバーでもあったアーネスト・ジョーンズは、「思考の流れは、決して容易に追うことはで きない...そして、この主題に関するフロイトの見解は、しばしばかなり誤って解釈されてきた」と述べている。[54] ジョーンズは「この本は、フロイトの著作の中で唯一、彼の信奉者たちからほとんど受け入れられていないという点でも注目に値する」と結論づけている。 [55] フロイトの同僚や学生の多くは、当初、『快楽原則の彼方』で提案された理論を拒絶した。なぜなら、死に向かう原動力という考え方は奇妙に思えたからだ。 [56][57] |
| Jacques Derrida's The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond Bernard Stiegler's "Desire and Knowledge: The Dead Seize the Living" |
|
| Beyond the Pleasure Principle (C. J. M. Hubback, trans., 1922.) Jenseits des Lustprinzips at Project Gutenberg (in German) |
|
★
Jenseits des
Lustprinzips ist eine Abhandlung von Sigmund Freud, die in den Jahren
1919 und 1920 entstand und 1920 veröffentlicht wurde. Ausgehend von
einer Analyse des Wiederholungszwangs entwirft Freud eine Konzeption
der Verdrängung und des Triebes. Die Abhandlung gilt als Wende in
Freuds theoretischer Entwicklung.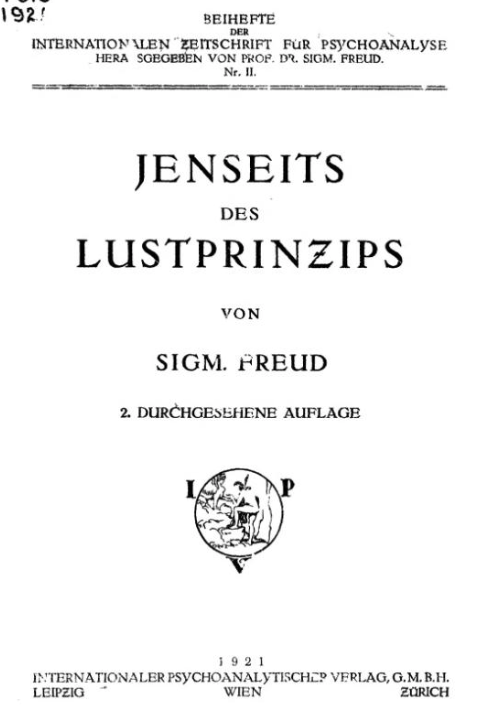 Jenseits des Lustprizips. Ausgabe 1921 Die Arbeit enthält drei theoretische Neuerungen: Die Beziehung zwischen dem psychischen System, das die Verdrängung ausübt, und dem Verdrängten wird neu gefasst. Als verdrängende Instanz gilt Freud jetzt nicht mehr, wie in seinen früheren Arbeiten, das Bewusstsein, sondern ein Ich, das in seinem Kern unbewusst ist. Die Triebe werden keineswegs nur vom Lustprinzip beherrscht, also dem Streben, Lust zu gewinnen und Unlust zu vermeiden, wie er früher annahm. Primär ist vielmehr für einen Trieb der Drang, einen früheren Zustand wiederherzustellen. Dieser Drang ist unabhängig vom Lustprinzip wirksam, nimmt also Unlust in Kauf, etwa in Form von Angst, und kann das Lustprinzip außer Kraft setzen. Es gibt zwei Triebgruppen, die Lebenstriebe und die Todestriebe. Die Lebenstriebe erschienen, unter anderem Namen, bereits in früheren Schriften Freuds; ihre Energie ist die Libido, die in zwei Formen auftritt, als Narzissmus und als objektbezogene Liebe. Das Konzept der Todestriebe wird in dieser Schrift eingeführt; Freud bezeichnet damit die Tendenz zur Selbstzerstörung, und die davon abgeleitete Neigung zur Aggression und zur Destruktion. Die Lebenstriebe zielen auf die Herstellung immer größerer Einheiten, die Todestriebe auf Rückführung des Organismus in einen anorganischen Zustand. |
快楽原則を超えては、ジークムント・フロイトが1919年から1920年に執筆し、1920年に出版された論文だ。フロイトは、反復強迫の分析から出発して、抑圧と本能の概念を構築している。この論文は、フロイトの理論的発展における転換点とされている。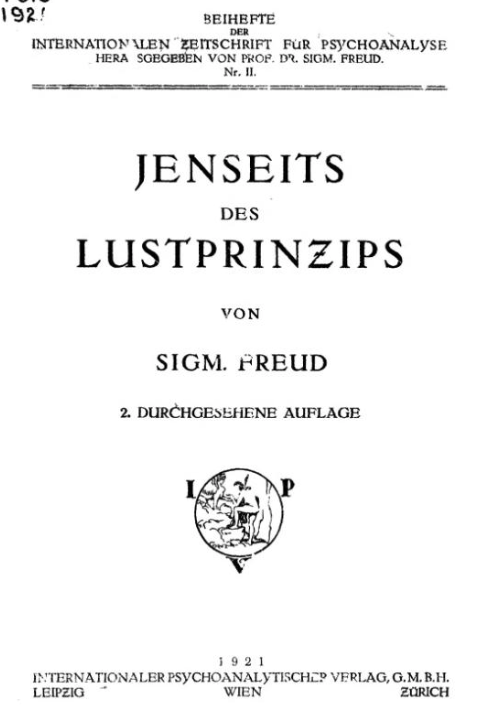 快楽原則を超えて。1921年版 この著作には、3つの理論上の革新が含まれている。 抑圧を行う精神システムと抑圧されたものとの関係が再定義されている。フロイトは、以前の著作では抑圧の主体を「意識」とみなしていたが、この著作では、その主体を「無意識」である「自我」とみなしている。 本能は、フロイトが以前考えていたように、快楽原則、つまり快楽を得、不快を回避しようとする欲求によってのみ支配されているわけではない。むしろ、本能 の第一の目的は、以前の状態を回復しようとする衝動である。この衝動は、快楽原則とは無関係に作用し、恐怖などの形で不快を甘受し、快楽原則を無効にする ことができる。 本能には、生命本能と死本能の 2 つのグループがある。生命本能は、フロイトの以前の著作にも別の名前で登場している。そのエネルギーはリビドーであり、ナルシシズムと対象への愛という 2 つの形で現れる。死の衝動の概念は、この著作で初めて導入された。フロイトは、この概念で自己破壊の傾向、およびそこから派生する攻撃性や破壊性を指して いる。生命の衝動は、より大きな単位の形成を目指し、死の衝動は、有機体を無機的な状態に戻すことを目指している。 |
| Inhalt Übersicht In früheren Schriften hatte Freud die Ansicht vertreten, die seelischen Vorgänge würden durch das Lustprinzip und das Realitätsprinzip reguliert. Das Lustprinzip besteht im Streben nach Lust und im Vermeiden von Unlust, wobei die Lustempfindung, Freud zufolge, in einer Verringerung der Spannung besteht, beruhend auf der Abfuhr von Energie. Die Unlust hat ihren Grund in einer Steigerung der Spannung, in der Zunahme von Energie. Unter dem Einfluss der Selbsterhaltungstriebe des Ichs wird das Lustprinzip durch das Realitätsprinzip abgelöst. Dieses zielt, wie das Lustprinzip, auf Lustbefriedigung, sorgt jedoch dafür, dass hierbei unlustvolle Umwege in Kauf genommen werden – das Realitätsprinzip ist eine Modifikation des Lustprinzips. (Teil I) Nun gibt es aber den Wiederholungszwang: bestimmte Unlusterfahrungen werden hartnäckig wiederholt. Dazu gehören die Unfallträume von Menschen, die an traumatischer Neurose erkrankt sind, sowie Kinderspiele, in denen Trennungserfahrungen re-inszeniert werden. Widersprechen sie dem Lustprinzip? Zumindest die Wiederholungsspiele der Kinder lassen sich durchaus im Rahmen des Lustprinzips deuten: als Befriedigung des Bemächtigungstriebs durch nachträgliche aktive Bewältigung eines passiv erfahrenen Erlebnisses oder als Befriedigung eines Racheimpulses. Das meiste, was der Wiederholungszwang in diesem Fall wiederbelebt, bringt zwar dem Ich Unlust, aber eine Unlust, die dem Lustprinzip nicht widerspricht: Unlust für das Ich und Lust für das Unbewusste. (Teil II) In der psychoanalytischen Therapie jedoch kommt es zu Formen des Wiederholungszwangs, die keineswegs dem Lustprinzip unterstehen. Wesentliche schmerzhafte Kindheitserinnerungen, etwa die Erfahrung des Zurückgewiesenwerdens durch die Eltern, werden nicht erinnert, sondern wiederholt, und zwar in der Beziehung zum Arzt, in der Übertragung. Ein ähnliches Phänomen findet man bei nicht-neurotischen Personen, die unter einem „Schicksalszwang“ stehen, d. h. die gezwungen sind, immer wieder Beziehungen herzustellen, die auf gleiche Weise schmerzlich enden, etwa im Verratenwerden durch einen Freund. In der Therapie zielt die Wiederholung des Patienten darauf ab, die Behandlung abzubrechen. Damit steht sie im Dienste des Widerstands des Ichs gegen die Aufdeckung des Verdrängten. Die Motive dieses Widerstands sind unbewusst. Also ist das Ich in seinem Kern unbewusst. (Teil III) Der Wiederholungszwang, der nicht dem Lustprinzip untersteht, hat zwei Quellen. Er beruht auf Erregungen, die von außen kommen, und auf solchen, die von innen stammen, vor allem von den Trieben. Um den Wiederholungszwang, der durch Einwirkung äußerer Reize entsteht, aufzuklären, bedient sich Freud eines Modells des „psychischen Apparats“, dessen Arbeitsweise er zunächst darlegt. Die im Apparat vorhandenen Erregungen entstehen durch Energien, die in zwei Formen existieren, als „freie“ und als „gebundene“ Energien: Im Unbewussten herrscht der „Primärvorgang“, das heißt, die hier vorhandenen Erregungen resultieren aus freier Energie, aus einer Energieform, die nach sofortiger Abfuhr drängt, was als Streben nach Spannungsverminderung empfunden wird. Im Vorbewussten (denjenigen Vorstellungen, die zwar aktuell nicht bewusst sind, die aber jederzeit bewusst gemacht werden können) und im Bewusstsein herrscht der „Sekundärvorgang“; die Erregungsabläufe beruhen hier auf einem anderen Typ von Energie, nämlich auf gebundener (oder ruhender) Energie. Diese drängt nicht danach, sofort abzufließen, sie kann vielmehr gespeichert werden und ihre Abfuhr – die vor allem durch die Motorik erfolgt – kann auf kontrollierte Weise stattfinden. Zum Schutz gegen allzu große von außen kommende Erregungsmengen dient dem Apparat der Reizschutz, vor allem in Form der Angstbereitschaft. Eine traumatische Überflutung des Apparats durch eine übergroße Reizmenge kommt dann zustande, wenn das Individuum unvorbereitet ist und einen Schreck erleidet, d. h. wenn der Reizschutz ausfällt und keine Angstbereitschaft entwickelt wird. Der psychische Apparat steht dann vor der Aufgabe, die eingedrungene Erregungsmenge zu bewältigen: sie zu binden, in gebundene Energie zu überführen. Zu diesem Zweck wird das Lustprinzip vorübergehend außer Kraft gesetzt; Unlust, etwa in Form von Angst, wird akzeptiert. Damit lässt sich die Wiederholung von Unfallträumen erklären. In diesen Träumen wird versucht, die durch den Unfall eingedrungene Reizmenge zu bewältigen, und zwar dadurch, dass die Wiederholung nachträglich mit der damals fehlenden Angstbereitschaft verbunden wird. (Teil IV) Der Wiederholungszwang beruht aber auch auf solchen Erregungen, die aus dem Inneren des psychischen Apparats stammen, von den Trieben. Um den intern verursachten Wiederholungszwang zu erklären, entwirft Freud eine neue Version seiner Triebtheorie. Die beiden Hauptthesen lauten: Alle Triebe streben nach Wiederholung. Und: Es gibt genau zwei große Triebgruppen: Lebenstriebe und Todestriebe. Wiederholungscharakter der Triebe – Ein Trieb ist ein dem belebten Organismus innewohnender Drang, einen früheren Zustand wiederherzustellen, ein ursprüngliches Befriedigungserlebnis zu wiederholen. Dieses Ziel kann aufgrund der Verdrängung niemals erreicht werden, es kann aber auch nicht aufgegeben werden. Triebe sind also konservativ, regressiv. Es gibt keinen Trieb zur Höherentwicklung; alle Höherentwicklung beruht auf äußerer Einwirkung. „Der verdrängte Trieb gibt es nie auf, nach seiner vollen Befriedigung zu streben, die in der Wiederholung eines primären Befriedigungserlebnisses bestünde; alle Ersatz-, Reaktionsbildungen und Sublimierungen sind ungenügend, um seine anhaltende Spannung aufzuheben, und aus der Differenz zwischen der gefundenen und der geforderten Befriedigungslust ergibt sich das treibende Moment, welches bei keiner der hergestellten Situationen zu verharren gestattet, sondern nach des Dichters Worten 'ungebändigt immer vorwärts dringt' (Mephisto im Faust, I, Studierzimmer).“ – Teil V, S. 251[1] Zwei Triebgruppen – Freud unterscheidet zwei Arten von Trieben, Lebenstriebe (oder „Eros“, griechisch für: Liebe) und Todestriebe. Er nimmt an, dass diese beiden Triebarten in jedem lebendigen Organismus am Werk sind, beginnend beim Einzeller. Die Todestriebe streben danach, das Lebewesen in den anorganischen Zustand zurückzuführen. „Das Ziel alles Lebens ist der Tod.“ (S. 248) Zu dieser Triebgruppe gehören das Streben nach Selbstzerstörung und die daraus abgeleitete Neigung zur Aggression und zur Destruktion. Die Lebenstriebe zielen darauf ab, das Leben für längere Zeit zu erhalten und es zu immer größeren Einheiten zusammenzufassen. Zu ihnen gehören der Narzissmus und die hieraus hervorgehenden objektbezogenen Sexualtriebe. Zwischen Lebenstrieben und Todestrieben gibt es einen Gegensatz, der, neben den von außen kommenden Störkräften, die Entwicklung der Lebewesen bestimmt. (Teil V) Freud sieht keine Möglichkeit, seine Annahmen über die beiden Triebgruppen wissenschaftlich zu untermauern. Eine Bestätigung scheinen sie zu finden in August Weismanns Unterscheidung zwischen dem sterblichen Teil des Körpers, dem Soma, und den Keimzellen, die bei Verschmelzung unsterblich sind. Jedoch hält Weismann den Tod für eine späte Erfindung der Evolution, er sieht darin nicht, wie Freud, eine von Anfang an in allem Lebendigen wirksame Kraft. Kann Ewald Herings Theorie als Bestätigung dienen, wonach die Vorgänge in der lebendigen Substanz in zwei Richtungen gehen, eine aufbauende Richtung – assimilatorisch – und eine abbauende Richtung – dissimilatorisch? Freud lässt die Frage offen. Eine Stütze für seine Spekulation findet er allein bei den Philosophen: für die Todestriebe bei Schopenhauer und für die Lebenstriebe, den Eros, bei Platon. Die Behauptung vom regressiven Charakter der Triebe beruht allerdings, so erklärt er, auch auf beobachtbarem Material, nämlich auf den Tatsachen des Wiederholungszwangs. (Teil VI) Freud schließt die Abhandlung mit Anmerkungen zur Beziehung zwischen den Trieben, dem Lustprinzip und dem Verhältnis von freier und gebundener Energie: Das Lustprinzip steht sowohl im Dienste der Todestriebe als auch der Lebenstriebe. Es zielt darauf ab, das Erregungsniveau konstant zu halten (Konstanzprinzip) oder vielleicht sogar auf Null zu bringen (Nirwanaprinzip); damit unterstützt es die Todestriebe, die Zurückführung zu einem anorganischen Zustand. Es wirkt jedoch zugleich in die entgegengesetzte Richtung: es wacht über Triebreize, die die Lebensaufgabe erschweren, und damit dient es den Lebenstrieben. Die im Unbewussten ablaufenden Vorgänge – hervorgerufen durch die freien Erregungsvorgänge des Primärprozesses – rufen weit intensivere Lust-/Unlust-Empfindungen hervor als die im Ich ablaufenden Denk- und Wahrnehmungsprozesse, die auf den gebundenen Erregungsvorgängen des Sekundärprozesses basieren. Am Anfang des Seelenlebens des Individuums gab es einzig den Primärprozess. In ihm herrschte das Lustprinzip, dies jedoch keineswegs uneingeschränkt, „es muss sich häufige Durchbrüche gefallen lassen“ (S. 271), Unterbrechungen durch den Wiederholungscharakter der Triebe. In späteren Zeiten, mit der Entwicklung des Ichs, ist die Herrschaft des Lustprinzips sehr viel stärker gesichert. Freud entlässt den Leser mit der Erklärung, man müsse bereit bleiben, einen Weg wieder zu verlassen, wenn man den Eindruck gewonnen hat, dass er zu nichts Gutem führe. (Teil VII) |
内容 概要 以前の著作で、フロイトは、精神的な過程は快楽原則と現実原則によって規制されているという見解を述べていた。快楽原則とは、快楽を追求し、不快を回避す ることであり、フロイトによれば、快楽の感覚は、エネルギーの放出による緊張の緩和にある。不快は、緊張の高まり、エネルギーの増加に起因する。自我の自 己保存本能の影響を受けて、快楽原則は現実原則に取って代わられる。現実原則は、快楽原則と同様に快楽の満足を目指すものの、その過程で不快な回り道を容 認する。現実原則は、快楽原則の変形である。(第 1 部) しかし、繰り返し強迫という現象がある。特定の不快な経験が執拗に繰り返されるのだ。これには、トラウマ的な神経症を患っている人の事故の夢や、分離の経 験を再現する子供たちの遊びなどが含まれる。これらは快楽原則に反しているのでしょうか?少なくとも子供たちの繰り返し遊びは、快楽原則の枠内で解釈する ことができます。それは、受動的に経験した出来事を事後に積極的に克服することで支配欲を満足させる、あるいは復讐の衝動を満足させるものと考えられま す。この場合、反復強迫によって復活するもののほとんどは、確かに自我に不快感をもたらすが、その不快感は快楽原則に反するものではない。自我にとっては 不快感であり、無意識にとっては快楽である。(第2部) しかし、精神分析療法では、快の原則にまったく従わない形の反復強迫が見られる。親に拒絶されたという重要な痛ましい子供時代の記憶は、記憶として思い出 すのではなく、医師との関係、つまり転移の中で繰り返される。同様の現象は、非神経症者で「運命の強制」に支配されている人、つまり、友人による裏切りな ど、同じように苦痛な結末を迎える関係を繰り返し築くことを余儀なくされている人にも見られる。治療において、患者の繰り返しの行動は、治療を中断するこ とを目的としている。したがって、それは抑圧されたものを明らかにすることに対する自我の抵抗に役立っている。この抵抗の動機は無意識である。つまり、自 我はその本質において無意識である。(第3部) 快楽原則に支配されない反復強迫には、2つの源がある。それは、外部から来る刺激と、内部、特に本能から来る刺激に基づいている。外部刺激によって生じる 反復強迫を説明するために、フロイトは「精神装置」というモデルを用いて、その働きをまず説明する。この装置にある刺激は、「自由」エネルギーと「結合」 エネルギーという2つの形態で存在するエネルギーによって生じる。 無意識には「一次過程」が支配しており、ここにある刺激は、自由エネルギー、つまり、即座に放出されるエネルギーから生じ、緊張の緩和を求める欲求として感じられる。 前意識(現在意識にはないが、いつでも意識化できる想像)と意識では、「二次過程」が支配的だ。ここでの興奮の過程は、別のタイプのエネルギー、つまり結 合エネルギー(または静止エネルギー)に基づいている。このエネルギーは、すぐに放出されることを求めず、むしろ蓄積され、その放出(主に運動機能によっ て行われる)は、制御された形で起こる。 外部からの過大な興奮量から装置を保護するのは、主に恐怖心という形の刺激保護機能だ。過大な刺激量によって装置がトラウマ的な過負荷状態になるのは、個 人が準備ができておらず、恐怖を経験した場合、つまり刺激保護機能が働かず、恐怖心が発達しなかった場合だ。その場合、精神装置は、侵入した刺激の量を処 理、つまり結合し、結合したエネルギーに変換するという課題に直面する。この目的のために、快楽原則は一時的に無効になり、恐怖などの不快感が受け入れら れる。これにより、事故の夢が繰り返される理由を説明することができる。これらの夢では、事故によって侵入した刺激の量を処理しようとし、その方法は、事 故当時欠けていた恐怖心と、その繰り返しの出来事を後付けで結びつけることだ。(第4部) しかし、反復強迫は、精神機構の内部、つまり本能から生じる興奮にも基づいています。内部で生じる反復強迫を説明するために、フロイトは本能理論の新しい バージョンを考案しました。その2つの主な主張は、次のとおりです。すべての本能は反復を求めます。そして、2つの大きな本能群、すなわち生の本能と死の 本能が正確に存在します。 本能の反復性 – 本能とは、生物に内在する、以前の状態を回復し、元の満足感を繰り返そうとする衝動だ。この目標は、抑圧のために決して達成することはできないが、放棄す ることもできない。したがって、本能は保守的で退行的だ。より高い発達への衝動は存在せず、すべてのより高い発達は外的要因によるものだよ。 「抑圧された衝動は、その完全な満足、すなわち、最初の満足体験の繰り返しを求めることを決して諦めない。すべての代替、反応形成、昇華は、その持続的な 緊張を止揚するには不十分であり、見出された満足と要求される満足との差から、推進力が生じ、その推進力は、作り出されたどの状況にも留まることを許さ ず、詩人の言葉によれば、「抑制されることなく、常に前進し続ける」 (『ファウスト』のメフィスト、 I、書斎)」。 – 第 V 部、251 ページ[1] 2 つの本能群 – フロイトは、2 種類の本能、すなわち生命本能(または「エロス」、ギリシャ語で「愛」を意味する)と死本能を区別している。彼は、これらの 2 種類の本能は、単細胞生物から始めて、あらゆる生物に作用していると仮定している。死の衝動は、生物を無機物の状態に戻そうとする。「すべての生命の目標 は死である」(248ページ)。この衝動群には、自己破壊の欲求、およびそこから派生する攻撃性や破壊性がある。生命本能は、生命を長期間維持し、より大 きな単位に統合することを目指している。これには、ナルシシズムや、そこから派生する対象指向の性的本能が含まれる。 生命本能と死本能の間には対立があり、外部からの妨害力とともに、生物の進化を決定している。(第 5 部 フロイトは、この2つの本能群に関する自分の仮定を科学的に立証する方法はないと考えている。この仮定は、アウグスト・ワイスマンが、死すべき身体の部分 であるソーマと、融合すると不死となる生殖細胞とを区別した考えによって裏付けられているように見える。しかし、ワイスマンは死を進化の遅い段階での発明 だと考えており、フロイトのように、死が最初からすべての生物に作用する力であるとは考えていない。エヴァルト・ヘリングの、生物の物質における過程は、 構築的な方向(同化)と破壊的な方向(異化)の 2 つの方向に進むという理論は、フロイトの仮定を裏付けるものとなるだろうか?フロイトはこの質問を未解決のまま残している。彼の推測を裏付けるものは、哲 学者たちだけだ。死の衝動についてはショーペンハウアー、生命の衝動、エロスについてはプラトンだ。しかし、衝動の退行的な性格に関する主張は、観察可能 な資料、すなわち反復強迫の事実にも基づいている、と彼は説明している。(第6部) フロイトは、本能、快楽原則、自由エネルギーと結合エネルギーの関係に関する考察で、この論文を締めくくっている。 快楽原則は、死の本能と生の本能の両方に奉仕している。それは、興奮のレベルを一定に保つ(恒常性原理)か、あるいはゼロにする(ニルヴァーナ原理)こと を目指しており、それによって死の衝動、つまり無機的な状態への回帰を支援している。しかし、それは同時に反対の方向にも作用し、生命の任務を困難にする 衝動の刺激を監視し、それによって生命の衝動に奉仕している。 無意識の中で起こるプロセス(一次過程の自由な興奮プロセスによって引き起こされる)は、自我の中で起こる思考や知覚のプロセス(二次過程の結合した興奮プロセスに基づく)よりも、はるかに強い快・不快の感覚を引き起こす。 個人の精神生活の始まりには、一次過程だけがあった。そこでは快楽原則が支配的だったが、それは決して無制限ではなく、「頻繁な突破を容認しなければなら ない」(271ページ)、つまり、衝動の反復性による中断があった。その後、自我が発達するにつれて、快楽原則の支配はより強固なものになっていく。 フロイトは、その道がよい結果につながらないと判断したら、その道から離れる用意をしておかなければならない、と読者に告げてこの章を締めくくっている。 (第 7 部) |
| Trieb-Terminologie Die in Jenseits des Lustprinzips vorgestellte dualistische Triebkonzeption wird von Freud bis ans Lebensende beibehalten. Die Terminologie jedoch ist schwankend: In Jenseits des Lustprinzips von 1920 heißen die beiden Triebgruppen „Lebenstriebe“ (oder „Eros“) und „Todestriebe“. In Das Ich und das Es von 1923 spricht Freud von „Sexualtrieben“ (oder „Eros“) im Gegensatz zu den „Todestrieben“; der Ausdruck „Lebenstrieb“ wird in dieser Arbeit nicht verwandt. Der Terminus „Destruktionstrieb“ dient hier dazu, den unter dem Einfluss der Sexualtriebe gegen die Außenwelt gerichteten Todestrieb zu bezeichnen. In Das Unbehagen in der Kultur von 1930 werden die beiden Triebgruppen als „Eros“ (oder „Lebenstrieb“) und als „Todestrieb“ bezeichnet. „Destruktionstrieb“ wird hier als Synonym für den Todestrieb verwendet; „Aggressionstrieb“ ist hier die Bezeichnung für einen Abkömmling des Todestriebs, nämlich den nach außen gerichteten Todestrieb. In der Neuen Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse von 1933 stellt er die „Sexualtriebe“ (oder den „Eros“ oder die „erotischen Triebe“) den „Aggressionstrieben“ (oder dem „Todestrieb“) gegenüber; auch hier wird der Ausdruck „Lebenstrieb“ nicht verwendet. Im Abriss der Psychoanalyse von 1939/1940 spricht er vom „Eros“ (oder „Liebestrieb“) im Gegensatz zum „Destruktionstrieb“. Immer verwendet er den Singular und den Plural nebeneinanderher, beispielsweise spricht er nicht nur von den „Todestrieben“, sondern auch vom „Todestrieb“. Auch mit dem Singular-Ausdruck ist immer eine Triebgruppe oder Triebart gemeint. |
本能の用語 『快楽原則の彼方』で提示された二元的な本能の概念は、フロイトが亡くなるまで維持された。しかし、その用語は変動している。 1920年の『快楽原則の彼方』では、2つの本能群は「生命本能」(または「エロス」)と「死本能」と呼ばれている。 1923年の『自我とイド』では、フロイトは「性衝動」(または「エロス」)を「死の衝動」と対比して述べている。この著作では「生命衝動」という表現は 使用されていない。ここで「破壊衝動」という用語は、性衝動の影響を受けて外界に向けられる死の衝動を指すために使用されている。 1930年の『文化の不安』では、2つの本能群は「エロス」(または「生命本能」)と「死の本能」と呼ばれている。「破壊本能」はここでは死の本能の同義語として使用されており、「攻撃本能」は死の本能の派生、すなわち外向きの死の本能を指す用語である。 1933年の『精神分析入門新講』では、「性衝動」(または「エロス」あるいは「エロティック衝動」)を「攻撃衝動」(または「死の衝動」)と対比している。ここでも「生命衝動」という表現は使用されていない。 1939/1940年の『精神分析の概要』では、彼は「エロス」(または「愛欲本能」)を「破壊本能」と対比して述べている。 彼は常に単数形と複数形を並行して使用しており、例えば「死の衝動」だけでなく「死の衝動」とも述べている。単数形でも、常に衝動のグループまたは衝動の種類を意味している。 |
| Metapsychologie An verschiedenen Stellen der Abhandlung entwickelt Freud ein Modell der Funktionsweise des Psychischen, des „psychischen Apparats“, wie er sagt. Freud nennt dieses Modell seine Metapsychologie. Sie verbindet drei Gesichtspunkte: Der psychische Apparat wird als ein Gebilde begriffen, das aus mehreren Systemen (oder Instanzen) besteht, dem Bewusstsein („System Bw“), dem Vorbewussten („System Vbw“) und dem Unbewussten („System Ubw“). Die Beziehungen zwischen diesen Systemen werden durch ein räumliches Modell dargestellt. Freud nennt dies den „topischen“, also räumlichen Gesichtspunkt. Im System gibt es Kräfte, die Triebe, zwischen denen konflikthafte Beziehungen bestehen. Dies ist der dynamische Gesichtspunkt, also die Beschreibung, die sich auf die Kräfte bezieht. Die Erregungsvorgänge im Apparat beruhen auf einer Energie, die sich quantifizieren lässt und die vermehrt und vermindert werden kann. Dieser Gesichtspunkt wird von Freud als „ökonomisch“ bezeichnet. Bei der Darstellung des Modells knüpft er an seinen Entwurf einer Psychologie von 1895 an sowie an das Kapitel Zur Psychologie der Traumvorgänge aus seiner Traumdeutung von 1900. Das Modell wird von Freud ausdrücklich als Spekulation bezeichnet. Freud stellt sich vor, dass der psychische Apparat durch die in ihm stattfindenden Erregungsabläufe bestimmt wird. Insgesamt hat der Apparat die Tendenz, die in ihm enthaltene Erregungsmenge möglichst gering zu halten oder wenigstens konstant zu halten, und in ebendieser Tendenz besteht das Lustprinzip. Die Tendenz in Richtung auf eine gleichbleibende Erregungsmenge wird von Freud als Konstanzprinzip bezeichnet. Die Strebung, die Erregungsmenge auf Null zurückzuführen, bezeichnet er mit einem Ausdruck der englischen Psychoanalytikerin Barbara Low als Nirwanaprinzip. Für das Konstanzprinzip beruft sich Freud auf Fechners Prinzip der Tendenz zur Stabilität. Das Nirwanaprinzip entspricht der Tendenz des Todestriebs, einen anorganischen Zustand wiederherzustellen. Die Erregungen existieren im Apparat in zwei unterschiedlichen Energieformen, als „freie“ und als „gebundene“ Energie. Der Unterschied bezieht sich auf die Art der Energieabfuhr. Die freie Energie hat strömenden Charakter, sie drängt nach sofortigem Abfluss. Die ruhende bzw. gebundene Energie hingegen kann gespeichert werden, das Streben nach Abfuhr ist hier gering. Veränderungen der freien Energie werden vom Ich als Lust oder Unlust wahrgenommen. Wenn die freie Energie sich verringert, wenn sie also so abfließen kann, wie es dem Konstanz- oder Nirwanaprinzip entspricht, wird dies vom Ich als Lust empfunden. Wenn die Quantität der freien Energie zunimmt, wenn ihre natürliche Abflusstendenz also gehemmt ist, wird dies als funktionswidrig erlebt und hierdurch entsteht im Ich das Unlustgefühl. Nur ein geringer Teil der Unlust beruht auf dem Realitätsprinzip, also auf dem Akzeptieren von Unlust als Umweg zur Lust. Eine intensivere Quelle der Unlust ist die Spaltung des psychischen Apparats in das verdrängende Ich einerseits und die verdrängten Triebe andererseits. Gelingt es den verdrängten Trieben, auf gewissen Umwegen doch noch zu einer Befriedigung zu kommen, so wird dies vom Ich als Unlust empfunden. Das Lustprinzip ist in diesem Fall durchbrochen worden – allerdings durch das Lustprinzip, nämlich dadurch, dass es verdrängten Trieben gelungen ist, Lust zu gewinnen. „[S]icherlich ist alle neurotische Unlust von solcher Art, ist Lust, die nicht als solche empfunden werden kann“ (S. 220). Diese Art der Unlust kann also im Rahmen des Lustprinzips gedeutet werden. Insgesamt stellt Freud sich den psychischen Apparat wie ein Bläschen vor, das aus verschiedenen Systemen zusammengesetzt ist. An der Außenseite liegen Bewusstsein und Wahrnehmung – das „System Bw“; darunter liegt das Vorbewusste („System Vbw“), bewusstseinsfähige, aber nicht aktuell bewusste Vorstellungen, und noch tiefer liegt das Unbewusste („System Ubw“). Das Bewusstsein unterscheidet sich von den anderen beiden Systemen des Apparats, dem Vorbewussten und dem Unbewussten, dadurch, dass Erregungen in ihm keine dauerhaften Veränderungen hinterlassen, keine Erinnerungsspuren. (Die Frage, wie sich das von Freud schon früher eingeführte „System Bw“ zum neu eingeführten Ich verhält, das wesentlich unbewusst ist, wird in dieser Arbeit nicht geklärt; Freud verwendet beide Beschreibungen nebeneinander.) Das Bewusstseinssystem wird durch Reize in Erregung versetzt, die ihm aus zwei Quellen zuströmen, aus der Außenwelt und aus dem Inneren des Apparats. Die äußerste Oberfläche des Bläschens, noch über dem System Bw, besteht aus dem „Reizschutz“. Der psychische Apparat kann nur mit kleinen Erregungsmengen arbeiten, und der Reizschutz hat die Aufgabe, die Quantität der von außen kommenden Erregungen zu reduzieren. Eine der Formen des Reizschutzes ist die Angstbereitschaft. Sie sorgt im Falle einer Gefahr dafür, dass die den Reiz aufnehmenden Systeme mit gebundener Energie „überbesetzt“ werden; dieses Mehr an gebundener Energie ist in der Lage, die von außen kommenden Energien in ruhende Energie umzuwandeln, zu „binden“. Von außen kommende Erregungen, die stark genug sind, den Reizschutz zu durchbrechen, werden von Freud als „traumatisch“ bezeichnet. Durch sie wird der gesamte seelische Apparat mit einer übergroßen Erregungsmenge überschwemmt. Um sie zu bewältigen, wird das Lustprinzip vorübergehend außer Kraft gesetzt und der Apparat konzentriert sich auf eine Aufgabe, die grundlegender ist als Lustgewinnung und Unlustvermeidung, auf die „Bindung“ der eingebrochenen Reizmengen. Die traumatische Neurose beruht auf einem Durchbrechen des Reizschutzes; Ursache war das Fehlen von Angstbereitschaft. Die Unfallträume versuchen, die Reizbewältigung nachzuholen, und zwar dadurch, dass die Wiederholung jetzt mit Angstentwicklung verbunden wird, deren Fehlen ja zur traumatischen Neurose geführt hatte. Träume dieser Art dienen also nicht der Wunscherfüllung, wie alle übrigen Träume (nach der Hypothese der „Traumdeutung“); sie gehorchen vielmehr dem Wiederholungszwang, der ursprünglicher ist als das Lustprinzip. Hauptquelle für die von innen stammenden Erregungen sind die Triebe. Die von ihnen ausgehenden Erregungen gehören zum Typ der frei beweglichen, nach sofortiger Abfuhr drängenden Energie. Diese Erregungen werden vom Bewusstsein als Lust und Unlust empfunden. In Richtung auf die von innen kommenden Trieberregungen verfügt der Apparat über keinerlei Reizschutz. Dieser Mangel führt zu Störungen, die denen der extern verursachten traumatischen Neurosen gleichzustellen sind. Der Apparat behilft sich, indem er von innen kommende starke Erregungen so behandelt, als ob sie von außen kämen; dies macht es möglich, den Reizschutz gegen sie einzusetzen. Diese Art der Abwehr ist die Projektion, ein Mechanismus, der bei der Entstehung pathologischer Prozesse eine beträchtliche Rolle spielt. |
メタ心理学 この論文のさまざまな箇所で、フロイトは精神の機能、すなわち彼が「精神装置」と呼ぶもののモデルを展開している。フロイトはこのモデルを「メタ心理学」と呼んでいる。このモデルは 3 つの観点を結びつけている。 精神装置は、意識(「システム Bw」)、前意識(「システム Vbw」)、無意識(「システム Ubw」)という複数のシステム(またはインスタンス)から構成される構造として理解される。これらのシステム間の関係は、空間的なモデルによって表現さ れる。フロイトはこれを「トピック的」、つまり空間的な視点と呼んでいる。 システム内には、対立関係にある力、つまり本能がある。これは動的な観点、つまり力に関する記述だ。 装置内の興奮過程は、定量化可能で、増減可能なエネルギーに基づいている。この観点は、フロイトによって「経済的」と表現されている。 このモデルの表現において、フロイトは1895年の『心理学の草案』および1900年の『夢の解釈』の「夢のプロセスに関する心理学」の章に言及している。フロイトは、このモデルを「推測」と明確に述べている。 フロイトは、精神機構は、その内部で起こる興奮過程によって決定されると考えている。全体として、この機構は、その内部にある興奮の量をできるだけ少な く、あるいは少なくとも一定に保つ傾向があり、この傾向こそが快楽原則である。興奮の量を一定に保つ傾向を、フロイトは「恒常性原則」と呼んでいる。興奮 の量をゼロに戻そうとする傾向を、フロイトは英国の精神分析医バーバラ・ロウの表現を用いて「ニルヴァーナ原理」と呼んでいる。恒常性原理については、フ ロイトはフェヒナーの安定傾向の原理を引用している。ニルヴァーナ原理は、無機的な状態に戻ろうとする死の衝動の傾向に相当する。 興奮は、装置内に「自由」エネルギーと「結合」エネルギーという 2 種類のエネルギー形態で存在する。この違いは、エネルギーの放出の性質による。自由エネルギーは流動性があり、すぐに放出される傾向がある。一方、静止ま たは結合エネルギーは蓄積することができ、放出への傾向は低い。 自由エネルギーの変化は、自我によって快または不快として知覚される。自由エネルギーが減少し、つまり、恒常性またはニルヴァーナ原理に従って放出される 場合、これは自我によって快として知覚される。自由エネルギーの量が増加し、その自然な流出傾向が阻害されると、これは機能不全として認識され、自我に不 快感が生じる。 不快感のほんの一部は、現実の原則、つまり快楽への回り道として不快感を受け入れることに基づいている。不快のより強い源は、精神機構が、抑圧する自我と 抑圧された本能とに分裂していることだ。抑圧された本能が、ある迂回経路を経て、結局満足に達した場合、これは自我によって不快として認識される。この場 合、快楽原則は破られたことになるが、それは快楽原則によって、つまり抑圧された衝動が快楽を得ることに成功したことによって破られたのだ。「確かに、す べての神経症的な不快感は、そのように感じられない快楽である」(220ページ)。したがって、この種の不快感は、快楽原則の枠内で解釈することができ る。 全体として、フロイトは精神機構を、さまざまなシステムで構成される泡のようなものと想像している。外側には意識と知覚、すなわち「Bw システム」があり、その下には前意識(「Vbw システム」)、意識可能だが現時点では意識されていない観念があり、さらにその下には無意識(「Ubw システム」)がある。意識は、装置の他の 2 つのシステム、前意識と無意識とは、刺激が永続的な変化や記憶の痕跡を残さないという点で異なる。(フロイトが以前に導入した「Bw システム」と、主に無意識である新たに導入された「自我」との関係については、この論文では明らかにされていない。フロイトは、この2つの記述を並行して 使用している。) 意識システムは、外界と装置の内部という2つの源から流入する刺激によって興奮状態になる。気泡の最外層、Bwシステムの上には、「刺激防御」がある。精 神装置は、ごくわずかな興奮量でしか機能しないため、刺激保護は、外部から入ってくる刺激の量を減らす役割を果たしている。刺激保護の一形態は、恐怖心で ある。恐怖心は、危険が発生した場合に、刺激を受け取るシステムに結合エネルギーが「過剰に供給」されるようにする。この余剰の結合エネルギーは、外部か ら入ってくるエネルギーを静止エネルギーに変換し、「結合」する働きがある。 刺激防御を突破するほど強い外部からの刺激は、フロイトによって「トラウマ」と呼ばれている。トラウマによって、精神機構全体が過剰な刺激で溢れかえる。 それを克服するために、快楽原則は一時的に無効になり、精神機構は快楽の獲得や不快の回避よりもより基本的な課題、すなわち侵入した刺激の「結合」に集中 する。 トラウマ性神経症は、刺激の防御が破られたことに起因する。その原因は、恐怖心がないことだった。事故の夢は、刺激の克服を補おうとするもので、その繰り 返しは、トラウマ的な神経症の原因となった恐怖の発生と結びついている。この種の夢は、他のすべての夢(「夢の解釈」の仮説による)のように願望の実現の ためではなく、快楽原則よりも根源的な反復強迫に従っている。 内面から生じる興奮の主な源は、本能だ。本能から生じる興奮は、自由に動き、即座に発散されるエネルギーの一種だ。この興奮は、意識によって快楽や不快感として感じられる。 内面から生じる本能の興奮に対して、装置は刺激を遮断する機能を持っていない。この欠如は、外部から引き起こされる外傷性神経症と同等の障害を引き起こ す。この装置は、内から生じる強い刺激を、外部から生じたものとして扱うことで対応している。これにより、刺激に対する防御機能を発揮することができる。 この種の防御は投影であり、病的なプロセスの発生に重要な役割を果たすメカニズムである。 |
| Einordnung Die in Jenseits des Lustprinzips entwickelte Konzeption wird von Freud in Das Ich und das Es von 1923 weiterentwickelt. Er entwirft hier ein neues topisches, also räumliches Modell über die Funktionsweise des psychischen Apparats. Das Modell kombiniert die Auffassung vom Ich als einer teilweise unbewussten verdrängenden Instanz aus Jenseits des Lustprinzips mit der älteren Auffassung vom psychischen Apparat als Verbindung der drei Systeme Wahrnehmung-Bewusstsein, Vorbewusstes und Unbewusstes. Das System Wahrnehmung-Bewusstsein ist demnach der Kern des Ichs; in Jenseits des Lustprinzips hingegen hieß es, der Kern des Ichs sei unbewusst. Das Vorbewusste wird in Das Ich und das Es als Teil des Ichs dargestellt, mit einer unscharfen Grenze zum Es. Aus dem Ich differenziert sich eine weitgehend unbewusste Instanz aus, das Über-Ich. In einer späteren Arbeit, Der Humor von 1927, wird das Über-Ich als Kern des Ichs bezeichnet. Auch die in Jenseits des Lustprinzips vorgestellte Hypothese über den Gegensatz von Lebens- und Todestrieben wird in Das Ich und das Es weiter ausgearbeitet; später bildet sie eine Grundlage von Freuds Abhandlung Das Unbehagen in der Kultur (1930). Laut Fritz Wittels, dem ersten Biographen Freuds, sei die Schrift durch den Tod seiner Tochter Sophie Halberstadt mitveranlasst worden, die 1920 starb und nur 27 Jahre alt wurde; eine Aussage, mit der Freud selbst nicht einverstanden war,[2] sowie auch vor dem Hintergrund der grausamen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs zu sehen. Die Urfassung der Schrift stammt aber nach neueren Erkenntnissen bereits aus dem Frühjahr 1919, so dass der Tod der Tochter keine Rolle gespielt haben kann.[3] Mit Blick auf die biologische Spekulation in Jenseits des Lustprinzips ist ferner auf die Rolle einer von Freud und Sándor Ferenczi anvisierten aber nie vollendeten "Bioanalyse" verwiesen worden, der zufolge psychoanalytische Begriffe und Methoden konsequent auf die Naturwissenschaften zu übertragen seien.[4] |
分類 快楽原則の彼方で開発された概念は、1923年の『自我とイド』でフロイトによってさらに発展した。ここでは、彼は精神機構の機能に関する新しいトピック 的、つまり空間的なモデルを考案している。このモデルは、『快の原則の彼方』における、部分的に無意識の抑圧機関としての自我の概念と、3つのシステム、 すなわち知覚・意識、前意識、無意識の結合としての精神機構という従来の概念を融合したものだ。 したがって、知覚・意識のシステムは自我の核心であり、一方、『快の原則の彼方』では、自我の核心は無意識であるとされていました。 前意識は、『自我とイド』では、自我の一部として、イドとの境界が曖昧なものとして描かれています。 自我から、大部分が無意識の機関である超自我が分化します。後の著作『ユーモア』 (1927) では、超自我が自我の核心であると述べられている。 『快楽原則の超越』で提示された、生と死の衝動の対立に関する仮説も、『自我とイド』でさらに詳しく考察され、後にフロイトの論文『文明と不安』 (1930) の基礎となった。 フロイトの最初の伝記作家であるフリッツ・ヴィッテルスによると、この著作は、1920年に27歳の若さで亡くなった娘ソフィー・ハルバーシュタットの死 がきっかけとなったとされていますが、フロイト自身はこれを否定しており[2]、第一次世界大戦の残酷な経験も背景にあると考えられます。しかし、最新の 知見によると、この著作の原稿は1919年の春にすでに執筆されていたため、娘の死は影響を与えていないと考えられる[3]。 快楽原則の彼方における生物学的推測に関しては、フロイトとサンドール・フェレンツィが構想したが、完成には至らなかった「生物分析」の役割も指摘されている。この分析では、精神分析の概念と手法は、自然科学に一貫して適用されるべきであるとされている[4]。 |
| Ausgaben Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig, Wien und Zürich 1920 (Erstdruck), 2. überarbeitete Auflage 1921, 3. überarb. Auflage 1923 In: Ders.: Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Bd. 13. Hg. v. Marie Bonaparte unter Mitarbeit von Anna Freud. Imago, London 1940, S. 1–69 In: Ders.: Studienausgabe, Bd. 3: Psychologie des Unbewußten. Hg. v. Alexander Mitscherlich, Angela Richards, James Strachey. Fischer, Frankfurt a. M. 2000, ISBN 3108227033, S. 213–272 (mit editorischer Vorbemerkung, Anmerkungen zur Entwicklung von Freuds Begrifflichkeit und Nachweis der Veränderungen in den verschiedenen Auflagen) |
出版 ジークムント・フロイト『快楽原則の彼方』 国際精神分析出版社、ライプツィヒ、ウィーン、チューリッヒ、1920年(初版)、1921年改訂第2版、1923年改訂第3版 同著『全集。年代順』第13巻、マリー・ボナパルト編、アンナ・フロイト協力、イマゴ、ロンドン、1940年、1-69ページ 同著『研究版』第3巻『無意識の心理学』、アレクサンダー・ミッチェルリッヒ、アンジェラ・リチャーズ、ジェームズ・ストラチェイ編、 フィッシャー、フランクフルト・アム・マイン、2000年、ISBN 3108227033、213-272 ページ(編集者による序文、フロイトの用語の発展に関する注釈、各版における変更の証明付き) |
| Einzelnachweise Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips. In: Ders.: Studienausgabe Bd. 3: Psychologie des Unbewußten. Fischer, Frankfurt a. M. 2000, S. 251; nach dieser Ausgabe wird im folgenden zitiert. Vgl. dazu: Elisabeth Roudinesco und Michel Plon: Dictionnaire de la Psychanalyse. (1997). Aus dem Französischen übersetzt von: Christoph Eissing-Christophersen u. a.: Wörterbuch der Psychoanalyse. Springer, Wien 2004, S. 495 f, ISBN 3-211-83748-5 Ulrike May: Der dritte Schritt in der Trieblehre. Zur Entstehungsgeschichte von Jenseits des Lustprinzips. In: Luzifer-Amor. Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse, Heft 51 (26. Jg. 2013), S. 92 ff. Jenny Willner: Neurotische Evolution: Bioanalyse als Kulturkritik in »Jenseits des Lustprinzips«. In: PSYCHE. Band 74, Nr. 11, November 2020, ISSN 0033-2623, S. 895–921, doi:10.21706/ps-74-11-895 (klett-cotta.de [abgerufen am 23. Oktober 2021]). |
参考文献 ジークムント・フロイト:快の原則を超えて。同著:研究版第 3 巻:無意識の心理学。フィッシャー、フランクフルト・アム・マイン、2000 年、251 ページ。以下、この版を引用する。 参照:エリザベス・ルディネスコ、ミシェル・プロン:Dictionnaire de la Psychanalyse(精神分析辞典)。(1997)。フランス語から翻訳:クリストフ・アイシング・クリストファーセンほか:『精神分析辞典』。ス プリンガー、ウィーン、2004 年、495 ページ以降、ISBN 3-211-83748-5 ウルリケ・メイ:『本能説の第三段階。快の原則の向こう側』の成立史について。ルツィファー・アモール。精神分析の歴史に関する雑誌、第 51 号(2013 年第 26 年)、92 ページ以降。 ジェニー・ウィラー:神経症的進化:「快楽原則の彼方」における文化批判としての生物分析。PSYCHE。第 74 巻、第 11 号、2020 年 11 月、ISSN 0033-2623、895–921 ページ、doi:10.21706/ps-74-11-895 (klett-cotta.de [2021 年 10 月 23 日閲覧])。 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Jenseits_des_Lustprinzips |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆