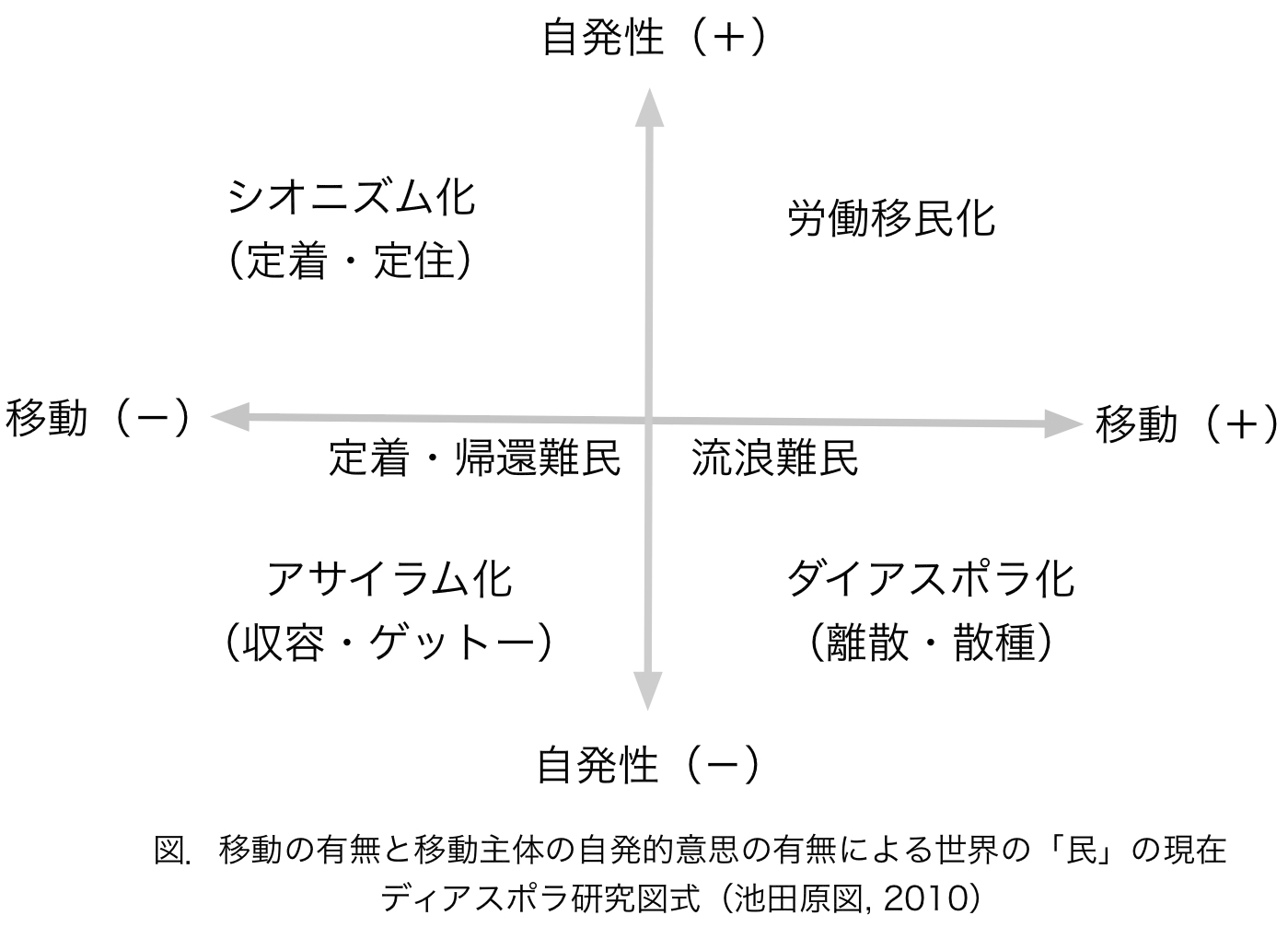
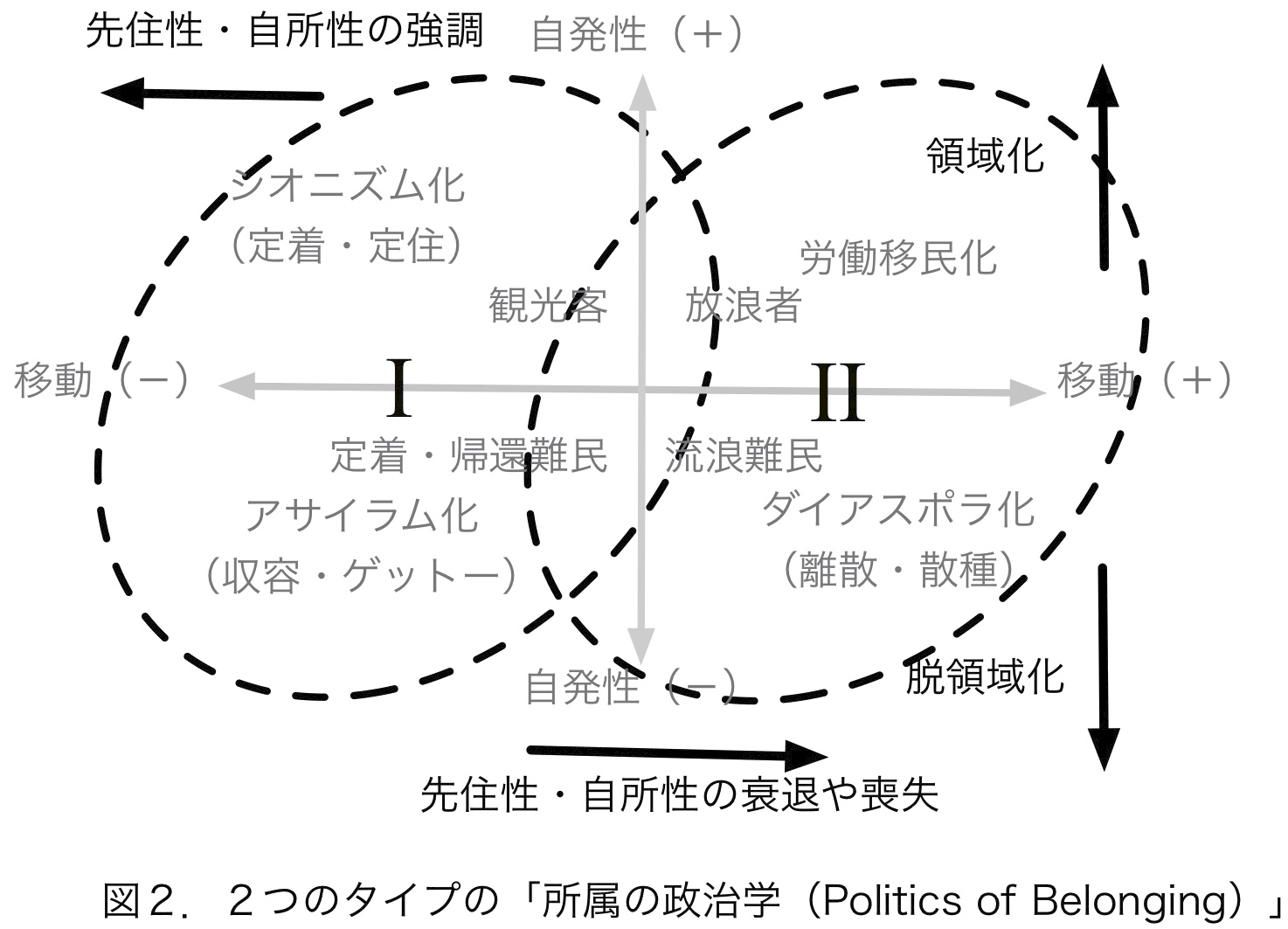
ディアスポラ・スタディーズ
Diaspora studies
☆ ディ アスポラ学とは、20世紀後半に確立された学問分野であり、分散した民族集団を研究するもので、しばしばそれはディアスポラ民族と呼ばれる。ディアスポラ という言葉には、追放、強制、奴隷制、人種差別、戦争(特に民族主義的紛争)などによる強制移住という意味合いが含まれている。
★「ディアスポラとは散種を意味するギリシャ語に由来するが、ユダヤ人のように民族が離散してばらばらになる状況のことをそのように言う」
| ★Diaspora
studies is an academic field established in the late 20th century
to
study dispersed ethnic populations, which are often termed diaspora
peoples. The usage of the term diaspora carries the connotation of
forced resettlement, due to expulsion, coercion, slavery, racism, or
war, especially nationalist conflicts. |
ディ
アスポラ学とは、20世紀後半に確立された学問分野であり、分散した民族集団を研究するもので、しばしばそれはディアスポラ民族と呼ばれる。ディアスポラ
という言葉には、追放、強制、奴隷制、人種差別、戦争(特に民族主義的紛争)などによる強制移住という意味合いが含まれている。 |
| The
International Institute for Diasporic and Transcultural Studies (IIDTS)
— a transnational institute incorporating Jean Moulin University
(Lyons, France), the University of Cyprus, Sun Yat-sen University
(Guangzhou, China) and Liverpool Hope University (UK) — is a dedicated
research network operating in a transdisciplinary logic and focused on
cultural representation (and auto-representation) of diasporic
communities throughout the world. The institute sponsors the trilingual
publication Transtext(e)s-Transcultures: A Journal of Global Cultural
Studies.[1] Nehru University's School of International Studies, www.jnu.ac.in[permanent dead link] has a strong research programme, DIMP (Diaspora and International Programme) and its faculty run a network www.odi.in (Organisation for Diaspora Initiatives), an international network of higher academic researchers focused on studying Diaspora from International Perspective and examining diaspora as a resource in international relations. ODI publishes a research journal www.tandfonline/rdst[permanent dead link] with Routledge, London. Golong Gilig Institute of Javanese Diaspora Studies, Indonesia. |
ジャン・ムーラン大学(フランス・
リヨン)、キプロス大学、中山大学(中国・広州)、リバプール・ホープ大学(英国)が参加するトランスナショナルな研究所であるディアスポラ・トランスカ
ルチュラル・スタディーズ国際研究所(IIDTS)は、学際的な論理で運営され、世界中のディアスポラ・コミュニティの文化的表象(および自己表象)に焦
点を当てた専門的な研究ネットワークである。同研究所は、3ヶ国語で出版される『Transtext(e)s-Transcultures』を後援してい
る: 『グローバル文化研究ジャーナル』[1]。 ネルー大学国際学部は、強力な研究プログラムであるDIMP(Diaspora and International Programme)を有し、その教員はネットワークwww.odi.in(Organisation for Diaspora Initiatives)を運営している。このネットワークは、国際的な視点からディアスポラを研究し、国際関係における資源としてのディアスポラを検討 することに焦点を当てた高等学術研究者の国際ネットワークである。ODIはロンドンのRoutledge社から研究ジャーナル を発行している。 Golong Gilig Institute of Javanese Diaspora Studies(ジャワ・ディアスポラ研究所)、インドネシア。 |
| Hall,
Stuart (1990). "Cultural Identity and
Diaspora.(pdf)" From Jonathan
Rutherford, e.d, Identity: Community, Culture, and Difference (Lawrence
& Wishart), pp. 222-37. https://en.wikipedia.org/wiki/Diaspora_studies |
|
| Diaspora
politics
is the political behavior of transnational ethnic diasporas, their
relationship with their ethnic homelands and their host states, and
their prominent role in ethnic conflicts.[1] The study of diaspora
politics is part of the broader field of diaspora studies. To understand a diaspora's politics, one must first understand its historical context and attachments.[2] A diaspora is a transnational community that defined itself as a singular ethnic group based upon its shared identity. Diasporas result from historical emigration from an original homeland. In modern cases, this migration can be historically documented, and the diaspora associated with a certain territory. Whether this territory is in fact the homeland of a specific ethnic group, is a political matter. The older the migration, the less evidence there is for the event: in the case of the Romani people the migration, the homeland, and the migration route have not yet been accurately determined. A claim to a homeland always has political connotations and is often disputed. Self-identified diasporas place great importance on their homeland, because of their ethnic and cultural association with it, especially if it has been 'lost' or 'conquered'. That has led ethnic nationalist movements within several diasporas,[example needed] often resulting in the establishment of a sovereign homeland. However, even when they are established, it is rare for the complete diaspora population to return to the homeland, and the remaining diaspora community typically retains significant emotional attachment to the homeland, and the co-ethnic population there. Ethnic diaspora communities are now recognized by scholars as "inevitable" and "endemic" features of the international system, writes Yossi Shain and Tamara Cofman Wittes,[1] for the following reasons: First, within each of a diaspora's host states, resident members can organize domestically to maximize their political clout. Second, a diaspora can exert significant pressure in its homeland's domestic political arena regarding issues of diaspora concern. Lately, a diaspora's transnational community can engage directly with third-party states and international organizations, in effect bypassing its homeland and host state governments. Diasporas are thus perceived as transnational political entities, operating on "behalf of their entire people" and capable of acting independently from any individual state (their homeland or their host states). https://en.wikipedia.org/wiki/Diaspora_politics |
ディ
アスポラ政治とは、国境を越えたエスニック・ディアスポラの政治的行動、彼らのエスニック・ホームランドやホスト国家との関係、そしてエスニック紛争にお
ける彼らの顕著な役割のことである[1]。ディアスポラ政治の研究は、より広範なディアスポラ研究の分野の一部である。 ディアスポラの政治を理解するためには、まずその歴史的背景と愛着を理解しなければならない。ディアスポラは、もともとの祖国からの歴史的な移住によって 生じる。現代の場合、この移住は歴史的に記録され、ディアスポラは特定の領土と関連付けられる。この領土が実際に特定の民族グループの祖国であるかどうか は、政治的な問題である。ロマーニ人の場合、移動、祖国、移動ルートはまだ正確に特定されていない。祖国に対する主張は常に政治的な意味合いを持ち、しば しば論争になる。 自称ディアスポラたちは、祖国が「失われた」あるいは「征服された」場合は特に、その民族的・文化的関連性から、祖国を非常に重視する。そのため、いくつ かのディアスポラでは民族主義運動が起こり[要出典]、その結果、主権を持つ祖国が樹立されることも多い。しかし、ディアスポラが設立されたとしても、 ディアスポラの全人口が祖国に帰還することはまれであり、残されたディアスポラ・コミュニティは通常、祖国やそこに住む同民族に対して大きな感情的愛着を 持ち続けている。 ヨッシ・シャインとタマラ・コフマン・ウィテス[1]は、民族的ディアスポラ・コミュニティは現在、国際システムの「必然的」かつ「風土病的」特徴である と学者たちに認識されている: 第一に、ディアスポラのそれぞれの受け入れ国において、居住メンバーは政治的影響力を最大化するために国内で組織化することができる。 第2に、ディアスポラは、ディアスポラが関心を持つ問題に関して、母国の国内政治舞台で大きな圧力をかけることができる。 最近では、ディアスポラの国境を越えたコミュニティは、事実上、祖国やホスト国政府をバイパスして、第三者国家や国際機関と直接関わることができる。 そのためディアスポラは、「国民全体を代表して」活動し、個々の国家(祖国や受け入れ国)から独立して行動できる、国境を越えた政治的存在として認識され ている。 |
| Cultural Identity and
Diaspora STUART HALL A new cinema of the Caribbean is emerging, joining the company of the other 'Third Cinemas'. It is related to, but different from the vibrant film and other forms of visual representation of the Afro-Caribbean (and Asian) 'blacks' of the diasporas of the West - the new post-colonial subjects. All these cultural practices and forms of representation have the black subject at their centre, putting the issue of cultural identity in question. Who is this emergent, new subject of the cinema? From where does he/she speak? Practices of representation always implicate the positions from which we speak or write - the positions of enunciation. What recent theories of enunciation suggest is that, though we speak, so to say 'in our own name', of ourselves and from our own experience, nevertheless who speaks, and the subject who is spoken of, are never identical, never exactly in the same place. Identity is not as transparent or unproblematic as we think. Perhaps instead of thinking of identity as an already accomplished fact, which the new cultural practices then represent, we should think, instead, of identity as a 'production', which is never complete, always in process, and always constituted within, not outside, representation. This view problematises the very authority and authenticity to which the term, 'cultural identity', lays claim. |
文化的アイデンティティとディアスポラ スチュアート・ホール カリブ海の新しい映画が、他の「第3の映画」の仲間入りをしつつある。それは、欧米のディアスポラ、つまりポストコロニアルの新たな主体であるアフロ・カ リビアン(そしてアジアの)「黒人」の活気に満ちた映画やその他の映像表現形式と関連はあるが、それとは異なる。これらの文化的実践や表現形式はすべて、 黒人の主体を中心に据えており、文化的アイデンティティの問題を突きつけている。映画の新たな主体とは誰なのか?彼/彼女はどこから語っているのか?表象 の実践は常に、私たちが話したり書いたりする立場、つまり発音の立場に関係している。最近の発音の理論が示唆するのは、私たちは、いわば「自分の名前 で」、自分自身について、また自分自身の経験から語るが、それにもかかわらず、語る者と語られる主体は決して同一ではなく、同じ場所にいることはないとい うことである。アイデンティティは、私たちが考えているほど透明なものでも、問題のないものでもない。おそらく、アイデンティティをすでに達成された事実 として考え、それを新しい文化的実践が表象するのではなく、代わりに、アイデンティティを「生産」として考えるべきである。この見解は、「文化的アイデン ティティ」という用語が主張する権威と信憑性そのものを問題にしている。 |
| We seek, here, to open a
dialogue, an investigation, on the subject
of cultural identity and representation. Of course, the 'I' who writes
here must also be thought of as, itself, 'enunciated'. We all write and
speak from a particular place and time, from a history and a culture
which is specific. What we say is always 'in context', positioned. I
was born into and spent my childhood and adolescence in a lowermiddle-
class family in Jamaica. I have lived all my adult life in
England, in the shadow of the black diaspora - 'in the belly of the
beast'. I write against the background of a lifetime's work in cultural
studies. If the paper seems preoccupied with the diaspora experience
and its narratives of displacement, it is worth remembering that all
discourse is 'placed', and the heart has its reasons. |
私
たちはここで、文化的アイデンティティと表現というテーマについて、対話と調査を開こうとしている。もちろん、ここに書く「私」は、それ自体が「宣言され
たもの」であるとも考えなければならない。私たちは皆、特定の場所と時間、特定の歴史と文化から書き、話す。私たちの発言は常に「文脈の中で」位置づけら
れる。私はジャマイカの中流以下の家庭で生まれ、幼少期と青年期を過ごした。大人になってからはずっと英国で、黒人のディアスポラの影、つまり「野獣の腹
の中」で暮らしてきた。私は、カルチュラル・スタディーズにおける生涯の仕事を背景に執筆している。本稿がディアスポラ体験とその変遷の物語に夢中になっ
ているように見えたとしても、すべての言説は「配置」されており、心には理由があることを思い出す価値がある。 |
| There are at least two different
ways of thinking about 'cultural
identity'. The first position defines 'cultural identity' in terms of
one,
shared culture, a sort of collective 'one true self', hiding inside the
many other, more superficial or artificially imposed 'selves', which
people with a shared history and ancestry hold in common. Within
the terms of this definition, our cultural identities reflect the
common
historical experiences and shared cultural codes which provide us, as
'one people', with stable, unchanging and continuous frames of
reference and meaning, beneath the shifting divisions and vicissitudes
of our actual history. This 'oneness', underlying all the other,
more superficial differences, is the truth, the essence, of
'Caribbeanness',
of the black experience. It is this identity which a Caribbean or
black diaspora must discover, excavate, bring to light and express
through cinematic representation. |
文
化的アイデンティティ」については、少なくとも2つの異なる考え方がある。最初の立場は、「文化的アイデンティティ」を、歴史と祖先を共有する人々が共通
に持つ、他の多くの、より表面的な、あるいは人為的に押し付けられた「自己」の内側に隠れている、ある種の集団的な「一つの真の自己」である、一つの共有
文化という観点から定義する。この定義に従えば、私たちの文化的アイデンティティは、共通の歴史的経験や共有された文化的規範を反映したものであり、それ
が「ひとつの民族」としての私たちに、実際の歴史の移り変わりや波乱の下にある、安定した、不変の、継続的な参照と意味の枠組みを与えているのである。こ
の "一体性 "こそが、他のあらゆる表面的な違いの根底にある "カリビアンらしさ
"の真実であり、黒人の経験の本質なのである。カリブ海や黒人のディアスポラが発見し、掘り起こし、明るみに出し、映画的表現を通して表現しなければなら
ないのは、このアイデンティティなのだ。 |
| Such a conception of cultural
identity played a critical role in all the
post-colonial struggles which have so profoundly reshaped our world.
It lay at the centre of the vision of the poets of 'Negritude', like
Aimee
Ceasire and Leopold Senghor, and of the Pan-African political project,
earlier in the century. It continues to be a very powerful and
creative force in emergent forms of representation amongst hitherto
marginalised peoples. In post-colonial societies, the rediscovery of
this identity is often the object of what Frantz Fanon once called a
"passionate research ... directed by the secret hope of discovering
beyond the misery of today, beyond self-contempt, resignation and
abjuration, some very beautiful and splendid era whose existence
rehabilitates us both in regard to ourselves and in regard to others."
New forms of cultural practice in these societies address themselves
to this project for the very good reason that, as Fanon puts it, in the
recent past, "Colonisation is not satisfied merely with holding a
people in its grip and
emptying the native's brain of all form and content. By a kind of
perverted logic, it turns to the past of oppressed people, and
distorts,
disfigures and destroys it." The question which Fanon's observation
poses is, what is the nature
of this 'profound research' which drives the new forms of visual and
cinematic representation? Is it only a matter of unearthing that
which the colonial experience buried and overlaid, bringing to light
the hidden continuities it suppressed? Or is a quite different
practice entailed - not the rediscovery but the production of
identity. Not an identity grounded in the archaeology, but in the
re-telling of the past? |
こ
のような文化的アイデンティティの概念は、私たちの世界を大きく変えたポストコロニアル闘争のすべてにおいて、重要な役割を果たした。それは、アイミー・
シーシールやレオポルド・センゴールのような「ネグリチュード」の詩人たちや、今世紀初頭の汎アフリカ政治プロジェクトのビジョンの中心にあった。それ
は、これまで社会から疎外されてきた人々の間に出現した表現形式において、非常に強力で創造的な力を持ち続けている。ポストコロニアル社会では、このアイ
デンティティの再発見は、かつてフランツ・ファノンが「情熱的な研究」と呼んだものの対象となることが多い。これらの社会における文化的実践の新たな形態
が、このプロジェクトに取り組んでいるのは、ファノンが言うように、近年、「植民地化は、単に民衆を掌中に収め、先住民の脳からあらゆる形式と内容を空っ
ぽにするだけでは満足しない。一種の倒錯した論理によって、植民地化は抑圧された人々の過去に目を向け、それを歪め、醜くし、破壊するのである」。ファノ
ンの観察が投げかける疑問は、視覚的・映画的表現の新しい形式を推進するこの「深遠な研究」の本質とは何か、ということである。それは、植民地体験が埋没
させ、重ね合わせたものを発掘し、それが抑圧した隠された連続性を明るみに出すだけの問題なのか。それとも、まったく異なる実践が必要なのだろうか--再
発見ではなく、アイデンティティの生産が。考古学に根ざしたアイデンティティではなく、過去を語り直すことなのか。 |
| We should not, for a moment,
underestimate or neglect the
importance of the act of imaginative rediscovery which this
conception of a rediscovered, essential identity entails. 'Hidden
histories' have played a critical role in the emergence of many of the
most important social movements of our time - feminist,
anti-colonial and anti-racist. The photographic work of a generation
of Jamaican and Rastafarian artists, or of a visual artist like Armet
Francis (a Jamaican-born photographer who has lived in Britain
since the age of eight) is a testimony to the continuing creative
power of this conception of identity within the emerging practices of
representation. Francis's photographs of the peoples of The Black
Triangle, taken in Africa, the Caribbean, the USA and the UK,
attempt to reconstruct in visual terms 'the underlying unity of the
black people whom colonisation and slavery distributed across the
African diaspora.' His text is an act of imaginary reunification. |
こ
の再発見された本質的なアイデンティティの概念が伴う、想像力豊かな再発見という行為の重要性を、私たちは少しも過小評価したり、軽視したりすべきではな
い。隠された歴史」は、フェミニズム、反植民地主義、反人種主義など、現代の最も重要な社会運動の多くにおいて、重要な役割を果たしてきた。ジャマイカや
ラスタファリアンのアーティストの世代や、アーメット・フランシス(ジャマイカ出身で8歳から英国に住む写真家)のようなビジュアル・アーティストの写真
作品は、新たな表象の実践の中で、このようなアイデンティティの概念が創造的な力を持ち続けていることを証明している。アフリカ、カリブ海諸国、アメリ
カ、イギリスで撮影されたフランシスのブラック・トライアングルの人々の写真は、「植民地化と奴隷制がアフリカン・ディアスポラ全体に分散させた黒人の根
底にある統一性」を視覚的に再構築しようと試みている。彼のテキストは、想像上の再統合の行為である。 |
| Crucially, such images offer a
way of imposing an imaginary
coherence on the experience of dispersal and fragmentation, which
is the history of all enforced diasporas. They do this by representing
or 'figuring' Africa as the mother of these different civilisations.
This
Triangle is, after all, 'centred' in Africa. Africa is the name of the
missing term, the great aporia, which lies at the centre of our
cultural identity and gives it a meaning which, until recently, it
lacked. No one who looks at these textural images now, in the light
of the history of transportation, slavery and migration, can fail to
understand how the rift of separation, the 'loss of identity', which
has
been integral to the Caribbean experience only begins to be healed
when these forgotten connections are once more set in place. Such
texts restore an imaginary fullness or plentitude, to set against the
broken rubric of our past. They are resources of resistance and
identity, with which to confront the fragmented and pathological
ways in which that experience has been reconstructed within the
dominant regimes of cinematic and visual representation of the
West. |
重 要なのは、こうしたイメージは、すべての強制されたディアスポラの歴史である離散と分断の経験に、想像上の一貫性を押しつける方法を提供することである。 それは、アフリカをさまざまな文明の母として表象し、「形象化」することによって実現する。この三角形は、結局のところ、アフリカを「中心」としている。 アフリカは、私たちの文化的アイデンティティの中心に位置し、最近まで欠けていた意味を与える、欠落した用語、偉大なるアポリアの名前である。輸送、奴 隷、移住の歴史に照らして、これらのテクストのイメージを今見る者は誰も、カリブ海の経験に不可欠であった分離の裂け目、「アイデンティティの喪失」が、 これらの忘れ去られたつながりが再び定位置に置かれたときに初めて癒され始めることを理解しないはずがない。このようなテキストは、私たちの過去という壊 れたルーブリックに対して、想像上の充足感や豊かさを回復してくれる。それは、西洋の映画や映像表現の支配的な体制の中で、カリブ海の経験が再構築されて きた断片的で病的な方法に立ち向かうための、抵抗とアイデンティティのリソースなのだ。 |
| There is, however, a second,
related but different view of cultural
identity. This second position recognises that, as well as the many
points of similarity, there are also critical points of deep and
significant difference which constitute 'what we really are'; or rather
- since history has intervened - 'what we have become'. We cannot
speak for very long, with any exactness, about 'one experience, one
identity', without acknowledging its other side - the ruptures and
discontinuities which constitute, precisely, the Caribbean's
'uniqueness'.
Cultural identity, in this second sense, is a matter of
'becoming' as well as of 'being'. It belongs to the future as much as
to
the past. It is not something which already exists, transcending
place, time, history and culture. Cultural identities come from
somewhere, have histories. But, like everything which is historical,
they undergo constant transformation. Far from being eternally
fixed in some essentialised past, they are subject to the continuous
'play' of history, culture and power. Far from being grounded in a
mere 'recovery' of the past, which is waiting to be found, and which,
when found, will secure our sense of ourselves into eternity,
identities are the names we give to the different ways we are
positioned by, and position ourselves within, the narratives of the
past. |
し
かし、文化的アイデンティティには、関連してはいるが異なる第二の見方がある。この第二の立場は、多くの類似点だけでなく、「私たちの本当の姿」を構成す
る深く重大な相違点も存在することを認識する。カリブ海の「独自性」を構成する断絶や不連続性というもう一方の側面を認めることなしに、「ひとつの経験、
ひとつのアイデンティティ」について、正確さをもって長く語ることはできない。この第二の意味での文化的アイデンティティは、「存在」すると同時に「なり
つつある」問題である。それは過去と同様に未来に属するものである。場所、時間、歴史、文化を超越してすでに存在しているものではない。文化的アイデン
ティティはどこからか生まれ、歴史を持っている。しかし、歴史的なものすべてがそうであるように、それらは絶え間ない変容を遂げている。本質化された過去
に永遠に固定されるのではなく、歴史、文化、権力の絶え間ない「戯れ」にさらされる。アイデンティティとは、過去の物語によって位置づけられ、過去の物語
の中で自分自身を位置づけるさまざまな方法に、私たちがつける名前なのである。 |
| It is only from this second
position that we can properly
understand the traumatic character of 'the colonial experience'. The
ways in which black people, black experiences, were positioned and
subject-ed in the dominant regimes of representation were the
effects of a critical exercise of cultural power and normalisation. Not
only, in Said's 'Orientalist' sense, were we constructed as different
and other within the categories of knowledge of the West by those
regimes. They had the power to make us see and experience
ourselves as 'Other'. Every regime of representation is a regime of
power formed, as Foucault reminds us, by the fatal couplet,
'power/knowledge'. But this kind of knowledge is internal, not
external. It is one thing to position a subject or set of peoples as
the
Other of a dominant discourse. It is quite another thing to subject
them to that 'knowledge', not only as a matter of imposed will and
domination, by the power of inner compulsion and subjective
con-formation to the norm. That is the lesson - the sombre majesty -
of Fanon's insight into the colonising experience in Black Skin,
White Masks. |
植
民地体験」のトラウマ的性格を正しく理解できるのは、この第二の立場からだけである。支配的な表象体制の中で、黒人が、黒人の経験が、どのように位置づけ
られ、主題化されたかは、文化的権力と正常化の批判的行使の結果であった。サイードの「オリエンタリズム」的な意味においてだけでなく、これらの体制に
よって、私たちは西洋の知識の範疇において、異なるもの、他者として構築された。彼らは、私たち自身を「他者」と見なし、経験させる力を持っていた。フー
コーが思い起こさせるように、あらゆる表象の体制は、「権力/知識」という宿命的な連句によって形成される権力の体制である。しかし、この種の知識は内的
なものであり、外的なものではない。ある主体や民族を支配的な言説の他者として位置づけることは、ひとつのことである。内的な強制と規範への主観的な適合
の力によって、押しつけられた意志と支配の問題としてだけでなく、彼らをその「知識」に服従させることは、まったく別のことなのだ。それこそが、『黒い
肌、白い仮面』における植民地化体験に対するファノンの洞察の教訓であり、厳粛な威厳なのである。 |
| This inner expropriation of
cultural identity cripples and deforms.
If its silences are not resisted, they produce, in Fanon's vivid
phrase,
'individuals without an anchor, without horizon, colourless,
stateless, rootless - a race of angels'.2 Nevertheless, this idea of
otherness as an inner compulsion changes our conception of 'cultural
identity'. In this perspective, cultural identity is not a fixed
essence
at all, lying unchanged outside history and culture. It is not some
universal and transcendental spirit inside us on which history has
made no fundamental mark. It is not once-and-for-all. It is not a fixed
origin to which we can make some final and absolute Return. Of
course, it is not a mere phantasm either. It is something - not a mere
trick of the imagination. It has its histories - and histories have
their
real, material and symbolic effects. The past continues to speak to
us. But it no longer addresses us as a simple, factual 'past', since
our
relation to it, like the child's relation to the mother, is
always-already
'after the break'. It is always constructed through memory, fantasy,
narrative and myth. Cultural identities are the points of
identification, the unstable points of identification or suture, which
are made, within the discourses of history and culture. Not an
essence but a positioning. Hence, there is always a politics of
identity, a politics of position, which has no absolute guarantee in an
unproblematic, transcendental 'law of origin'. |
こ
の文化的アイデンティティの内なる収奪は、不自由と変形をもたらす。その沈黙に抵抗しなければ、ファノンの鮮烈な表現を借りれば、「錨もなく、地平もな
く、無色透明で、無国籍で、根も葉もない、天使のような種族」を生み出すことになる2。
とはいえ、内なる強制としての他者性という考え方は、「文化的アイデンティティ」に対する私たちの概念を変える。この観点では、文化的アイデンティティと
は、歴史や文化の外に横たわる不変の本質ではない。私たちの内側にある普遍的で超越的な精神でもなく、歴史がその根源的な痕跡を残したわけでもない。それ
は一度限りのものではない。私たちが最終的かつ絶対的に帰結できるような、固定された起源でもない。もちろん、単なる幻想でもない。それは何かであり、単
なる想像のトリックではない。過去には歴史があり、歴史には現実的、物質的、象徴的な影響がある。過去は私たちに語りかけ続けている。というのも、私たち
と過去との関係は、子供と母親との関係と同じように、つねに「断絶の後」にあるからである。それは常に、記憶、空想、物語、神話を通して構築される。文化
的アイデンティティとは、歴史と文化の言説の中で作られる、アイデンティティの点であり、アイデンティティの不安定な点、あるいは縫合点である。本質では
なく、位置づけである。それゆえ、アイデンティティの政治学、位置の政治学が常に存在するのであり、それは問題のない超越的な「起源の法則」において絶対
的な保証があるわけではない。 |
| This second view of cultural
identity is much less familiar, and
more unsettling. If identity does not proceed, in a straight,
unbroken line, from some fixed origin, how are we to understand its
formation? We might think of black Caribbean identities as 'framed'
by two axes or vectors, simultaneously operative: the vector of
similarity and continuity; and the vector of difference and rupture.
Caribbean identities always have to be thought of in terms of the
dialogic relationship between these two axes. The one gives us some
grounding in, some continuity with, the past. The second reminds us
that what we share is precisely the experience of a profound
discontinuity: the peoples dragged into slavery, transportation,
colonisation, migration, came predominantly from Africa - and when
that supply ended, it was temporarily refreshed by indentured
labour from the Asian subcontinent. (This neglected fact explains
why, when you visit Guyana or Trinidad, you see, symbolically
inscribed in the faces of their peoples, the paradoxical 'truth' of
Christopher Columbus's mistake: you can find 'Asia' by sailing west,
if you know where to look!) In the history of the modern world, there
are few more traumatic ruptures to match these enforced
separations from Africa - already figured, in the European
imaginary, as 'the Dark Continent'. But the slaves were also from
different countries, tribal communities, villages, languages and gods.
African religion, which has been so profoundly formative in
Caribbean spiritual life, is precisely different from Christian
monotheism in believing that God is so powerful that he can only be
known through a proliferation of spiritual manifestations, present
everywhere in the natural and social world. These gods live on, in an
underground existence, in the hybridised religious universe of
Haitian voodoo, pocomania, Native pentacostalism, Black baptism,
Rastafarianism and the black Saints Latin American Catholicism.
The paradox is that it was the uprooting of slavery and transportation
and the insertion into the plantation economy (as well as the
symbolic economy) of the Western world that 'unified' these peoples
across their differences, in the same moment as it cut them off from
direct access to their past. |
文
化的アイデンティティに関するこの第二の見方は、あまり馴染みがなく、より不安なものである。もしアイデンティティが、ある固定された起源から一直線に、
途切れることなく続いていくものではないとしたら、その形成をどのように理解すればよいのだろうか。カリブ海の黒人のアイデンティティは、類似性と連続性
のベクトルと、差異と断絶のベクトルという、同時に作用する2つの軸やベクトルによって「フレーム化」されていると考えることができるだろう。カリブ海の
アイデンティティは、常にこの2つの軸の対話的関係から考えなければならない。一方は、私たちに過去との連続性という根拠を与えてくれる。奴隷制、輸送、
植民地化、移住に引きずり込まれた人々は、主にアフリカから来たものであり、その供給が終わると、アジア亜大陸からの年季奉公労働者によって一時的にリフ
レッシュされた。(ガイアナやトリニダードを訪れると、クリストファー・コロンブスの過ちの逆説的な「真実」を象徴的に人々の顔に刻まれているのを目にす
るのは、この軽視された事実が理由である。)
近代世界の歴史において、ヨーロッパ人の想像力の中ですでに「暗黒大陸」として描かれていたアフリカからの強制的な分離に匹敵するような、トラウマ的な断
絶はほとんどない。しかし、奴隷たちもまた、異なる国、部族共同体、村、言語、神々から来た人々だった。カリブ海の精神生活に大きな影響を与えたアフリカ
の宗教は、キリスト教の一神教とは異なり、神は非常に強力な存在であり、自然界や社会界のあらゆる場所に存在する、霊的な顕現の拡散によってのみ知ること
ができると信じている。これらの神々は、ハイチのブードゥー教、ポコマニア、先住民のペンタコスタリズム、黒人の洗礼、ラスタファリアニズム、黒人の聖者
ラテンアメリカのカトリシズムなど、ハイブリッド化された宗教世界の地下で生き続けている。逆説的なのは、奴隷制と輸送を根こそぎ奪い、西欧世界のプラン
テーション経済(象徴経済も同様)に組み込まれたことで、これらの民族はその違いを超えて「統一」されたのだが、それは同時に、過去への直接的なアクセス
を断ち切られたことでもある。 |
| Difference, therefore, persists
- in and alongside continuity. To
return to the Caribbean after any long absence is to experience again
the shock of the 'doubleness' of similarity and difference. Visiting
the French Caribbean for the first time, I also saw at once how
different Martinique is from, say, Jamaica: and this is no mere
difference of topography or climate. It is a profound difference of
culture and history. And the difference matters. It positions
Martiniquains and Jamaicans as both the same and different.
Moreover, the boundaries of difference are continually repositioned
in relation to different points of reference. Vis-a-vis the developed
West, we are very much 'the same'. We belong to the marginal, the
underdeveloped, the periphery, the 'Other'. We are at the outer
edge, the 'rim', of the metropolitan world - always 'South' to
someone else's El Norte. |
そ
れゆえ、「差異」は、「連続性」の中に、そして「連続性」と並行して存続している。久しぶりにカリブ海に戻ると、類似点と相違点の「二重性」の衝撃を再び
体験することになる。フランス領カリブ海を初めて訪れたとき、私はマルティニークとジャマイカがいかに違うかを目の当たりにした。これは単なる地形や気候
の違いではなく、文化や歴史の深い違いである。そしてこの違いは重要である。それは、マルティニーク人とジャマイカ人が同じであり、かつ異なる存在である
ということである。さらに、違いの境界線は、異なる参照点との関係において絶えず再配置される。西側先進国から見れば、私たちは非常に「同じ」である。私
たちは周縁部、未開発部、周縁部、「他者」に属している。私たちはメトロポリタン世界の外縁、「縁」に位置し、常に誰かのエル・ノルテに対して「南」にい
る。 |
| At the same time, we do not
stand in the same relation of the
'otherness' to the metropolitan centres. Each has negotiated its
economic, political and cultural dependency differently. And this
'difference', whether we like it or not, is already inscribed in our
cultural identities. In turn, it is this negotiation of identity which
makes us, vis-a-vis other Latin American people, with a very similar
history, different - Caribbeans, les Antilliennes ('islanders' to their
mainland). And yet, vis-a-vis one another, Jamaican, Haitian, Cuban,
Guadeloupean, Barbadian, etc ... |
同
時に、私たちは大都市中心部に対して同じ「他者性」の関係に立っているわけではない。それぞれが経済的、政治的、文化的依存関係を異なる形で交渉してき
た。そしてこの「違い」は、好むと好まざるとにかかわらず、すでに私たちの文化的アイデンティティに刻み込まれている。そして、このアイデンティティの交
渉が、よく似た歴史を持つ他のラテンアメリカの人々-カリブ人、アンティリエンヌ(本土の「島民」)-に対して、私たちを異なる存在にしているのである。
ジャマイカ人、ハイチ人、キューバ人、グアドループ人、バルバドス人などなど。 |
| How, then, to describe this play
of 'difference' within identity?
The common history — transportation, slavery, colonisation - has
been profoundly formative. For all these societies, unifying us across
our differences. But it does not constitute a common origin, since it
was, metaphorically as well as literally, a translation. The
inscription
of difference is also specific and critical. I use the word 'play'
because
the double meaning of the metaphor is important. It suggests, on the
one hand, the instability, the permanent unsettlement, the lack of
any final resolution. On the other hand, it reminds us that the place
where this 'doubleness' is most powerfully to be heard is 'playing'
within the varieties of Caribbean musics. This cultural play' could
not therefore be represented, cinematically, as a simple, binary
opposition - 'past/present', 'them/us'. Its complexity exceeds this
binary structure of representation. At different places, times, in
relation to different questions, the boundaries are re-sited. They
become, not only what they have, at times, certainly been -
mutually excluding categories, but also what they sometimes are -
differential points along a sliding scale. |
で
は、アイデンティティの中にあるこの「違い」の戯れをどう表現すればいいのだろうか。輸送、奴隷制度、植民地化といった共通の歴史は、私たちを大きく形成
してきた。これらすべての社会にとって、違いを超えて私たちを統合するものであった。しかし、それは文字どおりであると同時に比喩的にも翻訳であったた
め、共通の起源を構成するものではない。差異が刻み込まれることは、具体的かつ決定的なことでもある。私が「プレー」という言葉を使ったのは、この比喩の
二重の意味が重要だからである。一方では、不安定さ、恒久的な落ち着きのなさ、最終的な解決の欠如を示唆している。他方で、この「二重性」が最も力強く聞
こえる場所が、カリブ海音楽の多様性の中で「遊ぶ」ことであることを思い出させてくれる。したがって、この「文化的な遊び」は、映画的には「過去/現
在」、「彼ら/私たち」といった単純な二項対立として表現することはできない。その複雑さは、この二元的な表現構造を超えている。異なる場所、時代、異な
る問いに関連して、境界線は再配置される。境界線は、ある時は確かにそうであったもの、つまり相互に排除し合うカテゴリーになるだけでなく、ある時はそう
であったもの、つまりスライドする尺度に沿った微分点にもなる。 |
| One trivial example is the way
Martinique both is and is not
'French'. It is, of course, a department of France, and this is
reflected in its standard and style of life, Fort de France is a much
richer, more 'fashionable' place than Kingston - which is not only
visibly poorer, but itself at a point of transition between being 'in
fashion' in an Anglo-African and Afro-American way - for those who
can afford to be in any sort of fashion at all. Yet, what is
distinctively
'Martiniquais' can only be described in terms of that special and
peculiar supplement which the black and mulatto skin adds to the
'refinement' and sophistication of a Parisian-derived haute couture:
that is, a sophistication which, because it is black, is always
transgressive. |
些
細な例として、マルティニークが「フランス」であると同時に「フランス」でないことが挙げられる。フォート・ド・フランスはキングストンよりもはるかに豊
かで「ファッショナブル」な場所であり、キングストンは目に見えて貧しいだけでなく、英国系アフリカ人とアフロ・アメリカン的な「流行」の過渡期にある。
しかし、「マルティニケ」らしさとは、黒人と混血の肌がパリ由来のオートクチュールの「洗練」と「洗練」に加える、特別で独特な補足という点でしか表現で
きない。 |
| To capture this sense of
difference which is not pure 'otherness',
we need to deploy the play on words of a theorist like Jacques
Derrida. Derrida uses the anomalous 'a' in his way of writing
'difference' - differance - as a marker which sets up a disturbance in
our settled understanding or translation of the word/concept. It sets
the word in motion to new meanings without erasing the trace of its
other meanings. His sense of differance, as Christopher Norris puts
it, thus "remains suspended between the two French verbs 'to differ'
and 'to
defer' (postpone), both of which contribute to its textual force but
neither of which can fully capture its meaning. Language depends on
difference, as Saussure showed ... the structure of distinctive
propositions which make up its basic economy. Where Derrida breaks
new ground ... is in the extent to which 'differ' shades into 'defer'
... the
idea that meaning is always deferred, perhaps to this point of an
endless
supplementarity, by the play of signification." This second sense of
difference challenges the fixed binaries which
stablise meaning and representation and show how meaning is never
finished or completed, but keeps on moving to encompass other,
additional or supplementary meanings, which, as Norris puts it
elsewhere, 'disturb the classical economy of language and
representation'. Without relations of difference, no representation
could occur. But what is then constituted within representation is
always open to being deferred, staggered, serialised. |
こ
の純粋な「他者性」ではない差異の感覚を捉えるためには、ジャック・デリダのような理論家の言葉遊びを導入する必要がある。デリダは「差異」の書き方にお
いて、変則的な「a」、すなわち「difference」を、その言葉/概念の定まった理解や翻訳に乱れを生じさせる目印として用いる。それは、他の意味
の痕跡を消すことなく、新しい意味へと言葉を動かす。クリストファー・ノリスが言うように、彼の言う「差異」は、「『差異を生じる』と『延期する』という
2つのフランス語の動詞の間で宙吊りにされたままである。ソシュールが示したように、言語は差異に依存している。デリダが新境地を開いたの
は、......「差異」が「延期」へと変化する程度においてである。この相違の第二の意味は、意味と表象を安定させる固定された二項対立に挑戦し、意味
が決して完成されたものではなく、他の意味、付加的な意味、補足的な意味を包含するために動き続けていることを示す。差異の関係なしには、表象は成り立た
ない。しかし、表象の中で構成されるものは、常に延期され、時間をずらされ、連続化される可能性がある。 |
| Where, then, does identity come
in to this infinite postponement
of meaning? Derrida does not help us as much as he might here,
though the notion of the 'trace' goes some way towards it. This is
where it sometimes seems as if Derrida has permitted his profound
theoretical insights to be reappropriated by his disciples into a
celebration of formal 'playfulness', which evacuates them of their
political meaning. For if signification depends upon the endless
repositioning of its differential terms, meaning, in any specific
instance, depends on the contingent and arbitrary stop - the necessary
and temporary 'break' in the infinite semiosis of language. This
does not detract from the original insight. It only threatens to do so
if
we mistake this 'cut' of identity - this positioning, which makes
meaning possible - as a natural and permanent, rather than an
arbitrary and contingent 'ending' - whereas I understand every such
position as 'strategic' and arbitrary, in the sense that there is no
permanent equivalence between the particular sentence we close,
and its true meaning, as such. Meaning continues to unfold, so to
speak, beyond the arbitrary closure which makes it, at any moment,
possible. It is always either over- or under-determined, either an
excess or a supplement. There is always something 'left over'. |
で
は、この意味の無限の先送りに、アイデンティティはどこから入ってくるのだろうか。デリダはここで、「痕跡」という概念にいくらかの道筋をつけてはいる
が、彼 が期待するほどには我々を助けてはくれない。デリダがその深遠な理論的洞察を弟子たちによって形式的な「戯れ」の賛美へと再
流用することを許してしまったかのように思えることがある。意味づけが、その微分項の終わりなき再配置に依存しているのであれば、意味づけは、
いかなる具体例においても、偶発的かつ恣意的な停止、すなわち言語の無限のセミオシ
スにおける必要かつ一時的な「断絶」に依存しているのである。これは本来の洞察を損なうものではない。もし私たちが、このアイデンティティの「切れ目」-
-意味を可能にするこの位置づけ--を、恣意的で偶発的な「終わり」ではなく、自然で永続的なものだと誤解するなら、そうなる恐れがあるだけである。一
方、私は、私たちが閉じる特定の文とその真の意味との間には永続的な等価性がないという意味で、このような位置づけはすべて「戦略的」で恣意的なものだと
理解している。意味は、それを可能にする恣意的な閉じ方を超えて、いわば展開し続ける。それは常に過不足であり、過剰か補足のどちらかである。常に何かが
「余っている」のである。 |
| It is possible, with this
conception of 'difference', to rethink the
positionings and repositionings of Caribbean cultural identities in
relation to at least three 'presences', to borrow Aimee Cesaire's and
Leopold Senghor's metaphor: Presence Africaine, Presence
Europeenne, and the third, most ambiguous, presence of all - the
sliding term, Presence Americain. Of course, I am collapsing, for the
moment, the many other cultural 'presences' which constitute the
complexity of Caribbean identity (Indian, Chinese, Lebanese etc). I
mean America, here, not in its 'first-world' sense - the big cousin to
the North whose 'rim' we occupy, but in the second, broader sense:
America, the 'New World', Terra Incognita. |
こ
の「差異」の概念によって、カリブ海の文化的アイデンティティの位置づけと再配置を、エイミー・セゼールとレオポルド・センゴールの比喩を借りれば、少な
くとも3つの「プレゼンス」との関係で再考することが可能になる:
プレゼンス・アフリケーヌ」、「プレゼンス・ヨーロッパ」、そして3つ目の、最も曖昧な「プレゼンス」である「プレゼンス・アメリケーヌ」である。もちろ
ん、私はカリブ海のアイデンティティの複雑さを構成する他の多くの文化的「プレゼンス」(インド人、中国人、レバノン人など)をひとまず崩壊させている。
私がここで言うアメリカとは、「第一世界」の意味でのアメリカ、つまり私たちが「縁」を占める北の大きないとこではなく、第二の、より広い意味でのアメリ
カである: アメリカ、「新世界」、テラ・インコグニタ。 |
| Presence Africaine is the site
of the repressed. Apparently silenced
beyond memory by the power of the experience of slavery, Africa was,
in fact present everywhere: in the everyday life and customs of the
slave quarters, in the languages and patois of the plantations, in
names
and words, often disconnected from their taxonomies, in the secret
syntactical structures through which other languages were spoken, in
the stories and tales told to children, in religious practices and
beliefs,
in the spiritual life, the arts, crafts, musics and rhythms of slave
and
post-emancipation society. Africa, the signified which could not be
represented directly in slavery, remained and remains the unspoken,
unspeakable 'presence' in Caribbean culture. It is 'hiding' behind
every verbal inflection, every narrative twist of Caribbean cultural
life. It is the secret code with which every Western text was
're-read'.
It is the ground-bass of every rhythm and bodily movement. This was
- i s - the 'Africa' that 'is alive and well in the diaspora'. |
ア
フリカ的存在とは、抑圧されたものである。奴隷制度という体験の力によって、記憶の彼方で沈黙しているように見えるアフリカだが、実際にはあらゆるところ
に存在していた。奴隷居住区の日常生活や習慣の中に、プランテーションの言語や愛語の中に、しばしば分類学から切り離された名前や言葉の中に、他の言語が
話される秘密の構文構造の中に、子供たちに語られる物語や話の中に、宗教的慣習や信仰の中に、精神生活の中に、奴隷社会や奴隷解放後の社会の芸術、工芸、
音楽、リズムの中に。アフリカは、奴隷制の中で直接的に表現されることのなかった記号であり、カリブ海の文化の中で、語られることのない、語ることのでき
ない「存在」であり続けた。アフリカは、カリブ海の文化生活のあらゆる言葉の抑揚や物語のひねりの背後に「隠れて」いる。それは、あらゆる西洋のテキスト
が「再読」される際の秘密の暗号である。それは、あらゆるリズムと身体運動のグランドベースである。これが「ディアスポラで健在」な「アフリカ」なのであ
る。 |
| When I was growing up in the
1940s and 1950s as a child in
Kingston, I was surrounded by the signs, music and rhythms of this
Africa of the diaspora, which only existed as a result of a long and
discontinuous series of transformations. But, although almost
everyone around me was some shade of brown or black (Africa
'speaks'!), I never once heard a single person refer to themselves or
to others as, in some way, or as having been at some time in the past,
'African'. It was only in the 1970s that this Afro-Caribbean identity
became historically available to the great majority of Jamaican
people, at home and abroad. In this historic moment, Jamaicans
discovered themselves to be 'black' - just as, in the same moment,
they discovered themselves to be the sons and daughters of 'slavery'. |
1940
年代から1950年代にかけて、キングストンで子供として育った私は、長く不連続な変容の結果としてのみ存在する、このディアスポラのアフリカの標識、音
楽、リズムに囲まれていた。しかし、私の周りのほとんどの人は、褐色か黒色(アフリカは「話す」のだ!)であったにもかかわらず、自分自身や他人を、何ら
かの形で、あるいは過去のある時期において「アフリカ人」であったと呼ぶのを聞いたことは一度もなかった。このアフロ・カリビアンというアイデンティティ
が、国内外のジャマイカ人の大多数に歴史的に浸透したのは、1970年代のことである。この歴史的瞬間に、ジャマイカ人は自分たちが「黒人」であることを
発見した。同じ瞬間に、自分たちが「奴隷制度」の息子や娘であることを発見したように。 |
| This profound cultural
discovery, however, was not, and could not
be, made directly, without 'mediation'. It could only be made
through the impact on popular life of the post-colonial revolution,
the civil rights struggles, the culture of Rastafarianism and the music
of reggae - the metaphors, the figures or signifiers of a new
construction of'Jamaican-ness'. These signified a 'new' Africa of the
New World, grounded in an 'old' Africa: - a spiritual journey of
discovery that led, in the Caribbean, to an indigenous cultural
revolution; this is Africa, as we might say, necessarily 'deferred' -
as
a spiritual, cultural and political metaphor. |
し
かし、この深遠な文化的発見は、「媒介」なしに直接的になされたものではなく、またなされることもなかった。それは、ポスト植民地革命、公民権闘争、ラス
タファリズムの文化、レゲエの音楽が大衆生活に与えた影響によってのみもたらされた。これらは、「古い」アフリカに根ざした、新世界の「新しい」アフリカ
を意味した。カリブ海において、土着の文化革命へと導いた発見の精神的な旅。 |
| It is the presence/absence of
Africa, in this form, which has made
it the privileged signifier of new conceptions of Caribbean identity.
Everyone in the Caribbean, of whatever ethnic background, must
sooner or later come to terms with this African presence. Black,
brown, mulatto, white - all must look Presence Africaine in the face,
speak its name. But whether it is, in this sense, an origin of our
identities, unchanged by four hundred years of displacement,
dismemberment, transportation, to which we could in any final or
literal sense return, is more open to doubt. The original 'Africa' is
no
longer there. It too has been transformed. History is, in that sense,
irreversible. We must not collude with the West which, precisely,
normalises and appropriates Africa by freezing it into some timeless
zone of the primitive, unchanging past. Africa must at last be
reckoned with by Caribbean people, but it cannot in any simple
sense by merely recovered. |
ア
フリカの存在/不在は、このような形で、カリブ海のアイデンティティの新しい概念の特権的な記号となった。カリブ海の誰もが、民族的背景が何であれ、遅か
れ早かれ、このアフリカの存在と折り合いをつけなければならない。黒人、褐色人、混血、白人......誰もがプレゼンス・アフリケーヌを直視し、その名
を語らなければならない。しかし、この意味で、アフリカが400年にわたる移動、解体、輸送によって変わることのない、私たちのアイデンティティの原点で
あり、私たちが最終的な意味でも文字通りの意味でも戻ることのできる場所であるかどうかは、疑問の余地がある。本来の「アフリカ」はもはやそこにはない。
アフリカもまた変容してしまったのだ。その意味で、歴史は不可逆的である。私たちは、アフリカを原始的で不変の過去という時間を超越したゾーンに凍結させ
ることで、アフリカを正規化し、流用している西洋と結託してはならない。アフリカは、カリブ海の人々によって最終的に再評価されなければならないが、単に
回復されただけでは済まされない。 |
| It belongs irrevocably, for us,
to what Edward Said once called an
'imaginative geography and history', which helps 'the mind to
intensify its own sense of itself by dramatising the difference
between what is close to it and what is far away'. It 'has acquired an
imaginative or figurative value we can name and feel'.7 Our
belongingness to it constitutes what Benedict Anderson calls 'an
imagined community'.8 To this 'Africa', which is a necessary part of
the Caribbean imaginary, we can't literally go home again. |
そ
れは私たちにとって、エドワード・サイードがかつて「想像的な地理と歴史」と呼んだものに不可逆的に属しており、「心は身近なものと遠いものとの違いを劇
的に表現することによって、自分自身の感覚を強める」のに役立っている。私たちの帰属意識は、ベネディクト・アンダーソンが「想像上の共同体」と呼ぶもの
を構成している8。カリブ海の想像力に必要なこの「アフリカ」に、私たちは文字通り再び帰ることはできない。 |
| The character of this displaced
'homeward' journey - its length
and complexity - comes across vividly, in a variety of texts. Tony
Sewell's documentary archival photographs, Garvey's Children: the
Legacy of Marcus Garvey, tells the story of a 'return' to an African
identity which went, necessarily, by the long route-through London
and the United States. It 'ends', not in Ethiopia but with Garvey's
statue in front of the St Ann Parish Library in Jamaica: not with a
traditional tribal chant but with the music of Burning Spear and Bob
Marley's Redemption Song. This is our long journey' home. Derek
Bishton's courageous visual and written text, Black Heart Man - the
story of the journey of a white photographer 'on the trail of the
promised land' - starts in England, and goes, through Shashemene,
the place in Ethiopia to which many Jamaican people have found
their way on their search for the Promised Land, and slavery; but it
ends in Pinnacle, Jamaica, where the first Rastafarian settlements
was established, and 'beyond' - among the dispossessed of
20th-century Kingston and the streets of Handsworth, where
Bishton's voyage of discovery first began. These symbolic journies
are necessary for us all - and necessarily circular. This is the Africa
we must return to - but 'by another route': what Africa has become
in the New World, what we have made of 'Africa': 'Africa' - as we
re-tell it through politics, memory and desire. |
こ
の離散的な「帰郷」の旅の特徴-その長さと複雑さ-は、さまざまなテキストから鮮やかに伝わってくる。トニー・スウェルの記録写真集『Garvey's
Children: The Legacy of Marcus
Garvey』は、必然的にロンドンとアメリカを経由する長いルートで辿った、アフリカ人としてのアイデンティティへの「帰還」の物語である。エチオピア
ではなく、ジャマイカのセント・アン教区図書館の前にあるガーヴェイの銅像で、伝統的な部族の聖歌ではなく、バーニング・スピアの音楽とボブ・マーリーの
『Redemption
Song』で「終わる」。これは私たちの長い旅路の故郷なのだ」。デレク・ビシュトンの勇気あるビジュアルと文章による『Black Heart
Man』は、「約束の地を追い求める」白人写真家の旅の物語であり、イギリスから始まり、多くのジャマイカ人が「約束の地」、そして奴隷制度を求めて辿り
着いたエチオピアのシャシェメネを経由する;
そしてジャマイカのピナクル、最初のラスタファリアンの集落が設立された場所、そしてビシュトンの発見の旅が最初に始まった20世紀のキングストンやハン
ズワースの路上で、土地を奪われた人々の間で終わる。こうした象徴的な旅は、私たち全員にとって必要なものであり、必然的に循環するものである。新世界で
アフリカがどうなったか、私たちが「アフリカ」をどう作ったか、つまり「アフリカ」は、私たちが政治、記憶、欲望を通してアフリカを語り直すときに作られ
るのである。 |
| What of the second, troubling,
term in the identity equation - the
European presence? For many of us, this is a matter not of too little
but of too much. Where Africa was a case of the unspoken, Europe
was a case of that which is endlessly speaking - and endlessly
speaking us. The European presence interrupts the innocence of the
whole discourse of 'difference' in the Caribbean by introducing the
question of power. 'Europe' belongs irrevocably to the play' of
power, to the lines of force and consent, to the role of the dominant,
in Caribbean culture. In terms of colonialism, underdevelopment,
poverty and the racism of colour, the European presence is that
which, in visual representation, has positioned the black subject
within its dominant regimes of representation: the colonial
discourse, the literatures of adventure and exploration, the romance
of the exotic, the ethnographic and travelling eye, the tropical
languages of tourism, travel brochure and Hollywood and the
violent, pornographic languages of ganja and urban violence. |
ア
イデンティティの方程式における2つ目の厄介な用語、ヨーロッパの存在感についてはどうだろうか。私たちの多くにとって、これは少なすぎるという問題では
なく、多すぎるという問題である。アフリカが "語られざるもの "のケースであったのに対し、ヨーロッパは "語られ続けるもの
"のケースである。ヨーロッパ人の存在は、カリブ海における「違い」という言説全体の無邪気さを、権力の問題を導入することで中断させる。ヨーロッパ」
は、カリブ海の文化において、力の戯れ、力と同意の境界線、支配者の役割に不可逆的に属している。植民地主義、低開発、貧困、有色人種差別の観点から、
ヨーロッパの存在とは、視覚的表象において、黒人の主体をその支配的な表象体制の中に位置づけてきたものである。植民地的言説、冒険と探検の文学、エキゾ
チックなロマンス、民族誌的な目、旅する目、観光、旅行パンフレット、ハリウッドのトロピカルな言語、ガンジャと都市の暴力の暴力的でポルノ的な言語など
である。 |
| Because Presence Europeenne is
about exclusion, imposition and
expropriation, we are often tempted to locate that power as wholly
external to us - an extrinsic force, whose influence can be thrown off
like the serpent sheds its skin. What Frantz Fanon reminds us, in
Black Skin, White Masks, is how this power has become a
constitutive element in our own identities. "The movements, the
attitudes, the glances of the other fixed me there,
in the sense in which a chemical solution is fixed by a dye. I was
indignant; I demanded an explanation. Nothing happened. I burst apart.
Now the fragments have been put together again by another self." This
'look', from - so to speak - the place of the Other, fixes us, not
only in its violence, hostility and aggression, but in the ambivalence
of its desire. This brings us face to face, not simply with the
dominating European presence as the site or 'scene' of integration
where those other presences which it had actively disaggregated
were recomposed - re-framed, put together in a new way; but as the
site of a profound splitting and doubling - what Homi Bhaba has
called 'the ambivalent identifications of the racist world ... the
'otherness' of the self inscribed in the perverse palimpsest of
colonial
identity.' |
プ
レゼンス・ヨーロッペン』は排除、押しつけ、収奪をテーマにしているため、私たちはしばしば、その力を完全に私たちの外部にあるもの、つまり、蛇が皮を脱
ぐように、その影響力を捨て去ることができる外在的な力として位置づけたくなる。フランツ・ファノンは、『黒い肌、白い仮面』の中で、この力がいかに私た
ち自身のアイデンティティを構成する要素となっているかに気づかせてくれる。「相手の動き、態度、視線は、化学溶液が染料によって固定されるのと同じよう
に、私をそこに固定した。私は憤慨し、説明を求めた。何も起こらなかった。私はバラバラになった。そして今、その断片は別の自分によって再び組み合わされ
た」。この "視線
"は、いわば他者の場所からのものであり、その暴力性、敵意、攻撃性だけでなく、その欲望の両義性において私たちを固定する。このことは、単に支配的な
ヨーロッパ人の存在を、それが積極的に分離した他の存在が再構成され、新たな方法で組み合わされる統合の場や「場面」としてではなく、ホミ・バーバが「人
種差別的世界の両義的な同一性......植民地的アイデンティティの倒錯したパリンプセストに刻まれた自己の『他者性』」と呼ぶような、深遠な分裂と二
重化の場として、私たちを直面させる。 |
| The dialogue of power and
resistance, of refusal and recognition,
with and against Presence Europeenne is almost as complex as the
'dialogue' with Africa. In terms of popular cultural life, it is
nowhere
to be found in its pure, pristine state. It is always-already fused,
syncretised, with other cultural elements. It is always-already
creolised - not lost beyond the Middle Passage, but ever-present:
from the harmonics in our musics to the ground-bass of Africa,
traversing and intersecting our lives at every point. How can we
stage this dialogue so that, finally, we can place it, without terror
or
violence, rather than being forever placed by it? Can we ever
recognise its irreversible influence, whilst resisting its
imperialising
eye? The engima is impossible, so far, to resolve. It requires the
most complex of cultural strategies. Think, for example, of the
dialogue of every Caribbean filmmaker or writer, one way or
another, with the dominant cinemas and literature of the West - the
complex relationship of young black British filmmakers with the
'avant-gardes' of European and American filmmaking. Who could
describe this tense and tortured dialogue as a 'one way trip? |
権
力と抵抗、拒否と承認、プレゼンス・ヨーロッパとの対話は、アフリカとの「対話」と同じくらい複雑である。ポピュラーな文化的生活という点では、純粋な原
始的な状態ではどこにも存在しない。それは常に他の文化的要素と融合し、シンクレティッド化している。私たちの音楽のハーモニクスからアフリカのグランド
ベースまで、あらゆる地点で私たちの生活を横断し、交差している。この対話をどのように演出すれば、恐怖や暴力を伴わずに、永遠に対話に翻弄されることな
く、対話の場に身を置くことができるのだろうか。帝国化の眼差しに抗いながら、その不可逆的な影響力を認識することはできるのだろうか?エンギマを解決す
ることは、今のところ不可能である。最も複雑な文化的戦略を必要とする。例えば、カリブ海諸国の映画作家や作家が、何らかの形で西洋の支配的な映画や文学
と対話すること、また、イギリスの若い黒人映画作家とヨーロッパやアメリカの映画製作の「前衛」たちとの複雑な関係を考えてみよう。この緊張と苦悩に満ち
た対話を、誰が「片道旅行」と表現できるだろうか? |
| The Third, 'New World' presence,
is not so much power, as
ground, place, territory. It is the juncture-point where the many
cultural tributaries meet, the 'empty' land (the European colonisers
emptied it) where strangers from every other part of the globe
collided. None of the people who now occupy the islands - black,
brown, white, African, European, American, Spanish, French, East
Indian, Chinese, Portugese, Jew, Dutch - originally 'belonged'
there. It is the space where the creolisations and assimilations and
syncretisms were negotiated. The New World is the third term - the
primal scene - where the fateful/fatal encounter was staged between
Africa and the West. It also has to be understood as the place of
many, continuous displacements: of the original pre-Columbian
inhabitants, the Arawaks, Caribs and Amerindians, permanently
displaced from their homelands and decimated; of other peoples
displaced in different ways from Africa, Asia and Europe; the
displacements of slavery, colonisation and conquest. It stands for the
endless ways in which Caribbean people have been destined to
'migrate'; it is the signifier of migration itself- of travelling,
voyaging
and return as fate, as destiny; of the Antillean as the prototype of
the
modern or postmodern New World nomad, continually moving
between centre and periphery. This preoccupation with movement
and migration Caribbean cinema shares with many other 'Third
Cinemas', but it is one of our defining themes, and it is destined to
cross the narrative of every film script or cinematic image. |
第3
の、「新世界」の存在とは、権力というよりも、地面、場所、領土である。多くの文化的支流が交わる分岐点であり、地球上のあらゆる地域からやってきたよそ
者がぶつかり合う「何もない」土地である(ヨーロッパの植民地支配者たちはそこを空にした)。黒人、褐色人、白人、アフリカ人、ヨーロッパ人、アメリカ
人、スペイン人、フランス人、東インド人、中国人、ポルトガル人、ユダヤ人、オランダ人など、現在この島々を占める人々は誰一人として、もともとそこに
「属していた」わけではない。クレオライゼーションと同化とシンクレティズムが交渉された空間なのだ。新世界は、アフリカと西洋の運命的/宿命的な出会い
が演出された第3の場所、つまり原初の舞台である。コロンブス以前の原住民であるアラワク人、カリブ人、アメリカインディアンは、恒久的に故郷を追われ、
滅ぼされ、他の民族はアフリカ、アジア、ヨーロッパからさまざまな形で移住し、奴隷制、植民地化、征服による移住が行われた。それは、カリブ海の人々が
「移住」する運命にある無限の方法の象徴であり、移住そのもの、すなわち、運命としての旅、航海、帰還を意味するものである。この移動と移住に対するカリ
ブ海映画の偏愛は、他の多くの "第3の映画
"と共通しているが、私たちを定義するテーマのひとつであり、あらゆる映画脚本や映画イメージの物語を横断する運命にある。 |
| Presence Americaine continues to
have its silences, its
suppressions. Peter Hulme, in his essay on 'Islands of Enchantment'
11 reminds us that the word 'Jamaica' is the Hispanic form of
the indigenous Arawak name - 'land of wood and water' - which
Columbus's re-naming ('Santiago') never replaced. The Arawak
presence remains today a ghostly one, visible in the islands mainly
usable 'past'. Hulme notes that it is not represented in the emblem
of the Jamaican National Heritage Trust, for example, which chose
instead the figure of Diego Pimienta, 'an African who fought for his
Spanish masters against the English invasion of the island in 1655' -
a deferred, metonymic, sly and sliding representation of Jamaican
identity if ever there was one! He recounts the story of how Prime
Minister Edward Seaga tried to alter the Jamaican coat-of-arms,
which consists of two Arawak figures holding a shield with five
pineapples, surmounted by an alligator. 'Can the crushed and
extinct Arawaks represent the dauntless character of Jamaicans?
Does the low-slung, near extinct crocodile, a cold-blooded reptile,
symbolise the warm, soaring spirit of Jamaicans?' Prime Minister
Seaga asked rhetorically. There can be few political statements
which so eloquently testify to the complexities entailed in the
process of trying to represent a diverse people with a diverse history
through a single, hegemonic 'identity'. Fortunately, Mr Seaga's
invitation to the Jamaican people, who are overwhelmingly of
African descent, to start their 'remembering' by first 'forgetting'
something else, got the comeuppance it so richly deserved. |
プ
レゼンス・アメリケーヌは、その沈黙と抑圧を持ち続けている。ピーター・ハルムは「魅惑の島々」についてのエッセイ11の中で、「ジャマイカ」という言葉
は、先住民のアラワク族の名前である「木と水の土地」のヒスパニック語であり、コロンブスが改名した「サンティアゴ」は、その名前に取って代わることはな
かったことを思い起こさせる。アラワク族の存在は、今日でも亡霊のような存在であり、主に使用可能な「過去」の島々で見ることができる。ハルムは、例えば
ジャマイカ国家遺産トラストのエンブレムにはアラワク人が描かれていないことを指摘する。代わりに選ばれたのは、「1655年にイギリス人の島への侵略に
対してスペイン人の主人のために戦ったアフリカ人」ディエゴ・ピミエンタの姿である!彼は、エドワード・シーガ首相がジャマイカの紋章を変更しようとした
ときのエピソードを語っている。この紋章は、5つのパイナップルが描かれた盾を持つ2人のアラワク族の人物から成り、その上にはワニがいる。潰れて絶滅し
たアラワク族が、ジャマイカ人の勇敢な性格を表すことができるだろうか?低姿勢で絶滅寸前のワニは、冷血な爬虫類だが、ジャマイカ人の暖かく舞い上がる精
神を象徴しているのだろうか?シーガ首相は修辞的に問いかけた。多様な歴史を持つ多様な国民を、単一の覇権的な『アイデンティティ』によって代表しようと
する過程に伴う複雑さを、これほど雄弁に物語る政治的発言はそうないだろう。幸いなことに、圧倒的にアフリカ系が多いジャマイカ国民に、まず他の何かを
「忘れる」ことから「思い出す」ことを始めようと誘ったシーガ氏の発言は、それにふさわしい報いを受けた。 |
| The 'New World' presence -
America, Terra Incognita - is
therefore itself the beginning of diaspora, of diversity, of hybridity
and difference, what makes Afro-Caribbean people already people of
a diaspora. I use this term here metaphorically, not literally:
diaspora does not refer us to those scattered tribes whose identity
can only be secured in relation to some sacred homeland to which
they must at all costs return, even if it means pushing other people
into the sea. This is the old, the imperialising, the hegemonising,
form of 'ethnicity'. We have seen the fate of the people of Palestine
at the hands of this backward-looking conception of diaspora - and
the complicity of the West with it. The diaspora experience as I
intend it here is defined, not by essence or purity, but by the
recognition of a necessary heterogeneity and diversity; by a
conception of 'identity' which lives with and through, not despite,
difference; by hybridity. Diaspora identities are those which are
constantly producing and reproducing themselves anew, through
transformation and difference. One can only think here of what is
uniquely - 'essentially' - Caribbean: precisely the mixes of colour,
pigmentation, physiognomic type; the 'blends' of tastes that is
Caribbean cuisine; the aesthetics of the 'cross-overs', of
'cut-andmix',
to borrow Dick Hebdige's telling phrase, which is the heart
and soul of black music. Young black cultural practitioners and
critics in Britain are increasingly coming to acknowledge and
explore in their work this 'diaspora aesthetic' and its formations in
the post-colonial experience: "Across a whole range of cultural forms
there is a 'syncretic' dynamic
which critically appropriates elements from the master-codes of the
dominant culture and 'creolises' them, disarticulating given signs and
re-articulating their symbolic meaning. The subversive force of this
hybridising tendency is most apparent at the level of language itself
where Creoles, patois and black English decentre, destabilise and
carnivalise the linguistic domination of 'English' - the
nation-language of
master-discourse - through strategic inflections, re-accentuations and
other performative moves in semantic, syntactic and lexical codes." It
is because this New World is constituted for us as place, a
narrative of displacement, that it gives rise so profoundly to a
certain
imaginary plenitude, recreating the endless desire to return to 'lost
origins', to be one again with the mother, to go back to the
beginning. Who can ever forget, when once seen rising up out of
that blue-green Caribbean, those islands of enchantment. Who has
not known, at this moment, the surge of an overwhelming nostalgia
for lost origins, for 'times past? And yet, this 'return to the
beginning' is like the imaginary in Lacan - it can neither be fulfilled
nor requited, and hence is the beginning of the symbolic, of
representation, the infinitely renewable source of desire, memory,
myth, search, discovery - in short, the reservoir of our cinematic
narratives. |
ア
メリカ、テラ・インコグニタという "新世界
"の存在は、それ自体がディアスポラの始まりであり、多様性、混血性、差異であり、アフロ・カリビアン人をすでにディアスポラの人々にしている。ディアス
ポラとは、他の人々を海に突き落としてでも、何としても戻らなければならない神聖な祖国との関係においてのみアイデンティティを確保できるような、散り散
りになった部族を指すのではない。これは旧来の、帝国主義的、覇権主義的な「エスニシティ」である。私たちは、このような後ろ向きなディアスポラ概念の手
によるパレスチナの人々の運命を、そしてそれに加担する欧米の姿を目の当たりにしてきた。私がここで意図するディアスポラの経験とは、本質や純粋さによっ
てではなく、必要な異質性と多様性の認識によって、差異にもかかわらずではなく、差異とともに、差異を通して生きる「アイデンティティ」の概念によって、
混血性によって定義される。ディアスポラのアイデンティティとは、変容と差異を通じて、常に新たな自らを生み出し、再生産するものである。ここで考えられ
るのは、カリブ独特のもの、つまり「本質的に」カリブ的なものである。色、色素、人相のタイプのまさにミックス、カリブ料理である味の「ブレンド」、
ディック・ヘブディージュの言葉を借りれば「クロスオーバー」、「カット&ミックス」の美学、これらは黒人音楽の核心であり魂である。英国の若い黒人文化
実践者や批評家たちは、この「ディアスポラの美学」とポストコロニアル体験におけるその形成を認め、彼らの作品において探求するようになってきている:
さまざまな文化形態には、支配的な文化のマスター・コードから要素を批判的に流用し、それらを "クレオライズ
"し、与えられた記号をバラバラにし、その象徴的意味を再構築する "シンクレティック
"なダイナミズムがある。このハイブリッド化傾向の破壊的な力は、クレオール、パトワ、黒人英語が、意味的、統語的、語彙的コードにおける戦略的屈折、再
アクセント化、その他のパフォーマティヴな動きによって、マスター・ディスコースの国民言語である「英語」の言語的支配を破壊し、不安定化し、カーニヴァ
ル化する、言語そのもののレベルで最も明白である。この新世界が私たちにとって場所として構成され、変位の物語であるからこそ、ある種の想像的な豊かさを
深く生み出し、「失われた起源」に戻りたい、母なるものと再びひとつになりたい、始まりに戻りたいという果てしない欲望を再現するのである。青緑色のカリ
ブ海から立ち上がる、魅惑の島々を誰が忘れることができるだろう。この瞬間、失われた原点、「過ぎ去った時」への圧倒的な郷愁が湧き上がってこない人がい
るだろうか。そして、この「始まりへの回帰」は、ラカンにおけるイマジナリーのようなものであり、満たされることもなければ、報われることもない。 |
| We have been trying, in a series
of metaphors, to put in play a
different sense of our relationship to the past, and thus a different
way of thinking about cultural identity, which might constitute new
points of recognition in the discourses of the emerging Caribbean
cinema and black British cinemas. We have been trying to theorise
identity as constituted, not outside but within representation; and
hence of cinema, not as a second-order mirror held up to reflect
what already exists, but as that form of representation which is able
to constitute us as new kinds of subjects, and thereby enable us to
discover places from which to speak. Communities, Benedict
Anderson argues in Imagined Communities are to be distinguished,
not by their falsity/genuineness, but by the style in which they are
imagined.14 This is the vocation of modern black cinemas: by
allowing us to see and recognise the different parts and histories of
ourselves, to construct those points of identification, those
positionalities we call in retrospect our 'cultural identities'. |
私
たちは一連のメタファーにおいて、過去と私たちの関係について異なる感覚を働かせ、文化的アイデンティティについて異なる考え方をしようと試みてきた。私
たちはアイデンティティを、表象の外側ではなく内側で構成されるものとして理論化しようとしてきた。したがって映画とは、すでに存在するものを映し出す二
次的な鏡としてではなく、私たちを新しい種類の主体として構成し、それによって私たちが語るべき場所を発見することを可能にする表象の形式なのである。ベ
ネディクト・アンダーソンは『想像された共同体』の中で、共同体はその虚偽性/真正性によってではなく、想像される様式によって区別されるべきであると論
じている。 |
| "We must not therefore be content with delving into the past of a people
in order to find coherent elements which will counteract colonialism's
attempts to falsify and harm ... A national culture is not a folk-lore, nor
an abstract populism that believes it can discover a people's true nature.
A national culture is the whole body of efforts made by a people in the
sphere of thought to describe, justify and praise the action through
which that people has created itself and keeps itself in existence."
|
「そ
れゆえ、植民地主義による改ざんや害悪の試みに対抗する首尾一貫した要素を見つけるために、民族の過去を掘り下げることに満足してはならない。民族文化と
は、民俗伝承でもなければ、民族の本性を発見できると信じる抽象的なポピュリズムでもない。民族文化とは、その民族が自らを創造し、自らを存続させるため
に行ってきた行為を記述し、正当化し、賞賛するために、その民族が思想の領域で行った努力の総体である」15 Fanon, op.cit., 1963, p.188.。 |
| Notes 1 Frantz Fanon, 'On National Culture', in The Wretched of the Earth, London 1963, pl70. 2 Ibid., pl76. 3 Christopher Norris, Deconstruction: Theory and Practice, London 1982, p32. 4 Christopher Norris, Jacques Derrida, London 1987, pl5. 5 Stuart Hall, Resistance Through Rituals, London 1976. 6 Edward Said, Orientalism, London 1985, p55. 7 Ibid. 8 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Rise of Nationalism, London 1982. 9 Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, London 1986, pl09. 10 Homi Bhabha, 'Foreword' to Fanon, ibid., xv. 11 In New Formations, no.3, Winter 1987. 12 Jamaica Hansard, vol.9, 1983-4, p363. Quoted in Hulme, ibid. 13 Kobena Mercer, Diaspora Culture and the Dialogic Imagination', in M. Cham and C. Watkins (eds), Blackframes: Critical Perspectives on Black Independent Cinema, 1988, p57. 14 Anderson, op.cit., pl5. 15 Fanon, op.cit., 1963, p.188. This piece was first published in the journal Framework (no.36) and is reproduced by kind permission of the editor, Jim Pines. |
|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Diaspora_studies |
|
| Avtar Brah
is a Ugandan-British sociologist. She is Emeritus Professor of
Sociology at Birkbeck, University of London, and a pioneer of diaspora
studies. |
アヴター・ブラフはウガンダ系イギリス人の社会学者である。ロンドン大学バークベック校の社会学名誉教授であり、ディアスポラ研究の先駆者である。 |
| Life Avtar Brah was born in the Punjab and grew up in Uganda.[1] Her mother tongue was Punjabi, and she recalls reading the novelist Nanak Singh, the eighteenth-century poet Waris Shah and the contemporary poet Amrita Pritam as a young person. In the late 1960s she studied on a scholarship in the United States before coming to Britain in the early 1970s, where she worked as a researcher at the Ethnic Relations Unit at Bristol University. She was left a stateless refugee in Britain after Idi Amin's expulsion of Asians from Uganda. She began her PhD in the mid-1970s, researching Asian communities in Southall, and moved to Southall as a community worker when her research contract at Bristol University ended. She participated in a demonstration against the National Front at which hundreds of demonstrators were arrested, and was a founding member of the Southall Black Sisters.[2] Brah was a research associate at Leicester University from 1980 to 1982, and a lecturer at the Open University from 1982 to 1985, She joined Birkbeck in 1985 as a lecturer, eventually rising to the rank of professor there. She was also visiting professor at the University of California in 1992 and Cornell University in 2001.[3] Brah was appointed MBE in 2001, for services to race, gender and ethnic identity issues.[4] |
人生 アヴタル・ブラフはパンジャーブで生まれ、ウガンダで育った。[1] 彼女の母語はパンジャーブ語であり、若い頃には小説家ナナク・シン、18世紀の詩人ワリス・シャー、現代詩人アムリタ・プリタムを読んだことを覚えてい る。1960年代後半、奨学金を得てアメリカで学んだ後、1970年代初頭に英国に渡り、ブリストル大学の民族関係研究ユニットで研究員として働いた。イ ディ・アミンによるウガンダのアジア人追放後、英国で無国籍難民となった。1970年代半ばにサウスオールのアジア人コミュニティを研究対象に博士課程を 開始し、ブリストル大学の研究契約終了後はコミュニティワーカーとしてサウスオールに移住した。数百人のデモ参加者が逮捕された国民戦線反対デモに参加 し、サウスオール・ブラック・シスターズの創設メンバーとなった。[2] ブラは1980年から1982年までレスター大学の研究員、1982年から1985年までオープン大学の講師を務めた。1985年にバークベック大学に講 師として着任し、後に教授に昇進した。また1992年にはカリフォルニア大学、2001年にはコーネル大学の客員教授も務めた。[3] ブラは人種、性別、民族的アイデンティティ問題への貢献が認められ、2001年に大英帝国勲章(MBE)を受章した。[4] |
| Works Working choices: South Asian young Muslim women and the labour market. 1992. Cartographies of Diaspora: contesting identities. London; New York: Routledge, 1996. (ed. with Mary J. Hickman and Maírtín Mac an Ghaill) Thinking identities: ethnicity, racism, and culture. New York, N.Y.: St. Martin's Press, 1999.. Global futures : migration, environment, and globalization. New York: St. Martin's Press, 1999. (ed. with Annie E. Coombes) Hybridity and its discontents : politics, science, culture. London: Routledge, 2000. |
作品 働く選択肢:南アジアの若いイスラム教徒の女性と労働市場。1992年。 ディアスポラの地図:争われるアイデンティティ。ロンドン、ニューヨーク:Routledge、1996年。 (メアリー・J・ヒックマン、マーティン・マック・アン・ガイルと共編)アイデンティティを考える:民族性、人種主義、文化。ニューヨーク、ニューヨーク:セント・マーティンズ・プレス、1999年。 グローバルな未来:移住、環境、グローバル化。ニューヨーク:セント・マーティンズ・プレス、1999年。 (アニー・E・クームズと共編) ハイブリッド性とその不満:政治、科学、文化。ロンドン:ラウトレッジ、2000年。 |
| 1. Alison Donnell, ed. (2002).
"Brah, Avtar". Companion to Contemporary Black British Culture.
Routledge. p. 56. ISBN 978-1-134-70025-7. 2. Les Beck and Avtar Brah, 'activism, imagination and writing: Avtar Brah reflects on her life and work with Les Back', Feminist Review, No. 100 (2012), oo. 39-51. 3. Avtar Brah – Birkbeck, University of London 4. "No. 56070". The London Gazette (1st supplement). 30 December 2000. p. 15. |
1. アリソン・ドネル編(2002)『ブラフ、アヴタル』『現代英国黒人文化事典』ラウトリッジ刊、56頁。ISBN 978-1-134-70025-7。 2. レス・ベックとアヴター・ブラフ「活動主義、想像力、そして執筆:アヴター・ブラフがレス・ベックと共に歩んだ人生と仕事を振り返る」『フェミニスト・レビュー』第100号(2012年)、39-51頁。 3. アヴター・ブラフ – ロンドン大学バークベック校 4. 「第56070号」『ロンドン官報』(第1補遺)。2000年12月30日。15頁。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Avtar_Brah |
★Cartographies of diaspora : contesting identities / Avtar Brah ;London : Routledge , 1996. - (Gender, racism, ethnicity series)
| Avtar Brahの『Cartographies of Diaspora』は、ディアスポラ(移民や離散的なコミュニティ)の経験とその地理的、文化的、社会的な影響を探求する重要な著作です。本書では、以下のようなテーマが扱われています。 |
|
| ディアスポラの概念: Brahは、ディアスポラを単なる地理的な移動としてではなく、アイデンティティ、文化、社会的関係の複雑な相互作用として捉えています。 |
|
| 空間と場所: 本書では、ディアスポラの経験がどのように空間と場所によって形成されるかについて考察されています。特に、移民が新しい場所でどのようにアイデンティティを再構築するかに焦点が当てられています。 |
|
| 交差するアイデンティティ: Brahは、異なる文化的背景を持つ人々のアイデンティティがどのように交差し、相互作用するかを分析しています。この視点は、文化的な多様性とその複雑さを強調します。 |
|
| 政治と権力: ディアスポラの経験は、政治的な文脈や権力関係とも深く結びついています。Brahは、移民が直面する社会的、経済的、政治的な課題についても論じています。 |
|
| 学術的意義 新しい視点の提供: Brahの著作は、ディアスポラ研究において新たな視点を提供し、移民の経験を単なる受動的なものではなく、能動的な再構築のプロセスとして位置づけます。 |
|
| インターセクショナリティの強調: 彼女は、性別、人種、階級などの交差する要素がディアスポラの経験にどのように影響を与えるかを探求し、インターセクショナリティの重要性を強調します。 |
|
| 文化的理解の促進: 本書は、異なる文化的背景を持つ人々の相互理解を促進し、文化的多様性の価値を再確認させる役割を果たします。 |
|
| 社会的政策への示唆: Brahの分析は、移民政策や社会的包摂に関する議論に貢献し、実践的な示唆を提供します。このように、『Cartographies of Diaspora』は、ディアスポラの複雑な経験を深く理解するための重要な理論的枠組みを提供しており、社会学、人類学、文化研究の分野において重要な文献とされています。 |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099