
バリにおける人間・時間・行為
文
化の分析に関する考察:"Person, time, and conduct in Bali: an essay in cultural
analysis", pp. 360-411

Person, time, and conduct in Bali: an essay in cultural analysis. New-Haven/Ct./USA 1966: Yale University Press: ed. by the Department of Southeast Asia Studies (distributor: Cellar Book Shop, Detroit/Mi./USA), (ISBN 0598551581; III, 85 pp.; caption title), in Clifford Geertz: The interpretation of cultures (1973)
| Person, Time, and
Conduct in Bali. The Social Nature of Thought Clifford Geertz Human thought is consummately social: social in its origins, social in its functions, social in its forms, social in its applications. At base, thinking is a public activity--its natural habitat is the houseyard, the marketplace, and the town square. The implications of this fact for the anthropological analysis of culture, my concern here, are enormous, subtle, and insufficiently appreciated. I want to draw out some of these implications by means of what might seem at first glance an excessively special, even a somewhat esotric inquiry: an examination of the cultural apparatus in terms of which the people of Bali define, perceive, and react to--that is, think about--individual persons. Such an investigation is, however, special and esoteric only in the descriptive sense. The facts, as facts, are of little immediate interest beyond the confines of ethnography, and I shall summarize them as briefly as I can. But when seen against the background of a general theoretical aim--to determine what follows for the analysis of culture from the proposition that human thinking is essentially a social activity--the Balinese data take on a peculiar importance. Not only are Balinese ideas in this area unusually well developed, but they are, from a Western perspective, odd enough to bring to light some general relationships between different orders of cultural conceptualization that are hidden from us when we look only at our own all-too-familiar framework for the identification, classification, and handling of human and quasi-human individuals. In particular, they point up some unobvious connections between the way in which a people perceive themselves and others, the way in which they experience time, and the affective tone of their collective life--connections that have an import not just for the understanding of Balinese society but human society generally. |
バリにおける人、時間、行動。 思考の社会的性質 クリフォード・ギアーツ 人間の思考は完全に社会的である。その起源において社会的であり、機能においても社会的であり、形態においても社会的であり、応用においても社会的であ る。根本的には、思考とは公共的な活動であり、その自然の生息地は家屋の庭、市場、広場である。この事実が文化の人類学的分析に与える影響は、膨大かつ微 妙であり、十分に評価されているとは言えない。 私は、一見すると過度に特殊で、やや難解な調査と思われるかもしれない方法によって、これらの含意のいくつかを引き出したい。すなわち、バリの人々が個人 を定義し、知覚し、反応する、つまり考える際の文化装置を検証することである。しかし、このような調査は、記述的な意味においてのみ特殊で難解である。事 実を事実として捉える場合、民族誌学の枠組みを超えて、即座に興味を引くことはほとんどない。私は、できるだけ簡潔に事実を要約するつもりである。しか し、一般的な理論的目標、すなわち「人間の思考は本質的に社会的活動である」という命題から文化の分析に何が導かれるかを明らかにするという目標を背景に 考えると、バリ人のデータは独特の重要性を持つ。 バリ人のこの分野における考え方は、非常に良く練られているだけでなく、西洋の観点から見ると、奇妙なほど、人間や人間に準ずる個体の識別、分類、処理に 関する、私たちにとってあまりにも見慣れた枠組みだけを見ていると見えなくなってしまう、異なる文化の概念化の秩序間の一般的な関係を明らかにしてくれ る。特に、人々が自分自身や他人をどう認識するか、時間をどう経験するか、集団生活の情緒的なトーンといったものとのあいだにある、明白ではないいくつか のつながりを浮き彫りにしている。それはバリ社会の理解にとどまらず、人間社会一般にとって重要な意味を持つつながりである。 |
| The Study of Culture A great deal of recent social scientific theorizing has turned upon an attempt to distinguish and specify two major analytical concepts: culture and social structure.1 The impetus for this effort has sprung from a desire to take account of ideational factors in social processes without succumbing to either the Hegelian or the Marxist forms of reductionism. In order to avoid having to regard ideas, concepts, values, and expressive forms either as shadows cast by the organization of society upon the hard surfaces of history or as the soul of history whose progress is but a working out of their internal dialectic, it has proved necessary to regard them as independent but not self-sufficient forces--as acting and having their impact only within specific social contexts to which they adapt, by which they are stimulated, but upon which they have, to a greater or lesser degree, a determining influence. "Do you really expect," Marc Bloch wrote in his little book on The Historian's Craft, "to know the great merchants of Renaissance Europe, vendors of cloth or spices, monopolists in copper, mercury or alum, bankers of Kings and the Emperor, by knowing their merchandise alone? Bear in mind that they were painted by Holbein, that they read Erasmus and Luther. To understand the attitude of the medieval vassal to his seigneur you must inform yourself about his attitude to his God as well." Both the organization of social activity, its institutional forms, and the systems of ideas which animate it must be understood, as must the nature of the relations obtaining between them. It is to this end that the attempt to clarify the concepts of social structure and of culture has been directed. There is little doubt, however, that within this two-sided development it has been the cultural side which has proved the more refractory and remains the more retarded. In the very nature of the case, ideas are more difficult to handle scientifically than the economic, political, and social relations among individuals and groups which those ideas inform. And this is all the more true when the ideas involved are not the explicit doctrines of a Luther or an Erasmus, or the articulate images of a Holbein, but the half-formed, taken-for-granted, indifferently systematized notions that guide the normal activities of ordinary men in everyday life. If the scientific study of culture has lagged, bogged down most often in mere descriptivism, it has been in large part because its very subject matter is elusive. The initial problem of any science--defining its object of study in such a manner as to render it susceptible of analysis--has here turned out to be unusually hard to solve. It is at this point that the conception of thinking as basically a social act, taking place in the same public world in which other social acts occur, can play its most constructive role. The view that thought does not consist of mysterious processes located in what Gilbert Ryle has called a secret grotto in the head but of a traffic in significant symbols --objects in experience (rituals and tools; graven idols and water holes; gestures, markings, images, and sounds) upon which men have impressed meaning--makes of the study of culture a positive science like any other.2 The meanings that symbols, the material vehicles of thought, embody are often elusive, vague, fluctuating, and convoluted, but they are, in principle, as capable of being discovered through systematic empirical investigation--especially if the people who perceive them will cooperate a little--as the atomic weight of hydrogen or the function of the adrenal glands. It is through culture patterns, ordered clusters of significant symbols, that man makes sense of the events through which he lives. The study of culture, the accumulated totality of such patterns, is thus the study of the machinery individuals and groups of individuals employ to orient themselves in a world otherwise opaque. In any particular society, the number of generally accepted and frequently used culture patterns is extremely large, so that sorting out even the most important ones and tracing whatever relationships they might have to one another is a staggering analytical task. The task is somewhat lightened, however, by the fact that certain sorts of patterns and certain sorts of relationships among patterns recur from society to society, for the simple reason that the orientational requirements they serve are generically human. The problems, being existential, are universal; their solutions, being human, are diverse. It is, however, through the circumstantial understanding of these unique solutions, and in my opinion only in that way, that the nature of the underlying problems to which they are a comparable response can be truly comprehended. Here, as in so many branches of knowledge, the road to the grand abstractions of science winds through a thicket of singular facts. One of these pervasive orientational necessities is surely the characterization of individual human beings. Peoples everywhere have developed symbolic structures in terms of which persons are perceived not baldly as such, as mere unadorned members of the human race, but as representatives of certain distinct categories of persons, specific sorts of individuals. In any given case, there are inevitably a plurality of such structures. Some, for example kinship terminologies, are ego-centered: that is, they define the status of an individual in terms of his relationship to a specific social actor. Others are centered on one or another subsystem or aspect of society and are invariant with respect to the perspectives of individual actors: noble ranks, age-group statuses, occupational categories. Some--personal names and sobriquets--are informal and particularizing; others--bureaucratic titles and caste designations--are formal and standardizing. The everyday world in which the members of any community move, their taken-for-granted field of social action, is populated not by anybodies, faceless men without qualities, but by somebodies, concrete classes of determinate persons positively characterized and appropriately labeled. And the symbol systems which define these classes are not given in the nature of things--they are historically constructed, socially maintained, and individually applied. Even a reduction of the task of cultural analysis to a concern only with those patterns having something to do with the characterization of individual persons renders it only slightly less formidable, however. This is because there does not yet exist a perfected theoretical framework within which to carry it out. What is called structural analysis in sociology and social anthropology can ferret out the functional implications for a society of a particular system of person-categories, and at times even predict how such a system might change under the impact of certain social processes; but only if the system--the categories, their meanings, and their logical relationships--can be taken as already known. Personality theory in social-psychology can uncover the motivational dynamics underlying the formation and the use of such systems and can assess their effect upon the character structures of individuals actually employing them; but also only if, in a sense, they are already given, if how the individuals in question see themselves and others has been somehow determined. What is needed is some systematic, rather than merely literary or impressionistic, way to discover what is given, what the conceptual structure embodied in the symbolic forms through which persons are perceived actually is. What we want and do not yet have is a developed method of describing and analyzing the meaningful structure of experience (here, the experience of persons) as it is apprehended by representative members of a particular society at a particular point in time--in a word, a scientific phenomenology of culture. |
文化の研究 最近の社会科学の理論の多くは、2つの主要な分析概念、すなわち「文化」と「社会構造」を区別し、特定しようとする試みに基づいている。1 この取り組みの原動力は、ヘーゲル主義やマルクス主義の還元主義に屈することなく、社会過程における観念的要因を考慮に入れようとする願望から生じてい る。思想、概念、価値、表現形式を、社会の組織が歴史の硬い表面に投げかける影として、あるいは歴史の魂として、その進歩は内部の弁証法の産物に過ぎない としてみなすことを避けるためには、 それらを独立した、しかし自己充足的なものではない力として捉えることが必要である。すなわち、それらは特定の社会的な文脈の中でのみ作用し、影響を及ぼ す。それらはその文脈に適応し、刺激されるが、その文脈に対しては、程度の差こそあれ、決定的な影響力を持つ。「あなたは本当に、ルネサンス期ヨーロッパ の偉大な商人たち、つまり布や香辛料の商人、銅や水銀やミョウバンの独占業者、王や皇帝の銀行家たちについて、彼らの商品だけを知ることで理解できると期 待しているのか?」とマーク・ブロックは著書『歴史家の技法』で書いている。彼らはホルバインによって描かれ、エラスムスやルターを読んでいたことを念頭 に置いてほしい。中世の臣下が領主に対して取る態度を理解するには、領主が神に対して取る態度についても知っておく必要がある。」社会活動の組織、その制 度形態、そしてそれを活性化する思想体系は、それらの間に存在する関係の性質と同様に理解されなければならない。社会構造と文化の概念を明確にしようとす る試みは、まさにこの目的のために行われてきた。 しかし、この二面性のある発展の中で、より難治性があり、より遅れたままであるのは文化的な側面であることは疑いの余地がない。本質的に、個々人や集団間 の経済、政治、社会関係よりも、思想の方が科学的に扱うのが難しい。そして、ルターやエラスムスの明白な教義、あるいはホルバインの明晰なイメージではな く、半ば形成され、当然視され、無関心に体系化された概念が、日常生活における一般人の通常の活動を導くものである場合、この傾向はさらに強まる。文化の 科学的調査が遅れ、単なる記述主義に陥りがちであるのは、その主題が捉えどころのないものだからである。あらゆる科学の初期の問題、すなわち、分析可能な 形で研究対象を定義するという問題は、ここでは解決が非常に難しいことが判明した。 この点において、思考は基本的に社会的行為であり、他の社会的行為が起こるのと同じ公共の世界で行われるという考え方が、最も建設的な役割を果たすことが できる。思考は、ギルバート・ライルが「頭の中の秘密の洞窟」と呼んだ場所にある神秘的なプロセスではなく、意味のあるシンボル(儀式や道具、偶像や水 場、ジェスチャー、印、イメージ、音など)のやりとりから成り立っているという見解は、文化研究を 。2 思考の物質的な媒体である象徴が体現する意味は、しばしば捉えどころがなく、曖昧で、変動し、複雑であるが、それらは、特にそれらを認識する人々が多少協 力すれば、水素の原子量や副腎の機能を発見するのと同様に、体系的な実証的調査によって発見できる可能性がある。人間は、重要なシンボルを秩序ある集合体 として体系化した文化パターンを通じて、自らが生きる出来事を理解する。文化の研究とは、このようなパターンの集積全体を研究することであり、したがっ て、個人や個人集団が、それ以外の点では不透明な世界で自己を方向づけるために用いる仕組みの研究である。 特定の社会において一般的に受け入れられ、頻繁に使用される文化パターンの数は極めて多いため、最も重要なものを整理し、それらの間に存在するであろう関 係性をすべて追跡することは、途方もない分析作業となる。しかし、特定の種類のパターンやパターン間の特定の種類の関係性が社会から社会へと繰り返される という事実によって、この作業はいくらか軽減される。その理由は単純で、それらのパターンや関係性が果たす方向付けの要件は、一般的に人間的なものだから である。問題は実存的なものであるため普遍的であり、その解決策は人間的なものであるため多様である。しかし、これらの独特な解決策を状況に応じて理解す ること、そして私の意見では、それによってのみ、それらに匹敵する対応である根本的な問題の本質を真に理解することができる。多くの知識分野と同様に、科 学の壮大な抽象概念への道は、特異な事実の茂みを通り抜ける。 こうした広範な方向性の必要性のひとつは、間違いなく個々の人間を特徴づけることである。世界中の人々は、人間を単に飾り気のない人類の一員としてではな く、特定のカテゴリーに属する個人、特定の種類の個体として認識する記号体系を発達させてきた。いずれの場合も、このような構造は必然的に複数存在する。 例えば、親族関係の用語は自己中心的なものである。つまり、特定の社会的行為者との関係性において個人の地位を定義する。一方、社会のサブシステムや側面 のいずれかに焦点を当て、個々の行為者の視点とは無関係に変化しないものもある。例えば、貴族の位階、年齢層別の地位、職業カテゴリーなどである。個人名 や通称は非公式で個別化されたものである。一方、官僚的な肩書きやカーストの呼称は公式で標準化されたものである。 あらゆるコミュニティのメンバーが日常的に活動する世界、すなわち、社会活動の当然視された領域には、無名で特徴のない「だれでもない人々」ではなく、 「だれか」が存在する。「だれか」とは、明確な特徴を持ち、適切にラベル付けされた特定の個人階級である。そして、これらのカテゴリーを定義する記号体系 は、物事の本質として与えられているわけではない。それは歴史的に構築され、社会的に維持され、個別的に適用されるものである。 文化分析の課題を、個人の性格付けに関係するパターンだけに絞っても、それは依然として非常に困難な課題であることに変わりはない。なぜなら、それを実行 するための完成された理論的枠組みがまだ存在しないからだ。社会学や社会人類学で構造分析と呼ばれるものは、ある特定の個人カテゴリーの体系が社会に及ぼ す機能的意味を明らかにし、時には、ある特定の社会過程の影響下でそのような体系がどのように変化するかを予測することさえできる。しかし、体系(カテゴ リー、その意味、およびそれらの論理的関係)がすでに既知のものとして扱える場合に限られる。社会心理学における性格理論は、このような体系の形成と使用 の根底にある動機づけの力学を明らかにし、実際にそれを使用している個人の性格構造に対するその影響を評価することができる。しかし、それはある意味で、 すでに与えられている場合に限られる。つまり、問題となっている個人が自分自身と他者をどのように見ているかが、何らかの方法で決定されている場合に限ら れる。必要なのは、単に文学的あるいは印象的なものではなく、体系的な方法で、人が何を前提としているのか、人がどのように認識されるかという象徴的な形 態に具体化された概念的構造が実際にはどのようなものなのかを発見することである。私たちが望んでいるが、まだ持っていないのは、特定の社会の代表的な構 成員が特定の時点で把握する経験(ここでは、人の経験)の意味構造を記述し分析する発展した方法である。つまり、一言で言えば、科学的な文化現象学であ る。 |
| Predecessors, Contemporaries,
Consociates, and Successors There have been, however, a few scattered and rather abstract ventures in cultural analysis thus conceived, from the results of which it is possible to draw some useful leads into our more focused inquiry. Among the more interesting of such forays are those which were carried out by the late philosopher-cum-sociologist Alfred Sch¸tz, whose work represents a somewhat heroic, yet not unsuccessful, attempt to fuse influences stemming from Scheler, Weber, and Husserl on the one side with ones stemming from James, Mead, and Dewey on the other.3 Sch¸tz covered a multitude of topics--almost none of them in terms of any extended or systematic consideration of specific social processes--seeking always to uncover the meaningful structure of what he regarded as "the paramount reality" in human experience: the world of daily life as men confront it, act in it, and live through it. For our own purposes, one of his exercises in speculative social phenomenology--the disaggregation of the blanket notion of "fellowmen" into "predecessors," "contemporaries," "consociates," and "successors" --provides an especially valuable starting point. Viewing the cluster of culture patterns Balinese use to characterize individuals in terms of this breakdown brings out, in a most suggestive way, the relationships between conceptions of personal identity, conceptions of temporal order, and conceptions of behavioral style which, as we shall see, are implicit in them. The distinctions themselves are not abstruse, but the fact that the classes they define overlap and interpenetrate makes it difficult to formulate them with the decisive sharpness analytical categories demand. "Consociates" are individuals who actually meet, persons who encounter one another somewhere in the course of daily life. They thus share, however briefly or superficially, not only a community of time but also of space. They are "involved in one another's biography" at least minimally; they "grow older together" at least momentarily, interacting directly and personally as egos, subjects, selves. Lovers, so long as love lasts, are consociates, as are spouses until they separate or friends until they fall out. So also are members of orchestras, players at games, strangers chatting on a train, hagglers in a market, or inhabitants of a village: any set of persons who have an immediate, face-to-face relationship. It is, however, persons having such relations more or less continuously and to some enduring purpose, rather than merely sporadically or incidentally, who form the heart of the category. The others shade over into being the second sort of fellowmen: "contemporaries." Contemporaries are persons who share a community of time but not of space: they live at (more or less) the same period of history and have, often very attenuated, social relationships with one another, but they do not--at least in the normal course of things--meet. They are linked not by direct social interaction but through a generalized set of symbolically formulated (that is, cultural) assumptions about each other's typical modes of behavior. Further, the level of generalization involved is a matter of degree, so that the graduation of personal involvement in consociate relations from lovers through chance acquaintances--relations also culturally governed, of course--here continues until social ties slip off into a thoroughgoing anonymity, standardization, and interchangeability: Thinking of my absent friend A., I form an ideal type of his personality and behavior based on my past experience of A. as my consociate. Putting a letter in a mailbox, I, expect that unknown people, called postmen, will act in a typical way, not quite intelligible to me, with the result that my letter will reach the addressee within typically reasonable time. Without ever having met a Frenchman or a German, I understand "Why France fears the rearmament of Germany." Complying with a rule of English grammar, I follow [in my writings] a socially-approved behavior pattern of contemporary English-speaking fellow-men to which I have to adjust to make myself understandable. And, finally, any artifact or utensil refers to the anonymous fellow-man who produced it to be used by other anonymous fellow-men for attaining typical goals by typical means. These are just a few of the examples but they are arranged according to the degree of increasing anonymity involved and therewith of the construct needed to grasp the Other and his behavior.4 Finally, "predecessors" and "successors" are individuals who do not share even a community of time and so, by definition, cannot interact; and, as such, they form something of a single class over against both consociates and contemporaries, who can and do. But from the point of view of any particular actor they do not have quite the same significance. Predecessors, having already lived, can be known or, more accurately, known about, and their accomplished acts can have an influence upon the lives of those for whom they are predecessors (that is, their successors), though the reverse is, in the nature of the case, not possible. Successors, on the other hand, cannot be known, or even known about, for they are the unborn occupants of an unarrived future; and though their lives can be influenced by the accomplished acts of those whose successors they are (that is, their predecessors), the reverse is again not possible.5 For empirical purposes, however, it is more useful to formulate these distinctions less strictly also, and to emphasize that, like those setting off consociates from contemporaries, they are relative and far from clear-cut in everyday experience. With some exceptions, our older consociates and contemporaries do not drop suddenly into the past, but fade more or less gradually into being our predecessors as they age and die, during which period of apprentice ancestorhood we may have some effect upon them, as children so often shape the closing phases of their parents' lives. And our younger consociates and contemporaries grow gradually into becoming our successors, so that those of us who live long enough often have the dubious privilege of knowing who is to replace us and even occasionally having some glancing influence upon the direction of his growth. "Consociates," "contemporaries," "predecessors," and "successors" are best seen not as pigeonholes into which individuals distribute one another for classificatory purposes, but as indicating certain general and not altogether distinct, matter-of-fact relationships which individuals conceive to obtain between themselves and others. But again, these relationships are not perceived purely as such; they are grasped only through the agency of cultural formulations of them. And, being culturally formulated, their precise character differs from society to society as the inventory of available culture patterns differs; from situation to situation within a single society as different patterns among the plurality of those which are available are deemed appropriate for application; and from actor to actor within similar situations as idiosyncratic habits, preferences, and interpretations come into play. There are, at least beyond infancy, no neat social experiences of any importance in human life. Everything is tinged with imposed significance, and fellowmen, like social groups, moral obligations, political institutions, or ecological conditions are apprehended only through a screen of significant symbols which are the vehicles of their objectification, a screen that is therefore very far from being neutral with respect to their "real" nature. Consociates, contemporaries, predecessors, and successors are as much made as born.6 |
先人、同時代人、協力者、後継者 しかし、このような文化分析はこれまでにも断片的に、またかなり抽象的に試みられてきた。その成果から、より焦点を絞った調査に役立ついくつかの手がかり を引き出すことができる。そうした試みの中でも特に興味深いものの一つは、哲学者であり社会学者でもあった故アルフレッド・シュッツ(Alfred Sch?tz)によるもので、彼の研究は、シェーラー(Scheler)、ウェーバー(Weber)、フッサール(Husserl)に由来する影響と、 ジェームズ(James)、ミード(Mead)、デューイ(Dewey)に由来する影響とを融合させるという、ある意味で英雄的な、しかし決して失敗では ない試みを表している 。3 シュッツは、数多くのテーマを扱ったが、そのほとんどは特定の社会的プロセスに関する拡張的または体系的な考察という観点からはほとんどなかった。彼は、 人間が直面し、その中で行動し、その中で生きる日常生活の世界という、人間経験における「最も重要な現実」とみなされるものの意味のある構造を明らかにし ようと常に努めていた。我々の目的のためには、彼の思索的社会現象学の研究のひとつである「同胞」という包括的な概念を「先人」、「同時代人」、「仲 間」、「後継者」に分解するという試みは、特に価値ある出発点となる。バリ人がこの分類を用いて個人の特徴を表現する文化パターンの集合を観察すると、個 人としてのアイデンティティの概念、時間的秩序の概念、行動様式の概念の関係が、非常に示唆的な形で浮かび上がる。 これらの分類自体は難解なものではないが、各分類が重なり合い、相互に浸透しているという事実により、分析カテゴリーが要求するような明確な鋭さをもって それらを定式化することが困難になっている。「コンソシエイト」とは、実際に顔を合わせる人々、日常生活のどこかで互いに遭遇する人々のことである。 したがって、彼らは、たとえそれが短時間であったり表面的なものであったとしても、時間だけでなく空間も共有している。 彼らは少なくとも最低限、「互いの伝記に関わっている」し、少なくとも瞬間的には「一緒に年を取っている」のである。自我、主体、自己として直接かつ個人 的に交流しているのだ。愛が続く限り、恋人たちは仲間であり、別れるまで夫婦であり、仲違いするまでは友人である。オーケストラの団員、ゲームの対戦相 手、電車の中で立ち話をしている見知らぬ人々、市場での値引き交渉者、村の住人など、即座に顔を合わせる関係にある人々の集まりも同様である。しかし、こ のカテゴリーの中心となるのは、単に散発的または偶発的にではなく、ある程度継続的に、そして何らかの持続的な目的を持ってそのような関係を持つ人々であ る。それ以外の人は、2番目の種類の同胞である「同時代人」に分類される。 同時代人とは、空間ではなく時間を共有する人々である。彼らは(多少の差こそあれ)ほぼ同じ時代に生き、お互いに非常に希薄な社会的関係を持っているが、 少なくとも通常の流れにおいては、出会うことはない。彼らは直接的な社会的交流によってではなく、お互いの典型的な行動様式に関する象徴的に定式化された (つまり文化的)前提条件の一般化された集合によって結びついている。さらに、この一般化の度合いには程度の問題があるため、恋人から偶然の知り合いま で、文化によっても支配されている共同関係における個人的関与の段階は、 不在の友人Aのことを考えると、私は共同者としてのAとの過去の経験に基づいて、Aの人格と行動の理想型を思い描く。郵便ポストに手紙を投函するとき、私 は、郵便配達人と呼ばれる見知らぬ人々が、私には理解できない典型的な行動を取ることを期待する。その結果、私の手紙は通常妥当な時間内に宛先に届く。フ ランス人やドイツ人に会ったことがないにもかかわらず、私は「なぜフランスはドイツの再軍備を恐れるのか」を理解している。英語の文法の規則に従い、私は (自分の文章において)現代の英語話者たちの間で社会的に承認された行動パターンに従っている。そして、最終的に、あらゆる人工物や道具は、それを生産し た匿名の人物を指し、他の匿名の人物が典型的な手段で典型的な目標を達成するために使用される。これらはほんの一例に過ぎないが、匿名性の度合いに従って 分類されており、それによって「他者」とその行動を把握するために必要な構造が示されている。 最後に、「前任者」と「後任者」は、時間的にも共通点を持たないため、定義上、相互作用を持つことはできない。しかし、特定の行為者の観点から見ると、彼 らはまったく同じ重要性を持っているわけではない。先人たちはすでに生きていたので、知られている、あるいはより正確に言えば、知られている可能性があ る。彼らの成し遂げた行為は、彼らにとっての先人(つまり、彼らの後継者)の人生に影響を与える可能性がある。しかし、その逆は、本質的に不可能である。 一方、後継者は、まだ生まれていない未来の住人であるため、知られることも、知られることもない。また、後継者の先人(すなわち、先人)の達成された行為 によって、後継者の生活が影響を受けることはあっても、その逆はありえない。5 しかし経験的な目的のためには、これらの区別もあまり厳密に定式化せず、共同体の構成員と同時代の人々を区別するのと同様に、日常的な経験においては相対 的で明確なものではないことを強調する方がより有益である。いくつかの例外はあるものの、私たちの年長のコソシエイトや同時代人は、突然過去に消え去るの ではなく、年齢を重ねて死を迎えるにつれ、徐々に先人へとフェードアウトしていく。その間、私たちは見習い先祖として、彼らに少なからず影響を与える可能 性がある。子供が親の晩年を形作るように、というように。そして、私たちの若い仲間や同世代の人々は、徐々に私たちの後継者へと成長していく。そのため、 長生きする人ほど、誰が自分の後を継ぐことになるのかを知るという疑わしい特権を持ち、時にはその成長の方向性にわずかながら影響を与えることもある。 「同輩」、「同時代人」、「前任者」、「後継者」は、分類目的で個人が互いを振り分けるための分類項目としてではなく、個人と他者との間に存在すると考え られる、一般的で、完全に区別できるものではない、ある種の事実上の関係を示すものとして捉えるのが最善である。 しかし、繰り返しになるが、これらの関係は純粋にそれ自体として認識されるものではない。それらは、文化的な定式化を通じてのみ把握される。そして、文化 的に形成されているため、利用可能な文化パターンの品揃えが異なるため、社会によってその正確な性質は異なる。また、ひとつの社会の中でも、適用に適して いるとみなされる利用可能なパターンのうちの異なるパターンが存在するため、状況によっても異なる。さらに、類似した状況の中でも、独特の習慣、好み、解 釈が関わってくるため、行為者によっても異なる。少なくとも乳幼児期を過ぎた後においては、人間の生活において重要な、きちんとした社会経験など存在しな い。すべてに意味が与えられ、同時代の人々、社会集団、道徳的義務、政治制度、あるいは生態学的条件は、客観化の手段である象徴のフィルターを通してのみ 理解される。したがって、その「本質」に関して中立であるとは程遠い。仲間、同時代の人々、先人、後輩は、生まれながらに存在するのと同様に、作られた存 在でもある。 |
| Balinese Orders of
Person-Definition In Bali,7 there are six sorts of labels which one person can apply to another in order to identify him as a unique individual and which I want to consider against this general conceptual background: (1) personal names; (2) birth order names; (3) kinship terms; (4) teknonyms; (5) status titles (usually called "caste names" in the literature on Bali); and (6) public titles, by which I mean quasi-occupational titles borne by chiefs, rulers, priests, and gods. These various labels are not, in most cases, employed simultaneously, but alternatively, depending upon the situation and sometimes the individual. They are not, also, all the sorts of such labels ever used; but they are the only ones which are generally recognized and regularly applied. And as each sort consists not of a mere collection of useful tags but of a distinct and bounded terminological system, I shall refer to them as "symbolic orders of person-definition" and consider them first serially, only later as a more or less coherent cluster. PERSONAL NAMES The symbolic order defined by personal names is the simplest to describe because it is in formal terms the least complex and in social ones the least important. All Balinese have personal names, but they rarely use them, either to refer to themselves or others or in addressing anyone. (With respect to one's forebears, including one's parents, it is in fact sacrilegious to use them.) Children are more often referred to and on occasion even addressed by their personal names. Such names are therefore sometimes called "child" or "little" names, though once they are ritually bestowed 105 days after birth, they are maintained unchanged through the whole course of a man's life. In general, personal names are seldom heard and play very little public role. Yet, despite this social marginality, the personal-naming system has some characteristics which, in a rather left-handed way, are extremely significant for an understanding of Balinese ideas of personhood. First, personal names are, at least among the commoners (some 90 percent of the population), arbitrarily coined nonsense syllables. They are not drawn from any established pool of names which might lend to them any secondary significance as being "common" or "unusual," as reflecting someone's being named "after" someone--an ancestor, a friend of the parents, a famous personage--or as being propitious, suitable, characteristic of a group or region, indicating a kinship relation, and so forth.8 Second, the duplication of personal names within a single community--that is, a politically unified, nucleated settlement--is studiously avoided. Such a settlement (called a bandjar, or "hamlet") is the primary face-to-face group outside the purely domestic realm of the family, and in some respects is even more intimate. Usually highly endogamous and always highly corporate, the hamlet is the Balinese world of consociates par excellence; and, within it, every person possesses, however unstressed on the social level, at least the rudiments of a completely unique cultural identity. Third, personal names are monomials, and so do not indicate familial connections, or in fact membership in any sort of group whatsoever. And, finally, there are (a few rare, and in any case only partial, exceptions aside) no nicknames, no epithets of the "Richard-the-Lion-Hearted" or "Ivan-the-Terrible" sort among the nobility, not even any diminutives for children or pet names for lovers, spouses, and so on. Thus, whatever role the symbolic order of person-definition marked out by the personal-naming system plays in setting Balinese off from one another or in ordering Balinese social relations is essentially residual in nature. One's name is what remains to one when all the other socially much more salient cultural labels attached to one's person are removed. As the virtually religious avoidance of its direct use indicates, a personal name is an intensely private matter. Indeed, toward the end of a man's life, when he is but a step away from being the deity he will become after his death and cremation, only he (or he and a few equally aged friends) may any longer know what in fact it is; when he disappears it disappears with him. In the well-lit world of everyday life, the purely personal part of an individual's cultural definition, that which in the context of the immediate consociate community is most fully and completely his, and his alone, is highly muted. And with it are muted the more idiosyncratic, merely biographical, and, consequently, transient aspects of his existence as a human being (what, in our more egoistic framework, we call his "personality") in favor of some rather more typical, highly conventionalized, and, consequently, enduring ones. BIRTH ORDER NAMES The most elementary of such more standardized labels are those automatically bestowed upon a child, even a stillborn one, at the instant of its birth, according to whether it is the first, second, third, fourth, etc., member of a sibling set. There is some local and status-group variation in usage here, but the most common system is to use Wayan for the first child, Njoman for the second, Made (or Nengah) for the third, and Ktut for the fourth, beginning the cycle over again with Wayan for the fifth, Njoman for the sixth, and so on. These birth order names are the most frequently used terms of both address and reference within the hamlet for children and for young men and women who have not yet produced offspring. Vocatively, they are almost always used simply, that is, without the addition of the personal name: "Wayan, give me the hoe," and so forth. Referentially, they may be supplemented by the personal name, especially when no other way is convenient to get across which of the dozens of Wayans or Njomans in the hamlet is meant: "No, not Wayan Rugrug, Wayan Kepig," and so on. Parents address their own children and childless siblings address one another almost exclusively by these names, rather than by either personal names or kin terms. For persons who have had children, however, they are never used either inside the family or out, teknonyms being employed, as we shall see, instead, so that, in cultural terms, Balinese who grow to maturity without producing children (a small minority) remain themselves children--that is, are symbolically pictured as such--a fact commonly of great shame to them and embarrassment to their consociates, who often attempt to avoid having to use vocatives to them altogether.9 The birth order system of person-definition represents, therefore, a kind of plus Áa change approach to the denomination of individuals. It distinguishes them according to four completely contentless appellations, which neither define genuine classes (for there is no conceptual or social reality whatsoever to the class of all Wayans or all Ktuts in a community), nor express any concrete characteristics of the individuals to whom they are applied (for there is no notion that Wayans have any special psychological or spiritual traits in common against Njomans or Ktuts). These names, which have no literal meaning in themselves (they are not numerals or derivatives of numerals) do not, in fact, even indicate sibling position or rank in any realistic or reliable way.10 A Wayan may be a fifth (or ninth!) child as well as a first; and, given a traditional peasant demographic structure--great fertility plus a high rate of stillbirths and deaths in infancy and childhood--a Made or a Ktut may actually be the oldest of a long string of siblings and a Wayan the youngest. What they do suggest is that, for all procreating couples, births form a circular succession of Wayans, Njomans, Mades, Ktuts, and once again Wayans, an endless four-stage replication of an imperishable form. Physically men come and go as the ephemerae they are, but socially the dramatis personae remain eternally the same as new Wayans and Ktuts emerge from the timeless world of the gods (for infants, too, are but a step away from divinity) to replace those who dissolve once more into it. KINSHIP TERMS Formally, Balinese kinship terminology is quite simple in type, being of the variety known technically as "Hawaiian" or "Generational." In this sort of system, an individual classifies his relatives primarily according to the generation they occupy with respect to his own. That is to say, siblings, half-siblings, and cousins (and their spouses' siblings, and so forth) are grouped together under the same term; all uncles and aunts on either side are terminologically classed with mother and father; all children of brothers, sisters, cousins, and so on (that is, nephews of one sort or another) are identified with own children; and so on, downward through the grandchild, great-grandchild, etc., generations, and upward through the grandparent, great-grandparent, etc., ones. For any given actor, the general picture is a layer-cake arrangement of relatives, each layer consisting of a different generation of kin--that of actor's parents or his children, of his grandparents or his grandchildren, and so on, with his own layer, the one from which the calculations are made, located exactly halfway up the cake.11 Given the existence of this sort of system, the most significant (and rather unusual) fact about the way it operates in Bali is that the terms it contains are almost never used vocatively, but only referentially, and then not very frequently. With rare exceptions, one does not actually call one's father (or uncle) "father," one's child (or nephew/niece) "child," one's brother (or cousin) "brother," and so on. For relatives genealogically junior to oneself vocative forms do not even exist; for relatives senior they exist but, as with personal names, it is felt to demonstrate a lack of respect for one's elders to use them. In fact, even the referential forms are used only when specifically needed to convey some kinship information as such, almost never as general means of identifying people. Kinship terms appear in public discourse only in response to some question, or in describing some event which has taken place or is expected to take place, with respect to which the existence of the kin tie is felt to be a relevant piece of information. ("Are you going to Fatherof-Regreg's tooth-filing?" "Yes, he is my 'brother.'") Thus, too, modes of address and reference within the family are no more (or not much more) intimate or expressive of kin ties in quality than those within the hamlet generally. As soon as a child is old enough to be capable of doing so (say, six years, though this naturally varies) he calls his mother and father by the same term--a teknonym, status group title, or public title--that everyone else who is acquainted with them uses toward them, and is called in turn Wayan, Ktut, or whatever, by them. And, with even more certainty, he will refer to them, whether in their hearing or outside of it, by this popular, extradomestic term as well. In short, the Balinese system of kinship terminology defines individuals in a primarily taxonomic, not a face-to-face idiom, as occupants of regions in a social field, not partners in social interaction. It functions almost entirely as a cultural map upon which certain persons can be located and certain others, not features of the landscape mapped, cannot. Of course, some notions of appropriate interpersonal behavior follow once such determinations are made, once a person's place in the structure is ascertained. But the critical point is that, in concrete practice, kin terminology is employed virtually exclusively in service of ascertainment, not behavior, with respect to whose patterning other symbolic appliances are dominant.12 The social norms associated with kinship, though real enough, are habitually overridden, even within kinship-type groups themselves (families, households, lineages) by culturally better armed norms associated with religion, politics, and, most fundamentally of all, social stratification. Yet in spite of the rather secondary role it plays in shaping the moment-to-moment flow of social intercourse, the system of kinship terminology, like the personal-naming system, contributes importantly, if indirectly, to the Balinese notion of personhood. For, as a system of significant symbols, it too embodies a conceptual structure under whose agency individuals, one's self as well as others, are apprehended; a conceptual structure which is, moreover, in striking congruence with those embodied in the other, differently constructed and variantly oriented, orders of person-definition. Here, also, the leading motif is the immobilization of time through the iteration of form. This iteration is accomplished by a feature of Balinese kin terminology I have yet to mention: in the third generation above and below the actor's own, terms become completely reciprocal. That is to say, the term for "great-grandparent" and "great-grandchild" is the same: kumpi. The two generations, and the individuals who comprise them, are culturally identified. Symbolically, a man is equated upwardly with the most distant ascendant, downwardly with the most distant descendant, he is ever likely to interact with as a living person. Actually, this sort of reciprocal terminology proceeds on through the fourth generation, and even beyond. But as it is only extremely rarely that the lives of a man and his great-great-grandparent (or great-greatgrandchild) overlap, this continuation is of only theoretical interest, and most people don't even know the terms involved. It is the four-generation span (i.e., the actor's own, plus three ascending or descending) which is considered the attainable ideal, the image, like our threescore-and-ten, of a fully completed life, and around which the kumpikumpi terminology puts, as it were, an emphatic cultural parenthesis. This parenthesis is accentuated further by the rituals surrounding death. At a person's funeral, all his relatives who are generationally junior to him must make homage to his lingering spirit in the Hindu palms-to-forehead fashion, both before his bier and, later, at the graveside. But this virtually absolute obligation, the sacramental heart of the funeral ceremony, stops short with the third descending generation, that of his "grandchildren." His "great-grandchildren" are his kumpi, as he is theirs, and so, the Balinese say, they are not really junior to him at all but rather "the same age." As such, they are not only not required to show homage to his spirit, but they are expressly forbidden to do so. A man prays only to the gods and, what is the same thing, his seniors, not to his equals or juniors.13 Balinese kinship terminology thus not only divides human beings into generational layers with respect to a given actor, it bends these layers into a continuous surface which joins the "lowest" with the "highest" so that, rather than a layer-cake image, a cylinder marked off into six parallel bands called "own," "parent," "grandparent," "kumpi," "grandchild," and "child" is perhaps more exact. 14 What at first glance seems a very diachronic formulation, stressing the ceaseless progression of generations is, in fact, an assertion of the essential unreality--or anyway the unimportance--of such a progression. The sense of sequence, of sets of collaterals following one another through time, is an illusion generated by looking at the terminological system as though it were used to formulate the changing quality of face-to-face interactions between a man and his kinsmen as he ages and dies--as indeed many, if not most such systems are used. When one looks at it, as the Balinese primarily do, as a common-sense taxonomy of the possible types of familial relationships human beings may have, a classification of kinsmen into natural groups, it is clear that what the bands on the cylinder are used to represent is the genealogical order of seniority among living people and nothing more. They depict the spiritual (and what is the same thing, structural) relations among coexisting generations, not the location of successive generations in an unrepeating historical process. TEKNONYMS If personal names are treated as though they were military secrets, birth order names applied mainly to children and young adolescents, and kinship terms invoked at best sporadically, and then only for purposes of secondary specification, how, then, do most Balinese address and refer to one another? For the great mass of the peasantry, the answer is: by teknonyms.15 As soon as a couple's first child is named, people begin to address and refer to them as "Father-of" and "Mother-of" Regreg, Pula, or whatever the child's name happens to be. They will continue to be so called (and to call themselves) until their first grandchild is born, at which time they will begin to be addressed and referred to as "Grandfatherof" and "Grandmother-of" Suda, Lilir, or whomever; and a similar transition occurs if they live to see their first great-grandchild.16 Thus, over the "natural" four-generation kumpi-to-kumpi life span, the term by which an individual is known will change three times, as first he, then at least one of his children, and finally at least one of his grandchildren produce offspring. Of course, many if not most people neither live so long nor prove so fortunate in the fertility of their descendants. Also, a wide variety of other factors enter in to complicate this simplified picture. But, subtleties aside, the point is that we have here a culturally exceptionally well developed and socially exceptionally influential system of teknonymy. What impact does it have upon the individual Balinese's perceptions of himself and his acquaintances? Its first effect is to identify the husband and wife pair, rather as the bride's taking on of her husband's surname does in our society; except that here it is not the act of marriage which brings about the identification but of procreation. Symbolically, the link between husband and wife is expressed in terms of their common relation to their children, grandchildren, or great-grandchildren, not in terms of the wife's incorporation into her husband's "family" (which, as marriage is highly endogamous, she usually belongs to anyway). This husband-wife--or, more accurately, father-mother--pair has very great economic, political, and spiritual importance. It is, in fact, the fundamental social building block. Single men cannot participate in the hamlet council, where seats are awarded by married couple; and, with rare exceptions, only men with children carry any weight there. (In fact, in some hamlets men are not even awarded seats until they have a child.) The same is true for descent groups, voluntary organizations, irrigation societies, temple congregations, and so on. In virtually all local activities, from the religious to the agricultural, the parental couple participates as a unit, the male performing certain tasks, the female certain complementary ones. By linking a man and a wife through an incorporation of the name of one of their direct descendants into their own, teknonymy underscores both the importance of the marital pair in local society and the enormous value which is placed upon procreation.17 This value also appears, in a more explicit way, in the second cultural consequence of the pervasive use of teknonyms: the classification of individuals into what, for want of a better term, may be called procreational strata. From the point of view of any actor, his hamletmates are divided into childless people, called Wayan, Made, and so on; people with children, called "Father (Mother)-of"; people with grandchildren, called "Grandfather (Grandmother)-of"; and people with greatgrandchildren, called "Great-grandparent-of." And to this ranking is attached a general image of the nature of social hierarchy: childless people are dependent minors; fathers-of are active citizens directing community life; grandfathers-of are respected elders giving sage advice from behind the scenes; and great-grandfathers-of are senior dependents, already half-returned to the world of the gods. In any given case, various mechanisms have to be employed to adjust this rather too-schematic formula to practical realities in such a way as to allow it to mark out a workable social ladder. But, with these adjustments, it does, indeed, mark one out, and as a result a man's "procreative status" is a major element in his social identity, both in his own eyes and those of everyone else. In Bali, the stages of human life are not conceived in terms of the processes of biological aging, to which little cultural attention is given, but of those of social regenesis. Thus, it is not sheer reproductive power as such, how many children one can oneself produce, that is critical. A couple with ten children is no more honored than a couple with five; and a couple with but a single child who has in turn but a single child outranks them both. What counts is reproductive continuity, the preservation of the community's ability to perpetuate itself just as it is, a fact which the third result of teknonymy, the designation of procreative chains, brings out most clearly. The way in which Balinese teknonymy outlines such chains can be seen from the model diagram (Figure 1 ). For simplicity, I have shown only the male teknonyms and have used English names for the referent generation. I have also arranged the model so as to stress the fact that teknonymous usage reflects the absolute age not the genealogical order (or the sex) of the eponymous descendants. FIGURE 1 Balinese Teknonymy (not available) NOTE: Mary is older than Don; Joe is older than Mary, Jane, and Don. The relative ages of all other people, save of course as they are ascendants and descendants, are irrelevant so far as teknonymy is concerned. As Figure 1 indicates, teknonymy outlines not only procreative statuses but specific sequences of such statuses, two, three, or four (very, very occasionally, five) generations deep. Which particular sequences are marked out is largely accidental: had Mary been born before Joe, or Don before Mary, the whole alignment would have been altered. But though the particular individuals who are taken as referents, and hence the particular sequences of filiation which receive symbolic recognition, is an arbitrary and not very consequential matter, the fact that such sequences are marked out stresses an important fact about personal identity among the Balinese: an individual is not perceived in the context of who his ancestors were (that, given the cultural veil which slips over the dead, is not even known), but rather in the context of whom he is ancestral to. One is not defined, as in so many societies of the world, in terms of who produced one, some more or less distant, more or less grand founder of one's line, but in terms of whom one has produced, a specific, in most cases still living, half-formed individual who is one's child, grandchild, or great-grandchild, and to whom one traces one's connection through a particular set of procreative links.18 What links "Great-grandfather-of-Joe," "Grandfather-of-Joe," and "Father-of-Joe" is the fact that, in a sense, they have cooperated to produce Joe--that is, to sustain the social metabolism of the Balinese people in general and their hamlet in particular. Again, what looks like a celebration of a temporal process is in fact a celebration of the maintenance of what, borrowing a term from physics, Gregory Bateson has aptly called a "steady state."19 In this sort of teknonymous regime, the entire population is classified in terms of its relation to and representation in that subclass of the population in whose hands social regenesis now most instantly lies--the oncoming cohort of prospective parents. Under its aspect even that most time-saturated of human conditions, great-grandparenthood, appears as but an ingredient in an unperishing present. STATUS TITLES In theory, everyone (or nearly everyone) in Bali bears one or another title--Ida Bagus, Gusti, Pasek, Dauh, and so forth--which places him on a particular rung in an all-Bali status ladder; each title represents a specific degree of cultural superiority or inferiority with respect to each and every other one, so that the whole population is sorted out into a set of uniformly graded castes. In fact, as those who have tried to analyze the system in such terms have discovered, the situation is much more complex. It is not simply that a few low-ranking villagers claim that they (or their parents) have somehow "forgotten" what their titles are; nor that there are marked inconsistencies in the ranking of titles from place to place, at times even from informant to informant; nor that, in spite of their hereditary basis, there are nevertheless ways to change titles. These are but (not uninteresting) details concerning the day-to-day working of the system. What is critical is that status titles are not attached to groups at all, but only to individuals.20 Status in Bali, or at least that sort determined by titles, is a personal characteristic; it is independent of any social structural factors whatsoever. It has, of course, important practical consequences, and those consequences are shaped by and expressed through a wide variety of social arrangements, from kinship groups to governmental institutions. But to be a Dewa, a Pulosari, a Pring, or a Maspadan is at base only to have inherited the right to bear that title and to demand the public tokens of deference associated with it. It is not to play any particular role, to belong to any particular group, or to occupy any particular economic, political, or sacerdotal position. The status title system is a pure prestige system. From a man's title you know, given your own title, exactly what demeanor you ought to display toward him and he toward you in practically every context of public life, irrespective of whatever other social ties obtain between you and whatever you may happen to think of him as a man. Balinese politesse is very highly developed and it rigorously controls the outer surface of social behavior over virtually the entire range of daily life. Speech style, posture, dress, eating, marriage, even house-construction, place of burial, and mode of cremation are patterned in terms of a precise code of manners which grows less out of a passion for social grace as such as out of some rather far-reaching metaphysical considerations. The sort of human inequality embodied in the status title system and the system of etiquette which expresses it is neither moral, nor economic, nor political--it is religious. It is the reflection in everyday interaction of the divine order upon which such interaction, from this point of view a form of ritual, is supposed to be modeled. A man's title does not signal his wealth, his power, or even his moral reputation, it signals his spiritual composition; and the incongruity between this and his secular position may be enormous. Some of the greatest movers and shakers in Bali are the most rudely approached, some of the most delicately handled the least respected. It would be difficult to conceive of anything further from the Balinese spirit than Machiavelli's comment that titles do not reflect honor upon men, but rather men upon their titles. In theory, Balinese theory, all titles come from the gods. Each has been passed along, not always without alteration, from father to child, like some sacred heirloom, the difference in prestige value of the different titles being an outcome of the varying degree to which the men who have had care of them have observed the spiritual stipulations embodied in them. To bear a title is to agree, implicitly at least, to meet divine standards of action, or at least approach them, and not all men have been able to do this to the same extent. The result is the existing discrepancy in the rank of titles and of those who bear them. Cultural status, as opposed to social position, is here once again a reflection of distance from divinity. Associated with virtually every title there are one or a series of legendary events, very concrete in nature, involving some spiritually significant misstep by one or another holder of the title. These offenses-one can hardly call them sins--are regarded as specifying the degree to which the title has declined in value, the distance which it has fallen from a fully transcendent status, and thus as fixing, in a general way at least, its position in the overall scale of prestige. Particular (if mythic) geographical migrations, cross--title marriages, military failures, breaches of mourning etiquette, ritual lapses, and the like are regarded as having debased the title to a greater or lesser extent: greater for the lower titles, lesser for the higher. Yet, despite appearances, this uneven deterioration is, in its essence, neither a moral nor an historical phenomenon. It is not moral because the incidents conceived to have occasioned it are not, for the most part, those against which negative ethical judgments would, in Bali any more than elsewhere, ordinarily be brought, while genuine moral faults (cruelty, treachery, dishonesty, profligacy) damage only reputations, which pass from the scene with their owners, not titles which remain. It is not historical because these incidents, disjunct occurrences in a once-upona-time, are not invoked as the causes of present realities but as statements of their nature. The important fact about title-debasing events is not that they happened in the past, or even that they happened at all, but that they are debasing. They are formulations not of the processes which have brought the existing state of affairs into being, nor yet of moral judgments upon it (in neither of which intellectual exercises the Balinese show much interest): they are images of the underlying relationship between the form of human society and the divine pattern of which it is, in the nature of things, an imperfect expression--more imperfect at some points than at others. But if, after all that has been said about the autonomy of the title system, such a relationship between cosmic patterns and social forms is conceived to exist, exactly how is it understood? How is the title system, based solely on religious conceptions, on theories of inherent differences in spiritual worth among individual men, connected up with what, looking at the society from the outside, we would call the "realities" of power, influence, wealth, reputation, and so on, implicit in the social division of labor? How, in short, is the actual order of social command fitted into a system of prestige ranking wholly independent of it so as to account for and, indeed, sustain the loose and general correlation between them which in fact obtains? The answer is: through performing, quite ingeniously, a kind of hat trick, a certain sleight of hand, with a famous cultural institution imported from India and adapted to local tastes--the Varna System. By means of the Varna System the Balinese inform a very disorderly collection of status pigeonholes with a simple shape which is represented as growing naturally out of it but which in fact is arbitrarily imposed upon it. As in India, the Varna System consists of four gross categories--Brahmana, Satria, Wesia, and Sudra--ranked in descending order of prestige, and with the first three (called in Bali, Triwangsa--"the three peoples") defining a spiritual patriciate over against the plebeian fourth. But in Bali the Varna System is not in itself a cultural device for making status discriminations but for correlating those already made by the title system. It summarizes the literally countless fine comparisons implicit in that system in a neat (from some points of view all-too-neat) separation of sheep from goats, and first-quality sheep from second, second from third.21 Men do not perceive one another as Satrias or Sudras but as, say, Dewas or Kebun Tubuhs, merely using the Satria-Sudra distinction to express generally, and for social organizational purposes, the order of contrast which is involved by identifying Dewa as a Satria title and Kebun Tubuh as a Sudra one. Varna categories are labels applied not to men, but to the titles they bear--they formulate the structure of the prestige system; titles, on the other hand, are labels applied to individual men--they place persons within that structure. To the degree that the Varna classification of titles is congruent with the actual distribution of power, wealth, and esteem in the society--that is, with the system of social stratification--the society is considered to be well ordered. The right sort of men are in the right sort of places: spiritual worth and social standing coincide. This difference in function between title and Varna is clear from the way in which the symbolic forms associated with them are actually used. Among the Triwangsa gentry, where, some exceptions aside, teknonymy is not employed, an individual's title is used as his or her main term of address and reference. One calls a man Ida Bagus, Njakan, or Gusi (not Brahmana, Satria, or Wesia) and refers to him by the same terms, sometimes adding a birth order name for more exact specification ( Ida Bagus Made, Njakan Njoman, and so forth). Among the Sudras, titles are used only referentially, never in address, and then mainly with respect to members of other hamlets than one's own, where the person's teknonym may not be known, or, if known, considered to be too familiar in tone to be used for someone not a hamletmate. Within the hamlet, the referential use of Sudra titles occurs only when prestige status information is considered relevant ("Father-of-Joe is a Kedisan, and thus 'lower' than we Pande," and so on), while address is, of course, in terms of teknonyms. Across hamlet lines, where, except between close friends, teknonyms fall aside, the most common term of address is Djero. Literally, this means "inside" or "insider," thus a member of the Triwangsa, who are considered to be "inside," as against the Sudras, who are "outside" (Djaba); but in this context it has the effect of saying, "In order to be polite, I am addressing you as though you were a Triwangsa, which you are not (if you were, I would call you by your proper title), and I expect the same pretense from you in return." As for Varna terms, they are used, by Triwangsa and Sudra alike, only in conceptualizing the overall prestige hierarchy in general terms, a need which usually appears in connection with transhamlet political, sacerdotal, or stratificatory matters: "The kings of Klungkung are Satrias, but those of Tabanan only Wesias," or "There are lots of rich Brahmanas in Sanur, which is why the Sudras there have so little to say about hamlet affairs," and so on. The Varna System thus does two things. It connects up a series of what appear to be ad hoc and arbitrary prestige distinctions, the titles, with Hinduism, or the Balinese version of Hinduism, thus rooting them in a general world view. And it interprets the implications of that world view, and therefore the titles, for social organization: the prestige gradients implicit in the title system ought to be reflected in the actual distribution of wealth, power, and esteem in society, and, in fact, be completely coincident with it. The degree to which this coincidence actually obtains is, of course, moderate at best. But, however many exceptions there may be to the rule--Sudras with enormous power, Satrias working as tenant farmers, Brahmanas neither esteemed nor estimable--it is the rule and not the exceptions that the Balinese regard as truly illuminating the human condition. The Varna System orders the title system in such a way as to make it possible to view social life under the aspect of a general set of cosmological notions: notions in which the diversity of human talent and the workings of historical process are regarded as superficial phenomena when compared with the location of persons in a system of standardized status categories, as blind to individual character as they are immortal. PUBLIC TITLES This final symbolic order of person-definition is, on the surface, the most reminiscent of one of the more prominent of our own ways of identifying and characterizing individuals.22 We, too, often (all too often, perhaps) see people through a screen of occupational categories --as not just practicing this vocation or that, but as almost physically infused with the quality of being a postman, teamster, politician, or salesman. Social function serves as the symbolic vehicle through which personal identity is perceived; men are what they do. The resemblance is only apparent, however. Set amid a different cluster of ideas about what selfhood consists in, placed against a different religio-philosophical conception of what the world consists in, and expressed in terms of a different set of cultural devices--public titles --for portraying it, the Balinese view of the relation between social role and personal identity gives a quite different slant to the ideographic significance of what we call occupation but the Balinese call linggih-"seat," "place," "berth." This notion of "seat" rests on the existence in Balinese thought and practice of an extremely sharp distinction between the civic and domestic sectors of society. The boundary between the public and private domains of life is very clearly drawn both conceptually and institutionally. At every level, from the hamlet to the royal palace, matters of general concern are sharply distinguished and carefully insulated from matters of individual or familial concern, rather than being allowed to interpenetrate as they do in so many other societies. The Balinese sense of the public as a corporate body, having interests and purposes of its own, is very highly developed. To be charged, at any level, with special responsibilities with respect to those interests and purposes is to be set aside from the run of one's fellowmen who are not so charged, and it is this special status that public titles express. At the same time, though the Balinese conceive the public sector of society as bounded and autonomous, they do not look upon it as forming a seamless whole, or even a whole at all. Rather they see it as consisting of a number of separate, discontinuous, and at times even competitive realms, each self-sufficient, self-contained, jealous of its rights, and based on its own principles of organization. The most salient of such realms include: the hamlet as a corporate political community; the local temple as a corporate religious body, a congregation; the irrigation society as a corporate agricultural body; and, above these, the structures of regional--that is, suprahamlet--government and worship, centering on the nobility and the high priesthood. A description of these various public realms or sectors would involve an extensive analysis of Balinese social structure inappropriate in the present context.23 The point to be made here is that, associated with each of them, there are responsible officers--stewards is perhaps a better term--who as a result bear particular titles: Klian, Perbekel, Pekaseh, Pemangku, Anak Agung, Tjakorda, Dewa Agung, Pedanda, and so on up to perhaps a half a hundred or more. And these men (a very small proportion of the total population) are addressed and referred to by these official titles--sometimes in combination with birth order names, status titles, or, in the case of Sudras, teknonyms for purposes of secondary specification.24 The various "village chiefs" and "folk priests" on the Sudra level, and, on the Triwangsa, the host of "kings," "princes," "lords," and "high priests" do not merely occupy a role. They become, in the eyes of themselves and those around them, absorbed into it. They are truly public men, men for whom other aspects of personhood--individual character, birth order, kinship relations, procreative status, and prestige rank take, symbolically at least, a secondary position. We, focusing upon psychological traits as the heart of personal identity, would say they have sacrificed their true selves to their role; they, focusing on social position, say that their role is of the essence of their true selves. Access to these public-title-bearing roles is closely connected with the system of status titles and its organization into Varna categories, a connection effected by what may be called "the doctrine of spiritual eligibility." This doctrine asserts that political and religious "seats" of translocal--regional or Bali-wide--significance are to be manned only by Triwangsas, while those of local significance ought properly to be in the hands of Sudras. At the upper levels the doctrine is strict: only Satrias--that is, men bearing titles deemed of Satria rank--may be kings or paramount princes, only Wesias or Satrias lords or lesser princes, only Brahmanas high priests, and so on. At the lower levels, it is less strict; but the sense that hamlet chiefs, irrigation society heads, and folk priests should be Sudras, that Triwangsas should keep their place, is quite strong. In either case, however, the overwhelming majority of persons bearing status titles of the Varna category or categories theoretically eligible for the stewardship roles to which the public titles are attached do not have such roles and are not likely to get them. On the Triwangsa level, access is largely hereditary, primogenitural even, and a sharp distinction is made between that handful of individuals who "own power" and the vast remainder of the gentry who do not. On the Sudra level, access to public office is more often elective, but the number of men who have the opportunity to serve is still fairly limited. Prestige status decides what sort of public role one can presume to occupy; whether or not one occupies such a role is another question altogether. Yet, because of the general correlation between prestige status and public office the doctrine of spiritual eligibility brings about, the order of political and ecclesiastical authority in the society is hooked in with the general notion that social order reflects dimly, and ought to reflect clearly, metaphysical order; and, beyond that, that personal identity is to be defined not in terms of such superficial, because merely human, matters as age, sex, talent, temperament, or achievement--that is, biographically, but in terms of location in a general spiritual hierarchy-that is, typologically. Like all the other symbolic orders of person-definition, that stemming from public titles consists of a formulation, with respect to different social contexts, of an underlying assumption: it is not what a man is as a man (as we would phrase it) that matters, but where he fits in a set of cultural categories which not only do not change but, being transhuman, cannot. And, here too, these categories ascend toward divinity (or with equal accuracy, descend from it), their power to submerge character and nullify time increasing as they go. Not only do the higher level public titles borne by human beings blend gradually into those borne by the gods, becoming at the apex identical with them, but at the level of the gods there is literally nothing left of identity but the title itself. All gods and goddesses are addressed and referred to either as Dewa (f. Dewi) or, for the higher ranking ones, Betara (f. Betari). In a few cases, these general appellations are followed by particularizing ones: Betara Guru, Dewi Sri, and so forth. But even such specifically named divinities are not conceived as possessing distinctive personalities: they are merely thought to be administratively responsible, so to speak, for regulating certain matters of cosmic significance: fertility, power, knowledge, death, and so on. In most cases, Balinese do not know, and do not want to know, which gods and goddesses are those worshipped in their various temples (there is always a pair, one male, one female), but merely call them " Dewa (Dewi) Pura Such-and-Such"--god (goddess) of temple such-and-such. Unlike the ancient Greeks and Romans, the average Balinese shows little interest in the detailed doings of particular gods, nor in their motivations, their personalities, or their individual histories. The same circumspection and propriety is maintained with respect to such matters as is maintained with respect to similar matters concerning elders and superiors generally.25 The world of the gods is, in short, but another public realm, transcending all the others and imbued with an ethos which those others seek, so far as they are able, to embody in themselves. The concerns of this realm lie on the cosmic level rather than the political, the economic, or the ceremonial (that is, the human) and its stewards are men without features, individuals with respect to whom the usual indices of perishing humanity have no significance. The nearly faceless, thoroughly conventionalized, never-changing icons by which nameless gods known only by their public titles are, year after year, represented in the thousands of temple festivals across the island comprise the purest expression of the Balinese concept of personhood. Genuflecting to them (or, more precisely, to the gods for the moment resident in them) the Balinese are not just acknowledging divine power. They are also confronting the image of what they consider themselves at bottom to be; an image which the biological, psychological, and sociological concomitants of being alive, the mere materialities of historical time, tend only to obscure from sight. |
バリ人の呼称体系 バリでは、ある個人を唯一無二の個人として識別するために、他人に適用できる6種類の呼称がある。この一般的な概念的背景を考慮しながら、以下に検討して いきたい。(1)個人名、(2)出生順位名、(3)親族用語、(4)通称、(5)地位称号(バリに関する文献では通常「カースト名」と呼ばれる)、(6) 公的称号、すなわち、首長、支配者、司祭、神々が持つ準職業称号を意味する。これらの様々な呼称は、ほとんどの場合、同時に用いられることはなく、状況や 場合によっては個人によって使い分けられる。また、これらはこれまで使用されてきたあらゆる種類のラベルというわけではないが、一般的に認識され、日常的 に使用されているのはこれだけである。そして、それぞれの種類は単に役立つタグの集合体ではなく、明確な境界線のある用語体系であるため、私はこれらを 「象徴的な人名序列」と呼び、まず個別に、そして後に全体として考察することにする。 個人名 個人名によって定義される象徴的秩序は、形式的な面では最も複雑性が低く、社会的にも最も重要度が低いので、最も簡単に説明できる。バリ人は皆個人名を 持っているが、自分自身や他人を指したり、誰かに呼びかけたりする際にそれを使うことはほとんどない。(両親を含む先祖に対しては、それを使うことは実 際、冒涜にあたる。) 子供は、より頻繁に個人名で呼ばれ、時には呼びかけられることもある。そのため、このような名前は「子供」または「幼い」名前と呼ばれることもあるが、誕 生後105日目に儀式的に授けられた後は、その人の一生を通じて変更されることはない。一般的に、個人名はめったに聞かれることはなく、公的な役割はほと んどない。 しかし、このような社会的限界にもかかわらず、個人名命名システムには、一見すると不自然な方法ではあるが、バリ人の個人観を理解する上で非常に重要な特 徴がある。まず、個人名は少なくとも一般庶民(人口の約90%)の間では、恣意的に作られた無意味な音節である。それらは、誰かの名前を「誰々」にちなん で名付けるような、確立された名前のプールから選ばれたものではない。例えば、祖先、両親の友人、著名人などである。 あるいは縁起がよい、ふさわしい、グループや地域の特徴を表す、親族関係を示すなどである。8 第二に、単一のコミュニティ内での個人名の重複は、すなわち政治的に統一された核のある集落内での重複は、慎重に避けられている。このような集落(バンド ジャールまたは「村落」と呼ばれる)は、純粋に家庭的な家族の領域の外にある主な対面式のグループであり、いくつかの点ではさらに親密である。通常、非常 に同族婚的で、常に非常に協調的である村落は、バリ島における卓越した共同体の世界であり、その中では、社会的レベルでは重視されていないとしても、誰も が少なくとも完全に独自の文化的なアイデンティティの基礎を所有している。第三に、個人名は単語であり、家族のつながりや、実際にはあらゆる種類のグルー プのメンバーシップを示すものではない。そして最後に、貴族階級の間では、愛称や「獅子心王リチャード」や「恐ろしいイワン」のような異名は存在しない。 子供に対する愛称や恋人や配偶者に対するペットネームさえもない。 したがって、個人名付けシステムによって定められた人物の定義の象徴的秩序が、バリ人を互いに区別したり、バリ人の社会関係を秩序づけたりする上で果たす 役割は、本質的に限定的なものである。個人の名前とは、その人物に付随する他の社会的で顕著な文化的ラベルがすべて取り除かれたときに残るものである。直 接使用を避ける傾向が宗教的であることを示すように、個人名は極めて個人的な問題である。実際、人が死を迎え、火葬された後に神となる一歩手前まで来る と、もはやその人(あるいは同年代の友人数人)だけが、それが実際何であるかを知っているかもしれない。その人が消え去るとき、それはその人とともに消え 去る。明るく照らされた日常生活の世界では、個人の文化的な定義における純粋に個人的な部分、つまり、その個人が所属するコミュニティの文脈において、そ の個人に最も完全に属する部分は、ほとんど目立たない。そして、それによって、人間としての存在のより特異的で、単なる伝記的な、そして結果的に一過性の 側面(私たちのより利己的な枠組みでは「性格」と呼ぶもの)は、より典型的で、高度に定型化され、結果的に永続するものに取って代わられる。 出生順位名 このような標準化されたラベルの中で最も基本的なものは、死産児であっても、その子が生まれた瞬間に、兄弟姉妹の中で1番目、2番目、3番目、4番目な ど、何番目に生まれたかによって自動的に授けられるものである。この使用法には地域や身分グループによる多少の差異はあるが、最も一般的なシステムは、第 1子にはワヤン、第2子にはニョマン、第3子にはマデ(またはンエンガ)、第4子にはクトゥというように、第5子にはワヤン、第6子にはニョマン、という ように、サイクルを繰り返すというものである。 これらの出生順の名前は、その村で子供やまだ子供をもうけていない若い男女に対して、呼びかけや呼びかけに応える際に最も頻繁に使われる言葉である。呼び かけには、ほとんどの場合、単に、つまり個人名を付け加えずに使われる。「ワヤン、鍬を貸して」など。参照上、特に村に何十人もいるワヤンやニョマンの中 で誰を指しているのかを伝えるのに他の方法が都合よくない場合には、個人名で補われることがある。「いいえ、ワヤン・ルルグではなく、ワヤン・ケピグで す」など。親は自分の子供たちに、また子供を持たない兄弟姉妹は互いに、個人名や親族呼称ではなく、ほぼ専らこれらの名前で呼びかける。しかし、子供がい る人に対しては、家族内でも家族外でも、決してこれらの呼び名は使われず、代わりに「通称」が用いられる。文化的な観点から見ると、子供を持たずに成長し たバリ人(少数派)は、子供であるという状態のままであり、つまり、象徴的に子供として描かれる。これは、彼らにとって大きな恥であり、彼らと関わりを持 つ人々にとっては、彼らに対して呼びかけを用いることを完全に避けようとする場合が多いという、大きな恥ずかしさである。9 したがって、出生順による人物の定義は、個人を呼称する上での一種のプラスαの変化アプローチである。それは、4つのまったく中身のない呼称によって彼ら を区別するものであり、それは真の階級を定義するものではない(なぜなら、コミュニティ内のすべてのワヤンやすべてのクトゥツといった階級には、概念的に も社会的にも現実性はまったくないからだ)。また、適用される個人の具体的な特徴を示すものでもない(なぜなら、ワヤンが、ニョマンやクトゥツに対して、 心理的または精神的な共通した特徴を持っているという概念はないからだ)。これらの名称は、それ自体に文字通りの意味はなく(数字や数字の派生語ではな い)、実際には兄弟姉妹の順位や信頼性の高い地位を示すものでもない。10 ワヤンは第5子(または第9子!)であると同時に第1子である可能性もある。また、伝統的な農民の人口構成(高い出生率に加え、死産や乳幼児・小児の死亡 率が高い)を考慮すると、マデやクトゥは、実際には兄弟姉妹の長い列の中で最年長であり、ワヤンは末っ子である可能性もある。彼らが示唆しているのは、子 孫を残すすべての夫婦にとって、誕生はワヤン、ニョマン、マデ、クトゥ、そして再びワヤンという循環的な継承であり、不滅の形の終わりのない4段階の複製 であるということだ。肉体的に男性ははかない存在として現れては消えていくが、社会的には登場人物は永遠に変わらない。なぜなら、神々の時を超えた世界か ら新たなワヤンやクトゥが現れ(幼児も神性から一歩離れた存在である)、それによって再び溶解する人々を置き換えるからだ。 親族関係の用語 正式には、バリ人の親族関係の用語は、専門的には「ハワイ」または「世代」と呼ばれる種類の、非常にシンプルなものである。この種のシステムでは、個人は 主に、自分との関係における親族の世代によって親族を分類する。つまり、兄弟姉妹、異母兄弟、従兄弟(および配偶者の兄弟姉妹など)は同じ用語でグループ 化され、両親の兄弟姉妹はすべて用語上は母または父として分類され、兄弟姉妹、従兄弟などの子供たち(つまり、甥や姪など)はすべて実子として識別される 従兄弟、等(つまり、甥っ子や姪っ子)は、自分の子供として認識される。以下、孫、ひ孫、等、世代を下り、祖父母、曾祖父母、等、世代を上る。任意の行為 者について、一般的な図は、親族の層が何層にも重なったレイヤーケーキのような配置となる。各層は、行為者の両親やその子供たち、祖父母や孫たちなど、異 なる世代の親族で構成される。 このようなシステムが存在することを踏まえると、バリにおけるその運用方法について最も重要な(そしてかなり珍しい)事実は、そのシステムに含まれる用語 が、ほとんど呼称として使われることはなく、参照としてのみ使われること、そしてその頻度もそれほど高くないことである。まれな例外を除いて、自分の父親 (または叔父)を「父」、自分の子供(または甥・姪)を「子」、自分の兄弟(または従兄弟)を「兄弟」などと呼ぶことは実際にはない。自分より系図的に下 位の親族に対しては、呼びかけの形は存在しない。自分より上位の親族に対しては存在するが、個人名と同様に、それらを使用することは年長者に対する敬意の 欠如を示すとみなされる。実際、参照形ですら、親族関係の情報を伝えるために特に必要とされる場合のみに使用され、一般的な人物識別の手段として使用され ることはほとんどない。 親族関係の用語が公の会話に登場するのは、何らかの質問への回答、またはすでに起こった出来事や今後起こると予想される出来事を説明する場合のみであり、 その際には親族関係の存在が関連情報として必要とされる。(「父の歯の治療に行くの?」 「ええ、彼は私の『兄弟』です」)このように、家族内での呼びかけや呼び名も、村内でのそれらと比較して、親密さや血縁関係の表現において、それ以上(あ るいはそれほど)親密であったり、表現力に富んだものではない。子供がある程度の年齢に達すると(一般的には6歳だが、もちろん個人差はある)、両親を呼 ぶ際に、両親を知っている他の誰もが使うのと同じ言葉、すなわち、テクノン(teknonym)、地位グループの称号、または公的な称号を使うようにな る。そして、両親は、その子供をワヤン(Wayan)、クトゥ(Ktut)、またはその他の何と呼ぶ。そして、さらに確信を持って、彼らは彼らの耳に聞こ えるか、それとも聞こえないかに関わらず、この一般的な、国外でも通用する用語で彼らを呼ぶだろう。 つまり、バリ人の親族関係の用語体系は、主に分類学的なものであり、対面式のイディオムではなく、社会的な相互作用のパートナーではなく、社会的な分野に おける地域住民として個人を定義する。それは、ある特定の人物を位置づけ、風景の特徴としてマッピングされない特定の他の人物を位置づけない文化的な地図 としてほぼ完全に機能する。もちろん、このような決定がなされ、構造におけるある人物の位置が確認されれば、適切な対人関係の行動に関するいくつかの概念 が導かれる。しかし、重要な点は、実際の慣行においては、親族用語は、そのパターン形成に関して他の象徴的装置が優勢である場合、行動ではなく、確認のた めに事実上ほぼ独占的に使用されるということである。12 親族関係に関連する社会規範は、十分に現実的ではあるが、親族型の集団(家族、世帯、家系)内においても、宗教、政治、そして最も根本的には社会階層に関 連する、文化的により強力な規範によって、習慣的に無効にされる。 しかし、親族関係の用語体系は、個人を指名する体系と同様に、社会的な交流の瞬間ごとの流れを形成する上で二次的な役割しか果たさないにもかかわらず、間 接的にではあるが、バリ人の人間観に重要な貢献をしている。なぜなら、重要な象徴体系として、この体系もまた、個人(自分自身だけでなく他者も含む)が把 握される概念構造を体現しているからである。さらに、この概念構造は、異なる構造と多様な志向性を持つ、他の個人定義体系に体現されている概念構造と驚く ほど一致している。ここでも、主要なモチーフは、形態の反復による時間の固定化である。 この反復は、まだ触れていないバリの親族用語の特徴によって達成される。すなわち、本人から見て3世代上と3世代下の親族は、完全に相互的な関係となる。 つまり、「曾祖父母」と「曾孫」を表す用語は同じ「クンピ」である。この2世代と、その世代に属する個人は文化的に識別される。象徴的に、男性は最も遠い 先祖と上方で、最も遠い子孫と下方で同一視され、生きている人間として交流する可能性が高い。 実際、この種の相互呼称は4世代、さらにはそれ以上の世代にわたって用いられる。しかし、本人と曽祖父母(または曽孫)の人生が重なることは極めてまれで あるため、この継続性は理論的な関心のみであり、ほとんどの人はこの用語さえ知らない。達成可能な理想、つまり、60歳という年齢のように、人生が完全に 完成した状態のイメージと考えられているのは、4世代(すなわち、本人の世代と、その上下3世代)である。そして、クンピクンピの用語は、いわば強調した 文化的な括弧をこの世代に置いている。 この括弧は、死をめぐる儀式によってさらに強調される。人の葬儀では、その人物の世代的に後輩にあたる親族全員が、棺の前と、その後、墓の前で、ヒン ドゥー教式に手のひらを額に当てるしぐさで、その人物の残された魂に敬意を表さなければならない。しかし、この事実上絶対的な義務、つまり葬儀の中心とな る聖礼典は、その人物の「孫」にあたる3代目で途切れる。彼の「ひ孫」は、彼にとって「クンプイ(kumpi)」であり、バリ人は、彼らは彼より年下では なく、「同い年」であると言う。そのため、彼らは彼の霊に対して敬意を示す必要はないばかりか、それを禁じられている。人は神々に対してのみ、そしてそれ は同輩や年下に対してではなく、年長者に対してのみ祈りを捧げる。 バリ人の親族関係の用語は、特定の行為者に関して人間を世代層に分けるだけでなく、これらの層を「最下層」から「最高層」までを結ぶ連続した表面に折り曲 げる。そのため、レイヤーケーキのイメージというよりも、「自分」、「親」、「祖父母」、「クンピ」、「孫」、「子供」と呼ばれる6つの平行な帯に区切ら れた円筒の方がより正確である。14 一見すると、世代の絶え間ない進行を強調する非常に通時的な定式化のように見えるが、実際には、そのような進行の本質的な非現実性、少なくともその重要性 のなさを主張している。時間を通じて互いに続く一連の傍系親族という連続性は、用語体系をあたかも人間が年を重ねて死ぬまでの間、親族との対面式の交流の 質的変化を定式化するために使用されているかのように見ていることによって生じる錯覚である。実際、そのような体系の多くは、そうである。バリ人が主にそ うするように、人間が持つ可能性のある家族関係の分類として、また、親族を自然なグループに分類したものとしてこれを見ると、円筒上の帯が表しているの は、生きている人々の年長順の系図であることが明らかである。それらは、共存する世代間の精神的な(そして、同じことだが構造的な)関係を表しており、繰 り返されることのない歴史的過程における世代の順序を表しているのではない。 テクノニム もし個人名が軍事機密のように扱われ、出生順の名前が主に子供や若い思春期の若者たちに適用され、親族関係の用語がせいぜい散発的に、しかも二次的な特定 の目的にのみ使用される場合、バリ人のほとんどはどのようにして互いに呼びかけ、呼び合うのだろうか。農民の大半にとっては、その答えは「テクノニム」で ある。 子供が生まれると、人々はすぐにその夫婦を「父親の」、「母親の」と呼び始め、その子供がレグレグ、プラ、あるいはその子の名前が何であろうと、そのよう に呼ぶ。彼らは、最初の孫が生まれるまでそう呼ばれ(また自らもそう名乗る)、その時点で「祖父」や「祖母」としてスーダ、リリル、または誰それと呼ばれ 始める。そして、 最初のひ孫が生まれると、同様の変化が起こる。16 このように、自然な形で4世代にわたるクンプイ・トゥ・クンプイの寿命の中で、個人が知られる名称は3回変わる。まず本人、次に少なくとも1人の子供、最 後に少なくとも1人の孫が子孫をもうけることで、である。 もちろん、ほとんどの人々は、それほど長生きすることも、子孫繁栄の幸運に恵まれることもないだろう。また、この単純化された図式を複雑にする要因は他に も数多くある。しかし、細かいことはさておき、重要なのは、ここには文化的に非常に発達し、社会的に非常に影響力のあるテクノニミーのシステムがあるとい うことだ。バリ人個人が自分自身や自分の知人についてどう認識しているかに、どのような影響があるのだろうか? まず、私たちの社会で花嫁が夫の姓を名乗るように、夫婦が特定されるという効果がある。ただし、ここでは結婚という行為ではなく、生殖によって特定される ことになる。象徴的に、夫婦のつながりは、子供、孫、ひ孫との共通の関係によって表現される。妻が夫の「家族」に組み込まれるという表現は使われない(結 婚は高度な同族婚であるため、妻はすでに夫の家族の一員であることが多い)。 この夫と妻、あるいはより正確には父と母の組み合わせは、経済的、政治的、精神的に非常に重要な意味を持つ。実際、これは社会の基礎的な構成単位である。 独身男性は、議席が夫婦によって割り当てられる村議会に参加することはできない。また、まれな例外を除いて、そこで発言力を持つのは子供を持つ男性だけで ある。(実際、子供が生まれるまで議席が割り当てられない村もある。)同様のことは、親族グループ、任意団体、灌漑組合、寺院の信者などについても言え る。宗教から農業まで、事実上すべての地域活動において、両親である夫婦は一体となって参加し、男性は特定の作業を行い、女性はそれを補う特定の作業を行 う。 自身の姓に直系の子孫の名前を組み込むことで男性と妻を結びつけるテクノニミーは、地域社会における夫婦のペアの重要性を強調するとともに、子孫繁栄に置 かれる大きな価値を強調している。17 この価値観は、より明白な形で、テクノニムの広範な使用による2つ目の文化的帰結にも現れている。すなわち、より適切な言葉が見つからないため、ここでは 「生殖層」と呼ぶことにする、個人の分類である。あらゆる行為者の観点から、彼の村の仲間たちは、ワヤン、マデなどと呼ばれる子供を持たない人々、父 (母)と呼ばれる子供を持つ人々、祖父(祖母)と呼ばれる孫を持つ人々、曽祖父(曽祖母)と呼ばれるひ孫を持つ人々に分けられる。そして、この序列には、 社会的な階層の性質に関する一般的なイメージが結びつけられている。子供を持たない人は扶養される未成年者であり、父親は地域社会の運営を担う活動的な市 民であり、祖父は裏方から賢明な助言を与える尊敬すべき年長者であり、曾祖父はすでに半ば神の世界に戻っている上級扶養者である。いずれの場合も、このや や型にはまりすぎた公式を、実用的な現実と調和させ、機能的な社会階層を明確にするためには、さまざまな仕組みを導入しなければならない。しかし、こうし た調整によって、実際には、人は際立った存在となる。その結果、人間の「生殖能力」は、その人自身の目にも、また他の人々の目にも、その人の社会的アイデ ンティティの主要な要素となる。バリでは、人間の人生の段階は、生物学的な老化の過程ではなく、社会的な再生の過程として考えられている。 そのため、自分自身が何人の子供をもうけることができるかという、単なる生殖能力そのものが重要なのではない。10人の子供がいる夫婦も、5人の子供がい る夫婦も、同じように尊敬される。また、子供が1人しかいない夫婦でも、その子供が順番に1人ずつ子供をもうけると、両方の夫婦よりも上位に立つ。 重要なのは生殖の連続性であり、コミュニティがそのままの形で自己を永続させる能力を維持することである。これは、第三の「テクノニミー」、生殖連鎖の呼 称が最も明確に示している事実である。 バリ人のテクノニミーがこのような系列を概略化する方法は、モデル図(図1)から見て取れる。 単純化のため、ここでは男性のテクノニムのみを示し、参照世代には英語名を使用している。 また、テクノニミーの使用は、その名を継ぐ子孫の系統的な順序(あるいは性別)ではなく、絶対的な年齢を反映しているという事実を強調するために、このモ デルを構成した。 図1 バリ人のテクノンミー(入手不可) 注:メアリーはドンより年上である。ジョーはメアリー、ジェーン、ドンより年上である。もちろん、彼らが先祖や子孫である場合を除いて、他の人々の相対年 齢は、テクノンミーに関しては無関係である。 図1が示すように、テクノイミーは生殖能力の状態だけでなく、2世代、3世代、4世代(ごくまれに5世代)にわたる特定の系譜も概説する。どの特定の系譜 が強調されるかは、ほとんど偶然によるものである。もしメアリーがジョーより先に生まれていた場合、あるいはメアリーより先にドンが生まれていた場合、系 譜全体が変化していたであろう。しかし、参照対象とされる特定の個人、そしてそれゆえ象徴的な認知を受ける特定の系譜のつながりは、恣意的でさほど重要な 問題ではない。しかし、そのような系譜が明示されるという事実は、バリ人の個人としてのアイデンティティに関する重要な事実を強調する。すなわち、個人 は、その祖先が誰であったかという文脈で認識されるのではなく(死者を覆う文化的ベールがあるため、それすら知られていない)、むしろ誰の祖先であるかと いう文脈で認識される。世界の多くの社会のように、誰が自分を産んだか、つまり、自分と遠い関係にあるか近い関係にあるか、偉大な創始者であるか否かに よって定義されるのではなく、誰を自分が産んだか、つまり、特定の、ほとんどの場合まだ生きている、半人前の個人、つまり自分の子供、孫、ひ孫を産んだか 否かによって定義される。 「ジョーの曾祖父」、「ジョーの祖父」、「ジョーの父」を結びつけているのは、ある意味で彼らが協力してジョーを生み出したという事実、つまり、バリの人 々一般、特に彼らの村の社会的な新陳代謝を維持したという事実である。繰り返しになるが、一過性の過程を祝っているように見えるものは、実際には、グレゴ リー・ベイトソンが物理学の用語を借りて「定常状態」と呼んだものの維持を祝っているのである。19 この種のテクノクラート体制では、人口全体が、今まさに社会的再生が最も差し迫っている人口のサブクラスとの関係性と、そのサブクラスにおける表現という 観点から分類される。その観点では、最も時間と関係の深い人間の状態である曾祖父母であることさえ、不滅の現在を構成する要素にすぎないように見える。 地位の称号 理論的には、バリ島では誰もが(ほぼ)1つ以上の称号を持っている。イダ・バグース、グスティ、パセク、ダウなどである。これらの称号は、バリ島全体の地 位の階層における特定の地位に位置づけられる。各称号は、他のすべての称号と比較して、文化的な優越性または劣後性を特定の度合いで表している。そのた め、人口全体が均一に等級付けされたカーストに分類されることになる。実際には、このシステムをそのような観点で分析しようとした人々が発見したように、 状況ははるかに複雑である。 それは、少数の地位の低い村人が、自分(または両親)が何らかの理由で自分の称号を「忘れてしまった」と主張しているという単純なものではない。また、場 所によって、時には情報提供者によってさえも称号の序列に著しい矛盾があるというものでもない。また、世襲制にもかかわらず、称号を変更する方法があると いうものでもない。これらは、この制度の日常的な運用に関する(興味深いものではない)詳細に過ぎない。重要なのは、地位称号はグループにはまったく付与 されず、個人にのみ付与されるということである。 バリにおける地位、少なくとも称号によって決定されるような地位は、個人的な特性である。それは、いかなる社会的構造的要因からも独立している。もちろ ん、それは重要な実質的な結果をもたらし、その帰結は、親族集団から政府機関に至るまで、多種多様な社会的取り決めによって形作られ、表現される。しか し、デワ、プルオサリ、プリン、マスパダンであるということは、基本的にはその称号を継承し、それに付随する敬意の公的な証を要求する権利を持っていると いうことだけである。特定の役割を演じたり、特定のグループに属したり、特定の経済的、政治的、または聖職的地位を占めたりすることではない。 地位称号制度は純粋な威信制度である。ある男の称号を知れば、自分の称号を踏まえた上で、公的生活のほぼあらゆる場面において、その男に対して、またその 男から自分に対して、どのような態度を取るべきかがわかる。バリ人の礼儀正しさは非常に高度に発達しており、日常生活のほぼ全域にわたって、社会行動の表 層を厳格に制御している。話し方、姿勢、服装、食事、結婚、さらには家屋の建築、埋葬の場所、火葬の方法に至るまで、厳格なマナーのコードに則っている。 それは、社会的な優雅さを求める情熱からというよりも、むしろ広範囲にわたる形而上学的考察から生じている。 地位の称号制度とそれを表現するエチケットのシステムに体現されているような人間的な不平等は、道徳的でも経済的でも政治的でもない。それは宗教的なもの である。それは、神聖な秩序が日常的な交流に反映されたものであり、この観点から見ると、その交流は儀式の一形態として模範とされるべきものである。ある 人物の称号は、その人物の富や権力、あるいは道徳的な評判を示すものではなく、その人物の精神的な構成を示すものである。世俗的な地位とこの構成との間に 大きな不調和がある場合もある。バリで最も影響力のある有力者のなかには、最も無礼な扱いを受ける者もいれば、最も丁重に扱われるが尊敬されていない者も いる。称号は名誉を反映するものではなく、むしろ称号が人を反映するものであるというマキャベリの言葉ほど、バリ人の精神からかけ離れたものは考えられな いだろう。 理論上、バリ人の理論では、すべての称号は神々から授けられたものである。称号は父親から子供へと、常に変化を伴うことなく受け継がれてきたわけではない が、神聖な家宝のように受け継がれてきた。称号の威信価値の違いは、称号を授かった男性が、その称号に具現化された精神的な規定をどの程度遵守したかによ る。称号を名乗るということは、少なくとも暗黙のうちに、神聖な行動基準に同意し、少なくともそれに近づくことを意味する。そして、すべての人が同じ程度 にこれを達成できるわけではない。その結果、称号のランクとそれを名乗る人々との間に、現在の相違が生じている。社会的地位とは対照的に、文化的な地位 は、ここでも神性からの距離を反映している。 事実上、あらゆる称号には、その称号の保有者による精神的に重要な過ちを伴う、非常に具体的な伝説上の出来事が一つまたは複数存在する。これらの罪と呼ぶ には程遠い過ちは、称号の価値の低下の度合い、超越的な地位からの転落の距離を明確にし、少なくとも全体的な威信の尺度におけるその地位を概ね確定するも のとみなされる。特定の(神話的なものであっても)地理的な移動、爵位間の結婚、軍事的失敗、喪中のマナー違反、儀式の怠慢などは、程度の差こそあれ、爵 位を貶めたものとみなされる。低爵位であればあるほど、その程度は大きく、高爵位であればあるほど、その程度は小さい。 しかし、外見とは裏腹に、この不均等な劣化は、本質的には、道徳的現象でも歴史的現象でもない。なぜなら、その原因となったと考えられている事件のほとん どは、バリ島でも他の場所でも、否定的な倫理的判断が通常下されるような事件ではないからだ。一方、真の道徳的欠陥(残虐性、裏切り、不誠実、放蕩)は、 評判にのみダメージを与えるものであり、評判は持ち主とともに消え去るが、称号は残る。これらの事件は、昔々のおとぎ話の中での離れ離れな出来事であり、 現在の現実の原因としてではなく、その本質を述べたものとして引き合いに出されるわけではないからだ。称号を貶める出来事についての重要な事実は、それが 過去に起こったことでも、あるいは起こったことさえもないことでもなく、それが貶めるものであるということだ。それらは、現在の状況を作り出した過程の定 式化でもなければ、それに対する道徳的判断の定式化でもない(バリ人が関心を示さないのは、どちらの知的作業においてもである)。それらは、人間社会の形 と、それが不完全な表現であるという本質を持つ神聖なパターンとの間の根本的な関係のイメージである。 しかし、称号制度の自律性についてこれほどまでに語られた後で、宇宙のパターンと社会形態の間にそのような関係が存在すると考えられる場合、それは具体的 にどのように理解されるのだろうか? 宗教的観念や、個々の人間の精神的な価値の本質的な差異に関する理論のみに基づく称号制度が、社会を外部から眺めたときに、権力、影響力、富、名声など、 社会的な分業に内在する「現実」と呼ぶべきものと、どのように結びついているのか。要するに、実際の社会秩序は、それとはまったく独立した威信の序列シス テムにどのように組み込まれているのか。そして、実際には存在する両者の緩やかで一般的な相関関係を説明し、維持しているのは何か。答えはこうだ。インド から輸入され、現地の好みに合わせて適応された有名な文化制度、すなわちヴァルナ・システムという一種のトリックを、非常に巧妙に演じることによってであ る。ヴァルナ・システムによって、バリ人は、非常に無秩序な地位の分類を、単純な形にまとめる。その形は、その分類から自然に生じたものとして表現されて いるが、実際にはその分類に恣意的に押し付けられたものである。 インドと同様に、ヴァルナ・システムは4つの大カテゴリー、すなわちバラモン、サトリア、ウェシア、シュダラから構成され、それぞれに威信の序列が定めら れている。最初の3つ(バリではトリワンサ、「3つの民族」と呼ばれる)は、平民的な4つ目に対して、精神的な貴族階級を定義している。しかし、バリでは ヴァルナ・システムはそれ自体が地位の差別化のための文化装置ではなく、称号システムによってすでに作られた差別化を関連付けるためのものである。それ は、そのシステムに暗黙的に含まれる文字通り無数の細かい比較を、羊と山羊、そして1等級の羊と2等級、2等級と3等級という、簡潔な(ある観点から見る とあまりにも簡潔すぎる)区分に要約している。21 人々は、お互いをサトリアやスードラとして認識するのではなく、 、例えばデワやクブン・プスプといったように認識している。単にサトリア・スードラの区別を用いて一般的に表現し、社会組織の目的のために、デワをサトリ アの称号、クブン・プスプをスードラの称号として識別することで関わる対照の秩序を表現している。ヴァルナのカテゴリーは、人々に対してではなく、彼らが 担う称号に対して適用されるラベルである。称号は威信体系の構造を形作るものであり、一方、称号は個々の人々に対して適用されるラベルであり、その構造の 中で人々を位置づけるものである。称号のヴァルナ分類が、社会における実際の権力、富、尊敬の実際の分布と一致する程度、つまり、社会階層化のシステムと 一致する程度において、社会は秩序立っていると考えられる。ふさわしい人間がふさわしい地位に就く。精神的な価値と社会的地位が一致する。 称号とヴァルナの機能上の違いは、それらに関連する象徴的な形態が実際にどのように用いられているかを見れば明らかである。トリワンサの貴族階級では、い くつかの例外はあるものの、テクノンミーは用いられず、個人の称号が主な呼び名や参照用語として用いられる。ある人物をイダ・バグス、ンジャカン、グシ (ブラフマーナ、サトリア、ウェシアではない)と呼び、同じ言葉で呼ぶ。より正確に特定するために、出生順の名前を追加することもある(イダ・バグス・マ デ、ンジャカン・ニョマンなど)。スードラの間では、称号は参照目的でのみ使用され、決して呼び捨てにはしない。また、主に自分以外の他の村の住人に対し て使用され、その人物の通称が知られていない場合、あるいは知っていても、あまりにも馴れ馴れしい口調であるため、同じ村の住人以外には使用できない場合 もある。ハムレット内では、スードラの称号が参照的に用いられるのは、威信に関するステータス情報が関連性を持つとみなされる場合のみである(「ジョーの 父親はケディサン出身なので、我々パンデよりも『下』だ」など)。一方、住所は、もちろん、通称で表される。親しい友人同士を除いては、テクノニムは使用 されない。村落の境界を越えて、最も一般的な呼びかけの言葉は「Djero」である。文字通りには「内側」または「内輪」を意味し、つまり「内側」と見な されるTriwangsaの一員を指す。Triwangsaに対して「外側」と見なされるSudrasは「外側」である(Djaba)。しかし、この文脈 では、 「礼儀正しくあるために、私はあなたがトリワングサであるかのようにあなたに呼びかけている。あなたはトリワングサではない(もしあなたがトリワングサで あれば、私はあなたの正しい称号であなたを呼ぶだろう)。そして、あなたにも同じように見せかけてくれることを期待している」という意味になる。ヴァルナ の用語については、トリワンサとスダラは、一般的な用語で威信の階層全体を概念化する際にのみ使用する。これは通常、政治、聖職、階層に関する問題に関連 して必要となる。「クルンクンの王はサトリアだが、タバナンの王はウェシアだけだ」とか、「サヌールには裕福なバラモンがたくさんいるので、そこのスドラ は村の事柄についてほとんど発言権がない」などである。 このように、ヴァルナ・システムには2つの側面がある。一連の場当たり的で恣意的な威信の区別である称号をヒンドゥー教、またはバリ・ヒンドゥー教と結び つけ、それによって一般的な世界観に根ざすようにしている。そして、その世界観、つまり称号の含意を社会組織に当てはめて解釈している。称号制度に暗黙的 に含まれる威信の勾配は、社会における富、権力、尊敬の実際の配分に反映されるべきであり、実際、完全に一致するはずである。この一致が実際にどの程度ま で達成されているかといえば、もちろんせいぜい中程度である。しかし、膨大な権力をもつスードラ、小作人として働くサトリア、尊敬も評価もされないブラフ マンなど、ルールに対する例外がいくら多く存在しようとも、バリ人が真に人間の状態を明らかにしているとみなしているのは、ルールであって例外ではない。 ヴァルナ・システムは称号制度を、社会生活を宇宙論的観念の一般的な集合という観点から捉えることを可能にするような方法で体系化している。この観念で は、人間の才能の多様性や歴史的過程の働きは、標準化された地位カテゴリーの体系における個人の位置づけと比較すると表面的な現象であり、個人の性格を反 映しない永遠のものとみなされる。 公的な肩書 この人物定義の最後の象徴的な秩序は、表面的には、個人を識別し特徴づける我々自身の方法の中でも最も顕著なもののひとつを最も彷彿とさせるものである。 22 私たちもまた、職業カテゴリーというフィルターを通して人々を見ることがよくある(おそらくあまりにも頻繁にある)。社会的機能は、個人のアイデンティ ティが認識される象徴的な手段となる。人はその行動によって定義される。 しかし、この類似性は表面的なものである。自己とは何かという異なる概念群のなかで、世界とは何かという異なる宗教的・哲学的概念と対比され、それを描写 するための異なる文化装置(公的な肩書き)の観点から表現されるバリ人の社会的な役割と個人のアイデンティティの関係についての見解は、私たちが職業と呼 ぶものの表意文字としての意味に、バリ人が「座席」、「場所」、「寝床」と呼ぶリンギ(linggih)とはまったく異なる観点を与える。 この「座」という概念は、バリ人の思想と実践において、社会の市民的領域と家庭的な領域の間に極めて明確な区別が存在することに基づいている。生活におけ る公的領域と私的領域の境界は、概念的にも制度的にも非常に明確に引かれている。村落から王宮に至るあらゆるレベルにおいて、一般的な関心事と個人や家族 の関心事とは、他の多くの社会のように相互に浸透するのではなく、明確に区別され、慎重に隔離されている。バリ人の公共という概念は、独自の利害や目的を 持つ法人としての感覚が非常に発達している。いかなるレベルにおいても、それらの利害や目的に関して特別な責任を負うことは、そうした責任を負わない同胞 から一線を画すことを意味し、それが公的な肩書きが示す特別な地位である。 同時に、バリ人は社会の公共部門を限定的かつ自律的なものと捉えているが、それらが継ぎ目のない全体、あるいは全体ですらないと見なしているわけではな い。むしろ、彼らはそれをいくつかの別個の、連続性のない、時には競争関係にある領域から成り立っていると見ている。各領域はそれぞれ自立しており、自己 完結的で、自らの権利に固執し、独自の組織原則に基づいている。こうした領域の最も顕著な例としては、政治共同体としての村落、宗教団体としての地元寺 院、信徒会、農業団体としての灌漑組合、そしてそれらを統括する貴族や大祭司を中心とした地域政府や礼拝の構造、すなわちスプラムルン (suprahamlet)政府や礼拝の構造などがある。 これらの様々な公共領域や部門について説明することは、現在の文脈では不適切なバリの社会構造の広範な分析を必要とする。23 ここで言いたいことは、それぞれに関連して責任のある役人(stewardsという言葉の方が適切かもしれない)がおり、その結果、特定の称号を授けられ ているということである。クリアン、パーベケル、ペカセ、ペマンク、アナッ・アグン、チャコルダ、デワ・アグン、ペダンダなど、おそらく50以上もの肩書 きがある。そして、これらの人々(総人口の非常に小さな割合)は、これらの公式の肩書きで呼ばれ、参照される。時には出生順の名前や地位の肩書き、あるい はシュドラの場合は二次的な指定を目的としたテクニカルな名称と組み合わせて呼ばれることもある。2 4 スードラ階級におけるさまざまな「村長」や「民間神官」、そしてトリワングサ階級における「王」、「王子」、「領主」、「高僧」といった肩書きは、単に役 割を担っているだけではない。彼ら自身や周囲の人々から見ると、それらの肩書きに吸収されてしまうのだ。彼らは真の公人であり、個人の人格、出生順位、親 族関係、生殖能力、威信ランクといった他の側面は、少なくとも象徴的には二の次となる。 私たちは、個人のアイデンティティの中心として心理的特性に注目し、彼らは役割のために真の自己を犠牲にしたと言うだろう。彼らは社会的地位に注目し、役 割こそが真の自己の本質であると言うだろう。 これらの公的な肩書きを持つ役割へのアクセスは、地位の称号のシステムとヴァルナのカテゴリーへの組織化と密接に関連しており、この関連性は「精神的な適 格性の教義」と呼ばれるものによってもたらされている。この教義は、地域的またはバリ島全体に影響を与える政治的・宗教的な「地位」はトリワングサのみが 就くべきであり、地域的な影響力を持つ地位はスドラが就くのがふさわしいと主張している。上位レベルでは、この教義は厳格である。サトリア (Satria)階級とみなされる称号を持つ男性のみが王や最高君主となり、ヴェーシャ(Wesia)階級またはサトリア(Satria)階級の領主やそ の他の王子となり、バラモナ(Brahmanas)階級の高僧となることができる。下位レベルでは、それほど厳格ではないが、村落の首長、灌漑組合の代 表、民間神官はスードラ(Sudra)階級であるべきであり、トリワングサ(Triwangsas)階級は自らの地位を維持すべきであるという感覚は、か なり強い。しかし、いずれの場合も、ヴァルナの称号を持つ者の大多数、または公的な称号に付随する管理職に就く資格がある理論上のカテゴリーに属する者 は、そのような役割を持たず、おそらく持つこともない。トリワングサのレベルでは、その地位へのアクセスは主に世襲であり、長子相続でさえある。「権力を 所有する」一握りの個人と、そうでない大多数の貴族階級との間には、明確な区別がある。スードラ階級では、公職への就任はより頻繁に選挙で選ばれるが、奉 仕する機会のある男性の数は依然としてかなり限られている。威信の地位によって、どのような公的役割を担うことが可能かが決まる。そのような役割を担うか どうかは、まったく別の問題である。 しかし、威信的地位と公職の一般的な相関関係により、精神的な適格性の教義がもたらす社会における政治的・教会的な権威の序列は、社会秩序が形而上学的な 秩序をぼんやりと反映し、はっきりと反映すべきであるという一般的な概念と結びついている。さらに、 さらに、個人のアイデンティティは、年齢、性別、才能、気質、業績といった表面的な、つまり人間的な事柄によってではなく、つまり伝記的にではなく、一般 的な精神的な階層における位置、つまり類型論的に定義されるべきである。他のあらゆる象徴的な人間定義と同様に、公的な肩書きに由来するものは、異なる社 会的文脈における根本的な前提の定式化から成る。重要なのは、人間としての人間(私たちがそう呼ぶもの)が何であるかではなく、文化的なカテゴリーの集合 にどこに当てはまるかであり、それらのカテゴリーは変化することはないばかりか、超人間的であるため、変化することはない。 そして、ここでもまた、これらのカテゴリーは神性に向かって上昇し(あるいは同等の正確さで、神性から下降する)、個性を覆い隠し、時間を無効化する力が 強まっていく。人間が授けられた高位の公的な称号は、徐々に神々が授けられた称号と融合し、頂点では神々の称号と同一のものとなるだけでなく、神々のレベ ルでは、文字通り、称号以外にアイデンティティを示すものは何も残らない。すべての神や女神は、デワ(女性形はデウィ)または、より高位の神々については ベタラ(男性形はベタリ)と呼ばれている。 いくつかのケースでは、これらの一般的な呼称に特定の名称が続く。例えば、ベタラ・グル、デウィ・スリなどである。しかし、このように特定の名称で呼ばれ る神々も、個性的な人格を持っているとは考えられていない。彼らは、宇宙的な意義を持つ特定の事柄、すなわち、豊穣、力、知識、死などを管理する責任者で あると考えられているに過ぎない。ほとんどの場合、バリ人は自分たちの様々な寺院で崇拝されている神や女神が誰なのかを知らず、また知ろうともしない(寺 院には必ず一対の神が祀られており、一方は男性、もう一方は女性である)。ただ、それらを「デワ(デウィ)・プラ・スチャ・スチャ」と呼ぶだけである。古 代ギリシア人や古代ローマ人と異なり、一般のバリ人は特定の神々の詳細な行動や動機、性格、個々の歴史についてほとんど関心を示さない。同様の慎重さや礼 儀正しさは、一般的に年長者や目上の人々に関する同様の事柄に対しても維持されている。 神々の世界は、一言で言えば、他のあらゆる世界を超越したもう一つの公共領域であり、他の世界が自分たちの中に体現しようと努めるエートスに満ちている。 この領域の関心事は、政治的、経済的、儀式的なものではなく(つまり、人間的なもの)、その管理者は特徴のない人間であり、人間性を失うという通常の指標 は、彼らには何の意味も持たない。その島中の何千もの寺院祭事において、公的な称号のみで知られる名もなき神々が、何年にもわたって、ほとんど顔のない、 徹底的に型にはまった、変化のない偶像によって表現されている。バリ人の人格概念の最も純粋な表現である。バリ人は、それら(より正確に言えば、その時そ の時に宿る神)にひざまずくことで、神の力を認めるだけでなく、 彼らはまた、自分たちが根底で考えている自分の姿と向き合っている。それは、生きていることの生物学、心理学、社会学的な側面、単なる歴史的な時間の物質 性によって、視界から隠されてしまいがちな姿である。 |
| A Cultural Triangle of Forces There are many ways in which men are made aware, or rather make themselves aware, of the passage of time--by marking the changing of the seasons, the alterations of the moon, or the progress of plant life; by the measured cycling of rites, or agricultural work, or household activities; by the preparation and scheduling of projected acts and the memory and assessment of accomplished ones; by the preservation of genealogies, the recital of legends, or the framing of prophecies. But surely among the most important is by the recognition in oneself and in one's fellowmen of the process of biological aging, the appearance, maturation, decay, and disappearance of concrete individuals. How one views this process affects, therefore, and affects profoundly, how one experiences time. Between a people's conception of what it is to be a person and their conception of the structure of history there is an unbreakable internal link. Now, as I have been stressing, the most striking thing about the culture patterns in which Balinese notions of personal identity are embodied is the degree to which they depict virtually everyone--friends, relatives, neighbors, and strangers; elders and youths; superiors and inferiors; men and women; chiefs, kings, priests, and gods; even the dead and the unborn--as stereotyped contemporaries, abstract and anonymous fellowmen. Each of the symbolic orders of person-definition, from concealed names to flaunted titles, acts to stress and strengthen the standardization, idealization, and generalization implicit in the relation between individuals whose main connection consists in the accident of their being alive at the same time and to mute or gloss over those implicit in the relation between consociates, men intimately involved in one another's biographies, or between predecessors and successors, men who stand to one another as blind testator and unwitting heir. Of course, people in Baliare directly, and sometimes deeply, involved in one another's lives; they do feel their world to have been shaped by the actions of those who came before them and orient their actions toward shaping the world of those who will come after them. But it is not these aspects of their existence as persons--their immediacy and individuality, or their special, never-to-be-repeated, impact upon the stream of historical events--which are culturally played up, symbolically emphasized: it is their social placement, their particular location within a persisting, indeed an eternal, metaphysical order.26 The illuminating paradox of Balinese formulations of personhood is that they are --in our terms anyway--depersonalizing. In this way, the Balinese blunt, though of course they cannot efface, three of the most important sources of a sense of temporality: the apprehension of one's comrades (and thus oneself with them) as perpetually perishing; the awareness of the heaviness with which the completed lives of the dead weigh upon the uncompleted lives of the living; and the appreciation of the potential impact upon the unborn of actions just now being undertaken. Consociates, as they meet, confront and grasp one another in an immediate present, a synoptic "now"; and in so doing they experience the elusiveness and ephemerality of such a now as it slips by in the ongoing stream of face-to-face interaction. "For each partner [in a consociate relationship] the other's body, his gestures, his gait and facial expressions, are immediately observable, not merely as things or events of the outer world but in their physiognomical significance, that is as [expressions! of the other's thoughts. . . . Each partner participates in the onrolling life of the other, can grasp in a vivid present the other's thoughts as they are built up step by step. They may thus share one another's anticipations of the future as plans, or hopes, or anxieties. . . . [They] are mutually involved in one another's biography; they are growing older together. . . ."27 As for predecessors and successors, separated by a material gulf, they perceive one another in terms of origins and outcomes, and in so doing experience the inherent chronologicality of events, the linear progress of standard, transpersonal time--the sort whose passage can be measured with clocks and calendars.28 In minimizing, culturally, all three of these experiences--that of the evanescing present consociate intimacy evokes; that of the determining past contemplation of predecessors evokes; and that of the moldable future anticipation of successors evokes--in favor of the sense of pure simultaneity generated by the anonymized encounter of sheer contemporaries, the Balinese produce yet a second paradox. Linked to their depersonalizing conception of personhood is a detemporalizing (again from our point of view) conception of time. TAXONOMIC CALENDARS AND PUNCTUAL TIME Balinese calendrical notions--their cultural machinery for demarcating temporal units--reflect this clearly; for they are largely used not to measure the elapse of time, nor yet to accent the uniqueness and irrecoverability of the passing moment, but to mark and classify the qualitative modalities in terms of which time manifests itself in human experience. The Balinese calendar (or, rather, calendars; as we shall see there are two of them) cuts time up into bounded units not in order to count and total them but to describe and characterize them, to formulate their differential social, intellectual, and religious significance.29 The two calendars which the Balinese employ are a lunar-solar one and one built around the interaction of independent cycles of daynames, which I shall call "permutational." The permutational calendar is by far the most important. It consists of ten different cycles of daynames. These cycles are of varying lengths. The longest contains ten day-names, following one another in a fixed order, after which the first day-name reappears and the cycle starts over. Similarly, there are nine, eight, seven, six, five, four, three, two, and even--the ultimate of a "contemporized" view of time--one day-name cycles. The names in each cycle are also different, and the cycles run concurrently. That is to say, any given day has, at least in theory, ten different names simultaneously applied to it, one from each of the ten cycles. Of the ten cycles only those containing five, six, and seven day-names are of major cultural significance, however, although the three-name cycle is used to define the market week and plays a role in fixing certain minor rituals, such as the personal-naming ceremony referred to earlier. Now, the interaction of these three main cycles--the five, the six, and the seven--means that a given trinomially designated day (that is, one with a particular combination of names from all three cycles) will appear once in every two hundred and ten days, the simple product of five, six, and seven. Similar interactions between the five- and sevenname cycles produce binomially designated days which turn up every thirty-five days, between the six- and seven-name cycles binomially designated days which occur every forty-two days, and between the fiveand six-name cycles binomially designated days appearing at thirty-day intervals. The conjunctions that each of these four periodicities, supercycles as it were, define (but not the periodicities themselves) are considered not only to be socially significant but to reflect, in one fashion or another, the very structure of reality. The outcome of all this wheels-within-wheels computation is a view of time as consisting of ordered sets of thirty, thirty-five, forty-two, or two hundred and ten quantum units ("days"), each of which units has a particular qualitative significance of some sort indexed by its trinomial or binomial name: rather like our notion of the unluckiness of Friday-the-Thirteenth. To identify a day in the forty-two-day set--and thus assess its practical and/or religious significance--one needs to determine its place, that is, its name, in the six-name cycle (say, Ariang) and in the seven- (say, Boda): the day is Boda-Ariang, and one shapes one's actions accordingly. To identify a day in the thirty-five-day set, one needs its place and name in the five-name cycle (for example, Klion) and in the seven-: for example, Boda-Klion--this is rainan, the day on which one must set out small offerings at various points to "feed" the gods. For the two hundred and ten-day set, unique determination demands names from all three weeks: for example, Boda-Ariang-Klion, which, it so happens, is the day on which the most important Balinese holiday, Galungan, is celebrated.30 Details aside, the nature of time-reckoning this sort of calendar facilitates is clearly not durational but punctual. That is, it is not used (and could only with much awkwardness and the addition of some ancillary devices be used) to measure the rate at which time passes, the amount which has passed since the occurrence of some event, or the amount which remains within which to complete some project: it is adapted to and used for distinguishing and classifying discrete, self-subsistent particles of time--"days." The cycles and supercycles are endless, unanchored, uncountable, and, as their internal order has no significance, without climax. They do not accumulate, they do not build, and they are not consumed. They don't tell you what time it is; they tell you what kind of time it is.31 The uses of the permutational calendar extend to virtually all aspects of Balinese life. In the first instance, it determines (with one exception) all the holidays--that is, general community celebrations--of which Goris lists some thirty-two in all, or on the average about one day out of every seven.32 These do not appear, however, in any discernible overall rhythm. If we begin, arbitrarily, with RaditÈ-Tungleh-Paing as "one," holidays appear on days numbering: 1, 2, 3, 4, 14, 15, 24, 49, 51, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 109, 119, 125, 154, 183, 189, 193, 196, 205, 210.33 The result of this sort of spasmodic occurrence of festivals, large and small, is a perception of time --that is, of days--as falling broadly into two very general varieties, "full" and "empty": days on which something of importance goes on and others on which nothing, or at least nothing much, goes on, the former often being called "times" or "junctures" and the latter "holes." All of the other applications of the calendar merely reinforce and refine this general perception. Of these other applications, the most important is the determination of temple celebrations. No one knows how many temples there are on Bali, though Swellengrebel has estimated that there are more than 20,000.34 Each of these temples--family temples, descent-group temples, agricultural temples, death temples, settlement temples, associational temples, "caste" temples, state temples, and so on--has its own day of celebration, called odalan, a term which though commonly, and misleadingly, translated as "birthday" or, worse yet, "anniversary," literally means "coming out," "emergence," "appearance"--that is, not the day on which the temple was built but the day on which it is (and since it has been in existence always has been) "activated," on which the gods come down from the heavens to inhabit it. In between odalans it is quiescent, uninhabited, empty; and, aside from a few offerings prepared by its priest on certain days, nothing happens there. For the great majority of the temples, the odalan is determined according to the permutational calendar (for the remainder, odalans are determined by the lunar-solar calendar, which as we shall see, comes to about the same thing so far as modes of time-perception are concerned), again in terms of the interaction of the five-, six-, and seven-name cycles. What this means is that temple ceremonies--which range from the incredibly elaborate to the almost invisibly simple--are of, to put it mildly, frequent occurrence in Bali, though here too there are certain days on which many such celebrations fall and others on which, for essentially metaphysical reasons, none do.35 Balinese life is thus not only irregularly punctuated by frequent holidays, which everyone celebrates, but by even more frequent temple celebrations which involve only those who are, usually by birth, members of the temple. As most Balinese belong to a half-dozen temples or more, this makes for a fairly busy, not to say frenetic, ritual life, though again one which alternates, unrhythmically, between hyperactivity and quiescence. In addition to these more religious matters of holidays and temple festivals, the permutational calendar invades and secular ones of everyday life as well.36 There are good and bad days on which to build a house, launch a business enterprise, change residence, go on a trip, harvest crops, sharpen cock spurs, hold a puppet show, or (in the old days) start a war, or conclude a peace. The day on which one was born, which again is not a birthday in our sense (when you ask a Balinese when he was born his reply comes to the equivalent of "Thursday, the ninth," which is not of much help in determining his age) but his odalan, is conceived to control or, more accurately, to indicate much of his destiny.37 Men born on this day are liable to suicide, on that to become thieves, on this to be rich, on that to be poor; on this to be well, or long-lived, or happy, on that to be sickly, or short-lived, or unhappy. Temperament is similarly assessed, and so is talent. The diagnosis and treatment of disease is complexly integrated with calendrical determinations, which may involve the odalans of both the patient and the curer, the day on which he fell ill, as well as days metaphysically associated with the symptoms and with the medicine. Before marriages are contracted, the odalans of the individuals are compared to see if their conjunction is auspicious, and if not there will be--at least if the parties, as is almost always the case, are prudent--no marriage. There is a time to bury and a time to cremate, a time to marry and a time to divorce, a time--to shift from the Hebraic to the Balinese idiom--for the mountain top and a time for the market, for social withdrawal and social participation. Meetings of village council, irrigation societies, voluntary associations are all fixed in terms of the permutational (or, more rarely, the lunar-solar) calendar; and so are periods for sitting quietly at home and trying to keep out of trouble. The lunar-solar calendar, though constructed on a different basis, actually embodies the same punctual conception of time as the permutational. Its main distinction and, for certain purposes, advantage is that it is more or less anchored; it does not drift with respect to the seasons. This calendar consists of twelve numbered months which run from new moon to new moon.38 These months are then divided into two sorts of (also numbered) days: lunar (tithi) and solar (diwasa). There are always thirty lunar days in a month, but, given the discrepancy between the lunar and solar years, there are sometimes thirty solar days in a month and sometimes twenty-nine. In the latter case, two lunar days are considered to fall on one solar day--that is, one lunar day is skipped. This occurs every sixty-three days; but, although this calculation is astronomically quite accurate, the actual determination is not made on the basis of astronomical observation and theory, for which the Balinese do not have the necessary cultural equipment (to say nothing of the interest); it is determined by the use of the permutational calendar. The calculation was of course originally arrived at astronomically; but it was arrived at by the Hindus from whom the Balinese, in the most distant past, imported the calendar. For the Balinese, the double lunar day-the day on which it is two days at once--is just one more special kind of day thrown up by the workings of the cycles and supercycles of the permutational calendar--a priori, not a posteriori, knowledge. In any case, this correction still leaves a nine-eleven-day deviation from the true solar year, and this is compensated for by the interpolation of a leap-month every thirty months, an operation which though again originally a result of Hindu astronomical observation and calculation is here simply mechanical. Despite the fact that the lunar-solar calendar looks astronomical, and thus seems to be based on some perceptions of natural temporal processes, celestial clocks, this is an illusion arising from attending to its origins rather than its uses. Its uses are as divorced from observation of the heavens--or from any other experience of passing time--as are those of the permutational calendar by which it is so rigorously paced. As with the permutational calendar, it is the system, automatic, particulate, fundamentally not metrical but classificatory, which tells you what day (or what kind of day) it is, not the appearance of the moon, which, as one looks casually up at it, is experienced not as a determinant of the calendar but as a reflex of it. What is "really real" is the name--or, in this case, the (two-place) number--of the day, its place in the transempirical taxonomy of days, not its epiphenomenal reflection in the sky.39 In practice, the lunar-solar calendar is used in the same way for the same sorts of things as the permutational. The fact that it is (loosely) anchored makes it rather more handy in agricultural contexts, so that planting, weeding, harvesting, and the like are usually regulated in terms of it, and some temples having a symbolic connection with agriculture or fertility celebrate their reception of the gods according to it. This means that such receptions appear only about every 355 (in leap years, about 385) rather than 210 days. But otherwise the pattern is unchanged. In addition, there is one major holiday, Njepi ("to make quiet"), which is celebrated according to the lunar-solar calendar. Often called, by Western scholars, "the Balinese New Year," even though it falls at the beginning (that is, the new moon) of not the first but the tenth month and is concerned not with renewal or rededication but with an accentuated fear of demons and an attempt to render one's emotions tranquil. Njepi is observed by an eerie day of silence: no one goes out on the streets, no work is conducted, no light or fire is lit, while conversation even within houseyards is muted. The lunar-solar system is not much used for "fortune telling" purposes, though the new moon and full moon days are considered to have certain qualitative characteristics, sinister in the first case, auspicious in the second. In general, the lunarsolar calendar is more a supplement to the permutational than an alternative to it. It makes possible the employment of a classificatory, fulland-empty, "detemporalized" conception of time in contexts where the fact that natural conditions vary periodically has to be at least minimally acknowledged. CEREMONY, STAGE FRIGHT, AND ABSENCE OF CLIMAX The anonymization of persons and the immobilization of time are thus but two sides of the same cultural process: the symbolic de-emphasis, in the everyday life of the Balinese, of the perception of fellowmen as consociates, successors, or predecessors in favor of the perception of them as contemporaries. As the various symbolic orders of person-definition conceal the biological, psychological, and historical foundation of that changing pattern of gifts and inclinations we call personality behind a dense screen of ready-made identities, iconic selves, so the calendar, or rather the application of the calendar, blunts the sense of dissolving days and evaporating years that those foundations and that pattern inevitably suggest by pulverizing the flow of time into disconnected, dimensionless, motionless particles. A sheer contemporary needs an absolute present in which to live; an absolute present can be inhabited only by a contemporized man. Yet, there is a third side to this same process which transforms it from a pair of complementary prepossessions into a triangle of mutually reinforcing cultural forces: the ceremonialization of social intercourse. To maintain the (relative) anonymization of individuals with whom one is in daily contact, to dampen the intimacy implicit in face-to-face relationships--in a word, to render consociates contemporaries--it is necessary to formalize relations with them to a fairly high degree, to confront them in a sociological middle distance where they are close enough to be identified but not so close as to be grasped: quasi strangers, quasi friends. The ceremoniousness of so much of Balinese daily life, the extent (and the intensity) to which interpersonal relations are controlled by a developed system of conventions and proprieties, is thus a logical correlate of a thoroughgoing attempt to block the more creatural aspects of the human condition--individuality, spontaneity, perishability, emotionality, vulnerability--from sight. This attempt is, like its counterparts, only very partially successful, and the ceremonialization of Balinese social interaction is no closer to being complete than is the anonymization of persons or the immobilization of time. But the degree to which its success is wished for, the degree to which it is an obsessing ideal, accounts for the degree to which the ceremonialization obtains, for the fact that in Bali manners are not a mere matter of practical convenience or incidental decoration but are of deep spiritual concern. Calculated politesse, outward form pure and simple, has there a normative value that we, who regard it as pretentious or comic when we don't regard it as hypocritical, can scarcely, now that Jane Austen is about as far from us as Bali, any longer appreciate. Such an appreciation is rendered even more difficult by the presence within this industrious polishing of the surfaces of social life of a peculiar note, a stylistic nuance, we would not, I think, expect to be there. Being stylistic and being a nuance (though an altogether pervasive one), it is very difficult to communicate to someone who has not himself experienced it. "Playful theatricality" perhaps hits near it, if it is understood that the playfulness is not lighthearted but almost grave and the theatricality not spontaneous but almost forced. Balinese social relations are at once a solemn game and a studied drama. This is most clearly seen in their ritual and (what is the same thing) artistic life, much of which is in fact but a portrait of and a mold for their social life. Daily interaction is so ritualistic and religious activity so civic that it is difficult to tell where the one leaves off and the other begins; and both are but expressions of what is justly Bali's most famous cultural attribute: her artistic genius. The elaborate temple pageants; the grandiloquent operas, equilibristic ballets, and stilted shadow plays; the circuitous speech and apologetic gestures--all these are of a piece. Etiquette is a kind of dance, dance a kind of ritual, and worship a form of etiquette. Art, religion, and politesse all exalt the outward, the contrived, the well-wrought appearance of things. They celebrate the forms; and it is the tireless manipulation of these forms--what they call "playing"--that gives to Balinese life its settled haze of ceremony. The mannered cast of Balinese interpersonal relations, the fusion of rite, craft, and courtesy, thus leads into a recognition of the most fundamental and most distinctive quality of their particular brand of sociality: its radical aestheticism. Social acts, all social acts, are first and foremost designed to please--to please the gods, to please the audience, to please the other, to please the self; but to please as beauty pleases, not as virtue pleases. Like temple offerings or gamelan concerts, acts of courtesy are works of art, and as such they demonstrate, and are meant to demonstrate, not rectitude (or what we would call rectitude) but sensibility. Now, from all this--that daily life is markedly ceremonious; that this ceremoniousness takes the form of an earnest, even sedulous, kind of "playing" with public forms; that religion, art, and etiquette are then but differently directed manifestations of an overall cultural fascination with the worked-up semblance of things; and that morality here is consequently aesthetic at base--it is possible to attain a more exact understanding of two of the most marked (and most remarked) features of the affective tone of Balinese life: the importance of the emotion of what has been (wrongly) called "shame" in interpersonal relations, and the failure of collective activity--religious, artistic, political, economic--to build toward the definable consummations, what has been (acutely) called its "absence of climax."40 One of these themes, the first, leads directly back toward conceptions of personhood, the other, no less directly, toward conceptions of time, so securing the vertices of our metaphorical triangle connecting the Balinese behavioral style with the ideational environment in which it moves. The concept of "shame," together with its moral and emotional cousin "guilt," has been much discussed in the literature, entire cultures sometimes being designated as "shame cultures" because of the presumed prominence in them of an intense concern with "honor," "reputation," and the like, at the expense of a concern, conceived to be dominant in "guilt cultures," with "sin," "inner worth," and so forth.41 The usefulness of such an overall categorization and the complex problems of comparative psychological dynamics involved aside, it has proven difficult in such studies to divest the term "shame" of what is after all its most common meaning in English--"consciousness of guilt"--and so to disconnect it very completely from guilt as such--"the fact or feeling of having done something reprehensible." Usually, the contrast has been turned upon the fact that "shame" tends to be applied (although, actually, far from exclusively) to situations in which wrongdoing is publicly exposed, and "guilt" (though equally far from exclusively) to situations in which it is not. Shame is the feeling of disgrace and humiliation which follows upon a transgression found out; guilt is the feeling of secret badness attendant upon one not, or not yet, found out. Thus, though shame and guilt are not precisely the same thing in our ethical and psychological vocabulary, they are of the same family; the one is a surfacing of the other, the other a concealment of the one. But Balinese "shame," or what has been translated as such (lek), has nothing to do with transgressions, exposed or unexposed, acknowledged or hidden, merely imagined or actually performed. This is not to say that Balinese feel neither guilt nor shame, are without either conscience or pride, anymore than they are unaware that time passes or that men are unique individuals. It is to say that neither guilt nor shame is of cardinal importance as affective regulators of their interpersonal conduct, and that lek, which is far and away the most important of such regulators, culturally the most intensely emphasized, ought therefore not to be translated as "shame," but rather, to follow out our theatrical image, as "stage fright." It is neither the sense that one has transgressed nor the sense of humiliation that follows upon some uncovered transgression, both rather lightly felt and quickly effaced in Bali, that is the controlling emotion in Balinese face-to-face encounters. It is, on the contrary, a diffuse, usually mild, though in certain situations virtually paralyzing, nervousness before the prospect (and the fact) of social interaction, a chronic, mostly low-grade worry that one will not be able to bring it off with the required finesse.42 Whatever its deeper causes, stage fright consists in a fear that, for want of skill or self-control, or perhaps by mere accident, an aesthetic illusion will not be maintained, that the actor will show through his part and the part thus dissolve into the actor. Aesthetic distance collapses, the audience (and the actor) loses sight of Hamlet and gains it, uncomfortably for all concerned, of bumbling John Smith painfully miscast as the Prince of Denmark. In Bali, the case is the same, if the drama more humble. What is feared--mildly in most cases, intensely in a few--is that the public performance that is etiquette will be botched, that the social distance etiquette maintains will consequently collapse, and that the personality of the individual will then break through to dissolve his standardized public identity. When this occurs, as it sometimes does, our triangle falls apart: ceremony evaporates, the immediacy of the moment is felt with an excruciating intensity, and men become unwilling consociates locked in mutual embarrassment, as though they had inadvertently intruded upon one another's privacy. Lek is at once the awareness of the ever-present possibility of such an interpersonal disaster and, like stage fright, a motivating force toward avoiding it. It is the fear of faux pas--rendered only that much more probable by an elaborated politesse--that keeps social intercourse on its deliberately narrowed rails. It is lek, more than anything else, that protects Balinese concepts of personhood from the individualizing force of face-to-face encounters. "Absence of climax," the other outstanding quality of Balinese social behavior, is so peculiarly distinctive and so distinctively odd that only extended description of concrete events could properly evoke it. It amounts to the fact that social activities do not build, or are not permitted to build, toward definitive consummations. Quarrels appear and disappear, on occasion they even persist, but they hardly ever come to a head. Issues are not sharpened for decision, they are blunted and softened in the hope that the mere evolution of circumstances will resolve them, or better yet, that they will simply evaporate. Daily life consists of self-contained, monadic encounters in which something either happens or does not--an intention is realized or it is not, a task accomplished or not. When the thing doesn't happen--the intention is frustrated, the task unaccomplished--the effort may be made again from the beginning at some other time; or it may simply be abandoned. Artistic performances start, go on (often for very extended periods when one does not attend continually but drifts away and back, chatters for a while, sleeps for a while, watches rapt for a while), and stop; they are as uncentered as a parade, as directionless as a pageant. Ritual often seems, as in the temple celebrations, to consist largely of getting ready and cleaning up. The heart of the ceremony, the obeisance to the gods come down onto their altars, is deliberately muted to the point where it sometimes seems almost an afterthought, a glancing, hesitant confrontation of anonymous persons brought physically very close and kept socially very distant. It is all welcoming and bidding farewell, foretaste and aftertaste, with but the most ceremonially buffered, ritually insulated sort of actual encounter with the sacred presences themselves. Even in such a dramatically more heightened ceremony as the RangdaBarong, fearful witch and foolish dragon combat ends in a state of complete irresolution, a mystical, metaphysical, and moral standoff leaving everything precisely as it was, and the observer--or anyway the foreign observer--with the feeling that something decisive was on the verge of happening but never quite did.43 In short, events happen like holidays. They appear, vanish, and reappear--each discrete, sufficient unto itself, a particular manifestation of the fixed order of things. Social activities are separate performances; they do not march toward some destination, gather toward some denouement. As time is punctual, so life is. Not orderless, but qualitatively ordered, like the days themselves, into a limited number of established kinds. Balinese social life lacks climax because it takes place in a motionless present, a vectorless now. Or, equally true, Balinese time lacks motion because Balinese social life lacks climax. The two imply one another, and both together imply and are implied by the Balinese contemporization of persons. The perception of fellowmen, the experience of history, and the temper of collective life--what has sometimes been called ethos--are hooked together by a definable logic. But the logic is not syllogistic; it is social. |
文化のトライアングル 人間が時の流れを認識する方法、あるいは自ら認識する方法は数多くある。季節の移り変わり、月の満ち欠け、植物の成長を記録すること、儀式や農業、家事の 周期的な作業、計画された行為の準備とスケジュール、達成された行為の記憶と評価、家系図の保存、伝説の語り継ぎ、予言の作成などである。しかし、最も重 要なもののひとつは、自分自身や同胞の生物学的加齢の過程、すなわち、具体的な個人の出現、成熟、衰退、消滅を認識することである。この過程をどう見るか によって、時間の経験のされ方が影響を受ける。人々が「人であること」について抱く概念と、歴史の構造についての概念の間には、断ち切ることのできない内 的なつながりがある。 私が強調してきたように、バリ人の自己同一性に関する概念が体現されている文化パターンで最も印象的なのは、友人、親戚、隣人、見知らぬ人、年長者、若 者、目上、目下、男性、女性、首長、王、司祭、神、さらには死者や胎児まで、ほぼすべての人々を型にはまった同時代人、抽象的で匿名の同胞として描写して いる度合いである。隠された名前から誇示された肩書きに至るまで、人間を定義する象徴的な秩序のそれぞれは、同時に生きているという偶然によってつながっ ている個人間の関係に内在する標準化、理想化、一般化を強調し、強化する役割を果たしている。、同時代に生きているという偶然によって結びついている個人 間の関係に内在するものを強調し、強化する行為であり、また、同輩者、すなわち互いの伝記に深く関わっている者同士、あるいは先人・後継者、すなわち互い に盲目の遺言者と無知な相続人としての関係に内在するものを黙殺したり、ごまかしたりする行為である。もちろん、バリ人たちは互いの人生に直接、時には深 く関わっている。彼らは自分たちの世界が自分より先にやってきた人々の行動によって形作られてきたと感じ、自分たちの行動を自分より後にやってくる人々の 世界を形作る方向へと導いている。しかし、文化的に強調され、象徴的に強調されるのは、彼らの存在のこうした側面、すなわち、彼らの即時性や個性、あるい は歴史的出来事の流れに対する彼らの特別な、二度と繰り返されることのない影響力ではない。文化的に強調され、象徴的に強調されるのは、彼らの社会的地 位、永続する、まさに永遠の形而上学的秩序における彼らの特別な位置である。26 バリ人の人格の定義における洞察に満ちた逆説は、彼らが(少なくとも我々の観点では)脱人格化しているということである。 このように、バリ人は、もちろん消し去ることはできないが、時間感覚の最も重要な3つの源泉をあからさまにしている。すなわち、仲間(そして自分も仲間と ともに)が永遠に滅びていくという認識、死者の完成された人生が生きている者の未完成の人生に重くのしかかるという認識、そして今まさに着手された行動が これから生まれてくる者たちに与える潜在的な影響についての認識である。 コンソシエイトは、即時の現在、共観的な「今」において、互いに出会い、向き合い、理解し合う。そうすることで、彼らは、対面式の相互作用の継続的な流れ の中で過ぎ去っていく「今」の捉えどころのなさや儚さを経験する。「共同関係にある各パートナーにとって、他者の身体、その身振り、歩調、表情は、ただ外 界の事物や出来事としてではなく、その人相学的意味において、すなわち他者の思考の[表現!]として、即座に観察可能である。... それぞれのパートナーは、他者の展開する人生に参加し、他者の思考が段階的に構築されていく様子を、生き生きとした現在として把握することができる。 こうして、彼らは互いの未来に対する期待を、計画や希望、あるいは不安として共有することができる。彼らは互いの伝記に相互に関与し、共に年を重ねてい く。...」27 物質的な隔たりによって隔てられた先人や後継者たちは、互いを起源と結果という観点から認識し、そうすることで、出来事の内在的な時間性、標準的な超越論 的時間の直線的な進歩を経験する。 文化的に、親密さを想起させる儚い現在、先人たちの思索を想起させる決定的な過去、後継者たちの期待を想起させる形作ることのできる未来という、これら3 つの経験を最小限に抑え、同時代の人々との匿名的な出会いが生み出す純粋な同時性の感覚を優先させることで、バリ人はさらに2つ目のパラドックスを生み出 している。個人性を否定する彼らの考え方と関連しているのは、時間を否定する(再び私たちの視点から)考え方である。 分類学的暦と厳格な時間 バリ人の暦の概念、つまり時間単位を区切るための文化的な仕組みは、このことを明確に反映している。なぜなら、それは主に時間の経過を測るためでも、過ぎ 去る瞬間の唯一性や回復不能性を強調するためでもなく、人間の経験において時間がどのように現れるかという質的な様態を分類し、示すために使われるから だ。バリ人の暦(正確には暦は2つあるが)は、時間を区切られた単位に区切るが、それは時間を数えたり合計したりするためではなく、時間を描写し特徴づ け、その差異的な社会的、知的、宗教的な意義を明らかにするためである。 バリ人が用いる2つの暦は、太陰太陽暦と、独立したサイクルの日名(曜日名)の相互作用を基盤とする暦である。後者を私は「順列的」と呼ぶ。順列的暦は、 はるかに重要な暦である。これは10の異なるサイクルの日名から構成されている。これらのサイクルの長さは様々である。最も長いサイクルは10の日名から なり、固定された順序で次々と日名が現れ、最初のサイクルに戻って再び同じサイクルが繰り返される。同様に、9、8、7、6、5、4、3、2、そして1サ イクルの日名がある。これは、時間を「現代風」に捉えた究極の形である。各サイクルの日名も異なり、サイクルは同時に進行する。つまり、任意の日には、少 なくとも理論上は、10サイクルから1つずつ、合計10個の日名が同時に適用されることになる。10のサイクルのうち、5、6、7のサイクルに含まれる曜 日名は、文化的に大きな意味を持つが、3つのサイクルは市場の週を定義するために使用され、前述の個人名命名式のような特定の些細な儀式を定める役割を果 たす。 さて、この5、6、7の3つの主要なサイクルの相互作用により、3つのサイクルの特定の組み合わせによる名前を持つ日(つまり、5、6、7の単純な積であ る210日に1度現れる日)が現れることになる。5名数サイクルと7名数サイクルの間の同様の相互作用により、35日ごとに現れる2名数サイクルで指定さ れた日が生じ、6名数サイクルと7名数サイクルの間の2名数サイクルで指定された日は42日ごとに現れ、5名数サイクルと6名数サイクルの間の2名数サイ クルで指定された日は30日ごとに現れる。この4つの周期性(スーパーサイクル)が定義する結合(周期性そのものではない)は、社会的にも重要であるだけ でなく、何らかの形で現実の構造を反映していると考えられている。 こうした複雑な計算の結果、30、35、42、または210の量子単位(「日」)の順序だった集合からなる時間という見解が導かれる。各単位には、3項ま たは2項の名称によって示される、ある種の特定の質的意義がある。これは、13日の金曜日が不吉であるという私たちの考え方に似ている。42日間のセット の中の1日を特定し、その実用的および/または宗教的な重要性を評価するには、6つの名前のサイクル(例えば、Ariang)と7つのサイクル(例えば、 Boda)におけるその位置、すなわち名前を決定する必要がある。その日はBoda-Ariangであり、人はそれに応じて行動を決定する。35日間の セットの日を特定するには、5つの名前のサイクル(例えば、クリオン)と7つ(例えば、ボダ・クリオン)におけるその位置と名前を知る必要がある。これ は、雨の日であり、神々を「養う」ために、さまざまな場所に小さな供物を置かなければならない日である。210日間のセットでは、3週間すべてに名前を付 ける必要があるため、ユニークな決定が求められる。例えば、Boda-Ariang-Klionというように、バリ島で最も重要な祝日である Galunganが祝われる日となる。30 詳細はさておき、この種のカレンダーが容易にする時間計算の性質は、明らかに持続的なものではなく、特定の時点を指すものである。つまり、時間の経過速 度、ある出来事の発生から現在までの経過時間、あるいはあるプロジェクトを完了するまでに残された時間を測定するために使用されることはなく(使用できる としても、非常にぎこちない方法で、いくつかの補助的な装置を追加しなければならない)、「日」という独立した、自立した時間の粒子を区別し、分類するた めに適応され、使用されている。サイクルやスーパーサイクルは無限であり、始点も終点もなく、数えることもできず、その内部秩序に意味はないため、クライ マックスもない。蓄積することも、積み上げることも、消費することもできない。それは今が何時かを告げるのではなく、今がどのような時かを告げるのだ。 バリ人の生活のほぼすべての側面で、順列カレンダーが使用されている。まず第一に、この暦は(1つの例外を除いて)すべての祝日、つまり一般社会の祝祭日 を決定する。ゴリスでは、祝祭日は全部で32日、つまり7日に1日ほどの割合である。32 しかし、これらは明確な全体的なリズムには見られない。もし、任意にラディテ・トゥングレ・パイングを「1」として始めると、祝祭日は次の日付となる。 1、2、3、4、14、15、24、49、51、68、69、71、72、73、74、77、78、79、81、83 84, 85, 109, 119, 125, 154, 183, 189, 193, 196, 205, 210.33 このような大小の祭りが突発的に起こる結果、 大小さまざまな祭りが頻繁に起こる結果、時間の認識、つまり「満ちている」日と「空っぽ」な日の2つの非常に一般的な種類に大まかに分類されるという認識 が生まれる。重要な何かが起こる日と、何も起こらない日、少なくともあまり何も起こらない日、前者はしばしば「時間」または「機会」と呼ばれ、後者は 「穴」と呼ばれる。カレンダーのその他の用途は、すべてこの一般的な認識を補強し、洗練するだけである。 こうした用途の中で最も重要なのは、寺院の祭礼の決定である。バリ島に寺院がどれほどあるのかは誰も知らないが、スウェレングレベルは2万以上あると推定 している。34 家族寺院、一族寺院、農業寺院、死を悼む寺院、集落寺院、協会寺院、「カースト」寺院、国寺院など、これらの寺院はそれぞれ独自の祭礼日を持っており、オ ダランと呼ばれる。この言葉は一般的に、誤解を招くように「誕生日」あるいはさらに悪いことに「記念日」と訳されるが、文字通りには「出現」、「出現」、 「出現」を意味する。つまり、寺院が建てられた日ではなく、寺院が「活性化」された日、つまり神々が天から降りてきてそこに住み着いた日を指す。オダラン の間は、静寂で、無人、空虚であり、特定の日に司祭が用意するいくつかの供物以外には、何も起こらない。 大半の寺院では、オダランは順列カレンダーに従って決定される(残りの寺院では、太陰太陽暦に従ってオダランが決定される。これは、時間に対する認識の仕 方に関しては、これまで見てきたこととほぼ同じである)。つまり、バリでは、非常に手の込んだものからほとんど目立たないほど簡素なものまで、実にさまざ まな寺院の祭礼が頻繁に行われているということだ。ただし、特定の日は、多くの祭礼が集中する日であり、また別の日は、本質的に形而上学的な理由から、祭 礼が一切行われない日でもある。 バリ人の生活は、誰もが祝う休日が不規則に訪れるだけでなく、通常はその寺院の生まれである信者だけが参加する寺院の祭礼がさらに頻繁に訪れる。ほとんど のバリ人は6つ以上の寺院に属しているため、これはかなり忙しく、狂気的とも言える儀式的な生活となるが、それでもまた、過剰な活動と静寂が不規則に交互 に訪れる生活となる。 こうした宗教的な祝祭日や寺院の祭礼に加えて、世俗的な日々の生活にも、順番を入れ替えた暦が侵入してくる。36 家を建てる日、事業を立ち上げる日、引っ越しをする日、旅行に出かける日、農作物を収穫する日、雄鶏の爪を研ぐ日、人形劇を催す日、あるいは(昔は)戦争 を始める日、和平を結ぶ日など、吉日と凶日がある。その人が生まれた日、つまり、私たちの感覚でいう誕生日ではない日(バリ人に自分が生まれた日を尋ねる と、「木曜、9日」という答えが返ってくるが、それでは年齢を特定することはできない)であるが、その人のオダランは、その人の運命を支配する、あるいは より正確に言えば、 その人の運命の多くを決定する。37 この日に生まれた男性は、自殺しやすい、あるいは泥棒になる、この日に生まれた人は裕福になる、あるいは貧しくなる。この日に生まれた人は健康で長生き し、幸せになる、あるいは病弱で短命で不幸になる。気質も同様に評価され、才能も評価される。病気の診断と治療は、暦による決定と複雑に統合されており、 患者と治療者の両方のオダラン、病気に罹った日、そして症状や薬と形而上学的に関連する日も関わってくる。結婚が成立する前に、両者のオダランが比較さ れ、ふたりの結びつきが吉兆であるかどうかが判断される。もし吉兆でなければ、少なくとも当事者が賢明であるならば、結婚は行われない。埋葬には時期があ り、火葬には時期がある。結婚には時期があり、離婚には時期がある。ヘブライ語からバリ語の慣用句に変えると、山頂には時期があり、市場には時期がある。 社会から身を引く時期と社会に参加する時期もある。村議会、灌漑組合、任意団体などの会合はすべて、順列(または、よりまれに太陰太陽)暦に基づいて行わ れる。また、家で静かに過ごす期間や、トラブルに巻き込まれないようにする期間も同様である。 太陰太陽暦は、異なる基準に基づいて構築されているが、実際には順列暦と同じ時間に対する厳格な考え方を体現している。主な違いであり、特定の目的におい ては利点となるのは、季節に対してより固定されていることである。 この暦は新月から新月までの12の月で構成されている。38 これらの月はさらに、太陰(tithi)と太陽(diwasa)の2種類の(同じく番号のついた)日に分けられる。月の日数は常に30日だが、太陰年と太 陽年の食い違いを考慮すると、月の日数が30日になることもあれば、29日になることもある。後者の場合、2つの太陰日は1つの太陽日にあたる。つまり、 1つの太陰日がスキップされる。これは63日ごとに起こる。しかし、この計算は天文学的に非常に正確であるが、実際の決定は天文学的な観察や理論に基づい て行われるわけではない。バリ人はそのための文化的素養(興味は言うまでもなく)を持っていないため、順列カレンダーを使用して決定される。もちろん、こ の計算はもともと天文学的に導き出されたものだが、バリ人が最も遠い過去に暦を輸入したヒンドゥー人によって導き出されたものだ。バリ人にとって、1日が 2日となる二重の太陰日(1日が2日となる日)は、順列暦のサイクルとスーパーサイクルの働きによって生み出される特別な日の1つに過ぎない。 いずれにしても、この修正を加えても、真の太陽年との誤差は9日11日残ることになる。この誤差は、30か月に一度の閏月を挿入することで補正される。こ の操作は、もともとはヒンドゥーの天体観測と計算の結果として生まれたものだが、ここでは単に機械的な操作として行われている。太陰太陽暦は天文学的な外 観をしており、自然の時間経過や天体の動きに関する何らかの認識に基づいて作られたように見えるが、これは誤解である。その用途は、天体の動きの観察や、 時間の経過に関するその他の経験とはまったくかけ離れている。順列カレンダーと同様に、それは自動的で、個別的で、基本的に韻律的ではなく分類的なシステ ムであり、月相ではなく、それが何曜日(またはどんな曜日)であるかを教えてくれる。月相は、何気なく見上げた時にカレンダーの決定要因としてではなく、 その反射として経験される。本当に現実的な」のは、その日の名称、つまりこの場合は(2桁の)数字であり、経験則に基づく日の分類におけるその日の位置で あり、空に反射する付随的な現象ではない。 実際には、太陰太陽暦は順列と同じような用途で同じ種類のものに使用されている。 それが(緩やかに)固定されているという事実により、農業の文脈ではより便利になっている。そのため、通常、植え付け、除草、収穫などは太陰太陽暦に基づ いて行われ、農業や豊穣と象徴的なつながりを持ついくつかの寺院では、太陰太陽暦に従って神の恵みを祝っている。つまり、このような祭礼は210日ではな く、355日(うるう年では385日)ごとにしか行われないということである。しかし、それ以外はパターンに変更はない。 さらに、太陰太陽暦に従って祝われる主要な祝祭日、ニュピ(Njepi、「静寂をもたらす」の意)がある。 ニュピは西洋の学者たちによってしばしば「バリの新年」と呼ばれているが、これは新月が10月のはじまり(つまり10月1日)に訪れることと、改新や再献 身ではなく、悪霊に対する強調された恐怖と感情の静寂化を目的としていることによる。ニュピは不気味なほどの静寂の日として祝われる。誰も外に出ず、仕事 もせず、明かりも火も灯さない。家の中庭でさえ会話は控えめになる。太陰太陽暦は「占い」の目的ではあまり使われないが、新月と満月の日にはそれぞれ、前 者は不吉、後者は吉兆という定性的な特徴があると考えられている。一般的に、太陰太陽暦は、順列の代替案というよりも補足的なものと言える。自然条件が周 期的に変化するという事実を少なくとも最低限認めなければならない状況において、分類的、満ち欠け、そして「脱時間化」された時間の概念の採用を可能にす る。 儀式、あがり症、そしてクライマックスの欠如 このように、人物の匿名化と時間の固定化は、同じ文化過程の二つの側面である。バリ人の日常生活における、同時代人としての他者認識を優先した、仲間、後 継者、前任者としての他者認識の象徴的な軽視である。人間を定義するさまざまな象徴的秩序が、私たちが人格と呼ぶ才能や傾向の変化するパターンを、既製の アイデンティティ、象徴的な自己という分厚いスクリーンの背後に隠してしまうように、カレンダー、あるいはカレンダーの適用は、時間という流れを断片化 し、次元のない、静止した粒子へと粉砕することで、それらの基盤やパターンが必然的に暗示する、日々が溶け、年が蒸発していく感覚を鈍らせる。現代人は、 生きるために絶対的な現在を必要としている。絶対的な現在には、現代的な人間だけが住むことができる。しかし、この同じプロセスには、補完的な先入観のペ アを相互に補強する文化的な力の三角形に変える第3の側面がある。それは、社会的交流の儀式化である。 日常的に接触する個人の(相対的な)匿名性を維持し、対面関係に内在する親密さを和らげるために、つまり、共同社会の構成員を同時代人にするために、彼ら との関係をかなり高度に形式化し、彼らを社会学的な中間距離で対峙させる必要がある。そこでは、彼らは十分に身近で識別できるが、把握できるほどには近く はない。つまり、疑似的な他人であり、疑似的な友人である。バリ人の日常生活における儀礼的な態度、つまり、高度に発達した慣習や礼儀作法によって対人関 係が管理されている度合い(およびその強度)は、人間の本質的な側面である、個性、自発性、儚さ、感情的、傷つきやすさといったものを徹底的に隠そうとす る試みと論理的に相関している。この試みは、同様の試みと同様に、部分的な成功にとどまっている。バリの社会的交流の儀式化は、個人の匿名化や時間の固定 化ほどには完全なものにはなっていない。しかし、その成功がどれほど望まれているか、どれほど強迫観念的な理想であるかという度合いは、儀式化がどれほど 浸透しているかを説明するものであり、バリではマナーが単なる実用上の都合や付随的な装飾ではなく、深い精神的な関心事であるという事実を説明するもので ある。計算された礼儀正しさ、純粋な形式、それは規範的な価値を持っているが、私たちはそれを偽善的とは考えないものの、気取りがましい、あるいは滑稽だ と考えているため、ジェーン・オースティンがバリ島と同じくらい遠い存在となった今、それを理解することはほとんどできない。 このような評価は、社会生活の表面を丹念に磨き上げるこの勤勉な作業の中に、独特の音色、文体的なニュアンスが存在することによって、さらに難しくなって いる。 それは、私たちがそこに存在することを期待していないようなものだ。 文体であり、ニュアンスである(全体に浸透しているとはいえ)ため、それを経験したことのない人には伝えるのが非常に難しい。「遊び心のある演劇性」とい う表現がそれに近いかもしれない。ただし、その遊び心は軽薄なものではなく、ほとんど深刻であり、演劇性は自然発生的なものではなく、ほとんど強制的なも のであると理解される場合に限る。バリ人の社会関係は、厳粛なゲームであり、練り上げられたドラマである。 これは、彼らの儀式や(同じことであるが)芸術的生活において最も明確に見られる。その多くは、実際には彼らの社会生活の肖像であり、その型である。日常 的な交流は儀式的なものであり、宗教活動は市民的なものであるため、その境界を明確に区別することは難しい。そして、どちらもバリ島で最も有名な文化的な 特性である芸術的才能の表現に他ならない。手の込んだ寺院の祭礼、大げさなオペラ、曲芸的なバレエ、ぎこちない影絵芝居、回りくどい話し方や謝罪のしぐさ など、すべてが一体となっている。礼儀作法は一種の舞踊であり、舞踊は一種の儀式であり、儀式は礼儀作法の一形態である。芸術、宗教、礼儀作法はすべて、 外見、演出、巧みに作り上げられたものの外観を称賛する。それらは形を称賛する。そして、バリ人の生活に儀式の定着した霞を与えるのは、これらの形を絶え 間なく操る、彼らが「演じる」と呼ぶ行為である。 バリ人の人間関係における型にはまったやり方、儀式、工芸、礼儀の融合は、彼らの独特な社会性の最も根本的で最も際立った特質、すなわち徹底した審美主義 を認識することにつながる。社会的な行為、あらゆる社会的な行為は、何よりもまず、神々を喜ばせるため、観客を喜ばせるため、他者を喜ばせるため、そして 自己を喜ばせるために行われる。しかし、それは美が喜ぶように、徳が喜ぶようにではなく、喜ばせるのだ。寺院への供物やガムラン音楽のコンサートのよう に、礼儀作法は芸術作品であり、それゆえに、正しさ(あるいは、私たちが正しさと呼ぶもの)ではなく、感受性を示すものであり、示すことを目的としてい る。 さて、日常生活が著しく儀礼的であること、この儀礼性は、公的な形式を真剣に、時には熱心に「演じる」という形を取っていること、宗教、芸術、礼儀作法 は、物事の誇張された外見に対する文化的な全体的な魅力の、異なる方向性を示したものに過ぎないこと、そして、この地域の道徳は、結果的に美的なものであ ること バリの生活の情緒的なトーンの最も顕著な(そして最も注目される)特徴の2つについて、より正確な理解を得ることが可能である。すなわち、対人関係におい て「恥」と呼ばれる感情の重要性、そして、宗教、芸術、政治、経済といった集団活動が明確な結末に向かって構築されないこと、すなわち 定義可能な完成に向かって築き上げる宗教的、芸術的、政治的、経済的な集団活動の失敗、そして「クライマックスの欠如」と痛烈に呼ばれてきたもの。40 これらのテーマのうち、最初のテーマは、個人としての概念に直接つながり、もう一方のテーマは、それと同等に直接的に、時間の概念につながる。したがっ て、バリ人の行動様式とそれが存在する観念的環境を結びつける比喩的な三角形の頂点が確保される。 「恥」という概念は、道徳的・感情的な「罪悪感」と並んで、文献ではよく取り上げられており、時には「恥の文化」として文化全体が指定されることもある。 これは、「名誉」や「評判」などへの強い関心が際立っていると想定されるためである。一方、「罪悪感の文化」では、「罪」や「内面の価値」などへの関心が 支配的であると想定される。 。41 このような全体的なカテゴリー分けの有用性や、比較心理学的な力学の複雑な問題はさておき、このような研究では、「恥」という言葉を英語で最も一般的な意 味である「罪の意識」から切り離し、罪そのもの、すなわち「非難されるようなことをしたという事実や感情」から完全に切り離すことは難しい。通常、この対 比は、「恥」という言葉が(実際には、排他的というわけではないが)不正行為が公に暴露された状況に適用される傾向があり、「罪悪感」という言葉は(やは り排他的というわけではないが)そうではない状況に適用される傾向があるという事実に基づいている。恥とは、罪が露見した結果生じる屈辱感や羞恥心であ り、罪悪感とは、罪が露見していない、あるいは露見していない状態にある人が抱く秘密の悪事への感情である。したがって、恥と罪悪感は、倫理や心理学の用 語としては厳密には同じものではないが、同じ範疇に属するものである。一方は他方の表面化であり、他方は一方の隠蔽である。 しかし、バリ語で「恥」と訳されるlekは、罪を犯したか否か、暴露されたか否か、認めたか否か、隠したか否か、単に想像したか実際に実行したかに関係な く、罪や恥とは何の関係もない。これは、バリ人が罪悪感や恥を感じず、良心や誇りを持たないという意味ではない。バリ人が時間の経過や人間の個性を認識し ていないという意味でもない。つまり、罪悪感も羞恥心も、彼らの対人関係における行動を左右する感情として、決定的に重要なものではないということだ。そ して、そのような感情を左右するものの中で最も重要なレックは、文化的に最も強く強調されているものであるため、「恥」と訳すべきではなく、むしろ、私た ちの演劇的なイメージに従うならば、「舞台恐怖症」と訳すべきである。それは、何か悪いことをしたという感覚でもなければ、何か悪いことをしたことが露見 したことによる屈辱感でもない。どちらもバリでは軽く感じられ、すぐに消えてしまう。バリ人の対面での出会いで支配的な感情は、それらではない。それどこ ろか、それは社会的な交流の可能性(そして現実)に対する漠然とした、通常は穏やかな、しかし特定の状況下では事実上麻痺するような緊張感であり、また、 要求される機転を利かせることができないのではないかという慢性的な、ほとんどが軽度の不安である。 そのより深い原因が何であれ、あがり症とは、技術や自制心がないために、あるいは単なる偶然によって、美的な幻想が維持できず、俳優が役柄を演じきれず、 役柄が俳優に溶け込んでしまうのではないかという恐怖である。美的な距離が崩壊し、観客(そして俳優)はハムレットを見失い、デンマーク王子に不釣り合い なドジなジョン・スミスを見つける。バリ島でも事情は同じだが、演じられるドラマはより地味である。恐れられているのは、ほとんどの場合は穏やかに、一部 では激しく、エチケットとしての公の場での振る舞いが台無しになり、エチケットが維持する社会的距離が崩壊し、その結果、個人のパーソナリティが標準化さ れた公的なアイデンティティを打ち消して表に出てしまうことである。このようなことが起こると、私たちの三角形は崩壊する。儀式は蒸発し、その瞬間の緊迫 感が耐え難いほど強く感じられ、男性たちは、お互いのプライバシーに不用意に侵入してしまったかのように、お互いに気まずい思いを抱えたまま、不本意な共 同体の構成員となる。レックは、このような対人関係の破綻が常に起こりうるという認識であると同時に、あがり症のようにそれを回避しようとする原動力でも ある。 社交の場を意図的に狭いレールの上に保っているのは、緻密に練り上げられた礼儀正しさによって、より起こりうるものとなった失言への恐れである。 バリ人の人格概念を対面式の遭遇による個人化の力から守っているのは、何よりもレックなのである。 「クライマックスの欠如」というバリ人の社交行動のもう一つの際立った特徴は、あまりにも独特で、あまりにも異様であるため、具体的な出来事を詳しく説明 しなければ、適切に表現することはできない。それは、社会活動が明確な結末に向かって発展しない、あるいは発展することが許されないという事実を意味す る。争いは起こったり、収まったりを繰り返し、時には長引くこともあるが、決着がつくことはほとんどない。問題は決着をつけるために先鋭化されるのではな く、状況の変化によって解決されるか、あるいは、より望ましいことに、ただ消え去ることを期待して、先鋭化されるどころか、むしろ鈍化され、和らげられ る。日常生活は、何かが起こるか起こらないか、意図が実現するかしないか、課題が達成されるかされないかという、自己完結的で単一的な遭遇で成り立ってい る。物事が起こらない場合、つまり意図が挫折し、課題が達成されない場合、努力をまた別の機会に最初からやり直すこともできるし、あるいは単に放棄するこ ともできる。芸術的なパフォーマンスは始まり、進行し(継続的に参加していない場合、しばしば非常に長時間にわたって、しばらくおしゃべりをし、しばらく 眠り、しばらく熱心に観るなどして、離れたり戻ってきたりする)、そして停止する。それはパレードのように中心がなく、祭りのように方向性がない。儀式は しばしば、寺院の祭事のように、準備と後片付けが大部分を占めるように見える。儀式の核心である神々への敬意を表す参拝は、意図的に控えめにされ、時には ほとんど付け足しのようにさえ思える。匿名の人物たちが物理的に非常に接近し、社会的に非常に距離を置いている様子は、一瞥しただけでためらいがちに対峙 しているように見える。すべては歓迎と別れであり、前味と後味であり、神聖な存在そのものとの実際の遭遇は、儀式的に緩衝され、儀式的に隔離されたものに すぎない。ランダバロン(RangdaBarong)のような劇的に高められた儀式でさえ、恐ろしい魔女と愚かな竜の戦いは、完全な決着がつかないままに 終わる。神秘的な、形而上学的、道徳的な対峙は、すべてをそのままにしておく。そして、観察者、あるいはとにかく外国人の観察者は、何か決定的なことが起 こりそうだが、決して起こらないという感覚を抱く。 つまり、出来事は祝祭のように起こる。それらは現れ、消え、再び現れる。それぞれが独立しており、それ自体で十分であり、物事の固定された秩序の特定の現 れである。社交活動は個別のパフォーマンスであり、何らかの目的地に向かって進むことも、何らかの結末に向かって集まることもない。時間が正確であるよう に、人生もまた然りである。無秩序ではなく、質的に秩序づけられたものであり、日々のように、限られた数の確立された種類に分けられている。バリの社会生 活にはクライマックスがない。なぜなら、それは不動の現在、ベクトルを持たない今という時間の中で行われるからだ。あるいは、バリの社会生活にクライマッ クスがないから、バリの時間には動きがない、というのも同様に真実である。この2つはお互いを暗示し、また、バリ人の同時代的な人物像によって暗示され、 暗示されている。仲間に対する認識、歴史の経験、集団生活の気質、すなわち、エートスと呼ばれるものは、定義可能な論理によって結びつけられている。しか し、その論理は三段論法ではなく、社会的である。 |
| Cultural Integration, Cultural
Conflict, Cultural Change Referring as it does both to formal principles of reasoning and to rational connections among facts and events, "logic" is a treacherous word; and nowhere more so than in the analysis of culture. When one deals with meaningful forms, the temptation to see the relationship among them as immanent, as consisting of some sort of intrinsic affinity (or disaffinity) they bear for one another, is virtually overwhelming. And so we hear cultural integration spoken of as a harmony of meaning, cultural change as an instability of meaning, and cultural conflict as an incongruity of meaning, with the implication that the harmony, the instability, or the incongruity are properties of meaning itself, as, say, sweetness is a property of sugar or brittleness of glass. Yet, when we try to treat these properties as we would sweetness or brittleness, they fail to behave, "logically," in the expected way. When we look for the constituents of the harmony, the instability, or the incongruity, we are unable to find them resident in that of which they are presumably properties. One cannot run symbolic forms through some sort of cultural assay to discover their harmony content, their stability ratio, or their index of incongruity; one can only look and see if the forms in question are in fact coexisting, changing, or interfering with one another in some way or other, which is like tasting sugar to see if it is sweet or dropping a glass to see if it is brittle, not like investigating the chemical composition of sugar or the physical structure of glass. The reason for this is, of course, that meaning is not intrinsic in the objects, acts, processes, and so on, which bear it, but--as Durkheim, Weber, and so many others have emphasized--imposed upon them; and the explanation of its properties must therefore be sought in that which does the imposing--men living in society. The study of thought is, to borrow a phrase from Joseph Levenson, the study of men thinking;44 and as they think not in some special place of their own, but in the same place--the social world--that they do everything else, the nature of cultural integration, cultural change, or cultural conflict is to be probed for there: in the experiences of individuals and groups of individuals as, under the guidance of symbols, they perceive, feel, reason, judge, and act. To say this is, however, not to yield to psychologism, which along with logicism is the other great saboteur of cultural analysis; for human experience--the actual living through of events--is not mere sentience, but, from the most immediate perception to the most mediated judgment, significant sentience--sentience interpreted, sentience grasped. For human beings, with the possible exception of neonates, who except for their physical structure are human only in posse anyway, all experience is construed experience, and the symbolic forms in terms of which it is construed thus determine--in conjunction with a wide variety of other factors ranging from the cellular geometry of the retina to the endogenous stages of psychological maturation--its intrinsic texture. To abandon the hope of finding the "logic" of cultural organization in some Pythagorean "realm of meaning" is not to abandon the hope of finding it at all. It is to turn our attention toward that which gives symbols their life: their use.45 What binds Balinese symbolic structures for defining persons (names, kin terms, teknonyms, titles, and so on) to their symbolic structures for characterizing time (permutational calendars, and so forth), and both of these to their symbolic structures for ordering interpersonal behavior (art, ritual, politesse, and so on), is the interaction of the effects each of these structures has upon the perceptions of those who use them, the way in which their experiential impacts play into and reinforce one another. A penchant for "contemporizing" fellowmen blunts the sense of biological aging; a blunted sense of biological aging removes one of the main sources of a sense of temporal flow; a reduced sense of temporal flow gives to interpersonal events an episodic quality. Ceremonialized interaction supports standardized perceptions of others; standardized perceptions of others support a "steady-state" conception of society; a steady-state conception of society supports a taxonomic perception of time. And so on: one could begin with conceptions of time and go around, in either direction, the same circle. The circle, though continuous, is not in a strict sense closed, because none of these modes of experience is more than a dominant tendency, a cultural emphasis, and their subdued opposites, equally well-rooted in the general conditions of human existence and not without some cultural expression of their own, coexist with them, and indeed act against them. Yet, they are dominant; they do reinforce one another; and they are persisting. And it is to this state of affairs, neither permanent nor perfect, that the concept "cultural integration" --what Weber called "Sinnzusammenhang" --can be legitimately applied. In this view, cultural integration is no longer taken to be a sui generis phenomenon locked away from the common life of man in a logical world of its own. Perhaps even more important, however, it is also not taken to be an all-embracing, completely pervasive, unbounded one. In the first place, as just noted, patterns counteractive to the primary ones exist as subdominant but nonetheless important themes in, so far as we can tell, any culture. In an ordinary, quite un-Hegelian way, the elements of a culture's own negation are, with greater or lesser force, included within it. With respect to the Balinese, for example, an investigation of their witch beliefs (or, to speak phenomenologically, witch experiences) as inverses of what might be called their person beliefs, or of their trance behavior as an inverse of their etiquette, would be most enlightening in this respect and would add both depth and complexity to the present analysis. Some of the more famous attacks upon received cultural characterizations--revelations of suspicion and factionalism among the "harmony-loving" Pueblans, or of an "amiable side" to the rivalrous Kwakiutl--consist essentially in a pointing out of the existence, and the importance, of such themes.46 But beyond this sort of natural counterpoint there are also simple, unbridged discontinuities between certain major themes themselves. Not everything is connected to everything else with equal directness; not everything plays immediately into or against everything else. At the very least such universal primary interconnection has to be empirically demonstrated, not just, as so often has been the case, axiomatically assumed. Cultural discontinuity, and the social disorganization which, even in highly stable societies, can result from it, is as real as cultural integration. The notion, still quite widespread in anthropology, that culture is a seamless web is no less a petitio principii than the older view that culture is a thing of shreds and patches which, with a certain excess of enthusiasm, it replaced after the Malinowskian revolution of the early thirties. Systems need not be exhaustively interconnected to be systems. They may be densely interconnected or poorly, but which they are-how rightly integrated they are--is an empirical matter. To assert connections among modes of experiencing, as among any variables, it is necessary to find them (and find ways of finding them), not simply assume them. And as there are some rather compelling theoretical reasons for believing that a system which is both complex, as any culture is, and fully joined cannot function, the problem of cultural analysis is as much a matter of determining independencies as interconnections, gulfs as well as bridges.47 The appropriate image, if one must have images, of cultural organization, is neither the spider web nor the pile of sand. It is rather more the octopus, whose tentacles are in large part separately integrated, neurally quite poorly connected with one another and with what in the octopus passes for a brain, and yet who nonetheless manages both to get around and to preserve himself, for a while anyway, as a viable if somewhat ungainly entity. The close and immediate interdependency between conceptions of person, time, and conduct which has been proposed in this essay is, so I would argue, a general phenomenon, even if the particular Balinese form of it is peculiar to a degree, because such an interdependency is inherent in the way in which human experience is organized, a necessary effect of the conditions under which human life is led. But it is only one of a vast and unknown number of such general interdependencies, to some of which it is more or less directly connected, to others only very indirectly, to others for all practical purposes virtually not at all. The analysis of culture comes down therefore not to an heroic "holistic" assault upon "the basic configurations of the culture," an overarching "order of orders" from which more limited configurations can be seen as mere deductions, but to a searching out of significant symbols, clusters of significant symbols, and clusters of clusters of significant symbols--the material vehicles of perception, emotion, and understanding--and the statement of the underlying regularities of human experience implicit in their formation. A workable theory of culture is to be achieved, if it is to be achieved, by building up from directly observable modes of thought, first to determinate families of them and then to more variable, less tightly coherent, but nonetheless ordered "octopoid" systems of them, confluences of partial integrations, partial incongruencies, and partial independencies. Culture moves rather like an octopus too--not all at once in a smoothly coordinated synergy of parts, a massive coaction of the whole, but by disjointed movements of this part, then that, and now the other which somehow cumulate to directional change. Where, leaving cephalopods behind, in any given culture the first impulses toward progression will appear, and how and to what degree they will spread through the system, is, at this stage of our understanding, if not wholly unpredictable, very largely so. Yet that if such impulses appear within some rather closely interconnected and socially consequential part of the system, their driving force will most likely be high, does not appear to be too unreasonable a supposition. Any development which would effectively attack Balinese personperceptions, Balinese experiences of time, or Balinese notions of propriety would seem to be laden with potentialities for transforming the greater part of Balinese culture. These are not the only points at which such revolutionary developments might appear (anything which attacked Balinese notions of prestige and its bases would seem at least equally portentous), but surely they are among the most important. If the Balinese develop a less anonymized view of one another, or a more dynamic sense of time, or a more informal style of social interaction, a very great deal indeed--not everything, but a very great deal--would have to change in Balinese life, if only because any one of these changes would imply, immediately and directly, the others and all three of them play, in different ways and in different contexts, a crucial role in shaping that life. Such cultural changes could, in theory, come from within Balinese society or from without; but considering the fact that Bali is now part of a developing national state whose center of gravity is elsewhere--in the great cities of Java and Sumatra--it would seem most likely to come from without. The emergence for almost the first time in Indonesian history of a political leader who is human, all-too-human, not merely in fact but in appearance would seem to imply something of a challenge to traditional Balinese personhood conceptions. Not only is Sukarno a unique, vivid, and intensely intimate personality in the eyes of the Balinese, he is also, so to speak, aging in public. Despite the fact that they do not engage in face-to-face interaction with him, he is phenomenologically much more their consociate than their contemporary, and his unparalleled success in achieving this kind of relationship--not only in Bali, but in Indonesia quite generally--is the secret of a good deal of his hold on, his fascination for, the population. As with all truly charismatic figures his power comes in great part from the fact that he does not fit traditional cultural categories but bursts them open by celebrating his own distinctiveness. The same is true, in reduced intensity, for the lesser leaders of the New Indonesia, down to those small-frog Sukarnos (with whom the population does have face-to-face relations) now beginning to appear in Bali itself.48 The sort of individualism which Burckhardt saw the Renaissance princes bringing, through sheer force of character, to Italy, and bringing with it the modern Western consciousness, may be in the process of being brought, in rather different form, to Bali by the new populist princes of Indonesia. Similarly, the politics of continuing crisis on which the national state has embarked, a passion for pushing events toward their climaxes rather than away from them, would seem to pose the same sort of challenge to Balinese conceptions of time. And when such politics are placed, as they are increasingly being placed, in the historical framework so characteristic of New Nation nationalism almost everywhere--original greatness, foreign oppression, extended struggle, sacrifice and self-liberation, impending modernization--the whole conception of the relation of what is now happening to what has happened and what is going to happen is altered. And finally, the new informality of urban life and of the pan-Indonesian culture which dominates it--the growth in importance of youth and youth culture with the consequent narrowing, sometimes even the reversal, of the social distance between generations; the sentimental comradeship of fellow revolutionaries; the populist equalitarianism of political ideology, Marxist and non-Marxist alike--appears to contain a similar threat to the third, the ethos or behavioral style, side of the Balinese triangle. All this is admittedly mere speculation (though, given the events of the fifteen years of Independence, not wholly groundless speculation) and when, how, how fast, and in what order Balinese perceptions of person, time, and conduct will change is, if not wholly unpredictable in general, largely so in detail. But as they do change--which seems to me certain, and in fact already to have well begun49 --the sort of analysis here developed of cultural concepts as active forces, of thought as a public phenomenon with effects like other public phenomena, should aid us in discovering its outlines, its dynamics, and, even more important, its social implications. Nor, in other forms and with other results, should it be less useful elsewhere. |
文化の統合、文化の衝突、文化の変化 論理」という言葉は、形式的な推論の原則と事実や出来事の間の理性的なつながりの両方を指すため、危険な言葉である。そして、文化の分析において、この言 葉ほど危険な言葉はない。意味のある形態を扱う場合、それらの間に内在的な関係を見出そうとする誘惑に駆られる。そのため、文化の統合は意味の調和、文化 の変化は意味の不安定さ、文化の衝突は意味の不調和として語られ、調和、不安定さ、不調和は、例えば甘さが砂糖の特性であるとか、ガラスの脆さがガラスの 特性であるといったように、意味そのものの特性であるかのように言われる。 しかし、これらの特性を甘さや脆さと同様に扱おうとしても、期待通りに「論理的に」振る舞うことはない。調和、不安定さ、不調和の構成要素を探そうとして も、それらが特性として存在しているはずの場所には見つけることができない。象徴的な形態を何らかの文化的な分析にかけ、その調和の度合い、安定性の比 率、不調和の指標を見つけ出すことはできない。我々ができるのは、問題となっている形態が実際に共存しているか、変化しているか、あるいは何らかの形で互 いに干渉しているかを見ることだけである。それは砂糖が甘いか確かめるために砂糖を味わってみたり、ガラスの強度を確かめるためにグラスを落としてみたり することに似ており、砂糖の化学組成やガラスの物理的構造を調査することとは異なる。その理由は、もちろん、意味はそれを担う物、行為、プロセスなどには 本来的に備わっているものではなく、デュルケームやウェーバーをはじめとする多くの人々が強調しているように、それらに付与されたものだからである。した がって、その性質の説明は、付与するもの、すなわち社会で生きる人間に求められる。思考の研究とは、ジョセフ・レヴェンソンの言葉を借りれば、人間が思考 する研究である。44 そして、彼らは自分だけの特別な場所ではなく、他のあらゆることを行うのと同じ場所、すなわち社会世界で思考する。文化の統合、文化の変化、あるいは文化 の衝突の性質は、そこで探求されるべきである。すなわち、シンボルの導きのもと、個人や個人グループが知覚し、感じ、推論し、判断し、行動する経験におい てである。 しかし、これは心理主義に屈するものではない。心理主義は論理主義と並んで文化分析の大きな妨げとなるものだが、人間の経験、すなわち実際に経験する出来 事は、単なる感覚ではなく、最も直接的な知覚から最も媒介された判断に至るまで、重要な感覚、すなわち解釈された感覚、把握された感覚である。新生児を例 外として、肉体構造以外では人間として未熟な人間にとって、すべての経験は解釈された経験であり、その解釈の基盤となる象徴形態は、網膜の細胞構造から心 理的成熟の内的段階に至るまで、さまざまな要因と関連して、その本質的な質を決定する。ピタゴラス学派の「意味の領域」に文化の組織化の「論理」を見出す という希望を捨てることは、その希望を完全に捨てることではない。それは、シンボルに生命を与えるもの、すなわちその使用に目を向けることである。 バリ人の象徴構造を結びつけているものは、人(名前、親族用語、通称、称号など)を定義する象徴構造と、時間を特徴づける象徴構造(順列カレンダーなど) であり、さらに、これら両者を 対人行動の順序付け(芸術、儀式、礼儀作法など)のための象徴構造に及ぼす影響の相互作用であり、それらを使用する人々の知覚に対する各構造の影響の相互 作用、その経験的影響が互いに作用し合い、強化し合う方法である。同時代的な傾向は生物学的加齢感覚を鈍らせる。生物学的加齢感覚の鈍化は時間的流れの感 覚の主な原因の一つを取り除く。時間的流れの感覚の減少は対人関係の出来事にエピソード的な性質を与える。儀式化された相互作用は他者に対する標準化され た認識を支える。他者に対する標準化された認識は社会に対する「定常状態」の概念を支える。社会に対する定常状態の概念は時間の分類学的認識を支える。こ のように、時間の概念から始めて、どちらの方向にも同じ円を巡ることができる。円は連続しているが、厳密な意味では閉じていない。なぜなら、これらの経験 様式はいずれも支配的な傾向、文化的な強調、そしてそれらを抑制する対極的なものにすぎず、人間の存在の一般的な条件に等しく根ざしており、独自の文化的 表現を伴って共存し、実際にはそれらに逆らって作用しているからである。しかし、それらは支配的であり、互いに補強し合い、持続している。そして、この永 続的でも完璧でもない状態にこそ、ヴェーバーが「意味の統一性」と呼んだ「文化的統合」という概念が正当に適用できるのである。 この見解では、文化的統合はもはや、論理的な独自の領域に閉じこもった人間社会の共通の生活から隔絶された特異な現象とは見なされない。しかし、それ以上 に重要なのは、文化の統合が包括的で、完全に浸透し、境界のないものとして捉えられていないことである。そもそも、先ほど述べたように、主要なパターンに 対抗するパターンが、従属的ではあるが重要なテーマとして、あらゆる文化に存在している。ごくありふれた、ヘーゲル的ではない方法で、文化の否定の要素 は、程度の差こそあれ、その文化の中に含まれている。例えばバリ人に関して言えば、彼らの個人信仰の裏返しとして考えられる魔女信仰(あるいは現象学的に 言えば魔女体験)や、彼らの礼儀作法の裏返しとして考えられるトランス状態の行動を調査することは、この点において非常に有益であり、現在の分析に深みと 複雑さを加えることになるだろう。「調和を愛する」プエブロ族の間に潜む疑いと派閥主義、あるいは競争相手のクワクィウトル族の「愛想のよい側面」など、 既成の文化的な特徴に対する有名な攻撃のいくつかは、本質的には、そのようなテーマの存在と重要性を指摘することに集約される。46 しかし、この種の自然な対位法を超えて、主要なテーマ自体の間にも、単純な、橋渡しのできない不連続性がある。すべてがすべてに等しく直接的に結びついて いるわけではない。すべてがすべてに即座に作用したり、作用されたりするわけではない。少なくとも、このような普遍的な主要な相互関連性は、経験的に実証 されなければならない。 文化の断絶、そして、それが原因で生じる社会の混乱は、文化の統合と同様に現実である。文化は継ぎ目のない網であるという考え方は、文化は寄せ集めの寄せ 集めであるという古い見解と同じくらいに帰納法的な前提である。システムは、網羅的に相互に結びついていなくてもシステムたり得る。 密に結びついていても、疎であっても、それがどのようなものであれ、それがいかに正しく統合されているかは経験的な問題である。 経験の様式間のつながりを、あらゆる変数間のつながりと同様に主張するには、それらを見つけ出す(そして、それらを見つけ出す方法を見つけ出す)必要があ り、単純に仮定するだけでは不十分である。そして、文化がそうであるように複雑であり、かつ完全に統合されたシステムが機能しないという、説得力のある理 論的理由がいくつかあるため、文化分析の問題は、相互関係や橋だけでなく、独立性の決定の問題でもある。47 文化の組織について、イメージが必要だとすれば、適切なイメージは蜘蛛の巣でも砂の山でもない。むしろ、触手は大部分が個別に統合されており、神経的には 互いに、またタコの脳とされる部分ともほとんどつながっていないが、それでもなんとか移動し、生き延びることができる。少なくともしばらくの間は、なんと か生き延びることができる存在として。 本稿で提案した、個人、時間、行動に関する考え方の緊密かつ即時の相互依存関係は、バリ島特有の形がいくらか特殊であるとしても、一般的な現象であると私 は主張したい。なぜなら、このような相互依存関係は、人間の経験が組織化される方法に内在するものであり、人間の生活が営まれる状況の必然的な帰結だから である。しかし、それは広大で未知数のこのような一般的な相互依存関係のひとつに過ぎず、そのうちのいくつかとは多かれ少なかれ直接的に、また他のいくつ かとはごく間接的に、また他のいくつかとは事実上まったく関係がない。 したがって、文化の分析は、文化の基本構造に対する英雄的な「全体論的」攻撃、より限定的な構造が単なる推論として見られるような包括的な「命令の秩序」 ではなく、重要なシンボル、重要なシンボルの集まり、重要なシンボルの集まりの集まり、すなわち知覚、感情、理解の媒体となるものを探し出し、その形成に 内在する人間経験の根底にある規則性を明らかにすることである。文化に関する実用的な理論は、もしそれが達成されるのであれば、直接観察可能な思考様式か ら構築することによって達成される。まず、それらの思考様式を決定し、次に、より変化に富み、まとまりは弱いが、それでも秩序ある「タコ型」の思考様式へ と構築する。部分的な統合、部分的な不整合、部分的な独立性の合流である。 文化もまた、タコのように動く。すなわち、すべての部分がスムーズに連携し、全体が協調して動くのではなく、この部分、それからあそこ、そして今度は別の 部分がバラバラに動くことで、方向転換が起こる。頭足類を除いた場合、いかなる文化においても、進歩への最初の衝動が現れる場所、そして、それがどのよう に、どの程度までシステム全体に広がるのか、という点については、現段階での我々の理解では、完全に予測不可能ではないにしても、非常に大きな不確実性が 残る。しかし、もしそのような衝動が、システム内のかなり緊密に相互接続された社会的影響力のある部分で現れるのであれば、その推進力は高い可能性を秘め ている、という仮説は、それほど不合理なものではないと思われる。 バリ人のパーソナルな認識、バリ人の時間の感覚、バリ人の礼儀正しさの概念を効果的に攻撃するような発展は、バリ文化の大部分を変容させる潜在的可能性を 秘めているように思われる。このような革命的な発展が現れる可能性があるのは、これらが唯一のポイントではないが(バリ人の威信とその基盤を攻撃するもの は、少なくとも同様に重大であるように思われる)、最も重要なポイントのひとつであることは確かである。バリ人が互いに対してより匿名性の低い見方をした り、よりダイナミックな時間感覚を持ったり、よりカジュアルな社交スタイルを身につけたりすれば、バリ人の生活は実に多くの点で変化を迫られることになる だろう。すべてではなくても、実に多くの点で変化を迫られることになるだろう。なぜなら、これらの変化のどれかひとつをとっても、他の変化を即座に、直接 的に意味することになるからだ。そして、この3つの変化は、異なる方法で、異なる文脈において、バリ人の生活を形作る上で重要な役割を果たしている。 このような文化の変化は、理論的にはバリ社会の内部から、あるいは外部から生じる可能性がある。しかし、バリが今や重心をジャワやスマトラの大都市に置く 発展途上の国民国家の一部であるという事実を考慮すると、外部から生じる可能性が高いと思われる。 インドネシアの歴史上初めて、人間味あふれる政治的指導者が登場したことは、単に事実上だけでなく外見上も、バリ人の伝統的な人間観に対する挑戦を暗示し ているように思われる。スカルノはバリ人にとって、ユニークで生き生きとした、親密な人物であるだけでなく、いわば公の場で年を重ねている。彼と直接的な 交流を持たないにもかかわらず、彼は現象学的に見れば、彼らの同時代人というよりもむしろ彼らの共同存在者であり、バリ島のみならずインドネシア全体にお いて、このような関係を築くという類まれな成功を収めたことが、彼が人々を惹きつけ、人々を惹きつけて離さない秘密である。真のカリスマ的人物の例に漏れ ず、彼の力は、伝統的な文化カテゴリーに当てはまらないという事実から生じている。そして、彼は自身の独自性を称えることで、それらのカテゴリーを打ち 破っている。これは、バリ島に現れ始めたスカルノのような小物指導者(国民と直接的な関係がある)にも当てはまる。 ブルクハルトがルネサンス期の諸侯がイタリアにもたらしたと見たような個人主義は、その性格の強烈な力によって、近代西洋の意識を伴って、インドネシアの 新しい民衆主義の諸侯によって、かなり異なる形ではあるが、バリにもたらされつつあるのかもしれない。 同様に、国民国家が着手した継続的な危機という政治、つまり、物事を遠ざけるのではなく、クライマックスへと押し進めるという情熱は、バリ人の時間に対す る考え方にも同様の課題を突きつけているように思われる。そして、このような政治が、新国家主義のナショナリズムに特徴的な歴史的枠組みに置かれる場合、 それはますます多くなっているが、その場合、今起こっていることと過去に起こったこと、そしてこれから起こるであろうこととの関係についての全体的な概念 は変化する。 そして最後に、都市生活とそれを支配するインドネシア全土の文化における新しい非公式性、すなわち、若者と若者文化の重要性の高まりと、それに伴う世代間 の社会的距離の縮小、時には逆転、革命の同志たちとの感傷的な仲間意識、マルクス主義・非マルクス主義を問わず政治的イデオロギーの民衆的平等主義は、バ リの三角形の3つ目の要素であるエートス(精神)または行動様式にも同様の脅威をもたらす可能性がある。 これらはすべて単なる憶測に過ぎない(とはいえ、15年間の独立運動の経緯を考えると、まったくの憶測というわけではない)。バリ人が個人、時間、行動に ついてどのような認識を持つようになるのか、いつ、どのように、どのくらいのスピードで、どのような順序で変化していくのかは、一般論としては完全に予測 できないとしても、詳細についてはほぼ予測できる。しかし、変化は起こるだろう。それは私には確実なように思えるし、実際、すでにかなり始まっているよう に見える。49 ここで展開された文化概念を能動的な力として、思考を他の公共現象と同様の影響を持つ公共現象として分析する手法は、その輪郭、力学、そしてさらに重要な 社会的影響を発見する上で役立つはずである。また、他の形態や結果においても、他の場所ではそれほど有用ではないはずだ。 |
| Notes 1 The most systematic and extensive discussions are to be found in T. Parsons and E. Shils, eds., Toward a General Theory of Action ( Cambridge, Mass., 1959); and T. Parsons, The Social System ( Glencoe, Ill., 1951). Within anthropology, some of the more notable treatments, not all of them in agreement, include: S. F. Nadel , Theory of Social Structure ( Glencoe. Ill., 1957). E. Leach, Political Systems of Highland Burma ( Cambridge, Mass., 1954); E. E. Evans-Pritchard, Social Anthropology ( Glencoe, Ill., 1951); R. Redfield, The Primitive World and Its Transformations ( Ithaca, 1953); C. LÈvi-Strauss, "Social Structure," in his Structural Anthropology ( New York, 1963). pp. 277-323; R. Firth, Elements of Social Organization ( New York, 1951); and M. Singer, "Culture," in International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 3 ( New York, 1968), p. 527. 2 G. Ryle, The Concept of Mind ( New York, 1949). I have dealt with some of the philosophical issues, here passed over in silence, raised by the "extrinsic theory of thought," above, Chapter 3, pp. 55-61. and need now only re-emphasize that this theory does not involve a commitment to behaviorism, in either its methodological or epistemological forms; nor yet again to any disputation of the brute fact that it is individuals, not collectivities, who think. 3 For an introduction to Schutz work in this field, see his "The Problem of Social Reality", Collected Papers, 1, ed. M. Natanson ( The Hague, 1962). 4 Ibid., pp. 17 - 18. Brackets added, paragraphing altered. 5 Where "ancestor worship" on the one side or "ghost beliefs" on the other are present, successors may be regarded as (ritually) capable of interacting with their predecessors, or predecessors of (mystically) interacting with their successors. But in such cases the "persons" involved are, while the interaction is conceived to be occurring, phenomenologically not predecessors and successors, but contemporaries, or even consociates. It should be kept clearly in mind that, both here and in the discussion to follow, distinctions are formulated from the actor's point of view, not from that of an outside, third-person observer. For the place of actororiented (sometimes miscalled "subjective") constructs in the social sciences, see, T. Parsons, The Structure of Social Action ( Glencoe, Ill., 1937), especially the chapters on Max Weber's methodological writings. 6 It is in this regard that the consociate-contemporary-predecessor-successor formulation differs critically from at least some versions of the umwelt-mitweltvorwelt-vogelwelt formulation from which it derives, for there is no question here of apodictic deliverances of "transcendental subjectivity" ý la Husserl but rather of socio-psychologically developed and historically transmitted "forms of understanding" ý la Weber. For an extended, if somewhat indecisive, discussion of this contrast, see M. Merleau-Ponty, "Phenomenology and the Sciences of Man," in his The Primacy of Perception ( Evanston, 1964), pp. 43 - 55. 7 In the following discussion, I shall be forced to schematize Balinese practices severely and to represent them as being much more homogeneous and rather more consistent than they really are. In particular, categorical statements, of either a positive or negative variety ("All Balinese ..."; "No Balinese ..."), must be read as having attached to them the implicit qualification " ... so far as my knowledge goes," and even sometimes as riding roughshod over exceptions deemed to be "abnormal." Ethnographically fuller presentations of some of the data here summarized can be found in H. and C. Geertz, "Teknonymy in Bali: Parenthood, Age-Grading, and Genealogical Amnesia," Journal of the Royal Anthropological Institute 94 (part 2) ( 1964):94-108; C. Geertz, "Tihingan: A Balinese Village," Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 120 ( 1964):1-33; and C. Geertz, "Form and Variation in Balinese Village Structure," American Anthropologist 61 ( 1959):991-1012. 8 While personal names of commoners are mere inventions, meaningless in themselves, those of the gentry are often drawn from Sanskrit sources and "mean" something, usually something rather high-flown, like "virtuous warrior" or "courageous scholar." But this meaning is ornamental rather than denotative, and in most cases what the meaning of the name is (as opposed to the simple fact that it has one) is not actually known. This contrast between mere babble among the peasantry and empty grandiloquence among the gentry is not without cultural significance, but its significance lies mainly in the area of the expression and perception of social inequality, not of personal identity. 9 This is, of course, not to say that such people are reduced in sociological (much less psychological) terms to playing the role of a child, for they are accepted as adults, if incomplete ones, by their consociates. The failure to have children is, however, a distinct handicap for anyone desiring much local power or prestige, and I have for my part never known a childless man who carried much weight in hamlet councils, or for that matter who was not socially marginal in general. 10 From a merely etymological point of view, they do have a certain aura of meaning, for they derive from obsolete roots indicating "leading," "medial," and "following"; but these gossamery meanings have no genuine everyday currency and are, if at all, but very peripherally perceived. 11 In point of fact, the Balinese system (or, in all probability, any other system) is not purely generational; but the intent here is merely to convey the general form of the system, not its precise structure. For the full terminological system, see H. and C. Geertz, "Teknonymy in Bali." 12 For a distinction, similar to the one drawn here, between the "ordering" and the "role-designating" aspects of kin terminologies, see D. Schneider and G. Homans , "Kinship Terminology and the American Kinship System," American Anthropologist 57 ( 1955):1195-1208. 13 Old men of the same generation as the deceased do not pray to him either, of course, for the same reason. 14 It might seem that the continuation of terms beyond the kumpi level would argue against this view. But in fact it supports it. For, in the rare case where a man has a ("real" or "classificatory") great-great-grandchild (kelab) old enough to worship him at his death, the child is, again, forbidden to do so. But here not because he is "the same age" as the deceased but because he is "(a generation) older"--i.e., equivalent to the dead man's "father." Similarly, an old man who lives long enough to have a great-great-grandchild kelab who has passed infancy and then died will worship--alone--at the child's grave, for the child is (one generation) senior to him. In principle, the same pattern holds in more distant generations, when, as the Balinese do not use kin terms to refer to the dead or the unborn, the problem becomes entirely theoretical: "That's what we'd call them and how we would treat them if we had any, which we never do." 15 Personal pronouns are another possibility and might indeed be considered as a separate symbolic order of person-definition. But, in fact, their use also tends to be avoided whenever possible, often at the expense of some awkwardness of expression. 16 This use of a descendant's personal name as part of a teknonym in no way contradicts my earlier statements about the lack of public currency of such names. The "name" here is part of the appellation of the person bearing the teknonym, not, even derivatively, of the eponymous child, whose name is taken purely as a reference point and is without--so far as I can tell--any independent symbolic value at all. If the child dies, even in infancy, the teknonym is usually maintained unchanged; the eponymous child addresses and refers to his father and mother by the teknonym which includes his own name quite unself-consciously; there is no notion that the child whose name is embraced in his parents', grandparents', or great-grandparents' teknonyms is, on that account, any way different from or privileged over his siblings whose names are not; there is no shifting of teknonyms to include the names of favored or more able offspring, and so on. 17 It also underscores another theme which runs through all the orders of person-definition discussed here: the minimization of the difference between the sexes which are represented as being virtually interchangeable so far as most social roles are concerned. For an intriguing discussion of this theme, see J. Belo, Rangda and Barong (Locust Valley, N.Y., 1949). 18 In this sense, birth order terms could, in a more elegant analysis, be defined as "zero teknonyms" and included in this symbolic order: a person called Wayan, Njoman, etc., is a person who has produced no one, who has, as yet anyway, no descendants. 19 G. Bateson, "Bali: The Value System of a Steady State," in M. Fortes, ed., Social Structure: Studies Presented to Radcliffe-Brown ( New York, 1963), pp. 35 - 53. Bateson was the first to point out, if somewhat obliquely, the peculiar achronic nature of Balinese thought, and my more narrowly focused analysis has been much stimulated by his general views. See also his "An Old Temple and a New Myth," Djawa (Jogjakarta) 17 ( 1937):219-307. [These have now been reprinted in J. Belo, ed., Traditional Balinese Culture ( New York, 1970), pp. 384-402; 111 - 136.] 20 Neither how many different titles are found in Bali (though there must be well over a hundred) nor how many individuals bear each title is known, for there has never been a census taken in these terms. In four hamlets I studied intensively in southeastern Bali a total of thirty-two different titles were represented, the largest of which was carried by nearly two hundred and fifty individuals, the smallest by one, with the modal figure running around fifty or sixty. See C. Geertz, "Tihingan: A Balinese Village." 21 Varna categories are often subdivided, especially by high-status persons, into three ranked classes--superior (utama), medium (madia), and inferior (nista)--the various titles in the overall category being appropriately subgrouped. A full analysis of the Balinese system of social stratification--as much Polynesian as Indian in type--cannot be given here. 22 The existence of one other order, that having to do with sex markers (Ni for women, I for men) ought at least to be mentioned. In ordinary life, these titles are affixed only to personal names (most of which are themselves sexually neutral) or to personal names plus birth order name, and then only infrequently. As a result, they are, from the point of view of person-definition, of but incidental importance, and I have felt justified in omitting explicit consideration of them. 23 For an essay in this direction, see C. Geertz, "Form and Variation in Balinese Village Structure." 24 Place names associated with the function the title expresses are perhaps even more common as secondary specification: "Klian Pau," "Pau" being the name of the hamlet of which the person is klian (chief, elder); "Anak Agung Kaleran," "Kaleran"--literally "north" or "northern"--being the name (and the location) of the lord's palace. 25 Traditional texts, some of them fairly extensive, relating certain activities of the gods, do exist and fragments of the stories are known. But not only do these myths also reflect the typological view of personhood, the static view of time, and the ceremonialized style of interaction I am seeking to characterize, but the general reticence to discuss or think about the divine means that the stories they relate enter but slightly into Balinese attempts to understand and adapt to "the world." The difference between the Greeks and the Balinese lies not so much in the sort of lives their gods lead, scandalous in both cases, as in their attitude toward those lives. For the Greeks, the private doings of Zeus and his associates were conceived to illuminate the all-too-similar doings of men, and so gossip about them had philosophical import. For the Balinese, the private lives of Betara Guru and his associates are just that, private, and gossip about them is unmannerly--even, given their place in the prestige hierarchy, impertinent. 26 It is the overall order which is conceived to be fixed, not the individual's location within it, which is movable, though more along certain axes than others. (Along some, e.g., birth order, it is not movable at all.) But the point is that this movement is not, or anyway not primarily, conceived in what we would regard to be temporal terms: when a "father-of" becomes a "grandfather-of," the alteration is perceived as being less one of aging than a change in social (and what is here the same thing, cosmic) coordinates, a directed movement through a particular sort of unchanging attribute, space. Also, within some symbolic orders of person-definition, location is not conceived as an absolute quality because coordinates are origin-dependent: in Bali, as elsewhere, one man's brother is another man's uncle. 27 Sch¸tz, The Problem of Social Reality, pp. 16-17. Brackets added. 28 Ibid., pp. 221 - 222. 29 As a preface to the following, and an appendix to the preceding, discussion, it should be remarked that, just as the Balinese do have consociate relations with one another and do have some sense of the material connection between ancestors and descendants, so too they do have some, as we would put it, "true" calendrical concepts--absolute dates in the so-called Caka system, Hinduistic notions of successive epochs, as well as, indeed, access to the Gregorian calendar. But these are (ca. 1958) unstressed and of distinctly secondary importance in the ordinary course of everyday life; variant patterns applied in restricted contexts for specific purposes by certain sorts of persons on sporadic occasions. A complete analysis of Balinese culture--so far as such a thing is possible--would indeed have to take account of them; and from certain points of view they are not without theoretical significance. The point, here and elsewhere, in this quite incomplete analysis, however, is not that the Balinese are, as the Hungarians are reputed to be, immigrants from another planet entirely unlike ourselves, but merely that the major thrust of their thought concerning certain matters of critical social importance lies, at least for the moment, in a markedly different direction from ours. 30 Because the thirty-seven-name cycles (uku) which make up the two hundred and ten-day supercycle are also named, they can be, and commonly are, used in conjunction with five- and seven-day names, so eliminating the need to invoke names from the six-name cycle. But this is merely a notational matter: the result is exactly the same, though the days of the thirty- and forty-two-day supercycles are thus obscured. Balinese devices--charts, lists, numerical calculation, mnemonics--for making calendrical determinations and assessing their meaning are both complex and various, and there are differences in technique and interpretation between individuals, villages, and regions of the island. Printed calendars in Bali (a still not very widespread innovation) contrive to show at once the uku; the day in each of the ten permutating cycles (including the one that never changes!); the day and month in the lunar-solar system; the day, the month, and year in the Gregorian and Islamic calendars; and the day, month, year, and year-name in the Chinese calendar--complete with notations of all the important holidays from Christmas to Galungan these various systems define. For fuller discussions of Balinese calendrical ideas and their socioreligious meaning, see R. Goris, "Holidays and Holy Days," in J. L. Swellengrebel, ed., Bali ( The Hague, 1960), pp. 115 - 129, together with the references cited there. 31 More accurately: the days they define tell you what kind of time it is. Though the cycles and supercycles, being cycles, are recurrent, it is not this fact about them which is attended to or to which significance is attached. The thirty-, thirty-five-, forty-two-, and two hundred and ten-day periodicities, and thus the intervals they demarcate, are not, or are only very peripherally, perceived as such; nor are the intervals implicit in the elementary periodicities, the cycles proper, which generate them--a fact which has sometimes been obscured by calling the former "months" and "years" and the latter "weeks." It is--one cannot stress it too strongly--only the "days" which really matter, and the Balinese sense of time is not much more cyclical than it is durative: it is particulate. Within individual days there is a certain amount of short-range, not very carefully calibrated, durative measurement, by the public beating of slit-gongs at various points (morning, midday, sundown, and so on) of the diurnal cycle, and for certain collective labor tasks where individual contributions have to be roughly balanced, by water-clocks. But even this is of little importance: in contrast to their calendrical apparatus, Balinese horological concepts and devices are very undeveloped. 32 Goris, "Holidays and Holy Days," p. 121. Not all of these holidays are major, of course. Many of them are celebrated simply within the family and quite routinely. What makes them holidays is that they are identical for all Balinese, something not the case for other sorts of celebrations. 33 Ibid. There are, of course, subrhythms resulting from the workings of the cycles: thus every thirty-fifth day is a holiday because it is determined by the interaction of the five- and seven-name cycles, but in terms of the sheer succession of days there is none, though there is some clustering here and there. Goris regards RaditÈ-Tungleh-Paing as the "first day of the . . . Balinese [permutational] year" (and thus those days as the first days of their respective cycles); but though there may (or may not: Goris doesn't say) be some textual basis for this, I could find no evidence that the Balinese in fact so perceive it. In fact, if any day is regarded as something of what we would regard as a temporal milestone it would be Galungan (number seventy-four in the above reckoning). But even this idea is very weakly developed at best; like other holidays, Galungan merely happens. To present the Balinese calendar, even partially, in terms of Western flowof-time ideas is, in my opinion, inevitably to misrender it phenomenologically. 34 Swellengrebel, Bali, p. 12. These temples are of all sizes and degrees of significance, and Swellengrebel notes that the Bureau of Religious Affairs on Bali gave a (suspiciously precise) figure, ca. 1953, of 4,661 "large and important" temples for the island, which, it should be remembered, is, at 2,170 square miles, about the size of Delaware. 35 For a description of a full-blown odalan (most of which last three days rather than just one), see J. Belo, Balinese Temple Festival (Locust Valley, N.Y., 1953). Again, odalans are most commonly computed by the use of the uku rather than the six-name cycle, together with the five and seven-name cycles. See note 30. 36 There are also various metaphysical conceptions associated with days bearing different names--constellations of gods, demons, natural objects (trees, birds, beasts), virtues and vices (love, hate . . .), and so on--which explain "why" it has the character it has--but these need not be pursued here. In this area, as well as in the associated "fortune telling" operations described in the text, theories and interpretations are less standardized and computation is not confined to the five-, six-, and seven-name cycles, but extended to various permutations of the others, a fact which makes the possibilities virtually limitless. 37 With respect to individuals the term applied is more often otonan than odalan, but the root meaning is just the same: "emerging," "appearance," "coming out." 38 The names of the last two months--borrowed from Sanskrit--are not strictly speaking numbers as are those of the other ten; but in terms of Balinese perceptions they "mean" eleventh and twelfth. 39 In fact, as another Indic borrowing, the years are numbered too, but-outside of priestly circles where familiarity with it is more a matter of scholarly prestige, a cultural ornament, than anything else--year enumeration plays virtually no role in the actual use of the calendar, and lunar-solar dates are almost always given without the year, which is, with the rarest of exceptions, neither known nor cared about. Ancient texts and inscriptions sometimes indicate the year, but in the ordinary course of life the Balinese never "date" anything, in our sense of the term, except perhaps to say that some event--a volcanic eruption, a war, and so forth--happened "when I was small," "when the Dutch were here," or, the Balinese illo tempore, "in Madjapahit times," and so on. 40 On the "shame" theme in Balinese culture, see M. Covarrubias, The Island of Bali ( New York, 1956); on "absence of climax," G. Bateson and M. Mead, Balinese Character ( New York, 1942). 41 For a comprehensive critical review, see G. Piers and M. Singer, Shame and Guilt ( Springfield, Ill., 1953). 42 Again, I am concerned here with cultural phenomenology, not psychological dynamics. It is, of course, quite possible, though I do not think the evidence is available either to prove or disprove it, that Balinese "stage fright" is connected with unconscious guilt feelings of some sort or another. My only point is that to translate lek as either "guilt" or "shame" is, given the usual sense of these terms in English, to misrender it, and that our word "stage fright"--"nervousness felt at appearing before an audience," to resort to Webster's again--gives a much better, if still imperfect, idea of what the Balinese are in fact talking about when they speak, as they do almost constantly, of lek. 43 For a description of the Rangda-Barong combat, see J. Belo, Rangda and Barong; for a brilliant evocation of its mood, G. Bateson and M. Mead, Balinese Character. See also above, pp. 114-118. 44 J. Levenson, Modern China and Its Confucian Past ( Garden City, 1964), p. 212. Here, as elsewhere, I use "thinking" to refer not just to deliberate reflection but intelligent activity of any sort, and "meaning" to refer not just to abstract "concepts" but significance of any sort. This is perhaps somewhat arbitrary, and a little loose, but one must have general terms to talk about general subjects, even if what falls under such subjects is very far from being homogeneous. 45 ,"Every sign by itself seems dead. What gives it life?--in use it is alive. Is life breathed into it there?--Or is its use its life?" L. Wittgenstein, Philosophical Investigations ( New York, 1953), p. 128e. Italics in original. 46 Li An-che, "ZuÒi: Some Observations and Queries," American Anthropologist 39 ( 1937):62-76; H. Codere, "The Amiable Side of Kwakiutl Life," American Anthropologist 58 ( 1956):334-351. Which of two antithetical patterns or clusters of patterns, if either, is in fact primary, is of course an empirical problem, but not, particularly if some thought is given to what "primacy" means in this connection, an insoluble one. 47 "It has thus been shown that, for adaptations to accumulate, there must not be channels ... from some variables . . . to others. ... The idea so often implicit in physiological writings that all will be well if only sufficient cross-connections are available is ... quite wrong." W. R. Ashby, Design for a Brain, 2nd ed. rev. ( New York, 1960), p. 155. Italics in original. Of course, the reference here is to direct connections--what Ashby calls "primary joins." Any variable with no relations whatsoever to other variables in the system would simply not be part of it. For a discussion of the nest of theoretical problems involved here, see Ashby, pp. 171-183, 205-218. For an argument that cultural discontinuity may not only be compatible with the effective functioning of the social systems they govern but even supportive of such functioning, see J. W. Fernandez, "Symbolic Consensus in a Fang Reformative Cult." American Anthropologist 67 ( 1965):902-929. 48 It is perhaps suggestive that the only Balinese of much importance in the central Indonesian government during the early years of the Republic--he was foreign minister for a while--was the Satria paramount prince of Gianjar, one of the traditional Balinese kingdoms, who bore the marvellously Balinese "name" of Anak Agung Gde Agung. "Anak Agung" is the public title borne by the members of the ruling house of Gianjar, Gde is a birth order title (the Triwangsa equivalent of Wayan), and Agung though a personal name is in fact just an echo of the public title. As "gde" and "agung" both mean "big," and "anak" means man, the whole name comes to something like "Big, Big, Big Man"--as indeed he was, until he fell from Sukarno's favor. More recent political leaders in Bali have taken to the use of their more individualized personal names in the Sukarno fashion and to the dropping of titles, birth order names, teknonyms, and so on, as "feudal" or "old-fashioned." 49 This was written in early 1965; for the dramatic changes that, in fact, occurred later that year, see pp. 282-283 and Chapter 11. |
注 1 最も体系的な広範な議論は、T. ParsonsとE. Shils編『Toward a General Theory of Action』(マサチューセッツ州ケンブリッジ、1959年)とT. Parsons著『The Social System』(イリノイ州グレンコー、1951年)に記載されている。人類学の分野では、以下のような著名な研究があるが、すべてが一致しているわけで はない。S. F. ナデル著『社会構造の理論』(グレンコー、イリノイ州、1957年)。E. Leach, Political Systems of Highland Burma (ケンブリッジ、マサチューセッツ州、1954年); E. E. Evans-Pritchard, Social Anthropology (グレンコー、イリノイ州、1951年); R. Redfield, The Primitive World and Its Transformations (イサカ、1953年); C. LÈvi-Strauss, "Social Structure,」 『構造人類学』(ニューヨーク、1963年)所収、277-323ページ。R. ファース著『社会組織の要素』(ニューヨーク、1951年)、M. シンガー著「文化」『国際社会科学百科事典』第3巻(ニューヨーク、1968年)、527ページ。 2 G. Ryle, The Concept of Mind (ニューヨーク、1949 年)。私は、ここで言及しなかったが、第3章の55ページから61ページで取り上げた「思考の外在理論」によって提起されたいくつかの哲学的問題につい て、ここで取り扱った。そして、この理論が方法論的または認識論的な形態のいずれにおいても、行動主義へのコミットメントを伴うものではないことを再度強 調しておく。また、思考するのは個人であり集団ではないという事実をめぐる論争にも、一切関与していない。 3 この分野におけるシュッツの研究の入門編として、彼の論文「社会現実の問題」を参照のこと。M. Natanson編『論文集』第1巻(ハーグ、1962年)。 4 同書、17~18ページ。括弧内は追加、段落は変更。 5 一方に「祖先崇拝」、他方に「幽霊信仰」が存在する場合、後継者は(儀礼上)先祖と交流できる、あるいは先祖は(神秘的に)後継者と交流できるとみなされ る可能性がある。しかし、そのような場合、関与する「人物」は、交流が起こっていると考えられている間、現象学上は先祖でも後継者でもなく、同時代人、あ るいは共同者である。ここで、またこれ以降の議論においても、区別は行為者の視点からではなく、外部の第三者観察者の視点から定式化されていることを明確 に念頭に置いておくべきである。社会科学における行為者志向(時に「主観的」と誤称される)の構成の位置づけについては、T. パーソンズ著『社会行動の構造』(1937年、イリノイ州グレンコー)を参照のこと。特に、マックス・ウェーバーの方法論に関する章を参照のこと。 6 この点において、共同社会-同時代-前任者-後継者という概念は、少なくともその派生元である環境世界-ミットヴェルト-フォルヴェルトという概念のいく つかのバージョンとは決定的に異なる。なぜなら、フッサール流の「超越論的主観性」の公理的な提示ではなく、むしろ、ヴェーバー流の社会心理学的に発展し 歴史的に伝達された「理解の形態」が問題となっているからである。この対比に関する、やや曖昧ではあるが詳細な議論については、M. メルロ=ポンティ著『知覚の優先権』(1964年、エバンストン)の「現象学と人間科学」の章(43~55ページ)を参照のこと。 7 以下の議論では、私はバリ人の慣習を厳しく単純化し、実際よりもはるかに均質で一貫性があるものとして表現せざるを得ないだろう。特に、肯定的なもの、否 定的なものに関わらず、断定的な表現(「バリ人は...」や「バリ人には...がいない」)は、「...私の知る限り」という暗黙の条件が付いていると解 釈すべきであり、時には「異常」とみなされる例外を無視していると解釈されることもある。ここで要約したデータのいくつかについては、H.とC.ゲーツに よる民族誌学的なより詳細な発表が以下で見られる。「バリにおける職業名:親子関係、年齢による階級、系図上の記憶喪失」、王立人類学研究所紀要94(第 2部)(1964年):94-108;C.ゲーツ、「ティヒンガン: 「バリの村」、『言語・土地・民族学への寄稿』、120(1964):1-33;およびC. ゲルツ著「バリの村の構造における形式と変化」、『アメリカ人類学者』61(1959):991-1012。 8 平民の個人名は単なる作り話であり、それ自体には何の意味もないが、貴族の個人名はしばしばサンスクリット語に由来し、「意味」を持っている。通常は「徳 の高い戦士」や「勇敢な学者」といった、かなり大げさな意味である。しかし、この意味は指示的というよりも装飾的なものであり、ほとんどの場合、その名前 の意味(単に名前があるという事実とは対照的)が何であるかは実際には知られていない。農民たちのたわいもないおしゃべりと、貴族たちの空虚な大げさな言 葉遣いとの対比は、文化的には重要な意味を持っているが、その重要性は主に社会的格差の表現と認識の領域にあり、個人のアイデンティティの領域にあるので はない。 9 もちろん、このような人々が社会学(ましてや心理学)の観点から、子供の役割に甘んじているというわけではない。彼らは不完全ではあるが、共同体の一員と して大人として認められている。しかし、子供を持たないことは、地域社会で大きな権力や名声を望む人にとっては明らかにハンディとなる。私自身、村の評議 会で大きな影響力を持つ子供を持たない人物や、一般的に社会的に疎外されていない人物を知らない。 10 単に語源的な観点から見ると、それらは「指導する」、「中心」、「従う」を意味する廃れた語根に由来するため、ある種の意味合いを持っている。しかし、こ れらのうわべだけの意味は、日常的に通用するものではなく、通用するとしてもごく限られた範囲でしか認識されていない。 11 実際、バリ人のシステム(あるいは、おそらく他のシステムも)は純粋な世代別ではない。しかし、ここで意図しているのは、そのシステムの一般的な形を伝え ることであり、正確な構造ではない。用語体系全体については、H.とC.ゲーツの「バリにおけるテクノニミー」を参照のこと。 12 親族呼称の「序列化」と「役割指定」の側面を区別する類似の例については、D. SchneiderとG. Homansによる「親族呼称とアメリカ親族制度」(『アメリカ人類学』57巻、1955年、1195-1208ページ)を参照のこと。 13 もちろん、故人と同世代の老人も、同じ理由から彼に祈りを捧げることはない。 14 クンピのレベルを超えて用語が継続していることは、この見解に反論しているように思えるかもしれない。しかし実際には、この見解を裏付けている。なぜな ら、まれに、ある男性が死の際に彼を崇拝できるほど十分に年長の(「真の」または「分類上の」)ひ孫(kelab)を持つ場合、その子供は、やはり、それ を禁じられているからだ。しかし、この場合、その理由は、その子供が故人と「同い年」だからではなく、「(一世代)年上」であるから、つまり、故人の「父 親」に相当するからである。同様に、孫の子供が乳児期を過ぎてから亡くなるまで十分に長生きした老人は、その子供が自分より(一世代)年上であるため、そ の子供の墓で一人で祈りを捧げる。原則として、バリ人が死者や胎児に対して親族用語を使用しない場合、より遠い世代でも同じパターンが当てはまる。この問 題は完全に理論的なものとなる。「私たちが彼らをどう呼ぶか、そして、もし私たちが彼らを産んだとしたら、彼らをどう扱うか、それは私たちが決して産まな いからだ」 15 人称代名詞もまた可能性の一つであり、実際には、人定義の別の象徴的な秩序として考えられるかもしれない。しかし、実際には、その使用もまた可能な限り避 けられる傾向にあり、しばしば表現のぎこちなさを犠牲にしてしまう。 16 子孫の個人名を専門用語の一部として使用することは、このような名称が一般的に使用されていないという私の以前の主張に反するものではない。ここでいう 「名前」は、その専門用語を持つ人物の呼称の一部であり、たとえ派生的にでも、その名称の由来となった子供の名前の一部ではない。その子供の名前は、純粋 に参照点として使用されており、私が知る限り、独立した象徴的な価値は一切持っていない。その子供が幼児期に死亡した場合でも、通常、テクノニムは変更さ れない。名付けられた子供は、自分の名前を含むテクノニムをまったく意識することなく、父親や母親にそのテクノニムで呼びかけたり、そのテクノニムで呼び かけたりする。両親、祖父母、ひいおじいさんのテクノイムに組み込まれているからといって、そのために名前がテクノイムに組み込まれていない兄弟姉妹と比 べて、あるいはその兄弟姉妹よりも優遇されているという考えはない。テクノイムを、より愛されている子供やより有能な子供の名前に変更するといったことも ない。 17 また、ここで取り上げた人物の定義に関するすべての秩序に共通するもう一つのテーマも強調されている。それは、ほとんどの社会的役割に関しては、事実上交 換可能であるかのように表現される男女間の差異を最小限に抑えるというテーマである。このテーマに関する興味深い議論については、J. Belo著『Rangda and Barong』(1949年、ニューヨーク州ローカストバレー)を参照のこと。 18 この意味において、出生順位の用語は、より洗練された分析では「ゼロ・テクノンム」と定義され、この象徴的な序列に含まれる可能性がある。ワヤン、ニョマ ンなどと呼ばれる人物は、まだ誰一人として生んでいない、つまり、少なくとも現時点では子孫を持たない人物である。 19 G. ベイトソン、「バリ:定常状態の価値体系」、M. フォーテス編、『社会構造:ラドクリフ=ブラウンに捧げる研究』(ニューヨーク、1963年)、35-53ページ。ベイトソンは、やや遠回しな表現ではあ るが、バリ人の思考の独特な非時間的性質を最初に指摘した人物であり、私のより狭い範囲に焦点を絞った分析は、彼の一般的な見解から多くの刺激を受けてい る。また、彼の「古い寺院と新しい神話」『ジャワ』(ジョグジャカルタ)17(1937年):219-307も参照のこと。 [これらは現在、J. Belo編『伝統的バリ文化』(ニューヨーク、1970年)の384-402ページ、111-136ページに再版されている。] 20 バリ島にどれほどの称号があるのか(100以上はあるはずだが)、また、それぞれの称号を何人の個人が名乗っているのかは、これまで一度も人口調査が行わ れたことがないため、わかっていない。私がバリ島南東部で集中的に調査した4つの村落では、合計32の異なる称号が確認された。最も多い称号は250人近 くが名乗り、最も少ない称号は1人だけが名乗っており、最も多い称号は50~60人ほどが名乗っていた。C. ゲルツ著『ティヒンガン:バリの村』を参照。 21 ヴァルナのカテゴリーは、特に地位の高い人々によって、しばしば3つのランクに細分化される。すなわち、上位(utama)、中位(madia)、下位 (nista)である。カテゴリー全体におけるさまざまな称号は、適切にサブグループ化される。ポリネシア的でありながらインド的でもあるバリ人の社会階 層化システムに関する完全な分析は、ここではできない。 22 もう一つの序列、すなわち性別を表す序列(女性にはニ、男性にはイ)の存在は、少なくとも言及されるべきである。通常、これらの称号は個人名(そのほとん どは性別を問わない)または個人名と出生順位名にのみ付けられ、付けられる頻度も低い。そのため、人名定義の観点から見ると、それらは付随的な重要性しか 持たず、私はそれらを明確に考慮することを省略してもよいと判断した。 23 この方向性に関する論文としては、C. ゲーツ著「バリの村落構造における形式と変化」を参照のこと。 24 「クリアン・パウ」や「パウ」は、その人物がクリアン(首長、長老)である村落の名称である。「アナッ・アグン・カレラン」や「カレラン」は、文字通り 「北」または「北部」を意味し、領主の宮殿の名称(および所在地)である。 25 神々の特定の活動に関する伝統的なテキストは、かなり大規模なものもいくつか存在し、断片的なストーリーも知られている。しかし、これらの神話は、私が特 徴づけようとしている類型的な人間観、静的な時間観、儀式化された交流スタイルを反映しているだけでなく、神について語ることも考えることも一般的に控え めであるため、それらのストーリーはバリ人が「世界」を理解し、適応しようとする試みにほんの少ししか入り込めていない。ギリシア人とバリ人の違いは、神 々が送る生活の様式にあるのではなく、どちらもスキャンダラスなものであるが、むしろその生活に対する態度にある。ギリシア人にとって、ゼウスとその仲間 たちの私的な行動は、あまりにも似通った人間の行動を明らかにするものと考えられていたため、彼らに関する噂話には哲学的な意味合いがあった。バリ人に とって、ベタラ・グルとその仲間たちの私生活はあくまでもプライベートなものであり、彼らについての噂話は不作法であり、彼らの地位を考えると、無礼とさ え言える。 26 固定されていると考えられているのは、全体的な秩序であり、その秩序における個人の位置は、ある軸に沿っては動くが、他の軸に沿っては動かない。(出生順 など、一部の軸に沿っては、まったく動かない。)しかし、重要なのは、この動きは、私たちが時間的な観点で考えるようなものではない、あるいは、少なくと も、それが主な理由ではないということだ。「父親」が 「が「祖父」になるとき、その変化は加齢によるものというよりも、社会(そしてここでは宇宙)の座標の変化、つまり特定の不変の属性である空間を通る方向 づけられた動きとして認識される。また、ある象徴的な人物定義の秩序においては、座標が起源に依存しているため、場所は絶対的な性質として考えられていな い。バリ島でも他の場所でも、ある男の兄弟は他の男にとっては叔父である。 27 Schuetz, The Problem of Social Reality, pp. 16-17. 括弧は追加した。 28 同書、221-222ページ。 29 以下に述べることの前文として、また、前出の議論の付録として、バリ人は互いに結合関係を持ち、祖先と子孫の間に物質的なつながりがあるという感覚を持っ ているように、 彼らにも、私たちが「真の」暦の概念と呼ぶもの、すなわち、いわゆる「カカ」システムにおける絶対日付、ヒンドゥー教の時代観、そしてグレゴリオ暦へのア クセスもある。しかし、これらは(1958年頃)日常生活では重視されておらず、明らかに二次的な重要性しか持たれていない。バリ文化の完全な分析(その ようなことが可能である限り)では、確かにこれらを考慮する必要がある。また、特定の観点から見ると、それらは理論的に重要な意味を持っている。しかし、 この不完全な分析の要点は、バリ人がハンガリー人のように、自分たちとは全く異なる惑星からの移民であるということではなく、少なくとも現時点では、社会 的に重要な特定の問題に関するバリ人の考え方の主な方向性が、我々とは著しく異なっているということだけである。 30 210日間のスーパーサイクルを構成する37の名前のサイクル(ウク)にも名前が付けられているため、5日と7日の名前と組み合わせて使用することがで き、実際によくそうしている。そのため、6名のサイクルから名前を呼び出す必要がなくなる。しかし、これは単に表記上の問題にすぎず、結果はまったく同じ である。ただし、30日と42日のスーパーサイクルの日付は不明瞭になる。バリの暦決定方法と意味の評価方法は、複雑かつ多様であり、個人、村、島内の地 域によって技術や解釈に違いがある。バリ島では印刷カレンダー(まだあまり普及していない)が、ウク(十の順列のサイクルの各日(決して変わらない日も含 む!)、太陰太陽暦の日付と月、 グレゴリオ暦とイスラム暦における日、月、年、そして中国暦における日、月、年、年号など、クリスマスからガルンガンまでの重要な祝祭日をすべて網羅した もの。バリの暦の考え方と社会宗教的な意味合いについてより詳しく知りたい方は、R.ゴリス著『祝祭日と聖なる日』、J.L.スウェレングレーベル編『バ リ』(ハーグ、1960年)115~129ページを参照されたい。 31 より正確に言えば、彼らが定義する日数は、それがどのような時間であるかを教えてくれる。サイクルやスーパーサイクルはサイクルであるため繰り返される が、注目されるのは、あるいはそこに意義が置かれるのは、この事実ではない。30日、35日、42日、210日の周期、そしてそれによって区切られる間隔 は、そのようなものとして認識されていないか、あるいはごくわずかしか認識されていない。また、それらを生み出す基本的な周期、すなわちサイクルそのもの に内在する間隔も認識されていない。この事実は、前者を「月」や「年」、後者を「週」と呼ぶことによって、時折曖昧にされてきた。強調し過ぎることはない が、本当に重要なのは「日」だけである。バリ人の時間感覚は、循環的というよりも持続的である。個々の1日の中では、スリットゴングを叩くことで、1日の サイクルのさまざまなポイント(朝、正午、日没など)で、ある程度の長期的な測定が行われる。また、個々の貢献を大まかにバランスさせる必要がある特定の 集団労働の作業では、水時計が使用される。しかし、それさえもさほど重要ではない。バリ人の暦の装置とは対照的に、バリ人の時計の概念や装置は非常に未発 達である。 32 ゴリス著『祝祭日と聖なる日』、121ページ。もちろん、これらの祝祭日がすべて主要な祝祭日というわけではない。その多くは家族内でささやかに祝われ る、ごく日常的なものである。それらが祝祭日となるのは、バリ人すべてにとって同じであるからであり、他の種類の祝祭日とは異なる点である。 33 同上。もちろん、サイクルの作用から生じるサブリズムもある。例えば、35日目は祝日となるが、これは5と7の数字のサイクルの相互作用によって決定され るためである。しかし、日々の連続性という観点では、祝日となる日はなく、いくつかのグループに分かれている。ゴリスは、ラディテ・トゥングル・パイング を「バリの(順列)年の最初の日」と見なしている(したがって、これらの日はそれぞれのサイクルの最初の日である)。バリの[順列]年の最初の日」と見な している(したがって、これらの日はそれぞれのサイクルの最初の日である)。しかし、この考えにはいくらか(あるいはまったく)テキスト上の根拠があるか もしれないが(ゴリスは言及していない)、バリ人が実際にそう認識しているという証拠は見つからなかった。実際、もしある日が私たちが一時的なマイルス トーンと見なすようなものであるとすれば、それはガルンガン(上記の計算では74番目)である。しかし、この考えもせいぜいごく弱い程度にしか発展してい ない。他の祝祭日と同様に、ガルンガンはただ起こるだけなのだ。バリ暦を部分的にでも西洋の時間概念で表現することは、私の意見では、必然的に現象学的に 誤って表現することになる。 34 スウェルングレベル著『バリ島』12ページ。これらの寺院は大小様々であり、重要性も異なるが、スウェレングレベルは、1953年頃にバリの宗教局が発表 した「島にある4,661の『大規模かつ重要な』寺院」という数字(疑わしいほど正確な数字)を挙げている。バリ島は、2,170平方マイルの面積で、デ ラウェア州とほぼ同じ大きさであることを覚えておくべきである。 35 本格的なオダラン(そのほとんどは1日ではなく3日間続く)の説明については、J. Belo著『バリの寺院祭礼』(ニューヨーク州ローカストバレー、1953年)を参照のこと。繰り返しになるが、オダランは通常、6つの名前のサイクルで はなく、5つと7つの名前のサイクルとともに、ウクを用いて計算される。注30を参照のこと。 36 また、異なる名称を持つ日には、神々、悪魔、自然物(木々、鳥、獣)、美徳や悪徳(愛、憎しみなど)といった、さまざまな形而上学的な概念が関連付けられ ており、それによって「なぜ」その性格を持つのかが説明されているが、ここではそれらを追求する必要はない。この分野、および本文で説明されている関連す る「占い」業務においても、理論や解釈はそれほど標準化されておらず、計算も五、六、七名のサイクルに限定されず、他のさまざまな組み合わせにまで拡張さ れている。この事実により、可能性は事実上無限大となる。 37 個人に関して用いられる用語は、オダランよりもオトナンの方がより頻繁に用いられるが、語源の意味は同じである。「出現」、「出現」、「出現」である。 38 サンスクリット語から借用された最後の2ヶ月の名称は、厳密に言えば、他の10の名称のような数字ではない。しかし、バリ人の認識では、11月と12月を 「意味する」のである。 39 実際、インド語からのもう一つの借用語として、年にも番号が振られているが、僧侶のサークル以外では、年号の知識は学術的な威信や文化的装飾の問題であ り、実際のカレンダーの使用においては年号はほとんど役割を果たさない。太陰太陽暦の日付は、ほとんどの場合、年号なしで示される。年号は、ごくまれな例 外を除いて、知られておらず、気にも留められていない。古代の文献や碑文には時折年号が記載されているが、通常の生活では、バリ人は私たちが「日付」と呼 ぶものを一切使用しない。例外があるとすれば、火山の噴火や戦争など、ある出来事が「私がまだ幼かった頃」、「オランダ人がバリ島にいた頃」、あるいはバ リ語で「マジャパイト時代」などと表現する場合くらいである。 40 バリ文化における「恥」というテーマについては、M. コバルビアス著『バリ島』(ニューヨーク、1956年)を参照。「クライマックスの欠如」については、G. ベイトソンとM. ミード著『バリ人の性格』(ニューヨーク、1942年)を参照。 41 包括的な批判的レビューについては、G. PiersとM. Singer著『恥と罪悪感』(スプリングフィールド、イリノイ州、1953年)を参照のこと。 42 繰り返しになるが、ここで私が関心を抱いているのは文化現象学であり、心理学的力学ではない。もちろん、バリ人の「あがり症」が何らかの無意識の罪悪感と 関連している可能性は十分にあるが、それを証明または否定する証拠は存在しないと私は考えている。私が言いたいのは、lekを「罪悪感」や「羞恥心」と訳 すのは、英語におけるこれらの用語の一般的な意味から考えると誤訳であり、また、ウェブスター辞典を再び参照するならば、私たちの「舞台恐怖症」という言 葉は、「観客を前にして感じる緊張感」という意味であり、バリ人が実際にlekについて話すときに言わんとしていることを、まだ完全ではないにしても、よ りよく理解できるということだ。 43 ランダとバロンの戦闘の描写については、J. ベロ著『ランダとバロン』を参照。その雰囲気を鮮やかに描いたものとしては、G. ベイトソンとM. ミード著『バリ人の性格』がある。また、上記114~118ページも参照のこと。 44 J. レヴェンソン著『現代中国とその儒教的過去』(ガーデンシティ、1964年)212ページ。ここでは、他の箇所でもそうであるように、「思考」という言葉 は、意図的な考察だけでなく、あらゆる種類の知的活動を指すために使用し、「意味」という言葉は、抽象的な「概念」だけでなく、あらゆる種類の意義を指す ために使用している。これはおそらく、ある程度恣意的で、やや曖昧な表現であるが、たとえその対象が均質であるとは程遠いものであっても、一般的な主題に ついて語るためには一般的な用語が必要である。 45 「あらゆる記号はそれ自体では死んでいる。 生命を与えるものは何か? 使用されているとき、それは生きている。 生命はそこで吹き込まれるのか? それとも、使用が生命なのか?」 L. ウィトゲンシュタイン著『哲学探究』(ニューヨーク、1953年)、128ページ。 イタリック体は原文のまま。 46 李安喆、「帰納法:いくつかの観察と疑問」、アメリカ人類学者39(1937):62-76;H. コデレ、「クワキウトル族の愛すべき側面」、アメリカ人類学者58(1956):334-351。2つの相反するパターンまたはパターンの集合のうち、ど ちらが実際には主要なのか、もちろん経験的な問題であるが、特に「プライマシー」がこの文脈で何を意味するのかを考えるならば、解決不能な問題ではない。 47 「適応が蓄積されるためには、ある変数から他の変数への経路があってはならないことが示されている。... 生理学の文献では、十分な相互接続があればすべてうまくいくという考え方が暗黙のうちに示されていることが多いが、それは... まったくの間違いである。」W. R. Ashby著『Design for a Brain, 2nd ed. rev.』(ニューヨーク、1960年)、155ページ。イタリック体は原文のまま。もちろん、ここで言及されているのは直接的なつながり、つまりアシュ ビーが「一次結合」と呼ぶものである。システム内の他の変数とまったく関係のない変数は、単純にその一部ではない。ここで関連する理論的な問題の巣につい て議論する場合は、Ashby, pp. 171-183, 205-218を参照のこと。文化の不連続性は、それが支配する社会システムの有効な機能と両立するだけでなく、そのような機能の支援にもなり得るという 議論については、J. W. Fernandez著「ファン族の改革派カルトにおける象徴的合意」『アメリカン・アンソロポロジスト』67号(1965年):902-929を参照のこ と。 48 インドネシア共和国の初期に中央政府で重要な地位にあったバリ人は、ジャイジャール王国のサトリア王族の王子、アグン王子だけだった。彼は一時外務大臣も 務めた。アグン王子は、バリ人らしい「名前」、アグン王子という名前を持っていた。「Anak Agung」はジャイジャール王国の支配者一族のメンバーが持つ公的な称号であり、「Gde」は出生順位の称号(トリワングサの「ワヤン」に相当)であ り、「Agung」は個人名であるが、実際には公的な称号の響きをそのまま受け継いでいる。「グデ」と「アグン」はどちらも「大きい」という意味であり、 「アナッ」は「男」を意味するため、この名前全体は「ビッグ、ビッグ、ビッグマン」というような意味になる。最近のバリの政治指導者たちは、スカルノのや り方を真似て、より個性的な個人名を使用するようになり、称号、出生順の名前、通称などを「封建的」あるいは「時代遅れ」として廃止するようになった。 49 これは1965年初頭に書かれたものである。実際、その年後半に劇的な変化が起こったことについては、282~283ページおよび第11章を参照のこと。 |
| Person, time, and conduct in
Bali: an essay in cultural analysis, New-Haven/Ct./USA 1966: Yale
University Press; ed. by the Deptartment of Southeast Asia Studies cf. The interpretation of cultures: selected essays, New-York/N.Y./USA etc. 1973: Basic Books, pp. 360-411. |
|
| http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Person_Time_Conduct.htm |
++
★
| 1 | 295 |
・人間の思考はまったく社会的なものである(命題)。 ・思考とは根底において公の活動である——思考のおこなわれる場所は、屋敷、市場、 町の広場だ。 |
|
| 2 |
・文化的装置 |
||
| 3 |
・バリ島人の観念は、西洋人にとって異常に発達している(ギアツにとっ
てはそうではない?) |
||
| 4 |
296 |
【文化の研究】 ・文化と社会構造、という分析概念。 ・マルク・ブロック『歴 史家の仕事(metier d'historien)』——ルネサンスの豪商たちの頭の中を知りたければ、彼らが取り扱う商品のみならず、どのよ うな絵画を見、どのような書物を読んでいたのかを知らねばならない。臣下の君主に対する態度は、彼らの神への態度を知るべきだ。 |
|
| 5 |
297 |
・市井の人の文化を知るには、ブロックがみているような人たちではな
い、思考=公的活動を知る必要がある。 |
|
| 6 |
・文化のパターンの研究は難しい |
||
| 7 |
|||
| 8 |
・個々人の性格づけ ・象徴体系の歴史的構築性 |
||
| 9 |
|||
| 10 |
302 |
【同輩たち——先行者・同時代者・仲間・後継者】 ・シュッツの業績は、シェーラー・ウェーバー・フッサールの知的伝統と、新大陸の、ジェームズ、ミード、デューイの伝統の融合にある。 ・同輩たちを、先行者・同時代者・仲間・後継者の4つのカテゴリーにわけて解説していく(なかなかいいが、ジェンダ的区分がなく、男性中心的なのはいただ けない) |
|
| 11 |
303 |
・「仲間」 |
|
| 12 |
303 |
・「同時代者」 |
|
| 13 |
305 |
・「先行者」「後継者」 |
|
| 14 |
|||
| 15 |
|||
| 16 |
307 |
【バリの人間規定に関する秩序】 ・人間の標識の6種類:1)個人名、2)出生順位名、3)親族名称、4)テクノニーム、5)地位称号、6)公的称号。 |
|
| 17 |
308 |
・個人名 |
|
| 18 |
|||
| 19 |
|||
| 20 |
|||
| 21 |
|||
| 22 |
310 |
・出生順位名 |
|
| 23 |
|||
| 24 |
|||
| 25 |
312 |
・親族名称 |
|
| 26 |
|||
| 27 |
|||
| 28 |
314 |
・「要するに、バリの親族名称の体系は、個々人を直接具体的に接しあう
ような関係の名称によってではなく主として分類的な名称によって、社会的相互作用における相手としてではなく社会的状況の諸領域を占めている人びととし
て、捉えるのである」(314) |
|
| 29 |
|||
| 30 |
|||
| 31 |
|||
| 32 |
|||
| 33 |
|||
| 34 |
|||
| 35 |
318 |
・テクノニーム |
|
| 36 |
|||
| 37 |
|||
| 38 |
|||
| 39 |
|||
| 40 |
|||
| 41 |
321 |
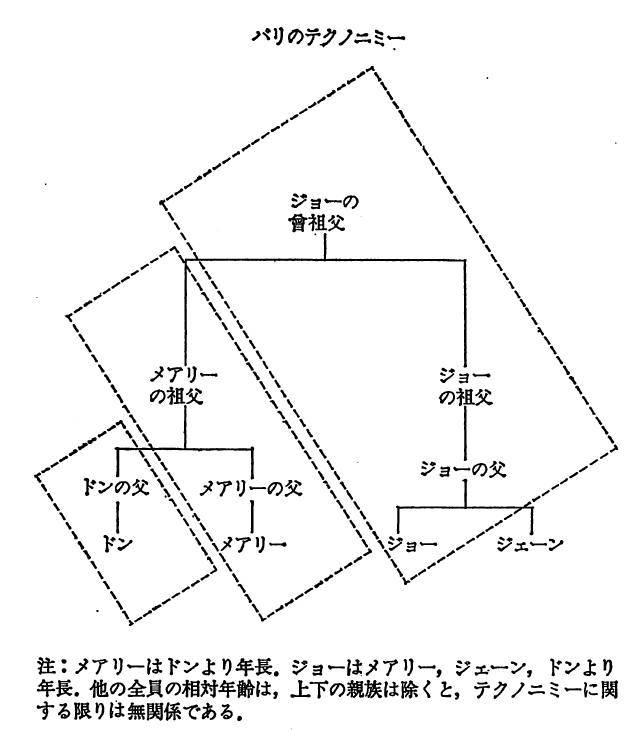 |
|
| 42 |
|||
| 43 |
・「不変の状態」(ベイトソン) |
||
| 44 |
323 |
・地位称号 |
|
| 45 |
|||
| 46 |
|||
| 47 |
325 |
・地位称号体系は純粋に威信体系。 |
|
| 48 |
|||
| 49 |
326 |
・あらゆる称号は神々に由来する |
|
| 50 |
|||
| 51 |
|||
| 52 |
328 |
・ヴァルナの4体系 |
|
| 53 |
|||
| 54 |
|||
| 55 |
330 |
・テクノニームが使われない集落もある |
|
| 56 |
|||
| 57 |
331 |
・公的称号 |
|
| 58 |
|||
| 59 |
|||
| 60 |
|||
| 61 |
|||
| 62 |
334 |
・「精神的選定の教義」 |
|
| 63 |
|||
| 64 |
|||
| 65 |
337 |
神々の世界は、もうひとつの公的領域 |
|
| 66 |
338 |
【力の文化的三角形】 ・「人びとが時間の推移について知らされる、あるいはむしろ自らそれについて知るい ろいろな方法が ある。たとえば季節の移り変り、月のみちかけ、植物の成長などを示すことによって時の推移がわか る。また、儀礼、農作業、家事労働などの定期的な周期による方法、特定の活動の準備や計画、すで に行なわれた活動の追憶や評価による方法、系譜を保持し、伝説を伝え、予言を行なうことなどによ る方法がある。なかんずく最も重要な方法の一つは、自分自身や自分の仲間が、生物学的に年をとっ ていく過程を認識することにより、つまり具体的な個々人の出生、成熟、衰弱、死去を認識すること によるものである。したがってこの過程をいかに見るかという見方は、人が時聞を経験する仕方に強 く影響する。人間であることは何かということに関する人びとの観念と、歴史の構造に 関する彼らの 観念との聞はたち切れない強い紳で結ばれている」(338)。 |
|
| 67 |
|||
| 68 |
|||
| 69 |
|||
| 70 |
|||
| 71 |
341 |
・分類的暦と点的時間 ・暦の概念 |
|
| 72 |
|||
| 73 |
|||
| 74 |
|||
| 75 |
|||
| 76 |
|||
| 78 |
|||
| 79 |
|||
| 80 |
|||
| 81 |
|||
| 82 |
|||
| 83 |
|||
| 84 |
|||
| 85 |
|||
| 86 |
350 |
・儀式、おびえ、クライマックスの欠如 |
|
| 87 |
351 |
「毎
日接している人びとの(相対的)匿名化を維持し、対面関係に含まれる密接さを弱め、一言でいえば仲間を同時代者にするためには、彼らとの関係をかなり形式
化する必要がある。つまり、毎日接している人びとがそれぞれ誰であるかがわかる程度には緊密ではあるが、抱擁するほどには親しくないような、社会的な中程
度の距離において接しあうことが必要なのである。彼らは、いわば異邦人であると共に
友人でもある」(351)。 |
|
| 88 |
352 |
「そのよさを感ずることは、こういう、社会生活の表面を丹念に磨きあげ
ることの中に形を重んずる
繊細さという特色があるためにいっそう困難になる。これはわれわれの予想しなかった特色である。
形を重んずると共に繊細であるために(両者はまざりあっているが)、こういう点を自ら体験したこと
のない人に理解させることは大変むずかしい。もし、遊戯性という語を気楽なものではなく、深刻に近い
い意味に理解し、演劇性という語を自発的なものでなく、強制されるに近い意味に理解するなら、「遊び
戯的演劇性」という言葉がおそらくこれに最も近いだろう。バリ人の社会関係は、厳粛な遊戯である
と共に作られた演劇なのである」(ギアーツ 1987:352)。 |
|
| 89 |
352-353 |
「このことは、彼らの儀礼的な、また(同じことであるが)芸術的な生活
の中にもっともはっきりと見
られる。こういう生活の多くは、たしかに彼らの社会生活を画きだしていると共に、社会生活に対す
るひな型でもある。日常の人間相互関係はたいへん儀礼的で、宗教活動は非常に日常的なので、一方
がどこから始まり、他方がどこで終るかを知ることは困難なくらいである。日常生活と宗教生活はと
もに、バリの最も著名な文化の属性である芸術的傾向の表われなのである。念入りな寺院の祭儀の時
の華麗な行列、壮大な音楽劇,曲芸じみた踊り、おおげさな影絵芝居、遠回しの言い方、言いわけじ
みた身振りなどはすべて同種のものである。礼儀作法は一種の舞踊であり、舞踊は一種の儀礼であり、
礼拝は一種の礼儀作法なのである。芸術と宗教といんぎんさはすべて表面の、工夫され、巧みに作ら
れた状況を促進し、外観の形態を賞讃する。儀式がまるで霞(→他の漢字)のようにパリ人の生活をおおいつくして
いる状態は、こういう外観の形態のたゆまない操作によるものであり、これは彼らが「遊び」と呼ん
でいるものである」(ギアーツ 1987:352-353)。 |
|
| 90 |
353 |
「バリ人の対人関係の型どられた状態、つまり儀式、技能、礼儀の融合状
態から、彼らの特殊な社会
性の最も基本的できわだった特色である徹底した審美主義が認識されるようになる。あらゆる社会的
行為は、何よりもまず神々を喜ばせるために、観衆を喜ばすために、他者を、自己を喜ばせるために
企てられている。それは徳行のためではなく、美しさのためなのである。寺院の供物やガムラン音楽
のように、いんぎんな振舞いは、美的行為であり、それだけで、清廉さ(または清廉さとわれわれが呼
ぶもの)ではなく、感受性を表わし、またそれを表わそうとするものである」(ギアーツ 1987:353)。 |
|
| 91 |
354 |
「これらすべてのこと——日常生活が非常に儀式的であること、この儀式
性が社会的形態を真摯で、
念入りなほどに「もて遊ぶ」という形をとっていること、宗教、芸術、礼儀は、事物の作りあげた装
いに対する全体の文化的陶酔の方向の異なる表現にすぎないこと、したがって道徳はここでは基本に
おいては美的であることから、バリ人の生活の情緒的側面の最も著しい(そして最もよく指摘されて
いる)二つの特徴をいっそう正確に理解することができる。その二つの特徴の一つは、対人関係にお
いて(まちがって)「恥」と呼ばれてきた特性に関する重要な感情であり、もう一つは、明確な完成を
行なうための宗教的、芸術的、政治的、経済的な集団活動の失敗、つまり(鋭くも)そのクライマックス
の欠如」と呼ばれてきた点である。この二者のうちの第一のものは、人間に関する観念に直接た
ち戻らせ、第二のものは、やはり直接時間の観念にたち戻らせる。このようにして、われわれの比喩
的な意味の三角形の各頂点は、バリ人の行動様式を、それが中で作動する理念的環境に結びつけるこ
とになる」(ギアーツ 1987:354)。 |
|
| 92 |
354-355 |
「「恥」の概念は、道徳的、感情的に隣接した「罪」の概念と共に文献で
はよく論じられており、文
化全体が時には「恥の文化」として捉えられたりした。これはいくつかの文化に、「名誉」、「評判」
などといったことに強い関心が存在すると思われたからである。こういう文化には、「罪」とか「内的
価値」どというものへの関心——これは「罪の文化」に顕著であるとされている——が欠けている
とされる。こういう一般的な分類の有効性は別として、また比較心理学的動態の複雑な問題がこれに
含まれていることはさておき、こういう考察で、「恥」という語から、この語が英語でもっている結
局最も普通の意味——「罪の意識」——を取り去って、この語を罪という意味l——「何か非難すべき
ことを行なったという事実または感情」——から完全に分離させることはむずかしいことは明らかで
ある。普通、両者の対比は、「恥」はあやまちが一般に知られたような状態に(もっとも、もっぱらと
はいえないが)適用される傾向があるという事実に、また「罪」はあやまちが知られていない状態に
(同じようにもっぱらとはいえないが)適用される傾向があるという事実に依拠している。恥はあやま
ちがみつかった後の恥辱と不面目の感情であり、罪はまだみつからないあやまちに伴う秘密の悪行の
感情である。このように、恥と罪は、われわれの倫理的、心理的語棄の中で決してまったく同じでは
ないが、両者はともに同じ種類の語であり、恥は罪の表面にあり、罪は恥の内面にあるといった関係
である」(ギアーツ 1987:354-355)。 |
|
| 93 |
355 |
「しかしバリ人の「恥」——つまり恥と訳されているもの(レク
lek)は、表面に表われるまたは
表われないあやまちとは関係がない。また、自白され、あるいは隠されたあやまちとも、単に想像さ
れ、あるいは実際に犯したあやまちとも関係がない。そのことは、バリ人が罪も恥も感じないという
のではないし、彼らは時聞が経過し、人びとが固有の個々人であることを知らないのではないように、
良心も誇りももたないというわけでもない。そのことは、罪も恥も、バリ人の対人行動の情意的規制
要因としてはそれほど重要でないということ、そういう規制要因の中ではるかに最も重要な、しかも/
バリの文化の中で最も強調されるレクというものはしたがって「恥」と訳すべきではなく、われわれ
の演劇の概念にしたがうなら、「舞台に出る前のおびえ」と訳すべきであるということなのである。バリ
人の対面関係の中で支配的な感情をなすものはあやまちを犯したという感情でも、あやまちが発覚
した後の屈辱感でもない。それは、まったく逆に、社会的相互関係を予想する時の(そして相互関係を
実際に行なう前の)、ある揚合にはほとんどからだが麻痔してしまうほどになるが、漠然とした、普通
は弱い心配である。この心配な気持は、必要とされる優雅さでやりとげることができないのではない
かという、常に持続しているが、たいていは、わずかないらいらの感情である」(ギアーツ 1987:355-356)。 |
|
| 94 |
|||
| 95 |
357 |
「バリ人の社会的行動の中でもう一つの顕著な性格である「クライマック
スの欠如」は、非常にきわ
だっており、たいへん奇妙であるため、具体的な現象について詳述しないとよく分らないと思われる。
これは、社会的活動が明確な達成を行なわないし、または、達成をするように許されていないという
ことである。たしかに喧嘩がおこり、和解し、ときには喧嘩が長びいたりするが、絶交するような状
態にまで発展することは稀である。もめごとは決断が迫られるほどに悪化せず、まわりの状況の発展
だけで解決するだろうとか、うまくいけば簡単に消滅してしまうだろうと期待しながら、争いをなだ
め、やわらげるのである。個々の出会いからなっている。日常生活は、それだけで完結した、こうい
う個々の出会いにおいては何かが起こったり、起こらなかったり、意図が実現したり、実現しなかっ
たり、仕事ができあがったり、仕上がらなかったりする。何かが起こらない時、つまり何かをやろう
とする意図がおさえられたり、仕事ができなかったりした時は、初めからあらためて別の機会にやり
なおす揚合もあり、あるいはやめてしまうこともある。美的な演技が始まり、進行し(人が続けて見る
ことなく、立ち去ったり、戻つできたり、一時しキべったり、しばらくの間眠ったり、またしばらく
我を忘れて見たりする問、しばしば非常に長いあいだ続けられてそして止まる。こういうもよおしも
のは、パレードのように中心がなく、祭りの行列のように方向がない。儀礼は、寺院の祝祭における
ように、主として、準備をし、あとかたづけをするということからなっているように思われる。儀式
の中心は祭壇に降臨する神々への礼拝であるが、それは意図的にぽかされ、結局は物理的に非常に密
接であるが社会的にはきわめて遠い名の知れない故人の追想であり、彼らの束の間のためらいがちな
対面であるように時には思われるほどである。儀式の中心はまた、迎えと別れを告げることにあり、
前の準備を楽しみ、また後の余韻を楽しむことでもある。それは最も儀式的に緩和され、儀礼的にか
こまれた、彼ら自身の聖なる存在との道過がともなう。ランダとバロンのように劇的性格がいっそう
強い儀式においても、恐ろしい魔女(ランダ)とおどけた獅子(バロン)との戦いはまったく未解決の状態
で終る。それは神秘的な、形而上の、精神的な引分けに終り、すべてが以前のままで何も変らないの
である。そしてこれを見る者——とにかく外国人の観察者——は、何か決定的なことが起こりそうだ
が決して何も起こらなかったという感情に包まれるのである」(ギアーツ 1987:357-359)。 |
|
| 96 |
359 |
「要するに、出来事は祭日がめぐってくるように起こる。つまりそれは表
われ、消え、また現われる。
それぞれが別個のもので、それ自体で自足し、事物の固定した秩序の特定の現われである。社会活動
は非連続的な演技であり、ある方向に向つてなされるものではなく、解決に向って行なわれるもので
もない。時間が点的であるように、生活も点に基づいているのだ。それは秩序がないのではなく、ち
ょうど日々のように、一定の質に整序されている。バリ人の社会生活にクライマックスが欠けている
のは、それが動きのない現在、方向のない現在に起こるからである。あるいは、バリ人の時間に動き
が欠けているのは、バリ人の社会生活にクライマックスが欠けているからだということも同時に正し
いのである。両者の一方は他方を暗示し、両者とも、バリ人の人間の現在化を暗示し、人間の現在化
によって暗示される。仲間に関する認知、歴史の経験、集団生活の性格ll 時にはエトスと呼ばれて
きたもの——は明確な論理によってつながれている。しかしその論理は三段論法的ではなく、社会的
なのである」(ギアーツ 1987:359)。 |
|
| 97 |
359 |
・文化の統合、葛藤、変化 「形式的な推論の原理について、また諸事実間および出来事間の納得のいく関連についていう場合、 「論理」という語はそぐわない言葉である。文化の分析の揚合ほどこの語が不適当な場合はない。意 味のある諸形態を扱うさいには、形態間の関係を内在的なものとみて、たがいにある種の内的な関係 (または無関係)からなっているとみる誘惑にかられる。したがって、文化の統合は意 味の調和として、 文化の変化は意味の不安定性として、文化の葛藤は意味の不適合として論じられる。この場合、たと えば、甘さが砂糖の属性であり、こわれやすさがガラスの属性であるように、調和、不安定、不適合 が意味そのものの属性であるということが合意されている」(ギアーツ 1987:359-360)。 |
・文化を「論理的に説明すること」の不可能性。 |
| 98 |
360 |
「ところが、こういう属性を、甘さとかこわれやすさと同じように捉えよ
うとすると、それは期待さ
れるように「論理的に」は作用しない。調和、不安定、不適合の構成要素をさぐってみると、それら
が属性であるものの中には見出されない。象徴的形態の調和内容、安定性の度合い、不適合の指標を
発見するために、象徴形態に何らかの文化的分析を試みてみることはできないのだ。われわれは、い
くつかの象徴形態が、事実何らかの形で共存し、変化し、あるいはたがいに妨げあっているかどうか
を知ることができるに過ぎないのである。これは砂糖が甘いかどうかを知るために砂糖を味わってみ
ることに似ており、また、ガラスがこわれやすいかどうかを知るためにこれを落としてみるようなもの
である。これは、砂糖の化学構成や、ガラスの物理構造を研究するのとは異なるのである。その理由
は、いうまでもなく、意味というものは、それをそなえている物体、行為、過程などに本来含まれて
いるものではなく、デュルケム、ウェーバーその他の人たちが力説したように、それらに与えらた
ものであるということにある。したがって、その属性の説明は、意味を与えるもの、つまり社会に生
活している人びとに求めなければならない。ジョゼフ・レヴェンソン(Joseph Levenson)の言葉を借
りれば、思考の研究は、考える人びとの研究である。人びとは彼らの何か特別な揚所で
考えるのでは
なく、他のすべてのことも行なう同じ揚所—— 社会的世界——において考える。このために、文化の
統合、変化、葛藤の性質はその中に探求されるべきである。つまり象徴の示す通りに人びとが知覚し、
感じ、考え、判断し、行なうときの個々人とその集団の経験の中に求めるべきなのである」(ギアーツ 1987:360-361)。 |
|
| 99 |
361 |
・「文化体系の「論理」をピタゴラス流の「意味の領域」の中に見出す希
望を捨てることは、それをみつける望みを完全に放棄することではない。それは、彼らの生活に象徴を与えているもの、すなわちそれが実際に用いられているこ
とにわれわれの注意を向けることなのである」(ギアーツ 1987:361)。 |
|
| 100 |
361-362 |
「人びとを規定するためのバリの象徴構造(名前、親族名称、テクノニー
ム、称号など)を、時間を特
色づける象徴構造(順列的な暦など)に結びつけるもの、および両方の象徴構造を、対人行動を整序す
るためのバリの象徴構造(芸術、儀礼、優雅さなど)に結びつけるものは、こういう象徴構造がそれを
用いる人びとの知覚に対して与える影響力の相互作用なのである。それは彼らの経験の影響がたがい
に作用しあい強化しあう仕方なのである。仲間を「同時代化する」傾向は、生物学的な年をとるとい
う感覚を鈍らせる。生物学的な年をとるという感覚の鈍化は、時間の流れの感覚の主な要因の一つを
取り去り、時間の流れの感覚が少なくなることは、対人間のできごとに挿話的性格を与える。儀式的
に色づけられた人間の相互作用は他人を標準的に捉える知覚を持続させ、他人を標準的に捉える知覚
は、社会の「静止状態」という捉え方を助長する。そして社会の静止状態という捉え方は時間の分類
的知覚を助長することになる。このように、時間の観念から出発して次ぎ次ぎに進み、どちらの方向
に行っても同じ円をまわるのである。この円は、とぎれない円であるが、厳密な意味では閉じた円で
はない。というのは、上述の経験の様式はいずれも文化の重点としての支配的な傾向以上のものでは
ないからである。また、抑圧されている方の側面も、生活の全体的状況の中に同じように存在してい
て、その文化的表現がないわけではなく、支配的傾向と共存し、支配的傾向に反発さえするからであ・
る。それでもなお、上述の経験の諸様式は主要なものであり、たがいに強めあうのである。それらは
また持続している。永続的でも完全なものでもない、このような状態に対して「文化の統合」という
概念——ウェーバーが「意味連関」と呼んだもの——を正しく用いることができるのである」(ギアーツ 1987:361-362)。 |
|
| 101 |
363 |
「こういう見方によれば、文化の統合は、人間の日常生活とは別個のそれ自体の論理的世界の中に
独自の現象としては捉えられないのである。だが、文化の統合は、またすべてを包みこんだ、隅々まで
およぶ無限の統合を意味しないことの方がいっそう重要である。まず第一に、前述のように、主要
なパターンに対抗するパターンが二次的なものとして存在するが、それにも拘らず、重要な主題は、
われわれが知るかぎりどんな文化にも存在する。普通の、まったく非へーゲル的な方法で、文化自体
を否定する要素は、多かれ少なかれ、その文化の中に含まれているのである。たとえばバリ人につい
てみると、彼らの妖術者に関する信仰(あるいは現象学的にいえば妖術者に関する諸経験)をバリ人
の人格に関する信仰といえるものの転倒として研究し、また、彼らのトランス(脱魂)行動を彼らの礼
儀作法にかなったふるまいを転倒したものとして検討してみることは、この点でたいへん示唆を与え、
当面の考察に深みと多様性を加えることになろう。広く知られた文化の特徴づけに対するよく知られ
たいくつかの批判——「調和を愛好する」プエブロ族の中にも猜疑心や派閥があることをあばきだし、
競争のさかんなクワキウトル族に「愛想のよい側面」があることをあきらかにしたこと——は、本質的
に、そういう主題の存在と重要性を指摘したことにあるのである」(ギアーツ 1987:363)。 |
|
| 102 |
|||
| 103 |
364 |
「文
化の非連続性と社会の解体——非常に安定した社会においても、文化の非連続性に由来する——
は文化の統合と同様に存在するのである。文化は縫い目のない織物のようなものだという、今なお人
類学に普及している考え方は、文化は断片のよせ集まりのようなものだという古い見解——これは
1930年代のマリノフスキーの革命的見解ののち、やや過度の熱狂によって前者の考え方と入れ代わっ
た——と同じように未証明の前提に基づく誤謬(petitio principii; 論点先取)なのである。体系が体系であるた
めには、すみずみまで完全に関連しあう必要は必ずしもない。体系は緊密に連関していることもある
し、ゆるく関連していることもある。体系がどのように正しく統合しているかということは経験的な
問題である。変数間の関係におけるように、経験の様式の間の関連を確認するためには、単にそれを
想定するのでなしに、それを見出すこと(そしてそれを見出す方法をみつけること)が必要なのである。
複雑であると共に、完全に結合している体系は、どんな文化もそうであるように、機能することがで
きないと信じさせる強力な理論的理由がある。このために、文化分析の問題は、体系内の連関性と同
じく自立性を、結びつきと共にへだたりを明らかにしていくことである。文化組織に関する正しい
イメージ——もしそのイメージを持たなければならないとすれば——は、クモの巣の網のようなもので
もなければ、また砂の堆積といったものでもなく、それはむしろタコのようなものである。タコの足
はだいたい分離しており、その神経系統はそれぞれの足やタコの頭脳とみなされるものとも不充分に
しか関連していない。しかもそれにも拘らず、動きまわることができ、自分を生命力のある、いくら
かぶざまな存在として少なくとも当分のあいだ維持していくことができる」(ギアーツ 1987:364-365)。 |
|
| 104 |
|||
| 105 |
365 |
「文化の分析は「文化の基本的複合体」に対する勇ましい「全体的」な突
撃を目指す
のではなく、さりとて、「諸秩序の秩序」——そこからより限界のある複合体が単なる演揮として見ら
れるような——を作りだすことでもない。それは意味のある象徴、意味のある象徴の群れ、意味ある
象徴の群れの群れ——知覚と感情と理解の物的媒体——を探り、さらにそれらの形成に内在する人間
の経験の基底にある規則性の内容を探り出すことになるのである。活用できる文化の理論に到達すべ
きであるとすれば、それは直接観察しうる思考様式から出発して、まずその明確な種類に向い、さら
にいっそう変化に富んだ、それほど緊密に統合されていないが秩序ある「タコのような」思考様式の
体系に向い、部分的な統合と部分的な不適合と部分的自立性との集合体を構成することによって達成
すべきである」(ギアーツ 1987:365-366)。 |
|
| 106 |
366 |
||
| 107 |
「バリ人の人間観、時間経験、あるいはバリ人の礼儀作法の観念などを崩
すようなことが発展すると、
そういう発展はパリ文化の多くを変形させる潜在カを含んでいるように思われる。バリ人の人間観な
どは、そういう革命的変化を起こす唯一の領域ではない(バリ人の威信の観念とその基盤を崩すもの
も、少なくとも同じように強力である)。しかし人間観その他のものは確かに最も重要なものに属し
ている。かりに、バリ人が、相互の匿名化の少ない見解や、いっそう力動的な時間の感覚あるいは社
会的相互作用のよりインフォーマルな様式を発展させるとすれば、バリ人の生活の中で、すべてでは
ないにしても非常に多くが、変化を余儀なくされることになるだろう。それは、これらの変化の中の
一つは他の変化をただちに直接意味し、これら三つの要素は、異なる方法と違った脈絡において、
バリ人の生活の形成に本質的な役割を果たしているからにほかならない」(ギアーツ 1987:366-367)。 |
||
| 108 |
|||
| 109 |
|||
| 110 |
|||
| 111 |
|||
| 112 |
369 |
「上述のことはすべてたしかに単なる思弁であり(もっとも、独立後の
15年間の出来事の出来事を見れば、そ
れはまったく根拠のない思弁ではないてバリ人の人問、時間、行為に関する認識が、いつ、どのよう
に、どのくらいの速さで、またどんな順序で変っていくかということは、全般的には、まったく予測
できないわけではないにしても、詳細については充分に予測できない。しかしバリ人の上述の認識が
変化するとき——変化はたしかであると思われ、事実すでに開始している——文化の概念を活動力と
し、思考を他の公的現象と同様な影響を持つ公的現象としてここで展開した分析は、変化の概要、動
態——より重要なものである——、変化の社会的意味あいを発見する助けになるはずである。この種
の分析は、他の形態や他の成果についても、他の揚所でも、役に立たないとは思われないのである」(ギアーツ 1987:369)。 |
|
++++
+++
Links
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆