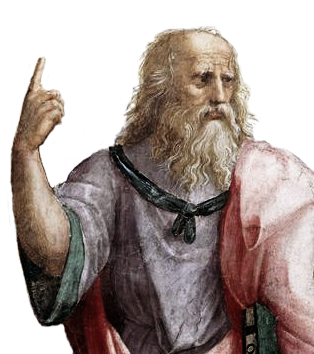
模倣
Mimesis
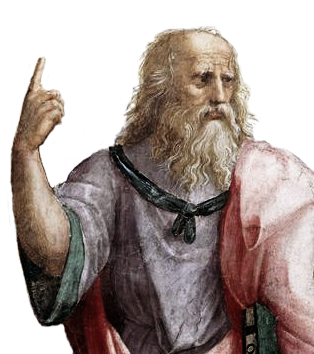
★ミメーシス(/mɪˈmiːsɪs, maɪ-/;[1]古代ギリシャ語:
μίμησις,
mīmēsis)は、文学批評や哲学で使用される用語で、模倣、類似、受容性、表現、模倣行為、似せる行為、自己の表現など、幅広い意味を持つ。
古代ギリシャ語の「mīmēsis (μίμησις)」は、「mīmeisthai
(μιμεῖσθαι、模倣する)」に由来し、さらに「mimos (μῖμος、模倣者、俳優)」に由来します。古代ギリシャでは、mīmēsis
は、特に、美、真実、善のモデルとして理解される物理的世界との対応において、芸術作品の創造を支配する概念でした。プラトンは、ミメーシス(模倣)と
ディエゲシス(叙述)を対比させた。プラトン以降、ミメーシスの意味は、古代ギリシャ社会において次第に文学的な機能に特化したものへと変化していった。
[3]
ミメーシス(文学における現実主義の一形態として理解される)に関する最も著名な現代の研究の一つは、エリヒ・アウエルバッハの『ミメーシス:西洋文学に
おける現実の表現』で、ホメロスの『オデュッセイア』における世界の表現と、聖書における世界の表現の比較から始まっている。[4]
プラトンとアウエルバッハに加え、ミメーシスは、アリストテレス[5]、フィリップ・シドニー、ジャン・ボードリヤール(『シミュラクラとシミュレーショ
ン』の概念を通じて)、ジル・ドゥルーズ(『意味の論理』の「意味の出来事」の概念を通じて)[6]、サミュエル・テイラー・コールリッジ、アダム・スミ
ス、ガブリエル・タルデ、ジグムント・フロイト、ウォルター・ベンヤミン[7]、テオドール・アドルノ[8]、ポール・リクール、ギ・ドボア(彼の概念的
論争的著作『スペクタクルの社会』を通じて)、ルース・イリガライ、ジャック・デリダ、ルネ・ジラール、ニコラス・コムプリディス、フィリップ・ラクー=
ラバルテ、マイケル・タウシグ[9]、マーリン・ドナルド、ホミ・バーハ、ロベルト・カラッソ、ニデシュ・ラトゥーなど、多様な思想家たちによって理論化
されてきた。19世紀、アフリカ系アメリカ人に対する模倣の民族政治は、ミメーシスという用語とその進化に影響を与えた[10]。
| Mimesis
(/mɪˈmiːsɪs, maɪ-/;[1] Ancient Greek: μίμησις, mīmēsis) is a term used
in literary criticism and philosophy that carries a wide range of
meanings, including imitatio, imitation, similarity, receptivity,
representation, mimicry, the act of expression, the act of resembling,
and the presentation of the self.[2] The original Ancient Greek term mīmēsis (μίμησις) derives from mīmeisthai (μιμεῖσθαι, 'to imitate'), itself coming from mimos (μῖμος, 'imitator, actor'). In ancient Greece, mīmēsis was an idea that governed the creation of works of art, in particular, with correspondence to the physical world understood as a model for beauty, truth, and the good. Plato contrasted mimesis, or imitation, with diegesis, or narrative. After Plato, the meaning of mimesis eventually shifted toward a specifically literary function in ancient Greek society.[3] One of the best-known modern studies of mimesis—understood in literature as a form of realism—is Erich Auerbach's Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, which opens with a comparison between the way the world is represented in Homer's Odyssey and the way it appears in the Bible.[4] In addition to Plato and Auerbach, mimesis has been theorised by thinkers as diverse as Aristotle,[5] Philip Sidney, Jean Baudrillard (via his concept of Simulacra and Simulation), Gilles Deleuze (via his "event of sense" concept from The Logic of Sense),[6] Samuel Taylor Coleridge, Adam Smith, Gabriel Tarde, Sigmund Freud, Walter Benjamin,[7] Theodor Adorno,[8] Paul Ricœur, Guy Debord ( via his conceptual polemical tract,The Society of the Spectacle ) Luce Irigaray, Jacques Derrida, René Girard, Nikolas Kompridis, Philippe Lacoue-Labarthe, Michael Taussig,[9] Merlin Donald, Homi Bhabha, Roberto Calasso, and Nidesh Lawtoo. During the nineteenth century, the racial politics of imitation towards African Americans influenced the term mimesis and its evolution.[10] |
ミメーシス(/mɪˈmiːsɪs, maɪ-/;[1]
古代ギリシャ語: μίμησις,
mīmēsis)は、文学批評や哲学で使用される用語で、模倣、類似、受容性、表現、模倣行為、似せる行為、自己の表現など、幅広い意味を持つ。 古代ギリシャ語の「mīmēsis (μίμησις)」は、「mīmeisthai (μιμεῖσθαι、模倣する)」に由来し、さらに「mimos (μῖμος、模倣者、俳優)」に由来します。古代ギリシャでは、mīmēsis は、特に、美、真実、善のモデルとして理解される物理的世界との対応において、芸術作品の創造を支配する概念でした。プラトンは、ミメーシス(模倣)と ディエゲシス(叙述)を対比させた。プラトン以降、ミメーシスの意味は、古代ギリシャ社会において次第に文学的な機能に特化したものへと変化していった。 [3] ミメーシス(文学における現実主義の一形態として理解される)に関する最も著名な現代の研究の一つは、エリヒ・アウエルバッハの『ミメーシス:西洋文学に おける現実の表現』で、ホメロスの『オデュッセイア』における世界の表現と、聖書における世界の表現の比較から始まっている。[4] プラトンとアウエルバッハに加え、ミメーシスは、アリストテレス[5]、フィリップ・シドニー、ジャン・ボードリヤール(『シミュラクラとシミュレーショ ン』の概念を通じて)、ジル・ドゥルーズ(『意味の論理』の「意味の出来事」の概念を通じて)[6]、サミュエル・テイラー・コールリッジ、アダム・スミ ス、ガブリエル・タルデ、ジグムント・フロイト、 ウォルター・ベンヤミン[7]、テオドール・アドルノ[8]、ポール・リクール、ギ・ドボア(彼の概念的論争的著作『スペクタクルの社会』を通じて)、 ルース・イリガライ、ジャック・デリダ、ルネ・ジラール、ニコラス・コムプリディス、フィリップ・ラクー=ラバルテ、マイケル・タウシグ[9]、マーリ ン・ドナルド、ホミ・バーハ、ロベルト・カラッソ、ニデシュ・ラトゥーなど、多様な思想家たちによって理論化されてきた。19世紀、アフリカ系アメリカ人 に対する模倣の民族政治は、ミメーシスという用語とその進化に影響を与えた[10]。 |
| Plato Both Plato and Aristotle saw in mimesis the representation of nature, including human nature, as reflected in the dramas of the period. Plato wrote about mimesis in both Ion and The Republic (Books II, III, and X). In Ion, he states that poetry is the art of divine madness, or inspiration. Because the poet is subject to this divine madness, instead of possessing "art" or "knowledge" (techne) of the subject,[i] the poet does not speak truth (as characterized by Plato's account of the Forms). As Plato has it, truth is the concern of the philosopher. As culture in those days did not consist in the solitary reading of books, but in the listening to performances, the recitals of orators (and poets), or the acting out by classical actors of tragedy, Plato maintained in his critique that theatre was not sufficient in conveying the truth.[ii] He was concerned that actors or orators were thus able to persuade an audience by rhetoric rather than by telling the truth.[iii] In Book II of The Republic, Plato describes Socrates' dialogue with his pupils. Socrates warns we should not seriously regard poetry as being capable of attaining the truth and that we who listen to poetry should be on our guard against its seductions, since the poet has no place in our idea of God.[iv]: 377 Developing upon this in Book X, Plato told of Socrates's metaphor of the three beds: One bed exists as an idea made by God (the Platonic ideal, or form); one is made by the carpenter, in imitation of God's idea; and one is made by the artist in imitation of the carpenter's.[v]: 596–599 So the artist's bed is twice removed from the truth. Those who copy only touch on a small part of things as they really are, where a bed may appear differently from various points of view, looked at obliquely or directly, or differently again in a mirror. So painters or poets, though they may paint or describe a carpenter, or any other maker of things, know nothing of the carpenter's (the craftsman's) art,[v] and though the better painters or poets they are, the more faithfully their works of art will resemble the reality of the carpenter making a bed, the imitators will nonetheless still not attain the truth (of God's creation).[v] The poets, beginning with Homer, far from improving and educating humanity, do not possess the knowledge of craftsmen and are mere imitators who copy again and again images of virtue and rhapsodise about them, but never reach the truth in the way the superior philosophers do. |
プラトン プラトンもアリストテレスも、ミメーシス(模倣)を、その時代の演劇に反映されている自然、人間性を含む自然の表現と見なした。プラトンは『イオン』と 『共和国』(第2巻、第3巻、第10巻)の両方でミメーシスについて書いている。『イオン』では、詩は神聖な狂気、すなわちインスピレーションの芸術であ ると述べている。詩人はこの神聖な狂気に支配されているため、対象に関する「技術」や「知識」(テクネー)を保有していないため、プラトンのイデア論で特 徴付けられる「真実」を語ることはない。プラトンによると、真実は哲学者(フィロソフ)の関心事である。当時の文化は、一人で本を読むことではなく、公 演、演説家(および詩人)の朗読、あるいは古典劇の俳優による演技を聞くことで構成されていたため、プラトンは、演劇は真実を伝えるには不十分であると批 判した[ii]。彼は、俳優や演説家が、真実を語るのではなく、レトリックによって聴衆を説得することができることを懸念していた[iii]。 『国家』の第2巻で、プラトンはソクラテスが弟子たちと交わした対話を描いている。ソクラテスは、詩が真実を捉える能力があるとは真剣に考えるべきではな いと警告し、詩を聴く者はその誘惑に警戒すべきだと述べている。なぜなら、詩人は私たちの神観念の中に位置付けられないからだ。[iv]: 377 この考えを第 10 巻でさらに発展させ、プラトンはソクラテスの 3 つのベッドの隠喩を語っています。1 つは、神によって作られたアイデア(プラトニックの理想、または形)として存在するベッド、1 つは、神のアイデアを模倣して大工によって作られたベッド、そして 1 つは、大工のベッドを模倣して芸術家によって作られたベッドである。[v]: 596–599 したがって、芸術家のベッドは真実から 2 段階離れている。模倣する者は、物事のほんの一部にしか触れていない。ベッドは、さまざまな視点から、斜めに見たり、正面から見たり、鏡で映したりする と、異なって見える。したがって、画家や詩人は、大工や他の物作りを絵に描いたり描写したりしても、大工(職人)の技を知らない。[v] 画家や詩人が優秀であればあるほど、彼らの芸術作品は、大工がベッドを作る現実を忠実に再現するが、模倣者はそれでも真実(神の創造)に到達することはで きない。[v] 詩人たちは、ホメロスから始まり、人類を向上させ教育するどころか、職人の知識を持たず、美徳のイメージを繰り返し模倣し、それについて熱狂的に語るだけ の模倣者に過ぎず、優れた哲学者たちが到達する真実には決して至らない。 |
| Aristotle Similar to Plato's writings about mimesis, Aristotle also defined mimesis as the perfection and imitation of nature. Art is not only imitation but also the use of mathematical ideas and symmetry in the search for the perfect, the timeless, and contrasting being with becoming.[citation needed] Nature is full of change, decay, and cycles, but art can also search for what is everlasting and the first causes of natural phenomena. Aristotle wrote about the idea of four causes in nature. The first, the formal cause, is like a blueprint, or an immortal idea. The second cause is the material cause, or what a thing is made out of. The third cause is the efficient cause, that is, the process and the agent by which the thing is made. The fourth, the final cause, is the good, or the purpose and end of a thing, known as telos. Aristotle's Poetics is often referred to as the counterpart to this Platonic conception of poetry. Poetics is his treatise on the subject of mimesis. Aristotle was not against literature as such; he stated that human beings are mimetic beings, feeling the urge to create texts (art) that reflect and represent reality. Aristotle considered it important that there be a certain distance between the work of art on the one hand and life on the other; we draw knowledge and consolation from tragedies only because they do not happen to us. Without this distance, tragedy could not give rise to catharsis. However, it is equally important that the text causes the audience to identify with the characters and the events in the text, and unless this identification occurs, it does not touch us as an audience. Aristotle holds that it is through "simulated representation," mimesis, that we respond to the acting on the stage, which is conveying to us what the characters feel, so that we may empathise with them in this way through the mimetic form of dramatic roleplay. It is the task of the dramatist to produce the tragic enactment to accomplish this empathy by means of what is taking place on stage. In short, catharsis can be achieved only if we see something that is both recognisable and distant. Aristotle argued that literature is more interesting as a means of learning than history, because history deals with specific facts that have happened, and which are contingent, whereas literature, although sometimes based on history, deals with events that could have taken place or ought to have taken place. Aristotle thought of drama as being "an imitation of an action" and of tragedy as "falling from a higher to a lower estate" and so being removed to a less ideal situation in more tragic circumstances than before. He posited the characters in tragedy as being better than the average human being, and those of comedy as being worse. Michael Davis, a translator and commentator of Aristotle writes: At first glance, mimesis seems to be a stylizing of reality in which the ordinary features of our world are brought into focus by a certain exaggeration, the relationship of the imitation to the object it imitates being something like the relationship of dancing to walking. Imitation always involves selecting something from the continuum of experience, thus giving boundaries to what really has no beginning or end. Mimêsis involves a framing of reality that announces that what is contained within the frame is not simply real. Thus the more "real" the imitation the more fraudulent it becomes.[11] |
アリストテレス プラトンのミメーシスに関する記述と同様に、アリストテレスもミメーシスを「自然を完璧に模倣すること」と定義した。芸術は単なる模倣ではなく、完璧、永 遠、そして変化と対比を求める上で、数学的な概念や対称性を活用するものだ。[要出典] 自然は変化、腐敗、循環に満ちているが、芸術は永遠のものや自然現象の第一原因を探求することもできる。アリストテレスは、自然における四原因の概念につ いて論じた。第一の原因は形式原因であり、青写真や不滅の理念のようなものだ。第二の原因は物質原因であり、物事が何から作られているかだ。第三の原因は 効率原因であり、物事が作られる過程と作用者だ。第四の原因は最終原因であり、善、または物事の目的と終着点であり、テロスと呼ばれる。 アリストテレスの『詩学』は、このプラトンの詩の概念に対応するものとしてよく引用される。詩学は、模倣(ミメーシス)をテーマにした彼の著作だ。アリス トテレスは文学そのものを否定していなかった。彼は、人間は模倣的な存在であり、現実を反映し表現するテキスト(芸術)を創造する衝動を抱えていると述べ た。 アリストテレスは、芸術作品と現実の生活との間に一定の距離があることが重要だと考えた。私たちは悲劇から知識や慰めを得る理由は、それが私たちに起こら ないからである。この距離がなければ、悲劇はカタルシスを生むことができない。しかし、テキストが観客にキャラクターや物語の出来事への共感を引き起こす ことも同様に重要であり、この共感が生じない限り、観客として私たちに響くことはない。アリストテレスは、私たちは「模倣的表現」であるミメーシスを通じ て、舞台上の演技に反応し、キャラクターが感じていることを伝えられることで、この模倣的な劇的役割演技を通じて彼らに共感するのだと主張している。劇作 家の任務は、舞台上で起こっていることを通じてこの共感を実現するために、悲劇的な演出を創作することだ。 要するに、カタルシスは、認識可能でありながら遠いものを見ることによってのみ達成される。アリストテレスは、文学は歴史よりも学習手段として興味深いと 主張した。なぜなら、歴史は起こった具体的な事実を扱うが、それらは偶然的なものであるのに対し、文学は歴史を基にすることもあるが、起こり得たことや起 こるべきだった出来事を扱うからである。 アリストテレスは、ドラマを「行動の模倣」と捉え、悲劇を「高い地位から低い地位へと陥る」こと、つまり、以前よりも悲劇的な状況にある、より理想からか け離れた状況へと追いやられることだと考えました。彼は、悲劇の登場人物は平均的な人間よりも優れている一方、喜劇の登場人物は平均的な人間よりも劣って いるとの立場を取りました。 アリストテレスの翻訳者であり評論家でもあるマイケル・デービスは、次のように述べている。 一見、ミメシスとは、現実を様式化することで、私たちの世界のありふれた特徴を、ある種の誇張によって強調し、模倣の対象との関係は、ダンスと歩行の関係 のようなもののように見える。模倣とは、常に経験の連続体から何かを選択することであり、それによって、実際には始まりも終わりもないものに境界を与え る。ミメシスには、その枠内に含まれるものが単に現実ではないことを示す、現実の枠組みの設定が伴う。したがって、模倣が「現実的」であればあるほど、そ れはより偽りになる[11]。 |
| Contrast to diegesis It was also Plato and Aristotle who contrasted mimesis with diegesis (Greek: διήγησις). Mimesis shows, rather than tells, by means of directly represented action that is enacted. Diegesis, however, is the telling of the story by a narrator; the author narrates action indirectly and describes what is in the characters' minds and emotions. The narrator may speak as a particular character or may be the "invisible narrator" or even the "all-knowing narrator" who speaks from above in the form of commenting on the action or the characters. In Book III of his Republic (c. 373 BC), Plato examines the style of poetry (the term includes comedy, tragedy, and epic and lyric poetry):[vi] all types narrate events, he argues, but by differing means. He distinguishes between narration or report (diegesis) and imitation or representation (mimesis). Tragedy and comedy, he goes on to explain, are wholly imitative types; the dithyramb is wholly narrative; and their combination is found in epic poetry. When reporting or narrating, "the poet is speaking in his own person; he never leads us to suppose that he is anyone else;" when imitating, the poet produces an "assimilation of himself to another, either by the use of voice or gesture."[vii] In dramatic texts, the poet never speaks directly; in narrative texts, the poet speaks as himself or herself.[12] In his Poetics, Aristotle argues that kinds of poetry (the term includes drama, flute music, and lyre music for Aristotle) may be differentiated in three ways: according to their medium, according to their objects, and according to their mode or manner (section I);[viii] "For the medium being the same, and the objects the same, the poet may imitate by narration—in which case he can either take another personality, as Homer does, or speak in his own person, unchanged—or he may present all his characters as living and moving before us."[ix] Though they conceive of mimesis in quite different ways, its relation with diegesis is identical in Plato's and Aristotle's formulations. In ludology, mimesis is sometimes used to refer to the self-consistency of a represented world, and the availability of in-game rationalisations for elements of the gameplay. In this context, mimesis has an associated grade: highly self-consistent worlds that provide explanations for their puzzles and game mechanics are said to display a higher degree of mimesis. This usage can be traced back to the essay "Crimes Against Mimesis".[13] |
ダイジェシスとの対比 ミメーシスとダイジェシス(ギリシャ語:διήγησις)を対比したのは、プラトンとアリストテレスだった。ミメーシスは、直接表現された行動によっ て、伝えるのではなく、見せるものだ。しかし、ディエゲシスは、語り手による物語の語りである。作者は、間接的に行動を語り、登場人物の考えや感情を記述 する。語り手は、特定の登場人物として話す場合もあれば、「目に見えない語り手」や、行動や登場人物についてコメントする形で上から話す「全知の語り手」 である場合もある。 プラトンは『共和国』(紀元前 373 年頃)の第 3 巻で、詩のスタイル(この用語には、喜劇、悲劇、叙事詩、叙情詩が含まれる)について考察している[vi]。彼は、あらゆる種類の詩は、異なる手段で出来 事を語る、と主張している。彼は、物語(ディエゲシス)と模倣または表現(ミメシス)を区別している。悲劇と喜劇は完全に模倣的な種類であり、ディティラ ムブは完全に叙述的であり、その組み合わせは叙事詩に見られると彼は説明する。報告や物語では、「詩人は自分の人格で語っており、自分が他の誰かであると 読者に想像させることは決してない」と彼は述べている。模倣では、詩人は「声や身振りを使って、自分自身を他の人物に同化させる」[vii]。劇のテキス トでは、詩人は決して直接的に語らない。物語のテキストでは、詩人は自分自身として語っている[12]。 アリストテレスは『詩学』において、詩の種類(アリストテレスにとってこの用語には劇、フルート音楽、リュート音楽が含まれる)は三つの方法で区別できる と主張している: 媒体による分類、対象による分類、様式または方法による分類(第 1 節)。[viii] 「媒体が同じで、対象も同じである場合、詩人は物語によって模倣することができる。その場合、詩人はホメロスのように別の人格を採り入れるか、あるいは自 分の人格のまま、変化なく話すことができる。あるいは、すべての登場人物たちを、私たちの目の前で生き生きと動き回る人物として表現することもできる」。 [ix] ミメシスについてまったく異なる考え方をしているものの、ミメシスとダイジェシスとの関係は、プラトンとアリストテレスの定式化では同じだ。 ゲーム理論では、ミメーシス(mimesis)は、表現された世界の自己一致性、およびゲームプレイの要素に対するゲーム内での合理化の説明可能性を指す ことがある。この文脈では、ミメーシスには関連する等級がある:パズルやゲームメカニクスに対する説明を提供する高度に自己一致した世界は、より高いミ メーシスの度合いを示すとされる。この用法は、エッセイ「Crimes Against Mimesis」に遡ることができる。[13] |
| Dionysian imitatio Main article: Dionysian imitatio Dionysian imitatio is the influential literary method of imitation as formulated by Greek author Dionysius of Halicarnassus in the 1st century BC, who conceived it as technique of rhetoric: emulating, adapting, reworking, and enriching a source text by an earlier author.[14][15] Dionysius' concept marked a significant departure from the concept of mimesis formulated by Aristotle in the 4th century BC, which was only concerned with "imitation of nature" rather than the "imitation of other authors."[14] Latin orators and rhetoricians adopted the literary method of Dionysius' imitatio and discarded Aristotle's mimesis.[14] |
ディオニュシオス的模倣 主な記事:ディオニュシオス的模倣 ディオニュシオス的模倣は、紀元前1世紀にギリシャの作家ディオニュシオス・ハリカルナッソスによって提唱された、影響力のある文学的手法である。これ は、修辞学の手法として考案され、先行する作家の原典を模倣、改作、再構成、充実させるものである。[14][15] ディオニュシウスの概念は、紀元前4世紀にアリストテレスが提唱した「ミメーシス」の概念から大きく逸脱したもので、後者は「自然の模倣」のみを重視し、 「他の作者の模倣」には関心を示さなかった。[14] ラテン語の雄弁家や修辞家たちは、ディオニュシウスの模倣の文学手法を採用し、アリストテレスのミメーシスを放棄した。[14] |
| Modern usage Samuel Taylor Coleridge Referring to it as imitation, the concept of mimesis was crucial for Samuel Taylor Coleridge's theory of the imagination. Coleridge begins his thoughts on imitation and poetry from Plato, Aristotle, and Philip Sidney, adopting their concept of imitation of nature instead of other writers. His departure from the earlier thinkers lies in his arguing that art does not reveal a unity of essence through its ability to achieve sameness with nature. Coleridge claims:[16] [T]he composition of a poem is among the imitative arts; and that imitation, as opposed to copying, consists either in the interfusion of the SAME throughout the radically DIFFERENT, or the different throughout a base radically the same. Here, Coleridge opposes imitation to copying, the latter referring to William Wordsworth's notion that poetry should duplicate nature by capturing actual speech. Coleridge instead argues that the unity of essence is revealed precisely through different materialities and media. Imitation, therefore, reveals the sameness of processes in nature. Erich Auerbach One of the best-known modern studies of mimesis—understood in literature as a form of realism—is Erich Auerbach's Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (1953), which opens with a famous comparison between the way the world is represented in Homer's Odyssey and the way it appears in the Bible. From these two seminal texts Auerbach builds the foundation for a unified theory of representation that spans the entire history of Western literature, including the Modernist novels being written at the time Auerbach began his study.[17] Walter Benjamin In his essay "On The Mimetic Faculty" (1933), Walter Benjamin outlines connections between mimesis and sympathetic magic, imagining a possible origin of astrology arising from an interpretation of human birth that assumes its correspondence with the apparition of a seasonally rising constellation augurs that new life will take on aspects of the myth connected to the star.[18] Luce Irigaray Belgian feminist Luce Irigaray used the term to describe a form of resistance where women imperfectly imitate stereotypes about themselves to expose and undermine such stereotypes.[19] |
現代的な用法 サミュエル・テイラー・コールリッジ 模倣として言及されるミメーシスという概念は、サミュエル・テイラー・コールリッジの想像力に関する理論にとって極めて重要だった。コールリッジは、プラ トン、アリストテレス、フィリップ・シドニーの考えから、他の作家ではなく自然を模倣するという概念を採用し、模倣と詩に関する考察を開始している。彼が 以前の思想家たちとは一線を画す点は、芸術は自然と同じものになる能力によって本質の一体性を明らかにするものではないと主張しているところだ。コール リッジは次のように述べている[16]。 詩の構成は模倣芸術の一つであり、その模倣は、コピーとは対照的に、根本的に異なるもの全体に同じものが融合すること、あるいは、根本的に同じ基盤全体に 異なるものが融合することのいずれかで構成される。 ここでコールリッジは、模倣をコピーと対比させている。後者は、ウィリアム・ワーズワースの、詩は実際の言葉を捉えることで自然を複製すべきであるという 考えを指している。コールリッジは、その代わりに、本質の一体性は、異なる物質性や媒体を通じてこそ正確に明らかにされると主張している。したがって、模 倣は、自然におけるプロセスの同一性を明らかにする。 エリヒ・アウエルバッハ 文学における現実主義の一形態として理解されるミメーシスに関する最も著名な現代の研究の一つは、エリヒ・アウエルバッハの『ミメーシス:西洋文学におけ る現実の表現』(1953年)で、この著作は、ホメロスの『オデュッセイア』における世界の表現と、聖書における世界の表現との有名な比較から始まってい る。アウエルバッハは、この2つの画期的なテキストから、アウエルバッハが研究を始めた当時書かれていたモダニズム小説を含む、西洋文学の歴史全体を網羅 する統一的な表現理論の基礎を築いたんだ。[17] ウォルター・ベンヤミン ウォルター・ベンジャミンは、エッセイ「模倣能力について」(1933年)で、ミメシスと共感呪術との関連性を概説し、人間の誕生を、季節ごとに昇る星座 の出現と対応すると解釈することで、占星術の起源を想像している。この星座は、新しい生命が星に関連する神話の側面を帯びることを予兆すると考えられてい た[18]。 ルース・イリガレイ ベルギーのフェミニスト、ルース・イリガライは、この用語を、女性が自分たちに関するステレオタイプを不完全な形で模倣することで、そのようなステレオタ イプを暴露し、弱体化させる抵抗の形態を説明するために使用した。[19] |
| Michael Taussig Further information: Cultural appropriation and Appropriation (sociology) In Mimesis and Alterity (1993), anthropologist Michael Taussig examines the way that people from one culture adopt another's nature and culture (the process of mimesis) at the same time as distancing themselves from it (the process of alterity). He describes how a legendary tribe, the "White Indians" (the Guna people of Panama and Colombia), have adopted in various representations figures and images reminiscent of the white people they encountered in the past (without acknowledging doing so). Taussig, however, criticises anthropology for reducing yet another culture, that of the Guna, for having been so impressed by the exotic technologies of the whites that they raised them to the status of gods. To Taussig this reductionism is suspect, and he argues this from both sides in his Mimesis and Alterity to see values in the anthropologists' perspective while simultaneously defending the independence of a lived culture from the perspective of anthropological reductionism.[20] |
マイケル・タウシグ 詳細情報:文化的流用および流用(社会学) 『ミメシスと他者性』(1993年)の中で、人類学者マイケル・タウシグは、ある文化の人々が別の文化の性質や文化を採用する(ミメシス)と同時に、そこ から距離を置く(他者性)という現象について考察している。彼は、伝説的な部族「ホワイト・インディアン」(パナマとコロンビアのグナ族)が、過去に遭遇 した白人を彷彿とさせる人物像やイメージを(それを認識することなく)さまざまな表現で採用してきたことを紹介している。 しかしタウシグは、人類学がグナ族の文化を、白人の異国的な技術に感銘を受けて神格化したとして、またしても文化を単純化していると批判している。タウシ グはこの単純化を疑わしいものと見なし、『ミメーシスと他者性』において、人類学者の視点から価値を見出す一方で、人類学的な単純化から見た文化の独立性 を擁護する両方の立場から論じている。[20] |
| René Girard In Things Hidden Since the Foundation of the World (1978), René Girard posits that human behavior is based upon mimesis, and that imitation can engender pointless conflict. Girard notes the productive potential of competition: "It is because of this unprecedented capacity to promote competition within limits that always remain socially, if not individually, acceptable that we have all the amazing achievements of the modern world," but states that competition stifles progress once it becomes an end in itself: "rivals are more apt to forget about whatever objects are the cause of the rivalry and instead become more fascinated with one another."[21] |
ルネ・ジラール 『世界の創世以来隠されていたもの』(1978年)の中で、ルネ・ジラールは、人間の行動は模倣に基づいており、模倣は無意味な紛争を引き起こす可能性が あると主張している。ジラールは競争の生産的な可能性を指摘している:「現代世界の驚くべき成果は、社会的に、あるいは個人レベルでは受け入れられる範囲 内で競争を促進するこの前例のない能力に由来する」と述べつつも、競争が目的化すると進歩を阻害すると指摘している:「ライバルは、競争の原因となってい る対象を忘れ、互いにますます魅了されるようになる」[21]。 |
| Roberto Calasso In The Unnameable Present, Calasso outlines the way that mimesis, called "Mimickry" by Joseph Goebbels—although it is a universal human ability—was interpreted by the Third Reich as being a sort of original sin attributable to "the Jew". Thus, an objection to the tendency of human beings to mimic one another instead of "just being themselves" and a complementary, fantasized desire to achieve a return to an eternally static pattern of predation by means of "will" expressed as systematic mass-murder became the metaphysical argument (underlying circumstantial, temporally contingent arguments deployed opportunistically for propaganda purposes) for perpetrating the Holocaust among the Nazi elite. Insofar as this issue or this purpose was ever even explicitly discussed in print by Hitler's inner circle, in other words, this was the justification (appearing in the essay "Mimickry" in a war-time book published by Joseph Goebbels).[22][23] The text suggests that a radical failure to understand the nature of mimesis as an innate human trait or a violent aversion to the same, tends to be a diagnostic symptom of the totalitarian or fascist character if it is not, in fact, the original unspoken occult impulse that has animated the production of totalitarian or fascist movements.[citation needed] Calasso's argument here echoes, condenses, and introduces new evidence to reinforce one of the major themes of Adorno and Horkheimer's Dialectic of the Enlightenment (1944),[24] which was itself in dialog with earlier work hinting in this direction by Walter Benjamin who died during an attempt to escape the gestapo.[18][25] Calasso insinuates and references this lineage throughout the text. The work can be read as a clarification of their earlier gestures in this direction, written while the Holocaust was still unfolding.[citation needed] Calasso's earlier book The Celestial Hunter, written immediately before The Unnamable Present, is an informed and scholarly speculative cosmology depicting the possible origins and early prehistoric cultural evolution of the human mimetic faculty.[26] In particular, the book's first and fifth chapters ("In The Time of the Great Raven" and "Sages & Predators") focus on the terrain of mimesis and its early origins, although insights on this motif permeate every other chapter of the book.[27] |
ロベルト・カラッソ 『名付けられない現在』の中で、カラッソは、ジョセフ・ゲッベルスが「ミミクリー」と呼んだミメーシス(模倣)が、普遍的な人間の能力であるにもかかわら ず、第三帝国によって「ユダヤ人」に起因する一種の原罪と解釈された経緯を概説している。つまり、人間が「単に自分らしくある」のではなく互いを模倣する 傾向への反発と、体系的な大量虐殺として表現された「意志」を通じて、永遠に静止した捕食のパターンへの回帰を幻想的に求める補完的な欲望が、ナチスエ リートがホロコーストを実行するための形而上学的な論拠(宣伝目的で機会主義的に利用された一時的な状況に依存する論拠の背景にあるもの)となった。つま り、この問題や目的がヒトラーの側近によって印刷物で明示的に議論された場合、これがその正当化(ヨゼフ・ゲッベルスが戦時中に発行した書籍『模倣』の エッセイに現れている)だった。[22][23] このテキストは、ミメーシス(模倣)を人間の先天的な特性として理解する根本的な失敗、またはそれに対する暴力的な嫌悪は、もしそれが実際、全体主義的ま たはファシスト的な運動の生産を駆動する原初的な言われなき秘密の衝動でない場合、全体主義的またはファシスト的な性格の診断的症状である傾向があること を示唆している。[出典が必要] カラッソのこの主張は、アドルノとホルクハイマーの『啓蒙の弁証法』(1944年)の主要なテーマの1つを補強するものであり、それを凝縮し、新たな証拠 を紹介している[24]。この著作自体は、ゲシュタポからの逃亡中に亡くなったウォルター・ベンヤミンが、この方向性を示唆した以前の著作と対話している [18][25]。カラッソは、この系譜を本文全体を通してほのめかし、参照している。この作品は、ホロコーストがまだ進行中の間に書かれた、この方向性 における彼らの以前の姿勢を明確にしたものと読むことができる。[要出典] カラッソの『The Unnamable Present』の直前に書かれた前作『The Celestial Hunter』は、人間の模倣能力の起源と先史時代の初期文化の進化について、知識と学識に裏打ちされた思弁的な宇宙論を描いた作品だ。[26] 特に、この本の第 1 章「大カラス時代」と第 5 章「賢者と捕食者」は、ミメシスの領域とその初期の起源に焦点を当てているが、このモチーフに関する洞察は、この本の他のすべての章にも浸透している。 [27] |
| Nidesh Lawtoo In Homo Mimeticus (2022) Swiss philosopher and critic Nidesh Lawtoo develops a relational theory of mimetic subjectivity arguing that not only desires but all affects are mimetic, for good and ill. Lawtoo opens up the transdisciplinary field of "mimetic studies" to account for the proliferation of hypermimetic affects in the digital age.[28] |
ニデシュ・ラウトゥ 『Homo Mimeticus』(2022年)において、スイスの哲学者であり批評家のニデシュ・ラウトゥは、欲望だけでなく、すべての感情が、良い面も悪い面も、 模倣的であるとの主張に基づき、関係性に基づく模倣的主体性の理論を展開している。ラウトゥは、デジタル時代におけるハイパー模倣的感情の蔓延を説明する ために、学際的な分野である「模倣研究」を開拓している。[28] |
| Similarity (philosophy) Man, Play and Games (Roger Caillois) Anti-mimesis Mimesis criticism Dionysian imitatio |
類似性(哲学 人間、遊び、ゲーム(ロジェ・カヨワ 反模倣 模倣批判 ディオニュソス的模倣 |
| Bibliography Auerbach, Erich . 1953. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature . Princeton: Princeton UP. ISBN 069111336X. Coleridge, Samuel T. 1983. Biographia Literaria, vol. 1, edited by J. Engell and W. J. Bate. Princeton, NJ: Princeton UP. ISBN 0691098743. Davis, Michael. 1999. The Poetry of Philosophy: On Aristotle's Poetics . South Bend, IN: St Augustine's P. ISBN 1890318620. Elam, Keir. 1980. The Semiotics of Theatre and Drama , New Accents series. London: Methuen. ISBN 0416720609. Esposito, Mariangela (2023). The Realm of Mimesis in Plato: Orality, Writing, and the Ontology of the Image. Leiden; Boston: Brill. ISBN 9789004533110. Gebauer, Gunter, and Christoph Wulf. [1992] 1995. Mimesis: Culture—Art—Society, translated by D. Reneau. Berkeley, CA: U of California Press. ISBN 0520084594. Girard, René. 2008. Mimesis and Theory: Essays on Literature and Criticism, 1953–2005, edited by R. Doran. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0804755801. Halliwell, Stephen. 2002. The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems . Princeton. ISBN 0691092583. Kaufmann, Walter . 1992. Tragedy and Philosophy . Princeton: Princeton UP. ISBN 0691020051. Lacoue-Labarthe, Philippe. 1989. Typography: Mimesis, Philosophy, Politics, edited by C. Fynsk. Cambridge: Harvard UP. ISBN 978-0804732826. Lawtoo, Nidesh. 2013. The Phantom of the Ego: Modernism and the Mimetic Unconscious. East Lansing: Michigan State UP. ISBN 978-1611860962. Lawtoo, Nidesh. 2022. Homo Mimeticus: A New Theory of Imitation Leuven: Leuven UP. ISBN 978-9462703469. Miller, Gregg Daniel. 2011. Mimesis and Reason: Habermas's Political Philosophy. Albany, NY: SUNY Press. ISBN 978-1438437408 Pfister, Manfred. [1977] 1988. The Theory and Analysis of Drama , translated by J. Halliday, European Studies in English Literature series. Cambridige: Cambridge UP. ISBN 052142383X. Potolsky, Matthew. 2006. Mimesis. London: Routledge. ISBN 0415700302. Prang, Christoph. 2010. "Semiomimesis: The influence of semiotics on the creation of literary texts. Peter Bichsel's Ein Tisch ist ein Tisch and Joseph Roth's Hotel Savoy." Semiotica (182):375–396. Sen, R. K. 1966. Aesthetic Enjoyment: Its Background in Philosophy and Medicine. Calcutta: University of Calcutta. —— 2001. Mimesis. Calcutta: Syamaprasad College. Sörbom, Göran. 1966. Mimesis and Art . Uppsala. Snow, Kim, Hugh Crethar, Patricia Robey, and John Carlson. 2005. "Theories of Family Therapy (Part 1)." As cited in "Family Therapy Review: Preparing for Comprehensive Licensing Examination." 2005. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0805843124. Tatarkiewicz, Władysław . 1980. A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics , translated by C. Kasparek . The Hague: Martinus Nijhoff. ISBN 9024722330. Taussig, Michael . 1993. Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses . London: Routledge. ISBN 0415906865. Tsitsiridis, Stavros. 2005. "Mimesis and Understanding. An Interpretation of Aristotle's 'Poetics' 4.1448b4–19." Classical Quarterly (55):435–446. |
参考文献 アウエルバッハ、エリック。1953. 『ミメーシス:西洋文学における現実の表現』. プリンストン:プリンストン大学出版局。ISBN 069111336X。 コールリッジ、サミュエル・T. 1983. 『文学伝記』第 1 巻、J. エンゲル、W. J. ベイト編。ニュージャージー州プリンストン:プリンストン大学出版局。ISBN 0691098743。 デイヴィス、マイケル。1999 年。『哲学の詩:アリストテレスの詩学について』 . サウスベンド、インディアナ州:セント・オーガスティンズ・パブリッシング。ISBN 1890318620。 エラム、キール。1980 年。『演劇とドラマの記号論』 , New Accents シリーズ。ロンドン:メトゥエン。ISBN 0416720609。 エスポジト、マリアンジェラ (2023)。プラトンのミメシス領域:口頭性、文字、そしてイメージの存在論。ライデン、ボストン:ブリル。ISBN 9789004533110。 ゲバウアー、ギュンター、クリストフ・ウルフ。[1992] 1995. 『ミメーシス:文化・芸術・社会』、D. レノー訳。カリフォルニア州バークレー:カリフォルニア大学出版局。ISBN 0520084594。 ジラール、ルネ。2008. ミメーシスと理論:文学と批評に関するエッセイ、1953-2005、R. Doran 編。スタンフォード:スタンフォード大学出版局。ISBN 978-0804755801。 Halliwell, Stephen. 2002. ミメーシスの美学。古代のテキストと現代の問題。プリンストン。ISBN 0691092583。 カウフマン、ウォルター。1992. 『悲劇と哲学』。プリンストン:プリンストン大学出版局。ISBN 0691020051。 ラクー=ラバルテ、フィリップ。1989. 『タイポグラフィ:ミメーシス、哲学、政治』、C. フィンスク編。ケンブリッジ:ハーバード大学出版局。ISBN 978-0804732826。 Lawtoo, Nidesh. 2013. The Phantom of the Ego: Modernism and the Mimetic Unconscious. East Lansing: Michigan State UP. ISBN 978-1611860962. Lawtoo, Nidesh. 2022. Homo Mimeticus: A New Theory of Imitation. ルーベン: Leuven UP. ISBN 978-9462703469. Miller, Gregg Daniel. 2011. Mimesis and Reason: Habermas's Political Philosophy. ニューヨーク州アルバニー: SUNY Press. ISBN 978-1438437408 フィスター、マンフレッド。[1977] 1988. 『ドラマの理論と分析』 J. ホールデイ訳、European Studies in English Literature シリーズ。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 052142383X。 ポトルスキー、マシュー。2006. 『ミメシス』。ロンドン:ラウトレッジ。ISBN 0415700302。 Prang, Christoph. 2010. 「セミオミミシス:文学テキストの創作における記号論の影響。ピーター・ビッヒセルの『Ein Tisch ist ein Tisch』とヨーゼフ・ロス『ホテル・サヴォイ』」『Semiotica』 (182):375–396。 セン, R. K. 1966. 『美的享受:その哲学的・医学的背景』. カルカッタ: カルカッタ大学. —— 2001. 『ミメーシス』. カルカッタ: シアマプラサド大学. ソーボム, ゲオルグ. 1966. 『ミメーシスと芸術』. ウプサラ. スノー、キム、ヒュー・クレサー、パトリシア・ロベイ、ジョン・カールソン。2005. 「家族療法の理論(第 1 部)」 『家族療法レビュー:総合免許試験の準備』 に引用。2005. ローレンス・エルバウム・アソシエイツ。ISBN 0805843124。 タタルキエヴィチ、ウワディスワフ。1980. 『6 つの思想の歴史: 美学に関するエッセイ」 C. カスパレック訳。ハーグ:Martinus Nijhoff。ISBN 9024722330。 タウシグ、マイケル。1993年。『ミメシスと他者性:感覚の個別史』。ロンドン:Routledge。ISBN 0415906865。 ツィツィリディス、スタヴロス。2005. 「ミメーシスと理解。アリストテレスの『詩学』4.1448b4–19 の解釈」。Classical Quarterly (55):435–446. |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Mimesis |
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆