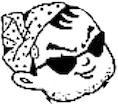
選好功利主義と普遍的指令主義
Preference utilitarianism and Universal
prescriptivism
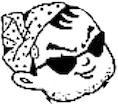
☆ 選好功利主義(Preference utilitarianism; 選好主義とも呼ばれる)は、現代哲学における功利主義の一形態である。価値一元論的な功利主義とは異なり、選好主義では、ある行為によって影響を受ける人 々の全体にとって、最も個人的な利益を満たす行為を重視する。 この理論は、1981年にR. M. ヘアが概説したものだが、Aの選好とBの選好の間の対立を解消できる何らかの基礎を前提としている限りにおいて、(例えば、数学的に重み付けすることによって)議論の余地がある。
★ 普遍的指令主義(しばしば単に指令主義や指令説と呼ばれる)は、命題を表現するのではなく、倫理的な命題(〜すべし)は「普遍化可能性」と同様に「指令する(→処方に従う)」というメタ倫理的な見 解である。すなわち、誰が倫理的な判断を下そうとも、同じ関連事実が該当するあらゆる状況において、同じ判断にコミットすることになる。
| Preference
utilitarianism
(also known as preferentialism) is a form of utilitarianism in
contemporary philosophy.[1] Unlike value monist forms of
utilitarianism, preferentialism values actions that fulfill the most
personal interests for the entire circle of people affected by said
action. Description Unlike classical utilitarianism, in which right actions are defined as those that maximize pleasure and minimize pain, preference utilitarianism entails promoting actions that fulfil the interests (i.e., preferences) of those beings involved.[2] Here beings might be rational, that is to say, that their interests have been carefully selected and they have not made some kind of error. However, 'beings' can also be extended to all sentient beings, even those who lack the capacity to contemplate long-term interests and consequences.[3] Since what is good and right depends solely on individual preferences, there can be nothing that is in itself good or bad: for preference utilitarians, the source of both morality and ethics in general is subjective preference.[3] Preference utilitarianism therefore can be distinguished by its acknowledgement that every person's experience of satisfaction is unique. The theory, as outlined by R. M. Hare in 1981,[4] is controversial, insofar as it presupposes some basis by which a conflict between A's preferences and B's preferences can be resolved (for example, by weighting them mathematically).[5] In a similar vein, Peter Singer, for much of his career a major proponent of preference utilitarianism and himself influenced by the views of Hare, has been criticised for giving priority to the views of beings capable of holding preferences (being able actively to contemplate the future and its interaction with the present) over those solely concerned with their immediate situation, a group that includes animals and young children. There are, he writes in regard to killing in general, times when "the preference of the victim could sometimes be outweighed by the preferences of others". Singer does, however, still place a high value on the life of rational beings, since killing them does not infringe upon just one of their preferences, but "a wide range of the most central and significant preferences a being can have".[6] Act utilitarianism R.G. Frey Rule utilitarianism Two-level utilitarianism Preferential option for the poor – Priority for the well-being of the poor 1. Peter Singer, Practical Ethics, 2011, p. 14 2. Peter Singer, Practical Ethics, 2011, p. 13 3. Susan F. Krantz (January 2002). Refuting Peter Singer's ethical theory: the importance of human dignity. Greenwood Publishing Group. pp. 28–29. ISBN 978-0-275-97083-3. 4. Hare, Richard Mervyn (1981). Moral Thinking: Its Levels, Method, and Point. Oxford, England: Clarendon Press. pp. 101–105. ISBN 978-0-19-824659-6. 5. Till Grüne-Yanoff; Sven Ove Hansson (2009). Preference Change: Approaches from Philosophy, Economics and Psychology. Springer. p. 187. ISBN 978-90-481-2592-0. 6. Peter Singer (1993). Practical ethics. Cambridge University Press. pp. 95. ISBN 978-0-521-43971-8. External links Sinnott-Armstrong, Walter (2023). "3. What is Good? Hedonistic vs. Pluralistic Consequentialisms". Consequentialism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Crisp, Roger (2021). "Well-Being". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Theories of Well-Being, in William MacAskill & Richard Yetter Chappell (2021), Introduction to Utilitarianism. |
選好功利主義(選好主義とも呼ばれる)は、現代哲学における功利主義の
一形態である。[1]
価値一元論的な功利主義とは異なり、選好主義では、ある行為によって影響を受ける人々の全体にとって、最も個人的な利益を満たす行為を重視する。 説明 正しい行動とは快楽を最大化し苦痛を最小化する行動であると定義される古典的功利主義とは異なり、選好功利主義では、関与する存在の利益(すなわち、選好)を満たす行動を促進することを意味す る。[2] ここでいう「存在」とは、すなわち、その利益が慎重に選択され、何らかの誤りを犯していないことを意味する。しかし、「存在するもの」は、長期的な利益や 結果を熟考する能力に欠けるものも含めた、すべての感覚を持つ存在にまで拡大される可能性もある。[3] 善と正義は個人の好みにのみ依存するため、それ自体が善であるものや悪であるものは存在し得ない。好み功利主義者にとって、道徳性や倫理一般の源は主観的 な好みである。[3] したがって、好み功利主義は、あらゆる人の満足の経験はそれぞれに異なるという認識によって区別される。 この理論は、1981年にR. M. ヘアが概説したものだが、[4] Aの選好とBの選好の間の対立を解消できる何らかの基礎を前提としている限りにおいて、議論の余地がある(例えば、数学的に重み付けすることによって)。 [5] 同様の観点から、ピーター・シンガーは、 長年にわたり選好功利主義の主要な提唱者であり、自身もヘアーの見解に影響を受けていたピーター・シンガーは、自身の立場を批判され、動物や幼い子供たち を含む、自身の置かれた状況のみに関心のある人々よりも、選好(能動的に未来と現在との相互作用を熟考できる)を持つことのできる存在の見解を優先してい ると批判されている。殺生全般に関して、シンガーは「犠牲者の選好が、他の者の選好に優先される場合もある」と書いている。しかし、シンガーは依然として 理性的な存在の生命を非常に重視しており、その理由として、彼らを殺すことは彼らの選好のひとつを侵害するのではなく、「存在が持つことのできる最も中心 的な重要な選好の広範な範囲」を侵害するからだとしている。[6] 功利主義 R.G. フレイ 規則功利主義 二段階功利主義 貧者への優先的選択 – 貧者の福祉を優先する 1. ピーター・シンガー『実践倫理学』2011年、14ページ 2. ピーター・シンガー『実践倫理学』2011年、13ページ 3. スーザン・F・クランツ(2002年1月)。ピーター・シンガーの倫理理論への反論:人間の尊厳の重要性。グリーンウッド出版グループ。28~29ページ。ISBN 978-0-275-97083-3。 4. Hare, Richard Mervyn (1981). 『道徳的思考:そのレベル、方法、そして要点』. 英国オックスフォード:クラレンドン・プレス. pp. 101–105. ISBN 978-0-19-824659-6. 5. ティル・グリューネ=ヤノフ、スヴェン・オーヴェ・ハンソン(2009)。『選好の変化:哲学、経済学、心理学からのアプローチ』。スプリンガー。187 ページ。ISBN 978-90-481-2592-0。 6. ピーター・シンガー (1993). 『実践倫理学』. ケンブリッジ大学出版局. pp. 95. ISBN 978-0-521-43971-8. 外部リンク Sinnott-Armstrong, Walter (2023). 「3. 善とは何か?快楽主義対多元主義的帰結主義」. 帰結主義. スタンフォード哲学百科事典. Crisp, Roger (2021). 「幸福」. スタンフォード哲学百科事典. 幸福の理論、ウィリアム・マカスキル&リチャード・イェッター・チャペル(2021)、『功利主義入門』。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Preference_utilitarianism |
|
| Universal prescriptivism In a series of books, especially The Language of Morals (1952), Freedom and Reason (1963), and Moral Thinking (1981), Hare gave shape to a theory that he called universal prescriptivism. According to this, moral terms such as 'good', 'ought' and 'right' have two logical or semantic properties: universalizability and prescriptivity. By the former, he meant that moral judgments must identify the situation they describe according to a finite set of universal terms, excluding proper names, but not definite descriptions. By the latter, he meant that moral agents must perform those acts they consider themselves to have an obligation to perform whenever they are physically and psychologically able to do so. In other words, he argued that it made no sense for someone to say, sincerely: "I ought to do X", and then fail to do X. This was identified by Frankena, Nobis and others as a major flaw in Hare's system, as it appeared to take no account of akrasia, or weakness of the will.[15][16][17] Hare argued that the combination of universalizability and prescriptivity leads to a certain form of consequentialism, namely, preference utilitarianism. In brief, this means that we should act in such a way as to maximise the satisfaction of people's preferences. https://navymule9.sakura.ne.jp/R_M_Hare.html |
普遍的指令主義(=普遍的指令説) 一連の著書、特に『道徳の言語』(1952年)、『自由と理性』(1963年)、『道徳的思考(邦訳:道徳的に考えること)』(1981年)の中で、ヘア は普遍的指令主義と呼ぶ理論 を形づくった。それによれば、「善」、「べき」、「正しい」といった道徳用語には、普遍化可能性と指令性という2つの論理的あるいは意味論的特性があると いう。前者とは、道徳的判断は、固有名詞を除く普遍的な用語の有限集合に従って記述する状況を特定しなければならないが、明確な記述は特定できないという 意味である。後者については、道徳的行為者は、身体的・心理的に実行可能なときにいつでも、自らに果たす義務があると考える行為を実行しなければならな い、という意味であった。つまり彼は、誰かが心から「私はXをすべきです」と言っても意味がないと主張したのである: 「これはフランケナやノビスらによって、アクラシア(意志の弱さ)を考慮していないように見えるヘアのシステムの大きな欠陥として指摘された[15] [16][17]。 ヘアは、普遍化可能性と規定性の組み合わせがある種の結果主義、すなわち選好功利主義につながると主張した。簡単に言えば、人々の選好を最大限に満足させ るように行動すべきだということである。 |
| Universal
prescriptivism
(often simply called prescriptivism) is the meta-ethical view that
claims that, rather than expressing propositions, ethical sentences
function similarly to imperatives which are universalizable—whoever
makes a moral judgment is committed to the same judgment in any
situation where the same relevant facts pertain.[1][2] This makes prescriptivism a universalist form of non-cognitivism. Prescriptivism stands in opposition to other forms of non-cognitivism (such as emotivism and quasi-realism), as well as to all forms of cognitivism (including both moral realism and ethical subjectivism).[3] Since prescriptivism was introduced by philosopher R. M. Hare in his 1952 book The Language of Morals, it has been compared to emotivism and to the categorical imperative of Immanuel Kant.[4][5] Unlike Kant, however, Hare does not invoke universalizability as a test of moral permissibility. Instead, he sees it as a consistency requirement that is built into the logic of moral language and helps to make moral thinking a rational enterprise. |
普
遍的指令説(しばしば単に指令説と呼ばれる)は、倫理的な命題は命題
を表現するのではなく、普遍化可能な命令と同様の機能を持つというメタ倫理的な見解
である。すなわち、道徳的判断を下す者は誰でも、同じ関連事実が該当するあらゆる状況において、同じ判断を下すことになる。[1][2] これにより、指令説は非認識論の普遍主義の一形態となる。指令説は、非認識論の他の形態(感情論や疑似現実主義など)や、認識論のすべての形態(道徳的実 在論や倫理的観念論を含む)と対立する。 指令説は、哲学者R. M. ヘアが1952年に著した『The Language of Morals』で紹介されて以来、感情主義やカントの「定言命法」と比較されてきた。[4][5] しかし、カントとは異なり、ヘアは普遍化可能性を道徳的許容性のテストとして用いることはない。その代わり、彼はそれを道徳的言語の論理に組み込まれた一 貫性の要件と見なし、道徳的思考を合理的な事業とするのに役立つものと考えている。 |
| What prescriptivists claim Hare originally proposed prescriptivism as a kind of amendment to emotivism.[6] Like emotivists, Hare believes that moral discourse is not primarily informative or fact-stating. But whereas emotivists claim that moral language is mainly intended to express feelings or to influence behavior, Hare believes that the central purpose of moral talk is to guide behavior by telling someone what to do. Its main purpose is to “prescribe” (recommend) a certain act, not to get someone to do that act or to express one's personal feelings or attitudes.[7] To illustrate the prescriptivist view, consider the moral sentence, “Suicide is wrong.” According to moral realism, such a sentence claims there to be some objective property of “wrongness” associated with the act of suicide. According to some versions of emotivism, such a sentence merely expresses an attitude of the speaker; it only means something like “Boo on suicide!”, but according to prescriptivism, the statement “Suicide is wrong” means something more like “Do not commit suicide.”. What it expresses is thus not primarily a description or an emotion, but an imperative. General value terms like “good”, “bad”, “right”, “wrong” and “ought” usually also have descriptive and emotive meanings, but these are not their primary meanings according to prescriptivists. |
指令説論者の主張 ヘ アは当初、指令説を感情主義に対する修正の一種として提案した。[6] 感情主義者と同様に、ヘアは道徳的言説は主として情報伝達や事実の提示を目的とするものではないと考える。しかし、感情主義者が道徳的言語は主として感 情を表現したり行動に影響を与えることを目的としていると主張するのに対し、ヘアは道徳的言説の中心的な目的は、誰かに何をすべきかを伝えることで行動 を導くことにあると考える。その主な目的は、ある行為を「処方する」(推奨する)ことであり、誰かにその行為を行わせたり、個人的な感情や態度を表明させ ることではない。[7] 指令主義の考え方を説明するために、「自殺は間違っている」という道徳的な文章を考えてみよう。道徳的リアリズムによれば、このような文は自殺という行為 に 「間違っている」という客観的な性質があることを主張している。感情論のいくつかのバージョンによれば、このような文は単に話し手の態度を表現しているに 過ぎず、「自殺なんて最低!」という程度の意味しかないが、指令説によれば、「自殺は間違っている」という文は「自殺してはいけない」というような意味を 持つ。したがって、表現されるのは、主として描写や感情ではなく、命令である。「良い」、「悪い」、「正しい」、「間違っている」、「〜すべきである」と いった一般的な価値用語は、通常、描写や感情的な意味も持つが、指令主義によれば、これらは主たる意味ではない。 |
| Criticisms Prescriptivism has faced extensive criticism and currently has few adherents.[8] Ethicists commonly dispute Hare's assertion that moral language lacks informativeness, challenging the idea that the primary purpose of moral discourse is not to convey moral truths or facts.[9] Hare's argument that offering guidance always constitutes the primary goal of moral discourse is also questioned by numerous critics.[10] [8] Price, Anthony, "Richard Mervyn Hare", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), [9]Feldman, Fred. Introductory Ethics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978, pp. 246-47. [10]Feldman, ibid., p. 247; Warnock, Contemporary Moral Philosophy, p. 35. Some critics observe that Hare seems to presume moral language is exclusively employed in discussions, debates, or commands, where one person instructs another or others on what to do. This perspective, it is argued, overlooks the broader usage of moral talk as a "language-game" serving diverse purposes. Lastly, critics contend that prescriptivism contradicts the common-sense differentiation between good and bad reasons for holding moral beliefs.[11] Hare's stance suggests that a racist "fanatic" advocating the deportation of all minority-group members, while maintaining consistency (even if the racist is a member of the minority group), cannot be criticized for either irrationality or falsehood.[12] According to Hare, ethics fundamentally involves non-rational choice and commitment.[13] However, critics of Hare argue that reason should and does play a more substantial role in ethics than he acknowledges. |
批判 指令主義は広範な批判にさらされ、現在では支持者はほとんどいない。[8] 倫理学者たちは一般的に、道徳的言語には情報伝達力がないというヘアの前提に異議を唱え、道徳的言説の主な目的は道徳的真理や事実を伝えることではないと いう考えに異議を唱えている。[9] ヘアの主張する、道徳的言説の主な目的は常に指針(ガイダンス)を与えることであるという主張も、多くの批判者によって疑問視されている。[10] [8] Price, Anthony, "Richard Mervyn Hare", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), [9]Feldman, Fred. Introductory Ethics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978, pp. 246-47. [10]Feldman, ibid., p. 247; Warnock, Contemporary Moral Philosophy, p. 35. 一部の批評家は、ヘアが道徳的な言語は議論、討論、または命令においてのみ用いられると想定しているように見えると指摘している。この見解は、多様な目的 を果たす「言語ゲーム」としての道徳的な会話のより幅広い用法を見落としていると論じられている。最後に、批評家たちは、指令主義は道徳的信念を持つ理由 と して良いものと悪いものを区別する常識と矛盾していると主張している。 ヘアの立場は、人種差別主義者の「狂信者」が、マイノリティ集団の全員の国外追放を主張している場合、一貫性を保っている限り(たとえその人種差別主義 者がマイノリティ集団のメンバーであったとしても)、その主張を非合理や虚偽として批判することはできない、というものである。[12] ヘアによれば、倫理とは本質的に非合理的な選択と献身を伴うものである。[13] しかし、ヘアの批判者たちは、倫理においては、ヘアが認めている以上に理性がより重要な役割を果たすべきであり、実際に果たしていると主張している。 |
| Act utilitarianism R.G. Frey Rule utilitarianism Two-level utilitarianism Non-cognitivism |
行為功利主義 R.G.フレイ ルール功利主義 二段階功利主義 非認知主義 |
| Notes of "Universal prescriptivism" 1. "Ethics - Existentialism". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2020-05-28. 2. Dahl, Norman O. (1987). "A Prognosis for Universal Prescriptivism". Philosophical Studies. 51 (3): 383–424. doi:10.1007/BF00354045. ISSN 0031-8116. JSTOR 4319897. 3. van Roojen, Mark (2004-01-23). "Moral Cognitivism vs. Non-Cognitivism". {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help) 4. Brandt, Theory, 221: "[The Language of Morals] by R. M. Hare has proposed a view, otherwise very similar to the emotive theory, with modifications ..." 5. Brandt, Theory, 224: "Hare's [universalizability] proposal is reminiscent of Kant's view that an act is morally permissible if and only if the maxim in terms of which the agent thinks of it could possibly serve as a universal rule of conduct, and if the agent is prepared to accept it as such." 6. Warnock, G. J., Contemporary Moral Philosophy. London: Macmillan, 1967, p. 30. 7. Norman, Richard. The Moral Philosophers: An Introduction to Ethics, 2nd ed. New York: Oxford University Press, pp. 166-67. 8. Price, Anthony, "Richard Mervyn Hare", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/hare/>. 9. Feldman, Fred. Introductory Ethics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978, pp. 246-47. 10. Feldman, ibid., p. 247; Warnock, Contemporary Moral Philosophy, p. 35. 11. Kerner, George C. The Revolution in Ethical Theory. New York: Oxford, 1966, pp. 192-96; Feldman, Introductory Ethics, pp. 246-47. 12. Hare, R. M. Freedom and Reason. Oxford: Clarendon Press, 1963, p. 220. 13. Kerner, The Revolution in Ethical Theory, p. 193. |
「普遍的規範主義」に関する注記 1. 「倫理 - 実存主義」。ブリタニカ百科事典。2020年5月28日取得。 2. ダール、ノーマン・O(1987)。「普遍的規範主義の予後」。哲学研究。51 (3): 383–424。doi:10.1007/BF00354045. ISSN 0031-8116. JSTOR 4319897. 3. ヴァン・ルーヘン、マーク (2004-01-23). 「道徳的認知主義対非認知主義」. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help) 4. Brandt, Theory, 221: 「R. M. Hareの『道徳の言語』は、感情論と非常に類似した見解を、修正を加えて提案している...」 5. Brandt, Theory, 224: 「Hare の [普遍化可能性] の提案は、行為は、行為者がそれを考える格律が普遍的な行動規範として機能しうる場合、そして行為者がそれをそのように受け入れる用意がある場合にのみ、 道徳的に許容されるというカントの見解を彷彿とさせる。」 6. ワーノック、G. J.、『現代道徳哲学』。ロンドン:マクミラン、1967年、30ページ。 7. ノーマン、リチャード。『道徳哲学者たち:倫理学入門』、第2版。ニューヨーク:オックスフォード大学出版局、166-67ページ。 8. プライス、アンソニー、「リチャード・マーヴィン・ヘア」、スタンフォード哲学百科事典(2014年夏版)、エドワード・N・ザルタ(編)、URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/hare/>。 9. フェルドマン、フレッド。『倫理学入門』。ニュージャージー州イングルウッドクリフス:プレンティスホール、1978年、246-47ページ。 10. フェルドマン、同上、247ページ、ワーノック、『現代道徳哲学』、35ページ。 11. カーナー、ジョージ・C。『倫理理論の革命』。ニューヨーク:オックスフォード、1966年、pp. 192-96;フェルドマン『倫理学入門』、pp. 246-47。 12. ヘア、R. M. 『自由と理性』。オックスフォード:クラレンドン・プレス、1963年、p. 220。 13. カーナー『倫理理論の革命』、p. 193. |
| References Brandt, Richard (1959). "Noncognitivism: The Job of Ethical Sentences Is Not to State Facts". Ethical Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall. LCCN 59010075. |
参考文献 ブラント、リチャード(1959)。「非認知主義:倫理的文の役割は事実を述べるのではない」。『倫理理論』。イングルウッドクリフス:プレンティス・ホール。LCCN 59010075。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_prescriptivism | |
| Non-cognitivism
is the meta-ethical view that ethical sentences do not express
propositions (i.e., statements) and thus cannot be true or false (they
are not truth-apt). A noncognitivist denies the cognitivist claim that
"moral judgments are capable of being objectively true, because they
describe some feature of the world."[1] If moral statements cannot be
true, and if one cannot know something that is not true, noncognitivism
implies that moral knowledge is impossible.[1] Non-cognitivism entails that non-cognitive attitudes underlie moral discourse and this discourse therefore consists of non-declarative speech acts, although accepting that its surface features may consistently and efficiently work as if moral discourse were cognitive. The point of interpreting moral claims as non-declarative speech acts is to explain what moral claims mean if they are neither true nor false (as philosophies such as logical positivism entail). Utterances like "Boo to killing!" and "Don't kill" are not candidates for truth or falsity, but have non-cognitive meaning. |
非
認知主義とは、倫理的文は命題(すなわち主張)を表現せず、したがって真偽を持たない(真偽可能性を持たない)とするメタ倫理学の見解である。非認知主義
者は「道徳的判断は世界の何らかの特徴を記述するため、客観的に真となり得る」という認知主義者の主張を否定する。[1]
もし道徳的発言が真になり得ず、かつ真でないものを知ることもできないならば、非認知主義は道徳的知識が不可能であることを示唆する。[1] 非認知主義は、道徳的言説の根底には非認知的態度が存在し、したがってこの言説は非宣言的発話行為から成ることを意味する。ただし、その表面的な特徴は、 道徳的言説が認知的であるかのように一貫して効率的に機能し得ることを認める。道徳的主張を非宣言的発話行為として解釈する意義は、それらが真でも偽でも ない場合(論理的実証主義などの哲学が導くように)に、道徳的主張が何を意味するのかを説明することにある。「殺すのはダメだ!」や「殺すな」といった発 話は、真偽の対象とはならないが、非認知的な意味を持つ。 |
| Varieties Emotivism, associated with A. J. Ayer, the Vienna Circle and C. L. Stevenson, though first defended by Axel Hägerström in the early 1900s, suggests that ethical sentences are primarily emotional expressions of one's own attitudes and are intended to influence the actions of the listener. Under this view, "Killing is wrong" is translated as "Killing, boo!" or "I disapprove of killing." A close cousin of emotivism, developed by R. M. Hare, is called universal prescriptivism. Prescriptivists interpret ethical statements as being universal imperatives, prescribing behavior for all to follow. According to prescriptivism, phrases like "Thou shalt not murder!" or "Do not steal!" are the clearest expressions of morality, while reformulations like "Killing is wrong" tend to obscure the meaning of moral sentences. Other forms of non-cognitivism include Simon Blackburn's quasi-realism and Allan Gibbard's norm-expressivism. |
種類 感情主義は、A. J. エイヤー、ウィーン学派、C. L. スティーブンソンに関連付けられるが、最初に提唱したのは1900年代初頭のアクセル・ヘーゲルストロームである。この立場では、倫理的文は主に自身の態 度の感情的表現であり、聞き手の行動に影響を与えることを意図していると主張する。この見解によれば、「殺人は悪い」は「殺すなんて、ブー!」あるいは 「私は殺人を非難する」と訳される。 感情主義と近縁の立場として、R・M・ヘアが発展させた普遍的規範主義がある。規範主義者は倫理的命題を普遍的命令と解釈し、全ての者が従うべき行動を規 定するものとする。規範主義によれば、「汝、殺すなかれ!」や「盗むなかれ!」といった表現こそが道徳の最も明確な表明であり、「殺すことは間違ってい る」のような言い換えは道徳的文の意味を曖昧にする傾向がある。 その他の非認知主義には、サイモン・ブラックバーンの準実在論やアラン・ギバードの規範表現主義がある。 |
| Arguments in favour This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources in this section. Unsourced material may be challenged and removed. (March 2007) (Learn how and when to remove this message) As with other anti-realist meta-ethical theories, non-cognitivism is largely supported by the argument from queerness: ethical properties, if they existed, would be different from any other thing in the universe, since they have no observable effect on the world. People generally have a negative attitude towards murder, which presumably keeps most of us from murdering. But does the actual wrongness of murder play an independent role? Is there any evidence that there is a property of wrongness that some types of acts have? Some people might think that the strong feelings we have when we see or consider a murder provide evidence of murder's wrongness. But it is not difficult to explain these feelings without saying that wrongness was their cause. Thus there is no way of discerning which, if any, ethical properties exist; by Occam's razor, the simplest assumption is that none do. The non-cognitivist then asserts that, since a proposition about an ethical property would have no referent, ethical statements must be something else. Universal prescriptivism Arguments for prescriptivism focus on the function of normative statements. Prescriptivists argue that factual statements and prescriptions are totally different, because of different expectations of change in cases of a clash between word and world. In a descriptive sentence, if one premises that "red is a number" then according to the rules of English grammar said statement would be false. Since said premise describes the objects "red" and "number", anyone with an adequate understanding of English would notice the falseness of such description and the falseness of said statement. However, if the norm "thou shalt not kill!" is uttered, and this premise is negated (by the fact of a person being murdered), the speaker is not to change his sentence upon observation of this into "kill other people!", but is to reiterate the moral outrage of the act of killing. Adjusting statements based upon objective reality and adjusting reality based upon statements are contrary uses of language; that is to say, descriptive statements are a different kind of sentence to normative statements. If truth is understood according to correspondence theory, the question of the truth or falsity of sentences not contingent upon external phenomena cannot be tested (see tautologies). Some cognitivists argue that some expressions like "courageous" have both a factual as well as a normative component which cannot be distinguished by analysis. Prescriptivists argue that according to context, either the factual or the normative component of the meaning is dominant. The sentence "Hero A behaved courageously" is wrong, if A ran away in the face of danger. But the sentence "Be brave and fight for the glory of your country!" has no truth value and cannot be falsified by someone who does not join the army. Prescriptivism is also supported by the actual way of speaking. Many moral statements are de facto uttered as recommendations or commands, e.g. when parents or teachers forbid children to do wrong actions. The most famous moral ideas are prescriptions: the Ten Commandments, the command of charity, the categorical imperative, and the Golden Rule command to do or not to do something rather than state that something is or is not the case. Prescriptivism can fit the theist idea of morality as obedience towards god. It is however different from the cognitivist supernaturalism which interprets morality as subjective will of god, while prescriptivism claims that moral rules are universal and can be found by reason alone without reference to a god. According to Hare, prescriptivists cannot argue that amoralists are logically wrong or contradictory. Everyone can choose to follow moral commands or not. This is the human condition according to the Christian reinterpretation of the Choice of Heracles. According to prescriptivism, morality is not about knowledge (of moral facts), but about character (to choose to do the right thing). Actors cannot externalize their responsibility and freedom of will towards some moral truth in the world, virtuous people do not need to wait for some cognition to choose what's right. Prescriptivism is also supported by imperative logic, in which there are no truth values for imperatives, and by the idea of the naturalistic fallacy: even if someone could prove the existence of an ethical property and express it in a factual statement, he could never derive any command from this statement, so the search for ethical properties is pointless. Emotivism Arguments for emotivism focus on what normative statements express when uttered by a speaker. A person who says that killing is wrong certainly expresses her disapproval of killing. Emotivists claim that this is all she does, that the statement "killing is wrong" is not a truth-apt declaration, and that the burden of evidence is on the cognitivists who want to show that in addition to expressing disapproval, the claim "killing is wrong" is also true. Emotivists ask whether there really is evidence that killing is wrong. We have evidence that Jupiter has a magnetic field and that birds are oviparous, but as yet, we do not seem to have found evidence of moral properties, such as "goodness". Emotivists ask why, without such evidence, we should think there is such a property. Ethical intuitionists think the evidence comes not from science or reason but from our own feelings: good deeds make us feel a certain way and bad deeds make us feel very differently. But is this enough to show that there are genuinely good and bad deeds? Emotivists think not, claiming that we do not need to postulate the existence of moral "badness" or "wrongness" to explain why considering certain deeds makes us feel disapproval; that all we really observe when we introspect are feelings of disapproval. Thus the emotivist asks why not adopt the simple explanation and say that this is all there is, rather than insist that some intrinsic "badness" (of murder, for example) must be causing feelings when a simpler explanation is available. |
「非認知主義に対する」賛成論 この節は検証可能な情報源を要する。信頼できる情報源をこの節に追加し、記事の改善に協力してほしい。出典のない記述は削除される可能性がある。(2007年3月)(このメッセージの削除方法と時期について) 他の反実在論的メタ倫理学理論と同様に、非認知主義は主に奇妙さからの議論によって支持されている。倫理的性質が存在するならば、それらは宇宙の他のあら ゆるものと異なるはずだ。なぜなら、それらは世界に観察可能な影響を与えないからである。人民は一般的に殺人に否定的な態度を持ち、おそらくそれが私たち のほとんどを殺人から遠ざけている。しかし、殺人の実際の不正さが独立した役割を果たしているのだろうか? ある種の行為が持つ「不正」という性質が存在するという証拠はあるのか?殺人を見たり考えたりした時に感じる強い感情が、殺人の不正さを証明していると思 う人もいるかもしれない。しかし、不正さがその原因だと言わなくても、これらの感情を説明するのは難しくない。したがって、もし存在するとしても、どの倫 理的性質が存在するかを判別する方法はない。オッカムの剃刀によれば、最も単純な仮定は、それらが存在しないというものだ。非認知主義者は、倫理的性質に 関する命題には参照対象が存在しないため、倫理的記述は別の何かなのだと主張する。 普遍的規範主義 規範主義を支持する議論は、規範的記述の機能に焦点を当てる。 規範主義者は、事実陳述と規範命令は全く異なる論じる。言葉と世界の衝突において変化への期待が異なるからだ。記述文において「赤は数である」という前提 を立てれば、英語文法の規則に従いその陳述は偽となる。この前提が「赤」と「数」という対象を記述しているため、英語を十分に理解する者なら誰でも、この 記述の偽性と陳述の偽性に気付くだろう。しかし「汝、殺すなかれ!」という規範が表明され、この前提が(人格が殺害された事実によって)否定された場合、 発言者はこの観察に基づいて文を「他人を殺せ!」と変更するのではなく、殺害行為に対する道徳的憤りを再表明すべきである。客観的現実に基づいて発言を調 整することと、発言に基づいて現実を調整することは言語の相反する用法である。つまり、記述的発言は規範的発言とは異なる種類の文だ。真偽を対応理論で理 解する場合、外部現象に依存しない文の真偽は検証できない(同語反復を参照)。 一部の認知主義者は、「勇敢」のような表現には分析によって区別できない事実的要素と規範的要素の両方が含まれると主張する。規範主義者は、文脈に応じて 意味の事実的要素か規範的要素のどちらかが支配的になると主張する。「英雄Aは勇敢に行動した」という文は、Aが危険に直面して逃げた場合、誤りとなる。 しかし「勇気を持ち、祖国の栄光のために戦え!」という文は真偽値を持たず、軍に入隊しない者が反証することはできない。 規範主義は実際の話し方にも支えられている。多くの道徳的発言は事実上、勧告や命令として発せられる。例えば親や教師が子供に悪い行為を禁じる場合だ。最 も有名な道徳観念は規範である:十戒、慈善の命令、定言命法、黄金律は、何かが真実であるか否かを述べるのではなく、何かをせよあるいはするなと命じる。 規範主義は、神への服従としての道徳という有神論的観念にも適合する。ただし、道徳を神の主観的意志と解釈する認知主義的超自然主義とは異なり、規範主義は道徳的規則が普遍的であり、神を参照せずとも理性だけで見出せると主張する。 ヘアーによれば、規範主義者は非道徳主義者が論理的に誤っている、あるいは矛盾していると主張できない。誰もが道徳的命令に従うか否かを選択できるから だ。これはキリスト教によるヘラクレスの選択の再解釈に基づく人間の条件である。規範主義によれば、道徳は(道徳的事実の)知識ではなく、(正しいことを 選択する)性格に関わる。行為者は自らの責任や意志の自由を世界にある道徳的真理に帰属させられない。徳ある人民は正しい選択をするために何らかの認知を 待つ必要はない。 規範主義は命令論理(命令文に真偽値が存在しない)や自然主義的誤謬の概念によっても支持される。たとえ誰かが倫理的性質の存在を証明し事実的命題で表現できたとしても、この命題からいかなる命令も導出できないため、倫理的性質の探求は無意味だというのだ。 感情主義 感情主義の論拠は、規範的命題が話者によって発話された際に何を表現するかに焦点を当てる。「殺人は間違っている」と言う人格は、確かに殺人を非難してい る。感情主義者は、これがその人格の行う全てであり、「殺人は間違っている」という主張は真偽を問う宣言ではないと主張する。さらに「殺人は間違ってい る」という主張が非難を表現するだけでなく真であることも示す責任は、認知主義者にあると主張する。感情主義者は問う、殺人が間違っているという証拠が本 当に存在するのかと。木星に磁場があることや鳥が卵生であることには証拠があるが、「善」のような道徳的性質の証拠は今のところ見つかっていないようだ。 感情主義者は、そのような証拠がないのに、なぜ我々がそのような性質があると考えるべきなのかと問う。倫理的直観主義者は、証拠は科学や理性からではなく 我々の感情から来ると考える。善行は我々に特定の感情を抱かせ、悪行は全く異なる感情を抱かせるのだ。だが、これだけで真に善悪の行為が存在すると証明で きるのか?感情主義者は否定する。特定の行為を不快に感じる理由を説明するのに、道徳的な「悪」や「不正」の存在を仮定する必要はないと主張する。内省で 実際に観察できるのは、不快感を覚える感情だけだと。したがって感情主義者は問う。より単純な説明が存在するのに、なぜ「殺人の本質的な悪さ」といったも のが感情を引き起こしていると主張する必要があるのかと。単純な説明で済むのに、なぜわざわざ複雑な説明を選ぶのかと。 |
| Arguments against This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources in this section. Unsourced material may be challenged and removed. (March 2007) (Learn how and when to remove this message) One argument against non-cognitivism is that it ignores the external causes of emotional and prescriptive reactions. If someone says, "John is a good person," something about John must have inspired that reaction. If John gives to the poor, takes care of his sick grandmother, and is friendly to others, and these are what inspire the speaker to think well of him, it is plausible to say, "John is a good person because he gives to the poor, takes care of his sick grandmother, and is friendly to others". If, in turn, the speaker responds positively to the idea of giving to the poor, then some aspect of that idea must have inspired a positive response; one could argue that that aspect is also the basis of its goodness. Another argument is the "embedding problem" in which ethical sentences are embedded into more complex sentences. Consider the following examples: Eating meat is not wrong. Is eating meat wrong? I think that eating meat is wrong. Mike doesn't think that eating meat is wrong. I once thought that eating meat was wrong. She does not realize that eating meat is wrong. Attempts to translate these sentences in an emotivist framework seem to fail (e.g. "She does not realize 'Boo to eating meat!'"). Prescriptivist translations fare only slightly better ("She does not realize that she is not to eat meat"). Even the act of forming such a construction indicates some sort of cognition in the process. According to some non-cognitivist points of view, these sentences simply assume the false premise that ethical statements are either true or false. They might be literally translated as: "Eating meat is wrong" is a false statement. Is "eating meat is wrong" a true statement? I think that "eating meat is wrong" is a true statement. Mike doesn't think that "eating meat is wrong" is a true statement. I once thought that "eating meat is wrong" was a true statement. She does not realize that "eating meat is wrong" is a true statement. These translations, however, seem divorced from the way people actually use language. A non-cognitivist would have to disagree with someone saying, "'Eating meat is wrong' is a false statement" (since "Eating meat is wrong" is not truth-apt at all), but may be tempted to agree with a person saying, "Eating meat is not wrong." One might more constructively interpret these statements to describe the underlying emotional statement that they express, i.e.: I disapprove/do not disapprove of eating meat, I used to, he doesn't, I do and she doesn't, etc.; however, this interpretation is closer to ethical subjectivism than to non-cognitivism proper. A similar argument against non-cognitivism is that of ethical argument. A common argument might be, "If killing an innocent human is always wrong, and all fetuses are innocent humans, then killing a fetus is always wrong." Most people would consider such an utterance to represent an analytic proposition which is true a priori. However, if ethical statements do not represent cognitions, it seems odd to use them as premises in an argument, and even odder to assume they follow the same rules of syllogism as true propositions. However, R.M. Hare, proponent of universal prescriptivism, has argued that the rules of logic are independent of grammatical mood, and thus the same logical relations may hold between imperatives as hold between indicatives. Many objections to non-cognitivism based on the linguistic characteristics of what purport to be moral judgments were originally raised by Peter Glassen in "The Cognitivity of Moral Judgments", published in Mind in January 1959, and in Glassen's follow-up article in the January 1963 issue of the same journal.[2] |
「非認知主義に対する」反対論 この節は検証可能な情報源を必要としている。信頼できる情報源をこの節に追加して、記事の改善に協力してほしい。出典のない記述は削除される可能性がある。(2007年3月)(このメッセージの削除方法と時期について) 非認知主義に対する一つの反論は、それが感情的・規範的反応の外的要因を無視している点だ。誰かが「ジョンは良い人格だ」と言う場合、ジョンの何かがその 反応を引き起こしたに違いない。もしジョンが貧しい者に施し、病気の祖母を世話し、他人に親切であり、これらが話者に彼を高く評価させる要因であるなら ば、「ジョンは貧しい者に施し、病気の祖母を世話し、他人に親切であるから良い人格だ」と言うのは妥当である。逆に、話者が貧しい人々に施すという考えに 肯定的に反応する場合、その考えの何らかの側面が肯定的な反応を引き起こしたに違いない。その側面こそが、その考えの良さの根拠でもあると主張できるだろ う。 別の議論として「埋め込み問題」がある。これは倫理的な文がより複雑な文に埋め込まれる問題だ。次の例を考えてみよう: 肉を食べることは間違っていない。 肉を食べるのは悪いことか? 肉を食べるのは悪いと思う。 マイクは肉を食べるのは悪いと思っていない。 かつては肉を食べるのは悪いと思っていた。 彼女は肉を食べるのは悪いと気づいていない。 これらの文を感情主義の枠組みで翻訳しようとすると失敗するようだ(例:「彼女は『肉を食べるのはダメだ!』と気づいていない」)。規範主義的翻訳もわず かにマシな程度だ(「彼女は肉を食べてはいけないと気づいていない」)。こうした構文を形成する行為そのものが、何らかの認知プロセスを示唆している。 非認知主義的立場によれば、これらの文は単に「倫理的命題は真か偽かのいずれかである」という誤った前提を仮定している。文字通り訳せばこうなる: 「肉を食べるのは悪い」は偽の命題だ。 「肉を食べるのは悪いことだ」は真の命題か? 私は「肉を食べるのは悪いことだ」は真の命題だと思う。 マイクは「肉を食べるのは悪いことだ」は真の命題だとは思わない。 私はかつて「肉を食べるのは悪いことだ」は真の命題だと思っていた。 彼女は「肉を食べるのは悪いことだ」が真の命題だと気づいていない。 しかし、これらの訳は人民が実際に言語を使う方法からかけ離れているように見える。非認知主義者は「『肉を食べるのは間違っている』は偽の命題だ」と言う 人格とは意見が合わないだろう(「肉を食べるのは間違っている」は全く真偽を問う対象ではないから)。だが「肉を食べるのは間違っていない」と言う人格に は同意したくなるかもしれない。 より建設的な解釈としては、これらの発言が表している根本的な感情的発言を記述するものとして捉えることができる。つまり:私は肉を食べることを非難する /非難しない、私は以前は非難していた、彼は非難しない、私は非難するが彼女は非難しない、などである。しかし、この解釈は非認知主義そのものというより は、倫理的主観主義に近い。 非認知主義に対する同様の反論として、倫理的議論がある。典型的な論法は「無実の人間を殺すことは常に間違っている。そして全ての胎児は無実の人間であ る。ゆえに胎児を殺すことは常に間違っている」というものだ。多くの人は、この発言がア・プリオリに真である分析命題を表していると考えるだろう。しか し、倫理的命題が認知を表さないなら、それを議論の前提として使うのは奇妙に思える。ましてや、それが真の命題と同じ三段論法の規則に従うと仮定するのは なおさら奇妙だ。しかし普遍的規範主義の提唱者であるR.M.ヘアは、論理の規則は文法上の法(モード)に依存せず、したがって命令形の間にも指示形の間 と同じ論理的関係が成り立つと主張した。 道徳的判断とされるものの言語的特性に基づく非認知主義への多くの反論は、もともとピーター・グラッセンが1959年1月『マインド』誌に掲載した「道徳的判断の認知性」および同誌1963年1月号の続編論文で提起されたものである。[2] |
| Amoralism→Moral nihilism Expressivism Theological noncognitivism Moral realism Moral skepticism Rudolf Carnap Richard Rorty Transcognition |
非道徳主義 表現主義 神学的非認知主義 道徳的現実主義 道徳的懐疑主義 ルドルフ・カルナップ リチャード・ローティ 超越認知 |
| References 1. Garner, Richard T.; Bernard Rosen (1967). Moral Philosophy: A Systematic Introduction to Normative Ethics and Meta-ethics. New York: Macmillan. pp. 219–220. ISBN 0-02-340580-5. 2. Glassen, P., "The Cognitivity of Moral Judgments", Mind 68:57-72 (1959); id. "The Cognitivity of Moral Judgments: A Rejoinder to Miss Schuster", Mind 72:137-140 (1963). |
参考文献 1. Garner, Richard T.; Bernard Rosen (1967). 『道徳哲学:規範倫理学とメタ倫理学への体系的入門』. ニューヨーク: Macmillan. pp. 219–220. ISBN 0-02-340580-5. 2. グラッセン, P., 「道徳的判断の認知性」, 『マインド』68:57-72 (1959); 同著, 「道徳的判断の認知性:シュスター嬢への反論」, 『マインド』72:137-140 (1963). |
| Moral Cognitivism vs. Non-Cognitivism - Stanford Encyclopedia of Philosophy entry by Mark van Roojen. Fieser, James; Dowden, Bradley (eds.). "Non-Cognitivism in Ethics". Internet Encyclopedia of Philosophy. ISSN 2161-0002. OCLC 37741658. rsrevision.com's pages on Metaethics Emotivism, Intuitionism and Prescriptivism with explanations, criticisms, and links. |
道徳的認知主義対非認知主義 - スタンフォード哲学百科事典、マーク・ヴァン・ルーエンによる記事。 ファイザー、ジェームズ、ダウデン、ブラッドリー(編)。「倫理における非認知主義」。インターネット哲学百科事典。ISSN 2161-0002。OCLC 37741658。 rsrevision.com のメタ倫理学に関するページ。感情主義、直観主義、規範主義について、説明、批判、リンクを掲載している。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Non-cognitivism |
★Sinnott-Armstrong, Walter (2023). 「3. 善とは何か?快楽主義対多元主義的帰結主義」. 帰結主義. スタンフォード哲学百科事典.
| What is Good? Hedonistic vs. Pluralistic Consequentialisms |
|
| 一部の道徳理論家は、より基本的な原理や理由が衝突した際に何が正しい
かを決めるには単純さが必要だと仮定するため、単一の単純な基本原理を求める。この仮定は快楽主義を魅力的に見せているようだ。しかし残念ながら、快楽主
義は彼らが想定するほど単純ではない。なぜなら快楽主義者は快楽と苦痛の両方を数えるからだ。快楽は苦痛の不在とは異なり、苦痛は快楽の不在とも異なる。
なぜなら、人民は時に快楽も苦痛も感じず、時に両方を同時に感じるからだ。それでも快楽主義が採用されたのは、競合する見解より単純に見えるためだった。 |
|
| 快楽主義の単純さは反対の根拠にもなった。古典的功利主義における快楽
主義は当初から軽蔑の対象だった。ベンサムやミルの同時代人の中には、快楽主義が人間の生命の価値を動物レベルにまで引き下げると主張する者もいた。なぜ
なら、ベンサムが述べたように、単純なゲーム(ピンポンゲームなど)が高度な知的詩と同等の価値を持つと暗示するからだ。ゲームが同等の快楽を生み出すな
らば(ベンサム
1843)。量的な快楽主義者は、偉大な詩はほとんどの場合、つまらないゲーム(あるいはセックスやドラッグ、ロックンロール)よりも多くの快楽を生み出
すと反論することがある。なぜなら詩の快楽はより確実(あるいは可能性が高い)、持続的(あるいは長続きする)、豊饒(他の快楽につながる可能性が高
い)、純粋(苦痛につながる可能性が低い)などであるからだ。 |
|
| ミルは、押しピンを詩と同等に扱わないために異なる戦略を用いた。彼
は、両方の種類の快楽を経験した人々の選好に基づいて、快楽の質を高いものと低いものとに区別した(ミル 1861, 56; プラトン 1993
および ハッチェソン 1755, 421–23
と比較せよ)。この質的快楽主義は、矛盾しており快楽主義とは認められないという批判を含む、多くの批判に晒されてきた(Moore 1903,
80–81; cf. Feldman 1997, 106–24)。 |
|
| 仮に質的快楽主義が首尾一貫しており、ある種の快楽主義であるとして
も、依然として説得力に欠けるように思えるかもしれない。一部の批判者は、例えばサディストが犠牲者を鞭打つことで得る快楽や、中毒者が薬物から得る快楽
には何の価値もないため、全ての快楽が価値あるとは限らないと主張する。他の反対者は、快楽だけが本質的に価値あるものではないと反論する。なぜなら、快
楽をもたらすか苦痛を回避するかにかかわらず、他のものにも価値があるからだ。例えば、妻が恐ろしい病にかかり、彼女から得られる快楽が減ったとしても、
妻への愛の価値が低下するとは思えない。同様に、自由は不安を生む場合でも、あるいは(祖国を離れるなど)望まないことをする自由であっても、価値がある
ように思える。また、遠くの銀河に関する知識は、それが快楽をもたらすか苦痛を避けるかに関わらず、多くの人々が価値を認めている。 |
|
| 快楽主義に対するこうした反論は、ノジック(1974年、42-45
頁;デ・ブリガード2010年参照)や映画『マトリックス』に登場する体験マシンの話で補足されることが多い。このマシンに乗った人々は、友人と過ごした
り、オリンピックの金メダルやノーベル賞を獲得したり、最愛の恋人と性行為をしたり、あるいは快楽と苦痛のバランスが最大になることをしていると思い込ん
でいる。実際には友人も恋人もおらず、何も達成していないにもかかわらず、体験マシンの利用者は、自らの信念が真実であるかのように同等の快楽を得る。さ
らに、苦痛は全く(あるいはほとんど)感じない。快楽主義者が主張するように、快楽と苦痛だけが重要だとすれば、この機械が信頼できると仮定すれば、自ら
を接続しないのは非合理的と思われるだろう。しかし実際にこの機械に接続することを拒むのは不合理ではない。ゆえに快楽主義は不十分だ。その理由は、快楽
主義が真の友情、知識、自由、達成といった価値を見落としているからだ。経験機械に乗った錯覚の人間には、これら全てが欠けている。 |
|
| 一部の快楽主義者は、この反論は快楽主義の誤解に基づいていると主張す
る。快楽主義者が快楽と苦痛を感覚と捉えるならば、機械はそれらの感覚を再現できるかもしれない。しかし、母親が娘の成績が良くなることを喜ぶという命題
的快楽も存在する。この種の快楽は、快楽の対象となる状態(つまり娘が実際に良い成績を取る状態)が存在する場合にのみ生じる。だが経験機械に接続された
状態では、その関連する状態は実際には存在しない。したがって、感覚的快楽ではなく、あるいはそれに加えて命題的快楽を重視する快楽主義者は、体験マシン
に接続することでより多くの快楽が得られるという主張を否定できる(Feldman 1997, 79–105;
快楽主義の詳細についてはTännsjö 1998およびFeldman 2004も参照)。 |
|
| 関連する立場は、善とは欲望の充足または選好の実現であり、悪とは欲望
や選好の挫折であるという主張に基づく。通常、欲望や選好の対象は感覚ではなく、友人を持つことや目標を達成することといった状況である。もし人が真の友
人や真の達成を望み、欺かれることを望まないのであれば、その人格を体験機械に接続しても欲望の充足は格律されない。この価値理論を採用する功利主義者
は、行為者が道徳的にある行為を行うべきなのは、その行為が欲望満足や選好充足(つまり行為が達成する所望・選好の度合い)を最大化するときに限られると
主張できる。所望・選好の対象が快楽の感覚でない場合、欲望満足や選好充足の最大化は快楽感覚の最大化を必要としない。この立場は通常、選好功利主義と呼
ばれる。 |
|
| 選好功利主義にとっての問題の一つは、個人間の比較をどう行うかである
(この問題は他のいくつかの価値理論でも生じる)。ある人格の選好を知りたい場合、その人格が選択の局面で何を選ぶかを尋ねればよい。しかし、ある人格の
選好が別の人格の選好より強いか弱いかを判断するには、同じ方法を使えない。なぜなら、異なる人々はその決定的な選択局面で異なる選択をする可能性がある
からだ。どちらの選好(あるいは快楽)が強いかを決定する必要がある。なぜなら、ジョーンズはAが行われることをAが行われないことよりも好む(そしてA
が行われることでより多くの快楽を得る)一方で、スミスはAが行われないことを好む(そしてAが行われないことでより多くの快楽を得る)と知っているかも
しれないからだ。Aを行うか行わないかの正しさを判断するには、ジョーンズとスミスの選好の強さ(あるいは各人が望む結果から得る快楽の量)を比較し、A
を行うことか行わないことの総合的な優劣を決められなければならない。功利主義者や結果主義者はこの対人比較の問題を解決する多くの方法を提案してきた
が、どの試みも批判を受けている。この問題に関する議論は今も続いている(最近の議論と参考文献についてはCoakley 2015を参照)。 |
|
| 選好功利主義はまた、一部の選好が誤った情報に基づく、狂気じみてい
る、恐ろしい、あるいは取るに足らないものであるという理由で批判されることが多い。例えば、私はグラスの中の液体をビールだと思い込んで飲むことを好む
かもしれないが、実際は強酸である。あるいは、単に臨床的うつ病であるという理由で死を好むかもしれない。あるいは、子供を拷問することを好むかもしれな
い。あるいは、人生をかけて極小の文字を書く技術を習得することを好むかもしれない。こうした全てのケースにおいて、選好功利主義の反対者は、私の好みが
真に良いものであることを否定できる。選好功利主義者は、治療後も消えない情報に基づいた欲求(Brandt
1979)など、善を構成する選好を限定することで反論できる。しかし、どの選好が善なるものかについて実質的な前提に依存することで理論を循環論法に陥
らせることなく、こうした限定が選好価値論の全問題を解決できるかは不明である。 |
|
| 多くの結果主義者は、全ての価値が快楽や欲望充足といった単一の根拠に
還元できることを否定する。そのため彼らは代わりに多元的な価値理論を採用する。例えばムーアの理想功利主義は、快楽に加えて美や真実(あるいは知識)の
価値を考慮に入れる(Moore 1903, 83–85, 194;
1912)。他の帰結主義者は、友情や愛、自由や能力、正義や公平性、当然の報い、生命、徳といった内在的価値を加える。 |
|
| 認識される価値がすべて個人の福祉に関わる場合、その価値理論は福祉主義的(ウェルファリスト)と呼べる(Sen 1979)。福祉主義的価値理論が古典的功利主義の他の要素と組み合わさると、その結果として生じる理論は福祉主義的帰結主義と呼べる。 |
|
| 非福祉主義的価値理論の一つに完全主義がある。これは特定の状態が、必
ずしも人格の福祉を増進する形で良いとは限らないが、人格の生活を良いものにするという主張である(Hurka 1993,
特に17頁)。この価値理論が古典的功利主義の他の要素と組み合わされると、結果として生じる理論は「完全主義的帰結主義」、あるいはそのアリストテレス
的起源に敬意を表して「幸福主義的帰結主義」と呼ぶことができる。 |
|
| 同様に、ある功利主義者は、ある行為が幸福と能力の両方の関数を格律化するとき、そしてそれのみの場合に正しいと主張する(Sen 1985, Nussbaum 2000)。障害は、痛みを伴うか快楽の喪失を伴うかに関わらず、悪いものと見なされる。 |
|
| あるいは、ある行為が特定の道徳的権利の充足(または侵害の最小化)を
格律化するとき、それが正しいと主張することもできる。こうした理論は時に権利功利主義と称される。このアプローチは、権利を幸福や他の価値と対比して評
価する完全な帰結主義に組み込むことも、あるいは権利侵害の負の価値を他のあらゆる損失や害よりも語彙的に上位に位置付けることも可能である(cf.
ロールズ 1971,
42)。結果主義的道徳理論におけるこのような語彙的順位付けは、幸福や権利以外の価値のために権利を侵害することが決して正当化されないという結果をも
たらす。ただし、他の権利侵害を回避または防止するために、一部の権利侵害を許容することは依然として可能である。 |
|
| 結果主義者が様々な価値を取り入れる場合、各価値を相互に順位付けまた
は比較衡量する必要がある。これはしばしば困難である。結果主義者の中には、特定の価値は、その価値を比較することが不可能であるという点で、共約不可能
性あるいは比較不可能なものであるとさえ主張する者もいる(Griffin 1986、Chang
1997)。この立場により、結果主義者は、解決不可能な道徳的ジレンマの可能性を認識することができる(Sinnott-Armstrong
1988, 81; Railton 2003, 249–91)。 |
|
| 価値に関する多元主義は、結果主義者が快楽主義的功利主義を悩ませてい
る多くの問題に対処することも可能にする。例えば、反対派は、古典的功利主義者は、苦痛が生じたり快楽が失われたりしない場合、約束を守り、嘘をつかない
という私たちの義務を説明できないと非難することが多い。快楽主義者がこの課題に対応できるかどうかに関わらず、多元主義者は、知識は本質的に良いもので
あり、誤った信念は本質的に悪いものであると主張することができる。すると、欺瞞が誤った信念を引き起こすならば、欺瞞は手段的に悪い行為であり、たとえ
嘘が苦痛や快楽の損失をもたらさなくても、正当な理由なく嘘をつくべきではない。嘘をつくことは欺く試みであり、嘘をつくことは(打ち消す要因がない限
り)道徳的に悪いことを行おうとする試みだからだ。同様に、ある行為を行うという約束が、約束者がその行為を行うと聴衆に信じさせる試みであるならば、約
束を破ることは、約束者が作り出した、あるいは作り出そうとした信念を虚偽にする行為である。説明はさらに続くが、虚偽の信念の価値の低さは、約束を破る
ことがなぜ道徳的に間違っているのかについての結果主義的な説明の一部となり得る。 |
|
| こうした多元主義的な帰結主義が福祉主義的でない場合、一部の哲学者は
それを功利主義とは呼ばない。しかしこの用法は統一されておらず、非福祉主義的見解さえ功利主義と呼ばれることがある。呼称はどうあれ、重要な点は帰結主
義や古典的功利主義の他の要素が、何が善か価値あるものかに関する多様な理論と両立し得るということだ。 |
|
| 多元主義に転換する代わりに、結果主義者の中には価値の集計を放棄する
者もいる。古典的功利主義は、結果の各部分における価値を合計して、どの結果の集合が最も価値が高いかを決定した。その代わりに、個人ごとに善を合計する
ことはできるが、別々の個人の善を合計することはできない(ロバーツ
2002)。あるいは、個人ごとの合計を含め、すべての合計を放棄し、その代わりに、世界や結果の部分の価値を合計することなく、行為によって引き起こさ
れる世界や結果の集合全体をランク付けすることもできる。この動きの動機の一つは、ムーアの有機的統一の原則(Moore 1903,
27–36)である。これは、2つ以上のものの組み合わせ、つまり「有機的統一」の価値は、組み合わせられたものの価値を単純に足して計算することはでき
ないと主張する。例えば、犯罪者への刑罰が苦痛をもたらす場合でも、功利主義者は、刑罰の苦痛という負の価値にこの正義の価値を加算することなく、犯罪と
刑罰が共存する世界が、犯罪のみ存在する世界よりも優れていると主張し得る。おそらく前者の方がより多くの正義を含むからである。同様に、人民が不当な快
楽を得ない世界は、たとえその快楽の価値を他の価値に加算して総和を算出しない判断であっても、より良い世界に見えるかもしれない。こうした事例から、結
果主義者の一部は、道徳的正しさが行為の特定の結果の価値を集計する関数ではないと否定する。代わりに彼らは、ある行為の結果として生じる世界全体と、そ
の行為を行わない結果として生じる世界全体を比較する。前者がより良い場合、その行為は道徳的に正しいとされる(J.J.C. Smart 1973,
32; Feldman 1997, 17–35)。このアプローチは全体論的帰結主義あるいは世界帰結主義と呼べる。 |
|
| 価値間の関係を組み込む別の方法は、分配を考慮することだ。大多数が貧
困に陥るが、少数の幸運な者が膨大な財を独占する結果と、総財はわずかに少ないが全員がほぼ同等の財を得る結果を比較する。古典的功利主義に対する平等主
義的批判は、後者の結果が優れていると主張する。つまり総財量以上の要素が重要だというのだ。後者の結果を好む伝統的な快楽主義的功利主義者は、限界効用
の逓減の原理に訴えて財の平等分配を正当化しようとする。しかし他の結果主義者は、より強固な平等へのコミットメントを取り入れる。初期のシジウィック
(1907,
417)は、他の価値間の同値状態を解消する手段として分配を考慮に入れることで、こうした反論に応えた。近年では、結果主義者の一部が、どの結果が最善
かを判断する基準に、公平性(Broome 1991, 192–200)や功績(Feldman 1997,
154–74)の概念を加えている(Kagan 1998,
48–59も参照)。また、より悪い状況にある人民により重きを置く優先主義に目を向ける者もいる(Adler and Norheim 2022,
Arneson 2022)。こうした結果主義者は単に価値を合計するのではなく、パターンを考察する。 |
|
| 人口変動に関連する問題が生じる。政府が人口増加抑制のため無料避妊具
の提供を検討していると仮定しよう。無料避妊具がなければ、過密状態が飢餓や疾病、苦痛をもたらし、人格の状態で悪化する。それでも、新たに生まれる人格
が十分な快楽やその他の利益を得るため、総効用は人口増加に伴って増加する。古典的功利主義は総効用に焦点を当てるため、この政府は無料避妊具を提供すべ
きでないことを示唆しているように見える。これは多くの功利主義者にとって不合理に思える。この結論を回避するため、一部の功利主義者は「行為の結果が代
替案よりも苦痛(その他の不利益)を多く含む場合、その行為は道徳的に誤りである」と主張する(R. N. Smart
1958年参照)。この否定的功利主義によれば、政府は避妊具を提供すべきだ。なぜならその政策は苦痛(その他の不利益)を減少させるからであり、たとえ
総快楽(その他の利益)を減少させるとしてもである。しかし残念なことに、否定的功利主義は同時に、政府は可能な限り全ての人民を苦痛なく殺すべきだと示
唆しているように見える。死者は苦痛を感じず(誤った信念や疾病、障害も持たない——ただし殺害は能力の喪失を引き起こす)。より一般的な対応策として平
均功利主義があり、最良の結果とは平均効用が最も高い結果だとする(cf. ロールズ 1971,
161–75)。避妊プログラムを実施しない場合と比べて、実施した方が平均効用は高くなる。したがって平均功利主義はより妥当な結論、すなわち政府は避
妊プログラムを採用すべきだという結果を導く。批判者は「最悪の境遇にある者を殺すことで平均効用も高められる」と主張することがあるが、この主張は全く
明確ではない。なぜならそのような殺害は全員を危険に晒すからだ(最悪の境遇の者が殺された後、別の集団が新たな最悪の境遇となり、次に彼らが殺される可
能性があるため)。とはいえ、平均功利主義自体にも問題がある(例えばパーフィット1984年、第19章の「単なる付加のパラドックス」など)。いずれに
せよ、多元主義者であるか否かにかかわらず、全ての結果主義者は、道徳的正しさが総体的な善の最大化に依存するのか、平均的な善の最大化に依存するのかを
決定しなければならない。 |
|
| 結果主義者の価値論に対する最終的な挑戦は、ギーチ1956年に端を発
し、トムソン2001年によって主張された。トムソンは「Aは良いXである」(例えば良い毒)が「Aは良い」を意味しないため、「良い」という語は修飾形
容詞であり、限定なしに正当に使用できないと論じる。この見解によれば、何かを「善い」と呼ぶのは、それが誰かにとって善い、あるいは何らかの点で善い、
何らかの用途において善い、何らかの活動において善い、あるいは何らかの種類の事例として善いという意味でない限り、無意味である。結果主義者は、総体的
な結果や平均的な結果、あるいは世界全体が、そのような限定なしに善いと言うとき、この制約に違反していると見なされる。しかし、結果主義者は、「良い」
という用語は、その形容詞的な用法に加えて、述語的な用法もある、あるいは、世界や結果の全体を「良い」と呼ぶ場合、結果や世界にとって「良い」と呼んで
いる、と反論することができる(Sinnott-Armstrong
2003a)。そうであれば、「良い」が形容詞としてよく使われるという事実は、結果主義者にとって何の問題も生じない。 |
|
| https://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/#WhatGoodHedoVsPlurCons |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆