サムエル・フォン・プフェンドルフ
Samuel von Pufendorf, 1632-1694
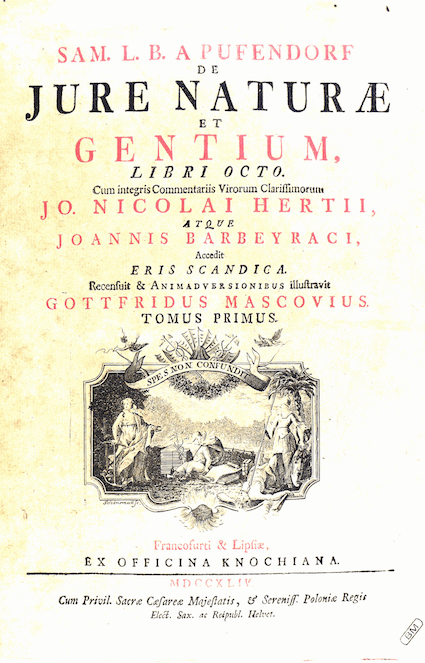

サムエル・フォン・プフェンドルフ
Samuel von Pufendorf, 1632-1694
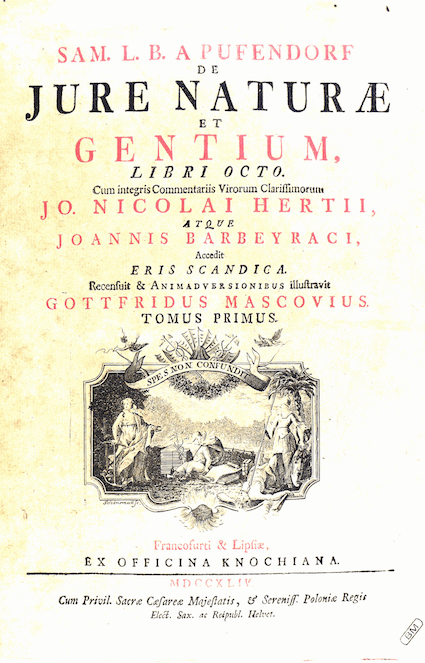

★サミュエル・プーフェンドルフ(プフェンドルフ)Samuel Freiherr von Pufendorf, 1632年1月8日 - 1694年10月26日)は、ドイツの法学者、政治哲学者、経済学者、歴史家である。1694年、62歳で亡くなる数カ月前にスウェーデン王チャールズ 11世から男爵に叙せられ、サミュエル・プーフェンドルフとして生まれた。ホッブズやグロティウスの自然法学説の解説と修正を行った
| Samuel Freiherr von
Pufendorf (8 January 1632 – 26 October 1694) was a German jurist,
political philosopher, economist and historian. He was born Samuel
Pufendorf and ennobled in 1694; he was made a baron by Charles XI of
Sweden a few months before his death at age 62. Among his achievements
are his commentaries and revisions of the natural law theories of
Thomas Hobbes and Hugo Grotius. His political concepts are part of the cultural background of the American Revolution. Pufendorf is seen as an important precursor of Enlightenment in Germany. He was involved in constant quarrels with clerical circles and frequently had to defend himself against accusations of heresy, despite holding largely traditional Christian views on matters of dogma and doctrine.[1] |
Samuel Freiherr von Pufendorf,
1632年1月8日 -
1694年10月26日)は、ドイツの法学者、政治哲学者、経済学者、歴史家である。1694年、62歳で亡くなる数カ月前にスウェーデン王チャールズ
11世から男爵に叙せられ、サミュエル・プーフェンドルフとして生まれた。ホッブズやグロティウスの自然法学説の解説と修正を行ったのが彼の業績のひとつ
である。 彼の政治思想は、アメリカ独立の文化的背景の一部となっている。 プフェンドルフは、ドイツにおける啓蒙主義の重要な先駆者と見なされている。彼は教義や教理に関してほぼ伝統的なキリスト教の見解を持っていたにもかかわ らず、聖職者界と絶えず争い、しばしば異端の告発から身を守る必要に迫られた[1]。 |
| Early life He was born at Dorfchemnitz in the Electorate of Saxony. His father Esaias Elias Pufendorf from Glauchau was a Lutheran pastor, and Samuel Pufendorf himself was destined for the ministry. Educated at the Fürstenschule at Grimma, he was sent to study theology at the University of Leipzig. The narrow and dogmatic teaching was repugnant to Pufendorf, and he soon abandoned it for the study of public law. Leaving Leipzig altogether, Pufendorf relocated to University of Jena, where he formed an intimate friendship with Erhard Weigel, the mathematician, whose influence helped to develop his remarkable independence of character. Under the influence of Weigel, he started to read Hugo Grotius, Thomas Hobbes and René Descartes. Pufendorf left Jena in 1658 as Magister and became a tutor in the family of Peter Julius Coyet, one of the resident ministers of King Charles X Gustav of Sweden, at Copenhagen with the help of his brother Esaias [de], a diplomat in the Swedish service. At this time, Charles was endeavoring to impose an unwanted alliance on Denmark. In the middle of the negotiations he opened hostilities and the Danes turned with anger against his envoys. Coyet succeeded in escaping, but the second minister, Steno Bielke, and the rest of the staff were arrested and thrown into prison. Pufendorf shared this misfortune, and was held in captivity for eight months. He occupied himself in meditating upon what he had read in the works of Hugo Grotius and Thomas Hobbes, and mentally constructed a system of universal law. At the end of his captivity, he accompanied his pupils, the sons of Coyet, to the University of Leiden. |
幼少期 ザクセン選帝侯のドルフケムニッツに生まれる。グラウハウ出身の父エシアス・プフェンドルフはルター派の牧師であり、プフェンドルフ自身も聖職に就くこと を希望していた。 プーフェンドルフはグリムマ大学付属学校で教育を受け、ライプツィヒ大学で神学を学ぶことになった。しかし、狭量で教条的な教えはプーフェンドルフには受 け入れられず、すぐに放棄して法律を学ぶことにした。 ライプツィヒを離れ、イエナ大学に移ったプーフェンドルフは、数学者のエアハルト・ヴァイゲルと親交を深め、その影響により、卓越した独立した人格を持つ に至った。ヴァイゲルの影響で、フーゴー・グロティウス、トマス・ホッブズ、ルネ・デカルトなどを読み始める。 プーフェンドルフは1658年にマジスターとしてイエナを離れ、スウェーデン王シャルル10世グスタフの駐在公使の一人、ピーター・ユリウス・コイエの家 の家庭教師となり、スウェーデン勤務の外交官である兄エセイアス[ド]の助けも借りてコペンハーゲンに赴任した。 この頃、シャルルはデンマークに望まぬ同盟を押し付けようと試みていた。交渉の途中で彼は敵対行為を開始し、デンマーク人は怒りに燃えて彼の使節団に敵対 した。コワイエは脱出に成功したが、第二公使ステノ・ビエルケをはじめとする幕僚たちは逮捕され、牢獄に入れられた。プーフェンドルフも同じ目に遭い、 8ヵ月間牢獄に入れられた。彼は、グロティウスやホッブズの著作を読み、普遍的な法体系を構築することに没頭していた。監禁が終わると、彼は弟子であるコ イエの息子たちを連れてライデン大学に入学した。 |
| At Leiden, he was permitted to
publish, in 1660, the fruits of his reflections under the title of
Elementa jurisprudentiae universalis libri duo ("Elements of Universal
Jurisprudence: Two Books"). The work was dedicated to Charles Louis,
elector palatine, who created for Pufendorf a new chair at the
University of Heidelberg, that of the law of nature and nations. This
professorship was first of its kind in the world. Pufendorf married
Katharina Elisabeth von Palthen, the widow of a colleague, in 1665. In 1667 he wrote, with the assent of the elector palatine, a tract De statu imperii germanici liber unus ("On the Present State of the German Empire: One Book"). Published under the cover of a pseudonym at Geneva in 1667, it was supposed to be addressed by a gentleman of Verona, Severinus de Monzambano, to his brother Laelius. The pamphlet caused a sensation. Its author directly challenged the organization of the Holy Roman Empire, denounced in the strongest terms the faults of the house of Austria, and attacked with vigour the politics of the ecclesiastical princes. Before Pufendorf, Bogislaw Philipp von Chemnitz [de], publicist and soldier, had written, under the pseudonym of "Hippolytus a Lapide", De ratione status in imperio nostro romano-germanico ("On The Reason of the Present State in Our Holy Roman Empire"). Inimical, like Pufendorf, to the Austrian House of Habsburg, Chemnitz had gone so far as to make an appeal to France and Sweden. Pufendorf, on the contrary, rejected all idea of foreign intervention, and advocated that of national initiative. When Pufendorf went on to criticise a new tax on official documents, he did not get the chair of law and had to leave Heidelberg in 1668. Chances for advancement were few in a Germany that still suffered from the ravages of the Thirty Years' War (1618-1648), so Pufendorf went to Sweden where that year he was called to the University of Lund. His sojourn there was fruitful. In 1672 appeared De jure naturae et gentium libri octo ("On The Law of Nature of Nations: Eight Books") and of, and in 1673 a résumé of it under the title De officio hominis et civis iuxta legem naturalem ("On the Duty of Man and Citizen, according to Natural Law"), which, among other topics, gave his analysis of just war theory. In De jure naturae et gentium Pufendorf took up in great measure the theories of Grotius and sought to complete them by means of the doctrines of Hobbes and of his own ideas on jus gentium ("Law of Man"). His first important point was that natural law does not extend beyond the limits of this life and that it confines itself to regulating external acts. He disputed Hobbes's conception of the state of nature and concluded that the state of nature is not one of war but of peace. But this peace is feeble and insecure, and if something else does not come to its aid it can do very little for the preservation of mankind. As regards public law Pufendorf, while recognizing in the state (civitas) a moral person (persona moralis), teaches that the will of the state is but the sum of the individual wills that constitute it, and that this association explains the state. In this a priori conception, in which he scarcely gives proof of historical insight, he shows himself as one of the precursors of Rousseau and of the Contrat social. Pufendorf powerfully defends the idea that international law is not restricted to Christendom, but constitutes a common bond between all nations because all nations form part of humanity. In 1677 Pufendorf was called to Stockholm as Historiographer Royal. To this new period belong Einleitung zur Historie der vornehmsten Reiche und Staaten ("Introduction to the History of the Most Distinguished Kingdoms and States" as well as Commentarium de rebus suecicis libri XXVI., ab expeditione Gustavi Adolphi regis in Germaniam ad abdicationem usque Christinae and De rebus a Carolo Gustavo gestis. In his historical works, Pufendorf wrote in a very dry style, but he professed a great respect for truth and generally drew from archival sources. However, his historical works were heavily pro-Swedish and he supported the claim that eastern Denmark was originally Swedish. In 1658 Denmark was forced to cede the eastern provinces of Skåne (Scania), Halland, and Blekinge (plus some Norwegian territories) to Sweden. Pufendorf defended this move and insisted that these provinces were "reunited" with Sweden and that the Scanian provinces had always belonged to "Götaland". He wrote that "Sweden’s old borders have been healed again".[2] In De habitu religionis christianae ad vitam civilem he traces the limits between ecclesiastical and civil power. This work propounded for the first time the so-called "collegial" theory of church government (Kollegialsystem), which, developed later by the learned Lutheran theologian Christoph Matthäus Pfaff [de], formed the basis of the relations of church and state in Germany and more especially in Prussia. |
ライデンでは、1660年に彼の考察の成果を「Elementa
jurisprudentiae universalis libri
duo」(「普遍的法学の要素:2冊」)という題名で出版することが許された。この著作は、プーフェンドルフのためにハイデルベルク大学に自然法・国家法
の新しい講座を創設したパラティーヌ選帝侯シャルル・ルイに献呈された。この教授職は世界で初めてのものだった。1665年、プーフェンドルフは同僚の未
亡人カタリーナ・エリザベス・フォン・パルテンと結婚した。 1667年、プーフェンドルフはドイツ帝国総選挙官の同意を得て、『ドイツ帝国の現状について:一冊の本』を執筆した。1667年、ジュネーヴで偽名を 使って出版されたこの小冊子は、ヴェローナの紳士セヴェリヌス・デ・モンザンバーノが兄のラエリウスに宛てたものとされた。この小冊子はセンセーションを 巻き起こした。その著者は神聖ローマ帝国の組織に真っ向から異議を唱え、オーストリア家の欠点を最も強い言葉で非難し、教会系の諸侯の政治を激しく攻撃し た。プーフェンドルフ以前には、宣伝家であり軍人でもあったボギスラフ・フィリップ・フォン・ケムニッツ[de]が、「ヒッポリュトス・ア・ラピデ」のペ ンネームで『我が神聖ローマ帝国の現状に関する理由』(De ratione status in imperio nostro romano-germanico )を執筆している。ケムニッツはプーフェンドルフ同様、オーストリア・ハプスブルク家に敵対し、フランスやスウェーデンにまで働きかけていた。これに対し てプーフェンドルフは、外国の介入を一切否定し、国家主導の介入を主張した。 プーフェンドルフが公文書への新しい課税を批判したため、彼は法学部の椅子を得ることができず、1668年にハイデルベルクを去らざるを得なかった。三十 年戦争(1618-1648)の傷跡が残るドイツでは出世のチャンスは少なく、プフェンドルフはスウェーデンに渡り、その年にルンド大学に召集されること になった。ルンド大学での生活は実り多いものであった。 1672年に『De jure naturae et gentium libri octo』(『国家の自然法:8冊』)と『De officio hominis et civis iuxta legem naturalem』(『自然法に従う人間と市民の義務について』)の題で、1673年にその要約を出版し、とりわけ正戦論について分析を行っている。 De jure naturae et gentium』では、グロティウスの理論を大幅に取り入れ、ホッブズの教義と彼自身のjus gentium(「人間の法」)についての考えによって、その完成を目指した。彼の最初の重要な指摘は、自然法は現世の限界を超えることはなく、外的行為 の規制に限定されるということであった。彼はホッブズの自然状態の概念に異議を唱え、自然状態は戦争ではなく、平和のものであると結論づけた。しかし、こ の平和は弱く、不安定であり、何か他のものが助けに来なければ、人類の維持のためにほとんど何もできないのである。 公法に関しては、プーフェンドルフは、国家(civitas)に道徳的人間(persona moralis)を認めながら、国家の意志は、それを構成する個々の意志の総和にすぎず、この連合が国家を説明すると教えている。この先験的な概念におい て、彼は歴史的な洞察力をほとんど証明することなく、ルソーと社会契約の先駆者の一人として自らを示している。プーフェンドルフは、国際法はキリスト教に 限定されるものではなく、すべての国が人類の一部を構成していることから、すべての国の間の共通の絆を構成しているという考えを力強く擁護している。 1677年、プーフェンドルフはストックホルムに王室史料編纂者として呼ばれた。この新しい時代に、Einleitung zur Historie der vornehmsten Reiche und Staaten(「最も著名な王国と国家の歴史への序論」)とCommentarium de rebus suecicis libri XXVI., ab expeditione Gustavi Adolphi regis in Germaniam ad abdicationem usque Christinaeと De rebus a Carolo Gustavo gestisが属することになった。プーフェンドルフの歴史書は、非常に乾いた文体で書かれているが、真実に対する尊敬の念を公言しており、一般に記録さ れた資料から引用している。しかし、彼の歴史書はスウェーデンびいきで、東デンマークがもともとスウェーデン人であったという主張を支持した。1658 年、デンマークは東部のスコーネ(スカニア)、ハランド、ブレキンゲの各州(および一部のノルウェー領)をスウェーデンに割譲することを余儀なくされた。 プーフェンドルフはこの動きを擁護し、これらの州はスウェーデンに「再統一」され、スカーンの州は常に「ヨータランド」に属していたと主張した。De habitu religionis christianae ad vitam civilem』では、教会権力と市民権力の間の限界について述べている[2]。この著作は、いわゆる「合議制」の教会統治理論 (Kollegialsystem)を初めて提唱し、後に学識あるルター派の神学者クリストフ・マテウス・プファフ[de]によって発展し、ドイツ、特に プロイセンにおける教会と国家の関係の基礎を形成することとなる。 |
| This theory makes a fundamental
distinction between the supreme jurisdiction in ecclesiastical matters
(Kirchenhoheit or jus circa sacra), which it conceives as inherent in
the power of the state in respect of every religious communion, and the
ecclesiastical power (Kirchengewalt or jus in sacra) inherent in the
church, but in some cases vested in the state by tacit or expressed
consent of the ecclesiastical body. The theory was of importance
because, by distinguishing church from state while preserving the
essential supremacy of the latter, it prepared the way for the
principle of toleration. It was put into practice to a certain extent
in Prussia in the 18th century; but it was not till the political
changes of the 19th century led to a great mixture of confessions under
the various state governments that it found universal acceptance in
Germany. The theory, of course, has found no acceptance in the Roman
Catholic Church, but it nonetheless made it possible for the Protestant
governments to make a working compromise with Rome in respect of the
Roman Catholic Church established in their states. In 1688 Pufendorf was called into the service of Frederick William, Elector of Brandenburg. He accepted the call, but he had no sooner arrived than the elector died. His son Frederick III fulfilled the promises of his father; and Pufendorf, historiographer and privy councillor, was instructed to write a history of the Elector Frederick William (De rebus gestis Frederici Wilhelmi Magni). The King of Sweden continued to testify his goodwill towards Pufendorf, and in 1694 created him a baron. In the same year while still in Sweden, Pufendorf suffered a stroke, and died on 26 October 1694[3] in Berlin. He was buried in the church of St Nicholas, where an inscription to his memory is still to be seen. He was succeeded as historiographer in Berlin by Charles Ancillon. |
こ
の理論は、教会に関する最高司法権(Kirchenhoheit or jus circa
sacra)を、あらゆる宗教的共同体に関して国家権力に内在すると考え、教会に内在するが、教会団体の暗黙の同意や表明によって国家に帰属する場合もあ
る教会的権力(Kirchengewalt or jus in
sacra)を根本的に区別するものであった。この理論は、教会と国家を区別する一方で、後者の本質的な優位性を維持することによって、寛容の原則への道
を開くという点で重要であった。この理論は、18世紀にプロイセンである程度実践された。しかし、19世紀の政治的変化によって、さまざま
な州政府のもとで多くの信条が混在するようになってから、ドイツで普遍的に受け入れられるようになったのである。もちろん、この理論はローマ・カトリック
教会には受け入れられなかったが、それにもかかわらず、プロテスタント政府は、自分たちの国に設立されたローマ・カトリック教会に関して、ローマとうまく
妥協することができるようになったのである。 1688年、プフェンドルフはブランデンブルク選帝侯フリードリヒ・ヴィレムの召集を受けることになった。プーフェンドルフはこの召集を受けたが、到着す るやいなや、選帝侯は死去した。息子のフリードリヒ3世は父の約束を果たし、歴史学者で枢密顧問官であったプーフェンドルフは、選帝侯フリードリヒ・ウィ リアムの歴史(De rebus gestis Frederici Wilhelmi Magni)を書くように指示された。 スウェーデン王はプーフェンドルフに好意を示し続け、1694年に彼を男爵に任命した。同年、スウェーデン滞在中に脳卒中で倒れ、1694年10月26日 にベルリンで死去した[3]。彼は聖ニコラウス教会に埋葬され、そこには彼を偲ぶ碑文が残されている。ベルリンの歴史学者としては、シャルル・アンシロン が後を継いだ。 |
| De iure naturae et gentium In 1672 appeared De iure naturae et gentium. This work took largely the theories of Grotius and many ideas from Hobbes, adding to them Pufendorf's own ideas to develop the law of nations. Pufendorf argues that natural law does not extend beyond the limits of this life and merely regulates only external acts. He also challenges the Hobbesian thesis of a state of nature which is a state of war or conflict. For Pufendorf too there is a state of nature, but it is a state of peace. This natural peace, however, is weak and uncertain. In terms of public law, which recognizes the state (civitas) as a moral person (persona moralis), Pufendorf argues that the will of the state is nevertheless nothing more than the sum of the individual wills that are associated within it; hence the state needs to submit to a discipline essential for human safety. This 'submission', in the sense of obedience and mutual respect, is for Pufendorf the fundamental law of reason, which is the basis of natural law. He adds that international law should not be limited or restricted only to the Christian nations, but must create a common link between all peoples, since all nations are part of humanity. |
自然の摂理と神の摂理 1672年、『De iure naturae et gentium』が出版された。この著作は、グロティウスの学説とホッブズの多くの思想を大きく取り入れ、それにプーフェンドルフ独自の思想を加えて、国 家法を発展させたものである。プーフェンドルフは、自然法は現世の限界を超えるものではなく、単に外的行為のみを規制するものであると主張する。また、戦 争や紛争の状態である自然状態というホッブズのテーゼに挑戦している。プーフェンドルフにとっても自然状態は存在するが、それは平和の状態である。しか し、この自然の平和は弱く、不確かである。国家(civitas)を道徳的人間(persona moralis)として認識する公法の観点から、プーフェンドルフは、国家の意志は、それにもかかわらず、その内部に関連する個々の意志の総和に他なら ず、それゆえ国家は、人間の安全のために不可欠な規律に服従しなければならないと主張する。従順と相互尊重という意味でのこの「服従」は、プフェンドルフ にとって、自然法の基礎となる理性の基本法である。そして、国際法はキリスト教国だけに限定されたものであってはならず、すべての国家が人類の一部である 以上、すべての民族の間に共通のつながりを作り出すものでなければならない、と付け加えるのである。 |
| De Officio Hominis et Civis
Juxta Legem Naturalem In De Officio Hominis et Civis Juxta Legem Naturalem ("On the Duty of Man and Citizen"), Pufendorf divides duties into several categories: duties towards God, duties towards oneself, and various forms of duty towards others. Duties towards oneself were classified as "duties of the soul", such as developing skills and talents, and "duties of the body", which involve not doing harm to oneself.[4][5] |
人間と市民の義務』(De Officio Hominis et
Civis Juxta Legem Naturalem プーフェンドルフは『De Officio Hominis et Civis Juxta Legem Naturalem』(「人間と市民の義務について」)において、義務を神に対する義務、自分に対する義務、他人に対する様々な義務に分類している。自分 に対する義務は、技術や才能を磨くなどの「魂の義務」と、自分を傷つけないという「身体の義務」に分類された[4][5]。 |
| John Locke, Jean-Jacques
Rousseau, and Denis Diderot all recommended Pufendorf's inclusion in
law curricula, and he greatly influenced Blackstone and Montesquieu. Pufendorf's feuds with Leibniz diminished his reputation. Pufendorf and Leibniz shared many theological views, but differed in their philosophical foundation, with Pufendorf leaning toward Biblical fundamentalism.[1] It was on the subject of the pamphlet of Severinus de Monzambano that their quarrel began. Leibniz once dismissed him as "Vir parum jurisconsultus, minime philosophus" ("A man barely a jurist, let alone a philosopher").[1] |
ジョン・ロック、ジャン・ジャック・ルソー、ドゥニ・ディドロは、プ
フェンドルフを法学のカリキュラムに加えることを推奨し、ブラックストーンやモンテスキューに大きな影響を与えた。 プフェンドルフは、ライプニッツとの確執から、その名声を落とすことになる。プフェンドルフとライプニッツは多くの神学的見解を共有していたが、哲学的基 盤は異なり、プフェンドルフは聖書原理主義に傾いていた[1]。二人の喧嘩の発端は、セヴェリヌス・デ・モンザンバーノの小冊子をめぐるものであった。ラ イプニッツは彼を「Vir parum jurisconsultus, minime philosophus」(「哲学者どころか、ほとんど法学者でない男」)と一蹴している[1]。 |
| Craig L. Carr (ed.), The
Political Writings of Samuel Pufendorf (Oxford 1994) Elementorum iurisprudentiae universalis (1660) von Pufendorf, Samuel (1660). Elementorum Iurisprudentiae Universalis libri duo [Elements of Universal Jurisprudence] (in Latin). Haga Comitum: Adriani Vlacq. von Pufendorf, Samuel (1663). De Obligatione Adversus Patriam (in Latin). Heidelbergae: Wyngaerden. De rebus gestis Philippi Augustae (1663) von Pufendorf (alias de Monzambano), Samuel (alias Severinus) (1667). De statu imperii Germanici ad Laelium fratrem, Dominum Trezolani, liber unus (in Latin). Geneva: Petrum Columesium. De statu imperii Germanici (Amsterdam 1669) von Pufendorf, Samuel (1672). De Jure Naturae Et Gentium Libri Octo [On the Law of Nature and of Nations] (in Latin). Londini Scanorum: Junghans. von Pufendorf, Samuel (1673). De Officio Hominis et Civis Juxta Legem Naturalem [On the Duty of Man and Citizen According to Natural Law] (in Latin). Londini Scanorum: Junghans. OCLC 759611925. English translation: von Pufendorf, Samuel (1927). De Officio Hominis et Civis Juxta Legem Naturalem Libri Duo [On the Duty of Man and Citizen According to Natural Law]. Translated by Moore, Frank Gardner. New York: Oxford University Press. OCLC 1110799161. von Pufendorf, Samuel (1683). Einleitung zu der Historie der Vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden (in German). Franckfurt am Mayn: Knoch. Commentarium de rebus suecicis libri XXVI., ab expeditione Gustavi Adolphi regis in Germaniam ad abdicationem usque Christinae De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege gestis commentariorum (Stockholm 1679) von Pufendorf, Samuel (1695). De Rebus Gestis Friderici Wilhelmi Magni, Electoris Brandenburgici, Commentariorum Libri Novendecim (in Latin). Vol. I. Berolini: Schrey. von Pufendorf, Samuel (1695). De Rebus Gestis Friderici Wilhelmi Magni, Electoris Brandenburgici, Commentariorum Libri Novendecim (in Latin). Vol. II. Berolini: Schrey. |
|
| 『自
然法にもとづく人間と市民の義務』 (近代社会思想コレクション) 前田俊文訳. 京都大学学術出版会, 2016 |
|
+++
Links
リンク
文献
その他の情報


