ドゥルーズ用語集
le froid et la cruel per Gilles Deleuze
ドゥルーズ用語集
le froid et la cruel per Gilles Deleuze
☆【ドゥルーズさんはどんな人?】ジル・ドゥ ルーズ(Gilles Deleuze) はフランスの哲学者で、1925年1月18日にパリ17区1で生まれ、1995年11月4日に同じパリ17区で自殺した。1960年代から亡くなるまで、 ドゥルーズは哲学そのもの、文学、政治、精神分析、映画、絵画について、影響力のある複雑な哲学的著作を残した。1988年に引退するまで、哲学の著名な 大学教授でもあった。 デイヴィッド・ヒューム、フリードリヒ・ニーチェ、イマヌエル・カント、バルーク・スピノザ、 アンリ・ベルクソンなど、さまざまな哲学者についての著作が ある。とはいえ、大学生活の終わりには哲学史に戻り、ミシェル・フーコー、フランソワ・シャトレ、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツの著作に傾 倒した。 彼の哲学論文は「差異」と「反復」の概念、すなわち同一と類似、コピーと二重の関係、オリジナルとの関係における無限反復の効果に焦点を当てた。彼は、形 而上学者であり数学者でもあったゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツを参考にした。その中でドゥルーズは……(→「ジル・ドゥルーズ 1.0」)
☆【ドゥルーズに対する固定的偏見から自由になる】
國分功一郎さん(2025)は、ドゥルーズのこれまでの古典的イメージから自由になることとしていくつかの「見方の変更」を示唆している:1)ドゥルーズはつねに(とくにガタリとの共著のなかで)政治的に語り、政治的に語ろうとしてる[政治的ドゥルーズ]——ジジェクはドゥルーズを政治的に読むのはネグリやハートなどのスピノザを政治理論として引き出したい連中の偏見であり、ドゥルーズの著作のなかに過剰に政治的メッセージを読み込んでいると批判している、2)ドゥルーズはスピノザ学者である、あるいは、スピノザ哲学に対して大きな貢献をおこなった学者である。3)「アンチ・オイディプス」「千のプラトー」「哲学とは何か」「カフカ」などの共著から、二者合体したドゥルーズ=ガタリという合体サイボーグ(こう言っているのは引用者)なのにかかわらず、そこにドゥルーズだけを読み取る偏見をやめよ(國分さんは一緒の著作から「この哲学者(ドゥルーズ)」を引き離せと主張する。ただし、ガタリにも配慮してそのことが「ガタリの貢献を最大限に評価する」國分 2025:344、と言っているが、それは当該の本はドゥルーズ解説本だからである)。結局のところ、よーするにこのような國分(2025)さんのまとめもまた、國分派ドゥルーズというトルソに魂を入れる創造的行為なのではあるが。
| Immanence |
内在 |
Immanence, meaning
residing or becoming within, generally offers a relative opposition to
transcendence, that which extends beyond or outside. Deleuze "refuses
to see deviations, redundancies, destructions, cruelties or contingency
as accidents that befall or lie outside life; life and death [are]
aspects of desire or the plane of immanence."[1] This plane is a pure
immanence which is an unqualified immersion or embeddedness, an
immanence which denies transcendence as a real distinction, Cartesian
or otherwise. Pure immanence is thus often referred to as a pure plane,
an infinite field or smooth space without substantial or constitutive
division. In his final essay entitled Immanence: A Life, Deleuze wrote:
"It is only when immanence is no longer immanence to anything other
than itself that we can speak of a plane of immanence."[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Plane_of_immanence |
内在とは、内側に存在する、あるいは内側になることを意味し、一般に、
超越とは、外側に広がる、あるいは外側にあるもので、相対的な対立を提供します。ドゥルーズは「逸脱、冗長性、破壊、残酷性、あるいは偶発性を生の外に降
りかかる事故として見ることを拒否し、生と死は[欲望の]側面、あるいは内在性の平面である」[1]。この平面とは無条件に没入あるいは埋め込まれた純粋
内在性であり、超越をデカルト的であれその他の現実的区別として否定した内在性なのである。したがって、純粋な内在性は、しばしば、純粋な平面、実質的あ
るいは構成的な分割のない無限の場あるいは滑らかな空間と呼ばれる。インマネンスと題された最後のエッセイで、ドゥルーズは次のように述べている。ドゥ
ルーズは『A
Life』と題した最後のエッセイにおいて、「我々が内在の平面について語ることができるのは、内在がもはやそれ以外の何ものに対しても内在でないときだ
けである」[2]と書いている。(→内在平面) |
| Combat |
闘い |
||
| Style |
スタイル |
||
| Critique et Clinique |
批判と臨床 |
||
| Le Virtuel |
ヴァーチャルなもの |
||
| Durée |
持続 |
||
| Vie |
生、生命、生活 |
||
| affirmation |
肯定 |
||
| Forces |
力 |
||
| Signes |
記号 |
||
| Apprentissage |
習得 |
||
| Point de Vue |
視点 |
||
| Problème |
問題 |
||
| Histoire de la
Philosophie |
哲学史 |
||
| Image de la Pensée |
思考のイメージ |
||
| Humeur / Ironie |
ユーモアー、皮肉 |
||
| Question |
問い |
||
| Différence |
差異 |
||
| Etnel Retour |
永劫回帰 |
||
| Univocité |
一義性 |
||
| Simulacre |
シュミラークル |
||
| Disparité |
格差 |
||
| Empirisme
Transcendantal |
先験的経験論 |
||
| Intensité |
強度 |
||
| Bêtise |
愚かさ |
||
| Rencontre |
遭遇 |
||
| Expression |
表現 |
||
| Individu |
個人、個体 |
||
| Multiplicité |
多様体 |
||
| Champ Transcendantal |
先験的領域 |
||
| Singularité |
特異点 |
特異点とは、一般性ではなく出来事であり、出来事のしずくである
(『襞』113) |
|
| Structure |
構造 |
||
| Non-Sens |
ノンセンス |
||
| Sens |
意味 |
||
| Surface |
表面 |
||
| Visagéité |
顔貌性 |
||
| Zone d'Indiscernabilité |
識別不可能ゾーン |
||
| Matériau-Forces |
マテリアルーフォルス |
||
| Espace Lisse, Espace
Strié |
平滑空間、条里空間 |
||
| Haptique |
触覚的、ハプティック |
||
| Sensation |
感覚 |
||
| Déformation |
変形 |
||
| Image-Mouvement |
運動イメージ |
||
| Image-Temps |
時間のイメージ |
||
| Image-Cristal |
結晶のイメージ |
||
| Histoire |
歴史 |
||
| Cartographie |
地図作成 |
||
| Heccéité |
この性質、これ性 |
||
| Subjectivation |
主体化 |
||
| Pli |
襞 |
||
| Concept |
概念 |
||
| Percept, Affect |
かんじること、影響 |
||
| Ritournelle |
リトルネロ |
The ritournelle is a
17th-century dance in quick triple time.[1][failed verification]
'Ritournelle' is the French equivalent of the Italian musical term
'ritornello |
|
| L'Épuisé |
消尽 |
||
| Séries |
セリー、シリーズ |
||
| Événement
(L'Incorporel) |
出来事 |
||
| Guerre |
戦争 |
||
| Danseur
(Représentation) |
ダンサー |
||
| Aiôn / Chronos |
アイオーン、クロノス |
||
| Paradoxe |
バラドクス |
||
| Divergence |
発散 |
||
| Nomade |
ノマド |
ノマドとはそこに留まるものである(千のプラトー
437;記号と事件277)。ノマドは土地の所有とは無縁であり、領域により境界を定めない。 |
|
| Corps sans Organes |
器官なき身体 |
||
| Livre |
書物。書 |
||
| Fragments |
断片 |
||
| Écrire à Deux |
共同執筆 |
||
| Désir (Machines
Désirantes) |
欲望(欲望機械) |
||
| Flux-Coupure |
流れと切断 |
||
| Schizo-Analyse |
スキゾ分析 |
Schizoanalysis
(or ecosophy, pragmatics, micropolitics, rhizomatics, or nomadology)
(French: schizoanalyse; schizo- from Greek σχίζειν skhizein, meaning
"to split") is a set of theories and techniques developed by
philosopher Gilles Deleuze and psychoanalyst Félix Guattari, first
expounded in their book Anti-Oedipus (1972) and continued in their
follow-up work, A Thousand Plateaus (1980).[1][2] [T]he goal of schizoanalysis: to analyze the specific nature of the libidinal investments in the economic and political spheres, and thereby show how, in the subject who desires, desire can be made to desire its own repression—whence the role of the death instinct in the circuit connecting desire to the social sphere. [...] Schizoanalysis is at once a transcendental and a materialist analysis.[3]— Deleuze and Guattari The practice acquired many different definitions, uses and articulations during the course of its development in collaborative work with Deleuze and individually in the work of Guattari; for instance, in Guattari's final work, Chaosmosis, he explained that "rather than moving in the direction of reductionist modifications which simplify the complex", schizoanalysis "will work towards its complexification, its processual enrichment, towards the consistency of its virtual lines of bifurcation and differentiation, in short towards its ontological heterogeneity" whereupon it could take on the same tasks expected of revolutionary ideologies and political projects. |
ス
キゾ分析(またはエコソフィー、プラグマティクス、マイクロポリティクス、リゾマティクス、ノマドロジー)(フランス語:スキゾ分析; schizo-
はギリシャ語の σχίζειν skhizein
に由来し、「分裂する」という意味)は、哲学者ジル・ドゥルーズと精神分析医フェリックス・ガタリによって開発された理論と技法の体系で、彼らの著書『ア
ンチ・オイディプス』(1972年)で初めて提唱され、続編の『千のプラトー』(1980年)で展開された。[1][2] [T]スキゾ分析の目的:経済的・政治的領域におけるリビドーの投資の特異性を分析し、欲望を持つ主体において、欲望が自身の抑圧を欲望させる仕組みを明 らかにすること——これにより、欲望と社会的領域を結ぶ回路における死の衝動の役割が浮き彫りになる。[...] スキゾ分析は、超越的かつ唯物論的な分析である。[3]— ドゥルーズとガタリ この実践は、ドゥルーズとの共同作業やガタリの個人作品の中で発展する過程で、さまざまな定義、用途、表現方法を獲得した。例えば、グアタリの最終著作 『カオスモシス』では、彼は「複雑さを単純化する還元主義的な改変の方向へ進むのではなく」、スキゾ分析は「その複雑化、過程的な豊かさの増大、仮想的な 分岐と分化の線の一貫性、要するにその存在論的異質性」へ向かって働き、その結果、革命的なイデオロギーや政治プロジェクトに期待される同じ任務を果たす ことができると説明している。 |
| Le Moléculaire /Le
Molaire |
分子的なもの、モル的なもの |
||
| L'Organique/
L'Inorganique |
有機的なもの、無機的なもの |
||
| Nature |
自然 |
||
| Littérature Mineure |
マイナー文学 |
||
| Écriture |
エクリチュール |
||
| Anexactitude Rigoureuse |
厳密な不正確さ |
||
| Sobriété |
簡素 |
||
| Devenir |
生成変化 |
"Développé
par Gilles Deleuze et Félix Guattari à partir de la publication de
Kafka. Pour une littérature mineure (1975), le concept de devenir va
être présenté sous des déclinaisons en cascade dans Mille plateaux
(1980) : devenir-enfant,
devenir-femme, devenir-animal, devenir-imperceptible.
Si le mouvement est immédiatement convoqué par le devenir, comme
l’écrit de manière pertinente René Schérer, « devenir est advenir »,
c’est surtout à une augmentation de la puissance de vie qu’il renvoie.
Autrement dit, devenir, werden en allemand, c’est « l’être en train de
se faire » (Schérer 1998, p. 53), non comme une « autoproduction de
l’être », mais comme mouvement ou, mieux, pur « événement ». - https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-1-page-43.htm |
"カフカ
"の出版後、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリによって開発された。Pour une littérature
mineure』(1975)では、「なる」という概念が、『Mille
Plateaux』(1980)では、「なる-子ども」「なる-女」「なる-動物」「ならない-知覚できない」というように、連鎖的に変化する形で提示さ
れることになった。ルネ・シェラーが「なることはなることだ」と的確に書いているように、なることによって運動が即座に呼び起こされるとすれば、それは何
よりも生命の力の増大を意味するものであろう。つまり、「なる」(ドイツ語では werden)とは「作られる過程にある存在」(Schérer
1998, p.53)であり、「存在の自己生産」ではなく、運動、もっと言えば、純粋な「出来事」なのである。 |
| Lignes |
線、線分 |
||
| Rhizome |
リゾーム |
||
| Plateau |
プラトー、高原 |
||
| Strates |
地層 |
||
| Diagramme (Machine
Abstraite) |
ダイアグラム(抽象機械) |
||
| Agencement |
アレンジメント |
||
| Territoire /
Déterritorialisation |
領土、脱領土化 |
||
| Voyage sur Place |
その場での旅 |
旅先に自分の自我を持ち込むこと
は、その人が移動しても移動していないことを意味はしないか?移動をしなくてもあるいは身体移動したはずなのだが、どこかに被疑者が隠れていたりあるいは
逃亡している際には、その人の自我はそこにいるはずなのに、そこには居ないということになる(→「虚
構観光」)。 |
|
| Bloc d'Enfance |
幼年期のブロック |
||
| Machine de Guerre |
戦争機械 |
||
| Ligne de Fuite |
逃亡線 |
||
●ジル・ドゥルーズ(Gilles Louis René Deleuze)とは誰か?https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
ジル・ドゥルーズ(サイト内ペー ジ)に移動しました!!(→「ジル・ドゥルーズ 1.0」「ジル・ドゥルーズ 2.0」)
●著作年譜
1925 1月18日パリ(第17区)に生まれる
1953 Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine selon Hume (1953)
1962 Nietzsche et la philosophie (1962)
1963 La philosophie critique de Kant (1963)
1964 Proust et les signes (1964)
1965 Nietzsche (1965)
1966 Le bergsonisme (1966)
1967 Présentation de Sacher-Masoch : le froid et le cruel (1967
n.d. Différence et différenciation
1968 Différence et répétition (1968)
1968 Spinoza et le problème de l'expression (1968
1969 Logique du sens (1969)
1972 L'Anti-OEdipe: Capitalisme et schizophrénie
1 (1972)
1975 Kafka: Pour une littérature mineure (1975)
1976 Rhizome, extrait de Mille Plateaux (1976)
1977 Dialogues avec Claire Parnet (1977)
1980 Mille Plateaux: Capitalisme et
schizophrenie 2 (1980)
1981 Spinoza: Philosophie pratique (1981)
1981 Francis Bacon: Logique de la sensation (1981
1983 Cinéma 1: L'image-mouvement (1983
1985 Cinéma 2: L'image-temps (1985
1986 Foucault (1986)
1988 Le Pli: Leibnitz et le Baroque (1988
1990 Pourparlers 1972 - 1990 (1990)
1991 Qu'est-ce que la
philosophie? (1991)
1993 Critique et clinique (1993)
n.d. Politique et
psychanalyse
1995 11月4日パリで死す
2002 L'Île déserte et autres textes: Textes et entretiens 1955-1974 (2002
2002 Deux Régimes de Fous (2002)
2015 L'Abécédaire de Gilles Deleuze
☆ドゥルーズの哲学原理 / 國分功一郎 [著], 東京 : 講談社 , 2025.9. - (講談社学術文庫 ; 2880)
第1章 自由間接話法的ヴィジョン―方法(自由間接話法;哲学研究の課題;哲学の課題)
第2章 超越論的経験論―原理(超越論哲学と経験論哲学;無人島;出来事;超越論的な原理;超越論的な原理の発生)
第3章 思考と主体性―実践(思考の強制;思考の習得と方法;物質に付け加わる主体性)
第4章 構造から機械へ―転回(ガタリとの出会い;構造と機械;構造と構造主義;セリー、ファルス、原抑制;『アンチ・オイディプス』と分裂分析)
第5章 欲望と権力―政治(ミシェル・フーコーの歴史研究;『監獄の誕生』における二つの編成;権力と二つの編成;一元論と二元論;欲望と権力;欲望のアレンジメントと権力装置―『千のプラトー』の理論的位置)
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
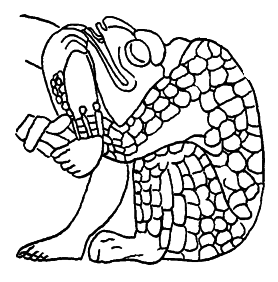
++
☆
 ☆
☆