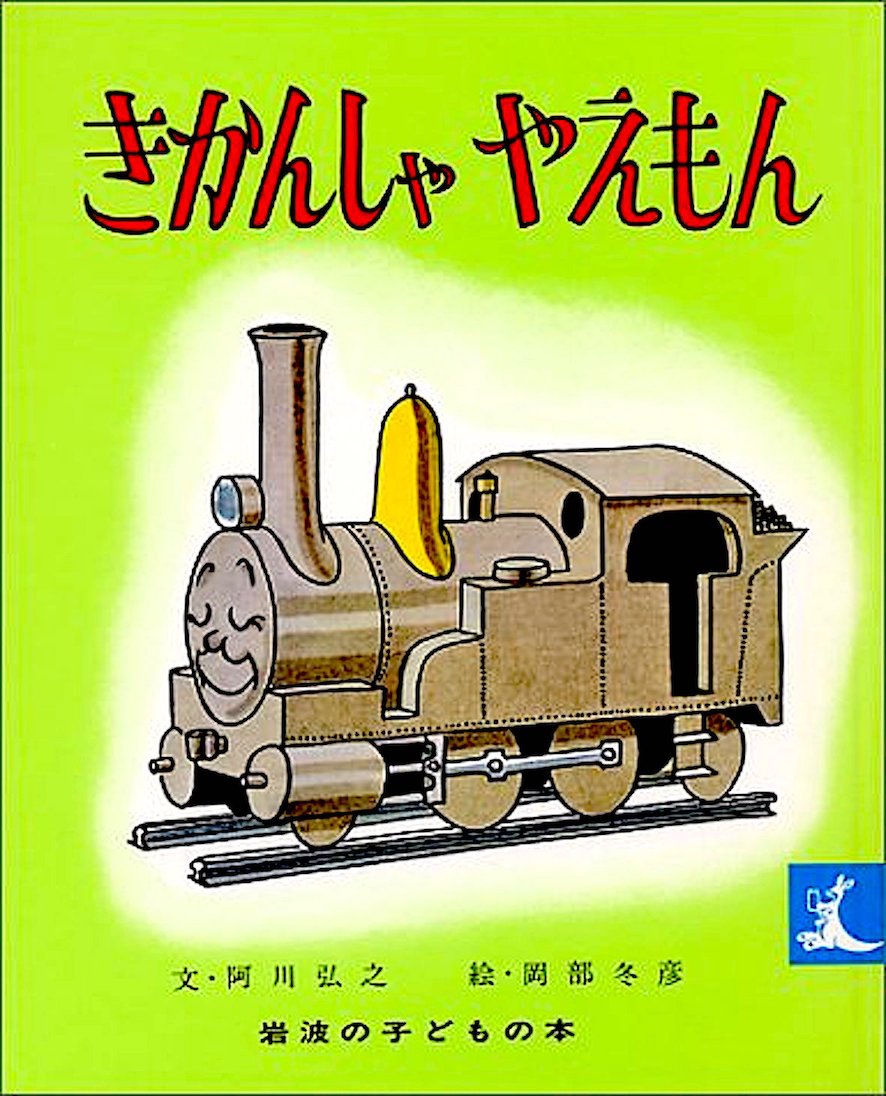フィールド・ライフ
──熱帯生態学者たちの微小社会活動に関する調査の概要──
Field Life: A Microsociological Research of Tropical
Ecologists in Rain Forest, revised
version
Mitsuho Ikeda,池田光穂
──お前は科学者の言うことを本当に信じるのか?(UC Berkeleyから来た魚類生態学者)
──森の中で一番怖いこと? そうだな‥‥、一番怖いのは密猟者に撃たれることだ。蛇?‥‥、蛇なんか怖くないよ。もう扱いに慣れてい るからね。まったく人間ほど怖いものはないよ。(保護区で助手として働くコスタリカ人)
※この論文の初出の論文は以下のサイトあるいは、《BJ0002_097-135.pdf》 より直接ダウンロードできます。
1. 問題の所在
これはコスタリカの熱帯雨林における生態学者たちの生活についての記録である。ただし、論述の目的は、彼[女]らとの生活をとおして得ら れた予備的な民族誌学的観察とそれに纏わる若干の理論的考察にあり、全体論的な民族誌の一部として提出されるものではない。
科学者のコミュニティについて具体的に研究したことがある者なら誰しも、彼[女]らの行動に参画し観察することは、“果てしなく続く会 話”につきあうようなものであることが実感できるはずだ。そこには、始めも終わりもない。あるのは絶え間なく続く行動と議論だけである。その会話の内容は 時として同じものはない。それは、社会の永続性を保証する点において民族誌学者の記述への野心をくすぐるが、他方で話される内容や構造自体は変化してお り、テクストの中に留めておくことの意義が疑問に附される点で、全く魅力のないものである。では、それらの構造の遷移を理論化すれば話はうまく片づくのだ ろうか。民族誌学者は、そのような骨格だけをみて、その肉づきを思い起こす行為を不誠実なものと見なし、欲求不満を覚えるだろう。
科学者のコミュニティを研究する民族誌学者は、研究対象の科学者たちから、彼[女]らのやっている行為を侵害したり、模倣されたりしてい るように思われがちであり、さまざまな抵抗に出会う。ところが、これはそのような苦痛を伴うが、同時に彼[女]らの世界を覗き込むことが、自分たちの背面 を見ることにつながるという、きわめて反照的で喜ばしい快楽を提供する。
私が具体的事例をともなわせ考察する問題は以下の4点である。
最初に、熱帯生態学者の活動現場に関する問題である。これには、空間の利用、道具の利用、予算、時間配分、そして研究の場所による下位文 化の影響や研究者の民族性にかかわるものが含まれる。次に、研究者の自己意識に関する問題である。我々は生態学者の心の内面──存在の有無はここでは不問 にする──は覗けないのであるから、外面に現れた行動や対話による解釈学的な“構築物”から、それを判断する他はない。この中には、科学者の性格の偏屈性 つまりエキセントリシティ(eccentricity)に関する情報のやりとりなども含まれる。第三は、彼[女]らの身近な社会的行為から構成される世界 についての問題である。これには、研究者たちが一過的に滞在するフィールドでのさまざまな行動が含まれる。彼らが研究に没頭している間の行為の他に、食堂 やフィールドでの会話、冗談、何気ない発話などは、それらを知る手掛かりになる。そのような行動から触知される意味を、ここではミクロ社会認識と呼んでお く。最後は、生態学研究のフィールドに従事している人たちが、外部のより大きな規模の社会現象にどのように関与しているのかという問題である。外部世界へ の関与は地域的・国家的・地球的なレベルの広がりをもつ。ここでは、自然保護や持続的開発のモデルとされているエコ・ツーリズムについての、彼[女]ら態 度表明に焦点をあてる。
2. 調査地および調査の概観
調査地はコスタリカにある熱帯研究機関( Organization for Tropical Studies Inc., OTS)が運営する3つのフィールドステーションの1つであるラ・セルバ生物保護区(La Selva Biological Station)である。ラ・セルバは、コスタリカ共和国エレディア県プエルト・ビエホ(Puerto Viejo, Provincia de Heredia)にある。この自然保護区は、熱帯生物学に関する調査が長年にわたり多角的に調査蓄積されており、その成果は数々の論文のほかに、分厚い報 告書にまとめられている(McDade et al. eds. 1994)。
調査に関する資料は、1997年2月22日から3月8日の私 の滞在期間中に採集された。私は、熱帯研究機関に対して、熱帯生物学の研究者や大学院生が調査計画を申請する“通常”の手続きと同様の方法をとって、人類 学のフィールドワークの調査を申請した。この申請に対して、日本とコスタリカの間で何通かの電子メールをとり交わし、現地に入った際に、正式の調査申請書 を提出し、受理された。調査は、通常の民族誌学の方法に則り、構造的ならびに非構造的インタビュー、参与観察、談話への参加などをおこなった。使用言語は 英語とスペイン語、および日本語であった。
フィールドとなる保護区で活動する人々は、大きく研究開発の部門とそれ以外の管理の運営部門に属すかで二分することができる。前者は、保 護区で調査する研究者への便宜をはかる職員である。このスタッフは博士号を取得する研究者であり、研究者への研究指導を行える能力をもち、実際に指導をお こなうこともある。この研究部門の職員は、北米の国籍をもつ人たちと、コスタリカおよび近隣のラテンアメリカの国籍をもつ人たちに、さらに二分することが できる。この民族的な属性を二分する根拠は、母語とする言語(英語とスペイン語)が異なり、後述するように、さまざまな局面で彼[女]らの間に微妙な境界 が形成されることが観察されるからである。
管理運営をする部門には、保護区に受け入れている短期間の訪問者および研修者へのガイド、保護区の縦横に設けられている案内路の保守整備 の労働者、フィールド調査の労働助手、実験室の技術助手、食堂の職員、ならびに運転手などが働いている。この部門の職員のほとんどはコスタリカ人である。 受付の秘書や食堂のコックや管理者を除いて、彼[女]らは緑のTシャツと棉パンツを着けており、容易に見分けることができる。スタッフの男女はほぼ同数で ある。これ以降の記述は「彼[女]ら」という記述を「彼ら」に統一するが、その場合に、女性は同数含まれていると読者は判断されたい。
管理と研究というセクションは確かに分化されているが、その機能は必ずしも厳密に色分けできるものではない。保護区の高位の責任者のうち 何人かは、研究者であったし、コスタリカ人を中心とした研究部門の中間管理職の職員は、自分で独自の研究をおこないながら、受け入れた研究者に対して、生 活ならびに学問上の便宜を図る職務にも従事していた。
空調装置が24時間働いている実験施設のある研究棟はラボラトリーあるいはラボ(laboratory, lab)と通常呼ばれている。ラボで働いている助手(assistants)は、OTSを通してではなく、それぞれの個別の研究者によって雇われている。 雇用問題もあるのでこれに関してはOTSは関与していないものと思われる。彼らの1日の日当は、調査時点では15米ドルであった──これは現地においては 高給の部類に属する。なお、経験の長い助手に言わせると、この種の雇用機会に恵まれるためには自分の家に電話が不可欠だという。というのは、特定の研究者 と雇用関係をもち、自分の仕事の内容に不満がなければ、次回もまた同じ研究者から声がかかるかもしれないし、また場合によっては助手仲間が、彼あるいは彼 女が仕えた別の研究者が、研究助手を調達しようとしている際に、電話によって紹介してくれるかも知れないからである。
上の人たちは、この保護区に逗留し研究を円滑にすすめるための研究者たちを受け入れるスタッフであった。狭義の私の研究対象は、このラ・ セルバの一時的な逗留者の生物学者たちである。彼らは、北アメリカの学部学生、大学院およびパートあるいは常勤の研究者である。彼らは数週間から数ヶ月 間、ここに逗留し、調査研究活動に従事する。OTSの経営母体は、北米および中米の大学をメンバーとする連合体である。つまり、この保護区は、それらの複 数の大学の教育研究のための演習林という機能をもつ。
私は、調査の期間中、研究および管理運営に携わるスタッフおよび外部からやって来る生態学の研究者に対して、自己紹介のなかで自らの調査 課題を披露するという彼らの流儀にしたがって、私の民族誌学的調査の内容と目的を話した。彼らは、私の調査課題に当惑したり、逆に面白がったりした。私の 調査の意図を話した後に、頻繁に出てきた質問は「なぜラ・セルバを選んだのか?」というものであった。私の答えは明白で、OTSは熱帯研究センター (Tropical Sciece Center)とならんでコスタリカでは著名な研究機関であり、ここが最も著名な論文の生産の拠点の一つになっていることであると説明した。さらに私は、 それまでコスタリカのエコ・ツーリズムについて調査研究(池田 1996)を重ねてきたので、エコ・ツーリズムや自然保護運動への情報を彼らに披瀝し、それらについてもさまざな質問をおこない、意見を交換した。
3. 観察
3.1 活動現場
3.1.1 定型的行動・実験室・時間配分
生態学者の活動のほとんどは研究室においてなされる。私は、生態学の領域に関する最後の調査研究(池田 1980)からずいぶん離れていたので、生態学者の研究活動のほとんどはフィールドでなされると長い間思い込んでいた。しかし事実はそうではない。生態学 者は、フィールドから持ち帰った資料やデータを研究室で分析し、そのデータを見ながら、研究のデザインの見直しや、新規の方法について考える。彼らの知的 生産の拠点は研究室にある。
またすべての生態学者の活動が自然保護と結びつくとも限らない。ウォースターの指摘(Worster 1990)を待つまでもなく、彼らの日常の活動と自然保護とは直接の接点を持つことは少ない。生態学者たちはデータをとりにフィールドに出かけるのであ り、自然を楽しみにゆくのではない。彼らの自然観は、自然との触れ合いによって形成されるというよりも、彼らが研究生活で親しむ生態学理論により大きく影 響される。
フィールドにおける生態学者とナチュラリストの行動は極めて類似しているが、違いもまた、さまざまなところで見られる。まず、フィールド に出るファッションは生態学者は洗練されていないというよりも彼ら自身関心をほとんど持たないが、フィールドワークには極めて適した服装を自分なりに編み 出している。エコ・ツーリスト兼ナチュラリストはすでに私がかつて指摘(池田 1996)したように、極めて洗練されたファッションに身を固めている。
生態学者の関心の焦点はいうまでもなくデータである。だから、フィールドに近い研究拠点が好まれる。また研究施設の充実は研究者にとって 大いなる魅力になる。そして、ここラ・セルバは、研究者は適宜フィールドに入りデータを採集して、ラボに持って帰り、分類や計測、あるいは様々な科学的分 析をおこなうことができる点で大きな魅力がある。得られたデータは施設内のコンピュータに入力され表計算ソフトなどで分析される。
昆虫生態学で、蟻の地域への侵入と定着に関する研究をしている大学院生のゴードンの1997年2月26日は次のようなものであった。6時 に朝食をとり、7時45分にラボに立ち寄り、チームを組んでフィールドに出かける。30分ほど歩いた調査地の予め登録してある2カ所で、1平方メートルの 表面の落ち葉や枯れ木などをビニール袋に入れて採集する。採集を開始する前に、葉で覆われた大きな木(Canopy)までの距離を測る。このような場所が 森林内の400の場所に設置してある。それぞれの作業は20分ほどで完了し、ラボに帰ってきたのが9時すぎである。標本を実験室に置きにゆく。他のメン バーと同様に、彼はシャワーをあび、着替えに宿舎にもどった。水曜日は郵便物が到着する日なので、郵便物をとりにいったりしてた後で、実験室で作業が始ま るのは、10時30分頃である。
これから昼食をはさみ、午後のあいだずっと採集した落ち葉や枯れ木を虱潰しに調べ、蟻の巣(nido)と女王やほかの蟻を採集しアルコー ルをつめた小さなプラスチックのケースの中に浸してゆく。これをヘンリーやメイビスなどを含めたボランティアの総員の5名のメンバーでやってゆく。遅いと きには夜の8時くらいまで続くことがあるが、2月26日は午後3時すぎには仕事を終えていた。これを1日おきに1カ月半やってきた。この前日のゴードン は、フィールドの関するデータをコンピュターに入力していた。従って、フィールドワーク、採集、サンプリング、データ入力のサイクルを一日おきに彼はくり 返している。自分の確固とした研究テーマをもたない学部学生のボランティアのメイビスやヘンリーは、空いた日には付近を散歩したりして自然観察を楽しんで いるようだ──ヘンリーは鳥類学者の男性ハンデルに一緒に観察にいこうと誘っていた。
ゴードンは、現在、全米科学基金(National Science Foundation, NSF)に研究費を申請中であるが、現在はOTSからだけ補助金をもらって仕事をしている。ヘンリーやメイビスなどの宿泊費や食費は、そこから捻出され る。
彼らの生活は極めて規則正しく、その意味では他の実験自然科学者と変わらない。
生態学者にとって、フィールドの中、あるいは近隣する場所に、条件を統制することのできる実験室環境を持ち込むことは、その調査研究の効 率を高める点で有用である。
リバーステーションの宿泊棟の1階の部分に備え付けられた一連の小さな水槽や実験装置はダグラスが持ち込んだものである。そこには数種類 の魚、大きさは5ミリから2センチぐらいの魚がエアレーションされて飼われている。彼は吊り橋の下のプエルト・ビエホ川で魚の繁殖・保育行動を観察してい る。これらの小さな魚や稚魚はそこから捕獲されたもので、行動観察のためにこの水槽で飼われている。降雨が続き川が増水し、ウエットスーツを着て川の中で 観察できないときやそれ以外の時間、彼はここで魚の行動などを調べている。
私が興味をもったのは、細長いO型の流水路(長さ80センチ幅50センチぐらい)である。これは既製品ではなく塩化ビニルの水道管を使っ たもので、流水の速度を変えて魚の行動を観察することができる。魚を呼ぶとき彼は "this guy", "another this guy"などと擬人化して連中をよぶ。この擬人化は、ワシントン州の林学者を前に食堂で図鑑を示しながら、図中の魚を示すときもダグラスは"guy"と呼 んで説明する。
魚のテリトリー防衛行動を観察するために模型の小さな魚の書き割りをその中に入れて行動観察している。ダグラスによると、魚はその模型に 果敢に噛みついたり、目の部分に攻撃をしかける。
プランクトンの乾燥卵を持ち込み孵化させてエアレーションして飼育しているが、これが魚の餌となる。私に説明してくれた際には、指を水槽 に浸し別の手の平にあてて刷り込んでいた。これは水の温度をチェックしているのだろうか、単なるダグラスの行動の癖なのか不明であった。
彼の創意工夫によるこれらの一連の機材は、まったくスマートなことにスーツケース2個分に入れられてカリフォルニア大学のバークレー校か ら持ち込まれたものである。彼のバークレーでの先生は、学生大学院生に対してフィールドでは常に工夫して自分の研究環境を臨機応変に作ることを強力に指導 してきたという。先のO型の流水路も彼の自作によるもので、向こうで作成され分解された後、こちらで組み立てられたものである。
彼はカナダ人でバークレーの講師だが、テニュアーはない。彼は魚の行動を観察することが何よりも好きで、それさえできれば満足であるとい う。彼はカナダ人であるためにNSFのグラントが申請できない。また直接の先生にあたる人がすでに引退しており彼を代表者にしてグラントをとることもでき ない。 ラ・セルバには今回で3回目の訪問である。前回は助手を連れてこれたので仕事ははかどったと言っているが、今回は1人でやってきた。 先進国から熱帯地域にやってきて調査することは、多大な経費がかかる。研究者は、さまざまな工夫をして経費を削減し、効率の良い調査をおこなおうとす る。
OTSで数日間の調査に来ているドイツ人研究者夫妻は、コスタリカ滞在中はサンホセに住み定期的にラ・セルバにやってきて資料を採集す る。今度は、それをサンホセにもって帰り、分析はコスタリカ大学でおこなうという。どうしてそんなことをしているかと私が聞くと、この夫婦はドイツ政府か らグラント(研究資金)をもらって調査しているが、調査経費が限られているのでラ・セルバには長くいれないのだと説明する。彼らはドイツ政府が、生態学研 究にはあまりグラントを出さないことに苦言を吐いていた──これについてはどの国の研究者もそれぞれの国の研究財政事情に関して似たりよったりの批判的意 見があった。
生態学者は、みな同じ時間サイクルの中で調査するのではない。研究対象や方法に応じてさまざまな時間帯に研究をおこなう必要性が生じる。 それらは結果的に、占有できる空間が限られたラボの利用効率を高めるのに貢献する。
フィールドワーカーにもいろいろあって、彼らのルーティンを一括することは困難である。例えば鳥類学者は昼間はほとんどラボに姿を表さず に、セルバのなかを彷徨いている。生化学的分析をしている学者は午前中は定期的に外に出て、資料を採集する。採集をした後の午後はずっと実験をしている。 夜中や朝方に仕事をする昆虫学者もいる。しかし、ラボに顔を出すのは、傾向からいうと北米の研究者で、長期間調査に従事し、かつ実験的な性格をもつプロ ジェクトを遂行している人ということになろう。ラテンアメリカの研究者の多くは、大学院の修士レベルかそれ以下で、実験室を占有するほどの規模の研究をお こなっていないか、あるいは短期間でフィールド調査を集中する先のドイツ人夫妻のような「経費節約型」のような研究スタイルをとる。
3.1.2 外部からの視点
保護区の中で何がおこなわれているのか、近隣に住む住民は何の関心も持たない。また、内部の研究者も、周りのコミュニティの人々が自分た ちにどのような印象をもっているのか、という関心を持たない。
マルガリータはOTSラ・セルバの土産物ショップで働く近くのプエルト・ビエホ出身の女性である。彼女はここで1994年から働いている が、ここに就職するまではOTSのことは何も知らなかったし、またここに入ったこともなかった。それはプエルト・ビエホの他の人たちも同じだろうという。 ここのことを「グリンゴのコロニア」(白人の居留地)と言われていたということを知っているか?──と私は聞いたが、これについては知らないと言った。 彼女は土曜日と日曜日も出勤してきているので、ウィークデイに休みをとっている。プエルト・ビエホはいいところか?──という質問には「多少ともね」と 遠慮がちに答える。というのは昔は小さくて、町の人は誰もが面識のあったほどの小さな町だったが、現在では、パナナプランテーション(bananera) ができて沢山の人たちが町の外からやってきて、町の雰囲気は一変した。町についてどんな変化を知っている?──と詳しく聞こうとすると、「私は一日のほと んどはラ・セルバにいるので、町のことはそんなに知らないわよ」と返事する。
彼女がグリンゴのコロニアのことを知らないと言ったのは無理がない。というのは、OTSは今でこそ人びとがたくさんやってくるが、その雇 用の経済的効果も知れたものであるし、文化的・社会的には現地にほとんどインパクトを与えていないようだからだ。町を変貌させたのはバナナだからである。 プエルト・ビエホはこの数年間の経済変化の主要な原動力になっているバナナと観光(エコ・ツーリズム)によって大きく変わってきたことを示している。
私は以前、ある論文(Laarman and Perdue 1989)で、このOTSが「科学観光」の推進母体であることを知った。もっともOTSのスタッフが、このことを特に意識しかつ推進しているわけでもな く、また科学観光という用語じたい、それほど知名度のあるものではないことがわかった。
OTSのスタッフであり植物生態学者であるクララと実験室で話す。彼女は助手の女性(現地人)と植物の根の直径を測って選別する作業に従 事しながら私に対応した。
私(=池田)が「ここの人間のミクロ社会のことに興味があります」と言うと、彼女は「それは興味深いわね」と言うと同時に、多少にやりと 笑い、「ここの組織は複雑だからね」とつけ加えた。「昨年はエコ・ツーリズムで論文を書きました」と私が言うと、次のようなことを述べた。
「ここへ訪れるひとたちはエコ・ツーリズムではなくて、もうすこし違ったもの、つまり科学観光(turismo cient断ico)をするためにやって来るのだけれども。しかし、それにしても、あなたの研究テーマは興味深いわ」。
会話の内容はそれ以上の深みはなかったが、「科学観光」という用語を強調していた点は、彼女の管理者としての立場からも非常に重要なこと である。
その後、コスタリカ人ガイドのアーニーから科学観光について聞くことができた。私が、アーニーに「クララが、ここでやっているのはエコ・ ツーリズムではなく科学観光だと言っていたよ」と話して、会話の糸口をみつけた。
アーニーによると、科学観光とは「一般の観光客よりも高度な知識をもった観光客あるいは科学者に対して、より訓練されたガイドが対応した り、実際の科学調査の手助けをおこなうこと」をいう。ラ・セルバで初めて使われたと私は思っていたのだが、彼女がグアナカステでエコ・ツーリズムのガイド をやっていた1989年当時にすでにこの言葉を聞いていたという。
これに関連しているのが、2月28日にアーニーに聞いたときに話に出た、現在計画中のラ・セルバの3つのプロジェクト、(1) Tur Nocturno、 (2) "Birding" B101,、(3) "Research Tour"、のうち一番最後の「研究ツアー」である。これは研究者にツアーを用意しようという類のものではなく、ここにくるビジターが研究者の調査をかい ま見たり、フィールド内に設置されてあるGIS(地理情報システム)のポールをみるたびに科学者の活動に強く興味を引かれることを契機に、観光客により研 究者の活動を理解してもらい、見学の魅力の目玉にするという計画が予定されているものである。
つまり研究ツアーにおいては、ビジターに対して研究者が特別に解説をしてあげることを理想としている。アーニーの説明によると、同じ実験 サイトを観光客に見せるにしても、ガイドが説明するよりも、当の研究者が説明するほうが観光客が喜ぶからだという。しかし、実際に研究者にそのような機会 をもってもらうことは不可能であるし、「研究者はビジターに対して好感をもたない」。だからその代替として、研究者の活動を解説したものや図表化した展示 などが計画されている。アーニーによると、ビジターは研究者の国籍や活動の内容を何人とか何パーセントとかの数字で知りたがるので、それをグラフ化したも のの展示も考えている。それ以外にも、OTSの保護区の概観を知ってもらうための森林の断面のイラストや模型なども考えられている。
このように科学観光は、当初は先進諸国の科学者が研究目的のために開発途上国にやって来るという実態を分析するための呼び名であった。し かし、当のこの科学観光のメッカであるラ・セルバでは、熱帯雨林における科学者の活動および彼らが科学的知識として生産したものを理解するための観光とい うふうに、意味するところが変化してきているところが興味ふかい。
3.1.3 研究者の下位文化
複数のフィールドステーションを知っている生態学者によると、どうもステーションの雰囲気には、それぞれ局所的な差異 (locality)があり、そこで生活する研究者の性格や振る舞い(character)を規定するものがあるらしい。これは研究者の下位文化に纏わる 現象である。
植物生理学者のジェームスに、熱帯生態学の研究では著名なパナマ海峡に浮かぶバロ・コロラド島(Barro Colorado Island, BCI)での体験やラ・セルバとの比較について話してもらった。以下の記述は、ジェームスの語り口をまねたものである。
君がBCIにいったら、そこは別世界と思ったほうがいい。あそこの研究部の部長は、いわゆるマッドサイエンティストタイプの男だよ。 BCIは研究者がやりたいことをやるという考えが伝統的に受け継がれている。そこに住みついたなら、ラボは調査者がそのようなことをサポートするものだと 研究者は考えるようになる。
BCIは世俗とは完全に隔絶した世界であり、世俗でのモラルは通用しない。全くクレイジーな世界である。研究者は好きなときに起きて好き なように研究する。ただしそのモードは都会的な生活がより誇張されたものである。フィールドでの仕事の後はビールを飲み、食事の後は酒を飲み葉巻をふかす のだ。研究者はなんでも非常に集中しておこなう傾向がある。たとえば夜の10時まで研究し、そこから1時間は酒を飲み葉巻をふかし議論をして11時には寝 るというふうである。
ラ・セルバは近隣の地元民が働き、現地のローカルな社会との交流がある。しかしBCIの職員のほとんどはパナマシティーという都会の人間 である。BCIは外部と隔絶した社会といっても町に出るのが不便というわけではない。ラ・セルバでは近隣のプエルト・ビエホは小さな町だし、サンホセにで るには「ものすごい」時間がかかる。ところがBCIからは船で30分、車で30分でパナマシティーという大都会に出れる。船は1日3往復出ているのでシ ティへの日帰りも可能である。だから森の生活に疲れたら、リッチなホテルで「酒を飲んで葉巻をふかす」ことだってできるのさ。
ラ・セルバへのビジターは同じOTSの組織がとりあつかい旅行者との接触の機会も多い。しかし、BCIは旅行者は外部のエージェントが許 可をとって来るだけで、それすら制限されているので、研究者だけの場所という性格がつよくなるわけだ。ラ・セルバは食事の時間が決められているが、BCI では研究者が仮に夜中の11時にサンドイッチが食べたいと考えていれば、施設の人間はそれを実現させなければならないと考える。この考え方は、ラ・セルバ が教育に、BCIが研究の場が中心と考えられている違いにもとづくものだろう。
ラ・セルバは基本的に教育施設であり、僕がみた限り学部学生の割合が高いが、BCIはほとんど博士課程かポスドクというシニア研究者、あ るいは教授などの職業的専門家によって占められている。もちろん、この差異はどちらがいいという問題には還元できないと思う。教育には一定の規則を守るこ とも要求されるからね。
BCIの食堂は、非常に長いひとつのテーブルからなる。ラ・セルバは研究者とビジター、そして現地の職員が固まって、しかしときには一緒 に食事をする、非常にゆるやかな集まりを形成するが、BCIはその長いテーブルに研究者が占拠して、片隅の別のテーブルに職員──ほとんどマシンガンで武 装した森林警備隊(guardabosque)──が座るという、きわめてはっきりとした区分がある。同様にBCIはドミトリーとダイニングとラボが同じ 建物のなかにあるが、ラ・セルバはそれぞれがバラバラに散らばっている。
BCIが、そのようなマッドな研究者にとってある種のパラダイスたりえる理由のひとつは、そこはスミソニアン研究所が運営しており、予算 が潤沢にあることがあげられる。ラ・セルバは大学のコンソーシアムで運営の予算がかぎられている。これは管理者のキャラクターの違いにも現れているね。 BCIにはクレイジーな研究部長がいるが、これにくらべたらラ・セルバの研究部長パーシーは非常にまともな紳士に感じるよ。
ジェームスは別のコンテクストでBCIについて再び語ってくれた。彼はカリフォルニア大学バークレー校出身で現在ハワイ大学の大学院に所 属しているが、私がバークレー校の客員研究員だったことを知った上で、誇張的話法と比喩を用いてBCIを次のように解説する。
ファーム(farm)はスタンフォード大学の愛称である。実際にキャンパスが農場だったからでもあるが、バークレー校とスタンフォードは いろいろな意味でライバルだ。しかし、その学問のスタイルや政治的なコミットメントでは、相互に対照的な大学である。バークレーは、左翼的伝統があり── ビートニクス、ベトナム反戦運動等──、また学問においても政治的ポジションにおいてもかなりエキセントリックでクレイジーなところがある。ジェームスは スタンフォードについては多くを語らない──なぜならバークレー出身だから──が、どちらかというと折り目正しいか「まとも」すぎると言いたいのだろう。
そこで彼は言う。ここが(=ラ・セルバ)がファームつまりスタンフォードなら、BCIはバークレーだよ。
ジェームスはBCIに精通してるようだが、じつは彼はBCIにまだ2週間半ほどしか滞在していない。ここで1週間、来週1週間パナマに戻 り、6月までラ・セルバで、ふたたびBCIに戻り今年の12月までに修士論文を完成し、来年度博士課程に進学するつもりだ。彼は現在27歳で、博士号をと るにはあと5、6年かかると見込んでいる。
このようなフィールドステーションが、研究者の性格や振る舞いを規定するのであれば、それは文化による生態学者の学説や振る舞いにも影響 しているのではないかと考えることができる。そのこと自体がはたして検証可能な命題であるのかどうか不明である。そして、当の生態学者はこの現象にどの程 度自覚的なのだろうか。ちょうど京都大学生態学センターの教授であった井上民二さんが、私のラ・セルバ滞在中にいらっしゃったので聞いてみた。
私が、生態学の下位分野の研究者の違いによる多様性と帰属する文化の違いによる多様性ではどちらのほうが著しいですか? という私の質問 に対して、井上さんは「文化の違いとは国による違いのことですね」と確認したあと、次のように答えている。
「僕とよく似た研究者は、国の違いをこえて、アメリカにもヨーロッパにもちらばっておりますよ」
──ということは学問の下位領域を同じくする者どうしが似ているのですね?
「僕らがやっている研究は、内容よりも体験を同じくしているということが重要に思いますよ。パナマに行ったときに私がサラワクに10年い たというと、尊敬の眼差しを持たれつつ同業の研究者に一目置かれましたからね」。
井上さんはスミソニアンのフェローで1年間BCIにいたことがある。
「BCIには30年間滞在してその研究成果を発表しようというようなマッドな科学者がいますからね。アメリカはそのような研究者の存在を 認めることができる余裕があります。日本の戦前には、そのような、30年間ひとつのことに取り組むことが容認されるようなところがありましたが、戦後には それがなくなりました。
生態学の領域は最先端の分野から時間をかける地道な研究まで非常に多様で幅がひろい。しかし、最近の研究はどこかしら底が浅いですね。
アメリカの研究者は、研究に取り組む集中力が僕らよりもかなりありますね。それはさまざまな頭脳をもった移民を受け入れて発展してきたア メリカの伝統なのかもしれませんね。日本はアメリカに追いついたと思っているが、教育や研究にかける予算はGNP比ではじつに8倍ちかくのひらきがある。 それが日進月歩の最先端の分野から長期にわたる生態学的な研究まで、きわめて多様性のある研究を保証している。
日本では文部省の全体の予算の比率が省庁間でとりきめてある。予算全体には大きな伸びはないにもかかわらず科学研究費は毎年10%の伸び をしている。では、そのしわ寄せはどこにきているかというと初等、中等教育にいっている。そのためいまだに15人学級が実現できないでいる。これは、長期 的にみれば大変憂うべきことなのです。
京都大学では授業をもっているが2カ月で終えるようにしている。自分のフィールドワークの時間に割きたいというよりも、学生に対して短期 に集中して勉強することが重要であると考えているからです。
京大以外に日本では生態学センターのようなものがないので、文部省の予算がわりと潤沢につくのです。そのため文部省との折衝の仕事も多い ですけど。そのときによく感じますが、日本の官僚も予算の運営を的確にやるためには学位をもった研究者がおこなう必要があります。あるいは役人をやったあ と数年間は研究生活に戻れるような制度があればいいですね。
アメリカの大学には停年がないそうですね。そのかわり長老政治もない。日本は逆ですね。研究能力の衰退した年輩の教官には教育のほうに専 念してもらって、アドミニストレーションは研究の事情に精通した中堅がしっかりやる必要がある。その意味で、僕らのような団塊の世代ががんばらなくてはな らないのですが‥‥」。
3.2 自己意識
3.2.1 調査されることへの嫌悪
私が調査を始めた頃、研究対象になった生態学者たちは、自らが研究調査の対象になることを嫌がった。同時に、彼らは観光客もまたとても 嫌っていた。これは、エコ・ツーリズムの研究経歴をもち、彼らのことを調査しようとしている私の位置がきわめて危険な存在であったことを意味していた。
生態学者は、観光客が自分たちの研究の邪魔になることをおそれていると言明する。しかし、この嫌悪には、他に説明可能なもう一つの理由が あるように思える。生態学者が自らを観察されることを嫌がるのは、自分たちが「自然」を観察していることと逆の現象、つまり自分たちが客体になることへの 反発であるように思える。つまり、彼らが自然を観察するように、観光客や人類学者は生態学者を観察するからである。彼らは観察する者に、ある種の優位性を おいている。見る側の主体は、見られる主体よりも優位に位置するのは、ミッシェル・フーコー(1977)が西洋近代の主体の確立に関する議論の中で展開し た議論である。その意味で、私の調査や観光客の覗き込みは、カテゴリー認識上の倒錯となる。つまり、見られる側に転落することを生態学者は嫌悪しているも のと思われる。
主体と客体が逆転するという、この倒錯的状況に彼らは違和感を覚える。この違和感は、嫌悪観を生むと同時に、そこから認識論的にある程度 距離をとれば、自己諧謔的なユーモアにもなる。というのは、ラテンアメリカからの学生たちと食事をしている時に、私が科学者の社会学的研究をしていると自 己紹介したときに、ちょうどその際に学生たちがおこなっている実習──虫の数を数えたり、分類し、それを記録する──するしぐさをまねて、私が行おうとし ていることを皮肉った冗談を言ったからである。この冗談は、このグループに属する一人の男子学生と私の偶然の関わりとも関係している。この日、私の傘をす でに放棄された遺失物として自分のものとして持っていた男子学生の一人から私は取り戻したのだが、他の学生たちは、この学生の窃盗行為を虫のカウントを真 似ながら、私がノートに記録するしぐさをしてテーブル・ジョークにした。この場合の皮肉が向けられた直接の対象は、表面的には私のことではなく、私の傘を 持っていた若い男性なのであるが、同時に、彼らになじみのない私の調査実践についても同時に茶化しているのである。このジョークは、あることを取り上げ非 難するのに、それとは全く関係のないものを非難するというアザンデ族のサンザ(sanza)と呼ばれる婉曲語法を思い起こさずにはおれない(Evans- Pritchard 1962)。
生態学者が、観光客を嫌うのは先に述べたように、カテゴリー認識上の反発にあるようだ。しかし、だからと言って、彼らが観光客のように振 る舞うことがないとは言えない。観光客が嫌悪されるのは、科学者と観光客の熱帯雨林での関係からであって、観光という状況が強いるある種の行動特性からで はない。観光客のように、生態学者も素朴に感動する瞬間が熱帯雨林の中でも見かけることができる。
3日の朝からストーンブリッジの横でハウラーモンキーの声がしていたが、午前11時頃に学生ボランティアのオリバーがやってきて橋の横で ハウラーが近くでみれるよ、と声をかけてくれた。早速カメラをもって橋の横で私も写真をとりはじめた。オリバーの友人のメイビスが先にいて写真にとってい た。彼らにとっても絶好の写真日和で近くで猿がみれることからシャッターを頻繁に切っていた。30分ほど見ていると植物生理学者のジェームスが現れて、彼 も「これはとても近いね」といってカメラを出して写しはじめた。OTSの労働者もまた自転車で通りかかりしばし見物していた。帰りがけには土壌学者のス カーロイや大学院生ステプニーが「ハウラーモンキーは、まだいるか」などとすれ違いざま私に聞いていた。
自分の専門外のことでは科学者も当然のことながら観光客と同じようにふるまうし、またそのようにふるまうことに何の衒いもない。
3.2.2 探究
科学共同体というものが虚構的性格をもつにしても、論理を操作し、議論を構築し、何か新しい認識の地平に立とうとする価値観を共有してい るのだという実感を、私は生態学者と議論するときに、しばしば持つことができた。例えば魚類生態学者のダグラスとの以下のような対話である。彼は私のやっ ている方法について興味をしめし、いろいろな質問をしてくれた。それを通して私は自分の考えているアイディアを開陳することができた。以下は、その概要の 一部である。
──生物のしくみはすべて合理的なものであると思うか?(池田、以下同様)
「合理的とはどういう意味?」(ダグラス、以下同様)
──つまり科学的な説明ですべて理解ができるかという、ことだ。
「もちろん! すべての生物のしくみや行動には理由が存在する。例えば蜜蜂の寿命だが、それは物理的な時間ではなくて彼らがとべる飛行時 間は身体の構造上決まっているというのだ」。
──例えば飛行機の金属疲労みたいなもの?
「そうだ。僕は魚の行動を調べているが、彼らの行動には、人間の側からの理解が十分可能であると思っている。また最初はよくわからない行 動も、だんだん理解可能になってゆく。君は生物には非合理的なものがあると思うかね?」
──生物学者の書いた本、とくに一般向けの本をよむとときどき非合理的な、例えば生命の神秘のような、箇所を見かける。これは、生物学者 が生物についてある解釈を与えるときにメタファーを使ってしか説明できないからではなかろうか。
「生物学者も非合理的なところがあるという意味?」
──そうではなく、生物学者がつかう2つのメタファーがあるということだ。つまり生物学者の言説には2つの使い分けがあると思う。ひとつ は専門下位領域を同じくするメンバーどうしの言説で、これは極めて専門的な用語を概念、すなわち狭い領域の特殊なメタファーを使って議論するもの。もうひ とつは専門以外の研究者や一般大衆にもわかる用語や概念をつかって説明するもの。
とくにこの後者のメタファーには日常生活のメタファーを利用するので、非合理的な説明もその中に大いに含まれる。これが読者に対して非合 理的なイメージを与えるのだろうと思うけど。
「我々(生態学者)が食堂のテーブルについて面識のない生物学者と対話を始めるとき、我々はその対話の中に探り針(probe)を入れ る。会話の相手の研究対象は何か、その方法論はどのようなものか、バックグラウンドの知識はどうなのか。これらの情報によって対話がスムースになるわけ だ。」
──もちろん生態学者は、狭い下位領域とひろい一般的な領域という2つの知識の領域を使い分けているだけではない。生態学者が共有できる いくつかのグランドセオリーがある。私によるとそれらは、行動の遺伝子決定仮説と進化論である。この2つのグランドセオリーは生態学者のだれもが共有する 知識なので、下位領域がことなってもお互いに知識を交換できる。
「生態学者はおろか分子生物学者でもミーム(meme:自己複製の単位)(ドーキンス 1976)を実際の目でみることはできないのに、その議論をするとあたかもそれらが存在するかのように取り扱う。 ところで、科学者どうしの会話や日常生活について僕はカール・シンダーマンの本から得るところが多かったけど、その本を読んだことがあるか?」
──日本でも何冊か翻訳されているよ(シンダーマン 1987,1988,1989)。あなたはその本をどうやって知ったの?。
「僕の習った先生が教材としてあげて、各章ごとに丁寧に読んだ。ところで、こんな話の内容を君は(ここではない別のところで)記録してい るのか?」[註:言葉の正確な意味におけるエキセントリックな私自身の行動も生態学者から注目されていた形跡がある]。
──そうだよ。
「さっきの合理性の話だけど、僕の職場の同僚に人間関係をすべて計算合理性から判断する人がいる。誰と議論するのか、誰と食事をするのか ということが彼の計画のなかにあってすべてその原理にもとづいて人間関係が形成されている。彼はあらゆるゲームに凝っていて、最近はフィールドやらず、 “ひじょうに大きな”理論の問題に取り組んでいる。」
──彼にとってserendipityについての考え方というのはないのだろうか。
「よく分からないが、彼にはないのではないだろうか」。
生態学者の調査地は、生態学者が自由に仕事が十二分に可能な理想的な空間とは言い難い。探究にまつわる危険(risk)も多い。熱帯雨林 ともなれば、蚊や吸血性の蛭、毒蛇などフィールド調査にとって障害になるものが多い。フィールドの生態学者は、実験室の研究者とは別種の困難さに直面す る。以下もダグラスとの対話である。
──森の中ではいろいろな危険があるという。蛇などはそうだ。川での仕事、クロコダイルだろうか。クロコダイルがいるところでは調査はしないの?
「必要があればするさ。けれどいろんな動物などそんなに怖くないよ。本当に怖いのは病気さ。」
──例えば下痢とか?
「たしかに下痢では仕事ができないが、もっと怖い病気、たとえばアフリカで淡水で魚を調査することは難しいよ。ビルハルツ、睡眠病、トリ パノソーマ症等々だ。僕の友達でパナマで魚類のことを調査している女性が、マラリアに似た病気にかかった。マラリアの症状を知っているかい?」
──高熱と寒気が繰り返し襲うのだろ?
「彼女はマラリアに似た病気にかかったのだが、原因がわからない。医者は彼女が罹ったような症状はみたことがないという。蛇なんか屁じゃ ないだろ?」
3.2.3 Eccentricity
生態学者には、偏屈な性格つまりエキセントリックな者が多いというのは、さまざなところで私が聞かされてきた「伝説」のひとつである。実 際、ジェームスに聞くと、生態学者は十分にエキセントリックな者が多いという。彼の経験では、知り合いの生化学の研究者の生活を知っているが、自分たちの ライフスタイルと比較したら、生化学者たちの生活態度はきわめてノーマルで真面目に感じるという。アルゼンチン人で蜘蛛の行動を観察しているトマスに言わ せると、生態学者がエキセントリックになる理由は、彼らがフィールドで料理をするような生活を営むからではないかと説明する。
また同じ生態学でも研究対象によって違いはしないだろうか、とジェームスに聞くと、「そうだ、例えば昆虫学者は丸一日でも顕微鏡を覗いて いることがあるだろうし、植物生理学者である自分自身は、森林にたくさんの調査機材を運んでいって計測するのが仕事だから、仕事の内容は同じ生態学といっ ても彼らの生活態度には極めて多様性があり、それが他者をエキセントリックだと判定してしまうのではないか」と説明する。
実際、エキセントリックというのは、第三者から指摘されてはじめて分かるものでもある。逆説的だが、それは一種の噂のネットワークという ものによって、事前に教示されていればいるほど、その指摘が事後的に確認されたときリアリティ豊かなものになる。噂のネットワークは、食堂でのテーブル・ トークで頻繁に生起する。
ゴードンのガールフレンドがアメリカ合衆国からやってきて、彼がラ・セルバ内を案内している。ダグラスと私がフィールドに調査器具を仕掛 けに出かけるとき、このカップルと我々が出会った。ダグラスはゴードンに出会うのは初めてだったので、両者を知る私はダグラスをゴードンに紹介した。ダグ ラスは、ゴードンが不在の間にOTSに到着したので、その時まで面識がなかった。しかし、ラ・セルバの他の研究者からこの数日間の間にダグラスはゴードン のことについてちゃんと聞いており、彼が非常にユニークな性格であることを知らされていたらしい。ゴードンとガールフレンドのカップルと別れてから、ダグ ラスは私に「君もそう(ゴードンが変人だと)思うか?」と聞いてきたので、私は「そうだな生態学者というのは一様に変わっている連中が多いからね」と返事 をする。
ここで重要な点は、我々の日常生活と同様、個人の性格に関する話は結構どこにでもあり、みんなはその噂に関して興味を持っており、よく話 題にするが、実際にはその噂は誇張されたものが多いということである。このラベルは、それを貼ることに意味がある。また噂のネットワークでは情報が社会的 に共有されることが重要なのである。このネットワークは、電子メールによって瞬時に遠くの研究者に伝達されうる。
ジェームスはBCIにいるときから、ラ・セルバではどんな研究者がいるのかについての情報収集をおこなうことができていたと言う。それは ひとつはラ・セルバにいたことがある研究者とBCIで何人かと会っていること。そしてもうひとつは、彼の情報収集の主力をなしているのだが、電子メールに よるラ・セルバの研究者との交信である。
これによって少なくとも数人の研究者の研究内容や人間的評価、噂に関する情報を入手している。これによって、ゴードンが変わり者であると いうことをラ・セルバに到着する前から知っていた。
ジェームスについて事前の情報と会ってからの印象について正してみたが、彼は電子メール上の噂は現実とはかならずしも一致しないと言う が、事前にそのような情報を知っておくことがきわめて彼のラ・セルバでの生活を考えるときに重要であったことを強調していた。
エキセントリックな人物であるかどうかを知ることは、単に人間関係の興味を満たす以上に、フィールドワークの遂行にも影響を与える。状況 を知るための鍵となる点で、彼らにとって重要な情報活動のひとつになるのだ。エキセントリックな仲間に関する情報を通して、その社会の価値観を予め学習し ておくのである。
ジェームスは言う。サンタ・クルースから来ているあの2人のカップルの研究者を知っているだろう。僕は昨日ラボでの途中の道で彼らにシャ ワーはどこか聞いたんだ。ところがあの二人は僕を一瞥して、何も言わずに通り過ぎていったのさ。あのとき、僕はプローブ(検知端子)を森に設置しにいって 正午まえぎりぎりにラボに帰ってきた。飯に遅れると困ることは君も知っているだろ。だからあせってたのに無視されたのは非常にショックだったね。
──僕もそういえば飯をたべているときに無視されたことがあるよ。あの時は、こいつらは人種差別主義者かと思ったね。 「いや彼らは人種主義者じゃないよ。ああいうところで変に気位の高い連中はカリフォルニアには時々いるよ。自分の親しくしている以外の連中には相手にし ないのさ。しかし、僕はまだラ・セルバにきたばかりだろう。ああいう無視のされかたをすると心が傷つくよね。しかしいろいろな連中によく聞くとあのカップ ルは他の連中にもそんな態度をとるらしい」。
──BCIにもそんなふうな協調性のない奴はいるのかな?、もし仮に彼らがBCIにいったらどうなるのかな?
「BCIではいないよ。まず協調性がないやつがBCIにきても、無愛想でいることなんて不可能だよ。“おい、そこの2人ここへきて何を やってるんだ?、研究の調子はどうだ?、俺たちはこんな風に考えるんだが、君たちはどうかな?”、などという議論の中に否応なく巻き込まれるからね」。
ラ・セルバでエキセントリックな行動とみなされるものが、BCIではその下位文化によって「矯正」される可能性もあるわけだ。BCIのこ のようなフラタニティ的雰囲気についてはジェイムスと親しくなるにつれてよく聞くようになった。ただし、ジェームスは、BCIでは長期の研究者は短期の研 究者を無視する傾向がある、と言っていることにも留意しなければならない。つまり、研究者が、その研究領域にどのようなスケジュールで、どのように組み込 まれるかということで、その研究組織へのコミットメントと「矯正」の度合いも決まってくるのである。
3.2.4 ボランティアのヘンリー
ラ・セルバの我々の共同生活者についての記述が、大学院の博士課程の若い学生たちに関するものに偏重しすぎたかもしれない。そこで研究領 域も関心も異なる白人の小学校教師のヘンリーについて記しておこう。彼は研究者ではなく、研究助手をしているボランティアである。蟻の生態学を研究してい るゴードンをリーダーとする研究グループ通称コミーに参加し、事実上のサブリーダーであり、またマネージャ的存在であった。ヘンリーの社会的背景や生態系 に対する考え方が、生態学者の文化生産とどのように関係するのかは、今後の私の課題であるが、ここで挿話的に彼について記すことは、そのような議論の展開 にとって何らかの示唆を与えることだろう。
ヘンリーはユーモア精神旺盛のボランティアである。彼はサンフランシスコ郊外の出身で年齢は40歳後半50歳前半ぐらい、オークランドで 小学校教師をしている。ラ・セルバには今まで2カ月いて、あと2カ月ほど滞在する予定である。現在はゴードンなどの学生大学院生などのアシスタントを買っ てでて、一緒に調査したり実験室で蟻の分類などを教えたりしている。ここには完全にボランティアとして来ていて、余所からはお金をもらっていない。
ヘンリーがなぜ大学院生のゴードンと一緒に仕事をしているかというと、ヘンリーはインターネットでゴードンのプロジェクトを知って電子 メールを交わすうちに、ラ・セルバでの研究への協力活動に興味が湧き、ラ・セルバではじめてゴードンに知り合った。ヘンリーによると、ゴードンは電子メー ルでは、より成熟していて頭のよい男だと感じたらしい。「現実はどうだ?」と私が聞くと、「自分とゴードンが議論しているのを見たことがあるだろう?」 (彼らはしばしば激しい議論をする)、「しかし君たちは仲もいいよね?」と私が念を押すと「もちろん」と答える。確かに彼らはよく議論をしている。ヘン リーに言わせると、自分自身は蟻の生態学に関する専門的な知識はあまり無いために、高度な理論や前提──とくに統計──を背景にするゴードンの議論にはつ いていけないことがある。
ヘンリーはオークランドの主に黒人が多く住む地区で教えている。生徒は黒人のほかにはベトナム、ラオス、ヒスパニック系の子供たちがい る。教師はすべて白人──この人種的不均衡には彼はかなり憤りを感じているようだ──であり、オークランドのインナーシティの問題が最も深刻化したような ところに学校がある。学校を出ればホームレスがごみ箱を漁っているという現実があるからだ。
彼はカウンターカルチャー世代の人間である。彼に、カウンターカルチャーの世代の人たちのその後は、どのようになったのだと質問してみ た。彼曰く、カウンターカルチャーの時代は、物質文化の否定、反戦、社会的あるいは公共指向の生活態度がもとめられて、社会参加の思想が説かれた。彼自身 も教師を指向したのはそのような理由による。「カウンターカルチャーの伝統は現在ではなくなってしまったのか?」と聞くと。表面的にはアメリカの文化は物 質をもとめる社会に「逆戻り」した。しかし、深い部分では、その影響を受けた人たちの生活態度には変わらないものがあるという。ラ・セルバ保護区のオード リー夫妻もカウンターカルチャー世代に属するのではないかと思うが、彼らはここで働きより深く環境問題に関わっている。環境問題に取り組むことは、ひろく 社会性をもつことに他ならないからだという。
ヘンリーの両親は英米文学の大学教授だった。家にはテレビがなく、自分の幼年時代にはテレビを友達の家に見に行った思い出がある。テレビ は人間を非常に受動的にしてしまうと両親は批判していたという。
彼の見解によるとエコ・ツーリズムは環境教育の助けになるだろうという。もっとも彼が描くエコ・ツーリストは先進諸国から来た年寄りで金 持ちの白人で、それよりも地元住民に対する自然保護教育のほうが重要ではないかともいう。
セルバでの経験について尋ねたところ、彼は「皮肉にも」カリフォルニアの子どもたちの熱帯動物に関する知識の向上に役立つだろうねとい う。ヘンリーとは自然史(Natural History)の教育的効果について、それとは別の機会に話したが、彼が私の理解を訂正しつつ主張するには次のようなことであった。
彼は他の学科に代えて自然史の「授業」を一部、学校教育に取り込もうという部分的な代替案ではなく、学校の授業のシステム全体をちょうど 自然の中で人間が一から自分自身で学ぶようなものにするという根本的改革が必要だという。彼によると現在の教育制度はそれぞれの教科をバラバラに教えてい るが、小学校1、2年生の教育でそのようなことはよくない。実際に彼はそう主張してしばしば学校の教育方針と対立してきた。彼によれば、森林で生活すれ ば、さまざまなことを一から学べるし、森林の中で学ぶことはさまざまな学科で行われている知識が動員される良い機会となるである。教育はこのような統合さ れた形でおこなわねればならないというのである。
3.3 ミクロ社会認識
3.3.1 係留点としてのラ・セルバ
研究者たちが一過的に滞在するフィールドでは、さまざまな相互行動が観察される。彼らが研究に没頭している行動を含めて、食堂やフィール ドでの会話、冗談、何気ない発話などがそれらである。ここでは、そのような行動から、観察者が触知することができる彼らの社会性に関する事柄について考え る。日常生活の中で彼らの行動が他者に投企し、影響を与えたり与えられたりする空間的および時間的射程の範囲は短い。そのため、この相互作用から観察者が 知りうる彼らの社会認識はきわめてミクロなものである。これは、彼らが論文の中で描く自然の時間的尺度に比べて大変短い。
ここで、研究者自身から見たラ・セルバの研究施設としての「ライフサイクル」について考えてみる。ラ・セルバが研究の拠点として一定の成 果を出した後は、先端研究の拠点よりも、教育施設として意味の重要性が増しつつある。これは、ちょうど日本のフィールド研究における霊長類学 (primatology)の出発点となった宮崎県の幸島もまた、そこでの研究成果の蓄積にともなって、最先端の調査地からやがて大学院生や学部生のため の演習場所としての性格が変化していったことと類似している。ラ・セルバが研究地域のライフサイクルの後半に位置すると認められる根拠はいくつかある。ま ずここで長期滞在している研究者で、別の研究施設で常勤のものはいなかったこと、ラ・セルバの教育施設──科学観光の目的地──としての機能の強化、およ びコスタリカおよびラテンアメリカの若い研究者の増加である。
ラボに長期滞在している学者の平均年齢は若く(おそら20歳代の後半から30歳代の前半であろう)、学生や研究者がひっきりなしに滞在す るので、人間関係は永続性をもちにくい。研究者のマジョリティをしめる英語の話者たちは、その中でも一番紐帯がつよいように思われるが、もっとも、それす ら一時的な同僚として参加するだけで、その関係は恒常的なものではない。かれらの研究テーマ(6.付録(1):研究題目を参照)は多岐にわたっていて、研 究上の議論は共同研究者以外には実質的にはできないのが現状である。特に大学院の学生は所属する大学院の学業のスケジュールに拘束され、かつ滞在経費がか かるので比較的集中的に調査をおこなう傾向がある。ラ・セルバは、名実共に、さまざまな研究ができるが、同時に高度には特殊化されてはいない「学生実験 室」と化してきたのである。
3.3.2 食堂(dining room)
係留点あるいは一過点としてのラ・セルバの研究ステーションの中で、彼らは効率よく、また快適に──すくなくとも退屈でないように──調 査期間を過ごそうとする。この一連の努力は、食堂における彼[女]からの着席の場所や、食事時におけるテーブル・トークにおいて顕著にみられる。有能なガ イドであるアーニーは研究者たちがこぞって固まって同じような面子で席につこうとすることを次のように解釈した。
「研究者たちは観光客──ラ・セルバでの公的用語では訪問者(visitors)──をいろいろと根堀り葉堀り聞く五月蝿い奴だと認識し ている。研究者たちは、もし彼らのテーブルに研究者たちが座ったなら自分たちのことについて聞かれるだろうし、またそのような経験を受けているはずだ。だ から仲間内で座ろうとするのだ。」
この解釈はアーニーあるいは周りの職員たちの一般的解釈なのだろう。留意すべき点は、次の「従業員たちもまた観光客と同じ食卓につきたく ない」という解釈とセットになっていることだ。彼らの説明は研究者たちが観光客を回避する理由とおなじである。
「従業員たちもまた従業員どうし同じテーブルにつく。ガイドたちは食事のテーブルにおいてさえも観光客にいろいろと聞かれることがあるか らだし、また他の従業員たちは食事のときぐらいは仕事のことを忘れたいからだ。食事のときに誰も仕事の話をしたくないのだ。たとえばホルヘなどは、その豊 富な知識を買われて、食事のときでもいろいろと研究者たちに相談を受ける。またラボのマネージャのホセのお昼はかならず1時になってからだということを 知ってますか?」
研究者の行動の解釈は、彼女の職員からの視点を反映しているように思われるが、極めて興味深くかつ鋭い観察の産物である。
研究者の食卓行動が同じインサイダーの目から見ても興味深いものであることについて彼女から私は学んだ。私は、研究者とは異なった理由 (データを効率よく採集すること)で食卓のどこに就くかという、いわゆる「食卓問題」で毎回悩んでいたのだが、それは研究者にとっては観光客や見知らぬ余 所者を回避したいという理由からである。この指摘によって、私は状況を相対化することができ、彼らの行動が極めて文化的なサンクションによって規定されて いる実態を知ることができた。
言うまでもなく管理者の食堂での行動は社交性に満ちたものである。ラ・セルバの最高管理者であるモンタギューは、OTSのパトロンないし はコンソーシアムの委員のメンバーが訪問したときにはきわめてきめ細かいアテンドをおこなっていた。これは食堂内でも同様であった。勿論OTSの運営の形 態や予算配分の決定に与える委員の影響力を想像すれば、この行動は十分に理解可能となる。このような行動をするのは彼のほかには、研究部長パーシーで、そ の任を離れている科学者のオードリー夫妻は、その人たちが科学者であればゲストとして扱うが、委員などの管理職の相手は特別にはしないようだ。
BCIでのフィールド調査の経験のあるジェームスとの会話をするうちに、彼らの食事の際の着席の行動やテーブル・トークの行動を解釈する 枠組みが見えてきた。彼の解釈によると、研究者が同じ席に固まって座ろうとすることは、俺たちは一時的な滞在者ではないということを態度で表明することで ある。まったく熱帯雨林の中にもゴフマン的世界が存在するということである。もちろんこれは対他的なアクションであると同時に、アイデンティティの確認と いう意味で儀礼的に重要な行為である。
ジェームスの理解を敷衍すると、名声の高いフィールド科学者というものが、時間をどのように利用しているのかということを、生態学者の仲 間入りをした大学院生たち模倣しているのではないかということも示唆される。つまり、フィールド科学者は(a)忙しく、(b)分野が多岐にわたり、かつ (c)彼らの興味の範囲が狭い、という世界に生きているために、食事の時にしかお互いにコミュニケーションをとれない。先のOTS職員のアーニーの解釈と 同様に、食事のときぐらいは仕事の話をしたくないし、またできない。そこで食事のときには仕事の話ではなくリラックスした馬鹿話に興じたいという暗黙の合 意ができあがる。またこれらの解釈によって、ヘンリーではなくゴードンが変わった性格の持ち主であるという噂の流通もまた説明される。ここでひとつの留保 をつけておきたいのは、食事の時も生態学の話に興じたい「クレイジーな」連中もまたいることである。蟻生態学者のゴードンや魚類生態学者ダグラスは食事の ときでも仕事の話をしたがるバークレー校的タイプの研究者だからである。
週間の単位のオーダーで見れば、テーブルの面子は入れ替わり、明らかにテーブルのメンバーには遷移が起こっていることが確認される。食堂 のテーブルはラ・セルバにおける社会空間全体の喚喩である。
ラ・セルバの社会空間を別の観点から隠喩的に表象するとすれば、ここは病棟だとも言える。入院患者はお互いの自己紹介を通して仲良くなる が、死んでいつのまにか居なくなる人もいる。入院している人たちの関係が重要であり、死んでいった者たちは患者の記憶にのみ残るだけである。私が滞在中の 2週間の間に何人かの大学院生は姿を消した──つまりもとの大学の教室や研究室に戻っていったのだが。そして病院のように大げさな退院ははばかられ、仲の よい人たちだけでつつましい挨拶が交わされ、何事もなかったように日々の研究が続く。
3.3.3 模倣行為
生態学者は、自然の解析をおこなう際に、彼らの模倣能力に依存しながら研究をおこなっている。模倣は彼らの学問的想像力の源泉である。彼 らの模倣的能力に関する挿話をいくつか記してみる。
彼らはフィールドでお互いに出会ったとき、自分たちを研究対象に同化させ、それらを対比させるような冗談を言い合う。それは、一種の自己 擬態とも言える行動である。
ラ・セルバでは、とくに動物を相手にする生態学者たちの間で、ときどき研究対象を含めた冗談を言い合う。たとえば蟻を研究しているヘン リーは、蜂の受粉行動を研究しているドイツ人の若い研究者ウィルヘルムを茶化して「蜂人間 Bee People はあちこちふらついて困る」と言う。すると彼も負けずに、「蟻人間 Ant People は群で固まって全くどうしようもないね」と言い返すというふうにである。
彼らの揶揄はフィールドやラボでかいま見る他分野の領域の研究者の方法論や調査についての考え方を大まかに把握して、巧みに冗談に言い替 える。
ただし、フィールドでの彼らは忙しく、実際に隣接領域間ではなかなかコミュニケーションがなく、他領域に関する理解は極めて浅くもあるの で、単純なステレオタイプの応酬の次元に留まっており、特に高度なレトリックに発展しうるものはない。
彼らは自分たちの得たデータを創造的に外部の現象──とくに人間および人間社会──に当てはめるというを危なっかしいことも、ときに平気 でおこなう。これは、どうも社会生物学論争が起こる以前からある彼らの「伝統」であるようだ。
井上さんは社会性昆虫について長年調査研究されてこられた。彼の研究対象は主に蜜蜂で、数十種類の蜜蜂の社会的行動を長年にわたって観察 してきた。蜜蜂には自分の「妹」と「叔母」と「赤の他人」を行動によって区別していることを知る実証的根拠がある。また隔離実験によって育てたものも、そ のような「認知」をおこなうことができると井上さんはいう。[私は彼の話を聞きながら心の中で自問する、これは「認知」の遺伝子的根拠と言っているのだろ うか?]。また、そのような一連の「他者」の区別の行動には蜜蜂の種類によって「親和的」なものから「敵対的」なものまで幅がひろい。このような行動の背 景にはその種がどのような環境を利用するのか?、その種類がどのような「社会生活」を営むかなどによって決まっているという。
すなわち、彼の研究領域は一言でいうと「社会生物学」である。もちろん「論争」の内容についても熟知されておられる。
井上さんはいう、「社会」のことを研究するのには人間より、昆虫のほうが適していると思う。社会について調べるには霊長類がいいという人 もいるが、霊長類の社会のタイポロジーはいくつのタイプに限られている。その点、昆虫の「社会」の多様性は極めてゆたかである。また生まれてすぐの双子を 別々の環境に放り込んで育てることの倫理的な問題もない。もっともあと数年したらそんなことも出来なくなるかもしれないが[註:彼はアニマル・ライト運動 のことを半ば冗談で言っている]。
フィールドで得られたデータをもとに研究者は論文を書く。しかしラ・セルバのステーションで彼らは論文を書くことはしない。ここでは、採 集されたデータを多角的に調べ、予備的な分析や考察をおこなうのみである。あるいは、研究計画の延長上で、補足的なデータをとる必要性が生じたとき、再び フィールドに出かける。基本的にこのことの繰り返しだけである。
食事のテーブルで論文執筆に関する話題はほとんど耳にすることはなかった。論文執筆は、彼らにとって自明の活動であるからなのだろうか。 唯一の例外はダグラスが、一度だけヘンリーに科学雑誌に寄稿するように示唆したことがあった。科学者であるダグラスが、ボランティア兼アマチュア生物学者 であるヘンリーに論文執筆を勧めるのも、それは生態学者の模倣を勧めていることなのだろうか。
蟻の研究プロジェクトのボランティアであるヘンリーと魚類生態学者のダグラスが夕食のテーブルで話している。ヘンリーはダグラスの質問に 答えて、彼が参加している蟻の調査研究のプロジェクトでの成果について話している。ダグラスはいくつかの点をヘンリーに質問して、それについての答えを彼 に求める。そのあとダグラスは「今聞いた話は、面白そうだからどこかで発表したらどうだろう?」と提案する。ヘンリーは自分は一介の教師で学問的な訓練を 公的に受けたことがないから、書き方がわからないと言う。ダグラスは学会誌などへの投稿ではなく、一般向けの科学雑誌などはどうだろうかと勧める。彼は自 分の属している専門の学会誌を彼の活動の場にしているが、同時に魚や魚釣りの雑誌などにも寄稿するという。ダグラスによると、学会誌は投稿しても匿名のレ フェリーのコメントが細かくいろいろと聞いてくるし、またそれらの修正などできわめて時間がとられる。それに対して科学雑誌は、文章にしてから掲載される までの時間が早いし、また──これは重要なことだが──ペイもいい。ただし、一般科学雑誌には何点かの写真が必要だ。ヘンリーはダグラスに、じゃあやって みるのでできた暁には見てはくれないだろうかと聞く。ダグラスは自分が一般雑誌に書いたものがあるのでそれを見せてあげると約束した。
3.4 外部社会への関与
3.4.1 北米の研究者と自然保護
私の最初からの印象どおり、このラボラトリーはアメリカの大学の研究室のようであった。フィールド・ステーションもまた実験室の延長にあ るわけだから、当初私がこの調査のデザインを描いたころに抱いていた「研究室は自然保護言説の生産拠点である」とは全くかけ離れた世界であった。
自然保護意識に関する違いは、彼らが従事している研究の内容や方法論よりも、彼らの出身国や個人的な体験に依存するようだ。例えば、かな り一般化して言えば、コスタリカ人の自然保護主義の考え方は北米人に比べてよりローカルな政治の視点から行われていることが会話の中から容易に受け取るこ とができる。他方、北米を中心とした研究者の自然保護主義的な見解は、ローカルな政治的な意味あいよりも、具体的な環境破壊への反発や批判を通してグロー バルな政治的問題に関心が移りがちであり、またその処方箋もいわゆる人間の生活よりも環境の保護を優先する環境主義の考え方に近い。
まず、北米を中心にした生態学者というものは、自然保護に対してどのように考えているのだろうか。最初は、ゴードンとの対話である。
分子生物学者はどうか知らないし、またその態度も異なるだろうが、コロラド大学の環境科学部のメンバー──そのほとんどが生態学者──は 環境問題に深く関心をもっていると思う。いったいどれくらいの生態学者が自然保護運動にどのように参加しているかは私(=ゴードン)は知らない。しかし実 際に保護運動に関わっている同僚たちもたくさんいる。私の場合は、具体的に自然保護運動に関わっているわけでもないし、またその時間もない。唯一関与して いるとはConservation Biologyを講読しているぐらいだろうか──この雑誌は学生や大学院生には安く購読することができるからね。
自分の研究は、将来自然保護運動にとって十分寄与するものと思っている。実際、農業関係の研究費の申請をしたが、そのなかにも自分の蟻の 研究が、生物と作物の関係を解明する問題に寄与できうるはずだと主張した。
魚類生態学者のダグラスと知り合ったときのことである。彼はリバーステーションの下でウェツトスーツに身をかため保育行動をする魚の行動 観察をおこなっている。ここには過去2度来たことがあり、一番最初は8年前だった。彼はテーブルにつくなり自己紹介をした直後に、自然保護について語り始 めた。
彼に言わせると現地人も科学者も、川の魚のことには全然科学的な関心がないという。魚はフライにして食べるだけと思っている。しかし、プ ランテーションの開拓によって川や沼はどんどん汚染されており、沢山の種類の魚が危機に曝されているという。
ある日の朝食時に私は熱帯生物学協会(TBA)の調査団の英国人の生態学者と話した。この協会はヨーロッパの大学のコンソーシアムであ る。彼女はこの協会が独自のフィールドをもたないために、協会認定のフィールドを探しにやってきた。ラ・セルバの他のOTSの研究施設も調査する予定。以 前にタンザニア(あるいはアフリカのあるサイト)を調査地にしていたが、経理上の運営がずさんで引き揚げた経験があるという。彼女によると、TBAが OTSのコンソーシアムとして参加可能かか、予算的にどうか、などの可能性を調べている。
彼女はエコ・ツーリズムに関しては極めて否定的な見解をもっていた。旅行者と生態学の研究者は決して接点をもたないという意見である。彼 女の悲観的ビジョンは、アフリカでの彼女の経験に影響されているという印象を私は強くした。そのときダグラスが同席していたが、彼はその考え方に同意せ ず、反論した。
ジョージア大学の土壌生態学者ドナルドとはなす。彼の解説は生態学の科学史の授業を聞くようであった。
彼によると、環境保全に関して生態学がもっとも論争的になった時期は1970年代である。この時期について興味深い本があるという。また Background of Ecologyを書いたマッキントッシュも、最近短い論文を発表した。
もうひとつの大きな論争は1950年代に大陸移動説に基づいてそれまでとは異なった生物地理学説が提案された時である。このときはニュー ヨークの自然史博物館のマルクス主義者の生物学者たちが大きな論戦を挑んだ。
彼によるとこのような生態学の理論の当否は結局歴史的な吟味を経て多少なりとも、公平な議論の俎上にのぼるという。彼はクーンやファイヤ アーベントなどの科学史なども引き合いに出して、この問題を論じるベースが歴史にあると言っている。
ドナルドは生態学者の知識が、きわめて強いパターン認識によって構成されていると指摘した。このパターンを学ぶことで、生態学上のさまざ まな議論をおこなうことが可能になるという。
彼はまた、他の生態学者の意見と同様に、生態学者には変わり者(strange, curious)が多いという。
生態学者には自然保護者が多いのか──という私の質問には、「生態学者は伝統的には左翼が多く、自然保護活動には熱心だよ」という。その 根拠としては、ドナルドがときどき参加するメーリングリスト上での議論は自然保護に関する議論がきわめて多いことをあげた。
3.4.1 OTS職員と自然保護
上に述べた者はすべて来訪研究者であり、彼らの自然保護をはじめとする外部世界との関係に関する主張は、抽象的な議論の範囲を超えるもの ではなかった──私と議論をした場所が食堂での食後のひとときだったからかも知れない。そこで、以下では、OTSで働く人々と自然保護やエコ・ツーリズム に対する対応──これらはすべてインタビューのための時間を彼らに特別に割いてもらって採集したものである──について述べてみよう。
ホルヘは1981年からOTSで仕事をする生態学者たちの調査助手──彼に言わせるとinvestigador──として働き、8年後の 1989年にツーリストガイドとして正式にOTSに採用され、90年からこの社会教育部門で働いている。彼に言わせるとOTSが行っている教育には、ひと つにはエコ・ツーリストと地元民という一般大衆へのものと、科学的調査研究のために専門家をサポートするものの2つに分けられる。後者は、専門家といえど もこのフィールドステーションを十分に利用してもらうためには、一定の支援つまり教育が必要ということになる。
この社会教育部門は、ビジターで最大30名で月間およそ40のグループ、コスタリカ国内の3〜6の学校、8つの地方コミュニティを受け入 れている。また近隣の学校と協力して「プエルト・ビエホの水のモニター調査」(Monitor de Agua, Puerto Viejo)というプロジェクトを組織して、付近流域の水質調査などをおこなっている。また昨年、はじめて「開放されたラ・セルバ」(La Selva Abierta)という行事をおこない付近の人びとにOTSを開放し、無料のガイドツアーを実施したが、300名ほどの来園者があった。近隣へのコミュニ ティのメンバーを定期的にOTSに招待して広報活動に専念している背景には、OTSが「グリンゴのコロニア」(白人の居住地)と近隣の人たちから批判され てきたことが背景にあるようだ。ホルヘが言うように、実際にほとんどの研究者は北アメリカ人で、研究者にもビジターにも非常に高い値段で施設やサービスを 提供することを彼は十分に理解している。もちろん近隣の人たちを招待するもっとも重要な目的は、人びとをOTSに招待し自然保護教育を通して、保護意識を 高めるという点にある。
このセクションが直面している障害とはなにか──との私の質問には、職員が少ない、近隣のコミュニティの人たちを招待するための輸送手段 が少ない、予算が少ない(2名の常勤、2名の非常勤職員で年間三千ドル)の3点をあげた。
ホルヘによるエコ・ツーリズムの定義は、彼の自然保護に対する経験的なビジョンが混じっているのか、きわめてユニークである。
彼によれば、観光がそれで儲けた金を自然保護のために利用できるとき、そして自然を破壊しないとき、それをエコ・ツーリズムと呼ぶことが できるという。セルバのOTSはエコ・ツーリズムの先進的な場所である。というのは1989年にWWF(世界野生生物基金)とOTSが共同で資金をだし て、ここにエコ・ツーリズムのシステムを創設したからだ。この年は言うまでもなく、ホルヘがナチュラリストガイドとしてOTSに就職した時である。
地理情報システム(Geographical Information Systems, GIS)の専門家のマリベルはコスタリカ人で自称「自然保護主義者conservacionista」である。
いつから、どうして?、という私(=池田)の質問に対して、エンジニアであった父親が彼女が小さい頃から自然に親しむためにいろいろなと ころに連れていってくれたからだという。したがって、OTSでGISの専門家を募集していることを聞いたとき、自分に相応しい仕事であると感じて応募した という。
彼女は付近の環境汚染問題──とくにニカラグアからの不法労働者が引き起こす──を危惧して見守っている。エコ・ツーリズムという言葉に 対しては、批判的に用語を定義して使わないとだめだという。あるいはエコという用語が我々の身の回りに氾濫しているとも。そのためにむしろ環境保全 (conservaci溶)のほうが適切ではないかと指摘する。環境教育は非常に重要であり、またボランティアとして自然保護官(Policia Ecologica)の仕事も進んで引き受けるという。
森林管理が専門の職員ダニエルに対して、君は自然保護主義者か?という質問を私はおこなう。
彼は、そうだと肯定した。しかし、コスタリカの自然保護運動に関しては、彼の印象によると偽善者(hip幼rita)だらけだと辛辣に批 判する。コスタリカは自然の天国であるというのは真っ赤な嘘で、ダニエルによればコスタリカの自然環境、とくに希少種の絶滅や森林伐採問題は深刻であると いう。彼は、昨夜みたテレビ番組の中でもここから北部の熱帯雨林の森林が無秩序に──業者たちが仮に許可をとっていても、法とその施行制度の不備で実際に はだれでも伐採できるという──伐採されていることを報じていたが、これがコスタリカの現実だという。彼によると、コスタリカの北部でまた南部で無秩序な 森林伐採がおこなわれていて、みんなそのような現実に目を背けて、自然保護を礼讃しているという。マヌエル・アントニオでは、公園の収容力に対して3倍以 上のホテルの部屋があるという。またホテルはエコロジカルを標榜しているが、実際は下水をそのまま川や海に流している。
ではどうすれば、この状況を改善できるのか?──という質問には、「教育しかない」という。ただし、彼の言う教育は単に学校教育だけを指 していない。親は子供をまねる。たとえば親子でバスで旅をして、父親がゴミをバスの窓から捨て、続いて母親が別のゴミをすてる。そうすれば子どももそれを 真似て窓からゴミを捨てることをまなぶだろう。だから家庭レベルでの自然保護教育が必要だという。
エコ・ツーリズムという言葉の定義をしてくれないだろうか?──という私の質問には、彼は観光客を教育して、結果的に彼らに対して自然に 対して敬意を払うようになれば、それがエコ・ツーリズムだという。そして彼の予測ではコスタリカのツーリズムのうちエコ・ツーリズムを実践しているのは2 割ぐらいにしかならないという。
OTSの職員ではないが、コロンビア共和国のWorld wildlife Conservation Foundationに属して自然保護を専門に調査している女性に聞いてみる。彼女は今回、22名のラテンアメリカの学生を対象にした熱帯生物学の短期研 修に教師として参加している。OTSのクルソには以前学生として参加したことがある。
彼女は、コロンビアのエコ・ツーリズムの流行に否定的な見解をとる。コロンビアのある保護地での彼女の経験によると、観光客は白人(グリ ンゴ)が中心で、金を払わない、指定された道以外のところに侵入するなどの問題をおこしている。エコ・ツーリストは自然を消費するだけで、自然から学ばな いのだという。
自然保護問題に関しては、コロンビアの彼女のフィールドもまたラ・セルバと同様に、近隣の住民が木を切ったり環境汚染を引き起こしたりし ているので、周辺住民と保護地が協力関係をもつ必要があると言う。とくに住民への自然保護教育がおこなわれるべきだと主張する。
エコ・ツーリズムに関してのOTSの造林学の研究職員アリエルにコメントを求めたら次のような返答が戻ってきた。
コスタリカではエコロジーがあまりにも「政治化−政治道具化 politiqueria」されている。エコロジーが政党政治おける大きな課題になっていると同時に、政党によるエコロジー政策が党派の権益誘導のために 行われているきらいがある。また庶民の間では、エコロジーやエコあるいはベルデ(=緑)を冠した商標やパッケージなどが流行しているが、これらの内容はほ とんどエコロジーとは無関係である。つまりエコロジーという用語は形骸化しているという。
エコ・ツーリズムに関しても多少なりとも──マリベルと同様に──距離をおいているように思える。彼に定義してもらったエコ・ツーリズム は、ネルソン・グレーバン教授の環境観光と生態観光の区別と似ている(池田 1996を参照)。つまり、自然をみて観光として消費するだけでは、あるいは自然から学ぶという行為がなければ、それは観光において自然を利用しているだ けだという。もし、自然環境のなかで旅行者が、そこで思索したり、そこから学ぶことがあればそれがエコ・ツーリズムだという。彼は海岸での観光客の過ごし 方を例にあげて、ビーチリゾートでくつろぐだけという行為と、海中に潜って、図鑑を引いたり生物について学ぼうとするという行為の差をあげてこの区別を説 明した。
アリエル、君は自然保護主義者?と聞くと、言葉を選びながら次のように答えた。保護には、環境保全(conservaci溶) と自然保護(preservaci溶)の2つの考え方がある。前者は自然を利用するために自然を保護していこう、あるいは賢く利用しようという立場で、後 者はとにかく保護しないといけないという見解である、と。
最後にメルク社とインビオ(コスタリカ国立生物多様性研究所)の関係について質問した。数パーセントのコンセッションあるいは利潤のシェ アについてはブラジルやインドネシアの反発について私は解説したが、彼は次のように答えた。シェアの割合については、どれくらい儲かったのか、生産物がど れくらいの影響力をもつか、ということが分からない限り適当かどうか判断することできない。世界の有数の製薬会社そのものの存在が問題があるということ だって言える。医薬品は人間の健康を損ねてきたということもあるからだ。ただし、このような契約がコスタリカにとって研究、教育、開発のインセンティブに なることは確かだ。
有能なガイドであるアーニーは大学で生物学を専攻し、11年間「観光客」に対してグアナカステで教育やツーリストマネージメントに関する 仕事をおこなってきた。最初は、国立公園局で自然保護教育のちには、あるホテルに雇われて「エコ・ツーリズム」のアレンジメントをやっていた。子どもたち に対する自然保護教育にも従事していた経歴をもつ。
彼女は「観光」や「エコロジー」という単語にかなり敏感に反応する。自分たちが現在OTSでおこなっている活動は、それではないことを強 調する。また一般に通用している観光用の言葉を使わずに言い替えをおこなう。例えば、OTSの訪問者はツーリストあるいはエコ・ツーリスト (turista, ecoturista) ではなく訪問者(visitante)、自然観察路でのガイド付きの案内は、ツアー(tur) はではなく 旅程(gira)だと言い換えられる[注:turはスペイン語の正書法にはないが、英語のtourのことである]。
OTSでの自然観察希望者に対する取り扱い方(のポリシー)は、彼女の言を整理すると、次の3段階で発展してきた。 最初は、無秩序にビジターを受け入れていた時代である。これは89年以前の時代で、OTSは訪問するビジターから料金を徴収し、ガイドはビジターによっ て直接あるいは旅行をアレンジした会社をとおして雇われていた。OTSはこれらのガイドには料金を徴収しかなった。料金はガイドが決められるし、またチッ プなども支払われただろうから、このような自由契約の時代のガイドの収入は今よりもよかっただろうとアーニーは推定する。
つぎに89年ごろからはじまった専属と自由契約のガイドをOTSが用意して園内を案内させる方式であるが、時間のスケジュールはフレキシ ブルであった時代である。ビジターの予約はサンホセとラ・セルバの両方でおこなっていて、ビジターの訪れる時間や彼らのスケジュールに合わせて適当に調整 されていた。彼女が就職したのもこのころである。
最後に昨年(96年)の3月から導入されるようになったビジターの観察時間帯を設定する方式である。現在では8時から11時半までと、1 時半から5時までの、それぞれの3時間の時間帯をきめて、一度に案内するビジター数を制限する方法である。さらにこの改革はツアーのカテゴリーを分類し て、それぞれにツーリスト/ビジターの国籍、グループサイズ、直前の訪問ホテル、ラ・セルバに関する情報の入手方法、今後の情報希望の有無──これは寄付 行為を重要な財源にしているOTSにとって重要である──などを調査している。
現在のこの方法におけるビジターの受け入れは、Day、 Full、 Overnightの3つのカテゴリーがある。Dayは時間帯の内の一部、Fullは午前と午後の全部をつかい、また人数と希望によってはOTSに関する レクチャー(charla)なども開催する。
さらにこれ以外に夜間ツアー(Tur Nocturno)、バードウォッチング("Birding 101")、研究ツアー("Research Tour")などのプログラムを用意しているが、現在までのところバードウォッチング以外は──ビジター数が少なく──十分な成果があがっていない。
彼女のエコ・ツーリズムに関する心証はきわめて悪い。コスタリカではどこでもエコを関した商品が氾濫していることを指摘していた。アー ニーにエコ・ツーリズムの定義をしてくれないかと質問したところ、次のような趣旨の発言をした。
エコ・ツーリズムは小規模の経営(micro-empresa)で、エコロジカルな考えを含めて人びとの生活を助ける形態の観光というこ とであり、これはエコ・ツーリズム自体の本来のあり方にもとづく定義ということになる。
4. 考察
生態学者は、2つの研究のドメインをもつ。ひとつは実験と調査で、もうひとつは論文生産のためのデスクワークである。後者には、さら学会 や国際シンポジウムなどの知的情報の交換活動なども加えることができる。前者の実験と調査は、彼らがプライマリーな情報を得る領域である。
ナチュラリストは、自然環境に親しむことをプライマリーな目的としてしており、その多くはアマチュアである。それに対して生態学者はナ チュラリストと異なり、「自然」そのものから何かを得るというものではなく、生態学のさまざまな概念装置や実際の計測計器を通して「自然」を、操作可能な 客体として取り扱う。彼らは自然科学者のなかのひとつの職業領域を形成する。しかし、生態学者の自然環境の中で仕事をおこない、また常に自然環境に親しん でいることから、ナチュラリストと同様に「自然」からさまざまなアイディアを得ている面も多い。
生態学者の活動の多くはデータ収集、分類、集計、解析に使われる点で他の実験系自然科学者と変わらない部分もある。つまり実験系科学者の 生活世界が「実験室の生活」(laboratory life)であれば、フィールド系科学者の生活世界は「実験室とフィールド生活」(laboratory and field life)なのである。科学社会学に関する実地調査においては、このフィールド生活に関する情報が圧倒的に不足している。
生態学には下位領域によってきわめて多様な概念装置と方法論がある。この事実は生態学者の間で経験的によく知られている。生態学の下位領 域が、研究者の性格や振る舞いに大いに影響するというサブカルチャー的機能をもつということは、研究者の間では経験的に広く認められていることである。
他方、科学は普遍であるという考え方が常識として存在する。生態学を含め自然科学者は英語──学問を規定するもっとも優位な言語──を通 して一種の「想像の共同体」を形成している。そこでは方法論のユニークさは尊ばれても、訴えかける主張には普遍的なものがなければならないというサンク ションがある。ではこのサンクションはどこから生まれるのか? 学生時代からの実験と観察の修業、学問的議論(=パラダイムの学習)、独自の実験と観察に よる論文の生産と流通によってである。このような常識を決定する媒介変数のなかでもっとも強力なものは、その領域でもっとも権威のある科学雑誌や、そこで 名声を得た人による教科書などである。そこには文化的な差異のようなノイズが存在してはならない[はずである]。しかし、先に述べたように経験的には自然 科学者においてもその出身の社会や文化との関連を論じる研究も存在し、かつ当の科学者においても功成り名を遂げた人において文化的影響の存在を明確に表明 したり意識する人も数多く実在する。
そのような多様性は、論理的に整理にできる2つの軸から形式的に四分割され、相互に比較することができる。つまり生態学の下位領域におけ るサブカルチャー間の比較の軸、および生態学者の帰属文化による比較の軸によって分けるのである。これによって2×2の4つの組み合わせ、次の(a)から (d)までの組み合わせが考えられる。
(a)生態学者は下位領域においても学者の帰属文化においても影響を受けるため、多様な科学者と多様な理論がみられる。
(b)生態学者は下位領域のサブカルチャーの影響を受けるが、科学者の帰属する文化の影響は少ない。
(c)生態学者はどのような下位領域であろうとも、また彼らがどのような文化に帰属しようとも、その理解も行動も普遍的に共通である。
(d)生態学者の下位領域による差異はほとんどなく、生態学はその学者の帰属する文化によって規定される。
このうち一番最後の(d)は一番受け入れにくい仮説であろう。また (c)の説は理念としては間違っていないが、経験的に妥当性が少ないことは、生態学者本人たちが認めることであろう。(a)と(b)を有力な仮説として チェックすることは、日常の経験や興味から言っても興味深いことである。もっとも、このような議論はあくまでも形式論に終わる。この形式論的議論を無効に する最も強力な反証は、科学者の創造性やエキセントリシティが、実際に科学理論に大きく反映されることであろう。
ラ・セルバで知り合ったある北米の土壌生態学者は、自分は日本の研究者と交流したことがないので日本との比較は分からないと留保した上 で、ヨーロッパ人とのつき合いの経験によると研究者の帰属する文化よりも下位領域に違いが大きいという。この心証は、私のフィールドワークにおいても同様 に持ったが、決定的な証拠をこの調査において得たわけではない。
彼らの文化生産の核心にせまるためには、ラ・セルバ以外の保護区での行動観察の他に、フィールド以外での彼らの社会的活動、すなわち実験 室での活動、論文生産、教室における講義やセミナーについても調べる必要がある。もちろん、それらの調査研究は、生態学者たちの生活の全体像を把握すると いう見込みのない希望に基づいて行われるのではなく、それぞれの過程において、彼らがどのように意味と実践を構築しているのかという文化の生産という観点 からなされなければならない。これは、そのひとつの試みであった。
謝辞
本稿で依拠した資料の大部分は、筆者に対して交付された平成9年度文部省科学研究費・海外開発動向調査「エコ・ツーリズム(生態観光)と持続 的開発に関する先端研究の動向調査」(在外研究・決定番号8-研-179)によって収集されたものである。この調査研究に先立って研究の機会を授けてくだ さったカリフォルニア大学バークレー校人類学科ネルソン・グレーバーン教授(Dr. Nelson Graburn)、コスタリカの熱帯研究機関での調査にさまざまな便宜をはかってくださったリー・ストレンジ・シェックさん(Ms. Ree Strange Sheck)、ブルース・ヤング博士(Dr. Bruce Young)およびすべての職員の皆さん、ラ・セルバにおいてさまざまな情報を授けてくださった諸大学の大学院生の方々、そしてラ・セルバで初めてお会い し、さまざまな示唆を授けてくださった京都大学生態学研究センターの故・井上民二教授、これらの方々に感謝いたします。井上先生のご冥福をお祈りします。 なお、井上先生のお名前を除いて、研究者や職員の方々のお名前は仮名にしました。
ACKNOWLEDGMENTS
The field research which forms the basis for the discussion in this paper was carried out in La Selva Biological Station, the Organization for Tropical Studies Inc., OTS, from February 22 to March 8, 1997. A Research Subsidy from the Ministry of Education, Science, Sports and Culture project , メThe Investigation on Advanced Studies in Eco-Tourism and Sustainable Development in the United States of America,モ allowed me to do research in both north America and Costa Rica. In OTS, Ms. Ree Strange Sheck, the Marketing Director and Dr. Bruce Young, Co-Director of La Selva station provided me with research opportunities. Dr. Tamiji Inoue, unfortunately is died by airplane accident in Malaysia September 6, 1997, was interested in my project and encouraged me to publish this paper. I Would like to thank all of them.
In the memory of Wilbert Vere Awdry,
1911-1997
5. 文献
ドーキンス、R. 1980
『生物=生存機械論:利己主義と利他主義の生物学』日高敏隆・岸由二・羽田節子訳、東京:紀伊國屋書店
Evans-Pritchard, E.E. 1962
Essays in Social Anthropology. New York: The Free Press.
フーコー、M.(Foucault, Michel) 1977
『監獄の誕生:監視と処罰』田村俶訳、東京:新潮社
池田光穂(Ikeda, Mitsuho) 1980
「幸島野生ニホンザルにおける採食行動の量的研究」、鹿児島大学理学部生物学科卒業論文、40pp.+27 plates.
池田光穂(Ikeda, Mitsuho)1996
「コスタリカのエコ・ツーリズム」青木保ほか編『移動の民族誌』、pp.61-93、東京:岩波書店
池田光穂(Ikeda, Mitsuho)Online
Laarman, Jan G. and Richard R. Perdue 1989
Science Tourism in Costa Rica. Annals of Tourism research 16: 205-215.
McDade, L., K.S. Bawa, H. A. Hespenhide, and G.S. Hartshorn eds. 1994
La Selva: Ecology and Natural History of a Neotropical Rain Forest. Chicago: University of Chicago Press.
シンダーマン、C.(Sindermann, Carl)
『サイエンティストゲーム:成功への道』山崎昶訳、東京:学会出版センター 1988
『成功するサイエンティスト:科学の喜び』山本祐靖・小林俊一訳、東京:丸善 1989
『続サイエンティストゲーム:若き科学者のための生き残り戦略』山崎昶訳、東京:学会出版センター 1987
Worster, Donald 1990
The Ecology of Order and Chaos. Environmental History Review 14:1-18.
6. 付録(1):研究題目 以下は、本研究の調査期間にOTSのラ・セルバ保護区で行われていた研究プロジェクトの一覧(Reseacher and Their Projects, Feb 1 through 15, 1997)である。なお、研究者の氏名と所属は省いた。
Alternative for reforastation with native tree in Sarapiqui. Design of a Geographic Information System for La Selva. Community Ecology of Exotic species Phenology and Reproductive biology of rain forest cycad. Demography and ecophysiology of regeneration of tropical rain forest trees. Current and future carbon budget for tropical rain forest: cross-scale analysis. Polinization of Ciclathaceae. Reproductive success in the bat Saccopteryx bilineata. Effects of Volcanic process on tropical streams. Seasonal variation in the blood parasites of Scarlet-rumped Tanagers. The role of tree architecture in structuring spider communities. The effects of hervivorous mammals on the regeneration of Dipteryx panamensis and Penthaclethera macroloba. The importance of environmental heterogenity in understory spider communities. Bee polination of tree in a tropical wet forest. Monitoring of endangered bird species in Braulio Carrillo - La Selva.
7. 付録(2):地図とラ・セルバの 入所規定等
図1.ラ・セルバ保護区の全体図 図2.施設配置図 文書資料1.宿泊者利用規定 文書資料2.研究施設利用規定
8. 付録(3):写真
写真1.ラ・セルバ保護区への入口 写真2.エコ・ツーリストが写真を撮る 写真3.生態学者がノートを取る 写真4.樹表面を伝う降水の量を測定する装置 写真5.フィールドに向かう魚類生態学者 写真6.フィールドに隣接した人工環境で魚の行動を観察する 写真7.フィールドで談笑する蟻生態学者と蜂生態学者 写真8.プローブ(検知端子)を対象木に接続する植物生理学者
【補足説明】
・この論文で登場する科学者たちの名前 (仮名)は、機関車トーマス(ウィル バート・オードリー原作)に出てくる機関車などの名前から取りました。当 時の豚児や職場の同僚の子息が、この物語に熱狂的になっていたからです(2013年10月13日附記)。