On Arendt's Human Condition,
1958
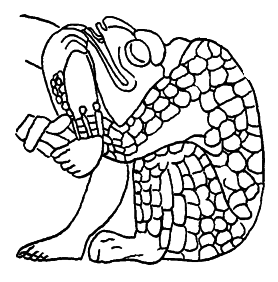
ハンナ・アーレント『人間の条件』ノート
On Arendt's Human Condition,
1958
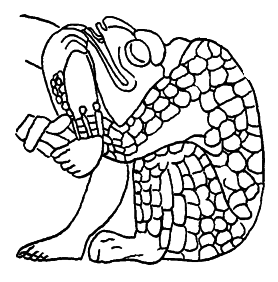
池田光穂
Arendt, Hanna. Human Condition. University of Chicago Press, 1958
中央公論社による翻訳、1973年5月、のちに筑摩 書房、アレント、ハンナ『人間の条件』志水速雄訳、Pp.43-131、筑摩書房、1994年。書籍案内→「条件づけられた人間が環境に働きかける内発的 な能力、すなわち「人間の条件」の最も基本的要素となる活動力は、《労働》《仕事》《活動》の三側面か ら考察することができよう。ところが《労働》の優位のもと、《仕事》《活動》が人間的意味を失った近代以降、現代世界の危機が用意されることになったので ある。こうした「人間の条件」の変貌は、遠くギリシアのポリスに源を発する「公的領域」の喪失と、国民国家の規模にまで肥大化した「私的領域」の支配をも たらすだろう。本書は、全体主義の現実的基盤となった大衆社会の思想的系譜を明らかにしようした、アレントの主著のひとつ」
講談社文庫版の牧野雅彦訳:ハンナ・アレント(一九 〇六‐七五年)の主著、待望の新訳!「労働」、「仕事」、「行為」という三つの活動の絡み合いの中で「世界からの疎外」がもたらされるさまを描き出した古 典。科学と技術に翻弄され続ける人類の行く末を考えるためには不可欠の書を第一人者が明快な日本語に訳し、懇切な訳注を施した。これぞ新訳、これぞ新しい スタンダード!
第1章 人間の条件
第2章 公的領域と私的領域(→読書ノート)
第3章 労働
第4章 仕事
第5章 行為
第6章 活動的生活と近代
●章立て
第1章 人間の条件 The Human Condition
第2章 公的領域と私的領域 The Public and the Private Realm
第3章 労働 Labor
第4章 仕事 Work
第5章 活動 Action
第6章 〈活動的生活〉と近代 The Vita Activa and the Modern Age
**
Chapter(課題文献 with
password)
***
★英語版「人間の条件」
| The Human Condition[1]
is a book published by Hannah Arendt in 1958. It is Arendt's account of
how "human activities" should be—and have been—understood throughout
Western history. Arendt reevaluates the modern relevance of the vita activa (active life), in contrast with the vita contemplativa (contemplative life), which was esteemed in older philosophy. She airs her concerns that the debate over the relative status of the two has blinded us to important insights about the vita activa and how it has changed since ancient times. She distinguishes three sorts of activity—labor, work, and action—and discusses how they have been affected by changes in Western history. |
『人間の条件』[1]は、ハンナ・アーレントが1958年に発表した著作である。これは西洋史を通じて「人間の活動」がどのように理解されるべきか、また実際に理解されてきたかをアーレントが論じたものである。 アーレントは、古来の哲学で尊ばれてきた「観想的生活(vita contemplativa)」と対比させつつ、「活動的生活(vita activa)」の現代的意義を再評価する。彼女は、この二つの活動の相対的な地位をめぐる議論が、ヴィータ・アクティヴァに関する重要な洞察や、古代以 来のその変遷を見えなくしてきたと懸念を表明する。労働(labor)、仕事(work)、行為(action)という三種類の活動を区別し、それらが西 洋史の変遷によってどのように影響を受けてきたかを論じている。 |
| History The Human Condition was first published in 1958. A second edition, with an introduction by Margaret Canovan, was issued in 1998. The work consists of a prologue and six parts.[1] |
歴史 『人間の条件』は1958年に初版が刊行された。1998年にはマーガレット・カノヴァンによる序文を付した第二版が発行された。本書はプロローグと六つの部で構成されている。[1] |
| Structure I – The Human Condition Arendt introduces the term vita activa (active life) by distinguishing it from vita contemplativa (contemplative life). Ancient philosophers insisted upon the superiority of the vita contemplativa, for which the vita activa merely provided necessities. Karl Marx flipped the hierarchy, claiming that the vita contemplativa is merely a superstructure on the fundamental basic life-processes of a society. Arendt's thesis is that the concerns of the vita activa are neither superior nor inferior to those of the vita contemplativa, nor are they the same. The vita activa may be divided into three sorts of activities: labor, work and action. [2] |
構造 I – 人間の条件 アレントは「ヴィータ・アクティヴァ」(活動的生活)という概念を「ヴィータ・コントンプラティヴァ」(思索的生活)と区別して導入する。古代の哲学者た ちはヴィータ・コントンプラティヴァの優位性を主張し、ヴィータ・アクティヴァは単にその必要を満たすに過ぎないと考えた。カール・マルクスはこの序列を 逆転させ、ヴィータ・コントンプレティヴァは社会の基礎的な生活過程の上に築かれた上部構造に過ぎないと主張した。アレントの主張は、ヴィータ・アクティ ヴァの関心事がヴィータ・コントンプレティヴァのそれよりも優れているわけでも劣っているわけでもなく、また同じでもないというものだ。ヴィータ・アク ティヴァは三種類の活動に分けられる:労働、仕事、そして行動である。[2] |
| II – The Public and the Private Realm According to Arendt, ancient Greek life was divided between two realms: the public realm in which "action" was performed, and the private realm, site of the household ruled by its head. The mark of the private was not intimacy, as it is in modern times, but biological necessity. In the private realm, heads of households took care of needs for food, shelter, and sex. By contrast, the public realm was a realm of freedom from these biological necessities, a realm in which one could distinguish oneself through "great words and great deeds." Property requirements for citizenship reflected the understanding that unless one was able to take care of one's biological necessities, one could not be free from them and hence could not participate in the public realm as a free person among equals. Slaves and subordinated women were confined to the private realm where they met the biological necessities of the head of the household. The public realm naturally was accorded higher status than the private.[3] With the fall of the Roman Empire, the church took over the role of the public realm (though its otherworldly orientation gave it a character distinct from the previous public realm), and the feudal lords ran their lands and holdings as private realms. The modern period saw the rise of a third realm, the social realm. The social realm is concerned with providing for biological needs, but it does so at the level of the state. Arendt views the social realm as a threat to both the private and the public realm. In order to provide for the needs of everyone, it must invade the private sphere, and because it makes biological needs a public matter, it corrupts the realm of free action: There is no longer a realm free from necessity.[4] |
II – 公的領域と私的領域 アーレントによれば、古代ギリシャの生活は二つの領域に分かれていた。一つは「行動」が行われる公的領域、もう一つは家長が支配する家庭という私的領域で ある。私的領域の特徴は、現代のように親密さではなく、生物学的必要性にあった。私的領域では、家長が食料・住居・性といった必要を満たした。これに対 し、公共領域はこうした生物学的必要性からの自由の領域であり、「偉大な言葉と偉大な行為」によって自己を顕彰できる場であった。市民権の財産要件は、生 物学的必要性を自ら満たせなければ、その束縛から解放されず、したがって等しく自由な人格として公共領域に参加できないという理解を反映していた。奴隷や 従属的な女性は私的領域に閉じ込められ、そこで世帯主の生物的必要を満たした。公的領域は当然、私的領域より高い地位を与えられた。[3] ローマ帝国の崩壊後、教会が公共領域の役割を引き継いだ(ただし、その超越的な指向性により、以前の公共領域とは異なる性格を持つ)。一方、封建領主は自 らの領地と所有地を私的領域として運営した。近代には第三の領域、社会的領域が出現した。社会的領域は生物学的欲求の充足に関わるが、それは国家のレベル で行われる。アレントは社会的領域を私的領域と公的領域の双方に対する脅威と見なす。万人の欲求を満たすためには私的領域に侵入せねばならず、生物学的欲 求を公的な問題とするため、自由な行動の領域を腐敗させる。もはや必然性から解放された領域は存在しないのだ。[4] |
| III – Labor Arendt claims that her distinction between labor and work has been disregarded by philosophers throughout history even though it has been preserved in many European languages. Labor is human activity directed at meeting biological (and perhaps other) necessities for self-preservation and the reproduction of the species. Because these needs cannot be satisfied once and for all, labor never really reaches an end. Its fruits do not last long; they are quickly consumed, and more must always be produced. Labor is thus a cyclical, repeated process that carries with it a sense of futility. In the ancient world, Arendt asserts, labor was contemptible not because it was what slaves did; rather, slaves were contemptible because they performed labor, a futile but necessary activity. In the modern world, not just slaves, but everyone has come to be defined by their labor: We are job-holders, and we must perform our jobs to meet our needs. Marx registers this modern idea in his assertion that man is animal laborans, a species that sets itself apart from the animals not by its thinking, but by its labor. But Marx then contradicts himself in foreseeing a day when production allows the proletariat to throw off the shackles of their oppressors and be free from labor entirely. By Marx's own lights, this would mean they cease to be human.[5] Arendt worries that if automation were to allow us to free ourselves from labor, freedom would be meaningless to us without the contrast with futile necessity that labor provides. Because we define ourselves as job-holders and have relegated everything outside of labor to the category of play and mere hobbies, our lives would become trivial to us without labor. Meanwhile, advances in production and the transformation of work into labor means that many things that were once to be lasting works are now mere disposable objects of consumption. "The solution…consists in treating all use objects as though they were consumer goods, so that a chair or a table is now consumed as rapidly as a dress and a dress used up almost as quickly as food."[6] |
III – 労働(Arbeit) アレントは、労働と仕事の区別が多くのヨーロッパ言語では維持されてきたにもかかわらず、歴史を通じて哲学者たちによって無視されてきたと主張する。労働 とは、自己保存と種の再生産のための生物学的(そしておそらくその他の)必要を満たすことを目的とした人間の活動である。これらの必要は一度で完全に満た されるものではないため、労働は決して終わることがない。その成果は長く続かず、すぐに消費され、常に新たな生産が求められる。労働はこうして循環的で反 復的なプロセスであり、無益さという感覚を伴う。アレントによれば、古代において労働が軽蔑されたのは、奴隷の行為だからではない。むしろ奴隷が軽蔑され たのは、彼らが労働——無益だが必要な活動——を行っていたからだ。現代においては、奴隷だけでなく誰もが自らの労働によって定義されるようになった: 我々は職を持つ者であり、必要を満たすために職を遂行せねばならない。マルクスはこの近代的観念を「人間は労働する動物(animal laborans)である」との主張で記録した。思考ではなく労働によって動物と区別される種だと。しかしマルクスはその後、生産がプロレタリアートを抑 圧者の枷から解放し、労働そのものから完全に自由になる日を予見することで自己矛盾に陥る。マルクス自身の論理によれば、それは彼らが人間でなくなること を意味する[5]。アレントは、自動化によって労働から解放されたとしても、労働が提供する無益な必然性との対比がなければ、自由は私たちにとって無意味 になると懸念する。私たちは職を持つ者として自己を定義し、労働以外の全てを遊びや単なる趣味の範疇に追いやったため、労働がなければ私たちの生活は取る に足らないものになってしまうのだ。一方、生産技術の進歩と労働の変容により、かつては永続的な作品であった多くのものが、今や単なる使い捨ての消費対象 となっている。「解決策は…あらゆる使用対象を消費財として扱うことにある。つまり椅子や机がドレスと同じ速さで消費され、ドレスが食物とほぼ同じ速さで 消耗されるようになるのだ」[6] |
| IV – Work Work, unlike labor, has a clearly defined beginning and end. It leaves behind a durable object, such as a tool, rather than an object for consumption. These durable objects become part of the world we live in. Work involves an element of violation or violence in which the worker interrupts nature in order to obtain and shape raw materials. For example, a tree is cut down to obtain wood, or the earth is mined to obtain metals. Work comprises the whole process, from the original idea for the object, to the obtaining of raw materials, to the finished product. The process of work is determined by the categories of means and end. Arendt thinks that thinking of ourselves primarily as workers leads to a sort of instrumental reasoning in which it is natural to think of everything as a potential means to some further end. Kant's claim that humanity is an end in itself shows just how much this instrumental conception of reason has dominated our thinking. Utilitarianism, Arendt claims, is based on a failure to distinguish between "in order to" and "for the sake of."[7] The homo faber mentality is further evident with the "confusion" in modern political economy when the ancient word "worth", still present in Locke, was replaced by that of "use value" as distinct from "exchange value" by Marx. Marx also thought that the prevalence of the latter over the former constituted the original sin of capitalism.[8] The substitution of the notion of "use value" for "worth" in economic discourse, marks the beginning of the disappearance of a notion of a kind of worth that is intrinsic, as opposed to value, which is the quality that a thing can never possess regardless of its relations to other things, and therefore depends on "market value".[8] Although use objects are good examples of the products of work, artworks are perhaps the best examples, since they have the greatest durability of all objects. Since they are never used for anything (least of all labor), they don't get worn down.[9] |
IV – 仕事 仕事は労働とは異なり、明確な始まりと終わりを持つ。消費のための物ではなく、道具のような耐久性のある物を残す。これらの耐久性のある物は、我々が生き る世界の一部となる。労働には、自然を中断して原材料を獲得し形作るという、侵害や暴力の要素が含まれる。例えば、木材を得るために木を伐採したり、金属 を得るために地中を掘削したりする。労働は、対象物の最初の構想から原材料の獲得、完成品に至るまでの全過程を包含する。労働の過程は、手段と目的という カテゴリーによって決定される。アーレントは、人間を主に労働者として捉えることが、あらゆるものをさらなる目的のための潜在的な手段と見なす道具的思考 へと導くと考える。カントが「人間は目的そのものである」と主張したことは、この道具的理性観念がいかに我々の思考を支配してきたかを示している。アーレ ントによれば、功利主義は「~するために」と「~のために」の区別がつかないことに基づいている。[7] ホモ・ファーベル的思考は、古代の「価値」という語がロックの時代にも残っていたのに、マルクスによって「使用価値」と「交換価値」という区別が導入され た現代政治経済学における「混乱」にも明らかだ。マルクスはまた、後者が前者に対して優勢となったことが資本主義の原罪だと考えた。[8] 経済言説における「価値」概念の「使用価値」概念への置換は、ある種の価値概念の消失の始まりを示す。それは本質的な価値概念であり、価値とは対照的であ る。価値とは、物事が他の物事との関係にかかわらず決して持ち得ない性質であり、したがって「市場価値」に依存する。[8] 使用対象は労働の産物として良い例だが、芸術作品はおそらく最良の例である。あらゆる対象の中で最も耐久性が高いからだ。何の用途にも(ましてや労働に)使われることがないため、摩耗しないのである。[9] |
| V – Action "Human plurality, the basic condition of both action and speech, has the twofold character of equality and distinction. If men were not equal, they could neither understand each other, nor understand their predecessors, nor make plans for the future and foresee the needs of their successors".[10] The third type of activity, action (which includes both speech and action), is the means by which humans disclose themselves to others, not that action is always consciously guiding such disclosure. Indeed, the self revealed in action is more than likely concealed from the person acting, revealed only in the story of her action. These stories can be recorded in documents or monuments and be visible in everyday objects and works of art. But the stories told are very different from these "reifications", because they "tell us more about their subjects, the ‘hero’ in the center of each story, than any product of human hands ever tells us about the master who produced it".[11] Action is the means by which we distinguish ourselves from others as unique and unexchangeable beings. With humans, unlike with other beings, there is not just a generic question of what we are, but of who each is individually. Action and speech are always between humans and directed toward them, and it generates human relationships. Diversity among the humans that see the action makes possible a sort of objectivity by letting an action be witnessed from different perspectives. Action has boundless consequences, often going far beyond what we could anticipate. The Greeks thought of the polis as a place where free people could live together so as to act. Philosophers like Plato, disliking action's unpredictability, modeled the ideal polis on the household. In it, the philosopher king produces the lasting work of legislation, and the people labor under him.[12] Against attempts to replace action with work and labor, Arendt offers two solutions to the two greatest problems action creates: forgiveness to temper action's irreversibility, and promises to mitigate its unpredictability:[13] "without being bound to the fulfillment of promises, we would never be able to keep our identities; we would be condemned to wander helplessly and without direction in the darkness of each man's lonely heart". [14] |
V – 行動 「人間の複数性、すなわち行動と言語の基本的条件は、平等と差異という二重の性質を持つ。もし人間が平等でなければ、互いを理解することも、先人を理解す ることも、未来の計画を立て後継者の必要を予見することもできない」 [10] 第三の活動形態である行動(言語と行為の両方を含む)は、人間が他者に対して自己を開示する手段である。ただし、行動が常に意識的にその開示を導くわけで はない。実際、行動において開示される自己は、行動する人格からはむしろ隠されている可能性が高く、その行動の物語においてのみ開示される。これらの物語 は文書や記念碑に記録され、日常の物や芸術作品にも表れる。しかし語られる物語は、こうした「物象化」とは大きく異なる。なぜなら物語は「その主題、各物 語の中心にいる『主人公』について、人間の手に作られたいかなる製品が作り手について語るよりも多くを語る」からだ。[11] 行動は、我々が他者と区別され、唯一無二で代替不可能な存在であることを示す手段である。人間においては、他の存在とは異なり、単に「我々とは何か」とい う一般的な問いだけでなく、「個々人が誰であるか」という問いが存在する。行動と言語は常に人間同士の間で交わされ、人間に向けられるものであり、それに よって人間関係が生み出される。行動を目撃する人間たちの多様性は、異なる視点から行動を捉えることを可能にし、ある種の客観性を生み出す。行動は予測を はるかに超える、無限の結果をもたらす。ギリシャ人はポリスを、自由な人々が共に行動するために生きる場所と考えました。プラトンら哲学者は行動の不確実 性を嫌い、理想のポリスを家屋に喩えました。そこでは哲人王が永続的な立法の業を生み出し、人民は彼のもとで労働します。[12] 行動を仕事や労働で置き換えようとする試みに対し、アレントは行動が生む二大問題への解決策を提示する。不可逆性を和らげる「許し」と、予測不可能性を緩 和する「約束」である。[13]「約束の履行に縛られなければ、我々は自らのアイデンティティを保てなくなる。各人の孤独な心の闇の中で、無力で方向性な く彷徨う運命に陥るだろう」。[14] |
| VI – The Vita Activa and the Modern Age Arendt thinks that three great events determined the character of the modern age: "the discovery of America and the ensuing exploration of the whole earth; the Reformation, which by expropriating ecclesiastical and monastic possessions started the two-fold process of individual expropriation and the accumulation of social wealth; the invention of the telescope and the development of a new science that considers the nature of the earth from the viewpoint of the universe."[15] None of these events could have been foreseen. They happened suddenly and had repercussions their instigators never intended. One effect of each of these events is to increase our alienation from the world, which Arendt thinks is far more characteristic of our age than alienation from the self (as Marx thought).[16] The shrinking distances brought about by exploration and transportation technology makes humans more an inhabitant of the Earth than of their particular place within it. The process of expropriation kicked off by the Reformation expropriated people from their land and place in the world. Galileo's discovery of the continuity between the Earth and the universe alienates people from their world by showing that an Earth-centered view of the world is illusory, that the Sun does not rise and set as it appears to. What set Galileo apart from other heliocentric theorists is that he proved that heliocentric theories were not merely useful instruments for predicting/explaining data but proper descriptions of reality. Ironically, the outcome of the scientific revolution is that current theories have become so bizarre and that perhaps no one can grasp the world they describe. They have turned out to be useful primarily as instruments, after having shattered our previous understanding of the world. Meanwhile, science now further alienates humans from the world by unleashing processes on Earth that previously occurred only further out in the universe. Humans may have found an Archimedean point to move the world, but only by losing their place in it.[17] The consequence of this world alienation for philosophy has been an intense focus on the self, the one remaining sphere of certainty and knowledge. The world described by science cannot be known, or not with certainty, but the self, Descartes and other moderns thought, could be known. Though his cogito, ergo sum was anticipated by Augustine, his "dubito ergo sum" (De libero arbitrio, Chapter III) is original and a hallmark of modernity: beginning from doubt.[18] The notion of common sense as a sense in which the other five were fitted to a common world ceded to a conception of common sense as an inner faculty with no relationship to the world, and the assumption that all humans had faculties like this in common became necessary to get theories going, but without the assumption of a common world, the assumption of faculties in common lost some warrant. [19] Galileo's discoveries also have implications for the 'vita activa' and 'contemplativa'. That he made the discoveries with a telescope, with a product of human work, signals an important change in science. Knowledge is acquired not simply by thinking, but by making. Homo faber and the life of work were thus exalted over the life of contemplation.[20] Indeed, the model of scientific inquiry, the experiment, is one in which the scientist unleashes a process by which the scientist produces results. This way of doing science is naturally understood in terms of work processes. The philosopher has consequently been relegated to a position of relative insignificance, merely puzzling over what the scientists have shown. But in the end, Homo faber ceded primacy to animal laborans. The life of labor became the central concern because all of these developments took place in a Christian society that valued life far more than others have. After secularization, this vestigial preoccupation with life as the central value dominates our activities. It has made us into a society of laborers. Judged by the historical significance of what they do, the people most capable of action now are perhaps the scientists, but unfortunately, they act into nature and not human relationships, and thus their action cannot be the source of meaningfulness that illuminates human existence. [21] Action is still possible in free societies, but fragile. |
VI – アクティヴァの生活(Vita Activa)と近代 アーレントは、三つの重大な出来事が近代という時代の性格を決定づけたと考えている。「アメリカ大陸の発見とそれに続く地球全体の探検、教会や修道院の財 産を没収した宗教改革によって始まった、個人の財産没収と社会的な富の蓄積という二重のプロセス、そして望遠鏡の発明と、宇宙という視点から地球の性質を 考察する新しい科学の発展である」 [15] これらの出来事はどれも予見できなかった。突然起こり、その発端者たちが意図しなかった影響をもたらした。それぞれの出来事の帰結の一つは、世界からの疎 外感を増大させることであり、アレントはこれが(マルクスが考えたような)自己からの疎外よりも、はるかに現代の特徴であると考えている。[16] 探検と交通技術によって縮まった距離は、人間を特定の場所の住人というより、地球の住人へと変えた。宗教改革によって始まった収奪の過程は、人民を土地と 世界における居場所から収奪した。ガリレオが地球と宇宙の連続性を発見したことは、地動説が幻想であり、太陽が視覚的に昇り沈むように見えるのは錯覚であ ることを示し、人民を世界から疎外した。ガリレオが他の太陽中心説提唱者と異なった点は、太陽中心説が単なるデータ予測・説明の有用な道具ではなく、現実 の適切な記述であることを証明したことだ。皮肉なことに、科学革命の結果、現在の理論は極めて奇妙なものとなり、おそらく誰もその記述する世界を理解でき なくなった。それらは、従来の世界理解を粉砕した後、主に道具として有用であることが判明したのだ。一方、科学は今や、かつては宇宙のより遠くでしか起こ らなかったプロセスを地球上で解き放つことで、人間を世界からさらに疎外している。人間は世界を動かすアルキメデスの支点を見つけたかもしれないが、それ は自らの居場所を失う代償を払ってのことだったのだ[17]。 この世界疎外が哲学にもたらした帰結は、確信と知識の唯一の残された領域である自己への強烈な焦点化であった。科学が描写する世界は、確証をもって知るこ とができない。しかしデカルトや他の近代思想家たちは、自己は知ることができると考えた。彼の「我思う、故に我あり」はアウグスティヌスに先駆けていた が、「我疑う、故に我あり」(『自由意志について』第三章)は独創的であり、近代性の特徴である:疑いから始めること。[18] 他の五感と共通の世界に適合する感覚としての「常識」の概念は、世界とは無関係な内面的能力としての常識概念に取って代わられた。理論を展開するには、全 ての人間がこのような能力を共有しているという前提が必要となったが、共通の世界という前提が失われると、能力の共有という前提も正当性を失った。 [19] ガリレオの発見は「活動的な生活」と「観想的な生活」にも示唆を与える。彼が望遠鏡という人間の労働の産物で発見した事実は、科学における重要な変化を示 している。知識は単に思考によってではなく、創造によって獲得されるのだ。こうしてホモ・ファベルと労働の生活は、観想の生活よりも高く評価されるように なった。[20] 実際、科学的探究のモデルである実験とは、科学者が結果を生み出すプロセスを解き放つ行為である。この科学の進め方は、当然ながら労働プロセスとして理解 される。その結果、哲学者は相対的に取るに足らない立場に追いやられ、科学者が示した事象をただ首をかしげる存在となった。しかし結局、ホモ・ファベルは 動物労働者(ホモ・ラボーランス)に優位性を譲った。労働の生活が中心的な関心事となったのは、こうした発展の全てが、他の社会よりもはるかに生命を重視 したキリスト教社会の中で起こったからである。世俗化後、この生命を中心的価値とする痕跡的な執着が我々の活動を支配する。それは我々を労働者の社会へと 変えた。彼らの行為の歴史的意義で判断すれば、今最も行動可能な人民は科学者かもしれない。しかし不幸なことに、彼らの行動は人間関係ではなく自然に向け られる。ゆえにその行動は、人間の存在を照らす意味の源泉となり得ない。[21] 自由な社会では行動は依然可能だが、それは脆い。 |
| Criticisms According to Maurizio Passerin d'Entreves, in Arendt there would be two conflicting conceptions of nature: On the one hand, with the advent of industrialization and capitalism, human beings increasingly lose their subjectivity to become mere elements of nature who are exclusively interested in their own survival and in the production of perishable objects; on the other hand, it is nature that is subjugated by man, who seeks more and more to replace it with artificial objects resulting from technology, and through laboratory experiments they even try to modify the very nature of man and to extend their dominion over nature in space and time. "The modern world would thus appear to be too natural and too artificial, too much under the dominance of labor and the life-process of the species, as well as too much under the dominance of techne".[22] According to Byung-Chul Han, The Human Condition neglects an essential dimension of human existence, that of contemplation: Arendt's absolutization of action deprives life of any festivity. The feast is the expression of an abundant life, an intensive form of life. In the feast, life refers to itself, rather than pursuing goals outside of oneself. It puts work and action out of play... It is not the determination to act, but the abandonment of the feast that elevates us above simple life, which would only be survival. Life, reduced to being active, is lethal. Until the end, Arendt was unaware that precisely the loss of the contemplative capacity leads to the victory, that she herself criticized, of the "animal laborans", which subjects all human activities to work... Life active degenerates into hyperactivity and ends in burnout, not only of the psyche, but also of the entire planet.[23][24] Judith Butler interpreted the central theme of the work as being that a measured life of everyday necessities is preferable to lives dominated either by endless private survival or by grandiose political spectacle, because only the modest interplay of beginnings and appearances preserves the fragile possibility of true human freedom.[25] [25] "Action and the Everyday: The Breadth and Depth of the Human Experience". Butler, Judith et al. Philosophical Quarterly, 28(111) (2008) 145–159. ISSN: 0031-8094 |
批判 マウリツィオ・パッセリン・デントレヴェスによれば、アレントには二つの相反する自然観が存在する。一方では、工業化と資本主義の到来により、人間は次第 に主体性を失い、自らの生存と消耗品の生産のみに関心を持つ自然の単なる要素へと変容していく。他方で、人間によって自然が隷属化される。人間は技術を介 して生み出される人工物で自然を置き換えようとますます追求し、実験室での試行を通じて人間の性質そのものを改変しようとし、空間と時間において自然への 支配を拡大しようとするのだ。「現代世界はこうして、あまりに自然でありながらあまりに人工的であり、労働と種の生命過程の支配下にありながら、同時にテ クネーの支配下にありすぎるように見える」。[22] ハン・ビョンチョルによれば、『人間の条件』は人間存在の本質的な側面、すなわち観想を軽視している: アレントの行動の絶対化は、人生からあらゆる祝祭性を奪う。祝祭とは豊かな人生の表現であり、集中的生命形態である。祝祭において人生は自己を省みるので あって、自己外部の目標を追求しない。それは労働と行動を無効化する... 行動への決意ではなく、祝宴の放棄こそが、単なる生存に過ぎない単純な生活を超越させる。活動に還元された生活は致命的だ。アレントは最後まで気づかな かった。まさに思索能力の喪失こそが、彼女自身が批判した「労働する動物」の勝利へと導くのだと。それはあらゆる人間的活動を労働に服従させる... 能動的な生活は過活動へと堕し、精神のみならず地球全体の燃え尽きへと終わるのだ。[23][24] ジュディス・バトラーはこの著作の核心的主題を、日常の必要性に則った節度ある生活こそが、果てしない私的生存や壮大な政治的スペクタクルに支配された生 活よりも優れていると解釈した。なぜなら、始まりと表層のささやかな相互作用のみが、真の人間の自由という脆い可能性を保つからだ。[25] [25] "Action and the Everyday: The Breadth and Depth of the Human Experience". Butler, Judith et al. Philosophical Quarterly, 28(111) (2008) 145–159. ISSN: 0031-8094 |
| 1. Arendt 1998. 2. Arendt 1998, p. 7–17. 3. Arendt 1998, p. 22–33. 4. Arendt 1998, p. 38. 5. Arendt 1998, p. 102–107. 6. Arendt 1998, p. 124. 7. Arendt 1998, p. 154. 8. Arendt 1998, p. 165. 9. Arendt 1998, p. 167–173. 10. Arendt 1998, p. 175. 11. Arendt 1998, p. 184. 12. Arendt 1998, p. 192. 13. Arendt 1998, p. 236-243. 14. Arendt 1998, p. 237. 15. Arendt 1998, p. 248. 16. Arendt 1998, p. 254. 17. Arendt 1998, p. 268–280. 18. Arendt 1998, p. 280. 19. Arendt 1998, p. 281–2. 20. Arendt 1998, p. 294. 21. Arendt 1998, p. 320–322. 22. d'Entreves, Maurizio Passerin. "H. Arendt (Stanford Encyclopedia of Philosophy)". plato.stanford.edu. Stanford University. Retrieved 4 September 2023. §3. 23. Han, Byung-Chul (2023). Vita Contemplativa: In Praise of Inactivity. Cambridge: Polity Press. ISBN 9781509558025. 24. "Interview with Byung-Chul Han". la Repubblica (in Italian). 13 December 2023. pp. 30–31. 25 "Action and the Everyday: The Breadth and Depth of the Human Experience". Butler, Judith et al. Philosophical Quarterly, 28(111) (2008) 145–159. ISSN: 0031-8094 |
1. アレント 1998。 2. アレント 1998、p. 7–17。 3. アレント 1998、p. 22–33。 4. アレント 1998、p. 38。 5. アレント 1998、p. 102–107。 6. アレント 1998、124 ページ。 7. アレント 1998、154 ページ。 8. アレント 1998、165 ページ。 9. アレント 1998、167-173 ページ。 10. アレント 1998、175 ページ。 11. アレント 1998、184 ページ。 12. アレント 1998、192 ページ。 13. アレント 1998、236-243 ページ。 14. アレント 1998、237 ページ。 15. アレント 1998、248 ページ。 16. アレント 1998、254 ページ。 17. アレント 1998、268-280 ページ。 18. アレント 1998、280 ページ。 19. アレント 1998、281-2 ページ。 20. アレント 1998、294 ページ。 21. アレント 1998、320-322 ページ。 22. d'Entreves, Maurizio Passerin. 「H. Arendt (スタンフォード哲学百科事典)」 plato.stanford.edu. スタンフォード大学。2023年9月4日取得。§3。 23. ハン、ビョンチョル (2023)。『Vita Contemplativa: In Praise of Inactivity』。ケンブリッジ:Polity Press。ISBN 9781509558025。 24. 「ハン・ビョンチョル氏へのインタビュー」。la Repubblica (イタリア語)。2023年12月13日。pp. 30–31。 25 「行動と日常:人間経験の幅と深さ」。バトラー、ジュディス他。Philosophical Quarterly、28(111) (2008) 145–159。ISSN: 0031-8094 |
| Bibliography — (1998) [1958]. The Human Condition (Second ed.). University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-92457-1. d'Entreves, Maurizio Passerin (2019). "H. Arendt (Stanford Encyclopedia of Philosophy)". plato.stanford.edu. Stanford University. Retrieved 6 February 2019. (Revision as of May 2018) Yar, Majid. "H. Arendt (Internet Encyclopedia Philosophy)". www.iep.utm.edu. Retrieved 18 July 2018. |
参考文献 — (1998) [1958]. 『人間の条件』(第二版). シカゴ大学出版局. ISBN 978-0-226-92457-1. d'Entreves, Maurizio Passerin (2019). 「H. Arendt (Stanford Encyclopedia of Philosophy)」. plato.stanford.edu. Stanford University. 2019年2月6日取得。(2018年5月時点の改訂版) ヤール、マジド。「H. アレント(インターネット哲学百科事典)」。www.iep.utm.edu。2018年7月18日取得。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/The_Human_Condition_(Arendt_book) |
★ドイツ語版:Vita activa oder Vom tätigen Leben(Vita activa、あるいは活動的な生活について)
| Vita activa oder Vom tätigen Leben
ist das philosophische Hauptwerk der politischen Theoretikerin Hannah
Arendt. Die auf Vorlesungen beruhende Arbeit wurde zunächst 1958 in den
USA unter dem Titel The Human Condition veröffentlicht. Die deutsche
Fassung, die sie selbst übersetzt hatte, erschien 1960. Vor dem
Hintergrund der Geschichte politischer Freiheit und
selbstverantwortlicher aktiver Mitwirkung der Bürger am öffentlichen
Leben in den USA entwickelte Arendt darin eine Theorie des politischen
Handelns. |
『Vita activa、あるいは活動的な生活について』は、政治理論家ハンナ・アーレントの哲学上の主要著作である。講義に基づいて書かれたこの労働は、1958 年に『人間の条件』というタイトルで米国で最初に出版された。彼女自身が翻訳したドイツ語版は1960年に出版された。米国の政治的自由と、市民が公的生 活に自主的かつ積極的に参加してきた歴史を背景に、アーレントは政治行動の理論を展開した。 |
| Überblick Arendts Text ist in sechs Hauptkapitel untergliedert: Das Eröffnungskapitel Die menschliche Bedingtheit ist der Entwicklung ihres Leitbegriffs, der Vita activa, gewidmet. Das zweite Kapitel dient der Unterscheidung zwischen dem „Raum des Öffentlichen“ und dem „Bereich des Privaten“. In den anschließenden Kapiteln drei bis fünf stellt sie unter den Überschriften Die Arbeit, Das Herstellen und Das Handeln jeweils zentrale menschliche Hervorbringungsprozesse in den Mittelpunkt ihrer Analyse. Im Schlusskapitel Die Vita activa und die Neuzeit beschreibt sie die einschneidenden Wandlungsprozesse zwischen europäischer Vormoderne und Moderne und endet mit ihrer Diagnose vom „Sieg des Animal laborans“, wonach das politische Handeln durch Konformität und Funktionalität begrenzt werde. |
概要 アーレントのテキストは、6つの主要章で構成されている。最初の章「人間の条件」は、彼女の主要概念である「活動的人生」の発展に捧げられている。第2章 は、「公共の領域」と「私的領域」の区別について論じている。続く第3章から第5章では、「労働」、「生産」、「活動」という見出しの下で、それぞれ人間 による生産と行動という2つの中心的な創造的プロセスを分析の中心に据えている。最終章「活動的人生と現代」では、ヨーロッパの近代以前の社会における劇 的な変革の過程について論じている。「生産」、「行動」という見出しで、それぞれ人間にとって中心的な生産プロセスを分析の中心に据えている。最終章 「ヴィータ・アクティヴァと近世」では、ヨーロッパの近世と近代の間における劇的な変化の過程を説明し、政治的な行動は順応性と機能性に制限されるという 「アニマル・ラボランス(労働する動物)の勝利」という診断で締めくくっている。 |
| Die Möglichkeit, einen Anfang zu machen, als Voraussetzung eines aktiven politischen Lebens Im Gegensatz zu Heidegger begründet Arendt ihr Denken von der Geburt des einzelnen Menschen her und nicht vom Tod. In Vita activa führt sie diesen Gedanken der „Gebürtlichkeit“ („Natalität“) aus. Mit der Geburt beginne die Möglichkeit, einen Anfang machen zu können. Das Individuum habe die Aufgabe, in Kooperation mit anderen Individuen die sie umgebende Welt aktiv zu beeinflussen, zu formen. Dabei geht es ihr um die basalen Existenz- und Persistenzbedingungen menschlichen Lebens, die sie auf drei „Grundtätigkeiten“ beschränkt: „Arbeiten, Herstellen und Handeln“ (nach den altgriechischen Begriffen ponos, poiesis und prāxis). Als davon unabhängig und letztlich nicht beschreibbar charakterisiert sie das menschliche „Wesen“ bzw. die menschliche „Natur“, die weder terminologisch noch ontologisch zu definieren seien. „Versuche, das Wesen des Menschen zu bestimmen, [enden] zumeist mit irgendwelchen Konstruktionen eines Göttlichen.“[1] „Alle drei Grundtätigkeiten […] sind nun nochmals in der allgemeinsten Bedingtheit menschlichen Lebens verankert, daß es nämlich durch Geburt zur Welt kommt und durch Tod aus ihm wieder verschwindet. Was die Mortalität anlangt, so sichert die Arbeit das Am-Leben-Bleiben des Individuums und das Weiterleben der Gattung; das Herstellen errichtet eine künstliche Welt, die von der Sterblichkeit der sie Bewohnenden in gewissem Maße unabhängig ist und so ihrem flüchtigen Dasein so etwas wie Bestand und Dauer entgegenhält; das Handeln schließlich, soweit es der Gründung und Erhaltung politischer Gemeinwesen dient, schafft die Bedingungen für eine Kontinuität der Generationen, für Erinnerung und damit für Geschichte.“ Das Handeln sei enger an die Gebürtlichkeit gebunden als das Arbeiten und Herstellen. Jeder, der neu in diese Welt geboren werde, besitze die Potenz, wiederum einen Anfang zu machen, also aktiv und damit verändernd zu handeln.[2] |
積極的な政治的生活の前提条件としての、新たなスタートを切る可能性 ハイデガーとは対照的に、アーレントは、個々の人間の誕生から、その思考の根拠を導き出しており、死からではない。『活動的人生』の中で、彼女は「誕生 性」(「ナタリティ」)というこの考えを展開している。誕生によって、新たなスタートを切る可能性が始まるのだ。個人は、他の個人と協力しながら、周囲の 世界に積極的に影響を与え、形作るという任務を負っている。ここで彼女が重視しているのは、人間の生活の基本的な存在条件と持続条件であり、それを「労 働、生産、行動」という 3 つの「基本的な活動」(古代ギリシャ語の ponos、poiesis、prāxis に由来)に限定している。それとは独立して、最終的には記述不可能なものとして、彼女は人間の「本質」あるいは「性質」を特徴づけ、それは用語的にも存在 論的にも定義できないと述べています。「人間の本質を決定しようとする試みは、ほとんどの場合、何らかの神聖な概念の構築で終わる」[1]。 「これら 3 つの基本的な活動はすべて、人間の人生が、誕生によってこの世に生まれて、死によってこの世から消えるという、最も一般的な条件に根ざしている。死につい て言えば、労働は、個人が生き続けること、そして種が存続することを保証する。生産は、そこに住む人々の死からある程度独立した人工的な世界を構築し、そ の儚い現存在(Dasein)に対して、ある種の永続性と持続性を対峙させる。そして、行動は、政治的な共同体の設立と維持に役立つ限り、世代の継続、記 憶、ひいては歴史のための条件を作り出す。」 行動は、労働や生産よりも、誕生とより密接に結びついている。この世界に新たに生まれる者は皆、再び新たな始まり、つまり、積極的に、そして変化をもたらす行動を起こす可能性を秘めている。 |
| Arbeiten und Herstellen Die Arbeit als erste Komponente der Vita activa „entspricht dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers“. Sie dient dem Fortbestand der Gattung. Daher gehört Arbeit notwendig zum menschlichen Leben, aber auch zu dem jedes anderen Lebewesens. Arbeit ist, so sieht es Arendt, nicht mit Freiheit verbunden, sondern stellt einen Zwang zur Erhaltung des Lebens dar, dem der Mensch von der Geburt bis zum Tod ständig unterliegt. Auf der Grundlage der Arbeit, die seine Existenz sichert, beginnt der Mensch über die Endlichkeit seines Daseins nachzudenken. Um dieser Gewissheit zu entfliehen, schafft er sich eine Welt aus Dingen, die er mit „Geist“ und „Kraft“ aus unterschiedlichen Materialien herstellt und die seine Lebenszeit überdauern. Das Wichtige ist hierbei, dass der Mensch sich nicht nur in einer Umgebung wiederfindet, so wie jedes Tier es tut, sondern er baut eine eigene Welt auf. Arendt geht davon aus, dass diese Welt beständig ist. Die einzelnen hergestellten Dinge, die sie ausmachen, sind so dauerhaft, dass das Individuum eine Beziehung dazu aufbauen kann. Eine starke Form einer solchen Beziehung stellt zum Beispiel das Gefühl des „nach Hause Kommens“ dar. Ohne gewisse beständige Eigenschaften des „zu Hause Seins“ kann eine Beziehung nicht aufgebaut werden. In einer sich ständig ändernden Welt kann der Mensch sich nicht zu Hause fühlen. Die von Arendt eingeführte Unterscheidung zwischen Arbeiten und Herstellen bezieht sie auch auf die Produktion. Als Produkte der Arbeit bezeichnet sie Konsumgüter, die „verbraucht“ werden, während Produkte des Herstellens oder des Werkens „gebraucht“ werden. |
労働と生産 ヴィータ・アクティヴァの最初の要素である労働は、「人体の生物学的プロセスに相当する」ものだ。それは、種族の存続に役立つ。したがって、労働は人間の 生活だけでなく、他のあらゆる生物の生活にも必要なものだ。アーレントは、労働は自由とは関係なく、人間が誕生から死まで絶えず服する、生命を維持するた めの強制であると考えている。 その現存在を確保する労働を基盤として、人間は自分の現存在の有限性について考え始める。この確実性から逃れるために、人間は「精神」と「力」を用いてさ まざまな素材から、自分の寿命よりも長生きする物からなる世界を作り出す。ここで重要なのは、人間は、あらゆる動物がそうであるように、単に環境の中に身 を置くだけでなく、独自の世界を構築するということだ。アーレントは、この世界は永続的であると考える。この世界を構成する個々の造られたものは、個人が それとの関係を構築できるほど永続的である。そのような関係の強力な形態の一例は、「家に帰る」という感覚である。「家にいる」という一定の特性がなけれ ば、関係は構築できない。絶えず変化し続ける世界では、人間は家にいるような感覚を持つことができない。 アーレントが導入した「労働」と「作ること」の区別は、生産にも当てはまる。彼女は、消費される消費財を「労働」の産物とし、一方、「作ること」や「仕事」の産物は「使用される」ものとしている。 |
| Handeln Die dritte Komponente stellt das Handeln dar, das sich „zwischen“ den Individuen abspielt und zugleich die Einzigartigkeit und Pluralität menschlichen Seins veranschaulicht. Das Handeln ist im ontologischen Sinne eine menschliche Fähigkeitsoption. Jedes Individuum kann, argumentiert Arendt, gesellschaftlich existieren, ohne jemals selbst zu arbeiten oder selbst etwas herzustellen. Handeln hingegen stellt den Kern menschlicher Interaktion und damit politischen Existierens dar, was für Arendt eine fundamentale Eigenschaft menschlichen Seins ist. Kommunikation, d. h., „Finden des rechten Wortes im rechten Augenblick“ ist immer schon Handeln. „Stumm ist nur die Gewalt, und schon aus diesem Grunde kann die schiere Gewalt niemals Anspruch auf Größe machen.“[3] Das Bewusstsein des eigenen Menschseins könne zwar auch ohne zu handeln beim Individuum vorhanden sein, für die anderen menschlichen Handelnden werde aber dieses nicht-handelnde Individuum niemals als Mensch wahrnehmbar sein. Handeln ist für Arendt wesentlich mit dem öffentlichen Raum verknüpft, ohne ihn nicht ausführbar oder denkbar. Am deutlichsten erkennbar wird dies, so Arendt, am Beispiel der antik-griechischen Polis, in der das Arbeiten, zumindest in ihrer historischen Perspektive, zum privaten Raum des Haushalts („Oikos“) gehört, während sich das gemeinschaftliche Handeln der individuellen Vollbürger der Polis im öffentlichen Raum auf dem Marktplatz (der Agora) abgespielt habe. Für Arendt scheint in dieser Epoche der europäischen Geschichte der paradigmatische Ort der Vita activa auf, der politischen Kommunikation und Interaktion unter Bürgern, die allesamt im Besitz der gleichen Freiheitsrechte gewesen seien. Obwohl Aristoteles die höchste Erfüllung in der Vita contemplativa, mithin in der philosophischen Suche der Weisheit, sah, erachtete er den Menschen nichtsdestoweniger als wesenhaft politisch (zoon politikon). |
行動 3つ目の要素は、個人間の「間」で起こる行動であり、同時に人間存在の独自性と多様性を体現している。行動は、存在論的な意味で、人間のもつ能力の選択肢 である。アーレントは、個人は、自ら労働したり、何かを製造したりすることなく、社会的に存在することができると主張している。一方、行動は人間関係の核 心であり、したがって政治的な存在の核心でもある。アーレントにとって、これは人間存在の基本的な特性だ。コミュニケーション、つまり「適切な瞬間に適切 な言葉を見つけること」は、常にすでに「行動」である。「沈黙しているのは暴力だけであり、その理由だけでも、暴力は偉大さを主張することは決してできな い」[3]。行動しなくても、個人は人間であるとの意識を持つことは可能だが、他の行動する人間にとって、この行動しない個人は人間として認識されること は決してない。 アーレントにとって、行動は公共の空間と本質的に結びついており、それなしでは実行も想像もできない。アーレントによれば、このことは、古代ギリシャのポ リスを例に最も明確に認識できる。ポリスでは、少なくとも歴史的な観点からは、労働は家庭(「オイコス」)という私的空間に属し、ポリスにおける個々の完 全市民による共同行動は、公共空間である市場(アゴラ)で行われていた。アーレントにとって、このヨーロッパの歴史の時代は、すべての市民が同等の自由の 権利を所有していた、政治的なコミュニケーションと相互作用、すなわち「活動的な生活(Vita activa)」の典型的な場所として現れている。アリストテレスは、「思索的な生活(Vita contemplativa)」、すなわち哲学的な知恵の探求に最高の充実を見出していたにもかかわらず、人間を本質的に政治的な存在(zoon politikon)と見なしていた。 |
| Verzeihen und Versprechen Für Arendt ist sowohl das Verzeihen als auch das Versprechen eine Voraussetzung für das Handeln. Ohne diese beiden Vorgänge wäre das Handeln in der Pluralität überhaupt nicht möglich. Dabei sieht Arendt beide dieser Vorgänge als ein Heilsmittel gegen die Aporien der Pluralität. Diese Aporien der Pluralität ergeben sich aus der Vorstellung, dass alle Menschen durch ihre Geburt in einem Bezugsgewebe der Pluralität miteinander verstrickt sind. In diesem Bezugsgewebe sind die Folgen von Handlungen sowohl unwiderruflich als auch unvorhersehbar.[4] Das Verzeihen ist das Heilsmittel gegen die Unwiderruflichkeit und erstreckt sich auf die Vergangenheit. Da das Getane nicht mehr veränderbar, also unwiderruflich, ist, bedarf der Mensch der Verzeihung des Gegenübers. Ohne dieses Verzeihen und das darin liegende Entbinden von den Folgen seiner Taten würde seine Handlungsfähigkeit auf eine einzige Tat beschränkt werden. Durch das Verzeihen wird dem Menschen immer wieder ein Neuanfang ermöglicht, den er oder sie zum Handeln braucht. Dem Verzeihen gegenüber steht demnach die Rache, die die handelnde Person auf ihre verfehlte Handlung beschränkt. Dadurch ist dann nach Arendt kein Handeln, keine Aktion, mehr möglich, da alle weiteren Taten nur noch Re-aktionen auf die ursprüngliche verfehlte Tat sind. Zentral für Arendt ist beim Vorgang des Verzeihens, dass nicht die Schuld selbst das Objekt des Verzeihens ist, dies darf immer nur die schuldige Person sein. Mit den Worten Arendts selbst bezieht sich das Vergeben „nur auf die Person und niemals auf die Sache“[5].[6] Das Versprechen ist für Arendt das Heilmittel gegen die Unvorhersehbarkeit des Handelns und erstreckt sich somit auf die Zukunft. Diese Zukunft ist immer von Dunkelheit und Unklarheit geprägt und die Menschen in ihrer Grundbestimmung der Pluralität sind unberechenbar. Diese Unklarheit und Unberechenbarkeit wirken lähmend auf das Handeln. Nur in einer gewissen Ordnung kann das Handeln gewährleistet werden. Diese Ordnung wird durch Versprechen, bzw. den Verträgen und Abkommen, die sich aus Versprechen ergeben, hergestellt. Es ist nach Arendt die einzige Art der Bindung von Menschen aneinander, die der Freiheit entspricht. Versprechen können und dürfen dabei nie die Zukunft klar festlegen, sie sind vielmehr voraussehbare Vorhaben innerhalb der Ungewissheit der Zukunft.[7] |
許しと約束 アーレントにとって、許しと約束は行動の前提条件だ。この二つがなければ、多元性の中で行動することはまったく不可能だ。アーレントは、この2つの行為 を、多元性のアポリアに対する救済策と捉えている。多元性のアポリアは、すべての人は、生まれながらにして多元性の関連性の網に絡み合っているという考え 方から生じる。この関連性の網の中では、行動の結果は取り返しのつかないものであり、また予測不可能なものである。[4] 許しは、取り返しのつかないことに対する救済策であり、過去にまで及ぶ。行ったことはもはや変更不可能、つまり取り返しのつかないものであるため、人間は 相手からの許しを必要とする。この許し、そしてそこにある自分の行動の結果からの解放がなければ、人間の行動能力は単一の行動に限定されてしまう。許すこ とによって、人間は行動に必要な新たなスタートを何度も切ることが可能になる。許すこととは対照的なのは、行動した人間をその過ちのある行動に限定してし まう復讐である。アーレントによれば、それにより、それ以上の行動、つまり反応は不可能になる。なぜなら、それ以降の行動はすべて、最初の過ちのある行動 に対する反応にすぎないからである。アーレントにとって、許すという行為において重要なのは、罪そのものが許しの対象ではなく、それは常に罪を犯した人物 でなければならないということだ。アーレント自身の言葉を借りれば、許すことは「人物に対してのみ行われ、決して事柄に対して行われるものではない」 [5]。[6] アーレントにとって、約束は行動の予測不可能性に対する救済策であり、したがって未来にまで及ぶ。この未来は常に暗闇と不透明さに特徴づけられ、その多元 性という基本的な性質から、人間は予測不可能な存在である。この不透明さと予測不可能性は、行動に麻痺的な影響を及ぼす。ある種の秩序があって初めて、行 動は保証される。この秩序は、約束、すなわち約束から生じる契約や合意によって構築される。アーレントによれば、これは自由に対応する、人間同士を結びつ ける唯一の手段である。約束は、未来を明確に決定することは決してできず、またそうしてはならない。むしろ、それは不確実な未来の中で予測可能な計画であ る[7]。 |
| Vom Verständigungsprozess im politischen Raum zur Massengesellschaft Demgegenüber kam es, so Arendt, im Mittelalter auf der Grundlage christlicher Dogmatik zu einer Verschiebung. Die höchste Freiheit für den Menschen lag nun in der auf Gott ausgerichteten Vita contemplativa. Dabei wurde das Element des handwerklich-künstlerischen Herstellens höher bewertet als das (philosophische) Denken und (politische) Handeln. Der Mensch wurde zum Homo faber, d. h. Erschaffer einer künstlichen Welt. Das „sprachlose Staunen“, welches seit der Antike als „Beginn und Ende aller Philosophie“ galt und nur Wenigen zugänglich war, verlor an Bedeutung zugunsten des „betrachtend anschauenden Blicks der handwerklich-Schaffenden“.[8] Eine erneute Verschiebung der Werte ergab sich in der Neuzeit. Durch Ausweitung der Ökonomie in den öffentlichen Raum trat die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit immer mehr in den Vordergrund und ist in der modernen Massengesellschaft dominierend geworden. Der Mensch wurde zum „animal laborans“ (arbeitenden Tier). Ziel ist die möglichst hohe Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Umwandlung aller Dinge in Konsumgüter. Der Begriff der Gesellschaft umfasst nunmehr auch tendenziell den politischen Bereich. Die Bedeutung des Politischen, des Handelns, ist somit in den Hintergrund getreten. Arendt kritisiert die christlich-abendländische Philosophie. Zwar hätten die meisten Philosophen sich zu politischen Fragen geäußert, aber kaum einer habe unmittelbar am politischen Diskurs teilgenommen. Als Ausnahme sah sie lediglich Machiavelli. Auch wenn bei Hegel das Politische eine Aufwertung gefunden habe, wendet sich Arendt vor allem gegen die geschichtsphilosophische Vorstellung Hegels von der Notwendigkeit der geschichtlichen Entwicklung. Die Idee des Absoluten als Ziel der Geschichte führe zur Ideologie und damit zur Rechtfertigung von undemokratischen Praktiken und schließlich zu den Formen der totalen Herrschaft. Das moderne Individuum entfernt sich ebenfalls vom Politischen auf Grund der „radikalen Subjektivität seines Gefühlslebens,“ der dauernd wechselnden „Stimmungen und Launen,“ die es in „endlose innere Konflikte“ verstricken. Die Einzelnen werden gesellschaftlich normiert. Abweichungen von dieser Norm werden als asozial oder anormal verbucht. Es kommt zum Phänomen der Massengesellschaft mit der Herrschaft der Bürokratie. Dabei werden die sozialen Klassen und Gruppierungen nivelliert. Alle Glieder der Gemeinschaft werden mit gleicher Macht kontrolliert. Das Gleichmachen, der Konformismus in der Öffentlichkeit führt dazu, dass Auszeichnungen und „Besonderheiten“ zu Privatangelegenheiten von Individuen werden. Große Anhäufungen von Menschen entwickeln die Tendenz zur Despotie, entweder eines Einzelnen oder zum „Despotismus der Mehrheit“.[9] Auch in der Vorstellung der Geschichtlichkeit als Grundbedingung der menschlichen Existenz bei Heidegger bleibt für die Autorin das Denken der Kontemplation verhaftet. Eine Vita activa erfordert hingegen die Fragen nach den Prinzipien des Politischen und den Bedingungen der Freiheit. Als Ansatz hierzu sah Arendt wie Jaspers die Moralphilosophie Kants, in der die Frage nach den Bedingungen der menschlichen Pluralität im Vordergrund gestanden habe. Kant habe nicht nur Staatsmänner und Philosophen betrachtet, sondern alle Menschen als Gesetzgeber und Richter angesehen und sei so zu der Forderung nach einer Republik gekommen, der sich die Forscherin anschließt. In diesem Werk geht Arendt der historischen Wandlung von Begriffen wie Freiheit, Gleichheit, Glück, Öffentlichkeit, Privatheit, Gesellschaft und Politik nach und beschreibt den Bedeutungswandel im jeweiligen historischen Kontext. Dabei ist ihr Bezugspunkt die Attische Demokratie, insbesondere zur Zeit des Sokratischen Dialogs. Ihrer Auffassung nach gilt es, die verlorenen Bereiche des Politischen wiederum in der Gegenwart modifiziert zu verankern und damit die Fähigkeiten politisch denkender und handelnder freier Individuen, die versuchen, sich voreinander auszuzeichnen, fruchtbar zu machen. Im Gegensatz dazu sieht sie den verbreiteten Behaviorismus, der darauf abziele, den Menschen in allen seinen Tätigkeiten „auf das Niveau eines allseitig bedingten und sich verhaltenden Lebewesens zu reduzieren.“[10] |
政治分野における合意形成プロセスから大衆社会へ 一方、アーレントによれば、中世ではキリスト教の教義に基づいて変化が起こった。人間にとって最高の自由は、神を中心とした「瞑想的な生活」にあるとされ た。そして、工芸的・芸術的な制作活動は、(哲学的な)思考や(政治的な)行動よりも高く評価されるようになった。人間はホモ・ファベル、つまり人工的な 世界を創り出す存在となった。古代から「哲学の始まりであり終わり」とされ、ごく少数の人しか到達できなかった「言葉にならない驚嘆」は、その重要性を失 い、「工芸的創造者たちの観察的な視線」に取って代わられた。[8] 近代において、価値観は再び変化した。経済が公共の領域にまで拡大したことで、労働の社会的意義がますます重要視されるようになり、現代の大衆社会では支 配的な存在となっている。人間は「動物労働者(animal laborans)」となった。その目的は、労働生産性を可能な限り高め、あらゆるものを消費財に変えることである。社会という概念は、もはや政治の分野 も包含する傾向がある。したがって、政治、つまり行動の重要性は、背景へと後退した。 アーレントは、キリスト教西洋哲学を批判している。ほとんどの哲学者は政治的な問題について意見を述べてはいたが、政治的な議論に直接参加した者はほとん どいなかった。彼女が例外とみなしたのは、マキャヴェッリだけだった。ヘーゲルは政治性を評価したが、アーレントは、ヘーゲルの歴史哲学における歴史的発 展の必然性という概念に特に反対している。歴史の目標としての絶対者の概念は、イデオロギー、ひいては非民主的な慣行の正当化、そして最終的には全体主義 的な支配形態につながる。 現代人は、「感情生活の急進的な主観性」、絶えず変化する「気分や気まぐれ」によって「果てしない内面の葛藤」に巻き込まれ、政治からも遠ざかっている。 個人は社会的に規範化され、この規範からの逸脱は反社会的あるいは異常とみなされる。その結果、官僚主義が支配する大衆社会という現象が生まれる。そこで は、社会階級や集団は平準化される。共同体の一員は皆、同じ権力によって統制される。平準化、つまり公の場での同調主義は、栄誉や「特質」を個人の私的な 問題に変えてしまう。大勢の人々が集まると、個人による専制、あるいは「多数派による専制」という傾向が生まれるんだ。[9] ハイデガーが、人間存在の基本条件として歴史性を想定していることも、著者にとっては、熟考の思考に固執していることに変わりはない。一方、活動的な人生 (Vita activa)には、政治の原則と自由の条件についての疑問が求められるんだ。このアプローチとして、アーレントはヤスパースと同様に、人間の多元性の条 件に関する疑問を最優先したカントの道徳哲学を参考にした。カントは政治家や哲学者だけでなく、すべての人間を立法者および裁判官と見なし、それにより共 和国の必要性を主張した。アーレントもこの見解に賛同している。 この著作の中で、アーレントは、自由、平等、幸福、公共性、私性、社会、政治といった概念の歴史的変遷を追跡し、それぞれの歴史的文脈における意味の変化 を記述している。その際、彼女の基準点は、アッティカの民主主義、特にソクラテスの対話が行われた時代である。彼女の考えでは、失われた政治の領域を、現 代に再び、修正を加えて定着させ、それによって、互いに差別化を図ろうとする、政治的に考え、行動する自由な個人の能力を、実りあるものにすべきだとして いる。それとは対照的に、彼女は、人間のあらゆる活動を 「あらゆる面で条件付けられ、行動する生物のレベルにまで低下させる」[10] |
| Kritik Ihr Schüler Richard Sennett (2008) hält die von Arendt getroffene Unterscheidung menschlicher Arbeit für falsch, „weil sie den praktisch tätigen Menschen zerlegt“: „Während «Animal laborans» auf die Frage des Wie fixiert ist, fragt «Homo faber» nach dem Warum.“[11] Sennett stellt heraus, dass auch das Animal laborans denken kann. Dieser Ansatz erfordere „ein tieferes Verständnis des Herstellens von Dingen, ein materialistischeres Engagement, als man es bei Denkern vom Schlage Hannah Arendts findet.“[12] Laut Sennett kann das „«Animal laborans» [...] «Homo faber» als Führer dienen.“[13] Der Philosoph Helmut Seidel wendet sich gegen die Trennung von Arbeiten, Herstellen und Handeln bei Arendt. Volker Caysa (2010) zufolge ist für Seidel „Praxis (also das o. g. Handeln) auch Herstellen durch Arbeit“. Seidel gehe von einer „konkreten Identität von Arbeit, Herstellen und Handeln“ aus, die durch ihre „Entfremdung in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft getrennt“ erscheine.[14] Als Ethnologe erkennt Gerd Spittler eine ungerechtfertigte Abwertung der Arbeit gegenüber dem Herstellen. Er schreibt, dass Arbeiten nicht so geistlos ist, wie unterstellt wird, und sich auch nicht systematisch vom Herstellen trennen lässt. Arbeit enthält „schöpferische, spielerische und ästhetische Momente. […] Sie fordert und fördert vielmehr vielseitige menschliche Fähigkeiten.“[15] |
批判 彼女の弟子であるリチャード・セネット(2008)は、アーレントが人間労働について行った区別は、「実践的な人間を分解している」という点で誤っている と考えている。「アニマル・ラボランス」は「どのように」という質問に固執しているのに対し、「ホモ・ファベル」は「なぜ」という質問を投げかけている。 [11] セネットは、アニマル・ラボランスも考えることができると強調している。このアプローチには、「物を作るという行為について、ハンナ・アーレントのような 思想家たちよりも、より深い理解と、より物質的な取り組みが必要だ」[12] と述べている。センネットによれば、「アニマル・ラボランス」は「ホモ・ファベル」の指針となりうるという[13]。 哲学者ヘルムート・ザイデルは、アーレントの「労働、生産、行動」の分離に反対している。フォルカー・カイサ(2010)によると、ザイデルにとって「実 践(すなわち上記の行動)は、労働による製造でもある」という。ザイデルは、「労働、製造、行動の具体的な同一性」を前提としており、それは「市民的資本 主義社会における疎外によって分離されている」ように見えるという。[14] 民族学者であるゲルト・スピットラーは、生産に対して労働が不当に軽視されていることを認識している。彼は、労働は、一般的に考えられているほど無意味な ものではなく、生産から体系的に分離できるものでもない、と書いている。労働には「創造的、遊び心のある、審美的な要素が含まれている。[…] むしろ、労働は、人間の多様な能力を要求し、促進するものである」[15]と。 |
| Ausgaben Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. Kohlhammer, Stuttgart 1960 (englisch: The human condition.). Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. Piper, München, Zürich 2002, ISBN 3-492-23623-5. wieder: ebd. 2009 Hannah Arendt: The human condition. University of Chicago Press, Chicago 1998, ISBN 0-226-02598-5. |
出版 ハンナ・アーレント『活動的人生、あるいは活動的な生活について』Kohlhammer、シュトゥットガルト、1960年(英語版:The human condition)。 ハンナ・アーレント:Vita activa oder Vom tätigen Leben(活動的な生活)。Piper、ミュンヘン、チューリッヒ、2002年、ISBN 3-492-23623-5。再版:同上、2009年 ハンナ・アーレント:The human condition(人間の条件)。シカゴ大学出版局、シカゴ、1998年、ISBN 0-226-02598-5。 |
| Literatur Wolfgang Heuer: Hannah Arendt. Rowohlt, Reinbek 1987, ISBN 3-499-50379-4, S. 52f., S. 92–101. Marie Luise Knott: Anmerkung zur Zweisprachigkeit. In: Wolfgang Heuer, Bernd Heiter, Stefanie Rosenmüller (Hrsg.): Arendt-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. J.B. Metzler, Stuttgart Weimar 2011, ISBN 978-3-476-02255-4, S. 68f. Ludger Lütkehaus: Natalität. Philosophie der Geburt. Die Graue Edition, Kusterdingen 2006, ISBN 978-3-906336-47-3 Anette Vowinckel: Arendt. Reclam, Leipzig 2006, ISBN 3-379-20303-3, S. 41–48. Maike Weißpflug, Jürgen Förster: The Human Condtion/Vita activa oder Vom tätigen Leben. In: Wolfgang Heuer, Bernd Heiter, Stefanie Rosenmüller (Hrsg.): Arendt-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar 2011, ISBN 978-3-476-02255-4, S. 61–68. Thomas Wild: Hannah Arendt. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-518-18217-X, S. 85–92. Elisabeth Young-Bruehl: Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit. Fischer, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-596-16010-3. S. 352–362, S. 414–423, S. 438–450 (Amerikanische Originalausgabe 1982). |
参考文献 ヴォルフガング・ホイヤー:ハンナ・アーレント。Rowohlt、ラインベック、1987年、ISBN 3-499-50379-4、52ページ以降、92~101ページ。 マリー・ルイーズ・ノット:二言語についての一考察。ヴォルフガング・ホイヤー、ベルント・ハイター、ステファニー・ローゼンミュラー(編):アーレン ト・ハンドブック。生涯、作品、影響。J.B. メッツラー、シュトゥットガルト・ワイマール 2011年、ISBN 978-3-476-02255-4、68ページ以降。 ルードガー・リュトケハウス:出生。出産の哲学。Die Graue Edition、クスターディンゲン、2006年、ISBN 978-3-906336-47-3 アネット・ヴォウィンケル:アーレント。Reclam、ライプツィヒ、2006年、ISBN 3-379-20303-3、41-48ページ。 Maike Weißpflug、Jürgen Förster:The Human Condtion/Vita activa oder Vom tätigen Leben。Wolfgang Heuer、Bernd Heiter、Stefanie Rosenmüller(編):Arendt-Handbuch。Leben、Werk、Wirkung。J.B. Metzler、シュトゥットガルト/ワイマール 2011、 ISBN 978-3-476-02255-4、61-68 ページ。 トーマス・ヴィルト:ハンナ・アーレント。スールカンプ、フランクフルト・アム・マイン 2006 年、ISBN 3-518-18217-X、85-92 ページ。 エリザベス・ヤング=ブリュール:ハンナ・アーレント。その生涯、作品、時代。フィッシャー、フランクフルト・アム・マイン、2004年、ISBN 3-596-16010-3。352~362 ページ、414~423 ページ、438~450 ページ(1982年、アメリカ版)。 |
| Fußnoten 1. Vita activa oder vom tätigen Leben (VA). München, Zürich -TB- 2002, S. 21. 2. VA -TB- 2002, S. 17f. 3. VA -TB- 2002, S. 36. 4. Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. Hrsg.: Thomas Meyer. erweiterte Neuausgabe Auflage. Piper, München 2021, ISBN 978-3-492-31691-0, S. 336 f. 5. Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. Hrsg.: Thomas Meyer. erweiterte Neuausgabe Auflage. Piper, München 2021, ISBN 978-3-492-31691-0, S. 344. 6. Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. Hrsg.: Thomas Meyer. erweiterte Neuausgabe Auflage. Piper, München 2021, ISBN 978-3-492-31691-0, S. 335–346. 7. Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. Hrsg.: Thomas Meyer. erweiterte Neuausgabe Auflage. Piper, München 2021, ISBN 978-3-492-31691-0, S. 347–353. 8. VA -TB- 2002, S. 387f. 9. VA -TB- 2002, S. 51ff. 10. VA -TB- 2002, S. 55f. 11. Richard Sennett: Handwerk, Berlin 2008, S. 16. 12. Richard Sennett: Handwerk, Berlin 2008, S. 17. 13. Richard Sennett: Handwerk, Berlin 2008, S. 18. 14. Volker Caysa: Über die Transformation des Geistes der Leipziger Bloch-Zeit in der praxisphilosophischen Debatte um und vor 1968 in der DDR, in: Klaus Kinner (Hrsg.): Die Linke – Erbe und Tradition, Teil 1, Berlin 2010, S. 194. 15. Gert Spittler: Anthropologie der Arbeit. Ein ethnographischer Vergleich. Springer VS, Wiesbaden 2016, S. 30, ISBN 978-3-658-10433-7 |
脚注 1. Vita activa oder vom tätigen Leben (VA)。ミュンヘン、チューリッヒ -TB- 2002、21 ページ。 2. VA -TB- 2002、17 ページ以降。 3. VA -TB- 2002、36 ページ。 4. ハンナ・アーレント:Vita activa oder Vom tätigen Leben。編者:トーマス・マイヤー。増補新版。パイパー、ミュンヘン 2021、ISBN 978-3-492-31691-0、336 ページ以降。 5. ハンナ・アーレント:Vita activa または活動的な生活について。編者:トーマス・マイヤー。増補新版。パイパー、ミュンヘン 2021、 ISBN 978-3-492-31691-0、344 ページ。 6. ハンナ・アーレント:Vita activa または活動的な生活。編集:トーマス・マイヤー。拡張新版。パイパー、ミュンヘン、2021 年、ISBN 978-3-492-31691-0、335-346 ページ。 7. ハンナ・アーレント『活動的な生活、あるいは活動的な人生』。編集:トーマス・マイヤー。増補新版。パイパー、ミュンヘン、2021年、ISBN 978-3-492-31691-0、347-353ページ。 8. VA -TB- 2002、387ページ以降。 9. VA -TB- 2002、51 ページ以降。 10. VA -TB- 2002、55 ページ以降。 11. リチャード・セネット『職人技』、ベルリン、2008 年、16 ページ。 12. リチャード・セネット『職人技』、ベルリン、2008 年、17 ページ。 13. リチャード・セネット『職人技』ベルリン、2008年、18ページ。 14. フォルカー・カイサ『1968年以前および1968年の東ドイツにおける実践哲学の議論におけるライプツィヒのブロッホ時代の精神の変容について』クラウス・キナー編『 『左翼 ― 遺産と伝統、第1部』ベルリン、2010年、194ページ。 15. ゲルト・スピットラー『労働の人類学。民族誌的比較』Springer VS、ヴィースバーデン、2016年、30ページ、ISBN 978-3-658-10433-7 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Vita_activa_oder_Vom_t%C3%A4tigen_Leben |
★
***
| 行為(action) | |
| 活動(activity) |
|
| 活動的生活(vita activa) |
|
| 観想的生(bios theoretikos) |
|
| 政治的生(bios politikos) |
|
| 観想的生活(vita contemplativa) |
|
| 活動的生活(vita activa) |
****
| 古代ギリシア(アリストテレス) |
ローマ(アウグスティヌス)から中世へ |
| bios theoretikos |
vita contemplative |
| bios politikos |
Vita activa |
| **** |
action -- Activity |
| 制作(ポイエーシス) |
work -- Activity |
| 労働(εργασία (エルガシア)/ άσχολία (アスホリア)) |
labour -- Activity |
****
| "Arendt introduces
the term vita activa (active life) by distinguishing it from vita
contemplativa (contemplative life). Ancient philosophers insisted upon
the superiority of the vita contemplativa, for which the vita activa
merely provided necessities. Karl Marx flipped the hierarchy, claiming
that the vita contemplativa is merely a superstructure on the
fundamental basic life-processes of a society. Arendt's thesis is that
the concerns of the vita activa are neither superior nor inferior to
those of the vita contemplativa, nor are they the same. The vita activa
may be divided into three sorts of activities: labor, work and action."
- "The Human Condition" |
アーレントは、ヴィータ・アクティバ(活動的生活)という言葉を、ヴィータ・コンテン
ポラティヴァ(観想的生活)と区別して紹介している。古代の哲学者たちは、「観照的生活」の優位性を主張し、「アクティバ」はそのための必需品を提供する
に過ぎないとした。カール・マルクスは、「観照的生活」は社会の基本的な生活プロセスの上部構造に過ぎないと主張し、そのヒエラルキーを逆転させた。アー
レントは、「アクティヴな生活」の関心事は「観照的な生活」の関心事と優劣がなく、また同じものでもない、と主張する。ヴィータ・アクティバは、労働、仕
事、行動という3つの種類の活動に分けられる |
| "According to Arendt, ancient
Greek life was divided between two realms: the public realm in which
"action" was performed, and the private realm, site of the household
ruled by its head. The mark of the private was not intimacy, as it is
in modern times, but biological necessity. In the private realm, heads
of households took care of needs for food, shelter, and sex. By
contrast, the public realm was a realm of freedom from these biological
necessities, a realm in which one could distinguish oneself through
"great words and great deeds." Property requirements for citizenship
reflected the understanding that unless one was able to take care of
one's biological necessities, one could not be free from them and hence
could not participate in the public realm as a free person among
equals. Slaves and subordinated women were confined to the private
realm where they met the biological necessities of the head of the
household. The public realm naturally was accorded higher status than
the private. With the fall of the Roman Empire, the church took over
the role of the public realm (though its otherworldly orientation gave
it a character distinct from the previous public realm), and the feudal
lords ran their lands and holdings as private realms. The modern period
saw the rise of a third realm, the social realm. The social realm is
concerned with providing for biological needs, but it does so at the
level of the state. Arendt views the social realm as a threat to both
the private and the public realm. In order to provide for the needs of
everyone, it must invade the private sphere, and because it makes
biological needs a public matter, it corrupts the realm of free action:
There is no longer a realm free from necessity." |
アーレントによれば、古代ギリシャの生活は、「行為」が行われる公的領
域と、家長が支配する家庭の私的領域の二つに分かれていた。私的領域の特徴は、現代のような親密さではなく、生物学的な必要性であった。私的領域では、家
長が衣食住と性の欲求を満たした。それに対して、公的領域は、こうした生物学的な必要性から解放された領域であり、「偉大な言葉と偉大な行為」によって自
らを際立たせることができる領域であった。市民権を得るための財産要件は、生物学的必需品の世話をすることができなければ、そこから自由になることはでき
ず、したがって、対等な自由人として公的領域に参加することはできないという理解を反映するものであった。奴隷や従属的な女性は、私的な領域に閉じ込めら
れ、そこで世帯主の生物学的な必要を満たすことになった。公的領域は当然、私的領域より高い地位を与えられていた。ローマ帝国の崩壊とともに、公界は教会
がその役割を担い(ただし、その異界志向はそれまでの公界とは異なる性格を持つ)、封建領主はその土地や領地を私的領域として運営するようになった。近代
になると、第三の領域である社会的領域が台頭してくる。社会的領域は生物学的欲求の充足に関わるものであるが、それは国家のレベルで行われる。アーレント
は、社会的領域を、私的領域と公的領域の両方に対する脅威として捉えている。すべての人の欲求を満たすためには、私的領域に侵入しなければならず、生物学
的欲求を公的な問題とするため、自由な行動の領域を腐敗させるのである。もはや必要性から自由な領域は存在しないのだ。 |
| Arendt claims that her
distinction between labor and work has been disregarded by philosophers
throughout history even though it has been preserved in many European
languages. Labor is human activity directed at meeting biological (and
perhaps other) necessities for self-preservation and the reproduction
of the species. Because these needs cannot be satisfied once and for
all, labor never really reaches an end. Its fruits do not last long;
they are quickly consumed, and more must always be produced. Labor is
thus a cyclical, repeated process that carries with it a sense of
futility. In the ancient world, Arendt asserts, labor was contemptible
not because it was what slaves did; rather, slaves were contemptible
because they performed labor, a futile but necessary activity. In the
modern world, not just slaves, but everyone has come to be defined by
their labor: We are job-holders, and we must perform our jobs to meet
our needs. Marx registers this modern idea in his assertion that man is
animal laborans, a species that sets itself apart from the animals not
by its thinking, but by its labor. But Marx then contradicts himself in
foreseeing a day when production allows the proletariat to throw off
the shackles of their oppressors and be free from labor entirely. By
Marx's own lights, this would mean they cease to be human. Arendt
worries that if automation were to allow us to free ourselves from
labor, freedom would be meaningless to us without the contrast with
futile necessity that labor provides. Because we define ourselves as
job-holders and have relegated everything outside of labor to the
category of play and mere hobbies, our lives would become trivial to us
without labor. Meanwhile, advances in production and the transformation
of work into labor means that many things that were once to be lasting
works are now mere disposable objects of consumption, "The
solution...consists in treating all use objects as though they were
consumer goods, so that a chair or a table is now consumed as rapidly
as a dress and a dress used up almost as quickly as food." |
アーレントは、労働と仕事の区別は、多くのヨーロッパの言語に残されて
いるにもかかわらず、歴史上の哲学者たちによって無視されてきたと主張している。労働は、自己保存と種の再生のための生物学的な(そしておそらく他の)必
要を満たすために向けられた人間の活動である。これらの欲求は一度きりでは満たされないので、労働は決して本当の意味で終わりを迎えることはない。その果
実は長くは続かず、すぐに消費され、さらに生産されなければならない。このように、労働は循環的に繰り返されるプロセスであり、無益な感覚を伴う。古代世
界では、労働は奴隷がすることだから軽蔑されるのではなく、奴隷は労働という無益だが必要な活動を行うから軽蔑されるのだと、アーレントは主張するのであ
る。現代社会では、奴隷だけでなく、すべての人が労働によって定義されるようになった。私たちは仕事を持つ者であり、私たちの欲求を満たすために仕事をし
なければならない。マルクスは、この近代的な考えを、人間は動物的労働者であり、思考によってではなく、労働によって動物から自己を分離する種である、と
いう主張として記録しているのである。しかし、マルクスは、生産によってプロレタリアートが抑圧者の束縛から解放され、労働から完全に自由になる日を予見
して、自分自身に矛盾しているのである。マルクス自身の見解では、これは彼らが人間でなくなることを意味する。アーレントは、オートメーションによって労
働から解放されたとしても、労働がもたらす無益な必然性との対比がなければ、自由はわれわれにとって無意味なものになると懸念している。私たちは自分たち
を仕事人間として定義し、労働以外のものを遊びや単なる趣味の範疇に追いやってきたのだから、労働がなければ私たちの生活はつまらないものになってしまう
だろう。一方、生産の進歩と仕事の労働への転換は、かつて永続的な作品であった多くのものが、今では単なる使い捨ての消費の対象になっていることを意味す
る。"解決策は...すべての使用物を消費財であるかのように扱うことで、椅子やテーブルは今やドレスと同じくらい急速に、ドレスは食料と同じくらい急速
に消費されている。"と。 |
| Work, unlike labor, has a
clearly defined beginning and end. It leaves behind a durable object,
such as a tool, rather than an object for consumption. These durable
objects become part of the world we live in. Work involves an element
of violation or violence in which the worker interrupts nature in order
to obtain and shape raw materials. For example, a tree is cut down to
obtain wood, or the earth is mined to obtain metals. Work comprises the
whole process, from the original idea for the object, to the obtaining
of raw materials, to the finished product. The process of work is
determined by the categories of means and end. Arendt thinks that
thinking of ourselves primarily as workers leads to a sort of
instrumental reasoning in which it is natural to think of everything as
a potential means to some further end. Kant's claim that humanity is an
end in itself shows just how much this instrumental conception of
reason has dominated our thinking. Utilitarianism, Arendt claims, is
based on a failure to distinguish between "in order to" and "for the
sake of."[3] The homo faber mentality is further evident in the
substitution of the notion of "use value" for "worth" in economic
discourse, which marks the beginning of the disappearance of a notion
of a kind of worth that is intrinsic, as opposed to value, which is
relative to human demand or need. Although use objects are good
examples of the products of work, artworks are perhaps the best
examples, since they have the greatest durability of all objects. Since
they are never used for anything (least of all labor), they don't get
worn down. |
仕事は、労働と違って、始まりと終わりが明確に定義されている。消費す
るための物ではなく、道具のような耐久性のある物を残す。これらの耐久性のあるオブジェクトは、私たちの住む世界の一部となる。労働は、原料を手に入れ、
形にするために、労働者が自然を中断させるという侵害や暴力の要素を含んでいます。例えば、木材を得るために木を切り倒し、金属を得るために大地を採掘す
る。仕事とは、物に対する最初のアイデアから、原材料の入手、そして完成品に至るまでの全過程から構成される。仕事のプロセスは、手段と目的というカテゴ
リーによって決定される。アーレントは、自分自身を主として労働者として考えることは、すべてのものをさらなる目的のための潜在的な手段と考えるのが当然
であるという、一種の道具的推論につながると考えている。カントが人間性それ自体が目的であると主張したのは、この道具的な理性の概念がいかに我々の思考
を支配してきたかを示している。アーレントは、功利主義は「ために」と「のために」を区別することの失敗に基づくと主張している[3]。ホモファーベルの
考え方は、経済的言説における「使用価値」の概念を「価値」に置き換えることでさらに明らかになり、人間の需要や必要性に相対する価値とは対照的に、内在
するある種の価値の概念の消滅の始まりとなったのである。仕事の成果物としては、使用目的のモノも良い例ですが、美術品は、モノの中で最も耐久性が高いの
で、最も良い例である。なぜなら、美術品はあらゆる物の中で最も耐久性があるからである。美術品は何にも(少なくとも労働には)使われないので、摩耗する
ことはない。 |
| The third type of activity,
action (which includes both speech and action), is the means by which
humans disclose themselves to others, not that action is always
consciously guiding such disclosure. Indeed, the self revealed in
action is more than likely concealed from the person acting, revealed
only in the story of her action. Action is the means by which we
distinguish ourselves from others as unique and unexchangeable beings.
With humans, unlike with other beings, there is not just a generic
question of what we are, but of who each is individually. Action and
speech are always between humans and directed toward them, and it
generates human relationships. Diversity among the humans that see the
action makes possible a sort of objectivity by letting an action be
witnessed from different perspectives. Action has boundless
consequences, often going far beyond what we could anticipate. The
Greeks thought of the polis as a place where free people could live
together so as to act. Philosophers like Plato, disliking action's
unpredictability, modeled the ideal polis on the household. In it, the
philosopher king produces the lasting work of legislation, and the
people labor under him. Against attempts to replace action with work
and labor, Arendt offers two solutions to the two greatest problems
action creates: forgiveness to temper action's irreversibility, and
promises to mitigate its unpredictability. “Human plurality, the basic
condition of both action and speech, has the twofold character of
equality and distinction. If men were not equal, they could neither
understand each other |
第三の活動である行動(発話と行為の両方を含む)は、人間が自己を他者
に開示する手段であるが、行動が常に意識的にその開示を誘導しているわけではない。実際、行動によって明らかにされる自己は、行動している本人には隠され
ていることが多く、その行動の物語の中でしか明らかにされない。行動とは、私たちが自分を他者と区別し、唯一無二の交換不可能な存在とするための手段であ
る。人間には、他の存在と違って、私たちが何であるかという一般的な問題だけでなく、それぞれが個々に誰であるかという問題が存在する。行動や言動は常に
人間同士であり、人間に向けて行われ、人間関係を生成する。行動を見る人間の多様性は、ある行動を異なる視点から目撃させることで、一種の客観性を可能に
する。行動は無限の結果をもたらし、しばしば我々の予想をはるかに超える結果をもたらす。ギリシアでは、ポリスを「自由な人々が行動するために共に暮らす
場所」と考えていた。プラトンのような哲学者は、行動の予測不可能性を嫌い、理想的なポリスを家庭をモデルとして考えた。そこでは、哲学者の王が立法とい
う永続的な仕事を生み出し、民衆は彼の下で労働する。行動を仕事や労働に置き換える試みに対抗して、アーレントは行動が生み出す二つの大きな問題に対して
二つの解決策を提示する。それは、行動の不可逆性を和らげる寛容と、行動の予測不可能性を緩和する約束である。「行動と言論の両方の基本条件である人間の
複数性は、平等と区別の二重の性格を持っている。もし人間が平等でなかったら、互いに理解することはできない。 |
| Arendt thinks that three great
events determined the character of the modern age: "the discovery of
America and the ensuing exploration of the whole earth; the
Reformation, which by expropriating ecclesiastical and monastic
possessions started the two-fold process of individual expropriation
and the accumulation of social wealth; the invention of the telescope
and the development of a new science that considers the nature of the
earth from the viewpoint of the universe."[4] None of these events
could have been foreseen. They happened suddenly and had repercussions
their instigators never intended. One effect of each of these events is
to increase our alienation from the world, which Arendt thinks is far
more characteristic of our age than alienation from the self (as Marx
thought).[5] The shrinking distances brought about by exploration and
transportation technology makes us more an inhabitant of the Earth than
of our particular place within it. The process of expropriation kicked
off by the Reformation expropriated people from their land and place in
the world. Galileo's discovery of the continuity between the earth and
the universe alienates people from their world by showing that our
earth-centered view of the world is illusory, that the sun does not
rise and set as it appears to. What set Galileo apart from other
heliocentric theorists is that he proved that heliocentric theories
were not merely useful instruments for predicting/explaining data but
proper descriptions of reality. Ironically, the outcome of the
scientific revolution is that current theories have become so bizarre
and that perhaps no one can grasp the world they describe. They have
turned out to be useful primarily as instruments, after having
shattered our previous understanding of the world. Meanwhile, science
now further alienates us from the world by unleashing processes on
earth that previously occurred only further out in the universe. We
have found an archimedean point to move the world, but only by losing
our place in it. The consequence of this world alienation for
philosophy has been an intense focus on the self, the one remaining
sphere of certainty and knowledge. The world described by science
cannot be known, or not with certainty, but the self, Descartes and
other moderns thought, could be known. Though his cogito ergo sum was
anticipated by Augustine, his dubito ergo sum is original and a
hallmark of modernity: beginning from doubt. The notion of common sense
as a sense in which the other five were fitted to a common world ceded
to a conception of common sense as an inner faculty with no
relationship to the world, and the assumption that all humans had
faculties like this in common became necessary to get theories going,
but without the assumption of a common world, the assumption of
faculties in common lost some warrant. Galileo's discoveries also have
implications for the 'vita activa' and 'contemplativa'. That he made
the discoveries with a telescope, with a product of human work, signals
an important change in science. Knowledge is acquired not simply by
thinking, but by making. Homo faber and the life of work were thus
exalted over the life of contemplation. Indeed, the model of scientific
inquiry, the experiment, is one in which the scientist unleashes a
process by which the scientist produces results. This way of doing
science is naturally understood in terms of work processes. The
philosopher has consequently been relegated to a position of relative
insignificance, merely puzzling over what the scientists have shown.
But in the end, Homo faber ceded primacy to animal laborans. The life
of labor became the central concern because all of these developments
took place in a Christian society that valued life far more than others
have. After secularization, this vestigial preoccupation with life as
the central value dominates our activities. It has made us into a
society of laborers. Judged by the historical significance of what they
do, the people most capable of action now are perhaps the scientists,
but unfortunately, they act into nature and not human relationships,
and thus their action cannot be the source of meaningfulness that
illuminates human existence. Action is still possible in free
societies, but fragile. |
それは、「アメリカの発見とそれに続く地球全体の探検、教会や修道院の
財産を収奪することによって、個人の収奪と社会的富の蓄積という二重のプロセスを始めた宗教改革、望遠鏡の発明と宇宙の視点から地球の性質を考える新しい
科学の発展」[4]であった。突然起こったことであり、その仕掛け人が意図しないところで影響を及ぼした。このことは、(マルクスが考えたような)自己か
らの疎外よりもはるかに現代に特徴的であるとアーレントは考えている[5]。
探査と輸送技術によってもたらされた距離の縮小は、我々を地球内の特定の場所というよりも地球の住人としているのである。宗教改革によって始まった収奪の
プロセスは、人々を世界における自分の土地と場所から収奪した。ガリレオは地球と宇宙の連続性を発見し、地球を中心とした世界観が幻想であること、太陽は
見かけ通りには昇らず沈まないことを示し、人々を自分たちの世界から疎外したのである。ガリレオが他の天動説論者と違うのは、天動説が単にデータを予測・
説明するための便利な道具ではなく、現実を正しく記述するものであることを証明した点である。皮肉なことに、科学革命の結果、現在の理論は非常に奇妙なも
のとなり、おそらく誰もその世界を理解することはできないであろう。科学は、それまでの世界観を打ち砕いた後、主に道具として役立つことがわかった。一
方、科学は、これまで宇宙の彼方にしか存在しなかったプロセスを地上に解き放ち、私たちをさらに世界から遠ざけている。私たちは世界を動かすためのアルキ
メデス点を見つけたが、それは私たちの居場所を失うことでしかないのだ。この世界からの疎外が哲学にもたらした結果は、唯一残された確実な知識の領域であ
る自己に強烈な焦点を当てることでした。デカルトをはじめとする近代人は、科学が描く世界を知ることはできないが、自己を知ることはできると考えたので
す。コギト・エルゴ・スムはアウグスティヌスの先取りであったが、デュビト・エルゴ・スムはオリジナルであり、疑いから始まるという近代の特徴である。常
識は他の5つが共通の世界に適合する感覚という概念から、世界とは関係のない内的な能力という概念に変わり、人間は皆このような能力を共通して持っている
という前提が理論を進める上で必要になったが、共通の世界という前提がなければ、能力の共通性という前提も意味を失ってしまうのだ。ガリレオの発見は、
「ヴィータ・アクティバ」と「コンテンポラティバ」についても示唆を与えている。彼が人間の仕事の産物である望遠鏡を使って発見したことは、科学における
重要な変化を示唆している。知識は単に考えるだけでなく、作ることによって獲得されるのである。こうして、ホモファーベルと労働の生活は、思索の生活より
も高く評価されるようになった。実際、科学的探求のモデルである実験は、科学者が結果を出すプロセスを解き放つものである。このような科学のあり方は、当
然、仕事のプロセスという観点から理解される。そのため、哲学者は、科学者が示したものに戸惑うだけで、相対的に重要でない
位置に追いやられてきた。しかし、結局のところ、ホモ・フェイバーは動物労働者に優先権を譲った。労働の生が中心的な関心事となったのは、生命を重視する
キリスト教社会でこうした発展がなされたからである。しかし、世俗化した現在では、その名残として、生命を中心とした価値観が私たちの活動を支配してい
る。その結果、私たちは労働者社会となった。歴史的な意義から判断して、いま最も行動的なのは科学者であろうが、残念ながら、彼らは人間関係ではなく、自
然の中に行動しているので、その行動は人間存在を照らす意義の源にはなり得ない。自由な社会では、行動はまだ可能だが、もろい。 |
| Synopsis from Wiki's "The Human
Condition" |
★一般的な意味での人間の条件
This painting, with symbols of life, death, and time, is an example of memento mori art.[1]
| The human condition
can be defined as the characteristics and key events of human life,
including birth, learning, emotion, aspiration, reason, morality,
conflict, and death. This is a very broad topic that has been and
continues to be pondered and analyzed from many perspectives, including
those of art, biology, literature, philosophy, psychology, and religion. As a literary term, "human condition" is typically used in the context of ambiguous subjects, such as the meaning of life or moral concerns.[2] |
人間の条件とは、誕生、学習、感情、願望、理性、道徳、葛藤、死といった、人間の生命の特徴と主要な出来事を指す。これは非常に広範な主題であり、芸術、生物学、文学、哲学、心理学、宗教など、様々な観点から考察され分析され続けてきた。 文学用語としての「人間の条件」は、通常、人生の意味や道徳的懸念といった曖昧な主題の文脈で使用される。 |
| Some perspectives Each major religion has definitive beliefs regarding the human condition. For example, Buddhism teaches that existence is a perpetual cycle of suffering, death, and rebirth from which humans can be liberated via the Noble Eightfold Path. Meanwhile, many Christians believe that humans are born in a sinful condition and are doomed in the afterlife unless they receive salvation through Jesus Christ. Philosophers have provided many perspectives. An influential ancient view was that of the Republic in which Plato explored the question "what is justice?" and postulated that it is not primarily a matter among individuals but of society as a whole, prompting him to devise a utopia. Two thousand years later René Descartes declared "I think, therefore I am" because he believed the human mind, particularly its faculty of reason, to be the primary determiner of truth; for this he is often credited as the father of modern philosophy.[3] One such modern school, existentialism, attempts to reconcile an individual's sense of disorientation and confusion in a universe believed to be absurd. Many works of literature provide a perspective on the human condition.[2] One famous example is Shakespeare's monologue "All the world's a stage" which pensively summarizes seven phases of human life.[4] Psychology has many theories, including Maslow's hierarchy of needs and the notions of identity crisis and terror management. It also has various methods, e.g. the logotherapy developed by Holocaust survivor Viktor Frankl to discover and affirm a sense of meaning. Another method, cognitive behavioral therapy, has become a widespread treatment for clinical depression.[5] Charles Darwin established the biological theory of evolution, which posits that the human species is related to all others, living and extinct, and that natural selection is the primary survival factor. This led to subsequent beliefs, such as social Darwinism, which eventually lost its connection to natural selection,[6] and theistic evolution of a creator deity acting through laws of nature, including evolution.[7] |
いくつかの視点 主要な宗教はそれぞれ、人間の状態について明確な信念を持っている。例えば仏教は、存在とは苦悩と死と再生の絶え間ない循環であり、人間は八正道を通じて そこから解脱できると教える。一方、多くのキリスト教徒は、人間は罪深い状態で生まれ、イエス・キリストによる救いを受けなければ来世で滅びると信じてい る。 哲学者たちは多くの見解を提供してきた。古代の有力な見解として『国家』がある。プラトンはそこで「正義とは何か」という問いを探求し、それは主に個人間 の問題ではなく社会全体の問題だと仮定した。これが彼にユートピア構想を促したのである。それから二千年後のルネ・デカルトは「我思う、故に我あり」と宣 言した。彼は人間の精神、特に理性の働きこそが真理の主要な決定要因だと考えたからだ。この功績から彼はしばしば近代哲学の父とされる[3]。そのような 近代学派の一つである実存主義は、不条理とされる宇宙における個人の方向感覚の喪失や混乱を和解させようとする。 多くの文学作品は人間の条件に関する視点を提供する。有名な例としてシェイクスピアの独白「世界は舞台」があり、人間の生涯の七つの段階を思索的に要約している。[4] 心理学には多くの理論がある。マズローの欲求階層説やアイデンティティ危機、恐怖管理といった概念も含まれる。また様々な手法も存在する。例えばホロコー スト生存者ヴィクトール・フランクルが開発したロゴセラピーは、意味を見出し肯定する療法だ。認知行動療法もまた、臨床的うつ病の広範な治療法となってい る。[5] チャールズ・ダーウィンは生物学的進化論を確立した。この理論は、人類が他の全ての生物(現存種・絶滅種を問わず)と関連しており、自然淘汰が生存の主要 因であると主張する。これに基づき、社会ダーウィニズム(後に自然淘汰との関連性を失った[6])や、創造主神が進化を含む自然法則を通じて作用するとい う神学的進化論[7]といった思想が発展した。 |
| Human nature Know thyself |
人間の本性 己を知れ |
| 1. Ostberg, R (18 January 2023). "Memento mori". 2. C. Welch. "The Human Condition in Literature". Retrieved 28 April 2021. 3. Bertrand Russell (2004), History of Western Philosophy, pp. 511, 516–7. 4. "'All The World's A Stage': Quote & Meaning". No Sweat Shakespeare. 12 December 2019. Retrieved 1 December 2023. 5.Driessen Ellen; Hollon Steven D (2010). "Cognitive Behavioral Therapy for Mood Disorders: Efficacy, Moderators and Mediators". Psychiatric Clinics of North America. 33 (3): 537–55. doi:10.1016/j.psc.2010.04.005. PMC 2933381. PMID 20599132. 6. Bowler, Peter J. (2003). Evolution: The History of an Idea (3rd ed.). University of California Press. p. 179. ISBN 978-0520236936. 7. "The Creation/Evolution Continuum". National Center for Science Education. 22 June 2022. Archived from the original on 26 January 2024. Retrieved 26 January 2024. |
1. オストバーグ, R (2023年1月18日). 「メメント・モリ」. 2. C. ウェルチ. 「文学における人間の条件」. 2021年4月28日閲覧. 3. バートランド・ラッセル (2004), 『西洋哲学史』, pp. 511, 516–7. 4. 「『世界は舞台』:引用と意味」. No Sweat Shakespeare. 2019年12月12日. 2023年12月1日取得. 5.Driessen Ellen; Hollon Steven D (2010). 「気分障害に対する認知行動療法:有効性、モデレーター及びメディエーター」. 北米精神医学クリニック。33巻3号:537-55頁。doi:10.1016/j.psc.2010.04.005。PMC 2933381。PMID 20599132。 6. ボウラー、ピーター・J.(2003)。進化:一つの思想の歴史(第3版)。カリフォルニア大学出版局。179頁。ISBN 978-0520236936。 7. 「創造論/進化論の連続体」。全米科学教育センター。2022年6月22日。2024年1月26日にオリジナルからアーカイブ。2024年1月26日に閲覧。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Human_condition |
|
★
★Arendt, Hanna. Human Condition. University of Chicago Press, 1958
| 第1章 人間の条件 The Human Condition |
|
| 1. Vita Activa and the Human Condition 7 |
|
| 2. The Term Vita Activa 12 |
|
| 3. Eternity versus Immortality 17 |
|
| 第2章 公的領域と私的領域 The Public and the Private Realm |
|
| 4. Man: A Social or a Political Animal 22 |
|
| 5. The Polls and the Household 28 |
|
| 6. The Rise of the Social 38 |
|
| 7. The Public Realm: The Common 50 |
|
| 8. The Private Realm: Property 58 | |
| 9. The Social and the Private 68 |
|
| 10. The Location of Human Activities 73 |
|
| 第3章 労働 Labor |
|
| 11. "The Labour of Our Body and the Work of Our Hands" 79 |
|
| 12. The Thing-Character of the WorId 93 |
|
| 13. Labor and Life 96 |
|
| 14. Labor and Fertility 101 |
|
| 15. The Privacy of Property and Wealth 109 |
|
| 16. The Instruments of Work and the Division of Labor 118 |
|
| 17. A Consumers' Society 126 |
|
| 第4章 仕事 Work |
|
| 18. The Durability of the World 13 6 |
|
| 19. Reification 139 |
|
| 20. Instrumentality and Animal Laborans 144 |
|
| 21. Instrumentality and Homo Faber 153 |
|
| 22. The Exchange Market 159 |
|
| 23. The Permanence of the World and the Work of Art 167 |
|
| 第5章 活動 Action |
|
| 24. The Disclosure of the Agent in Speech and Action 175 |
|
| 25. The Web of Relationships and the Enacted Stories 181 |
|
| 26. The Frailty of Human Affairs 188 |
|
| 27. The Greek Solution 192 |
|
| 28. Power and the Space of Appearance 199 |
|
| 29. Homo Faber and the Space of Appearance 207 |
|
| 30. The Labor Movement 212 |
|
| 31. The Traditional Substitution of Making for Acting 220 |
|
| 32. The Process Character of Action 230 |
|
| 33. Irreversibility and the Power To Forgive 236 |
|
| 34. Unpredictability and the Power of Promise 243 |
|
| 第6章 〈活動的生活〉と近代 The Vita Activa and the Modern Age | |
| 35. World Alienation 248 |
|
| 36. The Discovery of the Archimedean Point 257 |
|
| 37. Universal versus Natural Science 268 |
|
| 38. The Rise of the Cartesian Doubt 273 |
|
| 39. Introspection and the Loss of Common Sense 280 | |
| 40. Thought and the Modern World View 285 |
|
| 41. The Reversal of Contemplation and Action 289 |
|
| 42. The Reversal within the Vita Activa and the Victory of Homo Faber 294 |
|
| 43. The Defeat of Homo Faber and the Principle of Happiness 305 |
|
| 44. Life as the Highest Good 313 |
|
| 45. The Victory of the Animal Laborans 320 |
★
第1章 人間の条件 The Human Condition
1. Vita Activa and the Human Condition 7
2. The Term Vita Activa 12
3. Eternity versus
Immortality 17
第2章 公的領域と私的領域 The Public and the Private Realm
4. Man: A Social or a Political Animal 22
5. The Polls and the Household 28
6. The Rise of the Social 38
7. The Public Realm: The Common 50
8. The Private Realm: Property 58
9. The Social and the Private 68
10. The Location of
Human Activities 73
第3章 労働 Labor
11. "The Labour of Our Body and the Work of Our Hands" 79
12. The Thing-Character of the WorId 93
13. Labor and Life 96
14. Labor and Fertility 101
15. The Privacy of Property and Wealth 109
16. The Instruments of Work and the Division of Labor 118
17. A Consumers'
Society 126
第4章 仕事 Work
18. The Durability of the World 13 6
19. Reification 139
20. Instrumentality and Animal Laborans 144
21. Instrumentality and Homo Faber 153
22. The Exchange Market 159
23. The Permanence of
the World and the Work of Art 167
第5章 活動 Action
24. The Disclosure of the Agent in Speech and Action 175
25. The Web of Relationships and the Enacted Stories 181
26. The Frailty of Human Affairs 188
27. The Greek Solution 192
28. Power and the Space of Appearance 199
29. Homo Faber and the Space of Appearance 207
30. The Labor Movement 212
31. The Traditional Substitution of Making for Acting 220
32. The Process Character of Action 230
33. Irreversibility and the Power To Forgive 236
34. Unpredictability
and the Power of Promise 243
第6章 〈活動的生活〉と近代 The Vita Activa and the Modern Age
35. World Alienation 248
36. The Discovery of the Archimedean Point 257
37. Universal versus Natural Science 268
38. The Rise of the Cartesian Doubt 273
39. Introspection and the Loss of Common Sense 280
40. Thought and the Modern World View 285
41. The Reversal of Contemplation and Action 289
42. The Reversal within the Vita Activa and the Victory of Homo Faber 294
43. The Defeat of Homo Faber and the Principle of Happiness 305
44. Life as the Highest Good 313
45. The Victory of the
Animal Laborans 320
★精読アレント『人間の条件』 / 牧野雅彦著, 講談社 , 2023 . - (講談社選書メチエ, 781)
| 二〇世紀を代表する思想家ハンナ・アレント
(1906-1975年)。その主著は『人間の条件』(英語版1958年)にほかならない。科学と技術の進歩は世界大戦の惨禍をもたらす一方で、地球の外
にまで人間の活動領域を拡大する。「観照的生活」から「活動的生活」への移行を歴史的に跡づけ、「労働(labour)」「仕事(work)」「行為
(action)」の分類に基づいて、世界から疎外される「人間」の行く末を展望する古典—待望の新訳を成し遂げた第一人者が全六章を徹底解説! |
|
| はじめに—地球からの脱出と「人間の条件」の変容 序章 マルクスと西洋政治思想の伝統 第1章 観照的生活と活動的生活 第2章 公的なものと私的なもの 第3章 労働—自然と人間の物質代謝 第4章 仕事と制作 第5章 行為 第6章 近代の開幕と活動のヒエラルキーの転換 |
|
| はじめに—地球からの脱出と「人間の条件」の変容 | |
| 序章 マルクスと西洋政治思想の伝統 | |
| 第1章 観照的生活と活動的生活 | |
| 第2章 公的なものと私的なもの | |
| 第3章 労働—自然と人間の物質代謝 | |
| 第4章 仕事と制作 | |
| 第5章 行為 | |
| 第6章 近代の開幕と活動のヒエラルキーの転換 | |
★
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆