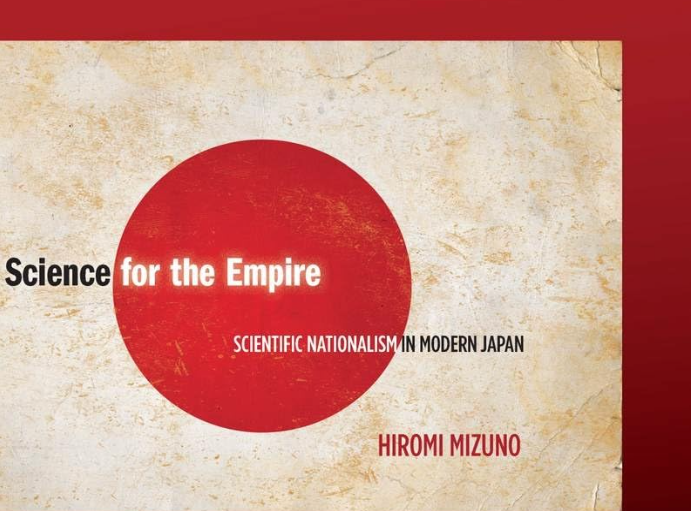
科学におけるナショナリズム
Scientific Nationalism
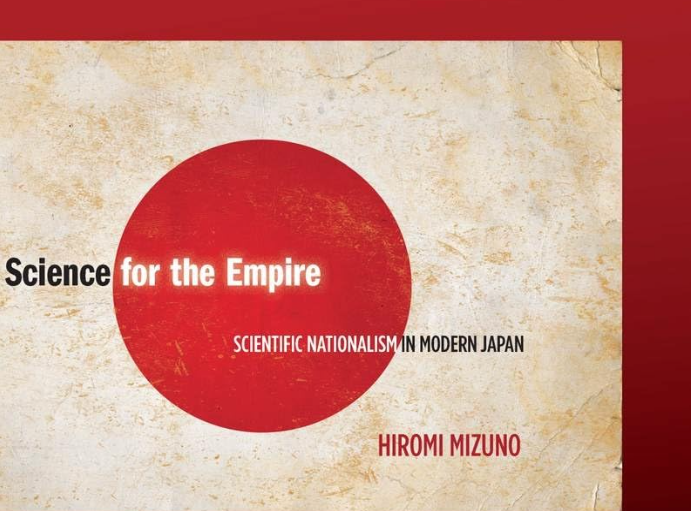
☆
「科学ナショナリズム(scientific nationalism)」は、(1)科学内部で発生したナショナリズムと、(2)科学に基づくナショナリ
ズムの両方を指す。後者の「科学に基づくナショナリズム」は、政治的目的のために科学を直接的に利用し、ナショナリズム政治の論拠や正当化の根拠としたも
のである。
| Science
for the empire : scientific nationalism in modern Japan / Hiromi Mizuno,
Stanford, Calif. : Stanford University Press , c2009 This fascinating study examines the discourse of science in Japan from the 1920s to the 1940s in relation to nationalism and imperialism. How did Japan, with Shinto creation mythology at the absolute core of its national identity, come to promote the advancement of science and technology? Using what logic did wartime Japanese embrace both the rationality that denied and the nationalism that promoted this mythology? Focusing on three groups of science promoters―technocrats, Marxists, and popular science proponents―this work demonstrates how each group made sense of apparent contradictions by articulating its politics through different definitions of science and visions of a scientific Japan. The contested, complex political endeavor of talking about and promoting science produced what the author calls "scientific nationalism," a powerful current of nationalism that has been overlooked by scholars of Japan, nationalism, and modernity. |
帝国のための科学:近代日本の科学的ナショナリズム /
水野広美、カリフォルニア州スタンフォード:スタンフォード大学出版局、2009年 この魅力的な研究は、1920年代から1940年代の日本の科学言説を、ナショナリズムと帝国主義との関連で検証している。神道創世神話を絶対的な核とし て国民のアイデンティティを確立していた日本が、なぜ科学技術の進歩を推進するようになったのか。戦時中の日本人は、この神話を否定する合理性と推進する ナショナリズムを、どのような論理で受け入れたのか。 本書では、科学振興を推進する3つのグループ、すなわちテクノクラート、マルクス主義者、大衆科学推進派に焦点を当て、各グループが科学の異なる定義や科 学的日本像を通じて政治的主張を明確化することで、一見したところの矛盾をどのように理解していたかを明らかにしている。科学について語り、科学を推進す るという、論争の的となり、複雑な政治的試みは、著者が「科学的ナショナリズム」と呼ぶものを生み出した。これは、日本、ナショナリズム、近代性に関する 研究者の間でこれまで見過ごされてきた、強力なナショナリズムの潮流である。 |
| Chapter One Toward Technocracy INTERNATIONALLY, during the 1910s elite engineers began to demand higher status and access to political power. Technocrats (technology-bureaucrats) in Japan, too, responded to the rapid development of heavy industrialization and the rigorous promotion of research and development by organizing themselves to make such demands. Civil engineers in the central government were particularly active in this technocrat movement. They were in charge of the development of the nation's land but had very limited access to policy-making power as a result of the discriminatory Civil Servant Appointment Law (bunkan nin'yorei). The fierce friction between technology-bureaucrats and law-bureaucrats was at the core of the technocracy movement in Japan that would later shape the Japanese Empire's science and technology policies based on the technocratic definition of science, "science-technology." At the center of this technocratic movement was Miyamoto Takenosuke, an engineer in the Civil Engineering Bureau in the Ministry of Home Affairs. This chapter looks at the early stages of the technocratic movement (1920-32) through Miyamoto and an engineers' organization he founded in 1920, the Kojin Club, whose objective was to unite engineers and demand access to political power. The trajectory of the Kojin Club demonstrates how a belief in science and rationality was closely related to class formation and nationalism. As large-scale technological networks were changing Japan's industrial and socioeconomic landscape, the Kojin Club engineers drew upon the proletarian movement to construct their own class consciousness in their efforts to unite engineers. But they soon abandoned the language and politics of the proletarian movement because they could not translate their engineering background into a unifying class identity. Rather, it was the "scientific" expertise that they realized affirmed their identity as a group regardless of class. The nation rather than class-industrial rationalization rather than class struggle-provided the language and ideology needed to transform their cultural capital into political power. Their trial-and-error search for an engineer's identity led them to develop their technocracy. Although the term "technocracy" (tekunokurashii) was introduced to Japan only after it became a buzzword in the United States in the early 1930s,2 the history of the Kojin Club demonstrates that Japanese engineers had begun to develop their own technocracy well before that. "Technocracy" has been defined in various ways, but it generally entails the rule by experts, technological determinism, and the belief that technological considerations render politics obsolete. I add to this common definition of technocracy that nationalism is often an important ingredient, at least until a recent global trend toward regional economic blocs (such as the European Union) rendered the nation-state less meaningful to technocratic governance. I use "technocrats" interchangeably with elite "technology-bureaucrats" (bureaucrats in the central government with degrees in engineering, agriculture, forestry, and other technical and professional fields), and "technocracy" for a specific vision of governance that these technocrats developed based on their definition of science. As such, Miyamoto and his engineer colleagues' movement to access political power was both justified and inspired by their concern for the nation. Miyamoto and Kojin Club members also remind us that technocracy, whether in Japan, the United States, or Europe, was proposed as an alternative to Marxism and thus competed with it to be the better solution to the economic and labor crises of the early twentieth century. Trust in science, although defined differently by Marxists, played a central role in their claim to offer better management of society. Like Marxism, technocracy was critical of the existing capitalist management of society, but unlike Marxism, which called for the ruling of society by the proletariat made possible by the "scientific" observation of the history of a society, technocracy called for management of the nation by engineers with "scientific" expertise. In Parts 1 and 2 of this book, I will demonstrate that the rivalry between technocracy and Marxism did not come only from the competing visions of an ideal society; it also came from their competing definitions of the "scientific." Defining Engineers as Creators The founder and leader of the Kojin Club, Miyamoto Takenosuke, was an ambitious and talented man with leadership capability. Miyamoto was born on Gogo Island, Ehime Prefecture, in 1892 to a once-wealthy merchant family. The decline of his family's fortune forced him to leave junior high school and find a job as a sailor when he was fourteen. With the help of his brother-in-law and a wealthy acquaintance, however, he was later able to enter a private junior high school in Tokyo. A smart, hardworking student, Miyamoto was always at the top of his class; in fact, his grades were so excellent that he was admitted to First Higher School (daiichi koto gakko), the most prestigious high school in prewar Japan, without taking the entrance examination. As expected of First Higher School graduates, he went on to Tokyo Imperial University and graduated in 1917 as the "silver watch" student of the Engineering Department (in prewar Japan the top imperial university students received a silver watch from the emperor). The same year, he entered the Bureau of Civil Engineering in the Ministry of Home Affairs. He worked on the nation's two largest river improvement projects, the Tone River project and the Arakawa River project, and proved himself to be a young leader in ferroconcrete construction, a cutting-edge field in engineering. After a state-funded study trip to Europe and the United States (1923-25), he steadily moved up the ladder in the bureaucracy, eventually to the vice-ministerial position, the highest rank that any bureaucrat could attain. Miyamoto was also a remarkably prolific writer. In addition to numerous technical writings, he published nine books on technology and society written for a general readership and was a regular contributor to the Kojin Club's monthly publication, Kojin, and other journals. This was highly unusual for engineers, especially for an engineer-bureaucrat. In fact, Miyamoto had once wished to become a writer. During his junior high years, he became attracted to literature, compiled three collections of original works, and seriously considered becoming a literary writer. This was the time in late Meiji Japan when elite youths began to ponder the meaning of life beyond material success-as portrayed well in Natsume Soseki's Kokoro (1914)-and naturalist literature seized the mind of youths like Miyamoto. Only after his brother-in-law persuaded him not to pursue his interest in literature did Miyamoto decide to major in engineering at First Higher School; he came to agree with his brother-in-law that literary life was a decadent, self-indulgent life of "the weak" and "the crippled." Miyamoto, instead, resolved to lead "a manly, splendid life" that was devoted to the improvement of society. He found this "manly, splendid life" in becoming an engineer in the central government. The "weak," in Miyamoto's mind, not only meant self-indulgent literary writers but also included the poor and the powerless. He was rather sympathetic to the latter but from an elitist perspective. Miyamoto was already greatly interested in labor issues in junior high school and read leftist newspapers such as Heimin shinbun and Yorozu choho to learn about the poor working conditions of destitute workers. He stated in his diary in 1915 that "I have sworn to fight for the human race and help the weak.... Oh, how miserable the fate of the weak is. I wish to never forget my responsibilities, to always believe in myself, and to work relentlessly toward my true vocation." 9 Miyamoto was convinced that engineers had a special obligation to solve labor issues because they could mitigate conflicts between laborers and factory owners through technology. He was never interested in joining the labor struggle; he wanted to manage conflicts rather than engage in them. Even though sympathetic to the weak, he differentiated himself from them. As is also clear from his thoughts on literary writers, Miyamoto's elitism led him to look down on the weak and to see himself as their "manly" savior. Historian Oyodo Shoichi rightly describes him as someone who strove to serve society through the ideal of management (keiseika). One large hurdle in the way of Miyamoto's ideal of a "manly, splendid" life was the low status of engineers in government offices and in society at large. Considered to be mere technical experts, engineers in public and private offices rarely attained positions powerful enough to direct the nation, companies, and factories. As in the West, where many professional engineers began to demand more power in politics and society in the 1910s, World War I raised the consciousness of elite Japanese engineers and their level of frustration with the status quo. For technology-bureaucrats, this had a concrete meaning. Civil servant engineers were subject to the Civil Servant Appointment Law and the Civil Servant Examination Rule, which together prevented them from attaining high-ranking positions. These positions were reserved for law-bureaucrats, those who studied in the department of law. The Civil Servant Appointment Law stipulated that only those who passed the higher civil servant examinations could be appointed to top positions such as vice-ministers, chiefs of bureaus, and section chiefs. Engineer-bureaucrats were exempted from the examination because it was written specifically for students majoring in law, covering no technical and scientific fields. They were instead hired as bureaucrats through separate appointment. The overwhelming majority of those who passed the examination before 1945 were Tokyo Imperial University law students, with a very small minority of economics majors. Among thousands of students who passed, only a handful were engineering majors ambitious enough to prepare for and pass the exam. This systematically excluded engineer-bureaucrats from the conventional career paths in government offices. For example, a successful career course for a law-bureaucrat would entail graduating from Tokyo Imperial University, passing the civil servant examination, moving around various sections and bureaus to be trained to be a generalist while climbing the bureaucratic ladder, and ultimately becoming a bureau chief or vice-minister. In contrast, technology-bureaucrats stayed in one section or bureau for their entire careers as specialists, and it took longer for them to be promoted. For engineers and other technical experts, the highest attainable position was "vice-minister for technological affairs" (gikan) in a ministry, but even this position was placed under the vice-minister of a ministry, the position held by law-bureaucrats. This system also created a wide gap in salaries between law-bureaucrats and technology-bureaucrats, as much as a difference of ten times at the point of retirement. Some technology-bureaucrats became bureau chiefs and section chiefs, but these were rare cases of individuals who skillfully used their political connections. Believing that technocrats as a whole deserved to be treated better, technocrats in various ministries began to voice their frustration during World War I. In 1918, leading engineers in industry, the universities, and the central government established Koseikai, the first political association of engineers, to pressure the government to amend the Civil Servant Appointment Law. In the same year, Furuichi Koi (1854-1934), a civil engineer and president of Kogakkai (Japan's first academic association of civil engineers), together with twenty other established civil engineers, submitted a recommendation to the government, requesting the revision of the Civil Servant Appointment Law. The following year, Noseikai (the association for those with agriculture degrees) and Rinseikai (the association for those with forestry degrees) were established based on Koseikai's model. Together, the three associations submitted a petition to the prime minister to amend the law. No meaningful response reached them, however. The government's reaction was disheartening to Japan's engineers: though the Civil Servant Appointment Law did go through minor changes, the discriminatory provision against engineers remained. When a group of young technocrats in the Ministry of Agriculture and Commerce proposed the promotion of Matsunami Yoshimi, a renowned forestry expert, to the office of bureau chief, the minister rejected the promotion because appointing a technocrat as head of a bureau would "destroy the bureaucratic order." It was becoming painfully clear that engineers needed to do something more than occasionally send petitions. Engineers as a whole needed to organize and stand up. Naoki Rintaro, a civil engineer in the Tokyo municipal government, began writing essays in various journals advocating a new type of engineer who was more socially and politically active. His 1918 book, From an Engineering Life, is full of inspirational and motivational calls to engineers to raise their consciousness and to work toward the advancement of their social standing as well as that of the nation. Ichinohe Naozo, a former instructor of astronomy at Tokyo Imperial University, succinctly summarized the frustration that Naoki and other engineers endured. In the periodical he edited, Contemporary Science, Ichinohe urged engineers to stand up and organize themselves: "Why can't engineers try to unite themselves? Even though there are probably differences among engineers of the public sector and those in the private sector ... they are all engineers who contribute to the world of engineering. I believe they should form some kind of organization for the advancement of their social position." Organizing the Kojin Club was Miyamoto's response to such a call. In October 1920, Miyamoto and eight other engineers gathered in an office in Tokyo and discussed plans to launch Japan's first engineers' trade union, the Kojin Club. They were all young-in their thirties-and elite engineers with Tokyo Imperial University degrees who were currently or formerly bureaucrats in the central government. Its official establishment with over two hundred members was announced in December 1921. The club made its main objectives the advancement of the status of engineers and the reform of society. Miyamoto wrote the inaugural manifesto, which clearly laid out his technocracy. The inaugural manifesto was ambitious and radical. Since this manifesto is crucial to understanding the organization's aspirations, its politics, and the direction it would later take, I quote the text at length below. Divided into five articles, the manifesto reads as follows: (1) Technology is a cultural creation that unites the natural sciences and technique: Technology is creation and an end, not a means; it is absolute, not relative. Culture is not created by technology alone, but human culture in a way has always been [a form of ] technological culture.... (2) Engineers are creators: Engineers are not materialists; they should go beyond materialism. It is the responsibility of engineers to actively engage in political economy through the mission of cultural creation. Our activities should not only concern one aspect of society but should embrace the whole of human life. (3) The position of the engineer is just like the pivot of a pole: We acknowledge that the capitalistic trade union is not a healthy social institution. Capitalists and workers should not be in a master-slave relationship. Capitalists and workers, who share rights and responsibilities, are equal tools in the creation of technological culture. It is the responsibility of engineers to lead capitalists and workers. (4) The Kojin Club is the source of the creation of technological culture: Its function and organization should include the whole society. We will establish an academic section to develop technology, a trade union section to train section, and a finance section. (Continues...) https://www.amazon.co.jp/Science-Empire-Scientific-Nationalism-Modern/dp/0804776563 |
第1章 テクノクラシーへの道 国際的に見ると、1910年代にエリート技術者たちが、より高い地位と政治権力へのアクセスを要求し始めた。日本でも、重厚長大産業の急速な発展と研究開 発の強力な推進に応える形で、テクノクラート(技術官僚)たちが自らを組織し、そのような要求を始めた。このテクノクラート運動では、中央政府の土木技術 者たちが特に活発だった。彼らは国民の土地開発を担当していたが、差別的な「文官任用令(ぶんかんにんようれい)」により政策決定権へのアクセスは限られ ていた。技術官僚と法律官僚の間の激しい摩擦は、科学技術政策を「科学技術」という技術官僚の定義に基づいて形成する、日本のテクノクラシー運動の中核で あった。このテクノクラート運動の中心人物は、内務省土木局の技師であった宮本武之輔(1892 -1941)であった。 本章では、宮本と、1920年に彼が設立した技術者団体「個人倶楽部」を通して、テクノクラート運動の初期段階(1920年~1932年)を考察する。個 人倶楽部の目的は、技術者たちの結束を図り、政治権力を要求することであった。個人主義クラブの軌跡は、科学と合理性の信念が階級形成とナショナリズムと 密接に関連していたことを示している。大規模な技術ネットワークが日本の産業と社会経済の構造を変えていく中、個人主義クラブのエンジニアたちは、エンジ ニアたちの団結を図るためにプロレタリア運動からヒントを得て、独自の階級意識を構築しようとした。しかし、彼らはすぐにプロレタリア運動の言語や政治を 放棄した。なぜなら、エンジニアとしての背景を統一された階級的アイデンティティに変換することができなかったからだ。むしろ、彼らは「科学的」専門知識 こそが、階級に関係なく自分たちのアイデンティティを確立するものであると気づいた。階級闘争よりも国民、あるいは産業合理化よりも階級闘争が、自分たち の文化的資本を政治的権力に変えるために必要な言語とイデオロギーを提供した。技術者のアイデンティティを模索する試行錯誤の末、彼らはテクノクラシーを 発展させた。 「テクノクラシー」(tekunokurashii)という用語は、1930年代初頭に米国で流行語となってから日本に導入されたが、2、個人主義倶楽部 の歴史は、日本の技術者たちがそれよりずっと以前から独自のテクノクラシーを開発し始めていたことを示している。「テクノクラシー」はさまざまな方法で定 義されてきたが、一般的に専門家による統治、技術決定論、そして技術的考察が政治を時代遅れにするという信念を伴う。私は、このテクノクラシーの一般的な 定義に、少なくとも最近の世界的な地域経済圏(EUなど)への傾向が国民国家をテクノクラシーによる統治にとって意味のないものにするまでは、ナショナリ ズムが重要な要素であることが多いという点を付け加えたい。私は「テクノクラート」という言葉と「技術官僚」(工学、農業、林学、その他の技術的・専門的 分野の学位を持つ中央政府の官僚)という言葉とを同義語として使い、また「テクノクラシー」という言葉は、これらの技術官僚たちが科学の定義に基づいて作 り出した特定の統治ビジョンを指すものとして使っている。このように、宮本や技術者仲間たちが政治権力を握ろうとした動きは、正当なものであり、また彼ら の国民に対する懸念から触発されたものでもあった。 また、宮本や考現学派のメンバーは、テクノクラシーが日本であれ、米国であれ、あるいはヨーロッパであれ、マルクス主義の代替案として提案されたものであ り、20世紀初頭の経済および労働危機に対するより良い解決策として、マルクス主義と競合していたことを私たちに思い出させる。科学に対する信頼は、マル クス主義者によって異なる定義がなされていたものの、社会をより良く管理するという彼らの主張において中心的な役割を果たしていた。テクノクラシーはマル クス主義と同様に、既存の資本主義による社会運営を批判したが、マルクス主義が社会の歴史を「科学的」に観察することでプロレタリアートによる社会統治を 主張したのに対し、テクノクラシーは「科学的」な専門知識を持つ技術者による国民の管理を主張した。本書の第1部と第2部では、テクノクラシーとマルクス 主義の対立は、理想社会のビジョンをめぐる競争から生じたものではなく、「科学的」の定義をめぐる競争から生じたものであることを明らかにする。 エンジニアを創造者と定義する 個人主義倶楽部の創設者であり指導者であった宮本武蔵は、野心的で才能に恵まれ、指導力も備えた人物であった。宮本は1892年に愛媛県の五色島で、かつ ては裕福な商家の家に生まれた。家運の傾きにより、彼は14歳の時に中学校を中退し、船乗りとして職を得なければならなかった。しかし、義兄と裕福な知人 の援助により、後に東京の私立中学校に入学することができた。賢く勤勉な学生であった宮本は常にクラスのトップにいた。実際、成績が優秀だったため、戦前 の日本で最も名門とされていた第一高等学校(daiichi koto gakko)に受験することなく入学を許可された。さすが第一高等学校の卒業生、東京帝国大学に進み、1917年に工学部で「銀時計」学生として卒業した (戦前の日本では、帝国大学で成績トップの学生に天皇から銀時計が授与された)。同年、内務省土木局に入局。国民の2大河川改修事業である利根川事業と荒 川事業に携わり、土木工学の最先端分野である鉄筋コンクリート構造の若きリーダーとしての実力を発揮した。 1923年から1925年にかけての欧米への官費留学を経て、官僚として着実に昇進し、最終的には官僚として最高の地位である事務次官にまで上り詰めた。 宮本はまた、非常に多作な作家でもあった。数多くの専門的な著作に加え、一般読者向けに技術と社会に関する9冊の著書を出版し、個人クラブの月刊誌『個 人』やその他の雑誌にも定期的に寄稿していた。これは技術者、特に技術官僚としては極めて異例のことである。実は宮本はかつて作家志望だった時期がある。 中学時代に文学に目覚め、3冊の創作集をまとめ、文筆家になることを真剣に考えた。これは、明治後期の日本において、エリート青年たちが物質的成功を超え た人生の意味について考え始めた時期であり、夏目漱石の『こころ』(1914年)に描かれているように、自然主義文学が宮本のような若者の心をつかんだ時 期でもあった。義兄に説得されて文学への興味を諦めた後、宮本は第一高等学校で工学を専攻することを決意した。彼は義兄の意見に同意するようになり、文学 的な生活は退廃的で、自己中心的な「弱者」や「障害者」の生き方であると考えた。その代わり、社会の改善に専念する「男らしい素晴らしい人生」を送ること を決意した。宮本は、中央政府のエンジニアになることで、この「男らしい素晴らしい人生」を手に入れようとした。 宮本にとって「弱者」とは、自己中心的な文学者だけでなく、貧困層や社会的弱者をも意味していた。 彼は後者に対してはむしろ共感していたが、エリート主義的な観点からであった。 宮本はすでに中学時代から労働問題に強い関心を抱いており、左派系の新聞である平民新聞や萬朝報を読み、貧困労働者の劣悪な労働環境について学んでいた。 1915年の日記には、「私は人類のために戦い、弱き者を助けることを誓った。ああ、弱き者の運命はなんと哀れなことか。私は自分の責任を決して忘れるこ となく、常に自分を信じ、真の天職に向かってひたすら努力したい」と書いている。9 宮本は、技術者は技術によって労働者と工場主の間の対立を緩和できるため、労働問題の解決に特別な義務があると確信していた。彼は労働争議に加わることに 全く興味がなく、争議に加わるよりもむしろ争議を管理することを望んでいた。 弱者に同情的な一方で、彼は自らを弱者とは区別していた。 文学者に対する考え方からも明らかなように、宮本はエリート主義者であり、弱者を軽蔑し、自らを彼らの「男らしい」救世主とみなしていた。 歴史家の大淀昭一は、宮本を「経営(経世済民)の理想を通じて社会に貢献しようとした人物」と正しく表現している。 宮本が理想とした「男らしく、立派な」人生の大きな障害のひとつは、官庁や社会全体における技術者の地位の低さであった。単なる技術専門家とみなされてい たため、官庁や民間企業の技術者が、国民や企業、工場を指導するほどの影響力を持つ地位に就くことはほとんどなかった。1910年代に多くの専門技術者が 政治や社会でより大きな権力を求めるようになった欧米と同様に、第一次世界大戦は日本のエリート技術者の意識と現状への不満を高めた。技術官僚にとって、 これは具体的な意味を持っていた。公務員の技術者は、公務員任用法と公務員試験規則の対象となり、それらによって高位の役職に就くことが妨げられていた。 これらの役職は、法律学科で学んだ法律官僚に独占されていた。公務員任用法では、高等試験に合格した者だけが、次官、局長、課長などの高級官僚に任命され ると規定されていた。技術官僚は試験の対象外であった。なぜなら、試験は法律専攻の学生を対象に書かれており、技術や科学の分野は対象外であったからだ。 代わりに、彼らは別の採用方法で官僚として採用された。1945年以前に試験に合格した者の大半は東京帝国大学の法律専攻の学生であり、経済学専攻の学生 はごく少数であった。合格した何千人もの学生のうち、試験に合格するほど意欲的で、技術専攻であった者はほんの一握りであった。これにより、技術官僚が従 来のキャリアパスから排除されることになった。 例えば、法律官僚の出世コースは、東京帝国大学を卒業し、公務員試験に合格した後、さまざまな部署や局を転々としてジェネラリストとしての訓練を受けなが ら官僚としての階段を上り、最終的には課長や次官になるというものだ。これに対し、技術官僚は生涯、ひとつの課や部局に留まり、専門家としてキャリアを積 むことになり、昇進にはより長い時間がかかった。技術官僚やその他の技術専門家にとって、最高到達可能な役職は、省庁における「技術担当事務次官」(技 監)であったが、この役職でさえ、法律官僚が務める事務次官の下に置かれていた。この制度は、法務官僚と技術官僚の給与に大きな格差を生み出し、退職時に は10倍もの差がつくこともあった。技術官僚の中には局長や課長になる者もいたが、それは政治的なコネをうまく利用したごく一部の例外であった。 技術官僚全体がもっと待遇されるべきだと考えた各省庁の技術官僚たちは、第一次世界大戦中に不満を口にし始めた。1918年には、産業界、大学、中央政府 の主要な技術者が、技術者による初の政治団体である「厚生会」を設立し、政府に公務員任用法の改正を迫った。同じ年、古市公(1854-1934)は、土 木技術者であり、日本初の土木技術者の学術団体である工学会の会長でもあったが、他の20名の著名な土木技術者とともに、政府に勅任官任用法の改正を求め る建白書を提出した。翌年には、高成会のモデルを基に農学士会(農学士会)と林学士会(林学士会)が設立され、3つの団体が連名で内閣総理大臣に勅令改正 の嘆願書を提出した。しかし、彼らに届いたのは無意味な回答だった。技術者たちにとって、政府の反応は落胆すべきものだった。公務員任用法は若干の改正が 行われたものの、技術者に対する差別的な規定はそのまま残された。農商務省の若き技術官僚グループが、著名な林業専門家である松波義三を局長に昇進させる よう提案した際、大臣は「技術官僚を局長に任命することは官僚秩序を破壊する」として昇進を却下した。 技術者たちは、折に触れて嘆願書を提出する以上のことをする必要があることは、痛いほど明らかになっていた。技術者全体が組織化し、立ち上がる必要があっ た。東京市役所の土木技師であった倫太郎は、社会や政治により積極的に関わる新しいタイプの技術者を提唱する論文をさまざまな雑誌に書き始めた。1918 年に出版された著書『工学人生』には、技術者たちが自覚を高め、国民の地位向上のために働くよう鼓舞する内容が満載である。 一方、東京帝国大学で天文学の講師を務めていた経験を持つ一戸直蔵は、直樹をはじめとする技術者たちが抱えていたフラストレーションを簡潔に要約してい る。 一戸は自身が編集する雑誌『現代科学』の中で、技術者たちが団結し、自らを組織化するよう促している。「技術者たちが団結しようとしないのはなぜだろう か。官と民の技術者たちに多少の相違があるにしても、彼らはみな技術の世界に貢献している技術者である。彼らの社会的地位向上のため、何らかの組織を作る べきではないだろうか」 個人主義倶楽部の結成は、そうした声に応える宮本たちの行動だった。1920年10月、宮本ら9人の技術者が東京の事務所に集まり、日本初の技術者組合で ある個人主義倶楽部の結成計画について話し合った。彼らは30代の若者で、東京帝国大学出身のエリート技術者であり、中央政府の官僚として現在または過去 に勤務していた。1921年12月には、200人以上の会員を擁する正式な団体として発足した。このクラブは、技術者の地位向上と社会改革を主な目的とし ていた。宮本は、テクノクラシーの明確な青写真を描いた設立宣言を起草した。 設立宣言は野心的かつ急進的であった。この宣言は、この団体の理想、政治、そしてその後の方向性を理解する上で極めて重要であるため、以下に全文を引用す る。5つの条項に分かれたマニフェストは以下の通りである。 (1) テクノロジーとは、自然科学と技術を統合する文化的創造である。テクノロジーは創造であり目的であり、手段ではない。テクノロジーは絶対的なものであり、 相対的なものではない。文化はテクノロジーのみによって創造されるものではないが、人間の文化はある意味で常にテクノロジー文化の一形態であった。 (2) 技術者は創造者である:技術者は唯物論者ではなく、唯物論を超えるべきである。文化創造という使命を通じて政治経済に積極的に関与することは、技術者の責 任である。我々の活動は社会の一側面のみに関わるのではなく、人間の生活全体を包含すべきである。 (3) 技術者の立場は、ちょうど棒の軸のようなものである。我々は、資本主義的な労働組合が健全な社会制度ではないことを認めている。資本家と労働者は、主従関 係にあるべきではない。権利と責任を共有する資本家と労働者は、技術的文化の創造における対等な道具である。資本家と労働者を導くことは、技術者の責任で ある。 (4) 個人クラブは技術的文化創造の源である。その機能と組織は社会全体を包含すべきである。私たちは技術開発のための学術部門、訓練部門としての労働組合部 門、そして財務部門を設立する。 (以下略) https://sekai.nichibun.ac.jp/researcher/edit/20542 |
| Natalie Koch, Scientific nationalism and museums of the future in Germany and the UAE. Political Geography. Volume 113, August 2024, 103144 Nationalist visions of the future are articulated through the language and logic of science. This article extends political geography research on the future by examining “scientific nationalism” expressed at two museums of the future in Germany and the UAE: Berlin's Futurium and Dubai's Museum of the Future. The techno-science ideals narrated in the museums are projected as planetary stories about building common futures through science, technological innovation, and concern for the environment, but fundamentally reinforce nationalist ideals and aspirations about their nations' success and prosperity in the future. In Germany and the United Arab Emirates (UAE), nationalist discourses celebrate science and technology – and technoscientific prowess is framed in the two museums of the future as holding the key to solving planetary challenges like the climate crisis. But in “technowashing” social, political, and environmental challenges, they reflect a conservative approach to centering technology-centered questions about the future, while working to persevere the energy-intensive, capitalist political economy that defines their present. By projecting these extractive and nationalist presents into the future, the two future-themed museums illustrate how the future animates nationalist visions not just through stories of survivance, but also through stories of science. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629824000933 |
ナタリー・コッホ、科学的ナショナリズムとドイツおよびアラブ首長国連邦における未来の博物館。政治地理学。第113巻、2024年8月、103144 ナショナリストの未来像は、科学の言語と論理によって明確に表現される。本稿では、ドイツとアラブ首長国連邦(UAE)の2つの未来博物館、ベルリンの フューチュリウムとドバイの未来博物館で表現された「科学的ナショナリズム」を検証することで、未来に関する政治地理学的研究をさらに深める。これらの博 物館で語られるテクノロジーと科学の理想は、科学、技術革新、環境への配慮を通じて共通の未来を築くという地球規模の物語として描かれているが、その本質 は、自国の将来における成功と繁栄に関するナショナリスト的な理想と願望を強化するものである。ドイツとアラブ首長国連邦(UAE)では、ナショナリスト 的な言説が科学と技術を称賛しており、テクノサイエンスの卓越性が、気候危機のような地球規模の課題を解決する鍵を握っているという構図が、この2つの未 来博物館で描かれている。しかし、「テクノウォッシング」による社会、政治、環境問題への取り組みは、未来に関する技術中心の問いに重点を置く保守的なア プローチを反映している。一方で、現在の姿を特徴づけるエネルギー集約型の資本主義的政治経済を維持しようともしている。こうした収奪的で国家主義的な現 状を未来に投影することで、未来をテーマとする2つの博物館は、未来が国家主義的なビジョンを生き残りの物語だけでなく、科学の物語によっても活性化させ る様子を示している。 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆