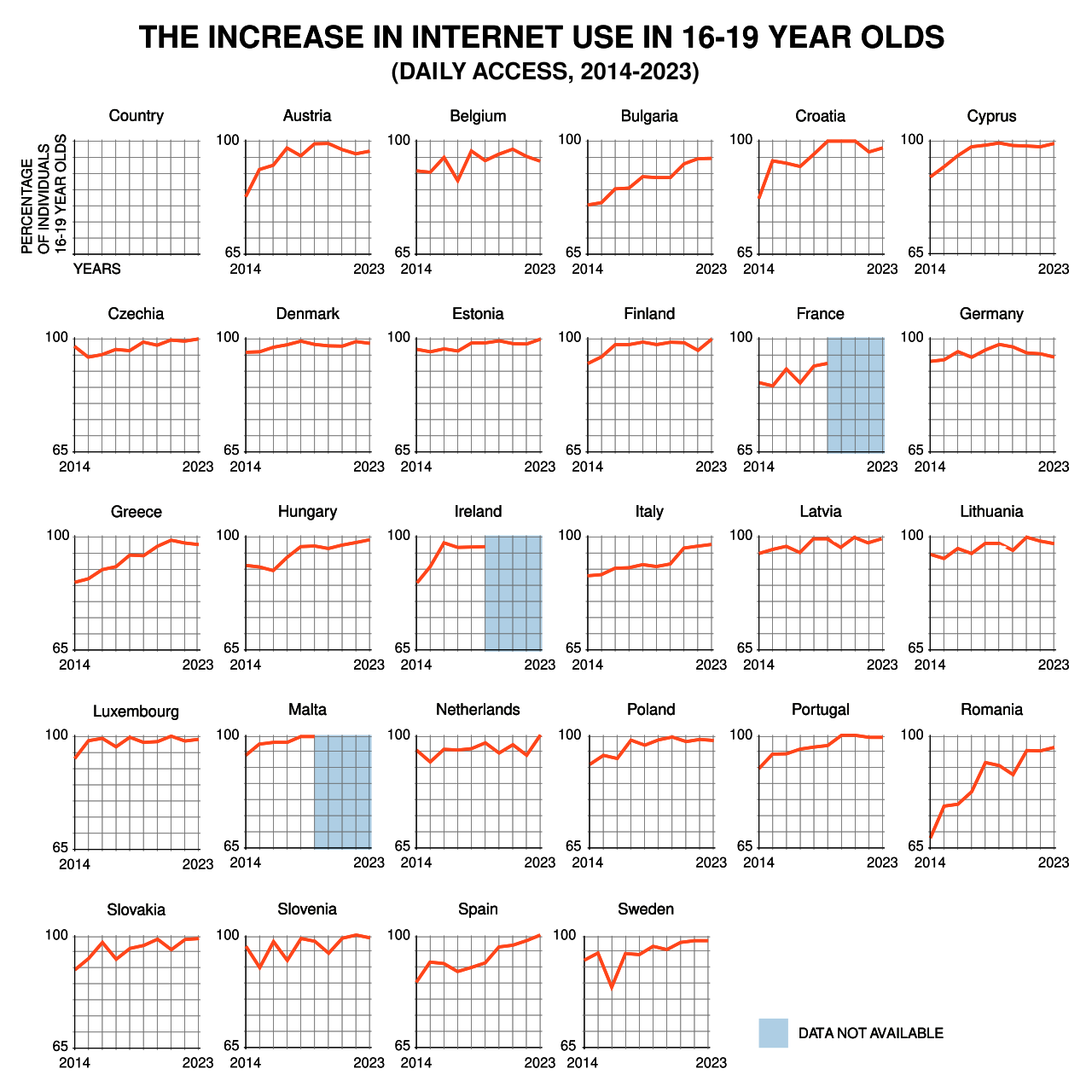
ソーシャル・メディア依存症
Social Media Addiction
The increase in Internet access in 16-19 year olds living in EU countries
☆
インターネット依存症(IAD)は、コンピューター使用やインターネットアクセスに関する過度または制御不能な執着、衝動、行動によって特徴づけられ、機
能障害や苦痛をもたらす。[295]
若年層は特にインターネット依存症を発症するリスクが高い[296]。事例研究では、オンライン時間を増やすにつれて学業成績が低下する学生が指摘されて
いる[297]。スクロールやチャット、ゲームに没頭して夜更かしする結果、睡眠不足による健康被害を経験する者もいる[298]。[299]
過剰なインターネット使用は、米国精神医学会のDSM-5や世界保健機関のICD-11では障害として認定されていない[300]。ただし、ゲーム障害は
ICD-11に記載されている[301]。この診断を巡る論争には、この障害が独立した臨床的実体なのか、それとも潜在的な精神障害の現れなのかという点
が含まれる。定義は標準化されておらず合意も得られていないため、エビデンスに基づく推奨事項の策定は複雑化している。
| Addiction Main article: Problematic social media use See also: Digital media use and mental health These paragraphs are an excerpt from Internet addiction disorder.[edit] Internet addiction disorder (IAD) is characterized by excessive or poorly controlled preoccupations, urges, or behaviors regarding computer use and Internet access that lead to impairment or distress.[295] Young people are at particular risk of developing internet addiction disorder,[296] with case studies highlighting students whose academic performance declines as they spend more time online.[297] Some experience health consequences from loss of sleep[298] as they stay up to continue scrolling, chatting, and gaming.[299] Excessive Internet use is not recognized as a disorder by the American Psychiatric Association's DSM-5 or the World Health Organization's ICD-11.[300] However, gaming disorder appears in the ICD-11.[301] Controversy around the diagnosis includes whether the disorder is a separate clinical entity, or a manifestation of underlying psychiatric disorders. Definitions are not standardized or agreed upon, complicating the development of evidence-based recommendations. Many different theoretical models have been developed and employed for many years in order to better explain predisposing factors to this disorder. Models such as the cognitive-behavioral model of pathological Internet have been used to explain IAD for more than 20 years. Newer models, such as the Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution model, have been developed more recently and are starting to be applied in more clinical studies.[302] In 2011 the term "Facebook addiction disorder" (FAD) emerged.[303] FAD is characterized by compulsive use of Facebook. A 2017 study investigated a correlation between excessive use and narcissism, reporting "FAD was significantly positively related to the personality trait narcissism and to negative mental health variables (depression, anxiety, and stress symptoms)".[304][305] In 2020, the documentary The Social Dilemma, reported concerns of mental health experts and former employees of social media companies over social media's pursuit of addictive use. For example, when a user has not visited Facebook for some time, the platform varies its notifications, attempting to lure them back. It also raises concerns about the correlation between social media use and child and teen suicidality.[306] Additionally in 2020, studies have shown that there has been an increase in the prevalence of IAD since the COVID-19 pandemic.[307] Studies highlighting the possible relationship between COVID-19 and IAD have looked at how forced isolation and its associated stress may have led to higher usage levels of the Internet.[307] Turning off social media notifications may help reduce social media use.[308] For some users, changes in web browsing can be helpful in compensating for self-regulatory problems. For instance, a study involving 157 online learners on massive open online courses examined the impact of such an intervention. The study reported that providing support in self-regulation was associated with a reduction in time spent online, particularly on entertainment.[309] Research suggests that social media platforms trigger a cycle of compulsive behavior, which reinforces addictive patterns and makes it harder for individuals to break the cycle.[310] Various lawsuits have been brought regarding social media addiction, such as the Multi-District Litigation alleging harms caused by social media addiction on young users.[311] |
依存症 主な記事: 問題のあるソーシャルメディア利用 関連項目: デジタルメディア利用とメンタル健康 これらの段落はインターネット依存症からの抜粋である。[編集] インターネット依存症(IAD)は、コンピューター使用やインターネットアクセスに関する過度または制御不能な執着、衝動、行動によって特徴づけられ、機 能障害や苦痛をもたらす。[295] 若年層は特にインターネット依存症を発症するリスクが高い[296]。事例研究では、オンライン時間を増やすにつれて学業成績が低下する学生が指摘されて いる[297]。スクロールやチャット、ゲームに没頭して夜更かしする結果、睡眠不足による健康被害を経験する者もいる[298]。[299] 過剰なインターネット使用は、米国精神医学会のDSM-5や世界保健機関のICD-11では障害として認定されていない[300]。ただし、ゲーム障害は ICD-11に記載されている[301]。この診断を巡る論争には、この障害が独立した臨床的実体なのか、それとも潜在的な精神障害の現れなのかという点 が含まれる。定義は標準化されておらず合意も得られていないため、エビデンスに基づく推奨事項の策定は複雑化している。 この障害の素因をよりよく説明するため、長年にわたり異なる理論モデルが開発・採用されてきた。病的なインターネット使用の認知行動モデルなどは、20年 以上も前からIADの説明に用いられてきた。近年では、PACE(Person-Affect-Cognition-Execution)相互作用モデル などの新しいモデルが開発され、より多くの臨床研究で適用され始めている。[302] 2011年には「フェイスブック依存症(FAD)」という用語が登場した[303]。FADはフェイスブックの強迫的使用を特徴とする。2017年の研究 では過剰使用とナルシシズムの相関を調査し、「FADは人格特性としてのナルシシズムおよび精神的健康の負の変数(抑うつ、不安、ストレス症状)と有意な 正の関連を示した」と報告している[304]。[305] 2020年公開のドキュメンタリー『ソーシャル・ジレンマ』は、ソーシャルメディア企業が中毒性のある利用を追求することに対する、精神保健専門家や元従 業員の懸念を報じた。例えば、ユーザーが一定期間Facebookを利用していない場合、プラットフォームは通知内容を変化させ、ユーザーを呼び戻そうと する。また、ソーシャルメディア利用と児童・青少年の自殺傾向との相関関係についても懸念が示されている。[306] さらに2020年には、COVID-19パンデミック以降、IAD(インターネット依存症)の有病率が上昇していることが研究で示された。[307] COVID-19とIADの関連性を指摘する研究では、強制的な隔離とそれに伴うストレスがインターネット利用量の増加につながった可能性を検証してい る。[307] ソーシャルメディアの通知をオフにすることは、利用削減に役立つ可能性がある。[308] 一部のユーザーにとって、ウェブ閲覧方法の変更は自己規制の問題を補うのに有効だ。例えば、大規模公開オンライン講座(MOOC)の受講者157名を対象 とした研究では、このような介入の影響を検証した。その結果、自己規制の支援を提供することで、特に娯楽目的のオンライン利用時間が減少することが報告さ れている。[309] 研究によれば、ソーシャルメディアプラットフォームは強迫的行動のサイクルを引き起こし、依存パターンを強化するため、個人がそのサイクルを断ち切るのが 困難になる。[310] ソーシャルメディア依存症に関する様々な訴訟が提起されている。例えば、若年ユーザーへのソーシャルメディア依存症による被害を主張する多地区訴訟 (MDL)などである。[311] |
| Debate over use by young people See also: Social media in education Whether to restrict the use of phones and social media among young people has been debated since smartphones became ubiquitous.[312] A study of Americans aged 12–15, reported that teenagers who used social media over three hours/day doubled their risk of negative mental health outcomes, including depression and anxiety.[313] Platforms have not tuned their algorithms to prevent young people from viewing inappropriate content. A 2023 study of Australian youth reported that 57% had seen disturbingly violent content, while nearly half had regular exposure to sexual images.[314] Further, youth are prone to misuse social media for cyberbullying.[315] As result, phones have been banned from some schools, and some schools in the US have blocked social media websites.[316] Intense discussions are taking place regarding the imposition of certain restrictions on children's access to social media. It is argued that using social media at a young age brings with it many problems. For example, according to a survey conducted by Ofcom, the media regulator in the UK, 22% of children aged 8-17 lie about being over 18 on social media. According to a system implemented in Norway, more than half of nine-year-olds and the vast majority of 12-year-olds spend time on social media. A series of measures have begun to be taken across Europe to prevent the risks caused by such problems. The countries that have taken concrete steps in this regard are Norway and France. Since June 2023, France has started requiring social media platforms to verify the ages of their users and to obtain parental consent for those under the age of 15. In Norway, there is a minimum age requirement of 13 to access social media. The Online Safety Law in the UK has given social media platforms until mid-2025 to strengthen their age verification systems.[317] |
若者の利用をめぐる議論 関連項目:教育におけるソーシャルメディア 若者のスマートフォンやソーシャルメディア利用を制限すべきか否かは、スマートフォンの普及以来議論されてきた。[312] 12~15歳のアメリカ人を対象とした研究では、1日3時間以上ソーシャルメディアを利用する十代の若者は、うつ病や不安症を含む精神健康上の悪影響を受 けるリスクが2倍になることが報告されている。[313] プラットフォームは若年層が不適切なコンテンツを閲覧するのを防ぐようアルゴリズムを調整していない。2023年のオーストラリアの若年層調査では、 57%が衝撃的な暴力コンテンツを目撃し、ほぼ半数が性的画像に定期的に接触していると報告された[314]。さらに若年層はソーシャルメディアをネット いじめに悪用しやすい傾向がある[315]。 その結果、一部の学校では携帯電話が禁止され、米国ではソーシャルメディアサイトをブロックする学校も存在する。[316] 子どものソーシャルメディア利用に一定の制限を設けるべきか否かについて、激しい議論が交わされている。幼い年齢でのソーシャルメディア利用は多くの問題 を引き起こすと主張される。例えば、英国のメディア規制機関Ofcomが実施した調査によれば、8~17歳の子供の22%がソーシャルメディア上で18歳 以上と虚偽の申告をしている。ノルウェーで導入された制度によれば、9歳児の半数以上と12歳児の大多数がソーシャルメディアを利用している。こうした問 題によるリスクを防ぐため、欧州各国で一連の対策が始まっている。具体的な措置を講じた国はノルウェーとフランスだ。フランスでは2023年6月から、 ソーシャルメディアプラットフォームに対し、ユーザーの年齢確認と15歳未満の親権者同意の取得を義務付け始めた。ノルウェーではソーシャルメディア利用 の最低年齢を13歳と定めている。英国のオンライン安全法は、ソーシャルメディアプラットフォームに対し、2025年半ばまでに年齢確認システムを強化す るよう求めている。[317] |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media |
|
| Problematic social media use |
問題のあるソーシャル・メディア利用 |
| Excessive
use of social media can lead to problems including impaired functioning
and a reduction in overall wellbeing, for both users and those around
them. Such usage is associated with a risk of mental health problems,
sleep problems, academic struggles, and daytime fatigue.[5] Psychological or behavioural dependence on social media platforms can result in significant negative functions in peoples daily lives.[6] Women are at a great risk for experiencing problems related to social media use.[citation needed] The risk of problems is also related to the type of platform of social media or online community being used. People of different ages and genders may be affected in different ways by problematic social media use.[citation needed] |
ソーシャルメディアの過剰使用は、利用者本人と周囲の人々双方に、機能障害や全体的な幸福感の低下といった問題を引き起こす可能性がある。このような使用は、精神健康上の問題、睡眠障害、学業不振、日中の疲労感といったリスクと関連している。[5] ソーシャルメディアプラットフォームへの心理的・行動的依存は、人民の日々の生活に重大な悪影響をもたらす可能性がある。[6] 女性はソーシャルメディア利用に関連する問題を抱えるリスクが特に高い。[出典が必要] 問題発生のリスクは、利用するソーシャルメディアプラットフォームやオンラインコミュニティの種類にも関連している。年齢や性別が異なる人民は、問題のあ るソーシャルメディア利用によって異なる影響を受ける可能性がある。[出典が必要] |
| Signs and symptoms Signs of social media addiction or excessive use of social media include many behaviours similar to substance use disorders, including mood modification, salience, tolerance, stress withdrawal symptoms, psychological distress, anxiety and depression, conflict, and relapse, and low self esteem.[7][8][9][10][11] People with problematic social media habits are at risk of being addicted and may require more time on social media as time passes.[12] Frequent social media use may also be associated self-reported symptoms of attention deficit hyperactivity disorder.[13] Social anxiety (or fear of missing out) is another potential symptom. Social anxiety is defined as having intense anxiety or fear of being judged, negatively evaluated, or rejected in a social or performance situation.[14][15][16] The fear of missing out can contribute to excessive usage due to frequent checking the media constantly throughout the day to check in and see what others are doing instead of doing other activities.[citation needed] Displacement, or replacing meaningful other activities with social media,[17] and loneliness[18][19] are common signs. |
兆候と症状 ソーシャルメディア依存症や過度な使用の兆候には、物質使用障害と類似した多くの行動が含まれる。具体的には、気分の変化、重要性の増大、耐性の形成、ス トレスによる離脱症状、心理的苦痛、不安や抑うつ、対人関係の衝突、再発、そして低い自尊心などである。[7][8][9][10][11] 問題のあるソーシャルメディア習慣を持つ人民は依存症のリスクがあり、時間の経過とともにソーシャルメディアに費やす時間を増やす必要があるかもしれな い。[12] ソーシャルメディアの頻繁な利用は、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の自己申告症状とも関連している可能性がある。[13] 社会的不安(あるいはFOMO:見逃すことへの恐怖)もまた潜在的な症状である。社会的不安とは、社会的状況やパフォーマンス状況において、判断された り、否定的に評価されたり、拒絶されたりする強い不安や恐怖を抱くことを指す。[14][15][16] FOMOは、他の活動を行う代わりに一日中頻繁にメディアをチェックし、他人の行動を確認する過剰使用の一因となり得る。[出典が必要] 置換、つまり意味のある他の活動をソーシャルメディアで置き換えること[17]や孤独感[18][19]は、よくある兆候だ。 |
| Causes and mechanisms There are many theories for the mechanism or cause behind a person having problematic social media use.[20] The transition from normal to problematic social media use occurs when a person relies on it to relieve stress, loneliness, depression, or provide continuous rewards.[21] 1. Cognitive-behavioral model – People increase their use of social media when they are in unfamiliar environments or awkward situations; 2. Social skill model – People pull out their phones and use social media when they prefer virtual communication as opposed to face-to-face interactions because they lack self-presentation skills; 3. Socio-cognitive model – This person uses social media because they love the feeling of people liking and commenting on their photos and tagging them in pictures. They are attracted to the positive outcomes they receive on social media. There are parallels to the gambling industry inherent to the design of various social media sites, with "'ludic loops' or repeated cycles of uncertainty, anticipation and feedback" potentially contributing to problematic social media use.[22] Another factor directly facilitating the development of addiction to social media is the implicit attitude toward the IT artifact.[23] Social media use may also stimulate the reward pathway in the brain.[24] There is also a theory that social media addiction fulfills a basic evolutionary drives in the wake of mass urbanization worldwide. The basic psychological needs of "secure, predictable community life that evolved over millions of years" remain unchanged, leading some to find online communities to cope with the new individualized way of life in some modern societies.[25] The “Evolutionary Mismatch” hypothesis holds that modern digital platforms amplify social competition and comparison in ways our ancestors never faced, possibly triggering maladaptive patterns such as anxiety, depression, or compulsive use. Similarly, some scholars compare social media to “junk food”:[26][27] The approach taken to develop social media platforms may contribute to problematic social media use.[28] The ability to scroll and stream content endlessly and how app developers distort time by affecting the 'flow' of content when scrolling,[29] potentially resulting in the Zeigarnik effect (the human brain will continue to pursue an unfinished task until a satisfying closure.[28][30] Autoplay modes,[28] the personalized nature of the content results in emotional attachment (ie, the user values this above its actual value, which is referred to as the endowment effect[31][32][33]), and the exposure effect (repeated exposure to a distinct stimulus by the user can condition the user into an enhanced or improved attitude toward it).[34][28] The interactive nature of the platforms, including the ability to "like" content has also been linked. Even though social media can satisfy personal communication needs, those who use it at higher rates are shown to have higher levels of psychological distress.[35] |
原因とメカニズム 問題のあるソーシャルメディア利用のメカニズムや原因については多くの理論がある。[20] 通常の利用から問題のある利用への移行は、ストレスや孤独感、抑うつを和らげたり、継続的な報酬を得るために依存した時に起こる。[21] 1. 認知行動モデル – 人民は見知らぬ環境や気まずい状況にいる時、ソーシャルメディアの利用を増やす。 2. 社会的スキルモデル – 自己表現スキルが不足しているため、対面交流よりも仮想コミュニケーションを好む人民は、スマートフォンを取り出してソーシャルメディアを利用する。 3. 社会認知モデル – この人格は、自分の写真に「いいね」やコメントが付いたり、写真にタグ付けされたりする感覚を好むためソーシャルメディアを利用する。ソーシャルメディア上で得られる肯定的な結果に惹かれているのである。 各種ソーシャルメディアサイトの設計にはギャンブル産業との類似性が内在しており、「不確実性、期待、フィードバックの反復サイクル(ルーディック・ルー プ)」が問題のあるソーシャルメディア利用に寄与する可能性がある[22]。ソーシャルメディア依存症の発達を直接促進する別の要因は、IT製品に対する 暗黙の態度である[23]。ソーシャルメディア利用は脳内の報酬経路を刺激する可能性もある。[24] また、ソーシャルメディア依存症は、世界的な大規模都市化の流れの中で、基本的な進化的な欲求を満たすという理論もある。「何百万年もの間進化してきた、 安全で予測可能な共同体生活」という基本的な心理的ニーズは変わらず、現代社会における新たな個人主義的な生活様式に対処するため、オンラインコミュニ ティを求める人々も現れている。[25] 「進化的ミスマッチ」仮説によれば、現代のデジタルプラットフォームは、先祖が経験したことのない形で社会的競争や比較を増幅させ、不安や抑うつ、強迫的 使用といった不適応パターンを引き起こす可能性がある。同様に、一部の学者はソーシャルメディアを「ジャンクフード」に例える。[26] [27] ソーシャルメディアプラットフォームの開発手法自体が、問題のある利用を助長している可能性がある[28]。コンテンツを無限にスクロール・ストリーミン グできる機能や、アプリ開発者がスクロール時のコンテンツ「流れ」を操作して時間を歪める手法[29]は、ツァイガルニク効果(未完了の課題は満足のいく 完結を得るまで脳が追い続ける現象)を引き起こす恐れがある。[28][30] 自動再生モード[28]、コンテンツのパーソナライズ化による感情的愛着(ユーザーが実際の価値以上に評価する「所有効果」[31][32][33])、 露出効果(特定の刺激への反復接触が態度強化を促す現象)[34]などが挙げられる。[28] コンテンツへの「いいね」機能を含むプラットフォームの双方向性も関連性が指摘されている。 ソーシャルメディアは人格のコミュニケーション欲求を満たす一方で、利用頻度が高いユーザーほど心理的苦痛のレベルが高いことが示されている。[35] |
| Diagnosis While there is no official diagnostic term or measurement, problematic social media use is conceptualized as a non-substance-related disorder, resulting in preoccupation and compulsion to engage excessively in social media platforms despite negative consequences.[36] No diagnosis exists for problematic social media use in either the ICD-11 or DSM-5. Excessive use of an activity, like social media, does not directly equate with addiction.[25] There are other factors that could lead to someone's social media addiction including personality traits and pre-existing tendencies.[25] While the extent of social media use and addiction are positively correlated, it is erroneous to employ use (the degree to which one makes use of the site’s features, the effort exerted during use sessions, access frequency, etc.) as a proxy for addiction.[37] Indicators of a potential dependence on social media include:[38] 1. Mood swings: a person uses social media to regulate his or her mood, or as a means of escaping real world conflicts. 2. Relevance: social media starts to dominate a person's thoughts at the expense of other activities. 3. Salience: social media becomes the most important part of someone's life. 4. Tolerance: a person increases their time spent on social media to experience previously associated feelings they had while using social media. 5. Withdrawal: when a person can not access social media their sleeping or eating habits change or signs of depression or anxiety can become present. 6.Conflicts in real life: when social media is used excessively, it can affect real-life relationships with family and friends. 7. Relapse: the tendency for previously affected individuals to revert to previous patterns of excessive social media use. There have been several scales developed and validated that help to understand the issues regarding problematic social media use.[39][40][41][42] There is not one single scale that is being used by all researchers.[43] |
診断 公式な診断用語や測定基準は存在しないが、問題のあるソーシャルメディア利用は非物質関連障害として概念化されている。これは、悪影響があるにもかかわら ず、ソーシャルメディアプラットフォームに過度に没頭し、強迫的に関与する状態を指す。[36] ICD-11やDSM-5のいずれにも、問題のあるソーシャルメディア利用の診断は存在しない。ソーシャルメディアのような活動の過剰な利用は、直接的に 依存症と同義ではない。[25] ソーシャルメディア依存症に至る要因には、人格特性や既存の傾向性も含まれる。[25] 利用頻度と依存症の程度には正の相関があるが、利用状況(サイト機能の使用度合い、利用時の集中度、アクセス頻度など)を依存症の代用指標とすることは誤 りである。[37] ソーシャルメディア依存の可能性を示す指標には以下がある:[38] 1. 気分の変動:気分を調節するため、あるいは現実世界の葛藤から逃れる手段としてソーシャルメディアを利用する人格。 2. 重要性:他の活動を犠牲にして、ソーシャルメディアが思考の大部分を占めるようになる。 3. 顕著性:ソーシャルメディアが生活の中で最も重要な部分となる。 4. 耐性:人格が以前感じていた感覚を得るために、ソーシャルメディア使用時に使用時間を増やす傾向。 5. 離脱症状:人格がソーシャルメディアにアクセスできない場合、睡眠や食事習慣の変化、抑うつや不安の兆候が現れる。 6. 現実生活での葛藤:ソーシャルメディアの過剰使用が、家族や友人との現実の人間関係に影響を与える。 7. 再発:問題を抱えた個人が、以前の過剰なソーシャルメディア使用パターンに逆戻りする傾向。 問題のあるソーシャルメディア使用に関する課題を理解するのに役立つ、いくつかの尺度(尺度)が開発され、検証されている。[39][40][41][42] 全ての研究者が使用する単一の尺度(尺度)は存在しない。[43] |
| Treatment Screen time recommendations for children and families have been developed by the American Academy of Pediatrics.[44][45] Possible therapeutic interventions published include: Self-help interventions, including application-specific timers; Cognitive behavioural therapy;[46] and Organisational and schooling support.[47] Medications have not been shown to be effective in randomized, controlled trials for the related conditions of Internet addiction disorder or gaming disorder.[47] |
治療 小児科学会が子供と家族向けのスクリーンタイム推奨時間を策定している。[44][45] 公表されている治療的介入法には以下が含まれる: アプリケーション専用タイマーを含む自助的介入法; 認知行動療法;[46]および 組織的・教育的支援。[47] インターネット依存症やゲーム障害といった関連疾患に対して、薬物療法が有効であることは無作為化比較試験で示されていない。[47] |
| Prevention Prevention approaches include screen time monitoring apps and other tech-based approaches to improve efficiency and decrease screen time and tools to help with addiction to online platform products.[48][49][50][51][52] Parents' methods for monitoring, regulating, and understanding their children's social media use are referred to as parental mediation.[53] Parental mediation strategies include active, restrictive, and co-using methods. Active mediation involves direct parent-child conversations that are intended to educate children on social media norms and safety, as well as the variety and purposes of online content. Restrictive mediation entails the implementation of rules, expectations, and limitations regarding children's social media use and interactions. Co-use is when parents jointly use social media alongside their children, and is most effective when parents are actively participating (like asking questions, making inquisitive/supportive comments) versus being passive about it.[54] Active mediation is the most common strategy used by parents, though the key to success for any mediation strategy is consistency/reliability.[53] When parents reinforce rules inconsistently, have no mediation strategy, or use highly restrictive strategies for monitoring their children's social media use, there is an observable increase in children's aggressive behaviours.[55][56] When parents openly express that they are supportive of their child's autonomy and provide clear, consistent rules for media use, problematic usage and aggression decreases.[55][57] Knowing that consistent, autonomy-supportive mediation has more positive outcomes than inconsistent, controlling mediation, parents can consciously foster more direct, involved, and genuine dialogue with their children. This can help prevent or reduce problematic social media use in children and teenagers.[55][56] |
予防 予防策には、画面時間の監視アプリやその他の技術ベースのアプローチが含まれる。これらは効率を向上させ画面時間を減らすためのものであり、オンラインプラットフォーム製品への依存症を助けるツールでもある。[48][49][50][51] 親が子供のソーシャルメディア利用を監視・規制・理解する方法を「親による仲介」と呼ぶ。[53] 親による仲介戦略には、積極的、制限的、共同利用の方法がある。積極的仲介は、ソーシャルメディアの規範や安全性、オンラインコンテンツの多様性と目的に ついて子供を教育することを目的とした、直接的な親子対話を伴う。制限的仲介は、子供のソーシャルメディア利用や交流に関するルール、期待、制限の実施を 伴う。共同利用は、親が子供と一緒にソーシャルメディアを利用することを指し、親が受動的ではなく(質問をしたり、探求的・支援的なコメントをしたりする など)積極的に参加する場合に最も効果的である。[54] 積極的仲介は親が最もよく用いる戦略だが、どの仲介戦略でも成功の鍵は一貫性と信頼性にある。[53] 親がルールを不規則に強化したり、仲介戦略を持たなかったり、子どものソーシャルメディア利用を監視するために過度に制限的な戦略を用いたりすると、子ど もの攻撃的行動が明らかに増加する。[55][56] 親が子どもの自律性を支持すると公に表明し、メディア利用について明確で一貫したルールを提供すると、問題のある利用や攻撃性は減少する。[55] [57] 一貫した自律性支持型仲介が、一貫性のない統制型仲介よりも良好な結果をもたらすことを理解すれば、親は意識的に子どもとの直接的で関与した本物の対話を 育める。これは子どもや青少年の問題のあるソーシャルメディア利用を予防・軽減するのに役立つ。[55][56] |
| Outcomes Adolescents and teens Increased social media use and exposure to social media platforms can lead to negative results and bullying over time.[58] While social media's main intention is to share information and communicate with friends and family, there is more evidence pertaining to negative factors rather than positive ones. Social media use has been linked to an increased risk of depression and self harm.[59] Those from the ages of 13-15 may struggle the most with these issues, but they can be seen in college students as well.[60] According to the Center for Disease Control and Prevention's 2019 Youth Risk Behavior Surveillance System, data showed that approximately 15% of high school students were electronically bullied in the 12 months prior to the survey that students were asked to complete.[61] Bullying over social media has sparked suicide rates immensely within the last decade.[62] Older people Older generations are affected by social media in different areas to teens and young adults. Social media plays an integral role in the daily lives of middle aged adults, especially in regards to their career and communication. Studies have suggested that many individuals feel that smartphones are vital for their career planning and success, but a pressure to connect with family and friends via social media becomes an issue.[63] This is reinforced by further studies suggesting that middle aged people feel more isolated and lonely due to the use of social media, to the extent of diagnosis of anxiety and depression with excessive use. Similarly to teens and young adults, comparisons to others is often the reason for negative mental impacts amongst middle aged individuals. Surveys suggest that a pressure to perform and feelings of inferiority due to observing others lives through social media has caused depression and anxiety amongst middle class individuals specifically.[64] However, older generations do reap the benefits of the rise of social media. The feelings of loneliness and isolation have decreased in elderly individuals who use social media to connect to others, ultimately leading to a more fulfilling and physically healthy lifestyle, due to the ability to communicate and stay in touch with people they would have physically not been able to see.[63] Education Excessive use of social media may impact academic performance negatively. An increase usage on social media may take time away from spending away from time dedicated to academics.[citation needed] In school, many teachers report that their students are unfocused and unmotivated.[65] There may be a link between spending free time on social media and weaker critical thinking skills, impatience, and a lack in perseverance.[citation needed] There is also a risk of students struggling with attention and focusing because of how fast their phone can change from topic to topic.[65] Eating disorders People with problematic social media use have an increased risk for eating disorders (especially in females),[66] Through the extensive use of social media, adolescents are exposed to images of bodies that are unattainable, especially with the growing presence of photo-editing apps that allow you to alter the way that your body appears in a photo and social media can foster an environment for harmful online communities such as those that promote unhealthy habits.[67][68] Along with that is the normalization of cosmetic surgery which sets unrealistic beauty standards as well. This can, in turn, influence both the diet and exercise practices of adolescents as they try to fit the standard that their social media consumption has set for them.[67] |
結果 思春期と十代の若者 ソーシャルメディアの利用増加とプラットフォームへの露出は、時間の経過とともに悪影響やいじめに繋がる可能性がある。[58] ソーシャルメディアの主な目的は情報や友人・家族との交流を共有することだが、ポジティブな要素よりもネガティブな要素に関する証拠の方が多い。ソーシャ ルメディアの利用は、うつ病や自傷行為のリスク増加と関連している。[59] 13~15歳の年齢層がこれらの問題に最も苦しむ可能性があるが、大学生にも同様の傾向が見られる。[60] 米国疾病予防管理センター(CDC)の2019年青少年リスク行動監視システムによると、調査実施前の12ヶ月間に電子的いじめの被害を受けた高校生は約 15%に上った。[61] ソーシャルメディアを通じたいじめは、過去10年間で自殺率を著しく増加させた。[62] 高齢者 高齢世代がソーシャルメディアの影響を受ける領域は、10代や若年成人とは異なる。ソーシャルメディアは、特にキャリアやコミュニケーションの面で、中高 年層の日常生活に不可欠な役割を果たしている。多くの個人がキャリア形成と成功にスマートフォンが不可欠と感じている一方、ソーシャルメディアを介した家 族・友人との繋がりへのプレッシャーが問題となっていることが研究で示されている。[63] さらに、ソーシャルメディア利用により中年の孤立感や孤独感が増幅され、過剰使用が不安や抑うつ症の診断に繋がる可能性を示唆する研究もある。青少年と同 様に、他者との比較が中年の精神的悪影響の主な要因である。調査によれば、ソーシャルメディアを通じて他人の生活を観察することで生じるパフォーマンスへ のプレッシャーや劣等感が、特に中流階級の人々にうつ病や不安を引き起こしている。[64] しかし、高齢世代はソーシャルメディアの普及による恩恵を確かに受けている。ソーシャルメディアを利用して他者と繋がる高齢者は、孤独感や孤立感が減少 し、結果としてより充実した身体的に健康な生活を送っている。これは、物理的に会うことが難しかった人々とコミュニケーションを取り、繋がりを保つ能力に よるものである。[63] 教育 ソーシャルメディアの過剰利用は学業成績に悪影響を及ぼす可能性がある。ソーシャルメディアの利用時間が増えると、学業に充てる時間が奪われる。[出典必 要] 学校では、多くの教師が生徒の集中力や意欲の低下を報告している。[65] 自由時間をソーシャルメディアに費やすことと、批判的思考力の低下、忍耐力の欠如、焦燥感の増加には関連性がある可能性がある。[出典必要] また、スマートフォンの画面が瞬時に話題を切り替える性質上、生徒が注意力を維持し集中することに困難をきたすリスクもある。[65] 摂食障害 ソーシャルメディアの使用に問題がある人は、摂食障害(特に女性)のリスクが高まる。[66] ソーシャルメディアの多用により、青少年は現実には達成不可能な身体像に晒される。特に、写真編集アプリが普及し、写真に写る自分の身体の見た目を変えら れるようになったことで、ソーシャルメディアは不健康な習慣を助長する有害なオンラインコミュニティを育む環境を作り出しうる。[67][68] これに加え、美容整形の一般化も非現実的な美の基準を定着させている。その結果、若者はソーシャルメディアが設定した基準に合わせようと、食事や運動習慣 に影響を受ける可能性がある。[67] |
| Epidemiology Psychologists estimate that as many as 5 to 10% of Americans meet the criteria for social media addiction today.[69] A survey conducted by Pew Research Center from January 8 through February 7, 2019, found that 80% of Americans go online every day.[70] Among young adults, 48% of 18- to 29-year-olds reported going online 'almost constantly' and 46% of them reported going online 'multiple times per day.'[70] Young adults going online 'almost constantly' increased by 9% just since 2018. On July 30, 2019, U.S. Senator Josh Hawley introduced the Social Media Addiction Reduction Technology (SMART) Act which is intended to crack down on "practices that exploit human psychology or brain physiology to substantially impede freedom of choice". It specifically prohibits features including infinite scrolling and Auto-Play.[71][72] A study conducted by Junling Gao and associates in Wuhan, China, on mental health during the COVID-19 outbreak revealed that there was a high prevalence of mental health problems including generalized anxiety and depression.[73] This had a positive correlation to 'frequent social media exposure.'[73] Based on these findings, the Chinese government increased mental health resources during the COVID-19 pandemic, including online courses, online consultation and hotline resources.[73] |
疫学 心理学者の推定によれば、現在アメリカ人の5~10%がソーシャルメディア依存症の基準を満たしているという。[69] ピュー・リサーチ・センターが2019年1月8日から2月7日にかけて実施した調査では、アメリカ人の80%が毎日インターネットを利用していることが判 明した。[70] 若年層では、18~29歳の48%が「ほぼ常に」オンラインを利用し、46%が「1日に複数回」利用していると報告した。[70] 「ほぼ常に」オンラインを利用する若年層は、2018年以降だけで9%増加した。2019年7月30日、米国上院議員ジョシュ・ホーリーは「ソーシャルメ ディア依存症削減技術(SMART)法案」を提出した。これは「人間の心理や脳の生理機能を悪用し、選択の自由を著しく阻害する行為」を取り締まることを 目的としている。具体的には無限スクロールや自動再生などの機能を禁止する。[71][72] 中国武漢で高俊玲らが実施したCOVID-19流行期のメンタルヘルス調査では、全般性不安障害やうつ病を含む精神健康問題の高い有病率が明らかになっ た。[73]これは「頻繁なソーシャルメディア接触」と正の相関を示した。[73]この結果を受け、中国政府はパンデミック期間中にオンライン講座・相談 窓口・ホットライン資源を拡充した。[73] |
| Cultural and history From an anthropological lens, addiction to social media is a socially constructed concept that has been medicalized because this behavior does not align with behavior accepted by certain hegemonic social groups.[74] Molly Russell case Main article: Death of Molly Russell In November 2017, a fourteen-year-old British girl from Harrow, London, named Molly Russell, took her own life after viewing negative, graphic, and descriptive content primarily on social media platforms such as Instagram and Pinterest.[75] The coroner of this case, Andrew Walker also concluded that Molly's death was "an act of self harm suffering from depression and the negative effects of online content".[75] Molly's case has sparked a lot of attention not only across the UK but in the U.S. as well. It raises the question on whether or not policies and regulations will either be set into place or changed to protect the safety of children on the Internet. Child safety campaigners hope that creating regulations will help to shift the fundamentals that are associated with social media platforms such as Instagram and Pinterest.[76] Laws, policies, and regulations to minimize harm Molly Russell's case sparked discussion both in the UK and the U.S. on how to protect individuals from harmful online content. In the UK, the Online Safety Bill was officially introduced into Parliament in March 2022: the bill covers a range of possible dangerous content such as revenge porn, grooming, hate speech, or anything related to suicide.[77] Overall, the bill will not only protect children from online content but talk about how they can deal with this content that may be illegal. It also covers verification roles and advertising as this will all be covered on the social media platform's terms and conditions page. If the social media platforms fail to comply with these new regulations, they will face a $7500 fine for each offense. When it comes to the U.S., recommendations were offered such as finding an independent agency to implement a system of regulations similar to the Online Safety Bill in the U.K.[78] Another potential idea was finding a specific rule making agency where the authority is strictly and solely focused on a digital regulator who is available 24/7.[78] California already launched an act called the Age Appropriate Design Code Act in August 2022, which aims to protect children under the age of eighteen especially regarding privacy on the Internet.[79] The overall hope and goal of these new laws, policies, and regulations set into place is to 1) ensure that a case such as Molly's never happens again and 2) protects individuals from harmful online content that can lead to mental health problems such as suicide, depression, and self-harm. In 2022, a case was successfully litigated that implicated a social media platform in the suicide of a Canadian teenage girl named Amanda Todd who died by hanging. This was the first time that any social media platform was held liable for a user's actions.[citation needed] |
文化と歴史 人類学的な視点から見ると、ソーシャルメディアへの依存は社会的に構築された概念であり、特定の支配的な社会集団によって受け入れられる行動と一致しないため、医療化されてきた。[74] モリー・ラッセル事件 主な記事:モリー・ラッセルの死 2017年11月、ロンドン、ハロー出身の14歳の英国人少女、モリー・ラッセルは、主にInstagramやPinterestなどのソーシャルメディ アプラットフォーム上で、否定的で、生々しく、描写的なコンテンツを閲覧した後、自らの命を絶った。[75] この事件の検死官であるアンドルー・ウォーカーも、モリーの死は「うつ病とオンラインコンテンツの悪影響による苦悩による自傷行為」であると結論づけた。 [75] モリーの事件は、英国だけでなく米国でも大きな注目を集めた。インターネット上で子供たちの安全を守るために、政策や規制が導入されるか、あるいは変更さ れるかという問題が提起されている。児童の安全を守る活動家たちは、規制を設けることで、Instagram や Pinterest などのソーシャルメディアプラットフォームに関連する根本的な問題の変化につながることを望んでいる。[76] 害を最小限に抑えるための法律、政策、規制 モリー・ラッセルの事件は、有害なオンラインコンテンツから個人をどのように保護すべきかについて、英国と米国の両方で議論を巻き起こした。英国では 2022年3月、オンライン安全法案が議会に正式提出された。同法案はリベンジポルノ、グルーミング、ヘイトスピーチ、自殺関連情報など多様な危険コンテ ンツを網羅する[77]。全体として、本法案は児童をオンラインコンテンツから保護するだけでなく、違法な可能性のあるコンテンツへの対処法についても規 定する。また、ソーシャルメディアプラットフォームの利用規約ページに記載される検証機能や広告も対象となる。プラットフォームが新規制に違反した場合、 違反1件につき7500ドルの罰金が科される。米国では、英国のオンライン安全法案に類似した規制システムを実施する独立機関の設置などが提案された。 [78] 別の案として、権限が厳密かつ専らデジタル規制機関に集中し、24時間体制で対応可能な特定の規則制定機関を設置することも検討されている。[78] カリフォルニア州では既に2022年8月、「年齢に応じたデザイン規範法」と呼ばれる法案を施行しており、特にインターネット上のプライバシーに関して 18歳未満の児童を保護することを目的としている。[79] こうした新たな法律・政策・規制の全体的な目的は、1) モリーのような事例が二度と起きないこと、2) 自殺・うつ病・自傷行為といった精神健康問題を引き起こす有害なオンラインコンテンツから個人を保護することにある。 2022年には、カナダ人少女アマンダ・トッドが首吊り自殺した事件で、ソーシャルメディアプラットフォームが関与したとして訴訟が成立した。これはソーシャルメディアプラットフォームがユーザーの行為に対して責任を問われた初めての事例である。[出典が必要] |
| Research Empirical research indicates that addiction to social media is triggered by dispositional factors (such as personality, desires, and self-esteem), but specific socio-cultural and behavioural reinforcement factors remain to be investigated empirically.[80] Social media addiction may also have other neurobiological risk factors; understanding this addiction is still being actively studied and researched, but there is some evidence that suggests a possible link between problematic social media use and neurobiological aspects.[81] |
研究 実証研究によれば、ソーシャルメディア依存は気質的要因(人格、欲求、自尊心など)によって引き起こされるが、具体的な社会文化的要因や行動的強化要因については、まだ実証的に調査される必要がある。[80] ソーシャルメディア依存症には他の神経生物学的リスク要因も存在する可能性がある。この依存症の理解は現在も活発に研究が進められているが、問題のあるソーシャルメディア利用と神経生物学的側面との関連性を示唆する証拠がいくつか存在する。[81] |
| Algorithmic radicalization – Radicalization via social media algorithms Computer addiction – Excessive or compulsive use of computers Digital media use and mental health – Mental health effects of using digital media Dopamine fasting – Temporary abstinence from addictive technologies Evolutionary mismatch – Scientific concept Facebook–Cambridge Analytica data scandal – 2010s social media data misuse Facebook Files – Document leak regarding harm done by social networks Instagram impact on people Social media bias Problematic smartphone use – Psychological dependence on smartphones Social media as a news source - How people use social media to consume news Social influence bias – Herd behaviours in online social media Social media restrictions on children in Australia The Social Dilemma – 2020 American docudrama film by Jeff Orlowski Vicarious trauma after viewing media Adolescence (TV series) – 2025 British crime drama TV series |
アルゴリズムによる過激化 – ソーシャルメディアのアルゴリズムを介した過激化 コンピューター依存症 – コンピューターの過剰または強迫的な使用 デジタルメディア利用とメンタル健康 – デジタルメディア利用がメンタル健康に及ぼす影響 ドーパミン断食 – 依存性技術の一時的な断ち 進化論的ミスマッチ – 科学的概念 フェイスブック・ケンブリッジアナリティカデータスキャンダル – 2010年代のソーシャルメディアデータ悪用 フェイスブックファイル – ソーシャルネットワークによる被害に関する文書流出 インスタグラムが人民に与える影響 ソーシャルメディアバイアス 問題のあるスマートフォン利用 – スマートフォンへの心理的依存 ソーシャルメディアをニュースソースとして - 人民がソーシャルメディアでニュースを消費する方法 社会的影響バイアス - オンラインソーシャルメディアにおける群畜行動 オーストラリアにおける子供へのソーシャルメディア制限 ソーシャル・ディレンマ - ジェフ・オルロウスキー監督による2020年アメリカ製ドキュメンタリードラマ映画 メディア視聴後の代理トラウマ 『アドルセンス』(TVシリーズ) - 2025年英国製犯罪ドラマTVシリーズ |
| National Institute of Mental
Health, (2099), Social Anxiety Disorder : More Than Just Shyness, U.S.,
retrieved from Social Anxiety Disorder: More Than Just Shyness -
National Institute of Mental Health (NIMH) Al-Rahmi WM, Othman MS (2013). "The Impact of Social Media use on Academic Performance among university students: A Pilot Study". Journal of Information Systems Research and Innovation: 1–10. Mateus, Samuel (2012). "Social Networks Scopophilic dimension – social belonging through spectatorship". Observatorio (OBS*) Journal (Special Issue). doi:10.15847/obsOBS000605. hdl:10400.13/2918. |
国民精神衛生研究所(2099年)。「社交不安障害:単なる内気以上のもの」。米国。出典:社交不安障害:単なる内気以上のもの - 国民精神衛生研究所(NIMH) Al-Rahmi WM, Othman MS (2013). 「大学生におけるソーシャルメディア利用が学業成績に与える影響:パイロット研究」 情報システム研究・革新ジャーナル:1–10. Mateus, Samuel (2012). 「ソーシャルネットワークのスコポフィリック次元 – 観客性を通じた社会的帰属」. Observatorio (OBS*) ジャーナル(特別号). doi:10.15847/obsOBS000605. hdl:10400.13/2918. |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Problematic_social_media_use |
|
★デジタル・メディアの利用と精神保健
【注意書き】こ
の記事はウィキペディアの品質基準に準拠するため、書き直す必要があるかもしれない。試験の一覧はWP:MEDMOSの引用基準を満たしておらず、出典が
明記されていない。出典は主に「関連する精神疾患」の節で、部分的にしか理解できない形で記述されている。協力してほしい。トークページに提案があるかも
しれない。(2024年7月)/本記事にはインライン引用が含まれているが、それらは適切にフォーマットされていない。それらを修正することで本記事を改
善してほしい。ハードコードされた脚注参照は引用リンクに置き換えるべきである。(2025年9月)
(このメッセージを削除する方法とタイミングについて)
| Digital media use and mental health |
デジタル・メディアの利用と精神保健 |
| Researchers from fields like
psychology, sociology, anthropology, and medicine have studied the
relationship between digital media use and mental health since the
mid-1990s, following the rise of the World Wide Web and text messaging.
Much research has focused on patterns of excessive use, often called
"digital addictions" or "digital dependencies," which can vary across
different cultures and societies. At the same time, some experts have
explored the positive effects of moderate digital media use, including
its potential to support mental health and offer innovative treatments.
For example, participation in online support communities has been found
to provide mental health benefits, although the overall impact of
digital media remains complex.[1] The difference between beneficial and pathological use of digital media has not been established. There are no widely accepted diagnostic criteria associated with digital media overuse, although some experts consider overuse a manifestation of underlying psychiatric disorders. The prevention and treatment of pathological digital media use are not standardized, although guidelines for safer media use for children and families have been developed. The fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, 2013) and the International Classification of Diseases (ICD-11) currently do not recognize problematic internet use or problematic social media use as official diagnoses. However, the ICD-11 does include gaming disorder—often referred to as video game addiction—while the DSM-5 does not. As of 2023, there remains ongoing debate about if and when these behaviors should be formally diagnosed. Additionally, the use of the term "addiction" to describe these conditions has been increasingly questioned. Digital media and screen time amongst modern social media apps such as Instagram, TikTok, Snapchat and Facebook have changed how children think, interact and develop in positive and negative ways, but researchers are unsure about the existence of hypothesized causal links between digital media use and mental health outcomes. Those links appear to depend on the individual and the platforms they use. |
心理学、社会学、人類学、医学などの分野の研究者は、1990年代半ば
のワールドワイドウェブとテキストメッセージの普及以降、デジタルメディアの使用とメンタルヘルスとの関係について研究してきた。多くの研究は、しばしば
「デジタル依存症」や「デジタル依存」と呼ばれる過剰使用のパターンに焦点を当ててきた。これは異なる文化や社会によって異なる場合がある。同時に、一部
の専門家は、適度なデジタルメディア利用のプラスの効果、すなわちメンタルヘルスを支え、革新的な治療法を提供する可能性を探求してきた。例えば、オンラ
イン支援コミュニティへの参加はメンタルヘルス上の利益をもたらすことが分かっている。ただし、デジタルメディアの全体的な影響は依然として複雑である。
[1] デジタルメディアの有益な利用と病的な利用の境界線は確立されていない。デジタルメディアの過剰利用に関連する広く受け入れられた診断基準は存在しない が、一部の専門家は過剰利用を潜在的な精神疾患の現れと見なしている。病的なデジタルメディア利用の予防と治療は標準化されていないが、子どもや家族向け の安全なメディア利用ガイドラインは開発されている。『精神障害の診断と統計マニュアル』第5版(DSM-5, 2013)および『国際疾病分類』(ICD-11)は現在、問題のあるインターネット使用やソーシャルメディア使用を正式な診断として認めていない。ただ しICD-11には「ゲーム障害」(しばしばビデオゲーム依存症と呼ばれる)が含まれる一方、DSM-5には含まれていない。2023年現在、これらの行 動を正式に診断すべきかどうか、またその時期については議論が続いている。さらに、これらの状態を「依存症」と呼ぶこと自体も疑問視される傾向が強まって いる。 Instagram、TikTok、Snapchat、Facebookといった現代のソーシャルメディアアプリにおけるデジタルメディアやスクリーンタ イムは、子供たちの思考、交流、発達を良い面も悪い面も変えてきた。しかし研究者たちは、デジタルメディア利用とメンタル健康結果の間に仮説的な因果関係 が存在するかどうか確信が持てない。それらの関連性は個人と利用するプラットフォームに依存しているようだ。 |
| History and terminology The relationship between digital technology and mental health has been studied from multiple perspectives.[1][2][3] Research has identified benefits of digital media use for childhood and adolescent development.[4][5] However, researchers, clinicians, and the public have also expressed concern over compulsive behaviors linked to digital media use, as increasing evidence shows correlations between excessive technology use and mental health issues.[2][3][4][5] Terminologies used to refer to compulsive digital-media-use behaviours are not standardized or universally recognised. They include "digital addiction", "digital dependence", "problematic use", or "overuse", often delineated by the digital media platform used or under study (such as problematic smartphone use or problematic internet use).[6] Unrestrained use of technological devices may affect developmental, social, mental and physical well-being and may result in symptoms akin to other psychological dependence syndromes, or behavioral addictions.[7][5] The focus on problematic technology use in research, particularly in relation to the behavioural addiction paradigm, is becoming more accepted, despite poor standardization and conflicting research.[8] Internet addiction has been proposed as a diagnosis since the 1998[9] and social media and its relation to addiction has been examined since 2009.[10] A 2018 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) report stated there were benefits of structured and limited internet use in children and adolescents for developmental and educational purposes, but that excessive use can have a negative impact on mental well-being. The report also noted a 40% overall increase in internet use among school-age children between 2010 and 2015, with significant variations in usage rates and platform preferences across different OECD countries.[1] The American Psychological Association recommends that adolescents receive training or coaching on social media use to help them develop psychologically informed skills and competencies, promoting balanced, safe, and meaningful engagement online.[11] The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) has not formally classified problematic digital media use as a diagnostic category but identified internet gaming disorder as a condition warranting further study in 2013.[1] Meanwhile, gaming disorder—commonly known as video game addiction—is recognized in the ICD-11.[2][3] The differing recommendations between the DSM and ICD partly reflect a lack of expert consensus, variations in the focus of each classification system, and challenges in applying animal models to behavioral addictions.[7] The utility of the term addiction in relation to the overuse of digital media has been questioned, in regard to its suitability to describe new, digitally mediated psychiatric categories, as opposed to overuse being a manifestation of other psychiatric disorders.[12][13] Usage of the term has also been criticised for drawing parallels with substance use behaviours. Careless use of the term may cause more problems—both downplaying the risks of harm in seriously affected people, as well as overstating risks of excessive, non-pathological use of digital media.[13] The evolution of terminology relating excessive digital media use to problematic use rather than addiction was encouraged by Panova and Carbonell, psychologists at Ramon Llull University, in a 2018 review.[14] Due to the lack of recognition and consensus on the concepts used, diagnoses and treatments are difficult to standardize or develop. Heightened levels of public anxiety around new media (including social media, smartphones and video games) adds confusion to the interpretation of population-based assessments, as well as posing management dilemmas.[12] Radesky and Christakis, the 2019 editors of JAMA Paediatrics, published a review that investigated "concerns about health and developmental/behavioral risks of excessive media use for child cognitive, language, literacy, and social-emotional development."[15] Due to the ready availability of multiple technologies to children worldwide, the problem is bi-directional, as taking away digital devices may have a detrimental effect, in areas such as learning, family relationship dynamics, and overall development.[16] |
歴史と用語 デジタル技術とメンタル健康の関係は、様々な観点から研究されてきた。[1][2][3] 研究により、デジタルメディアの利用が児童期および青年期の発達に有益であることが確認されている。[4][5] しかし、研究者、臨床医、一般市民は、デジタルメディア利用に関連する強迫的行動についても懸念を表明している。なぜなら、過度な技術利用とメンタル健康 問題との相関関係を示す証拠が増えているからだ。[2][3][4] [5] 強迫的なデジタルメディア利用行動を指す用語は標準化されておらず、普遍的に認知されているわけでもない。これには「デジタル依存症」「デジタル依存」 「問題のある利用」「過剰利用」などが含まれ、多くの場合、使用または研究対象のデジタルメディアプラットフォームによって区別される(例:問題のあるス マートフォン利用、問題のあるインターネット利用)。[6] 技術機器の無制限な使用は、発達的・社会的・精神的・身体的健康に影響を与え、他の心理的依存症候群や行動依存症に類似した症状を引き起こす可能性があ る。[7][5] 研究における問題のある技術使用への注目、特に行動依存症パラダイムとの関係性は、標準化が不十分で研究結果が矛盾しているにもかかわらず、より広く受け 入れられつつある。[8] インターネット依存症は1998年[9]から診断対象として提案され、ソーシャルメディアと依存症の関係は2009年[10]から検討されている。 2018年の経済協力開発機構(OECD)報告書は、発達・教育目的での構造化された限定的なインターネット利用には児童・青少年に利益がある一方、過剰 利用は精神的健康に悪影響を及ぼし得ると述べた。同報告書はまた、2010年から2015年にかけて学齢期児童のインターネット利用が全体で40%増加し たことを指摘し、OECD加盟国間で利用率やプラットフォーム選好に顕著な差異があることを示した[1]。アメリカ心理学会は、青少年が心理学的知見に基 づいたスキルと能力を育成し、オンライン上で均衡のとれた安全かつ有意義な関与を促進できるよう、ソーシャルメディア利用に関する指導やコーチングを受け ることを推奨している。[11] 精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)は、問題のあるデジタルメディア利用を正式な診断カテゴリーとして分類していないが、2013年にインターネッ トゲーム障害をさらなる研究が必要な状態として特定した。一方、ゲーム障害(一般にビデオゲーム依存症として知られる)はICD-11で認められている。 [2][3] DSMとICDの推奨内容は異なるが、その理由は専門家間の合意不足、各分類体系の焦点の違い、行動依存症への動物モデル適用における課題などを部分的に 反映している。[7] デジタルメディアの過剰使用に関連して「依存症」という用語の有用性は疑問視されている。過剰使用が他の精神疾患の現れである場合と異なり、デジタルを介 した新たな精神医学的カテゴリーを記述するのに適しているかどうかが問題だ。[12][13] また、この用語の使用は物質使用行動との類似性を強調する点でも批判されている。この用語の不注意な使用は、深刻な影響を受ける人々における危害リスクを 過小評価すると同時に、病的ではない過剰なデジタルメディア使用のリスクを過大評価するという二重の問題を引き起こす可能性がある。[13] ラモン・リュイ大学(Ramon Llull University)の心理学者パノバ(Panova)とカルボネル(Carbonell)は、2018年のレビューにおいて、過剰なデジタルメディア 使用を「依存症」ではなく「問題のある使用」に関連付ける用語の進化を推奨した。[14] 使用される概念に対する認識と合意が欠如しているため、診断と治療の標準化や開発は困難である。ソーシャルメディア、スマートフォン、ビデオゲームを含む 新メディアに対する公衆の不安の高まりは、集団ベースの評価の解釈に混乱をもたらすだけでなく、管理上のジレンマも生じさせている。[12] 2019年に『JAMA小児科学』の編集を担当したラデスキーとクリスタキスは、「過剰なメディア利用が子どもの認知・言語・リテラシー・社会情緒的発達 に及ぼす健康リスク及び発達・行動リスクに関する懸念」を検証したレビューを発表した。[15] 世界中の子どもが複数の技術を容易に入手できる現状では、問題は双方向性を持つ。デジタル機器を取り上げることが、学習や家族関係、総合的な発達といった 領域に悪影響を及ぼす可能性があるからだ。[16] |
| Problematic use See also: Cyberpathology, Digital Revolution, Social aspects of television, and Television consumption Though associations have been observed between digital media use and mental health symptoms or diagnoses, causality has not been established; nuances and caveats published by researchers are often misunderstood by the general public, or misrepresented by the media.[13] Problematic social media use can also result in fear of missing out (FoMO) in which symptoms of anxiety and psychological stress exasperated with the fear of potentially missing content present online leaving the individual feeling unfulfilled or left out of the loop.[17][18][19][20] Worsening mental health issues, such as anxiety and depression, have been linked to digital use—particularly among younger users who may be more vulnerable to social comparison.[1] Neuroscientific findings that support a structural change in the brain, similar to behavioural addictions; have not found a specific biological or neural processes that may lead to excessive digital media use.[13] When an individual has FoMo they will be more likely to constantly check their social media accounts using their personal devices to check social media or messages to ensure they are up to date with information that is occurring within the individual's social network. This constant need to check social media platforms for information induces feelings of anxiety driving individuals to get involved with problematic social media use.[21] |
問題のある利用 関連項目:サイバー病理学、デジタル革命、テレビの社会的側面、テレビ視聴 デジタルメディアの利用と精神健康症状や診断との関連性は観察されているが、因果関係は確立されていない。研究者が発表した微妙な差異や注意点は大衆に誤 解されがちであり、メディアによって誤って伝えられることもある。[13] 問題のあるソーシャルメディア利用は、FOMO(見逃す恐怖)を引き起こすこともある。これは、オンライン上のコンテンツを見逃すかもしれないという恐怖 によって不安や心理的ストレスの症状が悪化し、個人が満たされない感覚や取り残された感覚を抱く状態である。[17][18][19][20] 不安や抑うつといった精神健康問題の悪化は、デジタル利用と関連付けられている。特に社会的比較の影響を受けやすい若年層において顕著だ[1]。行動依存 症に類似した脳の構造的変化を示す神経科学的知見はあるものの、過剰なデジタルメディア利用につながる特定の生物学的・神経学的プロセスは特定されていな い。[13] FoMo(取り残される恐怖)を抱える個人は、自身のソーシャルネットワーク内で発生している情報に遅れを取らないよう、個人用デバイスでソーシャルメ ディアやメッセージを頻繁に確認する傾向が強くなる。この絶え間ない情報確認欲求は不安感を引き起こし、問題のあるソーシャルメディア利用へと駆り立てる のである。[21] |
| Screen time and mental health See also: Criticism of Facebook § Psychological/sociological effects, and Social media and suicide Certain types of problematic internet use have been linked to psychiatric and behavioral issues such as depression, anxiety, hostility, aggression, and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). However, studies have not established clear causal relationships—for instance, it remains unclear whether individuals with depression overuse the internet because of their condition, or if excessive internet use contributes to developing depression.[1] Research also suggests that social media’s effects can be both positive and negative, depending on individual circumstances.[2] While digital media overuse has been associated with depressive symptoms, it may also be used in some cases to improve mood.[3][4] A large prospective study found a positive correlation between ADHD symptoms and digital media use.[5] Although the ADHD symptom of hyperfocus may lead some individuals to spend excessive time on video games, social media, or online chatting, the link between hyperfocus and problematic social media use is relatively weak.[6]A 2018 review found associations between the self-reported mental health symptoms by users of the Chinese social media platform WeChat and excessive platform use. However, the motivations and usage patterns of WeChat users affected overall psychological health, rather than the amount of time spent using the platform.[5] The evidence, although of mainly low to moderate quality, shows a correlation between heavy screen time and a variety of physical and mental health problems.[4] However, moderate use of digital media has been linked to positive outcomes, including improved social integration, mental health, and overall well-being for young people.[4] In fact, certain digital platforms, when used in moderation, have even been associated with enhanced mental health.[22] In a 2022 review, it was discovered that when it comes to adolescents' well-being that perhaps there is too much focus on locating a negative correlation between digital technologies and adolescents' well-being, If a negative correlation between the two are located the impact would potentially be minimal to the point where it would have little to no impact on adolescent well-being or quality of life.[17]  Social media applications in which users can easily access social feeds, be notified of new content, and connect with others in real time |
スクリーンタイムとメンタル健康 関連項目:フェイスブックへの批判 § 心理的・社会学的影響、ソーシャルメディアと自殺 特定の種類の問題のあるインターネット利用は、うつ病、不安、敵意、攻撃性、注意欠陥・多動性障害(ADHD)などの精神医学的・行動的問題と関連してい る。しかし、研究では明確な因果関係は確立されていない。例えば、うつ病の個人がその状態のためにインターネットを過剰利用するのか、それとも過剰なイン ターネット利用がうつ病の発症に寄与するのかは不明である。[1] 研究はまた、ソーシャルメディアの影響は個人の状況によってプラスにもマイナスにもなり得ると示唆している。[2] デジタルメディアの過剰使用は抑うつ症状と関連しているが、場合によっては気分改善に利用されることもある。[3][4] 大規模な前向き研究では、ADHD症状とデジタルメディア使用の間に正の相関が認められた。[5] ADHD症状であるハイパーフォーカス(過集中)が、一部の人々にビデオゲーム、ソーシャルメディア、オンラインチャットへの過剰な時間を費やす原因とな る可能性があるが、ハイパーフォーカスと問題のあるソーシャルメディア使用の関連性は比較的弱い。[6]2018年のレビューでは、中国SNSプラット フォーム「WeChat」利用者の自己申告によるメンタルヘルス症状と過剰なプラットフォーム利用の関連性が確認された。ただし、WeChat利用者の動 機や使用パターンが心理的健康全体に影響を与えており、プラットフォーム利用時間そのものは影響要因ではなかった。[5] 証拠は主に低~中程度の質ではあるが、長時間の画面使用と様々な身体的・精神的健康問題との相関を示している。[4] しかし、デジタルメディアの適度な使用は、若年層の社会的統合性、精神的健康、全体的な幸福感の向上といった好ましい結果と関連している。[4] 実際、特定のデジタルプラットフォームは、適度に使用すれば精神的健康の向上とさえ関連している。[22] 2022年のレビューでは、青少年の幸福度に関して、デジタル技術と青少年の幸福度の間に否定的な相関関係を見出そうとする傾向が強すぎる可能性が指摘さ れた。仮に両者の間に否定的な相関関係が認められたとしても、その影響は青少年の幸福度や生活の質にほとんど、あるいは全く影響を与えないほど最小限であ る可能性が高い。[17]  ソーシャルメディアアプリケーションでは、ユーザーは簡単にソーシャルフィードにアクセスし、新しいコンテンツの通知を受け取り、リアルタイムで他者とつながることができる。 |
| Social media and mental health Excessive time spent on social media may be more harmful than digital screen time as a whole, especially for young people. Some research has found a "substantial" association between social media use and mental health issues, but most studies have found only a weak or inconsistent relationship.[23][24][25][26] Social media can have both positive and negative effects on mental health; whether the overall effect is harmful or helpful may depend on a variety of factors, including the quality and quantity of social media usage. In the case of those over 65, studies have found high levels of social media usage was associated with positive outcomes overall, such as flourishing, though it remains unclear if social media use is a causative factor.[27][28] Social media can be a valuable tool that, when used appropriately, brings positive benefits both online and offline. For adolescents, social media offers opportunities to build and maintain relationships, access information, connect with others in real time, and express themselves through creating and engaging with content.[1][2] However, improper use of social media can pose risks. Adolescents may be exposed to cyberbullying, sexual predators, inappropriate adult content, substance use, and unrealistic portrayals of people and lifestyles.[1][2] Digital technologies tend to focus more on hedonic well-being, in which users are exposed to content that evokes joy and laughter towards positive content, to anger and sadness towards negative content. In turn these negative impacts on adolescence or any users of social media will only experience temporary impacts on mental well-being, which will not have a permanent effect on the user's quality of life and life satisfaction.[17] When asked about the amount of time spent on social media teenagers reported that 55 percent have the right amount of time spent on social media. 35 percent of teenagers reported they spent too much time on social media, while 8 percent stated they spent too little time on social media.[17] Youth 95% of people between the ages of 13-17 have reported using some form of social media. Almost 2/3 of teenagers reported that they use social media daily. Social media in youth provides benefits and risks. Children who spend more than 3 hours per day using social media face a risk of problems including but not limited to depression, anxiety, and suicide risk.[29][30] |
ソーシャルメディアとメンタルヘルス ソーシャルメディアに費やす時間が過剰だと、デジタル画面を見る時間全体よりも有害な場合がある。特に若年層においてそうだ。一部の研究ではソーシャルメ ディア利用とメンタルヘルス問題の間に「顕著な」関連性が確認されているが、大半の研究では弱い関連性か一貫性のない関係しか見出せていない。[23] [24][25][26] ソーシャルメディアはメンタルヘルスに良い影響も悪い影響も与え得る。全体として有害か有益かは、利用の質や量を含む様々な要因に依存する。65歳以上で は、ソーシャルメディアの高頻度利用が「繁栄」といった全体的な好結果と関連すると研究で示されているが、利用が直接的な要因かは不明だ。[27] [28] ソーシャルメディアは、適切に使用すればオンライン上でもオフライン上でも有益な効果をもたらす貴重なツールとなり得る。青少年にとって、ソーシャルメ ディアは人間関係を構築・維持する機会、情報へのアクセス、リアルタイムでの他者との繋がり、コンテンツの作成や交流を通じた自己表現の場を提供する。 [1][2] しかし、ソーシャルメディアの不適切な使用はリスクをもたらす可能性がある。青少年は、ネットいじめ、性的加害者、不適切な成人向けコンテンツ、薬物使 用、非現実的な人々やライフスタイルの描写に晒される可能性がある。[1][2] デジタル技術は快楽的幸福感に重点を置く傾向があり、ユーザーはポジティブなコンテンツに対して喜びや笑いを、ネガティブなコンテンツに対して怒りや悲し みを引き起こすコンテンツに晒される。その結果、思春期やソーシャルメディア利用者に生じるこうした悪影響は、精神的な幸福感に一時的な影響を与えるだけ で、利用者の生活の質や人生の満足度に永続的な影響を与えることはない。[17] ソーシャルメディアの利用時間について尋ねたところ、10代の55%が「適切な時間」と回答した。35%は「時間をかけすぎている」と答え、8%は「時間が足りない」と述べた。[17] 若者 13~17歳の95%の人民が何らかのソーシャルメディアを利用していると報告している。ほぼ3分の2のティーンエイジャーが毎日ソーシャルメディアを利 用していると回答した。若年層におけるソーシャルメディアには利点とリスクがある。1日3時間以上ソーシャルメディアを利用する子供は、うつ病、不安、自 殺リスクなど(これらに限定されない)問題のリスクに直面する。[29][30] |
| Proposed diagnostic categories See also: Computer addiction, Internet addiction disorder, Internet sex addiction, Nomophobia, Problematic smartphone use, Problematic social media use, Television addiction, and Video game addiction Gaming disorder has been considered by the DSM-5 task force as warranting further study (as the subset internet gaming disorder), and was included in the ICD-11.[31] Concerns have been raised by Aarseth and colleagues over this inclusion, particularly in regard to stigmatization of heavy gamers.[32] Christakis has asserted that internet addiction may be "a 21st century epidemic".[33] In 2018, he commented that childhood Internet overuse may be a form of "uncontrolled experiment[s] on ... children".[34] International estimates of the prevalence of internet overuse have varied considerably, with marked variations by nation. A 2014 meta-analysis of 31 nations yielded an overall worldwide prevalence of six percent.[35] A different perspective in 2018 by Musetti and colleagues reappraised the internet in terms of its necessity and ubiquity in modern society, as a social environment, rather than a tool, thereby calling for the reformulation of the internet addiction model.[36] Some medical and behavioural scientists recommend adding a diagnosis of "social media addiction" (or similar) to the next Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders update.[37][38][5] A 2015 review concluded there was a probable link between basic psychological needs and social media addiction, stating, "Social network site users seek feedback, and they get it from hundreds of people—instantly. It could be argued that the platforms are designed to get users 'hooked'."[39] Internet sex addiction, also called cybersex addiction, is proposed as a sexual addiction involving virtual sexual activities online that can lead to significant negative effects on a person’s physical, mental, social, or financial well-being.[1][2] It is often regarded as a form of problematic internet use.[3] |
ソーシャルメディアとメンタルヘルス ソーシャルメディアに費やす時間が過剰だと、デジタル画面を見る時間全体よりも有害な場合がある。特に若年層ではそうだ。一部の研究ではソーシャルメディ ア利用とメンタルヘルス問題の間に「顕著な」関連性が確認されているが、大半の研究では弱い関連性か一貫性のない関係しか見出せていない。[23] [24][25][26] ソーシャルメディアはメンタルヘルスに良い影響も悪い影響も与え得る。全体として有害か有益かは、利用の質や量を含む様々な要因に依存する。65歳以上で は、ソーシャルメディアの高頻度利用が「繁栄」といった全体的な好結果と関連すると研究で示されているが、利用が直接的な要因かは不明だ。[27] [28] ソーシャルメディアは、適切に使用すればオンライン上でもオフライン上でも有益な効果をもたらす貴重なツールとなり得る。青少年にとって、ソーシャルメ ディアは人間関係を構築・維持する機会、情報へのアクセス、リアルタイムでの他者との繋がり、コンテンツの作成や交流を通じた自己表現の場を提供する。 [1][2] しかし、ソーシャルメディアの不適切な使用はリスクをもたらす可能性がある。青少年は、ネットいじめ、性的捕食者、不適切な成人向けコンテンツ、薬物使 用、非現実的な人々やライフスタイルの描写に晒される可能性がある。[1][2] デジタル技術は快楽的幸福感に重点を置く傾向があり、ユーザーはポジティブなコンテンツに対して喜びや笑いを、ネガティブなコンテンツに対して怒りや悲し みを引き起こすコンテンツに晒される。その結果、思春期やソーシャルメディア利用者に生じるこうした悪影響は、精神的な幸福感に一時的な影響を与えるだけ で、利用者の生活の質や人生の満足度に永続的な影響を与えることはない。[17] ソーシャルメディアの利用時間について尋ねたところ、10代の55%が「適切な時間」と回答した。35%は「時間をかけすぎている」と答え、8%は「時間が足りない」と述べた。[17] 若者 13~17歳の95%の人民が何らかのソーシャルメディアを利用していると報告している。ほぼ3分の2のティーンエイジャーが毎日ソーシャルメディアを利 用していると回答した。若年層におけるソーシャルメディアには利点とリスクが存在する。1日3時間以上ソーシャルメディアを利用する子供は、うつ病、不 安、自殺リスクを含む(ただしこれらに限定されない)問題のリスクに直面する。[29][30] |
| Related phenomena Online problem gambling Main article: Online gambling § Problem gambling A 2015 review found evidence of higher rates of mental health comorbidities, as well as higher amounts of substance use, among internet gamblers, compared to non-internet gamblers. Causation, however, has not been established. The review postulates that there may be differences in the cohorts between internet and land-based problem gamblers.[40] Cyberbullying Main article: Cyberbullying Cyberbullying, bullying or harassment using social media or other electronic means, has been shown to have effects on mental health. Victims may have lower self-esteem, increased suicidal ideation, decreased motivation for usual hobbies, and a variety of emotional responses, including being scared, frustrated, angry, anxious or depressed. These victims may also begin to distance themselves from friends and family members.[41][42][43] According to the EU Kids Online project, the incidence of cyberbullying across seven European countries in children aged 8–16 increased from 8% to 12% between 2010 and 2014. Similar increases were shown in the United States and Brazil.[44] Media multitasking Main article: Media multitasking Concurrent use of multiple digital media streams, commonly known as media multitasking, has been shown to be associated with depressive symptoms, social anxiety, impulsivity, sensation seeking, lower perceived social success and neuroticism.[45] A 2018 review found that while the literature is sparse and inconclusive, overall, heavy media multitaskers also have poorer performance in several cognitive domains.[46] One of the authors commented that the data does not "unambiguously show that media multitasking causes a change in attention and memory", therefore it is possible to argue that it is inefficient to multitask on digital media.[47] Distracted road use Main articles: Mobile phones and driving safety and Smartphones and pedestrian safety See also: Distracted driving, Human multitasking, and Texting while driving A 2023 systematic review of 47 samples across 45 studies investigating associations between problematic mobile phone use and road safety outcomes found that problematic mobile phone use was associated with greater risk of simultaneous mobile phone use and road use and risk of vehicle collisions and pedestrian collisions or falls.[48] Noise-induced hearing loss See also: Tinnitus and Occupational hearing loss This section is an excerpt from Noise-induced hearing loss § Video game sound levels.[edit] A 2024 systematic review of 14 studies investigating associations between sound-induced hearing loss and playing video games and esports found that a significant association between gaming and hearing loss or tinnitus and that the average measured sound levels during gameplay by subjects (which averaged 3 hours per week) exceeded or nearly exceeded permissible sound exposure levels.[49] Physical Affects Extended periods of screen use have been linked to poor posture, eye strain, and reduced physical activity, which may contribute to more serious health issues such as obesity, musculoskeletal pain, and even cardiovascular problems. Sedentary behavior, especially when combined with poor diet habits during screen time, increases the risk of long-term health complications. Also, blue light exposure from screens can disrupt sleep patterns, reducing sleep quality and affecting overall physical recovery.[50] |
関連現象 オンライン問題ギャンブル 詳細記事: オンラインギャンブル § 問題ギャンブル 2015年のレビューでは、インターネットギャンブラーは非インターネットギャンブラーと比較して、精神健康上の併存疾患の発生率が高く、薬物使用量も多 いという証拠が示された。ただし因果関係は確立されていない。このレビューは、インターネット問題ギャンブラーと実店舗型問題ギャンブラーの間には集団に 差異がある可能性を提唱している。[40] ネットいじめ 主な記事:ネットいじめ ソーシャルメディアやその他の電子的手段を用いたネットいじめ、いじめ、嫌がらせは、精神健康に影響を与えることが示されている。被害者は自尊心の低下、 自殺念慮の増加、通常の趣味への意欲減退、恐怖、欲求不満、怒り、不安、抑うつなど様々な感情的反応を示す可能性がある。また、友人や家族から距離を置き 始める場合もある。[41][42] [43] EU Kids Onlineプロジェクトによれば、欧州7カ国における8~16歳の児童・生徒のネットいじめの発生率は、2010年から2014年の間に8%から12%に増加した。米国とブラジルでも同様の増加が確認されている。[44] メディアマルチタスキング 詳細記事: メディアマルチタスキング 複数のデジタルメディアストリームを同時に使用すること(一般にメディアマルチタスキングと呼ばれる)は、抑うつ症状、社会不安、衝動性、刺激追求、低い 社会的成功感、神経症的傾向と関連していることが示されている。[45] 2018年のレビューでは、文献は乏しく決定的ではないものの、全体として、メディアマルチタスキングを頻繁に行う者は複数の認知領域でパフォーマンスが 低下していることが判明した。[46] 著者の一人は「メディアマルチタスキングが注意や記憶の変化を引き起こすことを明確に示しているわけではない」とコメントしており、デジタルメディアでの マルチタスキングは非効率的だと主張することも可能だ。[47] 注意散漫な道路利用 主な記事:携帯電話と運転安全、スマートフォンと歩行者安全 関連項目:注意散漫運転、人間のマルチタスク、運転中のテキストメッセージ送信 2023年の系統的レビュー(45研究47サンプル)は、問題のある携帯電話使用と道路安全結果の関連性を調査し、問題のある携帯電話使用が、携帯電話使 用と道路利用の同時発生リスク、車両衝突リスク、歩行者衝突または転倒リスクの増加と関連していることを発見した。[48] 騒音性難聴 関連項目:耳鳴り、職業性難聴 この節は騒音性難聴 § ビデオゲームの音量からの抜粋である。[編集] 2024年の系統的レビュー(14研究)は、騒音性難聴とビデオゲーム・eスポーツの関連性を調査した。その結果、ゲームプレイと難聴・耳鳴りの間に有意 な関連性が認められ、被験者のゲームプレイ中(週平均3時間)の平均測定音量は、許容騒音暴露レベルを超過またはほぼ超過していた。[49] 身体的影響 長時間の画面使用は、姿勢不良、眼精疲労、身体活動量の減少と関連しており、これらは肥満、筋骨格系の痛み、さらには心血管疾患といったより深刻な健康問 題の一因となり得る。特に画面使用中の不適切な食習慣と相まって、座りがちな行動は長期的な健康合併症のリスクを高める。また、画面からのブルーライト曝 露は睡眠パターンを乱し、睡眠の質を低下させ、身体全体の回復に影響を与える。[50] |
| Assessment and treatment Rigorous, evidence-based assessment of problematic digital media use is yet to be comprehensively established. This is due partially to a lack of consensus around the various constructs and lack of standardization of treatments.[51] The American Academy of Pediatrics (AAP) has developed a Family Media Plan, intending to help parents assess and structure their family's use of electronic devices and media more safely. It recommends limiting entertainment screen time to two hours or less per day.[52][53] The Canadian Paediatric Society produced a similar guideline. Ferguson, a psychologist, has criticised these and other national guidelines for not being evidence-based.[54] Other experts, cited in a 2017 UNICEF Office of Research literature review, have recommended addressing potential underlying problems rather than arbitrarily enforcing screen time limits.[13] Different methodologies for assessing pathological internet use have been developed, mostly self-report questionnaires, but none have been universally recognised as a gold standard.[55] For gaming disorder, both the American Psychiatric Association[56] and the World Health Organization (through the ICD-11)[57] have released diagnostic criteria. There is limited evidence supporting the effectiveness of cognitive behavioral therapy and family-based interventions for treating problematic digital media use. Randomized controlled trials have not demonstrated the efficacy of medications for this purpose.[1] A 2016 study involving 901 adolescents suggested that mindfulness techniques may help prevent and treat problematic internet use.[2] A 2019 UK parliamentary report emphasized the importance of parental engagement, awareness, and support in fostering "digital resilience" among young people and in managing online risks.[3] Treatment centers addressing digital dependence have grown in number, particularly in countries like China and South Korea, which have declared it a public health crisis and opened approximately 300 and 190 centers nationwide, respectively.[4] Several other countries have also established similar treatment facilities.[5][6] NGOs, support and advocacy groups provide resources to people overusing digital media, with or without codified diagnoses,[58][59] including the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.[60][61] A 2022 study outlines the mechanisms by which media-transmitted stressors affect mental well-being. Authors suggest a common denominator related to problems with the media's construction of reality is increased uncertainty, which leads to defensive responses and chronic stress in predisposed individuals.[62] |
評価と治療 問題のあるデジタルメディアの使用について、厳格で証拠に基づく評価は、まだ包括的に確立されていない。これは、さまざまな概念に関する合意が欠如してお り、治療法の標準化が進んでいないことが一因である。[51] 米国小児科学会 (AAP) は、親が家族の電子機器やメディアの使用をより安全に評価し、構造化するのを支援することを目的とした「家族メディア計画」を策定した。この計画では、娯 楽のためのスクリーンタイムを 1 日 2 時間以下に制限することを推奨している[52][53]。カナダ小児科学会も同様のガイドラインを作成している。心理学者であるファーガソンは、これらの ガイドラインやその他の国民のガイドラインが証拠に基づいていないことを批判している[54]。2017 年のユニセフ研究室の文献レビューで引用された他の専門家たちは、スクリーンタイムの制限を恣意的に実施するよりも、潜在的な根本的な問題に対処すること を推奨している[13]。 病的なインターネット使用を評価するための異なる方法論が開発されているが、そのほとんどは自己申告式アンケートであり、ゴールドスタンダードとして普遍 的に認められているものは存在しない。[55] ゲーム障害については、米国精神医学会[56] と世界保健機関(ICD-11 を通じて)[57] の両方が診断基準を発表している。 問題のあるデジタルメディアの使用を治療するための認知行動療法や家族ベースの介入の有効性を裏付ける証拠は限られている。この目的での薬物療法の有効性 は、無作為化比較試験で実証されていない。[1] 2016年の901人の青少年を対象とした研究では、マインドフルネス技術が問題のあるインターネット利用の予防と治療に役立つ可能性が示唆された。 [2] 2019年の英国議会報告書は、若者の「デジタルレジリエンス」育成とオンラインリスク管理において、親の関与・認識・支援の重要性を強調した。[3] デジタル依存症を扱う治療施設は増加しており、特に中国と韓国では公衆健康上の危機と宣言され、それぞれ全国に約300ヶ所と190ヶ所の施設を開設して いる。[4] 他のいくつかの国々でも同様の治療施設が設立されている。[5][6] NGOや支援団体、擁護団体は、診断の有無にかかわらずデジタルメディアを過剰利用する人々にリソースを提供している。[58][59] アメリカ小児青年精神医学会もその一例だ。[60][61] 2022年の研究は、メディアを介したストレス要因が精神的健康に及ぼす作用機序を明らかにしている。著者らは、メディアによる現実構築の問題に関連する 共通要因として「不確実性の増大」を指摘する。これは、素因を持つ個人において防御的反応と慢性ストレスを引き起こす。[62] |
| Associated psychiatric disorders ADHD Main article: Attention deficit hyperactivity disorder Meta-analysis and systematic reviews of studies have shown a link between internet use, gaming disorders, social media use, and ADHD or symptoms of ADHD including impulsive traits; however, associations and causality are not clear.[63][64][65] There is some evidence of a bi-directional relationship in which people with ADHD may be more likely to engage with problematic internet or gaming use, and higher digital media use may worsen existing ADHD symptoms.[66][67][68] An important group to talk about regarding the relationship between ADHD and digital media is adolescents, a meta-analysis has shown that it is more common for adolescents to have problematic gaming if they also have ADHD, it also showed results indicating that ADHD may predict future problematic gaming aswell. [69] Anxiety Main articles: Generalized anxiety disorder and Social anxiety disorder There is evidence of weak to moderate associations between gaming disorder or smartphone use and social anxiety and depressive symptoms,[64][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] and nomophobia.[80] However these are also not causal, the nature of the associations is not clear.[81][65][82][83] There is also some evidence of bi-directionality.[84] There are some conflicting results from systematic reviews.[85] There are also some links between the amount of personal information uploaded, and social media addictive behaviors all correlated with anxiety.[74] Autism Main article: Autism In August 2015, NeuroTribes identified autistic digital communities such as Autism Network International, Wrong Planet, and the Autism List mailing list at St. John's University (New York City).[86] Steve Silberman argued that these communities "provided a natural home" where autistic members "could interact at their own pace."[87] Jim Sinclair (activist) was a member of Autism List and participated in founding Autism Network International. A 2018 systematic review of 47 studies published from 2005 to 2016 concluded that associations between autism and screen time was inconclusive.[88] Another 2019 systematic review of 16 studies that found that autistic children and adolescents are exposed to more screen time than typically developing peers and that the exposure starts at a younger age.[89] A 2021 systematic review of 12 studies of video game addiction in autistic subjects found that children, adolescents, and autistic adults are at greater risk of video game addiction than non-autistic adults, and that the data from the studies suggested that internal and external factors (sex, attention and oppositional behavior problems, social aspects, access and time spent playing video games, parental rules, and game genre) were significant predictors of video game addiction in autistic subjects.[90] A 2022 systematic review of 21 studies investigating associations between autism, problematic internet use, and gaming disorder found that the majority of studies found positive associations between the disorders.[91] Another 2022 systematic review of 10 studies found that autistic subjects had more symptoms of problematic internet use than control group subjects, had higher screen time online and an earlier age of first-time use of the internet, and also greater symptoms of depression and ADHD.[92] A 2023 meta-analysis of 46 studies comprising 562,131 subjects that concluded that while screen time may be a developmental cause of autism in childhood, associations between autism and screen time were not statistically significant when accounting for publication bias.[93] |
関連する精神疾患 ADHD 詳細な記事: 注意欠陥・多動性障害 研究のメタ分析と系統的レビューは、インターネット利用、ゲーム障害、ソーシャルメディア利用とADHDまたは衝動性を含むADHD症状との関連性を示し ている。しかし、関連性と因果関係は明確ではない。[63][64] [65] 双方向の関係を示す証拠もある。つまり、ADHDを持つ人民は問題のあるインターネットやゲーム利用に陥りやすく、デジタルメディアの利用が増えると既存 のADHD症状が悪化する可能性がある。[66][67] [68] ADHDとデジタルメディアの関係で重要な対象は青少年である。メタ分析によれば、ADHDを併せ持つ青少年は問題のあるゲーム利用をしがちであり、 ADHDが将来の問題のあるゲーム利用を予測する可能性も示唆されている。[69] 不安 主な記事:全般性不安障害および社交不安障害 ゲーム障害やスマートフォン使用と、社交不安や抑うつ症状[64][70][71][72][73][74][75][76][77] [78][79] 及びノモフォビアとの関連性が示されている。[80] ただしこれらは因果関係ではなく、関連性の性質は不明確である。[81][65][82][83] 双方向性の証拠も一部存在する。[84] 系統的レビューからは矛盾する結果も報告されている。[85] さらに、人格の投稿量とソーシャルメディア依存行動の間には関連性が認められ、いずれも不安と相関している。[74] 自閉症 主な記事: 自閉症 2015年8月、NeuroTribesはAutism Network International、Wrong Planet、セントジョンズ大学(ニューヨーク市)のAutism Listメーリングリストなどの自閉症デジタルコミュニティを特定した。[86] スティーブ・シルバーマンは、これらのコミュニティが「自閉症のメンバーが自分のペースで交流できる自然な居場所を提供している」と主張した。[87] ジム・シンクレア(活動家)はAutism Listのメンバーであり、Autism Network Internationalの設立に関わった。 2005年から2016年までに発表された47の研究を対象とした2018年の系統的レビューは、自閉症とスクリーンタイムの関連性は決定的ではないと結 論づけた。[88] 別の2019年の系統的レビュー(16研究)では、自閉症の児童・青年は通常発達する同年代よりも多くのスクリーンタイムに曝露されており、その曝露はよ り幼い年齢から始まっていることが判明した。自閉症対象者におけるビデオゲーム依存症に関する12研究の2021年系統的レビューでは、自閉症の小・青 年・成人は非自閉症成人より依存症リスクが高く、研究データは内因的・外的要因(性別、注意欠陥・反抗行動問題、社会的側面、ゲームへのアクセス・プレイ 時間、 親のルール、ゲームジャンル)が自閉症対象者のビデオゲーム依存症の重要な予測因子であることを示唆している。[90] 自閉症、問題のあるインターネット利用、ゲーム障害の関連性を調査した21件の研究を対象とした2022年の系統的レビューでは、大多数の研究がこれらの 障害間に正の関連性を認めた。[91] 別の2022年の10研究を対象とした系統的レビューでは、自閉症対象者は対照群対象者よりも問題のあるインターネット使用の症状が多く、オンライン画面 時間が長く、インターネット初回使用年齢が早く、またうつ病とADHDの症状もより大きいことが判明した。[92] 2023年のメタ分析(46研究・562,131名対象)は、画面使用時間が小児期自閉症の発達要因となり得る一方、出版バイアスを考慮すると自閉症と画 面使用時間の関連性は統計的に有意でないと結論付けた。[93] |
| Bipolar disorder Main article: Bipolar disorder There is some evidence of an association between problematic internet use as a risk factor for bipolar disorder.[94] Depression Main article: Major depressive disorder There is a growing body of evidence demonstrating an association between screen-based behaviours and depressive symptoms or clinical depression.[64][81][95][96][65][97][82][78] Studies across a wide range of populations including different ages, genders, [98] and cultures report small to moderate associations between these behaviors and depression symptoms, with problematic use more strongly associated with depression than general use.[74][71][72][75][99] While some studies suggest these associations may be bidirectional or influenced by factors like social support or content type, the overall direction of findings points to screen-based behaviours as a potential risk factor for a person to experience depressive symptoms.[84][100] The strength and nature of these associations has been reported to vary and may depend on usage and patterns, individual vulnerabilities, and geographic context. Causality remains unclear.[101][73][76][83][77][102][103][79] Sleep Main article: Insomnia Sleep quality and screen time or digital media use have been linked, including studies looking at media type, time of day, and age of person.[104][105][71][65][106][107][108][109][110][111] Various sleep challenges or outcomes have been studied including a reduction in sleep duration, increased sleep onset latency, modifications to rapid eye movement sleep and slow-wave sleep, increased sleepiness and self-perceived fatigue, and impaired post-sleep attention span and verbal memory.[112] Narcissism Main article: Narcissistic personality disorder There are some reports of positive correlations between grandiose narcissism and social networking site usage, [113][96] highlighting the potential for a correlation between time spent on social media, frequency of status updates, number of friends or followers, and frequency of posting self-portrait digital photographs.[114][115] Obsessive–compulsive disorder Main article: Obsessive–compulsive disorder There is some evidence suggesting a significant correlation between digital media overuse and obsessive–compulsive disorder symptoms.[64][116] |
双極性障害 詳細記事: 双極性障害 問題のあるインターネット利用が双極性障害の危険因子となる可能性を示す証拠が存在する。[94] うつ病 詳細記事: 大うつ病性障害 画面ベースの行動と抑うつ症状または臨床的うつ病との関連性を示す証拠が増加している。[64][81][95][96][65] [97][82][78] 異なる年齢層、性別、[98] 文化圏を含む広範な対象集団を対象とした研究では、これらの行動と抑うつ症状との間に小~中程度の関連性が報告されており、問題のある使用は一般的な使用 よりも抑うつとの関連性が強い。[74][71][72][75] [99] 一部の研究では、この関連性が双方向である可能性や、社会的支援やコンテンツの種類などの要因の影響を受ける可能性が示唆されているが、研究結果の全体的 な方向性は、画面ベースの行動が人格が抑うつ症状を経験する潜在的な危険因子となり得ることを示している。[84][100] これらの関連性の強さや性質は様々であり、使用状況やパターン、個人の脆弱性、地理的背景に依存する可能性がある。因果関係は依然として不明である。 [101][73][76][83][77][102][103][79] 睡眠 詳細記事: 不眠症 睡眠の質とスクリーン時間またはデジタルメディアの使用には関連性が認められており、メディアの種類、時間帯、年齢層を調べた研究も含まれる。[104] [105][71] [65][106][107][108][109][110][111] 睡眠時間の短縮、入眠潜時の増加、レム睡眠と徐波睡眠の変化、眠気や自覚的疲労の増大、睡眠後の注意力や言語記憶の障害など、様々な睡眠障害や結果が研究 されている。[112] ナルシシズム 詳細記事: 自己愛性人格障害 誇大ナルシシズムとソーシャルネットワーキングサイト利用の間に正の相関関係があるとする報告がある。[113][96] これは、ソーシャルメディアの利用時間、ステータス更新頻度、友人やフォロワーの数、自撮り写真の投稿頻度との相関関係の可能性を示唆している。 [114] [115] 強迫性障害 詳細記事: 強迫性障害 デジタルメディアの過剰使用と強迫性障害症状の間に有意な相関関係があることを示唆する証拠が存在する。[64][116] |
| Mental health benefits See also: Video game controversies § Positive effects of video games  Smartphones and other digital devices are ubiquitous in many societies. There is some evidence that people with mental illness can have a positive outcomes based on digital media use, such as the potential to develop social connections over social media and foster a sense of social inclusion in online communities.[117][3] Digital communities or social media may also have the potential for some people with mental illness to share personal stories in a perceived safer space, as well as gaining peer support for developing coping strategies.[117][3] There are some reports of people avoiding stigma and gaining further insight into their mental health condition, including the potential for dialogue with healthcare professionals, as benefits of using social media.[117][118][119] This comes with the usual digital media risk of the potential for unhealthy influences, misinformation, and delayed access to traditional mental health outlets.[117] Other benefits include the potential to gain connections to supportive online communities, including illness or disability specific communities, as well as the LGBTQIA community.[3] Young people with cancer have reported an improvement in their coping abilities due to their participation in an online community.[120] Furthermore, in children, there may be educational benefits of digital media use.[117] For example, screen-based programs may help increase both independent and collaborative learning. A variety of quality apps and software may decrease learning gaps and increase skill in certain educational subjects.[121][122] The benefits (and risks) may also be specific to cultures and geographic locations.[123] Young people may have different experiences online, depending on their socio-economic background, noting lower-income youths may spend up to three hours more per day using digital devices, compared to higher-income youths.[124] Lower-income youths, who are already vulnerable to mental illness, may be more passive in their online engagements, being more susceptible to negative feedback online, with difficulty self-regulating their digital media use.[124] It has been suggested that this may be a new form of digital divide between at-risk young people and other young people, pre-existing risks of mental illness becoming amplified among the already vulnerable population.[124] |
健康に関する利点 関連項目:ビデオゲームの論争 § ビデオゲームの好影響  スマートフォンやその他のデジタル機器は多くの社会で広く普及している。 精神疾患を持つ人民がデジタルメディアの利用によって良好な結果を得られる可能性があるという証拠がいくつか存在する。例えば、ソーシャルメディアを通じ て社会的つながりを築き、オンラインコミュニティにおける社会的包摂感を育む可能性が挙げられる。[117][3] デジタルコミュニティやソーシャルメディアは、精神疾患を持つ一部の人々が、より安全と感じられる空間で個人的な経験を共有したり、対処法を開発するため の仲間からの支援を得たりする可能性も秘めている。[117][3] ソーシャルメディア利用の利点として、スティグマを回避し、自身の精神状態への理解を深める人民の事例が報告されている。これには医療専門家との対話の可 能性も含まれる。[117][118][119] ただし、不健全な影響や誤情報の可能性、従来の精神保健サービスへのアクセス遅延といった、デジタルメディアに共通するリスクも伴う。[117] その他の利点として、支援的なオンラインコミュニティ(特定の疾患や障害を持つコミュニティ、LGBTQIAコミュニティなど)との繋がりを得られる可能 性がある。[3] がんを患う若者は、オンラインコミュニティへの参加によって対処能力が向上したと報告している。[120] さらに、子どもにおいては、デジタルメディア利用に教育的利点があるかもしれない。[117] 例えば、画面ベースのプログラムは、自律的な学習と協調的な学習の両方を促進する可能性がある。質の高い様々なアプリやソフトウェアは、学習格差を縮小 し、特定の教科における技能向上に寄与しうる。[121][122] こうした利点(およびリスク)は、文化や地理的場所によっても異なる可能性がある。[123] 若者のオンライン体験は、社会経済的背景によって異なる。低所得層の若者は、高所得層の若者と比較して、デジタル機器の使用時間が1日あたり最大3時間長 い傾向がある。[124] 精神疾患のリスクが元々高い低所得層の若者は、オンライン上での関与が受動的になりがちで、ネット上の否定的なフィードバックを受けやすく、デジタルメ ディア利用の自己制御が困難である。[124] これは、リスクのある若者と他の若者との間に生じる新たなデジタルデバイドであり、既に脆弱な集団において既存の精神疾患リスクが増幅される可能性が示唆 されている。[124] |
| Impact on cognition There is research and development about the cognitive impacts of smartphones and digital technology. Some educators and experts have raised some concerns about how technology may negatively affect students’ thinking abilities and academic performance.[125] |
認知への影響 スマートフォンやデジタル技術が認知に与える影響に関する研究開発が行われている。 一部の教育者や専門家は、技術が学生の思考能力や学業成績に悪影響を及ぼす可能性について懸念を表明している。[125] |
| Impact on social life Worldwide adolescent loneliness in contemporary schools and depression increased substantially after 2012 and a study found this to be associated with smartphone access and Internet use.[126][127] 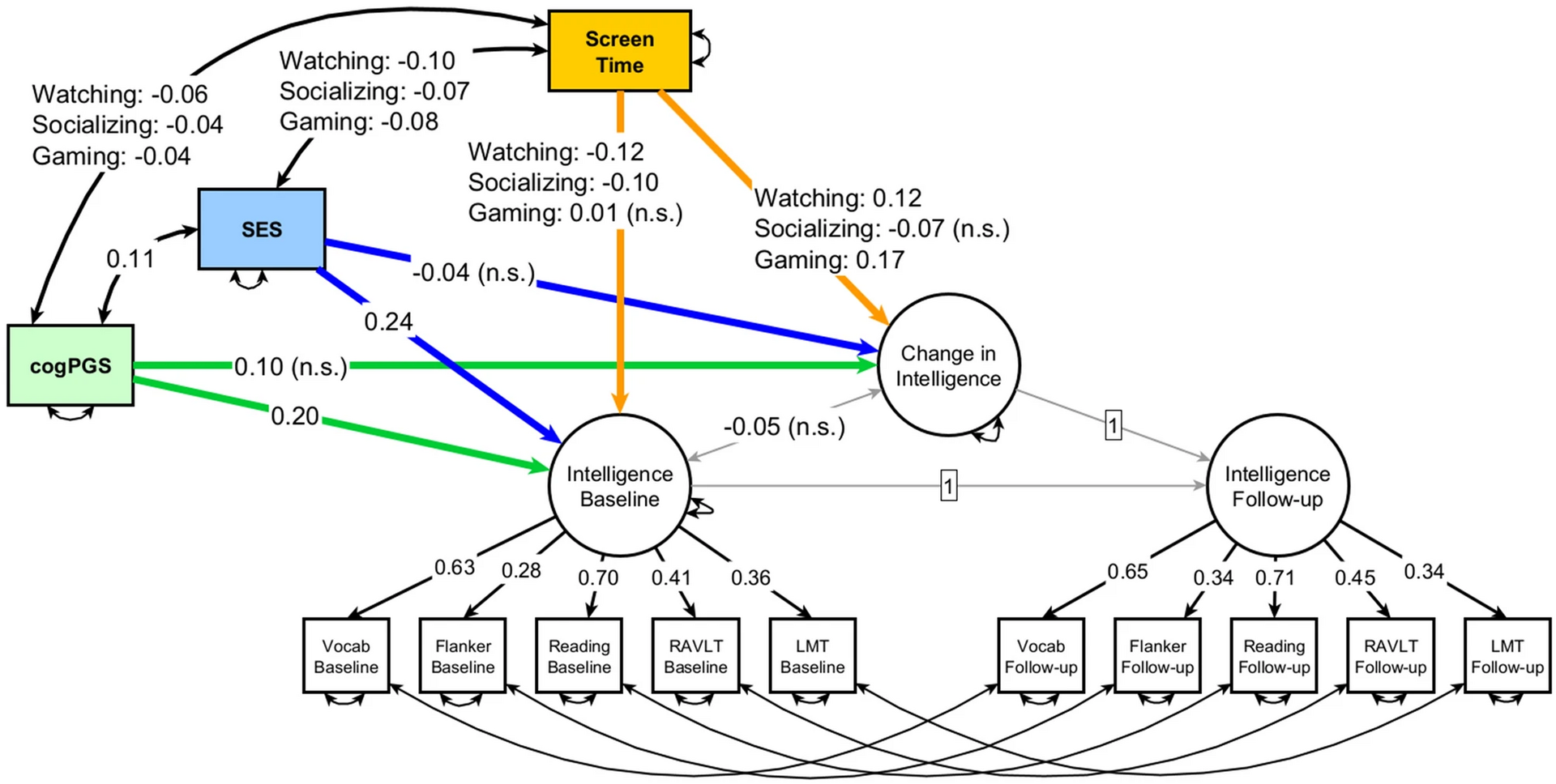 Measured results of the study |
社会生活への影響 現代の学校における世界的な青少年の孤独感と抑うつは、2012年以降大幅に増加した。ある研究では、これがスマートフォンの利用とインターネットの使用に関連していることが判明した。[126][127] 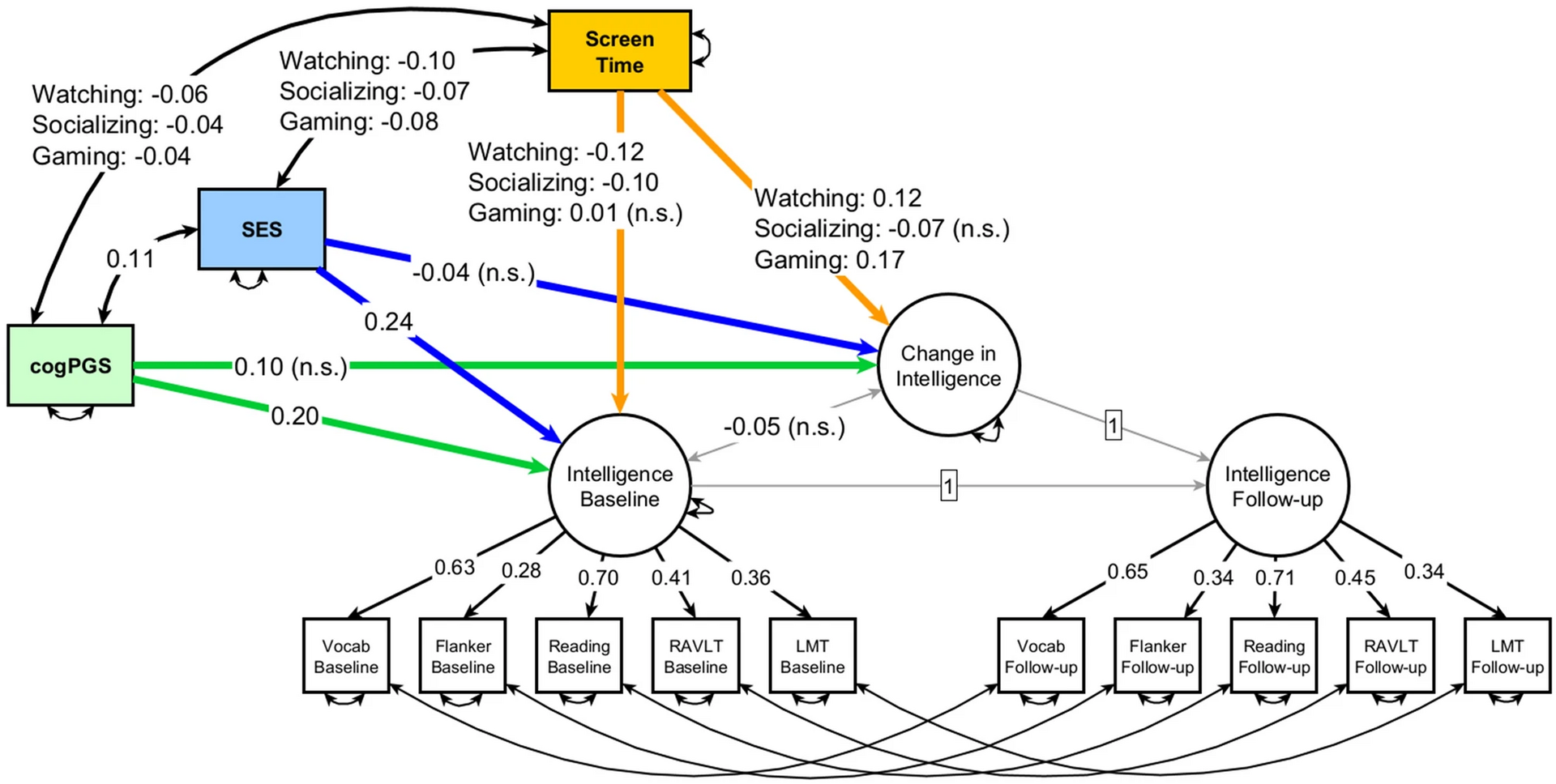 研究の測定結果 |
| Mitigation Industry Several technology firms have implemented changes intending to mitigate the adverse effects of excessive use of their platforms. In December 2017, Facebook admitted passive consumption of social media could be harmful to mental health, although they said active engagement can have a positive effect. In January 2018, the platform made major changes to increase user engagement.[128] In January 2019, Facebook's then head of global affairs, Nick Clegg, responding to criticisms of Facebook and mental health concerns, stated they would do "whatever it takes to make this environment safer online especially for youngsters". Facebook admitted "heavy responsibilities" to the global community, and invited regulation by governments.[129] In 2018 Facebook and Instagram announced new tools that they asserted may assist with overuse of their products.[130] In 2019, Instagram, which has been investigated specifically in one study in terms of addiction,[131] began testing a platform change in Canada to hide the number of "likes" and views that photos and videos received in an effort to create a "less pressurised" environment.[132] It then continued this trial in Australia, Italy, Ireland, Japan, Brazil and New Zealand[133] before extending the experiment globally in November of that year. The platform also developed artificial intelligence to counter cyberbullying.[134] In 2018, Alphabet Inc. released an update for Android smartphones, including a dashboard app enabling users to set timers on application use.[135] Apple Inc. purchased a third-party application and then incorporated it in iOS 12 to measure "screen time".[136] Journalists have questioned the functionality of these products for users and parents, as well as the companies' motivations for introducing them.[135][137] Alphabet has also invested in a mental health specialist, Quartet, which uses machine learning to collaborate and coordinate digital delivery of mental health care.[138] Two activist investors in Apple Inc voiced concerns in 2018 about the content and amount of time spent by youth. They called on Apple Inc. to act before regulators and consumers potentially force them to do so.[139] Apple Inc. responded that they have, "always looked out for kids, and [they] work hard to create powerful products that inspire, entertain, and educate children while also helping parents protect them online". The firm is planning new features that they asserted may allow them to play a pioneering role in regard to young people's health.[140] |
緩和策 業界 複数のテクノロジー企業は、自社プラットフォームの過剰利用による悪影響を緩和する意図で変更を実施した。 2017年12月、Facebookはソーシャルメディアの受動的利用が精神健康に有害となり得ると認めた。ただし能動的関与は好影響をもたらすと述べ た。2018年1月、同社はユーザーエンゲージメント向上のためプラットフォームに大幅な変更を加えた[128]。2019年1月、当時のフェイスブック 国際問題担当責任者ニック・クレッグは、同社への批判やメンタルヘルス懸念に応え、「特に若年層にとってオンライン環境をより安全にするため、あらゆる手 段を講じる」と表明した。フェイスブックは国際社会に対する「重い責任」を認め、政府による規制を要請した。[129] 2018年にはFacebookとInstagramが、自社製品の過剰利用対策として新たなツールを発表した。[130] 2019年には、依存症に関する研究で特に調査対象となったInstagramが、カナダでプラットフォーム変更のテストを開始。写真や動画への「いい ね」数や閲覧数を非表示にし、「プレッシャーの少ない」環境づくりを目指した。[132] その後、この試験運用をオーストラリア、イタリア、アイルランド、日本、ブラジル、ニュージーランド[133]に拡大し、同年11月には全世界に実験を拡 大した。また、サイバーいじめ対策として人工知能を開発した[134]。 2018年、アルファベット社はAndroidスマートフォン向けアップデートをリリースし、アプリ使用時間にタイマーを設定できるダッシュボードアプリ を含めた[135]。アップル社はサードパーティ製アプリを買収し、iOS 12に組み込んで「スクリーンタイム」を計測可能にした[136]。ジャーナリストらは、これらの製品がユーザーや保護者にとって機能的か、また企業が導 入した動機について疑問を呈している。[135][137] Alphabetはまた、機械学習を用いてメンタルヘルスケアのデジタル提供を連携・調整する専門企業Quartetにも投資している。[138] 2018年、Apple Inc.の2人のアクティビスト投資家が、若年層が消費するコンテンツと時間量について懸念を表明した。彼らは規制当局や消費者に強制される前に、 Apple Inc.が自ら行動を起こすよう求めた. [139] アップル社はこれに対し、「常に子供たちの安全を重視し、子供たちを鼓舞し、楽しませ、教育する強力な製品を開発すると同時に、保護者がオンライン上で子 供たちを守る手助けをするよう努めてきた」と応じた。同社は新たな機能を計画しており、それにより若者の健康に関して先駆的な役割を果たせる可能性がある と主張している。[140] |
| Public sector In China, Japan, South Korea and the United States, governmental efforts have been enacted to address issues relating to digital media use and mental health. China's Ministry of Culture has enacted several public health efforts from as early as 2006 to address gaming and internet-related disorders. In 2007, an "Online Game Anti-Addiction System" was implemented for minors, restricting their use to 3 hours or less per day. The ministry also proposed a "Comprehensive Prevention Program Plan for Minors' Online Gaming Addiction" in 2013, to promulgate research, particularly on diagnostic methods and interventions.[141] China's Ministry of Education in 2018 announced that new regulations would be introduced to further limit the amount of time spent by minors in online games.[142][143] In response, Tencent, the owner of WeChat and the world's largest video game publisher, restricted the amount of time that children could spend playing one of its online games, to one hour per day for children 12 and under, and two hours per day for children aged 13–18.[144] On 2 September 2023, those under the age of 18 can no longer access the Internet on their mobile device between 10 pm and 6 am without parental bypass. Smartphone usage is similarly capped by default at 40 minutes a day for children younger than eight and at two hours for 16- and 17-year-olds.[145] Japan's Ministry of Internal Affairs and Communications coordinates Japanese public health efforts in relation to problematic internet use and gaming disorder. Legislatively, the Act on Development of an Environment that Provides Safe and Secure Internet Use for Young People was enacted in 2008, to promote public awareness campaigns, and support NGOs to teach young people safe internet use skills.[141] South Korea has eight government ministries responsible for public health efforts in relation to internet and gaming disorders. A review article published in Prevention Science in 2018 stated that the "region is unique in that its government has been at the forefront of prevention efforts, particularly in contrast to the United States, Western Europe, and Oceania."[141] Efforts are coordinated by the Ministry of Science and ICT, and include awareness campaigns, educational interventions, youth counseling centres, and promoting healthy online culture.[141] In July 2022, Senators Richard Blumenthal and Marsha Blackburn introduced The Kids Online Safety Act (KOSA). This bill aims to protect minors from online harms by requiring social media platforms to mitigate online harms to minors through implementing safeguards (e.g. privacy settings), performing independent audits, and limiting the sharing of minors' personal information to third parties.[146] The bill passed the Senate in July 2024, but is still up for consideration by the House. Despite not being passed yet, KOSA is already incredibly polarizing legislation, with groups like The Electronic Frontier Foundation (EFF) opposing KOSA, saying the bill would lead to: "broad online censorship of lawful speech, including content designed to help children navigate and overcome the very same harms it identifies."[147] In May 2023, the United States' Surgeon general took the rare measure of issuing an advisory on Social media and mental health.[148][149] In October, 41 U.S. states commenced legal proceedings against Meta. This included the attorneys general of 33 states filing a combined lawsuit over concerns about the addictive nature of Instagram and its impact on the mental health of young people.[150][151] In November 2024, Australia passed the world's first ban on social media for under-16s.[152][153] |
公共部門 中国、日本、韓国、米国では、デジタルメディアの使用とメンタル健康に関する問題に対処するため、政府による取り組みが実施されている。 中国文化部は2006年という早い時期から、ゲームやインターネット関連の障害に対処するため、いくつかの公衆健康対策を打ち出してきた。2007年には 未成年者向けに「オンラインゲーム依存防止システム」を導入し、1日あたりの利用時間を3時間以下に制限した。同省は2013年には「未成年者のオンライ ンゲーム依存症総合予防プログラム計画」を提案し、特に診断方法と介入策に関する研究の普及を図った[141]。中国教育部は2018年、未成年者のオン ラインゲーム利用時間をさらに制限する新規制の導入を発表した[142]。これに対し、WeChatを所有し世界最大のゲームパブリッシャーであるテンセ ントは、自社のオンラインゲームにおける児童の利用時間を制限した。12歳以下は1日1時間、13~18歳は1日2時間である。[144] 2023年9月2日からは、18歳未満の者は親による解除がない限り、午後10時から午前6時までの間、モバイル端末でインターネットにアクセスできなく なった。同様に、スマートフォンの使用時間もデフォルトで制限され、8歳未満は1日40分、16~17歳は2時間に制限されている。[145] 日本の総務省は、問題のあるインターネット利用やゲーム依存症に関する公衆衛生対策を統括している。立法面では、2008年に「青少年のインターネット利 用環境整備に関する法律」が制定され、啓発キャンペーンの推進や、若者に安全なインターネット利用スキルを教えるNGOへの支援が行われている。 [141] 韓国では、インターネットおよびゲーム依存症に関する公衆衛生対策を管轄する政府省庁が8つ存在する。2018年に『Prevention Science』誌に掲載された総説は、「この地域は政府が予防活動の最前線に立っている点で独特であり、特に米国、西欧、オセアニアと対照的である」と 述べている。[141] 取り組みは科学技術情報通信省が調整し、啓発キャンペーン、教育的介入、青少年相談センター、健全なオンライン文化の促進などを含む。[141] 2022年7月、リチャード・ブルーメンソール上院議員とマーシャ・ブラックバーン上院議員は「キッズ・オンライン安全法(KOSA)」を提出した。この 法案は、ソーシャルメディアプラットフォームに対し、保護措置(例:プライバシー設定)の実施、独立監査の実施、第三者への未成年者の人格情報共有制限な どを通じて、未成年者へのオンライン上の危害を軽減することを義務付けることで、未成年者をオンライン上の危害から保護することを目的としている。 [146] 同法案は2024年7月に上院を通過したが、下院での審議は継続中である。未成立にもかかわらず、KOSAは既に極めて賛否両論の法案となっており、電子 フロンティア財団(EFF)などの団体は反対し、同法案が「合法的な発言に対する広範なオンライン検閲、特に同法案が特定する危害を子供たちが回避・克服 するための支援コンテンツを含む」結果を招くと主張している。[147] 2023年5月、米国公衆衛生局長官はソーシャルメディアとメンタルヘルスに関する勧告を発表するという異例の措置を取った[148][149]。同年 10月には、41の州がメタ社(現フェイスブック)を相手取り訴訟を開始。このうち33州の司法長官は、インスタグラムの中毒性と若年層のメンタルヘルス への影響を懸念し、共同訴訟を提起した。[150][151] 2024年11月、オーストラリアは16歳未満のソーシャルメディア利用を禁止する世界初の法律を可決した。[152][153] |
Digital mental health care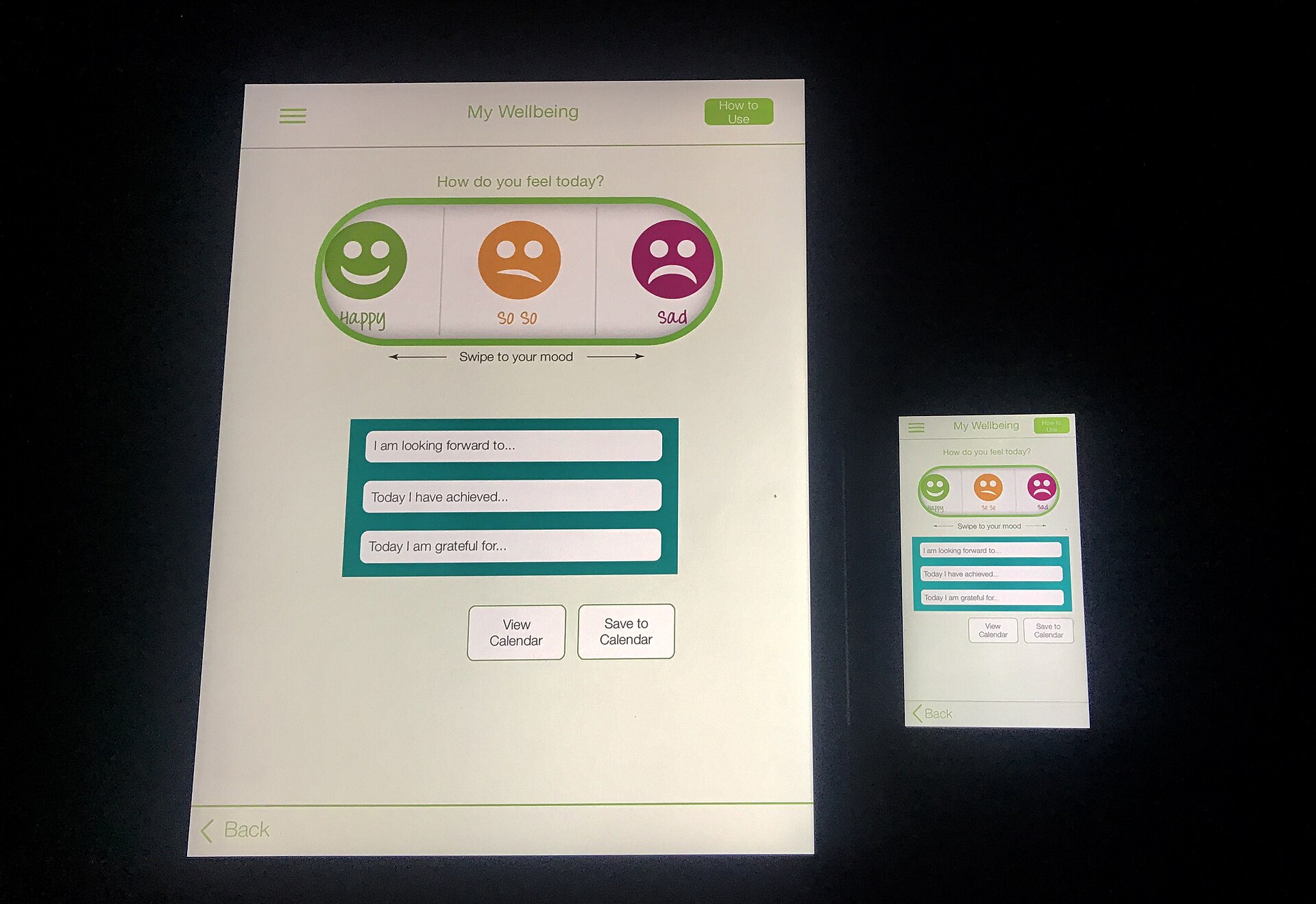 Photograph of a screen from the "Wellmind" smartphone application "Wellmind", a United Kingdom National Health Service smartphone application Digital technologies have also provided opportunities for delivery of mental health care online; benefits have been found with computerized cognitive behavioral therapy for depression and anxiety.[154] Mindfulness based online intervention has been shown to have small to moderate benefits on mental health. The greatest effect size was found for the reduction of psychological stress. Benefits were also found regarding depression, anxiety, and well-being.[155][156] The Lancet commission on global mental health and sustainability report from 2018 evaluated both benefits and harms of technology. It considered the roles of technologies in mental health, particularly in public education; patient screening; treatment; training and supervision; and system improvement.[157] A study in 2019 published in Front Psychiatry in the National Center for Biotechnology Information states that despite proliferation of many mental health apps there has been no "equivalent proliferation of scientific evidence for their effectiveness."[158] Steve Blumenfield and Jeff Levin-Scherz, writing in the Harvard Business Review, claim that "most published studies show telephonic mental health care is as effective as in-person care in treating depression, anxiety and obsessive-compulsive disorder." The also cite a 2020 study done with the Veterans Administration as evidence of this as well.[159] |
デジタルメンタルヘルスケア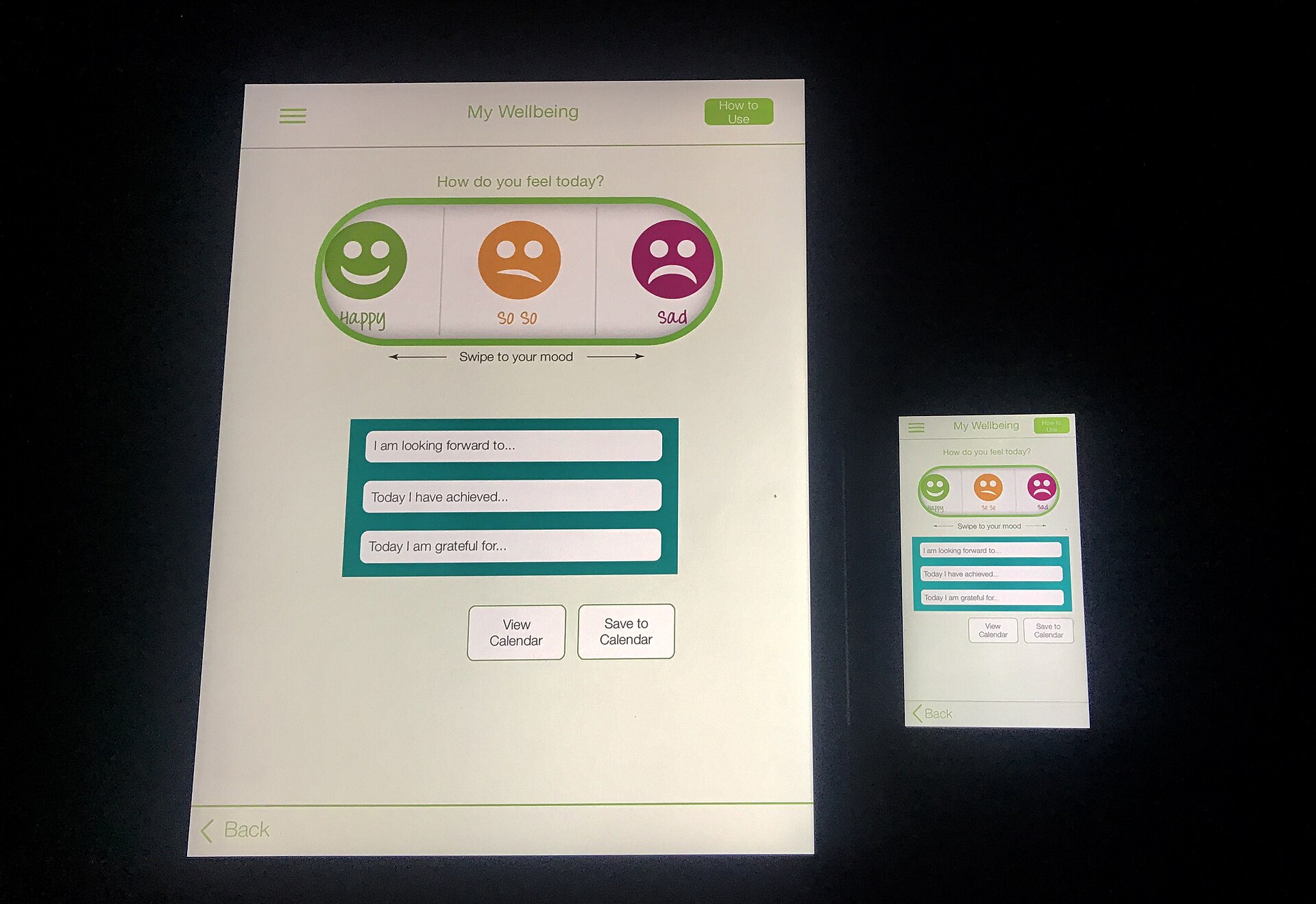 「Wellmind」スマートフォンアプリケーションの画面写真 英国国民保健サービス(NHS)のスマートフォンアプリケーション「Wellmind」 デジタル技術はオンラインでのメンタルヘルスケア提供の機会も生み出した。抑うつや不安に対するコンピューター化された認知行動療法には効果が認められて いる。[154] マインドフルネスに基づくオンライン介入は、メンタル健康に小~中程度の効果をもたらすことが示されている。心理的ストレスの軽減において最も大きな効果 サイズが認められた。うつ病、不安、幸福感に関しても有益性が確認されている。[155][156] 2018年のランセット委員会による「世界のメンタルヘルスと持続可能性に関する報告書」は、技術の有益性と有害性の両方を評価した。特に公衆教育、患者 スクリーニング、治療、研修・監督、システム改善における技術の役割を検討した。[157] 米国国立生物工学情報センター『Front Psychiatry』誌に掲載された2019年の研究によれば、多くのメンタルヘルスアプリが普及しているにもかかわらず、「その有効性を裏付ける科学 的証拠が同程度に普及しているわけではない」とされている。[158] スティーブ・ブルーメンフィールドとジェフ・レヴィン=シェルツは『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌で、「公表された研究の大半は、うつ病、不安障 害、強迫性障害の治療において、電話によるメンタルヘルスケアが対面ケアと同等の効果を持つことを示している」と主張している。彼らはまた、退役軍人省と 共同で実施された2020年の研究もこの証拠として引用している。[159] |
| Epidemiology In 1999, 58% of Finnish citizens had a mobile phone, including 75% of 15-17 year olds.[160] In 2000, a majority of U.S. households had at least one personal computer and internet access the following year.[161] In 2002, a majority of U.S. survey respondents reported having a mobile phone.[162] In September and December 2006 respectively, Luxembourg and the Netherlands became the first countries to completely transition from analog to digital television, while the United States commenced its transition in 2008. In September 2007, a majority of U.S. survey respondents reported having broadband internet at home.[163] In January 2013, a majority of U.S. survey respondents reported owning a smartphone.[164] An estimated 40% of U.S. households in 2006 owned a dedicated home video game console,[165][166] and by 2015, 51 percent of U.S. households owned a dedicated home video game console.[167][168] In April 2015, one survey of U.S. teenagers ages 13 to 17 reported that nearly three-quarters of them either owned or had access to a smartphone, and 92 percent went online daily, with 24 percent saying they went online "almost constantly."[169] In a 2024 survey, U.S. teenagers reported that 95 percent have access to smartphone, 97 percent spent time online daily, and 48 percent is spent online "almost constantly".[18] |
疫学 1999年、フィンランド国民の58%が携帯電話を所有しており、15~17歳の若年層では75%に達した。[160] 2000年には米国の世帯の大半が少なくとも1台の個人用コンピュータを所有し、翌年にはインターネット接続環境も普及した。[161] 2002年には米国の調査回答者の過半数が携帯電話を所有していると報告した。[162] 2006年9月と12月にそれぞれ、ルクセンブルクとオランダがアナログテレビからデジタルテレビへの完全移行を世界で初めて達成した。米国は2008年 に移行を開始した。2007年9月時点で、米国の調査回答者の過半数が自宅にブロードバンドインターネットを所有していると報告した。[163] 2013年1月時点で、米国の調査回答者の過半数がスマートフォンを所有していると報告した。[164] 2006年時点で、米国の世帯の約40%が専用家庭用ゲーム機を所有していた[165][166]。2015年までに、この割合は51%に上昇した [167]。[168] 2015年4月、13歳から17歳の米国ティーンエイジャーを対象としたある調査では、約4分の3がスマートフォンを所有または利用可能であり、92%が 毎日インターネットを利用し、24%が「ほぼ常に」オンライン状態であると回答した。[169] 2024年の調査では、米国の10代の若者の95%がスマートフォンを利用可能であり、97%が毎日オンラインで時間を過ごし、48%が「ほぼ常に」オン ラインで時間を過ごしていると報告された。[18] |
| Society and culture In August 2015, NeuroTribes identified autistic digital communities such as Autism Network International, Wrong Planet, and the Autism List mailing list at St. John's University (New York City).[170] Steve Silberman argued that these communities "provided a natural home" where autistic members "could interact at their own pace."[171] Jim Sinclair was a member of Autism List and participated in founding Autism Network International. |
社会と文化 2015年8月、NeuroTribesは自閉症ネットワーク・インターナショナル、Wrong Planet、セント・ジョンズ大学(ニューヨーク市)の自閉症メーリングリスト「Autism List」といった自閉症者のデジタルコミュニティを特定した。[170] スティーブ・シルバーマンは、これらのコミュニティが「自然な居場所を提供し」、自閉症のメンバーが「自分のペースで交流できる」と主張した。[171] ジム・シンクレアはAutism Listのメンバーであり、Autism Network Internationalの設立に関わった。 |
| Computer-induced medical problems Evolutionary psychiatry Screen time Social aspects of television |
コンピューターが引き起こす医学的問題 進化精神医学 インスタグラム スクリーンタイム テレビの社会的側面 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media_use_and_mental_health |
|
| Further reading Alter A (2017). Irresistible : the rise of addictive technology and the business of keeping us hooked. New York: Penguin Press. ISBN 978-0-7352-2284-7. OCLC 990286417. Bartlett V, Bowden-Jones H (2017). Are we all addicts now? : digital dependence. Beales, Katriona, MacDonald, Fiona. Liverpool: Liverpool University Press. ISBN 978-1-78694-081-0. OCLC 988053669. Young K, de Abreu CN (2017). Internet addiction in children and adolescents : risk factors, assessment, and treatment. New York: Springer Publishing Company. ISBN 978-0-8261-3373-1. OCLC 988278461. Haidt J (2024). The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness. Penguin Press. ISBN 978-0-593-65503-0. Galea S, Buckley GJ, Wojtowicz A, eds. (2024). Social Media and Adolescent Health: NASEM Consensus Study Report (Report). Washington, DC: The National Academies Press. doi:10.17226/27396. ISBN 978-0-309-71316-0. Retrieved 9 May 2024. Woods, H. C., & Scott, H. (2016). #Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self‐esteem. Journal of Adolescence, 51(1), 41–49. #Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem Jones, A., Hook, M., Podduturi, P., McKeen, H., Beitzell, E., & Liss, M. (2022). Mindfulness as a mediator in the relationship between social media engagement and depression in young adults. Personality and Individual Differences, 185. Mindfulness as a mediator in the relationship between social media engagement and depression in young adults White-Gosselin, C.-É., & Poulin, F. (2022). Associations between young adults' social media addiction, relationship quality with parents, and internalizing problems: A path analysis model. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement. Associations between young adults’ social media addiction, relationship quality with parents, and internalizing problems: A path analysis model. Hammad, M. A., & Alqarni, T. M. (2021). Psychosocial effects of social media on the Saudi society during the Coronavirus Disease 2019 pandemic: A cross-sectional study. PLoS ONE, 16(3). Psychosocial effects of social media on the Saudi society during the Coronavirus Disease 2019 pandemic: A cross-sectional study Huang, Chiungjung. “A Meta-Analysis of the Problematic Social Media Use and Mental Health.” A meta-analysis of the problematic social media use and mental health, December 9, 2020. A meta-analysis of the problematic social media use and mental health. Weigle, Paul E., and Pamela Hurst-Della Pietra. “Children and Screens: Youth Digital Media Use and Mental Health Outcomes.” Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 60, no. 10 (October 2, 2021): S297–S297. CHILDREN AND SCREENS: YOUTH DIGITAL MEDIA USE AND MENTAL HEALTH OUTCOMES. |
参考文献 Alter A (2017). 『抗えない誘惑:中毒性技術の発展と我々を依存状態に保つビジネス』. ニューヨーク: ペンギン・プレス. ISBN 978-0-7352-2284-7. OCLC 990286417. バートレット V、ボウデン=ジョーンズ H (2017). 『我々は皆中毒者か?:デジタル依存』. ビールズ カトリオナ、マクドナルド フィオナ. リバプール:リバプール大学出版局. ISBN 978-1-78694-081-0. OCLC 988053669. ヤング K、デ・アブレウ CN (2017). 『子どもと青少年のインターネット依存症:危険因子、評価、治療』. ニューヨーク: スプリンガー出版. ISBN 978-0-8261-3373-1. OCLC 988278461. ハイト J (2024). 『不安の世代:子供時代の大きな再配線が精神疾患の蔓延を引き起こしている理由』. ペンギン・プレス. ISBN 978-0-593-65503-0. ガレア S、バックリー GJ、ウォイトウィッチ A 編 (2024). ソーシャルメディアと青少年の健康:NASEMコンセンサス研究報告書(報告書)。ワシントンDC:国民学術会議出版局。doi: 10.17226/27396。ISBN 978-0-309-71316-0。2024年5月9日取得。 Woods, H. C., & Scott, H. (2016). #Sleepyteens: 青年期のソーシャルメディア利用は睡眠の質の低下、不安、抑うつ、低い自尊心と関連している。Journal of Adolescence, 51(1), 41–49. #Sleepyteens: 青年期のソーシャルメディア利用は睡眠の質の低下、不安、抑うつ、低い自尊心と関連している Jones, A., Hook, M., Podduturi, P., McKeen, H., Beitzell, E., & Liss, M. (2022). マインドフルネスが若年成人のソーシャルメディア利用とうつ病の関係における媒介変数としての役割. Personality and Individual Differences, 185. マインドフルネスが若年成人のソーシャルメディア利用とうつ病の関係における媒介変数としての役割 White-Gosselin, C.-É., & Poulin, F. (2022). 若年成人のソーシャルメディア依存、親との関係性、内向性問題の関連性:パス分析モデル. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement. 若年成人のソーシャルメディア依存、親との関係性、内向性問題の関連性:パス分析モデル. ハマド、M. A.、アルカルニ、T. M. (2021). 新型コロナウイルス感染症2019パンデミック下におけるソーシャルメディアのサウジアラビア社会への心理社会的影響:横断研究. PLoS ONE, 16(3). 新型コロナウイルス感染症2019パンデミック下におけるソーシャルメディアのサウジアラビア社会への心理社会的影響:横断研究 Huang, Chiungjung. 「問題のあるソーシャルメディア利用とメンタル健康に関するメタ分析」. 問題のあるソーシャルメディア利用とメンタル健康に関するメタ分析, 2020年12月9日. 問題のあるソーシャルメディア利用とメンタル健康に関するメタ分析. Weigle, Paul E., and Pamela Hurst-Della Pietra. 「子どもとスクリーン:青少年のデジタルメディア利用と精神的健康の結果」『米国小児・青年精神医学アカデミー誌』60巻10号(2021年10月2 日):S297–S297。子どもとスクリーン:青少年のデジタルメディア利用と精神的健康の結果。 |
★インターネット依存障害(Internet addiction disorder)
【注意】こ
の記事には複数の問題点がある。改善に協力するか、トークページで議論してほしい。(これらのメッセージを削除する方法とタイミングについてはこちらを参
照この記事は検証のため、より信頼性の高い医学的参考文献が必要であるか、一次資料に依存しすぎている。(2024年3月この記事には一般的な参考文献リ
ストが含まれているが、十分な対応する本文中の引用が欠けている。(2024年3月)
Internet addiction
disorder (IAD) is characterized by excessive or poorly controlled
preoccupations, urges, or behaviors regarding computer use and Internet
access that lead to impairment or distress.[1] Young people are at
particular risk of developing internet addiction disorder,[2] with case
studies highlighting students whose academic performance declines as
they spend more time online.[3] Some experience health consequences
from loss of sleep[4] as they stay up to continue scrolling, chatting,
and gaming.[5]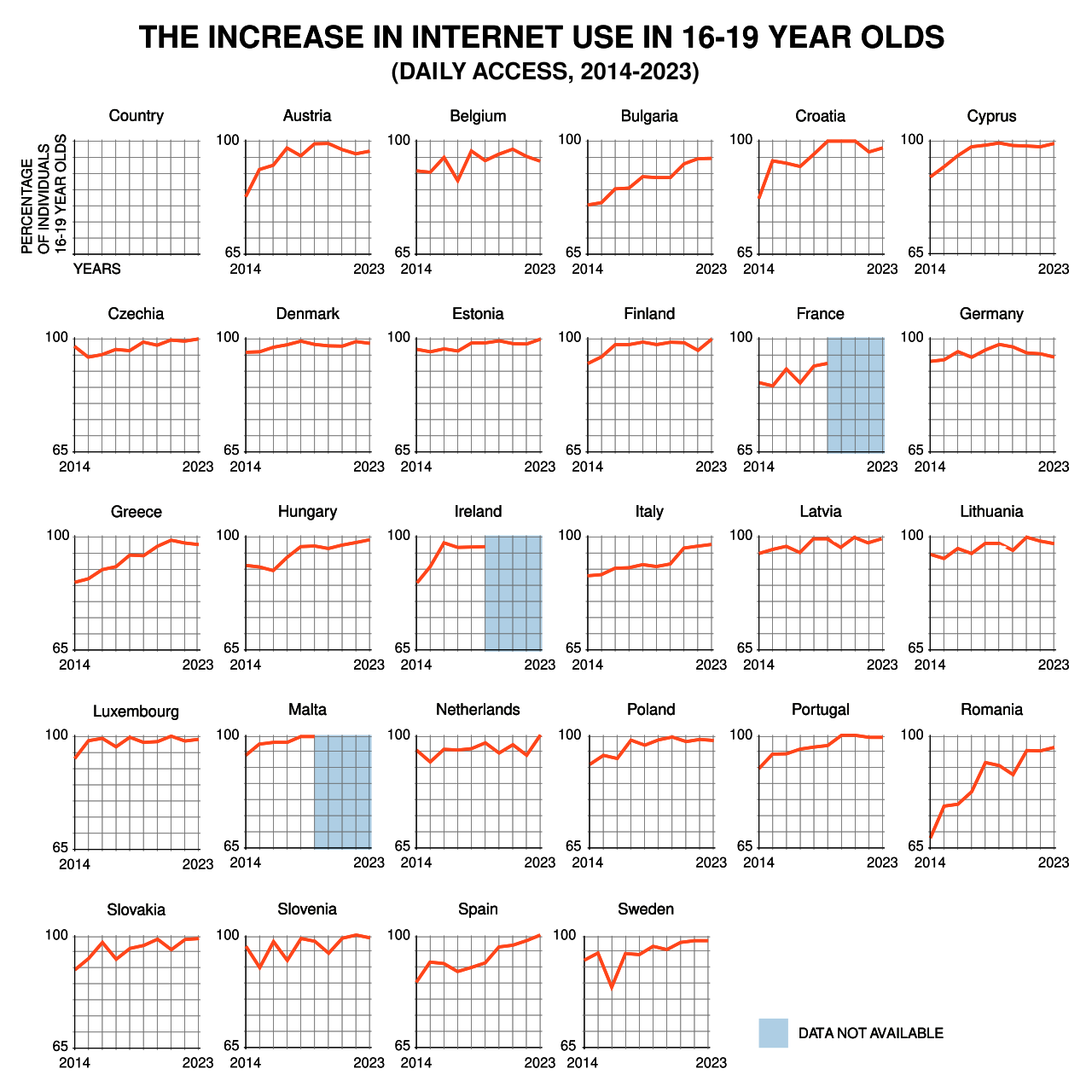 The increase in Internet access in 16-19 year olds living in EU countries Excessive Internet use is not recognized as a disorder by the American Psychiatric Association's DSM-5 or the World Health Organization's ICD-11.[6] However, gaming disorder appears in the ICD-11.[7] Controversy around the diagnosis includes whether the disorder is a separate clinical entity, or a manifestation of underlying psychiatric disorders. Definitions are not standardized or agreed upon, complicating the development of evidence-based recommendations. Many different theoretical models have been developed and employed for many years in order to better explain predisposing factors to this disorder. Models such as the cognitive-behavioral model of pathological Internet have been used to explain IAD for more than 20 years. Newer models, such as the Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution model, have been developed more recently and are starting to be applied in more clinical studies.[8] In 2011 the term "Facebook addiction disorder" (FAD) emerged.[9] FAD is characterized by compulsive use of Facebook. A 2017 study investigated a correlation between excessive use and narcissism, reporting "FAD was significantly positively related to the personality trait narcissism and to negative mental health variables (depression, anxiety, and stress symptoms)".[10][11] In 2020, the documentary The Social Dilemma, reported concerns of mental health experts and former employees of social media companies over social media's pursuit of addictive use. For example, when a user has not visited Facebook for some time, the platform varies its notifications, attempting to lure them back. It also raises concerns about the correlation between social media use and child and teen suicidality.[12] Additionally in 2020, studies have shown that there has been an increase in the prevalence of IAD since the COVID-19 pandemic.[13] Studies highlighting the possible relationship between COVID-19 and IAD have looked at how forced isolation and its associated stress may have led to higher usage levels of the Internet.[13] Turning off social media notifications may help reduce social media use.[14] For some users, changes in web browsing can be helpful in compensating for self-regulatory problems. For instance, a study involving 157 online learners on massive open online courses examined the impact of such an intervention. The study reported that providing support in self-regulation was associated with a reduction in time spent online, particularly on entertainment.[15] |
インターネット依存症(IAD)は、コンピューター使用やインターネッ
トアクセスに関する過度な、あるいは制御不能な執着、衝動、行動が特徴であり、機能障害や苦痛を引き起こす。[1]
若年層は特にインターネット依存症を発症するリスクが高く[2]、オンライン時間を増やすにつれて学業成績が低下する学生の事例が報告されている。[3]
スクロールやチャット、ゲームに没頭して夜更かしする結果、睡眠不足による健康被害を経験する者もいる。[4] [5]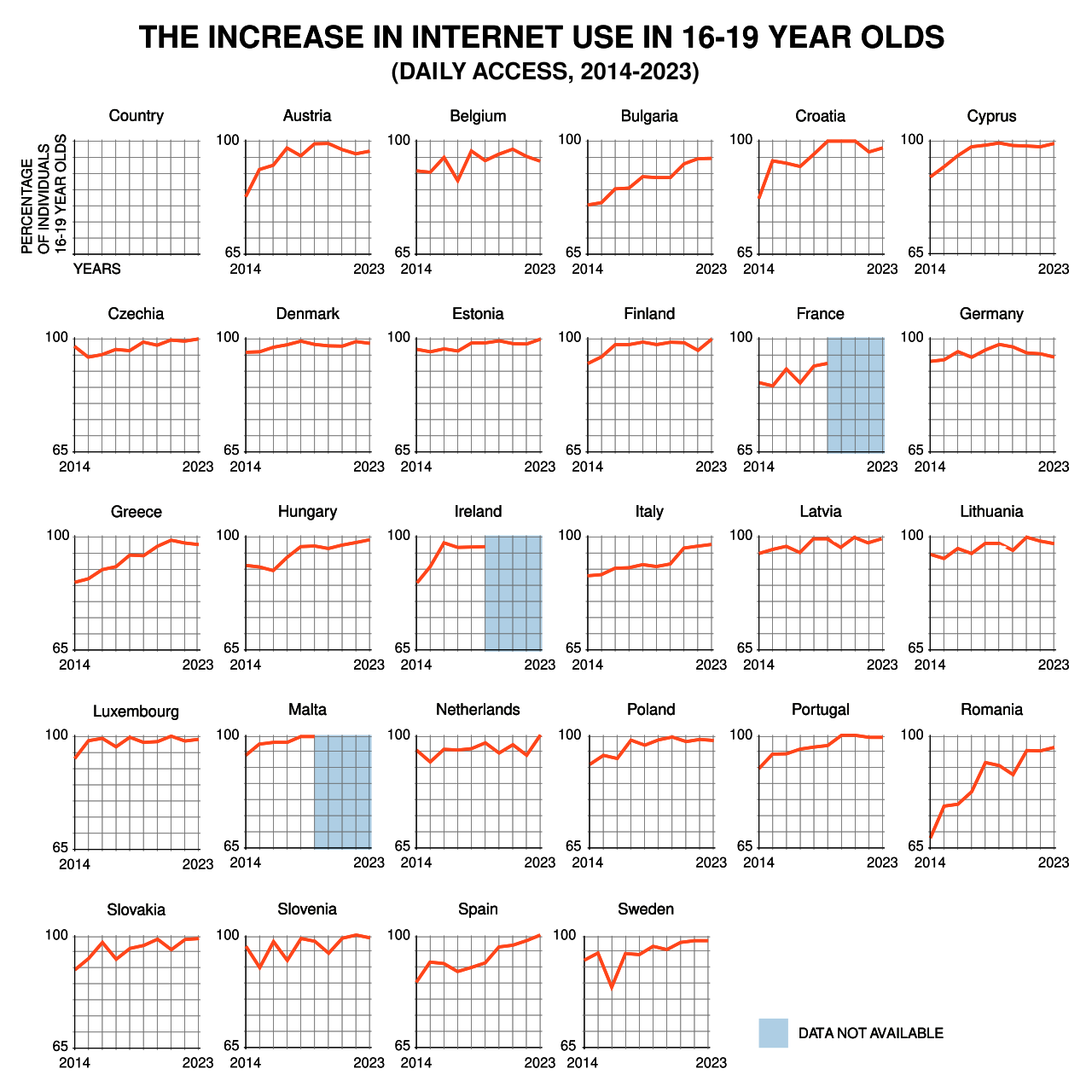 EU諸国在住の16~19歳におけるインターネット利用の増加 過剰なインターネット利用は、米国精神医学会のDSM-5や世界保健機関のICD-11では障害として認定されていない[6]。ただし、ゲーム障害は ICD-11に記載されている[7]。この診断を巡る論争には、この障害が独立した臨床的実体なのか、それとも潜在的な精神疾患の現れなのかが含まれる。 定義は標準化されておらず合意も得られていないため、エビデンスに基づく推奨事項の策定が複雑化している。 この障害の素因をよりよく説明するため、長年にわたり異なる理論モデルが開発・採用されてきた。病的なインターネット使用の認知行動モデルなどは、20年 以上も前からIADの説明に用いられてきた。近年では、PACE(Person-Affect-Cognition-Execution)相互作用モデル などの新しいモデルが開発され、より多くの臨床研究で適用され始めている。[8] 2011年には「フェイスブック依存症(FAD)」という用語が登場した。[9] FADはフェイスブックの強迫的使用を特徴とする。2017年の研究では過剰使用とナルシシズムの相関を調査し、「FADは人格特性としてのナルシシズム および精神的健康の負の変数(抑うつ、不安、ストレス症状)と有意な正の関連性があった」と報告している。[10] [11] 2020年公開のドキュメンタリー『ソーシャル・ジレンマ』は、ソーシャルメディア企業が中毒性のある利用を追求することに対する、精神保健専門家や元従 業員の懸念を報じた。例えば、ユーザーがFacebookをしばらく利用していない場合、プラットフォームは通知内容を変化させ、ユーザーを呼び戻そうと する。また、ソーシャルメディア利用と児童・青少年の自殺傾向との相関関係についても懸念を提起している。[12] さらに2020年には、COVID-19パンデミック以降、IAD(インターネット依存症)の有病率が上昇していることが研究で示された。[13] COVID-19とIADの関連性を指摘する研究では、強制的な隔離とそれに伴うストレスがインターネット利用量の増加につながった可能性を検証してい る。[13] ソーシャルメディアの通知をオフにすることは、利用頻度を減らす助けになるかもしれない。[14] 一部のユーザーにとっては、ウェブ閲覧方法の変更が自己制御の問題を補うのに有効である。例えば、大規模公開オンライン講座(MOOC)の受講者157名 を対象とした研究では、このような介入の影響が検証された。自己制御の支援を提供することが、特に娯楽目的でのオンライン利用時間の減少と関連しているこ とが報告されている。[15] |
| Consequences Mental health consequences A longitudinal study of Chinese high school students (2010) suggests that individuals with moderate to severe risk of Internet addiction are 2.5 times more likely to develop depressive symptoms than their IAD-free counterparts.[16] Researchers studied pathological or uncontrolled Internet use, and later mental health problems in 1,041 teenage students in China. The students were free of depression and anxiety at the start of the study. Nine months later, the youngsters were evaluated again for anxiety and depression, and 87 were judged as having developed depression, while 8 reported significant anxiety symptoms.[16] Another longitudinal study of high school students from Helsinki found that problematic internet usage and depressive symptoms may produce a positive feedback loop. Problematic internet usage is also associated with increased risk of substance abuse.[17] Internet Addiction Disorder (IAD) is linked to a wide range of negative psychological outcomes. Excessive or uncontrolled internet use can interfere with emotional regulation, social relationships, and cognitive functioning. The major mental health consequences include: 1. Depression and Anxiety IAD is strongly associated with increased risk of depressive symptoms, social anxiety, and generalized anxiety disorder.[18] 2. Sleep Disturbances & Fatigue Excessive internet use, especially late at night, contributes to insomnia, poor sleep quality, and daytime dysfunction.[19] 3. Stress and Emotional Dysregulation Individuals with IAD often experience higher levels of perceived stress and difficulty regulating emotions, leading to irritability and mood swings.[20] 4. Social Isolation and Loneliness Despite increased online interactions, IAD is linked to decreased face-to-face communication, loneliness, and impaired social functioning.[21] 5. Comorbid Disorders (ADHD, Substance Use, Impulse Control Problems) Research shows strong associations between IAD and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), substance abuse, and other impulse-control disorders.[22] |
結果 精神衛生上の結果 中国の高校生を対象とした縦断研究(2010年)によれば、中程度から重度のインターネット依存症リスクを持つ個人は、依存症のない同年代の若者より 2.5倍もうつ症状を発症しやすい。[16] 研究者らは中国の1041人の十代の学生を対象に、病的または制御不能なインターネット使用と、その後の精神健康上の問題を調査した。研究開始時点では、 生徒たちはうつ病や不安障害を患っていなかった。9か月後、再度不安と抑うつを評価したところ、87名がうつ病を発症したと判断され、8名が重大な不安症 状を報告した[16]。ヘルシンキの高校生を対象とした別の縦断研究では、問題のあるインターネット使用と抑うつ症状が正のフィードバックループを形成す る可能性が示された。問題のあるインターネット使用は薬物乱用のリスク増加とも関連している。[17] インターネット依存症(IAD)は、幅広い負の心理的結果と関連している。過度または制御不能なインターネット使用は、感情調節、社会的関係、認知機能に悪影響を及ぼす。主な精神的健康への影響は以下の通りだ: 1. うつと不安 IADは、抑うつ症状、社会不安、全般性不安障害のリスク増加と強く関連している。[18] 2. 睡眠障害と疲労 過度なインターネット利用、特に深夜の利用は、不眠症、睡眠の質の低下、日中の機能障害を引き起こす。[19] 3. ストレスと感情調節障害 IADを持つ個人は、しばしば高いレベルのストレスを感じ、感情を調節するのが困難で、イライラや気分の変動を招く。[20] 4. 社会的孤立と孤独感 オンライン交流が増える一方で、IADは対面コミュニケーションの減少、孤独感、社会的機能の障害と関連している。[21] 5. 併存障害(ADHD、物質使用障害、衝動制御障害) 研究によれば、IADと注意欠陥・多動性障害(ADHD)、物質乱用、その他の衝動制御障害との間に強い関連性が示されている。[22] |
| Social consequences Internet addiction increases the risk of many negative social and health outcomes, including poor academic performance, harmful personality effects, anxiety and depression.[23] The best-documented evidence of Internet addiction so far is time-disruption, which subsequently results in interference with regular social life, including academic, professional performance and daily routines.[24] Some studies also reveal that IAD can lead to disruption of social relationships in Europe and Taiwan.[25][26] It is, however, also noted by others that IAD is beneficial for peer relations in Taiwan.[27] Keith W. Beard (2005) states that "an individual is addicted when an individual's psychological state, which includes both mental and emotional states, as well as their scholastic, occupational and social interactions, is impaired by the overuse of [Internet]".[28] As a result of its complex nature, some scholars do not provide a definition of Internet addiction disorder and throughout time, different terms are used to describe the same phenomenon of excessive Internet use.[29] Internet addiction disorder is used interchangeably with problematic Internet use, pathological Internet use, and Internet addictive disorder. In some cases, this behavior is also referred to as Internet overuse, problematic computer use, compulsive Internet use, Internet abuse, harmful use of the Internet, and Internet dependency. Mustafa Savci and Ferda Aysan, reviewed existing research on internet addiction and identified a number of social and emotional factors that have been linked to this phenomenon. These include loneliness, social anxiety, depression, and low self-esteem. They argued that these factors can lead individuals to use the internet as a way of coping with negative emotions or social isolation, which can in turn lead to addictive behavior.[2] |
社会的影響 インターネット依存症は、学業成績の低下、人格への悪影響、不安や抑うつなど、多くの負の社会的・健康結果のリスクを高める。[23] 現時点で最もよく立証されているインターネット依存症の証拠は、時間の浪費である。これはその後、学業や職業上のパフォーマンス、日常の習慣を含む通常の 社会生活への干渉を引き起こす。[24] 一部の研究では、IADがヨーロッパや台湾において社会的関係の崩壊につながる可能性も示されている。[25] [26] しかし一方で、台湾ではインターネット依存症が仲間関係に有益であるという指摘もある。[27] キース・W・ビアード(2005)は「個人の心理状態(精神的・感情的状態を含む)および学業・職業・社会的相互作用が、[インターネットの]過剰使用によって損なわれる状態を依存症と定義する」と述べている。[28] その複雑な性質ゆえに、一部の学者はインターネット依存症の定義を提供せず、時代を通じて過剰なインターネット利用という同一現象を説明するために異なる 用語が用いられてきた。[29] インターネット依存症は、問題のあるインターネット利用、病的インターネット利用、インターネット中毒性障害と互換的に使用される。場合によっては、この 行動はインターネット過剰利用、問題のあるコンピューター利用、強迫的なインターネット利用、インターネット乱用、有害なインターネット利用、インター ネット依存とも呼ばれる。 ムスタファ・サヴチとフェルダ・アイサンは、インターネット依存に関する既存の研究をレビューし、この現象に関連付けられてきた数多くの社会的・感情的要 因を特定した。これには孤独感、社会不安、抑うつ、低い自尊心が含まれる。彼らは、これらの要因が個人を、負の感情や社会的孤立に対処する手段としてイン ターネットを利用させる可能性があり、それが結果として依存的行動につながることを主張した。[2] |
| Signs and symptoms Physical symptoms Physical symptoms include a weakened immune system due to lack of sleep, loss of exercise, and increased risk for carpal tunnel syndrome. Additionally, headaches, eye and back strain are common for those struggling with IAD.[30][31][32] Psychological and social symptoms The type of IAD (e.g. overuse of social media, gaming, gambling, etc.) will affect the types of symptoms experienced. For example, overuse of social media can lead to disruption in real-world relationships.[33] The overuse of video games can lead to neglecting family, home, and work-related responsibilities.[33] Additionally, the overconsumption of pornographic content can create interpersonal and relational problems and can negatively affect mental health.[33] Symptoms of withdrawal might include agitation, depression, anger and anxiety when the person is away from technology. These psychological symptoms might even turn into physical symptoms such as rapid heartbeat, tense shoulders and shortness of breath.[31] |
兆候と症状 身体的症状 身体的症状には、睡眠不足による免疫力の低下、運動不足、手根管症候群のリスク増加が含まれる。さらに、IADに悩む者には頭痛、目の疲れ、背中の痛みがよく見られる。[30][31] [32] 心理的・社会的症状 IADの種類(例:ソーシャルメディアの過剰利用、ゲーム、ギャンブルなど)によって、現れる症状の種類は異なる。例えば、ソーシャルメディアの過剰利用 は現実世界の人間関係の崩壊を招くことがある。[33] ビデオゲームの過剰利用は、家族、家庭、仕事に関する責任を怠る原因となる。[33] さらに、ポルノコンテンツの過剰消費は対人関係や人間関係の問題を引き起こし、精神健康に悪影響を及ぼす可能性がある。[33] 離脱症状には、テクノロジーから離れている際の興奮、抑うつ、怒り、不安などが含まれる。これらの心理的症状は、動悸、肩の緊張、息切れといった身体的症状に発展することさえある。[31] |
| Theoretical model Current researchers have proposed different theoretical models of IAD from different perspectives. Theories based on the characteristics of the Internet ACE model This theory suggests that addiction is caused by the characteristics of the Internet itself, including anonymity, convenience and escape, referred to as the ACE model.[34] Anonymity means that individuals are able to hide their true identity and personal information on the Internet and are thus freer to do what they want. Because of this anonymity, it is difficult to regulate what individuals do on the Internet, thus creating an Internet addiction. Convenience may be a benefit of the development of the Internet, as people can do certain things such as shopping online and watching movies without leaving their homes. However, this convenience can also lead to addiction and dependence on the Internet. Escape refers to the ability of users to find solace online when faced with difficulty or irritation, because the Internet offers a free virtual environment that entices people away from the actual world. Originally the ACE Model was used to describe Internet pornography addiction, but now it is applied to the whole field of IAD. Reduced social cues The invention of email and SMS made online chatting a reality. However, in online communication, the individual's ability to judge the mood, tone and content of the other person is reduced because the necessary social cues, such as situational and personal cues, are missing.[35] As online norms are currently imperfect, it is difficult to regulate individuals' behaviors on the Internet, and the anonymity of the Internet can make individuals' perceptions of themselves and others diminish, resulting in some anti-social behavior. Consequently, this can lead to inappropriate Internet use and addiction without proper restraints.[36] Theories based on interaction orientation Cognitive-behavioral model of pathological Internet use This model defines IAD as pathological Internet use (PIU).[37] In 2001, the cognitive-behavioral model for excessive use of the Internet was created. This model proposed that already existing psychosocial problems (e.g., depression, anxiety, substance abuse) were more likely to lead to the development of excessive and maladaptive behaviors related to the Internet.[38] Importantly, Davis categorized problematic behaviors on the Internet into two categories: specific pathological Internet use (SPIU) and generalized pathological Internet use (GPIU). SPIU behaviors include frequently accessing things such as pornography or other sexually explicit material, stock trading, and online gambling. GPIU behaviors simply include fixating on the Internet itself, rather than particular materials that are accessed through the Internet. Additionally, people engaged in GPIU behaviors are drawn by the different forms of communication that the Internet allows them to engage in.[38] In general, the Internet would lead to maladaptive cognitions, and predisposed vulnerability could reinforce this relationship. Moreover, the higher the individual's level of adaptation to undesirable behavior, the more likely pathological Internet use is to occur, which also means a higher level of addiction to the Internet. |
理論モデル 現在の研究者たちは、様々な観点からIADの異なる理論モデルを提案している。 インターネットの特性に基づく理論 ACEモデル この理論は、匿名性、利便性、逃避といったインターネット自体の特性が依存症を引き起こすと提唱している。これをACEモデルと呼ぶ。[34] 匿名性とは、個人がインターネット上で実名や個人情報を隠せるため、より自由に振る舞えることを意味する。この匿名性ゆえに、個人のインターネット上の行 動を規制することが難しく、インターネット依存症を生み出す。利便性はインターネット発展の利点であり、人々は自宅にいながらオンラインショッピングや映 画鑑賞などができる。しかしこの便利さが、逆にインターネットへの依存や中毒を招くこともある。逃避とは、困難や苛立ちに直面したユーザーがオンライン上 で慰めを見出せる能力を指す。インターネットは現実世界から人民を引き離す魅力的な仮想環境を提供するためだ。もともとACEモデルはインターネットポル ノ依存症の説明に使われたが、現在ではインターネット依存症(IAD)の全領域に適用されている。 社会的合図の減少 電子メールとSMSの発明により、オンラインチャットが現実のものとなった。しかしオンラインコミュニケーションでは、状況や個人に関する合図といった必 要な社会的合図が欠如しているため、個人が相手の気分や口調、内容を判断する能力が低下する。[35] 現在のオンライン規範は不完全であるため、インターネット上での個人行動を規制するのは困難だ。インターネットの匿名性は、自己や他者に対する認識を低下 させ、反社会的行動を引き起こす可能性がある。結果として、適切な抑制なしに不適切なインターネット利用や依存症につながる。[36] 相互作用指向に基づく理論 病的なインターネット使用の認知行動モデル このモデルは、IAD を病的なインターネット使用(PIU)と定義している。[37] 2001 年、インターネットの過剰使用に関する認知行動モデルが作成された。このモデルは、既存の心理社会的問題(うつ病、不安、薬物乱用など)が、インターネッ トに関連する過剰かつ不適応な行動の発達につながる可能性が高いと提唱した。[38] 重要なことに、デイヴィスはインターネット上の問題行動を 2 つのカテゴリーに分類した。すなわち、特定の病的なインターネット使用(SPIU)と、一般的な病的なインターネット使用(GPIU)である。SPIU の行動には、ポルノやその他の露骨な性的素材、株式取引、オンラインギャンブルなどの頻繁なアクセスが含まれる。GPIU の行動には、インターネットを通じてアクセスする特定の素材ではなく、インターネットそのものに固執することが含まれる。さらに、GPIU 行動に従事する人民は、インターネットによって可能になる異なる形態のコミュニケーションに惹かれている。[38] 一般的に、インターネットは不適応な認知につながり、その傾向のある脆弱性がこの関係を強化する可能性がある。 さらに、望ましくない行動への適応レベルが高い個人ほど、病的なインターネット利用が発生する可能性が高く、それはインターネットへの依存度が高いことも意味する。 |
| I-PACE Model This is an integrative theoretical framework model that specifically focuses on Internet Gaming Disorder (IGD). As compulsive gaming on the Internet can be a constituting factor of Internet Addiction Disorder, this model can be seen as applicable. The I-PACE model, which stands for Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution model, focuses on the process of predisposing factors and current behaviors leading to compulsive use of the Internet.[8] This model considers pre-disposing factors such as early childhood experiences, personality, cognitive-situational reactions, social cognition, and pre-disposition to mental illness as factors that may play into the development of Internet Gaming Disorder.[8] Game addiction and flow experience The flow experience is an emotional experience in which an individual shows a strong interest in an event or object that drives the individual to become fully engaged in it.[39] It was first introduced by Csikszentmihalyi in the 1960s, and he also proposed a systematic model of the flow experience. According to his theory, the flow experience comes from performing challenges at a level similar to the individual's own, which means that people could fully commit to the challenge and do their best to complete it. When individuals are faced with a challenge that is too different from their own level, they may lose interest because it is too easy or too difficult. Online games are a real-life application of this model. Based on Csikszentmihalyi's theory, the theory called GameFlow[40] suggests 8 characteristics that can create a sense of immersion in players: concentration, challenge, skills, control, clear goals, feedback, immersion, and social interaction. With these elements, games would be really addictive and result in Internet addiction.[7] |
I-PACEモデル これはインターネットゲーム障害(IGD)に特化した統合的理論枠組みモデルである。インターネット上での強迫的ゲーム行為はインターネット依存症の構成 要素となり得るため、本モデルは適用可能と見なせる。I-PACEモデル(Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution model)は、インターネットの強制的使用に至る素因と現在の行動の過程に焦点を当てる[8]。このモデルは、幼児期の経験、性格、認知的状況反応、社 会的認知、精神疾患への素因といった素因を、インターネットゲーム障害の発症に関与し得る要因として考慮する。[8] ゲーム依存とフロー体験 フロー体験とは、個人が特定の事象や対象に強い関心を示し、それに完全に没頭する状態を指す感情的体験である。[39] 1960年代にチクセントミハイによって初めて提唱され、彼はフロー体験の体系的なモデルも提案した。彼の理論によれば、フロー体験は個人の能力レベルに 近い挑戦を行うことで生じる。つまり、人は挑戦に完全に没頭し、最善を尽くしてそれを達成できるのだ。個人の能力レベルと異なる挑戦に直面すると、簡単す ぎるか難しすぎるため興味を失う可能性がある。オンラインゲームはこのモデルの現実応用例だ。チクセントミハイの理論に基づき、GameFlow[40] と呼ばれる理論は、プレイヤーに没入感を生み出す8つの特徴を提唱している:集中力、挑戦、スキル、制御感、明確な目標、フィードバック、没入感、社会的 交流である。これらの要素が揃うと、ゲームは中毒性が高く、インターネット依存症を引き起こすことになる[7]。 |
| Theories based on development orientation The word "development" has two meanings in this context; both the process and stages of development of Internet addictive behavior, and the development of the individual throughout the life cycle. John Grohol's 3-stage model The 3-stage model proposed by John Grohol suggests that Internet users would go through three stages:[41] Enchantment: This stage serves as the introduction to the Internet. Oftentimes, scholars will describe this phase as an obsession.[42] The Internet fascinates those new to it. In the first stage, users might be excited and curious about the Internet, leading to an increase in the amount of time spent on the Internet. Users start avoiding something addictive. After devoting a long time to using the Internet, individuals might realize that they should not spend too much time on the Internet, so they may reject games or websites that might be addictive. Disillusionment: Users start avoiding something addictive. After devoting a long time to using the Internet, individuals might realize that they should not spend too much time on the Internet, so they may reject games or websites that might be addictive. This leads to a decline in the amount of usage.[42] Balance: Users regulate time spent using the Internet and achieve a balance between surfing and other activities.[42] In the last stage, people might be able to manage their time online well and develop healthy online habits. John suggested that the reason why many people were addicted to the Internet was that they were struggling with the first stage and needed help. Furthermore, he suggested in this model that everyone would eventually reach stage three. However, the amount of time it took to reach this point depended on the individual. |
発達志向に基づく理論 ここで「発達」という言葉は二つの意味を持つ。インターネット依存行動の発達過程と段階、そして生涯にわたる個人の発達である。 ジョン・グローホールの3段階モデル ジョン・グローホールが提唱した3段階モデルは、インターネット利用者が三つの段階を経ると示唆している[41]: 魅了期:この段階はインターネットへの導入となる。多くの研究者はこの段階を「執着」と表現する[42]。インターネットは新規利用者を魅了する。第一段 階では、利用者はインターネットに興奮と好奇心を抱き、インターネット利用時間の増加につながる。第二段階:中毒回避。長時間インターネットを利用した 後、個人はインターネットに過度に時間を費やすべきではないと気づき、中毒性のあるゲームやウェブサイトを避けるようになる。 幻滅期:ユーザーは中毒性のあるものを避けるようになる。インターネットに長時間没頭した後、個人がインターネットに過度に時間を費やすべきではないと気づき、中毒性のあるゲームやウェブサイトを拒絶するようになる。これにより利用時間は減少する。[42] 均衡期:ユーザーはインターネット利用時間を調整し、ネットサーフィンと他の活動とのバランスを取るようになる。[42] 最終段階では、人民はオンライン時間をうまく管理し、健全なネット習慣を身につけられるようになる。 ジョンは、多くの人がインターネットに依存するのは第一段階で苦戦し、支援が必要だからだと指摘した。さらにこのモデルでは、最終的に全員が第三段階に到達すると示唆している。ただし、この段階に到達するまでの時間は個人差がある。 |
| Effects of COVID-19 A study conducted by Nassim Masaeli and Hadi Farhadi found that the prevalence of internet-based addictive behaviors during the COVID-19 pandemic increased compared to pre-pandemic levels. Specifically, the prevalence of IAD ranged from 4.7% to 51.6%, SMA ranged from 9.7% to 47.4%, and gaming addiction ranged from 4.4% to 32.4%. The authors also identified several risk factors that contribute to the development of internet-based addictive behaviors during the pandemic, including boredom, stress, anxiety, and social isolation. They also highlighted the importance of interventions to prevent and treat internet-based addictive behaviors during the pandemic. These interventions can include psychological therapies, educational interventions, and pharmacological treatments. The authors recommended that these interventions should be tailored to specific age groups and populations to maximize their effectiveness.[43] Another study that looked further into the effect of COVID-19 on the prevalence of IAD was "Internet Addiction Increases in the General Population During COVID‐19".[44] The study looked at how the likely increase in stress related to COVID-19 induced quarantine contributed to an increase in IAD among the Chinese population. The study was conducted among 20,472 participants who were asked to fill out the Internet Addiction Test (IAT) online. The study ultimately shows that the overall prevalence of Internet addiction amounted to 36.7% among the general, and according to IAT scores the level of severe Internet addiction was 2.8%. The conclusion drawn was that the pandemic increased the prevalence and severity of Internet addiction among the general population in China. |
COVID-19の影響(→「コロナ・パンデミックとインターネット依存症」) ナッシム・マサエリとハディ・ファルハディによる研究では、COVID-19パンデミック期間中のインターネット依存行動の有病率が、パンデミック前と比 較して増加したことが明らかになった。具体的には、インターネット依存症(IAD)の有病率は4.7%から51.6%、ソーシャルメディア依存症 (SMA)は9.7%から47.4%、ゲーム依存症は4.4%から32.4%の範囲であった。著者らはまた、パンデミック中にインターネット依存症の発症 に寄与する複数の危険因子を特定した。これには退屈、ストレス、不安、社会的孤立が含まれる。さらにパンデミック中のインターネット依存症予防・治療介入 の重要性を強調した。これらの介入には心理療法、教育的介入、薬物療法が含まれる。著者らは効果を最大化するため、特定の年齢層や集団に合わせた介入を推 奨した。[43] COVID-19がインターネット依存症(IAD)の有病率に与える影響をさらに調査した別の研究として、「COVID-19期間中の一般人口におけるイ ンターネット依存症の増加」がある。[44] この研究は、COVID-19関連の隔離措置に伴うストレスの増加が、中国人口におけるIADの増加にどのように寄与したかを検討した。調査は 20,472名の参加者を対象に実施され、オンラインでインターネット依存症テスト(IAT)への回答を求めた。結果として、一般人口におけるインター ネット依存症の全体的な有病率は36.7%に達し、IATスコアに基づく重度のインターネット依存症のレベルは2.8%であった。結論として、パンデミッ クは中国一般人口におけるインターネット依存症の有病率と重症度を増加させたとされた。 |
| Related disorders Problem gambling (online gambling disorder) Main article: Problem gambling Risks to gamblers and their families of problematic gambling have increased with the advent of online gambling.[45] This is particularly true for minors.[46] Video game addiction Main article: Video game addiction See also: ICD-11 § Gaming disorder Video game addiction (VGA), also known as gaming disorder or internet gaming disorder, is generally defined as a psychological addiction that is problematic, compulsive use of video games that results in significant impairment to an individual's ability to function in various life domains over a prolonged period of time. Internet sex addiction Main article: Internet sex addiction Internet sex addiction, also known as cybersex addiction, has been proposed as a sexual addiction characterized by virtual Internet sexual activity that causes serious negative consequences to one's physical, mental, social, and financial well-being.[47][48] Compulsive talking (communication addiction disorder) Main article: Compulsive talking Communication addiction disorder (CAD) is a supposed behavioral disorder related to the necessity of being in constant communication with other people, even when there is no practical necessity for such communication. CAD has been linked to Internet addiction.[49] Users become addicted to the social elements of the Internet, such as Facebook and YouTube. Users become addicted to one-on-one or group communication in the form of social support, relationships, and entertainment. However, interference with these activities can result in conflict and guilt. This kind of addiction is called problematic social media use. Social network addiction is a dependence of people by connection, updating, and control of their and their friend's social network page.[50] For some people, in fact, the only important thing is to have a lot of friends in the network regardless if they are offline or only virtual; this is particularly true for teenagers as a reinforcement of egos.[51][52] Sometimes teenagers use social networks to show their idealized image to others.[53] However, other studies claim that people are using social networks to communicate their real personality and not to promote their idealized identity.[54] Compulsive VR use Compulsive VR use (colloquially virtual-reality addiction) is a compulsion to use virtual reality or virtual, immersive environments. Currently, interactive virtual media (such as social networks) are referred to as virtual reality,[55] whereas future virtual reality refers to computer-simulated, immersive environments or worlds. Experts warn about the dangers of virtual reality,[56] and compare the use of virtual reality (both in its current and future form) to the use of drugs, bringing with these comparisons the concern that, like drugs, users could possibly become addicted to virtual reality.[56] Video streaming addiction Video streaming addiction is an addiction to watching online video content, such as those accessed through free online video sharing sites such as YouTube, subscription streaming services such as Netflix, as well as livestreaming sites such as Twitch. The social nature of the internet has a reinforcing effect on the individual's consumption habits, as well as normalizing binge-watching behavior for enthusiasts of particular television series.[57][58][59] |
関連する障害 問題ギャンブル(オンラインギャンブル障害) 詳細記事: 問題ギャンブル オンラインギャンブルの出現により、問題のあるギャンブルがギャンブラーとその家族に及ぼすリスクは増大している。[45] これは特に未成年者に当てはまる。[46] ビデオゲーム依存症 メイン記事: ビデオゲーム依存症 関連項目: ICD-11 § ゲーム障害 ビデオゲーム依存症(VGA)は、ゲーム障害またはインターネットゲーム障害とも呼ばれ、一般的に心理的依存症と定義される。これは問題のある強迫的なビデオゲームの使用であり、長期間にわたり個人の様々な生活領域における機能能力に重大な障害をもたらす。 インターネット性依存症 メイン記事:インターネット性依存症 インターネット性依存症(サイバーセックス依存症とも呼ばれる)は、身体的・精神的・社会的・経済的健康に深刻な悪影響を及ぼす仮想インターネット性行為を特徴とする性的依存症として提唱されている。[47][48] 強迫的会話(コミュニケーション依存症) 主な記事:強迫的会話 コミュニケーション依存症(CAD)とは、実質的な必要性がない場合でも他の人々との絶え間ないコミュニケーションを必要とする行動障害とされる。CAD はインターネット依存症と関連付けられている。[49] ユーザーはFacebookやYouTubeといったインターネットの社会的要素に依存するようになる。ユーザーは社会的支援、人間関係、娯楽といった形 態の1対1または集団コミュニケーションに依存するようになる。しかし、これらの活動が妨げられると、葛藤や罪悪感が生じる。この種の依存は問題のある ソーシャルメディア利用と呼ばれる。 ソーシャルネットワーク依存症とは、人々が自分や友人のソーシャルネットワークページへの接続、更新、管理に依存する状態である。[50] 実際、一部の人々にとって重要なのは、オフラインか仮想かを問わず、ネットワーク上に多くの友人がいることだけだ。これは特に、自己肯定感を強化する手段 として、十代の若者に顕著である。[51][52] 時に十代はソーシャルネットワークを、理想化された自己像を他者に示すために利用する。[53] しかし他の研究では、人民は理想化されたアイデンティティを宣伝するためではなく、現実の性格を伝えるためにソーシャルネットワークを利用していると主張 している。[54] 強迫的なVR利用 強迫的なVR利用(俗に仮想現実依存症)とは、仮想現実や没入型仮想環境を利用したいという強迫観念である。現在、ソーシャルネットワークなどのインタラ クティブな仮想メディアは仮想現実と呼ばれている[55]。一方、将来の仮想現実とは、コンピューターでシミュレートされた没入型環境や世界を指す。専門 家は仮想現実の危険性について警告し[56]、現在の形態と将来の形態の両方における仮想現実の使用を薬物使用と比較している。この比較から、薬物と同様 にユーザーが仮想現実に依存する可能性があるという懸念が生まれている[56]。 動画ストリーミング依存症 動画ストリーミング依存症とは、YouTubeのような無料動画共有サイト、Netflixのような有料ストリーミングサービス、Twitchのようなラ イブ配信サイトを通じてアクセスされるオンライン動画コンテンツを視聴することへの依存を指す。インターネットの社会的性質は個人の消費習慣を強化する効 果を持ち、特定のテレビシリーズ愛好家にとって一気見行為を正常化する。[57][58][59]s |
| Risk factors Interpersonal difficulties It is argued that interpersonal difficulties such as introversion, social problems,[60] and poor face-to-face communication skills[61] often lead to internet addiction. Internet-based relationships offer a safe alternative for people with aforementioned difficulties to escape from the potential rejections and anxieties of interpersonal real-life contact.[62] Social factors Individuals who lack sufficient social connection and social support are found to run a higher risk of Internet addiction. They resort to virtual relationships and support to alleviate their loneliness.[63][64] As a matter of fact, the most prevalent applications among Internet addicts are chat rooms, interactive games, instant messaging, or social media.[62] Some empirical studies reveal that conflict between parents and children and not living with a mother significantly associated with IA after one year.[65] Protective factors such as quality communication between parents and children[66] and positive youth development[67] are demonstrated, in turn, to reduce the risk of IA. Psychological factors Prior addictive or psychiatric history are found to influence the likelihood of being addicted to the Internet.[65][68] Some individuals with prior psychiatric problems such as depression and anxiety turn to compulsive behaviors to avoid the unpleasant emotions and situation of their psychiatric problems and regard being addicted to the Internet a safer alternative to substance addictive tendency. But it is generally unclear from existing research which is the cause and which is the effect partially due to the fact that comorbidity is common among Internet addicts. The most common co-morbidities that have been linked to IAD are major depression and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The rate of ADHD and IAD associating is as high as 51.6%.[69] Symptoms of ADHD are positively correlated with symptoms of IAD.[70] Internet addicts with no previous significant addictive or psychiatric history are argued to develop an addiction to some of the features of Internet use: anonymity, easy accessibility, and its interactive nature.[62] Neurobiological factors Like most other psychopathological conditions, Internet addiction belongs to the group of multifactorial polygenic disorders. For each specific case, there is a unique combination of inherited characteristics (nervous tissue structure, secretion, degradation, and reception of neuromediators), and many are extra-environment factors (family-related, social, and ethnic-cultural). One of the main challenges in the development of the bio-psychosocial model of Internet addiction is to determine which genes and neuromediators are responsible for increased addiction susceptibility.[71] A study conducted by Aviv Weinstein and Michel Lejoyeux (2020) titled "Neurobiological mechanisms underlying internet gaming disorder" highlights that IGD is associated with alterations in brain regions involved in reward processing, impulse control, decision-making, and executive functioning. These changes in neural activity may result in the persistent and excessive use of internet gaming and may contribute to the development of IGD. The study also highlights the role of neurotransmitters, such as dopamine, in the reinforcement and reward-seeking behavior associated with IGD. They suggest that the neurobiological mechanisms involved in IGD are similar to those observed in substance use disorders, and they propose a framework for understanding IGD as a behavioral addiction. The authors also discuss the potential implications of these findings for the treatment of IGD, suggesting that interventions targeting the neurobiological mechanisms underlying IGD may be effective in reducing problematic internet gaming behaviors.[5] Other factors Parental educational level, age at first use of the Internet, and the frequency of using social networking sites and gaming sites are found to be positively associated with excessive Internet use among adolescents in some European countries, as well as in the USA.[25][72] |
危険因子 対人関係の困難 内向性、社会的問題[60]、対面コミュニケーション能力の低さ[61]といった対人関係の困難が、しばしばインターネット依存症につながるという主張が ある。インターネット上の関係は、こうした困難を抱える人民にとって、現実の対人接触に伴う拒絶や不安から逃れる安全な代替手段となる。[62] 社会的要因 十分な社会的つながりや社会的支援を欠く個人は、インターネット依存症のリスクが高いことが判明している。彼らは孤独感を和らげるために仮想的な関係や支 援に頼るのである。[63][64] 実際、インターネット依存症者に最も普及しているアプリケーションは、チャットルーム、インタラクティブゲーム、インスタントメッセージング、ソーシャル メディアである。[62] 実証研究によれば、親子間の葛藤や母親と同居していない状態は、1年後のインターネット依存症(IA)と有意に関連している。[65] 一方、親子間の質の高いコミュニケーション[66] や青少年の健全な発達[67] といった保護的要因は、IAのリスクを低減することが示されている。 心理的要因 過去の依存症や精神疾患の病歴は、インターネット依存症になる可能性に影響を与えることが判明している。[65] [68] 抑うつや不安などの精神疾患歴を持つ個人の中には、精神疾患に伴う不快な感情や状況を回避するため強迫的行動に走り、物質依存傾向よりも安全な代替手段と してインターネット依存を捉える者もいる。しかし、インターネット依存症患者に併存症が頻発する事実もあり、既存研究では一般的に因果関係が不明確であ る。 IADと関連付けられる最も一般的な併存疾患は、大うつ病と注意欠陥・多動性障害(ADHD)である。ADHDとIADの併発率は51.6%にも達する。[69] ADHDの症状はIADの症状と正の相関関係にある。[70] これまでに重大な依存症や精神疾患の病歴がないインターネット依存症患者は、インターネット利用の特徴である匿名性、容易なアクセス性、双方向性といった要素に依存症を発症するとされる。[62] 神経生物学的要因 他の多くの精神病理学的状態と同様に、インターネット依存症は多因子性多遺伝子疾患のグループに属する。個々の症例には、遺伝的特性(神経組織構造、神経 伝達物質の分泌・分解・受容)と環境外的要因(家族関係、社会環境、民族文化)が独自に組み合わさっている。インターネット依存症の生物心理社会的モデル 構築における主要課題の一つは、依存症感受性増大に関与する遺伝子と神経伝達物質を特定することである。[71] Aviv WeinsteinとMichel Lejoyeux(2020)による「インターネットゲーム障害の神経生物学的メカニズム」と題された研究は、IGDが報酬処理、衝動制御、意思決定、実 行機能に関与する脳領域の変化と関連していることを強調している。こうした神経活動の変化は、インターネットゲームの持続的かつ過剰な使用をもたらし、 IGDの発症に寄与する可能性がある。本研究はまた、IGDに関連する強化と報酬追求行動におけるドーパミンなどの神経伝達物質の役割を強調している。著 者らは、IGDに関与する神経生物学的メカニズムが物質使用障害で観察されるものと類似していると示唆し、IGDを行動依存症として理解するための枠組み を提案している。著者らはさらに、これらの知見がIGD治療に与える潜在的な示唆について論じている。IGDの根底にある神経生物学的メカニズムを標的と した介入が、問題のあるインターネットゲーム行動の軽減に有効である可能性を示唆している。[5] その他の要因 親の学歴、インターネット初使用年齢、ソーシャルネットワーキングサイトやゲームサイトの利用頻度は、米国だけでなく一部の欧州諸国においても、青少年の過剰なインターネット利用と正の相関関係にあることが判明している。[25][72] |
| Identification Identifying Internet addiction disorder is empirically difficult. Various screening instruments have been employed to detect Internet addiction disorder. Initial indicators A study conducted by Lori C. Soule, L. Wayne Shell, and Betty A. Kleen (2003) titled "Exploring Internet Addiction: Demographic Characteristics and Stereotypes of Heavy Internet Users" found that heavy internet users were more likely to be male and younger than non-heavy users. The study also found that heavy internet users were more likely to use the internet for gaming and entertainment purposes, rather than for work or education. It also went on further to suggest that heavy internet use may be related to certain personality traits, such as sensation-seeking and impulsivity, and highlight the need for further research to better understand the psychological factors that contribute to internet addiction. The study also highlights the need for interventions that target specific groups, such as young males who are heavy internet users, and that address the underlying factors that contribute to problematic internet use behaviors.[17] Difficulties with diagnosis Given the newness of the Internet and the inconsistent definition of Internet addiction disorder, practical diagnosis is far from clear-cut. With the first research initiated by Kimberly S. Young in 1996, the scientific study of Internet addiction has merely existed for more than 20 years.[73] A few obstacles are present in creating an applicable diagnostic method for Internet addiction disorder. Wide and extensive use of the Internet: Diagnosing Internet addiction is often more complex than substance addiction as internet use has largely evolved into being an integral or necessary part of human lives. The addictive or problematic use of the internet is thus easily masked or justified.[62] Also, the Internet is largely a pro-social, interactive, and information-driven medium, while other established addiction behaviors such as gambling are often seen as a single, antisocial behavior that has very little socially redeeming value. Many so-called Internet addicts do not experience the same damage to health and relationships that are common to established addictions.[74] High comorbidity: Internet addiction is often accompanied by other psychiatric disorders such as personality disorder and intellectual disability.[62][75][76][77][78] It is found that Internet addiction is accompanied by another DSM-IV diagnosis 86% of the time.[79] In one study conducted in South Korea, 30% of the identified Internet addicts have accompanying symptoms such as anxiety or depression and another 30% have a second disorder such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).[80] Another study in South Korea found an average of 1.5 other diagnoses among adolescent internet addicts.[79] Further, it is noted in the United States that many patients only resort to medical help when experiencing difficulties they attribute to other disorders.[62][79] For many individuals, overuse or inappropriate use of the Internet is a manifestation of their depression, social anxiety disorders, impulse control disorders, or pathological gambling.[81] It generally remains unclear from existing literature whether other psychiatric disorders is the cause or manifest of Internet addiction. Despite the advocacy of categorizing Internet addiction as an established illness,[79][82] neither DSM-IV (1995) nor DSM-5 (2013) considers Internet addiction as a mental disorder.[83] A subcategory of IAD, Internet gaming disorder is listed in DSM-5 as a condition that requires more research in order to be considered as a full disorder in May 2013.[83][84][85] The WHO's International Classification of Diseases (ICD-11) recognizes gaming disorder as an illness category.[86]: 174 There is still considerable controversy over whether IAD should be included in the DSM-5 and recognized as a mental disease in general.[87] |
識別 インターネット依存症の識別は経験的に困難である。様々なスクリーニング手法がインターネット依存症の検出に用いられてきた。 初期指標 ロリ・C・ソウル、L・ウェイン・シェル、ベティ・A・クリーン(2003)による「インターネット依存症の探求:ヘビーユーザーのデモグラフィック特性 とステレオタイプ」と題された研究では、ヘビーユーザーは非ヘビーユーザーに比べて男性であり、若年層である可能性が高いことが判明した。また、ヘビー ユーザーは仕事や教育目的よりも、ゲームや娯楽目的でインターネットを利用する傾向が強いことも明らかになった。さらに、インターネットの多用は刺激追求 や衝動性といった特定の人格特性と関連している可能性を示唆し、インターネット依存症に寄与する心理的要因をより深く理解するためのさらなる研究の必要性 を強調した。本研究はまた、若年男性といった特定のグループを対象とし、問題のあるインターネット使用行動に寄与する根本的要因に対処する介入策の必要性 を指摘している。[17] 診断の難しさ インターネットの出現が比較的新しいこと、またインターネット依存症の定義が統一されていないことから、実用的な診断は明確とは言い難い。キンバリー・ S・ヤングによる1996年の最初の研究以来、インターネット依存症の科学的研究はわずか20年余りの歴史しかない。[73] インターネット依存症の診断法確立にはいくつかの障壁が存在する。 インターネットの広範かつ日常的な利用:インターネット依存症の診断は、物質依存症よりも複雑になりがちだ。インターネット利用は、人間の生活に不可欠な 要素として大きく進化してきたからだ。したがって、インターネットの依存的・問題的利用は容易に隠蔽されたり正当化されたりする。[62] また、インターネットは主に社会的な相互作用や情報伝達を目的とした媒体であるのに対し、ギャンブルなどの確立された依存行動は、社会的価値がほとんどな い反社会的な単独行動と見なされることが多い。いわゆるインターネット依存症の多くは、確立された依存症に共通する健康や人間関係への悪影響を経験してい ない。[74] 高い併存率:インターネット依存症は、人格障害や知的障害などの他の精神疾患を伴うことが多い。[62][75][76][77][78] インターネット依存症は、86%の確率で他のDSM-IV診断を併発することが判明している。[79] 韓国で行われたある研究では、特定されたインターネット依存症患者の30%が不安や抑うつなどの併存症状を示し、さらに30%が注意欠陥・多動性障害 (ADHD)などの二次障害を有していた。[80] 韓国の別の研究では、思春期のインターネット依存症患者に平均1.5件の他の診断が認められた。[79] さらに米国では、多くの患者が他の障害に起因すると考える困難を経験した際に初めて医療支援を求めることが指摘されている。[62][79] 多くの個人にとって、インターネットの過剰使用や不適切な使用は、うつ病、社会不安障害、衝動制御障害、病的賭博などの表れである。[81] 既存の文献からは、他の精神障害がインターネット依存症の原因なのか、それともその表れなのかは概ね不明のままである。 インターネット依存症を確立された疾患として分類すべきとの主張があるにもかかわらず[79][82]、DSM-IV(1995年)もDSM-5 (2013年)もインターネット依存症を精神障害とは見なしていない[83]。IADのサブカテゴリーであるインターネットゲーム障害は、2013年5月 時点でDSM-5に「完全な障害として認定するにはさらなる研究が必要な状態」として記載されている。[83][84][85] WHOの国際疾病分類(ICD-11)はゲーム障害を疾病カテゴリーとして認めている。[86]: 174 IADをDSM-5に含め、一般的な精神疾患として認めるべきかについては、依然として大きな論争がある。[87] |
| Screening instruments DSM-based instruments Most of the criteria utilized by research are adaptations of listed mental disorders (e.g., pathological gambling) in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) handbook.[29] Ivan K. Goldberg, who first broached the concept of Internet addiction in 1995, adopted a few criteria for IAD on the basis of DSM-IV, including "hoping to increase time on the network" and "dreaming about the network."[88][29] By adapting the DSM-IV criteria for pathological gambling, Kimberly S. Young in 1998 proposed one of the first integrated sets of criteria, Diagnostic Questionnaire (YDQ), to detect Internet addiction. A person who fulfills any five of the eight adapted criteria would be regarded as Internet addicted:[89][90] 1. Preoccupation with the Internet; 2. A need for increased time spent online to achieve the same amount of satisfaction; 3. Repeated efforts to curtail Internet use; 4. Irritability, depression, or mood liability when Internet use is limited; 5. Staying online longer than anticipated; 6. Putting a job or relationship in jeopardy to use the Internet; 7. Lying to others about how much time is spent online; and 8. Using the Internet as a means of regulating mood. While Young's YDQ assessment for IA has the advantage of simplicity and ease of use, Keith W. Beard and Eve M. Wolf in 2001 further asserted that all of the first five and at least one of the final three criteria (in the order above) be met to delineate Internet addiction in order for a more appropriate and objective assessment.[91] Young further extended her eight-question YDQ assessment to the now most widely used Internet Addiction Test (IAT),[89][92][93] which consists of 20 items with each on a five-point Likert scale. Questions included on the IAT expand upon Young's earlier eight-question assessment in greater detail and include questions such as "Do you become defensive or secretive when anyone asks you what you do online?" and "Do you find yourself anticipating when you go online again?". A complete list of questions can be found in Dr. Kimberly S. Young's 1998 book Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and A Winning Strategy for Recovery and Laura Widyanto and Mary McMurran's 2004 article titled The Psychometric Properties of the Internet Addiction Test. The Test score ranges from 20 to 100 and a higher value indicates a more problematic use of the Internet: 20–39 = average Internet users, 40–69 = potentially problematic Internet users, and 70–100 = problematic Internet users. Over time, a considerable number of screening instruments have been developed to diagnose Internet addiction, including the Internet Addiction Test (IAT),[89] the Internet-Related Addictive Behavior Inventory (IRABI),[94] the Chinese Internet Addiction Inventory (CIAI),[95] the Korean Internet Addiction Self-Assessment Scale (KS Scale),[96] the Compulsive Internet Use Scale (CIUS),[97] the Generalized Problematic Internet Use Scale (GPIUS),[98] the Internet Consequences Scale (ICONS),[99] and the Problematic Internet Use Scale (PIUS).[100] Among others, the Internet Addiction Test (IAT) by Young (1998) exhibits good internal reliability and validity and has been used and validated worldwide as a screening instrument.[101][102][93] Although the various screening methods are developed from diverse contexts, four dimensions manifest themselves across all instruments:[79][103] Excessive use: compulsive Internet use and excessive online time-use; Withdrawal symptoms: withdrawal symptoms including feelings such as depression and anger, given restricted Internet use; Tolerance: the need for better equipment, increased internet use, and more applications/software; Negative repercussions: Internet use caused negative consequences in various aspects, including problematic performance in social, academic, or work domains. More recently, researchers Mark D. Griffiths in 2000 and Jason C. Northrup and colleagues in 2015 claim that Internet per se is simply the medium and that the people are in effect addicted to processes facilitated by the Internet.[103][104] Based on Young's Internet Addiction Test (IAT),[89] Northrup and associates further decompose the internet addiction measure into four addictive processes: Online video game playing, online social networking, online sexual activity, and web surfing.[103] The Internet Process Addiction Test (IPAT)[103] is created to measure the processes to which individuals are addicted. Screening methods that heavily rely on DSM criteria have been accused of lacking consensus by some studies, finding that screening results generated from prior measures rooted in DSM criteria are inconsistent with each other.[26] As a consequence of studies being conducted in divergent contexts, studies constantly modify scales for their own purposes, thereby imposing a further challenge to the standardization in assessing Internet addiction disorder.[29] Single-question instruments Some scholars and practitioners also attempt to define Internet addiction by a single question, typically the time-use of the Internet.[80][105] The extent to which Internet use can cause negative health consequences is, however, not clear from such a measure.[29] The latter of which is critical to whether IAD should be defined as a mental disorder. |
スクリーニング検査法 DSMに基づく検査法 研究で用いられる基準の多くは、『精神障害の診断と統計マニュアル』(DSM)ハンドブックに記載された精神障害(例:病的賭博)を応用したものである。[29] 1995年にインターネット依存症の概念を初めて提唱したIvan K. Goldbergは、DSM-IVに基づき「ネットワーク利用時間の増加を望む」「ネットワークについて夢を見る」など、IAD(インターネット依存症) の幾つかの基準を採用した。[88][29] キムバリー・S・ヤングは1998年、病的なギャンブルに関するDSM-IV基準を応用し、インターネット依存症を検出するための最初の統合基準の一つで ある診断質問票(YDQ)を提案した。8つの応用基準のうち5つ以上を満たす人格はインターネット依存症と見なされる:[89][90] 1. インターネットへの執着 2. 同じ満足感を得るためにオンライン時間を増やす必要性 3. インターネット利用を制限しようとする繰り返しの努力 4. インターネット利用が制限された際のイライラ、抑うつ、または気分の不安定さ 5. 予定より長くオンラインに滞在すること 6. インターネット利用のために仕事や人間関係を危険にさらすこと 7. オンライン時間の長さについて他人に嘘をつくこと 8. 気分調節の手段としてインターネットを利用すること。 ヤングのYDQ評価法は簡便で使いやすい利点があるが、キース・W・ビアードとイブ・M・ウルフは2001年、より適切かつ客観的な評価のためには、上記 の順序で最初の5項目全てと最後の3項目のうち少なくとも1項目を満たすことがインターネット依存症の定義に必要だと主張した。[91] ヤングはさらに、8項目のYDQ評価を拡張し、現在最も広く用いられているインターネット依存症テスト(IAT)[89][92][93]を確立した。こ れは20項目から成り、各項目は5段階のリッカート尺度で評価される。IATに含まれる質問は、ヤングの初期の8項目評価を詳細に拡充したもので、「誰か にオンラインでの行動を尋ねられた時、防御的または秘密主義的になるか」「次にオンラインになるタイミングを予期しているか」といった内容が含まれる。質 問の完全なリストは、キンバリー・S・ヤング博士の1998年の著書『ネットに囚われて:インターネット依存症の兆候を見抜く方法と回復への勝利戦略』お よびローラ・ウィディヤントとメアリー・マクマランの2004年の論文『インターネット依存症テストの心理測定特性』で確認できる。テストのスコアは 20~100の範囲で、数値が高いほどインターネットの使用に問題があることを示す: 20~39 = 平均的なインターネット利用者、 40~69 = 問題のある可能性のあるインターネット利用者、 70~100 = 問題のあるインターネット利用者。 時を経て、インターネット依存症を診断するためのスクリーニングツールが数多く開発されてきた。これにはインターネット依存症テスト(IAT)[89]、 インターネット関連依存行動インベントリー(IRABI)[94]、中国語版インターネット依存症インベントリー(CIAI)[95]、 [95] 韓国インターネット依存自己評価尺度(KS尺度)[96]、強迫的インターネット使用尺度(CIUS)[97]、一般化問題インターネット使用尺度 (GPIUS)[98]、インターネット結果尺度(ICONS)[99]、問題インターネット使用尺度(PIUS)などである。[100] とりわけ、Young(1998)によるインターネット依存症テスト(IAT)は高い内部信頼性と妥当性を示し、スクリーニングツールとして世界中で使 用・検証されている。[101][102][93] 様々なスクリーニング手法は異なる文脈から開発されているが、全ての尺度において四つの次元が共通して現れる。[79] [103] 過度な使用:強迫的なインターネット使用と過度なオンライン時間使用。 離脱症状:インターネット使用が制限された場合に生じる、抑うつや怒りの感情などの離脱症状。 耐性:より優れた機器、インターネット使用の増加、より多くのアプリケーション/ソフトウェアの必要性。 悪影響:インターネット使用は、社会、学業、仕事などの分野における問題のあるパフォーマンスなど、さまざまな面で悪影響をもたらした。 さらに最近では、2000年にマーク・D・グリフィス、2015年にジェイソン・C・ノースラップらが、インターネット自体は単なる媒体であり、人々は実 際にはインターネットによって促進されるプロセスに依存していると主張している。[103][104] ヤングのインターネット依存症テスト(IAT)[89] に基づき、ノースラップらは、インターネット依存症の測定を、オンラインビデオゲームのプレイ、オンラインソーシャルネットワーキング、オンラインでの性 的活動、ウェブサーフィンの 4 つの依存プロセスにさらに分解している。[103] インターネットプロセス依存症テスト(IPAT)[103] は、個人が依存しているプロセスを測定するために作成された。 DSM基準に大きく依存するスクリーニング手法は、一部の研究によって合意形成が不十分であると批判されている。DSM基準に基づく従来の測定法から得ら れたスクリーニング結果が互いに矛盾していることが判明したためである[26]。研究が異なる文脈で実施される結果、研究者は常に自らの目的に合わせて尺 度を修正しており、これがインターネット依存症評価の標準化にさらなる課題を突きつけている。[29] 単一質問式尺度 一部の研究者や実践者は、単一の質問、典型的にはインターネットの使用時間によってインターネット依存症を定義しようとする試みも行っている。[80] [105] しかし、このような尺度からは、インターネット使用が健康に悪影響を及ぼす程度は明らかではない。[29] 後者は、IADを精神障害として定義すべきか否かの判断において極めて重要である。 |
| Neuroimaging techniques Emergent neuroscience studies investigated the influence of problematic, compulsive use of the internet on the human brain.[106] Neuroimaging studies revealed that IAD contributes to structural and functional abnormalities in the human brain, similar to other behavioral and substance additions. Therefore, objective non-invasive neuroimaging can contribute to the preliminary diagnosis and treatment of IAD.[106][107] Electroencephalography-based diagnosis Using electroencephalography (EEG) readings allows identifying abnormalities in the electrical activity of the human brain caused by IAD. Studies revealed that individuals with IAD predominantly demonstrate increased activity in the theta and gamma band and decreased delta, alpha, and beta activity.[108][109][110][111][112] Following these findings, studies identified a correlation between the differences in the EEG readings and the severity of IAD, as well as the extent of impulsivity and inattention.[108][110][111] Classification As many scholars have pointed out, the Internet serves merely as a medium through which tasks of divergent nature can be accomplished.[103][104] Treating disparate addictive behaviors under the same umbrella term is highly problematic.[113] A 1999 study asserts that Internet addiction is a broad term which can be decomposed into several subtypes of behavior and impulse control problems, namely,[114] Cybersexual addiction: compulsive use of adult websites for cybersex and cyberporn (see Internet sex addiction) Cyber-relationship addiction: Over-involvement in online relationships Net compulsions: Obsessive online gambling, shopping or day-trading Information overload: Compulsive web surfing or database searches Computer addiction: Obsessive computer game playing (see Video game addiction) For a more detailed description of related disorders please refer to the related disorders section above. Public concern Internet addiction has raised great public concern in Asia and some countries consider Internet addiction as one of the major issues that threatens public health, in particular among adolescents. Internet addiction has been seen as a growing concern among adolescents, with many spending a significant amount of time online and exhibiting problematic use behaviors such as compulsive internet use and withdrawal symptoms when offline. Certain demographic factors, such as gender and socioeconomic status, may be associated with higher rates of internet addiction.[115] Various factors may contribute to the development of Internet addiction, including individual factors such as depression, anxiety, and poor self-regulation, as well as environmental factors such as parental monitoring and peer influence. Poor academic performance, disrupted sleep patterns, and social isolation were found to be potential negative consequences of Internet addiction.[115] |
神経画像技術 新興神経科学研究は、問題のある強迫的なインターネット使用が人間の脳に及ぼす影響を調査した。[106] 神経画像研究により、IADが他の行動依存症や物質依存症と同様に、人間の脳の構造的・機能的異常に関与することが明らかになった。したがって、客観的で 非侵襲的な神経画像技術は、IADの初期診断と治療に貢献し得る。[106] [107] 脳波検査に基づく診断 脳波検査(EEG)の測定値を用いることで、IADによって引き起こされる人間の脳の電気的活動における異常を特定できる。研究により、IADを持つ個人 は主にシータ波とガンマ波の活動が増加し、デルタ波、アルファ波、ベータ波の活動が減少することが明らかになった。[108][109][110] [111][112] これらの知見を受け、EEG測定値の差異とIADの重症度、衝動性や不注意の程度との相関関係が研究で確認されている。[108][110][111] 分類 多くの研究者が指摘するように、インターネットは単に多様な性質の課題を遂行するための媒体に過ぎない。[103][104] 異なる依存行動を同一の包括的用語で扱うことは極めて問題が多い。[113] 1999年の研究は、インターネット依存症は広範な概念であり、以下の行動および衝動制御問題の亜型に分解可能だと主張している。[114] サイバーセックス依存症:サイバーセックスやサイバーポルノ目的でのアダルトサイト強迫的使用(インターネット性依存症参照) サイバー関係依存症:オンライン関係への過度な没入 ネット強迫行為:オンラインギャンブル・ショッピング・デイトレードへの執着 情報過負荷:強迫的なウェブ閲覧やデータベース検索 コンピューター依存症:コンピューターゲームへの執着(ビデオゲーム依存症参照) 関連障害の詳細な説明については、上記の関連障害セクションを参照のこと。 社会的懸念 インターネット依存症はアジア地域で大きな社会的懸念を引き起こしており、一部の国では特に青少年の公衆健康を脅かす主要な問題の一つと見なされている。 インターネット依存症は青少年の間で深刻化する懸念事項とされ、多くの者が長時間オンラインに没頭し、強迫的なインターネット使用やオフライン時の離脱症 状といった問題行動を示している。性別や社会経済的地位といった特定の人口統計学的要因は、インターネット依存症の高い発生率と関連している可能性があ る。[115] インターネット依存症の発症には、うつ病、不安、自己制御力の低さといった個人の要因や、親の監視や仲間からの影響といった環境的要因など、様々な要因が 関与している可能性がある。学業成績の低下、睡眠パターンの乱れ、社会的孤立は、インターネット依存症の潜在的な悪影響として確認されている。[115] |
| Treatment Current interventions and strategies used as treatments for Internet addiction stem from those practiced in substance abuse disorder. In the absence of "methodologically adequate research", treatment programs are not well corroborated.[116] Psychosocial treatment is the approach most often applied.[87] In practice, rehab centers usually devise a combination of multiple therapies.[95] Psychosocial treatment Cognitive behavioral therapy The cognitive behavioral therapy with Internet addicts (CBT-IA) is developed in analogy to therapies for impulse control disorder.[62][117] Several key aspects are embedded in this therapy:[118][119] Learning time management strategies; Recognizing the benefits and potential harms of the Internet; Increasing self-awareness and awareness of others and one's surroundings; Identifying "triggers" of Internet "binge behavior", such as particular Internet applications, emotional states, maladaptive cognitions, and life events; Learning to manage emotions and control impulses related to accessing the Internet, such as muscles or breathing relaxation training; Improving interpersonal communication and interaction skills; Improving coping styles; Cultivating interests in alternative activities. Three phases are implemented in the CBT-IA therapy:[62][117] Behavior modification to control Internet use: Examine both computer behavior and non-computer behavior and manage Internet addicts' time online and offline; Cognitive restructuring to challenge and modify cognitive distortions: Identify, challenge, and modify the rationalizations that justify excessive Internet use; Harm reduction therapy to address co-morbid issues: Address any co-morbid factors associated with Internet addiction, sustain recovery, and prevent relapse. Symptom management of CBT-IA treatment has been found to sustain six months post-treatment.[62] Motivational interviewing The motivational interviewing approach is developed based on therapies for alcohol abusers.[62][119] This therapy is a directive, patient-centered counseling style for eliciting behavior change through helping patients explore and resolve ambivalence with a respectful therapeutic manner. It does not, however, provide patients with solutions or problem solving until patients' decision to change behaviors.[118] Several key elements are embedded in this therapy:[62] Asking open-ended questions; Giving affirmations; Reflective listening Other psychosocial treatment therapies include reality therapy, Naikan cognitive psychotherapy, group therapy, family therapy, and multimodal psychotherapy.[118] Medication IAD may be associated with a co-morbidity, so treating a related disorder may also help in the treatment of IAD. When individuals with IAD were treated with certain antidepressants, the time online was reduced by 65% and cravings of being online also decreased. The antidepressants that have been most successful are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) such as escitalopram and the atypical antidepressant bupropion. A psychostimulant, methylphenidate, was also found to have beneficial effects.[69] However, the available evidence on treatment of IAD is of very low quality at this time and well-designed trials are needed.[120] |
治療 インターネット依存症の治療として用いられる現行の介入法や戦略は、薬物乱用障害で実践されている手法に由来する。「方法論的に適切な研究」が不足してい るため、治療プログラムの有効性は十分に裏付けられていない。[116] 心理社会的治療が最も頻繁に適用されるアプローチである。[87] 実際には、リハビリ施設では通常、複数の療法を組み合わせたプログラムを考案する。[95] 心理社会的治療 認知行動療法 インターネット依存症患者向け認知行動療法(CBT-IA)は、衝動制御障害の治療法を類推して開発されたものである。[62][117] この療法にはいくつかの重要な側面が組み込まれている。[118][119] 時間管理戦略の習得 インターネットの利点と潜在的な害の認識 自己認識および他者・周囲への認識を高めること; 特定のインターネットアプリケーション、感情状態、不適応的認知、生活上の出来事など、インターネット「過度の使用行動」の「引き金」を特定すること; 筋肉や呼吸のリラクゼーション訓練など、インターネットアクセスに関連する感情の管理や衝動の制御を学ぶこと; 対人コミュニケーションおよび相互作用スキルを向上させること; 対処スタイルの改善; 代替活動への興味の育成。 CBT-IA療法では三段階を実施する:[62][117] インターネット使用を制御する行動修正:コンピューター使用行動と非使用行動の両方を検証し、インターネット依存者のオンライン・オフライン時間を管理する; 認知的歪みに挑戦・修正する認知再構成:過剰なインターネット使用を正当化する合理化を特定・挑戦・修正する; 併存問題への対処を目的としたハームリダクション療法:インターネット依存に関連する併存要因に対処し、回復を維持し、再発を防止する。 CBT-IA治療の症状管理効果は、治療終了後6ヶ月間持続することが確認されている。[62] 動機付け面接法 動機付け面接法は、アルコール乱用者向け療法を基に開発された。[62] [119] この療法は、患者中心の指示的カウンセリングスタイルであり、敬意を払った治療的態度で患者の両価性を探索・解決させることで行動変容を促す。ただし、患 者が行動変容を決断するまでは、解決策や問題解決法を提供しない。[118] この療法にはいくつかの重要な要素が含まれる。[62] オープンエンドの質問を投げかけること; 肯定的フィードバックを与えること; 反射的傾聴を行うこと その他の心理社会的治療法には、現実療法、内観認知療法、集団療法、家族療法、多角的心理療法がある。[118] 薬物療法 IADは併存疾患と関連する場合があるため、関連する障害の治療もIAD治療に寄与する可能性がある。IAD患者に特定の抗うつ薬を投与したところ、オン ライン時間は65%減少し、オンラインへの渇望も低下した。最も効果的だった抗うつ薬は、エスシタロプラムなどの選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)と非定型抗うつ薬ブプロピオンである。精神刺激薬メチルフェニデートにも有益な効果が見られた。[69] ただし、現時点でIAD治療に関する利用可能なエビデンスの質は非常に低く、適切に設計された試験が必要である。[120] |
12-step recovery programs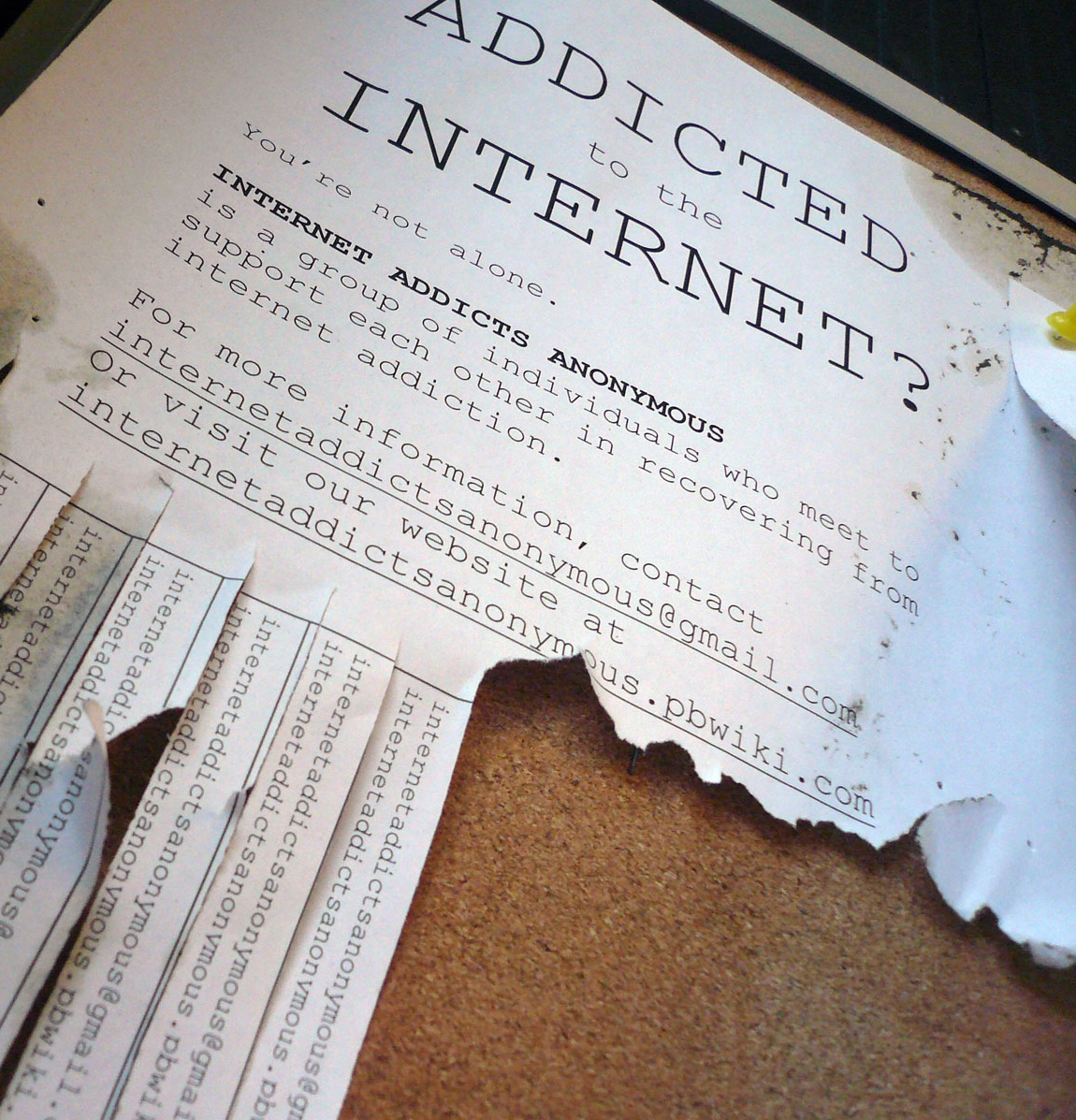 A flyer on a corkboard reads, "ADDICTED to the INTERNET?" and gives information for meeting up with an "Internet addicts anonymous" group. Some tabs at the bottom with contact information have already been pulled off. A 2009 flyer for an internet addiction support group in New York City Gaming Addicts Anonymous, founded in 2014 is a 12-step program focused on recovery from computer gaming addiction.[121][122] Internet and Technology Addicts Anonymous (ITAA), founded in 2017, is a 12-step program supporting users coping with the problems resulting from compulsive internet and technology use.[123][124][125] Some common sub-addictions include smartphone addiction, binge watching addiction, and social media addiction. There are face-to-face meetings in some cities. Telephone / online meetings take place every day of the week, at various times (and in various languages) that allow people worldwide to attend. Similar to 12-step fellowships related to behavioral addictions, such as Overeaters Anonymous, Workaholics Anonymous, or Sex and Love Addicts Anonymous, most members do not define sobriety as avoiding all technology use altogether.[126] Instead, most ITAA members come up with their own definitions of abstinence or problem behaviors, such as not using the computer or internet at certain hours or locations or not going to certain websites or categories of websites that have proven problematic in the past. They refer to these problematic behaviors as "bottom lines". In contrast, "top lines" are activities, both online and offline, they can do to enhance self esteem without falling into compulsive use. "Middle lines" are behaviors that may be OK sometimes, but can lead to bottom lines if a user is not careful.[127][128][126] Meetings provide a source of live support for people, to share struggles and victories, and to learn to better function in life once less of it is spent on problematic technology use. Media Addicts Anonymous (MAA), founded in 2020, is a 12-step program focused on recovery from media addiction. All forms of media sobriety are supported, including abstinence from electronic media, films, radio, newspapers, magazines, books, and music.[129][130] |
12ステップ回復プログラム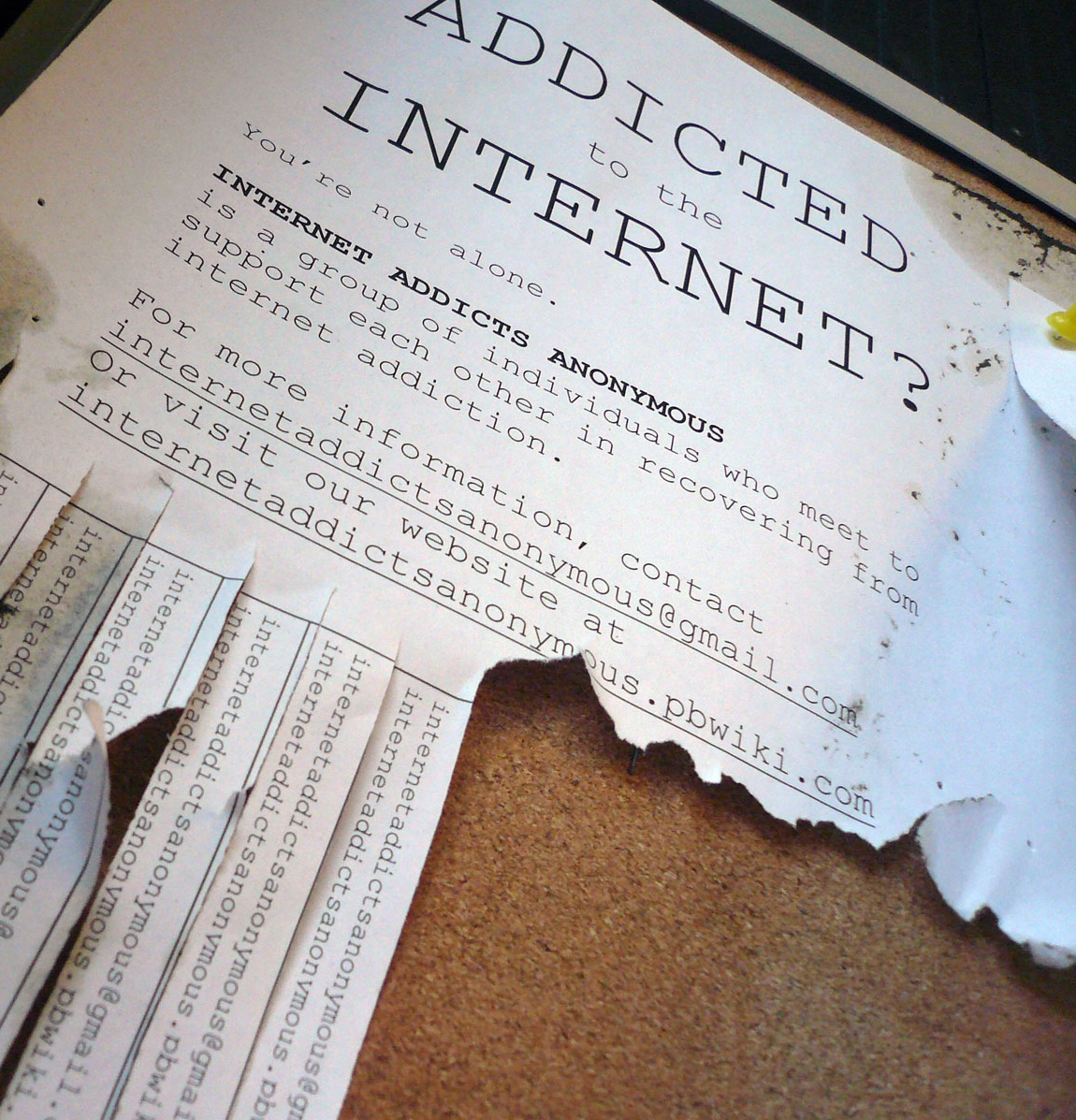 コルクボードに貼られたチラシには「インターネット中毒?」と書かれており、「インターネット中毒者匿名会」のミーティング情報を提供している。下部の連絡先タブは既に剥がされている。 2009年、ニューヨーク市のインターネット依存症支援グループ用チラシ ゲーミング・アディクツ・アノニマス(Gaming Addicts Anonymous)は2014年に設立された、コンピューターゲーム依存症からの回復に焦点を当てた12ステッププログラムである。[121] [122] インターネット・テクノロジー依存症匿名会(ITAA)は2017年に設立された12ステッププログラムで、強迫的なインターネット・テクノロジー使用に 起因する問題に対処するユーザーを支援する。[123][124][125] 一般的なサブ依存症には、スマートフォン依存症、一気見依存症、ソーシャルメディア依存症などがある。一部都市では対面ミーティングが開催されている。電 話/オンラインミーティングは毎日、様々な時間帯(及び言語)で実施され、世界中の人民が参加できる。 過食症匿名会、仕事中毒匿名会、性愛依存症匿名会など、行動依存症関連の12ステップ団体と同様に、ほとんどのメンバーは「断ち」を全ての技術使用を完全 に避けることとは定義していない。[126] 代わりに、多くのITAAメンバーは独自の禁断状態や問題行動の定義を確立している。例えば特定の時間帯や場所でコンピューターやインターネットを使用し ない、過去に問題を引き起こした特定のウェブサイトやカテゴリにアクセスしないなどだ。こうした問題行動を「ボトムライン」と呼ぶ。対照的に「トップライ ン」とは、強迫的な使用に陥ることなく自尊心を高められるオンライン・オフラインの活動を指す。「中間ライン」とは、時折なら許容されるが、注意を怠れば ボトムラインに繋がり得る行動を指す[127][128][126]。ミーティングは、参加者が苦闘や勝利を共有し、問題のある技術使用に費やす時間を減 らした後の生活でより良く機能する方法を学ぶための、生きた支援の場を提供する。 メディア中毒匿名会(MAA)は2020年に設立された、メディア依存からの回復に焦点を当てた12ステッププログラムである。電子メディア、映画、ラジオ、新聞、雑誌、書籍、音楽など、あらゆる形態のメディア断ちが支援対象となる。[129][130] |
| Prevalence Research-based prevalence rate of Internet addiction 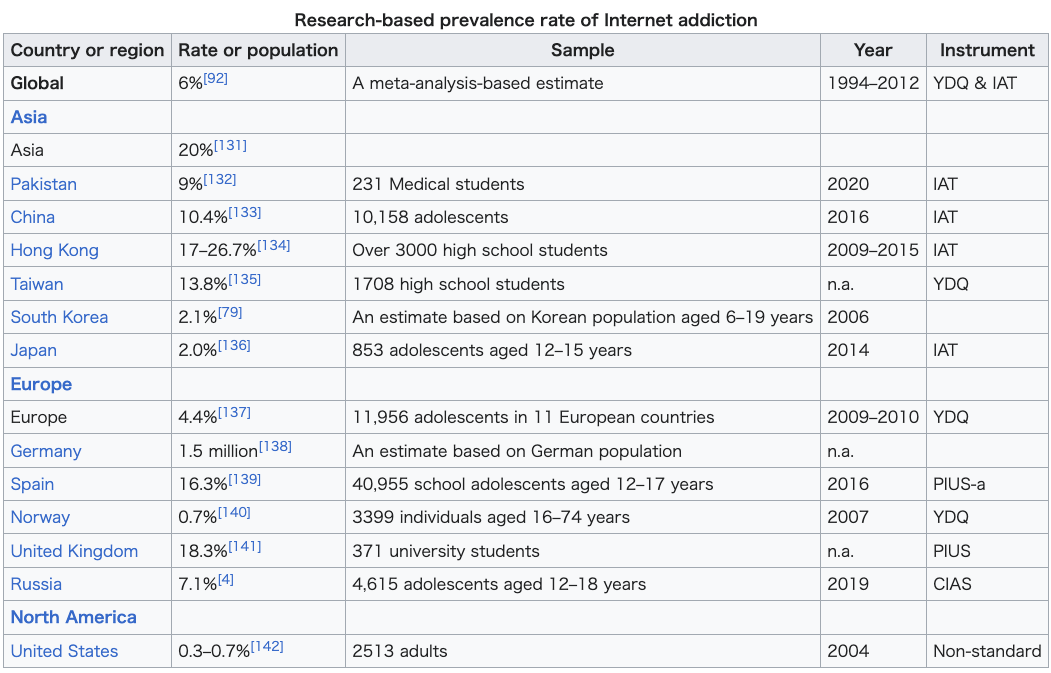 Different samples, methodologies, and screening instruments are employed across studies. |
有病率 研究に基づくインターネット依存症の有病率 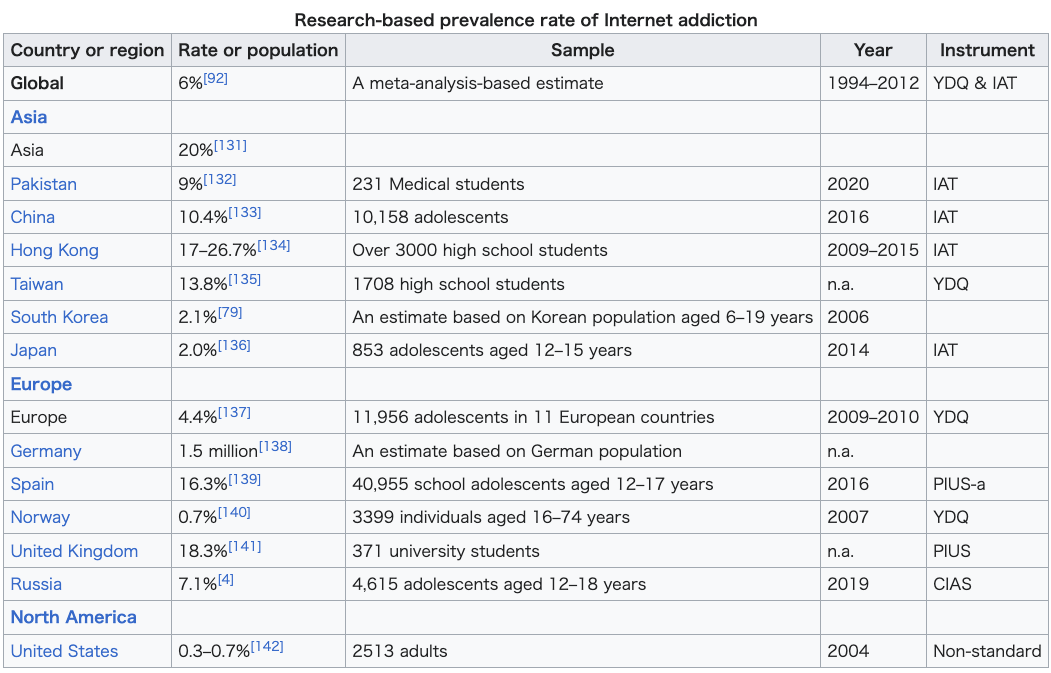 研究によって異なるサンプル、方法論、スクリーニングツールが用いられている。 |
| Terminology The notion of "Internet addictive disorder" was initially conjured up by Ivan K. Goldberg in 1995 as a joke to parody the complexity and rigidity of the American Psychiatric Association's (APA) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). In his first narration, Internet addictive disorder was described as having the symptoms of "important social or occupational activities that are given up or reduced because of Internet use", "fantasies or dreams about the Internet", and "voluntary or involuntary typing movements of the fingers".[143] The definition of Internet addiction disorder has troubled researchers ever since its inception. In general, no standardized definition has been provided despite that the phenomenon has received extensive public and scholar recognition.[24][29] Below are some of the commonly used definitions. In 1998, Jonathan J. Kandell defined Internet addiction as "a psychological dependence on the Internet, regardless of the type of activity once logged on."[144] English psychologist Mark D. Griffiths (1998) conceived Internet addiction as a subtype of broader technology addiction, and also a subtype of behavioral addictions.[145] In recent years, the validity of the term "Internet addiction" as a single psychological construct has been criticized.[146][147] New empirical evidence is emerging to support this view.[148] |
用語 「インターネット依存症」という概念は、1995年にアイバン・K・ゴールドバーグが、アメリカ精神医学会(APA)の『精神障害の診断と統計マニュア ル』(DSM)の複雑さと硬直性を揶揄する冗談として考案したものである。彼の最初の記述では、インターネット依存症は「インターネット使用のために重要 な社会的・職業的活動を放棄または減少させる」「インターネットに関する空想や夢」「自発的または不随意的な指のタイピング動作」といった症状を持つと説 明されていた。[143] インターネット依存症の定義は、その誕生以来、研究者たちを悩ませてきた。一般的に、この現象は広く一般や学者から認知されているにもかかわらず、標準化された定義は提供されていない。[24][29] 以下に、よく使われる定義をいくつか挙げる。 1998年、ジョナサン・J・カンデルは、インターネット依存症を「一度ログインした後の活動の種類に関係なく、インターネットに対する心理的依存」と定義した。[144] 英国の心理学者マーク・D・グリフィス(1998)は、インターネット依存症をより広範な技術依存症のサブタイプ、また行動依存症のサブタイプとして捉えた。[145] 近年、「インターネット依存症」という用語が単一の心理的構成概念として有効であるかどうかについて批判が寄せられている。[146][147] この見解を裏付ける新たな実証的証拠も出現している。[148] |
| Society and culture Internet addiction has raised great public concern in Asia and some countries consider Internet addiction as one of the major issues that threatens public health, in particular among adolescents.[79][118] China Internet addiction is commonly referred to as "electronic opium"[149] or "electronic heroin" in China.[150] A government entity in China became the first governmental body worldwide to recognize internet addiction when it established "Clinical Diagnostic Criteria for Internet Addiction" in 2008.[151][152] China's Ministry of Health does not formally recognize Internet addiction as a medical condition.[86]: 173 As a result of public outcry over parent-child online gaming conflicts, the government issued legislation.[86]: 175 In 2002, the government passed legislation which forbid Internet cafes from allowing minors.[86]: 175 The Law on Protection of Minors was amended in 2006 to state that the family and the state should guide minors' online behavior.[86]: 175 These amendments place "indulgence in the Internet" on par with misbehaviors like smoking and vagrancy.[86]: 175 The government has enacted other policies to regulate adolescents' Internet use, including limiting daily gaming time to 3 hours and requiring users' identification in online video games.[153] Mistreatment and abuse in China Internet addiction camps in China are private or semi-private.[86]: 174 The first such treatment center was founded in 2005.[86]: 174 In the absence of guidance from the Ministry of Health and a clear definition of Internet addiction, dubious treatment clinics have sprouted up in the country.[80] As part of the treatment, some clinics and camps impose corporal punishment upon patients of Internet addiction and some conducted electroconvulsive therapy (ECT) against patients, the latter of which has caused wide public concern and controversy.[80][154] Several forms of mistreatment have been well-documented by news reports. One of the most commonly used treatments for Internet-addicted adolescents in China is inpatient care, either in a legal or illegal camp. It is reported that children were sent to these camps against their will. Some are seized and bound by staff of the camp, some are drugged by their parents, and some are tricked into treatment.[152][155][156][157] In many camps and clinics, corporal punishment is frequently used in the treatment of Internet addiction disorder. The types of corporal punishment practiced include, but are not limited to, kilometers-long hikes, intense squats, standing, starving, and confinement.[80][158][159][160] After physical abuse caused the death of an adolescent at a treatment camp in 2009, the Chinese government officially prohibited the use physical violence in such places.[161] Among Internet addiction rehab centers that use corporal punishment in treatment, Yuzhang Academy in Nanchang, Jiangxi Province, is the most notorious. In 2017, the academy was accused of using severe corporal punishment against students, the majority of which are Internet addicts. Former students claimed that the academy hit problematic students with iron rulers, "whip them with finger-thick steel cables", and lock students in small cells week long.[162] Several suicidal cases emerged under the great pressure.[163] In November 2017, the academy stopped operating after extensive media exposure and police intervention.[164] Electroconvulsive therapy In China, electroconvulsive therapy (ECT) is legally used for schizophrenia and mood disorders. Its use in treating adolescent Internet addicts has raised great public concern and stigmatized the legal use of ECT.[165] The most reported and controversial clinic treating Internet addiction disorder is perhaps the Linyi Psychiatric Hospital in Shandong Province.[80] Its center for Internet addiction treatment was established in 2006 by Yang Yongxin.[166] Various interviews of Yongxin Yang confirm that Yang has created a special therapy, xingnao ("brain-waking") therapy, to treat Internet addiction. As part of the therapy, electroconvulsive therapy is implemented with currents of 1–5 milliampere.[167] As Yang put it, the electroconvulsive therapy only involves sending a small current through the brain and will not harm the recipient.[168] As a psychiatric hospital, patients are deprived of personal liberty and are subject to electroconvulsive treatment at the will of hospital staffs.[154] And before admission, parents have to sign contracts in which they deliver their guardianship of kids partially to the hospital and acknowledge that their kids will receive ECT.[154] Frequently, ECT is employed as a punishment method upon patients who breaks any of the center's rules, including "eating chocolate, locking the bathroom door, taking pills before a meal and sitting on Yang's chair without permission".[154] It is reported in a CCTV-12 segment that a DX-IIA electroconvulsive therapy machine is utilized to correct Internet addiction. The machine was, later on, revealed to be illegal, inapplicable to minor[169][170] and can cause great pain and muscle spasm to recipients.[80] Many former patients in the hospital later on stood out and reported that the ECT they received in the hospital was extremely painful, tore up their head,[156] and even caused incontinence.[166][171] An Interview of the Internet addiction treatment center in Linyi Psychiatric Hospital is accessible via the following link. Since neither the safety nor the effectiveness of the method was clear, the Chinese Ministry of Health banned electroconvulsive therapy in treating Internet addiction disorder in 2009.[168][172] Drugs In Yang's clinic, patients are forced to take psychiatric medication[155] in addition to Jiewangyin, a type of medication invented by himself. Neither the effectiveness nor applicability of the medication has been assessed, however. Physical abuse and death At clinics and rehab centers, at least 12 cases of physical abuse have been revealed by media in the recent years including seven deaths.[173][174] In 2009, a 15-year-old, Senshan Deng, was found dead eight hours after being sent to an Internet-addiction center in Nanning, Guangxi Province. It is reported that the teenager was beaten by his trainers during his stay in the center.[152] In 2009, another 14-year-old teenager, Liang Pu, was taken to hospital with water in the lungs and kidney failure after a similar attack in Sichuan Province.[161] In 2014, a 19-year-old, Lingling Guo, died in an Internet-addiction center with multiple injuries on head and neck in Zhengzhou, Henan Province.[152] In 2016, after escaping from an Internet addiction rehab center, a 16-year-old girl tied up and starved her mother to death as revenge for being sent to treatment in Heilongjiang Province.[152] In August 2017, an 18-year-old boy, Li Ao, was found dead with 20 external scars and bruises two days after his parents sent him to a military-style boot camp in Fuyang city, Anhui Province.[175] |
社会と文化 インターネット依存症はアジアで大きな社会的懸念を引き起こしており、一部の国では特に青少年の間で公衆健康を脅かす主要な問題の一つと見なされている。[79][118] 中国 中国ではインターネット依存症は一般的に「電子アヘン」[149] または「電子ヘロイン」と呼ばれる。[150] 中国の政府機関は2008年に「インターネット依存症の臨床診断基準」を制定し、世界で初めて政府機関としてインターネット依存症を認めた。[151] [152] ただし中国国家衛生健康委員会は、インターネット依存症を正式な医学的疾患とは認めていない。[86]: 173 親子間のオンラインゲーム紛争に対する世論の高まりを受け、政府は法規制を発令した。[86]:175 2002年には、インターネットカフェが未成年者の利用を許可することを禁止する法律が成立した。[86]:175 未成年者保護法は2006年に改正され、家族と国家が未成年者のオンライン行動を指導すべきと明記された。[86]: 175 これらの改正により「インターネットへの耽溺」は喫煙や浮浪行為などの非行と同等に扱われるようになった。[86]: 175 政府は青少年のインターネット利用を規制するため、1日のゲーム時間を3時間に制限する、オンラインゲーム利用時に本人確認を義務付けるなどの政策を実施 している。[153] 中国における虐待と不当扱い 中国のインターネット依存症治療キャンプは民間または準民間の施設である。[86]: 174 最初の治療センターは2005年に設立された。[86]: 174 厚生労働省の指導やインターネット依存症の明確な定義がないため、疑わしい治療クリニックが国内に乱立している。[80] 治療の一環として、一部のクリニックやキャンプではインターネット依存症患者に体罰を課し、電気けいれん療法(ECT)を実施するケースもあった。後者は 広く公衆の懸念と論争を引き起こした。[80][154] 複数の虐待形態が報道によって詳細に記録されている。 中国におけるインターネット依存症の青少年への最も一般的な治療法の一つは、合法・非合法を問わずキャンプ施設での入院治療である。子供たちが意思に反し てこれらのキャンプに送られたと報告されている。キャンプ職員に拘束される者、親によって薬物を投与される者、治療に騙される者もいる。[152] [155][156] [157] 多くのキャンプやクリニックでは、インターネット依存症の治療に体罰が頻繁に用いられている。実施される体罰の種類には、数キロに及ぶ長距離歩行、激しい スクワット、立ち続け、飢餓状態への放置、監禁などが含まれるが、これらに限定されない。[80][158][159][160] 2009年、治療キャンプでの身体的虐待が原因で10代の若者が死亡した事件を受け、中国政府はこうした施設での身体的暴力の使用を正式に禁止した。 [161] 体罰を治療に用いるインターネット依存症リハビリセンターの中で、江西省南昌市の「玉荘学院」が最も悪名高い。2017年、同学院は生徒(大半がインター ネット依存症患者)に対する過酷な体罰を非難された。元生徒らは、問題のある生徒を鉄の定規で殴打し、「指ほどの太さの鋼鉄ケーブルで鞭打ち」、生徒を小 さな独房に一週間閉じ込めたと証言している。[162] こうした過酷な圧力のもとで複数の自殺事例が発生した。[163] 2017年11月、メディアによる大規模な報道と警察の介入を受け、同学院は運営を停止した。[164] 電気けいれん療法 中国では、統合失調症や気分障害に対して電気けいれん療法(ECT)が合法的に使用されている。しかし、思春期のインターネット依存症治療への使用は大きな社会的懸念を招き、ECTの合法的使用に対する偏見を生んだ。[165] インターネット依存症治療で最も報告され、論争を呼んでいる施設は、おそらく山東省の臨沂精神病院であろう。[80] 同院のインターネット依存症治療センターは2006年、楊永信によって設立された。[166] 楊永信への様々なインタビューから、彼がインターネット依存症治療のための特殊療法「醒脳(脳覚醒)療法」を開発したことが確認されている。この療法の一 環として、1~5ミリアンペアの電流を用いた電気けいれん療法が実施される。[167] 楊永新によれば、電気けいれん療法は脳に微弱な電流を流すだけで、被験者に害はないという[168]。精神病院として、患者は人格を奪われ、病院スタッフ の裁量で電気けいれん治療を受けることになる[154]。また入院前には、保護者が契約書に署名し、子供の監護権の一部を病院に委譲するとともに、子供が 電気けいれん療法を受けることを承諾しなければならない。[154] しばしば電気けいれん療法は、施設の規則違反に対する懲罰手段として用いられる。違反行為には「チョコレートを食べる」「トイレのドアをロックする」「食 事前に薬を飲む」「許可なく楊の椅子に座る」などが含まれる。[154] CCTV-12の報道によれば、インターネット依存症の矯正にDX-IIA電気けいれん療法装置が使用されている。この装置は後に違法であることが判明 し、未成年への適用は不適切[169][170]で、被施術者に激しい痛みと筋肉痙攣を引き起こす可能性があるとされた[80]。多くの元患者が後に声を 上げ、病院で受けた電気けいれん療法が極めて苦痛で頭部を損傷させ[156]、失禁さえ引き起こしたと報告している。[166][171] 臨沂精神病院のインターネット依存症治療センターに関するインタビューは、以下のリンクから閲覧可能だ。この治療法の安全性も有効性も不明確であったた め、中国健康部は2009年にインターネット依存症治療における電気けいれん療法の使用を禁止した。[168][172] 薬物 楊のクリニックでは、患者は自ら開発した「絶望陰」という薬に加え、精神科の薬物を強制的に服用させられている。しかしこの薬物の有効性や適用可能性は評価されていない。 身体的虐待と死亡 近年、クリニックやリハビリ施設における身体的虐待事例が少なくとも12件(うち死亡7件)メディアによって暴露されている。[173] [174] 2009年、15歳の鄧森山(デン・センシャン)が広西チワン族自治区南寧市のインターネット依存症治療施設に送られてから8時間後に死亡した。同施設滞在中に指導員から暴行を受けていたと報じられている。[152] 2009年には四川省で、14歳の梁浦(リャン・プー)という少年が同様の暴行を受け、肺水腫と腎不全で病院に搬送された。[161] 2014年には河南省鄭州市のインターネット依存症治療施設で、19歳の郭玲玲が頭部と首に複数の外傷を負った状態で死亡した。[152] 2016年、黒竜江省のインターネット依存症治療施設から脱走した16歳の少女が、母親を縛り上げ飢え死にさせた。これは治療施設に送られたことへの復讐だった。[152] 2017年8月、安徽省阜陽市の軍事式訓練キャンプに両親に送り込まれた18歳の少年・李濤が、2日後に20ヶ所の外傷と打撲痕を残して死亡しているのが発見された。[175] |
| South Korea Being almost universally connected to the Internet and boasting online gaming as a professional sport, South Korea deems Internet addiction one of the most serious social issues[176] and describes it as a "national crisis".[177] Nearly 80% of the South Korean population have smartphones. As of 2013, according to government data, about two million of the country's population (less than 50 million) have Internet addiction problem, and approximately 680,000 10–19-year-olds are addicted to the Internet, accounting for roughly 10% of the teenage population.[178] Even the very young generation are faced with the same problem: Approximately 40% of South Korean children between age three to five are using smartphones over three times per week. According to experts, if children are constantly stimulated by smartphones during infancy period, their brain will struggle to balance growth and the risk of Internet addiction.[179] It is believed that due to Internet addiction, many tragic events have happened in South Korea: A mother, tired of playing online games, killed her three-year-old son. A couple, obsessed with online child-raising games, let their young daughter die of malnutrition. A 15-year-old teenager killed his mother for not letting him play online games and then committed suicide.[180] One Internet gaming addict stabbed his sister after playing violent games. Another addict killed one and injured seven others.[177] In response, the South Korea government has launched the first Internet prevention center in the world, the Jump Up Internet Rescue School, where the most severely addicted teens are treated with full governmental financial aid.[177] As of 2007, the government has built a network of 140 Internet-addiction counseling centers besides treatment programs at around 100 hospitals.[181] Typically, counselor- and instructor-led music therapy and equine therapy and other real-life group activities including military-style obstacle courses and therapeutic workshops on pottery and drumming are used to divert IAs' attention and interest from screens.[177][181] In 2011, the Korean government introduced the "Shutdown law", also known as the "Cinderella Act", to prevent children under 16 years old from playing online games from midnight (12:00) to 6 a.m.[178] |
韓国 ほぼ全国民がインターネットに接続され、オンラインゲームがプロスポーツとして確立している韓国では、インターネット依存症が最も深刻な社会問題の一つと 見なされている[176]。これは「国家的危機」と表現されることもある[177]。韓国国民の約80%がスマートフォンを所有している。2013年の政 府データによれば、同国人口(5000万人未満)のうち約200万人がインターネット依存症の問題を抱え、10~19歳の約68万人がインターネット依存 症であり、これは10代の約10%に相当する。[178] 幼い世代でさえ同様の問題に直面している:3~5歳の韓国人児童の約40%が週3回以上スマートフォンを使用している。専門家によれば、幼児期にスマート フォンによる刺激が絶え間なく続くと、脳の発育とインターネット依存症のリスクのバランスが取れなくなるという。[179] インターネット依存症が原因で、韓国では多くの悲劇が起きていると考えられている。オンラインゲームに疲れた母親が3歳の息子を殺害した事例。オンライン 育児ゲームに夢中になった夫婦が幼い娘を栄養失調で死なせた事例。15歳の少年は、オンラインゲームをするのを許さなかった母親を殺害し、その後自殺した [180]。あるインターネットゲーム依存症者は、暴力的なゲームをプレイした後、妹を刺した。別の依存症者は1人を殺害し、7人に重傷を負わせた [177]。 これに対し、韓国政府は世界で初めてのインターネット依存症予防センター「ジャンプアップインターネットレスキュースクール」を設立した。ここでは、最も 重度の依存症の青少年が、政府の全額財政支援を受けて治療を受けている。[177] 2007年時点で、政府は約100の病院における治療プログラムに加え、140のインターネット依存症カウンセリングセンターのネットワークを構築した。 [181] 典型的には、カウンセラーや指導者による音楽療法や馬を用いた療法、軍事スタイルの障害物コースや陶芸・打楽器療法ワークショップを含む現実のグループ活 動が用いられ、依存症患者の注意と関心を画面から逸らす。[177] [181] 2011年、韓国政府は「シャットダウン法」(通称「シンデレラ法」)を導入した。これにより16歳未満の児童が深夜0時(12:00)から午前6時までオンラインゲームをプレイすることを禁止している。[178] |
| Japan Many cases of social withdrawal have been occurring in Japan since the late 1990s which inclines people to stay indoors most of the time. The term used for this is hikikomori, and it primarily affects the youth of Japan in that they are less inclined to leave their residences. Internet addiction can contribute to this effect because of how it diminishes social interactions and gives young people another reason to stay at home for longer. Many of the hikikomori people in Japan are reported to have friends in their online games, so they will experience a different kind of social interaction which happens in a virtual space.[182] |
日本 1990年代後半から、日本では多くの社会引きこもり事例が発生している。これは人民がほとんど家の中に閉じこもる傾向を指す。この現象は「ひきこもり」 と呼ばれ、主に日本の若年層に影響を与えており、彼らは住居から出ることを好まなくなる。インターネット依存症はこの傾向を助長する可能性がある。なぜな ら、それは社会的交流を減らし、若者に家に長く留まる別の理由を与えるからだ。日本のひきこもりの人々はオンラインゲームで友人がいると報告されている。 つまり彼らは仮想空間で起こる、異なる種類の社会的交流を経験しているのだ。[182] |
| US lawsuits Numerous lawsuits have been filed in US courts by US states, US school districts and others asserting that social media platforms are deliberately designed to be addictive to minors and seeking damages.[183] These lawsuits include: In October 2023, several public school systems in Maryland joined to sue Meta Platforms, Snapchat, ByteDance, and Google, claiming that these companies knowingly cause harm to students by providing addictive social media platforms. This lawsuit was one of many filed in the US as part of a mass action with many other entities around the US filing similar lawsuits. According to attorneys representing the plaintiffs, these lawsuits, may or may not be combined into a class action. These lawsuits were in part inspired by the success of a similar lawsuit against Juul Labs, makers of electronic cigarettes that were marketed to minors. It is expected that the defendant social media companies will seek to have these cases dismissed.[184] In October 2023, Maryland, Virginia, and Washington, D.C. filed federal and state lawsuits against Facebook and Instagram, claiming that those platforms are designed to get children and teens addicted to social media. Meta Platforms, the parent company of Facebook and Instagram, responded that they have implemented many safety features and are disappointed that the states have not worked cooperatively with them.[185] In February 2024, the city of New York filed a lawsuit in the California Superior Court against Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, and YouTube, seeking to have the companies' behaviour declared a public nuisance and seeking monetary damages. The tech companies have responded that they have policies and procedures in place to insure public safety.[183] |
米国における訴訟 米国では、州政府や学区などがソーシャルメディアプラットフォームが未成年者に対して意図的に中毒性を生むように設計されていると主張し、損害賠償を求めて数多くの訴訟を提起している[183]。これらの訴訟には以下が含まれる: 2023年10月、メリーランド州の複数の公立学校システムが共同でMeta Platforms、Snapchat、ByteDance、Googleを提訴した。これらの企業が中毒性のあるソーシャルメディアプラットフォームを 提供することで学生に故意に危害を加えていると主張している。この訴訟は、米国各地の多くの団体が同様の訴訟を提起する集団訴訟の一環として米国で提起さ れた数多くの訴訟の一つである。原告側弁護士によれば、これらの訴訟は集団訴訟に統合される可能性もあるし、されない可能性もある。これらの訴訟は、未成 年者を対象に販売された電子タバコメーカーであるジュール・ラボ社に対する類似訴訟の成功に一部触発されたものである。被告であるソーシャルメディア企業 は、これらの訴訟の却下を求めるものと予想される。[184] 2023年10月、メリーランド州、バージニア州、ワシントンD.C.は、FacebookとInstagramが子どもや十代の若者をソーシャルメディ アに依存させるよう設計されていると主張し、連邦及び州の訴訟を提起した。FacebookとInstagramの親会社であるMeta Platformsは、多くの安全対策を実施しているとし、州が協力的に対応しなかったことに失望していると応じた。[185] 2024年2月、ニューヨーク市はカリフォルニア州高等裁判所にフェイスブック、インスタグラム、ティックトック、スナップチャット、ユーチューブを提訴 した。同市の目的は、これらの企業の行為を公害と認定させ、損害賠償を請求することである。これに対しテック企業側は、公共の安全を確保するためのポリ シーと手順を整備していると反論している。[183] |
| Addictive personality Criticism of Facebook Cyberslacking Digital addict Digital detox Digital media use and mental health Evolutionary mismatch Instagram's impact on people List of repetitive strain injury software (i.e. break reminders) Media multitasking Nomophobia (i.e., fear of being without a phone) Psychological effects of Internet use Soft addiction Terminally online Workaholic |
中毒性のある人格 フェイスブックへの批判 サイバースラック デジタル中毒者 デジタルデトックス デジタルメディア利用とメンタル健康 進化論的ミスマッチ インスタグラムの人民への影響 反復性ストレス障害防止ソフト一覧(休憩リマインダーなど) メディアマルチタスキング ノモフォビア(スマホがない状態への恐怖) インターネット利用の心理的影響 ソフト依存症 終日オンライン状態 仕事中毒 |
| Further reading Kuss D, Lopez-Fernandez O (2016). "Internet-use related addiction: The state of the art of clinical research". European Psychiatry. 33: S366. doi:10.1016/j.eurpsy.2016.01.1038. S2CID 148064363. Grohol JM (1999). "Internet Addiction Guide". Psych Central. Surratt CG (1999). Netaholics?: The creation of a pathology. Commack, NY: Nova Science Publishers. Young, Kimberly S. (1999). "Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment" (PDF). Innovations in Clinical Practice. 17. Archived from the original (PDF) on 2015-04-21. |
参考文献 Kuss D, Lopez-Fernandez O (2016). 「インターネット使用関連依存症:臨床研究の最新状況」. European Psychiatry. 33: S366. doi:10.1016/j.eurpsy.2016.01.1038. S2CID 148064363. Grohol JM (1999). 「インターネット依存症ガイド」. Psych Central. Surratt CG (1999). 『ネット中毒者?:病理の創造』. Commack, NY: Nova Science Publishers. ヤング、キンバリー・S.(1999)。「インターネット依存症:症状、評価、治療」(PDF)。臨床実践の革新。17。2015年4月21日にオリジナル(PDF)からアーカイブされた。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099