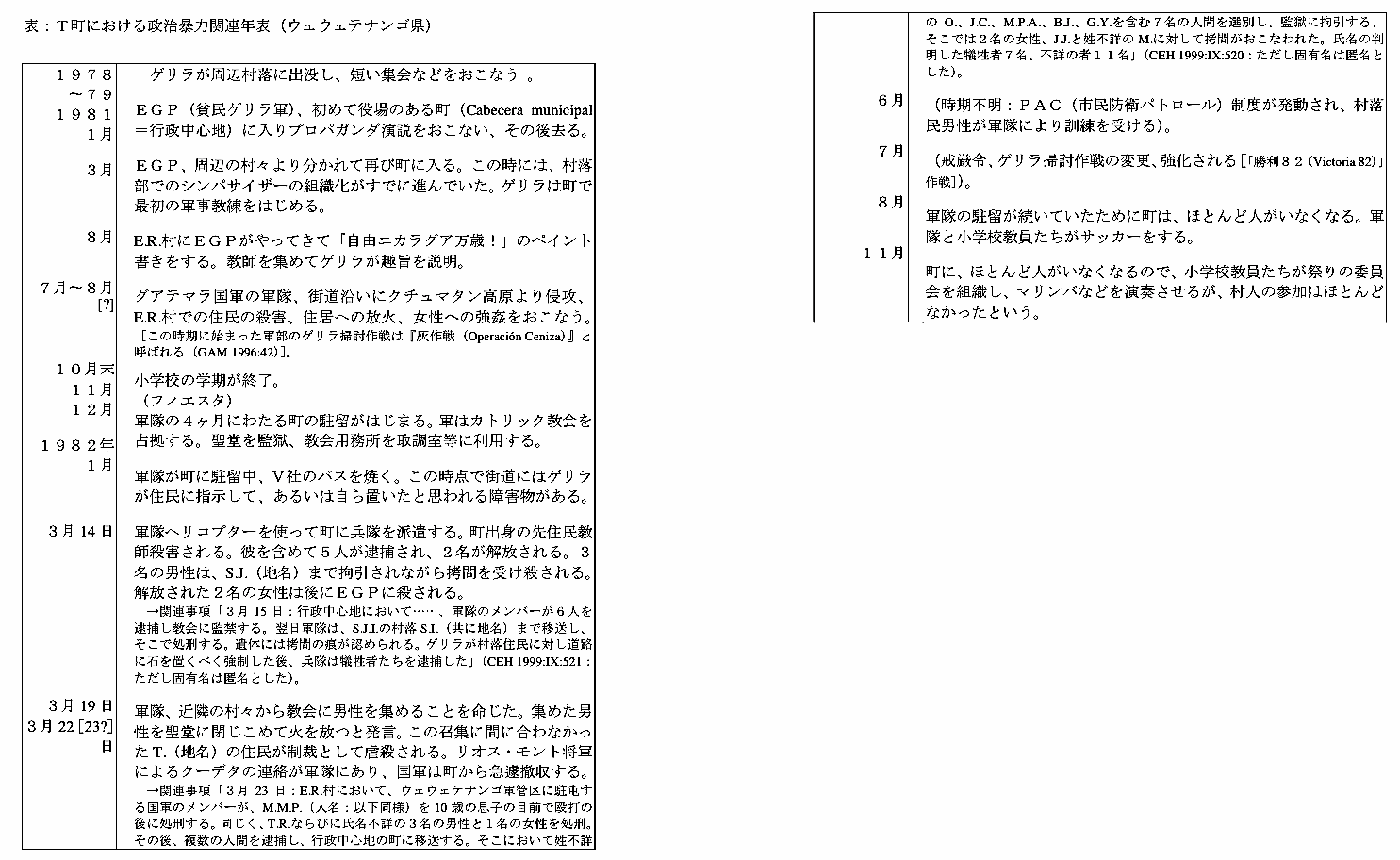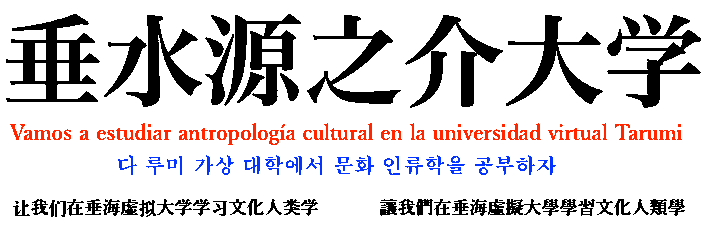はじめによんでください
暴力の内旋
―グアテマラ西部高地先住民共同体と経済―
Cultural Involution of Violence: A Guatemalan Highland Community
and World Economy
池田光穂 Mitsuho Ikeda
1. その町
2. 経済観念の変化
2.1 共体的共同体あるいは「搾
取の時期」・1980年以前
2.2 暴力・1981-82年
2.3 コスタからノルテへ
2.3.1 暴力の制度化
2.3.2 暴力がもたらした政
治経済的効果
2.3.3 経済活動の活性化
2.4 何が変化したのか
3. 暴力の内旋――結論
1. その町
その町は、欧米のみならず日本のガイドブックにも記されている観光地である。それらの書物によると魅力ある付近の景観とともに共同体には伝統
的な慣習が色濃く残されていると言われている。人びとの態度はあけすけで外国人に対して排他的なところが少ない。そして外国人と積極的に交渉を持とうとす
ることにこの地を訪れる観光客は誰しも驚くはずである。
この町に関する記録は、スペインの植民地時代から存在する。1840年代に北米の著名な旅行家ジョン・スティーブンスがこの地を通過したこと
を記録に留めている。民族誌に関する先行研究では、1930年代にトウモロコシの生産に関する調査が北米の人類学者によって始められ、1945年から46
年にかけて伝統的な宗教の調査がおこなわれている(Oakes
1951)。
私は1996年に民芸品生産と観光に関する調査をこの町でおこなった。調査において多くの人びととの対話のなかで聞かれ、また私の印象に残っ
た言葉は「今日びは競争が厳しい」(Hoy
hay mucha
competencia)である。この言葉は「進歩を選んだ」共同体が近代化や資本主義の波に巻き込まれてゆく過程を表象するにふさわしい言葉のひとつで
ある。この町もまた他のグアテマラやメキシコ南部(ユカタン半島やチアパス高地)と同じように文化変容の荒波の中に置かれているのだろう。しかし、多くの
民族誌学者同様、私もまた平板な用語法の中に閉じこめておくのではなく、自分のフィールドの特異性に読者の注意を促し、その特異性を通して我々に共通する
一般的な問題へと繋がっていることを確認したい。
この論考は、形式上は人びとの経済観念の通時的変化について解説する形式をとる。とくに私が主張したいことは、1981年初頭から2年間にわ
たるゲリラと政府軍による暴力という撹乱を挟んで、この社会が根本的に変化したということである。このような仮説を私に抱かせるようになったのは、人びと
の何気ない語りの中に、その暴力の記憶が刻印されており、この人びとが抱く文化の編年(chronology)にとって暴力がもたらした象徴的意味の大き
さを私が感じたからである。そのような印象が思い込みでないことを検証するために諸事実の確認とそこから派生する語りの積み重ねが必要である。これはその
ような作業の始まりである(1)。
2. 経済観念の変化
以下において私は、社会における人びとが抱く一種の文化の編年にとって1981-82年の暴力がもたらした象徴的意味について考察する。とく
に経済に関する人びとの考え方に関する側面に着目しながら暴力、とりわけ国家がこの地域にもたらした暴力の意味を考える。ここでは、この社会の1980年
以前、1981-82年、1983年以降の3つの時期の経済観念についての私の解釈を提出する。
2.1 共体的共同体*あるいは「搾取の時期」・1980年以前
この時代の人びとの生産の概念を支配していたのは富の源泉としての<土地>である。土地の豊饒さとはトウモロコシの生産のことを意味する。ト
ウモロコシを生産する伝統的な中央アメリカ小農民に関して書かれてきたほとんどの民族誌はこのことに触れており、彼らの経済的観念の中核をなすものと考え
られてきた。トウモロコシ畑すなわちミルパは人びとの主食を生産するというだけでなく、年間の労働サイクルをとおして生活にリズムを与え、農作物の生産を
支配する神や信仰によって人間の基盤を提供する場になっている。土地をもつことはトウモロコシを生産することであり、広大なミルパは豊かさを意味する。
この地域は狭隘な谷に囲まれた傾斜地である。現在はトウモロコシを含めて見渡すかぎりさまざまな農作物の作付がなされている。しかし、以前は
「土地は開拓すれば無限にあった」という。そして地味が失われると新たな耕作地が開拓され、休閑地は羊などの家畜の放牧地となった。休閑と放牧によって地
味の回復がなされ、再び数年後にはミルパとして再利用可能になった。
したがって富は土地を媒介にして生産され蓄積される。つまりより多くの土地を所有し耕作しているものがより多くの富を蓄積することができた。
このような富の不均衡を解消する機能をもっていると指摘されてきたのが信徒集団あるいはコフラディア(cofrad誕)であり、チアパス高地ではカルゴ・
システムという術語で呼ばれてきた社会組織である。コフラディアは我々の言うところの「宗教」と「政治」という2つの組織が合体したようなもので、おもに
成人男性によって運営され、職務を遂行するそれぞれの役割(カルゴ)には上下間の厳しい秩序がある。メンバーはコフラディアの地位が向上すれば、また社会
的な名誉も上昇するが、そのためにはコフラディア組織に対する寄付もまた要求される。寄贈される寄付のほとんどは儀礼を遂行するために酒や食物であるが、
これは経済的には共同体に対して富を再分配させる機能をもつと言われてきた。生活の世俗的な領域で経済な力をつけた男性が単純にコフラディア組織内での地
位をあげるかと思われるが、実際には構成メンバーに対して長幼の序列がありさまざまな儀礼的手続きに阻まれて、経済と権威の間は単純な相関関係にあるので
はなく、むしろ道徳を媒介とするような弁証法的な展開をとげる。コフラディアが共同体の生活ならびにその成員にとって重要な意味と強制力をもつとき、コフ
ラディアは共同体にとって富の再分配の機能をもつのである(Cancian
1992)。
このような土地に根ざした生産と富の概念を、共同体のなかに環流させるイデオロギーを、S・アニスにならって「ミルパの論理」(milpa
logic)と呼ぶこともできる(Annis 1987)。言うまでもなくミルパの論理はあくまでも理念的なモデルである。この論理を検証してみよう。
まずインディヘナ社会は一枚岩ではなく、経済的な格差に応じた活動が存在している。その格差は土地の所有面積に由来する。土地の所有面積に応
じて多様な「階層」に分解していた。ただし、そのような「階層」は彼らと我々の間にかろうじて想像可能な範疇的分類であり、彼ら自身にとってリアルな体系
として存在しない。土地なしあるいは生計維持を下回る土地面積の所有者は、必然的により多くの土地をもっている農民の分益農民になるか賃労働者となること
を意味しているし、実際にもそうであった。この地域における出稼ぎ賃金労働者は、すでに初期の民族誌が書かれたときからあった。土地を持たないもの――そ
の中には儀礼への出費のために現金が必要な者が含まれる――は、グアテマラ南西部の太平洋岸の綿花やサトウキビのプランテーション、後には1970年代以
降ではウエウエテナンゴ県からサン・マルコス県のコーヒープランテーションへ住み込みの移出労働者として家族ごと移住し前借りの契約労働に従事した。
【1970年代までのコスタへの労働】(C・J、58歳、インディヘナ、男性)(2)
それぞれの村や町にはカポラル(3)というのがいる。彼は労働者の長であり、プランテーションの農場主つまりパトロンと恒常的な関
係をもっていて、ふつうはそれぞれの村や町に住んでいる。パトロンは労働者を調達したいときに、それぞれのカポラルに連絡する。カポラルは要請に応じて農
場に赴き、パトロンと相談して、必要な労働力、それはホルナル(必要労働日={各人の労働日×日数}の総和)で計算されるが、それを調べ調達に必要な前金
の総額を受け取る。
カポラルは町に戻ってきて、個々の農民と接触し、彼らとの間に労働契約を結び前金を手渡す。この個々の前金のことをアビリタシオン
(4)という。前金の受け渡し時に、労働の開始日やトラックの到着日などが農民に知らされる。
カポラルが労働契約を結びにくるのは、農場で労働力が必要となるときだが、この町ではフィエスタ(守護聖人の祭)の前で人びとが金
が必要になる9月から10月にやってきて、フィエスタが終わった11月の第2週に海岸地方へのトラックが彼らを連れにやってくる。多くは家族単位で出か
け、場合によっては翌年の9月から11月まで農園で働く者もいた。
――「労働者はバス(camioneta)で運ばれていたのか?」[池田]
いやいやトラック(cami溶)で家畜のように運ばれるのさ。昔は8台くらいのトラックがやってきて農場に働きにいったものだ。最
後にはトラックではなくバスがやってきたが、大概はトラックだった。
このようにして自分たちは労働を手に入れたが、この8年から10年間[ca.1986-1988]にコスタ(海岸:太平洋岸のプラ
ンテーションの意)に働く人はほとんどいなくなってしまった。今でもコスタに働きにでる人はいるが少ない。なぜなら、今ではこの町の低地のR(地名)など
に働きにゆくことができて、コスタに働きにゆく必要がなくなった。
最近ではジャガイモ、タマネギ、ブロッコリーなどの換金作物を植えるようになって我々の大きな助けになった。また、コスタに行って
いたころ、人びとはコーヒーの栽培について知らなかった。現在コーヒー畑になっているところは昔はすべてトウモロコシ畑(ミルパ)であった。コーヒー栽培
に関して、協同組合や講習などは行われたことはなく、それぞれが各自に栽培方法を憶えた。私の場合は、コーヒーの農場で現場監督として働いた時にその仕事
を覚えた。今の収穫はこの町から、県庁のある町へ、そしてグアテマラ、さらには世界に広がってゆく。我々の収穫は世界へと鎖のように繋がっているのだ。
ミルパの論理にしたがうと、地域内の土地で生産された富とその蓄積の不均衡がコフラディアとそれに深く結びついたフィエスタの実施によって平
準化されることになる。ところが現実には少なくともこの半世紀はミルパの論理におけるコフラディアは外部経済に依存する賃労働を不可欠にするほど肥大化を
とげていた。というのは、コフラディアの組織を強化するのは定期的に開催される儀礼であり、経済の不均衡を平準化するほどの消費を伴う。プランテーション
労働者たちは自分たちの生計を維持するために賃労働者になるだけでなく、コフラディアの関与する年間の儀礼サイクルにあわせた形で自分の出身地に帰郷する
ものが多かった。それは、コフラディアの組織に参加し、儀礼的な消費をおこなうためである。したがって少なくとも今世紀の中頃にはコフラディアは、村落に
おける自律的な宗教=政治組織という組織上の形態を保ちながらも、儀礼的消費経済システムとして外部のプランテーションから得られた富(=貨幣)を共同体
の内部にもたらす機能をもつようになっていたと推測するができる。儀礼的な蕩尽は村落民の<村落外でのプロレタリア化>にともなって、さらにエスカレート
していった。
この時期におけるインディヘナ共同体における市場においては、地方生産の農作物および民芸品が交易されるが、工業製品のように共同体の外部か
ら流入するものも多くあった。この町から輸出(移出)されるものはトウモロコシを除いてはほとんどなく、またその移出量も産業化するにはほど遠いもので
あった。外部から共同体にもたらされた経済の収支を決済するものはプランテーション労働者の賃金であったと推定される。そのためこの村落共同体では賃金と
いう外部からもたらされた貨幣によって共同体の儀礼的消費の水準が高められることになった。
このような外部経済との節合によるコフラディアへの儀礼的消費の長期的な増加傾向は、直接的な経済効果よりも共同体と経済に関する考え方によ
り重要な影響をもたらした。その例として1970年代から始まったと思われる、民芸品生産の奨励とその販売をおこなう協同組合について考えてみよう。伝統
的な織物の生産と貧しき者たちによる協同組合による相互扶助の理念は瞬く間に人びとの間に普及した。また今日まで続いている組織以外にもいくつもの組合が
つくられたり消滅したりしてきた。
【民芸品の協同組合】(L・A、57歳、インディヘナ、男性)(5)
民芸品の協同組合(以下、組合)の始まりはM地区の女性たちがはじめたものだ。この組合は民芸品の始めての法人として、当初はちゃ
んと機能しており、町の外にも生産物を輸出していた。
しかし、組合の運営について組合員たち(socios)はみな素人で、おまけに組合によって雇われたAが売り上げの半分を着服して
いたので、正常には機能しなくなっていた。私は、当時農業に従事していたが、Aの代わりに組合を立て直すために組合員たちに呼ばれ、彼らと一緒に働くこと
になった。
私が組合で働きはじめる前は実質的に組合の経営は破綻していた。私は政府の組合助成局宛に手紙を書き、その中でさまざま人に援助を
もとめた。スウェーデンかスイスか、私自身は忘れてしまったが、その国の大使から援助の申し出があった。私ははじめて旅費をもらいチマルテナンゴ(グアテ
マラの都市)に組合の組織化に関する講習を受けにゆくことができた。私はそのときに初めて、組合には代表者、会計、理事などの役職が必要であることを知
り、またそれぞれの機能について学んだ。
当時の組合の仕事は、組合員から民芸品である織物やバッグなどを集めて店で委託販売するだけでなく、それらの民芸品をもって行商に
出かける活動もおこなっていた。行商先は、シェーラ、アンティグア、グアテマラなどの都市のほかに、コマラパ、ハカルテナンゴ、サンファン・アティタンな
どの定期市の日にこの町の生産物をもっていて売り、組合の収益としていた。
私は衣食を忘れて組合の仕事に専念した。また自腹を切ってさまざまな行事に参加し、組合について学んだ。朝の5時には起きて店の準
備をして、閉店後は帳簿をつけたあと、自分で勉強して夜中まで過ごした。そのようにして組合の資本金を少しづつ増やして自前の店のために土地を購入するま
でになった。
私にはそれまでに、別のいろいろな組合の組織化に際してさまざまな相談を受け、その要請に応じて出かけていった。また外国のさまざ
まな機関に手紙を書き、民芸品の販路を広げた。その結果、織物に関しては、最終的にはいろいろな国に輸出するまでになった。
また[多くの観光客や見物客がやってくる]フィエスタの日には、英語とスペイン語で書かれた小さなチラシを作り、やってくる観光客
に手渡した。チラシには「民芸品組合は貧しい人たちの生産物を売る店です」と書いた。そのような努力の結果、店にはいつもお客があふれていた。
組合員たちは月末になると、委託販売の利益を受けるために集まってくるが、組合の収益が今月もまた上がったと感謝した。組合員たち
は私にいろいろな食べ物をもってきてくれた。
しかし、ある日組合員の集まりの中で会計上の不備を指摘され、その責任を問われた。私に非はなく、組合員たちが必要経費に関する考
え方をよく理解しなかったからなのだ。結局、皆から退職を勧められて、その言葉に従った。
協同組合は、それまでの商業の実権を握っていた少数派のラディノではなく先住民族で多数派のインディヘナによる経営であったことも重要であ
る。初期の協同組合は営利を目的としながらも、どこかに道徳的な共同体の色彩を持っていた。これはコフラディアの編成原理と似てなくはない。コフラディア
による社会組織の編成は、宗教と政治がわかち難く結びついていたと同時に、儀礼と消費にもまた深い関係があった。純粋な投資行為や社会的威信の向上とは無
関係の富の蓄積と消費は、インディヘナにとって背徳的なものであった。ラディノたちの経済行為はインディヘナにとっては羨望と不道徳という両義的なものに
見えたのである。ラディノたちはカトリック教区支配を受けかつ共同体の祭礼行事に深い関わりをもつ巡礼の町チャントラと(ラディノが昔から住んでいて、か
つては行政上はこの町と対等な関係にあった)谷沿いの下流の村からこの町に移住してきたものが多かった。ラディノの多くはカトリック教徒だったが、コフラ
ディアによって異邦人は排除されていた。1970年代中頃にはじめてプロテスタント福音派のセントロアメリカ教会が宣教したときに信者の中核をなしたのは
これらのラディノたちだった。
1950年代の終わりにこの町とクチュマタン高原の道路と間に支線(現在まで未舗装)が通るようになり、60年代の中頃にはバスが開通するよ
うになった。人類学者や写真家はエキゾチックなこの町のインディヘナをもとめて1940年代から馬などを使ってやってきたが、外国人観光客がまとまって
やってくるようになるのは、はやく見積もっても1960年代の終わり確実なのは1970年代以降のことである。この時代にやってきた観光客は、今日でいう
ところのエスニック観光あるいはアドベンチャー観光の嚆矢をなす人たちである。当時の観光客数がどの程度であるかを推定する資料は今のところまったくな
い。この町の最初のホテル――シャワーのない部屋だけのもの――は60年代の中頃に営業をはじめ、2軒目のものは1968年頃である。
では、外部からの著しい経済変化にみまわれた、この時代の状況を、外部の人たちはどのように見てきたのだろうか。この時代のインディヘナ社会
観は、この社会に関わってきた次の3つのカテゴリーの人たちの言説に代表することができる。すなわち、その言説とは、(i)ゲリラの革命的知識人のもの、
(ii)軍事政権のもの、(iii)プロテスタントおよび革新的カトリックによるものである。
(i)ゲリラの言説によると、インディヘナはグアテマラの固有の人民を形成し、軍隊の庇護の元に発展してきた資本主義の犠牲者である。この地
域で軍事的な活動をしたゲリラ組織は、ラディノや白人の外国人で代表される教会や資本家を搾取の張本人、村落のインディヘナや都市のラディノ労働者たちを
その犠牲者としていた。インディヘナが経済発展の犠牲者であるという言説は、マルクス主義的な図式を脱色すれば、民芸品販売のための協同組合が組織された
ときに組織者とその運動に加わった人たちの視座と同じものである。商業や交通はラディノたちに牛耳られており、インディヘナたちは彼らに支払うだけの存在
だったからである。組合の結成時に強調されたのは、民芸品の協同組合は、貧しい人たち、とくに女性に対して経済的自立への機会を与えるというものであっ
た。
(ii)軍事政権によるインディヘナの位置づけに関する言説は、この町で実際に起こった事実から判断する限りでは、軍事政権の構成メンバーが
抱いていた人種主義の延長上にあるものだ。公式的にはインディヘナは近代化から取り残された人びとであり、近代化の教化と恩恵を必要とする人たちである。
このような言説は次にのべる「暴力の時期」に盛んに登場する。グアテマラ西部におけるゲリラの暴力的な排除と徹底的な軍事的支配の論理とは、そのようなイ
ンディヘナの近代化への遅れが共産主義者の暗躍を許すという解釈をもとにしたのであり、インディヘナの近代化には発展の阻害要因となる共産主義者のせん滅
が不可欠という思考へとエスカレートする。
(iii)宗教諸派の革新派――ここでは現状に不満をもち改革が必要であると主張する勢力をこのように一括する――は経済や政治などの改革に
関心があるのではなく、インディヘナの精神的な改革が必要であると主張していた。クチュマタン高地における福音主義派プロテスタント諸派の活動はすでに
1930年代にはいくつかの村落ではじまっていた(La
Farge
1974)。しかしそのような活動は局地的なものであったし、必ずしも永続的な活動とはいえなかった。この町では先にふれたが最初のプロテスタントによる
活動は70年代に入ってからである。プロテスタントはコフラデ(コフラディアのメンバー、信徒)のとりおこなう儀礼的消費を背教的で無駄なものとして批判
した。このことが、過重な出費に苦しむ特に経済的貧困層の入信に成功しながら、伝統的な宗教=政治組織であるコフラディアの成立基盤を蝕んでいった。
しかし、この町ではそのようなことが起こるかなり以前――1960年代の初頭――に革新派のカトリックが到来し、伝統的な組織の解体がはじ
まっていた。それは、この町にアメリカ合衆国からの白人神父がやってきたことに起源をもつ。アクション・カトリカなどと呼ばれるカトリックの革新運動は、
中央アメリカにおけるプロテスタントたちの急速な教勢の伸びに対する正統派からの抵抗であり、村落におけるフォーク・カトリシズム(民衆カトリック信仰)
の一掃がその目的にあった。この町にやってきたカトリック神父は、コフラデたちのおこなう異端的な儀礼を嫌い、まず教会内で彼らが儀礼をおこなうことを禁
止した。また、それまで教会内に多数にあった聖人像を片づけ、聖人崇拝をおこなうことを制限した。さらにカテキスタと呼ばれる在俗の説教師たちを養成し、
彼らに監視役の機能を持たせてローマ・カトリックの信仰から著しく逸脱する儀礼やそれをとりおこなう人たちを非難した。カトリック革新派の人たちは、コフ
ラディアの儀礼的消費について直接に批判することはなかったが、コフラディアの信仰を批判することを通して、儀礼的消費の構造を変容させていった。大まか
に言えば、これによってコフラディアの日常的な儀礼は抑圧されてゆき、守護聖人の祭礼など村落の大きな行事においてのみ伝統的な儀礼をとりおこなうことだ
けが許されていった。そのためコフラディアは町の生活を常時統制する機能を徐々に衰退させていったと思われる。
インディヘナの社会状況に関する前者の2つの勢力もまた宗教勢力に劣らず、彼らの理念にもとづく実践を社会でおこなっていた。彼らには、いっ
たいどのような処方箋が用意されていただろうか。それは<革命的変革>か<軍事主義的な秩序の尊重>である。この外部由来の2つの言説は、実際にゲリラと
軍隊という2つの組織を通して村落を支配を通して実現されることになる。この場合の「支配」とは彼らによる暴力と機制秩序の破壊のことを意味する。
2.2 暴力・1981-82年
革命勢力は、インディヘナを被抑圧階級であり革命の担い手と位置づけた。つまりインディヘナを中心とする民兵を組織し、最終的に都市に進攻し
政権を掌握するという設計図を描いたのである。1981年初頭に、この町にやってきた「貧民ゲリラ軍」(EGP,Ej屍cito
Guerillero de los
Pobres)はラディノたちを中心に組織されていた。彼らが始めてこの町にやってきて、土地の人びとの心をとらえて放さなかったのが土地をすべての人た
ちに解放するというメッセージであった。ゲリラの言説は教育を受けた一部のインディヘナ、たとえば教師たちに共鳴を与えた。農民にも共鳴者があらわれた。
ゲリラは少年や若者に対して軍事教練をおこなった。しかし、ラディノのゲリラ指導部においても人種主義が完全に克服されていたわけではない。例えば、イン
ディヘナのうち比較的土地をもった農民や商人は、ゲリラ支配の末期においては、テロリズムの対象になりやすくなった。あるいはゲリラ内部のモラルも低下
し、処刑が容易におこなわれた。一般にグアテマラのインディヘナは暴力の犠牲者として語られることが多いが、ゲリラによる軍事的な支配のもとでそれの枠組
みに自発的に組みしてゆく過程も多くみられる。
ゲリラを一掃したあとに、この町へ侵攻してきた軍隊は住民の暴力への馴化を極限にまで推し進める。軍隊は暴力がもたらす恐怖という支配の方法
にのみ依った。彼らは考えられ得る方法によって町の人たちをさまざまな拷問にかけ処刑した。恐怖によって秩序を維持しようとするが、支配の末期にはほとん
ど人びとにとって軍隊は恐怖を与える装置以外のなにものでもなくなっていた。その顛末についてある男性の記憶から説き起こしてみよう。
【ゲリラと軍隊】(C・J、30歳、インディヘナ、男性)
自分たちは30年間にわたって太平洋の農場(フィンカ)に搾取されてきた。しかし、どこにも、それらに抵抗する機会というものはな
かった。つまり1981年になるまでは・・・。
[最初のゲリラの到来]
土曜日の朝9時、頭巾をして武装した「貧民ゲリラ軍」がやってきた。彼らは男だけでなく、女もいた。250人は男で、50名は女
だった。彼らはペンキでさまざまな政治的スローガンを壁に書きなぐっていた。半時間ほどそんなことをした後で、コントラパルテ(ゲリラに協力的な地元民)
を使って中央公園に集まるようにという宣伝があって、2千人をこえる人びとがあつまってきた。
ゲリラのリーダーは人びとに挨拶して、スペインからの侵略から現在までの危機について演説し「今や革命の日は来たれり、連帯しよう
(武器をもって)闘うのだ」と言った。リーダーは演説のなかで人びとにとって非常に重要な鍵になる言葉を人びとに授けた。その言葉が人びとを惹きつけたの
だ。それは「土地を人々に解放する」(Abra
tierra)という言葉だった。これによって人びとのあいだから拍手がおこった。人びとは金を出し合ってゲリラたちにコーラやパンをふるまい歓待した。
ゲリラたちは公園にあったグアテマラの国旗を降ろし、代わりにチェ・ゲバラの顔が描かれた旗を揚げ、国旗を広場で燃やした。時刻はようやく正午になろう
としていた。
[2カ月後、1981年3月]
貧民ゲリラ軍は再びやってきた。彼らは最初に周辺の村に現れた。つまりM、L、J、P、Tから町にやってきた。ドン・Fの父親はド
ン・Cと呼ばれ、住民からはゲリラの共感者で町のリーダーと目されていた。ゲリラたちはドン・Cの家に集まり、2週間にわたって集会をおこなった。集会の
内容は最初は理論的な話から始まった。やがて各家から2人の男の子を出させ訓練させるという通達をゲリラたちは出した。Cの家からは、私とすぐ上の兄が出
た。訓練は夜に行われた。私と兄は当時太っていたので、訓練に耐えられないと判断された。これが私たちが救われたきっかけになった。
[さらに3カ月後、1981年6月頃]
それまでに貧民ゲリラ軍の「哲学」(filosof誕)が変わり、彼らは独自の保安官や弁護士をおいて、この町のなかの問題解決を
おこなおうとした。ただし、それは私からみてかなり非合理的な方法によってであった。
この町ではつねに土地の境界をめぐって争いがおこなわれていた。ゲリラの弁護士たちは、両方の当事者から話を聞いて調停するのでは
なく、一方から賄賂――500ケッツアルだ――をもらって、別の片方を夜のうちに暗殺した。恋人の取り合いで男が別のライバルの男の暗殺を依頼することも
あった。またゲリラたちは付近を巡回中に、品揃えのゆきとどいた店に入って、その店の主人を金持ちだと決めつけ、主人を殺し、店を破壊した。しかし、品揃
えがゆきとどいていることと主人が金持ちであることは違うだろう?。その店が借金で運営されているかもしれないからだ。
またゲリラたちはバスを燃やし、道路を寸断した。ゲリラたちは自分たちの法律を作り、夕方6時以降の外出を禁止した。しかし、遠く
に畑があり、その時間までに帰宅にまにあわなかった7時頃に帰ってきた農夫をスパイ容疑で殺した。「黒いホセ(Jos・Negro)」と呼ばれていた男は
村人を5、60人は殺したのではなかろうか。町/共同体は完全に外部との連絡が断たれ、(それまで住民がしばしば行っていた)県庁のある都会にも出かけな
くなった。道も閉ざされていたし、行けばスパイ容疑にされるからである。しかし、その頃にはこの町にも村人にカモフラージュした軍隊のスパイがすでに村の
中に潜んでいたのだ。
ゲリラの到来以来ラディノたちはほとんど村を捨てて出て行った。
[1981年7-8月]
200から300名の政府の軍隊がやってきた。軍隊にはさまざまな階級があるがカイビル(caibil)というクラスの兵隊がいた
(6)。彼らは赤いベレー帽をかぶり、顔には迷彩をほどこしていた。彼らはもっとも危険な連中で猫や鼠を殺すように人びとを殺害していった。初めに軍隊は
R(地名)に着いて、60戸の家を燃やし、2、3人を殺害したのを皮切りに道沿いの民家を次々に火をつけていった。そして町(プエブロ)までやってきた。
村の娘たちが20人から25人の兵隊に強姦された。強姦された者には、女性性器を切り取られて死んだ者もいるし、後に病気で死んだものもいる。町にある機
械という機械は壊された。
軍隊の隊長は人びとを中央公園に集めた。彼はまたゲリラのいる場所を教えないと、ヘリコプターで町を爆撃すると脅した。そして、民
兵組織を作れ、我々は武器を供与すると言った。しかし、後になってわかることだが、それはすべて嘘だった。隊長は、この町からリーダーたちを選出しようと
人びとに呼びかけた。何人かの男たちが選ばれて、兵隊たちの前に出てきた。男たちが出そろった後で、隊長は次のように言った。「お前たちは、ゲリラのリー
ダーだ、みんなで殺そう」と。カイビルが呼ばれ、一人づつ男たちの指をナイフで切り落とし、腹を裂き、男根を落とし、山刀(マチェーテ)で頭を割り、足の
裏の皮を剥ぎ、そして最後にピストルで殺害した。あるいは油をかけて火をつけて殺した。こうして140人ほどが殺された。最後の10人はゲリラの最も重要
な10人だと言われ、S(山向こうの隣り町の地名:山中を徒歩で5時間の場所)への道を歩かされた、道すがら兵隊は男たちの耳を削ぎ、手足の指を落とし歩
かせて、彼らの拷問の限りをつくし、最後まで痛めつけて殺した。
人びとは夜になって、犠牲になった男たちの死体を担ぎ、即席の通夜をしたり、そのまま墓場まで持っていって埋葬した。朝になると
(野犬が食べたために)骨と爪だけになった指が広場に落ちていたこともあった。兵隊は、人びとを集めた後に、老人をピストルで脅し彼を走らせ、ピストルで
足元を撃ち、老人が狼狽するところを楽しんだ後、殺した。
[1981年9-10月]
このようなことが連日続いたので人びとは町から逃げ、周辺の山の中に住んだり、太平洋岸のフィンカへ移住したりしていった。軍隊は
4カ月間教会を本部にして駐屯していた。その間、町はほとんど人が住まない状況が続いた。老人だけはゲリラの疑いがかけられなかったので町に住むことがで
きたのだ。
[1982年初頭]
軍隊は教会の前に人を集めて、そして教会の中に成年男子を閉じこめて、次のようなメッセージを発した。「今からすべてのものを焼き
尽くす。ここには人がもういられなくなるだろう」、と。このメッセージを聞いて、人びとのうちある者は泣いたり、また落ち込んだりした。しかし、翌朝軍隊
は突如として去ってしまった。人びとは不思議がってラジオをスイッチを捻ると、ルカス・ガルシア政権が、リオス・モント将軍によるクーデタによって倒され
たことを知ったのである。しかし、このことを聞いて人びとは再び軍隊が戻ってくるだろうと言い始めた。今までのようなことが二度とおこらないように、町の
人たちは代表者を首都に派遣して、モント将軍あるいはその秘書とかけあって次のような約束をとりつけた。新政権は町の代表者に次のように告げた。「グアテ
マラの国旗をそれぞれの家に掲げなさい。もし、国旗が掲げられなかったら、その地区に爆弾を落とすだろう」と。
同じ軍隊が戻ってきたが、その時には彼らの哲学が変わっていて、村人を不用意に殺すようなことはなくなった。軍人たちは人びとに識
字教育を授けるようになった。しかし、教室でもいつも「ゲリラ兵士はどこにいる(¿Dondé están guerrilleros
?)」などを質問していた。軍隊はまた、町の北側の山の斜面にこの町の名前を白い石を組んで文字をつくった。これが今でも見えるあの山腹の文字なのさ。
軍隊あるいは軍事政権が考える村落の共産化を防ぐ論理と方法とは次のようなものである。最初の軍隊の進攻の時点で、不在だった家はゲリラの共
鳴者の家であるから、このような不満分子の家は焼き払わねばならない。恐怖によって人間は真実を述べるものであるので、拷問は正当化される。破壊し尽くし
た村落をそのままにしておくと住民の不満がたまりゲリラに再び共鳴する危険性があるので、食事と雨露をしのぐトタン板を援助しなければならない。軍事侵攻
によってゲリラが一掃された地域には民兵組織を創り、国家が銃を貸与し自ら町を守らねばならない。この治安のための民兵組織の理念は「フリホーレスと銃」
(Frijol
y Fusil ;「食べ物を確保させ自らを共産化から防衛する」スローガン)と後に呼ばれるようになる。
このような暴力の常態化である民兵組織の形成は、すでに崩壊しつつあったコフラディアに代わる新しい社会秩序を提供し、それ以降の町の人たち
の経済活動に対して一定の社会的な条件を提供した。すなわち、民兵組織は男性を中心とした力による社会統制の制度化という一種のテロリズムの土着化の道を
たどる。そして経済力のある有力な家族が民兵組織の中で中心的な位置を占めることによって、権威と服従のヒエラルキーが形成された。
暴力が彼らの経済活動に与えた影響は、たんなるその中断にとどまらない。この2年間を境にして社会は根本的に変化した。まずこの時期ほとんど
すべてのラディノが転出したことである。これは、それまでラディノが支配していた経済活動の停止を意味する。もちろん転出したのは彼らだけでなく軍隊が支
配している間、この町は完全に住民が住まない空虚な空間になった。住民は軍隊の侵攻直後から付近の山中に逃げ、野営暮らしを余儀なくされた。さらに軍隊に
よる拷問や処刑が常態化されるなかで、町に残っていた人たちは山中に逃げたり、太平洋岸のプランテーションに職を求めて町を後にしていった。つまりイン
ディヘナの国内難民化が始まった。これらの難民はメキシコ領内に難民キャンプが設立され、彼らの受け入れがルーティン化されるにしたがって正式の難民とし
て認定される者もでてきた。いずれにしても町はゴーストタウンと化した。「町に残ったのは野獣だけになった。そして軍隊だけが残ったのだ」。
《下表:このT町における政治暴力関連年表》
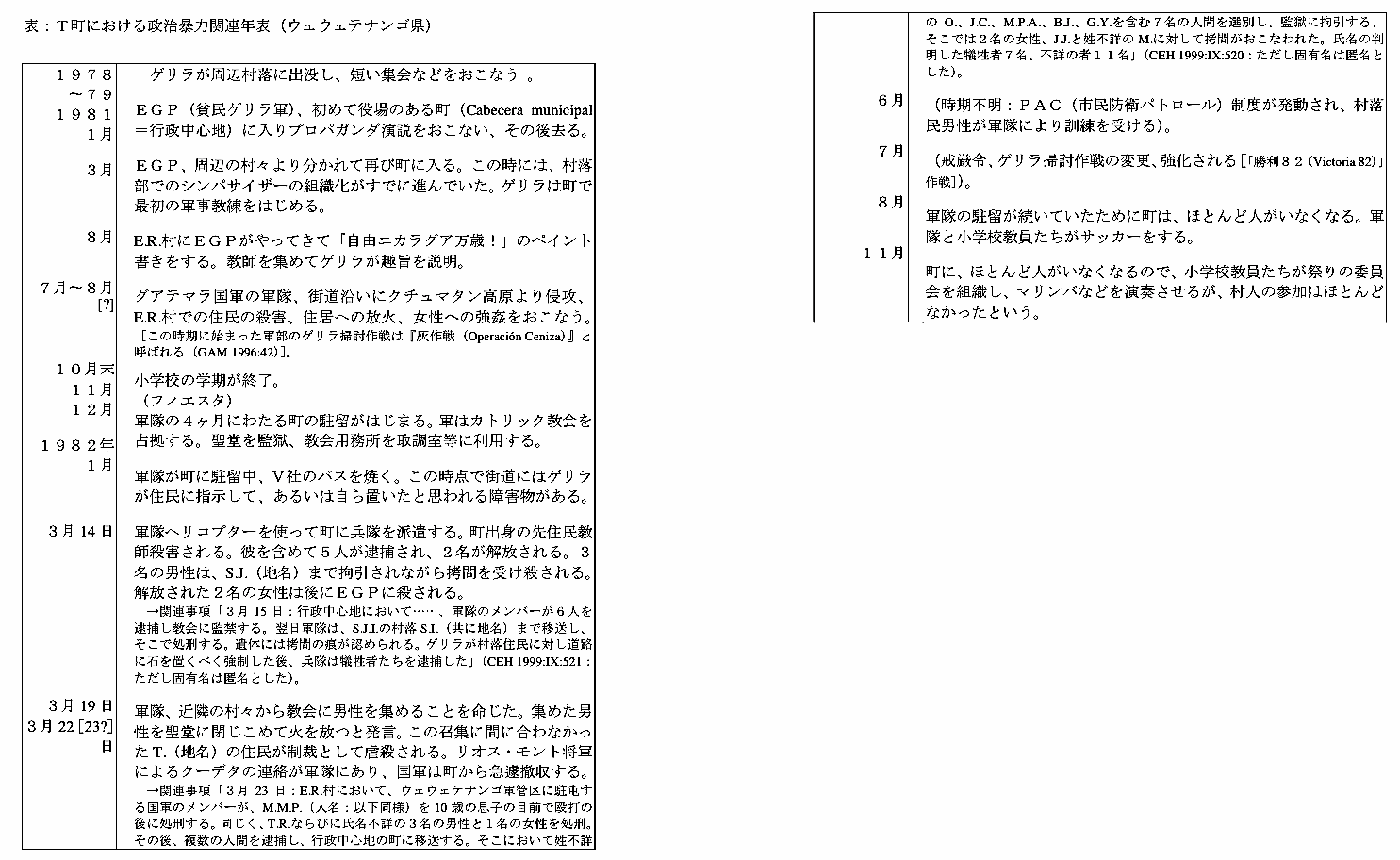
このような社会解体の後、つまり1983年以降インディヘナの人びとは徐々に町に戻ってくるようになったが、この町出身者を含めてラディノの
多くはこの町には戻らなかった。インディヘナはもともと人口において優勢であったが、これにより商業活動においてもイニシアチブを握るようにもなった。言
うなればラディノが占めていた経済的なニッチをインディヘナが占めるようになるのである。
破壊は村落の景観そのものを変えてしまった。その破壊のすさまじさは、予備知識なしに訪れた観光客が恐怖のあまり当惑して、滞在期間中ホテル
から一歩も出なかったという次のエピソードからも想像に難くない。
【暴力の町への帰還】(M・O、50歳後半、ラディナ、女性)
私たちは、夫の妹からこの旅館を買って、旅館業と食堂を営むようになりました。
ゲリラたちがやって来てから、ラディノたちは二束三文で自分たちの土地や家をインディヘナたちに売り飛ばして、この土地から逃げて
いきました。そのためにラディノの家は最後には私たちを含めて2家族だけになりました。
観光客もほとんどいなくなり、また情勢も芳しくないので、夫は県庁所在地の都会に出ようという決心していたようです。そのような矢
先に、軍隊がやってくることをラジオ放送で知り、着の身着のままで逃げたようなものです。私は、大きな篭ひとつにコップ一個しか持ち出せない有り様だった
のです。町から出るトラックの荷台にたったそれだけの荷物をもって逃げだしました。道すがら軍隊のトラック10数台とすれ違いました。R(地名)では多く
の家が燃やされていましたが、軍隊はそれらの留守の家はゲリラの支持者に違いないという理由らしいのです。私は涙がぽろぽろ出ました。
Hの町には1年ほど住んでいました。しかし、私たちの生活の基盤はこの町にあるといつも考えていたので、夫は町に帰る決心をしまし
た。だけど私は、この町を出たときの恐怖を思い出すと、ここに帰ってきたいとは思いませんでした。だから、この時も道すがらずっと泣いてました。この町に
帰ってきて、変わり果てた自分たちの家を見てまた涙がでてきました。というのは家財道具はすべて略奪された後でしたし、軍隊は自分たちの旅館を焼こうとし
たらしく建物の一部が焼けこげていたからです。幸い火は回らずに旅館がそのまま残っていました。
というわけで、また最初から旅館を始めることになったのです。もちろん最初は誰もこの町にやってくる人などいませんでした。やが
て、1人2人と観光客がやってきました。しかし、観光客はこちらにくる道すがら焼き払われた村々を見てきて、この町にやってくるころにはすっかり臆病に
なって、誰一人として旅館の外に出ていくものはいませんでした。私の夫は旅館の客に「もう危険な時期は済んだので、どこにでも好きな場所にいきなさい」と
観光客に勧めたのですが、誰もその言葉に耳を貸す者はいませんでしたね。
いうまでもなく、この破壊の経験は、町に残った人も町から戻ってきた人たちに対しても心理的な外傷をもたらしたことは想像に難くない。
1987年すなわち暴力の時期から5年後の私の研究テーマ――村落医療の現状――にも関連するだろうが私が3カ月の滞在において聞いた暴力関連の話は、す
べてインフォーマルな対話の中だけであり、話してくれた人たちはその会話の内容を秘密にすることを要求した。しかし、今回すなわち暴力から10数年後に
なって、人びとは当時の暴力についてさまざま解釈を交えて比較的自由に語り始めていた。
暴力がどうしてこの町に起こったのか、人びとはさまざまな角度から独自な解釈をおこなった。また、その議論は以前よりもオープンになった。そ
れらの解釈の中には、人びとが白人の神父の考えを受け入れて伝統的な慣習を放棄した時から、人びとは堕落し、それを罰するためにゲリラや軍隊がやってきた
とか、神がそれらを遣わしたのだという終末論的な解釈から、ゲリラがかつて説明したように都市による農村の搾取がもたらした結果であるというものまで多様
である。
沈黙の後での人々の多様な解釈と語りは聞き手である私にとって、人びとが現在の状況までの来歴であると同時に、そのように解釈を与え、経験を
中和することが暴力後の時代を積極的に生きようとする人びとの適応のプロセスの産物であるかのような印象を与えた。暴力から10数年を経て、人びとは暴力
を意味について考え、さまざまな解釈を与えることで、人びとの記憶の中に拭いがたい刻印を記した暴力を乗り越えようとしている。
2.3 コスタからノルテへ
私の理解によると暴力の時期(1981-82年)以降は、この社会は根本的に変わってしまった。私が調査したのは1987年と1996年であ
り、それ以前の状況についてはすべて調査時点での人びとの記憶や体験から再構成した。しかし、人びとの生活に関する記憶は、暴力の時期それ自体がその時代
を生きた町の人びとにとって時代を画するマーカーになっており、少なくとも現時点で成人の人びとが町の歴史について語る際にも重要な出来事となっている。
暴力後の時代こそは我々の時代なのだ。この時代の特徴を次の3つの要素に分けて考察してみる。すなわち、暴力の制度化、暴力がもたらした政治経済的効果、
経済活動の活性化の3点である。
2.3.1 暴力の制度化
民兵組織にもとづいた新しい社会秩序は何を意味するのか。それは低水準のテロリズムの持続でありテロリズムの土着化であった。村落においては
民兵組織によって<軍事主義的な秩序>が形成されゆく。人びとはそのような中で制度に自分たちの生活をあわせてゆくことを余儀なくされる。このことは心理
的に暴力の記憶を忘れたい人びとにとって、代替的で常態的な暴力が提示されることを通して彼らの感情を抑圧することにつながってゆく。人びとは暴力はおろ
か、おぞましい記憶につながる政治そのものについても語ることをはばかるようになるのだ。しかし、人びとは暴力後の世界を生きる新しいアイデンティティを
求める。コフラディアが提供してきた儀礼への服従は、民兵組織への自発的参加へとかわるようになる。それがインディヘナの排外主義的な心情と一致したから
である。ところが伝統的儀礼はもはや暴力後を生きる人びとに何ら拘束力を発揮しない。また富を生み出すと考えられてきた土地は「搾取の時期」の末期には、
慢性的な土地不足のためにもはや魅了するものではなくなっていた。彼らを魅了するようになったのは、新たに富(=金銭)を生み出す手段、つまり商業活動で
ある。
この状況は暴力の時期が生んだ別の要因によってさらに加速される。つまり暴力の時期を通してそれ以前の商業活動を牛耳っていたラディノが町か
ら逃亡したことである。このためラディノによる商業活動の支配という軛が外れた。この町のインディヘナたちはもともと商才がなかったというわけではない。
プラサと呼ばれる定期市のシステムを伝統的に発達させており、インディヘナが商才に欠けるという根拠はどこにもない。問題は運輸や工業製品の卸売り、仲買
のレベルにおいてラディノが先にそれらの活動を独占していて、あとから介入できる余地がなかったからである。この町のインディヘナもまた「小銭資本主義
Penny
Capitalism」(Tax
1953)の担い手であった。小銭資本主義は、通常のグアテマラの伝統的な社会の「ミルパの論理」に従うと、コフラディアなどの儀礼的な消費とそれによる
社会的威信の向上という村落共同体の論理を打ち固めてゆく回路に回収されると解釈される。しかし、この町では「搾取の時期」にはすでに白人の神父と革新的
カトリックによってコフラディアの論理が解体ないしは弱体化され、暴力の時期には完全にその息の根が止められていた(7)。
2.3.2 暴力がもたらした政治
経済的効果
70年代後半から80年代前半にわたってグアテマラ西部にもたらされたゲリラならびに軍隊による長期わたるテロリズムが村落のあらゆる制度・
慣習・文化を破壊したことが世界的に知れわたるようになった。そのため1980年代の中頃から先進諸国の政府および非政府組織は、医療と村落開発の援助に
乗り出す。先進諸国民による援助は、人道的な動機に基づきそれぞれ個々の活動においては公正な運営が行われた(はずである)が、少なくとも社会的影響力の
全体から言うと、1990年代以降顕在化する米国への不法就労とならぶ無秩序な外部からの貨幣がもたらされる基盤が整備されたと言っても過言ではない。
先に述べたように「搾取の時期」における現金収入の道はグアテマラ南西部の太平洋岸(コスタ)のプランテーションに季節労働者として働きに出
ることであった。コスタでの労働は過酷でかつ慣れない気候の影響もあって感染症やマラリアなどの熱帯病に罹患することが多かった。またプランテーション労
働を勧誘する労働調達人は、人びとが祭礼の準備をする季節に労働者の家を訪れ先に賃金を前貸しした。祭礼が終わり労働者たちがその金を使いきった時期に、
プランテーション行きのトラック、後にはバスがチャーターされるといった形の労働調達をおこなったために、コスタ行きの労働に関する人びとの印象は悲惨と
いう一言につきる。
しかし、1990年前後から登場した魅力ある出稼ぎ方法は、カリフォルニア州を中心とするアメリカ合衆国における不法移民・不法就労である。
彼らはコヨーテと呼ばれる運び屋に比較的高額の料金を渡してアメリカ国内への「旅行」を試みる。コヨーテがおこなっていることは違法であるが、首都の新聞
には「身分証明書だけでアメリカへ旅行できます」という広告が堂々と掲載されている。コヨーテが組織するこの種の「旅行」には実にさまざまな形態があり、
バスやトラックをチャーターするものから公共交通機関を使って、中継地ごとにエージェントの案内で国境までたどりつくものもある。またメキシコとアメリカ
合衆国の間にはアメリカの入国管理局(ミグラ、スペイン語の移民であるmigraci溶から転じた俗語)の厳しい監視がある。国境地帯にはアメリカに越境
するラテン系の人びとをねらった詐欺や犯罪が多発するために、米国への不法入国にはさらに大きな危険が伴う。グレゴリー・ナバ監督作品の『エル・ノルテ』
(1983年)に描かれているグアテマラ難民と同様、この種の過酷な経験談はこの町出身者の口からも数多く聞くことができる。
アメリカ合衆国はメキシコからの不法就労者の入国に対して厳しい締め出しの政策をとっていたが、人権保護の立場からグアテマラやエルサルバド
ルの政治難民に対しては就労許可を含むビザの交付には便宜をはかっていた。そのためこの町を含めたグアテマラ西部出身のインディヘナたちは、いつのころか
らか入国後に不法移民であることが発覚した際に政治的理由でグアテマラから逃れてきたと主張する者が増えてきた。さてグアテマラ国内において軍隊が町の人
を殺害した後にゲリラの宣伝(と思しき)文書を被害者のポケットに入れてその「殺害」を正当化したということを私は思い起こす。アメリカにおける「政治偽
装難民」について考えるとき、私は軍隊によって死者のアイデンティティを簡単に変更させられてしまったこの権力の暴力的な「技」が、まったく別の文脈の中
で形を変えて、町の人々自身によって今度はアメリカの入国管理局に対して自分たちの生計と生存を確保するための「技」として使われている気がしてならな
い。彼らが経済的な理由で越境してきたとしても、その人の出身地が係争地であり自らが「政治難民」と言っているかぎりそれを否定することは容易ではない。
そもそも一個の全体としての難民を「政治」と「経済」の機能に分割すること自体が無理な相談なのだ。抑圧に使われた権力者の「技」が、今度は生活者の生存
のための「技」として利用可能になった理由はここにある。
アメリカ合衆国におけるラテン系の不法移民は、リオ・グランデを泳いで渡ったという逸話にもとづいてモハードmojado(濡れた者の意味、
英語ではwet
back)と呼ばれている。モハードたちに関する正確な統計は手に入らないが、この町ではおよそ1500人ほどがアメリカで働いているという推測もある。
これをそのまま信じるとすると、この町全体の人口2万人に対して7.5パーセントにあたる。
元モハードあるいは現在家族の一員がアメリカで働いている人たちの話をまとめると次のような、モハードたちの一般像が描ける。アメリカに渡る
人たちは最初は男性が多かった。コヨーテに手渡す金はかなり高価なので、親から金を借りたり周りから借金をする者が多い。アメリカに行く動機は1にも2に
も賃金の高さである。外国を知りたいという動機からだと言う者もいるが「旅行」費用は生半可な額ではなく、経済的理由がその主たるものとしてみてよい。ア
メリカ渡航に失敗したものは、再び借金をして成功するまでそれを続ける者が多い。アメリカに行かねばコヨーテのために使った借金が返せないからである。渡
航した半分の人たちは行方不明、つまり出身地との連絡が途絶える。連絡をしてきた半分、つまり全体の4分の1の人たちが、まがりなりにも職を見つけて送金
をしてくるという。渡航の期間は1年から数年である。最近では渡航する女性も増えている。女性が増えた原因は、最初に渡った男性たちの生計が安定し彼女た
ちを呼ぶことができるようになったからだ。やがてアメリカに定住し、向こうで家族をもつことで出身地に送金することをやめる者も出てきた。アメリカに渡航
することは金もかかり難しいが、帰国は驚くほど容易である。彼らは、アメリカの入国管理局に出頭し不法移民であることを宣言しさえすれば、あとは強制送還
の手続きによって安全かつ無料で帰国することができるのである。
2.3.3 経済活動の活性化
モハードたちが送金する額は現地の彼らの生活水準によってまちまちだが、1回におよそ数百ドルが送金される。この額はグアテマラ一人あたりの
年間所得がおよそ3000米ドルであることを想像すればその経済影響力の大きさがわかる。90年代以降モハードの数は急増しているので彼らが出身家族に送
金するドルマネーの総額はかなりなものにのぼる。これらは現地の経済活動の成長からもたらされたものではないので、ある種の「バブル経済」的発展に寄与し
ていると言える。私の9年後の再訪においてもっとも印象的だったのは、町の家の数そのものが増えたのみならず、ブロック造りの2階建て家が多く目についた
ことであった。人びとはブロック造りの家を指して「あの家の息子は今アメリカで働いている」と異口同音に説明した。
送金された金は家を新築することだけではなく、商売を始める、トラックを買うなどのさまざまな投資行為を引き起こした。土地の値段も高騰した
が、土地転がしのような事態は起こらなかった。貯蓄や近代的な金融に対する考え方は十分には普及しておらず、ようやく銀行の支所を町に設置すべく銀行の職
員が派遣されて調査がおこなわれている。これもバブル経済の余波である。
【町の経済状況】(H・E、25歳、ラディノ、男性)
町(行政区)全体の人口は24000人で、そのうち18歳以上の人口は16500人だ。だいたい年間に1100人から1150人が
生まれ、175人から200人が死んでいる。つまり年間の増加はだいたい1000名である。しかし人口増加率が増したのは1990年以降で、おおよそだが
1982年から90年までは年間600名ほどの増加だったは90年ぐらいから年間1000人になった。
人口増加によって人びとは新たに耕地を開墾するようになった。土地はすべて私有地で共有地(エヒード)はない。現在でもコスタで働
く人はなくならないが、以前にくらべればコスタに行かなくなったし、またそれを好まない。
人びとは商品作物を栽培するようになって、去年はカリフラワーをそこかしこに植えていた。しかし最初は地元では誰も食べず、すべて
市場に送って売っていた。経済活動が盛んになったもっとも大きな理由は、援助団体や政府の組織が農業や民芸品に対して補助金を貸し付けるようになってきた
からだ。彼らが貸し付ける利息は年率18から28パーセントで、それを2、3年で返済するというものだ。それらの組織から金を借りる時にはペーパーワーク
がたくさんあって貸し付けする職種やプロジェクトにはさまざまな制限がある。
これに比べて個人や民間の貸し付けは利率は月額10パーセントで高い(単利なので年率120%となる―池田)が結構人びとは利用し
ている。この貸し付けの利点は受取書を作るだけで余計なペーパーワークがないことだ。ただし、返済不履行などのトラブルが絶えないので、貸し借りは近親間
が中心である。
また経済が活況である別の理由として、政府が4カ月おきに人口に応じて公共投資していることだ。この町では現在40万ケッツアル
(1996年秋のレート換算で、約6万7千米ドル)が支給されている。最近完成した公設市場の新築の際には150万ケッツアル(25万ドル)が支給され
た。
定期市は地方でできた農生産物を流通させるという伝統的な機能から、この10年間で外部からの農作物および工業生産物を流通させるという機能
のほうに大幅に比重が変化した。定期市は、すでに「搾取の時期」においてもコスタにおいて儲けた金がそこで支払われ経済の活況に貢献したのだが、今ではモ
ハードたちの送金は、かつてのコスタからの貨幣の流通を凌駕しており、その影響力は以前の比ではない。
また織物を中心とする民芸品が定期市において取引されるようになり、民芸品産業ともいえる部門が成長した。それにともない民芸品の性格が、自
分たちが身につけアイデンティティの表象する事物と、外部にむけて生産される商品という2つに分解することを促進させた。現在では、土地の民芸品である編
み物の袋の半完成品が出荷され、この町の圏外で加工をうけた民芸品がグアテマラ国内はおろか北米やヨーロッパにまで輸出されている(池田
1997)。
【民族衣装はもう着ない】(P・M、35歳、インディヘナ、男性)
P・Mさんは現在町を出て、妻と二人で県庁所在地の都会に移り住んでいる。彼は毎週末に自分の出身の町に戻り、土地の民芸品である
編み物の袋の半完成品を仲買している。彼は現在の居住地に小さな工房をもち、10人ほどの若者を雇用して、仕入れた編み物の半完成品に皮底や紐を縫いつけ
補強し、首都をはじめとした全国の観光地の民芸品店に卸している。
彼が出身の町で現地の同胞のインディヘナから仲買するときはジーンズに民族衣装のシャツを身につけ、その上に町の男たちが羽織るよ
うに皮ジャンパーを着ている。
それに対して、彼の妻はどこへ外出するときでも――私が高級レストランに彼らを招待したときも――民族衣装であるウィピルで出かけ
る。この都会の近くに住む彼らの遠縁の親戚の女性は、7年前出身の町を出てラディノ男性と結婚し、そして出身の町には決して戻らないと言っているが、彼女
は異邦のその土地でも糸を紡ぎ自分のウィピルを作り、そしてそれを脱ぐことはあり得ないといっている。
以下は私(I)と彼(P)との対話である。
――[I]君はもう町の民族衣装(traje típico)は着ないのか?
――[P]もうここ(都会)では着ることはないよ。
――[I]この都会で商売をするようになった当初から着ていないのか?
――[P]初めは着ていたよ、最初の何年かはね。
――[I]民族衣装を着ることで何か不都合なところでもあるのかな?、商売仲間のラディノは偏見をもつかな?
――[P]それはある。人種主義は無くならないよ。君に以前話したように、シェーラ(グアテマラ第二の都市)では市長選でインディヘ
ナの名前がでるだけでも(人種主義的な)問題が起きたのだからな。
2.4 何が変化したのか
町の現在の状況について語ることは、町の人たちが経験してきたことを語ることである。
まずインディヘナ自身は、この町の変化を説明する際に、自分たちを搾取の犠牲者として従属的な主体から、自由意思をもち好きなことをやれる自
立的な経済主体へ変化したことを明白に意識して語るようになった。この変化は彼/彼女らのふうアイデンティティの選択肢の多様化を意味する。例えばかつて
はコフラディアが否定された時点で、その未来への処方箋が<革命的変革>か<軍事主義的な秩序の尊重>という二者択一的選択しかなかったのに対して、現在
ではすべての人たちに経済自由主義のもとで自由に商売ができるというふうに信じるようになった。
はじめゲリラが人びとの心をつかんだのは、「土地の解放」というスローガンによってだった。土地は富の源泉だったからである。その後に登場し
た軍隊はこの社会を破壊した。しかし、この社会をあたかも更地のようにした軍隊は、民兵組織という秩序を通して暴力を土着化させ、人びとの政治的な意識を
忘却することを推し進めた。軍事政権が用意した低水準のテロリズムの施行つまり「暴力の土着化」によって、町には一定の秩序が戻った。そのような政治的な
安定、言葉を変えれば政治的な発想を抑圧すること、つまり政治の「忘却」は、結果的に人びとに対して、経済的利潤を追求する存在になることを強いたのであ
る。しかし暴力による社会の制御が、経済的発展に不可欠なものという認識から、最終的には現在のような「自由な経済」を束縛するものとして次第に意識され
るようになった。もはや暴力は世界レベルでの経済発展のためには重い軛以外のなにものでもない。もちろん、このような思潮が人びとによって受け入れられて
ゆく背景には、治安の安定や自由な政治的発言への保証など国内政治による成果のほかに、リゴベルタ・メンチュのノーベル平和賞受賞、援助に携わる外国人と
の人びとの直接的な対話、グアテマラの暴力に対する外国のメディアの影響など、多面的な変化の影響があったように思える。外国の援助団体のこの町への到来
は、新たな富の資源としての<商業>を発見すると同時に、そのもっとも効果的な商業が国境を越えた「交易」――それは外国への不法就労や民芸品などの輸出
をも意味する――であることを教えるきっかけとなった。もちろん、それは同時に外国人観光客を誘致することもまた富の源泉になるという考え方も普及した。
【観光について】(C・J、58歳、インディヘナ、男性)
この町の民芸品(男女の民族衣装、手編みのバッグなど)は最初から自分たちのために作るもので観光用にあったものではない。観光土
産として観光客が買っていけば、それはそれで家計の足しにはなるが、それらはあくまでも自分たちのものだ。いま、ここで娘が[女性用の民族衣装の]布を
織っているが、それは同じ家族の別の娘のためなのだ。特に最近は民芸品の手仕事の内容が込んできて、それが価格の高騰を招いているということだけど、それ
で観光客が買わなくなっても、それは仕方のないことだ。それだけ手が込んでいるということなんだからな。
観光が人びとの生計の助けになるという主張があるけれども自分はそうとは思えない。観光で儲けているのは、旅館や土産物店や食堂を
経営している人たちである。
この町はこの20年間に観光化された。外国人がくるようになって人びとは徐々に外国人に馴染んできて親切になったのだ。この町の人
が、どうして外国人に優しいのか?、その理由はよくわからないな。
【観光をとおしての侵略】(C・J、30歳、インディヘナ、男性)
観光侵略(invasi溶
tur痴tica)は確かにある。自分はこの町をパナハチェルのようにはしたくない。かの地では観光客やラディノがたくさんやってきて土地を買い占め、そ
の町の中心地にはインディヘナがいなくなってしまった。そしてインディヘナは周辺の山地に住むようになった。なぜか。なぜならラディノや外国人たちはパナ
ハチェルを気に入って、あるいは投資のために湖畔の土地を売り手の言い値で買ってしまった。そのため土地の価格が高騰し、地元の人たちはもはや湖畔の土地
を買うことができずに追い出されてしまったのだ。自分はこの町をそのような状況に追い込みたくない。
文化の側面ではすべてのモードが変わってしまった。男たちは髪の毛を長くするようになったし、ズボンも変わった。すべて外国の
ファッションをまねるようになったのだ。また疎外(alienaci溶)ということも招いた。外国文化の到来とともに同性愛、麻薬密輸、薬物や酒類の濫用
が心配されるようになってきた。
グアテマラの反政府勢力の連合体URNG, Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca(グアテマラ国民革命連合)と政府の1996年末の和平交渉もまた、見方を変えれば自由な経済主体たるインディヘナの人権を認め
ようとしているのだ。この町のNGOのひとつで、外国人に対するスペイン語ならびに文化教育を通して町の経済的自立をめざすプロジェクトの目標には、外部
世界と連動するネオ・リベラリズムの目標が掲げられている。つまり、インディヘナによる政治的経済的自立、独立採算性のクリニックへの補助事業、エコロ
ジー思想の影響を受けた植林計画や持続可能な開発への援助などである。くり返しになるがインディヘナのアイデンティティ形成における排外主義とネオ・リベ
ラリズムに基づく友愛主義は両立可能なのである。
1980年代後半の治安の安定とともに福音派のプロテスタント諸派の布教がはじまり、一定の改宗者を出すという成功を収めた。もっとも古い歴
史をもつセントロアメリカ教会も1981-82年の暴力の時期以降はその担い手はラディノからインディヘナへと変化していった。他方1982年当初は伝統
的な呪術信仰の復興運動が起こりかけたが、結局はそれは教会の前と山中の先史時代の遺跡の前の2つの十字架を建てるという象徴的行為にのみ終わった。復興
運動は衰退し、革新派カトリックのカテキスタたちによってフォーク・カトリシズムの伝統は衰退しローマ・カトリック信仰の強化をもたらした。これらのプロ
セスによってコフラディアはおろかコフラディアの伝統は中断に追い込まれてしまった。守護聖人の祭りなどの祭礼の機能も、伝統的な価値の教化から祝祭や家
族が楽しむ祭礼へと変化していった。
そして1996年の現在。アメリカでの不法就労者がもたらすドル・マネーによる彼らのバブル景気がこれらの変化に拍車をかける。だが私の印象
によるとそのピークは終わりつつある。彼らは異口同音に現在の経済の活況は少しづつ停滞しつつあると言う。「商売はいまゆるみかけている」「今日びは競争
が厳しい」。これは不況というよりも、バブル景気の初期にみられるような投機的な行動がもはや功を奏さなくなってきたということである。インディヘナ間の
経済的な格差も増大してきた。むろん言うまでもなく町全体は総じて豊かになった。
1996年の10月10日に国連の平和監視団の立ち会いのもとで市民自警団の解散式、つまり武器の引き渡し式があった。10数年におよぶこの
組織の解散にあたって、成人の男性からは、これによって社会秩序が崩壊するのではないか、今度はゲリラではなく若者の非行やバブルによる好景気による飲酒
者の増加などさまざまな社会問題がさらに悪化するのではないか、自警団によるコントロールがなくなりそれらの問題が一気に吹き出るのではないかという危惧
の声が町の何人かの男性から聞かれた。
あるいは「年々増加する」プロテスタントの増加によって伝統的な守護聖人の祭りの賑やかさが失われ、そのような「伝統」の崩壊が観光収入を減
らすのではないかという心配の声もあがりつつある。もちろん、そのような伝統は暴力以降登場した「伝統」であり、人びとが観光客に説明するほど伝統は続い
てはいないとみるほうが妥当なのであるが。
3. 暴力の内旋――結論
この町の人びとの経済意識の変化において1981-82年の暴力の時期がもたらした影響は測り知れないほど大きい。また「暴力の以前・以後」
という表現は、今回の調査で人びとの年代記憶にとって重要な意味をもつマーカーになっていることを幾度も確認した。
ここで着目したいのは暴力の象徴的意味についてである。従来、グアテマラの暴力以降、エリザベス・ブルゴスを代表格にして多くの人類学者たち
はこの暴力のもつ問題、より積極的には軍隊による組織的な不正義の実態を外部の世界に対して伝えようと努力してきた(eg.
Carmack
1988)。実際に彼らが経験してきた暴力や不正義の真実は経験したものしか分かり得ない過酷なもので、また聞くことすらも辛い史実である。また、そのよ
うな不正義が事実としてあったことを知ることは、同じ時代を生きるものにとって不可欠なのかもしれない。しかし、このような経験がもたらした別の側面つま
りそこに暮らす人たちの社会変化にも着目する必要があると私は思う。
最初に暴力は、現実にこの町を現実にも根本的に変えてしまったということだ。そして、暴力に適応する中で、人びとは暴力以前により多くを共有
していたと思われる習慣や制度を放棄してしまった。暴力を理解するという行為を通して、まったく新しいアイデンティティを持つことを要求されたということ
である。
1987年当時には沈黙して語らなかったものが今や外国人向けの語学教育プロジェクトでの恰好の講演のテーマになるほど、暴力はこの町の歴史
について語るにはなくてはならないものとなった。多くの人びとが沈黙を破って、暴力や苦痛の経験について語ることが、苦痛の追体験を共有する以上の意味を
もちはじめている。その可能な解釈の一つが暴力の経験の語りを通しての、彼らの新しいアイデンティティの構築である。
第二に暴力の以前と以後では「富の源泉」に対する考え方が変化したということである。つまり、暴力以前の「富の源泉」は土地、より具体的には
トウモロコシ畑(ミルパ)にあった。土地は開拓すれば無限にあると考えられた。またトウモロコシの生産のサイクルの永遠性は富の源泉としての土地のイメー
ジにも規定されていた。この土地を資本とする永遠の生産のサイクルがミルパ論理である。
しかし、暴力以降の「1ケッツアルでも儲けたい」「誰もが商店を持ちたがる」には、富の資源を土地に求めるような態度はもはやない。富は商業
活動を通して得られるものである。あるいは富の源泉は「外部」にある。リスクを侵してでもモハードとしてアメリカで働きたいとは、この富の源泉へもっとも
容易にアクセスできるからだ。この理想を成就するためには、人間は政治的にも経済的にも自由な主体にならなければならない。そのためにはインディヘナもま
たラディノ以上に教育が必要であり、ラディノからの自立が必要なのだ。それも革命や軍事主義ではなく、人権が確保された平和国家の一員になることを通して
である。国家がゲリラとの平和交渉をおこなうのは、平和が経済的な安定成長を結果的にもたらすと人々が信じているからである。
この町が経験した経済意識の変化は、通常の経験のなかで見られる漸進的な政治経済変化とはまったく異なった極めて特異的なものである。今回の
調査を通して社会変化のパターンの特異な例を報告した。ブルデュ(1993)の描く1960年当時のアルジェリアの下層プロレタリアのように、資本主義に
適合していないインディヘナ社会が<暴力>による破壊によって、新しく適合するように再編制された、というのが私の結論である。そこにはプランテーション
が生み出す交換価値を、前資本主義的な使用価値的世界から理解するという<住民の解釈学>は生まれなかった。グアテマラはおろかラテンアメリカの各地でも
聞かれる「悪魔との契約」のエピソード(Taussig
1980)がここでみられないのはこのためであると考えられる。
註
(1)私は1996年9月からおよそ2カ月間、グアテマラ西部高地のこの町において観光が民芸品生産に与える影響に関する民族誌学的調査に従
事した。町は私が9年前に僻地医療について調査したおなじ場所であった。私は再訪によって、自分と町の人びとの9年間の変化を知らされた。この記録は、そ
のような私的経験を、グアテマラに関するおびただしい文化人類学の言説にただ単につけ加えることだけを意図して書かれたものではない。私は民族誌を書くと
いう行為を通して書く主体を自己成型する物語について考察したい。従ってこれは民族誌の対象と見なされてきた土地と人々についての言説生産の過程に寄与す
る自-民族誌(auto-ethnography)であると同時に信条告白としての自伝(auto-biography)でもある。
(2)「調査地の概要と調査の方法に関する覚書」に触れてあるが、この資料は町の人びととのインタビューや会話や語り口を、筆者である私が
フィールドノートに基づいて再現したものである。この資料は語りの転写ではなく、むしろ要約にちかいものであり、またそのニュアンスも筆者の解釈が入って
いる。この資料の目的は、語りの様式を表現することではなく、そこで言及されている内容を読者に理解可能な姿で伝えるためのものである。
(3)カポラル(caporal)の原語の意味は農場管理人だが、この話者の説明では農場から委託を受けた地元の労働調達人のことをさして、
そう呼んでいる。
(4)アビリタシオン(habilitaci溶)はラテンアメリカでは現物貸与のことをいうが、ここでは手付け金、あるいは賃金の一部先払い
金のことをさしている。
(5)創生期の組合に関する書類の資料は軍隊による焼き討ちにあってすべて焼失した。L・Aさんの年代に関する記憶は著しく曖昧であるが、複
数の関係者から総合したところ、彼は1971年頃組合に呼ばれ、1978年頃まで働いていたものと考えられる。
(6)カイビル(caibil)というクラスの兵隊の階級はスペイン語にはない。カイビルについて憶測できるのは以下のような史実に関する記
述だけである。「ゴンサロ・デ・アルバラードによる『サクレウ征服記(el
relato de la conquista de
Zaculeu)』によると、およそ八千におよぶマムの兵隊についての記載があり、山岳中央部からやってきてカイビル・バラム(Caibil
Balam)に率いられたサクレウの守備隊を援護したとある。この兵隊は確かに、今日ではサン・マルティン、サンティアゴ・チマルテナンゴ、サン・ファ
ン・アティタンおよびトドス・サントス・クチュマタンとして知られるマムの人びと出身の兵士から構成されていた。1525年10月のサクレウ[王朝]の崩
壊後は、スペインの統治は今日ウエウエテナンゴ県で占められている地域に拡大された。」(FUNCEDE.
1996, "Municiparidad de Todos Santos Cuchumat㌻; Diagnostico del
Municipio
de Todos Santos Cuchumat㌻, Departamento de Huehuetenango". Ciudad
de Guatemala, p.7, Guatemala: Fundaci溶 Centroamericana de
Desarrollo(FUNCEDE).)
(7)伝統的な儀礼のシステムが完全に根絶やしにされたというわけではない。「王の箱」(Caja
Real)を維持するコフラディアは存在し、また伝統的な行事には呪術師・占師・司祭であるチマン(chiman)による儀礼が施行される。これらは非公
開でおこなわれるが決してその必要性が失われたわけでもない。インディヘナ文化の復権によってこれらが新たな社会的に文脈に位置づけられて「復興」するこ
とも十分ありえる。
文献
- 池田光穂「商品としての民族・文化・定期市――グアテマラ西部高地における民族観光」『市場史研究』、第17号、pp.93-99、
1997年
- ブルデュ、ピエール『資本主義のハビトゥス』原山哲訳、藤原書店、1993年[原著は1977年]
- Annis, Sheldon. 1987, God and Production in a Guatemalan Town.
Austin: University of
Texas
Press.
- Cancian, Frank. 1992, The Decline of Community in Zinacantan.
Stanford: Stanford
University
Press.( esp. chap.10 Changes in the meaning of Cargo service).
- Carmack, Robert M. ed. 1988, Harvest of Violence. Norman:
University of Oklahoma Press.
- La Farge, Oliver. 1994[1947], La Costumbre en Santa Eulalia.
Guatemala: Editorial Cholsamaj.
- Oakes, Maud. 1951, The Two Crosses of Todos Santos: Survival of
Mayan Religious
Ritual.
New York: Pantheon Books.
- Taussig, Michel T. 1980, The Devil and Commodity Fetishism in
South America. Chapel Hill:
The
University of North Carolina Press.
- Tax, Sol. 1953, Penny Capitalism: A Guatemalan Indian
Economy. Smithsonian
Institute
of Social Anthropology Publication no.16. Washington D.C.: U.S.
Governmnent
Printing Office.
調査地の概要と調査の方法に関する覚書
調査地はグアテマラ共和国のウエウエテナンゴ県(Departamento de
Huehuetenango)にあるひとつの町(municipio)である。ここにおける町とは、グアテマラにおける最下位の自治行政単位である。町の
首長は近代的な選挙制度のもとで4年ごとに公選されている。マヤ系の先住民族であるマム語をはなすインディヘナが主要な人口を構成している。インディヘナ
の多くは同一の種類の民族衣装を着用することから、この町のテリトリーは一種の主要な民族的な領域をも形成している。同じ言語の異なる方言を話すインディ
ヘナやスペイン語を話すラディノ(メスティソ)はマイノリティーである。町全体はグアテマラ西部のクチュマタン高原の南西部から標高千メートルから三千数
百メートルのいくつかの谷沿いに広がり、面積はおよそ300平方キロメートル、人口は19,735人(1994年調査)である。私はこの町の役場所在地
(Cabecera
municipal)に1996年の9月から10月まで居住し、40日間の期間この地域だけで調査をおこなった。したがって文中で「町」と表現していたの
は、この役場の所在地のことを意味する。この文章は調査対象になった人たちが読むことを前提にして書かれていないが、さりとて読者から現地の人びとを閉め
出す意図を私がもっているわけではない。聞き取り調査に応じてくださった人の中には、私の成果をいつぞやスペイン語で読んでみたいと申された方もいるの
で、その期待に将来は報いるべきであると私は考えている。
この記録で報告されるのは1996年の9月から10月までに聞き取り調査で得た資料が中心である。しかし、それに先立つ1987年に都合2カ
月半同じ場所に滞在し僻地医療に関する資料を収集している。この間、私と当時この町で知り合った何人かの友人たちとの間で音信は全くなかった。しかし多く
の友人たちが私のことを、私が彼らに関して記憶している以上に憶えていてくれた。この理由として、9年前私は住民とのラポールをとるために写真を撮影し、
それを無料で配ることをおこなっていたことも関係しているように思われる。例えば、私にとっては完全にその顔を失念していた男が町ですれ違いざまに私の現
地での名前("Mitzu")で呼びかけるので、その理由を聞いてみたところ、私が彼と肩を組んでいる撮った写真を居間に飾っているという。また、多くの
友人たちが私が音信を絶っていたことを、私がどこかで事故――例えば飛行機の墜落――にあって死んでしまったからだと説明してくれた。私に関する記憶は、
彼らのエピソードとしてくり返し語られるテーマになっていたため、私の9年前の行状と名前が記憶されていたふしがある。そのため我々の九年間の空白は比較
的容易に埋まり、友人たちの家を再訪した翌日から聞き取り調査が可能になったものと私は解釈している。
調査方法は自由質問法によるインタビューと参与観察による。フォーマル・インタビューにおいては録音機を使い、原則的に謝金を払った。しか
し、インフォーマントによっては謝金の受け取りをビジネスライクだと述べて断った人もいる。フォーマル、インフォーマルを問わずインタービューにおいて
フィールドノートは基本的にメモにとどめ、事後に適宜ノートを整理し注釈する方法をとった。半世紀前に同じ場所で呪術に関する調査をしたオークス
(Maud
Oakes)は、秘儀に対する敬意などの理由で彼らの眼前でノートをとるのを控え、自分の家に帰ってから彼らとの対話を再現するという方法をとったが、私
の方法論も結果的にその方法を踏襲することになった。私の主たるインフォーマントの一人でありかつ重要な友人は、50年前のオークスのインフォーマント兼
使用人の孫にあたる人だった。
謝辞
この考察の基礎になった資料は、平成8年度文部省科学研究費補助金「グァテマラ観光地おける文化創造と階級・人種・性差意識変化の民族
誌」(研究代表者・太田好信)の現地調査によるものである。旧年度の研究成果報告書に盛り込んだ資料とアイディアを整理して書き直したものがこれである。
代表者の太田さんをはじめ研究班のメンバーの方々にはお世話になりました。また現地では名前をあげることはできないが多くの人たちのお世話になった。とく
にホセ・カルモ・クルスさん、エンリケ・マルティネスさんの両家族には大変お世話になった。以上の方々に記して感謝したいと思います。
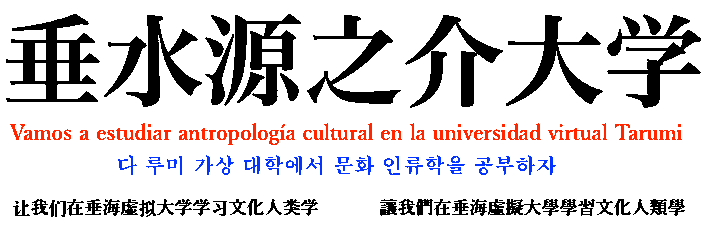
■内旋という名の由来
内旋という用語は、ジャワにおける人口稠密化の圧力が土地開墾の限界のために儀礼を含む慣習諸制度の巻き込む農業労働の集約化をすすめるという
Clifford
Geertzの"Agricultural
Involution"(農業の内旋)の所論に由来する。