グアテマラ先住民運動・ノート
Research Seminar on Indigenous People of the Mesoamerican Mayas
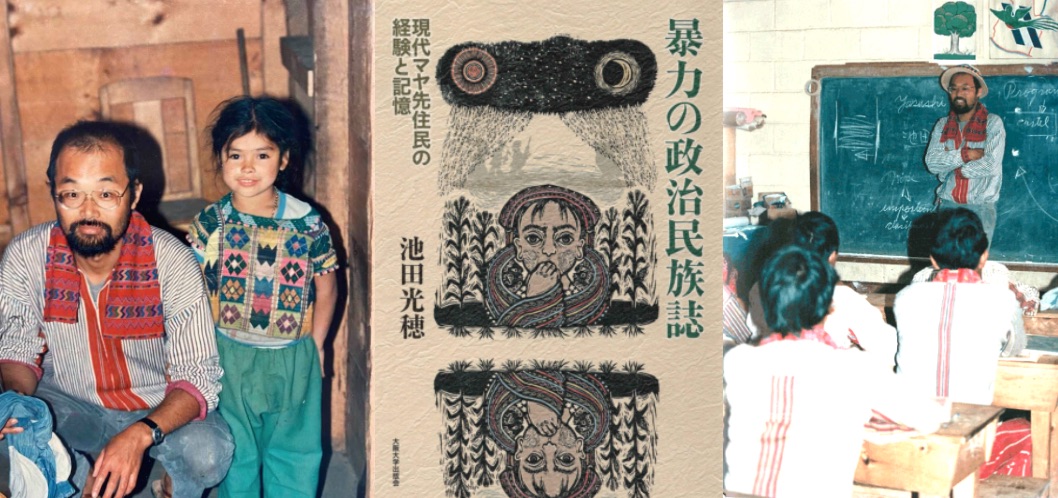
グアテマラ先住民運動・ノート
Research Seminar on Indigenous People of the Mesoamerican Mayas
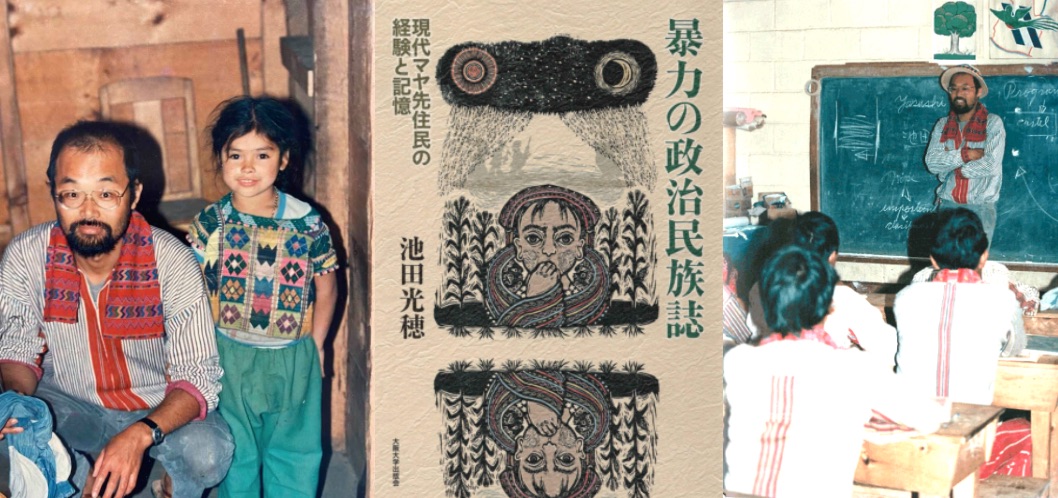
■グアテマラ先住民ノート(→「先住民とは誰か?」「先住民(先住民族)」)
【文献】
Fisher, Edward F.,1996. Induced Culture Change as a Strategy for Socioeconomic Development: The Pan-Maya movement in Guatemala. In "Maya Cultural Activism in Gualtemala," Edward F. Fisher and R. McKenna Brown eds., Austin: University of Texas Press.
+++++++++++++++++++++++++
・インターアメリカン・インディヘニスタ会議(1940)の開催
・Bonfil Batalla のによるインディヘニスモのテーゼ
(Bonfil Batalla, Guillermo., 1981)(Barre 1982)
これらの観点から、ラディーノ(メスティソ)の先住民に対するパターナリズムと、国民国家への統合を阻む先住民の文化的要素の排除(=文化の要 素が政治化されることを抑圧する支配者の論理)が、インディヘニスモにはみられた。
■アドリアン・イネス・チャーベス(1904-1987)
1945年、Primera Convencio´n de Maestros Indi´genas de Guatemala, Cobán, で Adrián Inés Chávez(1904-87) 27文字からなるキチェ語の新しい表記法を提唱。
・チャベスの理想は、キチェ語のみならず、マム語、カクチケル語、ケクチ語の話者が言語学の知識を必要とせずに、先住民言語を読み書きでき る能 力をもつことであった。(Chavez 1974:16)(Fisher 1996:57)。
・1948年、カトリックグループ内に先住民地域の反共と村落の近代化をめざす Acción Católica 運動がはじまる。[北米カソリック海外ミッション(Catholic Foreign Mission Society of America)に属するメリノール宣教会(Maryknoll missionaries)が、若い男性の先住民カテキストを育成する=植民地時代に形成されたコフラディーア制度にみられるマヤ土着宗教的要素の解体が ねらい]
・アクション・カトリカは、1962-65年第2バチカン会議および1968年のメデジン・ラテンアメリカ司教会議により、宗教的実践より も社 会活動に力点が移動する。このため、村落では協同組合、学校、保健センターなどが彼らにより設立される(→「解放の神学」)。
・1949年第1回国民言語学会議(primero Congreso Lingu¨istico Nacional)の開催[→1984年]
■SIL
・1952年 SIL(Summer Institute of Linguistics)がグアテマラでIIN(Institute Indigenista Nacional)のプログラムの一環として、先住民共同体で教科書配布と教師研修の活動をはじめる。SILの宣教師たちはマヤ語のコミュニティの方言の 特異的な独自の表記法を開発しはじめる。
・1959年 Academia de la Lengua Ki´-che`, ALMKがAdria´n Ine`s Cha´vez により創設される。
・1967年 ドイツ援助のコスタリカの大学支援によってTriumph Werk Nurnberg 社でマヤ語表記可能なタイプライターが開発される。
・1970-72年 Asociacio´n Indi´gena Pro Cultura Maya-Quiche´, Asociacii´n de Forjadores de Ideales Quichelenses, Asociacio´n de Escritores Mayaences de Guatemala (AEMG) の創設時期
・1971年 PLFM(Projecto Linguistico Francisco Marroquin)の指導部に、Jo Froman, Robert P. Gersony, Anthony M. Joackson が就く。
・PLFMは、ベネディクト修道会により創設されたもので、米国平和部隊、フィード財団、ならびにOXFAMという「信じられない組み合わ せ」 (Fischer 1996:59)の財政援助を受けて、アメリカの言語学者たちが、村落のそれほど教育を受けていない貧しいマヤの青年たちに対して専門の言語学を教授する ことを始めた。
・PLFMの主任言語学者 Terrence Kaufman (1976a)は、それまでの誤って教えられていた、マヤ言語の発音体系をスペイン語のそれに当てはめるという自民族中心主義的な手法を矯正し、近代言語 学にもとづく教育法を導入すると同時に、地方共同体ごとのSILによる言語表記法を批判した。グアテマラのSILのリーダーたちは、アメリカの本部に対し て、新しい表記法の開発を要請した。この当時PLFMにより研修をうけたマヤ先住民の数は80名を超えるといわれ、コフマンが指導したマヤ語の表記法と言 語学的手法にもとづいて文法・辞書編纂に従事している(Cojti Macario 1984)。
・1975年 PFLMの指導部に先住民の言語学者が就く。
・民政移管が軌道に載る1980年代後半にUSAIDによりラファエル・ランディバル大学、SILによりマリアノ・ガルベス大学、あるいは CEDIM(Centro de Documentacion e Investigacion Maya)などが創設されて、マヤ研究がさまざまな角度でから論じられるようになる(p.64)。
・Pan-Mayaの統一は、植民化以前の古代マヤの栄光と統一性——その片鱗は歴史言語学におけるプロト・マヤの概念や語彙の再構成に表 れる ——に焦点化されて論じられる。
・マヤ文化を「若返らせる」ことは、グアテマラ国家における多文化・多言語・多民族国家への平和的移行を意味する。
・マヤニストの多くは、本質主義者で、マヤの統一性や全体性を強調する。フィッシャーは、その本質主義者の代表にコホティ・クシルをあげ
て、彼
の主張を以下のように英訳・引用する。
"Cojti Cuxil wrights that "for the Indians of Guatemala, apart
from Mayan languages there is no authentic and complete expression of
their
sentiments"(1990a: 12)."(p.65)
・パン・マヤ運動は、西洋の文化的スタイルは拒絶しているが、その戦略や主張には、西洋的な文化要素の影響を受けていることも事実だ。
"Ostensibly, the ideology of the pan-Mayan movement rejects the Western
cultural tradition (Bonfil Batalla 1981:36-37). Yet the particular form
of pan-Maya cultural identity thay Maya leaders are promoting and the
historical
justifications of that identity are being constructed in the present
and
so are clouded by present situations. For the Maya cultural taradition,
which has long existed under Western-based Euramerican cultural
hegemony
and which is reasserting itself in the context of postcolonicalism, the
construction of a viable cultral identity involves the hybridization of
Western and indigenous traditions(Friedman 1992),"(Fisher 1996:68).
[池田コメント]
・マヤ中心的な主張は、西洋=植民者への批判というメッセージがあるためで、むしろ自分たちの主張に耳を傾けるグアテマラ以外の聴衆を意識した 反 植民地主義 的な主張に多く彩られている。そのような矛盾は、グアテマラ国内でもっとも脅威を感じているラディーノの保守派あるいは先住民嫌悪の感情からみると、きわ めて狭量な原理主義に映る(e.g., Mario Roberto Morales)。これはマヤの本質主義的主張を認める/認めないにかかわらずマヤ運動を見守る研究者にとっては、たしかに居心地は悪くないポジションで ある。それは今日においては、マヤ問題はマヤの先住民の主張の難しさではなく、それを受け入れる(べき?)ラディーノ国家がまだ国内問題としての先住民の 権利を認めていないことに起因し、外国人研究者にとっては、自分たちに疑問を突きつける問題系として登場していない証左であるかもしれない。マヤの人たち の存在様式という自己主張をめぐる研究が、グアテマラ国内における人権問題であるという研究の枠組みを超えて我々に対して興味深く感じるのは、それを外国 の研究者としてどのように理解し、自国の人たちにどのように伝え、どのように関わるべきなのかという問題を、実践的関与という標題を掲げなくても、常に フィールドワークを通してマヤの人たちが突きつけてくるからである。
・西洋における先住民の国家形成モデルとしては、ベルギー、スイス、フランス、スペインがあり、彼ら自身もその可能性を検討している (p.69)。
・マヤのグアテマラの場合は、そのようなマヤ運動の文化概念の形成にとって、言語学や文化人類学が貢献している。このような文化=政治運動にお ける文化人類学の貢献は、これまでの植民地状況下における先住民の統治制度に関して適切な助言をおこなうことを期待されたり、逆に人間の多様性の証明とい う文化相対主義的な使命をおびた現地資料の収集をしてきた、従来の文化人類学の活動とはまったく違った学問像を[学問実践を通して]提示している。
| Morales, Mario Roberto (1947–) Mario Roberto Morales (b. 5 September 1947), Guatemalan novelist. Morales came of age during the first cycle of the armed revolutionary struggle in Guatemala in the 1960s and 1970s. His participation in the guerrilla movement resulted in his arrest in Mexico in 1982 and subsequent deportation to Costa Rica, where he lived until 1991. Improved political conditions have allowed him to reestablish residency in Guatemala. His prize-winning novels combine autobiographical experiences with the linguistic, temporal, and structural experimentation found in Latin American "Boom" fiction. He is ranked by Seymour Menton as one of the leading representatives of the Guatemalan "new" novel. His experimental first novel, Obraje (1971), won the Floral Games Competition for Novel in Quetzaltenango; Los demonios salvajes (1978; 2d ed., 1993), which recounts his growing political awareness, won the Premio Unico Centroamericano de Novela: "15 de septiembre"; El esplendor de la pirámide (1985), about a love affair between a Mexican girl and a Guatemalan guerrilla, won the Latin American EDUCA Prize for the novel; and El ángel de la retaguardia (unpublished), about a Guatemalan expatriate in Italy, was a finalist for the Nueva Nicaragua Prize. His recent works, Señores bajo los árboles, a novelized testimony of Guatemalan Indian voices, and La ideología y la lírica de la lucha armada, a critical study of Guatemalan literature during the two decades of the armed struggle, were published in 1994. Several of his short stories and his Epigramas para interrogar a Patricia (1982) have been translated into English. In 1990 he published another work of poetry, Epigramas. In 1999, he published a collection of essays entitled La articulación de las diferencias o el síndrome de Maximón. In 2000, his Face of the Earth, Heart of the Sky was published in English. As of 2007, he taught in the department of Modern Languages at the University of Northern Iowa. In 2007, he won the National Miguel Angel Asturias Literature Prize. See alsoLiterature: Spanish America . |
モラレス、マリオ・ロベルト(1947年–) マリオ・ロベルト・モラレス(1947年9月5日生まれ)はグアテマラの小説家である。モラレスは1960年代から1970年代にかけてグアテマラで起き た武装革命闘争の第一期に成人期を迎えた。ゲリラ運動への参加が原因で1982年にメキシコで逮捕され、その後コスタリカへ強制送還され、1991年まで 同国で生活した。政治情勢の改善により、彼はグアテマラでの居住権を回復した。受賞歴のある彼の小説は、自伝的体験と、ラテンアメリカ文学の「ブーム」期 に見られる言語的・時間的・構造的な実験を融合させている。シーモア・メントンは彼をグアテマラの「新小説」を代表する作家の一人と位置づけている。実験 的な処女作『オブラヘ』(1971年)はケツァルテナンゴのフローラル・ゲームズ小説コンクールで受賞。『野生の悪魔たち』(1978年、第2版1993 年)は政治的自覚の成長を描き、中央アメリカ統一小説賞「9月15日」を受賞した。『ピラミッドの輝き』(1985年)はメキシコ人女性とグアテマラ人ゲ リラの恋愛を描き、ラテンアメリカEDUCA小説賞を受賞した。また『後衛の天使』(未発表)はイタリア在住のグアテマラ人亡命者を題材とし、ヌエバ・ニ カラグア賞の最終候補となった。近作では、グアテマラ先住民の声を集めた小説『木陰の紳士たち』と、武装闘争の20年間におけるグアテマラ文学を批評的に 考察した『武装闘争のイデオロギーと叙情』が1994年に刊行された。短編数編と『パトリシアを問うためのエピグラム』(1982年)は英語に翻訳されて いる。1990年には詩集『エピグラム』を、1999年にはエッセイ集『差異の連関、あるいはマシモン症候群』を出版した。2000年には英語訳『大地の 顔、天空の心』が刊行された。2007年時点で、ノーザンアイオワ大学現代言語学科にて教鞭を執っている。2007年にはミゲル・アンヘル・アストゥリア ス文学賞を受賞した。 関連項目:文学:スペイン語圏アメリカ |
| BIBLIOGRAPHY For a detailed review of the life and works of Morales, see Ann González, "Mario Roberto Morales," in Dictionary of Literary Biography: Modern Latin-American Fiction Writers (1994). For analyses specifically of Los demonios salvajes, see Ann González "La formación de la conciencia social en Los demonios salvajes de Mario Roberto Morales," in La literatura centroamericana, edited by Jorge Román Lagunas (1994), and Seymour Menton, Historia crítica de la novela guatemalteca, 2d ed. (1985). Morales discusses his own work, along with that of contemporary Guatemalan writers Marco Antonio Flores and Arturo Arias, in "La nueva novela guatemaleca y sus funciones de clase: La política y la ideología," in Ileana Rodríguez, Ramón Acevedo, and Mario Roberto Morales, Literatura y crisis en Centroamérica: Ponencias (1986). The English translation of his epigrams is "Epigrams to Interrogate Patricia," in Latin American Literary Review 18 (July-December 1990): 87-103. Additional Bibliography Asturias, Miguel Angel, and Mario Roberto Morales. Cuentos y leyendas. Madrid: Alica XX, 2000. Volek, Emil. Latin America Writes Back: Postmodernity in the Periphery (An Interdisciplinary Perspective.) New York: Routledge, 2002. |
参考文献 モラレスの生涯と作品に関する詳細な論考については、アン・ゴンサレス「マリオ・ロベルト・モラレス」『文学者事典:現代ラテンアメリカ小説作家』 (1994年)を参照のこと。『野生の悪魔たち』の分析については、アン・ゴンサレス「『野生の悪魔たち』における社会意識の形成」『中央アメリカ文学』 (ホルヘ・ロマン・ラグナス編、1994年)およびシーモア・メントン『グアテマラ小説批評史』(第2版、1985年)を参照のこと。モラレスは自身の作 品について、同時代のグアテマラ人作家マルコ・アントニオ・フローレスやアルトゥーロ・アリアスの作品と共に、「グアテマラの新小説とその階級的機能:政 治とイデオロギー」で論じている。この論文はイレアナ・ロドリゲス、ラモン・アセベド、マリオ・ロベルト・モラレス編『文学と危機:中央アメリカにおける 発表論文集』(1986年)に収録されている。彼のエピグラムの英訳は『ラテンアメリカ文学評論』18号(1990年7月-12月)87-103頁「パト リシアを問いただすエピグラム」に掲載されている。 追加文献 アストゥリアス、ミゲル・アンヘル、マリオ・ロベルト・モラレス共著。『物語と伝説』マドリード:アリカXX、2000年。 ヴォレック、エミル。『ラテンアメリカからの反論:周辺におけるポストモダニティ(学際的視点)』ニューヨーク:ラウトリッジ、2002年。 |
| https://x.gd/yiqV7 |
■ラテンアメリカの社会運動
【文献】
1990年代後半におけるエクアドルやボリビアにおいては先住民運動が高まり、国政レベルでの選挙にも大きな影響力をもつ。
→しかし、なぜグアテマラでは、そのような盛り上がりが欠けるのか?
[さまざまな歴史的条件から〈歴史の必然性 necessity〉という観点からではなく、〈歴史の蓋然性
probability〉から考える。]
・「見えなくされてしまった invisualization」先住民(アルゼンチン Gordillo and Hirsch 2003)、「隠蔽の言説 discourse of concealment」(グアテマラ Sam Colop 1996→ Fisher and Brown 1996:107-113)
・「栄光ある先住民の過去 glorious indigenous past」(Alonso 1994→Ann.
Reiew. Anthro.)という形での顕彰
"State nationalism associates indigenous communities with the nation's
"glorious indigenous past," marginalizaing them in the present
--- except for museum, tourism, and folkloric events"(p.551).
メスティソのヘゲモニーに握られている事例を検討したMallon(1992)、メキシコ、ペルー、ボリビア。
・それへの対抗。エクアドルでは、ケチュア語共同体の村落と土地の割当。アンデス諸国では、再先住民化(reindigenization) (de la Cadena 2000, Plant 2002)。
・国民国家の統治者たちは、メスティサッヘ・イデオロギー=民族・人種の差異よりも混交を尊ぶ(例:Vasconcelos' "raza cosmica")よりも、先住民性を強調したり、民族の多様性を尊ぶほうに力点を[ある意味でいやいやながら]置き直してきた。ラテンアメリカでは、憲 法改正などを通して、民族の多元主義を認める国には以下の国々がある。グアテマラ、ニカラグア、ブラジル、コロンビア、メキシコ、パラグアイ、エクアド ル、アルゼンチン、ペルー、ベネズエラ。
池田コメント:このような傾向は、ILO169条の批准、国際的なNGO団体の協力、人権を軸にした国際協力、およびIMFや世銀における国際 援助協力における戦術変更——民主主義の充実、人権や文化に配慮した政策運営[なぜならネオリベラル経済の安定には当該国の統治性 (governability)の実力が求められるゆえ]——による。これらの政策は社会調整(social adjustment)と呼ばれる。
【先住民像の移行】
・見えない(隠された)先住民から、国民国家と節合することが期待されている[また自分たちのアイデンティティや要求を放棄することなく政治的力をもちつ
づける]見える先住民へ(cf.
Diaz Polance 1997:98)。
【差別問題の洗練化】
・当事者からの意見や自画像に関する見解を当局者は受け入れないので、先住民の自己アイデンティティは曖昧で揺らいだまま、先住民への差別のステレオタイ
プは温存される。[過去30年間で先住民に対する抑圧が続いた国家:グアテマラ、ペルー、コロンビア]。
・文化に対する権利が、福祉や物質的サービス提供と相殺されているという主張(例:Van Cott 200, 2007*)がある。
* IN "Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies," Keith G. Banting et al eds.所収 "Some scholars believe multicultural citizenship reforms appealed to ruling elites as a way for the state to signal its citizens that it was attending to their interests, despite a decreasing ability to meet material demands."
・ネオリベラル経済の位置づけ(FTAのための構造調整政策、公共部門の民営化、地方分権化[decentralization])
・ビセンテ・フォックスの用語「企業による、企業のための、企業の国家」(出典 Speed 202:223)
・[池田コメント]ネオリベラル理論家の中には、多文化主義や人種差別反対は、ネオリベラルの主張と軌を一にするので、それまでの経済体制同様 に先住民への抑圧が続くということがありえないという主張がある。しかし、ネオリベラルの問題系においては、民族や文化の差はグローバリゼーションの過程 の中で消失してゆくので、文化や民族の差異に関する関心そのものがないということに過ぎない。ネオリベラリズムにおける人間観は、文化的アイデンティティ をもつ主体ではなく、経済的自己決定権をもち、自由競争のもとで自分の努力と能力を使って経済的に豊かになる主体を想定しているからだ。またそれ以上に、 ネオリベラル思想は、先住民の考え方とは連結しにくい。生物多様性や持続的可能性に対して、世界各地で、この2つの考え方は衝突を起こしている[→エクア ドルアマゾン河上流における石油会社と先住民、コロンビアのU'wa 人とOccidental Petroleum との対決における類似のケース Jackson 202]。
・村落レベルでの先住民の要求は、土地・資源・行政的空間の確保(Cojti Cuxil 1994)——「認証の政治学 politics of recognition」(Taylor 1994)。しかし、それは分離派を含めることではない(Cojti Cuxil 1997)。しかし、エクアドルのPachacutik党やCONAIE(Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador)、グアテマラの先住民運動のように、メスティソを排斥する運動ではないので、従来の政党政治のイメージからは研究者は自由になる必要があ る(Macdonald 2003)。
・実際、グアテマラのマヤ先住民運動は(その運動の当事者たちは国民国家教育により十分愛国者であるし——池田)「統一したグアテマラ国家」に 対する
・認証の政治学は、先住民運動に対するステレオタイプに対する抗争でもある。代表的なステレオタイプ:分離主義、地域のバルカン化 (balkanization)、分離独立派、反ラディーノ、復古主義者、反近代主義者、等々。
・グアテマラのpan-Maya運動においては、文化主義者と草の根の左翼との複雑な結びつきがある。(Bastos and Camus 1995,1996 )による指摘。
・Cholsamaj, Nawal vu'j などのNGOないしは先住民出版社の役割についても忘れてならない(Raxche'=Demeterio Rodriguez Guajan , 1995)。
・ユカタンのマヤ・アイデンティティを研究した、Castan‾eda (2004:41)によるマヤの定義:「所属・アイデンティティ・区分の争点をめぐって繰り広げられる紛争地帯」("an embattled zone of contestation of belonging, identity, and differentiation.")[p.555]
・人類学者=アクティビストの伝統:歴史的には、Rodolfo Stavenhagen, Alicida
Ramos, Myriam Jimeno, Stefano Verese, Nellie Arevalo-Jimenez, Manuela
Carneiro
da Cunha.
。新しくは、エクアドルの先住民と石油会社の闘争を描いたSawyer(2004)。——グアテマラでは、Kay
Warren, Nora
England. ただし、民族誌学者は中立的な傍観者でも、アクティビストでもない、あいまいで中間的な領域に留まる可能性がある——先住民問題を取り
扱う時には、先住民/非先住民の対立項の後者に属するわけだから、この種のジレンマにはある意味で特権的に陥り易い。ただし、人類学者にとっては、この二
分法を認めると同時に、それだけが事実ではないことを具体的事象を通して例示しようとする。
Rappaport, J., 2005. Intercultural Utopias: Public Intellecturals,
cultural
experimentation, and Ethnic pluralism in Columia. Durham, NC.:Duke
University
Press.
→彼女の処方せんは、同一/他者(same/other)という二項対立ではなく、他者性(Otherness)のなかに複雑なグラデーションにおいて理
解しようという考え。(例:先住民のアイデンティティにも、共同体に基礎をもつものと、個人に基礎をもつ2つの基軸があり、それらの間のなかで、同一/他
者という対立の総和はさまざまなグラデーションをもつと考えるのだ)。
"Similarly, Speed(2002) saw process she characterizes as "being
and becoming indigenous" in Chiapas to Occar at the community level,
during discussions concerned with "declaring ourselves a 'pueblo
indigena'"(p.212=Speed
2002)[p.557].
[池田コメント]
・言語=民族アイデンティティという等号(eg. Brown 1996=The Mayan Language Loyalty Movement in Guatemala)Language Loyalty Movement, LLM=社会言語学者Joshua Fishman(1988)の用語で、自分たちの言語の消失に対する危機感を感じ、それを維持/復権し、公定化しようとする人々の努力を意味する。グアテ マラでは、カクチケル>キチェ>マムの順にその傾向が強いが、それ以外のマヤ言語においても、現地のアクティビストが文学作品や口頭伝承の出版をとおし て、この種の努力をおこなっている。
・言語へのローヤリティ(言語忠誠運動、Language Loyalty Movement)については、Language
loyalty in the United States / Joshua A. Fishman, The Hague :
Mouton , 1966 . - (Janua linguarum ; Series maior ; 21)を参照のこと。
・LLMへの対抗運動が、ラディーノによるマヤ言語の否定で、これは先住民言語に関する現地の知識人や一般庶民の間でのステレオタイプになって きた。すな わち、マヤ言語は、方言(dialecto)である、マヤ文法は、スペイン語文法の亜流——「贋のスペイン語」(Hill 1999, AA 104:1086-97)——であり、独特の文法体系をもたない(=LLMあるいは専門の言語学者たちは、マヤ語言語が能格言語であるというユニークさを 特に強調するのとは、好対照である)。声門閉鎖音(Glottalized)などの特徴的な発音を理解できずに正常でない奇妙な発音(動物や鳥の鳴き声に 擬される)であると指摘する。もうひとつの先住民言語の否定表現は、家庭内と公的な場におけるバイリンガル的使い分けの実態を知らずに、先住民言語が使わ れなくなったという客観的表現を通して、先住民言語の存在を無自覚的に否定する場合がある——これは一般の人だけでなく、現地の学校教師やスペイン語だけ で調査する人類学者においてすら見られることがある。
・先住民アイデンティティは、アプリオリにあるのではなく、国民国家化に抵抗する過程の中で出てきた(Sam Colop 1999,Montejo 1999)。[コメント:これは先住民を経済階級として見てきたマルクス主義歴史家からみると、むしろ、先住民を経済的搾取の対象のままに維持するために は、先住民共同体の中に閉じこめておくことが重要で、そのために先住民が共同体の中で保守的な文化構造をもつことは経済的支配者にとっては都合のよいこと だった、という一種の文化的ゲットーの中で形成された現状維持の思想というビジョンとは好対照をなす]。
・ただし、この抵抗者のアイデンティティという見方は、支援者や人類学者にとってはロマン化する危険性があり、これに対する批判的意見がある (Rapapport and Dover 1996—コロンビアの例)。あるいは、国民国家意識形成のために、国民を敵からの抵抗の英雄というかたちで、容易に国家言説の中に取り込まれてしまう。 しかしながら、このようなイデオロギーを創造して先住民をひとつのアイデンティティに取りまとめることは、先住民自身のトランスナショナル化、都市化、プ ロレタリア化、越境化、複数言語使用化、ならびに専門職化により、容易に突き崩されてしまう(Kearney 1996, Warren and Jackson 2002b)。
・グアテマラの例では、Cojti Cuxil 2002, Warren 1998, Fisher and Brown 1996, Watanabe and Fisher 2004がある。
・ベネズエラの先住民に対する文化的ステレオタイプが「伝統的」という概念に関連づけられてコレラ流行時には差別と排除の対象になる(e.g. Briggs 2004)
・先住民の否定→先住民性の否定→「先住民らしくない」という言表の形式
・「伝統的でないことで先住民ではない」ことの証明になるというジレンマ。
コメント:彼は先住民ではない=先住民であることの証明が必要になる。自らが先住民であることを自称だけでは証明できない(例:クリフォードのマシュ
ピー)
→これに対する対抗的措置として、先住民を証明するカードを先住民自身が発行する。[Turner
2002, Ramirez 2002]
・ただし先住民の伝統的価値を否定することで新しい先住民アイデンティティを対抗的に獲得しようとする人たちもいる(例:社会参加が認められて こなかった女性が、発言権をもとめて伝統的価値を否定する——チアパスにおける事例は Assies 2000)。つまり、新しいエスニシティの構築というのは、つねに形成途上のもので、その終着点における状況にあるのではない。
・先住民運動におけるリーダーなどでは、戦略的本質主義を自己提示につかうものが、たしかにいるし、そのことについて多くの報告がある (pp.559-560)。
・女性であることが、先住民性をより強くより多く持つという主張もある。それは民族衣装を身につけ先住民言語をより多く保持していることや、伝 統的食事の作り続けることなどが、その本質主義的な印象をより大きく与えるからである。
・ダイアン・ネルソン(1999)の主張だと、マヤの女性は伝統的なmujer maya の役割を保持することが期待されている。これは文化的イメージとして、新しいPan-Maya運動にも、グアテマラのナショナリズムにも寄与することにす ることになる。ヘンドリクソン(1996)に言わせると、このマヤの民族衣装は、(布を織る自分たちの場所を離れて活動する)マヤの運動の外側に居続けさ せ、運動に参入させる機会を失わせるという(Fischer and Brown 1996の論集の論文)。[池田コメント:ただし、CONABIGUAの集会などをみている限り、むしろ、多様な地域からやって女性たちの連帯意識を共有 するには、そのような民族衣装の多様性の存在が、運動そのものの全国的広がりを感じさせ、運動への参入へのブレーキをかけるものとは判断されない/それゆ えに、ラディーノ社会の人種主義者には、このような盛り上がりそのものが挑発を含んだ先住民の敵意に移り、しばしば指導者に対する脅迫がおこなわれる。ま た、先住民の保守主義者の男性からも冷ややかな評価が浴びせられる——他方、その集会のパーティは一種のさかしまの世界のカーニバル状況とも言えるもの で、そこには先住民と非先住民、自国民と外国人、男性と女性の区別というような峻別が取り払われて〈内戦未亡人の人権擁護の活動家や支援者〉というひとつ のアイデンティティ構築を感じさせる集会であった——R・ウィルソン(1995)のいうように「想像もできない上滑りをした[別の]意味」ないしは、パロ ディとしてアイデンティティが形成される場が観察される——こういう現象は文化人類学者もつ古典的な民族アイデンティティ概念では、先住民運動の渦中にあ る人々のアイデンティティの現実を把握することができない証左になっている]。
・グアテマラ東部地域では、ラディーノ化がすすんでおり、西部高地をモデルとする先住民表象として機能する民族的マーカーそのものが少ない。そ のために、先住民−ラディーノという二分法が通用せず、機会において人々が使い分ける余地を残しているという指摘がある(Little-Siebold 2001)。——たぶん、これは先住民虐殺への関与を問われたケクチ地域出身のベネディクト・ルカス・ガルシーア将軍が公的な席上で自分自身がケクチ語を 知る先住民であり、先住民への選択的虐殺に関与したことを全面否定する論法と類似である。ラディーノそのものが先住民と植民者の両方の文化遺産を継承する ものだからである。ここから出てくる新しい人種区分は、よい先住民/悪い先住民、よいラディーノ/悪いラディーノという、善と悪の弁別である。
・先住民のアイデンティティに関しての論文の多くは「矛盾」や「パラドックス」という用語が満ちている。ここから帰結する結論は、アイデンティ ティを固定化したものとみるのではなく、流動的で、さまざまな社会的交渉の結果生じるダイナミックなものであるという見解である。
・多くの国家で、先住民の法的権利は保障されるよう憲法などで規定されている。しかし、現実社会には過酷な民族・人種差別がある。それは差別さ れる側からみると、市民社会で保証されている諸権利の侵害という事実があり、それは市民権にも等級が付されているという意味だ(graduated citizenship, Ong 1999)Flexible Citizenship: the cultural logics of transnationality.
[池田コメント]国家や政党がつくりあげる、先住民ならびに先住民文化を巻き込む人種化した国民国家形成の物語に、加担しないような別種の「先 住民像」我々はいかにして手に入れるのか?——このような文脈で「統治性」とは対抗する概念として登場するのが「公共性 publicness」「人権 human rights」「市民社会 civil society」
・Cojti Cuxil(1994)は、マヤの言語的な区分からマヤ国家ないしはラディカルな連邦主義をめざす。しかしながら他方で、戦略的には、文化的・言語的な復 興を通して、オルターナティブなマヤ文化にもとづく小学校、シャーマン、専門的言語学者、出版社、専門的活動家の養成という活動を地道におこなっている (p.562)
++++++++++++++++++++
【慣習法】
++++++++++++++++++++
・スタベンハーゲン(2002)によると、コロンビアの憲法裁判所の決定の影響がラテンアメリカ全体に広がっていったのかについて検討して いる。 [Sieder R., 2002の論文集, Multiculutralism in Latin America.]
・慣習法は、コスモロジーにもとづき、時にシャーマンなどが動員されて伝統的な方法の中で決定される(Jackson 2002=ワレンとの共編著の論文)。
[池田コメント]西洋的価値とは異なるの制度を採用するので、全国レベルでの報道は地方欄に(ラディーノの人種差別主義者の眼を通して)興味本 位に描かれる傾向がある——刑罰の公開ということもスペクタクルになる。たほうで、先住民の「伝統主義者」はそのような記事を好ましいものと受け止める。
・ここのでの対立は、実定法〈対〉慣習法[通常の対立は、実定法〈対〉自然法であり、慣習法は通常は実定法のなかに包摂される]。あるいは 法 〈対〉慣習の対立として表れる。
・現実には、法と慣習による制裁の実践は、それほど際だった対立を維持することはなく、公的司法当局と共同体(pueblo)は、双方に対 応を 変化させている。より複雑な紛争解決モデルについては現時点では不明瞭だが、その理解と研究が求められる。[→法の多元化論 legal pluralism][→法人類学入門]
・問題が、個人と共同体という対立項として理解されるようになると、個人の自由を制限する共同体の論理が優先されるべきかという論争に展開 す る。この場合は、リベラルあるいはネオリベラル経済が、自明視する「諸権利のホルダー」としての個人の権利擁護の必要性が強調されて、慣習法的実践の不当 性が過度に強調される可能性が出てくる。
++++++++++++++++++++
【文化問題】
++++++++++++++++++++
・間文化性(interculturality):多文化性(multiculturality)(Rappaport 2005)
・エクアドルの間文化性についてコメントするホウィトン(Whitten 2004)は、先住民たちは、雑種性や文化的多元主義のエトスに対抗して、間文化性が出てきたという。"Interculturality stresses a movement from one cultural system to another, with the explicit purpose of understanding other ways of thought and action "(Whitten 2004:440).
国家的/ローカルで地域的ないしはグローバル
地域主義的/より局所的
静的/ダイナミック
-----------------------------------------------------
Watanabe, John M. (John Mamoru) & Fischer, Edward F. eds., 2004. Pluralizing ethnography : comparison and representation in Maya cultures, histories, and identities. Santa Fe, N.M: School of American Research Press.[→L-PluralizingEthno2004.pdf]
■ リンク
■ 文献
■
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2009-2099
++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099