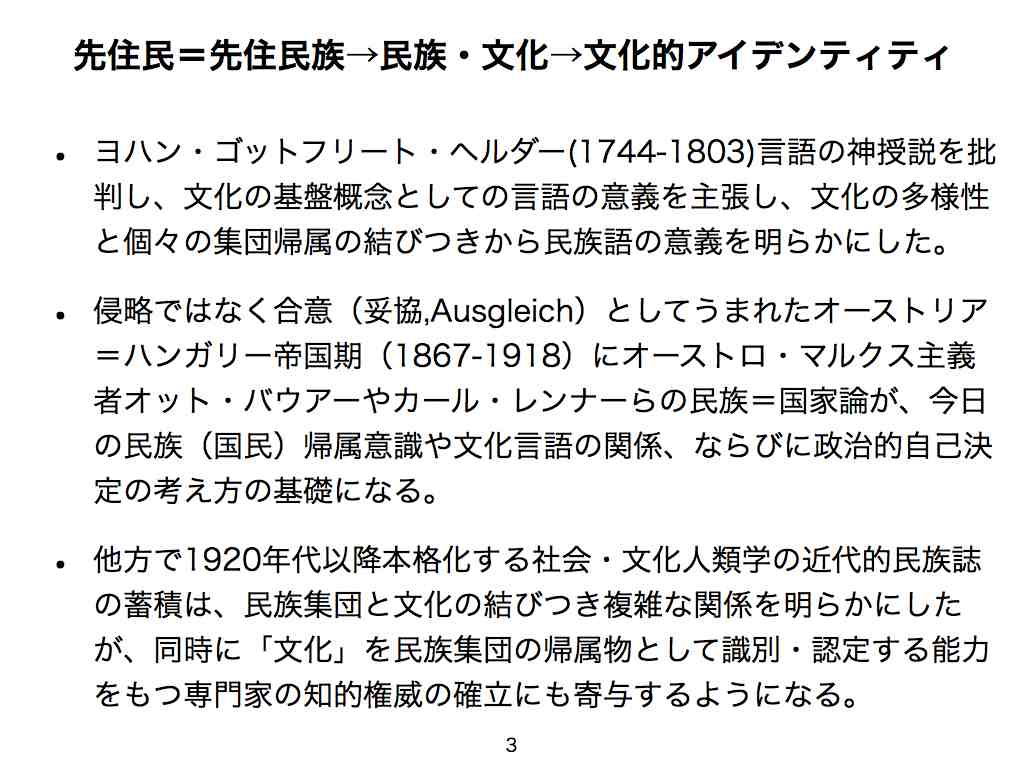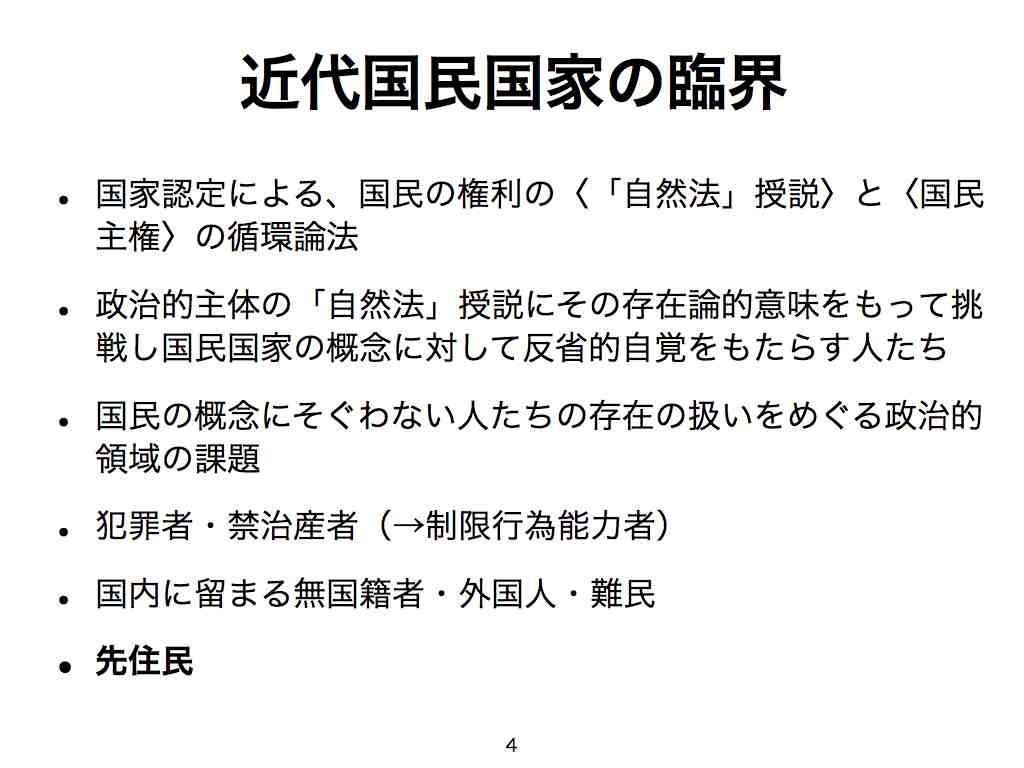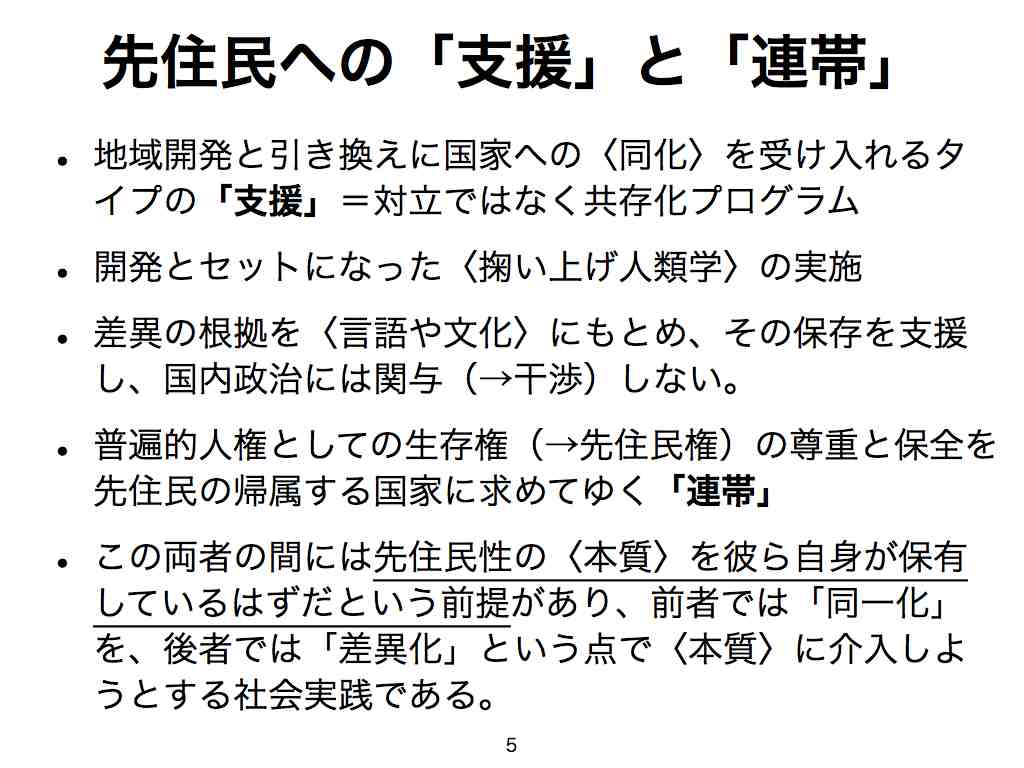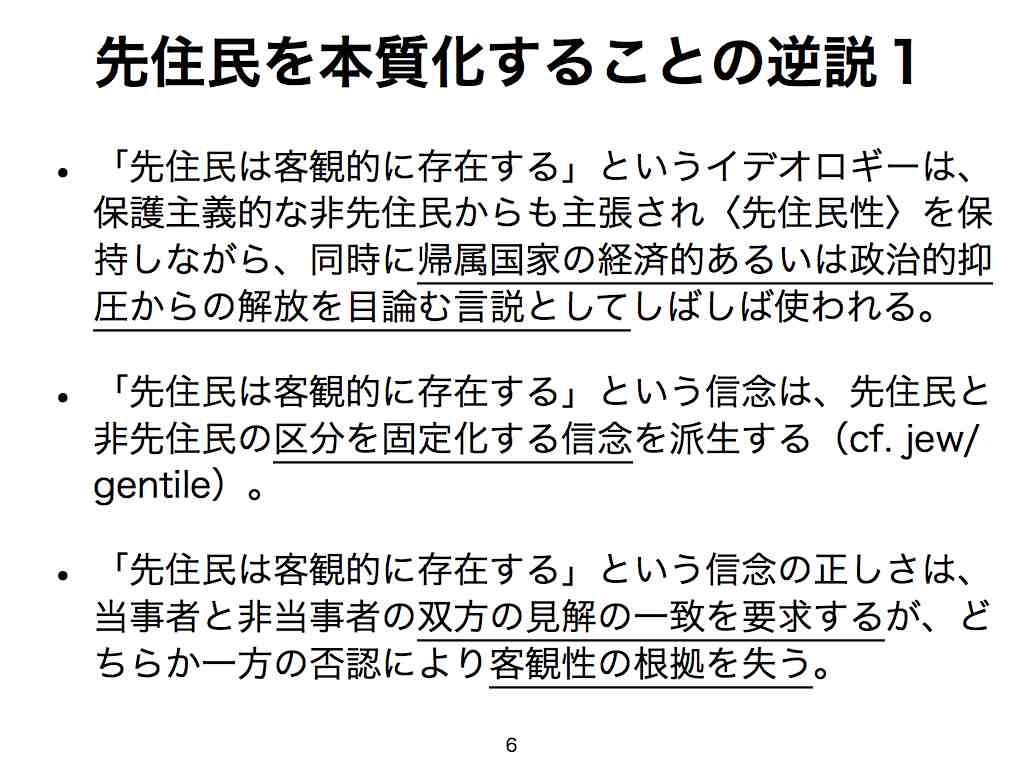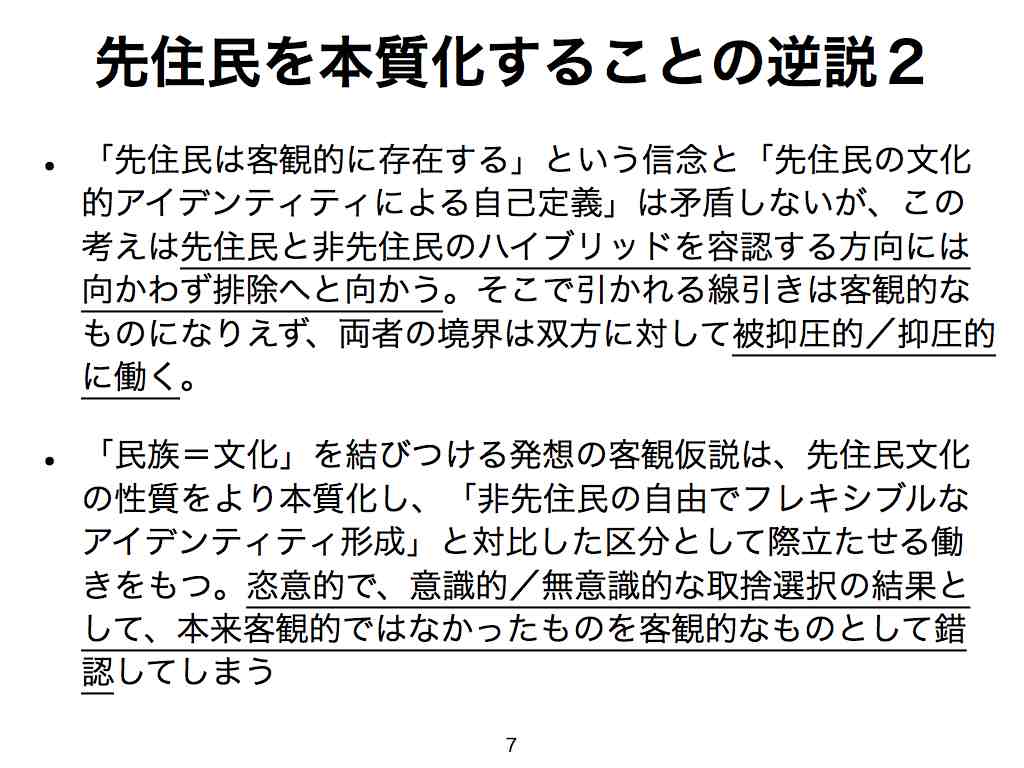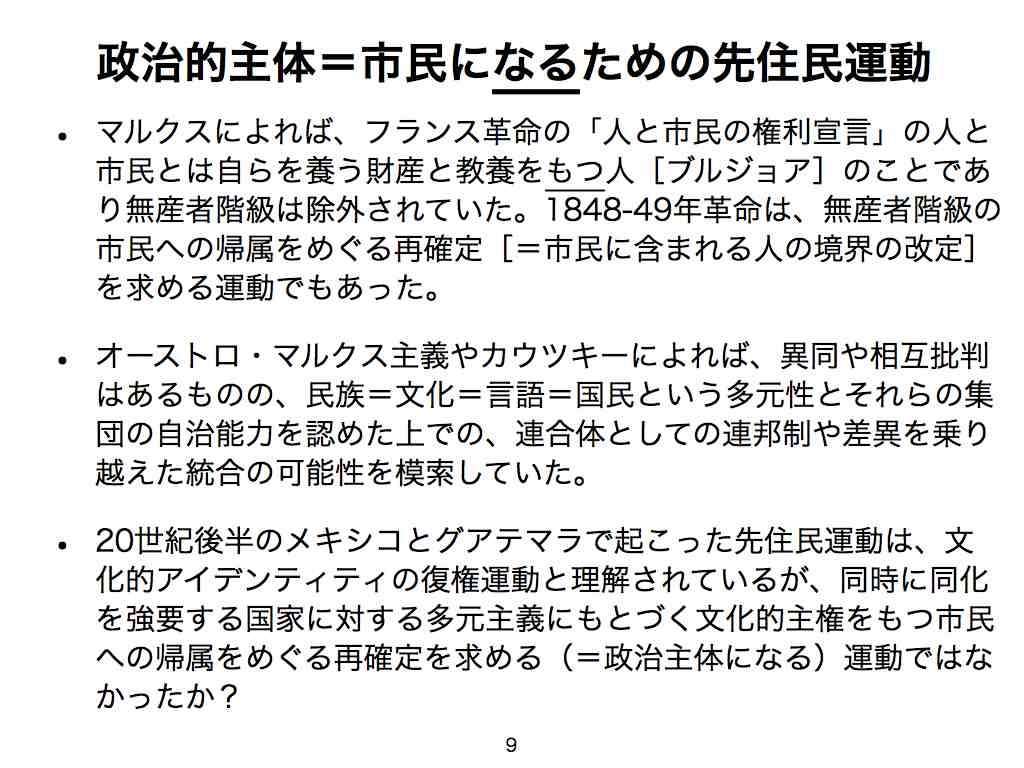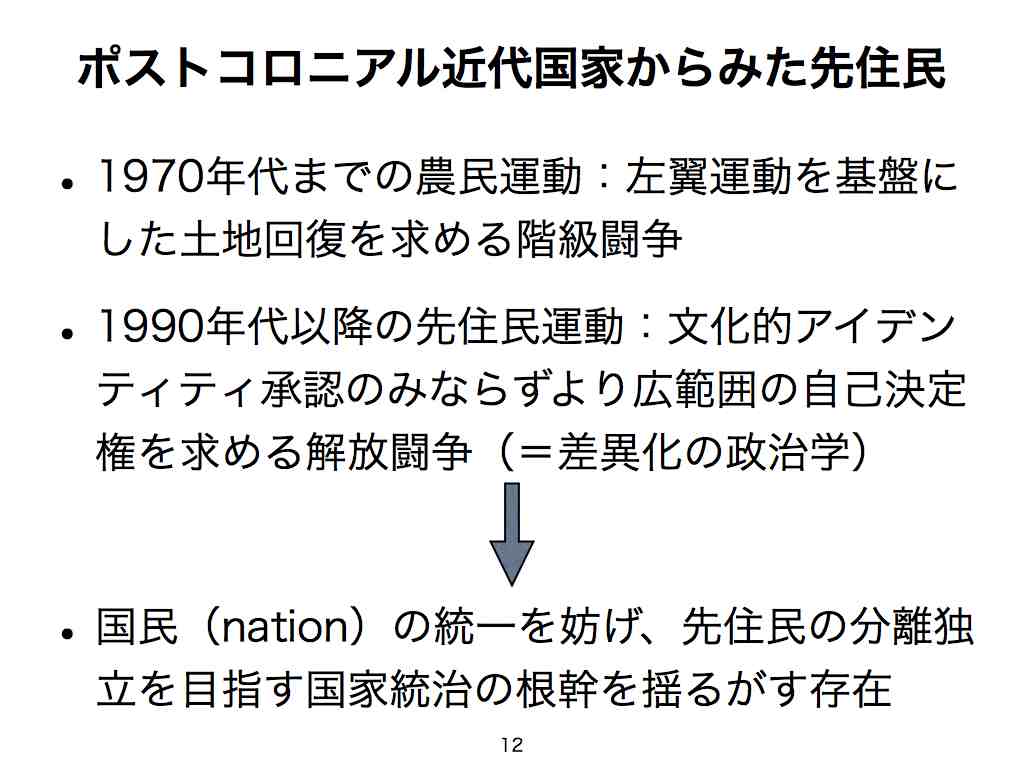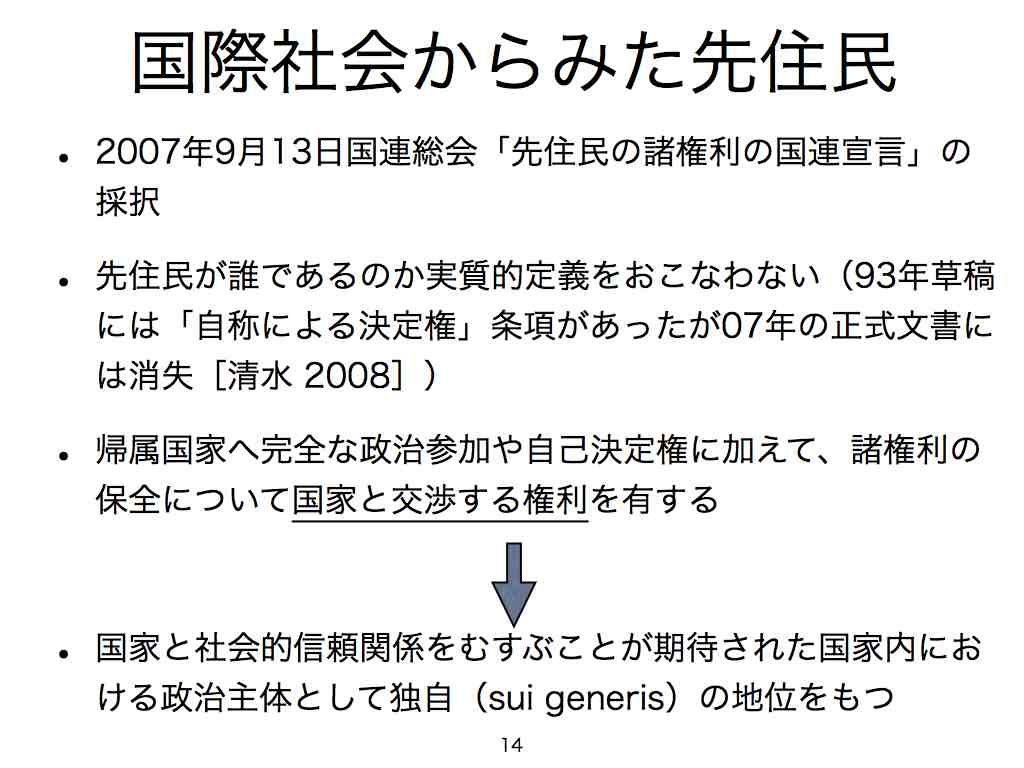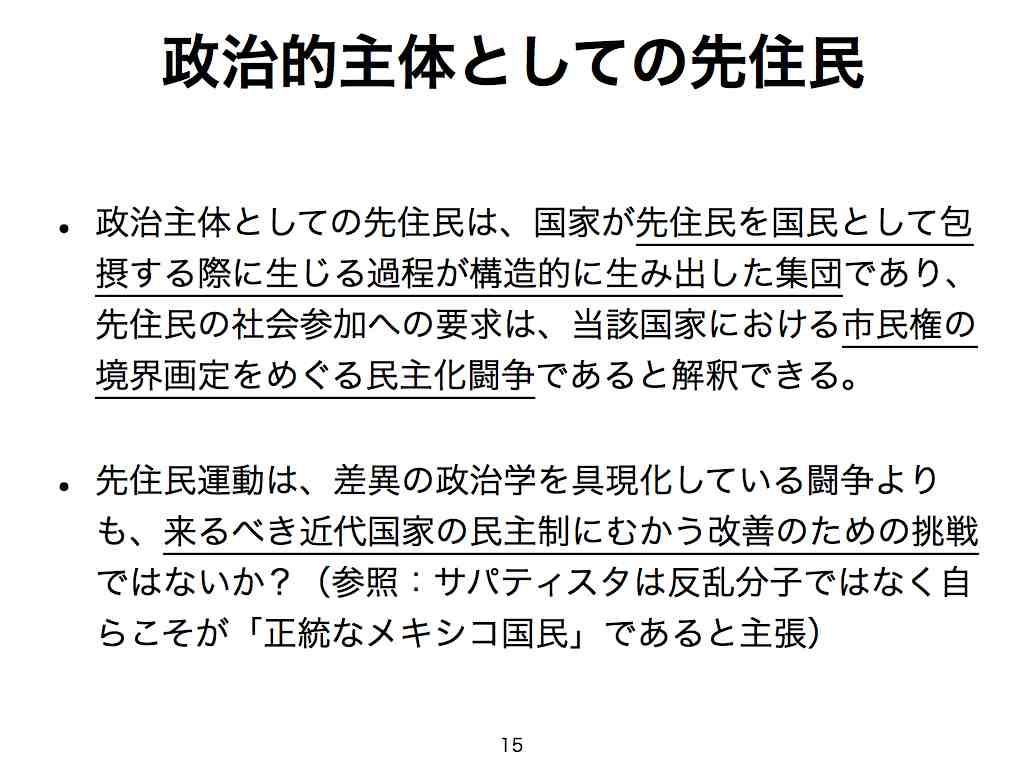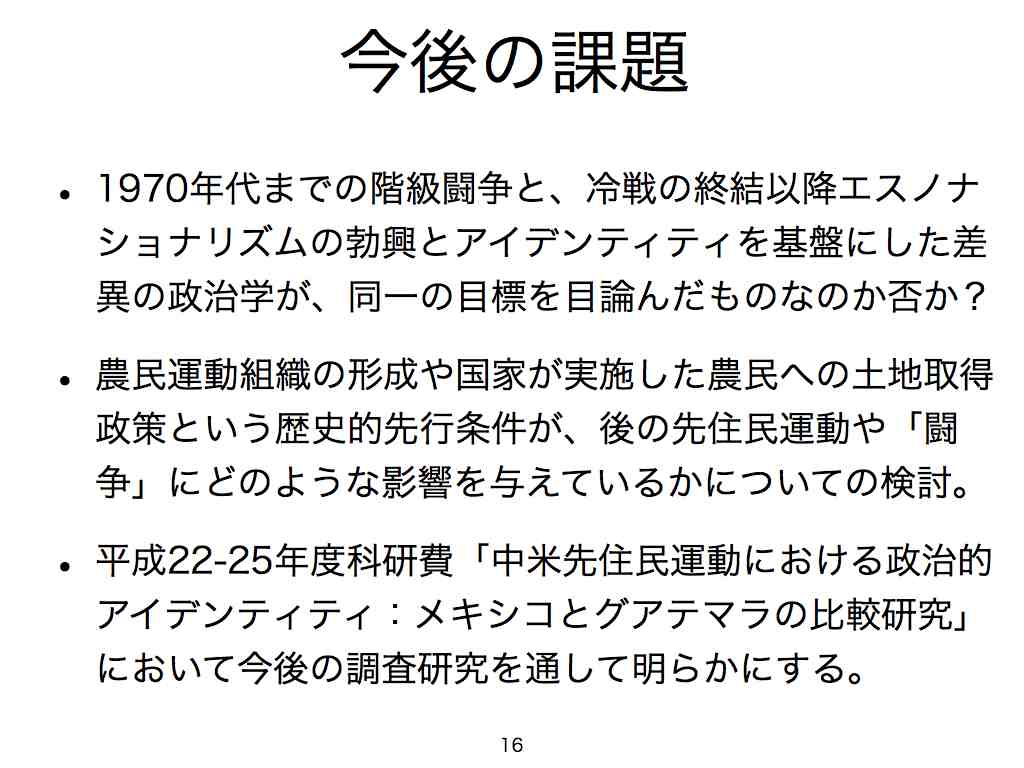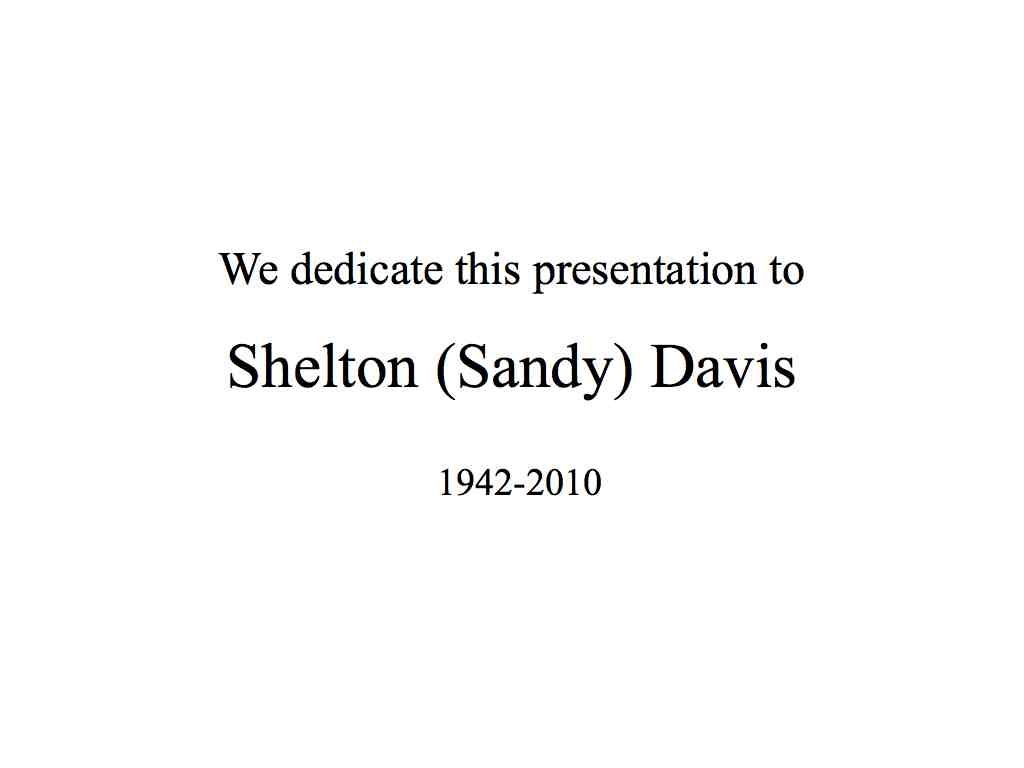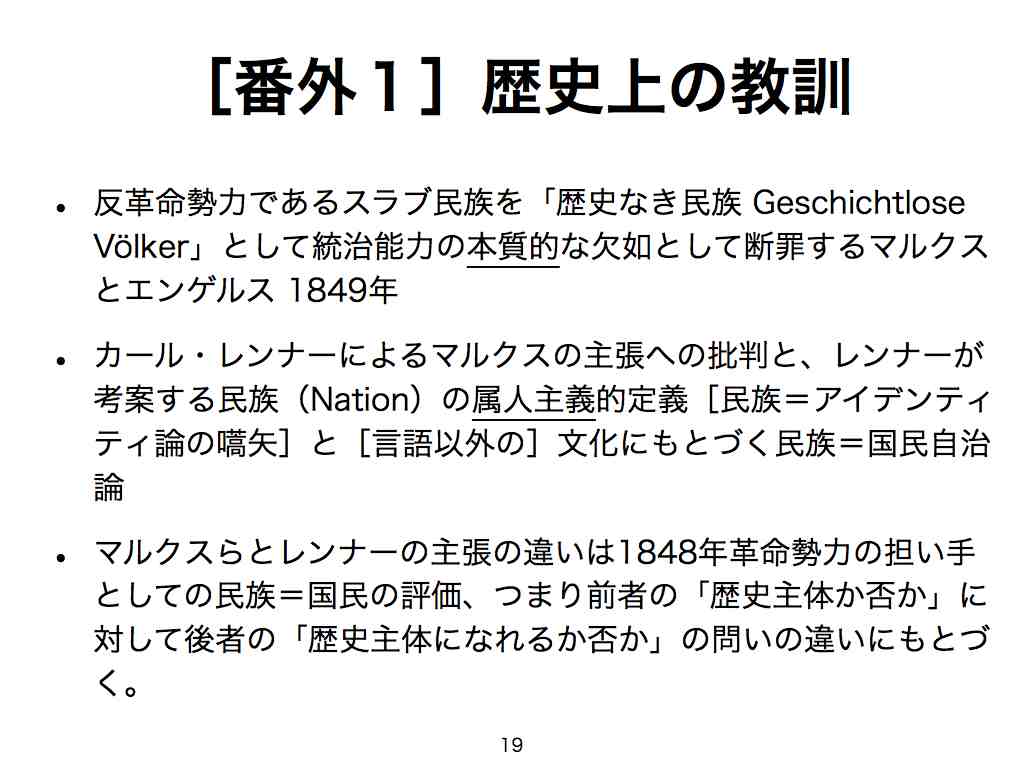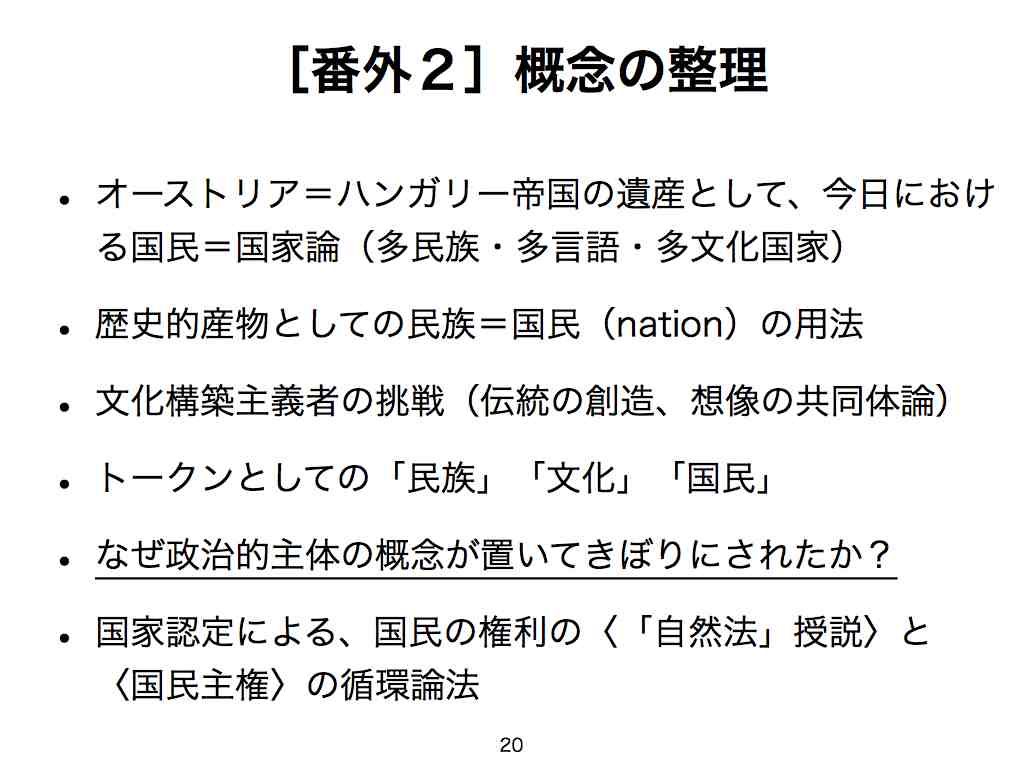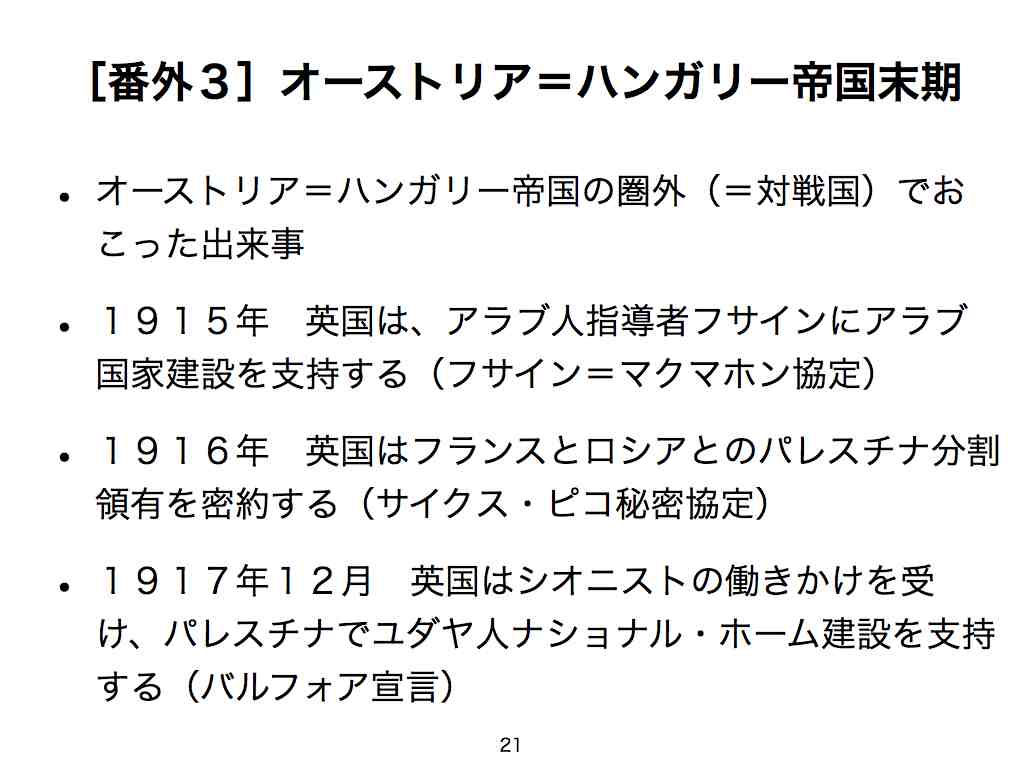解説:池田光穂(現在は、大阪大学名誉教授:2022年4月現在)
 |
【1】中米先住 民運動の民族誌学的研究を通した「先住民概念」の再検討 タイトル&キャプション:中米先住民運動と政治的アイデンティティ:メキシコと グアテマラの比較(日本ラテンアメリカ学会第31回定期大会・分 科会「先住民——アイデンティティ模索の歴史的考察」京大会館、2010年6月6日)大阪大学コミュニケーションデザイン・センター:池田光穂 (c) Mitzub'ixi Quq Chi'j 2010 スペイン語版はこちらです La Identidad Politica y los Movimientos Indigenas: Estudios Comparativo entre Guatemala y Mexico 連携研究機関 PROIMMSE-IIA-UNAM(メキシコ自治大学=人類学研究所=メソア メリカとメキシコ南東部に関する学際調査プログラム) Programa de Investicagiones Multidisciplinarias sobre Mesoamerica y el Sureste http://proimmse.unam.mx/ Centro de Estudios y Documentacion de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG(グアテマラ西部国境地帯に関する資料研究センター) http://bit.ly/kxHwv3 http://www.cedfog.org/webcedfog/index.php ※この研究の成果は『暴力の政治民族誌』(2020)に反映されました。 |
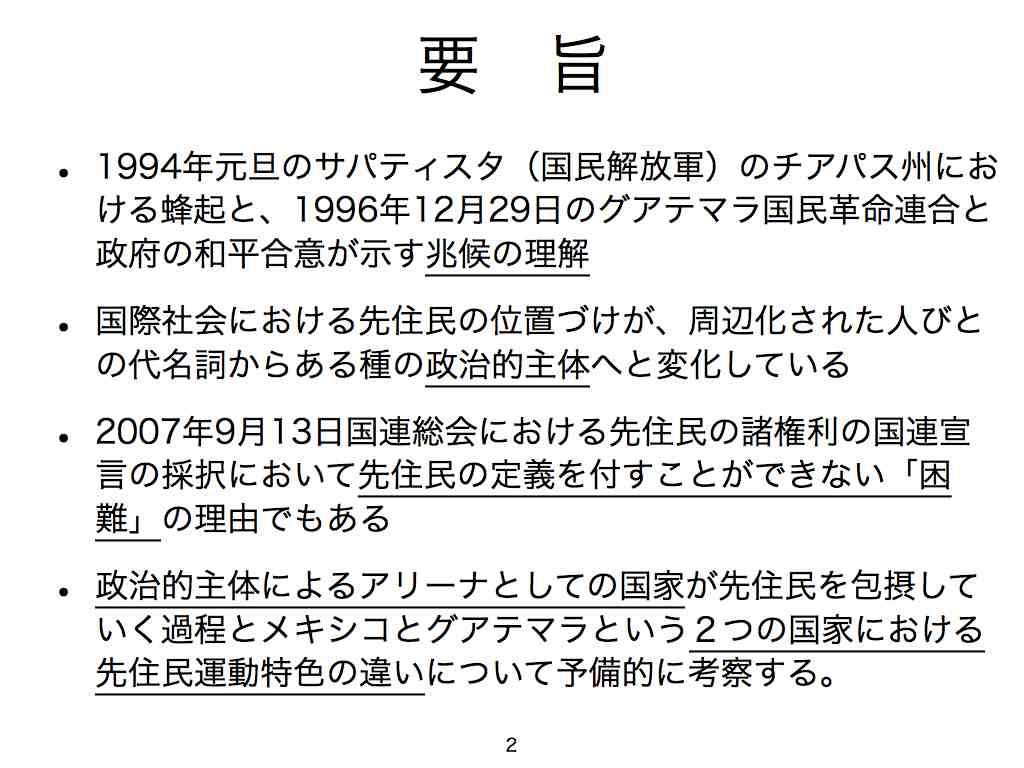 |
【2】 過去20年間における中米先住民運動にとってエポックメイキングなことを挙げるとすれば、それは1994年元旦のサパティスタ国民解放軍のチ アパス州における蜂起と、1996年12月29日のグアテマラ国民革命連合と政府の和平合意である。このことは、国際社会における先住民の位置づけが、周 辺化された人びとの代名詞から「ある種の政治的主体」へと変化している兆候であることを私は仮説的に示したい。先住民が誰のことであるのかについては、 2007年9月13日国連総会における先住民の諸権利の国連宣言の採択において先住民の定義を付すことができない「困難」に直面していることでもわかる が、先住民が政治的主体として顕示的に浮上してきたことをここでは主張する。端的に言うと21世紀における先住民とは政治的アイデンティティことをさす言 葉である。複数の政治的主体によるアリーナとしての国家が、先住民を後発的に包摂していく過程のなかで、「先住民運動が形成されたこと」と「階級闘争にも とづく農民運動」との歴史的社会的関係について、私たちはメキシコとグアテマラでケーススタディによる比較研究を予定しているが、その理論的枠組みについ て、本発表で予備的に考察したい。 ※サパティスタの武装蜂起と、20年後ののちにみたNetflixの「ナルコス(Narcos)」「ナルコス:メキシコ編("Narcos:Mexico")」や「エル・チャポ」をみると、麻薬マフィアと サリナス政権のおどろくべき癒着や、麻薬カルテルがメキシコ社会を激しく蝕んでゆく姿が、この背景に厳然としてあることに驚かされる。
|
|
|
【3】
今日、先住民が文化的アイデンティティと関連づけて論じられることの、歴史的起源は、18世紀末のヨーロッパに遡ることができる。ヨハ ン・ゴッ トフリート・ヘルダー(1744-1803)は、言語が神から与えられたという「言語の神授説」を批判し、文化の基盤概念としての言語の意義を主 張した。 そしてヘルダーは、文化の多様性と個々の集団帰属の結びつきから「民族語」の意義を明らかにしている。このことが実際の政治的問題になるのは、そこから半 世紀以上たったオーストリア=ハンガリー帝国期(1867-1918)であ る。侵略ではなく合意(妥協=アウスグライヒ)として生まれたこの帝国におい て、オーストロ・マルクス主義者オット・バウアーやカール・レンナーらの多民族による国家形成についての理論が議論されたが、彼らの関心は民族すなわち国 民がどのような政体に帰属するのか、その意識や文化言語の関係、ならびに政治的自己決定の考え方について、現実に直面する問題として議論された。他方で 1920年代以降本格化する社会人類学・文化人類学の近代的民族誌の蓄積は、民族集団と文化の結びつきの複雑な関係を明らかにしたが、同時に「文化」を民 族集団の帰属物として識別・認定する作業の政治的正当化を生み出した。そして、かつ、そのような能力をもつ専門家の知的権威の確立を必然とした。 |
|
|
【4】
啓蒙主義以降、国民の権利はあたかも「自然法」(natural law)のように国家によって保証されなければならないと主張されるが、他方、国家の至高性(sovereignity)はまさに国民にあるという〈国民 主権〉は、一種の循環論法をなし、国家が国民の主権(sovereignity)を侵す矛盾は今日でも事欠かない。近代の国民国家が内包する問題をあぶり 出すには、政治的主体が「自然法」のようには当てはまらず、その存在論的意味をもって国民国家の概念に対して挑戦をいどみ、国家概念への反省的自覚をもた らす人たちについて知ることが手がかりになる。国民の概念にそぐわない人たちの存在の扱いをめぐる政治的領域を課題とするのである。その中には、犯罪者・ 制限行為能力者、国内に留まる無国籍者、外国人、難民そして本報告が焦点化する先住民が含まれる。
※ |
|
|
【5】
|
|
|
【6】
このような先住民を本質化することには次のような逆説が生じる。「先住民は客観的に存在する」というイデオロギーは、保護主義的な非先 住民から も主張され〈先住民性〉を保持しながら、同時に帰属国家の経済的あるいは政治的抑圧からの解放を目論む言説としてしばしば使われる。次に「先住民は客観的 に存在する」という信念は、先住民と非先住民の区分を固定化する信念を派生する(cf. jew/gentile)。そして「先住民は客観的に存在する」という信念の正しさは、当事者と非当事者の双方の見解の一致を要求するが、どちらか一方の 否認により客観性の根拠を失う。 |
|
|
【7】
さらに、「先住民は客観的に存在する」という信念と「先住民の文化的アイデンティティによる自己定義」は矛盾しないが、この考えは先住 民と非先 住民のハイブリッドを——この場合は民族のみならず文化的要素のハイブリッドもまた——容認する方向には向かわず排除へと向かう。しかし、そこで引かれる 線引きは客観的なものになりえず、両者の境界は双方に対して被抑圧的/抑圧的に働く。最後に、「民族と文化」を結びつける発想にもとづく客観化仮説は、先 住民文化の性質をより本質化し、「非先住民の自由でフレキシブルなアイデンティティ形成」と対比した区分として際立たせる働きをもつ。以上をまとめると、 恣意的で、意識的/無意識的な取捨選択の結果として、本来客観的ではなかったものを客観的なものとして錯認してしまうことになるのである。 |
|
|
【8】
そのため先住民の異質性の強調は、自分たちのやり方でしか統治することができないステレオタイプの先住民像をはからずも容認してしま う。 |
|
|
【9】
先住民への介入ではなく、先住民の自己決定にもとづく新たなアイデンティティの覚醒を、政治的主体=市民になるためのものとして考える とどうな るだろうか。オーストリア=ハンガリー帝国期の経験は我々に次のように教えてくれる。マルクスによれば、フランス革命の「人と市民の権利宣言」の「人と市 民」とは自らを養う財産と教養をもつ人[ブルジョア]のことであり無産者階級は除外されていた。1848-49年革命は、無産者階級の市民への帰属をめぐ る再確定、つまり市民に含まれる人の境界の改定を求める運動でもあった。オーストロ・マルクス主義者たち(オットー・バウアーやカール・レンナーら)やカ ウツキーによれば、異同や相互批判はあるものの、民族=文化=言語=国民という多元性とそれらの集団の自治能力を認めた上での、連合体としての連邦制(レ ンナー)や差異を乗り越えた統合(カウツキー)の可能性を模索していた。20世紀後半のメキシコとグアテマラで起こった先住民運動は、文化的アイデンティ ティの復権運動と理解されているが、同時に同化を強要する国家に対する多元主義にもとづく文化的主権をもつ市民への帰属をめぐる再確定を求める(=すなわ ち政治的主体になるという)運動ではなかったかということだ。 |
|
|
【10】
メキシコとグアテマラという両地域とりわけ両国の国境を挟むチアパス州とグアテマラの西部高地の先住民と国家の関係の歴史を比較対照す る表を描 くと次のようになるが、これらの要素とそれぞれの先住民運動形成の関係について今後調べてゆくことが私たちの課題となる。 |
|
|
【11】
国家による先住民の国民への包摂過程は、ときに意外なところで生ずることがある。2006年初頭の国連平和維持活動でコンゴで亡くなっ た先住民 兵士たちは、グアテマラ「国民の英雄」として葬られることになった。 |
|
|
【12】
他方で、ポストコロニアル近代国家からみた先住民は、容易に国民に同化しようとせず、国民不和の元凶とみなされることもある。1970 年代まで の農民運動では、左翼運動を基盤にした土地回復を求める階級闘争があり、1990年代以降の先住民運動では、文化的アイデンティティの承認のみならず。よ り「広範囲の自己決定権」を求める解放闘争の様相を示す。これらは、アイデンティティによる「差異化の政治学」と呼ばれ、国民(nation)の統一を妨 げ、先住民の分離独立を目指す国家統治の根幹を揺るがすものとしばしば解釈されてきた。 |
|
|
【13】
先住民のテリトリーにおいておこなわれている多国籍企業と国家による鉱山開発は、天然資源の先住民の富の搾取や付近の環境汚染といった 「先住民 の生存権」への侵害であると主張される。国際社会の監視もあり、国家はこの告発を黙殺することはできなくなりつつある。 |
|
|
【14】
では国際社会からみた先住民は、どうであろうか。2007年9月13日国連総会では「先住民の諸権利の国連宣言」の採択があったが、宣 言におい て先住民が誰であるのか実質的定義をおこなわないこととなった。権利宣言では、帰属国家へ完全な政治参加や自己決定権に加えて、諸権利の保全について国家 と交渉する権利を有するものとされた。すなわち国家と社会的信頼関係をむすぶことが期待された国家内における政治主体として独自の地位(sui generis)をもつものとして認められつつある。 |
|
|
【15】
すなわち、政治的主体としての先住民とは国家が先住民を国民として包摂する際に生じる過程が構造的に生み出した集団であり、先住民の社 会参加へ の要求は、当該国家における市民権の境界画定をめぐる民主化闘争であると解釈することができる。したがって先住民運動は、「差異の政治学」を具現化してい る闘争であるよりも、多様性を認められながらも政治参加における平等性が確保されていない現状を鋭く批判し、来るべき近代国家の民主制にむかう改善のため の人びとの挑戦と理解することができる。 |
|
|
【16】
今後の課題として、1970年代までの階級闘争と、冷戦の終結以降、エスノナショナリズムの勃興とアイデンティティを基盤にした「差異 の政治 学」が、同一の目標を目論んだものなのか否かについてさらなる検証をつづけてゆく。また、農民運動組織の形成や国家が実施した農民への土地取得政策という 歴史的先行条件が、後の先住民運動や「闘争」にどのような影響を与えているかについての検討が必要になると思われる。このことは平成22-25年度科学研 究費補助金を受けた「中米先住民運動における政治的アイデンティティ:メキシコとグアテマラの比較研究」において今後の調査研究を通して明らかにしたい。 |
|
|
Shelton
H. Davis (August 13, 1942 – May 27, 2010) was an American cultural
anthropologist and activist for the rights of indigenous peoples. His
academic and organizational work with Latin American indigenous
communities contributed to the late 20th century public interest
anthropology movement. He created Harvard University's first
undergraduate course on Native Americans in the United States. Victims
of the Miracle, his in-depth account of the social and environmental
impact of the Brazilian Amazon development program in the 1970s, is
considered a seminal work in cultural anthropology.[1] The Anthropology
Resource Center, which Davis founded in 1975, was cited by Ralph Nader
as an exemplifier of anthropology in the public interest— anthropology
that, in Davis' words, "would give information not to bureaucrats for
the purpose of social engineering but to citizens and community groups
for the purpose of social change.”[2] His work as Principal Sociologist
at the World Bank was key to the mainstreaming of social issues – such
as social impact assessments and social inclusion of indigenous peoples
during Bank project preparation – into World Bank policy during the
1990s.[3] "In the words of his coworkers at the Bank, he was one of indigenous peoples’ “staunchest advocates” from inside the Bank, where he spent his time taking on “the struggle for minority rights—territorial rights, linguistic rights, cultural rights—as his professional mission.” Davis firmly believed that the “best qualified experts” on what a community needs development-wise are the community members themselves, and thus worked actively to ensure that the Bank included the poor and indigenous in the development decision-making process. As a result of his work “mainstreaming” social issues into Bank policy, social impact assessments and social inclusion of indigenous peoples during Bank project preparation became the norm. His colleagues write that he was an “indefatigable defender of indigenous peoples’ rights and an unshakable optimist,” and that “one could solidly count on Sandy whenever a battle for ‘Putting People First’ in development had to be carried out inside the Bank, or outside.” " - Shelton H. Davis. |
|
|
【17】
ご静聴ありがとうございました。これから始まる科研の調査研究チームの、太田好信さん、狐崎知己さん、小林致広さん、滝奈々子さんにも 御礼申し 上げます。 |
|
|
【番外1】 歴史上の教訓として、先住民運動をみればどうなるだろうか。反革命勢力であるスラブ民族を「歴史なき民族 Geschichtlose Voelker」として統治能力の本質的な欠如として断罪するマルクスとエンゲルス 1849年と、カール・レンナーによるマルクスの主張への批判と、レンナーが考案する民族(Nation)の属人主義的定義[民族=アイデンティティ論の 嚆矢]と[言語以外の]文化にもとづく民族=国民自治論という違いをなした。マルクスらとレンナーの主張の違いは1848年革命勢力の担い手としての民族 =国民の評価、つまり前者の「歴史主体か否か」に対して後者の「歴史主体になれるか否か」の問いの違いにもとづくものである。 |
|
|
【番外2】 これらを整理すると、オーストリア=ハンガリー帝国の遺産として、今日における国民=国家論(多民族・多言語・多文化国家)があり、そ の経験は 1992年のEUの同盟規約であるマーストリヒト条約にも反映されている。歴史的産物としての民族と国民をおなじ呼び名(nation)で理解する現在の 用法ができあがった。その後、近代国家の伝統は擬古的にねつ造されたものという「伝統の創造」論や、国民(ネイション)は印刷資本主義によって形成された 「想像の共同体論」など、国民国家の正統性の根拠は、いわゆる文化構築主義者の批判的挑戦を受けてきた。にもかかわらず国際政治においては、権利主体の 「民族」や「国民」が、そして彼らが保有する「文化」の尊重が政治をおこなう権利を有するいう信条(クレド)は共通のトークンとして流通している。だが文 化と政治の位置関係は依然として不明瞭なままで、「政治的主体」としての先住民についての概念は国民の間に不要な亀裂をいれる「差異の政治学」の主体とし て否定的に取り上げられるだけである。啓蒙主義移行、国民の権利はあたかも「自然法」のように国家によって保証されなければならないと主張されるが、他 方、国家の至高性(sovereignity)はまさに国民にあるという〈国民主権〉は、一種の循環論法をなし、国家が国民の主権 (sovereignity)を侵す事態は今日でも事欠かない。それどころか先住民は、構造的な人種・民族差別により二級市民としての資格しか付与されて いない。 |
|
|
【番外3】 オーストリア=ハンガリー帝国末期、すなわち第一次大戦中には、20世紀最大の民族問題であった「ホームレス民族」=ユダヤ人のパレス チナ帰還 をめぐる国際政治上の大きな事件がおこりつつあった。それは普仏戦争(1870-71)後の第三共和政下の1894年におきたフランス陸軍のユダヤ人将校 の冤罪事件に起源をもつ。ドレフュス事件に取材をしていたオーストリア帝国期(1804-1967)のブダペスト生まれのテオドール・ヘルツル(1840 -1904)はユダヤ人に対する差別や偏見を克服するためにパレスチナにユダヤ人国家を建設することを夢見、ドレフュス事件の3年後にバーゼルでシオニズ ム思想についての会議を主宰した[97年以降は1901年まで毎年開かれていた]。その18年後、ドイツ帝国やオーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝 国などからなる中央同盟国と英仏露を中心とする連合国が戦う第一次世界大戦の開始後の1915年に、英国はオスマン帝国と戦いをすすめるなかで、アラブ人 指導者フサインにアラブ国家の建設を約束していた(フサイン=マクマホン協定)。しかし、その翌年、英国はフランスとロシアと、戦後のパレスチナ分割につ いての密約を交わしていた(サイクス・ピコ秘密協定)。さらに翌1917年末に、英国は先のシオニストの働きかけを受け、パレスチナでユダヤ人のナショナ ル・ホーム建設を支持するバルフォア宣言を採択した。 |