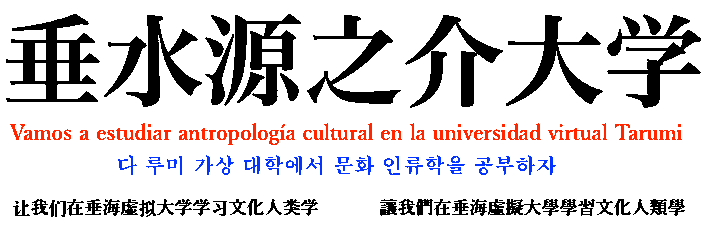ラカンドン・ジャングル・ブック
Lacandon Jungle Book

ラカンドン・ジャングル・ブック
Lacandon Jungle Book

マヤ遺跡を訪れる観光客にはほとんど知られることがないが、ユカタン半島の内奥の低地は被抑圧 先住民の解放を唱うゲリラの活動拠点でもある。チアパス高地で蜂起したサパティスタも、その後メキシコとグアテマラ国境に位置する「ラカンドンのジャング ル」と呼ばれる後背地に一時的に退き、代表を送って政府との交渉のテーブルについた。ところがこのラカンドンの人たちが住むジャングルとは、マヤ考古学に おけるいくつかの重要な発見があり、ラカンドンを含む現代マヤの人たちと古代マヤ遺跡を取り結ぶステレオタイプが生産されてきた土地でもあった(→「ラカンドン・コスモロジーに関するノート」)。
ラカンドンのジャングルの観光開発は、一九六四年にメキシコのグスターボ・ディアス・オルダス 大統領が選挙期間中に、ボナンパク、ヤシュチラン周辺地域の遺跡公園の整備ならびに周辺の道路や空港の建設など観光インフラストラクチャーの開発を公約し て以降本格的に着手されるようになる。(MacDonaldo,1981:155)。
ジャングルの奥地の密林でのマヤ遺跡にたたずみ「伝統的な儀礼」をおこなうラカンドンの人たち は数々の記録映画や『ナショナル・ジオグラフック』誌に代表されるような媒体を通して失われたマヤ文明の格好の表象となった。その起源は今から半世紀以上 にも遡れる。一九四四年ユナイティッド・フルーツ・カンパニーはジャイルズ・ヒリーにラカンドン族の映画を撮影するように要請し、そのスポンサーとなっ た。これがボナンパク遺跡のフレスコ画の発見の発端となる。発見された壁画には、それまでのマヤ人のイメージからはかけはなれた情景が描かれていた。当時 の考古学者が描いていた古代マヤ人のイメージでは、彼らは宿命論的な時間の概念に縛られ、司祭による神権政治によって平和的に統治されていたと考えられて いた(Fash,1994:183)。しかしボナンパクの壁画には、マヤの戦士が被征服民を斬首したり拷問している絵が描かれていたのだ。にもかかわらず ボナンパク遺跡の最初の報告書(一九五五年)には、その事実は過小に評価され、それまでのマヤ文明のイメージは踏襲されたままだった(ボーデとピカソ、一 九九一)。
このイメージが専門家によっても頑強に支持されていたことは注目に値する。例えば一九世紀末マ ヤ学者アルフレッド・モズリーのヤシュチラン遺跡の石碑解釈の場合もそうである。彼は、自己供犠によって身体の一部を傷つけている人物像を模写するさいに 意図的か非意図的かはともかく残酷にみえないように描いてしまった(落合、一九九一、三頁)。古代マヤ人があたかも平和で深遠なマヤ歴を刻む人たちである かのようなイメージを専門的な考古学者たちも抱きつづけた。後のマヤ学の権威エリック・トンプソンですら、ピエドラス・ネグラス遺跡の碑文には王位継承に 関することが書かれているというタティアナ・プロスクリアコスの主張の可能性を認めたが最終的に彼女の学説は受け入れなかった。このような古典期時代とよ ばれる古代マヤのイメージをウイリアム・ファーシュ(一九九四)は「神話」とまで言いきっている。
ところが、その「神話」には逆のモーメントも働いていた。古代マヤをとりあげた米国の大衆本に はマヤの残虐なイメージを誇張したものも現れ、血に飢えた供犠に熱狂したり、マヤ文明の崩壊を好戦的な性格にもとづく戦争の過剰で説明するものもあらわれ た。このような好戦的で残虐なマヤ人のイメージは、現在の先住民系のゲリラや農民の否定的なステレオタイプとして生き残り、彼らと政治的および利害的に対 立するラディノ(メスティソ)系エリートなどに流用されるにいたった(Fash,1994:187)。
「ラカンドンのジャングル」は、そのようなマヤ文明のイメージの生産地であったがゆえに、過去 三〇年間に多数の人たちがそこをめざしてやってきた。宣教師、伐採の請負業者、映画制作者、そして魂の探求者すなわちヒッピーなどである。もちろん日本人 も例外ではない(若林、一九八〇)。こうしたなかでは悪い冗談すら起こりうる。旅行作家キャンビーはラカンドンのジャングルを訪れた際に、そこにいた男た ちの一人をつかまえて、スペイン語で、ナハから来たのかと尋ねた。ナハというのはキリスト教の布教が成功していなかった村、すなわち「ほんもののマヤ文 化」が残る地区だった。男は彼を見下すかのように「俺はカリフォルニアから来た」と言った(キャンビー、一九九三、八五頁)。
ここにあげたことは、古代マヤの遺跡を訪れる現代の観光客には全く無関係なことであろうか。そ うではあるまい。古代マヤのイメージは、考古学的調査や研究の成果のみならずマヤについて書くすべての著述家の内容が一般に膾炙されてできあがったもので ある。そのイメージが観光を煽り、ガイドの説明やガイドブックではそれらが取捨選択されたうえで誇張されて観光客に伝わる。
文化遺産の「生産」とは、過去の歴史が改竄されたり遺跡遺物の偽物が捏造されることではない。 文化遺産の「恒久的な価値」とは、過去について解釈がつぎつぎと供給されているからこそ意味をもちつづけているのである。そのために「文化遺産」は現在の 権威ある正当な解釈、つまり科学的な考古学の研究成果をつねに必要とする。そして学問の権威とは宙に浮かんでいる存在ではなく、ときにその内容がチェック され、人びとの関心を通して社会の眼にさらされる。マッカネルは観光研究において、文化を合意(consensus)の一種とみて、それをマルクス的な 「生産」の概念と結びつけた(MacCannell,1976:25)。文化の「生産」とは、そのような中で文化遺産の価値についての社会の合意が維持さ れているあり方のこととしてとらえてみたい。
古代マヤの碑文・図像研究の第一人者リンダ・シールの学問の成り立ちとそれの社会への波及効果 を例として考えてみよう。彼女はいわゆる発掘屋ではない。それだけではなくマヤ学の考古学の専門的トレーニングを受けて研究者になったでもなかった。彼女 は一九七〇年にユカタン半島を旅行した足をのばしてパレンケ遺跡によるまでは、アラバマの小さな大学で一般学生に「芸術入門」を教える職業画家にすぎな かった。パレンケ遺跡を訪れてシールは言うならば「マヤおたく」(Maya-phile)の道をあゆみ始めることになる。かくして三年後、パレンケで三五 名が参加したマヤ研究の小さな国際会議でカルガリー大学の学部学生だったピーター・マシューズと連名でパレンケの王家の即位と退位年を確認し発表するにま でいたった。この会議は、それ以降のマヤ碑文研究の流れをかえる枢要なものとなった。シールはその後別の大学にマヤ研究者として職を得て、やがて碑文・図 像研究における重要な著作を発表するようになる。彼女たちの一連の研究は、それまでフィールド研究の成果の上に、美術史の図像学と文化人類学の親族研究と 王権の象徴研究を節合させたような新しい領域を開拓した(Shele and Freidel,1990:13-15)。
このようなマヤ研究の新しい領域のラディカルな開拓は『ナショナル・ジオグラフィック』誌など マスメディアを通して古代マヤ文明に関心をもつアマチュアに広がり、結果的に人びとが抱く古代マヤ文明やマヤのイメージにも影響を与えた。つまり、天文観 察に明け暮れる宿命論的でエキゾチックな民族から、戦争を指揮し王位継承をめぐって抗争する王を戴き、トウモロコシ畑を耕作し神話にもとづく儀礼を実践す るよりリアルな人間像へとである。
もちろん王朝研究に熱を入れあげることに対する専門家からの厳しい批判もある。それはマヤの王 国の経済的な基盤の問題や、歴史を刻んだ碑文そのもののイデオロギー性の検討を捨象してしまうことになるという指摘である(Fash,1994:194- 5)。
にもかかわらずシールたちの研究とその大衆化は、シールがかって歩んだような知的好奇心旺盛な アマチュアを再生産に寄与している。また水準の高い一般向けの科学雑誌が専門家ではない教養のある人たちに与える影響を考えることは重要である。現地では 英語版のみならずスペイン語の『ナショナル・ジオグラフィック』の抜刷の別冊(例えばコパン遺跡ならコパンの記事が、ティカル遺跡ならティカルの記事)が 印刷され、マヤ文化への高級な理解をもたらす書籍として実用的なガイドブックとならんで遺跡付属の博物館の売店におかれたり、現地人によって直接路上で売 られたりしている。マヤ遺跡がそれらのガイド・ブックによって中産階級の学習の場に変わることすら珍しい情景ではない。また今日のメキシコの遺跡において 国立人類学歴史学研究所の許可書をもって案内するガイドたちが語る、石碑の新しい読み方や王朝の歴史の語り方にもマヤ考古学者たちの最新の研究が投影され ている。そのようにしてマヤ研究の新知識は観光客のあいだに伝わる。
この論文(一部)は、同名の著者 による『観光の二〇世紀』[共著]石森秀三編,ドメス出 版, (担当箇所「遺跡観光の光と影――マヤ遺跡を中心に」および総合討論),pp.193-206,1996年12月と、ほぼ同じ内容のものです。文献と謝辞 は省いてあります。