Late-Imperial Japanese Medicine: An Example of Phantom Medicine

ファントム・メディシン
Late-Imperial Japanese Medicine: An Example of Phantom Medicine

池田光穂
|
|
[注意]この原稿は、2004年6月における、日本文化人類学会研究大会において、「後発帝国医 療——ファントム・メディシンの諸相——」のタイトルで発表されたものです。 池田光穂 * |
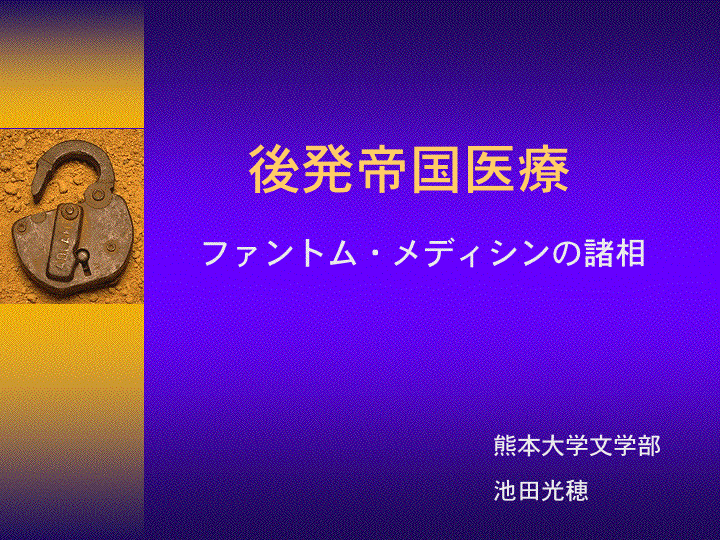 |
手足を切断した経験のある人が、手足(四肢)を切断した後も、しばらくの間手足の感覚が残ること
があります。さらに、眼に見えない幻の手足の痛みを訴えるという奇妙な現象があります。 これを医学用語では、幻肢あるいは幻影肢(phantom limb)と呼んできました。幻肢は、だいたい9歳未満の子どもは体験しないものだと言われています。つまり、幻肢は、大脳皮質に身体像が形成されるこの 時期以降の発達をとげた成人の切断者に認められる現象だとひとまず説明することができます。幻肢痛(phantom limb pain, phantom pain)はこのありえない幻の手足に、しびれ、疼くような痛み(疼痛)あるいは捻られるような痛み(絞扼痛:こうやくつう)などを伴うもので、幻肢の感 覚をもつものの5割から7割の人が体験するといいます。 |
|
|
幻肢痛には、切断される以前の手足の状態と痛み経験とのつながりがあると言われています。つま り、切断にある姿勢や動作をとったときに痛みを経験した場合、切断後に同じような姿勢をとった時に痛みが再来するといいます。他方、幻肢をあり得ない痛み であるというふうに唯物論的解釈をすると、幻肢痛(phantom limb pain)は文字通り「あり得ない痛み」(phantom pain)とされて、手足の切断者の痛みの増減は、生活不安、経済的家庭環境による心理的因子に関連すると説明されます。心理学説では、痛みの長期持続例 をその患者の環境に対する欲求不満の表象にされてしまいます。しかし、幻の手足(=幻肢)がなくなった時には痛みは消失します。また手足の感覚神経の伝達 路を切断すれば幻肢はなくなります。つまり幻の手足が感じられないものに幻の痛みはありません。 |
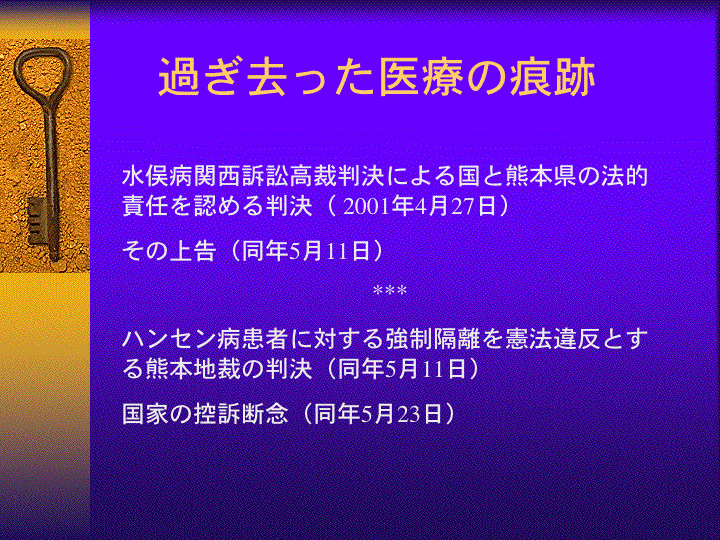 |
水俣病関西訴訟高裁判決による国と熊本県の法的責任を認める判決とその上告(2001年4月 27日/5月11日)、ハンセン病患者に対する強制隔離を憲法違反とする熊本地裁の判決と国家の控訴断念(同年5月11日/5月23日)。このような事件 には、過ぎ去ってしまった医療の痕跡というものが見え隠れします。水俣病事件においては、水俣病の原因究明において様々な医学的仮説と非難がくり返されま した。また決定的な証拠をめぐる情報の隠蔽の事実が暴露されたり、賠償に直面した際に、水俣病の認定をめぐって、医学的診断基準が当時の政治的な判断によ り左右していたことは明かです。ハンセン病患者に対する強制隔離政策のもとでは、医学的判断が社会的死を意味しただけでなく、療養所への入所が、親族や家 族の公的な記憶から末梢するという事態がさまざまな局面でおこっていました(→記憶の問題)。 水俣病の語り部の人が語った言葉で忘れがたいものがあります。祖父と父親を水俣病で亡くした彼女の家庭では水俣病の話はタブーでした。彼女が語り部になっ たのは、消したくても消えない記憶、亡くなる前までつけられていた父親の手帳の中にある記憶の断片の再発見と、そして水俣に住んでいながらそれまで手に取 ることのなかった原田正純の著書『水俣病』(岩波新書)を刊行後30年後に初めて読んだときに現れたと言います。彼女にとって水俣病について何も知らな かったという思いと、書物の中にある経験と自分の幼年時代の記憶の結びつきにより、自分がその歴史の真っ直中にいたという衝撃です。忘れようとして抑圧し てきたものが、偶然により亡霊のように甦るのです。その亡霊は「水俣病は終わっていない」ことを私たちに教えます。 |
|
|
帝国医療がなにを指すのかについての合意は研究者の間にはありません。たとえ歴史的にそのよう な用語法が登場しなくても、私はそれが当時の医療従事者を動員するためのかけ声であり、今日では、帝国的システムを憎む歴史家たちとイメージを共有する研 究者たちの一種の仮想敵(imagined enemy)こそが帝国医療の実態であると思います。2004年2月に地域研究企画交流センターと長崎大学熱帯医学研究所主催のシンポジウム『熱帯医学と 地域研究』において、今なお植民地医療のエートスを引き継ぐ熱帯医学研究者と、帝国医療批判という視座を引き受ける歴史学・人類学・社会医学の研究者が会 してさまざまな議論が交わされました。結局のところ、議論は平行線に終わり、近代医学の優位性を疑わない熱帯病撲滅論者と、熱帯医学のプロジェクトに対し て相対主義的な反省を促す歴史学・人類学者という対立が鮮明になりました。日頃お互いに陰口をたたき合う連中が同じ議論の席上についたという点では大成功 でした。しかし「熱帯医学」に対する関わり方が擁護と批判というそれぞれ正反対であるため、和睦や和解の調印ではなく一種の離婚訴訟という体を示していま した。その心は、これまでの我が儘な自己主張を控えて、お互いの理論上の欠点を双方認め合い、共に別々の新しい研究を歩むことという教訓を得たことです。 |
|
|
ここから私が学んだことは、次のようなことです。人文科学的な帝国医療研究が陥りがちな、医療 を統治のモデルとしてみなしたり、近代医療批判という結論を予め用意するようなことをやめ、なぜ実行者たちはそのような医療のシステムで巧くいくと思いこ んだのか、計画に巻き込まれた人たちがなぜそのような話に乗ったのか、あるいはそこに見られる実践と理念の調和や不協和を人びとはどのように説明してきた のかについてさらに一歩進めて議論をしようということです。もちろんこれは思いつくのは易し、実行するのは難しで、素材の選択から調理の仕方まで、さまざ まな創意工夫が必要であることは言うまでもありません。 |
|
|
細菌学説の提唱、それにもとづく化学療法、ワクチンなどの免疫療法の確立、あるいは経験的知識 にもとづいて行っていた隔離や検疫などが科学的に説明がつき、医療者が専門的知識とそれに基づく実践を通して、身体内部から身体の外部、家族や共同体さら には国家の統治に至るまで様々な介入が始まったとき、近代医療は国民国家システムの中で無くてはならない役割を担うようになります。〈黴菌〉により引き起 こされる病気は現代の〈妖術〉になり、近代医療の医師たちは人びとが畏怖と信頼を寄せる強力な〈妖術師〉となりました。このような妖術の体系は、それを裏 付ける社会の法的なシステムを発達させてゆきます。伝統社会の妖術も近代のそれもまた偶然性の社会的制御体系です。石井四郎の七三一部隊はその中でも特異 的な地位を占めていることは、すでに皆さんご存じのところです。細菌戦の準備は1920年代には各国で研究が始まっていました。1925年のジュネーブ議 定書での化学兵器や生物兵器の使用は禁止が明文化されていましたが、イギリスが批准を拒否し、議定書そのものは未発効のままでした。石井部隊をその後の発 展を阻害する国際法的な基準などが実質的に存在していなかったのは、戦後にアメリカ合衆国と関係者の間の戦犯免責が通用したことでも明らかです。医学者は 有用性にもとづくデータを提出し、より巨大な実験計画を立て、それを戦前の国家は承認し、予算を配分していました。マルタと呼ばれた人体実験の被験者たち を大陸各地から調達するにも「特移扱」という官僚的手続きが正式にとられました。七三一部隊の運営や実験に関わる予算は、関東軍参謀長や作戦部長からなる 特別委員会からなり、その使途は議会に報告の義務のない「関東軍非常軍事総予算」の部分を構成するものとして処理されたといいます(1940年の予算規模 は1千万で、現在の貨幣価値で100億あるいはそれ以上)。 |
|
|
イギリスやフランスの帝国医療と同様、日本においても軍陣医学(military medicine)と近代医学の関係は複雑です。熱帯や植民地における近代医学の研究成果は、マラリアやチフスの対策として軍陣医学に反映されました。し かし、近代医学の研究のデータ収集に貢献したのは、兵士をつかったさまざまな臨床実験でした。ただし兵士たちは実験動物群ような統制された集団ではありま せんし、兵士が実験に使われるのはワクチン接種などのような兵士の有用性の向上を目的としたものでした。日本の厚生省が内務省から独立した背景には、国民 の出生率の低下や徴兵検査における壮丁(そうてい)の体力低下などを背景とした国民の人口体力政策と、医療保険などの普及を目的とした福祉国家政策という 2つの目的がありました。日本の厚生省設置当時において予算規模や国家制度に大きな影響力もち、実験を中心とする医学研究の推進力となっていたのは、各地 にある陸軍病院でした。医学校を卒業した学生の研修先として条件のよい環境にありましたし、医師は軍隊上の身分(多くは士官)が与えられました。陸軍病院 では臨床教育を重視し——その分患者に対する人権意識は希薄でしたが——、傷病兵の供給から熱帯医学上の研究材料を得ることができ、熱帯医学の実践的な研 究教育に従事することができました。また軍人の階級制度とメリトクラシーが、学閥による序列が加わり、さまざまな出世栄達の回路を複雑にしていました(た だし、軍医部の三長官である陸軍省医務局長、陸軍軍医学校、東京陸軍病院長は東京帝大出身者で占められていた)。日中戦争以降は、それぞれの軍隊が占領し ている前線の医療者との情報の交流がありました。軍医は終身雇用ではなかったので、召集解除により大学に戻ったり開業というキャリアトラックの変更もあり ました。一度招集解除になり、必要に応じて再び招集されるというフレキシブルな人事をおこなっていました。このようにみるとネオリベラリズム状況における 今日の医療改革は、亡霊のように見え隠れしてきた帝国医療を、まさに未来になりつつある現在として人類学者にこれまでとは異なったリアリティをもたらしま す。 |
 |
冒頭でとりあげた幻肢と幻肢痛(phantom
pain)についてM.メルロ=ポンティは『知覚の現象学』「身体」において、その生理学的な説明と心理学的な説明の両方を論難して、幻肢は、手足の表象
ではなく、その両義的な現前だと解釈します。我々が「みずからに習慣的身体と与えることは、最もよく統合された実存にとって内的必然」(p.156)だか
らです。幻肢をもつことは「その腕だけに可能な一切の諸行動に今までどおり開かれてあろうとすることであり、切断以前にもっていた実践的領域をいまもなお
保持しようとすること」(p.147)になります。手足の記憶の問題にからめてメルロ=ポンティは、幻肢は過去の記憶が呼び戻されているのではなく、実存
的な身体もつ「準−現在」(p.153)そのものだと言います。つまり「腕の幻肢とは、抑圧された経験とおなじく、まだ過去になり切ってしまわない旧い現
在」であり「どんな記憶も失われた時をふたたび開き、それが喚起する状況を再現するよう、我々に呼びかける」(p.154)ものだというのです。
これまで我々は帝国医療という幻肢と、それが現在の我々のからみた異常性(=政治と医療の直 結)や反倫理性(社会の効率を優先する全体論理のもとで弱者を抹殺する)がもたらす幻肢痛に苛まれてきたのではないでしょうか。現在の帝国医療の研究にポ ストコロニアルな道徳性を嗅ぎ取ることはそれほど難しくはありません。私にとって帝国医療を考える際の関心事は、帝国医療の幻肢痛の治癒方策を立てること よりも、帝国医療という修辞上の産物が、どのような社会のなかにも幻肢のように表出している現在の状況にあります。それが健康なくせに病気ではないかと心 配する〈症状〉つまり心気症(ヒポコンデリー)の兆候なのか、よりポジティブな健康を増進するための不可欠なチェックポイントであるのか、そのような二者 択一の議論が問題の本質ではありません。メルロ=ポンティの表現に倣えば、過去になりきっていない帝国医療という現在を、我々の目の前に様々な形で呼び出 し再現しているものつまり、ファントム・メディシンの諸相を明らかにすること、これが重要です。それこそが帝国医療の実践者たちが夢見た理想の医療であ り、今日の批判者たちが嫌悪して止まない最悪の医療でした。 |
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099

チフスのマリー(Typhoid Mary)