Conceptual Bottlenecke of the Sociologies of Science Studies, SSS
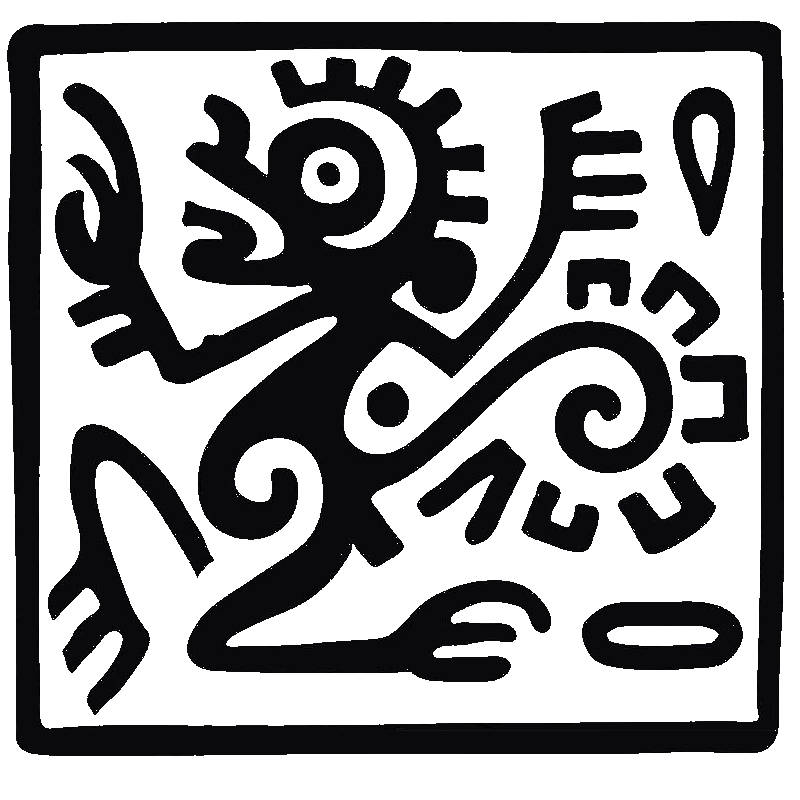
Mesoamerican Image of monkey
知識社会学の隘路
Conceptual Bottlenecke of the Sociologies of Science Studies, SSS
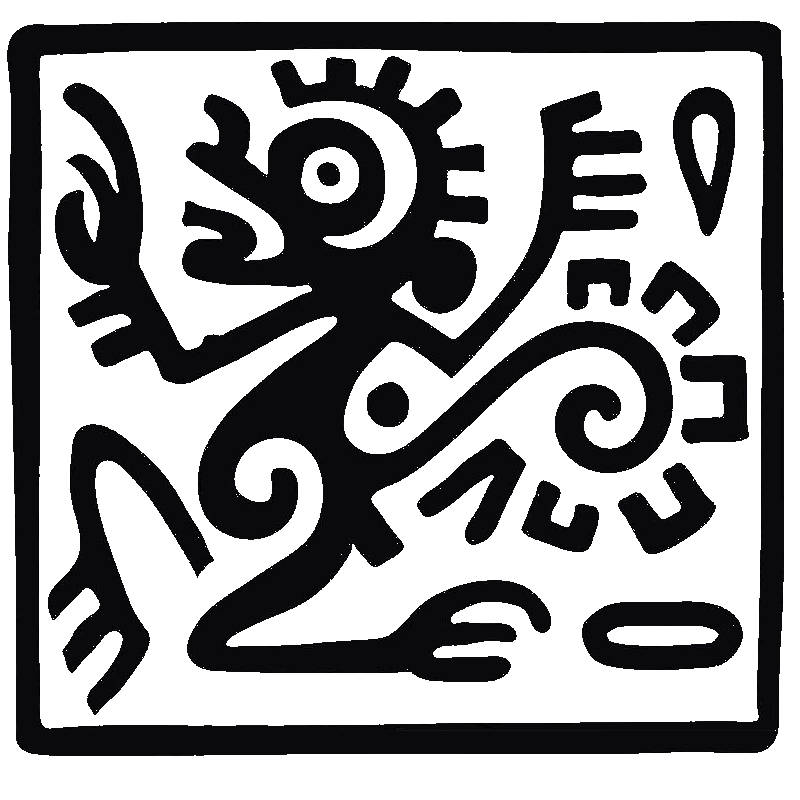
Mesoamerican Image of monkey
「このような科学的進歩概念の相対化とそれと 関連する科学者集団もつ「意識」に着目する流れは、研究者の関心を、科学研究者の著作や論文のみな らず、実験ノートや私信などへと移し、さらには科学者自身がどのように実験データから知識を構成していったのかという——「あまりにもカント的」な名称の ——知識社会学の細部への関心を生むにいたった[ギアーツ 1999:267]。その結果、科学者自身が生きた社会との関係、すなわち科学の社会史という研究下位領域の再活性化の契機にもなった[マルケイ 1985; 松本 1998]。もっとも有力なものがエジンバラ大学の科学研究グループ(ブルア[David Bloor, 1942- ]、バーンズ[S. Barry Barnes, ]、シェイピン[Steven Shapin, 1942- ]ら)のストロング・プログラムである。「科学的知識の社会学[Sociology of Scientific Knowledge, SSK]」のひとつであるストロング・プ ログラム[the strong programme]では、科学知識の信念や知識に関する社会的条件(因果性)、その時代におこった真偽、正否、合理/非合理の説明を価値判断ぬ きに行う(不偏性)、 それらの対立する要素の説明が同じ論理のなかで対称的に説明できる(対称性)、および説明がみずからの正しさを証明できる(自己反射性)という原則におい て科学の説明を試みようとした[ブルア 1986; バーンズ 1989]。ストロング・プログラムに代表される——科学論ではこれにバース学派が加わる——科学知識の社会学(Sociology of Scientific Knowledge, SSK)は、科学の社会現象を認識論的相対化によって理解しようとした立場である。さらにその認識論的な相対化ゆえに、あらゆる知識表象がその現 場の知識 生産のプロセスと無媒介的に認識論的に自由に操作されるという危険性を孕んでいた。そのもっとも悲劇的破綻の例はアラン・ソーカルの『ソーシャル・テキス ト』誌への意図的でっち上げ論文の投稿に始まるサイエンス・ウォーズであったと言える[GROSS and LIVITT 1994;キュセ 2010:IX-X, 319-323]。
科学研究への関心は歴史的発見から科学者自身が実験 室で行う日常的実践へと移動した。それは科学の発見のような歴史的事実の再構成では得られ ないような、より詳細で正確な情報が手に入るからであった。その背景には、会話分析やエスノメソドロジー、エスノサイエンスなど隣接経験科学(社会学や人 類学)の研究分析手法の発達があったこともその流行に拍車をかけた[ブラニガン 1984; ギルバートとマルケイ 1990]。科学の民族誌学研究の代表にあげられるのは、ラトゥールとウールガー『実験室の生活』[LATOUR and WOOLGAR 1986]、クノール=セティナ『知識の製作』[KNORR-CETINA 1981]、先にも触れたリンチ『実験室における技と人工物』[LYNCH 1985]、ラビノウ『PCRの誕生』(1998[1996])などである。今日では科学の人類学研究は、知識の権力性[e.g. NADER 1996; GOODMAN et al. 2003]に焦点があてられたものが多いが、この実験室から社会性への関心の移行は、後述するようにアクターネットワーク理論進展による(よい、そして悪 い)影響であることは明らかである。」(出典:池田光穂「科学的事実の産出と研究者の実践について」)
リンク
文献
その他の情報
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!

