On Hegel and Parricide
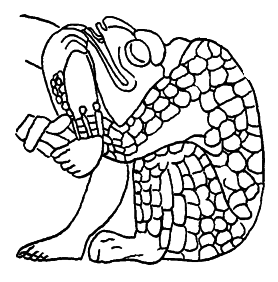
ヘーゲルと親殺し
On Hegel and Parricide
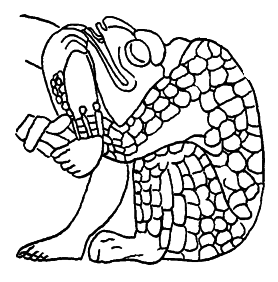
池田光穂
「北アメリカの未開人は親を殺し、私たちも同じこと をする」1)——ゲオルグ・ウィルヘルム・フーリドリヒ・ヘーゲル、すなわちドイツの観念論哲学者のヘーゲルは、1805年から1806年におこなった イェーナ大学での講義ノートの欄外に、このような奇妙な書き込みをしている。それから130年後に、このことを指摘したモスクワ生まれのフランスの哲学者 アレクサンドル・コージェブは、この書き込みがもつ意味を講釈してみせる。このコージェブのテキストもパリの高等研究院でのヘーゲル『精神現象学』に関す る講義録であった。
1) “die nordamericanischen Wilden tödten ihre Eltern, wir thun dasselbe.” ヘーゲル全集アカデミー版(Gesammelte Werke)Bd.8, S.211, Z.25
「親によって教育された子供は、親の存在そのもので もある親の社会的、政治的な行動を引き継ぎ、それによって親に此岸における「死後の存続」、自由と両立しうる唯一の(それも時間に制限された)「死後の存 続」を保証する。だが、歴史的な死後の存続は個体の行動の普遍性を保存するだけで、その個別性をまったく無化せしめる。この無化がまさに個体の死である。 子供を教育することによって、親は彼ら自身の人間的、歴史的な死を準備し、みずからの意志によって現在から過去へと移っていく」(コージェブ 1987:400)。
言うまでもなく、ヘーゲルのいう北アメリカの「未開 人」における親の殺害とは、かつてモンテーニュ(2007)が唱えた「高貴なる野蛮人」の食人と同様に、実際の親殺しのことを指している。そして、一九世 紀のヨーロッパ人における「同じこと」とは、子供への訓育を通して親の意識が世代継承を通して伝わり、それを最終的に子孫に受け渡すことにより(個別性が 無化されて)親は象徴的に「殺される」。コージェブは、ヘーゲルの1803-1804年の講義記録を引用しつつ次のようにいう——ヨーロッパ人は「子供を 教育することにより、親は子供のうちに形成された彼らの意識を植え付け、自己の死を生み出す」と(コージェブ1987:400)。私たちは過剰解釈に陥る ことを避けつつ、こう断言しよう。一九世紀の未開人とヨーロッパ人は共に「親の死」を媒介として、その社会の政治性が、その世代で終わることなく次世代へ と継承されていくことが確実になる。「子供を教育することにより、親は子供のうちにすでに形成された彼らの意識を植え付け、自己の死を生み出す」2)。親 の意識は死を媒介にして弁証法的にアウフヘーベン(aufheben; 止揚あるいは揚棄)されるのである(コージェブ 1987:400)。
2) “Indem sie es erziehen setzen sie ihr gewordenes Bewußtseyn in ihm, und sie erzeugen ihren Tod indem sie es zum Bewußtseyn beleben” ヘーゲル全集アカデミー版(Gesammelte Werke)Bd.6, S.305, Z.12-13.
近代啓蒙思想は、現在の文化人類学者が自明の理とし ている人類の普遍性・共通性の概念を、近代人類学の成立期(20世紀の最初の四半世紀)よりもはるか以前に確立したと言われている。この人類の普遍性・共 通性の根拠を、ヘーゲルによる欄外の書き込みは、親の死による人間集団の自己意識の歴史的継承という特質のなかに求めた。集団の自己意識の継承——民俗学 でいう歴史的「伝承」とはこのヘーゲル主義に由来する——が北アメリカの未開人とヨーロッパ人がともに持つ共通点であり、親の死を殺害によるのか、子供に よる訓育の後に高齢により死に絶えるのかは、ただ文化という社会の様相(モード)による表現=表象の違いに過ぎない、と。
しかしながら、実際に、一九世紀中葉以降、伝聞によ る不明瞭な記述が大幅に縮減された探検記や民族誌が陸続と公刊され、未開社会の風習が西洋世界に紹介されるにいたると、そこには夥しい事例の子殺しや(殺 害行為を含む)老人遺棄などが含まれることがわかった。乱婚制や母系制など西洋世界が歴史的にすでに「放棄した」と思われる遺習が、未開社会で未だ「残 存」していたことは、それらの社会への「平定」という軍事的制圧、すなわち彼らの社会の植民地化を正当化する根拠になった。「彼らは残忍なこと(=殺し) を平気でおこない、私たちはそれをおこなわない」という見解をヘーゲルは端的に批判をしている。彼が人間の普遍性・共通性に共鳴して「私たちも同じことを している」という重要な気づきが忘却され、それは今や「子どもや老人」を殺害したり遺棄したりするのは残忍で異質な他者に他ならないという識別記号へと変 わってしまったのである。このことは動物殺しをめぐる、他者(=動物)と自己(=人間)のあいだの非対称的峻別という類似の文化的操作ということに深く関 わる。
屠畜や殺人が、私たちにとって恐怖の対象になるの は、単純に生と死の暴力的な分離の出来事であるからではないのだ。むしろ、そのことを「悟性」がもつ分離という働きをとおして私たちが意識を通した時に、 死んだ者以外は誰も経験することのない「死」の情動——死の想像力——を私たち自身にもたらすからである。だが、私たちの死への感情には驚くべき多様性が ある。エルツ(2001:120)は、それは「同じ社会にあっても、死のもたらす感情は、死者の社会的性格により強度が」異なってくるからであり「こうし た感情をまったく欠いてくることさえもある」と述べている。屠畜や殺人をめぐる私たちの理解のパラドクスは、自己の死を嫌いかつ不死を望む人間が、なぜ他 者が死を迎えることにかんしては〈時間を前倒しにして〉も率先しておこなうのかということにある——「自己の死の否定/他者の死の容認」のテーゼと名づけ てもよいだろう。民族誌学的意味における理論的抽象度や説明の洗練度においていかに二世紀後の私たちが彼の言及の少なさについて身勝手な不満3)を持とう とも、ヘーゲルが指摘した「分離(わけるということ)」の意味について幾度も私たちは回帰していかざるを得ない。クラストルは言う:「もし獣を殺すことを 続けたいのなら、それを食べてはならない。土着の理論は、消費のレベルでの狩人とほふられた獣の結合は、「生産」のレベルでの狩人と生きた獣の分離をまね く、という観念のみに支えられている」(Clastres 1974:99=1987:139)。殺害(=分離)と「生産」の隠喩ともいえる性交と摂食(=結合)のコントロールとは、私たち〈ポリス的=国家的動物 〉が日々おこなっている活動にほかならないからである。
3)
ヘーゲル的解釈では、意識が親から子に伝わり終えた時、親は殺される運命にあるが、この論理では子殺しは上手に説明することができない。他方、アチェの伝
統的な論理(と生態人類学が共有している論理)では、老人殺害はノマド生活にとって機能的に足手まとい以外の何者でもないが(Hill and
Hurtado
1996)、子殺しも含めて殺害は、狩猟動物にも変身することができるイアンヴェ(死霊)が復讐という名の冥界への連れ戻しおこなうことが必ず背景にある
(Clastres
1972)。すなわち、アチェの論理では、殺害者と犠牲者のあいだでの意識の継承などはまったくナンセンスなことになる。しかし、ヘーゲルにもアチェにも
共通する基盤的理解がある。それは共同体にとってどのような殺害や死にもきちんと意味と正当性がある——無意味な殺害や死(カミユ「異邦人」
[1942])などない——ということなのである。
リンク
文献