解説:池田光穂
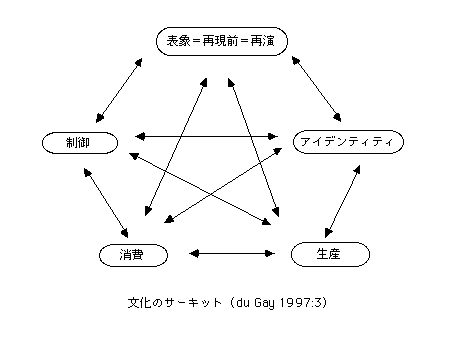
Du Gay , Paul, Stuart Hall, Linda James, Hugh
Mackay and
Keith Smith. 1997. Doing Cultural Studies: The story of the Sony
Walkman.
London: Sage.
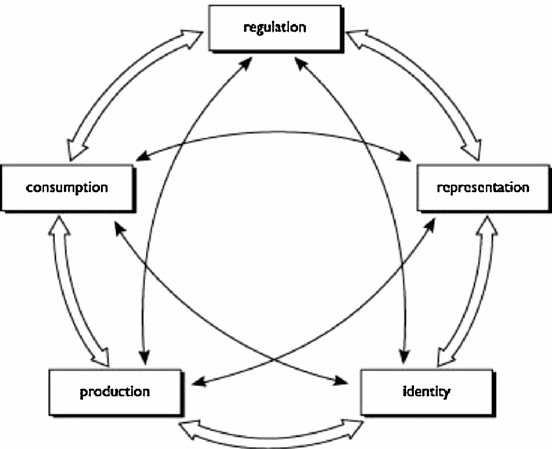
Source: https://goo.gl/3mlDAR
文化のサーキット
The Circuit of Culture
解説:池田光穂
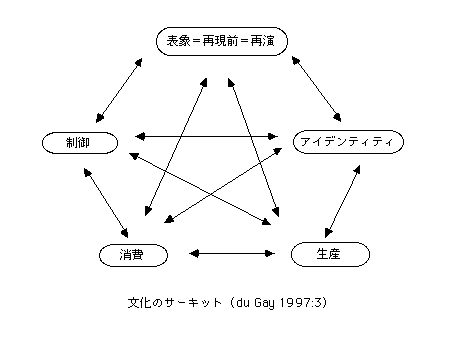
Du Gay , Paul, Stuart Hall, Linda James, Hugh
Mackay and
Keith Smith. 1997. Doing Cultural Studies: The story of the Sony
Walkman.
London: Sage.
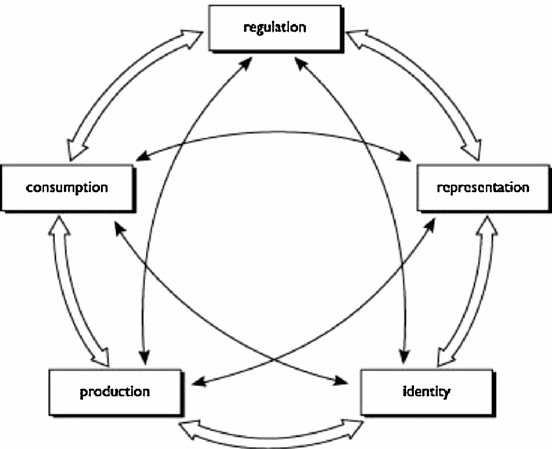
以下はシラバス(学務情報システム)からの再掲です。
授業の目標
「世界文化」(global culture)と呼べる地球規模の社会現象があります。この現象がいつから
起こったのか、またどれほどの規模で、どのように進行しつつあるのかについては、研究者の
間で多様な見解に分かれています。
この授業の目的としては、前年度の「世界文化論概説」の既習の前提にたって、植民地およ
び帝国という観点から、世界文化に関わる文化的社会的現象を歴史学・文学・文化人類学の観
点から自ら資料を集め分析する能力を身につけることにあります。
演習においてはそれぞれの教官は課題となる文献テクストを提示しますが、受講学生は関連
文献の渉猟に心がけて、学期末までに、世界文化に関する自らの研究テーマを発見し、そのた
めの研究の準備ができるようになることを目標に受講してください。
授業の内容
この授業は、1998年度に開講された際の世界文化論概説では、世界文化を理解するための分
析視座に則り、世界文化を、<空間>と<時間>、および<言語>と言語を含む総体としての
<文化>のそれぞれ組み合わせからなる4つの分析視角から考察されました。つまり(1)言
語の使用をめぐって空間が区切られ秩序づけられる現象、(2)文化が空間のなかで収斂した
り拡散する現象、(3)時間のなかで文化の維持されたり伝播したり、また断絶する現象、そ
して(4)文学という言語を中心とした現象が長期的な時間のなかで変容をとげてゆく現象、
に焦点が当てられるオムニバス形式の授業が実施されました。
1999年度は、このような基礎知識の上に立って、文化の収斂と拡散、文化の中心と周縁、文
化の優越と没落が、権力構造と深く結びついた諸相に焦点を当てることにします。このような
現象の具体例として、植民地と帝国という政治的状況下における文化の様態について検討しま
す。20世紀も終わろうとしている現在、植民地や帝国は、過去のものという認識をもつ受講生
も多いかも知れませんが、西欧社会、後に第三世界と呼ばれるかつての植民地世界、さらに西
欧に続いて国民国家の形態をとって独立を果たした諸社会を含めた、いわゆる近代社会の成り
立ちにとって、植民地や帝国は、現在に至るまで大いなる影を落としており、世界文化を考え
る上でも、このような歴史的所産についての検討は不可欠です。また、現代社会を植民地以降
つまりポストコロニアルの時代だと位置づける論者がいる一方で、他方では、現在においても
植民地主義や帝国主義と呼ばれる政治的経済的構図からそれほど現代は脱却していないという
指摘する(例えば、それを新植民地主義、ネオ・コロニアリズムと位置づける)研究者がいま
す。
このように世界文化の現代を、どのようなものとして位置づけるにせよ、我々にとって重要
なことは、授業でとりあげる文化現象に細心の注意をはらって、それを多角的に分析し、自ら
の仮説を妥当性をもって論証することにあります。授業は、以上のようなことを注意しながら
テクストとなる文献を読解してゆきます。
キーワード
世界文化、植民地、帝国、植民地主義、帝国主義、オリエンタリズム、ポストコロニアル批
評、国民国家、ナショナリズム
テキスト
E・サイード『文化と帝国主義1・2』大橋洋一訳、みすず書房、1999年(池田)、平野千果
子「第二次世界大戦とフランス植民地」『思想』No.895、pp.96-118、1999年1月、他(山田)
参考文献
E・サイード『オリエンタリズム 上・下』今沢紀子訳、平凡社、1993年;小熊英二『<日本
人>の境界』新曜社、1998年
関連リンク