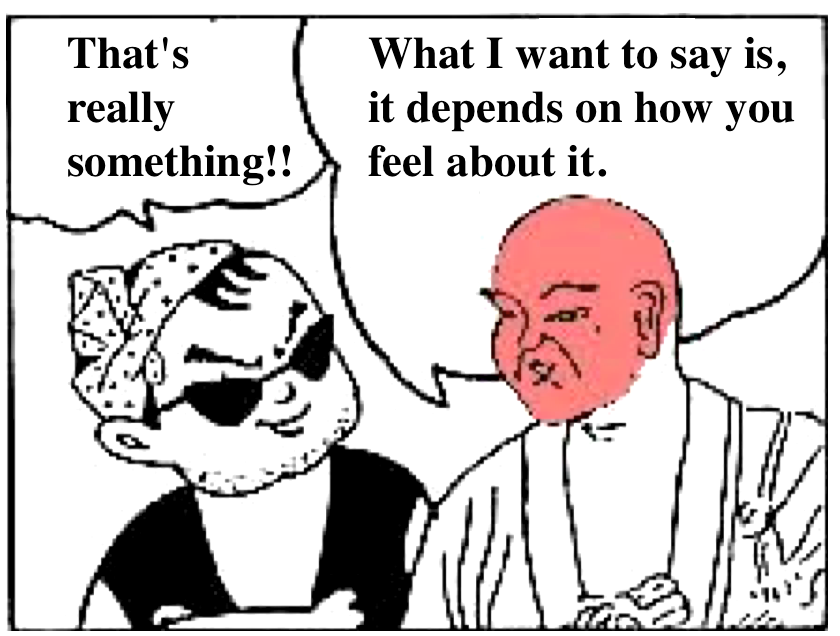

アフェクト
Affect, 情動/感情/感動
☆ アフェクト=情動/感情/感動(ラテン語のaffectusまたはadfectusに由来)とは、バルーフ・スピノザの哲学で用いられ、アンリ・ベルクソン、ジル・ドゥルー ズ、フェリックス・ガタリによって展開された概念である。これは身体的あるいは具現化された経験に重点を置く。心理学や他の分野では、アフェクトという言 葉は異なる意味を持つ。 スピノザにとって、その『倫理学(エチカ)』第二部および第三部で論じられているように、アフェクトとは心身の状態であり、感情や情動と関連しているが(ただし完全 に同義ではない)。彼はアフェクトには主に三種類あると述べている:快楽または喜び(ラエティティア)、苦痛または悲しみ(トリスティティア)、そして欲 望(クピディタス)または食欲である。[2] ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ、そして彼らの翻訳者ブライアン・マッスミによる後の哲学的用法は、明らかにスピノザに由来するものの、アフェク トと従来感情と呼ばれるものとの区別をスピノザよりも鋭くする傾向がある。アフェクトは把握や概念化が難しい。スピノザが言うように「精神の情動 (animi pathema)とは混同された観念」であり、身体の生命力の増減によってのみ知覚されるからだ[3]。「アフェクト」という用語は、人文社会科学におけ る「アフェクティブ・ターン」の核心をなす概念である。
| Affect (from Latin
affectus or adfectus) is a concept, used in the philosophy of Baruch
Spinoza and elaborated by Henri Bergson, Gilles Deleuze and Félix
Guattari, that places emphasis on bodily or embodied experience. The
word affect takes on a different meaning in psychology and other fields. For Spinoza, as discussed in Parts Two and Three of his Ethics, affects are states of mind and body that are related to (but not exactly synonymous with) feelings and emotions, of which he says there are three primary kinds: pleasure or joy (laetitia),[1] pain or sorrow (tristitia)[1] and desire (cupiditas) or appetite.[2] Subsequent philosophical usage by Gilles Deleuze, Félix Guattari and their translator Brian Massumi, while derived explicitly from Spinoza, tends to distinguish more sharply than Spinoza does between affect and what are conventionally called emotions. Affects are difficult to grasp and conceptualize because, as Spinoza says, "an affect or passion of the mind [animi pathema] is a confused idea" which is only perceived by the increase or decrease it causes in the body's vital force.[3] The term "affect" is central to what has become known as the "affective turn" in the humanities and social sciences. |
アフェクト(ラテン語のaffectusまたはadfectusに由
来)とは、バルーフ・スピノザの哲学で用いられ、アンリ・ベルクソン、ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリによって展開された概念である。これは身体
的あるいは具現化された経験に重点を置く。心理学や他の分野では、アフェクトという言葉は異なる意味を持つ。 スピノザにとって、その『倫理学(エチカ)』第二部および第三部で論じられているように、アフェクトとは心身の状態であり、感情や情動と関連しているが(ただし完全 に同義ではない)。彼はアフェクトには主に三種類あると述べている:快楽または喜び(ラエティティア)、苦痛または悲しみ(トリスティティア)、そして欲 望(クピディタス)または食欲である。[2] ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ、そして彼らの翻訳者ブライアン・マッスミによる後の哲学的用法は、明らかにスピノザに由来するものの、アフェク トと従来感情と呼ばれるものとの区別をスピノザよりも鋭くする傾向がある。アフェクトは把握や概念化が難しい。スピノザが言うように「精神の情動 (animi pathema)とは混同された観念」であり、身体の生命力の増減によってのみ知覚されるからだ[3]。「アフェクト」という用語は、人文社会科学におけ る「アフェクティブ・ターン」の核心をなす概念である。 |
| In Spinoza In Baruch Spinoza's Ethics, Part III Definition 3, the term "affect" (affectus, traditionally translated as "emotion")[4] is the modification or variation produced in a body (including the mind) by an interaction with another body which increases or diminishes the body's power of activity (potentia agendi): By affect I understand affections of the body by which the body's power of acting is increased or diminished, aided or restrained, and at the same time, the ideas of these affections.[5] Affect is thus a special case of the more neutral term "affection" (affectio), which designates the form "taken on" by some thing,[6] the mode, state or quality of a body's relation to the world or nature (or infinite "substance"). In Part III, "Definitions of the Emotions/Affects", Spinoza defines 48 different forms of affect, including love and hatred, hope and fear, envy and compassion. They are nearly all manifestations of the three basic affects of: - desire (cupiditas) or appetite (appetitus), defined as "the very essence of man insofar as his essence is conceived as determined to any action from any given affection of itself";[7] - pleasure (laetitia), defined as "man's transition from a state of less perfection to a state of greater perfection";[7] and - pain or sorrow (tristitia), defined as "man's transition from a state of greater perfection to a state of less perfection".[7] In Spinoza's view, since God's power of activity is infinite, any affection which increases the organism's power of activity leads to greater perfection. Affects are transitional states or modes in that they are vital forces by which the organism strives to act against other forces which act on it and continually resist it or hold it in check.[8] |
スピノザにおいて バルーク・スピノザの『倫理学』第三部定義3において、「アフェクト」(affectus、従来「感情」と訳されてきた)[4]とは、ある身体(精神を含 む)が別の身体と相互作用した際に生じる変化や変動を指す。この相互作用は、身体の活動力(potentia agendi)を増大させたり減衰させたりするものである: 情動とは、身体の作用力を増大または減少させ、促進または抑制する身体への影響、および同時にそれらの影響の観念を指す。[5] したがってアフェクトは、より中立的な用語「アフェクティオ(affectio)」の特殊な場合である。アフェクティオとは、何らかのものが「取り込む」 形態[6]、すなわち身体が世界や自然(あるいは無限の「実体」)と関わる様態・状態・性質を指す。第三部「情動/アフェクトの定義」において、スピノザ は愛と憎しみ、希望と恐怖、羨望と憐憫を含む48種類の異なるアフェクトを定義する。これらはほぼ全て、以下の三つの基本アフェクトの現れである: - 欲望(cupiditas)または食欲(appetitus)。これは「人間の本質そのもの、すなわちその本質が、自己の与えられた情動からいかなる行動 にも決定づけられるものとして捉えられる限りにおいて」と定義される。[7] - 喜び(ラエティティア)。「人間の状態がより低い完全性からより高い完全性へ移行すること」と定義される;[7] - 苦痛または悲しみ(トリスティティア)。「人間の状態がより高い完全性からより低い完全性へ移行すること」と定義される。[7] スピノザの見解では、神の活動力は無限であるため、有機体の活動力を増大させるあらゆる情動はより大きな完全性へと導く。情動は過渡的な状態あるいは様態 であり、それは有機体が作用する他の力、すなわち絶えず抵抗したり抑制したりする力に対して、有機体が作用しようと努める生命力である。[8] |
| In Bergson Henri Bergson contends in Matter and Memory (1896) that we do not know our body only "from without" by perceptions, but also "from within" by affections (French: affections).[9] |
ベルクソンにおいて アンリ・ベルクソンは『物質と記憶』(1896年)において、我々は身体を単に知覚によって「外部から」知るだけでなく、情動(フランス語: affections)によって「内部から」も知るのだと主張している。[9] |
| In Deleuze and Guattari The terms "affect" and "affection" came to prominence in Gilles Deleuze and Félix Guattari's A Thousand Plateaus, the second volume of Capitalism and Schizophrenia. In his notes on the terminology employed, the translator Brian Massumi gives the following definitions of the terms as used in the volume: AFFECT/AFFECTION. Neither word denotes a personal feeling (sentiment in Deleuze and Guattari). L'affect (Spinoza's affectus) is an ability to affect and be affected. It is a prepersonal intensity corresponding to the passage from one experiential state of the body to another and implying an augmentation or diminution in that body's capacity to act. L'affection (Spinoza's affectio) is each such state considered as an encounter between the affected body and a second, affecting, body (with body taken in its broadest possible sense to include "mental" or ideal bodies).[10] Deleuze takes up the term affect from Spinoza and transforms it to meet the central ethical and political problem he poses. Fundamentally, Deleuze uses the term "affect" in two ways: affect as becoming and affect as capacities.[11] Becoming as capacities corresponds to Spinoza's notion of affection, which designates a being's capacities to affect other beings and be affected by them. In A Thousand Plateaus, Deleuze and Guattari, famously argue that a tick has three affects: (1) a capacity to be affected by light, which drives the tick to climb onto a branch, (2) a capacity to be affected by the smell of mammals, which prompts the tick to drop onto a passing host, (3) and lastly a capacity to dig into the animal's skin.[12] The use of affects as becomings[13] delineates affects as drivers of "events or undergoings that have disruptive and creative effects both on an individual’s internal composition and its external relationships with other things."[14] One of the main results of viewing affects as becomings is that they are no longer seen as merely personal feelings, as "they go beyond the strength of those who undergo them"[13] In this respect, affects, according to Deleuze, are not simple affections, as they are independent from their subject. Artists create affects and percepts, "blocks of space-time", whereas science works with functions, according to Deleuze, and philosophy creates concepts. |
ドゥルーズとガタリにおいて 「アフェクト」と「アフェクション」という用語は、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの『資本主義と統合失調症』第二巻『千の平原』で注目されるよ うになった。翻訳者ブライアン・マッスミは用語解説の中で、本書におけるこれらの用語を次のように定義している: アフェクト/アフェクション。いずれの語も個人的感情(ドゥルーズ=ガタリにおける「感情」)を指さない。ラ・アフェクト(スピノザのaffectus) とは、影響を与え、また影響を受ける能力である。これは身体の経験状態から別の状態への移行に対応する前個人的強度であり、その身体の行動能力の増大また は減衰を意味する。アフェクション(スピノザのaffectio)とは、影響を受けた身体と、影響を与える第二の身体(身体を可能な限り広義に解釈し、 「精神的」あるいは観念的な身体も含む)との遭遇として捉えられた、そうした各状態を指す。[10] ドゥルーズはスピノザからアフェクトという概念を取り上げ、自身が提起する核心的な倫理的・政治的問題に対応させるべく変容させる。基本的にドゥルーズは 「アフェクト」という用語を二つの意味で用いる:生成としてのアフェクトと能力としてのアフェクトである。[11] 能力としての生成は、スピノザの「アフェクション」概念に対応する。これはある存在が他の存在に影響を与え、またそれらから影響を受ける能力を指す。『千 の平原』において、ドゥルーズとガタリは有名な議論を展開している。ダニには三つのアフェクトがあると:(1) 光によって影響を受ける能力。これがダニを枝に登らせる。(2) 哺乳類の匂いによって影響を受ける能力。これがダニを通りかかる宿主へ落下させる。(3) 最後に、動物の皮膚へ食い込む能力。[12] 情動を「生成」[13]として扱うことは、情動を「個人の内的構成と外的関係性の双方に破壊的かつ創造的な影響を及ぼす出来事や経験」[14]の駆動要因 として位置づける。情動を「生成」と捉える主な成果の一つは、情動が単なる人格感情ではなく「それを経験する者の力を超えるもの」[13]として認識され る点にある。この点において、ドゥルーズによれば、情動は単純な感情ではない。なぜなら情動は主体から独立しているからだ。芸術家は情動と知覚、すなわち 「時空間の塊」を創造する。一方、科学は機能と働き、哲学は概念を創造する。 |
| Affective turn Since 1995,[15][16] a number of authors in the social sciences and humanities have begun to explore affect theory as a way of understanding spheres of experience (including bodily experience) which fall outside of the dominant paradigm of representation (based on rhetoric and semiotics); this movement has been called the affective turn.[17] Consequently, these approaches are interested in the widest possible variety of interactions and encounters, interactions and encounters that are not necessarily limited to human sensibility.[18] The translator of Deleuze and Guattari's A Thousand Plateaus, Canadian political philosopher Brian Massumi, has given influential definitions of affect (see above) and has written on the neglected importance of movement and sensation in cultural formations and our interaction with real and virtual worlds.[19] Likewise, geographer Nigel Thrift has explored the role of affect in what he terms "non-representational theory".[20] In 2010, The Affect Theory Reader was published by Melissa Gregg and Gregory J. Seigworth and has provided the first compendium of affect theory writings.[21] Researchers such as Mog Stapleton, Daniel D. Hutto and Peter Carruthers[22][23][24] have pointed to the need to investigate and to develop the notions of affect and emotion. They hold that these are important in the developing paradigm of embodiment in cognitive science, in consciousness studies and the philosophy of mind. This step will be necessary for cognitive science, Mog Stapleton maintains, to be "properly embodied" cognitive science. |
情動的(アフェクト的)転回 1995年以降[15][16]、社会科学と人文科学の多くの研究者が、表象の支配的パラダイム(修辞学と記号論に基づく)の外側に位置する経験領域(身 体的経験を含む)を理解する手段として情動理論を探求し始めた。この動きは情動的転回と呼ばれている。[17] したがって、これらのアプローチは可能な限り多様な相互作用や遭遇に関心を持ち、それらは必ずしも人間の感性に限定されない。[18] デリューズとガタリの『千の平原』の翻訳者であるカナダの政治哲学者ブライアン・マッスミは、情動に関する影響力のある定義(前述参照)を示し、文化的形 成や現実世界・仮想世界との相互作用における運動と感覚の軽視された重要性について論じている。[19] 同様に、地理学者ナイジェル・スリフトは、彼が「非表象理論」と呼ぶものにおけるアフェクトの役割を探求している。[20] 2010年にはメリッサ・グレッグとグレゴリー・J・セイワースによる『アフェクト理論読本』が出版され、アフェクト理論の著作を初めて網羅した。 [21] モグ・ステイプルトン、ダニエル・D・ハット、ピーター・キャルーサーズといった研究者たち[22] [23][24]は、情動と感情の概念を調査・発展させる必要性を指摘している。彼らは、これらが認知科学における身体性の発展するパラダイム、意識研 究、心哲学において重要だと主張する。モグ・ステイプルトンは、認知科学が「真に身体化された」認知科学となるためには、このステップが不可欠だと述べて いる。 |
| Affect theory Affectionism Conatus Immanent evaluation Passions |
情動理論 情動主義 コナトゥス 内在的評価 情動 |
| 1. Part III, Proposition 56.
Spinoza, Benedictus de (2001) [1677]. Ethics. Trans. by W.H. White and
A.H. Stirling. London: Wordsworth Editions. p. 141. ISBN
978-1-84022-119-0. Retrieved 27 November 2011. 2. "In truth I cannot recognize any difference between human appetite and desire". Spinoza, Benedictus de (2001) [1677]. Ethics [heading= Affect. Trans. by W.H. White and A.H. Stirling. London: Wordsworth Editions. p. 146. ISBN 978-1-84022-119-0. Retrieved 27 November 2011. 3. Existendi vis or power of existence. Spinoza, Benedictus de (2001) [1677]. Ethics. Trans. by W.H. White and A.H. Stirling. London: Wordsworth Editions. p. 158. ISBN 978-1-84022-119-0. Retrieved 27 November 2011. 4. Of the two "standard" English translations, the version by Samuel Shirley uses "emotion" for affectus, whereas the more recent rendering by Edwin Curley uses "affect". Spinoza, Benedictus de (2002) [1677]. Complete Works. Trans. by Samuel Shirley. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing. p. 278. ISBN 978-0-87220-620-5. Retrieved 27 November 2011. Spinoza, Benedictus de (1994). A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works. Trans. by Edwin M. Curley. Princeton and Chichester: Princeton University Press. p. 154. ISBN 978-0-691-00067-1. Retrieved 27 November 2011. 5. Spinoza, Benedictus de (1994). A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works. Trans. by Edwin M. Curley. Princeton and Chichester: Princeton University Press. p. 154. ISBN 978-0-691-00067-1. Retrieved 27 November 2011. 6. Samuel Shirley, "Translator's Preface". Spinoza, Benedictus de (1992). The Ethics; Treatise on the Emendation of the Intellect; Selected Letters. Trans. by Samuel Shirley. Hackett Publishing. p. 24. ISBN 978-0-87220-130-9. Retrieved 27 November 2011. 7. Spinoza, Benedictus de (1994). A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works. Trans. by Edwin M. Curley. Princeton and Chichester: Princeton University Press. p. 311. ISBN 978-0-691-00067-1. Retrieved 27 November 2011. 8. Kisner, Matthew J. (2011). Spinoza on Human Freedom: Reason, Autonomy and the Good Life. Cambridge: Cambridge University Press. p. 20. ISBN 978-0-521-19888-2. Retrieved 28 November 2011. 9. Henri Bergson, Matter and Memory (1896), ch. 1. 10. Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (1987) [1980]. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Vol. 2. Trans. and foreword by Brian Massumi. Minneapolis and London: University of Minnesota Press. p. xvi. ISBN 978-0-8166-1401-1. OCLC 16472336. 11. Aktas, Ahmet (2025-05-01). "Was Spinoza a Deleuzian? Rethinking the Politics of Emotions and Affects". Theory, Culture & Society. 42 (3): 99–101. doi:10.1177/02632764241301334. ISSN 0263-2764. 12. Deleuze, Gilles; Guattari, Félix; Deleuze, Gilles (2007). A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia (12. print ed.). Minneapolis, Minn.: Univ. of Minnesota Press. p. 257. ISBN 978-0-8166-1401-1. 13. Deleuze, Gilles; Guattari, Félix; Tomlinson, Janis; Burchell III, Graham (2014). What Is Philosophy?. European Perspectives: A Series in Social Thought and Cultural Criticism. New York: Columbia University Press. p. 164. ISBN 978-0-231-07989-1. 14. Aktas, Ahmet (2025-05-01). "Was Spinoza a Deleuzian? Rethinking the Politics of Emotions and Affects". Theory, Culture & Society. 42 (3): 95–114. doi:10.1177/02632764241301334. ISSN 0263-2764. 15. Massumi, Brian (1995). "The Autonomy of Affect". Cultural Critique. Autumn (31): 83–109. doi:10.2307/1354446. JSTOR 1354446. 16. Sedgwick, Eve Kosofsky; Frank, Adam (1995). "Shame in the Cybernetic Fold: Reading Silvan Tomkins". Critical Inquiry. 21 (2): 496–522. doi:10.1086/448761. S2CID 143473392. 17. Patricia Ticineto Clough, Jean Halley (eds.), The Affective Turn: Theorizing the Social, Duke University Press, 2007, p. 1; Paul Hoggett, Simon Thompson (eds.), Politics and the Emotions: The Affective Turn in Contemporary Political Studies, Bloomsbury, 2012, p. 1. 18. Seyfert, Robert (2012). "Beyond Personal Feelings and Collective Emotions: A Theory of Social Affect". Theory, Culture & Society. 29/6: 35. doi:10.1177/0263276412438591. S2CID 143590063. 19. Massumi, Brian (2002). Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham and London: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-2897-1. Retrieved 27 November 2011. 20. Thrift, Nigel J. (2007). Non-representational Theory: Space, Politics, Affect. London: Routledge. ISBN 978-0-415-39320-1. Retrieved 27 November 2011. 21. Gregg, M.; Seigworth, G. (2010). The Affect Theory Reader. North Carolina: Duke University Press. ISBN 978-0822347767. Retrieved 30 April 2013. 22. Stapleton, M (2012). "Steps to a "Properly Embodied". Cognitive Science, Cognitive Systems Research. 22–23: 1–11. doi:10.1016/j.cogsys.2012.05.001. S2CID 1694792. 23. Hutto, D. Intersubjective Engagements without Theory of Mind: A Cross-Species Comparison[1] 24. Carruthers, P. (2000). Phenomenal Consciousness: A Naturalistic Theory. Cambridge: Cambridge University Press. |
1.
第3部、命題56。スピノザ、ベネディクトゥス・デ(2001年)[1677年]。『倫理学』。W.H.ホワイト及びA.H.スターリング訳。ロンドン:
ワーズワース・エディションズ。141頁。ISBN 978-1-84022-119-0。2011年11月27日取得。 2. 「実のところ、人間の食欲と欲望の間に異なる点を見いだせない」。「実のところ、人間の食欲と欲望の間に異なる点を見いだせない」。「実のところ、人間の 食欲と欲望の間に異なる点を見いだせない」。「実のところ、人間の食欲と欲望の間に異なる点を見いだせない」。「実のところ、人間の食欲と欲望の間に異な る点を見いだせない」。「実のところ、人間の食欲と欲望の間に異なる点を見いだせない」。「実のところ、人間の食欲と欲望の ISBN 978-1-84022-119-0. 2011年11月27日閲覧。 3. 存在の力(Existendi vis)。スピノザ、ベネディクトゥス・デ(2001年)[1677年]。『倫理学』。W.H.ホワイト及びA.H.スターリング訳。ロンドン:ワーズ ワース・エディションズ。p. 158. ISBN 978-1-84022-119-0。2011年11月27日閲覧。 4. 二つの「標準的」英訳のうち、サミュエル・シャーリーの訳は affectus を「emotion(感情)」と訳しているが、より新しいエドウィン・カーリーの訳は「affect(情動)」と訳している。スピノザ、ベネディクトゥ ス・デ(2002年)[1677年]。全集。サミュエル・シャーリー訳。インディアナポリスおよびケンブリッジ:ハケット出版。278頁。ISBN 978-0-87220-620-5。2011年11月27日閲覧。スピノザ、ベネディクトゥス・デ(1994)。『スピノザ読本:倫理学その他の著 作』。エドウィン・M・カーリー訳。プリンストンおよびチチェスター:プリンストン大学出版局。p. 154. ISBN 978-0-691-00067-1. 2011年11月27日閲覧。 5. スピノザ, ベネディクトゥス・デ (1994). 『スピノザ読本: 倫理学とその他の著作』. エドウィン・M・カーリー訳. プリンストン・チチェスター: プリンストン大学出版局. p. 154. ISBN 978-0-691-00067-1。2011年11月27日閲覧。 6. サミュエル・シャーリー「訳者序文」。スピノザ、ベネディクトゥス・デ(1992)。『倫理学;知性の修正に関する論文;選集書簡』。サミュエル・シャー リー訳。ハケット出版。p. 24。ISBN 978-0-87220-130-9。2011年11月27日閲覧。 7. スピノザ、ベネディクトゥス・デ(1994)。『スピノザ読本:倫理学その他の著作』。エドウィン・M・カーリー訳。プリンストンおよびチチェスター:プ リンストン大学出版局。p. 311。ISBN 978-0-691-00067-1。2011年11月27日閲覧。 8. マシュー・J・キスナー(2011)。『人間の自由に関するスピノザ:理性、自律、そして善き生活』。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。p. 20。ISBN 978-0-521-19888-2。2011年11月28日閲覧。 9. アンリ・ベルクソン『物質と記憶』(1896年)、第1章。 10. ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ(1987年)[1980年]。千の平原:資本主義と統合失調症. 第2巻. ブライアン・マッスミ訳・序文. ミネアポリス・ロンドン:ミネソタ大学出版局. p. xvi. ISBN 978-0-8166-1401-1. OCLC 16472336. 11. アクタス、アフメット (2025-05-01). 「スピノザはドゥルーズ主義者だったのか? 感情とアフェクトの政治学を再考する」『理論・文化・社会』42巻3号: 99–101頁. doi:10.1177/02632764241301334. ISSN 0263-2764. 12. ドゥルーズ、ジル; ガタリ、フェリックス; ドゥルーズ、ジル (2007). 『千のプラトー:資本主義と統合失調症』 (12. 印刷版). ミネアポリス、ミネソタ州: ミネソタ大学出版局. p. 257. ISBN 978-0-8166-1401-1. 13. ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ、ジャニス・トムリンソン、グラハム・バーチェル III (2014). 『哲学とは何か?』. ヨーロッパの視点:社会思想と文化批評のシリーズ. ニューヨーク:コロンビア大学出版局. p. 164. ISBN 978-0-231-07989-1. 14. アクタス、アフメット (2025-05-01). 「スピノザはドゥルーズ主義者だったか?感情と感情の政治を再考する」. 理論、文化、社会. 42 (3): 95–114. doi:10.1177/02632764241301334. ISSN 0263-2764. 15. マッスミ, ブライアン (1995). 「情動の自律性」. 『文化批評』. 秋号 (31): 83–109. doi:10.2307/1354446. JSTOR 1354446. 16. セジウィック、イヴ・コソフスキー; フランク、アダム (1995). 「サイバネティックな折り目の中の恥:シルヴァン・トンプキンスを読む」. 『クリティカル・インクワイアリー』. 21 (2): 496–522. doi:10.1086/448761. S2CID 143473392. 17. パトリシア・ティシネート・クラフ、ジャン・ハーレー(編)、『感情の転換:社会を理論化する』、デューク大学出版局、2007年、p. 1;ポール・ホゲット、サイモン・トンプソン(編)、『政治と感情:現代政治学における感情の転換』、ブルームズベリー、2012年、p. 1。 18. サイファート、ロバート (2012). 「人格感情と集団的感情を超えて:社会感情の理論」. 『理論、文化、社会』. 29/6: 35. doi:10.1177/0263276412438591. S2CID 143590063. 19. マスミ、ブライアン (2002). 仮想のための寓話:運動、情動、感覚。ダーラム及びロンドン:デューク大学出版局。ISBN 978-0-8223-2897-1。2011年11月27日取得。 20. スリフト、ナイジェル・J. (2007). 非表象理論:空間、政治、情動。ロンドン:ラウトリッジ。ISBN 978-0-415-39320-1。2011年11月27日取得。 21. グレッグ, M.; サイグワース, G. (2010). 『情動理論読本』. ノースカロライナ: デューク大学出版局. ISBN 978-0822347767. 2013年4月30日取得。 22. ステイプルトン, M (2012). 「『適切に身体化された』状態への段階」. 認知科学, 認知システム研究. 22–23: 1–11. doi:10.1016/j.cogsys.2012.05.001. S2CID 1694792. 23. Hutto, D. 心の理論を伴わない相互主観的関与:種間比較[1] 24. Carruthers, P. (2000). 現象的意識:自然主義的理論. ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. |
| Sources Deleuze, Gilles. 1983. Cinema 1: The Movement Image. Trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. London and New York: Continuum, 2005. ISBN 0-8264-7705-4. Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (1987) [1980]. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Vol. 2. Trans. and foreword by Brian Massumi. Minneapolis and London: University of Minnesota Press. p. xvi. ISBN 978-0-8166-1401-1. OCLC 16472336. Massumi, Brian (2002). Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham and London: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-2897-1. Retrieved 27 November 2011. Seyfert, Robert (2012). "Beyond Personal Feelings and Collective Emotions: A Theory of Social Affect". Theory, Culture & Society. 29 (6): 27–46. doi:10.1177/0263276412438591. S2CID 143590063. Spinoza, Benedictus de (2002) [1677]. Complete Works. Trans. by Samuel Shirley. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing. p. 278. ISBN 978-0-87220-620-5. Retrieved 27 November 2011. Skoggard, I. and Waterston, A. (2015), "Introduction: Toward an Anthropology of Affect and Evocative Ethnography." Anthropol Conscious, 26: 109–120. doi:10.1111/anoc.12041 Spinoza, Benedictus de (1994). A Spinoza Reader: The Ethics and Other Works. Trans. by Edwin M. Curley. Princeton and Chichester: Princeton University Press. p. 154. ISBN 978-0-691-00067-1. Retrieved 27 November 2011. Thrift, Nigel J. (2007). Non-representational Theory: Space, Politics, Affect. London: Routledge. ISBN 978-0-415-39320-1. Retrieved 27 November 2011. |
出典 ドゥルーズ、ジル。1983年。『シネマ 1:運動するイメージ』。ヒュー・トムリンソン、バーバラ・ハバージャム訳。ロンドンおよびニューヨーク:Continuum、2005年。ISBN 0-8264-7705-4。 ドゥルーズ、ジル;ガタリ、フェリックス (1987) [1980]。『 千のプラトー:資本主義と統合失調症。第 2 巻。ブライアン・マッスミによる翻訳および序文。ミネアポリスおよびロンドン:ミネソタ大学出版。p. xvi。ISBN 978-0-8166-1401-1。OCLC 16472336。 マッスミ、ブライアン(2002年)。『仮想のための寓話:運動、情動、感覚』。ダーラムおよびロンドン:デューク大学出版局。ISBN 978-0-8223-2897-1。2011年11月27日取得。 セイファート、ロバート(2012年)。「個人的感情と集団的情緒を超えて:社会的情動の理論」。理論、文化、社会。29 (6): 27–46。doi:10.1177/0263276412438591。S2CID 143590063。 スピノザ、ベネディクトゥス・デ(2002)[1677]。全集。サミュエル・シャーリー訳。インディアナポリス及びケンブリッジ:ハケット出版。p. 278。ISBN 978-0-87220-620-5。2011年11月27日閲覧。 スコガード、I. と ウォーターストン、A. (2015)、「序論:情動の人類学と喚起的民族誌に向けて」. 『人類学と意識』26: 109–120. doi:10.1111/anoc.12041 スピノザ、ベネディクトゥス・デ(1994)。『スピノザ読本:倫理学とその他の著作』。エドウィン・M・カーリー訳。プリンストンおよびチチェスター: プリンストン大学出版局。p. 154. ISBN 978-0-691-00067-1。2011年11月27日閲覧。 スリフト、ナイジェル・J.(2007)。『非表象理論:空間、政治、情動』。ロンドン:ラウトリッジ。ISBN 978-0-415-39320-1。2011年11月27日閲覧。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Affect_(philosophy) |
︎▶︎感情政治学/感情の政治(Affective politics) |
| Affective
politics explores how emotions, feelings, and moods shape political
behavior, power, and identity, moving beyond purely rational views to
show how politicians strategically use emotions (like fear, hope,
outrage) to influence citizens, and how citizens' collective feelings
(affective polarization, solidarity) create political realities,
especially in digital spaces. It studies how emotional appeals in
media, policy-making, and discourse create shared "feeling rules,"
influence governance, and build or challenge social bonds, impacting
everything from voting to national security. Affective politics is a field of study and a political practice that recognizes emotions—such as fear, anger, joy, and hope—not as distractions from rational thought, but as the primary drivers of political views, actions, and collective identities. |
感
情政治学(Affective
politics)は、感情や気分が政治行動、権力、アイデンティティをどう形作るかを研究する。純粋に合理的な見解を超え、政治家が恐怖や希望、怒りと
いった感情を戦略的に利用して市民に影響を与える方法、そして市民の集合的感情(感情的分極化や連帯感)が特にデジタル空間において政治的現実をどう生み
出すかを示す。メディアや政策決定、言説における感情的訴求が、いかに共有された「感情ルール」を生み出し、統治に影響を与え、社会的絆を構築あるいは挑
戦するのかを研究する。投票行動から国家安全保障に至るまで、あらゆる事象に影響を及ぼすのである。 感情政治学とは、恐怖や怒り、喜び、希望といった感情を、理性的な思考の妨げではなく、政治的見解や行動、集団的アイデンティティの主要な原動力として認識する研究分野であり、政治的実践である。 |
| Key Aspects of Affective Politics: Emotional Appeals: Politicians and actors deliberately use emotional rhetoric (e.g., inciting outrage, fostering compassion) to persuade and mobilize people, often by framing issues to trigger specific reactions. Digital Media's Role: Social media amplifies affective dynamics, making it crucial for understanding modern political communication, misinformation, and polarization. Affective Polarization: A key concept where partisans strongly dislike and distrust opponents, creating deep emotional divides rather than just policy disagreements. Emotions as Social Practices: Drawing from scholars like Sara Ahmed, it sees emotions not just as individual feelings but as social practices that produce political realities, power structures, and subjectivities. Ontological Security: How collective emotions (grief, solidarity) help communities cope with trauma and rebuild stability, with political leaders playing a role in restoring trust. Reciprocal Relationship: A two-way street where politicians use voters, but voters also "use" politicians to experience certain feelings, and shared feelings create collective political identities. |
感情政治の主要な側面: 感情的訴求:政治家や関係者は、意図的に感情的なレトリック(例:怒りを煽る、同情を育む)を用いて人々を説得し動員する。多くの場合、特定の反応を引き起こすよう問題を設定する。 デジタルメディアの役割:ソーシャルメディアは感情的な力学を増幅させる。現代の政治コミュニケーション、誤情報、分極化を理解する上で極めて重要だ。 感情的分極化: 支持者が対立する陣営を強く嫌悪し不信感を抱く核心概念であり、単なる政策上の意見の相違ではなく深い感情的な断絶を生む。社会的実践としての感情: サラ・アーメドら研究者の見解に基づき、感情を単なる個人の感情ではなく、政治的現実・権力構造・主体性を生み出す社会的実践と捉える。 存在論的安心感:集団的感情(悲嘆、連帯感)が、コミュニティがトラウマに対処し安定を再構築するのをどう助けるか。政治指導者は信頼回復に役割を果たす。 相互関係:双方向の関係性。政治家が有権者を利用する一方で、有権者も特定の感情を経験するために政治家を「利用」する。共有された感情が集団的政治的アイデンティティを形成する。 |
| Examples in Action: Bismarck's Doctored Telegram: A historical example of manipulating emotions (French outrage) to instigate war. Neoliberalism: How dependency discourses evoke emotions (shame, undeservingness) to enforce particular social values and identities. Post-Truth Era: How feelings of being unheard, rather than just facts, drive political belief and action. |
実例: ビスマルクの改ざん電報:戦争を煽るために感情(フランスの怒り)を操作した歴史的事例。 新自由主義:依存関係に関する言説が感情(恥、不適格感)を喚起し、特定の社会的価値観やアイデンティティを強要する仕組み。 ポスト・トゥルース時代:単なる事実ではなく、声を聞いてもらえないという感情が政治的信念と行動を駆り立てる仕組み。 |
| In
essence, affective politics argues that emotions are not just
background noise but a central, dynamic force in politics, shaping how
we understand the world and act within it. |
本質的に、感情政治学は、感情は単なる背景の雑音ではなく、政治における中心的で動的な力であり、私たちが世界をどう理解し、その中でどう行動するかを形作るものであると主張する。 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆