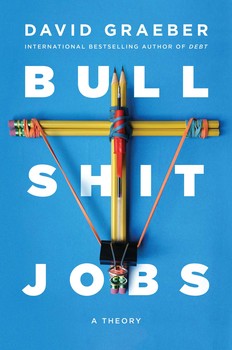
クソどうでもいい仕事
Bullshit Jobs [ブ
ルシット・ジョブズ]
☆
『クソみたいな仕事:理論』は人類学者デイヴィッド・グレイバーによる2018年の著作で、無意味な仕事の存在を提唱し、その社会的害悪を分析している。
彼は社会の労働の半分以上が無意味で、労働を自己価値と結びつける労働倫理と結びつくと心理的に破壊的になると主張する。グレイバーは、労働者が自らの役割が実際には無意味で有害だと知りつつも、そうではないふりを
する五種類の無意味な仕事を説明する。それは、取り巻き役、用心棒、ダクトテープ貼り、チェックリスト埋めの役、そして監督役である。彼
は、労働を美徳ある苦悩と結びつける考え方は人類史上では比較的新しいものであり、解決策として労働組合とベーシックインカムを提案している。
本書はグレイバーが2013年に発表した人気エッセイの拡張版である。同エッセイは後に12言語に翻訳され、その根底にある前提はユーガブの世論調査の主
題となった。グレイバーは無意味な仕事に従事する労働者から数百件の証言を募り、エッセイの主張を書籍形式に改訂。サイモン&シュスター社より2018年
5月に刊行された。
二つの研究が、グレイバーの主張はデータで裏付けられていないことを示した。彼が「仕事の50%は無意味だ」と主張する一方で、そう感じている労働者は
20%未満であり、自分の仕事が「無意味」と感じる人々は、その仕事が実際に無意味かどうかとは相関していない。(ごみ収集員、清掃員、その他の必須労働
者は、グレイバーが無意味と分類した職種の人々よりも、自分の仕事が「無意味」だと感じる傾向が強かった。)
研究によれば、そうした感情の背景には(マルクスの疎外理論で説明されるように)有害な職場文化や管理職の失態の方がより適切な説明となる。ただし「自分
の仕事が無駄だ」という認識が人格の幸福度を低下させる傾向は確認された。[1][2]
| Bullshit Jobs: A
Theory is a 2018 book by anthropologist David Graeber that postulates
the existence of meaningless jobs and analyzes their societal harm. He
contends that over half of societal work is pointless and becomes
psychologically destructive when paired with a work ethic that
associates work with self-worth. Graeber describes five types of
meaningless jobs, in which workers pretend their role is not as
pointless or harmful as they know it to be: flunkies, goons, duct
tapers, box tickers, and taskmasters. He argues that the association of
labor with virtuous suffering is recent in human history and proposes
unions and universal basic income as a potential solution. The book is an extension of Graeber's popular 2013 essay, which was later translated into 12 languages and whose underlying premise became the subject of a YouGov poll. Graeber solicited hundreds of testimonials from workers with meaningless jobs and revised his essay's case into book form; Simon & Schuster published the book in May 2018. Two studies found that Graeber's claims are not supported by data: while he claims that 50% of jobs are useless, less than 20% of workers feel that way, and those who feel their jobs are useless do not correlate with whether their job is useless. (Garbage collectors, janitors, and other essential workers more often felt like their jobs were useless than people in jobs classified by Graeber as useless.) The studies found that toxic work culture and bad management were better explanations of the reasons for those feelings (as described in Marx's theory of alienation). The studies did find that the belief that one's work is useless led to lower personal wellbeing.[1][2] |
『クソみたいな仕事:理論』は人類学者デイヴィッド・グレイバーによる
2018年の著作で、無意味な仕事の存在を提唱し、その社会的害悪を分析している。彼は社会の労働の半分以上が無意味で、労働を自己価値と結びつける労働
倫理と結びつくと心理的に破壊的になると主張する。グレイバーは、労働者が自らの役割が実際には無意味で有害だと知りつつも、そうではないふりをする五種
類の無意味な仕事を説明する。それは、取り巻き役、用心棒、ダクトテープ貼り、チェックリスト埋めの役、そして監督役である。彼は、労働を美徳ある苦悩と
結びつける考え方は人類史上では比較的新しいものであり、解決策として労働組合とベーシックインカムを提案している。 本書はグレイバーが2013年に発表した人気エッセイの拡張版である。同エッセイは後に12言語に翻訳され、その根底にある前提はユーガブの世論調査の主 題となった。グレイバーは無意味な仕事に従事する労働者から数百件の証言を募り、エッセイの主張を書籍形式に改訂。サイモン&シュスター社より2018年 5月に刊行された。 二つの研究が、グレイバーの主張はデータで裏付けられていないことを示した。彼が「仕事の50%は無意味だ」と主張する一方で、そう感じている労働者は 20%未満であり、自分の仕事が「無意味」と感じる人々は、その仕事が実際に無意味かどうかとは相関していない。(ごみ収集員、清掃員、その他の必須労働 者は、グレイバーが無意味と分類した職種の人々よりも、自分の仕事が「無意味」だと感じる傾向が強かった。) 研究によれば、そうした感情の背景には(マルクスの疎外理論で説明されるように)有害な職場文化や管理職の失態の方がより適切な説明となる。ただし「自分 の仕事が無駄だ」という認識が人格の幸福度を低下させる傾向は確認された。[1][2] |
| Summary The author interviewed at De Balie on the premise of the book, June 2018 The productivity benefits of automation have not led to a 15-hour workweek, as predicted by economist John Maynard Keynes in 1930, but instead to "bullshit jobs": "a form of paid employment that is so completely pointless, unnecessary, or pernicious that even the employee cannot justify its existence even though, as part of the conditions of employment, the employee feels obliged to pretend that this is not the case".[3] Many people who are working these bullshit or pointless jobs know that they are working jobs that do not contribute to society in a meaningful way. A review of the book notes: "Technology has advanced to the point where most of the difficult, labor-intensive jobs can be performed by machines."[4] Instead of producing more jobs that are fulfilling for our environment, they create meaningless jobs to provide everyone with an opportunity to work.[4] While these jobs can offer good compensation and ample free time, the pointlessness of the work grates at their humanity and creates a "profound psychological violence".[3] More than half of societal work is pointless, both large parts of some jobs and five types of entirely pointless jobs: 1. Flunkies, who serve to make their superiors feel important, e.g., receptionists, administrative assistants, door attendants, store greeters; 2. Goons, who act to harm or deceive others on behalf of their employer, or to prevent other goons from doing so, e.g., lobbyists, corporate lawyers, telemarketers, public relations specialists; 3. Duct tapers, who temporarily fix problems that could be fixed permanently, e.g., programmers repairing shoddy code, airline desk staff who calm passengers with lost luggage; 4. Box tickers, who create the appearance that something useful is being done when it is not, e.g., survey administrators, in-house magazine journalists, corporate compliance officers, academic administration;[5] 5. Taskmasters, who create extra work for those who do not need it, e.g., middle management, leadership professionals.[6][3] These jobs are largely in the private sector despite the idea that market competition would root out such inefficiencies. In companies, the rise of service sector jobs owes less to economic need than to "managerial feudalism", in which employers need underlings in order to feel important and maintain competitive status and power.[3][6] In society, the Puritan-capitalist work ethic is to be credited for making the labor of capitalism into religious duty: that workers did not reap advances in productivity as a reduced workday because, as a societal norm, they believe that work determines their self-worth, even as they find that work pointless. This cycle is a "profound psychological violence"[6] and "a scar across our collective soul".[7] One of the challenges to confronting our feelings about bullshit jobs is a lack of a behavioral script, in much the same way that people are unsure of how to feel if they are the object of unrequited love. In turn, rather than correcting this system, individuals attack those whose jobs are innately fulfilling.[7] Work as a source of virtue is a recent idea. In fact, work was disdained by the aristocracy in classical times but inverted as virtuous through then-radical philosophers like John Locke. The Puritan idea of virtue through suffering justified the toil of the working classes as noble.[6] And so, one could argue that bullshit jobs justify contemporary patterns of living: that the pains of dull work are suitable justification for the ability to fulfill consumer desires, and that fulfilling those desires could be considered as the reward for suffering through pointless work in contemporary society. Accordingly, over time, the prosperity extracted from technological advances has been reinvested into industry and consumer growth for its own sake rather than the purchase of additional leisure time from work.[3] Bullshit jobs also serve political ends, in which political parties are more concerned about having jobs than whether the jobs are fulfilling. In addition, populations occupied with busy work have less time to revolt.[7] One solution that is offered by many is the idea of a universal basic income, which would consist of a livable benefit paid to all people regardless of their status so that they may work at their leisure.[6] The common trends within society today point people towards a very uneven work cycle that consists of sprints followed by low periods of unproductive work. Jobs such as farmers, fishers, soldiers, and novelists vary the intensity of their work based on the urgency to produce and the natural cycles of productivity, not arbitrary standard working hours. Universal basic income offers the notion that this time pursuing pointless work could instead be spent pursuing creative activities.[3] |
要約 著者は2018年6月、 デ・バーリエで本書を前提にインタビューを受けた 自動化による生産性向上は、1930年に経済学者ジョン・メイナード・ケインズが予測した週15時間労働にはつながらなかった。代わりに生まれたのは「ク ソ仕事」だ。これは「完全に無意味で不要、あるいは有害な有償雇用形態であり、従業員自身でさえその存在意義を正当化できない。しかし雇用条件の一部とし て、そうではないふりをせざるを得ない」と定義される。[3] このような意味のない仕事に従事する多くの人々は、自らの仕事が社会に有意義な貢献をしていないことを自覚している。ある書評はこう指摘する:「技術は、 困難で労働集約的な仕事の大半を機械が担える段階まで進歩した」 [4] 環境にとって充実した仕事を増やす代わりに、彼らは皆に働く機会を与えるため、意味のない仕事を作り出す。[4] こうした仕事は良い報酬と十分な自由時間を提供できるが、仕事の無意味さが人間性を蝕み、「深い心理的暴力」を生み出す。[3] 社会の仕事の半分以上は無意味だ。特定の職種の大部分と、完全に無意味な5種類の職種がそれに当たる: 1. 取り巻き役:上司の重要感を演出する者。例:受付係、事務補助、ドアマン、店舗の挨拶係 2. 取り締まり役:雇用主の指示で他者を傷つけたり騙したり、あるいは他の取り締まり役の行動を阻止する者。例:ロビイスト、企業弁護士、テレマーケター、広 報担当者 3. ダクトテープ職:恒久的に解決できる問題を一時的にごまかす者。例:粗悪なコードを修正するプログラマー、紛失手荷物で動揺する乗客をなだめる航空会社の カウンター係。 4. チェックリスト職:実際には何も役に立たないのに、何か有用なことをしているように見せかける者。例:調査管理者、社内誌記者、企業コンプライアンス担当 者、大学事務職員。 5. タスクマスター:必要のない者に余計な仕事を課す者。例:中間管理職、リーダーシップ専門家。[6][3] こうした職種は、市場競争が非効率性を排除するという考えとは裏腹に、主に民間部門に存在する。企業におけるサービス部門職の増加は、経済的必要性よりも 「管理職封建主義」に起因する。これは雇用主が重要感を保ち、競争上の地位と権力を維持するために下位者を必要とする現象である。[3][6] 社会において、ピューリタン的資本主義の労働倫理は、資本主義の労働を宗教的義務へと変質させた。労働者は生産性向上の恩恵を労働時間短縮として享受しな かった。なぜなら社会的規範として、労働こそが自己価値を決定すると信じているからだ。たとえその労働が無意味だと感じてもなお。この循環は「深い心理的 暴力」[6]であり「我々の集合的魂に刻まれた傷跡」[7]だ。くだらない仕事に対する感情に向き合う際の課題の一つは、行動の指針が欠如していること だ。これは片思いの相手に対してどう感情を抱けば良いか分からない状況と似ている。結果として、このシステムを正す代わりに、個人は本質的に充実した仕事 を持つ者を攻撃する。[7] 労働が美徳の源泉であるという考え方は近年のものだ。実際、古典時代には貴族階級から軽蔑されていた労働が、ジョン・ロックのような当時としては急進的な 哲学者たちによって美徳へと転化されていった。ピューリタンの「苦悩を通じた美徳」という思想は、労働者階級の苦労を崇高なものとして正当化した。[6] したがって、くだらない仕事は現代の生活様式を正当化していると言える。つまり、退屈な仕事の苦痛は消費欲求を満たす能力の妥当な根拠となり、それらの欲 求を満たすことが現代社会における無意味な仕事を耐え抜く苦悩と見なされるのだ。このため、技術進歩から得られた繁栄は、仕事から解放される余暇を購入す るためではなく、産業と消費の成長そのものへ再投資されてきた。[3] くだらない仕事は政治的目的にも役立つ。政党は仕事の充実度より雇用そのものを重視するからだ。さらに、雑務に追われる人民は反乱を起こす時間が減る。 [7] 多くの人が提案する解決策の一つが、ベーシックインカムだ。これは身分に関係なく全人に生活可能な給付金を支給し、自由に働けるようにするものだ。[6] 現代社会の一般的な傾向は、人民に非常に不均等な労働サイクルを強いている。それは全力疾走の後に非生産的な仕事の低調期が続くサイクルだ。農民、漁師、 兵士、小説家といった職業は、恣意的な標準労働時間ではなく、生産の緊急性や生産性の自然サイクルに基づいて労働強度を変えている。ベーシックインカム は、この無意味な仕事に費やす時間を、代わりに創造的な活動に充てられる可能性を示唆している。[3] |
Publication The author in 2015 In 2013, Graeber published an essay in the radical magazine Strike!, "On the Phenomenon of Bullshit Jobs", which argued the pointlessness of many contemporary jobs, particularly those in fields of finance, law, human resources, public relations, and consultancy.[6] Its popularity, with over one million hits,[7] crashed the website of the essay's publisher. The essay was subsequently translated into 12 languages. YouGov undertook a related poll,[8] in which 37% of some surveyed Britons thought that their jobs did not contribute 'meaningfully' to the world. Graeber subsequently solicited hundreds of testimonials of bullshit jobs and revised his case into a book, Bullshit Jobs: A Theory.[6][3] By the end of 2018, the book was translated into French,[9] German,[10][11][12] Italian,[13] Spanish,[14] Polish,[15] and Chinese.[16] |
出版 2015年の著者 2013年、グレイバーは急進派雑誌『ストライク!』に「くだらない仕事の現象について」と題するエッセイを発表した。このエッセイは、現代の多くの仕 事、特に金融、法律、人事、広報、コンサルティング分野の仕事の無意味さを論じたものである[6]。100万回以上のアクセスを記録するほどの人気を博し [7]、エッセイを掲載した出版社のウェブサイトをダウンさせた。この論文はその後12言語に翻訳された。 ユーガブが関連調査を実施したところ[8]、回答した英国人の37%が自身の仕事が世界に「意味ある」貢献をしていないと考えていた。 グレイバーはその後、何百もの「くだらない仕事」の実例を募集し、その主張を書籍『くだらない仕事:理論』にまとめた。[6][3] 2018年末までに、この本はフランス語[9]、ドイツ語[10][11][12]、イタリア語[13]、スペイン語[14]、ポーランド語[15]、中国語[16]に翻訳された。 |
| Reception A review in The Times praises the book's academic rigor and humor, especially in some job examples, but altogether felt that Graeber's argument was "enjoyably overstated".[6] The reviewer found Graeber's historical work ethic argument convincing, but offered counterarguments on other points: that the average British workweek has decreased in the last century, that Graeber's argument for the overall proportion of pointless work is overreliant on the YouGov survey, and that the same survey does not hold that "most people hate their jobs". The reviewer maintains that while "managerial feudalism" can explain the existence of flunkies, Graeber's other types of bullshit jobs owe their existence to competition, government regulation, long supply chains, and the withering of inefficient companies—the same ingredients responsible for luxuries of advanced capitalism such as smartphones and year-round produce.[6] An article in Philosophy Now pointed to the initial definition of "bullshit" in philosophy. In his 1986 essay, Princeton philosopher Harry Frankfurt turned the word "bullshit" into an official philosophical term when defining bullshit as the deceptive misrepresentation of reality that remains different from lying because contrary to the liar, the "bullshitter" does not aim specifically to deceive (p. 6–7). Along these lines, administrators attempt to establish a work culture whose achievements are not factually false, but merely fake and phony.[17] |
書評 タイムズ紙の書評は、この本の学術的な厳密さとユーモア、特にいくつかの仕事の例を称賛しているが、全体としてグレイバーの主張は「愉快なほど誇張されて いる」と感じた。[6] 批評家はグレイバーの歴史的な労働倫理に関する議論は説得力があるとしたが、他の点については反論を提示した。具体的には、英国の平均労働時間は過去 100年で減少していること、無意味な仕事の割合に関するグレイバーの主張はユーガブ調査に過度に依存していること、そして同調査は「大多数の人が仕事を 嫌っている」とは結論付けていないことである。「管理職封建主義」が下僕的存在を説明できる一方で、グレイバーが指摘する他の種類の「くだらない仕事」 は、競争・政府規制・長いサプライチェーン・非効率企業の淘汰といった要因によって存在すると論評者は主張する。これらはスマートフォンや通年供給される 農産物といった先進資本主義の贅沢品を生み出すのと同じ要素だ。[6] 『フィロソフィー・ナウ』誌の記事は、哲学における「ブルシット」の初期定義に言及した。プリンストン大学の哲学者ハリー・フランクフルトは1986年の 論文で、「ブルシット」という言葉を正式な哲学用語として確立した。彼はブルシットを「現実を欺瞞的に誤って表現する行為」と定義し、嘘つきとは異なり、 ブルシッターは特に欺くことを目的としていない点で異なる(p. 6–7)。この流れに沿い、管理者たちは事実上虚偽ではないが、単なる偽物で偽りの成果を重視する職場文化の確立を試みる。[17] |
| Studies on Graeber's claims A 2021 study empirically tested several of Graeber's claims, such as that bullshit jobs were increasing over time and that they accounted for much of the workforce. Using data from the EU-conducted European Working Conditions Survey, the study found that a low and declining proportion of employees considered their jobs to be "rarely" or "never" useful.[1] The study also found that while there was some correlation between occupation and feelings of uselessness, they did not correspond neatly with Graeber's analysis; bullshit "taskmasters" and "goons" such as hedge-fund managers or lobbyists reported that they were vastly satisfied with their work, while essential workers like refuse collectors and cleaners often felt their jobs were useless. However, the study did confirm that feeling useless in one's job was correlated to poor psychological health and with higher rates of depression and anxiety. To account for the serious effects of working a bullshit job and why someone might feel their job is bullshit, the authors instead draw on the Marxist concept of alienation. The authors suggest that toxic management and work culture may lead individuals to feel that they are not realizing their true potential, regardless of whether or not their job is actually useful. A 2023 study, using data from the American Working Conditions Survey showed that 19% of respondents consider their jobs "rarely" or "never" useful to society. In addition, the survey shows that the occupations pointed out by Graeber are in fact most strongly perceived as socially useless, after controlling for working conditions. However this is still significantly below Graeber's claim that over 50% of all jobs are useless. It also does not show that the jobs are objectively useless, merely that the respondents feel this.[2] |
グレイバーの主張に関する研究 2021年の研究では、グレイバーの主張のいくつかを実証的に検証した。例えば、無意味な仕事が時間とともに増加していることや、それらが労働力の大部分 を占めているという主張である。EUが実施した欧州労働条件調査のデータを用い、研究は「自分の仕事が『ほとんど役に立たない』または『全く役に立たな い』」と考える従業員の割合が低く、減少傾向にあることを発見した。また、職業と無用感には相関関係があるものの、グレイバーの分析とは一致しなかった。 ヘッジファンドマネージャーやロビイストといった「タスクマスター」や「ゴーン」と呼ばれるブッシット職の従事者は仕事に非常に満足していると報告した一 方、ごみ収集員や清掃員といった必須労働者は自身の仕事を無用だと感じる傾向が強かった。ただし、仕事に無意味さを感じることは、心理の健康状態の悪化 や、うつ病・不安障害の発症率上昇と相関関係にあることは確認された。無意味な仕事による深刻な影響や、なぜその仕事が無意味に感じられるのかを説明する ため、著者らはマルクス主義の疎外概念を援用している。有害な管理手法や職場文化が、実際の仕事の有用性に関わらず、個人が真の可能性を発揮できていない と感じさせる要因となり得ると示唆している。 2023年の研究では、米国労働条件調査のデータを用い、回答者の19%が自身の仕事を「ほとんど」または「全く」社会に有用でないと認識していることが 示された。さらにこの調査では、労働条件を調整した後でも、グレイバーが指摘した職種こそが社会的に無用だと強く認識されていることが明らかになった。と はいえ、これはグレイバーの主張する「全職種の50%以上が無用」という数値には大きく及ばない。また、これらの職種が客観的に無用であることを示すもの ではなく、単に回答者がそう感じているに過ぎない。[2] |
| Critique of work Decent work – Employment that respects the fundamental rights of the human person Make-work job – Non-market jobs used to reduce unemployment On Bullshit by Harry Frankfurt Parkinson's law – Adage that work expands to fill its available time Refusal of work Tang ping – Chinese neologism, "lying flat" |
仕事の批判 まともな仕事 – 人間の基本的人格を尊重する雇用 見せかけの仕事 – 失業を減らすために作られた非市場的な仕事 ハリー・フランクフルト『虚偽と偽善』 パーキンソンの法則 – 仕事は与えられた時間を埋めるように膨張するという格言 労働拒否 タンピン – 中国の新造語、「横たわる」 |
| 1.
Soffia, Magdalena; Wood, Alex J; Burchell, Brendan (October 2022).
"Alienation Is Not 'Bullshit': An Empirical Critique of Graeber's
Theory of BS Jobs". Work, Employment and Society. 36 (5): 816–840.
doi:10.1177/09500170211015067.
hdl:1983/460fe471-7f93-4a6a-87dd-809316d5afbf. Nevertheless, the
empirical data do not support any of Graeber's hypotheses. Therefore,
the BS jobs theory must be rejected. Not only do our findings offer no
support to this theory, they are often the exact opposite of what
Graeber predicts. In particular, the proportion of workers who believe
their paid work is not useful is declining rather than growing rapidly,
and workers in professions connected to finance and with university
degrees are less likely to feel their work is useless than many manual
workers. 2. Walo, Simon (July 21, 2023). "'Bullshit' After All? Why People Consider Their Jobs Socially Useless". Work, Employment and Society. 37 (5): 1123–1146. doi:10.1177/09500170231175771. 3. Heller, Nathan (June 7, 2018). "The Bullshit-Job Boom". The New Yorker. ISSN 0028-792X. Archived from the original on June 10, 2018. Retrieved June 9, 2018. 4. Illing, Sean (May 8, 2018). "Bullshit jobs: why they exist and why you might have one". Vox. Retrieved February 21, 2024. 5. Husain, Masud (2025). "On the responsibilities of intellectuals and the rise of bullshit jobs in universities". Brain. 148 (3): 687–688. doi:10.1093/brain/awaf045. PMID 40048619. 6. Duncan, Emma (May 5, 2018). "Review: Bullshit Jobs: A Theory by David Graeber — quit now, your job is pointless". The Times. ISSN 0140-0460. Archived from the original on May 5, 2018. Retrieved May 5, 2018. 7. Glaser, Eliane (May 25, 2018). "Bullshit Jobs: A Theory by David Graeber review – the myth of capitalist efficiency". The Guardian. ISSN 0261-3077. 8. "37% of British workers think their jobs are meaningless". yougov.co.uk. Archived from the original on July 26, 2019. Retrieved July 26, 2019. 9. Sardier, Thibaut (September 15, 2018). "Et vous, avez-vous un job à la con? Faites le test". Libération.fr (in French). Retrieved June 26, 2020. 10. Lessenich, Stephan (November 10, 2018). "Buch über 'Bullshit Jobs': Sinn ist halt eine knappe Ressource". Frankfurter Allgemeine Zeitung (in German). ISSN 0174-4909. 11. Taverna, Erhard (January 16, 2019). "Bullshit Jobs". Schweizerische Ärztezeitung (in German). 100 (3): 65. doi:10.4414/saez.2019.17344. 12. Kaufmann, Stephan (November 17, 2018). "Arbeit: "Jobs, die die Welt nicht braucht'". Frankfurter Rundschau (in German). Archived from the original on January 20, 2019. Retrieved November 17, 2018. 13. Momigliano, Anna (October 2, 2018). "Il problema dei lavori che ci piacciono". Rivista Studio (in Italian). Archived from the original on April 4, 2020. Retrieved June 26, 2020. 14. Vallespín, Fernando (March 10, 2019). "Análisis – Socialismo milenial en EE UU". El País (in Spanish). Madrid. ISSN 1134-6582. Archived from the original on June 8, 2020. Retrieved June 26, 2020. 15. OCLC 1126618522 16. OCLC 1141782257 17. Thorsten Botz-Bornstein, "In Praise of Industry" in Philosophy Now, volume 137, 2020. |
1.
ソフィア, マグダレーナ; ウッド, アレックス・J; バーチェル, ブレンダン (2022年10月).
「疎外は『くだらない仕事』ではない:グレイバーのBSジョブ理論に対する実証的批判」. 『労働・雇用・社会』. 36 (5): 816–840.
doi:10.1177/09500170211015067.
hdl:1983/460fe471-7f93-4a6a-87dd-809316d5afbf.
しかしながら、実証データはグレイバーの仮説を一切支持しない。したがって、BSジョブ理論は退けられるべきだ。我々の調査結果は、この理論を支持するど
ころか、むしろグレイバーの予測とは正反対の傾向を示している。特に、有償労働が役に立たないと感じる労働者の割合は急増するどころか減少傾向にあり、金
融関連職種や大学卒業者ほど、多くの肉体労働者よりも自らの仕事を無意味だと感じる可能性が低い。 2. Walo, Simon (2023年7月21日). 「結局『くだらない仕事』なのか?人々が自身の仕事を社会的に無益と考える理由」. Work, Employment and Society. 37 (5): 1123–1146. doi:10.1177/09500170231175771. 3. ヘラー、ネイサン(2018年6月7日)。「くだらない仕事のブーム」。『ニューヨーカー』。ISSN 0028-792X。2018年6月10日時点のオリジナルからアーカイブ。2018年6月9日閲覧。 4. イリング、ショーン(2018年5月8日)。「くだらない仕事:なぜ存在するのか、そしてなぜ君がそれを持っているかもしれないのか」。ヴォックス。2024年2月21日に取得。 5. フセイン、マスード(2025)。「知識人の責任と大学におけるくだらない仕事の台頭について」。ブレイン。148 (3): 687–688頁。doi:10.1093/brain/awaf045。PMID 40048619。 6. ダンカン、エマ(2018年5月5日)。「書評:デイヴィッド・グレイバー著『ブッシット・ジョブズ:理論』―今すぐ辞めろ、お前の仕事は無意味だ」。タ イムズ。ISSN 0140-0460。2018年5月5日時点のオリジナルからアーカイブ。2018年5月5日に閲覧。 7. グラザー、エリアン(2018年5月25日)。「デヴィッド・グレイバー著『クソ仕事:理論』書評 ― 資本主義的効率性の神話」。ガーディアン。ISSN 0261-3077。 8. 「英国労働者の37%が自分の仕事に意味を見出せない」。yougov.co.uk。2019年7月26日時点のオリジナルからアーカイブ。2019年7月26日閲覧。 9. サルディエ、ティボー(2018年9月15日)。「あなたはどうだ?くだらない仕事をしているか?テストしてみよう」。リベラシオン.fr(フランス語)。2020年6月26日閲覧。 10. Lessenich, Stephan (2018年11月10日). 「『くだらない仕事』に関する本:意味は希少な資源なのだ」. フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング(ドイツ語)。ISSN 0174-4909。 11. タヴェルナ、エルハルト(2019年1月16日)。「くだらない仕事」。シュヴァイツァーリッシェ・アーツェツァイトゥング(ドイツ語)。100 (3): 65. doi:10.4414/saez.2019.17344. 12. カウフマン、ステファン(2018年11月17日)。「労働:『世界が必要としない仕事』」。フランクフルター・ルントシャウ(ドイツ語)。2019年1月20日にオリジナルからアーカイブ。2018年11月17日に取得。 13. モミリアーノ、アンナ(2018年10月2日)。「私たちが好きな仕事の問題」。リヴィスタ・スタジオ(イタリア語)。2020年4月4日にオリジナルからアーカイブされた。2020年6月26日に取得。 14. ヴァレスピン、フェルナンド(2019年3月10日)。「分析 – 米国のミレニアル世代社会主義」。エル・パイス(スペイン語)。マドリード。ISSN 1134-6582。2020年6月8日にオリジナルからアーカイブされた。2020年6月26日に取得。 15. OCLC 1126618522 16. OCLC 1141782257 17. トルステン・ボッツ=ボルンシュタイン、「産業を称えて」『フィロソフィー・ナウ』第137巻、2020年。 |
| David
Graeber (1961–2020) was a Professor of Anthropology at the London
School of Economics. His bestselling books include The Dawn of
Everything, cowritten with David Wengrow, and DEBT: The First 5,000
Years. He was a contributor to Harper’s Magazine, The Guardian, and The
Baffler. |
デイヴィッド・グ
レイバー(1961–2020)はロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの人類学教授であった。彼のベストセラーにはデイヴィッド・ウェングローとの共
著『万物の夜明け』や『債務:最初の五千年の歴史』がある。彼はハーパーズ・マガジン、ガーディアン紙、ザ・バフラー誌に寄稿していた。 |
David
Graeber - Bullshit Jobs
| ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論(英:
Bullshit Jobs:A
Theory)は、アメリカの人類学者デヴィッド・グレーバーによる2018年の著書で、無意味な仕事の存在と、その社会的有害性を分析している。彼は、
社会的仕事の半分以上は無意味であり、仕事を自尊心と関連付ける労働倫理と一体となったときに心理的に破壊的になると主張している。グレーバーは、5種類
の無意味な仕事について説明し、そこでは、労働者は自分の役割が自分の知っているほど無意味でも有害でもないふりをしているとする。労働と高潔な苦しみと
の関連は人類の歴史の中で最近のものであると述べ、潜在的な解決策としてベーシックインカムを提案している。 原題にある"Bullshit Jobs"のBullshitは、原義は「牛糞」だが比喩的な意味ではなく、辞書での定義は「でたらめ」「たわごと」「ほら話」などの俗語であり、その意味で一般的によく使われる言葉である[1]。 |
|
| 経緯 この本は、2013年に出版された人気のエッセイGraeberの拡張版[要出典]である。このエッセイは後に12以上の言語に翻訳[2]され、その基礎 となる前提がYouGov世論調査の対象となった[3]。その後、グレーバーは無意味な仕事をしている人々から数百の推薦状を募り、彼の事件をサイモン& シュスターが2018年5月に出版した本に改訂した[要出典]。 |
|
| 主張 この本で、グレーバーは、自動化の生産性の成果は、1930年に経済学者のジョン・メイナード・ケインズが予見したような「週15時間労働」には結びついておらず、代わりに「ブルシット・ジョブ」を生み出している、と主張している。 グレーバーは、美徳の源としての仕事は最近の考えであり、労働は古典時代の貴族によって軽蔑されていたが、ジョン・ロックのような当時の急進派の哲学者に よって美徳として賞賛されたと考えている。勤労=労働を美徳とするピューリタンの考えは、労働者階級の苦労を高貴なものとして正当化した。ブルシット・ ジョブは現代のライフスタイルを正当化する。鈍い仕事の痛みは消費者の欲求を満たす能力の適切な正当化であり、それらの欲求を満たすことは確かに無意味な 仕事を通して苦しむことに対する報酬だ。したがって、時間の経過とともに、技術の進歩から引き出された繁栄は、仕事から追加の余暇を購入するのではなく、 それ自体のために産業と消費者の成長に再投資されてきた。ブルシット・ジョブは政治的な目的にも役立つ。政党は、仕事が充実しているかどうかよりも、仕事 を持つことに関心がある。さらに、彼は、忙しい仕事で占められている人々は反乱を起こす時間が少ないと主張している。 問題の解決策として、グレーバーはベーシックインカムを提唱し、それにより人々にとって仕事が「レジャー」となると主張している。 |
|
| ブルシット・ジョブの定義 ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている。 —デヴィッド・グレーバー、[4] |
|
| ブルシット・ジョブの種類 グレーバーは、以下に述べる5種類の「ブルシット・ジョブ」について説明している[5]。 取り巻き[注釈 1] 誰かを偉そうにみせたり、偉そうな気分を味わわせたりするためだけに存在している仕事。例えば、受付係、管理アシスタント、ドアアテンダント。「管理職に 昇進した以上、部下をつけなければならない」と見做されて仕事もないのに雇われた人々。権威付けと序列、メンバシップを確認する為だけにある会議体。 脅し屋[注釈 2] 雇用主のために他人を脅したり欺いたりする要素を持ち、そのことに意味が感じられない仕事。ロビイスト、顧問弁護士、テレマーケティング業者、広報スペシャリストなど、雇用主に代わって他人を傷つけたり欺いたりするために行動する悪党。 尻ぬぐい[注釈 3] 組織のなかの存在してはならない欠陥を取り繕うためだけに存在している仕事。たとえば、粗雑なコードを修復するプログラマー、バッグが到着しない乗客を落ち着かせる航空会社のデスクスタッフ。 書類穴埋め人[注釈 4] 組織が実際にはやっていないことを、やっていると主張するために存在している仕事。たとえば、調査管理者、社内の雑誌ジャーナリスト、企業コンプライアンス担当者など。役に立たないときに何か便利なことが行われているように見せる。 タスクマスター[注釈 5] 他人に仕事を割り当てるためだけに存在し、ブルシット・ジョブを作り出す仕事。中間管理職や号令係、取り次ぎや仲介。 |
|
| https://x.gd/sLPtu |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099