エドマンド・バーク
Edmund
Burke, 1729-1797

A literary party at Sir Joshua Reynolds's, "The Club"
エドマンド・バーク
Edmund
Burke, 1729-1797

A literary party at Sir Joshua Reynolds's, "The Club"
★エドマンド・バーク(Edmund Burke
/bɜːrk/、1729年1月12日[NS] -
1797年7月9日)は、アングロ=アイリッシュの政治家、哲学者であり、そのキャリアの大半をイギリスで過ごした。ダブリン生まれのバークは、1766
年から1794年までホイッグ党の一員としてイギリス下院議員(MP)を務めた。
バークは、社会における礼儀作法と徳性の重要性を唱え、国家の道徳的安定と繁栄のために宗教的機関が重要であると主張した。[3]
これらの見解は、著書『自然社会の擁護』(1756年)で表明されている。彼は、アメリカ植民地に対する英国政府の政策、特に課税政策を批判した。また、
大都市の権力に抵抗する植民地の権利を支持したが、独立を達成しようとする試みには反対した。彼は、カトリック教徒の解放、東インド会社からのウォーレ
ン・ヘイストンの弾劾、そしてフランス革命への断固とした反対を支持したことで記憶されている。
著書『フランス革命についての省察』(1790年)の中で、バークは革命が「善良な」社会の組織や国家および社会の伝統的機関を破壊していると主張し、そ
の結果として生じたカトリック教会への迫害を非難した。これにより、彼はホイッグ党の保守派の中心人物となり、フランス革命を支持するチャールズ・ジェイ
ムズ・フォックス率いる新ホイッグ党に対して、自らを「旧ホイッグ党」と称した。
19世紀には、保守派とリベラル派の両方から賞賛された。[5]
その後、20世紀には、彼は特にアメリカ合衆国とイギリスで、超王党派でウルトラモンタヌス派のジョゼフ・ド・メイスター(Joseph de
Maistre)と並んで、保守主義の哲学的創始者として広く認められるようになった。[6][7][8][9]
★崇高と美にかんする我々の観念の起源に関する哲学的探究(A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful)は、1757年にエドモンド・バークが執筆した美学に関する論文である。美しいものと崇高なものをそれぞれの合理的なカテゴリーに分 離した、最初の完全な哲学的論説である。ドゥニ・ディドロやイマヌエル・カントと いった著名な思想家の注目を集めた。
| Edmund Burke
(/bɜːrk/; 12 January [NS] 1729[2] – 9 July 1797) was an Anglo-Irish
statesman and philosopher who spent most of his career in Great
Britain. Born in Dublin, Burke served as a member of Parliament (MP)
between 1766 and 1794 in the House of Commons of Great Britain with the
Whig Party. Burke was a proponent of underpinning virtues with manners in society and of the importance of religious institutions for the moral stability and good of the state.[3] These views were expressed in his A Vindication of Natural Society (1756). He criticised the actions of the British government towards the American colonies, including its taxation policies. Burke also supported the rights of the colonists to resist metropolitan authority, although he opposed the attempt to achieve independence. He is remembered for his support for Catholic emancipation, the impeachment of Warren Hastings from the East India Company, and his staunch opposition to the French Revolution. In his Reflections on the Revolution in France (1790), Burke asserted that the revolution was destroying the fabric of "good" society and traditional institutions of state and society, and he condemned the persecution of the Catholic Church that resulted from it. This led to his becoming the leading figure within the conservative faction of the Whig Party which he dubbed the Old Whigs as opposed to the pro-French Revolution New Whigs led by Charles James Fox.[4] In the 19th century, Burke was praised by both conservatives and liberals.[5] Subsequently, in the 20th century, he became widely regarded, especially in the United States and the United Kingdom, as the philosophical founder of conservatism,[6][7] along with his ultra-royalist and ultramontane counterpart Joseph de Maistre.[8][9] |
エドマンド・バーク(Edmund Burke
/bɜːrk/、1729年1月12日[NS] -
1797年7月9日)は、アングロ=アイリッシュの政治家、哲学者であり、そのキャリアの大半をイギリスで過ごした。ダブリン生まれのバークは、1766
年から1794年までホイッグ党の一員としてイギリス下院議員(MP)を務めた。 バークは、社会における礼儀作法と徳性の重要性を唱え、国家の道徳的安定と繁栄のために宗教的機関が重要であると主張した。[3] これらの見解は、著書『自然社会の擁護』(1756年)で表明されている。彼は、アメリカ植民地に対する英国政府の政策、特に課税政策を批判した。また、 大都市の権力に抵抗する植民地の権利を支持したが、独立を達成しようとする試みには反対した。彼は、カトリック教徒の解放、東インド会社からのウォーレ ン・ヘイストンの弾劾、そしてフランス革命への断固とした反対を支持したことで記憶されている。 著書『フランス革命についての省察』(1790年)の中で、バークは革命が「善良な」社会の組織や国家および社会の伝統的機関を破壊していると主張し、そ の結果として生じたカトリック教会への迫害を非難した。これにより、彼はホイッグ党の保守派の中心人物となり、フランス革命を支持するチャールズ・ジェイ ムズ・フォックス率いる新ホイッグ党に対して、自らを「旧ホイッグ党」と称した。 19世紀には、保守派とリベラル派の両方から賞賛された。[5] その後、20世紀には、彼は特にアメリカ合衆国とイギリスで、超王党派でウルトラモンタヌス派のジョゼフ・ド・メイスター(Joseph de Maistre)と並んで、保守主義の哲学的創始者として広く認められるようになった。[6][7][8][9] |
| Early life Illustration from "Treasury of Irish eloquence, being a compendium of Irish oratory and literature" (1882) Edmund Burke Burke was born in Dublin, Ireland. His mother Mary, née Nagle, was a Roman Catholic who hailed from a County Cork family and a cousin of the Catholic educator Nano Nagle, whereas his father Richard, a successful solicitor, was a member of the Church of Ireland. It remains unclear whether this is the same Richard Burke who converted from Catholicism.[10][11] The Burgh (Burke) dynasty descends from the Anglo-Norman knight, William de Burgh, who arrived in Ireland in 1185 following Henry II of England's 1171 invasion of Ireland and is among the "chief Gall or Old English families that assimilated into Gaelic society" (the surname de Burgh (Latinised as de Burgo) was gaelicised in Irish as de Búrca or Búrc which over the centuries became Burke).[12] Burke adhered to his father's faith and remained a practising Anglican throughout his life, unlike his sister Juliana, who was brought up as and remained a Roman Catholic.[13] Later, his political enemies repeatedly accused him of having been educated at the Jesuit College of St. Omer, near Calais, France; and of harbouring secret Catholic sympathies at a time when membership in the Catholic Church would disqualify him from public office per Penal Laws in Ireland. As Burke told Frances Crewe: Mr. Burke's Enemies often endeavoured to convince the World that he had been bred up in the Catholic Faith, & that his Family were of it, & that he himself had been educated at St. Omer—but this was false, as his father was a regular practitioner of the Law at Dublin, which he could not be unless of the Established Church: & it so happened that though Mr. B was twice at Paris, he never happened to go through the Town of St. Omer.[14] After being elected to the House of Commons, Burke took the required oath of allegiance and abjuration, the oath of supremacy and the declaration against transubstantiation.[15] As a child, Burke sometimes spent time away from the unhealthy air of Dublin with his mother's family near Killavullen in the Blackwater Valley in County Cork. He received his early education at a Quaker school in Ballitore, County Kildare, some 67 kilometres (42 mi) from Dublin; and possibly like his cousin Nano Nagle at a Hedge school near Killavullen.[16] He remained in correspondence with his schoolmate from there, Mary Leadbeater, the daughter of the school's owner, throughout his life. In 1744, Burke started at Trinity College Dublin,[17] a Protestant establishment which up until 1793 did not permit Catholics to take degrees.[18] In 1747, he set up a debating society, Edmund Burke's Club, which in 1770 merged with TCD's Historical Club to form the College Historical Society, the oldest undergraduate society in the world. The minutes of the meetings of Burke's Club remain in the collection of the Historical Society. Burke graduated from Trinity in 1748. Burke's father wanted him to read Law and with this in mind, he went to London in 1750, where he entered the Middle Temple, before soon giving up legal study to travel in Continental Europe. After eschewing the Law, he pursued a livelihood through writing.[19] |
幼少期 「アイルランド雄弁の宝庫、アイルランドの演説と文学の要約」(1882年)よりイラスト エドマンド・バーク バークはアイルランドのダブリンで生まれた。母親のメアリー(旧姓ナグル)は、コーク州出身のローマ・カトリック教徒であり、カトリック教育者ナノ・ナグ ルの従姉妹であった。一方、父親のリチャードは成功した弁護士であり、アイルランド国教会の信者であった。これがカトリックから改宗したリチャード・バー ク(Richard Burke)と同じ人物であるかどうかは不明である。[10][11] バーク(バーク)家は、イングランド王ヘンリー2世による1171年のアイルランド侵攻に続いて1185年にアイルランドに到着したアングロ=ノルマン人 の騎士、ウィリアム・ド・バーク(William de Burgh)の子孫である。アイルランドに到着し、「ゲール語社会に同化した主なアングロ人または古アングロ人の一族」の1つとなった。(de Burgh(ラテン語でde Burgo)という名字は、アイルランド語ではゲール語化され、de BúrcaまたはBúrcとなり、何世紀にもわたってBurkeとなった。)[12] バークは父の信仰を守り、生涯を通じて英国国教会の信者であり続けた。一方、妹のジュリアナはローマ・カトリックとして育てられ、そのままローマ・カト リックの信者となった。[13] 後に、彼の政治的敵対者は、彼がフランスのカレー近郊にあるサン・オメル・イエズス会カレッジで教育を受け、アイルランドの刑法ではカトリック信者は公職 に就くことができないにもかかわらず、ひそかにカトリックに共感していたと繰り返し非難した。バークがフランシス・クルーに語ったところによると、 バーク氏の敵は、彼がカトリックの信仰で育ち、家族もカトリックであり、セント・オマーで教育を受けたのだと世間に信じ込ませようと努力していたが、それ は誤りである。なぜなら、 父親はダブリンで法律を正規に実践していたが、それは国教会の信者でなければありえないことである。そして、B氏はパリに2度滞在していたにもかかわら ず、サン・オメル市には一度も立ち寄らなかったという偶然もあった。 [14] 庶民院議員に選出された後、バークは忠誠と棄教の誓い、最高権力者の誓い、および実体説反対の宣言を行った。 幼少期には、ダブリンの不健康な空気を避けて、母親の家族とともにコーク州のブラックウォーター渓谷にあるキラーヴォレン近郊で過ごすこともあった。彼は ダブリンから約67キロメートル(42マイル)離れたキルデア州バリトーレのクエーカー教徒の学校で初期の教育を受け、おそらく従兄弟のナノ・ナグルと同 じく、キルダヴォン近くのヘッジ校に通っていた可能性がある。[16] 彼は生涯を通じて、同校の校長令嬢で同級生だったメアリー・リードビーターと文通を続けた。 1744年、バークはトリニティ・カレッジ・ダブリンに入学した。[17] トリニティ・カレッジ・ダブリンはプロテスタント系の教育機関であり、1793年まではカトリック教徒の学位取得を認めていなかった。[18] 1747年、彼は討論会「エドマンド・バーク・クラブ」を設立し、1770年にはトリニティ・カレッジ・ダブリンの「ヒストリカル・クラブ」と合併し、 「カレッジ・ヒストリカル・ソサエティ」が設立された。これは世界最古の学部生による団体である。バーク・クラブの会議の議事録は、現在も歴史協会のコレ クションとして保管されている。バークは1748年にトリニティを卒業した。バークの父親は彼に法律を学ばせようとしており、その意向に沿う形で、 1750年にロンドンへ渡り、ミドル・テンプルに入学した。しかし、ほどなく法律の勉強を諦め、ヨーロッパ大陸を旅することになる。法律の道を断念した 後、彼は執筆活動で生計を立てた。[19] |
| Early writing The late Lord Bolingbroke's Letters on the Study and Use of History was published in 1752 and his collected works appeared in 1754. This provoked Burke into writing his first published work, A Vindication of Natural Society: A View of the Miseries and Evils Arising to Mankind, appearing in Spring 1756. Burke imitated Bolingbroke's style and ideas in a reductio ad absurdum of his arguments for deistic rationalism in order to demonstrate their absurdity.[20][21]  In A Vindication of Natural Society, Burke argued: "The writers against religion, whilst they oppose every system, are wisely careful never to set up any of their own." Burke claimed that Bolingbroke's arguments against revealed religion could apply to all social and civil institutions as well.[22] Lord Chesterfield and Bishop Warburton as well as others initially thought that the work was genuinely by Bolingbroke rather than a satire.[20][23] All the reviews of the work were positive, with critics especially appreciative of Burke's quality of writing. Some reviewers failed to notice the ironic nature of the book which led to Burke stating in the preface to the second edition (1757) that it was a satire.[24] Richard Hurd believed that Burke's imitation was near-perfect and that this defeated his purpose, arguing that an ironist "should take care by a constant exaggeration to make the ridicule shine through the Imitation. Whereas this Vindication is everywhere enforc'd, not only in the language, and on the principles of L. Bol., but with so apparent, or rather so real an earnestness, that half his purpose is sacrificed to the other".[24] A minority of scholars have taken the position that in fact Burke did write the Vindication in earnest, later disowning it only for political reasons.[25][26] In 1757, Burke published a treatise on aesthetics titled A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful that attracted the attention of prominent Continental thinkers such as Denis Diderot and Immanuel Kant. It was his only purely philosophical work, completed in 1753.[27] When asked by Sir Joshua Reynolds and French Laurence to expand it thirty years later, Burke replied that he was no longer fit for abstract speculation.[28] On 25 February 1757, Burke signed a contract with Robert Dodsley to write a "history of England from the time of Julius Caesar to the end of the reign of Queen Anne", its length being eighty quarto sheets (640 pages), nearly 400,000 words. It was to be submitted for publication by Christmas 1758.[29] Burke completed the work to the year 1216 and stopped; it was not published until after Burke's death, in an 1812 collection of his works, An Essay Towards an Abridgement of the English History. G. M. Young did not value Burke's history and claimed that it was "demonstrably a translation from the French".[30] On commenting on the story that Burke stopped his history because David Hume published his, Lord Acton said "it is ever to be regretted that the reverse did not occur".[31] During the year following that contract, Burke founded with Dodsley the influential Annual Register, a publication in which various authors evaluated the international political events of the previous year.[32] The extent to which Burke contributed to the Annual Register is unclear.[33] In his biography of Burke, Robert Murray quotes the Register as evidence of Burke's opinions, yet Philip Magnus in his biography does not cite it directly as a reference.[34] Burke remained the chief editor of the publication until at least 1789 and there is no evidence that any other writer contributed to it before 1766.[34] On 12 March 1757, Burke married Jane Mary Nugent (1734–1812), daughter of Dr. Christopher Nugent,[35] a Catholic physician who had provided him with medical treatment at Bath. Their son Richard was born on 9 February 1758 while a second son, Christopher (born that December), died in infancy. Burke also helped raise a ward, Edmund Nagle (later Admiral Sir Edmund Nagle), the son of a maternal cousin orphaned in 1763.[36] At about this same time, Burke was introduced to William Gerard Hamilton (known as "Single-speech Hamilton"). When Hamilton was appointed Chief Secretary for Ireland, Burke accompanied him to Dublin as his private secretary, a position he held for three years. In 1765, Burke became private secretary to the liberal Whig politician Charles, Marquess of Rockingham, then Prime Minister of Great Britain, who remained Burke's close friend and associate until his death in 1782. |
初期の著作 故ボリングブルック卿の『歴史の研究と利用に関する書簡』は1752年に出版され、全集は1754年に出版された。これに触発されたバークは、1756年 春に『自然社会の擁護:人類に降りかかる苦難と悪の考察』を出版した。バークは、ボリングブルックのスタイルと思想を模倣し、彼らの主張の不合理性を示す ために、神智論的合理主義の帰謬法を展開した。[20][21]  『自然社会の擁護』において、バークは次のように論じた。「宗教に反対する作家たちは、あらゆる体制に反対する一方で、自分自身の体制を決して確立しようとはしない。 バークは、ボリングブルックの啓示宗教に対する主張は、あらゆる社会制度や市民制度にも当てはまると主張した。[22] チェスターフィールド卿やウォーバートン司教をはじめとする人々は、当初、この著作は風刺ではなくボリングブルックの真の著作であると考えていた。 [20][23] この著作に対する批評はすべて好意的なもので、批評家たちは特にバークの文章の質を高く評価した。この本の皮肉な本質に気づかなかった批評家もおり、その ためバークは第二版(1757年)の序文で、これは風刺であると述べた。 リチャード・ハードは、バークの模倣は完璧に近いものであり、それによって彼の目的は失敗したと考えた。皮肉屋は「模倣において嘲笑を際立たせるために、 絶え間ない誇張に注意を払うべきである」と主張した。この『擁護論』は、言葉遣いやL. Bol.の原則だけでなく、あまりにも明白な、あるいはむしろあまりにも本物らしい真剣さをもって至る所で強調されているため、彼の目的の半分は犠牲に なっている」と主張した。[24] 一部の学者は、実際にはバークは『擁護論』を真剣に書き、後に政治的理由からそれを否定したという立場を取っている。[25][26] 1757年、バークは『崇高と美の起源についての哲学的な探究』という美学に関する論文を発表し、デニ・ディドロやイマヌエル・カントといった著名な大陸 の思想家の注目を集めた。これは1753年に完成した彼の唯一の純粋な哲学的な著作である。[27] 30年後、サー・ジョシュア・レイノルズとフランス人ローレンスにこの論文の拡大版を求められた際、バークはもはや抽象的な思索には向いていないと答え た。[28] 1757年2月25日、バークはロバート・ドッズリーと「ユリウス・カエサルからアン女王の治世の終わりまでのイングランドの歴史」を執筆する契約を交わ した。その分量は80枚の四つ折り判(640ページ)で、40万語近くに及んだ。1758年のクリスマスまでに出版される予定であった。[29] バークは1216年まで書き上げていたが、その後は執筆を中止した。この作品はバークの死後、1812年に出版された彼の作品集『英国史要約試論』で発表 されるまで出版されることはなかった。G. M. ヤングはバークの歴史を評価せず、「明らかにフランス語からの翻訳である」と主張した。[30] バークが歴史の執筆を中断したのはデイヴィッド・ヒュームが自著を出版したからだという話を評して、ロード・アクトンは「その逆が起こらなかったことは、 今でも残念に思われる」と述べた。[31] その契約の翌年、バークはドッズリーとともに、前年の国際政治情勢をさまざまな著述家が評価する出版物『Annual Register』を創刊した。[32] バークが『Annual Register』にどの程度貢献したかは不明である。[33] ロバート・マレーはバークの伝記の中で、『Register』を バークの意見の証拠として引用しているが、フィリップ・マグナスは自伝の中でそれを直接参照文献として引用していない。[34] バークは少なくとも1789年まで同誌の編集長であり続けたが、1766年以前に他の執筆者が寄稿していたことを示す証拠はない。[34] 1757年3月12日、バークはジェーン・メアリー・ニュージェント(1734年 - 1812年)と結婚した。彼女はクリストファー・ニュージェント博士(1734年 - 1812年)の娘であり、バークはバースで彼から医療処置を受けていたカトリックの医師であった。彼らの息子リチャードは1758年2月9日に、次男クリ ストファー(同年12月生まれ)は幼児期に死亡した。また、1763年に孤児となった母方の従兄弟の息子、エドマンド・ネーグル(後に海軍提督サー・エド マンド・ネーグル)の養育も支援した。 ほぼ同時期に、バークはウィリアム・ジェラード・ハミルトン(「単語話者ハミルトン」として知られる)と知り合った。ハミルトンがアイルランド首席秘書官 に任命されると、バークは彼の個人秘書としてダブリンに同行し、3年間その職を務めた。1765年、バークは自由党ホイッグ党の政治家であり、当時英国首 相であったロックインガム侯爵チャールズの個人秘書となった。ロックインガム侯爵は1782年に亡くなるまで、バークの親しい友人であり協力者であった。 |
Member of Parliament A literary party at Sir Joshua Reynolds's.[37] Left to right: James Boswell, Samuel Johnson, Joshua Reynolds, David Garrick, Edmund Burke, Pasquale Paoli, Charles Burney, a servant (possibly Francis Barber), Thomas Warton, Oliver Goldsmith. (select a detail of the image for more information) In December 1765, Burke entered the House of Commons of the British Parliament as Member for Wendover in Buckinghamshire, a pocket borough in the gift of Lord Fermanagh, later 2nd Earl Verney and a close political ally of Rockingham. After Burke delivered his maiden speech, William Pitt the Elder said he had "spoken in such a manner as to stop the mouths of all Europe" and that the Commons should congratulate itself on acquiring such a Member.[38] The first great subject Burke addressed was the controversy with the American colonies which soon developed into war and ultimate separation. In reply to the 1769 Grenvillite pamphlet The Present State of the Nation, he published his own pamphlet titled Observations on a Late State of the Nation. Surveying the finances of France, Burke predicts "some extraordinary convulsion in that whole system".[39] During the same year, with mostly borrowed money, Burke purchased Gregories, a 600-acre (2.4 km2) estate near Beaconsfield. Although the estate included saleable assets such as art works by Titian, Gregories proved a heavy financial burden in the following decades and Burke was never able to repay its purchase price in full. His speeches and writings, having made him famous, led to the suggestion that he was the author of the Letters of Junius. At about this time, Burke joined the circle of leading intellectuals and artists in London of whom Samuel Johnson was the central luminary. This circle also included David Garrick, Oliver Goldsmith and Joshua Reynolds. Edward Gibbon described Burke as "the most eloquent and rational madman that I ever knew".[40] Although Johnson admired Burke's brilliance, he found him a dishonest politician.[41][42] Burke took a leading role in the debate regarding the constitutional limits to the executive authority of the king. He argued strongly against unrestrained royal power and for the role of political parties in maintaining a principled opposition capable of preventing abuses, either by the monarch or by specific factions within the government. His most important publication in this regard was his Thoughts on the Cause of the Present Discontents of 23 April 1770.[43] Burke identified the "discontents" as stemming from the "secret influence" of a neo-Tory group he labelled as the "king's friends", whose system "comprehending the exterior and interior administrations, is commonly called, in the technical language of the Court, Double Cabinet".[44] Britain needed a party with "an unshaken adherence to principle, and attachment to connexion, against every allurement of interest". Party divisions, "whether operating for good or evil, are things inseparable from free government".[45] The Gregories estate purchased by Burke for £20,000 in 1768 During 1771, Burke wrote a bill that would have given juries the right to determine what was libel, if passed. Burke spoke in favour of the bill, but it was opposed by some, including Charles James Fox, not becoming law. When introducing his own bill in 1791 in opposition, Fox repeated almost verbatim the text of Burke's bill without acknowledgement.[46] Burke was prominent in securing the right to publish debates held in Parliament.[47] Speaking in a Parliamentary debate on the prohibition on the export of grain on 16 November 1770, Burke argued in favour of a free market in corn: "There are no such things as a high, & a low price that is encouraging, & discouraging; there is nothing but a natural price, which grain brings at an universal market".[48] In 1772, Burke was instrumental in the passing of the Repeal of Certain Laws Act 1772 which repealed various old laws against dealers and forestallers in corn.[49] In the Annual Register for 1772 (published in July 1773), Burke condemned the partition of Poland. He saw it as "the first very great breach in the modern political system of Europe" and as upsetting the balance of power in Europe.[50] On 3 November 1774, Burke was elected Member for Bristol, at the time "England's second city" with a large constituency in a genuine electoral contest.[51] At the conclusion of the poll, he made his Speech to the Electors of Bristol at the Conclusion of the Poll,[52] a remarkable disclaimer of the constituent-imperative form of democracy, for which he substituted his statement of the "representative mandate" form.[53] He failed to win re-election for that seat in the subsequent 1780 general election. In May 1778, Burke supported a Parliamentary motion revising restrictions on Irish trade. His constituents, citizens of the great trading city of Bristol, urged Burke to oppose free trade with Ireland. Burke resisted their protestations and said: "If, from this conduct, I shall forfeit their suffrages at an ensuing election, it will stand on record an example to future representatives of the Commons of England, that one man at least had dared to resist the desires of his constituents when his judgment assured him they were wrong."[54] Burke published Two Letters to Gentlemen of Bristol on the Bills relative to the Trade of Ireland in which he espoused "some of the chief principles of commerce; such as the advantage of free intercourse between all parts of the same kingdom ... the evils attending restriction and monopoly ... and that the gain of others is not necessarily our loss, but on the contrary an advantage by causing a greater demand for such wares as we have for sale."[55] Burke also supported the attempts of Sir George Savile to repeal some of the penal laws against Catholics.[56] Burke also called capital punishment "the Butchery which we call justice" in 1776 and in 1780 condemned the use of the pillory for two men convicted for attempting to practice sodomy.[36] This support for unpopular causes, notably free trade with Ireland and Catholic emancipation, led to Burke losing his seat in 1780. For the remainder of his Parliamentary career, Burke represented Malton, another pocket borough under the Marquess of Rockingham's patronage. |
国会議員 サー・ジョシュア・レイノルズの文学パーティーにて。[37] 左から右へ:ジェイムズ・ボズウェル、サミュエル・ジョンソン、ジョシュア・レイノルズ、デイヴィッド・ギャリック、エドマンド・バーク、パスクアーレ・ パオリ、チャールズ・バーニー、使用人(おそらくフランシス・バーバー)、トマス・ワートン、オリバー・ゴールドスミス。(画像をクリックして詳細をご覧 ください) 1765年12月、バークはバッキンガムシャーのウェンドーバー選出議員として英国議会下院に入った。ウェンドーバーはファーナガ伯爵(のちの第2代バー ニー伯爵)の贈与によるポケット・バラであり、ロッキングハムの政治的盟友であった。バークが初演説を行った後、ウィリアム・ピット(初代)は「ヨーロッ パ中の口を閉ざすような演説だった」と述べ、下院はこのような議員を得たことを祝うべきだと述べた。 バークが最初に取り組んだ大きな問題は、やがて戦争に発展し、最終的に分離に至ったアメリカ植民地との論争であった。1769年のグレンヴィル派のパンフ レット『国家の現状』への返答として、バークは『国家の最近の状況に関する考察』と題する自身のパンフレットを出版した。フランスの財政を調査したバーク は、「その全体的なシステムに何らかの異常な激変が起こる」と予測した。 同じ年、主に借り入れ金で、バークはビーコンズフィールド近郊の600エーカー(2.4 km2)の土地、グレゴリーズを購入した。この土地にはティツィアーノの絵画などの売却可能な資産も含まれていたが、その後の数十年間、グレゴリーズは経 済的に大きな負担となり、バークは購入価格を全額返済することはできなかった。彼の演説や著作は彼を有名にしたが、それにより、彼がジュニアウスの手紙の 作者ではないかという噂が持ち上がった。 ほぼ同時期に、バークはサミュエル・ジョンソンが中心的な存在であったロンドンの一流知識人や芸術家のサークルに参加した。このサークルには、デイヴィッ ド・ギャリック、オリバー・ゴールドスミス、ジョシュア・レイノルズも参加していた。エドワード・ギボンはバークを「私が知る限り最も雄弁で理性的な狂 人」と評した。[40] ジョンソンはバークの才気溢れる才能を賞賛したが、彼を不誠実な政治家であると見なしていた。[41][42] バークは、国王の行政権限に対する憲法上の制限に関する議論において主導的な役割を果たした。彼は、抑制の効かない王権に強く反対し、君主や政府内の特定 の派閥による濫用を阻止できる原則に基づく野党の役割を主張した。この点に関する彼の最も重要な著作は、1770年4月23日付の『現在の不満の原因につ いての考察』である。[43] バークは「不満」の原因を、彼が「国王の友人」と名付けた新トーリー党グループの「秘密の影響力」に求めている。 その体制は「対外政策と内政を包括するもので、宮廷の専門用語ではダブル・キャビネットと呼ばれるのが一般的である」と述べた。[44] 英国には「利益の誘惑に屈することなく、原則に揺るぎなく固執し、結びつきを重視する」政党が必要であった。政党間の対立は、「それが善きにつけ悪しきに つけ、自由な政治から切り離せないものである」と述べた。[45] 1768年にバークが2万ポンドで購入したグレゴリー家の屋敷 1771年、バークは、可決されれば陪審員に名誉棄損の判断を委ねる権利を与える法案を提出した。バークは法案を支持して演説したが、チャールズ・ジェー ムズ・フォックスを含む一部の議員から反対を受け、法案は成立しなかった。1791年に反対派として自身の法案を提出した際、フォックスは、バークの法案 の文言をほぼそのまま引用し、出典を明記せずに繰り返した。[46] バークは、議会での討論を公表する権利を確保することに尽力した。[47] 1770年11月16日の議会討論で穀物の輸出禁止について語ったバークは、穀物の自由市場を支持する立場から次のように主張した。「奨励するような高い 価格や、落胆させるような安い価格などというものは存在しない。自然な価格、つまり穀物が世界市場でもたらす価格以外にはないのだ」[48] 1772年、バークは穀物のディーラーや先物取引業者に対するさまざまな古い法律を廃止する1772年特定法廃止法の成立に尽力した。[49] 1772年の『年鑑』(1773年7月発行)において、バークはポーランド分割を非難した。彼はこれを「ヨーロッパの近代的政治体制における最初の重大な違反」であり、ヨーロッパの勢力均衡を乱すものだと考えた。 1774年11月3日、当時「イングランド第2の都市」であり、大規模な選挙区を持つ真の選挙戦であったブリストル選出議員に選出された。投票の締めくく りに、彼は「ブリストル有権者への投票締めくくり演説」を行った [52] これは、構成員が不可欠な民主主義の形式を否定するものであり、彼は「代表制」という形式に置き換えた。[53] 彼は、その後の1780年の総選挙では、その議席の再選に失敗した。 1778年5月、バークはアイルランド貿易の制限を改正する議会の動議を支持した。彼の選挙区民である大貿易都市ブリストルの市民たちは、バークにアイル ランドとの自由貿易に反対するよう強く求めた。バークは彼らの抗議に抵抗し、次のように述べた。「もしこの行動により、次の選挙で彼らの票を失うことに なっても、それは、少なくとも一人の男が、彼らの判断が誤りであると確信している場合に、彼らの要望に抵抗する勇気を持っていたという、将来の英国下院議 員への模範として記録されるだろう」[54] バークは『アイルランド貿易に関する法案についてブリストルの紳士たちに宛てた2通の手紙』を出版し、その中で「貿易の主要原則のいくつか、例えば、同一 の王国の各地方間の自由な交流の利点、制限や独占に伴う弊害、他者の利益が必ずしも我々の損失になるとは限らず、むしろ我々の販売する商品の需要が高まる ことで利点となる可能性があること」を支持した。 また、バークはサー・ジョージ・サヴィルのカトリック教徒に対する刑罰法規の一部撤廃の試みも支持した。[56] バークは1776年に死刑を「我々が正義と呼ぶ虐殺」と呼び、1780年には、ソドミー未遂で有罪となった2人の男に対するさらし台の使用を非難した。 [36] この不人気な大義への支持、特にアイルランドとの自由貿易やカトリック教徒解放は、1780年にバークが議席を失う原因となった。その後、議会の議員としてのキャリアの残りの期間、バークはロックリンガム侯爵の支援を受けていた別のポケットボロであるモルトンを代表した。 |
| American War of Independence Burke expressed his support for the grievances of the American Thirteen Colonies under the government of King George III and his appointed representatives. On 19 April 1774, Burke made a speech, "On American Taxation" (published in January 1775), on a motion to repeal the tea duty: Again and again, revert to your old principles—seek peace and ensue it; leave America, if she has taxable matter in her, to tax herself. I am not here going into the distinctions of rights, nor attempting to mark their boundaries. I do not enter into these metaphysical distinctions; I hate the very sound of them. Leave the Americans as they anciently stood, and these distinctions, born of our unhappy contest, will die along with it …. Be content to bind America by laws of trade; you have always done it …. Do not burthen them with taxes…. But if intemperately, unwisely, fatally, you sophisticate and poison the very source of government by urging subtle deductions, and consequences odious to those you govern, from the unlimited and illimitable nature of supreme sovereignty, you will teach them by these means to call that sovereignty itself in question …. If that sovereignty and their freedom cannot be reconciled, which will they take? They will cast your sovereignty in your face. No body of men will be argued into slavery.[57] On 22 March 1775, Burke delivered in the House of Commons a speech (published in May 1775) on reconciliation with America. Burke appealed for peace as preferable to civil war and reminded the House of Commons of America's growing population, its industry and its wealth. He warned against the notion that the Americans would back down in the face of force since most Americans were of British descent: [T]he people of the colonies are descendants of Englishmen.... They are therefore not only devoted to liberty, but to liberty according to English ideas and on English principles. The people are Protestants ... a persuasion not only favourable to liberty, but built upon it .... My hold of the colonies is in the close affection which grows from common names, from kindred blood, from similar privileges, and equal protection. These are ties which, though light as air, are as strong as links of iron. Let the colonies always keep the idea of their civil rights associated with your government—they will cling and grapple to you, and no force under heaven will be of power to tear them from their allegiance. But let it be once understood that your government may be one thing and their privileges another, that these two things may exist without any mutual relation—the cement is gone, the cohesion is loosened, and everything hastens to decay and dissolution. As long as you have the wisdom to keep the sovereign authority of this country as the sanctuary of liberty, the sacred temple consecrated to our common faith, wherever the chosen race and sons of England worship freedom, they will turn their faces towards you. The more they multiply, the more friends you will have; the more ardently they love liberty, the more perfect will be their obedience. Slavery they can have anywhere. It is a weed that grows in every soil. They may have it from Spain, they may have it from Prussia. But, until you become lost to all feeling of your true interest and your natural dignity, freedom they can have from none but you.[58] Burke prized peace with America above all else, pleading with the House of Commons to remember that the interest by way of money received from the American colonies was far more attractive than any sense of putting the colonists in their place: The proposition is peace. Not peace through the medium of war, not peace to be hunted through the labyrinth of intricate and endless negotiations, not peace to arise out of universal discord ... [I]t is simple peace, sought in its natural course and in its ordinary haunts. It is peace sought in the spirit of peace, and laid in principles purely pacific.[58] Burke was not merely presenting a peace agreement to Parliament, but rather he stepped forward with four reasons against using force, carefully reasoned. He laid out his objections in an orderly manner, focusing on one before moving to the next. His first concern was that the use of force would have to be temporary and that the uprisings and objections to British governance in Colonial America would not be. Second, Burke worried about the uncertainty surrounding whether Britain would win a conflict in America. "An armament," Burke said, "is not a victory."[59] Third, Burke brought up the issue of impairment, stating that it would do the British government no good to engage in a scorched earth war and have the object they desired (America) become damaged or even useless. The American colonists could always retreat into the mountains, but the land they left behind would most likely be unusable, whether by accident or design. The fourth and final reason to avoid the use of force was experience, as the British had never attempted to rein in an unruly colony by force and they did not know if it could be done, let alone accomplished thousands of miles away from home.[59] Not only were all of these concerns reasonable, but some turned out to be prophetic—the American colonists did not surrender, even when things looked extremely bleak and the British were ultimately unsuccessful in their attempts to win a war fought on American soil. It was not temporary force, uncertainty, impairment, or even experience that Burke cited as the primary reason for avoiding war with the American colonies. Rather, it was the character of the American people themselves: "In this character of Americans, a love of freedom is the predominating feature which marks and distinguishes the whole ... [T]his fierce spirit of liberty is stronger in the English colonies, probably, than in any other people of the earth ... [The] men [are] acute, inquisitive, dextrous, prompt in attack, ready in defence, full of resources."[59] Burke concludes with another plea for peace and a prayer that Britain might avoid actions which in Burke's words "may bring on the destruction of this Empire."[59] Burke proposed six resolutions to settle the American conflict peacefully: Allow the American colonists to elect their own representatives, settling the dispute about taxation without representation. Acknowledge this wrongdoing and apologise for grievances caused. Procure an efficient manner of choosing and sending these delegates. Set up a General Assembly in America itself, with powers to regulate taxes. Stop gathering taxes by imposition (or law) and start gathering them only when they are needed. Grant needed aid to the colonies.[59] Had they been passed, though the effect of these resolutions can never be known, they might have quelled the colonials' revolutionary spirit. Unfortunately, Burke delivered this speech less than a month before the explosive conflict at Concord and Lexington.[60] As these resolutions were not enacted, little was done that would help to prevent armed conflict. Among the reasons this speech was so greatly admired was its passage on Lord Bathurst (1684–1775) in which Burke describes an angel in 1704 prophesying to Bathurst the future greatness of England and also of America: "Young man, There is America—which at this day serves little more than to amuse you with stories of savage men, and uncouth manners; yet shall, before you taste of death, shew itself equal to the whole of that commerce which now attracts the envy of the world."[61] Samuel Johnson was so irritated at hearing it continually praised that he made a parody of it, where the devil appears to a young Whig and predicts that in a short time Whiggism will poison even the paradise of America.[61] The administration of Lord North (1770–1782) tried to defeat the colonist rebellion by military force. British and American forces clashed in 1775 and in 1776 came the United States Declaration of Independence. Burke was appalled by celebrations in Britain of the defeat of the Americans in New York and Pennsylvania. He claimed the English national character was being changed by this authoritarianism.[36] Burke wrote: "As to the good people of England, they seem to partake every day more and more of the Character of that administration which they have been induced to tolerate. I am satisfied, that within a few years there has been a great Change in the National Character. We seem no longer that eager, inquisitive, jealous, fiery people, which we have been formerly."[62] In Burke's view, the British government was fighting "the American English" ("our English Brethren in the Colonies"), with a Germanic king employing "the hireling sword of German boors and vassals" to destroy the English liberties of the colonists.[36] On American independence, Burke wrote: "I do not know how to wish success to those whose Victory is to separate from us a large and noble part of our Empire. Still less do I wish success to injustice, oppression and absurdity."[63] During the Gordon Riots in 1780, Burke became a target of hostility and his home was placed under armed guard by the military.[64] |
アメリカ独立戦争 バークは、ジョージ3世国王とその任命した代表者による統治下にあったアメリカ13植民地の不満に対する支持を表明した。1774年4月19日、バークは茶税廃止の動議に関して「アメリカ課税について」(1775年1月出版)という演説を行った。 繰り返しになるが、昔の原則に戻ろう。平和を求め、それを実現しよう。アメリカに課税すべき対象があるのなら、アメリカ自身に課税させるべきだ。私はここ で権利の区別について論じたり、その境界線を定めようとしているわけではない。私はこうした形而上学的な区別には立ち入らない。私はその響きを聞くだけで 嫌になる。アメリカ人を昔のままの状態にしておき、不幸な争いから生まれたこうした区別も、それとともに消え去るだろう…。貿易の法によってアメリカを束 縛することに満足せよ。 あなた方は常にそれをやってきたではないか。 彼らに税を課してはならない。 しかし、無分別で、賢明でなく、致命的に、微妙な控除を推奨し、最高主権の無限かつ無制限の性質から、統治される人々にとって不快な結果を導くことで、政 府のまさに源を巧妙に操作し、毒するならば、あなた方はその手段によって、彼らにその主権自体を疑問視することを教えることになるだろう。もしその主権と 彼らの自由が両立できないのであれば、彼らはどちらを選ぶだろうか?彼らは主権を君の顔に投げつけるだろう。議論によって奴隷となる人間はいない。 [57] 1775年3月22日、バークはアメリカとの和解に関する演説(1775年5月発表)を庶民院で行った。バークは内戦よりも平和を望むべきだと訴え、アメ リカ人口の増加、その産業、富について庶民院に思い出させた。そして、ほとんどのアメリカ人がイギリス系であることから、武力に屈するだろうという考えに 警告を発した。 「植民地の住民は英国人の子孫である。彼らは自由を愛するだけでなく、英国の理念と原則に基づく自由を愛している。住民はプロテスタントであり、自由を愛 するだけでなく、自由を基盤とする信念を持っている。私が植民地を掌握しているのは、共通の名前、血縁、類似した特権、平等な保護から育まれる親密な愛情 によるものである。これらは空気のように軽いが、鉄の鎖のように強固な絆である。植民地の人々が、市民としての権利の概念を常に貴国の政府と結びつけてお くようにさせよう。そうすれば、彼らは貴国に固執し、しがみつき、天の下のいかなる力も彼らの忠誠心を引き裂くことはできないだろう。しかし、政府と特権 は別物であることを一度理解させ、この2つのものが相互に関係なく存在できることを理解させなければならない。そうすれば、結合は失われ、結束は緩み、す べてが崩壊と分裂へと向かっていく。この国の主権を自由の聖域、私たちの共通の信仰に捧げられた神聖な神殿として維持する知恵がある限り、選ばれた民族で あり、イングランドの息子である彼らが自由を崇拝する場所はどこであろうと、彼らはあなた方に顔を向けるだろう。彼らが増えれば増えるほど、あなたの友人 は増えるだろう。彼らが自由を熱烈に愛するほど、彼らの服従はより完璧なものとなるだろう。奴隷制はどこにでも存在する。それはあらゆる土壌で育つ雑草の ようなものだ。スペインからでも、プロイセンからでも、彼らは奴隷制を手に入れることができるだろう。しかし、あなたが真の利益と自然の尊厳に対する感覚 をすべて失うまでは、奴隷制はあなた以外からは手に入らないだろう。 バークはアメリカとの平和を何よりも重視し、アメリカ植民地から受け取る金銭による利益は、植民地の人々を従属させることよりもはるかに魅力的であることを忘れないよう庶民院に訴えた。 その提案とは平和である。戦争を媒介とした平和ではなく、複雑で果てしない交渉の迷路をさまよう平和でもなく、普遍的な不和から生じる平和でもない。それ は、自然な流れの中で、通常の場所で求められる単純な平和である。平和の精神に基づいて求められ、純粋に平和的な原則に根ざした平和である。[58] バークは単に議会に和平案を提示しただけではなく、武力行使に反対する4つの理由を慎重に論理立てて提示した。彼は、1つの理由に焦点を当ててから次の理 由に移るというように、順序立てて反対意見を提示した。彼の最初の懸念は、武力行使は一時的なものでなければならないということ、そして、植民地アメリカ の反乱や英国統治への反対は一時的なものであってはならないということだった。第二に、バークはイギリスがアメリカでの紛争に勝利できるかどうかという不 確実性について懸念を示した。「軍備は勝利ではない」とバークは述べた。[59] 第三に、バークは損害の問題を取り上げ、焦土戦を展開して、目的の対象(アメリカ)が損害を受けたり、あるいは使用できなくなることは、イギリス政府に とって何の利益にもならないと述べた。アメリカ植民地の人々はいつでも山中に退却できるが、彼らが去った土地は、それが意図的なものであれ偶発的なもので あれ、おそらくは使用不可能になるだろう。武力行使を避けるべき4つ目の理由、そして最後の理由は経験であり、英国はこれまで手に負えない植民地を武力で 制圧しようとしたことはなく、それが可能かどうか、ましてや数千マイル離れた場所でそれが達成できるかどうかは分からなかった。 9] これらの懸念はすべて妥当なものであったばかりでなく、そのうちのいくつかは予言的なものとなった。アメリカ植民地の人々は、状況が極めて絶望的になった 後も降伏せず、イギリスは最終的にアメリカ本土での戦争に勝利することはできなかった。 バークがアメリカ植民地との戦争回避の主な理由として挙げたのは、一時的な力や不確実性、障害、あるいは経験ではなかった。そうではなく、それはアメリカ の人々そのものの性格であった。「アメリカ人の性格において、自由を愛する心が最も際立った特徴であり、全体を特徴づけている... この自由への激しい精神は、おそらく地球上のどの民族よりも、英国の植民地においてより強い。... [彼らは] 鋭敏で、好奇心旺盛で、器用で、攻撃は素早く、防御は万全で、あらゆる手段を講じることができる。」[59] バークは、平和を求めるもう一つの訴えと、バークの言葉によれば「この帝国の滅亡を招くかもしれない」行動を英国が避けることを祈る言葉で結んでいる。 [59] バークは、アメリカとの紛争を平和的に解決するための6つの決議を提案した。 アメリカ植民地住民に自分たちの代表を選出させ、代表なき課税に関する紛争を解決する。 この不正行為を認め、苦情に対して謝罪する。 これらの代表を選出し、派遣するための効率的な方法を確保する。 課税を規制する権限を持つ、アメリカ国内での総会を設置する。 課税(または法律)による徴税を中止し、必要な場合にのみ徴税を行う。 植民地に必要な支援を行うこと。[59] これらの決議案が可決されていたら、その効果は決して知られることはなかっただろうが、植民地の革命精神を鎮めることができたかもしれない。しかし、残念 ながら、バークがこの演説を行ったのは、コンコードとレキシントンでの爆発的な衝突の1か月足らず前であった。[60] これらの決議案は可決されなかったため、武力衝突を防ぐための措置はほとんど講じられなかった。 この演説がこれほどまでに賞賛された理由のひとつに、バースルート卿(1684年~1775年)に関するくだりがある。この中で、バークは1704年に天 使がバースルート卿にイングランドとアメリカの将来の偉大さを予言したと描写している。「若者よ、アメリカがある。今日では野蛮人の物語や粗野な風習であ なたを楽しませる程度の存在にすぎないが 。しかし、汝が死を経験する前に、今や世界の羨望を集めるその貿易全体に匹敵する国となるだろう」[61] サミュエル・ジョンソンは、その絶え間なく賞賛されるのを聞いて苛立ち、悪魔が若いホイッグ党員に現れ、ホイッグ主義が間もなくアメリカの楽園さえも毒す るだろうと予言するパロディを作った。 ノース卿の政権(1770年~1782年)は、植民地の反乱を武力で鎮圧しようとした。1775年に英米両国の軍が衝突し、1776年にはアメリカ合衆国 の独立宣言が発表された。バークは、ニューヨークやペンシルベニアにおけるアメリカ人の敗北を祝う英国での騒ぎに愕然とした。彼は、この権威主義によって 英国人の国民性が変化しつつあると主張した。[36] バークは次のように書いている。「善良な英国人たちは、自分たちが容認するように仕向けられてきたあの政権の性格を、日々ますます帯びてきているように見 える。私は、数年のうちに国民性が大きく変化したと確信している。私たちはもはや、かつてのあの熱心で、好奇心旺盛で、嫉妬深く、激情的な国民ではない」 [62] バークの見解では、英国政府は「アメリカ英語」(「植民地における我々の英語を話す同胞」)と戦っており、ゲルマン人の王が「ドイツの無骨者や家臣の雇わ れ剣」を用いて、植民地の英国人の自由を破壊しようとしているというのだ。[36] アメリカ独立に関して、バークは次のように書いている。「我々の帝国から大きな、そして高貴な部分を切り離すことが勝利である人々に対して、私はどう成功 を祈ればよいのかわからない。ましてや、不正や弾圧、不条理に成功を祈るつもりはない」と述べた。[63] 1780年のゴードン暴動の際、バークは敵意の的となり、自宅は軍隊によって武装警備された。[64] |
| Paymaster of the Forces In Cincinnatus in Retirement (1782), James Gillray caricatured Burke's support of rights for Catholics. The fall of North led to Rockingham being recalled to power in March 1782. Burke was appointed Paymaster of the Forces and a Privy Counsellor, but without a seat in Cabinet. Rockingham's unexpected death in July 1782 and replacement with Shelburne as Prime Minister put an end to his administration after only a few months, but Burke did manage to introduce two Acts. The Paymaster General Act 1782 ended the post as a lucrative sinecure. Previously, Paymasters had been able to draw on money from HM Treasury at their discretion. Instead, now they were required to put the money they had requested to withdraw from the Treasury into the Bank of England, from where it was to be withdrawn for specific purposes. The Treasury would receive monthly statements of the Paymaster's balance at the Bank. This Act was repealed by Shelburne's administration, but the Act that replaced it repeated verbatim almost the whole text of the Burke Act.[65] The Civil List and Secret Service Money Act 1782 was a watered-down version of Burke's original intentions as outlined in his famous Speech on Economical Reform of 11 February 1780. However, he managed to abolish 134 offices in the royal household and civil administration.[66] The third Secretary of State and the Board of Trade were abolished and pensions were limited and regulated. The Act was anticipated to save £72,368 a year.[67] In February 1783, Burke resumed the post of Paymaster of the Forces when Shelburne's government fell and was replaced by a coalition headed by North that included Charles James Fox. That coalition fell in 1783 and was succeeded by the long Tory administration of William Pitt the Younger which lasted until 1801. Accordingly, having supported Fox and North, Burke was in opposition for the remainder of his political life. |
軍の会計責任者 引退後のシンシナティウス(1782年)において、ジェームズ・ギレーは、カトリックの権利を支持するバークを風刺した。 ノースの失脚により、1782年3月、ロッキンガムが政権に復帰した。 バークは陸軍主計官および枢密顧問官に任命されたが、閣僚の地位は与えられなかった。 1782年7月、ロッキンガムが予期せず死去し、首相がシェルバーンに交代したため、彼の政権は数ヶ月で終焉を迎えたが、バークは2つの法案を成立させる ことに成功した。 1782年の会計官法は、高給の楽なポストを廃止するものであった。それまでは、会計官は自身の裁量で英国国庫から資金を引き出すことができた。しかし、 今後は国庫から引き出すよう申請した資金をイングランド銀行に入金し、そこから特定の目的のために引き出すことが義務付けられた。国庫は、銀行における会 計官の残高を毎月報告書で受け取ることになった。この法律はシェルバーン政権によって廃止されたが、それに代わる法律はバーク法のほぼ全文をそのまま繰り 返した。 1782年の「内廷費および秘密費法」は、1780年2月11日の有名な「経済改革に関する演説」でバークが示した当初の意図を弱めたものだった。しか し、彼は王室および行政機関の134の役職を廃止することに成功した。[66] 第3代国務大臣および貿易委員会は廃止され、年金は制限され、規制された。この法律により、年間72,368ポンドの節約が見込まれた。[67] 1783年2月、バークはシェルバーン内閣が倒れ、チャールズ・ジェームズ・フォックスを含むノース率いる連立政権が誕生すると、軍事費支払責任者の職務 に復帰した。この連立政権は1783年に崩壊し、1801年まで続いたウィリアム・ピット・ザ・ヤンガー率いる長きにわたるトーリー党の政権に取って代わ られた。それゆえ、フォックスとノースを支持したバークは、その後の政治生命のすべてを野党で過ごすこととなった。 |
| Representative government In 1774, Burke's Speech to the Electors at Bristol at the Conclusion of the Poll was noted for its defence of the principles of representative government against the notion that those elected to assemblies like Parliament are, or should be, merely delegates: Certainly, Gentlemen, it ought to be the happiness and glory of a Representative, to live in the strictest union, the closest correspondence, and the most unreserved communication with his constituents. Their wishes ought to have great weight with him; their opinion, high respect; their business, unremitted attention. It is his duty to sacrifice his repose, his pleasures, his satisfactions, to theirs; and above all, ever, and in all cases, to prefer their interest to his own. But his unbiassed opinion, his mature judgment, his enlightened conscience, he ought not to sacrifice to you, to any man, or to any sett of men living. These he does not derive from your pleasure; no, nor from the Law and the Constitution. They are a trust from Providence, for the abuse of which he is deeply answerable. Your Representative owes you, not his industry only, but his judgment; and he betrays, instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion. My worthy Colleague says, his Will ought to be subservient to yours. If that be all, the thing is innocent. If Government were a matter of Will upon any side, yours, without question, ought to be superior. But Government and Legislation are matters of reason and judgement, and not of inclination; and, what sort of reason is that, in which the determination precedes the discussion; in which one sett of men deliberate, and another decide; and where those who form the conclusion are perhaps three hundred miles distant from those who hear the arguments? To deliver an opinion is the right of all men; that of constituents is a weighty and respectable opinion which a Representative ought always to rejoice to hear; and which he ought always most seriously to consider. But authoritative instructions; mandates issued, which the member is bound blindly and implicitly to obey, to vote, and to argue for, though contrary to the clearest conviction of his judgment and conscience; these are things utterly unknown to the laws of this land, and which arise from a fundamental mistake of the whole order and tenour of our constitution. Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates; but Parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole; where, not local purposes, not local prejudices ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole. You choose a member, indeed; but when you have chosen him, he is not a member of Bristol, but he is a member of Parliament.[68][69] It is often forgotten in this connection[citation needed] that Burke, as detailed below, was an opponent of slavery, and therefore his conscience was refusing to support a trade in which many of his Bristol electors were lucratively involved. Political scientist Hanna Pitkin points out that Burke linked the interest of the district with the proper behaviour of its elected official, explaining: "Burke conceives of broad, relatively fixed interest, few in number and clearly defined, of which any group or locality has just one. These interests are largely economic or associated with particular localities whose livelihood they characterize, in his over-all prosperity they involve".[70] Burke was a leading sceptic with respect to democracy. While admitting that theoretically in some cases it might be desirable, he insisted a democratic government in Britain in his day would not only be inept, but also oppressive. He opposed democracy for three basic reasons. First, government required a degree of intelligence and breadth of knowledge of the sort that occurred rarely among the common people. Second, he thought that if they had the vote, common people had dangerous and angry passions that could be aroused easily by demagogues, fearing that the authoritarian impulses that could be empowered by these passions would undermine cherished traditions and established religion, leading to violence and confiscation of property. Third, Burke warned that democracy would create a tyranny over unpopular minorities, who needed the protection of the upper classes.[71] |
代表制政府 1774年、バークがブリストルで行った選挙人への演説は、議会のような集会に選出された者は、あるいは選出されるべき者は、単なる代議士であるという考えに対して、代表制政府の原則を擁護した演説として注目された。 確かに、諸君、代議士にとっての幸福と栄光は、有権者と緊密な連携、密接な連絡、そして何よりも遠慮のないコミュニケーションを保つことであるべきだ。彼 らの願いは彼にとって大きな意味を持つべきであり、彼らの意見は最大限の敬意を持って扱われるべきであり、彼らの業務には絶え間ない注意が払われるべきで ある。彼にとって安らぎや楽しみ、満足を犠牲にすることは当然の義務であり、何よりも、常に、あらゆる状況において、彼自身の利益よりも彼らの利益を優先 させるべきである。しかし、彼の中立的な意見、熟考した上での判断、啓蒙された良心は、あなた方や、特定の個人、あるいは特定の集団のために犠牲にすべき ではない。これらは、君の歓心を買おうとして得るものではない。いや、法律や憲法から得るものでもない。これらは神の摂理から託されたものであり、それを 悪用すれば、彼は深く責任を問われることになる。君の代表者は君に、自分の勤勉さだけでなく、自分の判断力を負っている。そして、もし彼が君の意見に判断 力を犠牲にすれば、君に奉仕するどころか、君を裏切ることになる。 私の尊敬する同僚は、自分の意志は君の意志に従属すべきだと言っている。もしそれがすべてであるならば、それは無害である。もし政府がいずれかの側の意志 の問題であるならば、疑いなく、あなたの意志が優先されるべきである。しかし、政府と立法は理性と判断の問題であり、気まぐれの問題ではない。議論に先 立って決定がなされ、ある集団が熟考し、別の集団が決定する。そして、結論を導く人々は、議論を聞く人々から300マイルも離れた場所にいるかもしれな い。 意見を述べることはすべての人の権利である。有権者の意見は重みがあり、尊重されるべき意見であり、代議士は常にそれを喜んで聞くべきであり、また常に真 剣に考慮すべきである。しかし、権威ある指示、すなわち、議員が盲目的かつ無条件に従うことを義務付ける命令、投票、そして、議員が自身の判断と良心の最 も明確な確信に反してでも主張すべきであるという命令は、この国の法律ではまったく知られていないものであり、憲法の秩序と存続に関する根本的な誤りから 生じるものである。 議会は、異なる利害関係を持つ国々の大使が集まる会議ではない。各利害関係者は、代理人や擁護者として、他の代理人や擁護者と対峙し、それぞれの利害関係 を維持しなければならない。しかし、議会は、一つの国民が一つの利害関係を持つ、一つの国民の審議機関である。そこでは、地域的な目的や偏見ではなく、全 体的な理性から生じる全体的な利益が導くべきである。確かに議員を選ぶのはあなた方だが、彼を選んだ時点で、彼はブリストルの議員ではなく、議会の議員と なるのだ。[68][69] この点に関して、しばしば忘れられていることだが(要出典)、以下に詳述するように、バークは奴隷制度の反対者であり、そのため、ブリストルの有権者の多くが利益を得ていた貿易を支持することを、彼の良心が拒んでいた。 政治学者ハンナ・ピトキンは、バークが選挙区の利益と選出された役人の適切な行動を関連付けていると指摘し、次のように説明している。「バークは、数が少 なく明確に定義された広範な利益を想定しており、どのグループや地域にも1つだけ存在する。これらの利益は主に経済的なものであり、特定の地域と関連して おり、その地域社会の生活を特徴づけ、その繁栄に影響を与えるものである」[70]。 バークは民主主義に対して懐疑的な考えを持つ第一人者であった。 理論的には、場合によっては望ましいかもしれないと認める一方で、当時の英国における民主主義政府は無能であるばかりか、抑圧的であると主張した。 彼は民主主義に反対する基本的な理由を3つ挙げていた。 まず、政府には一般市民にはほとんど見られない程度の知性と幅広い知識が必要である。第二に、彼は、もし一般市民に選挙権が与えられた場合、扇動家によっ て容易に扇動されてしまう危険で激しい情熱を彼らは持ち、その情熱によって権威主義的な衝動が強まり、大切にされてきた伝統や確立された宗教が損なわれ、 暴力や財産の没収につながることを懸念していた。第三に、バークは、民主主義は上流階級の保護を必要とする不人気の少数派に対する専制を生み出すと警告し た。[71] |
| Opposition to the slave trade Burke proposed a bill to ban slaveholders from being able to sit in the House of Commons, claiming they were a danger incompatible with traditional notions of British liberty.[72] He described slavery as a "weed that grows on every soil.[73] While Burke did believe that Africans were "barbaric" and needed to be "civilised" by Christianity, Gregory Collins argues that this was not an unusual attitude amongst abolitionists at the time. Furthermore, Burke seemed to believe that Christianity would provide a civilising benefit to any group of people, as he believed Christianity had "tamed" European civilisation and regarded Southern European peoples as equally savage and barbarous. Collins also suggests that Burke viewed the "uncivilised" behaviour of African slaves as being partially caused by slavery itself, as he believed that making someone a slave stripped them of any virtues and rendered them mentally deficient, regardless of race. Burke proposed a gradual program of emancipation called Sketch of a Negro Code,[74] which Collins argues was quite detailed for the time. Collins concludes that Burke's "gradualist" position on the emancipation of slaves, while perhaps seeming ridiculous to some modern-day readers, was nonetheless sincere.[75] |
奴隷貿易への反対 バークは、奴隷所有者は英国の伝統的な自由概念と相容れない危険な存在であるとして、奴隷所有者が庶民院で議席を持つことを禁止する法案を提出した。 [72] 彼は奴隷制度を「あらゆる土壌で育つ雑草」と表現した。[73] バークはアフリカ人が「野蛮」であり、キリスト教によって「文明化」される必要があると信じていたが、グレゴリー・コリンズは、これは当時の奴隷制度廃止 論者たちの間では珍しい態度ではなかったと主張している。さらに、バークはキリスト教がヨーロッパ文明を「飼い慣らした」と信じており、南ヨーロッパの人 々を同様に野蛮で残忍であると考えていたため、キリスト教はあらゆる人々に対して文明化の恩恵をもたらすと考えたようである。コリンズは、バークがアフリ カ人奴隷の「未開」な行動は奴隷制度そのものに一部起因すると考えていたと示唆している。バークは、奴隷にすることは人種に関係なく、あらゆる美徳を奪 い、精神的に欠陥のある人間にするものだと考えていた。バークは『黒人法典』という題の緩やかな解放計画を提案した。コリンズは、この計画は当時としては 非常に詳細であったと主張している。コリンズは、奴隷解放に関するバークの「漸進主義」の立場は、現代の読者には滑稽に思えるかもしれないが、それでも誠 実なものであったと結論づけている。 |
| India and the impeachment of Warren Hastings Main article: Impeachment of Warren Hastings For years, Burke pursued impeachment efforts against Warren Hastings, formerly Governor-General of Bengal, that resulted in the trial during 1786. His interaction with the British dominion of India began well before Hastings' impeachment trial. For two decades prior to the impeachment, Parliament had dealt with the Indian issue. This trial was the pinnacle of years of unrest and deliberation.[76] In 1781, Burke was first able to delve into the issues surrounding the East India Company when he was appointed Chairman of the Commons Select Committee on East Indian Affairs—from that point until the end of the trial, India was Burke's primary concern. This committee was charged "to investigate alleged injustices in Bengal, the war with Hyder Ali, and other Indian difficulties".[77] While Burke and the committee focused their attention on these matters, a second secret committee was formed to assess the same issues. Both committee reports were written by Burke. Among other purposes, the reports conveyed to the Indian princes that Britain would not wage war on them, along with demanding that the East India Company should recall Hastings. This was Burke's first call for substantive change regarding imperial practices. When addressing the whole House of Commons regarding the committee report, Burke described the Indian issue as one that "began 'in commerce' but 'ended in empire'".[78] On 28 February 1785, Burke delivered a now-famous speech, The Nabob of Arcot's Debts, wherein he condemned the damage to India by the East India Company. In the province of the Carnatic, the Indians had constructed a system of reservoirs to make the soil fertile in a naturally dry region, and centred their society on the husbandry of water: These are the monuments of real kings, who were the fathers of their people; testators to a posterity which they embraced as their own. These are the grand sepulchres built by ambition; but by the ambition of an insatiable benevolence, which, not contented with reigning in the dispensation of happiness during the contracted term of human life, had strained, with all the reachings and graspings of a vivacious mind, to extend the dominion of their bounty beyond the limits of nature, and to perpetuate themselves through generations of generations, the guardians, the protectors, the nourishers of mankind.[79] Burke claimed that the advent of East India Company domination in India had eroded much that was good in these traditions and that as a consequence of this and the lack of new customs to replace them the Indian populace under Company rule was needlessly suffering. He set about establishing a set of imperial expectations, whose moral foundation would in his opinion warrant an overseas empire.[80] On 4 April 1786, Burke presented the House of Commons with the Article of Charge of High Crimes and Misdemeanors against Hastings. The impeachment in Westminster Hall which did not begin until 14 February 1788 would be the "first major public discursive event of its kind in England",[81]: 589 bringing the morality of imperialism to the forefront of public perception. Burke was already known for his eloquent rhetorical skills and his involvement in the trial only enhanced its popularity and significance.[81]: 590 Burke's indictment, fuelled by emotional indignation, branded Hastings a "captain-general of iniquity" who never dined without "creating a famine", whose heart was "gangrened to the core" and who resembled both a "spider of Hell" and a "ravenous vulture devouring the carcasses of the dead".[82] The House of Commons eventually impeached Hastings, but subsequently the House of Lords acquitted him of all charges.[81][83] |
インドとウォーレン・ヘイストンの弾劾 詳細は「ウォーレン・ヘイストンの弾劾」を参照 長年にわたり、バークはベンガル州総督であったウォーレン・ヘイストンの弾劾を追求し、1786年に裁判が行われた。 ヘイストンの弾劾裁判よりもずっと以前から、バークはインドの英国領との関わりを持っていた。 弾劾裁判の20年前から、議会はインド問題を扱っていた。この裁判は、長年にわたる不安と審議の頂点であった。[76] 1781年、バークは東インド会社をめぐる問題を初めて掘り下げる機会を得た。下院の東インド問題特別委員会の委員長に任命されたのだ。この時点から裁判 が終わるまで、バークの最大の関心事はインドであった。この委員会は、「ベンガルにおける不正疑惑、ハイダー・アリーとの戦争、その他のインドにおける問 題」を調査するよう命じられていた。[77] バークと委員会がこれらの問題に注目している間、同じ問題を評価する第2の秘密委員会が結成された。両委員会の報告書はバークが執筆した。この報告書は、 インド諸侯に対して、英国は彼らに戦争を仕掛けるつもりはないことを伝えるとともに、東インド会社にヘイスティングスを本国に召還するよう要求するもので あった。これは、帝国の慣行に関する実質的な改革をバークが初めて求めたものであった。委員会の報告書について下院全体会議で演説した際、バークはインド 問題を「『商業』から始まり、『帝国』で終わる」ものだと表現した。 1785年2月28日、バークは現在では有名な演説「アーコットの太守の負債」を行い、そこで彼は東インド会社によるインドへの損害を非難した。カルナー タカ地方では、インド人は自然に乾燥した地域で土壌を肥沃にするため、貯水池のシステムを構築し、水の管理を社会の中心に据えていた。 これらは真の王の記念碑であり、民の父である。彼らは、自分たちの子孫を我が子として受け入れた。これらは、野望によって建てられた壮大な墓である。しか し、その野望は、飽くことのない博愛の心によるものであり、人間の限られた人生の中で幸福を分配する統治に満足せず、 活気あふれる精神のあらゆる可能性とあらゆる欲求を駆使して、自然の限界を超えてその恩恵の支配を拡大し、何世代にもわたって自分たち自身を永続させ、人 類の守護者、保護者、養育者となることを目指したのだ。 バークは、インドにおける東インド会社の支配の出現により、これらの伝統の多くの良い部分が損なわれたと主張し、その結果、それに代わる新しい習慣が生ま れなかったため、会社支配下のインド国民は不必要に苦しんでいると述べた。彼は、道徳的基盤が海外帝国を正当化するという一連の帝国の期待を確立しようと した。 1786年4月4日、バークは庶民院にヘイスティングスに対する重罪および軽犯罪に関する告発状を提出した。 1788年2月14日まで開始されなかったウェストミンスター・ホールでの弾劾裁判は、「英国で初めてのこの種の主要な公開討論イベント」となり [81]:589、帝国主義の道徳性を人々の認識の最前面に押し出した。バークはすでに雄弁な修辞家として知られていたが、この裁判への関与によってその 人気と重要性はさらに高まった。[81]: 590 バークの告発は、感情的な憤りに駆られたもので、ヘイスティングスを「飢饉を招かずに食事をしたことがない」「悪の総帥」と断罪し、その心は「 中心部まで腐敗しており」、まるで「地獄の蜘蛛」や「死骸を食い荒らすハゲタカ」のようだと非難した。[82] 最終的に庶民院はヘイスティングスを弾劾したが、その後、貴族院はすべての罪状について彼を無罪とした。[81][83] |
| French Revolution: 1688 versus 1789 Further information: Reflections on the Revolution in France Smelling out a Rat;—or—The Atheistical-Revolutionist disturbed in his Midnight "Calculations" (1790) by Gillray, depicting a caricature of Burke holding a crown and a cross while the seated man Richard Price is writing "On the Benefits of Anarchy Regicide Atheism" beneath a picture of the execution of Charles I of England Reflections on the Revolution in France, And on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris. By the Right Honourable Edmund Burke. Initially, Burke did not condemn the French Revolution. In a letter of 9 August 1789, he wrote: "England gazing with astonishment at a French struggle for Liberty and not knowing whether to blame or to applaud! The thing indeed, though I thought I saw something like it in progress for several years, has still something in it paradoxical and Mysterious. The spirit it is impossible not to admire; but the old Parisian ferocity has broken out in a shocking manner".[84] The events of 5–6 October 1789, when a crowd of Parisian women marched on Versailles to compel King Louis XVI to return to Paris, turned Burke against it. In a letter to his son Richard Burke dated 10 October, he said: "This day I heard from Laurence who has sent me papers confirming the portentous state of France—where the Elements which compose Human Society seem all to be dissolved, and a world of Monsters to be produced in the place of it—where Mirabeau presides as the Grand Anarch; and the late Grand Monarch makes a figure as ridiculous as pitiable".[85] On 4 November, Charles-Jean-François Depont wrote to Burke, requesting that he endorse the Revolution. Burke replied that any critical language of it by him should be taken "as no more than the expression of doubt", but he added: "You may have subverted Monarchy, but not recover'd freedom".[86] In the same month, he described France as "a country undone". Burke's first public condemnation of the Revolution occurred during the debate in Parliament on the army estimates on 9 February 1790 provoked by praise of the Revolution by Pitt and Fox: Since the House had been prorogued in the summer much work was done in France. The French had shewn themselves the ablest architects of ruin that had hitherto existed in the world. In that very short space of time they had completely pulled down to the ground, their monarchy; their church; their nobility; their law; their revenue; their army; their navy; their commerce; their arts; and their manufactures...[There was a danger of] an imitation of the excesses of an irrational, unprincipled, proscribing, confiscating, plundering, ferocious, bloody and tyrannical democracy...[In religion] the danger of their example is no longer from intolerance, but from Atheism; a foul, unnatural vice, foe to all the dignity and consolation of mankind; which seems in France, for a long time, to have been embodied into a faction, accredited, and almost avowed.[87] In January 1790, Burke read Richard Price's sermon of 4 November 1789 entitled A Discourse on the Love of Our Country to the Revolution Society.[88] That society had been founded to commemorate the Glorious Revolution of 1688. In this sermon, Price espoused the philosophy of universal "Rights of Men". Price argued that love of our country "does not imply any conviction of the superior value of it to other countries, or any particular preference of its laws and constitution of government".[89] Instead, Price asserted that Englishmen should see themselves "more as citizens of the world than as members of any particular community". A debate between Price and Burke ensued that was "the classic moment at which two fundamentally different conceptions of national identity were presented to the English public".[90] Price claimed that the principles of the Glorious Revolution included "the right to choose our own governors, to cashier them for misconduct, and to frame a government for ourselves". Immediately after reading Price's sermon, Burke wrote a draft of what eventually became Reflections on the Revolution in France.[91] On 13 February 1790, a notice in the press said that shortly Burke would publish a pamphlet on the Revolution and its British supporters, but he spent the year revising and expanding it. On 1 November, he finally published the Reflections and it was an immediate best-seller.[92][93] Priced at five shillings, it was more expensive than most political pamphlets, but by the end of 1790, it had gone through ten printings and sold approximately 17,500 copies. A French translation appeared on 29 November and on 30 November the translator Pierre-Gaëton Dupont wrote to Burke saying 2,500 copies had already been sold. The French translation ran to ten printings by June 1791.[94] What the Glorious Revolution had meant was as important to Burke and his contemporaries as it had been for the last one hundred years in British politics.[95] In the Reflections, Burke argued against Price's interpretation of the Glorious Revolution and instead, gave a classic Whig defence of it.[96] Burke argued against the idea of abstract, metaphysical rights of humans and instead advocated national tradition: The Revolution was made to preserve our antient indisputable laws and liberties, and that antient constitution of government which is our only security for law and liberty...The very idea of the fabrication of a new government, is enough to fill us with disgust and horror. We wished at the period of the Revolution, and do now wish, to derive all we possess as an inheritance from our forefathers. Upon that body and stock of inheritance we have taken care not to inoculate any cyon [scion] alien to the nature of the original plant...Our oldest reformation is that of Magna Charta. You will see that Sir Edward Coke, that great oracle of our law, and indeed all the great men who follow him, to Blackstone, are industrious to prove the pedigree of our liberties. They endeavour to prove that the ancient charter...were nothing more than a re-affirmance of the still more ancient standing law of the kingdom...In the famous law...called the Petition of Right, the parliament says to the king, "Your subjects have inherited this freedom", claiming their franchises not on abstract principles "as the rights of men", but as the rights of Englishmen, and as a patrimony derived from their forefathers.[97] Burke said: "We fear God, we look up with awe to kings; with affection to Parliaments; with duty to magistrates; with reverence to priests; and with respect to nobility. Why? Because when such ideas are brought before our minds, it is natural to be so affected".[98] Burke defended this prejudice on the grounds that it is "the general bank and capital of nations, and of ages" and superior to individual reason, which is small in comparison. "Prejudice", Burke claimed, "is of ready application in the emergency; it previously engages the mind in a steady course of wisdom and virtue, and does not leave the man hesitating in the moment of decision, sceptical, puzzled, and unresolved. Prejudice renders a man's virtue his habit".[99] Burke criticised social contract theory by claiming that society is indeed a contract, although it is "a partnership not only between those who are living, but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born".[100] The most famous passage in Burke's Reflections was his description of the events of 5–6 October 1789 and the part of Marie-Antoinette in them. Burke's account differs little from modern historians who have used primary sources.[101] His use of flowery language to describe it provoked both praise and criticism. Philip Francis wrote to Burke saying that what he wrote of Marie-Antoinette was "pure foppery".[102] Edward Gibbon reacted differently: "I adore his chivalry".[103] Burke was informed by an Englishman who had talked with the Duchesse de Biron that when Marie-Antoinette was reading the passage she burst into tears and took considerable time to finish reading it.[104] Price had rejoiced that the French king had been "led in triumph" during the October Days, but to Burke, this symbolised the opposing revolutionary sentiment of the Jacobins and the natural sentiments of those who shared his own view with horror—that the ungallant assault on Marie-Antoinette was a cowardly attack on a defenceless woman.[105] Louis XVI translated the Reflections "from end to end" into French.[106] Fellow Whig MPs Richard Sheridan and Charles James Fox disagreed with Burke and split with him. Fox thought the Reflections to be "in very bad taste" and "favouring Tory principles".[107] Other Whigs such as the Duke of Portland and Earl Fitzwilliam privately agreed with Burke, but they did not wish for a public breach with their Whig colleagues.[108] Burke wrote on 29 November 1790: "I have received from the Duke of Portland, Lord Fitzwilliam, the Duke of Devonshire, Lord John Cavendish, Montagu (Frederick Montagu MP), and a long et cetera of the old Stamina of the Whiggs a most full approbation of the principles of that work and a kind indulgence to the execution".[109] The Duke of Portland said in 1791 that when anyone criticised the Reflections to him, he informed them that he had recommended the book to his sons as containing the true Whig creed.[110] In the opinion of Paul Langford,[36] Burke crossed something of a Rubicon when he attended a levee on 3 February 1791 to meet the King, later described by Jane Burke as follows: On his coming to Town for the Winter, as he generally does, he went to the Levee with the Duke of Portland, who went with Lord William to kiss hands on his going into the Guards—while Lord William was kissing hands, The King was talking to The Duke, but his Eyes were fixed on [Burke] who was standing in the Crowd, and when He said His say to The Duke, without waiting for [Burke]'s coming up in his turn, The King went up to him, and, after the usual questions of how long have you been in Town and the weather, He said you have been very much employed of late, and very much confined. [Burke] said, no, Sir, not more than usual—You have and very well employed too, but there are none so deaf as those that w'ont hear, and none so blind as those that w'ont see—[Burke] made a low bow, Sir, I certainly now understand you, but was afraid my vanity or presumption might have led me to imagine what Your Majesty has said referred to what I have done—You cannot be vain—You have been of use to us all, it is a general opinion, is it not so Lord Stair? who was standing near. It is said Lord Stair;—Your Majesty's adopting it, Sir, will make the opinion general, said [Burke]—I know it is the general opinion, and I know that there is no Man who calls himself a Gentleman that must not think himself obliged to you, for you have supported the cause of the Gentlemen—You know the tone at Court is a whisper, but The King said all this loud, so as to be heard by every one at Court.[111] Burke's Reflections sparked a pamphlet war. Mary Wollstonecraft was one of the first into print, publishing A Vindication of the Rights of Men a few weeks after Burke. Thomas Paine followed with the Rights of Man in 1791. James Mackintosh, who wrote Vindiciae Gallicae, was the first to see the Reflections as "the manifesto of a Counter Revolution". Mackintosh later agreed with Burke's views, remarking in December 1796 after meeting him that Burke was "minutely and accurately informed, to a wonderful exactness, with respect to every fact relating to the French Revolution".[112] Mackintosh later said: "Burke was one of the first thinkers as well as one of the greatest orators of his time. He is without parallel in any age, excepting perhaps Lord Bacon and Cicero; and his works contain an ampler store of political and moral wisdom than can be found in any other writer whatever".[113] Charles James Fox In November 1790, François-Louis-Thibault de Menonville, a member of the National Assembly of France, wrote to Burke, praising Reflections and requesting more "very refreshing mental food" that he could publish.[114] This Burke did in April 1791 when he published A Letter to a Member of the National Assembly. Burke called for external forces to reverse the Revolution and included an attack on the late French philosopher Jean-Jacques Rousseau as being the subject of a personality cult that had developed in revolutionary France. Although Burke conceded that Rousseau sometimes showed "a considerable insight into human nature", he mostly was critical. Although he did not meet Rousseau on his visit to Britain in 1766–1767, Burke was a friend of David Hume, with whom Rousseau had stayed. Burke said Rousseau "entertained no principle either to influence of his heart, or to guide his understanding—but vanity"—which he "was possessed to a degree little short of madness". He also cited Rousseau's Confessions as evidence that Rousseau had a life of "obscure and vulgar vices" that was not "chequered, or spotted here and there, with virtues, or even distinguished by a single good action". Burke contrasted Rousseau's theory of universal benevolence and his having sent his children to a foundling hospital, stating that he was "a lover of his kind, but a hater of his kindred".[115] These events and the disagreements that arose from them within the Whigs led to its break-up and to the rupture of Burke's friendship with Fox. In a debate in Parliament on Britain's relations with Russia, Fox praised the principles of the Revolution, although Burke was not able to reply at this time as he was "overpowered by continued cries of question from his own side of the House".[116] When Parliament was debating the Quebec Bill for a constitution for Canada, Fox praised the Revolution and criticised some of Burke's arguments such as hereditary power. On 6 May 1791, Burke used the opportunity to answer Fox during another debate in Parliament on the Quebec Bill and condemn the new French Constitution and "the horrible consequences flowing from the French idea of the Rights of Man".[117] Burke asserted that those ideas were the antithesis of both the British and the American constitutions.[118] Burke was interrupted and Fox intervened, saying that Burke should be allowed to carry on with his speech. However, a vote of censure was moved against Burke for noticing the affairs of France which was moved by Lord Sheffield and seconded by Fox.[119] Pitt made a speech praising Burke and Fox made a speech—both rebuking and complimenting Burke. He questioned the sincerity of Burke, who seemed to have forgotten the lessons he had learned from him, quoting from Burke's own speeches of fourteen and fifteen years before. Burke's response was as follows: It certainly was indiscreet at any period, but especially at his time of life, to parade enemies, or give his friends occasion to desert him; yet if his firm and steady adherence to the British constitution placed him in such a dilemma, he would risk all, and, as public duty and public experience taught him, with his last words exclaim, "Fly from the French Constitution".[117] At this point, Fox whispered that there was "no loss of friendship". "I regret to say there is", Burke replied, "I have indeed made a great sacrifice; I have done my duty though I have lost my friend. There is something in the detested French constitution that envenoms every thing it touches".[120] This provoked a reply from Fox, yet he was unable to give his speech for some time since he was overcome with tears and emotion. Fox appealed to Burke to remember their inalienable friendship, but he also repeated his criticisms of Burke and uttered "unusually bitter sarcasms".[120] This only aggravated the rupture between the two men. Burke demonstrated his separation from the party on 5 June 1791 by writing to Fitzwilliam, declining money from him.[121] Burke was dismayed that some Whigs, instead of reaffirming the principles of the Whig Party he laid out in the Reflections, had rejected them in favour of "French principles" and that they criticised Burke for abandoning Whig principles. Burke wanted to demonstrate his fidelity to Whig principles and feared that acquiescence to Fox and his followers would allow the Whig Party to become a vehicle for Jacobinism. Burke knew that many members of the Whig Party did not share Fox's views and he wanted to provoke them into condemning the French Revolution. Burke wrote that he wanted to represent the whole Whig Party "as tolerating, and by a toleration, countenancing those proceedings" so that he could "stimulate them to a public declaration of what every one of their acquaintance privately knows to be...their sentiments".[122] On 3 August 1791, Burke published his Appeal from the New to the Old Whigs in which he renewed his criticism of the radical revolutionary programmes inspired by the French Revolution and attacked the Whigs who supported them as holding principles contrary to those traditionally held by the Whig Party. Burke owned two copies of what has been called "that practical compendium of Whig political theory", namely The Tryal of Dr. Henry Sacheverell (1710).[123] Burke wrote of the trial: "It rarely happens to a party to have the opportunity of a clear, authentic, recorded, declaration of their political tenets upon the subject of a great constitutional event like that of the [Glorious] Revolution".[123] Writing in the third person, Burke asserted in his Appeal: [The] foundations laid down by the Commons, on the trial of Doctor Sacheverel, for justifying the revolution of 1688, are the very same laid down in Mr. Burke's Reflections; that is to say,—a breach of the original contract, implied and expressed in the constitution of this country, as a scheme of government fundamentally and inviolably fixed in King, Lords and Commons.—That the fundamental subversion of this antient constitution, by one of its parts, having been attempted, and in effect accomplished, justified the Revolution. That it was justified only upon the necessity of the case; as the only means left for the recovery of that antient constitution, formed by the original contract of the British state; as well as for the future preservation of the same government. These are the points to be proved.[123] Burke then provided quotations from Paine's Rights of Man to demonstrate what the New Whigs believed. Burke's belief that Foxite principles corresponded to Paine's was genuine.[124] Finally, Burke denied that a majority of "the people" had, or ought to have, the final say in politics and alter society at their pleasure. People had rights, but also duties and these duties were not voluntary. According to Burke, the people could not overthrow morality derived from God.[125] Although Whig grandees such as Portland and Fitzwilliam privately agreed with Burke's Appeal, they wished he had used more moderate language. Fitzwilliam saw the Appeal as containing "the doctrines I have sworn by, long and long since".[126] Francis Basset, a backbench Whig MP, wrote to Burke that "though for reasons which I will not now detail I did not then deliver my sentiments, I most perfectly differ from Mr. Fox & from the great Body of opposition on the French Revolution".[126] Burke sent a copy of the Appeal to the King and the King requested a friend to communicate to Burke that he had read it "with great Satisfaction".[126] Burke wrote of its reception: "Not one word from one of our party. They are secretly galled. They agree with me to a title; but they dare not speak out for fear of hurting Fox...They leave me to myself; they see that I can do myself justice".[121] Charles Burney viewed it as "a most admirable book—the best & most useful on political subjects that I have ever seen", but he believed the differences in the Whig Party between Burke and Fox should not be aired publicly.[127] Eventually, most of the Whigs sided with Burke and gave their support to William Pitt the Younger's Tory government which in response to France's declaration of war against Britain declared war on France's Revolutionary Government in 1793. In December 1791, Burke sent government ministers his Thoughts on French Affairs where he put forward three main points, namely that no counter-revolution in France would come about by purely domestic causes; that the longer the Revolutionary Government exists, the stronger it becomes; and that the Revolutionary Government's interest and aim is to disturb all of the other governments of Europe.[128] As a Whig, Burke did not wish to see an absolute monarchy again in France after the extirpation of Jacobinism. Writing to an émigré in 1791, Burke expressed his views against a restoration of the Ancien Régime: When such a complete convulsion has shaken the State, and hardly left any thing whatsoever, either in civil arrangements, or in the Characters and disposition of men's minds, exactly where it was, whatever shall be settled although in the former persons and upon old forms, will be in some measure a new thing and will labour under something of the weakness as well as other inconveniences of a Change. My poor opinion is that you mean to establish what you call 'L'ancien Régime,' If any one means that system of Court Intrigue miscalled a Government as it stood, at Versailles before the present confusions as the thing to be established, that I believe will be found absolutely impossible; and if you consider the Nature, as well of persons, as of affairs, I flatter myself you must be of my opinion. That was tho' not so violent a State of Anarchy as well as the present. If it were even possible to lay things down exactly as they stood, before the series of experimental politicks began, I am quite sure that they could not long continue in that situation. In one Sense of L'Ancien Régime I am clear that nothing else can reasonably be done.[129] Burke delivered a speech on the debate of the Aliens Bill on 28 December 1792. He supported the Bill as it would exclude "murderous atheists, who would pull down Church and state; religion and God; morality and happiness".[130] The peroration included a reference to a French order for 3,000 daggers. Burke revealed a dagger he had concealed in his coat and threw it to the floor: "This is what you are to gain by an alliance with France". Burke picked up the dagger and continued: When they smile, I see blood trickling down their faces; I see their insidious purposes; I see that the object of all their cajoling is—blood! I now warn my countrymen to beware of these execrable philosophers, whose only object it is to destroy every thing that is good here, and to establish immorality and murder by precept and example—'Hic niger est hunc tu Romane caveto' ['Such a man is evil; beware of him, Roman'. Horace, Satires I. 4. 85.].[130] Burke supported the war against Revolutionary France, seeing Britain as fighting on the side of the royalists and émigres in a civil war, rather than fighting against the whole nation of France.[131] Burke also supported the royalist uprising in La Vendée, describing it on 4 November 1793 in a letter to William Windham as "the sole affair I have much heart in".[131] Burke wrote to Henry Dundas on 7 October urging him to send reinforcements there as he viewed it as the only theatre in the war that might lead to a march on Paris, but Dundas did not follow Burke's advice. Burke believed the British government was not taking the uprising seriously enough, a view reinforced by a letter he had received from the Prince Charles of France (S.A.R. le comte d'Artois), dated 23 October, requesting that he intercede on behalf of the royalists to the government. Burke was forced to reply on 6 November: "I am not in His Majesty's Service; or at all consulted in his Affairs".[132] Burke published his Remarks on the Policy of the Allies with Respect to France, begun in October, where he said: "I am sure every thing has shewn us that in this war with France, one Frenchman is worth twenty foreigners. La Vendée is a proof of this".[133] On 20 June 1794, Burke received a vote of thanks from the House of Commons for his services in the Hastings Trial and he immediately resigned his seat, being replaced by his son Richard. A blow fell upon Burke with the loss of Richard in August 1794, to whom he was tenderly attached and in whom he saw signs of promise[36] which were not patent to others and which in fact appear to have been non-existent, although this view may have rather reflected the fact that his son Richard had worked successfully in the early battle for Catholic emancipation. King George III, whose favour he had gained by his attitude on the French Revolution, wished to create him Earl of Beaconsfield, but the death of his son deprived the opportunity of such an honour and all its attractions, so the only award he would accept was a pension of £2,500. Even this modest reward was attacked by the Duke of Bedford and the Earl of Lauderdale, to whom Burke replied in his Letter to a Noble Lord (1796):[134] "It cannot at this time be too often repeated; line upon line; precept upon precept; until it comes into the currency of a proverb, To innovate is not to reform".[135] He argued that he was rewarded on merit, but the Duke of Bedford received his rewards from inheritance alone, his ancestor being the original pensioner: "Mine was from a mild and benevolent sovereign; his from Henry the Eighth".[136] Burke also hinted at what would happen to such people if their revolutionary ideas were implemented and included a description of the British Constitution: But as to our country and our race, as long as the well compacted structure of our church and state, the sanctuary, the holy of holies of that ancient law, defended by reverence, defended by power, a fortress at once and a temple, shall stand inviolate on the brow of the British Sion—as long as the British Monarchy, not more limited than fenced by the orders of the State, shall, like the proud Keep of Windsor, rising in the majesty of proportion, and girt with the double belt of its kindred and coeval towers, as long as this awful structure shall oversee and guard the subjected land—so long as the mounds and dykes of the low, fat, Bedford level will have nothing to fear from all the pickaxes of all the levellers of France.[137] Burke's last publications were the Letters on a Regicide Peace (October 1796), called forth by negotiations for peace with France by the Pitt government. Burke regarded this as appeasement, injurious to national dignity and honour.[138] In his Second Letter, Burke wrote of the French Revolutionary government: "Individuality is left out of their scheme of government. The State is all in all. Everything is referred to the production of force; afterwards, everything is trusted to the use of it. It is military in its principle, in its maxims, in its spirit, and in all its movements. The State has dominion and conquest for its sole objects—dominion over minds by proselytism, over bodies by arms".[139] This is held to be the first explanation of the modern concept of totalitarian state.[140] Burke regarded the war with France as ideological, against an "armed doctrine". He wished that France would not be partitioned due to the effect this would have on the balance of power in Europe and that the war was not against France, but against the revolutionaries governing her.[141] Burke said: "It is not France extending a foreign empire over other nations: it is a sect aiming at universal empire, and beginning with the conquest of France".[36] |
フランス革命:1688年対1789年 詳細情報:フランス革命についての考察 ギレイによる『ネズミを嗅ぎつける;あるいは、深夜の「計算」を邪魔された無神論革命家』(1790年)は、王冠と十字架を手にしたバークの風刺画と、イ ギリス王チャールズ1世の処刑の絵の下に「無政府状態の利点について」と「国王殺しの無神論」を書いている座っている男リチャード・プライスの絵を描いて いる フランス革命についての考察、およびその事件に関連するロンドンの特定の社会における動向。パリのある紳士に送る予定だった手紙による。右大臣エドマンド・バーク著 当初、バークはフランス革命を非難していなかった。1789年8月9日付の手紙で、彼は次のように書いている。「自由のために戦うフランスを驚きをもって 見つめるイングランドは、非難すべきか賞賛すべきか、判断に迷っている!確かに、私は数年前から同様のことが進行中であるように感じていたが、この事態に は依然として逆説的で不可解な要素がある。その精神には感嘆せずにはいられないが、昔ながらのパリの凶暴性が衝撃的な形で噴出したのだ」[84] 1789年10月5日と6日に、パリの女性たちがルイ16世にパリに戻るよう迫るためにヴェルサイユへ行進した事件は、バークをフランス革命に反対させる こととなった。10月10日付で息子リチャード・バークに宛てた手紙の中で、彼は次のように述べている。「今日、ローレンスからフランスが不吉な状態にあ ることを示す書類を受け取った。そこでは、人間社会を構成する要素がすべて溶解し、その代わりに怪物の世界が出現している。ミラボーが 大君主が哀れなほど滑稽な姿をさらしている」という内容の手紙を受け取った。[85] 11月4日、シャルル・ジャン・フランソワ・ドゥポンはバークに手紙を書き、革命を支持するよう求めた。バークは、彼が革命について批判的な言葉を使うこ とは「疑念の表明に過ぎない」と答えたが、こう付け加えた。「君は君主制を崩壊させたかもしれないが、自由を取り戻すことはできなかった」[86]。同 月、彼はフランスを「崩壊した国」と表現した。バークが革命を初めて公に非難したのは、1790年2月9日、ピットとフォックスによる革命の賞賛をきっか けに議会で行われた軍事予算に関する討論の最中であった。 「議会が夏に休会していた間に、フランスでは多くの仕事が行われた。フランス人は、これまで世界に存在した中で最も有能な破滅の建築家であることを自ら示 した。彼らは、その非常に短い期間に、君主制、教会、貴族、法律、歳入、軍隊、海軍、商業、芸術、そして製造業を完全に崩壊させた。[そこには、]非合理 で、無原則で、禁止し、没収し、略奪し、残忍で、血なまぐさく、暴政的な民主主義の行き過ぎをまねく危険性があった。[宗教において]彼らの手本となる危 険性は、もはや不寛容からではなく、無神論から生じている。それは、人間の尊厳と慰めをすべて敵対する、不潔で不自然な悪徳であり、 略奪、残忍、流血、専制的な民主主義の過ちを真似るという危険性があった。[宗教において] 彼らの手本となる危険性は、もはや不寛容からではなく、無神論から生じている。それは、人間の尊厳と安らぎのすべてを敵対する、不潔で不自然な悪徳であ り、フランスでは長い間、ある党派に体現され、公認され、ほとんど公言されているように見える。[87] 1790年1月、バークはリチャード・プライスの1789年11月4日の説教『革命協会への祖国愛に関する演説』を読んだ。[88] この協会は1688年の名誉革命を記念して設立されたものだった。この説教で、プライスは万人の普遍的な「権利」の哲学を支持した。プライスは、祖国への 愛は「他の国々よりも価値が高いという確信や、その国の法律や政府の憲法を特別に好むという意味を含んではいない」と主張した。[89] その代わりに、プライスは英国人は「特定のコミュニティの一員としてよりも、世界の市民として」自分自身を捉えるべきだと主張した。 プライスとバークの間の論争は、「国民としてのアイデンティティに関する根本的に異なる2つの考え方が英国国民に提示された典型的な瞬間」であった。 [90] プライスは、名誉革命の原則には「自分たちの統治者を自ら選び、不品行を理由に罷免し、自分たちのための政府を樹立する権利」が含まれていると主張した。 プライスの説教を読んだ直後、バークは『フランス革命についての考察』の草稿を書き上げた。[91] 1790年2月13日、新聞にバークが間もなく革命と英国の革命支持者に関するパンフレットを出版するという予告が掲載されたが、彼はその年の大半をその 原稿の修正と拡充に費やした。11月1日、ついに『考察』が出版され、たちまちベストセラーとなった。[92][93] 5シリングという価格は、ほとんどの政治パンフレットよりも高かったが、1790年末までに10回も増刷され、約17,500部が売れた。フランス語訳は 11月29日に出版され、11月30日には翻訳者のピエール=ガエトン・デュポンがバークに宛てた手紙で、すでに2,500部が売れたと伝えている。フラ ンス語訳は1791年6月までに10刷を重ねた。[94] 名誉革命が意味するものは、バークや同時代の人々にとって、過去100年の英国政治にとってと同様に重要なものだった。[95] 『省察』において、バークはプライスの名誉革命解釈に反対し、その代わりにホイッグ党の古典的な名誉革命擁護論を展開した。[96] バークは、人間の抽象的・形而上学的権利という考えに反対し、代わりに国民の伝統を擁護した。 革命は、我々の古く明白な法律と自由を守るために行われた。そして、その古くからの統治形態こそが、我々にとって唯一の法律と自由の保障である。新しい政 府を創設するという考えそのものが、我々を嫌悪と恐怖で満たすのに十分である。我々は革命の時代に、そして今も、先祖から受け継いだものすべてを望んでい る。その遺産と財産を基盤として、私たちは、元の植物の性質とは異なる接ぎ穂(接ぎ木)を一切植えないよう注意してきた...私たちの最も古い改革はマグ ナ・カルタによるものである。 サー・エドワード・コーク、すなわち私たちの法律の偉大な権威、そして彼に続くブラックストンに至るまで、偉大な人物たちは皆、私たちの自由の系譜を証明 することに熱心に取り組んできた。彼らは、その古い憲章が...王国のさらに古い成文法の再確認にすぎないことを証明しようと努めた...有名な権利請願 と呼ばれる法律において、議会は国王に対して「あなたの臣民は、この自由を受け継いできた」と述べ、彼らの権利を「人としての権利」という抽象的な原則で はなく、イングランド人の権利、そして先祖から受け継いだ財産として主張した。[97] バークは次のように述べた。「我々は神を畏れ、王には畏敬の念を抱き、議会には愛情を、裁判官には義務を、聖職者には敬意を、そして貴族には尊敬の念を抱 く。なぜか? このような考えが我々の心に浮かぶとき、そう感じるのは自然なことだからだ」[98] バークは、この偏見を「国民の、そして時代の一般的な基盤であり、資本である」とし、それに比べれば個人の理性は取るに足らないものだと主張した。「偏 見」は緊急時にすぐに適用できるとバークは主張した。「偏見」は、知恵と美徳の着実な道筋に事前に心を傾けさせ、決断の瞬間に人間をためらい、疑い、困惑 させ、決断できないままにしておくことはない。偏見は、人間の美徳を習慣にする」と主張した。[99] バークは社会契約説を批判し、社会は確かに契約であるが、それは「生きている者同士だけでなく、生きている者と死んだ者、そしてこれから生まれてくる者と の間のパートナーシップ」であると主張した。[100] バークの『反省』で最も有名な一節は、1789年10月5日と6日の出来事、およびその出来事におけるマリー・アントワネットの役割についての記述であ る。バークの記述は、一次資料を基に研究を行なっている現代の歴史家の見解とほとんど変わらない。[101] その出来事を描写するために、バークが詩的な表現を用いたことは、賞賛と批判の両方を引き起こした。フィリップ・フランシスはバークに宛てた手紙で、マ リー・アントワネットについて彼が書いたことは「純粋な虚飾」であると書いた。[102] エドワード・ギボンは異なる反応を示し、 「私は彼の騎士道精神に感服する」と述べた。[103] バークは、ビロン公爵夫人と話をした英国人から、マリー・アントワネットがその文章を読んでいるときに涙を流し、読み終えるまでにかなりの時間を要したと いう情報を得た。[104] プライスは、フランス王が 「勝利に導かれた」と喜んだが、バークにとっては、これはジャコバン派の革命的な感情と、マリー・アントワネットに対する無礼な暴行は無防備な女性に対す る卑劣な攻撃であるという、バークと同じ見解を持つ人々の自然な感情の対立を象徴するものだった。 ルイ16世は『反省録』を「最初から最後まで」フランス語に翻訳した。[106] 同党の議員であるリチャード・シェリダンとチャールズ・ジェイムズ・フォックスはバークに反対し、彼と袂を分かつこととなった。フォックスは『反省録』を 「非常に悪趣味」で「トーリー党の主義を支持するもの」と考えていた。[107] ポートランド公やフィッツウィリアム伯といった他のホイッグ党員は、内心ではバークに同意していたが、ホイッグ党の同僚たちとの公の決別は望んでいなかっ た。[108] バークは1790年11月29日に次のように書いている。「私はポートランド公爵、フィッツウィリアム卿、デヴォンシャー公爵、ジョン・キャヴェンディッ シュ卿、モンタギュー(フレデリック・モンタギュー下院議員)など、古くからのウィッグ党の有力者たちから、その著作の原則に対して最大限の賛同と、 その仕事と、その実行に対する寛大な寛容さに対して、最も完全な賛同を示した」と述べた。[109] ポートランド公爵は1791年に、誰かが『省察』を批判した際には、その本には真のホイッグ党の信条が含まれているとして、自分の息子たちにその本を推薦 したと伝えた。[110] ポール・ラングフォードの見解によると、[36] 1791年2月3日に国王に謁見するために出席したレヴィーにおいて、バークはルビコン川を渡ったようなものだった。この出来事は後にジェーン・バークによって次のように描写されている。 冬の間、彼がいつもするように、ロンドンにやってくると、ポートランド公爵とともにレベイに赴いた。ポートランド公爵は、ウィリアム卿が近衛連隊に入隊す る際に挨拶するために同行していた。ウィリアム卿が挨拶をしている間、国王は公爵と話をしていたが、その視線は群衆の中に立っていた[バーク]に注がれて いた。群衆の中に立っていたバークに目をやり、バークが順番に近づくのを待たずに、公爵に言いたいことを言うと、王は彼のもとへ近づき、いつからこの街に いるのか、天気はどうなのかといったお決まりの質問をした後、最近あなたは非常に忙しく、非常に閉じ込められているようですね、と述べた。バークは、いい え、陛下、いつも通りです。陛下は非常に良くお使いになっていますが、聞こうとしない者はこれほどまでに耳が遠く、見ようとしない者はこれほどまでに目が 不自由なのです。バークは深くお辞儀をし、 今では確かに理解しました。しかし、陛下がおっしゃったのは、私がしたことについて言及されたのではないかと、私の虚栄心や思い上がりが想像させたのでは ないかと恐れていたのです。陛下が虚栄心をお持ちであるはずがない。陛下は私たち皆に役立ってくださっている。それが一般的な意見だ。そうではないか、ス テア卿?近くに立っていた 「ステア卿がそう言ったそうです。陛下がそれを採用すれば、その意見が一般的になるでしょう」とバークが言った。「私はそれが一般的な意見であることを 知っています。そして、紳士を名乗る者で陛下に感謝しない者はいないと知っています。なぜなら、陛下は紳士の地位を守ってきたからです。紳士の権利を支持 したあなたに感謝しない者はいないはずだ。あなたは宮廷のトーンがささやき声であることを知っているが、国王は宮廷の全員に聞こえるように、すべてを大き な声で言ったのだ。 バークの『省察』は、パンフレットによる論争を引き起こした。メアリ・ウルストンクラフトは、バークの数週間後に『人間の権利の擁護』を出版し、最初に出 版した人物の一人となった。トマス・ペインは1791年に『人間の権利』を出版した。『Vindiciae Gallicae』を著したジェイムズ・マッキントッシュは、『反省録』を「反革命の宣言」と最初に評した人物であった。マッキントッシュは後にバークの 見解に同意し、1796年12月にバークと会った後、「バークはフランス革命に関するあらゆる事実について、驚くほど正確に詳細に精通していた」と述べ た。[112] マッキントッシュは後に次のように述べた。「バークは、当時、最も偉大な思想家の一人であり、また、最も優れた演説家の一人でもあった。 彼の作品には、他のどの作家にも見られないほど、政治的・道徳的な英知が詰まっている。 チャールズ・ジェームズ・フォックス 1790年11月、フランスの国民議会の一員であったフランソワ=ルイ=ティボー・ド・メノンヴィルは、バークに『反省』を賞賛する手紙を書き、さらに 「非常に爽快な精神的糧」を出版することを依頼した。[114] バークは1791年4月に『国民議会議員への手紙』を出版し、これに応えた。バークは革命を覆す外部からの力を求め、革命後のフランスで発展した個人崇拝 の対象であるとして、故フランスの哲学者ジャン=ジャック・ルソーを攻撃した。バークはルソーが「人間の本質に対する相当な洞察力」を示したこともあると 認めたが、ほとんどは批判的であった。1766年から1767年のルソーの英国訪問時にバークはルソーに会っていないが、バークはルソーが滞在していたデ イヴィッド・ヒュームの友人であった。バークは、ルソーは「心に影響を与える原則も、理解を導く原則も持たず、ただ虚栄心だけがあった」と述べ、ルソーは 「狂気の一歩手前の状態にあった」と主張した。また、ルソーの『告白』を証拠として挙げ、ルソーの人生は「不明瞭で下品な悪徳」に満ちており、「善行に よって際立ったものでも、あちこちに善行が散りばめられたものでも、波瀾万丈なものでもなかった」と述べた。バークは、ルソーの普遍的な博愛主義の理論 と、彼が自分の子供たちを孤児院に入れたことを対比させ、「彼は同類の者に対しては愛情を注ぐが、親族に対しては憎悪を抱いている」と述べた。[115] これらの出来事と、それらから生じたホイッグ党内の意見の相違が、ホイッグ党の分裂と、バークとフォックスの友情の決裂につながった。議会におけるイギリ スとロシアの関係に関する討論で、フォックスは革命の原則を賞賛したが、バークは「議場から続く自派からの質問の声に圧倒され」、この時は返答することが できなかった。[116] カナダの憲法に関するケベック法案を議会で審議していた際、フォックスは革命を賞賛し、世襲権力などのバークの主張の一部を批判した。1791年5月6 日、バークはケベック法案に関する議会での別の討論の機会を利用してフォックスに反論し、新しいフランス憲法と「フランス人の人間としての権利の考え方か ら生じる恐ろしい結果」を非難した。[117] バークは、それらの考え方はイギリスとアメリカの憲法の両方の対極にあると主張した。[118] バークが話を遮られ、フォックスが口を挟んだ。フォックスは、バークに話を続けさせるべきだと主張した。しかし、シェフィールド卿が動議を提出し、フォッ クスが賛成したため、フランス情勢に言及したバークに対する非難決議案が提出された。[119] ピットはバークを称賛する演説を行い、フォックスはバークを非難し、称賛する演説を行った。彼はバークの誠実さを疑い、バークが彼から学んだ教訓を忘れて しまったかのように見えた。バークは14年前と15年前の自身の演説を引用して反論した。バークの回答は以下の通りである。 確かに、いつの時代でも軽率な行為ではあったが、特に彼の年齢では、敵をあおったり、友人たちに彼を見限らせるようなことをするのは、特に軽率であった。 しかし、もし英国憲法への彼の確固とした忠誠心が彼をこのような苦境に立たせたのであれば、彼はすべてを賭け、公の義務と公の経験から学んだように、最後 の言葉として「フランス憲法から逃れよ」と叫ぶだろう。[117] この時点で、フォックスは「友情を失うことはない」とささやいた。「残念ながら、そうではない」とバークは答えた。「私は確かに大きな犠牲を払った。義務 を果たしたが、友人を失った。憎むべきフランス憲法には、触れるものすべてを毒する何かがあるのだ」[120] これにフォックスは反論したが、しばらくは涙と感情に圧倒されて演説できなかった。フォックスはバークに、自分たちの譲ることのできない友情を思い出して ほしいと訴えたが、バークに対する批判を繰り返し、「異常なほど辛辣な皮肉」を口にした。[120] これにより、2人の仲たがいはさらに悪化した。バークは1791年6月5日、フィッツウィリアムに宛てた手紙で、金銭の援助を断り、党からの離脱を表明し た。[121] バークは、一部のホイッグ党員が『省察』で彼が提示したホイッグ党の原則を再確認するのではなく、「フランス的」原則を支持してそれを拒絶し、バークがホ イッグ党の原則を放棄したと批判したことに落胆した。バークはホイッグ党の原則への忠誠を示そうとし、フォックスとその支持者たちに迎合することはホイッ グ党をジャコバン主義の手段に変えることになると恐れた。 バークは、ホックスの見解に賛同しないホイッグ党員が多数いることを知っており、彼らを挑発してフランス革命を非難させようとした。バークは、ホイッグ党 全体を「寛容であり、寛容によって、それらの手続きを容認している」と表現し、彼らに「各自が個人的に知っている彼らの感情を公に表明するよう促す」こと を望んでいたと書いている。[122] 1791年8月3日、バークは『新ホイッグ党から旧ホイッグ党への訴え』を出版し、フランス革命に触発された急進的な革命プログラムに対する批判をあらた めて展開し、それを支持するホイッグ党員を、ホイッグ党が伝統的に抱いてきた理念とは相反する理念を持つ者として攻撃した。 バークは「ホイッグ党政治理論の実用的な要約」と呼ばれる『ヘンリー・サチェヴェレル博士の裁判』(1710年)の2冊を所有していた。[123] バークはその裁判について次のように書いている。「革命のような偉大な憲法上の出来事を題材に、その政治信条を明確かつ真正に記録した宣言を行う機会が与 えられることはめったにない」と述べている。[123] 第三者の立場で執筆した『アピール』で、バークは次のように主張した。 1688年の革命を正当化するために、庶民院がサチェベリル博士の裁判で示した根拠は、まさにバークの『反省録』で示した根拠と同じである。つまり、 この国の憲法に暗示され、表現されている、国王、貴族、庶民の間で基本的に、そして不可侵に定められた政府の仕組みである。この古来の憲法の根本的な破壊 が、その一部によって試みられ、事実上達成されたことは、革命を正当化した。それは、その必要に迫られて正当化されたものであり、英国国家の当初の契約に よって形成された古来の憲法を回復し、同じ政府を将来にわたって維持するための唯一の手段であった。これらが証明すべき点である。[123] その後、バークはペイン著『人間権利論』からの引用を提示し、ニュー・ホイッグ党が何を信じていたかを示した。フォクシズムの原則がペインの主張と一致す るというバークの信念は本物であった。[124] 最終的に、バークは「人民」の大多数が政治において最終的な決定権を持っている、あるいは持つべきである、また彼らの気まぐれで社会を変えることができ る、という主張を否定した。人民には権利があるが、義務もある。そして、これらの義務は自発的なものではない。バークによれば、人民は神から導かれた道徳 を覆すことはできない。[125] ポートランドやフィッツウィリアムといったホイッグ党の重鎮たちは、バークの檄文に内心では同意していたものの、より穏健な表現を用いることを望んでい た。フィッツウィリアムは、この檄文を「私が長い間、固く信じてきた教義」が含まれているものと捉えていた。[126] ホイッグ党のバックベンチ議員であったフランシス・ベイセットは、バークに宛てた手紙の中で、「詳細を述べない理由から、当時、私は自分の考えを述べな かったが、 フォックス氏や野党の大多数とはフランス革命について完全に意見が異なる」とバークに書き送った。[126] バークは『国王への訴え』の写しを国王に送り、国王は友人を通じてバークに「大いに満足して」読んだと伝えた。[126] バークはその反応について次のように記している。「わが党の誰からも一言もない。彼らは内心苛立っている。彼らは私に同意しているが、フォックスを傷つけ ることを恐れて、あえて口に出そうとはしない...彼らは私を一人にしておく。彼らは私が自分自身で正当性を主張できることを理解しているのだ」 [121] チャールズ・バーニーはこれを「最も称賛に値する本であり、政治に関するテーマでは私がこれまで目にした中で最も優れ、最も役立つ本」と評価したが、バー クとフォックスのホイッグ党における相違を公にすべきではないと考えていた。 結局、ホイッグ党員のほとんどはバークに同調し、1793年にフランス革命政府に対してイギリスが宣戦布告したことに対して、ウィリアム・ピット・ザ・ヤンガーのトーリー党政府を支持した。 1791年12月、バークは政府閣僚たちに『フランス情勢に関する考察』を送り、その中で彼は3つの主要な主張を提示した。すなわち、フランスにおける反 革命は純粋に国内的な原因によって起こることはない、革命政府が存続する期間が長ければ長いほど、その力は強くなる、そして革命政府の利益と目的はヨー ロッパの他のすべての政府を混乱させることである、という3点である。 ホイッグ党員であったバークは、ジャコバン派の根絶後にフランスで再び絶対王政が復活することを望んではいなかった。1791年に亡命者に宛てた手紙の中で、バークはアンシャン・レジームの復活に反対する意見を述べている。 国家がこれほどまでに完全に揺さぶられ、市民生活の仕組みや人々の心構えや性格がほとんど元の状態のまま残っていない状況で、たとえ以前の人々や古い形式 に基づいて何らかの決定がなされたとしても、それはある程度は新しいものであり、変化に伴う弱点やその他の不都合を伴うことになるだろう。私の貧弱な意見 では、あなたが「旧体制」と呼ぶものを確立しようとしているということだ。もし誰かが、現在の混乱以前のヴェルサイユ宮殿で、宮廷陰謀と称される政府を、 その体制のまま確立すべきものだと考えているのであれば、それは絶対に不可能であると私は思う。そして、人物や事柄の本質を考慮するのであれば、あなたも 私の意見に同意するに違いないと私は思う。それは、現在ほどではないにしても、それなりに無政府状態であった。一連の実験的政治が始まる前の状態を正確に 再現することが可能であるならば、私は、その状態が長くは続かないだろうと確信している。旧体制の一つの側面において、他に合理的な選択肢はないと確信し ている。 バークは1792年12月28日、外国人法案に関する討論で演説を行った。彼は「教会と国家、宗教と神、道徳と幸福を破壊しようとする殺人者である無神論 者」を排除するとして、この法案を支持した。[130] 演説の結びでは、フランスが3,000本の短剣を注文したという逸話が引用された。バークは、自分のコートに隠していた短剣を取り出し、床に投げ捨てた。 「これがフランスと同盟を結ぶことで得られるものだ」と。バークは短剣を拾い上げ、こう続けた。 彼らが微笑むとき、私は彼らの顔を伝う血を見る。私は彼らの陰湿な目的を見る。彼らの甘い言葉の狙いが血であることを私は知っている!私は今、同胞たちに 警告する。この忌まわしい哲学者たちに用心せよ。彼らの唯一の目的は、この国にある善なるものをすべて破壊し、教えと手本によって不道徳と殺人を確立する ことだ。「Hic niger est hunc tu Romane caveto」[「このような男は悪だ。用心せよ、ローマ人よ」] ホラティウス、風刺詩第1巻第4章第85節。[130] バークは革命期のフランスに対する戦争を支持し、イギリスはフランス国民全体と戦っているのではなく、内戦における王党派と亡命者の側で戦っていると捉え ていた。[131] バークはまた、ラ・ヴァンドの王党派蜂起も支持し、1793年11月4日付けでウィリアム・ウィンダム宛ての手紙の中で「私が最も関心を寄せている唯一の 事件」と表現している。「私が最も心を砕いている唯一の事柄」とウィリアム・ウィンダムに宛てた手紙で述べている。[131] バークは10月7日付けでヘンリー・ダンダスに宛てた手紙で、この戦いがパリ進軍につながる可能性がある唯一の戦場であると見て、援軍を送るよう強く求め たが、ダンダスはバークの助言に従わなかった。 バークは、英国政府が蜂起を十分に深刻に捉えていないと考えており、その考えは、10月23日付でフランス王太子(S.A.R. le comte d'Artois)から受け取った、王党派のために政府に仲裁を求めるよう求める書簡によってさらに強まった。バークは11月6日に返答を余儀なくされ た。「私は陛下の奉公人ではない。陛下の事柄について一切相談されていない」[132] バークは10月に執筆を始めた『フランスに対する連合国の政策に関する所見』を出版した。その中で彼は次のように述べている。「このフランスとの戦争で は、フランス人1人が外国人20人に匹敵することは、あらゆる事柄が示している。ラ・ヴァンドは、その証拠である」[133] 1794年6月20日、ヘイスティングズ裁判における功績を称えられ、下院から感謝の意を表されたバークは、直ちに議席を辞し、息子のリチャードにその座 を譲った。1794年8月、バークは、彼が愛情を注ぎ、将来有望な兆しを見出していた息子リチャードを失った。しかし、この見解は、むしろ息子のリチャー ドがカトリック解放の初期の戦いで成功を収めたという事実を反映したものかもしれない。フランス革命に対する態度によって国王ジョージ3世の寵愛を得た彼 は、国王からベコンズフィールド伯爵の称号を授けられることを望んだが、息子の死によってその栄誉とそれに伴うあらゆる魅力を失い、彼が受け取ったのは年 金2,500ポンドだけだった。このささやかな報酬さえ、ベッドフォード公爵とローダーデール伯爵から攻撃されたため、バークは『高貴な貴族への手紙』 (1796年)で次のように反論した。「今こそ、繰り返し繰り返し、行を追って、教訓を ことわざとして定着するまで、改革とは革新ではないという教訓を繰り返し説く必要がある」と述べた。[135] 彼は、自分の報酬は功績によるものだと主張したが、ベッドフォード公爵は相続によってのみ報酬を得ており、彼の祖先は年金受給者であった。「私の報酬は穏 やかで慈悲深い君主によるものだったが、彼の報酬はヘンリー8世によるものだった」と述べた。[136] また、バークは、もし彼らの革命的な考えが実行された場合、そのような人々に何が起こるかをほのめかし、英国憲法の記述を含めた。 しかし、わが国と我々の種族に関しては、教会と国家の緊密に結合した構造、すなわち、畏敬の念によって守られ、権力によって守られ、要塞であり同時に神殿 でもある、あの古代の法の聖域が、ブリテン・シオンの頭上に侵すことのできないものとして存在する限り、すなわち、国家の秩序によって制限されるというよ りもむしろ守られているブリティッシュ・モナークが、 ウィンザー城の誇り高き天守閣のように、威厳に満ちた均整のとれた姿でそびえ立ち、同時代に建てられた親族の塔の二重のベルトで囲まれているように、この 畏怖すべき建造物が従属する土地を見守り、守る限り、低地で肥沃なベッドフォード平野の堤防や土手は、フランスの平等主義者たちのすべてのつるはしから何 も恐れることはないだろう。 バークの最後の著作は、ピット政権によるフランスとの和平交渉を受けて書かれた『国王殺人に関する平和についての書簡』(1796年10月)である。バー クはこれを宥和政策とみなし、国民の尊厳と名誉を傷つけるものだと考えた。[138] その続編『第二の手紙』で、バークはフランス革命政府について次のように述べている。「彼らの政治構想には個性が欠けている。国家がすべてである。すべて は力の生産に帰結し、その後、すべては力の使用に委ねられる。その原則、格言、精神、そしてすべての動きにおいて軍事的である。国家は、布教による精神の 支配、武力による身体の支配を唯一の目的としている」[139]。 これは、現代の全体主義国家の概念の最初の説明であると考えられている。[140] バークは、フランスとの戦争をイデオロギー的なもの、すなわち「武装した教義」に対するものとみなしていた。彼は、この戦争がヨーロッパの勢力均衡に影響 を及ぼすことを懸念し、フランスが分割されないことを望み、この戦争はフランスに対するものではなく、フランスを統治する革命家たちに対するものだと主張 した。[141] バークは次のように述べた。「外国の帝国を他の国民に拡大しているのはフランスではない。それは、普遍的な帝国を狙う一派であり、フランス征服から始まっ ているのだ」[36]。 |
| Later life In November 1795, there was a debate in Parliament on the high price of corn and Burke wrote a memorandum to Pitt on the subject. In December, Samuel Whitbread MP introduced a bill giving magistrates the power to fix minimum wages and Fox said he would vote for it. This debate probably led Burke to edit his memorandum as there appeared a notice that Burke would soon publish a letter on the subject to the Secretary of the Board of Agriculture Arthur Young, but he failed to complete it. These fragments were inserted into the memorandum after his death and published posthumously in 1800 as Thoughts and Details on Scarcity.[142] In it, Burke expounded "some of the doctrines of political economists bearing upon agriculture as a trade".[143] Burke criticised policies such as maximum prices and state regulation of wages and set out what the limits of government should be: That the State ought to confine itself to what regards the State, or the creatures of the State, namely, the exterior establishment of its religion; its magistracy; its revenue; its military force by sea and land; the corporations that owe their existence to its fiat; in a word, to every thing that is truly and properly public, to the public peace, to the public safety, to the public order, to the public prosperity.[144] The economist Adam Smith remarked that Burke was "the only man I ever knew who thinks on economic subjects exactly as I do, without any previous communications having passed between us".[145] Writing to a friend in May 1795, Burke surveyed the causes of discontent: "I think I can hardly overrate the malignity of the principles of Protestant ascendency, as they affect Ireland; or of Indianism [i.e. corporate tyranny, as practised by the British East Indies Company], as they affect these countries, and as they affect Asia; or of Jacobinism, as they affect all Europe, and the state of human society itself. The last is the greatest evil".[146] By March 1796, Burke had changed his mind: "Our Government and our Laws are beset by two different Enemies, which are sapping its foundations, Indianism, and Jacobinism. In some Cases they act separately, in some they act in conjunction: But of this I am sure; that the first is the worst by far, and the hardest to deal with; and for this amongst other reasons, that it weakens discredits, and ruins that force, which ought to be employed with the greatest Credit and Energy against the other; and that it furnishes Jacobinism with its strongest arms against all formal Government".[147] For more than a year prior to his death, Burke knew that his stomach was "irrecoverably ruind".[36] After hearing that Burke was nearing death, Fox wrote to Mrs. Burke enquiring after him. Fox received the reply the next day: Mrs. Burke presents her compliments to Mr. Fox, and thanks him for his obliging inquiries. Mrs. Burke communicated his letter to Mr. Burke, and by his desire has to inform Mr. Fox that it has cost Mr. Burke the most heart-felt pain to obey the stern voice of his duty in rending asunder a long friendship, but that he deemed this sacrifice necessary; that his principles continue the same; and that in whatever of life may yet remain to him, he conceives that he must live for others and not for himself. Mr. Burke is convinced that the principles which he has endeavoured to maintain are necessary to the welfare and dignity of his country, and that these principles can be enforced only by the general persuasion of his sincerity.[148] Burke died in Beaconsfield, Buckinghamshire, on 9 July 1797[149] and was buried there alongside his son and brother. |
晩年 1795年11月、議会でトウモロコシの高騰に関する討論が行われ、バークはピットにこの問題に関する覚え書きを書いた。12月には、サミュエル・ウィッ トブレッド議員が、最低賃金を定める権限を治安判事に与える法案を提出し、フォックスはこれに賛成票を投じると述べた。この討論により、おそらくバークは 自らの覚書を編集することになった。というのも、バークが間もなくこのテーマに関する書簡を農業委員会のアーサー・ヤング長官に宛てて発表するという予告 が掲載されたが、彼はそれを完成させることができなかった。これらの断片は、彼の死後にこの覚書に挿入され、1800年に『Thoughts and Details on Scarcity』として死後出版された。[142] その中で、バークは「農業を商業として捉えた政治経済学者の教義の一部」を展開した。[143] バークは、最高価格や賃金の国家規制などの政策を批判し、政府の限界について次のように述べた。 すなわち、国家は、国家に関すること、または国家が生み出したもの、すなわち、宗教の外部的な確立、その司法権、その歳入、海陸の軍事力、その命令によっ て存在する企業、一言で言えば、真に公共の利益となるものすべて、公共の平和、公共の安全、公共の秩序、公共の繁栄に限定すべきである。[144] 経済学者のアダム・スミスは、バークについて「私が知る限り、私と何の事前連絡も取らずに、経済問題について私とまったく同じように考える唯一の人物」と述べている。 1795年5月、友人宛てに書いた手紙の中で、バークは不満の原因を次のように概観している。「プロテスタント優位の原則の悪意を過大評価することはでき ないと思う。それはアイルランドに影響を及ぼし、インド主義(すなわち、イギリス東インド会社によって実践された企業による専制政治)はこれらの国々に影 響を及ぼし、アジアにも影響を及ぼしている。また、ジャコバン主義はヨーロッパ全体に影響を及ぼし、人間社会そのもののあり方に影響を及ぼしている。最後 のものは最大の悪である」[146] 1796年3月までに、バークは考えを変えていた。「わが政府とわが法は、その基盤を蝕む2つの異なる敵に囲まれている。インド教とジャコバン主義であ る。ある場合には、それらは別々に作用し、ある場合には、それらは連携して作用する。しかし、私が確信しているのは、前者がはるかに最悪であり、対処する のが最も難しいということだ。そして、この理由のひとつとして、前者は、他者に対して最大限の信用とエネルギーをもって対処すべき力を弱め、台無しにして しまうからだ。そして、それはジャコバン主義に、あらゆる正式な政府に対する最強の武器を与えることになるのだ。[147] 死の1年以上前から、バークは自分の胃が「回復不能なほど傷ついている」ことを知っていた。[36] バークが死期が近いことを知ったフォックスは、バーク夫人に彼の様子を尋ねる手紙を書いた。翌日、フォックスは返事を受け取った。 夫人はフォックス氏に敬意を表し、親切な問い合わせに感謝している。夫人は夫に手紙の内容を伝え、夫の希望により、長い友情を断ち切ることは義務の厳格な 声に従うことであり、夫にとって最も心苦しいことだったが、この犠牲は必要だと考えていること、自身の信念は変わらないこと、そして、残された人生がどの ようなものであれ、自分のためではなく他者のために生きなければならないと考えていることを、フォックス氏に伝えた。バーク氏は、自らが維持しようとして きた原則は自国の幸福と尊厳にとって必要であり、これらの原則は自らの誠実さを広く説得することによってのみ強化できると確信している。[148] バーク氏は1797年7月9日、バッキンガムシャー州のビーコンズフィールドで死去し[149]、息子と兄弟とともにそこに埋葬された。 |
| Burke is regarded by most
political historians in the English-speaking world as a liberal
conservative[150] and the father of modern British
conservatism.[151][152][153] Burke was utilitarian and empirical in his
arguments while Joseph de Maistre, a fellow European conservative, was
more providentialist and sociological and deployed a more
confrontational tone in his arguments.[154] Burke believed that property was essential to human life. Because of his conviction that people desire to be ruled and controlled, the division of property formed the basis for social structure, helping develop control within a property-based hierarchy. He viewed the social changes brought on by property as the natural order of events which should be taking place as the human race progressed. With the division of property and the class system, he also believed that it kept the monarch in check to the needs of the classes beneath the monarch. Since property largely aligned or defined divisions of social class, class too was seen as natural—part of a social agreement that the setting of persons into different classes, is the mutual benefit of all subjects. Concern for property is not Burke's only influence. Christopher Hitchens summarises as follows: "If modern conservatism can be held to derive from Burke, it is not just because he appealed to property owners in behalf of stability but also because he appealed to an everyday interest in the preservation of the ancestral and the immemorial".[155] Burke's support for the causes of the "oppressed majorities", such as Irish Catholics and Indians, led him to be at the receiving end of hostile criticism from Tories; while his opposition to the spread of the French Republic (and its radical ideals) across Europe led to similar charges from Whigs. As a consequence, Burke often became isolated in Parliament.[156][157] In the 19th century, Burke was praised by both liberals and conservatives. Burke's friend Philip Francis wrote that Burke "was a man who truly & prophetically foresaw all the consequences which would rise from the adoption of the French principles", but because Burke wrote with so much passion, people were doubtful of his arguments.[158] William Windham spoke from the same bench in the House of Commons as Burke had when he had separated from Fox and an observer said Windham spoke "like the ghost of Burke" when he made a speech against peace with France in 1801.[159] William Hazlitt, a political opponent of Burke, regarded him as amongst his three favourite writers (the others being Junius and Rousseau) and made it "a test of the sense and candour of any one belonging to the opposite party, whether he allowed Burke to be a great man".[160] William Wordsworth was originally a supporter of the French Revolution and attacked Burke in A Letter to the Bishop of Llandaff (1793), but by the early 19th century he had changed his mind and came to admire Burke. In his Two Addresses to the Freeholders of Westmorland, Wordsworth called Burke "the most sagacious Politician of his age", whose predictions "time has verified".[161] He later revised his poem The Prelude to include praise of Burke ("Genius of Burke! forgive the pen seduced/By specious wonders") and portrayed him as an old oak.[161] Samuel Taylor Coleridge came to have a similar conversion as he had criticised Burke in The Watchman, but in his Friend (1809–1810) had defended Burke from charges of inconsistency.[162] Later in his Biographia Literaria (1817), Coleridge hails Burke as a prophet and praises Burke for referring "habitually to principles. He was a scientific statesman; and therefore a seer".[163] Henry Brougham wrote of Burke that "all his predictions, save one momentary expression, had been more than fulfilled: anarchy and bloodshed had borne sway in France; conquest and convulsion had desolated Europe...[T]he providence of mortals is not often able to penetrate so far as this into futurity".[164] George Canning believed that Burke's Reflections "has been justified by the course of subsequent events; and almost every prophecy has been strictly fulfilled".[164] In 1823, Canning wrote that he took Burke's "last works and words [as] the manual of my politics".[165] The Conservative Prime Minister Benjamin Disraeli "was deeply penetrated with the spirit and sentiment of Burke's later writings".[166] The 19th-century Liberal Prime Minister William Gladstone considered Burke "a magazine of wisdom on Ireland and America" and in his diary recorded: "Made many extracts from Burke—sometimes almost divine".[167] The Radical MP and anti-Corn Law activist Richard Cobden often praised Burke's Thoughts and Details on Scarcity.[168] The Liberal historian Lord Acton considered Burke one of the three greatest Liberals, along with Gladstone and Thomas Babington Macaulay.[169] Lord Macaulay recorded in his diary: "I have now finished reading again most of Burke's works. Admirable! The greatest man since Milton".[170] The Gladstonian Liberal MP John Morley published two books on Burke (including a biography) and was influenced by Burke, including his views on prejudice.[171] The Cobdenite Radical Francis Hirst thought Burke deserved "a place among English libertarians, even though of all lovers of liberty and of all reformers he was the most conservative, the least abstract, always anxious to preserve and renovate rather than to innovate. In politics, he resembled the modern architect who would restore an old house instead of pulling it down to construct a new one on the site".[172] Burke's Reflections on the Revolution in France was controversial at the time of its publication, but after his death, it was to become his best-known and most influential work and a manifesto for Conservative thinking. Two contrasting assessments of Burke also were offered long after his death by Karl Marx and Winston Churchill. In a footnote to Volume One of Das Kapital, Marx wrote: The sycophant—who in the pay of the English oligarchy played the romantic laudator temporis acti against the French Revolution just as, in the pay of the North American colonies at the beginning of the American troubles, he had played the liberal against the English oligarchy—was an out-and-out vulgar bourgeois. "The laws of commerce are the laws of Nature, and therefore the laws of God." (E. Burke, l.c., pp. 31, 32) No wonder that, true to the laws of God and Nature, he always sold himself in the best market. In Consistency in Politics, Churchill wrote: On the one hand [Burke] is revealed as a foremost apostle of Liberty, on the other as the redoubtable champion of Authority. But a charge of political inconsistency applied to this life appears a mean and petty thing. History easily discerns the reasons and forces which actuated him, and the immense changes in the problems he was facing which evoked from the same profound mind and sincere spirit these entirely contrary manifestations. His soul revolted against tyranny, whether it appeared in the aspect of a domineering Monarch and a corrupt Court and Parliamentary system, or whether, mouthing the watch-words of a non-existent liberty, it towered up against him in the dictation of a brutal mob and wicked sect. No one can read the Burke of Liberty and the Burke of Authority without feeling that here was the same man pursuing the same ends, seeking the same ideals of society and Government, and defending them from assaults, now from one extreme, now from the other. The historian Piers Brendon asserts that Burke laid the moral foundations for the British Empire, epitomised in the trial of Warren Hastings, that was ultimately to be its undoing. When Burke stated that "[t]he British Empire must be governed on a plan of freedom, for it will be governed by no other",[173] this was "an ideological bacillus that would prove fatal. This was Edmund Burke's paternalistic doctrine that colonial government was a trust. It was to be so exercised for the benefit of subject people that they would eventually attain their birthright—freedom".[174] As a consequence of these opinions, Burke objected to the opium trade which he called a "smuggling adventure" and condemned "the great Disgrace of the British character in India".[175] According to political scientist Jennifer Pitts, Burke "was arguably the first political thinker to undertake a comprehensive critique of British imperial practice in the name of justice for those who suffered from its moral and political exclusions."[176] A Royal Society of Arts blue plaque commemorates Burke at 37 Gerrard Street now in London's Chinatown.[177] Statues of Burke are in Bristol, England, Trinity College Dublin and Washington, D.C. Burke is also the namesake of a private college preparatory school in Washington, Edmund Burke School. Burke Avenue, in The Bronx, New York, is named for him. |
英語圏の政治史家の多くは、バークをリベラル・コンサバティブ(自由主
義的保守主義者)[150]
であり、近代英国保守主義の父であるとみなしている[151][152][153]。バークは功利主義的かつ経験主義的な論法を用いるのに対し、同じく
ヨーロッパの保守主義者であるジョゼフ・ド・メイスターは、より予定説的かつ社会学的であり、論法にはより対立的なトーンが用いられている[154]。 バークは、財産は人間の生活に不可欠であると信じていた。人々は支配され管理されることを望むという信念から、財産の分割は社会構造の基礎となり、財産に 基づく階層内の統制を発展させるのに役立った。彼は、財産がもたらす社会の変化を、人類が進歩するにつれて起こるべき自然な成り行きであると捉えていた。 財産の分割と階級制度により、君主は君主の下位階級のニーズに配慮せざるを得ないとも考えていた。財産は社会階級の区分をほぼ一致させ、あるいは定義づけ るものであったため、階級もまた自然なものと見なされていた。すなわち、人々を異なる階級に配置することは、すべての臣民にとって相互利益をもたらすとい う社会的な合意の一部である。財産への関心は、バークの影響の唯一のものではない。クリストファー・ヒッチェンスは次のように要約している。「もし現代の 保守主義がバークに由来すると主張できるとすれば、それは彼が安定のために財産所有者に訴えたからだけではなく、先祖代々受け継がれてきたものを維持する ことへの日常的な関心に訴えたからでもある」[155] アイルランド・カトリック教徒やインディアンといった「虐げられた多数派」の主張を支持したことで、彼はトーリー党からの敵対的な批判の矢面に立たされる こととなった。一方、フランス共和国(およびその急進的な理想)のヨーロッパ全域への拡大に反対したことで、ホイッグ党からも同様の非難を浴びた。その結 果、バークは議会で孤立することが多かった。[156][157] 19世紀には、バークは自由主義者からも保守主義者からも賞賛された。バークの友人フィリップ・フランシスは、バークを「フランス流の原則の採用から生じ るであろうあらゆる結果を、真に、かつ予言的に予見した人物」と評したが、バークは情熱を込めて書きすぎたため、人々は彼の主張に疑いを抱いていた。ウィ リアム・ウィンダムは、バークがフォックスと決別した際に、バークと同じ議席から演説を行った。1801年にフランスとの講和に反対する演説を行った際に は、傍観者が「まるでバークの亡霊のようだった」と評したという。[159] バークの政治的反対派であったウィリアム・ヘイズリットは、バークをお気に入りの3人の作家の一人(他の二人はジュニアスとルソー)と見なし、「 「バークを偉大な人物と認めるかどうかで、反対派に属する人物の良識と率直さを試すことができる」と述べた。[160] ウィリアム・ワーズワースは当初フランス革命の支持者であり、『ランダフ司教への手紙』(1793年)でバークを攻撃したが、19世紀初頭には考えを変 え、バークを賞賛するようになった。『ウェストモーランドの自由保有者たちへの2つの演説』の中で、ワーズワースはバークを「同時代で最も賢明な政治家」 と呼び、その予言は「時が証明した」と述べた。[161] その後、ワーズワースは詩『プレリュード』の中でバークを称賛する内容を加筆し(「バークの天才よ! 魅惑的な驚異に魅入られたペンを許してくれ」)、バークを老いたオークの木として描いた。[161] サミュエル・テイラー・コールリッジは、当初『ウォッチマン』でバークを批判していたが、『友』(1809年~1810年)ではバークの一貫性のないとい う非難から擁護するなど、同様の転向を遂げた。[162] その後、コールリッジは『文学論』(1817年)でバークを預言者と称え、「常に原則に立ち返る」バークを賞賛した。彼は科学的な政治家であり、それゆえ に予見者であった」と述べた。[163] ヘンリー・ブラウームはバークについて、「彼のすべての予言は、一瞬の表現を除いて、すべて実現した。フランスでは無政府状態と流血が支配し、征服と激動 がヨーロッパを荒廃させた。... 人間の摂理が未来をこれほどまで見通すことは滅多にない」と書いた。[164] ジョージ・キャニングは、 「その後の出来事の推移によって正当性が証明された。そして、ほとんどすべての予言が厳密に実現した」と信じていた。[164] 1823年、カンニングは「バークの最後の作品と言葉は、私の政治のマニュアルである」と記している。[165] 保守党の首相ベンジャミン・ディズレーリは、「バークの晩年の著作の精神と感情に深く共感していた」という。[166] 19世紀のリベラル派の首相ウィリアム・グラッドストンは、バークを「アイルランドとアメリカに関する知恵の宝庫」と考え、日記に「バークから多くの引用 文を書き出した。時には神の啓示を受けたような気分だった」と記している。[167]急進党の国会議員で反コーン法運動の活動家リチャード・コブデンは は『思想と貧困についての考察』をしばしば賞賛した。[168] リベラルの歴史家であるロード・アクトンは、グラッドストンとトマス・バビントン・マコーリーとともに、バークを三大リベラルの一人と考えた。[169] マコーリー卿は日記に「バークの著作のほとんどを再び読み終えた。素晴らしい!ミルトン以来の偉大な人物である」と評した。[170] グラッドストーン自由党のジョン・モーリーは、バークに関する2冊の本(伝記を含む)を出版し、偏見に関する見解を含め、バークの影響を受けていた。 [171] コブデン自由党のフランシス・ハーストは、バークは「イギリスの自由主義者の一人に数えられるべきである。自由を愛する者、改革者の中で、彼は最も保守的 で、最も抽象的ではなく、常に革新よりも保存と刷新を望んでいた。政治においては、彼は古い家屋を取り壊してその跡地に新しい家屋を建設するのではなく、 古い家屋を修復する現代の建築家に似ている」と評した。[172] バークの著書『フランス革命についての省察』は出版当時は物議を醸したが、彼の死後、最もよく知られ、最も影響力のある著作となり、保守思想のマニフェス トとなった。 彼の死後、カール・マルクスとウィンストン・チャーチルは、対照的な2つの評価を提示した。マルクスは『資本論』第1巻の脚注で次のように書いている。 英国の寡頭制勢力の金で雇われ、フランス革命を賛美するロマン主義者として振る舞った追従者は、アメリカ独立戦争の初期に北米植民地から金をもらって英国 の寡頭制勢力に反対する自由主義者として振る舞ったのと同じように、あからさまな俗物的なブルジョワであった。 「商業の法は自然の法であり、したがって神の法である。」 (E. Burke, l.c., pp. 31, 32)神と自然の法則に従うのは当然であり、彼は常に最高の市場で自分を売り込んでいた。 政治における一貫性』の中で、チャーチルは次のように書いている。 一方では、バークは自由の最も優れた使徒として、他方では権威の恐るべき擁護者として明らかにされている。しかし、この生涯に適用された政治的な一貫性の 欠如という非難は、卑小なものと見える。歴史は、彼を突き動かした理由と力を容易に見抜くことができる。そして、彼が直面していた問題における大きな変化 が、同じ深遠な知性と誠実な精神から、これら全く相反する現象を引き起こしたのだ。彼の魂は、それが専制君主や腐敗した宮廷や議会制度の側面として現れた としても、あるいは、存在しない自由の合言葉を口にしながら、残忍な暴徒や邪悪な宗派の指図として彼に立ち向かったとしても、暴政に対して反旗を翻したの だ。自由のバークと権威のバークを読めば、同じ人物が同じ目的を追求し、社会と政府の理想を追い求め、それらを攻撃から守ろうとしていることが感じられ る。 歴史家のピアーズ・ブレンドンは、バークが大英帝国の道徳的基盤を築いたと主張している。その象徴がウォーレン・ヘイスティングスの裁判であり、それは最 終的に大英帝国を崩壊させることとなった。バークが「大英帝国は自由の原則に基づいて統治されなければならない。なぜなら、それ以外の方法では統治されな いからだ」と述べたとき、[173] これは「致命的な結果をもたらすことになる思想上の細菌」であった。これは、植民地政府は信託であるというエドマンド・バークの温情主義的な教義であっ た。それは、被治民が最終的に生得権である自由を獲得できるように、彼らの利益のために行使されるべきである」[174] これらの意見の結果、バークはアヘン貿易に反対し、それを「密輸の冒険」と呼び、「インドにおける英国人の大きな恥」と非難した 。政治学者ジェニファー・ピッツによると、バークは「道徳的・政治的排除の犠牲者に対する正義の名の下に、イギリス帝国の実践を包括的に批判した最初の政 治思想家である」とされる。 ロンドンのチャイナタウンにあるジェラルド・ストリート37番地には、英国王立芸術協会によるブルーク・プラークが設置され、ブルークを記念している。 ブルークの銅像は、英国ブリストル、ダブリンのトリニティ・カレッジ、ワシントンD.C.にある。また、ワシントンには私立の大学進学予備校エドマンド・ブルーク・スクールがあり、その名はブルークに由来する。 ニューヨーク市ブロンクス区のブルーク・アベニューは、彼の名にちなんで名付けられた。 |
| Criticism One of Burke's largest and most developed critics was the American political theorist Leo Strauss. In his book Natural Right and History, Strauss makes a series of points in which he somewhat harshly evaluates Burke's writings.[178] One of the topics that he first addresses is the fact that Burke creates a definitive separation between happiness and virtue and explains that "Burke, therefore, seeks the foundation of government 'in a conformity to our duties' and not in 'imaginary rights of man".[179][180] Strauss views Burke as believing that government should focus solely on the duties that a man should have in society as opposed to trying to address any additional needs or desires. Government is simply a practicality to Burke and not necessarily meant to function as a tool to help individuals live as well as possible. Strauss also argues that in a sense Burke's theory could be seen as opposing the very idea of forming such philosophies. Burke expresses the view that theory cannot adequately predict future occurrences and therefore men need to have instincts that cannot be practised or derived from ideology.[179][180] This leads to an overarching criticism that Strauss holds regarding Burke which is his rejection of the use of logic. Burke dismisses a widely held view amongst theorists that reason should be the primary tool in the forming of a constitution or contract.[179][180] Burke instead believes that constitutions should be made based on natural processes as opposed to rational planning for the future. However, Strauss points out that criticising rationality actually works against Burke's original stance of returning to traditional ways because some amount of human reason is inherent and therefore is in part grounded in tradition.[179] In regards to this formation of legitimate social order, Strauss does not necessarily support Burke's opinion—that order cannot be established by individual wise people, but exclusively by a culmination of individuals with historical knowledge of past functions to use as a foundation.[179][180] Strauss notes that Burke would oppose more newly formed republics due to this thought,[179] although Lenzner adds the fact that he did seem to believe that America's constitution could be justified given the specific circumstances.[180] On the other hand, France's constitution was much too radical as it relied too heavily on enlightened reasoning as opposed to traditional methods and values.[179] |
批判 バークの最も大規模で最も発展した批判者の一人は、アメリカの政治理論家レオ・シュトラウスであった。シュトラウスは著書『自然権と歴史』の中で、バークの著作を厳しく評価する一連の論点を提示している。 彼が最初に論じたトピックのひとつは、バークが幸福と徳を明確に区別し、「バークは、したがって、政府の基盤を『人間の想像上の権利』ではなく、『我々の 義務に適合する』ものとして求める」と説明しているという事実である。[179][180] ストラウスは、バークは政府が社会において人間が負うべき義務のみに焦点を当てるべきであり、その他のいかなるニーズや欲求にも対応しようとするべきでは ないと信じていたと見ている。政府はあくまで現実的なものであり、個人が可能な限り快適に暮らせるための道具として機能すべきであるとは限らない。 ストラウスはまた、ある意味ではバークの理論は、そのような哲学を形成するという考えそのものに反対するものとも見なされる可能性があると主張している。 バークは、理論では将来の出来事を十分に予測することはできないため、人間には訓練やイデオロギーから導き出されることのない本能が必要であるという見解 を示している。 これは、ストラウスがバークに対して抱いている批判、すなわち論理の使用を拒否しているという批判につながる。バークは、憲法や契約の形成において理性が 第一の手段であるべきだという、理論家たちの広く共有されている見解を否定している。[179][180] バークはむしろ、憲法は未来に対する合理的な計画とは対照的な自然なプロセスに基づいて作られるべきだと考えている。しかし、シュトラウスは、合理性を批 判することは、伝統的なやり方に立ち返るというバークの本来の立場に反するものであると指摘している。なぜなら、人間にはある程度の理性が備わっており、 それゆえ伝統の一部が根拠となっているからである。[179] この正当な社会秩序の形成に関して、シュトラウスは必ずしもバークの意見を支持しているわけではない。秩序は、個々の賢人によってではなく、過去の機能を 歴史的に知る個人の集大成によってのみ、基盤として確立されることはできないという意見である。 。[179][180] ストラウスは、この考え方から、バークはより新しく形成された共和国に反対するだろうと指摘しているが、[179] レンツナーは、バークはアメリカの憲法が特定の状況を考慮すれば正当化できると信じていたようだという事実を付け加えている。[180] 一方、フランスの憲法は、伝統的な方法や価値観とは対照的に、啓蒙的な理性に過度に依存しているため、あまりにも急進的であった。[179] |
| Religious thought Main article: Religious thought of Edmund Burke Burke's religious writing comprises published works and commentary on the subject of religion. Burke's religious thought was grounded in the belief that religion is the foundation of civil society.[181] He sharply criticised deism and atheism and emphasised Christianity as a vehicle of social progress.[182] Born in Ireland to a Catholic mother and a Protestant father, Burke vigorously defended the Church of England, but he also demonstrated sensitivity to Catholic concerns.[183] He linked the conservation of a state-established religion with the preservation of citizens' constitutional liberties and highlighted Christianity's benefit not only to the believer's soul, but also to political arrangements.[183] |
宗教思想 詳細は「エドマンド・バークの宗教思想」を参照 バークの宗教に関する著作は、宗教を主題とした出版作品と論評から成る。バークの宗教思想は、宗教が市民社会の基盤であるという信念に基づいている。 [181] 彼は、自然神論と無神論を厳しく批判し、社会進歩の手段としてキリスト教を強調した。[182] アイルランドでカトリックの母とプロテスタントの父の間に生まれたバークは、 イングランド国教会を擁護したが、カトリックの懸念にも配慮を示した。[183] 彼は、国家が定めた宗教の保護を、市民の憲法上の自由の保護と結びつけ、キリスト教が信者の魂だけでなく政治体制にも利益をもたらすことを強調した。 [183] |
| Bibliography A Vindication of Natural Society (1756) A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) An Account of the European Settlement in America (1757) The Abridgement of the History of England (1757) Annual Register editor for some 30 years (1758) Tracts on the Popery Laws (Early 1760s) On the Present State of the Nation (1769) Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770) On American Taxation (1774) Conciliation with the Colonies (1775) A Letter to the Sheriffs of Bristol (1777) Reform of the Representation in the House of Commons (1782) Reflections on the Revolution in France (1790) Letter to a Member of the National Assembly (1791) An Appeal from the New to the Old Whigs (1791) Thoughts on French Affairs (1791) Remarks on the Policy of the Allies (1793) Thoughts and Details on Scarcity (1795) Letters on a Regicide Peace (1795–97) Letter to a Noble Lord (1796) |
参考文献 自然社会の擁護(1756年 崇高と美の起源についての哲学的探究(1757年 アメリカにおけるヨーロッパ人の入植に関する記述(1757年 イングランド史の要約(1757年 年鑑編集者(1758年 「ポパーリー法に関する論文」(1760年代初頭) 「国民の現状について」(1769年) 「現在の不満の原因についての考察」(1770年) 「アメリカ課税について」(1774年) 「植民地との和解」(1775年) 「ブリストルの保安官への手紙」(1777年) 下院における代表制の改革(1782年) フランス革命についての考察(1790年) 国民議会の一議員への手紙(1791年) 新ホイッグ党から旧ホイッグ党への訴え(1791年) フランス情勢についての考察(1791年) 連合国の政策に関する発言(1793年) 『欠乏についての考察と詳細』(1795年) 『国王殺しの平和に関する書簡』(1795年~1797年) 『貴族への手紙』(1796年) |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke |
|
**
| A
Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and
Beautiful is a 1757 treatise on aesthetics written by Edmund Burke. It
was the first complete philosophical exposition for separating the
beautiful and the sublime into their own respective rational
categories. It attracted the attention of prominent thinkers such as Denis Diderot and
Immanuel Kant. |
崇
高と美にかんする我々の観念の起源に関する哲学的探究(A Philosophical Enquiry into the Origin of
Our Ideas of the Sublime and
Beautiful)は、1757年にエドモンド・バークが執筆した美学に関する論文である。美しいものと崇高なものをそれぞれの合理的なカテゴリーに分
離した、最初の完全な哲学的論説である。ドゥニ・ディドロやイマヌエル・カントと
いった著名な思想家の注目を集めた。 |
| According
to Burke, the Beautiful is that which is well-formed and aesthetically
pleasing, whereas the Sublime is that which has the power to compel and
destroy us. The preference for the Sublime over the Beautiful was to
mark the transition from the Neoclassical to the Romantic era. The origins of our ideas of the beautiful and the sublime, for Burke, can be understood by means of their causal structures. According to Aristotelian physics and metaphysics, causation can be divided into formal, material, efficient and final causes. The formal cause of beauty is the passion of love; the material cause concerns aspects of certain objects such as smallness, smoothness, delicacy, etc.; the efficient cause is the calming of our nerves; the final cause is God's providence. What is most peculiar and original to Burke's view of beauty is that it cannot be understood by the traditional bases of beauty: proportion, fitness, or perfection. The sublime also has a causal structure that is unlike that of beauty. Its formal cause is thus the passion of fear (especially the fear of death); the material cause is equally aspects of certain objects such as vastness, infinity, magnificence, etc.; its efficient cause is the tension of our nerves; the final cause is God having created and battled Satan, as expressed in John Milton's great epic Paradise Lost. |
バークによれば、「美」とは整った美的なものであり、「崇高」とは私た
ちを強制し、破壊する力を持つものである。そして、「美」よりも「崇高」なものが好まれ、新古典派からロマン派への移行が図られたのである。 バークにとって、美しいものと崇高なものという観念の起源は、その因果的な構造によって理解することができる。アリストテレスの物理学と形而上学によれ ば、因果関係は形式的原因、物質的原因、効率的原因、最終原因に分けられる。美の形式的原因は愛の情熱であり、物質的原因は小ささ、滑らかさ、繊細さなど 特定の物の側面に関係し、効率的原因は私たちの神経を落ち着かせることであり、最終的原因は神の摂理である。バークの美に対する考え方が最もユニークで独 創的なのは、美が従来の美の基本である比例、適合性、完全性では理解できないことである。また、崇高なものは、美とは異なる因果構造を持っている。その形 式的原因は恐怖の情熱(特に死の恐怖)であり、物質的原因は広大さ、無限性、壮大さなど特定の対象の等しい側面であり、効率的原因は神経の緊張であり、最 終的原因はジョン・ミルトンの大作「失楽園」で表現されているように、神がサタンを創造し戦ったことである。 |
| Kant's comments Immanuel Kant critiqued Burke for not understanding the causes of the mental effects that occur in the experience of the beautiful or the sublime. According to Kant, Burke merely gathered data so that some future thinker could explain them. To make psychological observations, as Burke did in his treatise on the beautiful and the sublime, thus to assemble material for the systematic connection of empirical rules in the future without aiming to understand them, is probably the sole true duty of empirical psychology, which can hardly even aspire to rank as a philosophical science. — Immanuel Kant, First Introduction to the Critique of Judgment, X.[1]- Kant, Immanuel, First Introduction to the Critique of Judgment, Library of Liberal Arts, 146, Bobbs-Merril Co., 1965 |
カントのコメント イマヌエル・カントは、美しいものや崇高なものの体験に生じる精神的作用の原因を理解していないとバークを批判している。カントによれば、バークは、将来 の思想家が説明できるようにデータを集めたに過ぎない。 バークが『美と崇高に関する論考』で行ったように、心理学的観察を行うこと、つまり、それらを理解しようとせずに、将来、経験則を体系的に結びつけるため の材料を集めること、これがおそらく、哲学的科学としての地位さえほとんど望めない経験心理学の唯一の真の任務であろう。 - イマヌエル・カント『判断力批判への第一序説』X.[1]。- Kant, Immanuel, First Introduction to the Critique of Judgment, Library of Liberal Arts, 146, Bobbs-Merril Co., 1965 |
| Vermeir,
Koen and Funk Deckard, Michael (eds.) The Science of Sensibility:
Reading Burke's Philosophical Enquiry (International Archives of the
History of Ideas, Vol. 206) (Springer, 2012) Doran, Robert. The Theory of the Sublime from Longinus to Kant. Cambridge:Cambridge University Press, 2015. https://en.wikipedia.org/wiki/A_Philosophical_Enquiry_into_the_Origin_of_Our_Ideas_of_the_Sublime_and_Beautiful |
https://www.deepl.com/ja/translator |
| A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of The Sublime and Beautiful With Several Other Additions, complete text | |
| Part I. Novelty Pain and Pleasure The Difference Between the Removal of Pain, and Positive Pleasure Of Delight and Pleasure as Opposed to Each Other Joy and Grief Of the Passions Which Belong to Self-Preservation Of the Sublime Of the Passions Which Belong to Society The Final Cause of the Difference Between the Passions Belonging to Self-Preservation and Those Which Regard the Society of the Sexes Of Beauty Society and Solitude Sympathy, Imitation, and Ambition Sympathy The Effects of Sympathy in the Distresses of Others Of the Effects of Tragedy Imitation Ambition The Recapitulation The Conclusion Part II. Of the Passion Caused by the Sublime Terror Obscurity Of the Difference Between Clearness and Obscurity with Regard to the Passions The Same Subject Continued Power Privation Vastness Infinity Succession and Uniformity Magnitude in Building Infinity in Pleasing Objects Difficulty Magnificence Light Light in Building Colour Considered as Productive of the Sublime Sound and Loudness Suddenness Intermitting The Cries of Animals Smell and Taste. Bitters and Stenches Feeling. Pain Part III. Of Beauty Proportion not the Cause of Beauty in Vegetables Proportion not the Cause of Beauty in Animals Proportion not the Cause of Beauty in the Human Species Proportion Further Considered Fitness not the Cause of Beauty The Real Effects of Fitness The Recapitulation Perfection not the Cause of Beauty How Far the Idea of Beauty May be Applied to the Qualities of the Mind How Far the Idea of Beauty May be Applied to Virtue The Real Cause of Beauty Beautiful Objects Small Smoothness Gradual Variation Delicacy Beauty in Colour Recapitulation The Physiognomy The Eye Ugliness Grace Elegance and Speciousness The Beautiful in Feeling The Beautiful in Sounds Taste and Smell The Sublime and Beautiful Compared Part IV. Of the Efficient Cause of the Sublime and Beautiful Association Cause of Pain and Fear Continued How the Sublime is Produced How Pain Can be a Cause of Delight Exercise Necessary for the Finer Organs Why Things not Dangerous Produce a Passion Like Terror Why Visual Objects of Great Dimensions are Sublime Unity, Why Requisite to Vastness The Artificial Infinite The Vibrations Must be Similar The Effects of Succession in Visual Objects Explained Locke’s Opinion Concerning Darkness Considered Darkness Terrible in its Own Nature Why Darkness is Terrible The Effects of Blackness The Effects of Blackness Moderated The Physical Cause of Love Why Smoothness is Beautiful Sweetness, Its Nature Sweetness, Relaxing Variation, Why Beautiful Concerning Smallness Of Colour Part V. Of Words The Common Effects of Poetry, Not by Raising Ideas of Things General Words Before Ideas The Effect of Words Examples that Words May Affect Without Raising Images Poetry not Strictly an Imitative Art How Words Influence the Passions https://www.bartleby.com/24/2/ |
|
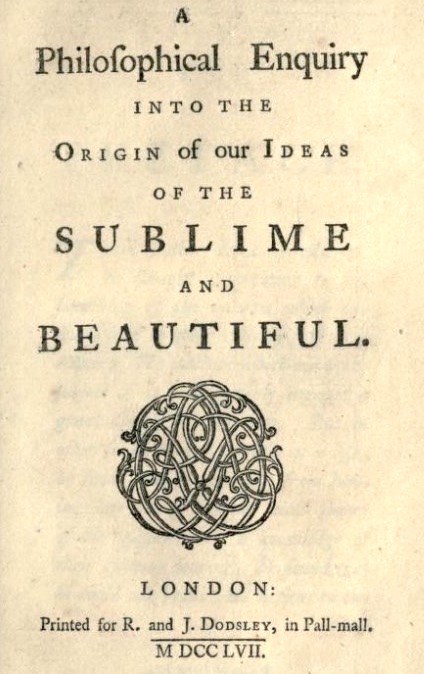
A philosophical enquiry
into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. 1757.
+++
Links
リンク
文献
その他の情報


