カントの「物自体」にまつわる疑問
The question on "Ding an sich (noumenon)," by I. Kant
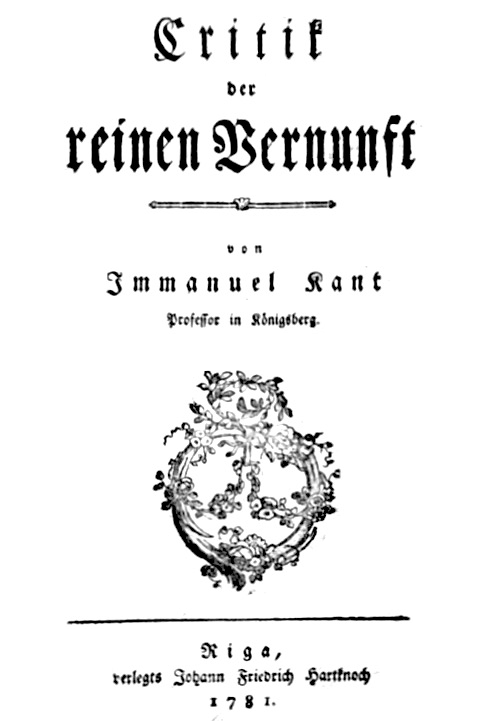
カントの「物自体」にまつわる疑問
The question on "Ding an sich (noumenon)," by I. Kant
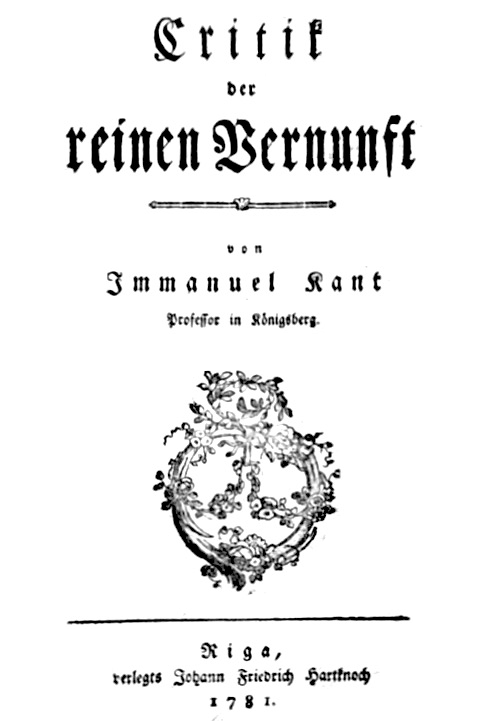
★物自体(Ding an sich, neumenon)は、イマニュエル・カ ントの二元論哲学によって本質的に特徴づけ られる概念であるが、彼の全集では、多数の、時には互換性のない意味で使用されている。しかし、この用語は、いわゆる理解可能な物体、または理解可能な原 因の思考可能な実体に対する総称として主に使用されており、両者とも純粋な直観(経験)には対応しないものと定義されている。
1781年『純粋理性批判』Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Riga: J. F. Hartknoch 1781, 856 Seiten, Erstdruck.
☆我々は、外から与える感覚情報を受け身に
捉えるのではない。
認識が可能なのは、我々の精神が経験を組織化し体系づける能動的な作業によっておこなわれる。
我々は、時間と空間と実体という枠組み(カテゴリー)により世界を認知している。
時間と空間と実体は、我々と独立して存在するのではない。それらは、我々の直観や理性(つまり想像)の産物であり、それなしには捉えられない。
では、世界の実体はどのようなものか?(このカントの問題の立て方が、アルキメデスの立場や視座を想定してナンセンスなのだが)カントはそれ答えられな
い。そのような「独立した実体」(←これもナンセンス)を物自体(Ding an
sich)と呼ぶ。物自体の世界には、永遠に認識できない世界がだが、それはかつてのキリスト教の「天国」のようだ。それゆえ、神学者は、カントのこの
「物自体」という仮想の(独立した実体の)世界を反キリスト教的なものだと、その匂いを嗅ぎつけた。
| Das Ding an sich
ist ein Begriff, der in der modernen Erkenntnistheorie wesentlich von
Immanuel Kants dualistischer Philosophie geprägt ist, wobei er in
dessen Gesamtwerk in zahlreichen, teils miteinander nicht vereinbaren
Bedeutungen verwendet wird. Vorwiegend gilt der Terminus aber als
Oberbegriff für sogenannte intelligible Gegenstände oder für die
denkmögliche Entität einer intelligiblen Ursache, die beide dadurch
bestimmt sind, keine Entsprechung in der reinen, folglich auch nicht in
der sinnlichen Anschauung (Erfahrung) zu haben. |
物自体は、イマニュエル・カントの二元論哲学によって本質的に特徴づけ
られる概念であるが、彼の全集では、多数の、時には互換性のない意味で使用されている。しかし、この用語は、いわゆる理解可能な物体、または理解可能な原
因の思考可能な実体に対する総称として主に使用されており、両者とも純粋な直観(経験)には対応しないものと定義されている。 |
| Begriffsgeschichte In der Folge der Einführung der aristotelischen Kategorien wird in der Scholastik zwischen dem unterschieden, was einer Sache als akzidentale Eigenschaft und was ihr „an sich“, also als notwendige Eigenschaft zukommt, wobei „an sich“ dem griechischen kath’auto (aus sich selbst heraus) und dem lateinischen per se entspricht. So ist der Mensch an sich, notwendigerweise, körperlich, der Körper aber nicht per se menschlich. Dabei war der scholastische Diskurs noch weithin von dem sogenannten Universalienstreit um den Nominalismus geprägt: letzterer betrachtete die allgemeinen Begriffe allein als im Namen (Wort) befindlich, also als Gedankendinge – etwa die „Menschheit“, die so wenig existiere wie die „Pferdheit“. Die annähernd kantische Bedeutung des Dinges an sich findet sich dagegen erstmals bei Descartes, der zwischen der Erscheinung von Dingen in der Einheit von Geist und Verstand und äußeren Körpern an sich unterscheidet, von denen er aber anmerkt, sie könnten sich der Erkenntnis gegebenenfalls erschließen: „Es genügt, wenn wir beachten, dass die sinnlichen Wahrnehmungen nur jener Verbindung des menschlichen Körpers mit der Seele zukommen und uns in der Regel sagen, wiefern äußere Körper derselben nützen oder schaden können, aber nur bisweilen und zufällig uns darüber belehren, was sie an sich selbst sind.“ (Phil. Pr., II, 3) Nach Auffassung von Alexander Gottlieb Baumgarten wurde das „Ding an sich“ eine weit verbreitete Konzeption der französischen Philosophie, von D’Alembert[1], Condillac[2], Bonnet[3] und Maupertuis (Lettres, IV) verwendet, wobei Schopenhauer die Darlegungen des letzteren zu der Annahme verleiteten, Kant habe den Gedanken von Maupertuis übernommen (WWuV, II). Doch von Frankreich aus fand das neue philosophische Modewort den Weg auch bald in die deutschsprachigen Lehrbücher der Metaphysik, so dass es schon zu Kants Studienzeiten auch in Königsberg ein Gemeinplatz der Philosophie war.[4] |
用語の歴史 アリストテレスの範疇論の導入に伴い、スコラ学では、物に帰属する偶発的性質と、物に「それ自体」帰属する性質、すなわち、必然的性質として区別されるよ うになった。「それ自体」は、ギリシャ語の「カタウト(それ自体の外)」とラテン語の「ペルセ(それ自体)」に対応する。したがって、人間はそれ自体必然 的に物理的であるが、身体はそれ自体人間ではない。同時に、スコラ学の議論は依然として、名実論を巡るいわゆる普遍論争によって特徴付けられていた。後者 は一般的な概念は名称(言葉)にすぎず、したがって「人間性」のような精神現象であるとみなしていた。「人間性」は「馬性」と同様に実在しない。 物自体(thing-in-itself)というほぼカント的な意味は、デカルトによって初めて用いられた。デカルトは、精神と理解の統一における事物の 表れと、外部の物体そのものを区別しているが、必要であればそれらを知ることができると指摘している。「 感覚は人間の肉体と魂のつながりだけを感知し、通常は外部の物体が肉体に利益をもたらすか害を与えるかを告げるが、それ自体が何であるかについては、時 折、偶発的にしか教えないことに留意すれば、」 (Phil. Pr., II, 3) アレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルテンによると、「物自体」という概念はフランス哲学において広く浸透し、ダランベール[1]、コンディヤック [2]、ボネ[3]、モーペルテュイ(『書簡』第4巻)によって用いられ、ショーペンハウアーの説明からカントがモーペルテュイの考えを借用したと考える ようになった(『世界観』第2巻)。しかし、フランスから新しい哲学用語はすぐにドイツ語の形而上学の教科書にも登場し、カントが学生だった頃には、ケー ニヒスベルクでも哲学の決まり文句となっていた。 |
| Die kantischen Definitionen Wie auch bei anderen Begriffen, die Kant übernimmt und neu definiert, ist die Bedeutung des Dinges an sich keineswegs einheitlich. Durch den Wandel des kantischen Gedankens von der vorkritischen zur kritischen Periode wird die Begriffsverwirrung in der Rezeption selbst in Fachlexika (z. B. Eisler) noch verstärkt, so dass als eine chronologische Grenze der Definition zunächst die Kritik der reinen Vernunft genannt werden muss, da Kant in der Dissertation von 1770 (Mund. sens.) davon überzeugt war, dass die Verstandesbegriffe die Dinge so geben, „wie sie sind“ (ebd., § 4), was in der Transzendentalen Deduktion des kritischen Hauptwerkes methodisch zurückgewiesen wird. Ist der Begriff dort aber noch im Wesentlichen als „problematisch“ bewertet, so erhält er im Verlauf der Formulierung in der Kritik der praktischen Vernunft einen zunehmend affirmativen Charakter, was sich auch in Kants Verteidigung gegen den Vorwurf des Idealismus in den Prolegomena niederschlägt. Im kantischen Gesamtwerk, in dem die Formulierung über hundert Mal verwendet wird, lassen sich wenigstens die folgenden Konnotationen erkennen, deren genaue Bestimmung dadurch weiter erschwert wird, dass diese Unterbegriffe zunächst voneinander abgegrenzt, dann aber gelegentlich als synonyme Zusätze – etwa in Klammern – teils auch ohne Bezug auf das Lemma, wieder gleichgesetzt werden. 1. reines Gedankending, Verstandeswesen, Noumenon 1.1 Gegenstand, der bleibt, wenn man von allen subjektiven Bedingungen der Anschauung und den Gesetzen des Erkennens absieht: gedachter Gegenstand ohne räumliche Ausdehnung jenseits der Zeit und der Kausalität, (KrV A 30; B 42; B 164; B 306) 1.2 Gegenstände der Sinnenwelt in „ihrer Beschaffenheit an sich selbst“, jenseits der „Art, wie wir sie anschauen“; andere Beziehung auf das Objekt, (KrV B 306; Convolut VII), unbekannter Gegenstand hinter den Erscheinungen, auch: „transzendentaler Gegenstand“ (KrV, A 191/B 236) 2. Transzendentales Objekt, (auch: „Transzendentaler Gegenstand“), „Correlatum der Einheit der Apperzeption“ (KrV, A 250), „Erfahrungseinheit“, (KrV A 108) 3. causa sui, die „intelligible Ursache“, die Ursache aus Freiheit, im Gegensatz zur Kausalität, als dem bestimmenden Merkmal der „Dinge an sich“, in diesem Kontext auch „Sachen an sich selbst“, (Prolegomena § 53; GMS BA 107; KrV B XXXI; B XXXVII f.; A 418; A 538-541/B 566-569) 4. allein durch die Kategorie gedachte Substanz, (AA IV, KrV, S. 217) 5. als Ausnahme: realer Gegenstand in der Überzeugung empirischer Lehren, d. i. eines positivistischen, unangezweifelten Daseins der Dinge (KrV B 164; A 130) Die Bestimmungen und damit die Bedeutungen innerhalb des kritischen Gedankens sind teils ergänzend, teils unterscheiden sie sich aber auch ganz erheblich: so sind die Noumena der ersten Bedeutung bestimmbar, das transzendentale Objekt dagegen nicht. Dem Letzteren kann also kein Prädikat zugewiesen werden, den Noumena schon. Diese stellen einen „Grenzbegriff“ der Möglichkeit des sinnlichen Erkennens dar, während aber die causa sui aus einem Vernunftschluss entsteht und den Regress in der Kette der Ursachen betrifft. Somit kann nur im jeweiligen Kontext entschieden werden, um welche der Bedeutungen es sich handelt, wobei die Exegese nicht in jedem Fall zu unstreitigen Resultaten führt. Wird der Terminus „Ding an sich“ als ein von Kant de facto, wenn auch nicht explizit so behandelter Oberbegriff betrachtet, so ist das gemeinsame Merkmal (dictum de omni et nullo) der gelisteten Unterbegriffe, bis auf die Ausnahme (5), aber als die Unmöglichkeit der reinen, darum auch der empirischen Anschauung des Gegenstandes zu erkennen. Dabei ist die Bedeutung (5) von Kant naturgemäß nicht gesetzt, sondern wird als apagogischer Beweis zu didaktischen Zwecken verwendet (d. i.: wäre es ein Ding an sich, so müsste – argumentum – also kann es kein solches sein.) Bezeichnend für die kantische Erkenntnistheorie ist folgendes Zitat aus der Kritik der reinen Vernunft: „Wenn wir aber auch von Dingen an sich selbst etwas durch den reinen Verstand synthetisch sagen könnten (welches gleichwohl unmöglich ist), so würde dieses doch gar nicht auf Erscheinungen, welche nicht Dinge an sich selbst vorstellen, gezogen werden können. Ich werde also in diesem letzteren Falle in der transscendentalen Überlegung meine Begriffe jederzeit nur unter den Bedingungen der Sinnlichkeit vergleichen müssen, und so werden Raum und Zeit nicht Bestimmungen der Dinge an sich, sondern der Erscheinungen sein: was die Dinge an sich sein mögen, weiß ich nicht und brauche es auch nicht zu wissen, weil mir doch niemals ein Ding anders als in der Erscheinung vorkommen kann.“[5] Gemäß der grundlegenden Satzung der Kritik der reinen Vernunft, die Grenzen der Möglichkeit einer Ontologie darzulegen, werden die Bedeutungen des Oberbegriffes und der gelisteten Unterbegriffe in der Elementarlehre also als „problematisch“ definiert und verwendet, demnach als bloße Möglichkeiten der seinsphilosophischen Reflexion. Schon in der Methodenlehre und dem dortigen Vorgriff auf die praktische Vernunft zeichnet sich aber ab, dass Kant daran nicht festhalten, sondern, wenn auch nur um einen Grad, die Konnotation des Affirmativen des Begriffes zulassen wird, was nicht allein der Notwendigkeit für die Konzeption des homo noumenon der Kritik der praktischen Vernunft entspringt, sondern auch jener, den transzendentalen Gedanken gegen den Idealismus im Sinne Berkeleys abzugrenzen. In den Prolegomena, dem Kommentar der Kritik der reinen Vernunft für die akademische Lehrtätigkeit, wird der Begriff in diesem Sinne gefasst: „Demnach gestehe ich allerdings, daß es außer uns Körper gebe, d. i. Dinge, die, obzwar nach dem, was sie an sich selbst sein mögen, uns gänzlich unbekannt, wir durch die Vorstellungen kennen, welche ihr Einfluß auf unsre Sinnlichkeit uns verschafft, und denen wir die Benennung eines Körpers geben; welches Wort also blos die Erscheinung jenes uns unbekannten, aber nichts desto weniger wirklichen Gegenstandes bedeutet. Kann man dieses wohl Idealismus nennen? Es ist ja gerade das Gegentheil davon.“[6] Neben dem homo noumenon ist die Formulierung des „wirklichen Gegenstandes“ wesentlich jene, mit der Kant, indem er die Kritiker der einen Seite zurückwies, die der anderen herausforderte, da die Wirklichkeit gemäß der transzendentalen Lehre ein Verstandesbegriff und nicht auf Dinge an sich anwendbar ist. Doch es heißt dort auch: „Der Grundsatz, der meinen Idealism durchgängig regiert und bestimmt, ist dagegen: 'Alles Erkenntniß von Dingen aus bloßem reinen, Verstande oder reiner Vernunft ist nichts als lauter Schein, und nur in der Erfahrung ist Wahrheit.'“[7] Rezeption und Wirkungsgeschichte Aenesidemus Das „Ding an sich“ wurde zu einem zentralen Sujet der Kritik an Kant, in der das Merkmal der Unerkenntlichkeit bald dazu führte, die Konzeption zurückzuweisen, beginnend mit dem Idealismus-Vorwurf der Göttinger Rezension und gefolgt von Gottlob Ernst Schulze (Aenesidemus, 1792), der auf Carl Leonhard Reinholds Briefe über die kantische Philosophie von 1786 bis 1787 reagierte. Kant hatte in der Kritik der reinen Vernunft[8] und den Prolegomena dargelegt, dass Naturgesetze und Kausalität nicht für Dinge an sich gelten. Wie die Seele nicht den Naturgesetzen unterworfen ist, kann das Gedankending, z. B. „das unendliche Wesen“, auch nicht in einer kausalen Zeitreihe oder in der Zeit überhaupt gedacht werden.[9] Dennoch wählte Schulze für seine Kritik das Argument, dass auf das „Ding an sich“ als „Ursache des Stoffs der empirischen Erkenntnis“ die Kategorie der Kausalität nicht anzuwenden sei, wobei er sich allerdings nicht direkt auf Kant, sondern auf Reinhold bezog: Ist „das Prinzip der Caussalität außer unserer Erfahrung ungiltig, so ist es ein Mißbrauch der Verstandesgesetze, wenn man den Begriff Ursache auf etwas anwendet, so außer unsern Erfahrungen und gänzlich unabhängig von den selben da seyn soll. Wenn also auch die kritische Philosophie gar nicht gerade zu leugnet, daß es Dinge an sich, als Ursachen des Stoffs der empirischen Erkenntnisse gäbe, so muß sie doch eigentlich, vermöge ihrer eigenen Prinzipien, der Annahme einer solchen obiektiven und transscendentalen Ursache des Stoffes unserer empirischen Erkenntniß alle Realität und Wahrheit absprechen, und nach ihren eigenen Grundsätzen ist also nicht nur der Ursprung des Stoffes der empirischen Erkenntniß, sondern auch deren ganze Realität, oder deren wirkliche Beziehung auf etwas außer unsern Vorstellungen völlig ungewiß und für uns = x.“[10] Dabei lag der Einwand nahe, dass ein Ding an sich selbst zwar nie Erscheinung ist, aber doch der denkbare Grund davon sein kann, und für die Erscheinungen gilt die Kausalität, auch eine durch Freiheit. Demnach müssen die „Ursachen des Stoffs der empirischen Erkenntnisse“ selbst nicht zu den letzteren gehören – wie der freie Wille als Ursache für ein Ereignis weder Erscheinung noch der (notwendigen) Kausalität unterworfen ist. In diesem Sinn unterscheidet Kant die „Ursache in der Erscheinung“ (das heißt, die Ursache ist Teil der Erscheinung) von der „Ursache der Erscheinung“.[11] In die gleiche Richtung wie Schulze argumentierte auch Friedrich Heinrich Jacobi. Nach ihm kommt man ohne das Ding an sich nicht in das Kantsche System hinein, mit ihm kann man nicht darin bleiben.[12] |
カントの定義 カントが採用し再定義した他の用語と同様に、「物自体」という概念の意味は決して一様ではない。カントの思想が前批判期から批判期へと変化したことによ り、専門的な百科事典(例えばアイスラー)でさえ、その概念の受容における混乱はさらに大きくなった。そのため、『純粋理性批判』は当初、定義の年代的な 境界として言及されるべきである。なぜなら、カントは 1770年の論文(『感覚の概念』)において、カントは「理解」の概念が物自体を「ありのまま」に捉えていると確信していたが(同書、第4項)、これは主 要な批判的著作である『超越論的導出』において系統的に否定されている。しかし、その概念が依然として本質的に「問題がある」と評価されている場合、実践 理性批判における定式化の過程で、その概念はますます肯定的な性格を帯びるようになる。これは、プロレゴメナにおける観念論の非難に対するカントの弁明に も反映されている。 この概念は、100回以上使用されているカント全集において、少なくとも以下の含意が認められる。しかし、これらの下位概念は、まず互いに区別されるが、 その後、時には同義語として括弧内に追加されるなど、同義語として同一視される場合もあり、厳密な定義はさらに複雑になる。 1. 純粋な思考-物、知的存在、ヌーメン 1.1 知覚の主観的条件や認識の法則をすべて無視したときに残る対象:時間や因果関係を超えた空間的拡張性なしに考えられる対象(KrV A 30; B 42; B 164; B 306) 1.2 感覚世界の対象は、「それ自体の性質」において、「我々の見方」を超えたものとなる。対象に対する他の関係、(KrV B 306; Convolut VII)、外見の背後にある未知の対象、また「超越論的対象」(KrV, A 191/B 236) 2. 超越論的対象(「超越論的主観」「超越論的主体」とも)、「統覚の統一の相関物」(KrV, A 250)、「経験の単位」(KrV A 108) 3. 原因、すなわち「理解可能な原因」、自由の原因、因果関係とは対照的に、「物自体」の定義的特徴として、この文脈では「物自体」も意味する(『プロレゴメ ナ 現象 § 53; GMS BA 107; KrV B XXXI; B XXXVII f.; A 418; A 538-541/B 566-569) 4. カテゴリーのみを通じて考えられる実体 (AA IV, KrV, p. 217) 5. 例外として:経験的教えの信念における実体、すなわち実証主義的で議論の余地のない物自体(KrV B 164; A 130) 批判的思考における決定およびそれゆえの意味は、部分的に補完的であるが、部分的にかなり異なる。つまり、最初の意味におけるヌーメンは決定可能である が、超越論的対象はそうではない。したがって、後者には述語を割り当てることができないが、物自体には可能である。これらは感覚知覚の可能性の「境界線上 の概念」を表している。一方、自己原因は理性の結論から生じ、原因の連鎖における後退に関係している。したがって、それぞれの文脈において、どちらの意味 が関わっているかを決定するしかない。それにより、解釈は常に議論の余地のない結果にはつながらない。「物自体」という用語が、カントがそう扱っている一 般的な用語であるとみなされる場合、明示的ではないにせよ、リストアップされた下位用語の共通の特徴(dictum de omni et nullo)は、(5)を除いて、対象の純粋な、したがって経験的な見方が不可能であると認識することができる。この文脈において、(5)の意味はカント によって定められたものではなく、教訓的な目的のためのアパゴニック証明として使用されている(すなわち、もしそれが物自体であるならば、論証として、そ れは物自体であることは不可能でなければならない)。 『純粋理性批判』からの次の引用は、カントの認識論の特徴を表している。「しかし、もし純粋理性によって物自体について何かを言えるとしても(それは不可 能 である)、それを物自体ではない現象に適用することはできない。後者の場合、私は超越論的考察における概念を常に感覚的な条件の下でのみ比較しなければな らない。したがって、空間と時間は物自体ではなく現象の決定となる。物自体がどのようなものであるかは私にはわからないし、知る必要もない。なぜなら、物 自体は決して現象以外の形で私に現れることはないからだ。」[5] 純粋理性批判の根本原則に従い、存在論の可能性の限界を示すことを目的とするこの方法論では、一般的な用語と列挙された下位用語の意味は、このように定義 され、初歩的な教義の中で「問題のある」ものとして使用され、したがって、存在の哲学における単なる反映の可能性として使用される。しかし、カントがこれ に固執せず、ある程度までは肯定的な概念の意味合いを許容することは、実践理性の方法論と予見においてすでに明らかである。肯定的な概念の意味合いは、実 践理性批判におけるホモ・ヌーメノンの概念の必要性から生じるだけでなく、バークレーの感覚における観念論から超越論的観念を区別する必要性からも生じ る。 純粋理性批判』の学術的な教授のための注釈書である『プロレゴメナ』では、この概念は次のように定義されている。「したがって、私は確かに、私たち以外の 物体、つまり、私たちがその存在をまったく知らない それ自体は、私たちにとってまったく未知のものであるが、それらのものが私たちの感覚に及ぼす影響によって得られる表象を通じて、私たちはそれらを知覚 し、それらに「物体」という名を与える。この言葉は、それゆえ、私たちにとって未知の対象の「外観」を意味するにすぎないが、それゆえといって、その実在 性が損なわれるわけではない。これを観念論と呼べるだろうか? 結局のところ、それは観念論の正反対である。」[6] ホモ・ヌーメノンに加えて、「現実の物体」という概念は、本質的には、カントが一方の批判を退ける一方で、もう一方の批判に挑んだものである。超越論的教 義によれば、現実とは心の概念であり、物自体に適用することはできないからだ。しかし、次のように述べている。「私の理想主義を貫く原則は、対照的に、 『純粋理性による物自体の知識は、純粋な現象にすぎず、真理は経験の中にある』というものである。」[7] 受容と影響 エネシデモス 「物自体」はカント批判の中心的なテーマとなり、その不可知性の特徴は、ゲッティンゲン批評の観念論的告発に始まり、カール・レオンハルト・ラインホルト の『カント哲学に関する書簡』(1786年から1787年)に反応したゴットロープ・エルンスト・シュルツ(『エネシデモス』、1792年)に引き継が れ、やがてその概念の拒絶へとつながった。純粋理性批判[8]およびプロレゴメナにおいて、カントは自然法則や因果関係は物自体には適用されないと説明し ている。魂が自然法則に従わないのと同様に、「無限の存在」といった思考の対象は、因果的な時間系列や時間そのものにおいて捉えることはできない。 それにもかかわらず、シュルツはカントではなくラインホルトを直接的に参照しているものの、「経験的知識の素材の原因」として「物自体」に因果性のカテゴ リーを適用できないという主張を批判することを選んだ。因果律の原則が我々の経験の外では無効であるならば、経験の外に存在し、経験とは完全に独立してい るはずの何かに原因という概念を適用することは、理解の法則の誤用である。批判哲学が経験的知識の素材の原因となる物自体の存在を厳密に否定しないとして も、しかし、実際には、その独自の原則に基づいて、経験的知識の素材のそのような客観的かつ超越的な原因の想定を否定しなければならない 。そして、その原則によれば、経験的知識の素材の起源だけでなく、その全体的な実在性、すなわち、観念の外にあるものとの現実的な関係性も、完全に不確か であり、私たちにとって=xである。」[10] これに対する明白な反論は、物自体は決して現象ではないかもしれないが、それでもなお、現象の原因として考えられるものであり、因果関係は自由によって決 定されるものも含めた現象に適用される、というものである。したがって、「経験的知識の素材の原因」自体は後者に属する必要はない。自由意志が、ある出来 事の原因であるように、それは現象でもなければ、(必然的な)因果関係に従属するものでもない。この意味において、カントは「現象における原因」(すなわ ち、原因は現象の一部である)と「現象の原因」を区別している。[11] フリードリヒ・ハインリヒ・ヤコビもシュルツと同じ方向で論じている。彼によれば、物自体なしにはカントの体系に入ることができず、物自体があればその体 系にとどまることができる。[12] |
| Die Position Hegels und Fichtes Auf der anderen Seite wurde der bei Kant für unmöglich erklärte Begriff des intellectus intuitivus, also eine rein begriffliche, intellektuelle Anschauung, von dem von Kant selbst noch geförderten Fichte als eine Möglichkeit benutzt – womit also das Problematische aufgehoben war –, das Ich zum Prinzip der Existenz an sich zu erheben (Wissenschaftslehre, 1794, § 4), was dazu beitrug, die romantische Periode der deutschen Philosophie einzuleiten. Auch Hegel erklärte Kants These, dass das „Ding an sich“ grundsätzlich nicht zu erkennen sei und nur Erscheinungen erkannt werden können, für eine Absage an den Wahrheitsanspruch der Philosophie. Das „Ding an sich“ bleibe so „jenseits des Denkens“.[13] Er hält ihm entgegen, dass das an sich seiende Ding selbst ein Gedankending ist und als „subjektive Bedingung des Erkennens“[14] damit wieder ins Denken (ins Subjekt) zurückfällt.[15] Er hält es für einen sonderbaren Widerspruch Kants. Die Konsequenz wäre eine nicht weiter zu schließende Differenz. Das Ich bleibe so immer in seiner Subjektivität eingeschlossen und komme nicht zum „wahren Inhalt“. Hegels philosophisches Denken bemühte sich darum, gerade dieses Problem zu überwinden. Im Erkennen der Erscheinung ist für Hegel schon die Wahrheit beider Momente (Subjektivität – Objektivität) enthalten. Doch Kant sieht dieses objektive Moment der Erscheinung nicht. „Erkennen ist in der Tat ihre Einheit; aber bei der Erkenntnis hat Kant immer das erkennende Subjekt als einzelnes im Sinne. Das Erkennen selbst ist die Wahrheit beider Momente; das Erkannte ist nur die Erscheinung, Erkennen fällt wieder ins Subjekt.(…) Denn es enthält (bei Kant, Anm.) die Dinge nur in der Form der Gesetze des Anschauens und der Sinnlichkeit.“[16] Er wirft Kant also im Grunde vor, seine Begrifflichkeiten nicht genau überprüft zu haben. Da es sich bei dem Ding an sich um eine Abstraktion von jeglichem Inhalt handele, sei nichts leichter, als das Ding an sich zu wissen.[17] In den Antinomien der Kritik der reinen Vernunft habe Kant die in sich widersprüchliche Natur der Vernunft aufgedeckt. „Die wahre und positive Bedeutung der Antinomien besteht nun überhaupt darin, dass alles Wirkliche entgegengesetzte Bestimmungen in sich enthält und dass somit das Erkennen und näher das Begreifen eines Gegenstandes eben nur soviel heißt, sich dessen als einer konkreten Einheit entgegengesetzter Bestimmungen bewusst zu werden.“[18] |
ヘーゲルとフィヒテの立場 一方、カントが不可能であると宣言した直観知(intellectus intuitus)の概念、すなわち純粋に概念的な知的直観は、カント自身に支持されていたフィヒテによって可能性として用いられた。これにより、自我を 存在の原理そのものに高めるという問題(『純粋理性批判』1794年、第4項)を克服し、ドイツ哲学におけるロマン主義の時代を先導することとなった。 ヘーゲルもまた、「物自体」は本質的に知ることができず、知ることができるのは外見だけであるというカントの命題は、哲学の真理への主張を否定するもので あると宣言した。したがって、「物自体」は「思考を超えたもの」のままである。[13] 彼は、「物自体」はそれ自体が思考の対象であり、「知識の主観的条件」[14] として、思考(主観)に回帰するものであると論じている。[15] 彼はこれをカントの奇妙な矛盾であると考えている。その結果、不可逆的な差異が生じる。自我は常に主観性に閉じ込められたままであり、「真のコンテンツ」 に到達することはない。ヘーゲルの哲学思想は、まさにこの問題の克服を目指した。ヘーゲルにとって、両者の瞬間(主観性-客観性)の真実は、現象の認識に すでに含まれている。しかし、カントは現象の客観的な瞬間を見出していない。 「認識は確かに両者の統一である。しかし、認識となると、カントは常に認識主体を単一の存在として念頭に置いている。認識そのものが両者の真実である。認 識されるものは外見にすぎず、認識は主体に立ち戻る。(...)なぜなら、カントの場合は、物自体は直観と感覚の法則の形でのみ物を含んでいるからだ」 [16] 彼は基本的にカントが自身の概念を注意深く検討していないと非難している。物自体はあらゆる内容から抽象されたものであるため、物自体を知る以上に簡単な ものはない。『純粋理性批判』の二律背反において、カントは理性の本質的な矛盾性を明らかにした。 「アンチノミーの真の意味と積極的な意味は、現実のすべてがそれ自体に相反する決定を含んでいるという事実であり、したがって、対象の認識、より正確には 理解とは、相反する決定の具体的な統一体としてそれを認識することに他ならない」[18] |
| Schopenhauer Arthur Schopenhauer machte von dem „Ding an sich“ einen Gebrauch, den Kant sicher abgelehnt hätte und gründete den Weltwillen auf diese Konzeption. Der Kommentar zu dem so begründeten kantischen Dualismus fiel wohl auch deshalb euphorisch aus: „Kants größtes Verdienst ist die Unterscheidung der Erscheinung vom Dinge an sich, – auf Grund der Nachweisung, daß zwischen den Dingen und uns immer noch der Intellekt steht, weshalb sie nicht nach dem, was sie an sich selbst seyn mögen, erkannt werden können.“ (Anhang der Die Welt als Wille und Vorstellung). Allerdings, so fuhr Schopenhauer fort, sei Kant eben nicht zu der Erkenntnis gelangt, „daß die Erscheinung die Welt als Vorstellung und das Ding an sich der Wille sei.“ Wie schon Fichte und Hegel geht somit auch Schopenhauer über den rein problematischen Gebrauch des Begriffes in der Kritik der reinen Vernunft hinaus und verwendet das „Ding an sich“ als affirmativen, also seienden Weltgrund: Kant, so heißt es in Die Welt als Wille und Vorstellung, „leitete das Ding an sich nicht auf die rechte Art ab, wie ich bald zeigen werde, sondern mittelst einer Inkonsequenz, die er durch häufige und unwiderstehliche Angriffe auf diesen Haupttheil seiner Lehre büßen mußte. Er erkannte nicht direkt im Willen das Ding an sich“ (ebd.). Die Philosophie des Willens, auf die sich später Friedrich Nietzsche beruft, wird also methodisch durch die Setzung des „Ding an sich“ des kosmischen Prinzips möglich. Die Musik nehme aufgrund ihrer Abstraktheit, ihres unmittelbaren Ausdrucks des Willens und ihres mathematischen Wesens innerhalb der Künste eine Sonderrolle ein. Schopenhauer betont, Musik stünde ganz abgesondert von allen andern schönen Künsten. Musik stelle „zu allem Physischen der Welt das Metaphysische, zu aller Erscheinung das Ding an sich dar.“[19] Für Schopenhauer bildet die Musik „den innersten aller Gestaltung vorhergängigen Kern, oder das Herz der Dinge […]. Dies Verhältniß ließe sich recht gut in der Sprache der Scholastiker ausdrücken, indem man sagte: die Begriffe sind die universalia post rem, die Musik aber giebt die universalia ante rem, und die Wirklichkeit die universalia in re.“[20] Schopenhauers Ausführungen zur „Metaphysik der Musik“ in Parerga und Paralipomena betrachtet er als „eine Auslegung der Pythagorischen Zahlenphilosophie“. Das „ganze Wesen der Welt“ sei mathematisch zu definieren und durch die Musik unmittelbar erfahrbar.[21] |
ショーペンハウアー アルトゥール・ショーペンハウアーは、「物自体」という概念をカントが間違いなく拒絶したであろう方法で利用し、この概念に基づいて世界意志を構築した。 正当化されたカントの二元論に関する論評も、おそらくこの理由から陶酔的なものだった。「カントの最大の功績は、現象と物自体の区別であり、物と我々の間 には常に知性が存在するという証明に基づいている。それゆえ、物自体がどうであるかによって知られることはありえないのだ。」(『意志と表象としての世 界』の付録) しかし、ショーペンハウアーは、カントは「現象が表象としての世界であり、物自体が意志である」という認識に至らなかったと述べている。 ショーペンハウアーは、フィヒテやヘーゲルと同様に、『純粋理性批判』における概念の純粋な問題としての使用を超え、「物自体」を肯定的な理由、すなわち 世界の存在理由として使用している。カントは、『世界 「物自体を正しい方法で導き出さなかった。私がこれから示すように、彼はその矛盾を償うために、自身の教義の主要部分に対して頻繁に、そして抗しがたい攻 撃を加えなければならなかった。彼は意志そのものを直接認識していなかった」(同書)。フリードリヒ・ニーチェが後に言及する「意志の哲学」は、宇宙原理 の「物自体」を前提とすることで、このように体系的に可能となる。音楽は、その抽象性、意志の直接的な表現、数学的本質により、芸術の中でも特別な位置を 占めている。ショーペンハウアーは、音楽は他のすべての芸術とは完全に別物であると強調している。音楽は「この世の物理的なものすべてに対する形而上学 的、目に見えるものすべてに対する物自体」を表している[19]。ショーペンハウアーにとって、音楽は「すべての創造に先立つ最も内なる核、あるいは物事 の中心」を形成している[...]。この関係はスコラ学の言葉で次のように表現することができる。概念は「レム(事後)の普遍」であるが、音楽は「レム (事前)の普遍」を、そして現実は「イン・レム(内在の普遍)」を与える。」[20] ショーペンハウアーは『付随事項と付随事項』における「音楽の形而上学」に関する自身の意見を「ピタゴラスの数論哲学の解釈」とみなしている。「世界のす べての本質」は数学的に定義でき、音楽を通じて直接的に経験できる。 |
| Neukantianismus Entgegen einer auch heute noch anzutreffenden Lehrmeinung war es nicht der Gründer des Neukantianismus, Hermann Cohen, der die Konzeption des „Ding an sich“ verwarf. In seinem Hauptwerk zur kantischen Philosophie, Kants Theorie der Erfahrung, bekräftigte er vielmehr durchaus philologisch korrekt, dass das „Ding an sich“ als intelligible Ursache der Erscheinungen nur ein „Grenzbegriff“[22] sein kann und legte dar: „Das Gerede, Kant habe die Erkenntnis zwar auf die der Erscheinungen eingeschränkt, dennoch aber das unerkennbare Ding an sich stehen gelassen, dieses oberflächliche Gerede wird doch nach hundert Jahren endlich einmal verstummen müssen. Aber es kann nicht anders verschwinden, als indem man zur Einsicht gelangt, dass das Ding an sich der Ausdruck eines Gedankens ist, den weder das Denken der Anschauung zu concediren, noch diese jenem nachzugeben hat.“[23] Die Behauptung, Cohen habe das Ding an sich weginterpretiert, wurde dagegen erstmals in einer anonymen Rezension der Blätter für Literarische Unterhaltung[24] erhoben, bald bekräftigt von A. Riehl.[25] Auch im Zeitgeist der positivistischen Philosophien und der Erfolge der empirischen Wissenschaften wurde der Begriff zunehmend zurückgewiesen, unter anderem von Johannes Volkelt (Immanuel Kants Erkenntnistheorie, Leipzig 1879), Friedrich Harms (Die Philosophie seit Kant, Berlin 1876), Eduard von Hartmann (Kritische Grundlegung des transcendentalen Realismus, Berlin 1875), Alfred Hölder (Darstellung der Kantischen Erkenntnistheorie, Tübingen 1874), Ernst Laas (Kants Analogien der Erfahrung, Berlin 1876), August Stadler (Die Grundsätze der reinen Erkenntnistheorie in der Kantischen Philosophie, Leipzig 1876) und Alois Riehl (Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft, Leipzig 1876). |
新カント主義 今日でも見られる説とは逆に、新カント主義の創始者ヘルマン・コーエンが「物自体」の概念を否定したわけではない。カント哲学に関する彼の主要著作『カン トの経験論』では、むしろ、現象の理解可能な原因としての「物自体」は、徹底した文献学的に正しい方法で、「境界線上の概念」[22]にすぎないことを確 認し、 「カントは確かに知識を現象のそれだけに限定したが、それにもかかわらず、不可知の物自体をそのままにしておいたという話は、この表面的な話は、100年 後にはついに沈黙せざるを得ないだろう。しかし、物自体は思考が直観に譲歩する必要も、直観が思考に譲歩する必要もない思考の表現であるという洞察に到達 することによってのみ、消滅を免れることができるのだ。」[23] コーエンが物自体を解釈し尽くしたという主張は、まず『文学娯楽誌』の匿名の書評で提起され、間もなくA. Riehlによって支持された。 実証主義哲学の精神と経験科学の成功により、この概念は次第に否定されるようになり、ヨハネス・フォルケルト(『イマヌエル・カントの認識論』、ライプ ツィヒ、1879年)、フリードリヒ・ハームス(『カント以降の哲学』、ベルリン、1876年)、エドゥアルト・フォン・ハルトマン(『超越論的観念論批 判的基礎づけ』、ベルリン、1875年)、アルフレッド・ヘー (カントの認識論の表現、テュービンゲン、1874年)、エルンスト・ラース(カントの経験の類推、ベルリン、1876年)、アウグスト・シュタドラー (カント哲学における純粋認識論の原理、ライプツィヒ、1876年)、アロイス・リール(哲学批評とその実証科学への意義、ライプツィヒ、1876年)な どである。 |
| Philosophische Grundlagen der
Quantenmechanik Der Physiker und Begründer der Quantenmechanik Werner Heisenberg äußert sich 1958 ausführlich zum Verhältnis von »Physics and Philosophy« (Physik und Philosophie), insbesondere auch zu Kant: „Für den Atomphysiker ist das ‚Ding an sich‘, sofern er diesen Begriff überhaupt gebraucht, schließlich eine mathematische Struktur.“[26] Auch bei Physikern wie Niels Bohr, Max Planck, Arnold Sommerfeld und Hans-Peter Dürr ist diese Auffassung nachzuweisen, allerdings wählen diese Physiker statt des Begriffs ‚Ding an sich‘ andere Ausdrucksweisen, in denen allerdings die philosophische Betrachtungsweise Heisenbergs bestätigt wird. Dieser beruft sich ähnlich wie Schopenhauer vielfach auf die Pythagorischen Zahlenphilosophie und auf die Musik. Diesbezüglich bestehe eine Übereinstimmung mit der Quantenphysik, denn „die moderne Physik schreitet also auf denselben geistigen Wegen voran, auf denen schon die Pythagoreer und Platon gewandelt sind.“[27]. „Der eigentliche Inhalt der Musik aber erschließt sich uns im unbewussten geistigen Aufnehmen jener rationalen Zahlenverhältnisse. In ähnlicher Weise ist die bewusste Kenntnis der mathematisch formulierten Naturgesetze die Voraussetzung für ein aktives, auf den praktischen Nutzen gerichtetes Eingreifen in die materielle Welt.“[28] |
量子力学の哲学的基礎 1958年、量子力学の創始者である物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクは、「物理学と哲学」、特にカントとの関係について詳細に論じている。「原子物理 学者にとって、『物自体』とは、この用語をまったく使用しない限り、究極的には数学的な 「[26] この見解は、ニールス・ボーア、マックス・プランク、アルノルト・ゾンマーフェルト、ハンス・ペーター・ドュアといった物理学者にも見られる。ただし、こ れらの物理学者は「物自体」という用語ではなく、異なる表現を用いているが、ハイゼンベルクの哲学的アプローチは確認されている。ハイゼンベルクは、しば しばピタゴラス学派の数哲学や音楽について言及しており、これはショーペンハウアーにも似ている。この点において、量子物理学との一致が見られる。なぜな ら、「現代物理学は、ピタゴラスやプラトンが歩んだのと同じ精神的な道筋に沿って進歩している」からである[27]。「しかし、音楽の実際のコンテンツ は、それらの合理的な数値関係の無意識的な精神的な吸収によって、私たちに明らかになる。同様に、自然界の数学的に定式化された法則についての意識的な知 識は、物質世界への能動的かつ実際的な介入の前提条件である。」[28] |
| Weitere Interpretationen Das Ding an sich wird vom Spiritualismus als etwas Seelisches, vom Voluntarismus als Wille, vom Intellektualismus als Vernunft interpretiert. Für den Materialismus ist es die Materie und für den subjektiven Idealismus gibt es überhaupt keine Dinge an sich. Während der (aprioristische) Kritizismus (und Agnostizismus) auf der prinzipiellen Unerkennbarkeit der Dinge an sich besteht.[29] |
さらなる解釈 スピリチュアリストは物自体を精神的なものとして解釈し、意志論者はそれを意志、知性論者は理性として解釈する。唯物論にとってはそれは物質であり、主観 的観念論にとっては物自体はまったく存在しない。(先験的)批判(および不可知論)は、物自体の根本的な不可知性を主張する。 |
| Siehe auch Abbild Evolutionäre Erkenntnistheorie Kantianismus Subjekt-Objekt-Spaltung |
関連項目 イメージ 進化論的認識論 カント主義 主客二元論 |
| Literatur Immanuel Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können Johann Friedrich Hartknoch, Riga 1783 Bibliotheca Augustana e-Text. Immanuel Kant: Critik der reinen Vernunft Johann Friedrich Hartknoch, Riga 1781, zweite Auflage 1787 Gutenberg e-text, zweite Auflage. Prauss, Gerold: Kant und das Problem der Dinge an sich. Bouvier, Bonn 1974, ISBN 3-416-00989-4. Hossenfelder, M.: Kants Konstitutionstheorie und die transzendentale Deduktion. Berlin/New York 1978, S. 47–56, ISBN 978-3-11005969-4. |
文献 イマニュエル・カント著『科学と名乗ることを敢えてするいかなる未来形而上学にも先立つもの』、ヨハン・フリードリヒ・ハルトノフ、リガ、1783年、ア ウグスチナ図書館電子テキスト。 イマニュエル・カント著『純粋理性批判』、ヨハン・フリードリヒ・ハルトノフ、リガ、1781年、第2版1787年、グーテンベルク電子テキスト、第2 版。 プルス、ゲロルド著『カントと物自体の問題』。ブーヴィエ、ボン 1974年、ISBN 3-416-00989-4。 Hossenfelder, M.: カントの憲法理論と超越論的演繹。ベルリン/ニューヨーク 1978年、47-56ページ、ISBN 978-3-11005969-4。 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Ding_an_sich |
★
| 先験的(超越論的)原理論 |
||
| 先験的(超越論的)感性論 |
||
| 空間について |
||
| 時間について |
||
| 先験的(超越論的)論理学 |
||
| 先験的(超越論的)分析論 |
||
| 概念の分析論 |
||
| 原則の分析論 |
||
| 先験的(超越論的)弁証論 |
||
| 純粋理性の概念について |
||
| 純粋理性の弁証的推理について |
||
| 純粋理性の誤謬推理について |
||
| 純粋理性のアンチノミー(二律背反) |
||
| 純粋理性の理想 |
||
| 先験的(超越論的)方法論 |
||
| 純粋理性の訓練 |
||
| 純粋理性の基準 |
||
| 純粋理性の建築術 |
||
| 純粋理性の歴史 | ||
| 定
言命法 |
Kategorischer Imperativ,
categorical imperative |
定言命法[1](ていげんめいほう、独:
Kategorischer Imperativ[2]、英: categorical
imperative)とは、カント倫理学における根本的な原理であり、無条件に
「~せよ」と命じる絶対的命法である[3]。定言的命令(ていげんてきめいれい)とも言う。『人倫の形而上学の基礎づけ』
(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten)
において提出され、『実践理性批判』において理論的な位置づけが若干修正された。『実践理性批判』の§7において「純粋実践理性の根本法則」として次のよ
うに定式化される。 あなたの意志の格律が常に同時に普遍的な立法の原理として妥当しうるよ うに行為せよ Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.- Immanuel Kant: AA IV, 421 Act as if the maxims of your action were to become through your will a universal law of nature. カントによれば、この根本法則に合致しうる行為が義務として我々に妥当する行為であり、道徳的法則に従った者だけが良い意志を実現させるということであ る。 他のあらゆる倫理学の原則は「~ならば、~せよ」という仮言命法であるのに対して、カントの定言命法は「~ならば」という条件が無い『無条件の行為』を要 求する。 一例として、「幸福になりたいならば嘘をつくな」という仮言命法を採用する場合の問題が挙げられる。ここでは「幸福になること」と「嘘をつかないこと」の 間に必然性が有るのか無いのかが問題となる。「嘘をつかないこと」は幸福になるための都合の良い手段にすぎない。従って、もし「幸福になること」と「嘘を つかないこと」の間に必然性が見出されない(つまり道徳で幸福を得られない)場合には、「幸福になることを目的にする人」は不道徳(嘘をつくこと)を行う ことになる。すなわち、カントは自身の意志を普遍的立法の原理と妥当するように行動することを求めているため、我々は一切の自愛の原理に基づく幸福への意 図を断ち切り、普遍的立法に合致する格率によって意志を確立しなければならないわけである。 また、仮言命法において何が道徳的かであるかの洞察は、行為(嘘をつくこと)と帰結(幸福)との間の自然必然性の洞察であり、経験論に属するものでしかな い。条件節を欠くカントの定言命法は、倫理学が経験論の範囲に陥ることを防ぎ、経験論から独立した純粋に実践的な倫理学の範囲を確保するのである。 |
我々は、外から与える感覚情報を受け身に 捉えるのではない。
認識が可能なのは、我々の精神が経験を組 織化し体系づける能動的な作業によっておこなわれる。
我々は、時間と空間と実体という枠組み (カテゴリー)により世界を認知している。
時間と空間と実体は、我々と独立して存在 するのではない。それらは、我々の直観や理性(つまり想像)の産物であり、それなしには捉えられない。
では、世界の実体はどのようなものか? (このカントの問題の立て方が、アルキメデスの立場や視座を想定してナンセンスなのだが)カントはそれ答 えられない。そのような「独立した実体」(←これもナンセンス)を物自体(Ding an sich)と呼ぶ。物自体の世界には、永遠に認識できない世界 がだが、それはかつてのキリスト教の「天国」のようだ。それゆえ、神学者は、カントのこの「物自体」という仮想の(独立した実体の)世界を反キリスト教的 なものだと、その匂いを嗅ぎつけた。
+++++++++++++++++
また、フィヒテ(1762-1814)
は、人間が知り得ない「物自体」をなぜカント自身が想定できるのかという矛盾に食ってかかる——多くの人
はフィヒテに同意できるだろう。フィヒテは、(カントがいった)能動的精神によって構築される世界がすべての世界であり、精神が知ることができないもの
は、そもそも存在しないと主張する。しかし、これは、唯名論のことあげ(=命名できないものは存在しない)と似ており、不可知論や懐疑論者に対して有益な
「トドメ」を刺すことができない点でまだ、改良の余地がある。
+++++++++++++++++
【そ れ以外のカントの問い】は御存知、以下の3つの問いから構成され る。1)何を知りうるか?、2)何をなすべきか?、3)何を望みうるか?
1)「私は何を知りうるか[‚Was kann ich wissen?‘]——理性は知識の能力(「私は何を知りうるか[‚Was kann ich wissen?‘]」)に向けられている。これが『純粋理性批判』の主題である。
2)「私は何をすべきか[‚Was soll ich tun?‘]」——人間の行動(「私は何をすべきか[‚Was soll ich tun?‘]」)は、まったく別の方向における理性的考察の内容である。これが『実践理性批判(KpV)』の 主題である。カントにとって、「存在すること」と「なすべきこと」は、一つの理性の非独立的な二つの側面である。人間の実践にとって、自由は自律的決定の 基礎として必要であり明白であるが、理論的理性においては、それは可能であることを示すことができるだけである。自由のない行動は考えられない。私たちは 道徳法則を意識することによってのみ、自由を認識する。
3)「私は何を望むか[‚Was
darf ich hoffen?‘]」——『純
粋実践理性の弁証法』では、「何を望むか[‚Was darf ich
hoffen?‘]」という問いが考察の対象となる。ここでカントは最高善の決定についての考えを展開する。実践的な意味での無 条
件の問題である。『実践理性批判(KpV)』においてカントは、自由、神、魂の不滅という無条件の観念は証明することはできないが、調整的観念としては可
能であると考えられ
ることを示した。カントの見解では、これらの観念は実践理性にとって必要であり、それゆえ純粋実践理性の真の定立とみなすことができる。『実践理性批判
(KpV)』の非常に短
い第二部である『方法序説』において、カントは道徳教育の簡単な概念を概説している。実践的な道徳哲学に関するカントの見解は、『道徳の形而上学』や『道
徳哲学講義』に見出すことができる。
☆哲学において、ヌメノン(/ˈnuːmənɒn/、/ˈnaʊ-/、古 代ギリシャ語: νοούμενoν、複数形: noumena)とは、人間の感覚とは独立して存在する対象として想定される知識である。[2] 現象(現象)とは対照的に、あるいは関連して用いられる用語である。現象とは感覚の対象を指す。イマヌエル・カントは超越的観念論の一環として現象の概念 を初めて展開し、人間の感覚性は受動的であるため現象界の存在は知ることができるが、現象界そのものは感覚的ではなく、したがって我々には他の方法では知 ることができないと示唆した。[3] カント哲学において、物自体はしばしば知ることのできない「物自体」(ドイツ語: Ding an sich)と結びつけられる。しかし、両者の関係の本質はカントの著作では明示されておらず、結果としてカント研究者の間で議論の的となっている。
| In philosophy, a noumenon
(/ˈnuːmənɒn/, /ˈnaʊ-/; from Ancient Greek: νοούμενoν; pl.: noumena) is
knowledge[1] posited as an object that exists independently of human
sense.[2] The term noumenon is generally used in contrast with, or in
relation to, the term phenomenon, which refers to any object of the
senses. Immanuel Kant first developed the notion of the noumenon as
part of his transcendental idealism, suggesting that while we know the
noumenal world to exist because human sensibility is merely receptive,
it is not itself sensible and must therefore remain otherwise
unknowable to us.[3] In Kantian philosophy, the noumenon is often
associated with the unknowable "thing-in-itself" (German: Ding an
sich). However, the nature of the relationship between the two is not
made explicit in Kant's work, and remains a subject of debate among
Kant scholars as a result. |
哲学において、ヌメノン(/ˈnuːmənɒn/、/ˈnaʊ-/、古
代ギリシャ語: νοούμενoν、複数形: noumena)とは、人間の感覚とは独立して存在する対象として想定される知識である。[2]
現象(現象)とは対照的に、あるいは関連して用いられる用語である。現象とは感覚の対象を指す。イマヌエル・カントは超越的観念論の一環として現象の概念
を初めて展開し、人間の感覚性は受動的であるため現象界の存在は知ることができるが、現象界そのものは感覚的ではなく、したがって我々には他の方法では知
ることができないと示唆した。[3] カント哲学において、物自体はしばしば知ることのできない「物自体」(ドイツ語: Ding an
sich)と結びつけられる。しかし、両者の関係の本質はカントの著作では明示されておらず、結果としてカント研究者の間で議論の的となっている。 |
| Etymology The Greek word νοούμενoν, nooúmenon (plural νοούμενα, nooúmena) is the neuter middle-passive present participle of νοεῖν, noeîn, 'to think, to mean', which in turn originates from the word νοῦς, noûs, an Attic contracted form of νόος, nóos, 'perception, understanding, mind'.[a=ontology][4][5] A rough equivalent in English would be "that which is thought", or "the object of an act of thought". |
語源 ギリシャ語のνοούμενoν(複数形:νοούμενα)は、動詞νοεῖν(意味:考える、意図する)の中性中動態現在分詞である。この動詞は、 アッティカ方言の縮約形であるνοῦς(原形:νόος)に由来する。νοῦςは「知覚、理解、心」を意味する。[a=存在論のこと][4][5] 英語での大まかな対応語は「考えられるもの」あるいは「思考行為の対象」となる。 |
| Historical predecessors The Indian Vedānta philosophy (specifically Advaita), the roots of which go back to the Vedic period, talks of the ātman (self) in similar terms as the noumenon.[6] Regarding the equivalent concepts in Plato, Ted Honderich writes: "Platonic Ideas and Forms are noumena, and phenomena are things displaying themselves to the senses... This dichotomy is the most characteristic feature of Plato's dualism; that noumena and the noumenal world are objects of the highest knowledge, truths, and values is Plato's principal legacy to philosophy."[7] |
歴史的先駆者 インドのヴェーダーンタ哲学(特にアドヴァイタ)は、その起源がヴェーダ時代に遡るが、アトマン(自我)を、ノウメノンと同様の概念として論じている。 [6] プラトンにおける同等の概念について、テッド・ホンデリッチは次のように記している。「プラトンのイデアと理念は物自体であり、現象は感覚に現れる事物で ある...この二分法こそがプラトンの二元論の最も特徴的な側面である。物自体と物自体の世界が最高の知識・真理・価値の対象であるという考えこそが、プ ラトンが哲学に遺した主要な遺産である。」[7] |
| Kantian noumena |
カントのヌメノン |
| Overview As expressed in Kant's Critique of Pure Reason, human understanding is structured by "concepts of the understanding" or pure categories of understanding, found prior to experience in the mind and which make outer experiences possible as counterpart to the rational faculties of the mind.[8][9] By Kant's account, when one employs a concept to describe or categorize noumena (the objects of inquiry, investigation or analysis of the workings of the world), one is also employing a way of describing or categorizing phenomena (the observable manifestations of those objects of inquiry, investigation or analysis). Kant posited methods by which human understanding makes sense of and thus intuits phenomena that appear to the mind: the concepts of the transcendental aesthetic, as well as that of the transcendental analytic, transcendental logic and transcendental deduction.[10][11][12] Taken together, Kant's "categories of understanding" are the principles of the human mind which necessarily are brought to bear in attempting to understand the world in which we exist (that is, to understand, or attempt to understand, "things in themselves"). In each instance the word "transcendental" refers to the process that the human mind must exercise to understand or grasp the form of, and order among, phenomena. Kant asserts that to "transcend" a direct observation or experience is to use reason and classifications to strive to correlate with the phenomena that are observed.[citation needed] Humans can make sense out of phenomena in these various ways, but in doing so can never know the "things-in-themselves", the actual objects and dynamics of the natural world in their noumenal dimension - this being the negative, correlate to phenomena and that which escapes the limits of human understanding. By Kant's Critique, our minds may attempt to correlate in useful ways, perhaps even closely accurate ways, with the structure and order of the various aspects of the universe, but cannot know these "things-in-themselves" (noumena) directly. Rather, we must infer the extent to which the human rational faculties can reach the object of "things-in-themselves" by our observations of the manifestations of those things that can be perceived via the physical senses, that is, of phenomena, and by ordering these perceptions in the mind help infer the validity of our perceptions to the rational categories used to understand them in a rational system. This rational system (transcendental analytic), being the categories of the understanding as free from empirical contingency.[13][14] According to Kant, objects of which we are cognizant via the physical senses are merely representations of unknown somethings—what Kant refers to as the transcendental object—as interpreted through the a priori or categories of the understanding. These unknown somethings are manifested within the noumenon—although we can never know how or why as our perceptions of these unknown somethings via our physical senses are bound by the limitations of the categories of the understanding and we are therefore never able to fully know the "thing-in-itself".[15] |
概観 カントの『純粋理性批判』で述べられているように、人間の理解は「理解の概念」、すなわち純粋な理解の範疇によって構造化されている。これらは経験に先 立って心の中に存在し、心の理性的能力に対応するものとして外部の経験を可能にするものである。[8][9] カントの説によれば、人が概念を用いて物自体(世界の働きに関する探究・調査・分析の対象)を記述したり分類したりするとき、同時に現象(それらの探究・ 調査・分析対象の観察可能な現れ)を記述・分類する方法も用いていることになる。カントは、人間の理解が心に現れる現象を理解し直観する方法として、超越 的審美的概念、超越的分析的概念、超越的論理的概念、超越的演繹的概念を提唱した。[10][11][12] カントの「理解の範疇」を総合すると、それは我々が存在する世界(すなわち「物自体」を理解する、あるいは理解しようとする)を理解しようとする際に必然 的に作用する、人間の精神の原理である。いずれの場合も「超越的」という言葉は、現象の形式や秩序を理解・把握するために人間の精神が行使せざるを得ない 過程を指す。カントは、直接的な観察や経験を「超越する」とは、観察された現象と関連付けようと努めるために理性と分類を用いることだと主張する。[出典 必要] 人間はこうした様々な方法で現象に意味を見出せるが、その過程で「物自体」―自然界の実際の対象や力学が持つ超現象的次元―を知ることは決してできない。 これは現象の否定的な相関物であり、人間の理解の限界を超越するものである。カントの『批判』によれば、我々の精神は宇宙の様々な側面の構造や秩序と、有 用な方法で、おそらくは極めて正確な方法でさえ関連付けようとするかもしれないが、これらの「物自体」(noumena)を直接知ることはできない。むし ろ我々は、物理的感覚を通じて知覚可能な現象、すなわち現象の現れを観察し、これらの知覚を心の中で秩序立てることによって、人間の理性的能力が「物自 体」という対象に到達し得る範囲を推論せねばならない。そしてこの知覚の秩序立ては、それらを理解するための理性的体系において用いられる理性的範疇に対 する我々の知覚の妥当性を推論するのに役立つのである。この理性体系(超越論的分析)は、経験的偶然性から解放された理解の範疇である。[13][14] カントによれば、物理的感覚を通じて認識される対象は、先験的範疇(理解の範疇)を通じて解釈される未知の何か――カントが超越論的対象と呼ぶもの――の 単なる表象に過ぎない。これらの未知の何かは、物自体の中に現れている。しかし我々は、物理的感覚を通じてこれらの未知の何かを認識する際に、理解の範疇 の限界に縛られるため、その方法や理由を決して知り得ず、したがって「物自体」を完全に知ることは決してできないのだ。[15] |
| Noumenon and the thing-in-itself Many accounts of Kant's philosophy treat "noumenon" and "thing-in-itself" as synonymous, and there is textual evidence for this relationship.[16] But Stephen Palmquist holds that "noumenon" and "thing-in-itself" are only loosely synonymous, inasmuch as they represent the same concept viewed from two different perspectives,[17][18] and other scholars also argue that they are not identical.[19] Schopenhauer criticised Kant for changing the meaning of "noumenon". But this opinion is far from unanimous.[20] Kant's writings show points of difference between noumena and things-in-themselves. For instance, he regards things-in-themselves as existing: though we cannot know these objects as things in themselves, we must yet be in a position at least to think them as things in themselves; otherwise we should be landed in the absurd conclusion that there can be appearance without anything that appears.[21] He is much more doubtful about noumena: But in that case a noumenon is not for our understanding a special [kind of] object, namely, an intelligible object; the [sort of] understanding to which it might belong is itself a problem. For we cannot in the least represent to ourselves the possibility of an understanding which should know its object, not discursively through categories, but intuitively in a non-sensible intuition.[22] A crucial difference between the noumenon and the thing-in-itself is that to call something a noumenon is to claim a kind of knowledge, whereas Kant insisted that the thing-in-itself is unknowable. Interpreters have debated whether the latter claim makes sense: it seems to imply that we know at least one thing about the thing-in-itself (i.e., that it is unknowable). But Palmquist argues that this is part of Kant's definition of the term, to the extent that anyone who claims to have found a way of making the thing-in-itself knowable must be adopting a non-Kantian position.[23] |
超現象と物自体 カント哲学の多くの解説では「超現象」と「物自体」を同義語として扱い、この関係を示す文脈上の根拠も存在する。[16] しかしスティーブン・パームクイストは、「超感覚的対象」と「物自体」は、異なる二つの視点から見た同一の概念を表すという点で、緩やかな同義語に過ぎな いと主張している[17][18]。他の学者たちも、両者が同一ではないと論じている[19]。ショーペンハウアーは、カントが「超感覚的対象」の意味を 変えたと批判した。しかしこの見解は決して一致したものではない。[20] カントの著作には、超感覚的対象と物自体との相違点が示されている。例えば彼は物自体の存在を認めている: 我々はこれらの対象を物自体として知り得ないが、少なくとも物自体として思考する立場には立たねばならない。さもなければ、現れるものがないのに現象があ るという不条理な結論に陥ってしまうからだ。[21] 彼は超現象についてははるかに懐疑的だ: しかしその場合、超現象は我々の理解にとって特別な対象、すなわち知性的対象ではない。それが属しうる理解そのものが問題なのだ。なぜなら我々は、対象を 範疇による演繹的ではなく、非感覚的直観によって直観的に知るような理解の可能性を、まったく想像できないからだ。[22] 現象と物自体との決定的な差異は、何かを現象と呼ぶことは一種の認識を主張することであるのに対し、カントは物自体は認識不可能だと主張した点にある。解 釈者たちは、この後者の主張が意味をなすかどうか議論してきた。それは、我々が物自体について少なくとも一つのこと(すなわち、それが不可知であること) を知っていることを示唆しているように思われるからだ。しかし、パームクイストは、物自体を可知にする方法を見つけたと主張する者は誰でも非カント的な立 場を取らざるを得ないという点で、これがカントの用語定義の一部であると論じている。[23] |
| Positive and negative noumena Kant also distinguishes between positive and negative noumena:[24][25] If by 'noumenon' we mean a thing so far as it is not an object of our sensible intuition, and so abstract from our mode of intuiting it, this is a noumenon in the negative sense of the term.[26] But if we understand by it an object of a non-sensible intuition, we thereby presuppose a special mode of intuition, namely, the intellectual, which is not that which we possess, and of which we cannot comprehend even the possibility. This would be 'noumenon' in the positive sense of the term.[26] The positive noumena, if they existed, would be immaterial entities that can only be apprehended by a special, non-sensory faculty: "intellectual intuition" (nicht sinnliche Anschauung).[26] Kant doubts that we have such a faculty, because for him intellectual intuition would mean that thinking of an entity and its being represented would be the same. He argues that we have no way to apprehend positive noumena: Since, however, such a type of intuition, intellectual intuition, forms no part whatsoever of our faculty of knowledge, it follows that the employment of the categories can never extend further than to the objects of experience. Doubtless, indeed, there are intelligible entities corresponding to the sensible entities; there may also be intelligible entities to which our sensible faculty of intuition has no relation whatsoever; but our concepts of understanding, being mere forms of thought for our sensible intuition, could not in the least apply to them. That, therefore, which we entitle 'noumenon' must be understood as being such only in a negative sense.[27] |
肯定的・否定的物自体 カントはまた、肯定的・否定的物自体を区別している:[24][25] 「物自体」を、感覚的直観の対象ではないもの、すなわち我々の直観の様式から抽象化されたものとして理解するなら、これは否定的意味での物自体である。 [26] しかし、もしそれを非感覚的直観の対象として理解するなら、それによって我々は特別な直観様式、すなわち知性的直観を前提とする。これは我々が有するもの ではなく、その可能性すら理解できないものだ。これが「物自体」の肯定的意味である。[26] もし肯定的超現象が存在するならば、それは特殊な非感覚的機能「知性的直観」(nicht sinnliche Anschauung)によってのみ把握され得る非物質的実体となるだろう。[26] カントは我々がそのような機能を有することを疑う。なぜなら彼にとって知性的直観とは、実体を思考することとそれが表象されることが同一であることを意味 するからだ。彼は我々が肯定的超現象を把握する手段を持たないと論じる: しかし、このような種類の直観、すなわち知的直観は、我々の認識能力のいかなる部分をも構成していない。したがって、範疇の適用は経験の対象を超えること は決してない。確かに、感覚的実体に対応する知性的実体が存在するかもしれない。また、我々の感覚的直観能力とは全く無関係な知性的実体も存在するかもし れない。しかし、我々の理解力による概念は、感覚的直観のための単なる思考形式に過ぎないため、それらには全く適用できない。したがって、我々が「物自 体」と呼ぶものは、否定的な意味でのみそう理解されなければならない。[27] |
| The noumenon as a limiting
concept Even if noumena are unknowable, they are still needed as a limiting concept,[28] Kant tells us. Without them, there would be only phenomena, and since potentially we have complete knowledge of our phenomena, we would in a sense know everything. In his own words: Further, the concept of a noumenon is necessary, to prevent sensible intuition from being extended to things in themselves, and thus to limit the objective validity of sensible knowledge.[29] What our understanding acquires through this concept of a noumenon, is a negative extension; that is to say, understanding is not limited through sensibility; on the contrary, it itself limits sensibility by applying the term noumena to things in themselves (things not regarded as appearances). But in so doing it at the same time sets limits to itself, recognising that it cannot know these noumena through any of the categories, and that it must therefore think them only under the title of an unknown something.[30] Furthermore, for Kant, the existence of a noumenal world limits reason to what he sees as its proper bounds, making many questions of traditional metaphysics, such as the existence of God, the soul, and free will unanswerable by reason. Kant derives this from his definition of knowledge as "the determination of given representations to an object".[31] As these entities do not appear in the phenomenal, Kant can claim that they cannot be known to a mind that works upon "such knowledge that has to do only with appearances".[32] These questions are ultimately the "proper object of faith, but not of reason".[33] |
物自体という制限概念 物自体は知ることができなくとも、制限概念として必要だとカントは言う。物自体なしでは現象だけが残る。そして我々は現象について完全な知識を持つ可能性 があるので、ある意味では全てを知ることになる。彼の言葉を借りれば: さらに、物自体への感覚的直観の拡張を防止し、それによって感覚的知識の客観的有効性を制限するために、物自体の概念は必要である。[29] この物自体という概念を通じて我々の理解が得るものは、否定的な拡張である。つまり、理解は感覚によって制限されるのではなく、逆に、物自体(現象として 扱われないもの)に「物自体」という概念を適用することで、それ自体が感覚を制限するのである。しかしそうすることで、同時に自己にも限界を設ける。すな わち、これらの超現象をいかなる範疇によっても知ることができず、したがって未知の何かという名目のもとでしか考えられないことを認識するのだ。[30] さらにカントにとって、超現象界の存在は理性をその本来的な限界に閉じ込め、神の存在、魂、自由意志といった伝統的な形而上学の多くの問いを理性では答え られないものとする。カントはこれを「与えられた表象をある対象に決定づけること」という知識の定義から導いている。[31] これらの実体は現象界に現れないため、カントは「現象のみに関わる知識」を扱う精神には知られ得ないと主張できる。[32] これらの問題は究極的に「信仰の正当な対象であって、理性の対象ではない」のである。[33] |
| The dual-object and dual-aspect
interpretations Kantian scholars have long debated two contrasting interpretations of the thing-in-itself. One is the dual object view, according to which the thing-in-itself is an entity distinct from the phenomena to which it gives rise. The other is the dual aspect view, according to which the thing-in-itself and the thing-as-it-appears are two "sides" of the same thing. This view is supported by the textual fact that "Most occurrences of the phrase 'things-in-themselves' are shorthand for the phrase, 'things considered in themselves' (Dinge an sich selbst betrachtet)."[34] Although we cannot see things apart from the way we do in fact perceive them via the physical senses, we can think them apart from our mode of sensibility (physical perception), thus making the thing-in-itself a kind of noumenon or object of thought. |
二重対象説と二重側面説 カント研究者たちは長年、物自体に関する二つの対照的な解釈を議論してきた。一つは二重対象説であり、これによれば物自体は、それが引き起こす現象とは異 なる実体である。もう一つは二重側面説である。これによれば、物自体と現象は同一のものの二つの「側面」である。この見解は「『物自体』という語句の大半 は、『それ自体において考察されたもの(Dinge an sich selbst betrachtet)』という語句の略語である」というテキスト上の事実によって支持されている。[34] 私たちは物理的感覚を通じて実際に知覚する方法とは別に物事を見ることはできないが、感覚性(物理的知覚)という様式とは別にそれらを思考することはでき る。こうして物自体はある種の超現象、あるいは思考の対象となるのである。 |
| Criticisms of Kant's noumenon |
カントの物自体に対する批判 |
| Pre-Kantian critique Though the term noumenon did not come into common usage until Kant, the idea that undergirds it, that matter has an absolute existence which causes it to emanate certain phenomena, had historically been criticized. George Berkeley, who predated Kant, asserted that matter, independent of an observant mind, is metaphysically impossible. Qualities associated with matter, such as shape, color, smell, texture, weight, temperature, and sound, all depend on minds, which allow for only relative, not absolute, perception. The complete absence of such minds (and more importantly an omnipotent mind) would render those same qualities unobservable and even unimaginable. Berkeley called this philosophy immaterialism. Essentially there could be no such thing as matter without a mind.[35]: 559–560 |
カント以前の批判 「物自体」という用語が一般に広まったのはカント以降だが、その概念の根底にある「物質が絶対的な存在を持ち、それが特定の現象を引き起こす」という考え は、歴史的に批判されてきた。カントより前のジョージ・バークリーは、観察する精神から独立した物質は形而上学的に不可能だと主張した。物質に結びつく性 質、例えば形、色、匂い、質感、重さ、温度、音などは、全て心によって依存している。心は絶対的な知覚ではなく、相対的な知覚しか許さない。そのような心 が完全に存在しない場合(さらに重要なのは全能の心が存在しない場合)、それらの性質は観察不可能であり、想像すらできないものとなる。バークリーはこの 哲学を非物質主義と呼んだ。本質的に、心なしに物質のようなものは存在し得ないのだ。[35]: 559–560 |
| Schopenhauer's critique Schopenhauer claimed that Kant used the word noumenon incorrectly. In his "Critique of the Kantian philosophy", which first appeared as an appendix to The World as Will and Representation, he writes: The difference between abstract and intuitive cognition, which Kant entirely overlooks, was the very one that ancient philosophers indicated as φαινόμενα [phainomena] and νοούμενα [nooumena]; the opposition and incommensurability between these terms proved very productive in the philosophemes of the Eleatics, in Plato's doctrine of Ideas, in the dialectic of the Megarics, and later in the scholastics, in the conflict between nominalism and realism. This latter conflict was the late development of a seed already present in the opposed tendencies of Plato and Aristotle. But Kant, who completely and irresponsibly neglected the issue for which the terms φαινομένα and νοούμενα were already in use, then took possession of the terms as if they were stray and ownerless, and used them as designations of things in themselves and their appearances.[36] The noumenon's original meaning of "that which is thought" is not compatible with the thing-in-itself, Kant's term for things as they exist apart from their observers' minds.[citation needed] In a footnote to this passage, Schopenhauer provides the following passage from the Outlines of Pyrrhonism (Bk. I, ch. 13) of Sextus Empiricus to demonstrate the original distinction between phenomenon and noumenon according to ancient philosophers: νοούμενα φαινομένοις ἀντετίθη Ἀναξαγόρας ('Anaxagoras opposed what is thought to what appears.') |
ショーペンハウアーの批判 ショーペンハウアーは、カントが「ヌメノン」という言葉を誤用していると主張した。『意志と表象としての世界』の付録として最初に発表された『カント哲学 批判』の中で、彼はこう書いている: カントが完全に無視した抽象的認識と直観的認識の差異こそが、古代哲学者たちが現象(φαινόμενα)と物自体(νοούμενα)として示したもの である。この二項の対立と不可測性は、エレア学派の哲学概念、プラトンのイデア論、メガラ学派の弁証法において非常に生産的であり、後世のスコラ学では名 目論と実在論の対立として結実した。この後者の対立は、プラトンとアリストテレスの対立する傾向の中に既に存在していた種子の後期的な発展であった。しか しカントは、現象(φαινομένα)と観念(νοούμενα)という用語が既に用いられていた問題を完全に無責任に無視し、あたかもそれらが放浪し 所有者のいないものかのようにこれらの用語を独占し、物自体とその現象を指す名称として用いた[36]。 「思考されるもの」というヌメノンの本来の意味は、観察者の精神から独立して存在するものとしてカントが用いた「物自体」とは相容れない。[出典必要] この箇所の脚注でショーペンハウアーは、古代哲学者の現象とヌメノンの本来の区別を示すため、セクストス・エンピリコスの『ピュロン主義概論』 (第1巻第13章)から次の引用を添えている。古代哲学者による現象と物自体の本来の区別を示すためである:「アナクサゴラスは、思考されるものと現れる ものを対置した」 |
| Always already Anatta Condition of possibility Essence–energies distinction Haecceity Hypokeimenon Ineffability Master argument by George Berkeley Observation Qualia Schopenhauer's criticism of the Kantian philosophy Transcendental idealism Unobservable |
常にすでに 無我 可能性の条件 本質とエネルギーの区別 ヘケシテ ヒポケイメノン 不可言性 ジョージ・バークリーの主論 観察 クオリア ショーペンハウアーのカント哲学批判 超越的観念論 観測不能 |
| References 1. "Formal Epistemology". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2021. 2. "Noumenon | Definition of Noumenon by Webster's Online Dictionary". Archived from the original on 28 September 2011. Retrieved 10 September 2015. 1. intellectual conception of a thing as it is in itself, not as it is known through perception; 2. The of-itself-unknown and unknowable rational object, or thing-in-itself, which is distinguished from the phenomenon through which it is apprehended by the physical senses, and by which it is interpreted and understood; – so used in the philosophy of Kant and his followers. 3. "noumenon | philosophy". Encyclopedia Britannica. Retrieved 4 September 2017. 4. νοεῖν, νοῦς, νόος. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon at the Perseus Project. 5. Harper, Douglas. "noumenon". Online Etymology Dictionary. 6. Bickmann, Claudia (2010). "9. Kant's Critical Concept of a Person: The Noumenal Sphere Grounding the Principle of Spirituality". Cultivating Personhood: Kant and Asian Philosophy. pp. 194–204. doi:10.1515/9783110226249.2.194. ISBN 978-3-11-022623-2. 7. Honderich, Ted, ed. (31 August 1995). The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press. p. 657. ISBN 0198661320. Retrieved 28 October 2014. 8. Hanna, Robert (2009). Completing the Picture of Kant's Metaphysics of Judgment. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 9. Stanford Encyclopedia of Philosophy on Kant's metaphysics. 10. The Encyclopedia of Philosophy (Macmillan, 1967, 1996) Volume 4, "Kant, Immanuel", section on "Critique of Pure Reason: Theme and Preliminaries", p. 308 ff. 11. The Encyclopedia of Philosophy (Macmillan, 1967, 1996) Volume 4, "Kant, Immanuel", section on "Transcendental Aesthetic", p. 310 ff. 12. The Encyclopedia of Philosophy (Macmillan, 1967, 1996) Volume 4, "Kant, Immanuel", section on "Pure Concepts of the Understanding", p. 311 ff. 13. See, e.g., The Encyclopedia of Philosophy (Macmillan, 1967, 1996) Volume 4, "Kant, Immanuel", section on "Critique of Pure Reason: Theme and Preliminaries", p. 308 ff. 14. See also, e.g., The Encyclopedia of Philosophy (Macmillan, 1967, 1996) Volume 4, "Kant, Immanuel", section on "Pure Concepts of the Understanding", p. 311 ff. 15. Kant 1999, p. 27, A256/B312. 16. Immanuel Kant (1781) Critique of Pure Reason, for example in A254/B310, p. 362 (Guyer and Wood), "The concept of a noumenon, i.e., of a thing that is not to be thought of as an object of the senses but rather as a thing-in-itself [...]"; But note that the terms are not used interchangeably throughout. The first reference to thing-in-itself comes many pages (A30) before the first reference to noumenon (A250). For a secondary or tertiary source, see: "Noumenon" in the Encyclopædia Britannica 17. "Noumenon: the name given to a thing when it is viewed as a transcendent object. The term 'negative noumenon' refers only to the recognition of something which is not an object of sensible intuition, while 'positive noumenon' refers to the (quite mistaken) attempt to know such a thing as an empirical object. These two terms are sometimes used loosely as synonyms for 'transcendental object' and 'thing-in-itself', respectively. (Cf. phenomenon.)" – Glossary of Kant's Technical Terms 18. Thing-in-itself: an object considered transcendentally apart from all the conditions under which a subject can gain knowledge of it via the physical senses. Hence the thing-in-itself is, by definition, unknowable via the physical senses. Sometimes used loosely as a synonym of noumenon. (Cf. appearance.)" – Glossary of Kant's Technical Terms. Palmquist defends his definitions of these terms in his article, "Six Perspectives on the Object in Kant's Theory of Knowledge", Dialectica 40:2 (1986), pp.121–151; revised and reprinted as Chapter VI in Palmquist's book, Kant's System of Perspectives (Lanham: University Press of America, 1993). 19. Oizerman, T. I., "Kant's Doctrine of the "Things in Themselves" and Noumena", Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 41, No. 3, Mar., 1981, 333–350; Karin de Boer, "Kant's Multi-Layered Conception of Things in Themselves, Transcendental Objects, and Monads", Kant-Studien 105/2, 2014, 221-260. 20. "Other interpreters have introduced an almost unending stream of varying suggestions as to how these terms ought to be used. A handful of examples will be sufficient to make this point clear, without any claim to represent an exhaustive overview. Perhaps the most commonly accepted view is expressed by Paulsen, who equates 'thing-in-itself' and 'noumenon', equates 'appearance' and 'phenomenon', distinguishes 'positive noumenon' and 'negative noumenon', and treats 'negative noumenon' as equivalent to 'transcendental object' [pp. 4:148-50, 154-5, 192]. Al-Azm and Wolff also seem satisfied to equate 'phenomenon' and 'appearance', though they both carefully distinguish 'thing-in-itself' from 'negative noumenon' and 'positive noumenon' [A4:520; W21:165, 313–5; s.a. W9:162]. Gotterbarn similarly equates the former pair, as well as 'thing-in-itself' and 'positive noumenon', but distinguishes between 'transcendental object', 'negative noumenon' and 'thing-in-itself' [G11: 201]. By contrast, Bird and George both distinguish between 'appearance' and 'phenomenon', but not between 'thing-in-itself' and 'noumenon' [B20:18,19, 53–7; G7:513-4n]; and Bird sometimes blurs the distinction between 'thing-in-itself' and 'transcendental object' as well.[2] Gram equates 'thing-in-itself' not with 'noumenon', but with 'phenomenon' [G13:1,5-6]! Allison cites different official meanings for each term, yet he tends to equate 'thing-in-itself' at times with 'negative noumenon' and at times with 'transcendental-object', usually ignoring the role of the 'positive noumenon' [A7:94; A10:58,69]. And Buchdahl responds to the fact that the thing-in-itself seems to be connected with each of the other object-terms by regarding it as 'Kant's umbrella term'.[3]" Stephen Palmquist on Kant's object terms 21. Kant 1999, Bxxvi-xxvii. 22. Kant 1999, p. 273, A256, B312. 23. "The Radical Unknowability of Kant's 'Thing in Itself'", Cogito 3:2 (March 1985), pp.101–115; revised and reprinted as Appendix V in Stephen Palmquist, Kant's System of Perspectives (Lanham: University Press of America, 1993). 24. Mattey, G. J. 25. Lecture notes by G. J. Mattey Archived 2010-06-12 at the Wayback Machine 26. Kant 1999, p. 267 (NKS), A250/B307. 27. Kant 1999, p. 270 (NKS), B309. 28. Allison, H (2006). "Transcendental Realism, Empirical Realism, and Transcendental Idealism". Kantian Review. 11: 1–28. doi:10.1017/S1369415400002223. S2CID 171078596. 29. Kant 1999, A253/B310. 30. Kant 1999, p. 273, A256/B312. 31. Kant 1999, p. 156, B/137. 32. Kant 1999, p. 24, B/xx.. 33. Rohmann, Chris. "Kant" A World of Ideas: A Dictionary of Important Theories, Concepts, Beliefs, and Thnkers. Ballantine Books, 1999. 34. Mattey, GJ. "Lecture Notes on the Critique of Pure Reason". 35. Anon., "Caird's Philosophy of Kant", Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art, vol 44, Nov 3, 1877, pp. 559–560. 36. Schopenhauer, Arthur (2014). The World as Will and Representation, Volume 1. Translated by Norman, Judith; Welchman, Alistair; Janaway, Christopher. Cambridge: Cambridge University Press. p. 506. ISBN 9780521871846. |
参考文献 1. 「形式認識論」. スタンフォード哲学百科事典. スタンフォード大学形而上学研究所. 2021年. 2. 「ヌメノン | ウェブスターオンライン辞典によるヌメノンの定義」. 2011年9月28日にオリジナルからアーカイブ. 2015年9月10日に取得。 1. 知覚を通じて知られるものではなく、それ自体として存在するものの知的概念。 2. それ自体として未知かつ不可知の合理的対象、あるいは物自体。これは物理的感覚によって把握され、解釈され理解される現象とは区別される。カント及びその 後継者たちの哲学においてこのように用いられる。 3. 「noumenon | 哲学」『ブリタニカ百科事典』2017年9月4日閲覧。 4. νοεῖν, νοῦς, νόος. リデル, ヘンリー・ジョージ; スコット, ロバート; 『ギリシャ語-英語辞典』(ペルセウス・プロジェクト)。 5. ハーパー, ダグラス. 「noumenon」『オンライン語源辞典』。 6. ビックマン、クラウディア(2010)。「9. カントの批判的人間観:精神性の原理を基盤とする超感覚的領域」。『人格の育成:カントとアジア哲学』。pp. 194–204。doi:10.1515/9783110226249.2.194。ISBN 978-3-11-022623-2. 7. ホンデリッチ, テッド, 編 (1995年8月31日). 『オックスフォード哲学事典』. オックスフォード大学出版局. p. 657. ISBN 0198661320. 2014年10月28日閲覧. 8. ハンナ, ロバート (2009). 『カントの判断力形而上学の全体像』. スタンフォード哲学百科事典. 9. スタンフォード哲学百科事典におけるカントの形而上学に関する記述. 10. 『哲学百科事典』(マクミラン、1967年、1996年)第4巻、「カント、イマヌエル」の項、「純粋理性批判:主題と予備的考察」の節、p. 308 ff. 11. 『哲学百科事典』(マクミラン、1967年、1996年)第4巻、「カント、イマヌエル」の「超越論的美学」の項、p. 310 以降。 12. 『哲学百科事典』(マクミラン、1967年、1996年)第4巻、「カント、イマヌエル」の項、「純粋理解概念」の節、p. 311 以降。 13. 例えば、『哲学百科事典』(マクミラン、1967年、1996年)第4巻、「カント、イマヌエル」の項、「純粋理性批判:主題と予備的考察」の節、308 頁以降を参照せよ。 14. 例えば『哲学百科事典』(マクミラン、1967年、1996年)第4巻「カント、イマヌエル」の「純粋理解概念」の項、311頁以降も参照せよ。 15. カント 1999年、27頁、A256/B312。 16. イマヌエル・カント(1781)『純粋理性批判』、例えばA254/B310、362頁(ガイヤーとウッド訳)において、「物自体、すなわち感覚の対象と してではなく、物自体として考えられるべきものの概念 [...]」と述べられている。ただし、これらの用語が全編を通じて互換的に使用されているわけではないことに注意せよ。物自体への最初の言及は、物自体 (A30)への最初の言及より何ページも前(A250)にある。二次・三次資料としては、ブリタニカ百科事典の「物自体」の項を参照せよ 17. 「物自体:超越的対象として見なされるものに与えられる名称。『否定的超然物』という用語は、感覚的直観の対象ではない何かを認識することのみを指す。一 方『肯定的超然物』は、そのようなものを経験的対象として知ろうとする(全く誤った)試みを指す。これら二つの用語は、時にそれぞれ『超越的対象』と『物 自体』の同義語として大まかに用いられることがある。(現象参照)" – カント専門用語集 18. 物自体:主体が物理的感覚を通じて知識を得る全ての条件から超越的に切り離された対象。したがって物自体は、定義上、物理的感覚を通じては知ることができ ない。時に「物自体」と同義語として大雑把に使われる。(参照:現象)——カント専門用語辞典 パルムクイストはこれらの用語の定義を、論文「カント認識論における対象の六つの視点」『Dialectica』40巻2号(1986年) pp.121–151で擁護している。改訂版は著書『カントの視点体系』(ランハム:アメリカ大学出版、1993年)第VI章として再録された。 19. オイゼルマン, T. I., 「カントの『物自体』と『超感覚的対象』の教義」, 『哲学と現象学研究』, 第41巻第3号, 1981年3月, 333–350頁; カリン・デ・ボーア「物自体、超越論的対象、モナドに関するカントの多層的構想」『カント研究』105/2、2014年、221-260頁。 20. 他の解釈者たちは、これらの用語をどう使うべきかについて、ほぼ尽きることのない様々な提案を提示してきた。この点を明らかにするには、例をいくつか挙げ るだけで十分であり、網羅的な概観を主張するものではない。おそらく最も広く受け入れられている見解はポールセンによって表明されている。彼は『物自体』 と『超現象』を同一視し、『表象』と『現象』を同一視し、『肯定的超現象』と『否定的超現象』を区別し、『否定的超現象』を『超越論的対象』と同等と見な している[pp. 4:148-50, 154-5, 192]。アル=アズムとウォルフも「現象」と「表象」を同義と見なすことに満足しているようだが、両者とも「物自体」を「否定的超然物」や「肯定的超然 物」とは慎重に区別している[A4:520; W21:165, 313–5; s.a. W9:162]。ゴッターバルンも同様に前者の対を同一視し、「物自体」と「肯定的超現象」も同一視するが、「超越論的対象」、「否定的超現象」、「物自 体」は区別している[G11: 201]。これに対し、バードとジョージは「表象」と「現象」を区別するが、「物自体」と「超現象」の区別はしない[B20:18,19, 53–7; G7:513-4n]。またバードは「物自体」と「超越論的対象」の区別も時に曖昧にする。[2] グラムは「物自体」を「超現象」ではなく「現象」と同一視している[G13:1,5-6]!アリソンは各用語に異なる公式定義を引用しながらも、『物自 体』を時に『否定的超然物』と、時に『超越的対象』と同一視する傾向があり、通常『肯定的超然物』の役割を無視している[A7:94; A10:58,69]。そしてブッハダールは、物自体(ものそのもの)が他の各対象用語と関連しているように見える事実に対して、それを「カントの包括的 用語」と見なすことで応答している[3]」スティーブン・パームクイストによるカントの対象用語論 21. カント 1999, Bxxvi-xxvii. 22. カント 1999, p. 273, A256, B312. 23. 「カントの『物自体』の根本的不可知性」、『コギト』3巻2号(1985年3月)、101-115頁;改訂版は付録Vとしてスティーブン・パームクイスト 『カントの視点体系』(ランハム:ユニバーシティ・プレス・オブ・アメリカ、1993年)に再録。 24. マティ、G. J. 25. G. J. マティの講義ノート Archived 2010-06-12 at the Wayback Machine 26. カント 1999, p. 267 (NKS), A250/B307. 27. カント 1999, p. 270 (NKS), B309. 28. アリソン, H (2006). 「超越的実在論、経験的実在論、そして超越的観念論」. カンティアン・レビュー. 11: 1–28. doi:10.1017/S1369415400002223. S2CID 171078596. 29. カント 1999, A253/B310. 30. カント 1999, p. 273, A256/B312. 31. カント 1999, p. 156, B/137. 32. カント 1999, p. 24, B/xx.. 33. ローマン, クリス. 「カント」『思想の世界:重要な理論、概念、信念、思想家の辞典』. バレティン・ブックス, 1999. 34. マティ、GJ。「純粋理性批判に関する講義ノート」。 35. 匿名、「カイドのカント哲学」、Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art、第 44 巻、1877 年 11 月 3 日、559-560 ページ。 36. ショーペンハウアー、アーサー (2014)。『意志と表象としての世界』第 1 巻。ノーマン、ジュディス、ウェルチマン、アリステア、ジャナウェイ、クリストファーによる翻訳。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。506 ページ。ISBN 9780521871846。 |
| Bibliography Kant, Immanuel (1999). Critique of Pure Reason (The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant). Cambridge University Press. ISBN 978-0521657297. |
参考文献 カント、イマヌエル(1999)。『純粋理性批判』(ケンブリッジ版イマヌエル・カント著作集)。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0521657297。 |
| The surd of
metaphysics; an inquiry into the question: Are there
things-in-themselves? (1903) by Paul Carus, 1852–1919 |
形而上学の根号;「物自体はあるのか?」という問いへの探究(1903
年)ポール・カラス著(1852–1919) |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Noumenon |
リンク
文献
その他の情報
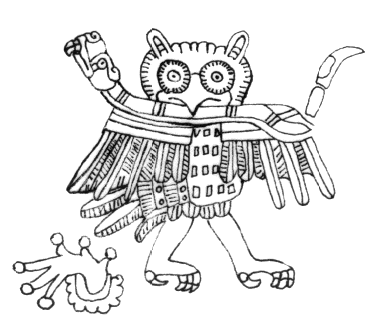

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099