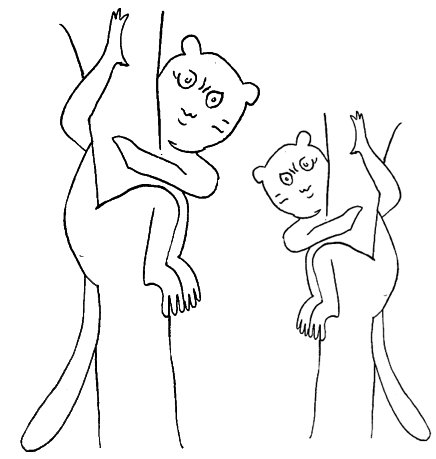
自由の否定あるいは越境
The Negative of Freedom or Transgression, by G.W.F. Hegel 1802/3
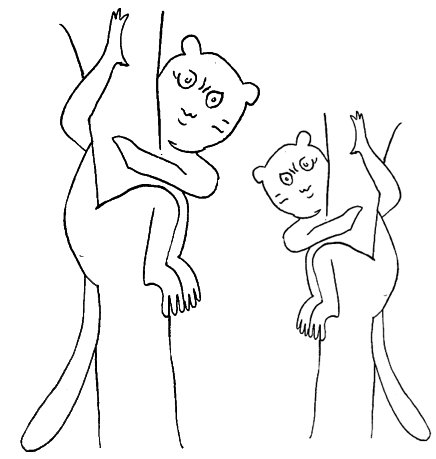
☆ヘーゲルの死後出版された原稿の中で、『倫理的生活の体系』はおそらく最も謎めいたものである。死後出版物を詳細に研究したドイツの学者たちでさえ、この評価に異 論を唱える者はいないようだ。例えばヘーゲルの初期著作を最も包括的に研究したハーリングはこう述べている。「確かに、これを理解する困難さは並外れてい る」(『ヘーゲル、その意志と業績』第2巻、338頁)。このため我々は、ドイツ語でさえほとんど理解不能な内容を、明快で理解しやすい英語に完全に翻訳 することが常に可能とは限らなかった。しかしながら、この試みは価値あるものだと我々は考えた。なぜなら本論文はヘーゲルの体系的草稿の中で現存する最古 のものであり、彼の成熟した社会思想が萌芽的な形で表れているからだ。ドイツの学者たちによって長く認識されてきたその重要性は、シュロモ・アヴィネリ (『ヘーゲルの近代国家論』、ケンブリッジ、1972年)によって、今やアングロサクソン系の研究者にも明らかになったのである(翻訳者T.M. ノックスによる序文より)(→「ポータル:倫理的生活の体系」)。
☆自由の否定、あるいは超越
| System of Ethical Life 2. The Negative of Freedom or Transgression The foregoing has singularity as its principle; it is the Absolute subsumed under the Concept; all the levels express specific characteristics, and the moments of indifference are formal; universality as opposed to particularity is undifferentiated only in relation to lower particulars, and these moments of indifference are themselves particulars once again. There is thus plainly no moment that is absolute; any one can be cancelled. The indifference which is the absolute totality of each level is not inherent, but lies beneath the form of singularity which is the subsuming moment.[25] The cancellation of specific characteristics must be absolute in itself, the assumption of all specific characteristics into absolute universality. This assumption is absolute and positive, but it is also purely negative. Just as, in the foregoing, absolute form expressed itself as the persistence of antithesis, so it expresses itself here in its opposite, or in the nullification of antithesis. But when this nullification is purely negative, it is dialectical, i.e., it is cognition of ideality and the real supersession of specific characteristics. Here the negative is not fixed, it is not in antithesis to the positive, and thus it is in the Absolute. Absolute ethical life rises above specific determinacy because the Absolute cancels the determinacy, though in such a way that the Absolute unites it with its opposite in a higher unity; thus the opposite is not left by the Absolute to persist in truth but is given a purely negative meaning; but owing to the perfect identity with its opposite, its form or ideality is cancelled by the Absolute, which precisely deprives it of its negative character and makes it absolutely positive or real. The cancellation of the negative is quite different. It is itself cancellation of cancellation, opposition to opposition, but in such a way that ideality or form likewise persists in it though in a converse sense; i.e., cancellation maintains the ideal determinate being of singularity and so determines it as negative; thus it allows the singularity and oppositeness of determinate being to persist, and does not annul the antithesis but transforms the real form into the ideal one. In the foregoing every level and every reality of a level is an identity of opposites, absolutely inherently. The identity is subsumed under the form, but the form is something external. The real persists; the form is what is on the surface, and its determinacy is enlivened, made indifferent; the real is indeed something determinate, but it is not determinate for itself; the real is not determined, and its essence is not posited, as determinate. But now the form, as negative, is the essence. The real becomes posited as something ideal; it is determined by pure freedom. This is the same transformation that occurs when sensation is posited as thinking. The specific characteristic remains the same; red as sensed remains red as thought, but the thought is determined at the same time as something nullified, cancelled, and negative. The freedom of intelligence has raised the specific character of the sensation of red to universality; it has not deprived the sensation of its opposition to other determinate sensations, but has only made the false attempt to do that. It has reflected on the sensation, raised it to infinity, but in such a way that finitude remains definitely persistent. It has transformed the objective reality of time and space into a subjective one. Objective ideality is “being other,” i.e., having other colours around it; quite simply and in every respect ideality and infinity are posited empirically as something everywhere “other.” Subjective ideality cleanses infinity of this multiplicity, gives to it the form of unity, binds the specific character itself together with the infinity which lies objectively outside it and is manifested as “being other,” and in this way makes infinity into a unity as the absolute determinacy of the subjective or ideal as opposed to the real. And while the determinacy as real, as sensation, had the form, infinity, as it were on the surface outside it, it is now bound up with it. Similarly in the practical sphere what in and by itself is negative is a determinacy posited by the same moment of negation according to the preceding level of necessity; it is itself something objective, ideal, and universal. The negation of this practical positing is the restoration of the first original particularity of the antithesis. Because the former objectivity is superseded, the practical sphere falls under the control of the inorganic and objective levels. Murder does away with the living thing as an individual or subject, but ethical life does this too. But ethical life does away with subjectivity or with the ideal specific character of the subject, whereas murder does away with his objective existence; it makes him something negative and particular which falls back under the control of the objective world from which he had torn himself free by being something objective himself. Absolute ethical life directly cancels the individual’s subjectivity by nullifying it only as an ideal determinacy, as an antithesis, but it lets his subjective essence persist quite unaffected. And he is allowed to persist, and is made real, as subject precisely because his essence is left undisturbed as it is. In ethical life intelligence remains a subjectivity of this kind. |
倫理的生活体系 2. 自由の否定、あるいは超越 前述の内容は特異性を原理とする。それは概念の下に包含される絶対である。全ての段階は特定の特性を表し、無差別な瞬間は形式的なものである。個別主義に 対する普遍性は、より低次の個別性との関係においてのみ未分化であり、これらの無差別な瞬間自体が再び個別性となる。したがって、絶対的な瞬間は明らかに 存在せず、いかなる瞬間も取り消されうる。各段階の絶対的総体である無差別性は内在するものではなく、包含する瞬間である特異性の形式の下に横たわる。 [25] 特定の特徴の取消しはそれ自体で絶対的でなければならない。すなわち、あらゆる特定の特徴を絶対的普遍性に取り込むことである。 この包含は絶対的かつ肯定的だが、同時に純粋に否定的でもある。前述のように絶対的形態が対立の持続として現れたのと同様に、ここではその反対、すなわち対立の無効化として現れる。 しかしこの無効化が純粋に否定的であるとき、それは弁証法的である。すなわち、それは観念性の認識であり、特定の特性の現実的な超越である。ここで否定は 固定されておらず、肯定と対立しておらず、したがってそれは絶対の中に存在する。絶対的倫理的生活は特定の決定性を超越する。なぜなら絶対者は決定性を取 消すからである。ただし絶対者はそれをより高次の統一において反対物と結合させる。したがって反対物は絶対者によって真実として存続させられるのではな く、純粋に否定的な意味を与えられる。しかし反対物との完全な同一性ゆえに、その形式あるいは観念性は絶対者によって取消される。絶対者はまさにその否定 性を剥奪し、それを絶対的に肯定的あるいは現実的なものとするのである。 否定の取消しは全く異なる。それはそれ自体が取消しの取消し、対立への対立であるが、その際にも観念性や形式は逆の意味で存続する。すなわち、取消しは特 異性の観念的決定的存在を維持し、それを否定として決定する。こうして決定的存在の特異性と対立性は存続を許され、反論は消滅せず、現実的形式が観念的形 式へと変容するのだ。 前述の通り、あらゆる段階と各段階の現実は、絶対的に内在的に、対立物の同一性である。この同一性は形式に包含されるが、形式は外在的なものである。実在 は持続する。形式は表面的なものであり、その確定性は活性化され、無関心なものとなる。実在は確かに確定されたものであるが、それ自体のために確定された ものではない。実在は確定されておらず、その本質は確定されたものとして設定されていない。しかし今や、否定としての形式が本質となる。実在は理想的なも のとして設定され、純粋な自由によって確定される。 これは感覚が思考として設定される際に生じる変容と同じである。特定の特性は変わらない。感覚された赤は思考された赤として赤のままだ。しかし思考は同時 に無効化され、取消され、否定的なものとして決定される。知性の自由は、赤の感覚の特定の特性を普遍性へと高めた。それは感覚を他の特定の感覚に対する対 立から剥奪したのではなく、そうしようとする誤った試みをしたに過ぎない。知性は感覚を省察し、無限へと高めたが、有限性が確実に持続する形でそうした。 時間と空間の客観的現実性を主観的なものへと変容させたのだ。客観的観念性は「他者であること」、すなわち周囲に他の色を持つことである。端的に言えば、 あらゆる点において観念性と無限性は、遍在する「他者」として経験的に設定される。主体性は無限からこの多様性を洗い流し、統一の形式を与え、特定性をそ れ自体と結びつける。客観的に外側にあり「他者であること」として現れる無限と結びつける。こうして無限を統一へと変え、現実に対する主体の絶対的決定性 とする。そして現実的、感覚的決定性が形を有していた一方で、無限性は、いわばその表面の外側にあったが、今やそれと結びついている。 同様に実践的領域において、それ自体として否定的なものは、先行する必然性の段階に従って、同じ否定的瞬間によって設定された決定性である。それはそれ自 体、客観的、観念的、普遍的なものである。この実践的設定の否定は、対立項の最初の原初的個別主義の回復である。以前の客観性が克服されるため、実践的領 域は無機的・客観的段階の支配下に置かれる。殺人は個体あるいは主体としての生き物を消滅させるが、倫理的生活もまたこれをなす。しかし倫理的生活は主体 性、すなわち主体の理想的特殊性を消滅させるのに対し、殺人はその客観的存在を消滅させる。殺人は彼を否定的な個別的存在とし、自らも客観的存在であるこ とによって客観的世界から解き放たれた彼が、再びその支配下に陥るようにするのだ。絶対的倫理的生活は、個人の主観性を、理想的決定性として、対立物とし てのみ無効化することで直接的に否定する。しかし主観的本質は全く無傷のまま存続する。そして本質がそのまま残されるからこそ、主体として存続を許され、 現実化されるのだ。倫理的生活において知性は、まさにこの種の主体性として存続する。 |
| This
negative, or pure freedom, leads to the cancelling of the objective in
such a way that the negative makes the ideal specific determinacy,
which in the sphere of necessity is only external and superficial, into
the essence.[26] Thus it negates reality in its specific determinacy,
but it fixes this negation. But against this negation there must be a reaction. Since the cancellation of the specific determinacy is only formal, determinacy as such persists. It is posited ideally, but remains in its real specific character. And in it life is only injured, not elevated to a higher level, and therefore must be restored. But in its actuality an injury of life cannot be restored (restoration by religion does not affect actuality); but the restoration here does affect actuality, and this reconstruction can only be a formal one, because it affects actuality as such and the fixedness of negation. It is therefore external equality; the negating subject makes himself a cause and posits himself as negative indifference, but therefore the proposition must be converted upon him who was the subject of it and he must be posited under the same characteristic of the indifference as he posited. What he negated is to be equally really negated in him, and he has to be subsumed just as he subsumes. And this conversion of the relation is absolute, for in what is determinate it is only possible for Reason to assert itself as indifference, and so in a formal mode, by positing the two opposites symmetrically. There is an absolute link between crime or transgression and the justice of revenge. They are bound together by absolute necessity, for one is the opposite of the other, the one is the opposite subsumption of the other. As negative life, as the concept constituting itself into intuition, transgression subsumes the universal, the objective, and the ideal; conversely, as universal and objective, avenging justice subsumes again the negation which is constituting itself as intuition. It must be noticed here that what is in question is the real reaction or reversal, and that the ideal, immediate, reversal according to the abstract necessity of the concept is included in general, but in this form of ideality it is only an abstraction and something incomplete. This ideal reversal is conscience and it is only something inner, not inner and outer simultaneously; it is something subjective but not objective at the same time. The criminal has directly injured something he regards as external and foreign to himself, but in doing so he has ideally injured and cancelled himself. Inasmuch as the external deed is at the same time an inner one, the transgression committed against a stranger has likewise been committed against himself. But the consciousness of this his own destruction is a subjective and inner one, or a bad conscience. It is to that extent incomplete and must also manifest itself externally as avenging justice. Because it is something inner and incomplete, it presses on to a totality. It betrays itself, reveals itself, and works of itself until it sees the ideal reaction or reversal confronting it and threatening its reality from without and as its enemy. Next it begins to be satisfied because it descries the beginning of its own reality in its enemy. It produces an attack on itself so as to be able to defend itself, and through its resistance to the attack it is at peace by defending against the threatened negation the most universal demand, that of indifference and totality, i.e., life, of which the conscience is one specific characteristic. But through victory in this set battle the same pang of conscience returns, and conscience is reconciled only in the danger of death and ceases only in that danger. But with the coming of every victory the fear becomes greater, the fear which is an ideal state of annihilation. It presses on the force of life and so brings with it weakness and also the reality of avenging justice. And it engenders this justice even when the enemy does not at once appear externally and when the conversion of the subsumption is not present as a reality. |
この否定、すなわち純粋な自由は、目的を次のように取消す。すなわち否定は、必然の領域において外部的かつ表層的なものに過ぎない理想的な具体的決定性を、本質へと変えるのである[26]。こうしてそれは現実をその具体的決定性において否定するが、この否定を固定化する。 しかしこの否定に対しては反動がなければならない。具体的決定性の取消しが形式的なものに過ぎない以上、決定性そのものは存続する。それは理想的に位置づ けられるが、現実的な具体的性格は残る。そしてそこでは生命は傷つけられるだけで、より高い段階へ高められるわけではない。ゆえに回復されねばならない。 しかし現実において生命の損傷は回復できない(宗教による回復は現実性に影響しない)。しかしここでの回復は現実性に影響し、この再構築は形式的なものに しかなりえない。なぜならそれは現実性そのものと否定の固定性に影響するからだ。したがってそれは外的な平等である。否定する主体は自らを原因とし、否定 的な無関心として自らを仮定する。しかしそれゆえに、その命題はそれの主体であった者に対して転化されねばならず、彼は自ら仮定したのと同じ無関心の特性 のもとで仮定されねばならない。彼が否定したものは、彼自身においても等しく現実的に否定されねばならず、彼は自らを帰属させるのと同じように帰属されね ばならない。そしてこの関係の転換は絶対的である。なぜなら、確定的なものにおいては、理性は両対立物を対称的に位置づけることによってのみ、無関心とし て、すなわち形式的な様式において自らを主張することが可能だからだ。 犯罪あるいは違反と復讐の正義の間には絶対的な連関がある。両者は絶対的必然性によって結びついている。なぜなら一方は他方の反対であり、一方は他方の反 対的帰属だからだ。否定的な生命として、直観へと自己を構成する概念として、違反は普遍的・客観的・理想的なものを帰属させる。逆に、普遍的・客観的とし て、復讐の正義は直観として自己を構成する否定を再び帰属させる。 ここで留意すべきは、問題となっているのは現実の反動あるいは逆転であり、概念の抽象的必然性に基づく理想的・直接的な逆転は一般的には包含されている が、この形式の観念性においては単なる抽象であり不完全なものに過ぎないという点だ。この理想的逆転は良心であり、それは内面的であるだけで、内面的かつ 外面的ではない。主体性ではあるが、同時に客観的ではない。犯罪者は自らを外部かつ異質と見なす対象を直接傷つけたが、その行為によって理想的には自らを 傷つけ消滅させたのである。外部への行為が同時に内部への行為である限り、他者に対する違反行為は同時に自己に対する違反行為でもある。しかしこの自己破 壊の意識は主体的かつ内面的、すなわち良心の呵責として現れる。それゆえ不完全であり、復讐の正義として外部に現れねばならない。内面的で不完全なもので あるゆえ、全体性へと迫る。自らを裏切り、自らを露呈し、自らを働かせ、理想的な反動や逆転が外部から現実を脅かし敵として対峙するのを目にするまで続 く。次に、敵の中に自らの現実の始まりを見出して満足し始める。それは自らを防衛するために自らへの攻撃を生み出し、その攻撃への抵抗を通じて、脅威とな る否定、すなわち無関心と全体性、つまり生命という最も普遍的な要求(良心はその一つの特質である)を防衛することで平安を得る。しかしこの決闘での勝利 によって、同じ良心の痛みは再び戻り、良心は死の危険においてのみ和解し、その危険においてのみ止む。しかし勝利が訪れるたびに、恐怖は増大する。その恐 怖とは、消滅という理想的な状態である。それは生命の力を圧迫し、それゆえ弱さと復讐の正義という現実をもたらす。そして敵が外部に即座に現れず、帰属の 転換が現実として存在しない場合でさえ、この正義を生み出すのである。 |
| (a) The first level of this thus determined negation is the formal one in accordance with the subsumption of concept under intuition. Annihilation by itself, apart from being related to something else, presupposes a specific deficiency, but a completely indeterminate and general one, affecting nothing individual but directed rather against the abstraction of culture as such.[27] This is natural annihilation or purposeless destruction and havoc. Nature is thus turned against the culture imparted to it by intelligence, as well as against its own production of the organic. And just as the element [the forces of unconscious life], the objective, is subsumed under intuition and life, so the element in return subsumes under itself, and destroys, what is organic and individualised; and this destruction is havoc. Thus culture alternates with destruction in human history. When culture has demolished inorganic nature long enough and has given determinacy in every respect to its formlessness, then the crushed indeterminacy bursts loose, and the barbarism of destruction falls on culture, carries it away, and makes everything level, free, and equal. In its greatest magnificence, havoc occurs in the East, and a Genghis Khan and a Tamerlane, as the brooms of God, sweep whole regions of the world completely clean. The northern barbarians who continually invaded the south belong to the level of understanding; their miserable enjoyment, which they have developed into at least a narrow range of culture has therefore a specific character, and their havoc is not mere havoc for the sake of havoc. The fanaticism of havoc, being absolutely elemental and assuming the form of nature, cannot be conquered from outside, for difference and specific character succumb before indifference and indefiniteness. But, like negation in general, it has its own negation in itself. The formless drives itself on towards indeterminacy until, because it is not after all absolutely formless, it bursts, just as an expanding bubble of water bursts into innumerable tiny drops; it departs from its pure unity into its opposite, i.e., the absolute formlessness of absolute multiplicity, and therefore becomes a completely formal form or absolute particularity and therefore the maximum of weakness. This advance from havoc to absolute havoc and hence to the absolute transition into its opposite is fury [or mania]; since havoc is wholly within the concept, mania must intensify purity, the very opposite of havoc, ad infinitum, until that opposite becomes opposed to itself and so has annihilated itself. Standing at the extreme, i.e., at absolute abstraction, mania is the absolute and unmediated urge, the absolute concept in its complete indeterminacy, the restlessness of the absolute concept’s infinity. This restlessness is nothing but this extreme, and in its annihilation of the opposites by one another, it annihilates itself, and so is the real being of absolute subjectivity. The absolute concept, the immediate opposite of itself, is real because what it produces is by no means an identity of subject and object, but pure objectivity or formlessness. |
(a) こうして決定された否定の第一段階は、概念が直観の下に包含されることに従った形式的なものである。他の何かとの関係を離れて単独で存在する消滅は、特定 の欠如を前提とするが、それは完全に不確定で一般的なものであり、個別の何ものにも影響を与えず、むしろ文化という抽象そのものに向けられている。 [27] これは自然の消滅、あるいは目的を欠いた破壊と荒廃である。こうして自然は、知性によって与えられた文化に対して、また自らの有機的生産物に対しても敵対 する。そして要素[無意識的生命の力]、すなわち客観が直観と生命の下に包含されるのと同様に、要素は逆に有機的・個別化されたものを自らの下に包含し、 破壊する。この破壊こそが荒廃である。こうして文化は人類史において破壊と交互に現れる。文化が無機的な自然を十分に破壊し、その無定形性にあらゆる面で 確定性を与えたとき、押し潰された不定性が解き放たれ、破壊の野蛮が文化に襲いかかり、それを運び去り、あらゆるものを平坦で自由かつ平等にする。破壊の 荒廃は東洋において最も壮大に現れ、チンギス・ハンやティムールといった神の手櫛が世界の広域を完全に清める。絶えず南方へ侵攻した北方蛮族は理解の段階 に属する。彼らが少なくとも狭い範囲の文化へと発展させたみじめな享楽はゆえに特有の性格を持ち、彼らの破壊は単なる破壊のための破壊ではない。破壊の狂 信は絶対的に根源的であり自然の形態を帯びるため、外部から征服することはできない。差異と特有の性格は無関心と不定性の前には屈服するからだ。しかし、 一般的な否定と同様に、それ自体に自らの否定を内包している。形なきものは不確定性へと自らを駆り立て、結局は絶対的に形なきものではないゆえに、膨張す る水泡が無数の微小な水滴へと破裂するように、破裂する。純粋な統一性からその反対、すなわち絶対的多様性の絶対的な形なき状態へと移行し、それゆえに完 全に形式化された形態、あるいは絶対的な個別主義となり、それゆえに弱さの極致となる。この破壊から絶対的破壊へ、ひいてはその反対への絶対的移行への前 進が狂気である。破壊は概念内に完全に収まるがゆえに、狂気は破壊の正反対である純粋性を無限に強化せねばならず、その反対が自己に反対するに至り、こう して自己を消滅させるまで続く。極限、すなわち絶対的抽象に立つ狂気は、絶対的かつ媒介されない衝動であり、完全な不確定性における絶対的概念、絶対的概 念の無限性における落ち着きのなさである。この落ち着きのなさはこの極限に他ならず、対立物同士による相互消滅において自らを消滅させる。それゆえ、絶対 的主体性の実在である。絶対概念、すなわち自己の直接的な対立物こそが実在する。なぜなら、それが生み出すものは決して主観と客観の同一性ではなく、純粋 な客観性、すなわち無形式だからである。 |
| (b) This havoc, subsumed under the concept, is, as a relation involving difference and specific determinacy, directly turned against the positive relation of difference. The havoc of nature, so far as it is specifically determined, can only tear possession away from him who has it; the presupposition is that havoc is in precisely the same characteristic position as what confronts it, and thus it lets this position persist; the indifferent moment of possession, the aspect of legal right, does not concern it; it only affects the particular situation. But ethical life, owing to its nature as intelligence, is at the same time objective and universal, and so in an identical relation with an “other”; the nullifying of a particular character of the other — and no other nullifying act is relevant here except one directed at an ethical being — is at the same time the nullification of indifference and the positing of it as something negative; the positive aspect of this positing lies in the fact that the specific thing remains as such and is only posited with a negative specification. Such letting the specific characteristic persist, though along with the nullifying of the indifference of recognition, is an infringement of the law. As a phenomenon, i.e., as a real nullifying of recognition, this infringement is also the cutting of the tie between the specific thing and the individual subject. For recognition recognises precisely this tie (in itself purely an ideal one) as a real one; owing to recognition, it is a matter of indifference whether the subject has absolutely and inseparably united this specific thing with himself or whether its connection with him is only relative and this unification is put only formally as a possibility. By recognition the relative connection itself becomes indifferent and its subjectivity also objective. The real cancellation of recognition cancels that tie too and is deprivation, or, when it purely affects the tied object, theft. In this tie between the object and the subject, which is what property means, the nullification of the moment of indifference or legal right makes no difference to the specific thing, which remains unaffected; the object stolen remains what it is, but the subject does not, for here, in the particular case, he is the indifference of the connection. Now in so far as it is not the abstraction of his tie with the object which is cancelled [as in voluntary alienation], but he himself who is injured in respect of that tie, something is cancelled in him — and what is cancelled in him is not the diminution of his possessions, for that does not affect him as a subject; on the contrary it is the destruction of his being as indifference by and in this single act. Now since the indifference of specific characteristics is the person and this personality is injured here, the diminution of his property is a personal injury, and this is necessarily so throughout this whole level of particularity. For the injury is directly non-personal if it is only the abstraction of the subject’s tie with the object that is infringed; but at this level this abstraction is not made as such; it does not yet have its reality and support in something itself universal [i.e., a legal system], but solely in the particularity of the person. And therefore every deprivation is personal. The tie here is personal, as it is elsewhere only when it is a real or empirical one; the possessor has the object he possesses directly before his eyes, or he holds it, or has made it secure in some other way in his premises, which is how he regards the space he occupies along with his possessions. This empirical connection, as a specific type, is here the type prevailing at this level generally, for at this level there is still no suggestion of any way whereby the empirical connection itself could be indifferenced and property protected without it, i.e., a way in which the ideal connection could be real without being empirical, so that personal integrity would not be infringed by the infringement of the ideal tie of possession qua property. Consequently theft is both personal and a deprivation; and the subsumption of a possession, which is a property, under the desire of someone else (or the negation of indifference, and the assertion of a quantitatively greater particularity against a quantitatively lesser one, of the subsumption of the more different under the lesser) is might, not in general, but against property, or robbery must have its reaction or the converse subsumption. Just as there is subjugation here, i.e., the lesser might is subsumed under the greater, so conversely what is momentarily the greater might must be posited as the lesser. And in accordance with absolute Reason this reversal is just as absolutely necessary as the former subsumption is actually robbery. But robbery exists only where the relation of lordship and bondage does not. But where this relation exists, where an individual is more indifferent, where thus the higher level is there as the other one, then there is naturally no robbery except in so far as robbery is pure and simple havoc and destruction, not in so far as if it were robbery proper. Therefore, because robbery becomes personal, person tries conclusions with person and the one subjugated becomes the bondslave of the other; and this entry to bondage is strictly the appearance of that relation which, in this relation of subsumption, accrues to each of the individuals; they cannot be beside one another without being connected. Robbery is the singular subsumption, not affecting the totality of the personality, and consequently the individual who makes this personal injury a matter of his entire personality must get the upper hand, and make the conversion real, because he posits himself as a totality while the other [the robber] posits himself as particularity only, and the reality of this relation is subjection, but the phenomenon of its coming-to-be is subjugation. In the foregoing relation [havoc] the reversal is absolutely annihilating, because annihilation itself is absolute, and so the reaction, like the treatment of an animal on the rampage, is absolute subjugation or death. But in this relation the reaction cannot be simply the recovery of what was stolen, on account of the personal character of the injury, but instead is only the moment of an establishment of lordship and bondage — the fact that being subsumed is real in the robber only for a moment and only in the determinate respect that corresponds with the determinate character of the personal injury that arose from his act ["an eye for an eye,” etc.]. But precisely because the assailant has not put his whole personality into his attack, the relation too cannot end with the totality of the personality in a subjecting relation, but can only exist for a moment. It is only through warfare that there is occasion for bondage, a war between men, a case of mutually self-recognising personality, or of necessity in respect of life as a whole — but otherwise men are slaves by nature. But except in war, the reaction to injury is formally the entirety of this relation, like adoption into the family, but materially it is equally single and particular. For the robber is too bad to be a slave, for he has not justified any trust in his own entire personality, since he has remained on the level of particularity.[28] |
(b) この破壊は、概念の下に包含されるものとして、差異と特定の決定性を伴う関係として、差異の肯定的関係に対して直接的に向けられる。自然の破壊は、それが 特定の決定性を持つ限りにおいて、所有者から所有権を引き剥がすことしかできない。前提として、破壊はまさにそれに対峙するものと同一の特性的位置にある ため、この位置を存続させる。所有という無差別な瞬間、法的権利という側面は、破壊の関心の外にある。破壊が影響を与えるのは、特定の状況のみである。し かし倫理的生活は、知性としての性質ゆえに、同時に客観的かつ普遍的であり、それゆえ「他者」との同一的な関係にある。他者の特定の特性を無効化すること ――ここで関連するのは倫理的存在に向けられた行為のみである――は同時に無関心の無効化であり、それを否定的なものとして設定することである。この設定 の肯定的側面は、特定のものがそのままで残り、否定的な規定をもってのみ設定されるという事実に存する。認識の無関心を無効化しつつも、この特異性を存続 させる行為は、法への違反である。現象として、すなわち認識の現実的無効化として、この違反は同時に、特異的なものと個別的主体との絆の断絶でもある。認 識はまさにこの結びつき(それ自体は純粋に観念的なもの)を現実のものとして認識する。認識によって、主体がこの特定のものを絶対的かつ不可分的に自己と 結びつけたか、あるいはその結びつきが相対的なものに過ぎず、この結合が形式的に可能性として提示されているかにかかわらず、それは無関心な問題となる。 認識によって、相対的な結びつきそのものが無関心なものとなり、その主体性もまた客観的になる。承認の現実的な取消しは、この結びつきをも取消し、剥奪と なる。あるいは、結びつけられた対象のみに影響する場合、窃盗となる。対象と主体の間のこの結びつき、すなわち所有を意味するこの結びつきにおいて、無関 心性あるいは法的権利の瞬間が無効化されても、特定の物自体には何の影響もなく、それはそのまま残る。盗まれた対象はそのままのままであるが、主体はそう ではない。なぜなら、この特定の事例において、主体こそが結びつきの無関心性だからだ。さて、対象との結びつきの抽象化が取消されるのではなく(自発的疎 外のように)、その結びつきに関して主体自身が傷つけられる場合、主体の中に何かが取消される。そして主体の中で取消されるのは、所有物の減少ではない。 なぜならそれは主体としての彼に影響を与えないからだ。むしろ、この単一の行為によって、そしてこの行為の中で、無関心としての彼の存在が破壊されるので ある。さて、特定の特質による無関心こそが人格であり、ここで傷つけられるのはこの人格である。ゆえに、彼の財産の減少は個人的損傷であり、この特異性の レベル全体において必然的にそうなる。なぜなら、侵害が単に主体と対象の結びつきの抽象化に留まる場合、その侵害は直接的に非個人的である。しかしこのレ ベルでは、その抽象化はそれ自体として成立しない。それはまだ普遍的なもの(すなわち法体系)に現実性と支えを持つのではなく、もっぱら個人の特殊性の中 にのみ存在する。したがってあらゆる剥奪は個人的である。この結びつきは、他の場所では実在的あるいは経験的な場合のみ個人的な属性を持つが、ここでは実 在的あるいは経験的な場合のみ個人に属する。所有者は、所有する対象を直接目の前に見ているか、手にしているか、あるいは所有物と共に占有する空間として 認識しているその敷地内で、何らかの方法で安全に保管している。この経験的結びつきは、特定の類型として、この段階では一般的に支配的な類型である。なぜ ならこの段階では、経験的結びつきそのものを無差別化し、それを介さずに財産を保護する方法、すなわち理想的結びつきが経験的でない形で現実となり、所有 権としての理想的結びつきの侵害によって個人の個人的な完全性が損なわれない方法が、まだ示唆されていないからである。 したがって窃盗は個人的な侵害であり剥奪でもある。そして財産としての所有物を他者の欲望の下に包含すること(すなわち無関心の否定、量的により少ない個 別性に対する量的により多い個別性の主張、より異なるもののより少ないものへの包含)は、一般的ではなく財産に対する力、すなわち強奪である。強奪には反 動、すなわち逆の包含が伴わねばならない。ここには服従、すなわちより小さな力がより大きな力に包含される関係があるのと同様に、逆に一時的により大きな 力はより小さな力として位置づけられねばならない。そして絶対的理性によれば、この逆転は、先の包含が実際に強奪であるのと同様に絶対的に必要である。し かし強奪は、支配と隷属の関係が存在しない場合にのみ存在する。しかしこの関係が存在する場所、つまり個人がより無関心な場所、つまりより高いレベルが他 者として存在する場所では、当然ながら強奪は存在しない。強奪が純粋かつ単純な破壊と荒廃である限りでは存在するが、強奪そのものとして存在するわけでは ない。したがって、略奪が個人的になるにつれ、人格は人格と対決し、征服された者は他者の奴隷となる。この隷属への陥落は、まさに包含関係において各個人 に帰属する関係性の表れである。彼らは結びつかない限り、互いに並存し得ないのだ。強奪とは特異な包含であり、人格の全体性に影響を及ぼさない。ゆえにこ の個人的な侵害を自己の全人格の問題とする個人は優位に立ち、この転換を現実のものとしねばならない。なぜなら彼は自己を全体性として位置づける一方、他 者[強奪者]は自己を個別主義のみとして位置づけるからである。この関係の現実性は服従であるが、その生成の現象は隷属である。 前述の関係[破壊]における逆転は絶対的な殲滅である。なぜなら殲滅そのものが絶対的だからだ。したがって反応は、暴れ回る動物への処置のように、絶対的 な服従か死である。しかしこの関係において、反応は単に奪われたものの回復ではありえない。なぜなら被害が個人的な性質を持つからだ。代わりにそれは支配 と隷属の確立の瞬間である——被包含される存在が強盗において現実となるのは、彼の行為から生じた個人的被害の決定的な性質に対応する決定的な側面におい て、一瞬だけであるという事実だ(「目には目を」など)。しかし加害者が攻撃に全人格を投入していないからこそ、この関係もまた人格の総体による服従関係 で終結できず、一瞬しか存在し得ない。隷属が生じるのは戦争を通じてのみである。すなわち人間同士の戦争、相互に自己を認識する人格間の事例、あるいは生 命全体に関わる必然性の場合に限られる。それ以外では人間は本来奴隷なのである。だが戦争以外では、傷害への反応は形式的にはこの関係の全体性をなす。家 族への養子縁組のように。しかし実質的には、それは同様に単一で個別的なものである。強盗は奴隷になるには悪すぎる。なぜなら彼は個別主義のレベルにとど まっているため、自らの人格全体に対する信頼を正当化したことがないからだ。[28] |
| (c) The indifference or totality of both these rogations affects the indifference of specific determinations, or life, and the whole personality; and the reversal (which is established equivocally and is not one-sided as it would be if the relation were quite definitely and certainly on one side) is likewise the loss of personality through slavery or death. Because the negation can only be one specific determinacy, this determinacy (the whole being out of the question) must be intensified into a whole. But because it is personal, it is immediately the whole, for the specific determinacy belongs to the person who is the indifference of the whole. And a particularity of a person, once denied, is only an abstraction, for in the person it is absolutely taken up into indifference. Denial here is an injury to life. But because this indifference has over against it the abstraction of the injured particularity, through the latter the former is posited ideally too, and what is injured is honour. Through honour the singular detail becomes something personal and a whole, and what is seemingly only the denial of a detail is an injury of the whole, and thus there arises the battle of one whole person against another whole person. There can be no question of the justice of the occasion for such a battle; when the battle as such starts, justice lies on both sides, for what is established is the equality of peril, the peril of perfect freedom indeed, because the whole personality of both is at issue. The occasion, i.e., the specific point which is posited as taken up into indifference and as personal, is strictly nothing in itself, precisely because it is only a personal matter. Anything can be posited as such in innumerable ways; nothing can be excluded and no limit can be set. Might, or rather might individualised as strength, decides who dominates; and here, where the entire real personality is the subject, the relation of lordship and bondage must enter immediately. Alternatively, if absolute equality, the impossibility of such a relation between differents, is presupposed, and so the impossibility of one being the indifferent and the other the different, then in battle, as absolute difference and reciprocal negation, indifference is to be maintained, and the strife is to be assuaged solely by death, in which subjugation is absolute, and precisely through the absoluteness of the negation the downright opposite of this absoluteness, freedom, is upheld. But it is a different thing when there is inequality in the negation and one-sidedness in the battle, which in that event is no battle. This inequality, where domination is purely on one side — not swaying from one to the other — and where the centre is set as possibility and therefore the indifferent possibility of either, is oppression and, when it proceeds to absolute negation, murder. Oppression and murder are not to be confused with battle and the relation of mastery. Genuine and unrighteous oppression is a personal attack and injury in a manner whereby all battle is simply cancelled. It is impossible for a person attacked to foresee the attack and thereby start a battle. But in itself this impossibility cannot be proved and demonstrated — the Italians advance as a reason for the lawfulness of assassination the immediacy of a declaration of war resulting from the offence — only in that event the impossibility is to be regarded as actually present when no offence is present and the murder is committed not at all on personal grounds but for the sake of robbery. But even if an offence has preceded, so that personality and the whole individual is in question, the offence is wholly unlike total negation on the side of reality; honour indeed has been injured, but honour is distinguishable from life. And since life is brought into play in order to restore to honour its reality, which as injured honour is only ideal, the linking of the ideality of honour with its reality is achieved only by raising to full reality the specific aspect injured; and honour consists in this, that when once one specific aspect is negated, then life, or the totality of specific aspects, is to be affected too. Thus the man’s own life must be brought in question as the means whereby alone that negation of a single detail is made into a whole as it should be. (margin: 3 levels: (a) murder, (b) revenge, (c) duel. The centre is battle, swinging to and fro. Duel, personal injury on some singular point). This totality of negation must be conceived under its three forms: (aa) Crude totality, the absolute indifference of negation without relation and ideality, is the transformation of specific determinacy into personality, and the immediate establishing of the reality of the negation or [in other words] murder simply. Murder precludes the recognition of this relation, the other’s knowing about this relation, and prevents equality of peril from preceding; moreover the injury is materially wholly unequal.[29] (bb) The second level must be the formal indifference in accordance with which domination and its reversal occur according to the law of equality, but in such a way that the equality as form, as consciousness, hovers over the opposition of the individuals, is not a consciousness and recognition of the opposition. Thus the form of equality is missing along with the equality of peril, for peril is nothing but the approach of negation; yet the knowledge of the negation, the indifference, is here not in the peril but is purely material; the relation is subsumed under the concept. The true and real reversal of the subsumption lies in this equality and is revenge. What has been killed must itself make the reversal, but as killed it is purely something ideal. Out of its life, which is its blood, only its spirit can rise in revenge. Either this spirit can so long pursue the murderer until, in whatever way, he sets a reality over against himself and himself creates a body for the spirit of the man he has slain, a body which, being no longer the same external appearance of the man slain, appears as something more generally universal, and the spirit wreaks its revenge in the form of fate, Or, however, the real life properly belonging to the spirit has remained; the spirit has preserved its body and the murder has destroyed only one single member or organ of the whole, and so this still living body, i.e., the family, takes on itself the work of revenge. Revenge is the absolute relation against murder and the individual murderer; it is simply the reverse of what the murderer has done; what he has done can in no other way be superseded and made rational. Nothing can be abstracted from it, for it has been established as an actuality which as such must have its right, i.e., Reason demands that the opposite of the situation created shall be created. The specific character of the relation remains, but within that character the relation is now transformed into the opposite one; what dominates is dominated. The only thing altered is the form. (gg) The totality of this relation is what is rational and it makes the middle term emerge. The indifference of the justice which lies in revenge, but as something material and external, enters the individuals as a like consciousness of the emerging negation, and therefore the reality of this emergence is alike too on both sides. Consequently an injustice seems to prevail, since the man who made the attack, the first unequal and one-sided domination (and both the opposed dominations must appear and display themselves as following on one another), should be in the wrong, but, owing to consciousness, would simply come into an equality of peril. When revenge is in question, undoubtedly only the man who was the murderer must be dominated in turn in some sure way, and the avengers thus escape from the equality of strength and they wreak revenge either by a superiority of might or by cunning, i.e., by the evasion of strength as such. But here in the totality of the relation, things are different, i.e., it directly excludes singleness in such a way that for revenge the avenger is not a stranger or even only a single individual, nor is the assailant, but the member of a family and so not an abstraction. But since this is the case, murder is not an absolute negation; the spirit has lost only one member of its body, and neither can revenge be an absolute negation. In the totality of revenge the form must be put as absolute consciousness, and so the injured party himself, and no stranger, must be the avenger — and this is only the family. Similarly the injurer is not a single individual; it is not as single individual but as the member of a whole that he has done injury; in the totality of revenge he is not posited as an abstraction. In this way the middle term is directly posited at the same time, i.e., negatively as the cancelling of the superiority and lack of consciousness in the one, and equality of peril for both, i.e., battle. Given perfect outward equality, the difference for the relation is in the inner life (and therefore the battle is a divine judgment): one side is only defending itself, the other side also attacking. Right is on the side that has been injured, or this side is the indifferent and dominant one. This it is absolutely because absolute equality must be displayed by the reversal and the side dominated was before now the one dominating. But with the magnitude of the still living body the loss of the lost member is diminished, and therefore also the right, and the right or indifference becomes honour and therefore equal on both sides, because the particularity of the injured party’s action is made into the indifference of the whole, into an affair of the whole. Through honour the bad conscience, the urge to self-destruction, is cancelled, for honour is the urge to dominate. And the injured party who utterly repudiates the singularity of the deed (which as this singular event is not his own) is given by honour exactly the same right as, in an isolated case of personal injury, the injured party has, because he is protecting his life. This equality of rights, in the face of which the aspect of legal right and necessary subsuming [or subjection] vanishes, is war.[30] In war the difference of the relation of subsuming has vanished, and equality is what rules. Both parties are identical; their difference is what is external and formal in the battle [i.e., they are on different sides], not what is internal, but something absolutely restless continually swaying to and fro (Mars flits from side to side), and which side will be subsumed [or conquered] is entirely doubtful and has to be decided. Either a decision is reached by the complete defeat of one party[31] — and since as a totality it is itself immortal, this means not that it is extirpated but that it is subjugated and enslaved. In this case it is a higher principle, not the trivial question of the original injury that is decisive, but the greater or lesser strength of the totality which submits in battle to that equality, and the test of it — an equality which was previously something merely ideal, and existed only in thought, while the parties lived side by side without connection. The question as to which of the totalities is truly more indifferent or stronger is submitted to the decision of battle, which may thus end with the establishment of a relationship of mastery. — Or there may be no absolute decision which would affect the entirety of the total individuals [i.e., families or clans]; on the contrary they find that they are more or less equal and, at least for the experienced moment, incapable, even in the case of an obvious superiority of one party, of carrying out to a finish the real constitution of the relationship. The abstract preponderance of one party would indeed be there, but not its reality at this moment of battle, since the force of this preponderance is necessarily devoted, not to the battle, but to other natural necessities not affecting the battle directly but the inner stability of the totality. Animus (qumoς) diminishes, because it is the feeling of the unrealised relation of the indifference of the dominating party. It reverts to the feeling of equality, since the reality of the battle contradicts this fancied superiority of animus. And so a peace is made in which — whether one side acquires the position of victor and the other that of being vanquished and surrendering some specific things or whether both give up the struggle with a sense of their complete equality — both parties put themselves into the previous position of difference from one another, difference without connection or relation, and thus with the cessation of their connection all interest ceases too. Hence the rationality of this totality is, in the antitheses, the equality of indifference, while the middle term [between the opposites] is their unity in their complete confusion and uncertainty. |
(c) これらの二つの要求の無関心さ、あるいは全体性は、特定の決定、すなわち生命と人格全体の無関心さに影響を及ぼす。そして逆転(これは曖昧に確立され、関 係が完全に明確かつ確実に一方に偏っている場合のように一方的ではない)は、同様に奴隷状態や死による人格の喪失である。否定はただ一つの特定の決定性し かありえないため、この決定性(全体性は問題外である)は全体へと強化されねばならない。しかしそれが個人的であるゆえ、それは即座に全体となる。なぜな ら特定の決定性は、全体性の無関心性である人格に属するからである。そして人格の個別性は、いったん否定されれば抽象に過ぎない。なぜなら人格においてそ れは無関心性へと完全に吸収されるからである。ここで否定は生命への侵害である。しかしこの無関心は、侵害された個別主義の抽象化を対峙させるため、後者 を通じて前者は観念的にも位置づけられ、侵害されるのは名誉である。名誉を通じて特異な細部は個人的なもの、全体となる。細部の否定に過ぎないように見え るものが、実は全体の侵害であり、こうして一人の全人格が別の全人格と戦う闘争が生じる。この戦いにおける正当性など問題外だ。戦いそのものが始まれば、 正義は双方にある。なぜなら確立されるのは危険の平等、完全なる自由の危険そのものだからだ。双方の全人格が問われているのだから。契機、すなわち無関心 の中に吸収されながら個人的なものとして位置づけられる特定の点は、まさに個人的な問題に過ぎないがゆえに、それ自体では厳密に何ものでもない。あらゆる ものが無数の方法でそのように設定されうる。何も排除できず、限界も設定できない。力、より正確には力として個別化された強さが、誰が支配するかを決め る。そしてここにおいて、現実の全個人的が主体となる以上、支配と隷属の関係が即座に介入せざるを得ない。あるいは、絶対的平等、すなわち異なるもの同士 の間にそのような関係が成立し得ないことが前提とされるならば、つまり一方が無関心で他方が異なるという関係が不可能であるならば、戦いにおいて、絶対的 差異と相互否定的関係として、無関心が維持されねばならず、争いは死によってのみ鎮められる。死においては服従が絶対的であり、まさに否定的関係の絶対性 によって、この絶対性の正反対である しかし、否定に不平等があり、戦いに一方性が存在する場合は事情が異なる。その場合、それは戦いではない。支配が純粋に一方に偏り(相互に揺れ動かな い)、中心が可能性として設定され、したがってどちらにも無差別な可能性として存在するこの不平等は、抑圧であり、それが絶対的否定へと進むとき、それは 殺害である。抑圧と殺害は、戦いと支配関係と混同してはならない。真に不正な抑圧は、あらゆる戦いを単純に無効化する形態の個人的攻撃であり傷害である。 攻撃を受けた者がその攻撃を予見し、それによって戦いを開始することは不可能だ。しかしこの不可能性自体は証明できない。イタリア人は暗殺の正当性とし て、冒涜行為に即座に宣戦布告が伴うことを理由に挙げるが、冒涜行為が存在せず、殺害が個人的動機ではなく強奪目的で行われる場合、この不可能性は実際に 存在すると見なされる。たとえ前段に侮辱行為があり、人格全体が問題となる場合でも、その侮辱は現実の全面的否定とは全く異なる。確かに名誉は傷つけられ たが、名誉は生命とは区別される。そして名誉が傷つけられた状態では理想に過ぎないため、その現実性を回復するために生命が賭けられる。名誉の理想性と現 実性を結びつけるのは、傷つけられた特定の側面を完全な現実へと引き上げることによってのみ達成される。名誉とは、いったん特定の側面が否定されたとき、 生命、すなわち特定の側面の総体もまた影響を受けねばならないという性質にある。したがって、単一の詳細の否定を本来あるべき全体へと昇華させる唯一の手 段として、その男自身の生命が問われねばならない。(余白:三段階:(a)殺害、(b)復讐、(c)決闘。中心は戦いで、揺れ動く。決闘は特定の点におけ る個人的損傷) この否定の総体は三つの形態で構想されねばならない: (aa) 粗雑な全体性、関係性と観念性を欠いた否定の絶対的無関心は、特定の決定性を人格へと転化させ、否定の現実性、すなわち単純な殺人を即座に確立する。殺人 はこの関係の認識、他者によるこの関係の認知を妨げ、危険の平等性を先行させることを阻む。さらに傷害は物質的に完全に不平等である。[29] (bb) 第二の段階は形式的無関心でなければならない。これによれば支配とその逆転は平等の法則に従って生じるが、形式としての平等、意識としての平等が個々の対 立の上に浮かんでいるだけで、対立の意識と認識ではない。したがって、危険の平等とともに平等という形式も欠如している。危険とは否定の接近に他ならない からだ。しかし否定の認識、すなわち無関心は、ここでは危険の中にあるのではなく純粋に物質的である。関係は概念の下に包含される。包含の真の逆転は、こ の平等の中にあり、復讐である。殺されたものは自ら逆転を行わねばならないが、殺されたものとしてそれは純粋に観念的なものに過ぎない。その生命、すなわ ち血の中から、復讐として立ち上がることができるのはその精神だけである。この精神は、殺害者を追跡し続け、いずれにせよ、殺害者が自らに対峙する現実を 確立し、自ら殺した男の精神のための身体を創造するまで追い詰める。その身体は、もはや殺された男の同じ外見ではなく、より普遍的なものとして現れ、精神 は運命の形で復讐を果たす。あるいは、精神に本来属する実在の生命が残されている場合、 霊魂は肉体を守り抜き、殺害は全体の一部分あるいは器官のみを破壊したに過ぎない。ゆえにこのなお生きる肉体、すなわち家族が復讐の業を引き受けるのであ る。復讐とは殺害と個々の殺人者に対する絶対的な関係であり、単に殺人者が行ったことの逆転に他ならない。彼の行いは他のいかなる方法でも置き換えられ ず、合理化されることはない。そこから抽象化できるものは何もない。なぜなら復讐は現実として確立されており、それゆえに権利を有さねばならないからだ。 すなわち理性は、創出された状況の対極が創出されることを要求する。関係の特質は残るが、その特質の中で関係は今や対極へと転化される。支配していたもの が支配される。変化するのは形態のみである。 (gg) この関係の総体が合理的であり、中項を出現させる。復讐に内在する正義の無差別性――ただし物質的・外在的なものとして――は、出現する否定の類似した意 識として個人内に侵入する。ゆえにこの出現の現実性も双方で同様である。したがって不正が蔓延しているように見える。なぜなら攻撃を加えた者、すなわち最 初の不平等で一方的な支配者(対立する支配は互いに後続するものとして現れ示されねばならない)が非難されるべきなのに、意識によって単に危険の平等状態 に陥るだけだからだ。復讐が問題となる場合、疑いなく殺害者だけが確実に支配されねばならず、復讐者はこうして力の平等から逃れ、力の優越か狡猾さ、すな わち力そのものの回避によって復讐を遂行する。しかし関係性の全体性においては事情が異なる。つまり復讐においては、復讐者が単なる他人や単独の個人では なく、加害者もまた家族の一員として抽象化されない形で直接的に単一性を排除するのだ。だが、この場合、殺人は絶対的否定ではない。精神はその身体の一員 を失ったに過ぎず、復讐もまた絶対的否定になり得ない。復讐の全体性においては、形式は絶対的意識として置かれねばならず、したがって被害者自身が、他人 ではなく復讐者とならねばならない——そしてそれは家族に他ならない。同様に加害者も単なる個人ではない。個人としてではなく、全体の一員として害をなし たのだ。復讐の全体性において、彼は抽象として位置づけられない。こうして中間項が同時に直接的に位置づけられる。すなわち否定的に、一方の優位性と無意 識を相殺し、双方に等しい危険、すなわち戦いを生む形で。外見上の完全な平等が与えられた場合、関係における差異は内面的な生活にある(ゆえに戦いは神聖 な審判となる):一方はただ自己防衛しているだけであり、他方は同時に攻撃もしている。権利は被害を受けた側にあり、あるいはこの側が無関心で支配的な側 である。これは絶対的な平等が逆転によって示されねばならないため、絶対的にそうである。支配されていた側が、今や支配する側であったのである。しかし、 なお生きる身体の大きさに比べれば、失われた肢体の損失は小さく、ゆえに権利もまた小さくなる。そして権利あるいは無関心は名誉となり、両者にとって等し くなる。なぜなら被害者の行為の特殊性は、全体の無関心、全体の事柄へと変容するからだ。名誉によって良心の呵責、自己破壊への衝動は消される。名誉とは 支配への衝動だからだ。そして行為の特異性を完全に否定する被害者(この特異的事件は彼自身のものではない)は、名誉によって、孤立した個人的傷害事件に おける被害者が持つのと全く同じ権利を与えられる。なぜなら彼は自らの生命を守っているからだ。法的権利と必然的帰属(あるいは服従)という側面が消え去 るこの権利の平等こそが、戦争である。戦争においては、従属関係の差異は消滅し、平等が支配する。双方は同一であり、その差異は戦闘において外的かつ形式 的なもの(すなわち敵味方であること)であって、内的ではない。それは絶えず揺れ動く不安定なものであり(戦神マルスは両陣営を行き来する)、どちらが従 属(あるいは征服)されるかは全く不確かであり、決着をつけねばならない。決着は一方の完全な敗北によってもたらされる[31]――全体として不死である 以上、それは根絶ではなく服従と隷属を意味する。この場合、決定的なのはより高い原理であって、最初の傷の些細な問題ではない。戦いでその平等に服従する 総体の強弱こそが試されるのだ。その平等とは、以前は単なる理想に過ぎず、思考の中にしか存在せず、両者が無関係に並存していた状態であった。どちらの全 体が真に無関心か、あるいは強いかという問題は、戦いの裁定に委ねられる。こうして支配関係が確立される形で終結することもある。あるいは、個々の集団全 体(すなわち家族や氏族)に影響を及ぼす絶対的な決着がつかない場合もある。むしろ両者は、少なくとも経験的な瞬間においては、一方が明らかに優位であっ ても、関係の本質を最後まで貫徹できないほど互角であることに気づくのだ。確かに一方の抽象的な優位性は存在するが、この戦いの瞬間においては現実のもの とはならない。なぜならその優位性の力は、戦いにではなく、戦いを直接的には影響しないが全体の内的な安定に関わる他の自然な必要性に必然的に注がれるか らである。アニムス(qumoς)は減衰する。なぜならそれは支配側の無関心という未実現の関係の感覚だからだ。戦いの現実がアニムスの幻想的な優越性に 矛盾するため、それは平等感へと回帰する。こうして成立する平和において――一方の側が勝利者の立場を獲得し他方が敗北者として特定のものを譲渡する場合 であれ、双方が完全な平等を自覚して争いを放棄する場合であれ――両者は互いに異なる以前の立場、すなわち繋がりや関係のない差異へと自らを置く。こうし て繋がりが絶たれると同時に、あらゆる関心もまた消滅するのだ。したがって、この全体性の合理性は、対立項においては無関心の平等であり、中項は両者の完 全な混同と不確実性における統一である。 |
| G.W.F. Hegel, System of Ethical Life (1802/3) | |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099