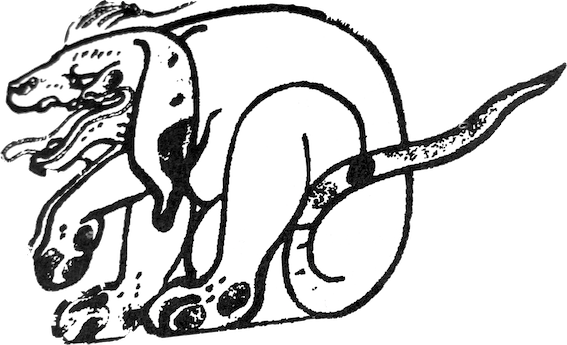
関係に基づく絶対的倫理的生活
Absolute Ethical Life
on the Basis of Relation, by G.W.F. Hegel 1802/3
☆ヘーゲルの死後出版された原稿の中で、『倫理的生活の体系』はおそらく最も謎めいたものである。死後出版物を詳細に研究したドイツの学者たちでさえ、この評価に異 論を唱える者はいないようだ。例えばヘーゲルの初期著作を最も包括的に研究したハーリングはこう述べている。「確かに、これを理解する困難さは並外れてい る」(『ヘーゲル、その意志と業績』第2巻、338頁)。このため我々は、ドイツ語でさえほとんど理解不能な内容を、明快で理解しやすい英語に完全に翻訳 することが常に可能とは限らなかった。しかしながら、この試みは価値あるものだと我々は考えた。なぜなら本論文はヘーゲルの体系的草稿の中で現存する最古 のものであり、彼の成熟した社会思想が萌芽的な形で表れているからだ。ドイツの学者たちによって長く認識されてきたその重要性は、シュロモ・アヴィネリ (『ヘーゲルの近代国家論』、ケンブリッジ、1972年)によって、今やアングロサクソン系の研究者にも明らかになったのである(翻訳者T.M. ノックスによる序文より)(→「ポータル:倫理的生活の体系」)。
☆1. 関係に基づく絶対的倫理的生活(1. Absolute Ethical Life on the Basis of Relation) by G.W.F. Hegel 1802/3
| System of Ethical Life 1. Absolute Ethical Life on the Basis of Relation Here too, as before, there must be subdivision. This absolute ethical life on the basis of relation, or natural ethical life must be so treated that (a) concept is subsumed under intuition and (b) intuition is subsumed under concept. In (a) the unity is the universal, the inner, while in (b) it enters over against the inner and is once more in a relation with the concept or with the particular.[5] In both cases ethical life is a drive [or impulse]. This means a drive which (a) is not absolutely one with the absolute unity, (b) affects the single individual, (g) is satisfied in this single individual — this singular satisfaction is itself a totality, but (d) it goes at the same time beyond the single individual, though this transcendence is here in general something negative and indeterminate. The satisfaction itself is nothing but the union of concept and intuition. Thus it is a totality, living but formal, precisely because this level, at which it is, is itself a determinate one, and thus absolute life hovers over it just as much as it remains something inner. But absolute life remains something inner because it is not the absolute concept, and so, as inner life, is not present at the same time under the form of the opposite, i.e., of the outer. And for this very reason it is not absolute intuition because it is not present to the subject in the relation as such, and so its identity likewise cannot be the absolute one. |
倫理的生活体系 1. 関係に基づく絶対的倫理的生活 ここでも、以前と同様に細分化が必要である。関係に基づくこの絶対的倫理的生活、すなわち自然的倫理的生活は、(a) 概念が直観の下に包含され、(b) 直観が概念の下に包含されるように扱われねばならない。(a) では統一性は普遍的・内面的であり、(b) では内面と対峙し、再び概念または個別性との関係に入る。[5] いずれの場合も倫理的生活は衝動である。これはすなわち、(a) 絶対的統一と絶対的に同一ではない衝動であり、(b) 単一の個人に影響を及ぼし、(c) この単一の個人において充足される——この特異的充足自体が総体であるが、(d) 同時に単一の個人を超越する衝動である。ただしこの超越はここでは概して否定的かつ不確定なものである。 この充足そのものは、概念と直観の結合に他ならない。ゆえにそれは全体性であり、生きているが形式的なものである。まさにこの充足が存在するレベル自体が 確定的なものであるがゆえに、絶対的生命は内的なものとして留まりつつ、同時にその上に浮かんでいるのである。しかし絶対的生命が内的なものとして留まる のは、それが絶対的概念ではないからであり、したがって内的な生命として、同時に反対の形態、すなわち外的な形態の下で現存しない。そしてまさにこの理由 から、それは絶対的直観ではない。なぜなら主体に対して関係そのものとして現存せず、したがってその同一性もまた絶対的な同一性ではありえないからであ る。 |
| A. First Level:[6] Feeling as Subsumption of Concept under Intuition The first level is natural ethical life as intuition[7] — the complete undifferentiatedness of ethical life, or the subsumption of concept under intuition, or nature proper. But the ethical is inherently by its own essence a resumption of difference into itself, reconstruction; identity rises out of difference and is essentially negative; its being this presupposes the existence of what it cancels. Thus this ethical nature is also an unveiling, an emergence of the universal in face of the particular, but in such a way that this emergence is itself wholly something particular — the identical, absolute quantity remains entirely hidden. This intuition, wholly immersed in the singular, is feeling, and we will call this the level of practice. The essence of this level is that feeling (not what is called “ethical feeling”) is something entirely singular and particular, but, as such, is separated, a difference not to be superseded by anything but its negation, the negation of the separation into subject and object; and this supersession is itself a perfect singularity and an identity without difference. The feeling of separation is need; feeling as separation superseded is enjoyment. The distinctive character of feeling as a level in ethical life as relation is that feeling lies in the particular and concerns the singular and that it is absolute feeling; but this feeling which proceeds to supersede the separation of subject and object must display itself as a totality and therefore be the totality of the levels of ethical life as relation. This feeling (a) subsuming the concept, and (b) subsumed under the concept is now to be considered. (a) If feeling is presented as subsuming the concept, the formal concept of feeling is presented. This is properly its concept which is adduced above, namely, that there is present (a) the supersession of what is wholly and absolutely identical and unconscious — separation, and this separation as feeling or need, (b) difference in contrast to this separation; but this difference is negative, namely, a nullification of separation — (margin: desire, ideal determination of the object); and so a nullification of the subjective and the objective and of the empirical objective intuition according to which the object of need is outside; or this nullification is effort and labour; (g) the nullification of the object, or the identity of the first two factors — conscious feeling, i.e., unity arising out of difference, i.e., enjoyment. The subsumption of feeling under the concept or, more objectively, the concept of practical feeling unfolded in all its dimensions, necessarily presents feeling (a) in its dimensions according to the nature of the form or the concept, (b) but in such a way that a whole, feeling, remains throughout, while the form is something wholly external for the feeling. |
A. 第一段階:[6] 直観における概念の包含としての感情 第一段階は直観としての自然的倫理的生活である[7]——倫理的生活の完全な未分化性、あるいは概念の直観への包含、あるいは自然そのものである。 しかし倫理的であることは、その本質によって、差異を自己の中に再び取り込むこと、再構築である。同一性は差異から生じ、本質的に否定的である。それがこ れであるということは、それが取消すものの存在を前提とする。したがってこの倫理的自然はまた、個別性に対して普遍性が現れること、顕現することでもあ る。しかしこの顕現自体が完全に個別的なものであるという形で——同一的な絶対的数量は完全に隠されたままである。この直観は、完全に特異なものの内に没 入したものであり、感情である。これを実践のレベルと呼ぼう。 この段階の本質は、感情(「倫理的感情」と呼ばれるものではない)が完全に特異的で個別的なものであるが、それゆえに分離された差異であり、主観と客観へ の分離の否定によってのみ超越される差異であることだ。そしてこの超越自体が完全な特異性であり、差異なき同一性である。 分離の感情は欲求である。分離として超越された感情は快楽である。 関係としての倫理的生活における段階としての感情の特質は、感情が個別性の中にあり、特異性を関与させ、絶対的感情であることだ。しかし主客の分離を克服するこの感情は、総体として現れねばならず、したがって関係としての倫理的生活の段階の総体でなければならない。 この感情が(a)概念を包含し、(b)概念に包含される状態を考察する。 (a) 感情が概念を包含する形で提示される場合、感情の形式的概念が提示される。これは厳密には、上述の概念、すなわち (a) 全く絶対的に同一で無意識的なもの——分離——の超越、そしてこの分離が感情または必要として存在する、 (b) この分離に対する差異が存在する。しかしこの差異は否定的であり、すなわち分離の無効化である——(境界:欲望、対象の理想的決定)。したがって、主観 的・客観的の無効化、そして必要の対象が外部にあるとする経験的客観的直観の無効化である。あるいはこの無効化は努力と労働である。 (g) 対象の無効化、あるいは最初の二要素の同一性——意識的感情、すなわち差異から生じる統一、すなわち享楽。 感情を概念の下に包含すること、あるいはより客観的に言えば、実践的感情の概念がその全次元において展開されることは、必然的に感情を(a)形式あるいは 概念の性質に応じた次元において提示する。しかし(b)その提示は、感情という全体が終始貫かれる一方で、形式が感情にとって完全に外部的なものであると いう形でなされる。 |
| (a)
Practical feeling, or enjoyment, an identity void of intuition, of
difference, and, therefore, of reason, proceeds thus to the absolute
nullification of the object. Consequently, it is a complete
indifference of the subject for ethical life, without making
conspicuous a middle term uniting the opposites in itself; so there is
no resumption of intuition into itself and there is no self-knowledge
in the subject. (aa) Need here is an absolute singleness, a feeling restricting itself to the subject and belonging entirely to nature. This is not the place for comprehending the manifold and systematic character of this feeling of need. Eating and drinking are the paradigms.[8] (bb) By this difference an inner and an outer are directly established and the outer is plainly determined (e.g., as edible or drinkable) according to the specific character of the feeling. Thereby this external thing ceases to be something universal, identical, quantitative, and becomes a single particular. The subject, despite his singularity in this feeling and in the relation posited in the separation of subject from object remains in himself undifferentiated; he is the universal, the subsuming power. The specific character which the object of enjoyment acquires at this level is entirely ideal or subjective — the object is directly its own opposite.[9] The specific character does not enter the objectivity of intuition in such a way that something might arise for the subject which he may recognise as the identity of subject and object. — Or this identity is transferred into the individual subject alone, with the result that, being determined purely ideally [or subjectively], the object is simply annihilated. (gg) This enjoyment in which the object is determined purely ideally, and entirely annihilated, is purely sensuous enjoyment; i.e., the satiation which is the restoration of the indifference and emptiness of the individual or of his bare possibility of being ethical or rational. The enjoyment is purely negative because it pertains to the individual’s absolute singularity and therefore involves the annihilation of the object and the universal. But it remains essentially practical and is distinguished from absolute self-feeling by reason of the fact that it proceeds from difference and to that extent involves a consciousness of the objectivity of the object.[10] |
(a)
実践的感情、すなわち享楽は、直観や差異、ひいては理性を欠いた同一性として、こうして対象の絶対的無効化へと進む。結果として、それは倫理的生活に対す
る主体の完全な無関心であり、対立物を自らに統合する中間項を顕著にしない。ゆえに直観の自己内への回帰はなく、主体に自己認識は存在しない。 (aa) ここで必要とされるのは絶対的な単一性、すなわち主体に限定され、完全に自然界に属する感覚である。この必要性の感覚が多様かつ体系的な性格を持つことを理解する場ではない。飲食がその典型例である。[8] (bb) この差異によって内と外が直接的に確立され、感覚の特異性に応じて外側が明瞭に規定される(例:食用の可否、飲用の可否)。それによりこの外部的なものは 普遍的・同一的・量的な存在ではなくなり、単一の個別物となる。主体は、この感覚における独自性や、主体と対象の分離によって設定される関係性にもかかわ らず、自己の中では未分化なままである。主体は普遍的存在、包含する力である。この段階で快楽の対象が獲得する特異性は完全に観念的あるいは主観的であ り、対象は直接的に自らの対立物となる。[9] この特異性は、主観が主客同一性として認識しうる何かが主観に生じるような形で、直観の客観性に入り込むことはない。あるいはこの同一性は個々の主観のみ に移され、その結果、純粋に観念的[あるいは主観的]に決定される対象は単に消滅する。 (gg) このように対象が純粋に観念的に決定され、完全に消滅する享楽は、純粋に感覚的な享楽である。すなわち、個人の無関心と空虚さ、あるいは倫理的・理性的な 存在可能性そのものの回復としての飽満である。この享楽は純粋に否定的である。なぜならそれは個人の絶対的単一性に関わるものであり、したがって対象と普 遍性の消滅を伴うからだ。しかしそれは本質的に実践的であり、差異から生じるという事実によって絶対的自己感覚と区別される。その限りにおいて、対象の客 観性に対する意識を伴うのである。[10] |
| (b)
This feeling in the form of difference or of the subsumption of
intuition under the concept must itself be likewise comprehended as a
totality: (aa) as negative practical intuition (labour), (bb)
difference (product) and possession, (gg) tool.[11] (aa) (margin: This is intuition subsumed under the concept; labour is itself the subsuming of the object; the subject is indifference, the subsumer; where the subject is the subsumer, the concept is dominant.) Practical feeling subsumed under the concept displays the dispersed moments of the totality as realities. These moments are: (a) The nullification of the object or of the intuition, but, qua moment, in such a way that this annihilation is replaced by another intuition or object; or pure identity, the activity of nullifying, is fixed; in this activity there is abstraction from enjoyment, i.e., it is not achieved, for here every abstraction is a reality, something that is. The object is not nullified as object altogether but rather in such a way that another object is put in its place,[12] for in this nullification, qua abstraction, there is no object or there is no enjoyment. But this nullification is labour whereby the object determined by desire is superseded in so far as it is real on its own account, an object not determined by desire, and determination by desire qua intuition is posited objectively. In labour the difference between desire and enjoyment is posited; the enjoyment is obstructed and deferred; it becomes ideal or a relation, and on this relation, as a result of labour, there is posited as now immediately emerging (i)[13] the bearing of the subject on the object, or the ideal determining of the object by desire: this is taking possession of the object; (ii) next, the real annihilation of the object’s form, for objectivity or difference remains — the activity of labour itself; (iii) finally, the possession of the product, or the possibility of annihilating the product as something explicitly real, through a connection of the first kind [i.e., consumption in eating] with respect to its matter, as well as through this second one [i.e., working on it], which consists in annihilating its form and in its being given a new form by the subject — i.e., the possibility of a transition to enjoyment which, however, remains wholly ideal [or purely subjective]. Possession is not present at all at the first stage of practical feeling, and likewise taking possession is there purely as a moment; or rather neither of them is a real moment; they are not fixed or kept distinct from one another. (There can be no question at all here of the legal basis or aspect of possession.) Taking possession is the ideal moment in this subsumption of the product under the subject, or the moment of rest; labour [the second moment] is the reality or movement, the entry of the subsuming subject into the reality of the object; the third moment, the synthesis, is the possession, preservation, and saving of the object. In this third moment there is present that ideal character according to the first moment, but it is present in the object as real according to the second moment. |
(b) この差異の形態、あるいは直観が概念の下に包含される形態としての感覚は、それ自体もまた総体として把握されねばならない:(aa) 否定的実践的直観(労働)として、(bb) 差異(生産物)と所有として、(gg) 道具として。[11] (aa) (境界:これは概念の下に帰属された直観である。労働はそれ自体、対象の帰属である。主体は無関心であり、帰属者である。主体が帰属者である場合、概念が 支配的である。)概念の下に帰属された実践的感情は、総体の分散した瞬間を現実として示す。これらの瞬間は次の通りである: (a) 対象または直観の無効化。ただし瞬間として、この消滅が別の直観または対象によって置き換えられる形で。あるいは純粋同一性、すなわち無効化する活動が固 定される。この活動には享楽からの抽象化、すなわち達成されない享楽が含まれる。なぜならここではあらゆる抽象化が現実、あるものだからだ。対象は対象と して完全に無効化されるのではなく、別の対象がその場所に置かれる形で無効化される[12]。なぜならこの無効化は、抽象化として、対象が存在しない、あ るいは享楽が存在しない状態だからだ。しかしこの無効化は労働であり、欲望によって決定された対象が、それ自体として現実的な限りにおいて、欲望によって 決定されない対象として超越され、欲望による決定が直観として客観的に設定される。労働において、欲望と享楽の差異が位置づけられる。享楽は妨げられ、延 期される。それは理想的関係となる。そしてこの関係の上に、労働の結果として、今や直ちに現出するものとして位置づけられるのは (i)[13] 主体が対象に対して持つ関係、すなわち欲望による対象の理想的決定である。これは対象の占有である。 (ii) 次に、対象の形態の現実的消滅。なぜなら客観性あるいは差異は残存するからである——労働活動そのものの営み。 (iii) 最後に、産物の所有、あるいは産物を明示的に現実的なものとして消滅させる可能性が、第一の種類の接続[すなわち、物質に対する飲食による消費]を通じ て、また第二の接続[すなわち、それに働きかけること]を通じて生じる。後者は、その形態を消滅させ、主体によって新たな形態を与えられることに存する ——すなわち、 しかし完全に観念的(あるいは純粋に主観的)なままの享楽への移行の可能性である。 所有は実践的感覚の第一段階では全く存在せず、同様に占有もそこでは純粋に一瞬間として存在する。むしろ、どちらも現実的な瞬間ではない。それらは固定されておらず、互いに区別されてもいない。(所有の法的根拠や側面については、ここでは全く問題にならない。) 占有は、この生産物を主体に帰属させる過程における理想的瞬間、すなわち静止の瞬間である。労働[第二の瞬間]は現実性あるいは運動であり、帰属させる主 体が対象の現実性へ介入する瞬間である。第三の瞬間、すなわち総合は、対象の占有・保存・蓄積である。この第三の瞬間には、第一の瞬間に基づく理想的性格 が存在するが、それは第二の瞬間に基づく現実性として対象の中に現れている。 |
| (b)
The product has already been defined formally in (a) as the identity of
the ideal character, but of it as objectively real and separate; but
the essential thing was the identity, activity as such, and so as
something inner and so as not emerging; it must emerge on the object,
and this second stage bb considers the relation of the inhibited
feeling to the object inhibited by its nullification [i.e., by the
labour expended to change it], or the difference present even in
labour, namely, the difference between the reality and proper nature of
the object and the way it is to be, and is, ideally determined by
labour. In (aa) it was the object that was subsumed, here it is the
subject. Or, in (aa), the ideal relation in labour was considered, here
the real one. Here labour is properly subsumed under intuition, for the
object is in itself the universal, so, where the object is subsuming,
the singularity of the subject has its proper rational place; the
subject is concept in itself, difference, and it subsumes [or is
dominant]. In (aa) labour is wholly mechanical, since individuality, abstraction, pure causality is present in the form of indifference; it is dominant and is therefore something external to the object. For therewith causality is posited in truth, since this subject is something single, absolutely existing on its own account, and therefore absolute separation and difference. Whereas, when the object and the universal are subsuming, causality is absent, since the object in itself is the indifference of the particular and one with the particular for which, it follows, particularity is a purely external form, not the inner essence, not subjective being. Because the object is subsuming labour under itself, it is in the relation as real (as previously it was nullified, posited as the pure abstraction of an object), for, as subsuming, it is an identity of universal and particular, of the latter in abstraction against the subject. In this way labour too is real and living, and its vitality is to be known as a totality, but each moment of the totality is to be known as itself a living individual labour, as a particular object. For the subsuming [or dominating] living object and living labour there is (a) intuition subsumed under the concept, then (b) the concept under intuition, and (c) the identity of the two. (aaa) The living object [the individual] subsumed under the concept [the universal] is the plant bound up with the element or the pure quantity of the earth and producing itself towards the element of air in the production, infinitely varied (by the concept), of its own entire individuality and totality. Every part of the plant is itself an individual, a complete plant; it maintains itself against its inorganic nature only because it produces itself wholly at every point of contact, or, withering on the stem, is devoted to producing (to the absolute concept, to being the opposite of itself). Because in this way the plant is in the power of the element [the earth], the labour [of horticulture] too is principally directed against the element and is mechanical, but it is left to the element to compel the plant to produce. Labour can have little or nothing of the specific life of the plant and is therefore alive in the sense that it alters just the external form of the element alone and does not destroy it chemically; and this form is an inorganic nature which itself is only related to something living and lets it alone. (bbb) The concept of the living thing subsumed under intuition is the animal. For since this subsumption itself is one-sided, not intuition subsumed under the concept in the like way over again, life here is an empirically real, infinitely dispersed life, displaying itself in the most manifold forms. For the form or the absolute concept is not itself unity or universality again. Thus here there is an individuality without intelligence, not, as in the case of the plant, where each unit of the individual is itself a mass of such units; on the contrary, here there is indifference in more extended difference and distinction. Labour on the animal is thus less directed to its inorganic nature than to its organic nature itself, because the object is not an external element but the indifference of individuality itself. The subsumption is determined as a taming of the animal’s particular character for the sort of use appropriate to its nature — now more negatively, as compulsion, now more positively as trust on the part of the animal; and now too, just as plants are determined by the elements, so the animals which are destined to be annihilated in being eaten, simply have their natural breeding [and rearing] determined. If the use of plants is very simple and if labour for them is to be exhibited as a need of the subject, or as how this labour is present in a subjective form, then the need they supply is that of nourishment, is non-organic, or only slightly organic and individualised, and so not a nourishment of a higher difference of the individual, whether human or animal — a weak irritability, impotent outgoing, a nullification which is itself a weak one owing to the weak individuality of the plant — and for our delight they provide sensuous enjoyments (smelling and seeing) which are finer than those of nullification, since the plant is not nullified. Or this is the level of the enjoyment of plants just as the level for animals is their domestication. The enjoyment involved is sensuous because the senses are the animal level in man, an individuality of feeling which as sense is an individual, not a member like an arm, etc., but a complete organism. As enjoyment, the eating of plants is the subsumption of the concept under intuition as feeling; whereas labour for plants is the subsumption of intuition under the concept. Thus, from the point of view of labour, the cultivation of plants, taming them, is the subsumption of concept under intuition; the converse is the case from the point of view of enjoyment, for the enjoyment of the single sense is the dispersal of enjoyment. (margin: N.B., as regards subsumption, enjoyment and labour are converse). Subjectively regarded, the domestication of animals is a more many-sided need, but in so far as they are means to enjoyment, they cannot be considered here yet, for this would not be a subsumption of the concept under intuition, not the aspect of living labour. This labour is an association of animals for movement and strength, and the delight of this propagation is above all the aspect that is relevant here. (ggg) The absolute identity of these two levels is that the concept of the first is one with the identity of the second or is the absolute concept, intelligence. Labour, subsumed under this intuition, is a one-sided subsumption, since in this very process the subsumption itself is superseded. The labour which produces intelligence is a totality, and with this totality, the separate subsumptions of the first and second levels are now posited together. Man is a power-level, universality, for his other, but so is his other for him; and so he makes his reality, his own peculiar being, his effectiveness in reality into an adoption into indifference, and he is now the universal in contrast to the first level. And formative education (Bildung) is this absolute exchanging in the absolute concept wherein every subject, and universal too, makes its particularity immediately into universality, and in the see-saw posits itself as universal at the very moment when it posits itself as one level and is thus confronted by its “being a level,” and by the unmediated universality in that being, so that it itself becomes a particular. The ideal determination of the other is objective, but in such a way that this objectivity is immediately posited as subjective and becomes a cause; for if something is to be a power [or level] for another, it must not be pure universality and indifference in a relation to it; it must be posited for itself [as what the other is to become] or a universal truly and absolutely — and the intelligence is this in the highest degree. In precisely one and the same respect it is a universal and a particular, both of these absolutely at once and without any mediation, whereas the plant and the animal are universal in ways distinct from their particularity. |
(b)
製品はすでに(a)において、理想的性格の同一性として形式的に定義されている。ただしそれは客観的に実在し分離されたものとしての同一性である。しかし
本質的なものは同一性、活動そのもの、すなわち内的なものとして、また現出しないものとしての活動であった。それは対象上に現出せねばならず、この第二段
階bbは、抑制された感情と、その無効化(すなわち、それを変えるために費やされた労働)によって抑制された対象との関係、あるいは労働の中にさえ存在す
る差異、すなわち対象の現実性と本質と、労働によって理想的に決定されるべき姿、そして実際に決定される姿との差異を考察する。(aa)では対象が包含さ
れていたが、ここでは主体が包含される。あるいは(aa)では労働における理想的関係が考察されたが、ここでは現実的関係が考察される。ここでは労働が直
観の下に適切に包含される。なぜなら対象はそれ自体普遍的であり、対象が包含する場において、主体の特異性はその正当な理性的位置を占めるからである。主
体はそれ自体概念であり差異であり、主体が包含する(あるいは支配的である)。 (aa)では労働は完全に機械的である。なぜなら個別性、抽象性、純粋な因果性が無差別性の形で現れているからだ。それは支配的であり、したがって対象の 外的なものである。なぜなら、この主体は単独のものであり、それ自体として絶対的に存在するため、絶対的な分離と差異であり、それによって因果性が真に置 かれるからである。一方、対象と普遍が包含する場合には、対象そのものが個別性の無関心であり、個別性と同質であるため、因果性は欠如する。したがって、 個別性は純粋に外的な形式であり、内的な本質でも主観的存在でもない。 対象が労働を自己の下に包含するとき、それは関係において実在的である(以前には無効化され、対象の純粋な抽象として設定されていたが)。なぜなら包含す る主体として、それは普遍と個別、すなわち主体に対する抽象化された後者の同一性だからだ。このように労働もまた実在的で生きたものであり、その生命力は 総体として認識されるべきだが、総体の各瞬間はそれ自体が生きている個別労働、すなわち個別対象として認識されねばならない。 包含する[あるいは支配する]生きた対象と生きた労働においては、(a)概念に包含される直観、(b)直観に包含される概念、(c)両者の同一性が存在する。 (aaa) 概念(普遍)に包含される生きた対象(個体)とは、大地の要素あるいは純粋な量と結びつき、自らの全個体性と全体性を(概念によって)無限に多様化させな がら、空気の要素へ向けて自らを生産する植物である。植物の各部分はそれ自体が個体であり、完全な植物である。無機的な性質に対して自己を維持するのは、 接触するあらゆる点で自己を完全に生産するからであり、あるいは茎上で枯れゆくことで(絶対的概念へ、自己の対極となる存在へと)生産に捧げられるからで ある。このように植物は元素[土]の支配下にあるため、[園芸の]労働も主に元素に対して向けられ機械的であるが、植物に生産を強いるのは元素に委ねられ ている。労働は植物の特異的な生命をほとんど、あるいは全く持たない。ゆえにそれは、元素の外部形態のみを変え、化学的に破壊しないという意味で生きてい る。そしてこの形態は無機的な性質であり、それ自体が生きているものとの関係性のみを持ち、それをそのままにしておく。 (bbb) 直観の下に包含される生命の概念は動物である。なぜならこの包含自体が一方的であり、直観が概念の下に再び同様に包含されるわけではないから、ここでの生 命は経験的に実在する、無限に分散した生命であり、最も多様な形態で現れる。形態あるいは絶対的概念自体が再び統一性や普遍性ではないからだ。したがって ここでは知性を持たない個別性が存在する。植物の場合のように、個体の各単位がそれ自体そのような単位の集合体であるのとは異なり、むしろここではより広 範な差異と区別における無差別性が存在する。 したがって動物に対する労働は、その無機的な性質よりもむしろ有機的な性質そのものに向けられる。なぜなら対象は外部の要素ではなく、個別性そのものの無 差別性だからである。この帰属は、動物の個性をその本性に適した利用形態へと馴致するものとして規定される。それは時に否定的には強制として、時に肯定的 には動物側の信頼として現れる。また植物が自然要素によって規定されるのと同様に、食されることで消滅する運命にある動物たちは、単にその自然繁殖が規定 されるに過ぎない。 植物の利用が極めて単純であり、それに対する労働が主体の必要性として、あるいはこの労働が主観的形式で如何に現れるかとして示されるならば、彼らが供給 する必要性は栄養であり、非有機的、あるいは僅かに有機的で個別化されたものであり、故に人間であれ動物であれ、個体のより高い差異の栄養ではない——弱 い刺激性、 無力な発散、植物の弱い個体性ゆえにそれ自体も弱い無効化である。そして我々の歓びのために、それらは無効化よりも洗練された感覚的愉悦(嗅覚と視覚)を 提供する。なぜなら植物は無効化されないからだ。あるいはこれは植物の愉悦の水準であり、動物の水準が家畜化であるのと同様である。この享受が感覚的であ るのは、感覚が人間における動物的レベルだからだ。感覚としての個体性——それは腕などの器官ではなく、完全な有機体である。享受として、植物を食べるこ とは感覚としての直観への概念の帰属である。一方、植物のための労働は直観の概念への帰属である。したがって労働の観点から、植物の栽培や飼いならしは概 念を直観に帰属させる行為である。享受の観点では逆の現象が起こる。単一の感覚による享受は享受の分散だからだ。(注:帰属に関して、享受と労働は逆の関 係にある) 主体的に見れば、動物の家畜化はより多面的な必要性である。しかし、それらが快楽の手段である限り、ここではまだ考慮できない。なぜなら、それは概念を直 観の下に包含するものではなく、生きた労働の側面ではないからである。この労働は、運動と力のための動物の結合であり、この繁殖の喜びが、とりわけここで 関連する側面である。 (ggg) この二つのレベルの絶対的同一性は、第一の概念が第二の同一性そのものと一致する、あるいは絶対的概念、すなわち知性である点にある。この直観の下に包含 される労働は片面的な包含である。なぜならこの過程において包含そのものが超越されるからだ。知性を生み出す労働は総体であり、この総体によって第一・第 二レベルの個別の包含が今や共に置かれる。人間は他者にとって力の水準、普遍性である。しかし他者もまた人間にとって同様である。こうして人間は自らの現 実性、固有の存在、現実における実効性を無差別性への帰属へと変容させ、第一の水準とは対照的に今や普遍者となる。そして形成的教育(ビルドゥング)と は、絶対的概念におけるこの絶対的交換である。そこではあらゆる主体、そして普遍性さえも、その特殊性を即座に普遍性へと変え、シーソーのように揺れ動く 中で、自らを一つのレベルとして位置づけるまさにその瞬間に、普遍性として自らを位置づける。こうして「レベルであること」と、その存在における媒介され ない普遍性に直面し、それ自体が一つの特殊性となるのである。他者に対する理想的決定は客観的であるが、この客観性が即座に主体性として位置づけられ原因 となる。なぜなら、何かが他者にとって力[あるいはレベル]となるためには、それに対する関係において純粋な普遍性や無関心であってはならず、自ら[他者 がなるべきものとして]位置づけられるか、あるいは真に絶対的な普遍でなければならない。そして知性はこの点を最高度に体現する。まさに同一の観点におい て、それは普遍であり個別でもある。両者は同時に絶対的に、いかなる媒介もなく共存する。一方、植物や動物は、その個別性とは異なる形で普遍性を有する。 |
| The
concept of this relation is the identity of both the two first levels,
but as a totality it falls itself under the form of the three levels. (i) As feeling or as pure identity: for feeling, the object is characterised as something desired. But here the living thing is not to be determined by being worked upon: it should be an absolutely living thing, and its reality, its explicit being-for-self, is simply so determined as what is desired, i.e., this relation of desire is by nature made perfectly objective, one side of it in the form of indifference, the other in that of particularity. This supreme organic polarity in the most complete individuality of each pole is the supreme unity which nature can produce. For it cannot get past this point: that difference is not real but absolutely ideal. The sexes are plainly in a relation to one another, one the universal, the other the particular; they are not absolutely equal. Thus their union is not that of the absolute concept but, because it is perfect, that of undifferentiated feeling. The nullification of their own form is mutual but not absolutely alike; each intuits him/ herself in the other, though as a stranger, and this is love. The inconceivability of this being of oneself in another belongs therefore to nature, and not to ethical life, for the latter, with respect to the different poles, is the absolute equality of both — and, with respect to their union, it is absolute union on the strength of its ideality. But the ideality of nature remains in inequality and therefore in desire in which one side is determined as something subjective and the other as something objective. (ii) Precisely this living relation, in which intuition is subsumed under the concept, is ideal as a determinacy of the opposites, but in such away that, owing to the dominance of the concept, difference remains, though without desire. Or the determinacy of the opposites is a superficial one, not natural or real, and practice does proceed to the supersession of this opposite determinacy, yet not in feeling but in such a way that it becomes intuition of itself in a stranger, and thus ends with a perfect opposing individuality, whereby the union of nature is rather superseded. This is the relation of parents and children: the absolute union of both is directly sundered into a relation. The child is man subjective but in such a way that this particular is ideal, and the form of humanity is only an outward appearance. The parents are the universal, and the work of nature proceeds to the cancelling of this relation, just as the work of the parents does, for they continually cancel the external negativity of the child and, just by so doing, establish a greater inner negativity and therefore a higher individuality. (iii) But the totality of labour is perfect individuality and therefore equality of the opposites, wherein relation is posited and superseded; appearing in time it enters every instant and turns over into the opposite moment, according to what has been said above; this is the universal reciprocal action and formative education of mankind. Here too the absolute equality of this, reciprocity exists in the inner life and, throughout the level we are at, the relation persists solely in the single individual — a recognition which is mutual or supreme individuality and external difference. In these levels there is a process from the first to the third separately, or [i] the unification of feeling is superseded, but for this very reason [ii] the same is true of desire and its corresponding need, and [iii] at the third level each is an essential being, alike and independent. The fact that the relation of these beings is one of love and feeling too is an external form, not affecting the essence of the relation which is the universality in which they stand. (c) The first two levels are relative identities. Absolute identity is something subjective, outside them. But since this level is itself a totality, rationality must enter as such and be real; it lies concealed in the idea of the formal levels. This rational element is what enters as mediator; it shares the nature of both subject and object or is the reconciliation of the two. |
この関係の概念は、最初の二つのレベルが同一であることにある。しかし全体として見れば、それは三つのレベルの形態に帰着する。 (i) 感情として、あるいは純粋な同一性として:感情においては、対象は望まれるものとして特徴づけられる。しかしここで生き物は、作用を受けることによって決 定されるものではない。それは絶対的に生きているものでなければならず、その現実性、明示的な自己のための存在は、単に欲されるものとして決定される。す なわち、この欲望の関係は本質的に完全に客観化され、一方の側面は無関心という形で、他方の側面は個別主義という形で現れる。この至高の有機的二極性は、 各極の最も完全な個別性において、自然が生み得る至高の統一である。なぜなら自然はこの点を超えることはできないからだ:すなわち差異は現実的ではなく、 完全に観念的なものである。両性は明らかに互いに関係にあり、一方は普遍的、他方は個別的であり、絶対的に平等ではない。したがって両者の結合は絶対的概 念の結合ではなく、完璧であるゆえに、未分化な感情の結合なのである。自らの形態の無効化は相互的だが、絶対的に同一ではない。各々が他者の中に自己を直 観する――たとえ他者としてであっても――これが愛である。この「他者における自己の存在」の不可解性は、したがって倫理的生活ではなく自然の本質に属す る。後者は異なる両極に対して絶対的平等を、そしてその結合に対しては、その観念性ゆえの絶対的結合を要求するからだ。しかし自然の観念性は不平等の中に 残り、したがって欲望の中に残る。そこでは一方の側面が主観的なものとして、他方が客観的なものとして決定される。 (ii) まさにこの生きた関係、すなわち直観が概念の下に包含される関係こそが、対立項の決定性として観念的である。しかし概念の優位性ゆえに差異は残り、欲望は 消える。あるいは対立物の決定性は表層的なものであり、自然的でも現実的でもない。実践は確かにこの対立的決定性を超越する方向へ進むが、それは感情にお いてではなく、他者における自己の直観として成立し、こうして完全に対立する個別性をもって終結する。それゆえ自然の結合はむしろ超越される。これが親子 関係である:両者の絶対的結合は直接的に関係へと分裂する。子は主観的人間であるが、この個別主義は理想的なものであり、人間性の形式は単なる外見に過ぎ ない。親は普遍的存在であり、自然の営みは親の営みと同様にこの関係を解消する。親は絶えず子の外的な否定性を解消し、それによってより大きな内的な否定 性、すなわちより高い個別性を確立するのだ。 (iii) しかし労働の総体は完全な個別性であり、したがって対立物の平等である。そこでは関係が設定されつつ超越される。時間内に現れるそれは、上述の通りあらゆ る瞬間に介入し、反対の瞬間へと転化する。これが人類の普遍的相互作用と形成的教育である。ここでもまた、この絶対的平等、相互性が内的な生活の中に存在 し、我々が現在いるレベル全体を通じて、関係は単一の個人の中にのみ存続する。これは相互的認識、あるいは至高の個性と外的な差異である。これらの段階に おいては、第一から第三へ個別に進行する過程がある。すなわち[i]感情の統一は超越されるが、このゆえに[ii]欲望とその対応する必要性も同様に超越 され、[iii]第三段階では各々が本質的存在として、同質かつ独立する。これらの存在の関係が愛と感情のものであるという事実もまた、外的な形態に過ぎ ず、関係の本質に影響を与えない。その本質とは、彼らが立つ普遍性である。 (c) 最初の二段階は相対的同一性である。絶対的同一性は主観的なものであり、それらを超越している。しかしこの段階自体が全体性を成す以上、合理性はそれ自体 として介入し現実的でなければならない。それは形式的段階の理念の中に隠されている。この合理的要素こそが媒介者として介入するものであり、主観と客観の 双方の性質を共有するか、あるいは両者の和解である。 |
| This mediating term consequently exists under the form of the three levels. (aa) Concept subsumed under intuition. This therefore belongs entirely to nature, because the difference involved in intelligent being is not present in the intelligent being as the subsumption of intuition under the concept. It is absolute indifference, not like the indifference of nature which occurs in the formal levels and cannot liberate itself from difference. At the same time this middle term is not the formal identity which came before us hitherto as feeling, but a real absolute identity, a real absolute feeling, the absolute middle term, explicit in this entire aspect of reality, existing as an individual. Such a middle term is the child, the highest individual natural feeling, a feeling of a totality of the living sexes such that they are entirely in the child, so that he is absolutely real and is individual and real in his own eyes. The feeling is made real so that it is the absolute identity of the natural beings, so that in this identity there is no one-sidedness, and no circumstance is missing. Their unity is therefore real immediately, and because they [the parents] are real and separate within the context of nature itself and cannot supersede their individuality, the reality of their unity is thus an essential being and an individual with a reality of its own. In this perfectly individualised and realised feeling, the parents contemplate their unity as a reality; they are this feeling itself and it is their visible identity and mediation, born from themselves. — This is the real rationality of nature wherein the difference of the sexes is completely extinguished, and both are absolutely one — a living substance. (bb) Intuition subsumed under the concept is the mediating term in difference or this is alone the form in which the real mediating term is, while the substance is dead matter; the mediating term as such is wholly external, according to the difference of the concept, while the inner is pure and empty quantity. This middle term is the tool. Because in the tool the form or the concept is dominant, it is torn away from the nature to which the middle term of sexual love belongs, and lies in the ideality, as belonging to the concept, or is the absolute reality present in accordance with the essence of the concept. In the concept, identity is unfilled and empty; annihilating itself, it exhibits only the extremes. Here annihilation is obstructed; emptiness is real and, moreover, the extremes are fixed. In one aspect the tool is subjective, in the power of the subject who is working; by him it is entirely determined, manufactured, and fashioned; from the other point of view it is objectively directed on the object worked. By means of this middle term [between subject and object] the subject cancels the immediacy of annihilation; for labour, as annihilation of intuition the particular object, is at the same time annihilation of the subject, positing in him a negation of the merely quantitative; hand and spirit are blunted by it, i.e., they themselves assume the nature of negativity and formlessness, just as, on the other side (since the negative, difference, is double), labour is something downright single and subjective. In the tool the subject makes a middle term between himself and the object, and this middle term is the real rationality of labour; for the fact that work as such, and the object worked upon, are themselves means, is only a formal mediation, since that for which they exist is outside them, and so the bearing of the subject on the object is a complete separation, remaining entirely in the subject within the thinking of intelligence. In the tool the subject severs objectivity and its own blunting from itself, it sacrifices an other to annihilation and casts the subjective side of that on to the other. At the same time its labour ceases to be directed on something singular. In the tool the subjectivity of labour is raised to something universal. Anyone can make a similar tool and work with it. To this extent the tool is the persistent norm of labour. On account of this rationality of the tool it stands as the middle term, higher than labour, higher than the object (fashioned for enjoyment, which is what is in question here), and higher than enjoyment or the end aimed at. This is why all peoples living on the natural level have honoured the tool, and we find respect for the tool, and consciousness of this, expressed in the finest way by Homer. |
この媒介項は結果として三つのレベルという形で存在する。 (aa) 直観の下に包含される概念。これはしたがって完全に自然界に属する。なぜなら知的な存在に内在する差異は、直観が概念の下に包含されるという形で知的な存 在の中に現れないからである。これは絶対的な無差別であり、形式的レベルで生じる自然界の無差別とは異なり、差異から自らを解放することはできない。同時 にこの中間項は、これまで我々の前に感情として現れた形式的同一性ではなく、実在的絶対的同一性、実在的絶対的感情、絶対的中間項であり、現実のこの全側 面において明示され、個体として存在する。このような中間項は子どもであり、最高の個別的自然感情である。生きている両性の総体としての感情であり、それ らが完全に子どもの中に存在するため、子どもは絶対的に実在し、自己の目に個別的かつ実在として映る。この感情は実在化され、自然的存在の絶対的同一性と なる。この同一性には偏りがなく、いかなる状況も欠落していない。ゆえに彼らの統一は即座に現実的である。そして彼ら[両親]が自然そのものの文脈におい て現実的かつ分離した存在であり、その個性を超越できないゆえに、彼らの統一の現実性は本質的存在であり、独自の現実性を持つ個体となる。この完全に個別 化され実現された感情において、両親は自らの統一を現実として観照する。彼らはこの感情そのものであり、それは彼ら自身から生まれた可視的な同一性と媒介 である。— これが自然の真の合理性であり、性差は完全に消滅し、両者は絶対的に一つとなる——生ける実体である。 (bb) 概念の下に包含される直観は差異における媒介項であり、あるいはこれこそが真の媒介項が存在する形態である。実体は死んだ物質である。媒介項そのものは概 念の差異に従って完全に外部に存在する。内面は純粋で空虚な量である。この中間項は道具である。道具においては形式、すなわち概念が支配的であるため、そ れは性的愛の中間項が属する自然から引き裂かれ、概念に属するものとして観念性に位置するか、あるいは概念の本質に従って現れる絶対的現実である。概念に おいては同一性は満たされず空虚であり、自らを消滅させ、両極端のみを示す。ここでは消滅が阻害される。虚無は現実的であり、さらに両極は固定される。道 具は一つの側面では主観的である。働く主体によって完全に決定され、製造され、形成される。他方の観点では、それは客観的に加工対象に向けられる。この中 間項によって主体は消滅の即時性を打ち消す。労働は、直観としての個別対象の消滅であると同時に、主体自身の消滅であり、彼の中に単なる量的要素の否定を 位置づける。手と精神はそれによって鈍化される、すなわちそれ自体が否定性と無形の性質を帯びる。一方で(否定性、差異は二重であるゆえ)、労働はまった く単一で主観的なものとなる。道具において主体は、自身と対象との間に中間項を置く。この中間項こそが労働の真の合理性である。なぜなら、労働そのものと 加工される対象が手段であるという事実は、形式的な媒介に過ぎないからだ。それらが存在する目的はそれらの外にあるため、主体が対象に向ける関係は完全な 分離であり、知性の思考の中に主体内に完全に留まる。道具において主体は、客観性と自らの鈍化を自らから切り離す。主体は他者を消滅に捧げ、その主観的側 面を他者に転嫁する。同時にその労働は、単一のものに向けられることをやめる。道具において労働の主体性は普遍的なものへと高められる。誰でも同様の道具 を作り、それを使って働ける。この意味で道具は労働の永続的な規範である。 道具のこの合理性ゆえに、それは労働よりも高く、対象(ここでは享楽のために造られたもの)よりも高く、享楽や目的される終点よりも高い中間項として立 つ。これが自然のレベルで生きるあらゆる民族が道具を尊んだ理由であり、道具への敬意とこの自覚がホメロスによって最も優れた形で表現されている。 |
| (gg)
The tool is under the domination of the concept and therefore belongs
to differentiated or mechanical labour; the child is the middle term as
absolutely pure and simple intuition. But the totality of both
[intuition and concept] must possess just this intuitive simplicity,
yet also the ideality of the concept; or in the child the ideality of
the extremes of the tool must enter its substantial essence, while for
this very reason in the tool an ideality must enter into its dead inner
being, and the reality of the extremes must vanish; there must be a
middle term which is perfectly ideal. The absolute concept, or
intelligence, is alone absolute ideality; the middle term must be
intelligent, but not individual or subjective; only an infinitely
vanishing and self-manifesting appearance of that; a light and ethereal
body which passes away as it is formed; not a subjective intelligence
or an accident of it, but rationality itself, real but in such a way
that this reality is itself ideal and infinite, in its existence
immediately its own opposite, i.e., non-existence; and so an ethereal
body which displays the extremes and therefore, while real according to
the concept, also has its ideality, since the essence of this body is
immediately to pass away, and its appearance is this immediate
conjunction of appearance and passing-away. Thus such a middle term is
intelligent; it is subjective or in intelligent individuals, but
objectively universal in its corporeality, and because of the immediacy
of the nature of this being, its subjectivity is immediately
objectivity. This ideal and rational middle term is speech, the tool of
reason, the child of intelligent beings. The substance of speech is
like the child — i.e., what is most indeterminate purest, most
negative, most sexless, and, on account of its absolute malleability
and transparency, capable of assuming every form. Its reality is
completely absorbed into its ideality, and it is also individual; it
has form or a reality; it is a subject aware of itself; it must
therefore be distinguished from the formal concept of speech, for which
[i.e., speech] objectivity itself is a form of speech; but this
objectivity is only an abstraction, since the reality of the object is
subjective in a way different from the way the subject is subjective.
Objectivity is not itself absolute subjectivity. The totality of speech in the form of the levels: (i) of nature, or inner identity. This is the unconscious attitude of a body which passes away as quickly as it comes, but which is something single, having only the form of objectivity, not bearing itself in or on itself, but appearing in a reality and substance foreign to itself. Gesture, mien, and their totality in the glance of the eye — this is not fixed objectivity or objective in the abstract; but it is fleeting, an accident, a shifting ideal play. But this ideality is only a play in another who is its subject and substance. The play expresses itself as feeling and pertains to feeling, or it exists in the form of pure identity, of a feeling, articulated indeed, but changing, yet the play is entire in every moment, without the ideality of its objective character or its own corporeality to which nature cannot attain. (ii) When the intuition of speech is subsumed under the concept, it has a body of its own, for its ideal nature is posited in the concept, and the body is the bearer, or what is fixed. This body is an external material thing, but one which as such is completely nullified in its substantial inwardness and self-awareness; it is ideal and without meaning. But because the concept is dominant, this body is something dead, not something that endlessly annihilates itself inwardly, but something which, being here at the stage of difference, is annihilated only externally for the dominant concept. Thus its doubled being is likewise an externality; it expresses nothing but the reference to the subject and the object, between which it is the ideal middle term; but this linkage is made clear by a subjective thinking outside the object. On its own account it expresses this linkage negatively, by its being annihilated as subject, or, having an explicit meaning of its own, it expresses the linkage by its inner meaninglessness, so that it is a middle term, in so far as it is a thing, something explicitly determinate, and yet not explicit to itself, not a thing, but immediately the opposite of itself — self-aware but flatly not self-aware, but being for another; and so the absolute concept is here really objective. A corporeal sign: this is the ideality of the tool, just as demeanour is the ideality of the child; and just as to make a tool is more rational than to make a child, so a corporeal sign is more rational than a gesture. Since the sign corresponds to the absolute concept, it does not express any shape adopted by the absolute concept that has been assumed into indifference. But because it expresses only the concept, it is bound up with what is formal and universal. Just as mien and gesture are a subjective language, so the corporeal sign is an objective one. Just as subjective speech is not torn loose from the subject and is not free, so this objective speech remains something objective and does not carry knowledge — its subjective element — in itself directly. Hence knowledge is also tacked on to the object; it is not a determinate character of the object but is only accosted by it and remains accidental to it. Precisely because the linkage is accidental, knowledge expresses in the object, but free from it, a reference to something subjective which, however, is set forth in a quite indefinite way and must first have thought added to it. Knowledge therefore expresses also the connection between the possession of an object and a subject who possesses it. (iii) The spoken word unites the objectivity of the corporeal sign with the subjectivity of gesture, the articulation of the latter with the self-awareness of the former. It is the middle term of intelligences; it is logos, their rational bond. Abstract objectivity, which is a dumb recognition, gains in it an independent body of its own, which exists for itself but according to the mode of the concept, and which, namely, immediately destroys itself. With the spoken word the inner directly emerges in its specific character, and in it the individual, intelligence, the absolute concept displays itself as purely single and fixed, or its specific character is the body of absolute singularity whereby all indefiniteness is articulated and established, and precisely on the strength of this body it is at once absolute recognition. The ring of metal, the murmur of water, the roaring of the wind does not proceed from within, changing from absolute subjectivity into its opposite, but arises by an impulse from without. An animal’s voice comes from its inmost point, or from its conceptual being, but, like the whole animal, it belongs to feeling. Most animals scream at the danger of death, but this is purely and simply an outlet of subjectivity, something formal, of which the supreme articulation in the song of the birds is not the product of intelligence, of a preceding transformation of nature into subjectivity. The absolute solitude in which nature dwells inwardly at the level of intelligence is missing in the animal which has not withdrawn this solitude into itself. The animal does not produce its voice out of the totality contained in this solitude; its voice is empty, formal, void of totality. But the corporeality of speech displays totality resumed into individuality, the absolute entry into the absolute monadic point of the individual whose ideality is inwardly dispersed into a system. — This is the supreme blossom of the first level, but treated here not in its content but only in form as the abstraction of the supreme rationality and shape of singularity; but as this pure speech it does not rise above singularity. The negative side of this level is distress, natural death, the power and havoc of nature, as well as of men reciprocally, or a relation, though a natural one, to organic nature. |
(gg)
道具は概念の支配下にあり、したがって分化した労働あるいは機械的労働に属する。子供は絶対的に純粋で単純な直観として中間項である。しかし両者(直観と
概念)の総体は、まさにこの直観的単純性と同時に概念の観念性を備えねばならない。つまり子供においては、道具の極限が持つ観念性がその実体的本質に入り
込む一方で、まさにこの理由により道具においては観念性がその死んだ内的な存在に入り込み、極限の現実性は消滅せねばならない。完全に観念的な中間項が存
在しなければならないのだ。絶対的概念、すなわち知性こそが唯一の絶対的観念性である。中間項は知性的でなければならないが、個別的でも主観的でもない。
それは知性の無限に消え去り自ら現れる表れに過ぎない。形成されるがままに消え去る軽やかでエーテル的な体である。主観的知性やその偶有性ではなく、理性
そのものである。現実的ではあるが、その現実性自体が観念的かつ無限であり、存在において即座に自らの対立物、すなわち非存在となる。ゆえにこのエーテル
的身体は両極端を顕現し、観念によれば現実的であると同時に観念性も有する。この身体の本質は即座に消滅することであり、その顕現は顕現と消滅のこの即時
的結合だからである。したがって、このような中間項は知的なものである。それは主体性であり、あるいは知的な個体の中に存在するが、その物質性においては
客観的に普遍的である。そしてこの存在の本質の即時性ゆえに、その主体性は即座に客観性となる。この理想的で合理的な中間項は言語であり、理性の道具であ
り、知的な存在の子である。言語の本質は子に似ている―すなわち最も不確定で純粋、最も否定的で無性であり、絶対的な可塑性と透明性ゆえにあらゆる形態を
とりうる。その現実性は完全に観念性に吸収され、同時に個別的である。それは形態あるいは現実性を持ち、自己を自覚する主体である。ゆえに形式的概念とし
ての言語とは区別されねばならない。後者にとって客観性そのものが言語の形態であるが、この客観性は抽象に過ぎない。対象の現実性は、主体が主観的である
のとは異なる形で主観的だからだ。客観性自体が絶対的な主体性ではない。 言語の総体は次のような段階の形態をとる: (i) 自然、あるいは内的な同一性。これは身体の無意識的な態度であり、現れたのと同じ速さで消え去るが、単一のものであり、客観性の形態のみを持ち、自己の中 に、あるいは自己の上に自己を保持せず、自己とは異質な現実と実体の中に現れる。身振り、風貌、そして眼差しに現れるそれらの総体——これは固定された客 観性でも抽象的な客観でもない。それは儚く、偶然であり、移ろいゆく理想的な戯れである。しかしこの理想性は、その主体であり実体である他者における戯れ に過ぎない。この戯れは感情として現れ、感情に属する。あるいは純粋な同一性、つまり感情の形態として存在する。確かに言語化されつつも変化する感情とし て。しかし戯れはあらゆる瞬間に完全であり、その客観的性格の観念性や、自然が到達し得ない自身の物質性を持たない。 (ii) 言語の直観が概念の下に包含されるとき、それは独自の身体を持つ。なぜならその理想的性質は概念に置かれ、身体は担い手、すなわち固定されたものだから だ。この身体は外的な物質的物であるが、その実体的内面性と自己意識においては完全に無効化されたものである。それは理想的で意味を持たない。しかし概念 が支配的であるゆえに、この身体は死んだものであり、内的に無限に自己を消滅させるものではなく、異なる段階にあるゆえに、支配的概念に対して外部的にの み消滅するものである。したがってその二重の存在もまた外部性であり、主観と客体の間の理想的な中間項として、両者への参照を表現するに過ぎない。しかし この連結は、客体の外側にある主観的思考によって明らかにされる。それ自体の観点では、主体として消滅することによってこの連結を否定的に表現する。ある いは、それ自体の明示的な意味を持つ場合、その内的な無意味さによって連結を表現する。つまり、物として、明示的に確定した何かである限りにおいて媒介項 でありながら、それ自身に対しては明示的ではなく、物ではなく、即座にそれ自身の反対物である——自己認識的でありながら、断固として自己認識的ではな く、他者への存在である。したがって絶対概念はここで真に客観的である。身体的記号:これが道具の観念性であり、態度が子供の観念性であるのと同様であ る。道具を作ることは子供を作るよりも合理的であるのと同様に、身体的記号は身振りよりも合理的である。 記号は絶対的概念に対応するゆえ、無関心の中に吸収された絶対的概念が取り込んだいかなる形も表現しない。しかし概念のみを表現するゆえ、それは形式的か つ普遍的なものと結びついている。態度や身振りが主観的言語であるように、身体的記号は客観的言語である。主観的言語が主体から切り離されず自由でないの と同様に、この客観的言語も客観的であり続け、知識——その主観的要素——を直接的に内包しない。ゆえに知識もまた対象に付随するものであり、対象の決定 的特性ではなく、対象によって呼びかけられるだけであり、対象に対して偶発的なままである。結びつきが偶然的であるからこそ、知識は対象において表現され るが、対象から独立して、主観的な何ものかへの言及を表現する。ただし、それは極めて不確定な形で提示され、まず思考が加えられねばならない。したがって 知識は、対象の所有と、それを所有する主体との間の結びつきをも表現するのだ。 (iii) 発話された言葉は、身体的記号の客観性と身振りの主体性、後者の明瞭化と前者の自己認識を結びつける。それは知性の中間項であり、ロゴス、すなわちそれら の理性的絆である。無言の認識である抽象的客観性は、この言葉において、概念の様式に従いながら自己のために存在する、独立した独自の身体を獲得する。す なわち、それは即座に自己を破壊するのである。発話された言葉において、内面はその固有の性格をもって直接に現出する。そしてそこにおいて、個体、知性、 絶対的概念は純粋に単一かつ固定されたものとして自らを顕現する。あるいはその固有の性格は、あらゆる不定性を明示し確立する絶対的単一性の身体であり、 まさにこの身体の力によって、それは同時に絶対的認識となる。金属の響き、水のささやき、風の唸りは、絶対的な主体性からその反対へと変化して内側から生 じるのではなく、外からの衝動によって生じる。動物の声はその最も内なる点、すなわちその概念的存在から発するが、動物全体と同様に、それは感情に属す る。ほとんどの動物は死の危険に直面して叫ぶが、これは純粋に主体性の発露であり、形式的なものに過ぎない。鳥の歌における最高の表現は、知性や自然から 主観性への先行する変容の産物ではない。知性のレベルにおいて内面的に宿る絶対的孤独は、この孤独を自己内に引きこめていない動物には欠けている。動物は その声の根底にある総体から声を生産しない。その声は空虚で形式的であり、総体を欠いている。しかし言語の身体性は、総体が個別性に取り戻された姿を示 す。それは個体の絶対的単子点への絶対的進入であり、その観念性は内面的に体系へと分散されている。— これは第一段階の至高の開花であるが、ここでは内容ではなく、至高の理性と特異性の形態の抽象として、形式のみが扱われている。しかしこの純粋な言語とし て、それは特異性を超えることはない。 この段階の否定的な側面は、苦痛、自然死、自然の力と破壊、また人間同士の相互的な力と破壊、あるいは有機的な自然との、自然ではあるが関係性である。 |
| B. Second Level: of Infinity and Ideality in Form or in Relation This is the subsumption of intuition under the concept, or the emergence of the ideal and the determining of the particular or the singular by the ideal. There is causality here, but only as purely ideal, for this level is itself a formal one;[14] the ideal is only the abstraction of the ideal. There is not yet any question of the ideal’s being constituted as such for itself [or realised] and becoming a totality. Just as the single individual was dominant at the first level so the universal is dominant here. At the first level the universal was hidden, something inner, and speech itself was considered there only as something singular, i.e., in its abstraction. In this subsumption singularity immediately ceases. It becomes something universal which plainly has a bearing on something else. Beyond this formal concept, however, the living natural relation becomes nevertheless a fixed relation which it was not previously; also universality must hover over this natural relation and overcome this fixed relation. Love, the child, culture, the tool, speech are objective and universal, and also are bearings and relations, but relations that are natural, not overcome, casual, unregulated, not themselves taken up into universality. The universal has not emerged in and out of them themselves, nor is it opposed to them. When this subsuming universality is looked at from the point of view of particularity, there is nothing in this level that is void of a bearing on other intelligences,[15] with the result that equality is posited among them, or it is universality which thus appears in them. a) The Subsumption of the Concept under Intuition This is the relation of the universal opposed to the particular as it appears in the particular, or the subsumption of the universal [the concept] under intuition. The universal, dominant itself in the singular or the particular, bears solely on this single being; or the single being is first, not the ideal hovering over it, nor a multiplicity of particulars subsumed under the ideal. The latter consists in the purely practical, real, mechanical relation of work and possession. (i) The particular, into which the universal is transferred, therefore becomes ideal and the ideality is a partition of it. The entire object in its determinate character is not annihilated altogether, but this labour, applied to the object as an entirety, is partitioned in itself and becomes a single labouring;[16] and this single labouring becomes for this very reason more mechanical, because variety is excluded from it and so it becomes itself something more universal, more foreign to the living whole.[17] This sort of labouring, thus divided, presupposes at the same time that the remaining needs are provided for in another way, for this way too has to be laboured on, i.e., by the labour of other men. But this deadening characteristic of mechanical labour directly implies the possibility of cutting oneself off from it altogether; for the labour here is wholly quantitative without variety, and since its subsumption in intelligence is self-cancelling, something absolutely external, a thing, can then be used owing to its self-sameness both in respect of its labour and its movement. It is only a question of finding for it an equally dead principle of movement, a self-differentiating power of nature like the movement of water, wind, steam, etc., and the tool passes over into the machine, since the restlessness of the subject, the concept, is itself posited outside the subject in the energy source. (ii) Just as the subject and his labour are determinate here, so the product of the labour is too. It is parcelled out and hence it is pure quantity so far as the subject is concerned. Since his quantity of the common product is not in a relation with the totality of his needs, but goes beyond them, it is quantity in general and abstractly. Thus this possession has lost its meaning for the practical feeling of the subject and is no longer a need of his, but a surplus;[19] its bearing on use is therefore a universal one and, this universality being conceived in its reality, the bearing is on the use of others. Because, from the point of view of the subject, the need is explicitly an abstraction of need in general, the bearing of the surplus on use is a general possibility of use, not just of the specific use that it expresses, since the latter is divorced from the subject. (iii) The subject is not simply determined as a possessor, but is taken up into the form of universality; he is a single individual with a bearing on others and universally negative as a possessor recognised as such by others. For recognition is singular being, it is negation, in such a way that it remains fixed as such (though ideally) in others, in short the abstraction of ideality, not ideality in the others. In this respect possession is property; but the abstraction of universality in property is legal right. (It is laughable to regard everything under the form of this abstraction as legal right; right is something entirely formal, (a) infinite in its variety, and without totality, and (b) without any content in itself.) The individual is not a property owner, a rightful possessor, absolutely in and of himself. His personality or the abstraction of his unity and singularity is purely an abstraction and an ens rationis. Moreover it is not in individuality that law and property reside, since individuality is absolute identity or itself an abstraction; on the contrary, they reside solely in the relative identity of possession, in so far as this relative identity has the form of universality. A right to property is a right to right; property right is the aspect, the abstraction in property, according to which property is a right remaining for its other, the particular, as possession. The negative of this level is the bearing of freedom as against the universal, or the negative in so far as it constitutes itself positively and sets itself up in difference against the universal, so that it bears on it and is not the lack and concealment of difference. In the latter undeveloped respect the preceding levels would be its negative. The mechanical negative, i.e., what conflicts with and does not fit a particularity determined by the subject, does not belong to this context. It does not apply at all to this determinacy in so far as this is practical; on the contrary, mechanical negation is a matter belonging entirely to nature. — The negative comes into consideration here only in so far as it conflicts with the universal as such, and in so far as it, as a single individuality, gives universality the lie and abstracts from it; not when singularity really annihilates the form of the universal — for in that case the negative posits the universal as truly ideal and itself as one with it — but, on the contrary, when the negative cannot annihilate the universal or unite itself with it but is differentiated from it.[20] — The negative thus consists in the non-recognition of property, in its cancellation. But property itself is here posited as not necessary, not tied to the use and enjoyment of the subject. The matter owned, so far as posited here as something universal, is itself therefore posited as something negative. The subject’s tie with it is itself determined as merely a possible one. Thus negation can affect merely this form, or not the matter itself but only the matter as universal quantity. A surplus, i.e., what already has no explicit bearing on need, is cancelled. As a surplus its destiny is to pass out of the producer’s possession. Whether this supersession, this negation, is or is not compatible with this destiny must emerge from the following level. |
B. 第二段階:形式または関係における無限性と観念性 これは直観が概念の下に包含されること、すなわち観念の出現と、観念による個別的・単一的なものの決定である。ここには因果関係が存在するが、それは純粋 に観念的なものに過ぎない。なぜならこの段階自体が形式的な段階だからだ[14]。観念は観念の抽象に過ぎない。理想がそれ自体として構成され(実現さ れ)、全体となることはまだ問題とされていない。第一段階で個体が支配的であったように、ここでは普遍が支配的である。第一段階では普遍は隠された内的な ものであり、言語そのものも単なる個別性、すなわちその抽象としてのみ考えられていた。 この包含において、個別性は即座に消滅する。それは明らかに他の何かに影響を及ぼす普遍的なものとなる。しかしこの形式的概念を超えて、生きた自然的関係 はそれまでなかった固定された関係となる。また普遍性は、この自然的関係の上に立ち、この固定された関係を克服しなければならない。愛、子供、文化、道 具、言語は客観的で普遍的であり、また影響力や関係でもある。しかしそれらは自然的な関係であり、克服されておらず、偶然的で、規制されておらず、それ自 体が普遍性に取り込まれていない。普遍性は、それら自身の中から、またそれら自身によって現れてはいない。また、それらに対立しているわけでもない。 この包含する普遍性を個別主義の観点から見たとき、このレベルにおいて他の知性への影響を欠くものは何もない[15]。その結果、それらの間に平等が仮定されるか、あるいは普遍性がこうしてそれらの中に現れるのである。 a) 概念の直観への包含 これは、個別性の中に現れる個別性に対する普遍性の関係、すなわち普遍性[概念]の直観への包含である。個別性や個別物の中に自らを支配する普遍性は、こ の単一の存在にのみ関わる。あるいは、単一の存在が先立ち、その上に漂う観念も、観念の下に包含される個別物の多様性もない。後者は、純粋に実践的・現実 的・機械的な労働と所有の関係に帰着する。 (i) したがって、普遍が転移される個別は、それ自体、観念的となり、その観念性は、その分割である。対象の全体性がその決定された性格において完全に消滅する わけではないが、対象の全体性に対して適用されるこの労働は、それ自体において分割され、単一の労働となる[16]。そしてこの単一の労働は、多様性が排 除されるゆえに、より機械的になる。それゆえに、それはそれ自体、より普遍的なもの、生きた全体にとってより異質なものとなる。[17] このように分割された労働は、同時に残りの必要が別の方法で満たされることを前提とする。なぜならこの方法もまた、すなわち他の人間の労働によって、労力 を要するからである。しかし機械的労働のこの死んだような特性は、そこから完全に切り離される可能性を直接的に含意している。なぜならここでの労働は多様 性なく完全に量的であり、知性への帰属が自己否定的であるため、労働と運動の両面において自己同一性を持つ絶対的に外的なもの、すなわち物が利用可能とな るからだ。問題は、それと同等に死んだ運動原理、すなわち水の動き、風、蒸気などの自然の自己差異化力を発見することにある。そうすれば道具は機械へと移 行する。なぜなら、主体、すなわち概念の落ち着きのなさは、エネルギー源において主体自身の外に置かれるからである。 (ii) 主体とその労働がここで確定的であるのと同様に、労働の産物もまた確定的である。それは分割され、したがって主体にとっては純粋な量である。共通の産物に おける彼の量は、彼の必要性の総体との関係にないが、それを超えるものであるため、それは一般的かつ抽象的な量である。したがってこの所有は、主体の実践 的感覚にとってその意味を失い、もはや彼の必要ではなく余剰となる[19]。ゆえにその使用への帰属は普遍的なものであり、この普遍性が現実として構想さ れる以上、その帰属は他者の使用に向けられる。主体の観点から、必要は明示的に一般の必要の抽象化であるため、余剰の用途への関係は、特定の用途(それは 主体から切り離されている)ではなく、用途の普遍的可能性である。 (iii) 主体は単なる所有者として決定されるのではなく、普遍性の形態に取り込まれる。すなわち、他者に対して影響力を持つ単一の個人であり、他者によってそのよ うに認識される所有者として普遍的に否定的な存在である。なぜなら、認識とは単一の存在であり、否定であり、他者において(理想的には)そのように固定さ れたまま残るもの、つまり他者における観念性そのものではなく、観念性の抽象だからだ。この点において所有は財産である。しかし財産における普遍性の抽象 化は法的権利である。(この抽象化の形式の下にある全てを法的権利と見なすのは滑稽である。権利とは完全に形式的なものであり、(a)その多様性は無限で あり総体を持たず、(b)それ自体に何ら内容を持たない。) 個人は、絶対的にそれ自体において、財産所有者でも正当な占有者でもない。その人格、すなわちその統一性と特異性の抽象は、純粋な抽象概念であり、概念上 の存在に過ぎない。さらに、法と財産は個性に内在するものではない。なぜなら個性は絶対的同一性、すなわちそれ自体が抽象概念だからだ。それどころか、そ れらは占有の相対的同一性、すなわちこの相対的同一性が普遍性の形式を持つ範囲においてのみ内在する。財産権とは権利に対する権利である。財産権とは、財 産が他者、すなわち個別性に対して保持として残る権利であるという観点、すなわち財産における抽象である。 この段階の否定形は、普遍に対する自由の担い手、すなわち自らを肯定的に構成し、普遍に対して差異として自らを確立する限りにおける否定である。したがっ てそれは差異を欠くものでも隠すものでもなく、差異を背負うものである。後者の未発達な観点においては、先行する段階がそれの否定となる。 機械的な否定、すなわち主体によって決定された個別主義と衝突し適合しないものは、この文脈には属さない。それが実践的である限りにおいて、この決定性に は全く適用されない。むしろ機械的否定は完全に自然の領域に属する事柄である。— 否定がここで考慮されるのは、普遍そのものと対立する限りにおいて、また単一の個別性として普遍性を虚偽とし、そこから抽象する限りにおいてである。個性 が普遍の形式を真に消滅させる場合ではない——その場合、否定は普遍を真に理想的なものとして、またそれ自体と一体のものとして位置づけるからだ——むし ろ、否定が普遍を消滅させたりそれと結合したりできず、それとは区別される場合にこそ、否定は存在する。[20]— したがって、否定とは所有権の非承認、すなわちその取消しに存する。しかし所有権そのものは、ここでは必要不可欠なものではなく、主体の使用や享受に結び つかないものとして位置づけられる。所有される物質は、ここで普遍的なものとして位置づけられる限り、それ自体が否定的なものとして位置づけられる。主体 との結びつきは、単なる可能性として決定される。したがって否定は、この形式のみに影響を与え得る。つまり物質そのものではなく、普遍的な量としての物質 のみに影響を与え得る。余剰、すなわちすでに必要性に明示的な関係を持たないものは、取り消される。余剰としてのその運命は、生産者の所有から離れること にある。この超越、この否定が、この運命と相容れるか否かは、次の段階から明らかになる。 |
| b) The Subsumption of Intuition under the Concept A relation is established between the subject and his surplus labour; the bearing of this labour for him is ideal, i.e., it has no real bearing on his own enjoyment. But at the same time this bearing has emerged as something universal or infinite, or as a pure abstraction — possession in law as property. But what is possessed here has by its nature a real bearing on the subject on his enjoyment only when it is annihilated [consumed], and the previously ideal tie of possession by the subject is now to become a real one. The infinite, i.e., legal right, as the positive element in this whole level, is something fixed and is to persist; the ideal tie of possession is to persist too and yet it is to be made real. This whole level is in general the level of difference, and the present dimension of this level is likewise difference, and so the difference of difference — previously difference at rest, here in movement. Difference is implied in the concept, i.e., the relation of a subject to something characterised as merely possible. Owing to the new difference, the relation of the subject to his labour is superseded, but because infinity, i.e., legal right as such, must remain, there appears instead of that ideal connection with the surplus possession its conceptual opposite, the real connection with use and need. The separation is starker, but for that very reason the urge for unification is stronger too, just as the magnet holds its poles apart, without any urge of their own to unity, but, when the magnet is severed, their identity being cancelled, we have electricity, a starker separation, real antithesis, and an urge for unification.[21] What is cancelled here is oneness with the object through one’s own labour, or the individual special characteristic of it as “mine” (magnetism [in the proposed analogy]). What is substituted is real difference, cancellation of the identity of subject and object; and therefore a real annihilation of the opposite or a difference which has a bearing on need. — In this whole level, both (a) and (b), thoroughgoing ideality first begins, as well as the true levels of practical intelligence; with surplus labour this intelligence ceases even in need and labour to belong to need and labour. The relation to an object which this intelligence acquires for need and use, and which is posited here, namely, the fact that intelligence has not worked up the object for its own use since it has not consumed its own labour on it, is the beginning of legal, and formally ethical, enjoyment and possession. What is absolute and ineradicable in this level is the absolute concept, the infinite itself, legal right at rest in (a), or subsisting in its opposition and therefore inwardly concealed and hidden; and, in (b), legal right in motion, one accident being cancelled by another, passing through nothingness, so that legal right emerges and stands over against the accidents as causality. This pure infinity of legal right, its inseparability, reflected in the thing, i.e., in the particular itself, is the thing’s equality with other things, and the abstraction of this equality of one thing with another, concrete unity and legal right, is value; or rather value is itself equality as abstraction, the ideal measure of things — but the actually found and empirical measure is the price. In the supersession of the individual tie of possession, there remains (a) legal right, (b) the same appearing in something specific in the form of equality, or value; (g) but the individually tied object loses its tie and (d) there enters in its stead something really determinate linked to the individuals desire. [a] The inner essence of this real exchange is, as has been shown, the concept that remains the same throughout, but is real in intelligences, more precisely in needy intelligences, beings who are concerned with both a surplus and an unsatisfied need at the same time. Each of them enters upon the transformation of the individual thing with which he is linked ideally and objectively as its legal owner into something that is subjectively linked with his need. This is exchange, the realisation of the ideal relation. Property enters reality through the plurality of persons involved in exchange and mutually recognising one another.[22] Value enters in the reality of things and applies to each of them as surplus; the concept enters as self-moving, annihilating itself in its opposite, taking on the opposite character in place of the one it possessed before, and indeed so determined that what was formerly ideal now enters as real, because the first level is that of intuition, the present one that of the concept; the former is ideal, the latter naturally prior, but the ideal in practice comes before enjoyment. [b] Externally exchange is twofold, or rather a repetition of itself, for the universal object, the surplus, and then the particular element in need is materially an object, but its two forms are necessarily a repetition of it. But the concept or essence of exchange is the transformation itself, and since the absolute character of the transformation is the identity of the opposite, this raises the question of how this pure identity, infinity, is to be displayed as such in reality. The transition in the exchange is a manifold, divided, externally connected series of the single moments of the whole transaction. It may take place in one moment, in a single present instant, by the transfer of the possessions of both parties from one to the other. But if the object is manifold, the transition is likewise manifold, and the desired quid pro quo is something manifold, and the opposite quid pro quo is not there until it is complete; it is not there at the start or in the continuation, except as only an advance. [23] Therefore exchange is itself something uncertain because of these empirical circumstances, which appear as the gradualness of the execution of the exchange, the postponement of the whole execution to a later date, etc.; the present moment does not appear here. The fact that the execution of the transaction is something inner and presupposes sincerity is something entirely formal, for the point about it is that the exchange has not happened. The transaction and transfer has not become a reality, and the uncertainty depends on the manifold aspects of the transaction, on their dispersal, and on the possibility of abstraction [i.e., withdrawal] from it or of freedom. (The third moment of this second level (b) ) (g) This irrationality or the antithesis between (i) this empty possibility and freedom and (ii) actuality and what appears, must be superseded, or the inner intentions of the intelligent agents who are making the exchange must emerge. This freedom must become equivalent to necessity, so that the transaction is deprived of its empirical contingencies, and the middle term of the transition, i.e., identity, is established as something necessary and firm. The nature and form of the exchange remains, but the exchange is taken up into quantity and universality. This transformation of exchange is contract. In it the absolutely present moment in a pure exchange is formed into a rational middle term which not only admits the empirical phenomena in exchange but, in order to be a totality, demands them as a necessary difference which is undifferentiated in a contract. Owing to the necessity acquired by the transition in a contract, the empirical aspect, the fact that the two sides of the bargain are fulfilled separately at different times, becomes unimportant — it is something accidental which does no harm to the security of the whole. It is as good as if the bargain had already been carried out. The right of each singular party to his property is already transferred to the other and the transfer itself is regarded as having happened. The outwardly apparent fact that the transaction has not yet been executed, that the transfer has not yet been empirically carried out in reality, is wholly empirical and accidental; or rather it has been nullified, so that the property has been entirely deprived of the external tie whereby it is not only marked as a possession but is still in the possession of the one who has already transferred it. [d] Thus since contract transforms the transfer from a real one into an ideal one, but in such a way that this ideal transfer is the true and necessary one, it follows that in order to be this it must itself have absolute reality. The ideality or universality which the present moment acquires must thus exist, but reality itself transcends the sphere of this formal level. This much results formally, that ideality as such, and also as reality in general, can be nothing other than a spirit which, displaying itself as existing, and wherein the contracting parties are nullified as single individuals, is the universal subsuming them, the absolutely objective essence and the binding middle term of the contract. Owing to the absolute oneness in the contract, freedom and possibility are superseded with respect to the members of the transfer. This oneness is not something inner like fidelity and faith, in which inner being the individual subsumes identity under himself; on the contrary, in face of the absolutely universal, the individual is what is subsumed. Thus his caprice and idiosyncrasy are excluded because in the contract he invokes this absolute universality. But though the whole force of universality likewise enters the contract, this still happens only formally. The determinate provisions linked by that form and subsumed under it are and remain determinate provisions; they are only empirically infinitely posited as this or that or the other, yet they subsist. They are treated as the singular aspect of the individuals or of the things about which the contract is made. And for this reason true reality cannot fall within this level. For the aspect of reality here is an explicitly subsisting finitude which is not to be annihilated in ideality, and it follows that it is impossible for reality here to be a true and absolute one. |
b) 直観の概念への帰属 主体とその余剰労働との間に関係が確立される。この労働が主体にとって持つ意味は理想的なものであり、すなわち、主体自身の享楽に対して現実的な影響を持 たない。しかし同時に、この関係は普遍的あるいは無限のもの、あるいは純粋な抽象物として現れた。すなわち、法における所有権としての財産である。しかし ここで所有されるものは、その性質上、主体がそれを消滅(消費)した時にのみ、主体の享楽に対して現実的な関係を持つ。そして以前には理想的であった主体 の所有関係は、今や現実的なものとなる。無限、すなわち法的権利は、この段階全体の積極的要素として固定されたものであり、持続する。所有という理想的絆 もまた持続するが、同時に現実化される。この段階全体は一般に差異の段階であり、この段階の現在の次元もまた差異、すなわち差異の差異である。以前には静 止した差異であったものが、ここでは運動する差異となる。差異は概念、すなわち主体が単なる可能性として特徴づけられた何ものかとの関係に内在する。新た な差異によって、主体と労働との関係は超越されるが、無限、すなわち法的な権利そのものが存続せねばならないため、余剰所有との理想的な結びつきに代わっ て、その概念的対極である使用と必要との現実的な結びつきが現れる。分離はより鮮明になるが、それゆえに統一への衝動も強まる。磁石が両極を離すように、 それ自体に統一への衝動はない。しかし磁石が切断され、同一性が解消されると、電気というより鮮明な分離、現実の対立、そして統一への衝動が生じる。 [21] ここで解消されるのは、自らの労働による対象との一体性、あるいは「私のもの」としての個別の特殊性(提案された類推における磁性)である。それに代わる のは、実在的な差異、主観と客観の同一性の消滅である。したがって、対立物の実在的な消滅、あるいは必要に関わる差異が生まれる。―この全体的なレベルに おいて、(a)と(b)の両方、徹底した観念性が初めて始まり、実践的知性の真のレベルも始まる。余剰労働によって、この知性は、必要と労働においても、 もはや必要と労働に属しなくなる。この知性が需要と使用のために獲得する対象との関係、すなわちここで前提されるのは、知性が対象を自らの使用のために加 工していないという事実である。なぜなら知性は対象に対して自らの労働を消費していないからだ。これが法的かつ形式的に倫理的な享受と所有の始まりであ る。 この段階において絶対的かつ根絶しがたいものは、絶対的概念、すなわち無限そのものであり、(a)においては静止した法的権利、あるいは対立関係に存しゆ えに内的に隠蔽された状態であり、(b)においては運動する法的権利、一つの偶有性が別の偶有性によって相殺され、無を通過して法的権利が現出する状態、 すなわち偶有性に対して因果性として対峙する状態である。 この法的権利の純粋な無限性、その不可分性は、物、すなわち個別物自体に反映される。それが物と他の物との平等性であり、この平等性、すなわち一つの物と 他の物との抽象化された平等性、具体的統一と法的権利が価値である。あるいはむしろ、価値そのものが抽象としての平等性、物の理想的尺度である。しかし実 際に発見され経験的に測定される尺度は価格である。 所有という個別的絆の超越において残るのは、(a)法的権利、(b)平等、すなわち価値の形態で個別的なものに現れる同一性、そして(c)個別的に結びつけられていた対象はその絆を失い、(d)その代わりに、個々の欲望に結びつけられた実在的に確定された何かが入り込む。 [a] この現実的交換の本質は、これまで示してきた通り、常に同一でありながら、知性、より正確には欠乏する知性、すなわち余剰と未充足の欲求を同時に抱える存 在において現実化する概念である。各者は、理想的かつ客観的に自らの法的所有物として結びついた個別物を、主観的に自らの必要と結びついたものへと変容さ せる過程に入る。これが交換であり、理想的関係の実現である。財産は、交換に関与し互いに認識し合う複数の人格を通じて現実に入る。[22] 価値は物の現実に入り込み、各々に剰余として適用される。概念は自己運動的に入り込み、その対立物において自らを消滅させ、以前に持っていた性格の代わり に反対の性格を帯びる。そして確かに、かつて理想であったものが今や現実として入るように決定づけられる。なぜなら最初の段階は直観の段階であり、現在の 段階は概念の段階だからだ。前者は理想的であり、後者は当然ながら先行するが、実践における理想は享受に先立つ。 [b] 交換は外的には二重、あるいはむしろ自己の反復である。普遍的対象である剰余と、次に物質的に対象となる特定の必要要素とが存在するが、その二形態は必然 的に自己の反復となる。しかし交換の概念あるいは本質は、変容そのものである。そして変容の絶対的性格は対立物の同一性であるから、この純粋な同一性、無 限性が現実において如何にそのように現れるべきかという問題が生じる。 交換における移行は、取引全体の単一の瞬間が、多様で分割され、外部的に連結された系列である。それは一瞬間、単一の現在において、双方の所有物を相互に 移転することで成立しうる。しかし対象が多元的であれば、移行もまた多元的であり、求められる対価は多元的なものであり、反対の対価は完成するまで存在し ない。それは開始時にも継続中にも存在せず、先行する段階としてのみ存在する。[23] したがって交換そのものが不確実なものである。その理由は、交換の実行が漸進的であること、実行全体が後日に延期されることなどといった経験的状況にあ る。ここには現在という瞬間は現れない。取引の実行が内面的であり誠実さを前提とするという事実は、まったく形式的なものに過ぎない。なぜなら、肝心なの は交換がまだ起こっていないという点だからだ。取引と移転は現実化しておらず、その不確実性は取引の多様な側面、それらの分散、そしてそこから抽象化(す なわち撤退)または自由の可能性に依存している。 (この第二段階(b)の第三の瞬間) (g) この非合理性、すなわち(i)この空虚な可能性と自由と、(ii)現実性と顕在化との間の対立は、克服されねばならない。さもなければ、交換を行う知的な 主体たちの内的な意図が現出せぬ。この自由は必然性に等しくならねばならず、それによって取引は経験的な偶然性を剥奪され、移行の中項、すなわち同一性が 必然的かつ確固たるものとして確立される。交換の本質と形式は残るが、交換は量と普遍性の中に取り込まれる。 この交換の変容が契約である。そこでは純粋な交換における絶対的な現在瞬間が、合理的な中間項として形成される。この中間項は交換における経験的現象を単に認めるだけでなく、全体性を成すために、契約においては未分化な必然的差異としてそれらを要求する。 契約における移行が獲得した必然性ゆえに、経験的側面、すなわち取引の双方が異なる時期に個別に履行されるという事実は重要性を失う。それは全体としての 安全を損なわない偶発的なものに過ぎない。あたかも取引が既に実行されたかのように扱われる。各当事者の財産に対する権利は既に他方へ移転しており、その 移転自体も既に生じたものと見なされる。取引がまだ実行されていないという外見上の事実、すなわち移転が現実において経験的にまだ行われていないという事 実は、完全に経験的かつ偶発的なものである。むしろそれは無効化されており、財産は、所有物として標示されているだけでなく、既にそれを移転した者の所有 下にあるという外部的な結びつきを完全に剥奪されているのである。 [d] したがって契約は、移転を現実的なものから理想的なものへと変容させるが、この理想的な移転こそが真に必要不可欠なものである。ゆえに、それが真に必要不 可欠であるためには、それ自体が絶対的な現実性を有していなければならない。現在が獲得する観念性あるいは普遍性は、したがって存在しなければならない。 しかし現実性そのものは、この形式的次元の領域を超越する。形式的に導かれる結論は、観念性そのもの、また一般としての現実性は、存在として現れ、契約当 事者を個々の個人として無効化する普遍的包含者、すなわち契約の絶対的客観的本質かつ拘束的中間項である精神に他ならないということである。契約における 絶対的一体性ゆえに、譲渡の構成員に関しては自由と可能性は超越される。この一体性は、忠実さや信頼のような内面的ものではなく、個人が自己の下に同一性 を包含する内面的存在ではない。むしろ、絶対的普遍性に対して、個人こそが包含されるものである。したがって、契約においてこの絶対的普遍性を呼び起こす 以上、個人の気まぐれや特異性は排除される。しかし普遍性の全力が同様に契約に入るとしても、それは依然として形式的にしか起こらない。その形式によって 結び付けられ、それに包含される特定の規定は、特定の規定であり続け、特定の規定として存在する。それらは経験的に無限に、これかあれか、あるいは別のも のとして設定されるに過ぎないが、それでも存続する。それらは契約の対象となる個人や事物の特異的な側面として扱われる。したがって真の現実はこのレベル には収まらない。なぜならここにおける現実の側面は、観念性において消滅させられない明示的に存続する有限性であり、結果としてここにおける現実が真に絶 対的なものであることは不可能だからだ。 |
| c) The Level of the Indifference of (a) and (b) The third level is the indifference of the preceding ones; that relation of exchange and the recognition of possession, which therefore is property and hitherto had a bearing on the single individual, here becomes a totality, but always within individuality itself; or the second relation is taken up into universality, the concept of the first. (a) Relative identity or the relation. The surplus set into indifference, as something universal and the possibility of satisfying all needs, is money, just as labour, which leads to a surplus, leads also, when mechanically uniform, to the possibility of universal exchange and the acquisition of all necessities. just as money is the universal, and the abstraction of these, and mediates them all, so trade is this mediation posited as activity, where surplus is exchanged for surplus. (b) But the intuition of this totality, yet of this totality as singularity, is the individual as the indifference of all specific characteristics, and this is how he displays his individuality as totality. (i) Formally, in simplicity or intuition, the individual is the indifference of all specific characteristics and as such is in form a living being and is recognised as such; just as he was recognised previously only as possessing single things, so now he is recognised as existing independently in the whole. But because the individual as such is purely and simply one with his life, not simply related to life, it is impossible to say of life, as it could be said of other things with which he is purely in relation, that he possesses it. This has sense only in so far as the individual is not one such living thing but an absolutely entire system, so that his singularity and life are posited like a thing, as something particular. The recognition of this formal livingness of the individual is, like recognition and empirical intuition in general, a formal ideality. Life is the supreme indifference of the single individual, but it is also something purely formal, since it is the empty unity of individual specific characteristics, and therefore no totality and no self-reconstructing whole is posited out of difference. As what is absolutely formal, life is for this very reason absolute subjectivity or the absolute concept, and the individual, considered under this absolute abstraction, is the person. The life of the individual is the abstraction, pushed to its extreme, of his intuition, but the person is the pure concept of this intuition, and indeed this concept is the absolute concept itself. In this recognition of life or in the thinking of the other as absolute concept, the other person exists as a free being, as the possibility of being the opposite of himself with respect to some specific characteristic. And in the single individual as such there is nothing which could not be regarded as a specific characteristic. Thus in this freedom there is just as easily posited the possibility of non-recognition and non-freedom. All things are likewise, owing to their concept, the possibility of being the opposite of themselves; but they remain in absolute determinacy or are lower levels of necessity; they are not all indifferently identical but absolutely different from one another. But intelligence or human life is the indifference of all specific characteristics. (ii) This formal, relationless, recognition, presented in relation and difference or according to the concept. At this level a living individual confronts a living individual, but their power (Potenz) of life is unequal. Thus one is might or power over the other. One is indifference, while the other is fixed in difference. So the former is related to the latter as cause; indifferent itself, it is the latter’s life and soul or spirit. The greater strength or weakness is nothing but the fact that one of them is caught up in difference, fixed and determined in some way in which the other is not, but is free. The indifference of the one not free is his inner being, his formal aspect, not something that has become explicit and that annihilates his difference. Yet this indifference must be there for him; it is his concealed inner life and on this account he intuits it as its opposite, namely, as something external, and the identity is a relative one, not an absolute one or a reconciliation of internal and external. This relation in which the indifferent and free has power over the different is the relation of lordship and bondage [or master and servant]. This relation is immediately and absolutely established along with the inequality of the power of life. At this point there is no question of any right or any necessary equality. Equality is nothing but an abstraction — it is the formal thought of life, of the first level, and this thought is purely ideal and without reality. In reality, on the other hand, it is the inequality of life which is established, and therefore the relation of lordship and bondage. For in reality what we have is shape and individuality and appearance, and consequently difference of power (Potenz) and might, or the relative identity where one individual is posited as indifferent and the other as different. Here plurality is the plurality of individuals, for, in the first level, absolute singularity has been posited in the formality of life, posited as the form of the inner life, since life is the form of external identity or absence of difference. And where there is a plurality of individuals, there is a relation between them, and this relation is lordship and bondage. Lordship and bondage is immediately the very concept of the plurality relation. There is no need for transition or conclusion here, as if some further ground or reason were still to be exhibited for it. Lordship and bondage are therefore natural, because individuals confront one another in this relation; but the relation of lordship and obedience is also set up whenever individuals as such enter into a moral relation in connection with what is most ethical, and it is a question of the formation of the ethical order as framed by the highest individuality of genius and talent. Formally this moral relation is the same as the natural one; the difference consists in the fact that in ethical lordship and obedience the power or might is at the same time something absolutely universal, whereas here it is only something particular; in ethical lordship individuality is only something external and the form; here it is the essence of the relation and on this account there is here a relation of bondage, since bondage is obedience to the single individual and the particular. The master [or overlord] is the indifference of the specific characteristics, but purely as a person or as a formally living being. He is also subject or cause [as opposed to object or instrument]. Indifference [or identity] is subsumed under “being the subject” or under the concept; and the bondsman is related to him as to formal indifference or the person. Because the commander is here qua person, it follows that the absolute, the Idea, the identity of the two is not what is posited in the master in the form of indifference and in the servant in the form of difference; on the contrary, the link between the two is particularity in general, and, in practice, need. The master is in possession of a surplus, of what is physically necessary; the servant lacks it, and indeed in such a way that the surplus and the lack of it are not single [accidental] aspects but the indifference of necessary needs. (iii) This relation of bondage or of person to person, of formal life to formal life, where one is under the form of indifference and the other under that of difference, must be undifferentiated or subsumed under the first level, so that the same relation between persons, the dependence of one on the other, remains, but that the identity is an absolute one yet inner, not explicit, and the relation of difference is only the external form. But the identity must necessarily remain an inner one, because at this whole level it is either only a formal one (legal right) hovering over the particular and opposed to it, or an inner one, i.e., one subsumed under individuality as such, under the intuition of particularity, and so appears as nature, not as an identity subjugating a pair of antitheses or as ethical nature in which that antithetic pair has been likewise superseded, but in such a way that particularity and individuality are what has been subsumed. This indifference of the lordship and bondage relation, an identity in which personality and the abstraction of life are absolutely one and the same, while this relation is only something qua apparent and external, is the [patriarchal] family. In it the totality of nature and all the foregoing are united; the entire foregoing particularity is transformed in the family into the universal. The family is the identity: (a) of external needs (b) of sex-relationship, the natural difference posited in the individuals themselves, and (g) of the relation of parents to children or of natural reason, of reason emergent, but existing as nature. (a) On account of the absolute and natural oneness of the husband, the wife, and the child, where there is no antithesis of person to person or of subject to object, the surplus is not the property of one of them, since their indifference is not a formal or a legal one. So too all contracts regarding property or service and the like fall away here because these things are grounded in the presupposition of private personality. Instead the surplus, labour, and property are absolutely common to all, inherently and explicitly; and on the death of one of them there is no transfer from him to a stranger; all that happens is that the deceased’s participation in the common property ends. Difference is [i.e., it has here] the superficial aspect of lordship. The husband is master and manager, but not a property owner as against the other members of the family. As manager he has only the appearance of free disposal of the family property. Labour too is divided according to the nature of each member of the family, but its product is common property. Precisely because of this division each member produces a surplus, but not as his own property. The transfer of the surplus is not an exchange, because the whole property is directly, inherently, and explicitly common. (b) The sex relation between husband and wife is naturally undifferentiated. I have said in (a) that in respect of personality, i.e., as holders of property, they are definitely one. But the sex relation gives a special form to their indifference, for it is something inherently particular. When the particular as such is made into a universal or the concept, it can only become something empirically universal. (In religion things are different.) Particularity becomes persistent, enduring, and fixed. The sex relation is restricted entirely to these two individuals together, and it is established permanently as marriage. Because this relation is grounded on a particular character of individuals — though its peculiarity is settled by nature and not by some capricious abstraction — this relation seems to be a contract. But it would be a negative contract which annuls just that presupposition on which the possibility of contract in general rests, namely, personality or being a subject possessing rights. All this is nullified in marriage, because there the person gives himself or herself up as an entirety. But what is supposed in a contractual relation to become the property of the other could simply not come into his or her possession. Since the relation is personal, what is supposed to be transferred remains the property of the person, just as, in general, no contract is inherently possible about personal service, because only the product, and not the personality, can be transferred into the possession of the other. The slave can become property as an entire personality, and so can the wife; but this relation is not marriage. There is no contract with the slave either, but there can be a contract with someone else about the slave or the woman, e.g., among many peoples the woman is bought from the parents. But there can be no contract with her, for in so far as she is to give herself freely in marriage, she gives up, along with herself, the possibility of a contract, and so does the man. The terms of their contract would be to have no contract and so the terms would be immediately self-destructive. But by a positive contract each party in a marriage would make himself or herself a thing in his own possession, would make his whole personality into a determinate characteristic of himself to which he is absolutely linked at the same time; yet as a free being he must not regard himself as absolutely bound up with any single characteristic of himself, but as the indifferent identity of all of them. We would have to think, as Kant does,[24] of the sexual organs as this characteristic. But to treat one’s self as an absolute thing (Sache), as absolutely bound up with a specific characteristic, is supremely irrational and utterly disgraceful. (g) In the child the family is deprived of its accidental and empirical existence or the singularity of its members, and is secured against the concept whereby the singulars or subjects nullify themselves. The child, contrary to appearance, is the absolute, the rationality of the relationship; he is what is enduring and everlasting, the totality which produces itself once again as such. But because in the family, as the supreme totality of which nature is capable, even absolute identity remains something inner, and is not posited in the absolute form itself, it follows that the reproduction of the totality is an appearance, i.e., the children. In the true totality the form is entirely one with the essence, and so its being is not the form driven into the separation of its constituent features. But here what is persistent is other than what is; or, reality surrenders its persistence to something else which itself endures over again only in the sense that it becomes, and transmits to another its being, which it cannot retain itself. The form, or infinity, is thus the empirical or negative form of being other, which cancels one determinate characteristic only by positing another, and is only really positive by being always in another. Might and the understanding, the differentiating characters of the parents, stand in an inverse relation with the youth and force of the child, and these two aspects of life fly from and follow one another and are external to one another. |
c) (a)と(b)の無差別性のレベル 第三のレベルは、先行する両者の無差別性である。交換関係と所有の承認、すなわちこれまで個別個人に影響を与えてきた財産関係が、ここでは全体性となる が、常に個別性そのものの内側においてである。あるいは第二の関係が普遍性、すなわち第一の関係の概念に取り込まれるのである。 (a) 相対的同一性、あるいは関係性。 無差別化された剰余は、普遍的なものとして、またあらゆる必要を満たす可能性として、貨幣となる。同様に、剰余を生み出す労働は、機械的に均一化されたと き、普遍的交換の可能性とあらゆる必需品の獲得をもたらす。貨幣が普遍であり、これらを抽象化し、すべてを媒介するように、取引は余剰が余剰と交換される 活動として設定されたこの媒介である。 (b) しかし、この全体性、しかも特異性としてのこの全体性の直観は、すべての特定の特性を無差別に持つ個人であり、こうして彼は全体性としての個性を示すのである。 (i) 形式的に、単純性あるいは直観において、個人はあらゆる特定特性の無差別性であり、その意味で形式的には生きている存在であり、そう認識される。以前には 単一のものを所有する者としてのみ認識されていたように、今や全体の中に独立して存在する者として認識されるのだ。しかし個体そのものは、単に生命と関係 しているのではなく、純粋かつ単純に生命と一体であるため、他のもの(個体が純粋に関係しているもの)について言えるように「生命を所有している」とは言 えない。これは、個体が単なる生き物ではなく絶対的に全体的な体系である場合にのみ意味を持つ。つまり、その特異性と生命が、物として、何か特定のものと して設定される場合である。この個体の形式的な生命性の認識は、一般的な認識や経験的直観と同様に、形式的な観念性である。生命は単一の個体にとって究極 の無関心性であるが、同時に純粋に形式的なものでもある。なぜならそれは個体の特異的特徴の空虚な統一であり、したがって差異から総体も自己再構成的な全 体も設定されないからである。絶対的に形式的なものとして、生命はまさにこのゆえに絶対的主体性、すなわち絶対的概念であり、この絶対的抽象の下で考察さ れる個人が人格である。個人の生命は、その直観を極限まで推し進めた抽象であるが、人はこの直観の純粋な概念であり、実際この概念こそが絶対的概念そのも のである。 この生命の認識、あるいは他者を絶対的概念として考えることにおいて、他者は自由な存在として、ある特定の特性に関して自己の反対である可能性として存在 する。そして単一の個人そのものには、特定の特性と見なせないものは何もない。したがってこの自由には、同様に容易に、非認識と非自由の可能性が前提され る。あらゆるものは同様に、その概念ゆえに、自己の反対となる可能性を有する。しかしそれらは絶対的決定性の中に留まるか、あるいは必然性のより低い段階 にある。それらは無差別に同一なのではなく、互いに絶対的に異なる。しかし知性あるいは人間的生命は、あらゆる特定の特質の無差別性である。 (ii) この形式的、無関係な認識は、関係と差異において、あるいは概念に従って提示される。 このレベルでは、生ける個人が生ける個人と対峙するが、その生命力(ポテンツ)は不平等である。ゆえに一方は他方に対する力や権力となる。一方は無差別で あり、他方は差異に固定されている。したがって前者は後者に対して原因として関係する。無差別であるそれ自体が、後者の生命と魂あるいは精神なのである。 強弱の差とは、単に一方が差異に囚われ、何らかの形で固定・決定されているのに対し、他方は自由であるという事実である。自由でない者の無関心さは、その 内的な存在、形式的側面であり、差異を消滅させる明示化されたものではない。しかしこの無差別性は彼にとって存在せねばならない。それは彼の隠された内的 な生命であり、このゆえに彼はそれを反対物、すなわち外部的なものとして直観する。そして同一性は相対的なものであり、絶対的なものでも、内面と外面の調 和でもない。無差別で自由なものが異なるものに対して権力を持つこの関係こそが、支配と隷属(あるいは主人と僕)の関係である。 この関係は、生命の力の不平等とともに、即座に絶対的に確立される。この段階では、いかなる権利や必然的な平等も問題にならない。平等とは抽象に過ぎない ——それは生命の形式的思考、第一段階の思考であり、この思考は純粋に理想的で現実を持たない。現実においては、逆に、確立されるのは生命の不平等であ り、したがって支配と隷属の関係である。現実にあるのは形態と個別性と表象であり、したがって力の差異(ポテンツ)と強さ、あるいは一方が無差別として、 他方が異なるとして位置づけられる相対的同一性である。ここでの多元性は個体の多元性だ。なぜなら第一段階において、絶対的単一性は生命の形式性の中に、 内的な生命の形式として位置づけられているからだ。生命とは外的な同一性、すなわち差異の不在の形式だからである。そして個体の複数性が存在するところに は、それらの間の関係が存在する。この関係こそが支配と隷属である。支配と隷属は、まさに複数性関係の概念そのものである。ここには、あたかもそれに対す るさらなる根拠や理由がまだ示されねばならないかのような、移行や結論は必要ない。 従って支配と隷属は自然である。なぜなら個人がこの関係において互いに向き合うからだ。しかし支配と服従の関係は、個人が最も倫理的なものに関わる道徳的 関係に入る際にも成立する。これは天才や才能という最高の個性が形作る倫理秩序の形成に関わる問題である。形式的にはこの道徳的関係は自然的な関係と同じ である。差異は、倫理的支配と服従においては力や権威が同時に絶対的に普遍的なものであるのに対し、ここでは単なる個別的なものに過ぎないという事実に存 する。倫理的支配においては個性は単なる外面的形態に過ぎないが、ここでは関係の本質であり、このゆえに隷属関係が生じる。隷属とは個別的な個人への服従 だからである。 主(あるいは支配者)は、特定の特質を超越した無差別性であるが、純粋に人格として、あるいは形式的に生ける存在としてである。彼はまた主体あるいは原因 (対象や道具とは対照的に)でもある。無差別性(あるいは同一性)は「主体であること」あるいは概念の下に包含される。そして被支配者は、形式的な無差別 性あるいは人格として彼と関係を持つ。ここで指揮官が人格として存在する以上、絶対者、理念、両者の同一性は、主人において無差別性の形で、僕において差 異性の形で設定されるものではない。むしろ両者を結ぶのは、一般としての個別主義、そして実践においては必要性である。主人は余剰、すなわち物理的に必要 なものを所有している。奴隷はそれを欠いており、しかもその余剰と欠如は単なる偶発的な側面ではなく、必要な欲求の無差別性として存在する。 (iii) この隷属関係、あるいは人格対人格の関係、形式的生命対形式的生命の関係は、一方が無差別性の形式に、他方が差異性の形式に置かれるものであるが、この関 係は第一のレベルに未分化のまま包含されなければならない。そうすることで、人格同士の依存関係という同一性は絶対的でありながら内面的で明示的ではな く、差異性の関係は単なる外形的形態に留まるのである。しかし同一性は必然的に内的なものでなければならない。なぜならこのレベル全体において、同一性は 個別性の上に浮かび上がりそれと対立する形式的なもの(法的権利)か、あるいは内的なもの、 すなわち、個体性そのもの、個別性の直観の下に包含された同一性として現れる。それは対立項の対を従属させる同一性として、あるいはその対立項の対が同様 に超越された倫理的自然としてではなく、個別性と個体性が包含されたものとして現れるのである。 この支配と隷属の関係における無関心さ、人格と生命の抽象化が絶対的に同一である同一性、そしてこの関係が単なる表面的・外在的なものに過ぎない状態こそ が[家父長制的な]家族である。そこでは自然の総体と前述の全てが統合され、前述の個別の総体は家族において普遍へと変容する。家族は次の同一性である: (a) 外的必要性の同一性 (b) 性関係、すなわち個人そのものに前提される自然的差異の同一性、そして (g) 親子関係、あるいは自然的理性、つまり自然として存在するが、そこから生じる理性の同一性. (a) 夫と妻と子が絶対的かつ自然に一体であるため、個人対個人や主体対客体の対立が存在せず、余剰は誰かの所有物ではない。彼らの無差別性は形式的・法的なも のではないからだ。同様に、財産や奉仕などに関するあらゆる契約もここでは消滅する。なぜなら、こうしたものは私的人格の前提に立脚しているからである。 代わりに、余剰、労働、財産は本質的かつ明示的に全員に絶対的に共有される。そして一人が死亡しても、彼から他者への移転は生じない。ただ、故人の共有財 産への参加が終了するだけである。 差異は(すなわちここでは)支配の表層的な側面である。夫は主人であり管理者であるが、家族の他の成員に対する財産所有者ではない。管理者として、彼は家 族財産を自由に処分する外観を持つに過ぎない。労働もまた家族各員の性質に応じて分業されるが、その生産物は共有財産である。まさにこの分業ゆえに各員は 余剰を生み出すが、それは自己の財産としてではない。余剰の移転は交換ではない。なぜなら全財産が直接的・本質的・明示的に共有だからだ。 (b) 夫婦間の性関係は本来、未分化である。(a)で述べたように、人格、すなわち財産保有者としての立場では、彼らは明らかに一体である。しかし性関係は彼ら の無差別性に特殊な形態を与える。なぜならそれは本質的に個別的なものだからだ。個別性が普遍性や概念として形成されるとき、それは経験的に普遍的なもの にしかなりえない。(宗教においては事情が異なる。)個別性は持続的、永続的、固定的なものとなる。性関係は完全にこの二人の個人に限定され、結婚として 恒久的に確立される。 この関係は個人の特殊性に基づく——その特殊性は気まぐれな抽象概念ではなく自然によって定められる——ゆえに契約のように見える。しかしそれは否定的な 契約であり、契約一般の可能性が依拠する前提、すなわち人格、すなわち権利を有する主体であることそのものを無効化する。結婚においてはこれら全てが無効 となる。なぜなら、そこで人格は自己を全体として捧げるからだ。しかし契約関係において他者の所有物となるはずのものは、そもそもその者の所有物となり得 ない。関係が個人的である以上、移転されるはずのものは依然として当人の所有物であり続ける。これは、一般的に個人的奉仕に関する契約が本質的に成立し得 ないのと同様である。なぜなら、人格そのものではなく、その産物のみが他者の所有物に移転し得るからだ。奴隷は人格全体として所有物となり得る。妻も同様 だ。だがこの関係は結婚ではない。奴隷との契約も存在しない。しかし奴隷や女性について、第三者との契約は成立し得る。例えば多くの民族では、女性は親か ら買い取られる。しかし彼女との契約は成立しえない。なぜなら結婚において自らを自由に捧げる限り、彼女は契約の可能性を自ら放棄するからであり、男性も 同様である。彼らの契約条件は「契約を持たない」ことであり、それは即座に自己破壊的となる。 しかし積極的な契約によって、婚姻の当事者は自らを自己所有の物とし、人格全体を自己の絶対的特性として結びつけることになる。だが自由な存在として、人 は自らのいかなる特性にも絶対的に縛られるべきではなく、それら全ての無差別な同一性として自らを捉えねばならない。カント[24]がそう考えたように、 この特性として性器を考えねばならない。しかし、自己を絶対的な物(Sache)として、特定の特徴に絶対的に結びつけられたものとして扱うことは、極め て非合理的であり、全く恥ずべきことだ。 (g) 子供において、家族は偶発的・経験的な存在や構成員の個別性を失い、個別者や主体が自らを無効化する概念から守られる。子供は、見かけとは裏腹に、絶対で あり、関係の合理性である。彼は永続的で永遠なるもの、それ自体として再び生み出される総体である。しかし家族という、自然が可能な最高の総体において、 絶対的同一性さえも内的なものに留まり、絶対的形式そのものに置かれることはない。ゆえに総体の再生産は表象、すなわち子供たちとなる。真の全体性におい ては、形式は本質と完全に一体であり、ゆえにその存在は構成要素の分離へと駆り立てられた形式ではない。しかしここでは、持続するものは存在するものとは 異なる。あるいは、現実性は自らの持続性を他の何かに譲り渡し、それ自体が再び永続するのは、自ら存在を保持できない存在を他者に伝達するという意味にお いてのみである。したがって、形式、すなわち無限性は、他者という経験的あるいは否定的存在形態であり、ある特定の特性を否定する代わりに別の特性を肯定 することでしか成立せず、常に他者の中にあって初めて真に肯定的となる。親の力と理解力という差別化特性は、子の若さと活力と逆の関係にあり、生命のこの 二つの側面は互いに逃れ合い、追いかける関係にあり、互いに外部的な存在である。 |
| next section |
|
| G.W.F. Hegel, System of Ethical Life (1802/3) | |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099