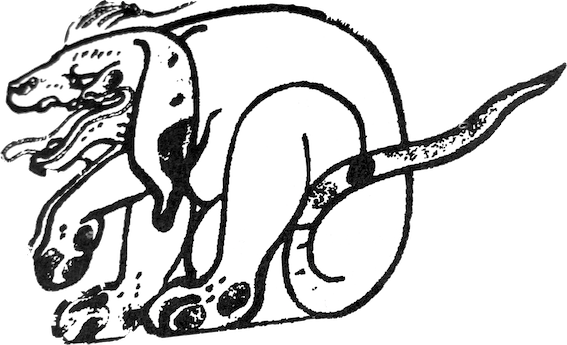
倫理的生活
Ethical Life, by G.W.F. Hegel 1802/3
☆ヘーゲルの死後出版された原稿の中で、『倫理的生活の体系』はおそらく最も謎めいたものである。死後出版物を詳細に研究したドイツの学者たちでさえ、この評価に異 論を唱える者はいないようだ。例えばヘーゲルの初期著作を最も包括的に研究したハーリングはこう述べている。「確かに、これを理解する困難さは並外れてい る」(『ヘーゲル、その意志と業績』第2巻、338頁)。このため我々は、ドイツ語でさえほとんど理解不能な内容を、明快で理解しやすい英語に完全に翻訳 することが常に可能とは限らなかった。しかしながら、この試みは価値あるものだと我々は考えた。なぜなら本論文はヘーゲルの体系的草稿の中で現存する最古 のものであり、彼の成熟した社会思想が萌芽的な形で表れているからだ。ドイツの学者たちによって長く認識されてきたその重要性は、シュロモ・アヴィネリ (『ヘーゲルの近代国家論』、ケンブリッジ、1972年)によって、今やアングロサクソン系の研究者にも明らかになったのである(翻訳者T.M. ノックスによる序文より)(→「ポータル:倫理的生活の体系」)。
☆倫理的生活
| System of Ethical Life 3. Ethical Life The foregoing levels incorporate the totality of particularity in both its aspects, particularity as such and universality as an abstract unity. The former is the family, but it is a totality such that, while in it all the levels of nature are united, intuition is at the same time involved in a relation. The really objective intuition of one individual in another is afflicted with a difference; the intuition of the father in the wife, the child, and the servant is not an absolutely perfect equality; equality remains inward, unspoken, still unborn; there is an invincible aspect of involvement in nature in it.[32] In universality, however, freedom from relation, the cancellation of one side of the relation by the other, is what matters most, and the cancellation is only rational as the absolute concept, in so far as it proceeds to this negativity. But at none of the previous levels does absolute nature occur in a spiritual shape; and for this reason it is also not present as ethical life; not even the family, far less still the subordinate levels, least of all the negative, is ethical. Ethical life must be the absolute identity of intelligence, with complete annihilation of the particularity and relative identity which is all that the natural relation is capable of; or the absolute identity of nature must be taken up into the unity of the absolute concept and be present in the form of this unity, a clear and also absolutely rich being, an imperfect self-objectification and intuition of the individual in the alien individual, and so the supersession of natural determinacy and formation, complete indifference of self-enjoyment. Only in this way is the infinite concept strictly one with the essence of the individual, and he is present in his form as true intelligence. He is truly infinite, for all his specific determinacy is annulled, and his objectivity is not apprehended by an artificial independent consciousness, nor yet by an intellectual intuition in which empirical intuition is superseded. Intellectual intuition is alone realised by and in ethical life; the eyes of the spirit and the eyes of the body completely coincide. In the course of nature the husband sees flesh of his flesh in the wife, but in ethical life alone does he see the spirit of his spirit in and through the ethical order. Accordingly ethical life is characterised by the fact that the living individual, as life, is equal with the absolute concept, that his empirical consciousness is one with the absolute consciousness and the latter is itself empirical consciousness, i.e., an intuition distinguishable from itself, but in such a way that this distinction is throughout something superficial and ideal, and subjective being is null in reality and in this distinction. This complete equalisation is only possible through intelligence or the absolute concept, in accordance with which the living being is made the opposite of itself, i.e., an object, and this object itself is made absolute life and the absolute identity of the one and the many, not put like every other empirical intuition under a relation, made the servant of necessity, and posited as something restricted, with infinity outside itself. Thus in ethical life the individual exists in an eternal mode; his empirical being and doing is something downright universal; for it is not his individual aspect which acts but the universal absolute spirit in him. Philosophy’s view of the world and necessity, according to which all things are in God and there is nothing singular, is perfectly realised in the eyes of the empirical consciousness, since that singularity of action or thought or being has its essence and meaning simply and solely in the whole. In so far as the ground of the singular is thought out, it is purely and simply this whole that is thought, and the individual does not know or imagine anything else. The empirical consciousness which is not ethical consists in inserting into the unity of universal and particular, where the former is the ground, some other singular thing between them as the ground. Here in ethical life, on the other hand, absolute identity, which previously was natural and something inner, has emerged into consciousness. But the intuition [individualisation] of this Idea of ethical life, the form in which it appears in its particular aspect, is the people. The identity of this intuition with the Idea must be understood — viz., in the people the connection of a mass of individuals with one another is established generally and formally. A people is not a disconnected mass, nor a mere plurality. Not the former: a mass as such does not establish the connection present in ethical life, i.e., the domination of all by a universal which would have reality in their eyes, be one with them, and have dominion and power over them, and, so far as they proposed to be single individuals, would be identical with them in either a friendly or an hostile way; on the contrary, the mass is absolute singularity, and the concept of the mass, since they are one, is their abstraction alien to them and outside them. Also not the latter, not a mere plurality, for the universality in which they are one is absolute indifference. In a plurality, however, this absolute indifference is not established; on the contrary, plurality is not the absolute many, or the display of all differences; and it is only through this “allness” that indifference can display itself as real and be a universal indifference. Since the people is a living indifference, and all natural difference is nullified, the individual intuits himself as himself in every other individual; he reaches supreme subject-objectivity; and this identity of all is just for this reason not an abstract one, not an equality of citizenship, but an absolute one and one that is intuited, displaying itself in empirical consciousness, in the consciousness of the particular. The universal, the spirit, is in each man and for the apprehension of each man, even so far as he is a single individual. At the same time this intuition and oneness is immediate, the intuition is not something other than thought; it is not symbolical. Between the Idea and reality there is no particularity which would first have to be destroyed by thinking, would not be already in and by itself equal to the universal. On the contrary the particular, the individual, is as a particular consciousness plainly equal to the universal, and this universality which has flatly united the particular with itself is the divinity of the people, and this universal, intuited in the ideal form of particularity, is the God of the people. He is an ideal way of intuiting it. Consciousness is, the infinite, the absolute concept, in the form of unity, but in empirical consciousness the concept is posited only as relation: the opposites united in the concept are, and so are opposed and their unity is as such a hidden one; it appears in both as quantity, i.e., under the form of being possibly parted (in one consciousness) and the actuality of this “being parted” is precisely opposition. But in ethical life this separation is in the eyes of empirical consciousness itself an ideal determinacy. Such a consciousness recognises in its opposite, i.e., its object, absolutely the same thing that the object is, and it intuits this sameness. This intuition is absolute because it is purely objective; in it all singular being and feeling is extinguished, and it is intuition because it is within consciousness. Its content is absolute because this content is the eternal, freed from everything subjective. The antitheses of the eternal, appearance and the empirical, fall so completely within absolute intuition itself that they display themselves as only child’s play. All connection with need and destruction is superseded, and the sphere of practice which began with the destruction of the object has passed over into its counterpart, into the destruction of what is subjective, so that what is objective is the absolute identity of both. This totality must be treated according to the moments of its Idea and therefore: first, at rest[33] as the constitution of the state, secondly, its movement i.e., the government; first, the Idea as intuition, secondly, the Idea according to relation, but in such a way that now the essence, the totality itself, is absolute identity of intuition and concept. And the form under which this identity appears is something superficial throughout. The extremes of the relation are simply the totality itself, not abstractions which would exist only through relation. |
倫理的生活の体系 3. 倫理的生活 前述の各段階は、特殊性の両側面、すなわち特殊性そのものと抽象的統一としての普遍性の両方を包含している。前者は家族であるが、それは自然のあらゆる段 階が統合されている総体であると同時に、直観が関係性の中に巻き込まれている総体である。ある個人が他者の中に持つ真に客観的な直観は差異に苦しむ。父が 妻や子や使用人の中に持つ直観は絶対的に完全な平等ではない。平等は内面的なまま、語られず、未だ生まれぬままである。そこには自然の中に巻き込まれる不 可避的な側面がある。[32] しかし普遍性においては、関係からの解放、すなわち関係の一方の側面が他方によって相殺されることが最も重要であり、この相殺は絶対的概念としてのみ合理 的である。それはこの否定性へと至る限りにおいてのみ合理的である。 しかし、これまでのどの段階においても、絶対的な自然は精神的な形態で現れない。このため、それは倫理的な生活としても現れない。家族でさえ倫理的ではな い。ましてや下位の段階、特に否定的な段階はなおさらである。倫理的な生活とは、知性の絶対的な同一性でなければならない。自然的な関係が可能な全てであ る、特殊性と相対的な同一性を完全に消滅させるものでなければならない。あるいは自然の絶対同一性が絶対概念の統一に取り込まれ、この統一の形態において 現れねばならない。それは明晰にして絶対的に豊かな存在であり、個人が他者的な個人において不完全な自己客観化と直観をなすものであり、それゆえ自然的な 決定性と形成の超越、自己享楽の完全な無関心である。この方法によってのみ、無限の概念は厳密に個体の本質と一致し、真の知性としての形態で現れる。彼は 真に無限である。なぜなら、彼のあらゆる特定の決定性は無効化され、彼の客観性は人工的な独立意識によっても、経験的直観が超越された知的直観によっても 把握されないからである。知性的直観は倫理的生活によってのみ、またその中で実現される。精神の眼と身体の眼は完全に一致する。自然の過程において夫は妻 に己の肉を見るが、倫理的生活においてのみ彼は倫理的秩序において、またそれを通して己の精神の精神を見るのである。 したがって倫理的生活は、生ける個人が生命として絶対概念と等しいこと、その経験的意識が絶対意識と一つであり、後者自体が経験的意識、すなわち自己から 区別可能な直観であるが、この区別は常に表面的で観念的なものであり、主体性は現実においてまたこの区別において無であるという事実によって特徴づけられ る。この完全な等価性は、知性、すなわち絶対概念によってのみ可能となる。それによれば、生ける存在は自己の対極、すなわち対象へと転化され、この対象そ のものが絶対的生命、一と多の絶対的同一性となる。それは他のあらゆる経験的直観のように関係下に置かれず、必然性の僕とされず、制限されたものとして設 定されず、無限を自己の外に持つこともない。 したがって倫理的生活において、個人は永遠の様態で存在する。その経験的な存在と行為は純然たる普遍的なものである。なぜなら作用するのは個人の側面では なく、彼の中の普遍的絶対精神だからだ。万物は神の中にあり特異なものは何もないとする哲学的世界観と必然性は、経験的意識の眼には完全に実現されてい る。なぜなら行為や思考や存在の特異性は、その本質と意味を単にそして唯一、全体の中に持つからである。個別の根拠が思考される限り、思考されるのは純粋 にこの全体であり、個人は他に何も知らず想像もしない。倫理的でない経験的意識は、普遍と個別の統一において、前者を根拠とする間に、別の個別的なものを 根拠として挿入することにある。一方、倫理的生活においては、以前には自然で内的なものだった絶対的同一性が、意識へと現出している。 しかしこの倫理的生活の理念、すなわち個別の側面において現れる形態の直観[個別化]こそが、人民である。この直観と理念との同一性を理解すべきだ――す なわち人民においては、個々の集合体同士の結びつきが一般的かつ形式的に確立されるのである。人民は、ばらばらの塊でもなければ、単なる多数でもない。前 者ではない。塊そのものは、倫理的生活に存在する結びつき、すなわち、彼らの目には現実として映り、彼らと一体となり、彼らに対して支配と権力を持ち、彼 らが単一の個人として存在しようとする限り、友好的にせよ敵対的にせよ彼らと同一となる普遍的なものによる支配を確立しない。むしろ大衆は絶対的な単一性 であり、彼らが一つである以上、大衆という概念は彼らにとって異質な抽象概念であり、彼らの外側に存在する。また後者、単なる多数性でもない。なぜなら彼 らが一つとなる普遍性は絶対的な無関心だからだ。しかし、複数性においては、この絶対的な無関心は確立されない。むしろ、複数性は絶対的な多数でも、あら ゆる差異の顕現でもない。そして、この「全体性」を通じてのみ、無関心は現実として現れ、普遍的な無関心となり得るのだ。 人民は生ける無関心であり、あらゆる自然的差異は無効化される。ゆえに個人はあらゆる他者において自らを直観する。彼は至高の主観的客観性に到達する。そ してこの万人の同一性は、まさにこのゆえに抽象的なものではなく、市民的平等でもなく、絶対的なものであり、直観されるものであり、経験的意識、個別性の 意識において自らを顕現する。普遍、すなわち精神は、各人の内にある。各人が単一の個人である限りにおいてさえ、各人の把握のために存在する。同時にこの 直観と一体性は直接的である。直観は思考とは別のものではない。象徴的ではない。理念と現実の間に、思考によってまず破壊されねばならない個別主義は存在 しない。個別主義はすでにそれ自体において普遍と同等なのである。むしろ個別性、個体は、個別的意識として明らかに普遍性に等しい。そしてこの個別性を自 らと完全に結びつけた普遍性こそが、人民の神性である。この普遍性は、個別性の理想的形式において直観されるものであり、人民の神である。それは理想的な 直観の方法である。 意識は、無限なるもの、絶対的概念であり、統一の形態において存在する。しかし経験的意識においては、概念は関係としてのみ置かれる。概念において結合さ れた対立物は存在し、それゆえに対立し、その統一は隠されたものである。それは両者において量として、すなわち(一つの意識において)分割され得る存在の 形態として現れ、この「分割され得る存在」の現実性はまさに対立である。しかし倫理的生活においては、この分離は経験的意識自身の目には理想的な確定性と して映る。この種の意識は、その対立物、すなわち対象において、対象が絶対的に同一の事物であることを認識し、この同一性を直観する。 この直観が絶対的なのは、それが純粋に客観的だからである。そこではあらゆる個別的存在と感情が消滅し、意識内に存在するゆえに直観なのである。その内容 は絶対的である。なぜならこの内容は、あらゆる主観性から解放された永遠なるものだからだ。永遠なるものの対立物である表象と経験は、絶対的直観そのもの の中に完全に収まるため、単なる子供遊びとして現れる。必要と破壊とのあらゆる結びつきは超越され、対象の破壊から始まった実践の領域は、その対極である 主観性の破壊へと移行した。こうして客観的なものは、両者の絶対的同一性となる。 この全体性は、その理念の諸段階に従って扱われねばならない。すなわち第一に、静止状態[33]としての国家の構成、第二にその運動、すなわち政府。第一 に理念としての直観、第二に関係としての理念。ただし、今や本質、すなわち全体性そのものが、直観と概念の絶対的同一性であるという形で。そしてこの同一 性が現れる形態は、終始表層的なものに過ぎない。関係の極点は、単に全体性そのものであり、関係によってのみ存在する抽象物ではない。 |
| First Section[34]: The Constitution of the State The people as an organic totality is the absolute identity of all the specific characteristics of practical and ethical life. The moments of this totality are, as such, the form of (i) identity or indifference, (ii) difference, and finally (iii) absolute living indifference; and every one of these moments is not an abstraction but a reality. I. Ethical Life as System, at rest. The concept of ethical life has been put into that life’s objectivity, into the annulling of singularity. This annihilation of the subjective in the objective, the absolute assumption of the particular into the universal is (a) Intuition: Here the universal is not something formal, opposed to consciousness and subjectivity or individual life, but simply one with that life in intuition. In every shape and expression of ethical life the antithesis of positive and negative is annulled by their integration. But the separation of particular and universal would seriously appear as a slavery of the particular, as something in subjection to the ethical law, and further as the possibility of a different subjection. In ethical life there would be no necessity. The grief would not endure, for it would not be intuited in its objectivity, would not be detached; and the ethical action would be an accident of judgment, for with separation the possibility of another consciousness is established.[35] (b) As this living and independent spirit, which like a Briareus[36] appears with myriads of eyes, arms, and other limbs, each of which is an absolute individual, this ethical life is something absolutely universal, and in relation to the individual each part of this universality and each thing belonging to it appears as an object, as an aim and end. The object as such or as it enters his consciousness is something ideal for the individual; but “it enters his consciousness” means nothing but “it is posited as individual.” But it is different if the individual subsumes absolute ethical life under himself and it appears in him as his individuality. Here, and generally, it is not by any means meant that the will, caprice, specific things posited by the individual have dominated ethical life so that they have come to command it and make it negative as an enemy and fate. On the contrary dominion is wholly and entirely the external form of subjectivity under which ethical life appears, though without its essence being affected thereby. This appearance of ethical life is the ethical life of the single individual, or the virtues. Because the individual is single, the negative, possibility, specific determinacy, so too the virtues in their determinate character are something negative, possibilities of the universal. Here, then, there is established the difference between morality and natural law; it is not as if they were sundered, the former being excluded from the latter, for on the contrary the subject matter of morality is completely contained in natural law; the virtues appear in the absolute ethical order, but only in their evanescence. Now ethical life is (a) as absolute ethical life: not the sum but the indifference of all virtues. It does not appear as love for country and people and law, but as absolute life in one’s country and for the people. It is the absolute truth, for untruth lies only in the fixation of something specific; but in the eternity of the people all individuality is superseded. It is the absolute process of formation (Bildung), for in what is eternal lies the real and empirical destruction of all specific things, and the exchange of all of them. It is absolute unselfishness, for in what is eternal nothing is one’s own. Like every one of its moments, it is supreme freedom and beauty, for the real being and configuration of the eternal is its beauty. It is serene and without suffering, for in it all difference and all grief are cancelled. It is the Divine, absolute, real, existent being, and unveiled, yet not in such a way that it would first have to be lifted up into the ideality of divinity and first extracted from appearance and empirical intuition; on the contrary absolute ethical life is absolute intuition immediately. But the movement of this absolute ethical life (as it is in the absolute concept) runs through all the virtues, but is fixed in none. In its movement ethical life enters difference and cancels it; its appearance is the transition from subjective to objective and the cancellation of this antithesis. This activity of production does not look to a product but shatters it directly and makes the emptiness of specific things emerge. The above-mentioned difference in its appearance is specific determinacy and this is posited as something to be negatived. But this, which is to be negatived, must itself be a living totality. What is ethical must itself intuit its vitality in its difference, and it must do so here in such a way that the essence of the life standing over against it is posited as alien and to be negatived. It is otherwise in education, where the negation, subjectivity, is only the superficial aspect of the child. A difference of this sort is the enemy, and this difference, posited in its ethical bearing, exists at the same time as its counterpart, the opposite of the being of its antithesis, i.e., as the nullity of the enemy, and this nullity, commensurate on both sides, is the peril of battle. For ethical life this enemy can only be an enemy of the people and itself only a people. Because single individuality comes on the scene here, it is for the people that the single individual abandons himself to the danger of death. But apart from this negative aspect there also appears the positive aspect of difference, and likewise as ethical life, but as ethical life in the single individual, or as the virtues. Courage is the indifference of the virtues; it is virtue as negativity, or virtue in a determinate form, but in the absoluteness of determinacy. It is thus virtue in itself, but formal virtue, since every other virtue is only one virtue. In the sphere of difference, specific determinacy appears as a multiplicity, and therefore there appears in it the whole garland of virtues. In war as the manifestation of the negative, and the multiple and its annihilation, there thus enters the multiplicity of specific relations, and in them of virtues. Those relations appear as what they are, established by empirical necessity, and therefore they quickly vanish again, and with them the existence of the virtues, which, having this speedy chasing of one another, are without any relation to a specific totality (the whole situation of a citizen) and so are just as much vices as virtues.[37] The exigency of war brings about supreme austerity and so supreme poverty and the appearance first of avarice and then of enjoyment, which is just debauchery, because it can have no thought for tomorrow or the whole of life and livelihood. Frugality and generosity become avarice and supreme hard-heartedness against self and others (when supreme misery demands this restriction) — and then prodigality; for property is thrown to the winds since it cannot remain secure, and its disbursement is wholly disproportionate to the use and need of self and others. Likewise the reality which has not been completely taken up into indifference is the immoral aspect of the specific situation, but what is present is existence in its negativity or the highest degree of annihilation. It is the same with labour as it was with the ethical aspect of the virtues. The exigency of war demands supreme bodily exertions and a complete formal universal unity of the spirit in mechanical labour as well as supreme subjection to an entirely external obedience. Just as the virtues are without outer and inner hypocrisy — for in the case of the former its appearance and externality would be created by the caprice of the subject, who, however, would have had something different, in his own mind and intention; this, however, cannot happen here because the ethical is the essence, the inner mind of the subject; neither can the inner hypocrisy occur, because it knows its ethical substance and through this consciousness maintains its subjectivity and is morality; (margin: in the former case there is an outward show of it, the fact that duty illuminates itself before the eyes of the individual himself) — so too, labour is without an aim, without need, and without a bearing on practical feeling, without subjectivity; neither having done one’s duty, in the latter an inner one, the consciousness has it a bearing on possession and acquisition, but with itself its aim and its product cease too. This war is not one of families against families but of peoples against peoples, and therefore hatred itself is undifferentiated, free from all personalities. Death proceeds from and afflicts something universal and is devoid of the wrath which is sometimes created and annulled again. Firearms are the invention of a death that is universal, indifferent, and non-personal; and the moving force is national honour, not the injury of a single individual. But the injury which occasions the war comes entirely home to every individual owing to the identity of the national honour in everyone. (b) Relative ethical life. This bears on relations and is not freely organised and moved in them but, while allowing the specific determinacy in them to subsist, brings it into equality with its opposite, i.e., into a superficial and partial determinacy which is only conceptual. Thus this form of ethical life fashions legal right and is honesty. Where it acts or is real, it clings to the right that his own shall accrue to everyone and, at that, not in accordance with written laws; on the contrary it takes the whole of the case into account and pronounces according to equity if the legal right has not been decided, and otherwise it must keep to legal right. But in equity it mitigates the objectivity of legal right according to pressing needs, whether it be a matter of empirical necessitous circumstances, or of an ignorance that is called pardonable, or of a subjective trust. The totality of relative ethical life is the empirical existence of the single individual, and the maintenance of that existence is left to devolve upon himself and others. Honesty cares for the family in accordance with the class to which the family belongs, and so for fellow citizens; it relieves the necessities of single individuals and is enraged about a bad action. The universal and absolute aspect of ethical life and the manner in which this aspect should have been present in its reality, and in which reality should have been subjugated, is for honesty a thought. Honesty’s highest flight is to have many sorts of thoughts about this, but at the same time its rationality is that it sees how the empirical situation would be changed, and this situation lies too near its heart for it to let anything happen to it. Thus its rationality is to perceive that absolute ethical life must remain a thought. In connection with the negative and with sacrifice, honesty offers from its acquisitions (a) to the people, for universal ends according to a universal principle, in taxes according to an equality of justice, and (b) in particular cases, for the poor and the suffering. But it may not sacrifice either a just man’s entire possessions or his life, since individuality is a fixture in it, and so person and life are not only something infinite but something absolute. Thus it cannot be courageous, neither may it go through the whole series of virtues or organise itself purely momentarily as a virtue. For purely momentary virtue is itself without aim and without connection with a totality other than the one it has in itself. The empirical totality of existence sets determinate limits to unselfishness and sacrifice and must stay under the domination of the understanding. (g) Trust lies in the identity of the first (a) and the difference of the second (b), so that that identity of absolute ethical life is a veiled intuition, not at the same time taken up into the concept and developed outwardly, and therefore this identity in the form of its intellectuality lies outside it. For intuition’s solidity and compactness, which lacks the knowledge and form of the understanding and so also the active use of it, precisely the same intuition, when developed, is a might against which that solidity is different but also mistrustful, because singular individuality, in which that might comes in question, may seem to destroy the whole and cannot illumine for it the identity of absolute intuition and form as a singular middle term. It is not by understanding — for from that quarter it fears, as is only fair, to be betrayed — that it is to be set in movement but by the entirety of trust and necessity, by an external impulse and so one affecting the whole. Just as trust’s ethical intuition is elemental, so is its labour. This labour does not issue from the understanding, nor is it differently parcelled out in the way characteristic of honesty, but is entire and solid. It does not proceed to the destruction and death of the object but lets utility act and produce naturally. So too, without knowledge of the legal right, trust’s property is preserved for it, and any dispute is composed by passion and discussion. This trust is after all capable of courage because it relies on something eternal. In the real absolute totality of ethical life these three forms of it [i.e., the three social classes] must also be real. Each must be organised independently, be an individual and assume a shape of its own; for a confusion of them is the formlessness of the naturally ethical and the absence of wisdom. Of course since each is organised, it is for that very reason a totality and carries in itself the other levels of its form, but conformably to themselves and unorganised, as they have already been exhibited in each case according to their concepts. Individualisation, vital life, is impossible without specification or dispersal. Each principle and level must unquestionably reach its own concept, because each is real and must strive after its own self-satisfaction and independence. In its concept or in its own indifference it has completely taken into itself its relative identity with the other’s concept and has thus formed itself; to this self-formation everything which is at one level must press on; for infinity is strictly one with reality, although within infinity there is the difference of levels. The fact that physical nature in its own way expresses the levels in their pure shape and makes each of them independently alive appears more readily acceptable only because, according to the principle of the multiplicity of nature, each single thing should be something incomplete. while in ethical life each must be something absolutely complete; and each makes for itself a plain claim to absolute real totality, because the singularity of each one is the absolute totality, or the pure concept, and so the negation of all specific determinacies. But this absolute concept and negation is precisely the highest abstraction and immediately the negative. The positive is the unity of this form with the essence, and this is the expansion of ethical life into a system of levels (and of nature), and the level of ethical life, self-organised, can only be organised in individuals as its material. The individual as such is not the true but only the formal absolute: the truth is the system of ethical life. Therefore this system cannot be thought as if it exists in purity in the individual, i.e., as developed, completely distributing itself in its levels; for its essence is ethereal, elemental, pure, having subordinated unities to itself and dissolved them out of their inflexibility into absolute malleability. The singularity of the individual is not the first thing, but the life of ethical nature, divinity, and for the essence of divinity the singularised individual is too poor, i.e., too poor to comprise divinity’s nature in its entire reality. As formal indifference it can display all features momentarily, but as formal indifference it is the negative, time, and destroys them again. But the ethical reality must apprehend itself as nature, as the persistence of all its levels, and each of them in its living shape; it must be one with necessity and persist as relative identity, but this necessity has no reality except in so far as each level has reality, i.e., is a totality. The levels of ethical life as it displays itself in this reality within the perfect totality are the classes, and the principle of each one of them is the specific form of ethical life as expounded above. Thus there is a class of absolute and free ethical life, a class of honesty, and a class of unfree or natural ethical life. According to the true concept of a class, the concept is not a universality which lies outside it and is an ens nationis; on the contrary universality is real in the class. The class knows itself in its equality and constitutes itself as a universal against a universal, and the relation between the different classes is not a relation between single individuals. On the contrary by belonging to a class the single individual is something universal and so a true individual, and a person. Consequently the class of slaves, for example, is not a class, for it is only formally a universal. The slave is related as a single individual to his master. (a) The absolute class [i.e., the military nobility] has absolute and pure ethical life as its principle, and in the above exposition of that life it has itself been set forth, for its real being and its Idea are simply one, because the Idea is absolute ethical life. But in the real being of absolute ethical life we have only to consider how this class behaves in respect to the persistence of difference and how its practical being can be differentiated in it. In the Idea itself, as was explained above, the life of practice is purely and simply negative, and contained in its reality are the relations and the virtues connected with them which are self-motivated and committed to empirical contingency. But, for this class as the reality of ethical life, the need and use of things is an absolute necessity which dogs it, yet one which is not allowed to dog it in its above-described form, in its separatedness; for the work of this class may only be universal, while work to supply a need would be singular. The satisfaction of a need is certainly itself just something particular, but here nothing is to occur in the shape of the satisfaction of a need or the particular character of something purely practical; for this satisfaction is as such pure destruction of the object, absolute negation, not a confusion of the ideal with the object or the prolongation of the consequences of this confusion, not a partial putting of intelligence into the object, nothing practical, not a development of something lifeless, the result of which would yet be destruction. Instead the work of this class can be nothing but the waging of war or training for this work; for its immediate activity in the people is not work but something organic in itself and absolute. The labour of this class can have no relation to its needs, but its needs cannot be satisfied without labour, and consequently it is necessary for this labour to be done by the other classes and for things to be transmitted to it which have been prepared and manufactured for it. All that is left to it is direct consumption of them in enjoying them. But this relation of this class to the other two is a relation in existing reality that has to be taken up into the indifference of the ethical totality in the only way possible. The way here is equality. And since the essence of the relation is the utility which the other classes have for the first one, so that they provide it with its necessities and it makes the goods and gains of the others its own, it must in turn, in accordance with equality, be useful to the others. But this it is first in the highest way and then, too, in their way. In its content the tie of mutual utility is partly one of difference on both sides, whereby the first class is the absolute power over the others, and partly one of equality, whereby it is negative and so immanent for them in the way they are immanent for it. The former utility is that the first class is the absolute and real ethical shape and so, for the other classes, the model of the self-moving and self-existent Absolute, the supreme real intuition which ethical nature demands. These classes, owing to their nature, do not get beyond this intuition. They are not in the sphere of the infinite concept whereby this intuition would only be posited for their consciousness as something external, but strictly [i.e., in their conceptual knowledge] it would be their own absolute moving spirit overcoming all their differences and determinacies. Their ethical nature’s achievement of this intuition, this utility, is provided to them by the first class. Since this, displayed in the shape of something objective, is their absolute inner essence, it remains for them something hidden, not united with their individuality and consciousness. The latter utility, according with the mode of the other classes, lies in the negative [i.e., in labour], and on the part of the first class labour is established likewise, but it is the absolutely indifferent labour of government and courage. In its bearing for the other classes, or to them, this labour is the security of their property and possessions, and the absolute security is that they are excused from courage, or at least the second class is. (b) The class of honesty [the bourgeoisie] lies in work for needs, in possessions, gain, and property. Since the unity involved in these relations is something purely ideal, an ens rationis, on account of the fixity of difference, it acquires reality only in the people. It is the abstract empty might in general, without wisdom[38] its content is settled by the contingency of real things and by the caprice involved in them, in gain, contracts, etc. The universal and legal element in these relations becomes a real physical control against the particularity which intends to be negative towards it. This immersion in possession and particularity ceases here to be slavery to absolute indifference; it is, as far as possible undifferentiated, or formal indifference, [i.e., what it is] to be a person, is reflected in the people, and the possessor does not lapse, owing to his difference, with his whole being and so does not lapse into personal dependence; on the contrary, his negative indifference is posited as something real, and he is thus a burgher, a bourgeois, and is recognised as something universal. In the first class all the particular character in individuality is nullified, and thus it is related as a universal to the second class, which in this way is itself determined similarly, but, owing to the fixity of its possession, it is only something formally universal, an absolute singular. Since the labour of this class is likewise universal, the result is that, for the sake of the satisfaction of physical need a system of universal dependence is set up because labour here affects the totality of need, not materially but only conceptually. The value and price of labour and its product is determined by the universal system of all needs, and the capricious element in the value, grounded as it is on the particular needs of others, as well as the uncertainty whether a surplus is necessary for others, is completely cancelled. — The universality of labour or the indifference of all labour is posited as a middle term with which all labour is compared and into which each single piece of labour can be directly converted; this middle term, posited as something real, is money. So too the active universal exchange, the activity which adjusts particular need to particular surplus, is the commercial class, the highest point of universality in the exchange of gain. What it produces is to take over the surplus available in particular activities and thereby make it into a universal, and what it exchanges is likewise money or the universal. Where barter or, in general, the transfer of property to another is ideal — partly owing to the universally known possession of the one, a universal recognition hindering the transfer (because property and its certainty rests in part on the transfer), partly because the two sides of the simultaneity of the barter become empirically separate — that ideality is posited in reality (by the fact that the whole might of the state hangs on it) as if that had actually happened which was to happen, and the empirical appearance of the exchange did not matter. just as the empirical appearance of possession or non-possession does not matter either, and what is important is whether the inward absolute tie between the individual and the thing is close or distant, i.e., whether the thing is his property or not. Both together constitute justice in connection with property in things. Personal injury was infinite at the natural stage; it was a matter of honour and the whole person; in the system of reality it becomes this specific abstraction of injury; for since the indifference of the individual is here absolute indifference, i.e., the people (which, however, cannot be injured by civil wrong), nothing is left but precisely the specific and particular character of the injury. In a citizen as such the universal is as little injured, and is so little to be revenged or in jeopardy, that nothing remains but to liberate the particular by superseding it, i.e., the injurer is subjected to the very same treatment. Revenge is transformed in this way into punishment, for revenge is indeterminate and belongs to honour and the whole family. Here it is undertaken by the people, since in the place of the particular injured party there enters the abstract but real universality, not his living universality, the universality of the individual. But, for honesty, the living totality is the family, or a natural totality, and a situation of property and livelihood which is secured, so far as possible, for the empirical totality of its life as a whole and for the education of the children. This class is incapable either of a virtue or of courage because a virtue is a free individuality. Honesty lies in the universality of its class without individuality and, in the particularity of its relations, without freedom. The greatest height which this class can attain by its productive activity is (a) its contribution to the needs of the first class and (b) aid to the needy. Both are a partial negation of its principle, because (a) is labour for a universal according to the concept, while (b) is devoted to something particular according to an empirical necessitous case. The former universal sacrifice is without vitality, while the latter more living sort of sacrifice is without universality. So too the inner relation of the family is determined according to the concept. Whoever out of necessity binds himself to the head of the house does so, despite all the personal aspects of the bond of service, only as an absolute person by way of a contract and for a definite term. For since each member of the household is an absolute person, he should be able to attain a living totality and become a paterfamilias. This is precisely the relation when the bond is less personal and only for specific services and labour. (c) The class of crude ethical life is that of the peasantry. The shape that the levels of ethical life have for it is that it is certainly involved with physical needs; it falls likewise into the system of universal dependence, though in a more patriarchal way, and its labour and gain forms a greater and more comprehensive totality. The character of its labour is also not wholly intellectual, nor is it directly concerned with the preparation of something to meet a need; on the contrary it is more of a means, affecting the soil or an animal, something living. The peasant’s labour masters the organic potency of the living thing and so, determines it, though the thing produces itself by itself. The ethical life of this class is trust in the absolute class, in accord with the totality of the first class, which must have every relation and every influence. The crude ethical life of this third class can only consist in trust, or, when placed under compulsion, it is open to the parcelling out of its activity.[39] On account of its totality it is also capable of courage and in this labour and in the danger of death can be associated with the first class. |
第一節[34]:国家の構成 有機的総体としての人々は、実践的・倫理的生活のあらゆる特殊性の絶対的同一性である。この総体の諸局面は、それ自体として、(i)同一性あるいは無差別 性、(ii)差異性、そして最後に(iii)絶対的生きた無差別性という形態をとり、これらの局面はいずれも抽象ではなく現実である。 第一節 倫理的生活としての体系、静止状態 倫理的生活の概念は、その生活の客観性、すなわち特異性の消滅の中に置かれている。主観的なものを客観的なものの中に消滅させ、個別的なものを普遍的なものの中に絶対的に吸収するこの過程は (a) 直観:ここで普遍的なものは、意識や主体性、あるいは個別的な生活に対立する形式的なものではなく、単に直観においてその生活と一体である。倫理的生活の あらゆる形態と表現において、肯定と否定の対立は統合によって解消される。しかし個別と普遍の分離は、個別性の隷属として、倫理法則への服従として、さら に異なる服従の可能性として深刻に現れるだろう。倫理的生活には必然性など存在しない。悲しみは持続しない。なぜならそれは客観性において直観されず、分 離されないからだ。そして倫理的行為は判断の偶然となる。分離によって別の意識の可能性が確立されるからである。[35] (b) この生き生きとした独立した精神は、ブリアレイオス[36]のように無数の目や腕やその他の肢を備えて現れる。それらの各々は絶対的な個別者である。同様 に、この倫理的生活は絶対的に普遍的なものであり、個別者との関係において、この普遍性の各部分およびそれに属する各事物はいずれも対象として、目的およ び終点として現れる。対象そのもの、あるいは個人の意識に現れる対象は、個人にとっては理想的なものである。しかし「個人の意識に現れる」とは、単に「個 人として位置づけられる」ことを意味するに過ぎない。しかし個人が絶対的倫理的生活を自己の下に包含し、それが個人の個性として現れる場合は異なる。ここ で、そして一般に、個人の意志や気まぐれ、個人が設定した特定のものたちが倫理的生活を支配し、それを敵や運命として否定的に支配するようになったという 意味は決してない。むしろ支配とは、倫理的生活が現れる主体性の外部形態に他ならず、その本質は影響を受けない。この倫理的生活の現れこそが、単一の個人 の倫理的生活、すなわち徳である。個人が単一である以上、否定性、可能性、特定の決定性、同様に徳もその決定的性格において、普遍の可能性としての否定的 なものである。ここに道徳と自然法の差異が確立される。両者が分離し、前者が後者から排除されるわけではない。むしろ道徳の主題は自然法に完全に包含され ている。美徳は絶対的倫理秩序に現れるが、それは儚さの中でのみである。 さて倫理的生活とは (a) 絶対的倫理的生活として:諸美徳の総和ではなく、それらの無差別性である。それは祖国や人民や法への愛として現れるのではなく、祖国において、そして人民 のために生きる絶対的生命として現れる。それは絶対的真理である。なぜなら虚偽は特定の何ものかの固定化にのみ存在するが、人民の永遠性においてはあらゆ る個別性が超越されるからである。それは絶対的な形成過程である。永遠なるものには、あらゆる特定的事物の実体的・経験的破壊と、それらの相互交換が内在 するからだ。それは絶対的な無私である。永遠なるものにおいては、何一つとして己のものとはならないからだ。そのあらゆる瞬間と同様に、それは至高の自由 であり美である。永遠なるものの実在と形態こそが、その美だからだ。それは穏やかで苦悩のない。なぜならそこではあらゆる異なることと悲嘆が解消されるか らだ。それは神聖なる絶対的実在であり、覆いが取れている。しかしそれは、まず神性の観念性へと引き上げられ、表象や経験的直観から抽出されなければなら ないような覆いの取り方ではない。むしろ絶対的倫理的生活は、即座に絶対的直観なのである。 しかしこの絶対的倫理的生活の運動(絶対的概念におけるものとして)は、あらゆる徳を貫くが、いずれにも固定されない。その運動において倫理的生活は差異に入り込み、それを解消する。その現れは主観から客観への移行であり、この対立の解消である。 この生産の活動は、製品を求めず、直接にそれを打ち砕き、特定のものの虚無を浮き彫りにする。上述の差異はその表れにおいて特定の決定性であり、これは否 定されるべきものとして設定される。しかし、この否定されるべきものは、それ自体が生きている全体でなければならない。倫理的なものは、その差異において 自らの生命力を直観しなければならず、ここでそうするとき、対峙する生命の本質が異質なものとして、また否定されるべきものとして設定される。教育におい ては事情が異なる。そこでは否定、主体性は、子供の表面的な側面に過ぎない。この種の差異は敵であり、倫理的意味において設定されたこの差異は、同時にそ の対極、すなわちその対立概念の存在の反対物、つまり敵の無として存在する。そしてこの無は、双方に等しく存在し、戦いの危険性となる。倫理的生活におい て、この敵は人民の敵でしかありえず、それ自体が人民でしかない。ここに単一の個性が登場するからこそ、単一の個人が死の危険に身を投じるのは人民のため である。 しかしこの否定的な側面とは別に、差異の肯定的な側面も現れる。これもまた倫理的生活として現れるが、単一の個人における倫理的生活、すなわち美徳として 現れるのだ。勇気は美徳の無関心さである。それは否定性としての美徳、あるいは決定された形態における美徳であるが、決定性の絶対性の中にある。したがっ てそれは美徳そのものだが、形式的な美徳である。他のあらゆる美徳はただ一つの美徳に過ぎないからだ。差異の領域においては、特定の決定性が多様性として 現れる。ゆえにそこには美徳の全冠が現れる。否定的現れとしての戦争、そして多様性とその消滅においては、特定の関係の多様性、そしてそれらにおける美徳 の多様性が入り込むのである。それらの関係は、経験的必然性によって確立されたものとして現れる。ゆえにそれらはすぐに再び消え去り、それに伴って美徳の 存在も消える。美徳は互いに速やかに追いかけ合う性質を持つため、特定の全体性(市民の全状況)とは何の関係もなく、美徳であると同時に悪徳でもあるの だ。[37] 戦争の緊急性は究極の倹約をもたらし、それゆえ究極の貧困と、まず貪欲、次いで享楽の出現をもたらす。この享楽は単なる放蕩に過ぎない。なぜなら明日や人 生全体、生計の全体を顧みる余裕などないからだ。倹約と寛大さは、究極の貧困がこれを強いる時には、自己と他者に対する貪欲と究極の冷酷さへと変質する。 そして放蕩へと転じる。財産は安全に保持できないため風前の灯となり、その支出は自己と他者の使用や必要性に全く見合わなくなるからだ。同様に、無関心の 中に完全に吸収されなかった現実とは、特定の状況における不道徳な側面である。しかし現存しているのは、否定性における存在、あるいは最高の消滅の度合い である。 労働についても、美徳の倫理的側面と同様である。戦争の緊急事態は、機械的労働における最高の身体的努力と、精神の完全な形式的普遍的統一、そして完全に 外的な服従への最高の服従を要求する。美徳が外面的・内面的偽善を伴わないのと同様である――前者の場合、その表層性と外在性は主体の気まぐれによって創 出されるが、主体は自らの心と意図において異なるものを保持していたはずだからだ。しかしここでは、倫理的であることが主体の本質、内なる精神であるた め、このようなことは起こりえない。また内なる偽善も起こりえない。なぜなら主体は自らの倫理的本質を知り、この自覚を通じて主体性を維持し、道徳そのも のだからである。(境界:前者の場合、義務が個人自身の眼前に自らを照らし出すという、外向きの見せかけがある)同様に、労働は目的も必要性も持たず、実 践的感情への関わりも、主体性も持たない。後者の場合、内的な義務を果たした後、意識は所有や獲得に関わるが、それ自体と共にその目的と産物もまた消滅す る。 この戦争は、家族対家族ではなく、人民対人民の戦争である。したがって、憎しみそのものは、あらゆる個人的なものを超越した、無差別なものである。死は、 普遍的なものから生じ、普遍的なものを苦しめるものであり、時には生じ、また消滅する怒りを伴わない。銃器は、普遍的で、無差別で、非個人的な死を発明し たものである。そして、その原動力は、個人の傷ではなく、ナショナリズムである。しかし、戦争を引き起こす傷は、すべての個人に国民の名誉が共通であるた めに、完全にすべての個人に及ぶ。 (b) 相対的な倫理的生活。これは関係に依存しており、その関係の中で自由に組織化され、動かされるわけではないが、その関係における特定の決定性を存続させな がら、それをその反対側、すなわち、概念的なものに過ぎない表面的かつ部分的な決定性と同等に持ち込む。したがってこの倫理的生活形態は法的権利を形成 し、誠実さである。それが作用する、あるいは現実となる場合、それは書かれた法律に従うのではなく、各人に自らの権利が帰属すべきだという点に固執する。 むしろ、法的権利が確定していない場合には事案全体を考慮し衡平法に従って判断し、そうでない場合には法的権利に固執しなければならない。しかし衡平にお いて、それは差し迫った必要性に応じて法的権利の客観性を緩和する。それが経験的な窮状であろうと、許容されるべき無知であろうと、主観的な信頼であろう と。相対的な倫理的生活の全体性は、単一の個人の経験的存在であり、その存在の維持は彼自身と他者に委ねられる。 誠実さは家族が属する階級に応じて家族を顧み、同様に同胞市民をも顧みる。それは個人の窮状を救済し、悪行には激怒する。倫理的生活の普遍的・絶対的側 面、そしてこの側面が現実において如何に存在すべきであったか、また現実が如何に服従すべきであったか――これらは誠実さにとっての思索である。誠実さの 最高の飛翔は、これについて様々な思考を持つことにある。しかし同時に、その合理性は経験的状況が如何に変化するかを認識する点にあり、この状況は誠実さ の核心に近すぎるため、何事も許容できない。故にその合理性は、絶対的倫理的生活が思考の域を出ないことを悟ることにある。 否定と犠牲に関連して、誠実さは自らの獲得物から(a)普遍的原理に基づく普遍的目的のために、正義の平等に基づく課税として人民に提供し、(b)特定の 事例においては貧者や苦悩する者へ提供する。しかしそれは、正義ある者の全財産もその生命も犠牲にすることはできない。なぜなら個性はその中に固定されて いるからであり、故に人格と生命は無限なるもののみならず絶対なるものだからだ。したがって誠実さは勇気を持つことも、美徳の全系列を貫くことも、純粋に 瞬間的な美徳として組織化することもできない。純粋に瞬間的な美徳はそれ自体目的を持たず、自己内に持つもの以外の全体性との繋がりも持たないからだ。経 験的存在の全体性は無私と犠牲に確定的な限界を設け、理解の支配下に留まらねばならない。 (g) 信頼は、第一の(a)の同一性と第二の(b)の差異に根ざす。ゆえに絶対的倫理的生活の同一性は、概念に取り込まれ外的に展開されることのない、覆い隠さ れた直観である。したがってこの同一性は、その知性的な形態において、概念の外側に位置する。直観の堅固さと凝縮性は、理解の知識と形式、ひいてはその能 動的運用を欠いている。しかし、まさにその直観が展開されるとき、それは力となる。その力に対して、堅固さは異なるが同時に不信を抱く。なぜなら、その力 が問われる特異的個別性は、全体を破壊するかに見え、絶対的直観と形式の同一性を、特異的中間項として照らし出すことができないからである。それは理解に よって動かされるのではない。理解の領域からは、当然のことながら裏切られることを恐れているからだ。むしろ信頼と必然性の全体性によって、外部からの衝 動によって、つまり全体に影響を及ぼすものによって動かされるのだ。 信頼の倫理的直観が根源的であるように、その労働もまた根源的だ。この労働は理解から生じるものではなく、誠実さに特徴的な方法で細分化されることもない。それは全体的で確固たるものだ。対象の破壊や死へと進むのではなく、有用性が自然に作用し生み出すことを許す。 同様に、法的権利の知識がなくても、信頼の財産は信頼のために守られ、いかなる争いも情熱と議論によって解決される。この信頼は結局のところ、永遠なるものに依拠するゆえに勇気を備えている。 倫理的生活の真の絶対的全体性において、これら三つの形態[すなわち三つの社会階級]もまた現実的でなければならない。それぞれが独立して組織化され、個 として独自の形を帯びる必要がある。なぜなら、それらの混同は自然的倫理の無秩序さであり、知恵の欠如だからだ。もちろん、それぞれが組織化されている以 上、それ自体が総体であり、自らの形態における他のレベルを内包している。しかしそれは、それぞれの概念に従って既に示された通り、それ自体に適合した形 で、かつ組織化されていない状態である。 個別化、すなわち生命的な営みは、特定化や分散なしには不可能である。各原理とレベルは疑いなく自らの概念に到達せねばならない。なぜなら各々は実在し、 自らの自己充足と独立を追求せねばならないからだ。その概念において、あるいは自らの無関心において、それは他者の概念との相対的同一性を完全に内包し、 こうして自らを形成する。この自己形成へ、同一レベルにあるあらゆるものは突き進まねばならない。無限は厳密に現実と一体であるが、無限の内にはレベルの 差異が存在するからだ。 物理的自然が独自の方法で各レベルを純粋な形で表現し、それぞれを独立して生き生きとさせるという事実は、自然の多様性の原理によれば、個々のものは不完 全なものであるべきだという理由だけで、より受け入れやすいように見える。一方、倫理的生活においては、各々が絶対的に完全なものでなければならない。そ して各々は、絶対的な実在的総体としての明白な主張を自らに課す。なぜなら各々の特異性は絶対的総体、すなわち純粋な概念であり、それゆえあらゆる特定の 決定性の否定だからだ。しかしこの絶対的概念と否定こそが、まさに最高の抽象であり、即座に否定的なものとなる。肯定的なものは、この形式と本質との統一 であり、これは倫理的生活が階層体系(および自然)へと展開するものであり、自己組織化された倫理的生活の階層は、その素材として個体においてのみ組織化 されうる。個体そのものは真実の絶対ではなく、形式的な絶対である。真実は倫理的生活の体系である。 したがってこの体系は、個体の中に純粋に存在するものとして、すなわち発展し、その階層に完全に分配されたものとして考えることはできない。なぜならその 本質は、霊的であり、元素的であり、純粋であり、従属した統一性を自らに服従させ、それらの硬直性から解き放って絶対的な可塑性へと溶解させるからであ る。個人の特異性は第一の事柄ではない。倫理的自然、神性の生命こそが第一であり、神性の本質にとって特異化された個人は貧弱すぎる。すなわち、神性の自 然をその全現実において包含するには貧弱すぎるのだ。形式的無関心として、それはあらゆる特徴を瞬間的に示すことができるが、形式的無関心としてそれは否 定的、時間的であり、それらを再び破壊する。しかし倫理的現実性は、自然として、そのすべての階層の持続として、そしてそれぞれの階層が生きた形態におい て持続するものとして、自らを把握しなければならない。それは必然と一体であり、相対的同一性として持続しなければならない。しかしこの必然は、各階層が 現実性を持つ、すなわち全体性である限りにおいてのみ現実性を持つ。 完全な全体性におけるこの現実の中で自らを現す倫理的生活のレベルは階級であり、それぞれの原理は上述した倫理的生活の特定の形態である。したがって、絶対的かつ自由な倫理的生活の階級、誠実さの階級、そして不自由あるいは自然的な倫理的生活の階級が存在する。 真の階級概念によれば、その概念は階級外に存在する普遍性、すなわちエン・ナティオニスではない。むしろ普遍性は階級内に実在する。階級は自らの平等性に おいて自己を認識し、普遍性に対して普遍性として自己を構成する。異なる階級間の関係は単なる個人間の関係ではない。むしろ階級に属することによって、個 々の個人は普遍的な存在となり、それゆえ真の個人、すなわち人格者となる。したがって、例えば奴隷階級は階級ではない。なぜならそれは形式的に普遍である に過ぎないからだ。奴隷は単一の個人として主人と関係を持つ。 (a) 絶対的階級[すなわち軍事貴族階級]は、絶対的かつ純粋な倫理的生活を原理としており、その生活に関する上記の説明において、それ自体が明らかにされている。なぜなら、その実在と理念は単に一つであり、理念こそが絶対的倫理的生活だからである。 しかし絶対的倫理的生活の実在においては、この階級が差異の持続に対して如何に振る舞い、その実践的存在が如何に差異化され得るかを考察すれば十分であ る。上述の通り、理念そのものにおいては実践的生活は純粋に否定的なものであり、その実在性には自己動機付けされ経験的偶然性に委ねられた関係性及びそれ に関連する徳性が内包されている。しかし、倫理的生活の実在としてのこの階級にとって、事物の必要性と使用は絶対的な必然性として付きまとう。ただし、上 述した形態、すなわち分離された状態では付きまとうことを許されない。なぜなら、この階級の労働は普遍的でなければならないが、必要を満たすための労働は 個別的だからだ。必要の充足は確かにそれ自体、単なる個別的なものに過ぎない。しかしここでは、必要の充足という形や、純粋に実践的なものの個別的な性格 といったものは一切起こってはならない。この充足は、それ自体として対象の純粋な破壊であり、絶対的否定であって、理想と対象の混同やその混同の結果の延 長でもなければ、対象への知性の部分的投入でもなく、実践的なものでもなく、無生物的なものの発展でもなく、その結果が破壊となるものでもない。代わり に、この階級の活動は戦争の遂行か、そのための訓練に他ならない。なぜなら、人民におけるその直接的活動は労働ではなく、それ自体が有機的かつ絶対的なも のだからだ。 この階級の労働は自らの必要性とは無関係だが、その必要性は労働なしには満たせない。したがって、この労働は他の階級によって行われ、そのために準備され 製造された物がこの階級に伝達されねばならない。彼らに残されたのは、それらを享受する直接的な消費だけだ。しかしこの階級と他の二階級との関係は、現実 において存在する関係であり、倫理的全体性の無関心の中に、唯一可能な方法で取り込まれねばならない。その道は平等である。そしてこの関係の本質は、他の 階級が第一階級にとって有用であること、すなわち彼らが第一階級の必要を満たし、第一階級が他の階級の財や利益を自らのものとする点にある。ゆえに第一階 級は、平等に従い、逆に他の階級にとって有用でなければならない。しかしそれはまず最高の方法で、そして次に彼らの方法においてもそうである。 相互有用性の絆は、内容において二面性を持つ。一方では差異の絆であり、第一階級が他階級に対する絶対的権力である。他方では平等の絆であり、第一階級が否定的な存在として他階級に内在する。それは他階級が第一階級に内在するのと同じ方式である。 前者の有用性とは、第一階級が絶対的かつ現実的な倫理的形態であり、それゆえ他の階級にとって、自己運動し自己存在する絶対者の模範、すなわち倫理的本性 が要求する至高の現実的直観であることだ。これらの階級は、その本性ゆえに、この直観を超えることはできない。彼らは無限概念の領域にはいない。この領域 では、この直観は彼らの意識にとって外部的なものとしてのみ位置づけられるが、厳密に言えば(すなわち彼らの概念的認識において)、それは彼らのあらゆる 異なる差異と決定性を克服する彼ら自身の絶対的な運動精神となる。彼らの倫理的本性がこの直観、この有用性を達成するのは、第一階級によって与えられる。 これは客観的な形で現れる彼らの絶対的な内的な本質であるがゆえに、彼らにとっては隠されたものであり、彼らの個性や意識と結びついていない。 後者の有用性は、他の階級の方式に従い、否定的なもの(すなわち労働)に存する。第一階級においても労働は同様に確立されるが、それは統治と勇気という絶 対的に無差別な労働である。他の階級に対する、あるいは彼らにとってのこの労働の意味は、彼らの財産と所有物の保障であり、絶対的な保障とは、彼らが勇気 を免除されること、少なくとも第二階級が免除されることである。 (b) 正直の階級[ブルジョワジー]は、必要のための労働、所有、利益、財産にある。これらの関係に内在する統一性は、差異の固定性ゆえに純粋に観念的なもの、 すなわち理性的存在(ens rationis)であるため、人民においてのみ現実性を獲得する。それは知恵[38]を内容としない抽象的な空虚な力であり、その内容は実在する事物の 偶然性と、利益や契約などに内在する気まぐれによって決定される。これらの関係における普遍的・法的要素は、それに対して否定的な意図を持つ個別性に対す る現実的な物理的支配となる。所有と個別性への没入は、ここで絶対的無関心への隷属ではなくなる。それは可能な限り無差別、すなわち形式的無関心、つまり 「人格であること」が人民に反映され、所有者は差異ゆえに全存在を喪失せず、従って個人的依存に陥らない。逆に、その否定的な無関心が現実として位置づけ られ、彼はこうして市民、ブルジョワとなり、普遍的なものとして認識される。第一階級においては、個体性におけるあらゆる特殊性が無効化される。それゆ え、第二階級に対して普遍として関係づけられる。第二階級もまた同様の決定を受けるが、その所有の固定性ゆえに、形式的に普遍な、絶対的単数に過ぎない。 この階級の労働もまた普遍的であるため、結果として、物理的欲求の充足のために普遍的依存の体系が構築される。なぜなら、ここでの労働は物質的にはではな く、概念的にのみ、欲求の総体に影響を与えるからである。労働とその産物の価値と価格は、あらゆる必要性の普遍的体系によって決定される。他者の個別的必 要性に基づく価値の恣意的要素、および他者にとって余剰が必要かどうかという不確実性は、完全に解消される。―労働の普遍性、すなわちあらゆる労働の無差 別性は、全ての労働と比較される中間項として、また個々の労働が直接変換される対象として設定される。この現実のものとして設定された中間項が貨幣であ る。同様に、特定の需要と特定の余剰を調整する能動的普遍交換、すなわち活動は、利得交換における普遍性の最高点である商業階級である。それが生み出すも のは、特定の活動で利用可能な余剰を掌握し、それによって普遍的なものへと変えることであり、それが交換するものは同様に貨幣、すなわち普遍的なものであ る。 物々交換、あるいは一般に財産を他者へ移転することが理想的な場合——それは部分的には、一方の所有が普遍的に知られていること、移転を妨げる普遍的な認 識(なぜなら財産とその確実性は部分的に移転に依存しているから)によるものであり、 その理想性は現実において(国家の全権力がそれに懸かっているという事実によって)あたかも実際に起こったかのように仮定され、交換の経験的表象は問題と ならない。所有の有無という経験的な表れも同様に重要ではない。重要なのは、個人と物との内面的絶対的結びつきが近いか遠いか、すなわちその物が彼の所有 物であるかどうかである。この両者が合わせて、物に対する所有権に関連する正義を構成する。 自然状態における個人的傷害は無制限であった。それは名誉と人格全体に関わる問題であった。現実の制度においては、それは傷害という特定の抽象概念とな る。なぜなら、個人の無関心はここでは絶対的な無関心、すなわち人民(ただし人民は民事上の不正行為によって傷つけられることはない)であるため、残され るのはまさに傷害の特定的で個別的な性質だけだからだ。市民という存在においては、普遍性が傷つけられることも、復讐や危険に晒されることもほとんどな い。ゆえに残された手段は、個別性を超越して解放すること、すなわち加害者を全く同じ扱いにかけることである。こうして復讐は刑罰へと変容する。復讐は不 確定であり、名誉と家族全体に属するものだからだ。ここでは人民がこれを担う。なぜなら、特定の被害者の代わりに、抽象的だが現実的な普遍性、すなわち生 きた普遍性ではなく、個人の普遍性が介入するからである。 しかし、誠実さにとっての生きた全体とは家族、すなわち自然的な全体性であり、その経験的な生命全体と子供の教育のために、可能な限り保障された財産と生計の状況である。 この階級は、徳も勇気も持ち得ない。なぜなら徳とは自由な個性だからだ。誠実さは、個性を欠いた階級としての普遍性と、自由を欠いた関係性という個別主義の中にこそ存在する。 この階級が生産活動によって到達し得る最高の境地は、(a)第一階級への需要への貢献と(b)困窮者への援助である。どちらもその原理の部分的否定であ る。なぜなら(a)は概念に基づく普遍のための労働であり、(b)は経験的必要性に基づく個別への献身だからだ。前者の普遍的犠牲には生命力がなく、後者 のより生きた犠牲には普遍性がない。 同様に家族の内面的関係も概念によって決定される。必要に迫られて家長と結びつく者は、奉仕の絆におけるあらゆる個人的側面にもかかわらず、契約による絶 対的人格として、かつ定められた期間のみそうする。なぜなら家内の各成員は絶対的人格であるから、生きた全体性を達成し家長となるべきだからだ。これはま さに、絆が個人的要素を減らし特定の奉仕と労働のみに限定される関係である。 (c) 粗野な倫理的生活の階級は農民階級である。その倫理的生活の段階が取る形態は、確かに物理的必要に関わることである。同様に普遍的依存の体系に組み込まれるが、より家父長的な方法で、その労働と獲得はより大きく包括的な全体性を形成する。 その労働の性質もまた、完全に知的ではなく、必要を満たすための何かを直接準備するものでもない。むしろそれは手段であり、土壌や動物といった生き物に影 響を与えるものだ。農民の労働は、生き物の有機的な潜在力を掌握し、それゆえにそれを決定する。ただし、その生き物は自らを生産する。 この階級の倫理的生活は、絶対的階級への信頼であり、第一階級の全体性との調和にある。あらゆる関係と影響力を保持せねばならない。この第三階級の未熟な 倫理的生活は、信頼にしか成り得ない。あるいは強制下に置かれた場合、その活動の分割を受け入れる。[39] その全体性ゆえに、勇気も持ち得る。この労働と死の危険において、第一階級と結びつくことも可能だ。 |
| II. Government In the preceding level the system of ethical life was set forth as it is at rest: the organic independently, as well as the inorganic absorbing itself in itself and forming, in its reality, a system. But this present level treats of how the organic is different from the inorganic; it knows the difference between universal and particular, and how the absolutely universal transcends this difference and everlastingly cancels and produces it; in other words, the Absolute is subsumed under the absolute concept, or we have the absolute movement or process of ethical life. This movement, spread throughout the unfolding of all levels and really first creating and producing this unfolding, must be displayed in this level. And since the essence of this level is the difference between universal and particular, but also the supersession of this difference, and since this organic movement must have reality (and the reality of the universal consists in its being a mass of individuals), this antithesis is to be so interpreted — since the universal is real or in the hands of individuals — that these are truly in the universal and undifferentiated, and in the separation of universal and particular adopt such a movement that through it the particular is subsumed under the universal and becomes purely and simply equal to it. So far as might is concerned, the universal in its reality is superior to the particular, for, no matter at what level, the government is formal, it is the absolutely universal; the might of the whole depends on it. But the government must also be the positively and absolutely universal, and hence it is the absolute level [i.e., the first class], and the question is always about the difference that the government is the true power against everything particular, whereas individuals necessarily dwell in universal and ethical life. This formal characterisation of the concept of a constitution, the reality of the universal in so far as it is in contrast to something particular and so enters as power [Potenz] and cause, must also be recognised as a totality in the separation of powers. And this system — determined according to the necessity in which they are separated, and as the power of the regime is framed at the same time in this separation for each of these determinate features — is the true constitution. A truly ethical totality must have proceeded to this separation, and the concept of the government must display itself as the wisdom of the constitution, so that the form and consciousness is as real as the Absolute is in the form of identity and nature. The totality exists only as the unity of essence and form: neither can be missing. Crudity, with respect to the constitution in which nothing is distinct and the whole as such is directly moved against every single determinacy, is formlessness and the destruction of freedom; for freedom exists in the form, and there in the fact that the single part, being a subordinate system in the whole organism, is independently self-active in its own specific character. This government is therefore directly divided into absolute government and government through the single powers. |
II. 政府 前の段階では、倫理的生活の体系が静止した状態として提示された。有機的なものは独立して存在し、無機的なものは自己の中に吸収され、その実体において体 系を形成する。しかしこの段階では、有機体が無機体とどう異なるかを扱う。普遍と個別の差異を認識し、絶対的普遍がこの差異を超越し、永遠にそれを解消し 生み出す過程を明らかにする。言い換えれば、絶対者は絶対的概念の下に包含され、倫理的生活の絶対的運動または過程が成立する。この運動は全段階の展開に 遍在し、実際にこの展開を創造・生成するものであり、本段階で示されねばならない。そしてこのレベルの本質は普遍と個別の差異であると同時に、この差異の 超越でもある。またこの有機的運動は現実性を有さねばならない(普遍の現実性は個体の集合体であることに存する)。この対立は、普遍が現実的である、ある いは個々の手に委ねられているという観点から、個々が真に普遍の中にあり未分化であること、そして普遍と個別の分離において、個別のものが普遍に包含さ れ、純粋かつ単純にそれに等しくなるような運動を採用することを意味する。 力に関して言えば、普遍性は現実において個別性より優位にある。なぜなら、いかなるレベルであれ、統治は形式的なものであり、絶対的な普遍性だからだ。全 体の力はこれに依存している。しかし統治はまた、積極的かつ絶対的に普遍的でなければならない。ゆえにそれは絶対的レベル(すなわち第一階級)であり、問 題は常に、統治があらゆる個別性に対する真の力であるのに対し、個人は必然的に普遍的・倫理的生活に存するという差異にある。 この憲法概念の形式的特徴付け、すなわち個別的なものと対比される限りにおいて現実性を帯び、力(ポテンツ)および原因として介入する普遍性の現実は、権 力分立においても全体性として認識されねばならない。そしてこの体系——それらが分離される必然性に従って決定され、かつこの分離において各々の決定的特 徴に対して体制の力が同時に枠組みづけられるもの——こそが真の憲法である。真に倫理的な全体性は、この分離へと至らねばならず、統治の概念は憲法の知恵 として現れねばならない。そうして初めて、形式と意識は、同一性と自然の形式における絶対者と同様に現実となる。全体性は本質と形式の統一としてのみ存在 する。いずれかが欠けてはならない。何も区別されず、全体そのものがあらゆる個別決定性に対して直接的に作用する憲法における未熟さは、無形式であり自由 の破壊である。なぜなら自由は形式の中に、そして個々の部分が全体有機体における従属体系でありながら、自らの特異的性格において独立して自律的に活動す るという事実の中に存在するからである。 したがってこの統治は、絶対的統治と個別権力による統治に直接的に分かれる。 |
| A. The Absolute Government seems immediately to be the first class because that class is the absolute power for the others, the reality of absolute ethical life, the real intuited spirit of the others, while they are in the sphere of the particular. But the first class is itself one class in contrast to the others, and there must be something higher than itself and its difference from the others. As absolute universal reality this class is, of course, the absolute government; but organic nature proceeds to the annihilation and absorption of the inorganic and the latter maintains itself by its own resources, by the inner spirit which posits organic nature and its reflection as an inorganic nature. This latter stands in the concept as something absolutely universal, and the annihilation and the empowering of it by organic nature necessarily affects its particular character. Inherently it is the particular, though assumed into the concept and infinity, and this is what its persistence means. Similarly the absolute class is the ethical organic nature in contrast to the inorganic nature of the relative classes and it consumes the latter in its particularity, so that the relative classes must provide the absolute one with the necessaries of life and work, while the first class is individualised in intuition by this contrast, and therefore, as a class, the first class has in its consciousness the difference of the second class and the crudity of the third, and so it separates itself from them and maintains a sense of its lofty individuality or the pride which, as an inner consciousness of nobility, abjures the consciousness of the non-noble and, what is precisely the same as that consciousness, namely, the action of the non-noble. This spiritual individualisation, like the former physical one, sets up a relation of organic to inorganic nature, and the unconscious limitation of this movement and of the annihilation of inorganic nature must be posited in ethical life as known, must emerge as the newborn and appearing middle term; it must not remain left to itself or fail to retain the form of nature; on the contrary it must be known precisely as the limit of the particularity which is to be annihilated. But such knowledge is the law. The movement of the first class against the other two classes is assumed into the concept by reason of the fact that both of them have reality, both are limited, and the empirical freedom of the one is cancelled like that of the others. This absolute maintenance of all the classes must be the supreme government and, in accordance with its concept, this maintenance can strictly accrue to no class, because it is the indifference of all. Thus it must consist of those who have, as it were, sacrificed their real being in one class and who live purely and simply in the ideal, i.e., the Elders and the Priests, two groups who are strictly one. In age the self-constitution of individuality vanishes. Age has lost from life the aspect of shape and reality, and at the threshold of the death which will carry the individual away entirely into the universal, it is already half dead. Owing to the loss of the real side of individuality, of its particular concerns, age alone is capable of being above everything in indifference, outside its class, which is the shape and particularity of its individuality, and of maintaining the whole in and through all its parts. The maintenance of the whole can be linked solely to what is supremely indifferent, to God and nature, to the Priests and the Elders, for every other form of reality lies in difference. But the indifference which nature produces in the Elders, and God produces in his Priests who are dedicated to him alone, appears to be an indifference lying outside ethical life, and ethical life seems to have to take flight out of its own sphere, to nature and the unconscious. But this must be because here the question is about reality, and reality belongs to nature and necessity. What belongs to ethical life is the knowledge of nature and the linkage (a) of that level of nature which formally and explicitly expresses the specific character of an ethical level with (b) that ethical level. Nature is here related to ethical life like a tool. It mediates between the specific Idea of ethical life and its outward appearance. As a tool it must be formally adequate to that Idea, without indeed having any independent ethical content of its own, but corresponding with the Idea according to its formal level and specific character. Or its content is nothing but precisely possibility, the negative of ethical specific character. This latter, posited ideally, requires a tool, or alternatively its subjective reality, its immediate, inherently undifferentiated body, taken up into its unity, appears, considered by itself, as its tool; and for the Idea, posited ideally, opposed to reality, this its body appears to reality as something accidental, something that finds itself, fits in, and conforms. In nature the soul frames its body directly and one can neither be supposed, nor conceived, without the other. There is an original unity, unconscious, without separation. But in ethical life the separation of soul from body is the primitive thing, and their identity is a totality or a reconstructed identity. Thus for the ideal the body is to be sought as something present, formal, inherently negative and to be bound up with the ideal; and herein consists the essence of the construction of the government, namely, that (a) for the specific character of the soul or the specific ethical character whose reality is to be known, that shall be found which lies outside difference, in the sense that what is found is a specific ethical character; but that (b) at the same time this tool shall not be something universal, adequate for many other things, but precisely and only for this specific function. For, for one thing, the tool would otherwise be restricted against its own nature, and, for another thing, it would be, for that on account of which it is restricting, power in general, predominance, and not one with it in essence and spirit. It must have its entire shape in common with that, be one with it in respect of particularity, or, so to speak, have the same interest as it has except that the antithesis of ruler and ruled is the external form of the indifferent in contrast to the different, of the universal in contrast to the particular. Thus age is the body of absolute indifference against all the classes. It lacks the individuality which is the form of every single person; and although the priesthood exists as the indifference not abandoned to nature but extorted from it and destructive by self-activity of what is individual, it must be noticed (a) that the Elders of the first class have led a divine [i.e., consecrated] life by belonging to it; (b) that the Elder of the first class must be a priest himself and, in the transition from an adult into a higher age, live as a priest and so must produce for himself an absolute and true age; (c) that the true priest needs the outward age as his body, that his consummation cannot be put, against nature, into an earlier age, but must await the highest one. The preservation (the absolute relation) of the whole is consigned simply to this supreme government; it is absolute rest in the endless movement of the whole and in connection with that movement. The wisdom of this government affects the life of all the parts, and this life is the life of the whole and is only through the whole. But the life of the whole is not an abstraction from the life force but absolute identity in difference, the absolute Idea. But this identity in difference is in its absolute and supreme outward articulation nothing but the relation of the classes constructed in the first level [i.e., within the absolute class itself]. It is the Absolute as something universal, without any of the specific determinacy which occurs at the particular levels. This indifferent Idea of the supreme government does not affect any form of the particularity and determinacy which is manifest in the ramification of the whole into its subordinate systems. The government does not have to repeat this Idea in these, for otherwise it would be a formal power over them; on the contrary once this difference of the classes is established, it proceeds to maintain it. Thus to this extent it is negative in its activity, for the maintenance of a living thing is negative. It is government and so opposed to the particular; the absolute positive soul of the living social whole lies in the entirety of the people itself. By being government, government is in the sphere of appearance and opposition. Thus as such it can only be negative.[40] But this absolute negation of everything that could conflict with the absolute relation of the absolute Idea and that had jumbled the distinction of the classes, must have a supreme oversight of the way in which any power is determined. No ordering whatever of any such power is exempt from its control, neither in so far as such a power establishes itself, nor in so far as it proposes to uphold itself when it is restricted by the movement of a higher power, either in general, in such a way as still to remain in existence, or as to be wholly superseded for a time. Anything that could have an influence on disturbing the relation between the classes or the free movement of a higher power is in an absolute sense organic and within the competence of the supreme government. But the government’s negative business in the field of appearance is not to be so conceived as if it behaved simply in a supervisory capacity and negatively in prohibitions by veto. On the contrary its negative activity is its essence, but it is the activity of a government, and its relation to the particular, or its appearance, is a positive activity, precisely in so far as it emerges in opposition to the particular. Thus it is legislative, establishing order where a relation is developed which intended to organise itself independently, or where some hitherto insignificant feature gradually develops itself in its previous unrestrictedness and begins to get strong. Above all it has to decide in every case where different rights of the systems [i.e., the class structures] come into collision and the present situation makes it impossible to maintain them in their positive stability. In all systems, theoretical or actual, we come across the formal idea that an absolute government is an organic central authority, and, in particular, one which preserves the constitution. But (a) such an idea, like Fichte’s ephorate,[41] is entirely formal and empty in its negative activity, (b) and then there has to be ascribed to it every possible oversight in the government of every single case, and consequently this oversight involves a crude confusion of universal and individual. It is supposed to dominate everything, giving commands and operating as predominant, and yet at the same time that it dominates to be nothing nevertheless; (g) the absolute government is only not formal because it presupposes the difference of the classes and so is truly the supreme government. Without this presupposition the whole might of reality falls into a clump (no matter how the clump might otherwise ramify internally) and this barbarian clump would have at its apex its equally barbarian power undivided and without wisdom. In the clump there cannot be any true and objective difference, and what was to hover over its internal differences is a pure nothing. For the absolute government, in order to be the absolute idea, posits absolutely the endless movement of the absolute concept. In the latter there must be differences and, because they are in the concept, universal and infinite, they must therefore be systems. And in this way alone is an absolute government and absolute living identity possible, but born into appearance and reality. The external form of this government’s absolute might is that it belongs to no class, despite the fact that it originated in the first one. From this one it must proceed, for in reality the crude living identity, without wisdom and undifferentiated, is the third thing, the third class, while the second is the one in which difference is fixed, and although it has unity as formal universality united with itself, it still has this unity floating over it. But the first class is clear, mirror-bright identity, the spirit of the other classes, though since it is fixed in antithesis to the others, it is the infinite side, while the others are the finite one. But the infinite is nearer to the Absolute than the finite is, and so, if the expression be allowed, rising from below, the Absolute mounts up and swings forth directly out of the infinity which is its formal and negative side. This government is absolute power for all the classes because it is above them. Its might whereby it is a power is not something external whereby it would be something particular against another particular, would have an army, or whatever else, to execute its commands. On the contrary it is entirely withdrawn from opposition; there is nothing against which it could set itself as something particular and thereby make itself into something particular. On the contrary it is absolutely and solely universality against the particular; and as this Absolute, this Ideal, this Universal, in contrast with which everything else is a particular; it is God’s appearance. Its words are his sayings, and it cannot appear or be under any other form. It is the direct Priesthood of the All Highest, in whose sanctuary it takes counsel with him and receives his revelations; everything human and all other sanction ceases here. It is neither the declaration that such an authority is to be inviolable nor the whole people’s choice of its representatives that gives this government its sanctity; on the contrary such a sanction rather detracts from it. Choice and declaration is an act proceeding from freedom and the will and so can just as easily be upset again. Force belongs to the empirical and conscious will and insight, and every such single act of will and judgment occurs in time, is empirical and accidental, and may, and must, be able to be retracted. A people is not bound by its word, its act, or its will, for all of these proceed from its consciousness and from the circumstances. The absolute government, on the other hand, is divine, is not made, has its sanction in itself, and is simply the universal. But any and every making of it would issue from freedom and the will. |
A. 絶対的統治 この階級が第一階級であるように思われるのは、他の階級にとって絶対的権力であり、絶対的倫理的生活の実体であり、他の階級が個別性の領域にある間におけ る、彼らにとっての実在として直観される精神だからだ。しかし第一階級はそれ自体が他の階級と対比される一つの階級であり、それ自身と他の階級との差異よ りも高い何かが存在しなければならない。 絶対的普遍的実体として、この階級は当然絶対的統治である。しかし有機的自然は無機的自然を消滅・吸収する過程を辿り、後者は自己の資源、すなわち有機的 自然とその反映である無機的自然を規定する内的な精神によって自己を維持する。この無機的自然は概念上絶対的普遍的存在として位置づけられ、有機的自然に よるその消滅と賦活は必然的にその個別的性格に影響を及ぼす。本質的には個別的な存在でありながら、概念と無限の中に包含される。これがその持続の意味す るところである。 同様に、絶対的階級は相対的階級群の無機的自然に対比される倫理的有機的自然であり、後者をその個別性において消費する。ゆえに相対的階級群は絶対的階級 に生活と労働の必需品を供給せねばならず、一方最初の階級はこの対比によって直観において個別化される。したがって第一階級は、第二階級の差異と第三階級 の未熟さを自らの意識内に保持し、それゆえそれらから分離し、高貴な個性の感覚、すなわち貴族性の内的意識としての誇りを維持する。この誇りは非貴族的な 意識、そしてまさにその意識と同一である非貴族的な行為を拒絶する。 この精神的個別化は、以前の物理的個別化と同様に、有機的自然と無機的自然との関係を構築する。そしてこの運動の無意識的制限と無機的自然の消滅は、既知 の倫理的生活において前提されねばならず、新生し現出する中間項として現れねばならない。それは自己に委ねられたままではならず、自然の形態を保持し損 なってはならない。むしろ、消滅すべき個別主義の限界として正確に認識されねばならない。しかし、そのような認識こそが法である。 第一階級が他の二階級に対して示す運動は、両者が現実性を持ち、両者が限定されているという事実ゆえに、その概念の中に包含される。すなわち、一方の経験 的自由は他方と同様に取消されるのである。この全階級の絶対的維持こそが至高の統治であり、その概念に従えば、この維持は厳密にはいかなる階級にも帰属し 得ない。なぜならそれは全階級の無関心だからである。したがって、それはある階級において実在を犠牲にした者たち、すなわち純粋に理想の中に生きる者た ち、つまり長老と祭司、厳密には一つの集団である二つの集団から成らねばならない。 年齢を重ねるにつれ、個性の自己構成は消え去る。老いは生命から形と現実の側面を失い、個を完全に普遍へと運び去る死の門辺にあって、すでに半ば死んでい る。個性の現実的側面、すなわち個別の関心事の喪失ゆえに、老いのみがあらゆるものを超越した無関心、すなわち個性の形と個別性である自らの階級の外側に 位置し、全体をそのすべての部分において、またそれらを通して維持しうるのである。 全体の維持は、至高の無関心、すなわち神と自然、司祭と長老たちとのみ結びつけられる。他のあらゆる現実の形態は差異の中に存在するからだ。しかし自然が 長老たちに、神が神のみに献身する司祭たちに生み出す無関心は、倫理的生活の外側に横たわる無関心のようであり、倫理的生活は自らの領域から逃れ、自然と 無意識へと飛び立つ必要があるように思われる。しかしこれは、ここで問題となるのが現実であり、現実が自然と必然に属するためであろう。倫理的生活に属す るのは、自然の認識と、(a)倫理的次元の特異性を形式的・明示的に表現する自然の次元と、(b)その倫理的次元との結びつきである。 ここで自然は道具のように倫理的生活と関係している。それは倫理的生活の特異な理念と、その外的な現れとの間を媒介する。道具として、自然はその理念に形 式的に適合していなければならない。確かに独自の倫理的内容を持つわけではないが、その形式的レベルと特異な性格に従って理念に対応するのだ。あるいはそ の内容は、まさに可能性、すなわち倫理的特殊性の否定に他ならない。後者は、観念的に設定される場合、道具を必要とする。あるいは逆に、その主観的現実 性、すなわち即物的で本質的に未分化な身体が、その統一性に取り込まれると、それ自体が道具として現れる。そして観念的に設定され、現実に反対する理念に とって、この身体は現実に対して偶然的なもの、自らを見出し、適合し、順応するものとして現れる。 自然においては、魂は直接的にその身体を形作り、一方は他方なしには想定も概念化もできない。分離のない、無意識の原始的統一が存在する。しかし倫理的生 活においては、魂と身体の分離が原初的なものであり、両者の同一性は全体性、あるいは再構築された同一性である。したがって、理念にとって身体は、現存す る、形式的な、本質的に否定的なものとして求められ、理念と結びつけられるべきである。ここに政府の構築の本質がある。すなわち、(a) 現実を知ろうとする魂の特定の性格、あるいは特定の倫理的性格にとって、差異の外側に存在するもの、つまり発見されるものが特定の倫理的性格であることが 求められる。しかし(b)同時に、この道具は普遍的なものであってはならず、他の多くの事柄に適したものであってはならず、まさにこの特定の機能のためだ けに用いられるものでなければならない。なぜなら、第一に、そうでなければ道具は自らの本性に対して制限されることになるからであり、第二に、それが制限 する対象、すなわち一般的な力や優位性に対して、本質と精神において一体となることはなくなるからである。それはそのものと完全に形を同じくし、特殊性に おいて一体でなければならない。あるいは、いわば、支配者と被支配者の対立が、異なるものに対する無関心、普遍的なものに対する特殊なものの対外的な形態 であるように、それと同じ関心を持たなければならない。 かくして年齢は、あらゆる階級に対する絶対的無関心の体である。それは個々の人格の形態たる個性に欠けている。また、聖職階級は自然に見捨てられた無関心 ではなく、自然から強奪され、自己活動によって個性を破壊する無関心として存在するが、次の点に留意されねばならない。(a) 第一階級の長老たちは、聖職に属することで神聖な[すなわち奉献された]生活を送ってきたこと; (b) 第一階級の長老は自ら司祭でなければならず、成人からより高い年齢への移行期において司祭として生き、それによって自らに絶対的かつ真の年齢を生み出さね ばならない;(c) 真の司祭は外的な年齢を自らの身体として必要とし、その完成は自然の摂理に反してより早い年齢に置くことはできず、最高位の年齢を待たねばならない。 全体の保存(絶対的関係)は、単にこの至高の統治に委ねられている。それは全体の無限の運動における、またその運動との結びつきにおける絶対的静止であ る。この統治の知恵は全ての部分の生命に影響を与え、この生命は全体の生命であり、全体を通してのみ存在する。しかし全体の生命は生命力からの抽象ではな く、差異における絶対的同一性、すなわち絶対理念である。だがこの差異における同一性は、その絶対的かつ至高の外的表現において、第一段階(すなわち絶対 的階級そのもの内)で構築された階級の関係に他ならない。それは普遍的なものとしての絶対であり、個別の段階において生じる特定の決定性を一切帯びない。 この至高の統治の無差別な理念は、全体が従属的なシステムへと分岐する際に現れる個別主義と決定性のいかなる形態にも影響を与えない。統治はこれらにおい てこの理念を繰り返す必要はない。さもなければそれはそれらに対する形式的な権力となるからだ。むしろ、この階級の差異が確立されると、統治はそれを維持 する方向へ進む。したがってこの点において、その活動は否定的である。なぜなら生き物の維持は否定的な行為だからだ。それは統治であり、故に個別主義に反 対する。生きている社会的全体の絶対的積極的魂は、人民全体の総体そのものにある。統治であることによって、統治は表象と対立の領域にある。したがってそ れ自体として、それは否定的なものにしかなりえない。[40] しかし、絶対的な理念の絶対的関係と対立し得るあらゆるもの、そして階級間の区別を混乱させてきたものを絶対的に否定するこの行為は、あらゆる権力が決定 される方法を最高に監督しなければならない。いかなる権力の秩序付けも、その支配から免れることはできない。それは、その権力が自らを確立する点において も、より高次の権力の動きによって制限された際に、一般的には存続する形で、あるいは一時的に完全に取って代わられる形で、自らを維持しようとする点にお いても同様である。 階級間の関係や上位の力の自由な動きを乱す可能性のあるものは、絶対的な意味で有機的であり、最高政府の管轄内にある。しかし、表層領域における政府の否 定的活動は、単に監督的立場で行動し、拒否権による禁止という否定的手段に徹するものと捉えるべきではない。むしろその否定的な活動こそが本質であるが、 それは政府の活動であり、個別性、すなわち表層への関わりは、個別性に対抗して現れる点において、まさに積極的な活動である。したがってそれは立法的であ り、自律的に組織化しようとする関係が発展した場所、あるいはこれまで取るに足らない特徴が以前の無制限な状態で次第に発展し、強まり始めた場所で秩序を 確立する。何よりも、システム(すなわち階級構造)の異なる権利が衝突し、現状ではそれらの積極的安定性を維持することが不可能となるあらゆる事例におい て、絶対的政府は決定を下さねばならない。 あらゆる体系において、理論的であれ現実的であれ、絶対的統治とは有機的な中央権威、特に憲法を維持する権威であるという形式的な観念に遭遇する。しかし (a) このような観念は、フィヒテのエフォレート[41]のように、その否定的な活動において完全に形式的で空虚である。 (b) したがって、あらゆる個別事例の統治におけるあらゆる見落としがこれに帰せられねばならず、結果としてこの見落としは普遍と個別の粗雑な混同を伴う。それは万物を支配し、命令を下し、支配的として機能すると同時に、支配しながらも何者でもないものとされる。 (g) 絶対的統治が形式的でないのは、階級間の差異を前提とするゆえに真に至高の統治だからだ。この前提がなければ、現実の全力は塊へと堕ちる(その塊が内部で いかに分岐しようと)そしてこの野蛮な塊は、頂点に同じく野蛮な、分割されず知恵なき権力を据えることになる。塊の中には真の客観的差異は存在し得ず、そ の内部差異の上に浮かぶべきものは純粋な無である。絶対的統治が絶対的理念であるためには、絶対的概念の無限運動を絶対的に設定する。後者には差異が存在 せねばならず、それらが概念内に存在する以上、普遍的かつ無限であるため、必然的に体系でなければならない。この方法によってのみ、絶対的統治と絶対的生 ける同一性が可能となるが、それは表象と現実の中に生み出されるのである。 この統治の絶対的権力の外的形態は、第一階級に起源を持ちながらも、いかなる階級にも属さないことである。現実には、未熟な生きた同一性、すなわち知恵を 持たず未分化なものは第三の事物、第三階級であり、第二階級は差異が固定されたものである。第二階級は形式的普遍性としての統一を自己と結びつけている が、それでもなおこの統一は第二階級の上に浮遊している。しかし第一階級は明晰で鏡のように輝く同一性、他の階級の精神である。ただし他の階級と対立的に 固定されているため、それは無限の側であり、他の階級は有限の側である。しかし無限は有限よりも絶対に近い。ゆえに、表現を許せば、下から立ち上がり、絶 対は上昇し、その形式的かつ否定的な側面である無限から直接に揺れ出るのである。 この統治は全ての階級に対して絶対的権力である。なぜならそれは階級の上に立つからだ。その権力たる力とは、外部的なものではなく、特定の何かが別の特定 の何かに対抗するものでもない。軍隊やその他の手段を用いて命令を執行するものでもない。むしろそれは対立から完全に離脱している。特定の何かとして自ら を対置し、それによって特定の何かとなる対象など存在しないのだ。むしろそれは、個別主義に対する絶対的かつ唯一の普遍性である。あらゆるものが個別主義 として対比されるこの絶対者、この理念、この普遍者こそが、神の顕現である。その言葉は神の言葉であり、他のいかなる形態でも現れ得ない。それは至高者の 直接の司祭職であり、その聖域において神と協議し啓示を受ける。ここにおいて人間的なもの、あらゆる他の権威は消滅する。 この政府に神聖性をもたらすのは、そのような権威が不可侵であるという宣言でも、国民の全人民の代表者選択でもない。むしろそのような認可は、むしろその神聖性を損なう。 選択と宣言は自由と意志から生じる行為であり、それゆえ容易に覆される。力は経験的かつ意識的な意志と洞察に属し、あらゆる意志と判断の行為は時間内に生 じ、経験的かつ偶然的であり、撤回可能でなければならない。人民はその言葉、行為、意志に縛られない。これら全ては人民の意識と状況から生じるからだ。一 方、絶対的統治は神聖であり、人為的に作られたものではなく、その正当性は自己に内在し、単に普遍的なものである。しかし、そのあらゆる形成は自由と意志 から生じるのだ。 |
| B. Universal Government Absolute government is the restful substance of universal movement, but universal government is this movement’s cause; or it is the universal in so far as the universal is opposed to the particular in the form of something particular; yet in its essence the universal is still the universal and, on account of its form, it is the determinant of the particular. Now since universal government is related to movement, while movement occurs in the sphere of individuality, shape, and relation, the content and object of this government is a universal situation. For what abides absolutely is the essence of absolute government; all that can accrue to universal government is a formal universal, a universal accident, a determinate situation of the people for this period of time. For this situation must itself not be an abstraction, something belonging in its reality entirely to the particular and not being any modification or particularisation of the universal, as, for example, the fact that every man lives, has clothes, etc. Such characteristics are only abstractions as universal and are needs of the single individual. But universal government is directed on what there is in those needs which qua universal is a power and subsumes the whole under itself and makes it a power. Universal government provides for the need which is universal, and provides for it in a universal way. The movement of the whole is a persistent separation of the universal from the particular and a subsumption of the latter under the former. But this particular is the persisting separation, and on this account there is stamped on it the form of the Absolute or its moments as mutually external to one another. And the movement is determined in ways that are similarly manifold. The particular against which the universal moves at the level of inwardly concealed identity and outwardly revealed difference determines the movement as one proceeding to nullity; for what is flatly set down as particular and cannot bring identity to birth, and so is not absolute concept or intelligence, can only become one with the universal through nullification. But the particular itself, as absolute concept and as organic totality, i.e., a people, is a particular; and consequently both particulars fail to recognise one another when they posit themselves as ideally negated — the aspect of negation in the absolute concept — and not as ideally persistent. The people that finds itself unrecognised must gain this recognition by war or colonies. But self-constituting individuality is not itself at this second level a level which takes its inorganic aspect, the absolute concept confronting it, up into itself and makes it really and absolutely one with itself. War produces only a recognition, an ideal positing of equality, a true living being. Since government is a subsumption of the particular under the universal, in this concept the moments of the universal opposed to the particular may be distinguished into two, like the subsumption itself; so this subsumption is again a double one, i.e., the real one and the ideal one — the former being the one in which it is formal universality under which the particular is posited, the latter being the true one in which the particular is posited as one with the universal. The moments in question are those which have been conceived as the different powers in the state: (i) the positing of the universal as the legislature, (ii) its ideal subsumption of the particular as the judiciary, or justice in general, and (iii) real subsumption as the executive. (Kant has conceived the real subsumption or the conclusion of the syllogism as the judicial power, but the ideal subsumption, or the minor premise as real subsuming, as the executive power.)[42] Every real or living movement is an identity of these three moments, and in every act of government all three are united. They are abstractions to which no reality of their own can be given or which cannot be constituted or organised as authorities. Legislation, giving judgment, and executive action are something completely formal, empty, and devoid of content. A content makes them real, but by this linking of form and content each of them would immediately become an identity of universal and particular, or, as movement, a subsumption of the particular under the universal, and so a movement which has united all three moments in itself. These abstractions may of course acquire reality; each of them may be independently linked with individuals who limit themselves to them. But in that case their true reality lies in the one which unites the three; or, since the conclusion of the syllogism, the executive, is this unification, the executive is properly always the government; and whether the others are not pure abstractions, empty activities, depends on the executive, and this is absolutely the government; and after the above-mentioned distinctions between legislature, judiciary, and executive have been made and the ineffective authorities set up, the first problem comes back again, the problem of knowing the executive, not as such, but as government. Therefore the movement of the people is government, because movement as such is something formal, since in it it is not absolutely determinate which of the terms standing in relation in the movement is power and which is the particular, and the fact that they are related in the movement seems accidental, whereas in the movement of the people universal and particular are plainly bound together; the absolutely universal as such is plainly determined and therefore the particular is too. Organic movement must be recognised, so far as intuition subsumes the concept and the concept intuition. But because what is self-moving is essentially organic, this distinction is formal throughout. The intuition which subsumes the concept is itself absolute concept, and the concept which subsumes intuition is itself absolute intuition. The appearance of this form of this antithesis is outside the organic itself; the antithesis lies in reflection on the movement. For the organic itself the antithesis is set up in such a way that, in so far as it is the concept which appears as subsuming, the organism is posited as an individual, as an independent single entity contrasted with other individual peoples as single entities; in so far as it is intuition which is subsuming, the organism is really and truly subsumed; it is the universal, the determinant of the particular, which is inherently nullified. In so far as the people, the totality, is directed against its own inner particular character, what is proper to the totality is this particular, because here the universal is posited as what is implicit. This separation, as was said, is a formal one. The movement itself is nothing but an alternation of these two subsumptions. From the subsumption under the concept, where the opposites are single individuals, indifference arises and ideally intuits the single individual, which is thus posited outside the organism as what is proper to indifference, but itself still in the form of particularity, until indifference intuits the single individual as also really itself, or absolute identity is reconstructed. Subsumption under the concept would be the abstraction of the mutual relation of the people to foreign peoples as individuals; but the organic process is directly an ideal cancellation of this difference, or the specific determinacy is directly the one belonging to the people, a difference in the people itself, and the living movement cancels it absolutely. There can thus be no absolute basis for the division of government into internal and external affairs; neither is an organic system comprehended within the universal system and subordinate, but at the same time independent and organic. But the moments of the absolute intuition, since they are known as organic, must themselves be systems in which those forms of inner and outer are subordinate. Those moments, being systems, must have difference wholly from outside, in reflection; but implicitly they must have absolute identity in themselves in such a way that it has hovered over them, not as such, but only as a form. The first system of movement in the totality is thus this — that absolute identity is wholly concealed in it as feeling. The second is the separation of universal from particular and thus is something duplex in its movement: either the particular remains what it is and the universal is therefore only formal, or the universal is absolute and the particular is completely absorbed in it. The first is justice and war, the second is education, culture, conquest, and colonisation. |
B. 普遍的統治 絶対的統治は普遍的運動の静止した実体である。しかし普遍的統治は、この運動の原因である。あるいは普遍的統治は、普遍が特定の形において個別に反対され る限りにおいて普遍なのである。しかしその本質において普遍は依然として普遍であり、その形式ゆえに個別を決定するものである。 さて、普遍的統治は運動と関連しているが、運動は個別性・形態・関係の領域で生じる。ゆえにこの統治の内容と対象は普遍的状況である。絶対的に存続するも のは絶対的統治の本質であり、普遍的統治に帰属し得るものは形式的普遍、普遍的偶有性、この期間における人民の確定的状況に過ぎない。この状況自体が抽象 であってはならず、現実において完全に個別に属し、普遍の変形や個別化ではないものでなければならない。例えば、あらゆる人間が生き、衣服を持つといった 事実などである。こうした特性は普遍としてのみ抽象であり、単一の個人の必要に過ぎない。しかし普遍的統治は、それらの必要の中に存在する、普遍として力 であり、全体を自己の下に包含し、それを力とするものに向けられる。普遍的統治は普遍的な必要を満たし、普遍的な方法でそれを満たす。 全体の運動とは、普遍から個別を絶えず分離し、後者を前者に包含する過程である。しかしこの個別は持続的な分離そのものであり、ゆえに絶対者の形式、あるいは相互に外部的な絶対者の諸段階が刻印される。そして運動は同様に多様な方法で決定される。 普遍が内面的には隠された同一性、外面的には顕在化した差異の次元で向かい合う個別は、その運動を無へと向かうものとして決定する。なぜなら、個別として 断固として設定され、同一性を生み出せず、したがって絶対的概念や知性ではないものは、無化を通じてのみ普遍と一体となることができるからだ。 しかし個別性そのものは、絶対的概念として、また有機的総体として、すなわち民族として、個別性である。したがって両個別性は、理想的に否定された状態― 絶対的概念における否定の側面―としてではなく、理想的に持続する状態として自らを位置づけるとき、互いを認識し得ない。認識されない民族は、戦争や植民 地によってこの認識を獲得せねばならない。 しかし自己構成的な個別性は、この第二の段階において、無機的な側面、すなわち対峙する絶対的概念を自らに取り込み、真に絶対的に自己と一体化する段階には至らない。戦争が生み出すのは、認識、すなわち平等という理想的な設定、真に生きた存在に過ぎない。 政府とは個別を普遍に帰属させることであるから、この概念において個別に対立する普遍の諸相は、帰属そのものと同様に二つに区別し得る。ゆえにこの帰属は 再び二重のものであり、すなわち現実的なものと理想的なもの——前者は個別が置かれる形式的普遍性のものであり、後者は個別が普遍と一体として置かれる真 のものである。問題の二つの側面は、国家における異なる権力として構想されてきたものである:(i) 普遍を立法府として位置づけること、(ii) 個別を司法府、すなわち一般の正義として理想的に包含すること、(iii) 個別を実体として包含する行政府である。(カントは実的帰属、すなわち三段論法の結論を司法権と捉え、一方、観念的帰属、すなわち小前提としての実的帰属 を行政権と捉えている。)[42] あらゆる現実的あるいは生きた運動は、これら三つの要素の同一性であり、あらゆる統治行為において三者は結合する。これらは抽象概念であり、それ自体に現 実性を与えることも、権威として構成・組織化することもできない。立法、判決、行政行為は完全に形式的で、空虚であり、内容を持たない。内容によってそれ らは現実性を帯びるが、この形式と内容の結びつきによって、それぞれが普遍と個別の同一性、あるいは運動として個別を普遍に帰属させるものとなり、こうし て三つの瞬間を自らに統合した運動となるのである。 これらの抽象概念は当然現実性を獲得しうる。それぞれが、それらに自らを限定する個人と独立して結びつく可能性もある。しかしその場合、その真の現実性は 三つを統合する一方にある。あるいは、三段論法の結論である行政機関がこの統合そのものである以上、行政機関は本質的に常に政府である。他の二者が純粋な 抽象概念、空虚な活動でないかは行政機関次第であり、これが絶対的に政府なのである。前述の立法府・司法府・行政府の区別がなされ、実効性のない権威が設 置された後、最初の問題が再び浮上する。すなわち、行政機関をそれ自体としてではなく、政府として認識するという問題である。 したがって、人民の運動こそが政府である。なぜなら運動そのものは形式的なものであり、運動において関係する項のうち、どれが権力でありどれが個別である かは絶対的に決定されておらず、それらが運動において関係しているという事実は偶然的に見える。一方、人民の運動においては普遍と個別が明らかに結びつい ている。絶対的普遍そのものは明らかに決定されており、したがって個別もまた決定されている。 有機的運動は、直観が概念を包含し概念が直観を包含する限りにおいて認識されねばならない。しかし自発的運動は本質的に有機的であるゆえ、この区別は終始 形式的なものである。概念を包含する直観はそれ自体が絶対的概念であり、直観を包含する概念はそれ自体が絶対的直観である。この対立形式の表出は有機体そ のものの外側にあり、対立は運動への省察の中に存在する。有機体自体においては、この対立は次のように設定される。概念が包含する側として現れる限り、有 機体は個別的存在として、他の個別的な人民と対比される独立した単一存在として位置づけられる。直観が包含する側である限り、有機体は真に包含される。普 遍的要素、すなわち個別的要素を規定する要素こそが、本質的に無効化されるのである。人民、すなわち全体が自らの内的個別性に対して向けられる限りにおい て、全体に固有なものはこの個別性である。なぜならここでは普遍性が暗黙のものとして位置づけられるからである。 この分離は、前述の通り形式的なものである。運動そのものは、この二つの包含の交替に他ならない。概念への包含においては、対立するものは単一の個体であ り、無差別性が生じ、単一の個体を理想的に直観する。こうして無差別性は、無差別性に固有のものとして有機体の外側に置かれるが、それ自体は依然として個 別主義の形態を保っている。無差別性が単一の個体をまた実体として自らであると直観するまで、あるいは絶対同一性が再構築されるまでである。 概念への帰属とは、国民と外国人民との相互関係を個体として抽象化することである。しかし有機的過程は、この差異を直接的に観念的に解消するものであり、 あるいは特定の決定性が直接的に人民に属するものであり、人民自身における差異であり、生きた運動がこれを絶対的に解消するのである。したがって、政府を 内政と外交に分割する絶対的な根拠は存在しえない。また有機的体系は普遍的体系内に包含され従属するものではなく、同時に独立し有機的である。しかし絶対 的直観の諸瞬間は、有機的として知られる以上、それ自体が内と外の形式が従属する体系でなければならない。それらの瞬間は体系である以上、差異を完全に外 部、すなわち反射において持たねばならない。しかし同時に、それらは暗黙のうちに、絶対的同一性をその内部に持たねばならない。それは、そのようなものと してではなく、単なる形式としてのみ、それらの上に漂っているような形で。 したがって、全体性における運動の最初の体系はこれである――絶対的同一性が、感覚として完全に隠されていること。 第二の体系は普遍と個別の分離であり、その運動において二重性を帯びる。すなわち、個別が個別として存続し普遍が形式のみとなるか、あるいは普遍が絶対的であり個別が完全に吸収されるかのいずれかである。前者は正義と戦争、後者は教育、文化、征服、植民地化である。 |
| a) The first system of Government: System of need The system of need has been conceived formally above as a system of universal physical dependence on one another. For the totality of his need no one is independent. His labour, or whatever capacity he has for satisfying his need, does not secure its satisfaction for him. Whether the surplus that he possesses gives him a totality of satisfaction depends on an alien power (Macht) over which he has no control. The value of that surplus, i.e., what expresses the bearing of the surplus on his need, is independent of him and alterable. This value itself depends on the whole of the needs and the whole of the surplus, and this whole is a scarcely knowable, invisible, and incalculable power,[43] because this power is, with respect to its quantity, a sum of infinitely many single contributions and, with respect to quality, it is compounded out of infinitely many qualities. This reciprocal action of the single contribution on the whole, which is composed of such contributions, and of the whole in turn, as something ideal, on the single contribution, determines value and so is a perpetual wave, surging up and down, in which the contributor, determined by the whole as possessing a high value, amasses his assets and hence there comes to be in the whole a surplus included in the entirety of need. As a result of this circumstance, the indifference of the whole, regarded as a mass of the other qualities, appears as a ratio between them, and this ratio has altered. These other qualities are necessarily connected with that surplus, and this which previously had a higher value is now depreciated. Every single kind of surplus is rendered indifferent in the whole, and through its reception into the whole it is measured to fit the whole of the general need; its place and worth is appointed for it. For this reason it is just as little the single contributor who determines the value of either his surplus or his need, or who can maintain it independently of its relation to everything else, as there is anything permanent and secure in the value. Thus in this system what rules appears as the unconscious and blind entirety of needs and the modes of their satisfaction. But the universal must be able to master this unconscious and blind fate and become a government. This whole does not lie beyond the possibility of cognition, in the great ratios treated en masse. Because the value, the universal, must be reckoned up quite atomistically, the possibility of knowledge in respect of the different kinds of surplus thus compounded is a matter of degree. But from the value of the kind itself it is possible to know how the surplus stands in relation to need; and this relation, or the value, has its significance from two aspects: (a) whether the production of such a surplus is the possibility of meeting the totality of needs, whether a man can subsist on it, and (b) the aspect of universality, i.e., whether this value of one sort of need is not disproportionate to the totality itself, for which the need exists. Both must be determined by intuition, in terms of the whole of what a man necessarily wants, and this is to be ascertained, partly from primitive natural conditions, according to the different climates, and partly from cultural conditions, by taking the average of what in a given people is regarded as necessary for existence. Natural influences bring it about automatically that sometimes the proper equilibrium is maintained with insignificant oscillation, while at other times, if it is disturbed more seriously by external conditions, it is restored by greater oscillations. But precisely in this last case the government must work against the nature which produces this sort of overbalancing sway through empirical accidents whose effect is sometimes more rapid — e.g., poor harvests — sometimes slower — e.g., the development of the same work in other districts and the resulting cheapness of the product which cancels elsewhere the symmetrical relation of the surplus to the whole; and since nature has cancelled the peaceful mean of the stable price system, the government must uphold that mean and the equilibrium. For the lowering of the value of one sort of surplus and the impracticability of that surplus’s meeting the entirety of need [i.e., the impossibility of making a living by producing that commodity] destroys the existence and confidence of part of the people, since that part has tied its existence to the practicability of this, with trust in the universal.[44] The government is the real authoritative whole which, indifferent to the parts of the people, is not anything abstract and thus is indeed indifferent to the singular type of surplus to which one part links its reality, but is not indifferent to the existence of that part itself. When one sort of surplus is no longer adequate to supply the totality of needs of those who produce it, the abstraction of equilibrium is sure to restore this proportion, and so the result will be that (a) only so many people will busy themselves with that sort as can live off it and their value will rise and that (b) if there are too few of them for those to whom this surplus is a need, their value will fall.[45] But on the one hand reality and the government have a concern about a [price] value that is too low because it puts in jeopardy some part of the people whose physical existence has been made dependent on the whole economy and is now threatened with complete ruin by it; and, on the other hand, the government is concerned about values [i.e., prices] being too high, which disturbs everyone in the totality of his enjoyment and customary life. These concerns are ignored by the abstraction of equilibrium, an abstraction which in the equilibrium’s oscillation remains outside it as the passive indifference of reflective observation, while the government remains outside the oscillation as the real authoritative indifference and the determinant of difference. But these empirical oscillations and formal non-necessary differences, to which the government is authoritatively indifferent, are accidental, not the necessary differential urge which proceeds to the destruction of the equilibrium. The organic principle of this level is singleness, feeling, and need, and this is empirically endless. In so far as it is independent and is to remain what it is, it sets no limits to itself, and since its nature is singleness, it is empirically endless. True, enjoyment does seem to be fixedly determinate and restricted; but its endlessness is its ideality, and in this respect it is endless. As enjoyment itself it idealises itself into the purest and clearest enjoying. Civilised enjoyment volatilises the crudity of need and therefore must seek or arrange what is noblest, and the more different its impulses, the greater the labour they necessitate. For both the difference of the impulses and also their indifference and concentration, these two aspects which the reality of nature separates, should be united. The neutrality which the natural product has by being a totality in itself should be cancelled and merely its difference should remain to be enjoyed. Moreover this ideality of enjoyment displays itself also as “being other,” as foreignness in the external connection of the product [i.e., it comes from “abroad"], and it is linked with scarcity; and this foreign sort of satisfaction, as well as the most domestic sort, the one already made most peculiarly our own by its manner of preparation, makes charges on the whole earth. Empirically endless, the ideality of enjoyment finally displays itself in objectified restricted enjoyment, in possession, and in this respect, consequently, all limitation ceases. Over against this infinity is the particularity of enjoyment and possession, and since possible possession — the objective element in the level of enjoyment — and labour have their limits, are determinate in quantity, it follows that with the accumulation of possession at one place, possession must diminish at another. This inequality of wealth is absolutely necessary. Every natural inequality can express itself as inequality of wealth if what is natural turns to this aspect. The urge to increase wealth is nothing but the necessity for carrying to infinity the specific individual thing which possession is. But the business that is more universal and more ideal is that which as such secures a greater gain for itself. This necessary inequality divides itself again within the business class (Erwerbsstand) into many particular types of business (Stände des Erwerbs), and it divides these into estates (Stände) of different wealth and enjoyment. But owing to its quantitative character, which is a matter of degree and is incapable of any definition except in degree, this inequality produces a relation of master and servant. The individual who is tremendously wealthy becomes a might; he cancels the form of thoroughgoing physical dependence, the form of dependence on a universal, not on a particular. Next, great wealth, which is similarly bound up with the deepest poverty (for in the separation between rich and poor labour on both sides is universal and objective), produces on the one side in ideal universality, on the other side in real universality, mechanically. This purely quantitative element, the inorganic aspect of labour, which is parcelled out even in its concept, is the unmitigated extreme of barbarism. The original character of the business class, namely, its being capable of an organic absolute intuition and respect for something divine, even though posited outside it, disappears, and the bestiality of contempt for all higher things enters. The mass of wealth, the pure universal, the absence of wisdom, is the heart of the matter (das Ansich). The absolute bond of the people, namely ethical principle, has vanished, and the people is dissolved. The government has to work as hard as possible against this inequality and the destruction of private and public life wrought by it. It can do this directly in an external way by making high gain more difficult, and if it sacrifices one part of this class to mechanical and factory labour and abandons it to barbarism, it must keep the whole people without question in the life possible for it. But this happens most necessarily, or rather immediately, through the inner constitution of the class. The relation of physical dependence is absolute particularisation and dependence on something abstract, an ens rationis. The constitution creates a living dependence and a relation of individuals, a different and an inwardly active connection which is not one of physical dependence. To say that this class is constituted inwardly means that within its restrictedness it is a living universal. What is its universal, its law and its right, is living at the same time in the individuals, realised in them through their will and their own activity. This organic existence of this class makes every single individual, so far as there is life in him, one with the others; but the class cannot subsist in absolute unity. Thus it makes some of the individuals dependent, but ethical on the score of their trust, respect, etc., and this ethical life cancels mere mass, quantity, and the elemental, and creates a living relation. The wealthy man is directly compelled to modify his relation of mastery, and even others’ distrust for it, by permitting a more general participation in it.[46] The external inequality is diminished externally, just as the infinite does not give itself up to determinacy but exists as living activity, and thus the urge to amass wealth indefinitely is itself eradicated. This constitution belongs rather to the nature of the class itself and its organic essence, not to the government; to the latter it is the external restrictions that belong. But this is its particular activity, i.e., provision for the subsistence of the single classes within this sphere by opposing the endless oscillations in the value of things. But the government, as the universal, itself has universal needs: (i) in general, for the first class which, exempt from property and business, lives in continual and absolute and universal need, (ii) for the formally universal class, i.e., for that which is the organ of government in the other classes and labours purely in the universal field, (iii) for the need of the community, of the entire people as a universal, e.g. for its public dwellings, etc., its temples, streets, and so forth. The government must earn enough for these needs, but its work can only consist in taking directly into its possession without work the ripe fruits of industry or in itself working and acquiring. The latter — since it is against the nature of the universal to rest in the particular, and here the government is something formally universal — can only be a possessing and a leasing of this possession, with the result that acquiring and working affect the government not directly but in the form of utility, a result, something universal. But the former is the appropriation of the ripe fruits, and so these ripe fruits are work completed and so in the form of something universal, as money or as the most universal needs. These are themselves a possession of individuals and the cancellation of this possession must have the form of formal universality or justice. But the system of taxes falls directly into the contradiction that while it should be absolutely just for each to contribute in proportion to the magnitude of his possessions, these possessions are not landed or immovable but, in industry, something living, infinite, and incalculable. Looked on abstractly, the calculation or estimation of the capital involved according to the income obtained is possible, but the income is something entirely particular, not something objective, knowable, and ascertainable, like landed property. So in this way private possessions cannot be taxed in accordance with justice because, by being private, they do not themselves have the form of something objective. But the objective, i.e., landed property, can be interpreted according to the value of its possible productivity (even though here, too, particularity always has a part to play); but because at the same time possession in the form of particularity is present as skilfulness, not everything is comprised under that value; and if the products of landed property are prodigiously assessed, the value of the product is not set in equilibrium, for the mass always remains the same, being that on which the value depends, and if production diminished, the state’s revenues would diminish to the same extent; production would have to be taxed all the more in a progressive rise and its receipts would behave in the opposite way. Thus skilfulness has to be taxed at the same time, not according to its receipts, which are something particular and one’s own, but according to what it expends; for the thing it buys makes the passage through the form of universality out of its particularity, or it becomes a commodity. And on account of the same circumstance, namely that the mass either remains the same, in which case the value of the article is not altered and this working class is impoverished, or, what follows in that event, less is produced, with the result that the revenue is less, and the same is the case on whatever branch of industry the tax falls; thus the tax must extend to the maximum possible particularity of commodities. Although for this reason it likewise results that less is needed, this is precisely the best external means for restricting gain, and in the taxes the government has a means of influencing this restriction or extension of single parts of the whole economy. |
a) 最初の統治システム 必要性のシステム 必要性のシステムは、形式的には、互いに依存し合う普遍的な物理的依存のシステムとして、上記のように考えられてきた。自分の欲求の総体については、誰も 独立していない。彼の労働力、あるいは彼が欲求を満たすために持っているいかなる能力も、彼のためにその満足を確保することはできない。彼が所有する余剰 が彼に全体的な満足を与えるかどうかは、彼がコントロールできない異質な力(Macht)に依存している。その余剰の価値、すなわち余剰が彼の必要性に与 える影響を表すものは、彼とは無関係であり、変化しうるものである。 この価値そのものは、ニーズの全体と余剰の全体とに依存しており、この全体は、ほとんど知ることのできない、目に見えない、計り知れない力[43]であ り、なぜならこの力は、その量に関しては、無限に多くの単一の貢献の総和であり、質に関しては、無限に多くの質から複合されているからである。このような 貢献によって構成される全体に対する単一の貢献の相互作用と、理想的なものとしての全体が単一の貢献に対して行う相互作用とが価値を決定し、その結果、全 体によって高い価値を有すると決定された貢献者が自分の資産を蓄積し、それゆえ、必要性の全体に含まれる余剰が全体の中に存在するようになる、上下に波打 つ永続的な波となる。このような状況の結果として、他の資質の塊とみなされる全体の無関心は、それらの間の比率として現れ、この比率は変化している。これ らの他の資質は必然的にその余剰と結びついており、以前はより高い価値を持っていたこの余剰は、今では減価している。あらゆる種類の余剰は、全体において は無関心にされ、全体への受容を通じて、一般的な必要性の全体に適合するように計られる。このような理由から、自分の余剰の価値を決めるのも、自分の必要 性の価値を決めるのも、その価値を他のあらゆるものとの関係とは無関係に維持できるのも、その価値に永続的で確実なものがあるのと同様に、一人の貢献者で ある。 したがって、このシステムにおいては、支配とは、ニーズとその充足様式との無意識的で盲目的な全体として現れるのである。しかし、普遍的なものは、この無意識的で盲目的な運命を使いこなし、政府となることができなければならない。 この全体は、一括して扱われる大きな比率の中に、認識の可能性を超えて横たわっているのではない。普遍という価値は、まったく原子論的に計算されなければ ならないから、こうして複合された異なる種類の剰余に関する知識の可能性は、程度の問題である。しかし、その種類の価値そのものから、その剰余が必要性と の関係においてどのような地位にあるかを知ることは可能であり、この関係、すなわち価値は、次の二つの側面からその意味をもつ。(a)そのような剰余の生 産が、必要性の総体を満たす可能性、すなわち人間がそれだけで生きていけるかどうかということ、(b)普遍性の側面、すなわち、ある種類の必要性について のこの価値が、その必要性が存在する総体そのものに不釣り合いでないかどうかということ。 この両者は、人間が必然的に欲するものの全体から見て、直感によって決定されなければならない。このことは、部分的には、さまざまな気候に応じた原始的な 自然条件から、部分的には、ある人々において生存に必要であるとみなされているものの平均をとることによって、文化的条件から、確認されなければならな い。自然の影響によって自動的に均衡が保たれることもあれば、外的条件によってより深刻に均衡が乱されると、より大きな変動によって均衡が回復されること もある。しかし、まさにこの最後の場合において、政府は、経験的な事故によって、この種の過度の均衡の揺れを生み出す自然に対して働かなければならない。 その影響は、あるときはより急速であり、たとえば不作であり、またあるときはより緩慢である。たとえば、同じ仕事が他の地区で発展し、その結果、生産物が 安くなり、全体に対する余剰の対称的な関係が他の場所で相殺される。というのも、ある種の剰余の価値が低下し、その剰余が必要全体を満たすことが現実的で なくなること[すなわち、その商品を生産して生計を立てることが不可能になること]は、人民の一部の存在と信頼を破壊するからである。 政府は、人民の部分に対して無関心であり、抽象的なものではなく、したがって、ある部分がその現実と結びつけている特異な種類の剰余に対しては確かに無関 心であるが、その部分自体の存在に対しては無関心ではない、現実の権威ある全体である。ある種の余剰が、それを生産する人々の必要性の総体を供給するのに 十分でなくなったとき、均衡という抽象は、この比率を確実に回復させるので、その結果、(a)その種の余剰で生活できる人民の数だけがその種の余剰に忙殺 され、その価値は上昇し、(b)この余剰が必要である人々にとってその数が少なすぎれば、その価値は下落することになる。[しかし、一方では、現実と政府 は、低すぎる[価格]価値に懸念を抱いている。なぜなら、それは、経済全体に身体的存在を依存させられ、それによって完全な破滅に脅かされている人民の一 部を危険にさらすからである、 一方、政府は価値[=物価]が高すぎることを懸念している。このような懸念は、均衡という抽象化されたものによって無視される。この抽象化は、均衡の振動 において、反省的観察の受動的無関心として均衡の外側にとどまり、一方、政府は、現実の権威ある無関心と差異の決定要因として振動の外側にとどまる。 しかし、政府が権威的に無関心であるこれらの経験的振動と形式的な非必要な差異は偶発的なものであって、均衡の破壊へと進む必要な差異的衝動ではない。 このレベルの有機的原理は、単一性、感情、必要性であり、これは経験的に無限である。それが独立したものであり、ありのままの姿であり続ける限り、それ自 体に限界はなく、その性質は単一性であるため、経験的に無限である。確かに、享楽は固定的に決定され、制限されているように見えるが、その果てしなさはそ の観念性であり、この点で、それは無限である。享楽そのものとして、それは最も純粋で明確な享楽へと理想化される。文明化された享楽は、必要性の粗雑さを 揮発させ、それゆえ、最も高貴なものを探し求め、整えなければならない。衝動の相違も、その無関心と集中も、自然の現実が分離しているこの二つの側面は、 統合されるべきである。自然の産物がそれ自体全体であることによって持っている中立性は取り消され、単にその差異だけが享受されるために残されるべきであ る。 さらに、この享受のイデア性は、「他者であること」としても、生産物の外的なつながりにおける異質さ[すなわち、それは「外国」からもたらされる]としても、それ自身を示し、それは希少性と結びついている。 経験的に無限であり、享受のイデア性は最終的に、対象化された限定された享受、所有の中に姿を現す。 この無限性に対して、享受と所有の個別主義があり、可能な所有-享受の水準における客観的要素-と労働には限界があり、数量が確定しているので、ある場所での所有の蓄積とともに、別の場所での所有は減少しなければならない。 この富の不平等は絶対に必要である。あらゆる自然的不平等は、自然的なものがこのような局面に転じれば、富の不平等として表現されうる。富を増大させよう とする衝動は、所有という特定の個別的なものを無限に拡大する必要性にほかならない。しかし、より普遍的でより理想的な事業は、それ自体としてより大きな 利得を確保するものである。 この必然的な不平等は、ビジネス・クラス(Erwerbsstand)の中で、それ自体を多くの個別主義的なビジネス(Stände des Erwerbs)に再び分割し、これらを異なる富と享受のエステート(Stände)に分割する。しかし、その量的な性格のために、それは程度の問題であ り、程度以外のいかなる定義も不可能である。とてつもなく裕福な個人は権力者となり、徹底した肉体的依存の形態、つまり個別主義ではなく普遍的なものに依 存する形態を打ち消す。 次に、巨万の富は、同様に最も深い貧困と結びついている(富める者と貧しい者との間の分離において、双方の労働は普遍的かつ客観的なものだからである) が、一方では理想的な普遍性を、他方では現実的な普遍性を、機械的に生み出す。この純粋に量的な要素、つまり労働の無機的な側面は、その概念においてさえ 分節化されており、野蛮の極みである。ビジネス・クラスの本来の性格、すなわち、たとえその外部に仮定されていても、有機的な絶対的直観と神的なものへの 尊敬が可能であるという性格は消え去り、あらゆる高次のものへの軽蔑という獣性が入り込む。富の塊、純粋普遍、知恵の不在が問題の核心である(das Ansich)。人々の絶対的な絆、すなわち倫理原則は消え去り、人民は溶解している。 政府は、この不平等と、それによってもたらされる私生活と公的生活の破壊に対して、できる限り努力しなければならない。それは、高額の利得をより困難にす ることによって、外的な方法で直接これを行うことができる。もしこの階級の一部分を機械労働や工場労働の犠牲にし、野蛮に捨て去ったとしても、人民全体 を、その人民にとって可能な生活の中に何の疑問も抱くことなくとどめなければならない。しかし、このことは、階級の内部構造を通じて、最も必然的に、い や、むしろ直ちに起こる。 肉体的な依存関係は、絶対的な特殊化であり、抽象的なものへの依存である。この構成は、物理的な依存とは異なる、異なる、内的に活動的なつながりである、 生きた依存と個人の関係を生み出す。この階級が内的に構成されるということは、その制限の中で、それが生きた普遍であることを意味する。その普遍であるも の、その法則であるもの、その権利であるものは、同時に個人の中に生きており、彼らの意志と彼ら自身の活動を通して彼らの中に実現されている。この階級の 有機的な存在は、一人一人の個人を、その中に生命がある限り、他の個人と一体化させる。したがって、この階級は、個人のいくつかを依存させるが、信頼や尊 敬などの点から倫理的な存在とする。この倫理的な生活は、単なる質量や量や要素的なものを打ち消し、生きた関係を生み出す。富める者は、より一般的な参加 を認めることによって、自分の支配関係、さらにはそれに対する他者の不信を修正するよう直接強制される[46]。無限が自らを決定論に委ねるのではなく、 生きた活動として存在するように、外的な不平等は外的に減少し、その結果、富を無限に蓄積しようとする衝動自体が根絶される。 この体質は、むしろ階級そのものの性質とその有機的本質に属するものであって、政府に属するものではない。しかし、これは政府の個別主義的活動、すなわ ち、物の価値の際限のない変動に対抗することによって、この領域内の単一階級の存続を規定することである。(i)一般に、財産と事業から免除され、絶え間 ない絶対的で普遍的な必要性の中で生活する第一階級のために、(ii)形式的に普遍的な階級のために、すなわち、他の階級において政府の機関であり、純粋 に普遍的な分野で労働するもののために、(iii)共同体の必要性のために、普遍的なものとしての人民全体の必要性のために、例えば、その公共の住居など のために、その寺院、街路などのために、である。 政府は、これらの必要を満たすために十分な収入を得なければならないが、その仕事は、産業の熟した果実を労働することなく直接自分のものにするか、自ら働 いて獲得することにしかならない。後者は--個別主義に安住することは普遍的なものの本性に反するからであり、ここで政府は形式的には普遍的なものである --所有し、この所有物を租借することでしかありえず、その結果、取得と労働は、政府に直接ではなく、効用という形で、結果、普遍的なものに影響を及ぼ す。しかし、前者は、熟した果実の充当であり、したがって、これらの熟した果実は、完成された仕事であり、したがって、貨幣として、あるいは、最も普遍的 なニーズとして、普遍的な何かの形をとる。これらはそれ自体、個人の所有物であり、この所有物の取り消しは、形式的な普遍性や正義の形を持たなければなら ない。 しかし、税制は、各人がその所有物の大きさに比例して拠出することが絶対的に公正であるべきであるにもかかわらず、これらの所有物は土地や不動物ではな く、産業においては、生きているもの、無限のもの、計り知れないものであるという矛盾に直接陥っている。抽象的に見れば、得られる収入に応じた資本の計算 や見積もりは可能であるが、その収入はまったく個別主義的なものであって、土地財産のように客観的で、知ることができ、確認できるものではない。このよう に、私有財産は、私有財産であるがゆえに、それ自体が客観的なものの形を持っていないため、正義に従って課税することはできない。 しかし、客観的なもの、すなわち しかし、同時に、特殊性という形の所有が巧みさとして存在するのであるから、すべてがその価値のもとに構成されるわけではない; 土地所有財産の生産物が突出して高く評価されても、生産物の価値は均衡を保てず、質量は常に変わらないからである。このように、巧みさも同時に課税されな ければならない。それは、個別主義的で自分だけのものであるその収入によってではなく、それが支出するものによってである。そして、同じ事情、すなわち、 大衆は変わらないか、その場合、商品の価値は変わらず、この労働者階級は困窮するか、あるいは、その場合、生産が少なくなり、その結果、歳入が少なくな る。したがって、税は、商品の可能な限り最大限の特殊性にまで及ばなければならない。このため、必要なものが少なくなるという結果も生じるが、これこそま さに、利潤を制限するための最良の外部手段であり、政府は、税において、経済全体の一部分の制限や拡張に影響を及ぼす手段を持っているのである。 |
| b) The second system of Government: System of justice In the first system the opposition of universal and particular is formal. Value, the universal, and needs and possessions, the particular do not determine the essence of the matter but are outside it. The essence remains its connection with a need. But in this system of the separation of universal and particular it is ideal determinacy which is the essence. The thing which is tied to need is, qua property, so determined that, even as this particular possession, it is essentially something universal; its connection with need — and the need is something entirely single — is something recognised. The thing is mine, and as mine has not been nullified. But the relative identity, in which I stand with it, or the ideality of nullification (i.e., possession), this objectivity is posited as a subjective one, existing in men’s minds. For this reason, as this identity, it [i.e., the property] is intuition, not a single intuition of this single thing, but absolute intuition. That connection with need has objective reality. The self is universal, established, and has being; that tie is determined as a universal one. The middle term, the reality of this connection is the government. The fact that a tie of possession is not something ideal but is also real is the fact that all selves establish this connection, that the empirical self of the tie exists as the whole mass of selves. This mass, according to the abstraction of its quantity, is the public authority, and this public authority as thinking and conscious (sich bewusst) is the government here as the administration of justice. As this administration, government is the entirety of all rights, but with complete indifference toward the interest of the connection of the thing with the need of this specific individual. For the government this individual is a completely indifferent universal person. All that comes in question in pure justice is simply the universal, the abstract aspect of the manner of possession and gain. But justice must itself be a living thing and have regard to the person. Right in the form of consciousness is law, which is here related to singular cases; but this form is arbitrary, although it is necessary for right to be present, in the form of consciousness, as law. Right concerns singular cases and is the abstraction of universality, for the singular case is to subsist in it. This singular case is either the living being of the individual or a relative identity of his [i.e., some piece of his property] or the life of the individual himself regarded as something singular or as relative identity. So too the negation of singular individuality (a negation produced by a single individual and not by the absolutely universal) is a negation of his right of possession purely as such, or the negation of a single living aspect of the individual, or the negation of the entirety of the living individual. The second negation is a violent deed, the third is death. Absolute government could in this matter leave the second class and the third (which through the first lies under civil law) to themselves and leave them alone in the vain endeavour to assume into the infinite the absolutely settled finitude of possession. This endeavour is displayed as the attempted completeness of the civil laws, as an absolute consciousness about judicial procedure, such that the rule would be self-sufficient in its form as rule and the judge would be purely an organ, the absolute abstraction of the singular case under discussion, without any life and intuition of the whole. This false infinite must be set aside by the organic character of the constitution, a character which, as organic, assumes the universal absolutely into the particular. The organic principle is freedom, the fact that the ruler is himself the ruled; but since here the government, as universal, remains opposed to the collision of rules involved in the single individual, this identity of ruler and ruled must in the first place be so established that the equality of birth typical of the same noble class, the constitution appropriate for a narrower circle of noble families, is expanded into a whole of all classes as dwelling together under the same citizenship, and this dwelling together as citizens constitutes the living unity. Secondly, in the actuality of single legal judgments the abstraction of the law must not be the absolute thing; on the contrary the whole affair must be a settlement according to equity, i.e., one that takes account of the whole situation of the parties as individuals, a settlement productive of satisfaction and reached with the conviction and assent of the parties. This principle of freedom in its mechanical constitution is comprehended as the organisation of law courts and is an analysis of the dispute and the decision thereon. In the administration of the civil law it is only determinacy as such that is absolutely negated in the dispute, and the living employment, work, what is personal, may become what is determinate. But in criminal law it is not anything determinate which is negated, but individuality, the indifference of the whole, life and personality. Negation in civil law is purely ideal, but in criminal law real, for the negation that effects a totality is real for that reason. In a case of civil wrong I am in possession of someone else’s property, not by robbery or theft, but because I claim it as mine and justly so. In this way I recognise the other man’s competence to possess property; but force and theft deny this recognition. They are compulsive, affecting the whole; they cancel freedom and the reality of being universal and recognised. If crime did not give the lie to this recognition, it could equally well surrender to another, to the universal, what it accomplishes. Justice in civil matters therefore simply affects something determinate; but penal justice must also cancel, apart from the determinate thing, both the negation of universality and also the universality put in place of the other — opposition is opposed by opposition. This cancellation is punishment, and it is determined precisely by the determinate way in which universality has been cancelled. 1. Civil punishment. 2. Penal punishment. 3. War. Here universality and singular individuality are one, and the essence is this totality. In 1 the essence is universality, in 2 singular individuality, in 3 identity: the people becomes the criminal who is in 2 and sacrifices the possessions of 1; it sides with the negative in 1 and 2; for the first class, 3 is appropriate. |
b) 第二の統治システム 正義のシステム 第一のシステムでは、普遍と個別の対立は形式的なものである。普遍的なものである価値と、個別的なものであるニーズや所有物は、問題の本質を決定するもの ではなく、問題の外側にある。本質とは、必要性との結びつきのままである。しかし、この普遍と特殊の分離のシステムにおいては、本質であるのは理想的な決 定主義である。必要性と結びついているものは、財産として、この個別主義的所有としてさえ、本質的に普遍的なものであるように決定されている。その所有物 は私のものであり、私のものとして無効化されてはいない。しかし、私がそれとともに立っている相対的同一性、すなわち無効化(すなわち所有)の観念性、こ の客観性は、人の心の中に存在する主観的なものとして仮定される。このため、この同一性として、それ[=性質]は直観であり、この単一のものに対する直観 ではなく、絶対的な直観である。必要性との結びつきは客観的な現実性を持っている。自己は普遍的であり、確立され、存在する。その結びつきは普遍的なもの として決定される。 この結びつきの中間項、現実が政府である。所有の結びつきが理想的なものではなく、現実的なものでもあるという事実は、すべての自己がこの結びつきを確立 しているという事実であり、結びつきの経験的自己が自己の全体的な塊として存在しているという事実である。この塊は、その量の抽象化によれば、公権力であ り、この公権力は、思考し意識する(sich bewusst)ものとして、ここでは正義の行政としての政府である。 この行政として、政府はすべての権利の全体であるが、この特定の個人の必要性と事物の結びつきの利益に対しては完全に無関心である。政府にとって、この個 人は完全に無関心な普遍的人格である。純粋な正義において問題となるのは、単に普遍的なもの、所有と利得の態様の抽象的な側面だけである。しかし、正義は それ自体が生きたものでなければならず、人格に配慮しなければならない。 しかし、この形式の法則は恣意的なものであり、正義が意識という形式において法則として存在することは必要である。 しかし、この形式は恣意的なものであり、権利にとって必要なものである。権利は特異な事例に関係し、普遍性の抽象である。この特異な場合とは、個々人の生 きている存在であるか、個々人の相対的同一性[すなわち、個々人の財産の一部]であるか、あるいは、個々人自身の生を特異なものとして、あるいは相対的同 一性としてとらえたものである。 だから、特異な個性の否定(絶対普遍的なものでなく、一個人によって生み出される否定)は、純粋にそのようなものとしての所有権の否定であり、あるいは、 個々人の生きている一側面の否定であり、あるいは、生きている個々人の全体の否定である。第二の否定は暴力的行為であり、第三は死である。 絶対的な政府は、この問題に関して、第二の階級と第三の階級(これは第一の階級を通じて民法の下にある)を自分たちに任せ、所有という絶対的に確定された 有限性を無限に想定しようとするむなしい努力に彼らを放っておくことができる。この試みは、民法の完全性の試み、司法手続に関する絶対的な意識として示さ れ、そのようなものは、規則が規則としての形式において自足し、裁判官は純粋に器官であり、全体に対する生命や直観を持たず、議論中の特異なケースの絶対 的な抽象であろう。 この誤った無限は、憲法の有機的な性格によって脇に置かれなければならない。有機的な性格とは、普遍的なものを個別主義の中に絶対的に取り込むものである。 有機的な原理は自由であり、支配者が自ら被支配者であるという事実である。しかし、ここでは、政府は普遍的なものとして、一個人に関わる規則の衝突に反対 したままであるため、支配者と被支配者の同一性は、第一に、同じ貴族階級に典型的な出生の平等、より狭い範囲の貴族の家系にふさわしい憲法が、同じ市民権 の下に共に住むものとして、すべての階級の全体へと拡大され、市民として共に住むことが生きた統一を構成するように確立されなければならない。第二に、単 一の法的判断の実際においては、法の抽象性が絶対的なものであってはならない。それどころか、全体が衡平性に従った和解、すなわち、当事者の個人としての 状況全体を考慮した和解、満足を生む和解でなければならず、当事者の納得と同意のもとに成立するものでなければならない。 この自由の原則は、その機械的な構成において、法裁判所の組織として理解され、紛争の分析とそれに対する決定である。 民法の運営においては、紛争において絶対的に否定されるのは、そのようなものとしての決定性だけであり、生業、仕事、個人的なものは、決定的なものになりうる。 しかし、刑法では、否定されるのは決定論的なものではなく、人格、全体の無関心、人生、人格である。民法における否定は純粋に理想的なものであるが、刑法 においては現実的なものである。民事上の不法行為の場合、私は他人の財産を所有しているが、それは強盗や窃盗によるものではなく、私がそれを自分のもので あると主張し、正当であるからである。このようにして私は、財産を所有する相手の能力を認識する。しかし武力と窃盗は、この認識を否定する。それらは強制 であり、全体に影響を及ぼす。自由と、普遍的で承認された存在であるという現実を打ち消すのだ。もし犯罪がこの認識を否定するものでなければ、犯罪が達成 するものを別のもの、普遍的なものに委ねることも同様に可能である。 従って、民事上の正義は、単に確定的なものに影響を与えるだけである。しかし、刑事上の正義は、確定的なものとは別に、普遍性の否定と、他者に取って代わられた普遍性の両方を打ち消さなければならない--対抗は対抗によって対抗されるのである。 この取り消しが刑罰であり、それはまさに普遍性が取り消された確定的な方法によって決定される。 1. 内罰である。2. 刑罰。3. 戦争。ここでは普遍性と特異な個性は一体であり、本質はこの全体性である。 1では本質が普遍性であり、2では特異な個性であり、3では同一性である。人民は2の犯罪者となり、1の財産を犠牲にし、1と2では否定的な側に立つ。 |
| c) The third system of Government: System of Discipline In this system the universal is the Absolute, and purely as such the determining factor. In the first system the universal is the crude, purely quantitative, and wisdomless universal, in the second the universality of the concept, formal universality, recognition. Thus for the absolutely universal, difference exists too; this difference superseded the universal in the universal’s movement, but it is a superficial and formal difference, and the essence of the differents is absolute universality. Similarly in the first system the essence of the different is feeling, need, and enjoyment, in the second the essence of the different is to be a singular person, something formally absolute. The universal, the cause, is determined by its essence like the particular. I. Education; II. Training (Bildung) and Discipline (Zucht); the first consists formally of talents, inventions, science. What is real is the whole, the absolutely universal, the inherently self-moving character of the people, the absolute bond, the true and absolute reality of science. Inventions affect only something singular, just as the single sciences do, and where these are absolute in the shape of philosophy, they yet are wholly ideal. Training in the truth, with the destruction of all appearance, is the self-developing and deliberating and conscious people; the other side is the police as disciplining singular cases. The great discipline consists of the universal mores, the social order, training for war, and the testing of the reliability of the single individual in war. III. Procreation of children; the way that a people becomes objective to itself as this people; the fact that the government, the people, produces another people. Colonisation. |
c) 第三の統治システム 規律制度 このシステムでは、普遍的なものは絶対的なものであり、純粋にそのようなものが決定要因である。第一の体系では、普遍は粗野で、純粋に量的で、知恵のない 普遍であり、第二の体系では、概念の普遍、形式的な普遍、認識である。この差異は普遍の運動において普遍に取って代わるが、それは表面的で形式的な差異で あり、差異の本質は絶対的普遍性である。同様に、第一の体系において異なるものの本質は、感情、必要性、享受であり、第二の体系において異なるものの本質 は、特異な人格であること、形式的に絶対的なものであることである。普遍的なもの、原因は、個別主義のようにその本質によって決定される。 I. 教育、II. 第一は形式的に才能、発明、科学からなる。実在するのは全体であり、絶対的に普遍的なものであり、人民の本質的に自己を動かす性格であり、絶対的な絆であ り、科学の真なる絶対的実在である。発明は、単一な科学がそうであるように、単一なものにしか影響を及ぼさず、これらが哲学の形で絶対的なものである場 合、それらはまだ完全に理想的なものである。あらゆる見かけを破壊して真理を訓練することは、自己を開発し熟議し自覚する人々であり、その反対は、特異な 事例を規律する警察である。偉大な規律は、普遍的な風俗、社会秩序、戦争のための訓練、戦争における一個人の信頼性のテストからなる。 III. 人民がその人民を客観視するようになる方法、政府、人民が別の人民を生み出すという事実。植民地化。 |
| C. Free government[47] Possible forms of a free government: I. Democracy. II. Aristocracy. III. Monarchy. Each is capable of becoming unfree: I. Ochlocracy. II. Oligarchy. III. Despotism. The external and mechanical element is the same. The difference is caused by the relation of ruler to ruled, i.e., whether the essence is the same and the form of opposition is only superficial. Monarchy is the exhibition of the absolute reality of ethical life in one individual, aristocracy in several individuals. The latter is distinguished from the absolute constitution by hereditariness, still more by landed estate, and, because it has the form of the absolute constitution and not its essence, it is the worst constitution. — Democracy exhibits this absolute reality in everyone; consequently it involves confusion with possession, and there is no separation of the absolute class. For the absolute constitution the form of aristocracy or monarchy is equally good. That constitution is democracy too in the organisation of the classes. In monarchy a religion must stand alongside the monarch. He is the identity of the whole, but in an empirical shape; and the more empirical he is, the more barbaric the people is, and the more the monarchy has authority, and the more independently it constitutes itself. The more the people becomes one with itself, with nature and ethical life, all the more does it take the Divine into itself and suffer loss [lose faith?] in this religion that resists it; and then by reconciliation with the world and itself it passes through the lack of imagination that typifies irreligion and the understanding. This is the case also in aristocracy, but on account of its patriarchal, or pap for the children[48] character, there is little imagination or religion. In democracy absolute religion does exist, but unstably, or rather it is a religion of nature; ethical life is bound up with nature, and the link with objective nature makes democracy easy of access for the intellect. For the positing of nature as something objective — Epicurean philosophy — the religion must be purely ethical, and so must the imagination of the absolute religion, and art, too, which has produced Jupiter, an Apollo, a Venus — not Homeric art, where Jupiter and Juno are air and Neptune is water [so that it is natural, not ethical]. This separation must be complete, the ethical movement of God absolute, not crime and weakness [as in the Homeric gods] but absolute crime — death [as in the Crucifixion]. |
C. 自由政府[47] 自由政府の可能な形態 I. 民主主義。II。貴族制。III. 君主制。 それぞれが不自由になる可能性がある: I. オクロクラシー。II. 寡頭政治。III. 専制君主制。外的・機械的要素は同じである。異なるのは、支配者と被支配者の関係、つまり本質が同じで対立の形が表面的なものにすぎないかどうかによって生じる。 君主制は、倫理的生活の絶対的な現実を一個人に示すものであり、貴族制は複数の個人に示されるものである。後者は、世襲性によって、さらに地所によって、 絶対的な憲法と区別され、絶対的な憲法の形式を持ち、その本質を持たないので、最悪の憲法である。- 民主主義は、この絶対的な現実をすべての人に示す。その結果、所有と混同され、絶対的な階級が分離されることはない。絶対憲法にとっては、貴族制や君主制 の形態も同様に良いものである。その憲法は、階級の組織においては民主主義でもある。 君主制では、宗教は君主と並立しなければならない。そして、彼が経験的であればあるほど、人民はより野蛮になり、君主制がより権威を持ち、より独自に構成 されるようになる。人民が自分自身と、自然や倫理的生活と一体化すればするほど、人民は神を自分自身の中に取り込み、それに抵抗するこの宗教に苦悩する。 これは貴族制にも言えることだが、その家父長制的な、あるいは子供のためのパパ[48]的な性格のために、想像力も宗教もほとんどない。 倫理的生活は自然と結びついており、客観的自然との結びつきによって、民主主義は知性にとってアクセスしやすいものとなっている。自然を客観的なものとし て措定すること-エピクロス哲学-にとって、宗教は純粋に倫理的でなければならず、絶対的宗教の想像力もそうでなければならず、芸術もそうでなければなら ない。この分離は完全なものでなければならず、神の倫理的な動きは絶対的なものであり、[ホメロスの神々のような]罪や弱さではなく、[十字架刑のよう な]絶対的な罪、すなわち死でなければならない。 |
| G.W.F. Hegel, System of Ethical Life (1802/3) |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099