
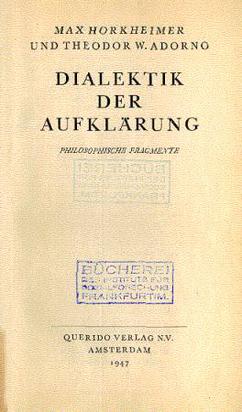
テオドール・アドルノ
Theodor Wiesengrund Adorno, 1903-1969

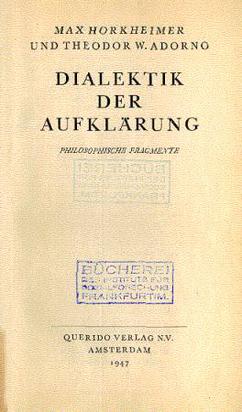
Horkheimer, Theodor W. Adorno, and Habermas
at Heidelberg / Dialektik der Aufklärung, 1947
☆ テオドール・W.アドルノ(1903-1969)は、フロイト、マルクス、ヘーゲルの著作が現代社会を批判する上で不可欠であったフランクフルト学派の批評理論の主要メンバーであり、エルンスト・ブロッホ、 ヴァルター・ベンヤミン、マックス・ホルクハイマー、エーリッヒ・フロム、ヘルベルト・マルクーゼといった思想家たちとその活動は関連づけられるように なった。ファシズムと、彼が文化産業と呼ぶものの両方を批判した彼の著作(『啓蒙の弁証法』(1947年)、『ミニマ・モラリア』(1951年)、『否定 弁証法』(1966年)など)は、ヨーロッパの新左翼に強い影響を与えた。古典的な訓練を受けたピアニストであったアドルノは、アーノルド・シェーンベルクの十二音技法に共鳴し、第二ウィーン楽派のアルバン・ベルクに作曲を師事 した。前衛音楽への傾倒がその後の著作の背景となり、第二次世界大戦中、亡命者としてカリフォルニアに住んでいた二人は、トーマス・マンの小説『ファウス トゥス博士』での共同作業につながった。新たに移転した社会研究所で働くようになったアドルノは、権威主義、反ユダヤ主義、プロパガンダに関する影響力の ある研究を共同で行い、後に同研究所が戦後ドイツで行った社会学的研究のモデルとなった。フランクフルトに戻ったアドルノは、実証主義科学の限界に関するカール・ポパーとの論争、ハイデガーの真正性の言葉に対する批判、ホロコーストに対するド イツの責任に関する著作、公共政策への継続的な介入などを通じて、ドイツの知的生活の再構築に関わった。ニーチェやカール・クラウスの伝統を受け継ぐポレ ミクスの作家として、アドルノは現代西洋文化を痛烈に批判した。死後に出版された『美学論』は、サミュエル・ベケットに捧げる予定だったもので、哲学史が 長年求めてきた感覚と理解の「致命的な分離」を撤回し、美学が形式よりも内容、没入よりも熟考に与える特権を爆発させようとする、現代芸術への生涯をかけ たコミットメントの集大成である。
| Theodor W. Adorno
(* 11. September 1903 in Frankfurt am Main; † 6. August 1969 in Visp,
Schweiz; eigentlich Theodor Ludwig Wiesengrund) war ein deutscher
Philosoph, Soziologe, Musikphilosoph, Komponist und Pädagoge. Er zählt
mit Max Horkheimer zu den Hauptvertretern der als Kritische Theorie
bezeichneten Denkrichtung, die auch unter dem Namen Frankfurter Schule
bekannt wurde. Mit Horkheimer, den er während seines Studiums
kennengelernt hatte, verband ihn eine enge lebenslange Freundschaft und
Arbeitsgemeinschaft. Adorno wuchs in großbürgerlichen Verhältnissen in Frankfurt auf. Als Kind erhielt er eine intensive musikalische Erziehung, und bereits als Schüler beschäftigte er sich mit der Philosophie Immanuel Kants. Nach dem Studium der Philosophie widmete er sich der Kompositionslehre im Kreis der Zweiten Wiener Schule um Arnold Schönberg und betätigte sich als Musikkritiker. Ab 1931 lehrte er zudem als Privatdozent an der Universität Frankfurt bis zum Lehrverbot 1933 durch die Nationalsozialisten. Sein Antrag auf Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer wurde am 20. Februar 1935 abgelehnt. Während der Zeit des Nationalsozialismus emigrierte er in die USA. Dort wurde er Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung, bearbeitete einige empirische Forschungsprojekte, unter anderem über den autoritären Charakter, und schrieb mit Max Horkheimer die Dialektik der Aufklärung. Nach seiner Rückkehr war er einer der Direktoren des in Frankfurt wiedereröffneten Instituts. Wie nur wenige Vertreter der akademischen Elite wirkte er als „öffentlicher Intellektueller“ mit Reden, Rundfunkvorträgen und Publikationen auf das kulturelle und intellektuelle Leben Nachkriegsdeutschlands ein und trug – mit allgemeinverständlichen Vorträgen – gewollt und mittelbar zur demokratischen Reeducation der deutschen Bevölkerung bei.[1] Adornos Arbeit als Philosoph und Sozialwissenschaftler steht in der Tradition von Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx und Sigmund Freud. Wegen der Resonanz, die seine schonungslose Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft unter den Studenten fand, galt er bei Befürwortern und Kritikern als einer der geistigen Väter der deutschen Studentenbewegung. Obwohl er die Kritik der Studenten an den restaurativen Tendenzen der spätkapitalistischen Gesellschaft teilte, stand er dem Wirken der Studentenbewegung wegen deren Hang zu blindem Aktionismus und wegen ihrer Gewaltbereitschaft mit Befremden und Distanz gegenüber.[2] |
テオドール・W・アドルノ(本名テオドール・ルートヴィヒ・ヴィーゼン
グルント、1903年9月11日 - 1969年8月6日)は、ドイツの哲学者、音楽学者、作曲家、教育者である。
生涯の友人であり同僚でもあったマックス・ホルクハイマーとともに、フランクフルト学派の前身である社会研究協会で展開した批判理論の分野における業績で
最もよく知られている。彼はホルクハイマーと生涯にわたって親密な交友関係と仕事上の関係を築き、ホルクハイマーとは学生時代に出会った。 アドルノはフランクフルトの上流中流階級の家庭で育った。幼少期から音楽教育を受け、学生時代にはすでにイマヌエル・カントの哲学を学んでいた。哲学を学 んだ後、彼はアルノルト・シェーンベルクを中心とする「第二ウィーン学派」のサークルで作曲の研究に専念し、音楽評論家としても活動した。1931年から はフランクフルト大学で非常勤講師として教鞭を執っていたが、1933年にナチスによって教壇から追放された。1935年2月20日、ドイツ文学院への入 会申請は却下された。 ナチス時代には米国に移住し、社会研究協会のメンバーとなり、権威主義的性格に関する研究を含むいくつかの実証的研究プロジェクトに従事し、ホルクハイ マーと『啓蒙の弁証法』を共著した。帰国後、フランクフルトで研究所が再開された際には、その理事の一人となった。学術エリートの代表的人物としては珍し く、彼は「公共の知識人」として講演、ラジオ講座、出版活動を通じて戦後ドイツの文化と知的活動に影響を与え、一般の人々にも理解できる講義を通じて、ド イツ国民の民主的な再教育に意図的かつ間接的に貢献した。 アドルノの哲学者および社会科学者としての業績は、イマニュエル・カント、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、カール・マルクス、ジークム ント・フロイトの伝統に根ざしている。資本主義社会に対する容赦ない批判が学生たちから大きな反響を得たため、アドルノは支持者からも批判者からも、ドイ ツの学生運動の精神的指導者の一人とみなされるようになった。彼は、後期資本主義社会の復古的な傾向に対する学生たちの批判には共感していたが、学生運動 の行動については、盲目的な活動主義や暴力に訴える傾向があるとして、疎外感と距離を持って見ていた。 |
| Inhaltsverzeichnis 1 Leben 1.1 Herkunft und Name 1.2 Frühe Frankfurter Jahre (bis 1924) 1.3 Aufenthalt in Wien (1925–1926) 1.4 Mittlere Frankfurter Jahre (1926–1934) 1.5 Zwischenstation Oxford (1934–1937) 1.6 Emigrant in den USA (1938–1953) 1.7 Späte Frankfurter Jahre (1949–1969) 2 Einflüsse auf das Werk 2.1 Hegel 2.2 Karl Marx 2.3 Sigmund Freud 2.4 Rezeption weiterer Autoren 3 Werk 3.1 Philosophie 3.1.1 Negative Dialektik: Adornos „Philosophie des Nichtidentischen“ 3.1.2 Kritik der Erkenntnistheorie 3.1.3 Negative Moralphilosophie 3.1.4 Metaphysik und Metaphysikkritik 3.1.5 Positivismuskritik 3.2 Soziologie 3.2.1 Gesellschaftskritik 3.2.2 Empirische Sozialforschung 3.3 Ästhetik und Kulturkritik 3.3.1 Ästhetische Theorie 3.3.2 Literatur: Interpretation und Kritik 3.3.3 Kulturkritische Schriften 3.3.4 Kulturindustrie 3.4 Pädagogik 3.4.1 Erziehung zur Mündigkeit 3.4.2 Halbbildung 3.5 Musikalische Schriften 3.6 Kompositionen 4 Sprache und Darstellungsformen 5 Wirkungsgeschichte 5.1 Gegenpositionen 5.2 Unverständlichkeitsvorwurf 5.3 Erinnerungen 5.3.1 Theodor-W.-Adorno-Preis 5.3.2 Denkmal und Platznamen 5.3.3 Fußgängerampel 5.3.4 Biographien 5.4 Ehrungen 6 Bekannte Schüler 7 Schriften 8 Briefwechsel 9 Kompositionen 10 Literatur 10.1 Einführungen 10.2 Biographien 10.3 Biographische Orte 10.4 Adorno Blätter 10.5 Adorno-Konferenzen 10.6 Frankfurter Seminare 10.7 Weiterführende Studien 11 Filme 12 Hörspiel 13 Frankfurter Adorno-Vorlesungen 14 Weblinks 15 Anmerkungen und Einzelnachweise |
目次 1 生涯 1.1 起源と名前 1.2 フランクフルト初期(1924年まで 1.3 ウィーン滞在(1925年~1926年 1.4 フランクフルト中期(1926年~1934年 1.5 オックスフォード滞在(1934年~1937年 1.6 アメリカへの亡命(1938年~1953年) 1.7 晩年のフランクフルト時代(1949年~1969年) 2 作品に与えた影響 2.1 ヘーゲル 2.2 カール・マルクス 2.3 ジークムント・フロイト 2.4 他の作家の受容 3 作品 3.1 哲学 3.1.1 ネガティブ・ダイアレクティーク:アドルノの「非同一の哲学」 3.1.2 認識論批判 3.1.3 否定的道徳哲学 3.1.4 形而上学と形而上学批判 3.1.5 実証主義批判 3.2 社会学 3.2.1 社会批判 3.2.2 経験的社会研究 3.3 美学と文化批評 3.3.1 美学理論 3.3.2 文学:解釈と批評 3.3.3 文化批評 3.3.4 文化産業 3.4 教育 3.4.1 成熟のための教育 3.4.2 半端な教育 3.5 音楽作品 3.6 作曲 4 言語と表現形式 5 受容の歴史 5.1 反対意見 5.2 理解不能という非難 5.3 記憶 5.3.1 テオドール・W・アドルノ賞 5.3.2 記念碑と広場の名称 5.3.3 歩行者用信号機 5.3.4 伝記 5.4 栄誉 6 著名な学生 7 著作 8 書簡 9 作曲 10 文学 10.1 紹介 10.2 伝記 10.3 伝記的な場所 10.4 アドルノ文書 10.5 アドルノ会議 10.6 フランクフルト・ゼミナール 10.7 さらなる研究 11 映画 12 ラジオドラマ 13 フランクフルト・アドルノ講座 14 ウェブリンク 15 注釈および参考文献 |
| Leben Herkunft und Name Adorno wurde 1903 in Frankfurt als Theodor Ludwig Wiesengrund geboren. Er war das einzige Kind des Weingroßhändlers Oscar Alexander Wiesengrund (1870–1946) und der Sängerin Maria Calvelli-Adorno (1865–1952). Die katholische Mutter war Tochter eines korsischen Offiziers, der sich um 1860 als mittelloser Fechtmeister in der Freien Stadt Frankfurt niedergelassen hatte. Sie trat als ausgebildete Sängerin auch am kaiserlichen Hof in Wien, an der Wiener Oper[3] und an den Stadttheatern Köln und Riga auf. Der Vater, Oscar Alexander Wiesengrund, stammte aus einer jüdischen Familie und gehörte zur Zeit der Geburt des Sohnes noch der mosaischen (jüdischen) Religion an;[4] erst später konvertierte er zum Protestantismus. Die von Theodor vorgenommene Ergänzung des väterlichen Nachnamens um den Namen der Mutter soll ein Wunsch der Mutter gewesen sein, er erfüllte sich jedoch erst später. Während die ersten Veröffentlichungen noch mit „Wiesengrund“ gezeichnet waren, verwendete er in seiner publizistischen Tätigkeit früh den Doppelnamen „Wiesengrund-Adorno“. Eine Verkürzung auf „W. Adorno“ nahm er bei seinen Veröffentlichungen in der US-amerikanischen Emigration vor. Nach der formellen Einbürgerung als US-Bürger Ende 1943 lautete sein amtlicher Name „Theodore Adorno“.[5] Seine Publikationen zeichnete er indes fortan mit Theodor W. Adorno. |
生涯 生い立ちと名前 アドルノは1903年、テオドール・ルートヴィヒ・ヴィーゼングルントとしてフランクフルトに生まれた。ワイン卸売業者のオスカー・アレクサンダー・ ヴィーゼングルント(1870年~1946年)と歌手のマリア・カルヴェッリ=アドルノ(1865年~1952年)の間の一人っ子であった。カトリック教 徒の母は、1860年頃に無一文のフェンシングの師範としてフランクフルト自由都市に移住したコルシカ人の士官の娘であった。彼女は訓練を受けた歌手であ り、ウィーンの宮廷やウィーン国立歌劇場[3]、ケルンやリガの市立劇場で公演も行っていた。父親のオスカー・アレクサンダー・ヴィーゼングルントはユダ ヤ人家庭の出身で、息子の誕生時にはまだモザイク教(ユダヤ教)に属していたが[4]、後にプロテスタントに改宗した。 テオドールが父の姓に母の名前を加えたのは、明らかに母の希望によるものだったが、それが実現したのはその後になってからだった。最初の著作ではまだ 「ヴィーゼングルント」の署名であったが、間もなくジャーナリストとしての活動では「ヴィーゼングルント=アドルノ」という2つの姓を組み合わせた名前を 使い始めた。米国に移住した際にはこれを「W.アドルノ」と短縮し、1943年末に米国市民として正式に帰化してからは、正式名称は「セオドア・アドル ノ」となった。[5] しかし、彼は自身の出版物の署名を「セオドア・W・アドルノ」と続けた。 |
| Frühe Frankfurter Jahre (bis 1924) Als Kind wurde der Junge „Teddie“ gerufen. Er wuchs in der Schönen Aussicht, Hausnummer 9, auf, einer Straße am Mainufer. Im Nebenhaus betrieb sein Vater eine Weinhandlung, zu der ein großes Weingut im Rheingau gehörte.[6] 1914 zog die Familie in ein neu erbautes Haus im Stadtteil Oberrad in die Seeheimer Straße 19.[7] Adorno wurde römisch-katholisch getauft und empfing die Erstkommunion. Auf Wunsch seiner gläubigen Mutter war er geraume Zeit auch als Ministrant tätig.[8] Anders als etwa seine Jugendfreunde Leo Löwenthal und Erich Fromm, die sich im – in Frankfurt einflussreichen – Freien Jüdischen Lehrhaus betätigten,[9] hatte er zur Religion seiner väterlichen Vorfahren keine besondere Beziehung. Ein engeres Verhältnis zum Judentum gewann er erst unter dem Eindruck des Völkermords an den Juden.[10] Die mit den Adornos befreundete Publizistin Dorothea Razumovsky brachte es auf den Punkt: Nicht sein toleranter und assimilierter Vater, sondern Hitler habe ihn zum Juden gemacht.[11] Im Haushalt der Familie lebte auch die Sängerin und Pianistin Agathe Calvelli-Adorno, eine unverheiratete Schwester seiner Mutter, die Adorno als seine „zweite Mutter“ bezeichnete.[12] Adornos „überaus behütete Kindheit“ war vornehmlich von den beiden „Müttern“ geprägt.[13] Von ihnen erlernte er das Klavierspiel. Die Musik bildete den kulturellen Mittelpunkt der kosmopolitisch ausgerichteten, großbürgerlichen Familie. So zog seine Mutter mit der Partie des Waldvögleins aus Richard Wagners Oper Siegfried durch Europa. Adorno wurde mit der kammermusikalischen und symphonischen Literatur durch das Vierhändigspielen vertraut gemacht und konnte somit seine musikalische Kompetenz schon früh ausbilden.[14] Er nahm neben dem Schulunterricht bei Bernhard Sekles Privatstunden in Komposition. Die Sommer verbrachte die Familie im Odenwaldidyll Amorbach; seitdem galt ihm Amorbach „als die Wirklichkeit gewordene Utopie […], mit der Welt eins zu sein“.[15] Nachdem er zwei Klassen übersprungen hatte, bestand der „privilegierte Hochbegabte“[16] 1921 am Kaiser-Wilhelms-Gymnasium (heute Freiherr-vom-Stein-Schule) in Frankfurt bereits mit 17 Jahren das Abitur als Jahrgangsbester.[17] Als Primus erlebte er Ressentiment und Feindseligkeit, die eine solche Begabung auf sich ziehen kann.[18] So erlitt er im Gymnasium Quälereien derjenigen, die „keinen richtigen Satz zustande brachten, aber jeden von mir zu lang fanden“ (GS 4: 219f).[19] Philosophisch geschult wurde er durch seinen 14 Jahre älteren Freund Siegfried Kracauer, den er bei einer Freundin seiner Eltern kennengelernt hatte. Kracauer war ein bedeutender Feuilletonredakteur der Frankfurter Zeitung. In einem Brief an Leo Löwenthal gestand er, zu seinem jüngeren Freund „eine unnatürliche Leidenschaft“ zu empfinden und sich für „geistig homosexuell“ zu halten.[20] Gemeinsam lasen sie über Jahre hinweg regelmäßig an Samstagnachmittagen Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, eine Erfahrung, die nach Adornos Selbstzeugnis für ihn prägend war: „Nicht im leisesten übertreibe ich, wenn ich sage, daß ich dieser Lektüre mehr verdanke als meinen akademischen Lehrern“ (GS 11: 388). Als Abiturient las er fasziniert die gerade erschienenen Bücher Die Theorie des Romans von Georg Lukács und Geist der Utopie von Ernst Bloch.[21] Im Gymnasium erlernte er Latein, Griechisch und Französisch;[22] später in der Emigration kam Englisch hinzu. An der Universität Frankfurt belegte er ab 1921 Philosophie, Musikwissenschaft, Psychologie und Soziologie; zur gleichen Zeit begann er seine Tätigkeit als Musikkritiker. Philosophie hörte er bei Hans Cornelius, Soziologie bei Gottfried Salomon-Delatour und Franz Oppenheimer.[23] In der Universität traf er 1922 in einem Seminar auf Max Horkheimer, mit dem er theoretische Anschauungen teilte und Freundschaft schloss. Auch mit Walter Benjamin, den er durch Vermittlung Kracauers als Student kennengelernt hatte, pflegte er eine enge und dauerhafte Freundschaftsbeziehung. Das Studium absolvierte er sehr zügig: Ende 1924 schloss er es mit einer Dissertation über Edmund Husserls Phänomenologie mit summa cum laude ab. Die Arbeit, die er im Geist seines Lehrers Cornelius abfasste, enthielt reine Schulphilosophie, die noch wenig von Adornos späterem Denken ahnen ließ. Aus der Geschäftsbeziehung zwischen der Frankfurter Weinhandlung Oscar Wiesengrund und der Berliner Fabrik für Lederverarbeitung Karplus & Herzberger entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Eigentümer-Familien beider Firmen. Zwischen dem temperamentvollen jungen „Teddie“ Wiesengrund und der Berlinerin Margarete (Rufname: Gretel) Karplus kam es zu einer Liebesbeziehung, die zu einer lebenslangen Bindung führen sollte.[24] |
フランクフルトでの初期(1924年まで) 少年時代、アドルノは「テディ」と呼ばれていた。彼はマイン川のほとりにあるSchönen Aussicht 9番地で育った。父親は隣家でワインショップを経営しており、ラインガウ地方に広大なブドウ畑も所有していた。6] 1914年、一家はオーバーラート地区のSeeheimer Straße 19番地に新築された家に引っ越した。 アドルノはローマ・カトリックの洗礼を受け、初聖体を受けた。敬虔な母親の希望で、彼はしばらくの間、侍者も務めた。[8] 幼馴染のレオ・レーヴェンタールやエーリッヒ・フロムなどとは異なり、例えば、フランクフルトで影響力を持っていた自由ユダヤ人学習センターで活動してい たが、[9] 父方の先祖の宗教とは特に縁がなかった。ユダヤ人大虐殺の影響を受けて初めて、ユダヤ教とのより深い関係を築くようになった。10] アドルノ一家の友人で広報担当のドロテア・ラズモフスキーは、簡潔にこう述べている。「彼をユダヤ人にしたのは、寛容で同化主義的な父親ではなく、ヒト ラーだった」11] 歌手でありピアニストでもあったアガタ・カルヴェリ・アドルノは、母の未婚の妹であり、家族と同居していたが、アドルノは彼女を「第二の母」と表現してい た。[12] アドルノの「非常に恵まれた子供時代」は、主にこの2人の「母」によって形作られた。[13] 彼は彼女らからピアノを学んだ。音楽は、国際的で中流の上流階級の家庭の文化の中心であった。例えば、アドルノの母親は、リヒャルト・ワーグナーのオペラ 『ジークフリート』で小鳥の役を演じ、ヨーロッパ中を巡業していた。アドルノは、二重奏を演奏することで室内楽や交響曲のレパートリーに触れ、幼い頃から 音楽のスキルを磨くことができた。彼は学校の授業と並行して、ベルンハルト・ゼクレスから作曲の個人レッスンを受けていた。家族は夏をオデンヴァルトの牧 歌的な町アムorbachで過ごした。それ以来、アムorbachは彼にとって「実現したユートピアであり、世界と一体となる場所」となった。[15] 飛び級で2学年を飛び越えた「恵まれ、非常に才能に恵まれた」[16]彼は、1921年にフランクフルトのカイザー・ヴィルヘルム・ギムナジウム(現在の フライヘア・フォン・シュタイン・シューレ)でAレベルの試験に17歳で首席で合格した。首席の生徒として、彼はその才能が引き寄せる反感や敵意を経験し た。彼は、文法学校の生徒たちから苦しめられた。「まともに文章を組み立てることができず、しかし、自分の文章はどれも長すぎると思っていた」生徒たちか らである(GS 4: 219f)。[19] 彼は、14歳年上の友人ジークフリート・クラカウアーから哲学を紹介された。クラカウアーは、両親の友人を通じて知り合った人物であった。クラカウアーは 『フランクフルター・ツァイトゥング』の重要な編集者であった。レオ・レーヴェンタールに宛てた手紙の中で、彼は年下の友人に対して「不自然な情熱」を抱 いていること、そして「知的同性愛者」であると自認していることを告白している。[20] 彼らは長年にわたり、土曜の午後に定期的にイマヌエル・カントの『純粋理性批判』を一緒に読んでいた。アドルノ自身の説明によると、この経験は彼にとって 形成的なものだった。「 「この読書から学んだことの方が、学問の師から学んだことよりも多い」と彼は述べている(GS 11: 388)。高校を卒業したばかりの頃、彼は最近出版されたゲオルク・ルカーチの『小説論』とエルンスト・ブロッホの『ユートピアの精神』に夢中になって読 んだ。21] 高校ではラテン語、ギリシャ語、フランス語を学んだ。22] その後亡命したことで、英語が加わった。 フランクフルト大学では、1921年より哲学、音楽学、心理学、社会学のコースを受講し、同時に音楽評論家としてのキャリアをスタートさせた。彼はハン ス・コーネリウスによる哲学、ゴットフリート・サロモン=デラトゥールとフランツ・オッペンハイマーによる社会学の講義を受講した。23] 1922年、彼は大学のセミナーでホルクハイマーと出会った。彼らは類似した理論的見解を共有し、友人となった。また、学生時代にクラカウアーを通じて知 り合ったヴァルター・ベンヤミンとも親交を深め、生涯にわたって交友関係を続けた。彼は非常に早く学業を修了し、1924年末にはエドムント・フッサール の現象学に関する論文で卒業し、最優等で卒業した。この論文は、師であるコーネリアスの精神に基づいて書かれたもので、純粋学派の哲学であり、アドルノの 後の思想を予見するものはほとんどなかった。 フランクフルトのワイン商オスカー・ヴィーゼングルントとベルリンの皮革加工工場カルプラス&ヘルツバーガーとのビジネス上の関係は、やがて両社のオー ナー一族の親交へと発展した。活発な若者「テディ」ことヴィーゼングルントと、ベルリン出身のマルガレーテ(愛称はグレーテル)カルプラスは恋に落ち、生 涯を通じて親しい関係を保ち続けた。[24] |
| Aufenthalt in Wien (1925–1926) Im März 1925 zog Adorno nach Wien, der Geburtsstätte der Zwölftonmusik, wo er sich ein Zimmer in der Pension „Luisenheim“ im 9. Bezirk nahm.[25] Bei Alban Berg, dem Schüler Arnold Schönbergs, begann er ein Aufbaustudium in Komposition und bei Eduard Steuermann nahm er gleichzeitig Klavierunterricht. Adorno hatte Alban Berg anlässlich der Uraufführung seiner Drei Bruchstücke für Gesang und Orchester aus Wozzeck 1924 in Frankfurt kennengelernt.[26] Der aus Polen stammende Steuermann, der die meisten Klavierwerke Schönbergs uraufgeführt hatte, war der maßgebliche Pianist der Zweiten Wiener Schule, mit deren Begründer er ebenfalls zusammentraf. Adorno schätzte Schönberg als „revolutionären Veränderer der überlieferten Kompositionsweise“.[27] Dessen Zwölftonkompositionen würdigte er später (1949) in der Philosophie der neuen Musik. Persönlich jedoch entwickelte sich eine „wechselseitige Antipathie“ zwischen beiden.[28] Schönberg hielt Adornos „Schreibstil für manieriert, die musiktheoretische Begriffsbildung für zu unverständlich“ und glaubte, dass dies der Neuen Musik in der öffentlichen Wirkung schade.[29] Adornos musikästhetische Wertschätzung und persönliche Sympathie galten vor allem Alban Berg,[30] zu dem er eine freundschaftliche Beziehung pflegte, die sich bis zu dessen frühem Tod (1935) in einem intensiven Briefwechsel niederschlug. Später veröffentlichte er über ihn die Monographie Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs (1968). Schon im ersten Jahr seines Aufenthalts in Wien verfasste er Aufsätze über Werke von Berg und Schönberg. Er setzte damit seine bereits als Student aufgenommene musikkritische Tätigkeit fort, die er 1928 mit dem Eintritt in die Redaktion der musikalischen Avantgarde-Zeitschrift Anbruch fundieren konnte.[31] Adornos Bestreben, die Zeitschrift als musikpolitisches Machtinstrument zur Durchsetzung avancierter Musik zu nutzen, war jedoch auf Widerstand in der Redaktion gestoßen, aus der er dann 1931 offiziell ausschied.[32] Die Jahre seines Wiener Aufenthalts waren für Adorno die kompositorisch intensivsten. Unter seinen Kompositionen machen eine Reihe von Klavierliederzyklen den umfangreichsten und auch gewichtigsten Teil aus. Daneben schrieb er Orchesterstücke, Kammermusik für Streicher und A-cappella-Chöre und bearbeitete französische Volkslieder. Zusammen mit Berg besuchte er Lesungen von Karl Kraus. Dessen spektakuläre Vortragsweise machte auf ihn anfänglich den Eindruck eines „halb priesterlichen und halb clownesken Komödianten“; erst später, vermittelt durch Lektüre, begann er ihn zu schätzen.[33] Zu den zahlreichen Bekanntschaften, die er in Wien machte, zählte die von Georg Lukács, der hier unter schwierigen Lebensbedingungen als Emigrant lebte. Gegenüber Berg gestand er, dass Lukács ihn „geistig […] tiefer fast als jeder andere beeinflusst“ habe. Dessen Theorie des Romans hatte ihn bereits als Abiturient begeistert und dessen 1922 in Wien abgeschlossene Arbeit Geschichte und Klassenbewußtsein war für seine Marx-Rezeption (wie für die seiner engeren Freunde) eminent wichtig.[34] Eine enge Freundschaft verband ihn in dieser Zeit auch mit dem Prager Schriftsteller und Musiker Hermann Grab. Das intellektuelle und künstlerische Milieu der Wiener Moderne um die Jahrhundertwende prägte anhaltend nicht nur Adornos Musiktheorie, sondern auch seine Kunstauffassung.[35] Mit Alban Berg und dessen Frau Helene besuchte er nicht nur Konzerte und Opern; die Bergs führten ihn auch in exzellente Restaurants. Überhaupt genoss er die sinnliche Lebensfreude der Donaumetropole, inklusive „vorsichtig erprobter Liebschaften“.[36] In die Wiener Zeit fällt ein knapp dreiwöchiger Aufenthalt mit Siegfried Kracauer am Golf von Neapel (September 1925), wo beide mit Walter Benjamin und Alfred Sohn-Rethel zu fruchtbarem Gedankenaustausch zusammentrafen. Martin Mittelmeier interpretiert diesen Aufenthalt als einen Wendepunkt in der intellektuellen Biographie Adornos. Hier habe er unter dem Einfluss Benjamins die für seine Texte bedeutsamste Darstellungsform, die „Konstellation“, gefunden.[37] |
ウィーン滞在(1925年~1926年) 1925年3月、アドルノは12音音楽の発祥の地であるウィーンに移り、9区にある「ルイゼンハイム」という下宿に部屋を借りた。 25] 彼はアルバン・ベルクの作曲の大学院課程に入学し、同時にエドゥアルト・シュトイアマンからピアノのレッスンを受けた。アドルノは1924年にフランクフ ルトで上演されたベルクの『ヴォツェック』の3つの断片の初演でベルクと出会っていた。 26] ポーランド出身で、シェーンベルクのピアノ曲のほとんどを初演したシュトイマンは、第二次ウィーン学派の最も重要なピアニストであり、その創始者とも面識 があった。アドルノはシェーンベルクを「伝統的な作曲法を革命的に変えた人物」と評価していた。[27] 彼は後に、1949年の著書『新音楽の哲学』でシェーンベルクの12音作曲法に敬意を表した。しかし、2人の間には「相互の反感」が芽生えた。28] シェーンベルクはアドルノの文章スタイルを気取りがちだと考え、音楽理論の概念化はあまりにも理解しがたいものだと考え、それは新しい音楽の一般への影響 を損なうものだと考えていた。29] アドルノの音楽美学への評価と個人的な共感は主にアルバン・ベルクに向けられており、30] 彼とは友好的な関係を維持していた そのことは、ベルクが1935年に早世するまで、彼らとの活発な文通に反映されていた。その後、アドルノはベルクに関する単行本『ベルク。最小限の転移の 達人』(1968年)を出版した。 ウィーンに滞在した最初の年に、アドルノはベルクとシェーンベルクの作品に関するエッセイを書いた。こうして、彼は学生時代にすでに始めていた音楽評論の 仕事を継続した。1928年には、前衛的な音楽雑誌『Anbruch』の編集スタッフに加わり、その地位を確立した。アドルノは、同誌を先進的な音楽を推 進する音楽政策の手段として活用しようとしたが、編集スタッフから抵抗を受け、1931年に正式に辞職した。 ウィーンに滞在していた数年間は、アドルノにとって作曲活動が最も活発だった時期であった。彼の作曲作品の中で、ピアノのための歌曲シリーズは最も広範囲 にわたるものであり、最も重要な部分を占めている。さらに、オーケストラ曲、弦楽合奏とアカペラ合唱のための室内楽、そしてフランス民謡の編曲も手がけ た。 ベルクとともに、カール・クラウスの朗読会にも出席した。クラウスの壮観な講演スタイルは、当初は「聖職者と道化師の中間のようなコメディアン」という印 象を与えたが、後に読書を通じて、彼を評価するようになった。[33] ウィーンで知り合った数多くの人物のうちの一人に、亡命者として困難な状況下で暮らしていたゲオルク・ルカーチがいた。彼はベルクに、ルカーチは「知的 に...ほとんど誰よりも深く」彼に影響を与えたと告白した。彼は高校を卒業した時点で既にルカーチの『小説論』に感銘を受けており、1922年にウィー ンで完成したルカーチの著作『歴史と階級意識』は、彼(および彼の親しい友人たち)がマルクスを受け入れる上で極めて重要な意味を持っていた。34] この時期、彼はプラハの作家兼音楽家ヘルマン・グラブとも親交があった。世紀転換期のウィーン・モダニズムの知的・芸術的環境は、アドルノの音楽理論だけ でなく、芸術に対する考え方にも長期的な影響を与えた。 アドルノは、アルバン・ベルクとその妻ヘレーネとともにコンサートやオペラを鑑賞しただけでなく、ベルク夫妻から素晴らしいレストランも紹介された。彼は 一般的に、ドナウの首都の官能的な生きる喜びを享受しており、その中には「慎重に試された恋愛関係」も含まれていた。[36] ウィーン滞在中、アドルノとクラカウアーはジークフリート・クラカウアーとともにナポリ湾で3週間近く過ごし(1925年9月)、そこでヴァルター・ベン ヤミンとアルフレート・ゾン=レーテルと出会い、有益な意見交換を行った。マルティン・ミッテルマイアーは、この滞在をアドルノの知的伝記における転換点 と解釈している。ベンヤミンの影響を受け、彼は自身のテキストに最もふさわしい表現形式、すなわち「コンステレーション」を見出したのである。[37] |
| Mittlere Frankfurter Jahre (1926–1934) Zurück aus Wien widmete er sich der musikpublizistischen Tätigkeit und dem Komponieren. Daneben begann Adorno die Arbeit an einer Habilitationsschrift. Die Ergebnisse einer ausführlichen Beschäftigung mit der Psychoanalyse verarbeitete er in einer umfangreichen philosophisch-psychologischen Abhandlung mit dem Titel Begriff des Unbewußten in der transzendentalen Seelenlehre, die er seinem Doktorvater Cornelius vorlegte. Nachdem dieser Bedenken geäußert hatte, denen sich sein Assistent Horkheimer anschloss, zog Adorno 1928 das Habilitationsgesuch zurück. Cornelius hatte bemängelt, dass die Arbeit zu wenig originell sei und sein eigenes, Cornelius’, Denken paraphrasiere.[38] Die Jahre 1928–1930 waren für Adorno Jahre der beruflichen Ungewissheit. Vergeblich bemühte er sich um eine feste Anstellung als Musikkritiker bei Ullstein in Berlin. Zahlreiche Kompositionen und musikkritische Beiträge aus dieser Zeit zeugen indessen von nicht erlahmter Produktivität. Über seine finanzielle Lage brauchte er sich keine Sorgen zu machen, sein Vater hatte ihm weitere Unterstützung zugesagt.[39] Adorno weilte in diesen Jahren mehrfach in Berlin bei der – mit ihm inzwischen verlobten – promovierten Chemikerin und Unternehmerin Gretel Karplus. Mit ihr unternahm er auch mehrere Reisen, u. a. nach Amorbach, Italien und Frankreich.[40] Während der Aufenthalte in Berlin traf er mit vielen zeitgenössischen Autoren und Künstlern zusammen, u. a. mit Ernst Bloch, Kurt Weill, Hanns Eisler und Bertolt Brecht. Adorno konzentrierte sich zudem auf die Abfassung einer zweiten Habilitationsschrift. Er hatte das Angebot des 1929 auf einen philosophischen Lehrstuhl neu berufenen evangelischen Theologen Paul Tillich, bei ihm zu habilitieren, angenommen. Nachdem er binnen eines Jahres die Arbeit über den dänischen Existentialphilosophen und Hegel-Kritiker Kierkegaard niedergeschrieben hatte, reichte er sie unter dem Titel Kierkegaard – Konstruktion des Ästhetischen ein und wurde damit im Februar 1931 an der Frankfurter Universität habilitiert. Die stark überarbeitete Buchausgabe (1933) trug die Widmung: „Meinem Freunde Siegfried Kracauer“. Kontakt zu linksorientierten Frankfurter Intellektuellen pflegte er in einem Kreis, „Kränzchen“ genannt, der im lockeren Turnus im Café Laumer zur Diskussion zusammentraf. Zu ihm gehörten Horkheimer, Tillich, Friedrich Pollock, der Nationalökonom Adolf Löwe und der frisch berufene Soziologe Karl Mannheim. Obwohl noch ohne Habilitation, genoss Adorno „das Privileg“, zu jenem „Kränzchen“ geladen zu werden.[41] Nachdem Adorno die Venia legendi verliehen worden war, hielt er im Mai 1931 seine Antrittsvorlesung als Privatdozent für Philosophie; ihr Titel: Die Aktualität der Philosophie, die viele Gedanken enthielt, die in sein späteres Werk eingingen.[42] Im Auftrag Tillichs hatte Adorno schon vor der Antrittsvorlesung an der Frankfurter Universität Seminare veranstaltet. Sie waren, wie die nach seiner Ernennung zum Privatdozenten selbstständig durchgeführten Kollegs, der Ästhetik gewidmet. Nach der ihm erteilten Lehrbefugnis verblieben ihm noch vier Semester an der Frankfurter Universität. Zu den angebotenen Lehrveranstaltungen gehörten – neben „Kierkegaard“ und „Erkenntnistheoretische Übungen (Husserl)“ – „Probleme der Kunstphilosophie“, eine Veranstaltung, in der er sich mit Benjamins Schrift Ursprung des deutschen Trauerspiels befasste,[43] die Benjamin bereits 1925 als Habilitationsschrift bei der Frankfurter Philosophischen Fakultät eingereicht hatte und die von dieser abgelehnt worden war. Vor seiner Emigration in die USA gehörte Adorno noch nicht zu den offiziellen Mitarbeitern des Instituts für Sozialforschung (anders als Horkheimer, Pollock, Fromm und Löwenthal), publizierte aber bereits im ersten Heft der von Horkheimer seit 1932 herausgegebenen Zeitschrift für Sozialforschung den Aufsatz Zur gesellschaftlichen Lage der Musik. Darin untersuchte er ideologiekritisch die Produktion und Konsumtion von Musik in der kapitalistischen Gegenwartsgesellschaft. Adornos Lehrtätigkeit endete mit dem Wintersemester 1933. Das nationalsozialistische Regime entzog ihm im Herbst wegen seiner väterlicherseits jüdischen Abstammung die Befugnis zur akademischen Lehre. Wie viele andere Intellektuelle seiner Zeit erwartete er keine lange Dauer des neuen Regimes und räumte rückblickend ein, dass er die politische Lage 1933 völlig falsch beurteilt hatte.[44] Er machte sich anfangs sogar noch Hoffnung auf den Posten eines Musikkritikers bei der Vossischen Zeitung. In der Zeitschrift Europäische Revue glossierte er das von den Nationalsozialisten durchgesetzte Verbot des „Negerjazz“ dahingehend, dass das Dekret nachträglich bestätige, was sich musikalisch bereits vollzogen habe. Auch lobte er 1934 Männerchöre, die vertonte Gedichte von Hitlers Jugendführer Baldur von Schirach sangen.[45] Im Wintersemester 1962/63 von der Frankfurter Studentenzeitung Diskus mit diesen Veröffentlichungen konfrontiert, bedauerte er in einem offenen Brief seine „dumm-taktischen Sätze“, die der Torheit dessen zuzuschreiben seien, „dem der Entschluß zur Emigration unendlich schwer fiel“.[46] Wie naiv er die anfängliche Lage nach der nationalsozialistischen Machtergreifung beurteilte, zeigt ein Brief vom 15. April 1933 an den im Pariser Exil befindlichen Siegfried Kracauer, in dem er ihm riet, nach Deutschland zurückzukehren, denn: „Es herrscht völlige Ruhe und Ordnung, ich glaube, die Verhältnisse werden sich konsolidieren. [...] auch ein übereilter und kostspieliger Umzug [nach Paris] schiene mir bedenklich“.[47] Leo Löwenthal vermerkte: „wir mußten ihn fast physisch dazu zwingen, endlich Deutschland zu verlassen“.[48] |
フランクフルト中期(1926年~1934年) フランクフルトに戻ったアドルノは、音楽ジャーナリストとしての仕事と作曲活動に専念した。同時に、アドルノは博士号取得後の論文の執筆に取り掛かった。 彼は精神分析学の広範な研究結果を、包括的な哲学的心理学論文「魂の超越論的教義における無意識の概念」に盛り込み、指導教官のコルネリウスに提出した。 後者が保留の意を示し、助手のホルクハイマーもそれに同調したため、アドルノは1928年にハビリタス申請を取り下げた。コーネリウスは、その作品が独創 性に欠け、自身の考えを言い換えていると批判した。 1928年から1930年にかけては、アドルノにとって職業上の不安定な時期であった。彼はベルリンのウルトシュタイン社で音楽評論家として常勤の職を得 ようとしたが、それは叶わなかった。しかし、この時期に作曲した数々の作品や音楽評論は、彼の創作意欲が衰えていないことを証明している。父親がさらなる 支援を約束していたため、経済的な心配をする必要はなかった。アドルノは、この時期に何度かベルリンに滞在し、グレテル・カルプラスと過ごした。彼女は化 学の博士号を取得しており、アドルノの婚約者であった。また、彼女とともにアモルバッハ、イタリア、フランスなどへの旅行も何度か行った。ベルリン滞在中 には、エルンスト・ブロッホ、クルト・ヴァイル、ハンス・アイスラー、ベルトルト・ブレヒトなど、多くの同時代の作家や芸術家と出会った。 アドルノは、2つ目のハビリテーション論文の執筆にも集中した。1929年に哲学教授職に任命されたプロテスタント神学者のパウル・ティリッヒの誘いを受 け、彼のもとでハビリテーションを行うことになったのだ。1年以内にデンマークの実存主義哲学者でヘーゲル批判者でもあるキルケゴールの論文を書き上げ、 タイトルを「キルケゴール - 美的構成」として提出し、1931年2月にフランクフルト大学でハビリテーション(ハビリタート)を取得した。大幅に改訂された書籍版(1933年)は 「友ジークフリート・クラカウアーに捧ぐ」と献辞が記されていた。 彼は、フランクフルトの左派系知識人たちと交流を保っていた。彼らは「クレンツェン」と呼ばれるサークルを結成し、不定期にカフェ・ラウマーで議論を行っ ていた。そのメンバーには、ホルクハイマー、ティリッヒ、フリードリヒ・ポロック、経済学者アドルフ・レーヴェ、そして新たに赴任した社会学者カール・マ ンハイムなどがいた。ハビリタート(大学教授資格)を取得していなかったアドルノだが、こうした「懇談会」に招待される「特権」を享受していた。[41] アドルノがハビリタートを取得した後、1931年5月に哲学の非常勤講師として就任講演を行い、そのタイトルは『哲学の現存在』であった。この講演では、後の作品で取り上げられることになる多くのアイデアが提示された。[42] ティリッヒの指示により、アドルノは就任講演に先立ってフランクフルト大学で既にセミナーを行っていた。個人講師として任命された後に独自に教えた講座と 同様に、それらは美学に専念したものだった。講師としての認可を得た後も、アドルノはさらに4学期間フランクフルト大学に留まった。キルケゴール』、『認 識論的練習(フッサール)』に加えて、彼が担当した科目には『芸術哲学の問題』があり、この科目ではベンヤミンが1925年にフランクフルト哲学部にハビ リテーション論文として提出し、却下されていた『ドイツ悲劇の起源』[43]を扱っていた。 アドルノは米国への移住前、社会研究機関の正式なスタッフではなかったが(ホルクハイマー、ポロック、フロム、ローウェンタールとは異なり)、ホルクハイ マーが1932年から編集していた雑誌『Zeitschrift für Sozialforschung』の創刊号に「音楽の社会的状況について」という論文をすでに発表していた。そこでは、現代の資本主義社会における音楽の 生産と消費をイデオロギー的な観点から考察している。 アドルノの教職は1933年の冬学期で終了した。その秋、父方がユダヤ人であったという理由で、ナチス政権はアドルノの大学での教職資格を取り消した。同 時代の多くの知識人と同様、アドルノは新しい政権が長く続くとは思っておらず、振り返ってみると、1933年の政治情勢を完全に誤って判断していたことを 認めた。44] 当初は、アドルノは『フォシッシェ・ツァイトゥング』紙の音楽評論家として採用されることをまだ期待していた。雑誌『ヨーロッパ・レヴュー』では、ナチス による「ニグロ・ジャズ」の禁止について、その法令が音楽界で既に起こっていたことを遡及的に確認したものであると、彼は好意的に取り扱った。1934年 には、ヒトラー青年団指導者バルター・フォン・シラッハが音楽にのせて詩を朗読する男声合唱団を称賛した。45] 1962/63年の冬学期にフランクフルトの学生新聞『ディスカス』がこれらの出版物を掲載したことに直面し、彼は公開書簡で「愚かな戦術的発言」を後悔 した。これは、「移住を決断する人物」の愚かさによるものかもしれない 。1933年4月15日付でパリに亡命していたジークフリート・クラカウアー宛ての手紙には、国家社会主義が政権を握った後の初期の状況を彼がどれほど甘 く見ていたかが示されている。その中で彼は、クラカウアーにドイツに戻るよう勧めており、「完全な平和と秩序が保たれており、状況は安定するだろう。パリ への)急いで費用のかかる引っ越しも、私には疑問に思える」[47] レオ・レーヴェンタールは次のように述べている。「私たちは、彼を物理的に強制的にドイツから去らせるしかなかった」[48] |
| Zwischenstation Oxford (1934–1937) Als durch die nationalsozialistische Rassengesetzgebung definiertem „Halbjuden“ blieb Adorno zunächst noch Bewegungsspielraum im nationalsozialistisch regierten Deutschland. Unter Beibehaltung seines amtlich gemeldeten Wohnsitzes in Frankfurt[49] ging er nach Großbritannien, wo er, obwohl bereits deutscher Philosophiedozent, nur als advanced student im Fach Philosophie am Merton College in Oxford aufgenommen wurde.[50] Er plante, mit einer Arbeit über die Philosophie Edmund Husserls den akademischen Grad Ph.D. zu erwerben. Sein Tutor war Gilbert Ryle, kompetenter Kenner der deutschen Philosophie, insbesondere Husserls und Heideggers, und später berühmter Autor von The Concept of Mind. Kontakt hatte er auch zu dem Ideengeschichtler Isaiah Berlin.[51] Wie er Freunden mitteilte, arbeitete er „in einer unbeschreiblichen Ruhe und unter sehr angenehmen äußeren Arbeitsbedingungen“ (Brief an Ernst Krenek),[52] wenngleich er „das Leben eines mittelalterlichen Studenten mit Cap und Gown“[53] zu führen gezwungen war, wie er an Walter Benjamin schrieb.[54] Die Oxforder Jahre nutzte Adorno nicht nur für seine Husserl-Studien. Er schrieb eine kritische Abhandlung über die Wissenssoziologie Karl Mannheims[55] und musiktheoretische Artikel für die der Avantgarde verpflichteten Wiener Musikzeitschrift 23 sowie den Aufsatz Über Jazz, der 1936 in der Zeitschrift für Sozialforschung unter dem Pseudonym Hektor Rottweiler erschien[56] und bis über Adornos Tod hinaus heftigste Reaktionen hervorrief. Da die damaligen Devisenbestimmungen nur die Ausfuhr geringer Beträge erlaubten, kehrte Adorno, um sein Leben in Oxford finanzieren zu können, regelmäßig nach den Semestern zu längeren Aufenthalten nach Deutschland zurück – in ein Land, das ihm zur „Hölle“ geworden war, wie er dem in die USA emigrierten Horkheimer schrieb. Er traf dort neben Freunden seine Eltern und seine Verlobte,[57] für die, als Jüdin, das Leben in Deutschland immer prekärer wurde und die daher im August 1937 nach London übersiedelte, wo beide am 8. September 1937 im Standesamt des Districts Paddington heirateten. Einer der Trauzeugen war Horkheimer, der zu dieser Zeit, aus den USA kommend, die Zweigstellen des Instituts für Sozialforschung in Europa (Genf, Paris, London) bereiste.[58] Adorno bestand auf einer traditionellen Arbeitsteilung mit seiner Frau: „er dachte nicht im entferntesten daran, sich an der Organisation und Führung des Haushaltes zu beteiligen“.[59] Während dieser Zeit unterhielt Adorno einen intensiven Briefwechsel mit dem bereits im amerikanischen Exil lebenden Max Horkheimer, den er im Dezember 1935 in Paris getroffen und im Juni 1937 für zwei Wochen in New York besucht hatte. Horkheimer machte ihm schließlich das Angebot, in den USA eine existenzsichernde wissenschaftliche Tätigkeit aufzunehmen und offizieller Mitarbeiter in seinem Institut für Sozialforschung zu werden.[60] Mitte Dezember 1937 verbrachten die Adornos noch einen Urlaub an der Ligurischen Küste, wo sie sich mit Walter Benjamin trafen, und in Brüssel verabschiedete sich Adorno von den Eltern, die später nachkommen sollten.[61] |
オックスフォードの中間駅(1934年~1937年) 国家社会主義の人種法で定義された「半ユダヤ人」であったアドルノは、ナチスが支配するドイツにおいて、当初はまだ行動の余地があった。公式の登録上の居 住地をフランクフルトに残したまま、彼はイギリスに渡り、すでに哲学のドイツ人講師であったにもかかわらず、オックスフォードのマーティン・カレッジで哲 学の優秀な学生として受け入れられた。彼はエドムント・フッサールの哲学に関する論文で博士号を取得するつもりであった。彼の指導教官は、ドイツ哲学、特 にフッサールとハイデガーの権威であり、後に『心の概念』の著者として著名なギルバート・ライルであった。また、イザヤ・ベルリンという思想史家とも交流 があった。友人たちに語ったところによると、彼は「何ともいえない静けさの中で、非常に快適な外的な労働条件のもと」で働いていたという(エルンスト・ク レーネクへの手紙)。しかし、彼は「中世的な生活」を強いられていた 帽子とガウンを身にまとった中世の学生のような生活を送っていた」[53]。しかし、ウォルター・ベンヤミンに宛てた手紙で述べているように、そうせざる を得なかったのだ。 アドルノはオックスフォード時代をフッサール研究だけに費やしたわけではなかった。彼はカール・マンハイムの知識社会学に関する批判的な論文[55]や、 ウィーンの前衛音楽雑誌『23』に音楽理論に関する記事を寄稿し、また1936年には『社会学研究誌』に「ジャズについて」というエッセイをヘクトール・ ロットワイラーというペンネームで発表し[56]、アドルノの死後もなお最も激しい反応を引き起こした。 当時の外国為替規制では輸出できる金額が限られていたため、アドルノは学期が終わると定期的にドイツに戻り、オックスフォードでの生活費を稼いでいた。ア メリカに移住したホルクハイマーに宛てた手紙の中で、アドルノはドイツを「地獄」と表現している。そこで彼は友人や両親、そしてユダヤ人であるフィアンセ と再会した。フィアンセはドイツでの生活がますます不安定になってきたため、1937年8月にロンドンに移住し、1937年9月8日にパディントン地区役 所で結婚した。結婚式の証人の一人はホルクハイマーで、当時アメリカから来ており、ヨーロッパの社会研究機関(ジュネーブ、パリ、ロンドン)の支部を訪問 していた。[58]アドルノは、伝統的な役割分担を妻に強く求めた。「彼は、家庭の運営や管理に参加することさえ考えなかった」[59] この間、アドルノはすでにアメリカに亡命していたマックス・ホルクハイマーと頻繁に文通を続けていた。1935年12月にパリでホルクハイマーと会い、 1937年6月には2週間ほどニューヨークを訪れている。ホルクハイマーはついにアドルノにアメリカでの職を提供し、生活を保障し、自身の社会研究機関の 正式なスタッフとして迎え入れることを申し出た。 1937年12月中旬、アドルノ夫妻はリグーリア海岸で休暇を過ごし、そこでヴァルター・ベンヤミンと出会った。ブリュッセルでアドルノは両親と別れを告げた。両親は後から合流することになっていた。 |
Emigrant in den USA (1938–1953) Christopher Street 45, 1938 zeitweise Wohnhaus der Adornos Horkheimers Einladung folgend, siedelte Adorno mit seiner Frau im Februar 1938 in die USA über und emigrierte damit aus dem Dritten Reich. Seinen Eltern, die bei den antijüdischen Ausschreitungen während der Novemberpogrome 1938 misshandelt und verhaftet worden waren, gelang im Jahr darauf die Ausreise nach Havanna.[62] Nachdem die Adornos in den ersten Wochen eine provisorische Wohnung in Greenwich Village (New York City) bezogen hatten, mieteten sie ein Apartment unweit der Columbia University, die dem Institut für Sozialforschung (nunmehr unter dem Namen Institute of Social Research) ein Gebäude zur Verfügung gestellt hatte. Das Paar richtete sich hier mit den aus Deutschland verschifften Möbeln ein und hatte von Anfang an keinen Mangel an privaten Kontakten und Beziehungen.[63] Gleich nach seiner Ankunft wurde Adorno Mitarbeiter des Princeton Radio Research Projects, eines von dem österreichischen Soziologen Paul Lazarsfeld geleiteten größeren Forschungsvorhabens. Adorno wurde die Durchführung eines Teilprojekts für den Bereich der Musik übertragen, die für ihn eine gänzlich ungewohnte und aufreibende Tätigkeit bedeutete.[64] Während er seine Arbeit zur Hälfte dem empirischen Projekt widmete, war er zur anderen Hälfte als nunmehr offizieller Mitarbeiter an Horkheimers Institute of Social Research tätig (GS 10/2: 705) und neben Leo Löwenthal für die redaktionelle Arbeit an der Zeitschrift für Sozialforschung verantwortlich. Überdies beteiligte er sich an den Seminaren, Vorträgen und internen Diskussionen über den Charakter des Nationalsozialismus.[65] Da Adorno auf seiner kritischen Einstellung gegenüber dem administrative research[66] beharrte, kam es zu einem „anhaltenden Disput zwischen dem Musiktheoretiker und dem Sozialforscher“,[67] der schließlich dazu führte, dass Lazarsfeld die Zusammenarbeit nach zwei Jahren beendete. Horkheimer, der Adorno nach seinem Ausscheiden aus dem Radio-Projekt eine volle Institutsstelle zugesagt hatte, suchte in dieser Zeit die engere Zusammenarbeit mit ihm. Er hatte ihn als Mitarbeiter an dem schon länger geplanten Buch über „dialektische Logik“, das die Selbstzerstörung der Vernunft zum Thema haben sollte, vorgesehen. Ab Herbst 1939 fanden zwischen beiden Gespräche statt, die Gretel Adorno teilweise protokollierte.[68] Zeitweilig war auch Herbert Marcuse, der damalige „hauptamtliche Philosoph des Instituts“,[69] mit dem Horkheimer in New York an einer materialistischen Kritik des Idealismus arbeitete, ebenfalls für die Mitarbeit vorgesehen. Da Horkheimer keineswegs mit letzter Deutlichkeit ausgeschlossen hatte, ihn an dem Dialektik-Buch zu beteiligen, war Adorno, „nicht frei von Eifersucht, […] alles dran gelegen, mit Horkheimer exklusiv das Buch zu schreiben“.[70] Bereits im Mai 1935 hatte Adorno aus Oxford an Horkheimer über Marcuse geschrieben, es mache ihn traurig, dass „Sie philosophisch unmittelbar mit einem Mann arbeiten, den ich schließlich für einen durch Judentum verhinderten Faszisten halte“.[71][72] Horkheimer und seine Frau Maidon siedelten 1940, vorwiegend aus gesundheitlichen Gründen – vor allem Maidon litt unter dem New Yorker Klima –, nach Los Angeles über und bezogen in Pacific Palisades einen eigens für sie gebauten Bungalow. Die Adornos zogen im November 1941 nach und dort in ein gemietetes Haus ein.[73] Beide wohnten in unmittelbarer Nähe und zudem in Nachbarschaft einer Kolonie deutscher und österreichischer Emigranten, wie Berthold und Salka Viertel, Thomas und Katia Mann, Hanns Eisler, Bertolt Brecht und Helene Weigel, Max Reinhardt, Arnold Schönberg und vielen anderen. Die meisten von ihnen waren gekommen, weil sie sich Aufträge von der Filmindustrie in Hollywood erhofften.[74] Anfang 1942 begannen Adorno und Horkheimer mit der Arbeit an dem Buch, das später den Titel Dialektik der Aufklärung tragen sollte. Mit ihm entstand als Gemeinschaftsarbeit beider, unter Mithilfe von Adornos Frau Gretel, das Hauptwerk der Kritischen Theorie, das erstmals 1944 im Herstellungsverfahren der Mimeographie unter dem Titel Philosophische Fragmente mit der Widmung „Friedrich Pollock zum 50. Geburtstag“ im Verlag des New York Institute of Social Research erschien und in seiner endgültigen Form 1947 im Amsterdamer Querido Verlag veröffentlicht wurde. Angesichts des an den Juden und anderen Bevölkerungsgruppen verübten Massenmords legten die beiden Autoren eine Geschichtsphilosophie der Gesellschaft nach Auschwitz vor, die eine grundsätzliche Kritik der Aufklärung darstellte, deren Fortschrittsoptimismus obsolet geworden sei. Programmatisch heißt es gleich auf der ersten Seite, es gehe um „die Erkenntnis, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt“ (GS 3: 11). Dies zu erklären, setzte das Buch mit der dialektischen These einer Verschränkung von Vernunft und Mythos, von Natur und Rationalität ein. Die Vernunftkritik erfolgte aus einer katastrophischen Perspektive.[75] Über das Ende des nationalsozialistischen Regimes und Hitlers Tod äußerte Adorno sich in privaten Briefen an seine Eltern (1. Mai 1945) und an Horkheimer (9. Mai 1945) mit einer Mischung aus Gefühlen von Freude, Trauer und Sarkasmus.[76] Hartmut Scheible bezeichnet die Jahre in Kalifornien als die fruchtbarsten in Adornos Leben.[77] Hier entstanden neben der Dialektik der Aufklärung die Minima Moralia und die Philosophie der neuen Musik. Für Rolf Wiggershaus stellten die Minima Moralia „so etwas wie die aphoristische Fortsetzung“ der Dialektik der Aufklärung dar.[78] In diese Jahre fällt auch die Zusammenarbeit mit Thomas Mann, der für seinen Roman Doktor Faustus zahlreiche Anregungen aus Adornos Manuskript zur Philosophie der neuen Musik bezog, insbesondere aus dem ersten Teil über Schönberg.[79] Im September 1943 hatte Thomas Mann Adorno in sein Haus am San Remo Drive eingeladen und aus dem achten Kapitel vorgelesen. Adornos Einwände und Ergänzungsvorschläge, die er „zunächst spontan, dann in schriftlicher Form machte, hat der Autor für die ersten Kapitel seines Romans […] weitgehend berücksichtigt“.[80] Er verdankte Adorno als dem intimen Kenner der Musik-Avantgarde wichtige Auskünfte zu musikphilosophischen und kompositionstechnischen Fragen. Bis ins kleinste musikalische Detail profitierte Thomas Mann sowohl in Gesprächen anlässlich mehrerer wechselseitiger Einladungen beider Familien, als auch durch die Korrespondenz von der Expertise eines „so erstaunlichen Kenners“ (Mann über Adorno).[81] Mann bedankte sich für diese Zusammenarbeit mit einer Anspielung auf Adorno im Roman. Dort wird das „d-g-g-“-Thema des zweiten Satzes von Beethovens Sonate op. 111 (Arietta) u. a. mit dem Wort „Wiesengrund“ unterlegt. Die Ähnlichkeit, die laut Hans Mayer der als Musikkritiker figurierende Teufel mit Adorno haben soll, nennt Thomas Mann „ganz absurd“.[82] Hanns Eisler, mit dem Adorno seit 1925 befreundet war und der nur ein paar Straßen weiter wohnte, trat im Dezember 1942 an Adorno mit dem Vorschlag heran, zusammen ein Buch über Filmmusik zu schreiben. Das 1944 auf Deutsch abgeschlossene Buch erschien erst 1949 unter dem Titel Composing for the Films auf Englisch, mit Eisler als alleinigem Autor. Adorno, der in einem Brief an seine Mutter beanspruchte, 90 Prozent des Textes verfasst zu haben, war als Co-Autor zurückgetreten, weil Eisler, ein Anhänger des Sowjetmarxismus, vor das Committee of Un-American Activities zitiert worden war und Adorno nicht „Märtyrer einer Sache“ werden wollte, „die nicht die meine war und nicht die meine ist“ (GS 15: 144), wie er 1969 im Nachwort zum Erstdruck der Originalfassung rückblickend sich rechtfertigte.[83] Nachdem Anfang 1944 das Manuskript des Dialektik-Buchs – zunächst noch mit Philosophische Fragmente betitelt – abgeschlossen worden war, begann Adorno, an dem gemeinsam von der University of Berkeley und dem Institute of Social Research betriebenen, großangelegten Forschungsprojekt zum Thema Antisemitismus mitzuwirken.[84] Seine letzte Tätigkeit in den USA trat er im Oktober 1952 als Forschungsdirektor der Hacker Psychiatric Foundation an und befasste sich in dieser Eigenschaft mit inhaltsanalytischen Untersuchungen über Zeitungshoroskope und Fernsehserien. Nachdem er mit dem Aggressionsforscher Friedrich Hacker in konfliktreiche Auseinandersetzungen geraten war, kündigte er seine Stellung und kehrte im August 1953 nach Deutschland zurück.[85] So kritisch der Emigrant Adorno auch die in den USA beobachtete konformistische Gleichschaltung, die konsequente „Hereinziehung der Kulturprodukte in die Warensphäre“ beurteilte, ja, das Schreckbild einer möglichen Konvergenz des „europäischen Faschismus und der amerikanischen Unterhaltungsindustrie“ heraufziehen sah, behielt er als „existentielle Dankespflicht“ im Gedächtnis, dass er den USA seine „Rettung vor der nationalsozialistischen Verfolgung“ zu verdanken hatte.[86] |
米国への移住者(1938年~1953年) 1938年、クリストファー・ストリート45番地、アドルノ夫妻の一時的な住居 アドルノと妻は、ホルクハイマーからの招待に応じて、1938年2月に第三帝国から米国へと移住した。1938年11月のポグロムにおける反ユダヤ暴動で 虐待を受け、逮捕されていたアドルノの両親は、翌年にはなんとかしてハバナに脱出することができた。62] ニューヨーク市グリニッジ・ヴィレッジの仮アパートに数週間住んだ後、アドルノ夫妻はコロンビア大学からほど近いアパートを借りた。。夫妻は落ち着き、当 初からプライベートな人脈や人間関係に事欠くことはなかった。 アドルノは到着後すぐに、オーストリアの社会学者ポール・ラザーズフェルドが主導する大規模な研究プロジェクトであるプリンストン・ラジオ・リサーチ・プ ロジェクトのスタッフに加わった。アドルノは音楽分野のサブプロジェクトを担当することになったが、それは彼にとってまったく未知の、疲労困憊する仕事で あった。[64] 彼は実証プロジェクトに半分の時間を費やしながら、残りの半分の時間はホルクハイマーの社会研究機関の正式なスタッフとして働いた(GS 10/2: 705)。また、レオ・レーヴェンタールとともに、 。また、セミナーや講義、国家社会主義の本質に関する内部での議論にも参加した。 アドルノが管理研究に対する批判的な態度を主張したため、「音楽理論家と社会研究者との間で継続的な論争」が起こり、最終的にラザーズフェルドは2年後に共同作業を終了することとなった。 この間、ホルクハイマーはアドルノにラジオプロジェクトを離れた後、研究所で常勤の職を用意することを約束しており、アドルノとのより緊密な共同作業を模 索していた。彼は、かねてから構想していた「弁証法的論理学」に関する著書の執筆にアドルノをスタッフとして迎え入れようとしていた。この著書では理性の 自己破壊が主題となるはずであった。1939年秋から、二人は議論を重ね、その一部はグレテル・アドルノによって記録された。68] 一時期、当時「研究所の専任哲学者」[69]であり、ホルクハイマーとともにニューヨークで観念論の唯物論的批判に取り組んでいたハーバート・マルクーゼ も共同執筆者として検討された。ホルクハイマーはマルクーゼが弁証法に関する書籍に参加する可能性を完全に排除していたわけではなかったため、アドルノは 「嫉妬心から解放されていたわけではなく、[...] ホルクハイマーと二人だけでその本を書くことに熱心だった」[70]。1935年5月には早くも、アドルノはオックスフォードからホルクハイマーにマル クーゼについて手紙を書き、ホルクハイマーが「私が嫌悪する人物と哲学的な作業を行っている」ことが悲しいと述べていた 最終的には、ユダヤ人であるがゆえにファシストになることを思いとどまった人物である。[71][72] 1940年、ホルクハイマーと妻のメイドンは主に健康上の理由からロサンゼルスに移住した。特にメイドンはニューヨークの気候に悩まされていた。そして、 パシフィック・パリセーズに自分たちのために建てられたバンガローに移り住んだ。アドルノ夫妻は1941年11月に続き、そこにある貸家に引っ越した。 [73] 両者は近距離に住み、また、ベルトルト・ブレヒトとヘレーネ・ヴァイゲル、マックス・ラインハルト、トーマス・マンとカティア・マン、ハンス・アイス ラー、ヘルマン・ゲーリング、サルカ・フィエルテル、アーノルド・シェーンベルク、その他多数のドイツとオーストリアからの亡命者たちのコロニーの近所に 住んでいた。彼らのほとんどは、ハリウッド映画業界から委託を受けることを期待してやって来た。 1942年の初め、アドルノとホルクハイマーは後に『啓蒙の弁証法』と題されることになる本の執筆を開始した。これはアドルノとホルクハイマーの共同作業 であり、アドルノの妻グレテルの助力も得て、批判理論の主要な著作となった。1944年にニューヨーク社会研究所が謄写版印刷法で『哲学的断片』というタ イトルで出版した。 ユダヤ人やその他の集団に対する大量虐殺を目の当たりにした2人の著者は、進歩に対する楽観的な見方が時代遅れとなった啓蒙主義に対する根本的な批判を体 現する、アウシュビッツ後の社会の歴史哲学を提示した。最初のページには、この本が「人類が真に人間的な境地に達するのではなく、新たな野蛮へと沈み込ん でいく理由の解明」について書かれたものであると述べられている(GS 3: 11)。この本は、理性と神話、自然と合理性の相互関連性という弁証法的命題によって、これを説明しようとした。理性の批判は、破滅的な見通しに基づいて いる。 アドルノは両親宛(1945年5月1日)とホルクハイマー宛(1945年5月9日)の私信で、ナチス体制の終焉とヒトラーの死について、喜び、悲しみ、皮肉の入り混じった感情を交えて表現している。 ハルトムート・シャイブルは、アドルノの生涯で最も実りの多い時期はカリフォルニアでの数年間であったと述べている。77] 啓蒙の弁証法に加えて、彼は『ミニマ・モラリア』と『新音楽の哲学』をこの地で著した。ロルフ・ヴィッゲルハウスの考えでは、『ミニマ・モラリア』は『啓 蒙の弁証法』の「格言的な続編のようなもの」であった。78] この時期、アドルノはトーマス・マンとも協力し、マンはアドルノの「新音楽の哲学」の草稿から、特にシェーンベルクに関する第1部から多くの着想を得て、 小説『ファウスト博士』を執筆した。1943年9月、トーマス・マンはアドルノをサンレモ・ドライブの自宅に招き、第8章を朗読した。アドルノの異議申し 立てや追加の提案は、「最初は即興で、その後は書面で」行われたが、それらは「著者が小説の最初の章でほぼ考慮した」[80]。音楽の前衛の親しい目利き として、アドルノは音楽哲学や作曲技法に関する重要な情報をマンに提供した。両家が互いに招待し合った際の会話や、書簡を通じて、トーマス・マンは「この ような素晴らしい鑑定家」(アドルノについてマンが述べた言葉)の専門知識から恩恵を受けた。[81] マンはアドルノに感謝の意を表し、小説の中で彼に言及した。そこでは、ベートーヴェンのソナタ作品111の第2楽章(アリア)の「d-g-g-」という テーマが、「Wiesengrund(草原の地)」という言葉とともに下敷きにされている。トーマス・マンは、ハンス・メイヤーによると、音楽評論家とし て登場する悪魔がアドルノと似ているという類似点を「まったくばかげている」と述べている。 アドルノとは1925年以来の友人であり、数軒しか離れていない場所に住んでいたハンス・アイスラーは、1942年12月にアドルノに映画音楽に関する本 を一緒に書くことを提案した。1944年にドイツ語で完成したこの本は、アイスラー単独著として『映画音楽作曲』というタイトルで出版されたのは1949 年のことであった。アドルノは、母への手紙の中で、この本の90パーセントを執筆したと主張していたが、ソビエト・マルクス主義の支持者であったアイス ラーが反米活動委員会に召喚されたため、共同執筆者としての仕事を辞退した。アドルノは、「自分とは関係のない大義のために殉教者となる」ことを望まな かったのである(GS 15: 144)。1969年に初版の初刷りのあとがきで、彼は自らを振り返って正当化した。 1944年初頭に弁証法に関する著書(当初は『哲学断片』というタイトル)の原稿を完成させた後、アドルノはカリフォルニア大学バークレー校と社会研究機関が共同で実施した反ユダヤ主義に関する大規模な研究プロジェクトに参加し始めた。 1952年10月には、米国における最後の職として、ハッカー精神医学財団の研究ディレクターに就任し、新聞の星占い欄やテレビ番組のコンテンツ分析に従事した。侵略研究家フリードリヒ・ハッカーと対立した後、1953年8月に辞職し、ドイツに戻った。 アメリカで観察された順応主義による強制的な順応と一貫した「文化製品の商品圏への組み込み」を批判的に見ていた亡命者アドルノは、ヨーロッパのファシズ ムとアメリカのエンターテイメント産業の収束の可能性を予見していたが、アメリカに「ナチスの迫害からの救済」を負っていることを覚えており、アメリカに 対して「実存的な恩義」を感じていた。 社会主義の迫害から救われた」という事実を、彼は「実存的な恩義」として記憶にとどめている。[86] |
Späte Frankfurter Jahre (1949–1969) Institut für Sozialforschung und „Adorno-Ampel“ an der Senckenberganlage in Frankfurt am Main. Adorno hatte sich seit 1962 für den Bau einer Ampel an der vielbefahrenen Straße zwischen dem Institut und dem Universitätscampus in Frankfurt-Bockenheim eingesetzt; allerdings wurde die Ampel erst 1987 installiert. Im Oktober 1949 kehrte Adorno erstmals aus den USA wieder nach Deutschland zurück. Unmittelbarer Grund war die Vertretung Horkheimers an der Frankfurter Universität, die Horkheimer bereits 1949 wieder zum ordentlichen Professor, diesmal für Philosophie und Soziologie, berufen hatte.[87] Nach wechselnden Aufenthalten in Deutschland und den USA kehrte Adorno im August 1953 endgültig nach Deutschland zurück, wo ihn die Frankfurter Universität vom außerplanmäßigen (1950) zum planmäßigen außerordentlichen Professor (1953) und schließlich 1956 zum ordentlichen Professor für Philosophie und Soziologie ernannte.[88] Adornos Motivation zur Rückkehr nach Deutschland war nach eigener Aussage subjektiv durch Heimweh und objektiv durch die Sprache bestimmt. Er war auf die deutsche Sprache angewiesen, die für ihn eine „besondere Verwandtschaft zur Philosophie“ habe.[89] Sein Denken „ließ sich nicht von der deutschen Sprache lösen“.[90] Als Wissenschaftler war er zurückgekommen, um an seiner Heimatuniversität an die ihm 1933 entzogene Privatdozentur für Philosophie anzuknüpfen. Er wurde aber bald als Repräsentant einer anderen Disziplin, der Soziologie, bekannt, für die er während seiner Emigrationsjahre vielfältige Qualifikationen erworben hatte. Über die frühen Erfahrungen, die Adorno im besiegten Deutschland machte, äußerte er sich einerseits sehr kritisch: Man treffe so gut wie keine Nationalsozialisten, keiner wolle es gewesen sein und man habe von allem nichts gewusst,[91] andererseits lobte er an den Studenten eine „leidenschaftliche Teilnahme“.[92] Mit der Dichterin Marie Luise Kaschnitz schloss er Freundschaft; eine enge Zusammenarbeit entstand mit den beiden Herausgebern der Frankfurter Hefte, Walter Dirks und Eugen Kogon.[93] Von den alten Institutsmitarbeitern war außer Horkheimer und Adorno nur noch Friedrich Pollock nach Frankfurt zurückgekehrt; Fromm, Löwenthal, Marcuse, Franz Neumann und Karl August Wittfogel zogen es vor, in den USA ihre akademische Karrieren fortzusetzen.[94] Für das am 14. November 1951 in einem neuen Gebäude wiedereröffnete Institut für Sozialforschung war Adorno von Anfang an als stellvertretender Direktor mitverantwortlich. Das Institut war die erste akademische Einrichtung, die ein Soziologiestudium im Deutschland der Nachkriegszeit ermöglichte.[95] Nach dem Rückzug Horkheimers nach Montagnola in der Schweiz ruhte die Hauptarbeit faktisch auf Adornos Schultern. 1958 übernahm er offiziell die Leitung des Instituts.[96] In seiner Frau Margarete fand er eine „wesentliche Stütze seines Schaffens“ und eine aktive Mitarbeiterin. Gemeinsam mit ihm betrat sie morgens das Institut und verließ es abends mit ihm. In ihrem eigenen Büro redigierte sie penibel alle Texte Adornos vor der Drucklegung. Selten verpasste sie eine seiner Vorlesungen. Den Studenten stand sie als „Beichtmutter“ und Vermittlerin zum „Übervater“ bei.[97] Dass ihre Ehe kinderlos blieb, war eine von beiden bewusst getroffene Entscheidung, die sie den ungewissen Zeitumständen und Zukunftsperspektiven zuschrieben.[98] Die wissenschaftliche Produktivität, die Adorno in den USA auf dem Gebiet der Sozialforschung entfaltet hatte, trug dazu bei, dass er in Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren als einer der wichtigsten Vertreter der deutschen Soziologie anerkannt wurde.[99] Nachdem 1955 Ludwig von Friedeburg als der für die empirischen Forschungsprojekte verantwortliche neue Abteilungsleiter des Instituts eingestellt worden war, zog sich Adorno allmählich aus der empirischen Forschung zurück, wiewohl er sich in der Folgezeit weiterhin zum Verhältnis von theoretischer Reflexion und empirischer Forschung zu Wort meldete.[100] Seine Skepsis steigerte sich zur Polarisierung im sogenannten Positivismusstreit, der 1961 mit einem Referat von Karl Popper und dem Koreferat Adornos zur „Logik der Sozialwissenschaften“ auf einer Tübinger Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie begonnen hatte und an dessen weiterem Verlauf sich Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas und Hans Albert beteiligten.[101] Von 1962 bis 1969 hatte Adorno eine Affäre mit der Münchnerin Arlette Pielmann, die ihn regelmäßig in Frankfurt besuchte. Adornos Ehefrau Gretel wusste darüber Bescheid und duldete dies, ohne es zu billigen.[102] Von 1963 bis 1967 amtierte Adorno als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und zeichnete für den 16. Deutschen Soziologentag verantwortlich, der unter dem Titel Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft 1968 in Frankfurt am Main veranstaltet wurde.[103] Der Zeitpunkt fiel mit dem Höhepunkt der Studentenbewegung zusammen. Die Vortragenden und Diskutanten auf den Podien reagierten meist gelassen auf wiederholte Störungen, Unterbrechungen und andere Regelverletzungen der Studenten. Neben seiner Tätigkeit als Universitätslehrer und als Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung verfasste Adorno bedeutende philosophische Schriften. Bereits 1951 war die aus der Emigration mitgebrachte und erweiterte Sammlung von Aphorismen: Minima Moralia erschienen, die er Max Horkheimer gewidmet hatte. Das mehr als 100.000-mal verkaufte Buch enthält die berühmt gewordene Sentenz „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ (GS 4: 43).[104] Das 1956 publizierte Werk über Husserl, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, ging in Teilen noch auf die Oxforder Studien zurück. Sein philosophisches Hauptwerk ist die Negative Dialektik, die Adorno selbst als „Antisystem“ (GS 6: 10) charakterisierte (erschienen erstmals 1966). Am westdeutschen Musikleben der Nachkriegszeit nahm Adorno durch seine musikphilosophischen und musiksoziologischen Veröffentlichungen teil, wie mit der schon in der Emigration entstandenen Philosophie der neuen Musik (1949), den Monographien über Richard Wagner (1952), Gustav Mahler (1960) und Alban Berg (1968) sowie der Einleitung in die Musiksoziologie (1962),[105] aber auch als Musiklehrer im Rahmen der bis in die späten 1960er Jahre im jährlichen Turnus stattfindenden Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, an denen er zwischen 1950 und 1966 als Referent und Kursleiter nahezu regelmäßig teilnahm.[106] Außer der Musik war es die Literatur, die Adornos ästhetisches Denken beflügelte; seine philosophischen Ansichten zu dieser Kunstgattung legte er in zahlreichen Aufsätzen nieder, die in den vier Bänden der Noten zur Literatur zusammengefasst sind (GS 11). Mit Schriftstellern wie Ingeborg Bachmann, Alexander Kluge und Hans Magnus Enzensberger pflegte er freundschaftliche Beziehungen. Er entwickelte eine starke Präsenz in den Medien, die ihn zum gefragten Kenner und Diskutanten nicht nur auf den Gebieten der Philosophie und Soziologie, sondern auch der Musiktheorie und Literaturkritik machte.[107] In den letzten Lebensjahren arbeitete er an seiner posthum erschienenen Ästhetik. Adorno war ein geschätzter Hochschullehrer. Seit dem Ende der 1950er Jahre strömten Studenten aller Fachrichtungen in seine Vorlesungen, welche im größten Hörsaal der Universität stattfanden. Sein sich auf wenige Notizen stützender, in nuancierter Diktion frei formulierter Vortrag schlug viele in seinen Bann. Die letzten Jahre Adornos standen ganz im Zeichen von Konflikten mit seinen Studenten. Als sich aus der außerparlamentarischen Opposition (APO) gegen die von der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD gebildete Regierung und deren geplante Notstandsgesetze wie auch gegen den Vietnamkrieg eine neuartige Studentenbewegung mit dem SDS an der Spitze bildete, verschärften sich die Spannungen.[108] Während Adorno sich den entschiedenen Kritikern dieser Gesetze anschloss und mit ihnen öffentlich auf einer Veranstaltung des Aktionskomitees Demokratie im Notstand am 28. Mai 1968 Stellung bezog, hielt er Distanz zum studentischen Aktionismus. Es waren Schüler Adornos, die den Geist der Revolte repräsentierten und „praktische Konsequenzen“ aus der Kritischen Theorie zu ziehen versuchten. Als der Polizist Karl-Heinz Kurras bei der Demonstration am 2. Juni 1967 in West-Berlin gegen den Schah den Studenten Benno Ohnesorg erschoss, begann sich die APO zu radikalisieren. Unmittelbar nach dem Tod Ohnesorgs hatte Adorno vor Beginn seiner Ästhetik-Vorlesung seine „Sympathie für den Studenten“ ausgesprochen, „dessen Schicksal […] in gar keinem Verhältnis zu seiner Teilnahme an einer politischen Demonstration steht“.[109] Die Köpfe der Frankfurter Schule hatten zwar Sympathie mit den studentischen Kritikern und deren Protesten gegen restaurative Tendenzen und „technokratische Hochschulreform“,[110] waren aber nicht bereit, deren aktionistisches Vorgehen zu unterstützen; als „Pseudo-Aktivität“ und „Ungeduld gegenüber der Theorie“ bezeichnete Adorno es 1969 in seinem Rundfunkvortrag Resignation (GS 10/2 756 f.). Zum Verhältnis von Theorie und Praxis äußerte sich Adorno in einem längeren Spiegel-Interview im Mai 1969: „Ich habe neulich in einem Fernsehinterview gesagt, ich hätte zwar ein theoretisches Modell aufgestellt, hätte aber nicht ahnen können, dass Leute es mit Molotow-Cocktails verwirklichen wollen. […] Seitdem es in Berlin 1967 zum erstenmal zu einem Zirkus gegen mich gekommen ist, haben bestimmte Gruppen von Studenten immer wieder versucht, mich zur Solidarität zu zwingen, und praktische Aktionen von mir verlangt. Das habe ich verweigert.“[111] Die Studenten agierten zunehmend gegen ihre einstigen Vorbilder, beschimpften sie in einem Flugblatt gar als „Büttel des autoritären Staates“.[112] Adornos Vorlesungen wurden wiederholt von studentischen Aktivisten gesprengt, besonders spektakulär war eine Aktion (in den Medien zum sogenannten Busenattentat stilisiert) im April 1969, als Hannah Weitemeier und zwei andere Studentinnen Adorno mit entblößten Brüsten auf dem Podium bedrängten und ihn mit Rosen- und Tulpenblüten bestreuten.[113] „Das Gefühl, mit einem Mal als Reaktionär angegriffen zu werden, hat immerhin etwas Überraschendes“, schrieb Adorno an Samuel Beckett.[114] Andererseits wurden Adorno und Horkheimer von der politischen Rechten vorgeworfen, sie seien die geistigen Urheber der studentischen Gewalt. |
フランクフルトでの晩年(1949年~1969年) フランクフルト・アム・マインのゼンケンベルクアナーゲルにある社会研究所と「アドルノ信号機」。アドルノは1962年から、研究所とフランクフルト・ ボッケンハイムの大学キャンパスを結ぶ交通量の多い道路に信号機を設置するよう運動を続けていたが、信号機が設置されたのは1987年になってからだっ た。 1949年10月、アドルノは初めてアメリカからドイツに戻った。その直接の理由は、1949年にすでに哲学と社会学の正教授に再任されていたホルクハイ マーの代理としてフランクフルト大学で教えることだった。87] ドイツとアメリカを行き来した後、アドルノはついに1953年8月にドイツに永住することとなった。フランクフルト大学は、彼を非常勤講師(1950年) から准教授( 1956年には哲学と社会学の正教授に昇進した。 アドルノがドイツに戻った動機は、彼自身の言葉によれば、主観的にはホームシック、客観的には言語によって決定された。彼はドイツ語に依存しており、彼に とってドイツ語は「哲学と特別な親和性を持つ」言語であった。[89] 彼の思考は「ドイツ語と切り離すことはできなかった」のである。[90] 彼は科学者として、1933年に奪われた母校での哲学の非常勤講師職に復帰した。しかし、彼はすぐに亡命中に幅広い資格を取得していた社会学という異なる 学問分野の代表者として知られるようになった。一方で、彼は敗戦後のドイツでの初期の経験を非常に批判的に見ていた。ナチス党員とほとんど会うことはな く、彼らは誰も自分が関与していたことを認めようとはせず、誰も何も知らなかったと述べている。[91] 一方で、彼は学生たちの「熱狂的な参加」を賞賛した。 、ウォルター・ディルクスとオイゲン・コーゴンと緊密な協力関係を築いた。 旧スタッフのうちフランクフルトに戻ったのはフリードリヒ・ポロックだけで、ホルクハイマーとアドルノも一緒だった。フロム、レヴェンタール、マルクー ゼ、フランツ・ノイマン、カール・アウグスト・ヴィトフォーゲルは、米国で学問的キャリアを継続することを選んだ。[94]アドルノは、1951年11月 14日に新築の建物で再開した社会研究所の共同責任者となり、当初から副所長を務めた 。この研究所は、戦後のドイツで社会学の学位プログラムを提供した最初の学術機関であった。 ホルクハイマーがスイスのモンタニョーラに引っ込んでからは、実質的な業務はアドルノの肩にのしかかった。1958年には、アドルノは研究所の経営を正式 に引き継いだ。96] 妻のマルガレーテは、アドルノにとって「自身の仕事にとって不可欠な支え」であり、積極的な協力者でもあった。彼女は朝、アドルノと一緒に研究所に入り、 夕方には一緒に帰宅した。彼女自身のオフィスでは、アドルノの文章が印刷される前に、すべてを入念に校正していた。彼女はアドルノの講義を一度も欠席する ことはなかった。彼女は「告解者」として学生に相談にのり、「偉大なる父」との仲介役も務めていた。[97] 彼らの結婚に子供がいなかったのは、両者による意識的な決断であり、その理由は当時の不安定な情勢と将来の見通しに起因するものだった。[98] アドルノがアメリカで社会研究の分野で培った科学的生産性は、1950年代と1960年代にドイツでアドルノがドイツ社会学の最も重要な代表者の一人とし て認められることに貢献した。99] 1955年にルートヴィヒ・フォン・フリーデブルクが研究所の実証研究プロジェクトを担当する部門の新しい責任者として採用された後、アドルノは徐々に 実証研究からは身を引いたが、その後も理論的考察と実証研究の関係について論評を続けた。彼の懐疑論は、1961年にカール・ポパーの講演とアドルノによ る「社会科学の論理」に関する反論講演という、いわゆる「実証主義論争」で極点に達した。この論争は、ドイツ社会学会のテュービンゲンでのワークショップ で始まった 、その後の経過ではラルフ・ダレナード、ユルゲン・ハーバーマス、ハンス・アルバートが参加した。 1962年から1969年にかけて、アドルノはミュンヘン出身でフランクフルトに定期的に訪れていた女性、アレッテ・ピールマンと不倫関係にあった。アドルノの妻グレーテルはそれを知っていたが、認めてはいないものの黙認していた。 1963年から1967年にかけてアドルノはドイツ社会学会の会長を務め、1968年にフランクフルト・アム・マインで開催された第16回ドイツ社会学会 議の責任者となった。この会議は「後期資本主義または産業社会」というタイトルで開かれた。この時期は学生運動が盛んになった時期と重なっていた。講演者 やパネリストたちは、学生たちによる度重なる妨害や中断、その他の規則違反に対して、概ね冷静に対応した。 大学講師やフランクフルト社会研究所の所長としての仕事に加え、アドルノは重要な哲学的な著作も残している。1951年には早くも、亡命先から持ち帰った 格言集を拡大した『ミニマ・モラリア』を出版し、ホルクハイマーに捧げた。10万部以上を売り上げたこの本には、今では有名な一文「間違った人生に正しい ものなどありえない」(GS 4: 43)が含まれている。[104] 1956年に出版された『認識論批判』は、オックスフォードでの研究を一部基にしている。彼の主要な哲学書は『否定弁証法』であり、アドルノ自身はこれを 「反体制」と評している(GS 6: 10)(1966年初版)。 アドルノは、亡命中に執筆した『新音楽の哲学』(1949年)や、リヒャルト・ワーグナー(1952年)、グスタフ・マーラー(1960年)、アルバン・ ベルク(1968年)に関する単行本、および『音楽社会学入門』(1962年)[105]といった音楽哲学や音楽社会学に関する著作を通じて、戦後の西ド イツの音楽界に参加した。また、 ダルムシュタットで開催された「新しい音楽のための国際夏季現代音楽講習会」で音楽講師を務めたこともあった。この講習会は1960年代後半まで毎年開催 され、アドルノは1950年から1966年まで講師や講演者として定期的に参加していた。 音楽以外では、アドルノの美的思考に影響を与えたのは文学であった。彼はこの芸術ジャンルに関する哲学的な見解を数多くのエッセイにまとめ、それらは 『Noten zur Literatur』(GS 11)の4巻にまとめられている。彼はインゲボルク・バッハマン、アレクサンダー・クルーゲ、ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーといった作家たちと 友好的な関係を維持していた。彼はメディアで強い存在感を示し、哲学や社会学の分野だけでなく、音楽理論や文学批評の分野でも、引っ張りだこの専門家や論 客となった。 アドルノは非常に評価の高い大学講師であった。1950年代後半から、あらゆる分野の学生たちが、大学最大の講堂で行われた彼の講義に押し寄せた。わずかなメモを基に、微妙かつ自由な表現で展開される講義は、多くの学生を魅了した。 アドルノの晩年は、学生たちとの対立に明け暮れた。SDSを先頭に、政府の計画する緊急事態法とベトナム戦争に抗議する新たな学生運動が形成されると、緊 張が高まった。アドルノはこれらの法律の批判派に加わり、緊急事態における民主主義行動委員会が主催するイベントで公然と彼らに同調した。1968年5月 28日、彼は学生運動とは距離を置いた。 反乱の精神を体現し、批判理論から「現実的な帰結」を引き出そうとしたのはアドルノの学生たちであった。1967年6月2日、西ベルリンでシャーに対する デモが行われている最中に、警察官カール・ハインツ・クーラスが学生ベノ・オネゾルクを射殺した事件をきっかけに、APOは急進化していった。オネゾルク の死の直後、アドルノは美学講義の冒頭で「政治的デモへの参加とはまったく不釣り合いな運命をたどった学生に同情する」と表明していた。 [109] フランクフルト学派の指導者たちは、保守回帰の傾向や「テクノクラートによる大学改革」に反対する学生の批判や抗議運動に共感していたが、[110] 彼らの行動主義的アプローチを支持するつもりはなかった。1969年のラジオ講義『諦念』(GS 10/2 756 f.)において、アドルノはそれを「偽りの活動」および「理論に対する焦り」と呼んだ。 1969年5月、アドルノは雑誌『シュピーゲル』のインタビューで、理論と実践の関係について長々と語っている。「私は最近、テレビのインタビューで、理 論モデルを構築したものの、人々がそれをモロトフ・カクテルで実行しようとするとは予見できなかったと述べた。[...] 1967年にベルリンで私に対して最初のサーカスが行われて以来、特定の学生グループは、私に連帯を示し、実際的な行動を要求しようと繰り返し迫ってき た。私は拒否した」[111] 学生たちは次第に、かつてのロールモデルに反旗を翻すようになり、彼らを「権威主義国家の手先」と呼ぶチラシまで作られた。アドルノの講義は学生活動家た ちによって何度も妨害され、1969年4月のある行動(メディアでは「胸ぐら攻撃」として様式化された)は特に壮観であった。ハンナ・ヴァイトマイヤーと 他の2人の学生が、アドルノを演壇で裸の バラとチューリップの花びらを彼に被せた。113] 「このような時に反動主義者として攻撃されるという感覚は、やはり、いくらか驚くべきものだ」とアドルノはサミュエル・ベケットに書き送った。114] 一方で、アドルノとホルクハイマーは、政治的右派から学生暴動の知的首謀者として非難された。 |
 Adornos Grab (2007) 1969 sah Adorno sich gezwungen, seine Vorlesungen einzustellen. Als am 31. Januar 1969 Studenten in das Institut für Sozialforschung eingedrungen waren, um kategorisch eine sofortige Diskussion über die politische Situation durchzusetzen, riefen die Institutsdirektoren – Adorno und Ludwig von Friedeburg – die Polizei und zeigten die Besetzer an. Adorno, der immer ein Gegner des Polizei- und Überwachungsstaats gewesen war, litt unter diesem Bruch seines Selbstverständnisses. Er musste als Zeuge vor dem Frankfurter Landgericht gegen Hans-Jürgen Krahl, einen seiner begabtesten Schüler, aussagen. Adorno äußerte sich dazu in einem Brief an Alexander Kluge: „Ich sehe nicht ein, warum ich mich zum Märtyrer des Herrn Krahl machen soll, von dem ich mir doch ausdachte, daß er mir ein Messer an die Kehle setzt, um mir diese durchzuschneiden, und auf meinen gelinden Protest erwidert: Aber Herr Professor, das dürfen Sie doch nicht personalisieren“.[115] Ab Februar 1969 bis zu Adornos Tod trugen Adorno und Herbert Marcuse in einem intensiven Briefwechsel einen Dissens aus, von dem Adorno in einem Brief an Horkheimer bereits befürchtete, er könnte einen „Bruch zwischen ihm und uns“ herbeiführen.[116] Marcuse kritisierte Adornos Praxis-Abstinenz ebenso wie Habermas’ Vorwurf des „linken Faschismus“ gegenüber den rebellierenden Studenten sowie die polizeiliche Räumung des besetzten Instituts.[117] Adorno verteidigte Habermas’ Vorwurf. Auch er sah jetzt Tendenzen, die „mit dem Faschismus unmittelbar konvergieren“, und nahm, wie er Marcuse schrieb, „die Gefahr des Umschlags der Studentenbewegung in Faschismus viel schwerer als Du“.[118] Am Tag nach der Gerichtsverhandlung gegen Krahl fuhr er mit seiner Frau in den üblichen Sommerurlaub in die Schweizer Berge. Statt des gewohnten Urlaubs in Sils Maria fuhren sie erstmals nach Zermatt (1600 m. ü. M.). Ungenügend akklimatisiert, fuhr er mit einer Seilbahn auf fast 3000 m. ü. M. und wanderte dann zur Gandegghütte (3030 m.ü.M.). Weil er Probleme mit seinem Bergschuh hatte, ließ er sich anschließend nach Visp (660 M. ü. M.) zu einem Schuhmacher fahren. Als er Herzbeschwerden bekam, wurde er ins Visper Krankenhaus St. Maria gebracht. Dort erlag er am Morgen des 6. Augusts 1969 einem Herzinfarkt.[119] Adornos Grab befindet sich auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. |
 アドルノの墓 (2007) 1969年、アドルノは講義を中止せざるを得なくなった。1969年1月31日、学生たちが政治情勢の即時討論を断固として要求するために社会研究所に押 し入った際、研究所の所長であるアドルノとルートヴィヒ・フォン・フリーデブルクは警察に通報し、占拠者たちを報告した。警察国家や監視国家に常に反対し てきたアドルノは、この自己イメージの侵害に苦しんだ。彼はフランクフルト地方裁判所で、最も優秀な学生の一人であったハンス=ユルゲン・クラールに対し て証人として証言しなければならなかった。アドルノはアレクサンダー・クルーゲ宛ての手紙で次のように述べている。「私が想像するに、クラール氏はナイフ を喉に突きつけてそれを切り落とすだろう。私が軽く抗議すると、彼は『しかし教授、これは個人的なことにしてはいけませんよ』と答えるだろう。」 [115] 1969年2月からアドルノが亡くなるまで、アドルノとハーバート・マルクーゼは激しい意見の相違を表明する書簡のやり取りを続けた。アドルノはホルクハ イマー宛ての手紙で、これが「彼と我々との決別」につながることを危惧した。[116] マルクーゼはアドルノの実践からの離脱を批判し、ハーバマスが反逆する学生たちや、 占拠された大学の警察による排除を非難した。アドルノはハーバーマスの非難を擁護した。アドルノもまた「ファシズムに直接収束する」傾向を認識しており、 マルクーゼに宛てた手紙の中で「学生運動がファシズムに転化する危険性を、君よりもずっと深刻に受け止めている」と述べている。 クラールに対する公判の翌日、彼は妻とともに、例年通り夏の休暇をスイスの山で過ごすために出かけた。いつもはシルス・マリアで過ごす休暇を、ツェルマッ ト(標高1600メートル)で過ごすことにした。 十分な高地順応をせずに、ケーブルカーで標高3000メートル近くまで登り、そこからガンデックヒュッテ(標高3030メートル)までハイキングした。登 山靴に問題があったため、その後、彼はヴィスプ(標高660メートル)まで乗用車に乗り、靴屋を訪れた。心臓に問題が生じ始めたため、彼はヴィスプの聖マ リア病院に搬送された。1969年8月6日の朝、彼は同病院で心臓発作により死亡した。 アドルノの墓はフランクフルトの中央墓地にある。 |
| Einflüsse auf das Werk Als besonders bedeutsame Einflüsse für das Denken Adornos lassen sich Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx und Sigmund Freud anführen. Die „Großtheorien“ von Hegel, Marx und Freud übten auf viele linke Intellektuelle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie auch auf einen Großteil der Theoretiker der Frankfurter Schule, eine große Faszination aus. Mit kritischem Unterton spricht Lorenz Jäger in seiner „politischen Biographie“ dabei von Adornos „Achillesferse“, das heißt dessen „fast unbegrenzte[m] Vertrauen auf fertige Lehren, auf den Marxismus, die Psychoanalyse, die Lehren der Zweiten Wiener Schule“.[120] Indessen vertraute Adorno dem Marxismus ebenso wenig unverändert wie der Hegel’schen spekulativen Dialektik. Die Zweite Wiener Schule freilich blieb in seinem Wirken als Musikkritiker und Komponist der Leitstern. |
作品への影響 アドルノの思想に特に大きな影響を与えた人物として、イマニュエル・カント、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、カール・マルクス、ジーク ムント・フロイトを挙げることができる。 ヘーゲル、マルクス、フロイトの「大理論」は、20世紀前半の多くの左派知識人、そしてフランクフルト学派の理論家の多くを魅了した。批判的な含みを持た せながら、ローレンツ・イェーガーはアドルノの「アキレス腱」、すなわち「既製の教義、マルクス主義、精神分析、第二ウィーン学派の教えに対するほぼ無制 限の信頼」について、彼の「政治的伝記」の中で語っている。[120] 一方で、アドルノはヘーゲル的な思弁的弁証法と同様に、マルクス主義もそのままではほとんど信用していなかった。もちろん、ウィーン学派は、音楽評論家お よび作曲家としての彼の作品における指針であり続けた。 |
Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel Adornos Aneignung der Hegel’schen Philosophie lässt sich mindestens bis zu seiner Antrittsvorlesung von 1931 zurückverfolgen; in ihr postulierte er: „Einzig dialektisch scheint mir philosophische Deutung möglich“ (GS 1: 338). Hegel lehne es ab, die philosophische Methode von ihrem Inhalt, den Gegenständen, zu trennen, da Denken immer schon Denken von etwas ist, sodass Dialektik „die begriffene Bewegung des Gegenstands selbst“ ist.[121] Der Argumentation der Phänomenologie des Geistes folgend, könne der wissenschaftliche Standpunkt weder als selbstverständlich vorausgesetzt, noch als losgelöst von den Gegenständen betrachtet werden. Eine wichtige Rolle für Adornos Philosophie und Gesellschaftskritik nimmt dabei eine der Hegelschen Grundkategorien ein – die bestimmte Negation.[122] Allerdings erhält diese Kategorie bei Adorno nun eine neue, kritische Funktion: Hatte Hegel als bestimmte Negation das Charakteristikum der Entwicklung und des Fortschreitens des Bewusstseins beschrieben, wobei dem Philosophen selbst nichts als „das reine Zusehen“ bleibe, so wird die bestimmte Negation bei Adorno zu einer Form der immanenten Kritik umgedeutet. Dies dient Adorno nicht nur zur radikalen Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern beinhaltet letztlich sogar ein Festhalten an Metaphysik als „Konstellation“. (GS 6: 399) Die Vorgehensweise der bestimmten Negation durchzieht nicht zuletzt einen Großteil der materialen Arbeiten Adornos, so etwa die Dialektik der Aufklärung und die Minima Moralia. Seine Drei Studien zu Hegel verstand Adorno als „Vorbereitung eines veränderten Begriffs von Dialektik“; sie hören dort auf, „wo erst zu beginnen wäre“ (GS 5: 249 f.). Dieser Aufgabe widmete sich Adorno in einem seiner späteren Hauptwerke, der Negativen Dialektik (1966). Der Titel dieses ‚Programms‘ bringt, wie Tilo Wesche es ausdrückt, „Tradition und Rebellion gleichermaßen zum Ausdruck“.[123] Tradition einerseits, da Adorno Dialektik, wie sie von Hegel als werdender Vermittlungsprozess neu gedacht und entfaltet wurde, aufgreift. Rebellion andererseits, insofern Adorno unter dem Vorbehalt des Negativen (auch: des „Nichtidentischen“) Hegels spekulative Dialektik angreift (siehe dazu weiter unten). Speziell kritisiert Adorno an Hegel dessen Übergang von der Dialektik zur spekulativen Vernunft. Als Bedingung für das Funktionieren von Hegels geschichtlichem System werde dabei das Moment „des Nichtaufgehenden“ mithilfe eines „Münchhausenkunststücks“ der Vernunft weggeschafft. (GS 5: 375) Dafür müsse sich das „zum absoluten [Geist, d. V.] sich stilisierende Subjekt“ (GS 6: 187) jedoch selbst betrügen, d. h. letztlich Realitätsverleugnung betreiben. Denn: „Vermittlung des Subjekts [bedeutet], daß es ohne das Moment der Objektivität buchstäblich nichts wäre.“ (GS 6: 187) Insofern verfolgt Adorno die Absicht, Dialektik – welche bei Hegel zwar mehr als der Verstand, jedoch weniger als die spekulative Vernunft geleistet habe – als Schlüsselmoment für Philosophie wiederzugewinnen.[124] |
ヘーゲル ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル アドルノによるヘーゲル哲学の借用は、少なくとも1931年の就任講演まで遡ることができる。その中で彼は次のように主張した。「私にとって哲学的な解釈 は弁証法的にのみ可能であるように思われる」(『ゲゼルシャフト・シュピーゲル』第1巻、338ページ)。ヘーゲルは、哲学的方法をその内容や対象から切 り離すという考えを否定した。思考とは常に何かについて考えることであるため、弁証法は「対象そのものの概念化された運動」である。[121] 『精神現象学』の議論に従えば、科学的視点は当然視されるものでも、対象から切り離されたものとして見なされるものでもない。 ヘーゲルの基本的なカテゴリーのひとつである「確実な否定」は、アドルノの哲学と社会批判において重要な役割を果たしている。122] しかし、アドルノは今、このカテゴリーに新たな批判的な機能を付与している。ヘーゲルは確実な否定を意識の発展と進歩の特徴として説明したが、その中で哲 学者自身は「純粋な観察」以外には何も残されていない。アドルノは確実な否定を再解釈し、 内在的批判の一形態として再解釈される。これはアドルノが社会状況を根本的に批判するのに役立つだけでなく、最終的には「星座」としての形而上学への固執 さえも含む。(GS 6: 399)明確な否定のアプローチは、啓蒙の弁証法や『ミニマ・モラリア』など、アドルノの著作の多くに浸透している。 アドルノは『ヘーゲルに関する三つの研究』を「修正された弁証法概念の準備」と捉えていた。この作品は「どこから始めなければならないか」というところで 終わっている(GS 5: 249 f.)。アドルノは、この課題に専念した。その成果が、彼の晩年の主要著作のひとつ『否定的弁証法』(1966年)である。この「プログラム」のタイトル は、ティロ・ヴェシェの表現を借りれば、「伝統と反逆の両方を表現している」[123]。伝統という側面は、アドルノがヘーゲルによって再考され発展した 弁証法を、新たな調停のプロセスとして取り上げたことによる。一方、反抗という点では、アドルノがヘーゲルの思弁的弁証法を否定(「非同一」)という条件 付きで攻撃していることによる(この点については後述)。 アドルノは特にヘーゲルが弁証法から思弁的理性へと移行したことを批判している。ヘーゲルの歴史体系が機能するための条件として、「非吸収」の瞬間が 「ミュンヒハウゼンのトリック」によって理性から取り除かれる。(GS 5: 375)しかし、そうするためには、「主体が自らを絶対的なものへと様式化する」(GS 6: 187)ことが必要であり、すなわち、究極的には現実の否定に自らを従事させることになる。なぜなら、「主体の媒介とは、客観性の瞬間がなければ文字通り 何もないことを意味する」からだ(GS 6: 187)。この点において、アドルノは、ヘーゲルの著作において理解以上のもの、しかし思弁的理性未満のものを達成した弁証法を、哲学の重要な瞬間として 取り戻すという意図を追求している。 |
| Karl Marx Die Marx’sche Kritik der politischen Ökonomie gehört zum Hintergrundverständnis des Adorno’schen Denkens, freilich – nach Jürgen Habermas – als „verschwiegene Orthodoxie, deren Kategorien […] sich in der kulturkritischen Anwendung [verraten], ohne als solche ausgewiesen zu werden“.[125] Seine Marx-Rezeption erfolgte zunächst vermittelt durch Georg Lukács’ einflussreiche Schrift Geschichte und Klassenbewußtsein; von ihm übernahm Adorno die marxistischen Kategorien des Warenfetischs und der Verdinglichung. Sie stehen in enger Verbindung zum Begriff des Tauschs, der wiederum im Zentrum von Adornos Philosophie steht und erkenntnistheoretisch weit über die Ökonomie hinausweist. Unschwer ist die entfaltete „Tauschgesellschaft“ mit ihrem „unersättlichen und destruktiven Expansionsprinzip“ (GS 5: 274) als die kapitalistische zu dechiffrieren. Neben dem Tauschwert nimmt der Marx’sche Ideologiebegriff in seinem gesamten Werk einen prominenten Stellenwert ein.[126] Auch der Klassenbegriff, den Adorno eher selten benutzte, hat seinen Ursprung in der Marx’schen Theorie. Zwei Texte Adornos beziehen sich explizit auf den Klassenbegriff: Der eine ist das Unterkapitel Klassen und Schichten aus der Einleitung in die Musiksoziologie, der andere ein unveröffentlichter Aufsatz aus dem Jahre 1942 mit dem Titel Reflexionen zur Klassentheorie, der erstmals posthum in den Gesammelten Schriften veröffentlicht wurde (GS 8: 373–391). |
カール・マルクス 確かに、ユルゲン・ハーバーマスによれば、マルクスの政治経済批判はアドルノの思想の背景にある理解の一部である。「暗黙の正統性」として、その カテゴリーは「[...] そのように特定されることなく、文化批判的な適用において自らを露呈する」のである。 [125] アドルノのマルクス受容は、当初はゲオルク・ルカーチの影響力のある著作『歴史と階級意識』によって仲介された。アドルノはルカーチから、商品フェティシ ズムと物象化というマルクス主義のカテゴリーを借用した。これらは交換の概念と密接に関連しており、交換の概念はアドルノの哲学の中心であり、認識論的に は経済をはるかに超えたところを指し示している。「飽くなき拡大の破壊的原則」(GS 5: 274)を持つ「交換社会」が資本主義社会であると解釈するのは難しいことではない。交換価値に加えて、彼の著作全体においてマルクス主義のイデオロギー 概念が重要な役割を果たしている。 アドルノがほとんど使用しなかった階級という概念も、その起源はマルクス主義理論にある。アドルノの著作のなかで階級概念に明確に言及しているものは2つ ある。1つは『音楽社会学序説』の「階級と階層」という小見出しの章であり、もう1つは1942年に書かれた未発表のエッセイ「階級理論についての考察」 で、これは死後に『全集』第8巻(GS 8: 373-391)で初めて出版された。 |
| Sigmund Freud Die Psychoanalyse ist ein konstitutives Element der Kritischen Theorie.[127] Zwar hat Adorno, im Gegensatz zu Horkheimer, sich nie der praktischen Erfahrung einer Psychoanalyse unterzogen,[128] aber schon früh das Werk Sigmund Freuds rezipiert. Seine Freud-Lektüre reicht in die Zeit seiner Arbeit an der ersten (zurückgezogenen) Habilitationsschrift – Der Begriff des Unbewußten in der transzendentalen Seelenlehre – von 1927 zurück. Darin vertrat Adorno die These, „daß die Heilung aller Neurosen gleichbedeutend ist mit der vollständigen Erkenntnis des Sinns ihrer Symptome durch den Kranken“ (GS 1: 236). In dem Aufsatz Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie (1955) begründete er als Notwendigkeit, „angesichts des Faschismus“ die „Theorie der Gesellschaft durch Psychologie, zumal analytisch orientierte Sozialpsychologie zu ergänzen“. Um den Zusammenhalt der repressiven, gegen die Interessen der Menschen gerichteten Gesellschaft erklären zu können, bedürfe es der Erforschung der in den Massen vorherrschenden Triebstrukturen (GS 8: 42). Adorno blieb immer Anhänger und Verteidiger der orthodoxen Freud’schen Lehre, der „Psychoanalyse in ihrer strengen Gestalt“.[129] Aus dieser Position heraus hat er schon früh Erich Fromm[130] und später Karen Horney wegen ihres Revisionismus angegriffen (GS 8: 20 ff.). Vorbehalte äußerte er sowohl gegen eine Soziologisierung der Psychoanalyse[131] als auch gegen ihre Reduzierung auf ein therapeutisches Verfahren.[132] Der Freud-Rezeption verdankte Adorno zentrale analytische Begriffe wie Narzissmus, Ich-Schwäche, Lust- und Realitätsprinzip. Freuds Schriften Das Unbehagen in der Kultur und Massenpsychologie und Ich-Analyse waren ihm wichtige Referenzquellen. Der „genialen und viel zu wenig bekannten Spätschrift über das Unbehagen in der Kultur“ (GS 20/1: 144) wünschte er „die allerweiteste Verbreitung gerade im Zusammenhang mit Auschwitz“; zeige sie doch, dass mit der permanenten Versagung, welche die Zivilisation auferlege, „im Zivilisationsprinzip selbst die Barbarei angelegt ist“ (GS 10/2: 674). |
ジークムント・フロイト 精神分析は批判理論の構成要素である。127] ホルクハイマーとは異なり、アドルノは精神分析の実践的な経験をしたことはなかったが、128] 彼は早くからジークムント・フロイトの著作を読んでいた。フロイトの著作を読んだのは、1927年の最初の(取り下げられた)博士論文『魂の超越論的教義 における無意識の概念』の執筆時まで遡る。その論文の中でアドルノは、「あらゆる神経症の治癒は、患者が自らの症状の意味を完全に理解することに等しい」 というテーゼを提示した(GS 1: 236)。論文「社会学と心理学の関係について」(1955年)において、アドルノは「ファシズムに直面する中で、社会理論を心理学、特に分析的社会心理 学によって補う」ことの必要性を説明した。人民の利益に反する抑圧的社会の結束を説明するためには、大衆に浸透する動因構造の研究が必要である(GS 8: 42)。 アドルノは常に正統派のフロイト学説、すなわち「厳格な形での精神分析」の支持者であり擁護者であった。[129] この立場から、彼は早い時期にエーリッヒ・フロム[130]を、後にカレン・ホルネイを修正主義者として攻撃した(GS 8: 20 ff.)。彼は精神分析の社会学化[131]と、それを治療手順に還元すること[132]の両方に懐疑的な見方を示した。アドルノはナルシシズム、自我の 脆弱性、快楽原則、現実原則といった主要な分析概念をフロイトの受容に負っていた。フロイトの著作『文化における不満』、『集団精神分析と自我の分析』 は、彼にとって重要な参照資料であった。彼は、「文化における不安に関するこの輝かしいが、あまりにも知られていない晩年の業績」が、「特にアウシュビッ ツに関連して」可能な限り広く普及することを望んでいた(GS 20/1: 144)。なぜなら、それは文明によって課された永続的な否定とともに、「野蛮は文明の原則そのものに内在する」ことを示しているからだ(GS 10/2: 674)。 |
| Rezeption weiterer Autoren Am dänischen Philosophen und Vorläufer der Existenzphilosophie Søren Kierkegaard schätzte Adorno dessen Kritik an Hegels Geringschätzung des Individuums, das hinter dem objektiven Geist verschwindet. Sie hat Adornos Blick auf Hegels Dialektik geschärft und nachhaltig beeinflusst. Viele später ausformulierte philosophische Motive Adornos finden sich in seiner Kierkegaard-Schrift bereits angedeutet. Horkheimer charakterisierte sie als „unerhört schwierig“.[133] Adornos Auseinandersetzung mit Edmund Husserls Phänomenologie fand ihren Niederschlag in der Schrift Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Adorno hatte an dem Manuskript von 1934 bis Herbst 1937 in Oxford gearbeitet, ohne es abzuschließen.[134] Nachdem in den folgenden Jahren einzelne Kapitel veröffentlicht worden waren, erschien das Werk erst 1956 als Monographie mit der Widmung „Für Max“. Das Buch gilt als „Solitär“, das keine größere Resonanz in der philosophischen Literatur fand,[135] obwohl Adorno 1968 die Arbeit als das ihm nächst der Negativen Dialektik wichtigste seiner Bücher bezeichnete (GS 5: 386). Als Antipode Heideggers, des führenden Vertreters der Fundamentalontologie, unterzog er im Jargon der Eigentlichkeit dessen Begrifflichkeit einer „ideologiekritischen Sprachanalyse“. Doch wusste er zu unterscheiden zwischen der substantiellen Philosophie Heideggers und der Plumpheit der „Imitatoren des existentiell-philosophischen Sprachgestus“.[136] Auf die Nähe des Denkens Adornos, seine Überschneidungen mit der Philosophie Heideggers, wurde häufig verwiesen.[137] → Hauptartikel: Jargon der Eigentlichkeit |
他の著者の評価 アドルノは、ヘーゲルが個人を軽視し、客観的精神の背後に消え失せてしまうという批判を行ったデンマークの哲学者であり実存主義の先駆者であるキルケゴー ルを高く評価した。 キルケゴール批判は、アドルノのヘーゲル弁証法に対する見方を鋭くし、長期的に影響を与えた。アドルノの後の哲学的主題の多くは、すでにキルケゴールに関 する著作に見出すことができる。ホルクハイマーはそれを「信じられないほど難しい」と評した。[133] アドルノのエドムント・フッサール現象学への関与は、著書『認識論批判』(Zur Metakritik der Erkenntnistheorie)に表現されている。アドルノは1934年から1937年秋にかけてオックスフォードでこの原稿に取り組んだが、完成 させることはできなかった。各章がその後出版された後、この著作は1956年まで単行本として出版されることはなく、「マックスに捧ぐ」とされた。この本 は哲学の文献では大きな反響を得られなかった「孤独な」作品とみなされているが[135]、1968年にアドルノは『否定的弁証法』に次いで自身の著作の 中で最も重要なものだと述べている(GS 5: 386)。 根本的な存在論の代表的人物であるハイデガーの対極に位置するアドルノは、「現実性」という概念を「イデオロギー批判的な言語分析」に服従させた。しか し、彼はハイデガーの実質的な哲学と、「実存哲学的な言語的ジェスチャーの模倣者」の不器用さの違いを見分ける術を知っていた。[136] アドルノの思想とハイデガーの哲学の近さ、重なり合いは、しばしば言及されてきた。[137] → 詳細は「実在性のための弁証法」を参照 |
| Werk Jan Philipp Reemtsma hat Adornos Publikationen zu den verschiedenen Themengebieten nach quantitativen Anteilen an seinen Gesammelten Schriften erfasst: Demnach entfallen auf im weitesten Sinne philosophische Fragen 2.600 Seiten, auf soziologische Themen 1.500 Seiten, auf literaturtheoretische bzw. -kritische rund 800 Seiten, auf die musikalischen Schriften hingegen mehr als 4.000 Seiten.[138] |
作品 ヤン・フィリップ・レームツマは、アドルノのさまざまなテーマに関する出版物を、彼の著作集における量的な割合に従って記録している。それによると、最も 広い意味での哲学的な問いかけに2,600ページ、社会学的なテーマに1,500ページ、文学理論と批評に約800ページ、音楽に関する著作に4,000 ページ以上が割かれている。 |
| Philosophie Als Adornos philosophische Hauptwerke gelten heute vier sehr unterschiedliche Werke. Die in der Emigration gemeinsam mit Max Horkheimer verfasste Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (1947) wird als zentraler Text der Frankfurter Schule angesehen und prägte den Begriff der Kulturindustrie. Ebenfalls in der Emigration entstanden die Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (1951), eine aphoristische „Diagnose einer global organisierten Unmündigkeit“.[139] Selbst betrachtete Adorno die Negative Dialektik (1966) als sein Hauptwerk, eine philosophische Kritik des „identifizierenden Denkens“; der Titel war für ihn gleichbedeutend mit dem Konzept der Kritischen Theorie. Posthum erschien 1970 Adornos Ästhetische Theorie, die seine Philosophie der Kunst darstellt.[140] Albrecht Wellmer verweist auf die hohe Kontinuität des philosophischen Denkens Adornos von seiner frühen Frankfurter Antrittsvorlesung Die Aktualität der Philosophie (1931), in der er sein Konzept der Philosophie als „Deutungswissenschaft“ (GS 1: 334) begründete, bis hin zu seinen Spätwerken. Mit 28 Jahren hätten sich bei ihm bereits „alle entscheidenden Motive seines Denkens, gleichsam dessen Grundkonstellationen“ herausgebildet. Seine spätere reiche Produktion, auch die in der Musikphilosophie und Musiksoziologie, beruhe auf der Entfaltung dieser Grundkonstellationen.[141] Anders als Horkheimer, der wenige Monate zuvor in seiner programmatischen Antrittsrede bei der Übernahme des Direktorats des Instituts für Sozialforschung[142] allein im interdisziplinären Zusammenwirken der Einzelwissenschaften das Ziel einer „Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft als ganzer“ erreichbar sah,[143] wies Adorno in der „dialektischen Kommunikation“ von Soziologie und Philosophie jener die Aufgabe zu, das empirische Material zu liefern, der Philosophie die Deutungsmuster zu generieren; Letzteres fasste er in das Bild: „Schlüssel zu konstruieren, vor denen die Wirklichkeit aufspringt“ (GS 1: 340). Erstmals wurde in der Antrittsvorlesung der Begriff der Totalität in Frage gestellt, die das Denken nicht zu begreifen vermöge; Philosophie müsse lernen, auf die Totalitätsfrage zu verzichten. Zeitgenössischen Philosophierichtungen wie der Phänomenologie und der Seinslehre Heideggers sprach er ab, „die philosophischen Kardinalfragen“ zu beantworten. Einer Liquidation der Philosophie käme die These gleich, dass diese Fragen prinzipiell unbeantwortbar seien, wie sie der Positivismus des Wiener Kreises vertrete, der die Philosophie in Wissenschaft aufzulösen vorschlage. Dem hielt Adorno entgegen: „die Idee der Wissenschaft ist Forschung, die der Philosophie Deutung“ (GS 1: 334). Der philosophische Gehalt der Texte Adornos lässt sich nur selten leicht erschließen. Philosophie ist ihm „der Musik verschwistert“; ihr Schwebendes sei „kaum […] recht in Worte zu bringen“ (GS 6: 115). Seine Kategorien sind janusköpfig: je nach Kontext verwendet er sie mit positiver oder negativer Konnotation.[144] Meistens ist Adorno der Analyse des Konkreten verpflichtet, in deren Mittelpunkt das Individuum in der zeitgenössischen Gesellschaft steht.[145] Den philosophischen Systemen wie der klassischen Erkenntnistheorie, die das Individuelle und Nichtidentische verstümmelten, statt es zu begreifen, stellt er seine negative Dialektik als „Antisystem“ entgegen. Dennoch hat Adorno an der Philosophie, sogar an Metaphysik im Sinn der Spekulation, die das Gegebene transzendiert, festgehalten. Nur als bestimmte Negation des Faktischen, so seine Lehre, lasse sich über das Bestehende hinausdenken. Wenn man nicht hinter Kant und Hegel zurückfallen wolle, müsse Philosophie Kritik sein: Sprachkritik, Gesellschaftskritik, Kunstkritik, die zudem die Übertreibung als Erkenntnismethode benutzt.[146] |
哲学 アドルノの主要な哲学作品は、今日では4つの非常に異なる作品であると考えられている。『啓蒙の弁証法』。亡命中にホルクハイマーと共著で執筆した『哲学 断片』(1947年)は、フランクフルト学派の中心的な文献とみなされており、「文化産業」という用語を考案した。同じく亡命中に執筆された『ミニマ・モ ラリア 『破損した人生からの省察』(1951年)は、格言的な「世界的に組織化された未熟さの診断」である。[139]アドルノ自身は『否定弁証法』(1966 年)を主要な著作とみなしており、これは「同一視する思考」に対する哲学的批判である。彼にとって、このタイトルは批判理論の概念と同義であった。芸術に 関する彼の哲学を提示した『アドルノの美学理論』は、1970年に死後出版された。 アルブレヒト・ウェルマーは、アドルノの哲学思想には、フランクフルトでの初期の就任講演『哲学の現存在』(1931年)で「解釈学としての哲学」という 哲学概念を打ち立てた時から、晩年の作品に至るまで、高度な連続性があることを指摘している。28歳までに、彼はすでに「いわばその基本星座とも言うべ き、彼の思考の決定的なモチーフのすべて」を開発していた。彼の後の多作な作品、音楽の哲学や社会学における作品を含め、それらはこれらの基本的な星座の 発展に基づいている。 [141] ホルクハイマーとは異なり、数ヶ月前に社会研究協会の所長に就任した際のプログラム的な就任演説で、[142] 「現代社会全体論」の目標は個々の科学の学際的な相互作用によってのみ達成可能であると主張した。 [1 43]アドルノは、社会学と哲学の「弁証法的コミュニケーション」に経験的資料を提供するという課題を社会学に、解釈的パターンの生成という課題を哲学に 割り当てた。彼は後者を次のように要約した。「現実が解き放たれる鍵を構築する」(GS 1: 340)。就任講演において、彼は思考が把握できない全体性の概念を疑問視し、哲学は全体性の問題を放棄することを学ばなければならないと主張した。彼 は、現象学やハイデガーの存在論といった現代の哲学の学派が「哲学の根本的な問い」に答えられるとは否定した。哲学の清算は、ウィーン学団の実証主義が唱 えたように、これらの問いは原理的に答えられないという命題と同義である。アドルノは次のように反論した。「科学の概念は研究であり、哲学の概念は解釈で ある」(GS 1: 334)。 アドルノのテキストの哲学的内容は、ほとんど理解するのが容易ではない。彼にとって哲学とは「音楽と関連する」ものであり、その浮遊性は「ほとんど言葉に 置き換えることができない」(GS 6: 115)。彼のカテゴリーは二面性を持つ。文脈によって、肯定的な意味合いまたは否定的な意味合いで用いられる。[144]アドルノは主に、現代社会にお ける個人に焦点を当てた具体的なものの分析に専念している。[145]彼は、個人を理解するのではなく、個人を切り刻み、同一ではないものとして扱う古典 的認識論などの哲学体系に反対し、自身の否定的弁証法を 「反体制」として。それでもアドルノは、与えられたものを超越する思索という意味において、哲学、さらには形而上学に固執した。彼の教義によれば、事実の 否定という形でこそ、人は既存のものを超えた思考が可能になる。カントやヘーゲルに後戻りしたくないのであれば、哲学は批判でなければならない。言語批 判、社会批判、芸術批判であり、それは誇張も洞察の方法として用いる。 |
| Negative Dialektik: Adornos „Philosophie des Nichtidentischen“ → Hauptartikel: Negative Dialektik Erstausgabe der Negativen Dialektik im Frankfurter Adorno-Denkmal Ausgangspunkt der Adorno’schen Philosophie, seiner negativen Dialektik, ist Hegels dialektische Implikation, die besagt, dass Subjekt und Objekt als vermittelt zu begreifen sind. Damit hatte Hegel Kants Bestimmung des transzendentalen Ichs kritisiert, welches dem zu erkennenden Objekt (dem Ding an sich bei Kant) verbindungslos gegenüberstehe.[147] Adorno knüpft nun an das Konzept der Vermittlung der Hegel’schen Dialektik an, kritisiert diesen jedoch zugleich, indem er die „Ungleichheit im Begriff der Vermittlung“ (GS 6: 184) hervorhebt. Diese Ungleichheit besage, dass „das Subjekt ganz anders ins Objekt“ (GS 6: 184) falle als das Objekt ins Subjekt. Subjektivität sei, der eigenen Beschaffenheit nach, vorweg immer auch Objekt, ohne ein Moment der Objektivität könne es damit aber nicht einmal existieren. Ganz anders das Objekt, dieses könne zwar auch nur durch Subjektivität hindurch gedacht werden, erhalte sich dem Subjekt gegenüber aber immer als Anderes, d. h. als ein mit dem Subjekt nicht Identisches. Wer dies nicht anerkenne, betrüge sich nicht nur selbst, sondern bestätige überhaupt „die Ohnmacht des Geistes in all seinen Urteilen wie bis heute in der Einrichtung der Realität.“ (GS 6: 187). Rolf Wiggershaus, der Chronist der Frankfurter Schule, bezeichnet in seiner Einführung zu Adornos Denken dessen „Philosophie des Nichtidentischen“ daher auch als den Horizont seiner kritischen Gesellschaftstheorie.[148] Als Nichtidentisches versteht Adorno das „Begriffslose, Einzelne und Besondere“, für das Hegel sein Desinteressement bekundet und worauf dieser „das Etikett der faulen Existenz“ geklebt habe (GS 6: 20). Auch Albrecht Wellmer nennt Adorno einen „Anwalt des Nicht-Identischen“.[149] Als Kritiker des „identifizierenden Denkens“ misstraut Adorno dem Denken in – vom Konkreten abstrahierenden – Begriffen: Dialektisches Denken erhebe Einspruch dagegen, dass der Begriff einen „Sachverhalt an sich“ als etwas Festes, Unveränderliches und sich Gleichbleibendes darstellt (GS 6: 156). Zugleich bleibt auch die (negative) Dialektik Adornos auf den Begriff angewiesen, sie ist selbst noch begriffliches Denken.[150] Insofern weckt ein „solcher Begriff von Dialektik […] Zweifel an seiner Möglichkeit.“ (GS 6: 21) Eine Philosophie des Nichtidentischen müsse dennoch an der utopischen Idee, sei diese auch zweifelhaft und paradox, festhalten: Dies gipfelt in der – nicht minder paradoxen – Forderung, „das Begriffslose mit Begriffen aufzutun, ohne es ihnen gleichzumachen.“ (GS 6: 21). Dabei wendet sich die Philosophie des Nichtidentischen sowohl gegen Ursprungsphilosophie (die ein Erstes – Geist oder Materie – voraussetzt) als auch gegen Subjektphilosophie (die das Objekt als ein dem Subjekt Unterworfenes oder Nachgeordnetes denkt). „Objekt“ hat bei Adorno verschiedene Bedeutungen: andere Subjekte, Natur, Dinge, Verdinglichtes. Das Subjekt ist als bewusstes Wesen für Adorno zugleich Teil des ihm gegenüberstehenden Naturzusammenhangs, den es im eigenen Bewusstsein hat, aber als etwas anderes erkennt. Mit dem Verweis auf das mit dem Subjekt nicht Identische plädiert Adorno für ein anderes Verhältnis zur eigenen und äußeren Natur, das nicht mehr durch Verfügung und Herrschaft bestimmt ist, sondern durch Versöhnung und Anverwandlung.[151] Für letzteres bemüht Adorno häufig den Begriff Mimesis. Zentral für Adornos Philosophie ist der Begriff der „Versöhnung“. Annäherungsweise lässt er sich mit der „gewaltlosen Integration des Divergierenden“ (GS 7: 283) übersetzen. Im Horizont des Adorno’schen Denkens kann Versöhnung so Vielfältiges heißen wie: Versöhnung von Geist und Natur, von Subjekt und Objekt, von Allgemeinem und Besonderem, von Individuum und Gesellschaft, von Moral und Natur. Vornehmlich die unterdrückte Natur, das bedrohte Individuum und das unbegriffene Vereinzelte steht im unversöhnten Verhältnis zu seinem Gegenpart. Versöhnung „gäbe das Nichtidentische frei, […] eröffnete erst die Vielheit des Verschiedenen“ (GS 6: 18). |
否定の弁証法:アドルノの「非同一性の哲学」 → 詳細は「否定の弁証法」を参照 フランクフルトのアドルノ記念碑に刻まれた『否定の弁証法』初版 アドルノの哲学の出発点である「否定的弁証法」は、主観と客観が媒介されたものとして理解されるべきであるとするヘーゲルの弁証法的な含意に基づいてい る。これによって、ヘーゲルはカントの超越論的自我の決定を批判した。超越論的自我は、認識されるべき対象(カントにおける「物自体」)と関係なく存在す る。 アドルノはここでヘーゲル弁証法における媒介概念と結びつけるが、同時に「媒介概念における不平等」を強調することでそれを批判している(GS 6: 184)。この不平等とは、「主体が対象に陥る」という意味であり(GS 6: 184)、対象が主体に陥るという意味とは全く異なる。主観性は、その本質上、常に客観性でもある。しかし、客観性の瞬間がなければ、主観性は存在するこ とすらできない。客観性はまったく異なる。主観性を通じてのみ思考することができるが、主観性に対しては常に他者であり、すなわち主観性と同一ではないも のとして存在する。このことを認識しない者は、自分自身を欺くだけでなく、「今日に至るまで、あらゆる判断や現実の構築における精神の無力さ」を自ら証明 しているのだ。(GS 6: 187) それゆえ、フランクフルト学派の研究者であるロルフ・ヴィッゲルハウゼンは、アドルノの思想の紹介のなかで、彼の「非同一の哲学」を批判的社会理論の地平 として説明している。148] アドルノは、非同一を「非概念的、個別的、特殊なもの」と理解しており、これに対してヘーゲルは関心を示さず、「腐った存在」というレッテルを貼っている (GS 6 。アルブレヒト・ヴェルマーもアドルノを「非同一の擁護者」と呼んでいる。[149] 「同一視する思考」の批判者として、アドルノは具体的なものを抽象化する思考を不信の目で見る。弁証法的な思考は、概念が「それ自体が事実」を固定され た、不変で恒常的なものとして提示しているという事実を問題視している(GS 6: 156)。 同時に、アドルノの(否定的な)弁証法もまたこの概念に依存しており、それ自体は依然として観念的な思考である。150] この点において、「このような弁証法の概念は[...]その可能性について疑いを生じさせる」(GS 6: 21)しかし、非同一の哲学は、それがいかに疑わしく、逆説的であろうとも、ユートピア的な考えに固執しなければならない。これは、「不可知を、それらを 同一視することなく概念によって開示する」という、これまた逆説的な要求に集約される(GS 6: 21)。 そうすることで、非同一の哲学は、起源の哲学(第一のもの、すなわち精神または物質を前提とする)と主題の哲学(対象を主体または主体に従属するものとし て捉える)の両方に反対する。アドルノにとって、「対象」という用語はさまざまな意味を持つ。すなわち、他の主体、自然、物自体、物自体化された対象など である。アドルノにとって、意識的存在としての主体は、同時に、自身の意識の中にある自然の文脈の一部であると同時に、それとは異なるものとして認識す る。主体と同一ではないものを指摘することで、アドルノは、もはや支配や制御によってではなく、和解と吸収によって決定される、自己と外部の自然との異な る関係を主張する。 アドルノの哲学の中心となるのは、「和解」という概念である。これは「相異なるものの非暴力的統合」と大まかに訳すことができる(GS 7: 283)。アドルノの思考の地平において、和解は多くのことを意味しうる。すなわち、精神と自然、主体と対象、一般と特殊、個人と社会、道徳と自然の和解 である。とりわけ、抑圧された自然、脅かされた個人、誤解された孤立した存在は、その相手と和解していない関係にある。和解は「同一でないものを解放し [...]、そして初めて異なるものの多様性を開放する」(GS 6: 18)だろう。 |
| Kritik der Erkenntnistheorie Zwar steht die philosophische Erkenntnistheorie nicht im Zentrum von Adornos philosophischen Vorlesungen und Schriften, aber die frühe, durch Kracauer vermittelte Kant-Lektüre und seine Dissertation über Husserls Phänomenologie brachte ihn bereits in den frühen Phasen seiner intellektuellen Entwicklung mit dieser philosophischen Disziplin in Kontakt. Er ist Erkenntnistheoretiker insoweit, als er „das Verhältnis des Denkens zur Wirklichkeit als den Prüfstein und die Vorbedingung zuverlässiger Erkenntnis diskutiert.“[152] Wie nahezu alle philosophischen Fragen hat Adorno auch die der Erkenntnistheorie unter Aspekten der Kritik behandelt. Seine Studien über Husserls Phänomenologie hat er mit Metakritik der Erkenntnistheorie überschrieben. In dem nur dürftig rezipierten Werk erörtert er das Verhältnis zwischen erkennendem Subjekt und zu erkennendem Objekt. Husserls Idee der Objektivität der Wahrheit und die Idee des denkenden Vollzugs wahrer Erkenntnis lagen auch Adorno am Herzen.[153] Doch Husserls Vorstellung, mit einer vorurteilsfreien Philosophie, die sich mit der Methode der „phänomenologischen Reduktion“ auf „die Sachen selbst“ beziehe, kritisiert er als „logischen Widersinn“, der mit Hegels „Lehre von der Vermitteltheit“ unvereinbar sei (GS 5: 13). Mit diesem teilt Adorno die Skepsis gegenüber einem „absolut Ersten als des zweifelfrei gewissen Ausgangspunktes der Philosophie“ (GS 5: 13) und insistiert auf der „Vermitteltheit eines jeglichen Unmittelbaren“ (GS 5: 160). Selbst wenn Adorno in materialistischer Denkweise häufig vom „Vorrang des Objekts“ (GS 6: 186) spricht und auf einer „dem Subjekt gegenübertretenden Alterität [= Andersheit, Andersartigkeit] beharrt“,[154] geschieht dies nicht ohne die Überzeugung, dass „die Beschaffenheiten der Erkenntnisobjekte immer nur durch das reflektierende Subjekt hindurch zu haben sind“.[155] Da Adornos „Erkenntnisutopie“ auf die unverkürzte Erfahrung des Nichtidentischen zielt, erwartet er von der Kunst „als ein[em] genuin andere[n] Medium der Erkenntnis […] Unterstützung“.[156] Rüdiger Bubner sieht hier eine „Konvergenz von Erkenntnis und Kunst“,[157] während Habermas gar von der „Abtretung der Erkenntnis-Kompetenzen an die Kunst“[158] spricht. |
認識論批判 哲学的認識論はアドルノの哲学講義や著作の中心ではないが、初期のカントの読解(クラカウアー編)やフッサール現象学に関する論文によって、彼は知的な成 長の初期段階でこの哲学分野に触れた。彼は「信頼できる知識の試金石であり前提条件としての思考と現実の関係」について論じている限りにおいて認識論者で ある。[152] ほとんどすべての哲学的な問いと同様に、アドルノも認識論の問いを批判的な視点から扱った。彼はフッサールの現象学に関する研究に『認識論のメタ批判』と いうタイトルをつけた。この作品はあまり評価されていないが、彼は知る主体と知られる対象の関係について論じている。真理の客観性に関するフッサールの考 えや、真の知識の思考過程に関する考えもアドルノの関心を引いた。[153] しかし、フッサールが「現象学的還元」の方法によって「物自体」を参照する偏りのない哲学の考えを「論理的なナンセンス」であり、ヘーゲルの「媒介の教 義」と両立しないものとして批判していることは、アドルノも知っていた(GS 5: 13)。アドルノは、「哲学の出発点として疑いなく絶対的に第一のもの」(GS 5: 13)に関するヘーゲルの懐疑論を共有し、「あらゆる即物性の媒介性」(GS 5: 160)を主張する。アドルノが「対象の優位性」(GS 6: 186)について語り、「主体に直面する他者性(=他者、他者性)」を主張する場合でさえも、[154] これは「認識の対象の本質は、反省的な主体を通じてのみ得られる」という確信なしには語れない。[155] アドルノの「認識論的ユートピア」は、同一ではないものの無修正の経験を目指しているため、彼は芸術から「知識の真に異なる媒体としての支援」を期待して いる。[156] リュディガー・ブブナーは、ここに「知識と芸術の収束」を見ている。[157] 一方、ハーバーマスは「芸術への認識能力の譲渡」についてさえ語っている。[158] 。 |
| Negative Moralphilosophie Der bekannte Ausspruch aus den Minima Moralia: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ (GS 4: 43) wurde in der Sekundärliteratur oft als eine Absage Adornos an die Moralphilosophie interpretiert. Entgegen dieser Auffassung hat Gerhard Schweppenhäuser Adornos untergründig präsente Moralphilosophie herausgearbeitet und sie als eine „negative Moralphilosophie“, eine „Ethik nach Auschwitz“ bezeichnet, wobei Auschwitz als Chiffre für den Holocaust steht.[159] Dagegen spricht auch, dass Adorno immerhin zwei Vorlesungen zur Moralphilosophie gehalten hat (Wintersemester 1956/57, Sommersemester 1963)[160] und seine Minima Moralia das Thema falsches versus richtiges Leben ständig umkreisen. Adorno selbst bezeichnete die Minima Moralia als „ein Buch über das richtige oder vielmehr das falsche Leben“.[161] Eine zentrale Rolle in Adornos Moralkritik nimmt die bestimmte Negation Hegels ein (s. oben zu Adornos Hegel-Rezeption). Diese impliziert für Adorno, dass man als Kritiker der Moral weder auf eine affirmative Gegenmoral noch auf eine abstrakte Negation jeder Moral hinsteuern dürfe.[162] Statt, wie Nietzsche[163], die Moral abstrakt zu negieren, müsse der Weg der bestimmten Negation erst beschritten werden, um so, wie Marx einmal sagt, „aus der Kritik der alten Welt die neue [zu] finden“.[164] In seinen Vorlesungen zur Moralphilosophie greift Adorno diese Vorgehensweise auf, indem er sich auf den Widerstand als „die eigentliche Substanz des Moralischen“[165] beruft. „Das einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, daß das richtige Leben heute in der Gestalt des Widerstands gegen die von dem fortgeschrittensten Bewusstsein durchschauten, kritisch aufgelösten Formen eines falschen Lebens bestünde.“[166] Dabei hat Adorno, ähnlich wie zur Metaphysik, auch zur Moralphilosophie ein ambivalentes Verhältnis. Er kritisiert, dass die christlich-abendländische Moral den Individuen eine Verantwortung für ihre Handlungen abverlange und dabei eine Handlungsfreiheit unterstelle, die sie als soziale Wesen gar nicht haben. Zugleich sieht er in der Moral aber die „Repräsentantin einer kommenden Freiheit“.[167] Moral sei in sich widersprüchlich; sie meine „gleichzeitig immer Freiheit und Unterdrückung“.[168] Ausgangspunkt Adornos ist Kants Moralphilosophie, die moralisches Handeln als Selbstbestimmung in Freiheit definiert.[169] Aber solange der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang hinter den Maßstab eines gerechten Lebens zurückfalle, sei es für die Menschen gar nicht möglich, moralisch richtig zu handeln.[170] Ethische Erwägungen bedürfen daher der Ergänzung durch gesellschaftliche Analyse und Kritik. Das moralische Prinzip vom gesellschaftlichen abzutrennen und in die private Gesinnung zu verlegen, bedeute „auf die Verwirklichung des im moralischen Prinzip mitgesetzten menschenwürdigen Zustands“ (GS 4: 103) zu verzichten. Die Frage, was das „richtige Leben“ ausmache, beantwortet Adorno durchgehend in negativer Weise, als bestimmte Negation. „Er setzt bei dem an, ‚was nicht sein soll‘, bzw. am Leben in seiner ‚verkehrten‘ oder ‚entfremdeten Gestalt‘.“[171] Adornos Lehre vom richtigen Leben finde sich nach Albrecht Wellmer „wie in Spiegelschrift“[172] in seinen Minima Moralia. Statt Inhalt und Ziel einer mündigen, emanzipierten Gesellschaft auf positive Weise zu bestimmen, formuliert Adorno negative Minimalbedingungen an den moralisch richtigen Zustand. Zentral ist in diesem Zusammenhang seine Forderung, „daß Auschwitz nicht noch einmal sei“ (GS 10/2: 674).[173] Dieser durch Hitler aufgezwungene Kategorische Imperativ (GS 6: 358) richtet sich dabei jedoch nicht an ein reines Vernunftsubjekt im Sinne Kants: Wie Alfred Schäfer in seinem „pädagogischen Porträt“ betont, unterscheidet sich Adornos Version des Kategorischen Imperativs von der kantischen vor allem dadurch, dass in ihr (der Adorno’schen) ein „Moment des Hinzutretenden am Sittlichen“ (GS 6: 358) sich fühlen lässt: Für Adorno ist es der unmittelbare, leiblich erfahrbare Abscheu angesichts der nationalsozialistischen Gräueltaten, der die „in sich problematische“ Vernunft komplementiert. Erst durch den impulsiv sich einstellenden Abscheu, also durch ihr Gegenteil, hindurch[174], werde die vernünftige moralische Reflexion demnach „praktisch“.[175] In der Achtung vor dem Individuellen sieht Martin Seel Adornos Kerngedanken eines guten menschlichen Lebens.[176] Ethik müsse daher politische Philosophie werden, die Frage nach dem richtigen Leben müsse in die Frage nach der richtigen Politik übergehen, heißt es zum Schluss von Adornos moralphilosophischer Vorlesung.[177] |
否定的な道徳哲学 『ミニマ・モラリア』の有名な格言「悪の中に正しさはない」(GS 4: 43)は、二次文献ではしばしばアドルノの道徳哲学の拒絶として解釈されてきた。これに対して、ゲルハルト・シュヴェッペンハウザーはアドルノの根底にあ る道徳哲学を明らかにし、それを「否定的な道徳哲学」、すなわち「アウシュヴィッツ以後の倫理」と表現している。159] これに対する別の反論は、アドルノは結局のところ、道徳哲学に関する2つの講義を行っている(1956/57年冬学期、1963年夏学期) [160] また、アドルノの『ミニマ・モラリア』は常に「誤った生き方」と「正しい生き方」というテーマを巡って展開されている。アドルノ自身、『ミニマ・モラリ ア』を「正しい生き方、あるいは誤った生き方についての本」と表現している。[161] アドルノの道徳批判の中心的な役割は、ヘーゲルの「ある否定」が担っている(アドルノのヘーゲル受容については前述)。アドルノにとって、これは、道徳の 批評家として、肯定的な対抗道徳や、あらゆる道徳の抽象的な否定を避けるべきであることを意味する。162] ニーチェのように抽象的に道徳を否定するのではなく、163 マルクスの言葉を借りれば「旧世界への批判から新しいものを見出す」ために、まず明確な否定の道を歩まなければならない。164] 彼の講義では アドルノは『道徳哲学講義』において、抵抗を「道徳の実際の実体」として呼び起こすことで、このアプローチを採用している。[165] 「おそらく唯一言えることは、今日における正しい生き方とは、最も進歩した意識によって見通され、批判的に解消された誤った生き方の形式に対する抵抗の形式において成り立つということだ」[166] アドルノは道徳哲学に対して、形而上学に対するのと同様に、複雑な関係を持っている。彼は、西洋キリスト教の道徳が個々人に自らの行動に対する責任を要求 し、それによって社会的な存在として持たない行動の自由を想定していることを批判している。しかし同時に、彼は道徳を「到来する自由の代表」と見なしてい る。[167] 道徳はそれ自体が矛盾であり、「常に自由と抑圧を同時に意味する」のである。[168] アドルノの出発点はカントの道徳哲学であり、そこでは道徳的行動は自由における自己決定として定義されている。しかし、社会全体の文脈が公正な生活の基準 に達していない限り、人々が道徳的に正しく行動することは不可能である。したがって、倫理的な考察は社会分析と批判によって補完されなければならない。道 徳的原則を社会から切り離し、私的な倫理観に移行させることは、「道徳的原則と共にある人間的な状態の実現」を放棄することを意味する(GS 4: 103)。 アドルノは「正しい人生」を構成するものは何かという問いに対して、全体を通してある種の否定として否定的に答えている。「彼は『あってはならないこ と』、あるいは『倒錯した』あるいは『疎外された』形での人生から出発する」[171] アルブレヒト・ウェルマーによると、アドルノの正しい人生についての教えは、彼の著書『ミニマ・モラリア』の中で「鏡文字のように」見られるという [172]。 成熟した解放された社会の内容と目標を積極的に定義するのではなく、アドルノは道徳的に正しい状態のための否定的な最低条件を定式化する。この文脈におい て中心的なのは、彼の「アウシュビッツを再び起こしてはならない」という主張である(GS 10/2: 674)[173]。しかし、ヒトラーが課したこの定言命法(GS 6: 358)は、カント的な意味での純粋な理性主体に向けられたものではない。アルフレッド・シェーファーが「教育的な肖像」で強調しているように、アドルノ の定言命法は カントのものと異なっているのは、アドルノの「道徳に付け加えられた瞬間」(GS 6: 358)を感じることができる点である。アドルノにとって、それは「それ自体が問題である」理性を補完する、ナチスによる残虐行為に対する直接的な、肉体 的に感じられる嫌悪感である。衝動的に生じる嫌悪感、つまりその反対の感情を通じてのみ、道理にかなった道徳的考察が「実践的」になるのである。 マルティン・ゼールは、アドルノの人間らしい人生の核心となる考えは、個人の尊重にあると見ている。176] したがって、倫理は政治哲学にならなければならない。正しい人生の問いは、正しい政治の問いに融合しなければならない。アドルノの道徳哲学講義の最後に述 べられているように。177] |
| Metaphysik und Metaphysikkritik Adornos Verhältnis zur Metaphysik ist ambivalent.[178] Seine Kritik gilt sowohl der klassischen Metaphysik als auch der Metaphysikkritik. Überlegungen zur Metaphysik ziehen sich durch sein ganzes Werk. Besonders ausgearbeitet hat er sie in der Negativen Dialektik, als deren zentrale Intention er gegenüber Gershom Scholem „die Rettung der Metaphysik“ nennt.[179] Adornos Verständnis der Metaphysik hängt eng mit seinem Verständnis abendländischer Rationalität zusammen. Diese gilt ihm als ein Projekt der Selbst- und der Naturbeherrschung (GS 3: 19). Das Ziel dieses Projektes ist es, dass der Mensch sich mittels seiner Rationalität, dem „identifizierenden Denken“, von der Kontingenz natürlicher Geschehnisse zu befreien versucht, um Herrschaft über sich und seine Umgebung zu erlangen. Innerhalb dieses Projektes spielt die Metaphysik als die „Lehre vom geschichtslos Unveränderlichen“ (GS 2: 261) eine wichtige Rolle. Indem sie der Kontingenz des empirischen Lebens ein System von begrifflichen Zusammenhängen entgegenstellt, die als unveränderlich aufgefasst werden, leitet die Metaphysik ein „Denken der Identität“ ein. Das identifizierende Denken richtet sich dabei nicht nur gegen das, was dem Subjekt äußerlich begegnet, sondern auch gegen seine eigene leibliche Natur. Auch sie soll durch Identifikation beherrschbar und überwunden werden, was Adorno auch als „Anpassung ans Tote“ bezeichnet (GS 3: 79, 206). Das metaphysische Denken richtet sich so gegen sein eigentliches Ziel, die rationale Selbstbestimmung und Freiheit des Menschen. Die Identitäten, die das Kontingente bewältigen sollen, beherrschen den, um dessen Freiheit willen sie gesucht worden sind. Adorno gilt dies als das Skandalon der Metaphysik, aber auch von Rationalität und Aufklärung (GS 6: 361). Auch die Metaphysikkritik, deren Grundprogramm eigentlich die Befreiung des Subjekts von der Metaphysik ist, führt für Adorno letztlich nur zu dessen Unfreiheit. Er setzt sich dabei vor allem mit der Philosophie Kants und dem Positivismus auseinander. Kants Philosophie wird von Adorno als Versuch interpretiert, aus der Metaphysikkritik heraus für die Freiheit des Menschen zu argumentieren. Für Kant ist der Mensch dabei ein Wesen, das nur unter Einbeziehung seiner Sinne und seines Verstandes zu Erkenntnissen zu kommen vermag. Wenn die Erkenntnisse demnach immer unter den feststehenden Anschauungsformen und Verstandesbegriffen stehen, so ist für Adorno damit die Unfreiheit des Subjekts besiegelt: Das menschliche Bewusstsein wird „gleichsam zu ewiger Haft in den ihm nun einmal gegebenen Formen der Erkenntnis verurteilt“ (GS 6: 378). Der Mensch wird so in seinen Erkenntnismöglichkeiten als ein vollkommen festgelegtes und unfreies Wesen begriffen. Diese Festlegung des Menschen auf das Tatsächliche findet nach Adorno ihre Fortsetzung im Positivismus. Gegen die traditionelle Metaphysik und Metaphysikkritik will Adorno eine Metaphysik der Transzendenz rehabilitieren. Metaphysik ist ein Denken des Absoluten, ein Denken dessen, was das Gegebene überschreitet: „Denken über sich selbst hinaus, ins Offene, genau das ist Metaphysik“.[180] Wesentlich für das Denken des Absoluten ist es dabei, dass es jenseits der Verfügungsgewalt eines Subjekts steht. Es darf nicht mit dem Begriff des Unveränderlichen charakterisiert werden, sondern muss als das Nichtidentische gedacht werden: „Das Absolute jedoch, wie es der Metaphysik vorschwebt, wäre das Nichtidentische, das erst hervorträte, nachdem der Identitätszwang zerging“ (GS 6: 398). Da die Erkenntnis immer auf das Identische gerichtet ist, kann es vom Absoluten als Nichtidentischem keine Erkenntnis geben. Das Nichtidentische kann aber den Subjekten gegenüber als „metaphysische Erfahrung“ (GS 6: 364) in Erscheinung treten. Sie ist die Erfahrung einer Unverfügbarkeit, Adorno spricht auch von „Unverlässlichkeit“ (GS 6: 364). Die metaphysische Erfahrung ist außerdem eine Erfahrung von Negativität. Das Subjekt erfährt seine eigene Ohnmacht, den Gegenstand der Erfahrung zu fassen zu bekommen. Metaphysische Erfahrungen sind für Adorno vor allem in der Kunst möglich. Er spricht ausdrücklich vom „metaphysischen Gehalt von Kunst“ (GS 7: 122). Kunstwerke deuten auf Nichtidentisches hin, indem sie ihre Rezipienten zu einer bestimmten Verhaltensweise nötigen. Da ein Kunstwerk sich nicht einfach entziffern lässt, sind Rezipienten gezwungen, sich von den Strukturen des Kunstwerks leiten zu lassen. Sie werden dadurch zu einer Praxis der Anverwandlung gedrängt, die Adorno Mimesis nennt. Die damit von den Kunstwerken eröffnete Erfahrung deutet auf etwas hin, das sich nicht identifizierend fassen lässt. Den Okkultismus beurteilt er dagegen in Minima Moralia Nr. 151[181] als Rückfall hinter die Rationalität der Moderne, nicht deren Überwindung, indem er von einer „Metaphysik der dummen Kerle“ spricht.[182] Okkultismus sei einerseits Reaktion auf Verdinglichung: „Wenn die objektive Realität den Lebendigen taub erscheint wie nie zuvor, so suchen sie ihr mit Abrakadabra Sinn zu entlocken.“ Andererseits werde „Arbeitsteilung und Verdinglichung […] auf die Spitze getrieben: Leib und Seele in gleichsam perennierender Vivisektion auseinandergeschnitten.“ Geist und Sinn werde als Faktum, als unmittelbare Erfahrung behauptet, die Vermittlung durch aufklärerisches Denken ignoriert. |
形而上学と形而上学批判 アドルノの形而上学との関係は複雑である。178] 彼の批判は古典的な形而上学と形而上学批判の両方に当てはまる。形而上学についての考察は彼の全作品に貫かれている。彼は『否定弁証法』において特にそれ を展開しており、その中心的な意図をゲルショム・シューレムとは対照的に「形而上学の救出」と表現している。179] アドルノの形而上学に対する理解は、西洋の理性に対する理解と密接に関連している。彼にとって、これは自己と自然を支配するプロジェクトである(GS 3: 19)。このプロジェクトの目的は、人間が「同一化思考」という理性を用いて、自然現象の偶然性から自らを解放し、自己と環境を制御することにある。この プロジェクトにおいて、形而上学は「非歴史的かつ不変の原理」として重要な役割を果たす(GS 2: 261)。経験的な生活の偶然性に、不変であると理解される概念的つながりの体系を対立させることで、形而上学は「同一性の思考」を導入する。同一化思考 は、主体が外部で遭遇するものに対してだけでなく、自身の身体性に対しても向けられる。それもまた、同一化によって克服され、克服されるべきものとなる。 アドルノはこれを「死への適応」とも表現している(GS 3: 79, 206)。このように、形而上学的な思考は、その目標である理性的自己決定や人間の自由を自ら否定するものとなる。偶発的なものを支配するはずのアイデン ティティが、まさにその自由のために求められた人々を支配している。アドルノはこれを形而上学のスキャンダルであるとみなしているが、同時に理性と啓蒙の スキャンダルでもあると考えている(GS 6: 361)。 アドルノにとって、形而上学の批判は、その基本的なプログラムが実際には形而上学からの主体の解放であるにもかかわらず、究極的には主体の不自由さにつな がるだけである。この文脈において、彼は主にカント哲学と実証主義を扱っている。アドルノは、カント哲学を形而上学批判を基礎とした人間の自由の主張の試 みとして解釈している。カントにとって人間とは、感覚と理解を統合することによってのみ知識を得ることができる存在である。知識が常に固定された直観と概 念の形式に従属するものであるならば、アドルノにとってこれは主体の不自由さを決定づけるものである。人間の意識は「あたかも与えられた知識の形式の中で 永遠に投獄されたかのように断罪される」(GS 6: 378)のである。このように、人間は、その認識能力において、完全に固定され、不自由な存在として理解される。アドルノによれば、人間が事実に対して固 定化されることは、実証主義の継続である。 アドルノは、伝統的な形而上学と形而上学批判に対抗する形で、超越の形而上学を復権させようとしている。形而上学とは、絶対的なものを思考することであ り、与えられたものを超えるものを思考することである。「それ自身を超えて、開かれたものへと思考すること、それこそがまさに形而上学である」 [180]。絶対的なものを思考する上で本質的なことは、それが主体がそれを処分する力の範囲を超えているということである。それは不変の概念によって特 徴づけられるものではなく、同一ではないものとして考えられなければならない。「しかし、形而上学が念頭に置く絶対とは、同一ではないものであり、同一で あるという強制が解消された後にのみ現れるものである」(GS 6: 398)。 知識はつねに同一性に向かうものであるため、非同一性としての絶対についての知識はありえない。しかし、非同一性は「形而上学的経験」として主体に現れる ことがある(GS 6: 364)。それは、手に入らないという経験であり、アドルノは「信頼性のなさ」についても語っている(GS 6: 364)。形而上学的経験は、否定性の経験でもある。主体は、経験の対象を把握できないという自身の無力を経験する。 アドルノにとって、形而上学的経験は主に芸術において可能である。彼は「芸術の形而上学的要素」について明確に述べている(GS 7: 122)。芸術作品は、受け手に特定の行動様式を強いることによって、同一ではないものを指し示す。芸術作品は容易に解読できるものではないため、受け手 は芸術作品の構造に導かれることを余儀なくされる。こうして受け手は、アドルノがミメーシスと呼ぶ、受容の実践へと向かわせられる。芸術作品によって開か れる経験は、同一化によって把握できない何かに向かわせる。 『ミニマ・モラリア』第151項[181]において、アドルノはオカルティズムを「愚かな愚か者の形而上学」と呼び、近代の合理性の後退であり、それを乗 り越えるものではないと判断している。[182] 一方で、オカルティズムは物象化への反応である。「客観的な現実がかつてないほど生きているものにとって耳を傾けがたいものに見えるとき、彼らはアブラカ ダブラでそこから意味を引き出そうとする 。他方では、「分業と物象化は極端なまでに推し進められ、肉体と精神は永遠の生体解剖のような形で切り離される。」心と意味は、事実として、直接的な経験 として主張され、啓発された思考による仲介は無視される。 |
| Positivismuskritik Adorno bestand darauf, dass in einer widersprüchlichen Welt auch das Denken widersprüchlich sein müsse und somit das Postulat der Widerspruchsfreiheit wie auch das „falsche Ideal“ der Systembildung, an dem sich die „große Philosophie“ orientiere, abzulehnen seien. „Das Ganze ist das Unwahre“, heißt ein zentraler Satz in den Minima Moralia (GS 4: 55). Er beschäftigte sich mit den Einzelwissenschaften, übte gleichwohl immanente Kritik an der Arbeitsteiligkeit, die immer mehr einzelne wissenschaftliche Disziplinen von der Philosophie abgespalten und zu gegeneinander abgegrenzten Fächern im Wissenschaftsbetrieb gemacht habe. Reflexion über die gesellschaftlichen Bedingungen der wissenschaftlichen Arbeitsteilung machte ihn zum Kritiker des Positivismus, den er weiter fasste als allgemein üblich. Neben dem Logischen Positivismus des „Wiener Kreises“ und der Analytischen Philosophie zählte er dazu auch Autoren wie Karl Popper und Hans Albert, die sich selbst als Positivismus-Kritiker verstanden,[183] und Ludwig Wittgenstein, den „reflektiertesten Positivisten“ (GS 8: 282). Seine Grundthese im Tractatus, „Die Welt ist alles, was der Fall ist“,[184] ist für Adorno ein Gedanke, der die Unfreiheit des Menschen besiegelt und ihn auf das Bestehende verpflichtet. Im so genannten Positivismusstreit zwischen den Kritischen Rationalisten Popper und Albert auf der einen Seite und Vertretern der Frankfurter Schule auf der anderen Seite, der in den 1960er Jahren um Methoden und Werturteile in den Sozialwissenschaften geführt wurde, war Adorno einer der Protagonisten. Von ihm stammte der Begriff Positivismusstreit, der von den Kontrahenten zunächst abgelehnt wurde, sich aber schließlich durchgesetzt hat.[185] |
実証主義への批判 アドルノは、矛盾に満ちた世界においては思考もまた矛盾的でなければならないとし、「偉大な哲学」が依拠する矛盾からの自由という命題と、体系形成の「偽 りの理想」は拒否されなければならないと主張した。「全体は偽りである」という文章は『ミニマ・モラリア』(GS 4: 55)の中心的な文章である。彼は個々の科学を扱っていたが、それにもかかわらず、分業を批判し、それが哲学からますます多くの個々の科学分野を切り離 し、科学界で独立した科目となるに至ったと批判した。科学分業の社会的条件について考え、彼は一般的に理解されているよりも広い意味で理解していた実証主 義の批判者となった。ウィーン学団」や分析哲学の論理実証主義に加え、アドルノは、自らを実証主義の批判者とみなすカール・ポパーやハンス・アルバート、 そして「最も思慮深い実証主義者」ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(GS 8: 282)もその範疇に含めた。アドルノにとって、彼の『トラークタートゥス』における基本命題「世界は存在するものすべてである」[184]は、人間の不 自由さを象徴する思想であり、人間に既存のものを容認することを強いるものである。 1960年代に社会科学の方法論と価値判断をめぐって展開された、批判的合理主義者のポパーとアルバートとフランクフルト学派の代表者たちとのいわゆる 「実証主義論争」において、アドルノは主役の一人であった。アドルノは「実証主義論争」という言葉を考案したが、当初は反対派に拒否されたものの、最終的 には定着した。[185] |
| Soziologie Gesellschaftskritik Adornos Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse und ihrer Ideologie richtet sich gegen die „verwaltete Welt“ (ein Synonym für den nachliberalen Spätkapitalismus) und die „Kulturindustrie“. Beiden wohne die Tendenz zur Liquidation des Individuums und alles Abweichenden inne, mit anderen Worten: die Beseitigung oder Unterwerfung des Nichtidentischen und Nichtverfügbaren. Im Rahmen des verordneten Konsums und der organisierten Ausfüllung der arbeitsfreien Zeit „durch Kulturindustrie, Technikbegeisterung und Sport“ erfolge eine „restlose Erfassung der Menschen bis in ihr Innenleben hinein“.[186] Durchgängig ist Adornos negativer Bezug auf die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Thomas Mann kritisierte 1952 diesen Aspekt der Negativität des Adorno’schen Denkens: „Gäbe es nur je ein positives Wort bei Ihnen, Verehrter, das eine auch nur ungefähre Vision der wahren, der zu postulierenden Gesellschaft gewährte! Die Reflexionen aus dem beschädigten Leben ließen es daran, nur daran, auch schon fehlen. Was ist, was wäre das Rechte?“[187] Diese Kritik Thomas Manns verfehlt nun aber den moralphilosophischen Kern der Sozialkritik Adornos – dessen bestimmte Negation: Denn Ziel Adornos soziologischer Bemühungen ist es, Gesellschaft als „universellen Verblendungszusammenhang“, als ausweglose Totalität, zu inszenieren. Das moralisch Rechte (wie etwa Mann es forderte) anzugeben bedürfte dabei eines moralischen Standpunktes jenseits gesellschaftlicher Vermittlung – ein solcher Standpunkt stellt für den Hegelianer Adorno jedoch selbst ein Problem dar, da sich das Moralische nicht einfach der eigenen gesellschaftlichen Vermitteltheit entziehen zu vermag. Wenn man nicht hinter Hegel zurückfallen wolle, damit aber die positive Angabe des moralisch Richtigen in sich problematisch erscheine, bleibe für den Kritiker nur noch der Weg der bestimmten Negation: Indem Gesellschaft provokativ „als Ding an sich, mit aller Schuld von Verdinglichung“ (GS 8: 292) dargestellt wird, soll folglich das moralisch Richtige gebildet werden. Das soziologische und sozialpsychologische Werk Adornos steht zudem in der Tradition von Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Georg Lukács und Sigmund Freud. Ihnen verdankte er Einsichten, an die er häufig anknüpfte. Der Warencharakter und die Verdinglichung aller menschlichen Beziehungen, generell der Tausch bilden den Resonanzboden seiner marxistisch geprägten Gesellschaftsanalysen, die Lukács’ Geschichte und Klassenbewußtsein zentrale Anregungen verdanken. Das Thema der instrumentellen Vernunft finden Horkheimer und er in Max Webers Begriff der „Zweckrationalität“ vorgebildet. Der Begriff der „verwalteten Welt“ bleibt dem Weber’schen Idealtypus der Bürokratie mit ihrer Tendenz zur Ausdehnung und Verselbständigung verwandt; wiederholt verweist er darauf in seinen Vorträgen Kultur und Verwaltung von 1960 (GS 8: 124) und Individuum und Organisation von 1954 (GS 8: 442). Wie Durkheim begreift er die Objektivität der gesellschaftlichen Tatsachen (faits sociaux), „die These von der Eigenständigkeit gesellschaftlicher Tendenzen gegenüber individuell-psychologischen“ (GS 8: 246)[188] als eine grundlegende soziologische Einsicht, die er in seiner Terminologie als „Vorrang des Objekts“ fasst (exemplarisch dazu in der Negativen Dialektik, GS 6: 184 ff.). Zwar spricht er sich gegen eine unvermittelte Zusammenführung von Erkenntnissen der Psychologie und Soziologie dezidiert aus – so in seinem Aufsatz Zum Verhältnis von Psychologie und Soziologie (GS 8: 42–92) –, weil angesichts „der gegenwärtigen Ohnmacht des Individuums“ Ökonomie und Soziologie mehr zur Erklärung gesellschaftlicher Vorgänge und Tendenzen beitragen könnten. Gleichwohl sei die Psychologie, insbesondere die Psychoanalyse, ein adäquates Medium zur Erklärung irrationaler Verhaltensweisen von Individuen und Gruppen (GS 8: 86). Wiederholt zog er Freuds Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse zur triebdynamischen Erklärung des autoritären Charakters wie der Massengefolgschaft faschistischer Führer heran. Mit seinem Vortrag Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft eröffnete Adorno 1968 den 16. Deutschen Soziologentag, der im Zeichen der Studentenbewegung und des 150. Geburtstags von Karl Marx stand. Anknüpfend an die Marx’sche Orthodoxie beantwortet er die Titelfrage dahingehend, dass die gegenwärtige Gesellschaft Industriegesellschaft „nach dem Stand ihrer Produktivkräfte“, jedoch „Kapitalismus in ihren Produktionsverhältnissen“ (GS 8: 361) sei. |
社会学 社会批判 アドルノの社会状況とそのイデオロギーに対する批判は、「管理された世界」(ポスト・リベラル後期資本主義の同義語)と「文化産業」に向けられている。両 者は、個人と個人から逸脱するあらゆるものを清算する傾向を本質的に有しているとされる。言い換えれば、非同一的で利用不可能なものを排除または従属させ る傾向である。規定された消費と、余暇を「文化産業、テクノロジー、スポーツへの熱狂」で埋め尽くすという文脈において、「人々の内面生活まで完全に把 握」されている。[186] アドルノの既存の社会状況に対する否定的な見方は一貫している。トーマス・マンは1952年にアドルノの思考の否定的な側面を批判した。「もしあなたが、 真の、想定される社会のビジョンをほのめかすような肯定的な言葉を一度でも口にしていたら!『破滅した人生からの省察』にはそれがない。それだけがすでに 欠けている。何が正しいのか、何が正しいはずなのか」[187] しかし、トーマス・マンによるこの批判は、アドルノの社会批判の道徳的・哲学的コア、すなわちその具体的な否定を捉えていない。アドルノの社会学的な取り 組みの目的は、社会を「普遍的な幻想の文脈」として、そこから逃れることのできない全体として提示することにある。例えばマンが要求するように)道徳的に 正しいことを示すには、社会的媒介を越えた道徳的立場が必要となるが、ヘーゲル主義者アドルノにとって、そのような立場自体が問題となる。なぜなら、道徳 は自身の社会的媒介から単純に逃れることはできないからだ。ヘーゲルに遅れを取りたくないが、道徳的に正しいことの肯定的な示唆は問題があるように思われ る場合、批評家が残された唯一の道は、明確な否定の道である。挑発的に「物自体として、物自体化の罪悪をすべて伴って」社会を提示することによって(GS 8: 292)、道徳的に正しいことが形成される。 アドルノの社会学および社会心理学的な研究は、カール・マルクス、エミール・デュルケーム、マックス・ヴェーバー、ゲオルク・ルカーチ、ジークムント・フ ロイトの伝統にも位置づけられる。アドルノは彼らから得た洞察を頻繁に引用した。商品の性格と、人間関係のすべてを物象化する傾向、一般的に交換は、彼の マルクス主義的な社会分析の基礎を形成しており、その分析はルカーチの歴史と階級意識に大きな影響を受けている。ホルクハイマーとともに、彼は手段として の理性というテーマが、マックス・ウェーバーの「目的の合理性」という概念に先取りされていると考える。「管理された世界」という概念は、拡大し自立する 傾向を持つ官僚制というヴェーバーの理想型と関連している。彼は1960年の文化と行政に関する講義(GS 8: 124)や、1954年の個人と組織に関する講義(GS 8: 442)で、この概念について繰り返し言及している。 デュルケムと同様に、彼は社会的事実(ソシアル・ファクト)の客観性を「個人心理学的傾向に対する社会学的傾向の自律性のテーゼ」(GS 8: 246)[188]として、社会学の根本的な洞察として理解しており、それを「対象の優位性」という用語で表現している(『否定弁証法』GS 6: 1 84 ff.)。彼は、心理学と社会学の洞察を媒介なしに組み合わせることに明確に反対している。なぜなら、「個人の現在の無力さ」を考慮すると、経済学と社会 学の方が社会的なプロセスや傾向の説明により貢献できるからだ。とはいえ、心理学、特に精神分析は、個人や集団の非合理的な行動を説明するのに適した手段 であった(GS 8: 86)。アドルノは、フロイトの著書『集団心理学と自我分析』を繰り返し引用し、権威主義的性格とファシスト指導者への大衆の忠誠を、動因力学の観点から 説明した。 1968年、アドルノは、学生運動とカール・マルクスの生誕150周年を記念して開催された第16回ドイツ社会学会議で、「後期資本主義または産業社会」 と題する講演を行った。講演の中で、彼は正統派マルクス主義と結びつき、現代社会は「生産力の状態によれば」産業社会であるが、「生産関係においては資本 主義である」と、タイトルにある質問に答えている(GS 8: 361)。 |
| Empirische Sozialforschung Erst während seiner Emigration in den USA sammelte Adorno Erfahrungen in der empirischen Sozialforschung. Auf Vermittlung von Horkheimer wurde er Mitarbeiter am Princeton Radio Research Project, einem von dem österreichischen Soziologen Paul Lazarsfeld geleiteten größeren Forschungsvorhaben mit dem Titel The Essential Value of Radio to all Types of Listeners. Adorno wurde die Durchführung eines Teilprojekts für den musikalischen Bereich übertragen. In seinem Rückblick auf Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika berichtete er, dass das Radio-Projekt „für kritische Sozialforschung wenig Raum“ ließ (GS 10/2: 707). So schien ihm die Technik, dass Probanden per Knopfdruck über Gefallen oder Nichtgefallen von Musikstücken abstimmten, „gegenüber der Komplexität des zu Erkennenden höchst unzulänglich“ (GS 10/2: 708). Da sich die Untersuchungen im Rahmen des etablierten kommerziellen Radiosystems vollzogen und „verwertbare Informationen“ erwartet wurden (GS 10/2: 709), war auf diese Weise kaum etwas für die Musiksoziologie zu ermitteln. Sein erster in den USA geschriebener Aufsatz – Über den Fetischcharakter der Musik und die Regression des Hörens –, der 1938 in der Zeitschrift für Sozialforschung erschien, war, nach des Autors eigenem Bekunden, der „erste Niederschlag“ seiner Arbeit am Radio Research Project (GS 14: 9). Adorno bewertete seine Erfahrungen als lehrreiche Auseinandersetzungen mit Sinn und Methoden der Sozialforschung sowie mit Radiomusik und Radiohörern. Aus dieser Tätigkeit resultierte schließlich eine umfangreiche Untersuchung in englischer Sprache: die unter dem Titel Current of Music zusammengefassten Studien, die Robert Hullot-Kentor rekonstruiert und herausgegeben hat.[189] Insgesamt betrachtet, fand Adorno in den New Yorker wie in den späteren kalifornischen Emigrationsjahren durch praktische Erfahrungen und Auseinandersetzungen einen Zugang zur empirischen Sozialforschung (GS 10/2: 703–738). Nachdem er mit Horkheimer 1944 die Dialektik der Aufklärung abgeschlossen hatte, wurde er Mitarbeiter an dem vom Institute of Social Research und von der University of Berkeley gemeinsam bearbeiteten großangelegten Forschungsprojekt zum Thema Antisemitismus.[190] Darauf geht die 1950 veröffentlichte soziologische Studie The Authoritarian Personality (Die autoritäre Persönlichkeit) zurück, die Vorurteilsstrukturen und den Zusammenhang von Autoritätsgläubigkeit und Faschismus untersucht. In einem Brief vom 19. Juli 1947 an Horkheimer äußerte sich Lazarsfeld geradezu begeistert über die gelungene Kombination von kritischer und empirischer Sozialforschung.[191] Die von Adorno verfassten Teile sowie die von ihm und den beteiligten Autoren (Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson und R. Nevitt Sanford) gemeinsam verfasste Einleitung, ferner das Kapitel über die F-Skala (engl. Fassung in GS 9/1: 143–508) ließ er von Milli Weinbrenner, einer Mitarbeiterin des Instituts, übersetzen; erst posthum erschienen diese Texte unter dem Titel Studien zum autoritären Charakter (1973) auf Deutsch in der Bundesrepublik Deutschland. 2019 wurde erstmals sein 1947 geschriebener Entwurf eines Schlusskapitels für The Authoritarian Personality in dem Band Bemerkungen zu „The Authoritarian Personality“ publiziert. Die von Adorno in den USA gemachten Erfahrungen mit der dort anders betriebenen Soziologie und Sozialforschung, vor allem seine Mitautorschaft an der Authoritarian Personality, bildeten die Grundlage dafür, dass er in Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren als einer der wichtigsten Vertreter der deutschen Soziologie anerkannt wurde. Beigetragen haben dazu auch seine Beiträge zu dem bedeutendsten empirischen Nachkriegsprojekt des Instituts für Sozialforschung: das an die Fragestellungen der Authoritarian Personality anknüpfende Gruppenexperiment.[192] Adorno hatte zu dem abschließenden Forschungsbericht das Kapitel Schuld und Abwehr und gemeinsam mit Horkheimer das Vorwort verfasst (GS 9/2: 121–324). Unbeschadet dessen hielt er sich nicht zurück mit kritischen Erörterungen über die empirische Sozialforschung. 1952 hielt er die Rede Zur gegenwärtigen Stellung der empirischen Sozialforschung in Deutschland, in der er deren Bedeutung in modifizierter Form für die Kritische Theorie betonte (GS 8: 478–531), und in dem erstmals 1957 veröffentlichten Vortrag Soziologie und empirische Forschung stellte Adorno seine Kritik an der zeitgenössischen Soziologie und empirischen Sozialforschung dar (GS 8: 196–216). Er hatte zunächst, unter Einbeziehung der aus den USA stammenden Methoden, für den Ausbau der empirischen Sozialforschung in Deutschland und die Verbindung von quantitativen mit qualitativen Verfahren (wie Inhaltsanalyse und Gruppendiskussion) votiert. Hatte er dabei noch die Möglichkeit einer Verknüpfung von Empirie mit Theorie betont, äußerte er sich später zunehmend skeptischer hinsichtlich einer derartigen Vermittlung.[193] Unverhohlen artikulierte er diese Skepsis im sogenannten Positivismusstreit. |
経験的社会研究 アドルノが経験的社会研究の経験を得たのは、アメリカに移住してからであった。ホルクハイマーの仲介により、彼はプリンストン・ラジオ研究プロジェクトの スタッフとなった。このプロジェクトは、オーストリアの社会学者ポール・ラザーズフェルドが指揮する大規模な研究プロジェクトであり、そのテーマは「あら ゆるタイプのリスナーにとってのラジオの本質的価値」であった。アドルノは音楽分野のサブプロジェクトを担当することになった。 アドルノは、著書『アメリカにおける科学的な経験』の中で、ラジオプロジェクトは「批判的社会研究の余地をほとんど残さなかった」と回顧している(GS 10/2: 707)。ボタンを押して音楽を好きか嫌いかを投票させるという手法は、彼には「認識されるべきものの複雑さの前に極めて不適切」に思えた(GS 10/2: 708)。調査は確立された商業ラジオシステムの枠組みの中で実施され、「利用可能な情報」が期待されていたため(GS 10/2: 709)、この方法では音楽社会学についてほとんど何も決定できなかった。1938年に『社会学研究誌』誌に掲載された、アメリカで書かれた彼の最初の論 文「音楽のフェティッシュな性格と聴覚の退行について」は、著者自身によると、ラジオ研究プロジェクト(GS 14: 9)における彼の研究の「最初の表現」であった。 アドルノは、自身の経験は、社会調査の意味と方法、そしてラジオ音楽とラジオのリスナーとの有益な対立であったと捉えていた。この研究は最終的に、英語に よる広範な研究に結実した。その研究は『音楽の流れ』というタイトルでまとめられ、ロベール・ユロ=ケントールが再構成し、編集した。189] 全体として、アドルノはニューヨーク、そして後にカリフォルニアに移住した時期の実務経験や議論を通じて、実証的社会研究へのアクセスを見出した(GS 10/2: 703-738)。 1944年にホルクハイマーとともに『啓蒙の弁証法』を完成させた後、彼は社会研究機関とカリフォルニア大学バークレー校の共同による反ユダヤ主義に関す る大規模な研究プロジェクトのスタッフとなった。 [190] 1950年に出版された社会学的研究『権威盲従の性格』は、この研究を基に、偏見の構造と権威への信仰とファシズムの関連性を検証している。 。1947年7月19日付のホルクハイマー宛ての手紙で、ラザーズフェルドは批判的かつ経験的な社会調査の成功的な組み合わせに対する熱意を表明した。 191]アドルノが執筆した部分、およびアドルノと参加執筆者(エルゼ・フレンケル=ブルンスウィック、ダニエル・J・レヴィンソン、R・ネヴィット・サ ンフォード)が共同執筆した序文、そしてFに関する章は (英語版はGS 9/1: 143–508)は、研究所の職員であったミリ・ヴァインブレンナーによって翻訳された。これらのテキストは、死後になってドイツ連邦共和国で『権威主義 についての研究』(1973年)というタイトルで出版されたのみである。2019年には、彼の1947年の『権威盲従の性格』最終章の草稿が初めて 『Bemerkungen zu 「The Authoritarian Personality」』という論文集で発表された。 アドルノが米国で経験した、社会学や社会調査に対する米国の異なるアプローチ、特に『権威盲従の性格』の共著は、1950年代と1960年代にドイツでア ドルノがドイツ社会学の最も重要な代表者の一人として認められる基盤となった。戦後最も重要な経験的研究プロジェクトである社会研究協会の集団実験に彼が 貢献したことも、この評価につながった。192] アドルノはホルクハイマーとともに最終研究報告書の「罪悪感と防衛」の章と序文を執筆した(GS 9/2: 121–324)。 しかし、彼は経験的社会研究に対する批判的な議論を控えることはなかった。1952年には「ドイツにおける経験的社会研究の現状について」という講演を行 い、批判理論の修正版としてその重要性を強調した(GS 8: 478-531)。また、1957年に初めて出版された「社会学と経験的研究」という講義で、アドルノは現代の社会学と経験的社会研究に対する批判を提示 した(GS 8: 196-2 。当初、アドルノはドイツにおける経験的社会研究の拡大と、量的・質的(内容分析やグループ・ディスカッションなど)手法の組み合わせに賛成票を投じてい た。米国発の手法を取り入れている。当初は経験論と理論の統合の可能性を強調していたが、その後、そうした仲介に対して次第に懐疑的になっていった。 193] 彼は、いわゆる「実証主義論争(Positivismusstreit)」において、この懐疑論を公然と表明した。 |
| Ästhetik und Kulturkritik Adornos Schriften zur Ästhetik und Kulturkritik sind von den Schriften Walter Benjamins, mit dem er in regem Austausch stand, stark beeinflusst. Angefangen vom Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) bis zum Passagen-Werk dienten sie Adorno als wichtige Inspirationsquellen. Der erkenntniskritischen Vorrede der Trauerspiel-Schrift entnahm Adorno die Anregung, eine spezifische Form des philosophischen Umgangs mit der Kunst zu entwickeln: Nicht begrifflich-deduktiv noch induktiv, sondern konfigurativ durch Anordnung der Phänomene in Konstellationen.[194] Auf Benjamins berühmte Schrift Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit reagierte Adorno jedoch kritisch und verärgert.[195] So hatte Benjamin Film und Kino als avantgardistische Medien bezeichnet und sich für sie begeistert, während Adorno darin Auswüchse der Kulturindustrie sah. Ausgangspunkt der kunstphilosophischen Überlegungen Adornos ist die Annahme einer „fundamentalen Differenz von Kunst und gesellschaftlicher Wirklichkeit“. Geschichte und Sein der Kunst rekonstruiert er „unter dem Vorzeichen der Negativität“. Sie ist „das konkrete Negative des allgemeinen Negativen“. Eine überhistorische Definition der Kunst kann es für ihn nicht geben; alle Vorstellungen und Theoreme der Kunstphilosophie werden radikal historisiert. Da das Kunstwerk noch nicht vollständig in die gesellschaftliche Totalität integriert ist, bildet es den archimedischen Punkt, von dem aus historische Erkenntnisse möglich werden.[196] |
美学と文化批評 アドルノの美学と文化批評に関する著作は、親交のあったヴァルター・ベンヤミンの著作から多大な影響を受けている。『ドイツ悲劇の起源』(1928年)か ら『アーケード・プロジェクト』まで、それらはアドルノにとって重要なインスピレーションの源となった。アドルノは、芸術に対する特定の形の哲学的関与を 展開するアイデアを、認識論的に批判的な序文から得た。概念的推論や帰納法ではなく、現象を星座のように配置することで構成的に。194] しかしアドルノは、ベンヤミンの有名な著作『複製技術時代の芸術作品』に対して批判的かつ怒りを込めて反応した。195] ベンヤミンは映画やシネマを前衛的なメディアとして捉え、熱狂的に支持していたが、アドルノはそれらを文化産業の行き過ぎと見なしていた。 アドルノの芸術哲学的な考察の出発点は、「芸術と社会現実の間の根本的な差異」という仮定である。彼は「否定性」の観点から芸術の歴史と本質を再構築す る。それは「一般的な否定性の具体的な否定」である。彼にとって、芸術に超歴史的な定義はありえない。芸術哲学の概念や定理はすべて根本的に歴史化されて いる。芸術作品はまだ完全に社会的全体性に統合されていないため、そこから歴史的洞察が可能となるアルキメデスの支点となる。 |
| Ästhetische Theorie → Hauptartikel: Ästhetische Theorie Der Philosoph Günter Figal sieht in der posthum erschienenen, vom Autor selbst nicht abgeschlossenen Ästhetischen Theorie Adornos Hauptwerk und Vermächtnis. Sie sei der Versuch, auf die Erfahrung des unverfügbaren „Individuellen und Nichtidentischen in der Kunst aufmerksam zu machen“. Konsequenter als in seinen anderen Schriften setze Adorno hier seine Leitbegriffe als eine Vielzahl von Zentren ein, um die sich seine Reflexionen bildeten und die erst in der Konstellation zueinander ein Ganzes ergäben.[197] Der Germanist Gerhard Kaiser versteht Adornos Kritische Theorie im Wesentlichen als „ästhetische Theorie“: In ihr würden „alle Motive seines Denkens enggeführt“.[198] Die zentrale These des Werks lautet für Günter Figal, dass Kunst das „Ergebnis einer rationalen Konstruktion“ ist, die das vielfältige „Material“ (Klänge, Worte, Farben, Holz, Metall etc.) zu einer Einheit stimmig zusammenfügt. Im Kunstwerk würde „das Material in seiner Individualität freigesetzt“ und dadurch das „Nichtidentische“ gerettet.[199] Obwohl zweckmäßig gestaltet, erscheine das Kunstwerk im Resultat, als sei es naturhaft erzeugt, weil das vermögende Gestalten selbst der „Natur im Subjekt“ (Immanuel Kant) zugehört – sei es als vorgeistige Sinnlichkeit oder als kreatürlicher Reflex. Adorno versteht Kunst nicht als Nachahmung der Natur, sondern des Naturschönen, das für Menschen etwas Überwältigendes habe, aber in seiner „Nichtgemachtheit“ sich menschlicher Verständlichkeit gleichzeitig entziehe.[200] Bereits im einleitenden Abschnitt der Ästhetischen Theorie spricht Adorno vom „Doppelcharakter der Kunst als autonom und als fait social“ (GS 7: 16). Der von Émile Durkheim übernommene Begriff des fait social bezeichnet einen gesellschaftlich erzeugten Tatbestand (weiter Sinn). Kunstwerke sind in die herrschenden Produktionsverhältnisse eingebunden und als Produkte gesellschaftlicher Arbeit (GS 7: 337) auch verkäufliche Waren. Ihre Autonomie ist eine sozial determinierte (GS 7: 313); sie wurde „mühsam der Gesellschaft abgezwungen“ (GS 7: 353). Autonomie verkörpere das Kunstwerk darin, dass es allein seinem eigenen Formgesetz gehorche. Aus ihrer Autonomie folge, dass Kunstwerke funktionslos sind: „Soweit von Kunstwerken eine gesellschaftliche Funktion sich prädizieren lässt, ist es ihre Funktionslosigkeit“ (GS 7: 337). In ihrer unversöhnlichen Gegenposition zur Gesellschaft behauptet die Kunst ihre Autonomie: „Indem sie sich als Eigenes in sich kristallisiert, statt bestehenden gesellschaftlichen Normen zu willfahren und als ‚gesellschaftlich nützlich‘ sich zu qualifizieren, kritisiert sie die Gesellschaft, durch ihr bloßes Dasein“ (GS 7: 337). Als Utopie repräsentiere Kunst das schwarz verhängte „noch nicht Seiende“, die „imaginäre Wiedergutmachung der Katastrophe Weltgeschichte“ (GS 7: 204). Adornos Satz – „In jedem genuinen Kunstwerk erscheint etwas, was es nicht gibt“ (GS 7: 127) – verweist auf ein Glücksversprechen (Stendhals promesse du bonheur), das als „Totalnegation der gegebenen Wirklichkeit“ gelesen werden kann. Glück gibt es nur „als Erscheinung, die eschatologisch der Erfüllung harrt“.[201] |
美学理論 → 詳細は美学理論を参照 哲学者ギュンター・フィガルは、アドルノの死後に未完のまま出版された『美学理論』を、彼の主要な著作であり遺産であると見なしている。これは、入手不可 能な「芸術における個別的かつ非同一的」な経験に注目を集める試みである。アドルノは、他の著作よりも一貫して、自身の指針となる概念を、自身の考察が形 成される多数の中心として使用しており、それらの中心は、互いの配置によってのみ全体を生み出す。197] ドイツの学者ゲルハルト・カイザーは、アドルノの批判理論を本質的に「美学理論」と理解している。その理論において「彼の思考のすべてのモチーフがまとめ られている」からである。198] ギュンター・フィガルにとって、この作品の中心的な命題は、芸術とは多様な「素材」(音、言葉、色、木、金属など)を首尾一貫して統合する「理性的構築の 結果」であるというものである。芸術作品においては、「素材は個性を発揮する」ため、「同一でないもの」が保存される。芸術作品は意図的に設計されている が、あたかも自然に創造されたかのように見える。なぜなら、優れた設計自体が「主題における自然」(イマヌエル・カント)に属しているからだ。それは、精 神以前の感覚性として、あるいは生物的な反射としてである。アドルノは芸術を自然の模倣ではなく、人々にとって圧倒的な何かを持ちながらも、同時に「非人 工性」において人間の理解を逃れる自然の美しさとして理解している。[200] 『美学理論』の序論でアドルノは、「芸術の自律性と社会的事実としての二重性」について語っている(GS 7: 16)。エミール・デュルケムから採用された「社会的事実」という用語は、社会的に生み出された事実(広義)を指す。芸術作品は支配的な生産関係に組み込 まれており、社会労働の産物(GS 7: 337)として市場で取引可能な商品でもある。芸術作品の自律性は社会的に決定される(GS 7: 313)。それは「社会から苦労して搾取された」(GS 7: 353)ものである。芸術作品の自律性は、それが自身の形式法則のみに従うという点において体現される。芸術作品が機能を持たないのは、その自律性から導 かれる。「芸術作品に社会的機能が帰属しうる限りにおいて、それは芸術作品の機能のなさである」(GS 7: 337)。社会との和解不可能な対立において、芸術は自律性を主張する。「芸術は、既存の社会規範に従うことなく、また『社会的に有用である』と認められ ることもなく、それ自体の中で独自のものとして結晶化することで、その存在だけで社会を批判する」(GS 7: 337)。 ユートピアとして、芸術は「まだ存在していない」ものを黒いベールで覆い隠し、「世界史のカタストロフィの想像上の補償」を表現する(GS 7: 204)。アドルノの「あらゆる真正な芸術作品には、存在しない何かが現れる」(GS 7: 127)という文章は、幸福の約束(スタンダールの「幸福の約束」)を指しており、それは「与えられた現実の全面否定」と読むことができる。幸福は「終末 論的に成就を待つ現れ」としてのみ存在する。[201] |
| Literatur: Interpretation und Kritik Der philosophischen Dechiffrierung von Dichtung sind Adornos unter dem Titel Noten zur Literatur zusammengefassten Essays gewidmet (GS 11). Neben dem für die Schreib- und Gestaltungsweise Adornos programmatischen Eröffnungsessay Der Essay als Form enthalten sie die in der Fachwelt mit großer Resonanz aufgenommenen Essays über Eichendorff und Hölderlin sowie über Goethes Iphigenie auf Tauris und Samuel Becketts Endspiel. In den beiden Essays, die einem einzelnen Werk gewidmet sind, gelinge Adorno, Jan Philipp Reemtsma zufolge, „die Synthese von Deutung eines Fremden und Explikation eigenster Intentionen“.[202] In polemischer Auseinandersetzung mit Georg Lukács’ Theorie des literarischen Realismus (Erpreßte Versöhnung) und mit einem Essay, der Jean-Paul Sartres Schrift Was ist Literatur? zum Anlass für die kritische Abfertigung der engagierten Literatur nimmt, expliziert er in bestimmter Negation seine eigene normative Literaturtheorie. Danach sollten literarische Kunstwerke weder durch kritische Widerspiegelung der objektiven Wirklichkeit noch durch Aufzeigen von Alternativen zu ihr, sondern „durch nichts anderes als ihre Gestalt dem Weltlauf widerstehen“ (GS 11: 413). Allein die rücksichtslos autonome Literatur, „die jedes Engagement für die Welt […] gekündigt“ hat (GS 11: 425), dünkt Adorno, neben der avancierten Musik, ein „letzte[r] Ort für den ‚Vor-Schein‘ des Utopischen als eines möglichen Anderen“.[203] So erklärt er auch den „Künstler, der das Kunstwerk trägt“, zum „Statthalter des gesellschaftlichen Gesamtsubjekts“ (GS 11: 126). |
文学:解釈と批判 詩の哲学的解読に関するアドルノのエッセイは、彼のエッセイ『文学ノート』(GS 11)にまとめられている。冒頭のエッセイ『形式としてのエッセイ』は、アドルノの執筆とデザインのプログラム的なものであり、アイヒェンドルフとヘル ダーリンに関するエッセイ、そしてゲーテの『タウリスのイフィゲニア』とサミュエル・ベケットの『エンダースピーレ』に関するエッセイが含まれている。1 つの作品に捧げられた2つのエッセイにおいて、アドルノはヤン・フィリップ・リームツマによると、「外国の作品の解釈と自身の意図の説明を統合することに 成功している」[202]。ゲオルク・ルカーチの文学的リアリズム理論(『苦役としての救済』)に関する論争的な議論と、ジャン=ポール・サルトルの『文 学とは何か』を批判する機会として書かれたエッセイで、 従事する文学に対する批判的な機会として、彼は自身の規範的な文学理論をある種の否定の中で説明している。これによると、芸術作品は客観的な現実を批判的 に反映したり、それに代わるものを指摘したりすることによってではなく、「その形式以外の何ものでもなく」(GS 11: 413)して世界の流れに抵抗すべきである。アドルノの意見では、冷酷なまでに自律的な文学、すなわち「世界へのあらゆるコミットメントを放棄した」文学 (GS 11: 425)だけが、先進的な音楽とともに、「ユートピアとしての可能的な他者の『予示』の最後の場所」である。[203] したがって、彼は「芸術作品を担う芸術家」を「社会全体の代表」であると宣言する。 (GS 11: 126)。 |
| Kulturkritische Schriften Die kulturkritischen Schriften Adornos umfassen zwei umfangreiche Bände (GS 10/1 und 10/2), beginnend mit der frühen Aufsatzsammlung Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, die verstreut publizierte Arbeiten aus den Jahren 1950 bis 1953 versammelt und 1955 erstmals im Suhrkamp Verlag erschien. Sie enthalten die Essays Charakteristik Benjamins und Aufzeichnungen zu Kafka. In einer neuerlichen polemischen Auseinandersetzung mit dem Jazz: Zeitlose Mode. Zum Jazz wiederholt er die pejorativen Urteile des frühen Aufsatzes Über Jazz von 1936, den er als Bestandteil der kommerziellen Popularmusik[204] und als „falsche Liquidation der Kunst“ (GS 10/1: 127) abwertet. In dem Aufsatz Kulturkritik und Gesellschaft formuliert Adorno eine seiner umstrittensten Aussagen: „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“. Das apodiktisch formulierte Verdikt erlangte wie kaum eine andere Aussage zur Gegenwartsliteratur eine solche Bekanntheit, dass sie über Jahrzehnte hinweg kontrovers diskutiert wurde und Adorno zu mehrfachen Erklärungen und Modifikationen motivierte, ohne dass er die zentrale Botschaft über das schmähliche Versagen der Kultur angesichts Auschwitz zurücknahm. „Ihr Missverhältnis zum geschehenen und drohenden Grauen verdammt sie zum Zynismus“, heißt es in der Ästhetischen Theorie von der „nach der Katastrophe auferstandenen Kultur“ (GS 7: 348). Neben ideologiekritischen Essays über Karl Mannheim, Oswald Spengler, Thorstein Veblen und Aldous Huxley enthalten die Bände Beiträge, die, als Kritische Modelle ausgewiesen, für Adornos Texte ein bis dato ungewohntes Interesse an praktischem Eingreifen in gesellschaftliche und politische Prozesse bekunden. Dazu gehören, neben seinen weit über die Kreise der kritischen Pädagogik hinaus aufgenommenen Vorträgen Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit (1959)[205] und Erziehung nach Auschwitz (1966), Fragen zu Sexualtabus heute, Fernsehkonsum, Lehrerausbildung etc., allerdings auch die dezidierte Absage an die ihm von aufbegehrenden Studenten abgeforderte Solidarisierung mit ihren Protestaktionen (Marginalien zu Theorie und Praxis sowie Resignation in GS 10/2). |
文化批評著作 アドルノの文化批評は、初期のエッセイ集『プリズメン』に始まり、2巻にわたる大著『文化批評と社会』(GS 10/1および10/2)で構成されている。『文化批評と社会』は、1950年から1953年の間にさまざまな場所で発表された作品をまとめたもので、 1955年にスールカンプ出版社から初めて出版された。この著作には、「ベンヤミンの特徴」と「カフカについての覚書」というエッセイが収められている。 最近のジャズ論争において:時代を超えた流行。ジャズについて、彼は1936年の初期のエッセイ『ジャズについて』における軽蔑的な判断を繰り返し、それ を商業的な大衆音楽の要素として価値を下げ[204]、「芸術の偽りの清算」として位置づけている(GS 10/1: 127)。 「文化批評と社会」というエッセイの中で、アドルノは最も物議を醸した主張のひとつを展開している。「アウシュビッツの後に詩を書くことは野蛮である」と いう主張である。断定的に述べられたこの評決は、現代文学に関する他のいかなる声明も到達し得なかったほどの著名度を獲得し、数十年にわたって物議を醸す 議論を巻き起こした。アドルノは、アウシュビッツを前にした文化の恥ずべき失敗に関する中心的なメッセージを撤回することなく、何度も説明や修正を加える ことになった。「起こってしまった、そして迫り来る恐怖に対する彼らの不釣り合いさは、彼らをシニシズムへと追いやる」と、美学理論は「大惨事の後に復活 した文化」について述べている(GS 7: 348)。 カール・マンハイム、オスヴァルト・シュペングラー、トールステイン・ヴェブレン、オルダス・ハクスリーらのスタイルで書かれたイデオロギー批判のエッセ イに加え、この著作集には、アドルノの著作では前例のない、社会や政治のプロセスへの実践的な介入に関心を寄せる批判的なモデルとして位置づけられる寄稿 も含まれている。批判的教育学の分野を超えて広く好評を博した彼の講義に加えて、これらには『過去を清算するとは何を意味するのか』(1959年) [205]や『アウシュヴィッツ後の教育』(1966年)など、今日の性的タブーやテレビの消費、教師の研修などに関する問題だけでなく、反抗的な学生た ちによる彼らの抗議行動への連帯を求める要求を断固として拒否する内容も含まれている(『理論と実践についての余白注釈』と『 GS 10/2における理論と実践と辞任について)。 |
| Kulturindustrie → Hauptartikel: Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbetrug Das Kulturindustrie-Kapitel in der Dialektik der Aufklärung lässt deutlicher als andere Partien des Buches die Handschrift Adornos erkennen.[206] Sein Thema ist die „ästhetische Barbarei heute“ (GS 3: 152). Im Gegensatz zur authentischen Kunst, die die Widersprüche des gesellschaftlichen Systems wenigstens zum Sprechen bringe und ein Bewusstsein radikaler Veränderung aufrechterhalte, würden die Produkte der Kulturindustrie den Menschen das Verlangen nach Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung austreiben.[207] Kino, Radio, Fernsehen, Jazz, Magazine und der organisierte Sport werden als die Medien benannt, die eine zunehmende „Uniformierung des individuellen Handelns, Denkens und Fühlens“ bewerkstelligen.[208] Der These, Adorno habe den Film grundsätzlich als Kunstform verachtet, widerspricht Detlev Clausen mit dem Hinweis auf Adornos Wertschätzung von Chaplin und Fritz Lang, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verband.[209] Der Begriff „Industrie“ bezieht sich auf die Standardisierung der Produkte und die Rationalisierung der Verbreitungstechniken (GS 10/1: 339). |
文化産業 → 詳細は「文化産業」を参照 - 大衆欺瞞としての啓蒙 『啓蒙の弁証法』の文化産業に関する章は、この本の他の部分よりもアドルノの考えがより明確に示されている。[206] その主題は「今日の美的野蛮」(GS 3: 152)である。真正な芸術が少なくとも社会システムの矛盾を表現し、急進的な変化に対する意識を維持しているのとは対照的に、文化産業の産物は人々から 自己認識と自己決定への欲求を追い出す。207] 映画、ラジオ、テレビ、ジャズ、雑誌、組織化されたスポーツは、個人の行動、思考、感情の「画一性」をますます高めるメディアとして挙げられている。。 [208] デトレフ・クラウゼンは、アドルノが長年友人であったチャップリンやフリッツ・ラングを高く評価していたことを指摘し、アドルノが芸術形式としての映画を 根本的に軽蔑していたという主張に異議を唱えている。[209] 「産業」という用語は、製品の標準化と流通技術の合理化を指している(GS 10/1: 339)。 |
| Pädagogik Adorno hat sich an verschiedenen Stellen mit pädagogischen Fragen der moralisch richtigen Form von Bildung und Erziehung auseinandergesetzt. Einen Großteil seiner – doch eher überschaubar gehaltenen – Auslassungen zur Pädagogik stellen die in den Gesammelten Schriften verstreuten und 1970 unter dem Titel Erziehung zur Mündigkeit gesondert publizierten Arbeiten und Rundfunkbeiträge der 1960er-Jahre dar.[210] Entgegen der Auffassung Jürgen Habermas’, der von einer Kluft „zwischen dem reformistischen, geradezu sozialdemokratischen Volkspädagogen und dem rabenschwarzen Totalitätsdenken des Philosophen“[211] sprach, ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich auch in Adornos pädagogischen Ausführungen eine bemerkenswerte Kontinuität zum moralphilosophischen Gehalt der Philosophie einer Negativen Dialektik feststellen lässt.[212] |
教育 アドルノは、さまざまな場所で教育上の問題を取り上げ、道徳的に正しい教育や育成のあり方について論じている。彼の教育に関する控えめなコメントのほとん どは、1960年代の著作やラジオ番組に含まれており、それらは1970年に『成熟のための教育』というタイトルで別々に出版され、全集にも散見される。 210] ユルゲン・ハーバーマスが「改革主義者、ほぼ社会民主主義的な大衆教育者と、 哲学者の真っ黒な全体主義的思考」[211]というユルゲン・ハーバーマスの見解とは逆に、この時点で注目すべきは、否定的弁証法の哲学の道徳哲学的内容 に関するアドルノの教育的説明にも、驚くべき連続性が見られるということである。 |
| Erziehung zur Mündigkeit Jürgen Habermas hat in einem Vortrag über jüdische Remigranten auf eine andere Seite des Gesellschaftskritikers Adorno aufmerksam gemacht.[213] In zahlreichen öffentlichen Auftritten und Vorträgen habe sich der vermeintlich pessimistische Sozialphilosoph und resignative Intellektuelle als „reformistischer, geradezu sozialdemokratischer […] Volkspädagoge“[214] gezeigt, der das Programm der amerikanischen Besatzungsmächte zur demokratischen Umerziehung (Reeducation) der Deutschen ernst nahm.[215] Bei allem in der akademischen Lehre vertretenen Negativismus und aller theoretischen Aufklärungskritik habe Adorno in der Öffentlichkeit „eine kantische Erziehung zur Mündigkeit“ praktiziert.[216] Emil Walter-Busch argumentiert, dass aus der Erkenntnis der Unmöglichkeit umwälzender Praxis in der Gegenwart Adorno mit bescheidenen Mitteln versucht habe, dem gesellschaftlichen Unheil entgegenzuarbeiten. Er tat dies insbesondere mit drei allgemeinverständlichen Vorträgen: Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit (1959; GS 10/2: 555–575), Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute (1962; GS 20/1: 360–383) und, als einer seiner bekanntesten pädagogischen Texte, Erziehung nach Auschwitz (1966; GS 10/2: 674–690). Der Kulturwissenschaftler Volker Heins hat nach der ersten Durchsicht der im Suhrkamp Verlag zur Veröffentlichung anstehenden Publikationen Adornos mit „improvisierten Vorträgen“ (2 Bände) und mit „Gesprächen, Diskussionen und Interviews“ (3 Bände) bei ihm eine „aufklärerische Prämisse der Einsichtsfähigkeit und Erziehbarkeit des Publikums“ entdeckt,[217] die deutliche Spannungen „zwischen seiner Kritischen Theorie und der Rhetorik seiner öffentlichen Vorträge“[218] erkennen lasse. Die vorgesehene zweibändige Publikation kam nicht zustande. Aus diesem Fundus stammt die Einzelveröffentlichung Aspekte des neuen Rechtsradikalismus,[219][220] die einen im April 1967 auf Einladung des Verbands Sozialistischer Studenten Österreichs an der Wiener Universität gehaltenen Vortrag enthält. In ihm setzte sich Adorno mit dem damaligen Aufstieg der NPD auseinander. Im Herbst 2019 erschien ein von Michael Schwarz herausgegebener Sammelband mit nach Tonbandaufnahmen und Abschriften rekonstruierten Vorträgen 1949–1968, der jedoch neben bildungspolitischen auch kultur- und musikkritische Vorträge enthält.[221] Halbbildung Eine für die Pädagogik im Rahmen der Bildungstheorie[222] bedeutsam gewordene Schrift ist Adornos Theorie der Halbbildung (1959). In diesem kurzen, aber programmatischen Essay übt Adorno eine radikale Kritik am Bildungsbegriff. Bildung ist für ihn „zu sozialisierter Halbbildung geworden, der Allgegenwart des entfremdeten Geistes. Nach Genesis und Sinn geht sie nicht der Bildung voran, sondern folgt auf sie.“ – Theorie der Halbbildung[223] Dies ist nun so zu verstehen, dass Adorno die Aufgabe von Bildung gerade darin sieht, sie als in sich gespalten zu begreifen: Bildung oszilliert für ihn zwischen denkbaren, aber gesellschaftlich niemals einholbaren Bezugspunkten wie „Autonomie und Freiheit“ (GS 8: 104) und der gesellschaftlichen Wirklichkeit, in die die Menschen verstrickt sind – damit zwischen einer vorgestellten Idee von Bildung und der gesellschaftlichen Vereinnahmung dieser Idee – Halbbildung.[224] Für Adorno bedeutet diese Gegensätzlichkeit von Bildung und Halbbildung als ihrer sozialisierten Form aber zunächst nichts „Schlechtes“, im Gegenteil, Zweck seiner bildungstheoretischen Bemühungen ist die Offenhaltung des „Kraftfeld[es], das Bildung hieß“ (GS 8: 96). Die Strategie, die er verwendet, um dies einsichtig zu machen, ist die der bestimmten Negation:[225] Diese an Hegel angelehnte Vorgehensweise stellt nicht nur den moralphilosophischen Kern seiner Gesellschaftskritik dar (s. dazu an mehreren Stellen weiter oben), sondern liegt auch seinen pädagogischen Überlegungen zugrunde. Die Inszenierung der Bildung als Halbbildung, als „der vom Fetischcharakter der Ware ergriffene Geist“ (GS 8: 108), ist, folgt man der Vorgehensweise der bestimmten Negation, nicht als Destruktion und Auflösung von Bildung zu verstehen.[226] Ziel der als ausweglos dargestellten Situation (in der Bildung unmöglich erscheint) ist vielmehr die Erzeugung einer Einsicht in die unauflösliche Spannung der Bildung, einer Einsicht dessen, dass, wer vorgibt, Bildung zu besitzen, diese im selben Moment „eigentlich schon nicht mehr“ (GS 8: 104) besitzt. „Das allbeliebte Desiderat einer Bildung, die durch Examina gewährleistet, womöglich getestet werden kann, ist bloß noch der Schatten jener Erwartung. Die sich selbst zur Norm, zur Qualifikation gewordene, kontrollierbare Bildung ist als solche so wenig mehr eine wie die zum Geschwätz des Verkäufers degenerierte Allgemeinbildung.“ – Theorie der Halbbildung[227] Wird also versucht, Bildung „dingfest“, d. h. am Einzelnen mess- und überprüfbar zu machen, so ist dies keine Bildung mehr, sondern Halbbildung. Daher gibt es in dem Augenblick, in dem davon geredet wird, gebildet zu sein, Kompetenzen zu besitzen usw. Bildung in Wirklichkeit schon nicht mehr. Im Eingestehen dessen, dass der vermeintliche Besitz von Bildung selbst bereits die Auflösung der Bildung darstellt, liegt für Adorno die Hoffnung und das bildende Moment. Insofern ist, so könnte man vielleicht abschließend sagen, Bildung für Adorno kein starres Sein, sondern sie ist im ständigen Werden zu begreifen. |
成熟のための教育 ユダヤ人の再移住者に関する講演で、ユルゲン・ハーバーマスは社会批評家としてのアドルノのもう一つの側面に注目した。[213] 多数の公の場や講演で、悲観論者で諦観した知識人と思われていたアドルノは、アメリカ占領軍の民主的再教育プログラムを真剣に受け止めている「改革主義 者、ほぼ社会民主主義的な[...]人民の教育者」[214] であることを示していた 。)ドイツ人の民主的な再教育プログラムを真剣に受け入れたのである。[215] 彼の学術的な教育や啓蒙の理論的批判に表れたすべての否定論にもかかわらず、アドルノは公の場で「成熟に向けたカント的な教育」を実践した。[216] エミール・ウォルター=ブッシュは、アドルノは現在の革命的実践の不可能を認識しており、ささやかな手段で社会的な惨事を食い止めようとしたと主張してい る。彼は、一般的に理解しやすい3つの講演で、特にこのことを試みた。「過去との和解とは何を意味するのか」(1959年、GS 10/2: 555–575)、「今日の反ユダヤ主義との闘い」(1962年、GS 20/1: 360–383)、そして彼の最も有名な教育論のひとつである「アウシュビッツ後の教育」(1966年、GS 10/2: 674–690)である。 アドルノの著作を初めて概観した文化研究学者フォルカー・ハインズは、スールカンプ出版社から出版される予定であったアドルノの著作のうち、「即興講義」 (全2巻)と「講演、討論、インタビュー」(全3巻)に「聴衆の理解力と教育力を前提とした啓蒙的な姿勢」を見出し、そこには「彼の批判理論と 彼の公開講演の修辞学」との間に明らかな緊張関係があった[218]。 予定されていた2巻構成での出版は実現しなかった。このコレクションから出版された『新右翼の諸相』[219][220]には、1967年4月にウィーン 大学オーストリア社会主義学生協会の招きでなされた講演が収録されている。アドルノは、この中で当時のNPDの台頭について扱っている。2019年秋に は、マイケル・シュヴァルツが編集したアンソロジーが出版され、1949年から1968年の講演がテープ録音や書き起こしから再構成されたが、教育政策に 関する講演に加えて、文化政策や音楽政策を批判する講演も含まれている。 半教育 教育理論の文脈において教育学にとって重要となったアドルノの著作のひとつに、『半教育の理論』(1959年)がある。この短いながらもプログラム的なエッセイにおいて、アドルノは教育概念に対する急進的な批判を提示している。アドルノにとって、教育とは 「社会化された半教育、疎外された精神の遍在」となっている。創世記と意味に従えば、教育に先行するものではなく、それに続くものである。 – 半教育論[223] これは、アドルノが教育の課題を、教育がそれ自体の中で分裂しているものとして理解することにあると理解すべきである。彼にとって、教育とは、社会では決 して達成されることのない「自律性と自由」(GS 8: 104)といった考えうる参照点と、人々が絡み合う社会的な現実との間を揺れ動くものであり、つまりは教育についての想像上の考えと、その考えの社会的受 容との間を揺れ動くものである。224] しかしアドルノにとって、教育と半教育というこの二分法は、その社会化された形態として 当初は「悪い」という意味ではない。それどころか、アドルノの教育への取り組みの目的は、「教育と呼ばれた力場」を維持することである(GS 8: 96)。 彼がこのことを明確にするために用いる戦略は、明確な否定である。[225] このアプローチはヘーゲルに基づくものであり、彼の社会批判の道徳哲学的な核心を表しているだけでなく(上記のいくつかの箇所を参照)、彼の教育に関する 考察の根底にもなっている。教育を半ば教育として、すなわち「商品というフェティッシュの性格に捕らわれた精神」(GS 8: 108)として演出することは、断固とした否定のアプローチに従うのであれば、教育の破壊や解消として理解されるべきではない。226] むしろ、絶望的(教育が不可能に見える)な状況として提示された状況の目的は、 。教育を所有していると主張する者は誰であれ、同時に「実際にはもはや」それを所有していないという洞察である(GS 8: 104)。 「試験で保証され、おそらくは試験で測定される教育に対する一般的な願望は、その期待の影に過ぎない。一般常識がセールスマンの口上へと退化したように、標準となった管理可能な教育、すなわち資格は、もはや教育ではない」 – 『半教育論』[227] 教育を「有形のもの」にしようとする試み、すなわち個人で測定可能かつ検証可能なものにしようとする試みは、もはや教育ではなく半教育である。したがっ て、教育を受けていることやスキルを持っていることなどを口にする瞬間、 教育を受けていること、スキルを持っていることなどを口にする瞬間、教育を受けていると見なされること自体がすでに教育の崩壊を表していることを認めるこ とで、アドルノは希望と教育的な瞬間を見出す。この点において、おそらく結論として、アドルノにとって教育とは硬直した状態ではなく、絶え間なく変化し続 けるものとして理解されるべきであると言えるだろう。 |
| Musikalische Schriften Rolf Wiggershaus sieht in der Musikphilosophie den „Ausgangs- und Endpunkt“ des Adorno’schen Denkens.[228] Für Heinz-Klaus Metzger ist er „der erste wahrhaft geschulte Musiker unter den Philosophen“.[229] Seine ersten musikphilosophischen und -soziologischen Aufsätze veröffentlichte er in der Zeitschrift für Sozialforschung (1932: Zur gesellschaftlichen Lage der Musik; 1936: Über Jazz, unter dem Pseudonym Hektor Rottweiler; 1938: Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens; 1939: Fragmente über Wagner; 1941: On Popular Music).[230] In der 20-bändigen Ausgabe seiner Gesammelten Schriften sind allein acht Bände den musikalischen Schriften Adornos vorbehalten (Bände 12 bis 19), beginnend mit der Philosophie der neuen Musik (Erstausgabe 1949), über die musikalischen Monographien zu Richard Wagner, Gustav Mahler und Alban Berg (GS 13) und endend mit der Sammlung seiner Opern- und Konzertkritiken. Dass die musikalischen mit den philosophischen Schriften Adornos eng verzahnt sind, bringt der Autor bereits in seiner ersten Buchveröffentlichung nach dem Zweiten Weltkrieg, der Philosophie der neuen Musik, zum Ausdruck. In der „Vorrede“ bezeichnet er sie als einen „ausgeführten Exkurs zur Dialektik der Aufklärung“ (GS 12: 11). Adorno spricht von der Affinität zwischen Musik und Philosophie: „Die Philosophie sehnt sich nach der Unmittelbarkeit der Musik, wie sich die Musik nach der ausdrücklichen Bedeutung der Philosophie sehnt.“[231] Zum Verständnis von Musik tragen nach Adorno sowohl sinnliches Erleben – in seinem Verständnis: mimetischer Nachvollzug durch Hören, Darstellen und Aufführen – als auch die begriffliche Reflexion bei. „Ästhetische Reflexion von Musik ohne mimetischen Nachvollzug ist leer, ästhetische Erfahrung von Musik ohne begrifflichen Nachvollzug ist taub.“[232] In seinem frühen Aufsatz von 1932 – Zur gesellschaftlichen Lage der Musik – befindet er, dass alle Musik das Zeichen der Entfremdung trage und als Ware fungiere. Über ihre Authentizität entscheide, ob sie sich Marktbedingungen widersetze oder unterwerfe. Ihre gesellschaftliche Funktion erfülle sie, wenn „sie in ihrem eigenen Material und nach ihren eigenen Formgesetzen die gesellschaftlichen Probleme zur Darstellung“ bringe (GS 18: 731). Unter den Formen der Neuen Musik billigt er Authentizität vornehmlich der atonalen Musik der Schönberg-Schule zu. Nach Aussage des Komponisten und Musikwissenschaftlers Dieter Schnebel hatte er „große Schwierigkeiten mit Musik, die anders strukturiert war als die der Wiener Schule“.[233] So galten ihm Strawinski als „technisch reaktionär“ (GS 12: 57) und Paul Hindemith als dessen neoklassizistisches Pendant; und so begegnete er dem Werk von John Cage reserviert.[234] Zu den umstrittensten Themen seiner musikalischen Schriften zählen sein Verdikt über den Jazz und seine These vom Materialfortschritt in der Musik. Mit der These „Der Jazz ist Ware im strikten Sinn“ (GS 17: 77) formulierte Adorno seine erste prinzipielle Polemik gegen die aufkommende Unterhaltungsindustrie, die später in der Dialektik der Aufklärung die Bezeichnung Kulturindustrie erhalten sollte. Martin Jay verweist darauf, dass Adorno den Jazz noch nicht aus erster Hand kannte.[235] Richard Klein, Mitbegründer des Projekts und der Zeitschrift Musik & Ästhetik und Mitherausgeber des Adorno-Handbuchs, spricht von Adornos „notorisch verständnislosen Äußerungen zum Jazz“.[236] Der Poptheoretiker Diedrich Diederichsen räumt hingegen ein, dass Adorno die musikalischen Phänomene im Jazz genau beschrieben, aber daraus die falschen Konsequenzen gezogen habe.[237] Adorno hat seine Auffassung vom Jazz auch in späteren Veröffentlichungen nie mehr grundsätzlich verändert.[238] Zentral für die Musikphilosophie Adornos ist das Theorem vom unilinearen Fortschritt des musikalischen Materials, der sich in der „Verbrauchtheit und dem Neuwerden von Klängen, Techniken und Formen“ manifestiere. Die Vorgeformtheit des musikalischen Materials verleihe ihm einen Eigensinn und stelle Anforderungen an die kompositorische Arbeit, die gleichwohl die Spontaneität des Subjekts verlange.[239] „Die Forderungen, die vom Material ans Subjekt ergehen, rühren davon her, daß das ‚Material‘ selber sedimentierter Geist, ein gesellschaftlich, durchs Bewußtsein von Menschen hindurch Präformiertes ist. Als ihrer selbstvergessene, vormalige Subjektivität hat solcher objektive Geist des Materials seine eigenen Bewegungsgesetze.“ (GS 12: 39) Der Materialbegriff sei gleichsam die „Schnittstelle zwischen Kunst und Gesellschaft“. Als „Objektivation künstlerischer, geistiger Arbeit“ berge es – vermittelt durch das in der Gesellschaft seiner Zeit verankerte Bewusstsein des Künstlers – „Spuren der jeweils herrschenden Gesellschaft“.[240] Als ein Schüler der Schönberg-Schule sieht Adorno im Übergang von der Tonalität zur Atonalität der Zwölftontechnik einen geschichtlich unausweichlichen Schritt, analog demjenigen von der Gegenständlichkeit zur Abstraktion in der Malerei (GS 12: 15). Der Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus beurteilt Adornos Stellung zum Zwölftonsystem wie folgt: Einerseits hielt er es „für die notwendige Konsequenz aus der fortschreitenden Verdichtung der thematischen Arbeit von Beethoven über Brahms bis zu Schönberg, andererseits sah er in ihr einen Systemzwang, der die Musik gleichsam aushöhlte. Das blieb bei ihm als offene Dialektik stehen.“[241] In seinem Kranichsteiner Vortrag von 1961 Vers une musique informelle betrachtet Adorno die Zwölftontechnik als notwendiges Durchgangsstadium „zur Überwindung der Tonalität und hin zu einer befreiten, nachtonalen Musik“ – einer musique informelle.[242] Zu ihrer Charakterisierung verwendet Adorno starke Bilder: Sie sei „in allen Dimensionen […] ein Bild der Freiheit“ und „ein wenig wie Kants ewiger Frieden“ (GS 16: 540). In den 1960er Jahren veröffentlichte er, nach Eislers Tod, die gemeinsam mit ihm in den USA geschriebene Arbeit Komposition für den Film unter beider Namen.[243] |
音楽に関する著作 ロルフ・ヴィッゲルスハウスの考えでは、アドルノの思想の「出発点であり終着点」は音楽哲学である。[228] ハインツ・クラウス・メッツガーは、彼を「哲学者の中で初めて本格的に音楽を学んだ人物」とみなしている。[229] 彼は『社会研究誌』に最初の音楽哲学・社会学的なエッセイを掲載した(1932年:「音楽の社会的状況について」、1936年: ジャズについて』、1938年:『音楽におけるフェティッシュな性格と聴覚の退行について』、1939年:『ワーグナーについての断片』、1941年: 『大衆音楽について』)[230] アドルノの著作集(Gesammelte Schriften)全20巻のうち、8巻がアドルノの音楽に関する著作に充てられている(第12巻から第19巻)。『新音楽の哲学』(初版1949年) から始まり、リヒャルト・ワーグナー、グスタフ・マーラー、アルバン・ベルクについての音楽論(GS 13)を経て、オペラとコンサートの批評のコレクションで終わる。アドルノの音楽論が彼の哲学的な著作と密接に織り交ぜられているという事実は、第二次世 界大戦後の最初の著作『新音楽の哲学』ですでに表現されている。「序文」でアドルノは、この著作を「啓蒙の弁証法に関する拡張された余談」と表現している (GS 12: 11)。アドルノは音楽と哲学の親和性について次のように述べている。「哲学は音楽の即時性を切望し、音楽もまた哲学の明示的な意味を切望している」 [231] アドルノによれば、感覚的な経験(彼の理解では、聴くこと、提示、演奏による模倣的理解)と概念的な考察の両方が音楽の理解に貢献する。「模倣的理解を伴わない音楽の美的な考察は空虚であり、概念的理解を伴わない音楽の美的な経験は無感覚である」[232] 1932年の初期の論文『音楽の社会的状況について』において、彼は、すべての音楽には疎外の痕跡があり、商品として機能していると論じている。それが市 場の状況に抵抗するか、それとも従属するかによって、その真正性が決まる。「社会問題を独自の素材で、独自の形式法則に従って提示」するときに、その社会 的機能が果たされる(GS 18: 731)。新音楽の形式の中でも、彼は主にシェーンベルク派の無調音楽に真正性を認めた。作曲家であり音楽学者でもあるディーター・シュネーベルによれ ば、彼は「ウィーン学派とは異なる構造を持つ音楽に大きな困難を感じていた」という。[233] 例えばストラヴィンスキーは「技術的には反動的」(GS 12: 57)とみなされ、ヒンデミットは新古典主義の対極に位置づけられていた。そのため、彼はジョン・ケージの作品には慎重な態度を示していた。[234] 彼の音楽に関する著作の中で最も論争を呼んだトピックは、ジャズに関する彼の評決と、音楽における物質的進歩に関する彼の論文である。 「ジャズは厳密な意味で商品である」(GS 17: 77)という論文で、アドルノは、後に『啓蒙の弁証法』で「文化産業」と呼ばれることになる興隆しつつあった娯楽産業に対する最初の根本的な論争を展開し た。マーティン・ジェイは、アドルノは当初、ジャズを直接的に知ることはなかったと指摘している。235] プロジェクトおよび雑誌『Musik & Ästhetik』の共同創設者であり、『アドルノ・ハンドブック』の共同編集者でもあるリチャード・クラインは、アドルノの「ジャズに関する悪名高い理 解不足の主張」について語っている。236] 一方、ポップ理論家のディートリヒ・ディートリヒセンは、アドルノが音楽現象の しかし、そこから導き出された結論は誤りであったと認めている。アドルノは、その後の著作においても、ジャズに対する見方を根本的に変えることはなかっ た。 アドルノの音楽哲学の中心にあるのは、音楽素材の一方向的な発展に関する定理であり、それは「消費され、更新された音、テクニック、形式」に現れている。 音楽素材がすでに形作られているという性質は、その素材に頑固さを与え、作曲作業に要求を課す。しかし、それにもかかわらず、作曲作業には主題の自発性が 求められる。239] 「素材から主題に生じる要求は、『素材』自体が沈殿した精神であり、人間の意識を通じて社会的に前もって形成されたものであるという事実から生じる。かつ ての主観性として、このような客観的な素材の精神は独自の運動法則を持っている」(GS 12: 39) 素材という概念は、いわば「芸術と社会の接点」である。「芸術的・知的労働の客観化」として、それは――その時代の社会に根ざした芸術家の意識を媒介とし て――「それぞれの支配的社会の痕跡」を含んでいる。[240] アドルノはシェーンベルク派の学生として、12音技法における調性から無調性への移行を、絵画における具象から抽象への移行に類似した歴史的に不可避なス テップと見なしている(GS 12: 15)。音楽学者カール・ダールハウスは、12音技法に関するアドルノの立場を次のように評価している。一方では、それは「ベートーヴェンからブラーム ス、シェーンベルクへと進むにつれ、主題の作業が徐々に圧縮されていく必然的な帰結である」と彼は考えた。他方では、彼は十二音技法を、いわば音楽を空洞 化するようなシステム上の制約と捉えた。彼にとって、それは開かれた弁証法として残った。」[241] 1961年のクランヒシュタイン講演「無定形音楽への道」において、アドルノは12音技法を「調性を克服し、解放されたポスト・トーナルな音楽」すなわち 無定形音楽を達成するための必要な過渡期の段階とみなしている。[242] アドルノはそれを特徴づけるために強いイメージを用いている。「あらゆる次元において、それは自由のイメージである」とし、「カントの永遠平和に少し似て いる」(GS 16: 540)と表現している。 1960年代、アイスラーの死後、彼はアメリカでアイスラーと共同で書いた作品『映画のための作曲』を、両者の名前で発表した。[243] |
| Kompositionen Adorno verstand sich in seiner Selbsteinschätzung als „Musiker der zweiten Wiener Schule“.[244] Als Komponist hat er jedoch nur ein schmales Werk hinterlassen, darunter Klavierstücke, meistens Miniaturen, Lieder, Orchesterstücke und zwei Fragmente aus einer geplanten Oper.[245] Nach 1945 hat er das Komponieren ganz aufgegeben.[246] Der französische Dirigent und Komponist René Leibowitz rechnet Adornos Kompositionen der freien Atonalität zu. Sie seien völlig von den klassischen tonalen Funktionen emanzipiert, ohne sich – bis auf wenige Ausnahmen – „den genauen Prinzipien der Reihen- oder Zwölftonkompositionen zu unterwerfen“.[247] Der Komponist Dieter Schnebel verortet sie zwischen den Kompositionen Anton Weberns und Alban Bergs.[248] Adornos „authentische kompositorische Aktivität“ ist Leibowitz zufolge dem hohen Niveau seiner musiktheoretischen Schriften zugutegekommen.[249] Dem Komponisten Hans Werner Henze klangen Adornos Lieder, die er ihm am Klavier vorgespielt und vorgesungen hatte, „wie eine intelligente Fälschung“.[250] Von Adornos Kompositionen wurden zu seinen Lebzeiten nur die Sechs kurzen Orchesterstücke. op. 4, gedruckt; die Partitur erschien 1968 bei Ricordi in Mailand. Heinz-Klaus Metzger, ein Freund Adornos, gab gemeinsam mit dem Komponisten Rainer Riehn Adornos Kompositionen in zwei Bänden in der Münchner edition text + kritik heraus (1981). 2007 erschien, herausgegeben von Maria Luisa Lopez-Vito und Ulrich Krämer, ein abschließender dritter Band von Adornos Kompositionen, der neben den Klavierstücken im Nachlass vorhandene, vom Komponisten jedoch verworfene Kompositionen enthält. Gespielt wurde der Komponist Adorno vor 1933 gelegentlich, erst seit den fünfziger Jahren etwas häufiger. 1923 wurde ein Streichquartett des jungen Komponisten als Teil eines Konzerts des Lange-Quartetts aufgeführt, das ihm die Anerkennung eines Kritikers eintrug, „fast gleichberechtigt neben seinem Lehrer Bernhard Sekles und seinem Rivalen Paul Hindemith genannt“ zu werden.[251] Im Dezember 1926 wurden seine unter der Ägide Bergs entstandenen Zwei Stücke für Streichquartett. op. 2, im Rahmen des Programms der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik vom Kolisch-Quartett uraufgeführt,[252] 1928 seine Sechs kurzen Orchesterstücke. op. 4, in Berlin unter Leitung von Walter Herbert.[253] Die Dirigenten Gary Bertini, Michael Gielen, Giuseppe Sinopoli und Hans Zender sowie der Violinist Walter Levin mit dem LaSalle String Quartet setzten sich für den Komponisten Adorno ein. Die Sängerin Carla Henius hat sich sehr für sein Schaffen eingesetzt; mit ihr trat er manchmal auch gemeinsam auf.[254] Die Pianistin Maria Luisa Lopez-Vito hat seit 1981 die Klavierstücke Adornos nach und nach bei Konzerten in Palermo, Bozen, Berlin, Hamburg und an anderen Orten uraufgeführt. Frühe Streichquartette wurden vom Neuen Leipziger Streichquartett, Streichtrios vom Freiburger trio recherche uraufgeführt. Unter dem schwachen Echo, das seine Kompositionen fanden, hat Adorno gelitten. |
作曲 アドルノは自らを「第二ウィーン学派の音楽家」とみなしていた。[244] しかし、作曲家としては、ピアノ曲(ほとんどが小品)、歌曲、管弦楽曲、そして計画されたオペラの断片2曲など、ごくわずかな作品しか残していない。 フランスの指揮者兼作曲家ルネ・レイボヴィッツは、アドルノの作曲を自由無調に分類している。それらは古典的な調性機能から完全に解放されており、いくつ かの例外はあるものの、「厳密な系列作曲法や12音作曲法の原則に従う」ことはなかった。[247] 作曲家のディーター・シュネーベルは、アドルノの作品をアントン・ヴェーベルンとアルバン・ベルクの作品の間に位置づけている。[248] ライボヴィッツによると、アドルノの「真正な作曲活動」は、彼の音楽理論に関する著作の水準の高さに寄与したという 。作曲家のハンス・ヴェルナー・ヘンツェは、アドルノがピアノで弾いて歌ってくれた曲を「知的な偽物」のように感じたという。 存命中に出版されたのは「Six Short Orchestral Pieces, op. 4」のみで、楽譜は1968年にミラノのリコルディ社から出版された。アドルノの友人であったハインツ・クラウス・メッツガーは、作曲家のライナー・リー エンとともに、アドルノの作品を2巻にまとめたものをミュンヘンのテキスト+クリティック社から出版した(1981年)。2007年には、マリア・ルイ サ・ロペス=ヴィトとウルリッヒ・クレーマーによってアドルノの作曲作品の最終的な第3巻が出版された。この第3巻には、ピアノ曲に加えて、作曲家によっ て却下された遺作の作曲作品も含まれている。 作曲家アドルノは、1933年以前にも時折演奏されていたが、1950年代以降はより頻繁に演奏されるようになった。1923年には、若い作曲家の弦楽四 重奏曲が、ランゲ弦楽四重奏団の演奏会で演奏され、批評家から「師ベルンハルト・ゼックレスとライバルのパウル・ヒンデミットとほぼ肩を並べる」と評され た。[251] 1926年12月には、ベルクの庇護を受けて作曲された彼の弦楽四重奏曲第2番作品2が、 1926年12月、国際新音楽協会のプログラムの一環として、コリッシュ弦楽四重奏団により初演された。[252] 1928年には、彼の「6つの短い管弦楽曲」作品4が、ベルリンでヴァルター・ハーバートの指揮により初演された。 指揮者のゲイリー・ベルティーニ、ミヒャエル・ギーレン、ジュゼッペ・シノーポリ、ハンス・ツェンダー、またラサール弦楽四重奏団のヴァイオリニスト、 ウォルター・レヴィンはアドルノを支援した。歌手のカルラ・ヘーニウスは彼の作品の熱心な支持者であり、時には彼女と共演した。ピアニストのマリア・ルイ サ・ロペス=ヴィトは、1981年以降、パレルモ、ボルツァーノ、ベルリン、ハンブルクなど各地のコンサートでアドルノのピアノ曲を初演している。初期の 弦楽四重奏曲はライプツィヒ弦楽四重奏団、弦楽三重奏曲はフライブルク・トリオ・レシェルシュによって初演された。アドルノは自身の作曲に対する反応の弱 さに苦しんだ。 |
| Sprache und Darstellungsformen Kenner und Analytiker von Adornos Arbeiten haben auf deren Verwandtschaft mit literarischen Texten, musikalischen Kompositionen und den „porösen“ Denkbildern Walter Benjamins hingewiesen.[255] Nach Albrecht Wellmer gleichen seine Texte „komplexen und in jeder Nuance durchgehörten Musikstücken“.[256] Der Komponist und Musikwissenschaftler Dieter Schnebel deutet auf Adornos „Komposition in Sprache“ hin. Während die übliche Sprachgestaltung von Satz zu Satz fortschreitet, gleichen Kompositionen Beziehungsmodellen, die auf Zukünftiges verweisen und an Zurückliegendes erinnern sowie mit Variationen und Kontrasten, Verkürzungen und Erweiterungen arbeiten.[257] Die von ihm häufig gesetzten Paradoxa gleichen Synkopen, die den Text zugleich aufhalten und beschleunigen.[258] Ruth Sonderegger spricht von einer „rhizomartigen Struktur“ der Texte.[259] Adornos Art zu schreiben ist ohne Benjamins Vorbild undenkbar; Adorno verdankt ihm den Hinweis auf das enge Verhältnis von Inhalt und Gestaltung. Seit seinen frühen Schriften betont Adorno ein komplementäres Verhältnis von Form und Inhalt philosophischer Texte. Insbesondere die von Adorno bevorzugten „kleinen Formen“ der philosophischen Darstellung – der Essay, der Traktat, der Aphorismus, das Fragment – sind Musterbeispiele seiner sprachlichen Ausbruchsversuche aus dem überkommenen philosophischen Systemdenken. Der Literaturwissenschaftler Detlev Schöttker weist auf Adornos teils verdeckte Aneignung von Benjamins Motiven hin.[260] Hierzu trägt auch Adornos Abneigung gegen Definitionen und die parataktische Struktur seiner Texte bei, das heißt: Aussagesätze werden nebeneinandergestellt, unter Vermeidung einer hierarchischen Ordnung der Subsumtion, weil in dieser – wie Habermas Adorno interpretiert – „die Allgemeinheit der logischen Form dem Individuellen unrecht tut“.[261] In den Minima Moralia fordert er: „In einem philosophischen Text sollten alle Sätze gleich nahe zum Mittelpunkt stehen“ (GS 4: 78). Das zugrundeliegende Gestaltungsprinzip, auf das Adorno immer wieder zurückgreift, bezeichnet er mit Konstellation oder Konfiguration. Als Merkmale dieses Verfahrens notiert Martin Mittelmeier die „möglichst differenzierte Aufsplitterung der Phänomene, das Herauslösen aus ihren angestammten Zusammenhängen und Neuzusammensetzung zu ungewohnten Kombinationen“.[262] Das paradoxe Vorhaben, „einen linearen Text nach einem räumlichen Muster zu organisieren“,[263] hat die wechselseitige Erhellung der Begriffe, bei der die Dominanz eines einzelnen Konzepts durch die Gegenüberstellung mit anderen gebrochen wird, zum Ziel.[264] Für einen philosophischen Text wie etwa die Ästhetische Theorie betrachtet Adorno eine stufenweise Argumentation vom Allgemeinen zum Besonderen oder umgekehrt und die „unabdingbare Folge des Erst-Nachher“ als der Sache inadäquat. Programmatischen Charakter für Adornos Schreiben wird seinem Aufsatz Der Essay als Form zugeschrieben.[265] Er ist einer der wenigen Texte, in denen Adorno „Einblicke in seine Werkstatt“ gewährt und metatheoretische Auskunft über die Formen der Darstellung in der Philosophie gibt.[266] In seiner anti-systematischen, parataktischen und von Montagen durchschnittenen Form, seinem „methodisch unmethodischen“ Verfahren (GS 11: 21) bildet der Essay „die Makrostruktur dessen, was auf einer Mikroebene Konstellation und Konfiguration heißt“.[267] Als Darstellungsform will der Essay „mit Begriffen aufsprengen, was in Begriffe nicht eingeht“; er lässt sich weder in die Welt der „organisierten Wissenschaft“ einsperren noch von einer Philosophie vereinnahmen, die mit dem „leeren und abstrakten Rest vorlieb nimmt, was der Wissenschaftsbetrieb noch nicht besetzte“; ihr „innerstes Formgesetz […] ist die Ketzerei“ (GS 11: 32 f.). Britta Scholze zufolge wurden auch die großen Werke – Negative Dialektik und Ästhetische Theorie – nach dem essayistischen Darstellungsmodus verfasst und stellen gewissermaßen „essayistische Mosaike“ dar.[268] |
言語と表現形式 アドルノの作品の専門家や分析家は、その文学的なテキスト、音楽作品、ヴァルター・ベンヤミンの「多孔性の」心的イメージとの親和性を指摘している。 255] アルブレヒト・ヴェルマーによると、彼のテキストは「あらゆるニュアンスが聞こえる複雑な音楽作品」に似ている。256] 作曲家で音楽学者のディーター・シュネーベルは、アドルノの「言語による作曲」を指摘している。通常の言語の形成は文から文へと進むが、作曲は未来を参照 し過去を想起する関係モデルに似ており、変形や対比、省略や拡張を扱う。257] 彼が頻繁に用いる逆説は、文章を停止させ加速させるシンコペーションに似ている。258] Ruth Sondereggerは、テキストの「根茎のような構造」について語っている。259] アドルノの書き方は、ベンヤミンの例なしには考えられない。アドルノは、内容と形式の密接な関係についての言及をベンヤミンに負っている。アドルノは初期 の著作以来、内容と形式の関係を強調してきた。 テキストの根のような構造」について語っている。 アドルノの書き方は、ベンヤミンの例なしには考えられない。アドルノは、内容と形式の密接な関係についての言及をベンヤミンに負っている。アドルノは初期 の著作から、哲学的なテキストの形式と内容の相補的な関係を強調してきた。とりわけ、アドルノが好んで用いた哲学的な表現形式である「小さな形式」―― エッセイ、論文、格言、断片――は、伝統的な哲学的な思考体系から脱却しようとする彼の言語的試みの典型的な例である。文学研究者のデトレフ・ショット カーは、アドルノがベンヤミンのモチーフを部分的に隠れて利用していることを指摘している。 定義を嫌い、パラタクティックな文章構造を好んだアドルノの姿勢も、この傾向に拍車をかけた。つまり、文章は隣り合わせに配置され、包含の階層的秩序を避 ける。なぜなら、ハーバーマスがアドルノを解釈するように、「論理形式の一般性は個々に対して不正義である」からだ。[261] 『ミニマ・モラリア』において、アドルノは次のように要求している。「哲学的な文章においては、すべての文章は すべてが等しく中心に近づくべきである」(GS 4: 78)。アドルノが繰り返し立ち返る基本的な設計原則は、彼が「星座」または「構成」と呼ぶものである。マルティン・ミッテルマイアーは、この手順の以下 の特徴を指摘している。「現象の最も細分化された断片化、それらの本来の文脈からの除去、そして見慣れない組み合わせへの再構成」[262] この逆説的な取り組みの目的は、「線形のテキストを空間的なパターンに従って組織化する」ことである[263]。この取り組みの目的は、概念を相互に解明 することであり、その目的のために、単一の概念の優位性が 他の概念と並置することで、単一概念の優位性が打ち破られるという相互啓発が、このアプローチの狙いである。『美学理論』のような哲学的なテキストについ て、アドルノは、一般から特殊へ、またはその逆の段階的な論証と、「必然的な最初と後の順序」を不十分であるとみなしている。 彼のエッセイ「形式としてのエッセイ」は、アドルノの著作のプログラム的なものとみなされている。265] これはアドルノが「自身の作業場への洞察」を認めた数少ないテキストのひとつであり、哲学における表現形式についてのメタ理論的な情報を提供している。 266] モンタージュによって交差する反体系的な並列形式において、その「系統的かつ非系統的な」手順(GS 11 :21)は、ミクロレベルでは「配置と構成」と呼ばれるものの「マクロ構造」を形成する。[267] 提示の形式として、エッセイは「概念では把握できないものを概念によって解明する」ことを目指している。エッセイは「組織化された科学」の世界に閉じ込め ることはできず、「科学的確立によってまだ占領されていない空虚で抽象的な残余物で間に合わせる」哲学によって利用することもできない。その「最も内奥の 形式的法則は異端である」(GS 11: 32 f.)。ブリッタ・ショルツによれば、主要な著作である『否定弁証法』と『美学理論』もまたエッセイの様式で書かれており、ある程度は「エッセイのモザイ ク」を代表しているという。[268] |
Wirkungsgeschichte Adorno-Gedenktafel an seinem Wohnhaus im Frankfurter Westend Adorno hat zumindest im institutionellen Sinn keine „Schule“ gebildet, obwohl es ihm an Schülern nicht mangelte. Das hatte Auswirkungen: Sein Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie wurde nach seinem Tod aufgeteilt und mit Wissenschaftlern besetzt, die teils entgegengesetzte Positionen vertraten. Das Institut für Sozialforschung wurde damit zu einem vorwiegend empirisch ausgerichteten Forschungsinstitut unter der Geschäftsführung Ludwig von Friedeburgs und Gerhard Brandts. Das schriftstellerische Werk Adornos wurde von seinem Schüler Rolf Tiedemann bald in umfangreichen Ausgaben herausgegeben: Gesammelte Schriften (1970 ff.) und Nachgelassene Schriften (1993 ff.), die im Frankfurter Suhrkamp Verlag erschienen. Tiedemann schildert in einem editorischen Nachwort Adornos Desinteresse an der Gesamtdarstellung seines Werkes: „Ihr macht das dann schon“, sei stets die ausweichende Antwort gewesen. Adorno habe es abgelehnt, zum „Museumswärter seines eigenen Denkens“ zu werden. Dies und der Rundfunkvortrag Erziehung zur Mündigkeit sowie Kritik an Denkschulen (Jargon der Eigentlichkeit) lassen den Schluss zu, dass Adorno kein Meister für seine Schüler sein, sondern eher das selbstständige, kritische Denken befördern wollte. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass er bestimmte Texte als „Flaschenpost“ bezeichnete, also als eine Botschaft, deren Dechiffrierung zeitlich, räumlich und in der Person des Finders äußerst unbestimmt in der Zukunft liegt. |
歴史的な影響 フランクフルトのヴェストエンドにあるアドルノの自宅に掲げられたアドルノの記念プレート アドルノは、制度的な意味での「学派」を形成したわけではないが、彼のもとには常に多くの学生が集まっていた。 彼の死後、彼の哲学・社会学の教授職は分割され、場合によっては対立する立場をとる学者たちによって埋められた。 こうして社会研究機関は、ルードヴィヒ・フォン・フリーデブルクとゲアハルト・ブラントの管理下で、実証的な研究を主とする研究所となった。 アドルノの文学的著作は、まもなく彼の教え子であるロルフ・ティードマンによって、大規模な版で出版された。『全集』(1970年以降)と『遺稿集』 (1993年以降)は、フランクフルトのシュールカンプ出版社から出版された。 編集後記で、ティードマンはアドルノが自身の著作の全体的な提示に興味を示さなかったことを次のように述べている。「君がやればいい」というのが、いつも 彼の逃げ口上だった。アドルノは「自身の思考のキュレーター」になるという考えを拒絶した。これは、ラジオ講義『道徳教育』や学派批判(『現実のジャルゴ ン』)と併せて考えると、アドルノは弟子たちの師となることを望まず、むしろ独立した批判的思考を促進することを望んでいたことがわかる。この文脈におい て注目すべきは、彼があるテキストを「ボトルメール」すなわち、時間、空間、発見者の観点から、解読が極めて遠い未来にしかできないメッセージと表現した ことである。 |
| Gegenpositionen Axel Honneth warf Adorno in Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie einen „gesellschaftstheoretischen Reduktionismus“ vor. Seine auf den zivilisatorischen Prozess der Naturbeherrschung fixierte Gesellschaftstheorie lasse eine eigenständige „Sphäre sozialen Handelns“ analytisch nicht mehr zu, worin Honneth eine „Verabschiedung der Soziologie“ sieht.[269] Jürgen Habermas verwies in seinem Philosophischen Diskurs der Moderne auf den „performativen Widerspruch“ in Adornos totalisierender Kritik von Vernunft, Geschichte, Kultur und Gesellschaft. Wenn jegliche Vernunft als korrumpierte kritisiert werde, stelle sich die Frage nach dem Ort dieser Vernunftkritik. Adorno sei zwar die paradoxe Struktur seines Denkens bewusst gewesen, er habe sich aber ad hoc auf die „bestimmte Negation“ Hegels zurückgezogen. In seiner „hemmungslosen Vernunftskepsis“ habe Adorno den vernünftigen Gehalt der kulturellen Moderne unterschätzt und gegenüber den „Errungenschaften des okzidentalen Rationalismus“ eine gewisse Unbekümmertheit gezeigt.[270] Mit Georg Lukács, dessen Frühwerke (Die Theorie des Romans, Geschichte und Klassenbewußtsein) Adorno überaus schätzte und die aus seinem Bildungsweg „schlechterdings nicht wegzudenken sind“,[271] geriet er in den 1950er und späteren Jahren in eine scharfe Kontroverse, die sich an ästhetischen Fragen entzündete, aber schließlich auch die wechselseitige Kritik an den politischen Optionen beider einbezog. Mit Lukács stimmte Adorno darin überein, dass Kunst ein Medium der Erkenntnis sei (Erpreßte Versöhnung. GS 11: 264), er lehnte aber vehement die von Lukács vertretene „Widerspiegelungstheorie“ ab, der zufolge ein Kunstwerk die objektive und gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegeln solle (Erpreßte Versöhnung, GS 11: 253). In dieser Frage wirft Adorno Lukács „verbissenen Vulgärmaterialismus“ vor. Das Verhältnis der Kunst zur Wirklichkeit sieht Adorno vielmehr darin, dass Kunst „in ihrer autonomen Konstitution ausspricht, was von der empirischen Gestalt der Wirklichkeit verschleiert wird“ (Erpreßte Versöhnung, GS 11: 264). Politisch wirft Adorno Lukács vor, sich dem „trostlosen Niveau“ bornierter Parteifunktionäre anzupassen, im Wahn, in einer nichtantagonistischen Gesellschaft zu leben (Erpreßte Versöhnung, GS 11: 279). Lukács hingegen bezeichnet Adorno als einen im „nonkonformistisch maskierten Konformismus“ Befangenen, der das „Grand Hotel Abgrund“ bezogen habe, wo er mit anderen westlichen Intellektuellen den raffinierten Komfort genieße.[272] Kritik an Adornos Negativer Dialektik übte Jean Améry 1967 in einem Aufsatz, den er in ironischer Abwandlung des Titels der von Adorno gegen Martin Heidegger gerichteten Schrift, Jargon der Eigentlichkeit, mit Jargon der Dialektik überschrieb. Als Überlebender von Auschwitz kritisierte er, dass unter der Formel „absolute Negativität“ Auschwitz zur dialektischen Selbsterhöhung des philosophischen Gedankens herhalten muss – in einer „von sich selber bis zur Selbstblendung entzückten Sprache“.[273] Konträre Positionen zu Adornos Wissenschaftsverständnis bezogen die Vertreter des Kritischen Rationalismus wie Karl Raimund Popper und Hans Albert sowie zahlreiche Vertreter der Mainstream-Soziologie, die sich als Erfahrungswissenschaftler verstanden oder der quantitativ orientierten empirischen Sozialforschung zurechneten. Ralf Dahrendorf vertrat im so genannten Positivismusstreit eine zwar eigene Position zwischen den Kontrahenten, die aber dem Denken Poppers näher stand als dem der Frankfurter Schule. In Alphons Silbermann hatte Adorno einen streitbaren Kontrahenten der empirischen Kunst- und Kultursoziologie. Die musiktheoretische Position Adornos wurde bereits vor der Postmoderne in Frage gestellt. In einer resümierenden Kritik monierte der Habermas-Schüler Albrecht Wellmer, dass Adorno mit seiner These eines unilateralen Fortschritts und eines eindeutig bestimmbaren Entwicklungsstandes des musikalischen Materials Debussy, Varèse, Bartók, Strawinsky und Ives beiseite geschoben oder offen als Irrwege diffamiert habe. Eine „eigentümliche Blickverengung“ und die „Fixierung auf die deutsch-österreichische Musiktradition“ hätten ihn den „produktiven Pluralismus von Wegen zur Neuen Musik im 20. Jahrhundert“ verkennen lassen.[274] Hans Robert Jauß, prominenter Vertreter der Rezeptionsästhetik, führt gegen Adornos „Ästhetik der Negativität“ ins Feld, dass er die „gesamte vorautonome Kunst“, die beachtliche affirmative Kunstwerke aufweise, „nicht auf den Generalnenner der Negativität zu bringen“ vermöge, dass er ästhetische Erfahrung und Wechselwirkung von Kunstwerk und Publikum ignoriere und den Kunstgenuss als banausenhaft missbillige.[275] |
反対意見 『権力批判』において、批判的社会理論の考察段階(『権力批判。批判的社会理論の考察段階』)において、アクセル・ホネットはアドルノを「社会理論的還元 主義」と非難した。自然を支配する文明化のプロセスに固執する彼の社会理論は、もはや独立した「社会的行動の領域」を分析的に認めておらず、ホネットはこ れを「社会学の放棄」と見なしている。[269] ユルゲン・ハーバーマスは著書『近代の哲学的言説』において、アドルノの理性、歴史、文化、社会に対する総括的な批判に「パフォーマティブな矛盾」がある ことを指摘した。もしも理性がすべて堕落しているとして批判されるのであれば、この理性批判の正当な位置づけが問われることになる。アドルノは自身の思考 の逆説的な構造を認識していたが、その場しのぎの方法としてヘーゲルの「確実な否定」に頼った。「理性に対する抑制なき懐疑」において、アドルノは文化の 近代性における合理的な内容を過小評価し、「西洋の合理主義の成果」に対する関心の欠如を示した。[270] 1950年代以降、アドルノはゲオルク・ルカーチの初期の作品(『小説理論』、『歴史と階級意識』)を高く評価しており、それらはアドルノの教育にとって 「絶対に不可欠」なものであった。271] 美学的問題から始まった論争は、最終的には両者の政治的 。アドルノは、芸術は知識の媒体であるというルカーチの意見に同意していた(『Erpreßte Versöhnung』GS 11: 264)が、芸術作品は客観的・社会的現実を反映すべきであるというルカーチの唱える「反映理論」を激しく拒絶した(『Erpreßte Versöhnung』GS 11: 253)。この点について、アドルノはルカーチを「頑迷な低俗唯物論者」と非難した。アドルノは、芸術と現実の関係を、芸術が「現実の実証的な形態によっ て覆い隠されているものを、その自律的な構成において表現する」ものとして、より深く捉えている(GS 11: 264)。政治的には、アドルノはルカーチが非敵対的社会に生きているという妄想の中で、偏狭な党幹部の「荒涼としたレベル」に順応していると非難してい る(『Erpreßte Versöhnung』GS 11: 279)。一方、ルカーチはアドルノを「非順応主義を装った順応主義」に囚われた人物と描写し、彼は「グランド・ホテル・アビス」に身を置き、他の西洋の 知識人たちとともに洗練された快適さを享受していると述べている。 1967年、ジャン・アメリは「弁証法の専門用語」と題したエッセイでアドルノの『否定弁証法』を批判した。このタイトルは、アドルノがマルティン・ハイ デッガーに対して書いた『真正性の専門用語』という作品のタイトルを皮肉ったものだった。アウシュビッツの生存者として、彼は「絶対的否定性」という公式 の下では、アウシュビッツは哲学思想の弁証法的な自己高揚に奉仕しなければならないという事実を批判した。「自己陶酔の域にまで達した自己満足の言語」に おいてである。[273] カール・ポパーやハンス・アルバートといった批判的合理主義の代表者たち、そして、自らを経験科学者とみなしたり、量的に志向する経験的社会学と関連付け られていた多数の主流派社会学の代表者たちは、アドルノの科学観とは対立する立場を取っていた。いわゆる実証主義論争において、ラルフ・ダレンドルフは両 者の間に独自の立場を取ったが、それはフランクフルト学派よりもポパーの考え方に近いものであった。アルフォンス・シルバーマンは、経験的な芸術と文化社 会学の分野におけるアドルノの好敵手であった。 アドルノの音楽理論に対する立場は、ポストモダニズム以前からすでに疑問視されていた。批判的な総括として、ハーバーマスの弟子であるアルブレヒト・ウェ ルマーは、アドルノが一方的な進歩論と音楽素材の明確に決定可能な発展状態というテーゼを掲げたことで、ドビュッシー、ヴァレーズ、バルトーク、ストラ ヴィンスキー、アイヴズを脇に追いやったり、あるいは公然と逸脱として中傷したりしたと不満を述べている。「偏狭な視野」と「ドイツ・オーストリアの音楽 伝統への固執」が、彼をして「20世紀における新音楽への多様な創造的アプローチ」を誤って判断させてしまったのである。[274] 受容美学の著名な代表者であるハンス・ロベルト・ヤウスの主張によると、アドルノの「否定の美学」は、優れた肯定的な芸術作品を含む「自律以前の芸術」を「否定の共通項」に還元できないこと、美的体験や芸術作品と観客との相互作用を無視していること、そして、 。 |
| Unverständlichkeitsvorwurf Adorno gilt gemeinhin als besonders schwer zu lesender oder zu verstehender Autor. Dem entgegnete Adorno häufig, dass er, „wenn es die Sache nur zulassen würde, gern einfacher schriebe.“[258] Henning Ritter hielt den Vorwurf der Unverständlichkeit Adornos für eine Legende, welche sich einerseits aus der Häufung von Fremdwörtern, aber mehr noch aus einer im philosophischen Zusammenhang überraschenden Simplizität erkläre: „Worte der Umgangssprache werden gleichrangig behandelt wie Begriffe“.[276] Indem er Worte aus unterschiedlichen Sprachdimensionen verwendet, fügt er ihnen Assoziationen und Motive eines bestimmten Materials hinzu, „ob es nun ‚tough baby‘ oder ‚ecriture‘ oder ‚dejavu‘ ist“.[258] Adorno benutze Alltagsworte als banale Einsprengsel, „um dann doch Dinge zu sagen, die jenseits jeder Banalität liegen – so wie Kunst aus irgendwo gefundenen Dingen gemacht wird“.[277] |
理解不能 アドルノは一般的に、とりわけ読みにくい、理解しがたい作家であると考えられている。アドルノはしばしば「主題がそれを許すのであれば」もっと簡単に書き たかったと答えている。[258] ヘニング・リッターは、アドルノが理解しがたいという非難は神話であるとみなしている。その理由は、外来語の蓄積という側面もあるが、それ以上に、哲学的 な文脈における驚くべき単純さによるものである。「日常的な言葉は、専門用語と同じ地位を持つものとして扱われている」[276]。 異なる言語次元の言葉を用いることで、彼は特定の素材の連想やモチーフをそれらに付け加える。「それが『タフな赤ん坊』であれ、『エクリチュール』であ れ、『デジャヴ』であれ」[258]。アドルノはありふれた言葉をありふれた散りばめとして用いる。「あらゆる平凡さを超えたことを言うために。芸術がど こかで見つけられた物自体から作られるように どこかで見つけた物自体」[277] |
| Erinnerungen Theodor-W.-Adorno-Preis → Hauptartikel: Theodor-W.-Adorno-Preis Die Stadt Frankfurt stiftete 1976 den Theodor-W.-Adorno-Preis. Ebendort wurde 1985 von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur das Theodor W. Adorno Archiv gegründet, in dem der wissenschaftliche und künstlerische Nachlass Adornos mit dem Nachlass Walter Benjamins vereinigt werden konnte. Das Archiv wurde von 1985 bis 2002 von Rolf Tiedemann aufgebaut und geleitet, der auch die Reihe Frankfurter Adorno Blätter, die Erstdrucke Adorno’scher Texte mit Diskussionsbeiträgen zu seinem Denken vereinigte und die Dialektischen Studien herausgab, in denen unzugängliche und neuere Arbeiten aus der Schule oder dem Geist Adornos publiziert wurden. 2004 wurde der Benjamin-Nachlass aus dem Theodor W. Adorno Archiv wieder ausgegliedert und in der Archivabteilung der Berliner Akademie der Künste deponiert; der Adorno-Nachlass befindet sich inzwischen im Frankfurter Institut für Sozialforschung. Zum 100. Geburtstag Adornos im Jahr 2003 rief die Stadt Frankfurt ein Adorno-Jahr aus.[278] |
追慕記念 テオドール・W・アドルノ賞 → 詳細は「テオドール・W・アドルノ賞」を参照 フランクフルト市は1976年にテオドール・W・アドルノ賞を創設した。 1985年にはハンブルク研究文化振興財団によってテオドール・W・アドルノ・アーカイブが設立され、アドルノの学術的・芸術的遺産とヴァルター・ベンヤ ミンの遺産が統合された。このアーカイブは1985年から2002年までロルフ・ティードマンによって構築・管理され、彼はまた、アドルノのテキストの初 版と彼の思想に関する論考を組み合わせたシリーズ『フランクフルター・アドルノ・ブラーテン』や、アドルノの学派や精神から生まれた入手困難な近年の作品 をまとめた『弁証法研究』を出版した。2004年には、ベンヤミンの遺品がテオドール・W・アドルノ・アーカイブから取り除かれ、ベルリン芸術アカデミー のアーカイブ部門に保管された。アドルノの遺品は現在、フランクフルト社会研究機関に保管されている。アドルノの生誕100周年にあたる2003年には、 フランクフルト市がアドルノ・イヤーを宣言した。 |
| Denkmal und Platznamen → Hauptartikel: Adorno-Denkmal  Adorno-Denkmal von Vadim Zakharov auf dem Theodor W. Adorno-Platz in Frankfurt am Main auf dem Westend-Campus In unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Universität am Campus Bockenheim wurde ein Platz in Theodor-W.-Adorno-Platz (jetzt: Tilly-Edinger-Platz) umbenannt und 2003 das Adorno-Denkmal für den Philosophen eingeweiht: ein Glaskasten mit Stuhl, Schreibtisch und einem darauf befindlichen Metronom. An seinem vormaligen Wohnhaus im Kettenhofweg im Frankfurter Westend, in dem Adorno von 1949 bis 1969 lebte, erinnert eine Gedenktafel an sein Wirken. Das Denkmal wurde 2016[279], der Platzname bereits 2015 an den Campus Westend verlegt.[280][281] |
モニュメントと広場の名称 → 詳細は「アドルノ・モニュメント」を参照  フランクフルト・アム・マインのヴェステント・キャンパスにあるテオドール・W・アドルノ広場のヴァディム・ザハロフによるアドルノ・モニュメント フランクフルト大学ボッケンハイム・キャンパスのすぐ近くにある広場は、テオドール・W・アドルノ広場(現:ティリー・エディンガー広場)と改名され、 2003年には哲学者アドルノの記念碑が落成した。ガラスケースに椅子、机、メトロノームが置かれている。1949年から1969年までアドルノが暮らし たフランクフルト・ヴェストエンドのケッテンホーフヴェークにあった彼の住居の建物には、彼の業績を称える銘板が掲げられている。記念碑は2016年に ヴェストエンドキャンパスに移設されたが[279]、広場の名称はすでに2015年に変更されていた。 |
| Fußgängerampel → Hauptartikel: Adorno-Ampel Die Adorno-Ampel, eine 1987 errichtete Fußgängerampel, neben dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Biographien Im Adorno-Jahr erschienen neben mehreren Einführungen und Text-Ausgaben auch drei umfangreiche Biographien Adornos: Stefan Müller-Doohm: Adorno. Eine Biographie Frankfurt am Main, Suhrkamp 2003, Detlev Claussen: Theodor W. Adorno. Ein letztes Genie. Fischer, Frankfurt am Main 2003, Lorenz Jäger: Adorno. Eine politische Biographie. DVA, München 2003.[282] Ehrungen  Deutsche Briefmarke von 2003 zum 100. Geburtstag Adornos 1954 Arnold-Schönberg-Medaille 1959 Deutscher Kritikerpreis für Literatur 1963 Goetheplakette der Stadt Frankfurt am Main 1987 Adorno forderte 1962 nach einem tödlichen Verkehrsunfall in der Senckenberganlage Ampelanlagen, diese wurde 25 Jahre später errichtet und trägt seinen Namen 2013 Ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels wird nach ihm benannt: (21029) Adorno 2015 Ein zentraler Platz in Frankfurt am Main auf dem Campus Westend der Goethe-Universität nach ihm „Theodor-W.-Adorno-Platz“ benannt.[283] Ein 2015 gegründetes Gymnasium in Frankfurt trägt seit Januar 2018 den Namen Adorno-Gymnasium. Es soll im Sommer 2019 einen provisorischen Standort auf dem Campus Westend erhalten und langfristig einen Neubau an der Miquelallee beziehen. Am 27. Juni 2021 wurden für Theodor W. Adorno und seine Eltern, Maria Calvelli-Adorno und Oskar Wiesengrund in Frankfurt am Main Stolpersteine verlegt. Die Zeremonie fand vor dem Haus, das die Familie Wiesengrund-Adorno 1914 bezog, statt.[284] Seit Dezember 2022 erinnert eine Informationstafel am Standort des früheren Geburtshauses Schöne Aussicht Nr. 9 in Frankfurt am Main mit einem historischen Foto an das Geburtshaus und die benachbarte Weinhandlung des Vaters.[285][286] |
歩行者用信号機 → 詳細はアドルノ信号機を参照 アドルノ信号機は、1987年にフランクフルト・アム・マインの社会研究所の隣に設置された歩行者用信号機である。 伝記 アドルノ年には、いくつかの入門書やテキスト版が出版されたほか、アドルノの伝記も3冊刊行された。 シュテファン・ミュラー=ドーム著『アドルノ伝』フランクフルト・アム・マイン、スールカンプ社、2003年、 デトレフ・クラウスゼン著『テオドール・W・アドルノ。最後の天才』フィッシャー社、フランクフルト・アム・マイン、2003年、 ロレンツ・イェーガー著『アドルノ。政治的伝記』DVA、ミュンヘン、2003年。 受賞  アドルノ生誕100周年を記念して2003年に発行されたドイツ切手 1954年 アルノルト・シェーンベルク・メダル 1959年 ドイツ文学賞 1963年 フランクフルト・アム・マイン市のゲーテ・メダル 1987年 1962年に起きた死亡交通事故の後、アドルノはゼンケンベルクアナーゲに信号機の設置を要求した。25年後にその信号機が設置され、彼の名が付けられた 2013年 外縁小帯にある小惑星が彼の名にちなんで命名された。(21029) Adorno 2015年 フランクフルト・アム・マインのゲーテ大学のヴェステント・キャンパスの中心広場が、彼にちなんで「テオドール・W・アドルノ広場」と名付けられた。 2015年に創立されたフランクフルトの高校は、2018年1月からアドルノ・ギムナジウムと名付けられている。2019年夏にはヴェストエンドキャンパスに一時的に移転し、長期的にはミケーラレーに新設される建物に移転する予定である。 2021年6月27日、テオドール・W・アドルノと両親であるマリア・カルヴェッリ=アドルノとオスカー・ヴィーゼングルントのために、フランクフルト・ アム・マインでつまずき石が敷かれた。式典は、1914年にヴィーゼングルント=アドルノ一家が引っ越してきた家の前で行われた。 2022年12月より、フランクフルト・アム・マインの旧居「シェーネ・アウスブルック(Schöne Aussicht)9番地」の跡地に、父親の生家と隣接するワイン店の跡地を記念する歴史的な写真付きの銘板が設置されている。 |
| Bekannte Schüler Regina Becker-Schmidt (1937–2024), Soziologin Heide Berndt (1938–2003), Stadtsoziologin Silvia Bovenschen (1946–2017), Schriftstellerin Bazon Brock (* 1936), Professor für Ästhetik Peter Bulthaup (1934–2004), Philosoph und Chemiker Detlev Claussen (* 1948), Soziologe Michaela von Freyhold (1940–2010), Entwicklungssoziologin Peter Furth (1930–2019), Sozialphilosoph Peter Gorsen (1933–2017), Kunstwissenschaftler Karl Heinz Haag (1924–2011), Philosoph Jürgen Habermas (* 1929), Politologe und Sozialphilosoph Peter von Haselberg (1908–1994), Journalist Hans Imhoff (* 1939), Aktionskünstler und Schriftsteller Joachim Kaiser (1928–2017), Musik- und Literaturkritiker Alexander Kluge (* 1932), Jurist, Autor und Filmer Hans-Jürgen Krahl (1943–1970), Studentenaktivist in 68er-Bewegung und SDS Elisabeth Lenk (1937–2022), Soziologin Kurt Lenk (1929–2022), Politologe Rudolf zur Lippe (1937–2019), Philosoph Werner Mangold (1927–2020), Soziologe Otwin Massing (1934–2019), Politikwissenschaftler und Soziologe Günther Mensching (* 1942), Philosoph Heinz-Klaus Metzger (1932–2009), Musiktheoretiker Karl Markus Michel (1929–2000), Schriftsteller und Publizist Ivan Nagel (1931–2012), Theaterwissenschaftler, Publizist und Intendant Oskar Negt (1934–2024), Sozialphilosoph Dieter Prokop (* 1941), Soziologe Ulrike Prokop (* 1945), Sozialwissenschaftlerin Helmut Reichelt (* 1939), Soziologe Alfred Schmidt (1931–2012), Philosoph Hermann Schweppenhäuser (1928–2015), Philosoph und Publizist Monika Seifert (1932–2002), Soziologin und Pädagogin Bassam Tibi (* 1944), Politikwissenschaftler Rolf Tiedemann (1932–2018), Philosoph und Philologe Albrecht Wellmer (1933–2018), Philosoph Rolf Wiggershaus (* 1944), Publizist Gisela von Wysocki (* 1940), Schriftstellerin |
著名な学生 レギーナ・ベッカー=シュミット(1937年 - 2024年)、社会学者 ハイデ・ベルント(1938年 - 2003年)、都市社会学者 シルヴィア・ボヴェンシェン(1946年 - 2017年)、作家 バゾン・ブロック(1936年生まれ)、美学教授 ペーター・ブルタウプ(1934年~2004年)、哲学者、化学者 デトレフ・クラウスゼン(1948年~)、社会学者 ミヒャエラ・フォン・フライホールド(1940年~2010年)、開発社会学者 ペーター・フース(1930年~2019年)、社会哲学者 ペーター・ゴルゼン(1933年~2017年)、美術史家 カール・ハインツ・ハーグ(1924年 - 2011年)、哲学者 ユルゲン・ハーバーマス(1929年生まれ)、政治学者、社会哲学者 ペーター・フォン・ハーゼルベルク(1908年 - 1994年)、ジャーナリスト ハンス・イムホフ(1939年生まれ)、パフォーマンス・アーティスト、作家 ヨアヒム・カイザー(1928年 - 2017年)、音楽・文芸評論家 アレクサンダー・クルーゲ(1932年生まれ)、弁護士、作家、映画監督 ハンス=ユルゲン・クラール(1943年~1970年)、1968年運動とSDSの学生活動家 エリザベス・レンク(1937年~2022年)、社会学者 クルト・レンク(1929年~2022年)、政治学者 ルドルフ・ツア・リッペ(1937年 - 2019年)、哲学者 ヴェルナー・マンゴルト(1927年 - 2020年)、社会学者 オットヴィン・マッシン(1934年 - 2019年)、政治学者、社会学者 ギュンター・メンシンク(1942年生まれ)、哲学者 ハインツ・クラウス・メッツガー(1932年 - 2009年)、音楽理論家 カール・マルクス・ミヒャエル(1929年 - 2000年)、作家、広報担当者 イヴァン・ナーゲル(1931年 - 2012年)、演劇学者、広報担当者、演劇監督 オスカー・ネグト(1934年 - 2024年)、社会哲学者 ディーター・プロコップ(1941年生まれ)、社会学者 ウルリケ・プロコップ(1945年生まれ)、社会科学者 ヘルムート・ライヒェルト(1939年生)、社会学者 アルフレッド・シュミット(1931-2012)、哲学者 ヘルマン・シュヴェッペンハウザー(1928-2015)、哲学者、広報担当者 モニカ・ザイファート(1932-2002)、社会学者、教育学者 バサム・ティービ(1944年生まれ)、政治学者 ロルフ・ティーデマン(1932年~2018年)、哲学者、文献学者 アルブレヒト・ヴェルマー(1933年~2018年)、哲学者 ロルフ・ヴィッゲルスハウス(1944年生まれ)、広報担当者 ギゼラ・フォン・ヴィソツキ(1940年生まれ)、作家 |
| Schriften Buchausgaben zu Lebzeiten: Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. Tübingen 1933. Willi Reich (Hrsg.): Alban Berg. Mit Bergs eigenen Schriften und Beiträgen von Theodor Wiesengrund-Adorno und Ernst Krenek. Wien, Leipzig, Zürich 1937. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Amsterdam 1947 Philosophie der neuen Musik. Tübingen 1949. Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson, R. Nevitt Sanford: The Authoritarian Personality. New York 1950, in Deutschland posthum erschienen unter dem Titel Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt am Main 1973 (vgl. auch Autoritäre Persönlichkeit) Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Berlin, Frankfurt am Main 1951 Versuch über Wagner. Berlin, Frankfurt am Main 1952. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt am Main 1955. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien. Stuttgart 1956. Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt. Göttingen 1956. Aspekte der Hegelschen Philosophie. Berlin, Frankfurt am Main. 1957. Noten zur Literatur I. Berlin, Frankfurt am Main 1958. Klangfiguren. Musikalische Schriften I. Berlin, Frankfurt am Main 1959. Mahler. Eine musikalische Physiognomik. Frankfurt am Main 1960. Noten zur Literatur II. Frankfurt am Main 1961. Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen. Frankfurt am Main 1962. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Sociologica II. Reden und Vorträge. Frankfurt am Main 1962. Drei Studien zu Hegel. Frankfurt am Main 1963. Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt am Main 1963. Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur musikalischen Praxis. Frankfurt am Main 1963. Quasi una fantasia. Musikalische Schriften II. Frankfurt am Main 1963. Moments musicaux. Neu gedruckte Aufsätze 1928–1962. Frankfurt am Main 1964. Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie. Frankfurt am Main 1964 Noten zur Literatur III. Frankfurt am Main 1965. Negative Dialektik. Frankfurt am Main 1966 Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. Frankfurt am Main 1967. Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs. Wien 1968. Impromptus. Zweite Folge neu gedruckter musikalischer Aufsätze. Frankfurt am Main 1968. Sechs kurze Orchesterstücke op. 4 <1929>. Milano 1968. Theodor W. Adorno, Hanns Eisler: Komposition für den Film. München 1969. Stichworte. Kritische Modelle 2. Frankfurt am Main 1969. Sammelausgaben: Gesammelte Schriften. Hrsg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz. Bde. 1–20 (in 23 Bdn. geb.). 1. Auflage. Frankfurt am Main 1970–1980. – [Rev. Taschenbuch-Ausg.] Frankfurt am Main 1997. – Lizenzausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt 1998. – [Revidierte und erweiterte elektronische Ausg. auf CD-ROM:] Digitale Bibliothek Band 97, Directmedia Publishing Berlin 2003, ISBN 3-89853-497-9. Nachgelassene Schriften. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main 1993 ff. [Bisher erschienen: 12 Bde.] Abteilung I: Fragment gebliebene Schriften: Band 1: Beethoven. Philosophie der Musik Band 2: Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion Band 3: Current of Music. Elements of a Radio Theory Abteilung IV: Vorlesungen: Band I: Erkenntnistheorie (1957/58) Band 4: Kants »Kritik der reinen Vernunft« (1959) Band 6: Philosophie und Soziologie (1960) Band 9: Philosophische Terminologie Band 10: Probleme der Moralphilosophie (1963) Band 11: Fragen der Dialektik (1963/64) Band 12: Philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft (1964) Band 15: Einleitung in die Soziologie (1968) Band 17: Kranichsteiner Vorlesungen Eine Auswahl. Hrsg. von Rolf Tiedemann. Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main 1971. – Lizenzausg. des Deutschen Bücherbundes, Stuttgart 1971. Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft. Hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1971. Philosophie und Gesellschaft. Fünf Essays. Auswahl und Nachwort Rolf Tiedemann. Stuttgart 1984. „Ob nach Auschwitz noch sich leben lasse.“ Ein philosophisches Lesebuch. Hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1997. Aufarbeitung der Vergangenheit. Reden und Gespräche. Auswahl und Begleittext von Rolf Tiedemann. München 1999, DerHörVerlag. (AUDIO BOOKS. Stimmen der Philosophie.) 5 CD: ISBN 3-89584-730-5; 2 MC: ISBN 3-89584-630-9. Kompositionen. Hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn. 2 Bde., München 1980 Kompositionen. Band 3: Kompositionen aus dem Nachlass. Hrsg. von Maria Luisa Lopez-Vito und Ulrich Krämer. München 2007 Klavierstücke. Hrsg. von Maria Luisa Lopez-Vito, Nachwort von Rolf Tiedemann. München 2001 Wichtige postume Einzelausgaben: Ästhetische Theorie. Hrsg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1970; 13. Auflage. 1995. Über Walter Benjamin. Hrsg. und mit Anmerkungen versehen von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1970. – [Revidierte und erweiterte Ausg.:] Frankfurt am Main 1990. Noten zur Literatur IV. Hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1974. Der Schatz des Indianer-Joe. Singspiel nach Mark Twain. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1979. Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte. Hrsg. von Rolf Tiedemann. (Nachgelassene Schriften. Hrsg. vom Theodor W. Adorno Archiv. Abt. I, Band 1.) Frankfurt am Main 1993. – 2. Auflage. 1994. – [Taschenbuch-Ausg.] Frankfurt am Main 2004. Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Aufzeichnungen, ein Entwurf und zwei Schemata. Hrsg. von Henri Lonitz. Frankfurt am Main 2001. (Nachgel. Schr., Abt. I, Band 2.) Ästhetik (1958/59). Hrsg. von Eberhard Ortland. Frankfurt am Main 2009. (Nachgel. Schr., Abt. IV, Band 3.) – [Taschenbuch-Ausg.] Berlin 2017. Ontologie und Dialektik <1960/61>. Hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 2002. (Nachgel. Schr., Abt. IV, Band 7.) Probleme der Moralphilosophie <1963>. Hrsg. von Thomas Schröder. Frankfurt am Main 1996. (Nachgel. Schr., Abt. IV, Band 10.) Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit <1964/65>. Hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 2001. (Nachgel. Schr., Abt. IV, Band 13.) Metaphysik. Begriff und Probleme <1965>. Hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1998. (Nachgel. Schr., Abt. IV, Band 14.) Vorlesung über Negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung 1965/66. Hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 2003. (Nachgel. Schr., Abt. IV, Band 16.) Traumprotokolle. Hrsg. von Christoph Gödde und Henri Lonitz. Nachwort von Jan Philipp Reemtsma. Frankfurt am Main 2005.[287] Hörspielbearbeitung Current of Music. Elements of a Radio Theory, hrsg. von Robert Hullot-Kentor. Frankfurt am Main 2006. Komposition für den Film. Text der Edition in Band 15 der Gesammelten Schriften, durchgesehen, korrigiert und ergänzt von Johannes C. Gall. Mit einem Nachwort von Johannes C. Gall und einer DVD „Hanns Eislers Rockefeller-Filmmusik-Projekt“, im Auftrag der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft hrsg. von Johannes C. Gall. Frankfurt am Main 2006. Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Ein Vortrag. Berlin 2019, ISBN 978-3-518-58737-9. Bemerkungen zu ›The Authoritarian Personality‹ und weitere Texte., hrsg. v. Eva-Maria Ziege, Suhrkamp, Berlin 2019, ISBN 978-3-518-29900-5. Vorträge 1949–1968. Hrsg. von Michael Schwarz. Suhrkamp, Berlin 2019. Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Ein Vortrag. Mit einem Nachwort von Jan Philipp Reemtsma, Suhrkamp, Berlin 2024, ISBN 978-3-518-58823-9. |
著作 生前出版された書籍: キルケゴール著『美学的構成』。テュービンゲン、1933年。 ウィリー・ライヒ編『アルバン・ベルク。ベルク自身の著作と、テオドール・ヴィーゼングラント・アドルノ、エルンスト・クレーネックの寄稿。ウィーン、ライプツィヒ、チューリッヒ、1937年。 ホルクハイマー、アドルノ著『啓蒙の弁証法。哲学断章。アムステルダム、1947年 新音楽の哲学。テュービンゲン、1949年。 テオドール・W・アドルノ、エルゼ・フレンケル=ブルンスウィック、ダニエル・J・レヴィンソン、R・ネヴィット・サンフォード著『権威盲従的な性格』。 ニューヨーク、1950年。ドイツでは『権威盲従的な性格に関する研究』というタイトルで死後に出版された。フランクフルト・アム・マイン、1973年 (『権威盲従的な性格』も参照)。 『ミニマ・モラリア――損なわれた生命についての省察』。ベルリン、フランクフルト・アム・マイン 1951年 『ワーグナー論』。ベルリン、フランクフルト・アム・マイン 1952年 『プリズム――文化批評と社会』。ベルリン、フランクフルト・アム・マイン 1955年 『認識論のメタ批判について――フッサールと現象学のアンチノミーに関する研究』。シュトゥットガルト 1956年 Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt. Göttingen 1956. ヘーゲル哲学の諸相。ベルリン、フランクフルト・アム・マイン。1957年。 文学ノート I。ベルリン、フランクフルト・アム・マイン。1958年。 音型。音楽論文 I。ベルリン、フランクフルト・アム・マイン。1959年。 マーラー:音楽人相学。フランクフルト・アム・マイン、1960年。 文学ノートII。フランクフルト・アム・マイン、1961年。 音楽社会学入門。12の理論的講義。フランクフルト・アム・マイン、1962年。 ホルクハイマー、アドルノ:Sociologica II。スピーチと講義。フランクフルト・アム・マイン、1962年。 ヘーゲルに関する3つの研究。フランクフルト・アム・マイン 1963年。 介入。9つの批判的モデル。フランクフルト・アム・マイン 1963年。 忠実な伴奏者。音楽的実践に関するエッセイ。フランクフルト・アム・マイン 1963年。 擬似幻想曲。音楽的著作第2集。フランクフルト・アム・マイン 1963年。 音楽の瞬間。新たに印刷されたエッセイ 1928-1962。フランクフルト・アム・マイン 1964年。 現実の専門用語。ドイツのイデオロギーについて。フランクフルト・アム・マイン 1964年 文献に関する注釈 III。フランクフルト・アム・マイン 1965年。 否定的弁証法。フランクフルト・アム・マイン 1966年 模範なし。小美学。フランクフルト・アム・マイン 1967年。 Berg. The Master of the Smallest Transition. Vienna 1968. Impromptus. Second Series of Newly Printed Musical Essays. Frankfurt am Main 1968. Six Short Orchestral Pieces, op. 4 <1929>. Milan 1968. Theodor W. Adorno, Hanns Eisler: Composition for the Film. Munich 1969. キーワード。批判モデル2。フランクフルト・アム・マイン 1969年。 全集: Gesammelte Schriften(全集)。編集:ロルフ・ティーデマン、グレテル・アドルノ、スーザン・バック=モース、クラウス・シュルツの協力。全23巻中第1巻 ~第20巻。初版。フランクフルト・アム・マイン 1970年~1980年。 – [改訂版ペーパーバック版] フランクフルト・アム・マイン 1997年。 – ダルムシュタットのWissenschaftliche Buchgesellschaftのライセンス版 1998年。 – [CD-ROM版の改訂・拡張版:] Digitale Bibliothek Band 97, Directmedia Publishing Berlin 2003, ISBN 3-89853-497-9. 死後出版された著作。Suhrkamp Verlag。フランクフルト・アム・マイン 1993年以降刊行。[現在までに刊行された巻:12巻] 第I部:未完の著作: 第1巻:ベートーヴェン。音楽哲学 第2巻:音楽再生理論に向けて 第3巻:音楽の流れ。ラジオ理論の要素 第IV部:講義: 第1巻:認識論(1957/58年 第4巻:カント『純粋理性批判』(1959年 第6巻:哲学と社会学(1960年 第9巻:哲学用語 第10巻:道徳哲学の問題(1963年 第11巻:弁証法の諸問題(1963/64年) 第12巻:社会理論の哲学的諸要素(1964年) 第15巻:社会学入門(1968年) 第17巻:クラーニヒシュタイン講演 Rolf Tiedemann編。Büchergilde Gutenberg、フランクフルト・アム・マイン、1971年。ドイツ・ブック・クラブのライセンス版、シュトゥットガルト、1971年。 批評。社会に関する小論文。Rolf Tiedemann編。フランクフルト・アム・マイン、1971年。 哲学と社会。5つのエッセイ。Rolf Tiedemann選集および後書き。シュトゥットガルト、1984年。 「アウシュビッツ以後、それでもなお生きることを自分に許すことができるのか」 哲学的リーダー。 ロルフ・ティードマン編。 フランクフルト・アム・マイン 1997年。 過去をくまなく捜索する。 演説と対話。 ロルフ・ティードマンによるテキストの抜粋と解説。ミュンヘン 1999, DerHörVerlag. (AUDIO BOOKS. Voices of Philosophy.) 5 CD: ISBN 3-89584-730-5; 2 MC: ISBN 3-89584-630-9. Compositions. Ed. by Heinz-Klaus Metzger and Rainer Riehn. 2 vols., Munich 1980 作品集。第3巻:遺作集。マリア・ルイサ・ロペス=ヴィトとウルリッヒ・クレーマー編。ミュンヘン2007年 ピアノ曲。マリア・ルイサ・ロペス=ヴィト編、ロルフ・ティーデマンによる後書き。ミュンヘン2001年 重要な死後刊行の個別版: 美学理論。グレテル・アドルノとロルフ・ティードマン編。フランクフルト・アム・マイン1970年、第13版。1995年。 ヴァルター・ベンヤミンについて。ロルフ・ティードマン編、注釈付き。フランクフルト・アム・マイン1970年。[改訂・増補版:]フランクフルト・アム・マイン1990年。 文学に関するノート IV。Rolf Tiedemann 編。フランクフルト・アム・マイン 1974年。 インディアン・ジョーの財宝。マーク・トウェインによるジングシュピール。Rolf Tiedemann 編、エピローグ付。フランクフルト・アム・マイン 1979年。 ベートーヴェン。音楽哲学。断章とテキスト。Rolf Tiedemann 編。(遺稿集。編:テオドール・W・アドルノ・アーカイブ。第1巻)フランクフルト・アム・マイン 1993年。第2版。1994年。[ペーパーバック版] フランクフルト・アム・マイン 2004年。 音楽再生理論について。ノート、草案、2つの図解。編者:Henri Lonitz。フランクフルト・アム・マイン 2001年。(遺稿集、第1部、第2巻) 美学(1958/59年)。編者:Eberhard Ortland。フランクフルト・アム・マイン 2009年。(遺稿集、第4部、第3巻)-[ペーパーバック版]ベルリン 2017年。 『存在論と弁証法』<1960/61>。ロルフ・ティーデマン編。フランクフルト・アム・マイン 2002年。(遺稿集、第4部、第7巻) 『道徳哲学の問題』<1963>。トーマス・シュレーダー編。フランクフルト・アム・マイン 1996年。(遺稿集、第4部、第10巻) 歴史と自由の理論について <1964/65>。 ロルフ・ティードマン編。フランクフルト・アム・マイン 2001年。(遺稿集、第4部、第13巻) 形而上学。概念と問題 <1965>。編者:ロルフ・ティードマン。フランクフルト・アム・マイン、1998年。(遺稿集、第IV部、第14巻) 否定弁証法講義。1965/66年の講義の断片。編者:ロルフ・ティードマン。フランクフルト・アム・マイン、2003年。(遺稿集、第IV部、第16巻) 夢の記録。編者:クリストフ・ゲッデとアンリ・ロニッツ。後書き:ヤン・フィリップ・リーメンシュマ。フランクフルト・アム・マイン 2005年。[287] ラジオ劇の翻案 音楽の流れ。ラジオ理論の要素、編者:ロバート・ユロ・ケントル。フランクフルト・アム・マイン 2006年。 映画のための作曲。Gesammelte Schriften 第15巻のテキスト、ヨハネス・C・ガルによる修正、訂正、補足。ヨハネス・C・ガルによる後書きと、国際ハンス・アイスラー協会を代表してヨハネス・ C・ガルが編集したDVD「ハンス・アイスラーのロックフェラー映画音楽プロジェクト」付き。フランクフルト・アム・マイン 2006年。 新右翼急進主義の諸相。講演。ベルリン 2019年、ISBN 978-3-518-58737-9。 『権威盲従的な性格』についての覚書とその他のテキスト、エヴァ=マリア・ツィーゲ編、シュルカンプ社、ベルリン 2019年、ISBN 978-3-518-29900-5。 講演 1949–1968。編集:ミヒャエル・シュヴァルツ。シュルカンプ、ベルリン 2019年。 反ユダヤ主義との闘いについて。講演。ヤン・フィリップ・リーメンシュマによる後書き付き。シュルカンプ、ベルリン 2024年、ISBN 978-3-518-58823-9。 |
| Briefwechsel Theodor W. Adorno – Walter Benjamin: Briefwechsel 1928–1940. Suhrkamp, Frankfurt am Main Theodor W. Adorno – Alban Berg: Briefwechsel 1925–1935. Suhrkamp, Frankfurt am Main Theodor W. Adorno – Elias Canetti: "Ich kann auch den kleinsten Weg nicht anders als allein gehen". Briefwechsel. Mit einer Vorbemerkung von Sven Hanuschek. In: Sinn und Form 6/2023, S. 790–810 Theodor W. Adorno – Max Horkheimer: Briefwechsel 1927–1937. Suhrkamp, Frankfurt am Main Theodor W. Adorno – Max Horkheimer: Briefwechsel 1938–1944. Suhrkamp, Frankfurt am Main Theodor W. Adorno – Max Horkheimer: Briefwechsel 1945–1949. Suhrkamp, Frankfurt am Main Theodor W. Adorno – Max Horkheimer: Briefwechsel 1950–1969. Suhrkamp, Frankfurt am Main Theodor W. Adorno – Rudolf Kolisch: Briefwechsel 1926–1969, Suhrkamp, Berlin Theodor W. Adorno – Siegfried Kracauer: Briefwechsel 1923–1966. Suhrkamp, Frankfurt am Main. Theodor W. Adorno – Ernst Krenek: Briefwechsel 1929–1964. Suhrkamp, Berlin 2020 (zuerst Frankfurt am Main 1974). Theodor W. Adorno – Thomas Mann: Briefwechsel 1943–1955. Suhrkamp, Frankfurt am Main Theodor W. Adorno – Heinz-Klaus Metzger: Briefwechsel 1954–1967. Suhrkamp, Frankfurt am Main. Asaf Angermann (Hrsg.): Theodor W. Adorno – Gershom Scholem: Der liebe Gott wohnt im Detail. Briefwechsel 1939–1969. Suhrkamp, Berlin 2015, ISBN 978-3-518-58617-4. Wolfgang Schopf (Hrsg.): „So müßte ich ein Engel und kein Autor sein“. – Adorno und seine Frankfurter Verleger. Der Briefwechsel mit Peter Suhrkamp und Siegfried Unseld. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003 Theodor W. Adorno – Lotte Tobisch: Der private Briefwechsel (1962–1969). Herausgegeben von Bernhard Kraller und Heinz Steinert. Droschl, Graz 2003 Theodor W. Adorno – Paul Celan: Briefwechsel 1960–1968. Hrsg. v. Joachim Seng. In: Frankfurter Adorno Blätter VIII. edition text + kritik 2003, S. 177–202. Theodor W. Adorno und Elisabeth Lenk: Briefwechsel 1962–1969. Herausgegeben von Elisabeth Lenk. edition text + kritik, München 2001 Theodor W. Adorno – Harald Kaufmann: Briefwechsel 1967–1969. In: Harald Kaufmann: Von innen und außen. Schriften über Musik, Musikleben und Ästhetik Hg. v. Werner Grünzweig und Gottfried Krieger. Wolke, Hofheim 1993, S. 261–300. Theodor W. Adorno und Alfred Sohn-Rethel: Briefwechsel 1936–1969. Herausgegeben von Christoph Gödde. edition text + kritik, München 1991. Theodor W. Adorno und Ulrich Sonnemann: Briefwechsel 1957–1969. Herausgegeben und kommentiert von Martin Mettin und Tobias Heinze. In: Zeitschrift für kritische Theorie. Band 25, Nr. 48/49, 2019, S. 167–222. Theodor W. Adorno: Briefe an die Eltern. 1939–1951. Herausgegeben von Christoph Gödde und Henri Lonitz. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003. Günther Anders: Briefwechsel mit Theodor W. Adorno. In: Günther Anders: Gut, dass wir einmal die hot potatos ausgraben. Briefwechsel mit Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und Helmuth Plessner. Beck, München 2022, S. 45-95 und 264-292. Theodor W. Adorno und Ludwig von Friedeburg: Briefwechsel 1950-1969. Und weitere Materialien. Im Auftrag des Instituts für Sozialforschung herausgegeben von Dirk Braunstein und Maischa Gelhard, Suhrkamp, Berlin 2024. |
書簡 テオドール・W・アドルノ―ヴァルター・ベンヤミン:書簡 1928-1940年。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン テオドール・W・アドルノ―アルバン・ベルク:書簡 1925-1935年。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン テオドール・W・アドルノ -エリアス・カネッティ:「私はどんなに小さな道でも一人で歩くのとは違った歩き方はできない」。書簡。スヴェン・ハヌシェクによる序文付。『意味と形式』6/2023、790~810ページ テオドール・W・アドルノ - マックス・ホルクハイマー:書簡 1927~1937年。フランクフルト・アム・マイン、スールカンプ テオドール・W・アドルノ - マックス・ホルクハイマー: 書簡集 1938–1944. Suhrkamp, Frankfurt am Main テオドール・W・アドルノ - マックス・ホルクハイマー: 書簡集 1945–1949. Suhrkamp, Frankfurt am Main テオドール・W・アドルノ - マックス・ホルクハイマー: 書簡集 1950–1969. Suhrkamp, Frankfurt am Main テオドール・W・アドルノ-ルドルフ・コリッシュ:書簡集 1926-1969、Suhrkamp、ベルリン テオドール・W・アドルノ-ジークフリート・クラカウアー:書簡集 1923-1966。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン。 テオドール・W・アドルノ - エルンスト・クレーン:書簡集 1929-1964。Suhrkamp、ベルリン 2020(初版は1974年にフランクフルト・アム・マインで出版)。 テオドール・W・アドルノ - トーマス・マン:書簡集 1943-1955。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン テオドール・W・アドルノ、ハインツ・クラウス・メッツガー著『書簡集 1954-1967』。フランクフルト・アム・マイン、Suhrkamp アサフ・アンゲルマン(編):テオドール・W・アドルノ-ゲルショム・ショーレム:神は細部に宿る。1939年から1969年の書簡。Suhrkamp, Berlin 2015, ISBN 978-3-518-58617-4. ヴォルフガング・ショフ(編):「天使でなければ作家でもない」。アドルノとフランクフルトの出版社。ペーター・ズーアカンプとジークフリート・ウンゼルドとの往復書簡。ズーアカンプ、フランクフルト・アム・マイン 2003年 テオドール・W・アドルノ-ロッテ・トビッシュ:私的な書簡のやりとり(1962-1969)。編者:ベルンハルト・クララー、ハインツ・シュタインアート。ドロシュル、グラーツ 2003 テオドール・W・アドルノ-パウル・ツェラン:書簡のやりとり 1960-1968。編者:ヨアヒム・ゼング。『フランクフルター・アドルノ・ブラーテン』第8号。edition text + kritik 2003年、177~202ページ。 テオドール・W・アドルノとエリザベート・レンク:書簡 1962~1969年。エリザベート・レンク編。edition text + kritik、ミュンヘン2001年 テオドール・W・アドルノ - ハラルド・カウフマン:書簡 1967-1969。ハラルド・カウフマン著『内側から、外側から』所収。音楽、音楽生活、美学に関する論文。ヴェルナー・グリュンツヴァイク、ゴットフ リート・クリーガー編。Wolke、ホーフハイム、1993年、261-300ページ。 テオドール・W・アドルノとアルフレッド・ゾーン=レーテル:1936年から1969年の書簡。編集:クリストフ・ゲッデ。edition text + kritik、ミュンヘン、1991年。 テオドール・W・アドルノとウルリッヒ・ゾネマン:1957年から1969年の書簡。編集および注釈:マーティン・メッティンとトビアス・ハインツェ。雑 誌『批判理論』第25巻第48/49号、2019年、167-222ページ。第25巻、第48/49号、2019年、167~222ページ。 テオドール・W・アドルノ:両親への手紙。1939~1951年。編集:クリストフ・ゲッデ、アンリ・ロニッツ。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン2003年。 ギュンター・アンダース著『テオドール・W・アドルノとの往復書簡』。ギュンター・アンダース著『ホットポテトを掘り起こしてよかった』所収。テオドー ル・W・アドルノ、エルンスト・ブロッホ、ホルクハイマー、ヘルベルト・マルクーゼ、ヘルムート・プレッツナーとの往復書簡。ベック社、ミュンヘン、 2022年、45-95ページおよび264-292ページ。 テオドール・W・アドルノとルートヴィヒ・フォン・フリーデブルク著『書簡集 1950-1969』。その他資料。ベルリン、2024年、シュルカンプ社、社会研究研究所を代表してディルク・ブラウネンシュタインとメイシャ・ゲルハルト編。 |
| Kompositionen Vier Gedichte von Stefan George für Singstimme und Klavier, op. 1 (1925–1928) Zwei Stücke für Streichquartett, op. 2 (1925–1926) Vier Lieder für eine mittlere Stimme und Klavier, op. 3 (1928) Sechs kurze Orchesterstücke, op. 4 (1929) Klage. Sechs Lieder für Singstimme und Klavier, op. 5 (1938–1941) Sechs Bagatellen für Singstimme und Klavier, op. 6 (1923–1942) Vier Lieder nach Gedichten von Stefan George für Singstimme und Klavier, op. 7 (1944) Drei Gedichte von Theodor Däubler für vierstimmigen Frauenchor a cappella, op. 8 (1923–1945) Zwei Propagandagedichte für Singstimme und Klavier, o. O. (1943) Sept chansons populaires francaises, arrangées pour une voix et piano, o. O. (1925–1939) Zwei Lieder mit Orchester aus dem geplanten Singspiel Der Schatz des Indianer-Joe nach Mark Twain, o. O. (1932/33) Kinderjahr. Sechs Stücke aus op. 68 von Robert Schumann, für kleines Orchester gesetzt, o. O. (1941) Kompositionen aus dem Nachlaß (Klavierstücke, Klavierlieder, Streichquartette, Streichtrios u. a.), vgl. Theodor W. Adorno: Kompositionen Band 3. hg. von Maria Luisa Lopez-Vito und Ulrich Krämer, München 2007. |
作曲 ステファン・ゲオルゲによる4つの詩、声楽とピアノのための作品1(1925年-1928年) 弦楽四重奏のための2つの小品、作品2(1925年-1926年) 中声域の声楽とピアノのための4つの歌曲、作品3(1928年) 6つの短い管弦楽曲、作品4(1929年) 嘆き。声楽とピアノのための6つの歌曲、作品5(1938年~1941年) 声楽とピアノのための6つのバガテル、作品6(1923年~1942年) シュテファン・ゲオルゲの詩による4つの歌曲、作品7(1944年) テオドール・デューブルの詩による3つの作品、女声4部合唱アカペラ、作品8(1923年~1945年) 日付不詳の2つのプロパガンダ詩、声楽とピアノのための(1943年) 日付不詳の7つのフランス民謡、声楽とピアノのための編曲(1925年~1939年) マーク・トウェイン原作のミュージカル・コメディ『インディアン・ジョーの秘宝』からオーケストラ伴奏付きの2曲、作曲地不明(1932/33年 ロベルト・シューマン作曲作品68の6曲、小編成オーケストラ用編曲、作曲地不明(1941年 遺作からの作品(ピアノ曲、ピアノ曲、弦楽四重奏曲、弦楽三重奏曲など)については、テオドール・W・アドルノ著『作曲作品集』第3巻を参照のこと。マリア・ルイサ・ロペス=ヴィトとウルリッヒ・クレーマー編、ミュンヘン2007年。 |
| Literatur Philosophiebibliographie: Theodor W. Adorno – Zusätzliche Literaturhinweise zum Thema Einführungen Deborah Cook (Hrsg.): Theodor Adorno: Key Concepts. Acumen, Stocksfield 2008, ISBN 978-1-84465-120-7. Richard Klein, Johann Kreuzer, Stefan Müller-Doohm (Hrsg.): Adorno-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 2., erweiterte und aktualisierte Auflage. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-476-02626-2 (zuerst 2011). Stefan Müller-Doohm: Die Soziologie Theodor W. Adornos. Eine Einführung. Campus, Frankfurt am Main 1996. Hartmut Scheible: Theodor W. Adorno mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek 1989. Gerhard Schweppenhäuser: Theodor W. Adorno zur Einführung. 7. ergänzte Auflage. Junius, Hamburg 2019, ISBN 978-3-88506-671-2. Tilo Wesche: Adorno. Eine Einführung. Reclam, Ditzingen 2018. Rolf Wiggershaus: Theodor W. Adorno. C. H. Beck, München 1987. Über Theodor W. Adorno. Mit Beiträgen von Kurt Oppens, Hans Kudszus, Jürgen Habermas, Bernard Willms, Hermann Schweppenhäuser und Ulrich Sonnemann. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1968. Biographien Detlev Claussen: Theodor W. Adorno. Ein letztes Genie. S. Fischer, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-10-010813-2. Lorenz Jäger: Adorno. Eine politische Biographie. 2. Auflage. DVA, München 2003, ISBN 3-421-05493-2. Stefan Müller-Doohm: Adorno. Eine Biographie Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-58378-6. Biographische Orte Martin Mittelmeier: Adorno in Neapel. Wie sich eine Sehnsuchtslandschaft in Philosophie verwandelt. Siedler, München 2013. Claus Offe: Kulturindustrie und andere Ansichten des amerikanischen Jahrhunderts. In: Ders.: Selbstbetrachtung aus der Ferne: Tocqueville, Weber und Adorno in den Vereinigten Staaten. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, S. 91–120. Reinhard Pabst (Hrsg.): Theodor W. Adorno. Kindheit in Amorbach. Bilder und Erinnerungen. Insel, Frankfurt am Main 2003. Wolfram Schütte (Hrsg.): Adorno in Frankfurt. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003 Heinz Steinert: Adorno in Wien. Über die (Un-)Möglichkeit von Kunst, Kultur und Befreiung. Fischer, Frankfurt am Main 1989 Viktor Žmegač: Adorno und die Wiener Moderne der Jahrhundertwende. In: Axel Honneth / Albrecht Wellmer (Hrsg.): Die Frankfurter Schule und die Folgen. Referate eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung vom 10.–15. Dezember 1984 in Ludwigsburg. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1986, S. 321–338. Adorno Blätter Rolf Tiedemann (Hrsg.): Frankfurter Adorno Blätter. Band I–VIII. edition text + kritik, 2003, ISBN 3-88377-752-8. Adorno-Konferenzen Ludwig von Friedeburg, Jürgen Habermas (Hrsg.): Adorno-Konferenz 1983. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983. Michael Löbig, Gerhard Schweppenhäuser (Hrsg.): Hamburger Adorno-Symposion. Lüneburg 1984, ISBN 3-924245-01-0. Frithjof Hager, Hermann Pfütze (Hrsg.): Das unerhört Moderne. Berliner Adorno-Tagung. zu Klampen, Lüneburg 1990, ISBN 3-924245-17-7. Axel Honneth (Hrsg.): Dialektik der Freiheit. Frankfurter Adorno-Konferenz 2003. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005. Andreas Gruschka, Ulrich Oevermann (Hrsg.): Die Lebendigkeit der kritischen Gesellschaftstheorie. Dokumentation der Arbeitstagung aus Anlass des 100. Geburtstages von Theodor W. Adorno. Wetzlar 2004, ISBN 3-88178-324-5. Frankfurter Seminare Frankfurter Seminare. Gesammelte Sitzungsprotokolle 1949–1969, Band 1 bis 4, hrsg. v. Dirk Braunstein, De Gruyter, Berlin, Boston 2021. Weiterführende Studien Alex Demirovic: Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-518-29040-1. Wolfram Ette, Günter Figal, Richard Klein, Günter Peters (Hrsg.): Adorno im Widerstreit. Zur Präsenz seines Denkens. Alber, Freiburg/ München 2004. Hans-Joachim Hahn: Kritik und Idealisierung. Theodor W. Adornos Verhältnis zur deutschen Sprache. In: Zeithistorische Forschungen 20 (2023), S. 297–312. Gillian Rose: The Melancholy Science. An Introduction to the Thought of Theodor W. Adorno. Macmillan, London 1978, ISBN 0-333-23214-3. Hermann Schweppenhäuser (Hrsg.): Theodor W. Adorno zum Gedächtnis. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971. Rolf Tiedemann: Niemandsland. Studien mit und über Theodor W. Adorno. München 2007, ISBN 978-3-88377-872-3. Zeitschrift für Ideengeschichte: Adorno. Heft XIII/1 – Frühjahr 2019. Philosophie Dirk Auer, Lars Rensmann, Julia Schulze Wessel (Hrsg.): Arendt und Adorno. 2. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-29235-8. Jürgen Habermas: „Ich selber bin ja ein Stück Natur“ – Adorno über die Naturverflochtenheit der Vernunft. In: Jürgen Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-58448-0, S. 187–215. Fredric Jameson: Spätmarxismus. Adorno oder Die Beharrlichkeit der Dialektik. Argument Verlag, Berlin 1992, ISBN 3-88619-391-8. Manuel Knoll: Theodor W. Adorno. Ethik als erste Philosophie, Fink, München 2002, ISBN 978-3-7705-3665-8. Ulrich Müller: Theodor W. Adornos Negative Dialektik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 3-534-15626-9. Gerhard Schweppenhäuser: Ethik nach Auschwitz. Adornos negative Moralphilosophie. 2. überarbeitete Auflage. Springer VS, Würzburg 2016, ISBN 978-3-658-11770-2. Martin Seel: Adornos Philosophie der Kontemplation. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-518-29294-3. Anke Thyen: Negative Dialektik und Erfahrung. Zur Rationalität des Nichtidentischen bei Adorno. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-518-57977-0. Rolf Tiedemann: Mythos und Utopie. Aspekte der Adornoschen Philosophie. München 2009, ISBN 978-3-86916-013-9. Albrecht Wellmer: Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-518-28132-1. Philipp von Wussow: Logik der Deutung. Adorno und die Philosophie. Königshausen & Neumann, Würzburg 2007, ISBN 978-3-8260-3547-0. Soziologie / Gesellschaftskritik / Politische Ökonomie Frank Böckelmann: Über Marx und Adorno. Schwierigkeiten der spätmarxistischen Theorie. Zweite, vom Autor mit einem Vorwort versehene Ausgabe der Auflage Frankfurt 1971. ça ira, Freiburg 1998, ISBN 3-924627-53-3. Dirk Braunstein: Adornos Kritik der politischen Ökonomie. Transcript, Bielefeld 2011. Iring Fetscher, Alfred Schmidt (Hrsg.): Emanzipation als Versöhnung. Zu Adornos Kritik der „Warentausch“-Gesellschaft und Perspektiven der Transformation. Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-8015-0356-9. Gerhard Schweppenhäuser (Hrsg.): Soziologie im Spätkapitalismus. Zur Gesellschaftstheorie Theodor W. Adornos. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-12309-3. Jan Weyand: Adornos kritische Theorie des Subjekts. 2. Auflage. Zu Klampen, 2021 Psychologie / Psychoanalyse Wolfgang Bock: Dialektische Psychologie. Adornos Rezeption der Psychoanalyse. VS-Springer Verlag, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-15325-0. Christine Kirchhoff, Falko Schmieder (Hrsg.): Freud und Adorno. Zur Urgeschichte der Moderne. Kadmos, Berlin 2014. Pädagogik / Erziehungswissenschaft Alfred Schäfer: Theodor W. Adorno. Ein pädagogisches Porträt. 2. Auflage. Beltz, Weinheim 2017, ISBN 978-3-7799-3705-0. Ästhetische Theorie / Kunst- und Literatursoziologie Klaus Baum: Die Transzendierung des Mythos. Zur Philosophie und Ästhetik Schellings und Adornos. Würzburg 1988. Martin Endres, Axel Pichler, Claus Zittel (Hrsg.): Eros und Erkenntnis – 50 Jahre Adornos „Ästhetische Theorie“, Berlin: De Gruyter 2019. Anne Eusterschulte, Sebastian Tränkle (Hrsg.): Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Berlin, Boston: De Gruyter, 2021. doi:10.1515/9783110672190 Pola Groß: Adornos Lächeln. Das „Glück am Ästhetischen“ in seinen literatur- und kulturtheoretischen Essays, Berlin: De Gruyter 2020, ISBN 978-3-11-065153-9. Gerhard Kaiser: Theodor W. Adornos „Ästhetische Theorie“. In: Ders.: Benjamin. Adorno. Zwei Studien. Athenäum, Frankfurt am Main 1974. Burkhardt Lindner, W. Martin Lüdke (Hrsg.): Materialien zur ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos. Konstruktion der Moderne. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980. Walther Müller-Jentsch: Adorno und Andere. Soziologische Exkurse zu Kunst und Literatur. transcript, Bielefeld 2022, ISBN 978-3-8376-6391-4. Heinz Paetzold: Neomarxistische Ästhetik. Teil 2: Adorno, Marcuse. Schwann, Düsseldorf 1974, ISBN 3-590-15705-4. Ulrich Plass: Language and History in Theodor W. Adorno's Notes to Literature. Routledge, New York & London 2007. Andreas Pradler: Das monadische Kunstwerk. Adornos Monadenkonzeption und ihr ideengeschichtlicher Hintergrund (= Epistemata. Würzburger wissenschaftliche Schriften. Bd. 426). Königshausen und Neumann, Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2411-7. Marcus Quent, Eckardt Lindner (Hrsg.): Das Versprechen der Kunst. Aktuelle Zugänge zu Adornos ästhetischer Theorie. Turia + Kant, Wien/Berlin 2014, ISBN 978-3-85132-741-0. Birgit Recki: Aura und Autonomie. Zur Subjektivität der Kunst bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno. Würzburg 1988, ISBN 3-88479-361-6. Britta Scholze: Kunst als Kritik. Adornos Weg aus der Dialektik. Königshausen & Neumann, Würzburg 2000, ISBN 3-8260-1828-1. O. K. Werckmeister: Das Kunstwerk als Negation. Zur geschichtlichen Bestimmung der Kunsttheorie Theodor W. Adornos. In: Ders.: Ende der Ästhetik. Essays über Adorno, Bloch, das gelbe Unterseeboot und der eindimensionale Mensch. S. Fischer, Frankfurt am Main 1971, S. 7–32. Albrecht Wellmer: Über Negativität und Autonomie der Kunst. Die Aktualität von Adornos Ästhetik und blinde Flecken seiner Musiksoziologie. In: Axel Honneth (Hrsg.): Dialektik der Freiheit. Frankfurter Adorno-Konferenz 2005. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, S. 237–278. Musiktheorie / Musiksoziologie Ulrich J. Blomann: „Nicht darüber reden!“ Der Strawinsky-Teil in Theodor W. Adornos Philosophie der neuen Musik - Strategien des Kalten Krieges, in: Kultur und Musik nach 1945. Ästhetik im Zeichen des Kalten Krieges, Pfau: Saarbrücken 2015, S. 124–144. Richard Klein, Claus-Steffen Mahnkopf (Hrsg.): Mit den Ohren denken. Adornos Philosophie der Musik. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998. Matteo Nanni: Auschwitz – Adorno und Nono. Philosophische und musikanalytische Untersuchungen. Freiburg i.Br. 2004, ISBN 3-7930-9366-2. Ralph Paland: „… eine sehr große Konvergenz“? Theodor W. Adornos und György Ligetis Darmstädter Form-Diskurs. In: Christoph von Blumröder (Hrsg.): Kompositorische Stationen des 20. Jahrhunderts: Debussy, Webern, Messiaen, Boulez, Cage, Ligeti, Stockhausen, Höller, Bayle. (Signale aus Köln: Beiträge zur Musik der Zeit 7). Münster 2003, ISBN 3-8258-7212-2, S. 87–115. Michael Turnheim: Zerfetzen der Zeit: Adorno und Derrida über Jazz, in: Eva Laquièze-Waniek, Erik M. Vogt (Hrsg.): Derrida und Adorno. Zur Aktualität von Dekonstruktion und Frankfurter Schule. Turia + Kant, Wien, Berlin 2008, S. 232-252, ISBN 978-3-85132-497-6. Nikolaus Urbanek: Auf der Suche nach einer zeitgemäßen Musikästhetik. Adornos „Philosophie der Musik“ und die Beethoven-Fragmente. transcript, Bielefeld 2010, ISBN 978-3-8376-1320-9. Hans Wollschläger: Moments musicaux. Tage mit TWA. Göttingen 2005, ISBN 3-89244-878-7. Ferdinand Zehentreiter: Adorno. Spurlinien seines Denkens. Eine Einführung. Wolke, Hofheim am Taunus 2019, ISBN 978-3-95593-120-9. Kompositionen Gabriele Geml, Han-Gyeol Lie (Hrsg.): »Durchaus rhapsodisch«. Theodor Wiesengrund Adorno: Das kompositorische Werk. J. B. Metzler, Stuttgart 2017. Martin Hufner: Adorno und die Zwölftontechnik. ConBrio, Regensburg 1996, ISBN 3-930079-74-7. René Leibowitz: Der Komponist Theodor W. Adorno. In: Max Horkheimer (Hrsg.): Zeugnisse. Theodor W. Adorno zum sechzigsten Geburtstag. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1963, S. 355–359. Kulturindustrie Dieter Prokop: Mit Adorno gegen Adorno. Negative Dialektik der Kulturindustrie. VSA Verlag, Hamburg 2003. Dieter Prokop: Das Nichtidentische der Kulturindustrie. Neue kritische Kommunikationsforschung über das Kreative der Medien-Waren. Herbert von Halem Verlag, Köln 2005. Dieter Prokop: Ästhetik der Kulturindustrie. Tectum Verlag, Marburg 2009. Heinz Steinert: Die Entdeckung der Kulturindustrie. Verlag für Gesellschaftskritik, Wien. Heinz Steinert: Kulturindustrie. 3. Auflage. Westfälisches Dampfboot, Münster 2008. |
文献 哲学文献目録:テオドール・W・アドルノ - 導入に関する追加文献 デボラ・クック(編):テオドール・アドルノ:主要概念。 リチャード・クライン、ヨハン・クロイツァー、シュテファン・ミュラー=ドーム(編):アドルノ事典。第2版、増補改訂版。J. B. Metzler Verlag、シュトゥットガルト2019年、ISBN 978-3-476-02626-2(初版は2011年)。 シュテファン・ミュラー=ドーム著『テオドール・W・アドルノの社会学。入門編』キャンパス、フランクフルト・アム・マイン1996年。 ハルトムート・シャイベレ著『テオドール・W・アドルノ 自伝的証言と画像資料』ローベルト・アールトルフ、ラインベック 1989年 ゲルハルト・シュヴェッペンハーゼ著『テオドール・W・アドルノ入門』第7版。ユニウス、ハンブルク 2019年、ISBN 978-3-88506-671-2。 ティロ・ヴェーシェ著『アドルノ。入門編。レクラン、ディツィンゲン 2018年。 ロルフ・ヴィッゲルスハウス著:テオドール・W・アドルノ。C. H. ベック、ミュンヘン 1987年。 テオドール・W・アドルノについて。クルト・オッペンズ、ハンス・クドゥスス、ユルゲン・ハーバーマス、ベルンハルト・ヴィルムス、ヘルマン・シュヴェッペンハウザー、ウルリッヒ・ゾネマンによる寄稿。シュールカンプ、フランクフルト・アム・マイン 1968年。 伝記 デトレフ・クラウスゼン著『テオドール・W・アドルノ。最後の天才』S.フィッシャー、フランクフルト・アム・マイン 2003年、ISBN 3-10-010813-2。 ロレンツ・イェーガー著『アドルノ。政治的伝記』第2版。DVA、ミュンヘン 2003年、ISBN 3-421-05493-2。 シュテファン・ミュラー=ドーム著『アドルノ伝』。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン 2003年、ISBN 3-518-58378-6。 伝記に登場する場所 マルティン・ミッテルマイアー著『ナポリのアドルノ』。憧れの風景がどのようにして哲学へと変容するのか。Siedler、ミュンヘン 2013年。 クラウス・オフ著『文化産業とその他のアメリカン・センチュリーの視点』。同著『遠方からの自己反省:アメリカ合衆国におけるトクヴィル、ウェーバー、アドルノ』シュルカンプ社、フランクフルト・アム・マイン、2004年、91~120ページ。 ラインハルト・パプスト(編):テオドール・W・アドルノ。アモルバッハでの幼少期。イメージと記憶。インセル、フランクフルト・アム・マイン 2003年 ヴォルフラム・シュッテ(編):フランクフルトのアドルノ。スールカンプ、フランクフルト・アム・マイン 2003年 ハインツ・シュタインアート:ウィーンのアドルノ。芸術、文化、解放の(非)可能性について。フィッシャー、フランクフルト・アム・マイン 1989年 ヴィクトール・ズメガチ著『アドルノと世紀転換期ウィーンのモダニズム』。アレクサンダー・フォン・フンボルト財団が1984年12月10日から15日ま でルートヴィヒスブルクで開催したシンポジウムの論文集。編者:アクセル・ホネット、アルブレヒト・ヴェルマー。発行所:ヴァルター・デ・グルイター、ベ ルリン、ニューヨーク、1986年、321~338ページ。 アドルノ・ブロッター ロルフ・ティードマン(編):『フランクフルト・アドルノ・ブロッター』第1巻~第8巻。edition text + kritik、2003年、ISBN 3-88377-752-8。 アドルノ会議 ルートヴィヒ・フォン・フリーデブルク、ユルゲン・ハーバーマス(編):『アドルノ会議1983』。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン、1983年。 マイケル・レービッグ、ゲルハルト・シュヴェッペンハウザー(編):ハンブルク・アドルノ・シンポジウム。リューネブルク1984年、ISBN 3-924245-01-0。 フリチョフ・ハーガー、ヘルマン・プフッツェ(編):未踏のモダン。ベルリン・アドルノ会議。ツークランペン、リューネブルク1990年、ISBN 3-924245-17-7。 アクセル・ホネット(編):『自由の弁証法』。フランクフルト・アドルノ会議2003。フランクフルト・アム・マイン、スールカンプ、2005年。 アンドレアス・グルシュカ、ウルリッヒ・エヴァーマン(編):『批判的社会理論の活力』。テオドール・W・アドルノ生誕100周年記念ワークショップの記録。ヴェッツラー 2004年、ISBN 3-88178-324-5。 フランクフルト・ゼミナール フランクフルト・ゼミナール。会議録集 1949年~1969年、第1巻~第4巻、ディルク・ブラウネンシュタイン編、De Gruyter、ベルリン、ボストン 2021年。 その他の研究 アレックス・デミロヴィッチ著『非順応的知識人。批判理論のフランクフルト学派への展開』シュールカンプ社、フランクフルト・アム・マイン、1999年、ISBN 3-518-29040-1。 ヴォルフラム・エッテ、ギュンター・フィガル、リヒャルト・クライン、ギュンター・ペータース編著『葛藤するアドルノ。その思想の存在について』アルベル社、フライブルク/ミュンヘン、2004年。 ハンス=ヨアヒム・ハーン著『批判と理想化。テオドール・W・アドルノのドイツ語観』『時代史研究』第20号(2023年)、297~312ページ。 ジリアン・ローズ著『憂鬱な科学。テオドール・W・アドルノの思想入門』マクミラン社、ロンドン、1978年、ISBN 0-333-23214-3。 ヘルマン・シュヴェッペンハーゼ(編):テオドール・W・アドルノ追悼。フランクフルト・アム・マイン、スールカンプ、1971年。 ロルフ・ティードマン:ニーマンズランド。テオドール・W・アドルノについての研究。ミュンヘン、2007年、ISBN 978-3-88377-872-3。 『思想史ジャーナル』:アドルノ。第13巻第1号、2019年春号。 哲学 ディルク・アウアー、ラース・レンスマン、ユリア・シュルツェ・ヴェッセル(編):『アーレントとアドルノ』第2版。シュルカンプ、フランクフルト・アム・マイン2003年、ISBN 3-518-29235-8。 ユルゲン・ハーバーマス著「私自身も自然の一部である」-アドルノによる理性の自然との融合について。ユルゲン・ハーバーマス著『自然主義と宗教の間』所 収。Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-518-58448-0, pp. 187–215. フレドリック・ジェイムスン著『レイト・マルクス主義。アドルノまたは弁証法の持続』。Argument Verlag、ベルリン、1992年、ISBN 3-88619-391-8。 マニュエル・クノール著『テオドール・W・アドルノ。倫理は第一哲学である』。Fink、ミュンヘン、2002年、ISBN 978-3-7705-3665-8。 ウルリッヒ・ミュラー著:テオドール・W・アドルノの『否定的弁証法』。Wissenschaftliche Buchgesellschaft、ダルムシュタット 2006年、ISBN 3-534-15626-9。 ゲルハルト・シュヴェッペンハーゼ著:『アウシュヴィッツ後の倫理。アドルノの否定的道徳哲学』第2版。Springer VS、ヴュルツブルク 2016年、ISBN 978-3-658-11770-2。 マーティン・ゼール著『アドルノの観照哲学』。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン 2004年、ISBN 3-518-29294-3。 アンケ・ティーエン著『否定弁証法と経験。アドルノにおける非同一性の合理性について』。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン 1989年、ISBN 3-518-57977-0。 Rolf Tiedemann: Mythos und Utopie. Aspekte der Adornoschen Philosophie. ミュンヘン 2009, ISBN 978-3-86916-013-9. Albrecht Wellmer: Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-518-28132-1. フィリップ・フォン・ヴュッソウ著『解釈の論理。アドルノと哲学』Königshausen & Neumann, Würzburg 2007, ISBN 978-3-8260-3547-0. 社会学 / 社会批評 / 政治経済学 フランク・ベッケルマン著『マルクスとアドルノについて。後期マルクス主義理論の困難』。1971年版フランクフルトの著者による序文付き第2版。ça ira、フライブルク1998年、ISBN 3-924627-53-3。 ディルク・ブラウネンシュタイン著『アドルノの政治経済批判』トランスクリプト社、ビーレフェルト、2011年。 イルリング・フェトシャー、アルフレッド・シュミット編著『和解としての解放』アドルノの「商品交換」社会批判と変革への展望。フランクフルト・アム・マイン、2002年、ISBN 3-8015-0356-9。 ゲルハルト・シュヴェッペンハウザー(編):『後期資本主義における社会学。テオドール・W・アドルノの社会理論について』。科学書協会、ダルムシュタット 1995年、ISBN 3-534-12309-3。 ヤン・ヴァイアンド:『アドルノの批判理論』。第2版。ツークランペン、2021年 心理学/精神分析 ヴォルフガング・ボック:弁証法的心理学。アドルノの精神分析受容。VS-Springer Verlag、ヴィースバーデン 2018年、ISBN 978-3-658-15325-0。 クリスティン・キルヒホフ、ファルコ・シュミーダー(編):フロイトとアドルノ。近代の起源について。カドモス、ベルリン 2014年。 教育学/教育科学 アルフレッド・シェーファー:テオドール・W・アドルノ。教育学的肖像。第2版。ベルトツ、ヴァインハイム2017年、ISBN 978-3-7799-3705-0。 美学理論/芸術・文学社会学 クラウス・バウム著『神話の超越。シェリングとアドルノの哲学と美学について』ヴュルツブルク、1988年。 マーティン・エンドレス、アクセル・ピヒラー、クラウス・ジッテル編『エロスと認識――アドルノ『美学的理論』刊行50周年』ベルリン、デ・グルィター、2019年。 アンネ・オイスターシュルテ、セバスチャン・トレンクル(編):テオドール・W・アドルノ:美学理論、ベルリン、ボストン:デ・グルイター、2021年。doi:10.1515/9783110672190 ポラ・グロース:アドルノの微笑。「美学的幸福」:彼の文学および文化理論的エッセイにおけるアドルノの微笑、ベルリン:デ・グルイター、2020年、ISBN 978-3-11-065153-9。 ゲルハルト・カイザー著『テオドール・W・アドルノの「美学的理論」』。アテネウム、フランクフルト・アム・マイン、1974年。 ブルクハルト・リンドナー、W. マーティン・リュドケ(編):『テオドール・W.アドルノの美学理論に関する資料』。『モダニティの構築』。シュールカンプ、フランクフルト・アム・マイン 1980年。 ヴァルター・ミュラー=イェンチ:『アドルノとその他』。『芸術と文学への社会学的な遠足』。トランスクリプト、ビーレフェルト 2022年、ISBN 978-3-8376-6391-4。 ハインツ・ペッツォルト:ネオマルクス主義的美学。第2部:アドルノ、マルクーゼ。シュヴァン、デュッセルドルフ1974年、ISBN 3-590-15705-4。 ウルリッヒ・プラス:テオドール・W・アドルノの『文学ノート』における言語と歴史。ルートレッジ、ニューヨーク&ロンドン2007年。 アンドレアス・プラドラー著『単体としての芸術作品』。アドルノのモナド概念とその背景にある観念史(『エピステマタ。ヴュルツブルク学術論文集』第426巻)。ケーニヒスハウゼン・ウント・ノイマン、ヴュルツブルク、2003年、ISBN 3-8260-2411-7。 マーカス・クエント、エッカート・リンドナー(編):『芸術の約束』。アドルノの美学理論への最新の接近。トゥリア+カント、ウィーン/ベルリン 2014年、ISBN 978-3-85132-741-0。 ブリギッテ・レッキ著『アウラと自律性。ヴァルター・ベンヤミンとテオドール・W・アドルノにおける芸術の主観性について』ヴュルツブルク、1988年、ISBN 3-88479-361-6。 ブリッタ・ショルツ著『芸術としての批判。アドルノの弁証法からの脱却』ケーニヒスハウゼン&ノイマン、ヴュルツブルク、2000年、ISBN 3-8260-1828-1。 O. K. ヴェルクマイスター著『否定としての芸術作品。芸術理論における歴史的決定に関するテオドール・W・アドルノの研究。同著『美学の終焉。アドルノ、ブロッ ク、黄色い潜水艦、そして一次元的な人間に関するエッセイ。S. フィッシャー、フランクフルト・アム・マイン、1971年、7-32ページ。 アルブレヒト・ヴェルマー:芸術の否定性と自律性について。アドルノ美学の妥当性と音楽社会学における盲点。アクセル・ホネット編『自由の弁証法。フランクフルト・アドルノ会議2005』シュールカンプ、フランクフルト・アム・マイン、2005年、237-278ページ。 音楽理論/音楽社会学 ウルリッヒ・J・ブロマン:「口にするな!」アドルノの『新音楽の哲学』におけるストラヴィンスキーの部分 - 冷戦戦略、1945年以降の文化と音楽。冷戦時代の美学、ファウ:ザールブリュッケン2015年、124-144ページ。 リヒャルト・クライン、クラウス=シュテフェン・マーンコプフ(編):『耳で考える。アドルノの音楽哲学』。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン、1998年。 マッテオ・ナンニ著『アウシュヴィッツ - アドルノとノーノ。哲学的および分析音楽学的調査』フライブルク・イム・ブライスガウ 2004年、ISBN 3-7930-9366-2。 ラルフ・パランド著「...非常に大きな収束」? テオドール・W・アドルノとジェルジ・リゲティのダルムシュタットにおける形式に関する討論。In: Christoph von Blumröder (ed.): Compositional Stations of the 20th Century: Debussy, Webern, Messiaen, Boulez, Cage, Ligeti, Stockhausen, Höller, Bayle. (Signals from Cologne: Contributions to the Music of the Time 7). Münster 2003, ISBN 3-8258-7212-2, pp. 87–115. マイケル・ターンハイム著『時代の断片:アドルノとデリダによるジャズ論』エヴァ・ラキエゼ=ワニェク、エリック・M・フォクト編『デリダとアドルノ。脱 構築とフランクフルト学派の現在性について』トゥリア+カント、ウィーン、ベルリン、2008年、232-252ページ、ISBN 978-3-85132-497-6。 ニコラウス・ウラネク著『現代音楽美学の探究。アドルノの「音楽哲学」とベートーヴェンの断片』transcript, ビーレフェルト 2010年、ISBN 978-3-8376-1320-9。 ハンス・ヴォルシュレッガー著『モーメント・ミュージカ』。TWAとの日々。ゲッティンゲン2005年、ISBN 3-89244-878-7。 フェルディナント・ツェーエンライター著『アドルノ。思考の軌跡。入門編。』Wolke、ホーフハイム・アム・タウヌス2019年、ISBN 978-3-95593-120-9。 作曲 Gabriele Geml, Han-Gyeol Lie (eds.): 「Durchaus rhapsodisch」。Theodor Wiesengrund Adorno: The Compositional Work. J. B. Metzler, Stuttgart 2017. Martin Hufner: Adorno and the twelve-tone technique. ConBrio, Regensburg 1996, ISBN 3-930079-74-7. レネ・ライボヴィッツ:「作曲家テオドール・W・アドルノ」ホルクハイマー編『証言。テオドール・W・アドルノの60歳の誕生日に』ヨーロッパ出版協会、フランクフルト・アム・マイン、1963年、355-359ページ。 文化産業 ディーター・プロコップ著『アドルノに抗してアドルノを批判する。文化産業の否定弁証法』VSA出版、ハンブルク、2003年。 ディーター・プロコップ著『文化産業の非同一性。メディア商品の創造性に関する新しい批判的コミュニケーション研究』ヘルベルト・フォン・ハレム出版、ケルン、2005年。 ディーター・プロコップ著『文化産業の美学』テクトゥム出版、マールブルク、2009年 ハインツ・シュタインアート著『文化産業の発見』ヴェルク・フュア・ゲゼルシャフトクリティック、ウィーン ハインツ・シュタインアート著『文化産業』第3版、ヴェストファーレン・ダンプフブート、ミュンスター、2008年 |
| Filme Adorno. 1. Der Bürger als Revolutionär. Dokumentarfilm, Deutschland, 2003, 58:40 Min., Buch und Regie: Meinhard Prill und Kurt Schneider, Produktion: arte, SWR, Erstsendung: 1. August 2003 bei arte, Inhaltsangabe von ARD, u. a. mit Alexander Kluge, Rüdiger Safranski, Rolf Wiggershaus, Regina Becker-Schmidt, Bazon Brock, Richard Sennett, Martin Jay, Besprechung in der FAZ:.[288] Adorno. 2. Wer denkt, ist nicht wütend. Dokumentarfilm, Deutschland, 2003, 58:50 Min., Buch und Regie: Meinhard Prill und Kurt Schneider, Produktion: arte, SWR, Erstsendung: 8. August 2003 bei arte, Inhaltsangabe von ARD. Hörspiel Traumprotokolle. Mit Andreas Dorau. Komposition und Realisation: zeitblom. BR-Hörspiel und Medienkunst 2016. Als Podcast/Download im BR Hörspiel Pool.[289] Frankfurter Adorno-Vorlesungen Seit 2002 werden vom Frankfurter Institut für Sozialforschung und dem Suhrkamp Verlag jährlich stattfindenden Adorno-Vorlesungen an der Frankfurter Universität veranstaltet. Die Preisträger widmen sich heutigen Möglichkeiten kritischer Gesellschaftstheorie als Philosophen, Soziologen, Historiker, Kunsthistoriker, Politologen und Literaturwissenschaftler von internationalem Rang. |
映画 アドルノ。1.革命家としての市民。ドキュメンタリー映画、ドイツ、2003年、58分40秒、脚本・監督:マンハルト・プリル、クルト・シュナイダー、 制作:アルテ、SWR、初放送:2003年8月1日、アルテ、ARDによる要約、出演:アレクサンダー・クルーゲ、リュディガー・サフランスキ、ロルフ・ ヴィッゲルスハウス、レギーナ・ベッカー=シュミット、バゾン・ブロック、リチャード・セネット、マーティン・ジェイ、その他 、FAZ紙の批評:[288] アドルノ。2. 考える者は怒らない。ドキュメンタリー、ドイツ、2003年、58:50分、脚本・監督:マンハルト・プリルとクルト・シュナイダー、制作:アルテ、SWR、初放送:2003年8月8日アルテ、ARDによる要約。 ラジオ劇 夢の記録。アンドレアス・ドーラウ出演。作曲・演出:ツァイトブロム。BRラジオドラマ・メディアアート2016。ポッドキャスト/ダウンロードはBR Hörspiel Poolで。 フランクフルト・アドルノ講座 2002年より、アドルノ・レクチャーはフランクフルト社会研究協会とズーアカンプ出版社により、毎年フランクフルト大学で開催されている。受賞者は、国 際的に著名な哲学者、社会学者、歴史家、美術史家、政治学者、文学者として、今日における批判的社会理論の可能性について講演を行う。 |
| Anmerkungen und Einzelnachweise Die von Rolf Tiedemann hrsgg. Gesammelten Schriften werden im Artikel mit dem Kürzel GS und der Angabe von Band- und Seitenzahl zitiert. Band 1: Philosophische Frühschriften. Frankfurt am Main 1973. Band 2: Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. Frankfurt am Main 1979. Band 3: Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main 1987. Band 4: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am Main 1980. Band 5: Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu Hegel. Frankfurt am Main 1970. Band 6: Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit. Frankfurt am Main 1973. Band 7: Ästhetische Theorie. Hrsg. v. Gretel Adorno und Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1970. Band 8: Soziologische Schriften I. Frankfurt am Main 1972. Band 9/1: Soziologische Schriften II. Erste Hälfte. Frankfurt am Main 1971. Band 9/2: Soziologische Schriften II. Zweite Hälfte. Frankfurt am Main 1971. Band 10/1: Kulturkritik und Gesellschaft I: Prismen. Ohne Leitbild. Frankfurt am Main 1977. Band 10/2: Kulturkritik und Gesellschaft II: Eingriffe. Stichworte. Frankfurt am Main 1977. Band 11: Noten zur Literatur. Frankfurt am Main 1974. Band 12: Philosophie der neuen Musik. Frankfurt am Main 1975. Band 13: Die musikalischen Monographien. Frankfurt am Main 1971. Band 14: Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main 1973. Band 15: Theodor W. Adorno und Hanns Eisler: Komposition für den Film. Theodor W. Adorno: Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur musikalischen Praxis. Frankfurt am Main 1976. Band 16: Musikalische Schriften I-III: Klangfiguren (I). Quasi una fantasia (II). Musikalische Schriften III. Frankfurt am Main 1978. Band 19: Musikalische Schriften VI. Hrsg. v. Rolf Tiedemann u. Klaus Schultz. Frankfurt am Main 1984. Band 20/1: Vermischte Schriften I. Frankfurt am Main 1986. |
注釈および個々の参考文献 Rolf Tiedemann 編『全集』は、本記事ではCWと巻数およびページ番号の略称で引用されている。 第1巻:哲学的初期著作集。フランクフルト・アム・マイン、1973年。 第2巻:キルケゴール。美的構築。フランクフルト・アム・マイン、1979年。 第3巻:ホルクハイマー、アドルノ著『啓蒙の弁証法』。哲学的断片。フランクフルト・アム・マイン、1987年。 第4巻:『ミニマ・モラリア』。傷ついた人生からの考察。フランクフルト・アム・マイン、1980年。 第5巻:『認識論のメタ批判について』。ヘーゲルに関する3つの研究。フランクフルト・アム・マイン、1970年。 第6巻:否定的弁証法。真正性の隠語。フランクフルト・アム・マイン、1973年。 第7巻:美学理論。グレテル・アドルノとロルフ・ティードマン編。フランクフルト・アム・マイン、1970年。 第8巻:社会学論文集I。フランクフルト・アム・マイン、1972年。 第9巻第1部:社会学論文集II。前半。フランクフルト・アム・マイン、1971年。 第9巻第2部:社会学論文集II。後半。フランクフルト・アム・マイン、1971年。 第10巻第1部:文化批評と社会I:プリズム。モデルなし。フランクフルト・アム・マイン、1977年。 第10巻第2部:文化批評と社会II:介入。キーワード。フランクフルト・アム・マイン、1977年。 第11巻:文学に関するノート。フランクフルト・アム・マイン、1974年。 第12巻:新音楽の哲学。フランクフルト・アム・マイン、1975年。 第13巻:音楽モノグラフ。フランクフルト・アム・マイン、1971年。 第14巻:不協和音。音楽社会学入門。フランクフルト・アム・マイン 1973年。 第15巻:テオドール・W・アドルノとハンス・アイスラー:映画のための作曲。テオドール・W・アドルノ:忠実なリピテューール。音楽実践に関するエッセイ。フランクフルト・アム・マイン 1976年。 第16巻:音楽著作集 I-III:Klangfiguren(I)。Quasi una fantasia(II)。音楽著作集 III。フランクフルト・アム・マイン 1978年。 第19巻:音楽著作集 VI。編集:Rolf TiedemannとKlaus Schultz。フランクフルト・アム・マイン 1984年。 第20巻第1部:その他の著作 I。フランクフルト・アム・マイン 1986年。 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno |
****
| Theodor W. Adorno
(/əˈdɔːrnoʊ/ ə-DOR-noh,[8] German: [ˈteːodoːɐ̯ ʔaˈdɔʁno] ⓘ;[9][10] born
Theodor Ludwig Wiesengrund; 11 September 1903 – 6 August 1969) was a
German philosopher, sociologist, psychologist, musicologist, and
composer. He was a leading member of the Frankfurt School of critical theory, whose work has come to be associated with thinkers such as Ernst Bloch, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Erich Fromm, and Herbert Marcuse, for whom the works of Freud, Marx, and Hegel were essential to a critique of modern society. As a critic of both fascism and what he called the culture industry, his writings—such as Dialectic of Enlightenment (1947), Minima Moralia (1951), and Negative Dialectics (1966)—strongly influenced the European New Left. Amidst the vogue enjoyed by existentialism and positivism in early 20th-century Europe, Adorno advanced a dialectical conception of natural history that critiqued the twin temptations of ontology and empiricism through studies of Kierkegaard and Husserl. As a classically trained pianist whose sympathies with the twelve-tone technique of Arnold Schoenberg resulted in his studying composition with Alban Berg of the Second Viennese School, Adorno's commitment to avant-garde music formed the backdrop of his subsequent writings and led to his collaboration with Thomas Mann on the latter's novel Doctor Faustus, while the two men lived in California as exiles during the Second World War. Working for the newly relocated Institute for Social Research, Adorno collaborated on influential studies of authoritarianism, antisemitism and propaganda that would later serve as models for sociological studies the Institute carried out in post-war Germany. Upon his return to Frankfurt, Adorno was involved with the reconstitution of German intellectual life through debates with Karl Popper on the limitations of positivist science, critiques of Heidegger's language of authenticity, writings on German responsibility for the Holocaust, and continued interventions into matters of public policy. As a writer of polemics in the tradition of Nietzsche and Karl Kraus, Adorno delivered scathing critiques of contemporary Western culture. Adorno's posthumously published Aesthetic Theory, which he planned to dedicate to Samuel Beckett, is the culmination of a lifelong commitment to modern art which attempts to revoke the "fatal separation" of feeling and understanding long demanded by the history of philosophy and explode the privilege aesthetics accords to content over form and contemplation over immersion. |
テ
オドール・W.アドルノ(/əˈdɔː、[8] ドイツ語:[ˈteːːɐ;[9][10]
テオドール・ルートヴィヒ・ヴィーゼングラント(Theodor Ludwig Wiesengrund; 1903年9月11日 -
1969年8月6日)は、ドイツの哲学者、社会学者、心理学者、音楽学者、作曲家。 フロイト、マルクス、ヘーゲルの著作が現代社会を批判する上で不可欠であったフランクフルト学派の批評理論の主要メンバーであり、エルンスト・ブロッホ、 ヴァルター・ベンヤミン、マックス・ホルクハイマー、エーリッヒ・フロム、ヘルベルト・マルクーゼといった思想家たちとその活動は関連づけられるように なった。ファシズムと、彼が文化産業と呼ぶものの両方を批判した彼の著作(『啓蒙の弁証法』(1947年)、『ミニマ・モラリア』(1951年)、『否定 弁証法』(1966年)など)は、ヨーロッパの新左翼に強い影響を与えた。 20世紀初頭のヨーロッパで実存主義と実証主義が流行する中、アドルノはキルケゴールやフッサールの研究を通じて、存在論と経験論の双子の誘惑を批判する 弁証法的なナチュラル・ヒストリーの概念を提唱した。古典的な訓練を受けたピアニストであったアドルノは、アーノルド・シェーンベルクの十二音技法に共鳴 し、第二ウィーン楽派のアルバン・ベルクに作曲を師事した。前衛音楽への傾倒がその後の著作の背景となり、第二次世界大戦中、亡命者としてカリフォルニア に住んでいた二人は、トーマス・マンの小説『ファウストゥス博士』での共同作業につながった。新たに移転した社会研究所で働くようになったアドルノは、権 威主義、反ユダヤ主義、プロパガンダに関する影響力のある研究を共同で行い、後に同研究所が戦後ドイツで行った社会学的研究のモデルとなった。 フランクフルトに戻ったアドルノは、実証主義科学の限界に関するカール・ポパーとの論争、ハイデガーの真正性の言葉に対する批判、ホロコーストに対するド イツの責任に関する著作、公共政策への継続的な介入などを通じて、ドイツの知的生活の再構築に関わった。ニーチェやカール・クラウスの伝統を受け継ぐポレ ミクスの作家として、アドルノは現代西洋文化を痛烈に批判した。死後に出版された『美学論』は、サミュエル・ベケットに捧げる予定だったもので、哲学史が 長年求めてきた感覚と理解の「致命的な分離」を撤回し、美学が形式よりも内容、没入よりも熟考に与える特権を爆発させようとする、現代芸術への生涯をかけ たコミットメントの集大成である。 |
| Life and career Early years: Frankfurt Theodor W. Adorno (alias: Theodor Adorno-Wiesengrund) was born as Theodor Ludwig Wiesengrund in Frankfurt am Main on 11 September 1903, the only child of Maria Calvelli-Adorno della Piana (1865–1952) and Oscar Alexander Wiesengrund (1870–1946). His mother, a Catholic from Corsica, was once a professional singer, while his father, an assimilated Jew who had converted to Protestantism, ran a successful wine-export business. Proud of her origins, Maria wanted her son's paternal surname to be supplemented by the addition of her own name, Adorno. Thus his earliest publications carried the name Theodor Wiesengrund-Adorno; upon his application for US citizenship, his name was modified to Theodor W. Adorno. His childhood was marked by the musical life provided by his mother and aunt: Maria was a singer who could boast of having performed in Vienna at the Imperial Court, while her sister, Agathe, who lived with them, had made a name for herself as both a singer and pianist. He was not only a precocious child but, as he recalled later in life, a child prodigy who could play pieces by Beethoven on the piano by the time he was twelve.[11] At the age of six, he attended the Deutschherren middle school, before transferring to the Kaiser-Wilhelm Gymnasium, where he studied from 1913 to 1921. Prior to his graduation at the top of his class, Adorno was already swept up by the revolutionary mood of the time, as is evidenced by his reading of György Lukács's The Theory of the Novel that year, as well as by his fascination with Ernst Bloch's The Spirit of Utopia, of which he would later write: Bloch's was a philosophy that could hold its head high before the most advanced literature; a philosophy that was not calibrated to the abominable resignation of methodology ... I took this motif so much as my own that I do not believe I have ever written anything without reference to it, either implicit or explicit.[12] Adorno circa 1919 Adorno's intellectual nonconformism was also shaped by the repugnance he felt towards the nationalism which swept through the Reich during the First World War. Along with future collaborators Walter Benjamin, Max Horkheimer and Bloch, Adorno was profoundly disillusioned by the ease with which Germany's intellectual and spiritual leaders—among them Max Weber, Max Scheler, Georg Simmel, as well as his friend Siegfried Kracauer—came out in support of the war. The younger generation's distrust for traditional knowledge arose from the way in which this tradition had discredited itself.[13] Over time, Oscar Wiesengrund's firm established close professional and personal ties with the factory of Karplus & Herzberger in Berlin. The eldest daughter of the Karplus family, Margarete, or Gretel, moved in the intellectual circles of Berlin, where she was acquainted with Benjamin, Bertolt Brecht and Bloch, each of whom Adorno would become familiar with during the mid-1920s; after fourteen years, Gretel Karplus and Adorno were married in 1937. At the end of his schooldays, Adorno not only benefited from the rich concert offerings of Frankfurt—where one could hear performances of works by Schoenberg, Schreker, Stravinsky, Bartók, Busoni, Delius and Hindemith—but also began studying music composition at the Hoch Conservatory while taking private lessons with well-respected composers Bernhard Sekles and Eduard Jung. At around the same time, he befriended Siegfried Kracauer, the Frankfurter Zeitung's literary editor, of whom he would later write: For years Kracauer read [Kant's] Critique of Pure Reason with me regularly on Saturday afternoons. I am not exaggerating in the slightest when I say that I owe more to this reading than to my academic teachers ... Under his guidance I experienced the work from the beginning not as mere epistemology, not as an analysis of the conditions of scientifically valid judgments, but as a kind of coded text from which the historical situation of spirit could be read, with the vague expectation that in doing so one could acquire something of truth itself.[14] Leaving gymnasium to study philosophy, psychology and sociology at Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt, Adorno continued his readings with Kracauer, turning now to Hegel and Kierkegaard, and began publishing concert reviews and pieces of music for distinguished journals like the Zeitschrift für Musik, the Neue Blätter für Kunst und Literatur and later for the Musikblätter des Anbruch. In these articles Adorno championed avant-garde music at the same time as he critiqued the failings of musical modernity, as in the case of Stravinsky's The Soldier's Tale, which in 1923 he called a "dismal Bohemian prank".[15] In these early writings he was unequivocal in his condemnation of performances that either sought or pretended to achieve a transcendence that Adorno, in line with many intellectuals of the time, regarded as impossible: "No cathedral", he wrote, "can be built if no community desires one."[16] In the summer of 1924 Adorno received his doctorate with a study of Edmund Husserl under the direction of the unorthodox neo-Kantian Hans Cornelius. Before his graduation Adorno had already met his most important intellectual collaborators, Horkheimer and Benjamin. Through Cornelius's seminars, Adorno met Horkheimer, through whom he was then introduced to Friedrich Pollock. Vienna, Frankfurt, and Berlin During the summer of 1924, the Viennese composer Alban Berg's "Three Fragments from Wozzeck", op. 7, premiered in Frankfurt, at which time Adorno introduced himself to Berg and both agreed the young philosopher and composer would study with Berg in Vienna. Upon moving to Vienna in February 1925, Adorno immersed himself in the musical culture that had grown up around Schoenberg: in addition to his twice-weekly sessions with Berg, Adorno continued his studies on piano with Eduard Steuermann and befriended the violinist Rudolf Kolisch. In Vienna he and Berg attended public lectures by the satirist Karl Kraus, and he met Lukács, who had been living in Vienna after the failure of the Hungarian Soviet Republic. Berg, whom Adorno called "my master and teacher", was among the most prescient of his young pupil's early friends: [I am] convinced that, in the sphere of the deepest understanding of music ... you are capable of supreme achievements and will undoubtedly fulfill this promise in the shape of great philosophical works.[17] After leaving Vienna, Adorno traveled through Italy, where he met with Kracauer, Benjamin, and the economist Alfred Sohn-Rethel, with whom he developed a lasting friendship, before returning to Frankfurt. In December 1926 Adorno's "Two Pieces for String Quartet", op. 2, were performed in Vienna, which provided a welcome interruption from his preparations for the habilitation. After writing the "Piano Pieces in strict twelve-tone technique", as well as songs later integrated into the Six Bagatelles for Voice and Piano, op. 6, Adorno presented his habilitation manuscript, The Concept of the Unconscious in the Transcendental Theory of the Psyche (Der Begriff des Unbewußten in der transzendentalen Seelenlehre), to Cornelius in November 1927. Cornelius advised Adorno to withdraw his application on the grounds that the manuscript was too close to his own way of thinking. In the manuscript Adorno attempted to underline the epistemological status of the unconscious as it emerged from Freud's early writings. Against the function of the unconscious in both Nietzsche and Spengler, Adorno argued that Freud's notion of the unconscious serves as a "sharp weapon ... against every attempt to create a metaphysics of the instincts and to deify full, organic nature."[18] Undaunted by his academic prospects, Adorno threw himself once again into composition. In addition to publishing numerous reviews of opera performances and concerts, Adorno's "Four Songs for Medium Voice and Piano", op. 3, were performed in Berlin in January 1929. Between 1928 and 1930 Adorno took on a greater role within the editorial committee of the Musikblätter des Anbruch. In a proposal for transforming the journal, he sought to use Anbruch for championing radical modern music against what he called the "stabilized music" of Pfitzner, the later Richard Strauss, as well as the neoclassicism of Stravinsky and Hindemith. During this period he published the essays "Night Music", "On Twelve-Tone Technique" and "Reaction and Progress". Yet his reservations about twelve-tone orthodoxy became steadily more pronounced. According to Adorno, twelve-tone technique's use of atonality can no more be regarded as an authoritative canon than can tonality be relied on to provide instructions for the composer. At this time Adorno struck up a correspondence with the composer Ernst Krenek, discussing problems of atonality and twelve-tone technique. In a 1934 letter he sounded a related criticism of Schoenberg: Twelve-tone technique alone is nothing but the principle of motivic elaboration and variation, as developed in the sonata, but elevated now to a comprehensive principle of construction, namely transformed into an a priori form and, by that token, detached from the surface of the composition.[19] At this point Adorno reversed his earlier priorities: now his musical activities came second to the development of a philosophical theory of aesthetics. Thus, in the middle of 1929 he accepted Paul Tillich's offer to present an habilitation on Kierkegaard, which Adorno eventually submitted under the title The Construction of the Aesthetic. At the time, Kierkegaard's philosophy exerted a strong influence, chiefly through its claim to pose an alternative to Idealism and Hegel's philosophy of history. Yet when Adorno turned his attention to Kierkegaard, watchwords like "anxiety", "inwardness" and "leap"—instructive for existentialist philosophy—were detached from their theological origins and posed, instead, as problems for aesthetics.[20] As the work proceeded—and Kierkegaard's overcoming of Hegel's idealism was revealed to be a mere interiorization—Adorno excitedly remarked in a letter to Berg that he was writing without looking over his shoulder at the faculty who would soon evaluate his work. Receiving favourable reports from Professors Tillich and Horkheimer, as well as Benjamin and Kracauer, the university conferred on Adorno the venia legendi in February 1931; on the very day his revised study was published, 23 March 1933, Hitler seized dictatorial powers.[21] Several months after qualifying as a lecturer in philosophy, Adorno delivered an inaugural lecture at the Institute for Social Research, an independent organization that had recently appointed Horkheimer as its director and, with the arrival of the literary scholar Leo Löwenthal, social psychologist Erich Fromm and philosopher Herbert Marcuse, sought to exploit recent theoretical and methodological advances in the social sciences. His lecture "The Actuality of Philosophy" created a scandal. In it Adorno not only deviated from the theoretical program Horkheimer had laid out a year earlier but challenged philosophy's very capacity for comprehending reality as such: "For the mind", Adorno announced, "is indeed not capable of producing or grasping the totality of the real, but it may be possible to penetrate the detail, to explode in miniature the mass of merely existing reality."[22] In line with Benjamin's The Origin of German Tragic Drama and preliminary sketches of the Arcades Project, Adorno likened philosophical interpretation to experiments that should be conducted "until they arrive at figurations in which the answers are legible, while the questions themselves vanish." Having lost its position as the Queen of the Sciences, philosophy must now radically transform its approach to objects so that it might "construct keys before which reality springs open."[23] Following Horkheimer's taking up the directorship of the institute, a new journal, Zeitschrift für Sozialforschung, was produced to publish the research of Institute members both before and after its relocation to the United States. Though Adorno was not an Institute member, the journal published many of his essays, including "The Social Situation of Music" (1932), "On Jazz" (1936), "On the Fetish-Character in Music and the Regression of Listening" (1938) and "Fragments on Wagner" (1938). In his new role as social theorist, Adorno's philosophical analysis of cultural phenomena heavily relied on the language of historical materialism, as concepts like reification, false consciousness and ideology came to play an ever more prominent role in his work. At the same time, however, and owing to both the presence of another prominent sociologist at the institute, Karl Mannheim, as well as the methodological problem posed by treating objects—like "musical material"—as ciphers of social contradictions, Adorno was compelled to abandon any notion of "value-free" sociology in favour of a form of ideology critique that held on to an idea of truth. Before his emigration in autumn 1934, Adorno began work on a Singspiel based on Mark Twain's The Adventures of Tom Sawyer titled The Treasure of Indian Joe, which he never completed; by the time he fled Hitler's Germany Adorno had already written over 100 opera or concert reviews and 50 critiques of music composition. As the Nazi party became the largest party in the Reichstag, Horkheimer's 1932 observation proved typical for his milieu: "Only one thing is certain", he wrote, "the irrationality of society has reached a point where only the gloomiest predictions have any plausibility."[24] In September Adorno's right to teach was revoked; in March, as the swastika was run up the flagpole of town hall, the Frankfurt criminal police searched the institute's offices. Adorno's house on Seeheimer Strasse was similarly searched in July and his application for membership in the Reich Chamber of Literature denied on the grounds that membership was limited to "persons who belong to the German nation by profound ties of character and blood. As a non-Aryan", he was informed, "you are unable to feel and appreciate such an obligation."[25] Soon afterwards Adorno was forced into 15 years of exile. |
生涯とキャリア 若い頃 フランクフルト 1903年9月11日、マリア・カルヴェッリ=アドルノ・デッラ・ピアーナ(1865-1952)とオスカー・アレクサンダー・ヴィーゼングラント (1870-1946)の間に生まれた。母親はコルシカ出身のカトリック教徒で、かつてはプロの歌手として活躍し、父親はプロテスタントに改宗した同化ユ ダヤ人で、ワインの輸出業を営み成功を収めた。自分の出自を誇りに思ったマリアは、息子の父方の姓に自分の名前であるアドルノを加えようとした。そのた め、彼の初期の出版物にはテオドール・ヴィーゼングラント=アドルノという名前が掲載され、アメリカ市民権を申請する際に、彼の名前はテオドール・W・ア ドルノに修正された。 彼の幼少期は、母親と叔母による音楽生活に彩られていた: マリアはウィーンの宮廷で演奏したことを自慢できる歌手であり、同居していた姉のアガーテは歌手としてもピアニストとしても名を馳せていた。彼は早熟な子 供であっただけでなく、後年、12歳までにベートーヴェンの曲をピアノで弾くことができた神童であったと回想している[11]。 6歳でドイチュヘレン中学校に入学した後、カイザー・ヴィルヘルム・ギムナジウムに転校し、1913年から1921年まで学ぶ。同年にギョルギー・ルカーチの『小説論』を読んだことや、エルンスト・ブロッホの『ユートピアの精神』に魅了されたことがその証左である: ブロッホの哲学は、最先端の文学の前で堂々と頭を垂れることができる哲学であり、方法論の忌まわしい諦観に合わせることのない哲学だった......」。 私はこのモチーフを自分自身のものだと考えていたので、暗黙的であれ明示的であれ、このモチーフに言及せずに何かを書いたことはないと思う[12]」。 1919年頃のアドルノ アドルノの知的不適合主義は、第一次世界大戦中に帝国を席巻したナショナリズムへの反感によっても形成された。後に共同研究者となるヴァルター・ベンヤミ ン、マックス・ホルクハイマー、ブロッホらとともに、アドルノはドイツの知的・精神的指導者たち、とりわけマックス・ヴェーバー、マックス・シェーラー、 ゲオルク・ジンメル、そして彼の友人ジークフリート・クラッカウアーらが安易に戦争支持を表明したことに深く幻滅した。若い世代が伝統的な知識に対して不 信感を抱くようになったのは、伝統的な知識が自らの信用を失墜させたことに起因していた[13]。 やがてオスカー・ヴィーゼングルントの会社は、ベルリンのカープラス & ヘルツベルガーの工場と仕事上でも個人的にも緊密な関係を築いた。カープラス家の長女マルガレーテ(グレーテル)はベルリンの知識人サークルに入り、そこ でベンヤミン、ベルトルト・ブレヒト、ブロッホらと知り合い、アドルノは1920年代半ばに彼らと親交を深めることになる。 14年後、グレテル・カルプラスとアドルノは1937年に結婚した。学生時代の終わりに、アドルノはフランクフルトでシェーンベルク、シュレーカー、スト ラヴィンスキー、バルトーク、ブゾーニ、デリウス、ヒンデミットの作品を聴くことができる豊かなコンサートの恩恵を受けただけでなく、ホッホ音楽院で作曲 を学び始め、著名な作曲家ベルンハルト・ゼクルスとエドゥアルド・ユングの個人レッスンを受けた。同じ頃、フランクフルター・ツァイトゥングの文芸編集者 ジークフリート・クラッカウアーと親しくなり、彼は後にこう書いている: クラッカウアーは何年もの間、土曜日の午後に定期的に私と一緒に『純粋理性批判』を読んでいた。学問の先生よりも、この読書のおかげだと言っても、少しも 誇張ではありません。彼の指導の下で、私は最初からこの著作を単なる認識論としてではなく、科学的に妥当な判断の条件の分析としてではなく、精神の歴史的 状況を読み取ることができる一種の暗号化されたテキストとして、そうすることで真理そのものの何かを得ることができるという漠然とした期待とともに体験し た[14]。 フランクフルトのヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学で哲学、心理学、社会学を学ぶためにギムナジウムを退学したアドルノは、クラッカウアーとともに読書 を続け、今度はヘーゲルとキルケゴールに目を向け、『Zeitschrift für Musik』、『Neue Blätter für Kunst und Literatur』、後には『Musikblätter des Anbruch』といった著名な雑誌にコンサート評や音楽作品を発表し始めた。これらの記事の中でアドルノは、前衛音楽を擁護すると同時に、1923年に 彼が「悲惨なボヘミアの悪ふざけ」と呼んだストラヴィンスキーの『兵士の物語』の場合のように、音楽的近代性の失敗を批評した[15]。これらの初期の著 作の中で彼は、当時の多くの知識人と同様に、アドルノが不可能とみなした超越を達成しようとしたり、達成するふりをしたりする演奏に対してはっきりと非難 した: 「いかなる聖堂も」、「共同体が聖堂を望まなければ建てることはできない」と彼は書いている[16]。1924年の夏、アドルノは異端的な新カント派のハ ンス・コルネリウスの指導の下、エドムント・フッサールの研究で博士号を取得した。卒業前に、アドルノはすでに最も重要な知的共同研究者であるホルクハイ マーとベンヤミンに出会っていた。コルネリウスのセミナーを通じて、アドルノはホルクハイマーに出会い、そのホルクハイマーを通じてフリードリヒ・ポロッ クに紹介された。 ウィーン、フランクフルト、ベルリン 1924年夏、ウィーンの作曲家アルバン・ベルクの《ヴォツェックからの3つの断片》作品7がフランクフルトで初演され、その時アドルノはベルクに自己紹 介し、若き哲学者と作曲家はウィーンでベルクに師事することで合意した。1925年2月にウィーンに移り住んだアドルノは、シェーンベルクを中心に発展し た音楽文化にどっぷりと浸かった。週2回のベルクとのセッションに加え、アドルノはエドゥアルド・シュテュアマンのもとでピアノの勉強を続け、ヴァイオリ ニストのルドルフ・コリシュとも親しくなった。ウィーンでは、ベルクとともに風刺作家カール・クラウスの公開講座に参加し、ハンガリー・ソビエト共和国崩 壊後にウィーンに住んでいたルカーチとも知り合った。アドルノが「私の師匠であり先生」と呼ぶベルクは、若き弟子の初期の友人たちの中で最も先見の明が あった: [音楽の最も深い理解の領域において......君は最高の業績を残すことができ、間違いなく偉大な哲学的著作の形でこの約束を果たすだろうと私は確信している」[17]。 ウィーンを離れたアドルノはイタリアを旅し、そこでクラッカウアー、ベンヤミン、経済学者のアルフレッド・ゾーン=レッテルらと会い、永続的な友情を育ん だ後、フランクフルトに戻った。1926年12月、アドルノが作曲した《弦楽四重奏のための2つの小品》作品2がウィーンで演奏され、ハビリテーションの 準備の合間を縫っての演奏となった。厳格な十二音技法によるピアノ小品」と、後に「声楽とピアノのための6つのバガテル」op.6に統合される歌曲を書い た後、アドルノは1927年11月、ハビリテーションの原稿『超越論的精神論における無意識の概念』(Der Begriff des Unbewußten in der transzendentalen Seelenlehre)をコルネリウスに提出した。コルネリウスは、この原稿が自分の考え方に近すぎるという理由で、アドルノに応募を取り下げるよう進 言した。この原稿でアドルノは、フロイトの初期の著作から生まれた無意識の認識論的地位を強調しようとした。ニーチェやシュペングラーにおける無意識の機 能に対して、アドルノは、フロイトの無意識の概念は「本能の形而上学を創造し、完全で有機的な自然を神格化しようとするあらゆる試みに対する...... 鋭い武器」であると主張した[18]。オペラの上演やコンサートの批評を数多く発表したほか、1929年1月には、アドルノの「中声とピアノのための4つ の歌」作品3がベルリンで上演された。1928年から1930年にかけて、アドルノはMusikblätter des Anbruchの編集委員会の中でより大きな役割を担うようになった。同誌の改革を提案する中で、彼は、プフィッツナーや後のリヒャルト・シュトラウス、 ストラヴィンスキーやヒンデミットの新古典主義と呼ばれる「安定化された音楽」に対して、急進的な現代音楽を支持するためにアンブルッフを利用しようとし た。この時期、彼は「夜の音楽」、「十二音技法について」、「反動と進歩」というエッセイを発表した。しかし、12音技法の正統性に対する彼の懸念は、次 第に顕著になっていった。アドルノによれば、十二音技法による無調性は、調性が作曲家に指示を与えるのと同様に、権威ある正典とみなすことはできない。 この頃、アドルノは作曲家のエルンスト・クレネックと文通を始め、無調性と十二音技法の問題について議論した。1934年の手紙の中で、彼はシェーンベルクに関連した批判をぶつけている: 十二音技法だけでは、ソナタで展開されたような動機の精緻化と変奏の原理に過ぎないが、今や包括的な構築の原理に昇華され、すなわち先験的な形式に変容され、そのために作曲の表面から切り離されている」[19]。 この時点でアドルノはそれまでの優先順位を逆転させ、今や彼の音楽活動は美学の哲学的理論の展開に次ぐものとなった。こうして1929年半ば、彼はパウ ル・ティリッヒの申し出を受け、キルケゴールに関するハビリテーションを発表する。当時、キルケゴールの哲学は、主に観念論とヘーゲルの歴史哲学に代わる ものとして強い影響力を持っていた。しかし、アドルノがキルケゴールに注目したとき、「不安」、「内面性」、「跳躍」といった実存主義哲学にとって有益な キーワードは、その神学的起源から切り離され、代わりに美学の問題として提起された[20]。 作品が進むにつれて、そしてキルケゴールがヘーゲルの観念論を克服したことが単なる内面化であったことが明らかになるにつれて、アドルノはベルクに宛てた 手紙の中で、やがて自分の作品を評価することになる教授陣を肩越しに見ることなく執筆していると興奮気味に述べている。ティリッヒ教授、ホルクハイマー教 授、ベンヤミン教授、クラッカウアー教授から好意的な報告を受けた大学は、1931年2月、アドルノにヴェニア・レジェンディを授与した。 ホルクハイマーが所長に任命されたばかりで、文学者のレオ・レーヴェンタール、社会心理学者のエーリッヒ・フロム、哲学者のヘルベルト・マルクーゼが加わ り、社会科学における最近の理論的、方法論的進歩を利用しようとしていた。彼の講義『哲学の実際』はスキャンダルを巻き起こした。この講義でアドルノは、 1年前にホルクハイマーが打ち出した理論的プログラムから逸脱しただけでなく、哲学が現実を理解する能力そのものに異議を唱えた: アドルノは、「心には実に現実の全体性を生み出す能力も把握する能力もないが、細部にまで入り込み、ただ存在しているだけの現実の塊をミニチュアとして爆 発させることは可能かもしれない」と発表した[22]。ベンヤミンの『ドイツ悲劇劇の起源』や『アルカデス・プロジェクト』の予備的スケッチに沿って、ア ドルノは哲学的解釈を、「問いそのものは消え去るが、答えが読み取れる造形に到達するまで」行われるべき実験になぞらえた。科学の女王としての地位を失っ た哲学は、「現実が開かれる鍵を構築する」ために、対象へのアプローチを根本的に変革しなければならない[23]。 ホルクハイマーが研究所の所長に就任した後、アメリカへの移転前と移転後の研究所のメンバーの研究を発表するための新しい雑誌『Zeitschrift für Sozialforschung』が創刊された。アドルノは研究所のメンバーではなかったが、同誌には「音楽の社会的状況」(1932年)、「ジャズにつ いて」(1936年)、「音楽におけるフェティッシュな性格と聴くことの退行について」(1938年)、「ワーグナーについての断片」(1938年)な ど、彼のエッセイが多数掲載された。社会理論家としての新たな役割において、文化現象に対するアドルノの哲学的分析は、史的唯物論の言語に大きく依存し、 再定義、虚偽意識、イデオロギーといった概念が、彼の仕事においてこれまで以上に重要な役割を果たすようになった。しかし同時に、研究所にはもう一人の著 名な社会学者カール・マンハイムがおり、また「音楽的素材」のような対象を社会的矛盾の暗号として扱うことによってもたらされる方法論的問題のために、ア ドルノは「価値のない」社会学という概念を放棄し、真理という観念を保持するイデオロギー批判の形式を取らざるを得なかった。1934年秋に移住する前 に、アドルノはマーク・トウェインの『トム・ソーヤーの冒険』を題材にした歌劇『インディアン・ジョーの宝物』の創作を始めたが、これは完成しなかった。 ナチス党が帝国議会で最大党派となる中、ホルクハイマーは1932年に「ただひとつ確かなことは、社会の非合理性は、最も陰鬱な予測だけがもっともらしい と思えるところまで来ている」と書いている[24]。9月にはアドルノの教授権が剥奪され、3月には市庁舎の旗竿に鉤十字が掲げられる中、フランクフルト の刑事警察が研究所の事務所を捜索した。7月にはゼーハイマー・シュトラーセにあったアドルノの家も捜索され、帝国文学会議所への入会申し込みは、「人格 と血の深い結びつきによってドイツ民族に属する者」という理由で拒否された。非アーリア人である」アドルノは、「そのような義務を感じ、理解することはで きない」と告げられた[25]。 |
| Exile: Oxford, New York, Los Angeles After the possibility of transferring his habilitation to the University of Vienna came to nothing, Adorno considered relocating to Britain upon his father's suggestion. With the help of the Academic Assistance Council, Adorno registered as an advanced student at Merton College, Oxford, in June 1934. During the next four years at Oxford, Adorno made repeated trips to Germany to see both his parents and Gretel, who was still working in Berlin. Under the direction of Gilbert Ryle, Adorno worked on a dialectical critique of Husserl's epistemology. By this time, the Institute for Social Research had relocated to New York City and begun making overtures to Adorno. After months of strained relations, Horkheimer and Adorno reestablished their essential theoretical alliance during meetings in Paris. Adorno continued writing on music, publishing "The Form of the Phonograph Record" and "Crisis of Music Criticism" with the Viennese musical journal 23, "On Jazz" in the institute's Zeitschrift, "Farewell to Jazz" in Europäische Revue. But Adorno's attempts to break out of the sociology of music were twice thwarted: neither the study of Mannheim he had been working on for years nor extracts from his study of Husserl were accepted by the Zeitschrift. Impressed by Horkheimer's book of aphorisms, Dawn and Decline, Adorno began working on his own book of aphorisms, what later became Minima Moralia. While at Oxford, Adorno suffered two great losses: his Aunt Agathe died in June 1935, and Berg died in December of the same year. To the end of his life, Adorno never abandoned the hope of completing Berg's unfinished opera Lulu. At this time Adorno was in intense correspondence with Walter Benjamin about the latter's Arcades Project. After receiving an invitation from Horkheimer to visit the Institute in New York, Adorno sailed for New York on 9 June 1937 and stayed for two weeks. While he was in New York, Horkheimer's essays "The Latest Attack on Metaphysics" and "Traditional and Critical Theory", which would soon become instructive for the institute's self-understanding, were the subject of intense discussion. Soon after his return to Europe, Gretel moved to Britain, where she and Adorno were married on 8 September 1937; a little over a month later, Horkheimer telegrammed from New York with news of a position Adorno could take with the Princeton Radio Project, then under the directorship of the Austrian sociologist Paul Lazarsfeld. Yet Adorno's work continued with studies of Beethoven and Richard Wagner (published in 1939 as "Fragments on Wagner"), drafts of which he read to Benjamin during their final meeting, in December on the Italian Riviera. According to Benjamin, these drafts were astonishing for "the precision of their materialist deciphering" as well as the way in which "musical facts ... had been made socially transparent in a way that was completely new to me."[26] In his Wagner study, the thesis later to characterize Dialectic of Enlightenment—man's domination of nature—first emerges. Adorno sailed for New York on 16 February 1938. Soon after settling into his new home on Riverside Drive, Adorno met with Lazarsfeld in Newark, New Jersey, to discuss the Project's plans for investigating the impact of broadcast music. Although he was expected to embed the Project's research within a wider theoretical context, it soon became apparent that the Project was primarily concerned with data collection to be used by administrators for establishing whether groups of listeners could be targeted by broadcasts specifically aimed at them. Expected to make use of devices with which listeners could press a button to indicate whether they liked or disliked a particular piece of music, Adorno bristled with distaste and astonishment: "I reflected that culture was simply the condition that precluded a mentality that tried to measure it."[27] Thus Adorno suggested using individual interviews to determine listener reactions and, only three months after meeting Lazarsfeld, completed a 160-page memorandum on the Project's topic, "Music in Radio." Adorno was primarily interested in how the musical material was affected by its distribution through the medium of radio and thought it imperative to understand how music was affected by its becoming part of daily life. "The meaning of a Beethoven symphony", he wrote, "heard while the listener is walking around or lying in bed is very likely to differ from its effect in a concert-hall where people sit as if they were in church."[28] In essays published by the institute's Zeitschrift, Adorno dealt with the atrophy of musical culture that had become instrumental in accelerating tendencies—toward conformism, trivialization and standardization—already present in the larger culture. Unsurprisingly, Adorno's studies found little resonance among members of the project. At the end of 1939, when Lazarsfeld submitted a second application for funding, the musical section of the study was left out. Yet during the two years during which he worked on the Project, Adorno was prolific, publishing "The Radio Symphony", "A Social Critique of Radio Music", and "On Popular Music", texts that, along with the draft memorandum and other unpublished writings, are found in Robert Hullot-Kentor's translation, Current of Music. In light of this situation, Horkheimer soon found a permanent post for Adorno at the institute. In addition to helping with the Zeitschrift, Adorno was expected to be the institute's liaison with Benjamin, who soon passed on to New York the study of Charles Baudelaire he hoped would serve as a model of the larger Arcades Project. In correspondence, the two men discussed the difference in their conceptions of the relationship between critique and artworks that had become manifest through Benjamin's "The Work of Art in the Age of its Technical Reproducibility". At around the same time Adorno and Horkheimer began planning for a joint work on "dialectical logic", which would later become Dialectic of Enlightenment. Alarmed by reports from Europe, where Adorno's parents suffered increasing discrimination and Benjamin was interned in Colombes, they entertained few delusions about their work's practical effects. "In view of what is now threatening to engulf Europe", Horkheimer wrote, "our present work is essentially destined to pass things down through the night that is approaching: a kind of message in a bottle."[29] As Adorno continued his work in New York with radio talks on music and a lecture on Kierkegaard's doctrine of love, Benjamin fled Paris and attempted to make an illegal border crossing. After learning that his Spanish visa was invalid and fearing deportation back to France, Benjamin took an overdose of morphine tablets. In light of recent events, the Institute set about formulating a theory of antisemitism and fascism. On one side were those who supported Franz Leopold Neumann's thesis according to which National Socialism was a form of "monopoly capitalism"; on the other were those who supported Friedrich Pollock's "state capitalist theory." Horkheimer's contributions to this debate, in the form of the essays "The Authoritarian State", "The End of Reason", and "The Jews and Europe", served as a foundation for what he and Adorno planned to do in their book on dialectical logic. In November 1941 Adorno followed Horkheimer to what Thomas Mann called "German California",[30] setting up house in a Pacific Palisades neighborhood of German émigrés that included Bertolt Brecht and Schoenberg. Adorno arrived with a draft of his Philosophy of New Music, a dialectical critique of twelve-tone music that Adorno felt, while writing it, was a departure from the theory of art he had spent the previous decades elaborating. Horkheimer's reaction to the manuscript was wholly positive: "If I have ever in the whole of my life felt enthusiasm about anything, then I did on this occasion", he wrote after reading the manuscript.[31] The two set about completing their joint work, which transformed from a book on dialectical logic to a rewriting of the history of rationality and the Enlightenment. First published in a small mimeographed edition in May 1944 as Philosophical Fragments, the text waited another three years before achieving book form when it was published with its definitive title, Dialectic of Enlightenment, by the Amsterdam publisher Querido Verlag. This "reflection on the destructive aspect of progress" proceeded through the chapters that treated rationality as both the liberation from and further domination of nature, interpretations of both Homer's Odyssey and the Marquis de Sade, as well as analyses of the culture industry and antisemitism. With their joint work completed, the two turned their attention to studies on antisemitism and authoritarianism in collaboration with the Nevitt Sanford-led Public Opinion Study Group and the American Jewish Committee. In line with these studies, Adorno produced an analysis of the Californian radio preacher Martin Luther Thomas. Fascist propaganda of this sort, Adorno wrote, "simply takes people for what they are: genuine children of today's standardized mass culture who have been robbed to a great extent of their autonomy and spontaneity".[32] The result of these labors, the 1950 study The Authoritarian Personality, was pioneering in its combination of quantitative and qualitative methods of collecting and evaluating data as well as its development of the F-scale personality test. After the USA entered the war in 1941, the situation of the émigrés, now classed "enemy aliens", became increasingly restricted. Forbidden from leaving their homes between 8pm and 6am and from going more than five miles from their houses, émigrés like Adorno, who was not naturalized until November 1943, were severely restricted in their movements. In addition to the aphorisms that conclude Dialectic of Enlightenment, Adorno put together a collection of aphorisms in honor of Horkheimer's 50th birthday that were later published as Minima Moralia: Reflections from Damaged Life. These fragmentary writings, inspired by a renewed reading of Nietzsche, treated issues like emigration, totalitarianism, and individuality, as well as everyday matters such as giving presents, dwelling and the impossibility of love. In California Adorno made the acquaintance of Charlie Chaplin and became friends with Fritz Lang and Hanns Eisler, with whom he completed a study of film music in 1944. In this study the authors pushed for the greater usage of avant-garde music in film, urging that music be used to supplement, not simply accompany, films' visual aspect. Adorno also assisted Thomas Mann with his novel Doktor Faustus after the latter asked for his help. "Would you be willing", Mann wrote, "to think through with me how the work—I mean Leverkühn's work—might look; how you would do it if you were in league with the Devil?"[33] At the end of October 1949, Adorno left America for Europe just as The Authoritarian Personality was being published. Before his return, Adorno had reached an agreement with a Tübingen publisher to print an expanded version of Philosophy of New Music and completed two compositions: Four Songs for Voice and Piano by Stefan George, op.7, and Three Choruses for Female Voices from the Poems of Theodor Däubler, op. 8. |
亡命: オックスフォード、ニューヨーク、ロサンゼルス ウィーン大学への編入の可能性がなくなったアドルノは、父の勧めでイギリスへの移住を考えた。1934年6月、学業援助評議会の援助を受けて、アドルノは オックスフォードのマートン・カレッジに上級生として登録した。オックスフォードでの4年間、アドルノは両親とまだベルリンで働いていたグレーテルに会う ために何度もドイツを訪れた。ギルバート・ライルの指導のもと、アドルノはフッサールの認識論に対する弁証法的批判に取り組んだ。この頃、社会研究所は ニューヨークに移転し、アドルノに接近を始めていた。ホルクハイマーとアドルノは、数ヵ月にわたる緊張した関係の後、パリでの会合で本質的な理論的同盟関 係を再構築した。アドルノは音楽に関する執筆を続け、ウィーンの音楽雑誌『23』誌に「蓄音機レコードの形式」と「音楽批評の危機」、研究所の『ツァイツ クリフト』誌に「ジャズについて」、『ヨーロッパ歌曲』誌に「ジャズよさらば」を発表した。しかし、音楽社会学から脱却しようとするアドルノの試みは二度 にわたって阻まれた。長年取り組んできたマンハイム研究も、フッサール研究の抜粋も、ツァイトシュリフトには受け入れられなかった。ホルクハイマーの格言 集『夜明けと衰退』に感銘を受けたアドルノは、自身の格言集『ミニマ・モラリア』の執筆に取りかかった。1935年6月に叔母アガーテが亡くなり、同年 12月にベルクが亡くなった。アドルノは最後まで、ベルクの未完のオペラ『ルル』を完成させるという希望を捨てなかった。 この頃、アドルノはヴァルター・ベンヤミンと、ベンヤミンの「アルカデス・プロジェクト」について激しい文通をしていた。ホルクハイマーからニューヨーク の研究所を訪問するよう招待を受けたアドルノは、1937年6月9日にニューヨークに向けて出航し、2週間滞在した。ニューヨーク滞在中、ホルクハイマー のエッセイ「形而上学に対する最新の攻撃」と「伝統的理論と批判的理論」は、やがて研究所の自己理解に有益なものとなり、激しい議論の対象となった。ヨー ロッパに戻った直後、グレーテルはイギリスに移住し、1937年9月8日にアドルノと結婚した。その1ヵ月余り後、ホルクハイマーはニューヨークから電報 で、当時オーストリアの社会学者ポール・ラザースフェルドがディレクターを務めていたプリンストン・ラジオ・プロジェクトにアドルノが参加できるという知 らせを伝えた。しかし、アドルノの仕事はベートーヴェンとリヒャルト・ワーグナーの研究(1939年に『ワーグナーについての断片』として出版)で続いて いた。ベンヤミンによれば、これらの草稿は「その唯物論的解読の正確さ」とともに、「音楽的事実が......私にとってまったく新しい方法で社会的に透 明化された」方法にも驚かされたという。1938年2月16日、アドルノはニューヨークに向けて出航。リバーサイド・ドライブの新居に落ち着いた直後、ア ドルノはニュージャージー州ニューアークでラザースフェルドと会い、放送音楽の影響を調査するプロジェクトの計画について話し合った。 彼はプロジェクトの研究をより広い理論的文脈の中に組み込むことを期待されていたが、すぐに明らかになったのは、プロジェクトは主に、リスナーのグループ を対象にした放送が可能かどうかを確認するために管理者が使用するデータ収集に関心があるということだった。リスナーがボタンを押して、特定の音楽が好き か嫌いかを示す装置を利用することを期待されたアドルノは、嫌悪感と驚きを露わにした: 「私は、文化とは単に、それを測定しようとするメンタリティを排除する条件であると考えた」[27]。こうしてアドルノは、リスナーの反応を調べるために 個人面接を使うことを提案し、ラザースフェルドに会ってからわずか3ヶ月後に、プロジェクトのテーマである "ラジオにおける音楽 "について160ページに及ぶ覚書を完成させた。アドルノは、音楽素材がラジオという媒体を通じて流通することによってどのような影響を受けるのかに第一 の関心を寄せており、音楽が日常生活の一部となることによってどのような影響を受けるのかを理解することが不可欠だと考えていた。「ベートーヴェンの交響 曲の意味は、聴き手が歩き回っているときやベッドに横になっているときに聴くのと、教会にいるかのように座っているコンサートホールで聴くのとでは大きく 異なるだろう」[28]。当然のことながら、アドルノの研究はプロジェクトのメンバーの間ではほとんど共感を得られなかった。1939年末、ラザースフェ ルドが2度目の資金援助申請書を提出したとき、研究の音楽的セクションは省かれた。しかし、プロジェクトに取り組んでいた2年間、アドルノは多作で、『ラ ジオ交響曲』、『ラジオ音楽の社会批判』、『ポピュラー音楽について』を出版している。これらの文章は、覚書の草稿やその他の未発表の文章とともに、ロベ ルト・ヒュロット=ケントールの翻訳『音楽の流れ』に収録されている。このような状況を踏まえ、ホルクハイマーはすぐにアドルノに研究所での永続的なポス トを与えた。 アドルノは『ツァイトシュリフト』を手伝うだけでなく、研究所とベンヤミンとの連絡役となることを期待されていた。ベンヤミンはすぐに、より大きなアルカ デス・プロジェクトのモデルとなることを期待したシャルル・ボードレールの研究をニューヨークに伝えた。文通の中で二人は、ベンヤミンの『技術的複製可能 性の時代における芸術作品』を通して明らかになった、批評と芸術作品の関係に対する考え方の違いについて話し合った。同じ頃、アドルノとホルクハイマー は、後に『啓蒙の弁証法』となる「弁証法的論理学」に関する共同著作の構想を練っていた。アドルノの両親が差別を受け、ベンヤミンがコロンブで抑留されて いるヨーロッパからの報告に警鐘を鳴らしながら、二人は自分たちの仕事の実際的な効果についてほとんど妄想を抱かなかった。「ホルクハイマーは「今ヨー ロッパを飲み込もうとしているものを考えれば、我々の現在の仕事は、本質的に、近づいてくる夜を通して物事を伝える運命にある。スペインのビザが無効であ ることを知り、フランスへの強制送還を恐れたベンヤミンは、モルヒネ錠剤を過剰摂取した。最近の出来事を踏まえて、研究所は反ユダヤ主義とファシズムに関 する理論の策定に着手した。一方は、国家社会主義が「独占資本主義」の一形態であるというフランツ・レオポルド・ノイマンのテーゼを支持する人々であり、 他方はフリードリヒ・ポロックの「国家資本主義理論」を支持する人々であった。この論争に対するホルクハイマーの貢献は、「権威主義的国家」、「理性の終 焉」、「ユダヤ人とヨーロッパ」というエッセイという形で、彼とアドルノが弁証法的論理学の本で計画していたことの基礎となった。 1941年11月、アドルノはホルクハイマーに続いて、トーマス・マンが「ドイツのカリフォルニア」と呼んだ[30]、ベルトルト・ブレヒトやシェーンベ ルクを含むドイツ人移民のパシフィック・パリセーズ地区に家を構えた。アドルノは『ニューミュージックの哲学』の草稿を携えて到着したが、この草稿は十二 音音楽を弁証法的に批判したもので、アドルノはこの草稿を書きながら、それまで何十年もかけて練り上げてきた芸術論からの逸脱を感じていた。この原稿を読 んだホルクハイマーは、「私の人生の中で、何かについて熱意を感じたことがあるとすれば、この時であった」と書いている[31]。1944年5月、ガリ版 刷りの小さな版で『哲学的断片』として初めて出版されたこのテキストは、アムステルダムの出版社Querido Verlagから『啓蒙の弁証法』という決定的なタイトルで出版されるまで、さらに3年の歳月を要した。この「進歩の破壊的側面に関する考察」は、合理性 を自然からの解放とさらなる支配の両方として扱った章、ホメロスの『オデュッセイア』とサド侯爵の解釈、文化産業と反ユダヤ主義の分析を通して進められ た。 共同研究を終えた2人は、ネヴィット・サンフォード率いる世論研究グループやアメリカン・ユダヤ委員会と共同で、反ユダヤ主義と権威主義に関する研究に目 を向けた。これらの研究に沿って、アドルノはカリフォルニアのラジオ伝道師マーティン・ルーサー・トーマスの分析を行った。この種のファシズムのプロパガ ンダは、「人々をありのままに受け止めているにすぎない。今日の標準化された大衆文化の純粋な子どもたちは、自律性と自発性を大いに奪われている」 [32]とアドルノは書いている。 1941年にアメリカが戦争に突入した後、「敵性外国人」に分類されるようになった移民たちの状況は、ますます制限されるようになった。午後8時から午前 6時までの外出と、家から5マイル以上離れた場所への外出を禁じられ、1943年11月まで帰化しなかったアドルノのような移民は、行動を厳しく制限され た。 啓蒙の弁証法』を締めくくる格言集に加え、アドルノはホルクハイマーの50歳の誕生日を記念して格言集をまとめ、後に『ミニマ・モラリア』として出版し た: Reflections from Damaged Life』として出版された。ニーチェの再読に触発されたこれらの断片的な文章は、移民、全体主義、個性といった問題や、プレゼントを贈ること、住居、愛 の不可能性といった日常的な問題を扱っていた。カリフォルニアでアドルノはチャーリー・チャップリンと知り合い、フリッツ・ラングやハンス・アイスラーと 親しくなり、1944年には彼らとともに映画音楽の研究を完成させた。この研究の中で、著者たちは映画における前衛音楽の活用を推し進め、映画の映像的側 面を単に伴奏するのではなく、それを補完するために音楽を使うよう求めた。アドルノはまた、トーマス・マンの小説『ファウストゥス独裁者』の執筆にも協力 した。「この作品、つまりレヴァーキューンの作品がどのように見えるか、あなたが悪魔と手を組んだらどうするか、私と一緒に考えていただけませんか」 [33]。 1949年10月末、アドルノは『権威主義的人格』が出版されるのと時を同じくして、アメリカからヨーロッパに向かった。帰国する前に、アドルノは『新し い音楽の哲学』の増補版を印刷することでチュービンゲンの出版社と合意し、2つの作品を完成させていた: シュテファン・ジョルジュによる声楽とピアノのための4つの歌曲(op.7)と、テオドール・ドーブラーの詩による女声合唱のための3つの合唱曲 (op.8)である。 |
| Postwar Europe Return to Frankfurt University Upon his return, Adorno helped shape the political culture of West Germany. Until his death in 1969, twenty years after his return, Adorno contributed to the intellectual foundations of the Federal Republic, as a professor at Frankfurt University, critic of the vogue enjoyed by Heideggerian philosophy, partisan of critical sociology, and teacher of music at the Darmstadt International Summer Courses for New Music. Adorno resumed his teaching duties at the university soon after his arrival,[when?] with seminars on "Kant's Transcendental Dialectic", aesthetics, Hegel, "Contemporary Problems in the Theory of Knowledge", and "The Concept of Knowledge". Adorno's surprise at his students' passionate interest in intellectual matters did not, however, blind him to continuing problems within Germany: The literary climate was dominated by writers who had remained in Germany during Hitler's rule, the government re-employed people who had been active in the Nazi apparatus and people were generally loath to own up to their own collaboration or the guilt they thus incurred. Instead, the ruined city of Frankfurt continued as if nothing had happened,[citation needed] holding on to ideas of the true, the beautiful, and the good despite the atrocities, hanging on to a culture that had itself been lost in rubble or killed off in the concentration camps. All the enthusiasm Adorno's students showed for intellectual matters could not erase the suspicion that, in the words of Max Frisch, culture had become an "alibi" for the absence of political consciousness.[34] Yet the foundations for what would come to be known as "The Frankfurt School" were soon laid: Horkheimer resumed his chair in social philosophy and the Institute for Social Research, rebuilt, became a lightning rod for critical thought. Essays on fascism Starting with his 1947 essay Wagner, Nietzsche and Hitler,[35] Adorno produced a series of influential works to describe psychological fascist traits. One of these works was The Authoritarian Personality (1950),[36] published as a contribution to the Studies in Prejudice performed by multiple research institutes in the US, and consisting of 'qualitative interpretations' that uncovered the authoritarian character of test persons through indirect questions.[citation needed] The books have had a major influence on sociology and remain highly discussed and debated. In 1951 he continued on the topic with his essay Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda, in which he said that "Psychological dispositions do not actually cause fascism; rather, fascism defines a psychological area which can be successfully exploited by the forces which promote it for entirely non-psychological reasons of self-interest."[37] In 1952 Adorno participated in a group experiment, revealing residual National Socialist attitudes among the recently democratized Germans. He then published two influential essays, The Meaning of Working Through the Past (1959), and Education after Auschwitz (1966), in which he argued on the survival of the uneradicated National Socialism in the mindsets and institutions of the post-1945 Germany, and that there is still a real risk that it could rise again.[38] Later on, however, Jean Améry—who had been tortured at Auschwitz—would sharply object that Adorno, rather than addressing such political concerns, was exploiting Auschwitz for his metaphysical phantom "absolute negativity" ("absolute Negativität"), using a language intoxicated by itself ("von sich selber bis zur Selbstblendung entzückte Sprache").[39] Public events In September 1951 Adorno returned to the United States for a six-week visit, during which he attended the opening of the Hacker Psychiatry Foundation in Beverly Hills, met Leo Löwenthal and Herbert Marcuse in New York and saw his mother for the last time. After stopping in Paris, where he met Daniel-Henry Kahnweiler, Michel Leiris and René Leibowitz, Adorno delivered a lecture entitled "The Present State of Empirical Social Research in Germany" at a conference on opinion research. Here he emphasized the importance of data collection and statistical evaluation while asserting that such empirical methods have only an auxiliary function and must lead to the formation of theories which would "raise the harsh facts to the level of consciousness."[40] With Horkheimer as dean of the Arts Faculty, then rector of the university, responsibilities for the institute's work fell upon Adorno. At the same time, however, Adorno renewed his musical work: with talks at the Kranichsteiner Musikgesellschaft, another in connection with a production of Ernst Krenek's opera Leben des Orest, and a seminar on "Criteria of New Music" at the Fifth International Summer Course for New Music at Kranichstein. Adorno also became increasingly involved with the publishing house of Peter Suhrkamp, inducing the latter to publish Benjamin's Berlin Childhood Around 1900, Kracauer's writings and a two-volume edition of Benjamin's writings. Adorno's own recently published Minima Moralia was not only well received in the press, but also met with great admiration from Thomas Mann, who wrote to Adorno from America in 1952: I have spent days attached to your book as if by a magnet. Every day brings new fascination ... concentrated nourishment. It is said that the companion star to Sirius, white in colour, is made of such dense material that a cubic inch of it would weigh a tonne here. This is why it has such an extremely powerful gravitational field; in this respect it is similar to your book.[41] Yet Adorno was no less moved by other public events: protesting the publication of Heinrich Mann's novel Professor Unrat with its film title, The Blue Angel; declaring his sympathy with those who protested the scandal of big-game hunting and penning a defense of prostitutes. More essays on mass culture and literature Because Adorno's American citizenship would have been forfeited by the middle of 1952 had he continued to stay outside the country, he returned once again to Santa Monica to survey his prospects at the Hacker Foundation. While there he wrote a content analysis of newspaper horoscopes (now collected in The Stars Down to Earth), and the essays "Television as Ideology" and "Prologue to Television"; even so, he was pleased when, at the end of ten months, he was enjoined to return as co-director of the institute. Back in Frankfurt, he renewed his academic duties and, from 1952 to 1954, completed three essays: "Notes on Kafka", "Valéry Proust Museum", and an essay on Schoenberg following the composer's death, all of which were included in the 1955 essay collection Prisms. In response to the publication of Thomas Mann's The Black Swan, Adorno penned a long letter to the author, who then approved its publication in the literary journal Akzente. A second collection of essays, Notes to Literature, appeared in 1958. After meeting Samuel Beckett while delivering a series of lectures in Paris the same year, Adorno set to work on "Trying to Understand Endgame", which, along with studies of Proust, Valéry, and Balzac, formed the central texts of the 1961 publication of the second volume of his Notes to Literature. Adorno's entrance into literary discussions continued in his June 1963 lecture at the annual conference of the Hölderlin Society. At the Philosophers' Conference of October 1962 in Münster, at which Habermas wrote that Adorno was "A writer among bureaucrats", Adorno presented "Progress".[42] Although the Zeitschrift was never revived, the Institute nevertheless published a series of important sociological books, including Sociologica (1955), a collection of essays, Gruppenexperiment (1955), Betriebsklima, a study of work satisfaction among workers in Mannesmann, and Soziologische Exkurse, a textbook-like anthology intended as an introductory work about the discipline. Public figure Throughout the fifties and sixties, Adorno became a public figure, not simply through his books and essays, but also through his appearances in radio and newspapers. In talks, interviews, and round-table discussions broadcast on Hessen Radio, South-West Radio, and Radio Bremen, Adorno discussed topics as diverse as "The Administered World" (September 1950), "What is the Meaning of 'Working Through the Past?"' (February 1960) to "The Teaching Profession and its Taboos" (August 1965). Additionally, he frequently wrote for Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau, and the weekly Die Zeit. At the invitation of Wolfgang Steinecke, Adorno took part in the Darmstadt Summer Courses for New Music in Kranichstein from 1951 to 1958. Yet conflicts between the so-called Darmstadt school, which included composers like Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Bruno Maderna, Karel Goeyvaerts, Luciano Berio and Gottfried Michael Koenig, soon arose, receiving explicit expression in Adorno's 1954 lecture, "The Aging of the New Music", where he argued that atonality's freedom was being restricted to serialism in much the same way as it was once restricted by twelve-tone technique. With his friend Eduard Steuermann, Adorno feared that music was being sacrificed to stubborn rationalization. During this time Adorno not only produced a significant series of notes on Beethoven (which was never completed and only published posthumously), but also published Mahler: A Musical Physiognomy in 1960. In his 1961 return to Kranichstein, Adorno called for what he termed a "musique informelle", which would possess the ability "really and truly to be what it is, without the ideological pretense of being something else. Or rather, to admit frankly the fact of non-identity and to follow through its logic to the end."[43] Post-war German culture At the same time Adorno struck up relationships with contemporary German-language poets such as Paul Celan and Ingeborg Bachmann. Adorno's 1949 dictum—"To write poetry after Auschwitz is barbaric"—posed the question of what German culture could mean after Auschwitz; his own continual revision of this dictum—in Negative Dialectics, for example, he wrote that "Perennial suffering has as much right to expression as a tortured man has to scream"; while in "Commitment", he wrote in 1962 that the dictum "expresses in negative form the impulse which inspires committed literature"—was part of post-war Germany's struggle with history and culture. Adorno additionally befriended the writer and poet Hans Magnus Enzensberger as well as the film-maker Alexander Kluge. In 1963, Adorno was elected to the post of chairman of the German Sociological Society, where he presided over two important conferences: in 1964, on "Max Weber and Sociology" and in 1968 on "Late Capitalism or Industrial Society". A debate launched in 1961 by Adorno and Karl Popper, later published as the Positivist Dispute in German Sociology, arose out of disagreements at the 1959 14th German Sociology Conference in Berlin. Adorno's critique of the dominant climate of post-war Germany was also directed against the pathos that had grown up around Heideggerianism, as practiced by writers like Karl Jaspers and Otto Friedrich Bollnow, and which had subsequently seeped into public discourse. His 1964 publication of The Jargon of Authenticity took aim at the halo such writers had attached to words like "angst", "decision" and "leap". After seven years of work, Adorno completed Negative Dialectics in 1966, after which, during the summer semester of 1967 and the winter semester of 1967–68, he offered regular philosophy seminars to discuss the book chapter by chapter. Among the students at these seminars were the Americans Angela Davis and Irving Wohlfarth. One objection, which would soon take on ever greater importance, was that critical thought must adopt the standpoint of the oppressed, to which Adorno replied that negative dialectics was concerned "with the dissolution of standpoint thinking itself." Confrontations with students At the time of Negative Dialectics' publication, student protests fragilized West German democracy. Trends in the media, an educational crisis in the universities, the Shah of Iran's 1967 state visit, German support for the war in Vietnam and the emergency laws combined to create a highly unstable situation. Like many of his students, Adorno too opposed the emergency laws, as well as the war in Vietnam, which, he said, proved the continued existence of the "world of torture that had begun in Auschwitz".[44] The situation only deteriorated with the police shooting of Benno Ohnesorg at a protest against the Shah's visit. This death, as well as the subsequent acquittal of the responsible officer, were both commented upon in Adorno's lectures. As politicization increased, rifts developed within both the institute's relationship with its students as well as within the Institute itself. Soon Adorno himself would become an object of the students' ire. At the invitation of Péter Szondi, Adorno was invited to the Free University of Berlin to give a lecture on Goethe's Iphigenie in Tauris. After a group of students marched to the lectern, unfurling a banner that read "Berlin's left-wing fascists greet Teddy the Classicist", a number of those present left the lecture in protest after Adorno refused to abandon his talk in favour of discussing his attitude on the current political situation. Adorno shortly thereafter participated in a meeting with the Berlin Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS) and discussed "Student Unrest" with Szondi on West German Radio. But as 1968 progressed, Adorno became increasingly critical of the students' disruptions to university life. His isolation was only compounded by articles published in the magazine alternative, which, following the lead of Hannah Arendt's articles in Merkur, claimed Adorno had subjected Benjamin to pressure during his years of exile in Berlin and compiled Benjamin's Writings and Letters with a great deal of bias. In response, Benjamin's longtime friend Gershom Scholem, wrote to the editor of Merkur to express his disapproval of the "in part, shameful, not to say disgraceful" remarks by Arendt.[45] Relations between students and the West German state continued deteriorating. In spring 1968, a prominent SDS spokesman, Rudi Dutschke, was gunned down in the streets; in response, massive demonstrations took place, directed in particular against the Springer Press, which had led a campaign to vilify the students. An open appeal published in Die Zeit, signed by Adorno, called for an inquiry into the social reasons that gave rise to this assassination attempt as well as an investigation into the Springer Press' manipulation of public opinion. At the same time, however, Adorno protested against disruptions of his own lectures and refused to express his solidarity with their political goals, maintaining instead his autonomy as a theoretician. Adorno rejected the so-called unity of theory and praxis advocated by the students and argued that the students' actions were premised upon a mistaken analysis of the situation. The building of barricades, he wrote to Marcuse, is "ridiculous against those who administer the bomb."[46] Adorno would refer to the radical students as stormtroopers (Sturmabteilung) in jeans."[47] In September 1968 Adorno went to Vienna for the publication of Alban Berg: Master of the Smallest Link. Upon his return to Frankfurt, events prevented his concentrating upon the book on aesthetics he wished to write: "Valid student claims and dubious actions", he wrote to Marcuse, "are all so mixed up together that all productive work and even sensible thought are scarcely possible any more."[48] After striking students threatened to strip the institute's sociology seminar rooms of their furnishings and equipment, the police were brought in to close the building. Later years Adorno began writing an introduction to a collection of poetry by Rudolf Borchardt, which was connected with a talk entitled "Charmed Language", delivered in Zürich, followed by a talk on aesthetics in Paris where he met Beckett again. Beginning in October 1966, Adorno took up work on Aesthetic Theory. In June 1969 he completed Catchwords: Critical Models. During the winter semester of 1968–69 Adorno was on sabbatical leave from the university and thus able to dedicate himself to the completion of his book of aesthetics. For the summer semester Adorno planned a lecture course entitled "An Introduction to Dialectical Thinking", as well as a seminar on the dialectics of subject and object. But at the first lecture Adorno's attempt to open up the lecture and invite questions whenever they arose degenerated into a disruption from which he quickly fled: after a student wrote on the blackboard "If Adorno is left in peace, capitalism will never cease", three women students approached the lectern, bared their breasts and scattered flower petals over his head.[49] Yet Adorno continued to resist blanket condemnations of the protest movement which would have only strengthened the conservative thesis according to which political irrationalism was the result of Adorno's teaching. After further disruptions to his lectures, Adorno canceled the lectures for the rest of the seminar, continuing only with his philosophy seminar. In the summer of 1969, weary from these activities, Adorno returned once again to Zermatt, Switzerland, at the foot of Matterhorn to restore his strength. On August 6 he died of a heart attack. |
戦後ヨーロッパ フランクフルト大学に戻る 帰国後、アドルノは西ドイツの政治文化の形成に貢献した。帰国から20年後の1969年に亡くなるまで、アドルノはフランクフルト大学教授、ハイデガー哲 学の流行の批判者、批判的社会学の党員、ダルムシュタット国際ニューミュージック夏期講習会の音楽教師として、連邦共和国の知的基盤に貢献した。カントの 超越論的弁証法」、美学、ヘーゲル、「知識論における現代的問題」、「知識の概念」などのセミナーを行った。しかし、学生たちの知的問題への情熱的な関心 に驚いたアドルノが、ドイツ国内で続く問題に目をつぶることはなかった: 文学界はヒトラーの支配下にあったドイツに残った作家たちによって支配され、政府はナチス組織で活躍した人々を再雇用し、人々は一般的に自分たちの協力や それによって負った罪について認めたがらなかった。その代わりに、廃墟と化したフランクフルトの街は何事もなかったかのように、残虐行為にもかかわらず、 真、美、善の観念を持ち続け[要出典]、それ自体が瓦礫の中で失われたか、強制収容所で消滅した文化にしがみついていた。マックス・フリッシュの言葉を借 りれば、文化は政治意識の不在のための「アリバイ」となっていたのではないかという疑念を、アドルノの学生たちが知的な問題に熱意を示しても、消し去るこ とはできなかった: ホルクハイマーは社会哲学の講座を再開し、再建された社会研究所は批判的思想の避雷針となった。 ファシズムに関するエッセイ 1947年に発表したエッセイ『ワーグナー、ニーチェ、ヒトラー』[35]を皮切りに、アドルノはファシストの心理的特質について述べた一連の影響力のあ る著作を発表した。これらの著作のひとつは『権威主義的パーソナリティ』(1950年)であり[36]、アメリカの複数の研究機関によって行われた『偏見 研究』への貢献として出版され、間接的な質問を通してテスト対象者の権威主義的性格を明らかにする「質的解釈」から構成されている[要出典]。 この著作は社会学に大きな影響を与え、現在でも非常に議論され残っている。1951年、彼はエッセイ『フロイト理論とファシストのプロパガンダのパター ン』でこのトピックを継続し、その中で彼は「心理的な気質は実際にはファシズムを引き起こすのではなく、むしろファシズムは、それを推進する勢力によっ て、利己主義というまったく心理学的でない理由からうまく利用されうる心理的領域を定義しているのである」と述べている[37]。 1952年、アドルノはグループ実験に参加し、民主化されたばかりのドイツ人の中に国家社会主義的な態度が残っていることを明らかにした。その後、彼は 『過去を通して働くことの意味』(1959年)と『アウシュヴィッツ以後の教育』(1966年)という2つの影響力のあるエッセイを発表し、その中で、 1945年以降のドイツの考え方や制度には、根絶されていない国家社会主義が存続しており、それが再び台頭する現実的なリスクが残っていると主張した [38]。 [しかしその後、アウシュヴィッツで拷問を受けたジャン・アメリは、アドルノはそのような政治的関心に取り組むのではなく、それ自体に酔いしれた言語 ("von sich selber bis zur Selbstblendung entzückte Sprache")を使い、形而上学的な幻影である「絶対否定性」("absolute Negativität")のためにアウシュヴィッツを利用していると鋭く反論することになる[39]。 公的な出来事 1951年9月、アドルノは6週間の予定でアメリカに戻り、ビバリーヒルズのハッカー精神医学財団のオープニングに出席し、ニューヨークでレオ・レーヴェ ンタールとヘルベルト・マルクーゼに会い、母親と最後の再会を果たす。パリに立ち寄り、ダニエル=ヘンリー・カーンヴァイラー、ミシェル・レイリス、ル ネ・ライボヴィッツに会った後、アドルノは世論調査に関する会議で「ドイツにおける実証的社会調査の現状」と題する講演を行った。ここで彼はデータ収集と 統計的評価の重要性を強調する一方で、そのような経験的手法は補助的な機能しか持たず、「過酷な事実を意識のレベルにまで引き上げる」ような理論の形成に つながらなければならないと主張していた[40]。 ホルクハイマーが芸術学部長、そして学長に就任したことで、研究所の活動に対する責任はアドルノに課せられた。クラーニヒシュタイナー音楽協会での講演、 エルンスト・クレーネクのオペラ『オレストの人生』の上演に関連した講演、クラーニヒシュタインで開催された第5回国際ニューミュージック夏期講習会での 「ニューミュージックの基準」に関するセミナーなどである。アドルノはまた、ペーター・スールカンプの出版社との関わりを深め、ベンヤミンの『1900年 前後のベルリン幼年時代』、クラカウアーの著作、ベンヤミンの著作の2巻からなる版を出版するよう働きかけた。アドルノ自身が最近出版した『ミニマ・モラ リア』はマスコミで好評を博しただけでなく、1952年にアメリカからアドルノに手紙を書いたトーマス・マンからも絶賛された: 私はまるで磁石に吸い寄せられるように、あなたの本と何日もつきあってきた。毎日が新たな魅力をもたらしてくれる......濃縮された栄養を。シリウス の伴星は白色で、1立方インチの重さがここでは1トンになるような高密度の物質でできていると言われている。この点で、あなたの本と似ている」[41]。 ハインリヒ・マンの小説『プロフェッサー・ウンラット』が映画『青い天使』のタイトルで出版されたことに抗議したり、大物狩猟のスキャンダルに抗議する人々に同調したり、娼婦を擁護する文章を書いたりした。 大衆文化と文学に関するその他のエッセイ 国外に留まり続ければ、1952年半ばにはアドルノのアメリカ市民権は失効していたため、彼はハッカー財団での展望を調査するために再びサンタモニカに 戻った。その間に彼は、新聞の星占いの内容分析(現在は『The Stars Down to Earth』に収録)、エッセイ『イデオロギーとしてのテレビジョン』、『テレビジョンへのプロローグ』を書いた。 フランクフルトに戻った彼は、学問的な仕事を再開し、1952年から1954年にかけて、「カフカについてのノート」、「ヴァレリー・プルースト博物 館」、そして作曲家の死後シェーンベルクについてのエッセイの3本を書き上げ、これらはすべて1955年のエッセイ集『Prisms』に収録された。トー マス・マンの『黒い白鳥』が出版されたのを受けて、アドルノは作者に宛てて長い手紙を書き、作者はそれを文芸誌『アクツェンテ』に掲載することを承認し た。1958年には2冊目のエッセイ集『文学ノート』が刊行された。同年、パリで連続講演を行ったサミュエル・ベケットと出会い、アドルノは『エンドゲー ムを理解しようとする』の執筆に取りかかった。この作品は、プルースト、ヴァレリー、バルザックに関する研究とともに、1961年に出版された『文学ノー ト』第2巻の中心的なテキストとなった。1963年6月、ヘルダーリン協会の年次大会での講演でも、アドルノの文学論への参入は続いた。1962年10月 にミュンスターで開催された哲学者会議では、ハーバーマスがアドルノを「官僚のなかの作家」と書いたが、アドルノは「進歩」を発表した[42]。 Zeitschriftが復活することはなかったが、それでも研究所は、エッセイ集『Sociologica』(1955年)、 『Gruppenexperiment』(1955年)、マンネスマンにおける労働者の労働満足度に関する研究『Betriebsklima』、学問の入 門書として意図された教科書のようなアンソロジー『Soziologische Exkurse』など、一連の重要な社会学書を出版した。 公人 50年代から60年代にかけて、アドルノは著書やエッセイだけでなく、ラジオや新聞にも出演し、公人となった。ヘッセンラジオ、南西ラジオ、ラジオ・ブ レーメンで放送された対談、インタビュー、座談会で、アドルノは「管理された世界」(1950年9月)、「『過去を通して働く』ことの意味とは何か? (1960年2月)から「教職とそのタブー」(1965年8月)まで。さらに、フランクフルター・アルゲマイネ、フランクフルター・ルンチャウ、週刊誌 『ディ・ツァイト』にも頻繁に寄稿した。 ヴォルフガング・シュタイネッケの招きで、アドルノは1951年から1958年までクラニヒシュタインで開催されたダルムシュタット夏期講習会に参加し た。しかし、ピエール・ブーレーズ、カールハインツ・シュトックハウゼン、ルイジ・ノーノ、ブルーノ・マデルナ、カレル・ゲーヴェールツ、ルチアーノ・ベ リオ、ゴットフリート・ミヒャエル・ケーニッヒといった作曲家を含む、いわゆるダルムシュタット学派の対立はすぐに生まれ、1954年のアドルノの講義 「ニューミュージックの老い」で明確な表現がなされた。アドルノは友人のエドゥアルド・シュテュアマンとともに、音楽が頑迷な合理化の犠牲にされることを 恐れた。この時期、アドルノはベートーヴェンに関する重要な一連の注釈書(これは完成せず、死後に出版されたのみ)を作成しただけでなく、1960年には 『マーラー:音楽的人相学』を出版した。1961年のクラニヒシュタインへの回帰の中で、アドルノは「アンフォルメル音楽(musique informelle)」と呼ぶものを求めた。というよりも、非同一性という事実を率直に認め、その論理を最後まで貫くこと」[43]。 戦後のドイツ文化 同じ頃、アドルノはパウル・ツェランやインゲボルグ・バッハマンといったドイツ語の現代詩人たちと交流を持っていた。1949年、アドルノは「アウシュ ヴィッツの後に詩を書くことは野蛮である」という独断を発表し、アウシュヴィッツの後にドイツ文化は何を意味しうるのかという問いを投げかけた。アドルノ はこの独断を絶えず修正し続け、例えば『否定弁証法』では「拷問を受けた人間が悲鳴を上げるのと同じように、永続的な苦しみにも表現する権利がある」と書 き、1962年には『コミットメント』で、この独断は「コミットメント文学を鼓舞する衝動を否定的な形で表現している」と書いている。さらにアドルノは、 作家で詩人のハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーや映画監督のアレクサンダー・クルーゲとも親交を深めた。 1963年、アドルノはドイツ社会学会の会長に選出され、1964年には「マックス・ウェーバーと社会学」、1968年には「後期資本主義か産業社会か」 という2つの重要な会議を主宰した。アドルノとカール・ポパーが1961年に開始した論争は、後に「ドイツ社会学における実証主義論争」として出版される が、これは1959年にベルリンで開催された第14回ドイツ社会学会議での意見の相違から生じたものである。 戦後ドイツの支配的な風潮に対するアドルノの批判は、カール・ヤスパースやオットー・フリードリヒ・ボルナウのような作家によって実践されたハイデガー主 義にまつわるパトスにも向けられていた。1964年に出版された『The Jargon of Authenticity(真正性の専門用語)』は、そうした作家たちが「苦悩」、「決断」、「飛躍」といった言葉につけていた後光を狙い撃ちした。その 後、1967年の夏学期と1967年から68年の冬学期にかけて、彼は定期的に哲学セミナーを開き、本書の各章について議論した。これらのセミナーの受講 生の中には、アメリカ人のアンジェラ・デイヴィスやアーヴィング・ウォールファースもいた。やがて重要性を増すことになる反論のひとつは、批判的思考は被 抑圧者の立場を採用しなければならないというものであったが、それに対してアドルノは、否定弁証法は "立場的思考そのものの解消 "に関係していると答えた。 学生たちとの対立 否定弁証法』が出版された当時、西ドイツの民主主義は学生の抗議運動によって脆弱化していた。メディアの動向、大学の教育危機、1967年のイラン国王の 国賓訪問、ベトナム戦争へのドイツの支持、有事法制などが相まって、非常に不安定な状況が生まれていた。多くの学生たちと同様、アドルノも有事法制に反対 し、ベトナム戦争にも反対していた。この死と、その後の責任者の無罪判決は、いずれもアドルノの講義で論評された。政治化が進むにつれ、研究所と学生との 関係にも、研究所自体にも亀裂が生じた。やがて、アドルノ自身も学生たちの怒りの対象となった。ペテル・ゾンディの招きで、アドルノはベルリン自由大学に 招かれ、ゲーテの『タウリスのイフィゲニー』について講義を行った。学生たちが「ベルリンの左翼ファシストが古典主義者テディを出迎える」という横断幕を 掲げて講義席まで行進した後、アドルノが現在の政治状況についての態度を論じるために講演を放棄することを拒否したため、出席者の多くが抗議のために講義 を退席した。アドルノはその後まもなく、ベルリンのドイツ学生同盟(SDS)との会合に参加し、西ドイツのラジオでションディと『学生の不安』について議 論した。しかし、1968年が進むにつれて、アドルノは学生による大学生活の混乱に批判的な姿勢を強めていった。雑誌『オルタナティヴ』に掲載された記事 は、『メルクール』誌に掲載されたハンナ・アーレントの記事に倣い、アドルノがベルリンに亡命していた数年間にベンヤミンに圧力をかけ、『ベンヤミンの著 作と書簡』をかなりの偏りをもって編纂したと主張した。これに対し、ベンヤミンの長年の友人であるゲルショム・ショレムは、『メルクール』誌の編集者に手 紙を送り、アーレントの「不名誉とまでは言わないまでも、恥ずべき部分もある」発言に賛意を表明した[45]。 学生と西ドイツ国家との関係は悪化の一途をたどっていた。1968年春、SDSの著名なスポークスマンであったルディ・ドゥチュケが路上で射殺された。こ れに対して、特に学生を中傷するキャンペーンを主導していたシュプリンガー新聞社に対して大規模なデモが行われた。Die Zeit』紙に掲載されたアドルノの署名入りの公開アピールは、この暗殺未遂事件を引き起こした社会的理由の究明と、シュプリンガー新聞社の世論操作の究 明を求めた。しかし同時に、アドルノは自身の講義が妨害されたことに抗議し、彼らの政治的目的への連帯を表明することを拒否し、代わりに理論家としての自 律性を維持した。アドルノは、学生たちの主張するいわゆる理論と実践の一致を否定し、学生たちの行動は誤った状況分析に基づいていると主張した。バリケー ドの建設は「爆弾を管理する者に対しては馬鹿げている」[46]とマルクーゼに書いている。アドルノは急進的な学生たちをジーンズのストームトルーパー (Sturmabteilung)と呼ぶようになる。 1968年9月、アドルノは『アルバン・ベルク:最も小さなリンクの巨匠』の出版のためにウィーンに向かった。フランクフルトに戻ると、彼が書きたかった 美学の本に集中することを妨げる出来事が起こった: 「有効な学生の主張と怪しげな行動が混ざり合い、生産的な仕事と賢明な思考さえもほとんど不可能になっている」とマルクーゼに手紙を書いている[48]。 ストライキを起こした学生たちが研究所の社会学セミナー室の備品や器具をはぎ取ると脅したため、警察は建物を閉鎖するために出動した。 後年 アドルノは、ルドルフ・ボルヒャルトの詩集の序文を書き始め、チューリッヒで行われた「魅惑された言語」と題された講演に関連し、その後、パリで美学に関 する講演を行い、そこでベケットと再会する。1966年10月、アドルノは『美学理論』の執筆に取りかかる。1969年6月、『キャッチ・ワード』を完 成: 批評モデル』。1968年から69年にかけての冬学期、アドルノは大学をサバティカル休暇で離れていたため、美学書の完成に専念することができた。 夏学期、アドルノは「弁証法的思考入門」と題する講義と、主体と客体の弁証法に関するセミナーを計画した。しかし、最初の講義でアドルノは、講義をオープ ンにし、質問が出るたびに呼びかけようとしたが、すぐに逃げ出した。学生が黒板に「アドルノを安らかに放置すれば、資本主義は決してなくならない」と書い た後、3人の女子学生が教壇に近づき、胸をあらわにし、彼の頭上に花びらを散らした[49]。 しかし、アドルノは、政治的非合理主義がアドルノの教えの結果であるという保守的なテーゼを強化するだけであろう、抗議運動に対する包括的な非難に抵抗し 続けた[49]。さらに講義が中断された後、アドルノは残りのゼミの講義をキャンセルし、哲学ゼミだけを続けた。1969年夏、これらの活動に疲れ果てた アドルノは、体力を回復するために再びスイスのツェルマット(マッターホルンの麓)に戻った。8月6日、彼は心臓発作で亡くなった。 |
| Intellectual influences Like most theorists of the Frankfurt School, Adorno was influenced by the works of Hegel, Marx and Freud. Their major theories fascinated many left-wing intellectuals in the first half of the 20th century. Lorenz Jäger speaks critically of Adorno's "Achilles' heel" in his political biography: that Adorno placed "almost unlimited trust in finished teachings, in Marxism, psychoanalysis, and the teachings of the Second Viennese School."[50] Hegel Adorno's adoption of Hegelian philosophy can be traced back to his inaugural lecture in 1931, in which he postulated: "only dialectically does philosophical interpretation seem possible to me" (Gesammelte Schriften 1: 338). Hegel rejected the idea of separating methods and content, because thinking is always thinking of something; dialectics for him is "the comprehended movement of the object itself."[51] Like Gerhard Schweppenhäuser [de], Adorno adopted this claim as his own, and based his thinking on one of the Hegelian basic categories, the determinate negation,[52] according to which something is not abstractly negated and dissolved into zero, but is preserved in a new, richer concept through its opposite.[53] Adorno understood his Three Studies of Hegel as "preparation of a changed definition of dialectics" and that they stop "where the start should be" (Gesammelte Schriften 5: 249 f.). Adorno dedicated himself to this task in one of his later major works, the Negative Dialectics (1966). The title expresses "tradition and rebellion in equal measure."[54] Drawing from Hegelian reason's speculative dialectic, Adorno developed his own "negative" dialectic of the "non-identical."[55] Karl Marx Marx's Critique of Political Economy clearly shaped Adorno's thinking. As described by Jürgen Habermas, Marxist critique is, for Adorno, a "silent orthodoxy, whose categories [are revealed] in Adorno's cultural critique, although their influence is not explicitly named."[56] Marx's influence on Adorno first came by way of György Lukács's History and Class Consciousness (Geschichte und Klassenbewußtsein); from this text, Adorno took the Marxist categories of commodity fetishism and reification. These are closely related to Adorno's concept of trade, which stands in the center of his philosophy, not exclusively restricted to economic theory. Adorno's "exchange society" (Tauschgesellschaft), with its "insatiable and destructive appetite for expansion", is easily decoded as a description of capitalism.[57] Furthermore, the Marxist concept of ideology is central for Adorno.[58] Class theory, which appears less frequently in Adorno's work, also has its origins in Marxist thinking. Adorno made explicit reference to class in two of his texts: the first, the subchapter "Classes and Strata" (Klassen und Schichten), from his Introduction to the Sociology of Music; the second, an unpublished 1942 essay, "Reflections on Class Theory", published postmortem in his Collected Works. Sigmund Freud Psychoanalysis is a constitutive element of critical theory.[59] Adorno read Sigmund Freud's work early on, although, unlike Horkheimer, he had never experienced psychoanalysis in practice.[60] He first read Freud while working on his initial (withdrawn) habilitation thesis, The Concept of the Unconscious in the Transcendental Theory of Mind (1927). In it Adorno argued that "the healing of all neuroses is synonymous with the complete understanding of the meaning of their symptoms by the patient". In his essay "On the Relationship between Sociology and Psychology" (1955), he justified the need to "supplement the theory of society with psychology, especially analytically oriented social psychology" in the face of fascism. Adorno emphasized the necessity of researching prevailing psychological drives in order to explain the cohesion of a repressive society acting against fundamental human interests.[61] Adorno always remained a supporter and defender of Freudian orthodox doctrine, "psychoanalysis in its strict form".[62] From this position, he attacked Erich Fromm[63] and later Karen Horney because of their revisionism. He expressed reservations about sociologized psychoanalysis[64] as well as about its reduction to a therapeutic procedure.[65] Theory Adorno's work sets out from a central insight he shares with all early 20th century avant-garde art: the recognition of what is primitive in ourselves and the world itself. Neither Picasso's fascination with African sculpture nor Mondrian's reduction of painting to its most elementary component—the line—is comprehensible outside this concern with primitivism Adorno shared with the century's most radical art. At that time, the Western world, beset by world-wars, colonialist consolidation and accelerating commodification, sank into the very barbarism civilization had prided itself in overcoming. According to Adorno, society's self-preservation had become indistinguishable from societally sanctioned self-sacrifice: of "primitive" peoples, primitive aspects of the ego and those primitive, mimetic desires found in imitation and sympathy. Adorno's theory proceeds from an understanding of this primitive quality of reality which seeks to counteract whatever aims either to repress this primitive aspect or to further those systems of domination set in place by this return to barbarism. From this perspective, Adorno's writings on politics, philosophy, music and literature are a lifelong critique of the ways in which each tries to justify self-mutilation as the necessary price of self-preservation. According to Adorno's translator Robert Hullot-Kentor, the central motive of Adorno's work thus consists in determining "how life could be more than the struggle for self-preservation".[66] In this sense, the principle of self-preservation, Adorno writes in Negative Dialectics, is nothing but "the law of doom thus far obeyed by history."[67] At its most basic, Adorno's thought is motivated by a fundamental critique of this law. Adorno was chiefly influenced by Max Weber's critique of disenchantment, György Lukács's Hegelian interpretation of Marxism, as well as Walter Benjamin's philosophy of history. Adorno, along with the other major Frankfurt School theorists Max Horkheimer and Herbert Marcuse, argued that advanced capitalism had managed to contain or liquidate the forces that would bring about its collapse and that the revolutionary moment, when it would have been possible to transform it into socialism, had passed. As he put it at the beginning of his Negative Dialectics (1966), philosophy is still necessary because the time to realise it was missed. Adorno argued that capitalism had become more entrenched through its attack on the objective basis of revolutionary consciousness and through liquidation of the individualism that had been the basis of critical consciousness. Adorno, as well as Horkheimer, critiqued all forms of positivism as responsible for technocracy and disenchantment and sought to produce a theory that both rejected positivism and avoided reinstating traditional metaphysics. Adorno and Horkheimer have been criticized for over-applying the term "positivism", especially in their interpretations of Ludwig Wittgenstein and Karl Popper as positivists.[68] Music and the Culture Industry Adorno criticized jazz and popular music, viewing it as part of the culture industry, that contributes to the present sustainability of capitalism by rendering it "aesthetically pleasing" and "agreeable".[69] In his early essays for the Vienna-based journal Anbruch, Adorno claimed that musical progress is proportional to the composer's ability to constructively deal with the possibilities and limitations contained within what he called the "musical material." For Adorno, twelve-tone serialism constitutes a decisive, historically developed method of composition. The objective validity of composition, according to him, rests with neither the composer's genius nor the work's conformity with prior standards, but with the way in which the work coherently expresses the dialectic of the material. In this sense, the contemporary absence of composers of the status of Bach or Beethoven is not the sign of musical regression; instead, new music is to be credited with laying bare aspects of the musical material previously repressed: The musical material's liberation from number, the harmonic series and tonal harmony. Thus, historical progress is achieved only by the composer who "submits to the work and seemingly does not undertake anything active except to follow where it leads." Because historical experience and social relations are embedded within this musical material, it is to the analysis of such material that the critic must turn. In the face of this radical liberation of the musical material, Adorno came to criticize those who, like Stravinsky, withdrew from this freedom by taking recourse to forms of the past as well as those who turned twelve-tone composition into a technique which dictated the rules of composition. Adorno saw the culture industry as an arena in which critical tendencies or potentialities were eliminated. He argued that the culture industry, which produced and circulated cultural commodities through the mass media, manipulated the population. Popular culture was identified as a reason why people become passive; the easy pleasures available through consumption of popular culture made people docile and content, no matter how terrible their economic circumstances. "Capitalist production so confines them, body and soul, that they fall helpless victims to what is offered them."[70] The differences among cultural goods make them appear different, but they are in fact just variations on the same theme. He wrote that "the same thing is offered to everybody by the standardized production of consumption goods" but this is concealed under "the manipulation of taste and the official culture's pretense of individualism".[71] By doing so, the culture industry appeals to every single consumer in a unique and personalized way, all while maintaining minimal costs and effort on their behalf. Consumers purchase the illusion that every commodity or product is tailored to the individual's personal preference, by incorporating subtle modifications or inexpensive "add-ons" in order to keep the consumer returning for new purchases, and therefore more revenue for the corporation system. Adorno conceptualized this phenomenon as pseudo-individualisation and the always-the-same.[citation needed] Adorno's analysis allowed for a critique of mass culture from the left which balanced the critique of popular culture from the right. From both perspectives—left and right—the nature of cultural production was felt to be at the root of social and moral problems resulting from the consumption of culture. However, while the critique from the right emphasized moral degeneracy ascribed to sexual and racial influences within popular culture, Adorno located the problem not with the content, but with the objective realities of the production of mass culture and its effects, e.g. as a form of reverse psychology.[citation needed] Thinkers influenced by Adorno believe that today's society has evolved in a direction foreseen by him, especially in regard to the past (Auschwitz), morals, or the Culture Industry. The latter has become a particularly productive, yet highly contested term in cultural studies. Many of Adorno's reflections on aesthetics and music have only just begun to be debated, as a collection of essays on the subject, many of which had not previously been translated into English, has only recently been collected and published as Essays on Music.[72] Adorno's work in the years before his death was shaped by the idea of "negative dialectics", set out especially in his book of that title. A key notion in the work of the Frankfurt School since Dialectic of Enlightenment had been the idea of thought becoming an instrument of domination that subsumes all objects under the control of the (dominant) subject, especially through the notion of identity, i.e. of identifying as real in nature and society only that which harmonized or fit with dominant concepts, and regarding as unreal or non-existent everything that did not.[citation needed] Adorno's "negative dialectics" was an attempt to articulate a non-dominating thought that would recognize its limitations and accept the non-identity and reality of that which could not be subsumed under the subject's concepts. Indeed, Adorno sought to ground the critical bite of his sociological work in his critique of identity, which he took to be a reification in thought of the commodity form or exchange relation which always presumes a false identity between different things. The potential to criticise arises from the gap between the concept and the object, which can never go into the former without remainder. This gap, this non-identity in identity, was the secret to a critique of both material life and conceptual reflection.[citation needed] Adorno's reputation as a musicologist remains controversial. His sweeping criticisms of jazz[73] and championing of the Second Viennese School in opposition to Stravinsky have caused him to fall out of favour. The distinguished American scholar Richard Taruskin[74] declared Adorno to be "preposterously over-rated." The eminent pianist and critic Charles Rosen saw Adorno's book The Philosophy of New Music as "largely a fraudulent presentation, a work of polemic that pretends to be an objective study."[75] Even a fellow Marxist such as the historian and jazz critic Eric Hobsbawm saw Adorno's writings as containing "some of the stupidest pages ever written about jazz".[76] The British philosopher Roger Scruton saw Adorno as producing "reams of turgid nonsense devoted to showing that the American people are just as alienated as Marxism requires them to be, and that their cheerful life-affirming music is a 'fetishized' commodity, expressive of their deep spiritual enslavement to the capitalist machine."[69] Irritation with Adorno's tunnel vision started even while he was alive. He may have championed Schoenberg, but the composer notably failed to return the compliment: "I have never been able to bear the fellow [...] It is disgusting, by the way, how he treats Stravinsky."[77] Another composer, Luciano Berio said, in interview, "It's not easy to completely refute anything that Adorno writes – he was, after all, one of the most acute, and also one of the most negative intellects to excavate the creativity of the past 150 years... He forgets that one of the most cunning and interesting aspects of consumer music, the mass media, and indeed of capitalism itself, is their fluidity, their unending capacity for adaptation and assimilation."[78] On the other hand, the scholar Slavoj Žižek has written a foreword to Adorno's In Search of Wagner,[79] where Žižek attributes an "emancipatory impulse" to the same book, although Žižek suggests that fidelity to this impulse demands "a betrayal of the explicit theses of Adorno's Wagner study."[80] Writing in the New Yorker in 2014, music critic Alex Ross, argued that Adorno's work has a renewed importance in the digital age: "The pop hegemony is all but complete, its superstars dominating the media and wielding the economic might of tycoons ... Culture appears more monolithic than ever, with a few gigantic corporations—Google, Apple, Facebook, Amazon—presiding over unprecedented monopolies.".[81] Adorno's critique of commercial media capitalism continues to be influential. There is much scholarship influenced by Adorno on how Western entertainment industries strengthen transnational capitalism and reinforce a Western cultural dominance.[82] Adornean critique can be found in works such as Tanner Mirrlees' "The US Empire's Culture Industry" which focus upon how Western commercial entertainment is artificially reinforced by transnational media corporations rather than being a local culture.[83] The five components of recognition Adorno states that a start to understand the recognition in respect of any particular song hit may be made by drafting a scheme which divides the experience of recognition into its different components. All the factors people enumerate are interwoven to a degree that would be impossible to separate from one another in reality. Adorno's scheme is directed towards the different objective elements involved in the experience of recognition, than the actual experience felt for the individual.[84] 1. Vague remembrance 2. Actual identification 3. Subsumption by label 4. Self-reflection and act of recognition 5.Psychological transfer of recognition-authority to the object Marxist criticisms Adorno posits social totality as an automatic system.[85] According to Horst Müller's Kritik der kritischen Theorie ("Critique of Critical Theory"), this assumption is consistent with Adorno's idea of society as a self-regulating system, from which one must escape (but from which nobody can escape). For him it was existent, but inhuman. Müller argues against the existence of such a system and claims that critical theory provides no practical solution for societal change. He concludes that Jürgen Habermas, in particular, and the Frankfurt School in general, misconstrue Marx.[citation needed] Standardization The phenomenon of standardization is "a concept used to characterize the formulaic products of capitalist-driven mass media and mass culture that appeal to the lowest common denominator in pursuit of maximum profit".[86] According to Adorno we inhabit a media culture driven society which has product consumption as one of its main characteristics. Mass media is employed to deliver messages about products and services to consumers in order to convince these individuals to purchase the commodity they are advertising. Standardization consists of the production of large amounts of commodities to then pursue consumers in order to gain the maximum profit possible. They do this, as mentioned above, by individualizing products to give the illusion to consumers that they are in fact purchasing a product or service that was specifically designed for them. Adorno highlights the issues created with the construction of popular music, where different samples of music used in the creation of today's chart-topping songs are put together in order to create, re-create, and modify numerous tracks by using the same variety of samples from one song to another. He makes a distinction between "Apologetic music" and "Critical music". Apologetic music is defined as the highly produced and promoted music of the "pop music" industry: music that is composed of variable parts and interchanged to create several different songs. "The social and psychological functions of popular music [are that it] acts like a social cement"[87] "to keep people obedient and subservient to the status quo of existing power structures."[88] Serious music, according to Adorno, achieves excellence when its whole is greater than the sum of its parts. The example he gives is that of Beethoven's symphonies: "[his] greatness shows itself in the complete subordination of the accidentally private melodic elements to the form as a whole."[88] Standardization not only refers to the products of the culture industry but to the consumers as well: many times every day consumers are bombarded by media advertising. Consumers are pushed and shoved into consuming products and services presented to them by the media system. The masses have become conditioned by the culture industry, which makes the impact of standardization much more important. By not realizing the impact of social media and commercial advertising, the individual is caught in a situation where conformity is the norm. "During consumption the masses become characterized by the commodities which they use and exchange among themselves."[89] Adorno's responses to his critics As a pioneer of a self-reflexive sociology who prefigured Bourdieu's ability to factor in the effect of reflection on the societal object, Adorno realized that some criticism (including deliberate disruption of his classes in the 1960s) could never be answered in a dialogue between equals if, as he seems to have believed, what the naive ethnographer or sociologist thinks of a human essence is always changing over time.[90]  The "Adorno-Ampel" (Adorno-traffic light) on Senckenberganlage, a street which divides the Institute for Social Research from Goethe University Frankfurt—Adorno requested its construction after a pedestrian death in 1962, and it was finally installed 25 years later.[91] |
知的影響 フランクフルト学派の多くの理論家と同様、アドルノもヘーゲル、マルクス、フロイトの著作に影響を受けた。彼らの主要な理論は、20世紀前半の多くの左翼 知識人を魅了した。ローレンツ・イェーガーはその政治伝記の中で、アドルノの「アキレス腱」について批判的に語っている。アドルノは「完成された教え、マ ルクス主義、精神分析、第二ウィーン学派の教えにほとんど無限の信頼を置いていた」[50]。 ヘーゲル アドルノがヘーゲル哲学を採用したのは、1931年の就任講演にまで遡ることができる:「哲学的解釈は弁証法的にのみ可能である」(Gesammelte Schriften 1: 338)。ヘーゲルは方法と内容を分離するという考えを拒絶していたが、それは思考とは常に何かを思考することであり、彼にとって弁証法とは「対象それ自 体の理解された運動」であったからである[51]。ゲルハルト・シュヴェッペンホイザー[デ]と同様に、アドルノもこの主張を自分のものとして採用し、 ヘーゲル的な基本カテゴリーの一つである確定的否定[52]に基づいて思考を行った。 アドルノは彼の『ヘーゲル三論』を「弁証法の定義を変える準備」として理解し、それらは「開始すべきところで」止まっているとしていた (Gesammelte Schriften 5: 249 f.)。アドルノは、後の主要著作の一つである『否定弁証法』(1966年)において、この課題に専念した。このタイトルは「伝統と反抗を等しく」表現し ている[54]。ヘーゲル理性の思弁的弁証法から引き出して、アドルノは「非同一」の彼自身の「否定的」弁証法を発展させた[55]。 カール・マルクス マルクスの『政治経済学批判』は明らかにアドルノの思考を形作った。ユルゲン・ハーバーマスが述べているように、マルクス主義批判はアドルノにとって「沈 黙の正統主義であり、その影響は明確に名指しされてはいないものの、そのカテゴリーはアドルノの文化批判の中で[明らかにされている]」[56]。アドル ノに対するマルクスの影響はまずギェルギ・ルカーチの『歴史と階級意識』(Geschichte und Klassenbewußtsein)によってもたらされた。これらは、経済理論に限定されることなく、彼の哲学の中心に位置するアドルノの貿易概念と密 接に関連している。交換社会」(Tauschgesellschaft)は、その「飽くなき破壊的な拡大欲望」をもっており、資本主義についての記述とし て容易に解読することができる[57]。さらに、マルクス主義的なイデオロギーの概念はアドルノにとって中心的なものである[58]。 階級論はアドルノの著作の中ではあまり頻繁に登場しないが、これもまたマルクス主義的思考に起源を持っている。1つ目は『音楽社会学入門』の「階級と地 層」(Klassen und Schichten)という小章であり、2つ目は1942年の未発表エッセイ「階級論についての考察」(Reflections on Class Theory)である。 ジークムント・フロイト 精神分析は批評理論の構成要素である[59]。 アドルノは早くからジークムント・フロイトの著作を読んでいたが、ホルクハイマーとは異なり、精神分析を実際に体験したことはなかった[60]。 彼が最初にフロイトを読んだのは、最初の(撤回された)ハビリテーション論文『超越論的精神理論における無意識の概念』(1927年)に取り組んでいると きであった。その中でアドルノは、「すべての神経症の治癒は、患者がその症状の意味を完全に理解することと同義である」と主張した。社会学と心理学の関係 について」(1955年)というエッセイでは、ファシズムに直面して「心理学、とりわけ分析志向の社会心理学で社会理論を補う」必要性を正当化した。アド ルノは、人間の根本的な利益に反して行動する抑圧的な社会の結束を説明するために、一般的な心理的衝動を研究する必要性を強調していた[61]。 この立場から、彼はエーリッヒ・フロム[63]や後のカレン・ホーニーをその修正主義のゆえに攻撃していた。彼は社会学化された精神分析[64]やその治療的手続きへの還元について懸念を表明していた[65]。 理論 アドルノの仕事は、彼が20世紀初頭の前衛芸術と共有している中心的な洞察、すなわち自分自身と世界そのものにある原始的なものの認識から出発している。 ピカソがアフリカの彫刻に魅了されたのも、モンドリアンが絵画をその最も基本的な構成要素である線に還元したのも、アドルノがこの世紀で最も先鋭的な芸術 と共有した原始主義への関心なしには理解できない。当時、西洋世界は世界大戦、植民地主義の強化、加速する商品化に悩まされ、文明が克服したと自負してい た野蛮さそのものに沈んでいた。アドルノによれば、社会の自己保存は、社会的に承認された自己犠牲と区別がつかなくなっていた。「原始的な」民族、自我の 原始的な側面、そして模倣や共感に見られる原始的で模倣的な欲望。アドルノの理論は、現実のこのような原始的な性質を理解し、この原始的な側面を抑圧しよ うとするもの、あるいはこのような野蛮への回帰によって設定された支配のシステムを促進しようとするものに対抗しようとするものである。この観点からする と、政治、哲学、音楽、文学に関するアドルノの著作は、それぞれが自己保存の必要な代償として自虐を正当化しようとする方法に対する生涯をかけた批判なの である。アドルノの翻訳者であるロベルト・ヒュロット=ケントールによれば、アドルノの仕事の中心的な動機はこのように「いかにして人生は自己保存のため の闘争以上のものでありうるか」を決定することにある[66]。この意味で、自己保存の原理は「歴史がこれまで従ってきた破滅の法則」にほかならないとア ドルノは『否定弁証法』の中で書いている[67]。アドルノは主にマックス・ウェーバーの幻滅批判、ギョルギー・ルカーチのマルクス主義のヘーゲル的解 釈、ヴァルター・ベンヤミンの歴史哲学から影響を受けていた。アドルノは、フランクフルト学派の他の主要な理論家であるマックス・ホルクハイマーやヘルベ ルト・マルクーゼとともに、先進資本主義はその崩壊をもたらす力をなんとか封じ込め、あるいは清算し、社会主義に転換することが可能であったであろう革命 の瞬間は過ぎ去ったと主張した。彼が『否定弁証法』(1966年)の冒頭で述べたように、哲学が依然として必要なのは、それを実現する時期を逸してしまっ たからである。アドルノは、革命意識の客観的基礎を攻撃し、批判意識の基礎であった個人主義を清算することによって、資本主義がより強固になったと主張し た。アドルノは、ホルクハイマーと同様に、あらゆる形の実証主義をテクノクラシーと幻滅の原因であると批判し、実証主義を否定し、伝統的な形而上学の復権 を避ける理論を生み出そうとした。アドルノとホルクハイマーは、特にルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインとカール・ポパーを実証主義者として解釈する際 に、「実証主義」という言葉を過剰に適用していると批判されている[68]。音楽と文化産業 アドルノはジャズやポピュラー音楽を文化産業の一部とみなし、それが「美的快楽」や「好感」を与えることによって資本主義の現在の持続可能性に寄与していると批判した[69]。 ウィーンを拠点とする雑誌『アンブルッフ』に寄せた初期のエッセイの中で、アドルノは、音楽の進歩は、彼が "音楽的素材 "と呼ぶものの中に含まれる可能性と限界に建設的に対処する作曲家の能力に比例すると主張していた。アドルノにとって、12音による直列主義は、歴史的に 発展した決定的な作曲法である。彼によれば、作曲の客観的妥当性は、作曲家の天才性でも、作品が事前の基準に適合しているかどうかでもなく、作品が素材の 弁証法を首尾一貫して表現しているかどうかにかかっている。この意味で、バッハやベートーヴェンのような地位の作曲家が現代に不在であることは、音楽的後 退の兆候ではない: 音楽素材が数、和声系列、調性和声から解放されたのだ。したがって、歴史的進歩は、"作品に服従し、それが導くところに従う以外には、一見何も積極的に引 き受けない "作曲家によってのみ達成されるのである。歴史的経験と社会的関係は、この音楽的素材の中に埋め込まれているのだから、批評家が目を向けなければならない のは、そうした素材の分析なのである。このように音楽的素材が根本的に解放される中で、アドルノは、ストラヴィンスキーのように過去の形式に依拠すること でこの自由から遠ざかる人々や、12音作曲を作曲のルールを規定する技法に変えてしまう人々を批判するようになった。 アドルノは、文化産業が批判的傾向や潜在性を排除する場であると考えた。彼は、マスメディアを通じて文化商品を生産し流通させる文化産業が、人々を操作し ていると主張した。大衆文化は、人々が受動的になる原因として特定された。大衆文化の消費を通じて得られる安易な快楽は、人々を従順にし、どんなにひどい 経済状況であっても満足させる。「資本主義的生産は、彼らを肉体的にも精神的にも窮屈にし、提供されたものに対して無力な犠牲者となる」[70] 。彼は「標準化された消費財の生産によって、誰にでも同じものが提供される」と書いているが、これは「嗜好の操作と公的な文化による個人主義の見せかけ」 の下に隠されている[71]。そうすることで、文化産業は消費者のために最小限のコストと労力を維持しながら、ユニークで個人化された方法で消費者一人ひ とりにアピールする。消費者は、新たな購入のために消費者をリピートさせ、したがって企業システムにとってより多くの収入を得るために、微妙な修正や安価 な「アドオン」を組み込むことによって、あらゆる商品や製品が個人の好みに合わせて作られているという幻想を購入する。アドルノはこの現象を「擬似個人 化」と「いつも同じもの」として概念化した[要出典]。 アドルノの分析によって、左派からの大衆文化批判が可能になり、右派からの大衆文化批判とバランスをとることができた。左派と右派の両方の視点から、文化 生産の本質が文化の消費から生じる社会的・道徳的問題の根底にあると考えられていた。しかし、右派からの批判が大衆文化における性的・人種的影響に起因す る道徳的退廃を強調するのに対して、アドルノは内容ではなく、例えば逆心理学の一形態としての大衆文化の生産とその影響の客観的現実に問題を置いていた [要出典]。 アドルノの影響を受けた思想家たちは、特に過去(アウシュヴィッツ)、道徳、あるいは文化産業に関して、今日の社会はアドルノが予見した方向に進化したと 考えている。後者は、カルチュラル・スタディーズにおいて、特に生産的でありながら、非常に論争的な用語となっている。美学と音楽に関するアドルノの考察 の多くは、議論され始めたばかりであり、このテーマに関するエッセイ集は、その多くがそれまで英語に翻訳されておらず、最近になってようやく『音楽論』と して収集・出版されたばかりである[72]。 アドルノが亡くなる前の数年間における彼の仕事は、「否定的弁証法」の考え方によって形成されており、特にそのタイトルの著書で述べられている。啓蒙の弁 証法』以降のフランクフルト学派の仕事における重要な概念は、思考が支配の道具となり、すべての対象を(支配的な)主体の支配下に置くという考え方であっ た。アドルノの「否定弁証法」は、その限界を認識し、主体の概念に包摂されないものの非同一性と現実性を受け入れる非支配的な思考を明確にしようとする試 みであった。実際、アドルノは自身の社会学的研究の批評的咬み合わせを、アイデンティティの批評に求めようとした。アイデンティティの批評とは、異なるも のの間に常に誤った同一性を前提とする、商品形態や交換関係の思考における再定義であるとした。批判の可能性は、概念と対象との間のギャップから生じる。 このギャップ、同一性における非同一性こそが、物質的生活と概念的考察の両方に対する批判の秘訣であった[要出典]。 音楽学者としてのアドルノの評判は、いまだに論争の的となっている。ジャズに対する徹底的な批判[73]や、ストラヴィンスキーと対立する第二ウィーン楽 派の擁護は、彼の人気を落とす原因となった。アメリカの著名な学者であるリチャード・タルスキン[74]は、アドルノを「とんでもなく過大評価されてい る」と断じた。著名なピアニストであり批評家でもあるチャールズ・ローゼンは、アドルノの著書『The Philosophy of New Music』を「大部分は詐欺的なプレゼンテーションであり、客観的な研究のふりをした極論の作品」[75]と見ている。 [イギリスの哲学者ロジャー・スクルトンは、アドルノが「アメリカ国民はマルクス主義が要求するように疎外されており、彼らの陽気な生を肯定する音楽は、 資本主義機械に対する彼らの深い精神的奴隷化を表現する『フェティシズム化された』商品であることを示すことに捧げられた、うんざりするようなナンセンス の数々」を生み出していると見ていた[69]。アドルノのトンネル・ビジョンに対する苛立ちは、彼が生きていたときから始まっていた。彼はシェーンベルク を支持したかもしれないが、シェーンベルクはその賛辞に応えることができなかった: 「ちなみに、彼がストラヴィンスキーをどう扱うかはうんざりするほどだ」[77]。別の作曲家ルチアーノ・ベリオはインタビューで、「アドルノが書くこと に完全に反論するのは簡単ではない。彼は、消費者音楽、マスメディア、ひいては資本主義そのものの最も狡猾で興味深い側面のひとつが、それらの流動性、適 応と同化の果てしない能力であることを忘れている」[78]。他方、学者スラヴォイ・ジジェクはアドルノの『ワーグナーを探して』への序文を書いており [79]、ジジェクは同書に「解放の衝動」があるとしているが、この衝動に忠実であることは「アドルノのワーグナー研究の明確なテーゼに対する裏切り」を 要求しているとジジェクは示唆している[80]。 2014年に『ニューヨーカー』誌に寄稿した音楽評論家のアレックス・ロスは、アドルノの著作がデジタル時代において改めて重要性を帯びていると主張して いる。グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンといった少数の巨大企業が前例のない独占を支配しており、文化はかつてないほど一枚岩に見える」 [81]。 商業メディア資本主義に対するアドルノの批判は、今もなお影響力を持ち続けている。アドルノによる批評は、タナー・ミルリーズの「アメリカ帝国の文化産業」のような著作の中に見出すことができる。 認識の5つの要素 アドルノは、特定の楽曲のヒットに関する認知を理解するには、認知の経験をさまざまな要素に分ける図式を起草することから始めることができると述べてい る。人々が列挙するすべての要素は、現実には互いに切り離すことが不可能な程度に織り込まれている。アドルノの図式は、個人に感じられる実際の経験より も、認識の経験に関わるさまざまな客観的要素に向けられている[84]。 1. Vague remembrance 漠然とした想起 2. Actual identification 実際の同一化 3. Subsumption by label ラベルによる服従 4. Self-reflection and act of recognition 自己反省と認識行為 5.Psychological transfer of recognition-authority to the object 対象への認識-権威の心理的移転 マルクス主義的批判 ホルスト・ミュラーの『批評理論批判』(Kritik der kritischen Theorie)によれば、この仮定は、人がそこから逃れなければならない(しかし誰もそこから逃れることはできない)自己調整システムとしての社会とい うアドルノの考えと一致している[85]。彼にとって社会は存在するが、非人間的である。ミュラーはそのようなシステムの存在に反対し、批判理論は社会を 変えるための実践的な解決策を提供しないと主張する。彼は、特にユルゲン・ハーバーマス、そしてフランクフルト学派一般がマルクスの解釈を誤っていると結 論づけている[要出典]。 標準化 標準化という現象は、「資本家が主導するマスメディアや大衆文化が、最大限の利益を追求するために最小公倍数に訴える定型的な製品を特徴づけるために用い られる概念」[86]である。マスメディアは、広告している商品を購入するよう消費者を説得するために、商品やサービスに関するメッセージを消費者に伝え るために使用される。標準化とは、可能な限り最大の利益を得るために、消費者を追い求める商品を大量に生産することである。 前述したように、商品を個別化することで、あたかも自分のために特別にデザインされた商品やサービスを購入しているかのように消費者に錯覚させるのであ る。アドルノは、ポピュラー音楽の構築によって生み出される問題を強調している。今日のチャート上位曲の制作に使われる音楽のさまざまなサンプルは、ある 曲から別の曲へと同じさまざまなサンプルを使うことで、数多くの楽曲を創造、再創造、修正するために組み合わされている。彼は "Apologetic music "と "Critical music "を区別している。アポロゲティック・ミュージックとは、"ポップ・ミュージック "産業の高度に生産され、宣伝された音楽のことである。「ポピュラー音楽の社会的・心理的機能とは、[それが]社会的セメントのように作用し[87]、 「人々を既存の権力構造の現状に従順に従わせ続けることである」[88]。 アドルノによれば、真剣な音楽は、その全体が部分の総和よりも大きいときに卓越性を達成する。彼が挙げる例は、ベートーヴェンの交響曲である: 「ベートーヴェンの偉大さは、偶発的な私的な旋律的要素が全体としての形式に完全に従属することで示される」[88]。 標準化とは、文化産業の製品だけでなく、消費者にとっても同様である。消費者は、メディア・システムによって提示された製品やサービスを消費するよう、押 し付けられ、押し込まれる。大衆は文化産業によって条件づけられ、標準化の影響をより重要なものにしている。ソーシャルメディアや商業広告の影響に気づか ないことで、個人は順応が規範である状況に巻き込まれる。「消費の間、大衆は自分たちが使用し、自分たちの間で交換する商品によって特徴づけられるように なる」[89]。 批評家たちに対するアドルノの反応 社会的対象への反省の影響を考慮するブルデューの能力を先取りした自己反省的社会学の先駆者として、アドルノは、彼が信じていたと思われるように、素朴な 民族誌学者や社会学者が人間の本質について考えていることが、時間とともに常に変化するものであるならば、(1960年代における意図的な授業の妨害を含 む)いくつかの批判は対等な者同士の対話では決して答えることができないことに気づいていた[90]。  ゲーテ大学フランクフルト校と社会研究所を隔てるゼンケンベルガンラーゲ通りにある「アドルノ・アンペル」(アドルノ信号機)は、1962年に歩行者が死亡した後にアドルノが建設を要請し、25年後にようやく設置された[91]。 |
| Adorno's sociological methods As Adorno believed that sociology needs to be self-reflective and self-critical, he also believed that the language the sociologist uses, like the language of the ordinary person, is a political construct in large measure that uses, often unreflectingly, concepts installed by dominant classes and social structures (such as our notion of "deviance" which includes both genuinely deviant individuals and "hustlers" operating below social norms because they lack the capital to operate above: for an analysis of this phenomenon, cf. Pierre Bourdieu's book The Weight of the World). He felt that those at the top of the Institute needed to be the source primarily of theories for evaluation and empirical testing, as well as people who would process the "facts" discovered ... including revising theories that were found to be false. For example, in an essay published in Germany on Adorno's return from the US, and reprinted in the Critical Models essays collection (ISBN 0-231-07635-5), Adorno praised the egalitarianism and openness of US society based on his sojourn in New York and the Los Angeles area between 1935 and 1955: "Characteristic for the life in America [...] is a moment of peacefulness, kindness and generosity". ("Dem amerikanischen Leben eignet [...] ein Moment von Friedlichkeit, Gutartigkeit und Großzügigkeit".)[92] One example of the clash of intellectual culture and Adorno's methods can be found in Paul Lazarsfeld, the American sociologist for whom Adorno worked in the late 1930s after fleeing Hitler. As Rolf Wiggershaus recounts in The Frankfurt School, Its History, Theories and Political Significance (MIT 1995), Lazarsfeld was the director of a project, funded and inspired by David Sarnoff (the head of RCA), to discover both the sort of music that listeners of radio liked and ways to improve their "taste", so that RCA could profitably air more classical music. Lazarsfeld, however, had trouble both with the prose style of the work Adorno handed in and what Lazarsfeld thought was Adorno's "lack of discipline in ... presentation".[93] Adorno himself provided the following personal anecdote: What I mean by reified consciousness, I can illustrate—without elaborate philosophical contemplation—most simply with an American experience. Among the frequently changing colleagues which the Princeton Project provided me with, was a young lady. After a few days, she had gained confidence in me, and asked most kindly: "Dr Adorno, would you mind a personal question?". I said, "It depends on the question, but just go ahead", and she went on: "Please tell me: are you an extrovert or an introvert?". It was as if she, as a living being, already thought according to the model of multi-choice questions in questionnaires.[94] Adorno translated into English While even German readers can find Adorno's work difficult to understand, an additional problem for English readers is that his German idiom is particularly difficult to translate into English. A similar difficulty of translation is true of Hegel, Heidegger, and a number of other German philosophers and poets. As a result, some early translators tended toward over-literalness. In recent years, Edmund Jephcott and Stanford University Press have published new translations of some of Adorno's lectures and books, including Introduction to Sociology, Problems of Moral Philosophy and his transcribed lectures on Kant's Critique of Pure Reason and Aristotle's "Metaphysics", and a new translation of the Dialectic of Enlightenment. Professor Henry Pickford, of the University of Colorado at Boulder, has translated many of Adorno's works such as "The Meaning of Working Through the Past." A new translation has also appeared of Aesthetic Theory and the Philosophy of New Music by Robert Hullot-Kentor, from the University of Minnesota Press. Hullot-Kentor is also currently working on a new translation of Negative Dialectics. Adorno's correspondence with Alban Berg, Towards a Theory of Musical Reproduction, and the letters to Adorno's parents, have been translated by Wieland Hoban and published by Polity Press. These fresh translations are slightly less literal in their rendering of German sentences and words, and are more accessible to English readers.[citation needed] The Group Experiment, which had been unavailable to English readers, is now available in an accessible translation by Jeffrey K. Olick and Andrew J. Perrin on Harvard University Press, along with introductory material explaining its relation to the rest of Adorno's work and 20th-century public opinion research. https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno |
ア
ドルノの社会学的方法アドルノは、社会学は自己反省的で自己批判的である必要があると考えていたため、社会学者が使用する言語は、一般人の言語と同様に、
支配的な階級や社会構造によって設置された概念を、しばしば無反省に使用する政治的な構成要素であるとも考えていた(例えば、我々の「逸脱」の概念には、
純粋に逸脱した個人と、社会規範の下で活動する「ハスラー」の両方が含まれる。この現象の分析については、ピエール・ブルデューの著書『世界の重さ』を参
照されたい)。彼は、研究所のトップに立つ者は、主に評価と実証的検証のための理論の供給源であると同時に、発見された「事実」を処理する人々である必要
があると感じていた...その中には、誤っていることが判明した理論を修正することも含まれる。例えば、アドルノがアメリカから帰国した際にドイツで出版
され、『批評モデル』エッセイ集(ISBN
0-231-07635-5)に再録されたエッセイの中で、アドルノは1935年から1955年にかけてニューヨークとロサンゼルス地域に滞在したことを
踏まえ、アメリカ社会の平等主義と開放性を称賛している:
「アメリカでの生活に特徴的なのは[......]平和で、親切で、寛大な瞬間である。(アメリカでの生活に特徴的なのは[......]穏やかで、親切
で、寛大な瞬間である」)[92]。 知的文化とアドルノの方法の衝突の一例は、ヒトラーから逃れたアドルノが1930年代後半に働いていたアメリカの社会学者ポール・ラザースフェルドに見る ことができる。ロルフ・ウィッガーハウスが『フランクフルト学派、その歴史、理論、政治的意義』(MIT 1995年)の中で語っているように、ラザースフェルドはデヴィッド・サルノフ(RCAのトップ)が資金を提供し触発したプロジェクトの責任者で、ラジオ のリスナーが好む音楽の種類と、彼らの「趣味」を改善する方法の両方を発見し、RCAがより多くのクラシック音楽を放送して利益を得られるようにすること を目的としていた。しかしラザースフェルドは、アドルノが手渡した仕事の散文的な文体と、ラザースフェルドが考えるアドルノの「・・・プレゼンテーション における規律の欠如」の両方に問題を抱えていた[93]。 アドルノ自身は次のような個人的な逸話を残している:私が言う「再定義された意識」とはどういう意味なのか、入念な哲学的思索を抜きにして、最も単純にア メリカの経験で説明することができる。プリンストン・プロジェクトで頻繁に入れ替わる同僚の中に、若い女性がいた。アドルノ先生、個人的な質問をしてもよ ろしいでしょうか」。私は「質問にもよりますが、どうぞ」と答え、彼女はこう続けた: 「あなたは外向的ですか、それとも内向的ですか?まるで彼女は、生き物として、すでにアンケートにおける多肢選択式の質問のモデルに従って考えているかの ようだった[94]。 英訳されたアドルノ ドイツ人読者でさえアドルノの著作を理解するのは難しいと感じることがあるが、英語読者にとってのさらなる問題は、彼のドイツ語のイディオムが特に英語に 翻訳するのが難しいということである。同様の翻訳の難しさは、ヘーゲルやハイデガー、その他多くのドイツの哲学者や詩人にも当てはまる。その結果、初期の 翻訳者の中には、字余りになる傾向があった。近年、エドモンド・ジェフコットとスタンフォード大学出版局は、『社会学入門』、『道徳哲学の問題』、カント の『純粋理性批判』やアリストテレスの『形而上学』に関する講義録、『啓蒙の弁証法』の新訳など、アドルノの講義や著書の新訳を出版した。コロラド大学ボ ルダー校のヘンリー・ピックフォード教授は、"The Meaning of Working Through the Past "などアドルノの著作の多くを翻訳している。また、ミネソタ大学出版局からロバート・ヒュロット=ケンター著『美学理論と新しい音楽の哲学』の新訳が出版 された。ヒュロット=ケントールは現在、『否定弁証法』の新訳にも取り組んでいる。アドルノとアルバン・ベルクの往復書簡『Towards a Theory of Musical Reproduction』、およびアドルノの両親に宛てた書簡は、ヴィーラント・ホーバンによって翻訳され、Polity Pressから出版されている。これらの新訳は、ドイツ語の文章や単語の表現がやや直訳的でなくなり、英語の読者にとってより親しみやすくなっている[要 出典]。これまで英語の読者が入手できなかった『集団実験』は、ジェフリー・K・オリックとアンドリュー・J・ペリンによる親しみやすい翻訳がハーバード 大学出版局から出版され、アドルノの他の著作や20世紀の世論調査との関連を説明する紹介資料も添えられている。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno | |
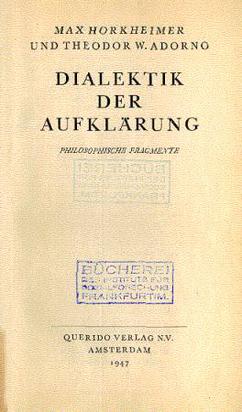 Dialectic of Enlightenment
(German: Dialektik der Aufklärung) is a work of philosophy and social
criticism written by Frankfurt School philosophers Max Horkheimer and
Theodor W. Adorno.[1] The text, published in 1947, is a revised version
of what the authors originally had circulated among friends and
colleagues in 1944 under the title of Philosophical Fragments (German:
Philosophische Fragmente).[2] Dialectic of Enlightenment
(German: Dialektik der Aufklärung) is a work of philosophy and social
criticism written by Frankfurt School philosophers Max Horkheimer and
Theodor W. Adorno.[1] The text, published in 1947, is a revised version
of what the authors originally had circulated among friends and
colleagues in 1944 under the title of Philosophical Fragments (German:
Philosophische Fragmente).[2]One of the core texts of critical theory, Dialectic of Enlightenment explores the socio-psychological status quo that had been responsible for what the Frankfurt School considered the failure of the Enlightenment. They argue that its failure culminated in the rise of Fascism, Stalinism, the culture industry and mass consumer capitalism. Rather than liberating humanity as the Enlightenment had promised, they argue it had resulted in the opposite: in totalitarianism, and new forms of barbarism and social domination.[3] Together with Adorno's The Authoritarian Personality (1950) and fellow Frankfurt School member Herbert Marcuse's One-Dimensional Man (1964), it has had a major effect on 20th-century philosophy, sociology, culture, and politics, especially inspiring the New Left of the 1960s and 1970s.[4] |
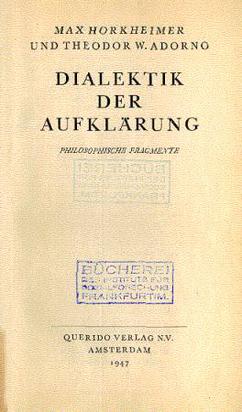 フ
ランクフルト学派の哲学者マックス・ホルクハイマーとテオドール・W・アドルノによって書かれた哲学と社会批評の著作である[1]。1947年に出版され
たこのテキストは、著者らが1944年に『哲学的断片』(ドイツ語:Philosophische
Fragmente)というタイトルで友人や同僚の間で回覧していたものを改訂したものである[2]。 フ
ランクフルト学派の哲学者マックス・ホルクハイマーとテオドール・W・アドルノによって書かれた哲学と社会批評の著作である[1]。1947年に出版され
たこのテキストは、著者らが1944年に『哲学的断片』(ドイツ語:Philosophische
Fragmente)というタイトルで友人や同僚の間で回覧していたものを改訂したものである[2]。啓蒙の弁証法』は、フランクフルト学派が啓蒙主義の失敗とみなした社会心理学的現状を探求している。彼らは、その失敗がファシズム、スターリニズム、文化 産業、大量消費資本主義の台頭に結実したと主張する。彼らは、啓蒙主義が約束したように人類を解放するどころか、全体主義、野蛮と社会支配の新たな形態と いう逆の結果をもたらしたと主張している[3]。 アドルノの『権威主義的人格』(1950年)やフランクフルト学派の仲間であるヘルベルト・マルクーゼの『一次元人間』(1964年)とともに、20世紀の哲学、社会学、文化、政治に大きな影響を与え、特に1960年代と1970年代の新左翼を刺激した[4]。 |
| Historical context Frankfurt School In the 1969 preface to the 2002 publication, Horkheimer and Adorno wrote that the original was written, "when the end of the National Socialist terror was in sight."[5]: xi One of the distinguishing characteristics of the new critical theory, as Adorno and Horkheimer set out to elaborate it in Dialectic of Enlightenment, is a certain ambivalence concerning the ultimate source or foundation of social domination.[5]: 229 Such would give rise to the "pessimism" of the new critical theory over the possibility of human emancipation and freedom.[5]: 242 Furthermore, this ambivalence was rooted in the historical circumstances in which Dialectic of Enlightenment was originally produced: the authors saw National Socialism, Stalinism, state capitalism, and culture industry as entirely new forms of social domination that could not be adequately explained within the terms of traditional theory.[6][7] For Adorno and Horkheimer (relying on the economist Friedrich Pollock's thesis[8] on National Socialism),[9] state intervention in the economy had effectively abolished the tension in capitalism between the "relations of production" and the "material productive forces of society," a tension that, according to traditional theory, constituted the primary contradiction within capitalism. The market (as an "unconscious" mechanism for the distribution of goods) had been replaced by centralized planning.[5]: 38 [G]one are the objective laws of the market which ruled in the actions of the entrepreneurs and tended toward catastrophe. Instead the conscious decision of the managing directors executes as results (which are more obligatory than the blindest price-mechanisms) the old law of value and hence the destiny of capitalism.— Dialectic of Enlightenment, p. 38 Because of this, contrary to Marx's famous prediction in his preface to A Contribution to the Critique of Political Economy, this shift did not lead to "an era of social revolution," but rather to fascism and totalitarianism. As such, traditional theory was left, in Jürgen Habermas' words, without "anything in reserve to which it might appeal; and when the forces of production enter into a baneful symbiosis with the relations of production that they were supposed to blow wide open, there is no longer any dynamism upon which critique could base its hope."[10]: 118 For Adorno and Horkheimer, this posed the problem of how to account for the apparent persistence of domination in the absence of the very contradiction that, according to traditional critical theory, was the source of domination itself.[4] |
歴史的背景 フランクフルト学派 2002年に出版された『啓蒙の弁証法』の1969年の序文で、ホルクハイマーとアドルノは、原著が「国家社会主義の恐怖の終焉が目前に迫っていた時」に 書かれたものであると書いている[5]: xi アドルノとホルクハイマーが『啓蒙の弁証法』で詳述しようとした新しい批判理論の際立った特徴の一つは、社会的支配の究極的な源泉や基盤に関するある種の 両義性である[5]: 229。 さらにこの両義性は、『啓蒙の弁証法』がもともと制作された歴史的状況に根ざしていた。著者たちは、国家社会主義、スターリン主義、国家資本主義、文化産 業を、伝統的な理論の用語の中では適切に説明することができない、まったく新しい社会支配の形態と見なしていた[6][7]。 アドルノとホルクハイマーにとって(経済学者であるフリードリヒ・ポロックの国家社会主義に関する論文[8]に依拠して)[9]、経済への国家の介入は、 「生産関係」と「社会の物質的生産力」との間の資本主義における緊張、すなわち伝統的な理論によれば資本主義における主要な矛盾を構成していた緊張を効果 的に消滅させていた。市場は(財の分配のための「無意識の」メカニズムとして)中央集権的な計画に取って代わられた[5]: 38 [企業家の行動を支配し、破局に向かう傾向にあった市場の客観的な法則が、中央集権的な計画に取って代わられたのである。その代わりに、経営責任者の意識 的な決定が、(盲目的な価格メカニズムよりも義務的な)古い価値法則を結果として実行し、それゆえに資本主義の運命を決定するのである。- 啓蒙の弁証法』38頁 このため、『政治経済学批判への貢献』の序文にあるマルクスの有名な予言に反して、この転換は「社会革命の時代」をもたらすものではなく、むしろファシズ ムと全体主義をもたらすものであった。そのため、伝統的な理論は、ユルゲン・ハーバーマスの言葉を借りれば、「訴えうる予備的な何ものもないまま残された のであり、生産力が、それが大きく吹き飛ばすはずであった生産関係との忌まわしい共生に入るとき、批評がその希望を基礎づけることのできるダイナミズムは もはや存在しないのである」[10]: 118 アドルノとホルクハイマーにとって、このことは、伝統的な批評理論によれば支配それ自体の源であった矛盾がまさに存在しない状況において、支配が見かけ上 持続していることをどのように説明するかという問題を提起していた[4]。 |
| Topics and themes The problems posed by the rise of fascism with the demise of the liberal state and the market (together with the failure of a social revolution to materialize in its wake) constitute the theoretical and historical perspective that frames the overall argument of the book—the two theses that "Myth is already enlightenment, and enlightenment reverts to mythology."[5]: xviii The history of human societies, as well as that of the formation of individual ego or self, is re-evaluated from the standpoint of what Horkheimer and Adorno perceived at the time as the ultimate outcome of this history: the collapse or "regression" of reason, with the rise of National Socialism, into something (referred to as merely "enlightenment" for the majority of the text) resembling the very forms of superstition and myth out of which reason had supposedly emerged as a result of historical progress or development. Horkheimer and Adorno believe that in the process of "enlightenment," modern philosophy had become over-rationalized and an instrument of technocracy. They characterize the peak of this process as positivism, referring to both the logical positivism of the Vienna Circle and broader trends that they saw in continuity with this movement.[11] Horkheimer and Adorno's critique of positivism has been criticized as too broad; they are particularly critiqued for interpreting Ludwig Wittgenstein as a positivist—at the time only his Tractatus Logico-Philosophicus had been published, not his later works—and for failing to examine critiques of positivism from within analytic philosophy.[12] To characterize this history, Horkheimer and Adorno draw on a wide variety of material, including the philosophical anthropology contained in Marx's early writings, centered on the notion of "labor;" Nietzsche's genealogy of morality, and the emergence of conscience through the renunciation of the will to power; Freud's account in Totem and Taboo of the emergence of civilization and law in murder of the primordial father;[13] and ethnological research on magic and rituals in primitive societies;[14] as well as myth criticism, philology, and literary analysis.[15] Theodor Adorno and Max Horkheimer argue that antisemitism is a deeply rooted, irrational phenomenon that stems from the failure of the Enlightenment project and the inherent contradictions of bourgeois society. They argue that Jews serve as a universal scapegoat onto which individuals and societies project their deepest fears, anxieties, and neuroses. According to their analysis, the complex and often contradictory nature of modern life generates a sense of alienation, powerlessness, and psychological distress. Unable to confront these feelings directly, people seek to externalize them by identifying a tangible "other" to blame for their problems. The Jews, with their historically marginalized status and perceived association with the disruptive forces of modernity, become an ideal target for this projection.[1] Adorno and Horkheimer suggest that antisemitic stereotypes, such as the Jews' alleged greed, cunning, and rootlessness, are not based on any objective reality but rather reflect the unconscious fears and desires of the antisemites themselves. By attributing their own negative impulses to the Jews, they are able to maintain a sense of psychological coherence and moral purity. This irrational, projective hatred is further reinforced by economic resentment and nationalistic ideology, which provide a broader social framework for antisemitism. Ultimately, Adorno and Horkheimer see the persecution of the Jews as a symptom of the unresolved contradictions and pathologies of modern society, which can only be addressed through a radical critique of the Enlightenment project and the social conditions that sustain it.[1] The authors coined the term culture industry, arguing that in a capitalist society, mass culture is akin to a factory producing standardized cultural goods—films, radio programmes, magazines, etc.[16] These homogenized cultural products are used to manipulate mass society into docility and passivity.[17] The introduction of the radio, a mass medium, no longer permits its listener any mechanism of reply, as was the case with the telephone. Instead, listeners are not subjects anymore but passive receptacles exposed "in authoritarian fashion to the same programs put out by different stations."[18] By associating the Enlightenment and Totalitarianism with Marquis de Sade's works—especially Juliette, in excursus II—the text also contributes to the pathologization of sadomasochist desires, as discussed by historian of sexuality Alison Moore.[19] |
トピックとテーマ 自由主義国家と市場の終焉とともにファシズムが台頭したことによってもたらされた問題(それに伴う社会革命の失敗)は、本書の全体的な議論を構成する理論的・歴史的視点を構成している。 人間社会の歴史は、個人の自我や自己の形成の歴史と同様に、ホルクハイマーとアドルノが当時、この歴史の究極的な帰結として認識していたもの、すなわち、 国家社会主義の台頭によって理性が崩壊あるいは「退行」し、歴史的進歩や発展の結果として理性が出現したとされていた迷信や神話の形態そのものに似たもの (本文の大部分では単に「啓蒙」と呼ばれている)になるという観点から再評価されている。 ホルクハイマーとアドルノは、「啓蒙」の過程で近代哲学は過剰に合理化され、テクノクラシーの道具になったと考える。ホルクハイマーとアドルノの実証主義 批判は広範すぎると批判されており、特にルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインを実証主義者として解釈したこと、当時は彼の『論理哲学綱要』のみが出版され ており、それ以降の著作は出版されていなかったこと、そして分析哲学内部からの実証主義批判を検証していないことが批判されている[12]。 この歴史を特徴づけるために、ホルクハイマーとアドルノは、「労働」の概念を中心としたマルクスの初期の著作に含まれる哲学的人間学、ニーチェの道徳の系 譜、権力への意志の放棄を通じた良心の出現など、多種多様な材料を用いている; フロイトの『トーテムとタブー』における、原初の父を殺害することで文明と法が出現したという説明[13]、原始社会における魔術と儀式に関する民族学的 研究[14]、さらには神話批評、言語学、文学分析。 [15] テオドール・アドルノとマックス・ホルクハイマーは、反ユダヤ主義は深く根ざした非合理的な現象であり、啓蒙主義プロジェクトの失敗とブルジョア社会に内 在する矛盾に由来すると主張している。ユダヤ人は、個人や社会が最も深い恐怖、不安、神経症を投影する普遍的なスケープゴートとして機能していると主張す る。彼らの分析によれば、現代生活の複雑でしばしば矛盾した性質が、疎外感、無力感、心理的苦痛を生み出している。このような感情に直接向き合うことがで きない人々は、自分の問題を非難する具体的な「他者」を特定することで、その感情を外在化しようとする。ユダヤ人は、歴史的に疎外された地位にあり、近代 の破壊的な力と結びついていると認識されているため、この投影の理想的なターゲットとなる[1]。 アドルノとホルクハイマーは、ユダヤ人の貪欲さ、狡猾さ、根無し草といった反ユダヤ主義的なステレオタイプは、客観的な現実に基づいているのではなく、む しろ反ユダヤ主義者自身の無意識的な恐怖や欲望を反映していると指摘する。自分自身の否定的な衝動をユダヤ人に帰することで、彼らは心理的な一貫性と道徳 的な純粋さを保つことができる。この非合理的で投影的な憎悪は、経済的憤慨や民族主義的イデオロギーによってさらに強化され、反ユダヤ主義のより広範な社 会的枠組みとなる。結局のところ、アドルノとホルクハイマーは、ユダヤ人迫害を現代社会の未解決の矛盾と病理の徴候とみなしており、それは啓蒙主義的プロ ジェクトとそれを支える社会状況に対する急進的な批判を通じてのみ対処可能であるとしている[1]。 著者たちは文化産業という言葉を作り、資本主義社会では大衆文化は標準化された文化商品-映画、ラジオ番組、雑誌など-を生産する工場に似ていると主張し た。その代わりに、リスナーはもはや主体ではなく、「権威主義的なやり方で、異なる放送局が出す同じ番組にさらされる」受動的な受け皿となる[18]。 啓蒙主義と全体主義をサド侯爵の作品、とりわけ『ジュリエット』(解説Ⅱ)と関連づけることによって、セクシュアリティの歴史家アリソン・ムーアが論じているように、このテキストはサドマゾヒストの欲望を病理化することにも寄与している[19]。 |
| Editions The book was first published as Philosophische Fragmente in New York in 1944, by the Institute for Social Research, which had relocated from Frankfurt am Main ten years earlier. A revised version was published as Dialektik der Aufklärung in Amsterdam by Querido in 1947. It was reissued in Frankfurt by S. Fischer in 1969, with a new preface by the authors. There have been two English translations: the first by John Cumming (New York: Herder and Herder, 1972; reissues by Verso from 1979 reverse the order of the authors' names), and another, based on the definitive text from Horkheimer's collected works, by Edmund Jephcott (Stanford: Stanford University Press, 2002). |
エディション 本書は1944年、フランクフルト・アム・マインから10年前に移転した社会研究所によって、ニューヨークで『Philosophische Fragmente』として初めて出版された。改訂版は1947年、アムステルダムでクエリド社から『アウフクラングの哲学』(Dialektik der Aufklärung)として出版された。1969年、フランクフルトでS.フィッシャーにより、著者らによる新たな序文とともに再版された。 ジョン・カミング(John Cumming)による最初の英訳(New York: Herder and Herder, 1972;1979年からは著者名の順序を逆にVersoから再刊)と、エドマンド・ジェフコット(Edmund Jephcott)による英訳(Stanford: Stanford University Press, 2002)がある。 |
| Counter-Enlightenment Das Kapital |
|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic_of_Enlightenment |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099