In between Anthropology of
Religion and Medical Religious Studies

In between Anthropology of
Religion and Medical Religious Studies

ひとは病む存在である、そして、治る存在でもある。(→「宗教と醫學が出会うとき」)
 ひ
とは〈病む存在〉である ひ
とは〈病む存在〉である〈病む〉ことは、人生において不可欠の経験である。 〈病む〉ことは、まず1人の人間存在の根源に関わる 個人的出来事である。しかしながら、人間が一時的に病んだり本復したりすることは、周りの人々のケアや配慮を派生させ、病んだ原因を追及し、さらに治療を 発動させるために、〈病む〉ことはまた他方で人間の社会性に深く関わる出来事でもある。 自殺や突然死でもない限り、人間は死ぬ前には必ず病む。いやそれど ころか自殺や突然死においてすら、病んでいる状態であるとみなされており、それを予知し〈治療〉する研究が進んでいる。 人間が不完全な存在であることを説明するのに、宗教 は〈病む〉ことに関するメタファーを多用する。あるいは、神には死や病いが不在であるという類推から、神や超自然的存在とは対照的に人間のユニークさは 〈病む存在〉——ラテン語の学名風に Homo patiens という——にあると規定し、そこから人間の自由と責任の問題を論じる者もいる[フランクル 1986]。 宗教聖典、説教、信徒の日々の会話は、病む存在の 苦しみと病いからの解放についての挿話に満ち満ちている。宗教において〈病む〉ことは枢要な概念である。そして、そのどれもが具体的諸相を帯びており、人 々は深遠な苦悩の神学よりも、どのように病んだか、そしてどのように癒されたかという細部に関心を向ける。 ところが他方で近代生活、つまり世俗的な生活体験に おいては、必ずしも〈病む〉ことが宗教と関連づけられるわけではない。 近代化は〈病む〉ことへの対処を、宗教ではなく近代医療にゆだねる。近代生活におい て宗教は、〈病む〉ことの具体的諸相に着目しなくなり、病むことを何か高度な精神の活動と関連づけて論じるようになった。病人は、病室で宗教的奇蹟を期待 することはなくなり〈治療〉を医療にゆだねて、身体と精神の全体論的本復や魂の平安を祈る。後者の働きは〈癒し〉と呼んでもよいだろう。 だがしかし、社会は〈癒し〉と〈治療〉の統合の夢を みることを忘れない。それどころか、近代医療において〈癒し〉が今日では最重要視され〈治療〉の概念に包摂されようとしている。〈病む〉ことの具体的な諸 相を扱わなくなった宗教は、自ずから〈癒し〉の実権を医療に譲り渡すのである[池田 2000a]。 宗教と医療の関係が将来どのように展開するのか、明 確に論じた人はいない。医療と宗教は現在までのところまったく異なった範疇の社会制度であると思われているからだ。しかし、〈病む存在〉としての人間の具 体的な諸相——宗教人類学が扱う大きなテーマのひとつであろう——から我々が眼を離さないかぎり、このことは軽んじられてはならない事柄である。 宗教と医 療の関係について吟味するには、まず〈病むこと〉や〈治ること〉が、具体的にどのようなことなのか、そして病む存在としての病人が社会のなかでどのように 振る舞うのかについての豊富な知識が不可欠である。 |
 〈病
む〉ことと〈治る〉ことの生物的決定 〈病
む〉ことと〈治る〉ことの生物的決定人間の生物種としての同一性は、生殖的事実から証明 される。また人間の社会的なクラスの違い――例えば人種や階級――は先天的なものでは断じてない[Montagu 1997]。したがって、もし宗教が人間を癒す具体的事象に、なにがしかの生物学的根拠があるとすると、それは社会的・心理的条件が揃えば、人間社会に属 する誰にでも起こりうることになる。 〈病む〉ことが、宗教的にみて人間存在の調和的なあ り方からの逸脱だとすれば、生物学的にはそれは身体の生理現象の逸脱である。 心理的側面を含めた人間身体は、しばしば〈内部環境〉という用語で説明され、 人間を取り囲む全体は〈外部環境〉と呼ばれる[ベルナール 1970]。 この概念で説明できることは、外部環境の変化が内部環境に対して不調をもたらすこ とがあるという病気の生理学的根拠を説明する。 他方で、内部環境の崩壊が外部環境に影響を与えることもあり、これは個人の病気や不調が、個人を取り囲む家 族や社会全体に悪い影響をもたらすという社会学的現象を説明する。したがって病気が〈治る〉ということは、単に人間の内部環境が調和を取り戻すだけでな く、外部環境そのものの安寧を実現することにつながる。 世界保健機関の健康の定義にあるように、健康は単なる個人の身体的な壮健さのみならず、心理的にも 社会的にも良好な状態にあるということも、これらの理念の反映である。 このような内部環境と外部環境の調和という見方は、 ヨーロッパ18世紀中頃のロマン主義に起源をもつ。つまり人間が内部と外部の二面性をもつことで人間性が維持されてゆくことの重要性は、啓蒙精神が明らか にしたような理性の作用だけでなく、非理性の社会的意義が再発見される過程の中で登場した。これらの見解は、社会学理論としての社会有機体説を生み、社会 そのものも個々の要素が集合した以上の働きがあることを示した。 〈病む〉ことと〈治る〉ことに関する生物学的な有機 体説は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、クロード・ベルナール(1813-78)の内分泌説、ウォルター・キャノン(1871-1945)のホメオ スタシス説、ハンス・セリエ(1907-82)のストレス説、によって医学生理学的根拠が明らかになった。 つまり、信仰による治療というのは、単に心理学 的な暗示によって自覚症状だけが改善されるのではなく、内分泌物質すなわちホルモンによって身体の全身に作用がもたらされ、病巣への生理学的かつ免疫学的 な治療効果を生むという説明がなされた。さらに心理学的な暗示も、生理学的効果が生じることがあり、これらはプラシーボ(偽薬)効果と呼ばれている。 勿論 すべての信仰に生理学的効果があるとは言えないが、信仰治療において自覚症状が改善されたときに、単に心理的暗示のみらなず、生理学的作用を持ちうること も一部ではあるが証明された。 |
 〈病
む〉ことと〈治る〉ことの社会的決定 〈病
む〉ことと〈治る〉ことの社会的決定〈病む〉ことや〈治る〉ことを学問的に厳密に定義す ることは容易ではない。まず病むことや治ることの具体的な諸相は、人間の個別な出来事であり、それを一般的な用語でとりまとめることは困難だからである。 この〈病む〉ことの個別性や多様性は経験的事実から傍証することができる。1980年代中頃の中央アメリカ・ホンジュラス西部のメスティソ農 民における病 気の語彙について調査していた時に、私は単純な事実を発見した。つまり、病気に関する語彙は、治療や治癒に関する語彙よりも多様で豊かであるということだ [池田 2001:255-260]。 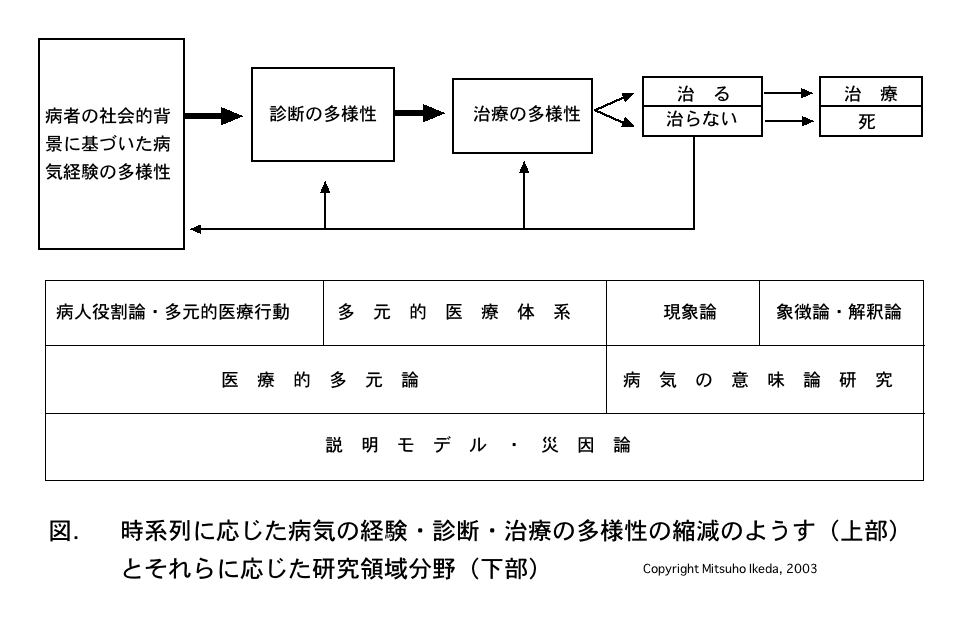 これは、一方では病気の具体的な成り立ちが予期も原因も不明瞭であり当てずっぽうも含めて多様で曖昧なところから出 発することに起因するからであろう。そして、治療においては、病気の成り立ちについて文化的説明が行われる際にはいくつかのパターンに収斂されるようであ り、その中から限定的な選択を通して、最終的に病気が治るときには、その結果は〈治る〉と〈治らない〉の判別レベルまで縮減されることにも起因する(図の 上半分を参照せよ)。 人間 は多様に病み、そして一様に治癒する。このことは、全世界の開発途上地域における保健政策において、しばしば中央政府が健康的な 生活のために声高に主張する具体的な対策――消毒や衛生――がなかなか普及成功しない歴史的事実とも関連している[池田 2001:43]。なぜなら、人 間が多様に病むことを無視し、選択肢を与えない近代医療で施術しようとしたからである。 病気の脅威に直面する人間集団が、さまざま治療手段 を発達させてきたことは論を待たない。伝統医療や民族医療と呼ばれることもあるこれらの治療手段は、単純な経験的知識の積み重ねだけではなく、しばしば、 現地の社会関係や象徴的な宇宙観や身体観の反映でもある。 従って〈病む〉ことも〈治る〉ことも社会構造やそれに関連した文化と深く関係する。 また、治療に は流行り廃りがあることから、〈病む〉ことも〈治る〉ことも、同じ社会においても長期に変化することも明らかである[ブロック 1998]。 〈病む〉ことと〈治る〉ことについて近代医療の用語 で説明すれば、前者は疾病の罹患あるいは症状の発生であり、後者は治癒あるいは緩解――症状が改善されたり一時的に治っている状態――のことをさす。 伝統 的な治療師と同様、近代医療の医師も、患者やその家族が〈病んでいる〉とか〈治った〉と主張することと、医学的に発病したり治癒したと判断することは区別 して考える。つまり自覚症状と他覚症状は区別して考えられている。従って患者の側の主観的判断と(伝統的および近代的を問わず)治療者の判断が相反するこ とがある。近代医療においては、原則的に医師の治癒の判断は客観的で正しいものとされ、患者や家族の判断はそれほど尊重されない。しかし、近代医療に比べ て非西洋医療では後者はより重視される傾向がある。 前節で述べたように、人が多様に〈病むこと〉から始 まり、〈治る/治らない〉という判別に終わる病気の挿話(illness episode)は、経験的事実に即して具体的に追跡することができる。 多くの社会において、病気と治療の挿話には、その文化が規定する因果的連関にもと づいた時系列的変化に応じて、共通する特徴が見られる。 それは(1)病気の原因、(2)発病の時期と様式、(3)病気の具体的な諸相の変化、(4)病気の 一般的な経緯と重さの度合い、(5)病気や症状に応じた治療法である。これらの5つの要素からなる病気と治療についての理論と行動のセットをアーサー・ク ラインマン[1992]は「説明モデル」(explanatory model)と名付けている。 病気の発生を、不幸をも含めた災い一般とそれを説明 する際の文化的に決定された論理とみると、それは「災因論」[長島 1987]として捉えることができる。 災いの原因の結果を結ぶ説明は、治療者と患者が もつそれぞれの固有の経験や歴史的経緯により多様性をもつが、他方で文化的にいくつかの類型化された説明体系と治療のシステムというものがみられる。 従っ て災因論は、当該社会における不幸の原因と結果を秩序づけて説明する際の文化的図式の描き方の技法でもある。この社会的な分析格子を通して、それぞれの社 会で不幸が偶発的な条件に左右され一定の多様性を確保しながらも、部外者に対して説明可能な論理として抽出することができるからである[池田 1992: 165]。 |
 〈病
む存在〉と〈癒す存在〉の社会的役割 〈病
む存在〉と〈癒す存在〉の社会的役割〈病むこと〉や〈治ること〉が社会的に決定されよう とも、その具体的な諸相は人々の行動の中に観察されなければならない。またそれらの行動に対して当事者がどのように語るのかについて耳を傾けないと、その 現象の内実に迫ることができない。このような研究領域は「病気の意味論」 (illness semantics)と呼ばれる[グッド 2001]。 一般に〈病む存在〉をどのように処遇するのかは、病 人の属する社会構造、文化的パターン、歴史的状況、社会経済的状況、という外部環境要因と、病人の属する社会階層、家族構成、年齢、ジェンダー、罹った病 気の種類といった病人の属性などの要因により様々に異なる。 これまでの学問的説明は機能論を使うことが多かった。一例として、生存環境が過酷な採集狩猟民 社会は、社会を維持してゆくためにはリスクが増えるために病人に対しては冷遇し、経済的に余裕ができた裕福な社会では病人を手厚く扱うと説明がある。 しか しながら、社会生活が豊かか否かは実際には余暇時間や日常生活におけるエネルギー取得効率などの様々な指標によって多元的に評価することが可能であり、ま た例外も多く機能論的説明は現在ではそれほど多くの支持者はいない[サーリンズ 1984;池田 2000b]。 むしろ、しばしば観察されることは、それぞれの社会 には、文化的に定型化した病人の役割行動の典型的なパターン[パーソンズ 1974]があ ること、そして、それらのパターンにおいて病人役割の遂行を上手 におこなっている病人や家族と、そこからさらに逸脱する病人や家族が存在するということである。勿論、逸脱を説明する論理も文化的拘束性から逃れられない [上野 1996]。 当該社会において生きる人が、病人役割をどのように 獲得してゆくであろうか。この問題はG・H・ミード[1995]が指摘したように、人間の社会化における他者との相互行為を通しての役割取得、特にその過 程における〈重要な他者〉(significant others)の存在が重要になる。 重要な他者は個人を取り巻く中でも最も影響を与える人間を概念化するものである。病人の社会化にとって重要な他者は、 家庭内治療の現場においては両親や親族である。病気に罹った子供は看病する親族の身体所作と質問という相互行為の中で、自分が病者としてどのように質問に 答え、また身体の振る舞いのやり方を学ぶのである。 他方、様々な病気を経験するうちに——つまり病気経験がより社会化されてゆく過程で、重要な他者は、医 師やシャーマンなどの治療者になってゆく。とくに伝統社会における呪術的治療者のイニシエーション過程を調べてみると、治療者自身がかつての重篤な病人で あったことがしばしば観察される。 また呪術的治療者の修行者においては、その技術の習得が比較的長期にわたるために、より洗練され強力な治療者の存在が役 割アイデンティティ構築において重要な意味をなす。ボアズの民族誌からレヴィ=ストロースが紹介し分析したクワキウトルのシャーマンのケサリード(= ジョージ・ハント)の話は、そのもっともよく知られたものの一つであろう[レヴィ=ストロース 1972]。 |
 〈病
む〉ことの宗教人類学の可能性 〈病
む〉ことの宗教人類学の可能性医療という用語を経験に基づいて定義しようとする と、それは宗教の定義と同様、さまざまな働きをする下位の諸要素が相互に関連して全体を構成することがわかる。つまり、医療は宗教と同様、多かれ少なかれ 体系をなすものである。 フレデリック・ダンによると、医療システムとは「行動の特定の項目が引き出した結果 が不健康かあるいはそうではないかに関わらず、 健康を増進するための意図的な行動から発達した社会制度と文化的伝統パターン」である[Dunn 1976:135]。 地球上のほとんどの社会においては、(1)近代医療 と、(2)公的あるは準公的な伝統医療、ならびに(3)非公的ないしはカルト化した伝統医療――後二者は歴史的にそれほど古くないものも含まれるので非西 洋医療と言い換えることもある――の少なくとも3種類ないしはそれ以上に分類しうる医療下位システムからなりたっている[池田 1995]。 このように治 療の資源が複数化している状況を多元的医療体系(pluralistic medical systems)と呼ぶ。 他方、患者と患者家族が、それらの医療資源を横断的に利用している際にみられる、人々の医療行動は多元的医療行動 (pluralistic medical behaviour)と名付けることができる。 このような制度と行動における医療現象を論じる視点を医療的多元論(medical pluralism)と呼ぶことができる[先に示した図の下半分を参照のこと]。医療多元論は宗教現象と類比してみると、いわゆるシンクレティズム――教 義と行動において異質な要素が習合しそれらの間に区分がみられない状況――を分析する読解格子となる。 シンクレティズムは、教義と行動を合致させる近代主 義な行動理念から見ると矛盾に満ちた奇妙な逸脱現象である。 しかし、そこにみられる仮定法的な行動原則――あれがだめならこれと効果を引き出すために試行 錯誤を繰り返すこと――には、最終的に有効な治療を得るための手段として合理化される点では、なんら奇妙なことではない。医療的多元論が生まれる根底に は、医療が〈治る/治らない〉という判別目標をもっているからである。言い換えると、医療とは〈治る/治らない〉という二分法に最終的に縮減される体系で ある。 宗教現象の経験的研究においては、その理念や実践か ら何か共通で本質的なものを抽出することに情熱が注がれる。しかしながら医療現象の文化研究では、医療のドグマ(中心的教説)を治療者や病者とのインタ ビューを通して手に入れること以上に、研究者の関心は医療行動の事象の細部に分け入ることが重要である。文化に修飾された人間の病理現象の驚くべき多様性 に関心と情熱が注がれるのだ。 宗教の古典的研究のスタイルと、ここで紹介した医療 の文化的研究のスタイルの間の方向性の相違に気づき、それらの研究アプローチを相互に刺激しあえば、〈病む存在〉としての人間の宗教人類学的探求に対する より実り豊かな成果を生むことは確実であろう。宗教人類学における様々研究の展開の中に〈医療〉の視座は欠かせないものとなっているからだ[Lambek 2002;黒岩 1991]。 |
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099
++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099