社会意識の審級としてのメディア
Hyper-Media
is one of instances of social consciousness
池田光穂
社会意識の審級としてのメディア
Hyper-Media
is one of instances of social consciousness
池田光穂
伝統的なマルクス主義の視点に立てば、メディアを含めたもろもろの上部構造 のあり方は、その社会の下部構造である経済によって規定され、 上部構造の一部たるメディアと下部構造の相互作用関係、つまり弁証法的な関係によって展開するという見方をとるだろう。実際に、マルクス主義からその批判 のためのアイディアをとる研究者は、1960年代のメディアの発達が人間の意識を変革するというA・トフラーやM・マクルーハンの立場を、プチブルジョア の発想と断定し、誰がメディアの支配権をもつかという観点から考察されていないと批判してきた。だが、メディアに関する唯物論的な批判には、貧困な図式の 虜になったものが多い。なぜだろう。上部構造の一部をなすメディアが下部構造に与えるフィードバックのスピードにマルクス主義者たちはついていけなかった のか。メディアそのものがもつ「下部構造」性──マーク・ポスターの言う情報様式──についての無理解に根ざす初歩的な誤りによるものなのか。それは19 世紀の機械のメタファー的想像力の限界でもあるように思える。
今日のメディア論を概観すれば、その多く はメディアが社会の構成員が持ちうる意識や知覚に大きな影響を与える、つまりメディアは社会意識 の審級であるという命題を前提にして議論されているものが多いことに気づくはずだ。教条的なマルクス主義者の感情を逆撫でするはずである。マクルーハンは 『メディアの理解』(1964)において、活字の登場と「電気」メディアの登場が人間の社会意識にどのような影響を与えるかを指摘しているが、彼はその命 題に忠実な論者の一人であった。
──活字による印刷は複雑な手工芸木版を最初に機械化したものであり、その後のいっさいの機械化の原型となった。‥‥活字印刷が 情報を蓄積する手段あるいは知識を迅速に回収する新しい手段に他ならないと見るならば、それによって時間と空間の両方において、心理的にも社会的にも、郷 党精神(parochialism)と部族精神(tribalism)とは終わりを遂げた。
──印刷もまたそれ以外の人間の拡張と同じであって、心理的ならびに社会的な影響を及ぼし、以前の文化の境界と模様を突然に変え てしまった。‥‥情報を移動するのに電気という手段を用いるようになって、われわれの活字文化はいま変わりつつある。それは、ちょうど、印刷術が発明され て、中世の写本やスコラの文化が変化を受けたのと同じである。
──アルファベット(およびその拡張である活字)が知識という力を拡張させることを可能にし、部族民の絆を壊滅させた。かくし て、部族民の紐帯を爆破させて、ばらばらの個人の集合としてしまった。電気による書字と速度は、瞬間的かつ持続的に、個人の上に他のすべての人に関心を注 ぐ。こうして、個人はふたたび部族民となる。人間の一族全体がもう一度、ひとつの部族となる。(邦訳pp.173-175を一部改訳、原著pp.170- 172)
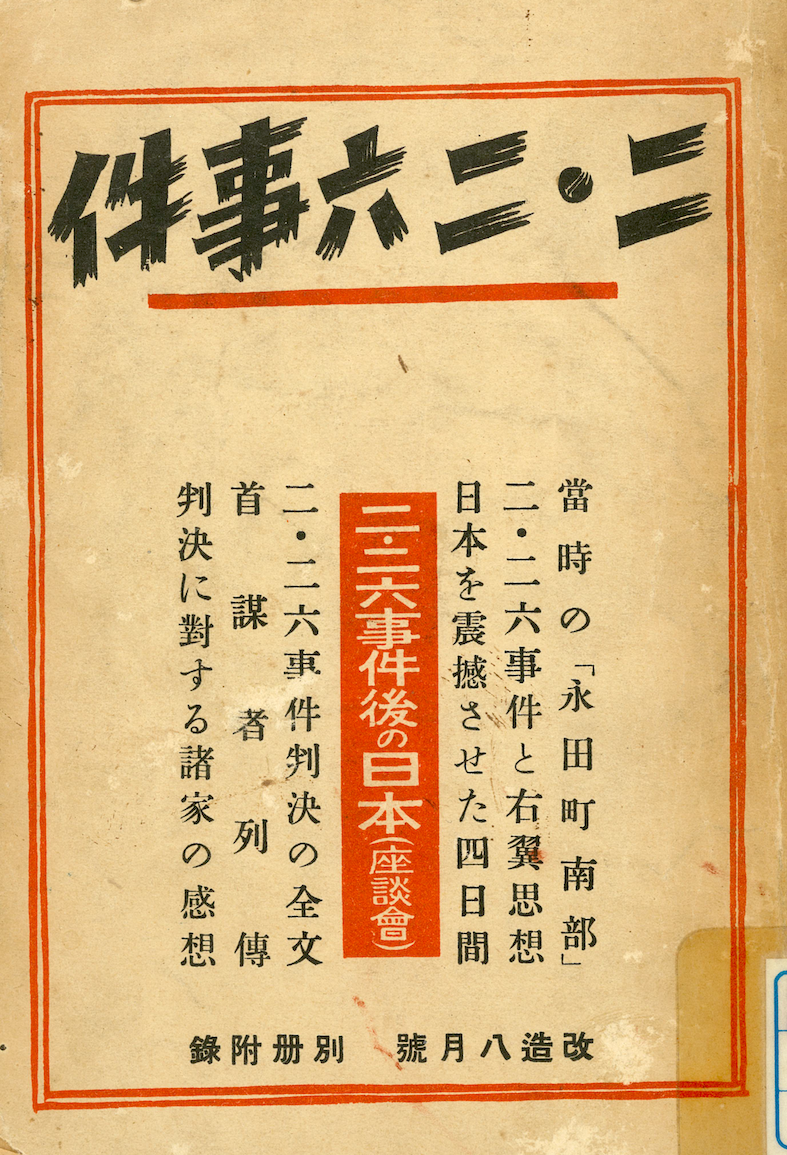 しかし、もちろん事態はこのような単純なものでない。新し
いメディアの普及が人々の意識を変容したということを、指摘することはたやすい
が、論証することはきわめて困難である。また、それ以前に、そのような問題提起の前提つまり、新しいメディアの普及が人間の認知に影響を与え、それが総体
としての人間の意識を変化させたという設問が、なぜ学問上の問題になり、それが真面目に議論されるようになったかということが、時代や社会の文脈から理解
される必要があるようだ。
しかし、もちろん事態はこのような単純なものでない。新し
いメディアの普及が人々の意識を変容したということを、指摘することはたやすい
が、論証することはきわめて困難である。また、それ以前に、そのような問題提起の前提つまり、新しいメディアの普及が人間の認知に影響を与え、それが総体
としての人間の意識を変化させたという設問が、なぜ学問上の問題になり、それが真面目に議論されるようになったかということが、時代や社会の文脈から理解
される必要があるようだ。
メディア研究史を繙けば、新しいメディア が人間の意識を変え、それが現代の我々の社会意識のあり方を知る上で重要な示唆を与えるという主 張は意外と新しいことに気づくはずである。W・ベンヤミンの「複製技術時代の芸術」(1935)はその嚆矢の一つであろうが、カナダのH・イニス (1951)、M・マクルーハン(1951,1962,1964)以降、議論は本格化し、現在の我々の議論により親和性をもつようになる。とくに北アメリ カにおける本格的なテレビ時代の到来によって、マクルーハンの議論は、きわめて大きな社会的影響力をもった。
メディアの普及とそれに影響を受ける人々 というアイディアは、識字を中心とした歴史上の「民衆」(Illich and Sanders 1988)や「未開の心」(Goody 1977)への影響力、政治思想史(Anderson 1987)や文化研究(Tomlinson 1991)などの随所にみられる。
総じて、1960年代のメディア論の中心 的な議論はテレビメディアに関するもので、この新興のメディアは人間の感覚や意識を変えつつある という主張であった。マクルーハンの『グーテンベルグの銀河系』(1962)は、それまで彼が蓄積してきたメディア論の総決算とも言えるものであり、そこ では、さまざまな時代や場所を超えて、新しいメディアの普及は旧来のメディアに慣れ親しんできた人間に衝撃を与えるだけでなく、メディアの理解に習熟する ことが、新しい世界観を得るということに深い関係をもつことを多面的に論じている。類似の議論も数多く見られた。このような現象は、今日の我々がコン ピュータやインターネットの普及に関する社会的影響力の過剰な期待や議論の沸騰という事態と似ていなくはない。
フランスを中心としておこった1970年 代以降の文化や消費の記号論的な解釈(Baudrillard, Barthes)は、それまで論じられることが少なかったメディアの否定的側面に関する説明を通してメディア論に衝撃を与えた。例えばモードの体系は一種 の言語的な記号の体系である、高度資本主義の矛盾は生産の場から消費の場に移行する(記号の消費)、非現実の現実化(ハイパーリアル)の世の中に我々はい る、という指摘がなされた。これは疎外論を通して大衆社会を批判したい知識人にうってつけの言説を提供することになる。また一般には、メディアがもつ消費 活動、それもどちからというと幻影に振り回される現代生活というニュアンスをもって大衆に膾炙した。
ところが1980年代後半からのパーソナ ル・コンピュータの能力の向上と低価格化による爆発的な普及を背景に、インターネットやヴァー チャル・リアリティに関する議論がおもにアメリカ合衆国など先進諸国のコンピュータ技術者の間でさかんに議論されるようになってきた。この議論の背景に は、膨大な情報が取り扱えるコンピュータメディアの発達や成熟、カメラや録音機、今日ではビデオ撮影機等のパーソナル・メディアのコンピュータによる管理 や、自己実現としての情報発信技術などが、ごく当たり前のものとなるほど普及してきたことがあげられる。
メディアの歴史的変化とその環境を利用す る人々の意識の変化という命題は、20世紀に起きた大衆向けの映画の普及(ベンヤミン)、テレビ の普及(マクルーハン)、そして今日のネットワークにつながれたパーソナルコンピュータの普及(現代の論客たち)という技術革新とその大衆化の時期を軌を 同じくして登場してきたことがわかる。メディアが我々の社会意識を変えつつあるという「自覚」は、新種のメディアが急速に普及する社会過程と同調的に、あ るいはやや遅延を伴って現れることが容易に推測されるだろう。少なくとも、人間にはメディアの影響力に脅威を感じたとき、従来維持してきた社会意識を再編 成させ、自分に合った形に鋳直す過程がそこには見られることを指摘しておきたい。
社会意識の審級としてメディアを考える際 には、このあたりの見極めをもって議論を整理する必要がある。
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099