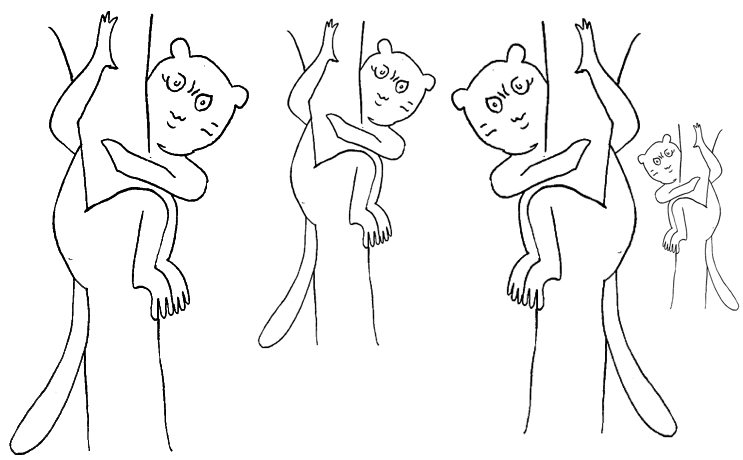
哲学における系譜学
philosophical Genealogy
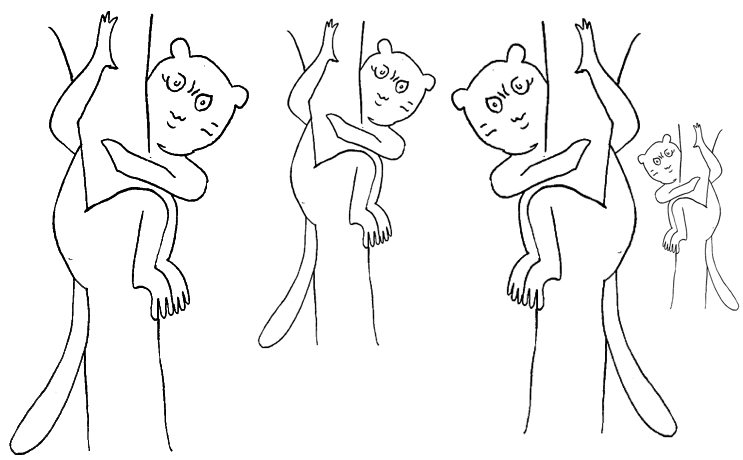
★哲学における系譜学(古代ギリシャ語のγενεαλογία genealogía「系図、家系図」に由来し、γενεά geneá「誕生、子孫、親族、家族」とλόγος lógos「教え」に遡る)は、一般的に認識されている真理と知識の現象の外見を 歴史的に構築されたものとして記述する。その目的は、現在を「非合理化」し、それによって近代と表裏一体の偶然性を明らかにすることにある。その際、権力 の「埋もれた」条件や手段を明らかにし、真理の自明性を奪うことが目的である(ドイツ語版ウィキペディア解説)。
☆ 哲学において系譜学(genealogy)とは、言説の範囲や広がり、あるいは全体性を説明しようとするこ とで、一般に理解されている様々な哲学的・社会的信念の出現に疑問を投 げかけ、分析の可能性を広げる歴史的手法である。さらに系譜学はしばしば、問題となっている言説を越えて、その可能性の条件へと目を向けよ うとする(特に ミシェル・フーコーの系譜学において)。それは、フリードリヒ・ニーチェの著作を引き継ぐものとして発展してきた。系譜学は、マルクス主義がイデオロギー を用いて、特異な、あるいは支配的な言説(イデオロギー)に焦点を当てることで、当該時代における歴史的言説の全体性を説明しようとするのとは対照的であ る。)(英語版ウィキペディア解説)
| In philosophy,
genealogy is a historical technique in which one questions the commonly
understood emergence of various philosophical and social beliefs by
attempting to account for the scope, breadth or totality of discourse,
thus extending the possibility of analysis. Moreover, a genealogy often
attempts to look beyond the discourse in question toward the conditions
of their possibility (particularly in Michel Foucault's genealogies).
It has been developed as a continuation of the works of Friedrich
Nietzsche. Genealogy is opposed to the Marxist use of the ideology to
explain the totality of historical discourse within the time period in
question by focusing on a singular or dominant discourse (ideology). For example, tracking the lineages of a concept such as 'globalization' can be called a 'genealogy' to the extent that the concept is located in its changing constitutive setting.[1] This entails not just documenting its changing meaning (etymology) but the social basis of its changing meaning. |
哲学において系譜学とは、言説の範囲や広がり、あるいは全体性を説明し
ようとすることで、一般に理解されている様々な哲学的・社会的信念の出現に疑問を投げかけ、分析の可能性を広げる歴史的手法である。さらに系譜学はしばし
ば、問題となっている言説を越えて、その可能性の条件へと目を向けようとする(特にミシェル・フーコーの系譜学において)。それは、フリードリヒ・ニー
チェの著作を引き継ぐものとして発展してきた。系譜学は、マルクス主義がイデオロギーを用いて、特異な、あるいは支配的な言説(イデオロギー)に焦点を当
てることで、当該時代における歴史的言説の全体性を説明しようとするのとは対照的である。 例えば、「グローバリゼーション」のような概念の系譜を追跡することは、その概念が変化する構成的設定の中に位置づけられる限りにおいて、「系譜学」と呼 ぶことができる[1]。このことは、単にその意味の変化(語源)を記録するだけでなく、その意味の変化の社会的基礎を記録することを伴う。 |
| Nietzsche Nietzsche criticized "the genealogists" in On the Genealogy of Morals and proposed the use of a historic philosophy to critique modern morality by supposing that it developed into its current form through power relations. But scholars note that he emphasizes that, rather than being purely necessary developments of power relations, these developments are to be exposed as at least partially contingent, the upshot being that the present conception of morality could always have been constituted otherwise.[2] Even though the philosophy of Nietzsche has been characterized as genealogy, he only uses the term in On the Genealogy of Morals. The later philosophy that has been influenced by Nietzsche, and which is commonly described as genealogy, shares several fundamental aspects of Nietzschean philosophical insight. Nietzschean historic philosophy has been described as "a consideration of oppositional tactics" that embraces, as opposed to forecloses, the conflict between philosophical and historical accounts.[3] |
ニーチェ ニーチェは『道徳の系譜学』において「系譜学者たち」を批判し、近代道徳が権力関係を通じて現在の形に発展したと仮定することで、近代道徳を批判するために歴史哲学を用いることを提案した。しかし研究者たちは、ニーチェが、権力関係の純粋に必要な発展というよりはむしろ、こうした発展は少なくとも部分的には偶発的なものとして暴露されるべきであり、その結果、現在の道徳観念は常に別の形で構成される可能性があったことを 強調していることに注目している。ニーチェの哲学が系譜学として特徴づけられてきたとしても、彼がこの言葉を使ったのは『道徳の系譜』においてだけであ る。ニーチェの影響を受け、一般に系譜学と形容される後世の哲学は、ニーチェの哲学的洞察のいくつかの基本的な側面を共有している。ニーチェの歴史哲学 は、哲学的説明と歴史的説明の間の対立を排除するのではなく、受け入れる「対立戦術の考察」と表現されている。 |
| Foucault In the late twentieth century, Michel Foucault expanded the concept of genealogy into a counter-history of the position of the subject which traces the development of people and societies through history.[4] His genealogy of the subject accounts "for the constitution of knowledges, discourses, domains of objects, and so on, without having to make reference to a subject which is either transcendental in relation to the field of events or runs in its empty sameness throughout the course of history."[5] As Foucault discussed in his essay "Nietzsche, Genealogy, History", Foucault's ideas of genealogy were greatly influenced by the work that Nietzsche had done on the development of morals through power. Foucault also describes genealogy as a particular investigation into those elements which "we tend to feel [are] without history".[6] This would include things such as sexuality, and other elements of everyday life. Genealogy is not the search for origins, and is not the construction of a linear development. Instead it seeks to show the plural and sometimes contradictory past that reveals traces of the influence that power has had on truth. As one of the important theories of Michel Foucault, genealogy deconstructs truth, arguing that truth is, more often than not, discovered by chance, backed up by the operation of Power/knowledge or the consideration of interest. Furthermore, all truths are questionable. Pointing out the unreliability of truth, which is often accused as "having tendency of relativity and nihilism",[citation needed] the theory flatly refuses the uniformity and regularity of history, emphasizing the irregularity and inconstancy of truth and toppling the notion that history progresses in a linear order. The practice of genealogy is also closely linked to what Foucault called the "archeological method:" In short, it seems that from the empirical observability for us of an ensemble to its historical acceptability, to the very period of time in which it is actually observable, the analysis goes by way of the knowledge-power nexus, supporting it, recouping it at the point where it is accepted, moving toward what makes it acceptable, of course, not in general, but only where it is accepted. This is what can be characterized as recouping it in its positivity. Here, then, is a type of procedure, which, unconcerned with legitimizing and consequently excluding the fundamental point of view of the law, runs through the cycle of positivity by proceeding from the fact of acceptance to the system of acceptability analyzed through the knowledge-power interplay. Let us say that this is, approximately, the archaeological level [of analysis].[7] |
フーコー 20世紀後半、ミシェル・フーコーは、系図の概念を、歴史を通じて人々と社会の発展をたどる主体の位置の反歴史へと拡大した。彼の主体の系譜学は、「諸事 象の場との関係において超越的であるか、歴史の過程を通じてその空虚な同一性を保っている主体に言及することなく、知識、言説、対象の領域などの構成を説 明する」ものである。 フーコーがそのエッセイ「ニーチェ、系譜、歴史」で論じているように、系譜に関するフーコーの考え方は、ニーチェが権力による道徳の発展について行った研究に大きな影響を受けていた。フー コーはまた、系譜学とは「私たちが歴史がないと感じがちな」要素に対する特別な調査であると述べている。系図は起源を探求するものではなく、直線的な発展 を構築するものでもない。その代わりに、権力が真実に及ぼした影響の痕跡を明らかにする、多元的で時に矛盾した過去を示そうとするものである。 ミシェル・フーコーの重要な理論の一つとして、系譜学は真理を脱構築し、真理は多くの場合、権力/知識の作用や利害の考慮によって裏打ちされた偶然によって発見されると主張する。さらに、すべての真実は疑わしい。しばしば「相対性と虚無主義の傾向を持つ」と非難される真実の信頼性の低さを指摘し、歴史の画一性と規則性を真っ向から否定し、真実の不規則性と不安定性を強調し、歴史が直線的な秩序で進行するという概念を覆す。 系譜学の実践はまた、フーコーが 「考古学的方法 」と呼ぶものと密接に結びついている。 要するに、あるアンサンブルの経験的な観察可能性から、その歴史的受容 可能性へ、そしてそれが実際に観察可能であるまさにその期間へと、分析は知識-権力の結びつきを経由し、それを支え、それが受容される時点でそれを回収 し、もちろん一般的なことではなく、それが受容されるところでのみ、それを受容させるものへと向かうようである。これこそ、積極性においてそれを回収する と特徴づけることができるものである。正統化することに無頓着で、その結果、法の根本的な観点を排除することに無頓着で、受容の事実から、知識と権力の相 互作用を通じて分析される受容可能性の体系へと進むことによって、肯定性の循環を貫く一種の手続きがここにある。これがおおよそ考古学的な[分析の]レベ ルであると言っておこう。 |
| History of ideas The Archaeology of Knowledge Geistesgeschichte Hermeneutics diachrony |
思想史 知識の考古学 思想史 解釈学 通時性 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogy_(philosophy) |
|
| The Archaeology of Knowledge (L’archéologie du savoir, 1969) by Michel Foucault is a treatise about the
methodology and historiography of the systems of thought (epistemes)
and of knowledge (discursive formations) which follow rules that
operate beneath the consciousness of the subject individuals, and which
define a conceptual system of possibility that determines the
boundaries of language and thought used in a given time and domain.[1]
The archaeology of knowledge is the analytical method that Foucault
used in Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of
Reason (1961), The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical
Perception (1963), and The Order of Things: An Archaeology of the Human
Sciences (1966).[1] |
ミシェル・フーコーの『知の考古学』(L'archéologie du savoir, 1969)は、主体である個人の意識下で作動する規則に従い、ある時代と領域で使用される言語と思考の境界を決定する可能性の概念体系を定義する思考(エピステーメー)と知識(言説的形成)のシステムの方法論と歴史学についての論考で
ある[1]: A History of Insanity in the Age of
Reason』(1961年)、『クリニックの誕生』(1961年)、『医学的知覚の考古学』(1961年)においてフーコーが用いた分析手法である:
医学的知覚の考古学』(1963年)、『物事の秩序』(1963年)である: 人間科学の考古学』(1966年)である[1]。 |
| Summary The contemporary study of the History of Ideas concerns the transitions between historical world-views, but ultimately depends upon narrative continuities that break down under close inspection. The history of ideas marks points of discontinuity between broadly defined modes of knowledge, but those existing modes of knowledge are not discrete structures among the complex relations of historical discourse. Discourses emerge and transform according to a complex set of relationships (discursive and institutional) defined by discontinuities and unified themes.[2] An énoncé (statement) is a discourse, a way of speaking; the methodology studies only the “things said” as emergences and transformations, without speculation about the collective meaning of the statements of the things said.[3] A statement is the set of rules that makes an expression — a phrase, a proposition, an act of speech — into meaningful discourse, and is conceptually different from signification; thus, the expression “The gold mountain is in California” is discursively meaningless if it is unrelated to the geographic reality of California.[4] Therefore, the function of existence is necessary for an énoncé (statement) to have a discursive meaning.[5] As a set of rules, the statement has special meaning in the archaeology of knowledge, because it is the rules that render an expression discursively meaningful, while the syntax and the semantics are additional rules that make an expression significative.[6] The structures of syntax and the structures of semantics are insufficient to determine the discursive meaning of an expression;[7] whether or not an expression complies with the rules of discursive meaning, a grammatically correct sentence might lack discursive meaning; inversely, a grammatically incorrect sentence might be discursively meaningful; even when a group of letters are combined in such a way that no recognizable lexical item is formulated can possess discursive meaning, e.g. QWERTY identifies a type of keyboard layout for typewriters and computers.[8] The meaning of an expression depends upon the conditions in which the expression emerges and exists within the discourse of a field or the discourse of a discipline; the discursive meaning of an expression is determined by the statements that precede and follow it.[9] To wit, the énoncés (statements) constitute a network of rules that establish which expressions are discursively meaningful; the rules are the preconditions for signifying propositions, utterances, and acts of speech to have discursive meaning. The analysis then deals with the organized dispersion of statements, discursive formations, and Foucault reiterates that the outlined archaeology of knowledge is one possible method of historical analysis.[10] |
概要 現代の思想史研究は、歴史的世界観の変遷に関わるものであるが、最終的には、綿密な検証のもとで破綻する物語の連続性に依存している。 思想史は、広範に定義された知識様式間の不連続点を示すものであるが、そうした既存の知識様式は、歴史的言説の複雑な関係の中にある個別の構造ではない。 言説は、不連続性と統一されたテーマによって定義される複雑な一連の関係(言説的・制度的関係)に従って出現し、変容する。 この方法論は、「語られたこと」の集合的な意味について推測することなく、出現と変容としての「語られたこと」のみを研究する。言明とは、ある表現(フ レーズ、命題、発話行為)を意味のある言説にするルールの集合であり、意味化とは概念的に異なる。したがって、「金山はカリフォルニアにある」という表現 は、カリフォルニアという地理的現実と無関係であれば、言説的には無意味である。したがって、存在という機能は、エノンセ(陳述)が言説的意味を持つために必要である。 というのも、構文と意味論は表現を有意味なものにする付加的な規則であるのに対して、文は規則の集合として、知識の考古学において特別な意味を持つからである。構文の構造も意味論の構造も、表現の言説的意味を決定するには不十分である。表現が言説的意味の規則に従っているかどうかにかかわらず、文法的に正しい文が言説的意味を欠いているかもしれない。逆に、認識可能な語彙項目が定式化されないような方法で文字が組み合わされても、文法的に正しくない文は、言説的意味を持つことがある。例えば、QWERTYはタイプライターやコンピュータのキーボードレイアウトの一種である。 表現の意味は、その表現がある分野の言説や学問分野の言説の中で出現し、存在する条件によって決まる。 表現の言説的意味は、その表現に先行し、後続する言説によって決定される。つまり、énoncés(陳述)は、どの表現が言説的に意味を持つかを定める ルールのネットワークを構成している。ルールは、命題、発話、発話行為を意味づける言説的意味を持つための前提条件である。そして分析は、記述の組織的分 散、言説的形成を扱う。そしてフーコーは、概説された知識の考古学が歴史分析の一つの可能な方法であると繰り返し述べている。 |
| Reception The philosopher Gilles Deleuze describes The Archaeology of Knowledge as, "the most decisive step yet taken in the theory-practice of multiplicities."[11] |
受容 哲学者のジル・ドゥルーズは、『知の考古学』を「多重性の理論-実践において、いまだかつてない決定的な一歩を踏み出した」と評している[11]。 |
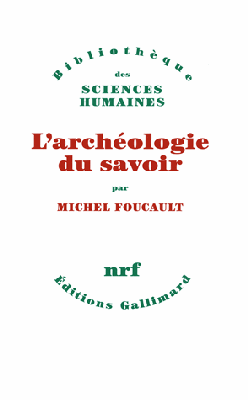
|
|
| https://en.wikipedia.org/wiki/The_Archaeology_of_Knowledge |
|
| Genealogie
(von altgriechisch γενεαλογία genealogía „Geschlechtsregister,
Stammbaum“; zurückgehend auf γενεά geneá „Geburt, Abstammung,
Sippschaft, Familie“ und λόγος lógos „Lehre“) in der Philosophie
beschreibt eine kritisch-historische Methode, mithilfe der das
gemeinhin als selbstverständlich wahrgenommene Erscheinen von
Wahrheits- und Wissensphänomenen in der Moderne als geschichtlich
konstruiert untersucht wird. Sie zielt darauf, Gegenwart zu
„deplausibilisieren“ und damit die mit der Moderne einhergehende
Kontingenz aufzuzeigen. Dabei sollen „vergrabene“ Bedingungen und
Machtinstrumente freigelegt werden, um Wahrheit ihrer
Selbstverständlichkeit zu berauben. |
哲学における系譜学(古代ギリシャ語のγενεαλογία
genealogía「系図、家系図」に由来し、γενεά geneá「誕生、子孫、親族、家族」とλόγος
lógos「教え」に遡る)は、一般的に認識されている真理と知識の現象の外見を
歴史的に構築されたものとして記述する。その目的は、現在を「非合理化」し、それによって近代と表裏一体の偶然性を明らかにすることにある。その際、権力
の「埋もれた」条件や手段を明らかにし、真理の自明性を奪うことが目的である。 |
| Inhaltsverzeichnis 1 Begriffsklärung 2 Genealogische Unternehmungen vor Nietzsche 3 Genealogie bei Nietzsche 4 Differenzierung zur Ursprungssuche 5 Genealogie bei Foucault 6 Literatur 7 Einzelnachweise |
目次 1 定義 2 ニーチェ以前の系譜学の試み 3 ニーチェにおける系譜学 4 起源の探究との相違 5 フーコーにおける系譜学 6 文献 7 参考文献 |
| Begriffsklärung Der Name leitet sich übertragend aus der Art der Recherche ab, die der jener Genealogen ähnelt, welche akribisch in Archiven ihrer Familiengeschichte nachspüren, und wurde durch Friedrich Nietzsche in seiner Genealogie der Moral in diesem Sinne gar im Titel verwendet. Bedeutend weitergeführt hat die Genealogie Michel Foucault. Die Metapher beflügelt sich dadurch, dass sowohl die Ahnenforschung als auch die Genealogie im neuen, Foucault’schen Sinn zum Gegenstand haben, dass kein Ursprung ausgemacht werden kann, sondern vielmehr ein immer komplexeres und sich verzweigendes System letztendlich zur Auflösung des Ichs führt. Beiden geht es dabei statt der Suche nach einer Wahrheit um eine Nachzeichnung von Um- und Irrwegen, von Verläufen und Entwicklungen, von parallelen Narrativen und Historiografien.[1] „Herkunft“ ist so also auch körperlich zu begreifen und zu beschreiben, wobei die Vergangenheit und ihre Fakten den Leib bilden, der nun von der Geschichte bearbeitet wird und Konflikte austrägt. Diese scheinbare somatische Einheit bereitet auch den Schauplatz für die Auflösung des Ichs. |
定義 この名称は、系図学者が記録文書から丹念に家系を辿るのと似た研究の種類に由来する。フリードリヒ・ニーチェも、著書『道徳の系譜学』のタイトルでこの意味でこの語を使用している。ミシェル・フーコーは系譜学を大きく前進させた。 この比喩は、系譜学とフーコー的な意味での新しい系譜学の両方が、起源を特定できないという事実を主題としているという事実から着想を得ている。むしろ、 ますます複雑で分岐するシステムが最終的に自己の崩壊につながるという事実である。真実の探究ではなく、どちらも迂回や蛇行、経過や展開、並行する物語や 歴史叙述の追跡に関心がある。 したがって、「起源」は物理的な用語でも理解され、記述される。過去とその事実が身体を形成し、それが今、歴史によって処理され、対立が解消される。この明白な身体的な統一性もまた、自己の崩壊の舞台となる。 |
| Genealogische Unternehmungen vor Nietzsche Als erster verband wohl Platon im ersten Buch des Staats Rechtfertigung von und Kritik an Institutionen politischer Art mit der Frage historischer Entwicklung, wobei Platon hier noch von Ursprüngen ausgeht. Im Diskurs über den Ursprung und die Grundlage der Ungleichheit unter den Menschen stellt Rousseau ähnliche philosophische Überlegungen an, die ihn schließlich zu einer historisch verfolgten Kritik frühmoderner sozialer Institutionen führt. Dabei entwickelt er Konzepte um Selbst und Macht, die später für Nietzsche und dann auch für Foucault prägend sein sollen. Weiter anzuführen sind, um eine „Genealogie der Genealogie“ bemüht, möglicherweise am Rande: Simmels und Webers Kultursoziologie, Schelers und Plessners philosophische Anthropologie, die „Urgeschichte der Subjektivität“ in Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung, Benjamins Zur Kritik der Gewalt, Hardt und Negris Empire bis hin zu Derridas Grammatologie.[2] |
ニーチェ以前の系譜学 プラトンは、おそらく国家の最初の書物において、政治制度の正当化と批判を歴史的発展の問題と結びつけた最初の人物であったが、プラトンは依然として起源 から出発している。 人間の間の不平等についての起源と根拠に関する彼の論説において、ルソーは同様の哲学的考察を行い、最終的には初期近代の社会制度の歴史的軌跡をたどる批 判へと導いた。そうすることで、彼は自己と権力の概念を発展させ、それは後にニーチェやフーコーにも影響を与えることとなった。「系譜学の系譜」という観 点では、ジンメルやウェーバーの文化社会学、シェーラーやプレッスナーの哲学的人間学、ホルクハイマーとアドルノの『啓蒙の弁証法』における「主観性の先 史時代」、ベンヤミンの『暴力批判について』、ハートとネグリの『帝国』、そしてデリダの『グラマトロジー』についても、簡単に触れておく価値があるだろ う。 |
| Genealogie bei Nietzsche In seiner Genealogie der Moral analysiert Nietzsche die Arbeit der (englischen) Psychologen – speziell am Beispiel von Dr. Paul Rees Untersuchung "der Ursprung der moralischen Empfindungen" (1877)[3] – und schlägt eine historische Philosophie als Gegenstand zur Kritik der modernen Moral vor. Dabei nimmt er an, dass jene durch Machtverhältnisse erst in ihre damalige Form gebracht worden war und legt die Konstruktion derselben offen. Moral als historisch gewachsen zu begreifen impliziert für Nietzsche auch, dass sie sich genauso auch anders konstituieren könne, hätten Machtverhältnisse anders gelegen, und stellt im Umkehrschluss damit deren grundlegende Unanfechtbarkeit infrage.[4] Obgleich die Philosophie Nietzsches zuweilen im Ganzen als Genealogie bezeichnet wird, benutzt Nietzsche selbst diesen Terminus ausschließlich in der Genealogie der Moral, hier sogar prominent im Titel. Dennoch wird deutlich, dass spätere Genealogie als etablierte philosophische Kategorie in der Tat viele der Einsichten Nietzsches teilt. Ideengeschichte, die sich an Nietzsches Arbeiten orientiert, wurde als „ein Bedenken oppositioneller Taktiken“ beschrieben, welche den Konflikt zwischen philosophischen und historischen Narrativen begrüßt statt verdrängt.[5] |
ニーチェにおける系譜学 『道徳の系譜学』において、ニーチェは(英国の)心理学者たちの研究を分析し、特にポール・リー博士の研究「道徳感情の起源」(1877年)を例に挙げな がら[3]、近代道徳の批判の対象として歴史哲学を提案している。彼は、近代道徳が権力関係によって現代的な形になったに過ぎないと想定し、その構造を明 らかにしている。ニーチェにとって、道徳が歴史的に発展してきたと理解することは、権力関係が異なっていたならば、道徳も異なった形で構成されていた可能 性があることを意味し、暗にその根本的な非の打ちどころのなさを問いただしている。4] ニーチェの哲学は全体として系譜学と呼ばれることもあるが、ニーチェ自身は『道徳の系譜学』においてのみこの用語を使用しており、ここではタイトルにもこ の用語が使われている。しかし、後に確立された哲学のカテゴリーとしての系譜学は、ニーチェの洞察の多くを確かに共有している。ニーチェの著作に焦点を当 てた思想史は、「対立する戦術の再考」であり、哲学と歴史の物語の間の対立を抑制するのではなく、むしろ歓迎するものであると説明されている。 |
| Differenzierung zur Ursprungssuche Insbesondere Foucault legt später Wert darauf, Nietzsches Genealogie die zugeschriebene Ursprungssuche abzusprechen, wenngleich Nietzsche selbst in seiner Genealogie der Moral den Begriff synonym für Entstehung, Geburt, Herkunft gebraucht, ohne dies genauer zu bestimmen. Genealogie sei demnach selbst bei Nietzsche keine Ursprungssuche. Trennend sei hierbei, dass die Ursprungssuche um einen klar umrissenen Gegenstand bemüht sei, der linear entsteht, während die Genealogie die Wesenlosigkeit und die historisch bedingte Veränderlichkeit von Gegenständen an sich zum Ausgangspunkt hat. So verbleibt eine Genealogie der Moral bei Zufällen und vielschichtigen Entwicklungen, ohne jene mit Wahrheit zu verwechseln, die Geschichte eines Irrtums also, der Wahrheit genannt wird.[6] |
起源の探究との区別 特にフーコーは、ニーチェ自身が『道徳の系譜学』において「出現」、「誕生」、「起源」という用語をより正確に定義することなく同義的に使用しているにも かかわらず、ニーチェの系譜学が起源の探究という属性を持つことを否定することの重要性を強調した。したがって、ニーチェの著作においても、系譜学は起源 の探究ではない。ここで異なるのは、起源の探索は明確に定義された対象が直線的に生じることを扱うのに対し、系譜学は対象の実体のなさや歴史的に偶発的な 変化を起点とする点である。したがって、道徳の系譜学は偶然性や多層的な展開を残し、後者を真理と混同することなく、真理と呼ばれる誤りの歴史を残す。 |
| Genealogie bei Foucault In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts erweiterte Michel Foucault die Methode der Genealogie zu einer Gegengeschichte der Position des Subjekts, welches die Entwicklung von Gesellschaften historisch nachvollzieht. In Die Ordnung des Diskurses sieht Foucault diese Methode untrennbar mit der Kritik verbunden, um die "Formierung des Diskurses"[7] zu erfassen. Seine Genealogie des Subjekts repräsentiert daher „die Konstitution von Wissen, Diskursen, Mengen von Objekten, und so weiter, ohne einen Verweis auf ein Subjekt machen zu müssen, das entweder transzendental in Bezug auf das Feld der Ereignisse ist, oder sich in seiner leeren Gleichheit durch den Verlauf der Geschichte zieht.“[8] Wie Foucault in seinem Aufsatz Nietzsche, die Genealogie, die Historie (1971) diskutiert, waren seine Ideen zur Genealogie in großen Zügen von Nietzsches Werk über die Entwicklung von Moral durch Machtverhältnisse beeinflusst. Foucault beschreibt Genealogie als eine besondere in jenen Elementen, von welchen „wir üblicherweise fühlen[, dass sie] ohne Geschichte“[9][10] seien. Darin bezieht er Gegenstände wie Sexualität oder Strafe ein. Genealogie meint demnach nicht die Suche nach tatsächlichen Ursprüngen und auch nicht die Erzählung linearer Entwicklungen, sondern die Rekonstruktion historischer Machtverhältnisse und Spannungsfelder, unter welchen das in Diskursen gewachsen ist, was gemeinhin als „Wissen“ oder „Wahrheit“ verstanden wird – Kategorien, die dann selbst auch Macht ausüben und verteilen. Eine der wichtigsten Thesen Foucaults ist, dass mithilfe der genealogischen Untersuchungen „Wahrheit“ insoweit dekonstruiert werden kann, als Letztere aufhört objektiv zu existieren. Stattdessen ist sie zufällig entdeckt, anerkannt durch das Arbeiten von Macht-Wissen-Komplexen oder im Sinne politischer Interessen. Eben aus diesem Grund sind für Foucault alle „Wahrheiten“ zu hinterfragen, da sie unzuverlässig sind. Obschon mit Relativierung und Nihilismus attribuiert, lehnt Foucault eine auf Einheitlichkeit, Linearität und Regularität bedachte Historiografie ab, indem er die Unregelmäßigkeit und Inkonsistenz von Wahrheit bzw. Wissen betont. Foucault beschreibt die Methode der Genealogie auch als „in etwa [auf dem] Niveau der Archäologie“: „Von der empirischen Beobachtbarkeit – für uns jetzt – zu seiner historischen Akzeptabilität – in seiner bestimmten Epoche – geht der Weg über eine Analyse des Nexus Macht-Wissen, der die Tatsache seines Akzeptiertseins auf das hin verständlich macht, was es akzeptabel macht – nicht im allgemeinen sondern eben dort, wo es akzeptiert ist: das heißt es in seiner Positivität zu erfassen. Es handelt sich also um ein Verfahren, das sich nicht um die Legitimierung kümmert und das folglich den grundlegenden Gesichtspunkt des Gesetzes eliminiert: es durchläuft den Zyklus der Positivität, indem es vom Faktum der Akzeptiertheit zum System der Akzeptabilität übergeht, welches als Spiel von Macht-Wissen analysiert wird. Das ist in etwa das Niveau der Archäologie.“[11] |
フーコーにおける系譜学 20世紀後半、ミシェル・フーコーは、社会の歴史的発展をたどる主体の位置の反歴史に系譜学の方法を拡大した。『言説の秩序』において、フーコーは、この 方法を「言説の形成」を把握するための批判と不可分に結びついたものと見なしている。したがって、彼の主題の系譜学は、「出来事の分野に対して超越論的で あるか、あるいはその空虚な同一性において歴史の過程を貫く主題を参照することなく、知識、言説、対象の集合体などの構成」を表している[8]。 フーコーは、1971年の論文『ニーチェ、系譜学、歴史』で、系譜学に関する自身の考えは、権力関係を通じての道徳の発展に関するニーチェの研究から大き な影響を受けたと述べている。フーコーは、系譜学を「通常、歴史がないと考える」要素の特別なものであると説明している[9][10]。これには、性や処 罰といった主題も含まれる。したがって系譜学とは、実際の起源の探索や直線的な発展の叙述を意味するものではなく、言説の中で成長してきたものが一般的に 「知識」や「真実」として理解されている歴史的な権力関係や緊張の領域の再構築を意味する。 フーコーの最も重要なテーゼのひとつは、系譜学的な調査の助けを借りれば、「真理」は客観的に存在しなくなるほどにまで解体できるというものである。その 代わりに、それは偶然発見され、権力と知識の複合体の活動を通じて、あるいは政治的利益のために認識される。まさにこの理由から、フーコーにとって、すべ ての「真理」は信頼できないものであるため、疑問視されるべきである。これは相対主義的でニヒルに聞こえるかもしれないが、フーコーは真実と知識の不規則 性と不整合性を強調することで、均一性、直線性、規則性に基づく歴史記述を否定している。 また、フーコーは系譜学の方法を「おおよそ考古学のレベル」にあるものとして説明している。 「経験的に観察可能なものから、特定の時代における歴史的に受容可能なものへと至る道筋は、権力と知識の結びつきを分析することによって通過する。この分 析により、受容可能なものという事実が、受容可能なものとなる要因という観点から理解可能となる。つまり、受容可能なものをその肯定性において把握するの だ。したがって、それは正当化とは無関係であり、その結果、法の根本的な側面を排除する手続きである。それは、受容のサイクルを通り、受容の事実から受容 の体系へと移行し、権力と知識のゲームとして分析される。これは、おおよそ考古学のレベルである。」[11] |
| Literatur Martin Saar: Genealogie als Kritik. Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche und Foucault. Campus Verlag, Frankfurt 2007, ISBN 978-3-593-38191-6. Michel Foucault: Nietzsche, die Genealogie, die Historie. In: Daniel Defert, Francois Ewald (Hrsg.): Michel Foucault. Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits (Band 2). 2. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-3-518-58353-1, S. 166–191. |
文献 Martin Saar: Genealogy as Critique: History and Theory of the Subject after Nietzsche and Foucault. Campus Verlag, Frankfurt 2007, ISBN 978-3-593-38191-6. ミシェル・フーコー:ニーチェ、系譜学、歴史。ダニエル・デフェール、フランソワ・エヴァルト(編):ミシェル・フーコー。4巻本。Dits et Ecrits(第2巻)。第2版。Suhrkamp、フランクフルト・アム・マイン2014年、ISBN 978-3-518-58353-1、166-191ページ。 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Genealogie_(Philosophie) |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆