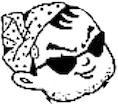
意味についての懐疑論
skepticism about meaning
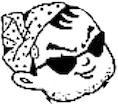
☆ 「懐疑主義(かいぎしゅぎ、英語: skepticism)と は、基本的原理・認識に対して、その普遍妥当性、客観性ないし蓋然性を吟味し、根拠のないあらゆるドクサ(独断)を排除しようと する主義である。懐疑論(かいぎろん)とも呼ばれる」ウィキペディア日本語)。その反対語は「独断論・独断主義(Dogmatismus)」で「絶対的な 明証性をもつとされる基本的原理(ドグマ)を根底におき、そこから世界の構造を明らかにしようとする立場」である。(「哲学的懐疑主義」「ピュロニズムあるいはフュロン主義」は別稿で説明する)
●
意味懐疑論
もう一つの解釈として、例えばアンソニー・ケニーが提出した報告[11]で述べられているのだが、私的な直示的定義に関する問題は間違って記憶されること
だけでなく、そういった定義は有意味な言明を導かないというものもあるということがある。
公共的言語における直示的定義の場合を考えてみよう。ジムとジェニーがある日どこか独特な木を「T」と呼ぶことに決めたかもしれない。しかし次の日に「二
人とも」自分たちがどの木に名づけたか記憶違いをする。この、通常の言語の場合は、「これが僕たちが昨日『T』と名付けた木だろうか?」と言う問いは意味
を成す。だから、人は生活形式の他の部分、ひょっとしたら論議に訴えることができる。「これが森の中のたった一本のオークだ。『T』はオークだった。だか
らこれが『T』だ」というように。
日常的な直示的定義は公共的言語に埋め込まれていて、そのため言語がその中で生じる生活形式の中に埋め込まれている。公共的な生活形式に参加することで起
こったことを正すことができるようになる。つまり、公共的言語の場合には直示的に定義された言葉を別の方法で確かめることができる。私たちは直示的定義を
多かれ少なかれはっきりさせることで私たちの「T」という新しい名前の用法の正当性をしめすことができる。
しかし「S」の場合はこうはいかない。「S」は私的言語の一部だから「S」のはっきりした定義を与えることはできないことを思い起こそう。唯一の「可能
な」定義は「S」を「あの」感覚と結びつけるという私的・直示的なものである。しかしそれは「まさに問われているそのもの」である。「誰かがこういってい
るのを想像しよう。『でも僕は自分の身長がわかっているんだ!』そしてそれを示すために自身の手を頭頂に乗せる」[12]。
ヴィトゲンシュタインの著作に繰り返し現れる主題として、意味を成す言葉や発話は疑い得るに違いないということがある。ヴィトゲンシュタインにとって、
トートロジーは意味をなさず、何も言っておらず、また疑いを挟み得ない。しかしさらに、他のいかなる発話も疑いを挟み得ないとすれば、その発話は無意味で
あるに違いない。ラッシュ・リーズは、ヴィトゲンシュタインの講義の記録に、一方で物理的対象の実在性について議論しつつこう書いている。:
我々は「p →
p」のようなトートロジーを記述する際に何かを同じように把握している。我々はそういった印象をまとめて疑い得ないように何かを把握している―たとえ意味
が疑いとともに消滅するとしても[13]。
ケニーの述べるところでは、「何かを『S』だと『間違って』考えるためにも、私は『S』の意味を知っていなければならない。また、これはヴィトゲンシュタ
インの主張することが日常言語では不可能だということである」[14]。私的な直示的定義「の他に」「S」の意味(あるいは用法)を確かめる方法がないの
で、「S」が意味すること「を知る」のは不可能である。意味は疑いとともに消滅する。
ヴィトゲンシュタインはさらに進んで、左手が右手に金銭をあげるという類推を用いている[15]。物理的な動きは存在するが、取引としては贈与の内に数え
られない。同様に。ある人は一方で感覚に注目して「S」と言っているが、実際に名づけという作用が起こってはいない。
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆