Transformation of tragedy
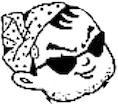
Transformation of tragedy
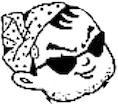
「周知のようにアリストテレスは悲劇における行動の根源として2つのこと、思考と性格(ディアノ イア・カイ・エートス)をあ げているが、同時に眼目は目的(テロス)であって、人物は性格を現すために行動するのではなく、性格が 行動(ハンドルング)のために受け入れられるのだと注意している※01。ここに現代悲劇との相違があるのは容易に気づ きうるであろう。
つまり古代の悲劇に特有なことは、行動が性格からのみ生ずるのではなく、行動 が十分に主観的に反省されておらず、行動自体が相対的な受苦の付加物を持っていることである。 したがって古代の悲劇は対話(デイアローグ)を、そのなかにいっさいがこめられるほど十分な反省にまでは発展さ せない。それは本来独白(モノローグ)とコロス※02のなかに対話とは別個の諸契機を持っている。なぜなら、コロ スがより多く叙事詩的な現実性や抒情詩的な感激に近づ<にしても、それはやはり、個性のなかでは 汲みつくされない、いわば余分のものを暗示するのである。また独白はより多く抒情詩的集中であっ て、行動とシュチュエーションのなかでは汲みつくされない余分のものを持っている。行動自体が 古代の悲劇においてはある叙事詩的契機を含んでいて、行動であると同時に事件なのである。
とこ ろでこのことはもちろん、古代世界は主体性を自己みずからのうちに反省していなかったということ に基づいている。個人が自由に活動しようとも、それはやはり国家・血族・運命などの現実的諸規定 のなかに包まれていた。この現実的諸規定がギリシア悲劇の本来的に運命的なものであって、その真 の特異性である。それゆえ主人公の没落は単に自分の行動の結果ではなく、同時に1つの受苦である が、それに反して近世の悲劇における主人公の没落は本来的には受苦ではなくて。1つの行為であ/ る。
したがって近世においては本来シュチュエーションと性格が支配的なものである。悲劇の主人公は
主観的に自己のなかに反省されており、この反省は彼を国家・一族・運命へのあらゆる直接的関係か
ら引き離すばかりか、しばしば自分自身のこれまでの生からさえ引き離したのである。われわれの関
心をひくのは、彼の生のなかで彼自身の業(わざ)として現われるある特定の契機である。したがって悲劇的
なものはシュチュエーションと対話(ダイアローグ)のなかで汲みつくれる。もはや直接的なものはなにも残ってい
ないからである。だから現代の悲劇は叙事詩的な前景も叙事詩的な残り物も持たない。主人公はひた
すら彼自身の行為とともに立ち、ともに倒れるのである
」(キルケゴール 1995:229-230)。
※01:アリストテレス「詩学」第6章、 ただし引用はヘーゲル『美学』からの引用。
「6.
悲劇の定義と悲劇の構成要素について
(6-1)ヘキサメートル詩で模倣する詩と喜劇については、この後で述べる。次に、悲劇について、すでに述べたことの結果として、その形式的な定義を再開
して論じよう。
(6-2)悲劇とは、重大で完結した、ある程度の規模を持つ行為の模倣である。あらゆる種類の芸術的装飾で彩られた言語によって表現され、それらの装飾は
劇の別々の部分に見られる。物語ではなく行為の形式によって、哀れみと恐怖を通じて、これらの感情の適切な浄化をもたらす。ここで「装飾された言語」と
は、韻律や「調和」、歌が入り込んだ言語を意味する。「各部分が別々に配置される」とは、ある部分は詩のみによって表現され、またある部分は歌の助けを借
りて表現されることを意味する。
(6-3)悲劇の模倣は人格の演技を意味するので、まず第一に、必然的に、スペクタクルな装置が悲劇の一部となる。次に、歌と語法であるが、これらは模倣
の媒体である。ディクション」とは、言葉の単なる計量的配列のことであり、「歌」については、誰もがその意味を理解する用語である。
(6-4)また、悲劇は行為の模倣であり、行為には人格的な主体が含まれ、その主体は必然的に、人格と思考の両方においてある種の特徴的な特質を有してい
る。したがって、筋書きとは行為の模倣であり、筋書きとは事件の配置を意味する。性格とは、行為者にある特質を与えることを意味する。思想が必要とされる
のは、ある主張が証明される場合、あるいは一般的な真理が宣言される場合であろう。したがって、あらゆる悲劇には6つの部分が必要であり、この部分がその
質を決定する。すなわち、筋、性格、語法、思考、スペクタクル、歌である。部分のうち2つは模倣の媒体を構成し、1つは模倣の方法、3つは模倣の対象を構
成する。そしてこれらがリストを完成させる。これらの要素は、詩人たちがこぞって採用してきたと言える。実際、どの劇にも、キャラクター、プロット、語
法、歌、思想のほかに、スペクタクルの要素が含まれている。
(6-5)しかし何よりも重要なのは、事件の構造である。悲劇は人間の模倣ではなく、行為と人生の模倣であり、人生は行為から成り立ち、その終わりは行為
様式であって、資質ではないからだ。人生とは行動であり、その目的とは行動様式であって、資質ではないのである。したがって、ドラマチックなアクション
は、人格を表現するためにあるのではない。それゆえ、事件と筋書きは悲劇の目的であり、目的こそがすべての最重要事項なのである。行動なくして悲劇はあり
えない。現代の詩人たちの悲劇は、人物の描写に失敗している。それは絵画においても同じで、ゼウキスとポリグノトスの違いはここにある。ポリグノトスは人
物描写に優れているが、ゼウクシスの作風には倫理性がない。また、性格を表現し、語法と思想の点でよく仕上がった一連の演説を並べたとしても、これらの点
で不十分であっても、筋書きと芸術的に構成された事件を持つ戯曲ほど、本質的な悲劇的効果は得られないだろう。その上、悲劇における最も強力な感情的要素
である「ペリペテイア」(状況の反転)や「認識」の場面は、プロットの一部である。さらにその証拠に、この芸術の初心者は、プロットを構築する前に、ディ
クションの完成度と肖像画の正確さに到達している。これは、ほとんどすべての初期の詩人について同じである。
(6-6)筋書きは悲劇の第一の原則であり、いわば魂である:性格はその次である。同じようなことが絵画にも見られる。どんなに美しい色彩でも、肖像画の
チョークで描かれた輪郭と同じような喜びは得られない。このように、悲劇とは行為を模倣することであり、行為者を模倣することである。
(6-7)第三に思考がある。つまり、与えられた状況において可能かつ適切なことを述べる能力だ。弁論においては、これが政治術と修辞術の役割である。実
際、古代の詩人たちは登場人物に市民生活の言葉を語らせ、現代の詩人たちは修辞家の言葉を語らせている。性格とは、道徳的目的を明らかにし、人が何を選
び、何を避けるかを示すものである。したがって、これを明らかにしない演説、あるいは演説者が何も選ばず、何も避けない演説は、性格を表現していない。一
方、思考は、何かが存在する、あるいは存在しないことが証明されたり、一般的な格律が述べられたりする時に見出される。
(6-8)列挙した要素の中で4番目に挙げられるのは「ディクション」である。ディクションとは、すでに述べたように、意味を言葉で表現することを意味す
る。
残りの要素の中で、「歌」は装飾の中で最も重要な位置を占めている。
スペクタクルは、確かに、それ自体の感情的な魅力を持っているが、すべての部分の中で、最も芸術的でなく、詩の芸術と最も関係が薄い。というのも、悲劇の
力は、表現と俳優を離れても感じられるからである。その上、スペクタクルな効果を生み出すには、詩人の技よりも舞台装置職人の技に頼るところが大きい。」アリストテレス「詩学」)
※02:コロス=コーラス隊、劇中で状況 の説明したりする役割を担う
「コ
ロス(古代ギリシャ語: χορός, khoros、 英:
chorus)は、古代ギリシア劇の合唱隊のこと。ディテュランボスおよびtragikon
dramaから発生したと考えられている。コロスは観客に対して、鑑賞の助けとなる劇の背景や要約を伝え、劇のテーマについて注釈し、観客がどう劇に反応
するのが理想的かを教える。また、劇中の一般大衆の代弁をすることもある。多くの古代ギリシア劇の中で、コロスは登場人物が劇中語れなかったこと(恐怖、
秘密など)を代弁する。コロスの台詞は通常、歌の形式を採るが、時にはユニゾンで詩を朗読する場合もある。
コロスは、悲劇・喜劇が抒情詩作品だった時期の古代ギリシア劇で、重要かつ主要な構成要素だった。とくに、アイスキュロスが複数の俳優を使いだす以前は、
たった一人しかいなかった俳優に対する重要な相手役だった[1]Haigh, 1898, p. 319, [2]Kitto, 2002, pp. 22, 27。その重要性が減衰していったのは紀元前5世紀以降で、コロスは劇の動きから切り離
されはじめる。後の時代の劇作家、たとえばソポクレスなどは、それ以前の作家ほどコロスに依存しなくなった。ソポクレスの『オイディプス王』を始めとする
テーバイ三部作の中で、コロスは全知の解説者の役割を果たし、しばしば物語の教訓性を補強した。コロスは「解説者」と「登場人物」の中間に位置するように
なり、登場人物である時は、他の登場人物たちに彼らが必要とする洞察を与えた。
コロスには、1〜3人の俳優で演じられる劇を説明して助ける役割があった。古代ギリシアの円形劇場は非常に大きかったので、遠くの観客にもわかるよう動き
は誇張され、また発声もはっきり聞き取れるようにした。技術的には、シンクロニゼーション(同期性)、エコー、波紋、身体表現を駆使し、仮面をつけてい
た」コロス)
「コロスとは感動している人びとだということです」——ジャック・ラカン『精神分析の倫理』(下)p.128
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099