——神経科学実験における動物殺し現象の分析——
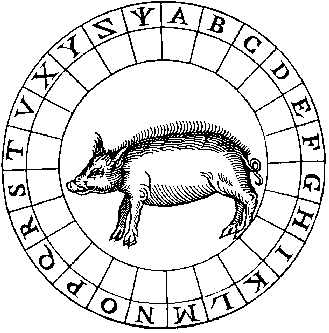
死は帰結であって目的ではなく
——神経科学実験における動物殺し現象の分析——
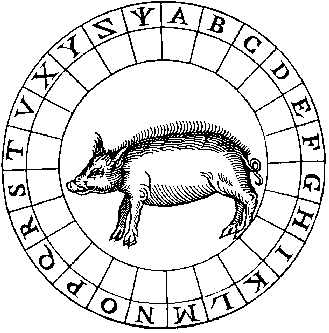
Mitsuho IKEDA, To be dead is a final consequence, is not the ultimate purpose: An anthropological analysis on death of experimental animals in a university neuroscience laboratory in Japan. Presentation synopsis on 26-29 December, 2012 at The Research Institute for Humanity and Nature (RIHN), Kyoto, Japan 603-8047.
——"[N]o animal must ever tyrannize over his own kind. Weak or strong, clever or simple, we are all brothers. No animal must ever kill any other animal. All animals are equal"--Animal Farm, by George Orwell, 1945.
——「人間とはかくももろい精神の主人公であり、殺すのが名を持ち人生を鮮 やかに描き出された個人ならば、殺めるという行為のはらむ精神的な後遺症の危険はより深刻になる」——伊藤計劃『虐殺器官』2007年
——「動物は死ぬ。[だが]動物の死は[人間的]意識の誕生[なのである]——ヘーゲ
ル(ただし[ ]ないはコジェーブによる補遺)
■今回の発表における私の趣旨
1.アリストテレスの太古から自然学者は、死んだ動 物、生きた動物を解体し、それを解体し、記載し、生命(いのち)の理念と実体、またそれらの関係(=構造)を理解しようとしてきた。そこに対象を痛めて虐 待しようとする「意図」を認めることは困難である。
2.生きた動物を解剖することを通してその生命の機 能を知ることは、動物を半殺しにして意識を無くすか、即死させて直後に見るという集団的制約があったが、麻酔の発見とその利用により、動物実験が「生きた ままにさせておく=死なせない」方法を獲得してからは、高度に洗練されたテクニックになった。これは動物を「本当は」痛めているのではないかという生物学 者の「苦痛」を和らげることになった。
3.死後の遺体の保存や死後の長期にわたる検査方法 の開発のために、実験が終わると動物を殺す必要があるが「安楽死/安楽殺(euthanasia)」という概念とその技術の開発は、動物実験者の道徳上の ジレンマを軽減することに役立った。そのことと関連して、動物実験の手技も「人道的配慮」が重要視されるようになる。他方、その現場は専門家しか関与でき ない場所に「聖域化」されるという事態を引き起こした。
4.実験室外では、動物愛護の倫理の向上と保護関連 法が制定されていくが、実験状況における「倫理的配慮」にも影響をもたらした。と同時に、当初は苦痛を感じないと言われてきた「動物」が次第に「苦痛を感 じる存在」へと(進化学上の根拠とは関係なく)格上げされることになった。また生物の種の保存や、実験室外における絶滅危惧種の急増などの流れをうけて、 実験に供される動物種において野生種や雑種はなるべく排除されるようになり、遺伝的に管理される事態が生まれつつある。
5.fMRIなどの非侵襲的な生体画像イメージング の開発は、それまで侵襲的な動物実験の独断場であった神経科学(neuroscience)——脳科学(brain science)はどちらかというと日本語ネイティブ表現で欧米には少ない——の分野に、人間を被験者にする手法がもたらされた。このことは動物実験の必 要性がなくなったわけではなく、むしろ双方の実験を補完するものとしてますます盛んになった。ただし、人間を被験者に使うことの意味は、これまでの動物中 心だった神経科学の実験の最終目標が、人間の認知や情動能力の「真の姿」を知ることを目的とすることにかわりはない。
6.一般人が想像する動物実験者は、実験動物に「冷 酷」だと想像力の中でステレオタイプされている。しかし、現実の実験者たちは、動物が苦痛を感じる存在であることを「知っており」また実験の最後に動物に 死を至らしめることに対する「道徳的躊躇」を持つことがあることがあることも知られている。現実には、彼らは実験上のプロトコルを正確に守ることで、この 道徳的ジレンマを回避しているように思われる。
7.これらの拭い切れない道徳的ジレンマと自身の情 動の管理を、ストレスと感じて動物から遠ざかる研究者もいるが、(成功して生き残っている)多くの研究者がこのジレンマを「克服すべき最初の課題」だと感 じている。これらは、儀礼の機能論的な説明の如く、通過儀礼の試練と解釈してもいいし、心理学者が説明するように、実験室と実験室の外での「認識論的ある いは情動論的切断」があり、これは一般の人が日常生活でおこなっている理念と行動の不一致やごく普通に観察できる御都合主義だと解釈することも可能であ る。あるいは神経科学的に、後天的な「可塑性」の結果、の理性と情動を繋ぐ脳の部位の神経連絡回路が、実験を通して動物実験をやる時には働くことがなくな るのだと解釈することもできる。しかし、これらの「洗練された」合理主義的解釈のほとんどはプロクルステスの寝台的な牽強附会——「トロブリアンド島民が 交易するドブ島のクラ・パートナーとほとんど同じように、動物は強力かつ危険な交易パートナーとしてみなさなければならない」(ナダスディ2012: 307-308)——をおこなっているという欠点をもつ。
8.[暫定的な結論ではあるが]神経科学実験におけ る動物殺しは、いくら外部から残虐な行為として見えようとも、科学的知識への貢献という「有用性」を引き出すための実践の帰結としての死が招来するのであ り、医学の(被験者の同意と倫理委員会の承認が)人体実験と同様、実験が始まったらその被験体(=動物)に確実に死が訪れる——実験者にとっては適切な時 に適切に死んでくれる/安楽殺させることのほうが重要だが——ことは了承済みのことである。動物の死は実験の必然的な帰結であり、動物を殺すことが目的な のではない。
9.動物の殺傷やその帰結としての死を通して、現代 社会のあり方を批判的に分析するこの科研費による研究:「その(=動物殺しの)具体的様相、諸社会・地域における殺しの具体的様態をもたらした条件、およ び動物殺しが持つ意味に関する詳細な民族誌を作成し、その比較考察から、これまで人類が形成してきた多様な人間と動物の関係を明らかにすること」(奥野克 巳)の目的に、この実験動物の「殺し」はどうも中心的なテーマになるとは思われない——『完全自殺マニュアル』のように多くの人にとって必要のない純粋な 蘊蓄になり、本当に必要な人には倫理的には提供したくない情報になる。
10. むしろ動物殺しの現象の背景には(青海省 ソッゴのツェタルのように)動物の生殺与奪が認知的なインデックス回路を通して行使可能になり、それが承認を得ている状態がどの社会にもあり、動物殺しの 事例検討は、社会というものの成立に関わる「暴力のオントロギー」(今村仁司)という議論には貢献するのではないかと私は思う。フーコーが描いた古典社会 の「命を奪う権力」から近代社会の「生かしておく権力」への「移行」という近代の良識派の人々の錯認(空想)の極端な逸脱例を、動物実験を嫌い阻止しよう とす るアニマルライツ派の主張と行動の混乱の中に見るからである。
クレジット:

Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!
附論:「動物殺し」という観点からみた動物実験につ いての諸相について(2016年1月24日作成)※表をクリックすると拡大します(出典:「動 物実験」)
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2012-2019