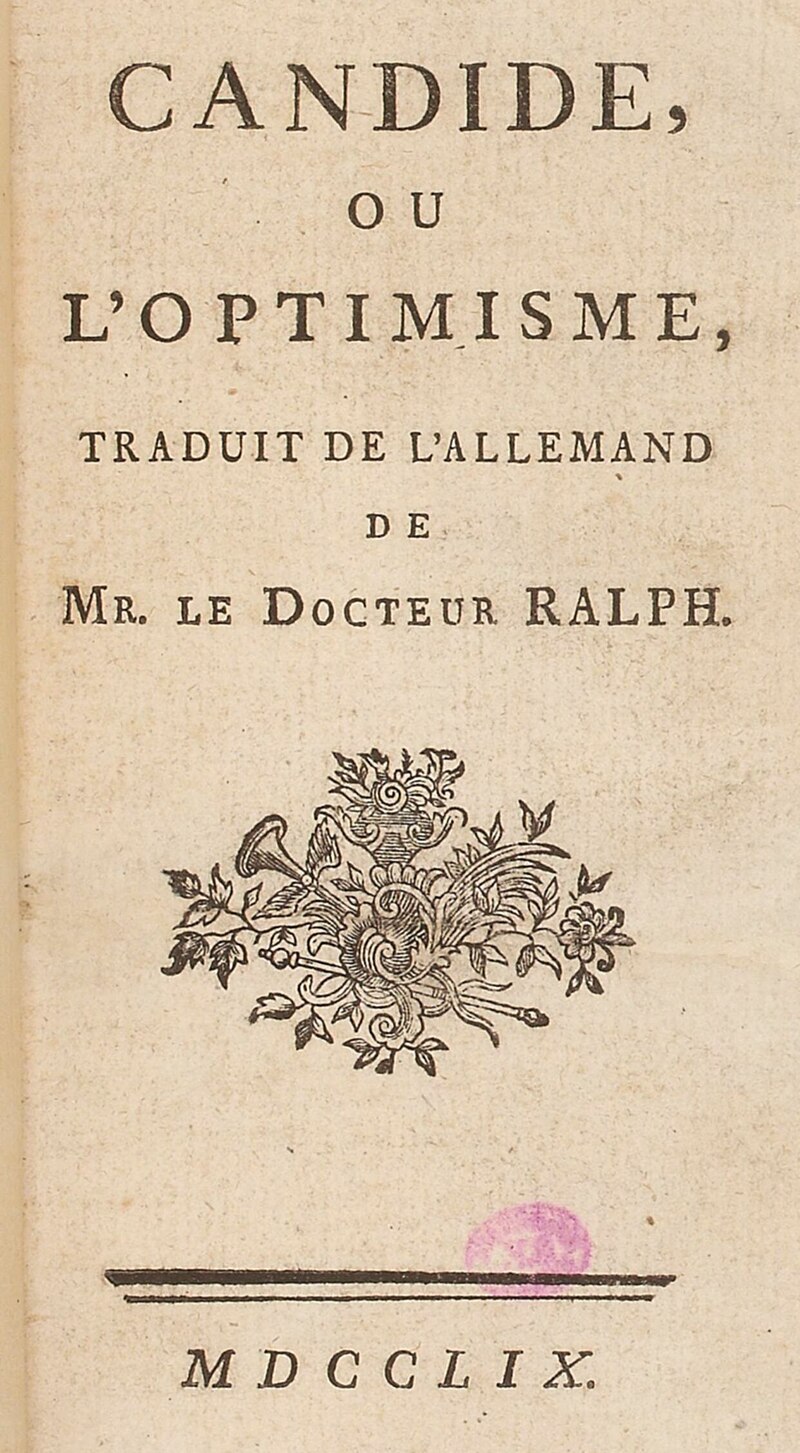
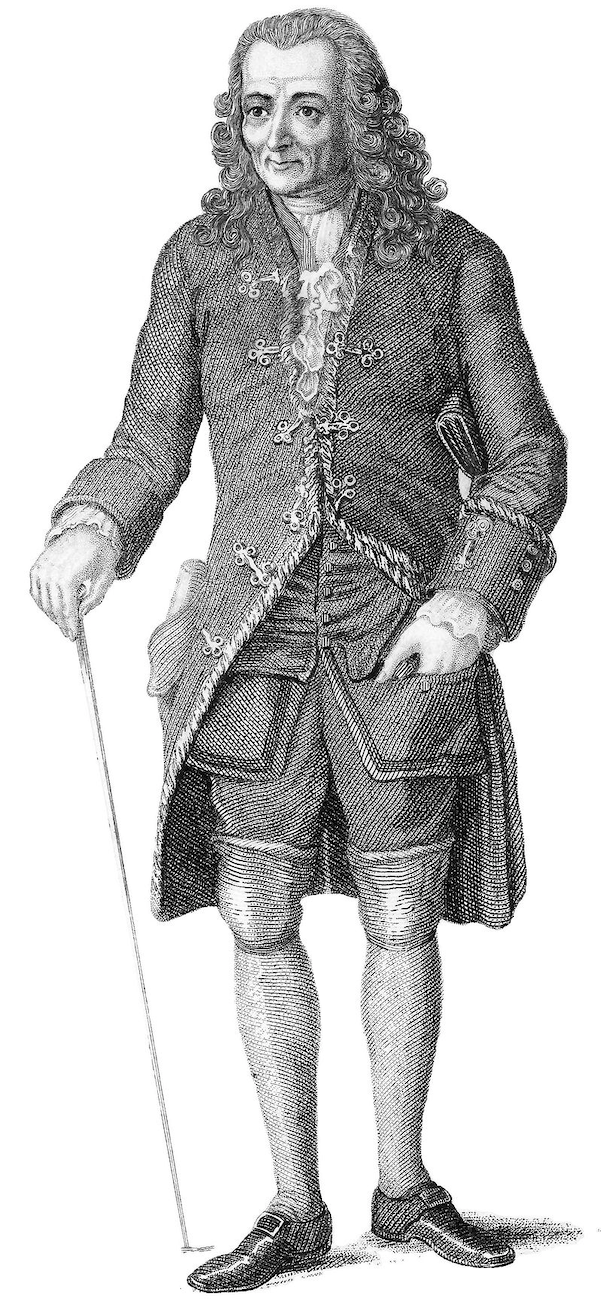
カンディードまたはカンディド
Candide, il faut cultiver notre jardin
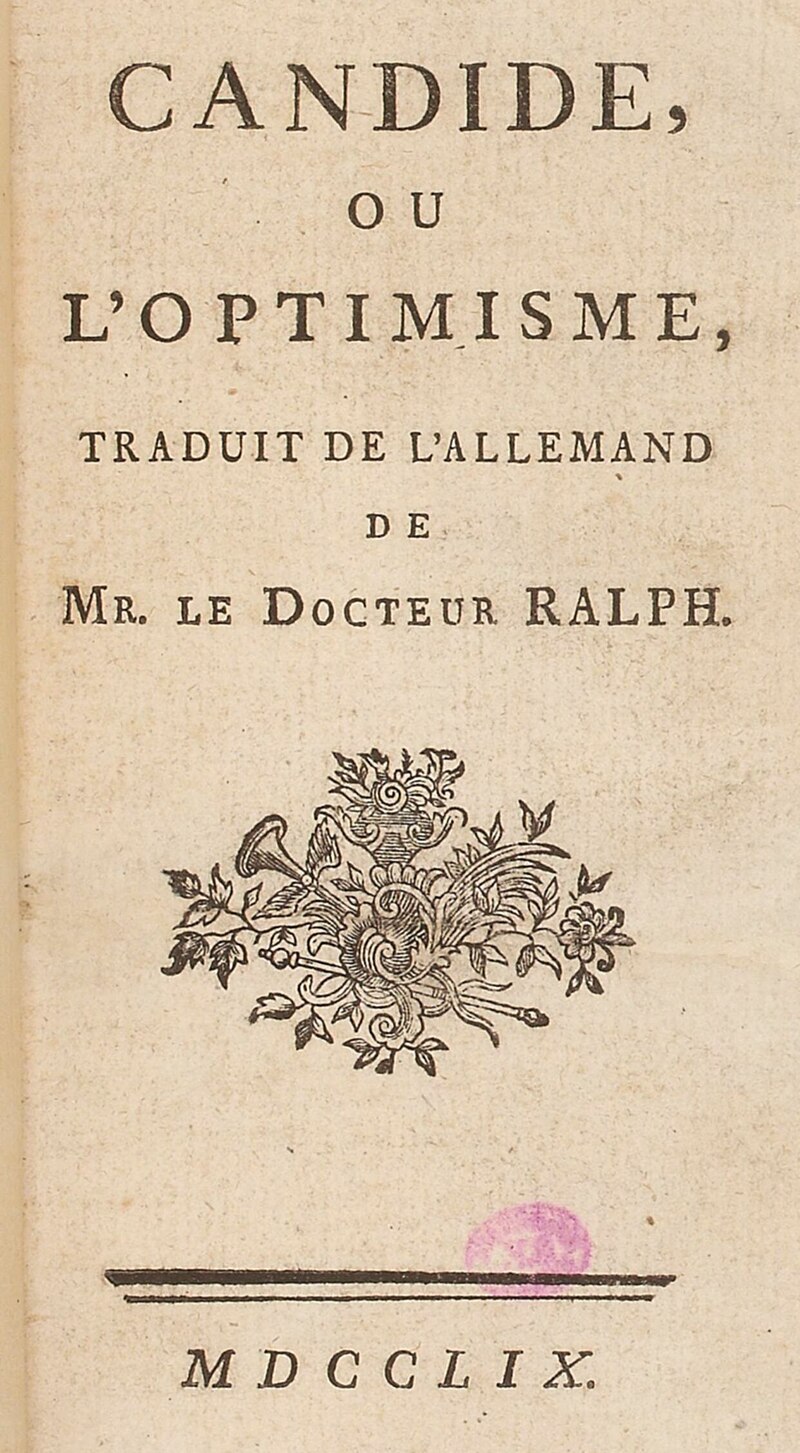
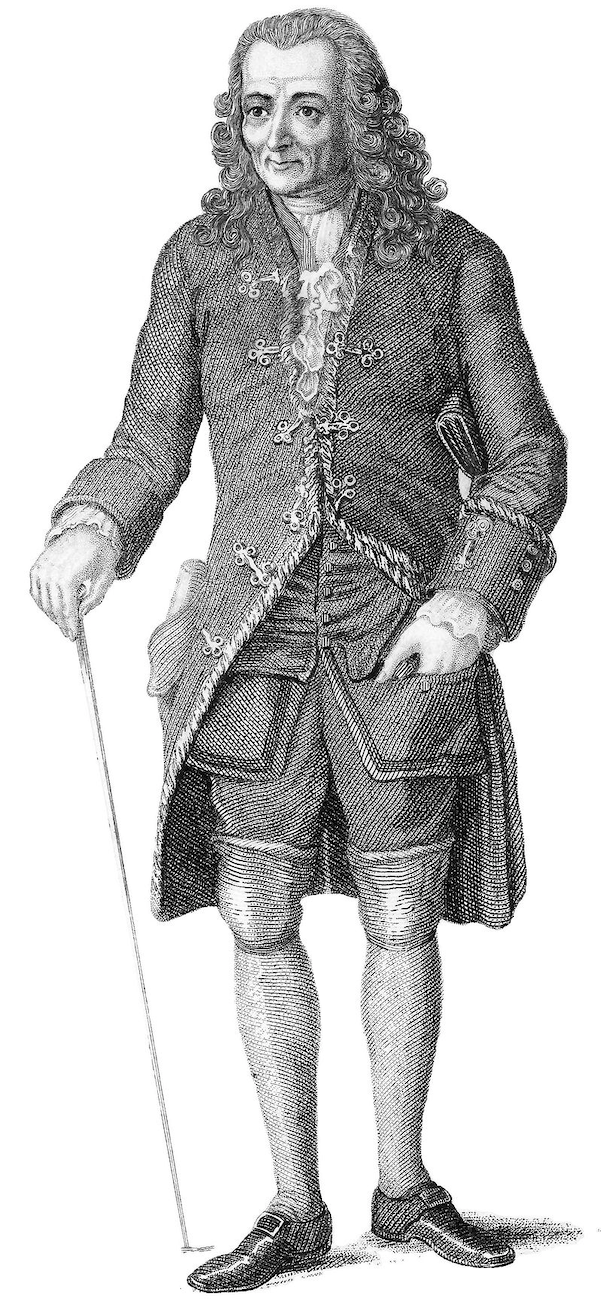
The title-page of the 1759 edition published by Cramer in Geneva, which reads, "Candide, or Optimism, translated from the German by Dr. Ralph."
Engraving
of Voltaire published as the frontispiece to an 1843 edition of his
Dictionnaire philosophique
 ☆
『カンディード、あるいはある楽観主義者』(Candide, ou
l'Optimisme)は、啓蒙時代の哲学者であるヴォルテール[6]が書いたフランスの風刺小説で、1759年に出版された。この小説は広く翻訳され
ており、英語版のタ
イトルは『Candide: or, All for the Best』(1759年)、『Candide: or, The
Optimist』(1762年)、『Candide』
この作品は、エデンの園のような楽園で保護された生活を送っていた青年カンディードが、師であるパングロス教授からライプニッツ的な楽観主義を教え込ま
れるところから始まる。ヴォルテールは『カンディード』の最後を、ライプニッツ的楽観主義を真っ向から否定するわけではないにせよ、パングロスの
マントラである「すべては最善のためにある」というライプニッツ的マントラの代わりに、「われわれは庭を耕さねばならない」という深く実践的な教訓を提唱
して締めくくる。
☆
『カンディード、あるいはある楽観主義者』(Candide, ou
l'Optimisme)は、啓蒙時代の哲学者であるヴォルテール[6]が書いたフランスの風刺小説で、1759年に出版された。この小説は広く翻訳され
ており、英語版のタ
イトルは『Candide: or, All for the Best』(1759年)、『Candide: or, The
Optimist』(1762年)、『Candide』
この作品は、エデンの園のような楽園で保護された生活を送っていた青年カンディードが、師であるパングロス教授からライプニッツ的な楽観主義を教え込ま
れるところから始まる。ヴォルテールは『カンディード』の最後を、ライプニッツ的楽観主義を真っ向から否定するわけではないにせよ、パングロスの
マントラである「すべては最善のためにある」というライプニッツ的マントラの代わりに、「われわれは庭を耕さねばならない」という深く実践的な教訓を提唱
して締めくくる。
ヴォルテール:"Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre
jardin"――「お説はごもっと も、なにはともあれ、われわれは自分の畑を耕さねばならぬ」
そうすることで、私は、
“Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je défendrai
jusqu’à la mort votre droit de le dire”――「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張
する権利は命をかけて守る」
と、主張することができるのだ。
du
docteur Ralph, Candide, ou L'optimisme, traduit de l'allemand de Mr. le
docteur Ralph, 1759
| Candide, ou l'Optimisme
(/kɒnˈdiːd/ kon-DEED,[5] French: [kɑ̃did] ⓘ) is a French satire written
by Voltaire, a philosopher of the Age of Enlightenment,[6] first
published in 1759. The novella has been widely translated, with English
versions titled Candide: or, All for the Best (1759); Candide: or, The
Optimist (1762); and Candide: Optimism (1947).[7] It begins with a
young man, Candide, who is living a sheltered life in an Edenic
paradise and being indoctrinated with Leibnizian optimism by his
mentor, Professor Pangloss.[8] The work describes the abrupt cessation
of this lifestyle, followed by Candide's slow and painful
disillusionment as he witnesses and experiences great hardships in the
world. Voltaire concludes Candide with, if not rejecting Leibnizian
optimism outright, advocating a deeply practical precept, "we must
cultivate our garden", in lieu of the Leibnizian mantra of Pangloss,
"all is for the best" in the "best of all possible worlds". Candide is characterized by its tone as well as by its erratic, fantastical, and fast-moving plot. A picaresque novel with a story similar to that of a more serious coming-of-age narrative (bildungsroman), it parodies many adventure and romance clichés, the struggles of which are caricatured in a tone that is bitter and matter-of-fact. Still, the events discussed are often based on historical happenings, such as the Seven Years' War and the 1755 Lisbon earthquake.[9] As philosophers of Voltaire's day contended with the problem of evil, so does Candide in this short theological novel, albeit more directly and humorously. Voltaire ridicules religion, theologians, governments, armies, philosophies, and philosophers. Through Candide, he assaults Leibniz and his optimism.[10][11] Candide has enjoyed both great success and great scandal. Immediately after its secretive publication, the book was widely banned because it contained religious blasphemy, political sedition, and intellectual hostility hidden under a thin veil of naivety.[10] However, with its sharp wit and insightful portrayal of the human condition, the novel has since inspired many later authors and artists to mimic and adapt it. Today, Candide is considered Voltaire's magnum opus[10] and is often listed as part of the Western canon. It is among the most frequently taught works of French literature.[12] The British poet and literary critic Martin Seymour-Smith listed Candide as one of the 100 most influential books ever written. |
『カ
ンディード、あるいはある楽観主義者』(Candide, ou l'Optimisme, /kɒdiːd/ kon-DEED, [5]
French: [kɒdid]
̃̈)は、啓蒙時代の哲学者であるヴォルテール[6]が書いたフランスの風刺小説で、1759年に出版された。この小説は広く翻訳されており、英語版のタ
イトルは『Candide: or, All for the Best』(1759年)、『Candide: or, The
Optimist』(1762年)、『Candide:
この作品は、エデンの園のような楽園で保護された生活を送っていた青年カンディードが、師であるパングロス教授からライプニッツ的な楽観主義を教え込ま
れるところから始まる[8]。ヴォルテールは『カンディード』の最後を、ライプニッツ的楽観主義を真っ向から否定するわけではないにせよ、パングロスの
マントラである「すべては最善のためにある」というライプニッツ的マントラの代わりに、「われわれは庭を耕さねばならない」という深く実践的な教訓を提唱
して締めくくる。 『カンディード』の特徴は、その調子だけでなく、不規則で空想的で展開の速いプロットにもある。より深刻な青春小説(ビルドゥングスロマン)に似たストー リーを持つピカレスク小説で、冒険やロマンスの決まり文句をパロディにしており、その苦闘は辛辣で事実に即した口調で戯画化されている。ヴォルテールと同 時代の哲学者たちが悪の問題と闘っていたように、この短い神学小説でもキャンディードは、より直接的かつユーモラスに悪の問題を論じている。ヴォルテール は宗教、神学者、政府、軍隊、哲学、哲学者を嘲笑する。キャンディード』を通して、彼はライプニッツとその楽観主義を攻撃している[10][11]。 『カンディード』は大きな成功とスキャンダルの両方を享受した。秘密裏に出版された直後は、宗教的冒涜、政治的扇動、素朴さの薄いベールに隠された知的敵 意が含まれているとして、広く発禁処分を受けた[10]。しかし、鋭いウィットと洞察に満ちた人間の状態の描写により、この小説はその後多くの後世の作家 や芸術家に模倣や翻案を促すことになった。今日、『キャンディード』はヴォルテールの大作とされ[10]、しばしば西洋の正典の一部として挙げられてい る。イギリスの詩人で文芸評論家のマーティン・シーモア=スミスは、『カンディード』を「これまでに書かれた本の中で最も影響力のある100冊」のひとつ に挙げている[12]。 |
| Historical and literary
background A number of historical events inspired Voltaire to write Candide, most notably the publication of Leibniz's "Monadology" (a short metaphysical treatise), the Seven Years' War, and the 1755 Lisbon earthquake. Both of the latter catastrophes are frequently referred to in Candide and are cited by scholars as reasons for its composition.[13] The 1755 Lisbon earthquake, tsunami, and resulting fires of All Saints' Day had a strong influence on theologians of the day and on Voltaire, who was himself disillusioned by them. The earthquake had an especially large effect on the contemporary doctrine of optimism, a philosophical system founded on the theodicy of Gottfried Wilhelm Leibniz, which insisted on God's benevolence in spite of such events. This concept is often put in the form, "all is for the best in the best of all possible worlds" (French: Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles). Philosophers had trouble fitting the horrors of this earthquake into their optimistic world view.[14]  This 1755 copper engraving shows the ruins of Lisbon in flames and a tsunami overwhelming the ships in the harbour. Voltaire actively rejected Leibnizian optimism after the natural disaster, convinced that if this were the best possible world, it should surely be better than it is.[15] In both Candide and Poème sur le désastre de Lisbonne ("Poem on the Lisbon Disaster"), Voltaire attacks this optimist belief.[14] He makes use of the Lisbon earthquake in both Candide and his Poème to argue this point, sarcastically describing the catastrophe as one of the most horrible disasters "in the best of all possible worlds".[16] Immediately after the earthquake, unreliable rumours circulated around Europe, sometimes overestimating the severity of the event. Ira Wade, a noted expert on Voltaire and Candide, has analyzed which sources Voltaire might have referenced in learning of the event. Wade speculates that Voltaire's primary source for information on the Lisbon earthquake was the 1755 work Relation historique du Tremblement de Terre survenu à Lisbonne by Ange Goudar.[17] Apart from such events, contemporaneous stereotypes of the German personality may have been a source of inspiration for the text, as they were for Simplicius Simplicissimus,[18] a 1669 satirical picaresque novel written by Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen and inspired by the Thirty Years' War. The protagonist of this novel, who was supposed to embody stereotypically German characteristics, is quite similar to the protagonist of Candide.[2] These stereotypes, according to Voltaire biographer Alfred Owen Aldridge, include "extreme credulousness or sentimental simplicity", two of Candide's and Simplicius's defining qualities. Aldridge writes, "Since Voltaire admitted familiarity with fifteenth-century German authors who used a bold and buffoonish style, it is quite possible that he knew Simplicissimus as well."[2] A satirical and parodic precursor of Candide, Jonathan Swift's Gulliver's Travels (1726) is one of Candide's closest literary relatives. This satire tells the story of "a gullible ingenue", Gulliver, who (like Candide) travels to several "remote nations" and is hardened by the many misfortunes which befall him. As evidenced by similarities between the two books, Voltaire probably drew upon Gulliver's Travels for inspiration while writing Candide.[19] Other probable sources of inspiration for Candide are Télémaque (1699) by François Fénelon and Cosmopolite (1753) by Louis-Charles Fougeret de Monbron. Candide's parody of the bildungsroman is probably based on Télémaque, which includes the prototypical parody of the tutor on whom Pangloss may have been partly based. Likewise, Monbron's protagonist undergoes a disillusioning series of travels similar to those of Candide.[2][20][21] |
歴史的・文学的背景 ライプニッツの『モナドロジー』(形而上学の小論文)の出版、七年戦争、1755年のリスボン地震などである。1755年のリスボン地震、津波、その結果 起こった万聖節の大火は、当時の神学者たちやヴォルテールに強い影響を与え、ヴォルテール自身もそれに幻滅していた。この地震は、ゴットフリート・ヴィル ヘルム・ライプニッツの神義論に基づく哲学体系である楽観主義の教義に特に大きな影響を及ぼし、このような出来事にもかかわらず神の博愛を主張した。この 概念は、しばしば「すべての可能な世界の中で最善のものはすべて最善である」(フランス語:Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles)という形で表現される。哲学者たちは、この地震の恐怖を楽観的な世界観に当てはめることに苦労した[14]。  この1755年の銅版画には、炎に包まれたリスボンの廃墟と、港の船を圧倒する津波が描かれている。 ヴォルテールは、この自然災害の後、ライプニッツ的な楽観主義を積極的に否定し、この世界が可能な限り最良のものであるならば、きっと今よりも良くなって いるはずだと確信した[15]。『カンディード』と『リスボン震災詩』の両方で、ヴォルテールはこの楽観主義者の信念を攻撃している。 [14]彼は『カンディード』と『リスボンの災難についての詩』の両方でリスボン地震を題材にしてこの点を主張し、この大災害を「可能な限り最良の世界に おける」最も恐ろしい災害のひとつであると皮肉った[16]。ヴォルテールと『カンディード』の専門家として知られるアイラ・ウェイドは、ヴォルテールが この出来事を知る際に参考にしたであろう情報源を分析している。ウェイドは、リスボン地震に関するヴォルテールの主な情報源は、1755年に出版されたア ンジュ・グーダールの『Relation historique du Tremblement de Terre survenu à Lisbonne』であると推測している[17]。 そのような出来事とは別に、同時代のドイツ人の性格に関するステレオタイプが、ハンス・ヤコブ・クリストフェル・フォン・グリメルスハウゼンが30年戦争 に触発されて書いた1669年の風刺ピカレスク小説『Simplicius Simplicissimus』[18]のインスピレーションの源となったかもしれない。ヴォルテールの伝記作家アルフレッド・オーウェン・アルドリッジ によれば、このステレオタイプには、カンディードとシンプリシムスの特徴的な性質である「極端な信心深さや感傷的な単純さ」が含まれる。アルドリッジは 「ヴォルテールは大胆で滑稽な文体を使う15世紀のドイツ人作家に親しんでいたことを認めているので、シンプリシウスも知っていた可能性は十分にある」と 書いている[2]。 『カンディード』の風刺的でパロディ的な先駆けであるジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』(1726年)は、『カンディード』に最も近い文学的親 戚の一人である。この風刺小説は、「騙されやすい純情な少女」ガリバーが、(カンディードと同じように)いくつかの「辺境の国」を旅し、彼に降りかかる多 くの不幸によって心を固めていく物語である。この2冊の本が似ていることからわかるように、ヴォルテールは『カンディード』を書く際に『ガリバー旅行記』 からインスピレーションを得たと思われる[19]。『カンディード』のインスピレーションの源となったと思われる他の作品には、フランソワ・フェネロンの 『Télémaque』(1699年)とルイ=シャルル・フジェレ・ド・モンブロンの『Cosmopolite』(1753年)がある。カンディード』の ビルドゥングスロマンのパロディは、おそらく『Télémaque』に基づいており、その中には『パングロス』のモデルとなった家庭教師のパロディの原型 が含まれている。同様に、モンブロンの主人公は『カンディード』と似たような幻滅的な旅の連続を経験する[2][20][21]。 |
| Creation Born François-Marie Arouet, Voltaire (1694–1778), by the time of the Lisbon earthquake, was already a well-established author, known for his satirical wit. He had been made a member of the Académie Française in 1746. He was a deist, a strong proponent of religious freedom, and a critic of tyrannical governments. Candide became part of his large, diverse body of philosophical, political, and artistic works expressing these views.[22][23] More specifically, it was a model for the eighteenth- and early nineteenth-century novels called the contes philosophiques. This genre, of which Voltaire was one of the founders, included previous works of his such as Zadig and Micromegas.[24][25][26] Engraving of Voltaire published as the frontispiece to an 1843 edition of his Dictionnaire philosophique  It is unknown exactly when Voltaire wrote Candide,[27] but scholars estimate that it was primarily composed in late 1758 and begun as early as 1757.[28] Voltaire is believed to have written a portion of it while living at Les Délices near Geneva and also while visiting Charles Théodore, the Elector-Palatinate, at Schwetzingen for three weeks in the summer of 1758. Despite solid evidence for these claims, a popular legend persists that Voltaire wrote Candide in three days. This idea is probably based on a misreading of the 1885 work La Vie intime de Voltaire aux Délices et à Ferney by Lucien Perey (real name: Clara Adèle Luce Herpin) and Gaston Maugras.[29][30] The evidence indicates strongly that Voltaire did not rush or improvise Candide, but worked on it over a significant period of time, possibly even a whole year. Candide is mature and carefully developed, not impromptu, as the intentionally choppy plot and the aforementioned myth might suggest.[31] There is only one extant manuscript of Candide that was written before the work's 1759 publication; it was discovered in 1956 by Wade and since named the La Vallière Manuscript. It is believed to have been sent, chapter by chapter, by Voltaire to the Duke and Duchess La Vallière in the autumn of 1758.[4] The manuscript was sold to the Bibliothèque de l'Arsenal in the late eighteenth century, where it remained undiscovered for almost two hundred years.[32] The La Vallière Manuscript, the most original and authentic of all surviving copies of Candide, was probably dictated by Voltaire to his secretary, Jean-Louis Wagnière, then edited directly.[29][33] In addition to this manuscript, there is believed to have been another, one copied by Wagnière for the Elector Charles-Théodore, who hosted Voltaire during the summer of 1758. The existence of this copy was first postulated by Norman L. Torrey in 1929. If it exists, it remains undiscovered.[29][34] Voltaire published Candide simultaneously in five countries no later than 15 January 1759, although the exact date is uncertain.[4][35] Seventeen versions of Candide from 1759, in the original French, are known today, and there has been great controversy over which is the earliest.[4] More versions were published in other languages: Candide was translated once into Italian and thrice into English that same year.[3] The complicated science of calculating the relative publication dates of all of the versions of Candide is described at length in Wade's article "The First Edition of Candide: A Problem of Identification". The publication process was extremely secretive, probably the "most clandestine work of the century", because of the book's obviously illicit and irreverent content.[36] The greatest number of copies of Candide were published concurrently in Geneva by Cramer, in Amsterdam by Marc-Michel Rey, in London by Jean Nourse, and in Paris by Lambert.[36]  1803 illustration of the two monkeys chasing their lovers. Candide shoots the monkeys, thinking they are attacking the women. Candide underwent one major revision after its initial publication, in addition to some minor ones. In 1761, a version of Candide was published that included, along with several minor changes, a major addition by Voltaire to the twenty-second chapter, a section that had been thought weak by the Duke of Vallière.[37] The English title of this edition was Candide, or Optimism, Translated from the German of Dr. Ralph. With the additions found in the Doctor's pocket when he died at Minden, in the Year of Grace 1759.[38] The last edition of Candide authorised by Voltaire was the one included in Cramer's 1775 edition of his complete works, known as l'édition encadrée, in reference to the border or frame around each page.[39][40] Voltaire strongly opposed the inclusion of illustrations in his works, as he stated in a 1778 letter to the writer and publisher Charles Joseph Panckoucke: Je crois que des Estampes seraient fort inutiles. Ces colifichets n'ont jamais été admis dans les éditions de Cicéron, de Virgile et d'Horace. (I believe that these illustrations would be quite useless. These baubles have never been allowed in the works of Cicero, Virgil and Horace.)[41] Despite this protest, two sets of illustrations for Candide were produced by the French artist Jean-Michel Moreau le Jeune. The first version was done, at Moreau's own expense, in 1787 and included in Kehl's publication of that year, Oeuvres Complètes de Voltaire.[42] Four images were drawn by Moreau for this edition and were engraved by Pierre-Charles Baquoy.[43] The second version, in 1803, consisted of seven drawings by Moreau which were transposed by multiple engravers.[44] The twentieth-century modern artist Paul Klee stated that it was while reading Candide that he discovered his own artistic style. Klee illustrated the work, and his drawings were published in a 1920 version edited by Kurt Wolff.[45] |
創造 フランソワ=マリー・アルーエに生まれたヴォルテール(1694-1778)は、リスボン地震の頃にはすでに風刺的なウィットで知られる著名な作家になっ ていた。1746年にはアカデミー・フランセーズの会員となっていた。彼は神学者であり、信教の自由を強く支持し、専制的な政府を批判した。カンディー ド』は、哲学的、政治的、芸術的にこれらの見解を表現した、彼の大規模で多様な作品群の一部となった[22][23]。より具体的には、18世紀から19 世紀初頭にかけての、哲学小説と呼ばれる小説のモデルとなった。ヴォルテールが創始者の一人であるこのジャンルには、『ザディグ』や『ミクロメガス』と いった彼の過去の作品も含まれていた[24][25][26]。  1843年版『哲学辞典』の扉絵として掲載されたヴォルテールのエングレーヴィング。 ヴォルテールが『カンディード』を執筆した正確な時期は不明であるが[27]、学者たちは、主に1758年後半に執筆され、1757年には執筆が始まって いたと推定している[28]。こうした主張には確かな証拠があるにもかかわらず、ヴォルテールは『カンディード』を3日で書いたという俗説が根強く残って いる。この考えはおそらく、ルシアン・ペレイ(本名:クララ・アデル・ルーチェ・エルパン)とガストン・モーグラスによる1885年の著作『La Vie intime de Voltaire aux Délices et à Ferney』の誤読に基づいている。カンディード』は、意図的にちぐはぐなプロットや前述の神話が示唆するように、即興的なものではなく、成熟した、注 意深く練られた作品である[31]。 現存する『カンディード』の写本は、1759年の出版以前に書かれたもので、1956年にウェイドによって発見され、ラ・ヴァリエール写本と名付けられ た。この写本は、1758年の秋にヴォルテールからラ・ヴァリエール公爵夫妻に章ごとに送られたと考えられている。 [32] ラ・ヴァリエール写本は、現存する『カンディード』の写本の中で最もオリジナルで真正なものであり、おそらくヴォルテールが秘書のジャン=ルイ・ワニエー ルに口述したものを直接編集したものであろう[29][33]。この写本の他に、1758年の夏にヴォルテールをもてなした選帝侯シャルル=テオドールの ためにワニエールが書写したものがあったと考えられている。この写本の存在は、1929年にノーマン・L・トーレイによって初めて提唱された。現存すると しても未発見のままである[29][34]。 ヴォルテールは『カンディード』を遅くとも1759年1月15日までに5カ国で同時に出版したが、正確な日付は不明である[4][35]。 1759年に出版された『カンディード』の原文フランス語版は現在17種類知られており、どれが最古のものであるかについては大きな論争がある[4]: カンディード』は同年、イタリア語に1度、英語に3度翻訳された[3]。『カンディード』の全版の相対的な出版年代を計算する複雑な科学については、ウェ イドの論文「『カンディード』の初版本: A Problem of Identification "に詳しく書かれている。カンディード』の出版過程は極めて秘密主義的であり、おそらく「今世紀で最も秘密主義的な仕事」であったと思われる。  1803年、恋人を追いかける二匹の猿の挿絵。カンディードは猿が女性を襲っていると思い、猿を撃つ。 カンディード』は最初の出版後、1度大きな改稿が行われ、さらに小さな改稿も行われた。1761年、『カンディード』の改訂版が出版され、いくつかの小さ な変更とともに、ヴァリエール公爵が弱いと考えていた第22章にヴォルテールによる大きな加筆が加えられた[37]。ヴォルテールによって公認された『カ ンディード』の最後の版は、1775年にクラマーによって出版された『カンディード』全集に収録されたものであり、各ページを囲む枠にちなんで l'édition encadréeとして知られている[39][40]。 ヴォルテールは自分の作品に挿絵を入れることに強く反対しており、1778年に作家で出版者のシャルル・ジョゼフ・パンクーケに宛てた手紙の中でこう述べ ている: エスタンプ(挿絵)は全く無意味である。これらの挿絵は、シセロン版、ヴァージル版、ホレス版では、これまで一度も認められていない。(これらの挿絵は全 く役に立たないだろうと思う。キケロ、ヴァージル、ホラーチェの作品にこれらのつまらないものが許されたことは一度もない)[41]。 この抗議にもかかわらず、『カンディード』の挿絵はフランスの画家ジャン=ミシェル・モロー・ル・ジューヌによって2セット制作された。最初の版は 1787年にモローの私費で制作され、その年のケールの出版物『Oeuvres Complètes de Voltaire』に収録された[42]。この版のためにモローが描いた4枚の絵はピエール=シャルル・バコワによってエングレーヴィングされた [43]。クレーはこの作品の挿絵を描き、彼の絵はクルト・ヴォルフが編集した1920年版として出版された[45]。 |
| List of characters Main characters Candide: The title character. The illegitimate son of the sister of the Baron of Thunder-ten-Tronckh. In love with Cunégonde. Cunégonde: The daughter of the Baron of Thunder-ten-Tronckh. In love with Candide. Professor Pangloss: The royal educator of the court of the baron. Described as "the greatest philosopher of the Holy Roman Empire". The Old Woman: Cunégonde's maid while she is the mistress of Don Issachar and the Grand Inquisitor of Portugal. Flees with Candide and Cunégonde to the New World. Illegitimate daughter of Pope Urban X. Cacambo: Born from a Mestizo father and an Indigenous mother. Lived half his life in Spain and half in Latin America. Candide's valet while in America. Martin: Dutch amateur philosopher and Manichaean. Meets Candide in Suriname, travels with him afterwards. The Baron of Thunder-ten-Tronckh: Brother of Cunégonde. Is seemingly killed by the Bulgarians, but becomes a Jesuit in Paraguay. Disapproves of Candide and Cunégonde's marriage. Secondary characters The baron and baroness of Thunder-ten-Tronckh: Father and mother of Cunégonde and the second baron. Both slain by the Bulgars. The king of the Bulgars: Frederick II Jacques the Anabaptist: Dutch manufacturer who takes Candide in after his escape from the Prussian Army. Drowns in the port of Lisbon after saving a sailor's life. Don Issachar: Jewish banker in Portugal. Cunégonde becomes his mistress, shared with the Grand Inquisitor of Portugal. Killed by Candide. The Grand Inquisitor of Portugal: Sentences Candide and Pangloss at the auto-da-fé. Cunégonde is his mistress jointly with Don Issachar. Killed by Candide. Don Fernando d'Ibarra y Figueroa y Mascarenes y Lampourdos y Souza: Spanish governor of Buenos Aires. Wants Cunégonde as a mistress. The king of El Dorado, who helps Candide and Cacambo out of El Dorado, lets them pick gold from the grounds, and makes them rich. Mynheer Vanderdendur: Dutch ship captain/pirate and slave holder. Offers to take Candide from America to France for 30,000 gold coins, but then departs without him, stealing most of his riches. Dies after his ship sinks. The abbot of Périgord: Befriends Candide and Martin in the hopes of scamming them. Tries to have them arrested. The marchioness of Parolignac: Parisian wench who takes an elaborate title. The scholar: One of the guests of the "marchioness". Argues with Candide about art. Paquette: A chambermaid from Thunder-ten-Tronckh who gave Pangloss syphilis after getting it herself from her Franciscan confessor. After the slaying by the Bulgars, works as a prostitute in Venice and becomes entangled with Friar Giroflée. Friar Giroflée: Theatine friar. In love with the prostitute Paquette. Signor Pococurante: A Venetian noble. Candide and Martin visit his estate, where he discusses his disdain of most of the canon of great art. In an inn in Venice, Candide and Martin dine with six men who turn out to be deposed monarchs: Ahmed III Ivan VI of Russia Charles Edward Stuart Augustus III of Poland Stanisław Leszczyński Theodore of Corsica |
登場人物一覧 主な登場人物 カンディード︎▶︎ 主人公。サンダー・テン・トロンク男爵の妹の隠し子。キュネゴンドに恋している。 クネゴンド (クネゴンデ・キュネゴンド)▶︎サンダー・テン・トロンク男爵の娘。カンディードに恋している。 パングロス教授▶︎ 男爵の宮廷教育係。「神聖ローマ帝国最大の哲学者」と評される。 老女(老婆): キュネゴンドがドン・イッサシャールとポルトガルの大審問官の愛人である間の女中。カンディード、クネゴンドとともに新大陸へ逃れる。教皇ウルバン10世 の嫡女。 カカンボ▶︎メスティーソの父と先住民の母の間に生まれる。人生の半分をスペイン、半分をラテンアメリカで過ごす。アメリカ滞在中はカンディードの付き 人。 マーティン▶︎オランダのアマチュア哲学者でマニ教信者。スリナムでカンディードと出会い、その後共に旅をする。 サンダー・テン・トロンク男爵▶︎ キュネゴンドの弟。ブルガリア人に殺されたかに見えたが、パラグアイでイエズス会士となる。カンディードとキュネゴンドの結婚に反対。 二次的登場人物 サンダー・テン・トロンク男爵夫妻▶︎ クネゴンドと2番目の男爵の父と母。二人ともブルガルに殺される。 ブルガールの王▶︎フリードリヒ2世 洗礼者ジャック▶︎プロイセン軍から逃亡したカンディードを引き取ったオランダの製造業者。船員の命を救った後、リスボンの港で溺死する。 ドン・イッサカル▶︎ポルトガルのユダヤ人銀行家。キュネゴンドを愛人とし、ポルトガルの大審問官と共有する。カンディードに殺される。 ポルトガル大審問官▶︎ カンディードとパングロスをオート・ダ・フェで処刑。キュネゴンドはドン・イッサシャルと共同で彼の愛人となる。カンディードに殺される。 ドン・フェルナンド・ディバラ・イ・フィゲロア・イ・マスカレーネス・イ・ランポウドス・イ・スーザ▶︎ スペインのブエノスアイレス総督。クネゴンドを愛人に欲しがる。 エルドラドの王▶︎カンディードとカカンボをエルドラドから助け出し、敷地内の金を採らせて金持ちにする。 マインヒア・ヴァンダーデンドゥール▶︎ オランダ人の船長/海賊/奴隷所有者。金貨3万枚でキャンディドをアメリカからフランスに連れて行くと申し出るが、キャンディドを置いて出港し、富の大半 を盗む。船が沈没して死亡。 ペリゴール大修道院長▶︎カンディードとマルタンに近づき、詐欺を働く。二人を逮捕させようとする。 パロリニャックの侯爵夫人▶︎凝った爵位を名乗るパリの女官。 学者▶︎ 侯爵夫人」の客の一人。カンディードと芸術について議論する。 パケット▶︎ フランシスコ会修道士から梅毒をうつされ、パングロスに梅毒をうつしたサンダー・テン・トロンクの侍女。ブルガール人に殺された後、ヴェネツィアで娼婦と して働き、ジロフレ修道士に絡まれる。 ジロフレ修道士▶︎ 演劇修道士。娼婦パケットと恋に落ちる。 ポコクランテ修道士▶︎ヴェネツィアの貴族。カンディードとマルタンが彼の屋敷を訪れ、偉大な芸術の規範のほとんどを軽んじていることを話す。 ヴェニスの宿屋で、カンディードとマルティンは、退位した君主であることが判明した6人の男たちと食事をする: アハメド3世▶︎ ロシアのイヴァン6世▶︎ チャールズ・エドワード・スチュアート▶︎ ポーランドのアウグスト3世▶︎ スタニスワフ・レシチンスキ▶︎ コルシカ王テオドール▶︎ |
| Synopsis Candide contains thirty episodic chapters, which may be grouped into two main schemes: one consists of two divisions, separated by the protagonist's hiatus in El Dorado; the other consists of three parts, each defined by its geographical setting. By the former scheme, the first half of Candide constitutes the rising action and the last part the resolution. This view is supported by the strong theme of travel and quest, reminiscent of adventure and picaresque novels, which tend to employ such a dramatic structure.[46] By the latter scheme, the thirty chapters may be grouped into three parts each comprising ten chapters and defined by locale: I–X are set in Europe, XI–XX are set in the Americas, and XXI–XXX are set in Europe and the Ottoman Empire.[47][48] The plot summary that follows uses this second format and includes Voltaire's additions of 1761. Chapters I–X The tale of Candide begins in the castle of the Baron Thunder-ten-Tronckh in Westphalia, home to the Baron's daughter, Lady Cunégonde; his bastard nephew, Candide; a tutor, Pangloss; a chambermaid, Paquette; and the rest of the Baron's family. The protagonist, Candide, is romantically attracted to Cunégonde. He is a young man of "the most unaffected simplicity" (l'esprit le plus simple), whose face is "the true index of his mind" (sa physionomie annonçait son âme).[2] Dr. Pangloss, professor of "métaphysico-théologo-cosmolonigologie" (English: "metaphysico-theologo-cosmolonigology") and self-proclaimed optimist, teaches his pupils that they live in the "best of all possible worlds" and that "all is for the best". 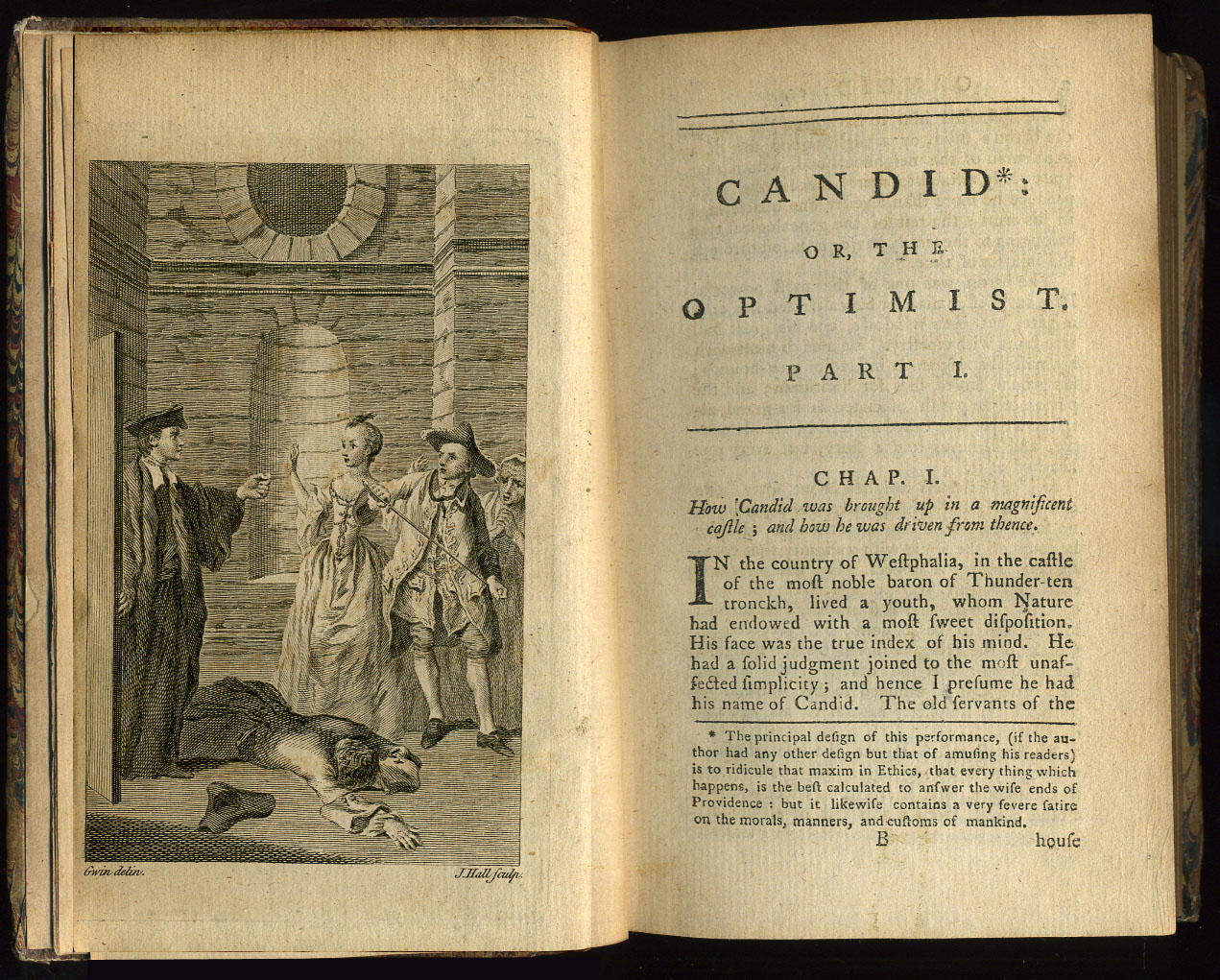 Frontispiece and first page of chapter one of an early English translation by T. Smollett (et al.) of Voltaire's Candide, London, printed for J. Newbery (et al.), 1762. All is well in the castle until Cunégonde sees Pangloss sexually engaged with Paquette in some bushes. Encouraged by this show of affection, Cunégonde drops her handkerchief next to Candide, enticing him to kiss her. For this infraction, Candide is evicted from the castle, at which point he is captured by Bulgar (Prussian) recruiters and coerced into military service, where he is flogged, nearly executed, and forced to participate in a major battle between the Bulgars and the Avars (an allegory representing the Prussians and the French). Candide eventually escapes the army and makes his way to Holland where he is given aid by Jacques, an Anabaptist, who strengthens Candide's optimism. Soon after, Candide finds his master Pangloss, now a beggar with syphilis. Pangloss reveals he was infected with this disease by Paquette and shocks Candide by relating how Castle Thunder-ten-Tronckh was destroyed by Bulgars, that Cunégonde and her whole family were killed, and that Cunégonde was raped before her death. Pangloss is cured of his illness by Jacques, losing one eye and one ear in the process, and the three set sail to Lisbon. In Lisbon's harbor, they are overtaken by a vicious storm which destroys the boat. Jacques attempts to save a sailor, and in the process is thrown overboard.[49] The sailor makes no move to help the drowning Jacques, and Candide is in a state of despair until Pangloss explains to him that Lisbon harbor was created in order for Jacques to drown. Only Pangloss, Candide, and the "brutish sailor" who let Jacques drown[50] survive the wreck and reach Lisbon, which is promptly hit by an earthquake, tsunami, and fire that kill tens of thousands. The sailor leaves in order to loot the rubble while Candide, injured and begging for help, is lectured on the optimistic view of the situation by Pangloss. The next day, Pangloss discusses his optimistic philosophy with a member of the Portuguese Inquisition, and he and Candide are arrested for heresy, set to be tortured and killed in an "auto-da-fé" set up to appease God and prevent another disaster. Candide is flogged and sees Pangloss hanged, but another earthquake intervenes and he escapes. He is approached by an old woman,[51] who leads him to a house where Lady Cunégonde waits, alive. Candide is surprised: Pangloss had told him that Cunégonde had been raped and disemboweled. She had been, but Cunégonde points out that people survive such things. However, her rescuer sold her to a Jewish merchant, Don Issachar, who was then threatened by a corrupt Grand Inquisitor into sharing her (Don Issachar gets Cunégonde on Mondays, Wednesdays, and the sabbath day). Her owners arrive, find her with another man, and Candide kills them both. Candide and the two women flee the city, heading to the Americas.[52] Along the way, Cunégonde falls into self-pity, complaining of all the misfortunes that have befallen her. Chapters XI–XX The old woman reciprocates by revealing her own tragic life: born the daughter of Pope Urban X and the Princess of Palestrina, she was kidnapped and enslaved by Barbary pirates, witnessed violent civil wars in Morocco under the bloodthirsty king Moulay Ismaïl (during which her mother was drawn and quartered), suffered constant hunger, nearly died from a plague in Algiers, and had a buttock cut off to feed starving Janissaries during the Russian capture of Azov. After traversing all the Russian Empire, she eventually became a servant of Don Issachar and met Cunégonde. The trio arrives in Buenos Aires, where Governor Don Fernando d'Ibarra y Figueroa y Mascarenes y Lampourdos y Souza asks to marry Cunégonde. Just then, an alcalde (a Spanish magistrate) arrives, pursuing Candide for killing the Grand Inquisitor. Leaving the women behind, Candide flees to Paraguay with his practical and heretofore unmentioned manservant, Cacambo.  1787 illustration of Candide and Cacambo meeting a maimed slave from a sugarcane mill near Suriname. At a border post on the way to Paraguay, Cacambo and Candide speak to the commandant, who turns out to be Cunégonde's unnamed brother. He explains that after his family was slaughtered, the Jesuits' preparation for his burial revived him, and he has since joined the order.[52] When Candide proclaims he intends to marry Cunégonde, her brother attacks him, and Candide runs him through with his rapier. After lamenting all the people (mainly priests) he has killed, he and Cacambo flee. In their flight, Candide and Cacambo come across two naked women being chased and bitten by a pair of monkeys. Candide, seeking to protect the women, shoots and kills the monkeys, but is informed by Cacambo that the monkeys and women were probably lovers.  Cacambo and Candide are captured by Oreillons, or Orejones; members of the Inca nobility who widened the lobes of their ears, and are depicted here as the fictional inhabitants of the area. Mistaking Candide for a Jesuit by his robes, the Oreillons prepare to cook Candide and Cacambo; however, Cacambo convinces the Oreillons that Candide killed a Jesuit to procure the robe. Cacambo and Candide are released and travel for a month on foot and then down a river by canoe, living on fruits and berries.[53] After a few more adventures, Candide and Cacambo wander into El Dorado, a geographically isolated utopia where the streets are covered with precious stones, there exist no priests, and all of the king's jokes are funny.[54] Candide and Cacambo stay a month in El Dorado, but Candide is still in pain without Cunégonde, and expresses to the king his wish to leave. The king points out that this is a foolish idea, but generously helps them do so. The pair continue their journey, now accompanied by one hundred red pack sheep carrying provisions and incredible sums of money, which they slowly lose or have stolen over the next few adventures. Candide and Cacambo eventually reach Suriname where they split up: Cacambo travels to Buenos Aires to retrieve Lady Cunégonde, while Candide prepares to travel to Europe to await the two. Candide's remaining sheep are stolen, and Candide is fined heavily by a Dutch magistrate for petulance over the theft. Before leaving Suriname, Candide feels in need of companionship, so he interviews a number of local men who have been through various ill-fortunes and settles on a man named Martin. Chapters XXI–XXX This companion, Martin, is a Manichaean scholar based on the real-life pessimist Pierre Bayle, who was a chief opponent of Leibniz.[55] For the remainder of the voyage, Martin and Candide argue about philosophy, Martin painting the entire world as occupied by fools. Candide, however, remains an optimist at heart, since it is all he knows. After a detour to Bordeaux and Paris, they arrive in England and see an admiral (based on Admiral Byng) being shot for not killing enough of the enemy. Martin explains that Britain finds it necessary to shoot an admiral from time to time "pour encourager les autres" (to encourage the others).[56]  Candide, horrified, arranges for them to leave Britain immediately. Upon their arrival in Venice, Candide and Martin meet Paquette, the chambermaid who infected Pangloss with his syphilis. She is now a prostitute, and is spending her time with a Theatine monk, Brother Giroflée. Although both appear happy on the surface, they reveal their despair: Paquette has led a miserable existence as a sexual object since she was forced to become a prostitute, and the monk detests the religious order in which he was indoctrinated. Candide gives two thousand piastres to Paquette and one thousand to Brother Giroflée. Candide and Martin visit the Lord Pococurante, a noble Venetian. That evening, Cacambo—now a slave—arrives and informs Candide that Cunégonde is in Constantinople. Prior to their departure, Candide and Martin dine with six strangers who had come for the Carnival of Venice. These strangers are revealed to be dethroned kings: the Ottoman Sultan Ahmed III, Emperor Ivan VI of Russia, Charles Edward Stuart (an unsuccessful pretender to the English throne), Augustus III of Poland (deprived, at the time of writing, of his reign in the Electorate of Saxony due to the Seven Years' War), Stanisław Leszczyński, and Theodore of Corsica. On the way to Constantinople, Cacambo reveals that Cunégonde—now horribly ugly—currently washes dishes on the banks of the Propontis as a slave for a fugitive Transylvanian prince by the name of Rákóczi. After arriving at the Bosphorus, they board a galley where, to Candide's surprise, he finds Pangloss and Cunégonde's brother among the rowers. Candide buys their freedom and further passage at steep prices.[52] They both relate how they survived, but despite the horrors he has been through, Pangloss's optimism remains unshaken: "I still hold to my original opinions, because, after all, I'm a philosopher, and it wouldn't be proper for me to recant, since Leibniz cannot be wrong, and since pre-established harmony is the most beautiful thing in the world, along with the plenum and subtle matter."[57] Candide, the baron, Pangloss, Martin, and Cacambo arrive at the banks of the Propontis, where they rejoin Cunégonde and the old woman. Cunégonde has indeed become hideously ugly, but Candide nevertheless buys their freedom and marries Cunégonde to spite her brother, who forbids Cunégonde from marrying anyone but a baron of the Empire (he is secretly sold back into slavery). Paquette and Brother Giroflée—having squandered their three thousand piastres—are reconciled with Candide on a small farm (une petite métairie) which he just bought with the last of his finances. One day, the protagonists seek out a dervish known as a great philosopher of the land. Candide asks him why Man is made to suffer so, and what they all ought to do. The dervish responds by asking rhetorically why Candide is concerned about the existence of evil and good. The dervish describes human beings as mice on a ship sent by a king to Egypt; their comfort does not matter to the king. The dervish then slams his door on the group. Returning to their farm, Candide, Pangloss, and Martin meet a Turk whose philosophy is to devote his life only to simple work and not concern himself with external affairs. He and his four children cultivate a small area of land, and the work keeps them "free of three great evils: boredom, vice, and poverty."[58] Candide, Pangloss, Martin, Cunégonde, Paquette, Cacambo, the old woman, and Brother Giroflée all set to work on this "commendable plan" (louable dessein) on their farm, each exercising his or her own talents. Candide ignores Pangloss's insistence that all turned out for the best by necessity, instead telling him "we must cultivate our garden" (il faut cultiver notre jardin).[58] |
あらすじ 1つは、主人公がエルドラドで中断することによって区切られた2つの部分からなり、もう1つは、それぞれが地理的な設定によって定義された3つの部分から なる。前者の方式では、『カンディード』の前半が起承転結、後半が決着となる。この考え方は、冒険小説やピカレスク小説を彷彿とさせる、旅と探求という強 いテーマによって支持されている: I-X章はヨーロッパ、XI-XX章はアメリカ大陸、XXI-XXX章はヨーロッパとオスマン帝国が舞台である。 1)I-X章はヨーロッパ 2)XI-XX章はアメリカ大陸 3)XXI-XXX章はヨーロッパとオスマン帝国 1)第I章から第X章 『カンディード』の物語は、男爵の娘クネゴンド夫人、私生児の甥カンディード、家庭教師のパングロス、客室係(女中)のパケット、男爵一家が住むヴェスト ファーレ ンのサンダー・テン・トロンク男爵の城から始まる。主人公のカンディードはクネゴンドに恋心を抱く。カンディードは、「最も素朴な」青年であり、その顔 は「彼の心の真の指標」である[2]。métaphysico-théologo-cosmolonigologie"(英語では "métaphysico-theologo-cosmolonigologie")の教授であり、楽観主義者を自称するパングロスは、弟子たちに、自分 たちは "あらゆる可能な世界の中で最良の世界 "に生きており、"すべては最良のためにある "と教えている。 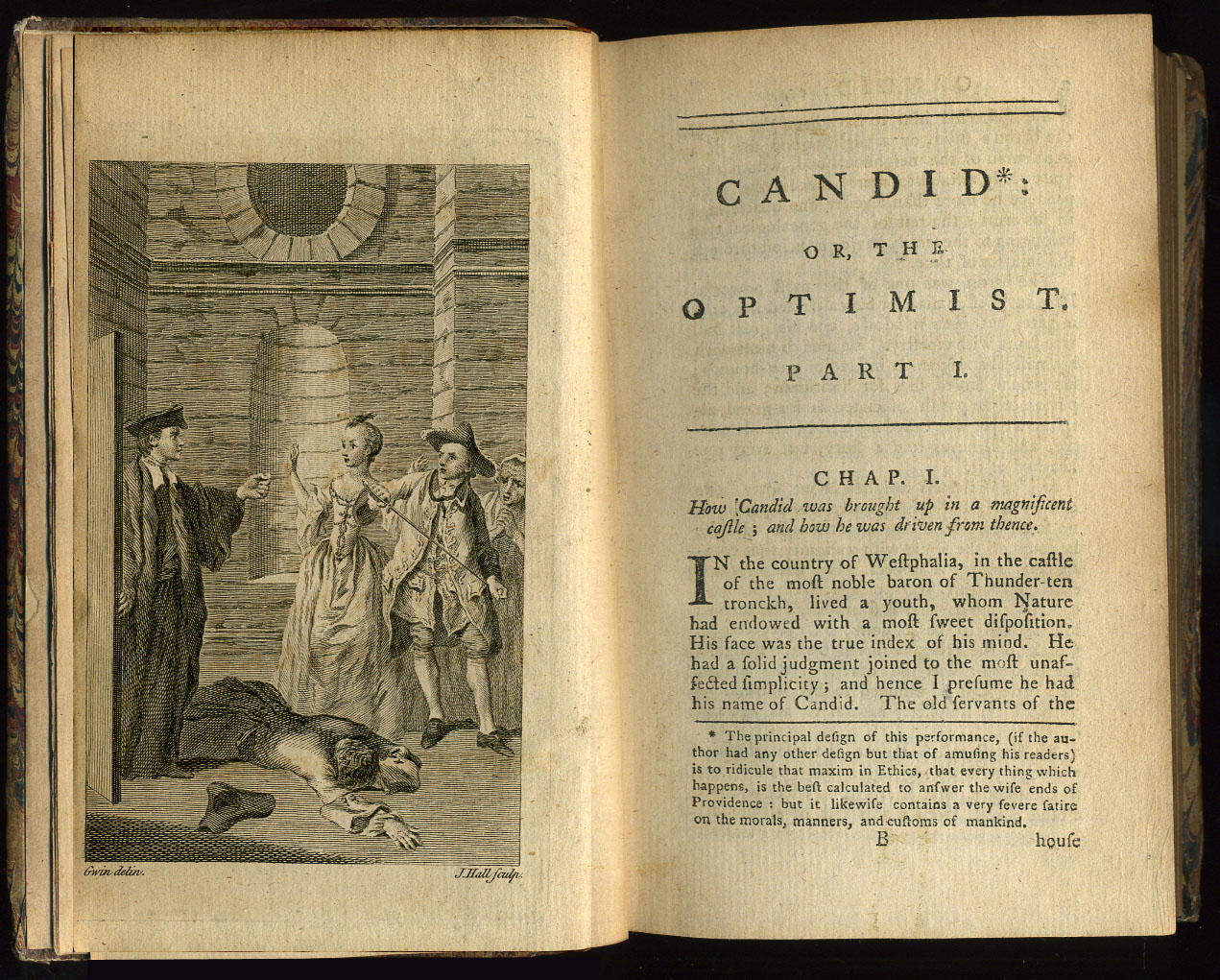 ヴォルテールの『カンディード』のT.スモレット(他)による初期の英訳版(ロンドン、J.ニューベリー(他)のために印刷、1762年)の扉絵と第1章 の最初のページ。 クネゴンドは、パングロスが茂みの中でパケットとセックスしているのを目撃する。この愛情表現に勇気づけられたクネゴンドは、ハンカチをカンディード の隣に落としてキスを誘う。この違反のために、カンディードは城から追い出され、ブルガール(プロイセン)の勧誘員に捕まって兵役を強要され、鞭打たれ、 処刑されそうになり、ブルガールとアヴァール(プロイセンとフランスを表す寓意)の大きな戦いに参加させられる。やがて軍を脱走したカンディードはオラン ダに向かい、そこでアナバプティストのジャックに助けられ、カンディードの楽観主義を強める。やがてカンディードは、梅毒で乞食となった師パングロスを見 つける。パングロスは、自分がパケットから梅毒をうつされたことを明かし、サンダー・テン・トロンク城がブルガリに破壊されたこと、キュネゴンドとその家 族が皆殺しにされたこと、クネゴンドが死ぬ前にレイプされたことを語り、カンディードを震え上がらせる。パングロスはジャックに病気を治してもらうが、 その過程で片目と片耳を失い、3人はリスボンに向けて出航する。 1)カンディード 2)パングロス 3)ジャック リスボンの港で激しい嵐に見舞われ、船は破壊される。船員は溺れるジャックを助けようとはせず、カンディードは絶望の淵に立たされるが、パングロスがリス ボン港はジャックを溺れさせるために造られたと説明する。パングロスとカンディード、そしてジャックを溺れさせた「残忍な船乗り」[50]だけが難破船か ら生き残り、リスボンにたどり着く。船員は瓦礫を略奪するために立ち去り、カンディードは怪我をして助けを求めていたが、パングロスに楽観的な見方を説教 される。 翌日、パングロスはポルトガルの異端審問官と彼の楽観的な哲学について話し合い、彼とカンディードは異端として逮捕され、拷問にかけられ、神の怒りを鎮 め、再び災害が起こるのを防ぐために設けられた「オート・ダ・フェ」で殺されることになる。カンディードは鞭打たれ、パングロスが絞首刑になるのを目撃す るが、再び地震が起こり、彼は逃げ出す。彼は老婆に声をかけられ[51]、クネゴンドが生きて待っている屋敷に案内される。カンディードは驚く: パングロスはクネゴンドがレイプされ、内臓を抜かれたと言っていたのだ。パングロスは、クネゴンドが強姦され、内臓を抜かれたと話していたのだ。しか し、クネゴンドはユダヤ人の商人ドン・イッサシャルに売られ、ドン・イッサシャルは悪徳大審問官に脅されてクネゴンドを分けてもらうことになる(ド ン・イッサシャルはクネゴンドを月、水、安息日に手に入れる)。彼女の所有者が現れ、彼女が他の男と一緒にいるのを見つけ、カンディードは二人を殺す。 カンディードと二人の女は街を逃げ出し、アメリカ大陸に向かう[52]。道中、クネゴンドは自分に降りかかったすべての不幸を訴え、自己憐憫に陥る。 2)第XI-XX章 教皇ウルバン10世とパレストリーナ王女の娘として生まれた彼女は、バーバリーの海賊に誘拐され奴隷にされ、血に飢えたムーレイ・イスマイール王のもとモ ロッコで激しい内戦を目撃し(その際に母親は四つ裂きにされた)、絶え間ない飢えに苦しみ、アルジェでは疫病で死にかけ、ロシアによるアゾフ占領の際には 飢えたジャニサリに食べさせるために臀部を切り落とされた。ロシア帝国全土を渡り歩いた彼女は、やがてドン・イッサシャルの下僕となり、クネゴンドと出 会う。 3人はブエノスアイレスに到着し、総督ドン・フェルナンド・ディバラ・イ・フィゲロア・イ・マスカレーネス・イ・ランポウドス・イ・スーザがクネゴンドと の結婚を申し込む。そこへ、大審問官を殺したとしてカンディードを追うアルカルデ(スペインの判事)がやって来る。カンディードは女たちを置き去りにし て、実用的でこれまで語られることのなかった下男のカカンボとともにパラグアイに逃亡する。  1787年、カンディードとカカンボがスリナム近郊のサトウキビ工場で手足の不自由な奴隷と出会う挿絵。 パラグアイに向かう途中の国境で、カカンボとカンディードは司令官と話すが、彼はクネゴンドの名も知らぬ兄であることが判明する。カンディードがクネゴン ドと結婚すると宣言すると、彼女の兄はカンディードを襲い、カンディードはレイピアで兄を打ち抜く。自分が殺したすべての人々(主に司祭)を嘆いた後、彼 とカカンボは逃げる。逃げる途中、カンディードとカカンボは2匹の猿に追いかけられ噛まれている2人の裸の女性に出くわす。カンディードは女性たちを守ろ うと猿を撃ち殺すが、カカンボから猿と女性は恋人同士だったのだろうと知らされる。  カカンボとカンディードはオレヨン(オレホネス)に捕らえられる。オレヨンはインカの貴族で、耳の小葉を広げた人々であり、ここではこの地域の架空の住民 として描かれている。カンディードをイエズス会士と勘違いしたオレヨンたちは、カンディードとカカンボを料理しようとするが、カカンボはカンディードがイ エズス会士を殺して衣を手に入れたとオレヨンたちを説得する。カカンボとカンディードは釈放され、徒歩とカヌーによる川下りで1ヶ月間旅をし、果物や木の 実で生活する[53]。 カンディドとカカンボはさらにいくつかの冒険をした後、エルドラドに迷い込む。エルドラドは地理的に隔離されたユートピアで、街路は宝石で覆われ、司祭は 存在せず、王の冗談はすべて面白い[54]。カンディドとカカンボはエルドラドに1ヶ月滞在するが、カンディドはクネゴンドがいないことにまだ苦痛を感じ ており、王に去りたいと申し出る。王はそれは愚かな考えだと指摘するが、寛大にも二人を助ける。二人は、食料と信じられないほどの大金を積んだ100頭の 赤い羊を従えて旅を続けるが、その後数回の冒険の間に、羊は徐々に失ったり盗まれたりする。 カンディードとカカンボはやがてスリナムに到着し、そこで別れる: カカンボはクネゴンデを取り戻すためにブエノスアイレスに向かい、 カンディードは2人を待つためにヨーロッパに向かう準備をする。 カンディードの残り の羊が盗まれ、 カンディードはオランダの判事から罰金を科される。スリナムを去る前に、カンディードは仲間が必要だと感じ、さまざまな不運を経験した地元 の男たちに話を聞き、マルタンという男に落ち着く。 3)XXI章からXXX章 このマルタンという伴侶は、ライプニッツの最大の敵であった実在の悲観主義者ピエール・バイユをモデルにしたマニ教の学者である[55]。航海の残りの期 間、マルタンとカンディードは哲学について議論し、マルタンが全世界を愚か者で占められていると描く。しかし、カンディードは、自分が知っているのはそれ しかないのだからと、根っからの楽観主義者であり続ける。ボルドーとパリに寄り道した後、イギリスに到着した二人は、敵を十分に殺さなかったという理由で 撃たれている提督(バイング提督がモデル)を見る。マーティンは、イギリスは時々提督を射殺する必要があることを "pour encourager les autres"(他の提督を励ますため)と説明する[56]。  ヴェネツィアに到着したカンディードとマルティンは、パングロスに梅毒をうつした客室係のパ ケットに出会う。彼女は現在娼婦で、テアティーヌ派の修道士ブラザー・ジロフレと過ごしている。二人とも表面的には幸せそうに見えるが、絶望を露わにして いる: パケットは娼婦にさせられて以来、性の対象として惨めな生活を送っており、修道士は自分が教え込まれた修道会を嫌悪している。カンディドはパケットに2千 ピアストル、ジロフレ修道士に1千ピアストルを贈る。 カンディードとマルタンは、高貴なヴェネツィア人ポコクランテ公を訪ねる。その夜、奴隷となったカカンボが到着し、キュネゴンドがコンスタンチノープルに いるとカンディードに知らせる。出発に先立ち、カンディードとマルティンは、ヴェニスの謝肉祭にやってきた6人の見知らぬ人々と食事をする。彼らはオスマ ン・トルコのスルタン、アフメド3世、ロシア皇帝イヴァン6世、チャールズ・エドワード・スチュアート(イギリス王位簒奪に失敗)、ポーランドのアウグス ト3世(執筆当時、七年戦争のためザクセン選帝侯国での統治権を剥奪された)、スタニスワフ・レシチンスキ、コルシカのテオドールであった。 コンスタンチノープルに向かう途中、カカンボは、クネゴンデが今は恐ろしいほど醜く、逃亡中のトランシルヴァニア王子ラーコチの奴隷としてプロポンティス 河岸で皿洗いをしていることを明かす。ボスポラス海峡に到着後、彼らはガレー船に乗り込むが、カンディードは驚いたことに、漕ぎ手の中にパングロスとキュ ネゴンドの兄を見つける。カンディードは二人の自由とさらなる航路を高値で買い取る[52]。二人は自分たちがどのように生き延びたかを語るが、恐怖を経 験したにもかかわらず、パングロスの楽観主義は揺るがない: 「というのも、結局のところ、私は哲学者であり、ライプニッツが間違っているはずはないし、あらかじめ確立された調和は、プレナムや微妙な物質と並んで、 この世で最も美しいものだからだ」[57]。 カンディード、男爵、パングロス、マルタン、カカンボはプロポンティス川のほとりに到着し、そこでクネゴンドと老婆と再会する。クネゴンドは確かに醜く なっていたが、それでもカンディードは二人の自由を買い取り、キュネゴンドに帝国の男爵以外との結婚を禁じた彼女の兄を恨んでクネゴンドと結婚する(彼 は密かに奴隷として売り戻される)。パケットとジロフレ兄は、3千ピエを浪費してしまったカンディードと、彼が最後の財産で買ったばかりの小さな農場 (une petite métairie)で和解する。 ある日、主人公たちはこの土地の偉大な哲学者として知られるダーヴィッシュを探す。カンディードは彼に、なぜ人間はこんなにも苦しまなければならないの か、人間はどうあるべきか、と問う。それに対してダー ヴィッシュは、なぜカンディードは悪と善の存在にこだわるのかと修辞的に問う。ダーヴィッシュは、人 間を王がエジプトに送る船のネズミのようなものだと表現する。そして一行に向かってドアを閉める。農場に戻ったカンディード、パングロス、 マーティンは、 単純労働にのみ人生を捧げ、対外的なことには関心を持たないという哲学を持つトルコ人に出会う。カンディード、パングロス、マルタン、クネゴンド、パ ケット、カカンボ、老女、そしてジロフレ兄は、この「称賛に値する計画」(louable dessein)のために、それぞれの才能を発揮して農場で働く。カンディードは、すべては必然的に最善になったというパングロスの主張を無視し、代わり に「私たちは庭を耕さなければならない」(il faut cultiver notre jardin)と告げる[58]。 |
| Style As Voltaire himself described it, the purpose of Candide was to "bring amusement to a small number of men of wit".[2] The author achieves this goal by combining wit with a parody of the classic adventure-romance plot. Candide is confronted with horrible events described in painstaking detail so often that it becomes humorous. Literary theorist Frances K. Barasch described Voltaire's matter-of-fact narrative as treating topics such as mass death "as coolly as a weather report".[59] The fast-paced and improbable plot—in which characters narrowly escape death repeatedly, for instance—allows for compounding tragedies to befall the same characters over and over again.[60] In the end, Candide is primarily, as described by Voltaire's biographer Ian Davidson, "short, light, rapid and humorous".[10][61] Behind the playful façade of Candide which has amused so many, there lies very harsh criticism of contemporary European civilization which angered many others. European governments such as France, Prussia, Portugal and England are each attacked ruthlessly by the author: the French and Prussians for the Seven Years' War, the Portuguese for their Inquisition, and the British for the execution of John Byng. Organised religion, too, is harshly treated in Candide. For example, Voltaire mocks the Jesuit order of the Roman Catholic Church. Aldridge provides a characteristic example of such anti-clerical passages for which the work was banned: while in Paraguay, Cacambo remarks, "[The Jesuits] are masters of everything, and the people have no money at all …". Here, Voltaire suggests the Christian mission in Paraguay is taking advantage of the local population. Voltaire depicts the Jesuits holding the indigenous peoples as slaves while they claim to be helping them.[62][63] Satire The main method of Candide's satire is to contrast ironically great tragedy and comedy.[10] The story does not invent or exaggerate evils of the world—it displays real ones starkly, allowing Voltaire to simplify subtle philosophies and cultural traditions, highlighting their flaws.[60] Thus Candide derides optimism, for instance, with a deluge of horrible, historical (or at least plausible) events with no apparent redeeming qualities.[2][59] A simple example of the satire of Candide is seen in the treatment of the historic event witnessed by Candide and Martin in Portsmouth harbour. There, the duo spy an anonymous admiral, supposed to represent John Byng, being executed for failing to properly engage a French fleet. The admiral is blindfolded and shot on the deck of his own ship, merely "to encourage the others" (French: pour encourager les autres, an expression Voltaire is credited with originating). This depiction of military punishment trivializes Byng's death. The dry, pithy explanation "to encourage the others" thus satirises a serious historical event in characteristically Voltairian fashion. For its classic wit, this phrase has become one of the more often quoted from Candide.[10][64] Voltaire depicts the worst of the world and his pathetic hero's desperate effort to fit it into an optimistic outlook. Almost all of Candide is a discussion of various forms of evil: its characters rarely find even temporary respite. There is at least one notable exception: the episode of El Dorado, a fantastic village in which the inhabitants are simply rational, and their society is just and reasonable. The positivity of El Dorado may be contrasted with the pessimistic attitude of most of the book. Even in this case, the bliss of El Dorado is fleeting: Candide soon leaves the village to seek Cunégonde, whom he eventually marries only out of a sense of obligation.[2][59] Another element of the satire focuses on what William F. Bottiglia, author of many published works on Candide, calls the "sentimental foibles of the age" and Voltaire's attack on them.[65] Flaws in European culture are highlighted as Candide parodies adventure and romance clichés, mimicking the style of a picaresque novel.[65][66] A number of archetypal characters thus have recognisable manifestations in Voltaire's work: Candide is supposed to be the drifting rogue of low social class, Cunégonde the sex interest, Pangloss the knowledgeable mentor, and Cacambo the skillful valet.[2] As the plot unfolds, readers find that Candide is no rogue, Cunégonde becomes ugly and Pangloss is a stubborn fool. The characters of Candide are unrealistic, two-dimensional, mechanical, and even marionette-like; they are simplistic and stereotypical.[67] As the initially naïve protagonist eventually comes to a mature conclusion—however noncommittal—the novella is a bildungsroman, if not a very serious one.[2][68] Garden motif Gardens are thought by many critics to play a critical symbolic role in Candide. The first location commonly identified as a garden is the castle of the Baron, from which Candide and Cunégonde are evicted much in the same fashion as Adam and Eve are evicted from the Garden of Eden in the Book of Genesis. Cyclically, the main characters of Candide conclude the novel in a garden of their own making, one which might represent celestial paradise. The third most prominent "garden" is El Dorado, which may be a false Eden.[69] Other possibly symbolic gardens include the Jesuit pavilion, the garden of Pococurante, Cacambo's garden, and the Turk's garden.[70] These gardens are probably references to the Garden of Eden, but it has also been proposed, by Bottiglia, for example, that the gardens refer also to the Encyclopédie, and that Candide's conclusion to cultivate "his garden" symbolises Voltaire's great support for this endeavour. Candide and his companions, as they find themselves at the end of the novella, are in a very similar position to Voltaire's tightly knit philosophical circle which supported the Encyclopédie: the main characters of Candide live in seclusion to "cultivate [their] garden", just as Voltaire suggested his colleagues leave society to write. In addition, there is evidence in the epistolary correspondence of Voltaire that he had elsewhere used the metaphor of gardening to describe writing the Encyclopédie.[70] Another interpretative possibility is that Candide cultivating "his garden" suggests his engaging in only necessary occupations, such as feeding oneself and fighting boredom. This is analogous to Voltaire's own view on gardening: he was himself a gardener at his estates in Les Délices and Ferney, and he often wrote in his correspondence that gardening was an important pastime of his own, it being an extraordinarily effective way to keep busy.[71][72][73] |
スタイル ヴォルテール自身が述べているように、『カンディード』の目的は「少数の機知に富んだ人々に娯楽をもたらす」ことであった[2]。著者は、機知と古典的な 冒険ロマンの筋立てのパロディを組み合わせることによって、この目的を達成している。カンディードは、ユーモラスになるほど頻繁に、細部まで丹念に描写さ れた恐ろしい出来事に直面する。文学理論家のフランシス・K・バラシュは、ヴォルテールの淡々とした語り口は、大量死のような話題を「天気予報のように冷 静に」扱っていると評している[59]。テンポが速く、ありえないプロット-たとえば、登場人物が何度も辛うじて死を免れる-は、同じ登場人物に何度も悲 劇が降りかかることを可能にしている[60]。 結局のところ、『カンディード』は、ヴォルテールの伝記作家イアン・デイヴィッドソンが評するように、「短く、軽く、速く、ユーモラス」である[10] [61]。 多くの人を楽しませた『カンディード』の遊び心に満ちた表情の裏には、現代ヨーロッパ文明に対する非常に厳しい批判があり、多くの人を怒らせた。フランス とプロイセンは七年戦争、ポルトガルは異端審問、イギリスはジョン・バイングの処刑などである。組織化された宗教もまた、『カンディード』では厳しく扱わ れている。例えば、ヴォルテールはローマ・カトリック教会のイエズス会を馬鹿にしている。パラグアイで、カカンボは「(イエズス会は)あらゆるものの支配 者であり、民衆はまったく金を持っていない......」と述べている。ここでヴォルテールは、パラグアイにおけるキリスト教宣教が地元住民を利用してい ることを示唆している。ヴォルテールは、イエズス会が先住民を助けていると主張する一方で、先住民を奴隷として拘束していることを描いている[62] [63]。 風刺 カンディード』の風刺の主な手法は、皮肉たっぷりに偉大な悲劇と喜劇を対比させることである[10]。この物語は、世の中の悪を作り出したり誇張したりす るのではなく、現実の悪を鮮明に表示することで、ヴォルテールは微妙な哲学や文化的伝統を単純化し、それらの欠点を強調することができる[60]。こうし て『カンディード』は、例えば、明らかに救いのない、恐ろしい歴史的(あるいは少なくとももっともらしい)出来事の洪水によって楽観主義を嘲笑する[2] [59]。 『カンディード』の風刺の単純な例は、カンディードとマーティンがポーツマス港で目撃した歴史的出来事の扱いに見られる。二人はそこで、ジョン・バングを 代 表すると思われる匿名の提督が、フランス艦隊との交戦に失敗した罪で処刑されるのを目撃する。提督は目隠しをされ、自分の船の甲板で撃たれるが、それは単 に「他の者を励ますため」(フランス語:pour encourageger les autres、この表現はヴォルテールが創始したとされている)であった。この軍事的処罰の描写は、ビングの死を矮小化している。他人を励ますため」とい う辛口で軽妙な説明は、このように、ヴォルテールらしいやり方で、重大な歴史的出来事を風刺している。その古典的な機知から、このフレーズは『カンディー ド』からよく引用されるようになった[10][64]。 ヴォルテールは、世の中の最悪の事態と、それを楽観的な見通しにはめ込もうとする哀れな主人公の必死の努力を描いている。カンディード』のほとんどすべて が、さまざまな形の悪についての議論であり、登場人物たちが一時的な安息すら見出すことはめったにない。少なくとも一つの顕著な例外がある。エルドラドの エピソードで、その幻想的な村の住民は単純に理性的であり、その社会は公正で合理的である。エルドラドの前向きさは、本書の大半の悲観的な態度と対照的か もしれない。この場合でも、エルドラドの至福はつかの間である: カンディードはすぐに村を出てクネゴンドを探すが、彼女とは結局、義務感から結婚しただけである[2][59]。 この風刺のもう一つの要素は、『カンディード』に関する多くの出版物の著者であるウィリアム・F・ボッティリアが「時代の感傷的な欠点」と呼ぶものと、そ れに対するヴォルテールの攻撃に焦点を当てている[65]。 カンディード』は冒険とロマンスの決まり文句をパロディ化し、ピカレスク小説のスタイルを模倣することで、ヨーロッパ文化の欠陥が強調されている[65] [66]: カンディードは社会的地位の低い流れ者のならず者、キュネゴンドは性欲の対象、パングロスは博識な指導者、カカンボは腕利きの付き人ということになってい る[2]。筋書きが展開するにつれ、読者はカンディードがならず者ではなく、キュネゴンドは醜くなり、パングロスは頑固な愚か者であることに気づく。カン ディード』の登場人物は非現実的で、二次元的で、機械的で、マリオネットのようでさえある。 庭園のモチーフ 多くの批評家によって、庭は『カンディード』において重要な象徴的役割を果たすと考えられている。一般的に庭とされる最初の場所は男爵の城であり、そこか らカンディードとキュネゴンドは、創世記でアダムとイヴがエデンの園から追い出されるのと同じように追い出される。循環的に、『カンディード』の主人公た ちは、天上の楽園を象徴するような、自分たちが作った庭で小説を締めくくる。三番目に目立つ「庭」はエルドラドで、これは偽のエデンかもしれない [69]。その他に象徴的と思われる庭には、イエズス会の館、ポコクランテの庭、カカンボの庭、トルコ人の庭などがある[70]。 これらの庭園はおそらくエデンの園を指しているのだろうが、例えばボッティリアは、庭園は百科全書も指しており、カンディードが「自分の庭」を耕すという 結論を出したのは、ヴォルテールがこの努力を大いに支援したことを象徴している、とも提唱している。カンディードとその仲間たちは、この小説の最後で、百 科全書を支えたヴォルテールの緊密な哲学サークルと非常に似た立場にいる。ヴォルテールが同僚たちに執筆のために社交界を離れることを勧めたように、『カ ンディード』の主人公たちも「(自分の)庭を耕す」ために隠遁生活を送るのである。さらに、ヴォルテールの書簡の中には、彼が百科全書執筆を表現するため に、他の場所でも園芸の比喩を使っていたという証拠がある[70]。もう一つの解釈の可能性は、カンディードが「自分の庭」を耕すということは、彼が自分 自身を養い、退屈と闘うといった必要な仕事だけに従事することを示唆しているということである。ヴォルテール自身、レ・デリスとフェルニーの邸宅で庭師を しており、書簡の中でしばしば、ガーデニングは自分にとって重要な娯楽であり、忙しくするための非常に効果的な方法であると書いている[71][72] [73]。 |
| Philosophy Optimism Candide satirises various philosophical and religious theories that Voltaire had previously criticised. Primary among these is Leibnizian optimism (sometimes called Panglossianism after its fictional proponent), which Voltaire ridicules with descriptions of seemingly endless calamity.[10] Voltaire demonstrates a variety of irredeemable evils in the world, leading many critics to contend that Voltaire's treatment of evil—specifically the theological problem of its existence—is the focus of the work.[74] Heavily referenced in the text are the Lisbon earthquake, disease, and the sinking of ships in storms. Also, war, thievery, and murder—evils of human design—are explored as extensively in Candide as are environmental ills. Bottiglia notes Voltaire is "comprehensive" in his enumeration of the world's evils. He is unrelenting in attacking Leibnizian optimism.[75] Fundamental to Voltaire's attack is Candide's tutor Pangloss, a self-proclaimed follower of Leibniz and a teacher of his doctrine. Ridicule of Pangloss's theories thus ridicules Leibniz himself, and Pangloss's reasoning is silly at best. For example, Pangloss's first teachings of the narrative absurdly mix up cause and effect: Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement; car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes; aussi avons-nous des lunettes. It is demonstrable that things cannot be otherwise than as they are; for as all things have been created for some end, they must necessarily be created for the best end. Observe, for instance, the nose is formed for spectacles, therefore we wear spectacles.[76] Following such flawed reasoning even more doggedly than Candide, Pangloss defends optimism. Whatever their horrendous fortune, Pangloss reiterates "all is for the best" ("Tout est pour le mieux") and proceeds to "justify" the evil event's occurrence. A characteristic example of such theodicy is found in Pangloss's explanation of why it is good that syphilis exists: c'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire; car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenille; it was a thing unavoidable, a necessary ingredient in the best of worlds; for if Columbus had not caught in an island in America this disease, which contaminates the source of generation, and frequently impedes propagation itself, and is evidently opposed to the great end of nature, we should have had neither chocolate nor cochineal.[50] Candide, the impressionable and incompetent student of Pangloss, often tries to justify evil, fails, invokes his mentor and eventually despairs. It is by these failures that Candide is painfully cured (as Voltaire would see it) of his optimism. This critique of Voltaire's seems to be directed almost exclusively at Leibnizian optimism. Candide does not ridicule Voltaire's contemporary Alexander Pope, a later optimist of slightly different convictions. Candide does not discuss Pope's optimistic principle that "all is right", but Leibniz's that states, "this is the best of all possible worlds". However subtle the difference between the two, Candide is unambiguous as to which is its subject. Some critics conjecture that Voltaire meant to spare Pope this ridicule out of respect, although Voltaire's Poème may have been written as a more direct response to Pope's theories. This work is similar to Candide in subject matter, but very different from it in style: the Poème embodies a more serious philosophical argument than Candide.[77] Conclusion The conclusion of the novel, in which Candide finally dismisses his tutor's optimism, leaves unresolved what philosophy the protagonist is to accept in its stead. This element of Candide has been written about voluminously, perhaps above all others. The conclusion is enigmatic and its analysis is contentious.[78] Voltaire develops no formal, systematic philosophy for the characters to adopt.[79] The conclusion of the novel may be thought of not as a philosophical alternative to optimism, but as a prescribed practical outlook (though what it prescribes is in dispute). Many critics have concluded that one minor character or another is portrayed as having the right philosophy. For instance, a number believe that Martin is treated sympathetically, and that his character holds Voltaire's ideal philosophy—pessimism. Others disagree, citing Voltaire's negative descriptions of Martin's principles and the conclusion of the work in which Martin plays little part.[80] Within debates attempting to decipher the conclusion of Candide lies another primary Candide debate. This one concerns the degree to which Voltaire was advocating a pessimistic philosophy, by which Candide and his companions give up hope for a better world. Critics argue that the group's reclusion on the farm signifies Candide and his companions' loss of hope for the rest of the human race. This view is to be compared to a reading that presents Voltaire as advocating a melioristic philosophy and a precept committing the travellers to improving the world through metaphorical gardening. This debate, and others, focuses on the question of whether or not Voltaire was prescribing passive retreat from society, or active industrious contribution to it.[81] Inside vs. outside interpretations Separate from the debate about the text's conclusion is the "inside/outside" controversy. This argument centers on the matter of whether or not Voltaire was actually prescribing anything. Roy Wolper, professor emeritus of English, argues in a revolutionary 1969 paper that Candide does not necessarily speak for its author; that the work should be viewed as a narrative independent of Voltaire's history; and that its message is entirely (or mostly) inside it. This point of view, the "inside", specifically rejects attempts to find Voltaire's "voice" in the many characters of Candide and his other works. Indeed, writers have seen Voltaire as speaking through at least Candide, Martin, and the Turk. Wolper argues that Candide should be read with a minimum of speculation as to its meaning in Voltaire's personal life. His article ushered in a new era of Voltaire studies, causing many scholars to look at the novel differently.[82][83] Critics such as Lester Crocker, Henry Stavan, and Vivienne Mylne find too many similarities between Candide's point of view and that of Voltaire to accept the "inside" view; they support the "outside" interpretation. They believe that Candide's final decision is the same as Voltaire's, and see a strong connection between the development of the protagonist and his author.[84] Some scholars who support the "outside" view also believe that the isolationist philosophy of the Old Turk closely mirrors that of Voltaire. Others see a strong parallel between Candide's gardening at the conclusion and the gardening of the author.[85] Martine Darmon Meyer argues that the "inside" view fails to see the satirical work in context, and that denying that Candide is primarily a mockery of optimism (a matter of historical context) is a "very basic betrayal of the text".[86][87] |
哲学 楽観主義 『カンディード』は、それまでヴォルテールが批判してきたさまざまな哲学的・宗教的理論を風刺している。ヴォルテールは、世の中に存在する様々な救いよう の ない悪を示しており、多くの批評家は、ヴォルテールの悪の扱い、特に悪の存在に関する神学的な問題がこの作品の焦点であると主張する[74]。また、『カ ンディード』では、戦争、泥棒、殺人といった、人間が作り出した悪も、環境問題と同様に広範囲にわたって探求されている。ボッティリアは、ヴォルテールは 世界の悪を「包括的に」列挙していると指摘する。彼はライプニッツ的楽観主義を容赦なく攻撃する[75]。 ヴォルテールの攻撃の基本は、ライプニッツの信奉者を自称し、彼の教義を教えるカンディードの家庭教師パングロスにある。パングロスの理論を嘲笑すること は、ライプニッツ自身を嘲笑することになる。例えば、パングロスの最初の教えは、原因と結果を無茶苦茶に混同している: すべてのことはある結末のためにあるのであって、すべてのことはよりよい結末のために必要なのである。nezがlunetteを運ぶために作られたことを よく思い出してほしい。 なぜなら、すべてのものが何らかの目的のために創造されたように、必然的に最良の目的のために創造されなければならないからである。たとえば、鼻は眼鏡の ために形成されたのであり、したがって我々は眼鏡をかけるのである[76]。 このような欠陥のある推論に、カンディード以上に執拗に従いながら、パングロスは楽観主義を擁護する。パングロスは「すべては最善のためにある」 ("Tout est pour le mieux")と繰り返し、自分たちの恐ろしい運命がどのようなものであったとしても、その悪い出来事の発生を「正当化」しようとする。このような神学の 特徴的な例は、梅毒が存在することがなぜ良いことなのかについてのパングロスの説明に見られる: もしコロンブがアメリ カのある島で、そのような悪疫に罹患していなければ、その悪疫は遺伝の根源を絶つものであり、またしばしば遺伝を阻害するものであり、しかも自然の大義に 反するものであったろう; もしコロンブスがアメリカのある島で、生成の源を汚染し、しばしば伝播そのものを妨げ、明らかに自然の大いなる目的に反するこの病気を発見しなかったら、 チョコレートもコチニールもなかっただろう[50]。 パングロスの弟子であるカンディードは、多感で無能であるがゆえに、しばしば悪を正当化しようとし、失敗し、師を呼び、ついには絶望する。このような失敗 によって、カンディードは(ヴォルテールに言わせれば)楽観主義を苦しまぎれに治していくのである。 ヴォルテールのこの批評は、ほとんどライプニッツ的楽観主義にのみ向けられているように思われる。カンディード』は、ヴォルテールと同世代のアレクサン ダー・ポープを嘲笑していない。カンディード』が論じているのは、ポープの「すべては正しい」という楽観主義ではなく、ライプニッツの「これはあらゆる可 能な世界の中で最良のものである」という楽観主義である。両者の違いがいかに微妙であろうとも、『カンディード』の主題がどちらであるかは明白である。 ヴォルテールはポープへの敬意から、このような揶揄を避けたかったのだろうと推測する批評家もいるが、ヴォルテールの詩はポープの理論に対するより直接的 な応答として書かれたのかもしれない。この作品は主題において『カンディード』に似ているが、文体において『カンディード』とは大きく異なっており、『詩 編』は『カンディード』よりもまじめな哲学的議論を体現している[77]。 結末 カンディードが家庭教師の楽観主義を最終的に否定する小説の結末は、主人公がその代わりにどのような哲学を受け入れるべきかを未解決のままにしている。 『カ ンディード』のこの要素については、おそらく他のどの作品よりも多く書かれている。結論は謎めいており、その分析は論争を呼んでいる[78]。 ヴォルテールは、登場人物たちが採用すべき正式で体系的な哲学を展開していない[79]。この小説の結論は、楽観主義に対する哲学的な代替案としてではな く、規定された実践的な展望として考えられるかもしれない(ただし、それが何を規定しているかは議論の余地がある)。多くの批評家は、ある脇役や別の人物 が正しい哲学を持っていると結論付けている。例えば、マルタンが同情的に扱われ、彼のキャラクターがヴォルテールの理想的な哲学-悲観主義-を持っている と考える者も少なくない。また、マルタンの主義主張に対するヴォルテールの否定的な描写や、マルタンがほとんど活躍しない作品の結末を引き合いに出して、 反対する者もいる[80]。 『カンディード』の結論を読み解こうとする議論の中には、『カンディード』のもう一つの主要な論争がある。この議論は、ヴォルテールがどの程度悲観的な哲 学 を提唱しているのか、つまりカンディードとその仲間たちがよりよい世界への希望を捨てているのか、という点に関わるものである。批評家たちは、一行が農場 に閉じこもるのは、カンディードと仲間たちが他の人類に対する希望を失ったことを意味すると主張する。この見解は、ヴォルテールがメリオリスティックな哲 学を提唱し、隠喩的な園芸を通じて世界を改善することを旅人に約束する戒律を提唱しているとする読み方と比較される。この議論やその他の議論は、ヴォル テールが社会からの消極的な後退を処方していたのか、それとも社会への積極的な勤勉な貢献を処方していたのかという問題に焦点を当てている[81]。 内的解釈と外的解釈 本文の結論に関する議論とは別に、「内部/外部」論争がある。この論争の中心は、ヴォルテールが実際に何かを処方していたかどうかという問題である。ロ イ・ウォルパー名誉教授(英語)は1969年の革命的な論文で、『カンディード』は必ずしも作者を代弁しているわけではない、この作品はヴォルテールの歴 史から独立した物語として見るべきであり、そのメッセージはすべて(あるいはほとんど)ヴォルテールの内部にある、と主張している。この "内側 "という視点は、特に『カンディード』や他の作品に登場する多くの人物の中にヴォルテールの "声 "を見出そうとする試みを否定する。実際、作家たちは少なくともカンディード、マルタン、トルコ人を通してヴォルテールが語っていると見てきた。ヴォル パーは、『カンディード』はヴォルテールの私生活における意味について、最小限の推測で読まれるべきであると主張する。彼の論文はヴォルテール研究の新時 代の到来を告げ、多くの学者がこの小説を違った角度から見るきっかけとなった[82][83]。 レスター・クロッカー、ヘンリー・スタヴァン、ヴィヴィアン・マイルンといった批評家たちは、カンディードの視点とヴォルテールの視点にはあまりにも多く の類似点があるため、「内面的」な見方を受け入れず、「外面的」な解釈を支持している。彼らは、カンディードの最終的な決断はヴォルテールと同じであり、 主人公の成長と作者の間には強いつながりがあると考える[84]。マルティーヌ・ダルモン・メイヤーは、「内面的」な見方は風刺作品を文脈の中で見ること に失敗しており、『カンディード』が主に楽観主義を嘲笑するもの(歴史的文脈の問題)であることを否定することは「テクストに対する非常に基本的な裏切 り」であると論じている[86][87]。 |
| Reception De roman, Voltaire en a fait un, lequel est le résumé de toutes ses œuvres ... Toute son intelligence était une machine de guerre. Et ce qui me le fait chérir, c'est le dégoût que m'inspirent les voltairiens, des gens qui rient sur les grandes choses! Est-ce qu'il riait, lui? Il grinçait ... — Flaubert, Correspondance, éd. Conard, II, 348; III, 219[88] Voltaire made, with this novel, a résumé of all his works ... His whole intelligence was a war machine. And what makes me cherish it is the disgust which has been inspired in me by the Voltairians, people who laugh about the important things! Was he laughing? Voltaire? He was screeching ... — Flaubert, Correspondance, éd. Conard, II, 348; III, 219[88] Though Voltaire did not openly admit to having written the controversial Candide until 1768 (until then he signed with a pseudonym: "Monsieur le docteur Ralph", or "Doctor Ralph"[89]), his authorship of the work was hardly disputed.[90][a] Immediately after publication, the work and its author were denounced by both secular and religious authorities, because the book openly derides government and church alike. It was because of such polemics that Omer-Louis-François Joly de Fleury, who was Advocate General to the Parisian parliament when Candide was published, found parts of Candide to be "contrary to religion and morals".[90] Despite much official indictment, soon after its publication, Candide's irreverent prose was being quoted. "Let us eat a Jesuit", for instance, became a popular phrase for its reference to a humorous passage in Candide.[92] By the end of February 1759, the Grand Council of Geneva and the administrators of Paris had banned Candide.[4] Candide nevertheless succeeded in selling twenty thousand to thirty thousand copies by the end of the year in more than twenty editions, making it a best seller. The Duke de La Vallière speculated near the end of January 1759 that Candide might have been the fastest-selling book ever.[90] In 1762, Candide was listed in the Index Librorum Prohibitorum, the Roman Catholic Church's list of prohibited books.[4] Bannings of Candide lasted into the twentieth century in the United States, where it has long been considered a seminal work of Western literature. At least once, Candide was temporarily barred from entering America: in February 1929, a US customs official in Boston prevented a number of copies of the book, deemed "obscene",[93] from reaching a Harvard University French class. Candide was admitted in August of the same year; however by that time the class was over.[93] In an interview soon after Candide's detention, the official who confiscated the book explained the office's decision to ban it, "But about 'Candide,' I'll tell you. For years we've been letting that book get by. There were so many different editions, all sizes and kinds, some illustrated and some plain, that we figured the book must be all right. Then one of us happened to read it. It's a filthy book".[94][95][96] |
レセプション ヴォルテールは、その全作品の要約である「一篇」を書いた。彼の知性はすべて戦争機械であった。それは、私がヴォルタイアンを奮い立たせ、壮大な出来事に 歓喜する人々を鼓舞している、その歓喜なのだ!それは何ですか?ニヤニヤして... - Flaubert, Correspondance, ed. Conard, II, 348; III, 219[88]. ヴォルテールはこの小説で、彼の全作品の履歴書を作った......。彼の全知性は戦争機械であった。私がこの小説を大切にしているのは、ヴォルテール主 義者たち、つまり、重要なことを笑い飛ばす人々によって、私の中に触発された嫌悪感である!彼は笑っていたのか?ヴォルテール?彼は金切り声をあげてい た... - Flaubert, Correspondance, éd. Conard, II, 348; III, 219[88]. ヴォルテールは1768年まで論争の的となった『カンディード』を書いたことを公には認めなかったが(それまでは「ラルフ医師」というペンネームで署名し ていた[89])。 出版直後から、この作品とその著者は世俗と宗教の両方の権威から非難された。カンディード』が出版された当時、パリ議会の法務官であったオメル=ルイ=フ ランソワ・ジョリー・ド・フルーリーは、『カンディード』の一部が「宗教と道徳に反している」と指摘した[90]。 多くの公式の非難にもかかわらず、『カンディード』の出版後すぐに、その不遜な散文が引用されるようになった。1759年2月末までに、ジュネーヴの大評 議会とパリの行政官は『カンディード』を出版禁止にした[4]。 それでも『カンディード』は20以上の版で年末までに2万部から3万部を売り上げるベストセラーとなった。1762年、『カンディード』はローマ・カト リック教会の禁書目録であるIndex Librorum Prohibitorumに掲載された[4]。 『カンディード』の発禁処分は20世紀まで続き、アメリカでは長い間、西洋文学の代表作とみなされてきた。少なくとも一度、『カンディード』は一時的にア メリカへの入国を禁止されたことがある。1929年2月、ボストンの税関職員が、ハーバード大学のフランス語の授業で、「わいせつ」[93]とみなされた この本のコピーが何冊も手に入るのを阻止した。カンディード』は同年8月に出版が許可されたが、その時点で授業は終了していた[93]。『カンディード』 が拘留された直後のインタビューで、この本を没収した職員は、この本を出版禁止にした当局の決定について次のように説明している。何年もの間、私たちはあ の本を放置してきました。大小さまざまな版があり、挿絵入りのものもあれば無地のものもあった。ある時、私たちの一人がたまたまその本を読んだ。不潔な本 だ」[94][95][96]。 |
| Legacy Candide is the most widely read of Voltaire's many works,[63] and it is considered one of the great achievements of Western literature.[11] William F. Bottiglia opines, "The physical size of Candide, as well as Voltaire's attitude toward his fiction, precludes the achievement of artistic dimension through plenitude, autonomous '3D' vitality, emotional resonance, or poetic exaltation. Candide, then, cannot in quantity or quality, measure up to the supreme classics" such as the works of Homer or Shakespeare, Sophocles, Chaucer, Dante, Cervantes, Fielding, Goethe, Dostoevsky, Tolstoy, Racine, or Molière.[97] Bottiglia instead calls it a miniature classic; but others have been more forgiving of its size.[11][97] As the only work of Voltaire which has remained popular up to the present day,[98] Candide is listed in Harold Bloom's The Western Canon: The Books and School of the Ages. It is included in the Encyclopædia Britannica collection Great Books of the Western World.[99] Candide has influenced modern writers of black humour such as Céline, Joseph Heller, John Barth, Thomas Pynchon, Kurt Vonnegut, and Terry Southern. Its parody and picaresque methods have become favourites of black humorists.[100] Charles Brockden Brown, an early American novelist, may have been directly affected by Voltaire, whose work he knew well. Mark Kamrath, professor of English, describes the strength of the connection between Candide and Brown's Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleep-Walker (1799): "An unusually large number of parallels...crop up in the two novels, particularly in terms of characters and plot." For instance, the protagonists of both novels are romantically involved with a recently orphaned young woman. Furthermore, in both works the brothers of the female lovers are Jesuits, and each is murdered (although under different circumstances).[101] Some twentieth-century novels that may have been influenced by Candide are some dystopian science-fiction works. Armand Mattelart, a French critic, sees Candide in Aldous Huxley's Brave New World, George Orwell's Nineteen Eighty-Four, and Yevgeny Zamyatin's We, three canonical works of the genre. Specifically, Mattelart writes that in each of these works, there exist references to Candide's popularisation of the phrase "the best of all possible worlds". He cites as evidence, for example, that the French version of Brave New World was entitled Le Meilleur des mondes (lit. '"The best of worlds"').[102] Readers of Candide often compare it with certain works of the modern genre the Theatre of the Absurd. Haydn Mason, a Voltaire scholar, sees in Candide a few similarities to this brand of literature. For instance, he notes commonalities of Candide and Waiting for Godot (1952). In both of these works, and in a similar manner, friendship provides emotional support for characters when they are confronted with harshness of their existences.[103] However, Mason qualifies, "the conte must not be seen as a forerunner of the 'absurd' in modern fiction. Candide's world has many ridiculous and meaningless elements, but human beings are not totally deprived of the ability to make sense out of it."[104] John Pilling, biographer of Beckett, does state that Candide was an early and powerful influence on Beckett's thinking.[105] Rosa Luxemburg, in the aftermath of the First World War, remarked upon re-reading Candide: "Before the war, I would have thought this wicked compilation of all human misery a caricature. Now it strikes me as altogether realistic."[106] The American alternative rock band Bloodhound Gang refer to Candide in their song "Take the Long Way Home", from the American edition of their 1999 album Hooray for Boobies. Derivative works In 1760, one year after Voltaire published Candide, a sequel was published with the name Candide, ou l'optimisme, seconde partie.[107] This work is attributed both to Thorel de Campigneulles, a writer unknown today, and Henri Joseph Du Laurens, who is suspected of having habitually plagiarised Voltaire.[108] The story continues in this sequel with Candide having new adventures in the Ottoman Empire, Persia, and Denmark. Part II has potential use in studies of the popular and literary receptions of Candide, but is almost certainly apocryphal.[107] In total, by the year 1803, at least ten imitations of Candide or continuations of its story were published by authors other than Voltaire.[90] Candide was adapted for the radio anthology program On Stage in 1953. Richard Chandlee wrote the script; Elliott Lewis, Cathy Lewis, Edgar Barrier, Byron Kane, Jack Kruschen, Howard McNear, Larry Thor, Martha Wentworth, and Ben Wright performed.[109] 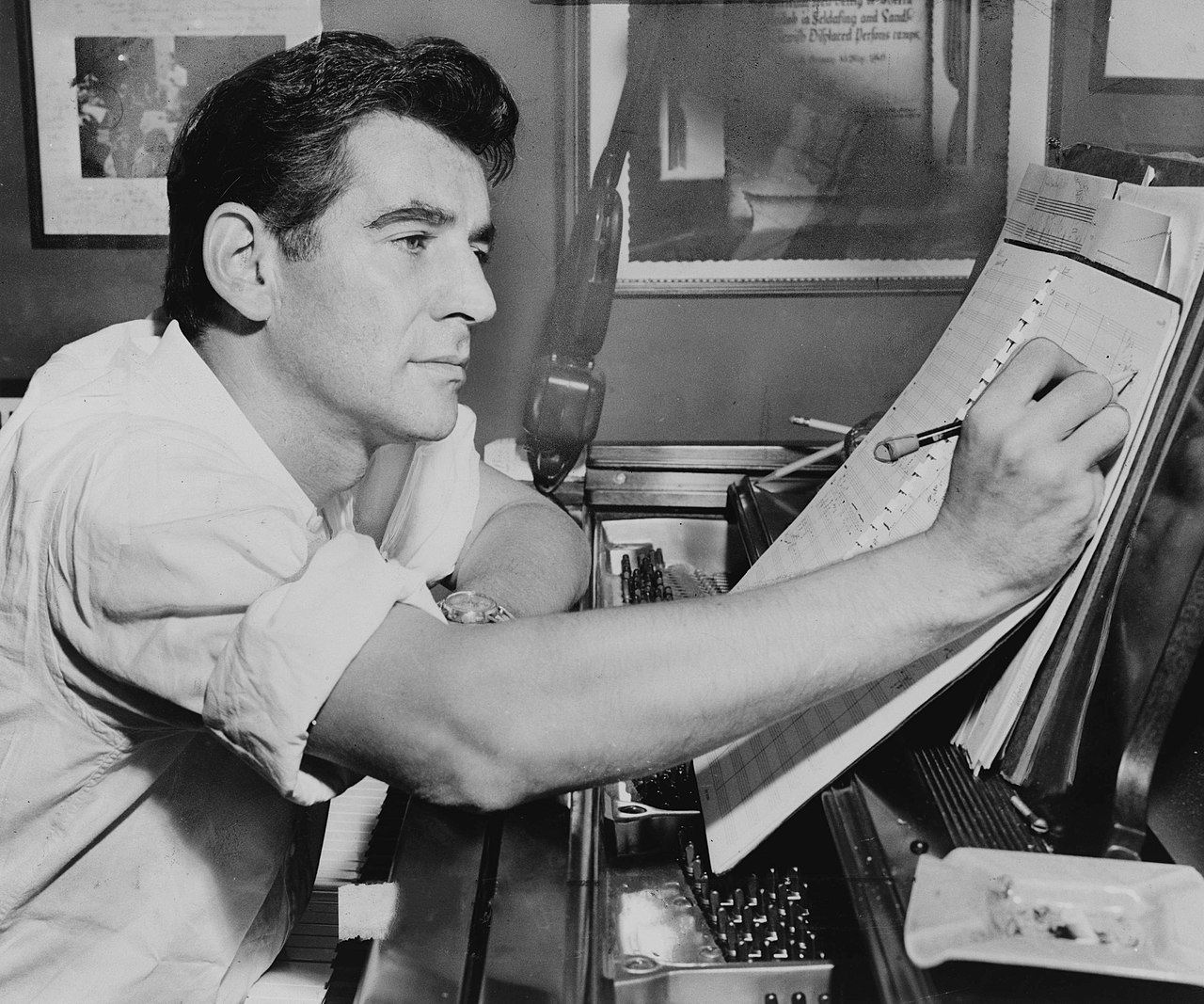 Leonard Bernstein in 1955 The operetta Candide was originally conceived by playwright Lillian Hellman, as a play with incidental music. Leonard Bernstein, the American composer and conductor who wrote the music, was so excited about the project that he convinced Hellman to do it as a "comic operetta".[110] Many lyricists worked on the show, including James Agee, Dorothy Parker, John Latouche, Richard Wilbur, Leonard and Felicia Bernstein, and Hellman. Hershy Kay orchestrated all the pieces except for the overture, which Bernstein did himself.[111] Candide first opened on Broadway as a musical on 1 December 1956. The premier production was directed by Tyrone Guthrie and conducted by Samuel Krachmalnick.[111] While this production was a box office flop, the music was highly praised, and an original cast album was made. The album gradually became a cult hit, but Hellman's libretto was criticised as being too serious an adaptation of Voltaire's novel.[112] Candide has been revised and reworked several times. The first New York revival, directed by Hal Prince, featured an entirely new libretto by Hugh Wheeler and additional lyrics by Stephen Sondheim. Bernstein revised the work again in 1987 with the collaboration of John Mauceri and John Wells. After Bernstein's death, further revised productions of the musical were performed in versions prepared by Trevor Nunn and John Caird in 1999, and Mary Zimmerman in 2010. Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia [it] (1977) or simply Candido is a book by Leonardo Sciascia. It was at least partly based on Voltaire's Candide, although the actual influence of Candide on Candido is a hotly debated topic. A number of theories on the matter have been proposed. Proponents of one say that Candido is very similar to Candide, only with a happy ending; supporters of another claim that Voltaire provided Sciascia with only a starting point from which to work, that the two books are quite distinct.[113][114] The BBC produced a television adaptation in 1973, with Ian Ogilvy as Candide, Emrys James as Dr. Pangloss, and Frank Finlay as Voltaire himself, acting as the narrator.[115] Nedim Gürsel wrote his 2001 novel Le voyage de Candide à Istanbul about a minor passage in Candide during which its protagonist meets Ahmed III, the deposed Turkish sultan. This chance meeting on a ship from Venice to Istanbul is the setting of Gürsel's book.[116] Terry Southern, in writing his popular novel Candy with Mason Hoffenberg adapted Candide for a modern audience and changed the protagonist from male to female. Candy deals with the rejection of a sort of optimism which the author sees in women's magazines of the modern era; Candy also parodies pornography and popular psychology. This adaptation of Candide was adapted for the cinema by director Christian Marquand in 1968.[117] In addition to the above, Candide was made into a number of minor films and theatrical adaptations throughout the twentieth century. For a list of these, see Voltaire: Candide ou L'Optimisme et autres contes (1989) with preface and commentaries by Pierre Malandain.[118] In May 2009, a play titled Optimism, based on Candide, opened at the CUB Malthouse Theatre in Melbourne. It followed the basic story of Candide, incorporating anachronisms, music, and stand up comedy from comedian Frank Woodley. It toured Australia and played at the Edinburgh International Festival.[119] In 2010, the Icelandic writer Óttar M. Norðfjörð published a rewriting and modernisation of Candide, titled Örvitinn; eða hugsjónamaðurinn. |
遺産 『カンディード』は、ヴォルテールの数ある作品の中で最も広く読まれており[63]、西洋文学の偉大な業績のひとつとみなされている[11]。ウィリア ム・ F・ボッティリアは、「『カンディード』の物理的な大きさと、ヴォルテールの小説に対する態度は、豊かさ、自律的な "3次元的 "活力、感情的共鳴、詩的高揚による芸術的次元の達成を妨げている。カンディード』は、量的にも質的にも、ホメロスやシェイクスピア、ソフォクレス、 チョーサー、ダンテ、セルバンテス、フィールディング、ゲーテ、ドストエフスキー、トルストイ、ラシーヌ、モリエールといった「至高の古典」には及ばな い。 [97]ボッティリアは代わりにこれを古典のミニチュアと呼ぶが、他の人々はその大きさに寛容である[11][97]。 今日まで人気を保っているヴォルテールの唯一の作品として[98]、『カンディード』はハロルド・ブルームの『西洋のカノン:時代の書物と学派』に掲載さ れている。カンディードは、セリーヌ、ジョセフ・ヘラー、ジョン・バース、トマス・ピンチョン、カート・ヴォネガット、テリー・サザンといった現代のブ ラックユーモア作家に影響を与えている。そのパロディとピカレスク的手法はブラックユーモア作家のお気に入りとなっている[100]。 初期のアメリカ人小説家であるチャールズ・ブロックデン・ブラウンは、彼がよく知るヴォルテールの作品から直接影響を受けたかもしれない。英語学のマー ク・カムラス教授は、『カンディード』とブラウンの『エドガー・ハントリー、あるいはある夢遊病者の回想』(1799年)とのつながりの強さについてこう 述べている: 「この2つの小説には、特に登場人物やプロットにおいて、非常に多くの類似点が見られる。例えば、両方の小説の主人公は、最近孤児になった若い女性と恋愛 関係にある。さらに、両作品とも恋人である女性の兄弟はイエズス会士であり、それぞれが(状況は異なるが)殺害されている[101]。 カンディード』に影響を受けたと思われる20世紀の小説には、ディストピア的なSF作品がある。フランスの批評家であるアルマン・マテラールは、カン ディードをオルダス・ハクスリーの『ブレイブ・ニュー・ワールド』、ジョージ・オーウェルの『ナインティーン188-フォー』、エフゲニー・ザミャーチン の『われら』の中に見ている。具体的には、マテラート氏は、これらの作品のそれぞれに、カンディードが広めた "the best of all possible worlds "という言葉への言及が存在すると書いている。例えば、『ブレイブ・ニュー・ワールド』のフランス語版のタイトルが『Le Meilleur des mondes』であったことを証拠として挙げている[102]。 『カンディード』の読者はしばしば、この作品を近代的ジャンルである「不条理劇場」のある作品と比較する。ヴォルテールの研究者であるヘイドン・メイソン は、『カンディード』にこの文学との類似点をいくつか見出している。例えば、彼は『カンディード』と『ゴドーを待ちながら』(1952年)の共通点を指摘 している。しかしメイソンは、「『カンディード』を、現代小説における『不条理』の先駆けとして見てはならない。ベケットの伝記作家であるジョン・ピリン グは、『カンディード』がベケットの思考に早くから強い影響を与えたと述べている。 ローザ・ルクセンブルクは、第一次世界大戦の後、『カンディード』を再読してこう述べている: 「戦争が始まる前なら、この邪悪な人間の不幸の集大成を戯画だと思っただろう。今となっては、まったく現実的な作品だと思う」[106]。 アメリカのオルタナティヴ・ロックバンド、ブラッドハウンド・ギャングは、1999年のアルバム『Hooray for Boobies』のアメリカ盤に収録されている「Take the Long Way Home」という曲の中で、『カンディード』に言及している。 派生作品 ヴォルテールが『カンディード』を出版した1年後の1760年、続編が『カンディード』(Candide, ou l'optimisme, seconde partie)という名前で出版された[107]。この作品は、今日では無名の作家であるソレル・ド・カンピニュレス(Thorel de Campigneulles)と、常習的にヴォルテールを盗用したと疑われているアンリ・ジョゼフ・デュ・ローランス(Henri Joseph Du Laurens)によるものとされている[108]。第II部は『カンディード』の大衆的・文学的受容の研究において利用される可能性があるが、ほぼ間違 いなく偽書である[107]。 1803年までに、ヴォルテール以外の作家によって、少なくとも10の『カンディード』の模倣や物語の続きが出版された[90]。 カンディード』は1953年にラジオのアンソロジー番組『オン・ステージ』のために脚色された。リチャード・チャンドリーが脚本を書き、エリオット・ルイ ス、キャシー・ルイス、エドガー・バリアー、バイロン・ケイン、ジャック・クルシェン、ハワード・マクニアー、ラリー・ソー、マーサ・ウェントワース、ベ ン・ライトが出演した[109]。 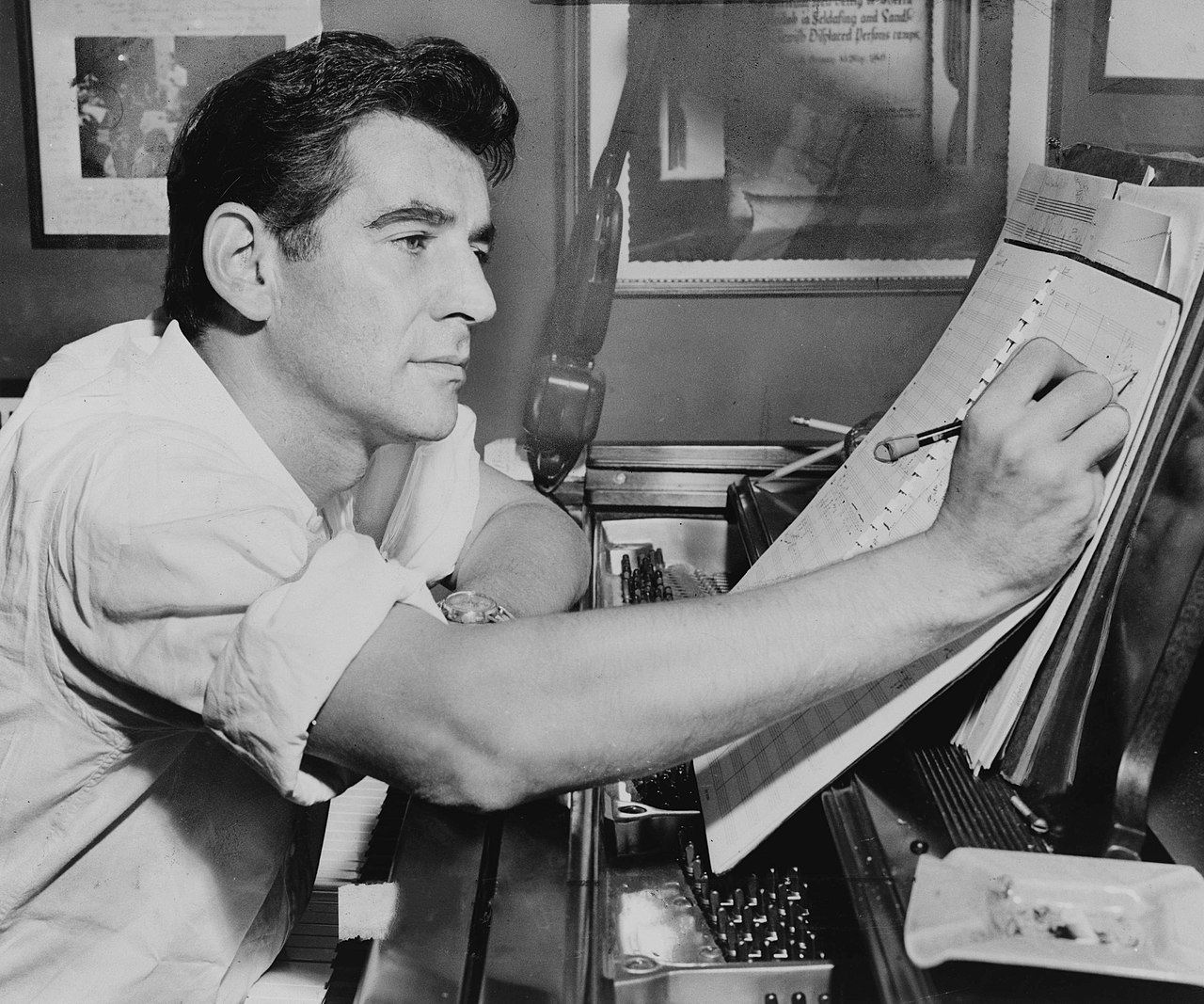 1955年のレナード・バーンスタイン オペレッタ『カンディード』は、もともと劇作家リリアン・ヘルマンによって、付随音楽付きの戯曲として構想された。音楽を担当したアメリカの作曲家兼指揮 者のレナード・バーンスタインは、このプロジェクトに非常に興奮し、「コミック・オペレッタ」として上演するようヘルマンを説得した[110]。ジェーム ズ・エイジ、ドロシー・パーカー、ジョン・ラトゥーシュ、リチャード・ウィルバー、レナード&フェリシア・バーンスタイン、ヘルマンなど、多くの作詞家が 上演に携わった。ハーシー・ケイは、序曲を除く全曲のオーケストレーションを担当し、バーンスタインはそれを自ら手がけた[111]。初演の演出はタイロ ン・ガスリー、指揮はサミュエル・クラクマルニックだった[111]。このプロダクションは興行的には失敗だったが、音楽は高く評価され、オリジナル・ キャスト・アルバムが制作された。このアルバムは次第にカルト的なヒットとなったが、ヘルマンの台本はヴォルテールの小説の脚色としては深刻すぎると批判 された[112]。ハル・プリンスが演出した最初のニューヨークでの再演では、ヒュー・ウィーラーによる全く新しい台本とスティーヴン・ソンドハイムによ る歌詞が追加された。バーンスタインは、ジョン・マウセリとジョン・ウェルズの協力を得て、1987年に再び作品を改訂した。バーンスタインの死後、 1999年にはトレヴァー・ナンとジョン・ケアードが、2010年にはメアリー・ジマーマンがこのミュージカルの改訂版を上演した。 Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia [it]』(1977)は、レオナルド・スキアシアの著書。少なくとも部分的にはヴォルテールの『カンディード』を下敷きにしているが、『カンディード』 が実際に『カンディード』に与えた影響については、熱い議論が交わされている。この問題については多くの説が提唱されている。ある説の支持者は、『カン ディード』は『カンディード』と非常によく似ているが、ハッピーエンドであるだけだと言い、別の説の支持者は、ヴォルテールはスキアシアに出発点を与えた だけで、2冊の本はまったく別物だと主張する[113][114]。 BBCは1973年にカンディードをイアン・オグルヴィ、パングロス博士をエムリス・ジェイムズ、ヴォルテール自身をフランク・フィンレイがナレーターを 務めるテレビドラマを制作した[115]。 ネディム・ギュセルは2001年、『カンディード』の小さな一節を題材にした小説『Le voyage de Candide à Istanbul』を書き、その中で主人公はトルコの退位したスルタン、アフメッド3世と出会う。このヴェネツィアからイスタンブールへの船上での偶然の 出会いが、ギュセルの本の舞台である[116]。テリー・サザンは、メイソン・ホッフェンバーグと人気小説『キャンディ』を執筆する際に、『カンディー ド』を現代の読者向けに脚色し、主人公を男性から女性に変えた。キャンディ』は、作者が現代の女性誌に見られるある種の楽観主義への拒絶を扱っており、ポ ルノや大衆心理学のパロディでもある。この『カンディード』の映画化は、1968年にクリスチャン・マルカン監督によって行われた[117]。 上記以外にも、『カンディード』は20世紀を通じて多くのマイナーな映画や舞台で翻案された。これらのリストについては、「ヴォルテール」を参照: Candide ou L'Optimisme et autres contes』(1989年、ピエール・マランダンによる序文と解説付き)を参照[118]。 2009年5月、メルボルンのCUB Malthouse Theatreで、『カンディード』を題材にした『Optimism』と題された演劇が上演された。カンディード』の基本的なストーリーに沿って、アナク ロニズム、音楽、コメディアンのフランク・ウッドリーによるスタンドアップコメディが盛り込まれた。2010年、アイスランドの作家オッタル・M・ノルズ フィョルズは、『カンディード』を現代風に書き直した『Örvitinn; eða hugsjónamaðurinn』を出版した。 |
| Candide ou l'optimisme au XXe
siècle (film, 1960) List of French-language authors Cannibalism in popular culture Pollyanna |
カンディード、二十世紀の楽観主義(映画、1960年) フランス語の作家一覧 大衆文化におけるカニバリズム ポリアンナ |
| Will Durant in The Age of
Voltaire: It was published early in 1759 as Candide, ou l'optimisme, purportedly "translated from the German of Dr. Ralph, with additions found in the pocket of the Doctor when he died at Minden." The Great Council of Geneva almost at once (March 5) ordered it to be burned. Of course Voltaire denied his authorship: "people must have lost their senses," he wrote to a friendly pastor in Geneva, "to attribute to me that pack of nonsense. I have, thank God, better occupations." But France was unanimous: no other man could have written Candide. Here was that deceptively simple, smoothly flowing, lightly prancing, impishly ironic prose that only he could write; here and there a little obscenity, a little scatology; everywhere a playful, darting, lethal irreverence; if the style is the man, this had to be Voltaire.[91] |
ウィル・デュラントは『ヴォルテールの時代』の中でこう述
べている: 1759年初頭、「ラルフ博士のドイツ語から翻訳され、博士がミンデンで死去したときにポケットから発見された加筆を加えた」とされる『カンディード』 (Candide, ou l'optimisme)として出版された。ジュネーブの大評議会は、ほとんどすぐに(3月5日)、この本の焼却を命じた。もちろん、ヴォルテールは自分 の著作であることを否定した: 「人々は正気を失っているに違いない」と彼はジュネーブの友好的な牧師に書き送った。私は神に感謝し、より良い職業を持っている"。しかし、フランス中の 意見は一致していた。ここには、彼にしか書けない、欺瞞に満ちたほど単純で、なめらかに流れ、軽やかに跳ね回り、不気味に皮肉った散文があり、あちこちに ちょっとした猥雑さ、スカトロジーがあり、いたるところに遊び心にあふれた、飛び抜けた、致命的な不遜さがある。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Candide |
+★Candide:
The shocking passages, Why is Voltaire's Candide controversial?
| Voltaire’s Candide,
or Optimism (1759), is a story of a young man who believed in his
tutor’s rosy worldview that “all is for the best.” Throughout the book,
he’s on a pursuit to find the girl he loves, while facing off a litany
of challenges which bring him against the worst humanity could offer.
Read below the thought-provoking passages from one of the most
controversial novels ever written. |
ヴォルテールの『カンディード、あるいは楽天主義』(1759年)は、
すべては最善であるという家庭教師の楽観的な世界観を信じた青年の物語である。この本全体を通して、彼は愛する女性を見つけるために奔走するが、その一方
で、人間が持つ最悪の側面を露わにする数々の試練に直面する。最も物議を醸した小説のひとつから、考えさせられる文章を以下に抜粋する。 |
| The German region of Westphalia
is where Candide lives. He’s the illegitimate son of the baron’s
sister. The castle’s mentor, and Candide’s personal tutor, is Pangloss
who believes that the world is “the best of all possible worlds.” One
day the gorgeous daughter of the baron, Cunégonde, flirts with Candide
(cousin relationships were not taboo) and they share a kiss behind a
screen. Her father catches them, and in a fury he kicks Candide out of
the castle. This marks the start of a series of tragic events which
will test his faith in his tutor’s ideas. |
ドイツのヴェストファーレン地方が、カンディドが暮らす場所である。彼
は男爵の妹の非嫡出子である。城の顧問であり、カンディドの個人教師でもあるパングロスは、世界は「この上なく素晴らしい世界」であると信じている。ある
日、男爵の美しい娘クネゴンデがカンディドに言い寄る(近親婚はタブーではなかった)。そして2人は衝立の後ろで口づけを交わす。彼女の父親に見つかり、
カンディドは城から追い出されてしまう。これは、彼の師の思想に対する彼の信念を試すことになる一連の悲劇的な出来事の始まりを告げる出来事だった。 |
| As he’s wandering out of town
cold and penniless, two men find him and act kindly at first, then
force him into military service for the King of the Bulgars. He gets
mistreated and abused everyday. One day, he goes on a walk, without
permission or understanding of the rules, he gets caught and sent to
execution as a deserter of the army. The King, passing by, stops the
execution at the last moment after explaining that Candide’s actions
and words betrays the naïveté of some kind of philosopher! He recovers from the pre-execution torture and joins a war of Bulgars versus Abares. On both sides, villages were burnt and civilians were killed. Candide then escapes to Hollande where his first experience will be literally shitty. He sees a Protestant orator (pastor) preaching publicly to a crowd about charity. Hungry Candide expects to receive some “brotherly love” with a bit of food from him but instead he gets questioned on his religious allegiance. (By the time of publishing this book Protestants and Catholics had long been enemies.) |
彼は寒さと無一文で町をさまよっているところを2人の男に発見され、最
初は親切にされたが、その後ブルガール王の軍隊に強制的に入隊させられた。彼は毎日虐待と罵倒を受けた。ある日、彼は許可も規則も理解せずに外出し、捕
まって脱走兵として処刑されることになった。通りかかった王は、カンディデの言動が哲学者の純真さを裏切っていると説明し、最後の瞬間に処刑を止める。 処刑直前の拷問から回復したカンディデは、ブルガール族対アバレス族の戦いに参加する。両軍とも村を焼き払い、民間人を殺害した。カンディデはその後、オ ランダに逃亡するが、そこで初めて文字通り最悪な経験をする。 彼は、プロテスタントの説教師(牧師)が慈善について群衆に公に説教しているのを目にする。空腹のカンディドは、彼から少しの食べ物とともに「兄弟愛」を 受け取れることを期待したが、代わりに宗教的忠誠心について問いただされた。(この本が出版された当時、プロテスタントとカトリックは長きにわたって敵対 関係にあった。) |
| ‘But
my friend,’ said the
orator, ‘do you believe that the Pope is AntiChrist?’ ‘I’ve not heard it said before now,’ replied Candide, ‘but whether he is or is not, I am in need of food.’ ‘You don’t deserve to eat,’ said the [orator]. ‘Be off, you wretch! Out of my sight, you miserable creature! And don’t ever approach my person again.’ The orator’s wife, putting her head out of the window and catching sight of somebody who could doubt that the Pope was Anti-Christ, discharged over his head a chamber pot full of … Heavens! To what extremes is religious zeal sometimes carried by the ladies!1 |
「し
かし、友よ」と演説家は言った。「教皇が反キリストだと信じている
のかね? 「今までにそんなことを言われたことはありません」とカンディドは答え た。「しかし、彼がそうであろうとなかろうと、私は食べ物を必要としているのです」 「お前には食べる資格などない」と演説家は言った。「失せろ、この惨め な人間め! 私の前から消え失せろ! 二度と私の前に現れるな!」 演説家の妻が窓から顔を出して、教皇が反キリストであると疑う人物を見 つけた。そして、その人物の頭めがけて、おまるいっぱいの…を浴びせた。なんと!女 性たちの宗教的熱狂は、時にどこまでエスカレートするのか!1 |
| Without questioning Candide’s
beliefs, an Anabaptist (of the same doctrine as the Amish) takes him
into his home, feeds him, gives him a job in his rug factory. The following day, he sees a beggar covered with sores, then realizes that it’s his tutor, Pangloss. He learns from Pangloss that the Baron, Baroness, Cunégonde and her brother were all killed by soldiers and that he contracted syphilis which he traces back, as was commonly misbelieved, to the Caribbean islands. Then Voltaire, through Pangloss, mocks the supposed celibacy of members of strict Catholic orders who engage in all kinds of sexual promiscuity of homosexual and even pedophilic nature: |
カンディードの信念を問いただすことなく、アナバプテスト(アーミッ
シュと同じ教義を持つ)は彼を自宅に連れて行き、食事を与え、自分の敷物工場で職を与える。 翌日、彼は膿だらけの乞食を目にし、それが自分の家庭教師パンゴロスであることに気づく。パングローから、男爵夫妻、クネゴンデとその兄弟は皆、兵士たち に殺されたこと、そして自分が梅毒にかかったのは、一般的に誤解されているようにカリブ海の島々で感染したからだと知る。そしてヴォルテールは、パング ローを通じて、厳格なカトリック修道会のメンバーが、同性愛や小児性愛を含むあらゆる種類の性的乱交に耽っているという、禁欲的な生活を送っているとされ る人々を嘲笑する。 |
| Pangloss
replied thus: ‘My dear
Candide! You remember Paquette, the pretty lady’s maid to our august
Baroness; well, in her arms I tasted the delights of paradise, which in
turn provoked the torments of hell by which you see me devoured; she
was herself infected, and may now be dead. Paquette received this
present from a very learned Franciscan, who could trace it back to its
source: for he had been given it by an old countess, who in turn had it
from a cavalry captain, who was indebted for it to a marquise, who
caught it from a page-boy, who contracted it from a Jesuit; who, while
a novice, had inherited it in a direct line from one of the shipmates
of Christopher Columbus. As for me, I will pass it on to no one, for I
am dying of it.’ ‘Oh Pangloss!’ cried Candide, ‘what a strange genealogy is this! Surely the devil is its source?’ ‘Not in the least,’ replied that great man. ‘It is an indispensable feature of the best of all possible worlds, a necessary ingredient: for if Columbus, on an island off the Americas, had not contracted this disease…we would have neither chocolate nor cochineal [an insect from Mexico used to create a red dye]’.2 |
パ
ングロスはこう答えた。「親愛なるカンディドよ!
君はパケットを覚えているだろう。彼女は、我らが高貴な男爵夫人の美しい侍女だ。彼女の腕の中で、私は楽園の喜びを味わった。それが引き金となって、今君
が見ているように、地獄の苦しみに襲われた。彼女自身も感染し、今ごろは死んでいるかもしれない。パケットは、この贈り物を非常に博識なフランシスコ会修
道士から受け取った。修道士は、その起源をたどることができた。なぜなら、彼は老伯爵夫人からそれを譲り受けたのだが、伯爵夫人は騎兵隊の大尉からそれを
譲り受けたのだが、大尉は侯爵夫人に借りがあったのだが、侯爵夫人は小姓からそれを譲り受けたのだが、小姓はイエズス会士からそれを譲り受けたのだが、イ
エズス会士は修練者だった頃、クリストファー・コロンブスの船仲間の一人からそれを直接受け継いでいたのだ。私としては、誰にもそれを伝えないでおこう。
なぜなら、私はそれによって死ぬからだ。 「パングロスさん!」と、カンディドは叫んだ。「なんと奇妙な系譜だろ う! きっと悪魔が原因なのだろう? 」 「とんでもない」と、その偉大な人物は答えた。「それは、あり得る世界の中で最も優れたものの不可欠な特徴であり、必要な要素なのだ。もしコロンブスがア メリカ大陸沖の島でこの病気に感染していなかったら…我々はチョコレートもコチニール(メキシコ原産の赤色色素を作るのに使われる昆虫)も手に入れられな かっただろう」2 |
| The unceasingly optimistic
Pangloss claims that the legendary explorations introduced a venereal
disease but let’s not forget they also brought us chocolate! The Anabaptist pays for the medical treatment of Pangloss who recovers although he loses an eye and an ear. Several weeks later the Anabaptist, Candide and Pangloss travel for business by boat to Lisbon. A storm overtakes and destroys their ship. The Anabaptist, one of the most humane characters in the story, drowns in the storm, while rescuing the sailor who survives with Pangloss and Candide. Everyone else on the ship drowns. They float on planks which take them to the shore. They’re received in Lisbon with a major earthquake that kills tens of thousands of people. (This is a reference to an actual 1755 Lisbon earthquake which was so violent that around 30,000 people perished.) The sailor gets drunk, steals money from the quake victims, and pays a whore for sex to a soundtrack of groans from people injured or still buried in the ruins. Pangloss can’t help but philosophize even in the face of corrupt characters like the sailor. He reprimands the sailor and tells him that his conduct breaks “the laws of universal reason.” The sailor retorts: |
絶え間なく楽観的なパングロスは、伝説の探検が性病をもたらしたと主張
するが、チョコレートももたらしたことを忘れてはならない! アナバプテスト信者は、片目と片耳を失ったものの回復したパンロッサの治療費を支払う。数週間後、アナバプテスト信者、カンディード、パンロッサは仕事で 船でリスボンに向かう。嵐に遭遇し、船が破壊される。物語の中で最も人間味のある登場人物の一人であるアナバプテスト信者は、パンロッサとカンディードと ともに生き残った船員を助けようとして嵐の中で溺死する。船の他の乗組員は全員溺死する。 彼らは板切れに乗り、岸まで流されていく。リスボンでは大地震が発生し、数万人が死亡する。(これは1755年に実際に起きたリスボン大地震を指してい る。この地震は非常に激しく、約3万人が命を落とした。) 船員は酔っ払って、地震の被災者から金を盗み、負傷者や瓦礫に埋まった人々のうめき声が聞こえる中、娼婦とセックスをする。パンゴラスは、船員のような堕 落した人物を目の前にしても、哲学的な考察をせずにはいられない。彼は船員を叱責し、彼の行動は「普遍的な理性の法則」に反していると告げる。船員は言い 返す。 |
| ‘Hell
and damnation! …I am a
sailor born in Batavia; I’ve made four voyages to Japan, and four times
I’ve trampled on the Cross; you’ve picked the wrong man, with your
drivel about “universal reason.”‘3 |
「地
獄と罰が下る!私はバタビア生まれの船乗りだ。私は4度日本へ航海
した。そして4度、十字架を踏みつけた。お前のくだらない「普遍的な理由」などという戯言に、お前は間違った男を選んだのだ。」3 |
| It
was reported that Europeans
had to repudiate their religion by trampling on a crucifix before they
could engage in trade with the Japanese who perceived Christian
missions as another arm of European imperialism. 4 Candide and Pangloss helped the quake victims while consoling them with their positive “all for the best” spiel and that somehow the disaster was a necessity. An officer of the Inquisition overhears Pangloss and traps him with two questions: How is this “the best of all possible worlds” if our very existence is a punishment for the original sin (Adam and Eve’s disobedience and subsequent banishment from the Garden of Eden)? Why would that “original sin” happen in the first place, putting us all in a state of guilt, if all is for the best? From the perspective of the Inquisition officer, Pangloss is essentially advocating a false doctrine. You can guess what’ll happen next… |
キ
リスト教宣教をヨーロッパ帝国主義の新たな一翼と捉える日本人との貿
易を行うには、ヨーロッパ人は十字架を踏みつけて信仰を否定しなければならないと伝えられていた。 カンディドとパングロスは、地震の被災者を助けながら、楽観的な「すべては最善」という持論で彼らを慰め、この災害は必然だったと説いた。異端審問の役人 がパンゴラスの話を耳にし、2つの質問で彼を追い詰めた。我々の存在そのものが原罪(アダムとイブの背信行為とそれに続くエデンの園からの追放)に対する 罰であるというのに、どうして「これは最善の世界なのか?」という質問と、「すべては最善であるというのなら、なぜそもそもその『原罪』が起こり、我々を 罪の意識に苛まれる状態に置くことになったのか?」という質問で、パングロスを罠にかけた。 異端審問官の視点では、パングロスは本質的に誤った教義を唱えていることになる。 さて、この後どうなるかはお察しの通りだ... |
| After
the earthquake, which had
destroyed three-quarters of Lisbon, the sages of that country could
think of no more effective means of averting further destruction than
to give the people a fine auto-de-fé [execution by burning]; it having
been decided by the University of Coïmbra [universities are not always
centers of enlightenment!] that the spectacle of a few individuals
being ceremonially roasted over a slow fire was the infallible secret
recipe for preventing the earth from quaking. Consequently they had rounded up a Biscayan [from the Spanish Basque] who stood convicted of marrying his fellow godparent [i.e. he married his godmother], and two Portuguese who were seen throwing away the bacon garnish while eating a chicken [most likely Jews]. After dinner some men arrived with ropes and tied up Doctor Pangloss and his disciple Candide – the one for what he had said, and the other for having listened with an air of approval.5 |
リ
スボンを4分の3破壊した地震の後、その国の賢者たちは、さらなる破
壊を回避するのにこれ以上効果的な手段はないと考えた。それは、立派な異端審問(火あぶりによる処刑)を国民に与えることだった。コインブラ大学(大学が
常に啓蒙の中心であるとは限らない!)により、少数の人間がゆっくりと火で焼かれるという光景が、地震を防ぐための絶対確実な秘策であると決定された。 その結果、洗礼名を同じくする者同士で結婚した罪で有罪判決を受けたビ スカヤ人(スペインのバスク地方出身者)と、鶏肉を食べながらベーコンの付け合わせ を投げ捨てているところを目撃されたポルトガル人2人(おそらくユダヤ人)を捕まえた。夕食後、何人かの男たちがロープを持ってやって来て、パングロス博 士と弟子のカンディードを縛り上げた。博士は発言したこと、弟子は賛同した様子で聞いていたことで有罪となった。5 |
| Pangloss was not burned at the
stake, he was sentenced to just a public hanging, as for Candide, his
punishment was a public flogging. Despite all the executions in the
name of God and the “magnificent auto-de-fé,” divine mercy never came
and another earthquake happened later that day. An old woman who works as a servant took Candide to treat his wounds after the flogging and to feed him. Later, the old woman leads him to the person who sent for his help: Cunégonde herself. Cunégonde explains to him that she, unlike her family, actually survived the Bulgar soldier attack. Later, when a Bulgar captain caught a soldier raping her, he killed him. The captain kept her as a sex slave for three months before he sold her to a Jewish businessman named Don Issachar. Then while Cunégonde was in church on a Sunday morning… |
パングロスは火あぶりの刑にはならず、ただの公開絞首刑に処された。一
方、カンディドは鞭打ちの刑に処された。神の名のもとに行われた処刑や「壮麗な異端審問」にもかかわらず、神の慈悲は訪れることはなく、その日のうちにま
たも地震が起こった。 鞭打ちの傷の手当てと食事を与えるため、召使として働く老女がカンディドを連れて行った。その後、老女は彼を助けを求めた人物、すなわちクネゴンデ自身の もとに導いた。クネゴンデは、ブルガール人の兵士の襲撃から生き延びたのは自分だけだったと彼に説明した。その後、ブルガルの隊長が彼女をレイプしている 兵士を捕らえ、その兵士を殺した。隊長は3か月間彼女を性奴隷として飼い、その後、ドン・イサクという名のユダヤ人実業家に彼女を売った。そして、クネゴ ンデが日曜の朝に教会にいたとき... |
| ‘The
Grand Inquisitor [the same
one who ordered the executions] noticed me one day at Mass; he ogled me
throughout the service, and then sent word that he had to speak to me
on private business. I was taken to his palace; I informed him of my
birth; he pointed out how far beneath my rank it was to be the chattel
of an Israelite. A proposition was made on his behalf to Don Issacar,
that he should hand me over to His Eminence the Inquisitor. Don
Issacar, who is the court banker and a man of parts, preferred to do no
such thing.’ ‘The Inquisitor threatened him with an auto-da-fé. At last my Jew, intimidated, agreed to a compromise, whereby the house and my person would belong to both of them in common; the Jew would have Mondays, Wednesdays and the Sabbath, the Inquisitor would have the other days of the week. This arrangement has lasted for six months. It has not been without its quarrels, namely as to whether the night between Saturday and Sunday belongs to the old law [Jewish Saturday] or to the new [Christian Sunday]. For my part, I have so far resisted them both, which I am sure is the reason they both love me still.’ ‘Finally, to avert the scourge of further earthquakes, and to intimidate Don Issacar, His Eminence the Inquisitor was pleased to hold an auto-da-fé. He did me the honour of inviting me. I had an excellent seat; refreshments were served to the ladies between the Mass and the executions.'6 |
「大
審問官(処刑を命じたのと同じ人物)は、ある日ミサで私に気づい
た。彼は礼拝の間ずっと私をじろじろ見ていた。そして、私用で話があるからと伝えた。私は彼の宮殿に連れて行かれ、自分の出生について彼に告げた。すると
彼は、自分がイスラエルの民の所有物であることがどれほど私の身分にふさわしくないかを指摘した。ドン・イサカルに、私を高位の異端審問官に引き渡すよう
申し出があった。宮廷の銀行家であり、多才な人物であるドン・イサカルは、そのようなことはしないことを選んだ。 「奉行は彼に異端審問をちらつかせた。ついに、私のユダヤ人はおびえ、 妥協案に同意した。それによれば、家屋と私は彼らの共有財産となり、ユダヤ人は月曜 日、水曜日、安息日を、奉行はその他の曜日を所有することになった。この取り決めは6か月間続いた。土曜と日曜の間の夜は、旧法(ユダヤ教の土曜)に属す るのか、それとも新法(キリスト教の日曜)に属するのかという点で、言い争いが絶えなかった。私のほうとしては、これまで両者に対して抵抗してきたが、そ れが理由で両者から今でも愛されているのは確かだ。 「最後に、さらなる地震の惨禍を回避し、ドン・イサカルを威圧するため に、異端審問官閣下は異端審問を行うことを快く承諾された。私を招待してくださっ た。私は素晴らしい席を用意していただいた。ミサと処刑の間には、女性たちに軽食が振る舞われた。」6 |
| And that’s where, to her horror,
she spotted Candide. While Cunegonde was telling him her story, Don Issachar walks into the house to find them alone. In a fit of protective rage, Candide kills him with a sword that the old woman swiftly handed him. Before Candide could even recover from his deed, the Inquisitor walks in. Candide kills him too. The three of them, Candide, his girl and the old woman, take their belongings and escape on horseback. The old woman was initially hesitant to ride because she said she has only one buttock. (More on this later.) In death, as in life, the Inquisitor received a different treatment from that of the Jew: |
そして、そこで彼女は恐ろしいことにカンディドを見つけた。 クネゴンデがカンディドに自分の身の上話をしていると、ドン・イサクァルが家に入ってきて、2人きりになる。カンディドは守るために怒りに駆られ、老婆が 素早く手渡した剣でドン・イサクァルを殺害した。カンディドが自分の行為から立ち直る間もなく、奉行が家に入ってきた。カンディドは奉行も殺害した。3人 (カンディド、その恋人、老女)は持ち物を持ち、馬に乗って逃げた。老女は当初、馬に乗ることをためらった。なぜなら、彼女には尻が1つしかないからだと 言ったからだ。(この件については後述する。)死においても、生においても、異邦人はユダヤ人とは異なる扱いを受けた。 |
| His
Eminence the Inquisitor was
buried in a beautiful church, and Don Issacar was thrown on to the town
refuse heap [a dunghill].7 |
審
問官は美しい教会に埋葬され、ドン・イサカーは町のゴミ捨て
場に投げ捨て |
| On their journey, they spent the
night at an inn, where Cunegonde’s jewels and money were stolen. In an
ironic twist, it seems like the thief belongs to a group whose members
vow to live in poverty for life: |
旅の途中、彼らは宿屋で夜を過ごしたが、そこでクネゴンデの宝石と金が
盗まれた。皮肉なことに、泥棒は生涯貧しい生活を送ることを誓ったグループのメンバーのようである。 |
| ‘Alas!’
said the old woman, ‘I
strongly suspect it was that reverend Franciscan who slept in the same
inn as us last night in Badajoz; God preserve me from making rash
Judgements, but he passed through our room twice and he set off long
before us.'8 |
「残
念だわ!」と老婆は言った。「昨夜バダホスで私たちと同じ宿屋に泊
まったのは、あのフランシスコ会の神父だったのではないかと強く疑っているの。軽率な判断をしないよう神に守られているけれど、彼は私たちの部屋を2度通
り過ぎて、私たちよりずっと前に出発したのよ。」8 |
| They sell one of the horses to
raise more money and decide to travel towards Cadiz, in Spain, where
there’s ships heading towards the New World (Buenos Aires is their
destination). Perhaps that New World of the Americas (that is, Latin
America) will prove to be truly the best of all possible worlds, which
many, back then, actually believed. Cunégonde is no longer certain that
things could be better, but the old woman admonishes her and tells her
basically “you’ve had it easy compared to me!” Then she started telling
her story: |
彼らは、さらなる資金を調達するために馬を1頭売り、新世界(彼らの目
的地はブエノスアイレス)に向かう船があるスペインのカディスに向かうことにした。おそらく、その新世界(つまりラテンアメリカ)は、当時多くの人が実際
に信じていたように、本当にあり得る世界の中で最も素晴らしい場所であることが証明されるだろう。クネゴンデは、もはや状況が良くなるとは思えなくなって
いたが、老婆は彼女を諭し、基本的に「あなたは私と比べればずっと楽だったのよ!」と言った。そして、彼女は自分の話を始めた。 |
| ‘I
did not always have
red-rimmed and bloodshot eyes; my nose did not always touch my chin,
nor was I always a servant. I am the daughter of Pope Urban X and the
Princess of Palestrina.'9 |
「私
はいつも赤く縁取られ、充血した目だったわけではない。私の鼻がい
つも顎に触れていたわけでも、召使だったわけでもない。私は教皇ウルバヌス10世とパレストリーナの王女の娘なのだ。」9 |
| (Although this pope is
fictitious, that line is a reference to the notorious religious
hypocrisy of some supposedly celibate popes who were either sexually
active or even promiscious. At least six of them fathered children
during the 15th and 16th centuries.) In her younger years, when she used to be gorgeous, she got engaged to a very handsome prince but his jealous mistress poisoned him. She and her mother set sail to a vacation estate for a mourning period in Gaeta, north of Naples under the protection of the Pope’s soldiers. (Yes, the Pope had an army that waged wars and forged treaties for hundreds of years.) |
(この法王は架空の人物だが、そのセリフは、独身のはずの法王の中に
は、性的関係を持つ者や、浮気者もいたという悪名高い宗教的偽善を指している。少なくとも6人の法王が、15世紀から16世紀にかけて子供をもうけた。) 若い頃、彼女が美しかった頃、彼女は非常にハンサムな王子と婚約したが、彼の嫉妬深い愛人が彼を毒殺した。彼女と母親は、ナポリの北にあるガエタの別荘地 へ出帆し、教皇の兵士の保護のもとで喪に服した。(そう、教皇は戦争を戦い、条約を偽造する軍隊を何百年も保有していたのだ。) |
| The
next moment a pirate ship
from Salé [a Moroccan port long associated with Moorish pirates] swept
down and boarded us. Our men defended themselves as the Pope’s soldiers
usually do: they all fell to their knees, threw down their weapons, and
begged the pirates to absolve them of their sins in articulo mortis‘.10 |
次
の瞬間、ムーア人の海賊と長年関わりのあるモロッコの港町サレから来
た海賊船が、我々の船に襲いかかり、乗り込んできた。我々の仲間は、ローマ教皇の兵士たちが通常するように身を守った。全員がひざまずき、武器を投げ捨
て、海賊たちに「死の危機に瀕しての罪の赦し」を求めた。10 |
| One of the most brilliant and
absurd moments in the book: Not only did the Pope’s soldiers act
cowardly, they also knelt before non-Christian criminals begging for
their in articulo mortis forgiveness (literally, at the moment of
death) which is a “sacrament” and a final act of penance that requires
a Catholic priest. |
この本の中で最も素晴らしく、かつ滑稽な瞬間の一つ:教皇の兵士たちは
卑怯な行動を取っただけでなく、キリスト教以外の犯罪者の前で跪き、彼らの「死の瞬間における」許し(文字通り、死の瞬間における)を乞うた。これは「聖
餐」であり、カトリック司祭を必要とする最後の懺悔行為である。 |
| ‘They
were promptly stripped
naked as monkeys, as were my mother, and our maids of honour, and I
myself… they then took each of us and inserted their fingers into that
orifice which we ladies usually reserve for an enema syringe [popular
and useless treatment to a range of illnesses from stomach ache to flu
symptoms]…I soon learned that its purpose was to discover if we had
hidden any diamonds there.'11 |
「彼
らはすぐに猿のように裸にされた。私の母や、私たちの付き添いの女
性たち、そして私もだ。そして、彼らは私たち一人一人を捕まえ、私たちが通常浣腸器(腹痛からインフルエンザの症状まで、さまざまな病気に効果があるとさ
れる一般的な治療法)を入れるために確保しているその穴に指を挿入した。私はすぐに、その目的が、私たちがそこにダイヤモンドを隠していないかどうかを見
極めることだと知った。」11 |
| The strip search was followed
with rape: (Note that the horrific crimes below have undertones that reveal common stereotypical views of foreigners. One could even describe them as racist however Voltaire’s views on race were complex as explained below in a scene with an African slave.) |
身体検査の後にレイプが続いた。 (以下の恐ろしい犯罪には、外国人に対する一般的なステレオタイプな見方を示すような含みがあることに注意してほしい。人種差別的と表現することもできる が、ヴォルテールの人種に関する見方は複雑であり、以下で説明するアフリカ人奴隷との場面で説明されている。) |
| ‘As for me, I was ravishing, I was beauty itself, grace incarnate – and a virgin to boot. Not for long, of course; this flower which had been reserved for the handsome Prince of Massa-Carrara, was plucked by the Corsair captain, an abominable negro, who of course believed he was doing me a great favour.'12 | 「私
としては、私はとても魅力的で、美そのものであり、優雅さの化身
だった。もちろん、長くは続かなかった。マッサ・カッラーラのハンサムな王子のためにとっておかれたこの花は、海賊の船長、忌まわしい黒人に摘み取られ
た。もちろん、彼は私にとても親切にしていると思っていた。」12 |
| The pirates took the captives to
sell them as slaves in Morroco, which was engulfed in a civil war, as
they found out upon disembarkment. Countless “horny African” men fought
the pirates over the women: |
海賊たちは捕虜たちをモロッコに奴隷として売り飛ばすつもりだったが、 上陸してみると、モロッコは内戦に巻き込まれていた。「性欲旺盛なアフリカ人」の男たちが、海賊たちと女たちを巡って争った。 |
| ‘Next to the
diamonds and gold,
we were the most precious part of his cargo. I was witness to a combat
the like of which would never be seen in your European climes.
Northerners do not have sufficiently hot blood. They do not have that
raging lust for women so common in Africa. … At length, I saw all our Italian maids and my mother cut to pieces, torn apart, massacred by the monsters who contended over them. My fellow captives, and their captors – soldiers, sailors, blacks, browns, whites, mulattos and finally my captain – all were dead; and I remained alone, dying under a heap of dead bodies. Similar scenes were taking place, as everyone knows, over an area of more than three hundred leagues, without anyone ever omitting to say their five daily prayers as required by Mahomet.'13 |
「ダ
イヤモンドや金塊に次いで、私たちは彼の積荷の中で最も貴重な品
だった。私は、ヨーロッパでは決して見られないような戦闘を目撃した。北方人には熱い血が流れていない。アフリカではよく見られるような、女性に対する激
しい欲望もない。.. . ついに、私たちのイタリア人メイドたちと私の母が、争う怪物たちによっ て切り刻まれ、引き裂かれ、虐殺されるのを見た。捕虜となった仲間たち、そして彼ら を捕らえた者たち、すなわち兵士、水兵、黒人、褐色人、白人、混血、そして最後に私の船長も、全員が死んだ。そして私は、死体の山の下で死にかけながら、 ひとり取り残された。周知の通り、同様の光景が300リーグ以上の広範囲にわたって繰り広げられたが、誰もが1日5回の礼拝を怠ることはなかった。 |
| (Voltaire here makes the same
point he made above that there is no connection between following
religious practice and being a good person. He’s using satire to show
that often Muslims, like Christians, are guilty of religious hypocrisy.) Eventually, after the battle was over, she came back to consciousness: |
(ここでヴォルテールは、宗教的慣習に従うことと善良であることの間に
関連性はないという、前述の主張と同じことを述べている。彼は風刺を用いて、しばしばイスラム教徒はキリスト教徒と同様に宗教的な偽善の罪を犯しているこ
とを示している。) 結局、戦いが終わった後、彼女は意識を取り戻した。 |
| ‘I
was in this state of
feebleness and insensibility, hovering between life and death, when I
felt the pressure of something rubbing up and down on my body. I opened
my eyes; I beheld a white man, rather attractive, who was moaning on
top of me and muttering through clenched teeth: O che sciagura d’essere
senza coglioni! [Oh, what a shame to be without testicles!]'14 |
「私
はこのとき、生命と死の狭間をさまようような衰弱と無感覚の状態に
あった。そのとき、何かが私の体を上下にこすっているような圧力を感じた。私は目を開けた。私の体の上でうめき声を上げながら、歯を食いしばって『O
che sciagura d’essere senza coglioni!
[ああ、なんて恥ずかしいんだ、睾丸がないなんて!]』と呟いている、かなり魅力的な白人男性が目に入った。」14 |
| (The man attempting to rape her
is one of the Italian castrati, the unfortunate choirboys dedicated to
the Catholic Church at a young age and castrated before puberty in
order to preserve their high pitch voice.) Despite the attempted rape, the woman is delighted to meet a fellow countryman! He carries her to his cottage to look after her. He promises to take her back to Italy, but instead he travels to Algiers (Algeria) where he sells her to the governor as a concubine. The bubonic plague sweeps though the region killing the governor and the eunuch. But doesn’t bring her freedom because she’s captured and sold several times. She ends up in the harem of a Muslim military commander who travels everywhere with his concubines. The commander, being from Algiers which was part of the expansive Ottoman Empire, had to follow orders and travel to fight with the Turks (the Ottomans are Turks) against Russians attacking the city of Azov. (Today Azov is part of Russia which is a clue to the outcome of the historically accurate battles and horrific siege which lasted from 1695 to 1697.) At one point in the woman’s story, she says the Russians destroyed the whole city and only their fort was left standing. While under siege and in the grip of starvation, they killed two eunuchs and ate them. (Eunuchs were not unique to Christian Europe: They had a constant presence in Ottoman harems.) Then as they were about to kill the women, an imam (a Muslim cleric) intervened: |
(彼女をレイプしようとした男は、イタリアのカストラート
(castrato)の一人である。カストラートとは、幼少時にカトリック教会に献身し、思春期前に去勢されて高い音域の声を維持する不運な少年聖歌隊員
のことである。) 強姦未遂にもかかわらず、女性は同胞に会えて大喜び! 彼は彼女を介抱するために自分の小屋に彼女を運び、イタリアに連れ戻すことを約束するが、その代わりにアルジェ(アルジェリア)に旅立ち、彼女を総督の妾 として売り渡す。 ペストがその地域を襲い、知事と宦官が死亡した。しかし、彼女は捕らえられ何度も売られたため、自由を手に入れることはできなかった。彼女は、愛妾たちを 連れてあちこちを旅するイスラム軍司令官のハーレムに送られた。司令官はアルジェ出身で、アルジェは広大なオスマン帝国の一部であったため、命令に従って アゾフ市を攻撃するロシア軍と戦うためにトルコ人(オスマン帝国はトルコ人)とともに戦うために旅をしなければならなかった。(今日、アゾフはロシアの一 部であり、1695年から1697年まで続いた歴史的に正確な戦いと恐ろしい包囲戦の結果を暗示している。) ある時点で、彼女の話では、ロシア軍が町全体を破壊し、彼らの砦だけが残ったという。包囲され飢えに苦しむ中、彼らは2人の宦官を殺して食べた。(宦官は キリスト教のヨーロッパ特有の存在ではなく、オスマン帝国のハーレムには常に存在していた。)そして、女性たちを殺そうとしたとき、イマーム(イスラム教 の聖職者)が介入した。 |
| ‘We
had a very pious and
compassionate imam, who delivered an excellent sermon persuading them
not to kill us outright. “Cut off one buttock,” he said, “from each of
these ladies, and you will be well provided for; if you have to come
back for more in a few days’ time, you can take as much again; heaven
will smile on so charitable an action, and you will be rescued.”‘ ‘He was all eloquence; they were convinced; and we were subjected to this dreadful operation. The imam applied to our wounds the ointment they use on boys who have just been circumcised. We were all at death’s door.'15 |
「私
たちはとても信心深く慈悲深い導師に恵まれていた。彼は素晴らしい
説教を行い、私たちをすぐに殺さないよう説得した。「これらの女性たちの尻を片方ずつ切り落とせ。そうすれば、お前たちは十分に満足できるだろう。数日後
にまた戻って来なければならない場合は、また好きなだけ取っていい。天国はこのような慈悲深い行為に微笑み、お前たちは救われるだろう」と彼は言った。 彼は雄弁だった。彼らは納得した。そして、私たちはこの恐ろしい手術を 受けることになった。導師は、割礼を受けたばかりの少年に使う軟膏を私たちの傷に 塗った。私たちは皆、死の淵をさまよっていた。 |
| After their lives were spared
and they were “mercifully” mutilated, the Russians attacked and killed
all the soldiers. She, along with the other women, were taken to Moscow
where she became a slave. Later, she managed to escape. At that point
in her storytelling the ship approaches Buenos Aires. After the ship is
docked, they visit the governor who was taken by the beauty of
Cunégonde. He asks Candide if they were married. |
命を助けられ、「慈悲深く」身体を傷つけられた後、ロシア人たちは全員
の兵士を攻撃し、殺害した。彼女は他の女性たちとともにモスクワに連れて行かれ、そこで奴隷となった。その後、なんとかして脱出に成功した。彼女の物語の
その時点まで船はブエノスアイレスに近づいていた。船が停泊した後、彼らはクネゴンデの美しさに魅了された知事を訪問した。知事はカンディドに結婚したか
どうか尋ねた。 |
| The
manner with which he asked
the question disturbed Candide, who dared not say yes, for she was not
in fact his wife, and who neither dared to call her his sister, for she
was not that either; and although this white lie was once very
fashionable among the Ancients, and could still have its uses for the
Moderns, his heart was too pure to betray the truth.16 |
彼
が質問した方法にカンディドは動揺した。彼は、実際には彼女は自分の
妻ではないので、あえて「はい」とは言えなかった。また、彼女は自分の妹でもないので、あえて「妹」と呼ぶこともできなかった。この小さな嘘は、かつて古
代の人々には非常に流行っていたし、現代人にとってもまだ役に立つかもしれないが、彼の心は真実を裏切るには純粋すぎた。16 |
| (“The Ancients” is a cunning
remark aimed at mocking biblical morality where both Abraham and Isaac
in different stories lied about their wives and claimed they’re their
sisters – Genesis 12:13 and Genesis 26:7.) Candide naïvely tells the truth that he intends to marry her one day. So the governor then sends him away on a mission, then offers to marry Cunégonde. The old woman advises her to do so to acquire wealth – not easy to resist such advice when you’re completely broke. In the meantime, the Franciscan friar tried to sell the jewels stolen from the main characters but officials recognize they belong to the murdered Grand Inquisitor. He gets executed but not before he makes a confession on whom he stole the jewels from. Now Portuguese officials are in town seeking to arrest the murderers of the Inquisitor. The old woman assures Cunégonde not to worry since the governor will protect her, but Candide should flee immediately. Candide and his servant, Cacambo, escape to a nearby Jesuit camp. Candide finds out that the colonel of the camp is the brother of Cunégonde, who actually survived the attack. Her brother is surprised to know from Candide that she, too, survived. Then he started telling of the misfortunes he experienced to Candide and how he ended up as a Jesuit in the Americas. He hints of a homosexual attraction as the reason behind a priest taking him into the religious order. |
(「The
Ancients」は、聖書の道徳性をあざける巧妙な表現である。創世記12:13と創世記26:7では、アブラハムとイサクの両方が妻について嘘をつ
き、彼女たちは自分の妹だと主張している。) カンディドは、いつか彼女と結婚するつもりだと、無邪気に真実を告げる。そこで総督は彼を任務に送り出し、クネゴンデとの結婚を申し出る。老女は、富を得 るためにそうするよう彼女に助言する。一文無しの状態では、そうした助言に抵抗するのは容易ではない。 一方、フランシスコ会の修道士は、主要登場人物から盗んだ宝石を売ろうとしたが、役人たちはそれが殺害された大審問官の所有物であると見抜いた。彼は処刑 されたが、宝石を盗んだ相手について告白する前にそうなることはなかった。今、ポルトガルの役人たちが町にいて、大審問官を殺害した犯人の逮捕を求めてい る。老女はクネゴンデに、知事が彼女を守ってくれるので心配ないが、カンディドはすぐに逃げた方が良いと保証した。 カンディドと召使のカカンボは近くのイエズス会の野営地に逃げ込んだ。カンディドは、野営地の隊長がクネゴンデの兄であり、実は襲撃から生き延びていたこ とを知る。彼女の兄は、カンディドからクネゴンデも生き延びたことを知らされ驚く。そして、カンディドに自分が経験した不幸について語り、自分がどうして アメリカ大陸のイエズス会士になったかを語り始めた。司祭が彼を修道会に入れた理由として、同性愛的な魅力があったことをほのめかした。 |
| You
will recall, my dear
Candide, how pretty I was; well I became even more so, to the point
that the Reverend Father Croust, who was Superior of the community,
conceived the most tender affection for me; he initiated me as a
novice.17 |
思
い出すだろう、親愛なるカンディードよ、私がどれほど可愛かったか
を。私はさらに可愛くなった。修道院長であるクルースト神父が、私に対して最も優しい愛情を抱くほどに。彼は私を新米として迎え入れた。17 |
| (Again, Voltaire is condemning
the hypocricy of priests and monks who vow celibacy yet engage in
scandalous affairs within the walls of their churches and monasteries.) Now that the father is dead, Cunégonde’s brother is the new baron, so Candide made a request: |
(繰り返すが、ヴォルテールは独身を誓いながら、教会や修道院の壁の中
でスキャンダラスな関係を持つ司祭や修道士たちの偽善を非難している。) 父親が亡くなった今、クネゴンデの弟が新しい男爵となったため、カンディードは頼みごとをした。 |
| ‘That
is all I could wish for…I
was intending to marry [Cunégonde], and hope to do so still.’ ‘What an extraordinary piece of insolence!’ retorted the Baron. ‘So you would have the effrontery to marry my sister, who has seventy-two quarterings on her coat of arms! I consider it highly presumptuous of you to dare to speak to me of so rash an intention!’ Candide, whose blood turned cold at this outburst, replied: ‘Reverend Father, all the quarterings in the world make no difference; I have rescued your sister from the arms of a Jew and an Inquisitor; she has certain obligations towards me, and she wishes to marry me. Maitre Pangloss always told me that all men are equal; you may depend on it that I shall marry her.’ ‘We shall see about that, you dog!’ said the Jesuit Baron of Thunder-ten-tronckh, and with these words struck him a great blow across the face with the flat of his sword. Candide instantly drew his own sword and plunged it up to the hilt in the Jesuit Baron’s belly; as he withdrew it, all steaming, he began to weep.18 |
「そ
れが私の望みです。私はクネゴンデと結婚するつもりでしたし、今で
もそうしたいと思っています」 「なんと厚かましいことを言うのだ!」と男爵は言い返した。「私の姉と 結婚する厚かましさだというのか!姉の紋章には72もの家紋が描かれているのだぞ! そんな無謀な考えを私に話すとは、君は思い上がりも甚だしい!」 この暴言に血の気が引いたカンディドは答えた。「神父様、世の中の家紋 の数など関係ありません。私はユダヤ人と異端審問官の腕の中からあなたの妹を救い出 しました。彼女には私に対する義務があり、私と結婚したいと思っているのです。パンロス先生はいつも、人は皆平等だと言っておられました。私は必ず彼女と 結婚します。 「それはどうかな、この犬め!」とイエズス会のサンダー=テン=トロン コ男爵は言い、そう言って剣の平で彼の顔を強打した。カンディドは即座に自分の剣を 抜き、イエズス会の男爵の腹に剣を柄まで突き刺した。熱い蒸気が立ち上る剣を引き抜くと、彼は泣き出した。18 |
| (Poverty is one of three vows
the Jesuits take. The others are obedience and chastity. As clear from
the story, many of them have trouble keeping the at least two of the
three. As obvious from the above passage, even though the brother was a
Jesuit priest, a world away from Europe’s class structure, he still
views Candide, who rescued his sister from sexual servitude, as too
inferior to marry her. Money, status and aristocratic superiority were
still of higher value than his own Jesuit vows or Candide’s gracious
character.) |
(イエズス会士が誓いを立てる3つの誓いのうちの1つが「貧困」であ
る。残りの2つは「服従」と「貞潔」である。物語からも明らかなように、彼らの多くは3つの誓いのうち少なくとも2つを守ることに苦労している。上記の文
章からも明らかなように、この修道士はイエズス会の司祭であり、ヨーロッパの階級制度とはかけ離れた世界にいたにもかかわらず、妹を性的な隷属状態から
救ったカンディドを、妹と結婚するにはあまりにも劣っていると見なしている。金銭、地位、貴族的な優越性は、彼自身のイエズス会の誓いやカンディデの気品
ある性格よりも、依然として高い価値を持つものだった。 |
| History Spotlight: What are the
seventy-two quarterings the younger baron is bragging about? Sixteen Quarterings (Seize Quartiers) refers to a coat of arms with sixteen partitions demonstrating four generations of pure noble ancestry, meaning not a single commoner between themselves and their 16 great-great-grandparents. It was considered the ultimate and hardest-to-obtain proof of pure blood. (View a visual example of a genealogy with sixteen quarterings.) Therefore, Cunégonde’s seventy-two quarterings is a ridiculously high number, and a joke at the expense of aristocratic families. It gets more absurd: Candide’s supposed inferiority, as perceived by Cunégonde’s family, is due to his lack of proof for more than seventy-one quarterings! |
歴史クイズ:若き男爵が自慢している72のクォータリングとは何だろう
か? 16のクォータリング(Seize Quartiers)とは、4世代にわたる純粋な貴族の家系を示す16の仕切りがある紋章を指し、自分たちと16人の曾曾祖父母との間に平民は一人もいな いことを意味する。それは純血の究極かつ最も取得困難な証とされていた。(16分割の家系図の例を見る)したがって、クネゴンダの72分割は途方もなく高 い数字であり、貴族階級を揶揄するような数字である。さらに、クネゴンダの家族がカンディドの劣等性とみなしているのは、彼が71分割以上の証明を欠いて いるからだ。 |
Cacambo walks in on the murder
scene. He dresses Candide in the Colonel’s habit and they flee. Then
they end up in a strange territory where they encounter “ass-biting
monkeys”: |
カカンボが殺人現場に踏み込む。彼は大佐の衣装をカンディドに着せ、2
人は逃亡する。そして、彼らは奇妙な土地にたどり着き、「お尻をかじる猿」と遭遇する。 |
| The
shrieks were coming from two quite naked girls, who were tripping
lightly along the edge of the meadow, pursued by a pair of apes
snapping at their bottoms. … So [Candide] now raises his double-barrelled Spanish rifle, fires and kills both apes. ‘God be praised, my dear Cacambo! I have delivered these two poor creatures from grave peril.’ … ‘Master; you have just despatched [killed] the two lovers of these young ladies…. Why do you find it so strange that in some countries it is apes who enjoy the favours of young ladies? After all, they are one-quarter human.'19 |
悲
鳴は、草原の縁を軽やかに歩いていた、ほとんど裸の二人の少女から聞こえてきた。二匹の猿が尻尾を振りながら追いかけている。 ... そこで、[カンディード]は二連銃身のスペイン製ライフル銃を構え、発 砲して二匹の猿を殺した。 「神に感謝しよう、親愛なるカカンボ!私はこの二匹の哀れな生き物を重 大な危険から救ったのだ。」 ... 「ご主人様、あなたは今、若い女性たちの恋人たちを殺してしまったので すよ。 なぜ、ある国々では若い女性たちに愛されているのが猿であることがそん なに不思議なのですか? 結局、彼らは人間の4分の1なのですから。」19 |
| (This is a bizarre story that
makes you wonder what purpose it might serve. Beyond being enigmatic it
also poses a problem regarding who the monkeys represent. Do they stand
for an “inferior” racial group at a time when theories of ethnic
hierarchy were commonly accepted? Or should we take the story at face
value that they are just that, monkeys, meaning they’re in the same
category with humans? There is evidence that the latter might be more
plausible considering that long before Darwin’s theory of Evolution
(1859), scientists controversially pointed to similarities between
humans and apes. That comparison was made by British scientist Edward
Tyson, 1651–1708, and in the 1735 book Systema Naturae by Carl
Linnaeus, 1707–1778.) They find a place to hide and fall asleep. But the tribe to which the two girls belong finds them: |
(これは、それが何の目的を果たすのか疑問に思わせる奇妙な話である。
不可解であるだけでなく、サルが何を象徴しているのかという問題も提起している。人種階層説が一般的に受け入れられていた時代に、サルは「劣った」人種を
象徴しているのだろうか?
それとも、サルはサルであり、人間と同じカテゴリーに属するという、この話の表面的な意味をそのまま受け取るべきなのだろうか?後者の説の方がより妥当で
ある可能性が高いことを示す証拠がある。ダーウィンの進化論(1859年)よりもずっと以前から、科学者たちは物議を醸しながらも人間と類人猿の類似性を
指摘していた。その比較を行ったのは、英国の科学者エドワード・タイソン(1651年~1708年)と、カール・フォン・リンネ(1707年~1778
年)の著書『Systema Naturae』(1735年)である。 彼らは隠れる場所を見つけて眠りにつく。しかし、2人の少女が属する部族が彼らを見つける。 |
| When
they awoke they found they were unable to move their limbs; the
explanation for which was that the Oreillon tribe…had tied them down
during the night with ropes made of bark. They were now surrounded by
fifty or so stark-naked Oreillons, armed with arrows, clubs and flint
axes: some were bringing a large cauldron to the boil; others were
preparing spits, and all of them were chanting: ‘It’s a Jesuit! It’s a
Jesuit! We will be avenged! And we’ll eat our fill! Let’s eat Jesuit!
Let’s eat Jesuit!’ … ‘Don’t despair,’ [Cacambo, who’s of mixed ethnicity] said to the dejected Candide. ‘I am familiar with the gibberish these people speak. I will address them.’ ‘Be sure to impress upon them,’ said Candide, ‘how frightful and inhuman it is to cook people alive, and how very unchristian.'20 |
彼
らが目を覚ますと、手足が動かせないことに気づいた。その説明によると、オレイヨン族が…夜の間、樹皮でできたロープで彼らを縛り付けていたのだという。
彼らは今、矢や棍棒、火打ち石斧で武装した、全裸のオレイヨン族50人ほどに囲まれていた。ある者は大きな釜を沸騰させ、またある者は串を用意し、皆で合
唱していた。「イエズス会だ!イエズス会だ!復讐してやる!思う存分食らってやる!イエズス会を食らうぞ!イエズス会を食らうぞ!」 ... 「落胆するな」と、落ち込んでいるカンディドに混血のカカンボが言っ た。「私は彼らの話す意味不明の言葉に精通している。私が彼らに話しかけるよ」 「彼らに、人を生きながら料理するなんて、なんと恐ろしく非人間的なこ とか、そして、なんとキリスト教らしくないことかを、しっかりと伝えてくれ」とカンディドは言った。20 |
| In their own native language,
Cacambo is able to convince them of the mistaken identity and that
Candide is not a Jesuit but a killer of one. They’re shown hopitality
after. (Note how our naïve hero would like the tribe to know that it’s unchristian to be cannibals yet most likely they’re not Christians! Voltaire intended with this story to attack the common view of the “noble savage” regarding the natives and to show the’re capable of violence – and worse, like cannibalism – just like other Europeans in the story. Soon after the publication of Candide, “Let’s eat Jesuit!” – Mangeons du Jésuite! – became proverbial with the French public whose hostility to the group increased to the point of expulsion in 1764.) They continue on their journey and they come across a utopian village, Eldorado, where the streets are paved with gold. They meet the oldest man in the village: |
彼らの母国語であるカカンボ語で、カカンボは彼らに誤認を説得し、カン
ディドがイエズス会士ではなく、イエズス会士殺しであることを納得させる。その後、彼らは歓待を受ける。 (純真な主人公が、その部族の人々に、人食いはキリスト教徒らしくないことだと知ってほしいと思っているが、おそらく彼らはキリスト教徒ではないだろ う!)ヴォルテールは、この物語で、原住民に対する一般的な見方である「高潔な野蛮人」という考えを攻撃し、彼らにも暴力を振るう能力があること、さらに 悪いことに、人食いのような行為も行うことを示そうとした。『カンディード』の出版後まもなく、「イエズス会を食べよう!」(Mangeons du Jésuite!)という言葉がフランス国民の間でことわざとなった。イエズス会に対する敵意は高まり、1764年には追放されるまでに至った。 彼らは旅を続け、通りが金で舗装された理想郷エルドラド村にたどり着く。そこで彼らは村で最高齢の老人に出会う。 |
| 「私
の友人たち」と彼は言った。「私たちは皆司祭だ。王と各家の長は、毎朝5、6千人の音楽家の伴奏で厳粛な感謝の賛美歌を歌うのだ。」 「なんと! 修道士たちが教えたり、議論したり、支配したり、陰謀を企てたり、自分たちの意見に賛成しない者を皆生きたまま焼いたりしていることはないのか?」 「我々は本当に愚か者でなければなりません」と老人は言った。「ここでは誰もが同じ考えであり、修道士についてあなたが言っていることが想像できませ ん。」21 |
「私
の友人たち」と彼は言った。「私たちは皆司祭だ。王と各家の長は、毎朝5、6千人の音楽家の伴奏で厳粛な感謝の賛美歌を歌うのだ。」 「なんと! 修道士たちが教えたり、議論したり、支配したり、陰謀を企てたり、自分たちの意見に賛成しない者を皆生きたまま焼いたりしていることはないのか?」 「我々は本当に愚か者でなければなりません」と老人は言った。「ここで は誰もが同じ考えであり、修道士についてあなたが言っていることが想像できません。」21 |
| (Here Voltaire criticizes his
own society by presenting the perfect world in his view: relative
equality, appreciation for science, no greed, nor religious persecution
or bigotry, and every night they worship God in unison and harmony.
Perhaps Voltaire knows that this place could never exist because it’s
one where all people agree on and believe in the same things.) Candide and Cacambo loaded 102 sheep with “pebbles” of gold collected off the side of the road in Eldorado then our hero (or, rather, anti-hero) started to dream of having his own kingdom. Next destination on their journey was Surinam, a Dutch Colony…  |
(ここでヴォルテールは、相対的な平等、科学への理解、強欲さや宗教的
迫害や偏見のないこと、そして毎晩、人々は一致団結して神を崇拝する、という彼の見解における完璧な世界を提示することで、自らの社会を批判している。お
そらくヴォルテールは、人々が皆同じことを信じ、同意する場所などありえないことを知っていたのだろう。) カンディドとカカムボは、エルドラドの道端で拾った金の「小石」を102匹の羊に積んだ。そして、主人公(というよりはアンチ・ヒーロー)は、自分の王国 を持つという夢を抱き始めた。彼らの旅の次の目的地は、オランダ領スリナムだった。  |
| As they drew
near to the city, they came across a negro stretched out on the ground,
with no more than half of his clothes left, which is to say a pair of
blue canvas drawers; the poor man had no left leg and no right hand. ‘Good God!’ said Candide to him in Dutch. ‘What are you doing there, my friend, in such a deplorable state?’ ‘I am waiting for my master, Monsieur Vanderdendur, the well-known merchant,’ answered the negro. ‘And was it Monsieur Vanderdendur,’said Candide, ‘who treated you like this?’ ‘Yes, Monsieur,’ said the negro, ‘it is the custom. Twice a year we are given a pair of blue canvas drawers, and this is our only clothing. When we work in the sugar-mills and get a finger caught in the machinery, they cut off the hand; but if we try to run away, they cut off a leg: I have found myself in both situations. It is the price we pay for the sugar you eat in Europe. Yet when my mother sold me for ten Patagonian écus [Spanish American coins] on the coast of Guinea, she told me: “My child, give thanks to our fetishes [sacred objects worshiped in tribal societies], and worship them always, for they will make your life happy; you have the honour to be a slave to our white masters, and therefore you are making the fortune of your father and mother.” Alas! I don’t know if I made their fortune, but they certainly didn’t make mine. Dogs, monkeys and parrots are a thousand times less miserable than we are; the Dutch fetishes [a reference to Protestant missionaries] who converted me to their religion tell me every Sunday that we are all children of Adam, whites and blacks alike. I am no genealogist; but if these preachers are telling the truth, then we are all second cousins. In which case you must admit that no one could treat his relatives more horribly than this.’ ‘Oh Pangloss! [addressing his absent mentor]’ cried Candide. ‘This is one abomination you could not have anticipated, and I fear it has finally done for me: I am giving up on your Optimism after all.’ ‘What is Optimism?” asked Cacambo ‘Alas!’ said Candide, ‘it is the mania for insisting that all is well when all is by no means well.’ And he wept as he looked down at his negro, and was still weeping as he entered Surinam.22I |
彼
らが町に近づくと、地面に横たわっている黒人に出くわした。その黒人の服は半分しか残っておらず、つまり青いキャンバス地のパンツ一枚だけだった。その貧
しい男には左足も右手もなかった。 「なんてことだ!」と、オランダ語で彼に言った。「こんなひどい状態 で、そこで何をしているんだい?」 「私は主人を待っているんです、ヴァンデルデンドゥールさんという名 の、有名な商人を」と、その黒人は答えた。 「そして、ヴァンデルデンドゥールさんが、あなたをこんな風に扱ってい るの?」と、カンディドは尋ねた。 「はい、旦那様」と黒人は答えた。「それが習慣なのです。年に2回、青 いキャンバスのズボンを一組もらえるのですが、それが唯一の衣服なのです。砂糖工場で働いていて機械に指を挟まれたら、手を切り落とされます。しかし、逃 げようとしたら足を切り落とされます。私は両方の状況を経験しました。それが、あなたがたがヨーロッパで食べる砂糖の代償なのです。しかし、ギニアの海岸 で、母が私を10パタゴニア・エキュ(スペイン領アメリカのコイン)で売ったとき、母は私にこう言った。「子供よ、私たちのフェティッシュ(部族社会で崇 拝される神聖な物体)に感謝し、常に崇拝しなさい。彼らはあなたの人生を幸せにしてくれるでしょう。あなたは白人の主人たちの奴隷になる名誉を得ました。 そして、それゆえに、父と母の財産を作っているのです。」ああ、残念なことに!私が彼らの財産を増やしたかどうかはわからないが、彼らが私の財産を増やし たことは確かだ。犬や猿やオウムは、私たちよりも千倍も不幸ではない。私を彼らの宗教に改宗させたオランダのフェティッシュ(プロテスタントの宣教師)た ちは、毎週日曜日に、白人であろうと黒人であろうと、私たちは皆アダムの子供たちだと言う。私は系図学者ではないが、もしこの説教師たちが真実を語ってい るのであれば、私たちは皆、従兄弟同士ということになる。その場合、誰も自分の親戚をこれほどひどく扱うことはできないと認めざるを得ないだろう。 「ああ、パングロス![不在の師に呼びかける]」と、カンディドは叫ん だ。「これは君が予想できなかった忌まわしいことだ。そして、ついに私は君の楽観主義に見切りをつけた。 「楽観主義とは何ですか?」とカカムボが尋ねた。 「ああ!」とカンディドは言った。「すべてが順調であると主張する狂気 だ。」そして、彼は黒人を見下ろしながら泣き、スリナムに入ってもまだ泣いていた。22I |
| This somber encounter with a
mutilated slave could be considered the most powerful and important
scene of the book. The conditions of slavery were so cruel that
Voltaire thought it inappropriate to use his typical dark humour found
in other scenes where, for example, Candide gets human excrement dumped
on his head or the old woman has one of her buttocks cut off and eaten. (Up to that point, Candide, being overwhelmed with misfortunes, had been oscillating between two views : “all for the best,” as taught by Dr. Pangloss and “this is a cruel, unjust world.” However, only at this epiphanic moment standing before a slave, he announces his rejection of optimism, at least for now.) |
この、傷ついた奴隷との陰惨な出会いは、この本の最も力強く重要な場面
であると考えられる。奴隷制度の状況があまりにも残酷であったため、ヴォルテールは、例えば、カンディドが人間の排泄物を頭に浴びせられたり、老婆が片方
の臀部を切り落とされて食べられたりする他の場面に見られるような、彼の典型的なブラックユーモアを使うのは不適切だと考えた。 (それまでは、不幸に打ちひしがれていたカンディドは、パンゴラス博士の教えである「すべては最善である」と「これは残酷で不公平な世界だ」という2つの 見解の間で揺れ動いていた。しかし、奴隷の前に立ったこの瞬間、彼は少なくとも現時点では楽観主義を拒絶すると宣言した。) |
| Candide sends Cacambo alone to
retrieve Cunégonde and the old woman and bring them to Venice where
they’ll all meet. He finds a man to take him to Venice who happens to
be the owner of the slave. He turns out to be a swindler who promises a
trip on his ship to Candide but after the latter puts his sheep on his
ship, loaded with riches, he sails away. Back in the city, he tries to
pursue a legal solution by complaining to a judge but he is not taken
seriously. He eventually finds another ship sailing to France which he
boards along with a miserable, hopeless companion named Martin. As the French coast came into view Candide asks Martin about his travels: |
カンディドはカカンボを単独でクネゴンデと老女を連れ出し、ヴェネツィ
アで合流するよう命じる。彼はヴェネツィアに連れて行ってくれる男を見つけ、その男が偶然にも奴隷の所有者だった。その男は詐欺師で、カンディドに自分の
船で旅をさせてくれると約束したが、カンディドが船に財産を積んだ羊を乗せると、船は出航してしまった。街に戻った彼は、判事に訴えて法的解決を試みる
が、相手にされない。やがて、フランス行きの船を見つけ、マーティンという名の気の毒な、絶望的な仲間とともにその船に乗り込む。 フランス沿岸が見えてきたとき、カンディードはマーティンに旅のことを尋ねた。 |
| ‘But
have you been to Paris,
Monsier Martin?’ ‘Yes, I’ve been to Paris… I stayed there only briefly; on my arrival I was robbed of all I had by pickpockets at the Saint-Germain fair; I was then taken for a thief myself, and spent eight days in prison…I came to know all sorts of rabble – the hacks and scribblers, the political intriguers, and the holy rabble who trade in religious convulsions. I am told there are some civilized people in that city; I should like to think so.'23I |
「し
かし、あなたはパリに行ったことがありますか、マルタンさん?」 「ええ、パリには行ったことがあります。滞在期間は短かったのですが、 到着早々、サンジェルマン広場でスリに全財産を盗まれ、さらに自分が泥棒と間違えら れて8日間も牢屋に入れられてしまいました。その都市には文明的な人々もいると聞いている。そうであってほしいものだ。』23I |
| After their ship arrives in
France, the two men decide to visit Paris where they meet an abbé, a
clergyman who might or might not be consecrated. (Through his
character, Voltaire will provide yet another example for the immorality
of Church clergy.) The abbé introduces the visitors to a woman who
insists on being called the Marchioness of Parolignac. She seduces
Candide into her dressing room and they have sex, after which he feels
remorseful because in his heart, he feels he belongs only to Cunégonde.
Then the abbé tricks him out of his gold and diamonds. By the time he
and Martin realize they have been duped, an officer arrives, at the
request of the abbé, to arrest them for being “suspicious strangers.”
They bribe the officer and flee on a ship to England. Then they had another travel-related conversation: |
船がフランスに到着すると、2人はパリを訪れることにし、そこで叙階さ
れているかもしれないし、されていないかもしれない司祭であるアベに出会う。(ヴォルテールは、この司祭のキャラクターを通して、教会聖職者の不道徳さに
ついて、また新たな例を挙げることになる。)アベは、訪問者たちに、パルリニャック侯爵夫人と名乗る女性を紹介する。彼女はカンディドを楽屋に誘い込み、
2人はセックスをする。カンディドは、心の中ではクネゴンデだけのものであると感じていたため、後悔の念に駆られる。その後、司祭はカンディドから金とダ
イヤモンドをだまし取る。カンディドとマルタンが騙されたことに気づいたときには、司祭の依頼を受けた役人が「疑わしい見知らぬ者」として2人を逮捕する
ために到着していた。彼らは役人に賄賂を渡し、船でイギリスに逃亡する。 それから、彼らはまた旅行に関する会話をした。 |
| ‘You
have been to England,’ said Candide. Are they, as mad there as in
France?’ ‘It’s a different type of madness, said Martin. As you know, the two countries are at war over a few acres of snow on the Canadian border, and they are spending rather more on their lovely war than the whole of Canada is worth.'24  While the ship was docked at a port in England, he witnesses an execution. He asked… |
「君はイギリスに行ったことが
あるのか」とカンディドが言った。「あそこはフランスと同じくらい狂気じみたところなのか?」 「それはまた違った種類の狂気だよ」とマーティンが言った。「ご存じのように、この2つの国はカナダ国境の雪の幾エーカーを巡って戦争中なんだ。そして、 その美しい戦争にはカナダ全土の価値を上回るほどの費用が投じられているんだ」24  船がイギリスの港に停泊している間、彼は処刑の現場を目撃した。彼 は尋ねた... |
| ‘And
why kill this admiral?’ ‘Because,’ came the reply, ‘he did not get enough people killed when he had the chance: he gave battle to a French admiral, and was said not to have engaged closely enough with the enemy.’ ‘In which case,’ said Candide, ‘surely the French admiral was just as far from the English admiral as the English admiral was from the French admiral?’ ‘Unquestionably so,’ came the reply, ‘but in this country it is considered useful now and again to shoot an admiral, to encourage the others.'25Ib |
「そ
れに、なぜこの提督を殺す必要があるのか?」 「なぜなら」と返事が返ってきた。「彼はチャンスがあったのに十分な数 の兵士を死なせなかった。彼はフランス提督と戦い、敵と十分に戦わなかったと言われている。 「それなら」とカンディードは言った。「確かに、フランス提督はイギリ ス提督から遠く離れていたのと同じくらい、イギリス提督もフランス提督から遠く離れていたということではないか?」 「確かにその通りだ」と返事が返ってきた。「しかし、この国では、他の 者たちを鼓舞するために、時折提督を撃つことが有益だと考えられているのだ」25Ib |
| Out of disgust with this
injustice, he decides not to set foot in England and requested that the
Captain continue sailing to Venice where he’s certain he’ll reunite
with Cunégonde. After a few months in Venice, he still couldn’t find his beloved and became depressed. One day he meets a seemingly happy couple, one of whom is a monk (another promiscuous friar). The woman turned out to be the former mistress of Pangloss who infected him with Syphilis. After a series of misfortunes, she had to resort to prostitution to support herself. It turns out that the monk is only one of her clients and she’s actually far from happy: |
この不公平に対する嫌悪感から、彼はイギリスに足を踏み入れることをや
め、船長にヴェネツィアまで航海を続けるよう依頼した。そこなら、クーネゴンと再会できると確信していたのだ。 数か月間ヴェネツィアに滞在したが、それでも愛する人を見つけることはできず、彼は落ち込んでいた。ある日、彼は一見幸せそうなカップルに出会った。その うちの一人は修道士(また別の放蕩修道士)だった。その女性はパングロスの元愛人で、彼に梅毒を感染させた張本人だった。不幸な出来事が続いた後、彼女は 生活費を稼ぐために売春に頼らざるを得なかった。その修道士は彼女の客の一人に過ぎず、実際には彼女は幸せとは程遠い生活を送っていた。 |
| ‘But
you looked so gay, so happy, when I ran into you just now,’ said
Candide to Paquette; ‘you were singing, you were caressing your monk so
naturally and affectionately; you seemed to be as happy as you now
claim to be miserable.’ ‘Ah! Monsieur,’ replied Paquette, ‘that is another of the miseries of our profession. Yesterday I was beaten and robbed by an officer of the law; today I must seem in good humour to please a monk.'26 |
「で
も、さっきあなたにばったり会ったとき、あなたはすごく楽しそうで、陽気そうだったわ」と、カンディドはパケットに言った。「あなたは歌っていたし、修道
僧を自然に愛情を込めて撫でていた。あなたは今、自分が不幸だと言っているように、幸せそうに見えたわ」 「ああ、旦那様」とパケットは答えた。「それが私たちの職業の苦悩のひ とつなのです。昨日は法の執行人に殴られ、物を奪われました。今日は修道士に機嫌よく振る舞わなければなりません。」26 |
| Then after finding out how
tragic the woman’s life has been, he turns to the monk to ask him if
he’s happy: |
そして、その女性の人生がどれほど悲惨なものだったかを知った後、彼は
僧侶に向かって、自分が幸せかどうか尋ねた。 |
| ‘I
wish every last Theatine [a Catholic order to which he belongs] at the
bottom of the sea. I have been tempted a hundred times to set fire to
the monastery and go and turn Turk [convert to Islam]. My parents
forced me at the age of fifteen to wear this loathsome habit, so as to
leave a larger fortune to my accursed elder brother, whom God confound!
The monastery is rife with jealousies, faction and ill-feeling. It is
true, I have preached a few wretched sermons which brought me a little
money, half of which the prior has stolen from me: the rest I use to
pay for the girls; but when I get back to the monastery in the evening
I feel like dashing my brains against the dormitory walls; all my
fellow friars are in the same situation.'27 |
「シ
トー会(彼が所属するカトリックの修道会)の者全員が海の底に沈んでしまえばいいのに。修道院に火を放って、イスラム教に改宗してやろうかと、これまで何
度も思った。15歳の時に両親に嫌々この忌まわしい修道服を着せられたのは、呪われた兄に多額の財産を残すためだった。神よ、彼を滅ぼしたまえ!修道院は
嫉妬、派閥、悪意に満ちている。確かに、私は少しばかりの金を稼ぐために、惨めな説教をいくつかした。その半分は院長が盗んだが、残りは少女たちに支払う
ために使っている。しかし、夕方に修道院に戻ると、寮の壁に頭を打ちつけたくなる。同僚の修道士たちは皆、同じ状況だ。 |
| Candide then meets a wealthy
count in Venice who has an great collection of art and books but he
finds no pleasure in them. The count makes a comment about freedom of
speech which is perfectly aligned with Voltaire’s views: |
その後、カンディードはヴェネツィアで、美術品や書籍の素晴らしいコレ クションを所有する裕福な伯爵と出会うが、彼はそれらに何の喜びも見出せない。伯爵は、言論の自由について、ヴォルテールの考えと完全に一致するようなコ メントを発する。 |
| ‘[I]t is a fine thing to write what one thinks; it is man’s natural privilege, after all. In Italy, wherever you go, we write only what we do not think; the descendants of the Caesars and the Antonines dare not entertain an idea without the permission of a Dominican monk. However, I would be happier with the freedom which inspires the English genius, except that doctrinaire passion and party spirit corrupt all that is estimable in their precious liberty.'28 | 「自分の考えを書くのは素晴ら しいことだ。結局のところ、それは人間にとって自然な特権なのだから。イタリアでは、どこに行っても、考えないことだけを書く。カエサルとアントニヌスの 末裔たちは、ドミニコ会の修道士の許可なしに考えを持つことを許されない。しかし、私は、イギリス人の天才性を鼓舞する自由の方が嬉しい。ただし、イギリ ス人の自由を貶めるような、教条的な情熱や党派心は別だ。 |
| History Spotlight: The
Dominicans: 'God's dogs' To modern readers, Voltaire’s reference to “the permission of a Dominican monk” might not be obvious but for centuries it was a clear allusion to the Inquisition. The Dominican monks played a prominent role in that dark chapter of Christian history where heretics were put on trial and subjected to torture, and countless of them were executed. The Inquisition started in the 12th century and lasted in some regions until the 19th century. Although the Spanish version was especially brutal, the Inquisition, as mentioned in the above quote, was established far beyond. Italy, in particular, had a long history of heresy trials before the Galileo affair (1633) thanks to the Papal Inquisition which lasted from 1231 to 1820. The shameful work undertaken by the Dominicans earned them a popular pun on their name in Latin: Domini Canes (God’s dogs). A graphic representation of that pun (i.e. dogs biting wolves, that is heretics) exists today in the Dominican church of Santa Maria Novella in Florence. |
歴史クローズアップ:ドミニコ会:「神の犬」 現代の読者にとって、ヴォルテールの「ドミニコ会の修道士の許可」という表現は、あまりピンとこないかもしれないが、何世紀にもわたって、それは異端審問 を明確に暗示する表現であった。ドミニコ会の修道士たちは、異端者が裁判にかけられ拷問を受け、そのうちの無数の者が処刑されたキリスト教の暗黒の歴史に おいて、重要な役割を果たした。異端審問は12世紀に始まり、一部の地域では19世紀まで続いた。スペインの異端審問は特に残忍だったが、異端審問は上記 の引用文にあるように、はるか昔から存在していた。特にイタリアでは、1231年から1820年まで続いたローマ教皇庁の異端審問のおかげで、ガリレオ事 件(1633年)以前から異端審問の長い歴史があった。ドミニコ会が引き受けた恥ずべき仕事により、彼らはラテン語で「ドミニコ会」を意味する「ドミニ・ カネス(神の犬)」というあだ名で呼ばれるようになった。このあだ名を視覚的に表現したもの(すなわち、犬が狼に噛み付いている様子、つまり異端)が、現 在もフィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ教会にあるドミニコ会教会に残っている。 |
| Candide’s hope in finding
Cunégonde is rekindled when Cacambo shows up to tell him that he has
become a slave and his beloved is in Constantinople working along with
the old woman as servants for a prince. Candide buys Cacambo’s freedom
then heads with him and Martin to Turkey to meet his girl. Upon his
arrival in Turkey, Candide recognizes two galley slaves: They’re
Cunégonde’s brother, who survived Candide’s stabbing and has no hard
feelings towards him and Pangloss who survived the execution. Candide
buys their freedom. Next Candide buys back Cunégonde and the old woman. Then he acts on his promise and marries her even though she’s now ugly. Her brother was an obstacle to the marriage again so Candide, instead of killing him, returns him to the galleys. Candide is finally settled on a small farm with his wife and other friends. Now that they all found each other, and are living out of harm’s way, did they find happiness? |
カンドゥデは、奴隷となり、最愛の女性がコンスタンティノープルで老女
とともに王子の召使いとして働いていることを告げるカカンボの登場により、クネゴンデを見つける望みが再び燃え上がる。カンディドはカカンボの自由を買
い、彼とマルタンとともにトルコへ向かい、愛する女性に会う。トルコに到着すると、カンディドは2人のガレー船の奴隷を認める。彼らはクネゴンデの兄であ
り、カンディドに刺されながらも生き延び、カンディドに対して何の恨みも抱いていない。そして、処刑を免れたパングラスだ。カンディドは彼らの自由を買い
取る。 次に、カンディドはクネゴンと老女を買い戻す。そして、約束を果たし、彼女と結婚する。彼女は今では醜くなっていたが。彼女の兄が結婚の障害となったた め、カンディドは彼を殺す代わりに、再びガレー船に送る。カンディドはついに、妻や他の友人たちと小さな農場で落ち着く。彼らは皆お互いを見つけ、危険の ない生活を送るようになったが、幸せを見つけたのだろうか? |
| It
would be altogether natural
to suppose that Candide, after so many disasters, would henceforth lead
the most agreeable of possible existences – married at last to his
mistress, living with the philosopher Pangloss, the Philosophical
Martin, the prudent Cacambo, the old woman – having moreover brought
back all those diamonds from the land of the ancient Incas. But he had
been swindled so many times by Jews [a passing anti-Semite remark about
the “swindling Jews”] that all he had left in the end was his little
farm; his wife, growing uglier by the day, had become shrewish and
insufferable. 29 |
こ
れほど多くの災難に見舞われた後、カンディドがこれからは最も快適な
生活を送るだろうと考えるのはごく自然なことだろう。愛人(クネンゴンド)とついに結婚し、哲学者パングロス、哲学的なマルタン、思慮深いカカムボ、老女とともに暮らし、
さらに古代インカの地からダイヤモンドをすべて持ち帰ったのだ。しかし、彼はユダヤ人に何度もだまされていたため(「詐欺師のユダヤ人」という一過性の反
ユダヤ主義的な発言)、最後に残ったのは小さな農場だけだった。日に日に醜くなっていく妻は、しつこく、耐え難い存在となっていた。29 |
| Not only does Candide feel
unfulfilled, another unexpected problem appeared… |
カンディードは満たされない思いを抱いていただけでなく、予期せぬ別の
問題 |
| [T]he
boredom was so extreme
that one day the old woman ventured to remark: I should like to know
which is worse: to be raped a hundred times by negro pirates…or simply
to sit here and do nothing?30 |
退屈が極限に達したため、ある 日、老女は思い切ってこう言った。「黒人 海賊に100回レイプされるのと、ただここに座って何もしないのと、どちらが悪いのか知りたいわ。」30 |
| Paradoxically, peace, safety and
the sudden lack of suffering might have been a reason why they were
bored. Their hard work on the garden though provided them with a
solution to counter that boredom and that’s how they ultimately find
happiness. Candide is no longer infatuated with the theories of
Pangloss which he makes clear in an iconic scene at the end of the
book. Pangloss starts philosophizing to him as he always had done, then
Candide, who now clearly prefers actual work, interrupts: That is well
said…but we must cultivate our garden. Note: All the above controversial passages are available in the original (French) language on this page. https://www.booksontrial.com/candide-de-voltaire-les-citations-les-plus-controversees/ |
逆説的ではあるが、平和で安全、そして突然の苦痛の欠如が、彼らが退屈
した理由であったのかもしれない。しかし、庭仕事に精を出すことで、その退屈を打ち消す解決策を見出し、最終的に幸福を見出すのである。カンディドは、パ
ンゴスの理論に夢中になることはなくなり、そのことは本の最後の象徴的な場面で明確に示されている。パングロスがいつものように彼に哲学を説き始めると、
実際の労働を好むようになったカンディドが口を挟む。「それはよく言った。しかし、私たちは庭を耕さなければならない」 注:上記の論争の的となった文章はすべて、このページのフランス語原文でご覧いただけます。 https://www.booksontrial.com/candide-de-voltaire-les-citations-les-plus-controversees/s |
| Endnotes
↑1 Voltaire, Candide, or Optimism, trans. Theo Cuffe (London, United
Kingdom: Penguin Classics, 2005), 9.
↑2 Ibid., 11.
↑3 Ibid., 14.
↑4 Ibid., 128.
↑5 Ibid., 15.
↑6 Ibid., 20.
↑7 Ibid., 23.
↑8 Ibid.
↑9 Ibid., 25.
↑10 Ibid., 26.
↑11 Ibid.
↑12 Ibid.
↑13 Ibid., 27.
↑14 Ibid., 28.
↑15 Ibid., 30.
↑16 Ibid., 32.
↑17 Ibid., 37.
↑18 Ibid., 38.
↑19 Ibid., 39.
↑20 Ibid., 40.
↑21 Ibid., 47.
↑22 Ibid., 51.
↑23 Ibid., 58.
↑24 Ibid., 69.
↑25 Ibid.
↑26 Ibid., 73.
↑27 Ibid.
↑28 Ibid., 77.
↑29 Ibid., 90.
↑30 Ibid. |
|
| https://www.booksontrial.com/candide-optimism-voltaire-shocking-bits/ |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆