Existentialism
Tsimshian Eagle Dance Headress ca.1870.
実存主義
Existentialism
Tsimshian Eagle Dance Headress ca.1870.
| Existentialism
is a
form of philosophical inquiry that explores the issue of human
existence.[1][2] Existentialist philosophers explore questions related
to the meaning, purpose, and value of human existence. Common concepts
in existentialist thought include existential crisis, dread, and
anxiety in the face of an absurd world and free will, as well as
authenticity, courage, and virtue.[3] Existentialism is associated with several 19th- and 20th-century European philosophers who shared an emphasis on the human subject, despite often profound differences in thought.[4][2][5] Among the earliest figures associated with existentialism are philosophers Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche and novelist Fyodor Dostoevsky, all of whom critiqued rationalism and concerned themselves with the problem of meaning. In the 20th century, prominent existentialist thinkers included Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, and Paul Tillich. Many existentialists considered traditional systematic or academic philosophies, in style and content, to be too abstract and removed from concrete human experience.[6][7] A primary virtue in existentialist thought is authenticity.[8] Existentialism would influence many disciplines outside of philosophy, including theology, drama, art, literature, and psychology.[9] Existentialist philosophy encompasses a range of perspectives, but it shares certain underlying concepts. Among these, a central tenet of existentialism is that personal freedom, individual responsibility, and deliberate choice ar |
実存主義とは、人間存在の問題を探求する哲学的探究の一形態である
[1][2]。実存主義の哲学者たちは、人間存在の意味、目的、価値に関する問題を探求する。実存主義思想に共通する概念として、不条理な世界や自由意志
を前にした実存的危機、恐怖、不安、また真正性、勇気、美徳などがある[3]。 実存主義は19世紀から20世紀にかけてのヨーロッパの哲学者たちと関連しており、彼らはしばしば思想に大きな違いがあるにもかかわらず、人間の主体に対 する強調を共有していた[4][2][5]。20世紀には、ジャン=ポール・サルトル、アルベール・カミュ、マルティン・ハイデガー、シモーヌ・ド・ボー ヴォワール、カール・ヤスパース、ガブリエル・マルセル、パウル・ティリッヒといった著名な実存主義思想家がいた。 実存主義思想における第一の美徳は真正性である[8]。実存主義は神学、演劇、芸術、文学、心理学など、哲学以外の多くの分野に影響を与えることになる [9]。 実存主義哲学は様々な視点を包含しているが、その根底にある概念は共通している。その中でも実存主義の中心的な信条は、個人の自由、個人の責任、意図的な 選択が、自己発見の追求と人生の意味の決定に不可欠であるというものである[10]。 |
| Etymology The term existentialism (French: L'existentialisme) was coined by the French Catholic philosopher Gabriel Marcel in the mid-1940s.[11][12][13] When Marcel first applied the term to Jean-Paul Sartre, at a colloquium in 1945, Sartre rejected it.[14] Sartre subsequently changed his mind and, on October 29, 1945, publicly adopted the existentialist label in a lecture to the Club Maintenant in Paris, published as L'existentialisme est un humanisme (Existentialism Is a Humanism), a short book that helped popularize existentialist thought.[15] Marcel later came to reject the label himself in favour of Neo-Socratic, in honor of Kierkegaard's essay "On the Concept of Irony". 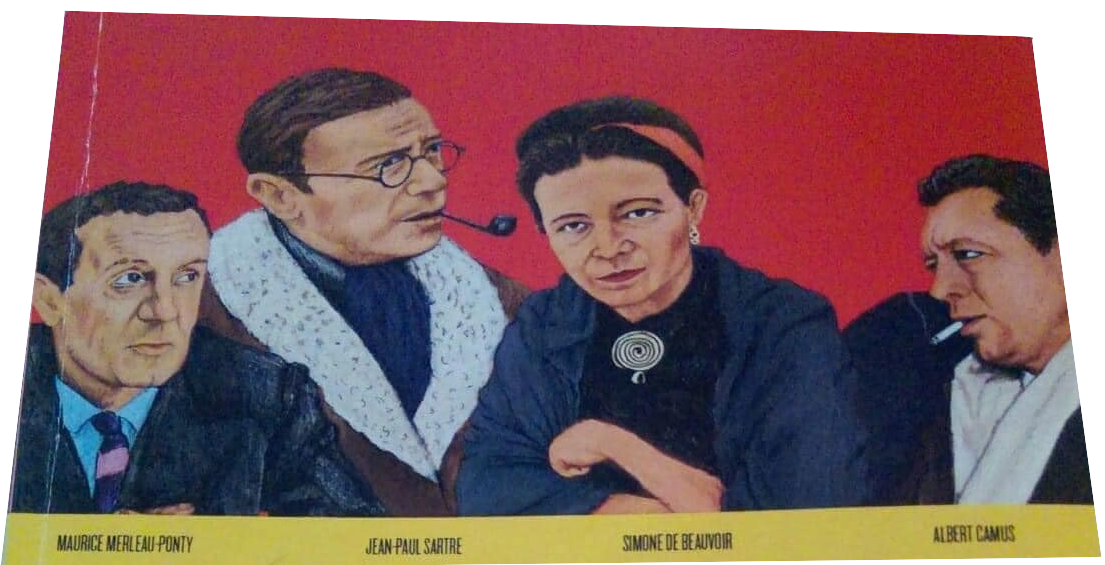 Some scholars argue that the term should be used to refer only to the cultural movement in Europe in the 1940s and 1950s associated with the works of the philosophers Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, and Albert Camus.[4] Others extend the term to Kierkegaard, and yet others extend it as far back as Socrates.[16] However, it is often identified with the philosophical views of Sartre.[4] |
語源[編集] 実存主義(フランス語:L'existentialisme)という用語は、1940年代半ばにフランスのカトリック哲学者ガブリエル・マルセルによって 作られた。 [その後、サルトルは考えを改め、1945年10月29日にパリのクラブ・マントナンで行われた講演で、実存主義のラベルを公に採用し、実存主義思想の普 及に貢献した短編集『実存主義はヒューマニズムである』(L'existentialisme est un humanisme)として出版された[15]。 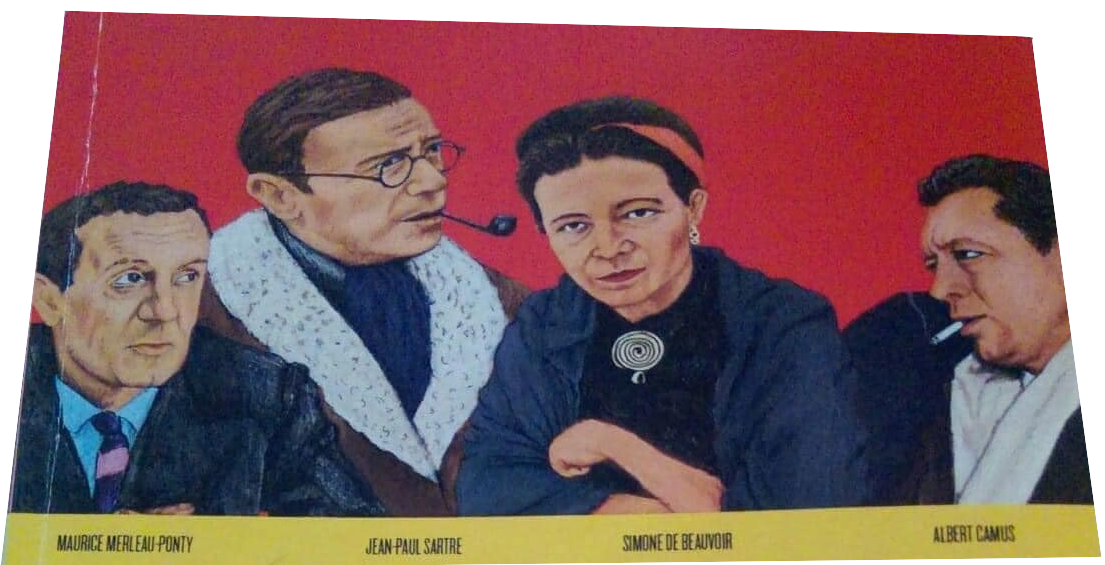 サルトル、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、モーリス・メルロ=ポンティ、アルベール・カミュといった哲学者の著作に関連する1940年代から1950年代 のヨーロッパにおける文化運動のみを指す言葉として使用されるべきであると主張する学者もいる。 |
| Definitional issues and
background The labels existentialism and existentialist are often seen as historical conveniences in as much as they were first applied to many philosophers long after they had died. While existentialism is generally considered to have originated with Kierkegaard, the first prominent existentialist philosopher to adopt the term as a self-description was Sartre. Sartre posits the idea that "what all existentialists have in common is the fundamental doctrine that existence precedes essence", as the philosopher Frederick Copleston explains.[17] According to philosopher Steven Crowell, defining existentialism has been relatively difficult, and he argues that it is better understood as a general approach used to reject certain systematic philosophies rather than as a systematic philosophy itself.[4] In a lecture delivered in 1945, Sartre described existentialism as "the attempt to draw all the consequences from a position of consistent atheism".[18] For others, existentialism need not involve the rejection of God, but rather "examines mortal man's search for meaning in a meaningless universe", considering less "What is the good life?" (to feel, be, or do, good), instead asking "What is life good for?".[19] Although many outside Scandinavia consider the term existentialism to have originated from Kierkegaard, it is more likely that Kierkegaard adopted this term (or at least the term "existential" as a description of his philosophy) from the Norwegian poet and literary critic Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven.[20] This assertion comes from two sources: The Norwegian philosopher Erik Lundestad refers to the Danish philosopher Fredrik Christian Sibbern. Sibbern is supposed to have had two conversations in 1841, the first with Welhaven and the second with Kierkegaard. It is in the first conversation that it is believed that Welhaven came up with "a word that he said covered a certain thinking, which had a close and positive attitude to life, a relationship he described as existential".[21] This was then brought to Kierkegaard by Sibbern. The second claim comes from the Norwegian historian Rune Slagstad, who claimed to prove that Kierkegaard himself said the term existential was borrowed from the poet. He strongly believes that it was Kierkegaard himself who said that "Hegelians do not study philosophy 'existentially;' to use a phrase by Welhaven from one time when I spoke with him about philosophy."[22] |
定義の問題と背景[編集] 実存主義と実存主義者というレッテルは、多くの哲学者が亡くなってから長い年月を経て初めて適用されたという点で、しばしば歴史的な便宜とみなされる。実 存主義は一般的にキルケゴールに端を発すると考えられているが、この言葉を自己記述として採用した最初の著名な実存主義哲学者はサルトルである。哲学者の フレデリック・コプルストンが説明するように、サルトルは「すべての実存主義者に共通するのは、実存が本質に先立つという基本的な教義である」という考え を提唱している[17]。哲学者のスティーヴン・クロウウェルによれば、実存主義の定義は比較的困難であり、体系的な哲学そのものというよりも、ある体系 的な哲学を否定するために用いられる一般的なアプローチとして理解されるのがよいと主張している。 [サルトルは1945年の講演で、実存主義を「一貫した無神論の立場からあらゆる結果を導き出そうとする試み」であると述べている。(いい人生とは何か」 (いい人生だと感じること、いい人生であること、いい人生であること)を考えるのではなく、「人生は何のためにあるのか」を問うのである[19]。 スカンジナビア国外では、実存主義という用語はキルケゴールから生まれたと考えている人が多いが、キルケゴールがこの用語(あるいは少なくとも彼の哲学を 説明する用語としての「実存主義」)をノルウェーの詩人であり文芸批評家であったヨハン・セバスティアン・カンマイヤー・ウェルハーフェンから採用した可 能性の方が高い[20]。 この主張は2つの情報源からきている: ノルウェーの哲学者エリック・ルンデスタッドは、デンマークの哲学者フレドリック・クリスチャン・シバーンに言及している。シッベルンは1841年に2 回、最初の会話をウェルハーヴェンと、2回目の会話をキルケゴールと交わしたとされている。最初の会話で、ウェルヘーヴェンは「人生に対して緊密で肯定的 な態度をとり、実存的な関係であると表現した、ある考え方をカバーする言葉」を思いついたとされている。 2つ目の主張はノルウェーの歴史家ルーン・スラグスタッドによるもので、彼はキルケゴール自身が実存的という言葉は詩人から借用したものだと言ったことを 証明すると主張した。彼は、「ヘーゲル主義者は哲学を『実存的』には研究しない。私が彼と哲学について話したあるときのウェルハーヴェンの言葉を使えば」 と言ったのはキルケゴール自身だと強く信じている[22]。 |
| Concepts Existence precedes essence Main article: Existence precedes essence Sartre argued that a central proposition of existentialism is that existence precedes essence, which is to say that individuals shape themselves by existing and cannot be perceived through preconceived and a priori categories, an "essence". The actual life of the individual is what constitutes what could be called their "true essence" instead of an arbitrarily attributed essence others use to define them. Human beings, through their own consciousness, create their own values and determine a meaning to their life.[23] This view is in contradiction to Aristotle and Aquinas, who taught that essence precedes individual existence.[24] Although it was Sartre who explicitly coined the phrase, similar notions can be found in the thought of existentialist philosophers such as Heidegger, and Kierkegaard: The subjective thinker's form, the form of his communication, is his style. His form must be just as manifold as are the opposites that he holds together. The systematic eins, zwei, drei is an abstract form that also must inevitably run into trouble whenever it is to be applied to the concrete. To the same degree as the subjective thinker is concrete, to that same degree his form must also be concretely dialectical. But just as he himself is not a poet, not an ethicist, not a dialectician, so also his form is none of these directly. His form must first and last be related to existence, and in this regard he must have at his disposal the poetic, the ethical, the dialectical, the religious. Subordinate character, setting, etc., which belong to the well-balanced character of the esthetic production, are in themselves breadth; the subjective thinker has only one setting—existence—and has nothing to do with localities and such things. The setting is not the fairyland of the imagination, where poetry produces consummation, nor is the setting laid in England, and historical accuracy is not a concern. The setting is inwardness in existing as a human being; the concretion is the relation of the existence-categories to one another. Historical accuracy and historical actuality are breadth. — Søren Kierkegaard (Concluding Postscript, Hong pp. 357–358.) Some interpret the imperative to define oneself as meaning that anyone can wish to be anything. However, an existentialist philosopher would say such a wish constitutes an inauthentic existence – what Sartre would call "bad faith". Instead, the phrase should be taken to say that people are defined only insofar as they act and that they are responsible for their actions. Someone who acts cruelly towards other people is, by that act, defined as a cruel person. Such persons are themselves responsible for their new identity (cruel persons). This is opposed to their genes, or human nature, bearing the blame. As Sartre said in his lecture Existentialism is a Humanism: "Man first of all exists, encounters himself, surges up in the world—and defines himself afterwards." The more positive, therapeutic aspect of this is also implied: a person can choose to act in a different way, and to be a good person instead of a cruel person.[25] Jonathan Webber interprets Sartre's usage of the term essence not in a modal fashion, i.e. as necessary features, but in a teleological fashion: "an essence is the relational property of having a set of parts ordered in such a way as to collectively perform some activity".[26]: 3 [4] For example, it belongs to the essence of a house to keep the bad weather out, which is why it has walls and a roof. Humans are different from houses because—unlike houses—they do not have an inbuilt purpose: they are free to choose their own purpose and thereby shape their essence; thus, their existence precedes their essence.[26]: 1–4 Sartre is committed to a radical conception of freedom: nothing fixes our purpose but we ourselves, our projects have no weight or inertia except for our endorsement of them.[27][28] Simone de Beauvoir, on the other hand, holds that there are various factors, grouped together under the term sedimentation, that offer resistance to attempts to change our direction in life. Sedimentations are themselves products of past choices and can be changed by choosing differently in the present, but such changes happen slowly. They are a force of inertia that shapes the agent's evaluative outlook on the world until the transition is complete.[26]: 5, 9, 66 Sartre's definition of existentialism was based on Heidegger's magnum opus Being and Time (1927). In the correspondence with Jean Beaufret later published as the Letter on Humanism, Heidegger implied that Sartre misunderstood him for his own purposes of subjectivism, and that he did not mean that actions take precedence over being so long as those actions were not reflected upon.[29] Heidegger commented that "the reversal of a metaphysical statement remains a metaphysical statement", meaning that he thought Sartre had simply switched the roles traditionally attributed to essence and existence without interrogating these concepts and their history.[30] The absurd Main article: Absurdism Sisyphus, the symbol of the absurdity of existence, painting by Franz Stuck (1920) The notion of the absurd contains the idea that there is no meaning in the world beyond what meaning we give it. This meaninglessness also encompasses the amorality or "unfairness" of the world. This can be highlighted in the way it opposes the traditional Abrahamic religious perspective, which establishes that life's purpose is the fulfillment of God's commandments.[31] This is what gives meaning to people's lives. To live the life of the absurd means rejecting a life that finds or pursues specific meaning for man's existence since there is nothing to be discovered. According to Albert Camus, the world or the human being is not in itself absurd. The concept only emerges through the juxtaposition of the two; life becomes absurd due to the incompatibility between human beings and the world they inhabit.[31] This view constitutes one of the two interpretations of the absurd in existentialist literature. The second view, first elaborated by Søren Kierkegaard, holds that absurdity is limited to actions and choices of human beings. These are considered absurd since they issue from human freedom, undermining their foundation outside of themselves.[32] The absurd contrasts with the claim that "bad things don't happen to good people"; to the world, metaphorically speaking, there is no such thing as a good person or a bad person; what happens happens, and it may just as well happen to a "good" person as to a "bad" person.[33] Because of the world's absurdity, anything can happen to anyone at any time and a tragic event could plummet someone into direct confrontation with the absurd. Many of the literary works of Kierkegaard, Beckett, Kafka, Dostoevsky, Ionesco, Miguel de Unamuno, Luigi Pirandello,[34][35][36][37] Sartre, Joseph Heller, and Camus contain descriptions of people who encounter the absurdity of the world. It is because of the devastating awareness of meaninglessness that Camus claimed in The Myth of Sisyphus that "There is only one truly serious philosophical problem, and that is suicide." Although "prescriptions" against the possible deleterious consequences of these kinds of encounters vary, from Kierkegaard's religious "stage" to Camus' insistence on persevering in spite of absurdity, the concern with helping people avoid living their lives in ways that put them in the perpetual danger of having everything meaningful break down is common to most existentialist philosophers. The possibility of having everything meaningful break down poses a threat of quietism, which is inherently against the existentialist philosophy.[38] It has been said that the possibility of suicide makes all humans existentialists. The ultimate hero of absurdism lives without meaning and faces suicide without succumbing to it.[39] Facticity Main article: Facticity This section may be too technical for most readers to understand. Please help improve it to make it understandable to non-experts, without removing the technical details. (November 2020) (Learn how and when to remove this message) Facticity is defined by Sartre in Being and Nothingness (1943) as the in-itself, which for humans takes the form of being and not being. It is the facts of one's personal life and as per Heidegger, it is "the way in which we are thrown into the world." This can be more easily understood when considering facticity in relation to the temporal dimension of our past: one's past is what one is, meaning that it is what has formed the person who exists in the present. However, to say that one is only one's past would ignore the change a person undergoes in the present and future, while saying that one's past is only what one was, would entirely detach it from the present self. A denial of one's concrete past constitutes an inauthentic lifestyle, and also applies to other kinds of facticity (having a human body—e.g., one that does not allow a person to run faster than the speed of sound—identity, values, etc.).[40] Facticity is a limitation and a condition of freedom. It is a limitation in that a large part of one's facticity consists of things one did not choose (birthplace, etc.), but a condition of freedom in the sense that one's values most likely depend on it. However, even though one's facticity is "set in stone" (as being past, for instance), it cannot determine a person: the value ascribed to one's facticity is still ascribed to it freely by that person. As an example, consider two men, one of whom has no memory of his past and the other who remembers everything. Both have committed many crimes, but the first man, remembering nothing, leads a rather normal life while the second man, feeling trapped by his own past, continues a life of crime, blaming his own past for "trapping" him in this life. There is nothing essential about his committing crimes, but he ascribes this meaning to his past. However, to disregard one's facticity during the continual process of self-making, projecting oneself into the future, would be to put oneself in denial of the conditions shaping the present self and would be inauthentic. The origin of one's projection must still be one's facticity, though in the mode of not being it (essentially). An example of one focusing solely on possible projects without reflecting on one's current facticity:[40] would be someone who continually thinks about future possibilities related to being rich (e.g. a better car, bigger house, better quality of life, etc.) without acknowledging the facticity of not currently having the financial means to do so. In this example, considering both facticity and transcendence, an authentic mode of being would be considering future projects that might improve one's current finances (e.g. putting in extra hours, or investing savings) in order to arrive at a future-facticity of a modest pay rise, further leading to purchase of an affordable car. Another aspect of facticity is that it entails angst. Freedom "produces" angst when limited by facticity and the lack of the possibility of having facticity to "step in" and take responsibility for something one has done also produces angst. Another aspect of existential freedom is that one can change one's values. One is responsible for one's values, regardless of society's values. The focus on freedom in existentialism is related to the limits of responsibility one bears, as a result of one's freedom. The relationship between freedom and responsibility is one of interdependency and a clarification of freedom also clarifies that for which one is responsible.[41][42] Authenticity Main article: Authenticity Many noted existentialists consider the theme of authentic existence important. Authenticity involves the idea that one has to "create oneself" and live in accordance with this self. For an authentic existence, one should act as oneself, not as "one's acts" or as "one's genes" or as any other essence requires. The authentic act is one in accordance with one's freedom. A component of freedom is facticity, but not to the degree that this facticity determines one's transcendent choices (one could then blame one's background for making the choice one made [chosen project, from one's transcendence]). Facticity, in relation to authenticity, involves acting on one's actual values when making a choice (instead of, like Kierkegaard's Aesthete, "choosing" randomly), so that one takes responsibility for the act instead of choosing either-or without allowing the options to have different values.[43] In contrast, the inauthentic is the denial to live[clarification needed] in accordance with one's freedom. This can take many forms, from pretending choices are meaningless or random, convincing oneself that some form of determinism is true, or "mimicry" where one acts as "one should".[citation needed] How one "should" act is often determined by an image one has, of how one in such a role (bank manager, lion tamer, sex worker, etc.) acts. In Being and Nothingness, Sartre uses the example of a waiter in "bad faith". He merely takes part in the "act" of being a typical waiter, albeit very convincingly.[44] This image usually corresponds to a social norm, but this does not mean that all acting in accordance with social norms is inauthentic. The main point is the attitude one takes to one's own freedom and responsibility and the extent to which one acts in accordance with this freedom.[45] The Other and the Look Main article: Other (philosophy) The Other (written with a capital "O") is a concept more properly belonging to phenomenology and its account of intersubjectivity. However, it has seen widespread use in existentialist writings, and the conclusions drawn differ slightly from the phenomenological accounts. The Other is the experience of another free subject who inhabits the same world as a person does. In its most basic form, it is this experience of the Other that constitutes intersubjectivity and objectivity. To clarify, when one experiences someone else, and this Other person experiences the world (the same world that a person experiences)—only from "over there"—the world is constituted as objective in that it is something that is "there" as identical for both of the subjects; a person experiences the other person as experiencing the same things. This experience of the Other's look is what is termed the Look (sometimes the Gaze).[46] While this experience, in its basic phenomenological sense, constitutes the world as objective and oneself as objectively existing subjectivity (one experiences oneself as seen in the Other's Look in precisely the same way that one experiences the Other as seen by him, as subjectivity), in existentialism, it also acts as a kind of limitation of freedom. This is because the Look tends to objectify what it sees. When one experiences oneself in the Look, one does not experience oneself as nothing (no thing), but as something (some thing). In Sartre's example of a man peeping at someone through a keyhole, the man is entirely caught up in the situation he is in. He is in a pre-reflexive state where his entire consciousness is directed at what goes on in the room. Suddenly, he hears a creaking floorboard behind him and he becomes aware of himself as seen by the Other. He is then filled with shame for he perceives himself as he would perceive someone else doing what he was doing—as a Peeping Tom. For Sartre, this phenomenological experience of shame establishes proof for the existence of other minds and defeats the problem of solipsism. For the conscious state of shame to be experienced, one has to become aware of oneself as an object of another look, proving a priori, that other minds exist.[47] The Look is then co-constitutive of one's facticity. Another characteristic feature of the Look is that no Other really needs to have been there: It is possible that the creaking floorboard was simply the movement of an old house; the Look is not some kind of mystical telepathic experience of the actual way the Other sees one (there may have been someone there, but he could have not noticed that person). It is only one's perception of the way another might perceive him.[48] Angst and dread Main article: Angst "Existential angst", sometimes called existential dread, anxiety, or anguish, is a term common to many existentialist thinkers. It is generally held to be a negative feeling arising from the experience of human freedom and responsibility.[49][50] The archetypal example is the experience one has when standing on a cliff where one not only fears falling off it, but also dreads the possibility of throwing oneself off. In this experience that "nothing is holding me back", one senses the lack of anything that predetermines one to either throw oneself off or to stand still, and one experiences one's own freedom.[51] It can also be seen in relation to the previous point how angst is before nothing, and this is what sets it apart from fear that has an object. While one can take measures to remove an object of fear, for angst no such "constructive" measures are possible. The use of the word "nothing" in this context relates to the inherent insecurity about the consequences of one's actions and to the fact that, in experiencing freedom as angst, one also realizes that one is fully responsible for these consequences. There is nothing in people (genetically, for instance) that acts in their stead—that they can blame if something goes wrong. Therefore, not every choice is perceived as having dreadful possible consequences (and, it can be claimed, human lives would be unbearable if every choice facilitated dread). However, this does not change the fact that freedom remains a condition of every action. Despair Main article: Despair See also: Existential crisis Despair is generally defined as a loss of hope.[52] In existentialism, it is more specifically a loss of hope in reaction to a breakdown in one or more of the defining qualities of one's self or identity. If a person is invested in being a particular thing, such as a bus driver or an upstanding citizen, and then finds their being-thing compromised, they would normally be found in a state of despair—a hopeless state. For example, a singer who loses the ability to sing may despair if they have nothing else to fall back on—nothing to rely on for their identity. They find themselves unable to be what defined their being. What sets the existentialist notion of despair apart from the conventional definition is that existentialist despair is a state one is in even when they are not overtly in despair. So long as a person's identity depends on qualities that can crumble, they are in perpetual despair—and as there is, in Sartrean terms, no human essence found in conventional reality on which to constitute the individual's sense of identity, despair is a universal human condition. As Kierkegaard defines it in Either/Or: "Let each one learn what he can; both of us can learn that a person's unhappiness never lies in his lack of control over external conditions, since this would only make him completely unhappy."[53] In Works of Love, he says: When the God-forsaken worldliness of earthly life shuts itself in complacency, the confined air develops poison, the moment gets stuck and stands still, the prospect is lost, a need is felt for a refreshing, enlivening breeze to cleanse the air and dispel the poisonous vapors lest we suffocate in worldliness. ... Lovingly to hope all things is the opposite of despairingly to hope nothing at all. Love hopes all things—yet is never put to shame. To relate oneself expectantly to the possibility of the good is to hope. To relate oneself expectantly to the possibility of evil is to fear. By the decision to choose hope one decides infinitely more than it seems, because it is an eternal decision. — Søren Kierkegaard, Works of Love |
概念[編集] 存在は本質に先立つ[編集] 主な記事 実存は本質に先立つ サルトルは、実存主義の中心的命題は「実存は本質に先立つ」ことであると主張した。つまり、個人は存在することによって自らを形成するのであり、先入観や アプリオリなカテゴリー、すなわち「本質」を通して認識することはできないということである。他者が恣意的に定義した本質ではなく、個人の実際の生活こそ が「真の本質」と呼べるものなのだ。この見解は、本質が個人の存在に先立つと説いたアリストテレスや アクィナスとは矛盾する[24]。この言葉を明確に作り出したのはサルトルであるが、ハイデガーやキルケゴールといった実存主義の哲学者の思想にも同様の 考え方が見られる: 主体的な思想家の形式、コミュニケーションの形式は、彼のスタイルである。主体的な思想家の形式、コミュニケーションの形式は、彼のスタイルである。彼の 形式は、彼が一緒に保持する対立物のように多様でなければならない。体系化されたeins, zwei, dreiは抽象的な形式であるが、それを具体的なものに適用しようとすれば、必ず問題にぶつかる。主体的な思想家が具体的であるのと同じ程度に、彼の形式 もまた具体的な弁証法的でなければならない。しかし、彼自身が詩人でもなく、倫理学者でもなく、弁証法学者でもないように、彼の形式もまた、直接にはこれ らのどれでもない。彼の形式は、最初で最後には存在と関係しなければならず、この点で、彼は詩的なもの、倫理的なもの、弁証法的なもの、宗教的なものを自 由に使わなければならない。従属的な性格、設定などは、美学的作品のバランスのとれた性格に属するものであるが、それ自体は幅のあるものである。主体的な 思想家は、ただ一つの設定-実存-しか持たず、地域性などとは何の関係もない。舞台は、詩が完成を生み出す想像のおとぎの国でもなければ、イギリスにある わけでもない。設定とは、人間として存在することの内面性であり、具体性とは、存在カテゴリーの相互関係である。歴史的正確さと歴史的実在性は幅がある。 - セーレン・キェルケゴール(『結びの言葉』ホン 357-358ページ) 自らを定義せよという命令は、誰でも何にでもなりたいと望むことができるという意味だと解釈する人もいる。しかし、実存主義の哲学者であれば、そのような 願いは不真面目な存在であり、サルトルが「悪意」と呼ぶようなものだと言うだろう。そうではなく、この言葉は、人は行動する限りにおいてのみ定義され、そ の行動には責任があると言うべきだろう。他人に対して残酷な行為をする人は、その行為によって残酷な人間として定義される。そのような人は、自分自身の新 しいアイデンティティ(残酷な人)に責任がある。これは、遺伝子や人間の本性が責任を負うのとは対照的である。 サルトルが『実存主義はヒューマニズムである』という講演の中で述べたように、「人間はまず存在し、自分自身に出会い、世界に湧き上がり、その後に自分自 身を定義する」のである。より肯定的で治療的な側面も暗示されている。人は別の方法で行動し、残酷な人間ではなく善良な人間になることを選択できるのだ [25]。 ジョナサン・ウェバーは、サルトルの本質という用語の用法を、モード的な方法、すなわち必要な特徴としてではなく、目的論的な方法で解釈している: 「本質とは、集合的に何らかの活動を行うように秩序づけられた部分の集合を持つという関係的特性である」[26]: 3[4]例えば、悪天候を防ぐことは 家の本質であり、そのために壁と屋根がある。人間は家とは異なり、家とは異なり、内蔵された目的を持っていない: 1-4 サルトルは自由の急進的な概念にコミットしている。私たちの目的を確定するものは私たち自身以外にはなく、私たちのプロジェクトは私たちがそれを支持する 以外には何の重みも慣性も持たない。[27][28]一方、シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、人生の方向性を変えようとする試みに抵抗を与える様々な要因 が存在し、それは堆積という言葉でまとめられているとする。堆積はそれ自体、過去の選択の産物であり、現在において異なる選択をすることによって変えるこ とができるが、そのような変化はゆっくりと起こる。沈殿は、移行が完了するまで、世界に対するエージェントの評価的見通しを形成する慣性の力である [26]: 5, 9, 66 サルトルの実存主義の定義は、ハイデガーの大著『存在と時間』(1927年)に基づいていた。後に『ヒューマニズムに関する書簡』として出版されたジャ ン・ボーフレとの往復書簡の中で、ハイデガーはサルトルが自身の主観主義の目的のために彼を誤解しており、それらの行為が反省されない限り、行為が存在に 優先するという意味ではないことを暗示していた[29]。ハイデガーは「形而上学的な発言の逆転は形而上学的な発言のままである」とコメントしており、つ まり彼はサルトルがこれらの概念とその歴史を問うことなく、本質と存在に伝統的に帰属してきた役割を単にすり替えただけだと考えていた[30]。 不条理[編集] 主な記事 不条理 存在の不条理の象徴であるシジフォス、フランツ・シュトゥックによる絵画(1920年) 不条理という概念には、私たちが世界に与える意味を超えて、世界には意味がないという考えが含まれている。この無意味さはまた、世界の不道徳さや「不公平 さ」をも包含している。このことは、人生の目的は神の戒めを成就することであるとする伝統的なアブラハム教の宗教的観点と対立する形で強調することができ る[31]。不条理の人生を生きるということは、発見されるべきものが何もない以上、人間の存在に特定の意味を見出したり追求したりする人生を拒否するこ とを意味する。アルベール・カミュによれば、世界や人間それ自体は不条理ではない。実存主義文学における不条理の2つの解釈のうちの1つがこの見解であ る。二つ目の見解は、セーレン・キェルケゴールによって最初に提唱されたもので、不条理は人間の行為や選択に限定されるとするものである。不条理は人間の 自由から生じるものであり、人間自身の外側にある基盤を損なうものであるため、これらは不条理であると考えられている[32]。 不条理は、「善人には悪いことは起こらない」という主張とは対照的である。世界にとって、比喩的に言えば、善人や悪人というものは存在しない。キルケゴー ル、ベケット、カフカ、ドストエフスキー、イヨネスコ、ミゲル・デ・ウナムーノ、ルイジ・ピランデッロ、[34][35][36][37] サルトル、ジョセフ・ヘラー、カミュの文学作品の多くには、世界の不条理に遭遇する人々の描写がある。 カミュが『シジフォスの神話』の中で「真に深刻な哲学的問題はただ一つ、それは自殺である」と主張したのは、無意味さを痛感したからである。キルケゴール の宗教的「段階」からカミュの不条理にもかかわらず忍耐することの主張まで、この種の出会いがもたらしうる有害な結果に対する「処方箋」はさまざまだが、 意味のあるものすべてが壊れてしまうという絶え間ない危険にさらされるような生き方を避ける手助けをしようという関心は、ほとんどの実存主義哲学者に共通 している。意味のあるものすべてが壊れてしまう可能性は、静寂主義の脅威をもたらすが、それは本質的に実存主義哲学に反するものである。不条理主義の究極 のヒーローは意味なく生き、それに屈することなく自殺に直面する[39]。 事実性[編集] 主な記事 ファクトシティ このセクションは、ほとんどの読者には専門的すぎて理解できないかもしれない。技術的な詳細を削除することなく、非専門家にも理解できるように改善するこ とにご協力を。(2020年11月)(このメッセージを削除する方法とタイミングを学ぶ) 事実性とは、サルトルが『存在と無』(1943年)の中で定義した「内なる自己」であり、人間にとっては「存在すること」と「存在しないこと」という形を とる。ハイデガーに言わせれば、それは"私たちが世界に投げ込まれる方法"である。このことは、事実性を過去の時間的次元との関係で考えると、より容易に 理解できる。つまり、過去こそが、現在存在する人間を形成しているのである。しかし、自分の過去だけが自分であると言うことは、現在と未来において人が受 ける変化を無視することになるし、自分の過去だけが自分であると言うことは、現在の自分から完全に切り離すことになる。自分の具体的な過去を否定すること は、不真面目なライフスタイルを構成し、他の種類の事実性(人間の身体を持つこと、例えば音速よりも速く走ることができないもの、アイデンティティ、価値 観など)にも当てはまる[40]。 事実性は制限であり、自由の条件でもある。自分の事実性の大部分は、自分が選んだのではないもの(出生地など)で構成されているという意味で制限である が、自分の価値観がそれに依存している可能性が高いという意味で自由の条件である。しかし、自分の事実性が(例えば過去のものとして)「決まっている」と しても、それがその人を決定することはできない。自分の事実性に帰属する価値は、やはりその人が自由に帰属させるものなのだ。例えば、2人の男がいて、1 人は過去の記憶がなく、もう1人はすべてを覚えている。どちらも多くの犯罪を犯しているが、何も覚えていない一人目の男は、ごく普通の生活を送っている。 一方、二人目の男は、自分の過去に囚われていると感じ、自分の過去が現世に「囚われている」ことを責めながら、犯罪の生活を続けている。彼が犯罪を犯すこ とに本質的な意味は何もないが、彼はその意味を自分の過去に帰している。 しかし、未来に自己を投影するという自己形成の継続的なプロセスにおいて、自己の事実性を無視することは、現在の自己を形成している状況を否定することで あり、真正性を欠くことになる。自分の投影の原点は、(本質的に)そうではないというモードではあるが、やはり自分の事実性でなければならない。自分の現 在の事実性を省みることなく、可能性のあるプロジェクトにのみ集中する例としては、[40]金持ちになることに関連する将来の可能性(例えば、より良い 車、より大きな家、より良い生活の質など)について、現在そのための経済的手段を持たないという事実性を認めることなく考え続ける人が挙げられる。この例 では、事実性と超越性の両方を考慮すると、正真正銘の存在様式とは、将来の事実性である適度な昇給に到達するために、現在の財政を改善する可能性のある将 来のプロジェクト(労働時間を増やす、貯蓄を投資するなど)を検討し、さらに手頃な価格の車を購入することだろう。 事実性のもう一つの側面は、それが怒りを伴うということである。事実性によって制限されると、自由は怒りを「生む」。また、自分のしたことに「踏み込ん で」責任を取る事実性を持つ可能性がないことも、怒りを生む。 実存的自由のもう一つの側面は、人は自分の価値観を変えることができるということである。社会の価値観に関係なく、自分の価値観には責任がある。実存主義 における自由の焦点は、自由の結果として人が負う責任の限界と関連している。自由と責任の関係は相互依存の関係であり、自由を明確にすることは、自分が責 任を負うことを明確にすることでもある[41][42]。 真正性[編集] 主な記事 真正性 多くの著名な実存主義者は、本物の存在というテーマを重要視している。真正性とは、人は「自分自身を創造」し、その自分自身に従って生きなければならない という考えを含む。真正な存在のためには、人は自分自身として行動すべきであり、「自分の行為」としてではなく、「自分の遺伝子」としてでもなく、他の本 質が要求するものでもない。本物の行為とは、自分の自由に従って行う行為である。自由の構成要素は事実性であるが、この事実性が自分の超越的な選択を決定 してしまうほどではない(その場合、自分のした選択[自分の超越性から選択されたプロジェクト]をした背景を非難することができる)。真正性との関係にお ける事実性とは、選択をする際に(キルケゴールの『麻酔医』のように無作為に「選択」するのではなく)自分の実際の価値観に基づいて行動することであり、 その結果、異なる価値を持つ選択肢を許容することなくどちらか一方を選択するのではなく、その行為に責任を持つことになる[43]。 対照的に、不真面目とは、自分の自由に従って生きること[要明記]を否定することである。これは、選択肢が無意味であったりランダムであったりするふりを したり、ある種の決定論が真実であると自分自身を納得させたり、あるいは「あるべき」ように行動する「模倣」など、さまざまな形をとることができる[要出 典]。 どのように「行動すべきか」は、そのような役割(銀行の支店長、ライオンのテイマー、風俗嬢など)に就いている人がどのように行動するかという、人が持つ イメージによって決定されることが多い。サルトルは『存在と無』の中で、「悪意」を持ったウェイターの例を用いている。彼は、非常に説得力があるとはい え、典型的なウェイターであるという「演技」に参加しているにすぎない[44]。このイメージは通常、社会規範に対応しているが、だからといって、社会規 範に従った演技がすべて不真面目だというわけではない。重要なのは、自分自身の自由と責任に対してとる態度であり、この自由に従ってどの程度行動するかで ある[45]。 他者と視線[編集] 主な記事 他者(哲学) 他者(大文字の "O "で表記される)は、現象学とその相互主観性の説明により適切に属する概念である。しかし、この概念は実存主義者の著作で広く使われており、引き出された 結論は現象学的な説明とは若干異なっている。他者とは、ある人と同じ世界に住む、別の自由な主体の経験である。最も基本的な形では、間主観性と客観性を構 成するのは、この他者の経験である。明確にしておくと、人が他者を経験し、その他者が世界(人が経験するのと同じ世界)を-ただ「あちら」から-経験する とき、その世界は、両主体にとって同一のものとして「そこにある」ものであるという点で、客観的なものとして構成される。この他者の視線の経験は、「視 線」(時に「まなざし」)と呼ばれるものである[46]。 この経験は、その基本的な現象学的な意味において、世界を客観的なものとして構成し、自分自身を客観的に存在する主観性として構成する(人は他者の視線の 中に見られる自分自身を、まさにその人から見られる他者を主観性として経験するのと同じように経験する)一方で、実存主義においては、それは一種の自由の 制限としても作用する。というのも、「視線」は見るものを客観化する傾向があるからである。人は「視線」の中で自分を経験するとき、自分を無(ないもの) として経験するのではなく、有(あるもの)として経験するのである。サルトルの、鍵穴から誰かを覗き見る男の例では、男は自分が置かれている状況に完全に とらわれている。彼の意識はすべて、部屋の中で起こっていることに向けられている。突然、背後で床板がきしむ音が聞こえ、彼は他者から見られている自分に 気づく。そのとき彼は、自分がしていることを他人がしていると認識するように、自分自身を認識することになり、恥ずかしさでいっぱいになる。サルトルに とって、この羞恥の現象学的体験は、他者の心の存在を証明し、独我論の問題を打ち砕くものである。羞恥心という意識的な状態を経験するためには、自分が他 の視線の対象であることを自覚しなければならず、それによって他の心が存在することが先験的に証明される[47]。 視線のもう一つの特徴は、他者がそこにいたことを本当に必要としないことである: 床板がきしむのは単に古い家屋の動きである可能性もある。「視線」は、他者 が実際に自分を見ている様子の、ある種の神秘的なテレパシー体験ではない(そこに誰か がいたかもしれないが、その人に気づかなかったかもしれない)。それは他者が自分を知覚する方法についての自分の知覚に過ぎない[48]。 怒りと恐怖[編集] 主な記事 怒り 実存的恐怖、不安、苦悩と呼ばれることもある「実存的苦悩」は、多くの実存主義思想家に共通する用語である。一般的に、人間の自由と責任の経験から生じる 否定的な感情であるとされている[49][50]。典型的な例は、崖の上に立っているときに経験することであり、崖から落ちることを恐れるだけでなく、自 分自身を投げ落とす可能性にも恐怖を感じる。この「何も私を引き留めるものはない」という経験において、人は身を投げ出すか立ち止まるかを決定するものが 何もないことを感じ取り、自分自身の自由を体験する[51]。 また、前の点との関連で見ることができるのは、怒りがいかに無の前にあるかということであり、これが対象を持つ恐怖と異なる点である。人は恐怖の対象を取 り除くための手段を講じることができるが、怒りにはそのような「建設的」な手段は不可能である。この文脈で「無」という言葉が使われているのは、自分の行 動の結果に対する本質的な不安と、アングストとして自由を経験することで、その結果に対する全責任が自分にあることにも気づくという事実に関連している。 人の中には(例えば遺伝的に)自分の代わりに行動してくれるもの、つまり何か問題が起きたときに非難できるものはない。したがって、すべての選択が恐ろし い結果をもたらす可能性があると認識されるわけではない(そして、すべての選択が恐怖を助長するならば、人間の生活は耐え難いものになるだろうと主張する こともできる)。しかし、自由があらゆる行動の条件であることに変わりはない。 絶望[編集] 主な記事 絶望 以下も参照のこと: 実存的危機 絶望は一般的に希望の喪失と定義される[52]。 実存主義においては、より具体的には、自己やアイデンティティを定義する一つ以上の特質が崩れたことに対する希望の喪失である。ある人が、バスの運転手や 立派な市民といった特定のものであることに投資しており、その後、その存在であることが損なわれていることに気づいた場合、その人は通常、絶望の状態、つ まり絶望的な状態に置かれることになる。例えば、歌唱力を失った歌手が絶望するのは、他に頼れるものがない、つまり自分のアイデンティティを確立できない からだ。自分の存在を定義していたものになりきれない自分に気づくのだ。 実存主義的な絶望の概念が従来の定義と異なるのは、実存主義的な絶望は、あからさまに絶望していないときでもその人が置かれている状態だということだ。サ ルトルの言葉を借りれば、従来の現実には個人のアイデンティティを構成する人間の本質が存在しないため、絶望は普遍的な人間の状態なのである。キルケゴー ルは『 どちらか/あるいは』の中で次のように定義している。「各自ができることを学ぼう。私たちはともに、人の不幸は決して外的条件を制御できないことにあるの ではないことを学ぶことができる: 神に見捨てられた地上生活の世俗性が自己満足に閉じこもり、閉ざされた空気が毒を発生させ、瞬間が動けなくなり、立ち止まり、展望が失われるとき、私たち が世俗性の中で窒息しないように、空気を浄化し、毒の蒸気を吹き飛ばす、さわやかで活気づける風が必要と感じられる。... 愛情をもってすべてを望むことは、絶望して何も望まないこととは正反対である。愛はあらゆることを望むが、決して恥じることはない。良いことの可能性に期 待して身を投じることは、希望を抱くことである。悪の可能性に期待することは恐れることである。希望を選ぶという決断は、永遠の決断であるため、見かけ以 上に無限に多くのことを決断する。 - セーレン・キルケゴール『愛の著作集 |
| Opposition to positivism and
rationalism See also: Positivism and Rationalism Existentialists oppose defining human beings as primarily rational, and, therefore, oppose both positivism and rationalism. Existentialism asserts that people make decisions based on subjective meaning rather than pure rationality. The rejection of reason as the source of meaning is a common theme of existentialist thought, as is the focus on the anxiety and dread that we feel in the face of our own radical free will and our awareness of death. Kierkegaard advocated rationality as a means to interact with the objective world (e.g., in the natural sciences), but when it comes to existential problems, reason is insufficient: "Human reason has boundaries".[54] Like Kierkegaard, Sartre saw problems with rationality, calling it a form of "bad faith", an attempt by the self to impose structure on a world of phenomena—"the Other"—that is fundamentally irrational and random. According to Sartre, rationality and other forms of bad faith hinder people from finding meaning in freedom. To try to suppress feelings of anxiety and dread, people confine themselves within everyday experience, Sartre asserted, thereby relinquishing their freedom and acquiescing to being possessed in one form or another by "the Look" of "the Other" (i.e., possessed by another person—or at least one's idea of that other person).[55] |
実証主義と合理主義への反対[編集]。 以下も参照のこと: 実証主義と合理主義 実存主義者は、人間を主として合理的であると定義することに反対し、したがって実証主義と合理主義の両方に反対する。実存主義は、人は純粋な合理性よりも 主観的な意味に基づいて意思決定を行うと主張する。意味の源泉としての理性の否定は、実存主義思想の共通テーマであり、自分自身の根本的な自由意志や死を 意識することで感じる不安や 恐怖に焦点を当てている。キルケゴールは、(自然科学など)客観的世界と対話する手段として合理性を提唱したが、実存的問題となると、理性では不十分であ る: 「人間の理性には限界がある」[54]。 キルケゴールのように、サルトルは合理性に問題があると考え、それを「悪意」の一形態であり、根本的に非合理的でランダムである現象世界-「他者」-に構 造を押し付けようとする自己の試みであると呼んだ。サルトルによれば、合理性や他の形態の悪意は、人々が自由の意味を見出すのを妨げる。不安や恐怖の感情 を抑えようとするために、人々は日常的な経験の中に自らを閉じ込め、それによって自由を放棄し、「他者」の「視線」(すなわち、他者によって、あるいは少 なくともその他者についての自分の考え)によって何らかの形で憑依されることを承諾するのだとサルトルは主張した[55]。 |
| Religion See also: Atheistic existentialism, Christian existentialism, and Jewish existentialism An existentialist reading of the Bible would demand that the reader recognize that they are an existing subject studying the words more as a recollection of events. This is in contrast to looking at a collection of "truths" that are outside and unrelated to the reader, but may develop a sense of reality/God. Such a reader is not obligated to follow the commandments as if an external agent is forcing these commandments upon them, but as though they are inside them and guiding them from inside. This is the task Kierkegaard takes up when he asks: "Who has the more difficult task: the teacher who lectures on earnest things a meteor's distance from everyday life—or the learner who should put it to use?"[56] Philosophers such as Hans Jonas and Rudolph Bultmann introduced the concept of existentialist demythologization into the field of Early Christianity and Christian Theology, respectively.[57] |
宗教[編集] 以下も参照のこと: 無神論的実存主義、キリスト教的実存主義、ユダヤ教的実存主義 実存主義的な聖書の読み方は、読者に対して、自分自身が現存する主体であることを認識し、その言葉を出来事の回想として研究することを要求する。これは、 読者の外側にあり、読者とは無関係であるが、現実/神の感覚を発展させるかもしれない「真理」の集まりを見るのとは対照的である。そのような読者は、あた かも外部の存在が戒律を強制しているかのように戒律に従う義務を負うのではなく、あたかも戒律が読者の内側にあり、内側から導いているかのように戒律に従 うのである。これが、キルケゴールが問いかける課題である: 「日常生活から流星のような距離を置いて切実なことを講義する教師と、それを活用すべき学習者の、どちらがより困難な任務を負っているのだろうか」 [56] ハンス・ヨナスや ルドルフ・ブルトマンといった哲学者は、実存主義的な脱神話化の概念を、それぞれ初期キリスト教と キリスト教神学の分野に導入した[57]。 |
| Confusion with nihilism See also: Existential nihilism Although nihilism and existentialism are distinct philosophies, they are often confused with one another since both are rooted in the human experience of anguish and confusion that stems from the apparent meaninglessness of a world in which humans are compelled to find or create meaning.[58] A primary cause of confusion is that Friedrich Nietzsche was an important philosopher in both fields. Existentialist philosophers often stress the importance of angst as signifying the absolute lack of any objective ground for action, a move that is often reduced to moral or existential nihilism. A pervasive theme in existentialist philosophy, however, is to persist through encounters with the absurd, as seen in Albert Camus's philosophical essay The Myth of Sisyphus (1942): "One must imagine Sisyphus happy".[59] and it is only very rarely that existentialist philosophers dismiss morality or one's self-created meaning: Søren Kierkegaard regained a sort of morality in the religious (although he would not agree that it was ethical; the religious suspends the ethical), and Jean-Paul Sartre's final words in Being and Nothingness (1943): "All these questions, which refer us to a pure and not an accessory (or impure) reflection, can find their reply only on the ethical plane. We shall devote to them a future work."[44] |
ニヒリズムとの混同[編集]。 以下も参照のこと: 実存的ニヒリズム ニヒリズムと実存主義は別個の哲学であるが、どちらも人間が意味を見出したり創造したりせざるを得ない世界の明白な無意味さから生じる苦悩や混乱という人 間の経験に根ざしているため、しばしば混同される。 実存主義の哲学者たちは、行動に対する客観的根拠の絶対的な欠如を意味するものとして、しばしば怒りの重要性を強調するが、この動きはしばしば道徳的 ニヒリズムや実存的ニヒリズムに還元される。しかし、実存主義哲学に蔓延するテーマは、アルベール・カミュの哲学的エッセイ『シジフォスの神話』 (1942年)に見られるように、不条理との出会いを耐え抜くことである: 「人はシジフォスの幸福を想像しなければならない」[59]。実存主義の哲学者が道徳や自分で作り出した意味を否定することはごく稀である: セーレン・キルケゴールは宗教的なものの中にある種の道徳性を取り戻し(彼はそれが倫理的なものだとは認めないだろうが;宗教的なものは倫理的なものを保 留する)、ジャン=ポール・サルトルは『存在と無』(1943年)の中で最後の言葉を残した: 「付属的な(あるいは不純な)反省ではなく、純粋な反省に私たちを導くこれらの問いはすべて、倫理的な面においてのみ答えを見出すことができる。われわれ は将来、この問題に取り組むことになるだろう」[44]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Existentialism |
| History Precursors Some have argued that existentialism has long been an element of European religious thought, even before the term came into use. William Barrett identified Blaise Pascal and Søren Kierkegaard as two specific examples.[60] Jean Wahl also identified William Shakespeare's Prince Hamlet ("To be, or not to be"), Jules Lequier, Thomas Carlyle, and William James as existentialists. According to Wahl, "the origins of most great philosophies, like those of Plato, Descartes, and Kant, are to be found in existential reflections."[61] Precursors to existentialism can also be identified in the works of Iranian Muslim philosopher Mulla Sadra (c. 1571–1635), who would posit that "existence precedes essence" becoming the principle expositor of the School of Isfahan, which is described as "alive and active".[according to whom?] 19th century Kierkegaard and Nietzsche Main article: Søren Kierkegaard and Friedrich Nietzsche Kierkegaard is generally considered to have been the first existentialist philosopher.[4][62][63] He proposed that each individual—not reason, society, or religious orthodoxy—is solely tasked with giving meaning to life and living it sincerely, or "authentically".[64][65] Kierkegaard and Nietzsche were two of the first philosophers considered fundamental to the existentialist movement, though neither used the term "existentialism" and it is unclear whether they would have supported the existentialism of the 20th century. They focused on subjective human experience rather than the objective truths of mathematics and science, which they believed were too detached or observational to truly get at the human experience. Like Pascal, they were interested in people's quiet struggle with the apparent meaninglessness of life and the use of diversion to escape from boredom. Unlike Pascal, Kierkegaard and Nietzsche also considered the role of making free choices, particularly regarding fundamental values and beliefs, and how such choices change the nature and identity of the chooser.[66] Kierkegaard's knight of faith and Nietzsche's Übermensch are representative of people who exhibit freedom, in that they define the nature of their own existence. Nietzsche's idealized individual invents his own values and creates the very terms they excel under. By contrast, Kierkegaard, opposed to the level of abstraction in Hegel, and not nearly as hostile (actually welcoming) to Christianity as Nietzsche, argues through a pseudonym that the objective certainty of religious truths (specifically Christian) is not only impossible, but even founded on logical paradoxes. Yet he continues to imply that a leap of faith is a possible means for an individual to reach a higher stage of existence that transcends and contains both an aesthetic and ethical value of life. Kierkegaard and Nietzsche were also precursors to other intellectual movements, including postmodernism, and various strands of psychotherapy.[citation needed] However, Kierkegaard believed that individuals should live in accordance with their thinking.[67] In Twilight of the Idols, Nietzsche's sentiments resonate the idea of "existence precedes essence." He writes, "no one gives man his qualities-- neither God, nor society, nor his parents and ancestors, nor he himself...No one is responsible for man's being there at all, for his being such-and-such, or for his being in these circumstances or in this environment...Man is not the effect of some special purpose of a will, and end..."[68] Within this view, Nietzsche ties in his rejection of the existence of God, which he sees as a means to "redeem the world." By rejecting the existence of God, Nietzsche also rejects beliefs that claim humans have a predestined purpose according to what God has instructed. Dostoyevsky The first important literary author also important to existentialism was the Russian, Dostoyevsky.[69] Dostoyevsky's Notes from Underground portrays a man unable to fit into society and unhappy with the identities he creates for himself. Sartre, in his book on existentialism Existentialism is a Humanism, quoted Dostoyevsky's The Brothers Karamazov as an example of existential crisis. Other Dostoyevsky novels covered issues raised in existentialist philosophy while presenting story lines divergent from secular existentialism: for example, in Crime and Punishment, the protagonist Raskolnikov experiences an existential crisis and then moves toward a Christian Orthodox worldview similar to that advocated by Dostoyevsky himself.[70] Early 20th century See also: Martin Heidegger In the first decades of the 20th century, a number of philosophers and writers explored existentialist ideas. The Spanish philosopher Miguel de Unamuno y Jugo, in his 1913 book The Tragic Sense of Life in Men and Nations, emphasized the life of "flesh and bone" as opposed to that of abstract rationalism. Unamuno rejected systematic philosophy in favor of the individual's quest for faith. He retained a sense of the tragic, even absurd nature of the quest, symbolized by his enduring interest in the eponymous character from the Miguel de Cervantes novel Don Quixote. A novelist, poet and dramatist as well as philosophy professor at the University of Salamanca, Unamuno wrote a short story about a priest's crisis of faith, Saint Manuel the Good, Martyr, which has been collected in anthologies of existentialist fiction. Another Spanish thinker, José Ortega y Gasset, writing in 1914, held that human existence must always be defined as the individual person combined with the concrete circumstances of his life: "Yo soy yo y mi circunstancia" ("I am myself and my circumstances"). Sartre likewise believed that human existence is not an abstract matter, but is always situated ("en situation").[citation needed] Although Martin Buber wrote his major philosophical works in German, and studied and taught at the Universities of Berlin and Frankfurt, he stands apart from the mainstream of German philosophy. Born into a Jewish family in Vienna in 1878, he was also a scholar of Jewish culture and involved at various times in Zionism and Hasidism. In 1938, he moved permanently to Jerusalem. His best-known philosophical work was the short book I and Thou, published in 1922.[71] For Buber, the fundamental fact of human existence, too readily overlooked by scientific rationalism and abstract philosophical thought, is "man with man", a dialogue that takes place in the so-called "sphere of between" ("das Zwischenmenschliche").[72] Two Russian philosophers, Lev Shestov and Nikolai Berdyaev, became well known as existentialist thinkers during their post-Revolutionary exiles in Paris. Shestov had launched an attack on rationalism and systematization in philosophy as early as 1905 in his book of aphorisms All Things Are Possible. Berdyaev drew a radical distinction between the world of spirit and the everyday world of objects. Human freedom, for Berdyaev, is rooted in the realm of spirit, a realm independent of scientific notions of causation. To the extent the individual human being lives in the objective world, he is estranged from authentic spiritual freedom. "Man" is not to be interpreted naturalistically, but as a being created in God's image, an originator of free, creative acts.[73] He published a major work on these themes, The Destiny of Man, in 1931. Gabriel Marcel, long before coining the term "existentialism", introduced important existentialist themes to a French audience in his early essay "Existence and Objectivity" (1925) and in his Metaphysical Journal (1927).[74] A dramatist as well as a philosopher, Marcel found his philosophical starting point in a condition of metaphysical alienation: the human individual searching for harmony in a transient life. Harmony, for Marcel, was to be sought through "secondary reflection", a "dialogical" rather than "dialectical" approach to the world, characterized by "wonder and astonishment" and open to the "presence" of other people and of God rather than merely to "information" about them. For Marcel, such presence implied more than simply being there (as one thing might be in the presence of another thing); it connoted "extravagant" availability, and the willingness to put oneself at the disposal of the other.[75] Marcel contrasted secondary reflection with abstract, scientific-technical primary reflection, which he associated with the activity of the abstract Cartesian ego. For Marcel, philosophy was a concrete activity undertaken by a sensing, feeling human being incarnate—embodied—in a concrete world.[74][76] Although Sartre adopted the term "existentialism" for his own philosophy in the 1940s, Marcel's thought has been described as "almost diametrically opposed" to that of Sartre.[74] Unlike Sartre, Marcel was a Christian, and became a Catholic convert in 1929. In Germany, the psychologist and philosopher Karl Jaspers—who later described existentialism as a "phantom" created by the public[77]—called his own thought, heavily influenced by Kierkegaard and Nietzsche, Existenzphilosophie. For Jaspers, "Existenz-philosophy is the way of thought by means of which man seeks to become himself...This way of thought does not cognize objects, but elucidates and makes actual the being of the thinker".[78] Jaspers, a professor at the university of Heidelberg, was acquainted with Heidegger, who held a professorship at Marburg before acceding to Husserl's chair at Freiburg in 1928. They held many philosophical discussions, but later became estranged over Heidegger's support of National Socialism. They shared an admiration for Kierkegaard,[79] and in the 1930s, Heidegger lectured extensively on Nietzsche. Nevertheless, the extent to which Heidegger should be considered an existentialist is debatable. In Being and Time he presented a method of rooting philosophical explanations in human existence (Dasein) to be analysed in terms of existential categories (existentiale); and this has led many commentators to treat him as an important figure in the existentialist movement. After the Second World War Following the Second World War, existentialism became a well-known and significant philosophical and cultural movement, mainly through the public prominence of two French writers, Jean-Paul Sartre and Albert Camus, who wrote best-selling novels, plays and widely read journalism as well as theoretical texts.[80] These years also saw the growing reputation of Being and Time outside Germany. French philosophers Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir Sartre dealt with existentialist themes in his 1938 novel Nausea and the short stories in his 1939 collection The Wall, and had published his treatise on existentialism, Being and Nothingness, in 1943, but it was in the two years following the liberation of Paris from the German occupying forces that he and his close associates—Camus, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, and others—became internationally famous as the leading figures of a movement known as existentialism.[81] In a very short period of time, Camus and Sartre in particular became the leading public intellectuals of post-war France, achieving by the end of 1945 "a fame that reached across all audiences."[82] Camus was an editor of the most popular leftist (former French Resistance) newspaper Combat; Sartre launched his journal of leftist thought, Les Temps Modernes, and two weeks later gave the widely reported lecture on existentialism and secular humanism to a packed meeting of the Club Maintenant. Beauvoir wrote that "not a week passed without the newspapers discussing us";[83] existentialism became "the first media craze of the postwar era."[84] By the end of 1947, Camus' earlier fiction and plays had been reprinted, his new play Caligula had been performed and his novel The Plague published; the first two novels of Sartre's The Roads to Freedom trilogy had appeared, as had Beauvoir's novel The Blood of Others. Works by Camus and Sartre were already appearing in foreign editions. The Paris-based existentialists had become famous.[81] Sartre had traveled to Germany in 1930 to study the phenomenology of Edmund Husserl and Martin Heidegger,[85] and he included critical comments on their work in his major treatise Being and Nothingness. Heidegger's thought had also become known in French philosophical circles through its use by Alexandre Kojève in explicating Hegel in a series of lectures given in Paris in the 1930s.[86] The lectures were highly influential; members of the audience included not only Sartre and Merleau-Ponty, but Raymond Queneau, Georges Bataille, Louis Althusser, André Breton, and Jacques Lacan.[87] A selection from Being and Time was published in French in 1938, and his essays began to appear in French philosophy journals. French philosopher, novelist, and playwright Albert Camus Heidegger read Sartre's work and was initially impressed, commenting: "Here for the first time I encountered an independent thinker who, from the foundations up, has experienced the area out of which I think. Your work shows such an immediate comprehension of my philosophy as I have never before encountered."[88] Later, however, in response to a question posed by his French follower Jean Beaufret,[89] Heidegger distanced himself from Sartre's position and existentialism in general in his Letter on Humanism.[90] Heidegger's reputation continued to grow in France during the 1950s and 1960s. In the 1960s, Sartre attempted to reconcile existentialism and Marxism in his work Critique of Dialectical Reason. A major theme throughout his writings was freedom and responsibility. Camus was a friend of Sartre, until their falling-out, and wrote several works with existential themes including The Rebel, Summer in Algiers, The Myth of Sisyphus, and The Stranger, the latter being "considered—to what would have been Camus's irritation—the exemplary existentialist novel."[91] Camus, like many others, rejected the existentialist label, and considered his works concerned with facing the absurd. In the titular book, Camus uses the analogy of the Greek myth of Sisyphus to demonstrate the futility of existence. In the myth, Sisyphus is condemned for eternity to roll a rock up a hill, but when he reaches the summit, the rock will roll to the bottom again. Camus believes that this existence is pointless but that Sisyphus ultimately finds meaning and purpose in his task, simply by continually applying himself to it. The first half of the book contains an extended rebuttal of what Camus took to be existentialist philosophy in the works of Kierkegaard, Shestov, Heidegger, and Jaspers. Simone de Beauvoir, an important existentialist who spent much of her life as Sartre's partner, wrote about feminist and existentialist ethics in her works, including The Second Sex and The Ethics of Ambiguity. Although often overlooked due to her relationship with Sartre,[92] de Beauvoir integrated existentialism with other forms of thinking such as feminism, unheard of at the time, resulting in alienation from fellow writers such as Camus.[70] Paul Tillich, an important existentialist theologian following Kierkegaard and Karl Barth, applied existentialist concepts to Christian theology, and helped introduce existential theology to the general public. His seminal work The Courage to Be follows Kierkegaard's analysis of anxiety and life's absurdity, but puts forward the thesis that modern humans must, via God, achieve selfhood in spite of life's absurdity. Rudolf Bultmann used Kierkegaard's and Heidegger's philosophy of existence to demythologize Christianity by interpreting Christian mythical concepts into existentialist concepts. Maurice Merleau-Ponty, an existential phenomenologist, was for a time a companion of Sartre. Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception (1945) was recognized as a major statement of French existentialism.[93] It has been said that Merleau-Ponty's work Humanism and Terror greatly influenced Sartre. However, in later years they were to disagree irreparably, dividing many existentialists such as de Beauvoir,[70] who sided with Sartre. Colin Wilson, an English writer, published his study The Outsider in 1956, initially to critical acclaim. In this book and others (e.g. Introduction to the New Existentialism), he attempted to reinvigorate what he perceived as a pessimistic philosophy and bring it to a wider audience. He was not, however, academically trained, and his work was attacked by professional philosophers for lack of rigor and critical standards.[94] |
歴史[編集] 前身[編集] 実存主義という言葉が使われるようになる以前から、実存主義はヨーロッパの宗教思想の要素であったと主張する者もいる。ウィリアム・バレットは ブレーズ・パスカルと セーレン・キェルケゴールを2つの具体例として挙げている[60]。ジャン・ウォールも ウィリアム・シェイクスピアの ハムレット王子(「To be, or not to be」)、ジュール・レキエ、トマス・カーライル、ウィリアム・ジェームズを実存主義者として挙げている。ワールによれば、「プラトン、デカルト、カント のようなほとんどの偉大な哲学の起源は、実存的考察の中に見出すことができる」[61]。実存主義の前身は、イランのイスラム哲学者であるムラ・サドラ (1571年頃~1635年)の著作にも見出すことができ、彼は「実存は本質に先行する」と唱え、「生き生きと活動している」と評されるイスファハン学派 の主要な論者となった。 19世紀[編集] キルケゴールとニーチェ[編集]。 主な記事 セーレン・キルケゴールとフリードリヒ・ニーチェ キルケゴールは一般的に最初の実存主義の哲学者であると考えられている[4][62][63]。 彼は、理性でも社会でも宗教の正統性でもなく、各個人が人生に意味を与え、それを誠実に生きること、すなわち「真正に」生きることだけが唯一の使命である と提唱した[64][65]。 キルケゴールとニーチェは実存主義運動の根幹をなすと考えられている最初の哲学者の2人であったが、どちらも「実存主義」という言葉は使っておらず、彼ら が20世紀の実存主義を支持していたかどうかは不明である。彼らは、数学や科学の客観的真理よりも、主観的な人間の経験に焦点を当てた。パスカルと同様、 彼らは、人生の無意味さとの静かな葛藤や、退屈から逃れるための気晴らしに関心を寄せていた。パスカルとは異なり、キルケゴールやニーチェはまた、特に基 本的な価値観や信念に関して、自由な選択をすることの役割や、そのような選択が選択者の性質やアイデンティティをどのように変化させるかについて考えてい た[66]。ニーチェの理想化された個人は、自分自身の価値観を発明し、その価値観が卓越する条件そのものを作り出している。対照的に、キルケゴールは、 ヘーゲルの抽象化のレベルに反対し、ニーチェほどキリスト教に敵対していない(実際には歓迎している)が、仮名を通して、宗教的真理(特にキリスト教)の 客観的確実性は不可能であるだけでなく、論理的逆説の上に成り立っているとさえ主張している。しかし彼は、個人が美的価値と倫理的価値の両方を超越した、 より高次の存在段階に到達するためには、信仰の飛躍が可能な手段であるとほのめかし続けている。キルケゴールとニーチェはまた、ポストモダニズムや様々な 心理療法など、他の知的運動の先駆者でもあった。 ニーチェは『偶像の黄昏』の中で、"存在は本質に先立つ "という考え方に共鳴している。神も、社会も、彼の両親や先祖も、彼自身も...人間がそこにいること、彼がそのような存在であること、彼がこのような状 況や環境にいることについては、誰も責任を負っていない...人間は、意志や目的といった特別な目的の結果ではない...」[68]。この見解の中で、 ニーチェは神の存在に対する拒絶を結びつけている。神の存在を否定することで、ニーチェは、神が指示したことに従って人間が定められた目的を持っていると 主張する信仰も否定している。 ドストエフスキー[編集] 実存主義にとっても重要な最初の文学者は、ロシアのドストエフスキーである[69]。ドストエフスキーの『地下からの覚書』は、社会に適合することができ ず、自ら作り出したアイデンティティに不満を抱く男を描いている。サルトルは実存主義に関する著書『実存主義はヒューマニズムである』の中で、実存的危機 の例としてドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を引用している。例えば、『罪と罰』では、主人公のラスコーリニコフが実存的危機を経験した後、ドス トエフスキー自身が提唱したのと同じようなキリスト教正統派の世界観へと向かっていく[70]。 20世紀初頭[編集] 以下も参照のこと: マルティン・ハイデガー 20世紀の最初の数十年間、多くの哲学者や作家が実存主義の思想を探求した。スペインの哲学者であるミゲル・デ・ウナムーノ・イ・ジュゴは、1913年に 出版した『人間と国家における生の悲劇的感覚』の中で、抽象的な合理主義とは対照的に「肉と骨」の生を強調した。ウナムーノは体系的な哲学を否定し、個人 の信仰の探求を支持した。彼は、ミゲル・デ・セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』の登場人物への永続的な関心に象徴されるように、探求の悲劇的で不条理 ですらある本質を感じ続けていた。小説家、詩人、劇作家であり、サラマンカ大学の哲学教授でもあったウナムーノは、司祭の信仰の危機を描いた短編小説『殉 教者聖マヌエル』を書き、実存主義小説のアンソロジーに収められている。もう一人のスペインの思想家、ホセ・オルテガ・イ・ガセットは1914年に、人間 の存在とは常に、個人と人生の具体的な状況との組み合わせとして定義されなければならないとした。サルトルも同様に、人間の存在は抽象的な問題ではなく、 常に状況に置かれていると考えていた。 マルティン・ブーバーは主要な哲学的著作をドイツ語で執筆し、ベルリン大学とフランクフルト大学で学び、教えていたが、ドイツ哲学の主流からは離れてい た。1878年にウィーンのユダヤ人家庭に生まれたブーバーは、ユダヤ文化の研究者でもあり、シオニズムや ハシディズムにさまざまな形で関わった。1938年にはエルサレムに永住した。ブーバーにとって、人間存在の根本的な事実は、科学的合理主義や抽象的な哲 学的思考によってあまりにも簡単に見過ごされてしまうが、「人間と人間」であり、いわゆる「間の領域」(「das Zwischenmenschliche」)で行われる対話である[72]。 レフ・シェストフと ニコライ・ベルジャエフという二人のロシア人哲学者は、革命後のパリ亡命中に実存主義思想家としてよく知られるようになった。シェストフは1905年、 『万物は可能である』という格言集で、早くも哲学における合理主義と体系化への攻撃を開始した。ベルジャエフは、精神の世界と日常的な物の世界とを根本的 に区別した。ベルニャエフにとって人間の自由とは、科学的な因果関係の概念から独立した精神の領域に根ざしている。個々の人間が客観的な世界に生きている 限り、彼は本物の精神的自由から遠ざかっている。「人間」は自然主義的に解釈されるべきものではなく、神に似せて創造された存在であり、自由で創造的な行 為の創始者である[73]。 ガブリエル・マルセル(Gabriel Marcel)は、「実存主義」という言葉を作るずっと前に、初期のエッセイ『実存と客観性』(1925年)や『形而上学雑誌』(1927年)の中で、フ ランスの聴衆に実存主義の重要なテーマを紹介している[74]。マルセルにとっての調和とは、「弁証法的」ではなく「対話的」な世界に対するアプローチで あり、「驚きと驚愕」を特徴とし、他者や神についての単なる「情報」ではなく、その「存在」に開かれた「二次的反省」によって求められるものであった。マ ルセルにとって、このような「プレゼンス」は、単にそこに存在する(あるものが別のものの前に存在するように)以上のことを意味し、「贅沢な」利用可能 性、そして他者の自由に身を委ねる意思を含意していた[75]。 マルセルは二次的な内省を抽象的で科学技術的な一次的な内省と対比させ、抽象的なデカルト的自我の活動と結びつけていた。サルトルは1940年代に自身の 哲学に「実存主義」という言葉を採用したが、マルセルの思想はサルトルのそれとは「ほとんど正反対」と評されている[74]。サルトルとは異なり、マルセ ルはキリスト教徒であり、1929年にカトリックに改宗した。 ドイツでは、心理学者であり哲学者であったカール・ヤスパースが、後に実存主義を大衆によって作り出された「幻影」であると評し[77]、キルケゴールと ニーチェの影響を強く受けた自身の思想を「実存哲学」と呼んでいた。ヤスパースにとって、「実存哲学とは、人間が自分自身になろうとする思考の方法であ る......この思考の方法は対象を認識するのではなく、思考者の存在を解明し、現実化するものである」[78]。 ハイデルベルク大学の教授であったヤスパースは、ハイデガーと面識があった。ハイデガーはマールブルクで教授職を務めた後、1928年にフライブルクで フッサールの講座に就任した。二人は多くの哲学的議論を交わしたが、ハイデガーが国家社会主義を支持していたことから、後に疎遠になった。二人はキルケ ゴールに対する尊敬の念を共有しており[79]、1930年代にはハイデガーはニーチェについて広く講義を行っていた。とはいえ、ハイデガーをどこまで実 存主義者とみなすべきかは議論の余地がある。ハイデガーは『存在と時間』において、哲学的説明を人間の存在(Dasein)に根付かせ、実存的カテゴリー (existentiale)の観点から分析するという方法を提示した。 第二次世界大戦後[編集] 第二次世界大戦後、実存主義は、主にジャン=ポール・サルトルと アルベール・カミュという二人のフランス人作家の活躍によって、よく知られた重要な哲学的・文化的運動となり、彼らは理論的なテキストだけでなく、ベスト セラーの小説や戯曲、広く読まれるジャーナリズムを書いた[80]。 フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルと シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、『存在と時間』を実存主義的な思想として扱った。 サルトルは1938年の小説『吐き気』や1939年の作品集『壁』の短編で実存主義のテーマを扱い、1943年には実存主義に関する論考『存在と無』を出 版していたが、彼と彼の側近であるカミュ、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、モーリス・メルロ=ポンティらが実存主義として知られる運動の中心人物として国 際的に有名になったのは、ドイツ占領軍からのパリ解放後の2年間であった。 [カミュとサルトルは特に短期間のうちに戦後フランスを代表する知識人となり、1945年末には「あらゆる聴衆に届く名声」を獲得した[82]。サルトル は左翼思想の雑誌『レ・タン・モダン』を創刊し、その2週間後にはクラブ・マントナンの満員の会合で実存主義と世俗的ヒューマニズムに関する講演を行い、 広く報道された。ボーヴォワールは「新聞が私たちのことを論じない週はなかった」と書いている[83]。実存主義は「戦後最初のメディア・ブーム」となっ た[84]。 1947年末までに、カミュの初期の小説と戯曲は再版され、新作の戯曲『カリギュラ』は上演され、小説『ペスト』は出版された。サルトルの『自由への道』 三部作の最初の二作が発表され、ボーヴォワールの小説『他人の血』も発表された。カミュとサルトルの作品はすでに海外版で出版されていた。パリを拠点とす る実存主義者たちは有名になっていた[81]。 サルトルは1930年にドイツに渡り、エドムント・フッサールと マルティン・ハイデガーの 現象学を学んでおり[85]、彼の主要な論考である『存在と無』には彼らの仕事に対する批判的なコメントが含まれていた。ハイデガーの思想はまた、アレク サンドル・コジェーヴが1930年代にパリで行った一連の講義でヘーゲルを説明する際に用いたことで、フランスの哲学界でも知られるようになっていた [86]。この講義は大きな影響力を持ち、聴衆のメンバーにはサルトルやメルロ=ポンティだけでなく、レイモン・クノー、ジョルジュ・バタイユ、ルイ・ア ルチュセール、アンドレ・ブルトン、ジャック・ラカンなどが含まれていた[87]。1938年には『存在と時間』からの抜粋がフランス語で出版され、彼の エッセイがフランスの哲学雑誌に掲載され始めた。 フランスの哲学者、小説家、劇作家であるアルベール・カミュは、サルトルのエッセイを読んでいた。 ハイデガーはサルトルの著作を読み、最初に感銘を受け、こうコメントした: 「私はここで初めて、私が考える領域を基礎から経験した独立した思想家に出会った。ハイデガーの評価は1950年代から1960年代にかけてフランスで高 まり続けた。1960年代、サルトルは『弁証法的理性批判』の中で実存主義とマルクス主義の融和を試みた。彼の著作の主要なテーマは自由と責任であった。 カミュはサルトルの友人であり、『反逆者』、『アルジェの夏』、『シジフォスの神話』、『ストレンジャー』など、実存主義をテーマにした作品を書いた。表 題作の中でカミュは、存在の無益さを示すためにギリシャ神話のシジフォスのアナロジーを用いている。神話では、シジフォスは永遠に石を転がして丘を登るこ とを宣告されるが、頂上に到達しても、石は再び下まで転がっていく。カミュは、このような存在は無意味だが、シジフォスは最終的に、ただひたすらその仕事 に打ち込むことによって、その仕事に意味と目的を見出すのだと考えている。本書の前半には、カミュがキルケゴール、シェストフ、ハイデガー、ヤスパースの 作品から実存主義哲学とみなしたものに対する反論が延々と書かれている。 シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、サルトルのパートナーとして人生の大半を過ごした重要な実存主義者であり、『第二の性』や『曖昧さの倫理学』などの著作 の中で、フェミニズムと実存主義の倫理について書いている。サルトルとの関係から見過ごされがちであるが[92]、ド・ボーヴォワールは実存主義をフェミ ニズムなどの他の思考形態と統合した。 キルケゴールやカール・バルトに続く重要な実存主義神学者であるパウル・ティリッヒは、キリスト教神学に実存主義の概念を適用し、実存主義神学を一般大衆 に紹介するのに貢献した。彼の代表的な著作『存在する勇気』は、キルケゴールの不安と人生の不条理についての分析を踏襲しつつも、現代人は人生の不条理に もかかわらず、神を介して自我を獲得しなければならないというテーゼを提唱している。ルドルフ・ブルルトマンは、キルケゴールとハイデガーの実存哲学を用 いて、キリスト教の神話的概念を実存主義的概念に解釈することで、キリスト教を脱神話化した。 実存現象学者であるモーリス・メルロ=ポンティは、一時期サルトルの仲間だった。メルロ=ポンティの『知覚の現象学』(1945年)はフランス実存主義の 主要な声明として認識されている。しかし後年、両者は修復不可能なほど意見が対立し、サルトルに味方したド・ボーヴォワール[70]など多くの実存主義者 を分裂させることになる。 イギリスの作家であるコリン・ウィルソンは、1956年に『アウトサイダー』という研究書を出版し、当初は批評家の称賛を浴びた。この本や他の本(『新実 存主義入門』など)において、彼は厭世的な哲学として認識されていたものを再活性化し、より多くの読者に届けようとした。しかし、彼はアカデミックな訓練 を受けておらず、彼の著作は厳密さや批評的基準が欠けているとして、プロの哲学者たちから攻撃された[94]。 |
| Influence outside philosophy Art Film and television Adolphe Menjou (left) and Kirk Douglas (right) in Paths of Glory (1957) Stanley Kubrick's 1957 anti-war film Paths of Glory "illustrates, and even illuminates...existentialism" by examining the "necessary absurdity of the human condition" and the "horror of war".[95] The film tells the story of a fictional World War I French army regiment ordered to attack an impregnable German stronghold; when the attack fails, three soldiers are chosen at random, court-martialed by a "kangaroo court", and executed by firing squad. The film examines existentialist ethics, such as the issue of whether objectivity is possible and the "problem of authenticity".[95] Orson Welles's 1962 film The Trial, based upon Franz Kafka's book of the same name (Der Prozeß), is characteristic of both existentialist and absurdist themes in its depiction of a man (Joseph K.) arrested for a crime for which the charges are neither revealed to him nor to the reader. Neon Genesis Evangelion is a Japanese science fiction animation series created by the anime studio Gainax and was both directed and written by Hideaki Anno. Existential themes of individuality, consciousness, freedom, choice, and responsibility are heavily relied upon throughout the entire series, particularly through the philosophies of Jean-Paul Sartre and Søren Kierkegaard. Episode 16's title, "The Sickness Unto Death, And..." (死に至る病、そして, Shi ni itaru yamai, soshite) is a reference to Kierkegaard's book, The Sickness Unto Death. Some contemporary films dealing with existentialist issues include Melancholia, Fight Club, I Heart Huckabees, Waking Life, The Matrix, Ordinary People, Life in a Day, Barbie, and Everything Everywhere All at Once.[96] Likewise, films throughout the 20th century such as The Seventh Seal, Ikiru, Taxi Driver, the Toy Story films, The Great Silence, Ghost in the Shell, Harold and Maude, High Noon, Easy Rider, One Flew Over the Cuckoo's Nest, A Clockwork Orange, Groundhog Day, Apocalypse Now, Badlands, and Blade Runner also have existentialist qualities.[97] Notable directors known for their existentialist films include Ingmar Bergman, Bela Tarr, Robert Bresson, Jean-Pierre Melville, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, Akira Kurosawa, Terrence Malick, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky, Éric Rohmer, Wes Anderson, Woody Allen, and Christopher Nolan.[98] Charlie Kaufman's Synecdoche, New York focuses on the protagonist's desire to find existential meaning.[99] Similarly, in Kurosawa's Red Beard, the protagonist's experiences as an intern in a rural health clinic in Japan lead him to an existential crisis whereby he questions his reason for being. This, in turn, leads him to a better understanding of humanity. The French film, Mood Indigo (directed by Michel Gondry) embraced various elements of existentialism.[citation needed] The film The Shawshank Redemption, released in 1994, depicts life in a prison in Maine, United States to explore several existentialist concepts.[100] Literature A simple book cover in green displays the name of the author and the book First edition of The Trial by Franz Kafka (1925) Existential perspectives are also found in modern literature to varying degrees, especially since the 1920s. Louis-Ferdinand Céline's Journey to the End of the Night (Voyage au bout de la nuit, 1932) celebrated by both Sartre and Beauvoir, contained many of the themes that would be found in later existential literature, and is in some ways, the proto-existential novel. Jean-Paul Sartre's 1938 novel Nausea[101] was "steeped in Existential ideas", and is considered an accessible way of grasping his philosophical stance.[102] Between 1900 and 1960, other authors such as Albert Camus, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, T. S. Eliot, Yukio Mishima, Hermann Hesse, Luigi Pirandello,[34][35][37][103][104][105] Ralph Ellison,[106][107][108][109] and Jack Kerouac composed literature or poetry that contained, to varying degrees, elements of existential or proto-existential thought. The philosophy's influence even reached pulp literature shortly after the turn of the 20th century, as seen in the existential disparity witnessed in Man's lack of control of his fate in the works of H. P. Lovecraft.[110] Theatre Sartre wrote No Exit in 1944, an existentialist play originally published in French as Huis Clos (meaning In Camera or "behind closed doors"), which is the source of the popular quote, "Hell is other people." (In French, "L'enfer, c'est les autres"). The play begins with a Valet leading a man into a room that the audience soon realizes is in hell. Eventually he is joined by two women. After their entry, the Valet leaves and the door is shut and locked. All three expect to be tortured, but no torturer arrives. Instead, they realize they are there to torture each other, which they do effectively by probing each other's sins, desires, and unpleasant memories. Existentialist themes are displayed in the Theatre of the Absurd, notably in Samuel Beckett's Waiting for Godot, in which two men divert themselves while they wait expectantly for someone (or something) named Godot who never arrives. They claim Godot is an acquaintance, but in fact, hardly know him, admitting they would not recognize him if they saw him. Samuel Beckett, once asked who or what Godot is, replied, "If I knew, I would have said so in the play." To occupy themselves, the men eat, sleep, talk, argue, sing, play games, exercise, swap hats, and contemplate suicide—anything "to hold the terrible silence at bay".[111] The play "exploits several archetypal forms and situations, all of which lend themselves to both comedy and pathos."[112] The play also illustrates an attitude toward human experience on earth: the poignancy, oppression, camaraderie, hope, corruption, and bewilderment of human experience that can be reconciled only in the mind and art of the absurdist. The play examines questions such as death, the meaning of human existence and the place of God in human existence. Tom Stoppard's Rosencrantz & Guildenstern Are Dead is an absurdist tragicomedy first staged at the Edinburgh Festival Fringe in 1966.[113] The play expands upon the exploits of two minor characters from Shakespeare's Hamlet. Comparisons have also been drawn to Samuel Beckett's Waiting for Godot, for the presence of two central characters who appear almost as two halves of a single character. Many plot features are similar as well: the characters pass time by playing Questions, impersonating other characters, and interrupting each other or remaining silent for long periods of time. The two characters are portrayed as two clowns or fools in a world beyond their understanding. They stumble through philosophical arguments while not realizing the implications, and muse on the irrationality and randomness of the world. Jean Anouilh's Antigone also presents arguments founded on existentialist ideas.[114] It is a tragedy inspired by Greek mythology and the play of the same name (Antigone, by Sophocles) from the fifth century BC. In English, it is often distinguished from its antecedent by being pronounced in its original French form, approximately "Ante-GŌN." The play was first performed in Paris on 6 February 1944, during the Nazi occupation of France. Produced under Nazi censorship, the play is purposefully ambiguous with regards to the rejection of authority (represented by Antigone) and the acceptance of it (represented by Creon). The parallels to the French Resistance and the Nazi occupation have been drawn. Antigone rejects life as desperately meaningless but without affirmatively choosing a noble death. The crux of the play is the lengthy dialogue concerning the nature of power, fate, and choice, during which Antigone says that she is, "... disgusted with [the]...promise of a humdrum happiness." She states that she would rather die than live a mediocre existence. Critic Martin Esslin in his book Theatre of the Absurd pointed out how many contemporary playwrights such as Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jean Genet, and Arthur Adamov wove into their plays the existentialist belief that we are absurd beings loose in a universe empty of real meaning. Esslin noted that many of these playwrights demonstrated the philosophy better than did the plays by Sartre and Camus. Though most of such playwrights, subsequently labeled "Absurdist" (based on Esslin's book), denied affiliations with existentialism and were often staunchly anti-philosophical (for example Ionesco often claimed he identified more with 'Pataphysics or with Surrealism than with existentialism), the playwrights are often linked to existentialism based on Esslin's observation.[115] Activism Black existentialism explores the existence and experiences of Black people in the world.[116] Classical and contemporary thinkers include C.L.R James, Frederick Douglass, W.E.B DuBois, Frantz Fanon, Angela Davis, Cornel West, Naomi Zack, bell hooks, Stuart Hall, Lewis Gordon, and Audre Lorde.[117] Psychoanalysis and psychotherapy Main article: Existential therapy A major offshoot of existentialism as a philosophy is existentialist psychology and psychoanalysis, which first crystallized in the work of Otto Rank, Freud's closest associate for 20 years. Without awareness of the writings of Rank, Ludwig Binswanger was influenced by Freud, Edmund Husserl, Heidegger, and Sartre. A later figure was Viktor Frankl, who briefly met Freud as a young man.[118] His logotherapy can be regarded as a form of existentialist therapy. The existentialists would also influence social psychology, antipositivist micro-sociology, symbolic interactionism, and post-structuralism, with the work of thinkers such as Georg Simmel[119] and Michel Foucault. Foucault was a great reader of Kierkegaard even though he almost never refers to this author, who nonetheless had for him an importance as secret as it was decisive.[120] An early contributor to existentialist psychology in the United States was Rollo May, who was strongly influenced by Kierkegaard and Otto Rank. One of the most prolific writers on techniques and theory of existentialist psychology in the US is Irvin D. Yalom. Yalom states that Aside from their reaction against Freud's mechanistic, deterministic model of the mind and their assumption of a phenomenological approach in therapy, the existentialist analysts have little in common and have never been regarded as a cohesive ideological school. These thinkers—who include Ludwig Binswanger, Medard Boss, Eugène Minkowski, V. E. Gebsattel, Roland Kuhn, G. Caruso, F. T. Buytendijk, G. Bally, and Victor Frankl—were almost entirely unknown to the American psychotherapeutic community until Rollo May's highly influential 1958 book Existence—and especially his introductory essay—introduced their work into this country.[121] A more recent contributor to the development of a European version of existentialist psychotherapy is the British-based Emmy van Deurzen.[122] Anxiety's importance in existentialism makes it a popular topic in psychotherapy. Therapists often offer existentialist philosophy as an explanation for anxiety. The assertion is that anxiety is manifested of an individual's complete freedom to decide, and complete responsibility for the outcome of such decisions. Psychotherapists using an existentialist approach believe that a patient can harness his anxiety and use it constructively. Instead of suppressing anxiety, patients are advised to use it as grounds for change. By embracing anxiety as inevitable, a person can use it to achieve his full potential in life. Humanistic psychology also had major impetus from existentialist psychology and shares many of the fundamental tenets. Terror management theory, based on the writings of Ernest Becker and Otto Rank, is a developing area of study within the academic study of psychology. It looks at what researchers claim are implicit emotional reactions of people confronted with the knowledge that they will eventually die.[123] Also, Gerd B. Achenbach has refreshed the Socratic tradition with his own blend of philosophical counseling; as did Michel Weber with his Chromatiques Center in Belgium.[citation needed] |
哲学以外への影響[編集] 芸術[編集] 映画とテレビ[編集] 栄光の道』(1957年)におけるアドルフ・メンジュー(左)とカーク・ダグラス(右) スタンリー・キューブリックの1957年の反戦映画『栄光の道』は、「人間状態の必要な不条理」と「戦争の恐怖」を検証することによって、「実存主義を説 明し、さらには照らし出している」[95]。この映画は、難攻不落のドイツ軍の要塞を攻撃するよう命じられた架空の第一次世界大戦のフランス軍連隊の物語 であり、攻撃が失敗すると、3人の兵士が無作為に選ばれ、「カンガルー法廷」によって軍法会議にかけられ、銃殺刑に処される。この映画は、客観性が可能か どうかという問題や「真正性の問題」といった実存主義的倫理を検証している[95]。フランツ・カフカの同名の著書(Der Prozeß)を原作としたオーソン・ウェルズの1962年の映画『裁判』は、罪状が本人にも読者にも明らかにされていない罪で逮捕された男(ヨーゼフ・ K)を描いている点で、実存主義と不条理主義の両方のテーマを特徴づけている。 新世紀エヴァンゲリオン』は、庵野秀明が監督・脚本を務め、 ガイナックスが制作した日本のSFアニメである。個性、意識、自由、選択、責任といった実存的なテーマが、シリーズ全体を通して、特にジャン=ポール・サ ルトルや セーレン・キェルケゴールの哲学に大きく依拠している。第16話のタイトル「死に至る病、そして...」は、キルケゴールの著書『死に至る 病』にちなんでいる。 実存主義の問題を扱った現代映画には、『メランコリア』、『ファイト・クラブ』、『アイ・ハート・ハッカビー』、『ウェイキング・ライフ』、『マトリック ス』、『普通の人々』、『ライフ・イン・ア・デイ』、『バービー』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』などがある。 [同様に、『第七の封印』、『生きる』、『タクシードライバー』、『トイ・ストーリー』、『大いなる沈黙』、『ゴースト・イン・ザ・シェル』、『ハロルド とモード』、『ハイ・ヌーン』、『イージー・ライダー』、『カッコーの巣の上で一羽』、『時計じかけのオレンジ』、『グラウンドホッグ・デイ』、『アポカ リプス・ナウ』、『バッドランズ』、『ブレードランナー』といった20世紀を通しての映画も実存主義的な特質を備えている[97]。 実存主義映画で知られる著名な監督には、イングマール・ベルイマン、ベラ・タル、ロベール・ブレッソン、ジャン=ピエール・メルヴィル、フランソワ・ト リュフォー、ジャン=リュック・ゴダール、ミケランジェロ・アントニオーニ、黒澤明、テレンス・マリック、スタンリー・キューブリック、アンドレイ・タル コフスキー、エリック・ロメール、ウェス・アンダーソン、ウディ・アレン、クリストファー・ノーランなどがいる。 [チャーリー・カウフマンの『シネクドシュ、ニューヨーク』では、実存的な意味を見出そうとする主人公の願望に焦点が当てられている[99]。同様に、黒 澤監督の『赤ひげ』では、日本の田舎の診療所で研修医として働いた主人公の体験が、自分の存在理由を問う実存的危機に彼を導く。その結果、彼は人間性をよ りよく理解するようになる。フランス映画『ムード・インディゴ』(ミシェル・ゴンドリー監督)は、実存主義の様々な要素を取り入れている [citation needed]1994年に公開された映画『ショーシャンクの空に』は、アメリカ・メイン州の刑務所での生活を描き、いくつかの実存主義の概念を探求して いる[100]。 文学[編集] フランツ・カフカの 『裁判』初版(1925年) 実存主義的な視点は、特に1920年代以降の現代文学にも程度の差こそあれ見られる。ルイ=フェルディナン・セリーヌの『夜の果てへの旅』(Voyage au bout de la nuit、1932年)は、サルトルとボーヴォワールの両者によって称賛され、後の実存文学に見られるようになるテーマの多くを含んでおり、ある意味で実 存小説の原型である。ジャン=ポール・サルトルが1938年に発表した小説『吐き気』[101]は「実存的思想に染まった」ものであり、彼の哲学的スタン スを理解するためのわかりやすい方法だと考えられている。エリオット、三島由紀夫、ヘルマン・ヘッセ、ルイジ・ピランデッロ、[34][35][37] [103][104][105] ラルフ・エリソン、[106][107][108][109] ジャック・ケルアックなどの作家が、程度の差こそあれ、実存的思想や原実存的思想の要素を含む文学や詩を書いた。この哲学の影響は、H・P・ラヴクラフト の作品における人間の運命のコントロールの欠如に見られる実存的格差に見られるように、20世紀に入って間もなくのパルプ文学にまで及んでいた [110]。 演劇[編集] サルトルは1944年に『出口なし』という実存主義的な戯曲を書き、当初はフランス語で『ハウ・クロ』(『カメラの中』または『閉ざされたドアの向こう 側』の意)として出版された。(フランス語で "L'enfer, c'est les autres")。戯曲は、ヴァレトが一人の男を部屋に案内するところから始まる。やがて彼に2人の女性が加わる。彼女たちが入ると、従者が立ち去り、ド アが閉められ鍵がかけられる。3人とも拷問されると思っていたが、拷問者は来なかった。その代わり、彼らは互いを拷問するためにそこにいるのだと悟り、互 いの罪、欲望、不快な記憶を探り合うことによって、効果的にそれを実行する。 サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』では、2人の男が、ゴドーという名の誰か(あるいは何か)を待ち望みながら、決してやってこないゴドーを自 分たちの気を紛らわせる。二人はゴドーを知人だと言うが、実際には彼のことをほとんど知らず、会ってもわからないだろうと認めている。サミュエル・ベケッ トは、ゴドーとは誰なのか、何なのかと聞かれたことがあるが、「もし知っていたら、戯曲の中でそう答えただろう」と答えている。この戯曲は「いくつかの典 型的な形式と状況を利用しており、そのすべてが喜劇とペーソスの両方に適している」[111]。 「不条理主義者の精神と芸術においてのみ調和しうる、人間の経験の痛切さ、抑圧、仲間意識、希望、腐敗、困惑である。この戯曲は、死、人間存在の意味、人 間存在における神の位置といった問題を考察している。 トム・ストッパードの『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』は、1966年にエディンバラ・フェスティバル・フリンジで初演された不条理 悲喜劇である 。また、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』との比較もなされている。登場人物たちは、質問をしたり、他の登場人物になりすましたり、お互いの 邪魔をしたり、長い間黙っていたりすることで時間をつぶしている。2人の登場人物は、理解の及ばない世界にいる2人の道化師か愚か者として描かれている。 二人は哲学的な議論につまずきながら、その意味するところを理解せず、世界の不合理さと無作為さに思いを馳せる。 ジャン・アヌイユの『アンチゴーヌ』もまた、実存主義的な考えに基づいた議論を展開している[114]。ギリシャ神話と紀元前5世紀の同名の戯曲(ソフォ クレスの『アンチゴーヌ』)に着想を得た悲劇である。英語では、フランス語の原形である "Ante-GŌN "と発音されることで、先行詞と区別されることが多い。ナチスによるフランス占領下の1944年2月6日、パリで初演された。ナチスの検閲下で上演された この戯曲は、(アンティゴネーに代表される)権威の拒絶と(クレオンに代表される)権威の受容を意図的に曖昧にしている。フランスのレジスタンスとナチス の占領との類似性が描かれている。アンチゴーヌは人生を絶望的に無意味なものとして拒絶するが、高貴な死を肯定的に選ぶことはない。戯曲の核心は、権力、 運命、選択の本質に関する長い対話であり、その中でアンティゴネは、「...平凡な幸福の約束にうんざりしている」と言う。平凡な人生を送るくらいなら、 死んだほうがましだと。 批評家のマーティン・エスリン氏は、その著書『不条理演劇』の中で、サミュエル・ベケット、ウジェーヌ・イヨネスコ、ジャン・ジュネ、アルトゥール・アダ モフといった多くの現代劇作家が、私たちは本当の意味など何もない宇宙に放たれた不条理な存在であるという実存主義的信念を、いかに戯曲に織り込んでいる かを指摘している。エスリンは、これらの劇作家の多くが、サルトルやカミュの戯曲よりも優れた哲学を示していると指摘した。後に(エスリンの著書に基づい て)「不条理主義者」とレッテルを貼られたこうした劇作家のほとんどは、実存主義との関係を否定し、しばしば断固として反哲学的であったが(例えばイヨネ スコはしばしば、自分は実存主義よりも「形而上学」やシュルレアリスムに共感していると主張していた)、エスリンの観察に基づいて、これらの劇作家はしば しば実存主義と結びつけられている[115]。 アクティヴィズム[編集] 黒人実存主義は世界における黒人の存在と経験を探求している[116]。古典的・現代的な思想家としては、C.L.R.ジェイムズ、フレデリック・ダグラ ス、W.E.B.デュボア、フランツ・ファノン、アンジェラ・デイヴィス、コーネル・ウェスト、ナオミ・ザック、ベル・フックス、スチュアート・ホール、 ルイス・ゴードン、オードレ・ロードなどが挙げられる[117]。 精神分析と心理療法[編集]。 主な記事 実存療法 哲学としての実存主義の主要な分派は実存主義心理学と精神分析であり、それはフロイトの20年来の側近であったオットー・ランクの著作の中で初めて結晶化 した。ルートヴィヒ・ビンスワンガーは、ランクの著作を意識することなく、フロイト、エドムント・フッサール、ハイデガー、サルトルの影響を受けた。後の 人物はヴィクトール・フランクルで、彼は若い頃にフロイトに短期間会ったことがある[118]。彼のロゴセラピーは実存主義的なセラピーの一形態とみなす ことができる。実存主義者たちはまた、ゲオルク・ジンメル[119]やミシェル・フーコーといった思想家たちによって、社会心理学、反実証主義的ミクロ社 会学、象徴的相互作用論、ポスト構造主義にも影響を与えることになる。フーコーはキルケゴールの偉大な読者であったが、キルケゴールについて言及すること はほとんどなかった。 アメリカにおける実存主義心理学の初期の貢献者はロロ・メイであり、彼はキルケゴールと オットー・ランクから強い影響を受けていた。アメリカにおける実存主義心理学の技法と理論に関する最も多くの著述家の一人がアーヴィン・D・ヤロムであ る。ヤロムは次のように述べている。 フロイトの機械論的、決定論的な心のモデルに対する反動と、セラピーにおける現象学的アプローチの前提を除けば、実存主義的分析者たちにはほとんど共通点 がなく、まとまった思想的学派とみなされたことはない。これらの思想家は、ルートヴィヒ・ビンスワンガー、メダード・ボス、ウジェーヌ・ミンコフスキー、 V. E. ゲバッテル、ローランド・クーン、G. カルーソ、F. T. ブイテンダイク、G. バリー、ヴィクトール・フランクルなどであるが、ロロ・メイの非常に影響力のある1958年の著書『実存』、特に彼の紹介エッセイによって彼らの研究がこ の国に紹介されるまで、アメリカの心理療法界ではほとんど知られていなかった[121]。 実存主義心理療法のヨーロッパ版の発展により最近貢献したのは、イギリスを拠点とするエミー・ファン・ドゥールゼンである[122]。 実存主義における不安の重要性は、心理療法において人気のあるトピックとなっている。セラピストはしばしば不安の説明として実存主義哲学を提示する。その 主張は、不安は、個人が決定する完全な自由と、そのような決定の結果に対する完全な責任から現れるというものである。実存主義的アプローチを用いる心理療 法家は、患者は不安を利用し、それを建設的に使うことができると信じている。患者は不安を抑圧する代わりに、それを変化の根拠として利用することを勧めら れる。不安を不可避なものとして受け入れることで、人は人生における潜在能力を最大限に発揮するために不安を利用することができるのである。人間性心理学 も実存主義心理学に大きな影響を受けており、基本的な考え方の多くを共有している。アーネスト・ベッカーと オットー・ランクの著作に基づく恐怖管理理論は、心理学の学問的研究の中でも発展途上の分野である。これは、いずれ死ぬという知識に直面した人々の暗黙の 感情反応であると研究者が主張するものに注目している[123]。 また、ゲルト・B・アッヘンバッハは、哲学的カウンセリングを独自にブレンドすることで、ソクラテスの伝統を刷新した。 |
| Criticisms General criticisms Walter Kaufmann criticized "the profoundly unsound methods and the dangerous contempt for reason that have been so prominent in existentialism."[124] Logical positivist philosophers, such as Rudolf Carnap and A. J. Ayer, assert that existentialists are often confused about the verb "to be" in their analyses of "being".[125] Specifically, they argue that the verb "is" is transitive and pre-fixed to a predicate (e.g., an apple is red) (without a predicate, the word "is" is meaningless), and that existentialists frequently misuse the term in this manner. Wilson has stated in his book The Angry Years that existentialism has created many of its own difficulties: "We can see how this question of freedom of the will has been vitiated by post-romantic philosophy, with its inbuilt tendency to laziness and boredom, we can also see how it came about that existentialism found itself in a hole of its own digging, and how the philosophical developments since then have amounted to walking in circles round that hole."[126] Sartre's philosophy Many critics argue Sartre's philosophy is contradictory. For example, see Magda Stroe's arguments. Specifically, they argue that Sartre makes metaphysical arguments despite his claiming that his philosophical views ignore metaphysics. Herbert Marcuse criticized Being and Nothingness for projecting anxiety and meaninglessness onto the nature of existence itself: "Insofar as Existentialism is a philosophical doctrine, it remains an idealistic doctrine: it hypostatizes specific historical conditions of human existence into ontological and metaphysical characteristics. Existentialism thus becomes part of the very ideology which it attacks, and its radicalism is illusory."[127] In Letter on Humanism, Heidegger criticized Sartre's existentialism: Existentialism says existence precedes essence. In this statement he is taking existentia and essentia according to their metaphysical meaning, which, from Plato's time on, has said that essentia precedes existentia. Sartre reverses this statement. But the reversal of a metaphysical statement remains a metaphysical statement. With it, he stays with metaphysics, in oblivion of the truth of Being.[128] |
批判[編集] 一般的な批判[編集] ウォルター・カウフマンは「実存主義において顕著であった深く不健全な方法と理性に対する危険な侮蔑」を批判している[124]。 ルドルフ・カルナップや A・J・エアーのような論理実証主義の哲学者は、実存主義者は「存在」の分析において「ある」という動詞をしばしば混同していると主張している [125]、 例えば、リンゴは赤い)(述語がなければ、「である」という言葉は無意味である)。ウィルソンはその著書『怒りの時代』の中で、実存主義は多くの困難を自 ら生み出してきたと述べている: 「この意志の自由という問題が、怠惰と退屈への傾向を内蔵したポスト・ロマン主義哲学によっていかに汚されたかを知ることができる。また、実存主義が自ら 掘った穴の中に身を置くことになった経緯や、それ以降の哲学的発展がいかにその穴の周囲を堂々巡りすることに等しかったかも知ることができる」 [126]。 サルトルの哲学[編集] サルトルの哲学は矛盾していると主張する批評家は多い。例えば、マグダ・シュトロエの議論を参照。具体的には、サルトルは自分の哲学的見解は形而上学を無 視していると主張しているにもかかわらず、形而上学的な議論をしていると主張している。ヘルベルト・マルクーゼは、『存在と無』が不安と無意味を存在の本 質そのものに投影していると批判した: 「実存主義が哲学的教義である限り、それは依然として観念論的教義である。こうして実存主義は、それが攻撃するイデオロギーの一部となり、その急進主義は 幻想的なものとなる」[127]。 ハイデガーは『ヒューマニズムに関する書簡』の中で、サルトルの実存主義を批判している: 実存主義は実存が本質に先立つと言う。実存主義は実存が本質に先立つと言う。この言明において、彼は実存と 本質を、プラトンの時代から本質が 実存に先立つと言われてきた形而上学的な意味に従って捉えている。サルトルはこの発言を逆転させている。しかし、形而上学的言明の逆転は形而上学的言明の ままである。サルトルは形而上学に留まり、「存在」の真理を忘却しているのである[128]。 |
| Abandonment (existentialism) Disenchantment Existential phenomenology Existential risk Existentiell List of existentialists Meaning (existential) Meaning-making Philosophical pessimism Self-reflection |
放棄(実存主義) 幻滅 実存的現象学 実存的リスク 実存主義 実存主義者のリスト 意味(実存的) 意味形成 哲学的悲観主義 自己反省 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Existentialism |
|
| Existentialism First published Fri Jan 6, 2023 As an intellectual movement that exploded on the scene in mid-twentieth-century France, “existentialism” is often viewed as a historically situated event that emerged against the backdrop of the Second World War, the Nazi death camps, and the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, all of which created the circumstances for what has been called “the existentialist moment” (Baert 2015), where an entire generation was forced to confront the human condition and the anxiety-provoking givens of death, freedom, and meaninglessness. Although the most popular voices of this movement were French, most notably Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir, as well as compatriots such as Albert Camus, Gabriel Marcel, and Maurice Merleau-Ponty, the conceptual groundwork of the movement was laid much earlier in the nineteenth century by pioneers like Søren Kierkegaard and Friedrich Nietzsche and twentieth-century German philosophers like Edmund Husserl, Martin Heidegger, and Karl Jaspers as well as prominent Spanish intellectuals José Ortega y Gasset and Miguel de Unamuno. The core ideas have also been illuminated in key literary works. Beyond the plays, short stories, and novels by French luminaries like Sartre, Beauvoir, and Camus, there were Parisian writers such as Jean Genet and André Gide, the Russian novelists Leo Tolstoy and Fyodor Dostoevsky, the work of Norwegian authors such as Henrik Ibsen and Knut Hamsun, and the German-language iconoclasts Franz Kafka and Rainer Maria Rilke. The movement even found expression across the pond in the work of the “lost generation” of American writers like F. Scott Fitzgerald and Ernest Hemingway, mid-century “beat” authors like Jack Kerouac, Allen Ginsburg, and William S. Burroughs, and the self-proclaimed “American existentialist,” Norman Mailer (Cotkin 2003, 185). What distinguishes existentialism from other movements in the intellectual history of the West is how it stretched far beyond the literary and academic worlds. Its ideas are captured in films by Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Goddard, Akira Kurosawa, and Terrence Malick. Its moods are expressed in the paintings of Edvard Munch, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Paul Cézanne, and Edward Hopper and in the vitiated forms of the sculptor Alberto Giocometti. Its emphasis on freedom and the struggle for self-creation informed the radical and emancipatory politics of Martin Luther King Jr. and Malcolm X as well as the writings of Black intellectuals such as Ralph Ellison, Richard Wright, and W.E.B. Du Bois. Its engagement with the relationship between faith and freedom and the incomprehensibility of God shaped theological debates through the lectures and writings of Karl Barth, Paul Tillich, and Martin Buber, among others. And, with its penetrating analyses of anxiety and the importance of self-realization, the movement has had a profound impact in the development of humanistic and existential approaches to psychotherapy in the work of a wide range of theorists, including R.D. Laing, Rollo May, Viktor Frankl, and Irvin Yalom. With this broad and diverse range of incarnations, it is difficult to explain what the term “existentialism” refers to. The word, first introduced by Marcel in 1943, is certainly not a reference to a coherent system or philosophical school.[1] Indeed, the major contributors are anything but systematic and have widely divergent views, and of these, only Sartre and Beauvoir explicitly self-identified as “existentialists.” In surveying its representative thinkers, one finds secular and religious existentialists, philosophers who embrace a conception of radical freedom and others who reject it. And there are those who regard our relations with others as largely mired in conflict and self-deception and others who recognize a deep capacity for self-less love and interdependence. Given these disparate threads and the fact that there is no unifying doctrine, one can nonetheless distill a set of overlapping ideas that bind the movement together. Nihilism: The emergence of existentialism as an intellectual movement was influenced by the rise of nihilism in late nineteenth century Europe as the pre-modern religious worldview was replaced with one that was increasingly secular and scientific. This historical transition resulted in the loss of a transcendent moral framework and contributed to the rise of modernity’s signature experiences: anxiety, alienation, boredom, and meaninglessness. Engagement vs. Detachment: Against a philosophical tradition that privileges the standpoint of theoretical detachment and objectivity, existentialism generally begins in medias res, amidst our own situated, first-person experience. The human condition is revealed through an examination of the ways we concretely engage with the world in our everyday lives and struggle to make sense of and give meaning to our existence. Existence Precedes Essence: Existentialists forward a novel conception of the self not as a substance or thing with some pre-given nature (or “essence”) but as a situated activity or way of being whereby we are always in the process of making or creating who we are as our life unfolds. This means our essence is not given in advance; we are contingently thrown into existence and are burdened with the task of creating ourselves through our choices and actions. Freedom: Existentialists agree that what distinguishes our existence from that of other beings is that we are self-conscious and exist for ourselves, which means we are free and responsible for who we are and what we do. This does not mean we are wholly undetermined but, rather, that we are always beyond or more than ourselves because of our capacity to interpret and give meaning to whatever limits or determines us. Authenticity: Existentialists are critical of our ingrained tendency to conform to the norms and expectations of the public world because it prevents us from being authentic or true to ourselves. An authentic life is one that is willing to break with tradition and social convention and courageously affirm the freedom and contingency of our condition. It is generally understood to refer to a life lived with a sense of urgency and commitment based on the meaning-giving projects that matter to each of us as individuals. Ethics: Although they reject the idea of moral absolutes and universalizing judgments about right conduct, existentialism should not be dismissed for promoting moral nihilism. For the existentialist, a moral or praiseworthy life is possible. It is one where we acknowledge and own up to our freedom, take full responsibility for our choices, and act in such a way as to help others realize their freedom. These ideas serve to structure the entry. 1. Nihilism and the Crisis of Modernity 2. Engagement vs. Detachment 2.1 Subjective Truth 2.2 Perspectivism 2.3 Being-in-the-World 2.4 Embodiment 3. Existence Precedes Essence 4. Freedom 4.1 The Anxiety of Choice 4.2 Mediated Freedom 5. Authenticity 5.1 The Power of Moods 5.2 Kierkegaard’s Knight of Faith 5.3 Nietzsche’s Overman 5.4 Heidegger’s Resolute Dasein 5.5 Self-Recovery in Sartre and Beauvoir 6. Ethics 6.1 Authentic Being-for-Others 6.2 The Ethics of Recognition 6.3 The Ethics of Engagement 7. Contemporary Relevance 7.1 Post-Structuralism 7.2 Narrative and Hermeneutic Philosophy 7.3 Philosophy of Mind and Cognitive Science 7.4 Critical Phenomenology 7.5 Comparative and Environmental Philosophy 7.6 Philosophy of Health and Illness 7.7 A New Generation Bibliography Academic Tools Other Internet Resources Related Entries https://plato.stanford.edu/entries/existentialism/ |
実存主義 初出 2023年1月6日(金) 20世紀半ばのフランスで爆発的に広まった知的運動として、「実存主義」はしばしば、第二次世界大戦、ナチスの死の収容所、広島と長崎の原爆投下を背景に 生まれた歴史的に位置づけられた出来事とみなされる。この運動で最も人気があったのはフランス人、とりわけジャン=ポール・サルトルやシモーヌ・ド・ボー ヴォワール、そしてアルベール・カミュ、ガブリエル・マルセル、モーリス・メルロ=ポンティといった同胞だった、 この運動の概念的な基礎は、セーレン・キルケゴールやフリードリヒ・ニーチェのような先駆者たちや、エドムント・フッサール、マルティン・ハイデガー、 カール・ヤスパースのような20世紀のドイツの哲学者たち、そしてホセ・オルテガ・イ・ガセットやミゲル・デ・ウナムーノのような著名なスペインの知識人 たちによって、19世紀のはるか以前に築かれていた。核となる考え方は、主要な文学作品にも照らし出されている。サルトル、ボーヴォワール、カミュといっ たフランスの著名人による戯曲、短編小説、小説にとどまらず、ジャン・ジュネやアンドレ・ジドといったパリの作家、レオ・トルストイやフョードル・ドスト エフスキーといったロシアの小説家、ヘンリック・イプセンやクヌート・ハムスンといったノルウェーの作家、フランツ・カフカやライナー・マリア・リルケと いったドイツ語の象徴的な作家たちの作品がある。この運動は、F・スコット・フィッツジェラルドやアーネスト・ヘミングウェイといった「失われた世代」の アメリカ人作家、ジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグ、ウィリアム・S・バロウズといった世紀半ばの「ビート」作家、そして自称「アメリカ実存主 義者」のノーマン・メイラー(Cotkin 2003, 185)の作品に、池を越えて表現されることさえあった。 実存主義が西洋の知的歴史における他の運動と異なるのは、それが文学や学問の世界をはるかに超えて広がっていったことである。実存主義の思想は、イング マール・ベルイマン、ミケランジェロ・アントニオーニ、ジャン=リュック・ゴダール、黒澤明、テレンス・マリックらの映画で表現されている。そのムード は、エドヴァルド・ムンク、マルセル・デュシャン、パブロ・ピカソ、ポール・セザンヌ、エドワード・ホッパーの絵画や、彫刻家アルベルト・ジョコメッティ の荒々しいフォルムに表現されている。自由と自己創造への闘いを強調するその姿勢は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアやマルコムXの急進的で解放 的な政治や、ラルフ・エリソン、リチャード・ライト、W.E.B.デュボワといった黒人知識人の著作に影響を与えた。信仰と自由の関係や神の不可解さとの 関わりは、カール・バルト、パウル・ティリッヒ、マルティン・ブーバーなどの講演や著作を通して神学論争を形成した。また、不安や自己実現の重要性を鋭く 分析したこの運動は、R.D.レイング、ロロ・メイ、ヴィクトール・フランクル、アーヴィン・ヤロムなど、幅広い理論家たちの研究において、心理療法への 人文主義的・実存主義的アプローチの発展に大きな影響を与えた。 このように広範かつ多様な変容を遂げているため、「実存主義」という言葉が何を指すのかを説明するのは難しい。1943年にマルセルによって初めて紹介さ れたこの言葉は、確かに首尾一貫した体系や哲学的流派を指す言葉ではない[1]。実際、主要な貢献者たちは体系的とは言い難く、見解も大きく異なってい る。その代表的な思想家を調べてみると、世俗的な実存主義者と宗教的な実存主義者、急進的な自由という概念を受け入れる哲学者とそれを否定する哲学者がい る。また、他者との関係を対立と自己欺瞞に陥っていると考える人もいれば、自己を超越した愛と相互依存の深い能力を認める人もいる。こうした異質な糸と、 統一的な教義が存在しないという事実を考慮すれば、それでも、この運動を結びつける一連の重なり合う思想を抽出することはできる。 ニヒリズム: 知的運動としての実存主義の出現は、19世紀後半のヨーロッパにおけるニヒリズムの台頭の影響を受けた。この歴史的変遷は、超越的な道徳的枠組みを失う結 果となり、不安、疎外感、退屈、無意味といった近代を象徴する体験の台頭の一因となった。 関与と離脱: 理論的な離隔と客観性の立場を特権とする哲学の伝統に対して、実存主義は一般的に、私たち自身の置かれた状況、一人称の経験の中で、メディアス・レスから 始まる。私たちが日常生活の中で具体的に世界と関わり、自分の存在を理解し、意味を与えようと奮闘する方法を検討することで、人間の状態が明らかにされ る。 実存は本質に先立つ: 実存主義者たちは、自己を、あらかじめ与えられた性質(あるいは「本質」)を持つ物質やモノとしてではなく、私たちが人生の展開とともに、常に自分自身を 作り、創造していく過程にある、位置づけられた活動や存在のあり方としてとらえる。つまり、私たちの本質はあらかじめ与えられているのではなく、私たちは 偶発的に存在に投げ込まれ、私たちの選択や行動を通じて自分自身を創造するという課題を背負っているのです。 自由: 実存主義者たちは、私たちの存在を他の存在と区別するのは、私たちが自意識を持ち、自分自身のために存在していることであり、それは私たちが自由であり、 自分が何者であるか、何をするかに責任があることを意味する。これは、私たちが完全に決定されていないという意味ではなく、私たちを制限したり決定したり するものを解釈し、それに意味を与える能力があるため、私たちは常に私たち自身を超えている、あるいはそれ以上の存在であるという意味である。 真正性: 実存主義者は、世間一般の規範や期待に合わせようとする私たちの染み付いた傾向を批判する。真正な人生とは、伝統や社会的慣例と決別し、勇気を持って私た ちの状態の自由と偶発性を肯定することである。それは一般的に、私たち一人ひとりにとって重要な意味を与えるプロジェクトに基づき、切迫感とコミットメン トをもって生きる人生を指すと理解されている。 倫理: 道徳的絶対性や、正しい行為についての普遍的判断を否定しているが、実存主義が道徳的ニヒリズムを助長しているとして否定されるべきではない。実存主義者 にとって、道徳的な、あるいは賞賛に値する人生は可能である。それは、自分の自由を認め、それを自認し、自分の選択に全責任を持ち、他者が自由を実現する のを助けるように行動することである。 これらの考え方は、このエントリーを構成するのに役立つ。 1. ニヒリズムと近代の危機 2. 関与と離脱 2.1 主観的真理 2.2 視点主義 2.3 世界における存在 2.4 身体化 3. 実存は本質に先立つ 4. 自由 4.1 選択の不安 4.2 媒介された自由 5. 真正性 5.1 気分の力 5.2 キルケゴールの『信仰の騎士 5.3 ニーチェの『オーバーマン 5.4 ハイデガーの毅然としたダゼイン 5.5 サルトルとボーヴォワールにおける自己回復 6. 倫理学 6.1 他者にとっての真正なる存在 6.2 認識の倫理 6.3 関わりの倫理 7. 現代的妥当性 7.1 ポスト構造主義 7.2 物語哲学と解釈哲学 7.3 心の哲学と認知科学 7.4 批判的現象学 7.5 比較哲学と環境哲学 7.6 健康と病気の哲学 7.7 新世代 書誌 学術ツール その他のインターネットリソース 関連項目 |
| 1. Nihilism and the Crisis of
Modernity We can find early glimpses of what might be called the “existential attitude” (Solomon 2005) in the Stoic and Epicurean philosophies of antiquity, in the struggle with sin and desire in St. Augustine’s Confessions, in the intimate reflections on death and the meaning of life in Michel de Montaigne’s Essays, and in the confrontation with the “dreadful silence” of the cosmos in Blaise Pascal’s Pensées. But it was not until the nineteenth century that the ideas began to coalesce into a bona fide intellectual movement. By this time, an increasingly secular and scientific worldview was emerging and the traditional religious framework that gave pre-modern life a sense of moral orientation and cohesion was beginning to collapse. Without a north star of moral absolutes to guide us, the modern subject was left abandoned and lost, “wandering,” as Nietzsche writes, “as if through an endless nothing” (1887 [1974], §125). But it wasn’t just the rise of modern science and its cold mechanistic view of the world as a value-less aggregate of objects in causal interaction that contributed to the anxiety and forlornness of the modern age. The rise of Protestantism also played a role. With its rejection of hierarchical Church authority, this new form of Christianity emphasized subjective inwardness and created a unique social configuration grounded in principles of individualism, freedom, and self-reliance. The result was the loss of a sense of community and belongingness rooted in the close-knit social bonds of traditional society. And the Protestant shift intensified the Christian attitude of contemptus mundi (“contempt for the world”), contributing to feelings of loneliness and creating a perception of public life as a domain that was fundamentally inauthentic and corrupt (Aho 2020; Guignon 2004; Taylor 1989). Along with these historical developments, social transformations associated with the Industrial Revolution and the formation of the modern state were emerging. With newly mechanized working conditions and bureaucratic forms of administration, an increasingly impersonal and alienating social order was established. When Ortega y Gasset introduces his notion of “the mass man,” he captures the automation and lifeless conformism of the machine age, where everybody “feels just like everybody else and is nevertheless not concerned about it” (1930 [1993, 15]). In their conceptions of “the public” (Kierkegaard), “the herd” (Nietzsche), and “the They” (Heidegger), existentialists offer powerful critiques of the leveled down and routinized ways of being that characterize mass society. And the novels and short stories of Dostoevsky, Camus, and Kafka capture the bourgeois emptiness and boredom of the managerial class and the paranoia and distrust that emerges when life is regulated and controlled by faceless bureaucrats. These social transformations created the conditions for nihilism, where modern humanity suddenly found itself adrift and confused, unsure of which path to take or where to look for a stable and enduring sense of truth and meaning. The condition of nihilism involves the shocking recognition that there is no overarching reason, order, or purpose to our existence, that it is all fundamentally meaningless and absurd. Of all the existentialists, Nietzsche was the most influential and prophetic in diagnosing and conceptualizing the crisis. With the death of God and the loss of moral absolutes, we are exposed to existence “in its most terrible form … without meaning or aim” (Nietzsche 1887 [1974], §55). And it is against this anomic background that the question of existence, of what it means to be, becomes so urgent. But it is a question that requires taking a radically different standpoint than the one privileged by the philosophical tradition. 2. Engagement vs. Detachment From Plato onward, Western philosophy has generally prioritized a methodology grounded in a perspective of rational detachment and objectivity to arrive at truths that are immutable and timeless. By practicing what Merleau-Ponty disparagingly calls, “high-altitude thinking” (1964 [1968], 73), the philosopher adopts a perspective that is detached and impersonal, a “God’s eye view” or “view from nowhere” uncorrupted by the contingencies of our emotions, our embodiment, or the prejudices of our time and place. In this way the philosopher can grasp the “reality” behind the flux of “appearances,” the essential and timeless nature of things “under the perspective of eternity” (sub specie aeternitatis). Existentialism offers a thoroughgoing rejection of this view, arguing that we cannot look down on the human condition from a detached, third-person perspective because we are already thrown into the self-interpreting event or activity of existing, an activity that is always embodied, felt, and historically situated. Existence, then, is generally grasped not just through dispassionate theorizing but through a careful analysis of first-person experience, of the concrete, flesh and blood particulars of everyday life and the feelings, relationships, and commitments that make us who we are. It is a philosophy that begins from the standpoint of the engagé, of the individual who is engaged in life and who confronts the givens of existence. 2.1 Subjective Truth The existentialist critique of theoretical detachment was pioneered by Kierkegaard whose scorn was directed primarily at G.W. F. Hegel, a philosopher who adopted the “perspective of eternity” to build a metaphysical system that would provide complete knowledge of reality. By taking a disengaged and panoptic view, Kierkegaard argues Hegel’s system invariably covers over the deeply personal project of being human and the specific needs and concerns of the existing individual. In his words, “it makes the subject accidental, and thereby transforms existence into something indifferent, something vanishing” (1846 [1941, 173]). In response, Kierkegaard reverses the traditional orientation that privileges objectivity by claiming that, when it comes to the question of existence, one’s own subjective truth is “the highest truth attainable” (1846 [1941, 182]). This means the abstract truths of philosophical detachment are always subordinate to the concrete truths of the existing individual. “The real subject,” writes Kierkegaard, “is not the cognitive subject … the real subject is the ethically existing subject” (1846 [1941, 281]). And subjective truth cannot be reasoned about or explained logically; it emerges out of the situated commitments, affects, and needs of the individual. For this reason, it does not disclose timeless and objective truths; it discloses “a truth which is true for me” (1835 [1959, 44]). For Kierkegaard, to live this truth invariably results in feelings of anxiety and confusion because it is objectively uncertain; it has no rational justification, and no one else can understand or relate to it. It is an ineffable truth that is felt rather than known. In this sense, the existing individual “discovers something that thought cannot think” (Kierkegaard 1844 [1936, 29]). But prioritizing the contingent and unrationalizable truths of existence does not mean Kierkegaard is forwarding a position of “irrationalism.” He is claiming, rather, that the standpoint of rational detachment cannot help us access the self-defining commitments and projects that matter to the existing individual. Truths of flesh and blood cannot be reduced to systematic explanation because such truths do not provide us with objective knowledge. Rather, they lay bare the passionate and urgent sense of how we should live our lives. They tell the individual: “what I am to do, not what I am to know” (Kierkegaard, 1835 [1959, 44]). 2.2 Perspectivism Nietzsche echoes Kierkegaard’s misgivings about methodological detachment and philosophical systems but he does so by forwarding a pragmatic and perspectival account of truth. He argues that philosophers don’t discover objective truths by means of detached reasoning because truth claims are always shaped by and embedded in specific sociohistorical contexts. Truths, for Nietzsche, are best understood as social constructs; they are created or invented by a historical people, and they endure only so long as they are socially useful. On Nietzsche’s account, truths are passed down historically for generations to the point where they are uncritically accepted as “facts.” But from the standpoint of perspectivism, “facts are precisely what there is not, [there are] only interpretations. [The world] has no meaning behind it, but countless meanings” (Nietzsche 1901 [1968], §481). Nietzsche’s genealogy is one that shows how the history of Western philosophy is largely a history of forgetting how truths are invented. “It is only by means of forgetfulness,” he writes, “that man can ever reach the point of fancying himself to possess a ‘truth’” (Nietzsche 1889a [1990a], §93). This means human beings are already bound up in socially constructed perspectives that they cannot disengage or detach from. To exist, then, is to live in one’s “own perspectival forms, and only in them. We cannot see around our own corner” (Nietzsche 1887 [1974], §374). There is no aperspectival “reality.” The epistemological distinction between “appearance” and “reality” is a pseudo-problem that is always parasitic on the perspectival forms that we inhabit. Nietzsche goes on to suggest there is a psychological motivation in our shared belief in objective truth. It shelters us from the terrifying contingency and mutability of existence. Nietzsche understands that human beings are vulnerable and frightened creatures, and the belief in truth—even though it is an illusion—has social and pragmatic utility by providing a measure of coherence and reliability. We need these truths for psychological protection, to help us cope with an otherwise chaotic and precarious existence. “Truth,” therefore, “is that sort of error without which a certain species of life could not live” (Nietzsche 1901 [1968], §493). 2.3 Being-in-the-World In Being and Time, Heidegger will expand on this critique of detachment and objectivity by developing his own phenomenological analysis of existence or “being-in-the-world” (In-der-Welt-sein). Following the core maxim of phenomenology introduced by his teacher Husserl, Heidegger’s philosophy attempts to return “to the things themselves,” to not explain but describe how things are given, reveal themselves, and make sense to us in our average everyday lives. Employing the word “Dasein,” a colloquial German term that refers to the kind of “existence” or “being” unique to humans, Heidegger makes it clear he is not interested in a systematic explanation of what we are, as if existence referred to the objective presence of a substance—e.g., a rational animal, an ego cogito, or an ensouled body. As a phenomenologist, he is concerned with how we are. In his version of phenomenology, Dasein is viewed not as a substance with what-like characteristics but as a self-interpreting, meaning-giving activity. Dasein refers to “the subject’s way of being” (Heidegger 1927 [1982, 123]), someone who is always already involved and engaged with the equipment, institutions, and practices of a shared world and that embodies a tacit understanding of how to be in that world. Heidegger’s conception of being-in-the-world articulates three related ideas that will become central to twentieth-century existentialism and phenomenology. First, it offers a thoroughgoing rejection of the Cartesian view of the self or “I” as a discrete mental container of “inner” thoughts and beliefs that is somehow separate and distinct from “outer” objects in the world. There is no inner-outer dualism because the self is not a disembodied mind or consciousness. It is the activity of existing, a relational activity that is structurally bound up in the world. Thus, “self and world belong together in the single entity, the Dasein” (Heidegger 1927 [1982, 297]). Second, Heidegger compels us to rethink what we mean by “world.” From a phenomenological perspective, the world is not a geometrical space nor is it the sum of objects. It is the relational setting of our lives, the shared context of meaning that we are already involved in. And our involvement in the world allows objects to count and matter to us in particular ways. Third, Heidegger suggests that being-in-the-world is a meaning-giving activity. When we engage with and handle objects in the world, we give them meaning; we encounter them as meaningful. What appears to us in the immediacy of lived experience is always shaped by the public meanings we grow into. The fact that our existence is “fraught with meaning” suggests that experience has an intentional structure; it is always directed towards objects; it is about or of something (Heidegger 1919 [2002, 60]). The experience of hearing, for example, is not a representation of bare sense data because sounds are invariably colored by the context of meaning we are thrown into. We hear some-thing: we hear “the thunder of the heavens, the rustling of the woods, the rumbling of the motors, the noises of the city” (Heidegger 1950 [1971, 65], emphasis added). Meaning, on this view, is not generated by detached cognitive associations. It emerges against the background of our functional involvement in the world, in the way we are situated and engaged in a shared network of equipment, roles, institutions, and projects. And this engagement reveals a kind of pre-reflective competence or practical “know how” (können) that can never be made theoretically explicit. 2.4 Embodiment We see, then, that in their critique of third-person detachment existentialists forward the idea that we are already “caught up in the world” (Merleau-Ponty 1945 [1962, 5]). And an essential aspect of being caught up in this way is the experience of one’s own embodiment and the crucial role that bodily orientation, affectivity, perception, and motility play in our everyday being-in-the-world. In this way, philosophers such as Merleau-Ponty, Sartre, Beauvoir, and Marcel challenge the traditional interpretation of the body. Against the standard “Cartesian account,” the body is not regarded as a discrete, causally determined object, extended in space, and set apart from the disinterested gaze of the cognizing mind. The body is not something I have. It is a site of affectivity and meaning. It is who I am. And I cannot obtain objective knowledge of my body because I am already living through it; it is the experiential medium of my existence. “The body,” as Sartre puts it, “is lived and not known.” (1943 [1956, 427])[2] By building on the analysis of the lived body (corps propre, corps vécu, corps vivant, Leib), existentialists reveal how our moods, perceptions, and experiences are already bound up in worldly meanings, how we internalize these meanings, and how this act of internalization shapes the way we live, how we handle the tools of daily life, maneuver through lived space, relate to others, and interpret and perform our identities. In her pathbreaking work The Second Sex, Beauvoir illuminates this point by showing how a woman tends to internalize the dominant androcentric worldview, resulting in a representation of herself as subordinate, weak, and inferior. She is the “second sex” not because she is born with a particular biological body, but because she inhabits, enacts, and embodies the oppressive meanings and practices unique to her patriarchal situation. As Beauvoir famously puts it, the woman “is not born, but rather becomes a woman.” This is because “the body is not a thing; it is a situation… subject to taboos [and] laws… It is a reference to certain values from which [she] evaluates [herself]” (1949 [1952, 34, 36]). The existentialist’s distinction between the object-body and the lived-body has made it possible for contemporary philosophers and social theorists to engage the lived experience of those who have been historically marginalized by the western tradition. By rejecting the standpoint of theoretical detachment and focusing on the structures of embodiment and being-in-the-world, influential thinkers such as Franz Fanon (1952 [1967]), Iris Marion Young (1984 [2000]), and Judith Butler (1990), among others, have explored different ways in which we enact and embody forms of oppression and how this can shape our self-image and inhibit the experience of movement, spatial orientation, and other forms of bodily comportment. These investigations help to broaden and pluralize our understanding of the human condition by shedding light on a diverse range of embodied perspectives, from ethnicity and race, sex and gender, and age and physical ability. And insofar as these analyses help capture what is distinct about the meaning-giving activity of humans, they illuminate what is arguably the unifying principle of existentialism: “existence precedes essence.” |
1. ニヒリズムと近代の危機 実存的態度」(Solomon 2005)とでも呼ぶべきものは、古代のストア派やエピクロス派の哲学、聖アウグスティヌスの『告白』における罪と欲望との闘い、ミシェル・ド・モンテー ニュの『随想録』における死と人生の意味についての親密な考察、ブレーズ・パスカルの『ペンセ』における宇宙の「恐るべき沈黙」との対決の中に、初期に垣 間見ることができる。しかし、これらの思想が本格的な知的運動としてまとまり始めたのは、19世紀になってからである。この頃には、ますます世俗的で科学 的な世界観が台頭し、近代以前の生活に道徳的な方向性とまとまりを与えていた伝統的な宗教的枠組みは崩壊し始めていた。私たちを導く道徳的絶対という北極 星がなければ、ニーチェが「果てしない無の中をさまようように」(1887 [1974], §125)と書いているように、近代的主体は見捨てられ、迷ったままになっていた。しかし、近代という時代の不安と寂しさを助長したのは、近代科学の台頭 と、因果的相互作用の中にある無価値な物体の集合体としての世界に対する冷徹な機械論的見方だけではなかった。プロテスタンティズムの台頭も一役買った。 階層的な教会権威を否定するこの新しいキリスト教の形態は、主観的な内面性を強調し、個人主義、自由、自立の原則に基づいた独自の社会構成を作り出した。 その結果、伝統的な社会の緊密な結びつきに根ざしていた共同体意識や帰属意識が失われた。プロテスタントへの移行は、キリスト教的態度である "contemptus mundi"(「世間に対する軽蔑」)を強め、孤独感を助長し、公共生活は根本的に不真面目で腐敗した領域であるという認識を生み出した(Aho 2020; Guignon 2004; Taylor 1989)。 このような歴史的発展とともに、産業革命と近代国家の形成に伴う社会的変容も生じていた。新たに機械化された労働条件と官僚主義的な管理形態によって、ま すます非人間的で疎外的な社会秩序が確立された。オルテガ・イ・ガセットが「大衆的人間」という概念を導入したとき、彼は機械時代の自動化と生気のない順 応主義をとらえ、そこでは誰もが「他のみんなと同じように感じ、それにもかかわらず、そのことに無関心である」(1930 [1993, 15])。公共」(キルケゴール)、「群衆」(ニーチェ)、「彼ら」(ハイデガー)という概念において、実存主義者たちは大衆社会を特徴づける平準化さ れ、ルーティン化された存在のあり方に対する強力な批判を提供している。また、ドストエフスキー、カミュ、カフカの小説や短編小説は、管理職階級のブル ジョワ的な空虚さや退屈さ、顔が見えない官僚たちによって生活が規制され管理されることで生まれるパラノイアや不信感をとらえている。 このような社会的変容は、ニヒリズムの条件を作り出した。近代人類は突然、どの道を進むべきか、安定した永続的な真理と意味の感覚をどこに求めるべきかわ からず、漂流し混乱していることに気づいたのだ。ニヒリズムの条件とは、私たちの存在には包括的な理由も秩序も目的もなく、すべてが根本的に無意味で不条 理であるという衝撃的な認識である。すべての実存主義者の中で、ニーチェは危機の診断と概念化において最も影響力があり、予言的であった。神の死と道徳的 絶対性の喪失によって、私たちは「最も恐ろしい形で......意味も目的もない」存在にさらされている(ニーチェ1887 [1974], §55)。そして、存在とは何か、存在するとはどういうことなのかという問いが切迫してくるのは、このようなアノミックな背景があるからである。しかしこ の問いは、哲学の伝統が特権としてきた立場とは根本的に異なる立場に立つことを必要とする。 2. 関与と離脱 プラトン以降、西洋哲学は一般的に、不変で時間を超越した真理に到達するために、合理的な離隔と客観性の視点に基づいた方法論を優先してきた。メルロ=ポ ンティが軽蔑的に「高高度思考」(1964 [1968], 73)と呼ぶものを実践することで、哲学者は、感情や身体性、時代や場所の偏見といった偶発的なものに邪魔されない「神の目」、あるいは「どこからともな く眺める」、切り離された非人間的な視点を採用する。そうすることで、哲学者は「見かけ」の流動性の背後にある「現実」、「永遠という観点のもとで」 (sub specie aeternitatis)物事の本質的で時間を超越した本質を把握することができる。実存主義はこの考え方を徹底的に否定し、私たちはすでに「存在す る」という自己解釈的な出来事や活動の中に投げ込まれており、その活動は常に体現され、感じられ、歴史的に位置づけられるものであるため、離れた第三者的 な視点から人間の状態を俯瞰することはできないと主張する。存在とは、一般的に、冷静な理論化によってではなく、一人称的な経験、日常生活の具体的で生身 の特殊性、そして私たちを私たちたらしめている感情、人間関係、コミットメントを注意深く分析することによって把握される。この哲学は、人生に従事し、存 在の本質に立ち向かう個人の立場から出発する哲学である。 2.1 主観的真理 理論的離人症に対する実存主義的な批判は、キルケゴールによって先駆的になされた。その軽蔑の矛先は、主にG.W.F.ヘーゲルに向けられた。ヘーゲル は、現実の完全な知識を提供する形而上学的体系を構築するために「永遠の視点」を採用した哲学者である。キルケゴールは、ヘーゲルの体系が、人間であるこ との深く個人的な計画や、現存する個人の具体的なニーズや関心事を常に覆い隠してしまうと主張する。彼の言葉を借りれば、「主体を偶発的なものにし、それ によって存在を無関心なもの、消え去るものに変えてしまう」(1846 [1941, 173])。これに対してキルケゴールは、存在の問題に関しては、自分自身の主観的真理こそが「到達しうる最高の真理」であると主張することで、客観性を 特権化する伝統的な方向性を逆転させる(1846 [1941, 182])。つまり、哲学的離脱の抽象的真理は、常に現存する個人の具体的真理に従属する。「キルケゴールは「真の主体は認識的主体ではない...... 真の主体は倫理的に存在する主体である」(1846 [1941, 281])と書いている。主観的な真理は、論理的に推論したり説明したりすることはできない。このため、主観的真理は時代を超えた客観的真理を開示するの ではなく、「私にとって真実である真理」(1835 [1959, 44])を開示するのである。キルケゴールにとって、この真理を生きることは、客観的に不確かであり、合理的な正当性を持たず、他の誰にも理解されず、関 わることもできないため、常に不安と混乱の感情をもたらす。それは、知ることよりも感じることの方が重要な不可解な真理なのだ。この意味で、現存する個人 は「思考が考えることのできない何かを発見する」のである(キルケゴール1844[1936, 29])。しかし、存在の偶発的で合理化不可能な真理を優先させることは、キルケゴールが "非合理主義 "の立場を提唱していることを意味しない。彼はむしろ、合理的な離隔の立場では、現存する個人にとって重要な自己規定的コミットメントやプロジェクトにア クセスすることはできないと主張しているのである。血と肉に裏打ちされた真理を体系的な説明に還元することはできない。なぜなら、そのような真理は客観的 な知識を与えてくれるものではないからである。真理は個々人に語りかける: 「私は何をなすべきか、何を知るべきかではなく」(Kierkegaard, 1835 [1959, 44])。 2.2 視点主義 ニーチェは、方法論的離隔や哲学体系に対するキルケゴールの疑念に共鳴するが、真理についてプラグマティックかつパースペクティヴな説明を提示することに よってそうしている。なぜなら、真理の主張は常に特定の社会史的文脈によって形成され、その中に組み込まれているからである。ニーチェにとって真理とは、 社会的構築物として理解するのが最も適切であり、歴史的な人々によって創造または発明され、社会的に有用である限り存続するものである。ニーチェの説明に よれば、真理は何世代にもわたって歴史的に受け継がれ、"事実 "として無批判に受け入れられるようになる。しかし、パースペクティヴィズムの立場からすれば、「事実とはまさにないものであり、(あるのは)解釈だけで ある。[世界は)その背後に意味を持たず、無数の意味を持つ」(ニーチェ1901[1968], §481)。ニーチェの系譜は、西洋哲学の歴史がいかに真理が発明されたかを忘れる歴史であったかを示すものである。「忘却の手段によってのみ、人間は 『真理』を所有していると思い込むことができる」(ニーチェ 1889a [1990a], §93)と彼は書いている。つまり、人間はすでに社会的に構築された視点に縛られており、そこから切り離すことも切り離すこともできないということだ。存 在するということは、「自分自身の視点形式の中に、そしてその中だけに生きる」ということである。われわれは自分の角を見渡すことができない」(ニーチェ 1887[1974], §374)。非視点的な "現実 "は存在しない。外見」と「現実」の認識論的区別は、私たちが住む視点的形態に常に寄生する擬似問題である。 ニーチェはさらに、私たちが客観的真理を共有して信じることには心理的動機があると指摘する。それは、存在の恐るべき偶発性と変転性から私たちを守るため である。ニーチェは、人間は傷つきやすく怯えやすい生き物であり、真理を信じることは、たとえそれが幻想であっても、一貫性と信頼性の尺度を提供すること で、社会的かつ実用的な効用を持つことを理解している。私たちは心理的な保護のためにこれらの真理を必要とし、そうでなければ混沌として不安定な存在に対 処する手助けをする。それゆえ「真理」とは、「ある種の生命がそれなしには生きられないような誤り」(ニーチェ 1901 [1968], §493)なのである。 2.3 世界における存在 ハイデガーは『存在と時間』において、存在あるいは「世界における存在」(In-der-Welt-sein)について独自の現象学的分析を展開すること で、この離隔と客観性への批判を発展させる。ハイデガーの哲学は、師であるフッサールが導入した現象学の核心的な格言に従って、「事物そのものに立ち戻 る」ことを試みており、事物がどのように与えられ、それ自身を現し、私たちの平均的な日常生活の中で意味をなすのかを説明するのではなく、記述しようとす る。ハイデガーは、人間特有の「存在」や「存在」を指す口語的なドイツ語である「Dasein」という言葉を用いて、あたかも「存在」が、理性的な動物、 自我のコギト、曖昧模糊とした身体など、ある物質の客観的な存在を指すかのような、私たちが何であるかの体系的な説明には興味がないことを明らかにしてい る。現象学者として、彼は私たちがどのように存在するかに関心を抱いている。現象学の彼のバージョンでは、Daseinは何ものかのような特徴を持つ物質 としてではなく、自己解釈し、意味を与える活動として捉えられている。ハイデガーは「主体のあり方」(Heidegger 1927 [1982, 123])を指しており、共有された世界の装置、制度、実践に常に関与しており、その世界におけるあり方についての暗黙の理解を体現している人物を指す。 ハイデガーの「世界における存在」の概念は、20世紀の実存主義と現象学の中心となる3つの関連した考え方を明確に示している。第一に、ハイデガーは、自 己や「私」を「内なる」思考や信念の個別的な精神的容器であり、世界の「外なる」対象とは何らかの形で切り離され、別個のものであるとするデカルト的な見 方を徹底的に否定している。自己は実体のない心や意識ではないので、内と外の二元論は存在しない。自己は存在するという活動であり、世界と構造的に結びつ いている関係的な活動なのである。したがって、「自己と世界は一つの実体であるDaseinの中に共に属している」(ハイデガー 1927 [1982, 297])。第二に、ハイデガーは私たちに、"世界 "とは何を意味するのかを再考させる。現象学的な観点からすれば、世界とは幾何学的な空間でもなければ、物体の総体でもない。それは私たちの生活の関係的 な設定であり、私たちがすでに関与している意味の共有された文脈である。そして、私たちが世界と関わることで、対象は私たちにとって特別な形で数えられ、 重要な意味を持つようになる。第三に、ハイデガーは、世界に存在することが意味を与える活動であることを示唆している。私たちが世界の対象と関わり、それ を扱うとき、私たちはそれらに意味を与える。生きている経験の即時性の中で私たちに現れるものは、常に私たちが成長する公的な意味によって形作られる。私 たちの存在が「意味にあふれている」という事実は、経験に意図的な構造があることを示唆している。経験はつねに対象に向けられており、それは何かについ て、あるいは何かについてである(ハイデガー1919 [2002, 60])。例えば、聴覚の経験は、むき出しの感覚データの表現ではない。なぜなら、音は常に、私たちが投げ込まれた意味の文脈によって彩られているから だ。私たちは「天の雷鳴、森のざわめき、モーター音、都市の騒音」(ハイデガー1950[1971、65]、強調)を聞く。この見解によれば、意味とは切 り離された認知的連想によって生み出されるものではない。意味とは、世界に対する私たちの機能的な関わりを背景として、私たちが装置、役割、制度、プロ ジェクトといった共有のネットワークに位置づけられ、関わっている様態の中で生まれるものなのである。そしてこの関わりは、決して理論的に明示することの できない、一種の事前反省的な能力、あるいは実践的な「ノウハウ」(können)を明らかにする。 2.4 具体化 実存主義者たちは、三人称的離人症に対する批判において、私たちはすでに「世界に巻き込まれている」(メルロ=ポンティ 1945 [1962, 5])という考えを提唱している。そして、このように巻き込まれることの本質的な側面は、自分自身の身体性の経験であり、身体的志向性、感情性、知覚、運 動性が私たちの日常的な「世界における存在」において果たす重要な役割なのである。このようにして、メルロ=ポンティ、サルトル、ボーヴォワール、マルセ ルといった哲学者たちは、伝統的な身体解釈に挑戦する。標準的な「デカルト的説明」に対して、身体は、空間に拡張され、認識する心の無関心な視線から切り 離された、因果的に決定された個別の物体とはみなされない。身体は私が持っているものではない。情動と意味の場なのだ。それが私なのだ。そして、私は自分 の身体について客観的な知識を得ることはできない。なぜなら、私はすでに身体を通して生きているからである。「サルトルが言うように、"身体は生きている が、知られていない"。(1943 [1956, 427])[2] 生きている身体(corps propre、corps vécu、corps vivant、Leib)の分析を土台に、実存主義者たちは、私たちの気分、知覚、経験がいかにすでに世俗的な意味と結びついているか、私たちがいかにこ れらの意味を内面化しているか、そしてこの内面化の行為がいかに私たちの生き方、日常生活の道具の扱い方、生活空間の操縦、他者との関係、アイデンティ ティの解釈と実行を形作っているかを明らかにする。ボーヴォワールは画期的な著作『第二の性』の中で、女性がいかに支配的なアンドロセントリックな世界観 を内面化する傾向があるかを示すことで、この点を明らかにしている。彼女が "第二の性 "であるのは、特定の生物学的身体を持って生まれたからではなく、家父長制的状況に特有の抑圧的な意味と慣習を宿し、実行し、体現しているからである。 ボーヴォワールが有名に言うように、女性は "生まれるのではなく、むしろ女性になる"。なぜなら「身体は物ではなく、状況であり......タブー[と]の対象となる......それは[彼女が] [自分自身を]評価する特定の価値への参照である」(1949年[1952年、34、36])からである。 実存主義者が客体=身体と生活=身体を区別したことで、現代の哲学者や社会理論家は、西洋の伝統によって歴史的に疎外されてきた人々の生活体験に関わるこ とが可能になった。フランツ・ファノン(1952[1967])、アイリス・マリオン・ヤング(1984[2000])、ジュディス・バトラー (1990)などの影響力のある思想家たちは、理論的な離隔の立場を否定し、身体化と世界における存在の構造に焦点を当てることで、私たちが抑圧の形態を 制定し、身体化するさまざまな方法を探求してきた。これらの研究は、民族や人種、性やジェンダー、年齢や身体能力など、多様な身体化された視点に光を当て ることで、人間の状態についての理解を広げ、多元化するのに役立っている。そして、これらの分析が人間の意味を与える活動についての特徴を捉えるのに役立 つ限りにおいて、「存在は本質に先立つ」という、間違いなく実存主義の統一原理を照らし出すことになる。 |
| 3. Existence Precedes Essence This principle was initially introduced early on in Heidegger’s Being and Time when he writes, “The ‘essence’ of Dasein lies in its existence” (1927 [1962, 42]).[3] Sartre will later repackage this line with the pithy adage, “existence precedes essence” (1946 [2001, 292]). What this statement suggests is that there is no pre-given or essential nature that determines us, which means that we are always other than ourselves, that we don’t fully coincide with who we are. We exist for ourselves as self-making or self-defining beings, and we are always in the process of making or defining ourselves through the situated choices we make as our lives unfold. This is, according to Sartre, “the first principle of existentialism,” and it “means, first, that man exists, turns up, appears on the scene, and, only afterwards, defines himself” (1946 [2001, 292–3]). The point here is that there can be no complete or definitive account of being human because there is nothing that grounds or secures our existence. Existence is fundamentally unsettled and incomplete because we are always projecting forward into possibilities, “hurling ourselves toward a future” as we imagine and re-imagine who we will be. Existence, then, is not a static thing; it is a dynamic process of self-making. Acknowledging existence as a self-making process does not mean the existentialist is denying that there are determinate aspects or “facts” about our situation that limit and constrain us. This is our givenness (or “facticity”), and it includes aspects of our being such as our embodiment and spatiality, our creaturely appetites and desires, and the socio-historical context we find ourselves in. But what distinguishes us as humans is that we have the capacity to rise above or “transcend” these facts in the way we relate to, interpret, and make sense of them. If I am compelled by a strong desire for sex, alcohol, or cigarettes, for instance, I do not out of necessity have to act on these desires. I have the freedom to question them and give them meaning, and the meanings I attribute to them shape my choices and the direction my life will take going forward. This means, unlike other organisms, we are self-conscious beings who can surpass our facticity by calling it into question, interpreting it in different ways, and making decisions about how to deal with it in the future. This is what Kierkegaard means when he describes existence as “a relation that relates to itself” (1849 [1989, 43]). Existence is a reflexive or relational tension between “facticity” and “transcendence,” where we are constrained by our facticity but simultaneously endowed with the freedom to exceed or transcend it. The human being is, as Ortega y Gasset writes, “a kind of ontological centaur, half immersed in nature, half transcending it” (1941, 111). We are not wholly determined by our nature because our nature is always a question or an issue for us. We have the capacity to reflect on and care about it. And the way we care about our nature informs how we create ourselves. Sartre will go so far as to say that human existence is fundamentally “indefinable” and that “there is no human nature” because there is no aspect of our facticity that can fully describe us. Our facticity reveals itself to us only through the self-defining meanings and values that we give to it. “If man […] is indefinable, it is because at first he is nothing. Only afterward will he be something, and he himself will have made what he will be” (1946 [2001, 293]). This idea that facticity can always be nullified or negated by our choices reveals the key to understanding the existentialist conception of freedom. 4. Freedom Recognizing that there is no pre-given essence that determines existence, the existentialist makes it clear that it is up to the individual to make his, her, or their own identity through choices and actions. Sartre explains that the coward, for instance, is not the way he is because of an unstable childhood or a particular genetic makeup. The coward “makes himself a coward” by means of his decisions (1946 [2001, 301]). In this way, the existentialist generally affirms the view that the human being has free will, is able to make decisions, and can be held responsible for their actions.[4] But, as we will see, this does not mean that we can do whatever we want. It means, rather, that existence is structured by our capacity to give meaning to our situation based on the actions and choices we make as our lives unfold. Insofar as we exist, we are envisioning a certain kind of life, assigning a value to our identity, and making ourselves into the kind of person we are. When we become aware of our freedom as an inescapable given of the human condition, the awareness is often accompanied by anxiety because we realize that we alone are responsible for our choices and the projects we undertake. There is no moral absolute, divine will, or natural law that can provide guidance or justify our actions. We are, in this sense, condemned to be free because “there are no excuses behind us nor justifications before us” (Sartre 1946 [2001, 296]). 4.1 The Anxiety of Choice In the canon of existentialist literature, no writer captures this idea better than Dostoevsky in his Notes from the Underground. The nameless “underground man” rebels against an increasingly scientized, rational, and mechanistic picture of human behavior promoted by Russian social reformers in the 1860s, where everything a person does was thought to be determined by causal laws. For the underground man, this view reduces the human being to a mechanical cog or “a piano key” (1864 [2009, 18]), and it undermines the one value that gives existence its meaning and dignity, that is, the capacity to choose and create our own lives.[5] To affirm his freedom, the underground man responds to this situation through self-immolating acts of revolt, doing the opposite of whatever the determinations of rationality, social convention, or the laws of nature demand. When he has a toothache, he refuses to see the doctor; when he is at a party with former school mates, he behaves in outrageous and humiliating ways; when the prostitute Liza reaches out to him in tenderness, he lashes out at her in rage. In this sense, the underground man is an anti-hero. He recognizes that freedom is the highest value, the “most advantageous advantage” (1864 [2009, 17]) for human beings, but at the same time he realizes there is no way of knowing what might come of our choices; they may, as they do for the underground man, result in our own self-destruction. As Dostoevsky writes: “What man wants is simply independent choice, whatever that independence may cost and wherever it may lead. And the choice, of course, the devil only knows what choice” (1864 [2009, 20]). This account of freedom suggests that my being (or identity) is always penetrated by the possibility of its own negation because I can always question myself and assign new meanings to and interpretations of who I am in the future. My self-interpretation is always insecure or unstable. I may interpret myself as a philosophy professor today, but I am also not a professor insofar as I can freely choose to reject this identity and resign from my job tomorrow. In this sense, I am no-thing, a “being-possible.” As Sartre puts it: “human existence is constituted as a being which is what it is not and which is not what it is” (1943 [1956, 107]). For the existentialist, anxiety discloses this predicament to me, revealing that I’ve been abandoned to a realm of possibilities, where I face a dizzying array of options, and I alone am answerable to whatever options I choose. Understood this way, anxiety is not directed at some external object or event in the world. If I am an incarnation of freedom, it is directed at me; I am the source of it. 4.2 Mediated Freedom In Being and Nothingness, Sartre forwards an account of “radical” or “absolute” freedom, an unconditioned “freedom-in-consciousness” where we make or create ourselves ex nihilo, through the sheer “upsurge” of choice alone. But in the wake of Marxist criticism in the 1940s and 1950s, his views changed; he realized that this early account was far too abstract, interiorized, and influenced by Cartesian assumptions.[6] It failed to engage the social, historical, and material conditions that invariably limit and constrain our freedom. He came to recognize that our choices and actions are always mediated by the world, by the sociohistorical situation we’ve been thrown into. He sees that the idea of radical, unconditioned freedom “is nonsense. The truth is that existence ‘is-in-society’ as it ‘is-in-the-world’” (Sartre 1952 [1963, 590]). Freedom must be understood as “freedom-in-situation.” It is true that we are free to create ourselves, but it is also true that we are already created by our situation. “Man,” is best understood as “a totally conditioned social being who does not render back completely what his conditioning has given him” (Sartre 1972 [2008, 35]). Sartre’s Marxist inspired conception of situated or mediated freedom is one that had already been forwarded and developed by Beauvoir in her major treatises The Second Sex and The Coming of Age and in her novels such as The Blood of Others (1945 [1970]) and The Mandarins (1954 [1991]). The view is also developed by her compatriot Merleau-Ponty. In Phenomenology of Perception, for example, Merleau-Ponty makes it clear that the options we choose to act on do not emerge out of nothing. They are already embedded in a sociohistorical situation “before any personal decision has been made.” (1945 [1962, 449]) The ways in which we create or make ourselves, then, are always circumscribed by the meanings of our situation. We are simultaneously self-making and already made. “We exist in both ways at once,” writes Merleau-Ponty. “We choose the world, and the world chooses us.” (1945 [1962, 453–454]). As we will see in section 6.3, the recognition of the extent to which freedom is mediated by the material conditions of our situation opened existentialism to a broader engagement with the social sphere and the structures of oppression and violence that shape our experience and self-understanding. https://plato.stanford.edu/entries/existentialism/ |
3. 実存は本質に先立つ この原則は、ハイデガーの『存在と時間』の初期に、彼が「ダーザインの『本質』はその存在にある」(1927 [1962, 42])と書いているところから導入された[3]。サルトルは後に、このセリフを「存在は本質に先立つ」(1946 [2001, 292])という簡潔な格言に言い換えている。この言葉が示唆するのは、私たちを決定するような、あらかじめ与えられた本質的な性質は存在しないというこ とである。つまり、私たちは常に私たち自身以外の存在であり、私たち自身と完全に一致することはないのである。私たちは、自己を創造する、あるいは自己を 定義する存在として自分自身のために存在し、私たちの人生が展開する中で私たちが行う状況的な選択を通して、私たちは常に自分自身を創造し、定義する過程 にある。サルトルによれば、これは「実存主義の第一原理」であり、「まず、人間が存在し、現れ、登場し、その後に初めて、自分自身を定義することを意味す る」(1946 [2001, 292-3])。ここで重要なのは、人間であることについての完全で決定的な説明はありえないということである。なぜなら、私たちは常に可能性に向かって 前進し、自分が何者であるかを想像し、再想像しながら、「未来に向かって自らを急き立てる」からである。存在とは静的なものではなく、自己形成の動的なプ ロセスなのだ。 実存が自己形成のプロセスであることを認めることは、実存主義者が、私たちを制限し束縛する、私たちの状況についての決定的な側面や「事実」が存在するこ とを否定することを意味しない。これは私たちの所与性(あるいは "事実性")であり、私たちの身体性や空間性、被造物としての食欲や欲望、私たちが置かれている社会史的文脈といった私たちの存在の側面を含んでいる。し かし、私たちが人間であることを際立たせているのは、これらの事実との関わり方、解釈の仕方、意味づけの仕方において、これらの事実を超越する、あるいは "超越 "する能力を持っているということである。例えば、私がセックスやアルコール、タバコに対する強い欲求に駆られたとしても、必然的にその欲求のままに行動 しなければならないわけではない。欲望に疑問を投げかけ、意味を与える自由が私にはあり、その意味づけが私の選択と今後の人生の方向性を形作るのだ。 つまり、他の生物とは異なり、私たちは事実性に疑問を投げかけ、それをさまざまな方法で解釈し、今後どのように対処するかを決定することによって、事実性 を凌駕することができる自己意識的存在なのである。これが、キルケゴールが存在を「それ自体に関係する関係」(1849 [1989, 43])と表現した意味である。存在とは、「事実性」と「超越性」の間の反射的な、あるいは関係的な緊張であり、そこでは私たちは事実性によって束縛され ているが、同時に事実性を超える、あるいは超越する自由を与えられている。オルテガ・イ・ガセットが書いているように、人間は「存在論的ケンタウロスのよ うなもので、半分は自然に没入し、半分は自然を超越している」(1941, 111)。なぜなら、私たちの本性は常に私たちにとって疑問であり、問題だからである。なぜなら、私たちの本性は常に私たちにとって疑問であり、問題だか らである。そして、私たちが自分の本性に関心を持つことが、私たち自身をどのように創造するかにつながるのである。サルトルは、人間の存在は基本的に「定 義不可能」であり、「人間の本性は存在しない」とまで言う。私たちの事実性は、私たちがそれに与える自己定義的な意味や価値を通してのみ、私たちに姿を現 すのである。「人間が[......]定義不可能であるとすれば、それは最初、人間は無であるからである。その後で初めて、彼は何かとなり、彼自身が、彼 がそうなるものを作り上げたのである」(1946 [2001, 293])。事実性は常に私たちの選択によって無効化され、否定されうるというこの考え方は、実存主義的な自由の概念を理解する鍵を明らかにする。 4. 自由 実存主義者は、実存を決定するようなあらかじめ与えられた本質は存在しないことを認識し、選択と行動を通じて彼、彼女、または彼ら自身のアイデンティティ を作るのは個人次第であることを明確にする。サルトルは、たとえば臆病者がそうであるのは、不安定な子供時代や特殊な遺伝的体質のせいではないと説明す る。臆病者は自分の決断によって「自分を臆病者にしている」のである(1946 [2001, 301])。このように、実存主義者は一般的に、人間には自由意志があり、意思決定が可能であり、自分の行動に責任を持つことができるという見解を肯定す る[4]。それはむしろ、私たちの存在が、私たちの人生が展開する中で私たちが行う行動や選択に基づいて、私たちの状況に意味を与える能力によって構成さ れていることを意味している。私たちが存在する限り、私たちはある種の人生を思い描き、アイデンティティに価値を与え、自分自身をそのような人間にしてい るのだ。 人間の条件から逃れられないものとして自由を自覚するとき、その自覚はしばしば不安を伴う。道徳的な絶対的存在も、神の意志も、私たちの行動を導いたり正 当化したりする自然法則もない。私たちの背後には言い訳もなければ、私たちの前には正当化もない」(サルトル 1946 [2001, 296])。 4.1 選択の不安 実存主義文学の規範の中で、『地下からの覚書』のドストエフスキーほどこの考えをよく捉えている作家はいない。名もなき「地下の男」は、1860年代にロ シアの社会改革者たちによって推進された、科学化され、合理化され、機械化されつつある人間の行動観に反抗する。地下の男にとって、この見方は人間を機械 的な歯車や「ピアノの鍵盤」(1864 [2009, 18])に貶め、存在に意味と尊厳を与える一つの価値、すなわち、自らの人生を選択し創造する能力を損なうものである。歯が痛いと医者にかかるのを拒否 し、かつての学生時代の仲間とのパーティーでは、とんでもない屈辱的な振る舞いをし、娼婦ライザが優しく手を差し伸べると、怒りに任せて彼女に暴力を振る う。この意味で、地下の男はアンチヒーローなのだ。彼は、自由が人間にとって最高の価値であり、「最も有利な利点」(1864 [2009, 17])であることを認識しているが、同時に、自分の選択によって何がもたらされるかを知る術がないことも認識している。ドストエフスキーが書いているよ うに、「人間が欲しているのは、自立した選択である。そして、その選択は、もちろん、悪魔にしかわからない」(1864 [2009, 20])。 この自由についての説明は、私の存在(あるいはアイデンティティ)は、それ自体が否定される可能性によって常に貫かれていることを示唆している。私の自己 解釈は常に不安定である。今日、私は自分を哲学教授と解釈するかもしれないが、明日、このアイデンティティを拒否し、職を辞することを自由に選択できる限 りにおいて、私は教授でもない。この意味で、私は無であり、"可能な存在 "なのである。サルトルが言うように 「人間の存在は、それが何でないかであり、何であるかでない存在として構成される」(1943 [1956, 107])。実存主義者にとって、不安はこの苦境を私に開示し、私がめくるめく選択肢の配列に直面する可能性の領域に見捨てられたことを明らかにする。こ のように理解すれば、不安は世界の外部の対象や出来事に向けられているのではない。私が自由の化身であるとすれば、それは私に向けられたものであり、私が 自由の源なのである。 4.2 媒介される自由 サルトルは『存在と無』において、「急進的な」あるいは「絶対的な」自由、すなわち無条件の「意識の中の自由」、すなわち選択の「高揚」のみによって、私 たちが虚無的に自らを創造する、あるいは創造する自由についての説明を提示した。しかし、1940年代から1950年代にかけてのマルクス主義批判をきっ かけに、彼の見解は変化した。彼は、この初期の説明があまりにも抽象的で、内面化され、デカルト的な仮定の影響を受けていることに気づいたのである。彼 は、私たちの選択と行動は常に世界によって、私たちが投げ込まれた社会歴史的状況によって媒介されていることを認識するようになった。彼は、根本的で無条 件の自由という考えは「ナンセンスである」と考える。真実は、存在が『世界の中にある』ように『社会の中にある』ということだ」(Sartre 1952 [1963, 590])。自由は "状況における自由 "として理解されなければならない。私たちが自分自身を創造する自由があることは事実だが、私たちがすでに状況によって創造されていることも事実である。 「人間」とは、「完全に条件づけられた社会的存在であり、その条件づけが彼に与えたものを完全に奪い返すことはない」(サルトル 1972 [2008, 35])と理解するのが最も適切である。 サルトルのマルクス主義に触発された状況化された自由、あるいは媒介された自由という概念は、ボーヴォワールが彼女の主要な論考『第二の性』や『青春』、 そして『他人の血』(1945[1970])や『マンダリン』(1954[1991])といった小説の中ですでに提唱し、発展させてきたものである。この 見解は、彼女の同胞であるメルロ=ポンティによっても展開されている。例えば、メルロ=ポンティは『知覚の現象学』の中で、私たちが選択する選択肢は無か ら生じるものではないことを明らかにしている。それらは、"個人的な決定がなされる前に "すでに社会歴史的状況に埋め込まれているのである。(1945[1962、449])それゆえ、私たちが自分自身を創造したり作ったりする方法は、常に 状況の意味によって制約される。私たちは同時に、自己を創造しているのであり、すでに創造されているのである。「メルロ=ポンティはこう書いている。「私 たちは世界を選び、世界は私たちを選ぶ。(1945 [1962, 453-454]). 6.3節で述べるように、自由が私たちの置かれた状況の物質的条件によって媒介される程度を認識することで、実存主義は社会圏や、私たちの経験と自己理解 を形作る抑圧と暴力の構造との、より広範な関わりへと開かれた。 |
| 5. Authenticity Existentialism is well known for its critique of mass society and our tendency to conform to the levelled-down norms and expectations of the public. Rather than living our own lives, we tend to get pulled along by the crowd, doing what “they” do. As Heidegger writes, “We take pleasure and enjoy ourselves as they take pleasure. We read, see, and judge about literature and art as they see and judge … we find ‘shocking’ what they find shocking. The ‘they’… prescribes the kind of being of everydayness” (1927 [1962, 126–7]). Living this way can be comforting, creating the illusion that we are living well because we are doing what everyone else does. But for the existentialist, this conformist way of being is a manifestation of inauthenticity or self-deception because it shows how we are unwilling or unable to face up to the freedom and contingency of our condition; it reveals the extent to which we are afraid of being an individual, of being true to ourselves, and of making our own life-defining choices. In The Sickness unto Death, Kierkegaard describes inauthenticity in terms of fleeing from ourselves, of “not wanting to be oneself, [of] wanting to be rid of oneself” (1849 [1989, 43]). Insofar as we let others decide our lives for us, we live a life that is bereft of passion, a life of “bloodless indolence,” where we are unwilling or unable to “make a real commitment.” (Kierkegaard 1846 [1946, 266–67]). Similarly, Heidegger will refer to this condition as a form of estrangement that “alienates Dasein from itself,” where we exist as a “they-self” (Man-selbst) that drifts along in lockstep with others. (1927 [1962, 254–55]) And this self-estrangement is numbing or “tranquilizing” (beruhigend) because it covers over the anxiety of own freedom and finitude. Sartre and Beauvoir refer to inauthenticity in terms of “bad faith” (mauvaise foi), where we either deny or over-identify with one of the two aspects of human existence, either facticity or transcendence. I am in bad faith, for example, when I over-identify with my factical situation and deny my freedom to act on and transform this situation. I am also in bad faith when I over-identify with freedom and deny my past conduct and the fact that my choices are limited and constrained by my situation. Sartre and Beauvoir recognize that the self is never wholly free or wholly determined; it is structurally unstable, it is a “double- property … that is at once a facticity and a transcendence” (Sartre 1943 [1956, 98]). When we cling to one or the other of these poles, we are denying this “double-property,” and this is a denial of the fundamental ambiguity and instability at the core of the human condition. 5.1 The Power of Moods For the existentialists, the possibility of breaking free from engrained patterns of self-deception is generally not something that is accomplished by means of detached reflection. It emerges in the wake of powerful emotional experiences or moods. When the existentialist refers to feelings of “nausea” (Sartre), “absurdity” (Camus), “anxiety” (Kierkegaard), “guilt” (Heidegger), or “mystery” (Marcel) they are describing uncanny affects that have the power to shake us out of our complacency, where the secure and familiar world breaks apart and collapses, and we are forced to confront the question of existence. Jaspers refers to these moments as “limit” or “boundary situations” (Grenzsituationen)—situations “when everything that is said to be valuable and true collapses before our eyes” (1932 [1956, 117]). Although terrifying, the existentialist makes it clear that we should not close our eyes or flee from these experiences because they are structural to the human condition. They are, as Jaspers puts it, “impassable, unchangeable situations that belong to human existence as such” (1913 [1997, 330]). Instead of turning away from this basic anxiety, the existentialist asks us to turn toward and face it, because it is amidst a collapsing world that the ultimate questions emerge: Who am I? and What now? In this way, the existentialist sees the experience of anxiety and its related moods as an opportunity for personal growth and transformation. World-shattering moods open me up to the possibility of being authentic, of accepting and affirming the unsettling givens of my condition, of being released from distractions and trivialities, and of recognizing the self-defining projects that matter to me as an individual. 5.2 Kierkegaard’s Knight of Faith For Kierkegaard, the authentic individual is someone that is “willing to be one’s own self.” (1843 [1989, 43]) He, she, or they recognize(s) that there is more to life than following the crowd or chasing surface pleasures. Such a life is invariably scattered and disjointed, pulled apart by temporal desires and the fleeting fads and fashions of the public. Authenticity requires a passionate, “personality defining” (personligheds definerende) decision or commitment that binds together and unifies the fragmented and disjointed moments of our life into a focused and coherent whole. The “unifying power” of commitment is embodied in, what Kierkegaard calls, an attitude of “earnestness” (alvor), a sober recognition that existence is a serious affair, not a pleasure-seeking masquerade. But authenticity cannot be achieved simply by means of renouncing temporal pleasures and doing one’s duty according to some universal moral principle—such as the Ten Commandments or Kant’s Categorical Imperative. This is because, for Kierkegaard, the subjective truth of the individual is higher than the universal truths of morality. And this means there may be times in our lives where we must suspend our obligation to the ethical sphere and accept the terrible fact that it may be more important to be authentic (to be true to oneself) than it is to be moral (to do what is right.) In Fear and Trembling, Kierkegaard draws on the biblical figure of Abraham to make this point. As a father, Abraham has a moral duty to love and protect his son, but when God demands that he break this commandment and kill Isaac, he is confronted with a personal truth that is higher than the universal. In committing himself to this truth, Abraham becomes a “knight of faith” by “leaping” (springer) into a paradox, one where the truth of “the singular individual is higher than the universal” (1843 [1985, 84]). As a religious existentialist, Kierkegaard contends that this is what is required to enter the sphere of faith and become a Christian. It has nothing to do with membership in a congregation or obedience to doctrinal statements. It is, rather, a willingness to commit to a truth that is fundamentally irrational and absurd. How, for example, can one make rational sense of God’s command to Abraham to kill his own son? “The problem,” writes Kierkegaard, “is not to understand Christianity, but to understand that it cannot be understood” (1835–1854 [1959, 146]).[7] An authentic or religious life, then, is always accompanied by anxiety and loneliness because the leap individualizes us; it cuts us off from the comforting truths of the public and its blanket conceptions of right and wrong. It compels us to follow a path that no one else may understand. Abraham’s decision is, for this reason, fraught with despair. In his willingness to suspend his moral duty, he appears “insane” because he “cannot make himself understood to anyone.” (1985 (1843], 103) But with the despair of faith comes feelings of intensity, even joy, as we recognize the absurdity of religious existence, that the eternal or divine is not found in some otherworldly realm, it is bound up in the temporal; that it is this life, the finite, that has infinite significance. Freed from the temptations of the crowd and of blind obedience to moral principles, the knight of faith “takes delight in everything he sees” because he is now fully aware of the majesty and richness of finitude. For him, “finitude tastes just as good as to one who has never known anything higher” (1843 [1985, 69–70]). 5.3 Nietzsche’s Overman Like Kierkegaard, Nietzsche is critical of our tendency to follow the herd and cling to universal moral principles. He forwards a conception of authenticity that accepts our nihilistic predicament and rises above Christian values of good and evil. He sees these values as representative of a tame and submissive way of being, a “slave morality” (Sklavenmoral) that is subservient to authority and bereft of any originality or style. Nietzsche contrasts this with a “master morality” (Herrenmoral) embodied in those who have the courage to face, even affirm, the cruel and tragic aspects of life and the self-directed power to create their own meanings and values against the backdrop of God’s death. Nietzsche refers to the individual who can overcome the meek and slavish values of tradition for the sake of self-creation as an “Overman” (Übermensch), an aristocratic figure who embodies the freedom, courage, and strength to be original, that is, to “give style” to life. “Such spirits,” writes Nietzsche, “are always out of fashion or explain themselves and their surroundings as free nature—wild, arbitrary, fantastic, and surprising” (1887 [1974], §290). The key to living with style is, for Nietzsche, a radical acceptance of one’s existence and the world as it is, embracing all our strengths and weaknesses and all the blessed and cursed events that have been and will be. The Overman is a “yes-sayer” who affirms every aspect of his life, “every truth, even the simple, bitter, ugly, unchristian, immoral truths” (1887 [1996], §1). In The Gay Science, Nietzsche captures this attitude with a famous thought experiment called the “doctrine of eternal recurrence.” Here, he asks if we have the audacity to live the same life we are living now over and over for eternity. “And there will be nothing new about it,” he explains, “but every pain and every pleasure, and every thought and sigh, and everything unspeakably small and great in your life must come back to you and all in the same series and sequence.” On Nietzsche’s view, most of us would recoil in horror at the prospect of eternally suffering through the same boredom, failures, and disappointments. But overflowing with amor fati (love of one’s fate), the Overman welcomes this possibility, proclaiming, “I have never heard anything more godlike” (1887 [1974], §341). Camus describes this attitude as a form of rebellion against servile and conformist ways of being. Like the Overman, “the rebel” is someone “born of abundance and fullness of spirit,” and he embodies “the unreserved affirmation of human imperfection and suffering, of evil and murder, of all that is problematic and strange in our existence. It is born of an arrested wish to be what one is in a world that is what it is” (1951 [1956, 72]). But not everyone has the inborn power to rebel against tradition and creatively express their unique style of living. For Nietzsche, only “the highest types” can manifest this kind of freedom and capacity for self-overcoming. To this end, his account of authenticity is unapologetically elitist and anti-democratic. Most of us are too mired in self-deception, too frightened and weak to break with the herd and become who we are. “Only a very few people can be free,” writes Nietzsche, “It is a prerogative of the strong” (1886 [1998], §29). 5.4 Heidegger’s Resolute Dasein Heidegger devotes much of the second half of Being and Time to an analysis of authenticity, employing the German term Eigentlichkeit—formed from the stem of the adjective eigen (“own” or “property”)—that literally means “being own’s own” or “ownnness.” But he sets up his analysis of authenticity by first claiming that self-deception or “inauthenticity” is unavoidable; it is a structure of the human condition, one that he refers to as “falling” (Verfallen). What this means is that in our everyday lives we invariably conform (or “fall prey”) to the norms and values of the public world. This results in a kind of complacency and indifference about the question of existence, where we are not our own selves, where “everyone is the other, and no one is himself” (1927 [1962, 128]). Falling creates the illusion that our existence (or being-in-the-world) is secure and thing-like because we are doing what everyone else does. But, for Heidegger, there is nothing that fundamentally secures our existence. As a self-making activity, I am not a stable thing. I am nothing, a “not yet” (noch nicht) that is always unsettled, always in the process of making myself. The awareness of our own unsettledness emerges in moments of anxiety when the familiar and routinized world “collapses into itself” (1927 [1962, 186]), and I “die” (sterben) because I am no longer able-to-be, that is, to understand or make sense of who I am.[8] Like Kierkegaard, Heidegger interprets anxiety as an individualizing mood, one that momentarily “snatches one back” from the tranquilizing routines of “the They,” leaving us vulnerable and exposed to confront our lives (1927 [1962, 384]). And this is potentially liberating because it can temporarily free us from patterns of self-deception, providing insight, a “moment of vision” (Augenblick) that can give our lives a renewed sense of urgency and focus. But this experience of individuation does not detach me from the world, turning me into a radical subject or “free floating ‘I’” (1927 [1962, 298]). Heidegger claims that our self-defining choices are always guided in advance by our historical embeddedness, what he calls “historicity” (Geschichtlichkeit). The meanings we choose to give to our lives, then, are not created out of thin air; they have already been interpreted and made intelligible by a historical community or “people” (Volk).[9] The moment of vision shakes me out of my fallen, everyday existence and allows me to come back to my historical world with fresh eyes, to seize hold of the publicly interpreted meanings that matter to me and make them “mine” (Jemeinig). Heidegger refers to this authentic attitude in terms of “resoluteness” (Entschlossenheit), where I “pull [myself] together,” giving life a sense of cohesion and focus that was missing when I was lost and scattered in “the They.” But being resolute does not mean that I stubbornly cling to whatever possibilities I happen to choose. For Heidegger, authenticity demands an openness and flexibility with how I interpret myself.[10] Understanding that existence is a situated process of self-making, whatever values or meanings I commit myself to, I must also be willing to let go or give up on them depending on the circumstances of my life, that is, to “hold [myself] free for the possibility of taking it back” (1927 [1962, 308]). Resoluteness, on this view, does not mean “becoming rigid” and holding fast to a chosen identity because my self-understanding is always insecure; it can die at any time. For this reason, authenticity requires “readiness” or “anticipation” (Vorgriff), where we passionately hold ourselves open and free for the inescapable breakdowns and emergencies of life. It is, in Heidegger’s words, “an impassioned freedom towards death—a freedom which has been released from the illusions of the ‘They’” (1927 [1962, 266]). 5.5 Self-Recovery in Sartre and Beauvoir Sartre and Beauvoir follow Heidegger in viewing self-deception as structural to the human condition. It is, as Sartre writes, “an immediate, permanent threat to every project of the human being” (1943 [1956, 116]). Although I can certainly deceive myself by over-identifying with freedom and denying the extent to which my possibilities are constrained by facticity, the most common and familiar form of bad faith is when I over-identify with my facticity, as if I were a fully realized object or thing, a being “in-itself” (en-soi). This form of self-deception is understandable as it creates the consoling impression that there is something secure and thing-like about my identity, that “I am what I am,” and there is nothing that can change me. But to live this way is to deny my freedom and transcendence, that I am self-making, that I live for myself—or, in the vernacular of Sartre and Beauvoir, “for-itself” (pour-soi). Human beings are, on their view, always in the process of making or constituting themselves, modifying and negating their being through moment-to-moment choices and actions. This means my identity is never fixed or stable because I can always choose to take a new path or interpret myself in other ways. Regardless of how I see myself at a given time—as a professor, a father, or a political activist—I am also “not” that person, because my identity is never realized and complete; I am always free to negate a given identity and define myself differently in the future. This means I am “what I am not” (1943 [1956, 103]). And this situation appears to undermine the prospect of authenticity altogether. If the self is always unstable, always in question, how can I ever be genuine or true to myself? In Being and Nothingness, Sartre provides an answer, referring to authenticity in terms of a “recovery” (récupération) of a self or way of being “that was previously corrupted” (1943 [1956, 116]).[11] But this act of “self-recovery” has nothing to do with creating or holding on to a particular identity. It involves, rather, a clear-eyed awareness and acceptance of the instability and ambiguity of the human condition. And, along with this acceptance, a willingness to act in the face of this ambiguity and to take responsibility, however horrible, for wherever these actions might lead. As Sartre writes, “authenticity consists in a lucid consciousness of the situation, in assuming the responsibilities and risks it involves, in accepting it […] sometimes with horror and hate” (1946 [1948, 90]). But just because existence is fundamentally ambiguous does not mean that our chosen projects are meaningless or absurd. My projects have meaning and value because I chose these projects, but the meaning is contingent; it is never enduring or stable. In The Ethics of Ambiguity, Beauvoir explains: “The notion of ambiguity must not be confused with that of absurdity. To declare that existence is absurd is to deny that it can ever be given a meaning; to say that it is ambiguous is to assert that its meaning is never fixed” (1947 [1948, 129]). The point of authenticity, then, is not to be concerned with who I am—because, at bottom, I am nothing. It is to be concerned with what I do. As Sartre writes, “Authenticity reveals that the only meaningful project is that of doing (not that of being)” (1948 [1992, 475]). For Sartre and Beauvoir, to be authentic is to recover and accept the ambiguous tension of the self, that: we are who we are not—and—we are not who are. And by means of this recovery, recognize that the task of existence involves acting and doing, that is, realizing our freedom through projects in the world but also, as we will see, taking responsibility for how these projects might enhance or diminish freedom for others. https://plato.stanford.edu/entries/existentialism/ |
5. 真正性 実存主義は、大衆社会を批判し、私たちが大衆の平板な規範や期待に合わせようとする傾向を批判することでよく知られている。私たちは自分自身の人生を生き るのではなく、群衆に引っ張られ、「彼ら」と同じことをする傾向がある。ハイデガーが書いているように、「彼らが喜びを感じるように、私たちも喜びを感 じ、楽しむ。私たちは、彼らが見て判断するように、文学や芸術を読み、見て、判断する......私たちは、彼らがショッキングだと思うことを『ショッキ ング』だと思う。彼ら』は...日常性という種類の存在を規定している」(1927[1962, 126-7])。このような生き方は慰めになり、みんながやっていることをやっているのだから自分もよく生きているのだという錯覚を生む。しかし、実存主 義者にとっては、このような適合主義的なあり方は、不真面目さや自己欺瞞の現れである。なぜなら、私たちがいかに自分の状態の自由や偶発性を直視したくな いか、あるいはできないかを示しているからである。 キルケゴールは『死に至る病』の中で、不真面目さを自分自身からの逃避、「自分自身でありたくない、自分自身から解放されたい」(1849 [1989, 43])という言葉で表現している。他人に自分の人生を決めてもらう限り、私たちは情熱のない人生、「血も涙もない怠惰」な人生を送ることになる。(キル ケゴール1846[1946、266-67])。同様に、ハイデガーはこの状態を「ダーザインを自分自身から疎外する」疎外と呼ぶ。(1927 [1962、254-55])そしてこの自己疎外は、自らの自由と有限性への不安を覆い隠すために、麻痺させるか、あるいは「精神安定」させる (beruhigend)。 サルトルとボーヴォワールは、人間存在の二つの側面(事実性か超越性か)のいずれかを否定するか、あるいは過剰に同一視する「悪意」(mauvaise foi)という言葉で、不真実性に言及している。例えば、事実的な状況に過剰に同一化し、この状況に対して行動し変容させる自由を否定するとき、私は不誠 実である。また、自由を過信し、自分の過去の行為や、自分の選択が状況によって制限され制約されているという事実を否定するときにも、私は悪意を持ってい る。サルトルとボーヴォワールは、自己は決して完全に自由でも完全に決定されたものでもなく、構造的に不安定なものであり、それは「二重の性 質......それは同時に事実性であり超越性である」(サルトル 1943 [1956, 98])と認識している。これらの両極のどちらか一方に固執するとき、私たちはこの「二重特性」を否定することになり、これは人間の条件の核心にある根本 的な両義性と不安定性を否定することになる。 5.1 気分の力 実存主義者にとって、染み付いた自己欺瞞のパターンから脱却する可能性は、一般的に、冷静な内省によって達成されるものではない。それは、強力な感情的体 験や気分の結果として現れるものである。実存主義者が「吐き気」(サルトル)、「不条理」(カミュ)、「不安」(キルケゴール)、「罪悪感」(ハイデ ガー)、「神秘」(マルセル)などの感情に言及するとき、それは私たちを自己満足から揺り動かす力を持つ不気味な影響について述べているのである。ヤス パースはこのような瞬間を「限界」あるいは「境界状況」(Grenzsituationen)と呼んでいる-「価値あるもの、真実であると言われているも のがすべて目の前で崩壊する」状況である(1932 [1956, 117])。 恐ろしいことではあるが、実存主義者は、このような体験は人間の条件にとって構造的なものであるため、目を閉じたり逃げたりすべきではないと明言してい る。ヤスパースが言うように、それらは「人間存在に属する、通過不可能で変更不可能な状況」なのである(1913 [1997, 330])。実存主義者は、この基本的な不安から目を背けるのではなく、その不安に向き合い、向き合うよう私たちに求める: なぜなら、崩壊した世界の中でこそ、究極の問いが立ち現れるからである。このように、実存主義者は不安とそれに関連する気分の経験を、個人の成長と変容の 機会として捉える。世界を打ち砕くような気分は、自分が本物である可能性、自分の状態にある不安な事実を受け入れ肯定する可能性、気晴らしや些細なことか ら解放される可能性、そして個人として自分にとって重要な自己定義プロジェクトを認識する可能性を開いてくれる。 5.2 キルケゴールの信仰の騎士 キルケゴールにとって本物の個人とは、"自分自身であることを厭わない "人である。(彼、彼女、あるいは彼らは、人生には群衆に従ったり、表面的な快楽を追い求めたりする以上のものがあると認識している。そのような人生は常 に散漫でバラバラであり、一時的な欲望や世間のはかない流行やファッションに引き離される。本物であるためには、情熱的で、「個性を定義する」 (personligheds definerende)決断やコミットメントが必要である。コミットメントの「統一力」は、キルケゴールが言うところの「真剣さ」(alvor)の態度 に具現化される。しかし、単に一時の快楽を捨て、十戒やカントの定言命法のような普遍的な道徳原理に従って義務を果たすだけでは、真正性は達成できない。 キルケゴールにとって、個人の主観的真理は道徳の普遍的真理よりも上位にあるからだ。そしてこれは、倫理的領域に対する義務を一時停止し、道徳的であるこ と(正しいことをすること)よりも、真正であること(自分自身に忠実であること)の方が重要かもしれないという恐ろしい事実を受け入れなければならない時 が、私たちの人生にはあるかもしれないということを意味している。 キルケゴールは『畏れとおののき』の中で、聖書に登場するアブラハムの姿を用いてこの点を指摘している。父親として、アブラハムは息子を愛し守る道徳的義 務を負っているが、神がこの戒めを破ってイサクを殺すよう要求したとき、彼は普遍的なものよりも高い個人的真理に直面する。この真理に身を委ねることで、 アブラハムは「信仰の騎士」となり、「一個人が普遍的なものよりも高い」(1843 [1985, 84])というパラドックスに「跳び込む」(springer)のである。宗教的実存主義者であるキルケゴールは、これが信仰の領域に入り、キリスト教徒 になるために必要なことだと主張する。それは、信徒の一員であることや教義上の声明に従うこととは何の関係もない。それはむしろ、根本的に非合理的で不条 理な真理にコミットする意志である。たとえば、神がアブラハムに自分の息子を殺せと命じたことを、どうすれば合理的に理解できるだろうか?「問題は、キリ スト教を理解することではなく、理解できないことを理解することである」(1835-1854 [1959, 146])とキルケゴールは書いている。誰にも理解されない道を歩むことを強いられるのだ。アブラハムの決断には絶望が伴う。道徳的義務を放棄しようとす る彼は、"誰にも自分を理解させることができない "ため、"正気でない "ように見える。(1985 (1843], 103) しかし、信仰の絶望とともに、宗教的存在の不条理を認識し、永遠や神聖なものがどこか別世界の領域にあるのではなく、現世に縛られていること、無限の意味 を持つのは有限である現世であることを認識することで、激しさや喜びさえも感じるようになる。群衆の誘惑や道徳的原則への盲従から解放された信仰の騎士 は、「見るものすべてに喜びを感じる」。彼にとって、「有限性は、より高次のものを知らな い者と同じようにおいしい」のである(1843 [1985, 69-70])。 5.3 ニーチェのオーバーマン キルケゴールのように、ニーチェは、群れに従い、普遍的な道徳原理に固執する私たちの傾向を批判している。彼は、私たちのニヒリスティックな苦境を受け入 れ、キリスト教的な善悪の価値観の上に立つ真正性の概念を提唱している。彼はこれらの価値観を、飼いならされた従順なあり方、権威に従順で独創性もスタイ ルもない「奴隷道徳」(Sklavenmoral)の代表とみなす。ニーチェはこれを、人生の残酷で悲劇的な側面に直面し、それを肯定する勇気と、神の死 を背景に自分自身の意味と価値を創造する自己主導的な力を持つ人々に体現される「主人道徳」(Herrenmoral)と対比させる。ニーチェは、自己創 造のために伝統のおとなしく隷属的な価値観に打ち勝つことができる個人を「超人」(Übermensch)と呼び、独創的であること、つまり人生に「様式 を与える」ことの自由、勇気、強さを体現する貴族のような人物だという。「ニーチェは「そのような精神は常に流行から外れているか、あるいは自分自身とそ の周囲を、自由な自然、すなわち野性的、恣意的、幻想的、驚くべきものとして説明している」(1887 [1974], §290)と書いている。 スタイリッシュに生きるための鍵は、ニーチェにとって、自分の存在と世界をありのままに根本的に受け入れることであり、自分の長所と短所、過去と未来に起 こった祝福された出来事と呪われた出来事をすべて受け入れることである。オーバーマンは、自分の人生のあらゆる側面、「単純で、苦く、醜く、非キリスト教 的で、不道徳な真理でさえも、あらゆる真理」を肯定する「イエス・セイヤー」である(1887 [1996], §1)。ゲイ・サイエンス』の中でニーチェは、"永遠回帰の教義 "と呼ばれる有名な思考実験によって、この態度をとらえている。ここで彼は、今生きているのと同じ人生を永遠に繰り返し生きる大胆さがあるかどうかを問う ている。"そして、それについて新しいことは何もないだろう。"と彼は説明する。"しかし、あらゆる苦痛、あらゆる快楽、あらゆる考えやため息、そしてあ なたの人生における言いようのないほど小さく偉大なものすべてが、あなたに戻ってくるに違いない。"そして、すべてが同じ系列と順序で。ニーチェの考えで は、私たちのほとんどは、同じ退屈、失敗、失望の中で永遠に苦しみ続けることに恐怖を感じるだろう。しかし、アモール・ファティ(運命への愛)に溢れる オーバーマンは、この可能性を歓迎し、「これほど神々しいことはない」(1887 [1974], §341)と宣言する。カミュはこの態度を、隷属的で順応的なあり方に対する反抗の一形態であると述べている。オーバーマンと同様、「反逆者」は「豊かで 満ち足りた精神から生まれた」人であり、「人間の不完全さや苦しみ、悪や殺人、私たちの存在にある問題や奇妙なものすべてを無条件に肯定すること」を体現 している。それは、ありのままの世界において、ありのままの自分でありたいという逮捕された願いから生まれる」(1951 [1956, 72])。 しかし、伝統に反抗し、自分独自の生き方を創造的に表現する力を誰もが先天的に持っているわけではない。ニーチェにとって、この種の自由と自己克服の能力 を発現できるのは「最高のタイプ」だけである。この目的のために、彼の真正性の説明は堂々とエリート主義的であり、反民主主義的である。私たちのほとんど は、自己欺瞞に陥っており、群れから抜け出し、ありのままの自分になるにはあまりに怯え、弱い。「自由になれるのはごく少数の人間だけであり、それは強者 の特権である」(1886 [1998], §29)とニーチェは書いている。 5.4 ハイデガーの断固たるダゼイン ハイデガーは『存在と時間』の後半の大部分を真正性の分析に費やしており、ドイツ語のEigentlichkeit(形容詞eigen(「自分の」または 「所有物」)の語幹から形成された)という用語を用いている。しかし、彼はまず、自己欺瞞や「不真正性」は避けられないものであり、それは人間の状態の構 造であると主張することで、真正性の分析を立ち上げる。その意味するところは、私たちは日常生活において、必ず世間一般の規範や価値観に適合してしまう (あるいは「餌食」になってしまう)ということである。その結果、「誰もが他者であり、誰も自分自身ではない」(1927 [1962, 128])存在という問題に対して、ある種の自己満足と無関心が生じる。堕落は、私たちの存在(あるいは世界における存在)が、他の誰もがしていることを しているのだから、安全であり、事物的であるという幻想を生み出す。しかしハイデガーにとって、私たちの存在を根本的に保証するものは何もない。自己を創 造する活動として、私は安定したものではない。私は無であり、常に未確定であり、常に自分自身を作る過程にある「まだ」(noch nicht)なのである。自分自身の不安定さの自覚は、慣れ親しんだ日常化された世界が「それ自体に崩壊する」(1927 [1962, 186])不安の瞬間に現れ、私は「死ぬ」(sterben)。 キルケゴールのように、ハイデガーは不安を個人化する気分、つまり「彼ら」の静謐な日常から一瞬「人を奪い返し」、私たちを無防備な状態に置き去りにし、 私たちの生に直面させるものとして解釈している(1927 [1962, 384])。そしてこのことは、私たちを自己欺瞞のパターンから一時的に解放し、洞察力、つまり私たちの人生に新たな切迫感と集中力を与えることができる 「ヴィジョンの瞬間」(Augenblick)を与えてくれるので、潜在的に解放的である。しかし、このような個性化の経験は、私を世界から切り離し、急 進的な主体、あるいは「自由に浮遊する『私』」へと変えるものではない。(1927 [1962, 298]). ハイデガーは、私たちの自己規定的な選択は、常に私たちの歴史的埋没性、彼が「歴史性」(Geschichtlichkeit)と呼ぶものによって事前に 導かれていると主張する。私たちが自分の人生に与えることを選択する意味は、何もないところから生み出されるのではなく、歴史的共同体や「民衆」 (Volk)によってすでに解釈され、理解可能なものとされているのである[9]。幻視の瞬間は、私を堕落した日常的存在から揺り動かし、新鮮な目で歴史 的世界に立ち戻らせ、私にとって重要な、公に解釈された意味をつかみ、それを「私のもの」(Jemeinig)にすることを可能にする。 ハイデガーは、この本物の態度を「毅然さ」(Entschlossenheit)という言葉で表現している。そこでは私は「(自分自身を)ひとつにまと め」、「彼ら」の中で迷い、散らばっていたときには欠けていたまとまりと焦点の感覚を人生に与える。しかし、毅然としているということは、私がたまたま選 んだどんな可能性にも頑なにしがみつくということではない。ハイデガーにとって真正性とは、私が自分自身をどのように解釈するかについての開放性と柔軟性 を要求するものである[10]。存在とは自己形成の状況的プロセスであることを理解した上で、私がどのような価値や意味にコミットしようとも、私は自分の 人生の状況に応じてそれを手放したりあきらめたりすることも厭わない、つまり「それを取り戻す可能性のために[自分を]自由にしておく」(1927 [1962, 308])。なぜなら、私の自己理解は常に不安定であり、いつでも死ぬ可能性があるからである。そのため、真正性には「準備」あるいは「予期」 (Vorgriff)が必要であり、そこでは、人生の避けがたい破綻や緊急事態に対して、情熱的に自分自身をオープンにし、自由にすることが求められる。 ハイデガーの言葉を借りれば、それは「死に向かう熱狂的な自由-『彼ら』の幻想から解き放たれた自由」(1927 [1962, 266])である。 5.5 サルトルとボーヴォワールにおける自己回復 サルトルとボーヴォワールはハイデガーにならって、自己欺瞞を人間の状態の構造的なものと見なしている。サルトルが書いているように、自己欺瞞は「人間の あらゆるプロジェクトにとって、直接的で永続的な脅威」なのである(1943 [1956, 116])。自由と過剰に同一化し、自分の可能性が事実性によって制約されている程度を否定することによって、私は確かに自分自身を欺くことができるが、 悪意の最も一般的で身近な形態は、私があたかも完全に実現された物体や事物であるかのように、自分の事実性と過剰に同一化することである。このような自己 欺瞞は、「私は私であり、私を変えるものは何もない」という、私のアイデンティティには何か安全で物事のようなものがあるという慰めの印象を与えるので、 理解できる。しかし、このように生きることは、私の自由と超越性を否定することであり、私が自己を創造していること、私が自分のために生きていること、サ ルトルやボーヴォワールの言葉を借りれば「自己のために」(pour-soi)生きていることを否定することになる。つまり、サルトルやボーヴォワールで 言うところの "for-itself"(pour-soi)なのだ。彼らの考えでは、人間は常に自分自身を作り、構成する過程にあり、瞬間瞬間の選択や行動を通して、 自分の存在を修正し、否定している。つまり、私のアイデンティティは決して固定的で安定したものではないということだ。教授として、父親として、政治活動 家として、その時々の自分をどのように見ているかにかかわらず、私はそのような人間でもない。つまり、私は「私でないもの」なのである(1943 [1956, 103])。そしてこのような状況は、真正性の見通しを根底から覆すように見える。自己がつねに不安定で、つねに疑問の中にあるのだとしたら、どうすれば 私は真正であり、自分自身に忠実でありうるのだろうか。 サルトルは『存在と無』において、「以前は堕落していた」(1943 [1956, 116])自己やあり方の「回復」(récupération)という観点から真正性に言及し、その答えを提示している。それはむしろ、人間の状態の不安 定さと曖昧さをはっきりと認識し、受け入れることである。そして、この受容とともに、この曖昧さに直面して行動する意思と、その行動が導く先がどこであろ うと、たとえ恐ろしいものであろうと、責任を取る意思を持つことである。サルトルが書いているように、「真正性とは、状況を明晰に認識すること、状況が内 包する責任とリスクを引き受けること、それを[......]時には恐怖と憎悪をもって受け入れることである」(1946 [1948, 90])。しかし、存在が根本的に曖昧だからといって、私たちが選んだプロジェクトが無意味であったり、不条理であったりするわけではない。しかし、その 意味は偶発的なものであり、決して永続的なものでも安定したものでもない。ボーヴォワールは『曖昧さの倫理学』の中でこう説明している: 「曖昧さの概念を不条理と混同してはならない。存在が不条理であると宣言することは、存在に意味が与えられることを否定することであり、存在があいまいで あると言うことは、その意味が決して確定されないことを主張することである」(1947 [1948, 129])。真正性のポイントは、私が誰であるかにこだわることではない。私が何をするかに関心を持つことである。サルトルが書いているように、「真正性 は、唯一の意味のあるプロジェクトが(存在することではなく)行うことであることを明らかにする」(1948 [1992, 475])。サルトルとボーヴォワールにとって、真正であるとは、自己のあいまいな緊張を回復し受け入れることである。そして、この回復によって、存在の 課題には行動することと実行することが含まれることを認識する。つまり、世界におけるプロジェクトを通じて自分の自由を実現することであるが、後述するよ うに、これらのプロジェクトが他者の自由をどのように高め、あるいは低下させるかについて責任を負うことでもある。 |
| 6.
Ethics Existentialist ethics generally begins with the idea that there is no external moral order or table of values that exists a priori. “It must be understood,” as Beauvoir writes in The Ethics of Ambiguity, “that the passion in which man has acquiesced finds no external justification. No outside appeal, no objective necessity permits of its being called useful.” But this does not mean that the existentialists are promoting a form of moral nihilism. Beauvoir admits it is true that the human being “has no reason to will itself. But this does not mean that it cannot justify itself, that it cannot give itself reasons for being that it does not have.” It is human existence itself “which makes values spring up in the world on the basis of which it will be able to judge the enterprise in which it will be engaged.” (1947 [1948, 12, 15]).[12] There is, then, a coherent account of ethical responsibility grounded in freedom, not as a theoretical abstraction but as a concrete expression of transcendence, and the obligation to help others realize their own freedom so that I can realize mine. When I acknowledge that freedom is my essence, I must also acknowledge that it is the essence of others and work, to the best of my ability, to help them realize it. My freedom, then, is not free-floating; it is invariably bound up in the freedom of others. As Sartre puts it: “We want freedom for freedom’s sake and in every particular circumstance. And in wanting freedom we discover that it depends entirely on the freedom of others, and that freedom of others depends on ours […] I am obliged to want others to have freedom at the same time that I want my own freedom” (1945 [2001, 306]). 6.1 Authentic Being-for-Others Sartre and Beauvoir argue that we generally exist as “a being-for-others” (un être-pour-autrui), which is to say that I understand or see myself in the way that I do through “the look” (le regard) of the Other. And the look has the power to strip away my freedom and turn me into an object. Human relations, on this account, are best understood as a form of conflict, a dyadic power struggle where I try to assert my freedom and subjectivity by turning the Other into an object, while the Other tries to do the same to me. “While I attempt to free myself from the hold of the Other,” writes Sartre, “the Other is trying to free himself from mine; while I seek to enslave the Other, the Other seeks to enslave me… Conflict is the original meaning of being-for-others” (1943 [1956, 475]). This struggle for self-assertion leads to Sartre’s famous claim in his play Huis Clos (No Exit) that “Hell is—other people” (1944 [1989, 45]). But the struggle to objectify and possess the Other by stripping them of their freedom is a manifestation of inauthentic being-for-others. There is an authentic counterpart. Beauvoir, for example, explores what it means to develop and cultivate freedom for others with her account of “authentic love” (l’amour authentique), describing it as a relationship where we acknowledge and nurture the other’s freedom and transcendence while at the same time resisting the temptations of bad faith, that is, to see the Other as an object or thing to be manipulated and possessed. As a moral stance, authentic being-for-others is a form of reciprocity that involves “the mutual recognition of two freedoms […] [where] neither would give up transcendence [and] neither would be mutilated” (1949 [1952, 667]). In this way authenticity and morality belong together, whereby we have a shared obligation to liberate or free each other so that we can create ourselves and take responsibility for the life we lead. Therefore, as Beauvoir puts it, “to will oneself moral and to will oneself free are one and the same decision” (1947 [1948, 24]). Heidegger develops a similar idea in Being and Time with his account of “liberating concern” (befreiend Fürsorge), a form of care where the central aim is to free the Other from patterns of self-deception so that they can anxiously face and create their own existence. It is a relational stance that “helps the Other become transparent to himself in his care and to become free for it” (1927 [1962, 122]). When we care in this way, we resist the temptation to “leap-in” (einspringen) for the Other, as if the Other were a dependent thing or object that needs to be sheltered from the unsettling question of existence. Heidegger refers to this sheltering tendency in terms of a kind of tacit mastery or “domination” (Beherrschung) that strips the Other of the anxious responsibility they have for their own life. Instead of leaping-in for the Other and disburdening them of their responsibility, an authentic relation is one that “leaps-ahead” (vorausspringt) of the Other, giving them back their anxiety and the freedom to care for and confront their condition. As Heidegger writes, we leap-ahead of the Other, “not in order to take away his ‘care’ but rather to give it back to them authentically as such for the first time” (1927 [1962, 122]). Here, we see the development of an ethical maxim: to act in such a way as to will the realization of your own freedom and the realization of freedom for others. 6.2 The Ethics of Recognition There is also heterodox current among some religious existentialists, one that suggests that moral demands are placed on us when we recognize ourselves not as voluntaristic subjects—or, in the words of Iris Murdoch, “brave naked wills” (1983, 46) severed from bonds of community and attachment—but as relational beings who are fundamentally bound together in mutual vulnerability. And this recognition may serve as the foundation for an ethics by pulling us out of our everyday self-absorption and awakening us, not to our freedom, but to our essential dependency. Speaking through the religious elder Father Zossima in The Brothers Karamazov, Dostoevsky offers a powerful indictment of the “terrible individualism” that he sees as endemic to modernity, where unfettered freedom and self-affirmation have become the highest values. Such a view leads not to self-actualization but to loneliness and despair. The modern man, says Zossima, “is accustomed to rely upon himself alone and to cut himself off from the whole; he has trained himself not to believe in the help of others, in men and in humanity […] but this terrible individualism must inevitably have an end, and all will suddenly understand how unnaturally they are separated from one another” (1879 [1957–80, 279]). Against the vision of the willful subject who makes choices without evaluative limits or constraints, Dostoevsky suggests it is only in recognizing the Other as dependent and vulnerable that we can come to recognize ourselves. True freedom emerges when we release ourselves from the bondage of our own egoistic striving and adopt an attitude of humility and self-sacrifice. The aim is to show that the human being is not an isolated will but a frail and defenseless being that is dependent on the self-less love, compassion, and charity of others.[13] When we free ourselves from the temptations of individualism in this way, Zossima says a moral demand is placed on us, one where we begin to see that “we are all responsible to all and for all” (1879–80 [1957, 228). The Jewish existentialist Martin Buber expands on this idea in his masterwork I and Thou. He claims that in our everyday lives we generally relate to others from an instrumental and objectifying standpoint, what he calls the “I-It” (Ich-Es) relation, where the other is encountered as a thing (or “it”) to be manipulated and controlled for one’s own use. This relation is comforting because it creates the illusion that we have control of our situation. But there are moments in our lives when this illusion collapses, and we become vulnerable to the other, not as an “it” but as a “you.” In the “I-You” (Ich-Du) relation, all the egoistic defenses we rely on to conceal our essential dependency and openness to the Other break down. Buber refers to this as an experience of grace, where the Other is revealed to me as a whole person, defenseless and exposed, and I am revealed in the same way. It is a moment where “two human beings reveal the You to one another” (1923 [1970, 95]). In this way, anxiety isn’t a radically individualizing affair, where the forlorn subject is cut off from the relational world to confront their own freedom. For Buber, exposure to the I-You relation shakes us out of our own egoistic concerns and awakens us to the fact that we are not isolated individuals but beings who are always in living relation with others. With this experience “the barriers of the individual are breached,” and this creates an affective union, a “bridge from self-being to self-being across the abyss of dread” (1938 [1965], 201, 207]). 6.3 The Ethics of Engagement The Nazi occupation of France, his own experience as a prisoner of war, and the attacks on his philosophy from influential Marxist critics, compelled Sartre to shift his focus from the individual to the social. Following the war, he, along with Merleau-Ponty and Beauvoir, launched the influential journal of social criticism Le Temps Modernes (Modern Times), and Sartre made his aims clear in the first issue, writing: “Our intention is to help effect certain changes in the Society that surrounds us… one is responsible for what one is … Totally committed and totally freed. And yet it is the free man who must be delivered, by enlarging his possibilities of choice” (Sartre 1945 [1988, 264–65]). Here we see existentialists making the connection that for the Other to realize their freedom, philosophy must engage the “bases and structures” that limit and constrain them. This is because these structures are not philosophical abstractions; they “are lived as schematic determinates of the individual’s future” (Sartre 1957 [1968, 94]). Society, here, is viewed not as an aggregate of voluntaristic subjects; it is the mediating background of our lives, and if we are going to create a situation of freedom and “enlarge the possibilities of choice,” we must recognize how this background can be violent and oppressive—especially to historically marginalized and undervalued people—and to act in such a way as to transform it. Of all the major developers of existentialism, it is unquestionably Beauvoir who offered the most sustained and influential analyses of oppression and of possibilities for emancipation, not only in her feminist masterwork The Second Sex, but in her bleak account of the dehumanization of the elderly in The Coming of Age (1970 [1996]) and her reflections on the experience of Black populations in the Jim Crow South in her memoir America Day by Day (1954 [1999]). In these works, Beauvoir illuminates how socioeconomic and political structures can restrict the human capacity for freedom and transcendence, how they have the power to “freeze” the Other, strip away possibilities for agency and self-creation, and trap them in “immanence.” But in these works, Beauvoir makes it clear that this situation is not a destiny. Human beings have no essential nature; no one is born inferior or submissive. We are constituted intersubjectively by growing into, internalizing, and enacting ready-made structures of oppression. But insofar as these structures are constituted and maintained by the choices and actions of individuals, they are not fixed and static. Like human beings, they too are subject to change. Here we see how the recognition that existence precedes essence moves from the ontological realm to the ethical, it becomes a call to action, to engage and transform the material conditions that limit the possibilities of choice for those who are oppressed and marginalized. In this way, postwar existentialism began to engage the realities of the social sphere and the painful “isms”—classism, racism, colonialism, sexism, anti-Semitism—haunting the western world. It was a philosophy that had come to recognize, in Sartre’s words, that “the individual interiorizes his social determinations; he interiorizes the relations of production, the family of his childhood, the historical past, the contemporary in institutions, and he then re-exteriorizes these acts and options which necessarily refer us back to them” (1972 [2008, 35]). And insofar as these social determinations are not fixed and timeless but contingent human constructs, they can be resisted and transformed to free others. https://plato.stanford.edu/entries/existentialism/ |
6.
倫理学 実存主義倫理学は一般的に、先験的に存在する外的な道徳秩序や価値表は 存在しないという考えから始まる。ボーヴォワールが『曖昧さの倫理学』で書いているように、「人間が黙認している情熱は、外的な正当性を見いだせない。外 部からの訴えも、客観的な必然性も、それを有用と呼ぶことを許さない」。しかしこれは、実存主義者が道徳的ニヒリズムを助長しているという意味ではない。 ボーヴォワールは、人間が「自ら意志する理由がない」ことは事実だと認めている。しかし、だからといって、自己を正当化できない、自己にない存在理由を与 えることができないということにはならない」。人間の存在そのものが、"それにもとづいて、自分が従事する事業を判断することができるようになる "のである。(1947[1948、12、15])[12] そこで、理論的抽象としてではなく、超越性の具体的表現としての自由と、私が私の自由を実現できるように他者が彼ら自身の自由を実現するのを助ける義務に 根ざした倫理的責任についての首尾一貫した説明がある。自由が私の本質であることを認めるとき、私は他者の本質であることも認めなければならない。つま り、私の自由は自由に浮遊しているのではなく、常に他者の自由と結びついているのである。サルトルは言う: 「私たちは自由のために、そしてあらゆる特定の状況において自由を求める。そして、自由を求めることによって、それが完全に他者の自由に依存し、他者の自 由がわれわれの自由に依存することを発見する[......私は、自分自身の自由を求めると同時に、他者の自由を求めることを余儀なくされる]」 (1945 [2001, 306])。 6.1 他者のための真正な存在 サルトルとボーヴォワールは、私たちは一般的に「他者の ための存在」(être-pour-autrui)として存在すると主張する。そしてその視線は、私の自由を奪い、私を物体に変えてしまう力がある。この ように考えると、人間関係は葛藤の一形態、つまり、私が他者を客体にすることで私の自由と主体性を主張しようとし、他者も私に同じことをしようとする、二 者間の権力闘争として理解するのが最も適切である。「私が他者の束縛から自分を解放しようとする一方で、他者は私の束縛から自分を解放しようとしている。 私が他者を奴隷にしようとする一方で、他者は私を奴隷にしようとする......葛藤とは、他者のための存在ということの本来の意味である」(1943 [1956, 475])。この自己主張のための闘争は、サルトルが戯曲『ハウ・クロ』(出口なし)の中で「地獄とは他者である」(1944 [1989, 45])という有名な主張をすることにつながる。 しかし、他者から自由を奪って客観化し、所有しようとする闘争は、他者 のための非本格的存在の現れである。本物には本物の対極がある。たとえばボーヴォワールは、「真正の愛」(l'amour authentique)の説明によって、他者のために自由を開発し育むとはどういうことかを探求している。道徳的な立場として、他者のための真正な存在 とは、「二つの自由の相互承認[...][...][...]どちらも超越性を放棄せず[...]、どちらも切断されない」(1949年[1952年、 667])ことを含む互恵性の一形態である。このように、真正性と道徳性は共に属するものであり、それによって私たちは、自分自身を創造し、私たちが送る 人生に責任を持つことができるように、互いを解放し、あるいは自由にする義務を共有しているのである。したがって、ボーヴォワールが言うように、「自分自 身を道徳的に意志することと、自分自身を自由に意志することは、一つの同じ決定なのである」(1947 [1948, 24])。 ハイデガーは『存在と時間』の中で、「解放的関心」 (befreiend Fürsorge)という説明で同様の考えを展開している。それは、「他者が自分のケアにおいて自分自身を透明にし、そのために自由になるのを助ける」 (1927 [1962, 122])関係的スタンスである。このように他者を気遣うとき、私たちは、あたかも他者が存在という不安な問題から守られる必要のある依存的な事物や対象 であるかのように、他者のために「飛び込む」(einspringen)誘惑に抵抗する。ハイデガーは、この庇護の傾向を、他者から自らの生に対する不安 な責任を奪う、一種の暗黙の支配や「支配」(Beherrschung)という言葉で表現している。真正な関係とは、他者のために飛び込み、その責任から 解放するのではなく、他者から「飛び出し」(vorausspringt)、不安を取り戻させ、自分の状態に気を配り、向き合う自由を与える関係である。 ハイデガーが書いているように、私たちは他者から「飛躍」するのであって、「彼の『ケア』を奪うためではなく、むしろそれを初めてそのようなものとして真 正に彼らに返すためである」(1927[1962, 122])。ここには、自分自身の自由を実現し、他者の自由を実現するように行動するという、倫理的な格言の発展が見られる。 6.2 承認の倫理学 一部の宗教的実存主義者の間にも異端的な潮流があり、そ れは、私たちが自分自身を自発的な主体としてではなく、アイリス・マードックの言葉を借りれば、共同体や愛着の絆から切り離された「勇敢な裸の意志」 (1983, 46)としてではなく、根本的に相互の脆弱性において結びついている関係的存在として認識するときに、道徳的要求が私たちに課されるというものである。そ してこの認識は、私たちを日常的な自己陶酔から引き離し、私たちの自由ではなく、本質的な依存関係に目覚めさせることによって、倫理の基礎となるかもしれ ない。 ドストエフスキーは『カラマーゾフの兄弟』の中で、宗教的な長老ゾシマ 神父を通して、自由と自己肯定が最高の価値観となった近代に蔓延する「恐ろしい個人主義」を力強く告発している。そのような見方は、自己実現ではなく、孤 独と絶望をもたらす。ゾシマは、近代人は「自分一人に依存し、全体から自分を切り離すことに慣れている。彼は他人の助けや人間や人間性を信じないように訓 練されている。ドストエフスキーは、評価的な限界や束縛なしに選択を行う意志的な主体というヴィジョンに対して、他者を依存的で脆弱な存在として認識する ことによってのみ、私たちは自分自身を認識できるようになると示唆する。真の自由は、自分自身のエゴイスティックな努力の束縛から解き放たれ、謙虚さと自 己犠牲の態度をとるときに現れる。このように個人主義の誘惑から解放されたとき、ゾシマは私たちに道徳的な要求が課せられ、「私たちは皆、皆に対して責任 があり、皆のために責任がある」(1879-80 [1957, 228])と理解し始めるのだと言う。 ユダヤ人の実存主義者マルティン・ブーバーは、その代表作『我と汝』の 中で、この考えを発展させている。ブーバーは、日常生活において私たちは一般的に、道具的で客観的な立場から他者と関わっていると主張する。ブーバーが 「I-It」(Ich-Es)と呼ぶ関係であり、そこでは他者は、自分が利用するために操作されコントロールされるべきもの(あるいは「それ」)として扱 われる。この関係は、私たちが自分の状況をコントロールできているかのような錯覚を起こさせるので、心地よい。しかし、私たちの人生には、この幻想が崩 れ、"それ "としてではなく、"あなた "として、他者に対して無防備になる瞬間がある。私-あなた」(Ich-Du)の関係において、私たちが他者への本質的な依存と開放性を隠すために頼りに しているエゴイスティックな防御はすべて崩壊する。ブーバーはこのことを、他者が無防備でむき出しの全人格として私の前に姿を現し、私も同じように姿を現 す、恵みの体験と呼んでいる。それは「二人の人間が互いにあなたという存在を明らかにする」瞬間である(1923 [1970, 95])。このように、不安は根本的に個人化するものではなく、孤独な主体が自分自身の自由と向き合うために関係世界から切り離されるものなのだ。ブー バーにとって、「私-あなた」の関係に触れることは、私たちを自分自身のエゴイスティックな懸念から揺り動かし、私たちが孤立した個人ではなく、常に他者 との生きた関係にある存在であるという事実に目覚めさせる。この経験によって「個人の障壁が破られ」、感情的な結合、すなわち「自己存在から自己存在へ の、恐怖の深淵を渡る橋」が生まれるのである(1938 [1965], 201, 207)。 6.3 関与の倫理 ナチスによるフランス占領、彼自身の捕虜としての経験、 そして影響力のあるマルクス主義の批評家たちからの彼の哲学に対する攻撃によって、サルトルはその焦点を個人から社会へと移さざるを得なくなった。戦争 後、サルトルはメルロ=ポンティ、ボーヴォワールとともに、社会批評の有力な雑誌『ル・タン・モダン』を創刊した: 「われわれの意図は、われわれを取り巻く社会にある種の変化をもたらす手助けをすることである。そして、選択の可能性を広げることによって、自由な人間を 解放しなければならない」(Sartre 1945 [1988, 264-65])。ここで実存主義者たちは、他者が自由を実現するためには、哲学は他者を制限し束縛する「基盤や構造」に関与しなければならないという関 連性を示している。なぜなら、これらの構造は哲学的抽象ではなく、「個人の未来を決定する図式として生きている」からである(Sartre 1957 [1968, 94])。そして、もし私たちが自由の状況をつくり出し、「選択の可能性を拡大」しようとするならば、この背景がいかに暴力的で抑圧的でありうるか、とり わけ歴史的に周縁化され、過小評価されてきた人々にとっていかに暴力的でありうるかを認識し、それを変革するように行動しなければならない。 実存主義の主要な開発者の中で、抑圧と解放の可能性について最も持続的 で影響力のある分析を行ったのは、紛れもなくボーヴォワールである。彼女のフェミニズムの代表作『第二の性』だけでなく、『成人』(1970年[1996 年])における高齢者の非人間化についての荒涼とした記述や、回顧録『一日一日のアメリカ』(1954年[1999年])におけるジム・クロウ支配下の南 部における黒人集団の経験についての考察においても、ボーヴォワールは最も持続的で影響力のある分析を行った。これらの作品においてボーヴォワールは、社 会経済的・政治的構造がいかに人間の自由と超越の能力を制限しうるか、いかに他者を「凍結」し、主体性と自己創造の可能性を奪い去り、「内在性」に閉じ込 める力を持っているかを明らかにしている。しかし、ボーヴォワールはこれらの作品の中で、この状況が宿命ではないことを明らかにしている。人間には本質的 な性質はなく、生まれながらに劣等であったり従順であったりする者はいない。私たちは、既成の抑圧の構造に成長し、内面化し、実行することによって、間主 観的に構成されている。しかし、こうした構造が個人の選択と行動によって構成され、維持されている限り、固定的で静的なものではない。人間と同じように、 構造もまた変化するものなのだ。存在が本質に先立つという認識が、存在論的な領域から倫理的な領域へと移行し、抑圧され疎外されている人々の選択の可能性 を制限している物質的な条件に関与し、それを変革するための行動への呼びかけとなる。 このようにして、戦後の実存主義は、社会圏の現実と、西欧世界を苦しめ ている「イズム」(階級主義、人種差別主義、植民地主義、性差別主義、反ユダヤ主義)に関わり始めた。サルトルの言葉を借りれば、「個人は自分の社会的決 定を内面化する。彼は生産関係、幼年期の家族、歴史的過去、制度における現代を内面化し、そして、必然的に私たちをそれらに引き戻すこれらの行為や選択肢 を再内面化する」(1972 [2008, 35])。そして、こうした社会的決定が固定的で時間を超越したものではなく、偶発的な人間の構築物である限り、他者を解放するために抵抗し、変容させる ことができる。 |
| 7. Contemporary Relevance Existentialism has had a profound impact on how philosophers conceptualize and understand the human condition, with rich accounts of affectivity and embodiment, facticity (or worldliness), and the ways in which we are constituted intersubjectively. It has opened new paths for philosophy to engage with concrete and acute human problems, from sexuality, race, disability, and old age to broader issues of social and political violence and oppressive relations in general. And the movement continues to thrive in the academy today. Not only is the Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP) flourishing as the second largest philosophical organization in the English-speaking world, with smaller research groups (or “Circles”) devoted to every major figure. There is a cascade of scholarship published every year in leading journals and academic presses that captures the enduring relevance of existentialist thought, including important new work engaging the significance of French existentialism as an ethical theory (Webber 2018), reframing our conceptions of virtue and human flourishing (McMullin 2019), and even addressing current analytic debates in philosophies of life-extension, anti-natalism, and transhumanism (Buben 2022). Indeed, the core ideas and major figures of existentialism are not just alive and well; they are shaping developments in a diverse range of areas across the humanities and social sciences. 7.1 Post-Structuralism The legacy is most clearly present in the European philosophies that proceeded it. Existentialism’s critique of foundationalism and the authority of reason as well as its rejection of universalism, essentialism, and “grand narratives” (or metanarratives) all had a decisive impact on post-structural philosophies in France. Nietzsche and Heidegger in particular served as decisive influences on the project of “de-centering the subject” in Jacques Derrida’s method of deconstruction and in Michel Foucault’s genealogy of power, demonstrating how the subject is not the privileged center or origin of truth and knowledge. The subject is, rather, shaped in advance by sociohistorical structures, an overlapping network of norms and practices, linguistic conventions, and shared meanings, and this shaping takes place in a way that we are never fully conscious of.[14] The individual, on this view, is more of a placeholder or crossing point in these anonymous structures, where the subject exists as “the inscribed surface of events […] totally imprinted by history” (Foucault 1977, 148). Of course, existentialists reject the idea that this historical imprinting or “decentering” is total or absolute. They are, after all, still committed to the value of freedom and authenticity, but they recognize that freedom is never unconditioned. Beyond the philosophies of Heidegger and Nietzsche, we see this recognition in Merleau-Ponty’s conception of mediated freedom, in Sartre’s postwar account of “freedom-in-situation,” and in what Beauvoir calls “la force des choses” (the power of circumstances). The recognition of historicity as an impersonal force that structures our identity had such an impact on Foucault’s work that he once remarked: “My entire philosophical development was determined by my reading of Heidegger” (Foucault 1985, cited in Dreyfus 1995, 9). 7.2 Narrative and Hermeneutic Philosophy In viewing the self not as a substance or thing but as a self-interpreting, meaning-giving activity that is always already bound up in the world, existentialism has also informed key developments in narrative and hermeneutic philosophy. Prominent anglophone philosophers such as Harry Frankfurt (1971), Charles Taylor (1985), and Alasdair MacIntyre (1981) have drawn on classical existentialism to illuminate how we exist in the meanings and self-interpretations that we create for ourselves. My sense of who I am is constituted by an ongoing process of choosing, pulling together, and consolidating the roles, projects, and meanings that matter to me and that are made available by the sociohistorical situation I find myself in. On this view, the story I create for myself is held together by the narrative unity and cohesion that I give to it. This is what Taylor means when he says that we can only understand or “grasp our lives in a narrative” (1989, 47). And this conception of narrative identity not only offers a response to overly reductive conceptions of the self that are grounded in the substance ontologies of mind and body; it demonstrates an attentiveness to the ambiguous tension of our condition, that our choices are both self-fashioning and socially embedded, that we simultaneously make ourselves and are already made. 7.3 Philosophy of Mind and Cognitive Science Beginning with Hubert Dreyfus’s (1972) groundbreaking critique of Artificial Intelligence (AI), philosophers of mind and cognitive scientists have been drawing on existentialist philosophy—especially Heidegger and Merleau-Ponty—to challenge the overly mentalistic picture of selfhood and agency that modern philosophy inherits from Descartes and Kant and to dismantle traditional representational theories of knowledge. Key works by Shaun Gallagher (2005), Thomas Fuchs, (2018), and Dan Zahavi (2005) have replaced the picture of the disembodied mind with the now widely accepted notion of the embedded, enactive, and embodied self. This is a rejection of the long-held assumption that human action must somehow be represented or “mirrored” in the mind. Existentialism illuminates how—as a situated way of being-in-the-world—human beings already embody a tacit understanding of the world in a way that we are not and can never be thematically conscious of. This means we do not understand things as discrete objects. We understand things in terms of how we use and handle them and in terms of the purposive, meaning-giving roles these things play in our everyday lives. The traditional view of the mind as something resembling the rule-governed processes of a computer program have continually failed to capture this ambiguous and embodied sense of being-in-the-world. 7.4 Critical Phenomenology The attentiveness to conditions of oppression, subjugation, and violence among postwar existentialists in France has had a decisive impact on recent developments in critical phenomenology by giving voice to those who have been historically marginalized or undervalued in the western tradition. Beauvoir’s pioneering account of the woman’s experience in The Second Sex is well known for laying the conceptual foundations for second wave feminism, and her late career phenomenology of aging broke new ground by shedding light on the existence of older persons and exposing the toxic ageism in contemporary capitalist societies. Together with Sartre and Merleau-Ponty, her ideas would inform Franz Fanon’s Black Skin, White Masks (1952 [1967]), a seminal work that disclosed the dehumanizing experience of colonized Black populations and helped give birth to Africana critical theory or “black existentialism” (Gordon 2000). The focus on the ways in which structures of discrimination along with the limits of our own embodiment can constrain our capacities for freedom and transcendence has, in turn, influenced recent phenomenological accounts of intersectionality and the lived experience of, among others, indigenous peoples, immigrants, and exiles (Coulthard 2014; Ortega 2016), queer and trans identities (Ahmed 2006; Salamon 2010), those who are imprisoned or in solitary confinement (Guenther 2013; Leder 2016), and the elderly, disabled, and chronically ill (Aho 2022; Reynolds 2022; Dickel 2022). 7.5 Comparative and Environmental Philosophy Interpreting existence in terms of the situated activity of being-in-the-world not only serves as a rejection of substance ontology and the metaphysical dualisms (subject-object; mind-body; inner-outer) that we inherit from Cartesian and empiricist epistemologies; it also reveals deep affinities with the nonduality of Buddhism and other incarnations of Eastern thought. (Loy 2018; Kalmanson 2020) And the recognition of our enmeshment in the world has informed a range of important advances in the philosophy of place, deep ecology, and eco-phenomenology (Brown & Toadvine 2003; Malpas 2017; Morton 2016; Rentmeester 2016). These endeavors have exposed the limitations of the scientific worldview and our uncritical dependence on technological innovation to address the current ecological crisis. Modern science generally assumes a binary paradigm of the subject as separate and distinct from a value-less domain of objects (or nature), a domain that can, in turn, be mastered and controlled by technoscience. In this way, it betrays our ordinary experience, that in our day-to-day lives we are not atomistic, self-certain subjects but beings that are fundamentally entwined with the world and the meaning and value that this intertwining brings to our experience. For the existentialist, then, extricating ourselves from environmental doom requires not a technoscientific fix but an ontological transformation in our own self-understanding, an awaking to the reality of our interdependence with nature, that the earth is not apart from us but rather part of us. 7.6 Philosophy of Health and Illness Outside of the humanities and social sciences, existentialism has also had a deep and lasting impact on the allied health professions. The role it has played in the development of existential and humanistic approaches to psychotherapy (Cooper 2003; Spinneli 2007; van Deurzen 2015) and to phenomenological psychopathology (Parnas & Gallagher 2015; Ratcliffe 2015; Stanghellini et al. 2019) is well-known, but in recent years we have seen its influence emerge in a range of different areas, from narrative medicine to nursing, and from gerontology to palliative care. To this end, existentialism has informed a move away from the reductive and objectifying tendencies of modern biomedicine to recover the first-person experience of health and illness, viewing the body not so much as a biophysical machine that needs to be adjusted and maintained but as the experiential and interpretative medium of our existence. This shift has not only allowed clinicians to challenge the emergent tendency to medicalize ever-expanding swaths of the human condition; it makes it possible for the clinician to better understand the patient’s experience by getting a sense of “what it means” and “what it feels like” to suffer when the body breaks down (Aho 2018; Slatman 2014; Svenaeus 2022; Zeiler & Käll 2014). 7.7 A New Generation Beyond its ascendency in the healing arts, its myriad cultural influences, and its wide-ranging impact on the humanities and social sciences, the enduring legacy of existentialism is perhaps most visible in the classroom. Existentialist-themed courses are often among the most popular in the philosophy curriculum as young students confront, for the first time, the unsettling questions of freedom and the meaning of their own existence. And these questions have never been more pressing as they develop against the backdrop of anthropogenic climate change, species extinction, global pandemics, and the reemergence of authoritarian and fascist politics. Amidst these planetary emergencies, a new generation is facing the predicament of nihilism and the death of God and owning up to the uncanny truth of the human condition: that existence precedes essence. https://plato.stanford.edu/entries/existentialism/ |
7. 現代との関連性 実存主義は、哲学者が人間の状態をどのように概念化し理解するかに大きな影響を与え、感情や身体性、事実性(あるいは世界性)、そして私たちが間主観的に 構成される方法について豊かな説明をしてきた。哲学は、セクシュアリティ、人種、障害、老齢から、社会的・政治的暴力や抑圧的関係全般といったより広範な 問題まで、人間の具体的かつ深刻な問題に関わるための新たな道を開いた。そしてこの運動は、今日もアカデミズムの中で繁栄し続けている。現象学・実存哲学 協会(SPEP)が英語圏で2番目に大きな哲学団体として繁栄しているだけでなく、主要な人物ごとに小規模な研究グループ(または「サークル」)が存在す る。倫理理論としてのフランス実存主義の意義に関わる重要な新しい研究(ウェバー 2018年)、徳と人間の繁栄の概念に再考を加える研究(マクマリン 2019年)、さらには延命、反出生主義、トランスヒューマニズムの哲学における現在の分析的議論に取り組む研究(ブーベン 2022年)など、実存主義思想の永続的な関連性を捉えた研究が、主要な学術誌や学術出版社で毎年次々と発表されている。実際、実存主義の中核となる思想 や主要な人物は健在であるだけでなく、人文科学や社会科学にまたがる多様な分野の発展を形成している。 7.1 ポスト構造主義 その遺産は、実存主義に続くヨーロッパの哲学の中に最も明確に存在している。実存主義による基礎づけ主義や理性の権威に対する批判、普遍主義や本質主義、 「グランド・ナラティブ」(あるいはメタナラティブ)の否定はすべて、フランスのポスト構造哲学に決定的な影響を与えた。特にニーチェとハイデガーは、 ジャック・デリダの脱構築の手法やミシェル・フーコーの権力の系譜における「主体の脱中心化」のプロジェクトに決定的な影響を与え、主体がいかに真理や知 識の特権的な中心や起源ではないことを示した。この見解によれば、個人はむしろ、こうした匿名的な構造におけるプレースホルダーや交差点であり、主体は 「歴史によって完全に刻印された、[...]出来事の刻まれた表面」(Foucault 1977, 148)として存在するのである。もちろん、実存主義者は、この歴史的刻印や「脱中心化」が完全で絶対的なものであるという考えを否定する。結局のとこ ろ、彼らは自由と真正性の価値に依然としてコミットしているが、自由は決して無条件ではないことを認識している。ハイデガーやニーチェの哲学にとどまら ず、メルロ=ポンティの媒介された自由という概念、サルトルの戦後の「状況における自由」という説明、そしてボーヴォワールの言う「状況の力(la force des choses)」にもこの認識が見られる。私たちのアイデンティティを構造化する非人間的な力としての歴史性の認識は、フーコーの仕事に大きな影響を与え た: 「私の哲学的発展のすべては、ハイデッガーの読書によって決定された」(Foucault 1985, cited in Dreyfus 1995, 9)。 7.2 物語と解釈哲学 自己を物質や事物としてではなく、常にすでに世界と結びついている、自己を解釈し、意味を与える活動として捉えることで、実存主義は物語哲学と解釈哲学の 重要な発展にも影響を与えた。ハリー・フランクフルト(1971年)、チャールズ・テイラー(1985年)、アラスデア・マッキンタイア(1981年)と いった英語圏の著名な哲学者たちは、古典的な実存主義を援用し、私たちが自分自身のために作り出す意味や自己解釈の中にどのように存在しているのかを明ら かにした。自分が何者であるかという感覚は、自分にとって重要であり、自分が置かれている社会歴史的状況によって利用可能となる役割、プロジェクト、意味 を選択し、まとめ、統合していく継続的なプロセスによって構成されている。この見方では、私が自分自身のために創り出す物語は、私がそれに与える物語の統 一性と凝集性によってまとめられる。テーラーが、私たちは物語の中でしか自分の人生を理解できない、あるいは「把握できない」(1989, 47)と言うのは、このことを意味しているのである。そして、この物語的アイデンティティの概念は、心と身体の実体存在論に根ざした、過度に還元的な自己 の概念への応答を提供するだけでなく、私たちの選択が自己形成的であると同時に社会的に埋め込まれたものであり、私たちは同時に自分自身を作り、またすで に作られているという、私たちの状態のあいまいな緊張への気配りを示している。 7.3 心の哲学と認知科学 ユベール・ドレフュス(Hubert Dreyfus)の人工知能(AI)に対する画期的な批評(1972年)に始まり、心の哲学者や認知科学者は実存主義哲学、特にハイデガーやメルロ=ポン ティを援用し、現代哲学がデカルトやカントから受け継いだ自己性や主体性に関する過度に精神主義的な図式に異議を唱え、伝統的な知識の表象理論を解体して きた。ショーン・ギャラガー(2005年)、トーマス・フックス(2018年)、ダン・ザハヴィ(2005年)による主要な著作は、実体のない心という図 式を、埋め込まれ、能動的で、身体化された自己という現在広く受け入れられている概念に置き換えている。これは、人間の行動は何らかの形で心の中に表象さ れ、あるいは「鏡のように映し出される」ものでなければならないという長年の思い込みを否定するものである。実存主義は、世界における存在の在り方とし て、人間はすでに世界に対する暗黙の理解を体現していることを明らかにする。つまり、私たちは物事を個別の対象として理解しているのではない。私たちは、 モノをどのように使い、どのように扱うかという観点から、また、モノが私たちの日常生活において果たす目的的な、意味を与える役割という観点から、モノを 理解しているのである。コンピュータ・プログラムの規則によって支配されたプロセスに似たものとして心を捉える伝統的な見方は、このような曖昧で体現され た「世界に存在する」という感覚を捉えることに、絶えず失敗してきたのである。 7.4 批判的現象学 戦後フランスの実存主義者たちの抑圧、被支配、暴力の状況への配慮は、西洋の伝統の中で歴史的に疎外され、過小評価されてきた人々に声を与えることで、批 判的現象学の最近の発展に決定的な影響を与えた。ボーヴォワールの『第二の性』における女性の経験に関する先駆的な記述は、第二波フェミニズムの概念的基 礎を築いたことでよく知られており、晩年の彼女の老いの現象学は、高齢者の存在に光を当て、現代の資本主義社会における有害なエイジズムを暴露すること で、新たな境地を切り開いた。サルトルやメルロ=ポンティとともに、彼女の思想はフランツ・ファノンの『黒い肌、白い仮面』(1952年[1967年]) に影響を与えた。差別の構造が、私たち自身の身体性の限界とともに、自由と超越のための私たちの能力を制約しうる方法に焦点を当てることは、その結果、交 差性と、とりわけ先住民、移民、亡命者の生きた経験についての最近の現象学的説明に影響を与えた(Coulthard 2014; Ortega 2016)、クィアやトランスのアイデンティティ(Ahmed 2006; Salamon 2010)、投獄されている人や独房にいる人(Guenther 2013; Leder 2016)、高齢者、障害者、慢性病患者(Aho 2022; Reynolds 2022; Dickel 2022)などである。 7.5 比較哲学と環境哲学 実存を「世界における存在」という位置づけられた活動の観点から解釈することは、物質存在論や、デカルトや経験主義的認識論から受け継いだ形而上学的二元 論(主体-客体、精神-身体、内面-外面)を否定するだけでなく、仏教や他の東洋思想の化身が持つ非二元性との深い親和性を明らかにする。(Loy 2018; Kalmanson 2020)そして、私たちが世界に取り込まれているという認識は、場所の哲学、ディープ・エコロジー、エコ現象学における様々な重要な進歩に影響を与えて きた(Brown & Toadvine 2003; Malpas 2017; Morton 2016; Rentmeester 2016)。これらの試みは、科学的世界観の限界と、現在の生態学的危機に対処するための技術革新への無批判な依存を露呈した。現代科学は一般的に、主体 は価値のないモノ(あるいは自然)の領域から切り離された別個の存在であるという二元的なパラダイムを前提としている。このように、私たちの日常生活にお いて、私たちは原子論的で自己確信的な主体ではなく、世界と根本的に絡み合った存在であり、この絡み合いが私たちの経験にもたらす意味や価値であるとい う、私たちの普通の経験を裏切ることになる。実存主義者にとって、環境の破滅から抜け出すには、技術科学的な解決ではなく、私たち自身の自己理解における 存在論的な変革が必要なのであり、地球は私たちから離れているのではなく、むしろ私たちの一部であるという、自然との相互依存の現実に目覚めることが必要 なのである。 7.6 健康と病気の哲学 人文科学や社会科学の分野以外でも、実存主義は医療専門職にも深く永続的な影響を与えてきた。心理療法(Cooper 2003; Spinneli 2007; van Deurzen 2015)や現象学的精神病理学(Parnas & Gallagher 2015; Ratcliffe 2015; Stanghellini et al. 2019)に対する実存的・人文主義的アプローチの発展において果たした役割はよく知られているが、近年ではナラティブ医学から看護学、老年学から緩和ケ アまで、さまざまな分野でその影響が現れている。この目的のために、実存主義は、現代の生物医学の還元的で客観化的な傾向から離れ、健康と病気の一人称的 な経験を回復するための動きを知らせてきた。この転換によって、臨床家は人間の状態を拡大し続ける医療化という新たな傾向に挑戦することができるように なっただけでなく、身体が壊れて苦しむことが「何を意味するのか」「どのように感じるのか」を感じ取ることで、患者の経験をよりよく理解することができる ようになった(Aho 2018; Slatman 2014; Svenaeus 2022; Zeiler & Käll 2014)。 7.7 新世代 ヒーリング・アートにおける隆盛、無数の文化的影響、人文科学や社会科学への広範な影響にとどまらず、実存主義の永続的遺産はおそらく教室で最もよく目に することができる。実存主義をテーマとした講座は、哲学のカリキュラムの中でも人気が高く、若い学生たちが初めて、自由や自分自身の存在の意味といった不 安な問いに直面することが多い。そしてこれらの問いは、人為的な気候変動、種の絶滅、世界的なパンデミック、権威主義的・ファシスト的政治の再来などを背 景に展開されるため、かつてないほど切迫したものとなっている。こうした地球規模の緊急事態の中で、新しい世代はニヒリズムと神の死という苦境に直面し、 「存在は本質に先立つ」という人間の条件の不気味な真理を自認している。 |
| Bibliography Adorno, T., 1964 [1973]. The jargon of authenticity, K. Tarnowski & F. Will (trans.), Evanston, IL: Northwestern University Press. Ahmed, S., 2006. Queer phenomenology: Orientations, objects, others, Durham, NC: Duke University Press. Aho, K., 2007. “Recovering play: On the relationship between leisure and authenticity in Heidegger’s thought,” Janus Head, 10(1): 217–238. –––, 2020. Existentialism: An introduction, 2nd edition. Cambridge: Polity. –––, 2022. One beat more: Existentialism and the gift of mortality, Cambridge: Polity. Aho, K. (ed.), 2018. Existential medicine: Essays on health and illness, London: Rowman and Littlefield. Baert, P., 2015. The existentialist moment: The rise of Sartre as a public intellectual, Cambridge: Polity. Beauvoir, S. de, 1947 [1948]. The ethics of ambiguity, B. Frechtman (trans.), New York: Philosophical Library. –––, 1949 [1952]. The second sex, H. M. Parshley (trans.), New York: Knopf. –––, 1945 [1970]. The blood of others, Y. Moyse and R. Senhouse (trans.), New York: Penguin. –––, 1956 [1991]. The mandarins, L. Friedman (trans.), New York: W.W. Norton. –––, 1963 [1992]. After the war: The force of circumstance, volume 1, 1944–1952, R. Howard (trans.), New York: Paragon House. –––, 1970 [1996]. The coming of age, P. O’Brian (trans.), New York: W. W. Norton. –––, 1954 [1999]. America day by day, C. Cosman (trans.), Berkeley, CA: University of California Press. Brown, C. & Toadvine, T. (eds.), 2003. Eco-phenomenology: Back to the earth itself, Albany, NY: State University of New York Press. Buben, A., 2022. Existentialism and the desirability of immortality, London: Routledge. Buber, M., 1923 [1970]. I and thou, W. Kaufmann (trans.), New York: Touchstone. –––, 1938 [1965]. “What is man?” in Martin Buber: Between man and man, R. Gregor-Smith (trans.), New York: Routledge Butler, J., 1990. Gender trouble: Feminism and the subversions of identity, New York: Routledge. Camus, A., 1951 [1956]. The rebel: An essay on man in revolt, H. Read (trans.), New York: Vintage Books. Cooper, M., 2003. Existential therapies, London: Sage. Cotkin, G., 2003. Existential America, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Coulthard, G., 2014. Red skin, white masks: Rejecting the colonial politics of recognition, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. Dickel, S., 2022. Embodying difference: Critical phenomenology and narratives of disability, race, and sexuality, Dordrecht: Springer. Dostoevsky, F., 1879–80 [1957]. The brothers Karamazov, C. Garnett (trans.), New York: Signet Classic. –––, 1864 [2009]. Notes from the underground, C. Garnett (trans.), Indianapolis, IN: Hackett Press. Dreyfus, H., 1972. What computers can’t do: A critique of artificial reason, New York: Harper and Row. –––, 1995. Being-in-the-world: A commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I, Cambridge, MA: MIT Press. Fanon, F., 1952 [1967]. Black skin, white masks, C. Markmann (trans.), New York: Grove Press. Foucault, M., 1977. “Nietzsche, genealogy, history,” in D. F. Bouchard (ed.), Language, counter-memory, practice: Selected essays and interviews, Ithaca, NY: Cornell University Press. –––, 1985. “Final interview,” Raritan, 5(1): 1–13. Frankfurt, H., 1971. “Freedom of the will and the concept of a person,” Journal of philosophy, 68(1): 5–20. Fuchs, T., 2018. Ecology of the brain: the phenomenology and biology of the embodied mind, Oxford: Oxford University Press. Gallagher, S., 2005. How the body shapes the mind, Oxford: Oxford University Press. Gordon, L. (ed.), 1997. Existence in black: An anthology of black existential philosophy, New York: Routledge. Guenther, L., 2013. Solitary confinement: Social death and its alternatives, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. Guignon, C., 1993. “Editor’s introduction,” in C. Guignon (ed.), Dostoevsky’s “The grand inquisitor”: With related chapters from The Brothers Karamazov, C. Garnett (trans.), Indianapolis, IN: Hackett. –––, 2004. On being authentic, London: Routledge. Guingon, C. & Aho, K., 2019. “Authenticity and social critique,” in K. Becker & I. Thomson (eds.), The Cambridge history of philosophy, 1945–2015, Cambridge: Cambridge University Press. Habermas, J., 1985 [1990]. The philosophical discourse of modernity: Twelve lectures, F. Lawrence (trans.), Cambridge, MA: MIT Press. Heidegger, M., 1927 [1962]. Being and time, J. Macquarrie and E. Robinson (trans.), New York: Harper and Row. –––, 1950 [1971] Poetry, language, thought, A. Hofstadter (trans.), New York: Harper & Row. –––, 1927 [1982]. The basic problems of phenomenology, A. Hofstadter (trans.), Bloomington, IN: Indiana University Press. (1927 is the year of the lecture course.) –––, 1919 [2000]. Towards the definition of philosophy, T. Sadler (trans.), London: Continuum Books. (1919 is the year of the lecture course.) Husserl, E., 1912 [1989]. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to Phenomenological Philosophy, Second Book, R. Rojcewicz and A. Schuwer (trans.), Dordrecht: Kluwer. (1912 is the year the second edition was initially drafted.) Jaspers, K., 1932 [1956]. Philosophie (Volume 2), Berlin: Springer. –––, 1913 [1997]. General Psychopathology (Volume 1), J. Hoenig & M. Hamilton (trans.), Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. Kalmanson, L., 2020. Cross-cultural existentialism: On the meaning of life in Asian and western thought, London: Bloomsbury. Kierkegaard, S., 1844 [1936]. Philosophical fragments, D. Swenson (trans.), Princeton, NJ: Princeton University Press. –––, 1846 [1941]. Concluding unscientific postscript, D. Swenson, L. Swenson, & W. Lowrie (trans.), Princeton, NJ: Princeton University Press. –––, 1846 [1946]. “The present age,” A. Dru (trans.), in R. Bretall (ed.), A Kierkegaard anthology, Princeton, NJ: Princeton University Press. –––, 1835–1854 [1959]. The journals of Kierkegaard, A. Dru (trans.), New York: Harper Torchbooks. (1835–1854 are the years of the journal entries.) –––, 1843 [1985]. Fear and trembling, A. Hannay (trans.), New York: Penguin Books. –––, 1849 [1989]. The sickness unto death, A. Hannay (trans.), New York: Penguin books. Leder, D., 2016. The distressed body. Rethinking illness, imprisonment, and healing, Chicago, IL: University of Chicago Press. Loy, D., 2018. Lack and transcendence: The problem of death and life in psychotherapy, existentialism, and Buddhism, Somerville, MA: Wisdom Publications. MacIntyre, A., 1981. After virtue, Notre Dame, IN: Notre Dame University Press. Malpas, J., 2017. Heidegger and the thinking of place: Explorations in the topology of being, Cambridge, MA: MIT Press. McMullin, I., 2019. Existential flourishing: A phenomenology of the virtues, Cambridge: Cambridge University Press. Merleau-Ponty, M., 1945 [1962]. Phenomenology of perception, C. Smith (trans.), London: Routledge & Keegan Paul. –––, 1964 [1968]. The visible and the invisible: Followed by working notes, A. Lingis (trans.), Evanston, IL: Northwestern University Press. Morton, T., 2016. Dark ecology: For a logic of future coexistence, New York: Columbia University Press. Murdoch, I., 1983. “Against dryness: A polemical sketch,” in S. Hauerwas and A. MacIntyre (eds.), Revisions: Changing perspectives in moral philosophy, Notre Dame, IN: Notre Dame University Press. Nietzsche, F., 1886 [1998]. Beyond good and evil, M. Faber (trans.), New York & Oxford: Oxford University Press. –––, 1887 [1974]. The gay science, W. Kaufmann (trans.), New York: Vintage Books. –––, 1887 [1996]. On the genealogy of morals, D. Smith (trans.), New York & Oxford: Oxford University Press. –––, 1889a [1990a]. Philosophy and truth: Selections from Nietzsche’s Notebooks of the early 1870s, D. Breazeale (trans. and ed.), Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press. –––, 1889b [1990b] Twilight of the idols, R. J. Hollingdale (trans.), New York: Penguin Books. –––, 1901 [1968]. The will to power, W. Kaufmann (trans.), New York: Vintage Books. Ortega y Gasset, J., 1941. Toward a philosophy of history, H. Weyl (trans.), New York: W.W. Norton. –––, 1930 [1993] The revolt of the masses, (anonymous trans.), New York: W.W. Norton. Ortega, M., 2016. In-between: Latina feminist phenomenology, multiplicity, and the self, Albany, NY: SUNY Press. Parnas, J. & Gallagher, S., 2015. “Phenomenology and the Interpretation of Psychopathological Experience,” in L. Kirmayer, R. Lemelson, and C. Cummings (eds.), Re-Visioning Psychiatry: Integrating Biological, Clinical and Cultural Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press. Ratcliffe, M., 2015. Experiences of depression. A study in phenomenology, Oxford: Oxford University Press. Reynolds, J. M., 2022. The life worth living: A philosophical challenge to the ableist conflation of disability and pain, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. Rentmeester, C., 2016. Heidegger and the environment, London: Rowman and Littlefield. Salamon, G., 2020. Assuming a body: Transgender and rhetorics of materiality, New York: Columbia University Press. Sartre, J-P., 1943 [1956]. Being and nothingness, H. Barnes (trans.), New York: Washington Square Press. –––, 1952 [1963]. Saint Genet, actor and martyr, B. Frechtman (trans.), New York: George Braziller Inc. –––, 1957 [1968]. Search for a method, H. Barnes (trans.), New York: Vintage Books. –––, 1945 [1988]. “What is literature?” and other essays, S. Ungar (ed.), J. Mehlman (trans.), Cambridge, MA: Harvard University Press. –––, 1944 [1989]. No exit, S. Gilbert (trans.), New York: Vintage Press. –––, 1948 [1992]. Notes for an ethics, D. Pellauer (trans.), Chicago, IL: University of Chicago Press. –––, 1946 [2001]. “Existentialism is a humanism,” B. Frechtman (trans.), in C. Guignon and D. Pereboom (eds.), Existentialism: Basic writings, Indianapolis, IN: Hackett Press. –––, 1972 [2008]. “The itinerary of thought,” in Jean-Paul Sartre: Between existentialism and Marxism, J. Matthews (trans.), New York: Verso Books. Slatman, J., 2014. Our strange body: Philosophical reflections on identity and medical interventions, Amsterdam: University of Amsterdam Press. Solomon, R., 2005. Existentialism, 2nd edition, New York & Oxford: Oxford University Press. Spinelli, E., 2007. Practising existential psychotherapy: The relational world, London: Sage. Stanghellini, G., Broome, M., Fernandez, A., Fusar-Poli, P., Raballo, A., Rosfort, R., 2019. The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology, New York & Oxford: Oxford University Press. Svenaeus, F., 2022. The hermeneutics of medicine and the phenomenology of health: Steps towards a philosophy of medical practice, 2nd edition, Dordrecht: Springer. Taylor, C., 1989. Sources of the self: the making of the modern identity, Cambridge, MA: Harvard University Press. van Deurzen, E., 2015. Paradox and passion in psychotherapy: An existential approach to counseling and therapy, 2nd edition, Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Vogel, L., 1994. The fragile “we”: Ethical implications of Heidegger’s Being and Time, Evanston, IL: Northwestern University Press. Webber, J., 2018. Rethinking existentialism, Oxford: Oxford University Press. Wolin, R., 1990. The politics of being: The political thought of Martin Heidegger, New York: Columbia University Press. –––, 1995. “Karl Löwith and Martin Heidegger—Contexts and Controversies: An Introduction,” in Karl Löwith, Martin Heidegger and European nihilism, G. Steiner (trans.), New York: Columbia University Press. Young, I. M., 1984 [2000]. On the female body experience: “Throwing like a girl” and others essays, New York: Oxford University Press. Zahavi, D., 2005. Subjectivity and selfhood: Investigating the first-person perspective, Cambridge, MA: MIT Press. Zeiler, K. & Käll, L., 2014. Feminist Phenomenology and Medicine, Albany, NY: SUNY Press. |
参考文献 アドルノ、T.、1964年[1973年]。『真正性の専門用語』、K. タルノフスキ & F. ウィル(訳)、イリノイ州エバンストン:ノースウェスタン大学出版。 アーメド、S.、2006年。『クィア現象学:オリエンテーション、オブジェクト、他者』、ノースカロライナ州ダーラム:デューク大学出版。 Aho, K., 2007. 「遊びの回復:ハイデガー思想におけるレジャーと本質性の関係について」『Janus Head』10(1): 217–238. –––, 2020. 『実存主義:入門』第2版。ケンブリッジ:Polity。 ――――、2022年。『ワン・ビート・モア:実存主義と死すべき定めの贈り物』ケンブリッジ:ポリティ。 Aho, K. (ed.), 2018. 『実存主義医学:保健と疾病に関するエッセイ』ロンドン:ローマン・アンド・リトルフィールド。 Baert, P., 2015. 『実存主義の瞬間:サルトルの知識人としての台頭』ケンブリッジ:ポリティ。 ボーヴォワール、S. de、1947年[1948年]。『あいまい性の倫理』B. Frechtman(訳)、ニューヨーク:Philosophical Library。 ―――、1949年[1952年]。『第二の性』H. M. Parshley(訳)、ニューヨーク:Knopf。 ―――、1945年[1970年]。他者の血、Y. Moyse and R. Senhouse(訳)、ニューヨーク:ペンギン。 ―――、1956年[1991年]。マンダリン、L. Friedman(訳)、ニューヨーク:W.W. Norton。 ―――、1963年[1992年]。戦後:状況の力、第1巻、1944年~1952年、R. ハワード(訳)、ニューヨーク:パラゴン・ハウス。 ―――、1970年[1996年]。成長期、P. オブライエン(訳)、ニューヨーク:W. W. ノートン。 ―――、1954年[1999年]。アメリカの日々、C. コズマン(訳)、カリフォルニア州バークレー:カリフォルニア大学出版。 ブラウン、C. & トードバイン、T.(編)、2003年。エコ現象学:地球そのものへ、ニューヨーク州オルバニー:ニューヨーク州立大学出版。 Buben, A., 2022. 『実存主義と不死の望ましさ』、ロンドン:Routledge. Buber, M., 1923 [1970]. 『我と汝』、W. Kaufmann(訳)、ニューヨーク:Touchstone. ―――、1938年[1965年]。「人間とは何か」マーティン・ブーバー:人間と人間の間で、R. グレゴール=スミス(訳)、ニューヨーク:ルートレッジ バトラー、J.、1990年。ジェンダー・トラブル:フェミニズムとアイデンティティの転覆、ニューヨーク:ルートレッジ。 カミュ、A.、1951年[1956年]。反逆者:反逆する人間についての試論、H.リード(訳)、ニューヨーク:ヴィンテージブックス。 クーパー、M.、2003年。実存主義的セラピー、ロンドン:セイジ。 コトキン、G.、2003年。実存主義的アメリカ、メリーランド州ボルチモア:ジョンズ・ホプキンス大学出版。 Coulthard, G., 2014. Red skin, white masks: Rejecting the colonial politics of recognition, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. Dickel, S., 2022. Embodying difference: Critical phenomenology and narratives of disability, race, and sexuality, Dordrecht: Springer. ドストエフスキー、F.、1879-80年[1957年]。『カラマーゾフの兄弟』、C. ガーネット(訳)、ニューヨーク:シグネット・クラシック。 ――――、1864年[2009年]。『地下からのノート』、C. ガーネット(訳)、インディアナポリス、IN:ハケット・プレス。 ドレフュス、H.、1972年。『コンピュータにできないこと:人工知能批判』、ニューヨーク:Harper and Row。 ――――、1995年。『世界における存在:ハイデガー著『存在と時間』第1部への注釈』、マサチューセッツ州ケンブリッジ:MIT Press。 ファン・ファン、F.、1952年[1967年]。『黒い肌と白い仮面』C. マークマン(訳)、ニューヨーク:グローヴ・プレス。 フーコー、M.、1977年。「ニーチェ、系譜学、歴史」D. F. ブシャール(編)、『言語・対抗記憶・実践:選ばれたエッセイとインタビュー』ニューヨーク州イサカ:コーネル大学出版。 ―――、1985年。「最終インタビュー」、Raritan、5(1): 1–13。 フランクフルト・H、1971年。「自由意志と人格概念」、Journal of philosophy、68(1): 5–20。 フックス、T.、2018年。『脳の生態学:身体化された心の現象学と生物学』オックスフォード:オックスフォード大学出版局。 ギャラガー、S.、2005年。『身体が心を形づくる仕組み』オックスフォード:オックスフォード大学出版局。 ゴードン、L.(編)、1997年。『黒人の存在:黒人実存哲学アンソロジー』ニューヨーク:ルートレッジ。 グエンサー、L.、2013年。独房監禁:社会的死とその代替策、ミネアポリス、ミネソタ州:ミネソタ大学出版。 ギニョン、C.、1993年。「編集者による序文」、C.ギニョン(編)、ドストエフスキー著『大審問官』:『カラマーゾフの兄弟』より関連章を収録、C.ガーネット(訳)、インディアナ州インディアナポリス:ハケット。 ―――、2004年。『真正であること』、ロンドン:Routledge。 ギゴン、C. & アホ、K.、2019年。「真正性と社会批判」ベッカー、K. & トムソン、I.(編)、『ケンブリッジ哲学史』、1945~2015年、ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。 ハーバーマス、J.、1985年[1990年]。『近代の哲学的言説:12の講義』F.ローレンス(訳)、マサチューセッツ州ケンブリッジ:MITプレス。 ハイデガー、M.、1927年[1962年]。『存在と時間』、J. マッカリーとE. ロビンソン(訳)、ニューヨーク:Harper and Row。 ――――、1950年[1971年]『詩・言語・思想』、A. ホフスタッター(訳)、ニューヨーク:Harper & Row。 ―――、1927年[1982年]。現象学の基本問題、A. ホフスタッター(訳)、インディアナ大学出版、ブルーミントン、IN。(1927年は講義が行われた年である。 ―――、1919年[2000年]。哲学の定義に向けて、T. サドラー(訳)、ロンドン:コンティニュアム・ブックス。(1919年は講義が行われた年である。 フッサール、E.、1912年[1989年]。『純粋現象学および現象学的哲学に関する諸概念』第2巻、R. RojcewiczとA. Schuwer(訳)、ドルドレヒト:Kluwer。(1912年は第2版の草稿が最初に作成された年である。 ヤスパース、K.、1932年[1956年]。哲学(第2巻)、ベルリン:シュプリンガー。 ―――、1913年[1997年]。一般病理学(第1巻)、J. ホーニッグ & M. ハミルトン(訳)、メリーランド州ボルチモア:ジョンズ・ホプキンス大学出版局。 カルマンソン、L.、2020年。異文化における実存主義:アジアと西洋の思想における人生の意味について、ロンドン:ブルームズベリー。 キルケゴール、S.、1844年[1936年]。『哲学断章』D. スウェンソン(訳)、プリンストン、ニュージャージー州:プリンストン大学出版。 ―――、1846年[1941年]。『非科学的な結論の付記』D. スウェンソン、L. スウェンソン、W. ローリー(訳)、プリンストン、ニュージャージー州:プリンストン大学出版。 1846年 [1946年]。「現代」、『キルケゴール詩集』、R. ブレッタル編、A. ドルー訳、プリンストン大学出版局、プリンストン、ニュージャージー州。 1835年~1854年 [1959年]。『キルケゴール日記』、A. ドルー訳、ニューヨーク:Harper Torchbooks。(1835年から1854年は、この雑誌への寄稿期間である。) ――――、1843年[1985年]。『恐れとおののき』、A. ハネイ(訳)、ニューヨーク:ペンギンブックス。 ――――、1849年[1989年]。『死に至る病』、A. ハネイ(訳)、ニューヨーク:ペンギンブックス。 Leder, D., 2016. The distressed body. Rethinking illness, imprisonment, and healing, Chicago, IL: University of Chicago Press. Loy, D., 2018. Lack and transcendence: The problem of death and life in psychotherapy, existentialism, and Buddhism, Somerville, MA: Wisdom Publications. マッキンタイア、A.、1981年。『徳の後で』、インディアナ州ノートルダム:ノートルダム大学出版。 マルパス、J.、2017年。『ハイデガーと場の思考:存在の位相学の探求』、マサチューセッツ州ケンブリッジ:MITプレス。 マクマリン、I.、2019年。『実存的繁栄:徳の現象学』、ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版。 メルロ=ポンティ、M.、1945年[1962年]。知覚の現象学、C. スミス(訳)、ロンドン:Routledge & Keegan Paul。 ――――、1964年[1968年]。見えるものと見えないもの:作業メモ付、A. リンギス(訳)、イリノイ州エバンストン:ノースウェスタン大学出版。 モートン、T.、2016年。『ダーク・エコロジー:未来の共存の論理のために』、ニューヨーク:コロンビア大学出版局。 マードック、I.、1983年。「乾燥に対するもの:論争的スケッチ」、S. ハウエルワスとA. マッキンタイア(編)、『改訂:道徳哲学における視点の変化』、ノートルダム、IN:ノートルダム大学出版局。 ニーチェ、F.、1886年[1998年]。『善悪の彼岸』、M. フェイバー(訳)、ニューヨーク&オックスフォード:オックスフォード大学出版局。 ―――、1887年[1974年]。『愉快な科学』、W. カウフマン(訳)、ニューヨーク:ヴィンテージブックス。 ―――、1887年[1996年]。『道徳の系譜学』D. スミス(訳)、ニューヨーク&オックスフォード:オックスフォード大学出版局。 ―――、1889年[1990年]。『哲学と真理:1870年代初頭のニーチェのノートからの抜粋』D. ブリーゼール(訳・編)、ニュージャージー州アトランティックハイランズ:Humanities Press。 ―――、1889b [1990b] 『偶像の黄昏』、R. J. Hollingdale(訳)、ニューヨーク:ペンギンブックス。 ―――、1901 [1968] 『力への意志』、W. Kaufmann(訳)、ニューヨーク:ヴィンテージブックス。 オルテガ・イ・ガセット、J.、1941年。歴史の哲学に向けて、H. ワイル(訳)、ニューヨーク:W.W. Norton. ――――、1930年[1993年]『大衆の反逆』、ニューヨーク:W.W. Norton. オルテガ、M.、2016年。『中間領域:ラテン系フェミニスト現象学、多元性、そして自己』、ニューヨーク州オルバニー:SUNY Press. Parnas, J. & Gallagher, S., 2015. 「現象学と精神病理学的経験の解釈」L. Kirmayer, R. Lemelson, and C. Cummings (eds.), 『精神医学の再考:生物学的、臨床的、文化的な視点の統合』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。 Ratcliffe, M., 2015. うつ病の体験。現象学的研究、オックスフォード:オックスフォード大学出版局。 Reynolds, J. M., 2022. 生きがいのある人生:障害と痛みを同一視するアビリストに対する哲学的挑戦、ミネアポリス、MN:ミネソタ大学出版。 Rentmeester, C., 2016. ハイデガーと環境、ロンドン:ローマン・アンド・リトルフィールド。 Salamon, G., 2020. Assuming a body: Transgender and rhetorics of materiality, New York: Columbia University Press. サルトル, J-P., 1943 [1956]. Being and nothingness, H. Barnes (trans.), New York: Washington Square Press. ―――、1952年[1963年]。『サン・ジュネ、俳優にして殉教者』B. フレクトマン(訳)、ニューヨーク:ジョージ・ブラジラー社。 ―――、1957年[1968年]。『方法の探究』H. バーンズ(訳)、ニューヨーク:ヴィンテージ・ブックス。 ―――、1945年[1988年]。「文学とは何か」およびその他のエッセイ、S. アンガー編、J. メルマン訳、ケンブリッジ、マサチューセッツ州:ハーバード大学出版局。 ―――、1944年[1989年]。出口なし、S. ギルバート訳、ニューヨーク:ヴィンテージ・プレス。 ―――、1948年[1992年]。『倫理ノート』D. Pellauer(訳)、イリノイ州シカゴ:シカゴ大学出版。 ―――、1946年[2001年]。「実存主義はヒューマニズムである」B. Frechtman(訳)、C. GuignonとD. Pereboom(編)、『実存主義:基本文献』インディアナ州インディアナポリス:Hackett Press。 ―――、1972年[2008年]。「思考の旅程」ジャン=ポール・サルトル:実存主義とマルクス主義の間、J. マシューズ(訳)、ニューヨーク:ヴァーソ・ブックス。 Slatman, J., 2014. 『私たちの奇妙な身体:アイデンティティと医療介入に関する哲学的考察』アムステルダム:アムステルダム大学出版局。 Solomon, R., 2005. 『実存主義』第2版、ニューヨーク&オックスフォード:オックスフォード大学出版局。 Spinelli, E., 2007. 『実存主義的心理療法の実践:関係性の世界』ロンドン:Sage。 Stanghellini, G., Broome, M., Fernandez, A., Fusar-Poli, P., Raballo, A., Rosfort, R., 2019. 『現象学的精神病理学ハンドブック』、ニューヨーク&オックスフォード:オックスフォード大学出版局。 Svenaeus, F., 2022. 『医学の解釈学と保健の現象学: 医療実践の哲学への歩み、第2版、ドルドレヒト:スプリンガー。 テイラー、C.、1989年。自己の源泉:近代的アイデンティティの形成、マサチューセッツ州ケンブリッジ:ハーバード大学出版局。 ファン・ドゥールゼン、E.、2015年。心理療法におけるパラドックスと情熱:カウンセリングとセラピーへの実存的アプローチ、第2版、チチェスター:ジョン・ワイリー・アンド・サンズ・リミテッド。 フォーゲル、L.、1994年。「壊れやすい「私たち」:ハイデガーの『存在と時間』の倫理的含意」、イリノイ州エバンストン:ノースウェスタン大学出版。 ウェバー、J.、2018年。「実存主義の再考」、オックスフォード:オックスフォード大学出版。 ウォリン、R.、1990年。「存在の政治学:マーティン・ハイデガーの政治思想」、ニューヨーク:コロンビア大学出版。 ―――、1995年。「カール・ロイヴィトとマルティン・ハイデガー――背景と論争:序説」、カール・ロイヴィト、マルティン・ハイデガーとヨーロッパのニヒリズム、G. スタイナー(訳)、ニューヨーク:コロンビア大学出版。 ヤング、I. M.、1984年[2000年]。女性の身体経験について:「女の子らしく投げる」とその他のエッセイ、ニューヨーク:オックスフォード大学出版。 Zahavi, D., 2005. 主観性と自己:一人称の視点の調査、マサチューセッツ州ケンブリッジ:MIT Press. Zeiler, K. & Käll, L., 2014. フェミニスト現象学と医学、ニューヨーク州オルバニー:SUNY Press. |
| https://plato.stanford.edu/entries/existentialism/ |
https://www.deepl.com/ja/translator |
リンク
文献
その他の情報




Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099