
ジョージ・バークリー
George Berkeley, 1685-1753

☆ ジョージ・バークリー(George Berkeley, 1685年3月12日 - 1753年1月14日)はアングロ・アイルランドの哲学者であり、バークリー主教(アイルランド国教会のクロイン主教)として知られている。この理論は、 物質的実体の存在を否定し、その代わりに、テーブルや椅子のような身近な物体は心によって知覚される観念であり、その結果、知覚されずに存在することはで きないと主張した。バークリーはまた、非物質主義を主張する際の重要な前提である抽象性を批判したことでも知られている。 1709年、バークリーは最初の主要著作である『An Essay Towards a New Theory of Vision』を出版し、その中で彼は人間の視覚の限界について論じ、視覚の適切な対象は物質的な物体ではなく、光と色であるという説を唱えた。 [1710年に出版された『人間の知識の原理に関する論考』(A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge)の評判は芳しくなかったが、その後、対話形式で書き直され、1713年に『ハイラスとフィロノウスの間の3つの対話』(Three Dialogues Between Hylas and Philonous)というタイトルで出版された。 バークリーは、1721年に出版された『運動論』(De Motu[10])で、アイザック・ニュートン(1642-1727)の絶対空間、絶対時間、絶対運動の教義に反論した。1732年には自由思想家たちに対するキリスト教的弁明 書である『アルシフロン』を出版し、1734年には微積分の基礎についての批評である『アナリスト』を出版し、数学の発展に影響を与えた[13]。 第二次世界大戦後、バークリーの著作への関心が高まったのは、彼が知覚の問題、第一次的性質と第二次的性質の違い、言語の重要性など、20世紀の哲学に とって最も関心の高い問題の多くに取り組んだからである[14]。
★ バークリーは、ジョン・ロック(1632-1704)の経験論を承継し、知覚によって得られる観念の結合・一致・不一致・背反の知覚が知識であり、全ての観念と知識は人間が経験 を通じて形成するものだとした。バークリーの著書『ハイラスとフィロナスとの三つの対話』は、素朴実在論的な考え方をするハイラスにバークリーの代弁者で あるフィロナスが反論する対話篇の形をとっている。素朴実在論によれば、わたしが知覚するものは存在する。わたしの心とわたしの体も存在する。わたしが知 覚している目の前の机も世界も存在している。しかし、バークリーによれば、世界は観念であり、たとえば私が目の前の机を叩いてその硬さを認識したとして も、「机の固さ」としてではなく、「知覚として」認識しているわけであり、「机自体」を認識していることにはならない。このような彼の考え方は、主観的観 念論、独我論と批判された。このような批判を受けた彼は『視覚新論』をまず発表して人々をある程度彼の考えに慣らし、続いて彼が本当に言いたかった『人知 原理論』を発表するという手順をとった。わたしの心は一つであり、分割することはできず、これ以上延長することもできず、形もない。ゆえに私の心は不滅で あり、これは実体である。わたしの目の前の机もわたしの身体も世界すらもわたしが知覚する限りにおいて「わたしの心の中に存在する」のであって、事物は観 念の束である[1]。彼は物質を否定し、感覚的な観念の原因は神であるとして、知覚する精神と神のみを実体と認めた。彼は聖職者であり、宗教的見地から魂 の不滅と神の存在を結びつける必要があった。また、彼は物質を実体であると認めることは唯物論的無神論に結びつくと考えたのである。
| George Berkeley
(/ˈbɑːrkli/ BARK-lee;[5][6] 12 March 1685 – 14 January 1753) – known as
Bishop Berkeley (Bishop of Cloyne of the Anglican Church of Ireland) –
was an Anglo-Irish philosopher whose primary achievement was the
advancement of a theory he called "immaterialism" (later referred to as
"subjective idealism" by others). This theory denies the existence of
material substance and instead contends that familiar objects like
tables and chairs are ideas perceived by the mind and, as a result,
cannot exist without being perceived. Berkeley is also known for his
critique of abstraction, an important premise in his argument for
immaterialism.[7] In 1709, Berkeley published his first major work, An Essay Towards a New Theory of Vision, in which he discussed the limitations of human vision and advanced the theory that the proper objects of sight are not material objects, but light and colour.[8] This foreshadowed his chief philosophical work, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, in 1710, which, after its poor reception, he rewrote in dialogue form and published under the title Three Dialogues Between Hylas and Philonous in 1713.[9] In this book, Berkeley's views were represented by Philonous (Greek: "lover of mind"), while Hylas ("hyle", Greek: "matter") embodies the Irish thinker's opponents, in particular John Locke. Berkeley argued against Isaac Newton's doctrine of absolute space, time and motion in De Motu[10] (On Motion), published 1721. His arguments were a precursor to the views of Ernst Mach and Albert Einstein.[11][12] In 1732, he published Alciphron, a Christian apologetic against the free-thinkers, and in 1734, he published The Analyst, a critique of the foundations of calculus, which was influential in the development of mathematics.[13] Interest in Berkeley's work increased after World War II because he tackled many of the issues of paramount interest to philosophy in the 20th century, such as the problems of perception, the difference between primary and secondary qualities, and the importance of language.[14] |
ジョージ・バークリー(George Berkeley, /ˈɑ
BARK-lee;[5][6] 1685年3月12日 -
1753年1月14日)はアングロ・アイルランドの哲学者であり、バークリー主教(アイルランド国教会のクロイン主教)として知られている。この理論は、
物質的実体の存在を否定し、その代わりに、テーブルや椅子のような身近な物体は心によって知覚される観念であり、その結果、知覚されずに存在することはで
きないと主張した。バークリーはまた、非物質主義を主張する際の重要な前提である抽象性を批判したことでも知られている[7]。 1709年、バークリーは最初の主要著作である『An Essay Towards a New Theory of Vision』を出版し、その中で彼は人間の視覚の限界について論じ、視覚の適切な対象は物質的な物体ではなく、光と色であるという説を唱えた。 [1710年に出版された『人間の知識の原理に関する論考』(A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge)の評判は芳しくなかったが、その後、対話形式で書き直され、1713年に『ハイラスとフィロノウスの間の3つの対話』(Three Dialogues Between Hylas and Philonous)というタイトルで出版された。 バークリーは、1721年に出版された『運動論』(De Motu[10])で、アイザック・ニュートンの絶対空間、絶対時間、絶対運動の教義に反論した。1732年には自由思想家たちに対するキリスト教的弁明 書である『アルシフロン』を出版し、1734年には微積分の基礎についての批評である『アナリスト』を出版し、数学の発展に影響を与えた[13]。 第二次世界大戦後、バークリーの著作への関心が高まったのは、彼が知覚の問題、第一次的性質と第二次的性質の違い、言語の重要性など、20世紀の哲学に とって最も関心の高い問題の多くに取り組んだからである[14]。 |
| Biography Ireland This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (January 2018) (Learn how and when to remove this message) Berkeley was born at his family home, Dysart Castle, near Thomastown, County Kilkenny, Ireland, the eldest son of William Berkeley, a cadet of the noble family of Berkeley whose ancestry can be traced back to the Anglo-Saxon period and who had served as feudal lords and landowners in Gloucester, England.[15][16] Little is known of his mother. He was educated at Kilkenny College and attended Trinity College Dublin, where he was elected a Scholar in 1702, being awarded BA in 1704 and MA and a Fellowship in 1707. He remained at Trinity College after the completion of his degree as a tutor and Greek lecturer. His earliest publication was on mathematics, but the first that brought him notice was his An Essay towards a New Theory of Vision, first published in 1709. In the essay, Berkeley examines visual distance, magnitude, position and problems of sight and touch. While this work raised much controversy at the time, its conclusions are now accepted as an established part of the theory of optics. The next publication to appear was the Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge in 1710, which had great success and gave him a lasting reputation, though few accepted his theory that nothing exists outside the mind. This was followed in 1713 by Three Dialogues Between Hylas and Philonous, in which he propounded his system of philosophy, the leading principle of which is that the world, as represented by our senses, depends for its existence on being perceived. For this theory, the Principles gives the exposition and the Dialogues the defence. One of his main objectives was to combat the prevailing materialism of his time. The theory was largely received with ridicule, while even those such as Samuel Clarke and William Whiston, who did acknowledge his "extraordinary genius," were nevertheless convinced that his first principles were false. England and Europe Shortly afterwards, Berkeley visited England and was received into the circle of Addison, Pope and Steele. In the period between 1714 and 1720, he interspersed his academic endeavours with periods of extensive travel in Europe, including one of the most extensive Grand Tours of the length and breadth of Italy ever undertaken.[17] In 1721, he took Holy orders in the Church of Ireland, earning his doctorate in divinity, and once again chose to remain at Trinity College Dublin, lecturing this time in Divinity and in Hebrew. In 1721/2 he was made Dean of Dromore and, in 1724, Dean of Derry. In 1723, Berkeley was named co-heir of Esther Vanhomrigh, along with the barrister Robert Marshall. This naming followed Vanhomrigh's violent quarrel with Jonathan Swift, who had been her intimate friend for many years. Vanhomrigh's choice of legatees caused a good deal of surprise since she did not know either of them well, although Berkeley as a very young man had known her father. Swift said that he did not grudge Berkeley his inheritance, much of which vanished in a lawsuit in any event. A story that Berkeley and Marshall disregarded a condition of the inheritance that they must publish the correspondence between Swift and Vanessa is probably untrue. In 1725, Berkeley began the project of founding a college in Bermuda for training ministers and missionaries in the colony, in pursuit of which he gave up his deanery with its income of £1100. Marriage and America A group portrait of Berkeley and his entourage by John Smibert Whitehall, Berkeley's home in Middletown, Rhode Island On 1 August 1728 at St Mary le Strand, London,[18] Berkeley married Anne Forster, daughter of John Forster, Chief Justice of the Irish Common Pleas, and Forster's first wife Rebecca Monck. He then went to America on a salary of £100 per annum. He landed near Newport, Rhode Island, where he bought a plantation at Middletown – the famous "Whitehall". Berkeley purchased several enslaved Africans to work on the plantation.[19][20] In 2023, Trinity College Dublin removed Berkeley's name from one of its libraries because of his slave ownership and his active defence of slavery.[21] It has been claimed that "he introduced Palladianism into America by borrowing a design from [William] Kent's Designs of Inigo Jones for the door-case of his house in Rhode Island, Whitehall".[22] He also brought to New England John Smibert, the Scottish artist he "discovered" in Italy, who is generally regarded as the founding father of American portrait painting.[23] Meanwhile, he drew up plans for the ideal city he planned to build on Bermuda.[24] He lived at the plantation while he waited for funds for his college to arrive. The funds, however, were not forthcoming. "With the withdrawal from London of his own persuasive energies, opposition gathered force; and the Prime Minister, Walpole grew steadily more sceptical and lukewarm. At last it became clear that the essential Parliamentary grant would be not forthcoming",[25] and in 1732 he left America and returned to London. He and Anne had four children who survived infancy – Henry, George, William and Julia – and at least two other children who died in infancy. William's death in 1751 was a great cause of grief for his father. Episcopate in Ireland Berkeley was nominated to be the Bishop of Cloyne in the Church of Ireland on 18 January 1734. He was consecrated as such on 19 May 1734. He was the Bishop of Cloyne until his death on 14 January 1753, although he died at Oxford (see below). Humanitarian work While living in London's Saville Street, he took part in efforts to create a home for the city's abandoned children. The Foundling Hospital was founded by royal charter in 1739, and Berkeley is listed as one of its original governors. Last works His last two publications were Siris: A Chain of Philosophical Reflexions and Inquiries Concerning the Virtues of Tarwater, And divers other Subjects connected together and arising one from another (1744) and Further Thoughts on Tar-water (1752). Pine tar is an effective antiseptic and disinfectant when applied to cuts on the skin, but Berkeley argued for the use of pine tar as a broad panacea for diseases. His 1744 work on tar-water sold more copies than any of his other books during Berkeley's lifetime.[26] He remained at Cloyne until 1752, when he retired. With his wife and daughter Julia, he went to Oxford to live with his son George and supervise his education.[27] He died soon afterwards and was buried in Christ Church Cathedral, Oxford. His affectionate disposition and genial manners made him much loved and held in warm regard by many of his contemporaries. Anne outlived her husband by many years, and died in 1786.[28] |
バイオグラフィー アイルランド このセクションは出典を引用していない。信頼できる情報源への引用を追加することで、このセクションの改善にご協力いただきたい。ソースのないものは異議 申し立てされ、削除されることがある。(2018年1月)(このメッセージを削除する方法とタイミングを学ぶ) バークリーはアイルランドのキルケニー州トーマスタウン近郊の実家ダイサート城で、先祖をアングロ・サクソン時代にまで遡ることができ、イングランドのグ ロスターで封建領主や地主を務めていた貴族バークリー家の士官候補生ウィリアム・バークリーの長男として生まれた[15][16]。キルケニー・カレッジ で教育を受けた後、トリニティ・カレッジ・ダブリンで学び、1702年にスカラーに選ばれ、1704年に学士号、1707年に修士号とフェローシップを授 与された。学位取得後もトリニティ・カレッジに残り、家庭教師とギリシャ語の講師を務めた。 彼の最も初期の出版物は数学に関するものであったが、最初に注目されたのは1709年に発表された『An Essay towards a New Theory of Vision』であった。このエッセイの中で、バークリーは視覚の距離、大きさ、位置、視覚と触覚の問題について考察している。この著作は当時多くの論争 を巻き起こしたが、現在ではその結論は光学理論の確立された一部として受け入れられている。 次に出版されたのが1710年の『人間の知識の原理に関する論考』であり、大きな成功を収め、彼に永続的な名声を与えたが、心の外に存在するものは何もな いという彼の説を受け入れた者はほとんどいなかった。この哲学体系の主要な原理は、感覚によって表現される世界は、知覚されることによってその存在を決定 するというものである。 この理論については、『原理篇』が説明し、『対話篇』が弁明している。彼の主な目的のひとつは、当時主流であった唯物論と闘うことであった。サミュエル・ クラークやウィリアム・ウィストンのように、彼の「非凡な才能」を認めていた人々でさえも、彼の第一原理は誤りであると確信していた。 イギリスとヨーロッパ その直後、バークリーはイギリスを訪れ、アディソン、ポープ、スティールの仲間に迎えられた。1714年から1720年にかけて、バークリーは学問的な努 力のかたわらヨーロッパを旅した。1721年と1724年には、ドロモアの学部長、デリーの学部長に任命された。 1723年、バークリーは法廷弁護士ロバート・マーシャルとともにエステル・ヴァンホムリの共同相続人に指名された。この指名は、ヴァンホムリーが長年親 しい友人であったジョナサン・スウィフトと激しく争ったことに続くものであった。若い頃のバークリーは彼女の父親を知っていたが、彼女は二人のことをよく 知らなかったからである。スウィフトは、バークリーの遺産を恨んではいないと語ったが、いずれにせよ、その多くは訴訟で消えてしまった。バークリーとマー シャルが、スウィフトとヴァネッサの往復書簡を出版しなければならないという相続の条件を無視したという話は、おそらく事実ではないだろう。 1725年、バークリーは植民地の牧師や宣教師を養成するための大学をバミューダに設立するプロジェクトを開始し、そのために1100ポンドの収入を持つ 学部長職を手放した。 結婚とアメリカ ジョン・スミベールによるバークリーと側近の群像画 ロードアイランド州ミドルタウンにあるバークリーの家、ホワイトホール 1728年8月1日、ロンドンのセント・メアリー・ル・ストランドで[18]、バークリーはアイルランドの庶民裁判長ジョン・フォースターとフォースター の最初の妻レベッカ・モンクの娘アン・フォースターと結婚した。その後、年俸100ポンドでアメリカに渡った。ロードアイランド州ニューポート近郊に上陸 し、ミドルタウンの農園(有名な「ホワイトホール」)を購入した。2023年、トリニティ・カレッジ・ダブリンは、彼の奴隷所有と奴隷制の積極的な擁護を 理由に、バークリーの名前を図書館のひとつから削除した[21]。 彼はロードアイランドのホワイトホールにある自分の家のドアケースのために、[ウィリアム]ケントの『イニゴ・ジョーンズの設計』からデザインを借りて、 パラディアニズムをアメリカに持ち込んだ」と主張されている[22]。 [22]彼はまた、イタリアで「発見」したスコットランド人画家で、一般にアメリカの肖像画の創始者とみなされているジョン・スミベルトをニューイングラ ンドに呼び寄せた[23]。一方、彼はバミューダに建設する予定の理想都市の設計図を描いた[24]。しかし、資金は届かなかった。「ウォルポール首相は 次第に懐疑的で生ぬるくなっていった。そして1732年、ウォルポールはアメリカを離れ、ロンドンに戻った。 彼とアンの間には、ヘンリー、ジョージ、ウィリアム、ジュリアの4人の子供がいたが、少なくとも2人の子供は幼児期に亡くなった。1751年のウィリアム の死は、父にとって大きな悲しみであった。 アイルランド司教座 バークリーは1734年1月18日、アイルランド教会のクロイン司教に指名された。1734年5月19日に聖別された。1753年1月14日に亡くなるま でクロイン司教を務めたが、オックスフォードで死去した(下記参照)。 人道的活動 ロンドンのサヴィル・ストリートに住んでいたとき、彼はロンドンの捨て子のための施設を作る活動に参加した。ファウンドリング・ホスピタルは1739年に 勅許によって設立され、バークリーはその初代院長のひとりとして名を連ねている。 遺作 バークリーの最後の著作は『シリス』(Siris)である: A Chain of Philosophical Reflexions and Inquiry Concerning the Virtues of Tarwater, And diversother Subjects connected together and arising one from another (1744)』と『Further Thoughts on Tar-water (1752)』である。松脂は皮膚の切り傷に塗ると効果的な防腐剤・殺菌剤となるが、バークリーは松脂を病気に対する幅広い万能薬として使用することを主 張した。1744年に出版されたタール水に関する著作は、バークリーが存命中に出版した他のどの本よりも多くの部数を売り上げた[26]。 1752年に引退するまでクロインに留まった。その後まもなく亡くなり、オックスフォードのクライスト・チャーチ大聖堂に埋葬された[27]。愛情深い性 格と温厚な人柄で、同時代の多くの人々から愛され、温かい寵愛を受けた。アンは夫より何年も長生きし、1786年に亡くなった[28]。 |
| Contributions to philosophy Main article: Subjective idealism According to Berkeley there are only two kinds of things: spirits and ideas. Spirits are simple, active beings which produce and perceive ideas; ideas are passive beings which are produced and perceived.[29] The use of the concepts of "spirit" and "idea" is central in Berkeley's philosophy. As used by him, these concepts are difficult to translate into modern terminology. His concept of "spirit" is close to the concept of "conscious subject" or of "mind", and the concept of "idea" is close to the concept of "sensation" or "state of mind" or "conscious experience". Thus Berkeley denied the existence of matter as a metaphysical substance, but did not deny the existence of physical objects such as apples or mountains ("I do not argue against the existence of any one thing that we can apprehend, either by sense or reflection. That the things I see with mine eyes and touch with my hands do exist, really exist, I make not the least question. The only thing whose existence we deny, is that which philosophers call matter or corporeal substance. And in doing of this, there is no damage done to the rest of mankind, who, I dare say, will never miss it.", Principles #35). This basic claim of Berkeley's thought, his "idealism", is sometimes and somewhat derisively called "immaterialism" or, occasionally, subjective idealism. In Principles #3, he wrote, using a combination of Latin and English, esse is percipi (to be is to be perceived), most often if slightly inaccurately attributed to Berkeley as the pure Latin phrase esse est percipi.[30] The phrase appears associated with him in authoritative philosophical sources, e.g., "Berkeley holds that there are no such mind-independent things, that, in the famous phrase, esse est percipi (aut percipere)—to be is to be perceived (or to perceive)."[26] Hence, human knowledge is reduced to two elements: that of spirits and of ideas (Principles #86). In contrast to ideas, a spirit cannot be perceived. A person's spirit, which perceives ideas, is to be comprehended intuitively by inward feeling or reflection (Principles #89). For Berkeley, we have no direct 'idea' of spirits, albeit we have good reason to believe in the existence of other spirits, for their existence explains the purposeful regularities we find in experience[31] ("It is plain that we cannot know the existence of other spirits otherwise than by their operations, or the ideas by them excited in us", Dialogues #145). This is the solution that Berkeley offers to the problem of other minds. Finally, the order and purposefulness of the whole of our experience of the world and especially of nature overwhelms us into believing in the existence of an extremely powerful and intelligent spirit that causes that order. According to Berkeley, reflection on the attributes of that external spirit leads us to identify it with God. Thus a material thing such as an apple consists of a collection of ideas (shape, colour, taste, physical properties, etc.) which are caused in the spirits of humans by the spirit of God. Theology A convinced adherent of Christianity, Berkeley believed God to be present as an immediate cause of all our experiences. He did not evade the question of the external source of the diversity of the sense data at the disposal of the human individual. He strove simply to show that the causes of sensations could not be things, because what we called things, and considered without grounds to be something different from our sensations, were built up wholly from sensations. There must consequently be some other external source of the inexhaustible diversity of sensations. The source of our sensations, Berkeley concluded, could only be God; He gave them to man, who had to see in them signs and symbols that carried God's word.[32] Here is Berkeley's proof of the existence of God: Whatever power I may have over my own thoughts, I find the ideas actually perceived by Sense have not a like dependence on my will. When in broad daylight I open my eyes, it is not in my power to choose whether I shall see or no, or to determine what particular objects shall present themselves to my view; and so likewise as to the hearing and other senses; the ideas imprinted on them are not creatures of my will. There is therefore some other Will or Spirit that produces them. (Berkeley. Principles #29) As T. I. Oizerman explained: Berkeley's mystic idealism (as Kant aptly christened it) claimed that nothing separated man and God (except materialist misconceptions, of course), since nature or matter did not exist as a reality independent of consciousness. The revelation of God was directly accessible to man, according to this doctrine; it was the sense-perceived world, the world of man's sensations, which came to him from on high for him to decipher and so grasp the divine purpose.[32] Berkeley believed that God is not the distant engineer of Newtonian machinery that in the fullness of time led to the growth of a tree in the university quadrangle. Rather, the perception of the tree is an idea that God's mind has produced in the mind, and the tree continues to exist in the quadrangle when "nobody" is there, simply because God is an infinite mind that perceives all. The philosophy of David Hume concerning causality and objectivity is an elaboration of another aspect of Berkeley's philosophy. A.A. Luce, the most eminent Berkeley scholar of the 20th century, constantly stressed the continuity of Berkeley's philosophy. The fact that Berkeley returned to his major works throughout his life, issuing revised editions with only minor changes, also counts against any theory that attributes to him a significant volte-face.[33] Relativity arguments See also: Three Dialogues Between Hylas and Philonous John Locke (Berkeley's intellectual predecessor) states that we define an object by its primary and secondary qualities. He takes heat as an example of a secondary quality. If you put one hand in a bucket of cold water, and the other hand in a bucket of warm water, then put both hands in a bucket of lukewarm water, one of your hands is going to tell you that the water is cold and the other that the water is hot. Locke says that since two different objects (both your hands) perceive the water to be hot and cold, then the heat is not a quality of the water. While Locke used this argument to distinguish primary from secondary qualities, Berkeley extends it to cover primary qualities in the same way. For example, he says that size is not a quality of an object because the size of the object depends on the distance between the observer and the object, or the size of the observer. Since an object is a different size to different observers, then size is not a quality of the object. Berkeley rejects shape with a similar argument and then asks: if neither primary qualities nor secondary qualities are of the object, then how can we say that there is anything more than the qualities we observe?[clarification needed] Relativity is the idea that there is no objective, universal truth; it is a state of dependence in which the existence of one independent object is solely dependent on that of another. According to Locke, characteristics of primary qualities are mind-independent, such as shape, size, etc., whereas secondary qualities are mind-dependent, for example, taste and colour. George Berkeley refuted John Locke's belief on primary and secondary qualities because Berkeley believed that "we cannot abstract the primary qualities (e.g shape) from secondary ones (e.g colour)".[34] Berkeley argued that perception is dependent on the distance between the observer and the object, and "thus, we cannot conceive of mechanist material bodies which are extended but not (in themselves) colored".[34] What perceived can be the same type of quality, but completely opposite from each other because of different positions and perceptions, what we perceive can be different even when the same types of things consist of contrary qualities. Secondary qualities aid in people's conception of primary qualities in an object, like how the colour of an object leads people to recognize the object itself. More specifically, the colour red can be perceived in apples, strawberries, and tomatoes, yet we would not know what these might look like without its colour. We would also be unaware of what the colour red looked like if red paint, or any object that has a perceived red colour, failed to exist. From this, we can see that colours cannot exist on their own and can solely represent a group of perceived objects. Therefore, both primary and secondary qualities are mind-dependent: they cannot exist without our minds. George Berkeley was a philosopher who opposed rationalism and "classical" empiricism. He was a "subjective idealist" or "empirical idealist", who believed that reality is constructed entirely of immaterial, conscious minds and their ideas; everything that exists is somehow dependent on the subject perceiving it, except the subject themselves. He refuted the existence of abstract objects that many other philosophers believed to exist, notably Plato. According to Berkeley, "an abstract object does not exist in space or time and which is therefore entirely non-physical and non-mental";[35] however, this argument contradicts his relativity argument. If "esse est percipi",[36] (Latin meaning that to exist is to be perceived) is true, then the objects in the relativity argument made by Berkeley can either exist or not. Berkeley believed that only the minds' perceptions and the Spirit that perceives are what exists in reality; what people perceive every day is only the idea of an object's existence, but the objects themselves are not perceived. Berkeley also discussed how, at times, materials cannot be perceived by oneself, and the mind of oneself cannot understand the objects. However, there also exists an "omnipresent, eternal mind"[37] that Berkeley believed to consist of God and the Spirit, both omniscient and all-perceiving. According to Berkeley, God is the entity who controls everything, yet Berkeley also argued that "abstract object[s] do not exist in space or time".[35] In other words, as Warnock argues, Berkeley "had recognized that he could not square with his own talk of spirits, of our minds and of God; for these are perceivers and not among objects of perception. Thus he says, rather weakly and without elucidation, that in addition to our ideas, we also have notions—we know what it means to speak of spirits and their operations."[38] However, the relativity argument violates the idea of immaterialism. Berkeley's immaterialism argues that "esse est percipi (aut percipere)",[39] which in English is: to be is to be perceived (or to perceive). That is saying only what is perceived or perceived is real, and without our perception or God's nothing can be real. Yet, if the relativity argument, also by Berkeley, argues that the perception of an object depends on the different positions, then this means that what is perceived can either be real or not because the perception does not show that whole picture and the whole picture cannot be perceived. Berkeley also believes that "when one perceives mediately, one perceives one idea by means of perceiving another".[40] By this, it can be elaborated that if the standards of what perceived at first are different, what perceived after that can be different, as well. In the heat perception described above, one hand perceived the water to be hot and the other hand perceived the water to be cold due to relativity. If applying the idea "to be is to be perceived", the water should be both cold and hot because both perceptions are perceived by different hands. However, the water cannot be cold and hot at the same time for it self-contradicts, so this shows that what perceived is not always true because it sometimes can break the law of noncontradiction. In this case, "it would be arbitrary anthropocentrism to claim that humans have special access to the true qualities of objects".[4] The truth for different people can be different, and humans are limited to accessing the absolute truth due to relativity. Summing up, nothing can be absolutely true due to relativity or the two arguments, to be is to be perceived and the relativity argument, do not always work together. New theory of vision In his Essay Towards a New Theory of Vision, Berkeley frequently criticised the views of the Optic Writers, a title that seems to include Molyneux, Wallis, Malebranche and Descartes.[41] In sections 1–51, Berkeley argued against the classical scholars of optics by holding that: spatial depth, as the distance that separates the perceiver from the perceived object is itself invisible. That is, we do not see space directly or deduce its form logically using the laws of optics. Space for Berkeley is no more than a contingent expectation that visual and tactile sensations will follow one another in regular sequences that we come to expect through habit. Berkeley goes on to argue that visual cues, such as the perceived extension or 'confusion' of an object, can only be used to indirectly judge distance, because the viewer learns to associate visual cues with tactile sensations. Berkeley gives the following analogy regarding indirect distance perception: one perceives distance indirectly just as one perceives a person's embarrassment indirectly. When looking at an embarrassed person, we infer indirectly that the person is embarrassed by observing the red colour on the person's face. We know through experience that a red face tends to signal embarrassment, as we've learned to associate the two. The question concerning the visibility of space was central to the Renaissance perspective tradition and its reliance on classical optics in the development of pictorial representations of spatial depth. This matter has been debated by scholars since the 11th-century Arab polymath and mathematician Alhazen (Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham) affirmed in experimental contexts the visibility of space. This issue, which was raised in Berkeley's theory of vision, was treated at length in the Phenomenology of Perception of Maurice Merleau-Ponty, in the context of confirming the visual perception of spatial depth (la profondeur), and by way of refuting Berkeley's thesis.[42] Berkeley wrote about the perception of size in addition to that of distance. He is frequently misquoted as believing in size–distance invariance—a view held by the Optic Writers. This idea is that we scale the image size according to distance in a geometrical manner. The error may have become commonplace because the eminent historian and psychologist E. G. Boring perpetuated it.[43] In fact, Berkeley argued that the same cues that evoke distance also evoke size, and that we do not first see size and then calculate distance.[44] It is worth quoting Berkeley's words on this issue (Section 53): What inclines men to this mistake (beside the humour of making one see by geometry) is, that the same perceptions or ideas which suggest distance, do also suggest magnitude ... I say they do not first suggest distance, and then leave it to the judgement to use that as a medium, whereby to collect the magnitude; but they have as close and immediate a connexion with the magnitude as with the distance; and suggest magnitude as independently of distance, as they do distance independently of magnitude. Berkeley claimed that his visual theories were "vindicated" by a 1728 report regarding the recovery of vision in a 13-year-old boy operated for congenital cataracts by surgeon William Cheselden. In 2021, the name of Cheselden's patient was published for the first time: Daniel Dolins.[45] Berkeley knew the Dolins family, had numerous social links to Cheselden, including the poet Alexander Pope, and Princess Caroline, to whom Cheselden's patient was presented.[45] The report misspelt Cheselden's name, used language typical of Berkeley, and may even have been ghost-written by Berkeley.[45] Unfortunately, Dolins was never able to see well enough to read, and there is no evidence that the surgery improved Dolins' vision at any point prior to his death at age 30.[45] Philosophy of physics See also: De Motu (Berkeley's essay) "Berkeley's works display his keen interest in natural philosophy [...] from his earliest writings (Arithmetica, 1707) to his latest (Siris, 1744). Moreover, much of his philosophy is shaped fundamentally by his engagement with the science of his time."[46] The profundity of this interest can be judged from numerous entries in Berkeley's Philosophical Commentaries (1707–1708), e.g. "Mem. to Examine & accurately discuss the scholium of the 8th Definition of Mr Newton's Principia." (#316) Berkeley argued that forces and gravity, as defined by Newton, constituted "occult qualities" that "expressed nothing distinctly". He held that those who posited "something unknown in a body of which they have no idea and which they call the principle of motion, are in fact simply stating that the principle of motion is unknown". Therefore, those who "affirm that active force, action, and the principle of motion are really in bodies are adopting an opinion not based on experience".[47] Forces and gravity existed nowhere in the phenomenal world. On the other hand, if they resided in the category of "soul" or "incorporeal thing", they "do not properly belong to physics" as a matter. Berkeley thus concluded that forces lay beyond any kind of empirical observation and could not be a part of proper science.[48] He proposed his theory of signs as a means to explain motion and matter without reference to the "occult qualities" of force and gravity. Berkeley's razor Berkeley's razor is a rule of reasoning proposed by the philosopher Karl Popper in his study of Berkeley's key scientific work De Motu.[10] Berkeley's razor is considered by Popper to be similar to Ockham's razor but "more powerful". It represents an extreme, empiricist view of scientific observation that states that the scientific method provides us with no true insight into the nature of the world. Rather, the scientific method gives us a variety of partial explanations about regularities that hold in the world and that are gained through experiments. The nature of the world, according to Berkeley, is only approached through proper metaphysical speculation and reasoning.[49] Popper summarises Berkeley's razor as such: A general practical result—which I propose to call "Berkeley's razor"—of [Berkeley's] analysis of physics allows us a priori to eliminate from physical science all essentialist explanations. If they have a mathematical and predictive content they may be admitted qua mathematical hypotheses (while their essentialist interpretation is eliminated). If not they may be ruled out altogether. This razor is sharper than Ockham's: all entities are ruled out except those which are perceived.[50] In another essay of the same book[51] titled "Three Views Concerning Human Knowledge", Popper argues that Berkeley is to be considered as an instrumentalist philosopher, along with Robert Bellarmine, Pierre Duhem and Ernst Mach. According to this approach, scientific theories have the status of serviceable fictions, useful inventions aimed at explaining facts, and without any pretension to being true. Popper contrasts instrumentalism with the above-mentioned essentialism and his own "critical rationalism". Philosophy of mathematics In addition to his contributions to philosophy, Berkeley was also very influential in the development of mathematics, although in a rather indirect sense. "Berkeley was concerned with mathematics and its philosophical interpretation from the earliest stages of his intellectual life."[7] Berkeley's "Philosophical Commentaries" (1707–1708) witness to his interest in mathematics: Axiom. No reasoning about things whereof we have no idea. Therefore no reasoning about Infinitesimals. (#354) Take away the signs from Arithmetic & Algebra, & pray what remains? (#767) These are sciences purely Verbal, & entirely useless but for Practise in Societys of Men. No speculative knowledge, no comparison of Ideas in them. (#768) In 1707, Berkeley published two treatises on mathematics. In 1734, he published The Analyst, subtitled A DISCOURSE Addressed to an Infidel Mathematician, a critique of calculus. Florian Cajori called this treatise "the most spectacular event of the century in the history of British mathematics."[52] However, a recent study suggests that Berkeley misunderstood Leibnizian calculus.[53] The mathematician in question is believed to have been either Edmond Halley, or Isaac Newton himself—though if to the latter, then the discourse was posthumously addressed, as Newton died in 1727. The Analyst represented a direct attack on the foundations and principles of calculus and, in particular, the notion of fluxion or infinitesimal change, which Newton and Leibniz used to develop the calculus. In his critique, Berkeley coined the phrase "ghosts of departed quantities", familiar to students of calculus. Ian Stewart's book From Here to Infinity captures the gist of his criticism. Berkeley regarded his criticism of calculus as part of his broader campaign against the religious implications of Newtonian mechanics – as a defence of traditional Christianity against deism, which tends to distance God from His worshipers. Specifically, he observed that both Newtonian and Leibnizian calculus employed infinitesimals sometimes as positive, nonzero quantities and other times as a number explicitly equal to zero. Berkeley's key point in "The Analyst" was that Newton's calculus (and the laws of motion based on calculus) lacked rigorous theoretical foundations. He claimed that: In every other Science Men prove their Conclusions by their Principles, and not their Principles by the Conclusions. But if in yours you should allow your selves this unnatural way of proceeding, the Consequence would be that you must take up with Induction, and bid adieu to Demonstration. And if you submit to this, your Authority will no longer lead the way in Points of Reason and Science.[54] Berkeley did not doubt that calculus produced real-world truth; simple physics experiments could verify that Newton's method did what it claimed to do. "The cause of Fluxions cannot be defended by reason",[55] but the results could be defended by empirical observation, Berkeley's preferred method of acquiring knowledge at any rate. Berkeley, however, found it paradoxical that "Mathematicians should deduce true Propositions from false Principles, be right in Conclusion, and yet err in the Premises." In The Analyst he endeavoured to show "how Error may bring forth Truth, though it cannot bring forth Science".[56] Newton's science, therefore, could not on purely scientific grounds justify its conclusions, and the mechanical, deistic model of the universe could not be rationally justified.[57] The difficulties raised by Berkeley were still present in the work of Cauchy whose approach to calculus was a combination of infinitesimals and a notion of limit, and were eventually sidestepped by Weierstrass by means of his (ε, δ) approach, which eliminated infinitesimals altogether. More recently, Abraham Robinson restored infinitesimal methods in his 1966 book Non-standard analysis by showing that they can be used rigorously. Moral philosophy See also: Passive obedience The tract A Discourse on Passive Obedience (1712) is considered Berkeley's major contribution to moral and political philosophy. In A Discourse on Passive Obedience, Berkeley defends the thesis that people have "a moral duty to observe the negative precepts (prohibitions) of the law, including the duty not to resist the execution of punishment."[58] However, Berkeley does make exceptions to this sweeping moral statement, stating that we need not observe precepts of "usurpers or even madmen"[59] and that people can obey different supreme authorities if there are more than one claims to the highest authority. Berkeley defends this thesis with deductive proof stemming from the laws of nature. First, he establishes that because God is perfectly good, the end to which he commands humans must also be good, and that end must not benefit just one person, but the entire human race. Because these commands—or laws—if practised, would lead to the general fitness of humankind, it follows that they can be discovered by the right reason—for example, the law to never resist supreme power can be derived from reason because this law is "the only thing that stands between us and total disorder".[58] Thus, these laws can be called the laws of nature, because they are derived from God—the creator of nature himself. "These laws of nature include duties never to resist the supreme power, lie under oath ... or do evil so that good may come of it."[58] One may view Berkeley's doctrine on Passive Obedience as a kind of 'Theological Utilitarianism', insofar as it states that we have a duty to uphold a moral code which presumably is working towards the ends of promoting the good of humankind. However, the concept of 'ordinary' utilitarianism is fundamentally different in that it "makes utility the one and only ground of obligation"[60]—that is, Utilitarianism is concerned with whether particular actions are morally permissible in specific situations, while Berkeley's doctrine is concerned with whether or not we should follow moral rules in any and all circumstances. Whereas act utilitarianism might, for example, justify a morally impermissible act in light of the specific situation, Berkeley's doctrine of Passive Obedience holds that it is never morally permissible to not follow a moral rule, even when it seems like breaking that moral rule might achieve the happiest ends. Berkeley holds that even though sometimes, the consequences of an action in a specific situation might be bad, the general tendencies of that action benefit humanity. Other important sources for Berkeley's views on morality are Alciphron (1732), especially dialogues I–III, and the Discourse to Magistrates (1738)."[61] Passive Obedience is notable partly for containing one of the earliest statements of rule utilitarianism.[62] Immaterialism George Berkeley’s theory that matter does not exist comes from the belief that "sensible things are those only which are immediately perceived by sense."[63] Berkeley says in his book called Principles of Human Knowledge that "the ideas of sense are stronger, livelier, and clearer than those of the imagination; and they are also steady, orderly and coherent."[64] From this we can tell that the things that we are perceiving are truly real rather than it just being a dream. All knowledge comes from perception; what we perceive are ideas, not things in themselves; a thing in itself must be outside experience; so the world only consists of ideas and minds that perceive those ideas; a thing only exists so far as it perceives or is perceived.[65] Through this we can see that consciousness is considered something that exists to Berkeley due to its ability to perceive. "'To be,' said of the object, means to be perceived, 'esse est percipi'; 'to be', said of the subject, means to perceive or 'percipere'."[66] Having established this, Berkeley then attacks the "opinion strangely prevailing amongst men, that houses, mountains, rivers, and in a word all sensible objects have an existence natural or real, distinct from being perceived".[64] He believes this idea to be inconsistent because such an object with an existence independent of perception must have both sensible qualities, and thus be known (making it an idea), and also an insensible reality, which Berkeley believes is inconsistent.[67] Berkeley believes that the error arises because people think that perceptions can imply or infer something about the material object. Berkeley calls this concept abstract ideas. He rebuts this concept by arguing that people cannot conceive of an object without also imagining the sensual input of the object. He argues in Principles of Human Knowledge that, similar to how people can only sense matter with their senses through the actual sensation, they can only conceive of matter (or, rather, ideas of matter) through the idea of sensation of matter.[64] This implies that everything that people can conceive in regards to matter is only ideas about matter. Thus, matter, should it exist, must exist as collections of ideas, which can be perceived by the senses and interpreted by the mind. But if matter is just a collection of ideas, then Berkeley concludes that matter, in the sense of a material substance, does not exist as most philosophers of Berkeley's time believed. Indeed, if a person visualizes something, then it must have some colour, however dark or light; it cannot just be a shape of no colour at all if a person is to visualize it.[68] Berkeley's ideas raised controversy because his argument refuted Descartes' philosophy, which was expanded upon by Locke, and resulted in the rejection of Berkeley's form of empiricism by several philosophers of the eighteenth century. In Locke's philosophy, "the world causes the perceptual ideas we have of it by the way it interacts with our senses."[65] This contradicts with Berkeley's philosophy because not only does it suggest the existence of physical causes in the world, but in fact, there is no physical world beyond our ideas. The only causes that exist in Berkeley's philosophy are those that are a result of the use of the will. Berkeley's theory relies heavily on his form of empiricism, which in turn relies heavily on the senses. His empiricism can be defined by five propositions: all significant words stand for ideas; all knowledge of things is about ideas; all ideas come from without or from within; if from without it must be by the senses, and they are called sensations (the real things), if from within they are the operations of the mind, and are called thoughts.[68] Berkeley clarifies his distinction between ideas by saying they "are imprinted on the senses," "perceived by attending to the passions and operations of the mind," or "are formed by help of memory and imagination."[68] One refutation of his idea was: if someone leaves a room and stops perceiving that room does that room no longer exist? Berkeley answers this by claiming that it is still being perceived and the consciousness that is doing the perceiving is God. (This makes Berkeley's argument hinge upon an omniscient, omnipresent deity.) This claim is the only thing holding up his argument which is "depending for our knowledge of the world, and of the existence of other minds, upon a God that would never deceive us."[65] Berkeley anticipates a second objection, which he refutes in Principles of Human Knowledge. He anticipates that the materialist may take a representational materialist standpoint: although the senses can only perceive ideas, these ideas resemble (and thus can be compared to) the actual, existing object. Thus, through the sensing of these ideas, the mind can make inferences as to matter itself, even though pure matter is non-perceivable. Berkeley's objection to that notion is that "an idea can be like nothing but an idea; a colour or figure can be like nothing but another colour or figure".[64] Berkeley distinguishes between an idea, which is mind-dependent, and a material substance, which is not an idea and is mind-independent. As they are not alike, they cannot be compared, just as one cannot compare the colour red to something that is invisible, or the sound of music to silence, other than that one exists and the other does not. This is called the likeness principle: the notion that an idea can only be like (and thus compared to) another idea. Berkeley attempted to show how ideas manifest themselves into different objects of knowledge: It is evident to anyone who takes a survey of the objects of human knowledge, that they are either ideas actually imprinted on the senses; or else such as are perceived by attending to the passions and operations of the mind; or lastly ideas formed by help of memory and imagination—either compounding, dividing, or barely representing those originally perceived in the aforesaid ways". (Berkeley's emphasis.)[69] Berkeley also attempted to prove the existence of God throughout his beliefs in immaterialism.[4] |
哲学への貢献 主な記事 主観的観念論 バークリーによれば、物事には精神と観念の2種類しかない。霊は単純で能動的な存在であり、イデアを生成し知覚する。イデアは受動的な存在であり、生成さ れ知覚される[29]。 精神」と「イデア」という概念の使用はバークリー哲学の中心である。バークリーが用いたこれらの概念は、現代の用語に置き換えることが難しい。彼の「精 神」という概念は「意識的主体」や「心」という概念に近く、「イデア」という概念は「感覚」や「心の状態」や「意識的経験」という概念に近い。 このようにバークリーは、形而上学的な物質としての物質の存在は否定したが、リンゴや山といった物理的な物体の存在は否定しなかった(「私は、感覚や反射 によって理解することができるいかなるものの存在にも反対しない。私が目で見、手で触れるものが存在すること、本当に存在することに、私はいささかの疑問 も抱かない。我々が存在を否定する唯一のものは、哲学者が物質あるいは身体的物質と呼ぶものである。そして、これを行うことによって、他の人類に損害を与 えることはない。) このバークリーの思想の基本的な主張、すなわち彼の「観念論」は、時として、やや揶揄的に「非物質論」、あるいは主観的観念論と呼ばれることがある。彼は 『原理』第3号で、ラテン語と英語を組み合わせて、esse is percipi(あることは知覚されることである)と書いた、 「バークリーは、そのような心に依存しないものは存在せず、有名なフレーズであるesse est percipi (aut percipere)-存在することは知覚されることである(あるいは知覚することである)[26]と主張している。 それゆえ、人間の知識は、精神とイデアという二つの要素に還元される(原則#86)。イデアとは対照的に、精神は知覚することができない。イデアを知覚す る人の精神は、内なる感覚や内省によって直観的に理解されるものである(『原理』第89号)。バークリーにとって、われわれは霊魂の直接的な「観念」を持 たないが、他の霊魂の存在を信じる十分な理由があるとはいえ、その存在はわれわれが経験[31]の中で見出す目的的な規則性を説明するからである(「他の 霊魂の存在は、その作用、あるいはそれらによってわれわれの中に励起される観念によってでなければ知ることができないことは明白である」『対話篇』 #145)。これが、他心の問題に対するバークリーの解決策である。最後に、私たちが経験する世界全体、とりわけ自然の秩序と目的意識は、私たちを圧倒 し、その秩序を引き起こす極めて強力で知的な精神の存在を信じさせる。バークリーによれば、その外的精神の属性に思いを馳せることで、私たちはそれを神と 同一視するようになる。したがって、リンゴのような物質的なものは、神の精神によって人間の精神に引き起こされる観念(形、色、味、物理的性質など)の集 合体からなるのである。 神学 キリスト教の信奉者であったバークリーは、神が私たちのすべての経験の直接的な原因として存在すると信じていた。 バークリーは、人間が自由に使える感覚データの多様性の外的な源についての疑問から逃れることはしなかった。なぜなら、私たちが物と呼び、根拠もなく感覚 とは異なるものだと考えているものは、すべて感覚から構築されたものだからである。その結果、無尽蔵にある多様な感覚には、何か別の外的な原因があるに違 いない。神は人間に感覚を与え、人間はその中に神の言葉を伝えるしるしや象徴を見なければならなかったのである[32]。 ここに神の存在についてのバークリーの証明がある: 私が自分自身の思考に対してどのような力を持っているとしても、センスが実際に知覚する観念は、私の意志に同じような依存性を持っていないことがわかる。 白昼、私が目を開けるとき、見えるか見えないかを選ぶことはできないし、どのような特定の対象が私の視界に入るかを決めることもできない。それゆえ、それ らを生み出す他の意志や精神が存在する。(バークリー、原理第29章) T. I. オイザーマンはこう説明している: バークリーの神秘主義的観念論(カントはこれをこう命名した)は、人間と神を隔てるものは何もないと主張した(もちろん、唯物論者の誤解を除いて)。この 教義によれば、神の啓示は人間にとって直接アクセス可能なものであり、それは感覚的に知覚される世界、つまり人間の感覚の世界であり、彼が神の目的を解読 し把握するために高みからもたらされたものであった[32]。 バークリーは、神はニュートン的な機械の遠い技術者ではなく、時が満ちれば大学の四角に木が生えるようになると信じていた。むしろ、木という知覚は神の心 が心の中に生み出した観念であり、木は「誰も」そこにいないときにも四角形の中に存在し続ける。 因果性と客観性に関するデイヴィッド・ヒュームの哲学は、バークリー哲学の別の側面を精緻化したものである。20世紀で最も著名なバークリー研究者である A.A.ルースは、バークリー哲学の連続性を常に強調していた。バークリーが生涯を通じて主要な著作に立ち返り、わずかな変更を加えただけの改訂版を発行 していたという事実も、彼に大きな転機が訪れたとする説を否定している[33]。 相対性理論 以下も参照のこと: ハイラスとフィロノスの3つの対話 ジョン・ロック(バークリーの知的前任者)は、我々は物体をその一次的性質と二次的性質によって定義すると述べている。彼は二次的性質の例として熱を挙げ ている。冷たい水の入ったバケツに片手を入れ、温かい水の入ったバケツにもう片方の手を入れ、次にぬるま湯の入ったバケツに両手を入れると、片方の手は 「冷たい」と言い、もう片方の手は「熱い」と言うだろう。ロックは、2つの異なる対象(両手)が水を熱いと感じ、冷たいと感じるのだから、熱さは水の質で はないと言う。 ロックが一次的性質と二次的性質を区別するためにこの議論を使ったのに対して、バークリーは同じように一次的性質をカバーするためにこの議論を拡張した。 例えば、彼は、物体の大きさは観察者と物体との間の距離、つまり観察者の大きさに依存するので、大きさは物体の質ではないと言う。観察者によって物体の大 きさは異なるのだから、大きさは物体の質ではない。バークリーは同様の論法で形状を否定した上で、次のように問うている:もし一次的な性質も二次的な性質 も物体のものでないのなら、我々が観察する性質以上のものが存在するとどうして言えるのか[clarification needed]。 相対性とは、客観的で普遍的な真理は存在しないという考え方であり、ある独立した対象の存在が、他の対象の存在にのみ依存しているという依存の状態であ る。ロックによれば、一次的性質の特徴は、形や大きさなど、心に依存しないものであるのに対し、二次的性質は、味や色など、心に依存するものである。 ジョージ・バークリーはジョン・ロックの一次的性質と二次的性質に関する信念に反論したが、それはバークリーが「我々は一次的性質(例えば形)を二次的性 質(例えば色)から抽象することはできない」と考えていたからである[34]。 [34]知覚されるものは同じ種類の質であっても、立場や知覚が異なるために全く正反対になることがあり、同じ種類のものが相反する質で構成されていて も、知覚されるものは異なることがある。二次的な性質は、物体の色が人々に物体そのものを認識させるように、人々が物体の一次的な性質を認識するのを助け る。より具体的には、赤という色はリンゴ、イチゴ、トマトで認識される。また、赤い絵の具や、赤色を知覚する物体が存在しなければ、赤色がどのような色な のかもわからないだろう。このことから、色は単独で存在することはできず、知覚される物体のグループを表すだけであることがわかる。したがって、一次的性 質も二次的性質も心に依存している。 ジョージ・バークリーは、合理主義と「古典的」経験主義に反対した哲学者である。彼は「主観的観念論者」または「経験的観念論者」であり、現実はすべて非 物質的で意識的な心とその観念によって構成されていると考えた。彼は、プラトンをはじめとする多くの哲学者が存在すると信じていた抽象的な物体の存在に反 論した。バークリーによれば、「抽象的な物体は空間にも時間にも存在せず、したがって完全に非物理的で非心理的である」[35]が、この議論は彼の相対性 理論と矛盾する。もし 「esse est percipi」[36](存在することは知覚されることであるというラテン語の意味)が真であるならば、バークリーの相対性理論における対象は存在する かしないかのどちらかである。バークリーは、心の知覚と知覚する精神のみが現実に存在するものであり、人々が日々知覚しているものは、物体の存在という観 念に過ぎず、物体そのものは知覚されていないと考えていた。バークリーはまた、物質が自分では知覚できないこともあり、自分の心では対象を理解できないこ ともあると論じた。しかし、「遍在する永遠の心」[37]も存在し、バークリーは全知全能の神と霊からなると考えていた。バークリーによれば、神はすべて を支配する存在であるが、バークリーは「抽象的な対象は空間にも時間にも存在しない」とも主張していた[35]。つまり、ウォーノックが論じているよう に、バークリーは「霊魂、われわれの心、そして神について語ることは、彼自身の話と折り合いがつかないことを認識していた。したがって彼は、われわれは観 念に加えて、観念も持っている-われわれは霊とその作用について語ることの意味を知っている-と、かなり弱々しく、解明もなしに語っている」[38]。 しかし、相対性理論は非物質論の考え方に違反している。バークリーの非物質論は「esse est percipi(aut percipere)」[39]、英語では「あることは知覚されることである(あるいは知覚することである)」と主張している。つまり、知覚されるもの、 認識されるものだけが現実であり、私たちの知覚や神の知覚がなければ、何も現実にはなり得ないということである。しかし、バークリーによる相対性理論が、 物体の知覚は位置によって異なると主張するならば、知覚はその全体像を示しておらず、全体像を知覚することはできないので、知覚されるものは実在するかし ないかのどちらかであるということになる。バークリーはまた、「人が媒介的に知覚するとき、人は別のものを知覚することによ って、ある考えを知覚する」[40]と考えている。これによって、最初に知覚した ものの基準が異なれば、その後に知覚するものも同様に異なりうるというこ とが詳しく説明できる。前述の熱の知覚では、相対性によって、一方の手は水を熱いと知覚し、もう一方の手は水を冷たいと知覚した。あることは知覚されるこ とである」という考えに当てはめれば、両方の知覚が異なる手によって知覚されるため、水は冷たくも熱くもなるはずである。しかし、水は冷たいと熱いと同時 に存在することはできず、自己矛盾に陥る。この場合、「人間が対象の真の性質に特別にアクセスできると主張するのは、恣意的な人間中心主義である」[4] 。まとめると、相対性理論によって絶対的に真理であるものはありえないし、存在するとは知覚されることであるという2つの議論と相対性理論は常に一緒に働 くわけではないということである。 新しい視覚理論 バークリーは『視覚の新理論にむけて』(Essay Towards a New Theory of Vision)の中で、モリニュー、ウォリス、マレブランシュ、デカルトを含むと思われる「光学作家たち」の見解を頻繁に批判している[41]。第1節か ら第51節において、バークリーは次のように主張し、古典的な光学学者たちに反論した。つまり、われわれは空間を直接見たり、光学の法則を使ってその形を 論理的に推論したりはしない。バークリーにとって空間とは、視覚と触覚が規則的な順序で互いに続くという偶発的な期待にすぎず、習慣によって期待するよう になるものなのである。 さらにバークリーは、視覚的な手がかり、たとえば物体の知覚される広がりや「混同」などは、間接的に距離を判断するためにしか使えないと主張する。バーク リーは、間接的な距離知覚に関して次のようなアナロジーを示している。人は、人の恥ずかしさを間接的に知覚するように、距離を間接的に知覚する。恥ずかし がっている人を見るとき、その人の顔の赤い色を観察することで、その人が恥ずかしがっていることを間接的に推測する。私たちは経験を通じて、赤い顔が恥ず かしさを示す傾向があることを知っている。 空間の見え方に関する問題は、ルネサンス期の遠近法の伝統と、空間的奥行きの絵画表現の発展における古典光学への依存にとって中心的なものであった。この 問題は、11世紀のアラブの数学者アルハーゼン(Abū + Alī al-Ḥasan ibn al-Haytham)が実験的な文脈で空間の可視性を肯定して以来、学者たちによって議論されてきた。バークリーの視覚理論で提起されたこの問題は、 モーリス・メルロ=ポンティの『知覚の現象学』において、空間の奥行き(la profondeur)の視覚的知覚を確認するという文脈で、またバークリーのテーゼに反論するという形で、長く扱われた[42]。 バークリーは距離の知覚に加えて大きさの知覚についても書いている。バークリーは、距離の知覚に加えて、大きさの知覚についても書いている。彼はしばし ば、大きさと距離の不変性を信じていると誤って引用される。これは幾何学的な方法で、距離に応じて像の大きさをスケーリングするという考え方である。この 誤りは、著名な歴史家であり心理学者であったE.G.ボーリングが広めたため、一般的になってしまったのかもしれない[43]。実際、バークリーは、距離 を想起させる同じ手がかりがサイズも想起させるのであり、私たちはまずサイズを見てから距離を計算するのではない、と主張していた[44]: 幾何学によって見させるというユーモアのほかに)人をこの過ちに向かわせるものは、距離を示唆する同じ知覚や観念が大きさも示唆するということである。し かし、それらは距離と同じように大きさとも密接で直接的な関係があり、距離と無関係に大きさを示唆するのと同じように、距離と無関係に大きさを示唆するの である。 バークリーは、外科医ウィリアム・チェゼルデンが先天性白内障の手術を行った13歳の少年の視力が回復したという1728年の報告によって、彼の視覚理論 が「正当化」されたと主張した。2021年、チェセルデンの患者の名前が初めて公表された: バークリーはドリンズ家を知っており、詩人のアレクサンダー・ポープや、チェゼルデンの患者が紹介されたキャロライン王女など、チェゼルデンと多くの社会 的つながりがあった[45]。 [45]報告書はチェゼルデンの名前を間違えており、バークリーらしい言葉が使われており、バークリーがゴーストライターを務めた可能性さえある [45]。残念ながら、ドリンズは字を読めるほど視力が回復することはなく、30歳で亡くなる前のどの時点においても、手術によって視力が回復したという 証拠はない[45]。 物理学の哲学 以下も参照: デ・モトゥ(バークリーのエッセイ) 「バークリーの著作は、初期の著作(Arithmetica, 1707)から最新の著作(Siris, 1744)に至るまで、自然哲学への強い関心を示している。さらに、彼の哲学の多くは、同時代の科学との関わりによって基本的に形成されている」 [46]。この関心の深さは、バークリーの『哲学注解』(1707-1708)の数多くの項目から判断することができる。(#316) バークリーは、ニュートンが定義した力と重力は「オカルト的な性質」であり、「はっきりしたものは何も表現していない」と主張した。彼は、「運動の原理と 呼ばれる、何も考えていない物体の中にある未知の何か」を措定する人々は、実際には運動の原理が未知であると述べているに過ぎないとした。したがって、 「活動的な力、作用、運動の原理が本当に物体の中にあると断言する人々は、経験に基づかない意見を採用している」[47]。力と重力は現象世界のどこにも 存在しなかった。一方、もしそれらが「魂」や「無体的なもの」の範疇にあるとすれば、それらは問題として「物理学に正しく属するものではない」。こうして バークリーは、力はあらゆる種類の経験的観測を超えたところにあり、適切な科学の一部にはなり得ないと結論づけた[48]。彼は力と重力の「オカルト的特 質」に言及することなく運動と物質を説明する手段として、記号の理論を提唱した。 バークリーのかみそり バークリーのかみそりは、哲学者のカール・ポパーがバークリーの重要な科学的著作『デ・モトゥ』の研究において提唱した推論のルールである[10]。これ は科学的観察に対する極端な経験主義的見解を表しており、科学的方法は世界の本質に対する真の洞察を私たちに提供しないと述べている。むしろ科学的方法 は、実験を通して得られた、世界に存在する規則性に関する様々な部分的説明を与えてくれる。バークリーによれば、世界の本質には、適切な形而上学的思索と 推論を通じてのみ近づくことができる: 物理学における[バークリーの]分析の一般的な実践的結果-私はこれを「バークリーのかみそり」と呼ぶことを提案する-は、物理科学からすべての本質主義 的説明を先験的に排除することを可能にする。もしそれらが数学的で予測的な内容を持っていれば、数学的仮説として認められるかもしれない(本質主義的な解 釈は排除される)。そうでない場合は、完全に排除することができる。この剃刀はオッカムの剃刀よりも鋭く、知覚されるものを除くすべての実体は除外される [50]。 人間の知識に関する3つの見解」と題された同書の別のエッセイ[51]において、ポパーはバークリーをロベール・ベラルミン、ピエール・デュエム、エルン スト・マッハと並ぶ道具主義哲学者とみなすべきであると論じている。このアプローチによれば、科学理論は、事実を説明することを目的とした有用な発明であ り、真実であることを気取ることのない、役に立つ虚構のようなものである。ポパーは、上記の本質主義や彼自身の「批判的合理主義」と道具主義を対比させ る。 数学の哲学 哲学への貢献に加え、バークリーは数学の発展にも大きな影響を与えた。「バークリーは知的生活の初期段階から数学とその哲学的解釈に関心を寄せていた: 公理。われわれが何も考えていない物事についての推論はできない。したがって、無限小についての推論はできない。(#354) 算術と代数から符号を取り除いたら、何が残るだろうか?(#767) これらは純粋に言葉による学問であり、人の社会で実践する以外にはまったく役に立たない。思弁的な知識もなければ、観念の比較もない。(#768) 1707年、バークリーは数学に関する2つの論文を発表した。1734年には、微積分を批判した『分析家』(A DISCOURSE Addressed to an Infidel Mathematician)を出版した。フロリアン・カジョリはこの論考を「イギリス数学史における今世紀最大の事件」と呼んだ[52]が、最近の研究 によれば、バークリーはライプニッツの微積分を誤解していたようである[53]。問題の数学者はエドモンド・ハレーかアイザック・ニュートン自身であった と考えられているが、もし後者であれば、ニュートンは1727年に亡くなっているので、この論考は死後に書かれたことになる。アナリストは、微積分の基礎 と原理、特に、ニュートンとライプニッツが微積分を発展させるために用いたフラクシオンや無限小変化の概念を直接攻撃した。バークリーはその批判の中で、 微積分を学ぶ学生にはおなじみの「亡き量の亡霊」という言葉を生み出した。イアン・スチュワートの著書『From Here to Infinity』は、彼の批判の要点をとらえている。 バークリーは、微積分に対する批判を、ニュートン力学の宗教的意味合いに対するより広範なキャンペーンの一環、つまり、神を崇拝する者たちから遠ざける傾 向のある神道に対する伝統的キリスト教の擁護の一環と考えていた。具体的には、ニュートン派とライプニッツ派の微積分学がともに無限小数を、あるときは正 の、あるときは0でない量として、またあるときは明確に0に等しい数として用いていることを指摘した。バークリーが『分析者』で重要視したのは、ニュート ンの微積分(および微積分に基づく運動法則)には厳密な理論的基礎が欠けているということだった。彼はこう主張した: 他のすべての科学において、人はその原理によってその結論を証明するのであって、結論によってその原理を証明するのではない。しかし、もしあなた方がこの ような不自然な進め方を認めるとすれば、その結果、あなた方は帰納法を採用し、実証に別れを告げなければならなくなる。そして、もしあなたがこれに服従す るならば、あなたの権威はもはや理性と科学の諸点において道を導くことはなくなるだろう」[54]。 バークリーは微積分が現実の世界の真理を生み出すことを疑っていなかった。簡単な物理学の実験によって、ニュートンの方法が主張したとおりに実行されるこ とを検証することができた。「フラクシオンの原因は理性によって擁護することはできない」[55]が、結果は経験的観察によって擁護することができた。し かしバークリーは、「数学者が誤った原理から真の命題を推論し、結論においては正しく、前提においては誤る」ことを逆説的であると考えた。したがって、 ニュートンの科学は純粋に科学的な根拠に基づいてその結論を正当化することはできず、機械的で神道的な宇宙のモデルは合理的に正当化することはできなかっ た[57]。 バークリーによって提起された困難は、無限小と極限の概念を組み合わせた微積分へのアプローチであったコーシーの研究にもまだ存在しており、最終的には、 無限小を完全に排除した彼の(ε, δ)アプローチによって、ヴァイアーシュトラスによって回避された。最近では、エイブラハム・ロビンソンが1966年に出版した『非標準解析学』におい て、無限小法が厳密に使用できることを示し、無限小法を復活させた。 道徳哲学 も参照のこと: 受動的服従 受動的服従に関する論考』(1712年)は、道徳哲学と政治哲学におけるバークリーの主要な貢献と考えられている。 受動的服従に関する論考』において、バークリーは、人々は「刑罰の執行に抵抗しない義務を含め、法の否定的な戒律(禁止事項)を守る道徳的義務」[58] を負っているというテーゼを擁護している。しかし、バークリーはこの包括的な道徳的声明に例外を設けており、「簒奪者あるいは狂人」[59]の戒律を守る 必要はなく、最高権威を主張する者が複数いる場合には、人々は異なる最高権威に従うことができると述べている。 バークリーは自然法則に由来する演繹的証明によってこのテーゼを擁護している。まず、神は完全な善であるから、神が人間に命じる目的もまた善でなければな らず、その目的は一人の人間だけを利するものではなく、全人類を利するものでなければならないとする。これらの命令(法則)は、実践されれば人類の一般的 な適性につながるので、正しい理性によって発見できることになる。例えば、至高の権力には決して抵抗しないという法則は、この法則が「われわれと完全な無 秩序との間に立つ唯一のもの」[58]であることから、理性から導き出すことができる。「これらの自然の法則には、最高権力に決して抵抗しないこと、宣誓 のもとに嘘をつかないこと、...善がもたらされるように悪を行わないことなどが含まれている」[58]。 受動的服従に関するバークリーの教義は、人類の善を促進するという目的に向かっていると思われる道徳規範を守る義務があると述べている点で、一種の「神学 的功利主義」とみなすことができる。つまり、功利主義は特定の行為が特定の状況において道徳的に許容されるかどうかを問題にしているのに対して、バーク リーの教義はあらゆる状況において道徳的規則に従うべきかどうかを問題にしているのである。行為功利主義が、例えば、特定の状況に照らして、道徳的に許さ れない行為を正当化するかもしれないのに対して、バークリーの受動的服従の教義は、道徳的ルールを破ることが最も幸福な目的を達成できるように思える場合 でも、道徳的ルールに従わないことは決して道徳的に許されないとする。バークリーは、特定の状況における行為の結果が悪いものであっても、その行為の一般 的傾向は人類に利益をもたらすと考える。 バークリーの道徳観に関するその他の重要な典拠は、『アルキフロン』(1732年)、特に第1-3対話と『司政官への談話』(1738年)である。 非物質主義 ジョージ・バークリーの「物質は存在しない」という理論は、「感覚的なものとは、感覚によって直ちに知覚されるものだけである」という信念に由来する [63]。バークリーは『人間知の原理』という著書の中で、「感覚の観念は、想像力の観念よりも強く、生き生きとしており、明瞭である。 すべての知識は知覚から生まれる。私たちが知覚しているのは観念であって、それ自体でモノがあるわけではない。対象について言われる「存在する」とは知覚 されること、「esse est percipi」を意味し、主体について言われる「存在する」とは知覚すること、「percipere」を意味する。 [なぜなら、知覚から独立した存在を持つそのような対象は、知覚可能な特質を持ち、したがって既知でなければならず(それをイデアとする)、また知覚不可 能な実在性をも持たなければならないからである。バークリーはこの概念を抽象的観念と呼んでいる。彼は、人は対象物の感覚的入力を想像することなしに対象 物を想像することはできないと主張することで、この概念に反論している。彼は『人間知の原理』の中で、人が感覚によって物質を感じることができるのは実際 の感覚を通してだけであるのと同様に、人は物質の感覚という観念を通してしか物質(というよりも物質についての観念)を思い浮かべることができないと論じ ている[64]。このことは、人が物質に関して思い浮かべることができるものはすべて物質についての観念でしかないということを意味している。したがっ て、物質が存在するとすれば、それは、感覚によって知覚され、心によって解釈されうる観念の集合体として存在しなければならない。しかし、もし物質が単な る観念の集合体であるならば、バークリーは、バークリーの時代の哲学者の多くが信じていたように、物質的な実体という意味での物質は存在しないと結論づけ る。実際、人が何かを視覚化するのであれば、それがどんなに暗かろうが明るかろうが、何らかの色を持っていなければならない。 バークリーの考えは論争を巻き起こしたが、それは彼の主張がデカルトの哲学を否定するものであったからであり、その哲学はロックによって拡張され、18世 紀の何人かの哲学者によってバークリーの経験論の形式が否定される結果となった。ロックの哲学では、「世界はわれわれの感覚との相互作用の仕方によって、 われわれがそれに対して抱く知覚的な観念を引き起こす」[65]。バークリーの哲学において存在する唯一の原因は、意志の使用の結果である。 バークリーの理論は、彼の経験主義に大きく依存しており、それは感覚に大きく依存している。彼の経験主義は、次の5つの命題によって定義することができ る:重要な言葉はすべて観念を表す;物事に関する知識はすべて観念に関するものである;すべての観念は外から来るか内から来るか;外から来るのであれば、 それは感覚によるものでなければならず、それらは感覚(実在するもの)と呼ばれる;内から来るのであれば、それらは精神の作用であり、思考と呼ばれる。 [68]バークリーは、観念は「感覚に刷り込まれたものである」、「情念や心の働きに注意を向けることによって知覚されたものである」、あるいは「記憶や 想像力の助けによって形成されたものである」[68]と言うことによって、観念の区別を明確にしている。バークリーはこれに対して、その部屋はまだ知覚さ れており、知覚している意識は神であると主張する。(この主張は、「世界についてのわれわれの知識、そして他の心の存在についてのわれわれの知識は、決し てわれわれを欺くことのない神に依存している」[65]という彼の議論を支える唯一のものである。感覚は観念を知覚することしかできないが、これらの観念 は現実に存在する対象物に似ている(したがって、それと比較することができる)。したがって、純粋な物質は知覚不可能であるにもかかわらず、このような観 念を知覚することによって、心は物質そのものについて推論することができる。この考え方に対するバークリーの反論は、「イデアはイデア以外の何ものでもな く、色や形は別の色や形以外の何ものでもない」[64]というものである。バークリーは、心に依存するイデアと、イデアではなく心に依存しない物質とを区 別している。赤という色と目に見えないもの、あるいは音楽の音と静寂を比較することができないように、一方が存在し他方が存在しないということ以外に、両 者は似ていないので比較することはできない。これは類似性の原理と呼ばれるもので、ある観念は他の観念と類似する(つまり比較される)ことしかできないと いう考え方である。 バークリーは、観念がどのようにして異なる知識の対象へと姿を変えるのかを示そうとした: 人間の知識の対象を観察すれば誰にでも明らかなことだが、それらは実際に感覚に刻み込まれた観念であるか、あるいは心の情熱や活動に注意を向けることに よって知覚される観念であるか、あるいは最後に記憶や想像力の助けによって形成された観念である。(バークリーの強調)[69]。 バークリーはまた、非物質主義の信念を通して神の存在を証明しようとした[4]。 |
| Influence Berkeley's Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge was published three years before the publication of Arthur Collier's Clavis Universalis, which made assertions similar to those of Berkeley's.[70] However, there seemed to have been no influence or communication between the two writers.[71] German philosopher Arthur Schopenhauer once wrote of him: "Berkeley was, therefore, the first to treat the subjective starting-point really seriously and to demonstrate irrefutably its absolute necessity. He is the father of idealism...".[72] Berkeley is considered one of the originators of British empiricism.[73] A linear development is often traced from three great "British Empiricists", leading from Locke through Berkeley to Hume.[74] Berkeley influenced many modern philosophers, especially David Hume. Thomas Reid admitted that he put forward a drastic criticism of Berkeleianism after he had been an admirer of Berkeley's philosophical system for a long time.[75] Berkeley's "thought made possible the work of Hume and thus Kant, notes Alfred North Whitehead".[76] Some authors[who?] draw a parallel between Berkeley and Edmund Husserl.[clarification needed][77] When Berkeley visited America, the American educator Samuel Johnson visited him, and the two later corresponded. Johnson convinced Berkeley to establish a scholarship program at Yale and to donate a large number of books, as well as his plantation, to the college when the philosopher returned to England. It was one of Yale's largest and most important donations; it doubled its library holdings, improved the college's financial position and brought Anglican religious ideas and English culture into New England.[78] Johnson also took Berkeley's philosophy and used parts of it as a framework for his own American Practical Idealism school of philosophy. As Johnson's philosophy was taught to about half the graduates of American colleges between 1743 and 1776,[79] and over half of the contributors to the Declaration of Independence were connected to it,[80] Berkeley's ideas were indirectly a foundation of the American Mind. Outside of America, during Berkeley's lifetime, his philosophical ideas were comparatively uninfluential.[81] But interest in his doctrine grew from the 1870s when Alexander Campbell Fraser, "the leading Berkeley scholar of the nineteenth century",[82] published The Works of George Berkeley. A powerful impulse to serious studies in Berkeley's philosophy was given by A. A. Luce and Thomas Edmund Jessop, "two of the twentieth century's foremost Berkeley scholars",[83] thanks to whom Berkeley scholarship was raised to the rank of a special area of historico-philosophical science. In addition, the philosopher Colin Murray Turbayne wrote extensively on Berkeley's use of language as a model for visual, physiological, natural and metaphysical relationships.[84][85][86][87] The proportion of Berkeley scholarship, in literature on the history of philosophy, is increasing. This can be judged from the most comprehensive bibliographies on George Berkeley. During the period of 1709–1932, about 300 writings on Berkeley were published. That amounted to 1.5 publications per year. During the course of 1932–1979, over one thousand works were brought out, i.e., 20 works per year. Since then, the number of publications has reached 30 per annum.[88] In 1977 publication began in Ireland of a special journal on Berkeley's life and thought (Berkeley Studies). In 1988, the Australian philosopher Colin Murray Turbayne established the International Berkeley Essay Prize Competition at the University of Rochester in an effort to advance scholarship and research on the works of Berkeley.[89][90] Other than philosophy, Berkeley also influenced modern psychology with his work on John Locke's theory of association and how it could be used to explain how humans gain knowledge in the physical world. He also used the theory to explain perception, stating that all qualities were, as Locke would call them, "secondary qualities", therefore perception laid entirely in the perceiver and not in the object. These are both topics today studied in modern psychology.[91] |
影響力 バークリーの『人智の原理に関する論考』は、バークリーと同様の主張を行ったアーサー・コリアーの『クラヴィス・ユニヴァーサリス』が出版される3年前に 出版された[70]。しかし、2人の作家の間に影響や交流はなかったようである[71]。 ドイツの哲学者アーサー・ショーペンハウアーはかつて彼についてこう書いている: 「それゆえ、バークリーは主観的出発点を真に真剣に扱い、その絶対的必然性を反論の余地なく証明した最初の人物である。彼は観念論の父である」[72]。 バークリーはイギリス経験論の創始者の一人とみなされている[73]。ロックからバークリーを経てヒュームへとつながる3人の偉大な「イギリス経験論者」 から直線的な発展がたどることが多い[74]。 バークリーは多くの近代哲学者、特にデイヴィッド・ヒュームに影響を与えた。トーマス・リードは、バークリーの哲学体系を長い間賞賛していた後に、バーク リー主義に対する思い切った批判を展開したことを認めている[75]。バークリーの「思想がヒューム、ひいてはカントの仕事を可能にした」とアルフレッ ド・ノース・ホワイトヘッドは指摘している[76]。バークリーとエドムント・フッサールの間に並列関係を描く著者[誰? バークリーがアメリカを訪れたとき、アメリカの教育者であるサミュエル・ジョンソンがバークリーを訪れ、2人は後に文通をするようになった。ジョンソン は、バークリーにイェール大学に奨学金制度を設けるよう説得し、哲学者がイギリスに帰国した際には、大量の書籍と彼の農園を大学に寄贈した。これはイェー ル大学にとって最大かつ最も重要な寄付のひとつであり、図書館の蔵書数を倍増させ、大学の財政状態を改善し、英国国教会の宗教思想とイギリス文化をニュー イングランドにもたらした[78]。ジョンソンはまた、バークリーの哲学を取り入れ、その一部を自身のアメリカ実践的観念論学派の哲学の枠組みとして用い た。ジョンソンの哲学は1743年から1776年にかけてアメリカの大学の卒業生の約半数に教えられており[79]、独立宣言の寄稿者の半数以上がこの哲 学に関係していたことから[80]、バークリーの思想は間接的にアメリカン・マインドの基礎となっていた。 しかし、1870年代に「19世紀を代表するバークリー研究者」[82]であるアレクサンダー・キャンベル・フレイザーが『ジョージ・バークリー著作集』 を出版すると、彼の学説に対する関心が高まった。20世紀を代表するバークリー研究者」[83]であるA.A.ルースとトーマス・エドモンド・ジェソップ によって、バークリー哲学の本格的な研究への強力な推進力が与えられ、彼らのおかげでバークリー研究は歴史哲学科学の特別な分野へと格上げされた。加え て、哲学者コリン・マレー・ターベインは、視覚的、生理学的、自然学的、形而上学的関係のモデルとしてのバークリーの言語の使用について幅広く執筆してい る[84][85][86][87]。 哲学史に関する文献の中で、バークリー研究の割合は増加しつつある。このことは、ジョージ・バークリーに関する最も包括的な書誌から判断することができ る。1709年から1932年の間に、バークリーに関する約300の著作が出版された。これは1年に1.5冊の出版物に相当する。1932年から1979 年にかけては、1,000以上の著作が出版された。1977年、アイルランドでバークリーの生涯と思想に関する専門誌『バークリー・スタディーズ』 (Berkeley Studies)が創刊された。1988年、オーストラリアの哲学者コリン・マレー・ターベインは、バークリーの著作に関する学問と研究を促進するため に、ロチェスター大学において国際バークリー論文賞コンテストを設立した[89][90]。 哲学以外の分野では、バークリーはジョン・ロックの連合論と、それが物理的世界において人間がどのように知識を得るかを説明するためにどのように利用でき るかを研究し、近代心理学にも影響を与えた。彼はまた、この理論を使って知覚を説明し、ロックが言うように、すべての性質は「二次的性質」であり、した がって知覚は対象ではなく、完全に知覚者にあると述べた。これらはいずれも、今日、現代の心理学で研究されているテーマである[91]。 |
| Appearances in literature Lord Byron's Don Juan references immaterialism in the Eleventh Canto: When Bishop Berkeley said 'there was no matter,' And proved it—'t was no matter what he said: They say his system 't is in vain to batter, Too subtle for the airiest human head; And yet who can believe it? I would shatter Gladly all matters down to stone or lead, Or adamant, to find the world a spirit, And wear my head, denying that I wear it. Herman Melville humorously references Berkeley in Chapter 20 of Mardi (1849), when outlining a character's belief of being on board a ghostship: And here be it said, that for all his superstitious misgivings about the brigantine; his imputing to her something equivalent to a purely phantom-like nature, honest Jarl was nevertheless exceedingly downright and practical in all hints and proceedings concerning her. Wherein, he resembled my Right Reverend friend, Bishop Berkeley–truly, one of your lords spiritual—who, metaphysically speaking, holding all objects to be mere optical delusions, was, notwithstanding, extremely matter-of-fact in all matters touching matter itself. Besides being pervious to the points of pins, and possessing a palate capable of appreciating plum-puddings:—which sentence reads off like a pattering of hailstones. James Joyce references Berkeley's philosophy in the third episode of Ulysses (1922): Who watches me here? Who ever anywhere will read these written words? Signs on a white field. Somewhere to someone in your flutiest voice. The good bishop of Cloyne took the veil of the temple out of his shovel hat: veil of space with coloured emblems hatched on its field. Hold hard. Coloured on a flat: yes, that's right. Flat I see, then think distance, near, far, flat I see, east, back. Ah, see now! In commenting on a review of Ada or Ardor, author Vladimir Nabokov alludes to Berkeley's philosophy as informing his novel: And finally I owe no debt whatsoever (as Mr. Leonard seems to think) to the famous Argentine essayist and his rather confused compilation "A New Refutation of Time." Mr. Leonard would have lost less of it had he gone straight to Berkeley and Bergson. (Strong Opinions, pp. 2892–90) James Boswell, in the part of his Life of Samuel Johnson covering the year 1763, recorded Johnson's opinion of one aspect of Berkeley's philosophy: After we came out of the church, we stood talking for some time together of Bishop Berkeley's ingenious sophistry to prove the non-existence of matter, and that every thing in the universe is merely ideal. I observed, that though we are satisfied his doctrine is untrue, it is impossible to refute it. I shall never forget the alacrity with which Johnson answered, striking his foot with mighty force against a large stone, till he rebounded from it,– "I refute it thus." |
文学への登場 バイロン卿の『ドン・ファン』は第11カントで非物質論に言及している: バークリー大司教が『物質は存在しない』と言った。 そしてそれを証明した-彼が何を言ったかは問題ではない: バークリー司教が『物質は存在しない』と言い、それを証明した、 最も風通しのよい人間の頭には、あまりに微妙すぎる; しかし、誰がそれを信じることができようか?私なら砕くだろう。 私なら喜んで、すべての問題を石や鉛に砕くだろう、 あるいは堅固に砕き、世界に霊魂を見出そう、 そして私の頭をかぶり、私がそれをかぶることを否定する。 ハーマン・メルヴィルは、『マルディ』(1849年)の第20章で、幽霊船に乗っているという登場人物の信念を概説する際に、バークリーをユーモラスに引 用している: そして、このブリガンチンについて迷信的な不安を抱き、そのブリガンチンを純粋に幻のようなものだと決めつけたが、正直なジャールは、それにもかかわら ず、ブリガンチンに関するすべての示唆と手続きにおいて、きわめて率直で実際的であった。形而上学的に言えば、すべての物体は単なる光学的錯覚に過ぎない としながらも、物質そのものに関わるすべての事柄に関しては、極めて現実的であった。そのうえ、ピンの先まで見通すことができ、プラムプディングを味わう ことのできる味覚を持っている。 ジェイムズ・ジョイスは『ユリシーズ』(1922年)の第3話でバークリーの哲学に言及している: 誰がここで私を見ているのだろう。この書かれた言葉を誰がどこかで読むのだろう?白い野原に書かれた標識だ。どこかの誰かへ、あなたの最も流麗な声で。ク ロインの善良な司教は、シャベルハットから寺院のベールを取り出した。強く握って。そう、その通りだ。平らに見える、そして距離を考える、近く、遠く、平 らに見える、東、後ろ。ああ、わかった! 作家ウラジーミル・ナボコフは、『エイダあるいは熱情』の書評に対するコメントの中で、バークリーの哲学が彼の小説に影響を与えたと言及している: そして最後に、私は(レナード氏が考えているような)有名なアルゼンチンのエッセイストと、彼のかなり混乱した編纂物である 「A New Refutation of Time 」に何の借りもない。レナード氏は、バークリーとベルクソンに直行した方が、その損失は少なかっただろう。(強い意見』2892-90頁)。 ジェームズ・ボズウェルは、『サミュエル・ジョンソンの生涯』の1763年の部分に、バークリー哲学の一面についてのジョンソンの意見を記している: 教会から出てきてから、私たちはしばらくの間、バークリー大司教が物質の非存在を証明する巧妙な詭弁を弄し、宇宙のあらゆるものは理想的なものに過ぎない という話をした。私は、彼の教義が真実でないことは確かだが、それに反論することは不可能だと述べた。私は、ジョンソンが大きな石に足を勢いよく打ちつ け、そこから跳ね返されるまで、「私はこう反論する」と答えたときの快活さを忘れることができない。 |
| Commemoration Both the University of California, Berkeley, and the city of Berkeley, California, were named after him, although the pronunciation has evolved to suit American English: (/ˈbɜːrkli/ BURK-lee). The naming was suggested in 1866 by Frederick H. Billings, a trustee of what was then called the College of California. Billings was inspired by Berkeley's Verses on the Prospect of Planting Arts and Learning in America, particularly the final stanza: "Westward the course of empire takes its way; the first four Acts already past, a fifth shall close the Drama with the day; time's noblest offspring is the last".[92] The Town of Berkley, currently the least populated town in Bristol County, Massachusetts, was founded on 18 April 1735 and named for George Berkeley. A residential college and an Episcopal seminary at Yale University also bear Berkeley's name. "Bishop Berkeley's Gold Medals" were two awards given annually at Trinity College Dublin, "provided outstanding merit is shown", to candidates answering a special examination in Greek. The awards were founded in 1752 by Berkeley.[93] However, they have not been awarded since 2011.[94] Other elements of Berkeley's legacy at Trinity are currently under review (As of 2023) due to his support of slavery. For example, the library at Trinity that was named after him in 1978 is to be "de-named", Trinity announced in April 2023. Another memorialization of him in the form of a stained glass window will remain, but used as part of "a retain-and-explain approach" where his legacy will be given further context.[94][95] An Ulster History Circle blue plaque commemorating him is located in Bishop Street Within, the city of Derry. Berkeley's farmhouse in Middletown, Rhode Island, is preserved as Whitehall Museum House, also known as Berkeley House, and was listed on the National Register of Historic Places in 1970. St. Columba's Chapel, located in the same town, was formerly named "The Berkeley Memorial Chapel", and the appellation still survives at the end of the formal name of the parish, "St. Columba's, the Berkeley Memorial Chapel". |
記念 カリフォルニア大学バークレー(バークリー)校とカリフォルニア州バークレー市は、彼の名にちなんで命名された。この名前は、1866年に当時カリフォル ニア大学と 呼ばれていた大学の理事であったフレデリック・H・ビリングスによって提案された。ビリングスは、バークリーの『アメリカに芸術と学問を植える展望につい ての詩』、特に最後の一節に感銘を受けた: 「帝国の航路は西へ向かう。最初の4つの行為はすでに過ぎ去り、5番目の行為がその日のうちにドラマを締めくくるだろう。 現在マサチューセッツ州ブリストル郡で最も人口の少ないバークリー町は、1735年4月18日にジョージ・バークリーにちなんで設立された。 エール大学の全寮制大学とエピスコパル神学校にもバークリーの名が冠されている。 「バークリー司教の金メダル」は、トリニティ・カレッジ・ダブリンで毎年、ギリシャ語の特別試験に合格した受験生に「傑出した成績が示された場合」に与え られる2つの賞である。この賞は1752年にバークリーによって創設された[93]が、2011年以降は授与されていない[94]。トリニティにおける バークリーの遺産の他の要素については、彼の奴隷制支持のため、現在(2023年現在)見直しが行われている。例えば、1978年に彼の名を冠したトリニ ティの図書館は、2023年4月に「名称変更」されることが発表された。ステンドグラスの窓という形で彼を記念する別のものは残るが、彼の遺産にさらなる 文脈を与える「保持と説明のアプローチ」の一部として使用される[94][95]。 バークリーを記念するアルスター・ヒストリー・サークルの青いプレートは、デリー市のビショップ・ストリート・ウィズインにある。 ロードアイランド州ミドルタウンにあるバークリーの農家は、バークリー・ハウスとしても知られるホワイトホール・ミュージアム・ハウスとして保存されてお り、1970年に国民歴史登録財に登録された。同町にある聖コロンバ礼拝堂は、以前は「バークリー記念礼拝堂」と名付けられ、現在も小教区の正式名称「聖 コロンバ、バークリー記念礼拝堂」の末尾にこの名称が残っている。 |
| Writings Original publications Arithmetica (1707) Miscellanea Mathematica (1707) Philosophical Commentaries or Common-Place Book (1707–08, notebooks) An Essay Towards a New Theory of Vision (1709) A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, Part I (1710) Passive Obedience, or the Christian doctrine of not resisting the Supreme Power (1712) Three Dialogues Between Hylas and Philonous (1713) An Essay Towards Preventing the Ruin of Great Britain (1721) De Motu (1721) A Proposal for Better Supplying Churches in our Foreign Plantations, and for converting the Savage Americans to Christianity by a College to be erected in the Summer Islands (1725) A Sermon preached before the incorporated Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts (1732) Alciphron, or the Minute Philosopher (1732) Essays toward a new theory of vision (in Italian). Venezia: Francesco Storti (2.). 1732. The Theory of Vision, or Visual Language, shewing the immediate presence and providence of a Deity, vindicated and explained (1733) The Analyst: A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician (1734) A Defence of Free-thinking in Mathematics, with Appendix concerning Mr. Walton's vindication of Sir Isaac Newton's Principle of Fluxions (1735) Reasons for not replying to Mr. Walton's Full Answer (1735) The Querist, containing several queries proposed to the consideration of the public (three parts, 1735–37). A Discourse addressed to Magistrates and Men of Authority (1736) Siris, a chain of philosophical reflections and inquiries, concerning the virtues of tar-water (1744). A Letter to the Roman Catholics of the Diocese of Cloyne (1745) A Word to the Wise, or an exhortation to the Roman Catholic clergy of Ireland (1749) Maxims concerning Patriotism (1750) Farther Thoughts on Tar-water (1752) Miscellany (1752) Collections The Works of George Berkeley, D.D. Late Bishop of Cloyne in Ireland. To which is added, an account of his life, and several of his letters to Thomas Prior, Esq. Dean Gervais, and Mr. Pope, &c. &c. Printed for George Robinson, Pater Noster Row, 1784. Two volumes. The Works of George Berkeley, D.D., formerly Bishop of Cloyne: Including Many of His Writings Hitherto Unpublished; With Prefaces, Annotations, His Life and Letters, and an Account of His Philosophy. Ed. by Alexander Campbell Fraser. In 4 Volumes. Oxford: Clarendon Press, 1901. Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Vol. 4 The Works of George Berkeley. Ed. by A. A. Luce and T. E. Jessop. Nine volumes. Edinburgh and London, 1948–1957. Ewald, William B., ed., 1996. From Kant to Hilbert: A Source Book in the Foundations of Mathematics, 2 vols. Oxford Uni. Press. 1707. Of Infinites, 16–19. 1709. Letter to Samuel Molyneaux, 19–21. 1721. De Motu, 37–54. 1734. The Analyst, 60–92. |
著作 オリジナル出版物 算術書 (1707) 数学雑学(1707年) 哲学的注釈書または通俗書 (1707-08, ノート) 新しい視覚理論への試論 (1709) 人間の知識の原理に関する論考 第一部 (1710) 受動的服従、あるいは最高権力に抵抗しないというキリスト教の教義 (1712) ハイラスとフィロノスの3つの対話 (1713) イギリスの破滅を防ぐための試論(1721年) デ・モトゥ(1721年) わが外国の農園に教会をよりよく供給し、夏の島に建てる大学によって野蛮なアメリカ人をキリスト教に改宗させるための提案 (1725) 外国における福音宣教のための社団法人で説教する (1732) アルシフロン、あるいは細々とした哲学者(1732年) 新しい視覚理論に向けた試論(イタリア語) Venezia: フランチェスコ・ストルティ (2.). 1732. 視覚の理論、あるいは視覚言語、神の即時的存在と摂理を証明し説明する (1733) 分析家 異教徒の数学者に宛てた講話 (1734) 数学における自由思想の擁護、アイザック・ニュートンの流転の原理に対するウォルトン氏の擁護に関する付録付き (1735) ウォルトン氏の全答弁に答えない理由 (1735) クエリスト、一般大衆に提案されたいくつかの質問を含む(3部、1735-37年)。 判事と権力者に宛てた講話(1736年) シリス、タール水の美徳に関する哲学的考察と探求の連鎖(1744年) クロイン教区のローマ・カトリック教徒への手紙(1745年) 賢者への言葉、またはアイルランドのローマ・カトリック聖職者への勧告(1749年) 愛国心に関する心得(1750年) タール水についての更なる考察(1752年) 雑文(1752年) コレクション アイルランドのクロイン司教であったジョージ・バークリー博士の著作。この本には、ジョージ・バークリーの生涯と、トーマス・プライヤー、ジェルヴェイス 学長、ミスター・デル・デル・デル・デル・デル・デルに宛てた手紙の一部が加えられている。また、彼の生涯と、トーマス・プライヤー、ジャーヴェイス学 長、ポープに宛てた書簡の数々も掲載されている。1784年、ペイター・ノスター・ロウ、ジョージ・ロビンソンのために印刷された。全2巻。 元クロイン司教ジョージ・バークリー著作集:これまで未刊の著作の多くを含む;序文、注釈、彼の生涯と書簡、彼の哲学の説明を付す。アレクサンダー・キャ ンベル・フレイザー編。全4巻。オックスフォード: Clarendon Press, 1901. 第1巻 第2巻 第3巻 第4巻 ジョージ・バークリー著作集 A.A.ルース、T.E.ジェソップ編。全9巻。Edinburgh and London, 1948-1957. Ewald, William B., ed., 1996. カントからヒルベルトへ:数学の基礎におけるソースブック』2巻。オックスフォード大学出版局。Press. 1707. Infinites, 16-19. 1709. サミュエル・モリノーへの手紙, 19-21. 1721. デ・モトゥ、37-54 1734. 分析家、60-92 |
| List of people on the postage
stamps of Ireland Solipsism "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" Yogacara and consciousness-only schools of thought |
アイルランドの切手に描かれた人物のリスト 独我論 「トロン、ウクバール、オルビス・テルティウス」 ヨガカラと意識だけの学派 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/George_Berkeley |
|
| ジョー
ジ・バークリー(George Berkeley、1685年3月12日 -
1753年1月14日)は、アイルランドの哲学者、聖職者である。主著は『人知原理論』。バークレー、バークリとも。 生涯 1685年3月12日 - キルケニーに生まれる。父ウィリアムは軍人。 1696年 - キルケニー大学入学。 1707年 - ダブリンのトリニティ・カレッジで修士号取得。フェローとして大学に残る。 1709年 - 『視覚新論』刊行。 1710年 - 『人知原理論』刊行。 1713年 - 『ハイラスとフィロナスの対話』刊行。 1721年 - トリニティ・カレッジで神学博士号取得。 1728-32年 - 結婚直後、アメリカ新大陸に神学校を作るべくロードアイランドのミドルタウンに移住するが資金が充分集まらず帰国。 1734年 - アイルランド国教会の主教に叙任される。 1753年1月14日 - 逝去。 思想 「存在することは知覚されることである」(羅: Esse percipi est、英: To be is to be perceived )という基本原則を提唱したとされている。 バークリーは、ジョン・ロックの経験論を承継し、知覚によって得られる観念の結合・一致・不一致・背反の知覚が知識であり、全ての観念と知識は人間が経験 を通じて形成するものだとした。バークリーの著書『ハイラスとフィロナスとの三つの対話』は、素朴実在論的な考え方をするハイラスにバークリーの代弁者で あるフィロナスが反論する対話篇の形をとっている。素朴実在論によれば、わたしが知覚するものは存在する。わたしの心とわたしの体も存在する。わたしが知 覚している目の前の机も世界も存在している。しかし、バークリーによれば、世界は観念であり、たとえば私が目の前の机を叩いてその硬さを認識したとして も、「机の固さ」としてではなく、「知覚として」認識しているわけであり、「机自体」を認識していることにはならない。このような彼の考え方は、主観的観 念論、独我論と批判された。このような批判を受けた彼は『視覚新論』をまず発表して人々をある程度彼の考えに慣らし、続いて彼が本当に言いたかった『人知 原理論』を発表するという手順をとった。わたしの心は一つであり、分割することはできず、これ以上延長することもできず、形もない。ゆえに私の心は不滅で あり、これは実体である。わたしの目の前の机もわたしの身体も世界すらもわたしが知覚する限りにおいて「わたしの心の中に存在する」のであって、事物は観 念の束である[1]。彼は物質を否定し、感覚的な観念の原因は神であるとして、知覚する精神と神のみを実体と認めた。彼は聖職者であり、宗教的見地から魂 の不滅と神の存在を結びつける必要があった。また、彼は物質を実体であると認めることは唯物論的無神論に結びつくと考えたのである。 バークリーは抽象観念の存在を否定する[2]。抽象観念とは、具体的な観念、例えば目の前の机やパソコンから抽出された机一般の観念やパソコン一般の観念 である。このような抽象観念の起源はプラトンにまで遡るが、その存在を肯定する立場(イデア論など)と否定する立場(唯名論など)とに分かれる。 またニュートンの流率法(微積分学)を厳密な数学ではないとしてしりぞけた。 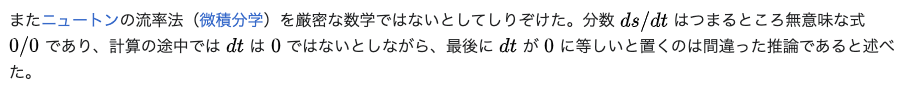 カリフォルニア大学バークレー校の所在地、カリフォルニア州バークレー市はジョージ・バークリーにちなんだものである。 著作 Philosophical Commentaries (1707–08)(『哲学的評注』)(バークリの研究ノート) 『哲学』10号(哲学書房、1990)に抄訳あり(一ノ瀬正樹訳) An Essay towards a New Theory of Vision (1709) 下條信輔・植村恒一郎・一ノ瀬正樹訳『視覚新論』(勁草書房、1990) A Treatise Concerning Principles of Human Knowledge (1710) 大槻春彦訳『人知原理論』(岩波文庫、1958) 宮武昭訳『人知原理論』(ちくま学芸文庫、2018) Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713) 名越悦・名越諭訳『ハイラスとフィロナスとの三つの対話』(薩摩書館) 戸田剛文訳『ハイラスとフィロナスの三つの対話』(岩波文庫、2008) De Motu(英:On Motion)(1721)(『運動論』) Alciphron: or the Minute Philosopher (1732)(『アルシフロン あるいは小粒な哲学者』) The Theory of Vision or Visual Language ... Vindicated and Explained (1733) 『視覚論弁明』、上述『視覚新論』所収 The Analyst (1734)(『アナリスト』) The Querist (1735–37) 川村大膳・肥前栄一訳『問いただす人』(東京大学出版会) Siris (1744)(『サイリス』) |
|
| https://x.gd/BOSUR |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆