軍事的インテリジェンスの人類学の射程と倫理
池田光穂(pdfプリント版はこ ちら)Ethical Implication of Doing Anthropology of Military Intelligence


軍事的インテリジェンスの人類学の射程と倫理
池田光穂(pdfプリント版はこ ちら)Ethical Implication of Doing Anthropology of Military Intelligence


| Abstruct
in English, Ethical Implication of Doing
Anthropology of Military Intelligence 1.軍事的インテリジェンスの人類学 2.戦争と軍事的インテリジェンスと人類学(学知)の関係 3.軍事的インテリジェンスの人類学に文化概念は必要か? 4.《戦争と軍事的インテリジェンスの人類学》の立場について 5.2つのレッスン 6.結論にかえて 謝辞 註 文献 |
00. Ethical Implication of Doing Anthropology of Military Intelligence
The word and concept of military intelligence (MI), has appeared from the end of the World War II even though actual operations of military intelligence among both the Allies and the Axis had started from end of 1920s. In this paper the author challenges to establish theoretical framework of the relations between military intelligence and ethnological knowledge in not only the time of those days but the present time. For clearing our mind set on "collaborations" between war operations and ethnological knowledge, the author classified three types of collaboration; (i) Positive collaboration, (ii) Oxymoronic coloration or Contradictive collaboration, and (iii) Neutral or Value-free collaboration. In the last section of this paper for scrutinizing in future research, the author indicated and exemplified two research subjects, the Operation Paperclip that U.S military had recruited ex-Nazi scientists for developing of post-war military sciences and the ODESSA connection of the ex-Nazi war criminals transferring to New World continent. To avert epistemological confusion between amoral intelligent facts and our moral disturbance of confronting with warfare atrocities, we need urgent establishment of academic arena where scientists can talk on anthropology of MI from the perspective of the Ethical, Legal, and Social Implications (ELSI).
keywords: military,
intelligence, military science, research ethics, Ethical Legal Social
Implications (ELSI)
キーワード:軍事、インテリジェンス(諜報)、軍事科学、研究倫理、ELSI
Is there not an appointed time to man upon earth? are not his days also like the days of an hireling?/ As a servant earnestly desireth the shadow, and as an hireling looketh for the reward of his work:. The Book of Job, 7:1-2. / 「この地上に生きる人間は兵役にあるようなもの。/ 傭兵のように日々をおくらなければならない。/奴隷のように日を暮れるのを待ち焦がれ/傭兵のように報酬を待ち望む」(ヨブ記 7:1-3)
謝辞:この研究は、日本学術振興会(19H04363)
より支援をうけたものです。ここで述べられていることは、池田個人のものであり、研究代表者や日本学術振興会・文部科学省などいかなる団体の意見でもあり
ません。
+++
01.軍事的インテリジェンス(Military Intelligence and counterintelligence) の人類学
軍事的インテリジェンス(military intelligence, MI)とは、軍事と諜報(インテリジェンス)を合成した言葉である。軍事と諜報というテーマは第二次世界大戦までは西洋軍事理論では正面切って論じられる ことはなかった。1811年のアントワーヌ=アンリ・ジョミニ『戦争概論(Traité des grandes opérations militaires)』 やクラウゼヴィッツ没後出版の1832年『戦争論(Vom Kriege)』には、諜報ないしは諜報作戦に関する具体的記述はない。さらに時代が下ってスウェーデンの政治学者でかつ「地政学 (geopolitics)」の考案者であるルドルフ・チェーレン(1917)の著作にいたっては地球レベルの空間分割の政治学の中に諜報(情報)がどの ように占めるのかについては示されていない(Mattern 1942:96) 。さすがに『孫子』においては「知彼知己、百戰不殆」とあることは誰でも知っているが、現代戦術論の標語以上の意味はない。結論を先に言おう。軍事とイン テリジェンスの結びつき(=軍事的インテリジェンス)は大戦間期の1920年代から1930年代に形成され、第二次大戦を戦った総力戦の当事国間でその重 要性が認識された。そして、実際に軍事理論のひとつとして軍事的インテリジェンスが地歩を占めるのは、戦勝国であった英国、米国、そしてソビエト連邦(ソ 連)であり、具体的には、敵側の戦争犯罪者の追求や軍事機密の入手、さらには敗戦国の元軍人や科学者などの「人的資源」の捕縛や獲得の過程の中で、それぞ れの国において諜報機関(MI-6, OSS 後のCIA, NKGB 後のKGB)から、軍事参謀に提供されるといった、それ自身で諜報戦争を継続するためのツールであった 。軍事的インテリジェンスが今日のように重要視され、かつ洗練されるようになるのは冷戦期である。1990年代中期から後半の冷戦構造の崩壊は、そのよう な軍事的インテリジェンスの戦略的意義が失いかけたことがある。つまり諜報のない平和の時代の光が差しかけたが、その次に到来するイスラム原理主義の台頭 や「テロとの戦争」、さらにはロシアによる米国大統領選挙介入、中国や北朝鮮あるいはイランによるサイバー戦争の問題化が、再度軍事的インテリジェンスの 概念に命を吹き込んだ。いやむしろ、拷問を含む査問などの非合法・超法規的手法が復活したのがこの時期である 。この状況は21世紀の四半世紀を迎えようとする現在でも続いている。
本稿は、過去1世紀にわたる、軍事的インテリジェ
ンスを歴史的に解明する一助として、文化人類学(民族学)の学知が軍事的インテリジェンスとどのように関わったのかを明らかにする研究の一環である。これ
は私が研究分担者として関わっている科学研究費補助金・基盤研究(B)「ファシズム期における日独伊のナショナリズムとインテリジェンスに関する人類学
史」(課題番号
19H04363)(研究代表者:中生勝美)の一環である。すなわち、戦間期の日本、ドイツ、イタリアにおける軍事的インテリジェンスの有無、制度、開発
のタイプ、諜報と軍事行動の関係、そして、作戦遂行の共通点と相違点を明らかにすることである。研究代表者の中生氏は、エドワード・サイード(1993)
とジェームズ・クリフォード(2003)の諸論をもとに人類学調査そのものが植民地統治の産物であり、それは植民地支配を強化するとともに植民地主義を批
判できる力を持ち得ると主張している(中生
2016:15-16)。それらの所論を整理しつつ本稿では、予備的な作業として、戦争と軍事的インテリジェンスと民族学・人類学という学知——以下「人
類学(学知)」と表現する——の協働関係についての立場とそれに対する倫理態度が生まれる理論的枠組みについて整理する。
これらの学的諸関係を理解する以前に、「戦争や軍 事的インテリジェンスを人類学史に位置づける」ことについて、私自身は次のことを明確にすべきだと思う。つまり「戦争」と「軍事的インテリジェンス」と 「人類学(学知)」の三者の倫理的-法的-社会的連累(ELSI, 後述)の位相関係はいったいどのようなものか、という設問だ 。その見取り図を仮設的に示しておこう。またそれは、日本の人文社会科学者における、ある種の「戦争嫌悪」や「反戦信条」という立場——私もどちらかと言 えばその立場を取る——と、どう折り合いをつけるのかという試みでもある。もちろん戦争遂行と学知の結びつきを肯定する立場も存在する。あるいは、あらゆ る政治的「意図」が入らない「純粋な学知」にのみ我々は関わるべきだという厳格派もいる。私は、それらの間の「対話のない共存」こそが問題であり、このま までは人類学(学知)を軍事的インテリジェンスに誘う社会環境を無自覚なまま引き起こす可能性があることを危惧している。


■1942年12月、ドイツ陸軍上級大将(第21軍
司令官ニコラウス・フォン・ファルケンホルスト、左端)以下、独陸海空軍の
将校らと写る小野寺信(中央)※ファルケンホルストの戦後の戦犯助命嘆願に探検家ヘディンが動いたとのこと。日本陸軍のソ連作戦の防諜のことをしらべてい
て、小野寺信との写真があるので、ここに到達する。小野寺はその後SD国外諜報局長であるヴァルター・シェレンベルクとも交流する。[右はMittelbau-Dora
concentration camp 近郊にあるKohnsteinの丘の洞窟内でV-2生
産に従事させられていたユダヤ人とロケット(1943年9月以降)]
この状況に対して「対話のある共存」をまずは引き出そうというのが私の立場である。ここで3つのエートス(=集合的な倫理道徳観)を示しておこう。各研
究者は、この立場を自覚化し、それぞれの研究の立場を相対的に比較考量しないかぎり、次のような「政治的混乱」の議論に巻き込まれることになる。すなわ
ち、東アジアの安全保障体制のダイナミズムをめぐるきな臭い議論、ネオリベラリズムが袋小路に入ったかのような全世界的な政治ポピュリズムの台頭、そし
て、日本の防衛装備庁が比較的多額の研究費を大学ならびに民間企業に配分していることをめぐる論争や議論などである。この状況の中で自分たちの立場と思念
の関係をクリアに自覚しないと、倫理的な批判と反論の堂々巡りがおこり、生産的な議論に向かわないだろう。
ここではそれらを回避するための予備的考察である。まず(α)戦争と軍事的インテリジェンスと学知の三者の協力は必然である、(β)かつて必然であった
からこそ分離ないし離脱すべき、(γ)前二者からの価値判断から自由になり、より仔細に中立的に検討すべき、の三分類の(派閥の)グループにわける。それ
らのグループの成員が持ち得るエートスの類型を示してみよう。
(α)三者の協力は必然である(=「戦争と学知は結びつく派」)
学問と軍事研究は結びついている。なぜならば、近年になればなるほど、戦争と軍事行動には、高度な知識情報処理とそれにもとづく意思決定が働いているか
らだ。情報コミュニケーション技術(ICT)や人工知能(AI)などの動員やそれらへの期待をみればわかるように、戦争と軍事の分析官の仕事はいままで以
上に高度に情報化かつ分業化している(Chamayou 2013; McFate
2019)。それらの分業と全体性を把握できない不全感こそが、軍事研究の刷新を求め、広く知識人にその改善が求められているのである。仮に受領していな
くても、そのような軍事研究資金提供から得られるものの恩恵という政治的文脈の中に当然我々はいる。米国のDARPA(Defense
Advanced Research Projects
Agency)は潤沢な資金を供給しており、さまざまな批判はあるものの成果を上げているのではないか。インターネットやGPS、無人ドローン技術など軍
事用であったものが民生にスピンオフ(spin
off)したり、パソコンやインターネットプロトコルなど民生のものが軍事にも使われたりするようになる(spin
on)のは、科学技術における常態であり、なんら驚くべきものではない(笹本1995;モレノ 2008;ジェイコブセン 2012,
2017)。いや、スピンオン/オフという二元論はもはや時代遅れだ。そのような両者の関係の区分や境界設定はナンセンスであり、今日ではデュアルユー
ス・テクノロジーが当然である。このような意見である。
(β)戦争と学知はかつて必然であったからこそ我々は冷静になりそれを分離し、学問は軍事研究を対象にしながらもその中心的なエートスから自らを遠ざける
べきだ(=「分離反戦派」)
かつては、そして今も学問と軍事行動は結びついている。英国軍に従軍した社会人類学者エヴァンズ=プリチャード、エドマンド・リーチ、グレゴリー・ベイ
トソン、米国のマーガレット・ミード、ジェフリー・ゴラー、ルース・ベネディクトを思い出せ
。だからこそ、その反省にたって良識ある科学者は、軍事研究に関与することから距離を取るばかりでなく、積極的に否定しなければならない。この立場には、
ライト・ミルズ、デル・ハイムズ、マーシャル・サーリンズ、そしてノーム・チョムスキーらがいる
。マンハッタン計画に加わったアルバート・アインシュタインですら、戦後ナチスドイツの科学者でナチに忠誠を誓ったことのある学者を米国に招聘するために
ビザを発給することに対して異を唱え、ハリー・トルーマン大統領に書簡を認めたではないか(ウィアート編
1982)。また湯川秀樹のパグウォッシュ会議の組織という英雄的な行動と彼の学術研究は完全に両立したではないか、などという主張である(日本パグ
ウォッシュ会議 Online)。
(γ)左派と右派の価値判断から自由になり仔細に中立的に検討すべき(=「価値中立分析派」)
文化人類学や社会学は、マックス・ウェーバーが言うように価値自由の学問である。もし、科学と軍事との関係を客観的に描写し、分析したいのであれば、価
値自由で中立的であることが必要であり、それが文化人類学者や社会学者にとっての善行(good conduct, good
deed)となるはずだ。「軍事と科学研究は協働すべきという」考え方も、また「科学研究者は軍事のことを批判的に研究すべきという考え方」も共に偏りが
ある。なぜなら、文化人類学や社会学は、そのような双方の姿勢がもつ予断から自由になり、認識論的相対主義の立場から、この軍事と科学と技術の関係を明ら
かにすることが先決なのである。良いか悪いかを判断をするのは、我々が客観的なデータを提示してからであり、それを判断するのは、高度な政治的判断が求め
られる専門家であろう。我々は、その専門家の一翼を担うだけであり、同様な努力をしている他の専門家との共同が欠かせない、というのが第三番目の主張であ
る。
文化人類学や社会学の研究対象との関わりのなか で、Anthropology for/of/in <Research Subject> あるいは Sociology for/of/in <Research Subject> という研究対象やテーマとの関連性についての形式的な分類と議論をすることをお許し願いたい。「〜のための人類学/〜の人類学/〜における人類学」という 表現を区分することで、その研究対象と人類学との利害=利益関係を明らかにしようとする形式論的な議論である。「〜のための人類学」は、その研究対象に対 してなんらかの学問的貢献を試みようとするもの。「〜の人類学」は、研究対象に価値中立的な立場から分析を冷静に行おうとする態度である。そして「〜にお ける人類学」は、実践状況の中でその研究対象に関わり、対象に貢献するだけでなく、その対象からも自分自身の学問が影響を受けていくさまを表す。
上掲の<Research
Subject> にmilitary intelligence
という言葉を代入して、人類学と軍事的インテリジェンスの関係を整理してみよう。すなわち「軍事的インテリジェンスのための人類学
(anthropology for military
intelligence)」、次に「軍事的インテリジェンスの人類学(anthropology of military
intelligence)」そして「軍事的インテリジェンスにおける人類学(anthropology in military
intelligence)」と表現する。そうすると、for/of/inという前置詞は、それぞれ上掲のα、β、γの立場に対応すると言えるかもしれな
い。より正確には、for/of/in の対応関係は、for/against/of
であるとの修正することも可能だ。では、なぜ、文化人類学者が軍事的インテリジェンスの研究に着手しなければならないのか。この国の軍事研究機関あるいは
研究助成機関にとって、これら研究の態度はどのような魅力や関心——あるいは嫌悪や無関心さ——をもつのだろうか。そして、この学問の未来はどのようなも
のだろうか。
文化人類学界のインサイダーとしての私は、このように文化人類学の研究対象の範囲を広げる活動を〈非常に好ましいもの〉だと思っている。が、しかし他方
で、研究対象の範囲を広げて戦争にまで対象を拡張することは、現在の「戦争社会学」の隆盛にくらべて、決して同業者に大きな関心をもたらしているものでは
ない。現実問題として、近年では文化人類学の魅力自体が欠けており、学問領域全体における文化人類学のヘゲモニーがとても低下しているように思える。
文化人類学の学問的衰退の理由はいったい何なのだ ろうか? その理由のひとつは、非常に表面的ではあるが厳然たる事実としてのマスコミの寵児として称えられるスター人類学者がいないこともあるだろう。少なくとも山 口昌男らが活躍した1970-2000年の四半世紀強の時代に比べてこの分野の凋落は否めない。内在的な理由として、文化の心理学的内面化 (enculturation) によって説明づけられることの多い局所化する〈文化〉の概念を通して、人類文化を論じる説明のタイプの衰退があげられる。他方、〈社会〉という概念の隆盛 はどうだろうか? おおくの社会の分析研究は、普遍化志向がつよく、全体社会の出来事——デュルケーム(1978)のFait social totalで表現される——である〈社会〉のイメージは、〈文化〉のそれに比べて、いまだに影響力が大きい。
ここでいう〈文化〉概念は、通常、文化研究者が使 い分けている2つの文化概念の一方の側のものをさす。すなわち文化は、(1)フランス的な普遍人間文化あるいは文明さらにはビルドゥング (Bildung;教養)に代表されるような単数の大文字の文化と、(2)「他者の異なる諸文化(other cultures)」で表現されるような複数形のボアズ流の文化概念に区分される。そして、私が衰退著しいと言うのは、文化人類学者がもっぱら専有してき た後者のほうである。もちろん、前者の普遍[人類]文化=文明の概念も、その中心モデルは西洋化あるいは西欧文明であり、サミュエル・ハンティントン的の パラダイムが言う「非西洋文明」からの挑戦を受け続けているのは周知のとおりである(Huntington 1996) 。
後者の文化の概念が、社会的影響力をもっていたの は、異文化理解が重要だと主張されていた時代である。それは、文化を分析することは「人々の相互理解のためによいものだ」という我々の信念つまりイデオロ ギーに訴えかけていたものである。他者の文化理解を通してこそ、戦争や人種偏見がなくなり、人々が平和裡に共存できるというプログラムを文化人類学がかつ ては強力に主張していた。だがこれは、この学問を「現実政治=リアルポリティーク」から目を背け、ユートピア的な文化に憧れるという逃避行動を同業者にも たらした。国際政治学(国際政治論)の教科書ですら、多文化主義の理想的なリベラル追求の面よりも、保守主義的な支配のためのイデオロギー装置として多文 化主義は機能するということを強調している 。ガヤトリ・スピヴァックは1990年には「多元論とは、中心的権威が反対意見を受け入れるかのように見せかけて実は骨抜きにするために用いる方法論のこ とである」と正しく指摘していた(スピヴァック1992:119)。異文化理解を通して世界が平和裡に共存できるという考え方は、冷戦後のスティーブン・ ピンカーのいう『我々の本性のよき天使たち』がリアルポリティークという雷に打ちのめされる直前のつかの間の幸福な出来事だったのかもしれない (Pinker 2011)。
現在の人文社会科学における異文化概念の扱いは、 人々の投資や消費の行動に見られる特異的なバイアスや変異を生み出す原因である。そして、文化化(enculturation)が脳内の活動として証明さ れるように、機能的核磁気共鳴装置(fMRI)が描き出す脳の活動マップが指し示す人間の認知や情動の局在の普遍性にもとづき、どのように統計的な偏差が 出るのかを表現する人種的区分とスレスレの人間的な行動の種的差異のインデックスにまで〈文化〉概念は凋落した、と言えよう。あるいは、ビジネスの現場で 相手と自分の「真意」がわかる教養のひとつにまで縮小化した知的道具にされてしまった(Meyer 2014)。
さてアーウィン・メイヤーの知的道具は、国際ビジ ネスの現場で「異文化の他者を理解することを通してwin-lose の関係ではなくwin-winの関係で平和裡に共存しよう=商売しよう」という理念が、いままさに実現しようとしている証左かもしれない。今から80年以 上も前に、Office of Strategic Services(OSS)に雇用されたり関係をもったりしたベイトソンやミード、あるいはOffice of War Information (OWI)で働いていたベネディクトが構想した、異文化が激突する戦場 を理解するために、これらの文化の専門家は、お互いに歯向かいあっている敵と味方どうしは理解可能であると主張し、かつ同時に、敵(=枢軸国側)に打ち勝 つためには敵の文化行動のパターンを合理的に理解することが必要だという、それぞれ相矛盾したことを主張していた 。
本節の見出し「軍事的インテリジェンスの人類学に
文化概念は必要か?」について考えよう。軍事的インテリジェンス活動が必要とするのは、異文化ならびに自文化の「文化」概念の手垢にまみれていない客観的
情報だといえる。客観的情報は、敵と味方の双方が共有する力と力の衝突における雌雄を決する要因としての科学技術を支えるからである。軍事的な科学技術を
使う人たちにとって、科学的事実は人間的な要素が入る余地がない客観的なものである。第5節で触れる「ペーパークリップ作戦」の歴史からみても、アメリカ
合衆国の軍隊や諜報部は、ナチスの科学者と同等のレベルの功利主義者だった、というのが私の基本的理解である。
04.《戦争と軍事的インテリジェンスの人類学》の立場 について
戦争と軍事的インテリジェンスと人類学(学知)の
関係の位相について思いを馳せる時、先に述べたα、β、γは、経験的に眺めると、その順に登場してきたと言える。はじめは、(α)戦争と軍事的インテリ
ジェンスと学知の協力がまさに臨戦状況の中で急ごしらえの中で生まれ、戦争や紛争が終わった時点で、次に(β)戦争の学知の残忍さが暴露され人々に反省す
べきであるという視座が生じ、それが歴史的な冷却化を経て、(γ)価値自由な客観的な研究が求められるようになった。つまり最後に登場した、(γ)価値自
由な客観的な研究は非の打ち所がないように思える。しかし、問題点がまったくないわけではない。
すなわち(1)研究の内実と倫理や価値の位相が、現実の世界に生きている我々の財政的支援者になってくれる個人や団体にとって見えにくいという問題。言
い方を変えると、我々は目の前にある仔細な研究を優先することで、倫理的な判断を含めた結論を先延ばしにしようとしている。そして(2)さまざまなイデオ
ロギーにまみれていた研究対象である歴史上の科学者や学者と同様に、我々もまた生きている現代の社会(あるいは文化!)のイデオロギー的被拘束性に無自覚
ではないかという自己反省(マンハイム 1968)。
軍事的インテリジェンスの人類学と我々の倫理や道
徳とα、β、γの立場の関係を通してここで整理しておこう。
(α)戦争と学知は結びつく派:
この派閥の問題は、効用に対する興味が過剰であ
り、科学の勝利者史観が強い。効用に焦点が当てられすぎると、研究発見の偶発性(セレンディピティ)がみられることを過小評価してしまう。ここでの、セレ
ンディピティとは、偶発的な発見や木に竹を継ぐような奇天烈なものが思いもよらない結果を生むことである。セレンディピティの阻害の他に、さらに(γ)に
も通底する問題だが、道徳的無感動(アパシー)つまり「これは不幸なことだが私がやらなくても他の誰かが研究をしてしまうだろう」という感情を我々の研究
にもたらしてしまう。
(β)分離反戦派:
戦争と学知の結びつきは常に悪であるという主張が
ある。これは、最初から結論があり、それを論証ではなく事例をあげつらい、非難の言語で粉飾する。典型的な論点先取(Begging the
question, Petitio
Principi)の論法である。この立場をとる多くの人は陰謀説を安易に採用してしまいがちだ。曰く「フェアな戦争などない。敵に対して不信感しか持た
ない軍事関係者はつねに軍事的インテリジェンスすら動員しかねないのだ!」というものである。アプリオリな平和教育の重要性を優先する余りに、軍事的イン
テリジェンスがもたらす意味に「価値中立的」な考察をその非難の中に見つけることが難しい。誇張して言えば、過去の自らの行為に対するマゾヒズム、過去の
他者の行為に対するサディスティックな趣味が見られる(ドゥルーズ
2018:24-25)。つまり加害と被害の欲望(=言説)は相補的な関係にある。あるいは、それらの両義的な解法をもとめるあまり、研究者自身が道徳的
企業家(moral entrepreneur)化してしまうという陥穽が待っている 。
(γ)価値中立分析派:
仔細を通り越した些細な歴史事象への拘り、反証例
を見つけて論証の細部に沈積すること。キャノン(主たる学説が依拠する原典)への信奉、歴史的史料フェティシズム。そして研究のための研究への埋没。それ
らの行動の帰結としての歴史の細部修正という無限後退、などがその欠点である。
私は、研究課題「ファシズム期における日独伊のナ
ショナリズムとインテリジェンスに関する人類学史」において、ファシズム期終焉以降の、ナチの戦争犯罪人たちの新大陸への脱出と、その後の人生について、
ファシズム時代の倫理違反事象と判断される各人の経験の、対位法的
な関係について考察するつもりである。そのために、アニー・ジェイコブセン(Jacobsen
2015)が描く「ペーパークリップ作戦」と、ウキ・ゴニェイ(Goñi
2002)の『真実のオデッサ』の所論を整理する。2つの事例と、そこから軍事的インテリジェンスの人類学にどのようなレッスンがあるのかということを紹
介する。
5.1 ペーパークリップ
第二次大戦中からアメリカは、ナチスドイツの科学 技術に関心をもっていた。ペーパークリップ作戦とは、ドイツの科学者を占領と共に米国に連れてきて、研究や技術開発に従事させようという計画である。ただ し、当初これには大きな問題があった。ひとつは、ナチスドイツに忠誠を誓った「体制派」の科学者は、潤沢の研究費の給付とともにナチスドイツに忠誠を誓っ ていた。また、Vロケット開発(V1, V2)のように、空襲に耐えることができる地下工場で、ユダヤ人を奴隷労働に従事させていた。つまり、すさまじいばかりの人的消耗=虐待行為を自ら率先し て、あるいは黙認して、そこから出る利益を享受していた。目覚ましい軍陣医学(=軍事医学)の進歩は、強制収容所の囚人を使って、非人道的な殺害を含む人 体実験をおこなった末の「成果」であった(池田a Online)。その結果、医学倫理に対するプロトコル原理が策定され、医学研究における人体実験の禁止を明記したニュルンベルク・コードは、ニュルンベ ルク裁判後におこなわれた、通称「ニュルンベルク医学裁判」にもとづいて生まれたものであった(池田b Online)。
当然、戦争犯罪を問われた被告たちを、米本国に召 喚するのは困難を極めた。しかし、軍部ならびに情報部は、たくみに戦争犯罪者である科学者たちをリストアップして、彼らの資質を評定し、あげくには「よき アメリカ人」になる可能性を示して(つまり偽装して)、結果的に1,600名以上を招聘することに成功した。つまり戦犯免責を偽装し、ビザを与え、アメリ カ本国において戦後、医学や化学、兵器開発あるいは宇宙開発に従事させることに成功したのだ。その背景には、戦後に激化する冷戦構造があった。ナチの科学 者をソビエトに奪われることは、米国の軍事的優位を損なうことになるという配慮からである。
我々がペーパークリップ作戦から学べることは、ア
メリカの科学技術政策がアメリカの戦争遂行ならびに国防的課題と深く関わっていることと、そして、それは第二次大戦後の現在にまで絶えることなく連続して
いるということである(Jacobsen 2014,
2016)。これは敗戦において根本的な断絶を経験した日本の民族学と軍事的インテリジェンスの展開の歴史とは根本的に異なる(中生 2016)。
5.2 オデッサ
書名『真実のオデッサ』の、オデッサ (ODESSA)とは、ナチスドイツの将校が敗戦後に組織した"Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen" (「元親衛隊SSの組織」) の略称で、ペーパークリップと同様に、ナチの戦争犯罪人を追跡していた米国人たちがつけた名前である。作家のフレデリック・フォーサイス(Forsyth 1972)が『オデッサファイル』というスパイ・フィクションとして出版しこの名称が有名になったが、サイモン・ウィーゼンタール(1998)らのナチハ ンターたちからは、そのネーミングが不適切だと指摘されている。実際オデッサは謎の組織で正体がわからず仕舞いになった。しかし、ナチハンティングに対し て1960年代から1980年代頃にいたるまで「オデッサ」の名称を騙ってテロ活動があったために、その存在を幻のものとすることはできない。
ゴニェイの作品『真実のオデッサ』は、その副題に アルゼンチンのファン・「ペロン(大統領)はいかにしてナチ戦争犯罪人をアルゼンチンに連れてきたか」とあるように、フォーサイス流のファンタジー的歴史 観を排して、実際のヨーロッパ(主にイタリアとオランダ)からのアルゼンチンへの移動ルートと旧大陸と新大陸の支援組織の存在とそれらの働きを歴史的に明 らかにしようと試みるものである。アルゼンチンは、大戦間期にユダヤ人受け入れをはじめてから、反ユダヤ主義と寛容的受け入れというものが並存するアンビ バレントな政策を取り続けたが、ユダヤ人移民支援組織化のおかげで、新大陸ではアメリカに次ぐ、ユダヤ人口を擁する国になった。また同時に、ナチの戦争犯 罪人も数多く受け入れたが、そのなかでも元ナチ親衛隊中佐で、全ヨーロッパでの強制絶滅収容所への移送責任者であったアドルフ・アイヒマンが、長年リカル ド・クレメントの偽名で潜伏していたのもアルゼンチンである。1960年にはアイヒマンはイスラエル・モサド(諜報特務庁)によりエルサレムに連行され裁 判にかけられ判決の後に1962年に処刑されている(Stangneth 2011)。
軍事的インテリジェンスの人類学にとってオデッサ
の教訓は、我々の研究対象の不可思議さ曖昧さ、そして調査不能の気持ちにさせることだ。ナチハンティングは民間ユダヤ人の組織的な努力でなされたが、当時
の——ユダヤ出自のフランクフルト検事総長だったフリッツ・バウアーを除いて——西ドイツもアルゼンチンの司法当局もナチハンティングには消極的であっ
て、時にはその捜査を妨害していたこともあげられる。そのため現地での情報の集積は極めて困難であり、十分に組織化されていない。どうしてもエルサレムの
ヤド・ヴァシェム(ホロコースト記念館)の公文書保存館とアルゼンチンの現地調査の往還というプロセスが必要になる 。
私が追求するのは、「ペーパークリップ」と「オ デッサ」という2つの方向性の異なる研究テーマ ではあるが、私の中では2つが繋がっており、それらは相互に関係している。それは、私が長年手がけてきた、世界的な労働移動民の比較研究(池田 2012)と、この数年間に急速に関心を持つようになった、研究倫理とりわけナチスや七三一部隊の人体実験に関する倫理的・法的・社会連累 (Ethical, Legal, and Social Implications; ELSI)すなわちエルシーに関与する事柄だからである。エルシー(ELSI)とは、倫理的・法的・社会的連累(=含意、インプリケーション)/事象=イ シューの頭文字表現(アクロニム)である。従来の研究倫理の枠組みを拡張して、理工系・医歯薬保健系、人文社会系を問わず、あらゆる研究者がエルシーに関 わっていることを自覚させる社会化の試みのひとつである。インプリケーションを連累と訳すのはテッサ・モーリス=スズキ(2013:65-66)に倣って いる 。
さて、エルシーという言葉の起源は古くは、 1988年にヒューマン・ゲノム・プロジェクト(HGP)が始まったときに、遺伝学者でプロジェクト責任者のジェームズ・ワトソン(James Watson, 1928- )がプレスコンファレンスで突如として述べたものである。そのため、ヒューマン・ゲノム・プロジェクトを扱うアメリカ国立衛生研究所(NIH)——現在は その下位部局である国立ヒューマンゲノム研究所(NHGRI)が管轄——は当時、急遽そのような体制を整備したと言われている(Cook-Deegan, 1995)。日本のエルシー(ELSI)は、倫理的・法的・社会的連累(=社会的含意)の米国流の概念を輸入したために、そう呼ばれるが、ヨーロッパで は、エルサ=倫理的・法的・社会的諸相(Ethical, Legal and Social Aspects, ELSA)と呼ばれているようである(Chadwick and Zwart 2013) 。
日本では、神里達博(2016)による「情報技術 におけるELSIの可能性」がそれを取り上げて考察している。彼によると、ワトソンのエルシー提案の際に法律家として関わったローリー・アンドルーズ (Andrews 1999)は、その著書『ヒト・クローン無法地帯』において、ワトソンが後年になって「私(=ワトソン)は,討論ばかりしていて実際には何も行動を起こさ ない監視団を望んでいた」と吐露したという。先に、私は研究費を取得するための受け皿としてのELSI概念と研究が使われるとすると、それは全く「破廉恥 な」行為になりエルシー(ELSI)という理念に反すると考えるものである。日本では、ワトソンがかつて望んでいたように「討論ばかりしていて実際には何 も行動を起こさない監視団」が本当にエルシーになってしまうかもしれないことを大いに危惧している。Ikeda (2020)は、日本における先住民の遺骨返還請求の社会状況を文化人類学的に分析した論文のなかで、この「倫理的・法的・社会的連累」(ELSI)とい う用語を用いているが、エルシーは研究を実施する機関がそのように標榜するためのものではなく、研究を監視する政府や市民団体が主体的にこの用語を使うべ きであると主張している。
軍事的インテリジェンスの人類学の研究は、エル
シーがもつ学問活動への監視や監督の精神と、学問と社会との連累(インプリケーション)が交錯する現場(arena)でこそ、はじめて学問的反省がそれに
携わる研究者に反照されるものであってほしいと私は考える。個々の文化人類学者にフィールドワークの研究倫理が必要であることは言うまでもないが、文化人
類学という学問が、つねに倫理的・法的・社会的連累を考えるものになる時にはじめて、言葉の厳密な意味での倫理的転回(ethical turn in
the strict sense of the term)というものが訪れるはずである。
本稿は、科学研究費補助金・基盤研究(B)「ファシ
ズム期における日独伊のナショナリズムとインテリジェンスに関する人類学史」(課題番号
19H04363)(研究代表者:中生勝美)の研究の一部である。「研究倫理入門」というウェブページを8年ほど前に作って以来、アクティブラーニング型
の授業の資料として使い、またサイトを見てきた全国の大学関係者から複数の講演などを行なってきた。この文章の中で研究倫理に関して私らしいものがあると
すれば、それはこれまで講演や授業で様々な質問やコメントを寄せてくれた学生や聴衆のお陰である。すべての各位に感謝したい。
n1) baron de Antoine Henri Jomini の著作は、Project Gutenberg(http://www.gutenberg.org/)にある英訳テキスト"The Art of War," 1862. を参照した。ジョミニのフランス語の著作の半世紀後にG.H. Mendell と W.P. Craighill により英訳された本書であるが、現在でもNATOの戦略マニュアルの中にその理論を留めている。ジョミニも含めてクラウゼウィッツやマハンなどの軍事行動 論がワーテルローの戦いをモデルとしているために、1950-1970年代のベトナム戦争など非軍事的要素が深く関わる紛争状態では全く使い物にならない ことをSean McFate (2019)は批判している。
n2) 科学史家の米本昌平(1998)氏は「地」と「知」の地口を使った『知政学のすすめ』という本を上梓している。興味深い言葉遊びではあるが、氏の関心は軍 事にとどまらず科学技術(=知)が現代社会生活の有り様を変えることを主題にしているが、本稿で述べた問題関心とは「軍民需要転換」のテーマを除けばあま り交錯しないように思われる。
n3) 科学技術史とりわけ西洋社会で発達した技術が世界覇権について果たす役割について考察を深めてきたダニエル・ヘドリック(2011)ですら情報を取り使っ た『情報時代の到来』において軍事作戦行動における情報循環のことについての言及は皆無である。軍事行動において情報は使われるもので、戦争が人間にとっ ての情報の概念を変容させるという発想が彼にはない。
n4) 私は2020年2月4〜8日に開講した東北大学大学院国際文化研究科での授業 " Ethics for Academic Research" において、Kathryn Bigelow監督の" Zero Dark Thirty" (2012)の映像を使って「テロとの戦争」時において、非合法拉致者への拷問による情報収集がテロリスト殲滅の秘密作戦行動を正当化できない倫理的根拠 を学生たちと一緒に列挙した。その後、2011年5月2日のホワイトハウスがアップロードした"President Obama on Death of Osama bin Laden"(9分27秒)を上映し米国大統領の「暗殺」の正当化言説との照合をおこなった。これも対位法的読解(注(14)を参照せよ)のひとつである と私は考えている。
n5) インプリケーション(implication)を連累(れんるい)と訳すのは、テッサ・モーリス=スズキ(2013)の用語法である。これは責任 (responsibility)は私達が作り上げるものであるのに対して、連累(implication)は私達(という関係性)を(新たに)造り上げ るものであるという含意である。脚注(16)を参照せよ。
n6) 本稿に関連する代表的なもののみをあげる;Evans-Pritchard (1954); Leach (1954); Lipset (1982) on Gregory Bateson; Lapsley(1999) on Margaret Mead and Ruth Benedict; Gorer and Rickman (1962).
n7) 本稿に関連する代表的なもののみをあげる;Wright Mills(1956); Hymes(1972); Sahlins(1976); チョムスキー(1981).
n8) Enculturation は「文化化」と翻訳されることが多いが、当該社会の人々の生活の中にある文化が活動を通して心理的な意味での心の中に内面化する心理人類学分野の術語であ る(池田f Online)。
n9) ここで「サミュエル・ハンティントンの『文明の衝突』は文明の衝突であり文化の衝突ではない」という反論は可能だ。しかしハンティントンの Political Order in Changing Societies(1968, 2006)の内容や問題関心は、Clifford Geertz, Interpretation of Cultures (1974 :247-248)のPart IV の9章「革命の後に:新興国家のナショナリズムの運命」や10章「統合的革命:新興国家における本源的感情と政治的市民」 とその問題関心はほぼ一致するし、実際にギアツは前著を引用している。フランシス・フクヤマは2006年に復刊された前著の序文に寄せて、当時の新興国家 のハンティントンの分析は、現在の政治的安定性の議論にとっても有効であると述べている。
n10) 池田c(Online)は「ジジェク教授による厄介な多文化主義批判」の中で、スラヴォイ・ジジェク(2005:385)の所論を取り上げ、人種主義に反 対し多文化状況を肯定しようとする普遍主義的な自己(=西洋社会を含意する)文化的=イデオロギー的論理が〈他者の相対化される文化〉との距離を作ってし まい、従前の人種主義に代わる「傍観する人種主義」を形成してしまうことを紹介している。
n11) ミードとベイトソンのOSSへの関与については、Lipset (1982)を参照のこと。
n12) 池田d(Online)「『文化』概念の検討:連続講義」を参照のこと。
n13) 「道徳企業家とは、世の中の「よき」道徳や規範を代弁するふりを通して、そのような規範を世の中の多くの人たちに吹聴する人たち、あるいは、そのような社 会的「役割」を自らかってでる人たちのこと」で、それ以外に道徳事業家、道徳起業家、モラル・アントゥルプルヌール(moral entrepreneur)、モラル・アントレプレナーとも言う。アントゥルプルヌールは、フランス語で企業家のことである(池田e Online)。
n14) 音楽における対位法のアディアからエドワード・サイード(1998:137)は「対位法的読解(Contrapuntal Reading)」を提唱した。これは、同時代的状況 の中で地理的にまったく離れたところで、まったく関係のないように思われた出来事によるテキストの生産をつき合わせることで、その相互に共通にみられる、 ないしは、独立した出来事(旋律)が絡み合う対位法的なハーモニーの生成——専門的には和声的対位法 harmonischer Kontrapunkt——を発見しようとすることである。
n15) 2019(令和元)年度の本研究課題「ファシズム期における日独伊のナショナリズムとインテリジェンスに関する人類学史」(課題番号 19H04363)の研究費ならびに大阪大学COデザインセンターの研究推進経費を受けてブエノスアイレスのユダヤ・シナゴーグ調査(2019年12月 27日-31日)とエルサレムのヤド・ヴァシェム(2020年1月21日-22日)を訪問できたことは幸いであった。
n16) 方向性が異なるとは、一方で「ペーパークリップ作戦」とはナチの戦争犯罪者の戦後の功利主義的利用という〈他者によるナチの利用〉ことであり、他方で「オ デッサ」は正体がわからないまま機能していたナチ自身の過去の犯罪の反省を回避しながらサバイバルするための支援組織つまり〈自分たち自身の生存手段〉で あるからだ。
n17) オーストラリアの移民であるモーリス=スズキ氏(2013:65-67)は、先住民アボリジニへの過去の収奪や虐殺と彼女自身の関係を「罪」ではなく「連 累(implication)」であると結論づけた。つまり、過去の不正義に対して責任がオーストラリアに住む自分自身にあるという。それは法律用語であ る事後共犯(an accessory after the fact)の現実を認知するという意味である。彼女による連累の感覚を次の文章は的確に表しているので引用する:「わたしは直接に土地を収奪しなかったか もしれないが、その盗まれた土地に住む。わたしは虐殺を実際に行わなかったかもしれないが、虐殺の記憶を抹殺するプロセスに関与する。わたしは『他者』を 迫害しなかったかもしれないが、正当な対応がなされていない過去の迫害によって受益した社会に生きている」。また責任と連累の関係を次のようにいう「『責 任』は、わたしたちが作った。しかし、『連累』は、わたしたちを作った」(共に モーリス=スズキ 2013:67.※引用文にある部分強調は省略した)。
n18)
Chadwick and
Zwart (2013)によると、各国ではさまざまな用語法が試みられてきたことが示されている( )内は初出年:ELSI (U.S.A.,
1992), GL3LS (Genomics-related Ethical, Environmental, Economic, Legal
and Social Aspects, Canada, 2000), ELSI (South Korea, 2001), EGN (ESRC
Genomics Network; Cesagen, Innogen, Egenis, Genomics Forum, United
Kingdom, 2002), CSG or MCG (Centre for Society and Genomics, or
Societal Component of Genomics Research, Netherlands, 2002), ELSA(ELSA
Program, Norway, 2002), ELSAGEN(Transnational Research Programme,
Germany, Austria, Finland, 2008).
| Andrews, Lori B (1999) The clone
age : adventures in the new world of reproductive technology. New York:
Henry Holt.=(2000) 望月弘子(訳)『ヒト・クローン無法地帯:生殖医療がビジネスになった日』紀伊國屋書店. Chadwick, Ruth and Hub Zwart (2013) From ELSA to responsible research and Promisomics. Life Sciences, Society and Policy 2013, 9:3. doi: 10.1186/2195-7819-9-3 Chamayou, Grégoire (2013) Théorie du drone. Paris: Fabrique. チョムスキー,ノーム(1981)河村望(訳)『知識人と国家』ティビーエス・ブリタニカ. Clausewitz, Carl von (1832) Vom kriege. Berlin. =(1968)篠田英雄(訳)『戦争論』岩波書店. Clifford, James (1988)The predicament of culture: twentieth-century ethnography, literature, and art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. = (2003) 太田好信ほか(訳)『文化の窮状 : 二十世紀の民族誌、文学、芸術』人文書院. Cook-Deegan, R. (1994) The gene wars: science, politics and the human genome. New York: Norton.= (1996) 石館宇夫・石館康平(訳)『ジーンウォーズ:ゲノム計画をめぐる熱い闘い』化学同人. ドゥルーズ, ジル(2018)堀千晶(訳)『ザッヘル=マゾッホ紹介:冷淡なものと残酷なもの』河出書房新社. Durkheim, Emile(1894) Les règles de la méthode sociologique. Paris: Les Presses universitaires de France =(1978) 宮島喬(訳)『社会学的方法の規準』岩波書店. Evans-Pritchard, E.E. (1954) The Sanusi of Cyrenaica. Oxford: Oxford University Press. Forsyth, Frederick (1973) The Odessa file. London: Corgi Books. Geertz, Clifford (1974) Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. Gorer, Geoffrey and John Rickman (1962) The people of great Russia: a psychological study. New York: W.W. Norton. Goñi, Uki (2003) The real Odessa: how Perón brought the Nazi war criminals to Argentina. London: Granta Books. ヘッドリク,ダニエル(2011)塚原東吾・隠岐さや香(訳)『情報時代の到来』法政大学出版局. Hymes, Dell ed.,(1972) Reinventing Anthropology. New York: Pantheon Books. Huntington, Samuel P.(1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster. =(1998)鈴木主税(訳)『文明の衝突』集英社. Huntington, Samuel P.(1968,2006) Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press. 池田光穂a(Online)「ペーパークリップ作戦」 https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/operation_paperclip.html (2020年7月18日確認) 池田光穂b(Online)「ニュルンベルク医学裁判」 https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/Arzteprozess_1946-1947.html (2020年7月18日確認) 池田光穂c(Online)「ジジェク教授による厄介な多文化主義批判」 https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/16-ticklish_multi-culturalism.html (2020年7月18日確認) 池田光穂d(Online)「『文化』概念の検討:連続講義」 https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/050228portal.htmll (2020年7月18日確認) 池田光穂e(Online)「道徳企業家」 https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/121031MoralEntreprene.html (2020年7月18日確認) 池田光穂f(Online)「心理人類学」https://www.cscd.osaka- u.ac.jp/user/rosaldo/tep015.html (2020年7月18日確認) 池田光穂・編(2012)『コンフリクトと移民:新しい研究の射程』大阪大学出版会. Ikeda, Mitsuho (2020) Repatriation of human remains and burial materials of Indigenous peoples in Japan : Who owns their cultural heritages and dignity? CO*Design 7:1-16. doi.org/10.18910/75574 Jacobsen, Annie (2014) Operation paperclip : the secret intelligence program that brought Nazi scientists to America. NY: Little, Brown and Company. = (2015) 加藤万里子(訳)『ナチ科学者を獲得せよ! 』太田出版. Jacobsen, Annie (2014) Area 51 : an uncensored history of America's top secret military base. London: Orion.= (2012) 田口俊樹(訳)『エリア51 世界でもっとも有名な秘密基地の真実』太田出版. Jacobsen, Annie (2016) The Pentagon's brain : an uncensored history of DARPA, America's top secret military research agency. New York: Back Bay Books =(2017) 加藤万里子(訳)『ペンタゴンの頭脳:世界を動かす軍事科学機関DARPA』太田出版. Jomini, Antoine Henri (1811) Traité des grandes opérations militaires. Paris: 2e éd, accompagnée d'un atlas militaire, augmenté de cartes et plans de batailles. = (2001)佐藤徳太郎(訳)『戦争概論』中央公論新社. 神里達博(2016) 「情報技術におけるELSIの可能性:歴史的背景を中心に」『情報管理』58(12):875-886. 金谷治(校訂)(2000)『新訂 孫子』岩波書店. Kjellen, Rudolf (1917) Der Staat als Lebensform. Leipzig. =(1943)金生喜造(訳)『領土・民族・国家』三省堂. Lapsley, Hilary. (1999). Margaret Mead and Ruth Benedict: The Kinship of Women. University of Massachusetts Press Leach, E.R. (1954) Political Systems of Highland Burma: A study of Kachin social structure. Boston: Beacon Press. Lipset, David (1982) Gregory Bateson: the Legacy of a Scientist. Boston: Beacon Press. マンハイム,カール (1968) 鈴木二郎(訳)『イデオロギーとユートピア』未来社. Mattern, Johannes (1942) Geopolitik : doctrine of national self-sufficiency and empire. Baltimore: Johns Hopkins Press. McFate, Sean (2019) The New Rules of War: Victory in the age of durable disorder. New York: Willoam Morrow. Meyer, Erin (2014) The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business. New York. Moreno, Jonathan (2006) Mind wars: Brain research and national defense. New York: Dana Press.= (2008) 西尾香苗(訳)『操作される脳』アスキー・メディアワークス. モーリス=スズキ,テッサ(2013)『批判的想像力のために:グローバル化時代の日本』平凡社. 中生勝美(2016)『近代日本の人類学史:帝国と植民地の記憶』風響社. 日本パグォッシュ会議(Online) https://www.pugwashjapan.jp/ (2020年2月29日閲覧) Pinker, Steven A.(2011)The Better Angels of Our Nature: why violence has declined . London:Penguin.= (2015) 幾島幸子・塩原通緒(訳)『暴力の人類史』青土社. Sahlins, Marchall D.(1976) Culture and practical reason. Chicago: University of Chicago Press. Said, Edward W.(1978) Orientalism. New York: Vintage Books. = (1993)今沢紀子(訳)『オリエンタリズム』平凡社. サーイド,エドワード(1998) 大橋洋一(訳)『文化と帝国主義1』みすず書房. 笹本征男(1995)『米軍占領下の原爆調査』新幹社. スピヴァック,ガヤトリ(1992) 清水和子・崎谷若菜(訳)『ポスト植民地主義の思想』彩流社. Stangneth, Bettina(2011) Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer. New York: Vintage. Weart, Spencer R. and Gertrud Weiss Szilard(1978) Leo Szilard, his version of the facts: selected recollections and correspondence. Cambridge, Mass.: MIT Press =(1982)伏見康治・伏見諭(訳)『シラードの証言』みすず書房. ヴィーゼンタール,サイモン(1998) 下村由一・山本達夫(訳)『ナチ犯罪人を追う:S・ヴィーゼンタール回顧録』時事通信社. Wright Mills, C.(1956) The Power Elite. Oxford: Oxford University Press. 米本昌平(1998)『知政学のすすめ:科学技術文明の読みとき』中央公論社. Žižek, Slavoj(2000) The ticklish subject: the absent center of political ontology, London: Verso 2000.=(2005) 鈴木俊弘・増田久美子(訳)『厄介なる主体:政治的存在論の空虚な中心』青土社. |
クレジット:
池田光穂「軍事的インテリジェンスの人類学序説」国
立民族学博物館共同研究会「人類学/民俗学の学知と国民国家の関係:20世紀前半のナショナリズムとインテリジェンス」(研究代表者:中生勝
美)、
2018年12月27日研究発表(アップロード日:2019年1月1日)
●「ファシズム期にお ける日独伊のナショナリズムとインテリジェンスに 関 する人類学史」(中生勝美・基盤研究(B)2019年度- 2023年度:19H04363)
1930年代から40年代ならびに戦後処理期の人類 学史を、日独伊に焦点をあてて研究する。
| 現段階での池田による評価 |
日本 |
ドイツ |
イタリア |
| 1. ナショナリズム:民族意識の高揚に自国の人類学を活用したか? |
★★★ |
★★★★★ | ★★ |
| 2.
インテリジェンス:対敵分析や宣伝のため、人類学者をいかに利用していたか? |
★★★★ | ★★★★★ | ★ |
| 3.
科学的レイシズム:人類学理論は、科学的レイシズムとどのような関係をもったか? |
★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
「日独伊の三カ国の戦時中の人類学を比較検討するこ とを通じて、総力戦が人類学に与えた影響、戦後の人類学との連続性、政治とアカデミズムの緊張関係、さらに人類学者の研究活動が、いかに戦争遂行に関係し ていたかを、「三角測量(トライアンギュレーション)」の手法で描き出す」中生申請書より)
「ドイツ研究班のうち池田光穂(研究分担者)は、ナ チハンティング、優生学に関して論文を用意しており、中生と共同してベルリンでの調査、および単独でイスラエルでの調査を実施する」同上)
2019年度の研究分担者(池田)の研究報告
人脈
Prof. Dr. Reinhard Johler - Deputy Director, Institute of Historical and Cultural Anthropology, Universitat Tubingen
アンニバーレ・ザンパルビエーリ University of Pavia
David Price - professor of anthropology at St. Martin's University in Lacey,
●諜報
インテリジェンス(intelligence)と は、軍 事あるいは現実政治(リアルポリティーク)の世界で、秘密裏にすすめられる、人または通信や機械(コンピュータ)を使っておこなわれる、情報の収集、蓄 積、分析、解析の報告からなる活動である。インテリジェンスはかつて、諜報(ちょ うほう)と翻訳されていたことばを外来語として読み直したものである。Google - Dictionary によると二番目の意味に、2. the collection of information of military or political value(=軍事的または政治的価値のある情報収集).とあり、その同義語(synonyms)として「 information gathering(情報の収集), surveillance(監視), observation(観察), reconnaissance(偵察), spying(スパイ行為), espionage(スパイ活動), undercover work(諜報), infiltration(潜入[調査]), ELINT(電子偵察:electronic intelligenceの略号), HUMINT(人間諜報活動:Human intelligence), cyberespionage(サイバースパイ活動), humint(情報分析)」からなる。(→「インテリジェンス (intelligence)」)
対敵 諜報部隊(Counter Intelligence Corps, The United States Army)
対日占領政策理解のための略号集
| ABC |
Australian
Broadcasting Company |
||
| AFPAC |
Army Forces Pacific |
||
| AP |
Associated Press |
||
| ATIS |
Allied Translator and
Interpreters Section |
||
| BBC |
Br itish Broadcast ing
Corporation |
||
| CCD |
Civil Censorship Detachment |
||
| CCS |
Civil Communication Section |
||
| CIA |
Centra l Intelligence Agency |
||
| Counter Intellig ence Corp |
|||
| Civil Information and Education
Section |
|||
| NARA |
National
Archives and Records Administration |
ア
メリカ国立公文書記録管理局. |
|
| NPRC |
National
Personnel Records Center(s) |
https://www.archives.gov/personnel-records-center/federal-records. |
|
リンク
リンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

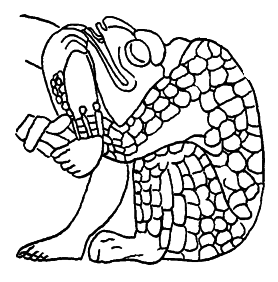
++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099